第一帖 桐壺 |
01 KIRITUBO (Myouyu-rinmo-bon) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 第一章 光る源氏前史の物語 |
1 Opening of the tale of Hikaru-Genji |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | 第一段 父帝と母桐壺更衣の物語 |
1-1 Father and mother's tragic love |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.1 | いづれの御時にか、 女御、更衣あまた さぶらひたまひけるなかに、 いとやむごとなき際にはあらぬが、すぐれて 時めきたまふありけり。 |
どの帝の御代であったか、女御や 更衣が大勢お仕えなさっていたなかに、たいして高貴な身分ではない方で、きわだって御寵愛をあつめていらっしゃる方があった。 |
どの天皇様の御代であったか、女御とか更衣とかいわれる後宮がおおぜいいた中に、最上の貴族出身ではないが深い御愛寵を得ている人があった。 |
Idure no ohom-toki ni ka, nyougo, kaui amata saburahi tamahi keru naka ni, ito yamgotonaki kiha ni ha ara nu ga, sugurete tokimeki tamahu ari keri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.2 | はじめより我はと 思ひ上がりたまへる御方がた、 めざましきものにおとしめ嫉みたまふ。 同じほど、それより下臈の更衣たちは、 ましてやすからず。 |
最初から自分こそはと気位い高くいらっしゃった女御方は、不愉快な者だと見くだしたり嫉んだりなさる。同じ程度の更衣や、その方より下の更衣たちは、いっそう心穏やかでない。 |
最初から自分こそはという自信と、親兄弟の勢力に恃む所があって宮中にはいった女御たちからは失敬な女としてねたまれた。その人と同等、もしくはそれより地位の低い更衣たちはまして嫉妬の焔を燃やさないわけもなかった。 |
Hazime yori ware ha to omohiagari tamahe ru ohom-katagata, mezamasiki mono ni otosime sonemi tamahu. Onazi hodo, sore yori gerahu no kaui-tati ha, masite yasukara zu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.3 | 朝夕の宮仕へにつけても、人の心をのみ動かし、 恨みを負ふ積もり にやありけむ、いと 篤しくなりゆき、もの心細げに里がちなるを、 いよいよあかずあはれなるものに思ほして、人の そしりをも え憚らせたまはず、世のためしにも なりぬべき御もてなしなり。 |
朝晩のお側仕えにつけても、他の妃方の気持ちを不愉快ばかりにさせ、嫉妬を受けることが積もり積もったせいであろうか、とても病気がちになってゆき、何となく心細げに里に下がっていることが多いのを、ますますこの上なく不憫な方とおぼし召されて、誰の非難に対してもおさし控えあそばすことがおできになれず、後世の語り草にもなってしまいそうなお扱いぶりである。 |
夜の御殿の宿直所から退る朝、続いてその人ばかりが召される夜、目に見耳に聞いて口惜しがらせた恨みのせいもあったかからだが弱くなって、心細くなった更衣は多く実家へ下がっていがちということになると、いよいよ帝はこの人にばかり心をお引かれになるという御様子で、人が何と批評をしようともそれに御遠慮などというものがおできにならない。御聖徳を伝える歴史の上にも暗い影の一所残るようなことにもなりかねない状態になった。 |
Asayuhu no miyadukahe ni tuke te mo, hito no kokoro wo nomi ugokasi, urami wo ohu tumori ni ya ari kem, ito adusiku nari yuki, mono-kokorobosoge ni satogati naru wo, iyoiyo akazu ahare naru mono ni omohosi te, hito no sosiri wo mo e habakara se tamaha zu, yo no tamesi ni mo nari nu beki ohom-motenasi nari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.4 | 上達部、上人なども、 あいなく目を側めつつ、「 いとまばゆき 人の御おぼえなり。 |
上達部や 殿上人なども、人ごとながら目をそらしそらしして、「とても眩しいほどの御寵愛である。 |
高官たちも殿上役人たちも困って、御覚醒になるのを期しながら、当分は見ぬ顔をしていたいという態度をとるほどの御寵愛ぶりであった。 |
Kamdatime, uhebito nado mo, ainaku me wo sobame tutu, "Ito mabayuki hito no ohom-oboye nari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.5 | 唐土にも、かかる事の起こりにこそ、世も乱れ、悪しかりけれ」と、やうやう天の下にもあぢきなう、人のもてなやみぐさになりて、 楊貴妃の例も 引き出でつべくなりゆくに、いとはしたなきこと多かれど、 かたじけなき御心ばへのたぐひなきを頼みにて まじらひたまふ。 |
唐国でも、このようなことが原因となって、国も乱れ、悪くなったのだ」と、しだいに国中でも困ったことの、人々のもてあましの種となって、楊貴妃の例までも引き合いに出されそうになってゆくので、たいそういたたまれないことが数多くなっていくが、もったいない御愛情の類のないのを頼みとして宮仕え生活をしていらっしゃる。 |
唐の国でもこの種類の寵姫、楊家の女の出現によって乱が醸されたなどと蔭ではいわれる。今やこの女性が一天下の煩いだとされるに至った。馬嵬の駅がいつ再現されるかもしれぬ。その人にとっては堪えがたいような苦しい雰囲気の中でも、ただ深い御愛情だけをたよりにして暮らしていた。 |
Morokosi ni mo, kakaru koto no okori ni koso, yo mo midare, asikari kere" to, yauyau amenosita ni mo adikinau, hito no motenayamigusa ni nari te, Yaukihi no tamesi mo hikiide tu beku nari yuku ni, ito hasitanaki koto ohokare do, katazikenaki mi-kokorobahe no taguhinaki wo tanomi nite mazirahi tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.6 | 父の大納言は亡くなりて、母北の方なむいにしへの人のよしあるにて、親うち具し、さしあたりて世のおぼえはなやかなる御方がたにも いたう劣らず、なにごとの儀式をももてなしたまひけれど、とりたててはかばかしき 後見しなければ、事ある時は、なほ拠り所なく心細げなり。 |
父親の大納言は亡くなって、母親の北の方が古い家柄の人の教養ある人なので、両親とも揃っていて、今現在の世間の評判が勢い盛んな方々にもたいしてひけをとらず、どのような事柄の儀式にも対処なさっていたが、これといったしっかりとした後見人がいないので、こと改まった儀式の行われるときには、やはり頼りとする人がなく心細い様子である。 |
父の大納言はもう故人であった。母の未亡人が生まれのよい見識のある女で、わが娘を現代に勢カのある派手な家の娘たちにひけをとらせないよき保護者たりえた。それでも大官の後援者を持たぬ更衣は、何かの場合にいつも心細い思いをするようだった。 |
Titi no Dainagon ha nakunari te, haha kitanokata nam inisihe no hito no yosi aru nite, oya uti-gusi, sasiatari te yo no oboye hanayaka naru ohom-katagata ni mo itau otora zu, nanigoto no gisiki wo mo motenasi tamahi kere do, toritate te hakabakasiki usiromi si nakere ba, koto aru toki ha, naho yoridokoro naku kokorobosoge nari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 | 第二段 御子誕生(一歳) |
1-2 Genji's birth (age 1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.1 | 先の世にも御契りや深かりけむ、世になく清らなる 玉の男御子さへ生まれたまひぬ。 いつしかと心もとながらせたまひて、急ぎ参らせて御覧ずるに、 めづらかなる稚児の御容貌なり。 |
前世でも御宿縁が深かったのであろうか、この世にまたとなく美しい玉のような男の御子までがお生まれになった。早く早くとじれったくおぼし召されて、急いで参内させて御覧あそばすと、たぐい稀な嬰児のお顔だちである。 |
前生の縁が深かったか、またもないような美しい皇子までがこの人からお生まれになった。寵姫を母とした御子を早く御覧になりたい思召しから、正規の日数が立つとすぐに更衣母子を宮中へお招きになった。小皇子はいかなる美なるものよりも美しいお顔をしておいでになった。 |
Sakinoyo ni mo ohom-tigiri ya hukakari kem, yo ni naku kiyora naru tama no wonoko-miko sahe mumare tamahi nu. Itusika to kokoro-motonagara se tamahi te, isogi mawirase te goranzuru ni, meduraka naru tigo no ohom-katati nari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
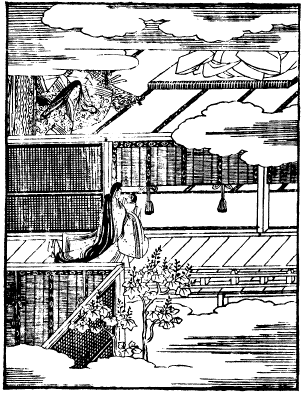 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.2 | 一の皇子は、右大臣の女御の御腹にて、 寄せ重く、 疑ひなき儲の君と、世にもてかしづききこゆれど、この御にほひには並びたまふべくもあらざりければ、 おほかたのやむごとなき御思ひにて、この君をば、私物に思ほしかしづきたまふこと限りなし。 |
第一皇子は、右大臣の娘の女御がお生みになった方なので、後見がしっかりしていて、正真正銘の皇太子になられる君だと、世間でも大切にお扱い申し上げるが、この御子の輝く美しさにはお並びになりようもなかったので、一通りの大切なお気持ちであって、この若君の方を、自分の思いのままにおかわいがりあそばされることはこの上ない。 |
帝の第一皇子は右大臣の娘の女御からお生まれになって、重い外戚が背景になっていて、疑いもない未来の皇太子として世の人は尊敬をささげているが、第二の皇子の美貌にならぶことがおできにならぬため、それは皇家の長子として大事にあそばされ、これは御自身の愛子として非常に大事がっておいでになった。 |
Iti-no-miko ha, Udaizin-no-nyougo no ohom-hara nite, yose omoku, utagahi naki mauke-no-kimi to, yo ni mote-kasiduki kikoyure do, kono ohom-nihohi ni ha narabi tamahu beku mo ara zari kere ba, ohokata no yamgotonaki ohom-omohi nite, kono Kimi woba, watakusimono ni omohosi kasiduki tamahu koto kagiri nasi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.3 | 初めよりおしなべての上宮仕へ したまふべき際にはあらざりき。 おぼえいとやむごとなく、上衆めかしけれど、わりなくまつはさせたまふあまりに、 さるべき御遊びの折々、何事にもゆゑある事のふしぶしには、まづ参う上らせたまふ。ある時には 大殿籠もり過ぐして、やがてさぶらはせたまひなど、あながちに御前去らずもてなさせたまひしほどに、おのづから軽き方にも見えしを、この御子生まれたまひて後は、いと心ことに思ほしおきてたれば、「 坊にも、ようせずは、この御子の居たまふべきなめり」と、一の皇子の女御は思し疑へり。人より先に参りたまひて、 やむごとなき御思ひなべてならず、皇女たちなどもおはしませば、この御方の御諌めをのみぞ、なほわづらはしう心苦しう 思ひきこえさせたまひける。 |
最初から女房並みの帝のお側用をお勤めなさらねばならない身分ではなかった。評判もとても高く、上流人の風格があったが、むやみにお側近くにお召しあそばされ過ぎて、しかるべき管弦の御遊の折々や、どのような催事でも雅趣ある催しがあるたびごとに、まっさきに参上させなさる。ある時にはお寝過ごしなされて、そのまま伺候させておきなさるなど、むやみに御前から離さずに御待遇あそばされたうちに、自然と身分の低い女房のようにも見えたが、この御子がお生まれになって後は、たいそう格別にお考えおきあそばされるようになっていたので、「東宮坊にも、ひょっとすると、この御子がおなりになるかもしれない」と、第一皇子の母女御はお疑いになっていた。誰よりも先に御入内なされて、大切にお考えあそばされることは一通りでなく、皇女たちなども生まれていらっしゃるので、この御方の御諌めだけは、さすがにやはりうるさいことだが無視できないことだとお思い申し上げあそばされるのであった。 |
更衣は初めから普通の朝廷の女官として奉仕するほどの軽い身分ではなかった。ただお愛しになるあまりに、その人自身は最高の貴女と言ってよいほどのりっぱな女ではあったが、始終おそばへお置きになろうとして、殿上で音楽その他のお催し事をあそばす際には、だれよりもまず先にこの人を常の御殿へお呼びになり、またある時はお引き留めになって更衣が夜の御殿から朝の退出ができずそのまま昼も侍しているようなことになったりして、やや軽いふうにも見られたのが、皇子のお生まれになって以後目に立って重々しくお扱いになったから、東宮にもどうかすればこの皇子をお立てになるかもしれぬと、第一の皇子の御生母の女御は疑いを持っていた。この人は帝の最もお若い時に入内した最初の女御であった。この女御がする批難と恨み言だけは無関心にしておいでになれなかった。この女御へ済まないという気も十分に持っておいでになった。 |
Hazime yori osinabete no uhemiyadukahe si tamahu beki kiha ni ha ara zari ki. Oboye ito yamgotonaku, zyauzu-mekasi kere do, warinaku matuhasa se tamahu amari ni, sarubeki ohom-asobi no woriwori, nanigoto ni mo yuwe aru koto no husibusi ni ha, madu maunobora se tamahu. Arutoki ni ha ohotonogomori sugusi te, yagate saburaha se tamahi nado, anagati ni o-mahe sara zu motenasa se tamahi si hodo ni, onodukara karoki kata ni mo miye si wo, kono Miko umare tamahi te noti ha, ito kokoro koto ni omohosi-oki te tare ba, "Bau ni mo, yousezuha, kono Miko no wi tamahu beki nameri." to, Iti-no-miko no Nyougo ha obosi-utagahe ri. Hito yori saki ni mawiri tamahi te, yamgotonaki ohom-omohi nabete nara zu, miko-tati nado mo ohasimase ba, kono ohom-kata no ohom-isame wo nomi zo, naho wadurahasiu kokoro-gurusiu omohi kikoye sase tamahi keru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.4 | かしこき御蔭をば頼みきこえながら、落としめ 疵を求めたまふ人は多く、わが身はか弱くものはかなきありさまにて、なかなかなるもの思ひをぞしたまふ。 |
もったいない御庇護をお頼り申してはいるものの、軽蔑したり落度を探したりなさる方々は多く、ご自身はか弱く何となく頼りない状態で、なまじ御寵愛を得たばっかりにしなくてもよい物思いをなさる。 |
帝の深い愛を信じながらも、悪く言う者と、何かの欠点を捜し出そうとする者ばかりの宮中に、病身な、そして無カな家を背景としている心細い更衣は、愛されれば愛されるほど苦しみがふえるふうであった。 |
Kasikoki mi-kage wo-ba tanomi kikoye nagara, otosime kizu wo motome tamahu hito ha ohoku, wagami ha kayowaku mono-hakanaki arisama nite, nakanaka naru mono-omohi wo zo si tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.5 | 御局は桐壺なり。あまたの御方がたを過ぎさせたまひて、 ひまなき御前渡りに、人の御心を尽くしたまふも、 げにことわりと見えたり。 参う上りたまふにも、あまりうちしきる折々は、打橋、渡殿のここかしこの道に、あやしきわざをしつつ、 御送り迎への人の衣の裾、堪へがたく、まさなきこともあり。またある時には、え避らぬ馬道の戸を鎖しこめ、こなたかなた心を合はせて、 はしたなめわづらはせたまふ時も多かり。 |
お局は桐壺である。おおぜいのお妃方の前をお素通りあそばされて、そのひっきりなしのお素通りあそばしに、お妃方がお気をもめ尽くしになるのも、なるほどごもっともであると見えた。参上なさるにつけても、あまり度重なる時々には、打橋や、渡殿のあちこちの通路に、けしからぬことをたびたびして、送り迎えの女房の着物の裾が、がまんできないような、とんでもないことがある。またある時には、どうしても通らなければならない馬道の戸を鎖して閉じ籠め、こちら側とあちら側とで示し合わせて、進むも退くもならないように困らせなさることも多かった。 |
住んでいる御殿は御所の中の東北の隅のような桐壼であった。幾つかの女御や更衣たちの御殿の廊を通い路にして帝がしばしばそこへおいでになり、宿直をする更衣が上がり下がりして行く桐壼であったから、始終ながめていねばならぬ御殿の住人たちの恨みが量んでいくのも道理と言わねばならない。召されることがあまり続くころは、打ち橋とか通い廊下のある戸口とかに意地の悪い仕掛けがされて、送り迎えをする女房たちの着物の裾が一度でいたんでしまうようなことがあったりする。またある時はどうしてもそこを通らねばならぬ廊下の戸に錠がさされてあったり、そこが通れねばこちらを行くはずの御殿の人どうしが言い合わせて、桐壼の更衣の通り路をなくして辱しめるようなことなどもしばしばあった。 |
Mi-tubone ha Kiritubo nari. Amata no ohom-katagata wo sugi sase tamahi te, himanaki o-mahewatari ni, hito no mi-kokoro wo tukusi tamahu mo, geni kotowari to miye tari. Mau-nobori tamahu ni mo, amari utisikiru woriwori ha, utihasi, watadono no koko-kasiko no miti ni, ayasiki waza wo si tutu, ohom-okuri-mukahe no hito no kinu no suso, tahe gataku, masanaki koto mo ari. Mata aru toki ni ha, e saranu medau no to wo sasi-kome, konata-kanata kokoro wo ahase te, hasitaname wadurahase tamahu toki mo ohokari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.6 | 事にふれて数知らず苦しきことのみまされば、いといたう思ひわびたるを、いとどあはれと御覧じて、後涼殿にもとよりさぶらひたまふ更衣の曹司を他に移させたまひて、上局に賜はす。その恨みましてやらむ方なし。 |
何かにつけて数知れないほど辛いことばかりが増えていくので、たいそうひどく思い悩んでいるのを、ますますお気の毒におぼし召されて、後凉殿に以前から伺候していらっしゃった更衣の部屋を他に移させなさって、上局として御下賜あそばす。その方の恨みはなおいっそうに晴らしようがない。 |
数え切れぬほどの苦しみを受けて、更衣が心をめいらせているのを御覧になると帝はいっそう憐れを多くお加えになって、清涼殿に続いた後涼殿に住んでいた更衣をほかへお移しになって桐壼の更衣へ休息室としてお与えになった。移された人の恨みはどの後宮よりもまた深くなった。 |
Koto ni hure te kazu sira zu kurusiki koto nomi masare ba, ito itau omohi-wabi taru wo, itodo ahare to goranzi te, Kourauden ni motoyori saburahi tamahu kaui no zausi wo hoka ni utusa se tamahi te, uhetubone ni tamaha su. Sono urami masite yaramkata-nasi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3 | 第三段 若宮の御袴着(三歳) |
1-3 Hakama-gi (age 3) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.1 | この御子三つになりたまふ年、御袴着のこと 一の宮のたてまつりしに劣らず、内蔵寮、納殿の物を尽くして、 いみじうせさせたまふ。それにつけても、世の誹りのみ多かれど、この御子の およすげもておはする 御容貌心ばへありがたくめづらしきまで見えたまふを、 え嫉みあへたまはず。ものの心知りたまふ人は、「 かかる人も世に出でおはするものなりけり」と、あさましきまで目をおどろかしたまふ。 |
この御子が三歳におなりの年に、御袴着の儀式を一宮がお召しになったのに劣らず、内蔵寮や 納殿の御物をふんだんに使って、大変に盛大におさせあそばす。そのことにつけても、世人の非難ばかりが多かったが、この御子が成長なさって行かれるお顔だちやご性質が世間に類なく素晴らしいまでにお見えになるので、お憎みきれになれない。ものごとの情理がお分かりになる方は、「このような方もこの末世にお生まれになるものであったよ」と、驚きあきれる思いで目を見張っていらっしゃる。 |
第二の皇子が三歳におなりになった時に袴着の式が行なわれた。前にあった第一の皇子のその式に劣らぬような派手な準傭の費用が宮廷から支出された。それにつけても世問はいろいろに批評をしたが、成長されるこの皇子の美貌と聡明さとが類のないものであったから、だれも皇子を悪く思うことはできなかった。有識者はこの天才的な美しい小皇子を見て、こんな人も人間世界に生まれてくるものかと皆驚いていた。 |
Kono Miko mi-tu ni nari tamahu tosi, ohom-hakamagi no koto Iti-no-miya no tatematuri si ni otora zu, kuradukasa, wosamedono no mono wo tukusi te, imiziu se sase tamahu. Sore ni tuke te mo, yo no sosiri nomi ohokare do, kono Miko no oyosuge mote-ohasuru ohom-katati kokorobahe arigataku medurasiki made miye tamahu wo, e sonemiahe tamaha zu. Mono no kokoro siri tamahu hito ha, "Kakaru hito mo yo ni ide ohasuru mono nari keri." to, asamasiki made me wo odorokasi tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4 | 第四段 母御息所の死去 |
1-4 Mother's death |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.1 | その年の夏、 御息所、 はかなき心地にわづらひて、 まかでなむとしたまふを、 暇さらに許させたまはず。 |
その年の夏、御息所が、頼りない感じに落ち入って、退出しようとなさるのを、お暇を少しもお許しあそばさない。 |
その年の夏のことである。御息所−皇子女の生母になった更衣はこう呼ばれるのである−はちょっとした病気になって、実家へさがろうとしたが帝はお許しにならなかった。 |
Sono tosi no natu, Miyasumdokoro, hakanaki kokoti ni wadurahi te, makade na m to si tamahu wo, itoma sarani yurusa se tamaha zu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.2 | 年ごろ、 常の篤しさになりたまへれば、御目馴れて、「なほしばしこころみよ」とのみのたまはするに、日々に重りたまひて、ただ五六日のほどにいと弱うなれば、母君泣く泣く奏して、 まかでさせたてまつりたまふ。 |
ここ数年来、いつもの病状になっていらっしゃるので、お見慣れになって、「このまましばらく様子を見よ」とばかり仰せられるているうちに、日々に重くおなりになって、わずか五、六日のうちにひどく衰弱したので、母君が涙ながらに奏上して、退出させ申し上げなさる。 |
どこかからだが悪いということはこの人の常のことになっていたから、帝はそれほどお驚きにならずに、 「もうしばらく御所で養生をしてみてからにするがよい」 と言っておいでになるうちにしだいに悪くなって、そうなってからほんの五、六日のうちに病は重体になった。母の未亡人は泣く泣くお暇を願って帰宅させることにした。 |
Tosigoro, tune no adusisa ni nari tamahe re ba, ohom-me nare te, "Naho sibasi kokoromi yo." to nomi notamahasuru ni, hibi ni omori tamahi te, tada itu-ka muyi-ka no hodo ni ito yowau nare ba, Hahagimi nakunaku sousi te, makade sase tatematuri tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.3 | かかる折にも、あるまじき恥もこそと心づかひして、御子をば留めたてまつりて、忍びてぞ出でたまふ。 |
このような時にも、あってはならない失態を演じてはならないと配慮して、御子はお残し申して、人目につかないようにして退出なさる。 |
こんな場合にはまたどんな呪詛が行なわれるかもしれない、皇子にまで禍いを及ぼしてはとの心づかいから、皇子だけを宮中にとどめて、目だたぬように御息所だけが退出するのであった。 |
Kakaru wori ni mo, arumaziki hadi mo koso to kokorodukahi si te, Miko wo ba todome tatematuri te, sinobi te zo ide tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.4 | 限りあれば、さのみもえ留めさせたまはず、御覧じだに送らぬおぼつかなさを、言ふ方なく思ほさる。 いとにほひやかにうつくしげなる人の、いたう面痩せて、いとあはれとものを思ひしみながら、 言に出でても聞こえやらず、あるかなきかに消え入りつつものしたまふを 御覧ずるに、来し方行く末思し召されず、よろづのことを泣く泣く契りのたまはすれど、御いらへもえ聞こえたまはず、まみなどもいとたゆげにて、いとどなよなよと、我かの気色にて臥したれば、いかさまにと思し召しまどはる。 輦車の宣旨などのたまはせても、 また入らせたまひて、さらにえ許させたまはず。 |
決まりがあるので、お気持ちのままにお留めあそばすこともできず、お見送りさえままならない心もとなさを、言いようもなく無念におぼし召される。たいそう照り映えるように美しくかわいらしい人が、ひどく顔がやつれて、まことにしみじみと物思うことがありながらも、言葉には出して申し上げることもできずに、生き死にもわからないほどに息も絶えだえでいらっしゃるのを御覧になると、あとさきもお考えあそばされず、すべてのことを泣きながらお約束あそばされるが、お返事を申し上げることもおできになれず、まなざしなどもとてもだるそうで、常よりいっそう弱々しくて、意識もないような状態で臥せっていたので、どうしたらよいものかとお惑乱あそばされる。輦車の宣旨などを仰せ出されても、再びお入りあそばしては、どうしてもお許しあさばされることができない。 |
この上留めることは不可能であると帝は思召して、更衣が出かけて行くところを見送ることのできぬ御尊貴の御身の物足りなさを堪えがたく悲しんでおいでになった。 はなやかな顔だちの美人が非常に痩せてしまって、心の中には帝とお別れして行く無限の悲しみがあったがロヘは何も出して言うことのできないのがこの人の性質である。あるかないかに弱っているのを御覧になると帝は過去も未来も真暗になった気があそばすのであった。泣く泣くいろいろな頼もしい将来の約束をあそばされても更衣はお返辞もできないのである。目つきもよほどだるそうで、平生からなよなよとした人がいっそう弱々しいふうになって寝ているのであったから、これはどうなることであろうという不安が大御心を襲うた。更衣が宮中から輦車で出てよい御許可の宣旨を役人へお下しになったりあそばされても、また病室へお帰りになると今行くということをお許しにならない。 |
Kagiri are ba, sa nomi mo e todome sase tamaha zu, goranzi dani okura nu obotukanasa wo, ihukatanaku omohosa ru. Ito nihohiyaka ni utukusige naru hito no, itau omo yase te, ito ahare to mono wo omohisimi nagara, koto ni ide te mo kikoyeyara zu, arukanakika ni kiyeiri tutu monosi tamahu wo goranzuru ni, kisikata yukusuwe obosimesa re zu, yorodu no koto wo nakunaku tigiri notamaha sure do, ohom-irahe mo e kikoye tamaha zu, mami nado mo ito tayuge nite, itodo nayonayo to, wareka no kesiki nite husi tare ba, ikasama ni to obosimesi madoha ru. Teguruma no senzi nado notamahase te mo, mata ira se tamahi te, sarani e yurusa se tamaha zu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.5 | 「 限りあらむ道にも、後れ先立たじと、 契らせたまひけるを。 さりとも、うち捨てては、 え行きやらじ」 |
「死出の旅路にも、後れたり先立ったりするまいと、お約束あそばしたものを。いくらそうだとしても、おいてけぼりにしては、行ききれまい」 |
「死の旅にも同時に出るのがわれわれ二人であるとあなたも約束したのだから、私を置いて家へ行ってしまうことはできないはずだ」 |
"Kagiri ara m miti ni mo, okure-sakidata zi to, tigira se tamahi keru wo. Saritomo, uti-sute te ha, e yukiyara zi." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.6 | とのたまはするを、 女もいといみじと、見たてまつりて、 |
と仰せになるのを、女もたいそう悲しいと、お顔を拝し上げて、 |
と、帝がお言いになると、そのお心持ちのよくわかる女も、非常に悲しそうにお顔を見て、 |
to notamahasuru wo, Womna mo ito imizi to, mi tatematuri te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.7 | 「 限りとて別るる道の悲しきに いかまほしきは命なりけり |
「人の命には限りがあるものと、今、別れ路に立ち、悲しい気持ちでいますが、 わたしが行きたいと思う路は、生きている世界への路でございます。 |
「限りとて別るる道の悲しきに いかまほしきは命なりけり |
"Kagiri tote wakaruru miti no kanasiki ni ika mahosiki ha inoti nari keri |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.8 | いとかく思ひたまへましかば」 |
ほんとうにこのようにと存じておりましたならば」 |
死がそれほど私に迫って来ておりませんのでしたら」 |
Ito kaku omohi tamahe masika ba." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.9 | と、息も絶えつつ、聞こえまほしげなることはありげなれど、いと苦しげにたゆげなれば、 かくながら、ともかくもならむを御覧じはてむと思し召すに、「 今日始むべき祈りども、さるべき人びとうけたまはれる、今宵より」と、聞こえ急がせば、わりなく思ほしながら まかでさせたまふ。 |
と、息も絶えだえに、申し上げたそうなことはありそうな様子であるが、たいそう苦しげに気力もなさそうなので、このままの状態で、最期となってしまうようなこともお見届けしたいと、お考えあそばされるが、「今日始める予定の祈祷などを、しかるべき僧たちの承っておりますのが、今宵から始めます」と言って、おせき立て申し上げるので、やむを得なくお思いあそばしながら退出させなさる。 |
これだけのことを息も絶え絶えに言って、なお帝にお言いしたいことがありそうであるが、まったく気カはなくなってしまった。死ぬのであったらこのまま自分のそばで死なせたいと帝は思召したが、今日から始めるはずの祈祷も高僧たちが承っていて、それもぜひ今夜から始めねばなりませぬというようなことも申し上げて方々から更衣の退出を促すので、別れがたく思召しながらお帰しになった。 |
to, iki mo taye tutu, kikoye mahosige naru koto ha arige nare do, ito kurusige ni tayuge nare ba, kaku nagara, tomokakumo nara m wo goranzi-hate m to obosimesu ni, "Kehu hazimu beki inori-domo, sarubeki hitobito uketamahare ru, koyohi yori." to, kikoye isogase ba, warinaku omohosi nagara makade sase tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.10 | 御胸つとふたがりて、つゆまどろまれず、明かしかねさせたまふ。御使の行き交ふほどもなきに、なほいぶせさを限りなくのたまはせつるを、「 夜半うち過ぐるほどになむ、絶えはてたまひぬる」とて泣き騒げば、御使もいとあへなくて帰り参りぬ。聞こし召す御心まどひ、何ごとも思し召しわかれず、籠もりおはします。 |
お胸がひしと塞がって、少しもうとうとなされず、夜を明かしかねあそばす。勅使が行き来する間もないうちに、しきりに気がかりなお気持ちをこの上なくお漏らしあそばしていらしたところ、「夜半少し過ぎたころに、お亡くなりになりました」と言って泣き騒ぐので、勅使もたいそうがっかりして帰参した。お耳にあそばす御心の転倒、どのような御分別をも失われて、引き籠もっておいであそばす。 |
帝はお胸が悲しみでいっぱいになってお眠りになることが困難であった。帰った更衣の家へお出しになる尋ねの使いはすぐ帰って来るはずであるが、それすら返辞を聞くことが待ち遠しいであろうと仰せられた帝であるのに、お使いは、 「夜半過ぎにお卒去になりました」 と言って、故大納言家の人たちの泣き騒いでいるのを見ると力が落ちてそのまま御所へ帰って来た。 更衣の死をお聞きになった帝のお悲しみは非常で、そのまま引きこもっておいでになった。 |
Ohom-mune tuto hutagari te, tuyu madoroma re zu, akasi-kane sase tamahu. Ohom-tukahi no yukikahu hodo mo naki ni, naho ibusesa wo kagirinaku notamahase turu wo, "Yonaka uti-suguru hodo ni nam, taye hate tamahi nuru." tote naki sawage ba, ohom-tukahi mo ito ahenaku te kaheri mawiri nu. Kikosimesu mi-kokoromadohi, nanigoto mo obosimesi-waka re zu, komori ohasimasu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.11 | 御子は、 かくてもいと御覧ぜまほしけれど、かかるほどにさぶらひたまふ、 例なきことなれば、 まかでたまひなむとす。何事かあらむとも思したらず、さぶらふ人びとの泣きまどひ、 主上も御涙のひまなく流れおはしますを、あやしと見たてまつりたまへるを、 よろしきことにだに、かかる別れの悲しからぬはなきわざなるを、 ましてあはれに言ふかひなし。 |
御子は、それでもとても御覧になっていたいが、このような折に宮中に伺候していらっしゃるのは、先例のないことなので、退出なさろうとする。何事があったのだろうかともお分かりにならず、お仕えする人々が泣き惑い、父主上もお涙が絶えずおこぼれあそばしているのを、変だなと拝し上げなさっているのを、普通の場合でさえ、このような別れの悲しくないことはない次第なのを、いっそうに悲しく何とも言いようがない。 |
その中でも忘れがたみの皇子はそばへ置いておきたく思召したが、母の忌服中の皇子が、穢れのやかましい宮中においでになる例などはないので、更衣の実家へ退出されることになった。皇子はどんな大事があったともお知りにならず、侍女たちが泣き騒ぎ、帝のお顔にも涙が流れてばかりいるのだけを不思議にお思いになるふうであった。父子の別れというようなことはなんでもない場合でも悲しいものであるから、この時の帝のお心持ちほどお気の毒なものはなかった。 |
Miko ha, kakute mo ito goranze mahosikere do, kakaru hodo ni saburahi tamahu, rei naki koto nare ba, makade tamahi na m to su. Nanigoto ka ara m to mo obosi tara zu, saburahu hitobito no naki madohi, Uhe mo ohom-namida no hima naku nagare ohasimasu wo, ayasi to mi tatematuri tamahe ru wo, yorosiki koto ni dani, kakaru wakare no kanasikara nu ha naki waza naru wo, masite ahare ni ihukahinasi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 | 第五段 故御息所の葬送 |
1-5 The funeral |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5.1 | 限りあれば、例の作法にをさめたてまつるを、母北の方、同じ煙にのぼりなむと、泣きこがれたまひて、 御送りの女房の車に 慕ひ乗りたまひて、 愛宕といふ所にいといかめしうその作法したるに、 おはし着きたる心地、いかばかりかはありけむ。「むなしき御骸を見る見る、なほおはするものと思ふが、いとかひなければ、 灰になりたまはむを見たてまつりて、今は亡き人と、ひたぶるに思ひなりなむ」と、さかしうのたまひつれど、車よりも落ちぬべう まろびたまへば、 さは思ひつかしと、人びともてわづらひきこゆ。 |
しきたりがあるので、先例の葬法どおりにお営み申すのを、母北の方は、娘と同じく煙となって死んでしまいたいと、泣きこがれなさって、御葬送の女房の車に後を追ってお乗りになって、愛宕という所でたいそう厳かにその葬儀を執り行っているところに、お着きになったお気持ちは、どんなであったであろうか。「お亡骸を見ながら、なおも生きていらっしゃるものと思われるのが、たいして何にもならないので、遺灰におなりになるのを拝見して、今はもう死んだ人なのだと、きっぱりと思い諦めよう」と、分別あるようにおっしゃっていたが、車から落ちてしまいそうなほどにお取り乱しなさるので、やはり思ったとおりだと、女房たちも手をお焼き申す。 |
どんなに惜しい人でも遺骸は遺骸として扱われねばならぬ、葬儀が行なわれることになって、母の未亡人は遺骸と同時に火葬の煙になりたいと泣きこがれていた。そして葬送の女房の車にしいて望んでいっしょに乗って愛宕の野にいかめしく設けられた式場へ着いた時の未亡人の心はどんなに悲しかったであろう。 「死んだ人を見ながら、やはり生きている人のように思われてならない私の迷いをさますために行く必要があります」 と賢そうに言っていたが、車から落ちてしまいそうに泣くので、こんなことになるのを恐れていたと女房たちは思った。 |
Kagiri are ba, rei no sahohu ni wosame tatematuru wo, Haha-kitanokata, onazi keburi ni nobori na m to, naki kogare tamahi te, ohom-okuri no nyoubau no kuruma ni sitahi nori tamahi te, Otagi to ihu tokoro ni ito ikamesiu sono sahohu si taru ni, ohasi tuki taru kokoti, ikabakari ka ha ari kem. "Munasiki ohom-kara wo miru-miru, naho ohasuru mono to omohu ga, ito kahinakere ba, hahi ni nari tamaha m wo mi tatematuri te, ima ha naki hito to, hitaburu ni omohi nari na m." to, sakasiu notamahi ture do, kuruma yori mo oti nu beu marobi tamahe ba, saha omohi tu kasi to, hitobito mote-wadurahi kikoyu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5.2 | 内裏より御使あり。 三位の位贈りたまふよし、勅使来てその宣命読むなむ、悲しきことなりける。 女御とだに言はせずなりぬるが、あかず口惜しう思さるれば、いま一階の位をだにと、贈らせたまふなりけり。これにつけても憎みたまふ人びと多かり。もの思ひ知りたまふは、 様、容貌などのめでたかりしこと、心ばせのなだらかにめやすく、憎みがたかりしことなど、今ぞ思し出づる。 さま悪しき御もてなしゆゑこそ、すげなう嫉みたまひしか、人柄のあはれに情けありし御心を、主上の女房なども恋ひしのびあへり。 なくてぞとは ★、かかる折にやと見えたり。 |
内裏からお勅使が参る。従三位の位を追贈なさる旨を、勅使が到着してその宣命を読み上げるのが、悲しいことであった。せめて女御とだけでも呼ばせずに終わったのが、心残りで無念に思し召されたので、せめてもう一段上の位階だけでもと、御追贈あそばすのであった。このことにつけても非難なさる方々が多かった。人の情理をお分かりになる方は、姿態や 容貌などが素晴しかったことや、気立てがおだやかで欠点がなく、憎み難い人であったことなどを、今となってお思い出しになる。見苦しいまでの御寵愛ゆえに、冷たくお妬みなさったのだが、性格がしみじみと情愛こまやかでいらっしゃったご性質を、主上づきの女房たちも互いに恋い偲びあっていた。亡くなってから人はと言うことは、このような時のことかと思われた。 |
宮中からお使いが葬場へ来た。更衣に三位を贈られたのである。勅使がその宣命を読んだ時ほど未亡人にとって悲しいことはなかった。三位は女御に相当する位階である。生きていた日に女御とも言わせなかったことが帝には残り多く思召されて贈位を賜わったのである。こんなことででも後宮のある人々は反感を持った。同情のある人は故人の美しさ、性格のなだらかさなどで憎むことのできなかった人であると、今になって桐壼の更衣の真価を思い出していた。あまりにひどい御殊寵ぶりであったからその当時は嫉妬を感じたのであるとそれらの人は以前のことを思っていた。優しい同情深い女性であったのを、帝付きの女官たちは皆恋しがっていた。「なくてぞ人は恋しかりける」とはこうした場合のことであろうと見えた。 |
Uti yori ohom-tukahi ari. Mi-tu-no-kurawi okuri tamahu yosi, tyokusi ki te sono senmyau yomu nam, kanasiki koto nari keru. Nyougo to dani iha se zu nari nuru ga, akazu kutiwosiu obosa rure ba, ima hito-kizami no kurawi wo dani to, okura se tamahu nari keri. Kore ni tuke te mo nikumi tamahu hitobito ohokari. Mono omohi-siri tamahu ha, sama, katati nado no medetakari si koto, kokorobase no nadaraka ni meyasuku, nikumi gatakari si koto nado, ima zo obosi-iduru. Sama asiki ohom-motenasi yuwe koso, sugenau sonemi tamahi sika, hitogara no ahare ni nasake ari si mi-kokoro wo, uhe-no-nyoubau nado mo kohi sinobiahe ri. Naku te zo to ha, kakaru wori ni ya to miye tari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last updated 12/05/2008(ver.2-1) 渋谷栄一校訂(C) Last updated 12/29/2008(ver.2-1) 渋谷栄一注釈 |
Last updated 6/25/2003 渋谷栄一訳(C)(ver.1-4-1) |
|
Last updated 12/13/2008 (ver.2-1) Written in Japanese roman letters by Eiichi Shibuya (C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Picture "Eiri Genji Monogatari"(1650 1st edition) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源氏物語の世界 再編集プログラム Ver 3.38: Copyright (c) 2003,2015 宮脇文経