第一帖 桐壺 |
01 KIRITUBO (Myouyu-rinmo-bon) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 第二章 父帝悲秋の物語 |
2 Mikado's grief |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1 | 第一段 父帝悲しみの日々 |
2-1 Mikado's grievous days |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.1 | はかなく日ごろ過ぎて、 後のわざなどにもこまかにとぶらはせたまふ。ほど経るままに、せむ方なう悲しう思さるるに、御方がたの御宿直なども絶えてしたまはず、ただ 涙にひちて明かし暮らさせたまへば、見たてまつる人さへ 露けき秋なり。「 亡きあとまで、人の胸あくまじかりける人の御おぼえかな」とぞ、 弘徽殿などにはなほ許しなうのたまひける。一の宮を見たてまつらせたまふにも、 若宮の御恋しさのみ思ほし出でつつ、親しき女房、御乳母などを遣はしつつ、ありさまを聞こし召す。 |
いつのまにか日数は過ぎて、後の法要などの折にも情愛こまやかにお見舞いをお遣わしあそばす。時が過ぎて行くにしたがって、どうしようもなく悲しく思われなさるので、女御更衣がたの夜の御伺候などもすっかりお命じにならず、ただ涙に濡れて日をお送りあそばされているので、拝し上げる人までが露っぽくなる秋である。「亡くなった後まで、人の心を晴ればれさせなかった御寵愛の方だこと」と、弘徽殿女御などにおかれては今もなお容赦なくおっしゃるのであった。一の宮を拝し上げあそばされるにつけても、若宮の恋しさだけがお思い出されお思い出されして、親しく仕える女房や 御乳母などをたびたびお遣わしになっては、ご様子をお尋ねあそばされる。 |
時は人の悲しみにかかわりもなく過ぎて七日七日の仏事が次々に行なわれる、そのたびに帝からはお弔いの品々が下された。 愛人の死んだのちの日がたっていくにしたがってどうしようもない寂しさばかりを帝はお覚えになるのであって、女御、更衣を宿直に召されることも絶えてしまった。ただ涙の中の御朝タであって、拝見する人までがしめっぽい心になる秋であった。 「死んでからまでも人の気を悪くさせる御寵愛ぶりね」 などと言って、右大臣の娘の弘徽殿の女御などは今さえも嫉妬を捨てなかった。帝は一の皇子を御覧になっても更衣の忘れがたみの皇子の恋しさばかりをお覚えになって、親しい女官や、御自身のお乳母などをその家へおつかわしになって若宮の様子を報告させておいでになった。 |
Hakanaku higoro sugi te, noti-no-waza nado ni mo komaka ni toburaha se tamahu. Hodo huru mama ni, semkatanau kanasiu obosa ruru ni, ohom-katagata no ohom-tonowi nado mo tayete si tamaha zu, tada namida ni hiti te akasi-kurasa se tamahe ba, mi tatematuru hito sahe tuyukeki aki nari. "Naki ato made, hito no mune aku mazikari keru hito no ohom-oboye kana!" to zo, Koukiden nado ni ha naho yurusi nau notamahi keru. Iti-no-miya wo mi tatematura se tamahu ni mo, Wakamiya no ohom-kohisisa nomi omohosi-ide tutu, sitasiki nyoubau, ohom-menoto nado wo tukahasi tutu, arisama wo kikosimesu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2 | 第二段 靫負命婦の弔問 |
2-2 The visit in Fall |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2.1 | 野分立ちて、にはかに肌寒き夕暮のほど、常よりも思し出づること多くて、靫負命婦といふを遣はす。 夕月夜のをかしきほどに出だし立てさせたまひて、やがて眺めおはします。かうやうの折は、 御遊びなどせさせたまひしに、心ことなる物の音を掻き鳴らし、はかなく聞こえ出づる言の葉も、人よりは ことなりしけはひ容貌の、面影につと添ひて思さるるにも、 闇の現にはなほ劣りけり ★。 |
野分めいて、急に肌寒くなった夕暮どき、いつもよりもお思い出しになることが多くて、靫負命婦という者をお遣わしになる。夕月夜の美しい時刻に出立させなさって、そのまま物思いに耽ってておいであそばす。このような折には、管弦の御遊などをお催しあそばされたが、とりわけ優れた琴の音を掻き鳴らし、ついちょっと申し上げる言葉も、人とは格別であった雰囲気や顔かたちが、面影となってひたとわが身に添うように思し召されるにつけても、闇の中の現実にはやはり及ばないのであった。 |
野分ふうに風が出て肌寒の覚えられる日の夕方に、平生よりもいっそう故人がお思われになって、靫負の命婦という人を使いとしてお出しになった。夕月夜の美しい時刻に命婦を出かけさせて、そのまま深い物思いをしておいでになった。以前にこうした月夜は音楽の遊びが行なわれて、更衣はその一人に加わってすぐれた音楽者の素質を見せた。またそんな夜に詠む歌なども平凡ではなかった。彼女の幻は帝のお目に立ち添って少しも消えない。しかしながらどんなに濃い幻でも瞬間の現実の価値はないのである。 |
Nowakidati te, nihaka ni hada samuki yuhugure no hodo, tune yori mo obosi-iduru koto ohoku te, Yugehi-no-myaubu to ihu wo tukahasu. Yuhudukuyo no wokasiki hodo ni idasitate sase tamahi te, yagate nagame ohasimasu. Kauyau no wori ha, ohom-asobi nado se sase tamahi si ni, kokoro-koto naru mono-no-ne wo kaki-narasi, hakanaku kikoyeiduru kotonoha mo, hito yori ha koto nari si kehahi katati no, omokage ni tuto sohi te obosa ruru ni mo, yami-no-ututu ni ha naho otori keri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2.2 | 命婦、かしこに 参で着きて、 門引き入るるより、けはひあはれなり。やもめ住みなれど、人一人の御かしづきに、とかくつくろひ立てて、めやすきほどにて過ぐしたまひつる、 闇に暮れて臥し沈みたまへるほどに、草も高くなり、野分にいとど荒れたる心地して、月影ばかりぞ ▼ 八重葎にも障はらず差し入りたる。 南面に下ろして、母君も、とみにえものものたまはず。 |
命婦は、あちらに参着して、門を潜り入るなり、しみじみと哀れ深い。未亡人暮らしであるが、娘一人を大切にお世話するために、あれこれと手入れをきちんとして、見苦しくないようにしてお暮らしになっていたが、亡き子を思う悲しみに暮れて臥せっていらっしゃったうちに、雑草も高くなり、野分のためにいっそう荒れたような感じがして、月の光だけが八重葎にも遮られずに差し込んでいた。寝殿の南面で車から下ろして、母君も、すぐにはご挨拶できない。 |
命婦は故大納言家に着いて車が門から中へ引き入れられた刹那からもう言いようのない寂しさが味わわれた。末亡人の家であるが、一人娘のために住居の外見などにもみすぼらしさがないようにと、りっぱな体裁を保って暮らしていたのであるが、子を失った女主人の無明の日が続くようになってからは、しばらくのうちに庭の雑草が行儀悪く高くなった。またこのごろの野分の風でいっそう邸内が荒れた気のするのであったが、月光だけは伸びた草にもさわらずさし込んだその南向きの座敷に命婦を招じて出て来た女主人はすぐにもものが言えないほどまたも悲しみに胸をいっぱいにしていた。 |
Myaubu, kasiko ni ma'de tuki te, kado hiki-iruru yori, kehahi ahare nari. Yamome-zumi nare do, hito hitori no ohom-kasiduki ni, tokaku tukurohi-tate te, meyasuki hodo nite sugusi tamahi turu, yami ni kure te husi sidumi tamahe ru hodo ni, kusa mo takaku nari, nowaki ni itodo are taru kokoti si te, tukikage bakari zo yahemugura ni mo sahara zu sasi-iri taru. Minami-omote ni orosi te, Hahagimi mo, tomi ni e mono mo notamaha zu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2.3 | 「 今までとまりはべるがいと憂きを、かかる御使の 蓬生の露分け入りたまふにつけても、いと恥づかしうなむ」 |
「今まで生きながらえておりましたのがとても情けないのに、このようなお勅使が草深い宿の露を分けてお訪ね下さるにつけても、とても恥ずかしうございます」 |
「娘を死なせました母親がよくも生きていられたものというように、運命がただ恨めしゅうございますのに、こうしたお使いが荒ら屋へおいでくださるとまたいっそう自分が恥ずかしくてなりません」 |
"Ima made tomari haberu ga ito uki wo, kakaru ohom-tukahi no yomogihu no tuyu wake-iri tamahu ni tuke te mo, ito hadukasiu nam." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2.4 | とて、 げにえ堪ふまじく泣いたまふ。 |
と言って、ほんとうに身を持ちこらえられないくらいにお泣きになる。 |
と言って、実際堪えられないだろうと思われるほど泣く。 |
tote, geni e tahu maziku nai tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
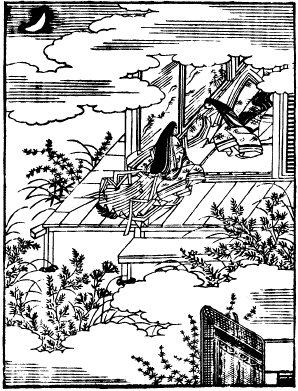 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2.5 | 「『 参りては、いとど心苦しう、心肝も 尽くるやうになむ』と、 典侍の 奏したまひしを、 もの思うたまへ知らぬ心地にも、げにこそいと忍びがたうはべりけれ」 |
「『お訪ねいたしたところ、ひとしおお気の毒で、心も魂も消え入るようでした』と、典侍が奏上なさったが、物の情趣を理解いたさぬ者でも、なるほどまことに忍びがとうございます」 |
「こちらへ上がりますと、またいっそうお気の毒になりまして、魂も消えるようでございますと、先日典侍は陛下へ申し上げていらっしゃいましたが、私のようなあさはかな人間でもほんとうに悲しさが身にしみます」 |
"'Mawiri te ha, itodo kokorogurusiu, kokorogimo mo tukuru yau ni nam' to, Naisi-no-suke no sousi tamahi si wo, mono omou tamahe sira nu kokoti ni mo, geni koso ito sinobi-gatau haberi kere." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2.6 | とて、 ややためらひて、 仰せ言伝へきこゆ。 |
と言って、少し気持ちを落ち着かせてから、仰せ言をお伝え申し上げる。 |
と言ってから、しばらくして命婦は帝の仰せを伝えた。 |
tote, yaya tamerahi te, ohosegoto tutahe kikoyu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2.7 | 「『 しばしは夢かとのみたどられしを、やうやう思ひ静まるにしも、覚むべき方なく堪へがたきは、いかにすべきわざにかとも、問ひあはすべき 人だになきを、 忍びては参りたまひなむや。若宮のいとおぼつかなく、露けき中に過ぐしたまふも、 心苦しう思さるるを、 とく参りたまへ』 など、はかばかしうものたまはせやらず、むせかへらせたまひつつ、かつは 人も心弱く見たてまつるらむと、思しつつまぬにしもあらぬ御気色の心苦しさに、 承り果てぬやうにてなむ、まかではべりぬる」 |
「『しばらくの間は夢かとばかり思い辿られずにはいられなかったが、だんだんと心が静まるにつれてかえって、覚めるはずもなく堪えがたいのは、どのようにしたらよいものかとも、相談できる相手さえいないので、人目につかないようにして参内なさらぬか。若宮がたいそう気がかりで、湿っぽい所でお過ごしになっているのも、おいたわしくお思いあそばされますから、早く参内なさい』などと、はきはきとは最後まで仰せられず、涙に咽ばされながら、また一方では人びともお気弱なと拝されるだろうと、お憚りあそばされないわけではない御様子がおいたわしくて、最後まで承らないようなかっこうで、退出いたして参りました」 |
「当分夢ではないであろうかというようにばかり思われましたが、ようやく落ち着くとともに、どうしようもない悲しみを感じるようになりました。こんな時はどうすればよいのか、せめて話し合う人があればいいのですがそれもありません。目だたぬようにして時々御所へ来られてはどうですか。若宮を長く見ずにいて気がかりでならないし、また若宮も悲しんでおられる人ばかりの中にいてかわいそうですから、彼を早く宮中へ入れることにして、あなたもいっしょにおいでなさい」 「こういうお言葉ですが、涙にむせ返っておいでになって、しかも人に弱さを見せまいと御遠慮をなさらないでもない御様子がお気の毒で、ただおおよそだけを承っただけでまいりました」 |
"'Sibasi ha yume ka to nomi tadora re si wo, yauyau omohi-sidumaru ni simo, samu beki kata naku tahegataki ha, ikani su beki waza ni ka to mo, tohi-ahasu beki hito dani naki wo, sinobi te ha mawiri tamahi na m ya? Wakamiya no ito obotukanaku, tuyukeki naka ni sugusi tamahu mo, kokorogurusiu obosa ruru wo, toku mawiri tamahe!' nado, hakabakasiu mo notamaha se yara zu, musekahera se tamahi tutu, katuha hito mo kokoro-yowaku mi tatematuru ram to, obosi-tutuma nu ni simo ara nu mi-kesiki no kokorogurusisa ni, uketamahari hate nu yau nite nam, makade haberi nuru." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2.8 | とて、 御文奉る。 |
と言って、お手紙を差し上げる。 |
と言って、また帝のお言づてのほかの御消息を渡した。 |
tote, ohom-humi tatematuru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2.9 | 「 目も見えはべらぬに、かくかしこき仰せ言を光にてなむ」とて、見たまふ。 |
「目も見えませんが、このような畏れ多いお言葉を光といたしまして」と言って、御覧になる。 |
「涙でこのごろは目も暗くなっておりますが、過分なかたじけない仰せを光明にいたしまして」 未亡人はお文を拝見するのであった。 |
"Me mo miye habera nu ni, kaku kasikoki ohosegoto wo hikari nite nam." tote, mi tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2.10 | 「ほど経ばすこしうち紛るることもやと、待ち過ぐす月日に添へて、いと忍びがたきはわりなきわざになむ。いはけなき人をいかにと思ひやりつつ、もろともに育まぬ おぼつかなさを。今は、なほ 昔のかたみになずらへて、ものしたまへ」 |
「時がたてば少しは気持ちの紛れることもあろうかと、心待ちに過す月日がたつにつれて、たいそうがまんができなくなるのはどうにもならないことである。幼い人をどうしているかと案じながら、一緒にお育てしていない気がかりさよ。今は、やはり故人の形見と思って、参内なされよ」 |
時がたてば少しは寂しさも紛れるであろうかと、そんなことを頼みにして日を送っていても、日がたてばたつほど悲しみの深くなるのは困ったことである。どうしているかとばかり思いやっている小児も、そろった両親に育てられる幸福を失ったものであるから、子を失ったあなたに、せめてその子の代わりとして面倒を見てやってくれることを頼む。 |
"Hodo he ba sukosi uti-magiruru koto mo ya to, mati sugusu tukihi ni sohe te, ito sinobigataki ha warinaki waza ni nam. Ihakenaki hito wo ikani to omohiyari tutu, morotomoni hagukuma nu obotukanasa wo. Ima ha, naho mukasi no katami ni nazurahe te, monosi tamahe." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2.11 | など、こまやかに書かせたまへり。 |
などと、心こまやかにお書きあそばされていた。 |
などこまごまと書いておありになった。 |
nado, komayaka ni kaka se tamahe ri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2.12 | 「 宮城野の露吹きむすぶ風の音に 小萩がもとを思ひこそやれ」 |
「宮中の萩に野分が吹いて露を結ばせたり散らそうとする風の音を聞くにつけ、 幼子の身が思いやられる」 |
宮城野の露吹き結ぶ風の音に 小萩が上を思ひこそやれ |
"Miyagino no tuyu huki musubu kaze no oto ni kohagi ga moto wo omohi koso yare |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2.13 | とあれど、え見たまひ果てず。 |
とあるが、最後までお読みきれになれない。 |
という御歌もあったが、未亡人はわき出す涙が妨げて明らかには拝見することができなかった。 |
to are do, e mi tamahi hate zu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2.14 | 「 命長さの、いとつらう 思うたまへ知らるるに、 松の思はむことだに、恥づかしう ★ 思うたまへはべれば、 百敷に行きかひはべらむことは、ましていと憚り多くなむ。 かしこき仰せ言をたびたび承りながら、みづからはえなむ思ひたまへたつまじき。 |
「長生きが、とても辛いことだと存じられますうえに、高砂の松がどう思うかさえも、恥ずかしう存じられますので、内裏にお出入りいたしますことは、さらにとても遠慮いたしたい気持ちでいっぱいです。畏れ多い仰せ言をたびたび承りながらも、わたし自身はとても思い立つことができません。 |
「長生きをするからこうした悲しい目にもあうのだと、それが世間の人の前に私をきまり悪くさせることなのでございますから、まして御所へ時々上がることなどは思いもよらぬことでございます。もったいない仰せを伺っているのですが、私が伺候いたしますことは今後も実行はできないでございましょう。 |
"Inoti nagasa no, ito turau omou tamahe sira ruru ni, matu no omoha m koto dani, hadukasiu omou tamahe habere ba, momosiki ni yukikahi habera m koto ha, masite ito habakari ohoku nam. Kasikoki ohosegoto wo tabitabi uketamahari nagara, midukara ha e nam omohi tamahe tatu maziki. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2.15 | 若宮は、いかに思ほし知るにか、参りたまはむことをのみなむ思し 急ぐめれば、 ことわりに悲しう見たてまつりはべるなど、うちうちに 思うたまふるさまを奏したまへ。 ゆゆしき身にはべれば、 かくておはしますも、忌ま忌ましうかたじけなくなむ」 |
若宮は、どのようにお考えなさっているのか、参内なさることばかりお急ぎになるようなので、ごもっともだと悲しく拝見しておりますなどと、ひそかに存じております由をご奏上なさってください。不吉な身でございますので、こうして若宮がおいでになるのも、忌まわしくもあり畏れ多いことでございます」 |
若宮様は、やはり御父子の情というものが本能にありますものと見えて、御所へ早くおはいりになりたい御様子をお見せになりますから、私はごもっともだとおかわいそうに思っておりますということなどは、表向きの奏上でなしに何かのおついでに申し上げてくださいませ。良人も早く亡くしますし、娘も死なせてしまいましたような不幸ずくめの私が御いっしょにおりますことは、若宮のために縁起のよろしくないことと恐れ入っております」 |
Wakamiya ha, ikani omohosi siru ni ka, mawiri tamaha m koto wo nomi nam obosi-isogu mere ba, kotowari ni kanasiu mi tatematuri haberu nado, utiuti ni omou tamahuru sama wo sousi tamahe. Yuyusiki mi ni habere ba, kakute ohasimasu mo, imaimasiu katazikenaku nam." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2.16 | とのたまふ。 宮は大殿籠もりにけり。 |
とおっしゃる。若宮はもうお寝みになっていた。 |
などと言った。そのうち若宮ももうお寝みになった。 |
to notamahu. Miya ha ohotonogomori ni keri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2.17 | 「 見たてまつりて、くはしう 御ありさまも奏しはべらまほしきを、 待ちおはしますらむに、 夜更けはべりぬべし」 とて急ぐ。 |
「拝見して、詳しくご様子も奏上いたしたいのですが、帝がお待ちあそばされていることでしょうし、夜も更けてしまいましょう」と言って急ぐ。 |
「またお目ざめになりますのをお待ちして、若宮にお目にかかりまして、くわしく御様子も陛下へ御報告したいのでございますが、使いの私の帰りますのをお待ちかねでもいらっしゃいますでしょうから、それではあまりおそくなるでございましょう」 と言って命婦は帰りを急いだ。 |
"Mi tatematuri te, kuhasiu mi-arisama mo sousi habera mahosiki wo, mati ohasimasu ram ni, yo huke haberi nu besi." tote isogu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2.18 | 「 ▼ 暮れまどふ心の闇も堪へがたき片端をだに、はるくばかりに 聞こえまほしうはべるを、私にも心のどかにまかでたまへ。年ごろ、 うれしく面だたしきついでにて 立ち寄りたまひしものを、かかる御消息にて見たてまつる、返す返すつれなき命にもはべるかな。 |
「子を思う親心の悲しみの堪えがたいその一部だけでも、晴らすほどに申し上げとうございますので、個人的にでもゆっくりとお出くださいませ。数年来、おめでたく晴れがましい時にお立ち寄りくださいましたのに、このようなお悔やみのお使いとしてお目にかかるとは、返す返すも情けない運命でございますこと。 |
「子をなくしました母親の心の、悲しい暗さがせめて一部分でも晴れますほどの話をさせていただきたいのですから、公のお使いでなく、気楽なお気持ちでお休みがてらまたお立ち寄りください。以前はうれしいことでよくお使いにおいでくださいましたのでしたが、こんな悲しい勅使であなたをお迎えするとは何ということでしょう。返す返す運命が私に長生きさせるのが苦しゅうございます。 |
"Kure-madohu kokoro-no-yami mo tahe gataki katahasi wo dani, haruku bakari ni kikoye mahosiu haberu wo, watakusi ni mo kokoro nodoka ni makade tamahe. Tosigoro, uresiku omodatasiki tuide nite tatiyori tamahi si mono wo, kakaru ohom-seusoko nite mi tatematuru, kahesugahesu turenaki inoti ni mo haberu kana! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2.19 | 生まれし時より、 思ふ心ありし人にて、 故大納言、いまはとなるまで、『 ただ、この人の宮仕への本意、かならず遂げさせたてまつれ。我れ亡くなりぬとて、口惜しう思ひくづほるな』と、返す返す諌めおかれはべりしかば、はかばかしう ▼ 後見思ふ人もなき交じらひは、なかなかなるべきことと思ひたまへながら、ただかの遺言を違へじとばかりに、出だし立てはべりしを、身に余るまでの御心ざしの、よろづにかたじけなきに、人げなき恥を隠しつつ、交じらひたまふめりつるを、人の嫉み深く積もり、安からぬこと多くなり添ひはべりつるに、 横様なるやうにて、つひにかくなりはべりぬれば、かへりてはつらくなむ、かしこき御心ざしを思ひたまへられはべる。これもわりなき心の闇になむ」 |
生まれた時から、心中に期待するところのあった人で、亡き夫大納言が、臨終の際となるまで、『ともかく、わが娘の宮仕えの宿願を、きっと実現させ申しなさい。わたしが亡くなったからといって、落胆して挫けてはならぬ』と、繰り返し戒め遺かれましたので、これといった後見人のない宮仕え生活は、かえってしないほうがましだと存じながらも、ただあの遺言に背くまいとばかりに、出仕させましたところ、身に余るほどのお情けが、いろいろともったいないので、人にあるまじき恥を隠し隠ししては、宮仕え生活をしていられたようでしたが、人の嫉みが深く積もり重なり、心痛むことが多く身に添わってまいりましたところ、横死のようなありさまで、とうとうこのようなことになってしまいましたので、かえって辛いことだと、その畏れ多いお情けを存じております。このような愚痴も理屈では割りきれない親心の迷いです」 |
故人のことを申せば、生まれました時から親たちに輝かしい未来の望みを持たせました子で、父の大納言はいよいよ危篤になりますまで、この人を宮中へ差し上げようと自分の思ったことをぜひ実現させてくれ、自分が死んだからといって今までの考えを捨てるようなことをしてはならないと、何度も何度も遺言いたしましたが、確かな後援者なしの宮仕えは、かえって娘を不幸にするようなものではないだろうかとも思いながら、私にいたしましてはただ遺言を守りたいばかりに陛下へ差し上げましたが、過分な御寵愛を受けまして、そのお光でみすぼらしさも隠していただいて、娘はお仕えしていたのでしょうが、皆さんの御嫉妬の積もっていくのが重荷になりまして、寿命で死んだとは思えませんような死に方をいたしましたのですから、陛下のあまりに深い御愛情がかえって恨めしいように、盲目的な母の愛から私は思いもいたします」 |
Umare si toki yori, omohu kokoro ari si hito nite, ko-Dainagon, imaha to naru made, 'Tada, kono hito no miyadukahe no ho'i, kanarazu toge sase tatemature. Ware nakunari nu tote, kutiwosiu omohi kuduhoru na.' to, kahesugahesu isame-oka re haberi sika ba, hakabakasiu usiromi omohu hito mo naki mazirahi ha, nakanaka naru beki koto to omohi tamahe nagara, tada kano yuigon wo tagahe zi to bakari ni, idasi-tate haberi si wo, mi ni amaru made no mi-kokorozasi no, yorodu ni katazikenaki ni, hitogenaki hadi wo kakusi tutu, mazirahi tamahu meri turu wo, hito no sonemi hukaku tumori, yasukara nu koto ohoku nari sohi haberi turu ni, yokosama naru yau nite, tuhi ni kaku nari haberi nure ba, kaherite ha turaku nam, kasikoki mi-kokorozasi wo omohi tamahe rare haberu. Kore mo warinaki kokoro-no-yami ni nam." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2.20 | と、言ひもやらずむせかへりたまふほどに、夜も更けぬ。 |
と、最後まで言えないで涙に咽んでいらっしゃるうちに、夜も更けてしまった。 |
こんな話をまだ全部も言わないで未亡人は涙でむせ返ってしまったりしているうちにますます深更になった。 |
to, ihi mo yara zu musekaheri tamahu hodo ni, yo mo huke nu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2.21 | 「 主上もしかなむ。『 我が御心ながら、あながちに人目おどろくばかり 思されしも、 長かるまじきなりけりと、今は つらかりける人の契りになむ。 世にいささかも人の心を曲げたることはあらじと思ふを、ただこの人のゆゑにて、あまた さるまじき人の恨みを負ひし果て果ては、かううち捨てられて、心をさめむ方なきに、いとど人悪ろうかたくなになり果つるも、 前の世ゆかしうなむ』とうち返しつつ、御しほたれがちにのみおはします」と 語りて尽きせず。泣く泣く、「 夜いたう更けぬれば、今宵過ぐさず、御返り奏せむ」と 急ぎ参る。 |
「主上様もご同様でございまして。『御自分のお心ながら、強引に周囲の人が目を見張るほど御寵愛なさったのも、長くは続きそうにない運命だったからなのだなあと、今となってはかえって辛い人との宿縁であった。決して少しも人の心を傷つけたようなことはあるまいと思うのに、ただこの人との縁が原因で、たくさんの恨みを負うなずのない人の恨みをもかったあげくには、このように先立たれて、心静めるすべもないところに、ますます体裁悪く愚か者になってしまったのも、前世がどんなであったのかと知りたい』と何度も仰せられては、いつもお涙がちばかりでいらっしゃいます」と話しても尽きない。泣く泣く、「夜がたいそう更けてしまったので、今夜のうちに、ご報告を奏上しよう」と急いで帰参する。 |
「それは陛下も仰せになります。自分の心でありながらあまりに穏やかでないほどの愛しようをしたのも前生の約束で長くはいっしょにおられぬ二人であることを意識せずに感じていたのだ。自分らは恨めしい因縁でつながれていたのだ、自分は即位してから、だれのためにも苦痛を与えるようなことはしなかったという自信を持っていたが、あの人によって負ってならぬ女の恨みを負い、ついには何よりもたいせつなものを失って、悲しみにくれて以前よりももっと愚劣な者になっているのを思うと、自分らの前生の約束はどんなものであったか知りたいとお話しになって湿っぽい御様子ばかりをお見せになっています」 どちらも話すことにきりがない。命婦は泣く泣く、 「もう非常に遅いようですから、復命は今晩のうちにいたしたいと存じますから」 と言って、帰る仕度をした。 |
"Uhe mo sika nam. 'Waga mi-kokoro nagara, anagati ni hitome odoroku bakari obosare si mo, nagakaru maziki nari keri to, ima ha turakari keru hito-no-tigiri ni nam. Yoni isasaka mo hito no kokoro wo mage taru koto ha ara zi to omohu wo, tada kono hito no yuwe nite, amata sarumaziki hito no urami wo ohi si hatehate ha, kau uti-sute rare te, kokoro wosame m kata naki ni, itodo hito warou katakuna ni nari haturu mo, saki-no-yo yukasiu nam.' to uti-kahesi tutu, ohom-sihotaregati ni nomi ohasimasu." to katari te tuki se zu. Nakunaku, "Yo itau huke nure ba, koyohi sugusa zu, ohom-kaheri souse m." to isogi mawiru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2.22 | 月は入り方の、空清う澄みわたれるに、風いと涼しくなりて、草むらの 虫の声ごゑもよほし顔なるも、いと立ち離れにくき草のもとなり。 |
月は入り方で、空が清く澄みわたっているうえに、風がとても涼しくなって、草むらの虫の声ごえが涙を誘わせるようなのも、まことに立ち去りがたい庭の風情である。 |
落ちぎわに近い月夜の空が澄み切った中を涼しい風が吹き、人の悲しみを促すような虫の声がするのであるから帰りにくい。 |
Tuki ha irigata no, sora kiyou sumi-watare ru ni, kaze ito suzusiku nari te, kusamura no musi no kowegowe moyohosi-gaho naru mo, ito tati hanare nikuki kusa no moto nari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2.23 | 「 鈴虫の声の限りを尽くしても 長き夜あかずふる涙かな」 |
「鈴虫が声をせいいっぱい鳴き振るわせても 長い秋の夜を尽きることなく流れる涙でございますこと」 |
鈴虫の声の限りを尽くしても 長き夜飽かず降る涙かな |
"Suzumusi no kowe no kagiri wo tukusi te mo nagaki yo akazu huru namida kana |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2.24 | えも乗りやらず。 |
お車に乗りかねている。 |
車に乗ろうとして命婦はこんな歌を口ずさんだ。 |
E mo nori-yara zu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2.25 | 「 いとどしく虫の音しげき浅茅生に 露置き添ふる雲の上人 |
「ただでさえ虫の音のように泣き暮らしておりました荒れ宿に さらに涙をもたらします内裏からのお使い人よ |
「いとどしく虫の音しげき浅茅生に 露置き添ふる雲の上人 |
"Itodosiku musi no ne sigeki asadihu ni tuyu oki sohuru kumo no uhebito |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2.26 | かごとも聞こえつべくなむ」 |
恨み言もつい申し上げてしまいそうで」 |
かえって御訪問が恨めしいと申し上げたいほどです」 |
Kagoto mo kikoye tu beku nam." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2.27 | と 言はせたまふ。をかしき御贈り物などあるべき折にもあらねば、ただかの御形見にとて、かかる用もやと残したまへりける御装束一領、 御髪上げの 調度めく物添へたまふ。 |
と言わせなさる。趣きのあるような御贈物などあらねばならない時でもないので、ただ亡き更衣のお形見にと、このような入用もあろうかとお残しになった御衣装一揃いに、御髪上げの調度のような物をお添えになる。 |
と未亡人は女房に言わせた。意匠を凝らせた贈り物などする場合でなかったから、故人の形見ということにして、唐衣と裳の一揃えに、髪上げの用具のはいった箱を添えて贈った。 |
to iha se tamahu. Wokasiki ohom-okurimono nado aru beki wori ni mo ara ne ba, tada kano ohom-katami ni tote, kakaru you mo ya to nokosi tamahe ri keru ohom-sauzoku hito-kudari, mi-gusiage no teudo-meku mono sohe tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2.28 | 若き人びと、悲しきことはさらにも言はず、内裏わたりを朝夕にならひて、いとさうざうしく、主上の御ありさまなど思ひ出できこゆれば、とく参りたまはむことを そそのかしきこゆれど、「 かく忌ま忌ましき身の 添ひたてまつらむも、いと人聞き憂かるべし、また、 見たてまつらでしばしもあらむは、いとうしろめたう」思ひきこえたまひて、 すがすがともえ参らせたてまつりたまはぬなりけり。 |
若い女房たちは、悲しいことは言うまでもない、内裏の生活を朝な夕なと馴れ親しんでいるので、たいそう物足りなく、主上のご様子などをお思い出し申し上げると、早く参内なさるようにとお勧め申し上げるが、「このように忌まわしい身が付き随って参内申すようなのも、まことに世間の聞こえが悪いであろうし、また、しばしも拝さずにいることも、気がかりに」お思い申し上げなさって、気分よくさっぱりとは参内させなさることがおできになれないのであった。 |
若い女房たちの更衣の死を悲しむのはむろんであるが、宮中住まいをしなれていて、寂しく物足らず思われることが多く、お優しい帝の御様子を思ったりして、若宮が早く御所へお帰りになるようにと促すのであるが、不幸な自分がごいっしょに上がっていることも、また世間に批難の材料を与えるようなものであろうし、またそれかといって若宮とお別れしている苦痛にも堪えきれる自信がないと未亡人は思うので、結局若宮の宮中入りは実行性に乏しかった。 |
Wakaki hitobito, kanasiki koto ha sarani mo iha zu, uti watari wo asayuhu ni narahi te, ito sauzausiku, Uhe no ohom-arisama nado omohi-ide kikoyure ba, toku mawiri tamaha m koto wo sosonokasi kikoyure do, "Kaku imaimasiki mi no sohi tatematura m mo, ito hitogiki ukaru besi, mata, mi tatematura de sibasi mo ara m ha, ito usirometau." omohi kikoye tamahi te, sugasuga to mo e mawira se tatematuri tamaha nu nari keri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3 | 第三段 命婦帰参 |
2-3 Messenger reports to Mikado |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.1 | 命婦は、「まだ大殿籠もらせたまはざりける」と、あはれに見たてまつる。 御前の壺前栽のいとおもしろき盛りなるを御覧ずるやうにて、忍びやかに心にくき限りの女房四五人さぶらはせたまひて、 御物語せさせたまふなりけり。 |
命婦は、「まだお寝みあそばされなかったのだわ」と、しみじみと拝し上げる。御前にある壺前栽がたいそう美しい盛りに咲いているのを御覧あそばされるようにして、しめやかにおくゆかしい女房ばかり四、五人を伺候させなさって、お話をさせておいであそばすのであった。 |
御所へ帰った命婦は、まだ宵のままで御寝室へはいっておいでにならない帝を気の毒に思った。中庭の秋の花の盛りなのを愛していらっしゃるふうをあそばして凡庸でない女房四、五人をおそばに置いて話をしておいでになるのであった。 |
Myaubu ha, "Mada ohotonogomora se tamaha zari keru!" to, ahare ni mi tatematuru. O-mahe no tubosenzai no ito omosiroki sakari naru wo goranzuru yau nite, sinobiyaka ni kokoronikuki kagiri no nyoubau sigo-nin saburaha se tamahi te, ohom-monogatari se sase tamahu nari keri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.2 | このごろ、明け暮れ御覧ずる長恨歌の御絵、 亭子院の描かせたまひて、 伊勢、貫之に詠ませたまへる、大和言の葉をも、唐土の詩をも、ただ その筋をぞ、枕言にせさせたまふ。 いとこまやかにありさま問はせたまふ。あはれなりつること忍びやかに奏す。御返り御覧ずれば、 |
最近、毎日御覧なさる「長恨歌」の御絵、それは亭子院がお描きあそばされて、伊勢や 貫之に和歌を詠ませなさったものだが、わが国の和歌や 唐土の漢詩などをも、ひたすらその方面の事柄を、日常の話題にあそばされている。たいそう詳しく里の様子をお尋ねあそばす。しみじみとした趣きをひそかに奏上する。お返事を御覧になると、 |
このごろ始終帝の御覧になるものは、玄宗皇帝と楊貴妃の恋を題材にした白楽天の長恨歌を、亭子院が絵にあそばして、伊勢や貫之に歌をお詠ませになった巻き物で、そのほか日本文学でも、支那のでも、愛人に別れた人の悲しみが歌われたものばかりを帝はお読みになった。帝は命婦にこまごまと大納言家の様子をお聞きになった。身にしむ思いを得て来たことを命婦は外へ声をはばかりながら申し上げた。未亡人の御返事を帝は御覧になる。 |
Konogoro, akekure goranzuru Tyaugonka no ohom-we, Teizi-no-win no kaka se tamahi te, Ise, Turayuki ni yoma se tamahe ru, yamato-kotonoha wo mo, morokosi no uta wo mo, tada sono sudi wo zo, makuragoto ni se sase tamahu. Ito komayaka ni arisama toha se tamahu. Ahare nari turu koto sinobiyaka ni sousu. Ohom-kaheri goranzure ba, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.3 | 「 いともかしこきは置き所もはべらず。 かかる仰せ言につけても、かきくらす乱り心地になむ。 |
「たいへんに畏れ多いお手紙を頂戴いたしましてはどうしてよいか分かりません。このような仰せ言を拝見いたしましても、心の中はまっくら闇に思い乱れておりまして。 |
もったいなさをどう始末いたしてよろしゅうございますやら。こうした仰せを承りましても、愚か者はただ悲しい悲しいとばかり思われるのでございます。 |
"Ito mo kasikoki ha okidokoro mo habera zu. Kakaru ohosegoto ni tuke te mo, kaki-kurasu midarigokoti ni nam. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.4 | 荒き風ふせぎし蔭の枯れしより 小萩がうへぞ静心なき」 |
荒い風を防いでいた木が枯れてからは 小萩の身の上が気がかりでなりません」 |
荒き風防ぎし蔭の枯れしより 小萩が上ぞしづ心無き |
Araki kaze husegi si kage no kare si yori Kohagi ga uhe zo sidugokoro naki |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
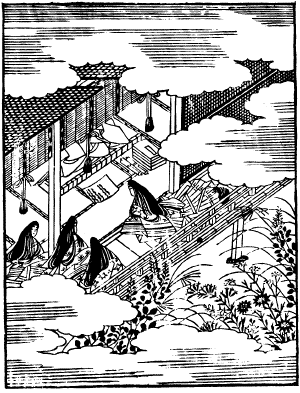 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.5 | などやうに乱りがはしきを、心をさめざりけるほどと御覧じ許すべし。 いとかうしも見えじと、思し静むれど、 さらにえ忍びあへさせたまはず、御覧じ初めし年月のことさへかき集め、よろづに 思し続けられて、「 時の間もおぼつかなかりしを、 かくても月日は経にけり」と、あさましう思し召さる。 |
などと言うようにやや不謹慎なのを、気持ちが静まらない時だからとお見逃しになるのであろう。決してこう取り乱した姿を見せまいと、お静めなさるが、まったく堪えることがおできあそばされず、初めてお召しあそばした年月のことまであれこれと思い出され、何から何まで自然とお思い続けられて、「片時の間も離れてはいられなかったのに、よくこうも月日を過せたものだ」と、あきれてお思いあそばされる。 |
というような、歌の価値の疑わしいようなものも書かれてあるが、悲しみのために落ち着かない心で詠んでいるのであるからと寛大に御覧になった。帝はある程度まではおさえていねばならぬ悲しみであると思召すが、それが御困難であるらしい。はじめて桐壼の更衣の上がって来たころのことなどまでがお心の表面に浮かび上がってきてはいっそう暗い悲しみに帝をお誘いした。その当時しばらく別れているということさえも自分にはつらかったのに、こうして一人でも生きていられるものであると思うと自分は偽り者のような気がするとも帝はお思いになった。 |
nado yau ni midarigahasiki wo, kokoro wosame zari keru hodo to goranzi yurusu besi. Ito kau simo miye zi to, obosi sidumure do, sarani e sinobiahe sase tamaha zu, goranzi hazime si tosituki no koto sahe kakiatume, yorodu ni obosi tuduke rare te, "Toki no ma mo obotukanakari si wo, kaku te mo tukihi ha he ni keri." to, asamasiu obosimesa ru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.6 | 「 故大納言の遺言あやまたず、宮仕への本意深くものしたりしよろこびは、 かひあるさまにとこそ 思ひわたりつれ ★。言ふかひなしや」とうちのたまはせて、いとあはれに思しやる。「 かくても、おのづから若宮など生ひ出でたまはば、 さるべきついでもありなむ。 命長くとこそ思ひ念ぜめ」 |
「故大納言の遺言に背かず、宮仕えの宿願をよく果たしたお礼には、その甲斐があったようにと思い続けていたが。詮ないことだ」とふと仰せになって、たいそう気の毒にと思いを馳せられる。「そうではあるが、いずれ若宮がご成長されたならば、しかるべき機会がきっとあろう。長生きをしてそれまでじっと辛抱するがよい」 |
「死んだ大納言の遺言を苦労して実行した未亡人への酬いは、更衣を後宮の一段高い位置にすえることだ、そうしたいと自分はいつも思っていたが、何もかも皆夢になった」 とお言いになって、未亡人に限りない同情をしておいでになった。 「しかし、あの人はいなくても若宮が天子にでもなる日が来れば、故人に后の位を贈ることもできる。それまで生きていたいとあの夫人は思っているだろう」 |
"Ko-Dainagon no yuigon ayamata zu, miyadukahe no hoi hukaku monosi tari si yorokobi ha, kahi aru sama ni to koso omohiwatari ture. Ihukahinasi ya!" to uti-notamahase te, ito ahare ni obosi-yaru. "Kaku te mo, onodukara Wakamiya nado ohi-ide tamaha ba, sarubeki tuide mo ari na m. Inoti nagaku to koso omohi-nenze me." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.7 | などのたまはす。 かの贈り物御覧ぜさす。「 亡き人の住処尋ね出でたりけむしるしの釵ならましかば」と思ほすも いとかひなし。 |
などと仰せになる。あの贈物を帝のお目に入れる。「亡くなった人の住処を探し当てたという証拠の釵であったならば」とお思いあそばしても まったく甲斐がない。 |
などという仰せがあった。命婦は贈られた物を御前へ並べた。これが唐の幻術師が他界の楊貴妃に逢って得て来た玉の簪であったらと、帝はかいないこともお思いになった。 |
nado notamahasu. Kano okurimono goranze sasu. "Naki hito no sumika tadune-ide tari kem sirusi no kamzasi nara masika ba." to omohosu mo ito kahinasi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.8 | 「 尋ねゆく幻もがなつてにても 魂のありかをそこと知るべく」 |
「亡き更衣を探し行ける幻術士がいてくれればよいのだがな、人づてにでも 魂のありかをどこそこと知ることができるように」 |
尋ね行くまぼろしもがなつてにても 魂のありかをそこと知るべく |
"Tadune yuku maborosi mogana tute nite mo tama no arika wo soko to siru beku |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.9 | 絵に描ける楊貴妃の容貌は、いみじき絵師といへども、筆限りありければいとにほひ少なし。 大液芙蓉未央柳も ★、 げに通ひたりし容貌を、 唐めいたる装ひは うるはしうこそ ありけめ ★、 なつかしうらうたげなりしを思し出づるに、花鳥の色にも音にもよそふべき方ぞなき。 |
絵に描いてある楊貴妃の容貌は、上手な絵師と言っても、筆力には限界があったのでまったく生気が少ない。「大液の芙蓉、未央の柳」の句にも、なるほど似ていた容貌だが、唐風の装いをした姿は端麗ではあったろうが、慕わしさがあって愛らしかったのをお思い出しになると、花や鳥の色や音にも喩えようがない。 |
絵で見る楊貴妃はどんなに名手の描いたものでも、絵における表現は限りがあって、それほどのすぐれた顔も持っていない。太液の池の蓮花にも、未央宮の柳の趣にもその人は似ていたであろうが、また唐の服装は華美ではあったであろうが、更衣の持った柔らかい美、艶な姿態をそれに思い比べて御覧になると、これは花の色にも鳥の声にもたとえられぬ最上のものであった。 |
We ni kake ru Yaukihi no katati ha, imiziki wesi to ihe do mo, hude kagiri ari kere ba ito nihohi sukunasi. 'Taieki-no-huyou Biyau-no-yanagi' mo, geni kayohi tari si katati wo, karamei taru yosohi ha uruhasiu koso ari keme, natukasiu rautage nari si wo obosi-iduru ni, hana tori no iro ni mo ne ni mo yosohu beki kata zo naki. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.10 | 朝夕の言種に、「 翼をならべ、枝を交はさむ」と ★契らせたまひしに、かなはざりける命のほどぞ、 尽きせず恨めしき。 |
朝夕の口癖に、「比翼の鳥となり、連理の枝となろう」とお約束あそばしていたのに、思うようにならなかった人の運命が、永遠に尽きることなく恨めしかった。 |
お二人の間はいつも、天に在っては比翼の鳥、地に生まれれば連理の枝という言葉で永久の愛を誓っておいでになったが、運命はその一人に早く死を与えてしまった。 |
Asayuhu no koto-gusa ni, "Hane wo narabe, eda wo kahasa m." to tigira se tamahi si ni, kanaha zari keru inoti no hodo zo, tukise zu uramesi ki. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.11 | 風の音、虫の音につけて、もののみ悲しう思さるるに、弘徽殿には、久しく 上の御局にも参う上りたまはず、月のおもしろきに、夜更くるまで 遊びをぞしたまふなる。いとすさまじう、ものしと聞こし召す。このごろの御気色を見たてまつる上人、女房などは、かたはらいたしと聞きけり。 いとおし立ちかどかどしきところものしたまふ御方にて、 ことにもあらず思し消ちて もてなしたまふなるべし。 月も入りぬ。 |
風の音や、虫の音を聞くにつけて、何とはなく一途に悲しく思われなさるが、弘徽殿女御におかれては、久しく上の御局にもお上がりにならず、月が美しいので、夜が更けるまで管弦の遊びをなさっているようである。実に興ざめで、不愉快だとお聞きあそばす。最近のご様子を拝する殿上人や 女房などは、はらはらする思いで聞いていた。たいへんに気が強くてとげとげしい性質をお持ちの方なので、何ともお思いなさらず無視して振る舞っていらっしゃるのであろう。月も沈んでしまった。 |
秋風の音にも虫の声にも帝が悲しみを覚えておいでになる時、弘徽殿の女御はもう久しく夜の御殿の宿直にもお上がりせずにいて、今夜の月明に更けるまでその御殿で音楽の合奏をさせているのを帝は不愉快に思召した。このころの帝のお心持ちをよく知っている殿上役人や帝付きの女房なども皆弘徽殿の楽音に反感を持った。負けぎらいな性質の人で更衣の死などは眼中にないというふうをわざと見せているのであった。 月も落ちてしまった。 |
Kaze no oto, musi no ne ni tuke te, mono nomi kanasiu obosa ruru ni, Koukiden ni ha, hisasiku uhe-no-mi-tubone ni mo maunobori tamaha zu, tuki no omosiroki ni, yo hukuru made asobi wo zo si tamahu naru. Ito susamaziu, monosi to kikosimesu. Konogoro no mi-kesiki wo mi tatematuru uhebito, nyoubau nado ha, kataharaitasi to kiki keri. Ito ositati kadokadosiki tokoro monosi tamahu ohom-kata nite, koto ni mo ara zu obosi-keti te motenasi tamahu naru besi. Tuki mo iri nu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.12 | 「 雲の上も涙にくるる秋の月 いかですむらむ浅茅生の宿」 |
「雲の上の宮中までも涙に曇って見える秋の月だ ましてやどうして澄んで見えようか、草深い里で」 |
雲の上も涙にくるる秋の月 いかですむらん浅茅生の宿 |
"Kumo no uhe mo namida ni kururu aki no tuki ikade sumu ram asadihu no yado |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.13 | 思し召しやりつつ、 ▼ 灯火をかかげ尽くして起きおはします。 右近の司の宿直奏の声聞こゆるは、 丑になりぬるなるべし。人目を思して、夜の御殿に入らせたまひても、 まどろませたまふことかたし。 |
お思いやりになりながら、灯芯をかき立てて油の尽きるまで起きておいであそばす。右近衛府の官人の宿直申しの声が聞こえるのは、丑の刻になったのであろう。人目をお考えになって、夜の御殿にお入りあそばしても、うとうととまどろみあそばすことも難しい。 |
命婦が御報告した故人の家のことをなお帝は想像あそばしながら起きておいでになった。 右近衛府の士官が宿直者の名を披露するのをもってすれば午前二時になったのであろう。人目をおはばかりになって御寝室へおはいりになってからも安眠を得たもうことはできなかった。 |
Obosimesi-yari tutu, tomosibi wo kakage-tukusi te oki ohasimasu. Ukon-no-tukasa no tonowimausi no kowe kikoyuru ha, usi ni nari nuru naru besi. Hitome wo obosi te, yorunootodo ni ira se tamahi te mo, madoroma se tamahu koto katasi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.14 | 朝に起きさせたまふとても、「 明くるも知らで」と ★思し出づるにも、なほ朝政は 怠らせたまひぬべかめり。 |
朝になってお起きあそばそうとしても、「夜の明けるのも分からないで」とお思い出しになられるにつけても、やはり政治をお執りになることは怠りがちになってしまいそうである。 |
朝のお目ざめにもまた、夜明けも知らずに語り合った昔の御追憶がお心を占めて、寵姫の在った日も亡いのちも朝の政務はお怠りになることになる。 |
Asita ni oki sase tamahu tote mo, "Akuru mo sira de." to obosi-iduru ni mo, naho asamaturigoto ha okotara se tamahi nu bekameri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.15 | ものなども聞こし召さず、 朝餉のけしきばかり触れさせたまひて、 大床子の御膳などは、いと遥かに思し召したれば、陪膳にさぶらふ限りは、心苦しき御気色を見たてまつり嘆く。すべて、近うさぶらふ限りは、男女、「 いとわりなきわざかな」と言ひ合はせつつ嘆く。「 さるべき契りこそはおはしましけめ。そこらの人の誹り、恨みをも憚らせたまはず、この御ことに触れたることをば、道理をも失はせたまひ、今はた、かく世の中のことをも、思ほし捨てたるやうになりゆくは、いとたいだいしきわざなり」と、 人の朝廷の例まで引き出で、 ささめき嘆きけり。 |
お食物などもお召し上がりにならず、朝餉には形だけお箸をおつけになって、大床子の御膳などは、まったくお心に入らぬかのように手をおつけあそばさないので、お給仕の人たちは皆、おいたわしいご様子を拝して嘆く。総じて、お側近くお仕えする人たちは、男も女も、「たいそう困ったことですね」とお互いに言い合っては溜息をつく。「こうなるはずの前世からの宿縁がおありあそばしたのでしょう。大勢の人びとの非難や 嫉妬をもお憚りあそばさず、あの方の事に関しては、御分別をお失いあそばされ、今は今で、このように政治をお執りになることも、お捨てになったようになって行くのは、たいへんに困ったことである」と、唐土の朝廷の例まで引き合いに出して、ひそひそと嘆息するのであった。 |
お食欲もない。簡単な御朝食はしるしだけお取りになるが、帝王の御朝餐として用意される大床子のお料理などは召し上がらないものになっていた。それには殿上役人のお給仕がつくのであるが、それらの人は皆この状態を歎いていた。すべて側近する人は男女の別なしに困ったことであると歎いた。よくよく深い前生の御縁で、その当時は世の批難も後宮の恨みの声もお耳には留まらず、その人に関することだけは正しい判断を失っておしまいになり、また死んだあとではこうして悲しみに沈んでおいでになって政務も何もお顧みにならない、国家のためによろしくないことであるといって、支那の歴朝の例までも引き出して言う人もあった。 |
Mono nado mo kikosimesa zu, asagarehi no kesiki bakari hure sase tamahi te, daisyauzi no o-mono nado ha, ito haruka ni obosimesi tare ba, haizen ni saburahu kagiri ha, kokorogurusiki mi-kesiki wo mi tatematuri nageku. Subete, tikau saburahu kagiri ha, wotoko womna, "Ito warinaki waza kana!" to ihiahase tutu nageku. "Sarubeki tigiri koso ha ohasimasi keme. Sokora no hito no sosiri, urami wo mo habakara se tamaha zu, kono ohom-koto ni hure taru koto wo ba, dauri wo mo usinaha se tamahi, ima hata, kaku yononaka no koto wo mo, omohosi-sute taru yau ni nari-yuku ha, ito taidaisiki waza nari." to, hito-no-mikado no tamesi made hiki-ide, sasameki nageki keri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last updated 12/05/2008(ver.2-1) 渋谷栄一校訂(C) Last updated 12/29/2008(ver.2-1) 渋谷栄一注釈 |
Last updated 6/25/2003 渋谷栄一訳(C)(ver.1-4-1) |
|
Last updated 12/13/2008 (ver.2-1) Written in Japanese roman letters by Eiichi Shibuya (C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Picture "Eiri Genji Monogatari"(1650 1st edition) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源氏物語の世界 再編集プログラム Ver 3.38: Copyright (c) 2003,2015 宮脇文経