第一帖 桐壺 |
01 KIRITUBO (Myouyu-rinmo-bon) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 第三章 光る源氏の物語 |
3 Tale of Hikaru-Genji |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1 | 第一段 若宮参内(四歳) |
3-1 Genji's return to the Court (age 4) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.1 | 月日経て、若宮参りたまひぬ。いとどこの世のものならず清らに およすげたまへれば、いとゆゆしう思したり。 |
月日がたって、若宮が参内なさった。ますますこの世の人とは思われず美しくご成長なさっているので、たいへん不吉なまでにお感じになった。 |
幾月かののちに第二の皇子が宮中へおはいりになった。ごくお小さい時ですらこの世のものとはお見えにならぬ御美貌の備わった方であったが、今はまたいっそう輝くほどのものに見えた。 |
Tukihi he te, Wakamiya mawiri tamahi nu. Itodo konoyo no mono nara zu kiyora ni oyosuge tamahe re ba, ito yuyusiu obosi tari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.2 | 明くる年の春、坊定まりたまふにも、 いと引き越さまほしう思せど、御後見すべき人もなく、また世のうけひくまじきことなりければ、なかなか危く思し憚りて、色にも出ださせたまはずなりぬるを、「 さばかり思したれど、限りこそありけれ」と、 世人も聞こえ、 女御も御心落ちゐたまひぬ。 |
翌年の春に、東宮がお決まりになる折にも、とても第一皇子を超えさせたく思し召されたが、ご後見すべき人もなく、また世間が承知するはずもないことだったので、かえって危険であるとお差し控えになって、顔色にもお出しあそばされずに終わったので、「あれほどおかわいがっていらっしゃったが、限界があったのだなあ」と、世間の人びともお噂申し上げ、弘徽殿女御もお心を落ち着けなさった。 |
その翌年立太子のことがあった。帝の思召しは第二の皇子にあったが、だれという後見の人がなく、まただれもが肯定しないことであるのを悟っておいでになって、かえってその地位は若宮の前途を危険にするものであるとお思いになって、御心中をだれにもお洩らしにならなかった。東宮におなりになったのは第一親王である。この結果を見て、あれほどの御愛子でもやはり太子にはおできにならないのだと世間も言い、弘徽殿の女御も安心した。 |
Akuru-tosi no haru, bau sadamari tamahu ni mo, ito hikikosa mahosiu obose do, ohom-usiromi su beki hito mo naku, mata yo no ukehiku maziki koto nari kere ba, nakanaka ayahuku obosi-habakari te, iro ni mo idasa se tamaha zu nari nuru wo, "Sabakari obosi tare do, kagiri koso ari kere." to, yohito mo kikoye, Nyougo mo mi-kokoro oti-wi tamahi nu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.3 | かの御祖母北の方、慰む方なく思し沈みて、 おはすらむ所にだに尋ね行かむと 願ひたまひししるしにや、つひに亡せたまひぬれば、 またこれを悲しび思すこと限りなし。 御子六つになりたまふ年なれば、 このたびは思し知りて恋ひ泣きたまふ。 年ごろ馴れ睦びきこえたまひつるを、見たてまつり置く悲しびをなむ、返す返すのたまひける。 |
あの祖母北の方は、悲しみを晴らすすべもなく沈んでいらっしゃって、せめて死んだ娘のいらっしゃる所にでも尋ねて行きたいと願っていらっしゃった現れか、とうとうお亡くなりになってしまったので、またこのことを悲しく思し召されることこの上もない。御子は六歳におなりのお年なので、今度はお分かりになって恋い慕ってお泣きになる。長年お親しみ申し上げなさってきたのに、後に残して先立つ悲しみを、繰り返し繰り返しおっしゃっていたのであった。 |
その時から宮の外祖母の未亡人は落胆して更衣のいる世界へ行くことのほかには希望もないと言って一心に御仏の来迎を求めて、とうとう亡くなった。帝はまた若宮が祖母を失われたことでお悲しみになった。これは皇子が六歳の時のことであるから、今度は母の更衣の死に逢った時とは違い、皇子は祖母の死を知ってお悲しみになった。今まで始終お世話を申していた宮とお別れするのが悲しいということばかりを未亡人は言って死んだ。 |
Kano ohom-oba Kitanokata, nagusamu kata naku obosi-sidumi te, ohasu ram tokoro ni dani taduneyuka m to negahi tamahi si sirusi ni ya, tuhini use tamahi nure ba, mata kore wo kanasibi-obosu koto kagirinasi. Miko mu-tu ni nari tamahu tosi nare ba, kono tabi ha obosi-siri te kohi-naki tamahu. Tosi-goro nare-mutubi kikoye tamahi turu wo, mi tatematuri oku kanasibi wo nam, kahesugahesu notamahi keru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2 | 第二段 読書始め(七歳) |
3-2 A child prodigy (age 7) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.1 | ▼ 今は内裏にのみさぶらひたまふ。 七つになりたまへば、 読書始めなどせさせたまひて、世に知らず聡う賢くおはすれば、あまり恐ろしきまで御覧ず。 |
今は内裏にばかりお暮らしになっている。七歳におなりになったので、読書始めなどをおさせになったところ、この世に類を知らないくらい聡明で賢くいらっしゃるので、空恐ろしいまでにお思いあそばされる。 |
それから若宮はもう宮中にばかりおいでになることになった。七歳の時に書初めの式が行なわれて学問をお始めになったが、皇子の類のない聡明さに帝はお驚きになることが多かった。 |
Ima ha uti ni nomi saburahi tamahu. Nana-tu ni nari tamahe ba, humihazime nado se sase tamahi te, yo ni sira zu satou kasikoku ohasure ba, amari osorosiki made goranzu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.2 | 「今は誰れも誰れもえ憎みたまはじ。母君なくてだにらうたうしたまへ」とて、弘徽殿などにも渡らせたまふ御供には、 やがて御簾の内に入れたてまつりたまふ。 いみじき武士、仇敵なりとも、見てはうち笑まれぬべきさまのしたまへれば、 えさし放ちたまはず。 女皇女たち二ところ、この御腹におはしませど、 なずらひたまふべきだにぞなかりける。 御方々も隠れたまはず、今よりなまめかしう恥づかしげにおはすれば、いとをかしう うちとけぬ遊び種に、誰れも誰れも思ひきこえたまへり。 |
「今はどなたもどなたもお憎みなされまい。母君がいないということだけでもおかわいがりください」と仰せになって、弘徽殿などにもお渡りあそばすお供としては、そのまま御簾の内側にお入れ申し上げなさる。恐ろしい武士や 仇敵であっても、見るとつい微笑まずにはいられない様子でいらっしゃるので、放っておくこともおできになれない。姫皇女たちがお二方、この御方にはいらっしゃったが、お並びになりようもないのであった。他の女御がたもお隠れにならずに、今から優美で立派でいらっしゃるので、たいそう趣きがある一方で気のおける遊び相手だと、どなたもどなたもお思い申し上げていらっしゃった。 |
「もうこの子をだれも憎むことができないでしょう。母親のないという点だけででもかわいがっておやりなさい」 と帝は些言いになって、弘徽殿へ昼間おいでになる時もいっしょにおつれになったりしてそのまま御簾の中にまでもお入れになった。どんな強さ一方の武士だっても仇敵だってもこの人を見ては笑みが自然にわくであろうと思われる美しい少童でおありになったから、女御も愛を覚えずにはいられなかった。この女御は東宮のほかに姫宮をお二人お生みしていたが、その方々よりも第二の皇子のほうがおきれいであった。姫宮がたもお隠れにならないで賢い遊び相手としてお扱いになった。 |
"Ima ha tare mo tare mo e nikumi tamaha zi. Hahagimi naku te dani rautau si tamahe." tote, Koukiden nado ni mo watara se tamahu ohom-tomo ni ha, yagate mi-su no uti ni ire tatematuri tamahu. Imiziki mononohu, ata kataki nari tomo, mi te ha uti-wema re nu beki sama no si tamahe re ba, e sasi-hanati tamaha zu. Womna-miko-tati huta-tokoro, kono ohom-hara ni ohasimase do, nazurahi tamahu beki dani zo nakari keru. Ohom-katagata mo kakure tamaha zu, ima yori namamekasiu hadukasige ni ohasure ba, ito wokasiu utitoke nu asobigusa ni, tare mo tare mo omohi kikoye tamahe ri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.3 | わざとの御学問はさるものにて、 琴笛の音にも 雲居を響かし、 すべて言ひ続けば、ことごとしう、うたてぞなりぬべき人の御さまなりける。 |
本格的な御学問はもとよりのこと、琴や笛の才能でも宮中の人びとを驚かせ、すべて一つ一つ数え上げていったら、仰々しく嫌になってしまうくらい、優れた才能のお方なのであった。 |
学問はもとより音楽の才も豊かであった。言えぼ不自然に聞こえるほどの天才児であった。 |
Wazato no go-gakumon ha saru mono nite, koto hue no ne ni mo kumowi wo hibikasi, subete ihi-tuduke ba, kotogotosiu, utate zo nari nu beki hito no ohom-sama nari keru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3 | 第三段 高麗人の観相、源姓賜わる |
3-3 A prophecy by Koma-udo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.1 | そのころ、 高麗人の参れる中に、かしこき相人ありけるを 聞こし召して、 宮の内に召さむことは、宇多の帝の御誡めあれば、いみじう忍びて、この御子を 鴻臚館に遣はしたり。 御後見だちて仕うまつる右大弁の子のやうに思はせて率てたてまつるに、相人驚きて、あまたたび傾きあやしぶ。 |
その当時、高麗人が来朝していた中に、優れた人相見がいたのをお聞きあそばして、内裏の内に召し入れることは 宇多帝の御遺誡があるので、たいそう人目を忍んで、この御子を鴻臚館にお遣わしになった。後見役のようにしてお仕えする右大弁の子供のように思わせてお連れ申し上げると、人相見は目を見張って、何度も首を傾け不思議がる。 |
その時分に高麗人が来朝した中に、上手な人相見の者が混じっていた。帝はそれをお聞きになったが、宮中へお呼びになることは亭子院のお誡めがあっておできにならず、だれにも秘密にして皇子のお世話役のようになっている右大弁の子のように思わせて、皇子を外人の旅宿する鴻臚館へおやりになった。 相人は不審そうに頭をたびたび傾けた。 |
Sonokoro, Komaudo no mawire ru naka ni, kasikoki saunin ari keru wo kikosimesi te, miya no uti ni mesa m koto ha, Uda-no-mikado no ohom-imasime are ba, imiziu sinobi te, kono Miko wo Kourokwan ni tukahasi tari. Ohom-usiromidati te tukau maturu Udaiben no ko no yau ni omoha se te wi te tatematuru ni, saunin odoroki te, amata tabi katabuki ayasibu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
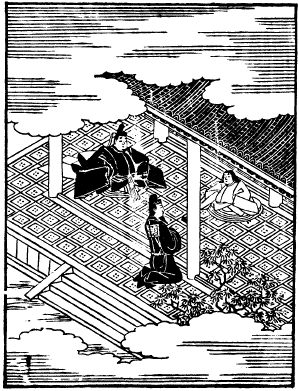 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.2 | 「 国の親となりて、帝王の上なき位に昇るべき相おはします人の、そなたにて見れば、 乱れ憂ふることやあらむ。 朝廷の重鎮となりて、天の下を輔くる方にて見れば、またその相違ふべし」と言ふ。 |
「国の親となって、帝王の最高の地位につくはずの相をお持ちでいらっしゃる方で、そういう人として占うと、国が乱れ民の憂えることが起こるかも知れません。朝廷の重鎮となって、政治を補佐する人として占うと、またその相ではないようです」と言う。 |
「国の親になって最上の位を得る人相であって、さてそれでよいかと拝見すると、そうなることはこの人の幸福な道でない。国家の柱石になって帝王の輔佐をする人として見てもまた違うようです」 と言った。 |
"Kuni no oya to nari te, teiwau no kami naki kurawi ni noboru beki sau ohasimasu hito no, sonata nite mire ba, midare urehuru koto ya ara m? Ohoyake no katame to nari te, amenosita wo tasukuru kata nite mire ba, mata sono sau tagahu besi." to ihu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.3 | 弁も、いと才かしこき 博士にて、言ひ交はしたることどもなむ、いと興ありける。 文など作り交はして、今日明日帰り去りなむとするに、 かくありがたき人に対面したるよろこび、 かへりては悲しかるべき心ばへをおもしろく作りたるに、御子もいとあはれなる句を作りたまへるを、限りなうめでたてまつりて、いみじき贈り物どもを捧げたてまつる。朝廷よりも多くの物賜はす。 |
右大弁も、たいそう優れた学識人なので、語り合った事柄は、たいへんに興味深いものであった。漢詩文などを作り交わして、今日明日のうちにも帰国する時に、このようにめったにない人に対面した喜びや、かえって悲しい思いがするにちがいないという気持ちを趣き深く作ったのに対して、御子もたいそう心を打つ詩句をお作りになったので、この上なくお褒め申して、素晴らしいいくつもの贈物を差し上げる。朝廷からもたくさんの贈物を御下賜なさる。 |
弁も漢学のよくできる官人であったから、筆紙をもってする高麗人との問答にはおもしろいものがあった。詩の贈答もして高麗人はもう日本の旅が終わろうとする期に臨んで珍しい高貴の相を持つ人に逢ったことは、今さらにこの国を離れがたくすることであるというような意味の作をした。若宮も送別の意味を詩にお作りになったが、その詩を非常にほめていろいろなその国の贈り物をしたりした。 朝廷からも高麗の相人へ多くの下賜品があった。 |
Ben mo, ito zae kasikoki hakase nite, ihi-kahasi taru kotodomo nam, ito kyou ari keru. Humi nado tukuri kahasi te, kehu asu kaheri-sari na m to suru ni, kaku arigataki hito ni taimen si taru yorokobi, kaherite ha kanasikaru beki kokorobahe wo omosiroku tukuri taru ni, Miko mo ito ahare naru ku wo tukuri tamahe ru wo, kagiri nau mede tatematuri te, imiziki okurimono-domo wo sasage tatematuru. Ohoyake yori mo ohoku no mono tamahasu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.4 | おのづから事広ごりて、漏らさせたまはねど、 春宮の祖父大臣など、いかなることにかと 思し疑ひてなむありける。 |
自然と噂が広がって、お漏らしあそばさないが、東宮の祖父大臣などは、どのようなわけでかとお疑いになっているのであった。 |
その評判から東宮の外戚の右大臣などは第二の皇子と高麗の相人との関係に疑いを持った。好遇された点が腑に落ちないのである。 |
Onodukara koto hirogori te, morasa se tamaha ne do, Touguu no ohodi Otodo nado, ikanaru koto ni ka to obosi-utagahi te nam ari keru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.5 | 帝、かしこき御心に、 倭相を仰せて、思しよりにける筋なれば、今まで この君を親王にも なさせたまはざりけるを、「 相人はまことにかしこかりけり」と思して、「 無品の親王の外戚の寄せなきにては漂はさじ。 わが御世もいと定めなきを、 ただ人にて朝廷の御後見をするなむ、行く先も頼もしげなめること」と思し定めて、いよいよ道々の才を習はさせたまふ。 |
帝は、畏れ多い考えから、倭相をお命じになって、既にお考えになっていたところなので、今までこの若君を親王にもなさらなかったが、「相人はほんとうに優れていた」とお思いになって、「無品の親王で外戚の後見のない状態で彷徨わすまい。わが御代もいつまで続くか分からないものだから、臣下として朝廷のご補佐役をするのが、将来も頼もしそうに思われることだ」とお決めになって、ますます諸道の学問を習わせなさる。 |
聡明な帝は高麗人の言葉以前に皇子の将来を見通して、幸福な道を選ぼうとしておいでになった。それでほとんど同じことを占った相人に価値をお認めになったのである。四品以下の無品親王などで、心細い皇族としてこの子を置きたくない、自分の代もいつ終わるかしれぬのであるから、将来に最も頼もしい位置をこの子に設けて置いてやらねばならぬ、臣下の列に入れて国家の柱石たらしめることがいちばんよいと、こうお決めになって、以前にもましていろいろの勉強をおさせになった。 |
Mikado, kasikoki mi-kokoro ni, yamatosau wo ohose te, obosiyori ni keru sudi nare ba, ima made kono Kimi wo miko ni mo nasa se tamaha zari keru wo, "Saunin ha makotoni kasikokari keri." to obosi te, "Mu-hon-no-sinwau no gesyaku no yose naki nite ha tadayohasa zi. Waga mi-yo mo ito sadamenaki wo, tadaudo nite ohoyake no ohom-usiromi wo suru nam, yukusaki mo tanomosige nameru koto." to obosi-sadame te, iyoiyo mitimiti no zae wo narahasa se tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.6 | 際ことに賢くて、ただ人にはいとあたらしけれど、親王となりたまひなば、 世の疑ひ負ひたまひぬべくものしたまへば、 宿曜の賢き道の人に勘へさせたまふにも、 同じさまに申せば、 源氏になしたてまつるべく思しおきてたり。 |
才能は格別聡明なので、臣下とするにはたいそう惜しいけれど、親王とおなりになったら、世間の人から立坊の疑いを持たれるにちがいなさそうにいらっしゃるので、宿曜道の優れた人に占わせなさっても、同様に申すので、源氏にして上げるのがよいとお決めになっていた。 |
大きな天才らしい点の現われてくるのを御覧になると人臣にするのが惜しいというお心になるのであったが、親王にすれば天子に変わろうとする野心を持つような疑いを当然受けそうにお思われになった。上手な運命占いをする者にお尋ねになっても同じような答申をするので、元服後は源姓を賜わって源氏の某としようとお決めになった。 |
Kiha kotoni kasikoku te, tadaudo ni ha ito atarasikere do, miko to nari tamahi na ba, yo no utagahi ohi tamahi nu beku monosi tamahe ba, sukuyeu no kasikoki miti no hito ni kamgahe sase tamahu ni mo, onazi sama ni mause ba, Genzi ni nasi tatematuru beku obosi-okite tari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4 | 第四段 先帝の四宮(藤壺)入内 |
3-4 Fujitsubo enters the Court |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.1 | 年月に添へて、御息所の御ことを思し忘るる折なし。「 慰むや」と、 さるべき人びと参らせたまへど、「 なずらひに思さるるだにいとかたき世かな」と、疎ましうのみよろづに思しなりぬるに、 先帝の四の宮の、御容貌すぐれたまへる聞こえ高くおはします、母后世になく かしづききこえたまふを、主上にさぶらふ典侍は、先帝の御時の人にて、かの宮にも親しう参り馴れたりければ、いはけなくおはしましし時より見たてまつり、今もほの見たてまつりて、 |
年月がたつにつれて、御息所のことをお忘れになる折がない。「心慰めることができようか」と、しかるべき婦人方をお召しになるが、「せめて準ずる程に思われなさる人さえめったにいない世の中だ」と、厭わしいばかりに万事が思し召されていたところ、先帝の四の宮で、ご容貌が優れておいでであるという評判が高くいらっしゃる方で、母后がまたとなく大切にお世話申されていられる方を、主上にお仕えする典侍は、先帝の御代からの人で、あちらの宮にも親しく参って馴染んでいたので、ご幼少でいらっしゃった時から拝見し、今でもちらっと拝見して、 |
年月がたっても帝は桐壼の更衣との死別の悲しみをお忘れになることができなかった。慰みになるかと思召して美しい評判のある人などを後宮へ召されることもあったが、結果はこの世界には故更衣の美に準ずるだけの人もないのであるという失望をお味わいになっただけである。そうしたころ、先帝−帝の従兄あるいは叔父君−の第四の内親王でお美しいことをだれも言う方で、母君のお后が大事にしておいでになる方のことを、帝のおそばに奉仕している典侍は先帝の宮廷にいた人で、后の宮へも親しく出入りしていて、内親王の御幼少時代をも知り、現在でもほのかにお顔を拝見する機会を多く得ていたから、帝へお話しした。 |
Tosituki ni sohe te, Miyasumdokoro no ohom-koto wo obosi-wasururu wori nasi. "Nagusamu ya?" to, sarubeki hitobito mawira se tamahe do, "Nazurahi ni obosa ruru dani ito kataki yo kana!" to, utomasiu nomi yorodu ni obosi-nari nuru ni, Sendai no Si-no-miya no, ohom-katati sugure tamahe ru kikoye takaku ohasimasu, Haha-gisaki yoni naku kasiduki kikoye tamahu wo, Uhe ni saburahu Naisi-no-suke ha, Sendai no ohom-toki no hito nite, kano miya ni mo sitasiu mawiri nare tari kere ba, ihakenaku ohasimasi si toki yori mi tatematuri, ima mo hono-mi tatematuri te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.2 | 「 亡せたまひにし御息所の御容貌に似たまへる人を、 三代の宮仕へに 伝はりぬるに、 え見たてまつりつけぬを、后の宮の姫宮こそ、いとようおぼえて生ひ出でさせたまへりけれ。ありがたき御容貌人になむ」と奏しけるに、「 まことにや」と、御心とまりて、 ねむごろに聞こえさせたまひけり。 |
「お亡くなりになった御息所のご容貌に似ていらっしゃる方を、三代の帝にわたって宮仕えいたしてまいりまして、一人も拝見できませんでしたが、后の宮の姫宮さまは、たいそうよく似てご成長あそばしていますわ。世にもまれなご器量よしのお方でございます」と奏上したところ、「ほんとうにか」と、お心が止まって、丁重に礼を尽くしてお申し込みあそばしたのであった。 |
「お亡れになりました御息所の御容貌に似た方を、三代も宮廷におりました私すらまだ見たことがございませんでしたのに、后の宮様の内親王様だけがあの方に似ていらっしゃいますことにはじめて気がつきました。非常にお美しい方でございます」 もしそんなことがあったらと大御心が動いて、先帝の后の宮へ姫宮の御入内のことを懇切にお申し入れになった。 |
"Use tamahi ni si Miyasumdokoro no ohom-katati ni ni tamahe ru hito wo, sam-dai no miyadukahe ni tutahari nuru ni, e mi tatematuri tuke nu wo, Kisai-no-miya no Himemiya koso, ito you oboye te ohi-ide sase tamahe ri kere. Arigataki ohom-katatibito ni nam." to sousi keru ni, "Makoto ni ya?" to, mi-kokoro tomari te, nemgoro ni kikoye sase tamahi keri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.3 | 母后、「 あな恐ろしや。 春宮の女御のいとさがなくて、 桐壺の更衣の、あらはにはかなくもてなされにし例もゆゆしう」と、思しつつみて、すがすがしうも思し立たざりけるほどに、后も亡せたまひぬ。 |
母后は、「まあ怖いこと。東宮の母女御がたいそう意地が悪くて、桐壺の更衣が、露骨に亡きものにされてしまった例も不吉で」と、おためらいなさって、すらすらとご決心もつかなかったうちに、母后もお亡くなりになってしまった。 |
お后は、そんな恐ろしいこと、東宮のお母様の女御が並みはずれな強い性格で、桐壷の更衣が露骨ないじめ方をされた例もあるのに、と思召して話はそのままになっていた。そのうちお后もお崩れになった。 |
Haha-gisaki, "Ana osorosi ya! Touguu-no-nyougo no ito saganaku te, Kiritubo-no-kaui no, araha ni hakanaku motenasa re ni si tamesi mo yuyusiu." to, obosi-tutumi te, sugasugasiu mo obosi-tata zari keru hodo ni, Kisaki mo use tamahi nu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.4 | 心細きさまにておはしますに、「 ただ、わが女皇女たちの同じ列に思ひきこえむ」と、いとねむごろに聞こえさせたまふ。さぶらふ人びと、御後見たち、御兄の 兵部卿の親王など、「 かく心細くておはしまさむよりは、内裏住みせさせたまひて、御心も慰むべく」など思しなりて、参らせたてまつりたまへり。 |
心細い有様でいらっしゃるので、「ただ、わが姫皇女たちと同列にお思い申そう」と、たいそう丁重に礼を尽くしてお申し上げあそばす。お仕えする女房たちや、御後見人たち、ご兄弟の兵部卿の親王などは、「こうして心細くおいでになるよりは、内裏でお暮らしあそばして、きっとお心が慰むように」などとお考えになって、参内させ申し上げなさった。 |
姫宮がお一人で暮らしておいでになるのを帝はお聞きになって、 「女御というよりも自分の娘たちの内親王と同じように思って世話がしたい」 となおも熱心に入内をお勧めになった。こうしておいでになって、母宮のことばかりを思っておいでになるよりは、宮中の御生活にお帰りになったら若いお心の慰みにもなろうと、お付きの女房やお世話係の者が言い、兄君の兵部卿親王もその説に御賛成になって、それで先帝の第四の内親王は当帝の女御におなりになった。 |
Kokoro-bosoki sama nite ohasimasu ni, "Tada, waga Womnamiko-tati no onazi tura ni omohi kikoye m." to, ito nemgoro ni kikoyesase tamahu. Saburahu hitobito, ohom-usiromi-tati, ohom-seuto no Hyaubukyau-no-miko nado, "Kaku kokorobosoku te ohasimasa m yori ha, utizumi se sase tamahi te, mi-kokoro mo nagusamu beku." nado obosi-nari te, mawira se tatematuri tamahe ri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.5 | 藤壺と聞こゆ。 げに、御容貌ありさま、あやしきまでぞおぼえたまへる。 これは、人の御際まさりて、思ひなしめでたく、人もえおとしめきこえたまはねば、うけばりて飽かぬことなし。 |
藤壺と申し上げる。なるほど、ご容貌や姿は 不思議なまでによく似ていらっしゃった。この方は、ご身分も一段と高いので、そう思って見るせいか素晴らしくて、お妃方もお貶み申すこともおできになれないので、誰に憚ることなく何も不足ない。 |
御殿は藤壼である。典侍の話のとおりに、姫宮の容貌も身のおとりなしも不思議なまで、桐壼の更衣に似ておいでになった。この方は御身分に批の打ち所がない。すべてごりっぱなものであって、だれも貶める言葉を知らなかった。 |
Huditubo to kikoyu. Geni, ohom-katati arisama, ayasiki made zo oboye tamahe ru. Kore ha, hito no ohom-kiha masari te, omohinasi medetaku, hito mo e otosime kikoye tamaha ne ba, ukebari te aka nu koto nasi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.6 | かれは、人の許しきこえざりしに、御心ざしあやにくなりしぞかし。 思し紛るとはなけれど、おのづから御心移ろひて、こよなう思し慰むやうなるも、あはれなるわざなりけり。 |
あの方は、周囲の人がお許し申さなかったところに、御寵愛が憎らしいと思われるほど深かったのである。ご愛情が紛れるというのではないが、自然とお心が移って行かれて、格段にお慰みになるようなのも、人情の性というものであった。 |
桐壼の更衣は身分と御愛寵とに比例の取れぬところがあった。お傷手が新女御の宮で癒されたともいえないであろうが、自然に昔は昔として忘れられていくようになり、帝にまた楽しい御生活がかえってきた。あれほどのこともやはり永久不変でありえない人間の恋であったのであろう。 |
Kare ha, hito no yurusi kikoye zari si ni, mi-kokorozasi ayaniku nari si zo kasi. Obosi-magiru to ha nakere do, onodukara mi-kokoro uturohi te, koyonau obosi-nagusamu yau naru mo, ahare naru waza nari keri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5 | 第五段 源氏、藤壺を思慕 |
3-5 Genji falls in love with Fujitsubo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5.1 | 源氏の君は、 御あたり去りたまはぬを、まして しげく渡らせたまふ御方は、え恥ぢあへたまはず。いづれの御方も、 われ人に劣らむと思いたるやはある、とりどりにいとめでたけれど、 うち大人びたまへるに、 いと若ううつくしげにて、切に隠れたまへど、 おのづから漏り見たてまつる。 |
源氏の君は、お側をお離れにならないので、誰より頻繁にお渡りあそばす御方は、恥ずかしがってばかりいらっしゃれない。どのお妃方も 自分が人より劣っていると思っていらっしゃる人があろうか、それぞれにとても素晴らしいが、お年を召しておいでになるのに対して、とても若くかわいらしい様子で、頻りにお姿をお隠しなさるが、自然と漏れ拝見する。 |
源氏の君−まだ源姓にはなっておられない皇子であるが、やがてそうおなりになる方であるから筆者はこう書く。−はいつも帝のおそばをお離れしないのであるから、自然どの女御の御殿へも従って行く。帝がことにしばしばおいでになる御殿は藤壼であって、お供して源氏のしばしば行く御殿は藤壼である。宮もお馴れになって隠れてばかりはおいでにならなかった。どの後宮でも容貌の自信がなくて入内した者はないのであるから、皆それぞれの美を備えた人たちであったが、もう皆だいぶ年がいっていた。その中へ若いお美しい藤壼の宮が出現されてその方は非常に恥ずかしがってなるべく顔を見せぬようにとなすっても、自然に源氏の君が見ることになる場合もあった。 |
Genzi-no-kimi ha, ohom-atari sari tamaha nu wo, masite sigeku watara se tamahu ohom-kata ha, e hadi-ahe tamaha zu. Idure no ohom-kata mo, ware hito ni otora m to oboi taru yaha aru, toridori ni ito medetakere do, uti-otonabi tamahe ru ni, ito wakau utukusige nite, seti ni kakure tamahe do, onodukara mori mi tatematuru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5.2 | 母御息所も、 影だにおぼえたまはぬを、「 いとよう似たまへり」と、典侍の聞こえけるを、若き御心地に いとあはれと思ひきこえたまひて、 常に参らまほしく、「なづさひ見たてまつらばや」とおぼえたまふ。 |
母御息所は、顔かたちすらご記憶でないのを、「大変によく似ていらっしゃる」と、典侍が申し上げたのを、幼心にとても慕わしいとお思い申し上げなさって、いつもお側に参りたく、「親しく拝見したい」と思われなさる。 |
母の更衣は面影も覚えていないが、よく似ておいでになると典侍が言ったので、子供心に母に似た人として恋しく、いつも藤壼へ行きたくなって、あの方と親しくなりたいという望みが心にあった。 |
Haha-Miyasumdokoro mo, kage dani oboye tamaha nu wo, "Ito you ni tamahe ri" to, Naisi-no-suke no kikoye keru wo, wakaki mi-kokoti ni ito ahare to omohi kikoye tamahi te, tune ni mawira mahosiku, "Nadusahi mi tatematura baya!" to oboye tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5.3 | 主上も限りなき 御思ひどちにて、「 な疎みたまひそ。あやしく よそへきこえつべき心地なむする。 なめしと思さで、らうたくしたまへ。 つらつき、まみなどは、いとよう似たりしゆゑ、 かよひて見えたまふも、 似げなからずなむ」など聞こえつけたまへれば、幼心地にも、はかなき花紅葉につけても心ざしを見えたてまつる。 こよなう心寄せきこえたまへれば、弘徽殿の女御、またこの宮とも御仲そばそばしきゆゑ、うち添へて、もとよりの憎さも立ち出でて、ものしと思したり。 |
主上もこの上なくおかわいがりのお二方なので、「お疎みなさいますな。不思議と若君の母君となぞらえ申してもよいような気持ちがする。失礼だとお思いなさらず、いとおしみなさい。顔だちや、目もとなど、大変によく似ているため、母君のようにお見えになるのも、母子として似つかわしくなくはない」などとお頼み申し上げなさっているので、幼心にも、ちょっとした花や紅葉にことつけても、お気持ちを表し申す。この上なく好意をお寄せ申していらっしゃるので、弘徽殿の女御は、またこの宮ともお仲が好ろしくないので、それに加えて、もとからの憎しみももり返して、不愉快だとお思いになっていた。 |
帝には二人とも最愛の妃であり、最愛の御子であった。 「彼を愛しておやりなさい。不思議なほどあなたとこの子の母とは似ているのです。失礼だと思わずにかわいがってやってください。この子の目つき顔つきがまたよく母に似ていますから、この子とあなたとを母と子と見てもよい気がします」 など帝がおとりなしになると、子供心にも花や紅葉の美しい枝は、まずこの宮へ差し上げたい、自分の好意を受けていただきたいというこんな態度をとるようになった。現在の弘徽殿の女御の嫉妬の対象は藤壼の宮であったからそちらへ好意を寄せる源氏に、一時忘れられていた旧怨も再燃して憎しみを持つことになった。 |
Uhe mo kagirinaki ohom-omohidoti nite, "Na utomi tamahi so. Ayasiku yosohe kikoye tu beki kokoti nam suru. Namesi to obosa de, rautaku si tamahe. Turatuki, mami nado ha, ito you ni tari si yuwe, kayohi te miye tamahu mo, nigenakara zu nam." nado kikoyetuke tamahe re ba, wosanagokoti ni mo, hakanaki hana momidi ni tuke te mo kokorozasi wo miye tatematuru. Koyonau kokoro-yose kikoye tamahe re ba, Koukiden-no-Nyougo, mata kono Miya to mo ohom-naka sobasobasiki yuwe, uti-sohe te, motoyori no nikusa mo tati-ide te, monosi to obosi tari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5.4 | 世にたぐひなしと 見たてまつりたまひ、 名高うおはする宮の御容貌にも、 なほ匂はしさはたとへむ方なく、うつくしげなるを、 世の人、「光る君」と聞こゆ。藤壺ならびたまひて、御おぼえもとりどりなれば、「 かかやく日の宮」と聞こゆ。 |
世の中にまたとないお方だと拝見なさり、評判高くおいでになる宮のご容貌に対しても、やはり照り映える美しさにおいては比較できないほど 美しそうなので、世の中の人は、「光る君」とお呼び申し上げる。藤壺もお並びになって、御寵愛がそれぞれに厚いので、「輝く日の宮」とお呼び申し上げる。 |
女御が自慢にし、ほめられてもおいでになる幼内親王方の美を遠くこえた源氏の美貌を世間の人は言い現わすために光の君と言った。女御として藤壼の宮の御寵愛が並びないものであったから対句のように作って、輝く日の宮と一方を申していた。 |
Yo ni taguhi nasi to mi tatematuri tamahi, nadakau ohasuru Miya no ohom-katati ni mo, naho nihohasisa ha tatohe m kata naku, utukusige naru wo, yonohito, "Hikarukimi" to kikoyu. Huditubo narabi tamahi te, ohom-oboye mo toridori nare ba, "Kakayakuhinomiya" to kikoyu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6 | 第六段 源氏元服(十二歳) |
3-6 Genji grows up (age 12) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6.1 | この君の御童姿、いと変へまうく思せど、 十二にて御元服したまふ。 居起ち思しいとなみて、限りある事に事を添へさせたまふ。 |
この君の御童子姿を、とても変えたくなくお思いであるが、十二歳で御元服をなさる。御自身お世話を焼かれて、作法どおりの上にさらにできるだけの事をお加えあそばす。 |
源氏の君の美しい童形をいつまでも変えたくないように帝は思召したのであったが、いよいよ十二の歳に元服をおさせになることになった。その式の準備も何も帝御自身でお指図になった。 |
Kono Kimi no ohom-warahasugata, ito kahe-ma-uku obose do, zihuni nite ohon-genpuku si tamahu. Wi-tati obosi-itonami te, kagiri aru koto ni koto wo sohe sase tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
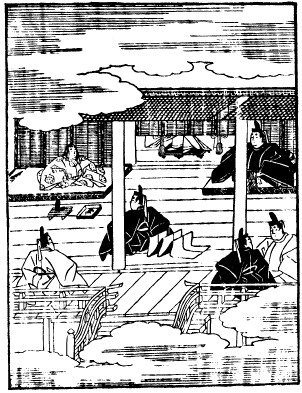 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6.2 | 一年の春宮の御元服、南殿にてありし 儀式、よそほしかりし御響きに落とさせたまはず。 所々の饗など、 内蔵寮、穀倉院など、公事に仕うまつれる、 おろそかなることもぞと、とりわき仰せ言ありて、清らを尽くして仕うまつれり。 |
先年の東宮の御元服が、紫宸殿で執り行われた儀式が、いかめしく立派であった世の評判にひけをおとらせにならない。各所での饗宴などにも、内蔵寮や 穀倉院など、規定どおり奉仕するのでは、行き届かないことがあってはいけないと、特別に勅命があって、善美を尽くしてお勤め申した。 |
前に東宮の御元服の式を紫宸殿であげられた時の派手やかさに落とさず、その日官人たちが各階級別々にさずかる饗宴の仕度を内蔵寮、穀倉院などでするのはつまり公式の仕度で、それでは十分でないと思召して、特に仰せがあって、それらも華麗をきわめたものにされた。 |
Hitotose no Touguu no ohon-genpuku, Naden nite ari si gisiki, yosohosikari si ohom-hibiki ni otosa se tamaha zu. Tokorodokoro no kyau nado, kuradukasa, kokusauwin nado, ohoyakegoto ni tukaumature ru, orosoka naru koto mozo to, toriwaki ohosegoto ari te, kiyora wo tukusi te tukaumature ri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6.3 | おはします殿の東の廂、東向きに椅子立てて、 冠者の御座、 引入の大臣の御座、 御前にあり。 申の時にて源氏参りたまふ。角髪結ひたまへるつらつき、顔のにほひ、さま変へたまはむこと惜しげなり。 大蔵卿、蔵人仕うまつる。いと清らなる御髪を削ぐほど、心苦しげなるを、主上は、「 御息所の見ましかば」と、思し出づるに、堪へがたきを、心強く念じかへさせたまふ。 |
おいでになる清涼殿の東廂の間に、東向きに椅子を立てて、元服なさる君のお席と 加冠役の大臣のお席とが、御前に設けられている。儀式は申の時で、その時刻に源氏が参上なさる。角髪に結っていらっしゃる顔つきや、童顔の色つやは、髪形をお変えになるのは惜しい感じである。大蔵卿が 理髪役を奉仕する。たいへん美しい御髪を削ぐ時、いたいたしそうなのを、主上は、「亡き母の御息所が見たならば」と、お思い出しになると、涙が抑えがたいのを、思い返してじっとお堪えあそばす。 |
清涼殿は東面しているが、お庭の前のお座敷に玉座の椅子がすえられ、元服される皇子の席、加冠役の大臣の席がそのお前にできていた。午後四時に源氏の君が参った。上で二つに分けて耳の所で輸にした童形の礼髪を結った源氏の顔つき、少年の美、これを永久に保存しておくことが不可能なのであろうかと惜しまれた。理髪の役は大蔵卿である。美しい髪を短く切るのを惜しく思うふうであった。帝は御息所がこの式を見たならばと、昔をお思い出しになることによって堪えがたくなる悲しみをおさえておいでになった。 |
Ohasimasu den no himgasi no hisasi, himgasi-muki ni isi tate te, kwanza no go-za, Hikiire-no-Otodo no go-za, o-mahe ni ari. Saru no toki nite Genzi mawiri tamahu. Midura yuhi tamahe ru turatuki, kaho no nihohi, sama kahe tamaha m koto wosige nari. Ohokurakyau, kurabito tukaumaturu. Ito kiyora naru mi-gusi wo sogu hodo, kokorogurusige naru wo, Uhe ha, "Miyasumdokoro no mi masika ba." to, obosi-iduru ni, tahe gataki wo, kokoro-duyoku nenzi-kahesa se tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6.4 | かうぶりしたまひて、御休所にまかでたまひて、 御衣奉り替へて、下りて拝したてまつりたまふさまに、皆人涙落としたまふ。 帝はた、ましてえ忍びあへたまはず、 思し紛るる折もありつる昔のこと、 とりかへし悲しく思さる。 いとかうきびはなるほどは、あげ劣りやと疑はしく思されつるを、あさましううつくしげさ添ひたまへり。 |
加冠なさって、御休息所にお下がりになって、ご装束をお召し替えなさって、東庭に下りて拝舞なさる様子に、一同涙を落としなさる。帝は帝で、誰にもまして堪えきれなされず、お悲しみの紛れる時もあった一時のことを、立ち返って悲しく思われなさる。たいそうこのように幼い年ごろでは、髪上げして見劣りをするのではないかと御心配なさっていたが、驚くほどかわいらしさも加わっていらっしゃった。 |
加冠が終わって、いったん休息所に下がり、そこで源氏は服を変えて庭上の拝をした。参列の諸員は皆小さい大宮人の美に感激の涙をこぼしていた。帝はまして御自制なされがたい御感情があった。藤壼の宮をお得になって以来、紛れておいでになることもあった昔の哀愁が今一度にお胸へかえって来たのである。まだ小さくて大人の頭の形になることは、その人の美を損じさせはしないかという御懸念もおありになったのであるが、源氏の君には今驚かれるほどの新彩が加わって見えた。 |
Kauburi si tamahi te, ohom-yasumidokoro ni makade tamahi te, ohom-zo tatematuri-kahe te, ori te haisi tatematuri tamahu sama ni, minahito namida otosi tamahu. Mikado hata, masite e sinobi-ahe tamaha zu, obosi-magiruru wori mo ari turu mukasi no koto, torikahesi kanasiku obosa ru. Ito kau kibiha naru hodo ha, ageotori ya to utagahasiku obosare turu wo, asamasiu utukusigesa sohi tamahe ri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6.5 | 引入の大臣の 皇女腹にただ一人かしづきたまふ御女、 春宮よりも御けしきあるを、 思しわづらふことありける、この君に奉らむの御心なりけり。 |
加冠役の大臣が皇女でいらっしゃる方との間に儲けた一人娘で大切に育てていらっしゃる姫君を、東宮からも御所望があったのを、ご躊躇なさることがあったのは、この君に差し上げようとのお考えからなのであった。 |
加冠の大臣には夫人の内親王との間に生まれた令嬢があった。東宮から後宮にとお望みになったのをお受けせずにお返辞を躊躇していたのは、初めから源氏の君の配偶者に擬していたからである。 |
Hikiire-no-Otodo no Miko-bara ni tada hitori kasiduki tamahu ohom-musume, Touguu yori mo mi-kesiki aru wo, obosi-wadurahu koto ari keru, kono Kimi ni tatematura m no mi-kokoro nari keri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6.6 | 内裏にも、 御けしき賜はらせたまへりければ、「 さらば、この折の後見なかめるを、添ひ臥しにも」と もよほさせたまひければ、さ思したり。 |
帝からの 御内意を頂戴させていただいたところ、「それでは、元服の後の後見する人がいないようなので、その添い臥しにでも」とお促しあそばされたので、そのようにお考えになっていた。 |
大臣は帝の御意向をも伺った。 「それでは元服したのちの彼を世話する人もいることであるから、その人をいっしょにさせればよい」 という仰せであったから、大臣はその実現を期していた。 |
Uti ni mo, mi-kesiki tamahara se tamahe ri kere ba, "Saraba, kono wori no usiromi naka' meru wo, sohibusi ni mo." to moyohosa se tamahi kere ba, sa obosi tari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6.7 | さぶらひにまかでたまひて、人びと 大御酒など参るほど、親王たちの御座の末に源氏着きたまへり。 大臣気色ばみきこえたまふことあれど、 もののつつましきほどにて、ともかくもあへしらひきこえたまはず。 |
御休息所に退出なさって、参会者たちが御酒などをお召し上がりになる時に、親王方のお席の末席に源氏はお座りになった。大臣がそれとなく仄めかし申し上げなさることがあるが、気恥ずかしい年ごろなので、どちらともはっきりお答え申し上げなさらない。 |
今日の侍所になっている座敷で開かれた酒宴に、親王方の次の席へ源氏は着いた。娘の件を大臣がほのめかしても、きわめて若い源氏は何とも返辞をすることができないのであった。 |
Saburahi ni makade tamahi te, hitobito ohomiki nado mawiru hodo, mikotati no ohom-za no suwe ni Genzi tuki tamahe ri. Otodo kesikibami kikoye tamahu koto are do, mono no tutumasiki hodo nite, tomokakumo ahe-sirahi kikoye tamaha zu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6.8 | 御前より、 内侍、宣旨うけたまはり伝へて、大臣参りたまふべき召しあれば、参りたまふ。御禄の物、主上の命婦取りて賜ふ。白き大袿に御衣一領、例のことなり。 |
御前から 掌侍が 宣旨を承り伝えて、大臣に御前に参られるようにとのお召しがあるので、参上なさる。御禄の品物を、主上づきの命婦が取りついで賜わる。白い大袿に御衣装一領、例のとおりである。 |
帝のお居間のほうから仰せによって内侍が大臣を呼びに来たので、大臣はすぐに御前へ行った。加冠役としての下賜品はおそばの命婦が取り次いだ。白い大袿に帝のお召し料のお服が一襲で、これは昔から定まった品である。 |
O-mahe yori, Naisi, senzi uketamahari tutahe te, Otodo mawiri tamahu beki mesi are ba, mawiri tamahu. Ohom-roku no mono, Uhe-no-Myaubu tori te tamahu. Siroki ohoutiki ni ohom-zo hito-kudari, rei no koto nari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6.9 | 御盃のついでに、 |
お盃を賜る折に、 |
酒杯を賜わる時に、次の歌を仰せられた。 |
Ohom-sakaduki no tuide ni, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6.10 | 「 いときなき初元結ひに長き世を 契る心は結びこめつや」 |
「幼子の元服の折、末永い仲を そなたの姫との間に結ぶ約束はなさったか」 |
いときなき初元結ひに長き世を 契る心は結びこめつや |
"Itokinaki hatu-motoyuhi ni nagaki yo wo tigiru kokoro ha musubi kome tu ya? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6.11 | 御心ばへありて、 おどろかさせたまふ。 |
お心づかいを示されて、はっとさせなさる。 |
大臣の女との結婚にまでお言い及ぼしになった御製は大臣を驚かした。 |
Mi-kokorobahe ari te, odoroka sase tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6.12 | 「 結びつる心も深き元結ひに 濃き紫の色し褪せずは」 |
「元服の折、約束した心も深いものとなりましょう その濃い紫の色さえ変わらなければ」 |
結びつる心も深き元結ひに 濃き紫の色しあせずば |
"Musubi turu kokoro mo hukaki motoyuhi ni koki murasaki no iro si ase zuha! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6.13 | と奏して、 長橋より下りて舞踏したまふ。 |
と奏上して、長橋から下りて拝舞なさる。 |
と返歌を奏上してから大臣は、清涼殿の正面の階段を下がって拝礼をした。 |
to sousi te, nagahasi yori ori te butahu si tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6.14 | 左馬寮の御馬、蔵人所の鷹据ゑて 賜はりたまふ。 御階のもとに親王たち上達部つらねて、禄ども品々に 賜はりたまふ。 |
左馬寮の御馬、蔵人所の鷹を留まり木に据えて頂戴なさる。御階のもとに親王方や上達部が立ち並んで、禄をそれぞれの身分に応じて頂戴なさる。 |
左馬寮の御馬と蔵人所の鷹をその時に賜わった。そのあとで諸員が階前に出て、官等に従ってそれぞれの下賜品を得た。 |
Hidari-no-tukasa no ohom-muma, kuraudo-dokoro no taka suwe te tamahari tamahu. Mi-hasi no moto ni mikotati kamdatime turane te, roku-domo sinazina ni tamahari tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6.15 | その日の御前の折櫃物、籠物など、 右大弁なむ承りて仕うまつらせける。屯食、禄の唐櫃どもなど、ところせきまで、春宮の御元服の折にも数まされり。 なかなか限りもなくいかめしうなむ。 |
その日の御前の折櫃物や、籠物などは、右大弁が仰せを承って調えさせたのであった。屯食や 禄用の唐櫃類など、置き場もないくらいで、東宮の御元服の時よりも数多く勝っていた。かえっていろいろな制限がなくて盛大であった。 |
この日の御饗宴の席の折り詰めのお料理、籠詰めの菓子などは皆右大弁が御命令によって作った物であった。一般の官吏に賜う弁当の数、一般に下賜される絹を入れた箱の多かったことは、東宮の御元服の時以上であった。 |
Sono hi no o-mahe no woribitumono, komono nado, U-daiben nam uketamahari te tukaumatura se keru. Tonziki, roku no karabitu-domo nado, tokoroseki made, Touguu no ohon-genpuku no wori ni mo kazu masare ri. Nakanaka kagiri mo naku ikamesiu nam. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.7 | 第七段 源氏、左大臣家の娘(葵上)と結婚 |
3-7 Genji gets married to Sadaijin's daughter |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.7.1 | その夜、大臣の御里に源氏の君 まかでさせたまふ。 作法世にめづらしきまで、もてかしづききこえたまへり。いときびはにておはしたるを、ゆゆしううつくしと思ひきこえたまへり。女君は すこし過ぐしたまへるほどに、 いと若うおはすれば、 似げなく恥づかしと 思いたり。 |
その夜、大臣のお邸に源氏の君を退出させなさる。婿取りの儀式は世に例がないほど 立派におもてなし申し上げなさった。とても若くおいでなのを、不吉なまでにかわいいとお思い申し上げなさった。女君は少し年長でおいでなのに対して、婿君がたいそうお若くいらっしゃるので、似つかわしくなく恥ずかしいとお思いでいらっしゃった。 |
その夜源氏の君は左大臣家へ婿になって行った。この儀式にも善美は尽くされたのである。高貴な美少年の婿を大臣はかわいく思った。姫君のほうが少し年上であったから、年下の少年に配されたことを、不似合いに恥ずかしいことに思っていた。 |
Sono yo, Otodo no ohom-sato ni Genzi-no-kimi makade sase tamahu. Sahohu yo ni medurasiki made, mote-kasiduki kikoye tamahe ri. Ito kibiha nite ohasi taru wo, yuyusiu utukusi to omohi kikoye tamahe ri. Womnagimi ha sukosi sugusi tamahe ru hodo ni, ito wakau ohasure ba, nigenaku hadukasi to oboi tari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.7.2 | この大臣の御おぼえいとやむごとなきに、 母宮、内裏の一つ后腹になむおはしければ、 いづ方につけても いとはなやかなるに、この君さへ かくおはし添ひぬれば、春宮の御祖父にて、つひに世の中を知りたまふべき右大臣の御勢ひは、 ものにもあらず圧されたまへり。 |
この大臣は帝のご信任が厚い上に、姫君の母宮が 帝と同じ母后のお生まれでいらっしゃったので、どちらから言っても立派な上に、この君までがこのように婿君としてお加わりになったので、東宮の御祖父で、最後には天下を支配なさるはずの右大臣のご威勢も、敵ともなく圧倒されてしまった。 |
この大臣は大きい勢力を持った上に、姫君の母の夫人は帝の御同胞であったから、あくまでもはなやかな家である所へ、今度また帝の御愛子の源氏を婿に迎えたのであるから、東宮の外祖父で未来の関白と思われている右大臣の勢カは比較にならぬほど気押されていた。 |
Kono Otodo no ohom-oboye ito yamgotonaki ni, Hahamiya, Uti no hito-tu-kisaibara ni nam ohasi kere ba, idukata ni tuke te mo ito hanayaka naru ni, kono Kimi sahe kaku ohasi sohi nure ba, Touguu no ohom-ohodi nite, tuhini yononaka wo siri tamahu beki Migi-no-otodo no ohom-ikihohi ha, mono ni mo ara zu osa re tamahe ri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.7.3 | 御子どもあまた腹々にものしたまふ。 宮の御腹は、蔵人少将にて いと若うをかしきを、 右大臣の、御仲はいと好からねど、え見過ぐしたまはで、かしづきたまふ 四の君にあはせたまへり。 劣らずもてかしづきたるは、あらまほしき 御あはひどもになむ。 |
ご子息たちが大勢それぞれの夫人方にいらっしゃる。宮がお生みの方は、蔵人少将でたいそう若く美しい方なので、右大臣が、左大臣家とのお間柄はあまりよくないが、他人として放っておくこともおできになれず、大切になさっている四の君に婿取りなさっていた。劣らず大切にお世話なさっているのは、両家とも理想的な婿舅の間柄である。 |
左大臣は何人かの妻妾から生まれた子供を幾人も持っていた。内親王腹のは今蔵人少将であって年少の美しい貴公子であるのを左右大臣の仲はよくないのであるが、その蔵人少将をよその者に見ていることができず、大事にしている四女の婿にした。これも左大臣が源氏の君をたいせつがるのに劣らず右大臣から大事な婿君としてかしずかれていたのはよい一対のうるわしいことであった。 |
Miko-domo amata harabara ni monosi tamahu. Miya no ohom-hara ha, Kuraudo-no-seusyau nite ito wakau wokasiki wo, Migi-no-otodo no, ohom-naka ha ito yokara ne do, e mi-sugusi tamaha de, kasiduki tamahu Si-no-kimi ni ahase tamahe ri. Otora zu mote-kasiduki taru ha, aramahosiki ohom-ahahi-domo ni nam. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.7.4 | 源氏の君は、主上の常に召しまつはせば、心安く里住みもえしたまはず。心のうちには、ただ藤壺の御ありさまを、類なしと思ひきこえて、「 さやうならむ人をこそ見め。似る人なくもおはしけるかな。大殿の君、いとをかしげにかしづかれたる人とは見ゆれど、心にもつかず」おぼえたまひて、幼きほどの心一つにかかりて、 いと苦しきまでぞおはしける。 |
源氏の君は、主上がいつもお召しになって放さないので、気楽に私邸で過すこともおできになれない。心中では、ひたすら藤壺のご様子を、またといない方とお慕い申し上げて、「そのような女性こそ妻にしたいものだ。似た方もいらっしゃらないな。大殿の姫君は、たいそう興趣ありそうに大切に育てられている方だと思われるが、少しも心惹かれない」というように感じられて、幼心一つに思いつめて、とても苦しいまでに悩んでいらっしゃるのであった。 |
源氏の君は帝がおそばを離しにくくあそばすので、ゆっくりと妻の家に行っていることもできなかった。源氏の心には藤壼の宮の美が最上のものに思われてあのような人を自分も妻にしたい、宮のような女性はもう一人とないであろう、左大臣の令嬢は大事にされて育った美しい貴族の娘とだけはうなずかれるがと、こんなふうに思われて単純な少年の心には藤壼の宮のことばかりが恋しくて苦しいほどであった。 |
Genzi-no-kimi ha, Uhe no tune ni mesi-matuhase ba, kokoro-yasuku satozumi mo e si tamaha zu. Kokoro no uti ni ha, tada Huditubo no ohom-arisama wo, taguhinasi to omohi kikoye te, "Sayau nara m hito wo koso mi me. Niru hito naku mo ohasi keru kana! Ohoidono-no-kimi, ito wokasige ni kasiduka re taru hito to ha miyure do, kokoro ni mo tuka zu." oboye tamahi te, wosanaki hodo no kokoro hito-tu ni kakari te, ito kurusiki made zo ohasi keru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.8 | 第八段 源氏、成人の後 |
3-8 Genji's life |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.8.1 | 大人になりたまひて後は、 ありしやうに御簾の内にも入れたまはず。御遊びの折々、 琴笛の音に聞こえかよひ、 ほのかなる御声を慰めにて、内裏住みのみ好ましうおぼえたまふ。五六日さぶらひたまひて、大殿に二三日など、絶え絶えにまかでたまへど、ただ今は幼き御ほどに、 罪なく思しなして、いとなみかしづききこえたまふ。 |
元服なさってから後は、かつてのように御簾の内側にもお入れにならない。管弦の御遊の時々、琴と笛の音に心通わし合い、かすかに漏れてくるお声を慰めとして、内裏の生活ばかりを好ましく思っていらっしゃる。五、六日は内裏に伺候なさって、大殿邸には二、三日程度、途切れ途切れに退出なさるが、まだ今はお若い年頃であるので、つとめて咎めだてすることなくお許しになって、婿君として大切にお世話申し上げなさる。 |
元服後の源氏はもう藤壼の御殿の御簾の中へは入れていただけなかった。琴や笛の音の中にその方がお弾きになる物の声を求めるとか、今はもう物越しにより聞かれないほのかなお声を聞くとかが、せめてもの慰めになって宮中の宿直ばかりが好きだった。五、六日御所にいて、二、三日大臣家へ行くなど絶え絶えの通い方を、まだ少年期であるからと見て大臣はとがめようとも思わず、相も変わらず婿君のかしずき騒ぎをしていた。 |
Otona ni nari tamahi te noti ha, arisi yau ni mi-su no uti ni mo ire tamaha zu. Ohom-asobi no woriwori, koto hue no ne ni kikoye kayohi, honoka naru ohom-kowe wo nagusame nite, utizumi nomi konomasiu oboye tamahu. Itu-ka muyi-ka saburahi tamahi te, Ohoidono ni hutu-ka mi-ka nado, tayedaye ni makade tamahe do, tada ima ha wosanaki ohom-hodo ni, tumi naku obosi-nasi te, itonami kasiduki kikoye tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.8.2 | 御方々の人びと、世の中におしなべたらぬを選りととのへすぐりて さぶらはせたまふ。 御心につくべき御遊びをし、 おほなおほな思しいたつく。 |
お二方の女房たちは、世間から並々でない人たちをえりすぐってお仕えさせなさる。お気に入りそうなお遊びをし、せいいっぱいにお世話していらっしゃる。 |
新夫婦付きの女房はことにすぐれた者をもってしたり、気に入りそうな遊びを催したり、一所懸命である。 |
Ohom-katagata no hitobito, yononaka ni osinabe tara nu wo eri totonohe suguri te saburaha se tamahu. Mi-kokoro ni tuku beki ohom-asobi wo si, ohonaohona obosi itatuku. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.8.3 | 内裏には、もとの淑景舎を御曹司にて、母御息所の御方の人びと まかで散らずさぶらはせたまふ。 |
内裏では、もとの淑景舎をお部屋にあてて、母御息所にお仕えしていた女房を退出して散り散りにさせずに引き続いてお仕えさせなさる。 |
御所では母の更衣のもとの桐壼を源氏の宿直所にお与えになって、御息所に侍していた女房をそのまま使わせておいでになった。 |
Uti ni ha, moto no Sigeisa wo ohom-zausi nite, Haha-miyasumdokoro no ohom-kata no hitobito makade tira zu saburaha se tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.8.4 | 里の殿は、修理職、内匠寮に宣旨下りて、二なう改め造らせたまふ。もとの木立、山のたたずまひ、 おもしろき所なりけるを、池の心広くしなして、めでたく造りののしる。 |
実家のお邸は、修理職や 内匠寮に宣旨が下って、またとなく立派にご改造させなさる。もとからの木立や、築山の様子、趣きのある所であったが、池をことさら広く造って、大騷ぎして立派に造営する。 |
更衣の家のほうは修理の役所、内匠寮などへ帝がお命じになって、非常なりっぱなものに改築されたのである。もとから築山のあるよい庭のついた家であったが、池なども今度はずっと広くされた。二条の院はこれである。 |
Sato no tono ha, surisiki, takumi-dukasa ni senzi kudari te, ninau aratame tukura se tamahu. Moto no kodati, yama no tatazumahi, omosiroki tokoro nari keru wo, ike no kokoro hiroku sinasi te, medetaku tukuri nonosiru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.8.5 | 「 かかる所に思ふやうならむ人を据ゑて住まばや」と のみ、嘆かしう思しわたる。 |
「このような所に理想とするような女性を迎えて一緒に暮らしたい」とばかり、胸を痛めてお思い続けていらっしゃる。 |
源氏はこんな気に入った家に自分の理想どおりの妻と暮らすことができたらと思って始終歎息をしていた。 |
"Kakaru tokoro ni omohu yau nara m hito wo suwe te suma baya!" to nomi, nagekasiu obosi wataru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.8.6 | 「 光る君といふ名は、高麗人のめできこえてつけたてまつりける」とぞ、言ひ伝へたるとなむ。 |
「光る君という名前は、高麗人がお褒め申してお付けしたものだ」と、言い伝えているとのことである。 |
光の君という名は前に鴻臚館へ来た高麗人が、源氏の美貌と天才をほめてつけた名だとそのころ言われたそうである。 |
"Hikarukimi to ihu na ha, Komaudo no mede kikoye te tuke tatematuri keru." to zo, ihitutahe taru to nam. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last updated 12/05/2008(ver.2-1) 渋谷栄一校訂(C) Last updated 12/29/2008(ver.2-1) 渋谷栄一注釈 |
Last updated 6/25/2003 渋谷栄一訳(C)(ver.1-4-1) |
|
Last updated 12/13/2008 (ver.2-1) Written in Japanese roman letters by Eiichi Shibuya (C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Picture "Eiri Genji Monogatari"(1650 1st edition) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源氏物語の世界 再編集プログラム Ver 3.38: Copyright (c) 2003,2015 宮脇文経