第五帖 若紫 |
05 WAKAMURASAKI (Ohoshima-bon) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光る源氏の十八歳春三月晦日から冬十月までの物語 |
Tale of Hikaru-Genji's Konoe-Chujo era from the last day in spring to October in winter at the age of 18 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 第二章 藤壺の物語 夏の密通と妊娠の苦悩物語 |
2 Tale of Fujitsubo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1 | 第一段 夏四月の短夜の密通事件 |
2-1 In a summer short night, Genji meets with Fujitsubo secretly |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.1 | 藤壺の宮、悩みたまふことありて、 まかでたまへり。上の、おぼつかながり、嘆ききこえたまふ御気色も、 いといとほしう見たてまつりながら、 かかる折だにと、心もあくがれ惑ひて、 何処にも何処にも、まうでたまはず、内裏にても里にても、昼は つれづれと眺め暮らして、暮るれば、 王命婦を責め歩きたまふ。 |
藤壺の宮に、ご不例の事があって、ご退出された。主上が、お気をもまれ、ご心配申し上げていらっしゃるご様子も、まことにおいたわしく拝見しながらも、せめてこのような機会にもと、魂も浮かれ出て、どこにもかしこにも お出かけにならず、内裏にいても里邸にいても、昼間は所在なくぼうっと物思いに沈んで、夕暮れになると、王命婦にあれこれとおせがみになる。 |
藤壼の宮が少しお病気におなりになって宮中から自邸へ退出して来ておいでになった。帝が日々恋しく思召す御様子に源氏は同情しながらも、稀にしかないお実家住まいの機会をとらえないではまたいつ恋しいお顔が見られるかと夢中になって、それ以来どの恋人の所へも行かず宮中の宿直所ででも、二条の院ででも、昼間は終日物思いに暮らして、王命婦に手引きを迫ることのほかは何もしなかった。 |
Huditubonomiya, nayami tamahu koto ari te, makade tamahe ri. Uhe no, obotukanagari, nageki kikoye tamahu mikesiki mo, ito itohosiu mi tatematuri nagara, kakaru wori dani to, kokoro mo akugare madohi te, iduku ni mo iduku ni mo, maude tamaha zu, Uti nite mo sato nite mo, hiru ha turedure to nagame kurasi te, kurure ba, Waumyaubu wo seme ariki tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.2 | いかがたばかりけむ、いとわりなくて見たてまつるほどさへ、現とはおぼえぬぞ、 わびしきや。 |
どのように手引したのだろうか、とても無理してお逢い申している間さえ、現実とは思われないのは、辛いことであるよ。 |
王命婦がどんな方法をとったのか与えられた無理なわずかな逢瀬の中にいる時も、幸福が現実の幸福とは思えないで夢としか思われないのが、源氏はみずから残念であった。 |
Ikaga tabakari kem, ito warinaku te mi tatematuru hodo sahe, ututu to ha oboye nu zo, wabisiki ya! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.3 | 宮も、あさましかりしを思し出づるだに、世とともの御もの思ひなるを、 さてだにやみなむと 深う思したるに、 いと憂くて、 いみじき御気色なるものから、なつかしうらうたげに、 さりとてうちとけず、心深う恥づかしげなる御もてなしなどの、 なほ人に似させたまはぬを、「 などか、 なのめなることだにうち交じりたまはざりけむ」と、 つらうさへぞ思さるる。 |
宮も、思いもしなかった出来事をお思い出しになるだけでも、生涯忘れることのできないお悩みの種なので、せめてそれきりで終わりにしたいと深く決心されていたのに、とても情けなくて、ひどく辛そうなご様子でありながらも、優しくいじらしくて、そうかといって馴れ馴れしくなく、奥ゆかしく気品のある御物腰などが、やはり普通の女人とは違っていらっしゃるのを、「どうして、わずかの欠点すら少しも混じっていらっしゃらなかったのだろう」と、辛くまでお思いになられる。 |
宮も過去のある夜の思いがけぬ過失の罪悪感が一生忘れられないもののように思っておいでになって、せめてこの上の罪は重ねまいと深く思召したのであるのに、またもこうしたことを他動的に繰り返すことになったのを悲しくお思いになって、恨めしいふうでおありになりながら、柔らかな魅力があって、しかも打ち解けておいでにならない最高の貴女の態度が美しく思われる源氏は、やはりだれよりもすぐれた女性である、なぜ一所でも欠点を持っておいでにならないのであろう、それであれば自分の心はこうして死ぬほどにまで惹かれないで楽であろうと思うと源氏はこの人の存在を自分に知らせた運命さえも恨めしく思われるのである。 |
Miya mo, asamasikari si wo obosi iduru dani, yo to tomo no ohom-monoomohi naru wo, sate dani yami na m to hukau obosi taru ni, ito uku te, imiziki mikesiki naru monokara, natukasiu rautage ni, saritote utitoke zu, kokorohukau hadukasige naru ohom-motenasi nado no, naho hito ni ni sase tamaha nu wo, "Nadoka, nanome naru koto dani uti-maziri tamaha zari kem?" to, turau sahe zo obosa ruru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.4 | 何ごとをかは聞こえ尽くしたまはむ。 ▼ くらぶの山に宿りも取らまほしげなれど、 あやにくなる 短夜にて、 あさましう、なかなかなり。 |
どのようなことをお話し申し上げきれようか。鞍馬の山に泊まりたいところだが、あいにくの短夜なので、情けなく、かえって辛い逢瀬である。 |
源氏の恋の万分の一も告げる時間のあるわけはない。永久の夜が欲しいほどであるのに、逢わない時よりも恨めしい別れの時が至った。 |
Nanigoto wo kaha kikoye tukusi tamaha m? Kurabunoyama ni yadori mo tora mahosige nare do, ayaniku naru mizikayo nite, asamasiu, nakanaka nari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
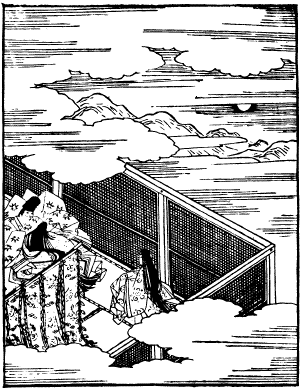 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.5 | 「 見てもまた逢ふ夜まれなる夢のうちに やがて紛るる我が身ともがな」 |
「お逢いしても再び逢うことの難しい夢のようなこの世なので 夢の中にそのまま消えてしまいとうございます」 |
見てもまた逢ふ夜稀なる夢の中に やがてまぎるるわが身ともがな |
"Mi te mo mata ahu yo mare naru yume no uti ni yagate magiruru wagami tomogana |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.6 | と、 むせかへりたまふさまも、 さすがにいみじければ、 |
と、涙にひどくむせんでいられるご様子も、何と言ってもお気の毒なので、 |
涙にむせ返って言う源氏の様子を見ると、さすがに宮も悲しくて、 |
to, musekaheri tamahu sama mo, sasuga ni imizikere ba, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.7 | 「 世語りに人や伝へむたぐひなく 憂き身を覚めぬ夢になしても」 |
「世間の語り草として語り伝えるのではないでしょうか、 この上なく辛い身の上を覚めることのない夢の中のこととしても」 |
世語りに人やつたへん類ひなく 憂き身をさめぬ夢になしても とお言いになった。 |
"Yogatari ni hito ya tutahe m taguhi naku uki mi wo same nu yume ni nasi te mo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.8 | 思し乱れたるさまも、いと道理にかたじけなし。命婦の君ぞ、御直衣などは、 かき集め持て来たる。 |
お悩みになっている様子も、まことに道理で恐れ多い。命婦の君が、お直衣などは、取り集めて持って来た。 |
宮が煩悶しておいでになるのも道理なことで、恋にくらんだ源氏の目にももったいなく思われた。源氏の上着などは王命婦がかき集めて寝室の外へ持ってきた。 |
Obosi-midare taru sama mo, ito kotowari ni katazikenasi. Myaubunokimi zo, ohom-nahosi nado ha, kaki-atume mote ki taru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.9 | 殿におはして、泣き寝に臥し暮らしたまひつ。 御文なども、 例の、御覧じ入れぬよしのみあれば、常のことながらも、つらういみじう思しほれて、内裏へも参らで、 二、三日籠もりおはすれば、 また、「いかなるにか」と、 御心動かせたまふべかめるも ★、 恐ろしうのみおぼえたまふ。 |
お邸にお帰りになって、泣き臥してお暮らしになった。お手紙なども、例によって、御覧にならない旨ばかりなので、いつものことながらも、全く茫然自失とされて、内裏にも参内せず、二、三日閉じ籠もっていらっしゃるので、また、「どうかしたのだろうか」と、ご心配あそばされているらしいのも、恐ろしいばかりに思われなさる。 |
源氏は二条の院へ帰って泣き寝に一日を暮らした。手紙を出しても、例のとおり御覧にならぬという王命婦の返事以外には得られないのが非常に恨めしくて、源氏は御所へも出ず二、三日引きこもっていた。これをまた病気のように解釈あそばして帝がお案じになるに違いないと思うともったいなく空恐ろしい気ばかりがされるのであった。 |
Tono ni ohasi te, naki ne ni husi kurasi tamahi tu. Ohom-humi nado mo, rei no, goranzi ire nu yosi nomi are ba, tune no koto nagara mo, turau imiziu obosi hore te, Uti he mo mawira de, ni, samniti komori ohasure ba, mata, "Ika naru ni ka?" to, mikokoro ugoka se tamahu beka' meru mo, osorosiu nomi oboye tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2 | 第二段 妊娠三月となる |
2-2 Fujitsubo gets pregnant and three months passed |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2.1 | 宮も、なほいと心憂き身なりけりと、思し嘆くに、悩ましさもまさりたまひて、 とく参りたまふべき御使、しきれど、 思しも立たず。 |
藤壺宮も、やはり実に情けないわが身であったと、お嘆きになると、ご気分の悪さもお加わりになって、早く参内なさるようにとの御勅使が、しきりにあるが、ご決心もつかない。 |
宮も御自身の運命をお歎きになって煩悶が続き、そのために御病気の経過もよろしくないのである。宮中のお使いが始終来て御所へお帰りになることを促されるのであったが、なお宮は里居を続けておいでになった。 |
Miya mo, naho ito kokorouki mi nari keri to, obosi nageku ni, nayamasisa mo masari tamahi te, toku mawiri tamahu beki ohom-tukahi, sikire do, obosi mo tata zu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2.2 | まことに、 御心地、例のやうにもおはしまさぬは、いかなるにかと、 人知れず思すこともありければ、心憂く、「いかならむ」とのみ思し乱る。 |
本当に、ご気分が、普段のようにおいであそばさないのは、どうしたことかと、密かにお思い当たることもあったので、情けなく、「どうなることだろうか」とばかりお悩みになる。 |
宮は実際おからだが悩ましくて、しかもその悩ましさの中に生理的な現象らしいものもあるのを、宮御自身だけには思いあたることがないのではなかった。情けなくて、これで自分は子を産むのであろうかと煩悶をしておいでになった。 |
Makoto ni, mikokoti, rei no yau ni mo ohasimasa nu ha, ika naru ni ka to, hitosirezu obosu koto mo ari kere ba, kokorouku, "Ika nara m?" to nomi obosi midaru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2.3 | 暑きほどは、いとど起きも上がりたまはず。 三月になりたまへば、いとしるきほどにて、 人びと見たてまつりとがむるに、 あさましき御宿世のほど、心憂し。人は思ひ寄らぬことなれば、「 この月まで、奏せさせたまはざりけること」と、驚ききこゆ。 我が御心一つには、しるう思しわくこともありけり。 |
暑いころは、ますます起き上がりもなさらない。三か月におなりになると、とてもよく分かるようになって、女房たちもそれとお気付き申すにつけ、思いもかけないご宿縁のほどが、恨めしい。他の人たちは、思いもよらないことなので、「この月まで、ご奏上あそばされなかったこと」と、意外なことにお思い申し上げる。ご自身一人には、はっきりとお分かりになる節もあるのであったのだ。 |
まして夏の暑い間は起き上がることもできずにお寝みになったきりだった。御妊娠が三月であるから女房たちも気がついてきたようである。宿命の恐ろしさを宮はお思いになっても、人は知らぬことであったから、こんなに月が重なるまで御内奏もあそばされなかったと皆驚いてささやき合った。 |
Atuki hodo ha, itodo oki mo agari tamaha zu. Mituki ni nari tamahe ba, ito siruki hodo nite, hitobito mi tatematuri togamuru ni, asamasiki ohom-sukuse no hodo, kokorousi. Hito ha omohiyora nu koto nare ba, "Kono tuki made, souse sase tamaha zari keru koto." to, odoroki kikoyu. Waga mikokoro hitotu ni ha, siruu obosi waku koto mo ari keri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2.4 | 御湯殿などにも親しう仕うまつりて、何事の御気色をもしるく見たてまつり知れる、 御乳母子の弁、命婦などぞ、あやしと思へど、かたみに言ひあはすべきにあらねば、 なほ逃れがたかりける御宿世をぞ、命婦はあさましと思ふ。 |
お湯殿などにも身近にお仕え申し上げて、どのようなご様子もはっきり存じ上げている、おん乳母子の弁や、命婦などは、変だと思うが、お互いに口にすべきことではないので、やはり逃れられなかったご運命を、命婦は驚きあきれたことと思う。 |
宮の御入浴のお世話などもきまってしていた宮の乳母の娘である弁とか、王命婦とかだけは不思議に思うことはあっても、この二人の間でさえ話し合うべき問題ではなかった。命婦は人間がどう努力しても避けがたい宿命というもののカに驚いていたのである。 |
Ohom-yudono nado ni mo sitasiu tukaumaturi te, nanigoto no mikesiki wo mo siruku mi tatematuri sire ru, ohom-menotogo no Ben, Myaubu nado zo, ayasi to omohe do, katami ni ihi ahasu beki ni ara ne ba, naho nogare gatakari keru ohom-sukuse wo zo, Myaubu ha asamasi to omohu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2.5 | 内裏には、御物の怪の紛れにて、とみに気色なう おはしましけるやうにぞ 奏しけむかし。 見る人もさのみ思ひけり。 いとどあはれに限りなう思されて、御使などの ひまなきも、 そら恐ろしう、ものを思すこと、ひまなし。 |
帝に対しては、おん物の怪のせいで、すぐには兆候がなくあそばしたように奏上したのであろう。周囲の人もそうとばかり思っていた。ますますこの上なく愛しくお思いあそばして、御勅使などがひっきりなしにあるにつけても、空恐ろしく、物思いの 休まる時もない。 |
宮中へは御病気やら物怪やらで気のつくことのおくれたように奏上したはずである。だれも皆そう思っていた。帝はいっそうの熱愛を宮へお寄せになることになって、以前よりもおつかわしになるお使いの度数の多くなったことも、宮にとっては空恐ろしくお思われになることだった。 |
Uti ni ha, ohom-mononoke no magire nite, tomi ni kesiki nau ohasimasi keru yau ni zo sousi kem kasi. Miru hito mo sa nomi omohi keri. Itodo ahare ni kagiri nau obosa re te, ohom-tukahi nado no hima naki mo, sora-osorosiu, mono wo, obosu koto, hima nasi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2.6 | 中将の君も、 おどろおどろしうさま異なる夢を見たまひて、 合はする者を召して、 問はせたまへば、 及びなう思しもかけぬ筋のことを合はせけり。 |
源氏中将の君も、ただごとではない異様な夢を御覧になって、夢解きをする者を呼んで、ご質問させなさると、及びもつかない思いもかけない方面のことを判断したのであった。 |
煩悶の合い間というものがなくなった源氏の中将も変わった夢を見て夢解きを呼んで合わさせてみたが、及びもない、思いもかけぬ占いをした。そして、 |
Tyuuzyounokimi mo, odoroodorosiu sama koto naru yume wo mi tamahi te, ahasuru mono wo mesi te, toha se tamahe ba, oyobi nau obosi mo kake nu sudi no koto wo ahase keri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2.7 | 「 その中に、違ひ目ありて、慎しませたまふべきことなむはべる」 |
「その中に、順調に行かないところがあって、お身を慎みあそばさななければならないことがございます」 |
「しかし順調にそこへお達しになろうとするのにはお慎みにならなければならぬ故障が一つございます」 |
"Sono naka ni, tagahime ari te, tutusima se tamahu beki koto nam haberu." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2.8 | と言ふに、わづらはしくおぼえて、 |
と言うので、面倒に思われて、 |
と言った。夢を現実にまざまざ続いたことのように言われて、源氏は恐怖を覚えた。 |
to ihu ni, wadurahasiku oboye te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2.9 | 「 みづからの夢にはあらず、 人の御ことを語るなり。この夢合ふまで、 また人にまねぶな」 |
「自分の夢ではない、他の方の夢を申すのだ。この夢が現実となるまで、誰にも話してはならぬ」 |
「私の夢ではないのだ。ある人の夢を解いてもらったのだ。今の占いが真実性を帯びるまではだれにも秘密にしておけ」 |
"Midukara no yume ni ha ara zu, hito no ohom-koto wo kataru nari. Kono yume ahu made, mata hito ni manebu na." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2.10 | とのたまひて、心のうちには、「いかなることならむ」と思しわたるに、 この女宮の御こと聞きたまひて、 「 もしさるやうもや」と、思し合はせたまふに、いとどしくいみじき言の葉尽くしきこえたまへど、命婦も思ふに、いとむくつけう、わづらはしさまさりて、 さらにたばかるべきかたなし ★。はかなき一行の御返りの たまさかなりしも、絶え果てにたり。 |
とおっしゃって、心中では、「どのようなことなのだろう」とお考えめぐらしていると、この女宮のご懐妊のことをお聞きになって、「あの夢はもしやそのようなことか」と、お思い合わせになると、ますます熱心に言葉のあらん限りを尽くして申し上げなさるが、命婦も考えると、まことに恐ろしく、難儀な気持ちが増してきて、まったく逢瀬を手立てする方法がない。ほんの一行のお返事がまれにはあったのも、すっかり絶えはててしまった。 |
とその男に言ったのであるが、源氏はそれ以来、どんなことがおこってくるのかと思っていた。その後に源氏は藤壼の宮の御懐妊を聞いて、そんなことがあの占いの男に言われたことなのではないかと思うと、恋人と自分の間に子が生まれてくるということに若い源氏は昂奮して、以前にもまして言葉を尽くして逢瀬を望むことになったが、王命婦も宮の御懐妊になって以来、以前に自身が、はげしい恋に身を亡しかねない源氏に同情してとった行為が重大性を帯びていることに気がついて、策をして源氏を宮に近づけようとすることを避けたのである。源氏はたまさかに宮から一行足らずのお返事の得られたこともあるが、それも絶えてしまった。 |
to notamahi te, kokoro no uti ni ha, "Ika naru koto nara m ?" to obosi wataru ni, kono Womnamiya no ohom-koto kiki tamahi te, "Mosi saru yau mo ya?" to, obosi ahase tamahu ni, itodosiku imiziki kotonoha tukusi kikoye tamahe do, Myaubu mo omohu ni, ito mukutukeu, wadurahasisa masari te, sarani tabakaru beki kata nasi. Hakanaki hitokudari no ohom-kaheri no tamasaka nari si mo, taye hate ni tari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3 | 第三段 初秋七月に藤壺宮中に戻る |
2-3 Fujitsubo comes back to the Court in July early fall |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.1 | 七月になりてぞ参りたまひける。 めづらしうあはれにて、いとどしき御思ひのほど限りなし。 すこしふくらかになりたまひて、うちなやみ、面痩せたまへる、 はた、げに似るものなくめでたし。 |
七月になって宮は参内なさった。珍しい事で感動深くて、以前にも増す御寵愛ぶりはこの上もない。少しふっくらとおなりになって、ちょっと悩ましげに、面痩せしていらっしゃるのは、それはそれでまた、なるほど比類なく素晴らしい。 |
初秋の七月になって宮は御所へおはいりになった。最愛の方が懐妊されたのであるから、帝のお志はますます藤壼の宮にそそがれるばかりであった。少しお腹がふっくりとなって悪阻の悩みに顔の少しお痩せになった宮のお美しさは、前よりも増したのではないかと見えた。 |
Huduki ni nari te zo mawiri tamahi keru. Medurasiu ahare ni te, itodosiki ohom-omohi no hodo kagiri nasi. Sukosi hukuraka ni nari tamahi te, uti-nayami, omoyase tamahe ru, hata, geni niru mono naku medetasi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.2 | 例の、明け暮れ、こなたにのみおはしまして、御遊びもやうやうをかしき空なれば、 源氏の君も暇なく召しまつはしつつ、御琴、笛など、さまざまに仕うまつらせたまふ。 いみじうつつみたまへど、忍びがたき気色の漏り出づる折々、 宮も、さすがなる事どもを多く思し続けけり。 |
例によって、明け暮れ、帝はこちらにばかりお出ましになって、管弦の御遊もだんだん興の乗る季節なので、源氏の君も暇のないくらいお側にたびたびお召しになって、お琴や、笛など、いろいろと君にご下命あそばす。つとめてお隠しになっているが、我慢できない気持ちが外に現れ出てしまう折々、藤壺宮も、さすがに忘れられない事どもをあれこれとお思い悩み続けていらっしゃるのであった。 |
以前もそうであったように帝は明け暮れ藤壼にばかり来ておいでになって、もう音楽の遊びをするのにも適した季節にもなっていたから、源氏の中将をも始終そこへお呼び出しになって、琴や笛の役をお命じになった。物思わしさを源氏は極力おさえていたが、時々には忍びがたい様子もうかがわれるのを、宮もお感じになって、さすがにその人にまつわるものの愁わしさをお覚えになった。 |
Rei no, akekure, konata ni nomi ohasimasi te, ohom-asobi mo yauyau wokasiki sora nare ba, Genzinokimi mo itoma naku mesi matuhasi tutu, ohom-koto, hue nado, samazama ni tukaumatura se tamahu. Imiziu tutumi tamahe do, sinobi gataki kesiki no mori iduru woriwori, Miya mo, sasuga naru koto-domo wo ohoku obosi tuduke keri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last updated 9/11/2010(ver.2-2) 渋谷栄一校訂(C) Last updated 3/7/2009(ver.2-1) 渋谷栄一注釈 |
Last updated 11/21/2013 渋谷栄一訳(C)(ver.1-3-2) |
|
Last updated 3/7/2009 (ver.2-1) Written in Japanese roman letters by Eiichi Shibuya (C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Picture "Eiri Genji Monogatari"(1650 1st edition) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源氏物語の世界 再編集プログラム Ver 3.38: Copyright (c) 2003,2015 宮脇文経