第七帖 紅葉賀 |
07 MOMIDI-NO-GA (Ohoshima-bon) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光る源氏の十八歳冬十月から十九歳秋七月までの宰相兼中将時代の物語 |
Tale of Hikaru-Genji's Konoe-Chujo era from October in winter at the age of 18 to July in fall at the age of 19 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 第三章 藤壺の物語(二) 二月に男皇子を出産 |
3 Tale of Fujitsubo (2) A baby boy is born on Fujitsubo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1 | 第一段 左大臣邸に赴く |
3-1 Genji visits to Sadaijin's residence |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.1 | 内裏より大殿にまかでたまへれば、例のうるはしうよそほしき御さまにて、心うつくしき御けしきもなく、苦しければ、 |
宮中から大殿にご退出なさると、いつものように端然と威儀を正したご態度で、やさしいそぶりもなく窮屈なので、 |
源氏は御所から左大臣家のほうへ退出した。例のように夫人からは高いところから多情男を見くだしているというようなよそよそしい態度をとられるのが苦しくて、源氏は、 |
Uti yori Ohoidono ni makade tamahe re ba, rei no uruhasiu yosohosiki ohom-sama nite, kokoroutukusiki mikesiki mo naku, kurusikere ba, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.2 | 「 今年よりだに、すこし世づきて改めたまふ御心見えば、いかにうれしからむ」 |
「せめて今年からでも、もう少し夫婦らしく態度をお改めになるお気持ちが窺えたら、どんなにか嬉しいことでしょう」 |
「せめて今年からでもあなたが暖かい心で私を見てくれるようになったらうれしいと思うのだが」 |
"Kotosi yori dani, sukosi yoduki te aratame tamahu mikokoro miye ba, ikani uresikara m." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.3 | など聞こえたまへど、「 わざと人据ゑて、かしづきたまふ」と聞きたまひしよりは、「 やむごと なく思し定めたることにこそは」と、心のみ置かれて、いとど疎く恥づかしく 思さるべし。 しひて見知らぬやうにもてなして、 乱れたる御けはひには、 えしも心強からず、御いらへなどうち聞こえたまへるは、なほ人よりはいとことなり。 |
などとお申し上げなさるが、「わざわざ女の人を置いて、かわいがっていらっしゃる」と、お聞きになってからは、「重要な夫人とお考えになってのことであろう」と、隔て心ばかりが自然と生じて、ますます疎ましく気づまりにお感じになられるのであろう。つとめて見知らないように振る舞って、冗談をおっしゃっるご様子には、強情もを張り通すこともできず、お返事などちょっと申し上げなさるところは、やはり他の女性とはとても違うのである。 |
と言ったが、夫人は、二条の院へある女性が迎えられたということを聞いてからは、本邸へ置くほどの人は源氏の最も愛する人で、やがては正夫人として公表するだけの用意がある人であろうとねたんでいた。自尊心の傷つけられていることはもとよりである。しかも何も気づかないふうで、 |
nado, kikoye tamahe do, "Wazato hito suwe te, kasiduki tamahu." to kiki tamahi si yori ha, "Yamgotonaku obosi sadame taru koto ni koso ha." to, kokoro nomi oka re te, itodo utoku hadukasiku obosa ru besi. Sihite mi sira nu yau ni motenasi te, midare taru ohom-kehahi ni ha, e simo kokoroduyokara zu, ohom-irahe nado uti-kikoye tamahe ru ha, naho hito yori ha ito koto nari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.4 | 四年ばかりがこのかみにおはすれば、うち過ぐし、恥づかしげに、盛りにととのほりて見えたまふ。「 何ごとかはこの人の飽かぬところはものしたまふ。我が心のあまりけしからぬすさびに、かく怨みられたてまつるぞかし」と、思し知らる。 同じ大臣と聞こゆるなかにも、おぼえやむごとなくおはするが、宮腹に一人いつきかしづきたまふ御心おごり、いとこよなくて、「すこしもおろかなるをば、めざまし」と思ひきこえたまへるを、男君は、「 などかいとさしも」と、 ならはいたまふ、御心の隔てどもなるべし。 |
四歳ほど年上でいらっしゃるので、姉様で、気後れがし、女盛りで非の打ちどころがなくお見えになる。「どこにこの人の足りないところがおありだろうか。自分のあまり良くない浮気心からこのようにお恨まれ申すのだ」と、お考えにならずにはいられない。同じ大臣と申し上げる中でも、御信望この上なくいらっしゃる方が、宮との間にお一人儲けて大切にお育てなさった気位の高さは、とても大変なもので、「少しでも疎略にするのは、失敬である」とお思い申し上げていらっしゃるのを、男君は、「どうしてそんなにまでも」と、お躾なさる、お二人の心の隔てがあるの生じさせたのであろう。 |
|
Yotose bakari ga konokami ni ohasure ba, uti-sugusi, hadukasige ni, sakari ni totonohori te miye tamahu. "Nanigoto ka ha kono hito no aka nu tokoro ha monosi tamahu. Waga kokoro no amari kesikara nu susabi ni, kaku urami rare tatematuru zo kasi." to, obosi sira ru. Onazi otodo to kikoyuru naka ni mo, oboye yamgotonaku ohasuru ga, miyabara ni hitori ituki kasiduki tamahu mikokoroogori, ito koyonaku te, "Sukosi mo oroka naru wo ba, mezamasi." to omohi kikoye tamahe ru wo, Wotokogimi ha, "Nadoka ito sasimo" to, narahai tamahu, mikokoro no hedate-domo naru besi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.5 | 大臣も、かく頼もしげなき御心を、つらしと思ひきこえたまひながら、見たてまつりたまふ時は、恨みも忘れて、かしづきいとなみきこえたまふ。つとめて、出でたまふところにさしのぞきたまひて、御装束したまふに、名高き御帯、 御手づから持たせてわたりたまひて、御衣のうしろひきつくろひなど、御沓を取らぬばかりにしたまふ、 いとあはれなり。 |
大臣も、このように頼りないお気持ちを、辛いとお思い申し上げになりながらも、お目にかかりなさる時には、恨み事も忘れて、大切にお世話申し上げなさる。翌朝、お帰りになるところにお顔をお見せになって、お召し替えになる時、高名の御帯、お手ずからお持ちになってお越しになって、お召物の後ろを引き結び直しなどや、お沓までも手に取りかねないほど世話なさる、大変なお気の配りようである。 |
左大臣も二条の院の新夫人の件などがあって、頼もしくない婿君の心をうらめしがりもしていたが、逢えば恨みも何も忘れて源氏を愛した。今もあらゆる歓待を尽くすのである。翌朝源氏が出て行こうとする時に、大臣は装束を着けている源氏に、有名な宝物になっている石の帯を自身で持って来て贈った。正装した源氏の |
Otodo mo, kaku tanomosige naki mikokoro wo, turasi to omohi kikoye tamahi nagara, mi tatematuri tamahu toki ha, urami mo wasure te, kasiduki itonami kikoye tamahu. Tutomete, ide tamahu tokoro ni sasi-nozoki tamahi te, ohom-sauzoku si tamahu ni, nadakaki ohom-obi, ohom-tedukara mota se te watari tamahi te, ohom-zo no usiro hiki-tukurohi nado, ohom-kutu wo tora nu bakari ni si tamahu, ito ahare nari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.6 | 「 これは、内宴などいふこともはべるなるを、さやうの折にこそ」 |
「これは、内宴などということもございますそうですから、そのような折にでも」 |
「こんないいのは、宮中の詩会があるでしょうから、その時に使いましょう」 |
"Kore ha, naien nado ihu koto mo haberu naru wo, sayau no wori ni koso." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.7 | など聞こえ たまへば、 |
などとお申し上げなさると、 |
と贈り物の帯について言うと、 |
nado kikoye tamahe ba, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.8 | 「 それは、まされるもはべり。これはただ目馴れぬさまなればなむ」 |
「その時には、もっと良いものがございます。これはちょっと目新しい感じのするだけのものですから」 |
「それにはまたもっといいのがございます。これはただちょっと珍しいだけの物です」 |
"Sore ha, masare ru mo haberi. Kore ha tada me nare nu sama nare ba nam." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.9 | とて、しひてささせたてまつりたまふ。げに、よろづにかしづき立てて見たてまつりたまふに、生けるかひあり、「 たまさかにても、かからむ人を出だし入れて見むに、ますことあらじ」と 見えたまふ。 |
と言って、無理にお締め申し上げなさる。なるほど、万事にお世話して拝見なさると、生き甲斐が感じられ、「たまさかであっても、このような方をお出入りさせてお世話するのに、これ以上の喜びはあるまい」とお見えである。 |
と言って、大臣はしいてそれを使わせた。この婿君を |
tote, sihite sasa se tatematuri tamahu. Geni, yorodu ni kasiduki tate te mi tatematuri tamahu ni, ikeru kahi ari, "Tamasaka ni te mo, kakara m hito wo idasi ire te mi m ni, masu koto ara zi." to miye tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2 | 第二段 二月十余日、藤壺に皇子誕生 |
3-2 A baby boy is born on 10 something day in February |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.1 | 参座しにとても、あまた所も歩きたまはず、 内裏、春宮、一院ばかり、さては、藤壺の三条の宮にぞ参りたまへる。 |
参賀のご挨拶といっても、多くの所にはお出かけにならず、内裏、春宮、一院だけ、その他では、藤壷の三条の宮にお伺いなさる。 |
源氏の参賀の場所は数多くもなかった。東宮、一院、それから藤壺の三条の宮へ行った。 |
Sanza si ni tote mo, amata tokoro mo ariki tamaha zu, Uti, Touguu, Itinowin bakari, sateha, Huditubo no Samdeunomiya ni zo mawiri tamahe ru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.2 | 「 今日はまたことにも見えたまふかな」 |
「今日はまた格別にお見えでいらっしゃるわ」 |
「今日はまたことにおきれいに見えますね、 |
"Kehu ha mata koto ni mo miye tamahu kana!" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.3 | 「ねびたまふままに、ゆゆしきまでなりまさりたまふ御ありさまかな」 |
「ご成長されるに従って、恐いまでにお美しくおなりでいらっしゃるご様子ですわ」 |
年がお行きになればなるほどごりっぱにおなりになる方なんですね」 |
"Nebi tamahu mama ni, yuyusiki made nari masari tamahu ohom-arisama kana!" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.4 | と、人びとめできこゆるを、宮、几帳の隙より、 ほの見たまふにつけても、思ほすことしげかりけり。 |
と、女房たちがお褒め申し上げているのを、宮、几帳の隙間からわずかにお姿を御覧になるにつけても、物思いなさることが多いのであった。 |
女房たちがこうささやいている時に、宮はわずかな |
to, hitobito mede kikoyuru wo, Miya, kityau no hima yori, hono-mi tamahu ni tuke te mo, omohosu koto sigekari keri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.5 | この御ことの、師走も過ぎにしが、心もとなきに、 この月はさりともと、宮人も待ちきこえ、内裏にも、さる 御心まうけどもあり、 つれなくて立ちぬ。「御もののけにや」と、世人も聞こえ騒ぐを、宮、いとわびしう、「 このことにより、身のいたづらになりぬべきこと」と思し嘆くに、御心地もいと苦しくて悩みたまふ。 |
御出産の予定の、十二月も過ぎてしまったのが、気がかりで、今月はいくら何でもと、宮家の人々もお待ち申し上げ、主上におかれても、そのお心づもりでいるのに、何事もなく過ぎてしまった。「御物の怪のせいであろうか」と、世間の人々もお噂申し上げるのを、宮、とても身にこたえてつらく、「このお産のために、命を落とすことになってしまいそうだ」と、お嘆きになると、ご気分もとても苦しくてお悩みになる。 |
御出産のあるべきはずの十二月を過ぎ、この月こそと用意して三条の宮の人々も待ち、 |
Kono ohom-koto no, sihasu mo sugi ni si ga, kokoromotonaki ni, kono tuki ha saritomo to, Miyabito mo mati kikoye, uti ni mo, saru mikokoro mauke-domo ari, turenaku te tati nu. "Ohom-mononoke ni ya?" to, yohito mo kikoye sawagu wo, Miya, ito wabisiu, "Kono koto ni yori, mi no itadura ni nari nu beki koto." to obosi nageku ni, mikokoti mo ito kurusiku te nayami tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.6 | 中将君は、いとど思ひあはせて、 御修法など、さとはなくて所々にせさせたまふ。「 世の中の定めなきにつけても、かくはかなくてや止みなむ」と、 取り集めて嘆きたまふに、 二月十余日のほどに、男御子生まれたまひぬれば、名残なく、内裏にも宮人も喜びきこえたまふ。 |
中将の君は、ますます思い当たって、御修法などを、はっきりと事情は知らせずに方々の寺々におさせになる。「世の無常につけても、このままはかなく終わってしまうのだろうか」と、あれやこれやとお嘆きになっていると、二月十日過ぎのころに、男御子がお生まれになったので、すっかり心配も消えて、宮中でも宮家の人々もお喜び申し上げなさる。 |
それを聞いても源氏はいろいろと思い合わすことがあって、目だたぬように産婦の宮のために |
Tyuuzyaunokimi ha, itodo omohi ahase te, misuhohu nado, sa to ha naku te tokorodokoro ni se sase tamahu. "Yononaka no sadame naki ni tuke te mo, kaku hakanaku te ya yami na m?" to, tori-atume te nageki tamahu ni, nigwatu zihuyoniti no hodo ni, Wotokomiko mumare tamahi nure ba, nagori naku, uti ni mo miyabito mo yorokobi kikoye tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.7 | 「 命長くも」と思ほすは心憂けれど、「弘徽殿などの、うけはしげにのたまふ」と聞きしを、「 むなしく聞きなしたまはましかば、人笑はれにや ★」と思し強りてなむ、やうやうすこしづつさはやいたまひける。 |
「長生きを」とお思いなさるのは、つらいことだが、「弘徽殿などが、呪わしそうにおっしゃっている」と聞いたので、「死んだとお聞きになったならば、物笑いの種になろう」と、お気を強くお持ちになって、だんだん少しずつ気分が快方に向かっていかれたのであった。 |
なお生きようとする自分の心は未練で恥ずかしいが、 |
"Inoti nagaku mo" to omohosu ha kokoroukere do, "Koukiden nado no, ukehasige ni notamahu." to kiki si wo, "Munasiku kiki nasi tamaha masika ba, hitowaraha re ni ya." to obosi tuyori te nam, yauyau sukosi dutu sahayai tamahi keru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.8 | 主上の、いつしかとゆかしげに思し召したること、限りなし。 かの、人知れぬ御心にも、いみじう心もとなくて、 人まに参りたまひて、 |
お上が、早く御子を御覧になりたいとおぼし召されること、この上ない。あの、密かなお気持ちとしても、ひどく気がかりで、人のいない時に参上なさって、 |
帝は新皇子を非常に御覧になりたがっておいでになった。人知れぬ父性愛の火に心を燃やしながら源氏は伺候者の少ない |
Uhe no, itusika to yukasige ni obosimesi taru koto, kagiri nasi. Kano, hito sire nu mikokoro ni mo, imiziu kokoromotonaku te, hitoma ni mawiri tamahi te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.9 | 「 主上のおぼつかながりきこえさせたまふを、まづ 見たてまつりて詳しく奏しはべらむ ★」 |
「お上が御覧になりたくあそばしてますので、まず拝見して詳しく奏上しましょう」 |
「陛下が若宮にどんなにお逢いになりたがっていらっしゃるかもしれません。それで私がまずお目にかかりまして御様子でも申し上げたらよろしいかと思います」 |
"Uhe no obotukanagari kikoyesase tamahu wo, madu mi tatematuri te kuhasiku sousi habera m." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.10 | と聞こえたまへど、 |
と申し上げなさるが、 |
と源氏は申し込んだのであるが、 |
to kikoye tamahe do, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.11 | 「 むつかしげなるほどなれば」 |
「まだ見苦しい程ですので」 |
「まだお生まれたての方というものは醜うございますからお見せしたくございません」 |
"Mutukasige naru hodo nare ba." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.12 | とて、見せたてまつりたまはぬも、 ことわりなり。 さるは、いとあさましう、めづらかなるまで写し取りたまへるさま、 違ふべくもあらず。 宮の、御心の鬼にいと苦しく、「 人の見たてまつるも、 あやしかりつるほどのあやまりを、まさに 人の思ひとがめじや。さらぬはかなきことをだに、 疵を求むる世に、いかなる名のつひに漏り出づべきにか」と思しつづくるに、身のみぞいと心憂き。 |
と言って、お見せ申し上げなさらないのも、ごもっともである。実のところ、とても驚くほど珍しいまでに生き写しでいらっしゃる顔形、紛うはずもない。宮が、良心の呵責にとても苦しく、「女房たちが拝見しても、不審に思われた月勘定の狂いを、どうして変だと思い当たらないだろうか。それほどでないつまらないことでさえも、欠点を探し出そうとする世の中で、どのような噂がしまいには世に漏れようか」と思い続けなさると、わが身だけがとても情けない。 |
という母宮の御挨拶で、お見せにならないのにも理由があった。それは若宮のお顔が驚くほど源氏に生き写しであって、別のものとは決して見えなかったからである。宮はお心の鬼からこれを苦痛にしておいでになった。この若宮を見て自分の過失に気づかぬ人はないであろう、何でもないことも捜し出して人をとがめようとするのが世の中である。どんな悪名を自分は受けることかとお思いになると、結局不幸な者は自分であると熱い涙がこぼれるのであった。 |
tote, mise tatematuri tamaha nu mo, kotowari nari. Saruha, ito asamasiu, meduraka naru made utusi tori tamahe ru sama, tagahu beku mo ara zu. Miya no, mikokoro no oni ni ito kurusiku, "Hito no mi tatematuru mo, ayasikari turu hodo no ayamari wo, masani hito no omohi togame zi ya? Saranu hakanaki koto wo dani, kizu wo motomuru yo ni, ika naru na no tuhini mori-idu beki ni ka." to obosi tudukuru ni, mi nomi zo ito kokorouki. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.13 | 命婦の君に、たまさかに逢ひたまひて、いみじき言どもを尽くしたまへど、何のかひあるべきにもあらず。若宮の御ことを、 わりなくおぼつかながりきこえたまへば、 |
命婦の君に、まれにお会いになって、切ない言葉を尽くしてお頼みなさるが、何の効果があるはずもない。若宮のお身の上を無性に御覧になりたくお訴え申し上げなさるので、 |
源氏は |
Myaubunokimi ni, tamasaka ni ahi tamahi te, imiziki koto-domo wo tukusi tamahe do, nani no kahi aru beki ni mo ara zu. Wakamiya no ohom-koto wo, warinaku obotukanagari kikoye tamahe ba, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.14 | 「 など、かうしもあながちにのたまはすらむ。今、おのづから見たてまつらせたまひてむ」 |
「どうして、こうまでもご無理を仰せあそばすのでしょう。そのうち、自然に御覧あそばされましょう」 |
「なぜそんなにまでおっしゃるのでしょう。自然にその日が参るのではございませんか」 |
"Nado, kau simo anagati ni notamahasu ram. Ima, onodukara mi tatematura se tamahi te m." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.15 | と聞こえながら、思へるけしき、かたみにただならず。かたはらいたきことなれば、まほにもえのたまはで、 |
と申し上げながら、悩んでいる様子、お互いに一通りでない。気が引ける事柄なので、正面切っておっしゃれず、 |
と答えていたが、無言で二人が読み合っている心が別にあった。口で言うべきことではないから、そのほうのことはまた言葉にしにくかった。 |
to kikoye nagara, omohe ru kesiki, katamini tada nara zu. Kataharaitaki koto nare ba, maho ni mo e notamaha de, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.16 | 「 いかならむ世に、人づてならで、聞こえさせむ」 |
「いったいいつになったら、直接に、お話し申し上げることができるのだろう」 |
「いつまた私たちは直接にお話ができるのだろう」 |
"Ika nara m yo ni, hitodute nara de, kikoye sase m." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.17 | とて、泣いたまふさまぞ、心苦しき。 |
と言ってお泣きになる姿、お気の毒である。 |
と言って泣く源氏が王命婦の目には気の毒でならない。 |
tote, nai tamahu sama zo, kokorogurusiki. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.18 | 「 いかさまに昔結べる契りにて この世にかかるなかの隔てぞ |
「どのように前世で約束を交わした縁で この世にこのような二人の仲に隔てがあるのだろうか |
「いかさまに昔結べる契りにて この世にかかる中の隔てぞ |
"Ika sama ni mukasi musube ru tigiri ni te Konoyo ni kakaru naka no hedate zo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.19 | かかることこそ心得がたけれ」 |
このような隔ては納得がいかない」 |
わからない、わからない」 |
Kakaru koto koso kokoroe gatakere." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.20 | とのたまふ。 |
とおっしゃる。 |
とも源氏は言うのである。 |
to notamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.21 | 命婦も、宮の 思ほしたるさまなどを見たてまつるに、 えはしたなうもさし放ちきこえず。 |
命婦も、宮のお悩みでいらっしゃる様子などを拝見しているので、そっけなく突き放してお扱い申し上げることもできない。 |
命婦は宮の御 |
Myaubu mo, Miya no omohosi taru sama nado wo mi tatematuru ni, e hasitanau mo sasi-hanati kikoye zu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.22 | 「 見ても思ふ見ぬはたいかに嘆くらむ こや世の人のまどふてふ闇 ★ |
「御覧になっている方も物思をされています。御覧にならないあなたはまたどんなにお嘆きのことでしょう これが世の人が言う親心の闇でしょうか |
「見ても思ふ見ぬはたいかに こや世の人の惑ふてふ |
"Mi te mo omohu mi nu hata ikani nageku ram koya yonohito no madohu tehu yami |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.23 | あはれに、心ゆるびなき御ことどもかな」 |
おいたわしい、お心の休まらないお二方ですこと」 |
どちらも同じほどお気の毒だと思います」 |
Ahare ni, kokoro yurubi naki ohom-koto-domo kana!" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.24 | と、忍びて聞こえけり。 |
と、こっそりとお返事申し上げたのであった。 |
と命婦は言った。 |
to, sinobi te kikoye keri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.25 | かくのみ言ひやる方なくて、帰りたまふものから、人のもの言ひもわづらはしきを、 わりなきことにのたまはせ思して、命婦をも、昔おぼいたりしやうにも、うちとけむつびたまはず。 人目立つまじく、なだらかにもてなしたまふものから、心づきなしと思す時もあるべきを、いとわびしく思ひのほかなる心地すべし。 |
このように何とも申し上げるすべもなくて、お帰りになるものの、世間の人々の噂も煩わしいので、無理無体なことにおっしゃりもし、お考えにもなって、命婦をも、以前信頼していたように気を許してお近づけなさらない。人目に立たないように、穏やかにお接しになる一方で、気に食わないとお思いになる時もあるはずなのを、とても身にこたえて思ってもみなかった心地がするようである。 |
取りつき所もないように源氏が悲しんで帰って行くことも、度が重なれば |
Kaku nomi ihiyaru kata naku te, kaheri tamahu monokara, hito no mono-ihi mo wadurahasiki wo, warinaki koto ni notamaha se obosi te, Myaubu wo mo, mukasi oboyi tari si yau ni mo, utitoke mutubi tamaha zu. Hitome tatu maziku, nadaraka ni motenasi tamahu monokara, kokorodukinasi to obosu toki mo aru beki wo, ito wabisiku omohi no hoka naru kokoti su besi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3 | 第三段 藤壺、皇子を伴って四月に宮中に戻る |
3-3 Fujitsubo comes back to the Imperial Court with hew baby in April |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.1 | 四月に内裏へ参りたまふ。ほどよりは大きにおよすけたまひて、やうやう起き返りなどしたまふ。あさましきまで、まぎれどころなき御顔つきを、 思し寄らぬことにしあれば、「 またならびなきどちは、げにかよひたまへるにこそは」と、思ほしけり。いみじう思ほしかしづくこと、限りなし。源氏の君を、限りなきものに思し召しながら、世の人のゆるしきこゆまじかりしによりて、坊にも据ゑたてまつらずなりにしを、飽かず口惜しう、ただ人にてかたじけなき御ありさま、容貌に、ねびもておはするを御覧ずるままに、心苦しく思し召すを、「かうやむごとなき御腹に、同じ光にてさし出でたまへれば、疵なき玉」と思しかしづくに、宮はいかなるにつけても、胸のひまなく、やすからずものを思ほす。 |
四月に参内なさる。日数の割には大きく成長なさっていて、だんだん寝返りなどをお打ちになる。驚きあきれるくらい、間違いようもないお顔つきを、ご存知ないことなので、「他に類のない美しい人どうしというのは、なるほど似通っていらっしゃるものだ」と、お思いあそばすのであった。たいそう大切にお慈しみになること、この上もない。源氏の君を、限りなくかわいい人と愛していらっしゃりながら、世間の人々のがご賛成申し上げそうになかったことによって、坊にもお据え申し上げられずに終わったことを、どこまでも残念に、臣下としてもったいないご様子、容貌で、ご成人していらっしゃるのを御覧になるにつけ、おいたわしくおぼし召されるので、「このように高貴な人から、同様に光り輝いてお生まれになったので、疵のない玉だ」と、お思いあそばして大切になさるので、宮は何につけても、胸の痛みの消える間もなく、不安な思いをしていらっしゃる。 |
四月に若宮は母宮につれられて宮中へおはいりになった。普通の |
Uduki ni uti he mawiri tamahu. Hodo yori ha ohoki ni oyosuke tamahi te, yauyau okikaheri nado si tamahu. Asamasiki made, magiredokoro naki ohom-kahotuki wo, obosi yora nu koto ni si are ba, "Mata narabinaki-doti ha, geni kayohi tamaheru ni koso ha." to, omohosi keri. Imiziu omohosi kasiduku koto, kagiri nasi. Genzinokimi wo, kagirinaki mono ni obosimesi nagara, yo no hito no yurusi kikoyu mazikari si ni yori te, bau ni mo suwe tatematura zu nari ni si wo, akazu kutiwosiu, tadaudo nite katazikenaki ohom-arisama, katati ni, nebi mote ohasuru wo goranzuru mama ni, kokorogurusiku obosimesu wo, "Kau yamgotonaki ohom-hara ni, onazi hikari ni te sasi-ide tamahe re ba, kizu naki tama." to obosi kasiduku ni, Miya ha ika naru ni tuke te mo, mune no hima naku, yasukara zu mono wo omohosu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.2 | 例の、 中将の君、 こなたにて御遊びなどしたまふに、 抱き出でたてまつらせたまひて、 |
いつものように、中将の君が、こちらで管弦のお遊びをなさっていると、お抱き申し上げあそばされて、 |
源氏の中将が音楽の遊びなどに参会している時などに帝は抱いておいでになって、 |
Rei no, Tiuzyaunokimi, konata nite ohom-asobi nado si tamahu ni, idaki ide tatematura se tamahi te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.3 | 「 御子たち、あまたあれど、 そこをのみなむ、かかるほどより明け暮れ見し。されば、思ひわたさるるにやあらむ。いとよくこそおぼえたれ。いと小さきほどは、皆かくのみあるわざにやあらむ」 |
「御子たち、大勢いるが、そなただけを、このように小さい時から明け暮れ見てきた。それゆえ、思い出されるのだろうか。とてもよく似て見える。とても幼いうちは皆このように見えるのであろうか」 |
「私は子供がたくさんあるが、おまえだけをこんなに小さい時から毎日見た。だから同じように思うのかよく似た気がする。小さい間は皆こんなものだろうか」 |
"Miko-tati, amata are do, soko wo nomi nam, kakaru hodo yori akekure mi si. Sareba, omohi watasa ruru ni ya ara m? Ito yoku koso oboye tare. Ito tihisaki hodo ha, mina kaku nomi aru waza ni ya ara m?" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.4 | とて、いみじくうつくしと 思ひきこえさせたまへり。 |
と言って、たいそうかわいらしいとお思い申し上げあそばされている。 |
とお言いになって、非常にかわいくお思いになる様子が拝された。 |
tote, imiziku utukusi to omohi kikoye sase tamahe ri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.5 | 中将の君、 面の色変はる心地して、 恐ろしうも、かたじけなくも、うれしくも、あはれにも、かたがた移ろふ心地して、 涙落ちぬべし。 もの語りなどして、うち笑みたまへるが、いとゆゆしううつくしきに、 わが身ながら、これに似たらむはいみじういたはしうおぼえたまふぞ、 あながちなるや。宮は、わりなくかたはらいたきに、汗も流れてぞおはしける。 中将は、なかなかなる心地の、乱るやうなれば、まかでたまひぬ。 |
中将の君は、顔色が変っていく心地がして、恐ろしくも、かたじけなくも、嬉しくも、哀れにも、あちこちと揺れ動く思いで、涙が落ちてしまいそうである。お声を上げたりして、にこにこしていらっしゃる様子が、とても恐いまでにかわいらしいので、自分ながら、この宮に似ているのは大変にもったいなくお思いになるとは、身贔屓に過ぎるというものであるよ。宮は、どうにもいたたまれない心地がして、冷汗をお流しになっているのであった。中将は、かえって複雑な思いが、乱れるようなので、退出なさった。 |
源氏は顔の色も変わる気がしておそろしくも、もったいなくも、うれしくも、身にしむようにもいろいろに思って涙がこぼれそうだった。ものを言うようなかっこうにお口をお動かしになるのが非常にお美しかったから、自分ながらもこの顔に似ているといわれる顔は尊重すべきであるとも思った。宮はあまりの片腹痛さに汗を流しておいでになった。源氏は若宮を見て、また予期しない父性愛の心を乱すもののあるのに気がついて退出してしまった。 |
Tyuuzyaunokimi, omote no iro kaharu kokoti si te, osorosiu mo, katazikenaku mo, uresiku mo, ahare ni mo, katagata uturohu kokoti si te, namida oti nu besi. Monogatari nado si te, uti-wemi tamahe ru ga, ito yuyusiu utukusiki ni, waga mi nagara, kore ni ni tara m ha imiziu itahasiu oboye tamahu zo, anagati naru ya! Miya ha, warinaku kataharaitaki ni, ase mo nagare te zo ohasi keru. Tyuuzyau ha, nakanaka naru kokoti no, midaru yau nare ba, makade tamahi nu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.6 | わが御かたに臥したまひて、「胸のやるかたなきほど過ぐして、大殿へ」と思す。 御前の前栽の、何となく青みわたれるなかに、常夏のはなやかに咲き出でたるを、折らせたまひて、 命婦の君のもとに、書きたまふこと、多かるべし。 |
ご自邸でお臥せりになって、「胸のどうにもならない悩みが収まってから、大殿へ出向こう」とお思いになる。お庭先の前栽が、どことなく青々と見渡される中に、常夏の花がぱあっと色美しく咲き出しているのを、折らせなさって、命婦の君のもとに、お書きになること、多くあるようだ。 |
源氏は二条の院の東の |
Waga ohom-kata ni husi tamahi te, "Mune no yaru kata naki hodo sugusi te, Ohoidono he." to obosu. Omahe no sensai no, nani to naku awomi watare ru naka ni, tokonatu no hanayaka ni saki ide taru wo, wora se tamahi te, Myaubunokimi no moto ni, kaki tamahu koto, ohokaru besi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.7 | 「 よそへつつ見るに心はなぐさまで ★ 露けさまさる撫子の花 |
「思いよそえて見ているが、気持ちは慰まず 涙を催させる撫子の花の花であるよ |
よそへつつ見るに心も慰まで |
"Yosohe tutu miru ni kokoro ha nagusama de tuyukesa masaru nadesiko no hana |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.8 | 花に咲かなむ、と ★思ひたまへしも、かひなき世にはべりければ」 |
花と咲いてほしい、と存じておりましたが、効ない二人の仲でしたので」 |
露けさまさる撫子の花 花を子のように思って愛することはついに不可能であることを知りました。 |
Hana ni saka nam, to omohi tamahe si mo, kahinaki yo ni haberi kere ba." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
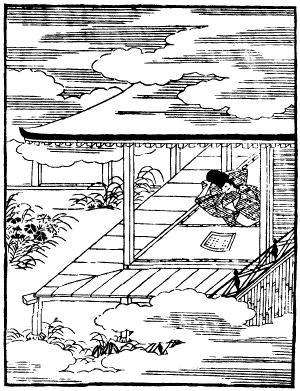 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.9 | とあり。 さりぬべき隙にやありけむ ★、御覧ぜさせて、 |
とある。ちょうど人のいない時であったのであろうか、御覧に入れて、 |
とも書かれてあった。だれも来ぬ |
to ari. Sarinubeki hima ni ya ari kem, goranze sase te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.10 | 「 ただ塵ばかり、この花びらに ★」 |
「ほんの塵ほどでも、この花びらに」 |
「ほんの |
"Tada tiri bakari, kono hanabira ni." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.11 | と聞こゆるを、わが御心にも、ものいとあはれに思し知らるるほどにて、 |
と申し上げるが、ご本人にも、もの悲しく思わずにはいらっしゃれない時なので、 |
と申し上げた。宮もしみじみお悲しい時であった。 |
to kikoyuru wo, waga mikokoro ni mo, mono ito ahare ni obosi sira ruru hodo ni te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.12 | 「 袖濡るる露のゆかりと思ふにも なほ疎まれぬ大和撫子」 |
「袖を濡らしている方の縁と思うにつけても やはり疎ましくなってしまう大和撫子です」 |
ふにもなほうとまれぬやまと撫子 |
"Sode nururu tuyu no yukari to omohu ni mo naho utomare nu yamatonadesiko |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.13 | とばかり、ほのかに書きさしたるやうなるを、 よろこびながらたてまつれる、「 例のことなれば、しるしあらじかし」と、くづほれて眺め臥したまへるに、胸うち騒ぎて、いみじくうれしきにも涙落ちぬ。 |
とだけ、かすかに中途で書き止めたような歌を、喜びながら差し上げたが、「いつものことで、返事はあるまい」と、力なくぼんやりと臥せっていらっしゃったところに、胸をときめかして、たいそう嬉しいので、涙がこぼれた。 |
とだけ、ほのかに、書きつぶしのもののように書かれてある紙を、喜びながら命婦は源氏へ送った。例のように返事のないことを予期して、なおも悲しみくずおれている時に宮の御返事が届けられたのである。胸騒ぎがしてこの非常にうれしい時にも源氏の涙は落ちた。 |
to bakari, honoka ni kaki sasi taru yau naru wo, yorokobi nagara tatemature ru, "Rei no kotonare ba, sirusi ara zi kasi." to, kuduhore te nagame husi tamahe ru ni, mune uti-sawagi te, imiziku uresiki ni mo namida oti nu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4 | 第四段 源氏、紫の君に心を慰める |
3-4 Genji comforts himself by seeing Murasaki |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.1 | つくづくと臥したるにも、やるかたなき心地すれば、 例の、慰めには西の対にぞ渡りたまふ。 |
つくづくと物思いに沈んでいても、晴らしようのない気持ちがするので、いつものように、気晴らしには西の対にお渡りになる。 |
じっと物思いをしながら寝ていることは堪えがたい気がして、例の慰め場所西の対へ行って見た。 |
Tukuduku to husi taru ni mo, yarukatanaki kokoti sure ba, rei no, nagusame ni ha nisinotai ni zo watari tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.2 | しどけなくうちふくだみたまへる鬢ぐき、あざれたる袿姿にて、笛をなつかしう吹きすさびつつ、のぞきたまへれば、 女君、ありつる花の露に濡れたる心地して、添ひ臥したまへるさま、うつくしうらうたげなり。 愛敬こぼるるやうにて、 おはしながらとくも渡りたまはぬ、なまうらめしかりければ、 例ならず、背きたまへるなるべし。端の方についゐて、 |
取り繕わないで毛羽だっていらっしゃる鬢ぐき、うちとけた袿姿で、笛を慕わしく吹き鳴らしながら、お立ち寄りになると、女君、先程の花が露に濡れたような感じで、寄り臥していらっしゃる様子、かわいらしく可憐である。愛嬌がこぼれるようで、おいでになりながら早くお渡り下さらないのが、何となく恨めしかったので、いつもと違って、すねていらっしゃるのであろう。端の方に座って、 |
少し乱れた髪をそのままにして部屋着の |
Sidokenaku uti-hukudami tamahe ru binguki, azare taru utikisugata nite, hue wo natukasiu huki susabi tutu, nozoki tamahe re ba, Womnagimi, arituru hana no tuyu ni nure taru kokoti si te, sohi husi tamahe ru sama, utukusiu rautage nari. Aigyau koboruru yau ni te, ohasi nagara toku mo watari tamaha nu, nama-uramesikari kere ba, rei nara zu, somuki tamahe ru naru besi. Hasi no kata ni tui-wi te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.3 | 「 こちや」 |
「こちらへ」 |
「こちらへいらっしゃい」 |
"Koti ya!" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.4 | とのたまへど、おどろかず、 |
とおっしゃるが、素知らぬ顔で、 |
と言っても素知らぬ顔をしている。 |
to notamahe do, odoroka zu, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.5 | 「 ▼ 入りぬる磯の」 |
「お目にかかることが少なくて」 |
「入りぬる |
"Iri nuru iso no" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.6 | と口ずさみて、口おほひしたまへるさま、いみじうされてうつくし。 |
と口ずさんで、口を覆っていらっしゃる様子、たいそう色っぽくてかわいらしい。 |
と口ずさんで、 |
to kutizusami te, kuti ohohi si tamahe ru sama, imiziu sare te utukusi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.7 | 「 あな、憎。かかること口馴れたまひにけりな。 ▼ みるめに飽くは、まさなきことぞよ」 |
「まあ、憎らしい。このようなことをおっしゃるようになりましたね。みるめに人を飽きるとは、良くないことですよ」 |
「つまらない歌を歌っているのですね。始終見ていなければならないと思うのはよくないことですよ」 |
"Ana, niku! Kakaru koto kuti nare tamahi ni keri na! Mirume ni aku ha, masa naki koto zo yo." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.8 | とて、人召して、御琴取り寄せて弾かせたてまつりたまふ。 |
と言って、人を召して、お琴取り寄せてお弾かせ申し上げなさる。 |
源氏は琴を女房に出させて紫の君に |
tote, hito mesi te, ohom-koto toriyose te hika se tatematuri tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.9 | 「 箏の琴は、中の細緒の堪へがたきこそところせけれ」 |
「箏の琴は、中の細緒が切れやすいのが厄介だ」 |
「十三 |
"Saunokoto ha, naka no hosowo no tahe gataki koso tokorosekere." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.10 | とて、平調におしくだして調べたまふ。 かき合はせばかり弾きて、 さしやりたまへれば、え怨じ果てず、いとうつくしう弾きたまふ。 |
と言って、平調に下げてお調べになる。調子合わせの小曲だけ弾いて、押しやりなさると、いつまでもすねてもいられず、とてもかわいらしくお弾きになる。 |
と言って、 |
tote, Hyaudeu ni osi-kudasi te sirabe tamahu. Kakiahase bakari hiki te, sasi-yari tamahe re ba, e wenzi hate zu, ito utukusiu hiki tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.11 | 小さき御ほどに、 さしやりて、ゆしたまふ御手つき、いとうつくしければ、らうたしと思して、 笛吹き鳴らしつつ教へたまふ。いとさとくて、かたき調子どもを、ただひとわたりに習ひとりたまふ。大方 らうらうじうをかしき御心ばへを、「 思ひしことかなふ」と思す。「 保曾呂惧世利」といふものは、名は憎けれど、おもしろう 吹きすさびたまへるに、かき合はせ、まだ若けれど、 拍子違はず上手めきたり。 |
お小さいからだで、左手をさしのべて、弦を揺らしなさる手つき、とてもかわいらしいので、愛しいとお思いになって、笛吹き鳴らしながらお教えになる。とても賢くて難しい調子などを、たった一度で習得なさる。何事につけても才長けたご性格を、「期待していた通りである」とお思いになる。「保曽呂具世利」という曲目は、名前は嫌だが、素晴らしくお吹きになると、合奏させて、まだ未熟だが、拍子を間違えず上手のようである。 |
小さい人が左手を伸ばして |
Tihisaki ohom-hodo ni, sasi-yari te, yusi tamahu ohom-tetuki, ito utukusikere ba, rautasi to obosi te, hue huki narasi tutu wosihe tamahu. Ito satoku te, kataki teusi-domo wo, tada hito watari ni narahi tori tamahu. Ohokata raurauziu wokasiki mikokorobahe wo, "Omohi si koto kanahu." to obosu. 'Hosoroguseri' to ihu mono ha, na ha nikukere do, omosirou huki susabi tamahe ru ni, kakiahase, mada wakakere do, hausi tagaha zu zyauzumeki tari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.12 | 大殿油参りて、絵どもなど御覧ずるに、「出でたまふべし」とありつれば、人びと声づくりきこえて、 |
大殿油を燈して、絵などを御覧になっていると、「お出かけになる予定」とあったので、供人たちが咳払いし合図申して、 |
|
Ohotonabura mawiri te, we-domo nado goranzuru ni, "Ide tamahu besi" to ari ture ba, hitobito kowadukuri kikoye te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.13 | 「 雨降りはべりぬべし」 |
「雨が降って来そうでございます」 |
「雨が降りそうでございます」 |
"Ame huri haberi nu besi." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.14 | など言ふに、 姫君、例の、心細くて屈したまへり。絵も見さして、うつぶしておはすれば、いとらうたくて、御髪のいとめでたくこぼれかかりたるを、かき撫でて、 |
などと言うので、姫君、いつものように心細くふさいでいらっしゃった。絵を見ることも止めて、うつ伏していらっしゃるので、とても可憐で、お髪がとても見事にこぼれかかっているのを、かき撫でて、 |
などと言うのを聞くと、紫の君はいつものように心細くなってめいり込んでいった。絵も見さしてうつむいているのがかわいくて、こぼれかかっている美しい髪をなでてやりながら、 |
nado ihu ni, Himegimi, rei no, kokorobosoku te ku'si tamahe ri. We mo mi sasi te, utubusi te ohasure ba, ito rautaku te, migusi no ito medetaku kobore kakari taru wo, kaki-nade te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.15 | 「 他なるほどは恋しくやある」 |
「出かけている間は寂しいですか」 |
「私がよそに行っている時、あなたは寂しいの」 |
"Hoka naru hodo ha kohisiku ya aru?" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.16 | とのたまへば、 うなづきたまふ。 |
とおっしゃると、こっくりなさる。 |
と言うと女王はうなずいた。 |
to notamahe ba, unaduki tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.17 | 「 我も、一日も見たてまつらぬはいと苦しうこそ ▼ あれど、幼くおはするほどは、心やすく思ひきこえて、まづ、くねくねしく怨むる人の心破らじと思ひて、 むつかしければ、しばしかくもありくぞ。 おとなしく見なしては、他へもさらに行くまじ。人の怨み負はじなど思ふも、世に長うありて、思ふさまに見えたてまつらむと思ふぞ」 |
「わたしも、一日もお目にかからないでいるのは、とてもつらいことですが、お小さくいらっしゃるうちは、気安くお思い申すので、まず、ひねくれて嫉妬する人の機嫌を損ねまいと思って、うっとうしいので、暫く間はこのように出かけるのですよ。大人におなりになったら、他の所へは決して行きませんよ。人の嫉妬を受けまいなどと思うのも、長生きをして、思いのままに一緒にお暮らし申したいと思うからですよ」 |
「私だって一日あなたを見ないでいるともう苦しくなる。けれどあなたは小さいから私は安心していてね、私が行かないといろいろな意地悪を言っておこる人がありますからね。今のうちはそのほうへ行きます。あなたが大人になれば決してもうよそへは行かない。人からうらまれたくないと思うのも、長く生きていて、あなたを幸福にしたいと思うからです」 |
"Ware mo, hitohi mo mi tatematura nu ha ito kurusiu koso are do, wosanaku ohasuru hodo ha, kokoroyasuku omohi kikoye te, madu, kunekunesiku uramuru hito no kokoro yabura zi to omohi te, mutukasikere ba, sibasi kaku mo ariku zo. Otonasiku minasi te ha, hoka he mo sarani iku mazi. Hito no urami oha zi nado omohu mo, yo ni nagau ari te, omohu sama ni miye tatematura m to omohu zo." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.18 | など、こまごまと語らひきこえたまへば、さすがに恥づかしうて、ともかくもいらへきこえたまはず。やがて御膝に寄りかかりて、寝入りたまひぬれば、いと心苦しうて、 |
などと、こまごまとご機嫌をお取り申されると、そうは言うものの恥じらって、何ともお返事申し上げなされない。そのままお膝に寄りかかって、眠っておしまになったので、とてもいじらしく思って、 |
などとこまごま話して聞かせると、さすがに恥じて返辞もしない。そのまま |
nado, komagoma to katarahi kikoye tamahe ba, sasuga ni hadukasiu te, tomokakumo irahe kikoye tamaha zu. Yagate ohom-hiza ni yorikakari te, neiri tamahi nure ba, ito kurusiu te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.19 | 「 今宵は出でずなりぬ」 |
「今夜は出かけないことになった」 |
「もう今夜は出かけないことにする」 |
"Koyohi ha ide zu nari nu." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.20 | とのたまへば、 皆立ちて、御膳などこなたに参らせたり。姫君起こしたてまつりたまひて、 |
とおっしゃると、皆立ち上がって、御膳などをこちらに運ばせた。姫君を起こしてさし上げにさって、 |
と侍たちに言うと、その人らはあちらへ立って行って。間もなく源氏の夕飯が西の対へ運ばれた。源氏は女王を起こして、 |
to notamahe ba, mina tati te, omono nado konata ni mawirase tari. Himegimi okosi tatematuri tamahi te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.21 | 「 出でずなりぬ」 |
「出かけないことになった」 |
「もう行かないことにしましたよ」 |
"Ide zu nari nu." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.22 | と聞こえたまへば、慰みて起きたまへり。もろともにものなど参る。いとはかなげにすさびて、 |
とお話し申し上げなさると、機嫌を直してお起きになった。ご一緒にお食事を召し上がる。ほんのちょっとお箸を付けになって、 |
と言うと慰んで起きた。そうしていっしょに食事をしたが、姫君はまだはかないようなふうでろくろく食べなかった。 |
to kikoye tamahe ba, nagusami te oki tamahe ri. Morotomoni mono nado mawiru. Ito hakanage ni susabi te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.23 | 「 さらば、寝たまひねかし」 |
「では、お寝みなさい」 |
「ではお |
"Saraba, ne tamahi ne kasi." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.24 | と、危ふげに思ひ たまへれば、 かかるを見捨てては、いみじき道なりとも、おもむきがたくおぼえたまふ。 |
と不安げに思っていらっしゃるので、このような人を放ってはどんな道であっても出かけることはできない、と思われなさる。 |
出ないということは |
to, ayahuge ni omohi tamahe re ba, kakaru wo misute te ha, imiziki miti nari to mo, omomuki gataku oboye tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.25 | かやうに、とどめられたまふ折々なども多かるを、 おのづから漏り聞く人、大殿に聞こえければ、 |
このように、引き止められなさる時々も多くあるのを、自然と漏れ聞く人が、大殿にも申し上げたので、 |
こんなふうに引き止められることも多いのを、侍などの中には左大臣家へ伝える者もあってあちらでは、 |
Kayau ni, todome rare tamahu woriwori nado mo ohokaru wo, onodukara mori-kiku hito, Ohoidono ni kikoye kere ba, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.26 | 「 誰れならむ。いとめざましきことにもあるかな」 |
「誰なのでしょう。とても失礼なことではありませんか」 |
「どんな身分の人でしょう。失礼な方ですわね。 |
"Tare nara m? Ito mezamasiki koto ni mo aru kana!" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.27 | 「今までその人とも聞こえず、さやうにまつはしたはぶれなどすらむは、あてやかに心にくき人にはあらじ」 |
「今まで誰それとも知れず、そのようにくっついたまま遊んだりするような人は、上品な教養のある人ではありますまい」 |
二条の院へどこのお嬢さんがお |
"Ima made sono hito to mo kikoye zu, sayau ni matuhasi tahabure nado su ram ha, ateyaka ni kokoronikuki hito ni ha ara zi." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.28 | 「内裏わたりなどにて、はかなく見たまひけむ人を、ものめかしたまひて、人やとがめむと 隠したまふななり。心なげにいはけて聞こゆるは」 |
「宮中辺りで、ちょっと見初めたような女を、ご大層にお扱いになって、人目に立つかと隠していられるのでしょう。分別のない幼稚な人だと聞きますから」 |
御所などで始まった関係の女房級の人を奥様らしく二条の院へお入れになって、それを批難さすまいとお思いになって、だれということを秘密にしていらっしゃるのですよ。幼稚な所作が多いのですって」 |
"Uti watari nado nite, hakanaku mi tamahi kem hito wo, mono-mekasi tamahi te, hito ya togame m to kakusi tamahu na' nari. Kokoronage ni ihake te kikoyuru ha." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.29 | など、さぶらふ人びとも聞こえあへり。 |
などと、お仕えする女房たちも噂し合っていた。 |
などと女房が言っていた。 |
nado, saburahu hitobito mo kikoye ahe ri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.30 | 内裏にも、かかる人ありと聞こし召して、 |
お上におかれても、「このような女の人がいる」と、お耳に入れあそばして、 |
御所にまで二条の院の新婦の問題が聞こえていった。 |
Uti ni mo, kakaru hito ari to kikosimesi te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.31 | 「 いとほしく、 大臣の思ひ嘆かる なることも、げに、ものげなかりしほどを、おほなおほなかくものしたる心を、さばかりのことたどらぬほどにはあらじを。などか情けなくはもてなすなるらむ」 |
「気の毒に、大臣がお嘆きということも、なるほど、まだ幼かったころを、一生懸命にこんなにお世話してきた気持ちを、それくらいのことをご分別できない年頃でもあるまいに。どうして薄情な仕打ちをなさるのだろう」 |
「気の毒じゃないか。左大臣が心配しているそうだ。小さいおまえを婿にしてくれて、十二分に尽くした今日までの好意がわからない年でもないのに、なぜその娘を冷淡に扱うのだ」 |
"Itohosiku, Otodo no omohi nageka ru naru koto mo, geni, monogenakari si hodo wo, ohonaohona kaku monosi taru kokoro wo, sabakari no koto tadora nu hodo ni ha ara zi wo. Nadoka nasakenaku ha motenasu naru ram?" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.32 | と、のたまはすれど、 かしこまりたるさまにて、御いらへも聞こえたまはねば、「 心ゆかぬなめり」と、いとほしく思し召す。 |
と、仰せられるが、恐縮した様子で、お返事も申し上げられないので、「お気に入らないようだ」と、かわいそうにお思いあそばす。 |
と陛下がおっしゃっても、源氏はただ恐縮したふうを見せているだけで、何とも御返答をしなかった。 |
to, notamahasure do, kasikomari taru sama nite, ohom-irahe mo kikoye tamaha ne ba, "Kokoro yuka nu na'meri" to, itohosiku obosimesu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.33 | 「 さるは、好き好きしううち乱れて、この見ゆる女房にまれ、またこなたかなたの人びとなど、なべてならずなども見え聞こえざめるを、いかなるもののくまに隠れありきて、かく人にも怨みらるらむ」とのたまはす。 |
「その一方では、好色がましく振る舞って、ここに見える女房であれ、またここかしこの女房たちなどと、浅からぬ仲に見えたり噂も聞かないようだが、どのような人目につかない所にあちこち隠れ歩いて、このように人に怨まれることをしているのだろう」と仰せられる。 |
「格別おまえは放縦な男ではなし、女官や女御たちの女房を情人にしている |
"Saruha, sukizukisiu uti-midare te, kono miyuru nyoubau ni mare, mata konata kanata no hitobito nado, nabete nara zu nado mo miye kikoye za' meru wo, ikanaru mono no kuma ni kakure ariki te, kaku hito ni mo urami raru ram?" to notamahasu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last updated 9/20/2010(ver.2-2) 渋谷栄一校訂(C) Last updated 4/15/2009(ver.2-3) 渋谷栄一注釈 |
Last updated 5/1/2001 渋谷栄一訳(C)(ver.1-2-1) |
|
Last updated 4/15/2009 (ver.2-3) Written in Japanese roman letters by Eiichi Shibuya (C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Picture "Eiri Genji Monogatari"(1650 1st edition) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源氏物語の世界 再編集プログラム Ver 3.38: Copyright (c) 2003,2015 宮脇文経