第十帖 賢木 |
10 SAKAKI (Ohoshima-bon) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光る源氏の二十三歳秋九月から二十五歳夏まで近衛大将時代の物語 |
Tale of Hikaru-Genji's Konoe-Daisho era from September at the age of 23 to summer at the age of 25 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 第一章 六条御息所の物語 秋の別れと伊勢下向の物語 |
1 Tale of Lady Rokujo A parting in fall |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | 第一段 六条御息所、伊勢下向を決意 |
1-1 Lady Rokujo determines to go to Ise with her daughter |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.1 | 斎宮の御下り、近うなりゆくままに、御息所、もの心細く思ほす。 やむごとなくわづらはしきものにおぼえたまへりし大殿の君も亡せたまひて後、 さりともと世人も聞こえあつかひ、 宮のうちにも心ときめきせしを、その後しも、かき絶え、 あさましき御もてなしを見たまふに、 まことに憂しと思すことこそありけめ ★と、知り果てたまひぬれば、よろづのあはれを思し捨てて、ひたみちに 出で立ちたまふ。 |
斎宮の御下向、近づくなるにつれて、御息所、何となく心細くいらっしゃる。重々しくけむたいご本妻だと思っていらした大殿の姫君もお亡くなりになって後、いくら何でもと世間の人々もお噂申し、宮の内でも期待していたのに、それから後、すっかりお通いがなく、あまりなお仕向けを御覧になると、本当にお嫌いになる事があったのだろうと、すっかりお分かりになってしまったので、一切の未練をお捨てになって、一途にご出立なさる。 |
|
Saiguu no ohom-kudari, tikau nari yuku mama ni, Miyasumdokoro, mono-kokorobosoku omohosu. Yamgotonaku wadurahasiki mono ni oboye tamaheri si Ohoidono-no-Kimi mo use tamahi te noti, saritomo to yohito mo kikoye atukahi, Miya no uti ni mo kokorotokimeki se si wo, sono noti simo, kaki-taye, asamasiki ohom-motenasi wo mi tamahu ni, makoto ni usi to obosu koto koso ari keme to, siri hate tamahi nure ba, yorodu no ahare wo obosi sute te, hitamiti ni ide-tati tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.2 | 親添ひて下りたまふ例も、ことになけれど、 いと見放ちがたき御ありさまなるにことつけて、「憂き世を行き離れむ」と思すに、 大将の君、 さすがに、今はとかけ離れたまひなむも、口惜しく思されて、 御消息ばかりは、あはれなるさまにて、たびたび通ふ。対面したまはむことをば、今さらにあるまじきことと、 女君も思す。「 人は心づきなしと、思ひ置きたまふこともあらむに、我は、今すこし思ひ乱るることのまさるべきを、 あいなし」と、心強く 思すなるべし。 |
母親が付き添ってお下りになる先例も、特にないが、とても手放し難いご様子なのに託つけて、「嫌な世間から逃れ去ろう」とお思いになると、大将の君、そうは言っても、これが最後と遠くへ行っておしまいになるのも残念に思わずにはいらっしゃれず、お手紙だけは情のこもった書きぶりで、度々交わす。お会いになることは、今さらありえない事と、女君も思っていらっしゃる。「相手は気にくわないと、根に持っていらっしゃることがあろうから、自分は、今以上に悩むことがきっと増すにちがいないので、無益なこと」と、固くご決心されているのだろう。 |
斎宮に母君がついて行くような例はあまりないことでもあったが、年少でおありになるということに託して、御息所はきれいに恋から離れてしまおうとしているのであるが、源氏はさすがに冷静ではいられなかった。いよいよ御息所に行ってしまわれることは残念で、手紙だけは愛をこめてたびたび送っていた。情人として |
Oya sohi te kudari tamahu rei mo, koto ni nakere do, ito mihanati-gataki ohom-arisama naru ni kototuke te, "Ukiyo wo yuki hanare m" to obosu ni, Daisyau-no-Kimi, sasuga ni, ima ha to kake-hanare tamahi na m mo, kutiwosiku obosa re te, ohom-seusoko bakari ha, ahare naru sama nite, tabi-tabi kayohu. Taimen si tamaha m koto wo ba, imasara ni arumaziki koto to, Womna-Gimi mo obosu. "Hito ha kokorodukinasi to, omohi-oki tamahu koto mo ara m ni, ware ha, ima sukosi omohi midaruru koto no masaru beki wo, ainasi." to, kokoroduyoku obosu naru besi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.3 | もとの殿には、あからさまに渡りたまふ折々あれど、いたう忍びたまへば、大将殿、え知りたまはず。 たはやすく御心にまかせて、参うでたまふべき御すみかにはたあらねば ★、おぼつかなくて 月日も隔たりぬるに、 院の上、おどろおどろしき御悩みにはあらで、例ならず、時々悩ませたまへば、いとど御心の暇なけれど、「 つらき者に思ひ果てたまひなむも、いとほしく、人聞き情けなくや」と思し起して、野の宮に参うでたまふ。 |
里の殿には、ほんのちょっとお帰りになる時々もあるが、たいそう内々にしていらっしゃるので、大将殿、お知りになることができない。簡単にお心のままに参ってよいようなお住まいでは勿論ないので、気がかりに月日も経ってしまったところに、院の上、たいそう重い御病気というのではないが、普段と違って、時々お苦しみあそばすので、ますますお気持ちに余裕がないけれど、「薄情な者とお思い込んでしまわれるのも、おいたわしいし、人が聞いても冷淡な男だと思われはしまいか」とご決心されて、野宮にお伺いなさる。 |
野の宮から六条の |
Moto no tono ni ha, akarasama ni watari tamahu wori-wori are do, itau sinobi tamahe ba, Daisyau-dono, e siri tamaha zu. Tahayasuku mi-kokoro ni makase te, maude tamahu beki ohom-sumika ni hata ara ne ba, obotukanaku te tukihi mo hedatari nuru ni, Win-no-Uhe, odoro-odorosiki ohom-nayami ni ha ara de, rei nara zu, toki-doki nayama se tamahe ba, itodo mi-kokoro no itoma nakeredo, "Turaki mono ni omohi hate tamahi na m mo, itohosiku, hitogiki nasakenaku ya" to obosi okosi te, Nonomiya ni maude tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 | 第二段 野の宮訪問と暁の別れ |
1-2 A parting at daybreak in Nonomiya |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.1 | 九月七日ばかりなれば、「むげに今日明日」と思すに、女方も心あわたたしけれど、「 立ちながら」と、たびたび御消息ありければ、「 いでや」とは思しわづらひながら、「 いとあまり埋もれいたきを、物越ばかりの対面は」と、 人知れず待ちきこえたまひけり。 |
九月七日ころなので、「まったく今日明日だ」とお思いになると、女の方でも気忙しいが、「立ちながらでも」と、何度もお手紙があったので、「どうしたものか」とお迷いになりながらも、「あまりに控え目過ぎるから、物越しにお目にかかるのなら」と、人知れずお待ち申し上げていらっしゃるのであった。 |
九月七日であったから、もう斎宮の出発の日は迫っているのである。女のほうも今はあわただしくてそうしていられないと言って来ていたが、たびたび手紙が行くので、最後の会見をすることなどはどうだろうと |
Nagatuki nanuka bakari nare ba, "Muge ni kehu asu" to obosu ni, Womna-gata mo kokoroawatatasikere do, "Tati nagara." to, tabitabi ohom-seusoko ari kere ba, "Ide ya?" to ha obosi wadurahi nagara, "Ito amari umore itaki wo, monogosi bakari no taimen ha." to, hitosirezu mati kikoye tamahi keri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.2 | 遥けき野辺を分け入りたまふより、いとものあはれなり。秋の花、みな衰へつつ、 浅茅が原も 枯れ枯れなる虫の音に、 松風、すごく吹きあはせて、そのこととも聞き分かれぬ ★ほどに、物の音ども絶え絶え聞こえたる、いと 艶なり。 |
広々とした野辺に分け入りなさるなり、いかにも物寂しい感じがする。秋の花、みな萎れかかって、浅茅が原も枯れがれとなり虫の音も鳴き嗄らしているところに、松風、身にしみて音を添えて、いずれの琴とも聞き分けられないくらいに、楽の音が絶え絶えに聞こえて来る、まことに優艶である。 |
町を離れて広い野に出た時から、源氏は身にしむものを覚えた。もう秋草の花は皆衰えてしまって、かれがれに鳴く虫の声と松風の音が混じり合い、その中をよく耳を澄まさないでは聞かれないほどの楽音が野の宮のほうから流れて来るのであった。 |
Harukeki nobe wo wakeiri tamahu yori, ito mono ahare nari. Aki no hana, mina otorohe tutu, asadigahara mo karegare naru musi no ne ni, matukaze, sugoku huki ahase te, sono koto to mo kikiwaka re nu hodo ni, mono no ne-domo tayedaye kikoye taru, ito en nari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.3 | むつましき御前、十余人ばかり、 ▼ 御随身、 ことことしき姿ならで、いたう忍びたまへれど、ことにひきつくろひたまへる御用意、いとめでたく見えたまへば、御供なる好き者ども、 所からさへ身にしみて思へり。御心にも、「などて、今まで立ちならさざりつらむ」と、過ぎぬる方、悔しう思さる。 |
気心の知れた御前駆の者、十余人ほど、御随身、目立たない服装で、たいそうお忍びのふうをしていられるが、格別にお気を配っていらっしゃるご様子、まことに素晴らしくお見えになるので、お供の風流者など、場所が場所だけに身にしみて感じ入っていた。ご内心、「どうして、今まで来なかったのだろう」と、過ぎ去った日々、後悔せずにはいらっしゃれない。 |
前駆をさせるのに |
Mutumasiki gozen, zihuyo-nin bakari, mizuizin, kotokotosiki sugata nara de, itau sinobi tamahe re do, koto ni hiki-tukurohi tamahe ru ohom-youi, ito medetaku miye tamahe ba, ohom-tomo naru sukimono-domo, tokorokara sahe mi ni simi te omohe ri. Mikokoro ni mo, "Nadote, ima made tatinarasa zari tu ram?" to, sugi nuru kata, kuyasiu obosa ru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.4 | ものはかなげなる小柴垣を大垣にて、板屋どもあたりあたりいと かりそめなり。 黒木の鳥居ども、さすがに神々しう見わたされて、わづらはしきけしきなるに、神司の者ども、ここかしこにうちしはぶきて、おのがどち、物うち言ひたるけはひなども、他にはさま変はりて見ゆ。 火焼屋 かすかに光りて、人気すくなく、しめじめとして、ここにもの思はしき人の、月日を隔てたまへらむほどを思しやるに、いといみじうあはれに心苦し。 |
ちょっとした小柴垣を外囲いにして、板屋が幾棟もあちこちに仮普請のようである。黒木の鳥居どもは、やはり神々しく眺められて、遠慮される気がするが、神官どもが、あちこちで咳払いをして、お互いに、何か話している様子なども、他所とは様子が変わって見える。火焼屋、微かに明るくて、人影も少なく、しんみりとしていて、ここに物思いに沈んでいる人が、幾月日も世間から離れて過ごしてこられた間のことをご想像なさると、とてもたまらなくおいたわしい。 |
野の宮は簡単な |
Mono-hakanage naru kosibagaki wo ohogaki nite, itaya-domo atari-atari ito karisome nari. Kuroki no toriwi-domo, sasuga ni kaugausiu miwatasa re te, wadurahasiki kesiki naru ni, kamdukasa no mono-domo, kokokasiko ni uti-sihabuki te, onoga-doti, mono uti-ihi taru kehahi nado mo, hoka ni ha sama kahari te miyu. Hitakiya kasuka ni hikari te, hitoke sukunaku, simezime to si te, koko ni mono omohasiki hito no, tukihi wo hedate tamahe ra m hodo wo obosi-yaru ni, ito imiziu ahare ni kokorogurusi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.5 | 北の対のさるべき所に立ち隠れたまひて、御消息聞こえたまふに、遊びはみなやめて、心にくきけはひ、あまた聞こゆ。 |
北の対の適当な場所に立ち隠れなさって、ご来訪の旨をお申し入れなさると、管弦のお遊びはみな止めて、奥ゆかしい気配、たくさん聞こえる。 |
北の対の下の目だたない所に立って案内を申し入れると音楽の声はやんでしまって、若い何人もの女の |
Kitanotai no sarubeki tokoro ni tati kakure tamahi te, ohom-seusoko kikoye tamahu ni, asobi ha mina yame te, kokoro-nikuki kehahi, amata kikoyu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.6 | 何くれの人づての御消息ばかりにて、みづからは対面したまふべきさまにもあらねば、「いとものし」と思して、 |
何やかやと女房を通じてのご挨拶ばかりで、ご自身はお会いなさる様子もないので、「まことに面白くない」とお思いになって、 |
取り次ぎの女があとではまた変わって出て来たりしても、自身で逢おうとしないらしいのを源氏は飽き足らず思った。 |
Nanikure no hitodute no ohom-seusoko bakari nite, midukara ha taimen si tamahu beki sama ni mo ara ne ba, "Ito monosi." to obosi te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.7 | 「 かうやうの歩きも、今はつきなきほどになりにてはべるを、思ほし知らば、かう 注連のほかにはもてなしたまはで。いぶせうはべることをも、あきらめはべりにし がな」 |
「このような外出も、今では相応しくない身分になってしまったことを、お察しいただければ、このような注連の外には、立たせて置くようなことはなさらないで。胸に溜まっていますことをも、晴らしたいものです」 |
「恋しい方を |
"Kauyau no ariki mo, ima ha tukinaki hodo ni nari ni te haberu wo, omohosi sira ba, kau sime no hoka ni ha motenasi tamaha de. Ibuseu haberu koto wo mo, akirame haberi ni si gana." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.8 | と、まめやかに聞こえたまへば、 人びと、 |
と、真面目に申し上げなさると、女房たち、 |
とまじめに源氏が頼むと女房たちも、 |
to, mameyaka ni kikoye tamahe ba, hitobito, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.9 | 「 げに、いとかたはらいたう」 |
「おっしゃるとおり、とても見てはいられませんわ」 |
「おっしゃることのほうがごもっともでございます。 |
"Geni, ito kataharaitau." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.10 | 「立ちわづらはせたまふに、いとほしう」 |
「お立ちん坊のままでいらっしゃっては、お気の毒で」 |
お気の毒なふうにいつまでもお立たせしておきましては済みません」 |
"Tatiwaduraha se tamahu ni, itohosiu." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.11 | など、あつかひきこゆれば、「 いさや。ここの人目も見苦しう、 かの思さむことも、若々しう、 出でゐむが、今さらにつつましきこと」と思すに、いともの憂けれど、情けなうもてなさむにもたけからねば、とかくうち嘆き、やすらひて、ゐざり出でたまへる御けはひ、いと心にくし。 |
などと、お取りなし申すので、「さてどうしたものか。ここの女房たちの目にも体裁が悪いだろうし、あの方がお思いになることも、年甲斐もなく、端近に出て行くのが、今さらに気後れして」とお思いになると、とても億劫であるが、冷淡な態度をとるほど気強くもないので、とかく溜息をつきためらって、いざり出ていらっしゃったご様子、まことに奥ゆかしい。 |
ととりなす。どうすればよいかと御息所は迷った。 |
nado, atukahi kikoyure ba, "Isaya! Koko no hitome mo migurusiu, kano obosa m koto mo, wakawakasiu, ide wi m ga, imasara ni tutumasiki koto." to obosu ni, ito mono-ukere do, nasakenau motenasa m ni mo takekara ne ba, tokaku uti-nageki, yasurahi te, wizari ide tamahe ru ohom-kehahi, ito kokoronikusi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.12 | 「 こなたは、簀子ばかりの許されははべりや」 |
「こちらでは、簀子に上がるくらいのお許しはございましょうか」 |
「お縁側だけは許していただけるでしょうか」 |
"Konata ha, sunoko bakari no yurusa re ha haberi ya?" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.13 | とて、上りゐたまへり。 |
と言って、上がっておすわりになった。 |
と言って、上に上がっていた。 |
tote, nobori wi tamahe ri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.14 | はなやかにさし出でたる夕月夜に、 うち振る舞ひたまへるさま、匂ひに、似るものなくめでたし。月ごろのつもりを、つきづきしう聞こえたまはむも、まばゆきほどになりにければ、榊をいささか折りて持たまへりけるを、挿し入れて、 |
明るく照り出した夕月夜に、立ち居振る舞いなさるご様子、美しさに、似るものがなく素晴らしい。幾月ものご無沙汰を、もっともらしく言い訳申し上げなさるのも、面映ゆいほどになってしまったので、榊を少し折って持っていらしたのを、差し入れて、 |
長い時日を中にした会合に、無情でなかった言いわけを散文的に言うのもきまりが悪くて、 |
Hanayaka ni sasi-ide taru yuhudukuyo ni, uti-hurumahi tamahe ru sama, nihohi ni, niru mono naku medetasi. Tukigoro no tumori wo, tukidukisiu kikoye tamaha m mo, mabayuki hodo ni nari ni kere ba, sakaki wo isasaka wori te mo' tamahe ri keru wo, sasiire te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.15 | 「 変らぬ色をしるべにてこそ、斎垣も越えはべりにけれ。さも心憂く ★ ★」 |
「変わらない心に導かれて、禁制の垣根も越えて参ったのです。何とも薄情な」 |
「私の心の |
"Kahara nu iro wo sirube nite koso, igaki mo koye haberi ni kere. Samo kokorouku." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.16 | と聞こえたまへば、 |
と申し上げなさると、 |
と言った。 |
to kikoye tamahe ba, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.17 | 「 神垣はしるしの杉もなきものを ★ いかにまがへて折れる榊ぞ」 |
「ここには人の訪ねる目印の杉もないのに どう間違えて折って持って来た榊なのでしょう」 |
いかにまがへて折れる榊ぞ |
"Kamigaki ha sirusi no sugi mo naki mono wo ika ni magahe te wore ru sakaki zo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.18 | と聞こえたまへば、 |
と申し上げなさると、 |
御息所はこう答えたのである。 |
to kikoye tamahe ba, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.19 | 「 少女子があたりと思へば榊葉の ★ ★ 香をなつかしみとめてこそ折れ」 |
「少女子がいる辺りだと思うと 榊葉が慕わしくて探し求めて折ったのです」 |
|
"Wotomego ga atari to omohe ba sakakiba no ka wo natukasimi tome te koso wore |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.20 | おほかたのけはひわづらはしけれど、御簾ばかりはひき着て、長押におしかかりてゐたまへり。 |
周囲の雰囲気は憚られるが、御簾だけを引き被って、長押に持たれかかって座っていらっしゃった。 |
と源氏は言ったのであった。潔斎所の空気に威圧されながらも御簾の中へ上半身だけは入れて |
Ohokata no kehahi wadurahasikere do, misu bakari ha hiki-ki te, nagesi ni osikakari te wi tamahe ri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.21 | 心にまかせて見たてまつりつべく、人も慕ひざまに思したりつる年月は、のどかなりつる御心おごりに、 さしも思されざりき。 |
思いのままにお目にかかることができ、相手も慕っているようにお思いになっていらっしゃった年月の間は、のんびりといい気になって、それほどまでご執心なさらなかった。 |
御息所が完全に源氏のものであって、しかも情熱の度は源氏よりも高かった時代に、源氏は慢心していた形でこの人の真価を認めようとはしなかった。 |
Kokoro ni makase te mi tatematuri tu beku, hito mo sitahi zama ni obosi tari turu tosituki ha, nodoka nari turu mikokoroogori ni, sasimo obosa re zari ki. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.22 | また、心のうちに、「 いかにぞや、疵ありて」、思ひきこえたまひにし後、はた、あはれもさめつつ、かく御仲も隔たりぬるを、めづらしき御対面の昔おぼえたるに、「あはれ」と、思し乱るること限りなし。来し方、行く先、思し続けられて、心弱く泣きたまひぬ。 |
また一方、心の中に、「いかがなものか、欠点があって」と、お思い申してから後、やはり、情愛も次第に褪めて、このように仲も離れてしまったのを、久しぶりのご対面が昔のことを思い出させるので、「ああ」と、悩ましさで胸が限りなくいっぱいになる。今までのこと、将来のこと、それからそれへとお思い続けられて、心弱く泣いてしまった。 |
またいやな事件も起こって来た時からは、自身の心ながらも恋を成るにまかせてあった。それが昔のようにして語ってみると、にわかに大きな力が源氏をとらえて御息所のほうへ引き寄せるのを源氏は感ぜずにいられなかった。自分はこの人が好きであったのだという認識の上に立ってみると、二人の昔も恋しくなり、別れたのちの寂しさも痛切に考えられて、源氏は泣き出してしまったのである。 |
Mata, kokoro no uti ni, "Ikani zo ya, kizu ari te", omohi kikoye tamahi ni si noti, hata, ahare mo same tutu, kaku ohom-naka mo hedatari nuru wo, medurasiki ohom-taimen no mukasi oboye taru ni, "Ahare!" to, obosi midaruru koto kagiri nasi. Kosikata, yukusaki, obosi tuduke rare te, kokoroyowaku naki tamahi nu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.23 | 女は、さしも見えじと 思しつつむめれど、え忍びたまはぬ御けしきを、いよいよ心苦しう、なほ思しとまるべきさまにぞ、 聞こえたまふめる。 |
女は、そうとは見せまいと気持ちを抑えていられるようだが、とても我慢がおできになれないご様子を、ますますお気の毒に、やはりお思い止まるように、お制止申し上げになるようである。 |
女は感情をあくまでもおさえていようとしながらも、堪えられないように涙を流しているのを見るといよいよ源氏は心苦しくなって、伊勢行きを思いとどまらせようとするのに身を入れて話していた。 |
Womna ha, sasimo miye zi to obosi tutumu mere do, e sinobi tamaha nu mikesiki wo, iyoiyo kokorogurusiu, naho obosi tomaru beki sama ni zo, kikoye tamahu meru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.24 | 月も入りぬるにや、あはれなる空を眺めつつ、怨みきこえたまふに、ここら思ひ集めたまへる つらさも消えぬべし。やうやう、「今は」と、思ひ離れたまへるに、「 さればよ」と、なかなか心動きて、思し乱る。 |
月も入ったのであろうか、しみじみとした空を物思いに耽って見つめながら、恨み言を申し上げなさると、積もり積もっていらした恨みもきっと消えてしまうことだろう。だんだんと、「今度が最後」と、未練を断ち切って来られたのに、「やはり思ったとおりだ」と、かえって心が揺れて、お悩みになる。 |
もう月が落ちたのか、寂しい色に変わっている空をながめながら、自身の真実の認められないことで |
Tuki mo iri nuru ni ya, ahare naru sora wo nagame tutu, urami kikoye tamahu ni, kokora omohi atume tamahe ru turasa mo kiye nu besi. Yauyau, "Ima ha." to, omohi hanare tamahe ru ni, "Sareba yo!" to, nakanaka kokoro ugoki te, obosi midaru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.25 | 殿上の若君達などうち連れて、とかく立ち わづらふなる庭の たたずまひも、げに艶なるかたに、うけばりたるありさまなり。思ほし 残すことなき御仲らひに、聞こえ交はしたまふことども、 まねびやらむかたなし。 |
殿上の若公達などが連れ立って、何かと佇んでは心惹かれたという庭の風情も、なるほど優艶という点では、どこの庭にも負けない様子である。物のあわれの限りを尽くしたお二人の間柄で、お語らいになった内容、そのまま筆に写すことはできない。 |
若い殿上役人が始終二、三人連れで来てはここの文学的な空気に浸っていくのを喜びにしているという、この構えの中のながめは源氏の目にも確かに |
Tenzyau no waka-Kimdati nado utiture te, tokaku tatiwadurahu naru niha no tatazumahi mo, geni en naru kata ni, ukebari taru arisama nari. Omohosi nokosu koto naki ohom-nakarahi ni, kikoyekahasi tamahu koto-domo, manebi yara m kata nasi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.26 | やうやう明けゆく空のけしき、ことさらに作り出でたらむやうなり。 |
だんだんと明けて行く空の風情、特別に作り出したかのようである。 |
ようやく白んできた空がそこにあるということもわざとこしらえた背景のようである。 |
Yauyau akeyuku sora no kesiki, kotosara ni tukuriide tara m yau nari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.27 | 「 暁の別れはいつも露けきを こは世に知らぬ秋の空かな」 |
「明け方の別れにはいつも涙に濡れたが 今朝の別れは今までにない涙に曇る秋の空ですね」 |
暁の別れはいつも露けきを こは世にしらぬ秋の空かな |
"Akatuki no wakare ha itumo tuyukeki wo ko ha yo ni sira nu aki no sora kana |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.28 | 出でがてに、御手をとらへてやすらひたまへる、いみじうなつかし。 |
帰りにくそうに、お手を捉えてためらっていられる、たいそう優しい。 |
と歌った源氏は、帰ろうとしてまた女の手をとらえてしばらく去りえないふうであった。 |
Ide-gate ni, ohom-te wo torahe te yasurahi tamahe ru, imiziu natukasi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.29 | 風、いと冷やかに吹きて、 松虫の鳴きからしたる声も、折知り顔なるを、さして思ふことなきだに、聞き過ぐしがたげなるに、 まして、わりなき御心惑ひどもに、なかなか、こともゆかぬにや。 |
風、とても冷たく吹いて、松虫が鳴き嗄らした声も、気持ちを知っているかのようなのを、それほど物思いのない者でさえ、聞き過ごしがたいのに、まして、どうしようもないほど思い乱れていらっしゃるお二人には、かえって、歌も思うように行かないのだろうか。 |
冷ややかに九月の風が吹いて、鳴きからした松虫の声の聞こえるのもこの恋人たちの寂しい別れの伴奏のようである。何でもない人にも身にしむ思いを与えるこうした晩秋の夜明けにいて、あまりに悲しみ過ぎたこの人たちはかえって実感をよい歌にすることができなかったと見える。 |
Kaze, ito hiyayaka ni huki te, matumusi no naki karasi taru kowe mo, worisirigaho naru wo, sasite omohu koto naki dani, kiki sugusi gatage naru ni, masite, warinaki mikokoromadohi-domo ni, nakanaka, koto mo yuka nu ni ya. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.30 | 「 おほかたの秋の別れも悲しきに 鳴く音な添へそ野辺の松虫」 |
「ただでさえ秋の別れというものは悲しいものなのに さらに鳴いて悲しませてくれるな野辺の松虫よ」 |
鳴く |
"Ohokata no aki no wakare mo kanasiki ni naku ne na sohe so nobe no matumusi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.31 | 悔しきこと多かれど、かひなければ、明け行く空もはしたなうて、出でたまふ。 道のほどいと露けし。 |
悔やまれることが多いが、しかたのないことなので、明けて行く空も体裁が悪くて、お帰りになる。道程はまことに露っぽい。 |
|
Kuyasiki koto ohokare do, kahi nakere ba, akeyuku sora mo hasitanau te, ide tamahu. Miti no hodo ito tuyukesi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.32 | 女も、え心強からず、名残あはれにて眺めたまふ。ほの見たてまつりたまへる月影の御容貌、なほとまれる匂ひなど、 若き人びとは身にしめて、あやまちも しつべく、めできこゆ。 |
女も、気強くいられず、その後の物思いに沈んでいらっしゃる。ほのかに拝見なさった月の光に照らされたお姿、まだ残っている匂いなど、若い女房たちは身に染みて、心得違いをしかねないほど、お褒め申し上げる。 |
女も冷静でありえなかった。別れたのちの物思いを抱いて弱々しく秋の朝に対していた。ほのかに月の光に見た源氏の姿をなお幻に御息所は見ているのである。源氏の衣服から散ったにおい、そんなものは若い女房たちを |
Womna mo, e kokoroduyokara zu, nagori ahare ni te nagame tamahu. Hono-mi tatematuri tamahe ru tukikage no ohom-katati, naho tomare ru nihohi nado, wakaki hitobito ha mi ni sime te, ayamati mo si tu beku, mede kikoyu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.33 | 「いかばかりの道にてか、かかる御ありさまを見捨てては、別れきこえむ」 |
「どれほどの余儀ない旅立ちだからといっても、あのようなお方をお見限って、お別れ申し上げられようか」 |
「どんないい所へだって、あの大将さんをお見上げすることのできない国へは行く気がしませんわね」 |
"Ikabakari no miti nite ka, kakaru ohom-arisama wo misute te ha, wakare kikoye m." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.34 | と、 あいなく涙ぐみあへり。 |
と、わけもなく涙ぐみ合っていた。 |
こんなことを言う女房は皆涙ぐんでいた。 |
to, ainaku namidagumi ahe ri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3 | 第三段 伊勢下向の日決定 |
1-3 It is decided the day to go to Ise |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.1 | 御文、常よりもこまやかなるは、思しなびくばかりなれど、またうち返し、定めかねたまふべきことならねば、いとかひなし。 |
後朝の御文、いつもより情愛濃やかなのは、お気持ちも傾きそうなほどであるが、また改めて、お思い直しなさるべき事でもないので、まことにどうにもならない。 |
この日源氏から来た手紙は情がことにこまやかに出ていて、御息所に旅を断念させるに足る力もあったが、官庁への通知も済んだ今になって変更のできることでもなかった。 |
Ohom-humi, tune yori mo komayaka naru ha, obosi nabiku bakari nare do, mata uti-kahesi, sadame-kane tamahu beki koto nara ne ba, ito kahinasi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.2 | 男は、さしも思さぬことをだに、情けのためには よく言ひ続けたまふべかめれば、まして、おしなべての列には思ひきこえたまはざりし御仲の、かくて背きたまひなむとするを、口惜しうもいとほしうも、思し悩むべし。 |
男は、それほどお思いでもないことでも、恋路のためには上手に言い続けなさるようなので、まして、並々の相手とはお思い申し上げていられなかったお間柄で、このようにしてお別れなさろうとするのを、残念にもおいたわしくも、お思い悩んでいられるのであろう。 |
男はそれほど思っていないことでも恋の手紙には感情を誇張して書くものであるが、今の源氏の場合は、ただの恋人とは決して思っていなかった御息所が、愛の清算をしてしまったふうに遠国へ行こうとするのであるから、残念にも思われ、気の毒であるとも反省しての |
Wotoko ha, sasimo obosa nu koto wo dani, nasake no tame ni ha yoku ihi tuduke tamahu beka' mere ba, masite, osinabete no tura ni ha omohi kikoye tamaha zari si ohom-naka no, kakute somuki tamahi na m to suru wo, kutiwosiu mo itohosiu mo, obosi nayamu besi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.3 | 旅の御装束よりはじめ、人びとのまで、何くれの御調度など、いかめしうめづらしきさまにて、とぶらひきこえたまへど、何とも思されず。あはあはしう心憂き名をのみ流して、あさましき身のありさまを、今はじめたらむやうに、ほど近くなるままに、起き臥し嘆きたまふ。 |
旅のご装束をはじめとして、女房たちの物まで、何かとご調度類など、立派で目新しいさまに仕立てて、お餞別を申し上げになさるが、何ともお思いにならない。軽々しく嫌な評判ばかりを流してしまって、あきれはてた身の有様を、今さらのように、下向が近づくにつれて、起きても寝てもお嘆きになる。 |
御息所の旅中の衣服から、女房たちのまで、そのほかの旅の用具もりっぱな物をそろえた |
Tabi no ohom-sauzoku yori hazime, hitobito no made, nanikure no miteudo nado, ikamesiu medurasiki sama nite, toburahi kikoye tamahe do, nani to mo obosa re zu. Ahaahasiu kokorouki na wo nomi nagasi te, asamasiki mi no arisama wo, ima hazime tara m yau ni, hodo tikaku naru mama ni, okihusi nageki tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.4 | 斎宮は、 若き御心地に、不定なりつる御出で立ちの、かく定まりゆくを、うれし、とのみ思したり。 世人は、例なきことと、もどきもあはれがりも、 さまざまに聞こゆべし。 何ごとも、人にもどきあつかはれぬ際はやすげなり。なかなか世に抜け出でぬる人の御あたりは、所狭きこと多くなむ。 |
斎宮は、幼な心に、決定しなかったご出立が、このように決まってゆくのを、嬉しい、とばかりお思いでいた。世間の人々は、先例のないことだと、非難も同情も、いろいろとお噂申しているようだ。何事でも、人から非難されないような身分の者は気楽なものである。かえって世に抜きん出た方のご身辺は窮屈なことが多いことである。 |
お若い斎宮は、いつのことともしれなかった出発の日の決まったことを喜んでおいでになった。世間では、母君がついて行くことが異例であると批難したり、ある者はまた御息所の強い母性愛に同情したりしていた。御息所が平凡な人であったら、決してこうではなかったことと思われる。傑出した人の行動は目に立ちやすくて気の毒である。 |
Saiguu ha, wakaki mikokoti ni, hudyau nari turu ohom-idetati no, kaku sadamari yuku wo, uresi, to nomi obosi tari. Yohito ha, rei naki koto to, modoki mo aharegari mo, samazama ni kikoyu besi. Nanigoto mo, hito ni modoki atukaha re nu kiha ha yasuge nari. Nakanaka yo ni nukeide nuru hito no ohom-atari ha, tokoroseki koto ohoku nam. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4 | 第四段 斎宮、宮中へ向かう |
1-4 Saigu goes to the Court |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.1 | 十六日、桂川にて御祓へしたまふ。常の儀式にまさりて、長奉送使など、さらぬ上達部も、やむごとなく、おぼえあるを 選らせたまへり。 院の御心寄せもあればなるべし。出でたまふほどに、大将殿より例の尽きせぬことども聞こえたまへり。「かけまくもかしこき御前にて」と、木綿につけて、 |
十六日、桂川でお祓いをなさる。慣例の儀式より立派で、長奉送使など、その他の上達部も身分高く、世間から評判の良い方をお選びさせた。院のお心遣いもあってのことであろう。お出になる時、大将殿から例によって名残尽きない思いのたけをお申し上げなさった。「恐れ多くも、御前に」と言って、木綿に結びつけて、 |
十六日に桂川で斎宮の |
Zihuroku-niti, Katuragaha nite, ohom-harahe si tamahu. Tune no gisiki ni masari te, Tyaubusousi nado, saranu Kamdatime mo, yamgotonaku, oboye aru wo era se tamahe ri. Win no mikokoroyose mo are ba naru besi. Ide tamahu hodo ni, Daisyau-dono yori rei no tuki se nu koto-domo kikoye tamahe ri. "Kakemakumo kasikoki omahe nite." to, yuhu ni tuke te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.2 | 「 鳴る神だにこそ ★、 |
「雷神でさえも、 |
いかずちの神でさえ恋人の中を裂くものではないと言います。 |
"Narukami dani koso, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.3 | 八洲もる国つ御神も心あらば 飽かぬ別れの仲をことわれ |
大八洲をお守りあそばす国つ神もお情けがあるならば 尽きぬ思いで別れなければならいわけをお聞かせ下さい |
飽かぬ別れの中をことわれ |
Yasima moru Kuni-tu-mikami mo kokoro ara ba aka nu wakare no naka wo kotoware |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.4 | 思うたまふるに、飽かぬ心地しはべるかな」 |
どう考えてみても、満足しない気が致しますよ」 |
どう考えましても神慮がわかりませんから、私は満足できません。 |
Omou tamahuru ni, aka nu kokoti si haberu kana!" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.5 | とあり。いとさわがしきほどなれど、御返りあり。宮の御をば、女別当して書かせたまへり。 |
とある。とても取り混んでいる時だが、お返事がある。斎宮のお返事は、女別当にお書かせになっていた。 |
と書かれてあった。取り込んでいたが返事をした。宮のお歌を |
to ari. Ito sawagasiki hodo nare do, ohom-kaheri ari. Miya no ohom wo ba, Nyobe'tau site kaka se tamahe ri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.6 | 「 国つ神空にことわる仲ならば なほざりごとをまづや糾さむ」 |
「国つ神がお二人の仲を裁かれることになったならば あなたの実意のないお言葉をまずは糺されることでしょう」 |
国つ神空にことわる中ならば なほざりごとを |
"Kuni-tu-Kami sora ni kotowaru naka nara ba nahozarigoto wo madu ya tadasa m |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.7 | 大将は、御ありさまゆかしうて、内裏にも参らまほしく思せど、うち捨てられて見送らむも、人悪ろき心地したまへば、思しとまりて、つれづれに眺めゐたまへり。 |
大将は、様子を見たくて、宮中にも参内したくお思いになるが、振り捨てられて見送るようなのも、人聞きの悪い感じがなさるので、お思い止まりになって、所在なげに物思いに耽っていらっしゃった。 |
源氏は最後に宮中である式を見たくも思ったが、捨てて行かれる男が見送りに出るというきまり悪さを思って家にいた。 |
Daisyau ha, ohom-arisama yukasiu te, Uti ni mo mawira mahosiku obose do, uti-sute rare te miokura m mo, hitowaroki kokoti si tamahe ba, obosi tomari te, turedure ni nagame wi tamahe ri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.8 | 宮の御返りのおとなおとなしきを、ほほ笑みて見ゐたまへり。「 御年のほどよりは、をかしうもおはすべきかな」と、ただならず。 かうやうに例に違へるわづらはしさに、かならず心かかる御癖にて ★、「 いとよう見たてまつりつべかりしいはけなき御ほどを、見ずなりぬるこそねたけれ。 世の中定めなければ、対面するやうもありなむかし」など思す。 |
斎宮のお返事がいかにも成人した詠みぶりなのを、ほほ笑んで御覧になった。「お年の割には、人情がお分かりのようでいらっしゃるな」と、お心が動く。このように普通とは違っためんどうな事には、きっと心動かすご性分なので、「いくらでも拝見しようとすればできたはずであった幼い時を、見ないで過ごしてしまったのは残念なことであった。世の中は無常であるから、お目にかかるようなこともきっとあろう」などと、お思いになる。 |
源氏は斎宮の |
Miya no ohom-kaheri no otonaotonasiki wo, hohowemi te mi wi tamahe ri. "Ohom-tosi no hodo yori ha, wokasiu mo ohasu beki kana!" to, tadanarazu. Kauyau ni rei ni tagahe ru wadurahasisa ni, kanarazu kokoro kakaru ohom-kuse nite, "Ito you mi tatematuri tu bekari si ihakenaki ohom-hodo wo, mi zu nari nuru koso netakere. Yononaka sadame nakere ba, taimen suru yau mo ari na m kasi." nado obosu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 | 第五段 斎宮、伊勢へ向かう |
1-5 Saigu starts off the Court for Ise |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5.1 | 心にくくよしある御けはひなれば、物見車多かる日なり。申の時に内裏に参りたまふ。 |
奥ゆかしく風雅なお人柄の方なので、見物の車が多い日である。申の時に宮中に参内なさる。 |
見識の高い、美しい貴婦人であると名高い存在になっている御息所の添った斎宮の出発の列をながめようとして |
Kokoronikuku yosi aru ohom-kehahi nare ba, monomiguruma ohokaru hi nari. Saru no toki ni Uti ni mawiri tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5.2 | 御息所、御輿に乗りたまへるにつけても、父大臣の 限りなき筋に思し志して、いつきたてまつりたまひしありさま、変はりて、末の世に内裏を見たまふにも、もののみ尽きせず、あはれに思さる。 十六にて故宮に参りたまひて、二十にて後れたてまつりたまふ。三十にてぞ、今日また九重を見たまひける。 |
御息所、御輿にお乗りになるにつけても、父大臣が限りない地位にとお望みになって、大切にかしずきお育てになった境遇が、うって変わって、晩年に宮中を御覧になるにつけても、感慨無量で、悲しく思わずにはいらっしゃれない。十六で故宮に入内なさって、二十で先立たれ申される。三十で、今日再び宮中を御覧になるのであった。 |
斎宮は午後四時に宮中へおはいりになった。宮の |
Miyasumdokoro, mikosi ni nori tamahe ru ni tuke te mo, Titi-Otodo no kagirinaki sudi ni obosi kokorozasi te, ituki tatematuri tamahi si arisama, kahari te, suwenoyo ni Uti wo mi tamahu ni mo, mono nomi tuki se zu, ahare ni obosa ru. Zihuroku nite ko-Miya ni mawiri tamahi te, nizihu nite okure tatematuri tamahu. Samzihu nite zo, kehu mata Kokonohe wo mi tamahi keru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5.3 | 「 そのかみを今日はかけじと忍ぶれど 心のうちにものぞ悲しき」 |
「昔のことを今日は思い出すまいと堪えていたが 心の底では悲しく思われてならない」 |
そのかみを 心のうちに物ぞ悲しき |
"Sonokami wo kehu ha kake zi to sinobure do kokoro no uti ni mono zo kanasiki |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5.4 | 斎宮は、十四にぞなりたまひける。いとうつくしうおはするさまを、うるはしうしたてたてまつりたまへるぞ、いとゆゆしきまで見えたまふを、帝、御心動きて、別れの櫛たてまつりたまふほど、いとあはれにて、しほたれさせたまひぬ。 |
斎宮は、十四におなりであった。とてもかわいらしういらっしゃるご様子を、立派に装束をお着せ申されたのが、とても恐いまでに美しくお見えになるのを、帝、お心が動いて、別れの御櫛を挿してお上げになる時、まことに心揺さぶられて、涙をお流しあそばした。 |
御息所の歌である。斎宮は十四でおありになった。きれいな方である上に、 |
Saiguu ha, zihusi ni zo nari tamahi keru. Ito utukusiu ohasuru sama wo, uruhasiu sitate tatematuri tamahe ru zo, ito yuyusiki made miye tamahu wo, Mikado, mikokoro ugoki te, wakare no kusi tatematuri tamahu hodo, ito ahare nite, sihotare sase tamahi nu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5.5 | 出でたまふを待ちたてまつるとて、八省に立て続けたる出車どもの袖口、色あひも、目馴れぬさまに、心にくきけしきなれば、殿上人どもも、私の別れ惜しむ多かり。 |
お出立になるのをお待ち申そうとして、八省院に立ち続けていた女房の車から、袖口、色合いも、目新しい意匠で、奥ゆかしい感じなので、殿上人たちも私的な別れを惜しんでいる者が多かった。 |
式の終わるのを |
Ide tamahu wo mati tatematuru tote, Ha'syau ni tatetuduke taru idasiguruma-domo no sodeguti, iroahi mo, menare nu sama ni, kokoronikuki kesiki nare ba, Tenzyaubito-domo mo, watakusi no wakare wosimu ohokari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
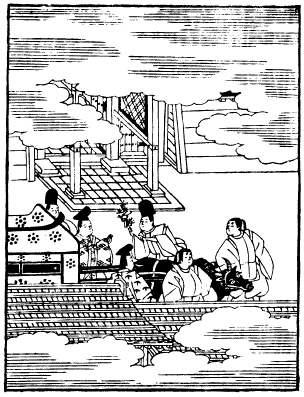 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5.6 | 暗う出でたまひて、 二条より洞院の大路を折れたまふほど、二条の院の前なれば、大将の君、いとあはれに思されて、榊にさして、 |
暗くなってからご出発になって、二条大路から洞院の大路ヘお曲がりになる時、二条の院の前なので、大将の君、まことにしみじみと感じられて、榊の枝に挿して、 |
暗くなってから行列は動いて、二条から |
Kurau ide tamahi te, Nideu yori Touwin-no-ohodi wo wore tamahu hodo, Nideu-no-win no mahe nare ba, Daisyau-no-Kimi, ito ahare ni obosa re te, sakaki ni sasi te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5.7 | 「 振り捨てて今日は行くとも鈴鹿川 八十瀬の波に袖は濡れじや」 |
「わたしを捨てて今日は旅立って行かれるが鈴鹿川を 渡る時に袖を濡らして後悔なさいませんでしょうか」 |
ふりすてて今日は行くとも |
"Hurisute te kehu ha yuku tomo Suzukagaha yasose no nami ni sode ha nure zi ya |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5.8 | と聞こえたまへれど、いと暗う、ものさわがしきほどなれば、またの日、関のあなたよりぞ、 御返しある ★。 |
とお申し上げになったが、たいそう暗く、何かとあわただしい時なので、翌日、逢坂の関の向こうからお返事がある。 |
その時はもう暗くもあったし、あわただしくもあったので、翌日 |
to kikoye tamahe re do, ito kurau, mono-sawagasiki hodo nare ba, matanohi, seki no anata yori zo, ohom-kahesi aru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5.9 | 「 鈴鹿川八十瀬の波に濡れ濡れず 伊勢まで誰れか思ひおこせむ」 |
「鈴鹿川の八十瀬の波に袖が濡れるか濡れないか 伊勢に行った先まで誰が思いおこしてくださるでしょうか」 |
鈴鹿川八十瀬の波に濡れ濡れず 伊勢までたれか思ひおこせん |
"Suzukagaha yasose no nami ni nure nure zu Ise made tare ka omohi okose m |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5.10 | ことそぎて書きたまへるしも、御手いとよしよししくなまめきたるに、「 あはれなるけをすこし添へたまへらましかば」と思す。 |
言葉少なにお書きになっているが、ご筆跡はいかにも風情があって優美であるが、「優しさがもう少しおありだったらば」とお思いになる。 |
簡単に書かれてあるが、貴人らしさのある巧妙な字であった。優しさを少し加えたら最上の字になるであろうと源氏は思った。 |
Kotosogi te kaki tamahe ru simo, ohom-te ito yosiyosisiku namameki taru ni, "Ahare naru ke wo sukosi sohe tamahe ra masika ba." to obosu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5.11 | 霧いたう降りて、ただならぬ朝ぼらけに、うち眺めて独りごちおはす。 |
霧がひどく降りこめて、いつもと違って感じられる朝方に、物思いに耽りながら独り言をいっていらっしゃる。 |
霧が濃くかかっていて、身にしむ秋の夜明けの空をながめて、源氏は、 |
Kiri itau huri te, tada nara nu asaborake ni, uti-nagame te hitorigoti ohasu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5.12 | 「 行く方を眺めもやらむこの秋は 逢坂山を霧な隔てそ」 |
「あの行った方角を眺めていよう、今年の秋は 逢うという逢坂山を霧よ隠さないでおくれ」 |
行くかたをながめもやらんこの秋は 逢坂山を霧な隔てそ |
"Yukukata wo nagame mo yara m kono aki ha Ahusakayama wo kiri na hedate so |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5.13 | 西の対にも渡りたまはで、人やりならず、もの寂しげに眺め暮らしたまふ。 まして、旅の空は、いかに御心尽くしなること多かりけむ。 |
西の対にもお渡りにならず、誰のせいというのでもなく、何とはなく寂しげに物思いに耽ってお過ごしになる。ましてや、旅路の一行は、どんなにか物思いにお心を尽くしになること、多かったことだろうか。 |
こんな歌を口ずさんでいた。西の対へも行かずに終日物思いをして源氏は暮らした。旅人になった御息所はまして堪えがたい悲しみを味わっていたことであろう。 |
Nisinotai ni mo watari tamaha de, hitoyarinarazu, monosabisige ni nagame kurasi tamahu. Masite, tabi no sora ha, ikani mikokorodukusi naru koto ohokari kem. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last updated 9/20/2010(ver.2-3) 渋谷栄一校訂(C) Last updated 9/5/2009(ver.2-2) 渋谷栄一注釈(C) |
Last updated 5/19/2001 渋谷栄一訳(C)(ver.1-2-2) |
|
Last updated 9/5/2009 (ver.2-2) Written in Japanese roman letters by Eiichi Shibuya(C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Picture "Eiri Genji Monogatari"(1650 1st edition) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源氏物語の世界 再編集プログラム Ver 3.38: Copyright (c) 2003,2015 宮脇文経