第三十二帖 梅枝 |
32 MUMEGAYE (Ohoshima-bon) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光る源氏の太政大臣時代 三十九歳一月から二月までの物語 |
Tale of Hikaru-Genji's Daijo-Daijin era, from January to February at the age of 39 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 第二章 光る源氏の物語 明石の姫君の裳着 |
2 Tale of Hikaru-Genji Genji's daughter, Akashi-Hime, grows up to be a woman |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1 | 第一段 明石の姫君の裳着 |
2-1 Akashi-Hime grows up to be a woman |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.1 | かくて、西の御殿に、 戌の時に渡りたまふ。宮のおはします西の放出をしつらひて、御髪上の内侍なども、 やがてこなたに参れり。 上も、このついでに、中宮に御対面あり。御方々の女房、押しあはせたる、数しらず見えたり。 |
こうして、西の御殿に、戌の刻にお渡りになる。中宮のいらっしゃる西の放出を整備して、御髪上の内侍なども、そのままこちらに参上した。紫の上も、この機会に、中宮にご対面なさる。お二方の女房たちが、一緒に来合わせているのが、数えきれないほど見えた。 |
|
Kakute, nisi no otodo ni, inu no toki ni watari tamahu. Miya no ohasimasu nisi no Hanatiide wo siturahi te, mi-gusiage no Naisi nado mo, yagate konata ni mawire ri. Uhe mo, kono tuide ni, Tyuuguu ni ohom-taimen ari. Ohom-katagata no nyoubau, osi-ahase taru, kazu sira zu miye tari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.2 | 子の時に御裳たてまつる。大殿油ほのかなれど、御けはひいとめでたしと、宮は見たてまつれたまふ。大臣、 |
子の刻に御裳をお召しになる。大殿油は微かであるが、御器量がまことに素晴らしいと、中宮はご拝見あそばす。大臣は、 |
裳を付ける式は十二時に始まったのである。ほのかな |
Ne no toki ni ohom-mo tatematuru. Ohotonabura honoka nare do, ohom-kehahi ito medetasi to, Miya ha mi tatemature tamahu. Otodo, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.3 | 「 思し捨つまじきを頼みにて、 なめげなる姿を、進み御覧ぜられはべるなり。 後の世のためしにやと、心狭く忍び思ひたまふる」 |
「お見捨てになるまいと期待して、失礼な姿を、進んでお目にかけたのでございます。後世の前例になろうかと、狭い料簡から密かに考えております」 |
「お愛しくださいますことを頼みにいたしまして、失礼な姿も御前へ出させましたのです。尊貴なあなた様がかようなお世話をくださいますことなどは例もないことであろうと感激に堪えません」 |
"Obosi sutu maziki wo tanomi nite, namege naru sugata wo, susumi goranze rare haberu nari. Notinoyo no tamesi ni ya to, kokorosebaku sinobi omohi tamahuru." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.4 | など聞こえたまふ。宮、 |
などと申し上げなさる。中宮、 |
と源氏は申し上げていた。 |
nado kikoye tamahu. Miya, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.5 | 「 いかなるべきこととも思うたまへ分きはべらざりつるを、かうことことしうとりなさせたまふになむ、なかなか心おかれぬべく」 |
「どのようなこととも判断せず致したことを、このように大層におっしゃって戴きますと、かえって気が引けてしまいます」 |
「経験の少ない私が何もわからずにいたしておりますことに、そんな御 |
"Ikanaru beki koto to mo omou tamahe waki habera zari turu wo, kau kotokotosiu torinasa se tamahu ni nam, nakanaka kokoro oka re nu beku." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.6 | と、 のたまひ消つほどの御けはひ、いと若く愛敬づきたるに、大臣も、思すさまにをかしき御けはひどもの、さし集ひたまへるを、あはひめでたく思さる。 母君の、かかる折だにえ見たてまつらぬを、いみじと思へりしも心苦しうて、 参う上らせやせましと思せど、人のもの言ひをつつみて、過ぐしたまひつ。 |
と、否定しておっしゃる御様子、とても若々しく愛嬌があるので、大臣も、理想通りに立派なご様子の婦人方が、集まっていらっしゃるのを、お互いの間柄も素晴らしいとお思いになる。母君が、このような機会でさえお目にかかれないのを、たいそう辛い事と思っているのも気の毒なので、参列させようかしらと、お考えになるが、世間の悪口を慮って、見送った。 |
と御 |
to, notamahi ketu hodo no ohom-kehahi, ito wakaku aigyauduki taru ni, Otodo mo, obosu sama ni wokasiki ohom-kehahi-domo no, sasi-tudohi tamahe ru wo, ahahi medetaku obosa ru. HahaGimi no, kakaru wori dani e mi tatematura nu wo, imizi to omohe ri simo kokorogurusiu te, maunobora se ya se masi to obose do, hito no monoihi wo tutumi te, sugusi tamahi tu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.7 | かかる所の儀式は、よろしきにだに、いとこと多くうるさきを、片端ばかり、例のしどけなくまねばむもなかなかにやとて、こまかに書かず。 |
このような邸での儀式は、まあまあのものでさえ、とても煩雑で面倒なのだが、一部分だけでも、例によってまとまりなくお伝えするのも、かえってどうかと思い、詳細には書かない。 |
こうした式についての記事は名文で書かれていてもうるさいものであるのを、自分などがだらしなく書いていっては、かえってきれいなりっぱなことをこわしてしまう結果になるのを恐れて、細かにはしるさない。 |
Kakaru tokoro no gisiki ha, yorosiki ni dani, ito koto ohoku urusaki wo, katahasi bakari, rei no sidokenaku maneba m mo nakanaka ni ya tote, komaka ni kaka zu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2 | 第二段 明石の姫君の入内準備 |
2-2 Genji prepares that he marries Akashi-Hime to Togu |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2.1 | 春宮の御元服は、二十余日のほどになむありける。いと大人しくおはしませば、人の女ども競ひ参らすべきことを、 心ざし思すなれど、この殿の思しきざすさまの、いとことなれば、なかなかにてや交じらはむと、 左の大臣なども、 思しとどまるなるを聞こしめして、 |
春宮の御元服は、二十日過ぎの頃に行われたのであった。たいそう大人でおいであそばすので、人々が娘たちを競争して入内させることを、希望していらっしゃるというが、この殿がご希望していらっしゃる様子が、まことに格別なので、かえって中途半端な宮仕えはしないほうがましだと、左大臣なども、お思い留まりになっているということをお耳になさって、 |
東宮の御元服は二十幾日にあった。もうりっぱな大人のようでいらせられたから、だれも令嬢たちを後宮へ入れたい志望を持ったが、源氏がある自信を持って、姫君を東宮へ奉ろうとしているのを知っては、強大な競争者のあるこの宮仕えはかえって娘を不幸にすることではなかろうかと、左大臣、左大将などもまた |
Touguu no ohom-genpuku ha, nizihu-yo-hi no hodo ni nam ari keru. Ito otonasiku ohasimase ba, hito no musume-domo kihohi mawirasu beki koto wo, kokorozasi obosu nare do, kono Tono no obosi kizasu sama no, ito koto nare ba, nakanaka nite ya maziraha m to, Hidari-no-Otodo nado mo, obosi todomaru naru wo kikosimesi te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2.2 | 「 いとたいだいしきことなり。 宮仕への筋は、あまたあるなかに、すこしのけぢめを挑まむこそ本意ならめ。そこらの警策の姫君たち、引き籠められなば、世に映えあらじ」 |
「じつにもってのほかのことだ。宮仕えの趣旨は、大勢いる中で、僅かの優劣の差を競うのが本当だろう。たくさんの優れた姫君たちが、家に引き籠められたならば、何ともおもしろくないだろう」 |
「それではお |
"Ito taidaisiki koto nari. Miyadukahe no sudi ha, amata aru naka ni, sukosi no kedime wo idoma m koso hoi nara me. Sokora no kyauzaku no HimeGimi tati, hiki-kome rare na ba, yo ni haye ara zi." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2.3 | とのたまひて、 御参り延びぬ。次々にもとしづめたまひけるを、かかるよし所々に聞きたまひて、 左大臣殿の三の君参りたまひぬ。麗景殿と聞こゆ ★ ★。 |
とおっしゃって、御入内が延期になった。その次々にもと差し控えていらっしゃったが、このようなことをあちこちでお聞きになって、左大臣の三の君がご入内なさった。麗景殿女御と申し上げる。 |
と言って、姫君の宮仕えの時期を延ばした。たとえ娘を出すにしてもあとのことにしようとしていた人たちはそれを聞いて、最初に左大臣が三女を東宮へ入れた。 |
to notamahi te, ohom-mawiri nobi nu. Tugitugi ni mo to sidume tamahi keru wo, kakaru yosi tokorodokoro ni kiki tamahi te, Sa-Daizin-dono no Sam-no-Kimi mawiri tamahi nu. Reikeiden to kikoyu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2.4 | この御方は、昔の御宿直所、淑景舎を改めしつらひて、御参り延びぬるを、 宮にも心もとながらせたまへば、 四月にと定めさせたまふ。御調度どもも、もとあるよりもととのへて、御みづからも、ものの下形、絵様などをも御覧じ入れつつ、すぐれたる道々の上手どもを召し集めて、こまかに磨きととのへさせたまふ。 |
こちらの御方は、昔の御宿直所の、淑景舎を改装して、ご入内が延期になったのを、春宮におかれても待ち遠しくお思いあそばすので、四月にとお決めあそばす。ご調度類も、もとからあったのを整えて、御自身でも、道具類の雛形や図案などを御覧になりながら、優れた諸道の専門家たちを呼び集めて、こまかに磨きお作らせになる。 |
源氏のほうは昔の |
Kono ohom-Kata ha, mukasi no ohom-tonowidokoro, Sigeisa wo aratame siturahi te, ohom-mawiri nobi nuru wo, Miya ni mo kokoro motonagara se tamahe ba, Uduki ni to sadame sase tamahu. Ohom-teudo-domo mo, moto aru yori mo totonohe te, ohom-midukara mo, mono no sitakata, we-yau nado wo mo goranzi ire tutu, sugure taru mitimiti no zyauzu-domo wo mesi atume te, komaka ni migaki totonohe sase tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2.5 | 草子の筥に入るべき草子どもの、やがて本にもしたまふべきを選らせたまふ。いにしへの上なき際の御手どもの、世に名を残したまへるたぐひのも、いと多くさぶらふ。 |
冊子の箱に入れるべき冊子類を、そのまま手本になさることのできるのを選ばせなさる。昔のこの上もない名筆家たちが、後世にお残しになった筆跡類も、たいそうたくさんある。 |
草紙の箱というような物に入れる草紙で、いずれは製本もさせて書物になるようなものを源氏は選んでいた。故人で、書道のほうの大家と言われている人たちの書いた物も源氏のところにはたくさんあった。 |
Sausi no hako ni iru beki sausi-domo no, yagate hon ni mo si tamahu beki wo era se tamahu. Inisihe no kami naki kiha no ohom-te-domo no, yo ni na wo nokosi tamahe ru taguhi no mo, ito ohoku saburahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3 | 第三段 源氏の仮名論議 |
2-3 Genji criticizes a late kana |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.1 | 「 よろづのこと、昔には劣りざまに、浅くなりゆく世の末なれど、仮名のみなむ、今の世はいと際なくなりたる。 古き跡は、定まれるやうにはあれど、広き心ゆたかならず、一筋に通ひてなむありける。 |
「すべての事が、昔に比べて劣って、浅くなって行く末世だが、仮名だけは、現代は際限もなく発達したものだ。昔の字は、筆跡が定まっているようではあるが、ゆったりした感じがあまりなくて、一様に似通った書法であった。 |
「すべてのことは昔より悪くなっていく末世ではあっても、仮名の字だけは、どこまでおもしろくなっていくかと思われるほど、近ごろのほうがよくなった。昔の仮名は正確ではあるが、融通がきかないで、変化の妙がなく単調だ。 |
"Yorodu no koto, mukasi ni ha otorizama ni, asaku nari yuku yo no suwe nare do, kamna nomi nam, ima no yo ha ito kiha naku nari taru. Huruki ato ha, sadamare ru yau ni ha are do, hiroki kokoro yutaka nara zu, hitosudi ni kayohi te nam ari keru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.2 | 妙にをかしきことは、 外よりてこそ書き出づる人びとありけれど、 女手を心に入れて習ひし盛りに、こともなき手本多く集へたりしなかに、 中宮の母御息所の、心にも入れず走り書いたまへりし一行ばかり、わざとならぬを得て、際ことにおぼえしはや。 |
見事で上手なものは、近頃になって書ける人が出て来たが、平仮名を熱心に習っていた最中に、特に難点のない手本を数多く集めていた中で、中宮の母御息所が何気なくさらさらとお書きになった一行ほどの、無造作な筆跡を手に入れて、格段に優れていると感じたものです。 |
巧妙な仮名を書く人は近代になってふえたが、私も仮名を習うのに熱心だったころ、無難な仮名字を手本にいろいろ集めたものだが、中宮の母君の |
Tahe ni wokasiki koto ha, to yori te koso kaki iduru hitobito ari kere do, womnade wo kokoro ni ire te narahi si sakari ni, koto mo naki tehon ohoku tudohe tari si naka ni, Tyuuguu no haha-Miyasumdokoro no, kokoro ni mo ire zu hasiri kai tamahe ri si hitokudari bakari, wazato nara nu wo e te, kiha koto ni oboye si haya! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.3 | さて、あるまじき御名も立てきこえしぞかし。悔しきことに思ひしみたまへりしかど、 さしもあらざりけり。宮にかく後見仕うまつることを、心深うおはせしかば、亡き御影にも見直したまふらむ。 |
そういうことで、とんでもない浮名までもお流し申してしまったことよ。残念なことと思い込んでいらっしゃったが、それほど薄情ではなかったのだ。中宮にこのように御後見申し上げていることを、思慮深くいらっしゃったので、亡くなった後にも見直して下さることだろう。 |
それがもとになって浮き名を立てることになり、私との関係をにがい経験だったように思って、くやしがったままで |
Sate, aru maziki ohom-na mo tate kikoye si zo kasi. Kuyasiki koto ni omohisimi tamahe ri sika do, sasimo ara zari keri. Miya ni kaku usiromi tukaumaturu koto wo, kokorohukau ohase sika ba, naki ohom-kage ni mo minahosi tamahu ram. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.4 | 宮の御手は、こまかにをかしげなれど、かどや後れたらむ」 |
中宮の御筆跡は、こまやかで趣はあるが、才気は少ないようだ」 |
中宮のお字はきれいなようだけれど才気が少ない」 |
Miya no ohom-te ha, komaka ni wokasige nare do, kado ya okure tara m." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.5 | と、うちささめきて聞こえたまふ。 |
と、ひそひそと申し上げなさる。 |
と源氏は夫人にささやいていた。 |
to, uti-sasameki te kikoye tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.6 | 「 故入道宮の御手は、いとけしき深うなまめきたる筋はありしかど、弱きところありて、にほひぞすくなかりし。 |
「故入道宮の御筆跡は、たいそう深味もあり優美な手の筋はおありだったが、なよなよした点があって、はなやかさが少なかった。 |
「入道の中宮様は最上の貴婦人らしい品のある字をお書きになったが、弱い所があって、はなやかな気分はない。 |
"Ko-Nihudau-no-Miya no ohom-te ha, ito kesiki hukau namameki taru sudi ha ari sika do, yowaki tokoro ari te, nihohi zo sukunakari si. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.7 | 院の尚侍こそ、今の世の上手におはすれど、あまりそぼれて癖ぞ添ひためる。さはありとも、 かの君と、前斎院と、ここにとこそは、書きたまはめ」 |
朱雀院の尚侍は、当代の名人でいらっしゃるが、あまりにしゃれすぎて欠点があるよだ。そうは言っても、あの尚侍君と、前斎院と、あなたは、上手な方だと思う」 |
院の |
Win no Kam-no-Kimi koso, ima no yo no zyauzu ni ohasure do, amari sobore te kuse zo sohi ta' meru. Saha ari tomo, kano Kimi to, saki-no-Saiwin to, koko ni to koso ha, kaki tamaha me." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.8 | と、聴しきこえたまへば、 |
と、お認め申し上げなさるので、 |
源氏から認められたことで、夫人は、 |
to, yurusi kikoye tamahe ba, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.9 | 「 この数には、まばゆくや」 |
「この方々に仲間入りするのは、恥ずかしいですわ」 |
「そんな方たちといっしょになすっては恥ずかしくてなりませんよ」 |
"Kono kazu ni ha, mabayuku ya!" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.10 | と聞こえたまへば、 |
と申し上げなさると、 |
と言っていた。 |
to kikoye tamahe ba, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.11 | 「 いたうな過ぐしたまひそ。にこやかなる方のなつかしさは、ことなるものを。 真名のすすみたるほどに、仮名はしどけなき文字こそ混じるめれ」 |
「ひどく謙遜なさってはいけません。柔和という点の好ましさは、格別なものですよ。漢字が上手になってくると、仮名は整わない文字が交るようですがね」 |
「 |
"Itau na sugusi tamahi so. Nikoyaka naru kata no natukasisa ha, koto naru mono wo! Mana no susumi taru hodo ni, kamna ha sidokenaki mozi koso maziru mere." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.12 | とて、まだ書かぬ草子ども作り加へて、表紙、紐などいみじうせさせたまふ。 |
とおっしゃって、まだ書写してない冊子類を作り加えて、表紙や、紐など、たいへん立派にお作らせになる。 |
などとも源氏は言っていて、書かない無地の草紙もまた何帳か新しく |
tote, mada kaka nu sausi-domo tukuri kuhahe te, heusi, himo nado imiziu se sase tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.13 | 「 兵部卿宮、左衛門督などにものせむ ★。みづから一具は書くべし。けしきばみいますがりとも、え書き並べじや」 |
「兵部卿宮、左衛門督などに書いてもらおう。わたし自身も二帖は書こう。いくら自信がおありでも、並ばないことはあるまい」 |
「 |
"Hyaubukyau-no-Miya, Sawemon-no-Kami nado ni monose m. Midukara hitoyorohi ha kaku besi. Kesikibami imasugari tomo, e kaki narabe zi ya." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.14 | と、われぼめをしたまふ。 |
と、自賛なさる。 |
と源氏は |
to, warebome wo si tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4 | 第四段 草子執筆の依頼 |
2-4 Genji requests young men to copy by all sorts of wrighting |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4.1 | 墨、筆、並びなく選り出でて、例の所々に、ただならぬ御消息あれば、人びと、難きことに思して、返さひ申したまふもあれば、まめやかに聞こえたまふ。高麗の紙の薄様だちたるが、せめてなまめかしきを、 |
墨、筆、最上の物を選び出して、いつもの方々に、特別のご依頼のお手紙があると、方々は、難しいこととお思いになって、ご辞退申し上げなさる方もあるので、懇ろにご依頼申し上げなさる。高麗の紙の薄様風なのが、はなはだ優美なのを、 |
墨も筆も選んだのを添えて、いつもそうした交渉のある所々へ執筆を源氏は頼んだのであったが、だれもこの委嘱に応じるのを困難なことに思って、その中には辞退してくる人もあったが、そんな時に源氏は再三懇切な言葉で執筆を望んだ。朝鮮紙の |
Sumi, hude, narabi naku eriide te, rei no tokorodokoro ni, tada nara nu ohom-seusoko are ba, hitobito, kataki koto ni obosi te, kahesahi mausi tamahu mo are ba, mameyaka ni kikoye tamahu. Koma no kami no usuyaudati taru ga, semete namamekasiki wo, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4.2 | 「 この、もの好みする若き人びと、試みむ」 |
「あの、風流好みの若い人たちを、試してみよう」 |
「風流好きな青年たちにこれを書かせてみよう」 |
"Kono, mono-gonomi suru wakaki hitobito, kokoromi m." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4.3 | とて、宰相中将、式部卿宮の兵衛督、内の大殿の頭中将などに、 |
とおっしゃって、宰相中将、式部卿宮の兵衛督、内の大殿の頭中将などに、 |
と言った。宰相中将、 |
tote, Saisyau-no-Tyuuzyau, Sikibukyau-no-Miya no Hyauwe-no-Kami, Uti-no-Ohoidono no Tou-no-Tyuuzyau nado ni, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4.4 | 「 葦手、歌絵を、思ひ思ひに書け」 |
「葦手、歌絵を、各自思い通りに書きなさい」 |
|
"Aside, utawe wo, omohi omohi ni kake." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4.5 | とのたまへば、皆心々に挑むべかめり。 |
とおっしゃると、皆それぞれ工夫して競争しているようである。 |
と源氏は言ったのであった。若い人たちは競って製作にかかった。 |
to notamahe ba, mina kokoro gokoro ni idomu beka' meri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4.6 | 例の寝殿に離れおはしまして書きたまふ。 花ざかり過ぎて、浅緑なる空うららかなるに ★、古き言どもなど思ひすましたまひて、御心のゆく限り、 草のも、ただのも、女手も、いみじう書き尽くしたまふ。 |
いつもの寝殿に独り離れていらっしゃってお書きになる。花盛りは過ぎて、浅緑色の空がうららかなので、いろいろ古歌などを心静かに考えなさって、ご満足のゆくまで、草仮名も、普通の仮名も、女手も、たいそう見事にこの上なくお書きになる。 |
いつもこんな時にするように、源氏は寝殿のほうへ行っていて書いた。花の盛りが過ぎて淡い緑色がかった空のうららかな日に、源氏は古い詩歌を静かに選びながら、みずから満足のできるだけの字を書こうと、漢字のも仮名のも熱心に書いていた。 |
Rei no sinden ni hanare ohasimasi te kaki tamahu. Hanazakari sugi te, asamidori naru sora uraraka naru ni, huruki koto-domo nado omohi-sumasi tamahi te, mi-kokoro no yuku kagiri, sau no mo, tada no mo, womnade mo, imiziu kaki tukusi tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
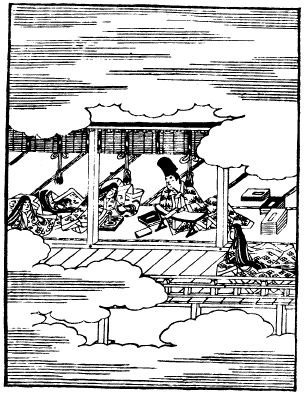 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4.7 | 御前に人しげからず、女房二、三人ばかり、墨など擦らせたまひて、ゆゑある古き集の歌など、いかにぞやなど選り出でたまふに、口惜しからぬ限りさぶらふ。 |
御前に人は多くいず、女房が二、三人ほどで、墨などをお擦らせになって、由緒ある古い歌集の歌など、どんなものだろうかなどと、選び出しなさるので、相談相手になれる人だけが伺候している。 |
その |
Omahe ni hito sigekara zu, nyoubau hutari, mitari bakari, sumi nado sura se tamahi te, yuwe aru huruki sihu no uta nado, ikani zo ya nado eriide tamahu ni, kutiwosikara nu kagiri saburahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4.8 | 御簾上げわたして、脇息の上に草子うち置き、端近くうち乱れて、筆の尻くはへて、思ひめぐらしたまへるさま、 飽く世なくめでたし。白き赤きなど、掲焉なる枚は、筆とり直し、用意したまへるさまさへ、 見知らむ人は、げにめでぬべき御ありさまなり ★。 |
御簾を上げ渡して、脇息の上に冊子をちょっと置いて、端近くに寛いだ姿で、筆の尻をくわえて、考えめぐらしていらっしゃる様子、いつまでも見飽きない美しさである。白や赤などの、はっきりした色の紙は、筆を取り直して、注意してお書きになっていらっしゃる様子までが、情趣を解せる人は、なるほど感心せずにはいられないご様子である。 |
部屋の |
Misu age watasi te, kehusoku no uhe ni sausi uti-oki, hasi tikaku uti-midare te, hude no siri kuhahe te, omohi megurasi tamahe ru sama, aku yo naku medetasi. Siroki akaki nado, ketien naru hira ha, hude tori nahosi, youi si tamahe ru sama sahe, misira m hito ha, geni mede nu beki ohom-arisama nari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5 | 第五段 兵部卿宮、草子を持参 |
2-5 Hyobukyo brings a copy of requested to Rokujo-in |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5.1 | 「 兵部卿宮渡りたまふ」と聞こゆれば、おどろきて、御直衣たてまつり、御茵参り添へさせたまひて、やがて待ち取り、入れたてまつりたまふ。この宮もいときよげにて、御階さまよく歩み昇りたまふほど、内にも人びとのぞきて見たてまつる。うちかしこまりて、かたみにうるはしだちたまへるも、いときよらなり。 |
「兵部卿宮がお越しになりました」と申し上げたので、驚いて御直衣をお召しになって、御敷物を持って来させなさって、そのまま待ち受けて、お入れ申し上げなさる。この宮もたいそう美しくて、御階を体裁よく歩いて上がっていらっしゃるところを、御簾の中からも女房たちが覗いて拝見する。丁重に挨拶して、お互いに威儀を正していらっしゃるのも、たいそう美しい。 |
兵部卿の宮がおいでになったということを聞いて源氏は驚いて上に |
"Hyaubukyau-no-Miya watari tamahu." to kikoyure ba, odoroki te, ohom-nahosi tatematuri, ohom-sitone mawiri sohe sase tamahi te, yagate mati tori, ire tatematuri tamahu. Kono Miya mo ito kiyoge nite, mi-hasi sama yoku ayumi nobori tamahu hodo, uti ni mo hitobito nozoki te mi tatematuru. Uti-kasikomari te, katamini uruhasidati tamahe ru mo, ito kiyora nari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5.2 | 「 つれづれに籠もりはべるも、苦しきまで思うたまへらるる 心ののどけさに、折よく渡らせたまへる」 |
「することもなく邸に籠もっておりますのも、辛く存じられますこの頃ののんびりとした折に、ちょうどよくお越し下さいました」 |
「引きこもっていますのが苦しいほど退屈なおりからでしたよ。よくおいでくださいました」 |
"Turedure ni komori haberu mo, kurusiki made omou tamahe raruru kokoro no nodokesa ni, wori yoku watara se tamahe ru." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5.3 | と、よろこびきこえたまふ。 かの御草子待たせて渡りたまへるなりけり。 やがて御覧ずれば、 すぐれてしもあらぬ御手を、 ただかたかどに、 いといたう筆澄みたるけしきありて書きなしたまへり。 歌も、ことさらめき、そばみたる古言どもを選りて、ただ三行ばかりに、 文字少なに好ましくぞ書きたまへる。大臣、御覧じ驚きぬ。 |
と、歓迎申し上げなさる。あの御依頼の冊子を持たせてお越しになったのであった。その場で御覧になると、たいして上手でもないご筆跡を、ただ一本調子に、たいそう垢抜けした感じにお書きになってある。和歌も、技巧を凝らして、風変わりな古歌を選んで、わずか三行ほどに、文字を少なくして好ましく書いていらっしゃった。大臣、御覧になって驚いた。 |
と源氏は言っていた。お頼まれになった書き物を宮は持っておいでになったのである。すぐこの席で源氏は拝見した。非常に巧妙な字というのではないが、一部分に澄み切った芸術味の見えるものだった。歌も常識的なものは避けて、変わったものが選ばれてあって、ただ三行ほどに字数を少なく感じよく書かれてあった。源氏は予想に越えたおできばえに驚いた。 |
to, yorokobi kikoye tamahu. Kano ohom-sausi motase te watari tamahe ru nari keri. Yagate goranzure ba, sugure te simo ara nu ohom-te wo, tada katakado ni, ito itau hude sumi taru kesiki ari te kaki nasi tamahe ri. Uta mo, kotosarameki, sobami taru hurukoto-domo wo eri te, tada mikudari bakari ni, mozi sukuna ni konomasiku zo kaki tamahe ru. Otodo, goranzi odoroki nu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5.4 | 「 かうまでは思ひたまへずこそありつれ。さらに筆投げ捨てつべしや」 |
「こんなにまで上手にお書きになるとは存じませんでした。まったく筆を投げ出してしまいたいほどですね」 |
「これほどにもとは思いませんでした。自分の書くことなどはいやになるほどです」 |
"Kau made ha omohi tamahe zu koso ari ture. Sarani hude nage sute tu besi ya!" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5.5 | と、ねたがりたまふ。 |
と、悔しがりなさる。 |
とも言っていた。 |
to, netagari tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5.6 | 「 かかる御中に面なくくだす筆のほど、さりともとなむ思う たまふる」 |
「このような名手の中で臆面もなく書く筆跡の具合は、いくら何でもさほどまずくはないと存じます」 |
「大家たちの中へ混じって書く自信だけはえらいものだと思っていますよ」 |
"Kakaru ohom-naka ni omonaku kudasu hude no hodo, saritomo to nam omou tamahuru." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5.7 | など、戯れたまふ。 |
などと、冗談をおっしゃる。 |
と宮は |
nado, tahabure tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5.8 | 書きたまへる草子どもも、隠したまふべきならねば、取う出たまひて、かたみに御覧ず。 |
お書きになった冊子類を、お隠しすべきものでもないので、お取り出しになって、お互いに御覧になる。 |
すでにできた源氏の帳などもお隠しすべきでないから出して宮の御覧に入れた。 |
Kaki tamahe ru sausi-domo mo, kakusi tamahu beki nara ne ba, toude tamahi te, katamini goranzu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5.9 | 唐の紙の、いとすくみたるに、草書きたまへる、すぐれてめでたしと見たまふに、 高麗の紙の、肌こまかに和うなつかしきが、色などははなやかならで、なまめきたるに、おほどかなる女手の、うるはしう心とどめて書きたまへる、たとふべきかたなし。 |
唐の紙で、たいそう堅い材質に、草仮名をお書きになっている、まことに結構であると、御覧になると、高麗の紙で、きめが細かで柔らかく優しい感じで、色彩などは派手でなく、優美な感じのする紙に、おっとりした女手で、整然と心を配って、お書きになっている、喩えようもない。 |
|
Kara no kami no, ito sukumi taru ni, sau kaki tamahe ru, sugure te medetasi to mi tamahu ni, Koma no kami no, hada komaka ni nagou natukasiki ga, iro nado ha hanayaka nara de, namameki taru ni, ohodoka naru womnade no, uruhasiu kokoro todome te kaki tamahe ru, tatohu beki kata nasi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5.10 | 見たまふ人の 涙さへ、水茎に流れ添ふ心地して、飽く世あるまじきに、また、ここの紙屋の色紙の、 色あひはなやかなるに、乱れたる草の歌を、筆にまかせて乱れ書きたまへる、見所限りなし。 ▼ しどろもどろに愛敬づき、見まほしければ、さらに残りどもに目も見やりたまはず。 |
御覧になる方の涙までが、筆跡に沿って流れるような感じがして、見飽きることのなさそうなところへ、さらに、わが国の紙屋院の色紙の、色合いが派手なのに、乱れ書きの草仮名の和歌を、筆にまかせて散らし書きになさったのは、見るべき点が尽きないほどである。型にとらわれず自在に愛嬌があって、ずっと見ていたい気がしたので、他の物にはまったく目もおやりにならない。 |
それは見る人の感動した涙も添って流れる気のする |
Mi tamahu hito no namida sahe, miduguki ni nagare sohu kokoti si te, aku yo aru maziki ni, mata, koko no Kamya no sikisi no, iroahi hanayaka naru ni, midare taru sau no uta wo, hude ni makase te midare kaki tamahe ru, midokoro kagiri nasi. Sidoromodoro ni aigyauduki, mi mahosikere ba, sarani nokori-domo ni me mo miyari tamaha zu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.6 | 第六段 他の人々持参の草子 |
2-6 The other men bring copies of requested too |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.6.1 | 左衛門督は、ことことしうかしこげなる筋をのみ好みて書きたれど、筆の掟て澄まぬ心地して、いたはり加へたるけしきなり。歌なども、ことさらめきて、選り書きたり。 |
左衛門督は、仰々しくえらそうな書風ばかりを好んで書いているが、筆法の垢抜けしない感じで、技巧を凝らした感じである。和歌なども、わざとらしい選び方をして書いていた。 |
|
Sawemon-no-Kami ha, kotokotosiu kasikoge naru sudi wo nomi konomi te kaki tare do, hude no okite suma nu kokoti si te, itahari kuhahe taru kesiki nari. Uta nado mo, kotosarameki te, eri kaki tari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.6.2 | 女の御は、まほにも取り出でたまはず。斎院のなどは、まして取う出たまはざりけり。葦手の草子どもぞ、心々に はかなうをかしき。 |
女君たちのは、そっくりお見せにならない。斎院のなどは、言うまでもなく取り出しなさらないのであった。葦手の冊子類が、それぞれに何となく趣があった。 |
女の手になったほうの帳は少しよりお見せしなかった。ことに斎院のなどはまったく隠してお出ししない源氏であった。青年たちによって |
Womna no ohom ha, maho ni mo toriide tamaha zu. Saiwin no nado ha, masite toude tamaha zari keri. Aside no sausi-domo zo, kokorogokoro ni hakanau wokasiki. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.6.3 | 宰相中将のは、水の勢ひ豊に書きなし、そそけたる葦の生ひざまなど、難波の浦に通ひて、 こなたかなたいきまじりて、いたう澄みたるところあり。また、 いといかめしう、ひきかへて、文字やう、石などのたたずまひ、好み書きたまへる枚もあめり。 |
宰相中将のは、水の勢いを豊富に書いて、乱れ生えている葦の様子など、難波の浦に似ていて、あちこちに入り混じって、たいそうすっきりした所がある。また、たいそう大仰に趣を変えて、字体、石などの様子、風流にお書きになった紙もあるようだ。 |
源中将のは水を豊かに描いて、そそけた蘆のはえた |
Saisyau-no-Tyuuzyau no ha, midu no ikihohi yutaka ni kaki nasi, sosoke taru asi no ohizama nado, Naniha no ura ni kayohi te, konata kanata iki maziri te, itau sumi taru tokoro ari. Mata, ito ikamesiu, hikikahe te, moziyau, isi nado no tatazumahi, konomi kaki tamahe ru hira mo a' meri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.6.4 | 「 目も及ばず。これは暇いりぬべきものかな」 |
「目も及ばぬ素晴らしさだ。これは手間のかかったにちがいない代物だね」 |
「驚いたものですね。これは見るのに時間を要するものですね」 |
"Me mo oyoba zu. Kore ha itoma iri nu beki mono kana!" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.6.5 | と、興じめでたまふ。何事ももの好みし、艶がりおはする親王にて、いといみじうめできこえたまふ。 |
と、興味深くお誉めになる。どのようなことにも趣味を持って、風流がりなさる親王なので、とてもたいそうお誉め申し上げなさる。 |
と宮はおもしろがっておいでになった。芸術家風の風流気に富んだ方であったから、お気にいったものはどこまでもおほめになるのである。 |
to, kyouzi mede tamahu. Nanigoto mo mono-gonomi si, engari ohasuru Miko nite, ito imiziu mede kikoye tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.7 | 第七段 古万葉集と古今和歌集 |
2-7 Genji makes a son of Hyobukyo to bring ko-Manyoshu and Kokin-wakasyu |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.7.1 | 今日はまた、手のことどものたまひ暮らし、さまざまの継紙の本ども、選り出でさせたまへるついでに、御子の侍従して、宮にさぶらふ本ども取りに遣はす。 |
今日はまた、書のことなどを一日中お話しになって、いろいろな継紙をした手本を、何巻かお選び出しになった機会に、御子息の侍従をして、宮邸に所蔵の手本類を取りにおやりになる。 |
この日はまた書の話ばかりをしておいでになって、色紙の継いだ巻き物が幾本となく席上へ現われるのであったが、宮は子息の侍従を |
Kehu ha mata, te no koto-domo notamahi kurasi, samazama no tugikami no hon-domo, eriide sase tamahe ru tuide ni, miko no Zizyuu site, Miya ni saburahu hon-domo tori ni tukahasu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.7.2 | 嵯峨の帝の、『 古万葉集』を選び書かせたまへる四巻、延喜の帝の、『古今和歌集』を、唐の浅縹の紙を継ぎて、同じ色の濃き紋の綺の表紙、同じき玉の軸、緞の唐組の紐など、なまめかしうて、巻ごとに御手の筋を変へつつ、いみじう書き尽くさせたまへる、大殿油短く参りて御覧ずるに、 |
嵯峨の帝が、『古万葉集』を選んでお書かせあそばした四巻。延喜の帝が、『古今和歌集』を、唐の浅縹の紙を継いで、同じ色の濃い紋様の綺の表紙、同じ玉の軸、だんだら染に組んだ唐風の組紐など、優美で、巻ごとに御筆跡の書風を変えながら、あらん限りの書の美をお書き尽くしあそばしたのを、大殿油を低い台に燈して御覧になると、 |
|
Saga-no-Mikado no, Ko-Man'ehusihu wo erabi kaka se tamahe ru yo-maki, Engi-no-Mikado no, Kokinwakasihu wo, kara no asahanada no kami wo tugi te, onazi iro no koki mon no ki no heusi, onaziki tama no ziku, dan no karakumi no himo nado, namamekasiu te, maki goto ni ohom-te no sudi wo kahe tutu, imiziu kaki tukusa se tamahe ru, ohotonabura mizikaku mawiri te goranzuru ni, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.7.3 | 「 尽きせぬものかな。このころの人は、ただかたそばをけしきばむにこそありけれ」 |
「いつまで見ていても見飽きないものだ。最近の人は、ただ部分的に趣向を凝らしているだけにすぎない」 |
「よくこんなにいろいろなふうにお書きになれたものですね。近ごろの人はほんのこの一部分の仕事をするのに骨を折っているという形ですね」 |
"Tuki se nu mono kana! Konokoro no hito ha, tada katasoba wo kesikibamu ni koso ari kere!" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.7.4 | など、めでたまふ。やがてこれはとどめたてまつりたまふ。 |
などと、お誉めになる。そのままこれらはこちらに献上なさる。 |
などと源氏はおほめしていた。この二種の物は宮から源氏へ御寄贈になった。 |
nado, mede tamahu. Yagate kore ha todome tatematuri tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.7.5 | 「 女子などを持てはべらましにだに、をさをさ見はやすまじきには伝ふまじきを、まして、朽ちぬべきを」 |
「女の子などを持っていましたにしても、たいして見る目を持たない者には、伝えたくないのですが、まして、埋もれてしまいますから」 |
「女の子を持っていたとしましても、たいしてこうした物の価値のわからないような子には残してやりたくない気のする物ですからね。それに私には娘もありませんから、お手もとへ置いていただいたほうがよい」 |
"Womnago nado wo mote habera masi ni dani, wosawosa mi hayasu maziki ni ha tutahu maziki wo, masite, kuti nu beki wo." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.7.6 | など聞こえてたてまつれたまふ。侍従に、唐の本などのいとわざとがましき、沈の筥に入れて、いみじき高麗笛添へて、奉れたまふ。 |
などと申し上げて差し上げなさる。侍従に、唐の手本などの特に念入りに書いてあるのを、沈の箱に入れて、立派な高麗笛を添えて、差し上げなさる。 |
などと宮はお言いになったのである。源氏は侍従へ唐本のりっぱなのを |
nado kikoye te tatemature tamahu. Zizyuu ni, Kara no hon nado no ito wazatogamasiki, din no hako ni ire te, imiziki Komabue sohe te, tatemature tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.7.7 | またこのころは、ただ仮名の定めをしたまひて、世の中に手書くとおぼえたる、上中下の人びとにも、さるべきものども思しはからひて、 尋ねつつ書かせたまふ。この御筥には、立ち下れるをば混ぜたまはず、わざと、人のほど、品分かせたまひつつ、草子、巻物、皆書かせたてまつりたまふ。 |
またこの頃は、ひたすら仮名の論評をなさって、世間で能書家だと聞こえた、上中下の人々にも、ふさわしい内容のものを見計らって、探し出してお書かせになる。この御箱には、身分の低い者のはお入れにならず、特別に、その人の家柄や、地位を区別なさりなさり、冊子、巻物、すべてお書かせ申し上げなさる。 |
近ごろの源氏は書道といってもことに仮名の字を鑑賞することに熱中して、よい字を書くと言われる人は上中下の階級にわたってそれぞれの物を選んで書を頼んでいた。源氏の書いた帳のはいる箱には、高い階級に属した人たちの手になった書だけを、帳も巻き物も珍しい |
Mata konokoro ha, tada kamna no sadame wo sitamahi te, yononaka ni te kaku to oboye taru, kami naka simo no hitobito ni mo, sarubeki mono-domo obosi hakarahi te, tadune tutu kaka se tamahu. Kono ohom-hako ni ha, tati-kudare ru wo ba maze tamaha zu, wazato, hito no hodo, sina wakase tamahi tutu, sausi, makimono, mina kaka se tatematuri tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.7.8 | よろづにめづらかなる御宝物ども、人の朝廷までありがたげなる中に、この本どもなむ、ゆかしと心動きたまふ若人、世に多かりける。御絵どもととのへさせたまふ中に、 かの『須磨の日記』は、末にも伝へ知らせむと思せど、「今すこし世をも思し知りなむに」と思し返して、まだ取り出でたまはず。 |
何もかも珍しい御宝物類、外国の朝廷でさえめったにないような物の中で、この何冊かの本を見たいと心を動かしなさる若い人たちが、世間に多いことであった。御絵画類をご準備なさる中で、あの『須磨の日記』は、子孫代々に伝えたいとお思いになるが、「もう少し世間がお分りになったら」とお思い返しなさって、まだお取り出しなさらない。 |
他の国の宮廷にもないと思われる |
Yorodu ni meduraka naru ohom-takaramono-domo, hito no mikado made arigatage naru naka ni, kono hon-domo nam, yukasi to kokoro ugoki tamahu wakaudo, yo ni ohokari keru. Ohom-we-domo totonohe sase tamahu naka ni, kano 'Suma no niki' ha, suwe ni mo tutahe sira se m to obose do, "Ima sukosi yo wo mo obosi siri na m ni." to obosi kahesi te, mada toriide tamaha zu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last updated 9/21/2010(ver.2-3) 渋谷栄一校訂(C) Last updated 2/18/2010(ver.2-2) 渋谷栄一注釈 |
Last updated 9/29/2001 渋谷栄一訳(C)(ver.1-2-2) |
|
Last updated 2/18/2010 (ver.2-2) Written in Japanese roman letters by Eiichi Shibuya (C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Picture "Eiri Genji Monogatari"(1650 1st edition) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源氏物語の世界 再編集プログラム Ver 3.38: Copyright (c) 2003,2015 宮脇文経