第四十帖 御法 |
40 MINORI (Ohoshima-bon) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光る源氏の准太上天皇時代 五十一歳三月から八月までの物語 |
Tale of Hikaru-Genji's Daijo Tenno era, from March to August, at the age of 51 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 第一章 紫の上の物語 死期間近き春から夏の物語 |
1 Tale of Murasaki From spring to summer, Murasaki's death will be soon arrived |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | 第一段 紫の上、出家を願うが許されず |
1-1 Murasaki desires to be a nun, but is not permitted by Genji |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.1 | 紫の上、いたうわづらひたまひし御心地の後、いと篤しくなりたまひて、そこはかとなく悩みわたりたまふこと久しくなりぬ。 |
紫の上、ひどくお患いになったご病気の後、とても衰弱がひどくおなりになって、どこそこがお悪いというのでなくご気分がすぐれない状態が長くなった。 |
紫夫人はあの大病以後病身になって、どこということもなく始終 |
Murasaki-no-Uhe, itau wadurahi tamahi si mi-kokoti no noti, ito atusiku nari tamahi te, sokohakatonaku nayami watari tamahu koto hisasiku nari nu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.2 | いとおどろおどろしうはあらねど、年月重なれば、頼もしげなく、いとどあえかになりまさりたまへるを、 院の思ほし嘆くこと、限りなし。 しばしにても後れきこえたまはむことをば、いみじかるべく思し、 みづからの御心地には、この世に飽かぬことなく、うしろめたきほだしだにまじらぬ御身なれば、あながちにかけとどめ まほしき御命とも 思されぬを、 年ごろの御契りかけ離れ、 思ひ嘆かせたてまつらむことのみぞ、人知れぬ御心のうちにも、ものあはれに 思されける。後の世のためにと、尊きことどもを多くせさせたまひつつ、「 いかでなほ本意あるさまになりて、 しばしもかかづらはむ命のほどは、行ひを紛れなく」と、たゆみなく思しのたまへど、 さらに許しきこえたまはず。 |
たいして重病ではないが、年月が重なるので、頼りなさそうに、ますます衰弱をお増しになったのを、院がご心痛になること、この上ない。少しの間でも先立たれ申されることは、堪えがたくお思いになり、ご自身のお気持ちは、この世に何の不足なこともなく、気がかりな子供たちさえおいででないお身の上なので、無理に生き残っていたいお命ともお思いなされないのだが、長年のご夫婦の縁を別れ、ご悲嘆申させるだろうことだけが、人知れず心の中でも、何となく悲しく思われなさるのであった。来世のためにと、尊い仏事を数多くなさりながら、「何とかしてやはり出家の本願を遂げて、暫くの間でも生きている命の限りは、勤行を一途に行いたい」と、いつもお思いになりお願いなさるが、まったくお許し申し上げなさらない。 |
たいした悪い容体になるのではなかったが、すぐれない、同じような不健康さが一年余りも続いた今では目に立って弱々しい姿になったことで、院は非常に心痛をしておいでになった。しばらくでもこの人の死んだあとのこの世にいるのは悲しいことであろうと知っておいでになったし、夫人自身も人生の幸福には不足を感じるところとてもなく、気がかりな思いの残る子もない人なのであるから、こまやかに思い合った過去を持っていて自分の先に欠けてしまうことは、院をどんなに不幸なお心持ちにすることであろうという点だけを心の中で物哀れに感じているのであった。未来の世のためにと思って夫人は功徳になることを多くしながらも、やはり出家して今後しばらくでも命のある間は仏勤めを十分にしたいということを始終院へお話しして、夫人は許しを得たがっているのであるが、院は御同意をあそばさなかった。 |
Ito odoroodorosiu ha ara ne do, tosituki kasanare ba, tanomosige naku, itodo ayekani nari masari tamahe ru wo, Win no omohosi nageku koto, kagiri nasi. Sibasi nite mo okure kikoye tamaha m koto wo ba, imizikaru beku obosi, midukara no mi-kokoti ni ha, konoyo ni aka nu koto naku, usirometaki hodasi dani mazira nu ohom-mi nare ba, anagatini kake todome mahosiki ohom-inoti to mo obosa re nu wo, tosigoro no ohom-tigiri kakehanare, omohi nageka se tatematura m koto nomi zo, hito-sire-nu mi-kokoro no uti ni mo, mono-ahare ni obosa re keru. Noti no yo no tame ni to, tahutoki koto-domo wo ohoku se sase tamahi tutu, "Ikade naho ho'i aru sama ni nari te, sibasi mo kakaduraha m inoti no hodo ha, okonahi wo magire naku" to, tayumi naku obosi notamahe do, sarani yurusi kikoye tamaha zu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.3 | さるは、わが御心にも、しか思しそめたる筋なれば、かくねむごろに思ひたまへるついでにもよほされて、 同じ道にも入りなむと 思せど、 一度、家を出でたまひなば、仮にもこの世を顧みむとは思しおきてず、後の世には、同じ蓮の座をも分けむと、契り交はしきこえたまひて、頼みをかけたまふ御仲なれど、ここながら勤めたまはむほどは、同じ山なりとも、峰を隔てて、あひ見たてまつらぬ住み処に かけ離れなむことをのみ 思しまうけたるに、かくいと頼もしげなきさまに 悩み篤いたまへば、いと心苦しき御ありさまを、今はと行き離れむきざみには捨てがたく、なかなか、 山水の住み処濁りぬべく、思しとどこほるほどに、 ただうちあさへたる、思ひのままの道心起こす人びとには、こよなう後れたまひぬべかめり。 |
そうは言うものの、ご自分のお気持ちにも、そのようにご決心なさっていることなので、このように熱心に思っていらっしゃる機会に促されて、一緒に出家生活に入ろうとお思いになるが、一度、出家をなさったらば、仮にもこの世の事を顧みようとはお思いにならず、来世では、一つの蓮の座を分け合おうと、お約束申し上げなさって、頼りにしていらっしゃるご夫婦仲であるが、この世のままで勤行なさる間は、同じ奥山であっても、峰を隔てて、お互いに顔を会わせない住まいで離れて生活することばかりをお考えになっていたので、このようにとても頼りない状態で病が篤くなってゆかれるので、とてもお気の毒なご様子を、いよいよ出家しようという時機には捨てることができず、かえって、山水の清い生活も濁ってしまいそうで、ぐずぐずしていらっしゃるうちに、ほんの浅い考えで、思うまま出家心を起こす人々に比べて、すっかり後れを取っておしまいになりそうである。 |
それは院御自身にも出家は希望していられることなのであるが、夫人が熱心にそうしたいと言っている時に、御自身もいっしょにそれを断行しようかというお心もないではないものの、いったん仏道にはいった以上は、仮にもこの世を顧みることはしたくないというお考えで、未来の世では一つの |
Saruha, waga mi-kokoro ni mo, sika obosi some taru sudi nare ba, kaku nemgoro ni omohi tamahe ru tuide ni moyohosa re te, onazi miti ni mo iri na m to obose do, hitotabi, ihe wo ide tamahi na ba, kari ni mo konoyo wo kaherimi m to ha obosi okite zu, noti no yo ni ha, onazi hatisu no za wo mo wake m to, tigiri kahasi kikoye tamahi te, tanomi wo kake tamahu ohom-naka nare do, koko nagara tutome tamaha m hodo ha, onazi yama nari tomo, mine wo hedate te, ahi mi tatematura nu sumika ni kakehanare na m koto wo nomi obosi mauke taru ni, kaku ito tanomosige naki sama ni nayami atui tamahe ba, ito kokorogurusiki ohom-arisama wo, ima ha to yuki hanare m kizami ni ha sute gataku, nakanaka, yamamidu no sumika nigori nu beku, obosi todokohoru hodo ni, tada uti-asahe taru, omohi no mama no dausin okosu hitobito ni ha, koyonau okure tamahi nu beka' meri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.4 | 御許しなくて、心一つに思し立たむも、さま悪しく本意なきやうなれば、 このことによりてぞ、 女君は、恨めしく思ひきこえたまひける。 わが御身をも、罪軽かるまじきにやと、うしろめたく思されけり。 |
お許しがなくて、一存でご決心なさるのも、体裁が悪く不本意のようなので、この一事によって、女君は、恨めしくお思い申し上げていらっしゃるのであった。ご自身でも、罪障が浅くない身の上ゆえかと、気がかりに思わずにはいらっしゃれないのであった。 |
院の同意されぬのを見ぬ顔にして尼になってしまうことも見苦しいことであるし、自分の心にも満足のできぬことであろうからと思って、この点で夫人は院をお恨めしく思った。また自分自身も前生の罪の深いものであろうと不安がりもした。 |
Ohom-yurusi naku te, kokoro hitotu ni obosi tata m mo, sama asiku ho'i naki yau nare ba, kono koto ni yori te zo, OmnaGimi ha, uramesiku omohi kikoye tamahi keru. Waga ohom-mi wo mo, tumi karokaru maziki ni ya to, usirometaku obosa re keri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 | 第二段 二条院の法華経供養 |
1-2 Murasaki holds a Hokekyo memorial service in Nijo-in |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.1 | 年ごろ、私の御願にて書かせたてまつりたまひける『 法華経』千部、いそぎて供養じたまふ。 わが御殿と思す二条院にてぞしたまひける。 七僧の法服など、品々賜はす。物の色、縫ひ目よりはじめて、きよらなること、限りなし。おほかた何ごとも、いといかめしきわざどもをせられたり。 |
長年、私的なご発願としてお書かせ申し上げなさった『法華経』一千部を、急いでご供養なさる。ご自身のお邸とお思いの二条院で催されるのであった。七僧の法服など、それぞれ身分に応じてお与えになる。法服の染色や、仕立て方をはじめとして、美しいこと、この上ない。だいたいどのようなことに対しても、実にご荘厳な法会を催された。 |
以前から自身の |
Tosi-goro, watakusi no ohom-gwan nite kaka se tatematuri tamahi keru "Hokekyau" sen-bu, isogi te kuyauzi tamahu. Waga ohom-tono to obosu Nideu-no-win nite zo si tamahi keru. Siti-sou no hohubuku nado, sinazina tamaha su. Mono no iro, nuhime yori hazime te, kiyoranaru koto, kagiri nasi. Ohokata nanigoto mo, ito ikamesiki waza-domo wo se rare tari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.2 | ことことしきさまにも聞こえたまはざりければ、 詳しきことどもも知らせたまはざりけるに、女の御おきてにてはいたり深く、 仏の道にさへ通ひたまひける御心のほどなどを、院はいと限りなしと見たてまつりたまひて、ただおほかたの御しつらひ、何かのことばかりをなむ、 営ませたまひける。楽人、舞人などのことは、 大将の君、取り分きて仕うまつりたまふ。 |
大層な催しには致されなかったので、詳細な事柄はお教えなさらなかったのに、女性のお指図としては行き届いており、仏道にまで通じていらっしゃるお心のほどなどを、院はまことにこの上ない方だと感心なさって、ただ大体のお飾り、何やかのことだけを、お世話なさるのであった。楽人、舞人などのことは、大将の君が特別にお世話を申し上げなさる。 |
|
Kotokotosiki sama ni mo kikoye tamaha zari kere ba, kuhasiki koto-domo mo sirase tamaha zari keru ni, womna no ohom-okite nite ha itari hukaku, Hotoke no miti ni sahe kayohi tamahi keru mi-kokoro no hodo nado wo, Win ha ito kagiri nasi to mi tatematuri tamahi te, tada ohokata no ohom-siturahi, nanika no koto bakari wo nam, itonama se tamahi keru. Gaku-nin, mahi-bito nado no koto ha, Daisyau-no-Kimi, toriwaki te tukaumaturi tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.3 | 内裏、春宮、后の宮たちをはじめたてまつりて、 御方々、ここかしこに御誦経、捧物などばかりのことをうちしたまふだに所狭きに、まして、そのころ、この御いそぎを仕うまつらぬ所なければ、 いとこちたきことどもあり。「 いつのほどに、いとかくいろいろ思しまうけけむ。げに、 石上の世々経たる 御願にや」とぞ見えたる。 |
帝、春宮、后宮たちをおはじめ申して、ご夫人方が、それぞれ御誦経、捧げ物など程度のことをご寄進なさるのでさえ所狭しなのに、それ以上に、その当時は、このご準備のご用をお務めしない人がないので、たいそう物々しいことがあれこれとある。「いつのまに、とてもこのようにいろいろとご用意なさったのであろう。なるほど、古い昔からの御願であろうか」と見えた。 |
宮中、東宮、院の |
Uti, Touguu, Kisai-no-Miya-tati wo hazime tatematuri te, ohom-katagata, koko-kasiko ni mi-zukyau, houmoti nado bakari no koto wo uti-si tamahu dani tokoroseki ni, masite, sonokoro, kono ohom-isogi wo tukaumatura nu tokoro nakere ba, ito kotitaki koto-domo ari. "Itu no hodo ni, ito kaku iroiro obosi mauke kem? Geni, Isonokami no yoyo he taru ohom-gwan ni ya?" to zo miye taru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.4 | 花散里と聞こえし御方、明石なども渡りたまへり。 南東の戸を開けておはします。 寝殿の西の塗籠なりけり。北の廂に、方々の御局どもは、障子ばかりを隔てつつしたり。 |
花散里と申し上げた御方、明石などもお越しになった。東南の妻戸を開けていらっしゃる。寝殿の西の塗籠であった。北の廂に、御方々のお席は、襖障子だけを仕切って設えてあった。 |
|
Hanatirusato to kikoye si Ohom-kata, Akasi nado mo watari tamahe ri. Minami-himgasi no to wo ake te ohasimasu. Sinden no nisi no nurigome nari keri. Kita no hisasi ni, katagata no mi-tubone-domo ha, sauzi bakari wo hedate tutu si tari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3 | 第三段 紫の上、明石御方と和歌を贈答 |
1-3 Murasaki and Akashi compose and exchange waka |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
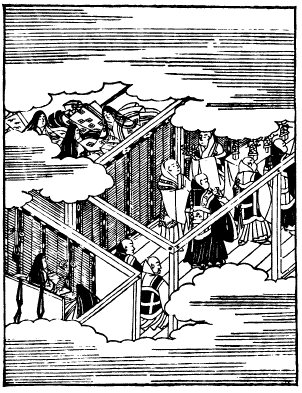 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.1 | 三月の十日なれば、花盛りにて、空のけしきなども、うららかにものおもしろく、 仏のおはすなる所のありさま、遠からず思ひやられて、ことなり。深き心もなき人さへ、罪を失ひつべし。 薪こる讃嘆の声も ★、 そこら集ひたる響き、おどろおどろしきを、うち休みて 静まりたるほどだにあはれに思さるるを、 まして、このころとなりては ★、何ごとにつけても、心細くのみ思し知る。 明石の御方に、三の宮して、聞こえたまへる。 |
三月の十日なので、花盛りで、空の様子なども、うららかで興趣あり、仏のいらっしゃる極楽浄土の有様が、身近に想像されて、格別である。信心のない人までが、罪障がなくなりそうである。薪こる行道の声も、大勢集い響き、あたりをゆるがすが、声が中断して静かになった時でさえしみじみ寂しく思わずにはいらっしゃれないのに、それ以上に、最近になっては、何につけても、心細くばかりお感じになられる。明石の御方に、三の宮を使いにして、申し上げなさる。 |
三月の十日であったから花の |
Samgwatu no towoka nare ba, hanazakari nite, sora no kesiki nado mo, urarakani monoomosiroku, Hotoke no ohasu naru tokoro no arisama, tohokara zu omohiyara re te, koto nari. Hukaki kokoro mo naki hito sahe, tumi wo usinahi tu besi. Takigi koru santan no kowe mo, sokora tudohi taru hibiki, odoroodorosiki wo, uti-yasumi te sidumari taru hodo dani ahareni obosa ruru wo, masite, konokoro to nari te ha, nanigoto ni tuke te mo, kokorobosoku nomi obosi-siru. Akasi-no-Ohomkata ni, Sam-no-Miya site, kikoye tamahe ru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.2 | 「 惜しからぬこの身ながらもかぎりとて 薪尽きなむことの悲しさ ★」 |
「惜しくもないこの身ですが、これを最後として 薪の尽きることを思うと悲しうございます」 |
惜しからぬこの身ながらも限りとて |
"Wosikara nu kono mi nagara mo kagiri tote takigi tuki na m koto no kanasi sa |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.3 | 御返り、心細き筋は、後の聞こえも心後れたるわざにや、そこはかとなくぞあめる。 |
お返事は、心細い歌意のことは、後の非難も気にかかったのであろうか、当り障りのない詠みぶりであったようだ。 |
夫人の心細い気持ちに共鳴したふうのものを返しにしては、認識不足を人から |
Ohom-kaheri, kokorobosoki sudi ha, noti no kikoye mo kokoro okure taru waza ni ya, sokohakatonaku zo a' meru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.4 | 「 薪こる思ひは今日を初めにて この世に願ふ法ぞはるけき」 |
「仏道へのお思いは今日を初めの日として この世で願う仏法のために千年も祈り続けられることでしょう」 |
薪こる思ひは今日を初めにて この世に願ふ |
"Takigi koru omohi ha kehu wo hazime nite konoyo ni negahu nori zo harukeki |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.5 | 夜もすがら、尊きことにうち合はせたる鼓の声、絶えずおもしろし。 ほのぼのと明けゆく朝ぼらけ、霞の間より見えたる花の色々、なほ春に心とまりぬべく匂ひわたりて、 百千鳥のさへづりも、笛の音に劣らぬ心地して、もののあはれもおもしろさも残らぬほどに、 陵王の舞ひ手急になるほどの末つ方の楽、はなやかににぎははしく聞こゆるに、皆人の脱ぎかけたるものの色々なども、もののをりからにをかしうのみ見ゆ。 |
一晩中、尊い読経の声に合わせた鼓の音、鳴り続けておもしろい。ほのぼのと夜が明けてゆく朝焼けに、霞の間から見えるさまざまな花の色が、なおも春に心がとまりそうに咲き匂っていて、百千鳥の囀りも、笛の音に負けない感じがして、しみじみとした情趣も感興もここに極まるといった感じで、陵王の舞が急の調べにさしかかった最後のほうの楽、はなやかに賑やかに聞こえるので、一座の人々が脱いで掛けていた衣装のさまざまな色なども、折からの情景に美しく見える。 |
経声も楽音も混じっておもしろく夜は明けていくのであった。朝ぼらけの |
Yomosugara, tahutoki koto ni uti-ahase taru tudumi no kowe, taye zu omosirosi. Honobono to ake yuku asaborake, kasumi no ma yori miye taru hana no iroiro, naho haru ni kokoro tomari nu beku nihohi watari te, momotidori no saheduri mo, hue no ne ni otora nu kokoti si te, mononoahare mo omosirosa mo nokora nu hodo ni, Ryauwau no mahite kihu ni naru hodo no suwe tu kata no gaku, hanayakani nigihahasiku kikoyuru ni, minabito no nugi kake taru mono no iroiro nado mo, mono no wori kara ni wokasiu nomi miyu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.6 | 親王たち、上達部の中にも、ものの上手ども、手残さず遊びたまふ。 上下心地よげに、興あるけしきどもなるを見たまふにも、残り少なしと身を思したる御心のうちには、よろづのことあはれにおぼえたまふ。 |
親王たち、上達部の中でも、音楽の上手な方々は、技を尽くして演奏なさる。身分の上下に関わらず気持ちよさそうに、うち興じている様子を御覧になるにも、余命少ないと身をお思いになっていらっしゃるお心の中には、万事がしみじみと悲しく思われなさる。 |
親王がた、高官らも音楽に名のある人はみずからその芸を惜しまずこの場で見せて遊んだ。上から下まで来会者が歓楽に酔っているのを見ても、余命の少ないことを知っている夫人の心だけは悲しかった。 |
Miko-tati, Kamdatime no naka ni mo, mono no zyauzu-domo, te nokosa zu asobi tamahu. Kami simo kokotiyoge ni, kyou aru kesiki-domo naru wo mi tamahu ni mo, nokori sukunasi to mi wo obosi taru mi-kokoro no uti ni ha, yorodu no koto ahare ni oboye tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4 | 第四段 紫の上、花散里と和歌を贈答 |
1-4 Murasaki and Hanachirusato compose and exchange waka |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.1 | 昨日、例ならず起きゐたまへりし名残にや、いと苦しうして臥したまへり。年ごろ、かかるものの折ごとに、参り集ひ遊びたまふ人びとの御容貌ありさまの、おのがじし才ども、琴笛の音をも、 今日や見聞きたまふべきとぢめなるらむ、とのみ思さるれば、さしも目とまるまじき人の顔どもも、 あはれに見えわたされたまふ。 |
昨日は、いつもと違って起きていらっしゃったせいであろうか、とても苦しくて臥せっていらっしゃる。長年、このような機会ごとに、参集して音楽をなさる方々のご容貌や態度が、それぞれの才能、琴笛の音色をも、今日が見たり聞いたりなさる最後になるだろう、とばかりお思いなさるので、格別に目にもとまらないはずの人達の顔も、しみじみと一人一人に目が自然とお止まりになる。 |
昨日は例外に終日起きていたせいか夫人は苦しがって横になっていた。これまでこうしたおりごとに必ず集まって来て、音楽舞楽の何かの一役を勤める人たちの |
Kinohu, rei nara zu oki wi tamahe ri si nagori ni ya, ito kurusiu si te husi tamahe ri. Tosigoro, kakaru mono no wori goto ni, mawiri tudohi asobi tamahu hitobito no ohom-katati arisama no, onogazisi zae-domo, koto hue no ne wo mo, kehu ya mi kiki tamahu beki todime naru ram, to nomi obosa rure ba, sasimo me tomaru maziki hito no kaho-domo mo, ahareni miye watasa re tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.2 | まして、夏冬の時につけたる遊び戯れにも、なま挑ましき下の心は、 おのづから立ちまじりもすらめど、さすがに 情けを交はしたまふ方々は ★、 誰れも久しくとまるべき世にはあらざなれど、まづ我一人行方知らずなりなむを思し続くる、いみじうあはれなり。 |
それ以上に、夏冬の四季折々の音楽会や遊びなどにも、何となく張り合う気持ちは、自然と沸き起こって来るようであるが、やはりお互いに親しくしあっていらっしゃる御方々は、誰もみな永久に生きていらっしゃれる世の中ではないが、まず自分独りが先立って行くのをお考え続けなさると、ひどく悲しいのである。 |
まして四季の遊び事に競争心は必ずあっても、さすがに長くつちかわれた友情というもののあった夫人たちに対しては、だれも永久に生き残る人はないであろうが、まず自分一人がこの中から消えていくのであると思われるのが女王の心に悲しかった。 |
Masite, natu huyu no toki ni tuke taru asobi tahabure ni mo, nama-idomasiki sita no kokoro ha, onodukara tati-maziri mo su rame do, sasugani nasake wo kahasi tamahu katagata ha, tare mo hisasiku tomaru beki yo ni ha ara za' nare do, madu ware hitori yukuhe sira zu nari na m wo obosi tudukuru, imiziu ahare nari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.3 | こと果てて、おのがじし帰りたまひなむとするも、 遠き別れめきて惜しまる。花散里の御方に、 |
法会が終わって、それぞれお帰りになろうとするのも、永遠の別れのように思われて惜しまれる。花散里の御方に、 |
宴が終わってそれぞれの夫人が帰って行く時なども、生死の別れほど別れが惜しまれた。花散里夫人の所へ、 |
Koto hate te, onogazisi kaheri tamahi na m to suru mo, tohoki wakare meki te wosima ru. Hanatirusato-no-Ohomkata ni, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.4 | 「 絶えぬべき御法ながらぞ頼まるる 世々にと結ぶ中の契りを」 |
「これが最後と思われます法会ですが、頼もしく思われます 生々世々にかけてと結んだあなたとの縁を」 |
絶えぬべき 世々にと結ぶ中の契りを |
"Taye nu beki mi-nori nagara zo tanoma ruru yoyo ni to musubu naka no tigiri wo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.5 | 御返り、 |
お返事は、 |
と書いて紫の女王は送った。 |
Ohom-kaheri, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.6 | 「 結びおく契りは絶えじおほかたの 残りすくなき御法なりとも」 |
「あなた様と御法会で結んだ御縁は未来永劫に続くでしょう 普通の人には残り少ない命とて、多くは催せない法会でしょうとも」 |
結びおく契りは絶えじおほかたの 残り少なき御法なりとも |
"Musubi oku tigiri ha taye zi ohokata no nokori sukunaki mi-nori nari tomo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.7 | やがて、このついでに、 不断の読経、懺法など、たゆみなく、 尊きことどもせさせたまふ。御修法は、ことなるしるしも見えで ほども経ぬれば、例のことになりて、うちはへさるべき所々、寺々にてぞせさせたまひける。 |
引き続き、この機会に、不断の読経や、懺法などを、怠りなく、尊い仏事の数々をおさせになる。御修法は、格別の効験も現れないで時が過ぎたので、いつものことになって、引き続いてしかるべきあちらこちら、寺々においておさせになった。 |
これは返事である。供養に続いて不断の |
Yagate, kono tuide ni, hudan no dokyau, senbohu nado, tayumi naku, tahutoki koto-domo se sase tamahu. Mi-suhohu ha, koto naru sirusi mo miye de hodo mo he nure ba, rei no koto ni nari te, utihahe sarubeki tokorodokoro, tera dera nite zo se sase tamahi keru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 | 第五段 紫の上、明石中宮と対面 |
1-5 Murasaki meets Akashi-empress, her an adopted daughter |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5.1 | 夏になりては、例の暑さにさへ、いとど消え入りたまひぬべき折々多かり。 そのことと、おどろおどろしからぬ御心地なれど、ただいと弱きさまになりたまへば、 むつかしげに所狭く悩みたまふこともなし。さぶらふ人びとも、いかにおはしまさむとするにか、と思ひよるにも、まづかきくらし、あたらしう悲しき御ありさまと見たてまつる。 |
夏になってからは、いつもの暑さでさえ、ますます意識を失っておしまいになりそうな時々が多かった。どこといって、特に苦しんだりなさらないご病状であるが、ただたいそう衰弱した状態におなりになったので、いかにも病人めいてたいそうにお悩みになることもない。伺候している女房たちも、この先どうおなりになるのだろうか、と思うにつけても、もう目の前がまっくらになって、もったいなくも悲しいご様子と拝する。 |
夏になると夫人は暑気のためにも死ぬようになることが多かった。病名も定まらぬ程度のものであるが、ただ衰弱がひどかった。堪えがたい苦しみをするというのでもない。女房たちの心にも、どうおなりになるのであろう、このまま危篤になっておしまいになるのではなかろうかという不安が生じてきて、惜しく悲しくばかりそれらの人々も思って歎いていた。 |
Natu ni nari te ha, rei no atusisa ni sahe, itodo kiye iri tamahi nu beki woriwori ohokari. Sono koto to, odoroodorosikara nu mi-kokoti nare do, tada ito yowaki sama ni nari tamahe ba, mutukasigeni tokoroseku nayami tamahu koto mo nasi. Saburahu hitobito mo, ikani ohasimasa m to suru ni ka, to omohiyoru ni mo, madu kaki-kurasi, atarasiu kanasiki ohom-arisama to mi tatematuru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5.2 | かくのみおはすれば、 中宮、この院にまかでさせたまふ。 東の対におはしますべければ、こなたにはた待ちきこえたまふ。儀式など、例に変らねど、 この世のありさまを見果てずなりぬるなどのみ思せば、よろづにつけてものあはれなり。 名対面を聞きたまふにも、その人、かの人など、耳とどめて聞かれたまふ。上達部など、いと多く仕うまつりたまへり。 |
こうした状態ばかりでいらっしゃるので、中宮が、この二条院に御退出あそばされる。東の対に御滞在あそばす予定なので、こちらでお待ち申し上げていらっしゃる。儀式など、いつもと変わらないが、この世の作法もこれが見納めだろうなどとばかりお思いになると、何かにつけても悲しい。名対面をお聞きになっても、あれは誰、これは誰などと、耳を止めてついお聞きになる。上達部なども大勢供奉なさっていた。 |
こんなふうであったから院は中宮を御所から二条の院へ退出おさせになった。当分東の |
Kaku nomi ohasure ba, Tyuuguu, kono win ni makade sase tamahu. Himgasinotai ni ohasimasu bekere ba, konata ni hata mati kikoye tamahu. Gisiki nado, rei ni kahara ne do, konoyo no arisama wo mi hate zu nari nuru nado nomi obose ba, yorodu ni tuke te mono-ahare nari. Nadaimen wo kiki tamahu ni mo, sono hito, kano hito nado, mimi todome te kika re tamahu. Kamdatime nado, ito ohoku tukaumaturi tamahe ri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5.3 | 久しき御対面のとだえを、 めづらしく思して、御物語こまやかに聞こえたまふ。院入りたまひて、 |
久しく御対面なさらなかったので、珍しくお思いになって、お話をこまごまと申し上げなさる。院がお入りになって、 |
しばらくぶりに、実母子以上の愛情が相互にある二人の女性はしめやかに語り合っておいでになった。院がはいっておいでになったが、 |
Hisasiki ohom-taimen no todaye wo, medurasiku obosi te, ohom-monogatari komayakani kikoye tamahu. Win iri tamahi te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5.4 | 「 今宵は、巣離れたる心地して、無徳なりや。まかりて休みはべらむ」 |
「今夜は、巣をなくした鳥の思いで、まったくぶざまなさまですね。退出して寝るとしよう」 |
「今夜は巣を追われた鳥のようでかわいそうな私はどこかで寝ることにしよう」 |
"Koyohi ha, subanare taru kokoti si te, mutoku nari ya! Makari te yasumi habera m." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5.5 | とて、渡りたまひぬ。 起きゐたまへるを、いとうれしと思したるも、いとはかなきほどの御慰めなり。 |
と言って、お帰りになってしまった。起きていらっしゃるのを、嬉しいとお思いになるのも、まことにはかないお慰めである。 |
と言って、他の |
tote, watari tamahi nu. Oki wi tamahe ru wo, ito uresi to obosi taru mo, ito hakanaki hodo no ohom-nagusame nari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5.6 | 「 方々におはしましては、 あなたに渡らせたまはむもかたじけなし。参らむこと、はたわりなくなりにてはべれば」 |
「別々のお部屋にいらっしゃったのでは、あちらにお越しあそばすのも恐れ多いことです。お伺いすること、それもできにくくなってしまいましたので」 |
「離れた所では、こちらからあちらへ歩いてお帰りになることがたいへんですし、私もまたあちらへ上がることはもうできなくなっていますから」 |
"Katagata ni ohasi masi te ha, anata ni watara se tamaha m mo katazikenasi. Mawira m koto, hata wari naku nari ni te habere ba." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5.7 | とて、 ▼ しばらくはこなたにおはすれば、明石の御方も渡りたまひて、心深げにしづまりたる御物語ども聞こえ交はしたまふ。 |
と言って、暫くの間はこちらにいらっしゃるので、明石の御方もお越しになって、心のこもった静かなお話などをお取り交わしなさる。 |
と夫人は言っていて、中宮はしばらくこの病室のあるほうの対におとどまりになることになった。 |
tote, sibaraku ha konata ni ohasure ba, Akasi-no-Ohomkata mo watari tamahi te, kokorobukage ni sidumari taru ohom-monogatari-domo kikoye kahasi tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 | 第六段 紫の上、匂宮に別れの言葉 |
1-6 Murasaki says good-bye to Niou-miya |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6.1 | 上は、御心の うちに思しめぐらすこと多かれど、さかしげに、 亡からむ後などのたまひ出づることもなし。ただなべての世の常なきありさまを、おほどかに言少ななるものから、 あさはかにはあらずのたまひなしたるけはひなどぞ、 言に出でたらむよりもあはれに、もの心細き御けしきは、しるう見えける。 宮たちを見たてまつりたまうても、 |
紫の上は、ご心中にお考えになっていらっしゃることがいろいろと多くあるが、利口そうに、亡くなった後はなどと、お口にされることもない。ただ世間一般の世の無常な有様を、おっとりと言葉少なでありながらも、並々ではないおっしゃりようをなさるご様子などを、言葉にお出しになるよりも、しみじみと何か心細いご様子は、はっきりと見えるのであった。宮たちを拝見なさっても、 |
女王の心の中では頼みたく、言っておきたく思うことが幾つかあったが、賢そうに死後のことを今から言うように取られるのを恥じて、そうした問題には触れないのであった。ただ人生のはかなさをおおように、言葉少なに、しかも軽々しくはなしに話すのが、露骨に死期の近いことを言うよりもどんなに心細い気持ちでいるかを思わせた。 |
Uhe ha, mi-kokoro no uti ni obosi megurasu koto ohokare do, sakasige ni, nakara m noti nado notamahi iduru koto mo nasi. Tada nabete no yo no tune naki arisama wo, ohodokani kotosukuna naru monokara, asahaka ni ha ara zu notamahi nasi taru kehahi nado zo, koto ni ide tara m yori mo ahareni, mono-kokorobosoki mi-kesiki ha, siruu miye keru. Miya-tati wo mi tatematuri tamau te mo, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6.2 | 「 おのおのの御行く末を、ゆかしく思ひきこえけるこそ、かくはかなかりける身を惜しむ心のまじりけるにや」 |
「それぞれのご将来を、見たいものだとお思い申し上げていましたのは、このようにはかなかったわが身を惜しむ気持ちが交じっていたからでしょうか」 |
「あなたがたがどうおなりになるだろうと、将来が見たいような気がしましたのも、私のようにつまらない者でいながら、知らず知らず命を惜しんでいたわけでしょうか」 |
"Onoono no ohom-yukusuwe wo, yukasiku omohi kikoye keru koso, kaku hakanakari keru mi wo wosimu kokoro no maziri keru ni ya?" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6.3 | とて、涙ぐみたまへる御顔の匂ひ、いみじうをかしげなり。「 などかうのみ思したらむ」と思すに、中宮、うち泣きたまひぬ。 ゆゆしげになどは聞こえなしたまはず、もののついでなどにぞ、年ごろ仕うまつり馴れたる人びとの、ことなるよるべなういとほしげなる、この人、かの人、 |
と言って、涙ぐんでいらっしゃるお顔の美しさ、素晴らしく見事である。「どうしてこんなふうにばかりお思いでいらっしゃるのだろう」とお思いになると、中宮は、思わずお泣きになってしまった。縁起でもない申し上げようはなさらず、お話のついでなどに、長年お仕えし親しんできた女房たちで、特別の身寄りがなく気の毒そうな、この人、あの人を、 |
こんなことを言って涙ぐむその顔が非常に美しかった。なぜそんなふうにばかり感ぜられるのであろうとお思いになって、中宮はお泣きになった。遺言のようにはせず話の中などで時々、「長く私に仕えてくれました人たちの中で、たいした身寄りのないようなかわいそうなだれだれなどを、 |
tote, namidagumi tamahe ru ohom-kaho no nihohi, imiziu wokasige nari. "Nado kau nomi obosi tara m?" to obosu ni, Tyuuguu, uti-naki tamahi nu. Yuyusige ni nado ha kikoye nasi tamaha zu, mono no tuide nado ni zo, tosi-goro tukaumaturi nare taru hitobito no, koto naru yorube nau itohosige naru, kono hito, kano hito, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6.4 | 「はべらずなりなむ後に、御心とどめて、尋ね思ほせ」 |
「私が亡くなりました後に、お心をとめて、お目をかけてやってください」 |
私がいなくなりましたあとで、あなたから気をつけてやってください」 |
"Habera zu nari na m noti ni, mi-kokoro todome te, tadune omohose." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6.5 | などばかり聞こえたまひける。 御読経などによりてぞ、 例のわが御方に渡りたまふ。 |
などとだけ申し上げなさるのであった。御読経などのために、いつものご座所にお帰りになる。 |
などというほどにしか死後のことは言わないのである。病室で |
nado bakari kikoye tamahi keru. Mi-dokyau nado ni yori te zo, rei no waga ohom-kata ni watari tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6.6 | 三の宮は、あまたの御中に、いとをかしげにて歩きたまふを、御心地の隙には、前に据ゑたてまつりたまひて、人の聞かぬ間に、 |
三の宮は、大勢の皇子たちの中で、とてもかわいらしくお歩きになるのを、ご気分の好い間には、前にお座らせ申されて、人が聞いていない時に、 |
三の宮は幾人もの宮様がたの中にことに愛らしいお姿でそばへ遊びにおいでになるのを、病苦の薄らいだ時などに女王は前へおすわらせして、女房たちの聞いていないのを見ると、 |
Sam-no-Miya ha, amata no ohom-naka ni, ito wokasige nite ariki tamahu wo, mi-kokoti no hima ni ha, mahe ni suwe tatematuri tamahi te, hito no kika nu ma ni, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6.7 | 「 まろがはべらざらむに、思し出でなむや」 |
「わたしが亡くなってからも、お思い出しになってくださいましょうか」 |
「私がいなくなりましたら、あなたは思い出してくださるでしょうね」 |
"Maro ga habera zara m ni, obosi ide na m ya?" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6.8 | と聞こえたまへば、 |
とお尋ね申し上げなさると、 |
などと言うのであったが、宮は、 |
to kikoye tamahe ba, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6.9 | 「 いと恋しかりなむ。まろは、 内裏の上よりも宮よりも、 婆をこそまさりて思ひきこゆれば、おはせずは、心地むつかしかりなむ」 |
「きっととても恋しいことでしょう。わたしは、御所の父上よりも母宮よりも、祖母様を誰よりもお慕い申し上げていますので、いらっしゃらなくなったら、機嫌が悪くなりますよ」 |
「恋しいでしょう。私は御所の陛下よりも中宮様よりもお |
"Ito kohisikari na m. Maro ha, Uti-no-Uhe yori mo Miya yori mo, Baba wo koso masari te omohi kikoyure ba, ohase zu ha, kokoti mutukasikari na m." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6.10 | とて、目おしすりて紛らはしたまへるさま、をかしければ、ほほ笑みながら涙は落ちぬ。 |
と言って、目を拭ってごまかしていらっしゃる様子、いじらしいので、ほほ笑みながらも涙は落ちた。 |
とお言いになって、目をこすって涙を紛らしておいでになる宮のお姿のおかわいいために、夫人は微笑をして見ているのであったが、目からは涙がこぼれた。 |
tote, me osi-suri te magirahasi tamahe ru sama, wokasikere ba, hohowemi nagara namida ha oti nu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6.11 | 「 大人になりたまひなば、ここに住みたまひて、 この対の前なる紅梅と桜とは、花の折々に、心とどめてもて遊びたまへ。 さるべからむ折は、仏にもたてまつりたまへ」 |
「大人におなりになったら、ここにお住まいになって、この対の前にある紅梅と桜とは、花の咲く季節には、大切にご鑑賞なさい。何かの折には、仏前にもお供えください」 |
「あなたが大人におなりになったら、ここへお住みになって、この対の前の紅梅と桜とは花の時分に十分愛しておながめなさいね。時々はまた仏様へもお供えになってね」 |
"Otona ni nari tamahi na ba, koko ni sumi tamahi te, kono tai no mahe naru koubai to sakura to ha, hana no woriwori ni, kokoro todome te mote-asobi tamahe. Saru bekara m wori ha, Hotoke ni mo tatematuri tamahe." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6.12 | と聞こえたまへば、うちうなづきて、御顔をまもりて、涙の落つべかめれば、立ちておはしぬ。取り分きて 生ほしたてまつりたまへれば、 この宮と姫宮とをぞ、見さしきこえたまはむこと、口惜しくあはれに思されける。 |
と申し上げなさると、こっくりとうなずいて、お顔をじっと見つめて、涙が落ちそうなので、立って行っておしまいになった。特別に引き取ってお育て申し上げなさったので、この宮と姫宮とを、途中でお世話申し上げることができないままになってしまうことが、残念にしみじみとお思いなさるのであった。 |
と言うと、宮はおうなずきになりながら、夫人の顔を見守っておいでになったが、涙が落ちそうになったので、立ってお行きになった。手もとでお育てしたために夫人はこの宮と姫君にお別れすることをことに悲しく思っていた。 |
to kikoye tamahe ba, uti-unaduki te, ohom-kaho wo mamori te, namida no otu bekamere ba, tati te ohasi nu. Toriwaki te ohosi tatematuri tamahe re ba, kono Miya to HimeMiya to wo zo, mi sasi kikoye tamaha m koto, kutiwosiku ahareni obosa re keru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last updated 9/22/2010(ver.2-3) 渋谷栄一校訂(C) Last updated 7/29/2010(ver.2-2) 渋谷栄一注釈(C) |
Last updated 2/3/2002 渋谷栄一訳(C)(ver.1-2-2) |
|
Last updated 7/29/2010 (ver.2-2) Written in Japanese roman letters by Eiichi Shibuya (C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Picture "Eiri Genji Monogatari"(1650 1st edition) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源氏物語の世界 再編集プログラム Ver 3.38: Copyright (c) 2003,2015 宮脇文経