第四十四帖 竹河 |
44 TAKEKAHA (Ohoshima-bon) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 薫君の中将時代 十五歳から十九歳までの物語 |
Tale of Kaoru's Chujo era, from the age of 15 to 19 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 第二章 玉鬘邸の物語 梅と桜の季節の物語 |
2 Tale of Tamakazura Tale of ume and cherry blossoms seasons |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1 | 第一段 正月、夕霧、玉鬘邸に年賀に参上 |
2-1 The New Year's Day, Yugiri visits to Tamakazura's residence |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.1 | 睦月の朔日ころ、 尚侍の君の御兄弟の大納言、「 高砂」謡ひしよ、 藤中納言、故大殿の太郎、真木柱の一つ腹など参りたまへり。 右の大臣も、御子ども六人ながらひき連れておはしたり。御容貌よりはじめて、飽かぬことなく見ゆる人の御ありさまおぼえなり。 |
正月朔日ころ、尚侍の君のご兄弟の大納言、「高砂」を謡った方だが、藤中納言、故大殿の太郎君で、真木柱と同じ母親の方などが参賀にいらっしゃった。右大臣も、ご子息たちを六人そのままお連れしていらっしゃった。ご器量をはじめとして、非のうちどころなく見える方のご様子やご評判である。 |
正月の元日に |
Mutuki no tuitati koro, Kam-no-Kimi no ohom-harakara no Dainagon, Takasago utahi si yo, Tou-Tiunagon, ko-Ohoidono no Tarau, Makibasira no hitotubara nado mawiri tamahe ri. Migi-no-Otodo mo, Miko-domo roku-nin nagara hikiture te ohasi tari. Ohom-katati yori hazime te, aka nu koto naku miyuru hito no ohom-arisama oboye nari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.2 | 君たちも、さまざまいときよげにて、年のほどよりは、官位過ぎつつ、 何ごと思ふらむと見えたるべし。世とともに、蔵人の君は、かしづかれたるさま異なれど、うちしめりて 思ふことあり顔なり。 |
ご子息たちも、それぞれとても美しくて、年齢の割合には、官位も進んで、きっと何の物思いもなく見えたであろう。いつも、蔵人の君は、大切にされていることは格別であるが、ふさぎ込んで悩み事のある顔をしている。 |
子息たちもそれぞれきれいで、年齢の割合からいって、皆官位が進んでいた。物思いなどは少しも知らずにいるであろうと見えた。いつものように蔵人少将はことに秘蔵 |
Kimitati mo, samazama ito kiyoge nite, tosi no hodo yori ha, tukasa kurawi sugi tutu, nanigoto omohu ram to miye taru besi. Yo to tomoni, Kuraudo-no-Kimi ha, kasiduka re taru sama koto nare do, uti-simeri te omohu koto ari gaho nari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.3 | 大臣は、御几帳隔てて、昔に変らず御物語聞こえたまふ。 |
大臣は、御几帳を隔てて、昔と変わらずお話し申し上げなさる。 |
大臣は |
Otodo ha, mikityau hedate te, mukasi ni kahara zu ohom-monogatari kikoye tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.4 | 「 そのこととなくて、しばしばもえうけたまはらず。年の数添ふままに、内裏に参るより 他のありき、うひうひしうなりにてはべれば、いにしへの御物語も、聞こえまほしき折々多く過ぐしはべるをなむ。 |
「これという用事もなくて、たびたびお話を承ることもできません。年齢が加わるとともに、宮中に参内する以外の外歩きなども、億劫になってしまいましたので、昔のお話も、申し上げたい時々も多くそのままになってしまいました。 |
「用のない時にも伺わなければならないのを、失礼ばかりしています。年がいってしまいまして、御所へまいる以外の外出がもういっさいおっくうに思われるものですから、昔の話を伺いたい気持ちになります時も、そのままに済ませてしまうようになるのを遺憾に思います。 |
"Sono koto to naku te, sibasiba mo e uke tamahara zu. Tosi no kazu sohu mama ni, Uti ni mawiru yori hoka no ariki, uhiuhisiu nari ni te habere ba, inisihe no ohom-monogatari mo, kikoye mahosiki woriwori ohoku sugusi haberu wo nam. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.5 | 若き男どもは、さるべきことには召しつかはせたまへ。かならずその心ざし御覧ぜられよと、いましめはべり」など聞こえたまふ。 |
若い男の子たちは、何かの時にはお呼びになってお使いください。かならずその気持ちを見て戴くようにと、言い聞かせてあります」など申し上げなさる。 |
若い息子たちは何の御用にでもお使いください。誠意を認めていただくようにするがいいと教えております」 |
Wakaki wonoko-domo ha, sarubeki koto ni ha mesi tukaha se tamahe. Kanarazu sono kokorozasi go-ran-ze rare yo to, imasime haberi." nado kikoye tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.6 | 「 今は、かく、世に経る数にもあらぬやうになりゆくありさまを、思し数まふるになむ、過ぎにし御ことも、いとど忘れがたく思うたまへられける」 |
「今では、このように、世間の人数にも入らぬ者のようになって行く有様を、お心に掛けてくださるので、亡くなった方のことも、ますます忘れ難く存じられるます」 |
「もうこの家などはだれの念頭にも置いていただけないものになっておりますのに、お忘れになりませんで御親切にお |
"Ima ha, kaku, yo ni huru kazu ni mo ara nu yau ni nariyuku arisama wo, obosi kazumahuru ni nam, sugi ni si ohom-koto mo, itodo wasure gataku omou tamahe rare keru." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.7 | と申したまひけるついでに、 院よりのたまはすること、 ほのめかし聞こえたまふ。 |
と申し上げなさったついでに、院から仰せになったことを、ちらっと申し上げなさる。 |
尚侍はこんなことを言ったついでに、冷泉院からあった仰せについて大臣へ相談をかけた。 |
to mausi tamahi keru tuide ni, Win yori notamahasuru koto, honomekasi kikoye tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.8 | 「 はかばかしう後見なき人の交じらひは、なかなか見苦しきをと、 思ひたまへなむわづらふ」 |
「これといった後見のない人の宮仕えは、かえって見苦しいと、あれこれ考えあぐねております」 |
「しかとした後援者を持ちませんものが、そうした所へ出てまいっては、かえって苦しみますばかりかとも思われますが」 |
"Hakabakasiu usiromi naki hito no mazirahi ha, nakanaka migurusiki wo to, omohi tamahe nam wadurahu." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.9 | と申したまへば、 |
と申し上げなさるので、 |
to mousi tamahe ba, |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.10 | 「 内裏に仰せらるることあるやうに承りしを、いづ方に思ほし定むべきことにか。院は、げに、御位を去らせたまへるにこそ、盛り過ぎたる心地すれど、世にありがたき御ありさまは、古りがたくのみおはしますめるを、 よろしう生ひ出づる女子はべら ましかばと、思ひたまへよりながら、恥づかしげなる御中に、交じらふべき物のはべらでなむ、口惜しう思ひたまへらるる。 |
「帝にも仰せられることがあるようにお聞きいたしておりましたが、どちらにお決めなさるべきでしょうか。院は、なるほど、お位を退かれあそばしました点では、盛りの過ぎた感じもしますが、世に二人といない御様子は、いっこうに変わらずにいらっしゃるようですので、人並みに成人した娘がおりましたらと、存じておりますが、立派な方々のお仲間入りできる者がございませんで、残念に存じております。 |
「宮中からもお話があるということですが、どちらへおきめになっていいことでしょうね。院は |
"Uti ni ohose raruru koto aru yau ni uketamahari si wo, idukata ni omohosi sadamu beki koto ni ka? Win ha, geni, mi-kurawi wo sara se tamahe ru ni koso, sakari sugi taru kokoti sure do, yo ni arigataki ohom-arisama ha, huri gataku nomi ohasimasu meru wo, yorosiu ohi iduru womnago habera masika ba to, omohi tamahe yori nagara, hadukasige naru ohom-naka ni, mazirahu beki mono no habera de nam, kutiwosiu omohi tamahe raruru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.11 | そもそも、 女一の宮の女御は、許しきこえたまふや。さきざきの人、さやうの憚りにより、とどこほることもはべりかし」 |
そもそも、女一宮の母女御は、お許し申し上げなさるでしょうか。これまでの方では、そのような遠慮によって、止めにしたこともございました」 |
いったい |
Somosomo, Womna-ItinoMiya no Nyougo ha, yurusi kikoye tamahu ya. Sakizaki no hito, sayau no habakari ni yori, todokohoru koto mo haberi kasi." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.12 | と申したまへば、 |
と申し上げなさると、 |
と大臣は |
to mausi tamahe ba, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.13 | 「 女御なむ、つれづれにのどかになりにたるありさまも、同じ心に 後見て、慰めまほしきをなど、かの勧めたまふにつけて、いかがなどだに思ひたまへよるになむ」 |
「女御が、する事もなくのんびりとなった生活も、同じ気持ちでお世話して、気を晴らしたいなどと、その方がお勧めなさったことにかこつけて、せめてどうしたらよいものかと思案しております」 |
「女御さんから、つれづれで退屈な時間もあなたに代わってその人の世話をしてあげることで紛らしたいなどとお勧めになるものですから、私も院参を問題として考えるようになったのでございます」 |
"Nyougo nam, turedure ni nodoka ni nari ni taru arisama mo, onazi kokoro ni usiromi te, nagusame mahosiki wo nado, kano susume tamahu ni tuke te, ikaga nado dani omohi tamahe yoru ni nam." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.14 | と聞こえたまふ。 |
と申し上げなさる。 |
と尚侍は言っていた。 |
to kikoye tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.15 | これかれ、ここに集まりたまひて、 三条の宮に参りたまふ。朱雀院の古き心ものしたまふ人びと、六条院の方ざまのも、かたがたにつけて、なほかの 入道宮をば、えよきず 参りたまふなめり。 この殿の左近中将、右中弁、侍従の君なども、やがて大臣の御供に出でたまひぬ。ひき連れたまへる勢ひことなり。 |
あの方この方と、こちらにお集まりになって、三条宮に参上なさる。朱雀院の昔から御厚誼のある方々、六条院の側の方々も、それぞれにつけて、やはりあの入道の宮を、素通りできず参上なさるようである。この殿の左近中将、右中弁、侍従の君なども、そのまま大臣のお供してお出になった。引き連れていらっしゃった威勢は格別である。 |
あとからも来た高官たちはここでいっしょになって三条の宮へ参賀をするのであった。 |
Korekare, koko ni atumari tamahi te, Samdeu-no-miya ni mawiri tamahu. Suzyaku-Win no huruki kokoro monosi tamahu hitobito, Rokudeu-no-Win no katazama no mo, katagata ni tuke te, naho kano Nihudau-no-Miya wo ba, e yoki zu mawiri tamahu na' meri. Kono Tono no Sakon-no-Tiuzyau, U-tiuben, Zizyuu-no-Kimi nado mo, yagate Otodo no ohom-tomo ni ide tamahi nu. Hikiture tamahe ru ikihohi koto nari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2 | 第二段 薫君、玉鬘邸に年賀に参上 |
2-2 Kaoru visits to Tamakazura's residence too |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2.1 | 夕つけて、 四位侍従参りたまへり。そこらおとなしき若君達も、あまたさまざまに、いづれかは悪ろびたりつる。皆めやすかりつる中に、立ち後れて この君の立ち出でたまへる、いとこよなく目とまる心地して、 例の、ものめでする若き人たちは、「 なほ、ことなりけり」など言ふ。 |
夕方になって、四位侍従が参上なさった。大勢の成人した若公達も、みなそれぞれに、どの人が劣っていようか。みな感じのよい方の中で、ひと足後れてこの君がお姿をお見せになったのが、たいそう際立って目に止まった感じがして、例によって、熱中しやすい若い女房たちは、「やはり、格別だわ」などと言う。 |
夕方になって源侍従の |
Yuhutuke te, Siwi-no-Zizyuu mawiri tamahe ri. Sokora otonasiki Waka-Kimdati mo, amata samazama ni, idure ka ha warobi tari turu. Mina meyasukari turu naka ni, tati-okure te kono Kimi no tati ide tamahe ru, ito koyonaku me tomaru kokoti si te, rei no, mono-mede suru wakaki hito-tati ha, "Naho koto nari keri." nado ihu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2.2 | 「 この殿の姫君の御かたはらには、これをこそさし並べて見め」 |
「この殿の姫君のお側には、この方をこそ並べて見たい」 |
「こちらのお姫様にはこの方を並べてみないでは」 |
"Kono Tono no HimeGimi no ohom-katahara ni ha, kore wo koso sasi-narabe te mi me." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2.3 | と、聞きにくく言ふ。 げに、いと若うなまめかしきさまして、うちふるまひたまへる 匂ひ香など、世の常ならず。「 姫君と聞こゆれど、心おはせむ人は、げに人よりはまさるなめりと、 見知りたまふらむかし」とぞおぼゆる。 |
と、聞きにくいことを言う。なるほど、実に若く優美な姿態をして、振る舞っていらっしゃる匂い香など、尋常のものでない。「姫君と申し上げても、物ごとのお分りになる方は、本当に人よりは優れているようだと、ご納得なさるに違いない」と思われる。 |
こんなことを聞きにくいまでに言ってほめる。そう騒がれるのにたるほどの優雅な挙止を源侍従は見せていて、身から放つ香も清かった。貴族の姫君といわれるような人でも頭のよい人はこの人をすぐれた人と言うのはもっともなことだとくらい認めるかと思われた。 |
to, kiki nikuku ihu. Geni, ito wakau namamekasiki sama si te, uti-hurumahi tamahe ru nihohi ka nado, yo no tune nara zu. "HimeGimi to kikoyure do, kokoro ohase m hito ha, geni hito yori ha masaru na' meri to, misiri tamahu ram kasi." to zo oboyuru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2.4 | 尚侍の殿、御念誦堂におはして、「 こなたに」とのたまへれば、東の階より昇りて、戸口の御簾の前にゐたまへり。御前近き若木の梅、心もとなくつぼみて、鴬の初声もいとおほどかなるに、 いと好かせたてまほしきさまのしたまへれば、人びとはかなきことを言ふに、言少なに心にくきほどなるを、ねたがりて、 宰相の君と聞こゆる上臈の詠みかけたまふ。 |
尚侍の殿は、御念誦堂にいらして、「こちらに」とおっしゃるので、東の階段から昇って、戸口の御簾の前にお座りになった。お庭先の若木の梅が、頼りなさそうに蕾んで、鴬の初音もとてもたどたどしい声で鳴いて、まことに好き心を挑発してみたくなる様子をしていらっしゃるので、女房たちが戯れ言を言うと、言葉少なに奥ゆかしい態度なのを、悔しがって、宰相の君と申し上げる上臈が詠み掛けなさる。 |
尚侍は 「こちらへ」 と言わせるので、東の |
Kam-no-Tono, ohom-nenzudau ni ohasi te, "Konata ni." to notamahe re ba, himgasi no hasi yori nobori te, toguti no misu no mahe ni wi tamahe ri. Omahe tikaki wakagi no mume, kokoromotonaku tubomi te, uguhisu no hatukowe mo ito ohodoka naru ni, ito suka se tate mahosiki sama no si tamahe re ba, hitobito hakanaki koto wo ihu ni, kotozukuna ni kokoronikuki hodo naru wo, netagari te, Saisyau-no-Kimi to kikoyuru zyaurau no yomi kake tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
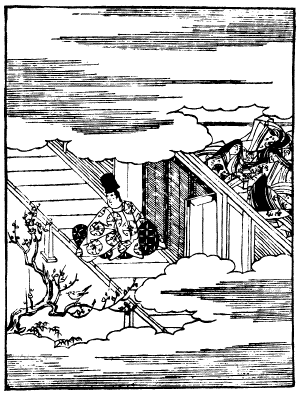 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2.5 | 「 折りて見ばいとど匂ひもまさるやと すこし色めけ梅の初花」 |
「手折ってみたらますます匂いも勝ろうかと もう少し色づいてみてはどうですか、梅の初花」 |
折りて見ばいとど 少し色めけ梅の初花 |
"Wori te mi ba itodo nihohi mo masaru ya to sukosi iromeke mume no hatuhana |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2.6 | 「口はやし」と聞きて、 |
「詠みぶりが早いな」と感心して、 |
速く歌のできたことを薫は感心しながら、 |
"Kuti hayasi." to kiki te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2.7 | 「 よそにてはもぎ木なりとや定むらむ 下に匂へる梅の初花 |
「傍目には枯木だと決めていましょうが 心の中は咲き匂っていつ梅の初花ですよ |
「よそにては 下に匂へる梅の初花 |
"Yoso nite ha mogiki nari to ya sadamu ram sita ni nihohe ru mume no hatuhana |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2.8 | さらば袖触れて見たまへ ★」など言ひすさぶに、 |
そう言うなら手を触れて御覧なさい」などと冗談を言うと、 |
疑わしくお思いになるなら |
Saraba sode hure te mi tamahe." nado ihi susabu ni, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2.9 | 「 まことは色よりも」と、口々、引きも動かしつべくさまよふ。 |
「本当は色よりも」と、口々に、袖を引っ張らんばかりに付きまとう。 |
「 口々にこんなことを言って、引き揺らんばかりに騒いでいるのを、 |
"Makoto ha iro yori mo." to, kutiguti, hiki mo ugokasi tu beku samayohu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2.10 | 尚侍の君、奥の方よりゐざり出でたまひて、 |
尚侍の君は、奥の方からいざり出ていらっしゃって、 |
奥のほうからいざって出た玉鬘夫人が見て、 |
Kam-no-Kimi, oku no kata yori wizari ide tamahi te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2.11 | 「 うたての御達や。恥づかしげなるまめ人をさへ、よくこそ、面無けれ」 |
「困った人達だわ。気恥ずかしそうなお堅い方までを、よくもまあ、厚かましくも」 |
「困った人、あなたたちは。きまじめな人をつかまえて恥ずかしい気もしないのかね」 |
"Utate no Gotati ya! Hadukasige naru mamebito wo sahe, yoku koso, omonakere." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2.12 | と忍びて のたまふなり。「 まめ人とこそ、付けられたりけれ。いと屈じたる名かな」と思ひゐたまへり。 主人の侍従、殿上などもまだせねば、所々もありかで、おはしあひたり。浅香の折敷、二つばかりして、くだもの、盃ばかりさし出でたまへり。 |
と小声でおっしゃるようである。「堅物と、あだ名されたようだ。まったく情けない名だな」と思っていらっしゃった。この家の侍従は、殿上などもまだしないので、あちらこちら年賀回りなどせずに、居合わせていらっしゃった。浅香の折敷、二つほどに、果物、盃などを差し出しなさった。 |
とそっと言っていた。きまじめな人にしてしまわれた、あわれむべき名だと源侍従は思った。この家の侍従はまだ殿上の勤めもしていないので、参賀する所も少なくて早く家に帰って来てここへ出て来た。 |
to sinobi te notamahu nari. "Mamebito to koso, tuke rare tari kere. Ito kunzi taru na kana!" to omohi wi tamahe ri. Aruzi-no-Zizyuu, tenzyau nado mo mada se ne ba, tokorodokoro mo arika de, ohasi ahi tari. Senkau no wosiki, hutatu bakari site, kudamono, sakaduki bakari sasi-ide tamahe ri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2.13 | 「 大臣は、ねびまさりたまふままに、故院にいとようこそ、おぼえたてまつりたまへれ。この君は、似たまへるところも見えたまはぬを、けはひのいとしめやかに、なまめいたる もてなししもぞ、かの御若盛り思ひやらるる。かうざまにぞおはしけむかし」 |
「大臣は、年をお取りになるにつれて、故院にとてもよくお似通い申していらっしゃる。この君は、似ていらっしゃるところもお見えにならないが、感じがとてもしとやかで、優美な態度が、あのお若い盛りの頃が思いやられてならない。このようなふうでいらっしゃったのであろうよ」 |
「右大臣はお年がゆけばゆくほど院によくお似ましになるが、侍従はお似になったところはお顔にないが、様子にしめやかな |
"Otodo ha, nebi masari tamahu mama ni, ko-Win ni ito you koso, oboye tatematuri tamahe re. Kono Kimi ha, ni tamahe ru tokoro mo miye tamaha nu wo, kehahi no ito simeyakani, namamei taru motenasi simo zo, kano ohom-wakazakari omohi yararuru. Kau zama ni zo ohasi kem kasi." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2.14 | など、 思ひ出でられたまひて、 うちしほれたまふ。 名残さへとまりたる香うばしさを、人びとはめでくつがへる。 |
となどと、お思い出し申し上げなさって、しんみりとしていらっしゃる。後に残った香の薫りまでを、女房たちは誉めちぎっている。 |
などと薫の帰ったあとで尚侍は言って、昔をなつかしくばかり追想していた。あたりに残ったかんばしい香までも女房たちはほめ合っていた。 |
nado, omohi ide rare tamahi te, uti-sihore tamahu. Nagori sahe tomari taru kaubasisa wo, hitobito ha mede kutugaheru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3 | 第三段 梅の花盛りに、薫君、玉鬘邸を訪問 |
2-3 Kaoru visits to Tamakazura's residence at full bloom of ume |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.1 | 侍従の君、まめ人の名をうれたしと思ひければ、 二十余日のころ、梅の花盛りなるに、「 匂ひ少なげに 取りなされじ。好き者ならはむかし」と思して、 藤侍従の御もとにおはしたり。 |
侍従の君、堅物の評判を情けないと思ったので、二十日過ぎのころ、梅の花盛りに、「色恋に無縁な男だと言われまい。風流者をまねしてみよう」とお思いになって、藤侍従のお邸にいらっしゃった。 |
源侍従はきまじめ男と言われたことを残念がって、二十日過ぎの梅の盛りになったころ、恋愛を解しない、一味の欠けた人のように言われる不名誉を清算させようと思って、 |
Zizyuu-no-Kimi, mamebito no na wo uretasi to omohi kere ba, nizihu-yo-hi no koro, mume no hanazakari naru ni, "Nihohi sukunage ni tori nasa re zi. Sukimono naraha m kasi." to obosi te, Tou-Zizyuu no ohom-moto ni ohasi tari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.2 | 中門入りたまふほどに、同じ直衣姿なる人立てりけり。 隠れなむと思ひけるを、 ひきとどめたれば、この常に立ちわづらふ 少将なりけり。 |
中門をお入りになる時、同じ直衣姿の男が立っているのだった。隠れようと思ったのを、引き止めてみると、あのいつもうろうろしている蔵人少将なのであった。 |
中門をはいって行くと、そこには自身と同じ |
Tyuumon iri tamahu hodo ni, onazi nahosisugata naru hito tate ri keri. Kakure na m to omohi keru wo, hiki-todome tare ba, kono tuneni tati wadurahu Seusyau nari keri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.3 | 「 寝殿の西面に、琵琶、箏の琴の声するに、 心を惑はして立てるなめり。苦しげや。人の許さぬこと思ひはじめむは、罪深かるべきわざかな」と思ふ。琴の声もやみぬれば、 |
「寝殿の西面で、琵琶や、箏の琴の音がするので、心をときめかして立っているようである。辛そうだな。親の許さない恋に心を染めることは、罪深いことだな」と思う。琴の音色も止んだので、 |
寝殿の西座敷のほうで |
"Sinden no nisiomote ni, biha, sau-no-koto no kowe suru ni, kokoro wo madohasi te tate ru na' meri. Kurusige ya! Hito no yurusa nu koto omohi hazime m ha, tumi hukakaru beki waza kana!" to omohu. Koto no kowe mo yami nure ba, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.4 | 「 いざ、しるべしたまへ。まろは、いとたどたどし」 |
「さあ、案内して下さい。わたしは、とても不案内です」 |
「さあ案内をしてください。私にはよく勝手がわかっていないから」 |
"Iza, sirube si tamahe. Maro ha, ito tadotadosi." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.5 | とて、ひき連れて、西の渡殿の前なる紅梅の木のもとに、「 梅が枝」をうそぶきて立ち寄るけはひの、花よりもしるく、さとうち匂へれば、妻戸おし開けて、人びと、東琴をいとよく掻き合はせたり。女の琴にて、 呂の歌は、かうしも合はせぬを、 いたしと思ひて、 今一返り、をり返し歌ふ、琵琶も二なく今めかし。 |
と言って、伴って、西の渡殿の前にある紅梅の木の側で、「梅が枝」を口ずさんで立ち寄った様子が、花の香よりもはっきりと、さっと匂ったので、妻戸を押し開けて、女房たちが、和琴をとてもよく合奏していた。女の琴なので、呂の調子の歌は、こうまでうまく合わせられないものなのに、大したものだと思って、もう一度、繰り返して謡うが、琵琶も又となく華やかである。 |
と言って、蔵人少将とつれだって西の |
tote, hikiture te, nisi no watadono no mahe naru koubai no ki no moto ni, Mumegae wo usobuki te tatiyoru kehahi no, hana yori mo siruku, sato uti-nihohe re ba, tumado osi ake te, hitobito, aduma wo ito yoku kaki-ahase tari. Womna no koto ni te, ryo no uta ha, kau simo ahase nu wo, itasi to omohi te, ima hito-kaheri, worikahesi utahu, biha mo ninaku imamekasi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.6 | 「 ゆゑありてもてないたまへるあたりぞかし」と、心とまりぬれば、今宵はすこしうちとけて、 はかなしごとなども言ふ。 |
「趣味高く暮らしていらっしゃる邸だ」と、心が止まったので、今宵は少し気を許して、冗談などを言う。 |
まったく芸術的な家であるとおもしろくなった薫は、元日とは変わった打ち解けたふうになって、 |
"Yuwe ari te motenai tamahe ru atari zo kasi." to, kokoro tomari nure ba, koyohi ha sukosi utitoke te, hakanasigoto nado mo ihu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.7 | 内より和琴さし出でたり。 かたみに譲りて、手触れぬに、 侍従の君して、尚侍の殿、 |
内側から和琴を差し出した。お互いに譲り合って、手を触れないので、藤侍従の君を介して、尚侍の殿が、 |
|
Uti yori wagon sasi-ide tari. Katamini yuduri te, te hure nu ni, Zizyuu-no-Kimi site, Kam-no-Tono, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.8 | 「 故致仕の大臣の御爪音になむ、通ひたまへる、と聞きわたるを、まめやかにゆかしうなむ。今宵は、なほ 鴬にも誘はれたまへ ★」 |
「故致仕の大臣のお爪音に、似ていらっしゃると、ずっと聞いていましたが、ほんとうに聞いてみたいです。今宵は、やはり鴬にもお誘われなさい」 |
「あなたのは昔の太政大臣の |
"Ko-Tizi-no-Otodo no ohom-tumaoto ni nam, kayohi tamahe ru, to kiki wataru wo, mameyakani yukasiu nam. Koyohi ha, naho uguhisu ni mo sasoha re tamahe." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.9 | と、のたまひ出だしたれば、「あまえて 爪くふべきことにもあらぬを」と思ひて、をさをさ心にも入らず掻きわたしたまへるけしき、いと響き多く聞こゆ。 |
と、おっしゃたので、「照れて爪をかんでいる場合でもない」と思って、あまり気乗りもせずに掻き鳴らしなさる様子、たいそう響きが多く聞こえる。 |
と言わせた。恥ずかしがって引っ込んでしまうほどのことでもないと思って、たいして熱心にもならず薫の弾きだした琴の音は、音波の遠く広がってゆくはなやかな気のされるものだった。 |
to, notamahi idasi tare ba, "Amaye te tume kuhu beki koto ni mo ara nu wo." to omohi te, wosawosa kokoro ni mo ira zu kaki-watasi tamahe ru kesiki, ito hibiki ohoku kikoyu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.10 | 「 常に見たてまつり睦びざりし親なれど、世におはせずなりにきと思ふに、いと心細きに、はかなきことのついでにも思ひ出でたてまつるに、いとなむあはれなる。 |
「いつもお目にかかって親しんだわけではない親ですが、この世にいらっしゃらなくなったと思うと、とても心細くて、ちょっとしたことの機会にもお思い出し申すと、とてもしみじみ悲しいのでした。 |
接近することの少なかった親ではあるが、 |
"Tune ni mi tatematuri mutubi zari si oya nare do, yo ni ohase zu nari ni ki to omohu ni, ito kokorobosoki ni, hakanaki koto no tuide ni mo omohi ide tatematuru ni, ito nam ahare naru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.11 | おほかた、この君は、あやしう 故大納言の御ありさまに、いとようおぼえ、琴の音など、ただそれとこそ、おぼえつれ」 |
だいたい、この君は、不思議と故大納言のご様子に、とてもよく似て、琴の音色など、まるでその人かと思われます」 |
「この人は不思議なほど亡くなった大納言によく似ておいでになって、琴の音などはそのままのような気がされました」 |
Ohokata, kono Kimi ha, ayasiu ko-Dainagon no ohom-arisama ni, ito you oboye, koto-no-ne nado, tada sore to koso, oboye ture." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.12 | とて泣きたまふも、 古めいたまふしるしの、涙もろさにや。 |
と言ってお泣きになるのも、お年のせいの、涙もろさであろうか。 |
と言って、尚侍の泣くのも年のいったせいかもしれない。 |
tote naki tamahu mo, hurumei tamahu sirusi no, namida morosa ni ya? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4 | 第四段 得意の薫君と嘆きの蔵人少将 |
2-4 Fortunate Kaoru and unfortunate Kurodo-shosho |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4.1 | 少将も、声いとおもしろうて、「 さき草」謡ふ ★。さかしら心つきて、うち過ぐしたる人もまじらねば、おのづからかたみにもよほされて遊びたまふに、主人の侍従は、 故大臣に 似たてまつりたまへるにや、かやうの方は後れて、盃をのみすすむれば、「 寿詞をだにせむや」と、恥づかしめられて、「 竹河」を同じ声に ★出だして、まだ若けれど、をかしう謡ふ。簾のうちより土器さし出づ。 |
少将も、声がとても美しくて、「さき草」を謡う。おせっかいな分別者で、出過ぎた女房もいないので、自然とお互いに気がはずんで合奏なさるが、この家の侍従は、故大臣にお似通い申しているのであろうか、このような方面は苦手で、盃ばかり傾けているので、「せめて祝い歌ぐらい謡えよ」と、文句を言われて、「竹河」を一緒に声を出して、まだ若いけれど美しく謡う。御簾の内側から盃を差し出す。 |
少将もよい声で「さき草」を歌った。批評家などがいないために、皆興に乗じていろいろな曲を次々に弾き、歌も多く歌われた。この家の侍従は父のほうに似たのか音楽などは不得意で、友人に杯をすすめる役ばかりしているのを、友から、 「君も勧杯の辞にだけでも何かをするものだよ」 と言われて、「 |
Seusyau mo, kowe ito omosirou te, Sakikusa utahu. Sakasiragokoro tuki te, uti-sugusi taru hito mo mazira ne ba, onodukara katamini moyohosa re te asobi tamahu ni, Aruzi-no-Zizyuu ha, ko-Otodo ni ni tatematuri tamahe ru ni ya, kayau no kata ha okure te, sakaduki wo nomi susumure ba, "Kotobuki wo dani se m ya!" to, hadukasime rare te, Takekaha wo onazi kowe ni idasi te, mada wakakere do, wokasiu utahu. Su no uti yori kaharake sasi-idu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4.2 | 「 酔のすすみては、忍ぶることもつつまれず。ひがことするわざとこそ聞きはべれ。いかにもてないたまふぞ」 |
「酔いが回っては、心に秘めていることも隠しておくことができません。詰まらないことを口にすると聞いております。どうなさるおつもりですか」 |
「あまり酔っては、平生心に抑制していることまでも言ってしまうということですよ。その時はどうなさいますか」 |
"Wehi no susumi te ha, sinoburu koto mo tutuma re zu. Higakoto suru waza to koso kiki habere. Ikani motenai tamahu zo." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4.3 | と、とみにうけひかず。小袿重なりたる細長の、人香なつかしう染みたるを、取りあへたるままに、 被けたまふ。「 何ぞもぞ」などさうどきて、 侍従は、主人の君にうち被けて去ぬ。引きとどめて被くれど、「 水駅にて夜更けにけり」とて、逃げにけり。 |
と、すぐには手にしない。小袿の重なった細長で、人の香がやさしく染みているのを、あり合わせのままに、お与えになる。「これはどういうおつもりですか」などとはしゃいで、侍従は、お邸の君に与えて出て行った。ひき止めて与えたが、「水駅で夜が更けてしまいました」と言って、逃げて行ってしまった。 |
などと言って、薫の侍従は杯を容易に受けない。 |
to, tomi ni uke-hika zu. Koutiki kasanari taru hosonaga no, hitoga natukasiu simi taru wo, tori ahe taru mama ni, kaduke tamahu. "Nani zo mo zo?" nado saudoki te, Zizyuu ha, Aruzi-no-Kimi ni uti-kaduke te inu. Hiki-todome te kadukure do, "Midumumaya nite yo huke ni keri." tote, nige ni keri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
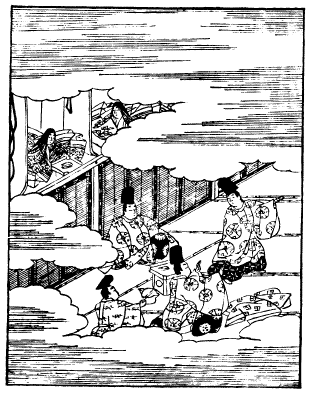 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4.4 | 少将は、「 この源侍従の君のかうほのめき寄るめれば、皆人これにこそ心寄せたまふらめ。わが身は、いとど屈じいたく思ひ弱りて」、あぢきなうぞ恨むる。 |
少将は、「この源侍従の君がこのように出入りしているようなので、こちらの方々は皆あの君に好意を寄せていらっしゃるだろう。わが身はますます塞ぎ込み元気をなくして」、つまらなく恨むのだった。 |
蔵人少将はこの源侍従が意味ありげに訪問した今夜のようなことが続けば、だれも皆好意をその人にばかり持つようになるであろう、自分はいよいよみじめなものになると悲観していて、 |
Seusyau ha, "Kono Gen-Zizyuu-no-Kimi no kau honomeki yoru mere ba, minahito kore ni koso kokoroyose tamahu rame. Waga mi ha, itodo kunzi itaku omohi yowari te", adikinau zo uramuru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4.5 | 「 人はみな花に心を移すらむ 一人ぞ惑ふ春の夜の闇 ★」 |
「人はみな花に心を寄せているのでしょうが わたし一人は迷っております、春の夜の闇の中で」 |
人は皆花に心を移すらん 一人ぞ惑ふ春の夜の |
"Hito ha mina hana ni kokoro wo utusu ram hitori zo madohu haru no yo no yami |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4.6 | うち嘆きて立てば、内の人の返し、 |
ため息をついて座を立つと、内側にいる女房の返し、 |
こう言って、 |
Uti-nageki te tate ba, uti no hito no kahesi, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4.7 | 「 をりからやあはれも知らむ梅の花 ただ香ばかりに移りしもせじ」 |
「時と場合によって心を寄せるものです ただ梅の花の香りだけにこうも引かれるものではありませんよ」 |
折からや哀れも知らん 梅の花ただかばかりに移りしもせじ |
"Wori kara ya ahare mo sira m mume no hana tada ka bakari ni uturi simo se zi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4.8 | 朝に、四位侍従のもとより、主人の侍従のもとに、 |
朝に、四位侍従のもとから、邸の侍従のもとに、 |
と返歌をした。翌朝になって源侍従から藤侍従の所へ、 |
Asita ni, Siwi-no-Zizyuu no moto yori, Aruzi-no-Zizyuu no moto ni, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4.9 | 「 昨夜は、いと乱りがはしかりしを、人びといかに見たまひけむ」 |
「昨夜は、とても酔っぱらったようだが、皆様はどのように御覧になったであろうか」 |
昨夜は失礼をして帰りましたが皆さんのお気持ちを悪くしなかったかと心配しています。 |
"Yobe ha, ito midarigahasikari si wo, hitobito ikani mi tamahi kem?" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4.10 | と、見たまへとおぼしう、 仮名がちに書きて、 |
と、御覧下さいとのおつもりで、仮名がちに書いて、 |
と、婦人たちにも見せてほしいらしく仮名がちに書いて、端に、 |
to, mi tamahe to obosiu, kanagati ni kaki te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4.11 | 「 竹河の橋うちいでし一節に 深き心の底は知りきや」 |
「竹河の歌を謡ったあの文句の一端から わたしの深い心のうちを知っていただけましたか」 |
深き心の底は知りきや |
"Takekaha no hasi uti-ide si hitohusi ni hukaki kokoro no soko ha siri ki ya |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4.12 | と書きたり。寝殿に持て参りて、 これかれ見たまふ。 |
と書いてある。寝殿に持って上がって、方々が御覧になる。 |
という歌もある手紙を送って来た。すぐに寝殿へこの手紙を持って行かれて、侍従の母夫人や兄弟たちもいっしょに見た。 |
to kaki tari. Sinden ni mote mawiri te, korekare mi tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4.13 | 「 手なども、いとをかしうもあるかな。 いかなる人、今よりかくととのひたらむ。幼くて、院にも後れたてまつり、母宮のしどけなう生ほし立てたまへれど、なほ人にはまさるべきにこそあめれ」 |
「筆跡なども、とても美しく書いてありますね。どのような人が、今からこのように整っているのでしょう。幼いころ、院に先立たれ申し、母宮がしまりもなくお育て申されたが、やはり人より優れているのでしょう」 |
「字も上手だね。まあどうして今からこんなに何もかもととのった人なのだろう。小さいうちに院とお別れになって、お母様の宮様が甘やかすばかりにしてお育てになった方だけれど、光った将来が今から見える人になっていらっしゃる」 |
"Te nado mo, ito wokasiu mo aru kana! Ikanaru hito, ima yori kaku totonohi tara m? Wosanaku te, Win ni mo okure tatematuri, Haha-Miya no sidokenau ohosi tate tamahe re do, naho hito ni ha masaru beki ni koso a' mere." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4.14 | とて、尚侍の君は、 この君たちの、手など悪しきことを恥づかしめたまふ。返りこと、 げに、いと若く、 |
と言って、尚侍の君は、自分の子供たちの、字などが下手なことをお叱りになる。返事は、なるほど、たいそう未熟な字で、 |
などと尚侍は言って、自分の息子たちの字の |
tote, Kam-no-Kimi ha, kono Kimitati no, te nado asiki koto wo hadukasime tamahu. Kaherikoto, geni, ito wakaku, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4.15 | 「 昨夜は、水駅をなむ、とがめきこゆめりし。 |
「昨夜は、水駅とおっしゃってお帰りになったことを、いかがなものかと申しておりました。 |
昨夜はあまり早くお帰りになったことで皆何とか言ってました。 |
"Yobe ha, midumumaya wo nam, togame kikoyu meri si. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4.16 | 竹河に夜を更かさじといそぎしも いかなる節を思ひおかまし」 |
竹河を謡って夜を更かすまいと急いでいらっしゃったのも どのようなことを心に止めておけばよいのでしょう」 |
竹河によを いかなる |
Takekaha ni yoru wo akasa zi to isogi simo ikanaru husi wo omohi oka masi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4.17 | げに、この節をはじめにて、 この君の御曹司におはして、 けしきばみ寄る。 少将の推し量りしもしるく、皆人心寄せたり。侍従の君も、若き心地に、近きゆかりにて、明け暮れ睦びまほしう思ひけり。 |
なるほど、この事件をきっかけとして、この君のお部屋にいらっしゃって、気のある態度で振る舞う。少将が予想していた通り、誰もが好意を寄せていた。侍従の君も、子供心に、近い縁者として、明け暮れ親しくしたいと思うのであった。 |
この時以来薫は藤侍従の |
Geni, kono husi wo hazime nite, kono Kimi no mi-zausi ni ohasi te, kesikibami yoru. Seusyau no osihakari simo siruku, minahito kokoro yose tari. Zizyuu-no-Kimi mo, wakaki kokoti ni, tikaki yukari nite, akekure mutubi mahosiu omohi keri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5 | 第五段 三月、花盛りの玉鬘邸の姫君たち |
2-5 Daughters of Tamakazura's residence at full bloom of cherry blossoms |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5.1 | 弥生になりて、 咲く桜あれば、散りかひくもり ★ ★、おほかたの盛りなるころ、 のどやかにおはする所は、紛るることなく、 端近なる罪もあるまじかめり。 |
三月になって、咲く桜がある一方で、空も覆うほど散り乱れ、ほぼ桜の盛りのころ、のんびりとしていらっしゃるところは、さしたる用事もなく、端近に出ていても非難されないようである。 |
三月になって、咲く桜、散る桜が混じって春の気分の高潮に達したころ、閑散な家では退屈さに婦人たちさえ端近く出て、庭の |
Yayohi ni nari te, saku sakura are ba, tiri kahi kumori, ohokata no sakari naru koro, nodoyaka ni ohasuru tokoro ha, magiruru koto naku, hasidika naru tumi mo aru mazika' meri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5.2 | そのころ、十八、九のほどやおはしけむ、御容貌も心ばへも、とりどりにぞをかしき。 姫君は、いとあざやかに気高う、今めかしきさましたまひて、 げに、ただ人にて見たてまつらむは、似げなうぞ見えたまふ。 |
その当時、十八、九歳くらいでいらっしゃったろうか、ご器量も気立ても、それぞれに素晴らしい。姫君は、とても際立って気品があり、はなやかでいらして、なるほど、臣下の人に縁づけ申すのは、ふさわしくなくお見えである。 |
|
Sonokoro, zihuhati, ku no hodo ya ohasi kem, ohom-katati mo kokorobahe mo, toridori ni zo wokasiki. HimeGimi ha, ito azayaka ni kedakau, imamekasiki sama si tamahi te, geni, tadaudo nite mi tatematura m ha, nigenau zo miye tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5.3 | 桜の細長、山吹などの、折にあひたる色あひの、なつかしきほどに重なりたる裾まで、愛敬のこぼれ落ちたるやうに見ゆる、御もてなしなども、らうらうじく、心恥づかしき気さへ添ひたまへり。 |
桜の細長に、山吹襲などで、季節にあった色合いがやさしい感じに重なっている裾まで、愛嬌があふれ出ているように見える、そのお振る舞いなども、洗練されて、気圧されるような感じまでが加わっていらっしゃった。 |
桜の色の細長に、 |
Sakura no hosonaga, yamabuki nado no, wori ni ahi taru iroahi no, natukasiki hodo ni kasanari taru suso made, aigyau no kobore oti taru yau ni miyuru, ohom-motenasi nado mo, raurauziku, kokorohadukasiki ke sahe sohi tamahe ri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5.4 | 今一所は、薄紅梅に、 桜色にて、柳の糸のやうに、 たをたをとたゆみ、いとそびやかになまめかしう、澄みたるさまして、重りかに心深きけはひは、まさりたまへれど、匂ひやかなるけはひは、 こよなしとぞ人思へる。 |
もうお一方は、薄紅梅に、桜色で、柳の枝のように、しなやかに、たいそうすらっとして優美に、落ち着いた物腰で、重々しく奥ゆかしい感じは、勝っていらっしゃるが、はなやかな感じは、この上ないと女房は思っていた。 |
もう一人の姫君はまた薄紅梅の上着にうつりのよいたくさんな黒々とした髪を持っていた。柳の糸のように掛かっているのである。背が高くて、 |
Ima hitotokoro ha, usukoubai ni, sakurairo nite, yanagi no ito no yau ni, tawotawo to tayumi, ito sobiyaka ni namamekasiu, sumi taru sama si te, omorika ni kokorohukaki kehahi ha, masari tamahe re do, nihohiyaka naru kehahi ha, koyonasi to zo hito omohe ru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5.5 | 碁打ちたまふとて、さし向ひたまへる髪ざし、御髪のかかりたるさまども、いと 見所あり。侍従の君、見証したまふとて、近うさぶらひたまふに、 兄君たちさしのぞきたまひて、 |
碁をお打ちなさろうとして、向かい合っていらっしゃる髪の生え際、髪の垂れかかっている具合など、たいそう見所がある。侍従の君が、審判をなさろうとして、近くに伺候なさると、兄君たちがお覗きになって、 |
碁を打つために |
Go uti tamahu tote, sasimukahi tamahe ru kamzasi, migusi no kakari taru sama-domo, ito midokoro ari. Zizyuu-no-Kimi, kenzo si tamahu tote, tikau saburahi tamahu ni, AniGimi-tati sasi-nozoki tamahi te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5.6 | 「 侍従のおぼえ、こよなうなりにけり。御碁の 見証許されにけるをや」 |
「侍従の寵愛は、大したものになったね。碁の審判を許されたとはね」 |
「侍従はすばらしくなったね。碁の審査役にしていただけるのだからね」 |
"Zizyuu no oboye, koyonau nari ni keri. Ohom-go no kenzo yurusa re ni keru wo ya!" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5.7 | とて、おとなおとなしきさましてついゐたまへば、御前なる人びと、とかうゐなほる。中将、 |
と言って、大人ぶった態度でお座りになったので、御前の女房たちは、あれこれ居ずまいを正す。中将が、 |
と、大人らしくからかいながら、 |
tote, otonaotonasiki sama si te tui-wi tamahe ba, omahe naru hitobito, tokau wi nahoru. Tiuzyau, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5.8 | 「 宮仕へのいそがしうなりはべるほどに、人に劣りにたるは、いと本意なきわざかな」 |
「宮仕えが忙しくなりましたので、弟に出し抜かれたのは、まことに残念なことだなあ」 |
「公務で忙しくしているうちに、姫君の愛顧を侍従に独占されてしまったのはつまらないね」 |
"Miyadukahe no isogasiu nari haberu hodo ni, hito ni otori ni taru ha, ito ho'i naki waza kana!" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5.9 | と愁へたまへば、 |
と愚痴をおこぼしになると、 |
と言うと、次の兄の右中弁が、 |
to urehe tamahe ba, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5.10 | 「 弁官は、まいて、私の宮仕へおこたりぬべきままに、 さのみやは思し捨てむ」 |
「弁官は、それ以上に、家でのご奉公はお留守になってしまうからと、そうお見捨てではありますまい」 |
「弁官はまた特別に御用が多いから、忠誠ぶりを見ていただけないからといっても、少しは |
"Benkwan ha, maite, watakusi no miyadukahe okotari nu beki mama ni, sa nomi yaha obosi sute m." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5.11 | など申したまふ。碁打ちさして、恥ぢらひておはさうずる、いとをかしげなり。 |
などと申し上げなさる。碁を打つのを止めて、恥ずかしがっていらっしゃる、たいそう美しい感じである。 |
と言う。兄たちの言う |
nado mausi tamahu. Go uti-sasi te, hadirahi te ohasauzuru, ito wokasige nari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5.12 | 「 内裏わたりなどまかりありきても、 故殿おはしまさましかば、と思ひたまへらるること多くこそ」 |
「宮中辺りなどに出歩きましても、亡き殿がいらっしゃったら、と存じられますことが多くて」 |
「御所の中を歩いていても、お父様がおいでになったらと思うことが多い」 |
"Uti watari nado makari ariki te mo, ko-Tono ohasimasa masika ba, to omohi tamahe raruru koto ohoku koso." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5.13 | など、涙ぐみて見たてまつりたまふ。 二十七、八のほどにものしたまへば、いとよくととのひて、この御ありさまどもを、「 いかで、いにしへ思しおきてしに、違へずもがな」と思ひゐたまへり。 |
などと、涙ぐんで拝し上げなさる。二十七、八歳くらいでいらっしゃったので、とても恰幅よくて、姫君たちのご様子を、「何とかして、昔父君がお考えになっていた通りに、したいものだ」と思っていらっしゃった。 |
などと言って、中将は涙ぐんで妹たちを見ていた。もう二十七、八であったから |
nado, namidagumi te mi tatematuri tamahu. Nizihusiti, hati no hodo ni monosi tamahe ba, ito yoku totonohi te, kono ohom-arisama-domo wo, "Ikade, inisihe obosi oki te si ni, tagahe zu mo gana!" to omohi wi tamahe ri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5.14 | 御前の花の木どもの中にも、匂ひまさりてをかしき桜を折らせて、「 他のには似ずこそ」など、もてあそびたまふを、 |
お庭先の花の木々の中でも、色合いの優れて美しい桜を折らせて、「他の桜とは違っている」などと、もて遊んでいらっしゃるのを、 |
庭の花の木の中でもことに美しい桜の枝を折らせて、姫君たちが、「この花が一番いいのね」などと言って楽しんでいるのを見て、中将が、 |
Omahe no hana no ki-domo no naka ni mo, nihohi masari te wokasiki sakura wo wora se te, "Hoka no ni ha ni zu koso." nado, mote-asobi tamahu wo, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5.15 | 「 幼くおはしましし時 ★、この花は、わがぞ、わがぞと、争ひたまひしを、故殿は、姫君の御花ぞと定めたまふ。 上は、若君の御木と定めたまひしを、 いとさは泣きののしらねど、やすからず思ひたまへられしはや」とて、「 この桜の老木になりにけるにつけても、過ぎにける齢を思ひたまへ出づれば、あまたの人に後れはべりにける、身の愁へも、止めがたうこそ」 |
「お小さくいらした時、この花は、わたしのよ、わたしのよと、お争いになったが、故殿は、姫君のお花だとお決めになる。母上は、若君のお花だとお決めになったが、それをひどくそんなには泣き叫んだりしませんでしたが、おもしろくなく存じられましたよ」と言って、「この桜が老木になったにつけても、過ぎ去った歳月を思い出されますので、大勢の人に先立たれてしまった身の悲しみも、きりがございません」 |
「あなたがたが子供の時に、この桜の木を私のだ私のだと取り合いをした時に、お父様は姉さんのものだとおきめになって、お母様は小さい人のだとおきめになったから、泣く騒ぎまではしなかったけれど、双方とも不満足な顔をしたことを覚えていますか」こんなことを言いだして、また、「この桜が老い木になったことでも、過ぎ去った歳月が数えられて、力になっていただけたどの方にもどの方にも死に別れてしまった不幸な自分のことが思われる」 |
"Wosanaku ohasimasi si toki, kono hana ha, waga zo, waga zo to, arasohi tamahi si wo, ko-Tono ha, HimeGimi no ohom-hana zo to sadame tamahu. Uhe ha, WakaGimi no ohom-ki to sadame tamahi si wo, ito sa ha naki nonosira ne do, yasukara zu omohi tamahe rare si haya!" tote, "Kono sakura no oyigi ni nari ni keru ni tuke te mo, sugi ni keru yohahi wo omohi tamahe idure ba, amata no hito ni okure haberi ni keru, mi no urehe mo, tome gatau koso." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5.16 | など、泣きみ笑ひみ聞こえたまひて、例よりはのどやかにおはす。 人の婿になりて、心静かにも今は見えたまはぬを、花に心とどめてものしたまふ。 |
などと、泣いたり笑ったりしながら申し上げなさって、いつもよりはのんびりとしていらっしゃる。他の家の婿となって、ゆっくりとは今ではお見えにならないが、花に心を惹かれておいでである。 |
とも言って、泣きもし、笑いもしながら平生ほど時間のたつのを気にせずに中将は母の家にいた。他家の婿になっていて、こちらへ来て静かに暮らす余裕のある日などを持たないのであるが、今日は花に心が |
nado, nakimi-warahimi kikoye tamahi te, rei yori ha nodoyakani ohasu. Hito no muko ni nari te, kokoro sidukani mo ima ha miye tamaha nu wo, hana ni kokoro todome te monosi tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.6 | 第六段 玉鬘の大君、冷泉院に参院の話 |
2-6 A rumor about Tamakazura's eldest daughter that she will be marry with Reizei-in |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.6.1 | 尚侍の君、かくおとなしき人の親になりたまふ御年のほど思ふよりは、いと若うきよげに、なほ盛りの御容貌と見えたまへり。 冷泉院の帝は、多くは、この御ありさまのなほゆかしう、昔恋しう思し出でられければ、 何につけてかはと、思しめぐらして、姫君の御ことを、あながちに聞こえたまふにぞありける。院へ参りたまはむことは、 この君たちぞ、 |
尚侍の君は、このように成人した子の親におなりのお年の割には、たいそう若く美しく、依然として盛りのご容貌にお見えになった。冷泉院の帝は、主として、この方のご様子が依然として心に掛かって、昔が恋しく思い出されなさったので、何にかこつけたらよいかと、思案なさって、姫君のご入内の事を、無理やりに申し込みなさるのであった。院に入内なさることは、この君たちが、 |
尚侍はまだこうした人々を子にして持っているほどの年になっているとは見えぬほど今日も若々しくて、盛りの |
Kam-no-Kimi, kaku otonasiki hito no oya ni nari tamahu ohom-tosi no hodo omohu yori ha, ito wakau kiyogeni, naho sakari no ohom-katati to miye tamahe ri. Reizeiwin-no-Mikado ha, ohoku ha, kono ohom-arisama no naho yukasiu, mukasi kohisiu obosi ide rare kere ba, nani ni tuke te kaha to, obosi megurasi te, HimeGimi no ohom-koto wo, anagatini kikoye tamahu ni zo ari keru. Win he mawiri tamaha m koto ha, kono Kimi-tati zo, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.6.2 | 「 なほ、ものの栄なき心地こそすべけれ。よろづのこと、時につけたるをこそ、世人も許すめれ。 げに、いと見たてまつらまほしき御ありさまは、この世にたぐひなくおはしますめれど、 盛りならぬ心地ぞするや。琴笛の調べ、 花鳥の色をも音をも、時に従ひてこそ、人の耳もとまるものなれ。春宮は、いかが」 |
「やはり、栄えない気がしましょう。万事が、時流に乗ってこそ、世間の人も認めましょう。なるほど、まことに拝したいお姿は、この世に類なくいらっしゃるようですが、盛りを過ぎた感じがしますね。琴や笛の調子、花や鳥の色や音色も、時期にかなってこそ、人の耳にも止まるものです。春宮は、どうでしょうか」 |
「どうしても見ばえのせぬことをするように思われますよ。現在の勢力のある所へ人が寄って行くのも、自然なことなのですからね。院はごりっぱな御 |
"Naho, mono no haye naki kokoti koso su bekere. Yorodu no koto, toki ni tuke taru wo koso, yohito mo yurusu mere. Geni, ito mi tatematura mahosiki ohom-arisama ha, konoyo ni taguhi naku ohasimasu mere do, sakari nara nu kokoti zo suru ya! Koto hue no sirabe, hana tori no iro wo mo ne wo mo, toki ni sitagahi te koso, hito no mimi mo tomaru mono nare. Touguu ha, ikaga?" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.6.3 | など申したまへば、 |
などと申し上げなさると、 |
などと中将が言う。 |
nado mausi tamahe ba, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.6.4 | 「 いさや、はじめより やむごとなき人の、かたはらもなきやうにてのみ、ものしたまふめればこそ。なかなかにて交じらはむは、胸いたく人笑へなることもやあらむと、つつましければ。殿 おはせましかば、行く末の御宿世宿世は知らず、ただ今は、かひあるさまにもてなしたまひてましを」 |
「さあ、どんなものかしら、最初から重々しい方が、並ぶ者がいないような勢いで、いらっしゃるようですからね。なまじっかの宮仕えは、胸を痛め物笑いになることもあろうかと、気が引けますので。殿が生きていらっしゃったならば、将来のご運は判らないが、この今は、張り合いのある状態になさっていたでしょうに」 |
「それはどうかね。初めからりっぱな方が上がっておいでになって、御 |
"Isaya, hazime yori yamgotonaki hito no, katahara mo naki yau ni te nomi, monosi tamahu mere ba koso. Nakanaka nite maziraha m ha, mune itaku hitowarahe naru koto mo ya ara m to, tutumasikere ba. Tono ohase masika ba, yukusuwe no ohom-sukuse sukuse ha sira zu, tadaima ha, kahi aru sama ni motenasi tamahi te masi wo." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.6.5 | などのたまひ出でて、皆ものあはれなり。 |
などとおっしゃって、皆しみじみと悲しい思いがする。 |
と |
nado notamahi ide te, mina mono ahare nari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.7 | 第七段 蔵人少将、姫君たちを垣間見る |
2-7 Kurodo-shosho peeps Tamakazura's daughters |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.7.1 | 中将など立ちたまひてのち、君たちは、打ちさしたまへる碁打ちたまふ。昔より争ひたまふ桜を賭物にて、 |
中将などがお立ちになった後、姫君たちは、途中で打ち止めていらした碁を打ちになる。昔からお争いになる桜を賭物として、 |
中将などが立って行ったあとで、姫君たちは打ちさしておいた碁をまた打ちにかかった。昔から争っていた桜の木を |
Tiuzyau nado tati tamahi te noti, Kimi-tati ha, uti-sasi tamahe ru go uti tamahu. Mukasi yori arasohi tamahu sakura wo kakemono nite, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.7.2 | 「 三番に、数一つ勝ちたまはむ方には、なほ花を寄せてむ」 |
「三番勝負で、一つ勝ち越しになった方に、やはり花を譲りましょう」 |
「三度打つ中で、二度勝った人の桜にしましょう」 |
"Sam ban ni, kazu hitotu kati tamaha m kata ni ha, naho hana wo yose te m." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.7.3 | と、戯れ交はし聞こえたまふ。 暗うなれば、端近うて打ち果てたまふ。御簾巻き上げて、人びと皆挑み念じきこゆ。折しも例の少将、侍従の君の御曹司に来たりけるを、 うち連れて出でたまひにければ、おほかた人少ななるに、廊の戸の開きたるに、やをら寄りてのぞきけり。 |
と、ふざけて申し合いなさる。暗くなったので、端近くで打ち終えなさる。御簾を巻き上げて、女房たちが皆競い合ってお祈り申し上げる。ちょうどその時、いつもの蔵人少将が、藤侍従の君のお部屋に来ていたのだが、兄弟連れ立ってお出になったので、だいたいが人の少ない上に、廊の戸が開いていたので、静かに近寄って覗き込んだ。 |
などと戯れに言い合っていた。 暗くなったので勝負を縁側に近い所へ出てしていた。 |
to, tahabure kahasi kikoye tamahu. Kurau nare ba, hasi tikau te uti-hate tamahu. Misu makiage te, Hitobito mina idomi nenzi kikoyu. Wori simo rei no Seusyau, Zizyuu-no-Kimi no mi-zausi ni ki tari keru wo, uti-ture te ide tamahi ni kere ba, ohokata hitozukuna naru ni, rau no to no aki taru ni, yawora yori te nozoki keri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
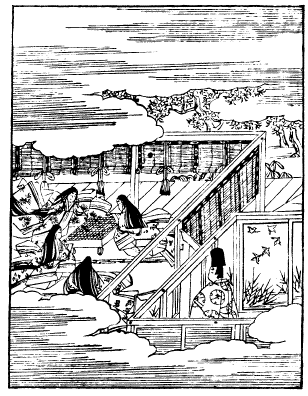 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.7.4 | かう、うれしき折を見つけたるは、仏などの現れたまへらむに参りあひたらむ心地するも、 はかなき心になむ。夕暮の霞の紛れは、さやかならねど、つくづくと見れば、 桜色のあやめも、それと見分きつ。 げに、散りなむ後の形見にも ★見まほしく、匂ひ多く見えたまふを、いとど 異ざまになりたまひなむこと、わびしく思ひまさらる。若き人びとのうちとけたる姿ども、夕映えをかしう見ゆ。 右勝たせたまひぬ。「 高麗の乱声、おそしや」など、はやりかに言ふもあり。 |
このように、嬉しい機会を見つけたのは、仏などが姿を現しなさった時に出会ったような気がするのも、あわれな恋心というものである。夕暮の霞に隠れて、はっきりとはしないが、よくよく見ると、桜色の色目も、はっきりそれと分かった。なるほど、花の散った後の形見として見たく、美しさがいっぱいお見えなのを、ますますよそに嫁ぎなさることを、侘しく思いがまさる。若い女房たちのうちとけている姿、姿が、夕日に映えて美しく見える。右方がお勝ちあそばした。「高麗の乱声が、遅い」などと、はしゃいで言う女房もいる。 |
こんな所を見ることのできたことは、仏の出現される前へ来合わせたと同じほどな幸福感を少将に与えた。夕明りも |
Kau, uresiki wori wo mituke taru ha, Hotoke nado no arahare tamahe ra m ni mawiri ahi tara m kokoti suru mo, hakanaki kokoro ni nam. Yuhugure no kasumi no magire ha, sayaka nara ne do, tukuduku to mire ba, sakurairo no ayame mo, sore to miwaki tu. Geni, tiri na m noti no katami ni mo mi mahosiku, nihohi ohoku miye tamahu wo, itodo kotozama ni nari tamahi na m koto, wabisiku omohi masara ru. Wakaki hitobito no utitoke taru sugata-domo, yuhubaye wokasiu miyu. Migi kata se tamahi nu. "Koma no ranzyau, ososi ya!" nado, hayarikani ihu mo ari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.7.5 | 「 右に心を寄せたてまつりて、 西の御前に寄りてはべる木を、 左になして、年ごろの御争ひの、かかれば、ありつるぞかし」 |
「右方にお味方申し上げて、西のお庭先の近くにあります木を、左方のものだとし、長年のお争いが、そのようなわけで、続いたのでございますよ」 |
「右がひいきで西のお座敷のほうに寄っていた花を、今まで左方に貸してお置きあそばしたきまりがつきましたのですね」 |
"Migi ni kokoro wo yose tatematuri te, nisi no omahe ni yori te haberu ki wo, hidari ni nasi te, tosigoro no ohom-arasohi no, kakare ba, ari turu zo kasi." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.7.6 | と、右方は心地よげにはげましきこゆ。何ごとと知らねど、 をかしと聞きて、さしいらへもせまほしけれど、「 うちとけたまへる折、心地なくやは」と思ひて、出でて去ぬ。「 また、かかる紛れもや」と、蔭に添ひてぞ、うかがひありきける。 |
と、右方は気持ちよさそうに応援申し上げる。どのような事情でと知りらないが、おもしろいと聞いて、返事もしたいが、「寛いでいらっしゃる時に、心ない態度では」と思って、邸をお出になった。「再び、このような機会はないか」と、物蔭に隠れて、窺い歩くのであった。 |
などと愉快そうに右方の者ははやしたてる。少将には何があるのかもよくわからないのであるが、その中へ混じっていっしょに遊びたい気のするものの、だれも見ないと信じている人たちの所へ出て行くことは無作法であろうと思ってそのまま帰った。もう一度だけああした機会にあえないであろうかと、少将はそののちも恋人の邸をうかがい歩いた。 |
to, migikata ha kokotiyoge ni hagemasi kikoyu. Nanigoto to sira ne do, wokasi to kiki te, sasi-irahe mo se mahosikere do, "Utitoke tamahe ru wori, kokotinaku yaha." to omohi te, ide te inu. "Mata, kakaru magire mo ya?" to, kage ni sohi te zo, ukagahi ariki keru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8 | 第八段 姫君たち、桜花を惜しむ和歌を詠む |
2-8 Tamakazura's daughters compose waka regretting cherry blossoms fall |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8.1 | 君達は、花の争ひをしつつ明かし暮らしたまふに、風荒らかに吹きたる夕つ方、乱れ落つるがいと口惜しうあたらしければ、負け方の姫君、 |
姫君たちは、花の争いをしながら日を送っていらっしゃると、風が激しく吹いている夕暮に、乱れ散るのがまことに残念で惜しいので、負け方の姫君は、 |
姫君たちは毎日花争いに暮らしているのであったが、風の荒く吹き出した日の夕方に |
Kimi-tati ha, hana no arasohi wo si tutu akasi kurasi tamahu ni, kaze araraka ni huki taru yuhutukata, midare oturu ga ito kutiwosiu atarasikere ba, makekata no HimeGimi, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8.2 | 「 桜ゆゑ風に心の騒ぐかな 思ひぐまなき花と見る見る」 |
「桜のせいで吹く風ごとに気が揉めます わたしを思ってくれない花だと思いながらも」 |
桜ゆゑ風に心の騒ぐかな 思ひぐまなき花と見る見る |
"Sakura yuwe kaze ni kokoro no sawagu kana omohi guma naki hana to miru miru |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8.3 | 御方の宰相の君、 |
御方の宰相の君が、 |
こんな歌を作った。そのほうにいる宰相の君が、 |
Ohom-kata no Saisyau-no-Kimi, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8.4 | 「 咲くと見てかつは散りぬる花なれば 負くるを深き恨みともせず」 |
「咲いたかと見ると一方では散ってしまう花なので 負けて木を取られたことを深く恨みません」 |
咲くと見てかつは散りぬる花なれば 負くるを深き |
"Saku to mi te katu ha tiri nuru hana nare ba makuru wo hukaki urami to mo se zu |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8.5 | と聞こえ助くれば、右の姫君、 |
とお助け申し上げると、右方の姫君は、 |
と慰める。右の姫君、 |
to kikoye tasukure ba, migi no HimeGimi, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8.6 | 「 風に散ることは世の常枝ながら 移ろふ花をただにしも見じ」 |
「風に散ることは世の常のことですが、枝ごとそっくり こちらの木になった花を平気で見ていられないでしょう」 |
風に散ることは世の常枝ながら うつろふ花をただにしも見じ |
"Kaze ni tiru koto ha yo no tune eda nagara uturohu hana wo tada ni simo mi zi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8.7 | この御方の大輔の君、 |
こちらの御方の大輔の君が、 |
右の女房の |
Kono ohom-kata no Taihu-no-Kimi, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8.8 | 「 心ありて池のみぎはに落つる花 ★ あわとなりてもわが方に寄れ」 |
「こちらに味方して池の汀に散る花よ 水の泡となってもこちらに流れ寄っておくれ」 |
心ありて池の |
"Kokoro ari te ike no migiha ni oturu hana awa to nari te mo waga kata ni yore |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8.9 | 勝ち方の童女おりて、花の下にありきて、散りたるをいと多く拾ひて、持て参れり。 |
勝ち方の女の童が下りて、花の下を歩いて、散った花びらをたいそうたくさん拾って、持って参った。 |
勝ったほうの童女が庭の花の下へ降りて行って、花をたくさん集めて持って来た。 |
Kati kata no Warahabe ori te, hana no sita ni ariki te, tiri taru wo ito ohoku hirohi te, mote mawire ri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8.10 | 「 大空の風に散れども桜花 おのがものとぞかきつめて見る」 |
「大空の風に散った桜の花を わたしのものと思って掻き集めて見ました」 |
大空の風に散れども桜花おのがものぞと |
"Ohozora no kaze ni tire domo sakurabana onoga mono to zo kakitume te miru |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8.11 | 左のなれき、 |
左方のなれきが、 |
左の童女の |
Hidari no Nareki, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8.12 | 「 桜花匂ひあまたに散らさじと おほふばかりの袖はありやは ★ |
「桜の花のはなやかな美しさを方々に散らすまいとしても 大空を覆うほど大きな袖がございましょうか |
「桜花 おほふばかりの |
"Sakurabana nihohi amata ni tirasa zi to ohohu bakari no sode ha ari yaha |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8.13 | 心せばげにこそ見ゆめれ」など言ひ落とす。 |
心が狭く思われます」などと悪口を言う。 |
気が狭いというものですね」 などと悪く言う。 |
Kokoro sebage ni koso miyu mere." nado ihi otosu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last updated 11/9/2010(ver.2-2) 渋谷栄一校訂(C) Last updated 11/9/2010(ver.2-2) 渋谷栄一注釈(C) |
Last updated 2/24/2002 渋谷栄一訳(C)(ver.1-2-2) |
|
Last updated 11/09/2010 (ver.2-2) Written in Japanese roman letters by Eiichi Shibuya (C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Picture "Eiri Genji Monogatari"(1650 1st edition) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源氏物語の世界 再編集プログラム Ver 3.38: Copyright (c) 2003,2015 宮脇文経