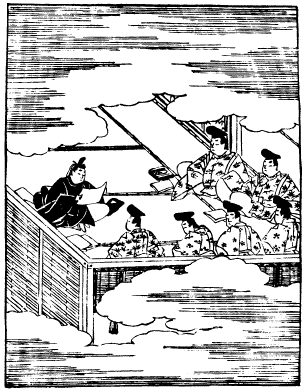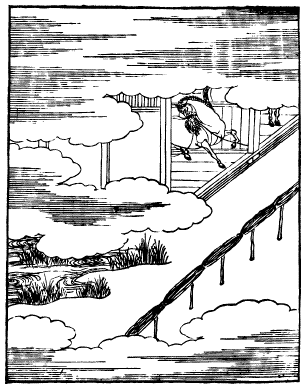第二十一帖 乙女
光る源氏の太政大臣時代三十三歳の夏四月から三十五歳冬十月までの物語
|
# |
本文 |
渋谷栄一訳 |
与謝野晶子訳 |
注釈 |
|
第一章 朝顔姫君の物語 藤壺代償の恋の諦め
|
|
第一段 故藤壺の一周忌明ける
|
| 1.1.1 |
|
年が変わって、宮の御一周忌も過ぎたので、世の人々の喪服が平常に戻って、衣更のころなどもはなやかであるが、それ以上に賀茂祭のころは、おおよその空模様も気分がよいのに、前斎院は所在なげに物思いに耽っていらっしゃるが、庭先の桂の木の下を吹く風、慕わしく感じられるにつけても、若い女房たちは思い出されることが多いところに、大殿から、
|
春になって女院の御一周年が過ぎ、官人が喪服を脱いだのに続いて四月の更衣期になったから、はなやかな空気の満ち渡った初夏であったが、前斎院はなお寂しくつれづれな日を送っておいでになった。庭の桂の木の若葉がたてるにおいにも若い女房たちは、宮の御在職中の加茂の院の祭りのころのことを恋しがった。
|
【年変はりて】- 前の「朝顔」巻の翌年、源氏三十三歳の正月。
【宮の御果ても過ぎぬれば】- 藤壷の一周忌をさす。崩御は前年三月。
【今めかしきを】- 『集成』は「はなやいだ気分だが」。『完訳』は「目新しくはなやかな趣きであるが」と訳す。
【心地よげなるに】- 接続助詞「に」逆接の意。
【前斎院はつれづれと眺めたまふを、前なる】- 朝顔姫君は父桃園式部卿宮の死去を悲しんでいる。 【眺めたまふを、前なる】-なかめ給ふおまへなる明-なかめ給おまへなる証 『集成』は「ながめたまふ。御前なる」と整定。藤原定家は格助詞「を」はかならず「を」と表記する。
【あるに】- 格助詞「に」時間の意。
【大殿より】- 源氏をさす。
|
| 1.1.2 |
|
「御禊の日は、どのようにのんびりとお過ごしになりましたか」
|
源氏から、神の御禊の日もただ今はお静かでしょうという
|
【御禊の日は、いかにのどやかに思さるらむ】- 源氏の消息文の一部。
|
| 1.1.3 |
|
と、お見舞い申し上げなさった。
|
挨拶を持った使いが来た。
|
【訪らひきこえさせたまへり】- 「きこえさせ」謙譲の補助動詞、朝顔に対する敬意。「たまへ」尊敬の補助動詞、源氏に対する敬意。
|
| 1.1.4 |
|
「今日は、
|
今日こんなことを思いました。
|
【今日は】- 以下、和歌の終わりまで、源氏の消息文。
|
| 1.1.5 |
|
思いもかけませんでした
再びあなたが禊をなさろうとは」
|
かけきやは川瀬の波もたちかへり
君が御禊の藤のやつれを
|
【かけきやは川瀬の波もたちかへり--君が禊の藤のやつれを】- 源氏から朝顔姫君への贈歌。「き」過去助動詞、終止形。「やは」連語、反語表現。「藤」(藤衣=喪服)と「淵」の掛詞。「淵」「河瀬の波」「禊」は縁語。
|
| 1.1.6 |
紫の紙、立文すくよかにて、藤の花につけたまへり。折のあはれなれば、御返りあり。 |
紫色の紙、立て文にきちんとして、藤の花におつけになっていた。
季節柄、感動をおぼえて、お返事がある。
|
紫の紙に書いた正しい立文の形の手紙が藤の花の枝につけられてあった。斎院はものの少し身にしむような日でおありになって、返事をお書きになった。
|
【立文すくよかにて】- 恋文の体裁ではない普通の手紙の体裁。
|
| 1.1.7 |
|
「喪服を着たのはつい昨日のことと思っておりましたのに
もう今日はそれを脱ぐ禊をするとは、
|
藤衣きしは昨日と思ふまに
今日はみそぎの瀬にかはる世を
|
【藤衣着しは昨日と思ふまに--今日は禊の瀬にかはる世を】- 朝顔の返歌。「藤のやつれ」を受けて「藤衣」と返し、「禊」「瀬」はそのまま用いて返す。「世の中は何か常なる飛鳥川昨日の淵ぞ今日は瀬になる」(古今集雑下、九三三、読人しらず)「飛鳥川淵にもあらぬ我が宿も瀬にかはりゆくものにぞありける」(古今集雑下、九九三、伊勢)を踏まえる。無常をいう。
|
| 1.1.8 |
はかなく」
|
はかなくて」
|
はかないものと思われます。
|
|
| 1.1.9 |
|
とだけあるのを、例によって、お目を凝らして御覧になっていらっしゃる。
|
とだけ書かれてある手紙を、例のように源氏は熱心にながめていた。
|
【御目止めたまひて】- 大島本は「御めとめ給て」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「御目とどめたまひて」と校訂する。
|
| 1.1.10 |
御服直しのほどなどにも、宣旨のもとに、所狭きまで、思しやれることどもあるを、院は見苦しきことに思しのたまへど、 |
喪服をお脱ぎになるころにも、宣旨のもとに、置き所もないほど、お心づかいの品々が届けられたのを、院は見苦しいこととお思いになりお口になさるが、
|
斎院が父宮の喪の済んでお服直しをされる時も、源氏からたいした贈り物が来た。
|
【院は】- 前斎院の意。朝顔をさす。
|
| 1.1.11 |
|
「意味ありげな、色めかしいお手紙ならば、何とか申し上げてご辞退するのですが、長年、表向きの折々のお見舞いなどはお馴れ申し上げになっていて、とても真面目な内容なので、どのように言い紛らわしてお断り申したらよいだろうか」
|
女王はそれをお受けになることは醜いことであるというように言っておいでになったが、求婚者としての言葉が添えられていることであれば辞退もできるが、これまで長い間何かの場合に公然の進物を送り続けた源氏であって、親切からすることであるから返却のしようがないように言って
|
【をかしやかに、けしきばめる御文などの】- 『完訳』は「懸想文めく思わせぶりの手紙なら」と注す。以下「紛らはすべからむ」まで、宣旨の心中。
【あらばこそ】- 係助詞「こそ」は「聞こえ返さめ」已然形に係る、逆接用法。
【いかがは聞こえも紛らはすべからむ】- 大島本「まきらかす」とある。字母「可」は「ハ」の誤写であろう。諸本によって訂正する。反語表現。
|
| 1.1.12 |
|
と、困っているようである。
|
女房たちは困っていた。
|
【と、もてわづらふべし】- 推量助動詞「べし」は語り手の推量。宣旨の心中を忖度。以下の物語展開を興味深々たるものにする表現効果。
|
|
第二段 源氏、朝顔姫君を諦める
|
| 1.2.1 |
|
女五の宮の御方にも、このように機会を逃さずお見舞い申し上げるので、とても感心して、
|
女五の宮のほうへもこんなふうにして始終物質的に御補助をする源氏であったから、宮は深く源氏を愛しておいでになった。
|
【女五の宮の御方にも】- 桃園式部卿宮の妹、朝顔の叔母。桃園式部卿宮邸に朝顔と同居。
|
| 1.2.2 |
「この君の、昨日今日の稚児と思ひしを、かくおとなびて、訪らひたまふこと。容貌のいともきよらなるに添へて、心さへこそ人にはことに生ひ出でたまへれ」 |
「この君が、昨日今日までは子供と思っていましたのに、このように成人されて、お見舞いくださるとは。
容貌のとても美しいのに加えて、気立てまでが人並み以上にすぐれていらっしゃいます」
|
「源氏の君というと、いつも美しい少年が思われるのだけれど、こんなに大人らしい親切を見せてくださる。顔がきれいな上に心までも並みの人に違ってでき上がっているのだね」
|
【この君の】- 以下「生ひ出でたまへれ」まで、女五宮の詞。
|
| 1.2.3 |
と、ほめきこえたまふを、若き人びとは笑ひきこゆ。
|
と、お褒め申し上げるのを、若い女房たちは苦笑申し上げる。
|
とおほめになるのを、若い女房らは笑っていた。
|
|
| 1.2.4 |
|
こちらの方にもお目にかかりなさる時には、
|
西の女王とお逢いになる時には、
|
【こなたにも対面したまふ折は】- 女五宮が朝顔の君に。
|
| 1.2.5 |
|
「この大臣が、このように心をこめてお手紙を差し上げなさるようですが、どうしてか、今に始まった軽いお気持ちではありません。
亡くなられた宮も、その関係が違ってしまわれて、お世話申し上げることができなくなったとお嘆きになっては、考えていたことを無理にお断りになったことだなどと、おっしゃっては、後悔していらっしゃったことがよくありました。
|
「源氏の大臣から熱心に結婚が申し込まれていらっしゃるのだったら、いいじゃありませんかね、今はじめての話ではなし、ずっと以前からのことなのですからね、お亡くなりになった宮様もあなたが斎院におなりになった時に、結婚がせられなくなったことで失望をなすってね、以前宮様がそれを実行しようとなすった時に、あなたの気の進まなかったことで、話をそのままにしておいたのを御後悔してお話しになることがよくありましたよ。
|
【この大臣の】- 以下「となむ思ひはべる」まで、女五宮の詞。
【何か、今始めたる御心ざしにもあらず】- 「何か」は「あらず」に係る、反語表現。
【故宮も】- 桃園式部卿宮をさす。
【筋異になりたまひて、え見たてまつりたまはぬ嘆きを】- 「筋異になりたまひて」は多義的内容を含む表現。『集成』は「(あなたが)斎院という神に仕える特別のご身分になられて、源氏を婿君としてお世話できないことをお悔みになっては」。『完訳』は「あのお方が他家の婿におなりになったので、こちらではお世話申すこともできなくなったとお嘆きになっては」と訳す。
【思ひ立ちしことをあながちにもて離れたまひしことなど】- 桃園式部卿宮の詞を引用。桃園式部卿宮が源氏を婿にと思っていたのを朝顔が強情に断ったという。
|
| 1.2.6 |
|
けれども、故大殿の姫君がいらっしゃった間は、三の宮がお気になさるのが気の毒さに、あれこれと言葉を添えることもなかったのです。
今では、そのれっきとした奥方でいらした方まで、お亡くなりになってしまったので、ほんとに、どうしてご意向どおりになられたとしても悪くはあるまいと思われますにつけても、昔に戻ってこのように熱心におっしゃていただけるのも、そうなるはずであったのだろうと存じます」
|
けれどもね、宮様がそうお思い立ちになったころは左大臣家の奥さんがいられたのですからね、そうしては三の宮がお気の毒だと思召して第二の結婚をこちらでおさせにはなりにくかったのですよ。あなたと従妹のその奥様が亡くなられたのだし、そうなすってもいいのにと私は思うし、一方ではまた新しく熱心にお申し込みがあるというのは、やはり前生の約束事だろうと思う」
|
【故大殿の姫君】- 葵の上をさす。
【三の宮の思ひたまはむこと】- 葵の上の母、五の宮の姉に当たる。
【やむごとなくえさらぬ筋にてものせられし人さへ、亡くなられにしかば】- 『集成』は「れっきとした正室で、のっぴきならぬ間柄でいらした方も。「えさらぬ」は、葵の上の母大宮が源氏の叔母であるという近い姻戚関係をいう」。『完訳』は「重々しく正妻の座にあった人、葵の上。「さへ」は、父式部卿宮はもちろん、葵の上までも、の気持」と注す。
【などてかは、さやうにておはせましも悪しかるまじと】- 「などてかは」は「悪しからまじ」に係る反語表現。「さやうにて」は式部卿宮の意向、すなわち源氏との結婚をさす。
【さるべきにもあらむと】- 前世からの因縁であろう、という。
|
| 1.2.7 |
など、いと古代に聞こえたまふを、心づきなしと思して、
|
などと、いかにも古風に申し上げなさるのを、気にそまぬとお思いになって、
|
などと古めかしい御勧告をあそばすのを、女王は苦笑して聞いておいでになった。
|
|
| 1.2.8 |
「故宮にも、しか心ごはきものに思はれたてまつりて過ぎはべりにしを、今さらに、また世になびきはべらむも、いとつきなきことになむ」 |
「亡き父宮からも、そのように強情な者と思われてまいりましたが、今さらに、改めて結婚しようというのも、ひどくおかしなことでございます」
|
「お父様からもそんな強情者に思われてきた私なのですから、今さら源氏の大臣の声名が高いからと申して結婚をいたしますのは恥ずかしいことだと思います」
|
【故宮にも】- 以下「ことになむ」まで、朝顔の君の詞。
|
| 1.2.9 |
|
と申し上げなさって、気恥ずかしくなるようなきっぱりとしたご様子なので、無理にもお勧め申し上げることもできない。
|
こんなふうに思いもよらぬように言っておいでになったから、宮もしまいにはお勧めにならなかった。
|
【しひてもえ聞こえおもむけたまはず】- 主語は女五の宮。
|
| 1.2.10 |
|
宮家に仕える人たちも、上下の女房たち、皆が心をお寄せ申していたので、縁談事を不安にばかりお思いになるが、かの当のご自身は、心のありったけを傾けて、愛情をお見せ申して、相手のお気持ちが揺らぐのをじっと待っていらっしゃるが、そのように無理してまで、お心を傷つけようなどとは、お考えにならないのであろう。
|
邸の人は上から下まで皆が皆そうなるのを望んでいることを女王は知って警戒しておいでになったが、源氏自身は至誠で女王を動かしうる日は待っているが、しいて力で結婚を遂げるようなことをしたくないと女王の感情を尊重していた。
|
【世の中いとうしろめたくのみ思さるれど】- 『集成』は「(前斎院は、女房たちがいつ源氏を手引きするかもしれないと)毎日ご心配でいらっしゃるが。「世の中」は、男女の仲。源氏との関係をいう」と注す。
【かの御みづからは、わが心を尽くし】- 源氏をさす。『集成』は「以下、草子地。前斎院側に立っているので「かの御みづからは」という」と注す。
【こそ待ちわたりたまへ】- 係助詞「こそ」--「たまへ」已然形は、逆接用法。
|
|
第二章 夕霧の物語 光る源氏の子息教育の物語
|
|
第一段 子息夕霧の元服と教育論
|
| 2.1.1 |
|
大殿腹の若君のご元服のこと、ご準備をなさるが、二条院でとお考えになるが、大宮がとても見たがっていっらしゃったのもごもっともに気の毒なので、やはりそのままあちらの殿で式を挙げさせ申し上げなさる。
|
故太政大臣家で生まれた源氏の若君の元服の式を上げる用意がされていて、源氏は二条の院で行なわせたく思うのであったが、祖母の宮が御覧になりたく思召すのがもっともで、そうしたことはお気の毒に思われて、やはり今までお育てになった宮の御殿でその式をした。
|
【大殿腹の若君の御元服のこと】- 葵の上の生んだ夕霧。十二歳。「大殿腹」は太政大臣の姫君(葵の上)の生んだの意。
【かの殿にて】- 三条宮邸をさす。
|
| 2.1.2 |
右大将をはじめきこえて、御伯父の殿ばら、みな上達部のやむごとなき御おぼえことにてのみものしたまへば、主人方にも、我も我もと、さるべきことどもは、とりどりに仕うまつりたまふ。おほかた世ゆすりて、所狭き御いそぎの勢なり。 |
右大将をはじめとして、御伯父の殿方は、みな上達部で高貴なご信望厚い方々ばかりでいらっしゃるので、主人方でも、我も我もとしかるべき事柄は、競い合ってそれぞれがお仕え申し上げなさる。
だいたい世間でも大騒ぎをして、大変な準備のしようである。
|
右大将を始め伯父君たちが皆りっぱな顕官になっていて勢力のある人たちであったから、母方の親戚からの祝品その他の贈り物もおびただしかった。かねてから京じゅうの騒ぎになるほど華美な祝い事になったのである。
|
【右大将】- もとの頭中将をさす。「薄雲」巻で、大納言兼右大将になっている。
【主人方にも】- 主催者方、すなわち右大将側をいう。
|
| 2.1.3 |
|
四位につけようとお思いになり、世間の人々もきっとそうであろうと思っていたが、
|
初めから四位にしようと源氏は思ってもいたことであったし、世間もそう見ていたが、
|
【四位になしてむ】- 源氏の心中。『集成』は「親王の子は従四位下に叙する規定であるが、一世の源氏の子の場合は従五位下が通例である。源氏の場合は親王に准じたものか」と注す。
|
| 2.1.4 |
「まだいときびはなるほどを、わが心にまかせたる世にて、しかゆくりなからむも、なかなか目馴れたることなり」 |
「まだたいそう若いのに、自分の思いのままになる世だからといって、そのように急に位につけるのは、かえって月並なことだ」
|
まだきわめて小さい子を、何事も自分の意志のとおりになる時代にそんな取り計らいをするのは、俗人のすることであるという気がしてきたので、
|
【まだいときびはなるほどを】- 以下「目馴れたることなり」まで、源氏の心中。
|
| 2.1.5 |
と思しとどめつ。
|
とお止めになった。
|
源氏は長男に四位を与えることはやめて、
|
|
| 2.1.6 |
|
浅葱の服で殿上の間にお戻りになるのを、大宮は、ご不満でとんでもないこととお思いになったのは、無理もなく、お気の毒なことであった。
|
六位の浅葱の袍を着せてしまった。大宮が言語道断のことのようにこれをお歎きになったことはお道理でお気の毒に思われた。
|
【浅葱にて】- 六位の浅緑色の袍姿。
【殿上に帰りたまふを】- 三条宮邸で元服の式を済ませて、六位の袍姿で清涼殿の殿上間に還る。すでに童殿上していたので「帰り」といったもの。
|
| 2.1.7 |
|
ご対面なさって、このことをお話し申し上げなさると、
|
源氏は宮に御面会をしてその問題でお話をした。
|
【御対面ありて】- 『集成』は「大宮が源氏にお会いになって」と訳す。
【このこと聞こえたまふに】- 主語は大宮。
|
| 2.1.8 |
|
「今のうちは、このように無理をしてまで、まだ若年なので大人扱いする必要はございませんが、考えていることがございまして、大学の道に暫くの間勉強させようという希望がございますゆえ、もう二、三年間を無駄に過ごしたと思って、いずれ朝廷にもお仕え申せるようになりましたら、そのうちに、一人前になりましょう。
|
「ただ今わざわざ低い位に置いてみる必要もないようですが、私は考えていることがございまして、大学の課程を踏ませようと思うのでございます。ここ二、三年をまだ元服以前とみなしていてよかろうと存じます。朝廷の御用の勤まる人間になりますれば自然に出世はして行くことと存じます。
|
【ただ今】- 以下「と思うたまへる」まで、源氏の詞。
【老いつかすまじう】- 大島本は「をいつかす」とある。すなわち「老(お)いつかす」。「大人にする、元服させる意」(集成)。「大人に扱う意」(新大系)『古典セレクション』は『玉の小櫛』の説に従って「お(生)ひつかす」と校訂する。
【いたづらの年に思ひなして】- 『完訳』は「学生のうちは昇進しない」と注す。
|
| 2.1.9 |
|
自分は、宮中に成長致しまして、世の中の様子を存じませんで、昼夜、御帝の前に伺候致して、ほんのちょっと学問を習いました。
ただ、畏れ多くも直接に教えていただきましたのさえ、どのようなことも広い知識を知らないうちは、詩文を勉強するにも、琴や笛の調べにしても、音色が十分でなく、及ばないところが多いものでございました。
|
私は宮中に育ちまして、世間知らずに御前で教養されたものでございますから、陛下おみずから師になってくだすったのですが、やはり刻苦精励を体験いたしませんでしたから、詩を作りますことにも素養の不足を感じたり、音楽をいたしますにも音足らずな気持ちを痛感したりいたしました。
|
【みづからは、九重のうちに生ひ出ではべりて】- 源氏、自らの体験を語る。
【広き心を知らぬほどは】- 『集成』は「いろいろな経験を積まぬうちは」。『完訳』は「何事をも広い教養を積まないうちは」と訳す。
|
| 2.1.10 |
はかなき親に、かしこき子のまさる例は、いとかたきことになむはべれば、まして、次々伝はりつつ、隔たりゆかむほどの行く先、いとうしろめたなきによりなむ、思ひたまへおきてはべる。
|
つまらない親に、賢い子が勝るという話は、とても難しいことでございますので、まして、次々と子孫に伝わっていき、離れてゆく先は、とても不安に思えますので、決めましたことでございます。
|
つまらぬ親にまさった子は自然に任せておきましてはできようのないことかと思います。まして孫以下になりましたなら、どうなるかと不安に思われてなりませんことから、そう計らうのでございます。
|
|
| 2.1.11 |
高き家の子として、官位爵位心にかなひ、世の中盛りにおごりならひぬれば、学問などに身を苦しめむことは、いと遠くなむおぼゆべかめる。戯れ遊びを好みて、心のままなる官爵に昇りぬれば、時に従ふ世人の、下には鼻まじろきをしつつ、追従し、けしきとりつつ従ふほどは、おのづから人とおぼえて、やむごとなきやうなれど、時移り、さるべき人に立ちおくれて、世衰ふる末には、人に軽めあなづらるるに、取るところなきことになむはべる。 |
高貴な家の子弟として、官位爵位が心にかない、世の中の栄華におごる癖がついてしまいますと、学問などで苦労するようなことは、とても縁遠いことのように思うようです。
遊び事や音楽ばかりを好んで、思いのままの官爵に昇ってしまうと、時勢に従う世の人が、内心ではばかにしながら、追従し、機嫌をとりながら従っているうちは、自然とひとかどの人物らしく立派なようですが、時勢が移り、頼む人に先立たれて、運勢が衰えた末には、人に軽んじらればかにされて、取り柄とするところがないものでございます。
|
貴族の子に生まれまして、官爵が思いのままに進んでまいり、自家の勢力に慢心した青年になりましては、学問などに身を苦しめたりいたしますことはきっとばかばかしいことに思われるでしょう。遊び事の中に浸っていながら、位だけはずんずん上がるようなことがありましても、家に権勢のあります間は、心で嘲笑はしながらも追従をして機嫌を人がそこねまいとしてくれますから、ちょっと見はそれでりっぱにも見えましょうが、家の権力が失墜するとか、保護者に死に別れるとかしました際に、人から軽蔑されましても、なんらみずから恃むところのないみじめな者になります。
|
【取るところなき】- 大島本は「とるところなき」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「かかりどころ」と校訂する。
|
| 2.1.12 |
|
やはり、学問を基礎にしてこそ、政治家としての心の働きが世間に認められるところもしっかりしたものでございましょう。
当分の間は、不安なようでございますが、将来の世の重鎮となるべき心構えを学んだならば、わたしが亡くなった後も、安心できようと存じてです。
ただ今のところは、ぱっとしなくても、このように育てていきましたら、貧乏な大学生だといって、ばかにして笑う者もけっしてありますまいと存じます」
|
やはり学問が第一でございます。日本魂をいかに活かせて使うかは学問の根底があってできることと存じます。ただ今目前に六位しか持たないのを見まして、たよりない気はいたしましても、将来の国家の柱石たる教養を受けておきますほうが、死後までも私の安心できることかと存じます。ただ今のところは、とにかく私がいるのですから、窮迫した大学生と指さす者もなかろうと思います」
|
【なほ、才をもととしてこそ、大和魂の世に用ゐらるる方も】- 『集成』は「やはり、学問という基礎があってこそ、政治家としての臨機の力量が世間に重んじられることも、一層強みがございましょう。「大和魂」は、「才」が、儒学(政治学)の知識であるのに対して、わが国の実情に応じた政治的判断や行政能力をいう」と注す。
【育みはべらば】- 主語は源氏。源氏がこのようにして夕霧の育てていったらの意。
|
| 2.1.13 |
など、聞こえ知らせたまへば、うち嘆きたまひて、
|
などと、わけをお話し申し上げになると、ほっと吐息をおつきになって、
|
と源氏が言うのを、聞いておいでになった宮は歎息をあそばしながら、
|
|
| 2.1.14 |
|
「なるほど、そこまでお考えになって当然でしたことを。
ここの大将なども、あまりに例に外れたご処置だと、不審がっておりましたようですが、この子供心にも、とても残念がって、大将や、左衛門督の子どもなどを、自分よりは身分が下だと見くびっていたのさえ、皆それぞれ位が上がり上がりし、一人前になったのに、浅葱をとてもつらいと思っていられるので、気の毒なのでございます」
|
「ごもっともなお話だと思いますがね、右大将などもあまりに変わったお好みだと不審がりますし、子供もね、残念なようで、大将や左衛門督などの息子の、自分よりも低いもののように見下しておりました者の位階が皆上へ上へと進んで行きますのに、自分は浅葱の袍を着ていねばならないのをつらく思うふうですからね。私はそれがかわいそうなのでした」
|
【げに、かくも思し寄るべかりけることを】- 以下「心苦しくはべるなり」まで、大宮の詞。
【かたぶけはべるめるを】- 大島本は「かたふけ」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「かたぶき」と校訂する。
【およすげ】- 『河海抄』に「け」に濁符がある。
【思はれたるに】- 大島本は「おもハれたるに」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「思はれたるが」と校訂する。
【心苦しくはべるなり】- 大島本は「心くるしく」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「心苦しう」と校訂する。
|
| 2.1.15 |
と聞こえたまへば、うち笑ひたまひて、
|
と申し上げなさると、ちょっとお笑いになって、
|
とお言いになる。
|
|
| 2.1.16 |
「いとおよすげても恨みはべるななりな。いとはかなしや。この人のほどよ」 |
「たいそう一人前になって不平を申しているようですね。
ほんとうにたわいないことよ。
あの年頃ではね」
|
「大人らしく父を恨んでいるのでございますね。どうでしょう、こんな小さい人が」
|
【いとおよすげても】- 以下「人のほどよ」まで、源氏の詞。「も」は係助詞、強調の意。接続助詞、逆接の意もあるが、とらない。
|
| 2.1.17 |
とて、いとうつくしと思したり。
|
と言って、とてもかわいいとお思いであった。
|
源氏はかわいくてならぬと思うふうで子を見ていた。
|
|
| 2.1.18 |
|
「学問などをして、もう少し物の道理がわかったならば、そんな恨みは自然となくなってしまうでしょう」
|
「学問などをいたしまして、ものの理解のできるようになりましたら、その恨みも自然になくなってまいるでしょう」
|
【学問などして】- 以下「解けはべりなむ」まで、源氏の詞。大宮に言う。
|
| 2.1.19 |
と聞こえたまふ。
|
とお申し上げになる。
|
と言っていた。
|
|
|
第二段 大学寮入学の準備
|
| 2.2.1 |
字つくることは、東の院にてしたまふ。東の対をしつらはれたり。上達部、殿上人、珍しくいぶかしきことにして、我も我もと集ひ参りたまへり。博士どももなかなか臆しぬべし。 |
字をつける儀式は、東の院でなさる。
東の対を準備なさった。
上達部、殿上人、めったにないことで見たいものだと思って、我も我もと参集なさった。
博士たちもかえって気後れしてしまいそうである。
|
若君の師から字をつけてもらう式は東の院ですることになって、東の院に式場としての設けがされた。高官たちは皆この式を珍しがって参会する者が多かった。博士たちが晴れがましがって気おくれもしそうである。
|
【博士どももなかなか臆しぬべし】- 文章博士、定員は一名。「ども」は複数を表す接尾語。『集成』は「「ども」とあるのは、そのほか詩文にすぐれた儒者が参加しているからであろう」と注す。「臆しぬべし」は語り手の推測。
|
| 2.2.2 |
|
「遠慮することなく、慣例のとおりに従って、手加減せずに、厳格に行いなさい」
|
「遠慮をせずに定りどおりに厳格にやってください」
|
【憚るところなく】- 以下「行へ」まで、源氏の詞。間接話法で引用であろう。
|
| 2.2.3 |
と仰せたまへば、しひてつれなく思ひなして、家より他に求めたる装束どもの、うちあはず、かたくなしき姿などをも恥なく、面もち、声づかひ、むべむべしくもてなしつつ、座に着き並びたる作法よりはじめ、見も知らぬさまどもなり。
|
とお命じになると、無理に平静をよそおって、他人の家から調達した衣装類が、身につかず、不恰好な姿などにもかまいなく、表情、声づかいが、もっともらしくしては、席について並んでいる作法をはじめとして、見たこともない様子である。
|
と源氏から言われたので、しいて冷静な態度を見せて、借り物の衣裳の身に合わぬのも恥じずに、顔つき、声づかいに学者の衒気を見せて、座にずっと並んでついたのははなはだ異様であった。
|
|
| 2.2.4 |
若き君達は、え堪へずほほ笑まれぬ。
さるは、もの笑ひなどすまじく、過ぐしつつ静まれる限りをと、選り出だして、瓶子なども取らせたまへるに、筋異なりけるまじらひにて、右大将、民部卿などの、おほなおほな土器とりたまへるを、あさましく咎め出でつつおろす。
|
若い君達は、我慢しきれず笑ってしまった。
一方では、笑ったりなどしないような、年もいった落ち着いた人だけをと、選び出して、お酌などもおさせになるが、いつもと違った席なので、右大将や、民部卿などが、一所懸命に杯をお持ちになっているのを、あきれるばかり文句を言い言い叱りつける。
|
若い役人などは笑いがおさえられないふうである。しかもこれは笑いやすいふうではない、落ち着いた人が酒瓶の役に選ばれてあったのである。すべてが風変わりである。右大将、民部卿などが丁寧に杯を勧めるのを見ても作法に合わないと叱り散らす、
|
|
| 2.2.5 |
|
「おおよそ、宴席の相伴役は、はなはだ不作法でござる。
これほど著名な誰それを知らなくて、朝廷にはお仕えしている。
はなはだばかである」
|
「御接待役が多すぎてよろしくない。あなたがたは今日の学界における私を知らずに朝廷へお仕えになりますか。まちがったことじゃ」
|
【おほし、垣下あるじ】- 以下「をこなり」まで、博士どもの詞。『集成』「「凡し」。総じての意。大学内で用いられた特殊の語であろう」。『完訳』「「凡そ」の転。「はなはだ」「非常」も漢文訓読調。儒者らしい語」と注す。
【はべりたうぶ】- 『集成』は「「はべりたまふ」と同じ。一座に対して、話者自身を卑下して「はべり」と言い、一方右大将たちに話者の敬意をあらわして「たうぶ」と言う。この物語では、博士や僧たちが使っているが、用例は稀である」。『完訳』は「古風なかたくるしい語感。ここは尊敬語」と注す。
【しるしとある】- 『完訳』は「著名な。これも漢文訓読調」と注す。
|
| 2.2.6 |
など言ふに、人びと皆ほころびて笑ひぬれば、また、
|
などと言うと、人々がみな堪えきれず笑ってしまったので、再び、
|
などと言うのを聞いてたまらず笑い出す人があると、
|
|
| 2.2.7 |
「鳴り高し。鳴り止まむ。はなはだ非常なり。座を引きて立ちたうびなむ」 |
「うるさい。
お静かに。
はなはだ不作法である。
退席していただきましょう」
|
「鳴りが高い、おやめなさい。はなはだ礼に欠けた方だ、座をお退きなさい」
|
【鳴り高し】- 以下「立ちたうびなむ」まで、博士どもの詞。『完訳』は「儒者が学生を静める際の用語。風俗歌にもみえる」と注す。
|
| 2.2.8 |
など、おどし言ふも、いとをかし。
|
などと、脅して言うのも、まことにおかしい。
|
などと威す。
|
|
| 2.2.9 |
見ならひたまはぬ人びとは、珍しく興ありと思ひ、この道より出で立ちたまへる上達部などは、したり顔にうちほほ笑みなどしつつ、かかる方ざまを思し好みて、心ざしたまふがめでたきことと、いとど限りなく思ひきこえたまへり。 |
見慣れていらっしゃらない方々は、珍しく興味深いことと思い、この大学寮ご出身の上達部などは、得意顔に微笑みながら、このような道をご愛好されて、大学に入学させなさったのが結構なことだと、ますますこのうえなく敬服申し上げていらっしゃった。
|
大学出身の高官たちは得意そうに微笑をして、源氏の教育方針のよいことに敬服したふうを見せているのであった。ちょっと彼らの目の前で話をしても博士らは叱る、
|
【かかる方ざまを思し好みて】- 主語は源氏。
|
| 2.2.10 |
いささかもの言ふをも制す。無礼げなりとても咎む。かしかましうののしりをる顔どもも、夜に入りては、なかなか今すこし掲焉なる火影に、猿楽がましくわびしげに、人悪げなるなど、さまざまに、げにいとなべてならず、さまことなるわざなりけり。 |
少し私語を言っても制止する。
無礼な態度であると言っても叱る。
騒がしく叱っている博士たちの顔が、夜に入ってからは、かえって一段と明るくなった燈火の中で、滑稽じみて貧相で、不体裁な様子などが、何から何まで、なるほど実に普通でなく、変わった様子であった。
|
無礼だと言って何でもないこともとがめる。やかましく勝手気ままなことを言い放っている学者たちの顔は、夜になって灯がともったころからいっそう滑稽なものに見えた。まったく異様な会である。
|
【猿楽がましく】- 『完訳』は「「猿楽」は当時の滑稽な物まねの演芸。儒者の道化じみた姿」と注す。
【人悪げなるなど】- 大島本は「人わるけ」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「人わろげなる」と校訂する。
|
| 2.2.11 |
大臣は、
|
大臣は、
|
源氏は、
|
|
| 2.2.12 |
「いとあざれ、かたくななる身にて、けうさうしまどはかされなむ」 |
「とてもだらしなく、頑固な者なので、やかましく叱られてまごつくだろう」
|
「自分のような規律に馴れないだらしのない者は粗相をして叱りまわされるであろうから」
|
【いとあざれ】- 以下「まどはかされなむ」まで、源氏の詞。
|
| 2.2.13 |
とのたまひて、御簾のうちに隠れてぞ御覧じける。
|
とおっしゃって、御簾の内に隠れて御覧になっていたのであった。
|
と言って、御簾の中に隠れて見ていた。
|
|
| 2.2.14 |
数定まれる座に着きあまりて、帰りまかづる大学の衆どもあるを聞こしめして、釣殿の方に召しとどめて、ことに物など賜はせけり。
|
用意された席が足りなくて、帰ろうとする大学寮の学生たちがいるのをお聞きになって、釣殿の方にお呼び止めになって、特別に賜物をなさった。
|
式場の席が足りないために、あとから来て帰って行こうとする大学生のあるのを聞いて、源氏はその人々を別に釣殿のほうでもてなした。贈り物もした。
|
|
|
第三段 響宴と詩作の会
|
| 2.3.1 |
事果ててまかづる博士、才人ども召して、またまた詩文作らせたまふ。上達部、殿上人も、さるべき限りをば、皆とどめさぶらはせたまふ。博士の人びとは、四韻、ただの人は、大臣をはじめたてまつりて、絶句作りたまふ。興ある題の文字選りて、文章博士たてまつる。短きころの夜なれば、明け果ててぞ講ずる。左中弁、講師仕うまつる。容貌いときよげなる人の、声づかひものものしく、神さびて読み上げたるほど、おもしろし。おぼえ心ことなる博士なりけり。 |
式が終わって退出する博士、文人たちをお召しになって、また再び詩文をお作らせになる。
上達部や、殿上人も、その方面に堪能な人ばかりは、みなお残らせになる。
博士たちは、律詩、普通の人は、大臣をはじめとして、絶句をお作りになる。
興趣ある題の文字を選んで、文章博士が奉る。
夏の短いころの夜なので、すっかり明けて披講される。
左中弁が、講師をお勤めした。
容貌もたいそうきれいで、声の調子も堂々として、荘厳な感じに読み上げたところは、たいそう趣がある。
世の信望が格別高い学者なのであった。
|
式が終わって退出しようとする博士と詩人をまた源氏はとどめて詩を作ることにした。高官や殿上役人もそのほうの才のある人は皆残したのである。博士たちは律の詩、源氏その他の人は絶句を作るのであった。おもしろい題を文章博士が選んだ。短夜のころであったから、夜がすっかり明けてから詩は講ぜられた。左中弁が講師の役をしたのである。きれいな男の左中弁が重々しい神さびた調子で詩を読み上げるのが感じよく思われた。この人はことに深い学殖のある博士なのである。
|
【博士、才人ども】- 文章博士や詩文の才ある学者たち。
【さぶらはせたまふ】- 大島本は「さふらハせ給」とある。『集成』『新大系』は底本のままとする。『古典セレクション』は諸本に従って「さぶらはせさせたまふ」と「させ」を補訂する。
【四韻】- 五言律詩をいう。
【おもしろし】- 大島本は「おもしろし」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「いとおもしろし」と副詞「いと」を補訂する。
【博士なりけり】- 『集成』は「ここは碩学の意」と注す。
|
|
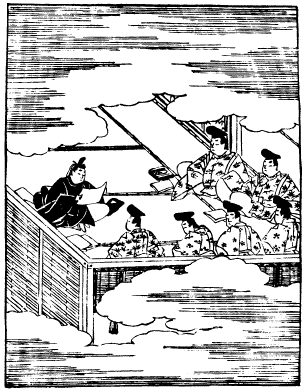 |
| 2.3.2 |
|
このような高貴な家柄にお生まれになって、この世の栄華をひたすら楽しまれてよいお身の上でありながら、窓の螢を友とし、枝の雪にお親しみになる学問への熱心さを、思いつく限りの故事をたとえに引いて、それぞれが作り集めた句がそれぞれに素晴らしく、「唐土にも持って行って伝えたいほどの世の名詩である」と、当時世間では褒めたたえるのであった。
|
こうした大貴族の家に生まれて、栄華に戯れてもいるはずの人が蛍雪の苦を積んで学問を志すということをいろいろの譬えを借りて讃美した作は句ごとにおもしろかった。支那の人に見せて批評をさせてみたいほどの詩ばかりであると言われた。
|
【かかる高き家に】- 『集成』は「以下「すぐれたるよし」まで、当夜の人々の、夕霧を称賛した詩の内容を概括したもの」と注す。
【窓の螢をむつび、枝の雪を馴らし】- 『晋書』と『孫氏世録』を出典とする故事。『蒙求』「孫康映雪車胤聚螢」にある。『源氏釈』が初指摘。
【唐土にも持て渡り伝へまほしげなる夜の詩文どもなり】- 世間の風評。間接話法で引用。
|
| 2.3.3 |
大臣の御はさらなり。親めきあはれなることさへすぐれたるを、涙おとして誦じ騷ぎしかど、女のえ知らぬことまねぶは憎きことをと、うたてあれば漏らしつ。 |
大臣のお作は言うまでもない。
親らしい情愛のこもった点までも素晴らしかったので、涙を流して朗誦しもてはやしたが、女の身では知らないことを口にするのは生意気だと言われそうなので、嫌なので書き止めなかった。
|
源氏のはむろん傑作であった。子を思う親の情がよく現われているといって、列席者は皆涙をこぼしながら誦した。
|
【女のえ知らぬことまねぶは】- 『集成』は「草子地」。『完訳』は「漢詩文は女の関知しえないこととして、省筆する語り手の言葉」と注す。
|
|
第四段 夕霧の勉学生活
|
| 2.4.1 |
うち続き、入学といふことせさせたまひて、やがて、この院のうちに御曹司作りて、まめやかに才深き師に預けきこえたまひてぞ、学問せさせたてまつりたまひける。
|
引き続いて、入学の礼ということをおさせになって、そのまま、この院の中にお部屋を設けて、本当に造詣の深い先生にお預け申されて、学問をおさせ申し上げなさった。
|
それに続いてまた入学の式もあった。東の院の中に若君の勉強部屋が設けられて、まじめな学者を一人つけて源氏は学ばせた。
|
|
| 2.4.2 |
大宮の御もとにも、をさをさ参うでたまはず。夜昼うつくしみて、なほ稚児のやうにのみもてなしきこえたまへれば、かしこにては、えもの習ひたまはじとて、静かなる所に籠めたてまつりたまへるなりけり。 |
大宮のところにも、めったにお出かけにならない。
昼夜かわいがりなさって、いつまでも子供のようにばかりお扱い申していらっしゃるので、あちらでは、勉強もおできになれまいと考えて、静かな場所にお閉じこめ申し上げなさったのであった。
|
若君は大宮の所へもあまり行かないのであった。夜も昼もおかわいがりにばかりなって、いつまでも幼児であるように宮はお扱いになるのであったから、そこでは勉学ができないであろうと源氏が認めて、学問所を別にして若君を入れたわけである。
|
【夜昼うつくしみて】- 以下、大宮から夕霧を遠ざけた理由を語る。
|
| 2.4.3 |
|
「一月に三日ぐらいは参りなさい」
|
月に三度だけは大宮を御訪問申してよい
|
【一月に三度ばかりを参りたまへ】- 源氏の詞、間接的話法で引用。令制でも官人には十日に一日の休暇が許されている。
|
| 2.4.4 |
とぞ、許しきこえたまひける。
|
と、お許し申し上げなさのであった。
|
と源氏は定めた。
|
|
| 2.4.5 |
つと籠もりゐたまひて、いぶせきままに、殿を、
|
じっとお籠もりになって、気持ちの晴れないまま、殿を、
|
じっと学問所にこもってばかりいる苦しさに、
|
|
| 2.4.6 |
「つらくもおはしますかな。かく苦しからでも、高き位に昇り、世に用ゐらるる人はなくやはある」 |
「ひどい方でいらっしゃるなあ。
こんなに苦しまなくても、高い地位に上り、世間に重んじられる人もいるではないか」
|
若君は父君を恨めしく思った。ひどい、こんなに苦しまないでも出世をして世の中に重んぜられる人がないわけはなかろうと考えるのであるが、
|
【つらくもおはしますかな】- 以下「人はなくやはある」まで、夕霧の心中。
|
| 2.4.7 |
と思ひきこえたまへど、おほかたの人がら、まめやかに、あだめきたるところなくおはすれば、いとよく念じて、
|
とお恨み申し上げなさるが、いったい性格が、真面目で、浮ついたところがなくていらっしゃるので、よく我慢して、
|
一体がまじめな性格であって、軽佻なところのない少年であったから、よく忍んで、
|
|
| 2.4.8 |
「いかでさるべき書どもとく読み果てて、交じらひもし、世にも出でたらむ」 |
「何とかして必要な漢籍類を早く読み終えて、官途にもついて、出世しよう」
|
どうかして早く読まねばならぬ本だけは皆読んで、人並みに社会へ出て立身の道を進みたい
|
【いかでさるべき】- 以下「世にも出でたらむ」まで、夕霧の心中。『集成』は「『史記』『漢書』『後漢書』の三史と『文選』などが紀伝道のテキストであった」と注す。「帚木」巻に「三史五経の道々しき」とあった。
|
| 2.4.9 |
|
と思って、わずか四、五か月のうちに、『史記』などという書物、読み了えておしまいになった。
|
と一所懸命になったから、四、五か月のうちに史記などという書物は読んでしまった。
|
【ただ四、五月のうちに、『史記』などいふ書、読み果てたまひてけり】- 大島本は「ふミ」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「書は」と係助詞「は」を補訂する。『史記』百三十巻、大著である。それを四、五月で読破とは夕霧の猛勉強ぶりを表す。
|
|
第五段 大学寮試験の予備試験
|
| 2.5.1 |
|
今では寮試を受けさせようとなさって、まずご自分の前で試験をさせなさる。
|
もう大学の試験を受けさせてもよいと源氏は思って、その前に自身の前で一度学力をためすことにした。
|
【寮試受けさせむとて】- 大学寮の試験。合格すると擬文章生になる。三史のうち、一史の五条を読ませ、三条以上に通じた者を合格とする。
【我が御前にて試みさせたまふ】- 源氏の御前での模擬試験。
|
| 2.5.2 |
例の、大将、左大弁、式部大輔、左中弁などばかりして、御師の大内記を召して、『史記』の難き巻々、寮試受けむに、博士のかへさふべきふしぶしを引き出でて、一わたり読ませたてまつりたまふに、至らぬ句もなく、かたがたに通はし読みたまへるさま、爪じるし残らず、あさましきまでありがたければ、 |
いつものとおり、大将、左大弁、式部大輔、左中弁などばかり招いて、先生の大内記を呼んで、『史記』の難しい巻々を、寮試を受けるのに、博士が反問しそうなところどころを取り出して、ひととおりお読ませ申し上げなさると、不明な箇所もなく、諸説にわたって読み解かれるさまは、爪印もつかず、あきれるほどよくできるので、
|
例の伯父の右大将、式部大輔、左中弁などだけを招いて、家庭教師の大内記に命じて史記の中の解釈のむずかしいところの、寮試の問題に出されそうな所々を若君に読ますのであったが、若君は非常に明瞭に難解なところを幾通りにも読んで意味を説明することができた。師の爪じるしは一か所もつける必要のないのを見て、
|
【かへさふべきふしぶしを】- 『集成』は「反問しそうな大事な箇所を」。『完訳』は「繰り返し質問しそうな箇所を」と訳す。
【至らぬ句もなく】- 大島本は「いたらぬくもなく」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従ってそれぞれ「至らぬ隈なく」「至らぬ隈もなく」と校訂する。
|
| 2.5.3 |
|
「お生まれが違っていらっしゃるのだ」
|
人々は若君に学問をする天分の豊かに備わっていることを喜んだ。
|
【さるべきにこそおはしけれ】- 世間の噂。間接話法であろう。
|
| 2.5.4 |
と、誰も誰も、涙落としたまふ。
大将は、まして、
|
と、皆が皆、涙を流しなさる。
大将は、誰にもまして、
|
伯父の大将はまして感動して、
|
|
| 2.5.5 |
|
「亡くなった大臣が生きていらっしゃったら」
|
「父の大臣が生きていられたら」
|
【故大臣おはせましかば】- 右大将(もとの頭中将)の詞。間接話法であろう。父太政大臣は「薄雲」巻に薨去。
|
| 2.5.6 |
と、聞こえ出でて泣きたまふ。
殿も、え心強うもてなしたまはず、
|
と、口に出されて、
お泣きになる。殿も、我慢がお
|
と言って泣いていた。源氏も冷静なふうを作ろうとはしなかった。
|
|
| 2.5.7 |
「人のうへにて、かたくななりと見聞きはべりしを、子のおとなぶるに、親の立ちかはり痴れゆくことは、いくばくならぬ齢ながら、かかる世にこそはべりけれ」 |
「他人のことで、愚かで見苦しいと見聞きしておりましたが、子が大きくなっていく一方で、親が代わって愚かになっていくことは、たいした年齢ではありませんが、世の中とはこうしたものなのだなあ」
|
「世間の親が愛におぼれて、子に対しては正当な判断もできなくなっているなどと私は見たこともありますが、自分のことになってみると、それは子が大人になっただけ親はぼけていくのでやむをえないことだと解釈ができます。私などはまだたいした年ではないがやはりそうなりますね」
|
【人のうへにて】- 以下「世にこそはべりけれ」まで、源氏の詞。
|
| 2.5.8 |
|
などとおっしゃって、涙をお拭いになるのを見る先生の気持ち、嬉しく面目をほどこしたと思った。
|
などと言いながら涙をふいているのを見る若君の教師はうれしかった。名誉なことになったと思っているのである。
|
【御師の心地】- 夕霧の先生、大内記をいう。
|
| 2.5.9 |
大将、盃さしたまへば、いたう酔ひ痴れてをる顔つき、いと痩せ痩せなり。
|
大将が、杯をおさしになると、たいそう酔っぱらっている顔つきは、とても痩せ細っている。
|
大将が杯をさすともう深く酔いながら畏まっている顔つきは気の毒なように痩せていた。
|
|
| 2.5.10 |
世のひがものにて、才のほどよりは用ゐられず、すげなくて身貧しくなむありけるを、御覧じ得るところありて、かくとりわき召し寄せたるなりけり。 |
大変な変わり者で、学問のわりには登用されず、顧みられなくて貧乏でいたのであったが、お目に止まるところがあって、このように特別に召し出したのであった。
|
変人と見られている男で、学問相当な地位も得られず、後援者もなく貧しかったこの人を、源氏は見るところがあってわが子の教師に招いたのである。
|
【すげなくて】- 『集成』は「顧みられなくて」。『完訳』は「人付合いが下手で」と訳す。
|
| 2.5.11 |
|
身に余るほどのご愛顧を頂戴して、この若君のおかげで、急に生まれ変わったようになったと思うと、今にまして将来は、並ぶ者もない声望を得るであろうよ。
|
たちまちに源氏の庇護を受ける身の上になって、若君のために生まれ変わったような幸福を得ているのである。将来はましてこの今の若君に重用されて行くことであろうと思われた。
|
【この君の御徳に、たちまちに身を変へたる】- 大内記の心中、間接話法。「この君」は夕霧をさす。
【まして行く先は、並ぶ人なきおぼえにぞあらむかし】- 「まして」「ぞ」「かし」は語り手の語気。
|
|
第六段 試験の当日
|
| 2.6.1 |
大学に参りたまふ日は、寮門に、上達部の御車ども数知らず集ひたり。おほかた世に残りたるあらじと見えたるに、またなくもてかしづかれて、つくろはれ入りたまへる冠者の君の御さま、げに、かかる交じらひには堪へず、あてにうつくしげなり。 |
大学寮に参上なさる日は、寮の門前に、上達部のお車が数知れないくらい集まっていた。
おおよそ世間にこれを見ないで残っている人はあるまいと思われたが、この上なく大切に扱われて、労られながら入ってこられる冠者の君のご様子、なるほど、このような生活には耐えられないくらい上品でかわいらしい感じである。
|
大学へ若君が寮試を受けに行く日は、寮門に顕官の車が無数に止まった。あらゆる廷臣が今日はここへ来ることかと思われる列席者の派手に並んだ所へ、人の介添えを受けながらはいって来た若君は、大学生の仲間とは見ることもできないような品のよい美しい顔をしていた。
|
【大学に参りたまふ日は】- 寮試を受けるために大学に行く日のこと。
|
| 2.6.2 |
|
例によって、賤しい者たちが集まって来ている席の末に座るのをつらいとお思いになるのは、もっともなことである。
|
例の貧乏学生の多い席末の座につかねばならないことで、若君が迷惑そうな顔をしているのももっともに思われた。
|
【座の末を】- 『集成』は「大学における席次は長幼の序による。学生は十三歳から十六歳までの者から選んだが、夕霧は今十二歳で、最年少である」と注す。
【ことわりなるや】- 語り手の同情の弁。
|
| 2.6.3 |
ここにてもまた、おろしののしる者どもありて、めざましけれど、すこしも臆せず読み果てたまひつ。
|
ここでも同様に、大声で叱る者がいて、目障りであるが、少しも気後れせずに最後までお読みになった。
|
ここでもまた叱るもの威嚇するものがあって不愉快であったが、若君は少しも臆せずに進んで出て試験を受けた。
|
|
| 2.6.4 |
昔おぼえて大学の栄ゆるころなれば、上中下の人、我も我もと、この道に志し集れば、いよいよ、世の中に、才ありはかばかしき人多くなむありける。文人擬生などいふなることどもよりうちはじめ、すがすがしう果てたまへれば、ひとへに心に入れて、師も弟子も、いとど励みましたまふ。 |
昔が思い出される大学の盛んな時代なので、上中下の人は、我も我もと、この道を志望し集まってくるので、ますます、世の中に、学問があり有能な人が多くなったのであった。
擬文章生などとかいう試験をはじめとして、すらすらと合格なさったので、ひたすら学問に心を入れて、先生も弟子も、いっそうお励みになる。
|
昔学問の盛んだった時代にも劣らず大学の栄えるころで、上中下の各階級から学生が出ていたから、いよいよ学問と見識の備わった人が輩出するばかりであった。文人と擬生の試験も若君は成績よく通ったため、師も弟子もいっそう励みが出て学業を熱心にするようになった。
|
【昔おぼえて大学の栄ゆるころなれば】- 平安時代初期、大学寮が重んじられていた時代をさす。
【文人擬生】- 文人擬生で一語。寮試に合格した擬文章生をいう。
|
| 2.6.5 |
|
殿でも、作文の会を頻繁に催し、博士、文人たちも得意である。
すべてどのようなことにつけても、それぞれの道に努める人の才能が発揮される時代なのだった。
|
源氏の家でも始終詩会が催されなどして、博士や文士の得意な時代が来たように見えた。何の道でも優秀な者の認められないのはないのが当代であった。
|
【殿にも】- 源氏の邸宅、二条院をさす。
【何ごとにつけても、道々の人の才のほど現はるる世になむありける】- 『集成』は「詩文に限らず、万事それぞれの道に励む人の才能のほどが発揮される時代であった。源氏の政道輔佐よろしく、万人所を得る聖代の様相」と注す。
|
|
第三章 光る源氏周辺の人々の物語 内大臣家の物語
|
|
第一段 斎宮女御の立后と光る源氏の太政大臣就任
|
| 3.1.1 |
|
そろそろ、
|
皇后が冊立されることになっていたが、
|
【かくて、后ゐたまふべきを】- 冷泉帝即位して五年になる。后が今まで未決定のままであった。
|
| 3.1.2 |
|
「斎宮の女御こそは、母宮も、自分の変わりのお世話役とおっしゃっていましたから」
|
斎宮の女御は母君から委託された方であるから、
|
【斎宮女御をこそは】- 以下「譲りきこえたまひしかば」まで、源氏の詞。
【母宮も、後見と】- 大島本は「うしろミ」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「御後見」と「御」を補訂する。冷泉帝の母宮である藤壺の宮をさす。
|
| 3.1.3 |
|
と、大臣もご遺志にかこつけて主張なさる。
皇族出身から引き続き后にお立ちになることを、世間の人は賛成申し上げない。
|
自分としてはぜひこの方を推薦しなければならないという源氏の態度であった。御母后も内親王でいられたあとへ、またも王氏の后の立つことは一方に偏したことであると批難を加える者もあった。
|
【ことづけたまふ】- 『集成』は「母宮のご遺志を持ち出して主張される」と注す。
【源氏のうちしきり后にゐたまはむこと】- この場合の「源氏」は皇族出身の意。桐壺帝の藤壺の宮に引き続いて冷泉帝の前斎宮の女御の立后をいう。
|
| 3.1.4 |
|
「弘徽殿の女御が、まず誰より先に入内なさったのもどうだらろうか」
|
そうした人たちは弘徽殿の女御がだれよりも早く後宮にはいった人であるから、その人の后に昇格されるのが当然であるとも言うのである。
|
【弘徽殿の】- 以下「いかが」まで、世間の風評。斎宮女御より二年前に入内した(「絵合」巻)。
|
| 3.1.5 |
など、うちうちに、こなたかなたに心寄せきこゆる人びと、おぼつかながりきこゆ。
|
などと、内々に、こちら側あちら側につく人々は、心配申し上げている。
|
双方に味方が現われて、だれもどうなることかと不安がっていた。
|
|
| 3.1.6 |
|
兵部卿宮と申し上げた方は、今では式部卿になって、この御世となってからはいっそうご信任厚い方でいらっしゃる、その姫も、かねての望みがかなって入内なさっていた。
同様に、王の女御として伺候していらっしゃるので、
|
兵部卿の宮と申した方は今は式部卿になっておいでになって、当代の御外戚として重んぜられておいでになる宮の姫君も、予定どおりに後宮へはいって、斎宮の女御と同じ王女御で侍しているのであるが、
|
【兵部卿宮と聞こえしは、今は式部卿にて】- 藤壺の宮の兄、紫の上の父宮をさす。
【御おぼえにておはする】- 連体中止法。述語であるとともに「御むすめ」をも修飾する。
|
| 3.1.7 |
|
「同じ皇族出身なら、御母方として親しくいらっしゃる方をこそ、母后のいらっしゃらない代わりのお世話役として相応しいだろう」
|
他人でない濃い御親戚関係もあることであって、母后の御代わりとして后に立てられるのが合理的な処置であろうと、
|
【同じくは】- 以下「後見に」まで、式部卿の宮方の主張。文末は地の文に流れる表現である。
【おはすべきにこそは】- 大島本は「こそハ」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「こそ」と「は」を削除する。
|
| 3.1.8 |
|
と理由をつけて、ふさわしかるべく、それぞれ競争なさったが、やはり梅壷が立后なさった。
ご幸福が、うって変わってすぐれていらっしゃることを、世間の人は驚き申し上げる。
|
そのほうを助ける人たちは言って、三女御の競争になったのであるが、結局梅壺の前斎宮が后におなりになった。女王の幸運に世間は驚いた。
|
【似つかはしかるべく】- 大島本は「につかハしかるへく」とある。『集成』『新大系』は底本のままとする。『古典セレクション』は諸本に従って「べくと」と「と」を補訂する。
【かく引きかへすぐれたまへりけるを】- 母六条御息所の人生との比較。
|
| 3.1.9 |
|
大臣は、太政大臣にお上がりになって、大将は、内大臣におなりになった。
天下の政治をお執りになるようにお譲り申し上げなさる。
性格は、まっすぐで、威儀も正しくて、心づかいなどもしっかりしていらっしゃる。
学問をとり立てて熱心になさったので、韻塞ぎにはお負けになったが、政治では立派である。
|
源氏が太政大臣になって、右大将が内大臣になった。そして関白の仕事を源氏はこの人に譲ったのであった。この人は正義の観念の強いりっぱな政治家である。学問を深くした人であるから韻塞ぎの遊戯には負けたが公務を処理することに賢かった。
|
【大臣、太政大臣に上がりたまひて、大将、内大臣になりたまひぬ】- 源氏は太政大臣に、かつての頭中将は内大臣に昇進。
【人がら、いとすくよかに】- 以下、内大臣の性格について語る。『完訳』は「内大臣の性格。「すくよか」は剛直で意志を貫く性格。「きらきらし」は派手好みで威を張る性格」と注す。
【韻塞には負けたまひしかど】- 「賢木」巻の韻塞ぎをさす。
|
| 3.1.10 |
|
いく人もの妻妾にお子たちが十余人、いずれも大きく成長していらっしゃるが、次から次と立派になられて、負けず劣らず栄えているご一族である。
女の子は、弘徽殿の女御ともう一人いらっしゃるのであった。
皇族出身を母親として、高貴なお血筋では劣らないのであるが、その母君は、按察大納言の北の方となって、現在の夫との間に子どもの数が多くなって、「それらの子どもと一緒に継父に委ねるのは、まことに不都合なことだ」と思って、お引き離させなさって、大宮にお預け申していらっしゃるのであった。
女御よりはずっと軽くお思い申し上げていらっしゃったが、性格や、器量など、とてもかわいらしくいらっしゃるのであった。
|
幾人かの腹から生まれた子息は十人ほどあって、大人になって役人になっているのは次々に昇進するばかりであったが、女は女御のほかに一人よりない。それは親王家の姫君から生まれた人で、尊貴なことは嫡妻の子にも劣らないわけであるが、その母君が今は按察使大納言の夫人になっていて、今の良人との間に幾人かの子女が生まれている中において継父の世話を受けさせておくことはかわいそうであるといって、大臣は引き取ってわが母君の大宮に姫君をお託ししてあった。大臣は女御を愛するほどには決してこの娘を愛してはいないのであるが、性質も容貌も美しい少女であった。
|
【劣らず栄えたる御家】- 源氏に劣らずの意。
【女御と今一所】- 大島本は「いまひと所」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「今一所と」と「と」を補訂する。
【あてなる筋は劣るまじけれど】- 『完訳』は「家筋の尊さでは弘徽殿の女御に負けをとるまいけれども」と注す。
【思ひおとしきこえたまひつれど】- 大島本は「給つれと」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「たまへれど」と校訂する。
|
|
第二段 夕霧と雲居雁の幼恋
|
| 3.2.1 |
冠者の君、一つにて生ひ出でたまひしかど、おのおの十に余りたまひて後は、御方ことにて、
|
冠者の君は、同じ所でご成長なさったが、それぞれが十歳を過ぎてから後は、住む部屋を別にして、
|
そうしたわけで源氏の若君とこの人は同じ家で成長したのであるが、双方とも十歳を越えたころからは、別な場所に置かれて、
|
|
| 3.2.2 |
|
「親しい縁者ですが、男の子には気を許すものではありません」
|
どんなに親しい人でも男性には用心をしなければならぬと、
|
【むつましき人なれど、男子にはうちとくまじきものなり】- 父内大臣の雲居雁に対する訓戒。
|
| 3.2.3 |
と、父大臣聞こえたまひて、けどほくなりにたるを、幼心地に思ふことなきにしもあらねば、はかなき花紅葉につけても、雛遊びの追従をも、ねむごろにまつはれありきて、心ざしを見えきこえたまへば、いみじう思ひ交はして、けざやかには今も恥ぢきこえたまはず。 |
と、父大臣が訓戒なさって、離れて暮らすようになっていたが、子供心に慕わしく思うことなきにしもあらずなので、ちょっとした折々の花や紅葉につけても、また雛遊びのご機嫌とりにつけても、熱心にくっついてまわって、真心をお見せ申されるので、深い情愛を交わし合いなさって、きっぱりと今でも恥ずかしがりなさらない。
|
大臣は娘を訓えて睦ませないのを、若君の心に物足らぬ気持ちがあって、花や紅葉を贈ること、雛遊びの材料を提供することなどに真心を見せて、なお遊び相手である地位だけは保留していたから、姫君もこの従弟を愛して、男に顔を見せぬというような、普通の慎みなどは無視されていた。
|
【はかなき花紅葉につけても】- 以下、夕霧の雲居雁に対する動作行動。源氏の藤壺に対する行為についても、「幼心地にも、はかなき花紅葉につけても心ざしを見えたてまつる」(「桐壺」第三章五段)とあった。
|
| 3.2.4 |
御後見どもも、
|
お世話役たちも、
|
乳母などという後見役の者も、
|
|
| 3.2.5 |
「何かは、若き御心どちなれば、年ごろ見ならひたまへる御あはひを、にはかにも、いかがはもて離れはしたなめはきこえむ」 |
「何の、子どもどうしのことなので、長年親しくしていらっしゃったお間柄を、急に引き離して、どうしてきまり悪い思いをさせることができようか」
|
この少年少女には幼い日からついた習慣があるのであるから、にわかに厳格に二人の間を隔てることはできない
|
【何かは】- 以下「はしたなめきこえむ」まで、後見人たちの考え。
【はしたなめは】- 大島本は「ハしたなめは(△&は)」とある。すなわち元の文字(判読不明)の上に重ね書きして「は(者)」と訂正する。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「はしたなめ」と「は」を削除する。
|
| 3.2.6 |
|
と思っていると、女君は何の考えもなくいらっしゃるが、男君は、あんなにも子どものように見えても、だいそれたどんな仲だったのであろうか、離れ離れになってからは、逢えないことを気が気でなく思うのである。
|
と大目に見ていたが、姫君は無邪気一方であっても、少年のほうの感情は進んでいて、いつの間にか情人の関係にまで到ったらしい。東の院へ学問のために閉じこめ同様になったことは、このことがあるために若君を懊悩させた。
|
【何心なくおはすれど】- 大島本は「なに心なくおハすれと」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「何心なく幼くおはすれど」と「幼く」を補訂する。
【男は、さこそ】- 係助詞「こそ」は「見きこゆれ」已然形に係る逆接用法。
【おほけなく、いかなる御仲らひにかありけむ】- 『集成』は「あんなにお話にもならぬお年頃とお見受けしていたのに、いっぱしに、どんなお二人の仲になったことやら。すでに二人が深い仲になったことを暗示する草子地」。『完訳』は「だいそれたどんな仲だったか。二人の逢瀬を暗示する語り手の弁」と注す。
【これをぞ静心なく思ふべき】- 『集成』は「これも草子地」と注す。
|
| 3.2.7 |
まだ片生ひなる手の生ひ先うつくしきにて、書き交はしたまへる文どもの、心幼くて、おのづから落ち散る折あるを、御方の人びとは、ほのぼの知れるもありけれど、「何かは、かくこそ」と、誰にも聞こえむ。見隠しつつあるなるべし。 |
まだ未熟ながら将来の思われるかわいらしい筆跡で、書き交わしなさった手紙が、不用意さから、自然と落としているときもあるのを、姫君の女房たちは、うすうす知っている者もいたのだが、「どうして、こんな関係である」と、どなたに申し上げられようか。
知っていながら隠しているのであろう。
|
まだ子供らしい、そして未来の上達の思われる字で、二人の恋人が書きかわしている手紙が、幼稚な人たちのすることであるから、抜け目があって、そこらに落ち散らされてもあるのを、姫君付きの女房が見て、二人の交情がどの程度にまでなっているかを合点する者もあったが、そんなことは人に訴えてよいことでもないから、だれも秘密はそっとそのまま秘密にしておいた。
|
【御方の人びと】- 雲居雁方の女房。
【何かは、かくこそ」と】- 以下「あるなるべし」まで、語り手の推測として語る。
|
|
第三段 内大臣、大宮邸に参上
|
| 3.3.1 |
|
あちらとこちらの新任の大饗の宴が終わって、朝廷の御用もなく、のんびりとしていたころ、時雨がさあっと降って、荻の上風もしみじみと感じられる夕暮に、大宮のお部屋に、内大臣が参上なさって、姫君をそこへお呼びになって、お琴などをお弾かせなさる。
大宮は、何事も上手でいらっしゃるので、それらをみなお教えになる。
|
后の宮、両大臣家の大饗宴なども済んで、ほかの催し事が続いて仕度されねばならぬということもなくて、世間の静かなころ、秋の通り雨が過ぎて、荻の上風も寂しい日の夕方に、大宮のお住居へ内大臣が御訪問に来た。大臣は姫君を宮のお居間に呼んで琴などを弾かせていた。宮はいろいろな芸のおできになる方で、姫君にもよく教えておありになった。
|
【所々の大饗どもも果てて】- 源氏と内大臣のそれぞれの昇進の大饗をさす。
【時雨うちして、荻の上風もただならぬ夕暮に】- 『源氏釈』は「秋はなほ夕まぐれこそただならね荻の上風萩の下露」(義孝集・和漢朗詠集)を引歌として指摘。
|
| 3.3.2 |
|
「琵琶は、女性が弾くには見にくいようだが、いかにも達者な感じがするものです。
今の世に、正しく弾き伝えている人は、めったにいなくなってしまいました。
何々親王、何々の源氏とか」
|
「琵琶は女が弾くとちょっと反感も起こりますが、しかし貴族的なよいものですね。今日はごまかしでなくほんとうに琵琶の弾けるという人はあまりなくなりました。何親王、何の源氏」
|
【琵琶こそ、女のしたるに憎きやうなれど】- 以下「何の親王くれの源氏」まで、内大臣の詞。宇津保物語に「琵琶なむ、さるは女のせむにうたて憎げなる姿したるものなる」(初秋巻)とある。
【何の親王、くれの源氏】- 何々親王、何々源氏の意。間接話法が混じる。
|
| 3.3.3 |
など数へたまひて、
|
などとお数えになって、
|
などと大臣は数えたあとで、
|
|
| 3.3.4 |
|
「女性の中では、太政大臣が山里に隠しおいていらっしゃる人が、たいそう上手だと聞いております。
音楽の名人の血筋ではありますが、子孫の代になって、田舎生活を長年していた人が、どうしてそのように上手に弾けたのでしょう。
あの大臣が、ことの他上手な人だと思っておっしゃったことがありました。
他の芸とは違って、音楽の才能はやはり広くいろんな人と合奏をし、あれこれの楽器に調べを合わせてこそ、立派になるものですが、独りで学んで、上手になったというのは珍しいことです」
|
「女では太政大臣が嵯峨の山荘に置いておく人というのが非常に巧いそうですね。さかのぼって申せば音楽の天才の出た家筋ですが、京官から落伍して地方にまで行った男の娘に、どうしてそんな上手が出て来たのでしょう。源氏の大臣はよほど感心していられると見えて、何かのおりにはよくその人の話をせられます。ほかの芸と音楽は少し性質が変わっていて、多く聞き、多くの人と合わせてもらうことでずっと進歩するものですが、独習をしていて、その域に達したというのは珍しいことです」
|
【女の中には】- 以下「珍しきことなれ」まで、内大臣の詞。
【山里に籠め置きたまへる人】- 大堰山荘の明石御方をさす。
【上手の後にはべれど】- 大島本は「上すのゝちに侍れと」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「後にははべれど」と「は」を補訂する。
【末になりて】- 『完訳』は「伝授の末流と家運の衰え、の両意を含める」と注す。
【通はしはべるこそ、かしこけれ】- 係助詞「こそ」--「かしこけれ」係結び、逆接用法。
|
| 3.3.5 |
などのたまひて、宮にそそのかしきこえたまへば、
|
などとおっしゃって、大宮にお促し申し上げになると、
|
こんな話もしたが、大臣は宮にお弾きになることをお奨めした。
|
|
| 3.3.6 |
|
「柱を押さえることが久しぶりになってしまいました」
|
「もう絃を押すことなどが思うようにできなくなりましたよ」
|
【柱さすことうひうひしくなりにけりや】- 大宮の詞。
|
| 3.3.7 |
とのたまへど、おもしろう弾きたまふ。
|
とおっしゃったが、美しくお弾きになる。
|
とお言いになりながらも、宮は上手に琴をお弾きになった。
|
|
| 3.3.8 |
|
「ご幸運な上に、さらにやはり不思議なほど立派な方なのですね。
お年をとられた今までに、お持ちでなかった女の子をお生み申されて、側に置いてみすぼらしくするでなく、れっきとしたお方にお預けした考えは、申し分のない人だと聞いております」
|
「その山荘の人というのは、幸福な人であるばかりでなく、すぐれた聡明な人らしいですね。私に預けてくだすったのは男の子一人であの方の女の子もできていたらどんなによかったろうと思う女の子をその人は生んで、しかも自分がつれていては子供の不幸になることをよく理解して、りっぱな奥さんのほうへその子を渡したことなどを、感心なものだと私も話に聞きました」
|
【幸ひにうち添へて】- 以下「聞きはべる」まで、大宮の詞。
【老いの世に、持たまへらぬ女子を】- 源氏についていう。
【やむごとなきに譲れる心おきて】- 明石姫君を紫の上の養女にしたことをいう。「薄雲」巻に語られている。
|
| 3.3.9 |
など、かつ御物語聞こえたまふ。
|
などと、一方ではお話し申し上げなさる。
|
こんな話を大宮はあそばした。
|
|
|
第四段 弘徽殿女御の失意
|
| 3.4.1 |
|
「女性はただ心がけによって、世間から重んじられるものでございますね」
|
「女は頭のよさでどんなにも出世ができるものですよ」
|
【女はただ心ばせよりこそ、世に用ゐらるるものにはべりけれ】- 内大臣の詞。『集成』は「心がけのいかんによって」。『完訳』は「気立てしだいで」と訳す。
|
| 3.4.2 |
など、人の上のたまひ出でて、
|
などと、他人の身の上についてお話し出されて、
|
などと内大臣は人の批評をしていたのであるが、それが自家の不幸な話に移っていった。
|
|
| 3.4.3 |
|
「弘徽殿の女御を、悪くはなく、どんなことでも他人には負けまいと存じておりましたが、思いがけない人に負けてしまった運命に、この世は案に相違したものだと存じました。
せめてこの姫君だけは、何とか思うようにしたいものです。
東宮の御元服は、もうすぐのことになったと、ひそかに期待していたのですが、あのような幸福者から生まれたお后候補者が、また後から追いついてきました。
入内なさったら、まして対抗できる人はいないのではないでしょうか」
|
「私は女御を完全でなくても、どんなことも人より劣るような娘には育て上げなかったつもりなんですが、意外な人に負ける運命を持っていたのですね。人生はこんなに予期にはずれるものかと私は悲観的になりました。この子だけでも私は思うような幸運をになわせたい、東宮の御元服はもうそのうちのことであろうかと、心中ではその希望を持っていたのですが、今のお話の明石の幸運女が生んだお后の候補者があとからずんずん生長してくるのですからね。その人が後宮へはいったら、ましてだれが競争できますか」
|
【女御を、けしうはあらず】- 以下「人ありがたくや」まで、内大臣の詞。
【思はぬ人におされぬる宿世に】- 娘の弘徽殿女御が斎宮女御に立后で負けたことをさす。
【この君をだに】- 雲居雁をさす。
【幸ひ人の腹の后がね】- 明石の君が生んだ姫君をさす。
【追ひ次ぎぬれ】- 大島本は「をひすき」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「おひすがひ」と校訂する。
|
| 3.4.4 |
とうち嘆きたまへば、
|
とお嘆きになると、
|
大臣が歎息するのを宮は御覧になって、
|
|
| 3.4.5 |
|
「どうして、そのようなことがありましょうか。
この家にもそのような人がいないで終わってしまうようなことはあるまいと、亡くなった大臣が思っていらっしゃって、女御の御ことも、熱心に奔走なさったのでしたが。
生きていらっしゃったならば、このように筋道の通らぬこともなかったでしょうに」
|
「必ずしもそうとは言われませんよ。この家からお后の出ないようなことは絶対にないと私は思う。そのおつもりで亡くなられた大臣も女御の世話を引き受けて皆なすったのだものね。大臣がおいでになったらこんな意外な結果は見なかったでしょう」
|
【などか、さしもあらむ】- 以下「こともなからまし」まで、大宮の詞。
【さる筋の人】- 后に立つような人の意。
【もてひがむることもなからまし】- 「まし」反実仮想の助動詞。『集成』は「こんな間違ったこともなかったでしょう」。『完訳』は「このような筋道の通らぬこともなかったでしょう」と訳す。
|
| 3.4.6 |
|
などと、あの一件では、太政大臣を恨めしくお思い申し上げていらっしゃった。
|
この問題でだけ大宮は源氏を恨んでおいでになった。
|
【この御ことにてぞ】- 立后の件。
【太政大臣をも恨めしげに思ひきこえたまへる】- 大宮が源氏を。
|
| 3.4.7 |
姫君の御さまの、いときびはにうつくしうて、箏の御琴弾きたまふを、御髪のさがり、髪ざしなどの、あてになまめかしきをうちまもりたまへば、恥ぢらひて、すこしそばみたまへるかたはらめ、つらつきうつくしげにて、取由の手つき、いみじう作りたる物の心地するを、宮も限りなくかなしと思したり。掻きあはせなど弾きすさびたまひて、押しやりたまひつ。 |
姫君のご様子が、とても子どもっぽくかわいらしくて、箏のお琴をお弾きになっていらっしゃるが、お髪の下り端、髪の具合などが、上品で艶々としてしているのをじっと見ていらっしゃると、恥ずかしく思って、少し横をお向きになった横顔、その恰好がかわいらしげで、取由の手つきが、非常にじょうずに作った人形のような感じがするので、大宮もこの上なくかわいいと思っていらっしゃった。
調子合わせのための小曲などを軽くお弾きになって、押しやりなさった。
|
姫君がこぢんまりとした美しいふうで、十三絃の琴を弾いている髪つき、顔と髪の接触点の美などの艶な上品さに大臣がじっと見入っているのを姫君が知って、恥ずかしそうにからだを少し小さくしている横顔がきれいで、絃を押す手つきなどの美しいのも絵に描いたように思われるのを、大宮も非常にかわいく思召されるふうであった。姫君はちょっと掻き合わせをした程度で弾きやめて琴を前のほうへ押し出した。
|
【うちまもりたまへば】- 父内大臣が娘の雲居雁を。
【恥ぢらひて、すこしそばみたまへるかたはらめ】- 雲居雁の態度をいう。
【取由の手つき】- 左手で絃を揺する技法。
|
|
第五段 夕霧、内大臣と対面
|
| 3.5.1 |
大臣、和琴ひき寄せたまひて、律の調べのなかなか今めきたるを、さる上手の乱れて掻い弾きたまへる、いとおもしろし。
御前の梢ほろほろと残らぬに、老い御達など、ここかしこの御几帳のうしろに、かしらを集へたり。
|
内大臣は、和琴を引き寄せなさって、律調のかえって今風なのを、その方面の名人がうちとけてお弾きになっているのは、たいそう興趣がある。
御前のお庭の木の葉がほろほろと落ちきって、老女房たちが、あちらこちらの御几帳の後に、集まって聞いていた。
|
内大臣は大和琴を引き寄せて、律の調子の曲のかえって若々しい気のするものを、名手であるこの人が、粗弾きに弾き出したのが非常におもしろく聞こえた。外では木の葉がほろほろとこぼれている時、老いた女房などは涙を落としながらあちらこちらの几帳の蔭などに幾人かずつ集まってこの音楽に聞き入っていた。
|
|
| 3.5.2 |
|
「風の力がおよそ弱い」
|
「風の力蓋し少なし」(落葉俟二微飈一以隕らくえふびふうをまつてもつておつ、而風之力蓋寡、孟嘗遭二雍門一而泣まうしやうがようもんにあひてなく、琴之感以末。)
|
【風の力蓋し寡し】- 内大臣の朗誦。「落葉、微風を俟ちて隕つ。而も風の力、蓋し寡し。孟嘗め、雍門に遭うて泣く。而も琴の感、已に未し」(文選、豪士賦)の一節。
|
| 3.5.3 |
と、うち誦じたまひて、
|
と、朗誦なさって、
|
と文選の句を大臣は口ずさんで、
|
|
| 3.5.4 |
|
「琴のせいではないが、不思議としみじみとした夕べですね。
もっと、弾きましょうよ」
|
「琴の感じではないが身にしむ夕方ですね。もう少しお弾きになりませんか」
|
【琴の感ならねど】- 以下「なほあそばさむや」まで、内大臣の詞。「琴の感」は前の『文選』の句を踏まえた表現。
|
| 3.5.5 |
|
とおっしゃって、「秋風楽」に調子を整えて、唱歌なさる声、とても素晴らしいので、みなそれぞれに、内大臣をも見事であるとお思い申し上げになっていらっしゃると、それをいっそう喜ばせようというのであろうか、冠者の君が参上なさった。
|
と大臣は大宮にお勧めして、秋風楽を弾きながら歌う声もよかった。宮はこの座の人は御孫女ばかりでなく、大きな大臣までもかわいく思召された。そこへいっそうの御満足を加えるように源氏の若君が来た。
|
【大臣をもいとうつくしと思ひきこえたまふに】- 主語は大宮。係助詞「も」は同類を表し、孫の雲居雁と同様に息子の内大臣もの意。
【いとど添へむとにやあらむ】- 挿入句。語り手の推測を交えた表現。
|
| 3.5.6 |
|
「こちらに」とおっしゃって、御几帳を隔ててお入れ申し上げになった。
|
「こちらへ」と宮はお言いになって、お居間の中の几帳を隔てた席へ若君は通された。
|
【御几帳隔てて入れたてまつり】- 雲居雁との間に。
|
| 3.5.7 |
|
「あまりお目にかかれませんね。
どうしてこう、このご学問に打ち込んでいらっしゃるのでしょう。
学問が身分以上になるのもよくないことだと、大臣もご存知のはずですが、こうもお命じ申し上げなさるのは、考える子細もあるのだろうと存じますが、こんなに籠もってばかりいらっしゃるのは、お気の毒でございます」
|
「あなたにはあまり逢いませんね。なぜそんなにむきになって学問ばかりをおさせになるのだろう。あまり学問のできすぎることは不幸を招くことだと大臣も御体験なすったことなのだけれど、あなたをまたそうおしつけになるのだね、わけのあることでしょうが、ただそんなふうに閉じ込められていてあなたがかわいそうでならない」
|
【をさをさ対面もえ賜はらぬかな】- 以下「心苦しうはべる」まで、内大臣の詞。
【あまり過ぎぬるも】- 大島本は「あまりすきぬるも」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「あまりぬるも」と「すき」を削除する。
|
| 3.5.8 |
と聞こえたまひて、
|
と申し上げなさって、
|
と内大臣は言った。
|
|
| 3.5.9 |
「時々は、ことわざしたまへ。笛の音にも古事は、伝はるものなり」 |
「時々は、別のことをなさい。
笛の音色にも昔の聖賢の教えは、伝わっているものです」
|
「時々は違ったこともしてごらんなさい。笛だって古い歴史を持った音楽で、いいものなのですよ」
|
【時々は】- 以下「伝はるものなり」まで、内大臣の詞。
|
| 3.5.10 |
とて、御笛たてまつりたまふ。
|
とおっしゃって、
|
内大臣はこう言いながら笛を若君へ渡した。
|
|
| 3.5.11 |
いと若うをかしげなる音に吹きたてて、いみじうおもしろければ、御琴どもをばしばし止めて、大臣、拍子おどろおどろしからずうち鳴らしたまひて、
|
たいそう若々しく美しい音色を吹いて、大変に興がわいたので、お琴はしばらく弾きやめて、大臣が、拍子をおおげさではなく軽くお打ちになって、
|
若々しく朗らかな音を吹き立てる笛がおもしろいためにしばらく絃楽のほうはやめさせて、大臣はぎょうさんなふうでなく拍子を取りながら、
|
|
| 3.5.12 |
|
「萩の花で摺った」
|
「萩が花ずり」
|
【萩が花摺り」--など歌ひたまふ】- 「更衣せむやさきむだちやわが衣は野原篠原萩の花摺りやさきむだちや」(催馬楽、更衣)。『花鳥余情』は、夕霧の六位の浅葱の衣が早く昇進して色が改まるようにという気持ちをこめて歌ったものと説く。
|
| 3.5.13 |
|
などとお歌いになる。
|
(衣がへせんや、わが衣は野原篠原萩の花ずり)など歌っていた。
|
|
| 3.5.14 |
「大殿も、かやうの御遊びに心止めたまひて、いそがしき御政事どもをば逃れたまふなりけり。げに、あぢきなき世に、心のゆくわざをしてこそ、過ぐしはべりなまほしけれ」 |
「大殿も、このような管弦の遊びにご熱心で、忙しいご政務からはお逃げになるのでした。
なるほど、つまらない人生ですから、満足のゆくことをして、過ごしたいものでございますね」
|
「太政大臣も音楽などという芸術がお好きで、政治のほうのことからお脱けになったのですよ。人生などというものは、せめて好きな楽しみでもして暮らしてしまいたい」
|
【大殿も】- 以下「過ぐしはべりなまほしけれ」まで、内大臣の詞。
|
| 3.5.15 |
などのたまひて、御土器参りたまふに、暗うなれば、御殿油参り、御湯漬、くだものなど、誰も誰もきこしめす。
|
などとおっしゃって、お杯をお勧めなさっているうちに、暗くなったので、燈火をつけて、お湯漬や果物などを、どなたもお召し上がりになる。
|
と言いながら甥に杯を勧めなどしているうちに暗くなったので灯が運ばれ、湯漬け、菓子などが皆の前へ出て食事が始まった。
|
|
| 3.5.16 |
姫君はあなたに渡したてまつりたまひつ。しひて気遠くもてなしたまひ、「御琴の音ばかりをも聞かせたてまつらじ」と、今はこよなく隔てきこえたまふを、 |
姫君はあちらの部屋に引き取らせなさった。
つとめて二人の間を遠ざけなさって、「お琴の音だけもお聞かせしないように」と、今ではすっかりお引き離し申していらっしゃるのを、
|
姫君はもうあちらへ帰してしまったのである。しいて二人を隔てて、琴の音すらも若君に聞かせまいとする内大臣の態度を、大宮の古女房たちはささやき合って、
|
【御琴の音ばかりをも】- 雲居雁の琴の音を夕霧にの意。
|
| 3.5.17 |
|
「お気の毒なことが起こりそうなお仲だ」
|
「こんなことで近いうちに悲劇の起こる気がします」
|
【いとほしきことありぬべき世なるこそ】- 『集成』は「困ったことが起りそうな二人の仲だこと。二人の仲がいずれ大臣に知れるであろうと危懼する」と注す。
|
| 3.5.18 |
と、近う仕うまつる大宮の御方のねび人ども、ささめきけり。
|
と、お側近くお仕え申している大宮づきの年輩の女房たちは、ひそひそ話しているのであった。
|
とも言っていた。
|
|
|
第六段 内大臣、雲居雁の噂を立ち聞く
|
| 3.6.1 |
|
内大臣はお帰りになったふうにして、こっそりと女房を相手なさろうと座をお立ちになったのだが、そっと身を細めてお帰りになる途中で、このようなひそひそ話をしているので、妙にお思いになって、お耳をとめなさると、ご自分の噂をしている。
|
大臣は帰って行くふうだけを見せて、情人である女の部屋にはいっていたが、そっとからだを細くして廊下を出て行く間に、少年たちの恋を問題にして語る女房たちの部屋があった。不思議に思って立ち止まって聞くと、それは自身が批評されているのであった。
|
【大臣出でたまひぬるやうにて】- 『完訳』は「邸から出たように見せかける。密かに召人に逢うためである」と注す。
【やをらかい細りて出でたまふ道に】- 『集成』は「そっと小さくなって女の部屋からお帰りになる途中で」と訳す。
|
| 3.6.2 |
「かしこがりたまへど、人の親よ。おのづから、おれたることこそ出で来べかめれ」 |
「えらそうにしていらっしゃるが、人の親ですよ。
いずれ、ばかばかしく後悔することが起こるでしょう」
|
「賢がっていらっしゃっても甘いのが親ですね。とんだことが知らぬ間に起こっているのですがね。
|
【かしこがりたまへど】- 以下「虚言なめり」まで、女房の詞。
|
| 3.6.3 |
|
「子を知っているのは親だというのは、嘘のようですね」
|
子を知るは親にしかずなどというのは嘘ですよ」
|
【子を知るといふは】- 大島本は「子をしるといふハ」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「子を知るはといふは」と「は」を補訂する。「明君は臣を知り、明父は子を知る」(史記、李斯伝)「子を知るは親に如くものはなし」(日本書紀、雄略紀二十三年)などがある。
|
| 3.6.4 |
|
などと、こそこそと噂し合う。
|
などこそこそと言っていた。
|
【つきしろふ】- 『集成』は「つつき合っている」。『完訳』は「こそこそと陰口をたたいている」と訳す。
|
| 3.6.5 |
「あさましくもあるかな。さればよ。思ひ寄らぬことにはあらねど、いはけなきほどにうちたゆみて。世は憂きものにもありけるかな」 |
「あきれたことだ。
やはりそうであったのか。
思いよらないことではなかったが、子供だと思って油断しているうちに。
世の中は何といやなものであるな」
|
情けない、自分の恐れていたことが事実になった。打っちゃって置いたのではないが、子供だから油断をしたのだ。人生は悲しいものであると大臣は思った。
|
【あさましくもあるかな】- 以下「世は憂きものにもありけるかな」まで、内大臣の心中。『集成』は「周章する内大臣の心中」。『完訳』は「事の意外さに動転する心中叙述」と注す。
|
| 3.6.6 |
と、けしきをつぶつぶと心得たまへど、音もせで出でたまひぬ。
|
と、ことの子細をつぶさに了解なさったが、音も立てずにお出になった。
|
すべてを大臣は明らかに悟ったのであるが、そっとそのまま出てしまった。
|
|
| 3.6.7 |
御前駆追ふ声のいかめしきにぞ、
|
前駆の先を払う声が盛んに聞こえるので、
|
前駆がたてる人払いの声のぎょうさんなのに、はじめて女房たちはこの時間までも大臣がここに留まっていたことを知ったのである。
|
|
| 3.6.8 |
|
「殿は、今お帰りあそばしたのだわ」
|
「殿様は今お帰りになるではありませんか。
|
【殿は、今こそ】- 以下「かかる御あだけこそ」まで、女房たちの詞。
|
| 3.6.9 |
「いづれの隈におはしましつらむ」
|
「どこに隠れていらっしゃったのかしら」
|
どこの隅にはいっておいでになったのでしょう。
|
|
| 3.6.10 |
|
「今でもこんな浮気をなさるとは」
|
あのお年になって浮気はおやめにならない方ね」
|
【あだけこそ】- 大島本は「あたけ」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「御あだけ」と「御」を補訂する。
|
| 3.6.11 |
と言ひあへり。
ささめき言の人びとは、
|
と言い合っている。
ひそひそ話をした女房たちは、
|
と女房らは言っていた。内証話をしていた人たちは困っていた。
|
|
| 3.6.12 |
|
「とても香ばしい匂いがしてきたのは、冠者の君がいらっしゃるのだとばかり思っていましたわ」
|
「あの時非常にいいにおいが私らのそばを通ったと思いましたがね、若君がお通りになるのだとばかり思っていましたよ。
|
【いとかうばしき香の】- 以下「わづらはしき御心を」まで、女房たちの詞。
【おはしつるとこそ】- 大島本は「おハしつる」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「おはしましつる」と「まし」を補訂する。
|
| 3.6.13 |
「あな、むくつけや。
しりう言や、ほの聞こしめしつらむ。
わづらはしき御心を」
|
「まあ、いやだわ。
陰口をお聞きになったかしら。
厄介なご気性だから」
|
まあこわい、悪口がお耳にはいらなかったでしょうか。意地悪をなさらないとも限りませんね」
|
|
| 3.6.14 |
と、わびあへり。
|
と、皆困り合っていた。
|
|
|
| 3.6.15 |
殿は、道すがら思すに、
|
殿は、道中お考えになることに、
|
内大臣は車中で娘の恋愛のことばかりが考えられた。
|
|
| 3.6.16 |
|
「まったく問題にならない悪いことではないが、ありふれた親戚どうしの結婚で、世間の人もきっとそう取り沙汰するに違いないことだ。
大臣が、強引に女御を抑えなさっているのも癪なのに、ひょっとして、この姫君が相手に勝てることがあろうかも知れないと思っていたが、くやしいことだ」
|
非常に悪いことではないが、従弟どうしの結婚などはあまりにありふれたことすぎるし、野合の初めを世間の噂に上されることもつらい。後宮の競争に女御をおさえた源氏が恨めしい上に、また自分はその失敗に代えてあの娘を東宮へと志していたのではないか、僥倖があるいはそこにあるかもしれぬと、
|
【いと口惜しく】- 以下「ねたくもあるかな」まで、内大臣の心中。
【めづらしげなきあはひに】- 『集成』は「ありふれた親戚同士の結婚だと」と訳す。『完訳』は「臣下との結婚では物足りない」と注す。
【人にまさることもやと】- 『集成』は「雲居の雁を東宮に入内させれば、やがて立后もあろうかと期待していたのに」と注す。
【こそ思ひつれ】- 係助詞「こそ」--「つれ」已然形の係結び。逆接用法。
|
| 3.6.17 |
と思す。殿の御仲の、おほかたには昔も今もいとよくおはしながら、かやうの方にては、挑みきこえたまひし名残も思し出でて、心憂ければ、寝覚がちにて明かしたまふ。 |
とお思いになる。
殿どうしのお仲は、普通のことでは昔も今もたいそう仲よくいらっしゃりながら、このような方面では、競争申されたこともお思い出しになって、おもしろくないので、寝覚めがちに夜をお明かしになる。
|
ただ一つの慰めだったこともこわされたと思うのであった。源氏と大臣との交情は睦まじく行っているのであるが、昔もその傾向があったように、負けたくない心が断然強くて、大臣はそのことが不快であるために朝まで安眠もできなかった。
|
【かやうの方にては】- 『完訳』は「権勢を張り合うという方面」と注す。
|
| 3.6.18 |
「大宮をも、さやうのけしきには御覧ずらむものを、世になくかなしくしたまふ御孫にて、まかせて見たまふならむ」 |
「大宮だって、そのような様子は御存じであろうに、たいへんにかわいがっていらっしゃるお孫たちなので、好きなようにさせていらっしゃるのだろう」
|
大宮も様子を悟っておいでになるであろうが、非常におかわいくお思いになる孫であるから勝手なことをさせて、見ぬ顔をしておいでになるのであろう
|
【大宮をも】- 以下「見たまふならむ」まで、内大臣の心中。
【けしきには】- 大島本は「けしきには」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「けしきは」と「に」を削除する。
|
| 3.6.19 |
|
と、女房たちが言っていた様子を、いまいましいとお思いになると、お心が穏やかでなくなって、少し男らしく事をはっきりさせたがるご気性にとっては、抑えがたい。
|
と女房たちの言っていた点で、大臣は大宮を恨めしがっていた。腹がたつとそれを内におさえることのできない性質で大臣はあった。
|
【ねたしと思すに】- 大島本は「ねたしとおほすに」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「めざましうねたしとおぼすに」と「めざましう」を補訂する。
【すこし男々しくあざやぎたる御心には、静めがたし】- 『完訳』は「勝気で物事にはっきり決着をつけたがる性分。内大臣の性格として特徴的」と注す。
|
|
第四章 内大臣家の物語 雲居雁の養育をめぐる物語
|
|
第一段 内大臣、母大宮の養育を恨む
|
| 4.1.1 |
|
二日ほどして、参上なさった。
頻繁に参上なさる時は、大宮もとてもご満足され、嬉しく思っておいであった。
尼削ぎの御髪に手入れをなさって、きちんとした小袿などをお召し添えになって、わが子ながら気づまりなほど立派なお方なので、直接顔を合わせずにお会いなさる。
|
二日ほどしてまた内大臣は大宮を御訪問した。こんなふうにしきりに出て来る時は宮の御機嫌がよくて、おうれしい御様子がうかがわれた。形式は尼になっておいでになる方であるが、髪で額を隠して、お化粧もきれいにあそばされ、はなやかな小袿などにもお召しかえになる。子ながらも晴れがましくお思われになる大臣で、ありのままのお姿ではお逢いにならないのである。
|
【二日ばかりありて、参りたまへり】- 内大臣が大宮邸に。
【子ながら恥づかしげにおはする御人ざま】- 大宮の子ながら気がひけるほど立派な人、すなわち内大臣をいう。
【まほならずぞ見えたてまつりたまふ】- 『集成』は「うちとけてまともに顔を合わすようなことをせず、横顔を向けながら話すのであろう」。『完訳』は「じかには顔を見合せない、半ば物越しの対面」と注す。
|
| 4.1.2 |
大臣御けしき悪しくて、
|
大臣は御機嫌が悪くて、
|
内大臣は不機嫌な顔をしていた。
|
|
| 4.1.3 |
「ここにさぶらふもはしたなく、人びといかに見はべらむと、心置かれにたり。はかばかしき身にはべらねど、世にはべらむ限り、御目離れず御覧ぜられ、おぼつかなき隔てなくとこそ思ひたまふれ。 |
「こちらにお伺いするのも体裁悪く、女房たちがどのように見ていますかと、気がひけてしまいます。
たいした者ではありませんが、世に生きていますうちは、常にお目にかからせていただき、ご心配をかけることのないようにと存じております。
|
「こちらへ上がっておりましても私は恥ずかしい気がいたしまして、女房たちはどう批評をしていることだろうかと心が置かれます。つまらない私ですが、生きておりますうちは始終伺って、物足りない思いをおさせせず、
|
【ここにさぶらふも】- 以下「おぼえはべりてなむ」まで、内大臣の詞。
【心置かれにたり】- 『集成』は「不快に思っております」。『完訳』は「気がひけてしまいます」と訳す。
|
| 4.1.4 |
よからぬもののうへにて、恨めしと思ひきこえさせつべきことの出でまうで来たるを、かうも思うたまへじとかつは思ひたまふれど、なほ静めがたくおぼえはべりてなむ」 |
不心得者のことで、お恨み申さずにはいられないようなことが起こってまいりましたが、こんなにはお恨み申すまいと一方では存じながらも、やはり抑えがたく存じられまして」
|
私もその点で満足を得たいと思ったのですが、不良な娘のためにあなた様をお恨めしく思わずにいられませんようなことができてまいりました。そんなに真剣にお恨みすべきでないと、自分ながらも心をおさえようとするのでございますが、それができませんで」
|
【よからぬもののうへにて】- 雲居雁をさす。
|
| 4.1.5 |
と、涙おし拭ひたまふに、宮、化粧じたまへる御顔の色違ひて、御目も大きになりぬ。
|
と、涙をお拭いなさるので、大宮は、お化粧なさっていた顔色も変わって、お目を大きく見張られた。
|
大臣が涙を押しぬぐうのを御覧になって、お化粧あそばした宮のお顔の色が変わった。涙のために白粉が落ちてお目も大きくなった。
|
|
| 4.1.6 |
「いかやうなることにてか、今さらの齢の末に、心置きては思さるらむ」 |
「どうしたことで、こんな年寄を、お恨みなさるのでしょうか」
|
「どんなことがあって、この年になってからあなたに恨まれたりするのだろう」
|
【いかやうなることにてか】- 以下「思さるらむ」まで、大宮の詞。
|
| 4.1.7 |
と聞こえたまふも、さすがにいとほしけれど、
|
と申し上げなさるのも、今さらながらお気の毒であるが、
|
と宮の仰せられるのを聞くと、さすがにお気の毒な気のする大臣であったが続いて言った。
|
|
| 4.1.8 |
|
「ご信頼申していたお方に、幼い子どもをお預け申して、自分ではかえって幼い時から何のお世話も致さずに、まずは身近にいた姫君の、宮仕えなどが思うようにいかないのを、心配しながら奔走しいしい、それでもこの姫君を一人前にしてくださるものと信頼しておりましたのに、意外なことがございましたので、とても残念です。
|
「御信頼しているものですから、子供をお預けしまして、親である私はかえって何の世話もいたしませんで、手もとに置きました娘の後宮のはげしい競争に敗惨の姿になって、疲れてしまっております方のことばかりを心配して世話をやいておりまして、こちらに御厄介になります以上は、私がそんなふうに捨てて置きましても、あなた様は彼を一人並みの女にしてくださいますことと期待していたのですが、意外なことになりましたから、私は残念なのです。
|
【頼もしき御蔭に】- 以下「心憂く思うたまふる」まで、内大臣の詞。
【さりとも人となさせたまひてむと】- 大宮が雲居雁を。
【思はずなることのはべりければ】- 夕霧と雲居雁とが恋仲であることをいう。
|
| 4.1.9 |
|
ほんとうに天下に並ぶ者のない優れた方のようですが、近しい者どうしが結婚するのは、人の外聞も浅薄な感じが、たいした身分でもないものどうしの縁組でさえ考えますのに、あちらの方のためにも、たいそう不体裁なことです。
他人で、豪勢な初めての関係の家で、派手に大切にされるのこそ、よいものです。
縁者どうしの、馴れ合いの結婚なので、大臣も不快にお思いになることがあるでしょう。
|
源氏の大臣は天下の第一人者といわれるりっぱな方ではありますがほとんど家の中どうしのような者のいっしょになりますことは、人に聞こえましても軽率に思われることです。低い身分の人たちの中でも、そんなことは世間へはばかってさせないものです。それはあの人のためにもよいことでは決してありません。全然離れた家へはなやかに婿として迎えられることがどれだけ幸福だかしれません。従姉の縁で強いた結婚だというように取られて、源氏の大臣も不快にお思いになるかもしれませんよ。
|
【かの人の御ためにも】- 夕霧をさす。
【さし離れ、きらきらしうめづらしげあるあたりに、今めかしうもてなさるるこそ、をかしけれ】- 内大臣の結婚観。『集成』は「世に時めいていて、今まで縁のなかった一族に、はなやかな婿扱いをされてこそ、晴れがましいものです。政治家として派閥を拡大したことになる」と注す。
【大臣も聞き思すところはべりなむ】- 「大臣」は源氏をさす。「思す」は不快に思う意。
|
| 4.1.10 |
|
それはそれとしても、これこれしかじかですと、わたしにお知らせくださって、特別なお扱いをして、少し世間でも関心を寄せるような趣向を取り入れたいものです。
若い者どうしの思いのままに放って置かれたのが、心外に思われるのです」
|
それにしましてもそのことを私へお知らせくださいましたら、私はまた計らいようがあるというものです。ある形式を踏ませて、少しは人聞きをよくしてやることもできたでしょうが、あなた様が、ただ年若な者のする放縦な行動そのままにお捨て置きになりましたことを私は遺憾に思うのです」
|
【すこしゆかしげあることをまぜてこそはべらめ】- 『集成』は「婿として改まった扱いをし、多少とも世間からさすがだと思われるようなことを加えるのがよいと存じます。家柄にふさわしい婚儀を挙げるべきだという意」と注す。
【心憂く思うたまふ」--など】- 大島本は「思ふ給ふ」とある。『集成』『新大系』『古典セレクション』は諸本に従って「たまふる」と「る」を補訂する。ただ『古典セレクション』は「な(奈)」を「る(留)」の誤写と見たものか、「と聞こえたまふに」と整定する。
|
| 4.1.11 |
など聞こえたまふに、夢にも知りたまはぬことなれば、あさましう思して、 |
と申し上げなさると、夢にも御存知なかったことなので、驚きあきれなさって、
|
くわしく大臣が言うことによって、はじめて真相をお悟りになった宮は、夢にもお思いにならないことであったから、あきれておしまいになった。
|
|
| 4.1.12 |
|
「なるほど、そうおっしゃるのもごもっともなことですが、ぜんぜんこの二人の気持ちを存じませんでした。
なるほど、とても残念なことは、こちらこそあなた以上に嘆きたいくらいです。
子どもたちと一緒にわたしを非難なさるのは、恨めしいことです。
|
「あなたがそうお言いになるのはもっともだけれど、私はまったく二人の孫が何を思って、何をしているかを知りませんでした。私こそ残念でなりませんのに、同じように罪を私が負わせられるとは恨めしいことです。
|
【げに、かうのたまふも】- 以下「人の御名や汚れむ」まで、大宮の詞。
【げに、いと口惜しきことは、ここにこそまして嘆くべくはべれ】- 『完訳』は「内大臣の「いと口惜しうなん」を受けて、「げに」と納得。自分(大宮)こそ。彼女も雲居雁の入内を諦めない」と注す。
|
| 4.1.13 |
|
お世話致してから、特別にかわいく思いまして、あなたがお気づきにならないことも、立派にしてやろうと、内々に考えていたのでしたよ。
まだ年端もゆかないうちに、親心の盲目から、急いで結婚させようとは考えもしないことです。
|
私は手もとへ来た時から、特別にかわいくて、あなたがそれほどにしようとお思いにならないほど大事にして、私はあの人に女の最高の幸福を受けうる価値もつけようとしてました。一方の孫を溺愛して、ああしたまだ少年の者に結婚を許そうなどとは思いもよらぬことです。
|
【そこに思しいたらぬことをも】- 『集成』は「「そこ」は、同等以下の者を呼ぶ二人称」と注す。
【心の闇に惑ひて】- 「人の親の心は闇にあらねども子を思ふ道に惑ひぬるかな」(後撰集雑一、一一〇二、藤原兼輔)を踏まえる。
【急ぎものせむとは思ひ寄らぬことになむ】- 夕霧と雲居雁を結婚させようとすることをさす。
|
| 4.1.14 |
|
それにしても、
誰がそのようなことを申したのでしょう。つまらぬ世間の噂を取り上げて、容赦なくおっしゃるのも、つまらないことで、根も葉もない噂で、姫君の
|
それにしても、だれがあなたにそんなことを言ったのでしょう。人の中傷かもしれぬことで、腹をお立てになったりなさることはよくないし、ないことで娘の名に傷をつけてしまうことにもなりますよ」
|
【よからぬ世の人の言につきて】- 『集成』は「身分の低い世間の者たちの噂を取り上げて」。『完訳』は「つまらない世間の噂を信用して」と訳す。
|
| 4.1.15 |
とのたまへば、
|
とおっしゃると、
|
|
|
| 4.1.16 |
|
「どうして、根も葉もないことでございましょうか。
仕えている女房たちも、陰ではみな笑っているようですのに、とても悔しく、面白くなく存じられるのですよ」
|
「何のないことだものですか。女房たちも批難して、蔭では笑っていることでしょうから、私の心中は穏やかでありようがありません」
|
【何の、浮きたることにかはべらむ】- 以下「思うたまへらるるや」まで、内大臣の詞。
|
| 4.1.17 |
とて、立ちたまひぬ。
|
とおっしゃって、お立ちになった。
|
と言って大臣は立って行った。
|
|
| 4.1.18 |
心知れるどちは、いみじういとほしく思ふ。一夜のしりう言の人びとは、まして心地も違ひて、「何にかかる睦物語をしけむ」と、思ひ嘆きあへり。 |
事情を知っている女房どうしは、実におかわいそうに思う。
先夜の陰口を叩いた女房たちは、それ以上に気も動転して、「どうしてあのような内緒話をしたのだろう」と、一同後悔し合っていた。
|
幼い恋を知っている人たちは、この破局に立ち至った少年少女に同情していた。先夜の内証話をした人たちは逆上もしてしまいそうになって、どうしてあんな秘密を話題にしたのであろうと後悔に苦しんでいた。
|
【心知れるどちは】- 大島本は「(+心)しれるとちハ」とある。すなわち底本は「心」を補訂する。『新大系』は底本の補訂に従う。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「心知れる人は」と校訂する。
|
|
第二段 内大臣、乳母らを非難する
|
| 4.2.1 |
|
姫君は、何もご存知でなくていらっしゃるのを、お覗きになると、とてもかわいらしいご様子なのを、しみじみと拝見なさる。
|
姫君は何も知らずにいた。のぞいた居間に可憐な美しい顔をして姫君がすわっているのを見て、大臣の心に父の愛が深く湧いた。
|
【さしのぞきたまへれば】- 主語は内大臣。
【あはれに見たてまつりたまふ】- 主語は内大臣。
|
| 4.2.2 |
|
「若いと言っても、無分別でいらっしゃったのを知らないで、ほんとうにこうまで一人前にと思っていた自分こそ、もっとあさはかであったよ」
|
「いくら年が行かないからといって、あまりに幼稚な心を持っているあなただとは知らないで、われわれの娘としての人並みの未来を私はいろいろに考えていたのだ。あなたよりも私のほうが廃り物になった気がする」
|
【若き人といひながら】- 以下「はかなかりけれ」まで、内大臣の詞。
【心幼くものしたまひけるを】- 『集成』は「こんなに無分別でいらっしゃったとは知らず。年頃の姫君として男女の仲に無知なことをいう」。『完訳』は「大人なら、もっと慎重だったのにと、として、幼い二人を思う」と注す。
【人なみなみに】- 大島本は「人なミ/\に」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「人並々にと」と「と」を補訂する。
【我こそ、まさりてはかなかりけれ】- 『完訳』は「幼い雲居雁よりも、もっとあさはかだった。内大臣は、自らの愚かさを嘆く形で乳母らを責める」と注す。
|
| 4.2.3 |
とて、御乳母どもをさいなみたまふに、聞こえむ方なし。
|
とおっしゃって、御乳母たちをお責めになるが、お返事の申しようもない。
|
と大臣は言って、それから乳母を責めるのであった。乳母は大臣に対して何とも弁明ができない。ただ、
|
|
| 4.2.4 |
|
「このようなことは、この上ない帝の大切な内親王も、いつの間にか過ちを起こす例は、昔物語にもあるようですが、二人の気持ちを知って仲立ちする人が、隙を窺ってするのでしょう」
|
「こんなことでは大事な内親王様がたにもあやまちのあることを昔の小説などで読みましたが、それは御信頼を裏切るおそばの者があって、男の方のお手引きをするとか、また思いがけない隙ができたとかいうことで起きるのですよ。
|
【かやうのことは】- 以下「さらに思ひ寄らざりけること」まで、乳母たちの詞。
【昔物語にもあめれど】- 『集成』は「物語を人生の指針としている当時の女性である」と注す。
|
| 4.2.5 |
「これは、明け暮れ立ちまじりたまひて年ごろおはしましつるを、何かは、いはけなき御ほどを、宮の御もてなしよりさし過ぐしても、隔てきこえさせむと、うちとけて過ぐしきこえつるを、一昨年ばかりよりは、けざやかなる御もてなしになりにてはべるめるに、若き人とても、うち紛ればみ、いかにぞや、世づきたる人もおはすべかめるを、夢に乱れたるところおはしまさざめれば、さらに思ひ寄らざりけること」 |
「この二人は、朝夕ご一緒に長年過ごしていらっしゃったので、どうして、お小さい二人を、大宮様のお扱いをさし越えてお引き離し申すことができましょうと、安心して過ごして参りましたが、一昨年ごろからは、はっきり二人を隔てるお扱いに変わりましたようなので、若い人と言っても、人目をごまかして、どういうものにか、ませた真似をする人もいらっしゃるようですが、けっして色めいたところもなくいらっしゃるようなので、ちっとも思いもかけませんでした」
|
こちらのことは何年も始終ごいっしょに遊んでおいでになった間なんですもの。お小さくはいらっしゃるし宮様が寛大にお扱いになる以上にわれわれがお制しすることはできないとそのままに見ておりましたけれど、それも一昨年ごろからははっきりと日常のことが御区別できましたし、またあの方が同じ若い人といってもだらしのない不良なふうなどは少しもない方なのでしたから、まったく油断をいたしましたわね」
|
【若き人とても】- 『完訳』は「以下、一般の若者。色恋ごとに傾く者もああるとして、「ゆめに乱れたる--」以下の夕霧と対比」と注す。
【いかにぞや】- 『集成』「どうであろうか、と非難する気持を表す」と注す。
【夢に乱れたるところおはしまさざめれば】- 夕霧についていう。
|
| 4.2.6 |
と、おのがどち嘆く。
|
と、お互いに嘆く。
|
などと自分たち仲間で歎いているばかりであった。
|
|
| 4.2.7 |
「よし、しばし、かかること漏らさじ。隠れあるまじきことなれど、心をやりて、あらぬこととだに言ひなされよ。今かしこに渡したてまつりてむ。宮の御心のいとつらきなり。そこたちは、さりとも、いとかかれとしも、思はれざりけむ」 |
「よし、暫くの間、このことは人に言うまい。
隠しきれないことだが、よく注意して、せめて事実無根だともみ消しなさい。
今からは自分の所に引き取ろう。
大宮のお扱いが恨めしい。
お前たちは、いくらなんでも、こうなって欲しいとは思わなかっただろう」
|
「で、このことはしばらく秘密にしておこう。評判はどんなにしていても立つものだが、せめてあなたたちは、事実でないと否定をすることに骨を折るがいい。そのうち私の邸へつれて行くことにする。宮様の御好意が足りないからなのだ。あなたがたはいくら何だっても、こうなれと望んだわけではないだろう」
|
【よし、しばし】- 以下「思はざりけむ」まで、内大臣の詞。
【かしこに渡したてまつりてむ】- 雲居雁を自分の邸の方に移そうの意。
|
| 4.2.8 |
|
とおっしゃるので、「困ったこととではあるが、嬉しいことをおっしゃる」と思って、
|
と大臣が言うと、乳母たちは、大宮のそう取られておいでになることをお気の毒に思いながらも、また自家のあかりが立ててもらえたようにうれしく思った。
|
【いとほしきなかにも】- 以下「うれしくのたまふ」まで、乳母の心中。『集成』は「困ったことと思いながらも」。『完訳』は「姫君にはおかわいそうだが」と訳す。
|
| 4.2.9 |
|
「まあ、とんでもありません。
按察大納言殿のお耳に入ることをも考えますと、立派な人ではあっても、臣下の人であっては、何を結構なことと考えて望んだり致しましょう」
|
「さようでございますとも、大納言家への聞こえということも私たちは思っているのでございますもの、どんなに人柄がごりっぱでも、ただの御縁におつきになることなどを私たちは希望申し上げるわけはございません」
|
【あな、いみじや】- 以下「思ひたまへかけむ」まで、乳母の詞。
【大納言殿に聞きたまはむことをさへ思ひはべれば】- 雲居雁の母が再婚した按察大納言をさす。
|
| 4.2.10 |
と聞こゆ。
|
と申し上げる。
|
と言う。
|
|
| 4.2.11 |
姫君は、いと幼げなる御さまにて、よろづに申したまへども、かひあるべきにもあらねば、うち泣きたまひて、 |
姫君は、とても子供っぽいご様子で、いろいろとお申し上げなさっても、何もお分かりでないので、お泣きになって、
|
姫君はまったく無邪気で、どう戒めても、訓えてもわかりそうにないのを見て大臣は泣き出した。
|
【よろづに申したまへど】- 『集成』は「ご注意申されても」と訳す。
|
| 4.2.12 |
「いかにしてか、いたづらになりたまふまじきわざはすべからむ」 |
「どうしたら、傷ものにおなりにならずにすむ道ができようか」
|
「どういうふうに体裁を繕えばいいか、この人を廃り物にしないためには」
|
【いかにしてか】- 以下「わざはすべからむ」まで、内大臣の心中。
|
| 4.2.13 |
|
と、こっそりと頼れる乳母たちとご相談なさって、大宮だけをお恨み申し上げなさる。
|
大臣は二、三人と密議するのであった。この人たちは大宮の態度がよろしくなかったことばかりを言い合った。
|
【大宮をのみぞ】- 大島本は「大宮をのミそ」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「大宮をのみ」と「そ」を削除する。
|
|
第三段 大宮、内大臣を恨む
|
| 4.3.1 |
|
大宮は、とてもかわいいとお思いになる二人の中でも、男君へのご愛情がまさっていらっしゃるのであろうか、このような気持ちがあったのも、かわいらしくお思いになられるが、情愛なく、ひどいことのようにお考えになっておっしゃったのを、
|
大宮はこの不祥事を二人の孫のために悲しんでおいでになったが、その中でも若君のほうをお愛しになる心が強かったのか、もうそんなに大人びた恋愛などのできるようになったかとかわいくお思われにならないでもなかった。
|
【男君の御かなしさはすぐれたまふにやあらむ】- 『集成』は「ここでいわば一人前の恋する男として「男君」という呼称が使われている」と注す。語り手の挿入句。作中人物の心理を忖度してみせ、読者の関心を引きつける。
【情けなく、こよなきことのやうに思しのたまへるを】- 主語は内大臣。
|
| 4.3.2 |
|
「どうしてそんなに悪いことがあろうか。
もともと深くおかわいがりになることもなくて、こんなにまで大事にしようともお考えにならなかったのに、わたしがこのように世話してきたからこそ、春宮へのご入内のこともお考えになったのに。
思いどおりにゆかないで、臣下と結ばれるならば、この男君以外にまさった人がいるだろうか。
器量や、態度をはじめとして、同等の人がいるだろうか。
この姫君以上の身分の姫君が相応しいと思うのに」
|
もってのほかのように言った内大臣の言葉を肯定あそばすこともできない。必ずしもそうであるまい、たいした愛情のなかった子供を、自分がたいせつに育ててやるようになったため、東宮の後宮というような志望も父親が持つことになったのである。それが実現できなくて、普通の結婚をしなければならない運命になれば、源氏の長男以上のすぐれた婿があるものではない。
|
【などかさしもあるべき】- 以下「とこそ思へ」まで、大宮の心中。
【もとよりいたう思ひつきたまふことなくて】- 主語は内大臣。
【思し立たざりしを】- 大島本は「たゝさりし」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「たらざりし」と校訂する。
【思しかけためれ】- 「こそ」--「めれ」已然形の係結び、逆接用法。
【人やはある】- 大島本は「人やハある」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「人やは」と「ある」を削除する。反語表現。
【人のあるべきかは】- 反語表現。
【これより及びなからむ際にも】- 『集成』は「雲居雁以上の、及びもつかぬような身分の方にでもふさわしいと思うのに。夕霧は内親王の婿にでもふさわしいと、大宮は思う」と注す。
|
| 4.3.3 |
|
と、ご自分の愛情が男君の方に傾くせいからであろうか、内大臣を恨めしくお思い申し上げなさる。
もしもお心の中をお見せ申したら、どんなにかお恨み申し上げになることであろうか。
|
容貌をはじめとして何から言っても同等の公達のあるわけはない、もっと価値の低い婿を持たねばならない気がすると、やや公平でない御愛情から、大臣を恨んでおいでになるのであったが、宮のこのお心持ちを知ったならまして大臣はお恨みすることであろう。
|
【わが心ざしのまさればにや】- 挿入句。大宮の内省と語り手の忖度両義。
【御心のうちを見せたてまつりたらば、ましていかに恨みきこえたまはむ】- 『完訳』は「以下、語り手の評」と注す。
|
|
第四段 大宮、夕霧に忠告
|
| 4.4.1 |
|
このように騷がれているとも知らないで、冠者の君が参上なさった。
先夜も人目が多くて、思っていることもお申し上げになることができずに終わってしまったので、いつもよりもしみじみと思われなさったので、夕方いらっしゃったのであろう。
|
自身のことでこんな騒ぎのあることも知らずに源氏の若君が来た。一昨夜は人が多くいて、恋人を見ることのできなかったことから、恋しくなって夕方から出かけて来たものであるらしい。
|
【思ふことをもえ聞こえずなりにしかば】- 主語は夕霧。
【夕つ方おはしたるなるべし】- 『完訳』は「語り手の推測。夕霧の恋の苦悩を想像させる語り口である」と注す。
|
| 4.4.2 |
宮、例は是非知らず、うち笑みて待ちよろこびきこえたまふを、まめだちて物語など聞こえたまふついでに、
|
大宮は、いつもは何はさておき、微笑んでお待ち申し上げていらっしゃるのに、まじめなお顔つきでお話など申し上げなさる時に、
|
平生大宮はこの子をお迎えになると非常におうれしそうなお顔をあそばしておよろこびになるのであるが、今日はまじめなふうでお話をあそばしたあとで、
|
|
| 4.4.3 |
|
「あなたのお事で、内大臣殿がお恨みになっていらっしゃったので、とてもお気の毒です。
人に感心されないことにご執心なさって、わたしに心配かけさせることがつらいのです。
こんなことはお耳に入れまいと思いますが、そのようなこともご存知なくてはと思いまして」
|
「あなたのことで内大臣が来て、私までも恨めしそうに言ってましたから気の毒でしたよ。よくないことをあなたは始めて、そのために人が不幸になるではありませんか。私はこんなふうに言いたくはないのだけれど、そういうことのあったのを、あなたが知らないでいてはと思ってね」
|
【御ことにより】- 以下「思へばなむ」まで、大宮の詞。
【いとほしき】- 『集成』は「困っています」。『完訳』は「つらく思われます」と訳す。
【ゆかしげなきこと】- 『集成』は人に感心されない、いとこ同士の恋愛沙汰をいう」と注す。
【さる心も知りたまはでやと】- 内大臣が雲居雁と夕霧の関係を知って立腹しているということをさす。
|
| 4.4.4 |
と聞こえたまへば、心にかかれることの筋なれば、ふと思ひ寄りぬ。
面赤みて、
|
と申し上げなさると、心配していた方面のことなので、すぐに気がついた。
顔が赤くなって、
|
とお言いになった。少年の良心にとがめられていることであったから、すぐに問題の真相がわかった。若君は顔を赤くして、
|
|
| 4.4.5 |
|
「どのようなことでしょうか。
静かな所に籠もりまして以来、何かにつけて人と交際する機会もないので、お恨みになることはございますまいと存じておりますが」
|
「なんでしょう。静かな所へ引きこもりましてからは、だれとも何の交渉もないのですから、伯父様の感情を害するようなことはないはずだと私は思います」
|
【何ごとにかはべらむ】- 以下「となむ思ひたまふる」まで、夕霧の詞。
【静かなる所に籠もりはべりにしのち】- 二条東院の夕霧の学問所。
|
| 4.4.6 |
とて、いと恥づかしと思へるけしきを、あはれに心苦しうて、
|
と言って、とても恥ずかしがっている様子を、かわいくも気の毒に思って、
|
と言って羞恥に堪えないように見えるのをかわいそうに宮は思召した。
|
|
| 4.4.7 |
|
「よろしい。
せめて今からはご注意なさい」
|
「まあいいから、これから気をおつけなさいね」
|
【よし。今よりだに用意したまへ】- 大宮の詞。
|
| 4.4.8 |
とばかりにて、異事に言ひなしたまうつ。
|
とだけおっしゃって、他の話にしておしまいになった。
|
とだけお言いになって、あとはほかへ話を移しておしまいになった。
|
|
|
第五章 夕霧の物語 幼恋の物語
|
|
第一段 夕霧と雲居雁の恋の煩悶
|
| 5.1.1 |
|
「今後いっそうお手紙などを交わすことは難しいだろう」と考えると、とても嘆かわしく、食事を差し上げても、少しも召し上がらず、お寝みになってしまったふうにしているが、心も落ち着かず、人が寝静まったころに、中障子を引いてみたが、いつもは特に錠など下ろしていないのに、固く錠さして、女房の声も聞こえない。
実に心細く思われて、障子に寄りかかっていらっしゃると、女君も目を覚まして、風の音が竹に待ち迎えられて、さらさらと音を立てると、雁が鳴きながら飛んで行く声が、かすかに聞こえるので、子供心にも、あれこれとお思い乱れるのであろうか、
|
これからは手紙の往復もいっそう困難になることであろうと思うと、若君の心は暗くなっていった。晩餐が出てもあまり食べずに早く寝てしまったふうは見せながらも、どうかして恋人に逢おうと思うことで夢中になっていた若君は、皆が寝入ったころを見計らって姫君の居間との間の襖子をあけようとしたが、平生は別に錠などを掛けることもなかった仕切りが、今夜はしかと鎖されてあって、向こう側に人の音も聞こえない。若君は心細くなって、襖子によりかかっていると、姫君も目をさましていて、風の音が庭先の竹にとまってそよそよと鳴ったり、空を雁の通って行く声のほのかに聞こえたりすると、無邪気な人も身にしむ思いが胸にあるのか、
|
【いとど文なども通はむことのかたきなめり】- 夕霧の心中。
【いと嘆かしう】- 大島本は「いとなけかし(し+う)」とある。すなわち「う」を補入する。『新大系』は底本の補訂に従う。『集成』『古典セレクション』は諸本と底本の訂正以前本文に従って「なげかし」と校訂する。
【物参り】- 食事、ここでは夕飯をいう。
【人の音もせず】- 女房のいる物音。
【女君も目を覚まして】- 雲居雁、「女君」の呼称は恋の場面。
【風の音の竹に待ちとられて、うちそよめくに、雁の鳴きわたる声の、ほのかに聞こゆるに】- 「風の竹に生る夜、窓の間に臥せり、月の松を照らす時、台の上に行く」(和漢朗詠集巻上、夏夜・白氏文集巻十九、贈駕部呉郎中七兄)による。
【幼き心地にも、とかく思し乱るるにや】- 語り手の作中人物の心中を忖度した挿入句。
|
| 5.1.2 |
|
「雲居の雁もわたしのようなのかしら」
|
「雲井の雁もわがごとや」(霧深き雲井の雁もわがごとや晴れもせず物の悲しかるらん)
|
【雲居の雁もわがごとや】- 雲居雁の詞。その呼称の由来となる。「霧深く雲居の雁もわがごとや晴れせずものは悲しかるらむ」(源氏釈所引、出典未詳)による。『奥入』は「霧深き」「晴れせずものの」とある。
|
| 5.1.3 |
と、独りごちたまふけはひ、若うらうたげなり。
|
と、独り言をおっしゃる様子、若々しくかわいらしい。
|
と口ずさんでいた。その様子が少女らしくきわめて可憐であった。
|
|
| 5.1.4 |
いみじう心もとなければ、
|
とてももどかしくてならないので、
|
若君の不安さはつのって、
|
|
| 5.1.5 |
|
「ここを、お開け下さい。
小侍従はおりますか」
|
「ここをあけてください、小侍従はいませんか」
|
【これ、開けさせたまへ。小侍従やさぶらふ】- 夕霧の詞。
|
| 5.1.6 |
|
とおっしゃるが、返事がない。
乳母子だったのである。
独り言をお聞きになったのも恥ずかしくて、わけなく顔を衾の中にお入れなさったが、恋心は知らないでもないとは憎いことよ。
乳母たちが近くに臥せっていて、起きていることに気づかれるのもつらいので、お互いに音を立てない。
|
と言った。あちらには何とも答える者がない。小侍徒は姫君の乳母の娘である。独言を聞かれたのも恥ずかしくて、姫君は夜着を顔に被ってしまったのであったが、心では恋人を憐んでいた、大人のように。乳母などが近い所に寝ていてみじろぎも容易にできないのである。それきり二人とも黙っていた。
|
【御乳母子なりけり】- 『集成』は「草子地による注釈」と注す。
【あはれは知らぬにしもあらぬぞ憎きや】- 『集成』は「無邪気な雲居の雁にもいっぱしの恋心があることをやや冗談めかしていう草子地」。『完訳』は「語り手の評。もう無邪気な子供でないとする。「あはれ」は恋心」と注す。
【うちみじろくも苦しければ】- 「みじろく」の主語は乳母と夕霧雲居雁の両義。
【かたみに音もせず】- 主語は夕霧と雲居雁。
|
| 5.1.7 |
|
「真夜中に友を呼びながら飛んでいく雁の声に
さらに悲しく吹き加わる荻の上を吹く風よ」
|
さ夜中に友よびわたる雁がねに
うたて吹きそふ荻のうは風
|
【さ夜中に友呼びわたる雁が音に--うたて吹き添ふ荻の上風】- 夕霧の独詠歌。
|
| 5.1.8 |
|
「身にしみて感じられることだ」と思い続けて、大宮の御前に帰って嘆きがちでいらっしゃるのも、「お目覚めになってお聞きになろうか」と憚られて、もじもじしながら臥せった。
|
身にしむものであると若君は思いながら宮のお居間のほうへ帰ったが、歎息してつく吐息を宮がお目ざめになってお聞きにならぬかと遠慮されて、みじろぎながら寝ていた。
|
【身にしみけるかな】- 大島本は「身にも(も$<朱>)」とある。すなわち朱筆で「も」をミセケチにする。『新大系』は底本の訂正に従う。『集成』『古典セレクション』は諸本と底本の訂正以前本文に従って「身にも」と校訂する。夕霧の心中。「吹きくれば身にもしみける秋風を色なきものと思ひけるかな」(古今六帖一、秋の風)を踏まえる。
【御目覚めてや聞かせたまふらむ】- 夕霧の心中。
|
| 5.1.9 |
|
むやみに何となく恥ずかしい気がして、ご自分のお部屋に早く出て、お手紙をお書きになったが、小侍従にも会うことがおできになれず、あの姫君の方にも行くことがおできになれず、たまらない思いでいらっしゃる。
|
若君はわけもなく恥ずかしくて、早く起きて自身の居間のほうへ行き、手紙を書いたが、二人の味方である小侍従にも逢うことができず、姫君の座敷のほうへ行くこともようせずに煩悶をしていた。
|
【あいなくもの恥づかしうて】- 翌朝の夕霧。
【わが御方にとく出でて】- 大宮の御前付近の寝所から自分の部屋の方に早く帰っての意。
【かの御方ざまにもえ行かず】- 雲居雁の部屋をさす。
|
| 5.1.10 |
|
女は女でまた、騒がれなさったことばかり恥ずかしくて、「自分の身はどうなるのだろう、世間の人はどのように思うだろう」とも深くお考えにならず、美しくかわいらしくて、ちょっと噂していることにも、嫌な話だとお突き放しになることもないのであった。
|
女のほうも父親にしかられたり、皆から問題にされたりしたことだけが恥ずかしくて、自分がどうなるとも、あの人がどうなっていくとも深くは考えていない。美しく二人が寄り添って、愛の話をすることが悪いこと、醜いこととは思えなかった。そうした場合がなつかしかった。
|
【女はた】- 「女君」の呼称から「女」と呼称。恋の場面が一層に盛り上がったことを意味する。
【騒がれたまひしことのみ恥づかしうて】- 『完訳』は「「のみ」に注意。内大臣らに騒がれた、そのことだけに執する」と注す。「れ」受身の助動詞。副助詞「のみ」限定・強調のニュアンスを添える。
【わが身やいかがあらむ、人やいかが思はむ】- 語り手が雲居雁の心中を忖度した文章。
【うち語らふさまなどを】- 『集成』は「女房たちが」。『完訳』は「乳母らが」と注す。
|
| 5.1.11 |
|
また、このように騒がれねばならないことともお思いでなかったのを、御後見人たちがひどく注意するので、文通をすることもおできになれない。
大人であったら、しかるべき機会を作るであろうが、男君も、まだ少々頼りない年頃なので、ただたいそう残念だとばかり思っている。
|
こんなに皆に騒がれることが至当なこととは思われないのであるが、乳母などからひどい小言を言われたあとでは、手紙を書いて送ることもできなかった。大人はそんな中でも隙をとらえることが不可能でなかろうが、相手の若君も少年であって、ただ残念に思っているだけであった。
|
【いみじうあはめきこゆれば】- 『集成』は「「あはむ」は、軽蔑的に非難する意」と注す。
【おとなびたる人や、さるべき隙をも作り出づらむ】- 挿入句。語り手の推測。
【男君も、今すこしものはかなき年のほどにて】- 雲居雁十四歳、夕霧十二歳。
|
|
第二段 内大臣、弘徽殿女御を退出させる
|
| 5.2.1 |
大臣は、そのままに参りたまはず、宮をいとつらしと思ひきこえたまふ。
北の方には、かかることなむと、けしきも見せたてまつりたまはず、ただおほかた、いとむつかしき御けしきにて、
|
内大臣は、あれ以来参上なさらず、大宮をひどいとお思い申していらっしゃる。
北の方には、このようなことがあったとは、そぶりにもお見せ申されず、ただ何かにつけて、とても不機嫌なご様子で、
|
内大臣はそれきりお訪ねはしないのであるが宮を非常に恨めしく思っていた。夫人には雲井の雁の姫君の今度の事件についての話をしなかったが、ただ気むずかしく不機嫌になっていた。
|
|
| 5.2.2 |
|
「中宮が格別に威儀を整えて参内なさったのに対して、わが女御が将来を悲嘆していらっしゃるのが、気の毒に胸が痛いので、里に退出おさせ申して、気楽に休ませて上げましょう。
立后しなかったとはいえ、主上のお側にずっと伺候なさって、昼夜おいでのようですから、仕えている女房たちも気楽になれず、苦しがってばかりいるようですから」
|
「中宮がはなやかな儀式で立后後の宮中入りをなすったこの際に、女御が同じ御所でめいった気持ちで暮らしているかと思うと私はたまらないから、退出させて気楽に家で遊ばせてやりたい。さすがに陛下はおそばをお離しにならないようにお扱いになって、夜昼上の御局へ上がっているのだから、女房たちなども緊張してばかりいなければならないのが苦しそうだから」
|
【中宮のよそほひことにて】- 以下「わぶめるに」まで、内大臣の詞。前斎宮女御、秋好中宮をいう。『集成』は「いったん里邸に下がって、立后の宣命を受け、皇后としての威儀を整えて、あらためて宮中に入る」と注す。
【女御の世の中思ひしめりて】- 『集成』は「弘徽殿の女御が、将来を悲観していらっしゃるのが」。『完訳』は「こちらの女御が主上との御仲を悲観しておいでなのが」と訳す。
【ある人びとも】- 仕えている女房もの意。
【心ゆるびせず】- 大島本は「心ゆるゐ」とある。『新大系』は「心ゆるゐ(ひ)」とし、「「ゆるふ」はゆるむ意」と注する。『集成』『古典セレクション』は「心ふるび」と整定する。
|
| 5.2.3 |
とのたまひて、にはかにまかでさせたてまつりたまふ。御暇も許されがたきを、うちむつかりたまて、主上はしぶしぶに思し召したるを、しひて御迎へしたまふ。 |
とおっしゃって、急に里にご退出させ申し上げなさる。
お許しは難しかったが、無理をおっしゃって、主上はしぶしぶでおありであったのを、むりやりお迎えなさる。
|
こう夫人に語っている大臣はにわかに女御退出のお暇を帝へ願い出た。御寵愛の深い人であったから、お暇を許しがたく帝は思召したのであるが、いろいろなことを言い出して大臣が意志を貫徹しようとするので、帝はしぶしぶ許しあそばされた。自邸に帰った女御に大臣は、
|
【うちむつかりたまて】- 『完訳』は「内大臣は不機嫌な態度をお見せになって」と訳す。
|
| 5.2.4 |
|
「所在なくていらっしゃるでしょうから、姫君を迎えて、一緒に遊びなどなさい。
大宮にお預け申しているのは、安心なのですが、たいそう小賢しくませた人が一緒なので、自然と親しくなるのも、困った年頃になったので」
|
「退屈でしょうから、あちらの姫君を呼んでいっしょに遊ぶことなどなさい。宮にお預けしておくことは安心なようではあるが、年の寄った女房があちらには多すぎるから、同化されて若い人の慎み深さがなくなってはと、もうそんなことも考えなければならない年ごろになっていますから」
|
【つれづれに思されむを】- 以下「なりにたればなむ」まで、内大臣の詞。
【姫君渡して】- 雲居雁を大宮の三条宮邸から弘徽殿女御の里下がりしているあちらの二条邸に移しての意。
【いとさくじりおよすけたる人立ちまじりて】- 『完訳』は「「人」は暗に夕霧。このあたり、内大臣の苦々しい口調」と注す。
|
| 5.2.5 |
と聞こえたまひて、にはかに渡しきこえたまふ。
|
とお申し上げなさって、急にお引き取りになさる。
|
こんなことを言って、にわかに雲井の雁を迎えることにした。
|
|
| 5.2.6 |
宮、いとあへなしと思して、
|
大宮は、とても気落ちなさって、
|
大宮は力をお落としになって、
|
|
| 5.2.7 |
「ひとりものせられし女亡くなりたまひてのち、いとさうざうしく心細かりしに、うれしうこの君を得て、生ける限りのかしづきものと思ひて、明け暮れにつけて、老いのむつかしさも慰めむとこそ思ひつれ、思ひのほかに隔てありて思しなすも、つらく」 |
「一人いらした女の子がお亡くなりになって以来、とても寂しく心細かったのが、うれしいことにこの姫君を得て、生きている間中お世話できる相手と思って、朝な夕なに、老後の憂さつらさの慰めにしようと思っていましたが、心外にも心隔てを置いてお思いになるのも、つらく思われます」
|
「たった一人あった女の子が亡くなってから私は心細い気がして寂しがっていた所へ、あなたが姫君をつれて来てくれたので、私は一生ながめて楽しむことのできる宝のように思って世話をしていたのに、この年になってあなたに信用されなくなったかと思うと恨めしい気がします」
|
【ひとりものせられし女】- 以下「思しなすもつらく」まで大宮の詞。
【つらく」--など聞こえたまへば】- 大島本は「つらくなと」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「つたくなむと」と校訂する。
|
| 5.2.8 |
|
などとお申し上げなさると、恐縮して、
|
とお言いになると、大臣はかしこまって言った。
|
|
| 5.2.9 |
|
「心中に不満に存じられますことは、そのように存じられますと申し上げただけでございます。
深く隔意もってお思い申し上げることはどうしていたしましょう。
|
「遺憾な気のしましたことは、その場でありのままに申し上げただけのことでございます。あなた様を御信用申さないようなことが、どうしてあるものでございますか。
|
【心に飽かず思うたまへらるることは】- 以下「よも思ひきこえさせじ」まで、内大臣の詞。『集成』は「大宮の「思ひのほかに隔てありて--」という言葉に対して、心に隔てがないゆえ、思うところを率直に言ったのだと反論する」。『完訳』は「内大臣らしい発言」と注す。
【いかでかはべらむ】- 反語表現。
|
| 5.2.10 |
内裏にさぶらふが、世の中恨めしげにて、このころまかでてはべるに、いとつれづれに思ひて屈しはべれば、心苦しう見たまふるを、もろともに遊びわざをもして慰めよと思うたまへてなむ、あからさまにものしはべる」とて、「育み、人となさせたまへるを、おろかにはよも思ひきこえさせじ」 |
宮中に仕えております姫君が、ご寵愛が恨めしい様子で、最近退出おりますが、とても所在なく沈んでおりますので、気の毒に存じますので、一緒に遊びなどをして慰めようと存じまして、ほんの一時引き取るのでございます」と言って、「お育てくださり、一人前にしてくださったのを、けっしていいかげんにはお思い申しておりません」
|
御所におります娘が、いろいろと朗らかでないふうでこの節邸へ帰っておりますから、退屈そうなのが哀れでございまして、いっしょに遊んで暮らせばよいと思いまして、一時的につれてまいるのでございます」
また、
「今日までの御養育の御恩は決して忘れさせません」
|
【世の中恨めしげにて】- 帝との夫婦仲が思わしくない様子。
|
| 5.2.11 |
|
と申し上げなさると、このようにお思いたちになった以上は、引き止めようとなさっても、お考え直されるご性質ではないので、大変に残念にお思いになって、
|
とも言った。こう決めたことはとどめても思い返す性質でないことを御承知の宮はただ残念に思召すばかりであった。
|
【かう思し立ちにたれば、止めきこえさせたまふとも、思し返すべき御心ならぬに】- 内大臣の性格。きっぱりとした性格で、いったん決心したら母親が制止しても思い直すことはしない性分。
|
| 5.2.12 |
|
「人の心とは嫌なものです。
あれこれにつけ幼い子どもたちも、わたしに隠し事をして嫌なことですよ。
また一方で、子どもとはそのようなものでしょうが、内大臣が、思慮分別がおありになりながら、わたしを恨んで、このように連れて行っておしまいになるとは。
あちらでは、ここよりも安心なことはあるまいに」
|
「人というものは、どんなに愛するものでもこちらをそれほどには思ってはくれないものだね。若い二人がそうではないか、私に隠して大事件を起こしてしまったではないか。それはそれでも大臣はりっぱなでき上がった人でいながら私を恨んで、こんなふうにして姫君をつれて行ってしまう。あちらへ行ってここにいる以上の平和な日があるものとは思われないよ」
|
【人の心こそ憂きものはあれ】- 以下「うしろやすきこともあらじ」まで、大宮の詞。
【幼き心どもにも】- 孫の夕霧と雲居雁をさす。
【また、さもこそあらめ】- 係結び、逆接用法。『集成』は「しかしまた、それはそれで(子供だから)仕方がないとしても」と訳す。
【かしこにて、これよりうしろやすきこともあらじ】- 継母のもとに引き取られることになるからである。
|
| 5.2.13 |
と、うち泣きつつのたまふ。
|
と、泣きながらおっしゃる。
|
お泣きになりながら、こう女房たちに宮は言っておいでになった。
|
|
|
第三段 夕霧、大宮邸に参上
|
| 5.3.1 |
折しも冠者の君参りたまへり。「もしいささかの隙もや」と、このころはしげうほのめきたまふなりけり。内大臣の御車のあれば、心の鬼にはしたなくて、やをら隠れて、わが御方に入りゐたまへり。 |
ちょうど折しも冠者の君が参上なさった。
「もしやちょっとした隙でもありやしないか」と、最近は頻繁にお顔を出しになられるのであった。
内大臣のお車があるので、気がとがめて具合悪いので、こっそり隠れて、ご自分のお部屋にお入りになった。
|
ちょうどそこへ若君が来た。少しの隙でもないかとこのごろはよく出て来るのである。内大臣の車が止まっているのを見て、心の鬼にきまり悪さを感じた若君は、そっとはいって来て自身の居間へ隠れた。
|
【わが御方に入りゐたまへり】- 大宮邸にある夕霧の部屋。
|
| 5.3.2 |
|
内大臣の若公達の、左近少将、少納言、兵衛佐、侍従、大夫などと言った人々も、皆ここには参集なさったが、御簾の内に入ることはお許しにならない。
|
内大臣の息子たちである左少将、少納言、兵衛佐、侍従、大夫などという人らもこのお邸へ来るが、御簾の中へはいることは許されていないのである。
|
【左少将、少納言、兵衛佐、侍従、大夫】- 内大臣の子息たち。それぞれ、左少将は正五位下、少納言は従五位下、兵衛佐は従五位上、侍従は従五位下相当官。大夫は五位の意だから従五位下、官職の有無は不明。
|
| 5.3.3 |
|
左兵衛督、権中納言なども、異腹の兄弟であるが、故大殿のご待遇によって、今でも参上して御用を承ることが親密なので、その子どもたちもそれぞれ参上なさるが、この冠者の君に似た美しい人はいないように見える。
|
左衛門督、権中納言などという内大臣の兄弟はほかの母君から生まれた人であったが、故人の太政大臣が宮へ親子の礼を取らせていた関係から、今も敬意を表しに来て、その子供たちも出入りするのであるが、だれも源氏の若君ほど美しい顔をしたのはなかった。
|
【左兵衛督、権中納言なども、異御腹なれど、故殿の御もてなしのままに】- 内大臣の異母兄弟たち。左兵衛督は従五位上、権中納言は従三位相当官。なお、「左兵衛督」は大島本の独自異文。他の青表紙本の多くは「左衛門督」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「左衛門督」と校訂する。
|
| 5.3.4 |
大宮の御心ざしも、なずらひなく思したるを、ただこの姫君をぞ、気近うらうたきものと思しかしづきて、御かたはらさけず、うつくしきものに思したりつるを、かくて渡りたまひなむが、いとさうざうしきことを思す。
|
大宮のご愛情も、この上なくお思いであったが、ただこの姫君を、身近にかわいい者とお思いになってお世話なさって、いつもお側にお置きになって、かわいがっていらっしゃったのに、このようにしてお引き移りになるのが、とても寂しいこととお思いになる。
|
宮のお愛しになることも比類のない御孫であったが、そのほかには雲井の雁だけがお手もとで育てられてきて深い御愛情の注がれている御孫であったのに、突然こうして去ってしまうことになって、お寂しくなることを宮は歎いておいでになった。
|
|
| 5.3.5 |
殿は、
|
内大臣殿は、
|
大臣は、
|
|
| 5.3.6 |
|
「今の間に、内裏に参上しまして、夕方に迎えに参りましょう」
|
「ちょっと御所へ参りまして、夕方に迎えに来ようと思います」
|
【今のほどに、内裏に参りはべりて、夕つ方迎へに参りはべらむ】- 内大臣の詞。
|
| 5.3.7 |
とて、出でたまひぬ。
|
と言って、お出になった。
|
と言って出て行った。
|
|
| 5.3.8 |
|
「今さら言っても始まらないことだが、穏便に言いなして、二人の仲を許してやろうか」とお思いになるが、やはりとても面白くないので、「ご身分がもう少し一人前になったら、不満足な地位でないと見做して、その時に、愛情が深いか浅いかの状態も見極めて、許すにしても、改まった結婚という形式を踏んで婿として迎えよう。
厳しく言っても、一緒にいては、子どものことだから、見苦しいことをしよう。
大宮も、まさかむやみにお諌めになることはあるまい」
|
事実に潤色を加えて結婚をさせてもよいとは大臣の心にも思われたのであるが、やはり残念な気持ちが勝って、ともかくも相当な官歴ができたころ、娘への愛の深さ浅さをも見て、許すにしても形式を整えた結婚をさせたい、厳重に監督しても、そこが男の家でもある所に置いては、若いどうしは放縦なことをするに違いない。宮もしいて制しようとはあそばさないであろうから
|
【いふかひなきことを】- 以下「さてもやあらまし」まで、内大臣の心中。
【さてもやあらまし】- 夕霧と雲居雁の結婚を許すことをさす。
【人の御ほどの】- 以下「制したまふことあらじ」まで、内大臣の心中。
【ことさらなるやうにもてなして】- 改まった結婚という形式をふんでの意。体裁や外見を重んじる内大臣の発想。
【制したまふこと】- 大島本は「せいし給こと」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「制しのたまふ」と校訂する。
|
| 5.3.9 |
と思せば、女御の御つれづれにことつけて、ここにもかしこにもおいらかに言ひなして、渡したまふなりけり。 |
とお思いになると、弘徽殿女御が寂しがっているのにかこつけて、こちらにもあちらにも穏やかに話して、お連れになるのであった。
|
とこう思って、女御のつれづれに託して、自家のほうへも官邸へも軽いふうを装って伴い去ろうと大臣はするのである。
|
【ここにもかしこにも】- 大宮にも北の方にも。
|
|
第四段 夕霧と雲居雁のわずかの逢瀬
|
| 5.4.1 |
宮の御文にて、
|
大宮のお手紙で、
|
宮は雲井の雁へ手紙をお書きになった。
|
|
| 5.4.2 |
「大臣こそ、恨みもしたまはめ、君は、さりとも心ざしのほども知りたまふらむ。渡りて見えたまへ」 |
「内大臣は、お恨みでしょうが、あなたは、こうはなってもわたしの気持ちはわかっていただけるでしょう。
いらっしゃってお顔をお見せください」
|
大臣は私を恨んでいるかしりませんが、あなたは、私がどんなにあなたを愛しているかを知っているでしょう。こちらへ逢いに来てください。
|
【大臣こそ】- 以下「見えたまへ」まで、大宮から雲居雁への手紙。
|
| 5.4.3 |
と聞こえたまへれば、いとをかしげにひきつくろひて渡りたまへり。
十四になむおはしける。
かたなりに見えたまへど、いと子めかしう、しめやかに、うつくしきさましたまへり。
|
と差し上げなさると、とても美しく装束を整えていらっしゃった。
十四歳でいらっしゃった。
まだ十分に大人にはお見えでないが、とてもおっとりとしていらして、しとやかで、美しい姿態をしていらっしゃった。
|
宮のお言葉に従って、きれいに着かざった姫君が出て来た。年は十四なのである。まだ大人にはなりきってはいないが、子供らしくおとなしい美しさのある人である。
|
|
| 5.4.4 |
|
「いままでお側をお離し申さず、明け暮れの話相手とお思い申していたのに、とても寂しいことですね。
残り少ない晩年に、あなたのご将来を見届けることができないことは、寿命と思いますが、今のうちから見捨ててお移りになる先が、どこかしらと思うと、とても不憫でなりません」
|
「始終あなたをそばに置いて見ることが、私のなくてならぬ慰めだったのだけれど、行ってしまっては寂しくなることでしょう。私は年寄りだから、あなたの生い先が見られないだろうと、命のなくなるのを心細がったものですがね。私と別れてあなたの行く所はどこかと思うとかわいそうでならない」
|
【かたはらさけたてまつらず】- 以下「いとこそあはれなれ」まで、大宮の詞。
【命をこそ思ひつれ】- 「こそ--つれ」係結び、逆接用法。「思ひ」は嘆く、悲しむ、意。
【いとこそあはれなれ】- 『集成』は「自分の存命仲に引き離されて行く先が、継母のもとであることをあわれむ」と注す。
|
| 5.4.5 |
とて泣きたまふ。姫君は、恥づかしきことを思せば、顔ももたげたまはで、ただ泣きにのみ泣きたまふ。男君の御乳母、宰相の君出で来て、 |
と言ってお泣きになる。
姫君は、恥ずかしいこととお思いになると、顔もお上げにならず、ただ泣いてばかりいらっしゃる。
男君の御乳母の、宰相の君が出て来て、
|
と言って宮はお泣きになるのであった。雲井の雁は祖母の宮のお歎きの原因に自分の恋愛問題がなっているのであると思うと、羞恥の感に堪えられなくて、顔も上げることができずに泣いてばかりいた。若君の乳母の宰相の君が出て来て、
|
【恥づかしきことを思せば】- 夕霧との関係をさす。
|
| 5.4.6 |
|
「同じご主人様とお頼り申しておりましたが、残念にもこのようにお移りあそばすとは。
内大臣殿は別にお考えになるところがおありでも、そのようにお思いあそばしますな」
|
「若様とごいっしょの御主人様だとただ今まで思っておりましたのに行っておしまいになるなどとは残念なことでございます。殿様がほかの方と御結婚をおさせになろうとあそばしましても、お従いにならぬようにあそばせ」
|
【同じ君とこそ】- 以下「思しなびかせたまふな」まで、宰相君の詞。
【殿はことざまに思しなることおはしますとも】- 「殿」は内大臣をさし、「ことざま」は夕霧以外との縁組をさす。
|
| 5.4.7 |
など、ささめき聞こゆれば、いよいよ恥づかしと思して、物ものたまはず。
|
などと、ひそひそと申し上げると、いっそう恥ずかしくお思いになって、何ともおっしゃらない。
|
などと小声で言うと、いよいよ恥ずかしく思って、雲井の雁はものも言えないのである。
|
|
| 5.4.8 |
「いで、むつかしきことな聞こえられそ。人の御宿世宿世、いと定めがたく」 |
「いえもう、
厄介なことは申し上げなさいますな。人の運命はそれぞれで、と
|
「そんな面倒な話はしないほうがよい。縁だけはだれも前生から決められているのだからわからない」
|
【いで、むつかしきこと】- 以下「定めがたく」まで、大宮の詞。
|
| 5.4.9 |
とのたまふ。
|
とおっしゃる。
|
と宮がお言いになる。
|
|
| 5.4.10 |
「いでや、ものげなしとあなづりきこえさせたまふにはべるめりかし。さりとも、げに、わが君人に劣りきこえさせたまふと、聞こしめし合はせよ」 |
「いえいえ、
一人前でないとお侮り申していらっしゃるのでしょう。今はそうですが、わたくしどもの若君が人にお劣り申していらっしゃる
|
「でも殿様は貧弱だと思召して若様を軽蔑あそばすのでございましょうから。まあお姫様見ておいであそばせ、私のほうの若様が人におくれをおとりになる方かどうか」
|
【いでや】- 以下「聞こしめし合はせよ」まで、宰相君の詞。
【わが君】- 大島本は「わか君」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「わが君や」と「や」を補訂する。
|
| 5.4.11 |
と、なま心やましきままに言ふ。
|
と、癪にさわるのにまかせて言う。
|
口惜しがっている乳母はこんなことも言うのである。
|
|
| 5.4.12 |
冠者の君、物のうしろに入りゐて見たまふに、人の咎めむも、よろしき時こそ苦しかりけれ、いと心細くて、涙おし拭ひつつおはするけしきを、御乳母、いと心苦しう見て、宮にとかく聞こえたばかりて、夕まぐれの人のまよひに、対面せさせたまへり。 |
冠者の君は、物陰に入って御覧になると、人が見咎めるのも、何でもない時は苦しいだけであったが、とても心細くて、涙を拭いながらいらっしゃる様子を、御乳母が、とても気の毒に見て、大宮にいろいろとご相談申し上げて、夕暮の人の出入りに紛れて、対面させなさった。
|
若君は几帳の後ろへはいって来て恋人をながめていたが、人目を恥じることなどはもう物の切迫しない場合のことで、今はそんなことも思われずに泣いているのを、乳母はかわいそうに思って、宮へは体裁よく申し上げ、夕方の暗まぎれに二人をほかの部屋で逢わせた。
|
【冠者の君、物のうしろに入りゐて見たまふに】- 『完訳』は「雲居雁を見ようと物陰に忍ぶ」と注す。
|
| 5.4.13 |
かたみにもの恥づかしく胸つぶれて、物も言はで泣きたまふ。
|
お互いに何となく恥ずかしく胸がどきどきして、何も言わないでお泣きになる。
|
きまり悪さと恥ずかしさで二人はものも言わずに泣き入った。
|
|
| 5.4.14 |
「大臣の御心のいとつらければ、さはれ、思ひやみなむと思へど、恋しうおはせむこそわりなかるべけれ。などて、すこし隙ありぬべかりつる日ごろ、よそに隔てつらむ」 |
「内大臣のお気持ちがとてもつらいので、ままよ、いっそ諦めようと思いますが、恋しくいらっしゃてたまらないです。
どうして、少しお逢いできそうな折々があったころは、離れて過ごしていたのでしょう」
|
「伯父様の態度が恨めしいから、恋しくても私はあなたを忘れてしまおうと思うけれど、逢わないでいてはどんなに苦しいだろうと今から心配でならない。なぜ逢えば逢うことのできたころに私はたびたび来なかったろう」
|
【大臣の御心の】- 以下「よそに隔てつらむ」まで、夕霧の詞。
|
| 5.4.15 |
とのたまふさまも、いと若うあはれげなれば、
|
とおっしゃる様子も、たいそう若々しく痛々しげなので、
|
と言う男の様子には、若々しくてそして心を打つものがある。
|
|
| 5.4.16 |
|
「わたしも、
|
「私も苦しいでしょう、きっと」
|
【まろも、さこそはあらめ】- 雲居雁の詞。『集成』は「親しい者同士の間で使う一人称」と注す。
|
| 5.4.17 |
とのたまふ。
|
とおっしゃる。
|
|
|
| 5.4.18 |
|
「恋しいと思ってくださるでしょうか」
|
「恋しいだろうとお思いになる」
|
【恋しとは思しなむや】- 夕霧の詞。
|
| 5.4.19 |
とのたまへば、すこしうなづきたまふさまも、幼げなり。
|
とおっしゃると、ちょっとうなずきなさる様子も、幼い感じである。
|
と男が言うと、雲井の雁が幼いふうにうなずく。
|
|
|
第五段 乳母、夕霧の六位を蔑む
|
| 5.5.1 |
御殿油参り、殿まかでたまふけはひ、こちたく追ひののしる御前駆の声に、人びと、
|
御殿油をお点けし、内大臣が宮中から退出なさって来た様子で、ものものしく大声を上げて先払いする声に、女房たちが、
|
座敷には灯がともされて、門前からは大臣の前駆の者が大仰に立てる人払いの声が聞こえてきた。女房たちが、
|
|
| 5.5.2 |
|
「それそれ、
|
「さあ、さあ」
|
【そそや】- 女房の声。
|
| 5.5.3 |
|
などと慌てるので、とても恐ろしくお思いになって震えていらっしゃる。
そんなにやかましく言われるなら言われても構わないと、一途な心で、姫君をお放し申されない。
姫君の乳母が参ってお捜し申して、その様子を見て、
|
と騒ぎ出すと、雲井の雁は恐ろしがってふるえ出す。男はもうどうでもよいという気になって、姫君を帰そうとしないのである。姫君の乳母が捜しに来て、はじめて二人の会合を知った。
|
【いと恐ろしと思して】- 主語は雲居雁。
【さも騒がればと、ひたぶる心に、許しきこえたまはず】- 主語は夕霧。
【御乳母参りて】- 雲居雁の乳母。
|
| 5.5.4 |
|
「まあ、いやだわ。
なるほど、大宮は御存知ないことではなかったのだわ」
|
何といういまわしいことであろう、やはり宮はお知りにならなかったのではなかったか
|
【あな、心づきなや】- 以下「あらざりけり」まで、雲居雁の乳母の心中。
|
| 5.5.5 |
と思ふに、いとつらく、
|
と思うと、実に恨めしくなって、
|
と思うと、乳母は恨めしくてならなかった。
|
|
| 5.5.6 |
|
「何とも、
情けないことですわ。内大臣殿がおっしゃることは、申すまでもなく、大納言殿にもどのようにお聞き
になることでしょう。結構な方であっても、初婚の相手が六位
|
「ほんとうにまあ悲しい。殿様が腹をおたてになって、どんなことをお言い出しになるかしれないばかしか、大納言家でもこれをお聞きになったらどうお思いになることだろう。貴公子でおありになっても、最初の殿様が浅葱の袍の六位の方とは」
|
【いでや、憂かりける世かな】- 以下「六位宿世よ」まで、雲居雁の乳母の詞。
【殿の思しのたまふことは】- 内大臣が腹立ち叱ること。
|
| 5.5.7 |
と、つぶやくもほの聞こゆ。
ただこの屏風のうしろに尋ね来て、嘆くなりけり。
|
と、つぶやいているのがかすかに聞こえる。
ちょうどこの屏風のすぐ背後に捜しに来て、嘆くのであった。
|
こう言う声も聞こえるのであった。すぐ二人のいる屏風の後ろに来て乳母はこぼしているのである。
|
|
| 5.5.8 |
|
男君は、「自分のことを位がないと軽蔑しているのだ」とお思いになると、こんな二人の仲がたまらなくなって、愛情も少しさめる感じがして、許しがたい。
|
若君は自分の位の低いことを言って侮辱しているのであると思うと、急に人生がいやなものに思われてきて、恋も少しさめる気がした。
|
【我をば位なしとて、はしたなむるなりけり】- 夕霧の心中。
|
| 5.5.9 |
|
「あれをお聞きなさい。
|
「そらあんなことを言っている。
|
【かれ聞きたまへ】- 以下「恥づかし」まで、夕霧の詞と歌。
|
| 5.5.10 |
|
真っ赤な血の涙を流して恋い慕っているわたしを
浅緑の袖の色だと言ってけなしてよいものでしょうか
|
くれなゐの涙に深き袖の色を
浅緑とやいひしをるべき
|
【くれなゐの涙に深き袖の色を--浅緑にや言ひしをるべき】- 大島本は「あさみとりにや」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「浅緑とや」と校訂する。「浅緑」は六位の色。「紅」と「浅緑」の色彩の対比。
|
| 5.5.11 |
恥づかし」
|
恥ずかしい」
|
恥ずかしくてならない」
|
|
| 5.5.12 |
とのたまへば、
|
とおっしゃると、
|
と言うと、
|
|
| 5.5.13 |
|
「色々とわが身の不運が思い知らされますのは
どのような因縁の二人なのでしょう」
|
いろいろに身のうきほどの知らるるは
いかに染めける中の衣ぞ
|
【いろいろに身の憂きほどの知らるるは--いかに染めける中の衣ぞ】- 雲居雁の返歌。夕霧の「紅」「浅緑」や「袖」の語句を受けて「色々」「染め」「衣」の語句を詠み込んで返した。
|
| 5.5.14 |
|
と、言い終わらないうちに、殿がお入りになっていらしたので、しかたなくお戻りになった。
|
と雲井の雁が言ったか言わぬに、もう大臣が家の中にはいって来たので、そのまま雲井の雁は立ち上がった。
|
【渡りたまひぬ】- 雲居雁が自分の部屋に戻ったという意。
|
| 5.5.15 |
男君は、立ちとまりたる心地も、いと人悪く、胸ふたがりて、わが御方に臥したまひぬ。 |
男君は、後に残された気持ちも、とても体裁が悪く、胸が一杯になって、ご自分のお部屋で横におなりになった。
|
取り残された見苦しさも恥ずかしくて、悲しみに胸をふさがらせながら、若君は自身の居間へはいって、そこで寝つこうとしていた。
|
【いと人悪く】- 大島本は「人わるく」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「人わろく」と校訂する。
|
| 5.5.16 |
|
お車は三輌ほどで、ひっそりと急いでお出になる様子を聞くのも、落ち着かないので、大宮の御前から「いらっしゃい」とあるが、寝ている様子をして身動きもなさらない。
|
三台ほどの車に分乗して姫君の一行は邸をそっと出て行くらしい物音を聞くのも若君にはつらく悲しかったから、宮のお居間から、来るようにと、女房を迎えにおよこしになった時にも、眠ったふうをしてみじろぎもしなかった。
|
【御車三つばかりにて、忍びやかに急ぎ出でたまふけはひ】- 後に真木柱姫君が母方の実家に引き取られて行く場面も車三台ほどで迎えに来る(真木柱)。
|
| 5.5.17 |
涙のみ止まらねば、嘆きあかして、霜のいと白きに急ぎ出でたまふ。うちはれたるまみも、人に見えむが恥づかしきに、宮はた、召しまつはすべかめれば、心やすき所にとて、急ぎ出でたまふなりけり。 |
涙ばかりが止まらないので、嘆きながら夜を明かして、霜がたいそう白いころに急いでお帰りになる。
泣き腫らした目許も、人に見られるのが恥ずかしいので、大宮もまた、お召しになって放さないだろうから、気楽な所でと思って、急いでお帰りになったのであった。
|
涙だけがまだ止まらずに一睡もしないで暁になった。霜の白いころに若君は急いで出かけて行った。泣き腫らした目を人に見られることが恥ずかしいのに、宮はきっとそばへ呼ぼうとされるのであろうから、気楽な場所へ行ってしまいたくなったのである。
|
【心やすき所にとて】- 二条東院の自分の部屋。
|
| 5.5.18 |
|
その道中は、誰のせいからでなく、心細く思い続けると、空の様子までもたいそう曇って、まだ暗いのであった。
|
車の中でも若君はしみじみと破れた恋の悲しみを感じるのであったが、空模様もひどく曇って、まだ暗い寂しい夜明けであった。
|
【空のけしきもいたう雲りて、まだ暗かりけり】- 『完訳』は「次の歌を先取りした心象風景」と注す。
|
| 5.5.19 |
|
「霜や氷が嫌に張り詰めた明け方の
空を真暗にして降る涙の雨だなあ」
|
霜氷うたて結べる明けぐれの
空かきくらし降る涙かな
|
【霜氷うたてむすべる明けぐれの--空かきくらし降る涙かな】- 夕霧の独詠歌。『集成』は「夕霧心中の独詠。「霜氷」は、凍てついた霜をいう歌語」と注す。
|
|
第六章 夕霧の物語 五節舞姫への恋
|
|
第一段 惟光の娘、五節舞姫となる
|
| 6.1.1 |
|
大殿の所では、今年、五節の舞姫を差し上げなさる。
何ほどといったご用意ではないが、童女の装束など、日が近くなったといって、急いでおさせになる。
|
今年源氏は五節の舞い姫を一人出すのであった。たいした仕度というものではないが、付き添いの童女の衣裳などを日が近づくので用意させていた。
|
【大殿には】- 太政大臣の源氏。
【五節たてまつりたまふ】- 新嘗祭の五節。十一月の中の丑、寅、卯、辰の日に行われる。舞姫を公卿から二人、殿上人・受領から二人差し出す。源氏は公卿として惟光の娘を差し出した。なお大嘗祭では五人の舞姫を差し出す。
|
| 6.1.2 |
東の院には、参りの夜の人びとの装束せさせたまふ。
殿には、おほかたのことども、中宮よりも、童、下仕への料など、えならでたてまつれたまへり。
|
東の院では、参内の夜の付人の装束を準備させなさる。
殿におかれては、全般的な事柄を、中宮からも、童女や、下仕えの人々のご料などを、並大抵でないものを差し上げなさった。
|
東の院の花散里夫人は、舞い姫の宮中へはいる夜の、付き添いの女房たちの装束を引き受けて手もとで作らせていた。二条の院では全体にわたっての一通りの衣裳が作られているのである。中宮からも、童女、下仕えの女房幾人かの衣服を、華奢に作って御寄贈になった。
|
|
| 6.1.3 |
|
昨年は、五節などは停止になっていたが、もの寂しかった思いを加えて、殿上人の気分も、例年よりもはなやかに思うにちがいない年なので、家々が競って、たいそう立派に善美の限りを尽くして用意をなさるとの噂である。
|
去年は諒闇で五節のなかったせいもあって、だれも近づいて来る五節に心をおどらせている年であるから、五人の舞い姫を一人ずつ引き受けて出す所々では派手が競われているという評判であった。
|
【過ぎにし年、五節など止まれりしが】- 昨年は藤壷中宮の崩御により諒暗のため停止。
【積もり取り添へ】- 大島本は「つもり」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「積もりも」と「も」を補訂する。
|
| 6.1.4 |
|
按察大納言、左衛門督と、殿上人の五節としては、良清が、今では近江守で左中弁を兼官しているのが、差し上げるのだった。
皆残させなさって、宮仕えするようにとの、仰せ言が特にあった年なので、娘をそれぞれ差し上げなさる。
|
按察使大納言の娘、左衛門督の娘などが出ることになっていた。それから殿上役人の中から一人出す舞い姫には、今は近江守で左中弁を兼ねている良清朝臣の娘がなることになっていた。
|
【按察使大納言】- 雲居雁の母が再婚した相手。公卿分の舞姫を差し出す。
【左衛門督】- 内大臣の弟か。前に内大臣の異母兄弟「左兵衛督」の異文に「左衛門督」とあった。同じく公卿分の舞姫を差し出す。『集成』は「この年は、太政大臣である源氏を加えて、特に公卿から三人出したことになる」。『完訳』は「以上二家は公卿」と注す。
【上の五節には】- 「上」は殿上人の意。以下、殿上人分として良清が一人差し出した。
【仰せ言ことなる】- 『完訳』は「大嘗祭の舞姫には叙位があるが、新嘗祭にはなく舞姫のなり手が少なかったという。ここは勅命があり、大嘗祭に准ずるほど盛大」と注す。
|
| 6.1.5 |
|
大殿の舞姫は、惟光朝臣が、摂津守で左京大夫を兼官しているその娘の、器量などもたいそう美しいという評判があるのをお召しになる。
つらいことと思ったが、
|
今年の舞い姫はそのまま続いて女官に採用されることになっていたから、愛嬢を惜しまずに出すのであると言われていた。源氏は自身から出す舞い姫に、摂津守兼左京大夫である惟光の娘で美人だと言われている子を選んだのである。惟光は迷惑がっていたが、
|
【殿の舞姫は、惟光朝臣の】- 『完訳』は「源氏の世話する舞姫。殿上受領分として、惟光を後援する形か」と注す。
【左京大夫かけたるが女】- 大島本は「かけたるか女」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「かけたる女」と「か」を削除する。
【からいことに思ひたれど】- 『集成』は「娘を人目にさらすのをつらがる」と注す。
|
| 6.1.6 |
|
「按察大納言が、異腹の娘を差し上げられるというのに、朝臣が大切なまな娘を差し出すのは、何の恥ずかしいことがあろうか」
|
「大納言が妾腹の娘を舞い姫に出す時に、君の大事な娘を出したっても恥ではない」
|
【大納言の、外腹の女】- 以下「何の恥かあるべき」まで、『集成』『新大系』は、源氏の詞。『古典セレクション』は、周囲の人々の詞とする。
|
| 6.1.7 |
と苛めば、わびて、同じくは宮仕へやがてせさすべく思ひおきてたり。
|
とお責めになるので、困って、いっそのこと宮仕えをそのままさせようと考えていた。
|
と責められて、困ってしまった惟光は、女官になる保証のある点がよいからとあきらめてしまって、主命に従うことにしたのである。
|
|
| 6.1.8 |
|
舞の稽古などは、里邸で十分に仕上げて、介添役など、親しく身近に添うべき女房などは、丹念に選んで、その日の夕方大殿に参上させた。
|
舞の稽古などは自宅でよく習わせて、舞い姫を直接世話するいわゆるかしずきの幾人だけはその家で選んだのをつけて、初めの日の夕方ごろに二条の院へ送った。
|
【里にて】- 惟光の邸で。
【その日の夕つけて参らせたり】- 『集成』は「当日(丑の日)の夕方に。宮中に参入するのは夜」。『完訳』は「当日の夕方になって二条院に参上させた」と注す。
|
| 6.1.9 |
|
大殿邸でも、それぞれのご婦人方の童女や、下仕えの優れている者をと、お比べになり、選び出される者たちの気分は、身分相応につけて、たいそう誇らしげである。
|
なお童女幾人、下仕え幾人が付き添いに必要なのであるから、二条の院、東の院を通じてすぐれた者を多数の中から選り出すことになった。皆それ相応に選定される名誉を思って集まって来た。
|
【御方々の童女、下仕へのすぐれたるをと、御覧じ比べ、選り出でらるる】- 舞姫の付添いに二条院や東院の童女や下仕え人の中から選び出す。
|
| 6.1.10 |
|
主上のお前に召されて御覧になられる前稽古に、殿のお前を通らせてみようとお決めになる。
誰一人落第する者もいないくらいに、それぞれ素晴らしい童女の姿態や、器量にお困りになって、
|
陛下が五節の童女だけを御覧になる日の練習に、縁側を歩かせて見て決めようと源氏はした。落選させてよいような子供もない、それぞれに特色のある美しい顔と姿を持っているのに源氏はかえって困った。
|
【御前に召して御覧ぜむうちならしに、御前を渡らせてと定めたまふ】- 帝が御前に召して御覧になる予行演習として源氏の御前を歩かせるという意。
|
| 6.1.11 |
|
「もう一人分の舞姫の介添役を、こちらから差し上げたいものだな」
|
「もう一人分の付き添いの童女を私のほうから出そうかね」
|
【今一所の料を、これよりたてまつらばや】- 源氏の詞。美しい童女たちに賛嘆した冗談。
|
| 6.1.12 |
など笑ひたまふ。
ただもてなし用意によりてぞ選びに入りける。
|
などと言ってお笑いになる。
わずかに態度や心構えの違いによって選ばれたのであった。
|
などと笑っていた。結局身の取りなしのよさと、品のよい落ち着きのある者が採られることになった。
|
|
|
第二段 夕霧、五節舞姫を恋慕
|
| 6.2.1 |
大学の君、胸のみふたがりて、物なども見入れられず、屈じいたくて、書も読まで眺め臥したまへるを、心もや慰むと立ち出でて、紛れありきたまふ。 |
大学の君は、ただ胸が一杯で、食事なども見たくなく、ひどくふさぎこんで、漢籍も読まないで物思いに沈んで横になっていらっしゃったが、気分も紛れようかと外出して、人目に立たないようにお歩きになる。
|
大学生の若君は失恋の悲しみに胸が閉じられて、何にも興味が持てないほど心がめいって、書物も読む気のしないほどの気分がいくぶん慰められるかもしれぬと、五節の夜は二条の院に行っていた。
|
【紛れありきたまふ】- 『集成』は「(二条の院内を)人々に入りまじってあちこち見てまわる」。『完訳』は「人目を避け物陰伝いに行く意」と注す。
|
| 6.2.2 |
さま、容貌はめでたくをかしげにて、静やかになまめいたまへれば、若き女房などは、いとをかしと見たてまつる。
|
姿態、器量は立派で美しくて、落ち着いて優美でいらっしゃるので、若い女房などは、とても素晴らしいと拝見している。
|
風采がよくて落ち着いた、艶な姿の少年であったから、若い女房などから憧憬を持たれていた。
|
|
| 6.2.3 |
|
対の上の御方には、御簾のお前近くに出ることさえお近寄らせにならない。
ご自分のお心の性癖から、どのようにお考えになったのであろうか、他人行儀なお扱いなので、女房なども疎遠なのだが、今日は舞姫の混雑に紛れて、入り込んで来られたのであろう。
|
夫人のいるほうでは御簾の前へもあまりすわらせぬように源氏は扱うのである。源氏は自身の経験によって危険がるのか、そういうふうであったから、女房たちすらも若君と親しくする者はいないのであるが、今日は混雑の紛れに室内へもはいって行ったものらしい。
|
【上の御方には、御簾の前にだに、もの近うももてなしたまはず】- 紫の上の御前をさす。『集成』は「主語は、源氏」。『完訳』は「源氏の、夕霧へのきびしいしつけ」と注す。
【わが御心ならひ、いかに思すにかありけむ】- 『集成』は「(源氏は)ご自分のお心癖から、どのようなお考えになったのだろうか。藤壷とのこともあったので、夕霧を義母に近づけないのか、という含み」。『完訳』は「源氏は、藤壷との体験から、夕霧の継母紫の上への接近を警戒。語り手の「いかに--ありけむ」の疑問をはさんで、源氏の深慮を想像」と注す。
【入り立ちたまへるなめり】- 「なめり」は語り手の想像。臨場感ある表現。
|
|
 |
| 6.2.4 |
|
舞姫を大切に下ろして、妻戸の間に屏風などを立てて、臨時の設備なので、そっと近寄ってお覗きになると、苦しそうに物に寄り臥していた。
|
車で着いた舞い姫をおろして、妻戸の所の座敷に、屏風などで囲いをして、舞い姫の仮の休息所へ入れてあったのを、若君はそっと屏風の後ろからのぞいて見た。苦しそうにして舞い姫はからだを横向きに長くしていた。
|
【舞姫かしづき下ろして】- 舞姫を牛車から大事に下ろしての意。
【かりそめのしつらひなるに】- 接続助詞「に」順接の意。『集成』は「臨時の座席を設けてあるところに」。『完訳』は「仮の部屋を設けてあるのだが」と訳す。
|
| 6.2.5 |
|
ちょうど、あの姫君と同じくらいに見えて、もう少し背丈がすらっとしていて、姿つきなどが一段と風情があって、美しい点では勝ってさえ見える。
暗いので、詳しくは見えないが、全体の感じがたいそうよく似ている様子なので、心が移るというのではないが、気持ちを抑えかねて、裾を引いてさらさらと音を立てさせなさると、何か分からず、変だと思っていると、
|
ちょうど雲井の雁と同じほどの年ごろであった。それよりも少し背が高くて、全体の姿にあざやかな美しさのある点は、その人以上にさえも見えた。暗かったからよくは見えないのであるが、年ごろが同じくらいで恋人の思われる点がうれしくて、恋が移ったわけではないがこれにも関心は持たれた。若君は衣服の褄先を引いて音をさせてみた。思いがけぬことで怪しがる顔を見て、
|
【ただ、かの人の御ほどと見えて】- 雲居雁と同じ年格好。
【衣の裾を引き鳴らいたまふに】- 大島本は「ひきならい給に」とある。『新大系』は底本のままとし文を続ける。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「たまふ」と校訂し文を切る。『集成』は「舞姫の衣の裾を引っ張って、衣ずれの音をおさせになる」。『完訳』は「ご自分の着物の裾を引き鳴らして注意をおひきになる」と訳す。
|
| 6.2.6 |
|
「天にいらっしゃる豊岡姫に仕える宮人も
わたしのものと思う気持ちを忘れないでください
|
「天にます豊岡姫の宮人も
わが志すしめを忘るな
|
【天にます豊岡姫の宮人も--わが心ざすしめを忘るな】- 夕霧から五節舞姫への贈歌。『集成』は「伊勢外宮の豊受大神であろう」。『完訳』は「天照大神」と注す。「みてぐらは我がにはあらず天にます豊岡姫の宮のみてぐら」(拾遺集、五七九、神楽歌)を引く。
|
| 6.2.7 |
|
瑞垣のずっと昔から思い染めてきましたのですから」
|
『みづがきの』(久しき世より思ひ初めてき)」
|
【乙女子が袖振る山の瑞垣の】- 大島本は「おとめこか袖ふる山のミつかきの」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「みづがきの」と「おとめこか袖ふる山の」を削除する。和歌に添えた詞。「乙女子が袖振る山の瑞垣の久しき世より思ひそめてき」(拾遺集雑恋、一二一〇、柿本人麿)を引く。
|
| 6.2.8 |
|
とおっしゃるのは、あまりにも唐突というものである。
|
と言ったが、藪から棒ということのようである。
|
【うちつけなりける】- 『完訳』は「読者の反応を先取りする評」と注す。
|
| 6.2.9 |
若うをかしき声なれど、誰ともえ思ひたどられず、なまむつかしきに、化粧じ添ふとて、騷ぎつる後見ども、近う寄りて人騒がしうなれば、いと口惜しうて、立ち去りたまひぬ。
|
若々しく美しい声であるが、誰とも分からず、薄気味悪く思っていたところへ、化粧し直そうとして、騒いでいる女房たちが、近くにやって来て騒がしくなったので、とても残念な気がして、お立ち去りになった。
|
若々しく美しい声をしているが、だれであるかを舞い姫は考え当てることもできない。気味悪く思っている時に、顔の化粧を直しに、騒がしく世話役の女が幾人も来たために、若君は残念に思いながらその部屋を立ち去った。
|
|
|
第三段 宮中における五節の儀
|
| 6.3.1 |
|
浅葱の服が嫌なので、宮中に参内することもせず、億劫がっていらっしゃるのを、五節だからというので、直衣なども特別の衣服の色を許されて参内なさる。
いかにも幼げで美しい方であるが、お年のわりに大人っぽくて、しゃれてお歩きになる。
帝をはじめ参らせて、大切になさる様子は並大抵でなく、世にも珍しいくらいのご寵愛である。
|
浅葱の袍を着て行くことがいやで、若君は御所へ行くこともしなかったが、五節を機会に、好みの色の直衣を着て宮中へ出入りすることを若君は許されたので、その夜から御所へも行った。まだ小柄な美少年は、若公達らしく御所の中を遊びまわっていた。帝をはじめとしてこの人をお愛しになる方が多く、ほかには類もないような御恩寵を若君は身に負っているのであった。
|
【浅葱の心やましければ、内裏へ参ることもせず】- 大島本は朱筆補入。
【されありきたまふ】- 『集成』は「浮かれて歩き廻られる」。『完訳』は「はしゃぎまわっていらっしゃる」と訳す。
|
| 6.3.2 |
五節の参る儀式は、いづれともなく、心々に二なくしたまへるを、「舞姫の容貌、大殿と大納言とはすぐれたり」とめでののしる。げに、いとをかしげなれど、ここしううつくしげなることは、なほ大殿のには、え及ぶまじかりけり。 |
五節の参内する儀式は、いずれ劣らず、それぞれがこの上なく立派になさっているが、「舞姫の器量は、大殿と大納言のとは素晴らしい」という大評判である。
なるほど、とてもきれいであるが、おっとりとして可憐なさまは、やはり大殿のには、かないそうもなかった。
|
五節の舞い姫がそろって御所へはいる儀式には、どの舞い姫も盛装を凝らしていたが、美しい点では源氏のと、大納言の舞い姫がすぐれていると若い役人たちはほめた。実際二人ともきれいであったが、ゆったりとした美しさはやはり源氏の舞い姫がすぐれていて、大納言のほうのは及ばなかったようである。
|
【大殿と大納言とは】- 惟光の娘と按察使大納言の娘とは、の意。
|
| 6.3.3 |
|
どことなくきれいな感じの当世風で、誰の娘だか分からないよう飾り立てた姿態などが、めったにないくらい美しいのを、このように褒められるようである。
例年の舞姫よりは、皆少しずつ大人びていて、なるほど特別な年である。
|
きれいで、現代的で、五節の舞い姫などというもののようでないつくりにした感じよさがこうほめられるわけであった。例年の舞い姫よりも少し大きくて前から期待されていたのにそむかない五節の舞い姫たちであった。
|
【かう誉めらるるなめり】- 「なめり」連語。断定の助動詞「な」+主観的推量の助動詞「めり」。『完訳』は「語り手の推測による語り口」と注す。
【げに心ことなる年なり】- 『完訳』は「「げに」は、帝の仰せ言(「宮仕へすべく仰せ言ことなる年なれば」)をさす」と注す。
|
| 6.3.4 |
|
大殿が宮中に参内なさって御覧になると、昔お目をとどめなさった少女の姿をお思い出しになる。
辰の日の暮方に手紙をやる。
その内容はご想像ください。
|
源氏も参内して陪観したが、五節の舞い姫の少女が目にとまった昔を思い出した。辰の日の夕方に大弐の五節へ源氏は手紙を書いた。内容が想像されないでもない。
|
【昔御目とまりたまひし少女の姿思し出づ】- 主語は源氏。筑紫五節(「花散里」巻初出)をさす。
【辰の日の暮つ方つかはす】- 五節舞の最終日。筑紫五節に歌を贈った。
【御文のうち思ひやるべし】- 語り手の詞。『完訳』は「源氏の心内を想像させる言辞」と注す。
|
| 6.3.5 |
|
「少女だったあなたも神さびたことでしょう
天の羽衣を着て舞った昔の友も長い年月を経たので」
|
少女子も神さびぬらし天つ袖
ふるき世の友よはひ経ぬれば
|
【乙女子も神さびぬらし天つ袖--古き世の友よはひ経ぬれば】- 源氏から筑紫五節への贈歌。
|
| 6.3.6 |
|
歳月の流れを数えて、ふとお思い出しになられたままの感慨を、堪えることができずに差し上げたのが、胸をときめかせるのも、はかないことであるよ。
|
五節は今日までの年月の長さを思って、物哀れになった心持ちを源氏が昔の自分に書いて告げただけのことである、これだけのことを喜びにしなければならない自分であるということをはかなんだ。
|
【をかしうおぼゆるも、はかなしや】- 『集成』は「源氏のお手紙を受け取った筑紫の五節の気持をいう草子地」。『完訳』は「「をかしう」は五節の君の反応。「はかなしや」は、語り手の評」と注す。
|
| 6.3.7 |
|
「五節のことを言いますと、
昔のことが今日のことのよう
|
かけて言はば今日のこととぞ思ほゆる
日かげの霜の袖にとけしも
|
【かけて言へば今日のこととぞ思ほゆる--日蔭の霜の袖にとけしも】- 筑紫五節の返歌。「袖」の語句を受けて返す。
|
| 6.3.8 |
青摺りの紙よくとりあへて、紛らはし書いたる、濃墨、薄墨、草がちにうち交ぜ乱れたるも、人のほどにつけてはをかしと御覧ず。 |
青摺りの紙をよく間に合わせて、誰の筆跡だか分からないように書いた、濃く、また薄く、草体を多く交えているのも、あの身分にしてはおもしろいと御覧になる。
|
新嘗祭の小忌の青摺りを模様にした、この場合にふさわしい紙に、濃淡の混ぜようをおもしろく見せた漢字がちの手紙も、その階級の女には適した感じのよい返事の手紙であった。
|
【人のほどにつけては】- 大宰大弐の娘という身分のわりにはの意。
|
| 6.3.9 |
|
冠者の君も、少女に目が止まるにつけても、ひそかに思いをかけてあちこちなさるが、側近くにさえ寄せず、たいそう無愛想な態度をしているので、もの恥ずかしい年頃の身では、心に嘆くばかりであった。
器量はそれは、とても心に焼きついて、つれない人に逢えない慰めにでも、手に入れたいものだと思う。
|
若君も特に目だった美しい自家の五節を舞の庭に見て、逢ってものを言う機会を作りたく、楽屋のあたりへ行ってみるのであったが、近い所へ人も寄せないような警戒ぶりであったから、羞恥心の多い年ごろのこの人は歎息するばかりで、それきりにしてしまった。美貌であったことが忘られなくて、恨めしい人に逢われない心の慰めにはあの人を恋人に得たいと思っていた。
|
【あたり近くだに寄せず】- 主語は五節舞姫の介添役たち。
【つらき人の慰めにも、見るわざしてむや】- 夕霧の心中。「つらき人」は雲居雁をさす。
|
|
第四段 夕霧、舞姫の弟に恋文を託す
|
| 6.4.1 |
|
そのまま皆宮中に残させなさって、宮仕えするようにとの御内意があったが、この場は退出させて、近江守の娘は辛崎の祓い、津守のは難波で祓いをと、競って退出した。
大納言も改めて出仕させたい旨を奏上させる。
左衛門督は、資格のない者を差し上げて、お咎めがあったが、それも残させなさる。
|
五節の舞い姫は皆とどまって宮中の奉仕をするようとの仰せであったが、いったんは皆退出させて、近江守のは唐崎、摂津守の子は浪速で祓いをさせたいと願って自宅へ帰った。大納言も別の形式で宮仕えに差し上げることを奏上した。左衛門督は娘でない者を娘として五節に出したということで問題になったが、それも女官に採用されることになった。
|
【やがて皆とめさせたまひて】- 主語は帝なので、「させたまひて」は使役助動詞+尊敬の補助動詞また二重敬語の最高尊敬とも解しうる。
【近江のは辛崎の祓へ、津の守は難波と】- 良清の娘は近江国の辛崎で、惟光の娘は津国の難波で、それぞれ父親の任国で神事を解くための祓いをする。
【左衛門督、その人ならぬをたてまつりて】- 『集成』は「実子でない娘を差し出したのだろう」。『完訳』は「資格のない人を。詳細は不明」と注す。
|
| 6.4.2 |
|
津守は、「典侍が空いているので」と申し上げさせたので、「そのように労をねぎらってやろうか」と大殿もお考えになっていたのを、あの冠者の君はお聞きになって、とても残念だと思う。
|
惟光は典侍の職が一つあいてある補充に娘を採用されたいと申し出た。源氏もその希望どおりに優遇をしてやってもよいという気になっていることを、若君は聞いて残念に思った。
|
【典侍あきたるに】- 惟光の詞の主旨。
【申させたれば】- 惟光が人をして源氏に間接的に意向を伝えさせた意。
【さもや労らまし】- 源氏の心中。
【かの人】- 夕霧をさす。
|
| 6.4.3 |
「わが年のほど、位など、かくものげなからずは、乞ひ見てましものを。思ふ心ありとだに知られでやみなむこと」 |
「自分の年齢や、位などが、このように問題でないならば、願い出てみたいのだが。
思っているということさえ知られないで終わってしまうことよ」
|
自分がこんな少年でなく、六位級に置かれているのでなければ、女官などにはさせないで、父の大臣に乞うて同棲を黙認してもらうのであるが、現在では不可能なことである。
|
【わが年のほど】- 以下「やみなむこと」まで、夕霧の心中。
|
| 6.4.4 |
と、わざとのことにはあらねど、うち添へて涙ぐまるる折々あり。 |
と、特別強く執心しているのではないが、あの姫君のことに加えて涙がこぼれる時々がある。
|
恋しく思う心だけも知らせずに終わるのかと、たいした思いではなかったが、雲井の雁を思って流す涙といっしょに、そのほうの涙のこぼれることもあった。
|
【うち添へて】- 雲居雁のことをさす。
|
| 6.4.5 |
|
兄弟で童殿上する者が、つねにこの君に参上してお仕えしているのを、いつもよりも親しくご相談なさって、
|
五節の弟で若君にも丁寧に臣礼を取ってくる惟光の子に、ある日逢った若君は平生以上に親しく話してやったあとで言った。
|
【兄弟の童殿上する】- 五節舞姫の弟で童殿上している者。
|
| 6.4.6 |
|
「五節はいつ宮中に参内なさるのか」
|
「五節はいつ御所へはいるの」
|
【五節はいつか内裏へ参る】- 大島本は「うちへ」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「内裏へは」と「は」を補訂する。夕霧の詞。
|
| 6.4.7 |
と問ひたまふ。
|
とお尋ねになる。
|
|
|
| 6.4.8 |
|
「今年と聞いております」
|
「今年のうちだということです」
|
【今年とこそは聞きはべれ】- 五節の弟の詞。
|
| 6.4.9 |
と聞こゆ。
|
と申し上げる。
|
|
|
| 6.4.10 |
|
「顔がたいそうよかったので、無性に恋しい気がする。
おまえがいつも見ているのが羨ましいが、もう一度見せてくれないか」
|
「顔がよかったから私はあの人が好きになった。君は姉さんだから毎日見られるだろうからうらやましいのだが、私にももう一度見せてくれないか」
|
【顔のいとよかりしかば】- 以下「また見せてむや」まで、夕霧の詞。
【ましが】- 「まし」は二人称。同等又は目下の者に対する呼称。「が」格助詞。
|
| 6.4.11 |
とのたまへば、
|
とおっしゃると、
|
|
|
| 6.4.12 |
「いかでかさははべらむ。心にまかせてもえ見はべらず。男兄弟とて、近くも寄せはべらねば、まして、いかでか君達には御覧ぜさせむ」 |
「どうしてそのようなことができましょうか。
思うように会えないのでございます。
男兄弟だといって、近くに寄せませんので、まして、あなた様にはどうしてお会わせ申すことができましょうか」
|
「そんなこと、私だってよく顔なんか見ることはできませんよ。男の兄弟だからって、あまりそばへ寄せてくれませんのですもの、それだのにあなたなどにお見せすることなど、だめですね」
|
【いかでかさははべらむ】- 以下「御覧ぜさせむ」まで、五節の弟の詞。
|
| 6.4.13 |
と聞こゆ。
|
と申し上げる。
|
と言う。
|
|
| 6.4.14 |
|
「それでは、せめて手紙だけでも」
|
「じゃあ手紙でも持って行ってくれ」
|
【さらば、文をだに】- 夕霧の詞。
|
| 6.4.15 |
|
といってお与えになった。
「以前からこのようなことはするなと親が言われていたものを」と困ったが、無理やりにお与えになるので、気の毒に思って持って行った。
|
と言って、若君は惟光の子に手紙を渡した。これまでもこんな役をしてはいつも家庭でしかられるのであったがと迷惑に思うのであるが、ぜひ持ってやらせたそうである若君が気の毒で、その子は家へ持って帰った。
|
【先々かやうのことは言ふものを】- 父親から姉妹への文使いを禁止されていたことをいう。
|
| 6.4.16 |
|
年齢よりは、ませていたのであろうか、興味をもって見るのであった。
緑色の薄様に、好感の持てる色を重ねて、筆跡はまだとても子供っぽいが、将来性が窺えて、たいそう立派に、
|
五節は年よりもませていたのか、若君の手紙をうれしく思った。緑色の薄様の美しい重ね紙に、字はまだ子供らしいが、よい将来のこもった字で感じよく書かれてある。
|
【年のほどよりは、されてやありけむ】- 語り手の挿入句。五節舞姫の人柄を推測したもの。
【緑の薄様の、好ましき重ねなるに】- 恋文にふさわしい紙及び和歌の文句(日蔭の葛)に因んだ色紙である。
|
| 6.4.17 |
|
「日の光にはっきりとおわかりになったでしょう
あなたが天の羽衣も翻して舞う姿に思いをかけたわたしのことを」
|
日かげにもしるかりけめや少女子が
天の羽袖にかけし心は
|
【日影にもしるかりけめや少女子が--天の羽袖にかけし心は】- 夕霧の五節舞姫への贈歌。
|
| 6.4.18 |
|
二人で見ているところに、父殿がひょいとやって来た。
恐くなってどうしていいか分からず、隠すこともできない。
|
姉と弟がこの手紙をいっしょに読んでいる所へ思いがけなく父の惟光大人が出て来た。隠してしまうこともまた恐ろしくてできぬ若い姉弟であった。
|
【二人見るほどに】- 五節舞姫とその弟が。
【父主】- 惟光。「主」は軽い敬語。
【恐ろしうあきれて】- 『集成』は「度を失って」。『完訳』は「恐ろしくてどうしてよいのか分らず」と訳す。
|
| 6.4.19 |
|
「何の手紙だ」
|
「それは、だれの手紙」
|
【なぞの文ぞ】- 惟光の詞。
|
| 6.4.20 |
とて取るに、面赤みてゐたり。
|
と言って取ったので、顔を赤らめていた。
|
父が手に取るのを見て、姉も弟も赤くなってしまった。
|
|
| 6.4.21 |
|
「けしからぬことをした」
|
「よくない使いをしたね」
|
【よからぬわざしけり】- 惟光の詞。
|
| 6.4.22 |
と憎めば、せうと逃げて行くを、呼び寄せて、
|
と叱ると、男の子が逃げて行くのを、呼び寄せて、
|
としかられて、逃げて行こうとする子を呼んで、
|
|
| 6.4.23 |
|
「誰からだ」
|
「だれから頼まれた」
|
【誰がぞ】- 惟光の詞。
|
| 6.4.24 |
と問へば、
|
と尋ねると、
|
と惟光が言った。
|
|
| 6.4.25 |
|
「大殿の冠者の君が、これこれしかじかとおっしゃってお与えになったのです」
|
「殿様の若君がぜひっておっしゃるものだから」
|
【殿の冠者の君の、しかしかのたまうて賜へる】- 五節舞姫の弟の詞。
|
| 6.4.26 |
と言へば、名残なくうち笑みて、
|
と言うと、すっかり笑顔になって、
|
と答えるのを聞くと、惟光は今まで怒っていた人のようでもなく、笑顔になって、
|
|
| 6.4.27 |
|
「何ともかわいらしい若君のおたわむれだ。
おまえたちは、同じ年齢だが、お話にならないくらい頼りないことよ」
|
「何というかわいいいたずらだろう。おまえなどは同い年でまだまったくの子供じゃないか」
|
【いかにうつくしき君の】- 以下「はかなかめりかし」まで、惟光の詞。
【きむぢらは】- 「きむぢ」は、二人称。「まし」よりやや敬意がある。「ら」は複数を表す接尾語。
|
| 6.4.28 |
など誉めて、母君にも見す。
|
などと褒めて、母君にも見せる。
|
とほめた。妻にもその手紙を見せるのであった。
|
|
| 6.4.29 |
|
「大殿の公達が、すこしでも一人前にお考えになってくださるならば、宮仕えよりは、差し上げようものを。
大殿のご配慮を見ると、一度見初めた女性を、お忘れにならないのがたいそう頼もしい。
明石の入道の例になるだろうか」
|
「こうした貴公子に愛してもらえば、ただの女官のお勤めをさせるより私はそのほうへ上げてしまいたいくらいだ。殿様の御性格を見ると恋愛関係をお作りになった以上、御自身のほうから相手をお捨てになることは絶対にないようだ。私も明石の入道になるかな」
|
【この君達の】- 以下「例にやならまし」まで、惟光の詞。「この君達」は夕霧をさす。
【御心おきて見るに】- 大島本は「御心をきて」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「御心おきてを」と「を」を補訂する。
【忘れたまふまじきとこそ】- 大島本は「とこそ」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「まじきにこそ」と校訂する。
|
| 6.4.30 |
など言へど、皆急ぎ立ちにたり。
|
などと言うが、皆は準備にとりかかっていた。
|
などと惟光は言っていたが、子供たちは皆立って行ってしまった。
|
|
|
第五段 花散里、夕霧の母代となる
|
| 6.5.1 |
かの人は、文をだにえやりたまはず、立ちまさる方のことし心にかかりて、ほど経るままに、わりなく恋しき面影にまたあひ見でやと思ふよりほかのことなし。宮の御もとへ、あいなく心憂くて参りたまはず。おはせしかた、年ごろ遊び馴れし所のみ、思ひ出でらるることまされば、里さへ憂くおぼえたまひつつ、また籠もりゐたまへり。 |
あの若君は、手紙をやることさえおできになれず、一段と恋い焦がれる方のことが心にかかって、月日がたつにつれて、無性に恋しい面影に再び会えないのではないかとばかり思っている。
大宮のお側へも、何となく気乗りがせず参上なさらない。
いらっしゃったお部屋や長年一所に遊んだ所ばかりが、ますます思い出されるので、里邸までが疎ましくお思いになられて、籠もっていらっしゃった。
|
若君は雲井の雁へ手紙を送ることもできなかった。二つの恋をしているが、一つの重いほうのことばかりが心にかかって、時間がたてばたつほど恋しくなって、目の前を去らない面影の主に、もう一度逢うということもできぬかとばかり歎かれるのである。祖母の宮のお邸へ行くこともわけなしに悲しくてあまり出かけない。その人の住んでいた座敷、幼い時からいっしょに遊んだ部屋などを見ては、胸苦しさのつのるばかりで、家そのものも恨めしくなって、また勉強所にばかり引きこもっていた。
|
【宮の御もとへ】- 大島本は「御もとへ」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「御もとへも」と「も」を補訂する。
【おはせしかた】- 主語は雲居雁。
【籠もりゐたまへり】- 夕霧は二条東院の学問所に。
|
| 6.5.2 |
|
大殿は、東院の西の対の御方に、お預け申し上げていらっしゃったのであった。
|
源氏は同じ東の院の花散里夫人に、母としての若君の世話を頼んだ。
|
【西の対にぞ、聞こえ預けたてまつりたまひける】- 源氏は、二条東院の西の対の花散里に夕霧のお世話を依頼。
|
| 6.5.3 |
「大宮の御世の残り少なげなるを、おはせずなりなむのちも、かく幼きほどより見ならして、後見おぼせ」 |
「大宮のご寿命も大したことがないので、お亡くなりになった後も、このように子供の時から親しんで、お世話してください」
|
「大宮はお年がお年だから、いつどうおなりになるかしれない。お薨れになったあとのことを思うと、こうして少年時代から馴らしておいて、あなたの厄介になるのが最もよいと思う」
|
【大宮の】- 以下「後見おぼせ」まで、源氏の詞。
|
| 6.5.4 |
と聞こえたまへば、ただのたまふままの御心にて、なつかしうあはれに思ひ扱ひたてまつりたまふ。
|
と申し上げなさると、ただおっしゃっるとおりになさるご性質なので、親しくかわいがって上げなさる。
|
と源氏は言うのであった。すなおな性質のこの人は、源氏の言葉に絶対の服従をする習慣から、若君を愛して優しく世話をした。
|
|
| 6.5.5 |
|
ちらっとなどお顔を拝見しても、
|
若君は養母の夫人の顔をほのかに見ることもあった。
|
【ほのかになど見たてまつるにも】- 夕霧が花散里を。
|
| 6.5.6 |
「容貌のまほならずもおはしけるかな。かかる人をも、人は思ひ捨てたまはざりけり」など、「わが、あながちに、つらき人の御容貌を心にかけて恋しと思ふもあぢきなしや。心ばへのかやうにやはらかならむ人をこそあひ思はめ」 |
「器量はさほどすぐれていないな。
このような方をも、父はお捨てにならなかったのだ」などと、「自分は、無性に、つらい人のご器量を心にかけて恋しいと思うのもつまらないことだ。
気立てがこのように柔和な方をこそ愛し合いたいものだ」
|
よくないお顔である。こんな人を父は妻としていることができるのである、自分が恨めしい人の顔に執着を絶つことのできないのも、自分の心ができ上がっていないからであろう、こうした優しい性質の婦人と夫婦になりえたら幸福であろうと、こんなことを若君は思ったが、
|
【容貌の】- 以下「思ひ捨てたまはざりけり」まで、夕霧の心中。
【わが、あながちに】- 以下「あひ思はめ」まで、夕霧の心中。
|
| 6.5.7 |
と思ふ。
また、
|
と思う。
また一方で、
|
しかし
|
|
| 6.5.8 |
|
「向かい合っていて見ていられないようなのも気の毒な感じだ。
こうして長年連れ添っていらっしゃったが、父上が、そのようなご器量を、承知なさったうえで、浜木綿ほどの隔てを置き置きして、何やかやとなさって見ないようにしていらっしゃるらしいのも、もっともなことだ」
|
あまりに美しくない顔の妻は向かい合った時に気の毒になってしまうであろう、こんなに長い関係になっていながら、容貌の醜なる点、性質の美な点を認めた父君は、夫婦生活などは疎にして、妻としての待遇にできるかぎりの好意を尽くしていられるらしい。それが合理的なようであるとも若君は思った。
|
【向ひて見るかひなからむも】- 以下「むべなりけり」まで、夕霧の心中。『完訳』は「かくて」以下を夕霧の心中とする。
【浜木綿ばかりの隔て】- 「み熊野の浦の浜木綿百重なる心は思へどただにあはぬかも」(拾遺集恋一、六六八、柿本人麿)を引く。
|
| 6.5.9 |
|
と考える心の中は、大したほどである。
|
そんなことまでもこの少年は観察しえたのである。
|
【恥づかしかりける】- 『集成』は「大人も顔負けの観察ぶりなのだった。草子地」。『完訳』は「語り手の夕霧評。彼の目と心が源氏の本性を捉え、その存在を相対化」と注す。
|
| 6.5.10 |
|
大宮の器量は格別でいらっしゃるが、まだたいそう美しくいらっしゃり、こちらでもあちらでも、女性は器量のよいものとばかり目馴れていらっしゃるが、もともとさほどでなかったご器量が、少し盛りが過ぎた感じがして、痩せてみ髪が少なくなっているのなどが、このように難をつけたくなるのであった。
|
大宮は尼姿になっておいでになるがまだお美しかったし、そのほかどこでこの人の見るのも相当な容貌が集められている女房たちであったから、女の顔は皆きれいなものであると思っていたのが、若い時から美しい人でなかった花散里が、女の盛りも過ぎて衰えた顔は、痩せた貧弱なものになり、髪も少なくなっていたりするのを見て、こんなふうに思うのである。
|
【容貌ことにおはしませど】- 出家した尼姿である。
【ここにもかしこにも】- 『集成』は「どちらへ行っても、女の人といえば美人だとばかり見つけていらっしゃるのに」。『完訳』は「大宮も雲居雁も惟光の娘も」と訳す。
【もとよりすぐれざりける】- 以下、花散里の描写。
|
|
第六段 歳末、夕霧の衣装を準備
|
| 6.6.1 |
年の暮には、睦月の御装束など、宮はただ、この君一所の御ことを、まじることなういそぎたまふ。あまた領、いときよらに仕立てたまへるを見るも、もの憂くのみおぼゆれば、 |
年の暮には、正月のご装束などを、大宮はただこの冠君の君の一人だけの事を、余念なく準備なさる。
いく組も、たいそう立派に仕立てなさったのを見るのも、億劫にばかり思われるので、
|
年末には正月の衣裳を大宮は若君のためにばかり仕度あそばされた。幾重ねも美しい春の衣服のでき上がっているのを、若君は見るのもいやな気がした。
|
【見るも、もの憂くのみおぼゆれば】- 主語は夕霧。六位の浅葱の衣裳だからである。
|
| 6.6.2 |
「朔日などには、かならずしも内裏へ参るまじう思ひたまふるに、何にかくいそがせたまふらむ」 |
「元旦などには、特に参内すまいと存じておりますのに、どうしてこのようにご準備なさるのでしょうか」
|
「元旦だって、私は必ずしも参内するものでないのに、何のためにこんなに用意をなさるのですか」
|
【朔日などには】- 以下「いそがせたまふらむ」まで、夕霧の詞。
|
| 6.6.3 |
と聞こえたまへば、
|
と申し上げなさると、
|
|
|
| 6.6.4 |
「などてか、さもあらむ。老いくづほれたらむ人のやうにものたまふかな」 |
「どうして、そのようなことがあってよいでしょうか。
年をとってすっかり気落ちした人のようなことをおっしゃいますね」
|
「そんなことがあるものですか。廃人の年寄りのようなことを言う」
|
【などてか】- 以下「のたまふかな」まで、大宮の詞。
|
| 6.6.5 |
とのたまへば、
|
とおっしゃるので、
|
|
|
| 6.6.6 |
|
「年はとっていませんが、何もしたくない気がしますよ」
|
「年寄りではありませんが廃人の無力が自分に感じられる」
|
【老いねど】- 以下「心地ぞするや」まで、夕霧の詞。
|
| 6.6.7 |
と独りごちて、うち涙ぐみてゐたまへり。
|
と独り言をいって、涙ぐんでいらっしゃる。
|
若君は独言を言って涙ぐんでいた。
|
|
| 6.6.8 |
|
「あの姫君のことを思っているのだろう」と、とても気の毒になって、大宮も泣き顔になってしまわれた。
|
失恋を悲しんでいるのであろうと、哀れに御覧になって宮も寂しいお顔をあそばされた。
|
【かのことを思ふならむ」と】- 大宮の心中。雲居雁のことを思っているのだろうの意。
|
| 6.6.9 |
「男は、口惜しき際の人だに、心を高うこそつかふなれ。あまりしめやかに、かくなものしたまひそ。何とか、かう眺めがちに思ひ入れたまふべき。ゆゆしう」 |
「男は、取るに足りない身分の人でさえ、気位を高く持つものです。
あまり沈んで、こうしていてはなりません。
どうして、こんなにくよくよ思い詰めることがありましょうか。
縁起でもありません」
|
「男性というものは、どんな低い身分の人だって、心持ちだけは高く持つものです。あまりめいったそうしたふうは見せないようになさいよ。あなたがそんなに思い込むほどの価値のあるものはないではないか」
|
【男は】- 以下「ゆゆしう」まで、大宮の詞。
|
| 6.6.10 |
|
とおっしゃるが、
|
|
【とのたまふも】- 大島本は「との給も」とある。『新大系』は底本のままとし文を続ける。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「とのたまふ」と文を切る。
|
| 6.6.11 |
|
「そんなことはありません。
六位などと人が軽蔑するようなので、少しの間だとは存じておりますが、参内するのも億劫なのです。
故祖父大臣が生きていらっしゃったならば、冗談にも、人からは軽蔑されることはなかったでございましょうに。
何の遠慮もいらない実の親でいらしゃいますが、たいそう他人行儀に遠ざけるようになさいますので、いらっしゃる所にも、気安くお目通りもかないません。
東の院にお出での時だけ、お側近く上がります。
対の御方だけは、やさしくしてくださいますが、母親が生きていらっしゃいましたら、何も思い悩まなくてよかったものを」
|
「それは別にないのですが、六位だと人が軽蔑をしますから、それはしばらくの間のことだとは知っていますが、御所へ行くのも気がそれで進まないのです。お祖父様がおいでになったら、戯談にでも人は私を軽蔑なんかしないでしょう。ほんとうのお父様ですが、私をお扱いになるのは、形式的に重くしていらっしゃるとしか思われません。二条の院などで私は家族の一人として親しませてもらうようなことは絶対にできません。東の院でだけ私はあの方の子らしくしていただけます。西の対のお母様だけは優しくしてくださいます。もう一人私にほんとうのお母様があれば、私はそれだけでもう幸福なのでしょうがお祖母様」
|
【何かは】- 以下「思ひはべらまし」まで、夕霧の詞。
【もの隔てぬ親におはすれど】- 実の親源氏をいう。
【対の御方こそ、あはれにものしたまへ】- 「対の御方」は花散里をさす。夕霧の母代。「こそ--たまへ」係結び、逆接用法。
【親今一所おはしまさましかば】- 実の親葵の上をさす。「ましか」反実仮想の助動詞。
|
| 6.6.12 |
とて、涙の落つるを紛らはいたまへるけしき、いみじうあはれなるに、宮は、いとどほろほろと泣きたまひて、
|
と言って、涙が落ちるのを隠していらっしゃる様子、たいそう気の毒なので、大宮は、ますますほろほろとお泣きになって、
|
涙の流れるのを紛らしている様子のかわいそうなのを御覧になって、宮はほろほろと涙をこぼしてお泣きになった。
|
|
| 6.6.13 |
「母にも後るる人は、ほどほどにつけて、さのみこそあはれなれど、おのづから宿世宿世に、人と成りたちぬれば、おろかに思ふもなきわざなるを、思ひ入れぬさまにてものしたまへ。故大臣の今しばしだにものしたまへかし。限りなき蔭には、同じことと頼みきこゆれど、思ふにかなはぬことの多かるかな。内大臣の心ばへも、なべての人にはあらずと、世人もめで言ふなれど、昔に変はることのみまさりゆくに、命長さも恨めしきに、生ひ先遠き人さへ、かくいささかにても、世を思ひしめりたまへれば、いとなむよろづ恨めしき世なる」 |
「母親に先立たれた人は、身分の高いにつけ低いにつけて、そのように気の毒なことなのですが、自然とそれぞれの前世からの宿縁で、成人してしまえば、誰も軽蔑する者はいなくなるものですから、思い詰めないでいらっしゃい。
亡くなった太政大臣がせめてもう少しだけ長生きをしてくれればよかったのに。
絶大な庇護者としては、同じようにご信頼申し上げてはいますが、思いどおりに行かないことが多いですね。
内大臣の性質も、普通の人とは違って立派だと世間の人も褒めて言うようですが、昔と違う事ばかりが多くなって行くので、長生きも恨めしい上に、生い先の長いあなたにまで、このようなちょっとしたことにせよ、身の上を悲観していらっしゃるので、とてもいろいろと恨めしいこの世です」
|
「母を亡くした子というものは、各階級を通じて皆そうした心細い思いをしているのだけれど、だれにも自分の運命というものがあって、それぞれに出世してしまえば、軽蔑する人などはないのだから、そのことは思わないほうがいいよ。お祖父様がもうしばらくでも生きていてくだすったらよかったのだね、お父様がおいでなんだから、お祖父様くらいの愛はあなたに掛けていただけると信じてますけれど、思うようには行かないものなのだね。内大臣もりっぱな人格者のように世間で言われていても、私に昔のような平和も幸福もなくなっていくのはどういうわけだろう。私はただ長生きの罪にしてあきらめますが、若いあなたのような人を、こんなふうに少しでも厭世的にする世の中かと思うと恨めしくなります」
|
【母にも後るる人は】- 大島本は「はゝにも」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「母に」と「も」を削除する。以下「恨めしき世なる」まで、大宮の詞。
【おろかに思ふもなきわざなるを】- 大島本は「おもふもなき」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「思ふ人も」と「人」を補訂する。
【さまにてものしたまへ】- 大島本は「さまにて」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「さまにてを」と「を」を補訂する。
|
| 6.6.14 |
とて、泣きおはします。
|
と言って、泣いていらっしゃる。
|
と宮は泣いておいでになった。
|
|
|
第七章 光る源氏の物語 六条院造営
|
|
第一段 二月二十日過ぎ、朱雀院へ行幸
|
| 7.1.1 |
|
元旦にも、大殿は御参賀なさらないので、のんびりとしていっらしゃる。
良房の大臣と申し上げた方の、昔の例に倣って、白馬を牽き、節会の日は、宮中の儀式を模して、昔の例よりもいろいろな事を加えて、盛大なご様子である。
|
元日も源氏は外出の要がなかったから長閑であった。良房の大臣の賜わった古例で、七日の白馬が二条の院へ引かれて来た。宮中どおりに行なわれた荘重な式であった。
|
【朔日にも】- 源氏三十四歳の春正月元旦。
【大殿は御ありきしなければ】- 太政大臣の源氏は宮中参賀はしなくてもよい。
【良房の大臣と聞こえける、いにしへの例になずらへて、白馬ひき】- 藤原良房(八〇四~八七二)、諡忠仁公。人臣として初の摂政関白となる。白馬を私邸で牽いたという例は記録に見えないが、それを真似て源氏の二条院に白馬を牽くとする。
【節会の日】- 大島本は「せちゑの日」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「節会の日々」と校訂する。『集成』は「正月の節会には、元日の節会、七日の白馬の節会、十四日の男踏歌、十六日の女踏歌がある」と注す。
|
| 7.1.2 |
|
二月の二十日余りに、朱雀院に行幸がある。
花盛りはまだのころであるが、三月は故藤壷の宮の御忌月である。
早く咲いた桜の花の色もたいそう美しいので、院におかれてもお心配りし特にお手入れあそばして、行幸に供奉なさる上達部や親王たちをはじめとして、十分にご用意なさっていた。
|
二月二十幾日に朱雀院へ行幸があった。桜の盛りにはまだなっていなかったが、三月は母后の御忌月であったから、この月が選ばれたのである。早咲きの桜は咲いていて、春のながめはもう美しかった。お迎えになる院のほうでもいろいろの御準備があった。行幸の供奉をする顕官も親王方もその日の服装などに苦心を払っておいでになった。
|
【如月の二十日あまり、朱雀院に行幸あり。花盛りはまだしきほどなれど】- 仲春二月二十日過ぎの朱雀院行幸。この年の桜の花盛りはまだであるという。
【弥生は故宮の御忌月なり】- 藤壺は一昨年の源氏三十二歳の春三月に崩御した。
|
| 7.1.3 |
|
お供の人々は皆、青色の袍に、桜襲をお召しになる。
帝は、赤色の御衣をお召しあそばされた。
お召しがあって、太政大臣が参上なさる。
同じ赤色を着ていらっしゃるので、ますますそっくりで輝くばかりにお美しく見違えるほどとお見えになる。
人々の装束や、振る舞いも、いつもと違っている。
院も、たいそうおきれいにお年とともに御立派になられて、御様子や態度が、以前にもまして優雅におなりあそばしていた。
|
その人たちは皆青色の下に桜襲を用いた。帝は赤色の御服であった。お召しがあって源氏の大臣が参院した。同じ赤色を着ているのであったから、帝と同じものと見えて、源氏の美貌が輝いた。御宴席に出た人々の様子も態度も非常によく洗練されて見えた。院もますます清艶な姿におなりあそばされた。
|
【人びとみな、青色に、桜襲を着たまふ】- 行幸に供奉する人々の服装は麹塵の袍に桜の下襲。麹塵の袍は常は天皇が着用するが、晴れの儀式の折には、諸臣に麹塵の袍を賜り、帝は赤色の袍をお召しになる。また最上席の公卿も同じ赤色を着用するという(西宮記・河海抄)。
【御さまの用意】- 大島本は「御さまのようい」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「御さま、用意」と「の」を削除する。
|
| 7.1.4 |
今日は、わざとの文人も召さず、ただその才かしこしと聞こえたる学生十人を召す。式部の司の試みの題をなずらへて、御題賜ふ。大殿の太郎君の試みたまふべきなめり。臆だかき者どもは、ものもおぼえず、繋がぬ舟に乗りて池に放れ出でて、いと術なげなり。 |
今日は、専門の文人もお呼びにならず、ただ漢詩を作る才能の高いという評判のある学生十人をお呼びになる。
式部省の試験の題になぞらえて、勅題を賜る。
大殿のご長男の試験をお受けなさるようである。
臆しがちな者たちは、ぼおっとしてしまって、繋いでない舟に乗って、池に一人一人漕ぎ出して、実に途方に暮れているようである。
|
今日は専門の詩人はお招きにならないで、詩才の認められる大学生十人を召したのである。これを式部省の試験に代えて作詞の題をその人たちはいただいた。これは源氏の長男のためにわざとお計らいになったことである。気の弱い学生などは頭もぼうとさせていて、お庭先の池に放たれた船に乗って出た水上で製作に苦しんでいた。
|
【試みたまふべきなめり】- 大島本は「心ミ給へきなめり」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「試みたまふべきゆゑなめり」と「ゆゑ」を補訂する。「なめり」は語り手の言辞。
|
| 7.1.5 |
日やうやうくだりて、楽の舟ども漕ぎまひて、調子ども奏するほどの、山風の響きおもしろく吹きあはせたるに、冠者の君は、
|
日がだんだんと傾いてきて、音楽の舟が幾隻も漕ぎ廻って、調子を整える時に、山風の響きがおもしろく吹き合わせているので、冠者の君は、
|
夕方近くなって、音楽者を載せた船が池を往来して、楽音を山風に混ぜて吹き立てている時、若君は
|
|
| 7.1.6 |
|
「こんなにつらい修業をしなくても皆と一緒に音楽を楽しめたりできるはずのものを」
|
こんなに苦しい道を進まないでも自分の才分を発揮させる道はあるであろうが
|
【かう苦しき道ならでも交じらひ遊びぬべきものを】- 夕霧の心中。
|
| 7.1.7 |
と、世の中恨めしうおぼえたまひけり。
|
と、世の中を恨めしく思っていらっしゃった。
|
と恨めしく思った。
|
|
| 7.1.8 |
|
「春鴬囀」を舞うときに、昔の花の宴の時をお思い出しになって、院の帝が、
|
「春鶯囀」が舞われている時、昔の桜花の宴の日のことを院の帝はお思い出しになって、
|
【昔の花の宴のほど思し出でて】- 「花宴」巻、源氏十九歳春のこと。
【院の帝も】- 大島本は「院のみかとも」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「院の帝」と「も」を削除する。
|
| 7.1.9 |
「また、さばかりのこと見てむや」
|
「もう一度、
|
「もうあんなおもしろいことは見られないと思う」
|
|
| 7.1.10 |
とのたまはするにつけて、その世のことあはれに思し続けらる。
舞ひ果つるほどに、大臣、院に御土器参りたまふ。
|
と仰せられるにつけても、その当時のことがしみじみと次々とお思い出されなさる。
舞い終わるころに、太政大臣が、院にお杯を差し上げなさる。
|
と源氏へ仰せられたが、源氏はそのお言葉から青春時代の恋愛三昧を忍んで物哀れな気分になった。源氏は院へ杯を参らせて歌った。
|
|
| 7.1.11 |
|
「鴬の囀る声は昔のままですが
馴れ親しんだあの頃とはすっかり時勢が変わってしまいました」
|
鶯のさへづる春は昔にて
むつれし花のかげぞ変はれる
|
【鴬のさへづる声は昔にて--睦れし花の蔭ぞ変はれる】- 源氏の詠歌。桐壺帝の代から朱雀帝の代を経て冷泉帝の代へという時勢の推移変化をいう。
|
| 7.1.12 |
院の上、
|
院の上は、
|
院は、
|
|
| 7.1.13 |
|
「宮中から遠く離れた仙洞御所にも
春が来たと鴬の声が聞こえてきます」
|
九重を霞へだつる住処にも
春と告げくる鶯の声
|
【九重を霞隔つるすみかにも--春と告げくる鴬の声】- 朱雀院の唱和歌。「鴬」の語句を用いる。今日の行幸に感謝。お礼歌。
|
| 7.1.14 |
帥の宮と聞こえし、今は兵部卿にて、今の上に御土器参りたまふ。
|
帥宮と申し上げた方は、今では兵部卿となって、今上帝にお杯を差し上げなさる。
|
とお答えになった。太宰帥の宮といわれた方は兵部卿になっておいでになるのであるが、陛下へ杯を献じた。
|
|
| 7.1.15 |
|
「昔の音色そのままの笛の音に
さらに鴬の囀る声までもちっとも変わっていません」
|
いにしへを吹き伝へたる笛竹に
さへづる鳥の音さへ変はらぬ
|
【いにしへを吹き伝へたる笛竹に--さへづる鳥の音さへ変はらぬ】- 兵部卿宮の唱和歌。源氏の「変はれる」を、昔の聖代を引き継ぎ「変はらぬ」と寿ぐ。
|
| 7.1.16 |
あざやかに奏しなしたまへる、用意ことにめでたし。
取らせたまひて、
|
巧みにその場をおとりなしなさった、心づかいは特に立派である。
杯をお取りあそばして、
|
この歌を奏上した宮の御様子がことにりっぱであった。帝は杯をお取りになって、
|
|
| 7.1.17 |
|
「鴬が昔を慕って木から木へと飛び移って囀っていますのは
今の木の花の色が悪くなっているからでしょうか」
|
鶯の昔を恋ひて囀るは
木づたふ花の色やあせたる
|
【鴬の昔を恋ひてさへづるは--木伝ふ花の色やあせたる】- 今上帝の唱和歌。『集成』は「朱雀院のさびしい気持を汲んで、卑下したもの」と注す。
|
| 7.1.18 |
とのたまはする御ありさま、こよなくゆゑゆゑしくおはします。これは御私ざまに、うちうちのことなれば、あまたにも流れずやなりにけむ、また書き落してけるにやあらむ。 |
と仰せになる御様子、この上なく奥ゆかしくいらっしゃる。
このお杯事は、お身内だけのことなので、多数の方には杯が回らなかったのであろうか、または書き洩らしたのであろうか。
|
と仰せになるのが重々しく気高かった。この行幸は御家庭的なお催しで、儀式ばったことでなかったせいなのか、官人一同が詞歌を詠進したのではなかったのかその日の歌はこれだけより書き置かれていない。
|
【これは御私ざまに】- 以下「また書き落してけるにやあらむ」まで、語り手のことわり。『集成』は「これ以上作中人物の歌を紹介しないことについての語り手(作者)のことわり。草子地」。『完訳』は「以下、歌の唱和について語り手の省筆の弁」と注す。
|
| 7.1.19 |
楽所遠くておぼつかなければ、御前に御琴ども召す。兵部卿宮、琵琶。内大臣、和琴。箏の御琴、院の御前に参りて、琴は、例の太政大臣に賜はりたまふ。せめきこえたまふ。さるいみじき上手のすぐれたる御手づかひどもの、尽くしたまへる音は、たとへむかたなし。唱歌の殿上人あまたさぶらふ。「安名尊」遊びて、次に「桜人」。月おぼろにさし出でてをかしきほどに、中島のわたりに、ここかしこ篝火ども灯して、大御遊びはやみぬ。 |
楽所が遠くてはっきり聞こえないので、御前にお琴をお召しになる。
兵部卿宮は、琵琶。
内大臣は和琴。
箏のお琴は、院のお前に差し上げて、琴の琴は、例によって太政大臣が頂戴なさる。
お勧め申し上げなさる。
このような素晴らしい方たちによる優れた演奏で、秘術を尽くした楽の音色は、何ともたとえようがない。
唱歌の殿上人が多数伺候している。
「安名尊」を演奏して、次に「桜人」。
月が朧ろにさし出して美しいころに、中島のあたりにあちこちに篝火をいくつも灯して、この御遊は終わった。
|
奏楽所が遠くて、細かい楽音が聞き分けられないために、楽器が御前へ召された。兵部卿の宮が琵琶、内大臣は和琴、十三絃が院の帝の御前に差し上げられて、琴は例のように源氏の役になった。皆名手で、絶妙な合奏楽になった。歌う役を勤める殿上役人が選ばれてあって、「安名尊」が最初に歌われ、次に桜人が出た。月が朧ろに出て美しい夜の庭に、中島あたりではそこかしこに篝火が焚かれてあった。そうしてもう合奏が済んだ。
|
【琴は、例の太政大臣に賜はりたまふ。せめきこえたまふ】- 大島本は「おほきおとゝに給ハりたまふ・せめきこえ給」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「太政大臣賜りたまふ」と「に」と「せめきこえたまふ」を削除する。
【安名尊】- 催馬楽、呂。「あな尊今日の尊さやいにしへもはれいにしへもかくやありけむや今日の尊さあはれそこよしや今日の尊さ」。
【桜人】- 催馬楽、呂。「桜人その船止め島つ田を十町作れる見て帰り来むやそよや明日帰り来むそよや/言をこそ明日とも言はめ遠方に妻ざる夫は明日もさね来じやそよやさ明日もさね来じやそよや」。
|
|
第二段 弘徽殿大后を見舞う
|
| 7.2.1 |
夜更けぬれど、かかるついでに、大后の宮おはします方を、よきて訪らひきこえさせたまはざらむも、情けなければ、帰さに渡らせたまふ。
大臣もろともにさぶらひたまふ。
|
夜は更けてしまったが、このような機会に、太后宮のいらっしゃる方を、避けてお伺い申し上げなさらないのも、思いやりがないので、帰りにお立ち寄りになる。
大臣もご一緒に伺候なさる。
|
夜ふけになったのであるが、この機会に皇太后を御訪問あそばさないことも冷淡なことであると思召して、お帰りがけに帝はそのほうの御殿へおまわりになった。源氏もお供をして参ったのである。
|
|
| 7.2.2 |
|
大后宮はお待ち喜びになって、ご面会なさる。
とてもたいそうお年を召されたご様子にも、故宮をお思い出し申されて、「こんなに長生きされる方もいらっしゃるものを」と、残念にお思いになる。
|
太后は非常に喜んでお迎えになった。もう非常に老いておいでになるのを、御覧になっても帝は御母宮をお思い出しになって、こんな長生きをされる方もあるのにと残念に思召された。
|
【いといたうさだ過ぎたまひにける御けはひにも】- 弘徽殿大后は、この時、五十七、八歳ぐらい。
【故宮を思ひ出できこえたまひて】- 故入道宮藤壺。
【かく長くおはしますたぐひもおはしけるものを】- 源氏の心中。
|
| 7.2.3 |
|
「今ではこのように年を取って、すべての事柄を忘れてしまっておりましたが、まことに畏れ多くもお越し戴きましたので、改めて昔の御代のことが思い出されます」
|
「もう老人になってしまいまして、私などはすべての過去を忘れてしまっておりますのに、もったいない御訪問をいただきましたことから、昔の御代が忍ばれます」
|
【今はかく】- 以下「思ひ出でられはべる」まで、弘徽殿大后の詞。『完訳』は「かつて敵視した相手への、ばつの悪い物言いであろう」と注す。
【昔の御世のこと】- 桐壺院時代をさす。
|
| 7.2.4 |
と、うち泣きたまふ。
|
と、お泣きになる。
|
と太后は泣いておいでになった。
|
|
| 7.2.5 |
「さるべき御蔭どもに後れはべりてのち、春のけぢめも思うたまへわかれぬを、今日なむ慰めはべりぬる。またまたも」 |
「頼りになるはずの人々に先立たれて後、春になった気分も知らないでいましたが、今日初めて心慰めることができました。
時々はお伺い致します」
|
「御両親が早くお崩れになりまして以来、春を春でもないように寂しく見ておりましたが、今日はじめて春を十分に享楽いたしました。また伺いましょう」
|
【さるべき御蔭どもに】- 以下「またまたも」まで、帝の詞。父桐壺院や母藤壺に先立たれたことをいう。
|
| 7.2.6 |
と聞こえたまふ。
大臣もさるべきさまに聞こえて、
|
と御挨拶申し上げあそばす。
太政大臣もしかるべくご挨拶なさって、
|
と陛下は仰せられ、源氏も御挨拶をした。
|
|
| 7.2.7 |
|
「また改めてお伺い致しましょう」
|
「また別の日に伺候いたしまして」
|
【ことさらにさぶらひてなむ】- 源氏の詞。
|
| 7.2.8 |
と聞こえたまふ。
のどやかならで帰らせたまふ響きにも、后は、なほ胸うち騒ぎて、
|
と、申し上げなさる。
ゆっくりなさらずにお帰りあそばすご威勢につけても、大后は、やはりお胸が静まらず、
|
還幸の鳳輦をはなやかに百官の囲繞して行く光景が、物の響きに想像される時にも、太后は過去の御自身の態度の非を悔いておいでになった。源氏はどう自分の昔を思っているであろうと恥じておいでになった。一国を支配する人の持っている運は、
|
|
| 7.2.9 |
|
「どのように思い出していられるのだろう。
結局、政権をお執りになるというご運勢は、押しつぶせなかったのだ」
|
どんな咀いよりも強いものである
|
【いかに思し出づらむ】- 以下「消たれぬものにこそ」まで、弘徽殿大后の心中。『集成』は「(源氏を憎んだ)昔のことをどのようにお思い出しのことだろう。草子地」。完訳「以下、大后の心中。かつての迫害を源氏はどう思っているか」と注す。
|
| 7.2.10 |
と、いにしへを悔い思す。
|
と昔を後悔なさる。
|
とお悟りにもなった。
|
|
| 7.2.11 |
|
尚侍の君も、ゆったりした気分でお思い出しになると、しみじと感慨無量な事が多かった。
今でも適当な機会に、何かの伝で密かに便りを差し上げなさることがあるのであろう。
|
朧月夜の尚侍も静かな院の中にいて、過去を思う時々に、源氏とした恋愛の昔が今も身にしむことに思われた。近ごろでも源氏は好便に託して文通をしているのであった。
|
【尚侍の君も】- 朧月夜尚侍、朱雀院と同居。
【風のつてにもほのめききこえたまふこと絶えざるべし】- 語り手の推量。源氏が朧月夜に手紙を差し上げるこの意。
|
| 7.2.12 |
|
大后は朝廷に奏上なさることのある時々に、御下賜された年官や年爵、何かにつけながら、ご意向に添わない時には、「長生きをしてこんな酷い目に遭うとは」と、もう一度昔の御代に取り戻したく、いろいろとご機嫌悪がっているのであった。
|
太后は政治に御註文をお持ちになる時とか、御自身の推薦権の与えられておいでになる限られた官爵の運用についてとかに思召しの通らない時は、長生きをして情けない末世に苦しむというようなことをお言い出しになり、御無理も仰せられた。
|
【命長くてかかる世の末を見ること】- 弘徽殿大后の心中。「寿則辱多」(荘子、外篇、天地)、長生きをすると辛いことが多いの慣用句。
【よろづ思しむつかりける】- 大島本は「よろつ」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「よろづを」と「を」を補訂する。
|
| 7.2.13 |
老いもておはするままに、さがなさもまさりて、院もくらべ苦しう、たとへがたくぞ思ひきこえたまひける。 |
年を取っていかれるにつれて、意地の悪さも加わって、院ももてあまして、例えようもなくお思い申し上げていらっしゃるのだった。
|
年を取っておいでになるにしたがって、強い御気質がますます強くなって院もお困りになるふうであった。
|
【たとへがたくぞ】- 大島本は「たとへ」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「堪へがたく」と「と」を削除する。
|
| 7.2.14 |
かくて、大学の君、その日の文うつくしう作りたまひて、進士になりたまひぬ。年積もれるかしこき者どもを選らばせたまひしかど、及第の人、わづかに三人なむありける。 |
さて、大学の君は、その日の漢詩を見事にお作りになって、進士におなりになった。
長い年月修業した優れた者たちをお選びになったが、及第した人は、わずかに三人だけであった。
|
源氏の公子はその日の成績がよくて進士になることができた。碩学の人たちが選ばれて答案の審査にあたったのであるが、及第は三人しかなかったのである。
|
【選らばせたまひしかど】- 大島本は「えらハせ」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「選らせ」と「は」を削除する。
|
| 7.2.15 |
秋の司召に、かうぶり得て、侍従になりたまひぬ。
かの人の御こと、忘るる世なけれど、大臣の切にまもりきこえたまふもつらければ、わりなくてなども対面したまはず。
御消息ばかり、さりぬべきたよりに聞こえたまひて、かたみに心苦しき御仲なり。
|
秋の司召に、五位に叙されて、侍従におなりになった。
あの人のことを、忘れる時はないが、内大臣が熱心に監視申していらっしゃるのも恨めしいので、無理をしてまでもお目にかかることはなさらない。
ただお手紙だけを適当な機会に差し上げて、お互いに気の毒なお仲である。
|
そして若君は秋の除目の時に侍従に任ぜられた。雲井の雁を忘れる時がないのであるが、大臣が厳重に監視しているのも恨めしくて、無理をして逢ってみようともしなかった。手紙だけは便宜を作って送るというような苦しい恋を二人はしているのであった。
|
|
|
第三段 源氏、六条院造営を企図す
|
| 7.3.1 |
|
大殿は、静かなお住まいを、同じことなら広く立派にして、あちこちに別居して気がかりな山里人などをも、集め住まわせようとのお考えで、六条京極の辺りに、中宮の御旧居の近辺を、四町をいっぱいにお造りになる。
|
源氏は静かな生活のできる家を、なるべく広くおもしろく作って、別れ別れにいる、たとえば嵯峨の山荘の人などもいっしょに住ませたいという希望を持って、六条の京極の辺に中宮の旧邸のあったあたり四町四面を地域にして新邸を造営させていた。
|
【静かなる御住まひを】- 「造らせたまふ」に続く。
【六条京極のわたりに、中宮の御古き宮のほとりを】- 秋好中宮が母六条御息所から伝領した旧宮。六条院はそれを含めて四町の敷地に造営される。
【四町をこめて】- 大島本は「こめて」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「占めて」と校訂する。
|
| 7.3.2 |
|
式部卿宮が、明年五十歳におなりになる御賀のことを、対の上がお考えなので、大臣も、「なるほど、見過ごすわけにはいかない」とお思いになって、「そのようなご準備も、同じことなら新しい邸で」と、用意させなさる。
|
式部卿の宮は来年が五十におなりになるのであったから、紫夫人はその賀宴をしたいと思って仕度をしているのを見て、源氏もそれはぜひともしなければならぬことであると思い、そうした式もなるべくは新邸でするほうがよいと、そのためにも建築を急がせていた。
|
【式部卿宮、明けむ年ぞ五十になりたまひける】- 大島本は「なり給ける」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「なりたまひけるを」と「を」を補訂する。紫の上の父宮、明年五十歳になる。
【げに、過ぐしがたきことどもなり】- 源氏の心中。「げに」は紫の上に賛同する気持ち。
【同じくめづらしからむ】- 大島本は「おなしく」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「同じくは」と「は」を補訂する。
【いそがせたまふ】- 六条院の造営を急がせる。
|
| 7.3.3 |
|
年が改まってからは、昨年以上にこのご準備の事、御精進落としの事、楽人、舞人の選定などを、熱心に準備させなさる。
経、仏像、法事の日の装束、禄などを、対の上はご準備なさるのだった。
|
春になってからは専念に源氏は宮の五十の御賀の用意をしていた。落し忌の饗宴のこと、その際の音楽者、舞い人の選定などは源氏の引き受けていることで、付帯して行なわれる仏事の日の経巻や仏像の製作、法事の僧たちへ出す布施の衣服類、一般の人への纏頭の品々は夫人が力を傾けて用意していることであった。
|
【年返りて】- 大島本は「年かへりて」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「年かへりては」と「は」を補訂する。源氏三十五歳春を迎える。
【法事の日の装束、禄など】- 大島本は「法事の日のさうそくろくなと」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「法事の日の御装束、禄どもなど」と「御」と「ども」を補訂する。
|
| 7.3.4 |
東の院に、分けてしたまふことどもあり。御なからひ、ましていとみやびかに聞こえ交はしてなむ、過ぐしたまひける。 |
東の院で、分担してご準備なさることがある。
ご間柄は、いままで以上にとても優美にお手紙のやりとりをなさって、お過ごしになっているのであった。
|
東の院でも仕事を分担して助けていた。花散里夫人と紫の女王とは同情を互いに持って美しい交際をしているのである。
|
【東の院に】- 大島本は「ひんかしの院に」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「東の院にも」と「も」を補訂する。二条東院の女主人花散里をさす。
|
| 7.3.5 |
世の中響きゆすれる御いそぎなるを、式部卿宮にも聞こしめして、
|
世間中が大騒ぎしているご準備なので、式部卿宮のお耳にも入って、
|
世間までがこのために騒ぐように見える大仕掛けな賀宴のことを式部卿の宮もお聞きになった。
|
|
| 7.3.6 |
|
「長年の間、世間に対しては広大なお心であるが、わたくしどもには理不尽にも冷たくて、何かにつけて辱め、宮人に対してもお心配りがなく、嫌なことばかり多かったのだが、恨めしいと思うことがあったのだろう」
|
これまではだれのためにも慈父のような広い心を持つ源氏であるが御自身と御自身の周囲の者にだけは冷酷な態度を取り続けられておいでになるのを、源氏の立場になってみれば、恨めしいことが過去にあったのであろう
|
【年ごろ、世の中には】- 以下「ことこそはありけめ」まで、式部卿宮の心中。
【宮人をも】- 式部卿宮家に仕える人々をさす。
|
| 7.3.7 |
と、いとほしくもからくも思しけるを、かくあまたかかづらひたまへる人びと多かるなかに、取りわきたる御思ひすぐれて、世に心にくくめでたきことに、思ひかしづかれたまへる御宿世をぞ、わが家まではにほひ来ねど、面目に思すに、また、 |
と、お気の毒にもまたつらくもお思いであったが、このように数多くの女性関係の中で、特別のご寵愛があって、まことに奥ゆかしく結構な方として、大切にされていらっしゃるご運命を、自分の家までは及んで来ないが、名誉にお思いになると、また、
|
と、その時代の源氏夫婦を今さら気の毒にもお思いになり、こうした現状を苦しがっておいでになったが、源氏の幾人もある妻妾の中の最愛の夫人で女王があって、世間から敬意を寄せられていることも並み並みでない人が娘であることは、その幸福が自家へわけられぬものにもせよ、自家の名誉であることには違いないと思っておいでになった。それに今度の賀宴が、
|
【かくあまた】- 以下「面目に」まで、式部卿宮の心中と地の文が融合した形。「面目と」とあれば「思す」で受ける心中文となる。
【思ひかしづかれたまへる御宿世をぞ】- 娘の紫の上の運勢をいう。
|
| 7.3.8 |
「かくこの世にあまるまで、響かし営みたまふは、おぼえぬ齢の末の栄えにもあるべきかな」 |
「このように世間の評判となるまで、大騒ぎしてご準備なさるのは、思いがけない晩年の慶事だ」
|
源氏の勢力のもとでかつてない善美を尽くした準備が調えられているということをお知りになったのであるから、思いがけぬ老後の光栄を受ける
|
【かくこの世に】- 以下「あるべきかな」まで、式部卿宮の心中。
|
| 7.3.9 |
|
と、お喜びになるのを、北の方は、「おもしろくなく、不愉快だ」とばかりお思いであった。
王女御の、ご入内の折などにも、大臣のご配慮がなかったようなのを、ますます恨めしいと思い込んでいらっしゃるのであろう。
|
と感激しておいでになるが、宮の夫人は不快に思っていた。女御の後宮の競争にも源氏が同情的態度に出ないことで、いよいよ恨めしがっているのである。
|
【北の方は】- 式部卿宮の北の方、紫の上の継母。
【女御】- 大島本は「女御」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「女御の」と「の」を補訂する。式部卿宮の娘中の君、王女御をさす。
【思ひしみたまへるなるべし】- 語り手の推測。
|
|
第四段 秋八月に六条院完成
|
| 7.4.1 |
八月にぞ、六条院造り果てて渡りたまふ。未申の町は、中宮の御古宮なれば、やがておはしますべし。辰巳は、殿のおはすべき町なり。丑寅は、東の院に住みたまふ対の御方、戌亥の町は、明石の御方と思しおきてさせたまへり。もとありける池山をも、便なき所なるをば崩し変へて、水の趣き、山のおきてを改めて、さまざまに、御方々の御願ひの心ばへを造らせたまへり。 |
八月に、六条院が完成してお引っ越しなさる。
未申の町は中宮の御旧邸なので、そのままお住まいになる予定である。
辰巳は、殿のいらっしゃる予定の区画である。
丑寅は、東の院にいらっしゃる対の御方、戌亥の区画は、明石の御方とお考えになって造営なさった。
もとからあった池や山を、不都合な所にあるものは造り変えて、水の情緒や、山の風情を改めて、いろいろと、それぞれの御方々のご希望どおりにお造りになった。
|
八月に六条院の造営が終わって、二条の院から源氏は移転することになった。南西は中宮の旧邸のあった所であるから、そこは宮のお住居になるはずである。南の東は源氏の住む所である。北東の一帯は東の院の花散里、西北は明石夫人と決めて作られてあった。もとからあった池や築山も都合の悪いのはこわして、水の姿、山の趣も改めて、さまざまに住み主の希望を入れた庭園が作られたのである。
|
【八月にぞ、六条院造り果てて渡りたまふ】- 昨年の秋に造営に着工して一年で完成。
【未申の町は】- 東南の町は秋好中宮、以下方位でその主人を紹介していく。東南の町は源氏と紫の上、東北の町は花散里、西北の町は明石御方である。
|
|
 |
| 7.4.2 |
南の東は、山高く、春の花の木、数を尽くして植ゑ、池のさまおもしろくすぐれて、御前近き前栽、五葉、紅梅、桜、藤、山吹、岩躑躅などやうの、春のもてあそびをわざとは植ゑで、秋の前栽をば、むらむらほのかに混ぜたり。 |
東南の町は、山を高く築き、春の花の木を、無数に植えて、池の様子も趣深く優れていて、お庭先の前栽には、五葉の松、紅梅、桜、藤、山吹、岩躑躅などといった、春の楽しみをことさらには植えないで、秋の前栽を、ひとむらずつ混ぜてあった。
|
南の東は山が高くて、春の花の木が無数に植えられてあった。池がことに自然にできていて、近い植え込みの所には、五葉、紅梅、桜、藤、山吹、岩躑躅などを主にして、その中に秋の草木がむらむらに混ぜてある。
|
【南の東は】- 東南の町、すなわち紫の上の御殿は春の趣の町。
【わざとは植ゑで】- 『集成』は「わざとは植ゑて」と清音で「特に選んで植えて」と訳す。
|
|
 |
| 7.4.3 |
|
中宮の御町は、もとからある山に、紅葉の色の濃い植木を幾本も植えて、泉の水を清らかに遠くまで流して、遣水の音がきわだつように岩を立て加え、滝を落として、秋の野を広々と作ってあるが、折柄ちょうどその季節で、盛んに咲き乱れていた。
嵯峨の大堰あたりの野山も、見るかげもなく圧倒された今年の秋である。
|
中宮のお住居の町はもとの築山に、美しく染む紅葉を植え加えて、泉の音の澄んで遠く響くような工作がされ、流れがきれいな音を立てるような石が水中に添えられた。滝を落として、奥には秋の草野が続けられてある。ちょうどその季節であったから、嵯峨の大井の野の美観がこのために軽蔑されてしまいそうである。
|
【中宮の御町をば】- 秋好中宮の御殿は秋の趣の町。
【植木どもを添へて】- 大島本は「そへて」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「植ゑ」と校訂する。
【泉の水遠く澄ましやり、水の音まさるべき巌立て加へ】- 「すましやり水」の「やり」は上文と下文の両方にかかる掛詞。「澄ましやり、遣水の」の意。『集成』は「すましやり、水の」と整定し、『新大系』『古典セレクション』は「すまし、遣水の」と整定する。
|
|
 |
| 7.4.4 |
北の東は、涼しげなる泉ありて、夏の蔭によれり。前近き前栽、呉竹、下風涼しかるべく、木高き森のやうなる木ども木深くおもしろく、山里めきて、卯の花の垣根ことさらにしわたして、昔おぼゆる花橘、撫子、薔薇、苦丹などやうの花、草々を植ゑて、春秋の木草、そのなかにうち混ぜたり。東面は、分けて馬場の御殿作り、埒結ひて、五月の御遊び所にて、水のほとりに菖蒲植ゑ茂らせて、向かひに御厩して、世になき上馬どもをととのへ立てさせたまへり。 |
北東の町は、涼しそうな泉があって、夏の木蔭を主としていた。
庭先の前栽には、呉竹があり、下風が涼しく吹くようにし、木高い森のような木は奥深く趣があって、山里めいて、卯花の垣根を特別に造りめぐらして、昔を思い出させる花橘、撫子、薔薇、くたになどといった花や、草々を植えて、春秋の木や草を、その中に混ぜていた。
東面は、割いて馬場殿を造って、埒を結って、五月の御遊の場所として、水のほとりに菖蒲を植え茂らせて、その向かい側に御厩舎を造って、またとない素晴らしい馬を何頭も繋がせていらっしゃった。
|
北の東は涼しい泉があって、ここは夏の庭になっていた。座敷の前の庭には呉竹がたくさん植えてある。下風の涼しさが思われる。大木の森のような木が深く奥にはあって、田舎らしい卯の花垣などがわざと作られていた。昔の思われる花橘、撫子、薔薇、木丹などの草木を植えた中に春秋のものも配してあった。東向いた所は特に馬場殿になっていた。庭には埒が結ばれて、五月の遊び場所ができているのである。菖蒲が茂らせてあって、向かいの厩には名馬ばかりが飼われていた。
|
【北の東は】- 花散里の御殿は夏の趣の町。
【昔おぼゆる花橘】- 「五月待つ花橘の香をかげば昔の人の袖の香ぞする」(古今集夏、一三九、読人しらず)を踏まえる。
【苦丹などやうの花】- 大島本は「花」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「花の」と「の」を補訂する。
【東面は】- 花散里の御殿のある夏の町の東半分は馬場殿及び厩舎となっている。
|
|
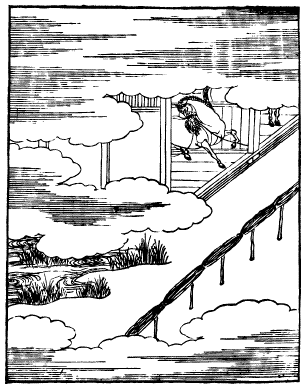 |
| 7.4.5 |
|
西北の町は、北面は築地で区切って、御倉町である。
隔ての垣として松の木をたくさん植えて、雪を鑑賞するのに都合よくしてある。
冬の初めの朝、霜が結ぶように菊の籬、得意げに紅葉する柞の原、ほとんど名も知らない深山木などの、木深く茂っているのを移植してあった。
|
北西の町は北側にずっと倉が並んでいるが、隔ての垣には唐竹が植えられて、松の木の多いのは雪を楽しむためである。冬の初めに初霜のとまる菊の垣根、朗らかな柞原、そのほかにはあまり名の知れていないような山の木の枝のよく繁ったものなどが移されて来てあった。
|
【西の町は、北面築き分けて、御倉町なり】- 明石御方の御殿のある冬の町。その北半分は築地で区切られて御倉町となっている。
【われは顔なる柞原】- 擬人法。『集成』は「わがもの顔に紅葉する柞の原」と訳す。『古典セレクション』は「姫君の「母」をひびかすか」と注す。さらにいえば、「母ぞ腹」の意がこめられているといえよう。
|
|
第五段 秋の彼岸の頃に引っ越し始まる
|
| 7.5.1 |
彼岸のころほひ渡りたまふ。ひとたびにと定めさせたまひしかど、騒がしきやうなりとて、中宮はすこし延べさせたまふ。例のおいらかにけしきばまぬ花散里ぞ、その夜、添ひて移ろひたまふ。 |
彼岸のころにお引っ越しになる。
一度にとお決めあそばしたが、仰々しいようだといって、中宮は少しお延ばしになる。
いつものようにおとなしく気取らない花散里は、その夜、一緒にお引っ越しなさる。
|
秋の彼岸のころ源氏一家は六条院へ移って行った。皆一度にと最初源氏は思ったのであるが、仰山らしくなることを思って、中宮のおはいりになることは少しお延ばしさせた。おとなしい、自我を出さない花散里を同じ日に東の院から移転させた。
|
【彼岸のころほひ渡りたまふ】- 秋の彼岸。秋分の日を中心とする前後七日間。
|
| 7.5.2 |
|
春のお庭は、今の秋の季節には合わないが、とても見事である。
お車十五台、御前駆は四位五位の人々が多く、六位の殿上人などは、特別な人だけをお選びあそばしていた。
仰々しくはなく、世間の非難があってはと簡略になさっていたので、どのような点につけても大仰に威勢を張ることはない。
|
春の住居は今の季節ではないようなもののやはり全体として最もすぐれて見えるのがここであった。車の数が十五で、前駆には四位五位が多くて、六位の者は特別な縁故によって加えられたにすぎない。たいそうらしくなることは源氏が避けてしなかった。
|
【御車十五、御前四位五位がちにて、六位殿上人などは、さるべき限りを選らせたまへり】- 紫の上の二条院から六条院への引っ越し。一台の車は定員四人。約四、五十人の女房が付き従ったものか。四位五位の前駆及び特別の関係ある六位の殿上人が警護した。
|
| 7.5.3 |
|
もうお一方のご様子も、大して劣らないようになさって、侍従の君が付き添って、そちらはお世話なさっているので、なるほどこういうこともあるのであったと見受けられた。
|
もう一人の夫人の前駆その他もあまり落とさなかった。長男の侍従がその夫人の子になっているのであるからもっともなことであると見えた。
|
【今一方の御けしきも】- 花散里をいう。
【侍従君添ひて】- 侍従の君すなわち夕霧。
【かうもあるべきことなりけりと見えたり】- 『完訳』は「諸説ある。夕霧の花散里への世話ぶりとも、夕霧を花散里に付き添わせた源氏の扱いぶりとも。いずれにせよ、申し分ない様子」と注す。
|
| 7.5.4 |
女房の曹司町ども、当て当てのこまけぞ、おほかたのことよりもめでたかりける。
|
女房たちの曹司町も、それぞれに細かく当ててあったのが、他の何よりも素晴らしく思われるのであった。
|
女房たちの部屋の配置、こまごまと分けて部屋数の多くできていることなどが新邸の建築のすぐれた点である。
|
|
| 7.5.5 |
五、六日過ぎて、中宮まかでさせたまふ。この御けしきはた、さは言へど、いと所狭し。御幸ひのすぐれたまへりけるをばさるものにて、御ありさまの心にくく重りかにおはしませば、世に重く思はれたまへること、すぐれてなむおはしましける。 |
五、六日過ぎて、中宮が御退出あそばす。
その御様子はそれは、簡略とはいっても、まことに大層なものである。
御幸運の素晴らしいことは申すまでもなく、お人柄が奥ゆかしく重々しくいらっしゃるので、世間から重んじられていらっしゃることは、格別でおいであそばした。
|
五、六日して中宮が御所から退出しておいでになった。その儀式はさすがにまた派手なものであった。源氏を後援者にしておいでになる方という幸福のほかにも、御人格の優しさと高潔さが衆望を得ておいでになることがすばらしいお后様であった。
|
【御ありさまの心にくく重りかに】- 人柄についていう。
|
| 7.5.6 |
この町々の中の隔てには、塀ども廊などを、とかく行き通はして、気近くをかしきあはひにしなしたまへり。
|
この町々の間の仕切りには、塀や廊などを、あちらとこちらとが行き来できるように作って、お互いに親しく風雅な間柄にお造りになってあった。
|
この四つに分かれた住居は、塀を仕切りに用いた所、廊で続けられた所などもこもごもに混ぜて、一つの大きい美観が形成されてあるのである。
|
|
|
第六段 九月、中宮と紫の上和歌を贈答
|
| 7.6.1 |
|
九月になると、紅葉があちこちに色づいて、中宮のお庭先は何ともいえないほど素晴らしい。
風がさっと吹いた夕暮に、御箱の蓋に、色とりどりの花や紅葉をとり混ぜて、こちらに差し上げになさった。
|
九月にはもう紅葉がむらむらに色づいて、中宮の前のお庭が非常に美しくなった。夕方に風の吹き出した日、中宮はいろいろの秋の花紅葉を箱の蓋に入れて紫夫人へお贈りになるのであった。
|
【長月になれば、紅葉むらむら色づきて】- 晩秋九月である。
【こなたにたてまつらせたまへり】- 秋好中宮が紫の上に。前に「御箱」とあり、ここに「せたまへり」という最高敬語が使用されている。
|
| 7.6.2 |
大きやかなる童女の、濃き衵、紫苑の織物重ねて、赤朽葉の羅の汗衫、いといたうなれて、廊、渡殿の反橋を渡りて参る。うるはしき儀式なれど、童女のをかしきをなむ、え思し捨てざりける。さる所にさぶらひなれたれば、もてなし、ありさま、他のには似ず、このましうをかし。御消息には、 |
大柄な童女が、濃い紫の袙に、紫苑の織物を重ねて、赤朽葉の羅の汗衫、とてももの馴れた感じで、廊や、渡殿の反橋を渡って参上する。
格式高い礼儀作法であるが、童女の容姿の美しいのを捨てがたくてお選びになったのであった。
そのようなお所に伺候し馴れていたので、立居振舞、姿つき、他家の童女とは違って、好感がもてて風情がある。
お手紙には、
|
やや大柄な童女が深紅の袙を着、紫苑色の厚織物の服を下に着て、赤朽葉色の汗袗を上にした姿で、廊の縁側を通り渡殿の反橋を越えて持って来た。お后が童女をお使いになることは正式な場合にあそばさないことなのであるが、彼らの可憐な姿が他の使いにまさると宮は思召したのである。御所のお勤めに馴れている子供は、外の童女と違った洗練された身のとりなしも見えた。お手紙は、
|
【いたうなれて】- 『集成』は「まことに落着いた態度で」。『完訳』は「たいそう物慣れた身のこなしで」と訳す。
|
| 7.6.3 |
|
「お好みで春をお待ちのお庭では、
せめてわたしの方の紅葉を風のたより
|
心から春待つ園はわが宿の
紅葉を風のつてにだに見よ
|
【心から春まつ園はわが宿の--紅葉を風のつてにだに見よ】- 秋好中宮から紫の上への贈歌。秋の町の素晴らしさを言ってよこした。
|
| 7.6.4 |
若き人びと、御使もてはやすさまどもをかし。
|
若い女房たちが、お使いを歓待する様子は風雅である。
|
というのであった。若い女房たちはお使いをもてはやしていた。
|
|
| 7.6.5 |
御返りは、この御箱の蓋に苔敷き、巌などの心ばへして、五葉の枝に、
|
お返事には、この御箱の蓋に苔を敷き、巌などの感じを出して、五葉の松の枝に、
|
こちらからはその箱の蓋へ、下に苔を敷いて、岩を据えたのを返しにした。五葉の枝につけたのは、
|
|
| 7.6.6 |
|
「風に散ってしまう紅葉は心軽いものです、
春の変わらない色をこの岩にどっしりと根をはった松の常磐の緑を御覧にな
|
風に散る紅葉は軽し春の色を
岩根の松にかけてこそ見め
|
【風に散る紅葉は軽し春の色を--岩根の松にかけてこそ見め】- 紫の上の返歌。秋よりも春が素晴らしいと、応酬する。
|
| 7.6.7 |
|
この岩根の松も、よく見ると、素晴らしい造り物なのであった。
このようにとっさに思いつきなさった趣向のよさを、感心して御覧あそばす。
御前に伺候している女房たちも褒め合っていた。
大臣は、
|
という夫人の歌であった。よく見ればこの岩は作り物であった。すぐにこうした趣向のできる夫人の才に源氏は敬服していた。女房たちも皆おもしろがっているのである。
|
【とりあへず思ひ寄りたまひつる】- 大島本は「とりあへすおもひより給つる」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「かくとりあへず思ひよりたまへる」と校訂する。
【をかしく御覧ず】- 主語は秋好中宮。
|
| 7.6.8 |
|
「この紅葉のお手紙は、何とも憎らしいですね。
春の花盛りに、このお返事は差し上げなさい。
この季節に紅葉を貶すのは、龍田姫がどう思うかということもあるので、ここは一歩退いて、花を楯にとって、強いことも言ったらよいでしょう」
|
「紅葉の贈り物は秋の御自慢なのだから、春の花盛りにこれに対することは言っておあげなさい。このごろ紅葉を悪口することは立田姫に遠慮すべきだ。別な時に桜の花を背景にしてものを言えば強いことも言われるでしょう」
|
【この紅葉の御消息】- 以下「強きことは出で来め」まで、源氏の詞。
【いとねたげなめり】- 『集成』は「なんともしゃくに思われますね」と訳す。『完訳』は「中宮にしてやられた感じ」と注す。
【花の蔭に立ち隠れてこそ、強きことは出で来め】- 『集成』は「春になって、花の美しさを頼みにしてこそ、勝ち目のある歌もできましょう」。『完訳』は「春になってから、花を押し立ててこそ強いことも言えましょう」と訳す。「胡蝶」巻にこの返歌がある。
|
| 7.6.9 |
|
と申し上げなさるのも、とても若々しくどこまでも素晴らしいお姿で魅力にあふれていらっしゃる上に、いっそう理想的なお邸で、お手紙のやりとりをなさる。
|
こんなふうにいつまでも若い心の衰えない源氏夫婦が同じ六条院の人として中宮と風流な戯れをし合っているのである。
|
【いと若やかに尽きせぬ御ありさまの】- 源氏の変わらぬ若々しさをいう。
【聞こえ通はしたまふ】- 主語は六条院の女君たち。『集成』は「理想的な六条院の生活ぶり」。『完訳』は「源氏には、自らの管理のもとでの女君同士の適度な交流も理想であった。六条院経営はそれを可能にしようとしている」と注す。
|
| 7.6.10 |
|
大堰の御方は、「このように御方々のお引っ越しが終わってから、人数にも入らない者は、いつか分からないようにこっそりと移ろう」とお考えになって、神無月にお引っ越しになるのであった。
お部屋の飾りや、お引っ越しの次第は他の方々に劣らないようにして、お移し申し上げなさる。
姫君のご将来をお考えになると、万事についての作法も、ひどく差をつけず、たいそう重々しくお扱いなさった。
|
大井の夫人は他の夫人のわたましがすっかり済んだあとで、価値のない自分などはそっと引き移ってしまいたいと思っていて、十月に六条院へ来たのであった。住居の中の設備も、移って来る日の儀装のことも源氏は他の夫人に劣らせなかった。それは姫君の将来のことを考えているからで迎えてからも重々しく取り扱った。
|
【大堰の御方は】- 明石御方をさす。
【かう方々の】- 以下「紛らはさむ」まで、明石御方の心中。
【神無月になむ渡りたまひける】- 初冬十月。冬の町の主人公にふさわしい設定。
【渡したてまつりたまふ】- 主語は源氏。明石御方に対する重々しい待遇である。
【姫君の御ためを思せば】- 『完訳』は「明石の姫君を将来の国母にと意図する源氏は、身分低い母君の格式を高めようとする」と注す。
|
| 著作権 |
| 底本 |
大島本 |
| 校訂 |
Last updated 9/21/2010(ver.2-3)
渋谷栄一校訂(C)
オリジナル
修正版
比較 |
| ローマ字版 |
Last updated 11/19/2009 (ver.2-2)
Written in Japanese roman letters
by Eiichi Shibuya (C)
オリジナル
修正版
比較 |
ルビ抽出
(ローマ字版から)
|
Powered by 再編集プログラム v4.05
ひらがな版
ルビ抽出 |
挿絵
(ローマ字版から)
|
'Eiri Genji Monogatari'
(1650 1st edition) |
|
Last updated 11/25/2013
渋谷栄一訳(C)(ver.1-2-3)
オリジナル
修正版
比較 |
|
|
Last updated 11/19/2009(ver.2-2)
渋谷栄一注釈(C)
オリジナル
修正版
比較 |
|