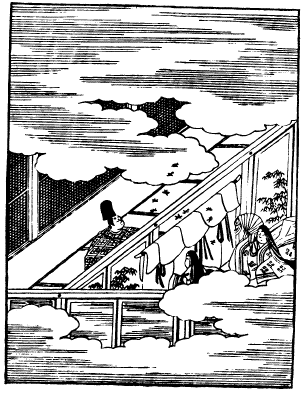第二十五帖 蛍
光る源氏の太政大臣時代三十六歳の五月雨期の物語
|
# |
本文 |
渋谷栄一訳 |
与謝野晶子訳 |
注釈 |
|
第一章 玉鬘の物語 蛍の光によって姿を見られる
|
|
第一段 玉鬘、養父の恋に悩む
|
| 1.1.1 |
|
今はこのように重々しい身分ゆえに、何事にももの静かに落ち着いていらっしゃるご様子なので、ご信頼申し上げていらっしゃる方々は、それぞれ身分に応じて、皆思いどおりに落ち着いて、不安もなく、理想的にお過ごしになっている。
|
源氏の現在の地位はきわめて重いがもう廷臣としての繁忙もここまでは押し寄せて来ず、のどかな余裕のある生活ができるのであったから、源氏を信頼して来た恋人たちにもそれぞれ安定を与えることができた。
|
【今はかく重々しきほどに】- 源氏、太政大臣、三十六歳夏五月。
【頼みきこえさせたまへる人びと】- 六条院や二条東院の御夫人方をさす。
|
| 1.1.2 |
|
対の姫君だけは、気の毒に、思いもしなかった悩みが加わって、どうしようかしらと困っていらしゃるようである。
あの監が嫌だった様子とは比べものにならないが、このようなことで、夢にも回りの人々がお気づき申すはずのないことなので、自分の胸一つをお痛めになりながら、「変なことで嫌らしい」とお思い申し上げなさる。
|
しかも対の姫君だけは予期せぬ煩悶をする身になっていた。大夫の監の恐ろしい懸想とはいっしょにならぬにもせよ、だれも想像することのない苦しみが加えられているのであったから、源氏に持つ反感は大きかった。
|
【対の姫君こそ】- 玉鬘をさす。夏の町の西の対屋の元文殿であった所を居所とする(「玉鬘」第四章四段)。
【いとほしく】- 『完訳』は「気の毒にも。語り手の評」と注す。
【かの監が憂かりし】- 筑紫にいたころの大夫督をさす。
【心ひとつに思しつつ】- 接続助詞「つつ」同じ動作の繰り返しの意。『完訳』は「度重なる源氏の求愛を暗示」と注す。
|
| 1.1.3 |
|
どのようなことでもご分別のついているお年頃なので、あれやこれやとお考え合わせになっては、母君がお亡くなりになった無念さを、改めて惜しく悲しく思い出される。
|
母君さえ死んでいなかったならと、またこの悲しみを新たにすることになったのであった。
|
【何ごとをも思し知りにたる御齢なれば】- 玉鬘二十二歳。前の「胡蝶巻」では、年齢のわりには男女関係に疎遠で無知であると語られていた。その間の経緯が想像される。
|
| 1.1.4 |
|
大臣も、お口にいったんお出しになってからは、かえって苦しくお思いになるが、人目を遠慮なさっては、ちょっとした言葉もお話しかけになれず、苦しくお思いになるので、頻繁にお越しになっては、お側に女房などもいなくて、のんびりとした時には、穏やかならぬ言い寄りをなさるたびごとに、胸を痛め痛めしては、はっきりとお拒み申し上げることができないので、ただ素知らぬふりをしてお相手申し上げていらっしゃる。
|
源氏も打ち明けてからはいっそう恋しさに苦しんでいるのであるが、人目をはばかってまたこのことには触れない。ただ堪えがたい心だけを慰めるためによく出かけて来たが、玉鬘のそばに女房などのあまりいない時にだけは、はっと思わせられるようなことも源氏は言った。あらわに退けて言うこともできないことであったから玉鬘はただ気のつかぬふうをするだけであった。
|
【ただならずけしきばみきこえたまふごとに】- 源氏が密かに玉鬘に対して恋情を訴える意。
【胸つぶれつつ、けざやかにはしたなく聞こゆべきにはあらねば】- 主語は玉鬘。源氏の身分や人柄を思い、また自分への厚意をも思うゆえの苦慮。
|
| 1.1.5 |
|
人柄が明朗で、人なつこくいらっしゃるので、とてもまじめぶって、用心していらっしゃるが、やはりかわいらしく魅力的な感じばかりが目立っていらっしゃる。
|
人柄が明るい朗らかな玉鬘であったから、自分自身ではまじめ一方な気なのであるが、それでもこぼれるような愛嬌が何にも出てくるのを、
|
【いたくまめだち、心したまへど】- 主語は玉鬘。『完訳』は「まじめに構えても、やはり可憐な魅力は紛れようもない、の意」と注す。
|
|
第二段 兵部卿宮、六条院に来訪
|
| 1.2.1 |
|
兵部卿宮などは、真剣になってお申し込みなさる。
お骨折りの日数はそれほどたってないのに、五月雨になってしまった苦情を訴えなさって、
|
兵部卿の宮などはお知りになって、夢中なほどに恋をしておいでになった。まだたいして長い月日がたったわけではないが、確答も得ないうちに不結婚月の五月にさえなったと恨んでおいでになって、
|
【五月雨になりぬる愁へ】- 五月は結婚を忌む風習があった。「神代より忌むといふなる五月雨のこなたに人を見るよしもがな」(信明集、五六)。
|
| 1.2.2 |
|
「もう少しお側近くに上がることだけでもお許し下さるならば、思っていることも、少しは晴らしたいものですね」
|
ただもう少し近くへ伺うことをお許しくだすったら、その機会に私の思い悩んでいる心を直接お洩らしして、それによってせめて慰みたいと思います。
|
【すこし気近きほどを】- 以下「はるけてしかな」まで、蛍兵部卿宮の詞。
|
| 1.2.3 |
と、聞こえたまへるを、殿御覧じて、
|
と、申し上げになさるのを、殿が御覧になって、
|
こんなことをお書きになった手紙を源氏は読んで、
|
|
| 1.2.4 |
「なにかは。この君達の好きたまはむは、見所ありなむかし。もて離れてな聞こえたまひそ。御返り、時々聞こえたまへ」 |
「何のかまうことがあろうか。
この公達が言い寄られるのは、きっと風情があろう。
そっけないお扱いをなさるな。
お返事は、時々差し上げなさい」
|
「そうすればいいでしょう。宮のような風流男のする恋は、近づかせてみるだけの価値はあるでしょう。絶対にいけないなどとは言わないほうがよい。お返事を時々おあげなさいよ」
|
【なにかは】- 以下「時々聞こえたまへ」まで、源氏の詞。
|
| 1.2.5 |
とて、教へて書かせたてまつりたまへど、いとどうたておぼえたまへば、「乱り心地悪し」とて、聞こえたまはず。
|
とおっしゃって、教えてお書かせ申し上げなさるが、ますます不愉快なことに思われなさるので、「気分が悪い」と言って、お書きにならない。
|
と源氏は言って文章をこう書けとも教えるのであったが、何重にも重なる不快というようなものを感じて、気分が悪いから書かれないと玉鬘は言った。
|
|
| 1.2.6 |
|
女房たちも、特に家柄がよく声望の高い者などもほとんどいない。
ただ一人、母君の叔父君であった、宰相程度の人の娘で、嗜みなどさほど悪くはなく、世に落ちぶれていたのを、探し出されたのが、宰相の君と言って、筆跡などもまあまあに書いて、だいたいがしっかりした人なので、しかるべき折々のお返事などをお書かせになっていたのを、召し出して、文言などをおっしゃって、お書かせになる。
|
こちらの女房には貴族出の優秀なような者もあまりないのである。ただ母君の叔父の宰相の役を勤めていた人の娘で怜悧な女が不幸な境遇にいたのを捜し出して迎えた宰相の君というのは、字などもきれいに書き、落ち着いた後見役も勤められる人であったから、玉鬘が時々やむをえぬ男の手紙に返しをする代筆をさせていた。
|
【母君の御叔父なりける、宰相ばかりの人の娘にて】- 夕顔の父三位中将の兄弟で、宰相になった人の娘。すなわち玉鬘とは従姉妹に当たる人。
【宰相の君とて】- 父親の官職名にちなむ女房名。上臈の格式。
【御返りなど書かせたまへば】- 『新大系』は「(源氏が宰相の君に)書かせていらっしゃるので、(この度も)お召し出しになり、宰相君が代筆しなれているので、受け取った宮は玉鬘の自筆と思うはずだとする源氏の思惑による」と注す。
|
| 1.2.7 |
|
お口説きになる様子を御覧になりたいのであろう。
|
その人を源氏は呼んで、口授して宮へのお返事を書かせた。
|
【ものなどのたまふさまを、ゆかしと思すなるべし】- 『集成』は「宮が玉鬘に言い寄られる様子を、見たいとお思いなのであろう。草子地。手紙が宮の訪問を許すような趣の文面であることを暗示して、次の場面の伏線」。『完訳』は「宮の反応に源氏が興味を抱くらしい、とする語り手の推測」と注す。
|
| 1.2.8 |
|
ご本人は、こうした心配事が起こってから後は、この宮などには、しみじみと情のこもったお手紙を差し上げなさる時は、少し心をとめて御覧になる時もあるのだった。
特に関心があるというのではないが、「このようなつらい殿のお振る舞いを見ないですむ方法がないものか」と、さすがに女らしい風情がまじる思いにもなるのだった。
|
聞いていて玉鬘が何と言うかを源氏は聞きたかったのである。姫君は源氏に恋をささやかれた時から、兵部卿の宮などの情をこめてお送りになる手紙などを、少し興味を持ってながめることがあった。心がそのほうへ動いて行くというのではなしに、源氏の恋からのがれるためには、兵部卿の宮に好意を持つふうを装うのも一つの方法であると思うのである。この人にも技巧的な考えが出るものである。
|
【この宮などは】- 係助詞「は」峻別の意。他の人はともかくもこの蛍兵部卿宮だけは、のニュアンス。
【かく心憂き御けしき見ぬわざもがな】- 玉鬘の心中。「御けしき」は源氏の懸想ばみた振る舞いをさす。
【さすがにされたるところつきて思しけり】- 『集成』は「なかなかのところがあってお思いなのだった」。『完訳』は「源氏を拒みながらも、やはり女らしく宮に情ある態度をとる」と注す。
|
| 1.2.9 |
|
殿は、勝手に心ときめかしなさって、宮をお待ち申し上げていらっしゃるのもご存知なくて、まあまあのお返事があるのを珍しく思って、たいそうこっそりといらっしゃった。
|
源氏自身がおもしろがって宮をお呼び寄せしようとしているとは知らずに、思いがけず訪問を許すという返事をお得になった宮は、お喜びになって目だたぬふうで訪ねておいでになった。
|
【殿は、あいなくおのれ心懸想して】- 形容詞「あいなく」は語り手の言辞、挿入語句。『完訳』も「「あいなく」は語り手の評」と注す。
【知りたまはで】- 主語は蛍兵部卿宮。
|
| 1.2.10 |
|
妻戸の間にお敷物を差し上げて、御几帳だけを間に隔てとした近い場所である。
|
妻戸の室に敷き物を設けて几帳だけの隔てで会話がなさるべくできていた。
|
【妻戸の間に御茵参らせて】- 妻戸を入った所の廂間に敷物を用意した。
|
| 1.2.11 |
|
とてもたいそう気を配って、空薫物を奥ゆかしく匂わして、世話をやいていらっしゃる様子、親心ではなくて、手に負えないおせっかい者の、それでも親身なお扱いとお見えになる。
宰相の君なども、お返事をお取り次ぎ申し上げることなども分からず、恥ずかしがっているのを、「引っ込み思案だ」と、おつねりになるので、まこと困りきっている。
|
心憎いほどの空薫きをさせたり、姫君の座をつくろったりする源氏は、親でなく、よこしまな恋を持つ男であって、しかも玉鬘の心にとっては同情される点のある人であった。宰相の君なども会話の取り次ぎをするのが晴れがましくてできそうな気もせず隠れているのを源氏は無言で引き出したりした。
|
【むつかしきさかしら人の】- 『完訳』は「手に負えないおせっかい者が。語り手の揶揄」と注す。
【人の御いらへ聞こえむこともおぼえず】- 「人」は玉鬘をさす。玉鬘の宮へのお返事をお取り次ぎ申し上げること。
【埋もれたり」と、ひきつみたまへば、いとわりなし】- 源氏が宰相の君を。『集成』は「気が利かぬと、おつねりになるので、困り果てている。やや諧謔を弄した筆致。「埋る」は、引っ込んでいる、の意。「いとわりなし」は、仕方なく取次ぎの役を勤めねばならぬ宰相の君の気持を直接書くことによって地の文としたもの」と注す。
|
|
第三段 玉鬘、夕闇時に母屋の端に出る
|
| 1.3.1 |
|
夕闇のころが過ぎて、はっきりしない空模様も曇りがちで、物思わしげな宮のご様子も、とても優美である。
内側からほのかに吹いてくる追い風も、さらに優れた殿のお香の匂いが添わっているので、とても深く薫り満ちて、予想なさっていた以上に素晴らしいご様子に、お心を惹かれなさるのだった。
|
夕闇時が過ぎて、暗く曇った空を後ろにして、しめやかな感じのする風采の宮がすわっておいでになるのも艶であった。奥の室から吹き通う薫香の香に源氏の衣服から散る香も混じって宮のおいでになるあたりは匂いに満ちていた。予期した以上の高華な趣の添った女性らしくまず宮はお思いになったのであった。
|
【夕闇過ぎて、おぼつかなき空のけしき】- 五月四日ごろの夕方。四日の月が西の空にあるのだが、五月雨のころゆえ雲ではっきり見えない。
【宮の御けはひも】- 『完訳』は「以下「けはひ」の語の繰返しに注意。宮も玉鬘も、微光と微香のなかのほのかな存在として形象」と注す。
|
| 1.3.2 |
うち出でて、思ふ心のほどをのたまひ続けたる言の葉、おとなおとなしく、ひたぶるに好き好きしくはあらで、いとけはひことなり。大臣、いとをかしと、ほの聞きおはす。 |
お口に出して、思っている心の中をおっしゃり続けるお言葉は、落ち着いていて、一途な好き心からではなく、とても態度が格別である。
大臣は、とても素晴らしいと、ほのかに聞いていらっしゃる。
|
宮のお語りになることは、じみな落ち着いた御希望であって、情熱ばかりを見せようとあそばすものでもないのが優美に感ぜられた。源氏は興味をもってこちらで聞いているのである。
|
【のたまひ続けたる言の葉】- 『完訳』は「「聞こゆ」など謙譲語がないので、話す相手が宰相の君と分る」と注す。
|
| 1.3.3 |
姫君は、東面に引き入りて大殿籠もりにけるを、宰相の君の御消息伝へに、ゐざり入りたるにつけて、 |
姫君は、東面の部屋に引っ込んでお寝みになっていらしたのを、宰相の君が宮のお言葉を伝えに、いざり入って行く後についていって、
|
姫君は東の室に引き込んで横になっていたが、宰相の君が宮のお言葉を持ってそのほうへはいって行く時に源氏は言づてた。
|
【ゐざり入りたるにつけて】- 源氏が宰相の君がいざって入って行く後について、の意。
|
| 1.3.4 |
「いとあまり暑かはしき御もてなしなり。よろづのこと、さまに従ひてこそめやすけれ。ひたぶるに若びたまふべきさまにもあらず。この宮たちをさへ、さし放ちたる人伝てに聞こえたまふまじきことなりかし。御声こそ惜しみたまふとも、すこし気近くだにこそ」 |
「とてもあまりに暑苦しいご応対ぶりです。
何事も、その場に応じて振る舞うのがよろしいのです。
むやみに子供っぽくなさってよいお年頃でもありません。
この宮たちまでを、よそよそしい取り次ぎでお話し申し上げなさってはいけません。
お返事をしぶりなさるとも、せめてもう少しお近くで」
|
「あまりに重苦しいしかたです。すべて相手次第で態度を変えることが必要で、そして無難です。少女らしく恥ずかしがっている年齢でもない。この宮さんなどに人づてのお話などをなさるべきでない。声はお惜しみになっても少しは近い所へ出ていないではいけませんよ」
|
【いとあまり暑かはしき】- 以下「気近くだにこそ」まで、源氏の詞。
|
| 1.3.5 |
|
などと、ご忠告申し上げなさるが、とても困って、注意するのにかこつけて中に入っておいでになりかねないお方なので、どちらにしても身の置き所もないので、そっとにじり出て、母屋との境にある御几帳の側に横になっていらっしゃった。
|
などと言う忠告である。玉鬘は困っていた。なおこうしていればその用があるふうをしてそばへ寄って来ないとは保証されない源氏であったから、複雑な侘しさを感じながら玉鬘はそこを出て中央の室の几帳のところへ、よりかかるような形で身を横たえた。
|
【ことづけてもはひ入りたまひぬべき御心ばへなれば】- 『集成』は「(源氏は)こんなことにかこつけてでも入っておいでになりかねない魂胆をお持ちの方だから。源氏を警戒する玉鬘の気持を書いたもの」。『完訳』は「注意するのにかこつけて部屋の中にはいりかねない源氏の気持」と注す。
【とざまかうざまにわびしければ】- 『完訳』は「このままでは源氏が近づき、出れば宮に応ずるほかない状態」と注す。
【かたはら臥したまへる】- 連体中止形。状態の持続から次の事態の展開へと一続きの文脈。
|
|
第四段 源氏、宮に蛍を放って玉鬘の姿を見せる
|
| 1.4.1 |
|
何やかやと長口舌にお返事を申し上げなさることもなく、ためらっていらっしゃるところに、お近づきになって、御几帳の帷子を一枚お上げになるのに併せて、ぱっと光るものが。
紙燭を差し出したのかと驚いた。
|
宮の長いお言葉に対して返辞がしにくい気がして玉鬘が躊躇している時、源氏はそばへ来て薄物の几帳の垂れを一枚だけ上へ上げたかと思うと、蝋の燭をだれかが差し出したかと思うような光があたりを照らした。玉鬘は驚いていた。
|
【何くれと言長き御応へ聞こえたまふこともなく、思しやすらふに】- 「言長き」は宮の長口舌、「御いらへ」はそれに対する玉鬘の返事。格助詞「に」時間を表す。
【寄りたまひて】- 源氏が。
【さと光るもの】- この語句をうける述語なし。間合い。
|
| 1.4.2 |
|
螢を薄い物に、この夕方たいそうたくさん包んでおいて、光を隠していらっしゃったのを、何気なく、何かと身辺のお世話をするようにして。
|
夕方から用意して蛍を薄様の紙へたくさん包ませておいて、今まで隠していたのを、さりげなしに几帳を引き繕うふうをしてにわかに袖から出したのである。
|
【薄きかたに】- 諸説あり、不明の語句。『新大系』は「「かた」は「かたびら」の誤りか。帷子の裏のこととも。諸説あるが未詳」と注す。
【とかくひきつくろふやうにて】- この語句を受ける述語なし。
|
| 1.4.3 |
|
急にこのように明るく光ったので、驚きあきれて、扇をかざした横顔、とても美しい様子である。
|
たちまちに異常な光がかたわらに湧いた驚きに扇で顔を隠す玉鬘の姿が美しかった。
|
【扇をさし隠したまへるかたはら目】- 扇で顔を隠しなさった横顔、の意。
|
| 1.4.4 |
|
「驚くほどの光がさしたら、宮もきっとお覗きになるだろう。
自分の娘だとお考えになるだけのことで、こうまで熱心にご求婚なさるようだ。
人柄や器量など、ほんとうにこんなにまで整っているとは、さぞお思いでなかろう。
夢中になってしまうに違いないお心を、悩ましてやろう」
|
強い明りがさしたならば宮も中をおのぞきになるであろう、ただ自分の娘であるから美貌であろうと想像をしておいでになるだけで、実質のこれほどすぐれた人とも認識しておいでにならないであろう。
|
【おどろかしき光見えば】- 以下「惑はさむ」まで、源氏の心中。『集成』は「以下、源氏の目論見の説明」と注す。
【わが女と思すばかりのおぼえに】- 『集成』は「玉鬘をご自分(源氏)の実の娘とお思いになるだけのことで」。『完訳』は「宮は、姫君をこの自分の娘だとお思いになっているぐらいの考えから」と注す。副助詞「ばかり」は程度を表す。
【人ざま容貌など】- 玉鬘をさす。
|
| 1.4.5 |
|
と、企んであれこれなさるのだった。
ほんとうの自分の娘ならば、このようなことをして、大騷ぎをなさるまいに、困ったお心であるよ。
|
好色なお心を遣る瀬ないものにして見せようと源氏が計ったことである。実子の姫君であったならこんな物狂わしい計らいはしないであろうと思われる。
|
【まことのわが姫君をば、かくしも、もて騷ぎたまはじ、うたてある御心なりけり】- 『集成』は「草子地」。『完訳』は「以下、語り手の推測と評言。読者の反発を見越しながら、源氏の特殊な心に注目させる」と注す。
|
| 1.4.6 |
|
別の戸口から、そっと抜け出て、行っておしまいになった。
|
源氏はそっとそのまま外の戸口から出て帰ってしまった。
|
【こと方より、やをらすべり出でて】- 『集成』は「以上、源氏に即した視点から事の始終を書く。次の「宮は」以下は、同じ場面を宮に即した視点から再現する」と注す。
|
|
第五段 兵部卿宮、玉鬘にますます執心す
|
|
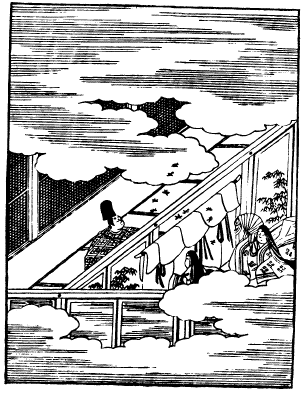 |
| 1.5.1 |
宮は、人のおはするほど、さばかりと推し量りたまふが、すこし気近きけはひするに、御心ときめきせられたまひて、えならぬ羅の帷子の隙より見入れたまへるに、一間ばかり隔てたる見わたしに、かくおぼえなき光のうちほのめくを、をかしと見たまふ。
|
宮は、姫のいらっしゃる所を、あの辺だと推量なさるが、割に近い感じがするので、つい胸がどきどきなさって、なんとも言えないほど素晴らしい羅の帷子の隙間からお覗きになると、柱一間ほど隔てた見通しの所に、このように思いがけない光がちらつくのを、美しいと御覧になる。
|
宮は最初姫君のいる所はその辺であろうと見当をおつけになったのが、予期したよりも近い所であったから、興奮をあそばしながら薄物の几帳の間から中をのぞいておいでになった時に、一室ほど離れた所に思いがけない光が湧いたのでおもしろくお思いになった。
|
|
| 1.5.2 |
|
間もなく見えないように取り隠した。
けれどもほのかな光は、風流な恋のきっかけにもなりそうに見える。
かすかであるが、すらりとした身を横にしていらっしゃる姿が美しかったのを、心残りにお思いになって、なるほど、この趣向はお心に深くとまったのであった。
|
まもなく明りは薄れてしまったが、しかも瞬間のほのかな光は恋の遊戯にふさわしい効果があった。かすかによりは見えなかったが、やや大柄な姫君の美しかった姿に宮のお心は十分に惹かれて源氏の策は成功したわけである。
|
【ほどもなく紛らはして隠しつ】- 主語は女房たち。
【艶なることのつまにもしつべく見ゆ】- 『集成』は「風流な恋のやりとりのきっかけにもできそうに見える」。『完訳』は「恋の語らい事の糸口にもなりそうな風情である」と訳す。
|
| 1.5.3 |
|
「鳴く声も聞こえない螢の火でさえ
人が消そうとして消えるものでしょうか
|
「鳴く声も聞こえぬ虫の思ひだに
人の消つには消ゆるものかは
|
【鳴く声も聞こえぬ虫の思ひだに--人の消つには消ゆるものかは】- 蛍の宮から玉鬘への贈歌。「思ひ」に「火」を掛ける。まして私の恋の炎は消えるものではない、の意。
|
| 1.5.4 |
|
ご存知いただけたでしょうか」
|
御実験なすったでしょう」
|
【思ひ知りたまひぬや】- 歌に添えた言葉。
|
| 1.5.5 |
と聞こえたまふ。
かやうの御返しを、思ひまはさむもねぢけたれば、疾きばかりをぞ。
|
と申し上げなさる。
このような場合のお返事を、思案し過ぎるのも素直でないので、早いだけを取柄に。
|
と宮はお言いになった。こんな場合の返歌を長く考え込んでからするのは感じのよいものでないと思って、玉鬘はすぐに、
|
|
| 1.5.6 |
|
「声には出さずひたすら身を焦がしている螢の方が
口に出すよりもっと深い思いでいるでしょう」
|
声はせで身をのみこがす蛍こそ
言ふよりまさる思ひなるらめ
|
【声はせで身をのみ焦がす蛍こそ--言ふよりまさる思ひなるらめ】- 玉鬘の返歌。「鳴く声」「虫」「思ひ」の語句を受けて「声はせで」「身をのみ焦がすこそこそ」「言ふよりまさる思ひなるらめ」と返す。「思ひ」に「火」を掛ける。「音もせで思ひに燃ゆる蛍こそ鳴く虫よりもあはれなりけれ」(重之集、二六四)。
|
| 1.5.7 |
など、はかなく聞こえなして、御みづからは引き入りたまひにければ、いとはるかにもてなしたまふ愁はしさを、いみじく怨みきこえたまふ。
|
などと、さりげなくお答え申して、ご自身はお入りになってしまったので、とても疎々しくおあしらいなさるつらさを、ひどくお恨み申し上げなさる。
|
とはかないふうに言っただけで、また奥のほうへはいってしまった。宮は疎々しい待遇を受けるというような恨みを述べておいでになった。
|
|
| 1.5.8 |
|
好色がましいようなので、そのまま夜をお明かしにならず、軒の雫も苦しいので、濡れながらまだ暗いうちにお出になった。
ほととぎすなどもきっと鳴いたことであろう。
わずらわしいので耳も留めなかった。
|
あまり好色らしく思わせたくないと宮は朝まではおいでにならずに、軒の雫の冷たくかかるのに濡れて、暗いうちにお帰りになった。杜鵑などはきっと鳴いたであろうと思われる。筆者はそこまで穿鑿はしなかった。
|
【好き好きしきやうなれば】- 蛍兵部卿宮の心中に即した叙述。
【軒の雫も苦しさに】- 「ながめつつわが思ふことはひぐらしに軒の雫の絶ゆる世もなし(新古今集雑下、一八〇一、具平親王)。『集成』は「「軒の雫」は歌語で、悲しみの涙の譬喩。五月雨と宮の悲しみの涙を重ねた趣の文飾」と注す。
【時鳥などかならずうち鳴きけむかし。うるさければこそ聞きも止めね】- 大島本は「とめね」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「とどめね」と校訂する。「五月雨に物思ひをればほととぎす夜深く鳴きていづち行くらむ」(古今集夏、一五三、紀友則)。『集成』は「以下、草子地」。『完訳』は「以下、語り手の弁。果たせぬ恋のまま立ち去る類型的な場面ゆえの省筆」と注す。
|
| 1.5.9 |
「御けはひなどのなまめかしさは、いとよく大臣の君に似たてまつりたまへり」と、人びともめできこえけり。昨夜、いと女親だちてつくろひたまひし御けはひを、うちうちは知らで、「あはれにかたじけなし」と皆言ふ。 |
「ご様子などの優美さは、とてもよく大臣の君にお似申していらっしゃる」と、女房たちもお褒め申し上げるのであった。
昨夜、すっかり母親のようにお世話やきなさったご様子を、内情は知らないで、「しみじみとありがたい」と女房一同は言う。
|
宮の御風采の艶な所が源氏によく似ておいでになると言って女房たちは賞めていた。昨夜の源氏が母親のような行き届いた世話をした点で玉鬘の苦悶などは知らぬ女房たちが感激していた。
|
【御けはひなどの】- 以下「似たてまつりたまへる」まで、女房たちの感想。
|
|
第六段 源氏、玉鬘への恋慕の情を自制す
|
| 1.6.1 |
|
姫君は、このようなうわべは親のようにつくろうご様子を、
|
玉鬘は源氏に持たれる恋心を
|
【かくさすがなる御けしきを】- 『集成』は「うわべは親のようでありながら、ひそかに自分に思いを寄せる源氏の気持を」。『完訳』は「表向き親らしくしながらも、やはり懸想を禁じえない源氏の」と訳す。
|
| 1.6.2 |
|
「自分自身の不運なのだ。
親などに娘と知っていただき、人並みに大切にされた状態で、このようなご寵愛をいただくのなら、どうしてひどく不似合いということがあろうか。
普通ではない境遇は、しまいには世の語り草となるのではないかしら」
|
自身の薄倖の現われであると思った。
実の父に娘を認められた上では、これほどの熱情を持つ源氏を良人にすることが似合わしくないことでないかもしれぬ、現在では父になり娘になっているのであるから、両者の恋愛がどれほど世間の問題にされることであろう
|
【わがみづからの憂さぞかし】- 以下「世語りにやならむ」まで、玉鬘の心中。『完訳』は「己が運命を痛恨。源氏への恨みではない」と注す。
【親などに知られたてまつり】- 『完訳』は「以下、反実仮想の構文。世間尋常の、親に養われる身で源氏と相対せるならば妻として似つかわしいと、その幸運を夢想する」と注す。
【かやうなる御心ばへならましかば】- 源氏の寵愛をさす。反実仮想「ならましかば--あらまし」の構文。
|
| 1.6.3 |
と、起き臥し思しなやむ。
|
と、寝ても起きてもお悩みになる。
|
と玉鬘は心を苦しめているのである。
|
|
| 1.6.4 |
|
一方では、「ほんとに世間にありふれたような悪い扱いにしてしまうまい」と、大臣はお思いになるのだった。
が、やはり、そのような困ったご性癖があるので、中宮などにも、とてもきれいにお思い申し上げていられようか、何かにつけては、穏やかならぬ申しようで気を引いてみたりなどなさるが、高貴なご身分で、及びもつかない事面倒なので、身を入れてお口説き申すことはなさらないが、この姫君は、お人柄も、親しみやすく現代的なので、つい気持ちが抑えがたくて、時々、人が拝見したらきっと疑いを持たれるにちがいないお振る舞いなどは、あることはあるが、他人が真似のできないくらいよく思い返し思い返しては、危なっかしい仲なのであった。
|
しかし真実は源氏もそんな醜い関係にまで進ませようとは思っていなかった。ただ恋を覚えやすい性格であったから、中宮などに対しても清い父親としてだけの愛以上のものをいだいていないのではない、何かの機会にはお心を動かそうとしながらも高貴な御身分にはばかられてあらわな恋ができないだけである。玉鬘は性格にも親しみやすい点があって、はなやかな気分のあふれ出るようなのを見ると、おさえている心がおどり出して、人が見れば怪しく思うほどのことも混じっていくのであるが、さすがに反省をして美しい愛だけでこの人を思おうとしていた。
|
【さるは、「まことにゆかしげなきさまにはもてなし果てじ」と】- 『集成』は「とはいえ、ほんとに世間にありふれたつまらぬことにはしてしまうまいと」。『完訳』は「とはいっても本当のところ、大臣は、姫君を真実聞きよくもない形に落ち着かせることだけはぜひ避けたいと」と訳す。
【中宮なども、いとうるはしくや思ひきこえたまへる】- 大島本は「うるハしくや」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「うるはしくやは」と校訂する。挿入句。秋好中宮に対する懸想心も養女への恋であるとする、語り手の弁。
【やむごとなき方の、およびなくわづらはしさに】- 『集成』は「中宮という歴としたご身分の方が、及びもつかぬ高さで事面倒でもあるので」。『完訳』は「先方は高貴なご身分の及びもつかないお方として厄介なので」と訳す。
【おり立ちあらはし聞こえ寄り】- 主語は源氏。
【さすがなる御仲なりけり】- 『集成』は「あぶないものの、何事もないお二人の仲だった」。『完訳』は「なんといってもやはり美しいお二人の御仲なのだった」と訳す。
|
|
第二章 光る源氏の物語 夏の町の物語
|
|
第一段 五月五日端午の節句、源氏、玉鬘を訪問
|
| 2.1.1 |
|
五日には、馬場殿にお出ましになった機会に、お越しになった。
|
五日には馬場殿へ出るついでにまた玉鬘を源氏は訪ねた。
|
【五日には、馬場の御殿に】- 五月五日、端午の節句。
|
| 2.1.2 |
「いかにぞや。宮は夜や更かしたまひし。いたくも馴らしきこえじ。わづらはしき気添ひたまへる人ぞや。人の心破り、ものの過ちすまじき人は、かたくこそありけれ」 |
「どうでしたか。
宮は夜更けまでいらっしゃいましたか。
あまりお近づけ申さないように。
やっかいなお癖がおありの方ですよ。
女の心を傷つけたり、何かの間違いをしないような男は、めったにいないものですよ」
|
「どうでしたか。宮はずっとおそくまでおいでになりましたか。際限なく宮を接近おさせしないようにしましょう。危険性のある方だからね。力で恋人を征服しようとしない人は少ないからね」
|
【いかにぞや】- 以下「かたくこそありけれ」まで、源氏の詞。
|
| 2.1.3 |
|
などと、誉めたりけなしたりしながら注意していらっしゃるご様子は、どこまでも若々しく美しくお見えになる。
光沢も色彩もこぼれるほどの御衣に、お直衣が無造作に重ね着されている色合いも、どこに普通と違う美しさがあるのであろうか、この世の人が染め出したものとも見えず、普通の直衣の色模様も、今日は特に珍しく見事に見え、素晴らしく思われる薫りなども、「物思いがなければ、どんなに素晴らしく思われるにちがいないお姿だろう」と姫君はお思いになる。
|
などと宮のことも活かせも殺しもしながら訓戒めいたことを言っている源氏は、いつもそうであるが、若々しく美しかった。色も光沢もきれいな服の上に薄物の直衣をありなしに重ねているのなども、源氏が着ていると人間の手で染め織りされたものとは見えない。物思いがなかったなら、源氏の美は目をよろこばせることであろうと玉鬘は思った。
|
【活けみ殺しみ戒めおはする御さま】- 『集成』は「手綱をゆるめたりしめたりといった具合に、玉鬘に注意していられるご様子は。前には宮を近づけるようなことを言い、今は危険な人だという」。『完訳』は「さきには宮をお近づけになるようおっしゃったかと思うと、今度はこれに水をさすといったおっしゃりかたをしてご注意をお与えになる大臣のご様子は」と訳す。
【いづこに加はれるきよらにかあらむ】- 語り手の挿入句。
【思ふことなくは、をかしかりぬべき御ありさまかな】- 玉鬘の心中。源氏からの厄介な懸想が悩みの種。
|
| 2.1.4 |
|
宮からお手紙がある。
白い薄様で、ご筆跡はとても優雅にお書きになっていらっしゃる。
見ていた時には素晴らしかったが、こう口にすると、たいしたことはないものだ。
|
兵部卿の宮からお手紙が来た。白い薄様によい字が書いてある。見て美しいが筆者が書いてしまえばただそれだけになることである。
|
【見るほどこそをかしけれ、まねび出づれば、ことなることなしや】- 大島本は「おかしけれ」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「をかしかりけれ」と校訂する。語り手の弁。『集成』は「草子地。その場にいた女房が語り伝える体。次の歌の批評である」。『完訳』は「語り手が宮の歌を平凡と評す」と注す。
|
| 2.1.5 |
|
「今日までも引く人もない水の中に隠れて生えている菖蒲の根のように
相手にされないわたしはただ声を上げて泣くだけなのでしょうか」
|
今日さへや引く人もなき水隠れに
生ふるあやめのねのみ泣かれん
|
【今日さへや引く人もなき水隠れに--生ふる菖蒲の根のみ泣かれむ】- 蛍宮から玉鬘への贈歌。「根」と「音」、「流れ」と「泣かれ」の掛詞。「水隠れて生ふる五月のあやめ草長きためしに人は引かなむ」(古今六帖一、菖蒲草、一〇〇)。
|
| 2.1.6 |
|
話題にもなりそうな長い菖蒲の根に文を結んでいらっしゃったので、「今日のお返事を」などとお勧めしておいて、お出になった。
誰彼も「やはり、ご返事を」と申し上げるので、ご自身どう思われたであろうか、
|
長さが記録になるほどの菖蒲の根に結びつけられて来たのである。「ぜひ今日はお返事をなさい」などと勧めておいて源氏は行ってしまった。女房たちもぜひと言うので玉鬘自身もどういうわけもなく書く気になっていた。
|
【例にも引き出で】- 水隠れて生ふる五月のあやめ草長きためしに人は引かなむ(続古今集夏-二二九 紀貫之)(text25.html 出典4 から転載)
【今日の御返り】- 源氏の詞。
【これかれも】- 周囲の女房をさす。
【御心にもいかが思しけむ】- 語り手の玉鬘の心中を忖度した挿入句。『完訳』は「語り手の玉鬘の心への疑問」と注す。
|
| 2.1.7 |
|
「きれいに見せていただきましてますます浅く見えました
わけもなく泣かれるとおっしゃるあなたのお気持ちは
|
あらはれていとど浅くも見ゆるかな
あやめもわかず泣かれけるねの
|
【あらはれていとど浅くも見ゆるかな--菖蒲もわかず泣かれける根の】- 玉鬘の返歌。「菖蒲」「根」「泣く」の語句を受けて返す。「洗はれて」と「現れて」、「文目」と「菖蒲」、「泣かれ」と「流れ」、「音」と「根」の掛詞。「洗ふ」は「水」の縁語。「現れて」は「水隠れに」の対語。
|
| 2.1.8 |
|
お年に似合わないこと」
|
少女らしく。
|
【若々しく】- 歌に添えた言葉。『集成』は「お年に似合わぬなさりようですこと」と訳す。
|
| 2.1.9 |
|
とだけ、薄墨で書いてあるようである。
「筆跡がもう少し立派だったら」と、宮は風流好みのお心から、少しもの足りないことと御覧になったことであろうよ。
|
とだけほのかに書かれたらしい。字にもう少し重厚な気が添えたいと芸術家的な好みを持っておいでになる宮はお思いになったようであった。
|
【手を今すこしゆゑづけたらば】- 蛍宮の感想。筆跡がもうすこし良かったらなあ、という気持ち。
【いささか飽かぬことと見たまひけむかし】- 語り手の推測。
|
| 2.1.10 |
楽玉など、えならぬさまにて、所々より多かり。思し沈みつる年ごろの名残なき御ありさまにて、心ゆるびたまふことも多かるに、「同じくは、人の疵つくばかりのことなくてもやみにしがな」と、いかが思さざらむ。 |
薬玉などを、実に趣向を凝らして、あちこちから多くあった。
おつらい思いをして来た長年の苦労もすっかりなくなったお暮らしぶりで、お気持ちにゆとりのおできになることも多かったので、「同じことなら、あちらが傷つくようなことのないようにして終わりにしたいものだ」と、どうしてお思いにならないことがあろうか。
|
今日は美しく作った薬玉などが諸方面から贈られて来る。不幸だったころと今とがこんなことにも比較されて考えられる玉鬘は、この上できるならば世間の悪名を負わずに済ませたいともっともなことを願っていた。
|
【多かるに】- 接続助詞「に」順接の意。
【同じくは】- 以下「やみにしがな」まで、玉鬘の心中。「人」は源氏をさす。
【いかが思さざらむ】- 語り手が玉鬘の心中を忖度した文章。反語表現。
|
|
第二段 六条院馬場殿の騎射
|
| 2.2.1 |
殿は、東の御方にもさしのぞきたまひて、
|
殿は、東の御方にもお立ち寄りになって、
|
源氏は花散里夫人の所へも寄った。
|
|
| 2.2.2 |
|
「中将が、今日の左近衛府の競射の折に、男たちを引き連れて来るようなことを言っていたが、そのおつもりでいて下さい。
まだ明るいうちにきっと来るでしょうよ。
不思議と、こちらでは目立たないようにする内輪の催しも、この親王たちが聞きつけて、見物にいらっしゃるので、自然と大げさになりますから、お心づもりなさい」
|
「中将が左近衛府の勝負のあとで役所の者を皆つれて来ると言ってましたからその用意をしておくのですね。まだ明るいうちに来るでしょう。私は何も麗々しく扱おうと思っていなかった姫君のことを、若い親王がたなどもお聞きになって手紙などをよくよこしておいでになるのだから、今日はいい機会のように思って、東の御殿へ何人も出ておいでになることになるでしょうから、そんなつもりで仕度をさせておいてください」
|
【中将の、今日の司の】- 以下「用意したまへ」まで、源氏の詞。「中将の」の格助詞「の」は主格を表す。
【さる心したまへ】- 近衛府の官人たちが多数夏の町に来るので、楽しみにまた注意もして下さいという意。
【この親王たち】- 蛍宮たち。
【用意したまへ】- 『集成』は「お心づかい下さい」。『完訳』は「支度をしておいてください」と訳す。
|
| 2.2.3 |
など聞こえたまふ。
|
などと申し上げなさる。
|
などと夫人に言っていた。
|
|
|
 |
| 2.2.4 |
|
馬場の御殿は、こちらの渡廊から見渡す距離もさほど遠くない。
|
馬場殿はこちらの廊からながめるのに遠くはなかった。
|
【こなたの廊より】- 夏の町の渡廊からの意。
|
| 2.2.5 |
「若き人びと、渡殿の戸開けて物見よや。左の司に、いとよしある官人多かるころなり。少々の殿上人に劣るまじ」 |
「若い女房たち、渡殿の戸を開けて見物をしなさいよ。
左近衛府に、たいそう素晴らしい官人が多い時だ。
なまじっかの殿上人には負けまい」
|
「若い人たちは渡殿の戸をあけて見物するがよい。このごろの左近衛府にはりっぱな下士官がいて、ちょっとした殿上役人などは及ばない者がいますよ」
|
【若き人びと】- 以下「劣るまじ」まで、源氏の詞。「若き人びと」は女房をさす。
|
| 2.2.6 |
とのたまへば、物見むことをいとをかしと思へり。
|
とおっしゃるので、見物することをとても興味深く思っていた。
|
と源氏が言うのを聞いていて、女房たちは今日の競技を見物のできることを喜んだ。
|
|
| 2.2.7 |
|
対の御方からも、童女など、見物にやって来て、渡廊の戸口に御簾を青々と懸け渡して、当世風の裾濃の御几帳をいくつも立て並べ、童女や下仕などがあちこちしている。
菖蒲襲の袙、二藍の羅の汗衫を着ている童女は、西の対のであろう。
|
玉鬘のほうからも童女などが見物に来ていて、廊の戸に御簾が青やかに懸け渡され、はなやかな紫ぼかしの几帳がずっと立てられた所を、童女や下仕えの女房が行き来していた。菖蒲重ねの袙、薄藍色の上着を着たのが西の対の童女であった。
|
【対の御方よりも】- 西の対の御方、玉鬘をさす。
【裾濃の御几帳ども】- 御几帳の上は白く下にいくほど紫または紺に濃く染めたもの。
【菖蒲襲の衵】- 以下、玉鬘方の童女の装束。「菖蒲襲」は表青、裏紅梅または白の襲。「衵」は童女の表着。
【二藍の羅の汗衫】- 紅と藍の中間色、また二度染の薄紫色の童女の表着。「汗衫」は女房の唐衣と裳に相当する童女の晴着。
【西の対のなめる】- 推量の助動詞「めり」は語り手の推量。
|
| 2.2.8 |
|
感じのいい物馴れた者ばかり四人、下仕え人は、楝の裾濃の裳、撫子の若葉色をした唐衣で、いずれも端午の日の装いである。
|
上品に物馴れたのが四人来ていた。下仕えは樗の花の色のぼかしの裳に撫子色の服、若葉色の唐衣などを装うていた。
|
【楝の裾濃の裳】- 以下、下仕えの女房の装束。下にいくほど濃く染めた楝の花の色に似た薄紫色の裳、また表紫、裏薄紫色の裳。
【撫子の若葉の色したる唐衣】- 薄萌黄色の唐衣。裳、唐衣を付けた正装。
|
| 2.2.9 |
|
こちらの童女は、濃い単衣襲に、撫子襲の汗衫などをおっとりと着て、それぞれが競い合っている振る舞い、見ていておもしろい。
|
こちらの童女は濃紫に撫子重ねの汗袗などでおおような好みである。双方とも相手に譲るものでないというふうに気どっているのがおもしろく見えた。
|
【こなたのは】- 花散里方の童女の装束、玉鬘方と対照的。
【濃き一襲】- 濃い紫色の単襲。
【撫子襲の汗衫】- 表紅梅、裏青の汗衫。
|
| 2.2.10 |
|
若い殿上人などは、目をつけては流し目を送る。
未の刻に、馬場殿にお出になると、なるほど親王たちがお集まりになっていた。
競技も公式のそれとは趣が異なって、中将少将たちが連れ立って参加して、風変りに派手な趣向を凝らして、一日中お遊びになる。
|
若い殿上役人などは見物席のほうに心の惹かれるふうを見せていた。午後二時に源氏は馬場殿へ出たのである。予想したとおりに親王がたもおおぜい来ておいでになった。左右の組み合わせなどに宮中の定例の競技と違って、中少将が皆はいって、こうした私の催しにかえって興味のあるものが見られるのであった。
|
【目をたててけしきばむ】- 大島本は「め越たてゝ」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「目をたてつつ」と校訂する。目をつけて流し目を送る、意。
【未の時に、馬場の御殿に出でたまひて】- 主語は源氏。午後二時ころに馬場殿にお出になる。
【げに】- 先に源氏が言っていたことを受ける。
【手結ひの】- 格助詞「の」主格を表す。
|
| 2.2.11 |
|
女性には、何も分からないことであるが、舎人連中までが優美な装束を着飾って、懸命に競技をしている姿などを見るのはおもしろいことであった。
|
女にはどうして勝負が決まるのかも知らぬことであったが、舎人までが艶な装束をして一所懸命に競技に走りまわるのを見るのはおもしろかった。
|
【身を投げたる手まどはしなどを見るぞ】- 『集成』は「我を忘れてうろたえる姿などを見るのは」。『完訳』は「懸命の秘術を尽くしているのを見ることは」と訳す。
|
| 2.2.12 |
南の町も通して、はるばるとあれば、あなたにもかやうの若き人どもは見けり。
「打毬楽」「落蹲」など遊びて、勝ち負けの乱声どもののしるも、夜に入り果てて、何事も見えずなり果てぬ。
舎人どもの禄、品々賜はる。
いたく更けて、人びと皆あかれたまひぬ。
|
南の町まで通して、ずっと続いているので、あちらでもこのような若い女房たちは見ていた。
「打毬楽」「落蹲」などを奏でて、勝ち負けに大騒ぎをするのも、夜になってしまって、何も見えなくなってしまった。
舎人連中が禄を、位階に応じてに頂戴する。
たいそう夜が更けてから、人々は皆お帰りになった。
|
南御殿の横まで端は及んでいたから、紫夫人のほうでも若い女房などは見物していた。「打毬楽」「納蘇利」などの奏楽がある上に、右も左も勝つたびに歓呼に代えて楽声をあげた。夜になって終わるころにはもう何もよく見えなかった。左近衛府の舎人たちへは等差をつけていろいろな纏頭が出された。ずっと深更になってから来賓は退散したのである。
|
|
|
第三段 源氏、花散里のもとに泊まる
|
| 2.3.1 |
|
大臣は、こちらでお寝みになった。
お話などを申し上げなさって、
|
源氏は花散里のほうに泊まるのであった。いろいろな話が夫人とかわされた。
|
【大臣は、こなたに大殿籠もりぬ】- 源氏は花散里のもとに泊まる。久し振りのことである。
|
| 2.3.2 |
|
「兵部卿宮が、誰よりも格別に優れていらっしゃいますね。
容貌などはそれほどでもないが、心配りや態度などが優雅で、魅力的なお方です。
こっそりと御覧になりましたか。
立派だと言うが、まだ物足りないところがあるね」
|
「兵部卿の宮はだれよりもごりっぱなようだ。御容貌などはよろしくないが、身の取りなしなどに高雅さと愛嬌のある方だ。そのほかはよいと言われている人たちにも欠点がいろいろある」
|
【兵部卿宮の】- 以下「なほこそあれ」まで、源氏の詞。
【よしといへど、なほこそあれ】- 『集成』は「人はほめますが、たいしたことはありません。「なほあり」は、平凡だの意。言葉の裏に源氏のわれぼめの気持がある」と注す。
|
| 2.3.3 |
とのたまふ。
|
とおっしゃる。
|
|
|
| 2.3.4 |
|
「弟君ではいらっしゃいますが、大人びてお見えになりました。
ここ何年か、このように機会あるごとにおいでになっては、お親しみ申し上げなさっていらっしゃるとうかがっておりますが、昔の宮中あたりでちらっと拝見してから後、よくわかりません。
たいそうご立派に、ご容貌など成長なさいました。
帥の親王が素晴らしくいらっしゃるようですが、感じが劣って、王族程度でいらっしゃいました」
|
「あなたの弟様でもあの方のほうが老けてお見えになりますね。こちらへ古くからよくおいでになると聞いていましたが、私はずっと昔に御所で隙見をしてお知り申し上げているだけですから、今日お顔を見て、そのころよりきれいにおなりになったと思いました。帥の宮様はお美しいようでも品がおよろしくなくて王様というくらいにしかお見えになりませんでした」
|
【御弟にこそものしたまへど】- 以下「ものしたまひける」まで、花散里の詞。
【ねびまさりてぞ見えたまひける】- 『完訳』は「源氏より老けて見える、の意。源氏の若さを賞賛。宮は年齢不詳」と注す。
【渡り、睦びきこえたまふと】- 蛍宮が六条院に。
【帥の親王よくものしたまふめれど】- 桐壷院の皇子、源氏や蛍宮たちの弟宮。ここだけに登場する人物。
【大君けしきにぞものしたまひける】- 『集成』は「諸王くらいの風格でいらっしゃいます。「大君」は親王宣下のない皇子、皇孫の意」と注す。
|
| 2.3.5 |
|
とおっしゃるので、「一目でお見抜きだ」とお思いになるが、にっこりして、その他の人々については、良いとも悪いとも批評なさらない。
|
この批評の当たっていることを源氏は思ったが、ただ微笑んでいただけであった。花散里夫人の批評は他の人たちにも及んだのであるが、よいとも悪いとも自身の意見を源氏は加えようとしないのである。
|
【ふと見知りたまひにけり】- 源氏の心中。花散里の眼力に感服。
【ほほ笑みて】- 主語は花散里。
【なほあるを、良しとも悪しともかけたまはず】- 『集成』は「取り柄のない人については、よいとも悪いとも批評がましいことはお口になさらない」と訳す。
|
| 2.3.6 |
|
人のことに欠点を見つけ、非難するような人を、困った者だと思っていらっしゃるので、
|
難をつけられる人とか、悪く見られている人とかに同情する癖があったから。
|
【人の上を】- 以下の文の主語は源氏。
|
| 2.3.7 |
|
「右大将などをさえ、立派な人だと言っているようだが、何のたいしたことがあろうか。
婿として見たら、きっと物足りないことであろう」
|
右大将のことを深味のあるような人であると夫人が言うのを聞いても、たいしたことがあるものでない、婿などにしては満足していられないであろう
|
【右大将などをだに、心にくき人にすめるを】- 以下「飽かぬことにやあらむ」まで、源氏の心中。「右大将」は鬚黒大将、玉鬘の求婚者の一人。
【近きよすがにて見むは】- 近い縁者、すなわち婿として見たら、の意。
|
| 2.3.8 |
と、見たまへど、言に表はしてものたまはず。
|
と、お思いだが、口に出してはおっしゃらない。
|
と源氏は否定したく思ったが、表へその心持ちを現わそうとしなかった。
|
|
| 2.3.9 |
|
今はただ一通りのご夫婦仲で、お寝床なども別々にお寝みになる。
「どうしてこのよう疎々しい仲になってしまったのだろう」と、殿は苦痛にお思いになる。
だいたい、何のかのと嫉妬申し上げなさらず、長年このような折節につけた遊び事を、人づてにお聞きになっていらっしゃったのだが、今日は珍しくこちらであったことだけで、自分の町の晴れがましい名誉とお思いでいらっしゃった。
|
睦まじくしながら夫人と源氏は別な寝床に眠るのであった。いつからこうなってしまったのかと源氏は苦しい気がした。平生花散里夫人は、源氏に無視されていると腹をたてるようなこともないが、六条院にはなやかな催しがあっても、人づてに話を聞くぐらいで済んでいるのを、今日は自身の所で会があったことで、非常な光栄にあったように思っているのであった。
|
【今はただおほかたの御睦びにて、御座なども異々にて大殿籠もる】- 源氏と花散里の夫婦生活。
【などてかく離れそめしぞ】- 源氏の心中。夫婦の契りの無くなったことをうらむ気持ち。
【おほかた、何やかやとも】- 以下、花散里の性格。
|
| 2.3.10 |
|
「馬も食べない草として有名な水際の菖蒲のようなわたしを
今日は節句なので、
|
その駒もすさめぬものと名に立てる
汀の菖蒲今日や引きつる
|
【その駒もすさめぬ草と名に立てる--汀の菖蒲今日や引きつる】- 花散里から源氏への贈歌。「香をとめてとふ人あるを菖蒲草あやしく人のすさめざりけり」(後拾遺集夏、二一〇、恵慶法師)を引歌とする。『完訳』は「「あやめ」は自分。「駒もすさめぬ」は、男に顧みられぬ女の嘆きの類型表現」と注す。
|
| 2.3.11 |
とおほどかに聞こえたまふ。
何ばかりのことにもあらねど、あはれと思したり。
|
とおっとりと申し上げなさる。
たいしたことではないが、しみじみとお感じになった。
|
とおおように夫人は言った。何でもない歌であるが、源氏は身にしむ気がした。
|
|
| 2.3.12 |
|
「鳰鳥のようにいつも一緒にいる若駒のわたしは
いつ菖蒲のあなたに別れたりしましょうか」
|
にほ鳥に影を並ぶる若駒は
いつか菖蒲に引き別るべき
|
【鳰鳥に影をならぶる若駒は--いつか菖蒲に引き別るべき】- 源氏の返歌。「駒」「菖蒲」「引き」を受けて返す。「引き」は「菖蒲」の縁語。「若駒とけふに逢ひくるあやめ草おひおくるるや負くるなるらむ」(和漢朗詠集上、端午、一五七)を引歌とする。『完訳』は「「若駒」が自分。「あやめ」が花散里。仲のよい「にほどり」に、二人の仲を擬える」と注す。
|
| 2.3.13 |
|
遠慮のないお二人の歌であること。
|
と源氏は言った。
|
【あいだちなき御ことどもなりや】- 語り手の揶揄。『集成』は「夫婦仲のことを遠慮なく詠んだ、色気のない歌だという揶揄気味の草子地」と注す。
|
| 2.3.14 |
|
「いつも離れているようですが、こうしてお目にかかりますのは、心が休まります」
|
意はそれでよいが夫人の謙遜をそのまま肯定した言葉は少し気の毒である。
|
【朝夕の隔てあるやうなれど】- 以下「こそあれ」まで、源氏の詞。
【心やすくこそあれ】- 大島本は「心やすくこそあれ」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「心やすくこそあれと」と「と」を補訂する。
|
| 2.3.15 |
戯れごとなれど、のどやかにおはする人ざまなれば、静まりて聞こえなしたまふ。
|
と、冗談を言うが、のんびりとしていらっしゃるお人柄なので、しんみりとした口ぶりで申し上げなさる。
|
「二六時中あなたといっしょにいるのではないが、こうして信頼をし合って暮らすのはいいことですね」戯れを言うのでもこの人に対してはまじめな調子にされてしまう源氏であった。
|
|
| 2.3.16 |
床をば譲りきこえたまひて、御几帳引き隔てて大殿籠もる。気近くなどあらむ筋をば、いと似げなかるべき筋に、思ひ離れ果てきこえたまへれば、あながちにも聞こえたまはず。 |
御帳台はお譲り申し上げなさって、御几帳を隔ててお寝みになる。
共寝をするというようなことを、たいそう似つかわしくないことと、すっかりお諦め申していらっしゃるので、無理にお誘い申し上げなさらない。
|
帳台の中の床を源氏に譲って、夫人は几帳を隔てた所で寝た。夫婦としての交渉などはもはや不似合いになったとしている人であったから、源氏もしいてその心を破ることをしなかった。
|
【気近くなどあらむ筋をば】- 共寝をすることをさす。
|
|
第三章 光る源氏の物語 光る源氏の物語論
|
|
第一段 玉鬘ら六条院の女性たち、物語に熱中
|
| 3.1.1 |
長雨例の年よりもいたくして、晴るる方なくつれづれなれば、御方々、絵物語などのすさびにて、明かし暮らしたまふ。明石の御方は、さやうのことをもよしありてしなしたまひて、姫君の御方にたてまつりたまふ。 |
長雨が例年よりもひどく降って、晴れる間もなく所在ないので、御方々は、絵や物語などを遊び事にして、毎日お暮らしになっていらっしゃる。
明石の御方は、そのようなことも優雅な趣向を凝らして仕立てなさって、姫君の御方に差し上げなさる。
|
梅雨が例年よりも長く続いていつ晴れるとも思われないころの退屈さに六条院の人たちも絵や小説を写すのに没頭した。明石夫人はそんなほうの才もあったから写し上げた草紙などを姫君へ贈った。
|
【晴るる方なく】- 『集成』は「空も心も」と注す。五月雨時期の景情一致、心象風景の描写。
【絵物語】- 『集成』は「絵物語(挿絵のついた物語)」。『完訳』は「絵や物語。一説に、絵物語」と注す。
|
| 3.1.2 |
|
西の対では、まして珍しく思われなさることの遊び事なので、毎日写したり読んだりしていらっしゃる。
そのうってつけの若い女房たちが大勢いる。
いろいろと珍しい人の身の上などを、本当のことか嘘のことかと、たくさんある物語の中でも、「自分の身の上と同じようなのはなかった」と御覧になる。
|
若い玉鬘はまして興味を小説に持って、毎日写しもし、読みもすることに時を費やしていた。こうしたことの相手を勤めるのに適した若い女房が何人もいるのであった。数奇な女の運命がいろいろと書かれてある小説の中にも、事実かどうかは別として、自身の体験したほどの変わったことにあっている人はないと玉鬘は思った。
|
【西の対には、まして】- 玉鬘をさす。筑紫の田舎育ちゆえに絵や物語に対して一層の興味と関心をしめす。
【つきなからぬ若人あまたあり】- 『集成』は「(物語の蒐集、書写、挿絵かきなどに)うってつけの若い女房は大勢いる」と注す。
【わがありさまのやうなるはなかりけり】- 玉鬘の心中。
|
| 3.1.3 |
|
『住吉物語』の姫君が、物語中での評判もさることながら、現実での評判もやはり格別のようだが、主計頭が、もう少しで奪うところであったことなどを、あの監の恐しさと思い比べて御覧になる。
|
住吉の姫君がまだ運命に恵まれていたころは言うまでもないが、あとにもなお尊敬されているはずの身分でありながら、今一歩で卑しい主計頭の妻にされてしまう所などを読んでは、恐ろしかった監のことが思われた。
|
【さしあたりけむ折はさるものにて】- 『集成』は「その当時の評判のすばらしかったことは当然として」。『完訳』は「いろいろなめにあったその時の話は話として」「玉鬘が物語の世界と現実の世界をやや混同するところを、次に源氏がからかう」と注す。
【なほ心ことなめるに】- 推量の助動詞「めり」の主観的推量は語り手の玉鬘の心中に即した叙述。
|
| 3.1.4 |
殿も、こなたかなたにかかるものどもの散りつつ、御目に離れねば、
|
殿も、あちらこちらでこのような絵物語が散らかっていて、お目につくので、
|
源氏はどこの御殿にも近ごろは小説類が引き散らされているのを見て玉鬘に言った。
|
|
| 3.1.5 |
「あな、むつかし。女こそ、ものうるさがらず、人に欺かれむと生まれたるものなれ。ここらのなかに、真はいと少なからむを、かつ知る知る、かかるすずろごとに心を移し、はかられたまひて、暑かはしき五月雨の、髪の乱るるも知らで、書きたまふよ」 |
「ああ、困ったものだ。
女性というものは、面倒がりもせず、人にだまされようとして生まれついたものですね。
たくさんの中にも真実は少ないだろうに、そうとは知りながら、このようなつまらない話にうつつをぬかし、だまされなさって、蒸し暑い五月雨の、髪の乱れるのも気にしないで、お写しになることよ」
|
「いやなことですね。女というものはうるさがらずに人からだまされるために生まれたものなんですね。ほんとうの語られているところは少ししかないのだろうが、それを承知で夢中になって作中へ同化させられるばかりに、この暑い五月雨の日に、髪の乱れるのも知らずに書き写しをするのですね」
|
【あな、むつかし】- 以下「書きたまふよ」まで、源氏の詞。
【五月雨の、髪】- 「ほととぎすをち返り鳴けうなゐ子がうち垂れ髪の五月雨の空」(拾遺集夏、一一六、躬恒)。
|
| 3.1.6 |
とて、笑ひたまふものから、また、
|
と言って、お笑いになる一方で、また、
|
笑いながらまた、
|
|
| 3.1.7 |
|
「このような古物語でなくては、なるほど、どうして気の紛らしようのない退屈さを慰めることができようか。
それにしても、この虚構の物語の中に、なるほどそうもあろうかと人情を見せ、もっともらしく書き綴ったのは、それはそれで、たわいもないこととは知りながらも、無性に興をそそられて、かわいらしい姫君が物思いに沈んでいるのを見ると、何程か心引かれるものです。
|
「けれどもそうした昔の話を読んだりすることがなければ退屈は紛れないだろうね。この嘘ごとの中にほんとうのことらしく書かれてあるところを見ては、小説であると知りながら興奮をさせられますね。可憐な姫君が物思いをしているところなどを読むとちょっと身にしむ気もするものですよ。
|
【かかる世の古言ならでは】- 以下「さしもあらじや」まで、源氏の詞。
【慰めまし】- 推量の助動詞「まし」反実仮想の意。
【偽りども】- 『完訳』は「女たちの理解に即して「いつはり」としたが、文意からは「そらごと」とあるべき。作り事が、人を勘当させる真実味や説得力をはらみうる、虚構の真実をいう」と注す。
【かた心つくかし】- 『集成』は「多少とも心がひかれるものですよ。以上、主人公が物思いに沈むといった情緒的な場面。物語の一つの要素である」と注す。
|
| 3.1.8 |
また、いとあるまじきことかなと見る見る、おどろおどろしくとりなしけるが目おどろきて、静かにまた聞くたびぞ、憎けれど、ふとをかしき節、あらはなるなどもあるべし。 |
また、けっしてありそうにないことだと思いながらも、大げさに誇張して書いてあるところに目を見張る思いがして、落ち着いて再び聞く時には、憎らしく思うが、とっさには面白いところなどがきっとあるのでしょう。
|
また不自然な誇張がしてあると思いながらつり込まれてしまうこともあるし、またまずい文章だと思いながらおもしろさがある個所にあることを否定できないようなのもあるようですね。
|
【いとあるまじきことかなと】- 『集成』は「以下、奇抜な人目を驚かすような物語の趣向。伝奇的な要素。これも物語の持つもう一つの要素である」と注す。
|
| 3.1.9 |
|
最近、幼い姫が女房などに時々読ませているのを立ち聞きすると、何と口のうまい者がいるものですね。
根も葉もない嘘をつき馴れた者の口から言い出すのだろうと思われますが、そうではないありませんか」
|
このごろあちらの子供が女房などに時々読ませているのを横で聞いていると、多弁な人間があるものだ、嘘を上手に言い馴れた者が作るのだという気がしますが、そうじゃありませんか」
|
【幼き人の女房などに時々読まするを立ち聞けば】- 明石姫君をさす。格助詞「の」主格を表す。当時の物語の観賞法が窺える。
【虚言をよくしなれたる口つきよりぞ言ひ出だすらむとおぼゆれど】- 『集成』は「根も葉もない嘘をつきなれた口から言い出すのであろうとおもわれますが」。『完訳』は「こんな物語も、さぞかし巧みにありもせぬ作り事を言いなれた人の、口からの出まかせなのだろうと思うのですが」と訳す。
|
| 3.1.10 |
とのたまへば、
|
とおっしゃると、
|
と言うと、
|
|
| 3.1.11 |
|
「おっしゃるとおり、嘘をつくことに馴れた人は、いろいろとそのようにご想像なさるでしょう。
ただどうしても真実のことと思われるのです」
|
「そうでございますね。嘘を言い馴れた人がいろんな想像をして書くものでございましょうが、けれど、どうしてもほんとうとしか思われないのでございますよ」
|
【げに、偽り馴れたる人や】- 以下「お思うたまへられけれ」まで、玉鬘の詞。「たまへ」謙譲の補助動詞。「られ」自発の助動詞。「けれ」過去の助動詞、詠嘆の意。
|
| 3.1.12 |
とて、硯をおしやりたまへば、
|
と言って、硯を押しやりなさるので、
|
こう言いながら玉鬘は硯を前へ押しやった。
|
|
| 3.1.13 |
|
「失礼にもけなしてしまいましたね。
神代から世の中にあることを、書き記したものだそうだ。
『日本紀』などは、ほんの一面にしか過ぎません。
物語にこそ道理にかなった詳細な事柄は書いてあるのでしょう」
|
「不風流に小説の悪口を言ってしまいましたね。神代以来この世であったことが、日本紀などはその一部分に過ぎなくて、小説のほうに正確な歴史が残っているのでしょう」
|
【こちなくも】- 以下「詳しきことはあらめ」まで、源氏の詞。
【記しおきけるななり】- 「な」断定の助動詞、連体形。「なり」伝聞推定の助動詞。『集成』は「伝承の記録という意味では国史と変らない、むしろ国史よりも委しいと次に言う」と注す。
【日本紀』などは、ただかたそばぞかし】- 『集成』は「『日本書紀』。わが国最初の正史」「ほんの片端にすぎないものです」。『完訳』は「六国史など官製国史の総称」「日本紀などはほんの一面にすぎないものです」と注す。
|
| 3.1.14 |
とて、笑ひたまふ。
|
と言って、お笑いになる。
|
と源氏は言うのであった。
|
|
|
第二段 源氏、玉鬘に物語について論じる
|
| 3.2.1 |
「その人の上とて、ありのままに言ひ出づることこそなけれ、善きも悪しきも、世に経る人のありさまの、見るにも飽かず、聞くにもあまることを、後の世にも言ひ伝へさせまほしき節々を、心に籠めがたくて、言ひおき始めたるなり。善きさまに言ふとては、善きことの限り選り出でて、人に従はむとては、また悪しきさまの珍しきことを取り集めたる、皆かたがたにつけたる、この世の他のことならずかし。 |
「誰それの話といって、事実どおりに物語ることはありません。善いことも悪いことも、この世に生きている人のことで、見飽きず、聞き流せないことを、後世に語り伝えたい事柄を、心の中に籠めておくことができず、語り伝え初めたものです。
善いように言おうとするあまりには、善いことばかりを選び出して、読者におもねろうとしては、また悪いことでありそうにもないことを書き連ねているのは、皆それぞれのことで、この世の他のことではないのですよ。
|
「だれの伝記とあらわに言ってなくても、善いこと、悪いことを目撃した人が、見ても見飽かぬ美しいことや、一人が聞いているだけでは憎み足りないことを後世に伝えたいと、ある場合、場合のことを一人でだけ思っていられなくなって小説というものが書き始められたのだろう。よいことを言おうとすればあくまで誇張してよいことずくめのことを書くし、また一方を引き立てるためには一方のことを極端に悪いことずくめに書く。全然架空のことではなくて、人間のだれにもある美点と欠点が盛られているものが小説であると見ればよいかもしれない。
|
【その人の上とて】- 以下「空しからずなりぬや」まで、源氏の詞。『集成』は「以下、物語の細論。物語には誇張はあるが、この世の人間の姿を伝える点では国史と変らないという主旨を展開する」と注す。
【見るにも飽かず、聞くにもあまることを】- 『完訳』は「人を感動させてやまぬ内容をいう」と注す。
【善きさまに言ふとては】- 以下、物語の誇張表現についていう。
|
| 3.2.2 |
|
異朝の作品は、記述のしかたが変わっているが、同じ日本の国のことなので、昔と今との相違がありましょうし、深いものと浅いものとの違いがありましょうが、一途に作り話だと言い切ってしまうのも、実情にそぐわないことです。
|
支那の文学者が書いたものはまた違うし、日本のも昔できたものと近ごろの小説とは相異していることがあるでしょう。深さ浅さはあるだろうが、それを皆嘘であると断言することはできない。
|
【人の朝廷の才、作りやう変はる、同じ大和の国のことなれば】- 『集成』は「異朝(中国の朝廷)では、学問(歴史についての考え)も記述の体裁もわが国と違います。この一句、解しがたく、異文も多く、諸説も多い」「(国史と物語とでは)同じ日本の国のことですから、昔からの国史と今出来の物語とでは違いがあるはずですし」。『完訳』は「異朝の物語でさえも--国が違うから書き方は変っているが、また日本の物語でも同じ国のことだから、昔のは今のと違っていて当然ですし」と注す。
【深きこと浅きことのけぢめこそあらめ】- 『集成』は「意味深い国史と浅はかな物語という差はありましょうが」。『完訳』は「その内容に深い浅いの相違はあるでしょうが」と訳す。
|
| 3.2.3 |
仏の、いとうるはしき心にて説きおきたまへる御法も、方便といふことありて、悟りなきものは、ここかしこ違ふ疑ひを置きつべくなむ。
『方等経』の中に多かれど、言ひもてゆけば、ひとつ旨にありて、菩提と煩悩との隔たりなむ、この、人の善き悪しきばかりのことは変はりける。
|
仏教で、まことに立派なお心で説きおかれた御法文も、方便ということがあって、分からない者は、あちこちで矛盾するという疑問を持つに違いありません。
『方等経』の中に多いが、詮じつめていくと、同一の主旨に落ち着いて、菩提と煩悩との相違とは、物語の、善人と悪人との相違程度に過ぎません。
|
仏が正しい御心で説いてお置きになった経の中にも方便ということがあって、大悟しない人間はそれを見ると疑問が生じるだろうと思われる。方等経の中などにはことに方便が多く用いられています。結局は皆同じことになって、菩提心はよくて、煩悩は悪いということが言われてあるのです。つまり小説の中に善悪を書いてあるのがそれにあたるのですよ。
|
|
| 3.2.4 |
よく言へば、すべて何ごとも空しからずなりぬや」
|
よく解釈すれば、全て何事も無駄でないことはなくなってしまうものですね」
|
だから好意的に言えば小説だって何だって皆結構なものだということになる」
|
|
| 3.2.5 |
と、物語をいとわざとのことにのたまひなしつ。
|
と、物語を実にことさらに大したもののようにおっしゃった。
|
と源氏は言って、小説が世の中に存在するのを許したわけである。
|
|
| 3.2.6 |
|
「ところで、このような昔物語の中に、わたしのような律儀な愚か者の物語はありませんか。
ひどく親しみにくい物語の姫君も、あなたのお心のように冷淡で、そらとぼけている人はまたとありますまいな。
さあ、二人の仲を世にも珍しい物語にして、世間に語り伝えさせましょう」
|
「それにしてもね、古いことの書いてある小説の中に私ほどまじめな愚直過ぎる男の書いてあるものがありますか。それからまた人間離れのしたような小説の姫君だってあなたのように恋する男へ冷淡で、知って知らぬ顔をするようなのはないでしょう。だからありふれた小説の型を破った小説にあなたと私のことをさせましょう」
|
【さて、かかる古言の中に】- 以下「世に伝へさせむ」まで、源氏の詞。
【まろがやうに実法なる痴者の物語はありや】- 『完訳』は「源氏は、自ら誠実を尽すが女に顧みられぬ男として、玉鬘へ哀訴」と注す。
|
| 3.2.7 |
と、さし寄りて聞こえたまへば、顔を引き入れて、
|
と、近づいて申し上げなさるので、顔を引き入れて、
|
近々と寄って来て源氏は玉鬘にこうささやくのであった。玉鬘は襟の中へ顔を引き入れるようにして言う。
|
|
| 3.2.8 |
|
「そうでなくても、このように珍しいことは、世間の噂になってしまいそうなことでございます」
|
「小説におさせにならないでも、こんな奇怪なことは話になって世間へ広まります」
|
【さらずとも】- 以下「はべりぬべかめれ」まで、玉鬘の詞。
【かく珍かなることは】- 父親が娘に言い寄ることをさす。
|
| 3.2.9 |
とのたまへば、
|
とおっしゃるので、
|
|
|
| 3.2.10 |
|
「珍しくお思いですか。
なるほど、またとない気持ちがします」
|
「珍しいことだというのですか。そうです。私の心は珍しいことにときめく」
|
【珍かにや】- 以下「またなき心地すれ」まで、源氏の詞。『集成』は「(私も)ほんとにこれほどまでにひとを思ったことはありません。玉鬘の言葉をそらして、からんでゆく」。『完訳』は「いかにもあなたのように冷淡な娘はまたとないような気がいたします」「玉鬘の「めづらか」に納得するかにみせ、「またなき心地」に親に冷淡な、の意をこめて歌に続ける」と注す。
|
| 3.2.11 |
|
と言って、寄り添っていらっしゃる態度は、たいそうふざけている。
|
ひたひたと寄り添ってこんな戯れを源氏は言うのである。
|
【いとあざれたり】- 語り手の批評の文。
|
| 3.2.12 |
|
「思いあまって昔の本を捜してみましたが
親に背いた子供の例はありませんでしたよ
|
「思ひ余り昔のあとを尋ぬれど
親にそむける子ぞ類ひなき
|
【思ひあまり昔の跡を訪ぬれど--親に背ける子ぞたぐひなき】- 源氏から玉鬘への贈歌。
|
| 3.2.13 |
|
親不孝なのは、仏の道でも厳しく戒めています」
|
不孝は仏の道でも非常に悪いことにして説かれています」
|
【不孝なるは】- 以下「いみじくこそ言ひけれ」まで、歌に続けた源氏の詞。
|
| 3.2.14 |
|
とおっしゃるが、顔もお上げにならないので、お髪を撫でながら、ひどくお恨みなさるので、やっとのことで、
|
と源氏が言っても、玉鬘は顔を上げようともしなかった。源氏は女の髪をなでながら恨み言を言った。やっと玉鬘は、
|
【御髪をかきやりつつ】- 源氏が玉鬘の御髪を。
|
| 3.2.15 |
|
「昔の本を捜して読んでみましたが、
おっしゃるとおりありませんでした
|
古き跡を尋ぬれどげになかりけり
この世にかかる親の心は
|
【古き跡を訪ぬれどげになかりけり--この世にかかる親の心は】- 玉鬘の返歌。「昔」を「古き」に変え、「跡」「訪ぬ」「親」の語句はそのまま受けて返す。
|
| 3.2.16 |
|
とお申し上げなさるにつけても、気恥ずかしいので、そうひどくもお戯れにならない。
|
こう言った。源氏は気恥ずかしい気がしてそれ以上の手出しはできなかった。
|
【心恥づかしければ】- 以下、主語は源氏。
|
| 3.2.17 |
|
こうして、どうなって行くお二方の仲なのであろう。
|
どうこの二人はなっていくのであろう。
|
【かくして、いかなるべき御ありさまならむ】- 語り手の弁。『集成』は「草子地」。『完訳』は「物語の後続に、読者の期待をつなぐ語り手の弁」と注す。
|
|
第三段 源氏、紫の上に物語について述べる
|
| 3.3.1 |
紫の上も、姫君の御あつらへにことつけて、物語は捨てがたく思したり。『くまのの物語』の絵にてあるを、 |
紫の上も、姫君のご注文にかこつけて、物語は捨てがたく思っていらっしゃった。
『くまのの物語』の絵の箇所を、
|
紫夫人も姫君に託してやはり物語を集める一人であった。「こま物語」の絵になっているのを手に取って、
|
【くまのの物語】- 河内本と別本は「こまののものかたり」あるいは「こまのものかたり」とある。『枕草子』には「こまのの物語」と見える。
|
| 3.3.2 |
|
「とてもよく描いた絵だわ」
|
「上手にできた画だこと」
|
【よく描きたる絵かな】- 紫の上の感想。
|
| 3.3.3 |
とて御覧ず。
小さき女君の、何心もなくて昼寝したまへるところを、昔のありさま思し出でて、女君は見たまふ。
|
と御覧になる。
小さい女君が、あどけなく昼寝をしていらっしゃる所を、昔の様子をご回想なさって、女君は御覧になる。
|
と言いながら夫人は見ていた。小さい姫君が無邪気なふうで昼寝をしているのが昔の自分のような気がするのであった。
|
|
| 3.3.4 |
|
「このような子供どうしでさえ、なんとませたことなのでしょう。
わたしなど、やはり語り草になるほど、気の長さは誰にも負けませんね」
|
「こんな子供どうしでも悪い関係がすぐにできるじゃありませんか。昔を言えば私などは模範にしてよいまれな物堅さだった」
|
【かかる童どちだに】- 以下「人に似ざりけれ」まで、源氏の詞。
【例にしつべく】- 『完訳』は「好色の経験がないとする冗談」と注す。
|
| 3.3.5 |
|
と申し上げなさる。
なるほど、世間に例の多くない恋愛を、数々なさってこられたことよ。
|
と源氏は夫人に言った。そのかわりにまれなことも好きであったはずである。
|
【げに、たぐひ多からぬことどもは、好み集めたまへりけりかし】- 語り手の批評。『集成』は「草子地」。『完訳』は「語り手の評。「源氏の「なほ例に--」を、類例の少ない好色事の意に解して、皮肉る」と注す。
|
| 3.3.6 |
「姫君の御前にて、この世馴れたる物語など、な読み聞かせたまひそ。みそか心つきたるものの娘などは、をかしとにはあらねど、かかること世にはありけりと、見馴れたまはむぞ、ゆゆしきや」 |
「姫君の御前で、この色恋沙汰の物語など、読み聞かせなさいますな。
秘め事をする物語の娘などは、おもしろいと思わぬまでも、このようなことが世間にはあるのものだと、当たり前のように思われるのが、困ったことなのですよ」
|
「姫君の前でこうした男女関係の書かれた小説は読んで聞かせないようにするほうがいい。恋をし始めた娘などというものが、悪いわけではないが、世間にはこんなことがあるのだと、それを普通のことのように思ってしまわれるのが危険ですからね」
|
【姫君の御前にて】- 以下「ゆゆしきや」まで、源氏の詞。
|
| 3.3.7 |
|
とおっしゃるにつけても、格段に違うと、対の御方がお聞きになったら、きっとひがまれよう。
|
こんな周到な注意が実子の姫君には払われているのを、対の姫君が聞いたら恨むかもしれない。
|
【こよなしと、対の御方聞きたまはば、心置きたまひつべくなむ】- 『完訳』は「以下、語り手の推測。玉鬘がこれを知れば、源氏の姫君への処遇は段違いだ、とひがまれよう」と注す。
|
| 3.3.8 |
上、
|
紫の上は、
|
|
|
| 3.3.9 |
|
「軽率な物語の人の物真似の類は、見ていてもたまりません。
『宇津保物語』の藤原の君の娘は、とても思慮深くしっかりした人で、間違いはないようですが、そっけない返事もそぶりも、女性らしいところがないようなのが、同じようですね」
|
「浅はかな、ある型を模倣したにすぎないような女は読んでいましてもいやになります。空穂物語の藤原の君の姫君は重々しくて過失はしそうでない性格ですが、あまり真直な線ばかりで、しまいまで女らしく書かれてないのが悪いと思うのですよ」
|
【心浅げなる人まねどもは】- 以下「一様なめる」まで、紫の上の詞。
【宇津保』の藤原君の女こそ】- 大島本は「うつほのふちハら君」とある。『集成』『新大系』は底本のままとする。『古典セレクション』は諸本によって「藤原の君」と「の」を補訂する。『集成』は「現存の『宇津保物語』には、巻名も「藤原の君」とあるが、幼名としては「の」を入れないのが慣例であるから、本来は底本(大島本)のように「の」のない表記が正しいであろう」と注す。
【こともしわざも】- 大島本は「(+事も<朱>)しわさも」とある。すなわち朱筆で「事も」を補入する。『新大系』は底本の補訂に従う。『集成』『古典セレクション』は諸本と底本の訂正以前本文に従って「しわざも」と校訂する。
【一様なめる】- 『集成』は「どうにも一本調子にすぎるように思われます。お手本にならない人物だという批評」。『完訳』は「「心浅げなる人まねども」と同様、魅力に欠ける」と注す。
|
| 3.3.10 |
とのたまへば、
|
と、おっしゃると、
|
と夫人が言うと、
|
|
| 3.3.11 |
「うつつの人も、さぞあるべかめる。人びとしく立てたる趣きことにて、よきほどにかまへぬや。よしなからぬ親の、心とどめて生ほしたてたる人の、子めかしきを生けるしるしにて、後れたること多かるは、何わざしてかしづきしぞと、親のしわざさへ思ひやらるるこそ、いとほしけれ。 |
「実際の人も、そういうもののようです。
一人前にそれぞれ主義主張を異にして、加減というものを知りません。
悪くはない親が、気をつかって育てた娘が、無邪気さだけがただ一つのとりえで、劣ったところが多いのは、いったいどんなふうにして育ててきたのかと、親の育て方までが想像されるのは、気の毒です。
|
「現実の人でもそのとおりですよ。風変わりな一本調子で押し通して、いいかげんに転向することを知らない人はかわいそうだ。見識のある親が熱心に育てた娘がただ子供らしいところにだけ大事がられた跡が見えて、そのほかは何もできないようなのを見ては、どんな教育をしたのかと親までも軽蔑されるのが気の毒ですよ。
|
【うつつの人も】- 以下「人ほめさせじ」まで、源氏の詞。
【よきほどにかまへぬや】- 終助詞「や」詠嘆の意。
【親の、心とどめて】- 格助詞「の」主格を表す。
|
| 3.3.12 |
げに、さいへど、その人のけはひよと見えたるは、かひあり、おもだたしかし。
言葉の限りまばゆくほめおきたるに、し出でたるわざ、言ひ出でたることのなかに、げにと見え聞こゆることなき、いと見劣りするわざなり。
|
なるほど、そうは言っても、身分にふさわしい感じがすると思えるのは、育てがいもあり、名誉なことです。
口をきわめて気恥ずかしいほど誉めていたのに、しでかしたことや、口に出した言葉の中に、なるほどと見えたり聞こえたりすることがないのは、まことに見劣りがするものです。
|
なんといってもあの親が育てたらしいよいところがあると思われるような娘があれば親の名誉になるのです。作者の賞めちぎってある女のすること、言うことの中に首肯されることのない小説はだめですよ。
|
|
| 3.3.13 |
|
だいたい、つまらない人には、どうか娘を誉めさせたくないものです」
|
いったいつまらない人に自分の愛する人は賞めさせたくない」
|
【すべて、善からぬ人に、いかで人ほめさせじ】- 『集成』は「下手の人間に下手な評判は立ててもらいたくないという気持」と注す。
|
| 3.3.14 |
など、ただ「この姫君の、点つかれたまふまじく」と、よろづに思しのたまふ。
|
などと、ひたすら「この姫君が非難されないように」と、あれやこれやといろいろ考えておっしゃる。
|
などと言って、源氏は姫君を完全な女性に仕上げることに一所懸命であった。
|
|
| 3.3.15 |
|
継母の意地悪な昔物語も多いが、最近は、「心が見透かされ底意地悪い」と思われなさるので、厳しく選んでは選んでは、清書させたり、絵などにもお描かせなさるのだった。
|
継母が意地悪をする小説も多かったから、その反対な継母のよさを見せつける気がして夫人はそんなものをいっさい省いて選択に選択をしたよいものだけを姫君のために写させたり絵に描かせたりした。
|
【このころ、「心見えに心づきなし】- 大島本は「(+此比<朱>)心みえに」とある。すなわち朱筆で「このころ」を補入する。『新大系』は底本の補入に従う。『集成』『古典セレクション』は諸本と底本の訂正以前本文に従って「此比」を削除する。『集成』は「そういう継母の心底がよく分って、気に入らぬとお思いになるので。紫の上の間柄を考慮した、姫君への教育的な配慮」と注す。
|
|
第四段 源氏、子息夕霧を思う
|
| 3.4.1 |
中将の君を、こなたには気遠くもてなしきこえたまへれど、姫君の御方には、さしもさし放ちきこえたまはずならはしたまふ。 |
中将の君を、こちらにはお近づけ申さないようにしていらっしゃったが、姫君の御方には、そんなにも遠ざけ申しなさらず、親しくさせていらっしゃる。
|
中将を源氏は夫人の住居へ接近させないようにしていたが、姫君の所へは出入りを許してあった。
|
【こなたには】- 紫の上方をさす。
|
| 3.4.2 |
「わが世のほどは、とてもかくても同じことなれど、なからむ世を思ひやるに、なほ見つき、思ひしみぬることどもこそ、取り分きてはおぼゆべけれ」 |
「自分が生きている間は、どちらにせよ同じことだが、死んだ後を想像すると、やはり平生から、馴染んでおいた方が、格別親しく思内側われるに違いない」
|
自分が生きている間は異腹の兄弟でも同じであるが、死んでからのことを思うと早くから親しませておくほうが双方に愛情のできることである
|
【わが世のほどは】- 以下「おぼゆべけれ」まで、源氏の心中。
|
| 3.4.3 |
|
と考えて、
南面の御簾の内側に入ることはお許しに
なっていた。台盤所、女房の中はお許しにならない。何人もいらっしゃらないお子たちの間柄なの
|
と思って、姫君のほうの南側の座敷の御簾の中へ来ることを許したのであるが台盤所の女房たちの集まっているほうへはいることは許してないのである。源氏のためにただ二人だけの子であったから兄妹を源氏は大事にしていた。
|
【御簾の内は許したまへり】- 御簾の内側(南の廂間)に出入りすることは許していたの意。
【台盤所、女房のなかは許したまはず】- 大島本は「たいはむ所女はうのなか」とある。『集成』『新大系』は底本のままとする。『古典セレクション』は諸本に従って「台盤所の」と「の」を補訂する。紫の上付きの女房の詰所への入室及びそれらの人との接触は禁じた。
【いとやむごとなくかしづききこえたまへり】- 主語について、『集成』は源氏と解し、『完訳』は夕霧と解す。
|
| 3.4.4 |
|
だいたいの性格なども、たいそう慎重で、真面目でいらっしゃる君なので、安心してお任せになっていらっしゃった。
まだ幼いお人形遊びなどの様子が見えるので、あの人が、一緒に遊んで過ごした昔の月日が、真先に思い出されるので、人形の殿の宮仕を、とても熱心になさりながら、時々は涙ぐんでいらっしゃるのであった。
|
中将は落ち着いた重々しいところのある性質であったから、源氏は安心して姫君の介添え役をさせた。幼い雛遊びの場にもよく出会うことがあって、中将は恋人とともに遊んで暮らした年月をそんな時にはよく思い出されるので、妹のためにもよい相手役になりながらも時々はしおしおとした気持ちになった。
|
【うしろやすく思し譲れり】- 源氏は夕霧に明石姫君の相手を安心して任せていたの意。
【まだいはけたる御雛遊びなどのけはひの見ゆれば】- 明石姫君八歳。
【かの人の、もろともに】- 雲居雁をさす。格助詞「の」主格を表す。
|
| 3.4.5 |
|
そうしてもよさそうなあたりには、軽い気持ちで言い寄ったりなさる女は大勢いるが、望みを懸けてくるようには仕向けない。
愛人にしてもよさそうだと、思い寄られそうな女も、無理に一時の浮気沙汰にして、やはり「あの、緑の袖よと馬鹿にされたのを見返してやりたいものだ」と思う気持ちだけが、重大事として忘れられないのであった。
|
若い女性たちに恋の戯れを言いかけても、将来に希望をつながせるようなことは絶対にしなかった。妻の一人にしたいと心の惹かれるような人も、しいて一時的の対象とみなして、それ以上関係を進行させることもなかった。今でも緑の袖とはずかしめられた人との関係だけを尊重して、その人以外の人を妻に擬して考えることは不可能であった。
|
【さもありぬべきあたりには】- 『完訳』は「恋の相手にしてもよさそうな」と注す。
【頼みかくべくもしなさず】- 夕霧は相手の女に期待を抱かせるようには仕向けない意。
【さる方になどかは見ざらむと】- 『集成』は「夫人あるいは愛人として世話してもよいなと」。『完訳』は「中には、この女なら自分の思い人としてもどこが悪かろうと」と訳す。
【なほ「かの、緑の袖を見え直してしがな】- 夕霧の心中。「緑の袖」はかつて夕霧が六位であった時に雲居雁の乳母から「六位宿世」と軽蔑されたことをさす(「少女」第五章五段)。
|
| 3.4.6 |
|
無理にでも何とかつきまとったならば、根負けしてお許しになるかも知れないが、「つらいと思った折々のことを、何とか内大臣にもお分りになっていただこう」と考えていたこと、忘れられないので、ご本人に対してだけは、並々ならぬ愛情の限りを表して、表面では恋い焦がれているようには見せない。
|
許されようと熱心ぶりを見せれば伯父の大臣も夫婦にしてくれるであろうが、恨めしかったころに、どんなことがあっても伯父が哀願するのでなければ結婚はすまいと思ったことが忘られなかった。
|
【つらしと思ひし折々】- 以下「たてまつらむ」まで、夕霧の心中。
【おほかたには焦られ思へらず】- 『集成』は「表向きはあせらずおっとり構えている」。『完訳』は「大方の人々には焦ったところを見せようとはしない」と訳す。
|
| 3.4.7 |
兄の君達なども、なまねたしなどのみ思ふこと多かり。対の姫君の御ありさまを、右中将は、いと深く思ひしみて、言ひ寄るたよりもいとはかなければ、この君をぞかこち寄りけれど、 |
ご兄弟の公達なども、小憎らしいなどとばかり思う事が多かった。
対の姫君のご様子を、右中将は、たいそう深く思いつめて、言い寄る手引きもたいそう頼りなかったので、この中将の君に泣きついて来たが、
|
雲井の雁の所へは情けをこめた手紙を常に送っていても、表面はあくまでも冷静な態度を保っているのである。この態度をまた雲井の雁の兄弟たちは恨んでいた。玉鬘に右近中将は深く恋をして仲介役をするのは童女のみるこだけであったから、たよりなさにこの中将を味方に頼むのであった。
|
【右中将】- 柏木。
【この君をぞ】- 夕霧をさす。
|
| 3.4.8 |
|
「他人事となると、感心できないことですね」
|
「人のことではそう熱心になれない問題だから」
|
【人の上にては、もどかしきわざなりけり】- 夕霧の詞。
|
| 3.4.9 |
と、つれなく応へてぞものしたまひける。
昔の父大臣たちの御仲らひに似たり。
|
と素っ気なく答えていらっしゃるのだった。
その昔の父大臣たちの御仲に似ていた。
|
などと左中将は冷淡に言っていた。
|
|
|
第五段 内大臣、娘たちを思う
|
| 3.5.1 |
|
内大臣は、お子様方が夫人たちに大勢いたが、その母方の血筋の良さや、子供の性質に応じて、思いどおりのような世間の声望や、御権勢に任せて、皆一人前に引き立てなさる。
女の子はたくさんはいないが、女御も、あのようにご期待していたこともうまくゆかず、姫君も、またあのように思惑と違うようなことでいらっしゃるので、とても残念だとお思いになる。
|
内大臣は腹々に幾人もの子があって、大人になったそれぞれの子息の人柄にしたがって政権の行使が自由なこの人は皆適した地位につかせていた。女の子は少なくて后の競争に負け失意の人になっている女御と恋の過失をしてしまった雲井の雁だけなのであったから、大臣は残念がっていた。
|
【その生ひ出でたるおぼえ】- 『集成』は「母方の身分による声望や」と訳す。
【人柄に従ひつつ】- 子供本人の性質に応じて。
【心にまかせたるやうなるおぼえ、御勢にて】- 大島本は「(+御<朱>)いきほひ」とある。すなわち朱筆で「御」を補入する。『新大系』は底本の補訂に従う。『集成』『古典セレクション』は諸本と底本の訂正以前本文に従って「勢い」と校訂する。『集成』は「子供たちそれぞれ思い通りというに近い声望や権勢の身の上で」。『完訳』は「それに大臣の何事も思いどおりになる声望や御権勢にまかせて」と訳す。
【女御も、かく思ししことのとどこほりたまひ】- 弘徽殿女御、「澪標」巻で冷泉帝に逸早く入内して、后の地位を望んでいたが、「少女」巻で、後から入内した源氏の養女梅壷女御に立后されたことをさす。
【姫君も、かくこと違ふさまに】- 雲居雁を春宮妃にと志していたにもかかわらず、夕霧との恋仲になってしまったことをさす。
|
| 3.5.2 |
|
あの撫子のことがお忘れになれず、何かのついでにもお口になさったことなので、
|
この人は今も撫子の歌を母親が詠んできた女の子を忘れなかった。
|
【かの撫子を】- 夕顔との間にできた遺児、玉鬘をさす。
【ものの折にも語り出でたまひしことなれば】- 「帚木」巻の「雨夜の品定め」の段で頭中将が常夏の女について語ったことをさす。
|
| 3.5.3 |
「いかになりにけむ。ものはかなかりける親の心に引かれて、らうたげなりし人を、行方知らずなりにたること。すべて女子といはむものなむ、いかにもいかにも目放つまじかりける。さかしらにわが子と言ひて、あやしきさまにてはふれやすらむ。とてもかくても、聞こえ出で来ば」 |
「どうなったのだろう。
頼りない親の心のままに、かわいらしかった子を、行く方不明にしてしまったことよ。
だいたい女の子というものは、どんなことがあっても目を放してはならないものであった。
勝手に自分の子供と名乗って、みじめな境遇でさまよっているのだろうか。
どのような恰好でいるにせよ、噂が聞こえて来たならば」
|
かつて人にも話したほどであるから、どうしたであろう、たよりない性格の母親のために、あのかわいかった人を行方不明にさせてしまった、女というものは少しも目が放されないものである、親の不名誉を思わずに卑しく零落をしながら自分の娘であると言っているのではなかろうか、それでもよいから出て来てほしいと大臣は恋しがっていた。
|
【いかになりにけむ】- 以下「聞こえ出で来ば」まで、内大臣の心中。
|
| 3.5.4 |
|
と、しみじみとずっと思い続けていらっしゃる。
ご子息たちにも、
|
息子たちにも、
|
【君達にも】- 内大臣の御子息たち。
|
| 3.5.5 |
|
「もし、そのように名乗り出る人があったら、聞き逃すな。
気紛れから、感心できない女性関係も多かった中で、あの人は、とても並々の愛人程度とは思われなかった人で、ちょっとした愛想づかしをして、このように少なかった娘一人を、行方不明にしてしまったことの残念なことよ」
|
「もしそういうことを言っている女があったら、気をつけて聞いておいてくれ。放縦な恋愛もずいぶんしていた中で、その母である人はただ軽々しく相手にしていた女でもなく、ほんとうに愛していた人なのだが、何でもないことで悲観して、私に少ない女の子一人をどこにいるかもしれなくされてしまったのが残念でならない」
|
【もし、さやうなる名のりする人あらば】- 以下「口惜しきこと」まで、内大臣の詞。
【心のすさびにまかせて】- 内大臣の若いころの女遊びをさす。
【これは、いとしか、おしなべての際にも思はざりし人の】- 夫人の一人に数える待遇を考えていたことをいう。
【もの倦むじをして】- 下に、姿を隠したの意が省略されている。
【もののくさはひ】- 大切に世話すべき種としての娘の意。
|
| 3.5.6 |
と、常にのたまひ出づ。中ごろなどはさしもあらず、うち忘れたまひけるを、人の、さまざまにつけて、女子かしづきたまへるたぐひどもに、わが思ほすにしもかなはぬが、いと心憂く、本意なく思すなりけり。 |
と、いつもお口に出される。
ひところなどは、そんなにでもなく、ついお忘れになっていたが、他人が、さまざまに娘を大切になさっている例が多いので、ご自分のお思いどおりにならないのが、とても情けなく、残念にお思いになるのであった。
|
とよく話していた。中ほどには忘れていもしたのであるが、他人がすぐれたふうに娘をかしずく様子を見ると、自身の娘がどれも希望どおりにならなかったことで失望を感じることが多くなって、近ごろは急に別れた女の子を思うようになったのである。
|
【人の、さまざまにつけて】- 『集成』は「源氏などが、あれこれと」。『完訳』は「他の人々がさまざまに」と訳す。
|
| 3.5.7 |
夢見たまひて、いとよく合はする者召して、合はせたまひけるに、
|
夢を御覧になって、たいそうよく占う者を召して、夢の意味をお解かせになったところ、
|
ある夢を見た時に、上手な夢占いをする男を呼んで解かせてみると、
|
|
| 3.5.8 |
|
「もしや、長年あなた様に知られずにいらっしゃるお子様を、他人の子として、お耳にあそばすことはございませんか」
|
「長い間忘れておいでになったお子さんで、人の子になっていらっしゃる方のお知らせをお受けになるというようなことはございませんか」
|
【もし、年ごろ御心に】- 以下「聞こし召し出づることや」まで、夢解きの詞。
|
| 3.5.9 |
と聞こえたりければ、
|
と申し上げたので、
|
と言った。
|
|
| 3.5.10 |
|
「女の子が他人の養女となることは、めったにないことだ。
どのようなことだろうか」
|
「男は養子になるが、女というものはそう人に養われるものではないのだが、どういうことになっているのだろう」
|
【女子の人の子になることは】- 以下「いかなることにかあらむ」まで、内大臣の詞。
|
| 3.5.11 |
|
などと、このころになって、お考えになったりおっしゃっているようである。
|
と、それからは時々内大臣はこのことを家庭で話題にした。
|
【思しのたまふべかめる】- 語り手の主観的推量のニュアンスでこの巻を語り収める。
|
| 著作権 |
| 底本 |
大島本 |
| 校訂 |
Last updated 9/21/2010(ver.2-3)
渋谷栄一校訂(C)
オリジナル
修正版
比較 |
| ローマ字版 |
Last updated 12/6/2009 (ver.2-2)
Written in Japanese roman letters
by Eiichi Shibuya (C)
オリジナル
修正版
比較 |
ルビ抽出
(ローマ字版から)
|
Powered by 再編集プログラム v4.05
ひらがな版
ルビ抽出 |
挿絵
(ローマ字版から)
|
'Eiri Genji Monogatari'
(1650 1st edition) |
|
Last updated 8/26/2001
渋谷栄一訳(C)(ver.1-2-2)
オリジナル
修正版
比較 |
|
|
Last updated 12/6/2009(ver.2-2)
渋谷栄一注釈(C)
オリジナル
修正版
比較 |
|