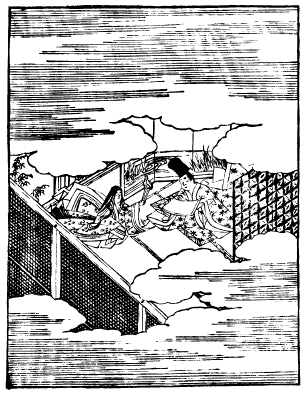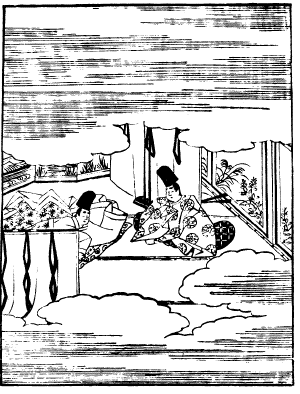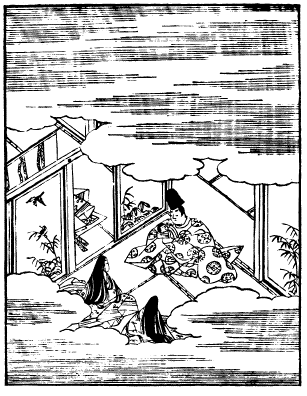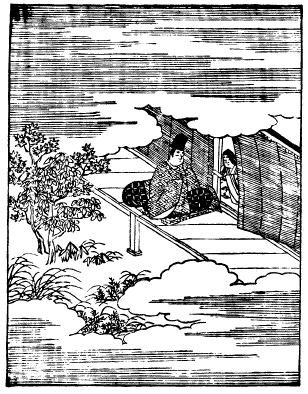第三十六帖 柏木
光る源氏の准太上天皇時代四十八歳春一月から夏四月までの物語
|
# |
本文 |
渋谷栄一訳 |
与謝野晶子訳 |
注釈 |
|
第一章 柏木の物語 女三の宮、薫を出産
|
|
第一段 柏木、病気のまま新年となる
|
| 1.1.1 |
|
衛門督の君、このようにばかりお病み続けになること、依然として回復せぬまま、年も改まった。
大臣、北の方、お嘆きになる様子を拝見すると、
|
右衛門督の病気は快方に向くことなしに春が来た。父の大臣と母夫人の悲しむのを見ては、
|
【衛門督の君】- 「柏木」巻頭の語句。格助詞や係助詞が無い。話題の提示のいわば独立格。衛門督の君、その人はどうしたかといえば、というニュアンス。ただ、下文の述語「悩みたまふ」との関係から、改めて主語と規定される。さらに「悩みわたりたまふこと」が主語となるので、複文構造、さらに「年も返りぬ」の主語-述語関係が続くので、冒頭の一文全体は重文構造である。
【悩みわたりたまふこと】- 主格。述語「おこたらで」に掛かる。
【年も返りぬ】- 係助詞「も」強調のニュアンスを添える。
【大臣、北の方】- 『細流抄』は「此已下柏木の心也」と指摘。『全書』・『評釈』も柏木の心中文とする。
【見たてまつるに】- 主語は柏木。この巻冒頭の語りの視点、また座標軸。
|
| 1.1.2 |
|
「無理して死のうと思う命、その甲斐もなく、罪障のきっと重いだろうことを思う、その考えは考えとして、また一方で、むやみに、この世から出離しがたく、惜しんで留めて置きたい身の上であろうか。
幼かったときから、思う考えは格別で、どのようなことでも、人にはいま一段抜きんでたいと、公事私事につけて、並々ならず気位高く持していたが、その望みも叶いがたかった」
|
死を願うことは重罪にあたることであると一方では思いながらも、自分は決して惜しい身でもない、子供の時から持っていた人に違った自尊心も、
|
【しひてかけ離れなむ命】- 「しひてかけ離れなむ」の文中の機能について、『源氏物語講読』(佐伯梅友)は「命」に掛かるとする見方に「この場合、かいがないというのはどういうことをいうのか解しかねる」と疑問を呈する。「それで、「命かひなく、罪重かるべきこと」に対する主語のようには見られないかと考えた。しいてかけ離れてしまおうとしても、自然のままでは命が消えないとすればそう思うかいがないだろうし、またそれがかなったとしたら、親に嘆きをかけて重い罪業となるだろうと考えている意を、「命かひなく、罪重かるべし」といったと見るのである。そう思う一方では、今が死に時だとも考える気持が、次の心中の部分の終りの方に出ている」と注す。
【罪重かるべきことを】- 『湖月抄』は「父母にさきだつはその歎きをかけて不孝の罪をもきる也」と注す。
【あながちにこの世に】- 『講読』は「ことばの続きぐあいやら、ことばの調子やらを考えて」、以下「あはれも出で来なむ」までを柏木の心中文とする。 【この世に】-格助詞「に」基点を表す。この世から出離しがたく、の意。
【惜しみ留めまほしき身かは】- 連語「かは」反語表現。言語主体は柏木。
【思ひ上りしかど】- 過去の助動詞「しか」已然形、自己体験のニュアンス。
【その心叶ひがたかりけり】- 『全集』は「挫折してはじめて事柄のむずかしさに気づく」と注す。
|
| 1.1.3 |
|
と、一つ二つのつまずき事に、わが身に自信をなくして以来、大方の世の中がおもしろくなく思うようになって、来世の修業に心深く惹かれたのだが、両親のご悲嘆を思うと、山野にもさまよい込む道の強い障害ともなるにちがいなく思われたので、あれやこれやと紛らわし紛らわし過ごしてきたのだが、とうとう、
|
ある一つ二つの場合に得た失望感からゆがめられて以来は厭世的な思想になって、出家を志していたにもかかわらず、親たちの歎きを顧みると、この絆が遁世の実を上げさすまいと考えられて、自己を紛らしながら俗世界にいるうちに、ついに
|
【なべての世の中】- 明融臨模本、朱合点、付箋C型「大かたのわか身一のうきからになへての世をもうらみつるかな」(拾遺集恋五、九五三、紀貫之)とあり、大島本も、朱合点、細字注記「大方は我身一のうきからになへての世をもうらみつるかな」とある。
【後の世の行なひに本意深く進みにしを】- 『全集』は「柏木に出家の意志のあったことは初出」と指摘。連語「にし」完了の助動詞と過去の助動詞の複合。すでに出家へと心がすっかり傾いてしまっていた、というニュアンス。
【親たちの御恨みを思ひて】- 接続助詞「て」順接の仮定条件、お嘆きを考えたら、お嘆きを考えると、の意。「重きほだしにもなりぬべく」に掛かる。
【野山にも】- 明融臨模本、付箋「いつくにか世をはいとはむ心こそ野にも山にもまとふへらなれ」(古今集雑下、九四七、素性)とあり、大島本も、朱合点、付箋「いつくにか世をはいとはん心こそ野にも山にもまとふへらなれ」とある。
【ほだしなるべく】- 大島本、朱合点。『河海抄』は「世の憂きめ見えぬ山路へ入らむには思ふ人こそほだしなりけれ」(古今集雑下、九五五、物部吉名)を指摘。
|
| 1.1.4 |
「なほ、世に立ちまふべくもおぼえぬもの思ひの、一方ならず身に添ひにたるは、我より他に誰かはつらき、心づからもてそこなひつるにこそあめれ」 |
「やはり、世の中には生きていけそうにも思われない悩みが、並々ならず身に付き纏っているのは、自分より外に誰を恨めようか、自分の料簡違いから破滅を招いたのだろう」
|
生きがたいほどの物思いを同時に二つまで重ねてする身になったことは、
|
【一方ならず】- 『大系』は「一方だけでなく(女三宮への恋と、源氏に知られたこととが)」。『全集』は「並み一とおりでなく」と訳す。
【誰かはつらき】- 反語表現。『大系』は「誰がまあ、苦しいのか(皆、自分の罪である)」。『全集』は「自分自身よりほかに誰を恨むことができようか」と訳す。
|
| 1.1.5 |
と思ふに、恨むべき人もなし。
|
と思うと、恨むべき相手もいない。
|
だれを恨むべくもない自己のあやまちである、
|
|
| 1.1.6 |
|
「神、仏にも不平の訴えようがないのは、これは皆前世からの因縁なのであろう。
誰も千年を生きる松ではない一生は、結局いつまでも生きていられるものではないから、このように、あの人からも、少しは思い出してもらえるようなところで、かりそめの憐れみなりともかけて下さる方があろうということを、一筋の思いに燃え尽きたしるしとはしよう。
|
神も仏も冥助を垂れたまわぬ境界に堕ちたのは、皆前生での悲しい約束事であろう、だれも永久の命を持たない人間なのであるから、少しは惜しまれるうちに死んで、簡単な同情にもせよ、恋しい方に憐れだと思われることを自分の恋の最後に報いられたことと見よう、
|
【神、仏をもかこたむ方なきは】- 『全書』は「神仏にも不平の言ひやうがないのは」。『評釈』は「神仏のせいだともできないのは」と訳す。
【誰も千年の松ならぬ世は】- 尊経閣文庫本、付箋「うくも世の思心にかなはぬかたれもちとせの松ならなくに」(古今六帖四、二〇九六)。明融臨模本は、朱合点、付箋「うくも世の思心にかなはぬかたれもちとせの松ならなくに」で同文。しかし大島本は、朱合点、行間書入「うくも世に心に物のかなはぬそたれも小野」とあり、引歌の文句が異なる。中山家本、朱合点、奥入「うくも世のおもふ心にかなはぬかたれもちとせのまつならなくに」と指摘。
【かく、人にも、すこしうちしのばれぬべきほどにて】- 『全書』は「女三宮に少しは思い出して貰へさうな内に死んで」。『評釈』は「このように誰かに少しは死後思い出してもらえる間に」と訳す。
【一つ思ひに燃えぬるしるし】- 尊経閣文庫本、付箋「夏虫の身をいたつらになすこともひとつおもひによりてなりけり」(古今集恋一、五四四、読人しらず)。明融臨模本、朱合点、付箋「夏むしの身をいたつらになす事も一思ひによりてなりけり」。大島本、朱合点、行間書入、「なつむしの身をいたつらになす事もひとつ」。中山家本、朱合点、奥入「なつむしのみをいたつらになす事もひとつ思ひによりてなりけり」とある。
|
| 1.1.7 |
せめてながらへば、おのづからあるまじき名をも立ち、我も人も、やすからぬ乱れ出で来るやうもあらむよりは、なめしと、心置いたまふらむあたりにも、さりとも思し許いてむかし。
よろづのこと、今はのとぢめには、皆消えぬべきわざなり。
また、異ざまの過ちしなければ、年ごろものの折ふしごとには、まつはしならひたまひにし方のあはれも出で来なむ」
|
無理に生き永られていれば、自然ととんでもない噂もたち、自分にも相手にも、容易ならぬ面倒なことが出て来るようになるよりは、不届き者よと、ご不快に思われた方にも、いくら何でもお許しになろう。
何もかものこと、臨終の折には、一切帳消しになるものである。
また、これ以外の過失はほんとないので、長年何かの催しの機会には、いつも親しくお召し下さったことからの憐れみも生じて来よう」
|
しいて生きていて自己の悪名も立ち、なお自分をもあの方をも苦しめるような道を進んで行くよりは、無礼であるとお憎しみになる院も、死ねばすべてをお許しになるであろうから、やはり死が願わしい、そのほかの点で過去に院の御感情を害したことはなく、長く恩顧を得ていた以前の御愛情が死によって蘇ってくることもあるであろう
|
|
| 1.1.8 |
|
などと、所在なく思い続けるが、いくら考えてみても、実にどうしようもない。
|
とこんなふうに思われることが多い哀れな衛門督であった。
|
【うち返し、いとあぢきなし】- 語り手の評言。
|
|
第二段 柏木、女三の宮へ手紙
|
| 1.2.1 |
「などかく、ほどもなくしなしつる身ならむ」と、かきくらし思ひ乱れて、枕も浮きぬばかり、人やりならず流し添へつつ、いささか隙ありとて、人びと立ち去りたまへるほどに、かしこに御文たてまつれたまふ。 |
「どうしてこのように、生きる瀬もなくしてしまった身の上なのだろう」と、心がまっくらになる思いがして、枕も浮いてしまうほどに、誰のせいでもなく涙を流しては、少しは具合が好いとあって、ご両親たちがお側を離れなさっていた時に、あちらにお手紙を差し上げなさる。
|
なぜこう短時日の間に自分をめちゃめちゃにしてしまったのであろうと煩悶して、苦しい涙を流しているのであるが、病苦が少し楽になったようであると、家族たちが病室を出て行った間に衛門督は女三の宮へ送る手紙を書いた。
|
【などかく、ほどもなく】- 『湖月抄』は「世の不義をなす人はじめよりやがてあらはれむと思ひてはせざれども終にあらはれて悔るにもかひなくいたづらに身をころし名をくたす事なべて柏木にことなる事なし是をしるしていましめとするなるべし」注す。
【枕も浮きぬばかり】- 明融臨模本、付箋「泪川枕なかるゝうきねには夢もさたかに見えすそ有ける」(古今集恋一、五二七、読人しらず)。大島本、行間書入「古今 涙川枕なかるゝうきねには」と指摘する。『源注余滴』は「独り寝の床にたまれる涙には石の枕も浮きぬべらなり」(古今六帖五、枕)を指摘する。
|
| 1.2.2 |
「今は限りになりにてはべるありさまは、おのづから聞こしめすやうもはべらむを、いかがなりぬるとだに、御耳とどめさせたまはぬも、ことわりなれど、いと憂くもはべるかな」 |
「今はもう最期となってしまいました様子は、自然とお耳に入っていらっしゃいましょうが、せめていかがですかとだけでも、お耳に止めて下さらないのも、無理もないことですが、とても情けなく存じられますよ」
|
もう私の命の旦夕に迫っておりますことはどこからとなくお耳にはいっているでしょうが、どんなふうかともお尋ねくださいませんことはもっともなことですが、私としては悲しゅうございます。
|
【今は限りになりにて】- 以下「いと憂くもはべるかな」まで、柏木の女三の宮への手紙文。死の間近に迫っていることを言い、最期の憐愍の情をかけてくれるよう訴える。
|
| 1.2.3 |
など聞こゆるに、いみじうわななけば、思ふことも皆書きさして、
|
などと申し上げるにつけても、ひどく手が震えるので、思っていることも皆書き残して、
|
こんなことを書くのにも衛門督は手が慄えてならぬために、書きたいことも書きさして先を急いだ。
|
|
| 1.2.4 |
|
「もうこれが最期と燃えるわたしの荼毘の煙もくすぶって
空に上らずあなたへの諦め切れない思いがなおもこの世に残ることでしょう
|
今はとて燃えん煙も結ぼほれ
絶えぬ思ひのなほや残らん
|
【今はとて燃えむ煙もむすぼほれ--絶えぬ思ひのなほや残らむ】- 柏木から女三の宮への贈歌。女三の宮への愛執とこの世への執着をうたう。「思ひ」は「火」との掛詞。「煙」「火」は縁語。前の柏木の心中「一つ思ひに燃えぬるしるし」と呼応する表現。 【燃えむ煙】-明融臨模本、朱合点、付箋「この世をは後をもいかにいかにせむもえむ煙のむすほゝれつゝ」(出典未詳)。『河海抄』がこの歌を引く(ただし、第一句「この世をも」)。『異本紫明抄』は「むすぼほれ燃えむ煙をいかがせむ君だにこめよ長き契りを」(出典未詳)を指摘するが、『紹巴抄』が「引歌不及歟」と否定し、現行の注釈書でも指摘されない。
|
| 1.2.5 |
|
せめて不憫なとだけでもおっしゃって下さい。
気持ちを静めて、自分から求めての無明の闇を迷い行く道の光と致しましょう」
|
哀れであるとだけでも言ってください。それに満足します心を、暗い闇の世界へはいります道の光明にもいたしましょう。
|
【あはれとだにのたまはせよ】- 以下「道の光にもしはべらむ」まで、柏木の手紙文の続き。
【人やりならぬ】- 明融臨模本、朱合点。大島本、合点、行間書入「古今 人やりの道ならなくに大方」。『異本紫明抄』は「人やりならぬ道ならなくに大方はいきうしと言ひていざ帰りなむ」(古今集離別、三八八、源さね)を指摘するが、現行の注釈書では指摘されない。
|
| 1.2.6 |
と聞こえたまふ。
|
と申し上げなさる。
|
と結んだのであった。
|
|
| 1.2.7 |
|
侍従にも、性懲りもなく、つらい思いの数々を書いてお寄こしになった。
|
小侍従にもなお懲りずに督は恋の苦痛を訴えて来た。
|
【こりずまに】- 大島本、朱合点、行間書入「こりすまに又も」。『異本紫明抄』は「こりずまに又もなき名は立ちぬべし人にくからぬ世にし住まへば」(古今集恋三、六三一、読人しらず)を指摘するが、現行の注釈書では指摘されない。「こりずまに」は歌語。
【あはれなる】- 『集成』は「悲しい思いのたけの数々を」。『完訳』は「胸にしみるようなせつない言葉の数々を」と訳す。
|
| 1.2.8 |
|
「直接お会いして、もう一度申し上げたい事がある」
|
直接もう一度あなたに逢って言いたいことがある。
|
【みづからも、今一度言ふべきことなむ】- 柏木から小侍従への手紙の要旨である。
|
| 1.2.9 |
とのたまへれば、この人も、童より、さるたよりに参り通ひつつ、見たてまつり馴れたる人なれば、おほけなき心こそうたておぼえたまひつれ、今はと聞くは、いと悲しうて、泣く泣く、 |
とおっしゃるので、この人も、子供の時から、あるご縁で行き来して、親しく存じ上げている人なので、大それた恋心は疎ましく思われなさるが、最期と聞くと、とても悲しくて、泣き泣き、
|
とも書いてあった。小侍従も童女時代から伯母の縁故で親しい交情があったから、だいそれた恋をする点では、迷惑な主人筋の変わり者であると面倒には思っていたものの、生きる望みのなくなっている様子を知っては悲しくて、泣きながら、
|
【さるたよりに】- 小侍従の母は女三の宮の乳母だが、その姉が柏木の乳母でもある。「若菜下」巻に語られていた。
【心こそうたておぼえたまひつれ】- 『集成』は「「おぼえたまふ」は、思われなさる。「たまふ」は柏木に対する敬語」。『完訳』は「柏木が小侍従に思われなさる」と注す。客体敬語。
|
| 1.2.10 |
|
「やはり、このお返事。
本当にこれが最後でございましょう」
|
「このお返事だけはどうかなすってくださいまし。これが最後のことでございましょうから」
|
【なほ、この御返り】- 以下「こそはべれ」まで、小侍従の女三の宮への詞。柏木の手紙に対する返事を促す。
|
| 1.2.11 |
と聞こゆれば、
|
と申し上げると、
|
と宮へ申し上げた。
|
|
| 1.2.12 |
|
「わたしも、今日か明日かの心地がして、何となく心細いので、人の死は悲しいものと思いますが、まことに嫌な事であったと懲り懲りしてしまったので、とてもその気になれません」
|
「私だってもういつ死ぬかわからないほど命に自信がなくなっているのだから、そうした気の毒な容体でいる人としてだけに同情もされるけれど、私はもう苦しめられることに懲りているのだから、返事などをしてかかりあいになるのは非常にいやに思われる」
|
【われも、今日か明日かの心地して】- 以下「いみじうなむつつましき」まで、女三の宮の詞。返事のできないことをいう。 【今日か明日かの心地】-尊経閣文庫本、付箋「人の世をおいをはてにしせましかはけふかあすかもいそかさらまし」(朝忠集)。明融臨模本、付箋「人の世をおいを限(はて)にしせましかはけふかあすかもいそかさらまし」。『源氏釈』が「人のよのをいをはてにしせましかはけふかあすかもいそかさらまし」(前田家本)と指摘。しかし現行の注釈書では指摘されない。
【おほかたのあはればかりは思ひ知らるれど】- 『完訳』は「死に直面した人一般への憐愍」と注す。
|
| 1.2.13 |
とて、さらに書いたまはず。
|
とおっしゃって、どうしてもお書きにならない。
|
こうお言いになって、宮は書こうとあそばさない。
|
|
| 1.2.14 |
|
ご性質が、しっかりしていて重々しいというのではないが、気の置ける方のご機嫌が時々良くないのが、とても恐く辛く思われるのであろう。
けれども、御硯などを用意して是非にとお促し申し上げるので、しぶしぶとお書きになる。
受け取って、こっそりと宵闇に紛れて、あちらに持って上がった。
|
自重心がおありになるのではなくて、これは院のお心に御自身のあそばされた過失の影がおりおりさして、悩ましい御様子をお見せになることもあるのを、恐ろしく苦しいことと深く思っておいでになるからである。小侍従はそれでも硯などを持って来て責めたてるので、しぶしぶお書きになった宮のお手紙を持って、宵闇に紛れてそっと小侍従は衛門督の所へ行った。
|
【御心本性の、強くづしやかなるにはあらねど、恥づかしげなる人の御けしきの、折々にまほならぬが、いと恐ろしうわびしきなるべし】- 『細流抄』は「草子地也」と指摘。『集成』は「以下、女三の宮の心中を忖度する草子地の体」。『完訳』は「語り手の評言。宮が返書を書くまいとするのは、「恥づかしげなる人」源氏への恐れゆえであり、思慮深さからではないとする」と注す。 【恥づかしげなる人の御けしきの】-源氏をさす。 【まほならぬが】-『完訳』は「密通事件をほのめかす言動」と注す。
|
|
第三段 柏木、侍従を招いて語る
|
| 1.3.1 |
大臣、かしこき行なひ人、葛城山より請じ出でたる、待ち受けたまひて、加持参らせむとしたまふ。御修法、読経なども、いとおどろおどろしう騷ぎたり。人の申すままに、さまざま聖だつ験者などの、をさをさ世にも聞こえず、深き山に籠もりたるなどをも、弟の君たちを遣はしつつ、尋ね召すに、けにくく心づきなき山伏どもなども、いと多く参る。患ひたまふさまの、そこはかとなくものを心細く思ひて、音をのみ、時々泣きたまふ。 |
大臣は、優れた行者で、葛城山から招き迎えたのを、お待ち受けになって、加持をして上げようとなさる。
御修法、読経なども、まことに大声で行なっていた。
誰彼のお勧め申すがままに、いろいろと聖めいた験者などで、ほとんど世間では知られず、深い山中に籠もっている者などをも、弟の公達をお遣わしお遣わしになって、探し出して召し出しになるので、無愛想で気にくわない山伏連中なども、たいそう大勢参上する。
お病みになっているご様子が、ただ何となく物心細く思って、声を上げて時々お泣きになる。
|
大臣は大和の葛城山から呼んだ上手な評判のある修験者にこの晩は督の加持をさせようとしていた。祈祷や読経の声も騒がしく病室へはいって来た。人が勧めるままに、世の中へ出ることをしない高僧などで、世間からもまたあまり知られていないような人も、遠い土地へ息子たちを派遣などして呼び迎えて衛門督の病気に効験の現われることを期している大臣であるから、見て感じの悪いような野卑な僧などがあとへあとへとこのごろはたくさん来るのである。病人は何という名の病患でもなくて、ただ心細いふうに時々泣き入っていたりするのを、
|
【大臣】- 定家筆本と大島本は「おとゝ」とある。明融臨模本は「おとゝ(ゝ+は)」と、「は」を補入する。『集成』『新大系』は底本(定家筆本・大島本)のままとする。『完本』は明融臨模本の補訂と諸本に従って「大臣は」と校訂する。
|
| 1.3.2 |
陰陽師なども、多くは女の霊とのみ占ひ申しければ、さることもやと思せど、さらにもののけの現はれ出で来るもなきに、思ほしわづらひて、かかる隈々をも尋ねたまふなりけり。 |
陰陽師なども、多くは女の霊だとばかり占い申したので、そういう事かも知れないとお考えになるが、まったく物の怪が現れ出て来るものがないので、お困り果てになって、こうした辺鄙な山々にまでお探しになったのであった。
|
陰陽師なども多くは女の霊が憑いていると占っているので、そうかもしれぬと大臣は思い、他へ憑きものを移そうとしてもなんら物怪の手がかりが得られないのに困り、こうして遠国の修験者などを呼び集めることもするのであった。
|
【さることもやと思せど】- 主語は大臣。
|
| 1.3.3 |
この聖も、丈高やかに、まぶしつべたましくて、荒らかにおどろおどろしく陀羅尼読むを、 |
この聖も、背丈が高く、眼光が鋭くて、荒々しい大声で陀羅尼を読むのを、
|
今度山から来た僧も大男で、恐ろしい目つきをして荒々しく陀羅尼を読んでいるのを、衛門督は、
|
【まぶしつべたましくて】- 明融臨模本「つへたましくて」に傍書「ツヘツヘシキナト云心」とあり、大島本にも「つへつへしきなといふ心なり」という傍書がある。『集成』は「まなざしも冷酷な光を放って」。『完訳』は「まなざしがけわしくて」と訳す。
|
| 1.3.4 |
|
「ええ、嫌なことだ。
罪障の深い身だからであろうか、陀羅尼の大声が聞こえて来るのは、まことに恐ろしくて、ますます死んでしまいそうな気がする」
|
「ああいやになる。私は罪が深いせいなのか、陀羅尼を大声で読まれると恐ろしくて、ますますそれで死ぬ気がする」
|
【いで、あな憎や】- 以下「こそおぼゆれ」まで、柏木の独語。
【いよいよ死ぬべくこそ】- 大島本に「時平卿御子あつたゝの中納言事」という傍書がある。敦忠は誤りで保忠が正しい。『大鏡』時平伝に見え、大島本の傍書や『花鳥余情』の説は誤り。
|
| 1.3.5 |
とて、やをらすべり出でて、この侍従と語らひたまふ。
|
と言って、そっと病床を抜け出して、この侍従とお話し合いになる。
|
と言いながら病床を出て、小侍従のいる所へ来た。
|
|
| 1.3.6 |
大臣は、さも知りたまはず、うち休みたると、人びとして申させたまへば、さ思して、忍びやかにこの聖と物語したまふ。おとなびたまへれど、なほはなやぎたるところつきて、もの笑ひしたまふ大臣の、かかる者どもと向ひゐて、この患ひそめたまひしありさま、何ともなくうちたゆみつつ、重りたまへること、 |
大臣は、そうともご存知でなく、お休みになっていると、女房たちに申し上げさせなさったので、そうお思いになって、小声でこの聖とお話なさっている。
お年は召していらっしゃるが、相変わらず陽気なところがおありで、よくお笑いになる大臣が、このような山伏どもと対座して、この病気におなりになった当初からの様子、どうということもなくはっきりしないままに、重くおなりになったこと、
|
大臣はそんなことを知らず、病人は寝入っていると女房たちに言わせてあったのでそう信じて、ひそかにこの山の僧と語っていた。大臣は年がいってもなおはなやかな派手な人で、よく笑う性質なのであるが、こうした侮蔑するに価する山の修験僧と向き合って、衛門督の病気の当初から、その後なんということなしに重くばかりなってゆくことなどをこまごまと語っていた。
|
【人びとして申させたまへば】- 柏木が女房たちをして父大臣に。
【おとなびたまへれど】- 大臣の性格。お年は召していらっしゃるが。
|
| 1.3.7 |
|
「本当に、この物の怪の正体が、現れるよう祈祷して下さい」
|
「どうかあなたの力で物怪が正体を現わして来るようにやってほしいものです」
|
【まことに、このもののけ、現はるべう念じたまへ】- 大臣の山伏への詞。柏木平癒の懇願。
|
| 1.3.8 |
|
などと、心からお頼みなさるのも、まことにいたいたしい。
|
とも信頼したふうで言っているのも哀れであった。
|
【いとあはれなり】- 語り手の評言。『万水一露』は「草子の地也」と指摘。『完訳』は「大臣がわが子の延命のため身分いやしい行者に対面する場面を、語り手の勘当をもって結び、次に柏木と小侍従の対面場面へと転じる」と注す。
|
| 1.3.9 |
|
「あれをお聞きなさい。
何の罪咎ともご存じならないのに、占い当てたという女の霊、本当にそのようなあの方のご執念がわたしの身に取りついているならば、愛想の尽きたこの身もうって変わって、大切なものとなるだろう。
|
「小侍従、聞いてごらん。何の罪で私がこうなっているかをご存じないものだから、女の霊が憑いているなどとごまかされておいでになるが、あの方以外に女として惹くもののない私の心へ、あの方の霊が真実憑いていてくれるのなら、いやでならない自分の身もありがたくなるだろうよ。
|
【かれ聞きたまへ】- 以下「結びとどめたまへよ」まで、柏木の小侍従に対しての詞。しかし、途中やや心中文的また独語的性格をおびた発言。
【御執の身に添ひたるならば】- 明融臨模本、付箋「諸佛既離我執」。『集成』は「本当に、そんな女三の宮のご執心がこの身に取り憑いているのなら」と注す。
|
| 1.3.10 |
|
それにしても身分不相応な望みを抱いて、とんでもない過ちをしでかして、相手のお方の浮名をも立て、身の破滅を顧みないといった例は、昔の世にもないではなかった、と考え直してみるが、どうしても様子が何となく恐ろしくて、かのお心に、このような過失をお知られ申したからには、この世に生き永らえることも、まことに顔向けができなく思われるのは、なるほど特別なご威光なのだろう。
|
それにしてもだいそれた恋をして、あるまじい過失を引き起こして、人のお名を穢し、自身を顧みないようになる人は自分だけではない、昔の人にもあった罪なのだとみずから慰めようとするがね、そんなことで私の心は救われないのだよ。相手があの方なのだから、自責の念に堪えられまいではないか。生きていることももうまぶしくてならなくなったというのは、昔から世の中の人が言うように、一種特別な光の添った方らしい。
|
【昔の世にもなくやはありける】- 明融臨模本、付箋「伊物かゝるほとにみかときこしめしつけて此男をはなかしつかはしてけれは此女のいとこの宮す所(五条后)女をはまかてさせてくらにこめてしほりけれはこもりてなくあまのかるもにすむ虫のー」と注す。
【いとまばゆくおぼゆるは】- 『集成』は「大それた分不相応のことと思われるのは」。『完訳』は「じつに目のくらむほど恥ずかしい気持になるのは」と訳す。
【げに異なる御光なるべし】- 『完訳』は「源氏の威光にいまさらのごとく恐懼。「光」は「まばゆく」と照応」と注す。
|
| 1.3.11 |
|
大きな過失でもないのに、目をお合わせした夕方から、そのまま気分がおかしくなって、抜け出した魂が、戻って来なくなってしまったのですが、あの院の中で彷徨っていたら、魂結びをして下さいよ」
|
大罪人でもないのに、お顔を見合わせた瞬間から私の心は混乱してしまって、脱け出した魂魄が六条院をさまよっているようなことに気がついた時には君、まじないをしてくれたまえ」
|
【深き過ちもなきに】- 『集成』は「ひどい間違いを犯したというわけでもないのに。相手は后妃というわけでもないのに、という思い」。『完訳』は「后を犯した大罪でもないのに、源氏への裏切りはそれ以上と思う」と注す。
【見合はせたてまつりし夕べのほど】- 六条院で行われた試楽の夕の宴席。
【かの院のうちにあくがれありかば】- 明融臨模本、付箋「思あまり出にし玉の有ならむよふかくみえは玉結せよ/恋侘てよるよるまとふわか玉は中々身にもかへらさりけり/玉はみつ主は誰ともしらね共結ひとむる下かひのつま」と指摘。最初の和歌は『伊勢物語』第百十段の和歌。『源氏釈』が「なけきあま(わひ)りいてにしたまのあるな覧よふかくみえはむすひとゝめよ」(前田家本)と指摘。現行の注釈書でも指摘する。第二首目の和歌は出典未詳。『異本紫明抄』が指摘し、現行の注釈書でも指摘する。最後の和歌も出典未詳。『異本紫明抄』が指摘し、現行の注釈書では、『大系』が指摘するのみである。
【結びとどめたまへ】- 大島本、朱合点、行間書入「伊 思あまりいてにし玉のあるならん夜ふかく見へは玉むすひせよ」(伊勢物語、一八九)と指摘。
|
| 1.3.12 |
など、いと弱げに、殻のやうなるさまして、泣きみ笑ひみ語らひたまふ。 |
などと、とても弱々しく、脱殻のような様子で、泣いたり笑ったりしてお話しになる。
|
などと、衰弱して殻のようになった姿で、泣きも笑いもして衛門督は語るのであった。
|
【殻のやうなる】- 明融臨模本、付箋「うつせみはからをみつゝも」。大島本、朱合点、行間書入「うつせみはからを見つゝもなくさめつ」。「うつ蝉は殻を見つつもなぐさめつ深草の山煙だに立て」(古今集哀傷、八三一、僧都勝延)を指摘。現行の注釈書では指摘されない。
|
|
第四段 女三の宮の返歌を見る
|
| 1.4.1 |
|
宮も何かと恥ずかしく顔向けできない思いでいられる様子を話す。
そのようにうち沈んで、痩せていらっしゃるだろうご様子が、目の前にありありと拝見できるような気がして、ご想像されるので、なるほど抜け出した霊魂は、あちらに行き通うのだろうかなどと、ますます気分もひどくなるので、
|
宮が非常にお恥じになっている御様子、物思いばかりをしておいでになるということも小侍従は告げた。自身が今冗談で言い出したことではあるが、その宮をおいたわしく、恋しく思う魂魄はそちらへ行くかもしれぬというような気も衛門督はしていっそう思い乱れた。
|
【ものをのみ恥づかしうつつましと思したるさま】- 『集成』は「何かにつけて空恐ろしく顔向けもできぬ思いでいられる様子を」。『完訳』は「ただ何かにつけて後ろめたく気がねしていらっしゃるご様子を」と訳す。
【げにあくがるらむ魂や、行き通ふらむ】- 柏木の心中。間接的叙述。『集成』は「もの思へば沢の螢もわが身よりあくがれ出づる魂かとぞ見る」(後拾遺集、神祇、和泉式部)を指摘。
|
| 1.4.2 |
|
「今となっては、もう宮の御事は、いっさい申し上げますまい。
この世はこうしてはかなく過ぎてしまったが、未来永劫の成仏する障りになるかもしれないと思うと、お気の毒だ。
気にかかるお産の事を、せめてご無事に済んだとお聞き申しておきたい。
見た夢を独り合点して、また他に語る相手もいないのが、たいそう堪らないことであるなあ」
|
「もう宮様のお話はいっさいすまい。不幸で短命な生涯に続いて、その執着が残るために未来をまた台なしにすると思うのがつらい。心苦しいあのことを無事にお済ましになったとだけはせめて聞いて死にたい気もするがね、私たちを繋ぎ合わせた目に見えぬものを私が夢で見た話なども申し上げることができないままになるのが苦痛だよ」
|
【今さらに】- 以下「いぶせくもあるかな」まで、柏木の独語。小侍従に向かっての発言ではないだろう。
【長き世のほだしにもこそ】- 明融臨模本、付箋「一念五百生ー」とある。連語「もこそ」は危惧の気持ちを表す。『集成』は「これから先来世をかけていつまでも成仏の障りになるであろうと思うと、つらいことだ」。『完訳』は「この思いが未来永劫成仏の妨げになるかもしれないと思うと、まったくせつないのです」と訳す。
【いとほしき】- 定家筆本と明融臨模本は「いとおしき」とある。大島本は「いといとおしき」とある。『集成』と『新大系』はそれぞれ底本(定家筆本・大島本)のままとする。『完本』は大島本及び諸本に従って「いといとほしき」と「いと」を補訂する。
【心苦しき御ことを】- お産のこと。
【平らかにとだにいかで】- 副助詞「だに」最小限の願望。副詞「いかで」願望の意。柏木の女三の宮のお産の報を聞いてから死にたいという切なる願い。
【見し夢を】- 猫の夢。懐妊の予兆という俗信がある。
【また語る人もなきが、いみじういぶせくもあるかな】- 『集成』は「女三の宮が自分の胤を宿していることを、誰にも知らせることができないのをいう」「ほかに打ち明ける人もいないのが、何とも心残りでならないことだ」。『完訳』は「ほかの誰にも打ち明ける人のいないのが、ひどく胸のふさがる思いなのです」と訳す。『完訳』などのように小侍従を前にした発言とするよりも、小侍従の存在は無視して独語または心中文のほうが面白みがある。
|
| 1.4.3 |
など、取り集め思ひしみたまへるさまの深きを、かつはいとうたて恐ろしう思へど、あはれはた、え忍ばず、この人もいみじう泣く。
|
などと、あれこれと思い詰めていらっしゃる執着の深いことを、一方では嫌で恐ろしく思うが、おいたわしい気持ちは、抑え難く、この人もひどく泣く。
|
と言って深く督の悲しむ様子を見ていては、小侍従も堪えきれずなって泣きだすと、その人もまた泣く。
|
|
|
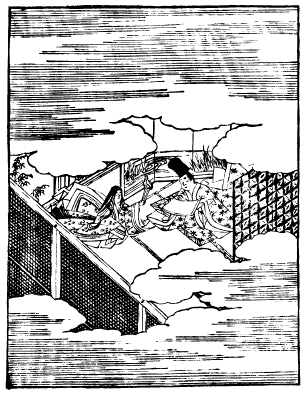 |
| 1.4.4 |
紙燭召して、御返り見たまへば、御手もなほいとはかなげに、をかしきほどに書いたまひて、
|
紙燭を取り寄せて、お返事を御覧になると、ご筆跡もたいそう弱々しいが、きれいにお書きになって、
|
蝋燭をともさせてお返事を読むのであったが、それは今も弱々しいはかない筆の跡で、美しくは書かれてあった。
|
|
| 1.4.5 |
|
「お気の毒に聞いていますが、どうしてお伺いできましょう。
ただお察しするばかりです。
お歌に『残ろう』とありますが、
|
御病気を心苦しく聞いていながらも、私からお尋ねなどのできないことは推察ができるでしょう。「残るだろう」とお言いになりますが、
|
【心苦しう聞きながら】- 以下「後るべうやはある」まで、女三の宮の手紙文。
【残らむ』とあるは】- 柏木の和歌(第一章二段)をさす。
|
| 1.4.6 |
|
わたしも一緒に煙となって消えてしまいたいほどです
辛いことを思い嘆く悩みの競いに
|
立ち添ひて消えやしなましうきことを
思ひ乱るる煙くらべに
|
【立ち添ひて消えやしなまし憂きことを--思ひ乱るる煙比べに】- 明融臨模本、付箋「柏木 今はとてもえむ煙もむすほゝれたへぬ思ひの猶や残らん」という、作中の柏木の歌を貼付する。『完訳』は「「煙比べ」には、柏木の理不尽な恋への抗議も含まれるか」と注す。
|
| 1.4.7 |
|
後れをとれましょうか」
|
私はもう長く生きてはいないでしょう。
|
【後るべうやは】- 「やは」反語。後れをとれようか、いや後れはとらぬ、の意。
|
| 1.4.8 |
とばかりあるを、あはれにかたじけなしと思ふ。
|
とだけあるのを、しみじみともったいないと思う。
|
内容はこんなのであった。衛門督は宮のお手紙を非常にありがたく思った。
|
|
| 1.4.9 |
|
「いやもう、この煙だけが、この世の思い出であろう。
はかないことであったな」
|
「このお言葉だけがこの世にいるうちのもっともうれしいことになるだろう。はかない私だね」
|
【いでや、この煙ばかりこそ】- 以下「ありけるかな」まで、柏木の心中。
|
| 1.4.10 |
と、いとど泣きまさりたまひて、御返り、臥しながら、うち休みつつ書いたまふ。
言の葉の続きもなう、あやしき鳥の跡のやうにて、
|
と、ますますお泣きになって、お返事、横に臥せりながら、筆を置き置きしてお書きになる。
文句の続きもおぼつかなく、筆跡も妙な鳥の脚跡のようになって、
|
いっそう強く督は泣き入って、またこちらからのお返事を、横になりながら休み休み書いた。鳥の足跡のような字ができる。
|
|
| 1.4.11 |
|
「行く方もない空の煙となったとしても
思うお方のあたりは離れまいと思う
|
「行くへなき空の煙となりぬとも
思ふあたりを立ちは離れじ
|
【行方なき空の煙となりぬとも--思ふあたりを立ちは離れじ】- 柏木の女三の宮への贈歌。「煙」と「立ち」は縁語。
|
| 1.4.12 |
|
夕方は特にお眺め下さい。
咎め立て申されるお方の目も、今はもうお気になさらずに、せめて何にもならないことですが、憐みだけは絶えず懸けて下さいませ」
|
とりわけ夕方には空をおながめください。人目をおはばかりになりますことも、対象が実在のものでなくなるのですからいいわけでしょう。そうしてせめて永久に私をお忘れにならぬようにしてください」
|
【咎めきこえさせたまはむ人目】- 源氏をさす。
【今は心やすく思しなりて、かひなきあはれをだにも、絶えずかけさせたまへ】- 「あはれ」について、『集成』は「今はもうお気になさらず、死んでしまっては詮ないことですが、かわいそうな者よとだけでもいつまでもお心をおかけ下さい」。『完訳』は「私の亡き後はご心配にならないで、いまさらかいのないことですが、せめてもの憐れみだけはおかけくださいまし」と訳す。
|
| 1.4.13 |
など書き乱りて、心地の苦しさまさりければ、
|
などと乱れ書きして、気分の悪さがつのって来たので、
|
などと乱れ書きにした。病苦に堪えられなくなって、
|
|
| 1.4.14 |
|
「もうよい。
あまり夜が更けないうちに、お帰りになって、このように最期の様子であったと申し上げて下さい。
今となって、人が変だと感づくのを、自分の死んだ後まで想像するのは情けないことだ。
どのような前世からの因縁で、このような事が心に取り憑いたのだろうか」
|
「ではもういいから、あまりふけないうちに帰って行って、宮様に、こんなふうに死が迫っているということを申し上げてください。どうした前生の因縁からこんなに道にはずれた思いが心に染みついた私だろう」
|
【よし。いたう更けぬさきに】- 以下「心にしみけむ」まで、柏木の詞。
【今さらに、人あやしと】- 『集成』は「女三の宮への恋ゆえに死んだのだと、疑惑を招くかもしれないが、の意」と注す。
【口惜しけれ】- 定家筆本と大島本は「くちおしけれ」とある。明融臨模本は「くちおしけれ(=苦シイケレ)」と
【いかなる昔の契りにて】- 明融臨模本、付箋「別てふことは色にもあらなくに心にしみてわひしかるらむ」(古今集離別、三八一、貫之)。
|
| 1.4.15 |
|
と、泣き泣きいざってお入りになったので、いつもはいつまでも前に座らせて、とりとめもない話までをおさせになりたくなさっていたのに、お言葉の数も少ない、と思うと悲しくてならないので、帰ることも出来ない。
ご様子を乳母も話して、ひどく泣きうろたえる。
大臣などがご心配された有様は大変なことであるよ。
|
泣く泣く病床へ衛門督は膝行り入るのであった。平生はいつまでもいつまでも小侍従を前に置いて、宮のお噂を一つでも多く話させたいようにする人であるのに、今日は言葉も少ないではないかと思うのも物哀れで、小侍従は出て行けない気がした。容体を伯母の乳母も話して大泣きに泣いていた。大臣などの心痛は非常なもので、
|
【ゐざり入りたまひぬれば】- 床の中へ。
【例は無期に】- 以下「言少なにも」まで、小侍従の心中に即した叙述。
【御ありさまを乳母も】- 柏木の容態について、柏木の乳母が姪に当たる小侍従に話してきかせる。
【大臣などの思したるけしきぞいみじきや】- 語り手の評言。
|
| 1.4.16 |
|
「昨日今日と、少し好かったのだが、どうしてたいそう弱々しくお見えなのだろう」
|
「昨日今日少しよかったようだったのに、どうしてこんなにまた弱ったのだろう」
|
【昨日今日】- 以下「見えたまふ」まで、大臣の詞。
|
| 1.4.17 |
と騷ぎたまふ。
|
とお騷ぎになる。
|
と騒いでいた。
|
|
| 1.4.18 |
|
「いいえもう、生きていられそうにないようです」
|
「そんなに御心配をなさることはありません。どうせもう私は死ぬのですから」
|
【何か、なほとまりはべるまじきなめり】- 柏木の詞。
|
| 1.4.19 |
と聞こえたまひて、みづからも泣いたまふ。
|
と申し上げなさって、ご自身もお泣きになる。
|
と衛門督は父に言って、自身もまた泣いていた。
|
|
|
第五段 女三の宮、男子を出産
|
| 1.5.1 |
宮は、この暮れつ方より悩ましうしたまひけるを、その御けしきと、見たてまつり知りたる人びと、騷ぎみちて、大殿にも聞こえたりければ、驚きて渡りたまへり。御心のうちは、 |
宮は、この日の夕方から苦しそうになさったが、産気づかれた様子だと、お気づき申した女房たち、一同に騷ぎ立って、大殿にも申し上げたので、驚いてお越しになった。
ご心中では、
|
女三の宮はこの日の夕方ごろから御異常の兆が見え出して悩んでおいでになるので、経験のある人たちがそれと気づき、騒ぎ出して院へ御報告をしたので、院は驚いてこちらの御殿へおいでになった。お心のうちでは
|
【驚きて渡りたまへり】- 主語は源氏。紫の上のいる東の対から女三の宮いる寝殿の西面へ。
|
| 1.5.2 |
|
「ああ、残念なことよ。
疑わしい点もなくてお世話申すのであったら、おめでたく喜ばしい事であろうに」
|
なんら不純なことがなくて、こうしたことにあうのであったら、珍しくてうれしいであろう
|
【あな、口惜しや】- 以下「うれしからまし」まで、源氏の心中。反実仮想の構文。『集成』は「柏木の子という疑いがなければ、正室の腹でもあり、子供の少ない源氏にとって晩年の慶事であるはず」と注す。
|
| 1.5.3 |
と思せど、人にはけしき漏らさじと思せば、験者など召し、御修法はいつとなく不断にせらるれば、僧どもの中に験ある限り皆参りて、加持参り騒ぐ。
|
とお思いになるが、他人には気づかれまいとお考えになるので、験者などを召し、御修法はいつとなく休みなく続けてしていられるので、僧侶たちの中で効験あらたかな僧は皆参上して、加持を大騷ぎして差し上げる。
|
と思召されるのであったが、人にはそれを気どらすまいと思召すので、修験の僧などを急に迎えることを命じたりしておいでになった。修法のほうはずっと前から続いて行なわれているので、祈祷の効験をよく現わすものばかりを今度はお集めになって加持をさせておいでになった。
|
|
| 1.5.4 |
夜一夜悩み明かさせたまひて、日さし上がるほどに生まれたまひぬ。
男君と聞きたまふに、
|
一晩中お苦しみあそばして、日がさし昇るころにお生まれになった。
男君とお聞きになると、
|
一晩じゅうお苦しみになって日の昇るころにお産があった。男君であるということをお聞きになって、
|
|
| 1.5.5 |
「かく忍びたることの、あやにくに、いちじるき顔つきにてさし出でたまへらむこそ苦しかるべけれ。女こそ、何となく紛れ、あまたの人の見るものならねばやすけれ」 |
「このように内証事が、あいにくなことに、父親に大変よく似た顔つきでお生まれになることは困ったことだ。
女なら、何かと人目につかず、大勢の人が見ることはないので心配ないのだが」
|
また院は隠れた秘密を容貌の似た点などでだれの目にも映りやすい男であることが、苦しい、女はよく紛らすこともできるし、多くの人が顔を見るのでないからいいのであるがと
|
【かく忍びたることの】- 以下「やすけれ」まで、源氏の心中。男の子であると、人前に出ることが多い。女の子であると、深窓にあって顔を見られることもなくてすむ。
|
| 1.5.6 |
と思すに、また、
|
とお思いになるが、また一方では、
|
お思いになった。しかし素姓の紛らわしいことは男の身にあってもよいが、
|
|
| 1.5.7 |
「かく、心苦しき疑ひ混じりたるにては、心やすき方にものしたまふもいとよしかし。さても、あやしや。わが世とともに恐ろしと思ひしことの報いなめり。この世にて、かく思ひかけぬことにむかはりぬれば、後の世の罪も、すこし軽みなむや」 |
「このように、つらい疑いがつきまとっていては、世話のいらない男子でいらしたのも良かったことだ。
それにしても、
不思議なことだなあ。自分が一生涯恐ろしいと思ってい
た事の報いのようだ。この世で、このような思いもかけなかった応報を受けたのだから、来世での罪も、少しは
|
どんな高貴な方の母になるかもしれぬ女性は生まれが確かでなければならぬ点から言えば、これがかえってよいかもしれぬとまたお思い返しになった。忘れることもない自分の罪のこれが報いであろう、この世でこうした思いがけぬ罰にあっておけば、後世で受ける咎は少し軽くなるかもしれぬ
|
【かく、心苦しき】- 以下「すこし軽みなむや」まで、源氏の心中。「心苦しき」は源氏自身の胸の痛み、疑念。『集成』は「こんな胸の痛む疑惑のかかったお子であるからには」。『完訳』は「こうした気がかりな疑念がつきまとうのでは」と訳す。
【むかはりぬれば】- 明融臨模本、付箋「要集云有智之人以智恵力能令地獄極重之業現世軽受愚癡之人現世軽業獄重轉重軽受住也出弥鉢経」とある。『新大系』は「以前と同じことが起きる」と注す。
|
| 1.5.8 |
と思す。
|
とお思いになる。
|
などとお考えになった。
|
|
| 1.5.9 |
|
周囲の人は他に誰も知らない事なので、このように特別なお方のご出産で、晩年にお生まれになったご寵愛はきっと大変なものだろうと、思って大事にお世話申し上げる。
|
宮の秘密はだれ一人知らぬことであったから、尊貴な内親王を母にして最後にお設けになった若君を、院はどんなにお愛しになるだろうという想像をして、家司たちは大がかりな仕度を御出産祝いにした。
|
【かく心ことなる御腹にて】- 以下「いみじかりなむ」まで、一般の人々の心中を忖度して間接的に叙述。
|
| 1.5.10 |
御産屋の儀式、いかめしうおどろおどろし。御方々、さまざまにし出でたまふ御産養、世の常の折敷、衝重、高坏などの心ばへも、ことさらに心々に挑ましさ見えつつなむ。 |
御産屋の儀式は、盛大で仰々しい。
ご夫人方が、さまざまにお祝いなさる御産養、世間一般の折敷、衝重、高坏などの趣向も、特別に競い合っている様子が見えるのであった。
|
六条院の各夫人から産室への見舞い品、祝品はさまざまに意匠の凝らされたものであった。折敷、衝重、高杯などの作らせようにも皆それぞれの個性が見えた。
|
【いかめしうおどろおどろし】- 池田利夫氏は定家本「いかめしう」(尊経閣文庫本、一二丁ウ5行)までを定家自筆という。以下は定家風の書で別人である。
|
| 1.5.11 |
五日の夜、中宮の御方より、子持ちの御前の物、女房の中にも、品々に思ひ当てたる際々、公事にいかめしうせさせたまへり。御粥、屯食五十具、所々の饗、院の下部、庁の召次所、何かの隈まで、いかめしくせさせたまへり。宮司、大夫よりはじめて、院の殿上人、皆参れり。 |
五日の夜、中宮の御方から、御産婦のお召し上がり物、女房の中にも、身分相応の饗応の物を、公式のお祝いとして盛大に調えさせなさった。
御粥、屯食を五十具、あちらこちらの饗応は、六条院の下部、院庁の召次所の下々の者たちまで、堂々としたなさり方であった。
中宮の宮司、大夫をはじめとして、冷泉院の殿上人が、皆参上した。
|
五日の夜には中宮のお産養があった。母宮のお召し料をはじめとして、それぞれの階級の女房たちへ分配される物までも、お后のあそばすことらしく派手にそろえておつかわしになったのである。産婦の宮への御粥、五十組の弁当、参会した諸官吏への饗応の酒肴、六条院に奉仕する人々、院の庁の役人、その他にまでも差等のあるお料理を交付された。院の殿上人とともに中宮職の諸員は大夫をはじめ皆参っていた。
|
【子持ちの御前の】- 女三の宮をさす。
【御粥】- 定家筆本、明融臨模本、大島本は「御かゆて」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「御粥」と「て」を削除する。『新大系』は底本(大島本)のまま「御粥て」とし、「「て」が難解。「ごて(碁手)の脱字という見方がある。うつほ及び宿木に「碁手(の銭)」が見える」と脚注を付ける。
|
| 1.5.12 |
七夜は、内裏より、それも公ざまなり。
致仕の大臣など、心ことに仕うまつりたまふべきに、このころは、何ごとも思されで、おほぞうの御訪らひのみぞありける。
|
お七夜は、帝から、それも公事に行われた。
致仕の大臣などは、格別念を入れてご奉仕なさるはずのところだが、最近は、何を考えるお気持ちのゆとりもなく、一通りのお祝いだけがあった。
|
七日の夜には宮中からのお産養があった。これも朝廷のお催しで重々しく行なわれたのである。太政大臣などはこの祝賀に喜んで奔走するはずの人であったが、子息の大病のためにほかのことを思う間もないふうで、ただ普通に祝品を贈って来ただけであった。宮がたや高官の参賀も多かった。
|
|
| 1.5.13 |
|
親王方、上達部などが、大勢お祝いに参上する。
表向きのお祝いの様子にも、世にまたとないほど立派にお世話して差し上げなさるが、大殿のご心中に、辛くお思いになることがあって、そう大して賑やかなお祝いもしてお上げにならず、管弦のお遊びなどはなかったのであった。
|
院内にもこの若君を珍重する空気が濃厚に作られていながら、院のお心にだけは羞恥をお感じになるようなところがあって、宴席をはなやかにすることなどはお望みになれないで、音楽の遊びなどは何もなかった。
|
【おほかたのけしきも、世になきまでかしづききこえたまへど】- 『完訳』は「世間の噂を集めるような盛儀。それとは対蹠的な源氏の苦衷」と注す。
|
|
第六段 女三の宮、出家を決意
|
| 1.6.1 |
宮は、さばかりひはづなる御さまにて、いとむくつけう、ならはぬことの恐ろしう思されけるに、御湯などもきこしめさず、身の心憂きことを、かかるにつけても思し入れば、 |
宮は、あれほどか弱いご様子で、とても気味の悪い、初めてのご出産で、恐く思われなさったので、御薬湯などもお召し上がりにならず、わが身の辛い運命を、こうしたことにつけても心底お悲しみになって、
|
女三の宮は弱いお身体で恐ろしい大役の出産をあそばしたあとであったから、まだ米湯などさえお取りになることができなかった。御自身の薄命であることをこの際にもまた深くお思われになって、
|
【身の心憂きことを】- 『完訳』は「わが身の不運を、不義の子の出生によって思い知らされる」と注す。
|
| 1.6.2 |
|
「いっそのこと、
|
この衰弱の中で死んでしまいたいともお思いになるのであった。
|
【さはれ、このついでにも死なばや】- 女三の宮の心中を客観的に地の文で叙述。
|
| 1.6.3 |
と思す。大殿は、いとよう人目を飾り思せど、まだむつかしげにおはするなどを、取り分きても見たてまつりたまはずなどあれば、老いしらへる人などは、 |
とお思いになる。
大殿は、まことにうまく表面を飾って見せていらっしゃるが、まだ生まれたばかりの扱いにくい状態でいらっしゃるのを、特別にはお世話申されるというでもないので、年老いた女房などは、
|
院は人から不審を起こさせないことを期して、上手に表面は繕っておいでになるが、生まれたばかりの若君を特に見ようともなされないのを、老いた女房などは、
|
【老いしらへる人などは】- 『集成』は「年取って遠慮のない女房」と訳す。
|
| 1.6.4 |
「いでや、おろそかにもおはしますかな。めづらしうさし出でたまへる御ありさまの、かばかりゆゆしきまでにおはしますを」 |
「何とまあ、
お冷たくていらっしゃること。おめでたくお生まれになったお子様が、こんなにこわいほどお
|
「御愛情が薄いではありませんか。久しぶりにお持ちになった若様が、こんなにまできれいでいらっしゃるのに」
|
【いでや、おろそかにも】- 以下「おはしますめるものを」まで、女房の詞。
|
| 1.6.5 |
|
と、おいとしみ申し上げるので、小耳におはさみなさって、
|
などと言っているのを、宮は片耳におはさみになって、
|
【片耳に聞きたまひて】- 主語は女三の宮。
|
| 1.6.6 |
|
「そんなにもよそよそしいことは、これから先もっと増えて行くことになるのだろう」
|
この薄いと言われておいでになる愛情は、成長するにつれてますます薄くなるであろう
|
【さのみこそは、思し隔つることもまさらめ】- 女三の宮の心中。
|
| 1.6.7 |
と恨めしう、わが身つらくて、尼にもなりなばや、の御心尽きぬ。
|
と恨めしく、わが身も辛くて、尼にもなってしまいたい、というお気持ちになられた。
|
と、院がお恨めしく、過去の御自身も恨めしくて、尼になろうというお心が起こった。
|
|
| 1.6.8 |
夜なども、こなたには大殿籠もらず、昼つ方などぞさしのぞきたまふ。
|
夜なども、こちらにはお寝みにならず、昼間などにちょっとお顔をお見せになる。
|
夜などもこちらの御殿で院はお寝みにならずに、昼の間に時々お顔をお見せになるだけであった。
|
|
| 1.6.9 |
「世の中のはかなきを見るままに、行く末短う、もの心細くて、行なひがちになりにてはべれば、かかるほどのらうがはしき心地するにより、え参り来ぬを、いかが、御心地はさはやかに思しなりにたりや。心苦しうこそ」 |
「世の中の無常な有様を見ていると、この先も短く、何となく頼りなくて、勤行に励むことが多くなっておりますので、このようなご出産の後は騒がしい気がするので、参りませんが、いかがですか、ご気分はさわやかになりましたか。
おいたわしいことです」
|
「人生の無常をいろんな形で見ていて、もう自分は未来が短くなっているのだからと思うと心細くて、仏勤めばかりをする癖がついて、産屋の騒がしい空気と自分とはしっくり合わない気がされてたびたびは来ないのですが、気分はどうですか。少しさっぱりしたように思いますか。気の毒ですね」
|
【世の中のはかなきを】- 以下「心苦しうこそ」まで、源氏から女三の宮への詞。
|
| 1.6.10 |
とて、御几帳の側よりさしのぞきたまへり。
御頭もたげたまひて、
|
と言って、御几帳の側からお覗き込みになった。
御髪をお上げになって、
|
と、お言いになりながら院は几帳の上から宮をおのぞきになった。宮は頭を少しお上げになって、
|
|
| 1.6.11 |
|
「やはり、生きていられない気が致しますが、こうしたわたしは罪障も重いことです。
尼になって、もしやそのために生き残れるかどうか試してみて、また死んだとしても、罪障をなくすことができるかと存じます」
|
「まだ私には快くなる自信ができません。でね、こんな際に死んでは罪が深いと聞いておりますから、尼になりまして、その功徳であるいは生きることができるかどうかためしたくもありますし、また死にましても罪が軽くなるでしょうからと思われまして、そういたしたくなりました」
|
【なほ、え生きたるまじき心地なむしはべるを】- 以下「なむ思ひはべる」まで、女三の宮から源氏への詞。
【かかる人は罪も重かなり】- 「かかる人」について、『集成』は「こういう人は罪も重いと申します」。『完訳』は「こうしたことで死ぬ人は罪も重いと申しますから」と訳す。
【罪を失ふこともや】- 定家筆本、明融臨模本、大島本は「こともや」とある。『集成』『新大系』は底本のままとする。『完本』は諸本に従って「ことにもや」と「に」を補訂する。
|
| 1.6.12 |
と、常の御けはひよりは、いとおとなびて聞こえたまふを、
|
と、いつものご様子よりは、とても大人らしく申し上げなさるので、
|
平生にも似ずおとなびてお言いになった。
|
|
| 1.6.13 |
「いとうたて、ゆゆしき御ことなり。などてか、さまでは思す。かかることは、さのみこそ恐ろしかなれど、さてながらへぬわざならばこそあらめ」 |
「まことに嫌な、縁起でもないお言葉です。
どうして、そんなにまでお考えになるのですか。
このようなことは、そのように恐ろしい事でしょうが、それだからと言って命が永らえないというなら別ですが」
|
「とんでもないことですよ。なぜそうまで悲観するのですか、産をするとだれも皆そんなふうに恐ろしく不安になるものですが、子を産んだ人が皆死ぬものではありませんからね。気を静めるようになさい。そんなことは言わずに」
|
【いとうたて】- 以下「こそあらめ」まで、源氏の詞。女三の宮の出家の希望を諌める。
|
| 1.6.14 |
と聞こえたまふ。
御心のうちには、
|
とお申し上げなさる。
ご心中では、
|
と院はお言いになった。お心の中では
|
|
| 1.6.15 |
|
「本当にそのようにお考えになっておっしゃるのならば、出家をさせてお世話申し上げるのも、思いやりのあることだろう。
このように連れ添っていても、何かにつけて疎ましく思われなさるのがおいたわしいし、自分自身でも、気持ちも改められそうになく、辛い仕打ちが折々まじるだろうから、自然と冷淡な態度だと人目に立つこともあろうことが、まことに困ったことで、院などがお耳になさることも、すべて自分の至らなさからとなるであろう。
ご病気にかこつけて、そのようにして差し上げようかしら」
|
その希望が自発的に起こったのなら、そうさせてしまったほうが自分の心が楽になって、深く今後もこの人を愛することが可能かもしれぬ、今までと同じように取り扱っていても、同じにならぬものが自分の心にあってはおかわいそうである、自分ながらも以前の愛情がこのまままた帰って来ようとは思われない、自分はどんなに努めても暗い霧が心を横切ることは免れまい、自然宮への愛が薄くなったように他人が思うことも予想され、その時の宮のお立場も苦しかろうと思われる。法皇がお聞きになっても自分が悪いことにばかりなるであろう、病気に託してそうおさせしようか
|
【まことにさも】- 以下「なしたてまつりてまし」まで、源氏の心中。『完訳』は「源氏は、言葉でこそ出家を諌止しながら、心中これを容認」と注す。
【あはれなりなむかし】- 『集成』は「しみじみと心深いことであろう」。『完訳』は「それが思いやりということになるのだろう」と訳す。
【心置かれたまはむが心苦しう】- 「れ」受身の助動詞。女三の宮が源氏から疎ましく思われる意。
【憂きことうち混じりぬべきを】- 定家筆本と明融臨模本は「うきこと」とある。大島本は「うき(き+事<朱>)の」と「事」を朱筆で補入する。『集成』と『新大系』はそれぞれ底本(定家筆本・大島本)のまま「憂きこと」「うき事の」とする。『完本』は諸本に従って「うきことの」と「の」を補訂する。
|
| 1.6.16 |
など思し寄れど、また、いとあたらしう、あはれに、かばかり遠き御髪の生ひ先を、しかやつさむことも心苦しければ、 |
などとお考えになるが、また一方では、大変惜しくていたわしく、これほど若く生い先長いお髪を、尼姿に削ぎ捨てるのはお気の毒なので、
|
とお思われになるのであったが、またそれを実現させるのが惜しくも哀れにもお思われになり、若盛りの姿を尼に変えさせるのも残酷に思召されて、
|
【生ひ先】- 『集成』は「「生ひ先」は、人生の将来の意と、髪の延びて行く先の意を掛ける」と注す。
|
| 1.6.17 |
|
「やはり、気をしっかりお持ちなさい。
心配なさることはありますまい。
最期かと思われた人も、平癒した例が身近にあるので、やはり頼みになる世の中です」
|
「ぜひとも強く生きようとお努めなさい。この上そうまで悪くなるわけはありませんよ。もうだめかと思われていた人さえ癒ってきた例が近い所にあるのですから、それを思うとまだこの世は頼みになりますよ」
|
【なほ、強く思しなれ】- 以下「頼みある世になむ」まで、源氏の詞。女三の宮に気をしっかり持つように言う。
【けしうはおはせじ】- 『集成』は「大したことはないと思います」。『完訳』は「ご心配なことはございません」と訳す。
【限りと見ゆる人も】- 紫の上をさす。
【たひらなる】- 定家筆本と明融臨模本は「たひらなる」とある。大島本は「たいらかなる」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「たひらかなる」と「ら」を補訂する。『新大系』は底本(大島本)のままとする。
|
| 1.6.18 |
など聞こえたまひて、御湯参りたまふ。
いといたう青み痩せて、あさましうはかなげにてうち臥したまへる御さま、おほどき、うつくしげなれば、
|
などと申し上げなさって、御薬湯を差し上げなさる。
とてもひどく青く痩せて、何とも言いようもなく頼りなげな状態で臥せっていらっしゃるご様子、おっとりして、いじらしいので、
|
などとお言いになって、白湯を勧めたりして院はおいでになるのであった。宮のお顔色は非常に青くて力もないふうに寝ておいでになるが、たよりない美しさをなしているのを御覧になっては、
|
|
| 1.6.19 |
|
「大層な過失があったにしても、心弱く許してしまいそうなご様子だな」
|
どんな過失があっても自分のうちの愛の力が勝って許しうるに違いないのはこの人である
|
【いみじき過ちありとも、心弱く許しつべき御さまかな】- 源氏の心中。
|
| 1.6.20 |
と見たてまつりたまふ。
|
と拝見なさる。
|
と院は思召した。
|
|
|
第二章 女三の宮の物語 女三の宮の出家
|
|
第一段 朱雀院、夜闇に六条院へ参上
|
| 2.1.1 |
山の帝は、めづらしき御こと平かなりと聞こし召して、あはれにゆかしう思ほすに、
|
山の帝は、初めてのご出産が無事であったとお聞きあそばして、しみじみとお会いになりたくお思いになるが、
|
御寺の院は、珍しい出産を女三の宮が無事にお済ませになったという報をお聞きになって、非常にお逢いになりたく思召したところへ、
|
|
| 2.1.2 |
「かく悩みたまふよしのみあれば、いかにものしたまふべきにか」
|
「このようにご病気でいらっしゃるという知らせばかりなので、どうおなりになることか」
|
続いて御容体のよろしくないたよりばかりがあるために、
|
|
| 2.1.3 |
と、御行なひも乱れて思しけり。
|
と、御勤行も乱れて御心配あそばすのであった。
|
専心に仏勤めもおできにならなくなった。
|
|
| 2.1.4 |
|
あれほどお弱りになった方が、何もお召し上がりにならないで、何日もお過ごしになったので、まことに頼りなくおなりになって、幾年月もお目にかからなかった時よりも、院を大変恋しく思われなさるので、
|
衰弱しきった方がまた幾日も物を召し上がらないでおいでになったのであるから、いっそう頼み少なくお見えになる宮が、
|
【年ごろ見たてまつらざりしほどよりも】- 『集成』は「宮は源氏に嫁して七年、父院との対面がなかったが、昨年暮れの御賀でお会いして、恋しさがかえってつのるという気持」と注す。
【院のいと恋しくおぼえたまふを】- 『集成』は「「たまふ」は、院に対する敬語」「父院がとても恋しく思われなさるのに」。『完訳』は「宮は、対面後かえって父院が。一説には、「おぼえたまふ」の主語を院と解し、前の「年ごろ」以下を宮の言葉とする」と注す。
|
| 2.1.5 |
|
「再びお目にかかれないで終わってしまうのだろうか」
|
「長いことお目にかかれずに暮らしておりましたころよりも、もっともっと私はお父様が恋しくてなりませんのに、もうお目にかかれないまま死んでしまうのでしょうか」
|
【またも見たてまつらずなりぬるにや】- 女三の宮の心中。
|
| 2.1.6 |
|
と、ひどくお泣きになる。
このように申し上げなさるご様子、しかるべき人からお伝え申し上げさせなさったので、とても我慢できず悲しくお思いになって、あってはならないこととはお思いになりながら、夜の闇に隠れてお出ましになった。
|
と言って、非常にお泣きになったので、六条院はそのことを人から法皇にお伝えさせになると、法皇は堪えがたく悲しく思召して、よろしくない行動であるとは思召しながら、人目をはばかって夜になってから六条院へにわかに御幸あそばされた。
|
【かく聞こえたまふさま】- 『完訳』は「「かく」は前行「またも--なりぬるにや」の内容か。一説には、出家を訴えたこと」と注す。
【あるまじきこととは思し召しながら】- 出家の身でありながら親子の情の執着に引かれることをいう。
|
| 2.1.7 |
かねてさる御消息もなくて、にはかにかく渡りおはしまいたれば、主人の院、おどろきかしこまりきこえたまふ。
|
前もってそのようなお手紙もなくて、急にこのようにお越しになったので、主人の院、驚いて恐縮申し上げなさる。
|
御主人の院はお驚きになって、恐懼の意を表しておいでになった。
|
|
| 2.1.8 |
|
「世俗の事を顧みすまいと思っておりましたが、やはり煩悩を捨て切れないのは、子を思う親心の闇でございましたが、勤行も懈怠して、もしも親子の順が逆になって先立たれるようなことになったら、そのまま会わずに終わった怨みがお互いに残りはせぬかと、情けなく思われたので、世間の非難を顧みず、こうして参ったのです」
|
「もうこの世のことは顧みますまいと決心していたのですが、こうなってもまだ迷うのは子を思う道の闇だけで宮が重態だと聞くと仏のお勤めも怠るばかりで恥ずかしくてなりませんが、だれが先とも後とも定まらない人の命であれば、逢いたがる子に逢ってやらずに死なせましたら、親の心残りが道の妨げになる気がするので、人間世界の譏りも無視して出て来たのです」
|
【世の中を】- 以下「ものしはべる」まで、朱雀院の詞。
【子の道の闇になむ】- 大島本、朱合点。『異本紫明抄』は「人の親の心は闇にあらねども子を思ふ道に惑ひぬるかな」(後撰集雑一、一一〇二、兼輔朝臣)を指摘し、現行の注釈書でも指摘する。
【後れ先立つ道の道理】- 『異本紫明抄』は「末の露もとの雫や後れ先立つためしなるらむ」(古今六帖、露・和漢朗詠集、無常、良僧正)を指摘。
|
| 2.1.9 |
と聞こえたまふ。
御容貌、異にても、なまめかしうなつかしきさまに、うち忍びやつれたまひて、うるはしき御法服ならず、墨染の御姿、あらまほしうきよらなるも、うらやましく見たてまつりたまふ。
例の、まづ涙落としたまふ。
|
とお申し上げになる。
御姿、僧形であるが、優雅で親しみやすいお姿で、目立たないように質素な身なりをなさって、正式な法服ではなく、墨染の御法服姿で、申し分なく素晴らしいのにつけても、羨ましく拝見なさる。
例によって、まっさきに涙がこぼれなさる。
|
法皇はこう仰せられた。御僧形ではあるが艶なところがなお残ってなつかしいお姿にたいそうな御法服などは召さずに墨染め衣の簡単なのを御身にお着けあそばされたのがことに感じよくお美しいのを、院はうらやましく拝見されて、例のようにまず落涙をあそばされた。
|
|
| 2.1.10 |
「患ひたまふ御さま、ことなる御悩みにもはべらず。ただ月ごろ弱りたまへる御ありさまに、はかばかしう物なども参らぬ積もりにや、かくものしたまふにこそ」 |
「患っていらっしゃるご様子、特別どうというご病気ではありません。
ただここ数月お弱りになったご様子で、きちんとお食事なども召し上がらない日が続いたせいか、このようなことでいらっしゃるのです」
|
「御容体は何という名のある病気ではないのでございますが、今まで衰弱がはなはだしゅうございましたところへ、お食慾のないことが重態に導いたのでございます」
|
【患ひたまふ御さま】- 以下「かくものしたまふ」まで、源氏の詞。女三の宮の容態をさしていう。
|
| 2.1.11 |
など聞こえたまふ。
|
などと申し上げなさる。
|
などと六条院はお話しになって、
|
|
|
第二段 朱雀院、女三の宮の希望を入れる
|
| 2.2.1 |
|
「はなはだ恐縮な御座所ではありますが」
|
「失礼な場所でございますが」
|
【かたはらいたき御座なれど】- 源氏の詞。朱雀院を女三の宮の病床近くに招き入れる。
|
| 2.2.2 |
とて、御帳の前に、御茵参りて入れたてまつりたまふ。宮をも、とかう人びと繕ひきこえて、床のしもに下ろしたてまつる。御几帳すこし押しやらせたまひて、 |
と言って、御帳台の前に、御褥を差し上げてお入れ申し上げなさる。
宮を、あれこれと女房たちが身なりをお整い申して、浜床の下方にお下ろし申し上げる。
御几帳を少し押し除けさせなさって、
|
と、宮のお寝みになった帳台の前へお敷き物の座を作って法皇を御案内された。宮を女房たちがいろいろとお引き繕いして御介抱をしながら、宮をもお床の下へお降ろしした。法皇は間の几帳を少し横へお押しになって、
|
【床のしもに】- 御帳台の下の浜床に。
|
| 2.2.3 |
|
「夜居の加持僧などのような気がするが、まだ効験が現れるほどの修業もしていないので、恥ずかしいけれど、ただお会いしたく思っていらっしゃるわたしの姿を、そのままとくと御覧になるがよい」
|
「夜居の加持の僧のような気はしても、まだ効験を現わすだけの修行ができていないから恥ずかしいが、逢いたがっておいでになった顔をそこでよく見るがいい」
|
【夜居加持僧などの】- 以下「さながら見たまふべきなり」まで、朱雀院の詞。
【おぼえたまふらむ】- 主語は女三の宮。
|
| 2.2.4 |
とて、御目おし拭はせたまふ。
宮も、いと弱げに泣いたまひて、
|
とおっしゃって、お目をお拭いあそばす。
宮も、とても弱々しくお泣きになって、
|
と法皇は仰せられて目をおふきになった。宮も弱々しくお泣きになって、
|
|
| 2.2.5 |
「生くべうもおぼえはべらぬを、かくおはしまいたるついでに、尼になさせたまひてよ」 |
「生き永らえそうにも思われませんので、このようにお越しになった機会に、尼になさって下さいませ」
|
「私の命はもう助かるとは思えないのでございますから、おいでくださいましたこの機会に私を尼にあそばしてくださいませ」
|
【生くべうも】- 以下「尼になさせたまひてよ」まで、女三の宮の詞。僧形姿の父に出家の受戒を懇願。
|
| 2.2.6 |
と聞こえたまふ。
|
と申し上げなさる。
|
こうお言いになるのであった。
|
|
| 2.2.7 |
「さる御本意あらば、いと尊きことなるを、さすがに、限らぬ命のほどにて、行く末遠き人は、かへりてことの乱れあり、世の人に誹らるるやうありぬべき」 |
「そのようなご希望があるならば、まことに尊いことであるが、そうはいえ、人の寿命は分からないものゆえ、生き先長い人は、かえって後で間違いを起こして、世間の非難を受けるようなことになりかねないだろう」
|
「その志は結構だが、命は予測することを許されないものだから、あなたのような若い人は今後長く生きているうちに、迷いが起こって、世間の人に譏られるようなことにならぬとは限らない。慎重に考えてからのことにしては」
|
【さる御本意あらば】- 以下「やうありぬべき」まで、朱雀院の詞。
【ありぬべき」--など】- 定家筆本と明融臨模本は「ありぬへきなと」とある。大島本は「ありぬへきなんと」とある。『集成』と『新大系』はそれぞれ底本のまま「…ありうべき」など」「…ありぬべき」なんど」とする。『完本』は諸本に従って「…ありぬべきことになん、なほ憚りぬべき」など」と「ことになんなほ憚りぬべき」を補訂する。
|
| 2.2.8 |
|
などと仰せられて、大殿の君に、
|
などと法皇はお言いになって、六条院に、
|
|
| 2.2.9 |
「かくなむ進みのたまふを、今は限りのさまならば、片時のほどにても、その助けあるべきさまにてとなむ、思ひたまふる」 |
「このように自分から進んでおっしゃるので、もうこれが最期の様子ならば、ちょっとの間でも、その功徳があるようにして上げたい、と存じます」
|
「こう進んで言いますが、すでに危篤な場合とすれば、しばらくもその志を実現させることによって仏の冥助を得させたいと私は思う」
|
【かくなむ進み】- 以下「となむ思ひたまふる」まで、朱雀院の詞。
|
| 2.2.10 |
とのたまへば、
|
と仰せになるので、
|
と仰せられた。
|
|
| 2.2.11 |
|
「この日頃もそのようにおっしゃいますが、物の怪などが、宮のお心を惑わして、このような方面に勧めるようなこともございますこととて、お聞き入れ致さないのです」
|
「この間からそのことをよくお話しになるのですが、物怪が人の心をたぶらかして、そんなふうのことを勧めるのでしょうと申して私は御同意をしないのでございます」
|
【日ごろもかく】- 以下「聞きも入れはべらぬなり」まで、源氏の詞。
【かかる方にて】- 定家筆本と明融臨模本、大島本は「かゝるかたにて」とある。『集成』と『新大系』はそれぞれ底本のままとする。『完本』は諸本に従って「かかる方に」と「て」を削除する。
|
| 2.2.12 |
と聞こえたまふ。
|
とお申し上げになる。
|
|
|
| 2.2.13 |
「もののけの教へにても、それに負けぬとて、悪しかるべきことならばこそ憚らめ、弱りにたる人の、限りとてものしたまはむことを、聞き過ぐさむは、後の悔い心苦しうや」 |
「物の怪の教えであっても、それに負けたからといって、悪いことになるのならば控えねばならないが、衰弱した人が、最期と思って願っていらっしゃるのを、聞き過ごすのは、後々になって悔やまれ辛い思いをするのではないか」
|
「物怪の勧めでそれを行なうと言っても、悪いことはとめなければなりませんが、衰弱してしまった人が最後の希望として言っていることを無視しては、後悔することがあるかもしれぬと私は思う」
|
【もののけの】- 以下「心苦しうや」まで、朱雀院の詞。
|
| 2.2.14 |
とのたまふ。
|
と仰せになる。
|
法皇の仰せはこうであった。
|
|
|
第三段 源氏、女三の宮の出家に狼狽
|
| 2.3.1 |
御心の内、限りなううしろやすく譲りおきし御ことを、受けとりたまひて、さしも心ざし深からず、わが思ふやうにはあらぬ御けしきを、ことに触れつつ、年ごろ聞こし召し思しつめけること、色に出でて恨みきこえたまふべきにもあらねば、世の人の思ひ言ふらむところも口惜しう思しわたるに、 |
御心中、この上なく安心に思ってお任せ申した姫宮の御ことを、お引き受けなさったが、それほど愛情も深くなく、自分の思っていたのとは違ったご様子を、何かにつけて、ここ幾年もお聞きあそばして積もりに積もったご不満、顔色に現してお恨み申し上げなさるべきことでもないので、世間の人が想像したり噂したりすることも残念にお思い続けていられたので、
|
お心のうちでは限りもない信頼をもって託しておいた内親王を妻にしてからのこの院の愛情に飽き足らぬところのあるのを何かの場合によく自分は聞いていたが、恨みを自分から言い出すこともできぬ問題であって、しかも世間に取り沙汰されるのも忍ばねばならぬことを始終残念に思っているのであるから、
|
【限りなう】- 以下「その心ばへをも見果てむ」まで、朱雀院の心中に即した文章。
【世の人の思ひ言ふらむところも】- 源氏と女三の宮の結婚について。
|
| 2.3.2 |
|
「このような機会に、出家するのが、どうしてか、物笑いになるような、夫婦仲を恨んでのことのようでなく、それで不都合があろうか。
一通りのお世話は、やはり頼りになれそうなお気持ちであるから、ただそれだけをお預け申し上げた甲斐と思うことにして、面当てつけがましく出家した恰好ではなくとも、ご遺産に広くて美しい宮邸をご伝領なさっていたのを、修繕してお住ませ申そう。
|
この機会に決断して尼にさせてしまうとしても、良人に捨てられたのだと、世間から嘲罵されるわけのものではない。少しも遠慮はいらぬ。現在において宮の望みは遂げさせなくてはならない、夫婦関係の解消したのちに、単に兄の子として保護してくれる好意はあるはずであるから、せめてそれだけを自分から寄託された最後の義務に負ってもらうことにして反抗的にここを出て行くふうでなくして、自分からかつて宮に分配した財産のうちに広くてりっぱな邸宅もあるのであるから、そこを修繕して住ませよう、
|
【かかる折に、もて離れなむも】- 『完訳』は「どうせ離れるのなら、重病の現在出家するのが最良、の気持」と注す。
【人笑へに】- 『完訳』は「健康の身で出家しては、世間の物笑いにもなり、源氏を恨んで行為ともみられようが、の気持」と注す。
【広くおもしろき宮賜はりたまへるを】- 三条宮(院)をさす。『集成』は「女三の宮が朱雀院から」。『完訳』は「父桐壺院からの伝領」と注す。
【繕ひて住ませたてまつらむ】- 朱雀院は女三の宮を六条院から三条宮に引き取って別居させようとする。
|
| 2.3.3 |
わがおはします世に、さる方にても、うしろめたからず聞きおき、またかの大殿も、さいふとも、いとおろかにはよも思ひ放ちたまはじ、その心ばへをも見果てむ」 |
自分の生きている間に、そのようにしてでも、不安がないようにしておき、またあの大殿も、そうは言っても、冷淡には決してお見捨てなさるまい。その気持ちも見届けよう」
|
自分がまだ生きておられるうちにそれらの処置を皆しておくことにしたい。この院も妻としては冷ややかに見ても、今からの宮を不人情に放ってはおくまい。自分はその態度を見きわめておく必要がある
|
【わがおはします世に】- 『集成』は「「おはします」は、筆者の朱雀院に対する敬意が文面に現れたもの」と注す。
|
| 2.3.4 |
と思ほし取りて、
|
とお考え決めなさって、
|
と思召して、
|
|
| 2.3.5 |
「さらば、かくものしたるついでに、忌むこと受けたまはむをだに、結縁にせむかし」 |
「それでは、このように参った機会に、せめて出家の戒をお受けになることだけでもして、仏縁を結ぶことにしよう」
|
「では私がこちらへ来たついでにあなたの授戒を実行させることにして、それを私は御仏から義務の一つを果たしたことと見ていただくことにする」
|
【さらば、かく】- 以下「結縁にせむかし」まで、朱雀院の詞。
|
| 2.3.6 |
とのたまはす。
|
と仰せになる。
|
と仰せられた。
|
|
| 2.3.7 |
|
大殿の君、厭わしいとお思いになる事も忘れて、これはどうなることかと、悲しく残念でもあったので、堪えることがおできになれず、御几帳の中に入って、
|
六条院は遺憾にお思いになった宮の御過失のこともお忘れになって、なんとなることかと心をお騒がせになって、悲しみにお堪えにならずに、几帳の中へおはいりになって、
|
【憂しと思す方も忘れて】- 柏木と女三の宮の密通事件をさす。かつて六条御息所の生霊事件も源氏にとって「憂し」とあった。
|
| 2.3.8 |
「などか、いくばくもはべるまじき身をふり捨てて、かうは思しなりにける。なほ、しばし心を静めたまひて、御湯参り、物などをも聞こし召せ。尊きことなりとも、御身弱うては、行なひもしたまひてむや。かつは、つくろひたまひてこそ」 |
「どうしてか、そう長くはないわたしを捨てて、そのようにお考えになったのですか。
やはり、もう暫く心を落ち着けなさって、御薬湯を上がり、食べ物を召し上がりなさい。
尊い事ではあるが、お身体が弱くては、勤行もおできになれようか。
ともかくも、
|
「なぜそういうことをなさろうというのですか。もう長くも生きていない老いた良人をお捨てになって、尼になどなる気になぜおなりになったのですか。もうしばらく気を静めて、湯をお飲みになったり、物を召し上がったりすることに努力なさい。出家をすることは尊いことでも、身体が弱ければ仏勤めもよくできないではありませんか。ともかくも病気の回復をお計りになった上でのことになさい」
|
【などか、いくばくも】- 明融臨模本、付箋「いく世しもあらしわか身をなそもかくあまのかるもに思みたるゝ」(古今集雑下、九三四、読人しらず)。大島本、行間書入れ「古今 いく世しもあらし我身をなそもかく海人のかるもに思みたるゝ」とある。古注では『河海抄』が指摘する。現行の注釈書では指摘されない。以下「つくろひたまひてこそ」まで、源氏から女三の宮への詞。
|
| 2.3.9 |
と聞こえたまへど、頭ふりて、いとつらうのたまふと思したり。つれなくて、恨めしと思すこともありけるにやと見たてまつりたまふに、いとほしうあはれなり。とかく聞こえ返さひ、思しやすらふほどに、夜明け方になりぬ。 |
と申し上げなさるが、頭を振って、とても辛いことをおっしゃると思っておいでである。
表面ではさりげなく振る舞っているが、心中恨めしいとお思いになっていらしたことがあったのかと拝見なさると、不憫でおいたわしい。
あれやこれやと反対を申して、ためらっていらっしゃるうちに、夜明け近くなってしまいまった。
|
とお話しになるのであるが、宮は頭をお振りになって、おとめになるのを恨めしくお思いになるふうであった。何もお言いにはならなかったが、自分を恨めしくお思いになったこともあるのではないかとお気がつくと、かわいそうでならない気があそばされたのであった。いろいろと宮の御意志を翻えさせようと院が言葉を尽くしておいでになるうちに夜明け方になった。
|
【つれなくて】- 以下「ありけるにや」まで、源氏の心中を間接的に叙述。『集成』は「宮の思い詰めた様子に、源氏も悔恨に似た思いを抱く」と注す。
|
|
第四段 朱雀院、夜明け方に山へ帰る
|
| 2.4.1 |
帰り入らむに、道も昼ははしたなかるべしと急がせたまひて、御祈りにさぶらふ中に、やむごとなう尊き限り召し入れて、御髪下ろさせたまふ。
いと盛りにきよらなる御髪を削ぎ捨てて、忌むこと受けたまふ作法、悲しう口惜しければ、大殿はえ忍びあへたまはず、いみじう泣いたまふ。
|
山に帰って行くのに、道中が昼間では不体裁であろうとお急がせあそばして、御祈祷に伺候している中で、位が高く有徳の僧だけを召し入れて、お髪を下ろさせなさる。
まことに女盛りで美しいお髪を削ぎ落として、戒をお受けになる儀式、悲しく残念なので、大殿は堪えることがおできになれず、ひどくお泣きになる。
|
御寺へお帰りになるのが明るくなってからでは見苦しいと法皇はお急ぎになって、祈祷のために侍している僧の中から尊敬してよい人格者ばかりをお選びになり、産室へお呼びになって、宮のお髪を切ることをお命じになった。若い盛りの美しいお髪を切って仏の戒をお受けになる光景は悲しいものであった。残念に思召して六条院は非常にお泣きになった。
|
|
| 2.4.2 |
院はた、もとより取り分きてやむごとなう、人よりもすぐれて見たてまつらむと思ししを、この世には甲斐なきやうにないたてまつるも、飽かず悲しければ、うちしほたれたまふ。 |
院は院で、もとから特別大切に、誰よりも幸福にしてさし上げたいとお思いになっていたのだが、この世ではその甲斐もないようにおさせ申し上げるのも、どんなに考えても悲しいので、涙ぐみなさる。
|
また法皇におかせられては、御子の中でもとりわけお大事に思召された内親王で、だれよりも幸福な生涯を得させたいとお思いあそばされた方を、未来の世は別としてこの世でははかない姿にお変えさせになったことで萎れておいでになって、
|
【人よりも】- 『集成』は「誰よりもしあわあせな生涯を送らせようとお思いだったのに。そのために、源氏を婿に選んだのである」と注す。
|
| 2.4.3 |
|
「こうした姿にしたが、健康になって、同じことなら念仏誦経をもお勤めなさい」
|
「たとえこうおなりになっても、健康が回復すればそれを幸福にお思いになって、できれば念誦だけでもよくお唱えしているようになさい」
|
【かくても】- 以下「念誦をも勤めたまへ」まで、朱雀院の詞。
【同じうは】- 出家姿でいるなら、何もせずにいるのでなく、の気持。『完訳』は「出家したうえは来世の救済に期待して精進しなさい」と訳す。
|
| 2.4.4 |
と聞こえ置きたまひて、明け果てぬるに、急ぎて出でさせたまひぬ。
|
と申し上げなさって、夜が明けてしまうので、急いでお帰りになった。
|
とお言いになった院は、まだ暗いうちに六条院をお去りになることにあそばされた。
|
|
| 2.4.5 |
宮は、なほ弱う消え入るやうにしたまひて、はかばかしうもえ見たてまつらず、ものなども聞こえたまはず。
大殿も、
|
宮は、今も弱々しく息も絶えそうでいらっしゃって、はっきりともお顔も拝見なさらず、ご挨拶も申し上げなさらない。
大殿も、
|
宮は今もなおお命がおぼつかない御様子で、はかばかしく御父法皇を目送あそばすこともおできにならず、ものもお言われにならなかった。
|
|
| 2.4.6 |
|
「夢のように存じられて心が乱れておりますので、このように昔を思い出させます御幸のお礼を、御覧に入れられない御無礼は、後日改めて参上致しまして」
|
「夢を見ておりますようなことが起こりまして、心が混乱しております際で、昔の御厚情をまたお見せくださいました御幸に感謝の意もまだ表してお目にかけることができませんような不都合さも、また私が伺ってお詫びすることにいたしましょう」
|
【夢のやうに】- 以下「参りはべりてなむ」まで、源氏の詞。
【昔おぼえたる御幸】- 九年前の六条院行幸をさす。「藤裏葉」巻に語られていた。
【かしこまり】- 『集成』は「恐懼の気持。具体的には、饗応、贈り物その他のしかるべきもてなしをいう」と注す。
|
| 2.4.7 |
と聞こえたまふ。
御送りに人びと参らせたまふ。
|
と申し上げなさる。
お帰りのお供に家臣を差し上げなさる。
|
と六条院は御挨拶をあそばされた。そしてこの院の役人たちを御寺へお見送りにお出しになるのであった。
|
|
| 2.4.8 |
|
「わたしの寿命も、今日か明日かと思われました時に、また他に面倒を見る人もなくて、寄るべもなく暮らすことが、気の毒で放っておけないように思われましたので、あなたの本意ではなかったでしょうが、このようにお願い申して、今まではずっと安心しておりましたが、もしも宮が命を取り留めましたら、普通とは変わった尼姿で、人の大勢いる中で生活するのは不都合でしょうが、適当な山里などに離れ住む様子も、またそうはいっても心細いことでしょう。
尼の身の上相応に、やはり、今まで通りお見捨てなさらずに」
|
「もう今日か明日かに終わるように自分の命の危険さが思われた際に、あとに残して保護者もなく寂しくこの世を渡らせることが憐れまれてならぬ時に、御本意ではなかったでしょうが、あなたへお託しさせていただいて、今までは安心していたのですが、万一かれの命の助かることがありますれば、もう普通の人ではなくなりました者が、人出入りの多い宮殿にいますことは似合わしく思われませんし、郊外の寂しい所へ住ませるのもさすがにまた心細く思うことでしょうから、その点をあなたがお考えくだすって住居を移させることにしていただきたい。どうか今後もかれを念頭にお置きください」
|
【世の中の】- 以下「思し放つまじうなむ」まで、朱雀院の詞。
【また知る人もなくて】- 大島本、朱合点、行間書入「古今 枕より又しる人も」とある。古注では『異本紫明抄』が「枕よりまた知る人もなき恋を涙せきあへず漏らしつるかな」(古今集恋三、六七〇、平貞文)を指摘。女三の宮の身の上をさす。
【御本意にはあらざりけめど】- 『完訳』は「この言葉、院自身には他意がなくとも、源氏には痛烈な皮肉」と注す。
【もしも生きとまりはべらば】- 主語は女三の宮。
|
| 2.4.9 |
など聞こえたまへば、
|
などとお頼み申し上げなさると、
|
と法皇がお言いになると、
|
|
| 2.4.10 |
「さらにかくまで仰せらるるなむ、かへりて恥づかしう思ひたまへらるる。乱り心地、とかく乱れはべりて、何事もえわきまへはべらず」 |
「改めてこのようにまで仰せ下さいましたことが、かえってこちらが恥ずかしく存じられます。
乱れ心地に、何やかやと思い乱れまして、何事も判断がつきかねております」
|
「そんな仰せまでも受けましてはかえって私が恥じ入ります。自分の精神がよく統一されていくのを待ちましてすべてのことに善処いたしましょう」
|
【さらにかくまで】- 以下「えわきまへはべらず」まで、源氏の詞。
|
| 2.4.11 |
とて、げに、いと堪へがたげに思したり。
|
と答えて、
|
院は実際悲しみに堪えぬ御様子であった。
|
|
| 2.4.12 |
後夜の御加持に、御もののけ出で来て、
|
後夜の御加持に、御物の怪が現れ出て、
|
後夜の加持の時に物怪が人に憑って来て、
|
|
| 2.4.13 |
|
「それごらん。
みごとに取り返したと、一人はそうお思いになったのが、まことに悔しかったので、この辺に、気づかれないようにして、ずっと控えていたのだ。
今はもう帰ろう」
|
「どう、こんなことになってしまったではないか。上手に一人を取り返したと思っておいでになる様子がくやしかったから、それからは気のつかぬようにしてこちらへ私は来ていたのだ。もう帰りますよ」
|
【かうぞあるよ】- 以下「今は帰りなむ」まで、物の怪の詞。女三の宮の出家は物の怪のしわざであった。
【一人をば思したりしが】- 「一人」は紫の上をさし、「思す」の主語は源氏。
|
| 2.4.14 |
|
と言って、ちょっと笑う。
まことに驚きあきれて、
|
と笑った。
|
【うち笑ふ】- 明融臨模本、付箋「栄花小一条院女御<顕光女>の邪気にて御堂の御女のひさしく患給ひてつゐに御くしおろさせ給ふその時邪気人に付て今こそうれしけれとて手をうちて笑けるよしみえたり」とある。『河海抄』にほぼ同文の内容が見える。小一条院女御(道長女、寛子)が危篤に陥ったとき、藤原顕光とその女小一条院女御延子が死霊となって現れ出て、手を打って喝采をさけんだという話。『栄華物語』「峰の月」に見える。
|
| 2.4.15 |
|
「それでは、この物の怪がここにも、離れずにいたのか」
|
これによれば紫夫人を悩ました物怪が、それ以来こちらへ憑いていたのであったか、
|
【さは、このもののけのここにも、離れざりけるにやあらむ】- 源氏の心中。物の怪の正体を六条御息所と知る。
|
| 2.4.16 |
と思すに、いとほしう悔しう思さる。宮、すこし生き出でたまふやうなれど、なほ頼みがたげに見えたまふ。さぶらふ人びとも、いといふかひなうおぼゆれど、「かうても、平かにだにおはしまさば」と、念じつつ、御修法また延べて、たゆみなく行なはせなど、よろづにせさせたまふ。 |
とお思いになると、お気の毒に悔しく思わずにはいらっしゃれない。
宮は、少し生き返ったようだが、やはり頼りなさそうにお見えになる。
伺候する女房たちも、まことに何とも言いようもなく思われるが、「こうしてでも、せめてご無事でいらっしゃったならば」と、祈りながら、御修法をさらに延長して、休みなく行わせたりなど、いろいろとおさせになる。
|
あらゆる不祥事はかれがなさしめたのかもしれぬとお気づきになった時、女三の宮がおかわいそうでならぬ気のされる院でおありになった。宮の御容体は少し持ち直したようであったが、まだ危険状態を脱したとはお見えにならないのである。女房たちも御出家をあそばしたことで失望した様子であったが、たとえこうおなりになっても御健康さえ取りもどすことができればと、今はそれを院もお念じになって、修法もまた延ばさせて、油断なく祈らせることもあそばしたし、そのほかのあらゆる方法もおとりになって、宮のお命の助かるようにとばかり苦心あそばされるのであった。
|
【いとほしう悔しう思さる】- 『集成』は「おいたわしく残念にお思いになる」。『完訳』は「宮がいじらしくもあり、また尼にしてさしあげたことを悔まずにはいらっしゃれない」「物の怪の出現は、宮出家の種明かしでもあるが、源氏の人生を根源的に捉え直す視点ともなろう」と注す。
|
|
第三章 柏木の物語 夕霧の見舞いと死去
|
|
第一段 柏木、権大納言となる
|
| 3.1.1 |
|
あの衛門督は、このような御事をお聞きになって、ますます死んでしまいそうな気がなさって、まるきり回復の見込みもなさそうになってしまわれた。
女宮がしみじみと思われなさるので、こちらにお越しになることは、今さら軽々しいようにも思われますが、母上も大臣もこのようにぴったり付き添っていらっしゃるので、何かの折にうっかりお顔を拝見なさるようなことがあっては、困るとお思いになって、
|
右衛門督は六条院の宮の御出産から出家と続いての出来事を病床に聞いて、いっそう頼み少ない容体になってしまった。夫人の女二の宮をおかわいそうにばかり思われる衛門督は、助からぬ命にきまった今になって、ここへ宮がおいでになることは軽々しく世間が見ることであろうし、父母が始終近くへ来ている病室では、自然お姿をそれらの近親者に見られておしまいになる隙ができることになってはもったいないと思って、
|
【かかる御事を聞きたまふに】- 女三の宮の出家をさす。
【女宮のあはれにおぼえたまへば】- 落葉の宮をさす。「おぼえたまふ」の主体は柏木、その対象は落葉の宮。『集成』は「北の方の女二の宮(落葉の宮)がおいたわしく思われなさるので。「おぼえたまふ」の「たまふ」は、落葉の宮に対する敬語」と注す。
【ここに渡りたまはむことは】- 『集成』は「以下、柏木の心中」と注す。間接的叙述。
【上も大臣も】- 柏木の母北の方と父大臣。
|
| 3.1.2 |
|
「あちらの宮邸に、何とかしてもう一度参りたい」
|
「どんな無理をしてでも一条の宮へもう一度行ってみたいのです」
|
【かの宮に、とかくして今一度参うでむ】- 柏木の詞。
|
| 3.1.3 |
とのたまふを、さらに許しきこえたまはず。誰にも、この宮の御ことを聞こえつけたまふ。はじめより母御息所は、をさをさ心ゆきたまはざりしを、この大臣の居立ちねむごろに聞こえたまひて、心ざし深かりしに負けたまひて、院にも、いかがはせむと思し許しけるを、二品の宮の御こと思ほし乱れけるついでに、 |
とおっしゃるが、まったくお許し申し上げなさらない。
皆にも、この宮の御事をお頼みなさる。
最初から母御息所は、あまりお気が進みでなかったのだが、この大臣自身が奔走して熱心に懇請申し上げなさって、そのお気持ちの深いことにお折れになって、院におかれても、しかたないとお許しになったのだが、二品の宮の御事にお心をお痛めになっていた折に、
|
と言い続けるのであるが、両親は許さなかった。衛門督はだれにも自分の死後はこの宮を御保護申すようにということを頼んでいた。もともと宮の母君の御息所はこの結婚に不賛成であったのが、衛門督の父の大臣の熱心な懇望が法皇を動かしたてまつって、お許しになることになったものであって、六条院の二品の宮の御幸福のかんばしくない噂などがお耳にはいったころには、
|
【許しきこえたまはず】- 主語は柏木の両親。
【二品の宮】- 女三の宮をさす。
|
| 3.1.4 |
|
「かえって、この宮は将来安心で、実直な夫をお持ちになったことだ」
|
「かえって二の宮のほうが将来の頼もしい良人を得たというものだ」
|
【なかなか、この宮は】- 以下「後見まうけたまへり」まで、朱雀院の詞。引用。
|
| 3.1.5 |
と、のたまはすと聞きたまひしを、かたじけなう思ひ出づ。
|
と、仰せられたとお聞きになったのを、恐れ多いことだと思い出す。
|
と法皇が仰せられると聞いたこともあったのに、なんという成り行きになることかと今は悲しむばかりであった。
|
|
| 3.1.6 |
「かくて、見捨てたてまつりぬるなめりと思ふにつけては、さまざまにいとほしけれど、心よりほかなる命なれば、堪へぬ契り恨めしうて、思し嘆かれむが、心苦しきこと。御心ざしありて訪らひものせさせたまへ」 |
「こうして、後にお残し申し上げてしまうようだと思うにつけても、いろいろとお気の毒だが、思う通りには行かない命なので、添い遂げられない夫婦の仲が恨めしくて、お嘆きになるだろうことがお気の毒なこと。
どうか気をつけてお世話してさし上げて下さい」
|
「こんなふうで宮様を未亡人にしてしまうのかと思いますと堪えられません。あちらにもこちらにもお気の毒なことばかりですが、自分の心に任せないのが命ですからしかたもありません。宮様の今後の寂しい生活を思いますと心苦しくてなりませんから、お母様は親切にしてあげてください。始終お世話をしてあげてくださいお母様」
|
【かくて】- 以下「ものせさせたまへ」まで、柏木の詞。
【さまざまにいとほしけれど】- 『集成』は「どなたに対してもおいたわしいことですが。父院や母御息所のお嘆きも思われるが、というほどの意」と注す。
|
| 3.1.7 |
と、母上にも聞こえたまふ。
|
と、母上にもお頼み申し上げなさる。
|
と督は母夫人にも言っていた。
|
|
| 3.1.8 |
「いで、あなゆゆし。後れたてまつりては、いくばく世に経べき身とて、かうまで行く先のことをばのたまふ」 |
「まあ、何と縁起でもないことを。
あなたに先立たれては、どれほど生きていられるわたしだと思って、こうまで先々の事をおっしゃるの」
|
「縁起の悪い話をしますね。あなたに死なれたあとで、お母様はどれだけ生きておられると思ってそんな未来のことまでも言うのですか」
|
【いで、あなゆゆし】- 以下「ことをばのたまふ」まで、母北の方の詞。
|
| 3.1.9 |
とて、泣きにのみ泣きたまへば、え聞こえやりたまはず。右大弁の君にぞ、大方の事どもは詳しう聞こえたまふ。 |
と言って、ただもうお泣きになるばかりなので、十分にお頼み申し上げになることができない。
右大弁の君に、一通りの事は詳しくお頼み申し上げなさる。
|
と言って、母はまず泣き入ってしまうので、衛門督はよく話すこともできないのである。すぐ下の弟である左大弁に兄はくわしく宮の御事は遺言しておいた。
|
【右大弁の君】- 柏木の弟。もし次弟と考えれば、「若菜下」巻に「左大弁」とあった人物と同一人となり、いずれかに誤写があろう。
|
| 3.1.10 |
心ばへののどかによくおはしつる君なれば、弟の君たちも、まだ末々の若きは、親とのみ頼みきこえたまへるに、かう心細うのたまふを、悲しと思はぬ人なく、殿のうちの人も嘆く。 |
気性が穏やかでよくできたお方なので、弟の君たちも、まだ下の方の幼い君たちは、まるで親のようにお頼り申していらっしゃったのに、このように心細くおっしゃるのを、悲しいと思わない人はなく、お邸中の人達も嘆いている。
|
善良な性質の人であったから、弟たちにも皆親しまれていて、末のほうの弟などは親のように頼みにしているこの人が、遺言をしたりするようになったのを、だれも心細がらぬ者はなくて、家の使用人なども皆悲しんでいるのである。
|
【心ばへののどかに】- 定家筆本と明融臨模本、大島本は「心はへの」とある。『集成』『新大系』は底本のままとする。『完本』は諸本に従って「心ばへ」と「の」を削除する。
|
| 3.1.11 |
公も、惜しみ口惜しがらせたまふ。かく限りと聞こし召して、にはかに権大納言になさせたまへり。よろこびに思ひ起こして、今一度も参りたまふやうもやあると、思しのたまはせけれど、さらにえためらひやりたまはで、苦しきなかにも、かしこまり申したまふ。大臣も、かく重き御おぼえを見たまふにつけても、いよいよ悲しうあたらしと思し惑ふ。 |
帝も、惜しがり残念がりあそばす。
このように最期とお聞きあそばして、急に権大納言にお任じあそばした。
喜びに気を取り戻して、もう一度参内なさるようなこともあろうかと、お考えになって仰せになったが、一向に病気が好くおなりにならず、苦しい中ながら、丁重にお礼申し上げなさる。
大臣も、このようにご信任の厚いのを御覧になるにつけても、ますます悲しく惜しいとお思い乱れなさる。
|
朝廷でも非常にお惜しみになって、いよいよ危篤ということが天聴に達すると、にわかに権大納言に昇任おさせになった。この感激によって元気が出てもう一度だけは参内をするかと帝は期しておいでになったのであるが、それをすることがもう衛門督にはできなかった。ただ病苦の中で拝任の表だけを草して奉った。大臣はこの朝恩の厚さを見てもさらに惜しく悲しくわが子が思われるのであった。
|
【さらにえためらひやりたまはで】- 一向に病勢がとどまらず、よくならない、の意。
|
|
第二段 夕霧、柏木を見舞う
|
| 3.2.1 |
大将の君、常にいと深う思ひ嘆き、訪らひきこえたまふ。御喜びにもまづ参うでたまへり。このおはする対のほとり、こなたの御門は、馬、車たち込み、人騒がしう騷ぎ満ちたり。今年となりては、起き上がることもをさをさしたまはねば、重々しき御さまに、乱れながらは、え対面したまはで、思ひつつ弱りぬること、と思ふに口惜しければ、 |
大将の君、いつも大変に心配して、お見舞い申し上げなさる。
ご昇進のお祝いにも早速参上なさった。
このいらっしゃる対の屋の辺り、こちらの御門は、馬や、車がいっぱいで、人々が騒がしいほど混雑しあっていた。
今年になってからは、起き上がることもほとんどなさらないので、重々しいご様子に、取り乱した恰好では、お会いすることがおできになれないで、そう思いながら会えずに衰弱してしまったこと、と思うと残念なので、
|
左大将は常に親友の病をいたんで見舞いを書き送っているのであるが、昇任の祝いを述べに真先に大臣家を訪問したのもこの人であった。衛門督の住んでいるほうの対の門内には馬や車がたくさん来ていて、忙しそうに人々が出入りしていた。今年にはいってからは起き上がることもあまりできない衛門督であったから、大官の親友を病室に招くことが遠慮されて恋しく思いながら逢えないことを思うと残念で、督は、
|
【馬、車たち込み】- 「馬」は身分低い者の乗り物。「車」は高い者の乗り物。
【重々しき御さまに】- 夕霧の「大将」という身分の重さをいう。
|
| 3.2.2 |
|
「どうぞ、こちらへお入り下さい。
まことに失礼な恰好でおりますご無礼は、何とぞお許し下さい」
|
「失礼ですがやはりここへ来ていただくことにします。この場合のことでやむをえないとお許しくださるでしょう」
|
【なほ、こなたに】- 以下「思し許されなむ」まで、柏木の詞。
【おのづから思し許されなむ】- 『集成』は「事情お察しの上大目に見て頂けましょう」。『完訳』は「もしやお許しくださることかと存じまして」と訳す。
|
| 3.2.3 |
とて、臥したまへる枕上の方に、僧などしばし出だしたまひて、入れたてまつりたまふ。
|
と言って、臥せっていらっしゃる枕元に、僧たちを暫く外にお出しになって、お入れ申し上げなさる。
|
と挨拶をさせて、病室の床の近くに侍している僧などをしばらく外のほうへ出して大将を迎えた。
|
|
| 3.2.4 |
|
幼少のころから、少しも分け隔てなさることなく、仲好くしていらっしゃったお二方なので、別れることの悲しく恋しいに違いない嘆きは、親兄弟の思いにも負けない。
今日はお祝いということで、元気になっていたらどんなによかろうと思うが、まことに残念に、その甲斐もない。
|
少年時代から隔てなく交際して来た間柄であったから、近く迫った死別の悲しみは大将にとって親兄弟の思いに劣らないのである。今日だけは昇任の悦びで気分もよくなっているであろうとこの人は想像していたのであるが、期待ははずれてしまった。
|
【早うより】- 明融臨模本、付箋「栄 粟田殿(道兼也)御病(母同道長公)の中に関白になり給御よろこひに小野宮殿参給へりたるをもやのみすおろしてよひいれ奉り給へりふしなからたいめんありてみたり心ちいとあしう侍てとにはまかりいてねはかく申侍なりし」とある。付箋の位置は、「こなたに入らせたまへ」が適切である。『河海抄』には「栄花物語粟田殿御病の中に関白になり給御よろこひに小野宮殿まいり給へりけるをもやの御すおろしてよひいれたてまつり給へりふしなから御対面ありてみたり心ちいとあしう侍てとにはまかりいてねはかくて申侍なり(以下略)」というさらに詳細な注記がある。
【今日は喜びとて、心地よげならましを】- 夕霧の心中を間接的に叙述。「まし」反実仮想の助動詞。
|
| 3.2.5 |
|
「どうしてこんなにお弱りになってしまわれたのですか。
今日は、このようなお祝いに、少しでも元気になったろうかと思っておりましたのに」
|
「どうしてこんなにまた悪くおなりになったのでしょう。今日だけはめでたいのですから少し気分でもよくなっておられるかと思って来ましたよ」
|
【などかく頼もしげなく】- 以下「思ひはべれ」まで、夕霧の詞。
【こそ思ひはべりつれ】- 『完訳』は「「--こ--已然形」は逆接の文脈。下に、しかし--と無念の気持」と注す。
|
| 3.2.6 |
|
と言って、几帳の端を引き上げなさったところ、
|
と言って、病床に添えた几帳の端を上げて中を見ると、
|
【几帳のつま】- 定家筆本と明融臨模本は「木丁のつま」とある。大島本は「木丁のつまを」とある。『集成』『新大系』はそれぞれ底本(定家筆本・大島本)のままとする。『完本』は諸本に従って「几帳のつまを」と「を」を補訂する。
|
| 3.2.7 |
|
「まことに残念なことに、本来の自分ではなくなってしまいましたよ」
|
「全然私のようでなくなってしまいましたよ」
|
【いと口惜しう】- 以下「はべりや」まで、柏木の返事。
|
| 3.2.8 |
とて、烏帽子ばかりおし入れて、すこし起き上がらむとしたまへど、いと苦しげなり。白き衣どもの、なつかしうなよよかなるをあまた重ねて、衾ひきかけて臥したまへり。御座のあたりものきよげに、けはひ香うばしう、心にくくぞ住みなしたまへる。 |
と言って、烏帽子だけを押し入れるように被って、少し起き上がろうとなさるが、とても苦しそうである。
白い着物で、柔らかそうなのをたくさん重ね着して、衾を引き掛けて臥していらっしゃる。
御座所の辺りをこぎれいにしていて、あたりに香が薫っていて、奥ゆかしい感じにお過ごしになっていた。
|
と言いながら、衛門督は烏帽子だけを身体の下へかって、少し起き上がろうとしたが、苦しそうであった。柔らかい白の着物を幾枚も重ねて、夜着を上に掛けているのである。病床の置かれた室は清潔に整理がされてあって感じがよい。
|
【烏帽子ばかりおし入れて】- 『完訳』は「烏帽子をとらぬのが、当時の礼儀。髪を押し入れるべくかぶる」と注す。源氏物語絵巻「柏木」第二段、参照。
|
|
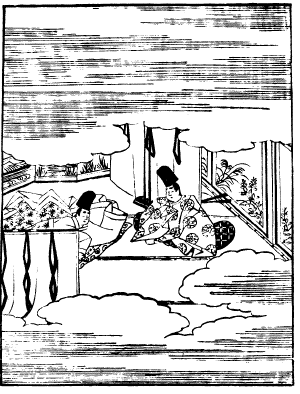 |
| 3.2.9 |
うちとけながら、用意ありと見ゆ。重く患ひたる人は、おのづから髪髭も乱れ、ものむつかしきけはひも添ふわざなるを、痩せさらぼひたるしも、いよいよ白うあてなるさまして、枕をそばだてて、ものなど聞こえたまふけはひ、いと弱げに、息も絶えつつ、あはれげなり。 |
くつろいだままながら、嗜みがあると見える。
重病人というものは、自然と髪や髭も乱れ、むさくるしい様子がするものだが、痩せてはいるが、かえって、ますます白く上品な感じがして、枕を立ててお話を申し上げなさる様子、とても弱々しそうで、息も絶え絶えで、見ていて気の毒そうである。
|
こんな場合にも規律の正しい病人の性格がうかがえるようであった。病人というものは髪や髭も乱れるにまかせて気味の悪い所もできてくるものであるが、この人の痩せ細った姿はいよいよ品のよい気がされて、枕から少し顔を上げてものを言う時には息も今絶えそうに見えるのが非常に哀れであった。
|
【うちとけながら、用意ありと見ゆ】- 『集成』は「くつろいだままながら、たしなみありげに」。『完訳』は「遠慮のいらぬ病人ながら嗜みを忘れていないと見える」と訳す。
【あてなるさまして】- 定家筆本と明融臨模本、大島本は「あてなる」とある。『集成』『新大系』は底本のままとする。『完本』は諸本に従って「あてはかなる」と「はか」を補訂する。
|
|
第三段 柏木、夕霧に遺言
|
| 3.3.1 |
|
「長らくご病気でいらっしゃったわりには、ことにひどくもやつれていらっしゃらないね。
いつものご容貌よりも、かえって素晴らしくお見えになります」
|
「御病気の長かったことから言えば、特別ひどく病人らしいお顔になったとも言えませんよ。平生よりも美男に見えますよ」
|
【久しう患ひたまへる】- 以下「見えたまふ」まで、夕霧の詞。
【そこなはれたまはざりけり】- 過去の助動詞「けり」詠嘆の意。
|
| 3.3.2 |
とのたまふものから、涙おし拭ひて、
|
とおっしゃるものの、涙を拭って
|
こんなことを口では言いながらも大将は涙をぬぐっていた。
|
|
| 3.3.3 |
|
「後れたり先立ったりすることなく死ぬ時は一緒にとお約束申していたのに。
ひどいことだな。
このご病気の様子を、何が原因でこうもご重態になられたのかと、それさえ伺うことができないでおります。
こんなに親しい間柄ながら、もどかしく思うばかりです」
|
「同じ時に死のうなどと約束もしたではありませんか。悲しいことですよ。あなたの症状は何がどうして悪くなったのだということも言ってくれる者がありませんから、親しい私でさえ何の御病気だか知らないのがたよりないことですよ」
|
【後れ先立つ】- 明融臨模本、朱合点。大島本、朱合点。古注では『異本紫明抄』が「末の露もとの雫や世の中の後れ先立つためしなるらむ」(古今六帖、雫。五九三)を指摘。現行の注釈書では『評釈』が指摘する。以下「おぼつかなくのみ」まで、夕霧の詞。
【何事にて重りたまふとだに、え聞き分きはべらず】- 『完訳』は「何が原因でこうも重態になられたのか、それさえうかがえない。後に柏木の告白を引き出す契機」と注す。
|
| 3.3.4 |
などのたまふに、
|
などとおっしゃると、
|
|
|
| 3.3.5 |
|
「わたし自身には、いつから重くなったのか分かりません。
どこといって苦しいこともありませんで、急にこのようになろうとは思ってもおりませんでしたうちに、月日を経ずに衰弱してしまいましたので、今では正気も失せたような有様で。
|
「自分ではいつ悪くなって行くかわからずに来ましたよ。どこか苦しいときまった患部もないものですから、病がこうまで早く進行するとも思わないうちに重態になってしまったのですから、私はもう今では何が何やら知覚もなくなっている気がしています。
|
【心には】- 以下「御徳にはべるべき」まで、柏木の詞。
【うつし心も失せたるやうに】- 『完訳』は「生きている心地もしないような有様で」と訳す。
|
| 3.3.6 |
惜しげなき身を、さまざまにひき留めらるる祈り、願などの力にや、さすがにかかづらふも、なかなか苦しうはべれば、心もてなむ、急ぎ立つ心地しはべる。
|
惜しくもない身を、いろいろとこの世に引き止められる祈祷や、願などの力でしょうか、そうはいっても生き永らえるのも、かえって苦しいものですから、自分から進んで、早く死出の道へ旅立ちたく思っております。
|
惜しくもない私の命が祈りとか、願とかの力でさすがに引きとめられていることは苦痛なものですから、自身から早くなるのを望むようにもなって変なものですよ。
|
|
| 3.3.7 |
|
そうは言うものの、この世の別れに、捨て難いことが数多くあります。
親にも孝行を十分せずに、今になって両親にご心配をおかけし、主君にお仕えすることも中途半端な有様で、わが身の立身出世を顧みると、また、なおさら大したこともない恨みを残すような世間一般の嘆きは、それはそれとして。
|
私とすればこの世から去ってしまうことで、いろいろな堪えがたい気持ちのすることもそれは少なくありません。親への孝行も中途までしかしてありませんし、私自身のためにも遺憾なことはありますが、
|
【親にも仕うまつりさし】- 「夫孝始於事親 中於事君 終於立身」(孝経)による表現。
【身を顧みる】- 『集成』「わが身を修めるという面ではもちろん」。『完訳』は「立身出世」と注す。
【大方の嘆き】- 『完訳』は「前述の孝・忠・立身の儒教的な徳目。権門の長子らしい発想だが、それをしりぞけ、あらためて心中の惑乱を告白しようとする」と注す。
|
| 3.3.8 |
また心の内に思ひたまへ乱るることのはべるを、かかる今はのきざみにて、何かは漏らすべきと思ひはべれど、なほ忍びがたきことを、誰にかは愁へはべらむ。これかれあまたものすれど、さまざまなることにて、さらにかすめはべらむも、あいなしかし。 |
また、心中に思い悩んでおりますことがございますが、このような臨終の時になって、どうして口に出そうかと思っておりましたが、やはり堪えきれないことを、あなたの他に誰に訴えられましょう。
誰彼と兄弟は多くいますが、いろいろと事情があって、まったく仄めかしたところで、何にもなりません。
|
そうしたいっさいのことよりも大事な煩悶を私はいだいているのです。この命の末になってほかへ洩らす必要はないとも思いますが、やはり自分一人だけで思っているには堪えられないのでもあるのです。身内の者はあっても、その人たちに言い出す勇気を私は持っていません。それであなたにだけ言わせていただきますが、
|
【何かは漏らすべきと思ひはべれど】- 「何かは--べき」反語表現。『集成』は「何で人に打ち明けてよいものかと思いますけれども」。『完訳』は「どうして口にすべきことかと存じますものの」と訳す。
|
| 3.3.9 |
六条院にいささかなる事の違ひ目ありて、月ごろ、心の内にかしこまり申すことなむはべりしを、いと本意なう、世の中心細う思ひなりて、病づきぬとおぼえはべしに、召しありて、院の御賀の楽所の試みの日参りて、御けしきを賜はりしに、なほ許されぬ御心ばへあるさまに、御目尻を見たてまつりはべりて、いとど世にながらへむことも憚り多うおぼえなりはべりて、あぢきなう思ひたまへしに、心の騷ぎそめて、かく静まらずなりぬるになむ。 |
六条院にちょっとした不都合なことがありまして、ここ幾月、心中密かに恐縮申していることがございましたが、まことに不本意なことで、世の中に生きて行くのも心細くなって、病気になったと思われたのですが、お招きがあって、朱雀院の御賀の楽所の試楽の日に参上して、ご機嫌を伺いましたところ、やはりお許しなさらないお気持ちの様子に、御目差しを拝見致しまして、ますますこの世に生き永らえることも憚り多く思われまして、どうにもならなく存じられましたが、魂がうろうろ離れ出しまして、このように鎮まらなくなってしまいました。
|
私が六条院様の感情をそこねているらしいことがありましてね、それを苦しんで心の中でお詫びをして暮らすうちに病気のようになってしまったのですが、お招きがありまして、あの法皇様の賀宴の試楽の日に伺いました時に、お目にかかったのですが、なお許していただけない御感情のあるのをお顔で私は知って、それからの私はもう生きていることがはばかりのあることのように思われ出して、憂鬱な気持ちで暮らして来たのですが、その際に受けた衝動が強かったために、起ちがたい衰弱に自分で自分を導いてしまったのですよ。
|
【あぢきなう思ひたまへしに】- 『集成』は「何もかも終りだと思いましたのがもとで」。『完訳』は「もうどうにもならぬといった気持になりましたが」と訳す。
|
| 3.3.10 |
人数には思し入れざりけめど、いはけなうはべし時より、深く頼み申す心のはべりしを、いかなる讒言などのありけるにかと、これなむ、この世の愁へにて残りはべるべければ、論なうかの後の世の妨げにもやと思ひたまふるを、ことのついではべらば、御耳留めて、よろしう明らめ申させたまへ。
|
一人前とはお考え下さいませんでしたでしょうが、幼うございました時から、深くお頼り申す気持ちがございましたが、どのような中傷などがあったのかと、このことが、この世の恨みとして残りましょうから、きっと来世への往生の妨げになろうかと存じますので、何かの機会がございましたら、お耳に止めて下さって、よろしく申し開きなさって下さい。
|
自身の無能なことは承知しながらも少年時代から深く御信頼して、誠心誠意この方のためにお尽くししようと決心していた私ですが、中傷した者でもあったろうかと、死んで残るこの問題への関心はむろん後世の往生の妨げになるだろうと思っていますが、何かの機会にこの話をあなたは覚えていてくださって六条院へ弁明の労を取ってください。
|
|
| 3.3.11 |
亡からむ後ろにも、この勘事許されたらむなむ、御徳にはべるべき」
|
死んだ後にも、このお咎めが許されたらば、あなたのお蔭でございましょう」
|
死にましてからでもこのお取りなしがいただければ私はあなたに感謝します」
|
|
| 3.3.12 |
などのたまふままに、いと苦しげにのみ見えまされば、いみじうて、心の内に思ひ合はすることどもあれど、さして確かには、えしも推し量らず。
|
などとおっしゃるうちに、たいそう苦しそうになって行くばかりなので、おいたわしくて、心中に思い当たることもいくつかあるが、どうしたことなのか、はっきりとは推量できない。
|
新大納言はこう語るうちにも病苦の堪えがたいもののある様子も見えて、大将は悲しんだのであるが、その話について思いあたることが、この人にあっても、不確かな断定はそれでできない気がした。
|
|
| 3.3.13 |
|
「どのような良心の呵責なのでしょうか。
全然、そのようなご様子もなく、このように重態になられた由を聞いて驚きお嘆きになっていること、この上もなく残念がり申されていたようでした。
どうして、このようにお悩みになることがあって、今まで打ち明けて下さらなかったのでしょうか。
こちらとあちらとの間に立って弁解して差し上げられたでしょうに。
今となってはどうしようもありません」
|
「あなた自身の誤解ではないのですか、少しもそんな御様子を私は見受けませんよ。あなたの御病気の重くなったことで御心配をしておられて、いつも遺憾がっておいでになりますよ。そんな煩悶をあなたがしておいでになるのなら、なぜ今までに私へ言ってくださらなかったのでしょう。私が及ばずながら双方の誤解を解いてあげるのでした。もう間に合いませんね」
|
【いかなる御心の鬼にかは】- 以下「今はいふかひなしや」まで、夕霧の詞。「かは」疑問の意。
【御けしき】- 「源氏物語絵巻」詞書に仮名表記で「おほむけしき」とある。「御けしき」を「おほむ--」と読む例。源氏の態度表情をさす。
【聞きおどろき嘆きたまふこと】- 主語は源氏。
|
| 3.3.14 |
とて、取り返さまほしう悲しく思さる。
|
と言って、昔を今に取り戻したくお思いになる。
|
取り返したいように大将は残念がった。
|
|
| 3.3.15 |
「げに、いささかも隙ありつる折、聞こえうけたまはるべうこそはべりけれ。されど、いとかう今日明日としもやはと、みづからながら知らぬ命のほどを、思ひのどめはべりけるもはかなくなむ。このことは、さらに御心より漏らしたまふまじ。さるべきついではべらむ折には、御用意加へたまへとて、聞こえおくになむ。 |
「おっしゃる通り、少しでも具合の良い時に、申し上げてご意見を承るべきでございました。
けれども、ほんとうに今日か明日かの命になろうとは、自分ながら分からない寿命のことを、悠長に考えておりましたのも、はかないことでした。
このことは、決してあなた以外にお漏らしなさらないで下さい。
適当な機会がございました折には、ご配慮戴きたいと申し上げて置くのです。
|
「そうですよ。少し快い時もあったのですから、そんな時に御相談をすればよかったのです。自分自身でわからないのが命にもせよ、まさかこんなに早く終わろうとは思わなかったというのもはかないわけですね。このことは絶対にだれへもお話しにならないでください。よい機会に私のために御好意のある弁解をしていただきたいと思ってお話ししただけです。
|
【げに、いささかも】- 以下「つくろひたまへ」まで、柏木の詞。
【今日明日としもやはと】- 明融臨模本、付箋「今日不知死明日不知死何故造作栖安穏無常身」とある。大島本、朱合点、行間書入「つゐにゆく道と」。古注では、『源氏釈』が「ついにゆくみちとはかねてきゝしかと昨日今日とはおもはさりしを」(古今集哀傷、八六一、業平朝臣)を指摘。現行の注釈書では指摘しない。
|
| 3.3.16 |
一条にものしたまふ宮、ことに触れて訪らひきこえたまへ。
心苦しきさまにて、院などにも聞こし召されたまはむを、つくろひたまへ」
|
一条の邸にいらっしゃる宮を、何かの折にはお見舞い申し上げて下さい。
お気の毒な様子で、父院などにおかれても御心配あそばされるでしょうが、よろしく計らって上げて下さい」
|
一条にいらっしゃる宮様には何かの時に御好意を寄せてあげてください。お聞きになって法皇様が御心配をあそばさないように、御生活の上のことも気をつけてあげてください」
|
|
| 3.3.17 |
などのたまふ。
言はまほしきことは多かるべけれど、心地せむかたなくなりにければ、
|
などとおっしゃる。
言いたいことは多くあるに違いないようだが、気分がどうにもならなくなってきたので、
|
などとも大納言は言った。もっと言いたいことは多かったであろうが、我慢のならぬほど苦しくなった衛門督は、
|
|
| 3.3.18 |
|
「お出になって下さい」
|
もう帰れ
|
【出でさせたまひね】- 柏木の詞。『完訳』は「臨終の近さを知り、夕霧への失礼がないように帰邸を促す」と注す。
|
| 3.3.19 |
と、手かききこえたまふ。加持参る僧ども近う参り、上、大臣などおはし集りて、人びとも立ち騒げば、泣く泣く出でたまひぬ。 |
と、手真似で申し上げなさる。
加持を致す僧たちが近くに参って、母上、大臣などがお集まりになって、女房たちも立ち騒ぐので、泣く泣くお立ちになった。
|
と手を振って見せた。加持をする僧などが近くへ来て、母の夫人や大臣も出てくるふうで、騒がしくなったので大将は泣く泣く辞し去った。
|
【と、手かききこえたまふ】- と、手真似でお促し申し上げなさる、意。
|
|
第四段 柏木、泡の消えるように死去
|
| 3.4.1 |
|
女御は申し上げるまでもなく、この大将の御方などもひどくお嘆きになる。
思ひやりが、誰に対しても兄としての面倒見がよくていらっしゃったので、右の大殿の北の方も、この君だけを親しい人とお思い申し上げていらしたので、万事にお嘆きになって、ご祈祷などを特別におさせになったが、薬では治らない病気なので、何の役にも立たないことであった。
女宮にも、とうとうお目にかかることがおできになれないで、泡が消えるようにしてお亡くなりになった。
|
同胞である院の女御はもとより、妹の一人である大将夫人も衛門督のことを非常に歎いていた。だれのためにもよき兄であろうとする善良な性格であったから、右大臣夫人などもこの人とだけは今まで非常に親しんでいて、今度も玉鬘は心配のあまり自身の手でも祈祷をさせていたが、そうしたことも不死の薬ではなかったから効果は見えなかった。夫人の宮にもしまいにお逢いできないままで、泡が消えたように衛門督は死んでしまった。
|
【女御をばさらにも聞こえず、この大将の御方なども】- 柏木と同腹の弘徽殿女御はいうまでもなく、異腹の雲居雁も、のニュアンス。
【心おきての、あまねく】- 『集成』は「柏木は、気立てが、誰にも分け隔てせず、兄貴分然とした面倒見のいいお方だったので」と訳す。
【右の大殿の北の方】- 鬚黒右大臣。その北の方、玉鬘をいう。
【やむ薬ならねば】- 定家本、付箋「我こそや見ぬ人こふるくせつけれあふよりほかのやむくすりなし」(拾遺集恋一、六六五、読人しらず)。明融臨模本、朱合点、付箋「我こそや(は)みぬ人こふるくせつけれあふより外のやむくすりなし」。大島本、朱合点、行間書入、朱「われこそはみぬ人こふるくせつけれ」とある。中山家本、朱合点、奥入、同歌指摘。『源氏釈』(抄・前)が指摘し、現行の注釈書でも指摘する。
【泡の消え入るやうに】- 明融臨模本、朱合点、付箋「水の泡のきえてうき身と知なから流て猶もたのまるゝ哉/世皆不牢固如水沫泡□法花/幻世春来夢浮世水上泡白氏」。大島本、朱合点、行間書入「古今 水の泡の消てうき世とありなからなかれて猶もたのまるゝかな」(古今集恋五、七九二、友則)。『異本紫明抄』が指摘し、現行の注釈書でも指摘する。
|
| 3.4.2 |
年ごろ、下の心こそねむごろに深くもなかりしか、大方には、いとあらまほしくもてなしかしづききこえて、気なつかしう、心ばへをかしう、うちとけぬさまにて過ぐいたまひければ、つらき節もことになし。ただ、 |
長年の間、心底から真心こめて愛していたのではなかったが、表面的には、まことに申し分なく大事にお世話申し上げて、素振りもお優しく、気立てもよく、礼節をわきまえてお過ごしになられたので、辛いと思った事も特にない。
ただ、
|
今まで愛情の点では批議すべき点もあったが、形式的にはよく御待遇をして、あくまで御降嫁を得た夫人として敬意を失わない優しい良人であったのであるから、恨めしい思いを格別宮は抱いておいでにならなかった。
|
【年ごろ】- 『完訳』は「以下、宮が柏木との結婚生活を回顧。柏木が心からは宮を愛さなかったが」と注す。
【うちとけぬさまにて】- 『集成』は「けじめ正しい態度で終始されたので。柏木の、落葉の宮に対して礼を失わなかったさま」。『完訳』は「礼儀をわきまえたお扱いを受けてお過しになったのだから」と注す。
|
| 3.4.3 |
|
「このように短命なお方だったので、不思議なことに普通の生活を面白くなくお思いであったのだわ」
|
こんな短命で終わる人であったから何にも興味が持てない寂しいふうを見せたのであったか
|
【かく短かりける御身にて】- 以下「思ひたまへけるなりけり」まで、落葉の宮の心中。
【なべての世すさまじう思ひたまへけるなりけり】- 「世」について、『集成』は「何でもこの世の中のことをおもしろくなくお思いだったのだろう」。『完訳』は「世間並の夫婦仲をおもしろくなくお思いだったのかと」と訳す。
|
| 3.4.4 |
と思ひ出でたまふに、いみじうて、思し入りたるさま、いと心苦し。
|
とお思い出されると、悲しくて、沈み込んでいらっしゃる様子、ほんとうにおいたわしい。
|
と追想あそばされるのが悲しかった。
|
|
| 3.4.5 |
御息所も、「いみじう人笑へに口惜し」と、見たてまつり嘆きたまふこと、限りなし。
|
母御息所も、「大変に外聞が悪く残念だ」と、拝見しお嘆きになること、この上もない。
|
御息所も早く不幸な未亡人に宮のおなりになったことを悲しんでいた。
|
|
| 3.4.6 |
|
大臣や、北の方などは、それ以上に何とも言いようがなく、
|
衛門督の死で大臣と夫人はまして言いようもない、悲歎に沈んでいた。
|
【大臣、北の方】- 明融臨模本、付箋「或説清慎公(致仕大臣)の敦敏(柏木)の少将にをくれ給へるに准す末の御子廉義公の□をは廉義公に准世継に東のかたより敦忠少将のうせ給へるともしらて馬を奉たりけれはおとゝ清慎公(小野宮)またしらぬ人もありけり東ちに我も行てそすむへかりける」と指摘。
|
| 3.4.7 |
「我こそ先立ため。世のことわりなうつらいこと」 |
「自分こそ先に死にたいものだ。
世間の道理もあったものでなく辛いことよ」
|
自分が先に死ぬのが当然なことであるのに、あまりにも道理にはずれた死である
|
【我こそ】- 以下「つらいこと」まで、両親の嘆きの詞。
|
| 3.4.8 |
と焦がれたまへど、何のかひなし。
|
と恋い焦がれなさったが、何にもならない。
|
と泣きこがれているが、それが何のかいのあることとも見えなかった。
|
|
| 3.4.9 |
尼宮は、おほけなき心もうたてのみ思されて、世に長かれとしも思さざりしを、かくなむと聞きたまふは、さすがにいとあはれなりかし。 |
尼宮は、大それた恋心も不愉快なこととばかりお思いなされて、長生きして欲しいともお思いではなかったが、このように亡くなったとお聞きになると、さすがにかわいそうな気がした。
|
女三の宮は衛門督の恋を苦しくばかりお思いになって、長く生きていようとお望みにならなかったのであるが、死の報をお得になってはさすがに物哀れなお気持ちになった。
|
【かくなむと】- 柏木が死んだということをさす。
【いとあはれなりかし】- 『完訳』は「柏木逝去の報に接すると、さすがに愛憐の情が起る」と注す。
|
| 3.4.10 |
「若君の御ことを、さぞと思ひたりしも、げに、かかるべき契りにてや、思ひのほかに心憂きこともありけむ」と思し寄るに、さまざまもの心細うて、うち泣かれたまひぬ。 |
「若君のご誕生を、自分の子だと思っていたのも、なるほど、こうなるはずの運命であってか、思いがけない辛い事もあったのだろう」とお考えいたると、あれこれと心細い気がして、お泣きになった。
|
若君を自身の子のように衛門督は思っていたが、衛門督の死におあいになってみると、神秘なかかわりもある気があそばされて、衛門督が信じていたことがほんとうであったかもしれぬとお思われになり、いよいよ御自身の運命の悲しさにお泣きになるのであった。
|
【若君の御ことを】- 以下「こともありけむ」まで、女三の宮の心中。
【さぞと】- 自分(柏木)の子だと、の意。
|
|
第四章 光る源氏の物語 若君の五十日の祝い
|
|
第一段 三月、若君の五十日の祝い
|
| 4.1.1 |
|
三月になると、空の様子もどことなく麗かな感じがして、この若君、五十日のほどにおなりになって、とても色白くかわいらしくて、日数の割に大きくなって、おしゃべりなどなさる。
大殿がお越しになって、
|
三月になると空もうららかな日が続き、六条院の若君の五十日の祝い日も来た。色が白くて、美しいかわいい子でもう声を出して笑ったりするのであった。院がおいでになって、
|
【弥生になれば、空のけしきもものうららかにて】- 季節は晩春三月になる。『完訳』は「晩春のはなやぐ情景に転じる」と注す。
【五十日のほどになりたまひて】- 柏木、生後五十日ほどになる。五十日の祝いがある。
|
| 4.1.2 |
|
「ご気分は、さっぱりなさいましたか。
いやもう、
何とも張り合いのないことだな。普通のお姿で、このようにお祝い申し上げるのであるならば、ど
んなにか嬉しいことであろうに。残念なこ
|
「もうさっぱりした気分になりましたか。でも御恢復になったかいもありませんね。今までのあなたでこうして快くおなりになったのを見ることができたらどんなにうれしいだろう。あなたは冷酷に私を捨てておしまいになりましたね」
|
【御心地は】- 以下「思し捨てけること」まで、源氏の詞。
【見なしたてまつらましかば】- 「ましかば--まし」の反実仮想の構文。
|
| 4.1.3 |
と、涙ぐみて怨みきこえたまふ。
日々に渡りたまひて、今しも、やむごとなく限りなきさまにもてなしきこえたまふ。
|
と、涙ぐんでお恨み申し上げなさる。
毎日お越しになって、今になって、この上なく大切にお世話申し上げなさる。
|
と涙ぐんで恨みをお言いになった。毎日こちらの御殿へおいでにならぬ日はなくなって、こうした今になって最上のお扱いをあそばされるのであった。
|
|
| 4.1.4 |
御五十日に餅参らせたまはむとて、容貌異なる御さまを、人びと、「いかに」など聞こえやすらへど、院渡らせたまひて、
|
五十日の御祝いに餅を差し上げなさろうとして、尼姿でいられるご様子を、女房たちは、「どうしたものか」とお思い申して躊躇するが、院がお越しあそばして、
|
五十日の儀式に母君が尼姿でおいでになるのは、若君の将来を祝うことに不都合ではないかという意見をもつ女房たちもあって、どうしようかと言われているところへ院がおいでになって、
|
|
| 4.1.5 |
「何か。女にものしたまはばこそ、同じ筋にて、いまいましくもあらめ」 |
「何のかまうことはない。
女の子でいらっしゃったら、同じ事で、縁起でもなかろうが」
|
「少しもさしつかえない。若君が女であれば母君の運命にあやかってはならないとも考慮すべきだが」
|
【何か】- 以下「あらめ」まで、源氏の詞。
|
| 4.1.6 |
とて、南面に小さき御座などよそひて、参らせたまふ。御乳母、いとはなやかに装束きて、御前のもの、いろいろを尽くしたる籠物、桧破籠の心ばへどもを、内にも外にも、もとの心を知らぬことなれば、取り散らし、何心もなきを、「いと心苦しうまばゆきわざなりや」と思す。 |
と言って、南面に小さい御座所などを設定して、差し上げなさる。
御乳母は、とても派手に衣装を着飾って、御前の物、色々な色彩を尽くした籠物、桧破子の趣向の数々を、御簾の中でも外でも、本当の事は知らないことなので、とり散らかして、無心にお祝いしているのを、「まことに辛く目を背けたい」とお思いになる。
|
とお言いになり、南向きの座敷に若君の小さい席を設けて祝い膳が供えられた。新しい乳母たちは皆はなやかな服装をしていて、お膳部から女房たちのためのお料理の盛られた器まで皆きれいな感じのする式場であった。真相を知らぬ人々の寄贈したおびただしい祝品のあるのを御覧になっても、この誤りを正しくしがたい心苦しさから恥ずかしくばかりおなりになる院であった。
|
【もとの心】- 『完訳』は「若君が柏木の実子という真相」と注す。
【いと心苦しう】- 明融臨模本、付箋「柏木喪の説入ホカ也不用ー」と指摘。以下「わざなりや」まで、源氏の心中。『集成』は「とても見るに見かねる面映ゆいことよ」。『完訳』は「つらく、目をそむけたい思い。盛儀に酔う人々のなかで、源氏の心は醒めて、宮の罪をも許せない」と注す。
|
|
第二段 源氏と女三の宮の夫婦の会話
|
| 4.2.1 |
宮も起きゐたまひて、御髪の末の所狭う広ごりたるを、いと苦しと思して、額など撫でつけておはするに、几帳を引きやりてゐたまへば、いと恥づかしうて背きたまへるを、いとど小さう細りたまひて、御髪は惜しみきこえて、長う削ぎたりければ、後ろは異にけぢめも見えたまはぬほどなり。 |
宮もお起きなさって、御髪の裾がいっぱいに広がっているのを、とてもうるさくお思いになって、額髪などを撫でつけていらっしゃる時に、御几帳を引き動かしてお座りになると、とても恥ずかしい思いで顔を背けていらっしゃるが、ますます小さく痩せ細りなさって、御髪は惜しみ申されて、長くお削ぎになってあるので、後姿は格別普通の人と違ってお見えにならない程である。
|
尼宮も起きておいでになった。切りそろえられた髪の尖が厚くいっぱいに拡がるのを苦しくお思いになり、額の毛などを後ろへなでつけておいでになる時に、院は几帳を横へ寄せてそこへおすわりになると、宮は羞じて横のほうへお向きになったが、以前よりもいっそう小柄にお見えになって、髪は授戒の日にお扱いした僧が惜しんで長く残すようにして切ったのであるから、ちょっと見ては普通の方のように思われた。
|
【御髪の末の所狭う広ごりたるを】- 尼削ぎの裾が広がっている様子。
【背きたまへるを】- 定家筆本と明融臨模本は「そむきたまへるを」とある。大島本は「そむかせ給へる」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「背きたまへる」と「を」を削除する。『新大系』は底本(大島本)のままとする。
|
| 4.2.2 |
すぎすぎ見ゆる鈍色ども、黄がちなる今様色など着たまひて、まだありつかぬ御かたはらめ、かくてしもうつくしき子どもの心地して、なまめかしうをかしげなり。
|
次々と重なって見える鈍色の袿に、黄色みのある今流行の紅色などをお召しになって、まだ尼姿が身につかない御横顔は、こうなっても可憐な少女のような気がして、優雅で美しそうである。
|
次々に濃くした鈍の幾枚かをお重ねになった下には黄味を含んだ淡色の単衣をお着になって、まだ尼姿になりきってはお見えにならず、美しい子供のような気がしてこれが最もよくお似合いになる姿であるとも艶に見えた。
|
|
| 4.2.3 |
|
「まあ、何と情けない。
墨染の衣は、やはり、まことに目の前が暗くなる色だな。
このようになられても、お目にかかることは変わるまいと、心を慰めておりますが、相変わらず抑え難い心地がする涙もろい体裁の悪さを、実にこのように見捨てられ申したわたしの悪い点として思ってみますにつけても、いろいろと胸が痛く残念です。
昔を今に取り返すことができたらな」
|
「墨染めという色は少し困りますね。どうしても悲しい色でね、目がくらむ気がします。こうおなりになってもいっしょに暮らすことができるのだからと思って、みずから慰めようとしていますが、まだ今でも涙だけはあきらめてくれずに流れ出すので困りますよ。こんなふうにあなたに捨てられたのも、私自身の罪であると考えられることも苦痛のきわみですよ。取り返せないものだろうか」
|
【いで、あな心憂】- 以下「取り返す物にもがなや」まで、源氏の詞。
【思ひ捨てられたてまつる身の咎に思ひなすも】- 『集成』は「ほんとにこうして見捨てられ申した私の悪い点と思ってみますにつけても。未練がましいところがあるから、あなたから見捨てられたのだろう、の意」と注す。
【取り返すものにもがなや】- 明融臨模本、朱合点。大島本、朱合点、行間書入「古今とりかへす物にもかなや世中を」。中山家本、朱合点、奥入「とりかへすものにもかなやよのなかを」。『源氏釈』が「とりかへすものにもかなやいにしへをありしなからのわか身と思はん」(前田家本所引、出典未詳)と指摘する。
|
| 4.2.4 |
と、うち嘆きたまひて、
|
とお嘆きになって、
|
と院は御歎息をあそばして、
|
|
| 4.2.5 |
|
「もうこれっきりとお見限りなさるならば、本当に本心からお捨てになったのだと、顔向けもできず情けなく思われることです。
やはり、いとしい者と思って下さい」
|
「ほんとうの尼の気持ちになっておしまいになれば、それは病気のためでなく、私がいやにおなりになったためにそうおなりになった気もして、私は情けないでしょうよ。やはり私を愛してください」
|
【今はとて】- 以下「あはれと思せ」まで、源氏の詞。『完訳』は「宮が六条院から他所へ出る不都合さを思う。源氏には朱雀院への義理、宮への執着がある」と注す。
【なほ、あはれと思せ】- 『完訳』は「自分を捨てないでほしい気持」と注す。
|
| 4.2.6 |
と聞こえたまへば、
|
と申し上げなさると、
|
こうお言いになると、
|
|
| 4.2.7 |
「かかるさまの人は、もののあはれも知らぬものと聞きしを、ましてもとより知らぬことにて、いかがは聞こゆべからむ」 |
「このような出家の身には、もののあわれもわきまえないものと聞いておりましたが、ましてもともと知らないことなので、どのようにお答え申し上げたらよいでしょうか」
|
「この境地にいては人を愛したりすることができないものだと聞いていますもの、まして私などは初めから愛するということがわからなかったのですから、どうお返事を申し上げればいいか存じません」
|
【かかるさまの人は】- 以下「いかがは聞こゆべからむ」まで、女三の宮の返事。反語表現。何とも申し上げようがない、意。
|
| 4.2.8 |
とのたまへば、
|
とおっしゃるので、
|
と宮はお返辞をあそばされる。
|
|
| 4.2.9 |
|
「情けないことだ。
お分りになることがおありでしょうに」
|
「しかたのない方ですね、おわかりになることもあるでしょうが」
|
【かひなのことや】- 以下「あらむものを」まで、源氏の詞。痛烈な皮肉がまじる。
【思し知る方もあらむものを】- 『集成』は「柏木とは愛を交わしたではないか、という気持」。『完訳』は「柏木と心交したのに、の気持」と注す。
|
| 4.2.10 |
とばかりのたまひさして、若君を見たてまつりたまふ。
|
とだけ途中までおっしゃって、若君を拝見なさる。
|
と言いさしたまま院は言葉をお切りになって、若君を見ようとあそばされた。
|
|
|
第三段 源氏、老後の感懐
|
| 4.3.1 |
御乳母たちは、やむごとなく、めやすき限りあまたさぶらふ。
召し出でて、仕うまつるべき心おきてなどのたまふ。
|
御乳母たちは、家柄が高く、見た目にも無難な人たちばかりが大勢伺候している。
お呼び出しになって、お世話申すべき心得などをおっしゃる。
|
乳母には貴族の出の人ばかりが何人も選ばれて付いていた。その人たちを呼び出して、若君の取り扱いについての注意をお与えに院はなるのであった。
|
|
| 4.3.2 |
|
「ああかわいそうに、残り少ない晩年に、ご成人して行くのだな」
|
「かわいそうに未来の少ない老いた父を持って、おくればせに大きくなってゆこうとするのだね」
|
【あはれ、残り少なき世に、生ひ出づべき人にこそ】- 源氏の詞。独言。 【生ひ出づべき人に】-明融臨模本、朱合点。『孟津抄』は「いまさらに何生ひ出づらむ竹の子の憂きふししげきよとは知らずや」(古今集雑下、九五七、凡河内躬恒)を指摘。
|
| 4.3.3 |
とて、抱き取りたまへば、いと心やすくうち笑みて、つぶつぶと肥えて白ううつくし。
大将などの稚児生ひ、ほのかに思し出づるには似たまはず。
女御の御宮たち、はた、父帝の御方ざまに、王気づきて気高うこそおはしませ、ことにすぐれてめでたうしもおはせず。
|
と言って、お抱きになると、とても人見知りせずに笑って、まるまると太っていて色白でかわいらしい。
大将などが幼い時の様子、かすかにお思い出しなさるのには似ていらっしゃらない。
明石女御の宮たちは、それはそれで、父帝のお血筋を引いて、皇族らしく高貴ではいらっしゃるが、特別優れて美しいというわけでもいらっしゃらない。
|
と言って、お抱き取りになると、若君は快い笑みをお見せした。よく肥って色が白い。大将の幼児時代に思い比べてごらんになっても似ていない。女御の宮方は皆父帝のほうによく似ておいでになって、王者らしい相貌の気高いところはあるが、ことさらお美しいということもないのに、
|
|
| 4.3.4 |
この君、いとあてなるに添へて、愛敬づき、まみの薫りて、笑がちなるなどを、いとあはれと見たまふ。思ひなしにや、なほ、いとようおぼえたりかし。ただ今ながら、眼居ののどかに恥づかしきさまも、やう離れて、薫りをかしき顔ざまなり。 |
この若君、とても上品な上に加えて、かわいらしく、目もとがほんのりとして、笑顔がちでいるのなどを、とてもかわいらしいと御覧になる。
気のせいか、やはり、とてもよく似ていた。
もう今から、まなざしが穏やかで人に優れた感じも、普通の人とは違って、匂い立つような美しいお顔である。
|
この若君は貴族らしい上品なところに愛嬌も添っていて、目つきが美しくよく笑うのを御覧になりながら院は愛情をお感じになった。思いなしか知らぬが故衛門督によく似ていた。これほどの幼児でいてすでに貴公子らしいりっぱな眼眸をして艶な感じを持っていることも普通の子供に違っているのである。
|
【思ひなしにや、なほ、いとようおぼえたりかし】- 『集成』は「そう思って見るせいか、やはりとてもよく柏木に似ていることだ。源氏の心をそのまま地の文としたもの」。『完訳』は「気のせいか、やはり柏木に似ている。源氏の心中に即した叙述」と注す。
|
|
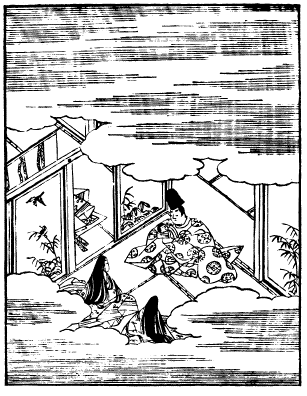 |
| 4.3.5 |
|
宮はそんなにもお分りにならず、女房たちもまた、全然知らないことなので、ただお一方のご心中だけが、
|
母の宮はそうであるとも確かにはわかっておいでにならなかったし、その他の人はもとより気のつかぬことであったから、ただ院お一人の心の中だけで、
|
【ただ一所の御心】- 源氏をさす。
|
| 4.3.6 |
|
「ああ、はかない運命の人であったな」
|
哀れな因縁である
|
【あはれ、はかなかりける人の契りかな】- 源氏の心中。
|
| 4.3.7 |
|
とお思いになると、世間一般の無常の世も思い続けられなさって、涙がほろほろとこぼれたのを、今日の祝いの日には禁物だと、拭ってお隠しになる。
|
と故人のことを考えておいでになると、人生の無常さも次々に思われて涙のほろほろとこぼれるのを、今日は祝いの式ではないかと恥じてお隠しになり
|
【今日は言忌みすべき日を】- 源氏の心中。
|
| 4.3.8 |
|
「静かに思って嘆くことに堪へた」
|
『五十八翁方有後静思堪喜亦堪嗟』
|
【静かに思ひて嗟くに堪へたり】- 明融臨模本、朱合点、付箋「いとふにたえんとかきたり不用之」、付箋「五十八翁方有後静思堪喜亦堪嗟持盃祝願無他語慎勿頑愚似汝爺白」(白氏文集巻二十八、自嘲)。尊経閣文庫本奥入・明融臨模本奥入・自筆本奥入、同詩句を指摘。ただし、尊経閣文庫本系統奥入は「白楽天は子なくして老にのそむ人也五十八にてはしめて男子むまれたりむまるゝ事をそきによりて生遅と名つくその子にむかひてつくりける詩也」(尊・明・大・中)、自筆本奥入は「白楽天は子なくして老にのそむ人也おいのゝちはしめて生遅といふ子いてきてむまるゝ事をそきによりて(名を傍書)生遅とつけたりその子にむかひてつくりける詩也」とある。『源氏釈』は「此身何足恋万劫煩悩之恨此身何足厭一聚虚空之庵/文集/又云堪□云」(白氏文集巻十一、逍遥詠)と指摘。
|
| 4.3.9 |
|
と、朗誦なさる。
五十八から十とったお年齢だが、晩年になった心地がなさって、まことにしみじみとお感じになる。
「おまえの父親に似るな」とでも、お諌めなさりたかったのであろうよ。
|
とお歌いになった。五十八から十を引いたお年なのであるが、もう晩年になった気があそばされて白楽天のその詩の続きの『慎勿頑愚似汝爺』を歌いたく思召したかもしれない。
|
【心地したまひて】- 大島本、行間書入「白楽天子生遅にむかひてつくれる詩云五十八翁方有後静思堪喜又堪嗟持盃祝願無他語慎勿頑愚似汝爺」とある。
【汝が爺に」とも、諌めまほしう思しけむかし】- 明融臨模本、朱合点。『一葉抄』は「双紙詞也」と指摘。『集成』は「「汝が爺に」(そちの実の父、柏木の轍を踏むでないぞ)とでも、いましめたくお思いになったことであろうよ。前引の詩中の句による草子地」。『完訳』は「実父柏木に似てはならぬと、源氏は思ったはず。前引の漢詩によって、語り手が推測」と注す。
|
|
第四段 源氏、女三の宮に嫌味を言う
|
| 4.4.1 |
|
「この事情を知って人、女房の中にもきっといることだろう。
知らないのは、悔しい。
馬鹿だと思っているだろう」、と穏やかならずお思いになるが、「自分の落度になることは堪えよう。
二つを問題にすれば、女宮のお立場が、気の毒だ」
|
あの秘密にあずかった者がここの女房の中にいるはずである。その人たちは自分を愚人として侮蔑しているのであろうとお思われになることは不快であったが、自分のことは忍んでもよいが、宮をその人たちはどう思っているかという点までを思うと、宮のためにおかわいそうである
|
【このことの心知れる人】- 以下「見るらむ」まで、源氏の心中。
【わが御咎ある】- 以下「いとほしけれ」まで、源氏の心中。
【二つ言はむには、女の御ため】- 『集成』は「男と女、双方どちらかと言おうなら」。『完訳』は「自分と宮のどちらかといえば」と訳す。
|
| 4.4.2 |
|
などとお思いになって、顔色にもお出しにならない。
とても無邪気にしゃべって笑っていらっしゃる目もとや、口もとのかわいらしさも、「事情を知らない人はどう思うだろう。
やはり、父親にとてもよく似ている」、と御覧になると、「ご両親が、せめて子供だけでも残してくれていたらと、お泣きになっていようにも、見せることもできず、誰にも知られずはかない形見だけを残して、あれほど高い望みをもって、優れていた身を、自分から滅ぼしてしまったことよ」
|
などと院はお思いになって、あくまでも知らぬ顔を続けておいでになるのであった。無邪気にうれしそうな声をたてる若君の目つき、口つきは知らぬ人にわからぬことであろうが、自分が見れば全くよく似ているとお思いになる院は、親たちが子供でもあればよかったと言って悲しんでいるのに、これを見せてやることもできず、秘密な所にこの子だけを形見に残して、あの思い上がった男が、自身の心から命を縮めて死んだかと衛門督が哀れ
|
【いと何心なう】- 若君(薫)の無邪気な表情。
【心知らざらむ人は】- 以下「似通ひたりけり」まで、源氏の心中。
【親たちの】- 以下「失ひつるよ」まで、源氏の心中。
【子だにあれかしと】- 明融臨模本、付箋「結をくかたみの子たに」と指摘。「結び置きし形見のこだになかりせば何に忍ぶの草を摘ままし」(後撰集雑二、一一八七、兼忠朝臣の母の乳母)。
【さばかり思ひ上がり】- 『完訳』は「柏木の気位高くすぐれた人柄を回想し、その自滅の運命を思う」と注す。
|
| 4.4.3 |
と、あはれに惜しければ、めざましと思ふ心もひき返し、うち泣かれたまひぬ。
|
と、しみじみと惜しまれるので、けしからぬと思う気持ちも思い直されて、つい涙がおこぼれになった。
|
にお思われになって、失敬なことであると罪を憎んでおいでになった感情も消え、泣かれておしまいになるのであった。
|
|
| 4.4.4 |
人びとすべり隠れたるほどに、宮の御もとに寄りたまひて、
|
女房たちがそっと席をはずした間に、宮のお側に近寄りなさって、
|
女房たちがいつの間にかお居間を出てしまったのを御覧になってから、院は宮の近くへお寄りになって、
|
|
| 4.4.5 |
「この人をば、いかが見たまふや。かかる人を捨てて、背き果てたまひぬべき世にやありける。あな、心憂」 |
「この子を、どのようにお思いになりますか。
このような子を見捨てて、出家なさらねばならなかったものでしょうか。
何とも、
|
「この人を何と思うのですか、こんなにかわいい人を置いて、この世をよくも捨てられましたね。冷酷ですよ」
|
【この人をば】- 以下「あな心憂」まで、源氏の詞。
|
| 4.4.6 |
と、おどろかしきこえたまへば、顔うち赤めておはす。
|
と、ご注意をお引き申し上げなさると、顔を赤くしていらっしゃる。
|
と不意にお言いかけになった。宮は顔を赤めておいでになった。
|
|
| 4.4.7 |
|
「いったい誰が種を蒔いたのでしょうと人が尋ねたら
誰と答えてよいのでしょう、
|
たが世にか種は蒔きしと人問はば
いかが岩根の松は答へん
|
【誰が世にか種は蒔きしと人問はば--いかが岩根の松は答へむ】- 源氏の贈歌。「岩根」に「言はね」を響かす。「松」は若君(薫)を喩える。明融臨模本、付箋「あつさ弓いそへの小松たか世にか万代かけて種をまきけむ」(古今集雑上、九〇七、読人しらず)。『異本紫明抄』が指摘する。
|
| 4.4.8 |
あはれなり」
|
不憫なことだ」
|
かわいそうですよ」
|
|
| 4.4.9 |
など、忍びて聞こえたまふに、御いらへもなうて、ひれふしたまへり。
ことわりと思せば、しひても聞こえたまはず。
|
などと、そっと申し上げなさると、お返事もなくて、うつ臥しておしまいになった。
もっともなことだとお思いになるので、無理に催促申し上げなさらない。
|
ともそっとお言いになったが、宮はお返辞もあそばさずにひれ伏しておしまいになった。もっともであるとお思いになって、しいてものをお言わせしようともあそばされない。
|
|
| 4.4.10 |
|
「どうお思いでいるのだろう。
思慮深い方ではいらっしゃらないが、どうして平静でいられようか」
|
どんなお気持ちでおられるのであろう、奥深い感情などは持っておられぬが、虚心平気でおいでにはなれないはずである
|
【いかに思すらむ】- 以下「いかでかはただには」まで、源氏の心中。女三の宮の心中を推測。『集成』は「どうして平気でおいでになれよう。柏木の死に悲しい思いでいられるだろう、というほどの意」。『完訳』は「宮が柏木の死を平静に受けとめているはずがない、の意」と注す。
|
| 4.4.11 |
|
と、ご推察申し上げなさるのも、とてもおいたわしい思いである。
|
と想像ができるのも心苦しいことであった。
|
【いと心苦しうなむ】- 『集成』は「とてもおいたわしい思いだ」。『完訳』は「まったくせつないことではある」と訳す。
|
|
第五段 夕霧、事の真相に関心
|
| 4.5.1 |
大将の君は、かの心に余りて、ほのめかし出でたりしを、
|
大将の君は、あの思い余って、ちらっと言い出した事を、
|
大将は衛門督が思い余って自分に洩らしたことはどんな訳のあることであろう。
|
|
| 4.5.2 |
「いかなることにかありけむ。すこしものおぼえたるさまならましかば、さばかりうち出でそめたりしに、いとようけしきは見てましを。いふかひなきとぢめにて、折悪しういぶせくて、あはれにもありしかな」 |
「どのような事であったのだろうか。
もう少し意識がはっきりしている状態であったならば、あれほど言い出した事なのだから、十分に事情が察せられたろうに。
何とも言いようのない最期であったので、折も悪くはっきりしないままで、残念なことであったな」
|
故人があれほどまで弱っていない時であったなら、自身から言い出したことなのであるから、もう少し核心に触れたことも聞き出せたであろうが、もうあの際であったのがおりを得ないことで残念であった
|
【いかなることにか】- 以下「ありしかな」まで、夕霧の心中。
【ましかば--ましを】- 反実仮想の構文。
|
| 4.5.3 |
と、面影忘れがたうて、兄弟の君たちよりも、しひて悲しとおぼえたまひけり。
|
と、その面影が忘れることができなくて、兄弟の君たちよりも、特に悲しく思っていらっしゃった。
|
などと考えていて、兄弟たち以上にこの人は故人を恋しがっていた。
|
|
| 4.5.4 |
「女宮のかく世を背きたまへるありさま、おどろおどろしき御悩みにもあらで、すがやかに思し立ちけるほどよ。また、さりとも、許しきこえたまふべきことかは。 |
「女宮がこのように出家なさった様子、大したご病気でもなくて、きれいさっぱりとご決心なさったものよ。
また、そうだからといって、お許し申し上げなさってよいことだろうか。
|
女三の宮がにわかに出家を遂げられたことも何か訳のあることらしい、そう大病でもおありにならなかった方を、院が何の抗議もあそばされずに尼にさせておしまいになってよいはずはないのである。
|
【女宮のかく世を】- 以下「たまへるものを」まで、夕霧の心中。
|
| 4.5.5 |
二条の上の、さばかり限りにて、泣く泣く申したまふと聞きしをば、いみじきことに思して、つひにかくかけとどめたてまつりたまへるものを」
|
二条の上が、あれほど最期に見えて、泣く泣くお願い申し上げなさったと聞いたのは、とんでもないことだとお考えになって、とうとうあのようにお引き留め申し上げなさったものを」
|
二条の院の夫人があの重態になっていられた場合に、泣く泣く許しを乞われたのさえもお拒みになったのであるから
|
|
| 4.5.6 |
|
などと、あれこれと思案をこらしてみると、
|
というようなことも大将は考えられ、衛門督の問題と女三の宮の御出家とは関連したことに違いないということに思いは帰着した。
|
【取り集めて思ひくだくに】- 『集成』は「あれこれと思案をこらしてみるのに。敬語を使わず、夕霧の心理に密着した地の文」と注す。
|
| 4.5.7 |
「なほ、昔より絶えず見ゆる心ばへ、え忍ばぬ折々ありきかし。いとようもて静めたるうはべは、人よりけに用意あり、のどかに、何ごとをこの人の心のうちに思ふらむと、見る人も苦しきまでありしかど、すこし弱きところつきて、なよび過ぎたりしけぞかし。 |
「やはり、昔からずっと抱き続けていた気持ちが、抑え切れない時々があったのだ。
とてもよく静かに落ち着いた表面は、誰よりもほんとうに嗜みがあり、穏やかで、どのようなことをこの人は考えているのだろうかと、周囲の人も気づまりなほどであったが、少し感情に溺れやすいところがあって、もの柔らか過ぎたためだ。
|
昔から宮をお思いしていて、忍び余るような物思いの影を自分などに見せたこともある人である、自制していて表面だけはあくまでも冷静で、この人の心には何を思っているのかとうかがうのに苦しむほどであったが、感情に負けるところがあって、あまりに彼は弱い男であった、
|
【なほ、昔より】- 以下「あぢきなきことなりかし」まで、夕霧の心中。
【もて静めたる】- 明融臨模本、付箋「夕霧ノ上ニミル説不用」と指摘。
【すこし弱きところつきて】- 『集成』は「すこし情に溺れるところがあって」。『完訳』は「すこし情に負けるところがあって」と訳す。
|
| 4.5.8 |
|
どんなにせつなく思い込んだとしても、あってはならないことに心を乱して、このように命を引き換えにしてよいことだろうか。
相手のためにもお気の毒であるし、わが身は滅ぼすことではないか。
そのようになるはずの前世からの因縁と言っても、まことに軽率で、つまらないことであるぞ」
|
どんなにすぐれた恋人であっても、許されない恋に狂熱を傾け、最後に身をあやまるようなことをしてはならないのである、一方の人のためにも気の毒なことであるし、彼が自身の命をそれに捨てたのも賢明なことではない、皆前生の因縁とはいいながらも、やはり軽率なことであったと、
|
【いみじうとも、さるまじきことに心を乱りて】- 『完訳』は「柏木の不義密通を推測」と注す。
【やはありける】- 『完訳』は「「--やはありける」「--やなすべき」と、柏木への強い批判」と注す。
|
| 4.5.9 |
など、心一つに思へど、女君にだに聞こえ出でたまはず。さるべきついでなくて、院にもまだえ申したまはざりけり。さるは、かかることをなむかすめし、と申し出でて、御けしきも見まほしかりけり。 |
などと、自分独りで思うが、女君にさえ申し上げなさらない。
適当な機会がなくて、院にもまだ申し上げることができなかった。
とはいえ、このようなことを小耳にはさみました、と申し出て、ご様子も窺って見てみたい気持ちでもあった。
|
大将は自身一人で思っていて夫人にも話さなかった。またよい機会もなくて院に故人の心をお伝えすることもまだ果たさなかった。大将としてはまたそれを話し出した時に秘密の全貌の見られることも願っているのであるから好機は容易に見いだせないのであるらしい。
|
【女君にだに】- 副助詞「だに」最小限のニュアンス。最も気を許してよい妻(雲居雁)にさえ話さない。
|
| 4.5.10 |
父大臣、母北の方は、涙のいとまなく思し沈みて、はかなく過ぐる日数をも知りたまはず、御わざの法服、御装束、何くれのいそぎをも、君たち、御方々、とりどりになむ、せさせたまひける。 |
父大臣と、母北の方は、涙の乾かぬ間なく悲しみにお沈みになって、いつの間にか過ぎて行く日数をもお分かりにならず、ご法要の法服、ご衣装、何やかやの準備も、弟の君たち、姉妹の方々が、それぞれ準備なさるのであった。
|
故大納言の父母は涙の晴れ間もないほど悲しみにおぼれて暮らしているのであって、日のたつ数もわからなかった。法事などの用意も子息たちや婿君たちの手でするばかりであった。
|
【過ぐる日数】- 大島本、朱合点、行間書入「物おもふすくる月日もしらぬまに雁こそ鳴て秋とつけくれ」(後撰集秋下、三五八、読人しらず)と指摘。『異本紫明抄』が指摘するが、『岷江入楚』に「私不及此歌」と批判され、現行の注釈書では指摘しない。
【君たち、御方々】- 柏木の弟たち姉妹たちをいう。
|
| 4.5.11 |
経仏のおきてなども、右大弁の君せさせたまふ。
七日七日の御誦経などを、人の聞こえおどろかすにも、
|
経や仏像の指図なども、右大弁の君がおさせになる。
七日七日ごとの御誦経などを、周囲の人が注意を促すにつけても、
|
供養する経巻や仏像も二男の左大弁が主になって作らせていた。七日七日の誦経の日が次々来るたびに、その注意を子息たちがすると、
|
|
| 4.5.12 |
|
「わたしに何も聞かせるな。
このようにひどく悲しい思いに暮れているのに、かえって往生の妨げとなってはいけない」
|
「もういっさい何も聞かせないようにしてくれ。あれに関した話を聴けばまた悲しみが湧くばかりだから、かえってあれの行く道を妨げることになる」
|
【我にな聞かせそ】- 以下「道妨げにもこそ」まで、大臣の詞。
【道妨げにも】- 大島本、朱合点、行間書入「拾 おもふ事ありてこそ行け春かすみみちさまたけに立ちなかくしそ」(拾遺集雑春、一〇一七、紀貫之)を指摘。
|
| 4.5.13 |
とて、亡きやうに思し惚れたり。
|
と言って、死んだ人のようにぼんやりしていらっしゃる。
|
と言うだけで、大臣も死んだ人のようになっていた。
|
|
|
第五章 夕霧の物語 柏木哀惜
|
|
第一段 夕霧、一条宮邸を訪問
|
| 5.1.1 |
一条の宮には、まして、おぼつかなうて別れたまひにし恨みさへ添ひて、日ごろ経るままに、広き宮の内、人気少なう心細げにて、親しく使ひ慣らしたまひし人は、なほ参り訪らひきこゆ。 |
一条宮におかれては、それ以上に、お目にかかれぬままご逝去なさった心残りまでが加わって、日数が過ぎるにつれて、広い宮の邸内も、人数少なく心細げになって、親しく使い馴らしていらした人は、やはりお見舞いに参上する。
|
一条の宮はまして終わりの病床に見ることもおできにならないままで良人を死なせておしまいになったというお悲しみもあって、その後の日の重なるにつけて広いお邸はますます寂しいものになって、お召使いの人たちも減っていくばかりであった。大納言の恩顧を受けていた人たちだけは、故人の未亡人の宮に今も敬意を表しに来ることを忘れなかった。
|
【親しく使ひ慣らしたまひし】- 主語は柏木。
|
| 5.1.2 |
|
お好きであった鷹、馬など、その係の者たちも、皆主人を失ってしょんぼりとして、ひっそりと出入りしているのを御覧になるにつけても、何かにつけてしみじみと悲しみの尽きないものであった。
お使いになっていらしたご調度類で、いつもお弾きになった琵琶、和琴などの絃も取り外されて、音を立てないのも、あまりにも引き籠もり過ぎていることであるよ。
|
愛していた鷹狩りの鷹とか、馬とかを預かっていた侍たちはたよる所を失ったように力を落としながらも寂しい姿で出仕しているのがお目にはいったりすることなども宮のお心を悲しくさせた。手馴らしていた居間の道具類、始終弾いていた琵琶、和琴などの、今は絃の張られていないものなども御覧になるのが苦しかった。
|
【出で入るを見たまふも】- 主語は落葉宮。
【あはれは尽きぬものになむありける】- 過去の助動詞「ける」詠嘆の意。『完訳』は「「ける」に注意。邸内の返歌一つ一つに、はっと気づかせられる」と注す。
【いと埋れいたきわざなりや】- 終助詞「や」詠嘆。語り手の感慨。
|
| 5.1.3 |
|
御前の木立がすっかり芽をふいて、花は季節を忘れない様子なのを眺めながら、何となく悲しく、伺候する女房たちも、鈍色の喪服に身をやつしながら、寂しく所在ない昼間に、先払いを派手にする声がして、この邸の前に止まる人がいる。
|
庭の木立ちがけむり、時を忘れずに花の咲こうとするのをおながめになっていて寂しかった。女房たちも皆喪服姿になっていて、あらゆるものから受ける印象が物哀れであったある日の昼ごろに、高い前駆の声がしてお邸の門にとまった車があった。
|
【御前の木立いたう煙りて、花は時を忘れぬけしきなるを】- 『完訳』は「梢の芽ぶく様子。このあたり三月の情景に寂寥の気分が際だつ。季節の甦りに対して、不帰の生命のはかなさが痛感される」と注す。
|
| 5.1.4 |
|
「ああ、亡くなられた殿のおいでかと、ついうっかり思ってしまいました」
|
「ぼんやりしていますとお亡くなりになった殿様がおいでになったのかと思いますよ」
|
【あはれ、故殿の】- 以下「思ひつれ」まで、女房の詞。
|
| 5.1.5 |
|
と言って、泣く者もいる。
大将殿がいらっしゃったのであった。
ご案内を申し入れなさった。
いつものように弁の君や、宰相などがいらっしゃったものかとお思いになったが、たいそう気おくれのするほど立派な美しい物腰でお入りになった。
|
と言って泣く女房もあった。それは左大将が訪問して来たのであった。まず訪問の意を通じて来た。いつものように大納言の弟の左大弁とか、参議とかの来訪したのかと邸の人は思っていた所へ、品がよくてきれいな風采で身の取りなしのすぐれてりっぱな大将がはいって来たのであった。
|
【大将殿のおはしたるなりけり】- 『弄花抄』は「注の心也」と指摘。『集成』も「草子地」と指摘。
【弁の君、宰相などのおはしたると】- 『集成』は「柏木の弟たち。柏木の遺言で、今までに何度か弔問に訪れている趣」と注す。
|
| 5.1.6 |
|
母屋の廂間に御座所を設けてお入れ申し上げなさる。
普通の客人と同様に、女房たちがご応対申し上げるのでは、恐れ多い感じのなさる方でいらっしゃるので、御息所がご対面なさった。
|
中央の間に続いた南向きの座敷に席を作って客は迎えられた。普通の人たちのように女房だけが出て応接をするのは失礼であるといって、宮の母君の御息所が逢った。
|
【母屋の廂に御座よそひて入れたてまつる】- 寝殿の南廂の間。
【御息所ぞ対面したまへる】- 一条宮邸の主人、母御息所。
|
| 5.1.7 |
|
「悲しい気持ちでおりますことは、身内の方々以上のものがございますが、世のしきたりもありますから、お見舞いの申し上げようもなくて、世間並になってしまいました。
臨終の折にも、ご遺言なさったことがございましたので、いいかげんな気持ちでいたわけではありません。
|
「あの不幸な友人を悲しみます心は身内の人たち以上ですが、形式的にはそれだけの志も見せられないのでございました。臨終のころ私へ託しましたこともありますから、宮様に対して十分の好意を私はお持ちしております。
|
【いみじきことを】- 以下「いと尽きせずなむ」まで、夕霧の詞。
【さるべき人びと】- 『集成』は「身内の人々」。『完訳』は「死を当然悲しむ血縁の者」と注す。
【世の常に】- 明融臨模本、付箋「恋しさもうき世のつねに成行を心は猶そもの思ひける」(出典未詳)。大島本、合点、行間書入「恋しきはうき世のつねに成ゆくを心は猶そ物思ひける」。古注では、『異本紫明抄』が指摘するが、現行の注釈書では指摘されない。
|
| 5.1.8 |
誰ものどめがたき世なれど、後れ先立つほどのけぢめには、思ひたまへ及ばむに従ひて、深き心のほどをも御覧ぜられにしがなとなむ。神事などのしげきころほひ、私の心ざしにまかせて、つくづくと籠もりゐはべらむも、例ならぬことなりければ、立ちながらはた、なかなかに飽かず思ひたまへらるべうてなむ、日ごろを過ぐしはべりにける。 |
誰でも安心してはいられない人生ですが、生き死にの境目までは、自分の考えが及ぶ限りは、浅からぬ気持ちを御覧いただきたいものだと思っております。
神事などの忙しいころは、私的な感情にまかせて、家に籠もっておりますことも、例のないことでしたので、立ったままではこれまた、かえって物足りなく存じられましょうと思いまして、日頃ご無沙汰してしまったのです。
|
だれにも死はめぐってくるはずですが、しばらくでもあとへ残りました以上は友人の縁故でできますだけのお世話を申し上げたいと思いまして、もう少し早く伺うつもりだったのですが神事などで御所の中の忙しいころに触穢のはばかりに引きこもらなければならなくなりますのもいかがと遠慮がいたされましたし、またお庭へ立たせていただくような伺い方は私の心も満足できることでないと思いまして、つい日をたたせてしまったのでございます。
|
【神事などのしげきころほひ】- 二月には春日祭、大原野祭、祈年祭などの神事がある。今、三月になった。
【立ちながらはた】- 『集成』は「お庭先で失礼いたしますのでは、これまた。「立ちながら」は上にあがらないこと。神事に出仕する身として、その時期に訪問しても、死の穢れに触れるのを避けねばならない、という意」と注す。
|
| 5.1.9 |
大臣などの心を乱りたまふさま、見聞きはべるにつけても、親子の道の闇をばさるものにて、かかる御仲らひの、深く思ひとどめたまひけむほどを、推し量りきこえさするに、いと尽きせずなむ」
|
大臣などが悲嘆に暮れていらっしゃるご様子、見たり聞いたり致すにつけても、親子の恩愛の情は当然のことですが、ご夫婦の仲では、深いご無念がおありだったでしょうことを、推量致しますと、まことにご同情に堪えません」
|
大臣などのお歎きの深いのを聞いておりますが、親子の愛情とは別な御夫婦の間でいらっしゃった宮様を、故人があんなに気がかりに考えておりましたことを思いますと、宮様のほうでもお悲しみになっていらっしゃる程度もどれほどのことかと恐察されまして御同情に堪えません」
|
|
| 5.1.10 |
とて、しばしばおし拭ひ、鼻うちかみたまふ。
あざやかに気高きものから、なつかしうなまめいたり。
|
と言って、しばしば涙を拭って、鼻をおかみになる。
きわだって気高い一方で、親しみが感じられ優雅な物腰である。
|
こう語っているうちにも大将はたびたび流れる涙をふいていた。清明な気高さがあって、しかも美しく艶な姿を大将は持っていた。
|
|
|
第二段 母御息所の嘆き
|
| 5.2.1 |
御息所も鼻声になりたまひて、
|
御息所も鼻声におなりになって、
|
御息所も鼻声になって、
|
|
| 5.2.2 |
|
「死別の悲しみは、この無常の世の習いでございましょう。
どんなに悲しいといっても、世間に例のないことではないと、この年寄りは、無理に気強く冷静に致しておりますが、すっかり悲しみに暮れたご様子が、とても不吉なまでに、今にも後を追いなさるように見えますので、すべてまことに辛い身の上であったわたしが、今まで生き永らえまして、このようにそれぞれに無常な世の末の様子を拝見致して行くのかと、まことに落ち着かない気持ちでございます。
|
「悲しいのが無常の世の常と存じまして、悲しいことはまだほかにもいろいろあるのを思いまして、私たち年のいった者はしいて気を強く持とうと努めることもいたしますが、宮様はまだお若いのでございますから、悲しみに沈みきっておしまいになりまして、同じ世界へ行っておしまいになるのではないかと危険でなりませんほどのお歎きをしておいでになります。不幸な生まれの私が今まで生きておりまして、大納言をお死なせしたり、宮様を未亡人におさせしたりしていく運命をじっとそばでながめていねばならぬかと苦しゅうございます。
|
【あはれなることは】- 以下「瀬はまじりはべりける」まで、御息所の詞。
【年積もりぬる人は】- 自分のことを謙遜していう。
【さらに思し入りたる】- 自分以上に。落葉宮をさしていう。
【すべていと心憂かりける身の】- 『完訳』は「以下、娘の不幸をもかみしめながら、わが身を回顧。朱雀院の更衣として苦悩が多かったか」と注す。
【かくかたがたに】- 『完訳』は「柏木が早世し、宮は気力を失う。自分も朱雀院出家後は孤独な晩年を送る」と注す。
|
| 5.2.3 |
おのづから近き御仲らひにて、聞き及ばせたまふやうもはべりけむ。初めつ方より、をさをさうけひききこえざりし御ことを、大臣の御心むけも心苦しう、院にもよろしきやうに思し許いたる御けしきなどのはべしかば、さらばみづからの心おきての及ばぬなりけりと、思ひたまへなしてなむ、見たてまつりつるを、かく夢のやうなることを見たまふるに、思ひたまへ合はすれば、みづからの心のほどなむ、同じうは強うもあらがひきこえましを、と思ひはべるに、なほいと悔しう。それは、かやうにしも思ひ寄りはべらざりきかし。 |
自然と親しいお間柄ゆえで、お聞き及んでいらっしゃるようなこともございましたでしょう。
最初のころから、なかなかご承知申し上げなかったご縁組でしたが、大臣のご意向もおいたわしく、院におかれても結構な縁組のようにお考えであった御様子などがございましたので、それではわたしの考えが至らなかったのだと、自ら思い込ませまして、お迎え申し上げたのですが、このように夢のような出来事を目に致しまして、考え会わせてみますと、自分の考えを、同じことなら強く押し通し反対申せばよかったものを、と思いますと、やはりとても残念で。
それは、こんなに早くとは思いも寄りませんでした。
|
近い御親戚関係でいらっしゃいますから、もうお聞き及びでもございましょうが、私はこの御結婚談の最初から御賛成は申し上げていなかったのでございますが、大臣が熱心に御運動をなさいましたし、また法皇様もお許しになる様子でございましたから、それではそのほうがよろしいことで、私の考え方は間違っていたのかと考え直しまして、とうとう御結婚をおさせ申したのでございますが、こんな夢のような不幸が起こってくるのでございましたら、もっと自分の信じましたところを強く主張しておれば、宮様をこうした目におあわせせずに済んだはずであると残念でなりません。
|
【をさをさうけひききこえざりし御ことを】- 宮と柏木の縁組をさす。
【見たてまつりつるを】- 『集成』は「お世話申し上げたのですが。柏木を夫として迎えた宮をお世話した、の意」と注す。
【みづからの心のほどなむ】- 『集成』は「そうした私の存じよりのほどを、どうせなら強く反対して申し上げればよかったのにと思いますと」。『完訳』は「こんなことになるくらいなら、強く反対して、この私の存じよりのほどを申しあげればよかったものをと思いますにつけても」と訳す。
【あらがひきこえましを】- 「まし」反実仮想の助動詞。「を」間投助詞、詠嘆の意。
|
| 5.2.4 |
皇女たちは、おぼろけのことならで、悪しくも善くも、かやうに世づきたまふことは、え心にくからぬことなりと、古めき心には思ひはべしを、いづかたにもよらず、中空に憂き御宿世なりければ、何かは、かかるついでに煙にも紛れたまひなむは、この御身のための人聞きなどは、ことに口惜しかるまじけれど、さりとても、しかすくよかに、え思ひ静むまじう、悲しう見たてまつりはべるに、いとうれしう、浅からぬ御訪らひのたびたびになりはべめるを、有り難うもと聞こえはべるも、さらば、かの御契りありけるにこそはと、思ふやうにしも見えざりし御心ばへなれど、今はとて、これかれにつけおきたまひける御遺言の、あはれなるになむ、憂きにもうれしき瀬はまじりはべりける」 |
内親王たちは、並大抵のことでは、よかれあしかれ、このように結婚なさることは、感心しないことだと、老人の考えでは思っていましたが、結婚するしないにかかわらず、中途半端な中空にさまよった辛い運命のお方であったので、いっそのこと、このような時にでも後をお慕い申したところで、このお方にとって外聞などは、特に気にしないでよろしいでしょうが、そうかといっても、そのようにあっさりとも、諦め切れず、悲しく拝し上げておりますが、まことに嬉しいことに、懇ろなお見舞いを重ね重ね頂戴しましたようで、有り難いこととお礼申し上げますが、それでは、あのお方とのお約束があったゆえと、願っていたようには見えなかったお気持ちでしたが、今はの際に、誰彼にお頼みなさったご遺言が、身にしみまして、辛い中にも嬉しいことはあるものでございました」
|
私は初めから宮様がたはよくよくの御因縁のあることでなければ結婚などはあそばしてはならないものである、神聖なものとしてお置き申し上げたいと昔風な心に願っていたのでございますから、こんなどちらつかずの御不幸なお身の上におなりあそばした以上は、いっそ悲しみでお亡くなりになるのもよろしかろう、不幸な宮様としてお残りになるよりはなどとも思いますが、さてそうもあきらめきれるものではございませんから、やはり悲しんでばかりおりましたうちにも、御親切な御慰問のお手紙を始終おいただきになるようでございますから、ありがたいことと存じておりまして、こうしていただけるのも故人が特に宮様のことでお頼みされたことがあったのかと、必ずしも御愛情の見える御良人ではなかったのですが、最後にどなたへも宮様についての遺言をなさいましたことで、悲しみにもまた慰めというもののあるのを発見いたしたのでございます」
|
【え心にくからぬこと】- 定家筆本と明融臨模本は「え心にくからぬこと」とある。大島本は「心にくからぬこと」とある。『集成』『新大系』はそれぞれ底本(定家本・大島本)のままとする。『完本』は諸本に従って「心にくからぬこと」と「え」を削除する。
【御訪らひのたびたびになりはべめるを】- 『集成』は「自身の訪問ははじめてだが、今まで何度も弔問の使者がさし向けられていた趣」と注す。
【御心ばへ】- 柏木の気持をさす。
【憂きにもうれしき瀬は】- 明融臨模本、朱合点、付箋「うれしきもうきも心はひとつにて別ぬものは泪なりけり」(後撰集雑二、一一八九、読人しらず)。大島本、朱合点、行間書入「うれしきもうきも心は一にてわすれぬ物は涙なりけり」とある。古注では、『異本紫明抄』が指摘するが、現行の注釈書では指摘されない。
|
| 5.2.5 |
とて、いといたう泣いたまふけはひなり。
|
と言って、とてもひどくお泣きになる様子である。
|
と言って、御息所はひどく泣き入る様子であった。
|
|
|
第三段 夕霧、御息所と和歌を詠み交わす
|
| 5.3.1 |
大将も、とみにえためらひたまはず。
|
大将も、すぐには涙をお止めになれない。
|
大将もそぞろに誘われて泣いた。
|
|
| 5.3.2 |
|
「どうしたわけか、実に申し分なく老成していらっしゃった方が、このようになる運命だったからでしょうか、ここ二、三年の間、ひどく沈み込んで、どことなく心細げにお見えになったので、あまりに世の無常を知り、考え深くなった人が、悟りすまし過ぎて、このような例で、心が素直でなくなり、かえって逆に、てきぱきしたところがないように人に思われるものだと、いつも至らない自分ながらお諌め申していたので、思慮が浅いとお思いのようでした。
何事にもまして、人に優れて、おっしゃる通り、宮のお悲しみのご心中、恐れ多いことですが、まことにおいたわしゅうございます」
|
「昔は不思議な冷静な人でしたが、短命で亡くなるせいか、この二、三年は非常にめいって見える時が多くて、心細いふうを見せられましたから、あまりに人生を考えた末に悟ってしまった清澄な心境というものかもしれぬが、それでは今までに持っていたすぐれたよさが消えてしまうことにならないかとも不安に思われると、小賢しく私が時々忠告らしいことをしますと、あの人は私を憐むような表情で見ていました。何よりも宮様のお悲しみになっていらっしゃいます御様子を伺いまして、もったいないことですが、おいたわしく存じ上げます」
|
【あやしう、いとこよなく】- 以下「心苦しうもはべるかな」まで、夕霧の詞。
【およすけたまへりし人】- 柏木をさす。
【澄み過ぎて】- 明融臨模本、付箋「とにかくに物は思はすひたゝくみうつすみなはのたゝ一筋に」(拾遺集恋五、九六〇、人麿)。大島本、朱合点、行間書入「とにかくに物はおもはすひたゝくみうつすみなはのたゝ一すちに」とある。古注では、『異本紫明抄』が指摘するが、現行の注釈書では指摘されない。
【あざやかなる方のおぼえ薄らぐものなりとなむ】- 『集成』は「はきはきしたところがないように人に思われるようになるものだと」。『完訳』は「その人らしいと噂される面が」「かえってその人らしさが見えなくなってしまうものだと」と注す。
【心浅しと思ひたまへりし】- 主語は柏木。柏木は夕霧を。
【かの思し嘆くらむ御心の内の】- 落葉宮の心をさす。
|
| 5.3.3 |
など、なつかしうこまやかに聞こえたまひて、ややほど経てぞ出でたまふ。
|
などと、優しく情愛こまやかに申し上げなさって、やや長居してお帰りになる。
|
などとなつかしいふうに話して、しばらくして大将は去って行こうとした。
|
|
| 5.3.4 |
|
あの方は、五、六歳くらい年上であったが、それでも、とても若々しく、優雅で、人なつっこいところがおありであった。
この方は、実にきまじめで重々しく、男性的な感じがして、お顔だけがとても若々しく美しいことは、誰にも勝っていらっしゃった。
若い女房たちは、もの悲しい気持ちも少し紛れてお見送り申し上げる。
|
衛門督はこの人より五つ六つの年長であったが、彼はきわめて若々しく見えて、女性的な柔らかさの見える人であったが、これは重々しく端正で、しかも顔だけはあくまでも美しいのを、若女房などは悲しさも少し紛れたように興奮して、帰って行こうとする大将の姿にながめ入った。
|
【かの君は、五、六年のほどのこのかみなりしかど】- 柏木は夕霧よりも五、六歳年長であった意。夕霧、二十七歳。柏木、三十二、三歳。
【これは、いとすくよかに】- 夕霧をさす。『集成』は「きりりとして」。『完訳』は「じつにきまじめで」と訳す。
|
| 5.3.5 |
御前近き桜のいとおもしろきを、「今年ばかりは」と、うちおぼゆるも、いまいましき筋なりければ、 |
御前に近い桜がたいそう美しく咲いているのを、「今年ばかりは」と、ふと思われるのも、縁起でもないことなので、
|
前の庭の桜の美しいのをながめて、「深草の野べの桜し心あらば今年ばかりは墨染めに咲け」と口へ出てくる大将であったが、尼姿を言うようなことはここで言うべきでないと遠慮がされて、
|
【今年ばかりは】- 明融臨模本、朱合点、付箋「深草の野への桜し心あらはことしはかりは墨染にさけ」(古今集哀傷、八三二、上野岑雄)。大島本、朱合点、行間書入「古今深草野ゝへの」。中山家本、朱合点。古注では、『源氏釈』(吉川家本勘物)が指摘し、現行の注釈書でも指摘する。
|
| 5.3.6 |
|
「再びお目にかかれるのは」
|
「春ごとに花の盛りはありなめど逢ひ見んことは命なりける」
|
【あひ見むことは】- 夕霧の詞。口ずさみ。尊経閣文庫本、付箋「春ことに花のさかりはありなめとあひみん事は命なりけり」(古今集春下、九七、読人しらず)。明融臨模本、朱合点、付箋「春毎に花のさかりはありなめとあひ見むことはいのちなりけり」。大島本、朱合点、行間書入「古今春ことに花のさかりは」。中山家本、朱合点、奥入に同歌を指摘。古注では『源氏釈』が指摘し、現行の注釈書でも指摘する。
|
| 5.3.7 |
と口ずさびて、
|
と口ずさみなさって、
|
と歌って、
|
|
| 5.3.8 |
|
「季節が廻って来たので変わらない色に咲きました
片方の枝は枯れてしまったこの桜の木にも」
|
時しあれば変はらぬ色に匂ひけり
片枝折れたる宿の桜も
|
【時しあれば変はらぬ色に匂ひけり--片枝枯れにし宿の桜も】- 夕霧の贈歌。
|
| 5.3.9 |
わざとならず誦じなして立ちたまふに、いととう、
|
さりげないふうに口ずさんでお立ちになると、とても素早く、
|
と自然なふうに口ずさんで、花の下に立ちどまっていると、御息所はすぐに、
|
|
| 5.3.10 |
|
「今年の春は柳の芽に露の玉が貫いているように泣いております
咲いて散る桜の花の行く方も知りませんので」
|
この春は柳の芽にぞ玉は貫く
咲き散る花の行くへ知らねば
|
【この春は柳の芽にぞ玉はぬく--咲き散る花の行方知らねば】- 御息所の返歌。贈歌の「時」「桜」を「春」「柳」と趣向を変えて返す。「芽」に「目」を響かす。尊経閣文庫本、付箋「よりあはせてなくなるこゑをいとにしてわかなみたをはたまにぬかなむ」(伊勢集)。明融臨模本、付箋「あさみとり糸よりかけてー/よりあはせてなくなる聲をいとにしてわか涙をは玉にぬかなん」。古注では『源氏釈』が指摘。
|
| 5.3.11 |
|
と申し上げなさる。
格別深い情趣があるわけではないが、当世風で、才能があると言われていらした更衣だったのである。
「なるほど、無難なお心づかいのようだ」と御覧になる。
|
という返しを書いてきた。高い才識の見えるほどの人ではないが、前には才女と言われた更衣であったのを思って、評判どおりに気のきいた人であると大将は思った。
|
【いと深きよしにはあらねど】- 『完訳』は「即座に返歌しえた嗜みを評す」と注す。
【げに、めやすきほどの用意なめり】- 夕霧の一条御息所の返歌に対する感想。
|
|
第四段 夕霧、太政大臣邸を訪問
|
| 5.4.1 |
致仕の大殿に、やがて参りたまへれば、君たちあまたものしたまひけり。
|
致仕の大殿に、そのまま参上なさったところ、弟君たちが大勢いらっしゃっていた。
|
大将はそれから太政大臣家を訪問したが、子息たちの幾人かが出て、
|
|
| 5.4.2 |
|
「こちらにお入りあそばせ」
|
こちらへと案内をしたので、
|
【こなたに入らせたまへ】- 「君たち」(柏木の弟たち)の詞。
|
| 5.4.3 |
|
と言うので、大臣の御客間の方にお入りになった。
悲しみを抑えてご対面なさった。
いつまでも若く美しいご容貌、ひどく痩せ衰えて、お髭などもお手入れなさらないので、いっぱい生えて、親の喪に服するよりも憔悴していらっしゃった。
お会いなさるや、とても堪え切れないので、「あまりだらしなくこぼす涙は体裁が悪い」と思うので、無理にお隠しになる。
|
大臣の離れ座敷のほうへ行っては無遠慮でないかと躊躇をしながらはいって行って舅に逢った。いつまでも端麗な大臣の顔も非常に痩せ細ってしまって、髭なども剃らせないで伸びて、親を失った時に比べて子を死なせたあとの大臣は衰え方がひどいと世間で言われるとおりに見えた。顔を見た瞬間から悲しくなって流れ出した涙がいつまでも続いて流れてくるのを恥ずかしく思って大将は押し隠しながら、
|
【大臣の御出居の方】- 『集成』は「主人の、来客との対面所のような所。廂の間である」。『完訳』は「寝殿の表座敷のほうに」と注す。
【ためらひて対面したまへり】- 『集成』は「かたちを改めて。悲嘆にくれていた涙を収めて、の意」。『完訳』は「大臣は悲しいお気持を静めて大将とご対面になった」と訳す。
【親の孝よりも、けにやつれたまへり】- 子が親の喪に服する以上のお悲しみようである、の意。 【けにやつれたまへり】-明融臨模本、付箋「孝経/哭弗依礼亡容」とある。
【見たてまつりたまふより】- 主語は夕霧。夕霧が致仕太政大臣を。
【あまりにをさまらず】- 以下「はしたなけれ」まで、夕霧の心中。
|
| 5.4.4 |
|
大臣も、「特別仲好くいらしたのに」とお思いになると、ただ涙がこぼれこぼれて、お止めになることができず、語り尽きせぬ悲しみを互いにお話しなさる。
|
|
【取り分きて御仲よくものしたまひしを】- 定家筆本と明融臨模本は「とりわきて」とある。大島本は「とりわき」とある。『集成』『新大系』はそれぞれ底本定家筆本・大島本)のままとする。『完本』は諸本に従って「とりわき」と「て」を削除する。大臣の心中。夕霧と柏木の仲を思う。
|
| 5.4.5 |
|
一条宮邸に参上した様子などを申し上げなさる。
ますます、春雨かと思われるまで、軒の雫と違わないほど、いっそう涙をお流しになる。
畳紙に、あの「柳の芽に」とあったのを、お書き留めになっていたのを差し上げなさると、「目も見えませんよ」と、涙を絞りながら御覧になる。
|
一条の宮をお訪ねして来た話などをした。初めからしめっぽいふうであった大臣はさらに多くの涙を見せて、故人の話を婿とし合った。懐紙へ一条の御息所が書いて渡した歌を大将が見せようとすると、「目もよく見えないが」と涙の目をしばたたきながらそれを読もうとした。
|
【春雨かと見ゆるまで、軒の雫に】- 『集成』は「「春雨」「軒の雫」は歌語」。『完訳』は「「ただ降りに降り落ちて」とある縁で、涙を季節の雨と見立てた」と注す。
【畳紙に】- 夕霧は御息所の返歌を自分の畳紙に書付けておいた。
【柳の芽にぞ】- 御息所の返歌の第二句の文句。
【目も見えずや】- 大臣の詞。終助詞「や」詠嘆。
|
| 5.4.6 |
うちひそみつつぞ見たまふ御さま、例は心強うあざやかに、誇りかなる御けしき名残なく、人悪ろし。さるは、異なることなかめれど、この「玉はぬく」とある節の、げにと思さるるに、心乱れて、久しうえためらひたまはず。 |
泣き顔をして御覧になるご様子、いつもは気丈できっぱりして、自信たっぷりのご様子もすっかり消えて、体裁が悪い。
実のところ、特別良い歌ではないようだが、この「玉が貫く」とあるところが、なるほどと思わずにはいらっしゃれないので、心が乱れて、暫くの間、涙を堪えることができない。
|
見栄も思わず目のためにしかめている顔は、平生の誇りに輝いた時の面影を失って見苦しかった。歌は平凡なものであったが、「玉は貫く」ということばは大臣自身にも痛切に感じていることであったから、相憐む涙が流れ出るふうで、すぐにまた言うのであった。
|
【玉はぬく】- 御息所の返歌の第三句の文句。
|
| 5.4.7 |
「君の御母君の隠れたまへりし秋なむ、世に悲しきことの際にはおぼえはべりしを、女は限りありて、見る人少なう、とあることもかかることもあらはならねば、悲しびも隠ろへてなむありける。 |
「あなたの母上がお亡くなりになった秋は、本当に悲しみの極みに思われましたが、女性というものはきまりがって、知る人も少なく、あれこれと目立つこともないので、悲しみも表立つことはないのであった。
|
「あなたのお母さんが亡くなられた時に、私はこれほど悲しいことはないと思ったが、女の人は世間と交渉を持つことが少ないために、不意にいろんな言葉が自分の痛い傷にさわるというようなこともなくて、今度のような苦しみをそのあとで感じることはなかったものです。
|
【君の御母君の】- 以下「思ひさますべからむ」まで、大臣の詞。夕霧の母葵の上の死去の際を回想。
|
| 5.4.8 |
はかばかしからねど、朝廷も捨てたまはず、やうやう人となり、官位につけて、あひ頼む人びと、おのづから次々に多うなりなどして、おどろき口惜しがるも、類に触れてあるべし。 |
ふつつかな者でしたが、帝もお見捨てにならず、だんだんと一人前になって、官位も昇るにつれて、頼りとする人々が、自然と次々に多くなってきたりして、驚いたり残念に思う者も、いろいろな関係でいることでしょう。
|
賢くもありませんでしたが、朝廷の御恩を受けて地位を得てゆくにしたがって彼の庇護を受けようとするものが次第に多くなっていたのですから、彼の死に失望をした者もずいぶんあるでしょう。
|
【はかばかしからねど】- 話題転じて、柏木についていう。
【あひ頼む人びと】- 『完訳』は「追従する者の多いのは、柏木が権勢家の道を歩んでいた証拠」と注す。
|
| 5.4.9 |
かう深き思ひは、その大方の世のおぼえも、官位も思ほえず。ただことなることなかりしみづからのありさまのみこそ、堪へがたく恋しかりけれ。何ばかりのことにてか、思ひさますべからむ」 |
このように深い嘆きは、その世間一般の評判も、官位のことは考えていません。
ただ格別人と変わったところもなかった本人の有様だけが、堪え難く恋しいのです。
いったいどのようにして、この悲しみが忘れられるのでしょう」
|
しかし親である私は、そんなふうに勢力を得ていたのに惜しいとか、官位がどうなっていたかというようなことではなくて、平凡な息子である裸の彼が堪えがたく恋しいのです。どんなことが私のこの悲しみを慰めるようになるのでしょう。それはありうることとは思われません」
|
【みづからのありさま】- 柏木の身の上をいう。
【何ばかりのことにてか】- 定家筆本と明融臨模本、大島本は「ことにてか」とある。『集成』『新大系』は底本のままとする。『完本』は諸本に従って「ことにてかは」と「は」を補訂する。
|
| 5.4.10 |
と、空を仰ぎて眺めたまふ。
|
と言って、空を仰いで物思いに耽っていらっしゃる。
|
大臣は空間に向いて歎息をした。
|
|
| 5.4.11 |
|
夕暮の雲の様子、鈍色に霞んで、花の散った梢々を、今日初めて目をお止めになる。
さきほどの御畳紙に、
|
夕方の雲が鈍色にかすんで、桜の散ったあとの梢にもこの時はじめて大臣は気づいたくらいである。御息所の歌の紙へ、
|
【夕暮の雲のけしき】- 明融臨模本、朱合点、付箋「夕暮の雲の気色を見るからになかめしとそおもふ心こそつけ/大空は恋しき人のかたみかは物おもふことに詠らるらん」(新古今集雑下、一八〇六、和泉式部と古今集恋四、七四三、酒井人真)。大島本、朱合点、行間書入「夕暮の雲の気しきをみるからになかめしとそおもふ心こそつけ」。古注では、新古今集歌は、『異本紫明抄』が指摘するが、現行の注釈書では指摘されない。古今集歌は旧注の『休聞抄』が指摘し、現行の注釈書でも指摘する。
【この御畳紙】- 夕霧が差し上げた御息所の和歌を書いてある懐紙。
|
| 5.4.12 |
|
「木の下の雫に濡れて逆様に
親が子の喪に服している春です」
|
このもとの雪に濡れつつ逆まに
霞の衣着たる春かな
|
【木の下の雫に濡れてさかさまに--霞の衣着たる春かな】- 大臣の歌。親が子の喪に服すことを「さかさまに」と言った。「霞の衣」は喪服を喩える。「木の下の雫」は亡き子を偲ぶ涙の意をこめる。
|
| 5.4.13 |
大将の君、
|
大将の君、
|
と書いた。大将も、
|
|
| 5.4.14 |
|
「亡くなった人も思わなかったことでしょう
親に先立って父君に喪服を着て戴こうとは」
|
亡き人も思はざりけん打ち捨てて
夕べの霞君着たれとは
|
【亡き人も思はざりけむうち捨てて--夕べの霞君着たれとは】- 夕霧の唱和歌。「亡き人」は柏木、「君」は父の大臣をさす。「着る」はそのまま用いるが、「霞の衣」を「夕の霞」と趣向を変える。
|
| 5.4.15 |
弁の君、
|
弁の君、
|
と書く。左大弁も、
|
|
| 5.4.16 |
|
「恨めしいことよ、
墨染の衣を誰が着ようと思って春より先に
|
恨めしや霞の衣たれ着よと
春よりさきに花の散りけん
|
【恨めしや霞の衣誰れ着よと--春よりさきに花の散りけむ】- 柏木の弟の弁の君の唱和歌。大臣の「霞の衣」「着る」「春」をそのまま用いるが、夕霧の「君」は「誰」と趣向を変える。「花」に柏木を喩える。
|
| 5.4.17 |
御わざなど、世の常ならず、いかめしうなむありける。大将殿の北の方をばさるものにて、殿は心ことに、誦経なども、あはれに深き心ばへを加へたまふ。 |
ご法要などは、世間並でなく、立派に催されたのであった。
大将殿の北の方はもちろんのこと、殿は特別に、誦経なども手厚くご趣向をお加えなさる。
|
と書いた。大納言の法事は非常に盛んなものであった。左大将夫人が兄のためにささげ物をしたのはいうまでもないが、大将自身も真心のこもったささげ物をしたし、誦経の寄付などにも並み並みならぬ友情を示した。
|
【大将殿の北の方】- 雲居雁をさす。
|
|
第五段 四月、夕霧の一条宮邸を訪問
|
| 5.5.1 |
|
あの一条宮邸にも、常にお見舞い申し上げなさる。
四月ごろの卯の花は、どこそことなく心地よく、一面新緑に覆われた四方の木々の梢が美しく見わたされるが、物思いに沈んでいる家は、何につけてもひっそりと心細く、暮らしかねていらっしゃるところに、いつものように、お越しになった。
|
左大将は一条の宮へ始終見舞いを言い送っていた。四月の初夏の空はどことなくさわやかで、あらゆる木立ちが一色の緑をつくっているのも、寂しい家ではすべて心細いことに見られて、宮の御母子が悲しい退屈を覚えておいでになるころにまた左大将が来訪した。
|
【常に訪らひきこえたまふ】- 主語は夕霧。
【卯月ばかりの卯の花は】- 定家筆本と明融臨模本、大島本は「う月はかりのうのはなは」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「四月ばかりの空は」と校訂する。『新大系』は底本のままとする。
【一つ色なる】- 大島本、合点、行間書入「みとりなる一色とそ春はみし」。「緑なるひとつ草とぞ春は見し秋は色々の花にぞありける」(古今集秋上、二四五、読人しらず)。古注では『河海抄』が指摘する。現行の注釈書では指摘しない。『完訳』は「一面新緑に彩られる。以下、その初夏の明るさが、悲傷のうちに荒廃した邸内を照らし出す趣」と注す。
【もの思ふ宿は】- 大島本、朱合点、行間書入「古今 鳴わたるかりの涙や」と指摘。「鳴きわたる雁の涙や落ちつらむもの思ふ宿の萩の上の露」(古今集秋上、二二一、読人しらず)。古注では『異本紫明抄』が指摘する。
|
| 5.5.2 |
庭もやうやう青み出づる若草見えわたり、ここかしこの砂子薄きものの隠れの方に、蓬も所得顔なり。前栽に心入れてつくろひたまひしも、心にまかせて茂りあひ、一村薄も頼もしげに広ごりて、虫の音添へむ秋思ひやらるるより、いとものあはれに露けくて、分け入りたまふ。 |
庭もだんだんと青い芽を出した若草が一面に見えて、あちらこちらの白砂の薄くなった物蔭の所に、雑草がわが物顔に茂っている。
前栽を熱心に手入れなさっていたのも、かって放題に茂りあって、一むらの薄も思う存分に延び広がって、虫の音が加わる秋が想像されると、もうとても悲しく涙ぐまれて、草を分けてお入りになる。
|
植え込みの草などもすでに青く伸びて、敷き砂の間々には強い蓬が広がりかえっていた。林泉に対する趣味を大納言は持っていて、美しくさせていたものであるが、そうした植え込みの灌木類や花草の類もがさつに枝を伸ばすばかりになって、一むら薄はその蔭に鳴く秋の虫の音が今から想像されるほどはびこって見えるのも、大将の目には物哀れでしめっぽい気分がまず味わわれた。
|
【一村薄も】- 明融臨模本、朱合点、付箋「夕暮の一村薄露ちりて虫のねそはぬ秋かせそ吹□□僧正」。大島本、朱合点、行間書入「古今 君かうへし一むらすゝき虫の音の」と指摘。「君が植ゑし一むら薄虫の音のしげき野辺ともなりにけるかな」(古今集哀傷、八五三、御春有輔)。古注では『異本紫明抄』が指摘し、現行の注釈書でも指摘する。
【思ひやらるるより】- 「るる」自発の助動詞。格助詞「より」起点を表す。『集成』は「思いやられるともう」。『完訳』は「さぞかしと思いやらずにはいられないので」と訳す。
|
| 5.5.3 |
|
伊予簾を一面に掛けて、鈍色の几帳を衣更えした透き影が、涼しそうに見えて、けっこうな童女の、濃い鈍色の汗衫の端、頭の恰好などがちらっと見えているのも、趣があるが、やはりはっとさせられる色である。
|
喪の家として御簾に代えて伊予簾が掛け渡され夏のに代えられたのも鈍色の几帳がそれに透いて見えるのが目には涼しかった。姿のよいきれいな童女などの濃い鈍色の汗袗の端とか、後ろ向きの頭とかが少しずつ見えるのは感じよく思われたが、何にもせよ鈍色というものは人をはっとさせる色であると思われた。
|
【鈍色の几帳の衣更へしたる透影、涼しげに見えて】- 『集成』は「ここは几帳の帷を夏向きにしたのが、伊予簾の隙から見える趣」と注す。
|
|
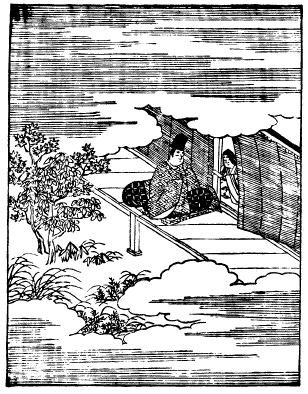 |
| 5.5.4 |
今日は簀子にゐたまへば、茵さし出でたり。「いと軽らかなる御座なり」とて、例の、御息所おどろかしきこゆれど、このごろ、悩ましとて寄り臥したまへり。とかく聞こえ紛らはすほど、御前の木立ども、思ふことなげなるけしきを見たまふも、いとものあはれなり。 |
今日は簀子にお座りになったので、褥をさし出した。
「まことに軽々しいお座席です」と言って、いつものように、御息所に応対をお促し申し上げるが、最近、気分が悪いといって物に寄り臥していらっしゃった。
あれこれと座をお取り持ちする間、御前の木立が、何の悩みもなさそうに茂っている様子を御覧になるにつけても、とてもしみじみとした思いがする。
|
今日は宮のお座敷の縁側にすわろうとしたので敷き物が内から出された。例の話し相手をする御息所に出てくれと女房たちは勧めているのであったが、このころは身体が悪くて今日も寝ていた。御息所の出て来るまで、何かと女房が挨拶をしている時に、人間の思いとは関係のないふうに快く青々とした庭の木立ちに大将はながめ入っていたが、気持ちは悲しかった。
|
【いと軽らかなる御座なり】- 女房の詞。
【思ふことなげなるけしきを】- 擬人法。木立が何の悩みもなさそうに生い茂る風情を夕霧がご覧になるにつけても、の意。
|
| 5.5.5 |
柏木と楓との、ものよりけに若やかなる色して、枝さし交はしたるを、
|
柏木と楓とが、他の木々よりも一段と若々しい色をして、枝をさし交わしているのを、
|
柏の木と楓が若々しい色をして枝を差しかわして立っているのを指さして、大将は女房に、
|
|
| 5.5.6 |
|
「どのような前世の縁でか、枝先が繋がっている頼もしさだ」
|
「どんな因縁のある木どうしでしょう。枝が交じり合って信頼をしきっているようなのがいい」
|
【いかなる契りにか、末逢へる頼もしさよ】- 夕霧の詞。独言。連理の枝を見ての感想。
|
| 5.5.7 |
|
などとおっしゃって、目立たないように近寄って、
|
などと言い、さらに簾のほうへ寄って、
|
【さし寄りて】- 御簾の際に近づいて、の意。
|
| 5.5.8 |
|
「同じことならばこの連理の枝のように親しくして下さい
葉守の神の亡き方のお許があったのですからと
|
「ことならばならしの枝にならさなん
葉守の神の許しありきと
|
【ことならば馴らしの枝にならさなむ--葉守の神の許しありきと】- 明融臨模本、付箋「柏木に葉守の神のましけるをしらてそおりしたゝりなさるな/大和ニ枇杷殿<左大臣仲平>よりとしこか家に柏木のありけるを折におこせたりけるを/我やとはいつならしてかならのはのならしかほには折にをこする」。大島本、行間書入「我やとをいつかは君かならの葉のならしかほにもおりにおこするとしこ返事/かしは木に葉もりの神のましけるをしらてそおりしたゝりなさるな左大臣仲平」と指摘。「我が宿をいつならしてか楢の葉をならし顔には折りておこする」(後撰集雑二、一一八三、俊子)「楢の葉の葉守の神のましけるを知らで折りしたたりなさるな」(後撰集雑二、一一八四、枇杷左大臣)。古注では『異本紫明抄』が指摘する。
|
| 5.5.9 |
御簾の外の隔てあるほどこそ、恨めしけれ」
|
御簾の外に隔てられているのは、恨めしい気がします」
|
まだ御簾の隔てをお除きくださらないのが遺憾です」
|
|
| 5.5.10 |
とて、長押に寄りゐたまへり。
|
と言って、長押に寄りかかっていらっしゃった。
|
と言った。一段高くなった室の長押へ外から寄りかかっているのである。
|
|
| 5.5.11 |
|
「くだけたお姿もまた、とてもたいそうしなやかでいらっしゃること」
|
「柔らかい形をしていらっしゃる時に、また別な美しさがおありになりますよ」
|
【なよび姿】- 以下「たをやぎけるをや」まで、女房の噂。
|
| 5.5.12 |
と、これかれつきしろふ。
この御あへしらひきこゆる少将の君といふ人して、
|
と、お互いにつつき合っている。
お相手を申し上げる少将の君という人を使って、
|
と女房らはささやき合うのであった。今まで話していた少将という女房を取り次ぎにして宮はお返辞をおさせになった。
|
|
| 5.5.13 |
|
「柏木に葉守の神はいらっしゃらなくても
みだりに人を近づけてよい梢でしょうか
|
「柏木に葉守の神は坐すとも
人馴らすべき宿の梢か
|
【柏木に葉守の神はまさずとも--人ならすべき宿の梢か】- 少将の君の返歌。「葉守の神」は柏木に宿るということから、「柏木」「葉守の神」を用い、「神の許し」に対して、「神はまさずとも」「なさすべき」という反語表現で切り返す。
|
| 5.5.14 |
うちつけなる御言の葉になむ、浅う思ひたまへなりぬる」 |
唐突なお言葉で、いい加減なお方と思えるようになりました」
|
突然にそうしたお恨みをお言いかけになりますことで御好意が疑われます」
|
【うちつけなる】- 以下「思ひたまへなりぬる」まで、歌に添えた詞。
|
| 5.5.15 |
と聞こゆれば、げにと思すに、すこしほほ笑みたまひぬ。
|
と申し上げたので、なるほどとお思いになると、少し苦笑なさった。
|
と伝えられたお言葉に道理があると思って大将は微笑した。
|
|
|
第六段 夕霧、御息所と対話
|
| 5.6.1 |
御息所ゐざり出でたまふけはひすれば、やをらゐ直りたまひぬ。
|
御息所のいざり出でなさるご様子がするので、静かに居ずまいを正しなさった。
|
その時に御息所がいざって来る気配がしたので大将は少しいずまいを直した。
|
|
| 5.6.2 |
「憂き世の中を、思ひたまへ沈む月日の積もるけぢめにや、乱り心地も、あやしうほれぼれしうて過ぐしはべるを、かくたびたび重ねさせたまふ御訪らひの、いとかたじけなきに、思ひたまへ起こしてなむ」 |
「嫌な世の中を、悲しみに沈んで月日を重ねてきたせいでしょうか、気分の悪いのも、妙にぼうっとして過ごしておりますが、このように度々重ねてお見舞い下さるのが、まことにもったいので、元気を奮い起こしまして」
|
「世の中のことをあまりに悲しく思い過ぐしますせいですか、身体のぐあいが悪うございまして、ぼけたようにもなって暮らしておりますが、こうしてたびたびの御親切な御訪問に力づけられまして出てまいりました」
|
【憂き世の中を】- 以下「思ひたまへ起こしてなむ」まで、御息所の詞。
|
| 5.6.3 |
とて、げに悩ましげなる御けはひなり。
|
と言って、本当に苦しそうなご様子である。
|
と御息所は言ったが、言葉どおりに病気らしく感じられた。
|
|
| 5.6.4 |
|
「お嘆きになるのは、世間の道理ですが、またそんなに悲しんでばかりいられるのもいかがなものかと。
何事も、前世からの約束事でございましょう。
何といっても限りのある世の中です」
|
「故人をお悲しみになりますことはごもっとも至極なことですが、しかしそんなにまで深くお歎きになってはよろしくないでしょう。この世のことはみな前生からのきまっている因縁の現われですから、そう思えばさすがに際限もなく悲しみばかりの続くものでないことがわかると思いますが」
|
【思ほし嘆くは】- 以下「限りある世になむ」まで、夕霧の詞。
【世のことわりなれど】- 大島本、朱合点、行間書入「松風のふけはさすかにわひしはた世のことはりと思ふ物から」と指摘。「秋風の吹けばさすがに侘しきは世のことわりと思ふ物から」(後撰集秋上、二五〇、読人しらず)。古注では『異本紫明抄』が指摘するが、現行の注釈書では指摘されない。
【さすがに限りある世になむ】- 『集成』は「やはり世間とはそうしたものでございます。いくら悲しくても、いつまでも悲しんではいられない、というほどの意」と注す。
|
| 5.6.5 |
と、慰めきこえたまふ。
|
と、お慰め申し上げなさる。
|
などと大将は慰めていた。
|
|
| 5.6.6 |
|
「この宮は、聞いていたよりも奥ゆかしいところがお見えになるが、お気の毒に、なるほど、どんなにか外聞の悪い事を加えてお嘆きになっていられることだろう」
|
この宮は以前噂に聞いていたよりも優美な女性らしいが、お気の毒にも良人にお別れになった悲しみのほかに、世間から不幸な人におなりになったことを憐れまれるのを苦しく思っておいでになるのであろう
|
【この宮こそ】- 以下「取り添へて思すらむ」まで、夕霧の心中。落葉宮を思う。
【げに、いかに人笑はれなることを取り添へて思すらむ】- 『集成』は「ほんとに、どんなにか世間の笑いものになることを、死別の悲しみに加えて、お悩みのことだろう。皇女としての体面を苦にしておいでだろう、の意」と注す。
|
| 5.6.7 |
と思ふもただならねば、いたう心とどめて、御ありさまも問ひきこえたまひけり。
|
と思うと心が動くので、たいそう心をこめて、ご様子をもお尋ね申し上げなさった。
|
と思う同情の念がいつかその方を恋しく思う心に変わってゆくのをみずから認めるようになった大将は熱心に宮の御近状などを御息所に尋ねていた。
|
|
| 5.6.8 |
|
「器量などはとても十人並でいらっしゃるまいけれども、ひどくみっともなくて見ていられない程でなければ、どうして、見た目が悪いといって相手を嫌いになったり、また、大それたことに心を迷わすことがあってよいものか。
みっともないことだ。
ただ、気立てだけが、結局は、大切なのだ」とお考えになる。
|
御容貌はそうよくはおありでならないであろうが、醜くて気の毒な気持ちのする程度でさえなければ、外見だけのことでその人がいやになるようなことがあったり、ほかの人に心を移すようなことは自分にできるはずがない、そんな恥知らずなことは自分の趣味でない、性格のよしあしで尊重すべき女と、そうでない女は別けらるべきであるなどと思っていた。
|
【容貌ぞいとまほには】- 以下「やむごとなかるべけれ」まで、夕霧の心中。『完訳』は「ご器量はそれほど申し分のないというほどではいらっしゃらないようだけれど」「柏木の情愛の薄さを根拠に推量」と注す。
【見る目により】- 明融臨模本、朱合点。大島本、朱合点、行間書入「伊勢の海人の朝な夕なに」。「伊勢の海人の朝な夕なにかづくてふみるめに人をあくよしもがな」(古今集恋四、六八三、読人しらず)。古注では『異本紫明抄』が指摘する。
【人をも思ひ飽き、また、さるまじきに心をも惑はすべきぞ】- 『集成』は「柏木のことを思うのである」と注す。
|
| 5.6.9 |
「今はなほ昔に思ほしなずらへて、疎からずもてなさせたまへ」 |
「今はやはり故人と同様にお考え下さって、親しくお付き合い下さいませ」
|
「もうお心安くなったのですから、衛門督をお取り扱いになりましたごとく、私を他人らしくなく御待遇くださいますように」
|
【今はなほ】- 以下「もてなさせたまへ」まで、夕霧の詞。
|
| 5.6.10 |
など、わざと懸想びてはあらねど、ねむごろにけしきばみて聞こえたまふ。直衣姿いとあざやかにて、丈だちものものしう、そぞろかにぞ見えたまひける。 |
などと、特に色めいたおっしゃりようではないが、心を込めて気のある申し上げ方をなさる。
直衣姿がとても鮮やかで、背丈も堂々と、すらりと高くお見えであった。
|
などと、恋を現わして言うのではないが、持ってほしい好意をねんごろに要求する大将であった。
|
【そぞろかに】- 定家筆本と明融臨模本は「そろゝかに」とある。大島本は「そゝろかに」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「そぞろかに」と校訂する。『新大系』は底本(大島本)のままとする。
|
| 5.6.11 |
「かの大殿は、よろづのことなつかしうなまめき、あてに愛敬づきたまへることの並びなきなり」 |
「お亡くなりになった殿は、何事にもお優しく美しく、上品で魅力的なところがおありだったことは無類でした」
|
その直衣姿は清楚で、背が高くりっぱに見えた。六条院様はなつかしく艶な美貌で、そしてお品のよい愛嬌が無類なのですよ。
|
【かの大殿は】- 以下「人に似ぬや」まで、女房の詞。「かの大殿」は柏木をさす。夕霧との比較。
|
| 5.6.12 |
「これは、男々しうはなやかに、あなきよらと、ふと見えたまふにほひぞ、人に似ぬや」
|
「こちらは、男性的で派手で、何と美しいのだろうと、直ぐにお見えになる美しさは、ずば抜けています」
|
この方は男らしくはなやかで、ああきれいだと思う第一印象がだれよりもすぐれておいでになりますよ」
|
|
| 5.6.13 |
と、うちささめきて、
|
と、ささやいて、
|
などと女房たちは言って、
|
|
| 5.6.14 |
|
「同じことなら、このようにしてお出入りして下さったならば」
|
「かなうことなら宮様の殿様におなりになって始終おいでくださることになればいい」
|
【同じうは、かやうにても出で入りたまはましかば】- 女房の詞。反実仮想がやがて本物の事態となる。
|
| 5.6.15 |
など、人びと言ふめり。
|
などと、女房たちは言っているようである。
|
こんなことまでも思ったに違いない。
|
|
| 5.6.16 |
|
「右将軍の墓に草初めて青し」
|
「右将軍が墓に草はじめて青し」
|
【右将軍が墓に草初めて青し】- 夕霧の詞。口ずさみ。明融臨模本、付箋「右大将保忠カ事ヲ作レル也/天與善人吾不信/右将軍墓草初青(秋)紀在昌」。大島本、行間書入「時平子右大将保忠墓ヲシテ紀在昌作詩右将軍カ墓草初秋ナリ」。中山家本、朱合点、奥入「天與善人吾不信右将軍墓草初青」と指摘。古注では『源氏釈』が「天與善人吾不信右将軍墓草初青(秋)」と指摘する。紀在昌の詩句は『本朝秀句』所収。現在逸書。『河海抄』所引によれば、原詩は「初青」ではなく「初秋」とあった。夕霧が言い換えたものか。
|
| 5.6.17 |
と、うち口ずさびて、それもいと近き世のことなれば、さまざまに近う遠う、心乱るやうなりし世の中に、高きも下れるも、惜しみあたらしがらぬはなきも、むべむべしき方をばさるものにて、あやしう情けを立てたる人にぞものしたまひければ、さしもあるまじき公人、女房などの年古めきたるどもさへ、恋ひ悲しびきこゆる。まして、上には、御遊びなどの折ごとにも、まづ思し出でてなむ、しのばせたまひける。 |
と口ずさんで、それも最近の事だったので、あれこれと近頃も昔も、人の心を悲しませるような世の中の出来事に、身分の高い人も低い人も、惜しみ残念がらない者がないのも、もっともらしく格式ばった事柄はそれとして、不思議と人情の厚い方でいらっしゃったので、大したこともない役人、女房などの年取った者たちまでが、恋い悲しみ申し上げた。
それ以上に、主上におかせられては、管弦の御遊などの折毎に、まっさきにお思い出しになって、お偲びあそばされた。
|
と大将は口ずさみながらも、この詩も近ごろ逝った人を悼んだ詩であることから、詩の中の右将軍の惜しまれたと同じように、世人が上下こぞって惜しんだ幾月か前の友人の死を思うのであった。帝も音楽の遊びを催される時などには、いつの場合にも衛門督を御追憶あそばすのであった。
|
【それもいと近き世のことなれば】- 右大将藤原保忠の死去は朱雀天皇の承平六年(九三六)七月十四日。四十七歳。
【むべむべしき方をばさるものにて】- 『集成』は「人柄の表立った面は言うまでもないとして」「公人としての才幹、学識、技芸といった面をいう」。『完訳』は「もっともらしく格式ばった事柄。公人としての才学、技芸」と注す。
|
| 5.6.18 |
|
「ああ、衛門督よ」
|
「ああ衛門督が」
|
【あはれ、衛門督】- 『新し大系』は「あああ、衛門督よ。物語の読者は前の女三宮へことづけた柏木の「あはれとだにのたまはせよ」という遺志が残されたみなに行き渡っている感じを受け取る」と注す。
|
| 5.6.19 |
といふ言種、何ごとにつけても言はぬ人なし。
六条院には、ましてあはれと思し出づること、月日に添へて多かり。
|
と言う口癖を、何事につけても言わない人はいない。
六条院におかれては、まして気の毒にとお思い出しになること、月日の経つにつれて多くなっていく。
|
という言葉を何につけても言わない人はないのである。六条院はまして故人をお憐れみになることが月日に添えてまさっていった。
|
|
| 5.6.20 |
この若君を、御心一つには形見と見なしたまへど、人の思ひ寄らぬことなれば、いとかひなし。秋つ方になれば、この君は、ゐざりなど。 |
この若君を、お心の中では形見と御覧になるが、誰も知らないことなので、まことに何の張り合いもない。
秋頃になると、この若君は、這い這いをし出したりなどして。
|
宮の若君を院のお心だけでは衛門督の形見と見ておいでになるのであるが、だれも、この形見のあるのは知らぬことであったから、何ものからも面影をとらえることは不可能だと思って衛門督を悲しんでいるのであった。秋になったころからこの若君は這いなどなさる様子が言いようもないくらいかわいいので、院は人前ばかりでなく、しんからいとしくて、いつも抱いて大事になさるのであった。
|
【この君は、ゐざりなど】- 河内本はこの後にさらに五十八字の文章が続く。別本では御物本と保坂本に同文がある。大島本は切り裂いて削除した跡が見られる。言いさした終わり方である。
|
| 著作権 |
| 底本 |
定家自筆本 |
| 校訂 |
Last updated 9/22/2010(ver.2-3)
渋谷栄一校訂(C)
オリジナル
修正版
比較 |
| ローマ字版 |
Last updated 6/4/2010 (ver.2-2)
Written in Japanese roman letters
by Eiichi Shibuya (C)
オリジナル
修正版
比較 |
ルビ抽出
(ローマ字版から)
|
Powered by 再編集プログラム v4.05
ひらがな版
ルビ抽出 |
挿絵
(ローマ字版から)
|
'Eiri Genji Monogatari'
(1650 1st edition) |
|
Last updated 1/18/2002
渋谷栄一訳(C)(ver.1-2-2)
オリジナル
修正版
比較 |
|
|
Last updated 6/4/2010(ver.2-2)
渋谷栄一注釈(C)
オリジナル
修正版
比較 |
|