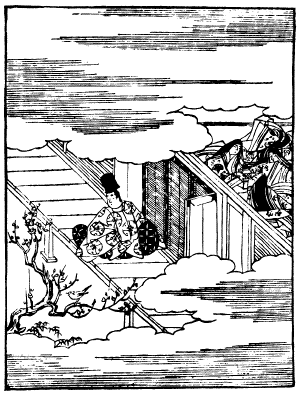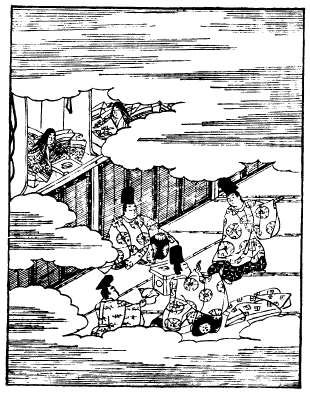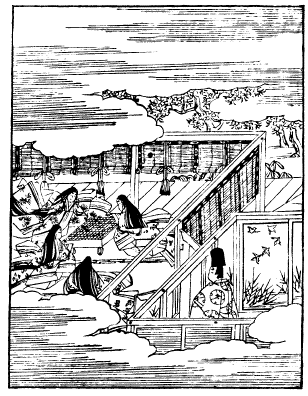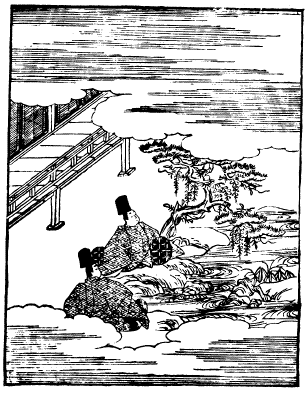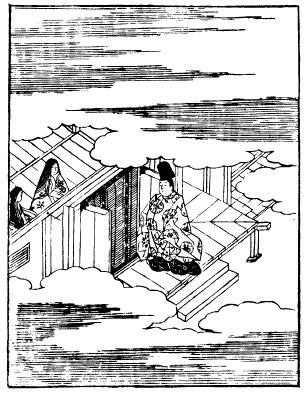第四十四帖 竹河
薫君の中将時代十五歳から十九歳までの物語
|
# |
本文 |
渋谷栄一訳 |
与謝野晶子訳 |
注釈 |
|
第一章 鬚黒一族の物語 玉鬘と姫君たち
|
|
第一段 鬚黒没後の玉鬘と子女たち
|
| 1.1.1 |
|
これは、源氏のご一族からも離れていらっしゃった、後の大殿あたりにいたおしゃべりな女房たちで、死なずに生き残った者が、問わず語りに話しておいたのは、紫の物語にも似ないようであるが、あの女どもが言ったことは、「源氏のご子孫について、間違った事柄が交じって伝えられているのは、自分よりも年輩で、耄碌した人のでたらめかしら」などと不審がったが、どちらが本当であろうか。
|
ここに書くのは源氏の君一族とも離れた、最近に亡くなった関白太政大臣の家の話である。つまらぬ女房の生き残ったのが語って聞かせたのを書くのであるから、紫の筆の跡には遠いものになるであろう。またそうした女たちの一人が、光源氏の子孫と言われる人の中に、正当の子孫と、そうでないのとがあるように思われるのは、自分などよりももっと記憶の不確かな老人が語り伝えて来たことで、間違いがあるのではないかと不思議がって言ったこともあるのであるから、今書いていくことも皆真実のことでなかったかもしれないのである。
|
【これは、源氏の御族にも離れたまへりし、後の大殿わたりにありける悪御達の】- 『弄花抄』は「凡此物語を紫式部か作とも見せす其意也紫式部か決したる語也古き事と見えたり紫式部が作せさる心也」。『玉の小櫛』は「上の語をうけて、此物語の作りぬしのいふ也。そは後の大殿わたりの女房は、紫上の御方の女房の、源氏君の御末々の人々の事を、かたりおきたるは、ひがことども多きを、我らが申す、此大殿わたりの事共は、みなまこと也とて、語りたる。二方ともに、年老いたる人々の、語りしことなれば、いづ方かまことならん、ともにさだかならぬ事なれども、まづ聞きたるまゝに、いづ方をもすてず、しるしおくぞといふ意にて、その紫上の御方の女房の語れるは、匂宮の巻、後の大殿わたりの女房のかたれるは、即ち此巻也。さて此物語は、すべてみな作り物がたりなるを、実に世に有し事を、人の語れるを聞て、書るごとく、ことさらおぼめきて、かくいへるも一つの興也」と指摘する。鬚黒大将家の物語。 【悪御達の】-『集成』は「おしゃべりな女房たちで」。『完訳』は「いかがわしい女房たちの」と訳す。
【源氏の御末々に】- 以下「ひがことにや」まで、鬚黒周辺の御達の噂。
|
| 1.1.2 |
|
尚侍のお生みになった、故殿のご子息女は、男三人、女二人がいらっしゃったが、それぞれに大切にお育てすることをお考えおきになっていて、年月がたつのも待ち遠しく思っていらっしゃったうちに、あっけなくお亡くなりになってしまったので、夢のようで、早く早くと急いで思っていらした宮仕えもたち消えになってしまった。
|
玉鬘の尚侍の生んだ故人の関白の子は男三人と女二人であったが、どの子の未来も幸福にさせたい、どんなふうに、こんなふうにと空想を大臣は描いて、成長するのをもどかしいほどに思っているうちに、突然亡くなったので、遺族は夢のような気がして、大臣の志していた姫君を宮中へ入れることもそのままに捨てておくよりしかたがなかった。
|
【尚侍の御腹に】- 玉鬘をさす。
【いつしかといそぎ思しし御宮仕へも】- 姫君の入内の件。
|
| 1.1.3 |
人の心、時にのみよるわざなりければ、さばかり勢ひいかめしくおはせし大臣の御名残、うちうちの御宝物、領じたまふ所々のなど、その方の衰へはなけれど、おほかたのありさま引き変へたるやうに、殿のうちしめやかになりゆく。 |
人の心は、時の権勢にばかりおもねるものだから、あれほど威勢よくいらした大臣の亡くなった後は、内々のお宝物、所領なさっている所々など、その方面の衰退はなかったが、大方の有様はうって変わったように、お邸の中はひっそりとなってゆく。
|
世間の人は目の前の勢いにばかり寄ってゆくものであったから、強大な権力をふるっていた関白のあとも、財産、領地などは少なくならないが、出入りする人が見る見る減って、寂しく静かな家になった。
|
【領じたまふ所々のなど】- 大島本は「所々の」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「所々」と「の」を削除する。『新大系』は底本のままとする。
|
| 1.1.4 |
|
尚侍の君のご身辺の縁者は、大勢世の中に広がっていらっしゃったが、かえって高貴な方々のお間柄で、もともと親しくはなかったので、故殿の、人情味が少し欠け、好き嫌いがはげしくいらっしゃるご性質なので、けむたがられることもあったせいであろうか、誰とも親しく交際申し上げられないでいらっしゃる。
|
玉鬘夫人の兄弟たちは広く栄えているのであるが、貴族たちの肉親どうしの愛は一般人よりもかえって薄いもので、大臣の生きている間さえもそう親密に往来をしなかった上に、大臣が少し思いやりのない、むら気な性質で恨みを買うこともしたためにか、遺族の力になろうとする人も格別ないのであった。
|
【御仲らひの】- 格助詞「の」は同格。
【心おかれたまふこともありけるゆかりにや】- 語り手の挿入句。
【誰れにも】- 『集成』が「ご兄弟のどなたとも」と注す。
|
| 1.1.5 |
|
六条院におかれては、総じて、やはり昔と変わらず娘分としてお扱い申されて、お亡くなりになった後のことも、お書き残しなさったご相続の文書などにも、中宮のお次にお加え申されていたので、右の大殿などは、かえってその気持ちがあって、しかるべき折々にはご訪問申される。
|
六条院は初めと変わらず子の一人として尚侍を見ておいでになって、御遺言状の遺産の分配をお書きになったものにも、冷泉院の中宮の次へ尚侍をお加えになったために、夕霧の右大臣などはかえって兄弟の情をこの夫人に持っていて、何かの場合には援助することも忘れなかった。
|
【六条院には、すべて、なほ昔に変らず数まへきこえたまひて】- 「六条院」は源氏をさす。生前のこと。『集成』は「家族の一員として」と注す。
【中宮の御次に】- 明石中宮の次に。
【右の大殿などは】- 夕霧。
|
|
第二段 玉鬘の姫君たちへの縁談
|
| 1.2.1 |
|
男君たちは、ご元服などして、それぞれ成人なさったので、殿がお亡くなりになって後、不安で気の毒なこともあるが、自然と出世なさって行くようである。
「姫君たちをどのようにお世話申し上げよう」と、お心を悩ましなさる。
|
男の子たちは元服などもして、それぞれ一人並みになっていたから、父の勢力に引かれておれば思うようにゆくところがゆかぬもどかしさはあるといっても、自然に放任しておいても年々に出世はできるはずであった。姫君たちをどうさせればよいことかと尚侍は煩悶しているのである。
|
【殿のおはせでのち】- 大島本は「殿の」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「殿」と「の」を削除する。『新大系』は底本のままとする。
【おのづからなり出でたまひぬべかめり】- 推量助動詞「めり」主観的推量のニュアンスは語り手のもの。
|
| 1.2.2 |
|
帝におかれても、是非とも宮仕えの願いが深い旨を、大臣が奏上なさっていたので、成人なさったであろう年月を御推察あそばして、入内の仰せ言がしきりにあるが、中宮が、ますます並ぶ人のいないようになって行かれる御様子に圧倒されて、誰も彼も無用の人のようでいらっしゃる末席に入内して、遠くから睨まれ申すのも厄介で、また人より劣って、数にも入らない様子なのを世話するのも、はたまた、気苦労であろうことを思案なさっている。
|
帝にも宮仕えを深く希望することを大臣は申し上げてあったので、もう妙齢に達したはずであると、年月をお数えになって入内の御催促が絶えずあるのであるが、中宮お一人にますます寵が集まって、他の後宮たちのみじめである中へ、おくれて上がって行ってねたまれることも苦しいことであろうと思われるし、また存在のわからぬ哀れな後宮に娘のなっていることも親として見るに堪えられないことであるからと思って、尚侍はお請けをするのに躊躇されるのであった。
|
【内裏にも】- 帝に対してもの意。
【おとなびたまひぬらむ】- 推量助動詞「らむ」、作中人物の帝の視界外推量のニュアンス。
【推し量らせたまひて】- 帝の動作についての最高尊敬。
【中宮の、いよいよ並びなく】- 『完訳』は「以下、玉鬘の心」と注す。
【皆人無徳にものしたまふめる末に参りて】- 『集成』は「どなたも形なしといった有様でいらっしゃる末席に列なって」。『完訳』は「どなたもみなあってなきがごとくでいらっしゃる、その末席に連なって」と訳す。
【遥かに目を側められたてまつらむも】- 『奥入』は「未だに君王に面を見ること得ること容されざるに已に楊妃に遥かに目を側められたり」(白氏文集、上陽白髪人)を指摘。
|
| 1.2.3 |
|
冷泉院から、たいそう御懇切に御所望あそばして、尚侍の君が、昔、念願叶わずに今までお過ごしになって来た辛さまでを、思い出してお恨み申し上げられて、
|
冷泉院から御懇切に女御として院参をさせるようにとお望みになって、昔尚侍がお志を無視して大臣へ嫁いでしまったことまでもまた恨めしげに仰せられて、
|
【冷泉院よりは】- 大島本は「れせい院よりハ」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「冷泉院より」と「は」を削除する。『新大系』は底本のままとする。
【尚侍の君の、昔、本意なくて過ぐしたまうし辛さを】- 玉鬘が尚侍として冷泉院の在位中にに出仕したにもかかわらず鬚黒の北の方となってしまったことをさす。
|
| 1.2.4 |
|
「今はもう、いっそう年も取って、つまらない様子だとお思い捨てていらっしゃるとも、安心な親と思いなぞらえて、お譲りください」
|
今ではいっそう年もとり、光の淡い身の上になっていて取柄はないでしょうが、安心のできる親代わりとして私にください。
|
【今は、まいて】- 以下「譲りたまへ」まで、冷泉院の詞。
【さだ過ぎ、すさまじきありさまに】- 冷泉院自身の退位した有様をいう。
|
| 1.2.5 |
と、いとまめやかに聞こえたまひければ、「いかがはあるべきことならむ。みづからのいと口惜しき宿世にて、思ひの外に心づきなしと思されにしが、恥づかしうかたじけなきを、この世の末にや御覧じ直されまし」など定めかねたまふ。 |
と、たいそう真面目に申し上げなさったので、「どうしたらよいことだろう。
自分自身のまことに残念な運命で、思いの外に気にくわないとお思いあそばされたのが、恥ずかしく恐れ多いことだが、この晩年に御機嫌を直していただけようか」などと決心しかねていらっしゃる。
|
お手紙にはこんなふうなお言葉もあるのであったから、これはどうであろう、自分が前生の宿縁で結婚をしたあとでお目にかかったのを飽きたらず思召したことが、恥ずかしくもったいないことだったのであるから、お詫びに代えようかなどとも思って、なお尚侍は迷っていた。
|
【いかがはあるべきことならむ】- 以下「御覧じ直されまし」まで、玉鬘の心中。
|
|
第三段 夕霧の息子蔵人少将の求婚
|
| 1.3.1 |
容貌いとようおはする聞こえありて、心かけ申したまふ人多かり。右の大殿の蔵人少将とかいひしは、三条殿の御腹にて、兄君たちよりも引き越し、いみじうかしづきたまひ、人柄もいとをかしかりし君、いとねむごろに申したまふ。 |
器量がたいそう優れていらっしゃるという評判があって、思いをお寄せ申し上げる人びとが多かった。
右の大殿の蔵人少将とか言った人は、三条殿がお生みになった方は、兄弟たちを越えて、たいそう大事になさり、人柄もとても素晴らしかった方なので、とても熱心に求婚なさる。
|
美人であるという評判があって恋をする人たちも多かった。右大臣家の蔵人少将とか言われている子息は、三条の夫人の子で、近い兄たちよりも先に役も進み大事がられている子で、性質も善良なできのよい人が熱心な求婚者になっていた。
|
【三条殿の御腹にて】- 雲居雁所生の子。
|
| 1.3.2 |
|
どちらの関係からしても、血縁の繋がっているお間柄なので、この君たちが慕ってお伺いなどなさる時は、よそよそしくお扱いなさらない。
女房にも親しくなじんでは、意中を伝えるにも手立てがあって、昼夜、お側近くお耳に入れる騒がしさを、煩わしいながらも、お気の毒なので、尚侍の殿もお思いになっていた。
|
父母のどちらから言っても近い間柄であったから、右大臣家の息子たちの遊びに来る時はあまり隔てのない取り扱いをこの家ではしているのであって、女房たちにも懇意な者ができ、意志を通じるのに便宜があるところから、夜昼この家に来ていて、うるさい気もしながら心苦しい求婚者とは尚侍も見ていた。
|
【いづ方につけても、もて離れたまはぬ御仲らひなれば】- 玉鬘の姫君と夕霧の子の蔵人少将は、玉鬘と夕霧は義理の姉弟、また玉鬘と雲居雁は異腹の姉妹の関係である。
【尚侍の殿も】- 玉鬘。尚侍の殿という呼称。
|
| 1.3.3 |
|
母北の方からのお手紙も、しばしば差し上げなさって、「とても軽い身分でございますが、お許しいただける点もございましょうか」と、大臣も申し上げなさるのだった。
|
母の雲井の雁夫人からもそのことについての手紙も始終寄せられていた。
まだ軽い身分ですが、しかもお許しくださる御好意を、あるいはお持ちくださることかと思われます。
と夕霧の大臣からも言ってよこされた。
|
【母北の方】- 蔵人少将の母雲居雁。
【いと軽びたるほどにはべるめれど、思し許す方もや】- 雲居雁の手紙文かと思えるが、後文により、夕霧の詞である。「母北の方の」云々と「大臣も」云々が並列の構文になっている。
|
| 1.3.4 |
|
姫君を、まったく臣下に縁づけようとはなさらず、中の君を、もう少し世間の評判が軽くなくなったら、そうとも考えようか、とお思いでいらっしゃるのだった。
お許しにならなかったら、盗み取ってしまおうと、気持ち悪いまで思っていた。
不釣合な縁談だとはお思いにならないが、女のほうで承知しない間違いが起こるのは、世間に聞こえても軽率なことなので、取り次ぐ女房に対しても、「ゆめゆめ、間違いを起こすな」などとおっしゃるので、気がひけて、億劫がるのであった。
|
玉鬘夫人は上の姫君をただの男とは決して結婚させまいと思っていた。次の姫君はもう少し少将の官位が進んだのちなら与えてもさしつかえがないかもしれぬと思っていた。少将は許しがなければ盗み取ろうとするまでに深い執着を持っているのである。もってのほかの縁と玉鬘夫人は思っているのではないが、女のほうで同意をせぬうちに暴力で結婚が遂行されることは、世間へ聞こえた時、こちらにも隙のあったことになってよろしくないと思って、蔵人少将の取り次ぎをする女房に、
「決して過失をあなたたちから起こしてはなりませんよ」
といましめているので、その女も恐れて手の出しようがないのである。
|
【姫君をば、さらにただのさまにも思しおきてたまはず】- 「姫君」は大君。臣下との結婚、すなわち蔵人少将との結婚は考えていない。
【中の君をなむ】- 玉鬘は、蔵人少将を中君の結婚相手に考えている。
【今すこし世の聞こえ軽々しからぬほどになずらひならば】- 主語は蔵人少将。
【あな、かしこ。--過ち引き出づな】- 玉鬘の詞。
【朽たされてなむ、わづらはしがりける】- 主語は、姫君付の女房たち。
|
|
第四段 薫君、玉鬘邸に出入りす
|
| 1.4.1 |
|
六条院のご晩年に、朱雀院の姫宮からお生まれになった君、冷泉院におかれて、お子様のように大切にされている四位の侍従は、そのころ十四、五歳ほどになって、とても幼い子供の年の割合には、心構えも大人のようで、好ましく、人より優れた将来性がはっきりお見えになるので、尚侍の君は、婿として世話したくお思いになっていた。
|
六条院が晩年に朱雀院の姫宮にお生ませになった若君で、冷泉院が御子のように大事にあそばす四位の侍従は、そのころ十四、五で、まだ小さく、幼いはずであるが、年齢よりも大人びて感じのよい若公達になっていて、将来の有望なことが今から思われる風貌の備わった人であるのを、尚侍は婿にしてみたいように思っていた。
|
【朱雀院の宮の御腹に生まれたまへりし君】- 朱雀院の内親王女三の宮が生んだ源氏の子、薫、の意。
【四位侍従、そのころ十四、五ばかりにて】- 『完訳』は「十四歳の二月に侍従、秋、右近中将に昇進(匂宮巻)。侍従は従五位下。官位相当より上の位の者は、位を示して呼ぶ」と注す。
【尚侍の君は】- 玉鬘は夕霧の子の蔵人少将よりも源氏の子の薫四位侍従を重んじ、中君の婿にと思っている。
|
| 1.4.2 |
この殿は、かの三条の宮といと近きほどなれば、さるべき折々の遊び所には、君達に引かれて見えたまふ時々あり。心にくき女のおはする所なれば、若き男の心づかひせぬなう、見えしらひさまよふ中に、容貌のよさは、この立ち去らぬ蔵人少将、なつかしく心恥づかしげに、なまめいたる方は、この四位侍従の御ありさまに、似る人ぞなかりける。 |
この邸は、あの三条宮とたいそう近い距離なので、しかるべき折々の遊び所としては、公達に連れられてお見えになる時々がある。
奥ゆかしい女君のいらっしゃる邸なので、若い男で気取らない者はなく、これ見よがしに振る舞っている中で、器量のよい人は、この立ち去らない蔵人少将、親しみやすく気恥ずかしくて、優美な点では、この四位侍従のご様子に、似る者はいなかった。
|
この邸は女三の尼宮の三条のお邸に近かったから、源侍従は何かの時にはよくここの子息たちに誘われて遊びにも来るのであった。妙齢の女性のいる家であるから、出入りする若い男で、自身をよく見られたいと願わぬ人はないのであるが、容貌の美しいのは始終来る蔵人少将、感じのよい貴人らしい艶な姿のあることはこの四位の侍従に超えた人もなかった。
|
【この殿は】- 玉鬘邸。
【三条の宮と】- 薫邸。母女三の宮邸。
【見えしらひさまよふ中に】- 大島本は「見えしらひ」とある。『集成』『完本』『新大系』は諸本に従って「見えしらがひ」と「が」を補訂する。
|
| 1.4.3 |
|
六条院の感じを引く方と思うのが、格別なのであろうか、世間から自然と大切にされていらっしゃる方、若い女房たちは、特に誉め合っていた。
尚侍の殿も、「ほんとうに、感じのよい人だわ」などとおっしゃって、親しくお話し申し上げたりなさる。
|
六条院の御子という思いなしがしからしめるのか、源侍従はほかからも特別なすぐれた存在として扱われている人である。若い女房たちはことさら大騒ぎしてこの人をほめたたえるのであった。尚侍も、「人が言うとおりだね、実際すばらしい公達ね」などと言っていて、自身が出て親しく話などもするのであった。
|
【六条院の御けはひ近うと思ひなすが、心ことなるにやあらむ】- 『完訳』は「源氏の子と世人が思い込むせいか。源氏の子でない真相を知ったうえでの、語り手の言辞」と注す。
【もてかしづかれたまへる人】- 大島本は「もてかしつかれ給へる人」とある。『集成』『完本』『新大系』は諸本に従って「人なり」と「なり」を補訂する。
【若き人びと】- 玉鬘邸の若い女房たち。
【げにこそ、めやすけれ】- 玉鬘の詞。
|
| 1.4.4 |
「院の御心ばへを思ひ出できこえて、慰む世なう、いみじうのみ思ほゆるを、その御形見にも、誰れをかは見たてまつらむ。右の大臣は、ことことしき御ほどにて、ついでなき対面もかたきを」 |
「院のご性質をお思い出し申し上げて、慰められる時もなく、ひどく悲しくばかり思われるので、そのお形見として、どなたをお思い申し上げたらよいのでしょう。
右の大臣は、重々しい方で、機会のない対面は難しいし」
|
「院の御親切を思うと、お別れしてしまったことが、ひどい損失のような気がして、悲しくばかりなる私が、お形見と思ってお顔を見ることのできる方でも、右大臣はあまりにごりっぱな御身分で、何かの機会でもなければお逢いすることもできないのだから」
|
【院の御心ばへを】- 以下「かたきを」まで、玉鬘の詞。
|
| 1.4.5 |
|
などおっしゃって、姉弟のようにお思い申し上げていらっしゃるので、あの侍従君も、そのような所と思って参上なさる。
世間によくある好色がましいところも見えず、とてもひどく落ち着いていらっしゃるので、あちらこちらの邸の若い女房たちは、残念に物足りなく思って、言葉をかけて困らせまるのであった。
|
と言っていて、尚侍は源侍従を弟と思って親しみを持っているのであったから、その人も近い親戚の家としてここへ出てくるのである。若い人に共通した浮わついたことも言わず、落ち着いたふうを見せていることで、二人の姫君付きの女房は皆物足らぬように思って、いどみかかるふうな冗談もよく言いかけるのだった。
|
【兄弟のつらに思ひきこえたまへれば】- 玉鬘は薫を弟(義理弟)と思っている。
【かの君も】- 薫をさす。薫も玉鬘邸を姉の邸と思って。
【ここかしこの若き人ども】- 三条宮邸や玉鬘邸の若い女房たち。
|
|
第二章 玉鬘邸の物語 梅と桜の季節の物語
|
|
第一段 正月、夕霧、玉鬘邸に年賀に参上
|
| 2.1.1 |
|
正月朔日ころ、尚侍の君のご兄弟の大納言、「高砂」を謡った方だが、藤中納言、故大殿の太郎君で、真木柱と同じ母親の方などが参賀にいらっしゃった。
右大臣も、ご子息たちを六人そのままお連れしていらっしゃった。
ご器量をはじめとして、非のうちどころなく見える方のご様子やご評判である。
|
正月の元日に尚侍の弟の大納言、子供の時に父といっしょに来て、二条の院で高砂を歌った人であるその人、藤中納言、これは真木柱の君と同じ母から生まれた関白の長子、などが賀を述べに来た。右大臣も子息を六人ともつれて出てきた。容貌を初めとしてまた並ぶ人なきりっぱな大官と見えた。
|
【尚侍の君の御兄弟の大納言】- 玉鬘の実の姉弟の紅梅大納言。ただし異母姉弟。
【高砂」謡ひしよ】- 『弄花抄』は「注也」。『評釈』は「大納言についての説明。大納言はすでに「紅梅」の巻で活躍しているから、説明がなくても一応は判るが、語り手は一言つけ加えた。その理由の一つはこの巻の語り手が、それまでと違ってかんの君方の古女房だからである。他の一つはこういうさりげない一言で、物語の世界に深みをあたえ、時間的遠近法の効果をはかった」と注す。
【藤中納言、故大殿の太郎、真木柱の一つ腹など】- 藤中納言の説明。故鬚黒の太郎君で真木柱の姫君と同腹の人、という説明。
【右の大臣も、御子ども六人ながらひき連れておはしたり】- 『集成』は「北の方(雲居の雁)腹の長男、三、五、六男と、藤典侍腹の二、四男。蔵人の少将は、五男であろう」と注す。
|
| 2.1.2 |
|
ご子息たちも、それぞれとても美しくて、年齢の割合には、官位も進んで、きっと何の物思いもなく見えたであろう。
いつも、蔵人の君は、大切にされていることは格別であるが、ふさぎ込んで悩み事のある顔をしている。
|
子息たちもそれぞれきれいで、年齢の割合からいって、皆官位が進んでいた。物思いなどは少しも知らずにいるであろうと見えた。いつものように蔵人少将はことに秘蔵息子らしくその中でも見えたが、気の浮かぬふうが見え、恋をしている男らしく思われた。
|
【何ごと思ふらむと】- 大島本は「なにこと」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「何ごとを」と「を」を補訂する。『新大系』は底本のままとする。
【思ふことあり顔なり】- 恋煩いのさま。
|
| 2.1.3 |
大臣は、御几帳隔てて、昔に変らず御物語聞こえたまふ。
|
大臣は、御几帳を隔てて、昔と変わらずお話し申し上げなさる。
|
大臣は几帳だけを隔てにして、尚侍と昔に変わらぬふうで語るのであった。
|
|
| 2.1.4 |
「そのこととなくて、しばしばもえうけたまはらず。年の数添ふままに、内裏に参るより他のありき、うひうひしうなりにてはべれば、いにしへの御物語も、聞こえまほしき折々多く過ぐしはべるをなむ。 |
「これという用事もなくて、たびたびお話を承ることもできません。
年齢が加わるとともに、宮中に参内する以外の外歩きなども、億劫になってしまいましたので、昔のお話も、申し上げたい時々も多くそのままになってしまいました。
|
「用のない時にも伺わなければならないのを、失礼ばかりしています。年がいってしまいまして、御所へまいる以外の外出がもういっさいおっくうに思われるものですから、昔の話を伺いたい気持ちになります時も、そのままに済ませてしまうようになるのを遺憾に思います。
|
【そのこととなくて】- 以下「いましめはべり」まで、夕霧の玉鬘への詞。
【他のありき】- 大島本は「ありき」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「ありきなど」と「など」を補訂する。『新大系』は底本のままとする。
|
| 2.1.5 |
若き男どもは、さるべきことには召しつかはせたまへ。
かならずその心ざし御覧ぜられよと、いましめはべり」など聞こえたまふ。
|
若い男の子たちは、何かの時にはお呼びになってお使いください。
かならずその気持ちを見て戴くようにと、言い聞かせてあります」など申し上げなさる。
|
若い息子たちは何の御用にでもお使いください。誠意を認めていただくようにするがいいと教えております」
|
|
| 2.1.6 |
「今は、かく、世に経る数にもあらぬやうになりゆくありさまを、思し数まふるになむ、過ぎにし御ことも、いとど忘れがたく思うたまへられける」 |
「今では、このように、世間の人数にも入らぬ者のようになって行く有様を、お心に掛けてくださるので、亡くなった方のことも、ますます忘れ難く存じられるます」
|
「もうこの家などはだれの念頭にも置いていただけないものになっておりますのに、お忘れになりませんで御親切にお訪ねくださいましたのをうれしく存じますにつけましても、院の御厚志が私を今になっても幸福にしてくださるのだとかたじけなく思うのでございます」
|
【今は、かく】- 以下「思うたまへられける」まで、玉鬘の詞。
|
| 2.1.7 |
|
と申し上げなさったついでに、院から仰せになったことを、ちらっと申し上げなさる。
|
尚侍はこんなことを言ったついでに、冷泉院からあった仰せについて大臣へ相談をかけた。
|
【院より】- 冷泉院。
【ほのめかし聞こえたまふ】- 主語は玉鬘。『完訳』は「冷泉院の、姫君に参院せよとの仰せ言。蔵人の少将の求婚を婉曲に断るために言い出したか」と注す。
|
| 2.1.8 |
|
「これといった後見のない人の宮仕えは、かえって見苦しいと、あれこれ考えあぐねております」
|
「しかとした後援者を持ちませんものが、そうした所へ出てまいっては、かえって苦しみますばかりかとも思われますが」
|
【はかばかしう】- 以下「なむわづらふ」まで、玉鬘の詞。
【思ひたまへ】- 大島本は「おもひたまへ」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「かたがた思ひたまへ」と「かたがた」を補訂する。『新大系』は底本のままとする。
|
| 2.1.9 |
と申したまへば、
|
と申し上げなさるので、
|
|
|
| 2.1.10 |
「内裏に仰せらるることあるやうに承りしを、いづ方に思ほし定むべきことにか。院は、げに、御位を去らせたまへるにこそ、盛り過ぎたる心地すれど、世にありがたき御ありさまは、古りがたくのみおはしますめるを、よろしう生ひ出づる女子はべらましかばと、思ひたまへよりながら、恥づかしげなる御中に、交じらふべき物のはべらでなむ、口惜しう思ひたまへらるる。 |
「帝にも仰せられることがあるようにお聞きいたしておりましたが、どちらにお決めなさるべきでしょうか。
院は、なるほど、お位を退かれあそばしました点では、盛りの過ぎた感じもしますが、世に二人といない御様子は、いっこうに変わらずにいらっしゃるようですので、人並みに成人した娘がおりましたらと、存じておりますが、立派な方々のお仲間入りできる者がございませんで、残念に存じております。
|
「宮中からもお話があるということですが、どちらへおきめになっていいことでしょうね。院は御位をお去りになりまして、盛りの御時代は過ぎたように、ちょっと考えては思うでしょうが、たぐいもない御美貌でいらっしゃるのですから、まだお若々しくて、りっぱに育った娘があれば、差し上げたいという気に私もなるのですが、すぐれた後宮がおありになるのですから、その中へはいらせてよいような娘は私になくて、いつも残念に思われるのです。
|
【内裏に仰せらるること】- 以下「とどこほることもはべらじ」まで、夕霧の詞。
【よろしう生ひ出づる女子はべらましかば】- 大島本は「侍らましかハ」とある。『集成』『完本』『新大系』は諸本に従って「はべらましかばと」と「と」を補訂する。夕霧の娘。六人。うち大君は東宮に、中君は二の宮に入内。六の君は美貌で知られる。
|
| 2.1.11 |
|
そもそも、女一宮の母女御は、お許し申し上げなさるでしょうか。
これまでの方では、そのような遠慮によって、止めにしたこともございました」
|
いったい女一の宮の女御は同意されているのですか。これまでもよく人がそちらへの御遠慮から院参を断念したりするのでしたが」
|
【女一の宮の女御は】- 女一の宮の母女御の意。冷泉院の弘徽殿女御。
|
| 2.1.12 |
と申したまへば、
|
と申し上げなさると、
|
と大臣は質した。
|
|
| 2.1.13 |
|
「女御が、する事もなくのんびりとなった生活も、同じ気持ちでお世話して、気を晴らしたいなどと、その方がお勧めなさったことにかこつけて、せめてどうしたらよいものかと思案しております」
|
「女御さんから、つれづれで退屈な時間もあなたに代わってその人の世話をしてあげることで紛らしたいなどとお勧めになるものですから、私も院参を問題として考えるようになったのでございます」
|
【女御なむ、つれづれに】- 以下「思ひたまへよるになむ」まで、玉鬘の詞。
【後見て、慰めまほしきを】- 玉鬘の大君を。
|
| 2.1.14 |
と聞こえたまふ。
|
と申し上げなさる。
|
と尚侍は言っていた。
|
|
| 2.1.15 |
|
あの方この方と、こちらにお集まりになって、三条宮に参上なさる。
朱雀院の昔から御厚誼のある方々、六条院の側の方々も、それぞれにつけて、やはりあの入道の宮を、素通りできず参上なさるようである。
この殿の左近中将、右中弁、侍従の君なども、そのまま大臣のお供してお出になった。
引き連れていらっしゃった威勢は格別である。
|
あとからも来た高官たちはここでいっしょになって三条の宮へ参賀をするのであった。朱雀院の御恩顧を受けた人たちとか、六条院に近づいていた人たちとかは今も入道の宮へ時おりの敬意を表しにまいることを怠らないのであった。この家の左近中将、右中弁、侍従なども大臣の供をして出て行った。大臣の率いて行く人数にも勢力の強大さが思われた。
|
【これかれ、ここに集まりたまひて】- 夕霧右大臣や紅梅大納言らが玉鬘邸に参集なさって、の意。
【三条の宮に】- 薫の母宮、女三の宮邸。
【入道宮をば】- 源氏の正妻女三の宮。
【参りたまふなめり】- 語り手の推量。
【この殿の左近中将、右中弁、侍従の君なども】- 玉鬘邸の子息たち三人。
|
|
第二段 薫君、玉鬘邸に年賀に参上
|
| 2.2.1 |
|
夕方になって、四位侍従が参上なさった。
大勢の成人した若公達も、みなそれぞれに、どの人が劣っていようか。
みな感じのよい方の中で、ひと足後れてこの君がお姿をお見せになったのが、たいそう際立って目に止まった感じがして、例によって、熱中しやすい若い女房たちは、「やはり、格別だわ」などと言う。
|
夕方になって源侍従の薫がこの家へ来た。昼間玉鬘夫人の前へ現われたこの人よりもやや年長の公達も、それぞれの特色が備わっていて悪いところもなく皆きれいであったが、あとに来たこの人にはそれらを越えた美があって、だれの目も引きつけられるのであった。美しい物好きな若い女房たちなどは、「やっぱり違っておいでになる」などと言った。
|
【四位侍従】- 薫。
【この君の立ち出でたまへる】- 薫が姿を見せた。
【例の、ものめでする若き人たちは】- 玉鬘邸の若い女房たち。
【なほ、ことなりけり】- 玉鬘邸の若い女房たちの詞。薫を絶賛。
|
| 2.2.2 |
|
「この殿の姫君のお側には、この方をこそ並べて見たい」
|
「こちらのお姫様にはこの方を並べてみないでは」
|
【この殿の姫君の】- 以下「さしな並べて見め」まで、女房の詞。玉鬘の大君と薫の結婚を仮想。
|
| 2.2.3 |
|
と、聞きにくいことを言う。
なるほど、実に若く優美な姿態をして、振る舞っていらっしゃる匂い香など、尋常のものでない。
「姫君と申し上げても、物ごとのお分りになる方は、本当に人よりは優れているようだと、ご納得なさるに違いない」と思われる。
|
こんなことを聞きにくいまでに言ってほめる。そう騒がれるのにたるほどの優雅な挙止を源侍従は見せていて、身から放つ香も清かった。貴族の姫君といわれるような人でも頭のよい人はこの人をすぐれた人と言うのはもっともなことだとくらい認めるかと思われた。
|
【げに、いと若う】- 『林逸抄』は「双紙の詞也」と注す。「げに」は語り手が女房の詞に納得する気持ち。
【姫君と聞こゆれど】- 『一葉抄』は「傍人の批判したる也」と注す。
【見知りたまふらむかし」とぞおぼゆる】- 語り手の感想。
|
| 2.2.4 |
|
尚侍の殿は、御念誦堂にいらして、「こちらに」とおっしゃるので、東の階段から昇って、戸口の御簾の前にお座りになった。
お庭先の若木の梅が、頼りなさそうに蕾んで、鴬の初音もとてもたどたどしい声で鳴いて、まことに好き心を挑発してみたくなる様子をしていらっしゃるので、女房たちが戯れ言を言うと、言葉少なに奥ゆかしい態度なのを、悔しがって、宰相の君と申し上げる上臈が詠み掛けなさる。
|
尚侍は念誦堂にいたのであったが、
「こちらへ」
と言わせるので、東の階から上がって、妻戸の口の御簾の前へ薫はすわった。前になった庭の若木の梅が、まだ開かぬ蕾を並べていて、鶯の初声もととのわぬ背景を負ったこの人は、恋愛に関した戯れでも言わせたいような美しい男であったから、女房たちはいろいろな話をしかけるのであるが、静かに言葉少なな応対だけより侍従がしないのをくやしがって、宰相の君という高級の女房が歌を詠みかけた。
|
【こなたに】- 玉鬘の詞。薫を招く。
【いと好かせたてまほしきさま】- 大島本は「すかせたてまほしき」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「すかせたてまつらまほしき」と「まつら」を補訂する。『新大系』は底本のままとし、「「好(す)かせたつ」で一語」と注す。
【宰相の君と聞こゆる上臈の詠みかけたまふ】- 『集成』は「「聞こゆる」は、下の「たまふ」とともに、語り手の女房より宰相の君に対する敬語」。『完訳』は「螢に登場する女房とは別人か」と注す。
|
|
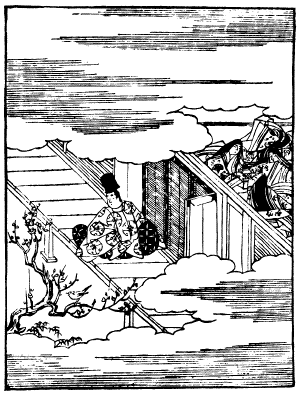 |
| 2.2.5 |
|
「手折ってみたらますます匂いも勝ろうかと
もう少し色づいてみてはどうですか、
|
折りて見ばいとど匂ひもまさるやと
少し色めけ梅の初花
|
【折りて見ばいとど匂ひもまさるやと--すこし色めけ梅の初花】- 宰相の君から薫への贈歌。真淵『新釈』は「よそにのみあはれとぞ見し梅の花あかぬ色香は折りてなりけり(古今集春上、三七、素性法師)を指摘。『完訳』は「「折りて見る」は情交を暗示。「梅の初花」は薫。女から男に戯れた歌」と注す。
|
| 2.2.6 |
「口はやし」と聞きて、
|
「詠みぶりが早いな」と感心して、
|
速く歌のできたことを薫は感心しながら、
|
|
| 2.2.7 |
|
「傍目には枯木だと決めていましょうが
心の中は咲き匂っていつ梅の初花ですよ
|
「よそにては捥木なりとや定むらん
下に匂へる梅の初花
|
【よそにてはもぎ木なりとや定むらむ--下に匂へる梅の初花】- 薫の返歌。「梅の初花」の語句をそのまま用いて返す。『完訳』は「内心の魅力を主張して戯れた歌」と注す。
|
| 2.2.8 |
|
そう言うなら手を触れて御覧なさい」などと冗談を言うと、
|
疑わしくお思いになるなら袖を触れてごらんなさい」などと言っていると、また女房は、
|
【さらば袖触れて見たまへ】- 薫の歌に添えた言葉。『源氏釈』は「色よりも香こそあはれと思ほゆれたが袖触れし宿の梅ぞも」(古今集春上、三三、読人しらず)を指摘。
|
| 2.2.9 |
|
「本当は色よりも」と、口々に、袖を引っ張らんばかりに付きまとう。
|
「真実は色よりも香」
口々にこんなことを言って、引き揺らんばかりに騒いでいるのを、
|
【まことは色よりも】- 女房の詞。「香が素晴らしい」の意が下に省略。
|
| 2.2.10 |
尚侍の君、奥の方よりゐざり出でたまひて、
|
尚侍の君は、奥の方からいざり出ていらっしゃって、
|
奥のほうからいざって出た玉鬘夫人が見て、
|
|
| 2.2.11 |
|
「困った人達だわ。
気恥ずかしそうなお堅い方までを、よくもまあ、厚かましくも」
|
「困った人、あなたたちは。きまじめな人をつかまえて恥ずかしい気もしないのかね」
|
【うたての御達や】- 以下「面無けれ」まで、玉鬘の詞。
|
| 2.2.12 |
|
と小声でおっしゃるようである。
「堅物と、あだ名されたようだ。
まったく情けない名だな」と思っていらっしゃった。
この家の侍従は、殿上などもまだしないので、あちらこちら年賀回りなどせずに、居合わせていらっしゃった。
浅香の折敷、二つほどに、果物、盃などを差し出しなさった。
|
とそっと言っていた。きまじめな人にしてしまわれた、あわれむべき名だと源侍従は思った。この家の侍従はまだ殿上の勤めもしていないので、参賀する所も少なくて早く家に帰って来てここへ出て来た。浅香の木の折敷二つに菓子と杯を載せて御簾から出された。
|
【のたまふなり】- 「なり」伝聞推定の助動詞。薫に即した表現。
【まめ人とこそ】- 以下「いと屈じたる名かな」まで、薫の心中。
【主人の侍従、殿上などもまだせねば】- 玉鬘と鬚黒の三男。薫と区別するために「主人の」と言った。『完訳』は「侍従は従五位下だが、新任のためか勅許がない」と注す。
|
| 2.2.13 |
「大臣は、ねびまさりたまふままに、故院にいとようこそ、おぼえたてまつりたまへれ。この君は、似たまへるところも見えたまはぬを、けはひのいとしめやかに、なまめいたるもてなししもぞ、かの御若盛り思ひやらるる。かうざまにぞおはしけむかし」 |
「大臣は、年をお取りになるにつれて、故院にとてもよくお似通い申していらっしゃる。
この君は、似ていらっしゃるところもお見えにならないが、感じがとてもしとやかで、優美な態度が、あのお若い盛りの頃が思いやられてならない。
このようなふうでいらっしゃったのであろうよ」
|
「右大臣はお年がゆけばゆくほど院によくお似ましになるが、侍従はお似になったところはお顔にないが、様子にしめやかな艶なところがあって、院のお若盛りがそうでおありになったであろうと想像されます」
|
【大臣は】- 以下「おはしけむかし」まで、玉鬘の詞。
【もてなししもぞ】- 大島本は「もてなしゝもそ」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「もてなしぞ」と「し」を削除する。『新大系』は底本のままとする。
|
| 2.2.14 |
|
となどと、お思い出し申し上げなさって、しんみりとしていらっしゃる。
後に残った香の薫りまでを、女房たちは誉めちぎっている。
|
などと薫の帰ったあとで尚侍は言って、昔をなつかしくばかり追想していた。あたりに残ったかんばしい香までも女房たちはほめ合っていた。
|
【思ひ出でられたまひて】- 大島本は「思いてられ給て」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「思ひ出できこえたまひて」と校訂する。『新大系』は底本のままとする。
【うちしほれたまふ】- 大島本は「うちしほれ」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「うちしほたれ」と「た」を補訂する。『新大系』は底本のままとする。
【名残さへ】- 薫が立ち去った後の残香。
|
|
第三段 梅の花盛りに、薫君、玉鬘邸を訪問
|
| 2.3.1 |
|
侍従の君、堅物の評判を情けないと思ったので、二十日過ぎのころ、梅の花盛りに、「色恋に無縁な男だと言われまい。
風流者をまねしてみよう」とお思いになって、藤侍従のお邸にいらっしゃった。
|
源侍従はきまじめ男と言われたことを残念がって、二十日過ぎの梅の盛りになったころ、恋愛を解しない、一味の欠けた人のように言われる不名誉を清算させようと思って、藤侍従を訪問に行った。
|
【二十余日のころ、梅の花盛りなるに】- 正月二十日過ぎ。梅の花盛り。
【匂ひ少なげに】- 以下「ならはむかし」まで、薫の心中。
【取りなされじ】- 「じ」について、『集成』は、過去助動詞「し」に解し、『完訳』、打消推量助動詞「じ」に解す。
【藤侍従の御もとに】- 玉鬘の三男。前出の「主人の侍従」。
|
| 2.3.2 |
|
中門をお入りになる時、同じ直衣姿の男が立っているのだった。
隠れようと思ったのを、引き止めてみると、あのいつもうろうろしている蔵人少将なのであった。
|
中門をはいって行くと、そこには自身と同じ直衣姿の人が立っていた。隠れようとその人がするのを引きとめて見ると蔵人少将であった。
|
【隠れなむと思ひけるを】- 相手の男。先に来ていた男の動作。
【ひきとどめたれば】- 主語は薫。
【少将なりけり】- 夕霧の子息。
|
| 2.3.3 |
|
「寝殿の西面で、琵琶や、箏の琴の音がするので、心をときめかして立っているようである。
辛そうだな。
親の許さない恋に心を染めることは、罪深いことだな」と思う。
琴の音色も止んだので、
|
寝殿の西座敷のほうで琵琶と十三絃の音がするために、夢中になって立ち聞きをしていたらしい。苦しそうだ、人が至当と認めぬ望みを持つことは仏の道から言っても罪作りなことになるであろうと薫は思った。琴の音がやんだので、
|
【寝殿の西面に】- 以下「深かるべきわざかな」まで、薫の心中。
【心を惑はして立てるなめり】- 薫と語り手が一体化した視点で語る。
|
| 2.3.4 |
|
「さあ、案内して下さい。
わたしは、
|
「さあ案内をしてください。私にはよく勝手がわかっていないから」
|
【いざ、しるべしたまへ。まろは、いとたどたどし】- 薫の蔵人少将への詞。叔父甥の関係でもある。
|
| 2.3.5 |
|
と言って、伴って、西の渡殿の前にある紅梅の木の側で、「梅が枝」を口ずさんで立ち寄った様子が、花の香よりもはっきりと、さっと匂ったので、妻戸を押し開けて、女房たちが、和琴をとてもよく合奏していた。
女の琴なので、呂の調子の歌は、こうまでうまく合わせられないものなのに、大したものだと思って、もう一度、繰り返して謡うが、琵琶も又となく華やかである。
|
と言って、蔵人少将とつれだって西の渡殿の前の紅梅の木のあたりを歩きながら、催馬楽の「梅が枝」を歌って行く時に、薫の侍従から放散する香は梅の花の香以上にさっと内へにおってはいったために、家の人は妻戸を押しあけて和琴を歌に合わせて弾きだした。呂の声の歌に対しては女の琴では合わせうるものでないのに、自信のある弾き手だと思った薫は、少将といっしょにもう一度「梅が枝」を繰り返した。琵琶も非常にはなやかな音だった。
|
【梅が枝】- 梅が枝に 来居る鴬 や 春かけて はれ 春かけて 鳴けどもいまだ や 雪は降りつつ あはれ そこよしや 雪は降りつつ(催馬楽-梅が枝)(text44.html 出典3から転載)
【呂の歌は】- 律はわが国固有の俗楽的音階で秋の調べ、呂は中国伝来の正式な音階で春の調べという。
【いたしと思ひて】- 主語は薫。敬語が付かないのは緊張した臨場感を出すためである。
【今一返り、をり返し歌ふ】- 大島本は「おりかへしうたふ」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「をり返しうたふを」と「を」を補訂する。『新大系』は底本のままとする。主語は侍従の君。
|
| 2.3.6 |
|
「趣味高く暮らしていらっしゃる邸だ」と、心が止まったので、今宵は少し気を許して、冗談などを言う。
|
まったく芸術的な家であるとおもしろくなった薫は、元日とは変わった打ち解けたふうになって、冗談なども今夜は言った。
|
【ゆゑありて】- 以下「あたりぞかし」まで、薫の感想。
【はかなしごとなども言ふ】- 主語は薫。ここでも敬語が付かない。
|
| 2.3.7 |
|
内側から和琴を差し出した。
お互いに譲り合って、手を触れないので、藤侍従の君を介して、尚侍の殿が、
|
御簾の中から和琴を差し出されたが、二人の公達は譲り合って手を触れないでいると、夫人は末の子の侍従を使いにして、
|
【かたみに譲りて】- 薫と蔵人少将とが互いに。
【侍従の君して】- 玉鬘の三男、侍従の君。
|
| 2.3.8 |
|
「故致仕の大臣のお爪音に、似ていらっしゃると、ずっと聞いていましたが、ほんとうに聞いてみたいです。
今宵は、やはり鴬にもお誘われなさい」
|
「あなたのは昔の太政大臣の爪音によく以ているということですから、ぜひお聞きしたいと思っているのです。今夜は鶯に誘われたことにしてお弾きくだすってもいいでしょう」
|
【故致仕の大臣の】- 以下「誘はれたまへ」まで、玉鬘の薫への詞。和琴の弾奏をすすめる。
【鴬にも誘はれたまへ】- 『奥入』は「花の香を風のたよりにたぐへてぞ鴬誘ふしるべにはやる(古今集春上、一三、紀友則)。『異本紫明抄』は「鴬の声に誘引せられて花の下に来る草の色に拘留せられて水の辺に坐り」(白氏文集巻十八、春江・和漢朗詠集上、春、鴬)を指摘。
|
| 2.3.9 |
と、のたまひ出だしたれば、「あまえて爪くふべきことにもあらぬを」と思ひて、をさをさ心にも入らず掻きわたしたまへるけしき、いと響き多く聞こゆ。 |
と、おっしゃたので、「照れて爪をかんでいる場合でもない」と思って、あまり気乗りもせずに掻き鳴らしなさる様子、たいそう響きが多く聞こえる。
|
と言わせた。恥ずかしがって引っ込んでしまうほどのことでもないと思って、たいして熱心にもならず薫の弾きだした琴の音は、音波の遠く広がってゆくはなやかな気のされるものだった。
|
【爪くふべきことにもあらぬを】- 薫の心中。
|
| 2.3.10 |
「常に見たてまつり睦びざりし親なれど、世におはせずなりにきと思ふに、いと心細きに、はかなきことのついでにも思ひ出でたてまつるに、いとなむあはれなる。 |
「いつもお目にかかって親しんだわけではない親ですが、この世にいらっしゃらなくなったと思うと、とても心細くて、ちょっとしたことの機会にもお思い出し申すと、とてもしみじみ悲しいのでした。
|
接近することの少なかった親ではあるが、亡くなったと思うと心細くてならぬ尚侍が、和琴に追慕の心を誘われて身にしむ思いをしていた。
|
【常に見たてまつり】- 以下「おぼえつれ」まで、玉鬘の詞。薫の和琴を聴いて、亡き父致仕太政大臣を思い出す。
|
| 2.3.11 |
|
だいたい、この君は、不思議と故大納言のご様子に、とてもよく似て、琴の音色など、まるでその人かと思われます」
|
「この人は不思議なほど亡くなった大納言によく似ておいでになって、琴の音などはそのままのような気がされました」
|
【故大納言の御ありさまに】- 柏木。薫の実の父親。
|
| 2.3.12 |
|
と言ってお泣きになるのも、お年のせいの、涙もろさであろうか。
|
と言って、尚侍の泣くのも年のいったせいかもしれない。
|
【古めいたまふしるしの、涙もろさにや】- 語り手の批評。『首書』は「草子地也」と指摘。『完訳』は「語り手の言辞。薫の出生の秘事をはぐらかし、老の涙かとする」と注す。
|
|
第四段 得意の薫君と嘆きの蔵人少将
|
| 2.4.1 |
|
少将も、声がとても美しくて、「さき草」を謡う。
おせっかいな分別者で、出過ぎた女房もいないので、自然とお互いに気がはずんで合奏なさるが、この家の侍従は、故大臣にお似通い申しているのであろうか、このような方面は苦手で、盃ばかり傾けているので、「せめて祝い歌ぐらい謡えよ」と、文句を言われて、「竹河」を一緒に声を出して、まだ若いけれど美しく謡う。
御簾の内側から盃を差し出す。
|
少将もよい声で「さき草」を歌った。批評家などがいないために、皆興に乗じていろいろな曲を次々に弾き、歌も多く歌われた。この家の侍従は父のほうに似たのか音楽などは不得意で、友人に杯をすすめる役ばかりしているのを、友から、
「君も勧杯の辞にだけでも何かをするものだよ」
と言われて、「竹河」をいっしょに歌ったが、まだ少年らしい声ではあるがおもしろく聞こえた。御簾の中からもまた杯が出された。
|
【さき草」謡ふ】- 『源氏釈』は「この殿は 宜も 宜も富みけり 三枝の あはれ 三枝の はれ 三枝の 三つば四つばの中に 殿づくりせりや 殿づくりせりや」(催馬楽、この殿は)を指摘。
【故大臣に】- 鬚黒。
【似たてまつりたまへるにや】- 語り手の想像。
【寿詞をだにせむや】- 薫または蔵人少将の詞。
【竹河」を同じ声に】- 『源氏釈』は「竹河の 橋のつめなるや 橋のつめなるや 花園に はれ 花園に 我をば放てや 我をば放てや少女伴へて」(催馬楽、竹河)を指摘。
|
| 2.4.2 |
「酔のすすみては、忍ぶることもつつまれず。ひがことするわざとこそ聞きはべれ。いかにもてないたまふぞ」 |
「酔いが回っては、心に秘めていることも隠しておくことができません。
詰まらないことを口にすると聞いております。
どうなさるおつもりですか」
|
「あまり酔っては、平生心に抑制していることまでも言ってしまうということですよ。その時はどうなさいますか」
|
【酔のすすみては】- 以下「もてないたまふぞ」まで、薫の詞。『源氏釈』は「思ふには忍ぶることぞ負けにける色に出でじと思ひしものを」(古今集恋一、五〇三、読人しらず)を指摘。
|
| 2.4.3 |
|
と、すぐには手にしない。
小袿の重なった細長で、人の香がやさしく染みているのを、あり合わせのままに、お与えになる。
「これはどういうおつもりですか」などとはしゃいで、侍従は、お邸の君に与えて出て行った。
ひき止めて与えたが、「水駅で夜が更けてしまいました」と言って、逃げて行ってしまった。
|
などと言って、薫の侍従は杯を容易に受けない。小袿を下に重ねた細長のなつかしい薫香のにおいの染んだのを、この場のにわかの纏頭に尚侍は出したのであるが、「どうしたからいただくのだかわからない」と言って、薫はこの家の藤侍従の肩へそれを載せかけて帰ろうとした。引きとめて渡そうとしたのを、「ちょっとおじゃまするつもりでいておそくなりましたよ」とだけ言って逃げて行った。
|
【被けたまふ】- 主語は玉鬘。玉鬘が薫に。
【何ぞもぞ】- 薫の詞。男踏歌にちなんだ言葉遣い。
【侍従は、主人の君にうち被けて去ぬ】- 薫源侍従がこの家の藤侍従に与えて、の意。
【水駅にて夜更けにけり】- 薫の詞。『集成』は「ちょっと立ち寄ったつもりが、つい夜更かししました」と注す。
|
|
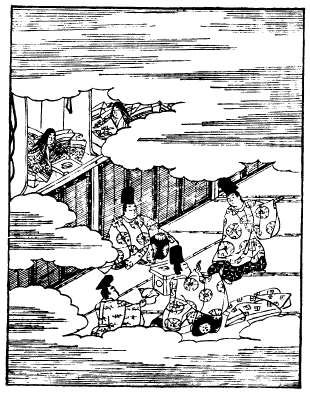 |
| 2.4.4 |
少将は、「この源侍従の君のかうほのめき寄るめれば、皆人これにこそ心寄せたまふらめ。わが身は、いとど屈じいたく思ひ弱りて」、あぢきなうぞ恨むる。 |
少将は、「この源侍従の君がこのように出入りしているようなので、こちらの方々は皆あの君に好意を寄せていらっしゃるだろう。
わが身はますます塞ぎ込み元気をなくして」、つまらなく恨むのだった。
|
蔵人少将はこの源侍従が意味ありげに訪問した今夜のようなことが続けば、だれも皆好意をその人にばかり持つようになるであろう、自分はいよいよみじめなものになると悲観していて、御簾の中の人へ恨めしがるようなこともあとに残って言っていた。
|
【この源侍従の君の】- 以下「思ひ弱りて」まで、蔵人少将の心中。末尾は地の文に流れる。
|
| 2.4.5 |
|
「人はみな花に心を寄せているのでしょうが
わたし一人は迷っております、
|
人は皆花に心を移すらん
一人ぞ惑ふ春の夜の闇
|
【人はみな花に心を移すらむ--一人ぞ惑ふ春の夜の闇】- 蔵人少将の詠歌。真淵『新釈』は「春の夜の闇はあやなし梅の花色こそ見えね香やは隠るる」(古今集春上、四一、凡河内躬恒)を指摘。
|
| 2.4.6 |
うち嘆きて立てば、内の人の返し、
|
ため息をついて座を立つと、内側にいる女房の返し、
|
こう言って、歎息しながら帰ろうとしている少将に、御簾の中の人が、
|
|
| 2.4.7 |
|
「時と場合によって心を寄せるものです
ただ梅の花の香りだけにこうも引かれるものではありませんよ」
|
折からや哀れも知らん
梅の花ただかばかりに移りしもせじ
|
【をりからやあはれも知らむ梅の花--ただ香ばかりに移りしもせじ】- 女房の返歌。「香ばかり」「かばかり」の掛詞。蔵人少将を慰める。
|
| 2.4.8 |
朝に、四位侍従のもとより、主人の侍従のもとに、
|
朝に、四位侍従のもとから、邸の侍従のもとに、
|
と返歌をした。翌朝になって源侍従から藤侍従の所へ、
|
|
| 2.4.9 |
「昨夜は、いと乱りがはしかりしを、人びといかに見たまひけむ」 |
「昨夜は、とても酔っぱらったようだが、皆様はどのように御覧になったであろうか」
|
昨夜は失礼をして帰りましたが皆さんのお気持ちを悪くしなかったかと心配しています。
|
【昨夜は】- 以下「いかに見たまひけむ」まで、薫の文。
|
| 2.4.10 |
|
と、御覧下さいとのおつもりで、仮名がちに書いて、
|
と、婦人たちにも見せてほしいらしく仮名がちに書いて、端に、
|
【仮名がちに書きて】- 大島本は「かなかちにかきて」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「仮名がちに書きて、端に」と「端に」を補訂する。『新大系』は底本のままとする。
|
| 2.4.11 |
|
「竹河の歌を謡ったあの文句の一端から
わたしの深い心のうちを知っていただけましたか」
|
竹河のはしうちいでし一節に
深き心の底は知りきや
|
【竹河の橋うちいでし一節に--深き心の底は知りきや】- 薫から玉鬘への贈歌。催馬楽「竹河」の詞章を踏まえる。「橋」と「端」の掛詞。「竹」-「節」、「河」-「深き」-「底」は縁語。
|
| 2.4.12 |
|
と書いてある。
寝殿に持って上がって、方々が御覧になる。
|
という歌もある手紙を送って来た。すぐに寝殿へこの手紙を持って行かれて、侍従の母夫人や兄弟たちもいっしょに見た。
|
【これかれ見たまふ】- 玉鬘や姫君たちが。
|
| 2.4.13 |
「手なども、いとをかしうもあるかな。いかなる人、今よりかくととのひたらむ。幼くて、院にも後れたてまつり、母宮のしどけなう生ほし立てたまへれど、なほ人にはまさるべきにこそあめれ」 |
「筆跡なども、とても美しく書いてありますね。
どのような人が、今からこのように整っているのでしょう。
幼いころ、院に先立たれ申し、母宮がしまりもなくお育て申されたが、やはり人より優れているのでしょう」
|
「字も上手だね。まあどうして今からこんなに何もかもととのった人なのだろう。小さいうちに院とお別れになって、お母様の宮様が甘やかすばかりにしてお育てになった方だけれど、光った将来が今から見える人になっていらっしゃる」
|
【手なども】- 以下「こそあめれ」まで、玉鬘の詞。
【いかなる人、今より】- 『集成』は「いかなる前世の因縁か、という気持」。『完訳』は「どんな前世の因縁を持つ人が」と訳す。
|
| 2.4.14 |
|
と言って、尚侍の君は、自分の子供たちの、字などが下手なことをお叱りになる。
返事は、なるほど、たいそう未熟な字で、
|
などと尚侍は言って、自分の息子たちの字の拙さをたしなめたりした。藤侍従の返事は実際幼稚な字で書かれた。
|
【この君たちの、手など】- 玉鬘の子供たちの筆跡。
【げに、いと若く】- 「げに」は語り手の納得した気持ち。
|
| 2.4.15 |
|
「昨夜は、水駅とおっしゃってお帰りになったことを、いかがなものかと申しておりました。
|
昨夜はあまり早くお帰りになったことで皆何とか言ってました。
|
【昨夜は、水駅をなむ】- 以下、歌の終わりまで、藤侍従の文。
|
| 2.4.16 |
|
竹河を謡って夜を更かすまいと急いでいらっしゃったのも
どのようなことを心に止めておけばよいのでしょう」
|
竹河によを更かさじと急ぎしも
いかなる節を思ひおかまし
|
【竹河に夜を更かさじといそぎしも--いかなる節を思ひおかまし】- 藤侍従の返歌。「夜」と「よ(竹の節と節の間)」の掛詞。「竹」-「節」は縁語。
|
| 2.4.17 |
|
なるほど、この事件をきっかけとして、この君のお部屋にいらっしゃって、気のある態度で振る舞う。
少将が予想していた通り、誰もが好意を寄せていた。
侍従の君も、子供心に、近い縁者として、明け暮れ親しくしたいと思うのであった。
|
この時以来薫は藤侍従の部屋へよく来ることになって、姫君への憧憬を常に伝えさせるのであった。少将が想像したとおりに、家の者は皆この人をひいきにすることになった。まだ少年らしい弟の侍従も、この人を姉の婿にして、同じ家の中で睦み合いたいと願っていた。
|
【げに、この節をはじめにて】- 「げに」は語り手の感情移入による。
【この君の御曹司に】- 藤侍従。
【少将の推し量りしもしるく】- 蔵人少将の心配は、前に「この源侍従の君の」(第二章四段)以下に語られていた。
|
|
第五段 三月、花盛りの玉鬘邸の姫君たち
|
| 2.5.1 |
|
三月になって、咲く桜がある一方で、空も覆うほど散り乱れ、ほぼ桜の盛りのころ、のんびりとしていらっしゃるところは、さしたる用事もなく、端近に出ていても非難されないようである。
|
三月になって、咲く桜、散る桜が混じって春の気分の高潮に達したころ、閑散な家では退屈さに婦人たちさえ端近く出て、庭の景色ばかりがながめまわされるのであった。
|
【咲く桜あれば、散りかひくもり】- 『源氏釈』は「桜咲く桜の山の桜花咲く桜あれば散る桜あり」(出典未詳)「桜花散りかひ曇れ老いらくの来むといふなる道まがふがに」(古今集賀、三四九、在原業平)を指摘。
【のどやかにおはする所は】- 玉鬘邸。
【端近なる罪もあるまじかめり】- 「めり」は語り手の推量。
|
| 2.5.2 |
|
その当時、十八、九歳くらいでいらっしゃったろうか、ご器量も気立ても、それぞれに素晴らしい。
姫君は、とても際立って気品があり、はなやかでいらして、なるほど、臣下の人に縁づけ申すのは、ふさわしくなくお見えである。
|
玉鬘夫人の姫君たちはちょうど十八、九くらいであって、容貌にも性質にもとりどりな美しさがあった。姫君のほうは鮮明に気高い美貌で、はなやかな感じのする人である。普通の人の妻にはふさわしくないと母君が高く評価しているのももっともに思われるのである。
|
【そのころ、十八、九のほどやおはしけむ】- 玉鬘の娘姉妹の年齢。『評釈』は「古女房が昔の有様を思い出して語っている痕跡の一つである。「けむ」と推量しているのは語り手の女房である」と注す。
【姫君は、いとあざやかに】- 大君。
【げに、ただ人にて見たてまつらむは】- 語り手が作中人物に納得同意する気持ち。
|
| 2.5.3 |
桜の細長、山吹などの、折にあひたる色あひの、なつかしきほどに重なりたる裾まで、愛敬のこぼれ落ちたるやうに見ゆる、御もてなしなども、らうらうじく、心恥づかしき気さへ添ひたまへり。
|
桜の細長に、山吹襲などで、季節にあった色合いがやさしい感じに重なっている裾まで、愛嬌があふれ出ているように見える、そのお振る舞いなども、洗練されて、気圧されるような感じまでが加わっていらっしゃった。
|
桜の色の細長に、山吹などという時節に合った色を幾つか下にして重なった裾に至るまで、どこからも愛嬌がこぼれ落ちるように見えた。身のとりなしにも貴女らしい品のよさが添っている。
|
|
| 2.5.4 |
|
もうお一方は、薄紅梅に、桜色で、柳の枝のように、しなやかに、たいそうすらっとして優美に、落ち着いた物腰で、重々しく奥ゆかしい感じは、勝っていらっしゃるが、はなやかな感じは、この上ないと女房は思っていた。
|
もう一人の姫君はまた薄紅梅の上着にうつりのよいたくさんな黒々とした髪を持っていた。柳の糸のように掛かっているのである。背が高くて、艶に澄み切った清楚な感じのする聡明らしい顔ではあるが、はなやかな美は全然姉君一人のもののように女房たちも認めていた。
|
【今一所は、薄紅梅に】- 中の君。
【桜色にて】- 大島本は「さくら色にて」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「御髪いろにて」と校訂する。『新大系』は底本のままとする。
【たをたをとたゆみ】- 大島本は「たゆみ」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「見ゆ」と校訂する。『新大系』は底本のままとする。
【こよなしとぞ】- 『完訳』は「大君のほうが格別と」と注す。
|
| 2.5.5 |
碁打ちたまふとて、さし向ひたまへる髪ざし、御髪のかかりたるさまども、いと見所あり。侍従の君、見証したまふとて、近うさぶらひたまふに、兄君たちさしのぞきたまひて、 |
碁をお打ちなさろうとして、向かい合っていらっしゃる髪の生え際、髪の垂れかかっている具合など、たいそう見所がある。
侍従の君が、審判をなさろうとして、近くに伺候なさると、兄君たちがお覗きになって、
|
碁を打つために姉妹は今向き合っていた。髪の質のよさ、鬢の毛の顔への掛かりぐあいなど両姫君とも共通してみごとなものであった。侍従が審査役になって、姫君たちのそばについているのを兄たちがのぞいて、
|
【兄君たちさしのぞきたまひて】- 藤侍従の兄、左中将と右中弁。
|
| 2.5.6 |
|
「侍従の寵愛は、大したものになったね。
碁の審判を許されたとはね」
|
「侍従はすばらしくなったね。碁の審査役にしていただけるのだからね」
|
【侍従のおぼえ】- 以下「許されにけるをや」まで、兄君の詞。
|
| 2.5.7 |
とて、おとなおとなしきさましてついゐたまへば、御前なる人びと、とかうゐなほる。
中将、
|
と言って、大人ぶった態度でお座りになったので、御前の女房たちは、あれこれ居ずまいを正す。
中将が、
|
と、大人らしくからかいながら、几帳のすぐそばにすわってしまうと、女房たちは急に居ずまいを直したりした。上の兄の中将が、
|
|
| 2.5.8 |
|
「宮仕えが忙しくなりましたので、弟に出し抜かれたのは、まことに残念なことだなあ」
|
「公務で忙しくしているうちに、姫君の愛顧を侍従に独占されてしまったのはつまらないね」
|
【宮仕へのいそがしう】- 以下「本意なきわざかな」まで、左近中将の詞。
|
| 2.5.9 |
と愁へたまへば、
|
と愚痴をおこぼしになると、
|
と言うと、次の兄の右中弁が、
|
|
| 2.5.10 |
|
「弁官は、それ以上に、家でのご奉公はお留守になってしまうからと、そうお見捨てではありますまい」
|
「弁官はまた特別に御用が多いから、忠誠ぶりを見ていただけないからといっても、少しは斟酌していただかないでは」
|
【弁官は、まいて】- 以下「思し捨てむ」まで、右中弁の詞。
【さのみやは思し捨てむ】- 反語表現。『集成』は「そうまでお見捨てになっていいものでしょうか」と訳す。
|
| 2.5.11 |
など申したまふ。
碁打ちさして、恥ぢらひておはさうずる、いとをかしげなり。
|
などと申し上げなさる。
碁を打つのを止めて、恥ずかしがっていらっしゃる、たいそう美しい感じである。
|
と言う。兄たちの言う冗談に困って碁を打ちさして恥じらっている姫君たちは美しかった。
|
|
| 2.5.12 |
|
「宮中辺りなどに出歩きましても、亡き殿がいらっしゃったら、と存じられますことが多くて」
|
「御所の中を歩いていても、お父様がおいでになったらと思うことが多い」
|
【内裏わたりなど】- 以下「多くこそ」まで、左中将の詞。
【故殿おはしまさましかば】- 左中将や右中弁らの父、鬚黒。
|
| 2.5.13 |
|
などと、涙ぐんで拝し上げなさる。
二十七、八歳くらいでいらっしゃったので、とても恰幅よくて、姫君たちのご様子を、「何とかして、昔父君がお考えになっていた通りに、したいものだ」と思っていらっしゃった。
|
などと言って、中将は涙ぐんで妹たちを見ていた。もう二十七、八であったから風采もりっぱになっていて、妹たちを父の望んでいたようにはなやかな後宮の人として見たく思っているのである。
|
【二十七、八のほどにものしたまへば】- 左中将の年齢。『完訳』は「左近中将の誕生は、真木柱。今は二十五歳のはず」と注す。
【いかで、いにしへ】- 以下「違へずもがな」まで、左中将の心中。
|
| 2.5.14 |
御前の花の木どもの中にも、匂ひまさりてをかしき桜を折らせて、「他のには似ずこそ」など、もてあそびたまふを、 |
お庭先の花の木々の中でも、色合いの優れて美しい桜を折らせて、「他の桜とは違っている」などと、もて遊んでいらっしゃるのを、
|
庭の花の木の中でもことに美しい桜の枝を折らせて、姫君たちが、「この花が一番いいのね」などと言って楽しんでいるのを見て、中将が、
|
【他のには似ずこそ】- 姫君の詞。係助詞「こそ」の下に「はべれ」などの語句が省略。
|
| 2.5.15 |
|
「お小さくいらした時、この花は、わたしのよ、わたしのよと、お争いになったが、故殿は、姫君のお花だとお決めになる。
母上は、若君のお花だとお決めになったが、それをひどくそんなには泣き叫んだりしませんでしたが、おもしろくなく存じられましたよ」と言って、「この桜が老木になったにつけても、過ぎ去った歳月を思い出されますので、大勢の人に先立たれてしまった身の悲しみも、きりがございません」
|
「あなたがたが子供の時に、この桜の木を私のだ私のだと取り合いをした時に、お父様は姉さんのものだとおきめになって、お母様は小さい人のだとおきめになったから、泣く騒ぎまではしなかったけれど、双方とも不満足な顔をしたことを覚えていますか」こんなことを言いだして、また、「この桜が老い木になったことでも、過ぎ去った歳月が数えられて、力になっていただけたどの方にもどの方にも死に別れてしまった不幸な自分のことが思われる」
|
【幼くおはしましし時】- 以下「思ひたまへられしはや」まで、左中将の詞。
【上は】- 母上は、の意。
【いとさは泣きののしらねど、やすからず思ひたまへられしはや】- 『集成』は「父母が姫君たちにかまけて自分を顧みてくれない、と思った幼時の回想」と注す。
【この桜の】- 以下「止めがたうこそ」まで、左中将の詞。
|
| 2.5.16 |
など、泣きみ笑ひみ聞こえたまひて、例よりはのどやかにおはす。人の婿になりて、心静かにも今は見えたまはぬを、花に心とどめてものしたまふ。 |
などと、泣いたり笑ったりしながら申し上げなさって、いつもよりはのんびりとしていらっしゃる。
他の家の婿となって、ゆっくりとは今ではお見えにならないが、花に心を惹かれておいでである。
|
とも言って、泣きもし、笑いもしながら平生ほど時間のたつのを気にせずに中将は母の家にいた。他家の婿になっていて、こちらへ来て静かに暮らす余裕のある日などを持たないのであるが、今日は花に心が惹かれて落ち着いているのである。
|
【人の婿になりて】- 他家の婿に入って。
|
|
第六段 玉鬘の大君、冷泉院に参院の話
|
| 2.6.1 |
|
尚侍の君は、このように成人した子の親におなりのお年の割には、たいそう若く美しく、依然として盛りのご容貌にお見えになった。
冷泉院の帝は、主として、この方のご様子が依然として心に掛かって、昔が恋しく思い出されなさったので、何にかこつけたらよいかと、思案なさって、姫君のご入内の事を、無理やりに申し込みなさるのであった。
院に入内なさることは、この君たちが、
|
尚侍はまだこうした人々を子にして持っているほどの年になっているとは見えぬほど今日も若々しくて、盛りの美貌とさえ思われた。冷泉院の帝は姫君を御懇望になっているが真実はやはり昔の尚侍を恋しく思われになるのであって、何かによって交渉の起こる機会がないかとお考えになった末、姫君のことを熱心にお申し入れになったのである。院参の問題はこの子息たちが反対した。
|
【尚侍の君、かくおとなしき人の親になりたまふ御年のほど思ふよりは】- 玉鬘は、二十七八歳の左中将らの母親、四十八歳。
【冷泉院の帝は、多くは】- 『完訳』は「大君参院を望む理由の大半は、後宮に入らなかった玉鬘への未練」と注す。
【何につけてかは】- 冷泉院の心中。
【この君たちぞ】- 左中将や右中弁ら。
|
| 2.6.2 |
|
「やはり、栄えない気がしましょう。
万事が、時流に乗ってこそ、世間の人も認めましょう。
なるほど、まことに拝したいお姿は、この世に類なくいらっしゃるようですが、盛りを過ぎた感じがしますね。
琴や笛の調子、花や鳥の色や音色も、時期にかなってこそ、人の耳にも止まるものです。
春宮は、どうでしょうか」
|
「どうしても見ばえのせぬことをするように思われますよ。現在の勢力のある所へ人が寄って行くのも、自然なことなのですからね。院はごりっぱな御風采で、あの方の後宮に侍することができれば女として幸福至極だろうとは思いますが、盛りの過ぎた方だと今の御位置からは思われますからね。音楽だって、花だって、鳥だってその時その時に適したものでなければ魅力はありません。東宮はどうですか」
|
【なほ、ものの栄なき心地】- 以下「春宮はいかが」まで、左中将らの詞。
【げに、いと見たてまつらまほしき御ありさまは】- 冷泉院の美しい姿態。
【盛りならぬ心地】- 退位後という感じ。
【花鳥の色をも音をも】- 花鳥の色をも音をもいたづらにもの憂かる身は過ぐすのみなり(後撰集夏-二一二 藤原雅正)(text44.html 出典10から転載)
|
| 2.6.3 |
など申したまへば、
|
などと申し上げなさると、
|
などと中将が言う。
|
|
| 2.6.4 |
|
「さあ、どんなものかしら、最初から重々しい方が、並ぶ者がいないような勢いで、いらっしゃるようですからね。
なまじっかの宮仕えは、胸を痛め物笑いになることもあろうかと、気が引けますので。
殿が生きていらっしゃったならば、将来のご運は判らないが、この今は、張り合いのある状態になさっていたでしょうに」
|
「それはどうかね。初めからりっぱな方が上がっておいでになって、御寵愛をもっぱらにしておいでになるのだから、それだけでも資格のない人があとではいって行っては、苦痛なことばかり多いだろうと思うからね。お父様がほんとうにいてくだすったら、この人たちの遠い未来まではわからないとしても、さしあたっては何の引け目もなしにどこへでもお出しになっただろうがね」
|
【いさや】- 以下「たまひてましを」 まで、玉鬘の詞。
【やむごとなき人の、かたはらもなきやうにてのみ】- 夕霧の大君が入内していることをいう。
【おはせましかば】- 「もてなしたまひてましを」 に係る反実仮想の構文。
|
| 2.6.5 |
などのたまひ出でて、皆ものあはれなり。
|
などとおっしゃって、皆しみじみと悲しい思いがする。
|
と尚侍が言いだしたために、めいった空気に満ちてきたのもぜひないことである。
|
|
|
第七段 蔵人少将、姫君たちを垣間見る
|
| 2.7.1 |
中将など立ちたまひてのち、君たちは、打ちさしたまへる碁打ちたまふ。
昔より争ひたまふ桜を賭物にて、
|
中将などがお立ちになった後、姫君たちは、途中で打ち止めていらした碁を打ちになる。
昔からお争いになる桜を賭物として、
|
中将などが立って行ったあとで、姫君たちは打ちさしておいた碁をまた打ちにかかった。昔から争っていた桜の木を賭けにして、
|
|
| 2.7.2 |
|
「三番勝負で、一つ勝ち越しになった方に、やはり花を譲りましょう」
|
「三度打つ中で、二度勝った人の桜にしましょう」
|
【三番に、数一つ勝ちたまはむ方には、なほ花を寄せてむ】- 大島本は「かたにハ猶花を」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「方に花を」と「ハ猶」を削除する。『新大系』は底本のままとする。姫君たちの詞。
|
| 2.7.3 |
|
と、ふざけて申し合いなさる。
暗くなったので、端近くで打ち終えなさる。
御簾を巻き上げて、女房たちが皆競い合ってお祈り申し上げる。
ちょうどその時、いつもの蔵人少将が、藤侍従の君のお部屋に来ていたのだが、兄弟連れ立ってお出になったので、だいたいが人の少ない上に、廊の戸が開いていたので、静かに近寄って覗き込んだ。
|
などと戯れに言い合っていた。
暗くなったので勝負を縁側に近い所へ出てしていた。御簾を巻き上げて、双方の女房も固唾をのんで碁盤の上を見守っている。ちょうどこの時にいつもの蔵人少将は侍従の所へ来たのであったが、侍従は兄たちといっしょに外へ出たあとであったから、人気も少なく静かな邸の中を少将は一人で歩いていたが、廊の戸のあいた所が目について、静かにそこへ寄って行って、のぞいて見ると、向こうの座敷では姫君たちが碁の勝負をしていた。
|
【暗うなれば、端近うて打ち果てたまふ】- 「なれば」は単純な順接。「端近うて」は挿入句。
【うち連れて出でたまひにければ】- 侍従が兄左中将や右中弁らと一緒に。
|
|
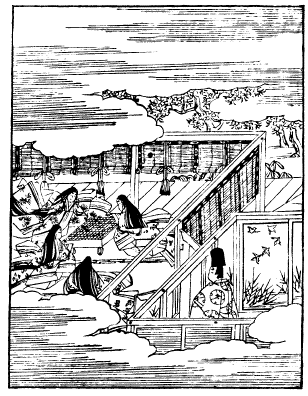 |
| 2.7.4 |
|
このように、嬉しい機会を見つけたのは、仏などが姿を現しなさった時に出会ったような気がするのも、あわれな恋心というものである。
夕暮の霞に隠れて、はっきりとはしないが、よくよく見ると、桜色の色目も、はっきりそれと分かった。
なるほど、花の散った後の形見として見たく、美しさがいっぱいお見えなのを、ますますよそに嫁ぎなさることを、侘しく思いがまさる。
若い女房たちのうちとけている姿、姿が、夕日に映えて美しく見える。
右方がお勝ちあそばした。
「高麗の乱声が、遅い」などと、はしゃいで言う女房もいる。
|
こんな所を見ることのできたことは、仏の出現される前へ来合わせたと同じほどな幸福感を少将に与えた。夕明りも霞んだ日のことでさやかには物を見せないのであるが、つくづくとながめているうちに、桜の色を着たほうの人が恋しい姫君であることも見分けることができた。「散りなんのちの」という歌のように、のちの形見にも面影をしたいほど麗艶な顔であった。いよいよこの人をほかへやることが苦しく少将に思われた。若い女房たちの打ち解けた姿なども夕明りに皆美しく見えた。碁は右が勝った。「高麗の乱声(競馬の時に右が勝てば奏される楽)がなぜ始まらないの」と得意になって言う女房もある。
|
【かう、うれしき折を見つけたるは】- 蔵人少将と語り手の地の文が一体化した叙述。
【はかなき心になむ】- 語り手の蔵人少将の心情批評。『全集』は「語り手の評」と注す。
【桜色のあやめも】- 大君の衣裳。
【げに、散りなむ後の形見にも】- 「げに」語り手の同意納得する気持ち。『奥入』は「さくら色に衣は深く染めて着む花の散りなむ後の形見に(古今集春上、六六、紀有朋)を指摘。
【異ざまになりたまひなむこと】- 大君が他人に嫁ぐこと。
【右勝たせたまひぬ】- 中君が勝つ。「せたまふ」最高敬語。玉鬘邸の古女房の語りという性格上、敬語の使用基準も従来と異なる。
【高麗の乱声、おそしや】- 右方の女房の詞。右方が勝ったので、「高麗楽の乱声」を催促。高麗楽は右楽、唐楽は左楽。
|
| 2.7.5 |
|
「右方にお味方申し上げて、西のお庭先の近くにあります木を、左方のものだとし、長年のお争いが、そのようなわけで、続いたのでございますよ」
|
「右がひいきで西のお座敷のほうに寄っていた花を、今まで左方に貸してお置きあそばしたきまりがつきましたのですね」
|
【右に心を寄せたてまつりて】- 大島本は「心越よせ」とある。『完本』は諸本に従って「心寄せ」と「を」を削除する。『集成』『新大系』は底本のままとする。以下「ありつるぞかし」まで、右方の女房の詞。
【西の御前に寄りてはべる木を】- 西の庭先すなわち右方にあった桜の木を、の意。
【左になして】- 父鬚黒が大君のものだと言ったことで。
|
| 2.7.6 |
|
と、右方は気持ちよさそうに応援申し上げる。
どのような事情でと知りらないが、おもしろいと聞いて、返事もしたいが、「寛いでいらっしゃる時に、心ない態度では」と思って、邸をお出になった。
「再び、このような機会はないか」と、物蔭に隠れて、窺い歩くのであった。
|
などと愉快そうに右方の者ははやしたてる。少将には何があるのかもよくわからないのであるが、その中へ混じっていっしょに遊びたい気のするものの、だれも見ないと信じている人たちの所へ出て行くことは無作法であろうと思ってそのまま帰った。もう一度だけああした機会にあえないであろうかと、少将はそののちも恋人の邸をうかがい歩いた。
|
【をかしと聞きて】- 主語は蔵人少将。
【うちとけたまへる折、心地なくやは】- 蔵人少将の心中。
【また、かかる紛れもや】- 蔵人少将の心中。下に「あらむ」などの語句が省略。
|
|
第八段 姫君たち、桜花を惜しむ和歌を詠む
|
| 2.8.1 |
君達は、花の争ひをしつつ明かし暮らしたまふに、風荒らかに吹きたる夕つ方、乱れ落つるがいと口惜しうあたらしければ、負け方の姫君、
|
姫君たちは、花の争いをしながら日を送っていらっしゃると、風が激しく吹いている夕暮に、乱れ散るのがまことに残念で惜しいので、負け方の姫君は、
|
姫君たちは毎日花争いに暮らしているのであったが、風の荒く吹き出した日の夕方に梢から乱れて散る落花を、惜しく残念に思って、負け方の姫君は、
|
|
| 2.8.2 |
|
「桜のせいで吹く風ごとに気が揉めます
わたしを思ってくれない花だと思いながらも」
|
桜ゆゑ風に心の騒ぐかな
思ひぐまなき花と見る見る
|
【桜ゆゑ風に心の騒ぐかな--思ひぐまなき花と見る見る】- 大君の詠歌。『全集』は「折りて見ば近まさりせよ桃の花思ひ暮らして桜惜しまじ」(紫式部集)を指摘。
|
| 2.8.3 |
御方の宰相の君、
|
御方の宰相の君が、
|
こんな歌を作った。そのほうにいる宰相の君が、
|
|
| 2.8.4 |
|
「咲いたかと見ると一方では散ってしまう花なので
負けて木を取られたことを深く恨みません」
|
咲くと見てかつは散りぬる花なれば
負くるを深き怨みともせず
|
【咲くと見てかつは散りぬる花なれば--負くるを深き恨みともせず】- 大君方の女房宰相の君の唱和歌。
|
| 2.8.5 |
と聞こえ助くれば、右の姫君、
|
とお助け申し上げると、右方の姫君は、
|
と慰める。右の姫君、
|
|
| 2.8.6 |
|
「風に散ることは世の常のことですが、
枝ごとそっくりこちらの木になった花を平気で見てい
|
風に散ることは世の常枝ながら
うつろふ花をただにしも見じ
|
【風に散ることは世の常枝ながら--移ろふ花をただにしも見じ】- 中君の詠歌。
|
| 2.8.7 |
この御方の大輔の君、
|
こちらの御方の大輔の君が、
|
右の女房の大輔、
|
|
| 2.8.8 |
|
「こちらに味方して池の汀に散る花よ
水の泡となってもこちらに流れ寄っておくれ」
|
心ありて池の汀に落つる花
泡となりてもわが方に寄れ
|
【心ありて池のみぎはに落つる花--あわとなりてもわが方に寄れ】- 中君方の女房大輔の君の唱和歌。『河海抄』は「枝よりもあだに散りにし花なれば落ちても水の泡とこそなれ」(古今集春下、八一、菅野高世)を指摘。
|
| 2.8.9 |
|
勝ち方の女の童が下りて、花の下を歩いて、散った花びらをたいそうたくさん拾って、持って参った。
|
勝ったほうの童女が庭の花の下へ降りて行って、花をたくさん集めて持って来た。
|
【勝ち方の童女】- 右方の童女。
|
| 2.8.10 |
|
「大空の風に散った桜の花を
わたしのものと思って掻き集めて見ました」
|
大空の風に散れども桜花おのがものぞと
掻き集めて見る
|
【大空の風に散れども桜花--おのがものとぞかきつめて見る】- 右方の童女の詠歌。
|
| 2.8.11 |
左のなれき、
|
左方のなれきが、
|
左の童女の馴君がそれに答えて、
|
|
| 2.8.12 |
|
「桜の花のはなやかな美しさを方々に散らすまいとしても
大空を覆うほど大きな袖がございましょうか
|
「桜花匂ひあまたに散らさじと
おほふばかりの袖はありやは
|
【桜花匂ひあまたに散らさじと--おほふばかりの袖はありやは】- 左方の童女なれきの反論歌。『河海抄』は「大空におほふばかりの袖もがな春咲く花を風にまかせじ」(後撰集春中、六四、読人しらず)を指摘。
|
| 2.8.13 |
心せばげにこそ見ゆめれ」など言ひ落とす。
|
心が狭く思われます」などと悪口を言う。
|
気が狭いというものですね」
などと悪く言う。
|
|
|
第三章 玉鬘の大君の物語 冷泉院に参院
|
|
第一段 大君、冷泉院に参院決定
|
| 3.1.1 |
|
こうしているうちに、月日をいたづらに送るのも、将来が不安なので、尚侍の殿はいろいろとお考えになる。
院からは、お手紙が毎日ある。
女御は、
|
そんなことをしているうちにずんずん月日のたっていくことも妙齢の娘たちを持っている尚侍を心細がらせて、一人で姫君たちの将来のことばかりを考えていた。
院からは毎日のように御催促の消息をお送りになった。女御からも、
|
【院よりは、御消息日々にあり】- 冷泉院から大君入内の要請がある。
【女御】- 冷泉院の弘徽殿女御。
|
| 3.1.2 |
|
「よそよそしく他人行儀にお考えなのでしょうか。
お上は、わたしがあなたに邪魔をしているらしいと、とても憎らしそうにおっしゃるので、冗談でも辛いことです。
同じことなら、今のうちにご決心なさいませ」
|
私を他人のようにお思いになるのですか。院は、私が中ではばんでいるように憎んでおいでになりますから、それはお戯れではあっても、私としてつらいことですから、できますならなるべく近いうちにそのことの実現されますように。
|
【うとうとしう】- 以下「思し立ちね」まで、弘徽殿女御の詞。
【上は、ここに聞こえ疎むるなめりと】- お上は、わたし弘徽殿女御があなた玉鬘の大君の入内を邪魔しているようだと。
|
| 3.1.3 |
など、いとまめやかに聞こえたまふ。「さるべきにこそはおはすらめ。いとかうあやにくにのたまふもかたじけなし」など思したり。 |
などと、たいそう懇切に申し上げなさる。
「前世からの因縁でいらっしゃるのだろう。
とてもこのように反対する立場の方がお勧め申すのも恐れ多い」などとお思いになった。
|
こんなふうに懇切に言って来た。それが宿命であるために、こうまでお望みになるのであろうから、御辞退するのはもったいないと尚侍は考えるようになった。
|
【さるべきにこそは】- 以下「かたじけなし」まで、玉鬘の心中。同じ妻妾の関係にある女性は嫉妬したり妨害するのだが、好意的に勧誘している。
|
| 3.1.4 |
|
御調度類は、たくさん準備なさっていたので、女房たちの衣装や、何やかやのこまごましたことをご準備なさる。
これを聞くと、蔵人少将は、悶え死ぬほど思いつめて、母北の方をお責め申したので、聞くのもお困りになって、
|
手道具類は父の大臣がすでに十分の準備をしておいたのであるから、新しく作らせる必要もなくて、ただ女房の装束類その他の簡単な物だけを、娘の院参のために玉鬘夫人は用意していた。姫君の運命が決せられたことを聞いて、蔵人少将は死ぬほど悲しんで、母の夫人にどうかしてほしいと責めた。夫人は困って、
|
【これを聞くに】- 玉鬘の大君の冷泉院入内のこと。
【母北の方をせめたてまつれば】- 雲居雁を。雲居雁は玉鬘と異母姉妹の関係。
|
| 3.1.5 |
|
「とても恥ずかしいことですが、お耳に入れますのも、まことに愚かな親心でございます。
ご同情下さるならば、ご推察いただき、やはり安心させてやって下さい」
|
私の出てまいる問題でないことに私が触れますのも、盲目的な親の愛からでございます。この気持ちを御理解してくださいますならば、なんとか子供の心を慰むるようにお計らいくださいませんか。
|
【いとかたはらいたきことに】- 以下「慰めさせたまへ」まで、雲居雁から玉鬘への文。
【闇の惑ひに】- 『異本紫明抄』は「人の親の心は闇にあらねども子を思ふ道に惑ひぬるかな」(後撰集雑一、一一〇二、藤原兼輔)を指摘。
|
| 3.1.6 |
|
などと、不憫でならないように申し上げなさるが、「困ったことだわ」と、お嘆きになって、
|
などといたいたしく訴えて来たのを、尚侍は、「気の毒で困ってしまうばかり」と歎息をしながら、
|
【苦しうもあるかな】- 玉鬘の心中。
|
| 3.1.7 |
|
「どのようなことやらと、決心も致しかねますが、院から無理やりにおっしゃるので、迷っております。
ご本心からならば、ここ暫くの間は我慢なさって、お心のゆくようお計らい申すのを御覧になって、世間の評判も穏やかでしょう」
|
どの道をとりますことが娘の幸福であるかもわからないのですが、院からの仰せがたびたびになるものですから、私は思い悩んでいます。御愛情をお持ちくださるなら、しばらくお忍びくだすって、慰安の方法を私が講じますのを待ってもらいますことが、世間体もよろしいかと思われます。
|
【いかなることと】- 以下「なだらかならむ」まで、玉鬘の雲居雁への返書。
【まめやかなる御心ならば】- 蔵人少将の気持ちが。
【このほどを思ししづめて、慰めきこえむさまをも】- 大君の冷泉院入内の後に考えるところ、すなわち中君を許してもよい、という含み。
|
| 3.1.8 |
|
などと申し上げなさるのも、この院に参るのを過ごして、中の君をとお思いなのであろう。
「時期を一緒にしては、あまりに得意顔に見えよう。
まだ、位なども低いほどだから」などとお思いになると、男は、まったく気持ちを移せそうもなく、ちらっと拝見した後は、面影に立って恋しく、どのような機会にとばかり思っていたが、このように頼みの綱も切れてしまったのを、お嘆きになることはこの上もない。
|
こんな返事を書いたのは、姉君の院参を済ませてから妹を与えたいという考えらしい。同時にそれをするのも世間へ見せびらかすようなことにもなるし、少将の官をも少し進ませてからにしたほうがいいからと、こんなふうに玉鬘夫人は思っているのであったが、男はこの望みどおりに妹の姫君へ恋を移すのは不可能に思っているのである。ほのかに顔を見てからは面影に立つほど恋しくて、どんな日にこの人をまた見ることができるであろうかとばかり歎いているのであったから、もう望みのないこととしてあきらめねばならぬことになったのを非常に悲しんだ。
|
【この御参り過ぐして、中の君をと思すなるべし】- 手紙の趣を語り手が解説してみせる。『紹巴抄』は「此注也」。『全集』は「語り手の解説」と注す。
【さし合はせては】- 以下「あさへたるほどを」まで、玉鬘の心中。
【男は】- 蔵人少将。
【思ひ移るべくもあらず】- 大君から中君に心を移す意。
【いかならむ折に】- 蔵人少将の心中。
|
|
第二段 蔵人少将、藤侍従を訪問
|
| 3.2.1 |
|
愚痴でもこぼそうと思って、いつものように、藤侍従のお部屋に来たところ、源侍従の手紙を見ていらっしゃるのであった。
さっと隠すので、さてはと思って、奪い取った。
「意味有りげな顔にとられては」と思って、強く隠さない。
どことなく、ただ男女関係のつれなさを恨めしそうに書いてあった。
|
今さら何のかいもあることではなくても、なお自分の気持ちだけは通じておきたいと思って、少将が侍従の部屋へ訪ねて行くと、その時侍従は源侍従から来た手紙を読んでいたのであって、隠してしまおうとするのを、少将は奪い取ってしまった。秘密があるように思われたくもないと思って、侍従はしいて取り返そうとはしなかった。それは表面にそのことは言わずに、ただなんとなく人生が暗くなったというようなことばかりの書かれた手紙であった。
|
【侍従の曹司】- 玉鬘邸の藤侍従の部屋。
【源侍従】- 薫。
【見ゐたまへりける】- 主語は藤侍従。
【さなめりと見て、奪ひ取りつ】- 主語は蔵人少将。
【そこはかとなく】- 大島本は「そこはかとなくて(て$、#)」とある。すなわち、「て」をミセケチにした後、さらに抹消している。『集成』『完本』は諸本に従って「そこはかとなくて」と底本の訂正以前本文に従う。『新大系』は底本の訂正に従って「て」を削除する。
【世を恨めしげに】- 「世」は男女関係。
|
| 3.2.2 |
|
「わたしの気持ちを分かっていただけずに過ぎてゆく年月を数えていますと
恨めしくも春の暮になりました」
|
つれなくて過ぐる月日を数へつつ
物怨めしき春の暮れかな
|
【つれなくて過ぐる月日をかぞへつつ--もの恨めしき暮の春かな】- 薫から藤侍従への贈歌。
|
| 3.2.3 |
|
「他人はこのように、悠長に体裁よく恨んでいるようだが、自分のまことに物笑いになる焦りかたを、一つには馴れっこになって、軽んじられることになってしまったのだ」と思うのも、胸が痛むので、特に何も言うことができず、いつも、親しくしている中将のおもとのお部屋の方に行くが、例によって、効のないことだと、溜息をつきがちである。
|
ともある。こんなふうに、余裕のある恨み方をするだけで足りている人もある。自分があまりに無我夢中になって恋にあせることが一つはこの家の人に好感を与えなかったのであろうと、少将はこんなことを思ってさえも胸の痛くなるのを覚えるために、あまり侍従とも話をせずに、親しくする女房の中将の君の部屋のほうへ歩いて行きながらも、これもむだなことに違いないと歎息ばかりをしていた。
|
【人はかうこそ】- 以下「あなづりそめられにたる」まで、蔵人少将の心中。係助詞「こそ」は「ねたげなめれ」に係る。逆接用法。「わが」と対比。
【あなづりそめられにたる」など】- 大島本は「たるなと」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「…たる」と」と「な」を削除する。『新大系』は底本のままとする。
【中将の御許】- 大君付の女房。
【例の、かひあらじかし】- 蔵人少将の心中。
|
| 3.2.4 |
|
侍従の君は、「この返事をしよう」と思って、母上のもとに参上なさるのを見ると、実に腹立たしくおもしろくなく、若いだけに、一途に思いつめているのであった。
|
侍従が源侍従へ書く返事の相談をするために、母の所へ出て行くのを見ても少将は腹がたつのであった。若い人であるから失恋の悲しみに落ちては救われようもなくなったようにばかり思うのだった。
|
【この返りことせむ】- 薫への返事。
【上に参りたまふを】- 母上玉鬘のもとへ、返事の相談に行く。
|
| 3.2.5 |
あさましきまで恨み嘆けば、この前申しも、あまり戯れにくく、いとほしと思ひて、いらへもをさをさせず。かの御碁の見証せし夕暮のことも言ひ出でて、 |
見苦しいまでに恨み嘆くので、この取次役も、たいして冗談にもできず、お気の毒と思って、返事もなかなかしない。
あの碁に立ち会った夕暮のことも言い出して、
|
見苦しいほどにも恨めしがり、悲しがって言い続ける少将の相手になっている中将の君は、いたましく思って返辞もあまりできないのであった。碁の勝負のあった夕方に隙見をしたことも少将は言いだして、
|
【前申し】- 一語。取り次ぎ役、中将の御許のこと。
【いとほしと思ひて】- 主語は中将の御許。
|
| 3.2.6 |
|
「あれくらいの夢でも、再び見たいものだなあ。
ああ、何を頼みにして生きていよう。
このように申し上げることも、寿命少なく思われますので、つれない仕打ちも懐かしい、ということは、本当ですね」
|
「せめてあの瞬間の楽しさだけでも、もう一度経験したい。何を目的にして今後私は生きて行くのでしょう。けれど先はもう短い気のする私ですよ。無情も情けであるというように、死んでしまえるならかえってこれがよかったかもしれませんね」
|
【さばかりの夢をだに】- 以下「まことなりけれ」まで、蔵人少将の詞。
【つらきもあはれ、といふことこそ、まことなりけれ】- 『花鳥余情』は「立ち返りあはれとぞ思ふよそにても人に心をおきつ白波」(古今集恋一、四七四、在原元方)。『弄花抄』は「うれしくは忘るる事もありなましつらきぞ長き形見なりける」(新古今集恋五、一四〇三、清原深養父)を指摘。【あはれと】-大島本は「あハれと」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「あはれとて」と「て」を補訂する。『新大系』は底本のままとする。以下「添ひたるならむ」まで、中将の御許の心中。
|
| 3.2.7 |
と、いとまめだちて言ふ。「あはれと、言ひやるべき方なきことなり。かの慰めたまふらむ御さま、つゆばかりうれしと思ふべきけしきもなければ、げに、かの夕暮の顕証なりけむに、いとどかうあやにくなる心は添ひたるならむ」と、ことわりに思ひて、 |
と、実に真顔になって言う。
「お気の毒だと言って、も慰めようもないことである。
あのお慰め下さるというお話は、少しも嬉しいと思うような様子もないので、なるほど、あの夕暮のはっきりと見えたことに、ますますこのように無闇な思いが募ったのだろう」と、無理もないことに思って、
|
まじめにこんなことを言うのである。同情はしていても、何とも慰める言葉のないことではないかと中将の君は思うのであった。夫人が姉君に代えて二女を許そうとしていることが少しもうれしいふうでないのは、あの桜の夕べにあけ放された座敷までことごとくこの人は見ることができたために、こうした病的なまでの恋を一人の姫君に寄せるようになったのであろうと思うと、道理にも思えた。
|
【慰めたまふらむ御さま】- 大島本は「なくさめ給らん」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「慰めたまはむ」と校訂する。『新大系』は底本のままとする。玉鬘からの返事に、中君を結婚相手にとあったことをさす。
|
| 3.2.8 |
|
「お耳にあそばしたら、ますますなんとけしからぬお心の人なのだと、お恨み申されましょう。
お気の毒だとお思い申していました気持ちもなくなってしまいました。
とても油断のできないお方だったのですね」
|
「姫君がお聞きになりましたら、いっそうけしからん考えを持っておいでになるとお思いになって、御同情が減るでしょう。私のお気の毒に思っておりました気持ちも、もうなくなりましたよ。むちゃなことばかりお言いになるから」
|
【聞こしめさせたらば】- 以下「御心なりけり」まで、中将のおもとの詞。蔵人少将が垣間見たということを姫君がお知りになったら、の意。
【心苦しと思ひきこえつる心】- 中将の御許が蔵人少将を気の毒だと思う気持ち。
|
| 3.2.9 |
と、向ひ火つくれば、
|
と、反対に文句を言うと、
|
正面から中将が攻撃すると、
|
|
| 3.2.10 |
「いでや、さはれや。今は限りの身なれば、もの恐ろしくもあらずなりにたり。さても負けたまひしこそ、いといとほしかりしか。おいらかに召し入れてやは。目くはせたてまつらましかば、こよなからましものを」など言ひて、 |
「ええい、どうともなれ。
もうおしまいの身だから、何も恐くはなくなってしまった。
それにしてもお負けになったことが、実にお気の毒であった。
あっさりと招き入れてくれたら。
目配せ申したら、絶対に勝ったろうものを」などと言って、
|
「そんなことはかまわない。人は死ぬ時になると何もこわいものはなくなりますよ。それにしても碁の勝負にお負けになったのは気の毒だった。私を寛大にお扱いくだすって、あの時目くばせをしてそばへ呼んでくだすったら、よい助言ができたのに、勝たせてあげたのに」などと言って、また、
|
【いでや】- 以下「こよなからましものを」まで、蔵人少将の詞。
【目くはせたてまつらましかば】- 碁にこっそり助言してやれたものを、の意。
|
| 3.2.11 |
|
「いったい何ということか、
物の数でもない身なのにかなえることができ
|
いでやなぞ数ならぬ身にかなはぬは
人に負けじの心なりけり
|
【いでやなぞ数ならぬ身にかなはぬは--人に負けじの心なりけり】- 蔵人少将の詠歌。『集成』は「「数」「負く」は、会話から続いて、碁の縁語」と注す。
|
| 3.2.12 |
中将、うち笑ひて、
|
中将は、吹き出して、
|
とも歌った。中将の君が笑いながら、
|
|
| 3.2.13 |
|
「無理なこと、
強い方が勝つ勝負事をあなたのお心
|
わりなしや強きによらん勝ち負けを
心一つにいかが任する
|
【わりなしや強きによらむ勝ち負けを--心一つにいかがまかする】- 中将の御許の返歌。「強き」「勝ち負け」は碁の縁語。「強き」は冷泉院を暗示。
|
| 3.2.14 |
といらふるさへぞ、つらかりける。
|
と答えるのさえ、辛いことであった。
|
と言う態度までも、冷淡に思われる少将であった。
|
|
| 3.2.15 |
|
「かわいそうだと思って、
姫君をわたしに許してくださいこの先の生死はあなた
|
哀れとて手を許せかし生き死にを
君に任するわが身とならば
|
【あはれとて手を許せかし生き死にを--君にまかするわが身とならば】- 蔵人少将の詠歌。『集成』は「「手をゆるす」は、碁で相手に何目か置き意志を許すこと。「生き死に」は碁の縁語」と注す。
|
| 3.2.16 |
泣きみ笑ひみ、語らひ明かす。
|
泣いたり笑ったりしながら、一晩中語らい明かす。
|
冗談を混ぜては笑いもし、また泣きもして少将は夜通し中将の君の局から去らなかった。
|
|
|
第三段 四月一日、蔵人少将、玉鬘へ和歌を贈る
|
| 3.3.1 |
またの日は、卯月になりにければ、兄弟の君たちの、内裏に参りさまよふに、いたう屈じ入りて眺めゐたまへれば、母北の方は、涙ぐみておはす。大臣も、 |
翌日は、四月になったので、兄弟の君たちが、宮中に参内するために慌ただしくしているのに、ひどく萎れて物思いに沈んでいらっしゃるので、母北の方は、涙ぐんでいらっしゃる。
大臣も、
|
翌日はもう四月になっていた。兄弟たちは季の変わり目で皆御所へまいるのであったが、少将一人はめいりこんで物思いを続けているのを、母の夫人は涙ぐんで見ていた。大臣も、
|
【兄弟の君たち】- 蔵人少将の兄弟たち。夕霧右大臣の子息。
|
| 3.3.2 |
|
「院がお耳にあそばすこともあろう。
どうして、真剣に聞き入れてくれることがあろう、と思って、悔しいことに、お会いした時に申し上げずじまいだった。
自分が無理を押して申し上げたら、いくらなんでもお断りになならなかっただろうに」
|
「院の御感情を害してはならないし、自分がそうした間題に携わるのもいかがと思ったので、せっかく正月に逢っていながら何も言いださなかったのは間違いだった。私の口からぜひと懇望すれば同意の得られないことはなかったろうにと思われるのに」
|
【院の聞こしめすところもあるべし】- 以下「え違へたまはざらまし」まで、夕霧の詞。冷泉院が蔵人少将の執心ぶりを聞いたら不快に思うだろう、の意。
【何にかは】- 「聞き入れむ」に係る。反語表現。
【対面のついでにも】- 玉鬘との面会の折。
【申さましかば】- 「え違へたまはざらまし」に係る、反実仮想の構文。
|
| 3.3.3 |
などのたまふ。
さて、例の、
|
などとおっしゃる。
そのようなことがあって、
|
などと言っていた。この日もいつものように、少将からは、
|
|
| 3.3.4 |
|
「花を見て春は過ごしました。今日からは
茂った木の下で途方に暮れることでしょう」
|
花を見て春は暮らしつ今日よりや
繁きなげきの下に惑はん
|
【花を見て春は暮らしつ今日よりや--しげき嘆きの下に惑はむ】- 蔵人少将の独詠歌。「嘆き」に「木」を響かせ、「繁き」と縁語。
|
| 3.3.5 |
と聞こえたまへり。
|
と申し上げなさった。
|
という歌が恋人へ送られた。
|
|
| 3.3.6 |
|
御前において、あれこれ上臈めいた女房たち、この懸想人が、いろいろと気の毒なことをお話し申し上げる中で、中将のおもとが、
|
姫君の居間で高級な女房たちだけで、失望した求婚者たちのいたましいことが言い並べられている時に、中将の君が、
|
【御前にて】- 大君の御前。
【この御懸想人の】- 蔵人少将ら求婚者をいう。
|
| 3.3.7 |
|
「生き死にをと言った様子が、言葉だけではなく、お気の毒でした」
|
「生き死にを君に任すとお言いになりました時には、それを言葉だけのこととは思われなかったのですから気の毒でございましたよ」
|
【生き死にをと】- 以下「心苦しげなりし」まで、中将の御許の詞。
|
| 3.3.8 |
|
などと申し上げると、尚侍の君も、不憫だとお聞きになる。
大臣や、北の方のお考えにより、どうしても少将の恨みが深いのならばと、中の君を少将にと代わりをお考えになった上でのこのお参りを、邪魔しているように思っているのはけしからぬこと、この上ない身分の方でも、臣下であっては、絶対に許さないと、故殿がご遺言なさっていたものを、院に参りなさることでさえ、将来見栄えがしないものをとお思いになっていた、ちょうどその時に、このお手紙を受け取って気の毒がる。
お返事は、
|
と言っているのを、尚侍は哀れに聞いていた。大臣やその夫人に対する義理と思って、なお娘を忘れぬ志があるなら、その時には誠意の見せ方があると、妹君をそれにあてて玉鬘夫人は思っているのである。しかし院参を阻止しようとするような態度はきわめて不愉快であるとしていた。どれほどりっぱな人であっても、普通人には絶対に与えられぬと父である関白も思っていた娘なのであるから、院参をさせることすら未来の光明のない点で尚侍は寂しく思っていたところへ、少将のこの手紙が来て女房たちはあわれがっていた。中将の君の返事、
|
【大臣、北の方】- 以下「はえばえしからぬを」まで、玉鬘の心中。末尾は地の文に流れる。
【取り替へありて思すこの御参りを】- 大君に代えて中君を蔵人少将にと考えている、この大君の冷泉院入内を、の意。「思す」という敬語の前後は地の文。
【さまたげやうに思ふらむ】- 主語は夕霧や雲居雁。敬語抜きの表現。推量助動詞「らむ」視界外推量、はるかに想像しているニュアンス。
【故殿の思しおきてたりしものを】- 故鬚黒の遺言。
【御文取り入れてあはれがる】- 主語は女房たち。
【御返事】- 大島本は「御返事」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「御返し」と校訂する。『新大系』は底本のままとする。
|
| 3.3.9 |
|
「今日こそ分かりました、
空を眺めているようなふりをして
|
今日ぞ知る空をながむるけしきにて
花に心を移しけりとも
|
【今日ぞ知る空を眺むるけしきにて--花に心を移しけりとも】- 『集成』は「中将のおもとがしたのだろう」。『完訳』は「女房の代作である」と注す。
|
| 3.3.10 |
|
「まあ、お気の毒な。
冗談事にしてしまうのですね」
|
「まあお気の毒な、ただ言葉の遊戯にしてしまうことになるではありませんか」
|
【あな、いとほし】- 以下「取りなすかな」まで、女房の詞。
|
| 3.3.11 |
など言へど、うるさがりて書き変へず。
|
などと言うが、面倒がって書き変えない。
|
などと横から言う人もあったが、中将の君はうるさがって書き変えなかった。
|
|
|
第四段 四月九日、大君、冷泉院に参院
|
| 3.4.1 |
|
九日に、院に参上なさる。
右の大殿は、お車、御前駆の人びとを大勢差し上げなさった。
北の方も、恨めしくお思い申し上げなさったが、長年それほどでもなかったっが、このご一件で、しきりに手紙のやりとりなさったのに、再び途絶えてしまうこともおかしいので、禄や、立派な女の装束などを、たくさん差し上げなさった。
|
四月の九日に尚侍の長女は院の後宮へはいることになった。右大臣は車とか、前駆をする人たちとかを数多くつかわした。雲井の雁夫人は姉の尚侍をうらめしくは思っているが、今まではそれほど親密に手紙も書きかわさなかったのに、あの問題があって、たびたび書いて送ることになったのに、それきりまたうとくなってしまうのもよろしくないと思って、纏頭用として女の衣裳を幾組みも贈った。
|
【九日にぞ、参りたまふ】- 『河海抄』は、藤原時平の娘が宇多上皇に四月九日に入内した例を引く。
【年ごろさもあらざりしに、この御ことゆゑ、しげう聞こえ通ひたまへるを】- 雲居雁と玉鬘は姉妹でありながら、長年親しく文通してこなかったが、蔵人少将の大君への求婚の件で頻繁に文を交わすようになったのだが、の意。
|
| 3.4.2 |
|
「不思議と、気の抜けたような息子の様子を、お世話していますうちに、はっきりと承ることもなかったので、お知らせ下さらなかったことを、他人行儀なと思っております」
|
気の抜けたようになっております人を介抱いたしますのにかかっておりまして、私はまだ何も知らなかったのでしたが、知らせてくださいませんことは、うとうとしいあそばされ方だとお怨みいたします。
|
【あやしう、うつし心もなきやうなる人の】- 以下「うとうとしくなむ」まで、雲居雁から玉鬘への文。子息蔵人少将の落胆ぶりを訴える。
【承りとどむることもなかりけるを】- 大君の冷泉院入内の件。
【おどろかさせたまはぬ】- 主語はあなた玉鬘。「驚かす」は、知らせる意。「せたまふ」二重敬語表現。
|
| 3.4.3 |
とぞありける。おいらかなるやうにてほのめかしたまへるを、いとほしと見たまふ。大臣も御文あり。 |
とあったのだった。
穏やかなようでいてそれとなく恨み言をこめなさったのを、困ったことと御覧になる。
大臣からもお手紙がある。
|
という手紙が添っていた。おおように言いながらも恨みのほのめかせてあるのを尚侍は哀れに思った。大臣からも手紙が送られた。
|
【ほのめかしたまへるを】- 『集成』は「それとなく恨み言をおっしゃっているのを」と訳す。
|
| 3.4.4 |
「みづからも参るべきに、思うたまへつるに、慎む事のはべりてなむ。男ども、雑役にとて参らす。疎からず召し使はせたまへ」 |
「わたし自身参上しなければ、と存じましたが、物忌みがございまして。
子息たちを、雑用にと思って伺わせます。
ご遠慮なさらずお使い下さい」
|
私も上がろうと思っていたのですが、あやにく謹慎日にあたるものですから失礼いたします。息子たちはどんな御用にでもお心安くお使いください。
|
【みづからも参るべきに】- 以下「召し使はせたまへ」まで、夕霧から玉鬘への文。
|
| 3.4.5 |
|
と言って、源少将、兵衛佐など、を差し上げなさった。
「ご厚意ありがとうございます」と、お礼申し上げなさる。
大納言殿からも、女房たちのお車を差し上げなさる。
北の方は、故大臣の娘で、真木柱の姫君なので、どちらの関係から見ても、親しくご交際なさり合うはずでいらっしゃるが、そんなにでもない。
|
と言って、源少将、兵衛佐などをつかわした。
「御親切は十分ある方だ」
と言って玉鬘夫人は喜んでいた。弟の大納言の所からも女房用にする車をよこした。この人の夫人は故関白の長女でもあったから、どちらからいっても親密でなければならないのであるが、実際はそうでもなかった。
|
【源少将、兵衛佐など】- 夕霧の子息、蔵人少将の兄弟たち。源少将は四男(藤典侍腹)、兵衛佐は六男。蔵人少将は五男。
【情けはおはすかし】- 玉鬘のお礼の詞。
【大納言殿よりも】- 紅梅大納言。玉鬘の実家の主人、姉弟でもある。
【真木柱の姫君なれば】- 真木柱は故鬚黒と北の方の娘、蛍兵部卿宮に嫁して死別後、紅梅大納言の後の北の方となる。玉鬘の継子でもある。
|
| 3.4.6 |
|
藤中納言は、ご自身でいっしゃって、中将や、弁の君たちと、一緒に準備をなさる。
殿が生きていらっしゃったならばと、何事につけても悲しい思いがする。
|
藤中納言は自身で来て、異腹の弟の中将や弁の公達といっしょになり、今日の世話に立ち働いていた。父の関白がいたならばと、何につけてもこの人たちは思われるのであった。
|
【藤中納言は】- 鬚黒の長男。真木柱の兄。大君とは異母兄妹。
【中将、弁の君たち、もろともに】- 玉鬘腹の子息の左中将と右中弁。
|
|
第五段 蔵人少将、大君と和歌を贈答
|
| 3.5.1 |
|
蔵人の君は、いつもの女房に大げさな言葉の限りを尽くして、
|
蔵人少将は例のように綿々と恨みを書いて、
|
【蔵人の君】- 夕霧の子息、蔵人少将。
【例の人に】- 中将の御許に。
|
| 3.5.2 |
|
「もうお終いだと思っております命も、そうはいっても悲しいよ。
せめてお気の毒ぐらいに思う、とだけでも、一言おっしゃって下さったら、その言葉に引かれて、もう暫く生きていられましょうか」
|
もう生ききれなく見えます命のさすがに悲しい私を、哀れに思うとただ一言でも言ってくださいましたら、それが力になってしばらくはなお命を保つこともできるでしょう。
|
【今は限りと思ひはべる命の】- 大島本は「思はへる」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「思ひ果つる」と校訂する。『新大系』は底本のままとする。以下「ながらへやせむ」まで、蔵人少将の手紙。
|
| 3.5.3 |
|
などと書いてあるのを、持参して見ると、姫君たちお二方がお話して、とてもひどく沈み込んでいらっしゃった。
昼夜一緒に居馴れて、中の戸だけを隔てた西と東の間でさえ、邪魔にお思いになって、お互いに行き来なさっていたが、離れ離れになろうことをお考えなのであった。
|
などとも言ってあるのを、中将の君が持って行った時に、居間では二人の姫君が別れることを悲しんでめいったふうになっていた。夜も昼もたいていいっしょにいた二人で、居間と居間の間に戸があって西東になっていることをすら飽き足らぬことに思って、双方どちらかが一人の居間へ行っていたような姉妹が、別れ別れになるのを悲観しているのである。
|
【持て参りて見れば】- 中将の御許が大君のもとに持参して様子を見ると、の意。
【中の戸ばかり隔てたる西東】- 『集成』は「「中の戸」は、中仕切りの戸。障子(襖)であろう」と注す。
【よそよそにならむことを思すなりけり】- 前の「いといたう屈じたまへり」の理由説明の叙述。『完訳』「別れの悲しみに、あらためて気づく気持」と注す。
|
| 3.5.4 |
|
特別に注意して準備して、お着付け申したご様子は、とても立派である。
殿がご遺言なさった様子などをお思い出しになって、悲しい時だったせいか、手に取って御覧になる。
「大臣や、北の方が、あれほど揃って、頼もしそうなご家庭で、どうしてこのようなわけの分からないことを思ったり言ったりするのだろう」と不思議なのにつけても、「お終いだ」とあるので、「本当だろうか」とお思いになって、そのままこのお手紙の端に、
|
ことに美しく化粧がされ、晴れ着をつけさせられている姫君は非常に美しかった。父が天子の後宮の第一人にも擬していた自分であったがと、そんなことを思い出していて、寂しい気持ちに姫君がなっていた時であったから、少将の手紙も手に取って読んでみた。りっぱに父もあり母もそろっている家の子でいて、なぜこうした感情の節制もない手紙を書くのであろうと姫君はいぶかりながらも、それかぎりであきらめようと書かれてあるのを、真実のことかとも思って、少将の手紙の端のほうへ、
|
【取りて見たまふ】- 大君が蔵人少将からの手紙を。
【大臣、北の方の、さばかり立ち並びて】- 以下「思ひ言ふらむ」まで、大君の心中。蔵人少将の両親揃っていることを思い比べる。
【限り」とあるを】- 蔵人少将の手紙に「今は限りと思ひはべる命」とあったことをさす。
【まことや」と思して】- 大島本は「まことや」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「まことにや」と「に」を補訂する。『新大系』は底本のままとする。
|
| 3.5.5 |
|
「あわれという一言も、
この無常の世にいったいどなたに言い掛けた
|
哀れてふ常ならぬ世の一言も
いかなる人に掛くるものぞは
|
【あはれてふ常ならぬ世の一言も--いかなる人にかくるものぞは】- 大君の返歌。「あはれと思ふとばかりだに一言のたまはせば」とあったことを受けて返す。
|
| 3.5.6 |
|
縁起でもない方面のこととしては、少しは存じております」
|
生死の問題についてだけほのかにその感じもいたします。
|
【ゆゆしき方にてなむ、ほのかに思ひ知りたる】- 歌に添えた文言。「あはれ」を愛情としてでなく無常一般のこととした。
|
| 3.5.7 |
|
とお書きになって、「このように言いなさい」とおっしゃるのを、そのまま差し上げたところ、この上なく有り難いと思うにつけても、最後の機会をお考えになっていたのまでが嬉しくて、ますます涙が止まらない。
|
とだけ書いて、「こう言ってあげたらどう」と姫君が言ったのを、中将の君はそのまま蔵人少将へ送ってやった。珍しい獲物のようにこれが非常にうれしかったにつけても、今日が何の日であるかと思うと、また少将の涙はとめどもなく流れた。
|
【かう言ひやれかし】- 『集成』は「こう言っておやり。書き換えて返事せよ、の意」。『完訳』は「清書して伝えよ、の気持か」と注す。
【とのたまふを、やがてたてまつれたる】- 接続助詞「を」逆接の意。大君の言葉に反して、中将の御許は書き変えずそのまま蔵人少将に与えた。
【折思しとむる】- 大島本は「おり」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「をりを」と「を」を補訂する。『新大系』は底本のままとする。『集成』は「院に御参りの当日、最後の折であることをお心に止めて返事を下さったのも(胸に迫って)」。『完訳』は「参院の当日、最後の機会と思って返事をくれたのも」と注す。
|
| 3.5.8 |
|
折り返し、「誰の浮名が立たないで済みましょう」などと、恨みがましく書いて、
|
またすぐに、「恋ひ死なばたが名は立たん」などと恨めしそうなことを書いて、
|
【誰が名は立たじ】- 『源氏釈』は「恋ひ死なば誰が名は立たじ世の中の常なきものと言ひはなすとも」(古今集恋二、六〇三、清原深養父)を踏まえたものであることを指摘。
【かことがましくて】- 『集成』は「恨みがましく書いて」と訳す。
|
| 3.5.9 |
|
「生きているこの世の生死は思う通りにならないので
聞かずに諦めきれましょうか、
|
生ける世の死には心に任せねば
聞かでややまん君が一言
|
【生ける世の死には心にまかせねば--聞かでややまむ君が一言】- 蔵人少将の返歌。『完訳』は「死ねば「あはれ」と思ってくれるとのこと、生きている限りは「あはれ」と言ってくれぬのか」と訳す。
|
| 3.5.10 |
|
墓の上でもあわれという一言をおかけになるようなお心の中と、存じられましたら、一途に死ぬことも急がれましょうに」
|
塚の上にでも哀れをかけてくださるあなただと思うことができましたら、すぐにも死にたくなるでしょうが。
|
【塚の上にも掛けたまふべき御心のほど】- 大島本は「ほと」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「ほどと」と「と」を補訂する。『新大系』は底本のままとする。以下「急がれはべらましを」まで、歌に添えた文言。『源氏釈』は、季札の剣の故事(史記、呉世家・和漢朗詠集下、風)を踏まえることを指摘。
【思ひたまへましかば】- 「たまへ」下二段活用、謙譲の補助動詞。主語は蔵人少将。「ましかば」--「まし」反実仮想の構文。死に急ぐ気になれない、生きて「あはれ」と言ってもらいたい、の意。
|
| 3.5.11 |
|
などとあるので、「まずいこと返事をしてしまったな。
書き変えないでやってしまったことよ」と辛そうにお思いになって、何もおっしゃらなくなった。
|
こんなことも二度めの手紙にあるのを読んで、姫君はせねばよい返事をしたのが残念だ、あのまま送ってやったらしいと苦しく思って、もうものも言わなくなった。
|
【うたてもいらへをしてけるかな。書き変へでやりつらむよ】- 大君の心中。
|
|
第六段 冷泉院における大君と薫君
|
| 3.6.1 |
|
女房や、女童、無難な者だけを揃えられた。
大方の儀式などは、帝に入内なさる時と、違った所がない。
まず、女御の御方に参上なさって、尚侍の君は、ご挨拶など申し上げなさる。
夜が更けてから院の御座所にお上がりになった。
|
院へ従って行く女房も童女もきれいな人ばかりが選ばれた。儀式は御所へ女御の上がる時と変わらないものであった。尚侍はまず女御のほうへ行って話などをした。新女御は夜が更けてからお宿直に上がって行ったのである。
|
【ととのへられたり】- 「られ」尊敬の助動詞。「たまふ」より敬意が軽い。
【まづ、女御の御方に渡りたまひて、尚侍の君は、御物語など聞こえたまふ】- 冷泉院の弘徽殿の女御に玉鬘は挨拶する。弘徽殿の女御は玉鬘の異母姉、女一の宮の母女御として最も気をつかうところ。
|
| 3.6.2 |
|
后や、女御など、皆、長年、院にあって年配になっていらっしゃるので、とてもかわいらしく、女盛りで見所のある様子をお見せ申し上げなさっては、どうしていいかげんに思われよう。
はなやかに御寵愛を受けられなさる。
臣下のように、気安くお暮らしになっていらっしゃる様子が、なるほど、申し分なく立派なのであった。
|
后の宮も女御たちも、もう皆長く侍しておられる人たちばかりで、若い人といってはない所へ、花のような美しい新女御が上がったのであるから、院の御寵愛がこれに集まらぬわけはない。たいへんなお覚えであった。上ない御位におわしました当時とは違って、唯人のようにしておいでになる院の御姿は、よりお美しく、より光る御顔と見えた。
|
【后、女御など、みな年ごろ経て】- 秋好中宮は五十三歳、弘徽殿女御は四十五歳など。
【などてかはおろかならむ】- 語り手の感情移入の句。
【ただ人だちて、心やすく】- 冷泉院が。譲位後の堅苦しくない生活の様子。
|
| 3.6.3 |
|
尚侍の君を、暫くの間伺候なさるようにと、お心にかけていらっしゃったが、とても早く、静かに退出なさってしまったので、残念に情けなくお思いなさった。
|
尚侍が当分娘に添って院にとどまっていることであろうと、院は御期待あそばされたのであるが、早く帰ってしまったのを残念に思召し、恨めしくも思召した。
|
【口惜しう心憂しと思したり】- 主語は冷泉院。
|
| 3.6.4 |
|
源侍従の君を、明け暮れ御前にお召しになって離さずにいられるので、なるほど、まるで昔の光る源氏がご成人なさった時に劣らない御寵愛ぶりである。
院の内では、どの御方とも別け隔てなく、親しくお出入りしていらっしゃる。
こちらの御方にも、好意を寄せているように振る舞って、内心では、どのように思っていらっしゃるのだろうという考えまでがおありであった。
|
院は源侍従を始終おそばへお置きになって愛しておいでになるのであって、昔の光源氏が帝の御寵児であったころと同じように幸福に見えた。院の中では后の宮のほうへも、女一の宮の御母女御のほうへもこの人は皆心安く出入りしているのである。新女御にも敬意を表しに行くことをしながら、心のうちでは、失敗した求婚者をどう見ているかと知りたく思っていた。
|
【げに、ただ昔の光る源氏の】- 語り手の感想を交えた表現。
【生ひ出でたまひしに劣らぬ人の御おぼえなり】- 『集成』は「ご成人なさった時に劣らぬご寵愛ぶりである」と訳す。
【この御方にも】- 大君。
【心寄せあり顔にもてなして】- 主語は薫。
|
|
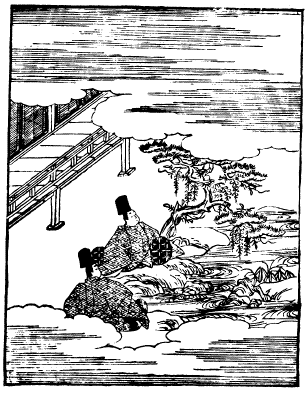 |
| 3.6.5 |
夕暮のしめやかなるに、藤侍従と連れてありくに、かの御方の御前近く見やらるる五葉に、藤のいとおもしろく咲きかかりたるを、水のほとりの石に、苔を蓆にて眺めゐたまへり。まほにはあらねど、世の中恨めしげにかすめつつ語らふ。 |
夕暮のひっそりとした時に、藤侍従と連れ立って歩いていると、あちらの御前の近くに眺められる五葉の松に、藤がとても美しく咲きかかっているのを、遣水のほとりの石の上に、苔を敷物として腰掛けて眺めていらっしゃった。
はっきりとではないが、姫君のことを恨めしそうにほのめかしながら話している。
|
ある夕方のしめやかな気のする時に、薫の侍従は藤侍従とつれ立って院のお庭を歩いていたが、新女御の住居に近い所の五葉の木に藤が美しくかかって咲いているのを、水のそばの石に、苔を敷き物に代えて二人は腰をかけてながめていた。露骨には言わないのであるが、失恋の気持ちをそれとなく薫は友にもらすのであった。
|
【世の中恨めしげにかすめつつ語らふ】- 『集成』は「敬語がないのは、薫に密着した書き方」と注す。
|
| 3.6.6 |
|
「手に取ることができるものなら、
藤の花の松の緑より勝れた色を空しく眺めていま
|
手にかくるものにしあらば藤の花
松よりまさる色を見ましや
|
【手にかくるものにしあらば藤の花--松よりまさる色を見ましや】- 薫の詠歌。『集成』は「私の力の及ぶものなら、姫君を人のものにはしなかったのに、の含意」と注す。大君を藤の花に喩える。
|
| 3.6.7 |
|
と言って、花を見上げている様子など、妙に気の毒に思われるので、自分の本心からでないことにほのめかす。
|
と言って、花を見上げた薫の様子が身に沁んで気の毒に思われた藤侍従は、自身は無力で友のために尽くすことができなかったということをほのめかして薫をなだめていた。
|
【わが心にあらぬ世のありさまにほのめかす】- 冷泉院への憚りから。
|
| 3.6.8 |
|
「紫の色は同じだが、
あの藤の花はわたしの思う通りにできな
|
紫の色は通へど藤の花
心にえこそ任せざりけれ
|
【紫の色はかよへど藤の花--心にえこそかからざりけれ】- 藤侍従の返歌。「色は通へど」は大君と姉弟であることをいう。「藤に花」「かかる」は縁語。
|
| 3.6.9 |
まめなる君にて、いとほしと思へり。
いと心惑ふばかりは思ひ焦られざりしかど、口惜しうはおぼえけり。
|
まじめな君なので、気の毒にと思っていた。
さほど理性を失うほど思い込んだのではなかったが、残念に思っていたのであった。
|
まじめな性質の人であったから深く同情をしていた。薫は失恋にそれほど苦しみもしていなかったが残念ではあった。
|
|
|
第七段 失意の蔵人少将と大君のその後
|
| 3.7.1 |
かの少将の君はしも、まめやかに、いかにせましと、過ちもしつべく、しづめがたくなむおぼえける。聞こえたまひし人びと、中の君をと、移ろふもあり。少将の君をば、母北の方の御恨みにより、さもやと思ほして、ほのめかし聞こえたまひしを、絶えて訪れずなりにたり。 |
あの少将の君は、真剣に、どのようにしようかと、間違い事もしでかしそうに、抑え難く思っているのであった。
求婚申された方々で、中の君にと、鞍替えする人もいる。
少将の君を、母北の方のお恨み言があるので、中の君を許そうかとお思いになって、それとなく申し上げなさったが、すっかり音沙汰がなくなってしまった。
|
蔵人少将はどうすればよいかも自身でわからぬほど失恋の苦に悩んで、自殺もしかねまじい気色に見えた。求婚者だった人の中では目標を二女に移すのもあった。蔵人少将を母夫人への義理で二女の婿にもと思い、かつて尚侍はほのめかしたこともあったが、あの時以後もう少将はこの家を訪ねることをしなくなった。
|
【母北の方の御恨みにより】- 蔵人少将の母北の方、雲居雁。
|
| 3.7.2 |
|
冷泉院には、あの君たちも、親しくもともと伺候なさっていたが、この姫君が参上なさってから後は、ほとんど参上せず、まれに殿上の方に顔を見せても、つまらなく、逃げて退出するのであった。
|
院へは右大臣家の子息たちが以前から親しくまいっているのであったが、蔵人少将は新女御のまいって以来あまり伺候することがなくて、まれまれに殿上の詰め所へ顔を出してもその人はすぐに逃げるようにして帰った。
|
【殿上の方にさしのぞきても】- 冷泉院の御所の殿上間。
|
| 3.7.3 |
|
帝におかせられては、故大臣のご意向に格別なものがあったので、このように遺志に反したお宮仕えを、どうしたことにか、とお思いあそばして、中将を呼んで仰せになった。
|
帝は、故人の関白の意志は姫君を入内させることであって、院へ奉ることではなかったのを、遺族のとった処置は腑に落ちぬことに思召して、中将をお呼びになってお尋ねがあった。
|
【内裏には、故大臣の心ざしおきたまへるさまことなりしを、かく引き違へたる御宮仕へを】- 今上帝は故鬚黒大臣が大君を入内させたい旨奏上していたが、冷泉院に参院してしまったことをいぶかしく思う。
【中将を召して】- 故鬚黒と玉鬘の長男。左近中将。
|
| 3.7.4 |
「御けしきよろしからず。さればこそ、世人の心のうちも、傾きぬべきことなりと、かねて申しし事を、思しとるかた異にて、かう思し立ちにしかば、ともかくも聞こえがたくてはべるに、かかる仰せ言のはべれば、なにがしらが身のためも、あぢきなくなむはべる」 |
「ご機嫌ななめです。
それだからこそ、世間の人の思惑も、不審に思うに違いないと、かねて申し上げていたことを、ご判断を間違えて、このように御決心なさったので、何とも申し上げにくうございますが、このような仰せ言がございましたので、わたしどもの身のためにも、困ったことでございます」
|
「天機よろしくはありませんでした。ですから世間の人も心の中でまずいことに思うことだと私が申し上げたのに、お母様は、信じるところがおありにでもなるように院参のほうへおきめになったものですから、私らが意見を異にしているようなことは言われなかったのです。ああしたお言葉をお上からいただくようでは私の前途も悲観されます」
|
【御けしきよろしからず】- 以下「あぢきなくなむはべる」まで、左中将の詞。
【かかる仰せ言のはべれば】- 帝の御不快の言葉。
|
| 3.7.5 |
と、いとものしと思ひて、尚侍の君を申したまふ。
|
と、とても不愉快に思って、尚侍の君をお責め申し上げなさる。
|
中将は不愉快げに母を責めるのだった。
|
|
| 3.7.6 |
|
「さあね。
たった今、このように、急に思いついたのではなかったのに。
無理やりに、お気の毒なほど仰せになったので、後見のない宮仕えの宮中生活は、頼りないようですが、今では気楽な御生活のようなので、お預け申して、と思ったからです。
誰も彼もが、不都合なことは、率直に注意なさらずに、今頃むし返して、右大臣殿も、間違っていたような、おっしゃりようをなさるので、辛いことです。
これも前世からの因縁でしょうよ」
|
「何も私がそうでなければならぬときめたことではなく、ずいぶん躊躇をしたことなのだがね。お気の毒に存じ上げるほどぜひにと院の陛下が御懇望あそばすのだもの、後援者のない人は宮中にはいってからのみじめさを思って、はげしい競争などはもうだれもなさらないような院の後宮へ奉ったのですよ。だれも皆よくないことであれば忠告をしてくれればいいのだけれど、その時は黙っていて、今になると右大臣さんなども私の処置が悪かったように、それとなくおっしゃるのだから苦しくてなりませんよ。皆宿命なのですよ」
|
【いさや。ただ今】- 以下「これもさるべきにこそは」まで玉鬘の詞。
【あながちに、いとほしうのたまはせしかば】- 主語は冷泉院。
【後見なき交じらひの内裏わたりは】- 今上帝の後宮生活をいう。
【今は心やすき御ありさまなめるに】- 冷泉院の後宮生活をいう。
【誰れも誰れも、便なからむ事は、ありのままにも諌めたまはで】- 『完訳』は「実際には中将たちが参院に反対した。これは当座の言いのがれ」と注す。
|
| 3.7.7 |
と、なだらかにのたまひて、心も騒がいたまはず。
|
と、穏やかにおっしゃって、動揺なさらない。
|
と穏やかに尚侍は言っていた。心も格別騒いではいないのである。
|
|
| 3.7.8 |
|
「その前世からのご宿縁は、目には見えないものなので、このように思し召し仰せになるのを、これは御縁がございませんと、どうして弁解申し上げることができましょう。
中宮に御遠慮申されるとして、院の女御を、どのようにお扱い申されるおつもりですか。
後見や何やかやと、以前よりお互いに親しくなさっていても、そうもまいりませんでしょう。
|
「その前生の因縁というものは、目に見えないものですから、お上がああ仰せられる時に、あの妹は前生からの約束がありましてなどという弁解は申し上げられないではありませんか。中宮がいらっしゃるからと御遠慮をなすっても、院の御所には叔母様の女御さんがおいでになったではありませんか。世話をしてやろうとか、何とか、言っていらっしゃって御了解があるようでも、いつまでそれが続くことですかね、
|
【その昔の】- 以下「聞き耳もはべらむ」まで、左中将の詞。
【思しのたまはするを】- 主語は帝。
【中宮を憚りきこえたまふとて】- 明石中宮。源氏の娘。玉鬘の娘大君とは叔母姪の関係妹。
【院の女御をば、いかがしたてまつりたまはむとする】- 冷泉院の弘徽殿の女御。故致仕大臣の娘。玉鬘の娘大君とは伯母姪の関係。『完訳』は「入内の場合、明石の中宮に遠慮すべきとはいえ、参院の場合、弘徽殿女御には遠慮がいらぬのか」と注す。
|
| 3.7.9 |
|
まあよい、
拝見致しましょう。よく考えれば、宮中は、中宮がいらっしゃるとて、他のお方は宮仕えなさ
らないでしょうか。帝にお仕え申すことは、それが気楽にできるところを、昔から興趣あるこ
ととしたものです。女御は、ちょっとした行き違いでもあって、不愉快にお思い申し上げなさったら、間違った宮仕えのように、世間も取り
|
私は見ていましょう。御所には中宮がおいでになるからって、後宮がほかにだれも侍していないでしょうか。君に仕えたてまつることでは義理とか遠慮とかをだれも超越してしまうことができると言って、宮仕えをおもしろいものに昔から言うのではありませんか。院の女御が感情を害されるようなことが起こってきて、世間でいろんな噂をされるようになれば、初めからこちらのしたことが間違いだったとだれにも思われるでしょう」
|
【異人は交じらひたまはずや】- 係助詞「や」反語表現。後宮には大勢の妃がいるものだ、という趣旨。
【君に仕うまつることは】- 帝に入内することをいう。
【女御は】- 弘徽殿女御。
【よろしからず思ひきこえたまはむに】- 主語は弘徽殿女御。推量助動詞「む」仮定の意。
【ひがみたるやうに】- 伯母姪の関係でうまくいっていない。
|
| 3.7.10 |
|
などと、二人して申し上げなさるので、尚侍の君、とても辛くお思いになって、その一方では、この上ない御寵愛が、月日とともに深まって行く。
|
などとも中将は言った。兄弟がまたいっしょになっても非難するのを玉鬘夫人は苦しく思った。その新女御を院が御寵愛あそばすことは月日とともに深くなった。
|
【二所して】- 左中将と右中弁の兄弟して。
【さるは、限りなき御思ひのみ、月日に添へて】- 『集成』は「とはいえ、(大君に対しては)院のこの上なもないご寵愛が、ただもう月日のたつにつれてまさる」と訳す。
|
| 3.7.11 |
|
七月からご懐妊なさったのであった。
「苦しそうにしていらっしゃる様子は、なるほど、男性たちがいろいろと求婚申して困らせたのも、もっともである。
どうしてこのような方を、軽く見聞きしてそのまま放っていられようか」と思われる。
毎日のように、管弦の御遊をなさっては、侍従もお側近くにお召しになるので、お琴の音などをお聞きになる。
あの「梅が枝」に合奏した中将のおもとの和琴も、いつも召し出して弾かせなさるので、それと聞くにつけても、平静ではいられなかった。
|
七月からは妊娠をした。悪阻に悩んでいる新女御の姿もまた美しい。世の中の男が騒いだのはもっともである、これほどの人を話だけでも無関心で聞いておられるわけはないのであると思われた。御愛姫を慰めようと思召して、音楽の遊びをその御殿でおさせになることが多くて、院は源侍従をも近くへお招きになるので、その人の琴の音などを薫は聞くことができた。この侍従が正月に「梅が枝」を歌いながら訪ねて行った時に、合わせて和琴を弾いた中将の君も常にそのお役を命ぜられていた。薫は弾き手のだれであるかを音に知って、その夜の追想が引き出されもした。
|
【七月よりはらみたまひにけり】- 四月九日に冷泉院に参院した。大君の懐妊。
【うち悩みたまへるさま】- 悪阻のさま。
【げに、人のさまざまに聞こえわづらはすも、ことわりぞかし】- 語り手の批評。『紹巴抄』は「双地」と指摘。
【いかでかはかからむ人を、なのめに見聞き過ぐしてはやまむ」とぞおぼゆる】- 語り手の感想。『細流抄』は「草子地也」と指摘。
【侍従も気近う召し入るれば】- 冷泉院が薫を側近くに招き入れる。
【御琴の音などは】- 大君が弾く琴の音。
【中将の御許】- 大君の女房として一緒に冷泉院に入っている。
|
|
第四章 玉鬘の物語 玉鬘の姫君たちの物語
|
|
第一段 正月、男踏歌、冷泉院に回る
|
| 4.1.1 |
|
その年が改まって、男踏歌が行われた。
殿上の若人たちの中に、芸達者な者が多いころである。
その中でも、優れた人をお選びあそばして、この四位侍従は、右の歌頭である。
あの蔵人少将は、楽人の数の中にいた。
|
翌年の正月には男踏歌があった。殿上の若い役人の中で音楽のたしなみのある人は多かったが、その中でもすぐれた者としての選にはいって薫の侍従は右の歌手の頭になった。あの蔵人少将は奏楽者の中にはいっていた。
|
【男踏歌せられけり】- 正月十四日、宮中で行われる。女踏歌は毎年行われたが、男踏歌は隔年または数年間を置いて行われた。
【四位の侍従】- 薫。
【楽人の数のうちにありけり】- 『完訳』は「音楽を奏する役、九人」と注す。
|
| 4.1.2 |
|
十四日の月が明るく雲がないので、御前を出発して、冷泉院に参る。
女御も、この御息所も、院の御殿に上局を設けて御覧になる。
上達部、親王たちが、連れ立って参上なさる。
|
初春の十四日の明るい月夜に、踏歌の人たちは御所と冷泉院へまいった。叔母の女御も新女御も見物席を賜わって見物した。親王がた、高官たちも同時に院へ伺候した。
|
【御前より出でて、冷泉院に参る】- 踏歌のコースは宮中の清涼殿東庭から、院、中宮、春宮の順に回り、暁に宮中に帰って来る。
【この御息所も】- 大君をいう。御子出産の妃をいう呼称。まだ御子は誕生していない。四月に女宮が生まれる。
【上に御局して見たまふ】- 冷泉院御所の寝殿の一角に部屋を設けての意。
|
| 4.1.3 |
|
「右の大殿と、致仕の大殿の一族とを除くと、端正で美しい人はいない世の中だ」と思われる。
帝の御前よりも、この院をたいそう気の置ける、格別の所とお思い申し上げて、「すべての人が気をつかう中でも、蔵人少将は、御覧になっていらっしゃるだろう」と想像して、落ち着いていられない。
|
源右大臣と、その舅家の太政大臣の二系統の人たち以外にはなやかなきれいな人はないように見える夜である。宮中で行なった時よりも、院の御所の踏歌を晴れがましいことに思って、人々は細心な用意を見せて舞った。また奏し合った中でも蔵人少将は、新女御が見ておられるであろうと思って興奮をおさえることができないのである。
|
【右の大殿、致仕の大殿の族を離れて】- 夕霧と致仕大臣の一族(紅梅大納言他)以外は、の意。
【見たまふらむかし】- 主語は大君。
|
| 4.1.4 |
|
匂いもなく見苦しい綿花も、插頭す人によって見分けられて、態度も声も、実に美しかった。
「竹河」を謡って、御階のもとに踏み寄る時、過ぎ去った夜のちょっとした遊びも思い出されたので、調子を間違いそうになって涙ぐむのであった。
|
美しい物でもないこの夜の綿の花も、挿頭す若公達に引き立てられて見えた。姿も声も皆よかった。「竹河」を歌って階のもとへ歩み寄る時、少将の心にもまた去年の一月の夜の記憶がよみがえってきたために、粗相も起こしかねないほどの衝動を受けて涙ぐんでいた。
|
【過ぎにし夜のはかなかりし遊びも】- 昨年正月二十日過ぎの玉鬘邸の夜のこと。
【思ひ出でられければ】- 主語は蔵人少将。
|
| 4.1.5 |
|
后の宮の御方に参ると、上もそちらにおいであそばして御覧になる。
月は、夜が更けて行くにつれて、昼よりきまりが悪いくらい澄み昇って、どのように御覧になっているだろうとばかり思われるので、踏む所も分からずふらふら歩いて、盃も、名指しで一人だけ責められるのは、面目ないことである。
|
后の宮の御前で踏歌がさらにあるため、院もまたそちらへおいでになって御覧になるのであった。深更になるにしたがって澄み渡った月は昼より明るく照らすので、御簾の中からどう見られているかということに上気して、少将は院のお庭を歩くのでなく漂って行く気持ちでまいった。杯を受けて飲むことが少ないと言って、自身一人が責められることになるのも恥ずかしかった。
|
【后の宮の御方に参れば】- 秋好中宮の御殿。冷泉院の中の御殿。
【上もそなたに渡らせたまひて御覧ず】- 冷泉院も秋好中宮の御殿に移って一緒に御覧になる。
【夜深くなるままに】- 大島本は「夜ふかく」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「夜累ふかう」と校訂する。『新大系』は底本のままとする。
【いかに見たまふらむとのみ】- 蔵人少将は大君(御息所)がどのように見ているかと。
【さして一人をのみとがめらるるは】- 名指しで一人だけ飲みぶりが悪いと責められる意。
|
|
第二段 翌日、冷泉院、薫を召す
|
| 4.2.1 |
|
一晩中、方々を歩いて、とても気分が苦しくて臥せっているところに、源侍従を、院から召されたので、「ああ、苦しい。
もう暫く休みたいのに」と文句を言いながら参上なさった。
宮中でのことなどをお尋ねあそばす。
|
踏歌の人たちは夜通しあちらこちらとまわったために翌日は疲労して寝ていた。薫侍従に院からのお召があった。「苦しいことだ。しばらく休養したいのに」と言いながら伺候した。御所で踏歌を御覧になった様子などを院はお尋ねになるのであった。
|
【あな、苦し。しばし休むべきに】- 薫の詞。
【御前のことどもなど問はせたまふ】- 主語は冷泉院。冷泉院が薫に。
|
| 4.2.2 |
「歌頭は、うち過ぐしたる人のさきざきするわざを、選ばれたるほど、心にくかりけり」 |
「歌頭は、年配者がこれまでは勤めた役なのに、選ばれたことは、大したものだね」
|
「歌頭は今まで年長者がするものなのだが、それに選ばれるほど認められているのだと思って満足した」
|
【歌頭は】- 以下「心にくかりけり」まで、冷泉院の詞。
|
| 4.2.3 |
|
とおっしゃって、かわいいとお思いになっているようである。
「万春楽」をお口ずさみなさりながら、御息所の御方にお渡りあそばすので、お供して参上なさる。
見物に参った里方の人が多くて、いつもより華やかで、雰囲気が賑やかである。
|
と仰せられてかわいく思召す御さまである。「万春楽」(踏歌の地に弾く曲)の譜をお口にあそばしながら新女御の御殿へおいでになる院のお供を薫はした。前夜の見物に自邸のほうから来ていた人たちが多くて、平生よりも御簾の中のけはいがはなやかに感ぜられるのである。
|
【うつくしと思しためり】- 推量の助動詞「めり」主観的推量のニュアンスは語り手の推測。
【万春楽」を御口ずさみにしたまひつつ】- 主語は冷泉院。
【御供に参りたまふ】- 主語は薫。
【物見に参りたる里人多くて】- 男踏歌見物に来た冷泉院の後宮の実家の人々。
|
| 4.2.4 |
渡殿の戸口にしばしゐて、声聞き知りたる人に、ものなどのたまふ。
|
渡殿の戸口に暫く座って、声を聞き知っている女房に、お話などなさる。
|
渡殿の口の所にしばらく薫はいて、声になじみのある女房らと話などをしていた。
|
|
|
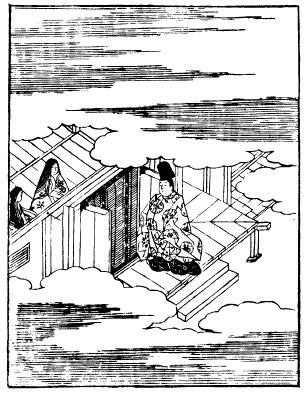 |
| 4.2.5 |
|
「昨夜の月の光は、体裁の悪かったことだなあ。
蔵人少将が、月の光に面映ゆく思っていた様子も、桂の影に恥ずかしがっていたのではなかろうか。
雲の上近くでは、そんなには見えませんでした」
|
「昨夜の月はあまりに明るくて困りましたよ。蔵人少将が輝くように見えましたね。御所のほうではそうでもありませんでしたが」
|
【一夜の月影は】- 以下「さしも見えざりき」まで、薫の詞。
【雲の上近くては】- 宮中をさす。
|
| 4.2.6 |
など語りたまへば、人びとあはれと、聞くもあり。
|
などとお話なさると、女房たちはお気の毒にと、聞く者もいる。
|
などと言う薫の言葉を聞いて、心に哀れを覚えている女房もあった。
|
|
| 4.2.7 |
|
「闇でははっきりしませんが、月に照らされたお姿は、あなたのほうが素晴らしかった、とお噂しました」などとおだてて、内側から、
|
夜のことでよくわかりませんでしたが、あなたがだれよりもごりっぱだったということは一致した評でございました」などと口上手なことも言って、また中から、
|
【闇はあやなきを】- 以下「定めきこえし」まで、女房の詞。『源氏釈』は「春の夜の闇はあやなし梅の花色こそ見えね香やはかくるる」(古今集春上、四一、凡河内躬恒)を指摘。
【今すこし】- 蔵人少将に比較してあなた薫は、の意。
|
| 4.2.8 |
|
「竹河を謡ったあの夜のことは覚えていらっしゃいますか
思い出すほどの出来事はございませんが」
|
竹河のその夜のことは思ひいづや
忍ぶばかりの節はなけれど
|
【竹河のその夜のことは思ひ出づや--しのぶばかりの節はなけれど】- 女房から薫への贈歌。「夜」と「世」の掛詞。「竹」と「よ(節と節の間)」と「節」は縁語。
|
| 4.2.9 |
|
と言う。
ちょっとしたことだが、涙ぐまれるのも、「なるほど、浅いご思慕ではなかったのだ」と、自分ながら分かって来る。
|
だれかの言ったこの歌に、薫は涙ぐまれたことで、自分の心にも深くしみついている恋であることがわかった。
|
【みづから思ひ知らる】- 主語は薫。
|
| 4.2.10 |
|
「今までの期待も空しいとことと分かって
世の中は嫌なものだとつくづく思い知りました」
|
流れての頼みむなしき竹河に
世はうきものと思ひ知りにき
|
【流れての頼めむなしき竹河に--世は憂きものと思ひ知りにき】- 薫の返歌。「竹河」の語句を用いて返す。「竹」と「よ(節と節の間)」と「節」は縁語。
|
| 4.2.11 |
|
しんみりした様子を、女房たちは面白がる。
とはいえ、態度に現して少将のようには泣き言はおっしゃらなかったが、人柄がそうは言ってもお気の毒に見えるのである。
|
と答えて、物思いのふうの見えるのを女房たちはおかしがった。その人たちも薫は蔵人少将などのように露骨に恋は告げなかったが、心の中に思いを作っていたのであろうと憐んではいたのである。
|
【さるは、おり立ちて】- 『紹巴抄』は「双地」と指摘。『全集』は「語り手の薫評」と注す。
【人のやうにも】- 蔵人少将のようには、の意。
|
| 4.2.12 |
|
「おしゃべりし過ぎましては。
では、失礼」
|
「少しよけいなことまでも言ったようですが、他言をなさいませんように」
|
【うち出で過ぐすことも】- 以下「あなかしこ」まで、薫の詞。
|
| 4.2.13 |
とて、立つほどに、「こなたに」と召し出づれば、はしたなき心地すれど、参りたまふ。 |
と言って、立つところに、「こちらへ」とお召しがあったので、きまりの悪い思いがしたが、参上なさる。
|
と言って、薫が立って行こうとする時に、
「こちらへ来るように」
と、院の仰せが伝えられたので、晴れがましく思いながら新女御の座敷のほうへ薫はまいった。
|
【こなたに】- 冷泉院の詞。使者が伝えたもの。
|
| 4.2.14 |
|
「故六条院が、踏歌の翌朝に、女方で管弦の遊びをなさったのは、とても素晴らしかったと、右大臣が話されました。
どのようなことにつけても、あのような方の後継者が、いなくなってしまった時代だね。
とても音楽の上手な女性までが大勢集まって、どんなにちょっとしたことでも、面白かったことであろう」
|
「以前六条院で踏歌の翌朝に、婦人がたばかりの音楽の遊びがあったそうで、おもしろかったと右大臣が言っていた。何から言っても六条院がその周囲へお集めになったほどのすぐれた人が今は少なくなったようだ。音楽のよくできる婦人などもたくさん集まっていたのだからおもしろいことが多かったであろう」
|
【故六条院の】- 以下「をかしかりけむ」まで、冷泉院の詞。「初音」巻に見える男踏歌の後の管弦の遊びをいう。
【女楽にて】- 大島本は「女かく」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「女方にて」と校訂する。『新大系』は底本のままとする。
【いと物の上手なる女さへ多く集まりて】- 六条院の女性をいう。
|
| 4.2.15 |
|
などとご想像なさって、お琴類を調子を合わせあそばして、箏は御息所、琵琶は侍従にお与えになる。
和琴をお弾きあそばして、「この殿」などを演奏なさる。
御息所のお琴の音色は、まだ未熟なところがあったが、とてもよくお教え申し上げなさったのであった。
華やかで爪音がよくて、歌謡の伴奏と、楽曲などを上手にたいそうよくお弾きになる。
どのようなことも、心配で、至らないところはおありでない方のようである。
|
などと、その時代を御追想になる院は、楽器の用意をおさせになって、新女御には十三絃、薫には琵琶をお与えになった。御自身は和琴をお弾きになりながら「この殿」などをお歌いあそばされた。新女御の琴は未熟らしい話もあったのであるが、今では傷のない芸にお手ずからお仕込みになったのである。はなやかできれいな音を出すことができ、歌もの、曲ものも上手に弾いた。
|
【御琴ども調べさせたまひて】- 主語は冷泉院。「せたまふ」は最高敬語。
【いとよう教へないたてまつりたまひてけり】- 主語は冷泉院。語り手の立ち入った批評的叙述ともまた薫の感想とも読める叙述。
【何ごとも、心もとなく、後れたることはものしたまはぬ人なめり】- 語り手の批評。
|
| 4.2.16 |
|
器量は、もちろんまた、実に素晴らしいのだろうと、やはり心が惹かれる。
このような機会は多いが、自然とうとうとしくなく、程度を越すことはなく、馴れ馴れしく恨み言を言わないが、折々にふれて、望みが叶わなかった残念さをほのめかすのも、どのようにお思いになったであろうか、よく分からない。
|
何にもすぐれた素質を持っているらしい、容貌も必ず美しいであろうと薫は心の惹かれるのを覚えた。こんなことがよくあって、新女御と薫の侍従は親しくなっていた。反感を引くようにまでは怨みかけたりはしなかったが、何かのおりには失恋の歎きをかすめて言う薫を、女御のほうではどう思ったか知らない。
|
【をかしかべしと、なほ心とまる】- 主語は薫。
【いかが思しけむ、知らずかし】- 『一葉抄』は「双紙詞也」と指摘。『集成』は「語り手の言葉をそのまま記す体」。『完訳』は「語り手の、薫の独自な内心に注目させる言辞」と注す。
|
|
第三段 四月、大君に女宮誕生
|
| 4.3.1 |
|
四月に、女宮がお生まれになった。
特別に目立ったことはないようであるが、院のお気持ちによって、右の大殿をはじめとして、御産養をなさる所々が多かった。
尚侍の君が、ぴったりと抱いておかわいがりなさるので、早く参院なさるようにとばかりあるので、五十日のころに参院なさった。
|
四月に院の第二皇女がお生まれになった。きわめてはなやかなことの現われてきたのではないが、院のお心持ちを尊重して、右大臣を初めとして産養を奉る人が多かった。尚侍はお抱きした手から離せぬようにお愛し申し上げていたが、院から早くまいるようにという御催促がしきりにあるので、五十日目ぐらいに、新女御は宮をおつれ申して院へまいった。
|
【卯月に、女宮生まれたまひぬ】- 御息所、女宮を出産。冷泉院の御子は弘徽殿女御の生んだ女一の宮がいるのみ。したがって、女二の宮の誕生となる。
【院の御けしきに従ひて】- 院が喜ぶ気持ちによって、それを無視できない。
【疾う参りたまふべきよしのみあれば】- 出産は里に下がって行われる。
【五十日のほどに参りたまひぬ】- 生後五十日のお食初めの祝いがある。
|
| 4.3.2 |
|
女一宮が、お一方いらっしゃったが、実にひさしぶりでかわいらしくいらっしゃるので、たいそう嬉しくお思いであった。
ますますただこちらにばかりおいであそばす。
女御方の女房たちは、「ほんとにこんなでなくあってほしいことですわ」と、不満そうに言ったり思ったりしている。
|
院はただお一人の内親王のほかには御子を持たせられなかったのであるから、珍しく美しい少皇女をお得になったことで非常な御満足をあそばされた。以前よりもいっそう御寵愛がまさって、院のこの御殿においでになることの多くなったのを、叔母の女御付きの女房たちなどは、こんな目にあわないではならなかったろうかなどと思ってねたんだ。
|
【いといみじう思したり】- はなはだ嬉しい気持ち。
【いとかからでありぬべき世かな】- 弘徽殿女御方の女房の詞。
|
| 4.3.3 |
|
ご本人どうしのお気持ちは、特に軽々しくお背きになることはないが、伺候する女房の中に、意地悪な事も出て来たりして、あの中将の君が、そうは言っても兄で、おっしゃったことが実現して、尚侍の君も、「むやみにこのように言い言いして最後はどうなるのだろう。
物笑いに、体裁の悪い扱いを受けるのではないだろうか。
お上の御愛情は浅くはないが、長年仕えていらっしゃる御方々が、面白からずお見限りになったら、辛いことになるだろう」とお思いになると、帝におかせられては、ほんとうにけしからぬとお思いになり、再々御不満をお洩らしになると、人がお知らせ申すので、厄介に思って、中の君を、女官として宮仕えに差し上げることをお考えになって、尚侍をお譲りなさる。
|
叔母と姪との二人の女御の間には嫉妬も憎しみも見えないのであるが、双方の女房の中には争いを起こす者があったりして、中将が母に言ったことは、兄の直覚で真実を予言したものであったと思われた。尚侍も、こんな問題が続いて起こる果てはどうなることであろう、娘の立場が不利になっていくのは疑いないことである、院の御愛情は保てても、長く侍しておられる人たちから、不快な存在のように新女御が見られることになっては見苦しいと思っていた。
帝も院へ姫君を奉ったことで御不快がっておいでになり、たびたびその仰せがあるということを告げる人があったために、尚侍は申しわけなく思って、二女を公式の女官にして宮中へ差し上げることにきめて、自身の尚侍の職を譲った。
|
【かの中将の君の】- 左中将、御息所の兄。
【のたまひしことかなひて】- 主語は左中将。弘徽殿方からよくない事が起こるだろうという予言。
【むげにかく言ひ言ひの果て】- 以下「苦しくもあるべきかな」まで、玉鬘の心中。『異本紫明抄』は「世の中をかくいひいひのはてはいかにやいかにやならむとすらむ」(拾遺集雑上、五〇七、読人しらず)を指摘。
【年経てさぶらひたまふ御方々】- 秋好中宮や弘徽殿女御ら。
【内裏には、まことにものしと】- 帝。大君の参院を不快に思っていた。
【公ざまにて交じらはせたてまつらむことを思して、尚侍を譲りたまふ】- 玉鬘は中君を一般の女官として帝に出仕させるべく、自らの尚侍の官職を譲ることを申し出る。
|
| 4.3.4 |
|
朝廷は、尚侍の交替をそう簡単にお認めなさらないことなので、長年、このようにお考えになっていたが、辞任することができなかったのを、故大臣のご遺志をお思いになって、遠くなってしまった昔の例などを引き合いに出して、そのことが実現なさった。
この君のご運命で、長年申し上げなさっていたことは難しいことだったのだ、と思えた。
|
尚侍の辞任と新任命は官で重大なこととして取り扱われるのであったから、ずっと以前から玉鬘には辞意があったのに許されなかったところへ、娘へ譲りたいと申し出たのを、帝は御伯父であった大臣の功労を思召す御心から、古い昔に例のあったことをお思いになって、大臣の未亡人の願いをお納れになり、故太政大臣の女は新尚侍に任命された。これはこの人に定められてあった運命で、母の夫人の単独に辞職を申し出た時にはお許しがなかったのであろうと思われた。
|
【朝廷、いと難うしたまふことなりければ】- 朝廷は尚侍辞任をそう簡単に許可しないのが普通なので、の意。
【故大臣の御心を思して】- 主語は帝。鬚黒が娘を入内させたいと奏上していたこと。
【昔の例など引き出でて】- 『集成』は「尚侍を母娘譲任の史上の例は現存文献の上に見出せない」と注す。
【この君の御宿世にて、年ごろ申したまひしは難きなりけり、と見えたり】- 長年尚侍辞任を申し出ていたが、娘の中君が尚侍を譲り受けるべき宿縁にあって、それまで願いが叶わなかったように思えたという意。語り手の推測判断。
|
|
第四段 玉鬘、夕霧へ手紙を贈る
|
| 4.4.1 |
|
「こうして、気楽に宮中生活をなさってください」と、お思いになるが、「お気の毒に、少将のことを、母北の方がわざわざおっしゃったものを。
お頼み申したようにほのめかしてくださったが、どのように思っていらっしゃるだろう」と気になさる。
|
真実は後宮であって、尚侍の動かない地位だけは得ているのであるから、競争者の中に立つようなこともなくて、気楽に宮中におられることとして玉鬘夫人は安心したのであるが、少将のことを雲井の雁夫人から再度申し込んで来た以前のことに対して、自分はそれに代える優遇法を考えていると言ったのであったがどう思っているであろうと、そのことだけを気の済まぬことに思った。
|
【かくて、心やすくて】- 「かくて」以下「したまへかし」まで、玉鬘の思い。「かくて」は地の文とも心中文とも読める。
【いとほしう、少将のことを】- 以下「いかに思ひたまふらむ」まで、玉鬘の心中。蔵人少将とその母雲居雁のことが気になる。
|
| 4.4.2 |
|
弁の君を介して、他意のないように、大臣に申し上げなさる。
|
二男の弁を使いにして玉鬘夫人は右大臣へ隔てのない相談をすることにした。
|
【弁の君して、心うつくしきやうに、大臣に聞こえたまふ】- 玉鬘の二郎、右中弁を使いとして夕霧に他意ないことを申し上げる。
|
| 4.4.3 |
|
「帝から、あのような仰せ言があるので、あれこれと、無理な宮仕えの好みだと、世間の人聞きもどのようなものかと存じられまして、困っております」
|
宮中からこういう仰せがあるということを言って、「娘を宮仕えにばかり出したがると世間で言われるようなことがないかと、そんなことを私は心配しております」
|
【内裏より、かかる仰せ言のあれば】- 以下「わづらひぬる」まで、玉鬘から夕霧への文。
【あながちなる交じらひの好みと、世の聞き耳も】- 『完訳』は「高望みして宮仕えをしたがると。予想される世間の悪評に先手を打つ形で、縁談を断ったと弁解」と注す。
|
| 4.4.4 |
と聞こえたまへば、
|
と申し上げなさると、
|
と伝えさせると、
|
|
| 4.4.5 |
「内裏の御けしきは、思しとがむるも、ことわりになむ承る。公事につけても、宮仕へしたまはぬは、さるまじきわざになむ。はや、思し立つべきになむ」 |
「帝の御不興は、お咎めがあるのも、ごもっともなことと拝します。
公事に関しても、宮仕えなさらないのは、よくないことです。
早く、ご決心なさい」
|
「お上が不愉快に思召すのがお道理であるように私も承っております。それに公職におつきになったのですから、その点ででも宮中に出仕しないのは間違いです。早くお上げになるほうがいいと思います」
|
【内裏の御けしきは】- 以下「思し立つべきになむ」まで、夕霧の返書。
|
| 4.4.6 |
と申したまへり。
|
と申し上げなさった。
|
という言葉で大臣は答えて来た。
|
|
| 4.4.7 |
|
また、今度は、中宮の御機嫌伺いして参内する。
「大臣が生きていらっしゃったならば、どなたもないがしろになさりはしないだろうに」などと、しみじみと悲しい思いをする。
姉君は、器量なども評判高く、美しいとお聞きあそばしていらしたが、代わりなさったので、ご不満のようであるが、こちらもとても気が利いていて、奥ゆかしく振る舞って伺候なさっている。
|
院の女御の場合のように、中宮の御了解を得ることに努めてから、玉鬘は二女を御所へ奉った。良人の大臣が生きておれば、わが子は肩身狭くかくしてまでの宮仕えはせずともよかったはずであると夫人は物哀れな気持ちをまた得たのであった。姉君は有名な美人であることを帝もお知りあそばされていたのであったが、その人でない妹のまいったことで御満足はあそばされないようであったが、この人も洗練された貴女のふうのある人であった。
|
【中宮の御けしき取りてぞ参りたまふ】- 明石中宮に御機嫌伺いの後に、中君参内。
【大臣おはせましかば、おし消ちたまはざらまし】- 玉鬘の心中。
【あはれなることどもをなむ】- 下に「思しける」「思しのたまひける」などの語句が省略。
【姉君は、容貌など名高う、をかしげなりと、聞こしめしおきたりけるを】- 主語は帝。大君は美貌であるという評判を聞いていた。
【これもいとらうらうじく、心にくくもてなしてさぶらひたまふ】- 中君をいう。才気あり奥ゆかしく振る舞う。
|
|
第五段 玉鬘、出家を断念
|
| 4.5.1 |
|
前尚侍の君は、出家しようと決意なさったが、
|
前尚侍はこれが終わってのち尼になる考えを持っていたが、
|
【前の尚侍の君、容貌を変へてむと思し立つを】- 玉鬘出家を決意。尚侍の職を中君に譲ったので、「前の尚侍の君」と呼称される。
|
| 4.5.2 |
「かたがたに扱ひきこえたまふほどに、行なひも心あわたたしうこそ思されめ。今すこし、いづ方も心のどかに見たてまつりなしたまひて、もどかしきところなく、ひたみちに勤めたまへ」 |
「それぞれにお世話申し上げなさっている時に、勤行も気忙しく思われなさることでしょう。
もう少し、どちらの方も安心できる状態を拝見なさってから、誰にも非難されるところなく、一途に勤行なさい」
|
「あちらもこちらもまだお世話をなさらなければならぬことが多いのですから、今日ではまだ仏勤めをなさいますのに十分の時間がなくて、尼におなりになったかいもなくなるでしょう。もうしばらくの間そのままで、どちらの姫君のことも、これで安心というところまで見きわめになってから、専念に道をお求めになるほうがいい」
|
【かたがたに扱ひきこえたまふほどに】- 以下「勤めたまへ」まで、「君たち」左中将・右中弁らの詞。「方々に」は大君・中君をさす。
|
| 4.5.3 |
|
と、君たちが申し上げなさるので、思いお留まりなさって、宮中へは、時々こっそりと参内なさる時もある。
院へは、厄介なお気持ちがなおも続いているので、参上なさるべき時にも、まったく参上なさらない。
昔の事を思い出したが、そうは言っても、恐れ多く思われたお詫びに、誰も不賛成に思っていたことを、知らず顔に院に差し上げて、「自分自身までが、冗談にせよ、年がいもない浮名が世間に流れ出したら、とても目も当てられず恥ずかしいことだろう」とお思いになるが、そのような憚りがあるからとは、はたまた、御息所にも打ち明けて申し上げなさらないので、「わたしを、昔から、故大臣は特別にかわいがり、尚侍の君は、若君を、桜の木の争いや、ちょっとした時にも、味方なさった続きで、わたしをあまり思ってくださらないのだ」と、恨めしくお思い申し上げていらっしゃるのであった。
院の上は、院の上でまた、それ以上に辛いとお思いになりお口にお出しあそばすのであった。
|
と子息たちが言うので、そのことも停滞した形であった。
御所の娘のほうへは時々夫人が出かけて行って、二、三日とどまって世話をやいていもするのであったが、昔をお忘れきりにならぬお心の見える院の御所のほうへは、まいらねばならぬことがあっても夫人は行かないのであった。迷惑しながら、もったいなく心苦しく存じ上げた昔があるために、だれの反対をも無視して長女を院へ差し上げたが、自分の上にまで仮にもせよ浮いた名の伝えられることになっては、これほど恥ずかしいことはないのであるからと夫人は思っていても、そのことは新女御に言われぬことであったから、自分を昔から父は特別なもののように愛してくれて、母は桜の争いの時を初めとして、何によらず妹の肩を持つほうであったから、こんなふうに愛の厚薄をお見せになるのであると長女は恨めしがっていた。昔にかかわるお恨めしさのほうが深い院も、女御に御同情あそばして、母夫人を冷淡であると言っておいでになった。
|
【内裏には、時々】- 「院には」云々と並列構文。
【院には、わづらはしき御心ばへのなほ絶えねば】- 冷泉院の玉鬘への執心が未だに絶えない。
【いにしへを思ひ出でしが】- 以下、玉鬘と御息所の心中に密着した長い叙述になる。
【かたじけなうおぼえしかしこまりに】- 在位中の冷泉院の意向に反して鬚黒の北の方となったこと。
【人の皆許さぬことに思へりしを】- 左中将や右中弁らが大君の冷泉院への参院に対して反対していた。
【参らせたてまつりて】- 大君を冷泉院へ参院させた。
【さる罪によりと】- 大島本は「つ(つ&つ、つ=いイ)ミにより」とある。すなわち「「つ」の上に重ねて「つ」と書き、異本には「い」とあることを記す。『集成』『完本』は諸本と底本の異本に従って「忌(いみ)」と校訂する。『新大系』は底本の本行本文のままとする。
【われを、昔より】- 以下、御息所の心中に即した叙述となる。
【故大臣は取り分きて思しかしづき】- 「尚侍の君は」云々の並列構文。父鬚黒は私大君をかわいがってくれた。
【尚侍の君は、若君を】- 母玉鬘は妹の中君を大事にした。
|
| 4.5.4 |
「古めかしきあたりにさし放ちて。思ひ落とさるるも、ことわりなり」 |
「年老いたわたしのところは放っておいて。
軽くお思いなさるのも、無理のないことだ」
|
「過去の人間の所へよこされたあなたが軽蔑されるのももっともだ」
|
【古めかしき】- 以下「ことわりなり」まで、冷泉院の御息所への詞。『集成』は「はなやかな宮中には時々参内して、と裏に皮肉をこめる」と注す。
|
| 4.5.5 |
|
と、お語らいになって、いとしく思われる気持ちはますます深まる。
|
などと仰せになって、そんなことによってもますますこの人をお愛しになった。
|
【あはれにのみ思しまさる】- 『完訳』は「大君がひがんでいるのを」と注す。
|
|
第六段 大君、男御子を出産
|
| 4.6.1 |
|
数年たって、また男御子をお産みになった。
大勢いらっしゃる御方々に、このようなことはなくて長年になったが、並々でなかったご宿世などを、世人は驚く。
帝は、それ以上にこの上なくめでたいと、この今宮をお思い申し上げなさった。
「退位なさらない時であったら、どんなにか意義のあることであったろうに。
今では何事も見栄えがしない時なのを、まことに残念だ」とお思いになるのであった。
|
次の年にはまた新女御が院の皇子をお生みした。院の多くの後宮の人たちにそうしたことは絶えてなかったのであるから、この宿命の現われに世人も驚かされた。院はまして限りもなく珍しく思召してこの若宮をお愛しになった。在位の時であったなら、どれほどこの宮の地位を光彩あるものになしえたかもしれぬ、もう今では過去へ退いた自分から生まれた一親王にこの宮はすぎないのが残念であるとも院は思召した。
|
【年ごろありて】- 『完訳』は「年立では五年経過」と注す。
【おろかならざりける御宿世】- 大君の宿縁。『集成』は「子供が生れるのは、前世からの深い宿縁によると考えられていた」と注す。
【帝は、まして限りなくめづらしと】- 冷泉院。院の帝、の意。今上帝は内裏(うち)と呼称している。
【おりゐたまはぬ世ならましかば】- 以下「いと口惜し」まで、冷泉院の心中。
|
| 4.6.2 |
女一の宮を、限りなきものに思ひきこえたまひしを、かくさまざまにうつくしくて、数添ひたまへれば、めづらかなる方にて、いとことにおぼいたるをなむ、女御も、「あまりかうてはものしからむ」と、御心動きける。 |
女一の宮を、この上なく大切にお思い申し上げていらっしゃったが、このようにそれぞれにかわいらしく、お子様がお加わりになったので、珍しく思われて、たいそう格別に寵愛なさるのを、女御も、「あまりにこういう有様では不愉快だろう」と、お心が穏やかでないのであった。
|
女一の宮を唯一の御子としてお愛しになった院が、こんなふうに新しい皇子、皇女の父におなりあそばされたことも、かねて思いがけぬことであった中にも、はじめてお得になった男宮をことさら院の御珍重あそばすようになったことで、女一の宮の母女御も、こんなにまで専寵の人をおつくりにならないでもいいはずであると、院をお恨み申し上げるようになり、新女御をねたむようにもなった。
|
【あまりかうてはものしからむ】- 弘徽殿女御の気持ち。
|
| 4.6.3 |
|
何か事ある毎に、面白くない面倒な事態が出て来たりなどして、自然とお二方の仲も隔たったようである。
世間の常として、身分の低い人の間でも、もともと本妻の地位にある方は、関係のない一般の人も、味方するもののようなので、院の内の身分の上下の女房たち、まことにれっきとした身分で、長年連れ添っていらっしゃる御方にばかり道理があるように言って、ちょっとしたことでも、この御方側を良くないように噂したりなどするのを、御兄君たちも、
|
そうなってから新女御の立場はますます苦しくなり、双方の女房の間に苦い空気がかもされてゆけば、自然二人の女御の交情も隔たってゆく。世間のこととしても、人の新しい愛人に対するよりも、古い妻に同情は多く寄るものであるから、院に奉仕する上下の役人たちも、貴い御地位にあらせられる后の宮、女一の宮の女御のほうに正しい道理のあるように見て、新女御のことは反感を持って何かと言い歩くというような状態になったのを、兄の公達らも、夫人に、
|
【隔たるべかめり】- 語り手の推測。
【世のこととして】- 『林逸抄』は「双紙也」と指摘。
【もとよりことわりえたる方にこそ】- 『集成』は「もとからの妻だという言い分のある者の方に」。『完訳』は「本妻の地位にあたる人」と注す。
【いとやむごとなくて、久しくなりたまへる御方に】- 女一の宮の母弘徽殿女御。
【この方ざまを】- 大島本は「この方さま」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「御方」と「御」を補訂する。『新大系』は底本のままとする。大君をさす。
|
| 4.6.4 |
|
「それ見たことよ。
間違ったことを申し上げたでしょうか」
|
「だから私たちの申したことは間違っていなかったでしょう」
|
【さればよ。悪しうやは聞こえおきける】- 大君の兄弟、左中将や右中弁らの玉鬘への詞。連語「やは」反語表現。
|
| 4.6.5 |
|
と、ますますお責めになる。
心穏やかならず、聞き苦しいままに、
|
と言って責めた。夫人もまた世間の噂と院の御所の空気に苦労ばかりがされて、
|
【心やすからず、聞き苦しきままに】- 主語は玉鬘。
|
| 4.6.6 |
|
「このようにでなく、のんびりと無難に結婚生活を送る人も多いだろうに。
この上ない幸運に恵まれないでは、宮仕えの事は、考えるべきことではなかったのだ」
|
「かわいそうな女御さんほどに苦しまないでも幸福をやすやすと得ている人は世間に多いのだろうがね。条件のそろった幸運に恵まれている人でなければ宮仕えを考えてはならないことだよ」
|
【かからで、のどやかに】- 以下「思ひ寄るまじきわざなりけり」まで玉鬘の心中。
【限りなき幸ひなくて】- 『集成』は「この上もなく幸運に恵まれた人でなくては」。『完訳』は「中宮・国母として最高の地位につくのでないと苦労するばかり」と訳す。
|
| 4.6.7 |
|
と、大上はお嘆きになる。
|
と歎息していた。
|
【大上は嘆きたまふ】- 玉鬘。大君に男御子が誕生したことにより呼称が「大上」となる。
|
|
第七段 求婚者たちのその後
|
| 4.7.1 |
|
求婚申し上げた人びとで、それぞれ立派に昇進して、結婚なさったしても、不似合いでない方は大勢いることよ。
その中で、源侍従と言って、たいそう若く、ひ弱に見えた方は宰相中将になって、「匂うよ、薫よ」と、聞き苦しいほどもてはやされるが、なるほど、人柄も落ち着いて奥ゆかしいので、高貴な親王方、大臣が、娘を結婚させようとおっしゃるのなどにも、聞き入れないなどと聞くにつけても、「あの頃は、若く頼りないようであったが、立派に成人なさったようだ」などと、言っていらっしゃる。
|
以前の求婚者で、順当に出世ができ、婿君であっても恥ずかしく思われない人が幾人もあった。その中でも源侍従と言われた最も若かった公子は参議中将になっていて、今では「匂いの人」「薫る人」と世間で騒ぐ一人になっていた。重々しく落ち着いた人格で、尊い親王がた、大臣家から令嬢との縁談を申し込まれても承知しないという取り沙汰を聞いても、「以前はまだたよりない若い方だったが、りっぱになってゆかれるらしい」玉鬘夫人は寂しそうに言っていた。
|
【聞こえし人びとの、めやすくなり上りつつ】- 薫や蔵人少将ら、かつての求婚者。
【さてもおはせましに】- 『集成』は「婿君になっていらしたとしても」。「まし」反実仮想の助動詞。
【あまたあるや】- 間投助詞「や」詠嘆。語り手の口吻。
【匂ふや、薫るや」と】- 「匂兵部卿、薫中将」と「匂宮」巻にあった。
【げに、いと人柄】- 「げに」は語り手の納得した気持ちの現れ。
【そのかみは】- 以下「ねびまさりぬべかめり」まで、玉鬘の詞。
|
| 4.7.2 |
少将なりしも、三位中将とか言ひて、おぼえあり。
|
少将であった方も、三位中将とか言って、評判が良い。
|
蔵人の少将だった人も三位の中将とか言われて、もう相当な勢いを持っていた。
|
|
| 4.7.3 |
|
「器量まで、が立派だった」
|
「あの方は風采だっておよろしかったではありませんか」
|
【容貌さへ、あらまほしかりきや】- 女房の詞。
|
| 4.7.4 |
など、なま心悪ろき仕うまつり人は、うち忍びつつ、
|
などと、意地悪な女房たちは、こっそりと、
|
などと言って、少し蓮葉な性質の女房らは、
|
|
| 4.7.5 |
|
「厄介な御様子の所に参るよりは」
|
「今のうるさい御境遇よりはそのほうがよかったのですね」
|
【うるさげなる御ありさまよりは】- 女房の詞。冷泉院より三位中将のほうがよかったという意。
|
| 4.7.6 |
|
などと言う者もいて、お気の毒に見えた。
|
とささやいたりしていた。
|
【いとほしうぞ見えし】- 玉鬘の様子。『首書或抄』は「草子地也」と指摘。
|
| 4.7.7 |
|
この中将は、依然として思い染めた気持ちがさめず、嫌で辛くも思いながら、左大臣の姫君を得たが、全然愛情を感じず、「道の果てなる常陸帯の」と、手習いにも口ぐせにもしているのは、どのように思ってのことであろうか。
|
しかし今も玉鬘夫人の長女に好意を持つ者があった。この三位中将は初恋を忘れることができず、悲しくも、恨めしくも思って、左大臣家の令嬢と結婚をしたのであるが、妻に対する愛情が起こらないで「道のはてなる常陸帯」(かごとばかりも逢はんとぞ思ふ)などと、もう翌日はむだ書きに書いていたのは、まだ何を空想しているのかわからない。
|
【この中将は、なほ思ひそめし心絶えず】- 三位中将。大君を思う気持ちが今だに絶えない。
【左大臣の御女を得たれど】- この左大臣は系図不詳。竹河左大臣。夕霧右大臣の上位者。
【道の果てなる常陸帯の】- 三位中将の詞。『源氏釈』は「東路の道の果てなる常陸帯のかごとばかりもあひ見てしがな」(古今六帖五、帯)を指摘。
【いかに思ふやうのあるにかありけむ】- 『一葉抄』は「双紙詞也」と指摘。『完訳』は「語り手の評」と注す。
|
| 4.7.8 |
|
御息所は、気苦労の多い宮仕えの煩わしさに、里にいることが多くおなりになってしまった。
尚侍の君は、思っていたようにならなかったご様子を、残念にお思いになる。
内裏の君は、かえって派手に気楽に振る舞って、大変風雅に、奥ゆかしいとの評判を得て、宮仕えなさっている。
|
院の新女御は人事関係の面倒さに自邸へ下がっていることが多くなった。母の夫人は娘のために描いた夢が破れてしまったことを残念がっていた。御所へ上がったほうの姫君はかえってはなやかに幸福な日を送っていて、世間からも聡明で趣味の高い後宮の人と認められていた。
|
【尚侍の君、思ひしやうにはあらぬ御ありさまを、口惜しと思す】- 玉鬘。『集成』は「「尚侍の君」と呼ぶのは、次に、現在の尚侍である中の君を「内裏の君」と呼ぶからであろう」と注す。
【内裏の君は、なかなか今めかしう】- 中君。尚侍。姉の御息所に比較して「なかなか」とある。
|
|
第五章 薫君の物語 人びとの昇進後の物語
|
|
第一段 薫、玉鬘邸に昇進の挨拶に参上
|
| 5.1.1 |
|
左大臣がお亡くなりになって、右は左に、藤大納言は、左大将を兼官なさった右大臣におなりになる。
順々下の人びとが昇進して、この薫中将は、中納言に、三位の君は宰相になって、ご昇進なさった方々は、これら一族以外に人もいないといった時勢であった。
|
左大臣が薨くなったので、右が左に移って、按察使大納言で左大将にもなっていた玉鬘夫人の弟が右大臣に上った。それ以下の高官たちにも異動が及んで、薫中将は中納言になり、三位の中将は参議になった。幸運な人は前にも言った二つの系統のほかに見られない時代と思われた。
|
【右は左に】- 夕霧は右大臣から左大臣に。『集成』は「ただし、後の宇治十帖を通じて、夕霧は右大臣のままである」と注す。
【藤大納言、左大将かけたまへる右大臣になりたまふ】- 紅梅大納言は左大将兼右大臣に。『集成』は「ただしこの人、後の宿木、東屋の巻には、按察使の大納言のままである」。『完訳』は「右の昇進人事のうち、夕霧左大臣と紅梅の右大臣は宇治十帖での官と符合しない」と注す。
【この薫中将は、中納言に】- 宰相中将の薫は中納言に。『集成』は「紅梅に「源中納言」とあり、椎本に中納言昇進のことが見える」と注す。
【三位の君は、宰相になりて】- 三位中将、もと蔵人少将であった人。薫の後任宰相中将となる。
|
| 5.1.2 |
中納言の御喜びに、前の尚侍の君に参りたまへり。
御前の庭にて拝したてまつりたまふ。
尚侍の君対面したまひて、
|
中納言の昇進のお礼参りに、前尚侍の君の所に参上なさった。
御前の庭先で拝舞申し上げなさる。
尚侍の君がお目にかかりなさって、
|
源中納言は礼まわりに前尚侍の所へ来て、庭で拝礼をした。夫人は客を前に迎えて、
|
|
| 5.1.3 |
|
「このように、とても草深くなって行く葎の門を、お避けにならないお心使いに対して、まず昔の六条院の御事が思い出されまして」
|
「こんなあばら家になっていきます家を、お通り過ぎにならず、お寄りくださいます御好意を拝見いたしましても、六条院の皆御恩だと昔が思われてなりません」
|
【かく、いと草深くなりゆく】- 以下「思ひ出でられてなむ」まで、玉鬘の詞。
【葎の門を】- 『集成』は「見捨てられた家という歌語的表現」と注す。
【昔の御こと】- 『完訳』は「源氏生前の昔。源氏が自分を養女にしたから、薫も親しむ」と注す。
|
| 5.1.4 |
など聞こえたまふ、御声、あてに愛敬づき、聞かまほしう今めきたり。「古りがたくもおはするかな。かかれば、院の上は、怨みたまふ御心絶えぬぞかし。今つひに、ことひき出でたまひてむ」と思ふ。 |
などと申し上げなさる、お声は、上品で愛嬌があって、耳に快く響く。
「いつまでもお若くいらっしゃるな。
これだから、院のお上はお恨みになるお心が褪せないのだ。
そのうちきっと、事件をお起こしになるだろう」と思う。
|
などと言っている声に愛嬌があって、はなやかに美しい顔も想像されるのであった。こんなふうでいられるから、院の陛下は今もこの人がお忘れになれないのであるとそのうち一つの事件をお引き起こしになる可能性もあることを薫は感じた。
|
【古りがたくもおはするかな】- 以下「引き出でたまひてむ」まで、薫の感想と思い。
|
| 5.1.5 |
|
「喜びなどは、わたしはさほど嬉しく存じませんが、まず知って戴こうと参上したのでございます。
避けないなどとおっしゃるのは、御無沙汰の罪を皮肉って言われたのでしょうか」とご挨拶申し上げなさる。
|
「陞任をたいした喜びとは思っておりませんが、この場合の御挨拶にはどこよりも先にと思って上がったのです。通り過ぎるなどというお言葉は平生の怠慢をおしかりになっておっしゃることですか」新中納言はこう言うのであった。
|
【喜びなどは】- 以下「うちかへさせたまふにや」まで、薫の玉鬘への詞。
【御覧ぜられにこそ】- 敬語はあなた、玉鬘に御覧になっていただきたいために、の意。
【よきぬなどのたまはするは】- 「避き」は上二段動詞、未然形。「ぬ」打消の助動詞。玉鬘の詞「葎の門をよきたまはぬ」を受ける。
【おろかなる罪にうちかへさせたまふにや】- 『完訳』は「わざと反対のことを言われたのか。薫のまわりくどい応じ方」と注す。
|
| 5.1.6 |
「今日は、さだすぎにたる身の愁へなど、聞こゆべきついでにもあらずと、つつみはべれど、わざと立ち寄りたまはむことは難きを、対面なくて、はた、さすがにくだくだしきことになむ。 |
「今日は、老人の繰り言などを、申し上げるべき時ではないと、気がとがめますが、わざわざお立ち寄りになることは難しいので、お会いしなくては、また、いくらなんでもごたごたした話ですから。
|
「今日のようなおめでたい日に老人の繰り言などはお聞かせすべきでないと御遠慮はされますが、ただの日にお訪ねくださるお暇はおありにならないのですし、手紙に書いてあげますほどの筋道のあることではないのですから、聞いてくださいませ。
|
【今日は】- 以下「もどかしくなむ」まで、玉鬘の詞。
|
| 5.1.7 |
|
院に伺候しておられるのが、とてもひどく宮仕えのことを思い悩んで、宙に浮いたような恰好でうろうろしていますが、女御をご信頼申して、また后の宮の御方にも、そうは言ってもお許し戴けるだろうと、存じておりましたのに、どちらにも礼儀知らずで堪忍できない者とお思いなされたそうなので、とても具合が悪くて、宮たちは、そのまま残しておいでになる。
この、とても生活しにくそうな本人は、こうしてせめて気楽にぼんやりとお過ごしなさいと思って、退出させたのですが、それに対しても聞きにくい噂です。
|
院に侍しております人がね、苦しい立場に置かれまして煩悶をばかりしておりましてね。はじめは女一の宮の女御さんを力のように思っていましたし、后の宮様も六条院の御関係で御寛大に御覧くださるだろうと考えていたことですが、今日はどちらも無礼な闖入者としてお憎みあそばすようでしてね。困りましてね。宮様がただけは院へお置き申して、存在を皆様にきらわれる人だけを、せめて家で気楽に暮らすようにと思いまして帰らせたのですが、それがまた悪評の種を蒔くことになったらしゅうございます。
|
【院にさぶらはるるが】- 大君をさす。
【世の中を思ひ乱れ】- 冷泉院の後宮生活。
【中空なるやうにただよふを】- 里がちな生活をいう。
【なめげに心ゆかぬものに】- 大島本は「心ゆかぬ」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「ゆるさぬ」と校訂する。『新大系』は底本のままとする。
【宮たちは、さてさぶらひたまふ】- 女二の宮と男宮を冷泉院に残したまま里下がりしている意。
【かくて心やすくだにながめ過ぐいたまへ】- 玉鬘の大君への助言。
|
| 5.1.8 |
|
上様にもけしからぬとお思いになりお口になさるそうです。
機会がありましたら、ちらっとよろしく申し上げてください。
あちら様こちら様と、頼もしく存じて、出仕させました当座は、どちら様も安心して、信頼申し上げたが、今では、このような間違いに、子供っぽく大それた自分自身の考えを、恨んでおります」
|
院も御機嫌を悪くあそばしたようなお手紙をくださいますのですよ。機会がありましたら、あなたからこちらの気待ちをほのめかしてお取りなしくださいませ。離れようのない関係を双方にお持ちしているのですから、お上げしました初めは、どちらからも御好意を持っていただけるものと頼みにしたものですが、結果はこれでございますもの、私の考えが幼稚であったことばかりを後悔いたしております」
|
【思しのたまはすなる】- 「なる」伝聞推定の助動詞。
【とざまかうざまに】- 中宮や弘徽殿女御に。
【幼うおほけなかりけるみづからの心を、もどかしくなむ】- 後見もなく娘を院に参院させ、このような事態が起こることを見通せなかった、幼稚で身分不相応な我が身であったと後悔。
|
| 5.1.9 |
|
と、涙ぐみなさる様子である。
|
玉鬘夫人は歎息をしていた。
|
【と、うち泣いたまふけしきなり】- 『完訳』は「簾越しに感取される」と注す。断定助動詞「なり」は登場人物薫と語り手の判断が一体化した表現。
|
|
第二段 薫、玉鬘と対面しての感想
|
| 5.2.1 |
「さらにかうまで思すまじきことになむ。かかる御交じらひのやすからぬことは、昔より、さることとなりはべりにけるを、位を去りて、静かにおはしまし、何ごともけざやかならぬ御ありさまとなりにたるに、誰れもうちとけたまへるやうなれど、おのおのうちうちは、いかがいどましくも思すこともなからむ。 |
「まったくそんなにまでお考えなることはありません。
このような宮仕えの楽でないことは、昔から、そのようなことと決まっておりますが、位を去って、静かにお暮らしでいらっしゃり、どのようなことでも華やかでないご生活となってしまったので、皆が気を許し合っていらっしゃるようですが、それぞれ内心では、どんなに競争心をお持ちになることもないでしょうか。
|
「そんなにまで御心配をなさることではないと思います。昔から後宮の人というものは皆そうしたものになっているのですからね、ただ今では御位をお去りになって無事閑散な御境遇でも、後宮にだけは平和の来ることはないのですから、
|
【さらにかうまで】- 以下「はべらぬことになむ」まで、薫の詞。
【いかがいどましく】- 「なからむ」に係る反語表現。
|
| 5.2.2 |
|
他人は何の過失と思わないことでも、ご自身にとっては恨めしいものでして、つまらないことに心を動かしなさることは、女御や、后のいつものお癖でしょう。
それくらいのいざこざもない起こらないものと思って、ご決心なさったのですか。
ただ穏やかに振る舞って、お見過ごしなさることでございます。
男の者が、申し上げるべきことではございません」
|
第三者が見れば君寵に変わりはないと見えることもその人自身にとっては些細な差が生じるだけでも恨めしくなるものらしいですよ。つまらぬことに感情を動かすのが女御后の通弊ですよ。それくらいの故障もないとお思いになって宮廷へお上げになったのですか。御認識不足だったのですね。ものを気におかけにならないで冷静にながめていらっしゃればいいのです。男が出て奏上するような問題ではありませんよ」
|
【心動かいたまふこと】- 大島本は「心うこかひ」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「心を」と「を」を補訂する。『新大系』は底本のままとする。
【男の方にて、奏すべきことにもはべらぬことになむ】- 『完訳』は「後宮の女たちの葛藤は、公的立場の男子官僚には関わらぬこととして、玉鬘の懇願を冷たく突き放す。薫らしい冷静な反応に注意」と注す。
|
| 5.2.3 |
と、いとすくすくしう申したまへば、
|
と、たいそうそっけなく申し上げなさるので、
|
と遠慮なく薫が言うと、
|
|
| 5.2.4 |
|
「お会いした時に愚痴をこぼそうと、お待ち申していた効もなく、あっさりしたご判断ですこと」
|
「お逢いしたら聞いていただこうと思って、あなたをお待ちばかりしていましたのに、私をおたしなめにばかりなるそのあなたの理窟も、私は表面しか御覧にならない理窟だと思いますよ」
|
【対面のついでに】- 以下「御ことわりや」まで、玉鬘の詞。
【あはの御ことわりや】- 『集成』は「「あは」は「淡し」の語幹。「ことわる」は、是非を判断する意」と注す。
|
| 5.2.5 |
|
と、笑っていらっしゃる、人の親として、てきぱきと事を処理していらっしゃる割には、とても若くおっとりとした感じがする。
「御息所も、このようなふうでいらっしゃるのだろう。
宇治の姫君が心にとまって思われるのも、このような様子に興味惹かれるからだ」と思って座っていらっしゃった。
|
こう言って玉鬘夫人は笑っていた。人の母らしく子のために気をもむらしい様子ではあるが、態度はいたって若々しく娘らしかった。新女御もこんな人なのであろう、宇治の姫君に心の惹かれるのも、こうした感じよさをその人も持っているからであると源中納言は思っていた。
|
【いと若やかにおほどいたる心地す】- 『集成』は「大層若々しくおっとりとした感じがする。薫の印象」と注す。
【御息所も】- 以下「をかしきぞかし」まで、薫の感想。
【かやうにぞ】- 大君も母玉鬘同様に若々しく魅力的な女性だろうの意。
【宇治の姫君の心とまりておぼゆるも】- 宇治八の宮の大君をさす。『完訳』は「紅梅巻末「八の宮の姫君」と同じく、やや唐突。構想・成立上の問題点とされる。女君たちを次々と連想する点が、薫らしい」と注す。
|
| 5.2.6 |
|
尚侍の君も、この頃退出なさっていた。
こちらとあちらとに住んでいらっしゃる様子は素晴らしく、全体がのんびりと忙しさに、紛れることないご様子で、御簾の内側が、気恥ずかしく感じられるので、自然と気づかいがされて、ますます静かで感じが良いのを、大上は、「近くでお世話するのだったなら」と、お思いになるのであった。
|
若い尚侍もこのごろは御所から帰って来ていた。そちらもあちらも姫君時代よりも全体の様子の重々しくなった、若い閑暇の多い婦人の居所になっていることが思われ、御簾の中の目を晴れがましく覚えながらも、静かな落ち着きを見せている薫を、夫人は婿にしておいたならと思って見ていた。
|
【尚侍も】- 中君。
【こなたかなた住みたまへるけはひをかしう】- 寝殿の東西の部屋に。参院・参内以前にも同様に住んでいた。
【簾の内、心恥づかしうおぼゆれば、心づかひせられて】- 主語は薫。
【大上は、「近うも見ましかば」と】- 玉鬘。「ましかば」反実仮想。薫を婿として世話するのだったらと思う。
|
|
第三段 右大臣家の大饗
|
| 5.3.1 |
|
大臣殿は、ちょうどこちらの殿の東であった。
大饗の垣下の公達などが、大勢参上なさる。
兵部卿宮や、左の大臣殿の賭弓の還立や、相撲の饗応などには、いらっしゃったことを思って、今日の光を添えて戴きたいとご招待申し上げなさったが、いらっしゃらなかった。
|
新右大臣の家はすぐ東隣であった。大臣の任官披露の大饗宴に招かれた公達などがそこにはおおぜい集まっていた。兵部卿の宮は左大臣家の賭弓の二次会、相撲の時の宴会などには出席されたことを思って、第一の貴賓として右大臣は御招待申し上げたのであったが、おいでにならなかった。
|
【大臣の殿は、ただこの殿の東なりけり】- 先に右大臣に昇進した紅梅大納言邸。もと致仕太政大臣の後継者(一男の柏木は死去)。玉鬘邸の東に位置する。
【大饗の垣下の君達など、あまた集ひたまふ】- 右大臣昇進の祝宴。
【左の大臣殿の賭弓の還立、相撲の饗応などには】- 夕霧。先の人事で左大臣に昇進。「賭弓の還立」は匂宮巻の「賭弓の帰饗」をさす。「相撲の饗応」は、七月の相撲の節会に催される。
|
| 5.3.2 |
|
奥ゆかしく大切にお世話なさっている姫君たちを、一方では、特に気を配って、何とか婿君に、と思い申し上げなさっているようであるが、宮は、どうしたことであろうか、お心を止めにならなかった。
源中納言が、ますます理想的に成長して、どのような事にも劣ったことがなくいらっしゃるのを、大臣も北の方も、お目を止めていらっしゃった。
|
大臣は秘蔵にしている二女のためにこの宮を婿に擬しているらしいのであるが、どうしたことか宮は御冷淡であった。来賓の中で源中納言の以前よりもいっそうりっぱな青年高官と見える欠点のない容姿に右大臣もその夫人も目をとめた。
|
【心にくくもてかしづきたまふ姫君たちを】- 紅梅右大臣が大切に育てている姫君たち。中君と宮の御方。大君は春宮に入内。宮の御方は後の北の方真木柱の連れ子、蛍兵部卿宮との間の子。
【思ひきこえたまふべかめれど、宮ぞ、いかなるにかあらむ】- 推量の助動詞「めり」は語り手の推量、「宮ぞいかなるにかあらむ」は挿入句、語り手の疑問提示。
【大臣も北の方も】- 紅梅右大臣と北の方真木柱。
|
| 5.3.3 |
|
隣でこのように大騒ぎして、行き交う車の音、前駆の声々も、昔の事が自然と思い出されて、こちらの殿では、しみじみと物思いなさっている。
|
饗宴の張られる隣のにぎやかな物の気配、行きちがう車の音、先払いの声々にも昔のことが思い出されて、故太政大臣家の人たちは物哀れな気持ちになっていた。
|
【昔のこと思ひ出でられて】- 主語は玉鬘。夫鬚黒生前の頃の事が。
|
| 5.3.4 |
|
「故宮がお亡くなりになって、間もなく、この大臣がお通いになったことを、まことに軽薄なように世間の人は非難したというが、愛情も薄れずにこのように暮らしておいでなのも、やはり無難なことであった。
無常の世の中よ。
どちらが良いものでしょうか」などとおっしゃる。
|
「兵部卿の宮がお薨れになって間もなく、今度の右大臣が通い始めたのを、軽佻なことのように人は非難したものだけれど、愛情が長く変わらず夫婦にまでなったのは、一面から見て感心な人たちと言っていい。だから世の中のことは何を最上の幸福の道とはきめて言えないのだね」
などと玉鬘夫人は言っていた。
|
【故宮亡せたまひて】- 以下「いづれにかよるべき」まで、玉鬘の詞。「故宮」は蛍兵部卿宮。蛍兵部卿宮が薨じて後、その北の方の真木柱のもとに紅梅大納言が通うようになり、やがて真木柱は紅梅大納言の今の北の方となった。蛍兵部卿宮はかつて玉鬘に懸想した人でもあった。
【通ひたまひしほどを】- 大島本は「ほとを」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「ことを」と校訂する。『新大系』は底本のままとする。
【かくてものしたまふも】- 大島本は「かくてものし給」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「思ひも消えずかくて」と「思ひも消えず」を補訂する。『新大系』は底本のままとする。
【さすがなる方に】- 大島本は「さすかなるかたに」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「さすがさる方に」と校訂する。『新大系』は底本のままとする。
【いづれにか寄るべき】- 『集成』は「継子の真木柱の再婚生活の幸福、実子の御息所の苦労など、つい比較しての感慨」と注す。
|
|
第四段 宰相中将、玉鬘邸を訪問
|
| 5.4.1 |
|
左の大殿の宰相中将は、大饗の翌日、夕方にこちらに参上なさった。
御息所が、里にいらっしゃると思うと、ますます緊張して、
|
左大臣の息子の参議中将が隣に大饗のあった翌日の夕方ごろにこの家へ訪ねて来た。院の女御が家に帰っていることでいっそう美しく見える身の作りもして来たのである。
|
【左の大殿の宰相中将】- 夕霧の子、元の蔵人少将。薫と同時に昇進。
|
| 5.4.2 |
「朝廷のかずまへたまふ喜びなどは、何ともおぼえはべらず。私の思ふことかなはぬ嘆きのみ、年月に添へて、思うたまへはるけむ方なきこと」 |
「朝廷が忘れずに加えてくださった昇進の喜びなどは、特に何とも思いません。
私事で思い通りにならない嘆きばかりが、年月とともに積もり重なって、晴らしようもございません」
|
「よい役人にしていただきましたことなどは何とも思われません。心に願ったことのかなわない悲しみは月がたてばたつほど積っていってどうしようもありません」
|
【朝廷のかずまへたまふ】- 以下「はるけむ方なきこと」まで宰相中将の詞。
|
| 5.4.3 |
と、涙おしのごふも、ことさらめいたり。
二十七、八のほどの、いと盛りに匂ひ、はなやかなる容貌したまへり。
|
と、涙を拭うのも、わざとらしい。
二十七、八歳のほどで、とても男盛りで、華やかな容貌をしていらっしゃった。
|
と言いながら涙をぬぐう様子でややわざとらしい。二十七、八で、盛りの美貌を持つはなやかな人である。帰ったあとで、
|
|
| 5.4.4 |
|
「困った息子たちの、世の中を思いのままになると思って、官位を何とも思わず、過ごしていらっしゃる。
故殿が生きていらっしゃったら、自分の家の子供たちも、このようなのんきな遊び事に、心を奪われたでしょうに」
|
「困った公達だね。何でも思いのままになるものと見ていて、官位の問題などは念頭に置いていないようだね。こちらの大臣がお薨れにならなければ、ここの若い人たちもあの人ら並みに、恋愛の遊戯を夢中になってしただろうにね」
|
【見苦しの君たちの】- 以下「心は乱らまし」まで、玉鬘の詞。宰相中将の詞に対する批判。
【いますがらふや】- 『集成』は「いますからふや」と清音。『完訳』は「いますがらふや」と濁音に読む。
【故殿のおはせましかば】- 「心は乱らまし」に係る反実仮想の構文。
【ここなる人びとも】- 我が子たちも。
|
| 5.4.5 |
|
とお泣きになる。
右兵衛督や、右大弁になったが、皆非参議でいるのを嘆かわしいことと思っていた。
侍従と言われていたらしい人は、この頃、頭中将と呼ばれているようである。
年齢から言えば、不十分ではないが、人に後れたと嘆いていらっしゃった。
宰相は、何やかやとうまいことを言って来て。
|
と言って、玉鬘夫人は歎息をしていた。右兵衛督、右大弁で参議にならないため太政官の政務に携わらないのを夫人は愁わしがっていた。侍従と言われていた末子は頭中将になっていた。年齢からいってだれも官等の陞進がおそいほうではないのであるが、人におくれると言って歎いている。参議の職はいかにも若い高官らしく、ぐあいがいいのだけれど。
|
【右兵衛督、右大弁にて、皆非参議なるを、うれはしと思へり】- もと左中将は右兵衛督(従四位下相当官)に、またもと右中弁は右大弁(従四位上相当官)に、わずかずつ昇進、しかし参議にはなれない。かつての蔵人少将は宰相中将になり、四位侍従の薫は中納言に昇っている。『完訳』は「宰相中将が参議なのに、自分の子らが資格があっても参議になれないのを悲嘆」と注す。
【侍従と聞こゆめりしぞ、このころ、頭中将と聞こゆめる】- 頭中将はエリートコースのポスト、従四位下相当官。二人の兄に比較して日の当たる官職。推量の助動詞「めり」。語り手の婉曲的推量のニュアンス。
【宰相は、とかくつきづきしく】- 宰相中将。『集成』は「玉鬘の姫君にかかわる貴公子として、薫よりはこの人を終始表面に立てた書き方」。『完訳』は「後続の物語があるような巻末形式である」と注す。
|
| 著作権 |
| 底本 |
大島本 |
| 校訂 |
Last updated 11/9/2010(ver.2-2)
渋谷栄一校訂(C)
オリジナル
修正版
比較 |
| ローマ字版 |
Last updated 12/14/2010 (ver.2-2)
Written in Japanese roman letters
by Eiichi Shibuya (C)
オリジナル
修正版
比較 |
ルビ抽出
(ローマ字版から)
|
Powered by 再編集プログラム v4.05
ひらがな版
ルビ抽出 |
挿絵
(ローマ字版から)
|
'Eiri Genji Monogatari'
(1650 1st edition) |
|
Last updated 3/10/2002
渋谷栄一訳(C)(ver.1-2-2)
オリジナル
修正版
比較 |
|
|
Last updated 12/14/2010(ver.2-2)
渋谷栄一注釈(C)
オリジナル
修正版
比較 |
|