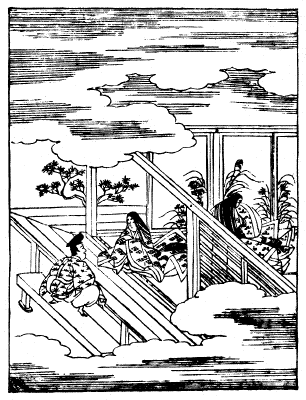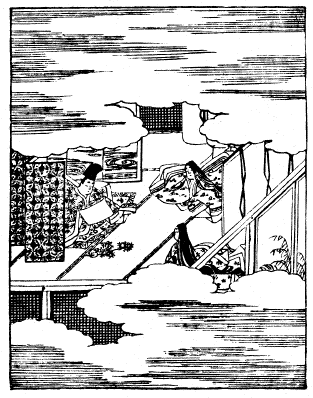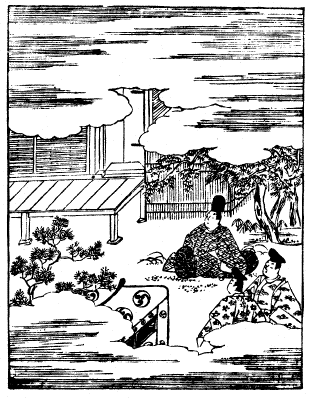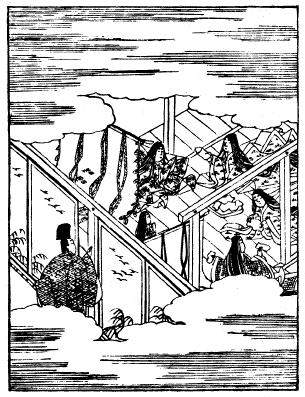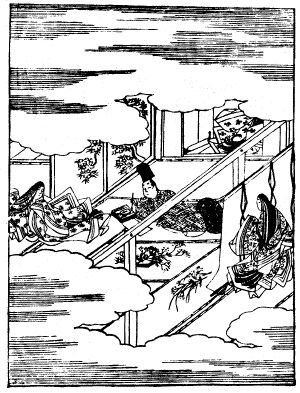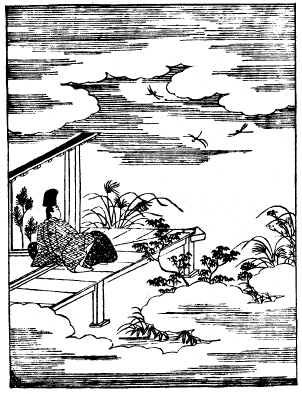第五十二帖 蜻蛉
薫君の大納言時代二十七歳三月末頃から秋頃までの物語
|
# |
本文 |
渋谷栄一訳 |
与謝野晶子訳 |
注釈 |
|
第一章 浮舟の物語 浮舟失踪後の人びとの動転
|
|
第一段 宇治の浮舟失踪
|
| 1.1.1 |
|
あちらでは、女房たちが、いらっしゃらないのを探して大騷ぎするが、その効がない。
物語の姫君が、誰かに盗まれたような朝のようなので、詳しくは話し続けない。
京から、先日の使者が帰れなくなってしまったので、気がかりに思って、再び使者をよこした。
|
宇治の山荘では浮舟の姫君の姿のなくなったことに驚き、いろいろと捜し求めるのに努めたが、何のかいもなかった。小説の中の姫君が人に盗まれた翌朝のようであって、このいたましい騒ぎはくわしく書くことができない。京からの前日の使いが泊まって帰らなかったため、母夫人は不安がってまた次の使いをよこした。
|
【かしこには、人びと、おはせぬを求め騒げど】- 浮舟失踪の翌朝。「おはせぬ」の主語は浮舟。「人びと」の述語は「求め騒げど」。
【物語の姫君の--やうなれば】- 『伊勢物語』第六段、『大和物語』第百五十四段、同百五十五段など。
【詳しくも言ひ続けず】- 三光院説「作者の分別となり」と指摘。
【京より、ありし使の】- 浮舟の母からの使者。
【また人おこせたり】- 主語は浮舟母。
|
| 1.1.2 |
|
「まだ、鶏が鳴く時刻に、出立させなさった」
|
まだ鶏の鳴いているころに出立たせた
|
【まだ、鶏の鳴くになむ、出だし立てさせたまへる】- 使者の詞。
|
| 1.1.3 |
と使の言ふに、いかに聞こえむと、乳母よりはじめて、あわて惑ふこと限りなし。思ひやる方なくて、ただ騷ぎ合へるを、かの心知れるどちなむ、いみじくものを思ひたまへりしさまを思ひ出づるに、「身を投げたまへるか」とは思ひ寄りける。 |
と使者が言うと、どのように申し上げようと、乳母をはじめとして、あわてふためることこの上ない。
推量しても見当がつかず、ただ大騷ぎし合っているのを、あの事情を知っている者どうしは、ひどく物思いなさっていた様子を思い出すと、「身を投げなさったのか」と思い寄るのであった。
|
と言っている使いにどうこの始末を書いて帰したものであろうと、乳母をはじめとして女房たちは頭を混乱させていた。何のわけでどうなったかと推理してゆくことができずに、ただ騒いでいる時、浮舟の秘密に関与していた右近と侍従だけには最近の姫君の悲しみよう、煩悶のしようの並み並みでなかったことから、川へ身を投げたという想像がつくのであった。
|
【かの心知れるどち】- 右近と侍従。
【身を投げたまへるか】- 主語は浮舟。宇治川に身を投げたか、の意。『異本紫明抄』は「世の中の憂きたびごとに身を投げば深き谷こそ浅くなりなめ」(古今集俳諧、一〇六一、読人しらず)を指摘。
|
| 1.1.4 |
|
泣きながらこの手紙を開くと、
|
泣く泣く夫人の送ってきた手紙をあけて見ると、
|
【泣く泣くこの文を開けたれば】- 主語は乳母や右近など。
|
| 1.1.5 |
|
「とても気がかりなので、眠れませんでしたせいでしょうか、今夜は夢でさえゆっくりと見えません。
悪夢にうなされうなされして、気分も普段と違って悪うございますよ。
やはりとても恐ろしく、あちらにお移りになる日は近くなったが、その前後に、こちらにお迎え申しましょう。
今日は雨が降りそうでございますので」
|
あまりにあなたが心配で安眠のできないせいでしょうか、今夜は夢の中であなたを見ることすらよくできないのです。眠ったかと思うと何かに襲われて苦しむのです。そんなことで気分もよろしくなくて困ります。移転される日の近くなったことは知っていますが、それまでの間をこの家へあなたを来させていたく思います。今日は雨になりそうですからだめでしょうが。
|
【いとおぼつかなさに】- 以下「はべりぬべければ」まで、浮舟母の手紙。
【なほいと恐ろしく】- 『集成』は「本妻方の呪詛など恐れるのであろう」と注す。
【ものへ渡らせたまはむことは】- 薫の京の新築した邸へ移ること。四月十日の予定であった(浮舟巻)。
【そのほど】- 薫の邸へ移る前に。
|
| 1.1.6 |
|
などとある。
昨夜のお返事を開いて見て、右近はひどく泣く。
|
と書かれてあった。昨夜浮舟の書いた返事もあけて読みながら右近は非常に泣いた。
|
【昨夜の御返りをも開けて見て】- 浮舟から母への返事。主語は右近ら。
|
| 1.1.7 |
「さればよ。心細きことは聞こえたまひけり。我に、などかいささかのたまふことのなかりけむ。幼かりしほどより、つゆ心置かれたてまつることなく、塵ばかり隔てなくてならひたるに、今は限りの道にしも、我を後らかし、けしきをだに見せたまはざりけるがつらきこと」 |
「そうであったか。
心細いことを申し上げなさっていたのだ。
わたしに、どうして少しもおしゃってくださらなかったのだろう。
幼かった時から、少しも分け隔て申し上げることもなく、塵ほども隠しだてすることなくやって来たのに、最期の別れ路の時に、わたしを後に残して、そのそぶりさえお見せにならなかったのがつらいことだ」
|
こんな覚悟をしておいでになったので心細いようなことをお言いになったのである、小さい時から少しの隔てもなく親しみ合った主従ではないか、隠し事は塵ほどもなかった間柄ではないか、それだのに最後に自分をおうとみになり自殺の気ぶりもお見せにならなかったのは恨めしい
|
【さればよ】- 以下「つらきこと」まで、右近の心中の思い。
【聞こえたまひけり】- 浮舟が母に。辞世の歌をさす。
【幼かりしほどより】- 右近は浮舟の乳母子。
|
| 1.1.8 |
と思ふに、足摺りといふことをして泣くさま、若き子どものやうなり。いみじく思したる御けしきは、見たてまつりわたれど、かけても、かくなべてならずおどろおどろしきこと、思し寄らむものとは見えざりつる人の御心ざまを、「なほ、いかにしつることにか」とおぼつかなくいみじ。 |
と思うと、足摺りということをして泣く有様は、若い子供のようである。
ひどくお悩みのご様子は、ずっと拝見して来たが、まったく、このように普通の人と違って大それたこと、お思いつくとは見えなかった方のお気持ちを、「やはり、どうなさったことか」と分からず悲しい。
|
と思うと、泣いても泣いても足らず足摺りということをしてもだえているのが子供のようであった。悲しんでいたことにはよく気はついていたのであるが、自殺などという恐ろしいことの決行できる方とは見えず、優しい柔らかい心の持ち主だったではないかと、まだ事実を事実として信じることができずにただ悲しいばかりの右近であった。
|
【足摺りといふことを】- 『異本紫明抄』は「白玉か何ぞと人の問ひし時露と答へて消えなましものを」(伊勢物語)を指摘。
【いみじく思したる御けしきは】- 以下「いかにしつることにか」まで、右近の心中の思い。浮舟の苦悩の様子を思う。『完訳』は「以下、右近の心情に即した行文」と注す。
|
| 1.1.9 |
乳母は、なかなかものもおぼえで、ただ、「いかさまにせむ。いかさまにせむ」とぞ言はれける。 |
乳母は、かえって何も分からなくなって、ただ、「どうしよう。
どうしよう」と言うだけであった。
|
乳母はかえってはげしい驚きのために放心して、「どうすればいいだろう、どうすれば」とばかり言っているのである。
|
【言はれける】- 「れ」自発の助動詞。
|
|
第二段 匂宮から宇治へ使者派遣
|
| 1.2.1 |
|
宮にも、まことにいつもと違った様子であったお返事に、「どのように思っているのだろう。
わたしを、そうはいっても愛している様子でいながら、浮気な心だとばかり、深く疑っていたので、他へ身を隠したのであろうか」とお慌てになって、お使者がある。
|
兵部卿の宮も普通でない気配のある返事をお読みになったため、どんなふうな気になっているのであろう、自分を愛していることは確かであるが、移り気であると自分の言われていることに疑いを持っていたから、大将の手へ行くのではなくどこともなく行くえをくらまそうとするのではあるまいか、と不安でならずお思いになって使いをお出しになった。
|
【例ならぬけしきありし御返り】- 浮舟から匂宮への返書。「からをだに」の歌(浮舟巻)。
【いかに思ふならむ】- 以下「行き隠れむとにやあらむ」まで、匂宮の心中の思い。匂宮は入水したとは思いもよらない。
【思し騷ぎ】- 大島本は「おほしさハき」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「思し騒ぎて」と「て」を補訂する。『新大系』は底本のまま「おぼしさは(わ)ぎ」とする。
|
| 1.2.2 |
ある限り泣き惑ふほどに来て、御文もえたてまつらず。
|
居合わせた者たちが泣き騒いでいるところに来て、お手紙も差し上げられない。
|
使いが来てみると家の中は女の泣き叫ぶ声に満ちていてお手紙を受け取ろうとする者もない。
|
|
| 1.2.3 |
|
「どうしたことか」
|
どうしたことか
|
【いかなるぞ】- 匂宮の使者の詞。
|
| 1.2.4 |
と下衆女に問へば、
|
と下衆女に尋ねると、
|
と下の女中に聞くと、
|
|
| 1.2.5 |
|
「ご主人様が、今夜、急にお亡くなりになったので、何もかも分からなくいらっしゃいます。
頼りになる方もいらっしゃらない時なので、お仕えなさっている方々は、ただ物に突き当たっておろおろなさっています」
|
「姫君が昨晩にわかにお亡れになりましたので、女房がたはだれも気を失ったようになっていらっしゃるのですよ。御用をお取り次ぎしましてもだめでしょう」
|
【上の、今宵】- 以下「惑ひたまふ」まで、下衆女の詞。
【ものもおぼえたまはず】- 主語は女房たち。下衆女から見れば上位の身分。
【頼もしき人も】- 『集成』は「母君のことなどであろう」と注す。
【さぶらひたまふ人びとは】- 女房たち。
【惑ひたまふ】- 主語は女房たち。会話文中なので、敬語がつく。
|
| 1.2.6 |
|
と言う。
事情を深く知らない男なので、詳しくは尋ねないで帰参した。
|
と言った。何の事情も知らぬ男であったから、くわしく聞くこともせずに帰ってまいった。
|
【詳しう問はで】- 大島本は「くハしうとハて」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「くはしくも」と「も」を補訂する。『新大系』は底本のまま「くはしう」とする。
|
| 1.2.7 |
|
「こうこうでした」と申し上げさせたところ、夢のように思われて、
|
そして山荘の出来事を取り次ぎによっておしらせしたのであった。宮は夢とよりお思われにならない。
|
【かくなむ」と申させたるに】- 使者が取次の者に、これこれしかじかでしたと、匂宮に申し上げさせる。
【夢とおぼえて】- 主語は匂宮。
|
| 1.2.8 |
「いとあやし。いたくわづらふとも聞かず。日ごろ、悩ましとのみありしかど、昨日の返り事はさりげもなくて、常よりもをかしげなりしものを」 |
「まことに変だ。
ひどく患っていたとも聞いてない。
日頃、気分が悪いとばかりあったが、昨日の返事は変わったこともなくて、いつものよりも興趣があったものを」
|
ひどく病をしているというふうでもなく、いつも気分がすぐれぬとは書いてあったが、昨日の返事にはそれも書かず、平生のものよりも情の見えることを言って来たではないかと不思議にばかりお思われになって、
|
【いとあやし】- 以下「をかしげなりしものを」まで、匂宮の心中の思い。
|
| 1.2.9 |
と、思しやる方なければ、
|
と、ご想像もおつきにならないので、
|
|
|
| 1.2.10 |
|
「時方、行って様子を見て、はっきりとしたことを尋ね出せ」
|
時方に自身で宇治へ行き確かなことを調べて来るように
|
【時方、行きて】- 以下「問ひ聞け」まで、匂宮の詞。
|
| 1.2.11 |
とのたまへば、
|
とおっしゃると、
|
お命じになった。
|
|
| 1.2.12 |
「かの大将殿、いかなることか、聞きたまふことはべりけむ、宿直する者おろかなり、など戒め仰せらるるとて、下人のまかり出づるをも、見とがめ問ひはべるなれば、ことづくることなくて、時方まかりたらむを、ものの聞こえはべらば、思し合はすることなどやはべらむ。さて、にはかに人の亡せたまへらむ所は、論なう騒がしう、人しげくはべらむを」と聞こゆ。 |
「あの大将殿は、どのようなことか、お聞きになっていることがございましたのでしょう、宿直をする者が怠慢である、などと訓戒なさったと言って、下人が退出するのさえ、注意して調べると言いますので、口実もなくて、時方が参ったのを、事が漏れたりしましたら、お気づきになることがございましょう。
そうして、急に人のお亡くなりになった所は、言うまでもなく騒がしく、人目が多くございましょうから」と申し上げる。
|
「あの大将のお耳にどんなことがはいったのですか、宿直をする者が忠実に役を勤めないというお叱りがあったとかで、私の侍が使いにまいったり、帰ったりいたしますのさえ、見つけますと調べ立てるようなことをする者らがあるそうなのですから、口実なしに私が行きまして、それが大将さんへ知れますとあなた様の御迷惑になることが起こるのではございませんでしょうか。そしてまた人が急病でお死にになった所などというものはおおぜいの人が集まってもいるでしょうから」
|
【かの大将殿】- 以下「人しげくはべらむを」まで、時方の詞。
【下人の】- 宇治山荘の下人。
【思し合はすること】- 匂宮が浮舟に通じているということ。実は薫は既に知ってしまっている。
|
| 1.2.13 |
「さりとては、いとおぼつかなくてやあらむ。なほ、とかくさるべきさまに構へて、例の、心知れる侍従などに会ひて、いかなることをかく言ふぞ、と案内せよ。下衆はひがことも言ふなり」 |
「そうかといって、まことに気がかりなままでいられようか。
やはり、何か適当に計らって、いつものように、事情を知っている侍従などに会って、どうしたわけでこのように言うのか、と尋ねよ。
下衆も間違ったことを言うものだ」
|
「だからといって、訳のわからぬままにしておけるものではない。何とか口実を作って行って、こちらの味方になっている侍従などに逢って、真相を確かめて来てくれ。どんなことをこういうふうに言っているかをね。下人というものはよくまちがったことを聞いて来たりするものだから」
|
【さりとては】- 以下「言ふなり」まで、匂宮の詞。
|
| 1.2.14 |
とのたまへば、いとほしき御けしきもかたじけなくて、夕つ方行く。
|
とおっしゃるので、お気の毒なご様子も恐れ多くて、夕方に行く。
|
こう仰せられる宮の御様子においたましいところの見えるのももったいなくて時方はその夕方から宇治へ出かけた。
|
|
|
第三段 時方、宇治に到着
|
| 1.3.1 |
かやすき人は、疾く行き着きぬ。雨少し降り止みたれど、わりなき道にやつれて、下衆のさまにて来たれば、人多く立ち騷ぎて、 |
身分の軽い者は、すぐに行き着いた。
雨が少し降り止んだが、難儀な山道を身を簡略にして、下衆の恰好で来たところ、人が大勢立ち騒いで、
|
この人たちが急いで行けば早く行き着くこともできるのであった。少し降っていた雨はやんだが泥濘の路につかれていたし、はじめから侍風に装っていたのであるし、目だつこともなく門をはいることのできた山荘の中は混雑していた。
|
【かやすき人は】- 時方をさす。
|
| 1.3.2 |
|
「今夜、このままご葬送申し上げるのです」
|
今夜のうちにお葬儀をしてしまうのである
|
【今宵、やがてをさめたてまつるなり】- 浮舟方の人々の詞。
|
| 1.3.3 |
など言ふを聞く心地も、あさましくおぼゆ。
右近に消息したれども、え会はず、
|
などと言うのを聞く気分も、驚き呆れて思われる。
右近に案内を乞うたが、会うことはできない。
|
などと皆の言っているのを聞いて時方はひどく驚かされた。右近に面会を求めたが逢えない。
|
|
| 1.3.4 |
|
「ただ今は、何も分かりません。
起き上がる気持ちもしません。
それにしても、今夜を最後に、このようにお立ち寄りになるのでしょうが、お話しできませんことが」
|
「何が何やらわからぬふうになっていまして、起き上がる力もないのです。夜分おそくにでもなりましたらおいでくださいませ。お目にかかれませんのは残念でございます」
|
【ただ今、ものおぼえず】- 以下「え聞こえぬこと」まで、右近の詞。
【今宵ばかりこそ、かくも立ち寄りたまはめ】- 大島本は「う(う#<朱>こ<墨>)そ」とある。すなわち「う」を朱筆で抹消して傍らに墨筆で「こ」と訂正する。『集成』『完本』『新大系』は底本の訂正に従って「こそ」と訂正する。係結び「こそ--め」逆接用法。『完訳』は「浮舟が死ねば交渉もなくなるとする」と注す。
|
| 1.3.5 |
と言はせたり。
|
と言わせた。
|
と取り次ぎをもって言わせた。
|
|
| 1.3.6 |
「さりとて、かくおぼつかなくては、いかが帰り参りはべらむ。今一所だに」 |
「そうは言っても、このようにはっきり分かりませんでは、どうして帰参できましょう。
せめてもうお一方にでも」
|
「そうではありましょうが、こちらの御事情がわからぬままでは帰りようがありません。もう一人の方にでも逢わせてください」
|
【さりとて】- 以下「今一所だに」まで、時方の詞。もうお一方に、すなわち侍従に会いたい。
|
| 1.3.7 |
と切に言ひたれば、侍従ぞ会ひたりける。
|
と切に言ったので、侍従が会ったのであった。
|
時方がせつに言ったために侍従が出て来た。
|
|
| 1.3.8 |
|
「まことに呆れたことです。
ご自身も思いがけない様子でお亡くなりになったので、悲しいと言っても言い足りず、夢のようで、誰も彼もが途方に暮れています旨を申し上げてくださいませ。
少しでも気分が落ち着きましたら、日頃、物思いなさっていた様子や、先夜、ほんとうに申し訳なくお思い申し上げていらした有様などを、お聞かせ申し上げましょう。
この穢など、世間の人が忌む期間が過ぎてから、もう一度お立ち寄りくださいませ」
|
「とんだことになりまして、だれも想像のできませんようなふうでお亡くなりになったものですから、悲しいなどと申す言葉では私どもの心持ちは出てまいりません。夢のように思いまして、だれも皆呆然としておりますとだけ申し上げてくださいませ。少しこうしました気持ちの納りますころになれば、その前にどんなに煩悶をしておいでになりましたかと申すことや、あの宮様のおいであそばした晩に心苦しく思召した御様子などもお話し申し上げることができるかと思います。触穢の期間の過ぎました時分にもう一度またお立ち寄りください」
|
【いとあさまし】- 大島本は「あさまし」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「あさましく」と「く」を補訂する。『新大系』は底本のまま「あさまし」とする。以下「立ち寄りたまへ」まで、侍従の詞。
【思しもあへぬ】- 主語は浮舟。突然の急死。
【申させたまへ】- 時方から匂宮へ。
【いと心苦しと思ひきこえさせたまへりし】- 浮舟が匂宮を。先夜、逢わずに帰したこと。
【この穢らひなど】- 死の穢れ。近親者は三十日間家に籠もる。
|
| 1.3.9 |
と言ひて、泣くこといといみじ。
|
と言って、泣く様子はまことに大変である。
|
と言って侍従ははげしく泣く。
|
|
|
第四段 乳母、悲嘆に暮れる
|
| 1.4.1 |
|
内側でも泣く声ばかりがして、乳母であろう、
|
奥のほうにも泣き声が幾いろにも聞こえて、乳母らしく思われる声で、
|
【内にも】- 邸宅の中。
【乳母なるべし】- 時方の目を通しての叙述。
|
| 1.4.2 |
|
「わが姫君は、どこに行かれてしまったのか。
お帰りください。
むなしい亡骸をさえ拝見しないのが、効なく悲しいことよ。
毎日拝見しても物足りなくお思い申し、早く立派なご様子を拝見しようと、朝夕にお頼み申し上げていたので、寿命も延びました。
お見捨てになって、このように行く方もお知らせにならないこと。
|
「お姫様どこへいらっしゃいました。帰っておいでくださいませ。御遺骸さえ見られませんとはなんたる悲しいことでしょう。毎日毎日拝見しても飽くことのないあなた様でした。そのあなた様の御幸福におなりになるのを祈りますことで生きがいのあった私ではございませんか、それにあなた様は打ちやってお行きになりまして、どこへ行ったとも知らせてくださらない。
|
【あが君や】- 以下「見たてまつらむ」まで、乳母の詞。
【おぼえたまひ】- 「たまふ」は浮舟に対する敬意。乳母が思う。
【頼みきこえつるにこそ、命も延びはべりつれ】- 【頼みきこえつるにこそ】-浮舟が京の薫に引き取られる日を楽しみにしていたこと。 【きこえつるにこそ--延びはべりつれ】-係結び法則、逆接用法。
|
| 1.4.3 |
鬼神も、あが君をばえ領じたてまつらじ。人のいみじく惜しむ人をば、帝釈も返したまふなり。あが君を取りたてまつりたらむ、人にまれ鬼にまれ、返したてまつれ。亡き御骸をも見たてまつらむ」 |
鬼神も、わが姫君をお取り申すことはできまい。
皆がたいそう惜しむ人を、帝釈天もお返しになるという。
姫君をお取り申し上げたのは、人であれ鬼であれ、お返し申し上げてください。
御亡骸を拝見したい」
|
鬼神でもあなた様を取り込めてしまうことはできないはずです。人が非常に惜しむ人は帝釈天も返してくださるものです。お姫様を取ったのは人にもせよ鬼にもせよ返しに来てください。御遺骸だけでも見せてほしい」
|
【帝釈も返したまふなり】- 帝釈天のせん子蘇生仏説を踏まえる(仏説せん子経)。
|
| 1.4.4 |
と言ひ続くるが、心得ぬことども混じるを、あやしと思ひて、
|
と言い続けるが、合点の行かないことがあるのを、変だと思って、
|
こう叫んでいるうちに不審な点のあるのに気のついた時方は、
|
|
| 1.4.5 |
|
「やはり、おっしゃってください。
もしや、誰かがお隠し申し上げなさったのか。
確かな事をお聞きなさろうとして、ご自身の代わりに出立させなさったお使いです。
今は、何にしても効のないことですが、後にお聞き合わせになることがございましょうが、違ったことがございましたら、聞いて参ったお使いの落度になるでしょう。
|
「真相を知らせてください。だれかがお隠しになったのですか。確かに知りたく思召して、御自身の代わりにおよこしになった私は使いです。今ははっきりしないままでも事は済むでしょうがあとでほんとうのことがお耳にはいった節、御報告が違っていたものでしたら使いの罪になります。
|
【なほ、のたまへ】- 以下「見たてまつる」まで、時方の詞。
【聞こし召さむと】- 主語は匂宮。
【御使なり】- わたし時方は匂宮の使いである。
【聞こし召し合はする】- 主語は匂宮。
【罪なるべし】- 大島本は「つミなるへし」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「罪に」と「に」を補訂する。『新大系』は底本のまま「罪」とする。
|
| 1.4.6 |
|
また、そのようなことはあるまいとご信頼あそばして、『あなた方にお会いせよ』と仰せになったお気持ちを、もったいないとはお思いになりませんか。
女の道に迷いなさることは、異国の朝廷にも、古い幾つもの例があったが、またこのようなことは、この世にない、と拝見しています」
|
まただれだれに逢えと、御好意を持つものと思召して御名ざしになったのに対しても相済まぬこととお思いになりませんか。一人の女性に傾倒される方は外国の歴史などにもありますが、宮様のあの方への御熱愛ほどのものはこの世にもう一つとはないと私は拝見しているのです」
|
【また、さりともと頼ませたまひて】- 主語は匂宮。『集成』は「それに、いくら何でも(確実なことを話してくれるだろう)と頼みなさって」。『完訳』は「さすが右近や侍従は嘘をつくまいと宮は信頼し。一説に、浮舟は死んではいまいと。前者に従う」と注す。
【君たちに】- 右近や侍従をさす。
【人の朝廷にも、古き例どもありけれど】- 中国の漢武帝と李夫人や玄宗皇帝と楊貴妃の話が有名。
【かかること、この世には】- 大島本は「かゝることこのよにハ」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「かかることはこの世に」を校訂する。『新大系』は底本のまま「かゝることこの世には」とする。
|
| 1.4.7 |
|
と言うので、「おっしゃるとおり、まことに恐れ多いお使いだ。
隠そうとしても、こうして珍しい事件の様子は、自然とお耳に入ろう」と思って、
|
と言った。道理なことで、この場合の宮の御感情はさもこそと恐察される、隠しても姫君の普通の死でない噂は立つことであろうから、今申し上げておくほうがよいと侍従は思い、
|
【げに、いとあはれなる】- 以下「聞こえなむ」まで、侍従の心中の思い。
【例ならぬことのさま】- 姫君浮舟の突然の失踪事件。
|
| 1.4.8 |
「などか、いささかにても、人や隠いたてまつりたまふらむ、と思ひ寄るべきことあらむには、かくしもある限り惑ひはべらむ。日ごろ、いといみじくものを思し入るめりしかば、かの殿の、わづらはしげに、ほのめかし聞こえたまふことなどもありき。 |
「どうして、少しでも、誰かがお隠し申し上げなさったのだろう、と思い寄るようなことがあったら、こんなにも皆が泣き騒ぐことがございましょうか。
日頃、とてもひどく物を思いつめているようでしたので、あの殿が、厄介なことに、ちらっとおっしゃってくることなどもありました。
|
「だれかがお隠ししたかという疑いも起こることでしたなら、こんなふうに家じゅうの人が悲しみにおぼれることもないでしょう。お悲しみになってめいったふうになっていらっしゃいましたころに、殿様のほうから少しめんどうなふうの仰せがあったのです。
|
【などか、いささかにても】- 以下「言ひ続けらるるなめり」まで、侍従の詞。
【かの殿の】- 薫をさす。
|
| 1.4.9 |
|
お母上でいらっしゃる方も、このように大騷ぎする乳母なども、初めから知り合った方のほうにお引っ越しなさろう、と準備し出して、宮とのご関係を、誰にも知られない状態にばかり、恐れ多くもったいないとお思い申し上げていらっしゃいましたので、お気持ちも乱れたのでしょう。
驚き呆れますが、ご自分から身をお亡くしになったようなので、このように心の迷いに、愚痴っぽく言い続けてしまうのでしょう」
|
お母様である方も、あのわめいております乳母なども初めからの方へ迎えられておいでになりますことの用意に夢中でしたし、宮様のお志に感激しておいでになりました姫君の思召しはまた別でしたから、それでお頭が混乱してしまったのでしょう、思いも寄らぬことになりまして心身ともに失っておしまいになったので、あの乳母のようなむちゃな叫びもされるのですよ」
|
【初めより知りそめたりし方に】- 薫をさす。
【この御ことをば】- 匂宮との関係。
【思ひきこえさせ】- 大島本は「思ひきえさせ」とある。『集成』『完本』『新大系』は諸本に従って「思ひきこえさせ」と「こ」を補訂する。
【御心乱れけるなるべし】- 浮舟の心。
【あさましう、心と身を亡くなしたまへるやうなれば】- 暗に自殺したことをほのめかす。
【かく心の惑ひに--なめり】- 乳母の発言の背景を推測して説明する。
|
|
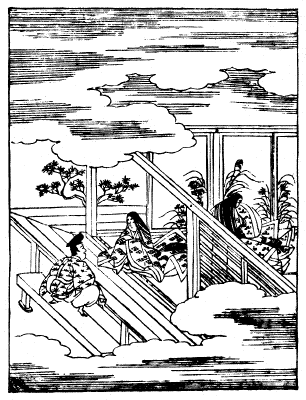 |
| 1.4.10 |
|
と、そうはいっても、ありのままにではなく暗示する。
合点が行かず思われて、
|
さすがに正面から言おうとはせずにほのめかしていることのあるのを内記も知った。
|
【心得がたくおぼえて】- 大島本は「おほえて」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「思ひて」と校訂する。『新大系』は底本のまま「おぼえて」とする。
|
| 1.4.11 |
|
「それでは、落ち着いてから参りましょう。
立ちながら話しますのも、まことに簡略なようです。
いずれ、宮ご自身でもお出でになりましょう」
|
「それではまたお静かになってから改めて伺いましょう。立ちながらの話にしてはあまりに失礼なことになります。そのうち宮様御自身でもおいでになることになりましょう」
|
【さらば、のどかに】- 以下「おはしましなむ」まで、時方の詞。「のどかに」に下に、なってからの意が含まれる。
【御みづからも】- 匂宮ご自身。
|
| 1.4.12 |
と言へば、
|
と言うと、
|
|
|
| 1.4.13 |
「あな、かたじけな。今さら、人の知りきこえさせむも、亡き御ためは、なかなかめでたき御宿世見ゆべきことなれど、忍びたまひしことなれば、また漏らさせたまはで、止ませたまはむなむ、御心ざしにはべるべき」 |
「まあ、恐れ多い。
今さら、人がお知り申すのも、亡きお方のためには、かえって名誉なご運勢と見えることですが、お隠しになっていた事なので、またお漏らしあそばさないで、終わりなさることが、お気持ちに従うことでしょう」
|
「もったいない、それはいけません。今になりましていっさいの秘密の暴露してしまいますことは、お亡くなりになりました方のためにあるいは光栄なことかも存じませんが、十分隠したく思召したことですから、秘密は秘密のままにしてお置きくださいますほうが御好志になります」
|
【あな、かたじけな】- 以下「御心ざしにはべるべき」まで、侍従の詞。
【今さら、人の】- 大島本は「いまさら」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「今さらに」と「に」を補訂する。『新大系』は底本のまま「いまさら」とする。
|
| 1.4.14 |
ここには、かく世づかず亡せたまへるよしを、人に聞かせじと、よろづに紛らはすを、「自然にことどものけしきもこそ見ゆれ」と思へば、かくそそのかしやりつ。
|
こちらでは、このように異常な形でお亡くなりになった旨を、人に聞かせまいと、いろいろと紛らわしているが、「自然と事件の子細も分かってしまうのでは」と思うと、このように勧めて帰らせた。
|
などと侍従は言い、姫君の最後が普通の死でないことをほかへ洩らすまいとしていても、自然に事実は事実として人が悟ってしまうことであろうと思い、こんな会談を長くしていることも避けねばならぬと思う心から時方を促して去らしめた。
|
|
|
第五段 浮舟の母、宇治に到着
|
| 1.5.1 |
雨のいみじかりつる紛れに、母君も渡りたまへり。
さらに言はむ方もなく、
|
雨がひどく降ったのに隠れて、母君もお越しになった。
まったく何とも言いようなく、
|
雨の降る最中に常陸夫人が来た。
|
|
| 1.5.2 |
「目の前に亡くなしたらむ悲しさは、いみじうとも、世の常にて、たぐひあることなり。これは、いかにしつることぞ」 |
「目の前で亡くなった悲しさは、どんなに悲しくあっても、世の中の常で、いくらでもあることだ。
これは、いったいどうしたことか」
|
遺骸があっての死は悲しいといっても無常の世にいては、どれほど愛していた人でもある時は甘んじて受けなければならぬのが人生の掟であるが、これは何と思いあきらめてよいことか
|
【目の前に】- 以下「いかにしつることぞ」まで、浮舟母の詞。
|
| 1.5.3 |
と惑ふ。
かかることどもの紛れありて、いみじうもの思ひたまふらむとも知らねば、身を投げたまへらむとも思ひも寄らず、
|
とうろうろする。
このような込み入った事件があって、ひどく物思いなさっていたとは知らないので、身を投げなさったとは思いも寄らず、
|
と悲しがった。苦しい恋の結末をそうしてつけたことなどは想像のできぬことで、身を投げたなどとは思い寄ることもできず、
|
|
| 1.5.4 |
「鬼や食ひつらむ。狐めくものや取りもて去ぬらむ。いと昔物語のあやしきもののことのたとひにか、さやうなることも言ふなりし」 |
「鬼が喰ったのか。
狐のような魔物が連れさらったのか。
まことに昔物語の妙な事件の例にか、そのような事も言っていた」
|
鬼が食ってしまったか、狐というようなものが取って行ったのであろうか、昔の怪奇な小説にはそんなこともあるが
|
【鬼や食ひつらむ】- 以下「言ふなりし」まで、浮舟母の心中の思い。
|
| 1.5.5 |
と思ひ出づ。
|
と思い出す。
|
と夫人は思うのであった。
|
|
| 1.5.6 |
|
「それとも、あの恐ろしいとお思い申し上げる方の所で、意地悪な乳母のような者が、このようにお迎えになる予定と聞いて、目障りに思って、誘拐を企んだ人でもあろうか」
|
また常に恐れている大将の正妻の宮の周囲に性質の悪い乳母というような者がいて、薫が浮舟をここへ隠して置いてあることを知り、だまして人につれ出させるようなことがあったのではあるまいか
|
【さては】- 以下「人もやあらむ」まで、浮舟母の心中の思い。
【かの恐ろしと思ひきこゆるあたりに】- 薫の正室女二宮をさす。
【かう迎へたまふべしと】- 薫が浮舟を迎えることをいう。
【たばかりたる人もやあらむ】- 浮舟を誘拐した人が。
|
| 1.5.7 |
と、下衆などを疑ひ、
|
と、下衆などを疑って、
|
と、召使いに疑いをかけて、
|
|
| 1.5.8 |
|
「新参者で、気心の知れない者はいないか」
|
「近ごろ来た女房で気心の知れなかったのがいましたか」
|
【今参りの、心知らぬやある】- 浮舟母の詞。
|
| 1.5.9 |
|
と尋ねるが、
|
と問うた。
|
【と問へば】- 大島本は「とゝへハ」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「問へど」を校訂する。『新大系』は底本のまま「問へば」とする。
|
| 1.5.10 |
|
「とても世間離れした所だといって、住み馴れない新参者は、こちらではちょっとしたこともできず、又すぐに参上しましょう、と言っては、皆、その引っ越しの準備の物などを持っては、京に帰ってしまいました」
|
「そんなのはあまりにこちらが寂しいと申していやがりまして、辛抱もできませんで、京へお移りになればすぐにまいりますというような挨拶をしまして、仕事などだけを引き受けて持って帰ったりしまして、現在ここにいるのはございません」
|
【いと世離れたりとて】- 以下「帰り出ではべりにし」まで、女房の詞。宇治はたいそう不便な田舎だと言って、の意。
【今とく参らむ】- 新参の女房の詞を引用。
【と言ひてなむ】- 大島本は「いひて」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「言ひつつ」を校訂する。『新大系』は底本のまま「言ひて」とする。
【帰り出ではべりにし】- 京に帰ってしまった。
|
| 1.5.11 |
とて、もとよりある人だに、片へはなくて、いと人少ななる折になむありける。
|
と言って、元からいる女房でさえ、半分はいなくなって、まことに人数少ないときであった。
|
答えはこうであった。もとからいた女房も実家へ行っていたりして人数は少ない時だったのである。
|
|
|
第六段 侍従ら浮舟の葬儀を営む
|
| 1.6.1 |
侍従などこそ、日ごろの御けしき思ひ出で、「身を失ひてばや」など、泣き入りたまひし折々のありさま、書き置きたまへる文をも見るに、「亡き影に」と書きすさびたまへるものの、硯の下にありけるを見つけて、川の方を見やりつつ、響きののしる水の音を聞くにも、疎ましく悲しと思ひつつ、 |
侍従などは、日頃のご様子を思い出して、「死んでしまいたい」などと、泣き入っていらした時々の様子、書き置きなさった手紙を見ると、「亡くなった後形に」と書き散らしていらっしゃったものが、硯の下にあったのを見つけて、川の方角を見やりながら、ごうごうと轟いて流れている川の音を聞くにつけても、気味悪く悲しいと思いながら、
|
侍従などはそれまでの姫君の煩悶を知っていて、死んでしまいたいと言って泣き入っていたことを思い、書いておいたものを読んで「なきかげに」という歌も硯の下にあったのを見つけては、騒がしい響きを立てる宇治川が姫君を呑んでしまったかと、恐ろしいものとしてそのほうが見られるのであった。
|
【身を失ひてばや】- 侍従、浮舟が日頃口にしていた詞を想起。
【亡き影に】- 浮舟の「なげきわび身をば捨つとも亡き影に憂き名流さむことをこそ思へ」(浮舟)とあった歌の文句。
|
| 1.6.2 |
|
「こうして、お亡くなりになった方を、あれこれと噂し合って、どなたもどなたも、どのようなふうにお亡くなりになったのか、とお疑いになるのも、お気の毒なこと」
|
ともかくも死んでおしまいになった人が、どこへだれに誘拐されて行っているかというように疑われているのは気の毒なことである
|
【さて、亡せたまひけむ人を】- 以下「いとほしきこと」まで、侍従の詞。
|
| 1.6.3 |
|
と相談し合って、
|
と右近と話し合い、
|
【言ひ合はせて】- 右近と話し合って。
|
| 1.6.4 |
|
「秘密の事とは言っても、ご自身から引き起こした事ではない。
母親の身として、後に聞き合わせなさったとしても、別に恥ずかしい相手ではないのを、ありのままに申し上げて、このようにひどく気がかりなことまで加わって、あれこれ思い迷っていらっしゃる様子は、少しは合点の行くようにして上げよう。
お亡くなりになった方としても、亡骸を安置し弔うのが、世間一般であるが、世間の例と変わった様子で幾日もたったら、まったく隠しおおせないだろう。
やはり、申し上げて、今は世間の噂だけでも取り繕いましょう」
|
あの秘密の関係も自発的に招いた過失ではないのであるから、親である人に死後に知られても姫君として多く恥じるところもないのであると言い、ありのままに話して、五里霧中に迷っているような心境をだけでも救いたいと夫人を思い、また故人も遺骸を始末するのが世の常の営みなのであるから、そのまま空で悲しんでばかりいることをしていては日が重なるにしたがい秘密は早く世の中へ知られてしまうことでもある、その体裁も相談して作るほうがよい、
|
【忍びたる事とても】- 以下「つくろはむ」まで、侍従の詞。
【いとやさしきほどならぬを】- 『集成』は「別に恥ずかしいお相手ではないのですから」と訳す。
【かくいみじくおぼつかなきことどもをさへ】- 『集成』は「このように全くどうなったやら分らないといった心配ごとまで」。『完訳』は「真相を明らかにしえない不安」と注す。
【かたがた思ひ惑ひたまふさま】- 主語は浮舟母。
【骸を置きてもて扱ふこそ】- 亡骸を安置して葬儀を執行すること。
【聞こえて】- 浮舟母に浮舟の死を。
|
| 1.6.5 |
と語らひて、忍びてありしさまを聞こゆるに、言ふ人も消え入り、え言ひやらず、聞く心地も惑ひつつ、「さは、このいと荒ましと思ふ川に、流れ亡せたまひにけり」と思ふに、いとど我も落ち入りぬべき心地して、 |
と相談し合って、こっそりと生前の状態を申し上げると、言う人も正気を失って、言葉も続かず、聞く気持ちも乱れて、「それでは、このとても荒々しい川に、身を投じて亡くなったのだ」と思うと、ますます自分も落ち込んでしまいそうな気がして、
|
どうしても真実を母夫人に知らす必要があるとして、ひそかに兵部卿の宮との関係、そののち大将に秘密を悟られて姫君が煩悶した話をするのであったが、語る人も魂が消えるようになり、聞く人もさらに予期せぬ悲哀の落ち重なってきたふためきをどうすることもできないふうであった。それではこの荒い川へ身を投げて死んだのかと思うと、母の夫人は自身もそこへはいってしまいたい気を覚えた。
|
【と語らひて】- 侍従が右近と相談しあって。
【さは、この】- 以下「亡せたまひにけり」まで、浮舟母の心中。
|
| 1.6.6 |
|
「流れて行かれた方角を探して、せめて亡骸だけでもちゃんと葬儀したい」
|
流れて行ったほうを捜させて遺骸だけでも丁寧に納めたい
|
【おはしましにけむ方を】- 以下「はかばかしくをさめむ」まで浮舟母の詞。
|
| 1.6.7 |
とのたまへど、
|
とおっしゃるが、
|
と夫人は言いだしたが、
|
|
| 1.6.8 |
「さらに何のかひはべらじ。行方も知らぬ大海の原にこそおはしましにけめ。さるものから、人の言ひ伝へむことは、いと聞きにくし」 |
「全然何の効もありません。
行く方も知れない大海原にいらっしゃったでしょう。
それなのに、人が言い伝えることは、とても聞きにくい」
|
もう大海へ押し流されたに違いない、効果は収めることができずに人の噂だけが高くなることははばからなければならぬことを二人は忠告した。
|
【さらに何のかひはべらじ】- 以下「いと聞きにくし」まで右近たちの詞。
|
| 1.6.9 |
|
と申し上げるので、あれやこれやと思うと、胸がこみ上げてくる気がして、どうにもこうにもなすすべもなく思われなさるが、この女房たち二人で、車を寄せさせて、ご座所や、身近にお使いになったご調度類など、みなそのままそっくり脱いで置かれた御衾などのようなものを詰めこんで、乳母子の大徳や、その叔父の阿闍梨、その弟子の親しい者など、昔から知っていた老法師など、御忌中に籠もる者だけで、人が亡くなった時の例にまねて、出立させたのを、乳母や、母君は、まことにひどく不吉だと倒れ転ぶ。
|
どうすればよいかと思うと胸がせき上がってくる気のする常陸夫人は、どうと定めることもできずに茫としているのを二人がたすけて、車を寄せさせて姫君の常に坐していた敷き物、身近に置いた手道具、もぬけになっていた夜具などを入れ、乳母の子の僧と、それの叔父にあたる阿闍梨、そのまた親しい弟子、もとから心安い老僧などで忌中を籠ろうとして来ていた人たちなどだけに真実のことを知らせ遺骸のあってする葬式のように繕わせて出す時、乳母は悲しがって泣き転んだ。
|
【とざまかくざまに】- 『完訳』は「浮舟の行方をあれこれ想像」と注す。
【この人びと二人して】- 右近と侍従。
【車寄せさせて】- 『集成』は「遺骸を運び入れる体を装う」と注す。
【乳母子の大徳】- 浮舟の乳母の子である大徳。
【それが叔父の阿闍梨】- 乳母子の大徳の叔父である阿闍梨。
【御忌に籠もるべき限りして】- 近親者による三十日間の忌籠もり。
【出だし立つるを】- 葬送の車を。
【いといみじくゆゆしと】- 大島本は「いといみしくゆゝしと」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「いとゆゆしくいみじと」を校訂する。『新大系』は底本のまま「いといみじくゆゝしと」とする。『完訳』は「まだ生きているかもしれないのに、の気持から、不吉だとする」と注す。
|
|
第七段 侍従ら真相を隠す
|
| 1.7.1 |
大夫、内舎人など、脅しきこえし者どもも参りて、
|
大夫や、内舎人など、脅迫申し上げた者どもが参って、
|
宇治の五位、その舅の内舎人などという以前に嚇しに来た人たちが来て、
|
|
| 1.7.2 |
|
「ご葬送の事は、殿に事情を申し上げさせなさって、日程を決められて、厳かにお勤め申し上げるのがよいでしょう」
|
「お葬式のことは殿様と御相談なすってから、日どりもきめてりっぱになさるのがよろしいでしょう」
|
【御葬送の事は】- 以下「仕うまつらめ」まで、大夫らの詞。
|
| 1.7.3 |
など言ひけれど、
|
などと言ったが、
|
などと言っていたが、
|
|
| 1.7.4 |
|
「特別に、今夜のうちに行いたいのです。
たいそうこっそりにと思っているところがありますので」
|
「どうしても今夜のうちにしたい理由があるのです、目だたぬようにと思う理由もあるのです」
|
【ことさら】- 大島本は「ことさら」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「ことさらに」と「に」を補訂する。『新大系』は底本のまま「ことさら」とする。以下「あればなむ」まで、右近らの詞。
【思ふやうあればなむ】- 『完訳』は「子細があるとするが、具体的に言わない。不審がられるゆえん」と注す。
|
| 1.7.5 |
とて、この車を、向かひの山の前なる原にやりて、人も近うも寄せず、この案内知りたる法師の限りして焼かす。いとはかなくて、煙は果てぬ。田舎人どもは、なかなか、かかることをことことしくしなし、言忌みなど深くするものなりければ、 |
と言って、この車を、向かいの山の前の野原に行かせて、人も近くに寄せず、この事情を知っている法師たちだけで火葬させる。
まことにあっけなくて、煙は消えた。
田舎者どもは、かえって、このようなことを仰々しくして、言忌などを深くするものだったので、
|
と言い、その車を川向かいの山の前の原へやり、人も近くは寄せずに、真実のことを知らせてある僧たちだけを立ち合わせて焼いてしまった。火は長くも燃えていなかった。田舎の人はこうした作法はかえって都人より大事にするもので、そしてこの場合の縁起を言ったりすることもうるさいほどにするものであったから、
|
【田舎人どもは、なかなか、かかることを】- 田舎人とは大夫や内舎人をさす。『完訳』は「彼らは都人よりかえって、葬送などを丁重に扱い縁起などもかつぎやすい」と注す。
|
| 1.7.6 |
|
「まことに変なこと。
きまりの作法などが、あることもなさらずに、いかにも下衆のように、あっけなくなさったことよ」
|
大家の夫人の葬儀とも思われぬ貧弱な式であったと譏る人があったり、
|
【いとあやしう】- 以下「せられぬることかな」まで、大夫らの詞。
【例の作法など】- 葬式の入棺や拾骨の儀式など。
【あることども知らず】- 大島本は「あることゝもしらす」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「ことどももしたまはず」と校訂する。『新大系』は底本のまま「ことども知らず」とする。
|
| 1.7.7 |
|
と非難すると、
|
|
【誹りければ】- 非難すると、またその一方で、というつながり方。
|
| 1.7.8 |
|
「兄弟などのいらっしゃる方は、わざとこのように、京の方はなさる」
|
また側室であった人の場合はこんなふうにして済まされるのが京の風俗であるなど
|
【片へおはする人は】- 以下「京の人はしたまふ」まで、大夫らの詞。『完訳』は「兄弟のいらっしゃるお方。一説には、一方で妻妾をお持ちの薫、とする」と注す。
【したまふ」--などぞ】- 大島本は「し給なとそ」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「したまふなるなど」と校訂する。『新大系』は底本のまま「し給などぞ」とする。
|
| 1.7.9 |
|
などと、いろいろと感心しないことを言うのであった。
|
と言ったり、いずれにもせようれしくない取り沙汰を人はした。
|
|
| 1.7.10 |
|
「このような者どもが言ったり思ったりするだけでも憚れるのに、それ以上に、噂が漏れて広がる世の中では、大将殿あたりで、亡骸もなくお亡くなりになった、とお聞きになったら、きっとお疑いになることがあろうが、宮もまた、親しいお間柄であるから、そのような人がいらっしゃるかいらっしゃらないかは、しばらくの間は隠していると疑っても、いつかは明らかになるであろう。
|
そうした階級の人がどう思ったかということさえもつつましいこの場合に、大将が遺骸も残さず死んだと聞いては必ずどこかへ失踪をしてしまったことと疑うであろうし、親族関係の濃い宮様のほうへその話の伝わってゆかぬはずもない、
|
【かかる人どもの】- 以下「疑はれたまはむ」まで、右近や侍従の心中の思い。
【亡せたまひにけり、と聞かせたまはば】- 大島本は「うせ給にけりときかせ給ハゝ」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「亡せたまへりと聞こしめさば」と校訂する。『新大系』は底本のまま「亡せ給にけりと聞かせ給はば」とする。
【同じ御仲らひにて】- 匂宮は薫と同族の親しい間柄。
|
| 1.7.11 |
|
また一方、
きっと宮だけをお疑い申し上げることはなさらないだろう。どのような人が連れ
て行って隠したのだろうなどと、お考え寄りになるだろう。生きていらした間のご運勢は、とても高くいらした方が、なるほど亡く
|
その時に宮がお隠しになったと大将は思うまい、どんな人が隠しているかと思い想像もされるに違いない、生きていた間は高い貴人たちに愛される運命を持った人が、死後に醜い疑いをかけられるのはもってのほかである
|
【いと気高くおはせし人の】- 浮舟をいう。
【げに亡き影に】- 「げに」は浮舟の独詠歌「なげきわび」歌を受ける。「亡き影に」はその歌中の語句。
|
| 1.7.12 |
|
と思うと、この家にいる下人どもにも、今朝の慌ただしかった騒動に、「その様子を見たり聞いたりした者には口止めをし、事情を知らない者には聞かせまい」などとごまかしたのであった。
|
と女房らは思い、山荘の中の下人たちにも今朝姫君の姿の見えなかった騒ぎに、思わずも実相を悟らせることになった者らへは口堅めを厳重にし、知らなかったのにはあくまでも普通の死であったように取り繕うことに侍従と右近は骨を折った。
|
【けしきも見聞きつるには口かため、案内知らぬには聞かせじ】- 右近らの思い。
|
| 1.7.13 |
|
「年月が経ったら、どちらにも、静かに、生前のご様子を申し上げよう。
ただ今は、悲しみも覚めるようなことを、ふと人伝てにお聞きなさると、やはりとてもお気の毒なことになるであろう」
|
時間がたったのちには浮舟の姫君が死を決意するまでの経過を宮へも大将へもお話しすることができようが、今は興ざめさせるような死に方を人の口から次へ次へと聞こえることは故人のために気の毒である
|
【ながらへては】- 以下「なるべし」まで、右近らの思い。『集成』は「悲しみのあまり、とても生き永らえそうにもないが、という含み」と注す。
【悲しさ覚めぬべきこと】- 『完訳』は「真相を知っては疑惑が先立つとする」と注す。
|
| 1.7.14 |
|
と、この人ら二人は、深く良心が咎めるので、隠すのであった。
|
と思い、この二人が自身らの責任を感じる心から深く隠すことに努めた。
|
【この人二人ぞ】- 右近と侍従。
|
|
第二章 浮舟の物語 浮舟失踪と薫、匂宮
|
|
第一段 薫、石山寺で浮舟失踪の報に接す
|
| 2.1.1 |
|
大将殿は、母入道の宮がお悩みになったので、石山寺に参籠なさって、おとりこみの最中であった。
そうして、ますますあちらを気がかりにお思いになったが、はっきりと、「こうだ」と言う人がいなかったので、このような大変な事件にも、まっさきにご使者がないのを、世間体もつらいと思うが、御荘園の者が参上して、「これこれしかじかです」とご報告申し上げさせたので、驚き呆れた気がなさって、ご使者が、その翌日のまだ早朝に参上した。
|
この時に薫は母宮が御病気におなりになって石山寺へ参籠をあそばされるのに従って行っていて騒がしく暮らしていたのであった。京よりもまだ遠くにいて宇治のことが気がかりでならぬ薫でもあったが、はかばかしく消息をする人もなかったために、葬儀にも大将家の使いの立ち合わなかったのは山荘の人々の情けなく思うところであったが、荘園の人が石山へ行ってはじめて姫君の死は薫へ報じられたのであった。使いはその翌日の早朝に宇治へ来た。
|
【入道の宮】- 薫の母女三宮。
【かしこを】- 浮舟をさす。
【さなむ」と】- 浮舟の入水。
【御使のなきを】- 薫の使者。
【人目も心憂しと思ふに】- 主語は浮舟の家人たち。
【御荘の人なむ参りて】- 薫の荘園の人が石山寺に参籠中の薫のもとに。
【御使、そのまたの日、まだつとめて】- 浮舟の失踪事件が判明した翌日の早朝。薫の使者が宇治に来る。浮舟の葬送は当日の夜に執行され、その後となる。
|
| 2.1.2 |
|
「ご一大事は、聞くなりすぐに自分が駆けつけるべきところ、このようにご病気でいらっしゃる御事のために、身を清めて、このような所に日数を決めて参籠しておりますので。
昨夜の事は、どうして、こちらに連絡して、日を延期してでもそういうことはするべきものを、たいそう簡略な様子で、急いでなさったのか。
どのようにしたところで、同じく言っても始まらないことだが、最後の葬儀さえ、山賤の非難を受けるのが、わたしにとってもつらい」
|
非常なことの起こったしらせを受け、すぐにも自分で行くべきですが、母宮の御病気のために日数をきめて籠っているために、それも実行ができません、昨夜にもう葬送を行なったということですが、なぜそれは私へ相談をしませんでしたか、そして日を延べることが普通ではありませんか。しかも簡単に儀式をしてしまったと聞いて残念に思います。どうしてもこうしても同じことですが、一人の人間の最後の式ですから、田舎の人たちの譏りを受けたりすることになっては、自分のためにも迷惑です。
|
【いみじきことは】- 以下「ここのためもからき」まで、使者の伝える薫の詞。
【かく悩みたまふ御ことにより】- 母女三宮の病気平癒のための参籠。
【昨夜のことは】- 葬送のこと。夜に荼毘にふす。
【などか】- 「急ぎせられにける」に係る。
【とぢめのことを】- 葬儀の事。
【山賤の誹りをさへ】- 『完訳』は「大夫・内舎人らの批判も薫の耳に入ったらしい」と注す。
|
| 2.1.3 |
など、かの睦ましき大蔵大輔してのたまへり。御使の来たるにつけても、いとどいみじきに、聞こえむ方なきことどもなれば、ただ涙におぼほれたるばかりをかことにて、はかばかしうもいらへやらずなりぬ。 |
などと、あの信任厚い大蔵大輔を使者としておっしゃった。
お使いが来たことにつけても、ますます悲しいので、何とも申し上げようのないことなので、ただ涙にくれているだけを口実にして、はっきりともお答え申し上げずに終わった。
|
と、あの親しく思っている大蔵大輔を使いにして言わせたのであった。使いの来たことでまた悲しみが新しくなったし、答える言葉も何と言ってよいかわからぬ時であってみれば、人々は泣くのを挨拶に代えて何とも申し出すことはできなかった。
|
【大蔵大輔】- 薫の腹心の家司で大蔵大輔仲信。
|
|
第二段 薫の後悔
|
| 2.2.1 |
殿は、なほ、いとあへなくいみじと聞きたまふにも、
|
殿は、やはり、実にあっけなく悲しいとお聞きなるにも、
|
薫は思いがけぬ愛人の死に落胆をして、
|
|
| 2.2.2 |
|
「何という嫌な土地であろう。
鬼などが住んでいるのだろうか。
どうして、今までそのような所に置いておいたのだろう。
思いがけない方面からの過ちがあったようなのも、こうして放っておいたので、気楽さから、宮も言い寄りなさったのだろう」
|
情けない場所である、幽鬼などが住んでいてそうした災厄をしばしば起こすのでなかろうか、それと気もつかずにどうして長く宇治などへ置いていたのだろう、不快な関係がほかに結ばれたらしいことなども、ああした不用心な所へ住ませておいたために隙をうかがわせることになったに違いない、
|
【心憂かりける所かな】- 以下「犯したまふなりけむかし」まで、薫の心中の思い。『新釈』は「わが庵は都の巽しかぞ住む世を宇治山と人はいふなり」(古今集雑下、八九三、喜撰法師)を指摘。
【人も言ひ犯したまふなりけむかし】- 「人」は匂宮をさす。
|
| 2.2.3 |
|
と思うにつけても、自分の迂闊で世間離れした心ばかりが悔やまれて、お胸が痛く思われなさる。
お患いあそばしているところで、このような事件でご困惑なさるのも不都合なことなので、京にお帰りになった。
|
と思われるのも皆自分の非常識に原因したことであると胸が痛くなるほどにも悔まれた。御病気で専念に仏へ祈っておいでになる母宮のおそばでこんな煩悶をしているのはよろしくないと思い薫は京の邸へ帰った。
|
【悩ませたまふあたりに】- 母女三宮が病気中。
【京におはしぬ】- 薫は宇治に赴かず、京へ帰った。
|
| 2.2.4 |
|
宮の御方にもお渡りにならず、
|
夫人の宮のところへは行かずに、
|
【宮の御方にも】- 薫の正室女二宮。
|
| 2.2.5 |
|
「大したことではございませんが、不吉な事を身近に聞きましたので、気持ちが静まらない間は縁起でもないので」
|
「たいしたことではないのですが、身辺に不幸が起こったものですから、しばらく落ち着きますまで、縁起の悪いことにもなりますから謹慎していようと思います」
|
【ことことしきほどにも】- 以下「いまいましうて」まで、薫の詞。浮舟について言う。『完訳』は「浮舟を、低い身分で表だった妻妾ではないとする」と注す。
【ゆゆしきことを】- 浮舟の死を言う。
【聞きつれば】- 大島本は「きゝつれハ」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「聞きはべれば」と校訂する。『新大系』は底本のまま「聞きつれば」とする。
|
| 2.2.6 |
|
などと申し上げなさって、どこまでもはかなく無常の世をお嘆きになる。
生前の容姿、まことに魅力的で、かわいらしかった雰囲気などが、たいそう恋しく悲しいので、
|
などと御挨拶をしておいて、一人で人生の深い悲しみを味わっていた。浮舟の容姿の愛嬌があって、美しかったことなどを思い出すと、非常に恋しくなり、悲しくなる薫は、
|
【など聞こえたまひて】- 大島本は「なときこえ給て」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「なむと聞こえたまひて」と校訂する。『新大系』は底本のまま「など聞こえ給て」とする。
【ありしさま容貌】- 『完訳』は「以下、薫の回想と感慨」と注す。
|
| 2.2.7 |
|
「現世には、どうしてこのようにも夢中にならず、のんびりと過ごしていたのだろう。
今では、まったく気持ちを静めるすべもないままに、後悔されることが数知れない。
このような方面の事につけて、ひどく物思いをする運命なのだ。
世人と異なって道心を身上とした人生なのに、思いの外に、このように普通の人のように生き永らえているのを、仏などが憎いと御覧になるのではなかろうか。
人に道心を起こさせようとして、仏がなさる方便は、慈悲をも隠して、このようになさるのであろうか」
|
その人の生きていた時には、それをそうと認めようとはせずに、たびたび逢いに行こうともせず、寂しい思いばかりをさせて来たのであろうと思う後悔があとからあとからわいてくる。恋愛について物思いの絶えない宿命をになっている自分である、信仰生活を志していながら俗から離れずにいるのを仏が憎んでおいでになるのであろうか、悟らせようとしての方便には未来の慈悲を隠してこんな残酷な目も仏はお見せになるものであると、
|
【うつつの世には】- 以下「こそはあなれ」まで、薫の心中の思い。
【思ひ晴れず】- 大島本は「思はれす」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「思ひ入れず」と校訂する。『新大系』は底本のまま「思はれず」とする。
【かかることの筋につけて】- 女性関係のこと。
【ものすべき】- 大島本は「ものすへき」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「もの思ふべき」と校訂する。『新大系』は底本のまま「ものすべき」とする。
【さま異に心ざしたりし身の、思ひの外に、かく例の人にて】- 『集成』は「世間の人とは違った願いを持っていた身なのに。この世の栄華を求めず仏道修行を志していたのに」。『完訳』は「世人に異なって道心を身上としたはずのわが人生なのに、現世に執着する結果となったと反省」と注す。
【仏などの】- 大島本は「ほとけなとの」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「仏なども」と校訂する。『新大系』は底本のまま「仏などの」とする。
|
| 2.2.8 |
と思ひ続けたまひつつ、行ひをのみしたまふ。
|
と思い続けなさりながら、勤行ばかりをなさる。
|
思い続けて仏勤めをばかりしていた。
|
|
|
第三段 匂宮悲しみに籠もる
|
| 2.3.1 |
|
あの宮はまた宮で、彼以上に、二、三日は何も考えることができず、正気もない状態で、「どのような御物の怪であろうか」などと騒ぐうち、だんだんと涙も流し尽くして、お気持ちが静まって、生前のご様子が恋しく悲しく思い出されなさるのであった。
周囲の人には、ただご病気が篤い様子ばかりに見せて、「このような無性に涙顔でいる様子を知らせまい」と、気強く隠そうとお思いになったが、自然とはっきりしていたので、
|
浮舟をお失いになった兵部卿の宮は、まして二、三日は失心したようになっておいでになったため、どうした物怪が憑いたかと周囲の人たちが騒いでいるうちに、ようやく涙が流れ尽くしてお心が静まってきたと同時に、生きていた日の浮舟が恋しくばかりお思い出されになるのであった。他人には重く病気をしているふうを見せて、亡き恋人を思う悲歎に沈んでいることは知らせないでいるのであると、御自身では思召したが、自然御様子にそれが現われるものであるから、
|
【かの宮はた】- 匂宮。
【いかなる御もののけならむ」など騒ぐに】- 主語は匂宮の女房たち。
【思し静まるにしもぞ】- 『完訳』は「気持が落ち着くとかえって」と注す。
【人には】- 周囲の人、さらには世間の人。
【かくすぞろなる】- 大島本は「すそろなる」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「すずろなる」と校訂する。『新大系』は底本のまま「すぞろなる」とする。
|
| 2.3.2 |
「いかなることにかく思し惑ひ、御命も危ふきまで沈みたまふらむ」 |
「どのような事にこんなにご困惑なさり、お命も危ないまでに嘆き沈んでいらっしゃるのだろう」
|
どんなことにお出逢いになって、こんなに命もあぶないまでに悲しんでおいでになるのであろう
|
【いかなることに】- 以下「沈みたまふらむ」まで、女房たちの詞。
|
| 2.3.3 |
|
と、言う人もいたので、あちらの殿におかれても、とてもよくこのご様子をお聞きになると、「そうであったか。
やはり、単なる文通だけではなかったのだ。
御覧になっては、きっとそのように熱中なさるはずの女である。
もし生きていたら、他人の関係以上に、自分にとって馬鹿らしい事が出て来るところだった」とお思いになると、恋い焦がれる気持ちも少しは冷める気がなさった。
|
という人もあるために、大将もそれを知り、故人とは自分の想像したような関係を作っておいでになったらしい、手紙をおやりになったりするだけのことではないのであった、宮が御覧になれば必ず深い愛着をお覚えになるはずの人であった、生きていたならば自分は裏切られた男としての醜名を取らなければならないのであったと、こう思うようになってからは少し故人へのあこがれがさめた気のする薫であった。
|
【かの殿にも】- 薫をさす。
【この御けしきを】- 匂宮の状態。
【さればよ】- 以下「出で来なまし」まで、薫の心中の思い。『完訳』は「文通のみならず、情交もあったとうと推測。「--けり」と、確信」と注す。
【見たまひては】- 主語は匂宮。浮舟を見たら、の意。
【さ思しぬべかりし人ぞかし】- 『完訳』は「宮が必ず執心するはずの女。男を魅了させる浮舟の美貌をいう」と注す。
【ながらへましかば--出で来なまし】- 反実仮想の構文。主語は浮舟。
【ただなるよりぞ】- 大島本は「たゝなるよりそ」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「ただなるよりは」と校訂する。『新大系』は底本のまま「ただなるよりぞ」とする。 『集成』は「匂宮と浮舟の関係は、やがて世間に知れ、そうなれば匂宮とは叔父甥の間柄だけに、自分も恥を晒すことになるのだった」と注す。
【胸もすこし冷むる心地したまひける】- 『完訳』は「浮舟の死に胸をなでおろす気持さえまじる」と注す。
|
|
第四段 薫、匂宮を訪問
|
| 2.4.1 |
|
宮のお見舞いに、毎日参上なさらない方はなく、世間の騷ぎとなっているころ、「大した身分でもない女のために閉じ籠もって、参上しないのも変だろう」とお思いになって参上なさる。
|
兵部卿の宮の御病気見舞いに伺候せぬ人もなく、世間の騒ぎにもなっている場合であるのに、たいした喪というわけでもないのに、自分がお見舞いにならないのも僻見をいだいているように見られることであろうからと思い、薫は二条の院へ伺った。
|
【宮の御訪らひに】- 匂宮のお見舞い。
【ことことしき際ならぬ思ひに籠もりゐて】- 以下「ひがみたるべし」まで、薫の心中の思い。「ことことしき際」は浮舟の身分。 【思ひに籠もりゐて】- 浮舟の喪に服す。
|
| 2.4.2 |
|
そのころ、式部卿宮と申し上げた方もお亡くなりになったので、御叔父の服喪で薄鈍でいるのも、心中しみじみと思いよそえられて、ふさわしく見える。
少し顔が痩せて、ますます優美さがまさっていらっしゃる。
お見舞い客が退出して、ひっそりとした夕暮である。
|
この時分に式部卿の宮と言われておいでになった親王もお薨れになったので、薫は父方の叔父の喪に薄鈍色の喪服を着けているのも、心の中では亡き愛人への志にもなる似合わしいことであると思っていた。顔は少し痩せていよいよ艶に見えた。お見舞い客が皆去ったあとの静かな夕方であった。
|
【式部卿宮】- 蜻蛉式部卿宮、以前に娘を薫にと志したことがある宮(東屋)。
【御叔父の服にて】- 薫の叔父。軽服三ケ月の喪。
【思ひよそへられて】- 叔父の服喪に浮舟を悼む。
【人びとまかり出でて】- 大島本は「まかりいてゝ」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「まかでて」と校訂する。『新大系』は底本のまま「まかり出でて」とする。匂宮邸の様子。
|
| 2.4.3 |
|
宮は、臥せって沈んでばかりいられないお気持ちなので、疎遠な客にはお会いにならないが、御簾の内側にもいつもお入りになる方には、お会いなさらないことできもない。
顔をお見せになるのも何となく気がひける。
お会いなさるにつけても、ますます涙が止めがたいのをお思いになるが、冷静になって、
|
宮は御病気らしくお見えにはなっても、ただお気持ちが重く沈んでしかたがないという御状態にすぎないのであったから、うとうとしい人とは御面会にならぬが、お居間の中へ平生はお通しになる御親交のある人たちとはお逢いになるのであったから、薫を御引見になったが、その人の顔を御覧になると理由もなく恥ずかしくお思われになり、心弱くなっておいでになるのが隠しきれぬような涙になって出るのをきまり悪く思召しながらも、よく心持ちをお抑えになり、
|
【臥し沈みてはなき】- 大島本は「ふししつミてハなき」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「臥し沈みてのみはあらぬ」と校訂する。『新大系』は底本のまま「臥し沈みてはなき」とする。
【御簾の内にも例入りたまふ人には】- 薫のような人。
【見たまふにつけても】- 匂宮が薫を。
|
| 2.4.4 |
|
「大した病気ではございませんが、誰もが、用心しなければならない病状だ、とばかり言うので、帝におかれても母宮におかれても、御心配なさるのがとてもつらくて、なるほど、世の中の無常を、心細く思っております」
|
「たいした病気ではありませんが、だれもが悪くなってゆく兆候のある容体だと言って騒ぐものですから、お上も中宮様も御心配あそばされるのが苦しく思われてね。それにつけてもまた人生の心細さが感ぜられてなりませんよ」
|
【おどろおどろしき心地にも】- 以下「おもひはべる」まで、匂宮の詞。
【皆人】- 大島本は「ミな人」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「皆人は」と「は」を補訂する。『新大系』は底本のまま「みな人」とする。
【慎むべき病のさまなり、と】- 『集成』は「物の怪かもしれないと疑っている」と注す。
【内裏にも宮にも】- 帝と明石中宮。匂宮の両親。
【げに、世の中の常なきをも】- 『完訳』は「現世の無常が薫の口癖。それに「げに」と納得しながら、浮舟の死を悼む気持も言外に出る趣」と注す。
|
| 2.4.5 |
とのたまひて、おし拭ひ紛らはしたまふと思す涙の、やがてとどこほらずふり落つれば、いとはしたなけれど、「かならずしもいかでか心得む。ただめめしく心弱きとや見ゆらむ」と思すも、「さりや。ただこのことをのみ思すなりけり。いつよりなりけむ。我をいかにをかしと、もの笑ひしたまふ心地に、月ごろ思しわたりつらむ」 |
とおっしゃって、押し拭ってお隠しになろうとする涙が、そのまま防ぎようもなく流れ落ちたので、たいそう体裁が悪いが、「必ずしもどうして気がつこうか。
ただ女々しく心弱い者のように見るだろう」とお思いになるが、「そうであったのか。
ただこの事だけをお悲しみになっていたのだ。
いつから始まったのだろうか。
自分を、どんなにも滑稽に物笑いなさるお気持ちで、この幾月もお思い続けていらしたのだろう」
|
こうお言いになり、ちょっと袖で押すほどに拭うてお済ませになるつもりでおありになった涙が、どうしたかとめどもなく流れ落ちるのを、見苦しいと思召すのであるが、浮舟のために泣くとは大将に気のつくはずもなかろう、ただ人生にめめしく執着をしていると見えるだけであろうと、薫の心中を御推測のできぬ宮は思っておいでになった。やはり恋人の死ばかりを悲しんでおいでになるのであった、いつごろからあった事実なのであろう、自分を滑稽な男と長い間笑っておいでになったのであろう
|
【かならずしも】- 以下「見ゆらむ」まで、匂宮の心中の思い。薫は浮舟との関係を気づくまい、と思う。
【さりや。ただこのことをのみ】- 以下「思しわたりつらむ」まで、薫の心中の思い。『集成』は「匂宮には「とおぼすも」と敬語、薫は「と思ふに」と書き分ける。以下、薫、匂宮の思惑の違いを相互に書く」。『完訳』「以下、秘事を確信する薫の心中」と注す。
|
| 2.4.6 |
と思ふに、この君は、悲しさは忘れたまへるを、
|
と思うと、この君は、悲しみはお忘れになったが、
|
と思い、薫は悲しみもそれで忘れることができているのを宮は御覧になり、
|
|
| 2.4.7 |
|
「何とまあ、薄情な方であろうか。
物を切に思う時は、ほんとこのような事でない時でさえ、空を飛ぶ鳥が鳴き渡って行くのにつけても、涙が催されて悲しいのだ。
わたしがこのように何となく心弱くなっているのにつけても、もし真相を知っても、それほど人の悲しみを分からない人ではない。
世の中の無常を身にしみて思っている人は冷淡でいられることよ」
|
死んだ愛人に対して非常に冷淡なものである、ものの痛切に悲しい時には全然関係のないことにさえ涙が誘われ、空を鳴いて通る鳥の声にも哀傷の思いは催されるはずではないか、自分が何の悲しみによって病んでいるかを知ったなら、同情から平気には見ておられぬ人なのであるが、人生の無常を深く悟り澄ました人はこんなに冷静なふうでいられるのであろう
|
【こよなくも】- 以下「人しもつれなき」まで、匂宮の心中の思い。『完訳』は「薫はなんと薄情な人か。以下、冷静な薫を見ての匂宮の心中」と注す。
【かからぬことにつけてだに】- 人の死去ということ。
【空飛ぶ鳥の鳴き渡るにも】- 『完訳』は「景物に感情の増幅される趣」と注す。
【すぞろに】- 大島本は「すそろに」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「すずろに」と校訂する。『新大系』は底本のまま「すぞろに」とする。
【もし心得たらむに】- 大島本は「心えたらむに」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「心を得たらむに」と「を」を補訂する。『新大系』は底本のまま「心得たらむに」とする。
【もののあはれも知らぬ人にもあらず】- 薫をさす。
【世の中の常なきこと惜しみて思へる人しもつれなき】- 『集成』は「世間無常の道理を深く悟っている人は、かえって(身辺の不幸には)冷静でいられるのだな」。『完訳』は「薫の独自な道心ぶりを評す」と注す。
|
| 2.4.8 |
|
と、羨ましくも立派だともお思いなさる一方で、女のゆかりと思うとなつかしい。
この人に向かい合っている様子をご想像になると、「形見ではないか」と、じっと見つめていらっしゃる。
|
とうらやましく、御自身の及びがたさをお覚えになるのであるが、「我妹子が来ては寄り添ふ真木柱そも睦まじやゆかりと思へば」という歌のように、あの人を愛した男であるとお思いになるとこの人にさえ愛のお持たれになる兵部卿の宮であった。この人とある日は向かい合っていたのかとお思いになると、形見であるというように薫の顔がお見守られになった。
|
【真木柱はあはれなり】- 『源氏釈』は「わぎもこが来ても寄り立つ真木柱そもむつましやゆかりと思へば」(出典未詳、源氏釈所引)を指摘。薫も浮舟ゆかりの人と思えば懐かしく思われる、の意。
【これに向かひたらむさまも】- 浮舟が薫に向かい合っているさまを。
【形見ぞかし」とも】- 大島本は「かたみそかしとも」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「形見ぞかしと」と「も」を削除する。『新大系』は底本のまま「形見ぞかしとも」とする。薫は浮舟の形見だ、の意。
|
|
第五段 薫、匂宮と語り合う
|
| 2.5.1 |
|
だんだんと世間の話を申し上げなさると、「とても隠しておくこともあるまい」とお思いになって、
|
いろいろな世間話を申しているうちに、絶対に浮舟のことは言いださぬという態度はお取りしたくないと思い、
|
【いと籠めてしもはあらじ」と思して】- 主語は薫。薫と浮舟との関係を。
|
| 2.5.2 |
|
「昔から、胸のうちに秘めて少しも申し上げなかったことを残しております間は、ひどくうっとうしくばかり存じられましたが、今は、かえって身分も高くなりました。
わたくし以上に、お暇もないご様子で、のんびりとしていらっしゃる時もございませんので、宿直などにも、特に用事がなくては伺候することもできず、何となく過ごしておりました。
|
「私は昔からどんなこともあなた様に申し上げないで、自分だけで思っているのがとても苦しいのではございますが、今では知らぬまに私のような者も大官になっておりますし、ましてあなた様はいろいろとお忙しい身の上でお閑暇などはありますまいと存じまして、宿直などをいつでも申し上げて話を聞いていただくようなこともできませず日を過ごしておりましたが、こんなことをひとつお聞きください。
|
【昔より、心に籠めてしばしも】- 大島本は「心にこめてしハしも」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「心にしばしも籠めて」を校訂する。『新大系』は底本のまま「心に籠めてしばしも」とする。以下「聞こし召すやうもはべるらむかし」まで、薫の詞。
【なかなか上臈に】- 大島本は「中/\」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「なかなかの」と「の」を補訂する。『新大系』は底本のまま「なかなか」とする。
【御暇なき御ありさまにて】- 匂宮をいう。
【宿直などに、そのこととなくてはえさぶらはず】- 主語は薫。
【そこはかとなくて過ぐしはべるをなむ】- 係助詞「なむ」の下に、今まで話さなかったことを申し訳なく思う、などの意が省略。以上、まえおき。
|
| 2.5.3 |
|
昔、御覧になった山里に、あっけなく亡くなった方の、同じ姉妹に当たる人が、意外な所に住んでいると聞きつけまして、時々逢いもしようか、と存じておりましたが、不都合にも世間の人の非難もきっとあるような時でしたので、あの山里に置いておきましたところ、あまり行って逢うこともなく、また一方、女も、わたくし一人を頼りにする気持ちも特になかったのであろうか、と拝見しましたが、れっきとした重々しい扱いをいたす夫人ならともかく、世話するのには、格別の落度もございませんのに、気楽でかわいらしいと存じておりました女が、まことにあっけなく亡くなってしまいました。
すべて世の中の有様を思い続けますと、悲しいことだ。
お聞き及びのこともございましょう」
|
昔も御承知のあの山里に若死にをしました恋人と同じ血統の人が意外な所に一人いると聞きまして、昔の人の形見にときどき顔を見て慰めにしようと思ったのですが、ちょうど私といたしましては、そんなことをしては、世間からわけもなく悪く批評をされる時だったものですから、昔の寂しい山里へつれて行ってあったのでございます。そして始終は訪ねて行ってやることもない間柄になっていましたし、その人も私一人にたよる心もなかったように見えましたが、唯一の妻としては、そうした不純な心のあることは捨ておけないことですが、愛人としておくぶんには許されなくはないものですから、可憐に見ておりましたが突然亡くなったのでございます。人生の悲哀がまたしみじみと味わわれまして、寂しい思いをしております。もうそのことはお耳にもどちらからかはいっておりますでしょう」
|
【はかなくて亡せはべりにし人の、同じゆかりなる人】- 故大君の妹の浮舟。
【あいなく人の誹りもはべりぬべかりし折なりしかば】- 女二宮との結婚の時期であった。
【このあやしき所に】- 宇治の山荘をさす。
【かれも、なにがし一人をあひ頼む心もことになくてやありけむ、とは見たまひつれど】- 『完訳』は「女(浮舟)の方も、私一人を頼りにする気も特になかったのではないか。匂宮との仲を暗に皮肉る」と注す。
【やむごとなくものものしき筋に】- 正妻待遇をいう。
【見るにはた】- 世話する。
【悲しくなむ】- 係助詞「なむ」の下に「はべる」などの語句が省略。
【聞こし召すやうも】- 浮舟のことをさす。『完訳』は「匂宮の秘事にさりげなく迫る」と注す。
|
| 2.5.4 |
とて、今ぞ泣きたまふ。
|
と言って、今初めてお泣きになる。
|
と言って、この時になって泣き出した。
|
|
| 2.5.5 |
|
この方も、
「まこと涙顔はお見せ申すまい。馬鹿らしい」と思ったが、い
ったん流れ出しては止めがたい。態度がやや取り乱しているようなので、「いつもと違っている、気の毒だ」と
|
薫としてもこれほど悲しむふうはお見せすまいと自戒していたのであったが、こぼれ始めてはとどめがたい涙になった。その様子に別な意味もあるふうなのを宮もお悟りになり、気の毒に思召したが、素知らぬふうをあそばした。
|
【これも】- 薫をさす。
【いとかうは】- 以下「をこなり」まで、薫の心中の思い。『集成』は「匂宮に奪られた女のことを、宮の前で嘆くのは間抜けなこと、という気持」と注す。
【けしきのいささか乱り顔なるを】- 薫のやや取り乱した態度。
【あやしく、いとほし」と思せど】- 『集成』は「浮舟との秘事を知られたか、とようやくこのあたりで気づく体」と注す。
|
| 2.5.6 |
|
「まことにお気の毒なことを。
昨日ちらっと聞きました。
どのようにお悔やみ申し上げようかと存じながら、特に世間にお知らせなさらないことと、聞きましたので」
|
「御愁傷をお察しします。そのことは昨日ちょっと聞いたのでした。御弔問をしたく思いましたが、秘密にしておありになるのだとも聞いたものですから」
|
【いとあはれなることにこそ】- 以下「聞きはべりしかばなむ」まで、匂宮の詞。
【思ひはべりながら】- 大島本は「思侍なから」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「思ひたまへながら」を校訂する。『新大系』は底本のまま「思侍ながら」とする。
|
| 2.5.7 |
|
と、さりげなくおっしゃるが、とても我慢できないので、言葉少なくいらっしゃる。
|
言葉少なにこうお言いになった。長く言うに堪えがたいお気持ちになっておいでになったのである。
|
【いと堪へがたければ】- 主語は匂宮。
|
| 2.5.8 |
|
「適当なお方としてお目にかけたい、と存じておりました女でした。
自然とそのようなこともございましたでしょうか、お邸にも出入りする縁故もございましたので」
|
「お目にかけましたら興味をお覚えになりますだけの価値のある女性でしたが、それは私の思いますだけでなくあなたの奥様のほうの縁故のある人でしたから、もう顔など知っておいでになったかもしれません」
|
【さる方にても】- 以下「参り通ふべきゆゑはべりしかば」まで、薫の詞。『完訳』は「あなたのしかるべき相手として。匂宮の愛人として紹介したかったとする。匂宮への痛烈な皮肉」と注す。
【思ひたまへりし】- 大島本は「思給へりし」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「思ひたまへし」と「り」を削除する。『新大系』は底本のまま「思給へりし」とする。
【人になむ】- 係助詞「なむ」の下に「ありける」などの語句が省略。
【宮にも参り通ふべきゆゑ】- 「ゆゑ」は理由。中君と浮舟は異母姉妹の関係。
|
| 2.5.9 |
など、すこしづつけしきばみて、
|
などと、少しずつ当てこすって、
|
などと少しほのめかして薫は、
|
|
| 2.5.10 |
|
「ご気分がすぐれないうちは、つまらない世間話をお聞きになって、驚きなさるのも、つまらないことです。
どうぞ大事になさってください」
|
「御病気中はうるさい世の中のことなどをお耳に入れましては御安静をお妨げすることになってもよろしくございません。よく御養生をなさいまし」
|
【御心地例ならぬほどは】- 以下「おはしませ」まで、薫の詞。
【すぞろなる世のこと聞こし召し入れ】- 大島本は「すそろなる」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「すずろなる」と校訂する。『新大系』は底本のまま「すぞろなる」とする。『集成』は「つまらぬ世間話をお耳にあそばし、お心を騒がせられますのもよろしくないことですございます。暗に、浮舟の死をそう嘆かれますな、と言い、それゆえの病と察していることを仄めかす」と注す。
【あいなきこと】- 大島本は「あいなきこと」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「あいなきわざ」と校訂する。『新大系』は底本のまま「あいなきこと」とする。
|
| 2.5.11 |
など、聞こえ置きて、出でたまひぬ。
|
などと、申し上げ置いて、お帰りになった。
|
と申して辞し去った。
|
|
|
第六段 人は非情の者に非ず
|
| 2.6.1 |
|
「ひどくご執心であったな。
まことにあっけなかったが、やはりよい運勢の女であった。
今上の帝や、后が、あれほど大切になさっていらっしゃる親王で、顔かたちをはじめとして、今の世の中には他にいらっしゃらないようだ。
寵愛なさる夫人でも、並一通りでなく、それぞれにつけて、この上ない方をさしおいて、この女にお気持ちを尽くし、世間の人が大騒ぎして、修法、読経、祈祷、祓いと、それぞれ専門に騒ぐのは、この女に執着したための、ご病気であったのだ。
|
非常に悲しがっておいでになった、故人を哀れな存在とは見たが、現在の帝王と后があれほど御大切にあそばされる皇子で、御容貌といい、学才と申して今の世に並ぶ人もない方で、すぐれた夫人たちをお持ちになりながら、あの人に心をお傾け尽くしになり、修法、読経、祭り、祓とその道々で御恢復のことに騒ぎ立っているのも、ただあの人の死の悲しみによってのことではないか、
|
【いみじくも思したりつるかな】- 以下「かからじ」まで、薫の心中の思い。
【高き人の宿世なりけり】- 『完訳』は「高貴な匂宮に愛された点で浮舟をすぐれた宿運の人とみる。前の女房たちと同じ見方」と注す。
【見たまふ人とても】- 『集成』は「妻となさる方とても、並一通りではなく。正夫人の六の君、側室の中の君、それぞれ一方ならずすばらしい女性である」と注す。
【これに】- 浮舟に。
【この人を思すゆかりの、御心地のあやまりに】- 『完訳』は「実は、浮舟に執心するあまりの錯乱だった、と薫は合点」と注す。
|
| 2.6.2 |
|
自分も、これほどの身分で、今上の帝の内親王をいただきながら、この女がいじらしく思えたのは、宮に負けていようか。
それ以上に、今は亡き人かと思うと、心の静めようがない。
とはいえ、愚かしいことだ。そうはすまい」
|
自分も今日の身になっていて、帝の御女を妻にしながら、可憐なあの人を思ったことは第一の妻に劣らなかったではないか、まして死んでしまった今の悲しみはどうしようもないほどに思われる、見苦しい、こんなふうにはほかから見られまい
|
【この人のらうたくおぼゆる方は、劣りやはしつる】- 『集成』は「この人(浮舟)がいとしく思われたことでは(匂宮に)劣っていただろうか。以下、高貴の身の自分からも、宮に劣らず思われる浮舟の宿世に感嘆する気持」と注す。
【今はと】- 浮舟は今は亡き人と。
【かからじ】- 『集成』は「もう嘆くまい」と訳す。
|
| 2.6.3 |
と思ひ忍ぶれど、さまざまに思ひ乱れて、
|
と我慢するが、いろいろと思い乱れて、
|
と忍んでいるのであるがと薫は思い乱れながら
|
|
| 2.6.4 |
|
「人は木や石ではないので、
|
「人非木石皆有情、不如不逢傾城色」
|
【人木石に非ざれば皆情けあり】- 薫の詞。「人は木石に非ず、皆情有り、如かず、傾城の色に遇はざらんには」(白氏文集・李夫人)の一節。
|
| 2.6.5 |
と、うち誦じて臥したまへり。
|
と、口ずさみなさって臥せっていらっしゃった。
|
と口ずさんで寝室にはいった。
|
|
| 2.6.6 |
|
後の葬送なども、まことに簡略にしてしまったのを、「宮におかれてもどのようにお聞きになろうか」と、お気の毒で張り合いがないので、「母が普通の身分で、兄弟のある人はなどと、そのような人は言うことがあるというのを思って、簡略にするのであったろう」などと、気にくわなくお思いになる。
|
葬儀なども簡単に済ませたことを宮も飽き足らず思召したことであろうと哀れに思われて、母の身分がよろしくなくて、異父の弟などが幾人も立ち合ってなどとあとに言われることを避けて急いでしたのであろうがと不愉快に薫は思った。
|
【後のしたためなども】- 浮舟の葬送の儀式。
【宮にも】- 『完訳』は「匂宮。一説には中の君」と注す。
【母のなほなほしく】- 以下「こと削ぐなりけむかし」まで、薫の想像。浮舟の母は八宮の女房中将の君、現在は受領の北の方という低い身分。
【兄弟あるはなど】- 『完訳』は「兄弟のある人は葬儀を簡略にするとの風習」と注す。
|
| 2.6.7 |
おぼつかなさも限りなきを、ありけむさまもみづから聞かまほしと思せど、「長籠もりしたまはむも便なし。行きと行きて立ち帰らむも心苦し」など、思しわづらふ。 |
気がかりさも限りがないので、その時の実際の様子を自分でも聞きたくお思いになるが、「長い忌籠もりなさるのも不都合である。
行くには行ってもすぐ帰るのは心苦しい」などと、ご思案なさる。
|
くわしい様子も聞かないでいることも物足らず思われ、自身で宇治へ行ってみたいと思うのであるが、喪の家へそのまま忌の明けるまで籠っているのも自分としてははばかられる、行くだけ行ってすぐに帰るのも心苦しいことであると思いもだえていた。
|
【長籠もりしたまはむも便なし】- 以下「心苦し」まで、薫の思い。宇治に行き三十日間の忌籠もりをするのは不都合と考える。
|
|
第三章 匂宮の物語 匂宮、侍従を迎えて語り合う
|
|
第一段 四月、薫と匂宮、和歌を贈答
|
| 3.1.1 |
|
月が変わって、「今日が引き取る日であったのに」と思い出しなさった夕暮、まことにもの悲しい。
御前近くの橘の香がやさしい感じのところに、ほととぎすが二声ほど鳴いて飛んで行く。
「亡くなった人の所に行くなら」と独り言をおっしゃっても物足りないので、北の宮邸に、そこにお渡りになる日であったので、橘を折らせて申し上げなさる。
|
月が変わって、今日は宇治へ行ってみようと薫の思う日の夕方の気持ちはまた寂しく、橘の香もいろいろな連想を起こさせてなつかしい時に、杜鵑が二声ほど鳴いて通った。「亡き人の宿に通はばほととぎすかけて音にのみなくと告げなん」などと古歌を口にしたままではまだ物足らず思われ、二条の院へ兵部卿の宮の来ておいでになる日であったから、橘の枝を折らせて、歌をつけて差し上げた。
|
【月たちて】- 四月となる。
【今日ぞ渡らまし」と】- 薫の思い。四月十日が引っ越しの日であった。
【思し出でたまふ】- 大島本は「おほしいて給」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「思ひ出たまふ」を校訂する。『新大系』は底本のまま「おぼし出で給」とする。
【御前近き橘の香のなつかしきに】- 『集成』は「五月待つ花橘の香をかげば昔の人の袖の香ぞする」(古今集夏、一三九、読人しらず)を指摘。
【宿に通はば】- 薫の口ずさみ。『源氏釈』は「亡き人の宿に通はばほととぎすかけて音にのみ泣くと告げなむ」(古今集哀傷、八五五、読人しらず)を指摘。
【北の宮に】- 二条院をいう。薫邸は三条宮。
【渡りたまふ日なりければ】- 主語は薫。
|
|
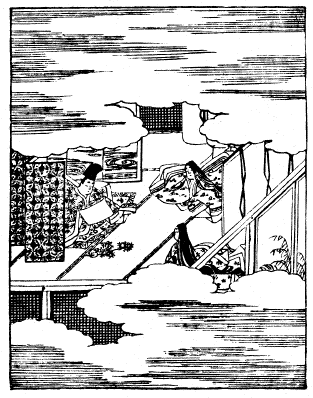 |
| 3.1.2 |
|
「忍び音にほととぎすが鳴いていますが、
あなた様も泣いていらっしゃいましょうかい
|
忍び音や君も泣くらんかひもなき
しでのたをさに心通はば
|
【忍び音や君も泣くらむかひもなき--死出の田長に心通はば】- 薫から匂宮への贈歌。『河海抄』は「いくばくの田を作ればかほととぎすしでの田長朝な朝な呼ぶ」(古今集雑体、一〇一三、藤原敏行)。『花鳥余情』は「死出の山越えて来つらむほととぎす恋しき人のうへ語らなむ」(拾遺集哀傷、一三〇七、伊勢)を指摘。
|
| 3.1.3 |
|
宮は、女君のご様子がとてもよく似ているのを、しみじみとお思いになって、お二方で物思いに耽っていらっしゃるところであった。
「意味のありそうな手紙だ」と御覧になって、
|
宮は中の君の顔の浮舟によく似たのに心を慰めて、二人で庭をながめておいでになる時であった。言外に意味のあるような歌であると宮は御覧になり、
|
【あはれと思して】- 大島本は「あはれとおほして」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「いとあはれに」と校訂する。『新大系』は底本のまま「あはれと」とする。
【二所】- 匂宮と中君。
【けしきある文かな」と見たまひて】- 『完訳』は「浮舟のことをほのめかしたと気づく」と注す。
|
| 3.1.4 |
|
「橘が薫っているところは、
ほととぎすよ気をつけて
|
橘の匂ふあたりはほととぎす
心してこそ鳴くべかりけれ
|
【橘の薫るあたりはほととぎす--心してこそ鳴くべかりけれ】- 匂宮の返歌。『全書』は「五月待つ花橘の香をかげば昔の人の袖の香ぞする」(古今集夏、一三九、読人しらず)を指摘。
|
| 3.1.5 |
わづらはし」
|
迷惑なことを」
|
なんだかかかりあいのあるようなことが言われますね。
|
|
| 3.1.6 |
と書きたまふ。
|
とお書きになる。
|
とお返事をあそばした。
|
|
| 3.1.7 |
|
女君は、この事件の経緯は、みなご存知なのであった。
「しみじみと言いようもないほどあっけなかった、あれこれにつけて感慨深い中で、自分一人が物思いを知らないので、今まで生き永らえていたのであろうか。
それもいつまで続くやら」と心細くお思いになる。
宮も、隠すことのできないものから、分け隔てなさるのもとてもお気の毒なので、生前の様子などを、少し取り繕いながらお話し申し上げなさる。
|
宮と浮舟の姫君の関係もまたその人の死も何に基因するかも今は皆わかってしまった中の君は、姉の女王も妹の姫君も物思いがもとで皆若死にをしたあとに、自分だけが残っているのは感情の鈍い質であるからであろうか、それといってもいつまでも生きていられることかと心細く思った。宮も隠してお置きになっても、いずれは知れてしまうことであるのに、隔てを置いたままでいるのは苦しいことであると思召して、浮舟との関係を少しは取り繕って夫人へお話しになった。
|
【このことのけしきは】- 夫の匂宮と浮舟との関係及び浮舟の死。
【あはれにあさましき】- 以下「それもいつまで」まで、中君の心中の思い。
【我一人もの思ひ知らねば】- 姉の大君や妹の浮舟と比較して。
【隔てたまふも】- 大島本は「へたて給も」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「隔てたまへるも」と校訂する。『新大系』は底本のまま「隔て給も」とする。
|
| 3.1.8 |
|
「隠していらっしゃったのがつらかった」
|
「だれであるのかをあなたがどこまでも隠そうとしたのが恨めしかったために反発的にそんなことにまで進んでしまったのですよ」
|
【隠したまひしがつらかりし】- 匂宮の詞。『完訳』は「中君が浮舟の素姓や境遇を」と注す。
|
| 3.1.9 |
|
などと、泣いたり笑ったりしながら申し上げなさるにつけても、他の人よりは親しみを感じ胸を打つ。
大げさに格式ばって、ご病気の件でも、大騒ぎをなさる所では、お見舞い客が多くて、父大臣や、兄の公達がひっきりなしなのも、とてもうるさいが、ここはたいそう気楽で、慕わしい感じにお思いなさるのであった。
|
など、泣きも笑いもしながらお語りになる相手が、恋人の姉であることにお慰みになるところも多かった。形式が簡単でなく、ちょっとお身体の悪いことのあっても騒ぎがはなはだしくなり、見舞いに集まる人も多く、父の大臣、その息子たちと絶え間なしに病床に付き添っているようなところと変わり、二条の院においでになることは気楽でなつかしい気分を十分お得になられることであったのである。
|
【異人よりは睦ましくあはれなり】- 浮舟は中君と姉妹ゆえに。
【ことことしくうるはしくて】- 六条院の様子。
【例ならぬ御ことのさまも】- 婿の匂宮の病気。
【おどろき惑ひたまふ所にては】- 主語は夕霧。
【父大臣、兄の君たち】- 六君の父大臣夕霧や兄弟の公達。
【ここはいと心やすくて】- 匂宮の本邸二条院。正妻のいる六条院と比較。
|
|
第二段 匂宮、右近を迎えに時方派遣
|
| 3.2.1 |
|
まことに夢のようにばかり、やはり、「どうして、とても急なことであったのか」とばかり気が晴れないので、いつもの人びとを召して、右近を迎えにやる。
母君も、まったくこの川の音や感じを聞くと、自分もころがり込んでしまいそうで、悲しく嫌なことが休まる間もないので、とても侘しくてお帰りになったのであった。
|
浮舟の死んだことはまだ夢のようにばかりお思われになり、どうして急にそうなったかという不審がお解けにならぬため、例の内記たちをお召しになり、右近を呼びにおつかわしになった。母の常陸夫人も宇治川の音を聞くと自身も引き入れられるような悲しみが続くために困って京へ帰って行った。
|
【いと夢のやうにのみ】- 『完訳』は「以下、匂宮の心中。いまだに浮舟の死が信じられない。「なほ」は「いぶせければ」にかかる」と注す。
【右近を迎へに遣はす】- 時方や道定をして宇治に右近を迎えにやる。
【母君も】- 浮舟母。その葬儀には立ち合った。
|
| 3.2.2 |
|
念仏の僧どもを頼りとする人として、たいそうひっそりとしているところにやって来たので、厳重に、急に警戒していた宿直人どもも、見咎めない。
「皮肉にも、最期の折にお入れ申し上げることができずに終わってしまったことよ」と、思い出すのもおいたわしい。
|
念仏の役を勤める僧だけが頼もしい人のようなかすかな家と見えたが、内記がはいって行っても、人が来るとすぐに外を見まわりに来るような宿直の侍もない。今はこうであるのに、あの最後の時にだけはこんな者たちが妨げて宮をお入れしなかったと時方らは思い出して悲しんだ。
|
【頼もしき者にて】- 主語は宇治の人々。
【入り来たれば】- 主語は匂宮の使者たち。
【あやにくに】- 以下「なりにしよ」まで、時方らの感想。『完訳』は「皮肉にも、今にして思えば最後の対面の機会だったのに、宮を邸内に導くことができなかった。以下、時方たちの回想である」と注す。
|
| 3.2.3 |
|
「とんでもないことをご執着なさったことよ」と、見苦しく拝見したが、こちらに来ては、お越しになった夜々の有様や、お抱かれなさって、舟にお乗りになった感じが、上品でかわいらしかったことなどを思い出すと、気丈な人などもなくしみじみとなる。
右近が会って、ひどく泣くのも道理である。
|
それほどまでに悲しみにお溺れにならずともよいではないかと、常は非難がましく宮をお思いしている人たちであるが、ここへ来て見ると、あの無理をして通っておいでになったあの場合、その場合が思い出され、宮にお抱かれして船に乗った方の美しかったことなどを思い出すと、だれも心強くなっておられる者はなくなって皆泣いていた。右近が出て来て非常に泣くのももっともなことと思われた。
|
【さるまじきことを思ほし焦がるること】- 時方らの感想。
【おはしましし】- 主語は匂宮。
【抱かれたてまつりたまひて】- 「れ」受身の助動詞。主語は浮舟。
|
| 3.2.4 |
|
「このようにおっしゃるので、お使いに来ました」
|
宮がこういう思召しで迎えのために自分らをおつかわしになった
|
【かくのたまはせて、御使になむ参りつる】- 大島本は「まいりつる」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「参り来つる」と「き」を補訂する。『新大系』は底本のまま「まいりつる」とする。時方の詞。
|
| 3.2.5 |
と言へば、
|
と言うと、
|
ということを語ると、
|
|
| 3.2.6 |
|
「今さら、皆が変だと言い思うのも気がひけまして、参上しても、はきはきとご納得の行くようには、何か申し上げられそうな気がしません。
このご忌中が終わって、ちょっとどこそこにと人に言っても、少しふさわしいころになってから、思いの他に生きていましたら、少し気持ちが静まったような時に、ご命令がなくても参上して、おっしゃるようにとても夢のようだった事柄を、お話し申し上げとう存じます」
|
今になって他の女房たちからも怪しいことと言われ、思われするであろうことが苦しく考えられて、「まいりましてもよくおわかりいただきますほどな細かなお話がまだできます自信がございません。お四十九日が済みましたあとで、ちょっと外へまいると申すような体裁を作りましても不自然でないころになりました時、私はもう生きても居られない気はいたしますものの、まだ生き延びておられましたなら、お召しがございませんでも伺いまして、ほんとうに夢のようでございました悲しいお話も申し上げたいと思います」
|
【今さらに】- 以下「語りきこえまほしき」まで、右近の詞。
【聞こし召し明らむばかり】- 主語は匂宮。
【あからさまにもなむ】- 大島本は「あからさまにもなん」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「あからさまにものになん」と校訂する。『新大系』は底本のまま「あからさまにもなん」とする。『完訳』は「京に用事がと言いつくろっても、おかしくない時期を待って」と注す。
【げにいと夢のやうなりしことども】- 匂宮の「いと夢のやうにのみ」を受ける。使者が伝えたのであろう。
【語りきこえまほしき】- 大島本は「かたりきこえまほしき」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「語りきこえさせはべらまほしき」と「させはべら」を補訂する。『新大系』は底本のまま「語りきこえまほしき」とする。
|
| 3.2.7 |
と言ひて、今日は動くべくもあらず。
|
と言って、今日は動きそうにもない。
|
と言い、今は動きそうにもない。
|
|
|
第三段 時方、侍従と語る
|
| 3.3.1 |
|
大夫も泣いて、
|
内記も泣いて、
|
【大夫も泣きて】- 左衛門大夫時方。
|
| 3.3.2 |
|
「まったく、お二方の事は、詳しくは存じ上げません。
物の道理もわきまえていませんが、無類のご寵愛を拝見しましたので、あなた方を、どうして急いでお近づき申し上げよう。
いずれはお仕えなさるはずの方だ、と存じていましたが、何とも言いようもなく悲しいお事の後は、わたし個人としても、かえって悲しみの深さがまさりまして」
|
「私は何も細かい御関係のことまでは知らないのですし、事情もわかりませんが、宮様がどんなに深い愛をお持ちになりましたかということだけは存じ上げていたものですから、あなたがたとも急いで御懇意にならずとも、しまいには御主人としてお仕えする方についておいでになる方と思いまして呑気にして来たのですが、お亡れになってはじめてあなたがたにもいろいろと御心配をお掛けしたことが相済まぬ、あなた様はよくお尽くしくださいましたと感謝の念でいっぱいに心がなりました」
|
【さらに、この御仲の】- 以下「まさりてなむ」まで、時方の詞。
【物の心】- 大島本は「物の心」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「ものの心も」と「も」を補訂する。『新大系』は底本のまま「物の心」とする。
【君たちをも】- 右近や侍従。
【言ふかひなく悲しき御こと】- 浮舟の死をさしていう。
【私の御心ざしも、なかなか深さまさりて】- 『集成』は「浮舟存生中は、主命による奉公だったが、もはやそれもないかと思うとかえって、の意」と注す。
|
| 3.3.3 |
と語らふ。
|
と懇切に言う。
|
などと言っていた。
|
|
| 3.3.4 |
|
「わざわざお車などをお考えめぐらされて、差し向けなさったのを、空っぽで帰るのは、まことにお気の毒です。
もうお一方でも参上なさい」
|
「車も宮御自身でお指図になってお持たせになったのですから、あき車をまた引かせては帰れません。もう一人の方でも来てくださいませんか」
|
【わざと御車など】- 以下「参りたまへ」まで、時方の詞。
【思しめぐらして】- 主語は匂宮。
【今一所にても】- 侍従をさしていう。
|
| 3.3.5 |
と言へば、侍従の君呼び出でて、
|
と言うので、侍従の君を呼び出して、
|
と内記が言うので、右近は侍従を呼び、
|
|
| 3.3.6 |
|
「それでは、参上なさい」
|
「あなたが伺ってください、私の代わりに」
|
【さは、参りたまへ】- 右近が侍従に言った詞。
|
| 3.3.7 |
と言へば、
|
と言うと、
|
と言った。
|
|
| 3.3.8 |
|
「あなた以上に何を申し上げることができましょう。
それにしても、
やはり、このご忌中の間にはどうして
|
「あなたでさえもお話を申し上げる自信が持てないのに、私にどうしてそれができましょう。それにしましても忌中の者がお邸へまいったりすることは縁起の悪いことではございませんか」
|
【まして何事をかは】- 大島本は「なに事をかハ」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「何ごとをか」と「は」を削除する。『新大系』は底本のまま「何事をかは」とする。
|
| 3.3.9 |
と言へば、
|
と言うと、
|
|
|
| 3.3.10 |
|
「ご病気で大騒ぎをして、いろいろなお慎みがございますようですが、忌明けをお待ち切れになれないようなご様子です。
また、このように深いご宿縁では、忌籠もりあそばすのでいらっしゃいましょう。
忌明けまでの日も幾日でもない。
やはりお一方参上なさい」
|
「御病気のためにいろいろなふうに御謹慎をなさらねばならなくなっていらっしゃいますが、そんなこともかまっておいでになれない御様子なのです。また考えてみますと、あれほどお愛しになった方のためには宮様御自身が忌におこもりになってもよろしいわけなのですからね、もう忌の残りが幾日もあるのではないのですから、ぜひお一人だけは来てください」
|
【悩ませたまふ御響きに】- 以下「参りたまへ」まで、時方の詞。
【残りの日】- 忌明けまでの残りの日数。
|
| 3.3.11 |
|
と責めるので、侍従が、以前のご様子もとても恋しく思い出し申し上げるので、「いつの世にかお目にかかることができようか、この機会に」と思って参上するのであった。
|
内記がこう責めるので、侍従も宮の御様子をおなつかしく思い出している心から、もう一度お目にかかりうる機会などというものはありえないことであるから、こうした時にでもと願うようになり、まいることにした。
|
【ありし御さまも】- 匂宮の姿。橘小島に同行した折の印象。
【いかならむ世にかは見たてまつらむ、かかる折に】- 侍従の心中の思い。匂宮にお目にかかれる機会を思う。
|
|
第四段 侍従、京の匂宮邸へ
|
| 3.4.1 |
|
黒い衣装類を着て、化粧をした容貌もとても美しそうである。
裳は、今後は自分より目上の人はいないとうっかりして、色も染め変えなかったので、薄い紫色のを持たせて参上する。
|
黒い服ながら引き繕って着た姿はきれいであった。裳は現在では主人のいない家であったから喪の色のも作らなかったため、淡紫のを持たせて車に乗った。
|
【裳は、ただ今我より上なる人なきにうちたゆみて】- 『完訳』は「裳は、唐衣とともに、主人の前に出る際の礼装。今はお仕えする主人も亡くなったので、油断して鈍色のを染めておかなかった」と注す。
【薄色なるを持たせて参る】- 『集成』は「薄紫色の裳を持たせて参上する。お供の女の童などに持たせるのであろう」と注す。
|
| 3.4.2 |
|
「生きていらっしゃったら、この道を人目を忍んでお出になるはずだったのに。
人知れずお心寄せ申し上げていたのに」などと思うにつけ悲しい。
道中泣きながらやって来た。
|
姫君がおいでになったなら、宮にこうして迎えられておいでになったであろう、自分はその時にお付きして行こうと心にきめていたのであったがと思い出すのは悲しかった。途中をずっと泣きながら侍従は二条の院へまいった。
|
【おはせましかば】- 以下「心寄せきこえしものを」まで、侍従の心中の思い。「ましかば--まし」反実仮想の構文。浮舟が生きていたら。
【忍びて出でたまはまし】- 主語は浮舟。匂宮に密かに京へ連れ出されたろうに、と仮想。
【人知れず心寄せきこえしものを】- 主語は侍従。匂宮に対して。
|
| 3.4.3 |
|
宮は、この人が参った、とお耳にあそばすにつけてもお胸が迫る。
女君には、あまりに憚れるので、申し上げなさらない。
寝殿にお出でになって、渡殿に降ろさせなさった。
生前の様子などを詳しくお尋ねあそばすと、日頃お嘆きになっていた様子や、その夜にお泣きになった様子を、
|
兵部卿の宮は侍従の来たしらせをお受けになっても身にしむようにお思われになった。夫人へは恥ずかしくてお話しにはならなかったのである。宮は寝殿のほうへおいでになり、そこの廊のほうへ車を着けさせて侍従を下ろさせになった。浮舟のことをくわしく聞こうとあそばすと、そのずっと前から煩悶をし続けていたこと、その前夜にひどく泣いたことなどを言い、
|
【女君には】- 中君。
【寝殿におはしまして、渡殿に降ろしたまへり】- 大島本は「おろし給へり」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「おろさせたまへり」と校訂する。『新大系』は底本のまま「おろし給へり」とする。『集成』は「ご自身は寝殿においでになって。中の君のいる西の対にいたのを、侍従到着と聞いて、自室(寝殿)に赴いたのである。侍従を渡殿に降ろさせなさった。寝殿の東の渡殿に車を着けさせたのであろう。西の対から遠く、人目にも付かぬよう計らう体」と注す。
|
| 3.4.4 |
「あやしきまで言少なに、おぼおぼとのみものしたまひて、いみじと思すことをも、人にうち出でたまふことは難く、ものづつみをのみしたまひしけにや、のたまひ置くこともはべらず。夢にも、かく心強きさまに思しかくらむとは、思ひたまへずなむはべりし」 |
「不思議なまでに言葉少なく、ぼんやりとばかりしていらっしゃって、大変だとお思いになることも、他人にお話しになることはめったになく、遠慮ばかりなさったせいでしょうか、言い残しなさることもございません。
夢にも、このような心強いことをお覚悟だったとは、存じませんでした」
|
「怪しいほどお口数の少ない方で、内気でいらっしゃいましたから、遺言らしいことは何もなさいませんでした。夢にも自殺などという強いことのおできになるとは思われませんでした」
|
【あやしきまで】- 以下「なむはべりし」まで、侍従の詞。
【かく心強きさまに】- 浮舟の入水という事件をさす。
|
| 3.4.5 |
など、詳しう聞こゆれば、ましていといみじう、「さるべきにても、ともかくもあらましよりも、いかばかりものを思ひ立ちて、さる水に溺れけむ」と思しやるに、「これを見つけて堰きとめたらましかば」と、湧きかへる心地したまへど、かひなし。 |
などと、詳しく申し上げると、ひとしお実に悲しく思われて、「前世からの因縁で、病死などすることなどよりも、どんなに覚悟なさって、そのような川の中に溺死したのだろう」とお思いやりなさると、「その場を見つけてお止めできたら」と、煮えかえる気持ちがなさるが、どうしようもない。
|
などと侍従が話すことによって、宮はいっそうお悲しみが深くなり、命数が尽きて死んだということよりも、どんなに物思いを多くして恐ろしい川へなど身を投げたのであろうと御想像あそばすのが苦しく、その時に見つけることができてとどめえたならばと、沸きかえるような心持ちにおなりになるのであるが、今ではすべてむなしいことであった。
|
【さるべきにても】- 大島本は「さるへきにても」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「さるべきにて」と「も」を削除する。『新大系』は底本のまま「さるべきにても」とする。以下「溺れけむ」まで、匂宮の心中の思い。『集成』は「詮方もない病気で」。『完訳』は「避けられぬ前世の因縁によって病死することなどよりも」と注す。
【これを見つけて】- 浮舟の入水現場を見つけて。
|
| 3.4.6 |
|
「お手紙をお焼き捨てになったことなどに、どうして不審に思わなかったのでございましょう」
|
「あのお手紙を始末してお焼きになりました時に、なぜ私らの頭が働かなかったのでございましょう」
|
【御文を焼き】- 以下「はべらざりけむ」まで、侍従の詞。
|
| 3.4.7 |
|
などと、一晩中お聞きなさるので、お話し申し上げて夜が明ける。
あの巻数にお書きつけになった、母君の返事などを申し上げる。
|
と侍従は言ったりして、夜の明けるまで語っても語り足りないというふうであった。寺からもらった経巻へ書いて母君の返事にした歌のことなどもお話しした。
|
【かの巻数に書きつけたまへりし】- 浮舟の母へ返書として巻数に書きつけた。
|
|
第五段 侍従、宇治へ帰る
|
| 3.5.1 |
|
何程の者ともお考えでなかった侍従も、親しくしみじみと思われなさるので、
|
侍従などは何とも宮の思っておいでにならなかった女であったが、哀れに思召すために、
|
【御覧ぜざりし人も】- 侍従をさす。
|
| 3.5.2 |
|
「わたしの側にいなさい。
あちらにも縁がないではない」
|
「自分の所にいるがよい。あちらにいる奥さんもあの人には他人でなかったのだから」
|
【わがもとに】- 以下「離るべくやは」まで、匂宮の詞。
【あなたももて離るべくやは】- 「あなた」は中君をさす。浮舟の異母姉であることをいう。反語表現。
|
| 3.5.3 |
とのたまへば、
|
とおっしゃると、
|
と仰せられたが、
|
|
| 3.5.4 |
|
「そのようにして、お仕えしますにつけても、何となく悲しく存じられますので、もう暫くこの御忌みなどを済ませましてから」
|
「そうしてお仕えさせていただきましては何も何も悲しいことになりましょう。ともかくもお忌を済ませましてから、どうとも身の振り方を考えます」
|
【さて、さぶらはむに】- 以下「過ぐして」まで、侍従の詞。
【この御果てなど】- 一周忌。
|
| 3.5.5 |
と聞こゆ。「またも参れ」など、この人をさへ、飽かず思す。 |
と申し上げる。
「再び参るように」などと、この人までも、別れがたくお思いになる。
|
侍従はこう申し上げた。「また来るがいい」こんな人とすらも別れるのを悲しく宮は思召した。
|
【またも参れ】- 匂宮の詞。
|
| 3.5.6 |
|
早朝に帰る時に、あの方の御料にと思って準備なさっていた櫛の箱一具、衣箱一具を、贈物にお遣わしになる。
いろいろとお整えさせになったことは多かったが、仰々しくなってしまいそうなので、ただ、この人に与えるのに相応な程度であった。
|
浮舟のために作らせておありになった櫛の箱一具、衣裳箱一つを宮は贈り物にあそばした。その人のためにお設けになった物は多かったのであるが、これはただ内記に託しておこしらえになっただけのものであった。
|
【暁帰るに】- 大島本は「あか月」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「暁に」と「に」を補訂する。『新大系』は底本のまま「あか月」とする。
【かの御料に】- 浮舟をさす。
【贈物にせさせたまふ】- 匂宮が侍従に持たせる。
【さまざまにせさせたまふことは】- 『一葉抄』は「双紙詞也」と指摘。
|
| 3.5.7 |
「なに心もなく参りて、かかることどものあるを、人はいかが見む。すずろにむつかしきわざかな」 |
「何も考えなく参上して、このようなことがあったのを、女房はどのように見るだろうか。
何となく厄介なことだわ」
|
突然山荘を出て来て、こうした戴き物をして帰っては他の人々が何と思うであろう、
|
【なに心もなく】- 以下「わざかな」まで、侍従の感想。
|
| 3.5.8 |
と思ひわぶれど、いかがは聞こえ返さむ。
|
と困るが、どうして辞退申し上げられよう。
|
少し困ったことであると侍従は思ったのであるが、御辞退のできることでもなかった。
|
|
| 3.5.9 |
右近と二人、忍びて見つつ、つれづれなるままに、こまかに今めかしうし集めたることどもを見ても、いみじう泣く。
装束もいとうるはしうし集めたるものどもなれば、
|
右近と二人で、こっそりと見ながら、所在ないままに、精巧で今風に仕立ててあるのを見ても、ひどく泣く。
装束もたいそう立派に仕立て上げられたものばかりなので、
|
宇治へ帰った侍従は右近と二人でひそかに櫛の箱と衣箱の衣裳をつれづれなままにこまごまと見た。はなやかな錦繍の服と精巧な作の箱、その中の小箱を見ながらも二人は非常に泣いた。
|
|
| 3.5.10 |
|
「このような服喪期間中なので、これをどう隠したものか」
|
喪にこもっている自分たちはこれをどう隠しておればいいかということにも苦心を要した。
|
【かかる御服に、これをばいかでか隠さむ】- 大島本は「いかてか」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「いかで」と「か」を削除する。『新大系』は底本のまま「いかでか」とする。侍従の感想。
|
| 3.5.11 |
など、もてわづらひける。
|
などと、困るのであった。
|
薫も思い余って宇治へ行くことにした。
|
|
|
第四章 薫の物語 薫、浮舟の法事を営む
|
|
第一段 薫、宇治を訪問
|
| 4.1.1 |
大将殿も、なほ、いとおぼつかなきに、思し余りておはしたり。道のほどより、昔の事どもかき集めつつ、 |
大将殿も、同じように、まことに不審でしょうがないので、思い余りなさってお出でになった。
道中から、昔の事を一つ一つ思い出して、
|
途中からもう昔のことがいろいろと胸へ集まってきて、
|
【大将殿も、なほ】- 『完訳』は「「なほ」とあり、前に宇治行を決しかねていた気持が揺曳」と注す。
|
| 4.1.2 |
「いかなる契りにて、この父親王の御もとに来そめけむ。かかる思ひかけぬ果てまで思ひあつかひ、このゆかりにつけては、ものをのみ思ふよ。いと尊くおはせしあたりに、仏をしるべにて、後の世をのみ契りしに、心きたなき末の違ひめに、思ひ知らするなめり」 |
「どのような縁で、この父親王のお側に来初めたのだろう。
このように思いもかけなかった人の最期まで世話をし、この一族のことにつけては、物思いばかりすることよ。
たいそう尊くおいでになった所で、仏のお導きによって、来世ばかりを祈願していたのに、心汚い末路の思惑違いによって、世の無常を思い知らせるようだ」
|
どんな因縁で八の宮の所へ自分は行き始めたのであろう、二人の女王に失恋をして、父宮から子とも認められなかった人にまで縁が生じ、この一家との結ばれによって物思いばかりを自分はし続ける、尊い悟りをお持ちになった方へ仏の導きで近づき、未来の世界での交わりを約していながら、女王に心を引かれ始めて、信仰をよそにした報いを受けるのであろう
|
【いかなる契りにて】- 以下「思ひ知らするなめり」まで、薫の心中の思い。『集成』は「世の無常を悟らせようとするのであろう」。『完訳』は「仏が懲らしめようとする」と訳す。
【かかる思ひかけぬ】- 大島本は「かゝる」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「かく」と校訂する。『新大系』は底本のまま「かゝる」とする。
|
| 4.1.3 |
とぞおぼゆる。
右近召し出でて、
|
と思われなさる。
右近を召し出して、
|
と、こんなことも思われた。大将は右近を前に呼んで話そうとしたが、悲しみが先に立ちはかばかしい質問もできない。
|
|
| 4.1.4 |
「ありけむさまもはかばかしう聞かず、なほ、尽きせずあさましう、はかなければ、忌の残りもすくなくなりぬ。過ぐして、と思ひつれど、静めあへずものしつるなり。いかなる心地にてか、はかなくなりたまひにし」 |
「生前の様子もはっきりとは聞かず、やはり、尽きせず呆れて、あっけないので、忌中期間も少なくなった。
過ぎてから、と思っていたが、抑えきれずにやって来たのです。
どのような気持ちで、お亡くなりになったのですか」
|
「もう忌の残りの日も少なくなったのだから済んでからと思ったが、どうしても待ちきれないものがあって来た。どんな病状でにわかにあの方は死ぬようになられたか」
|
【ありけむさまも】- 以下「はかなくなりたまひにし」まで、薫の詞。浮舟の死にいたるまでの経緯。
|
| 4.1.5 |
と問ひたまふに、「尼君なども、けしきは見てければ、つひに聞きあはせたまはむを、なかなか隠しても、こと違ひて聞こえむに、そこなはれぬべし。あやしきことの筋にこそ、虚言も思ひめぐらしつつならひしか。かくまめやかなる御けしきにさし向かひきこえては、かねて、と言はむ、かく言はむと、まうけし言葉をも忘れ、わづらはしう」おぼえければ、ありしさまのことどもを聞こえつ。 |
とお尋ねなさると、「尼君なども、経緯は知ってしまったので、結局はお聞き合わせになるであろうから、なまじ隠しだてしても、話がくいちがって聞かれるのも、具合の悪いことになろう。
変な話には、嘘を考えて何度も言ってきたが、このような真面目な態度のお前に対座申し上げては、前もって、ああ言おう、こう言おうと、用意していた言葉も忘れ、困ること」と思われたので、生前の様子のあれこれを申し上げた。
|
と問われ、右近は弁の尼なども姫君の遺骸のなくなっていたことは気どっているのであるから、隠してもしまいには薫の耳にはいることに違いない、かえってことを蔽おうとして誤解を招くことになっては姫君が気の毒である、あの不始末を処理するためにはいろいろな嘘も言われたのであるが、このまじめな人に対しては、今までも逢った時にはこうも弁解しああも言ってと考えていたことは皆忘れてしまい、嘘は恐ろしくなり真実の話をした。
|
【尼君なども】- 以下「わづらはしう」あたりまで、右近の心中の思い。
【あやしきことの筋にこそ】- 匂宮との関係。『集成』は「不埒なこと」。『完訳』は「匂宮との秘密の情事」と注す。
|
|
第二段 薫、真相を聞きただす
|
| 4.2.1 |
|
驚き呆れて、思いもかけなかったことなので、一言も暫くの間はおっしゃれない。
|
これは薫の想像にものぼらなかったことであったから、驚きのためにしばらくはものも言われなかった。
|
【あさましう、思しかけぬ筋なるに】- 入水事件をさす。
|
| 4.2.2 |
「さらにあらじとおぼゆるかな。なべての人の思ひ言ふことをも、こよなく言少なに、おほどかなりし人は、いかでかさるおどろおどろしきことは思ひ立つべきぞ。いかなるさまに、この人びと、もてなして言ふにか」 |
「難とも信じがたいと思われることだ。
普通誰でもが思ったり言ったりすることも、この上なく言葉少なく、おっとりしていた人が、どうしてそのような恐ろしいことを思い立ったのだろう。
どのような様子のために、この人びとは、取り繕って言うのであろうか」
|
それを真実とは信じがたい、普通の人が煩悶をしたり、悲しんだりする場合にも多くは口に言わずおおようにしていた人にどうしてそんな恐ろしいことが思い立たれるか、そのほかの事実を自分へこう取り繕って言うのではなかろうか
|
【さらにあらじと】- 以下「いふにかあらむ」まで、薫の心中の思い。
【いかなるさまに】- 『集成』は「入水ではなくて、匂宮がどこかへ隠しているのではないか、と疑う」と注す。
【言ふにか】- 大島本は「いふにか」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「言ふにかあらむ」と「あらむ」を補訂する。『新大系』は底本のまま「言ふにか」とする。
|
| 4.2.3 |
|
とお気持ちもいっそう困惑なさるが、「宮もお嘆きになっていた様子、まことにはっきりしていたし、事の成り行きも、そんなそ知らぬふりを装った態度は、自然と分かってしまうものだから、このようにお出でになったにつけても、悲しくてやりきれないことを、身分の上下の人が皆集まって泣き騒いでいるのだから」と、お聞きになると、
|
と、いっそう心の乱れてゆくのを覚える薫であったが、しかしあの人をお隠しになったようでもなく宮が悲しんでおいでになったことは著しいことであったし、この家の様子も、死が作り事であれば自然に気配が違っているはずであるのに、自分の来たのを見ると人は上から下まで集まって来て泣き騒いでいるではないかと考え、
|
【宮も思し嘆きたる】- 以下「泣き騒ぐを」まで、薫の心中の思い。
【事のありさまも】- 大島本は「ことの」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「ここの」と校訂する。『新大系』は底本のまま「事の」とする。
【かくおはしましたるにつけても】- 主語は薫。心中文に語り手の薫に対する敬語が紛れ込んだ表現。
|
| 4.2.4 |
「御供に具して失せたる人やある。なほ、ありけむさまをたしかに言へ。我をおろかに思ひて背きたまふことは、よもあらじとなむ思ふ。いかやうなる、たちまちに、言ひ知らぬことありてか、さるわざはしたまはむ。我なむえ信ずまじき」 |
「お供をしていなくなった人はいないか。
さらに、その時の状況をはっきり言いなさい。
わたしを薄情だと思ってお裏切になることは、決してないと思う。
どのような、急に、わけの分からないことがあってか、そのようなことをなさったのだろう。
わたしは信じることができない」
|
「奥さんといっしょに行ってしまった人があるか、もっと詳細にその時のことを言ってくれ。私に誠意がないからほかへ行ってしまう気にあの人がなったとは思われない。何もなくてにわかにそんなことができるか、私は信じることができない」
|
【御供に具して】- 以下「え信ずまじき」まで、薫の詞。『集成』は「逃げ隠れているなら、供の女房を連れているはず」と注す。
|
| 4.2.5 |
|
とおっしゃるので、「一段として、心配していたとおりであったよ」と厄介なことに思って、
|
と言った。予期した詰問であると右近は恐れた。
|
【いとどしく】- 大島本は「いとゝしく」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「いといとほしく」と校訂。『新大系』は底本のまま「いとどしく」とする。『集成』は「大層困ってしまって」。『完訳』は「右近は大将がおいたわしくて」と訳す。
【さればよ】- 『完訳』は「薫の詰問は懸念どおり」と注す。
|
| 4.2.6 |
|
「自然とお耳に入っておりましょう。
初めから不如意な境遇でお育ちになりました方で、人里離れたお住まいで暮らした後は、いつとなく物思いばかりをなさっていたようでしたが、たまにこのようにお越しになりますのを、お待ち申し上げなさることで、もともとのお身の上の不幸までをお慰めになりながら、のんびりとした状態で、時々お逢い申し上げなされるように、早く早くとばかり、言葉に出してはおっしゃいませんが、ずっとお思いでいらしたらしいのを、そのご念願が叶うように承ったことがございましたのに、こうしてお仕えする者どもも、嬉しいことと存じて準備致し、あの筑波山の母君も、やっとのことで念願が叶ったような様子で、お移りになることをご準備なさっていたのに、納得できないお手紙がございましたので、ここの宿直などに仕える者どもも、女房たちがふしだらなようだ、などと、厳しくご命令なさったことなどを申して、物の情理をわきまえない荒々しいのは田舎者どもの、間違いでもあったかのように取り扱い申すことがございましたが、その後、長らくお手紙などもございませんでしたので、情けない身の上だとばかり、幼かった時から思い知っていたが、何とか一人前にしようとばかり、いろいろとお世話なさっていた母君が、なまじその事によって、世間の物笑いになったら、どんなに嘆くだろう、などと悪いほうに考えて、いつも嘆いていらっしゃいました。
|
「もうおわかりになっていらっしゃいましたでしょうが、宮様の姫君としてお育てられになったのではございませんでしたから、心でいろいろ御苦労をなされた方でございます。それが寂しいお住まいをなさることになりましてからはいつからともなく物思いをなさいますことになりましたのですが、たまさかにもせよあなた様がおいでになります時のお喜びで過去の不幸も御自身でお慰めになりながらも始終お逢いあそばすことのできますような日の出現を、口に出してはおっしゃいませんでしたが始終そればかり待っておいでになったふうでございました。ようやくそのお望みのかないます御様子と私どもにもうかがえますことがございまして、うれしく存じて御用意にかかっておりまして、常陸守の奥様もやっとお喜びになることができた御様子でお仕度のことなどをあちらからもいろいろとお世話をしていらっしゃいましたころになりまして、姫君には御合点のゆかぬような御消息がございましたそうで、それと同時に宿直をいたしている侍たちが女房の中に品行の修まらぬ者があるとか京のお邸で申されたとか言いだしまして、ものの理解のない田舎の人が無遠慮なことをよく言ってまいったりすることになりますし、あなた様から久しくおたよりもございませんことなどから、自分は薄命なものだと小さい時から知っていたのを、人並みの幸福を得させようと心を砕いておいでになる母君が、また今になって自分が世間の笑われものになったりしては、どんなに力を落とすだろうと、こんなお心持ちをそれとなく私どもへ始終言ってお歎きになりました。
|
【おのづから聞こし召しけむ】- 以下「はべるなるものを」まで、右近の詞。
【時々も見たてまつらせたまふべきやうには】- 大島本は「やうにハ」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「やうに」と「は」を削除する。『新大系』は底本のまま「やうに」とする。
【かの筑波山も】- 浮舟の母。夫が常陸介なのでこう呼ぶ。また「筑波山」は常陸国の歌枕。風情ある言い方。
【渡らせたまはむことを】- 浮舟が京の薫のもとに。
【心得ぬ御消息はべりけるに】- 『完訳』は「納得できぬ文。薫からの「波こゆる--」と心変りを非難された。それが浮舟を一方的に追いつめた、の気持もこもる」と注す。
【この宿直仕うまつる】- 大島本は「このとのゐ」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「宿直など」と「など」を補訂する。『新大系』は底本のまま「宿直」とする。
【荒々しきは田舎人どもの】- 大島本は「あら/\しきハ」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「荒々しき」と「は」を削除する。『新大系』は底本のまま「荒々しきは」とする。
【あやしきさまにとりなしきこゆることども】- 『集成』は「おかしな具合に歪めて推測申し上げることもいろいろございましたが。宿直人が気をまわして山荘の警備を厳重にしたことをいう」と注す。
【御消息などもはべらざりしに】- 薫からの手紙。接続助詞「に」原因理由の意をこめた順接条件。下文の浮舟の悲観・絶望の気持ちへと続く。
【よろづに思ひ扱ひたまふ】- 大島本は「思ひあつかひ」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「あつかひ」と「思ひ」を削除する。『新大系』は底本のまま「思ひあつかひ」とする。
【人笑はれになりては】- 大島本は「なりてハ」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「なりはてば」と「は」を補訂する。『新大系』は底本のまま「なりては」とする。
【などおもむけてなむ】- 『完訳』は「悪いほうに考えて、の気持」と注す。
|
| 4.2.7 |
|
その方面より他に、何があろうかと、考えめぐらして見ますに、思い当たることはございません。
鬼などがお隠し申したとしても、少しは残るものがございますと聞いておりますものを」
|
それ以外に何があるかと考えましても、何も思い当たることはございません。鬼が隠すことがありましても片端くらいは残すでしょうのに」
|
【その筋よりほかに】- 『完訳』は「薫の不信をかった以外には」と注す。
【いささか残る所もはべるなるものを】- 『完訳』は「証拠を残していくもの。入水以外には考えられぬという気持」と注す。「なる」伝聞推定の助動詞。
|
| 4.2.8 |
|
と言って、泣く様子もたいそうなので、「どのようなことでか」とお疑いになっていた気持ちも消えて、お涙が抑えがたい。
|
と言って右近の泣く様子は、見ていても堪えられなくなるほどのものであったから、宮との例の恋愛の事実は無根でないらしいと悟った時から少し紛れていた薫の悲しみがよみがえり、せきあえぬふうにこの人も泣いた。
|
【紛れつる御心も失せて】- 匂宮が隠しているのではないかと疑って紛らされていた悲しみの気持ち。わずかの希望も消え失せる。
|
|
第三段 薫、匂宮と浮舟の関係を知る
|
| 4.3.1 |
|
「わたしは思いどおりに振る舞うこともできず、何事も目立ってしまう身分であるから、気がかりだと思う時にも、いずれ近くに迎えて、何の不満足もなく、世間体もよく持てなして、将来末長く添い遂げよう、とはやる心を抑えながら過ごして来たが、冷淡だとおとりになったのは、かえって他に分ける心がおありだったのだろう、と思われます。
|
「自分の身が自分の思っているとおりにはできず、晴れがましい身の上になってしまったのだから、逢って慰めたいという心の起こる時も、そのうち近くへ呼び寄せ、家の妻にも不安を覚えさせないようにしてから、長い将来を幸福にしたいと、自分をおさえてきたのを、誠意がなかったように思われたのも、かえってあの人に二心があったからではないかという気がされる。
|
【我は心に身をもまかせず】- 以下「さらにな隠しそ」まで、薫の詞。
【今近くて】- 近々京に浮舟を迎えて、の意。
【おろかに見なしたまひつらむこそ】- 大島本は「給つらん」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「たまひけむ」と校訂する。『新大系』は底本のまま「給つらん」とする。主語は浮舟。
【分くる方ありける】- 『集成』は「悠長な自分より、熱心だと思う恋人がいたからだろうと、匂宮のことをほのめかす」と注す。
|
| 4.3.2 |
今は、かくだに言はじと思へど、また人の聞かばこそあらめ。宮の御ことよ。いつよりありそめけむ。さやうなるにつけてや、いとかたはに、人の心を惑はしたまふ宮なれば、常にあひ見たてまつらぬ嘆きに、身をも失ひたまへる、となむ思ふ。なほ、言へ。我には、さらにな隠しそ」 |
今さら、こんなことは言うまいと思うが、他に人が聞いているのならともかくだが。
宮のお事ですよ。
いつから始まったのでしょうか。
そのようなことが原因でか、まことに不都合にも、女の心を迷わしなさる宮だから、いつもお逢いできない嘆きで、身をなきものにされたのか、と思う。
ぜひ、言え。
わたしには、少しも隠すな」
|
もうそんなことは言わずにおこうと思ったが、だれも聞いていないのだから事実を私に聞かせてくれ、それは兵部卿の宮様のことだ。いつごろからのことだったのか、恋愛の技術には長じておいでになる方だから、女の心をよくお引きつけになって、始終お逢いできぬ歎きがこうさせておしまいになり、命もなくしたのではないかと思う。隠さずに真実を言ってくれ。自分に少しの欺瞞もないことを言ってほしい」
|
【いとかたはに】- 『集成』は「全くけしからぬほど」。『完訳』は「まったく不都合にも」と訳す。
【人の心を】- 女性の心を。
|
| 4.3.3 |
|
とおっしゃると、「確かな事をお聞きになっているのだ」と、とても困ってしまって、
|
と薫の言うのを聞いて、確かなことを皆知っておしまいになったようである、この方もお気の毒であるし、故人もおかわいそうであると右近は思った。
|
【たしかにこそは聞きたまひてけれ】- 右近の心中。
【いといとほしくて】- 『集成』は「とても困ってしまって」。『完訳』は「まことにお気の毒に思われるので」と訳す。
|
| 4.3.4 |
|
「まことに情けないことをお聞きになったようでございます。
右近めもお側に伺候していません折はございませんでしたものを」
|
「情けないことをお聞きあそばしたものでございますね。右近がおそばにおらぬ時といってはございませんでしたのに」
|
【いと心憂きことを】- 以下「はべらぬものを」まで、右近の詞。浮舟身辺の出来事は委細に見届けている自分の話こそ真実だ、という含み。
|
| 4.3.5 |
と眺めやすらひて、
|
と物思いにふけりためらって、
|
と言い、右近はしばらく黙っていたが、
|
|
| 4.3.6 |
|
「自然とお聞き及びになったことでございましょう。
この宮の上のお所に、こっそりとお行きになったとき、呆れたことに思いがけない間に、お入りになって来ましたが、たいそう手厳しいことを申し上げまして、お出になりました。
その事に恐がりなさって、あの見苦しうございました隠れ家にお移りになったのです。
|
「そんなこともお聞きになっていらっしゃいましょうが、お姉様の二条の院の奥様の所へ行っておいでになりました時、思いがけずそのお部屋へ宮様がお見えになったことがあるのでございますが、失礼なことも皆でいろいろ申し上げましてお立ち去りを願ったのでございました。実はそれを恐ろしいことに思召して、あの三条の仮屋のような所にしばらくお住いになったのでございます。
|
【おのづから聞こし召しけむ】- 以下「見たまへず」まで、右近の詞。
【この宮の上の御方に】- 京の二条院の中君の所に。
【入りおはしたりしかど】- 大島本は「いりおハしたりしかと」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「入りおはしましたりしかど」と「まし」を補訂する。『新大系』は底本のまま「入りおはしたりしかど」とする。
【いみじきことを聞こえさせはべりて】- 『集成』は「お側の女房たちの才覚で事無きを得た、と言う」と注す。
【出でさせたまひにき】- 主語は匂宮。
【それに懼ぢたまひて】- 主語は浮舟。
【かのあやしくはべりし所に】- 三条の小家。隠れ家。
|
| 4.3.7 |
|
その後は、噂としてでも知られまい、とお思いになって終わったのを、どうしてお耳にあそばしたのでしょうか。
ちょうど、この二月頃から、お便りを頂戴するようになりましたのでしょう。
お手紙は、とても頻繁にございましたようですが、御覧になることもございませんでした。
まことに恐れ多く、失礼な事になりましょうと、右近めなどが申し上げましたので、一度か二度はお返事申し上げましたでしょうか。
それ以外の事は存じません」
|
それからは決してお在処をお知らせしますまいと警戒をいたしておりましたのに、どういたしましたことか今年の二月ごろからおたよりがまいるようになりました。お手紙はたびたびまいったのですが、丁寧にお頼みになることもございませんでしたのを、もったいないことで、そうしてお置きになりますことはかえって悪い結果を生みますと私などがお勧めいたしましたので、一度か二度はお返事をあそばしたことがあったようでございます。それ以外のことは何もございません」
|
【音にも聞こえじ、と】- 匂宮に噂としても知られまい、の意。
【この如月ばかりより】- 『完訳』は「匂宮が浮舟の宇治の住いをかぎつけたのは一月上旬、同月下旬に宇治行を実行。事実を意識的にぼかして過小の言い方をした」と注す。
【訪れきこえたまふべし】- 大島本は「をとつれきこえ給へし」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「訪れきこえさせたまひし」と校訂する。『新大系』は底本のまま「をとづきこえ給べし」とする。
【たびたびはべりしかど】- 大島本は「侍しかと」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「はべめりしかど」と「めり」を補訂する。『新大系』は底本のまま「侍しかど」とする。
【うたてあるやうに】- 大島本は「ミ(ミ$う<朱>)たてあるやうに」とある。すなわち「み」をミセケチにして「う」と訂正する。『集成』『完本』は諸本に従って「なかなかうたてあるやうに」と「なかなか」を補訂する。『新大系』は底本のまま「うたてあるやうに」とする。
【それより他のことは見たまへず】- 『集成』は「きっぱりと密通の事実を否定する」。『完訳』は「密通などなかったとする言いぶり。事実をまげて語り収める」と注す。
|
| 4.3.8 |
と聞こえさす。
|
と申し上げる。
|
こう言った。
|
|
| 4.3.9 |
|
「このように言うに決まっていることなのだ。
無理に問い質すのも気の毒だから」と、つくづくと物思いに耽りながら、
|
そう言うべきことである、しいてそれ以上を聞くのもこの人がかわいそうであると薫は思い、じっとひと所をながめながら、
|
【かうぞ言はむかし】- 『集成』は「以下、薫の心中に添って書く」。『完訳』は「こんな場合はこう答えるもの。主人を弁護し自分たち女房の過失を隠のが女房の常」と注す。
|
| 4.3.10 |
|
「宮をめったにないいとしい方と思い申し上げても、自分のほうをやはりいい加減には思っていなかったために、どうしたらよいか分からなくなって、頼りない考えで、この川に近いのを手だてにして、思いついたのであろう。
自分がここに放って置かなかったら、たいそうつらい生活であっても、どうして、必ず深い谷を探して身投げをしなかっただろうに」
|
宮をお愛ししたのであろうが、自分をもおろそかには思えなかったらしい、迷い迷って死におもむいたのであろう、自分がこうした寂しい場所へさえ置かなんだならば、世の中の波にもまれることはあっても、自殺までもすることはなかったであろうと思うと、
|
【宮をめづらしく】- 以下「求め出でまし」まで、薫の心中の思い。
【いと明らむるところなく】- 『集成』は「〔もともと〕はっきりした考えもなく」。『完訳』は「浮舟はまるで判断力に乏しく」と注す。
【さし放ち据ゑざらましかば--深き谷をも求め出でまし】- 反実仮想の構文。浮舟を放置していたことに対する後悔。 【深き谷をも求め】-『紫明抄』は「世の中の憂きたびごとに身を投げば深き谷こそ浅くなりけれ」(古今集俳諧、一〇六一、読人しらず)を指摘。
|
| 4.3.11 |
|
と、「ひどく嫌な川の名の縁であるよ」と、この川が疎ましく思われなさること、甚だしい。
長年、恋しいと思われなさっていた所で、荒々しい山路を行き来したのも、今では、また情けなくて、この里の名を聞くのさえ耐えがたい気がなさる。
|
この川のあったがために悲しい結末を見ることになったのであると、宇治の流れを憎く思う薫であった。恋しい人の縁で荒い山路を往復することを何とも思わなかった薫は、この時になって宇治という名を聞くことさえいやであるように思った。
|
【いみじう憂き水の契りかな】- 薫の感想。
【あはれと思ひそめたりし方にて】- 大島本は「思そめたりし」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「思ひそめてし」と校訂する。『新大系』は底本のまま「思そめたりし」とする。
【この里の名をだに】- 宇治の地名。「宇治」は「憂し」に通じる。
|
|
第四段 薫、宇治の過去を追懐す
|
| 4.4.1 |
|
「宮の上が、おっしゃり始めた、人形と名付けたのまでが不吉で、ただ、自分の過失によって亡くした人である」と考え続けて行くと、「母親がやはり身分が軽いので、葬送もとても風変わりに、簡略にしたのであろう」と合点が行かず思っていたが、詳しくお聞きになると、
|
宮の夫人があの姫君のことを初めに戯れて人型と名づけて言ったのも、川へ流れてゆく前兆を作ったものであったかと思うと、何にもせよ自分の軽率さから死なせたという責任も感じられた。母の現在の身分が身分であったから、葬式なども簡単にしてしまったのであろうと不快に思ったこともくわしく聞いたことによって、そうした想像をしたことが気の毒になり、
|
【宮の上の】- 中君が。
【人形とつけそめたりしさへ】- 「人形」は祓いの後に水に流されもの。
【ただ、わが過ちに失ひつる人なり】- 薫の後悔の念。
【母のなほ】- 以下「しなしけるなめり」まで、薫の心中の思い。
【後の後見も】- 死後の世話、葬送の儀式。
|
| 4.4.2 |
「いかに思ふらむ。さばかりの人の子にては、いとめでたかりし人を、忍びたることはかならずしもえ知らで、わがゆかりにいかなることのありけるならむ、とぞ思ふなるらむかし」 |
「どのように思っているだろう。
あの程度の身分の子としては、まことに結構であった人を、秘密の事は必ずしも知らないで、自分との縁でどのようなことがあったのであろう、と思っているであろう」
|
母としてはどんなに悲しがっていることであろう、あの身分の母の子としてはりっぱ過ぎた姫君であったのを、陰のことは知らずに自分との縁により、姫君が煩悶をしたこともあったとして悲しんでいることかもしれぬ
|
【いかに思ふらむ】- 以下「思ふなるらむかし」まで、薫の心中の思い。浮舟の母の心中を忖度。
【わがゆかりに】- 自分の縁者、薫の正室女二宮の方から何かあったのではないか、と。
|
| 4.4.3 |
|
などと、いろいろとお気の毒にお思いになる。
穢れということはないであろうが、お供の人の目もあるので、お上がりにならず、お車の榻を召して、妻戸の前で座っていたのも、見苦しいので、たいそう茂った樹の下で、苔をお敷物として、暫くお座りになった。
「今ではここに来て見ることさえつらいことであろう」とばかり、まわりを御覧になって、
|
などと同情がされるのであった。穢れというものはこの家にないはずであるが、供の人たちへの手前もあって家の上へは上がらず車の榻という台を腰掛けにして妻戸の前で今まで薫は右近と語っていたのである。これを長く続けているのも見苦しく思われて茂った木の下の苔の上を座にしてしばらく休んでいた。もう山荘に来てみることも心を悲しくするばかりであろうから、今後来ることはないであろうと思い、その辺を見まわして、
|
【穢らひといふことは】- 浮舟が死んだ場所の穢れ。
【御供の人目もあれば】- 世間や供人には病死と言ってある。
【昇りたまはで】- 穢れに触れないよう室内に上がらない。
【今は】- 以下「心憂かるべし」まで、薫の思い。
|
|
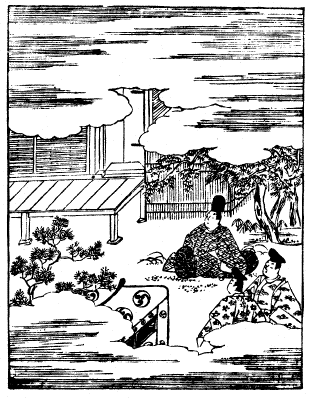 |
| 4.4.4 |
|
「わたしもまた、
嫌なこの古里を離れて、荒れてしまったら
|
われもまたうきふるさとをあれはてば
たれ宿り木の蔭をしのばん
|
【我もまた憂き古里を荒れはてば--誰れ宿り木の蔭をしのばむ】- 薫の独詠歌。八宮、大君、中君に続いて自分薫までが、の意。
|
| 4.4.5 |
|
阿闍梨は、今では律師になっていた。
呼び寄せて、この法事の事をお命じ置きになる。
念仏僧の数を増やしたりなどおさせになる。
「罪障のとても深いことだ」とお思いになると、その軽くなることをするように、七日七日ごとにお経や仏を供養するようになど、こまごまとお命じになって、たいそう暗くなったのでお帰りになるのも、「もしも生きていたら、今夜のうちに帰ろうか」とばかりである。
|
こんな歌を口ずさんだ。以前の阿闍梨も今は律師になっていた。その人を呼び寄せて浮舟の法事のことを大将は指図していた。念仏の僧の数を増させることなども命じたのであった。自殺者の罪の重いことを考えてその滅罪の方法も大将はとりたい、七日七日に経巻と仏像の供養をすることなども言い置いて、暗くなったのに帰って行く時、あの人がいたならば今夜は帰ることでないのであると悲しかった。
|
【阿闍梨、今は律師なりけり】- 律師は、僧正、僧都に次ぐ地位。
【罪いと深かなるわざ】- 薫の思い。「自殺者殺生之随一也」(河海抄所引)。「なる」伝聞推定の助動詞。
【あらましかば、今宵帰らましやは】- 薫の思い。浮舟が生きていたら。反実仮想の構文。反語表現。
|
| 4.4.6 |
尼君に消息せさせたまへれど、
|
尼君にも挨拶をおさせになったが、
|
尼君の所へ人をやったが、
|
|
| 4.4.7 |
|
「とてもとても不吉な身だとばかり存じられ沈み込んで、ますます何も考えられず、茫然として、臥せっております」
|
「私と申すものが凶事のしるしのように思われまして、心をめいらせておりますこのごろは、以前よりもいっそうぼけてしまいまして、うつ伏しに寝んだままでおります」
|
【いともいとも】- 以下「臥してはべる」まで、弁尼の返事。
【うつぶし臥して】- 『河海抄』は「世を厭ひ木のもとごとに立ちよりてうつぶし染めの麻の衣なり」(古今集雑体、一〇六八、読人しらず)を指摘。
|
| 4.4.8 |
と聞こえて、出で来ねば、しひても立ち寄りたまはず。
|
と申し上げて、出て来ないので、無理してはお立ち寄りにならない。
|
と言い、話しに出てこなかったので、しいて逢おうとは言わなかった。
|
|
| 4.4.9 |
道すがら、とく迎へ取りたまはずなりにけること悔しう、水の音の聞こゆる限りは、心のみ騷ぎたまひて、「骸をだに尋ねず、あさましくてもやみぬるかな。いかなるさまにて、いづれの底のうつせに混じりけむ」など、やる方なく思す。 |
道中、早くお迎えしなかったことが悔しく、川の音が聞こえる間は、心も落ち着きなさらず、「亡骸さえも捜さず、情けないことに終わってしまったなあ。
どのような状態で、どこの川底に貝殻とともにいるのであろうか」などと、やるせなくお思いになる。
|
途すがら薫は浮舟を早く京へ迎えなかったことの後悔ばかりを覚えて、水の音の聞こえてくる間は心が騒いでしかたがなかった。遺骸だけでも捜してやることをしなかったと残念でならないのであった。どんなふうになってどこの海の底の貝殻に混じってしまったかと思うと遣瀬なく悲しいのであった。
|
【骸をだに】- 以下「混じりけむ」まで、薫の心中の思い。
【いづれの底のうつせに混じりけむ】- 大島本は「ましりけむ」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「まじりにけむ」と「に」を補訂する。『新大系』は底本のまま「まじりけむ」とする。「うつせ」は「うつせ貝」、空になった貝。『弄花抄』は「今日今日とわが待つ君は石川の貝に交じりてありといはずやも」(万葉集巻二、依羅娘子)を指摘。
|
|
第五段 薫、浮舟の母に手紙す
|
| 4.5.1 |
|
あの母君は、京で子を産む予定の娘のことによって、穢れを騒ぐので、いつものわが家にも行かず、心ならずも旅寝ばかり続けて、思い慰む時もないので、「また、この娘もどうなるのだろうか」と心配するが、無事に出産したのであった。
穢れているので、立ち寄ることもできず、残りの家族のことも考えられず、茫然として過ごしていると、大将殿からお使いがこっそりと来た。
何も考えられない気持ちにも、たいそう嬉しく感動した。
|
常陸夫人は京に産をする娘のあるために潔斎潔斎ときびしく言われる家へははいれないで、他のところにいて悲しみの休む間もないのである、その娘もまたどうなることかと不安だったがそれは安産した。穢れがあってはこれも見に行くことができないのである、そのほかの子供たちのことも皆忘れたようになり、茫然としている時に右大将からそっと使いが来て手紙をもらった。ぼけている心にもそれはうれしかったが、また悲しくもなった。
|
【慎み騒げば】- 京の娘は出産を控えて死穢に触れることを避けている。
【例の家にも】- 夫常陸介の家。
【旅居のみして】- 『集成』は「三条の小家にでもいるのであろう」と注す。
【残りの人びとの上も】- 浮舟以外の娘たちの身の上。
|
| 4.5.2 |
「あさましきことは、まづ聞こえむと思ひたまへしを、心ものどまらず、目もくらき心地して、まいていかなる闇にか惑はれたまふらむと、そのほどを過ぐしつるに、はかなくて日ごろも経にけることをなむ。世の常なさも、いとど思ひのどめむ方なくのみはべるを、思ひの外にもながらへば、過ぎにし名残とは、かならずさるべきことにも尋ねたまへ」 |
「あまりの出来事に、さっそくお見舞い申そうと存じてましたが、気持ちも落ち着かず、目も涙に暮れた心地がして、それ以上にどんなにか心が闇に暮れていらっしゃるだろうかと、暫く待っていましたうちに、あっという間に幾日もたってしまったこと。
世の中の無常も、ますます呑気に構えていられない気がしますが、案外に生き永らえましたら、亡くなった方の縁者として、きっと何かの時には声をかけてください」
|
思いがけぬ不幸にあい、まずあなたに悲しみを訴えたいと思ったのですが、心が落ち着かず、また涙に目も暗くなる気がして実行はできませんでした。ましてあなたはどんなに悲しんでおいでになることだろう。涙に沈んでおいでになることだろうと思いますと、手紙をあげてもお読みにはなれまいと遠慮も申しているうちに日がずんずんとたちました。人生の常なさがことごとに形となってわれらをおびやかします。この悲しみにも堪える力の許されて、私が生きていましたなら、故人の縁のあった者として何かのことは御相談もしてください。
|
【あさましきことは】- 以下「尋ねたまへ」まで、薫の手紙。浮舟の死をさす。
【闇にか惑はれたまふらむと】- 『河海抄』は「人の親の心は闇にあらねども子を思ふ道に惑ひぬるかな」(後撰集雑一、一一〇二、藤原兼輔)を指摘。
【過ぎにし名残とは】- 『集成』は「亡き人(浮舟)の形見とも思われて」と注す。
|
| 4.5.3 |
|
などと、こまごまとお書きになって、お使いには、あの大蔵大輔を差し向けなさった。
|
などとこまやかな心で書かれたものだった。使いにはあの大蔵大輔が来たのである。
|
【かの大蔵大輔】- 薫の家司、仲信。
|
| 4.5.4 |
「心のどかによろづを思ひつつ、年ごろにさへなりにけるほど、かならずしも心ざしあるやうには見たまはざりけむ。されど、今より後、何ごとにつけても、かならず忘れきこえじ。また、さやうにを人知れず思ひ置きたまへ。幼き人どももあなるを、朝廷に仕うまつらむにも、かならず後見思ふべくなむ」 |
「悠長に万事を構えて、幾年もたってしまったので、必ずしも誠意があるようには御覧にならなかったでしょう。
けれども、今から後は、何事につけても、必ずお忘れ申し上げまい。
また、そのように内々にお思いおきください。
幼いお子様もいると聞いていますが、朝廷にお仕えなさるにつけても、必ず力添えしましょう」
|
「すべてを気長に考えていたものですから、かなり月日はたっていても、必ずしも私を誠意のある婿とは思ってくださらなかったでしょう。しかし今は何につけてもあなたの御一家のことは念頭に置いて忘れますまい。またそのように内々信じてくだすって、お力になるものと思っていてください。小さい息子さんたちもあるそうですが、仕官をおさせになる場合には必ず後援をするつもりで私はいます」
|
【心のどかに】- 以下「思ふべくなむ」まで、薫が仲信に伝えさせた口上。
【年ごろにさへなりにけるほど】- 昨秋から今年の四月までの間。浮舟を宇治に置いておいた間。
|
| 4.5.5 |
など、言葉にものたまへり。
|
などと、口頭でもおっしゃった。
|
と、言葉でも伝えさせた。
|
|
|
第六段 浮舟の母からの返書
|
| 4.6.1 |
|
たいそう厳重に慎まなくてもよい穢れなので、「大して穢れに触れていません」などと言って、強いて招じ入れた。
お返事は、泣きながら書く。
|
ひどく忌む性質の穢れでもないからと言って、夫人はしいて大輔を座敷へ招じた。そして返事を泣く泣く書いていた。
|
【いたくしも忌むまじき穢らひなれば】- 浮舟の死は邸宅内での死ではないので。
【深うしも触れはべらず】- 大島本は「ふかうしも」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「深うも」と「し」を削除する。『新大系』は底本のまま「深うしも」とする。浮舟母の詞。
【御返り】- 浮舟母から薫への返書。
|
| 4.6.2 |
「いみじきことに死なれはべらぬ命を、心憂く思うたまへ嘆きはべるに、かかる仰せ言見はべるべかりけるにや、となむ。 |
「大変な悲しみにも死ぬことができません命を、情けなく存じ嘆いておりますが、このような仰せ言を拝見するためだったのでしょうか、と思います。
|
悲しい思いをいたしますだけでは死なれませぬ命を歎いております私へ、もったいないおいたわりの言葉などのいただけますとは夢想もいたしませんでした。
|
【いみじきことに】- 以下「やすからずなむ」まで、浮舟母の返書。
|
| 4.6.3 |
|
長年、心細い様子を拝見しながら、それは一人前でない身のつたなさのせいであると存じましたが、恐れ多いお言葉を、将来末長くご信頼申し上げておりましたが、何とも言いようのない事になってしまって、里の名の縁もまことに情けなく悲しうございます。
|
故人がおりました間、心細い様子は見ておりながら、それは私自身の無力からであると存じまして、ただおそれ多い行く末かけてのあたたかいお言葉一つを頼みにいたしておりましたが、死なせましてあとではあの地との因縁が悲しくばかり思われてなりません。
|
【かたじけなき御一言を】- 薫が浮舟を京の邸に迎えようと言ったこと。
【頼みきこえはべりしに】- 大島本は「きこえ侍しに」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「きこえさせ」と「させ」を補訂する。『新大系』は底本のまま「きこえ」とする。
【里の契りも】- 宇治という地名。「憂し」に通じる。
|
| 4.6.4 |
|
いろいろと嬉しい仰せ言を戴き、寿命も延びまして、もう暫く長生きしましたら、やはり、お頼り申し上げますこと、と存じますにつけても、目の前が涙に暮れまして、何事も申し上げ切れません」
|
いろいろと将来のことでうれしい仰せを賜わりましたことで、命の延びることにもなりまして、今しばらく生きてまいれますことになりましたら、その息子たちのことであなた様のお力におすがり申し上げる日もあろうと思いますにつけましても、あの人の亡くなってありませぬ現在の悲しみに目も涙で暗くなるばかりでございまして、感謝の思いも書き尽くすことができませんのをお許しください。
|
【さまざまにうれしき仰せ言に】- 自分のことや子供たちの将来のことに目をかけてくれるという言葉に。
【目の前の涙にくれて】- 大島本は「なミたにくれて」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「くれはべりて」と「はべり」を補訂する。『新大系』は底本のまま「くれて」とする。『全書』は「行く先を知らぬ涙の悲しきはただ目の前に落つるなりけり」(後撰集、離別羇旅、一三三三、源済)を指摘。
|
| 4.6.5 |
|
などと書いた。
お使いに、普通の禄では見苦しいときである。
不満足な気もするにちがいないので、あの君に差し上げようと用意して持っていた、立派な斑犀の帯や、太刀の素晴らしいのなどを、袋に入れて、車に乗る時に、
|
などと書いた。使いへの贈り物に普通の品を出すべき場合ではないし、またそれだけでは不満足な感じをあとでみずから覚えさせられることであろうからと思い、貴重品として将来は故人の姫君に与えようと考えていた高級な斑犀の石帯とすぐれた太刀などを袋に入れ、車へ使いが乗る時いっしょに積ませた。
|
【かの君に】- 浮舟に。
【よき班犀の帯、太刀のをかしきなど】- 斑犀の帯、太刀。『集成』は「浮舟にさし上げて、家臣の料などに与えてもらう積りだったのであろう。「斑犀の帯」は、斑文のある犀角を飾りにした石帯。四位五位の束帯に用いる」と注す。
|
| 4.6.6 |
|
「これは故人のお志です」
|
「これは故人の志でございます」
|
【これは昔の人の御心ざしなり】- 浮舟母の詞。 【昔の人】-故人浮舟。
|
| 4.6.7 |
|
と言って、贈らせた。
|
と言わせて贈ったのであった。
|
【贈らせてけり】- 召使をして贈らせた。使者に帰り際に贈り物ををする作法。
|
| 4.6.8 |
殿に御覧ぜさすれば、
|
殿に御覧に入れると、
|
帰った使いは贈られた品を大将に見せると、
|
|
| 4.6.9 |
|
「今さらしなくてもよいことをしたものだな」
|
「よけいなことをするものだね」
|
【いとすぞろなるわざかな】- 大島本は「すそろなる」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「すずろなる」と校訂する。『新大系』は底本のまま「すぞろなる」とする。薫の詞。
|
| 4.6.10 |
|
とおっしゃる。
口上には、
|
と薫は言った。使いの伝えた言葉は、
|
【言葉には】- 口上には、の意。
|
| 4.6.11 |
|
「ご自身がお会いくださって、ひどく泣きながらいろいろなことをおっしゃって、幼い子のことまでご心配になったのが、まこともったいなくて、また一人前でもない身分の者にとっては、かえってまことに恥ずかしく、誰にもどのような関係でなどとは知らせませんで、不出来な子供たちをも皆参上させまして、お仕えさせましょう、と言っておりました」
|
「奥さんが自身でお逢いになりまして、非常に悲しい御様子で、泣く泣くいろいろの話をなさいました。若い息子たちのことまでも御親切におっしゃっていただきましたことはもったいないことで、うれしく存じますが、しかしながらまたあまりに恐縮な当方の身分でございますから、人には何のためにとは絶対に知らせぬようにいたしまして、できのよろしい子供たちだけを皆お邸へ差し上げることにしましょうということでした」
|
【みづから会ひはべりたうびて】- 浮舟母自身が。
【幼き者どもの】- 以下「さぶらはせむ」まで、浮舟母の詞を引用。
【恥づかしう】- 大島本は「はつかしう」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「はづかしうなむ」「恥づかしくなむ」と「なむ」を補訂する。『新大系』は底本のまま「はづかしう」とする。
【人に何ゆゑなどは知らせはべらで】- 『完訳』は「浮舟が薫の妻妾にまでならなかったことからの配慮」と注す。
【あやしきさまどもを】- 浮舟の異母弟たちを謙遜していう。
|
| 4.6.12 |
と聞こゆ。
|
と申し上げる。
|
|
|
| 4.6.13 |
|
「なるほど、見栄えのしない親戚付き合いのようだが、帝にも、その程度の身分の人の娘を差し上げなかったことがあろうか。
それに、前世からの因縁で、寵愛なさるのを、人が非難することであろうか。
臣下では、また、卑しい女や、いったん結婚した女などをもっている例は多かった。
|
その言葉どおりに奇妙な親戚関係と人には見られることであろうが、宮中へそうした地方官が娘を差し上げないこともないのであるし、また素質がよくて帝王がそれをお愛しになることになってもお譏りする者はないはずである、人臣である人たちはまして世間から無視されている階級の家の娘を妻にしている類も多いのである、
|
【げに、ことなることなき】- 以下「見すべきこと」まで、薫の心中の思い。
【ゆかり睦び】- 親戚付き合い。
【さばかりの人の娘たてまつらずやはある】- 反語表現。受領の娘が後宮に入内した例はある。
【時めかし思さむは】- 大島本は「おほさんハ」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「思さむをば」と「を」を補訂する。『新大系』は底本のまま「おぼさんは」とする。
【人の誹るべきことかは】- 反語表現。非難できない。
【世に古りにたるなどを】- いちど結婚したことのある女。
|
| 4.6.14 |
かの守の娘なりけりと、人の言ひなさむにも、わがもてなしの、それに穢るべくありそめたらばこそあらめ、一人の子をいたづらになして思ふらむ親の心に、なほこのゆかりこそおもだたしかりけれ、と思ひ知るばかり、用意はかならず見すべきこと」と思す。 |
あの介の娘であったと、人が取り沙汰しても、自分の取り扱いが、そのことで汚点とされるような形で始まったのならともかく、一人の子を亡くして悲しんでいる親の気持ちを、やはり娘の縁で面目を施すことができた、と分かる程度に、配慮は必ずしてやろう」とお思いになる。
|
常陸守の娘であったと人が言っても自分の恋愛の径路が悪いものであれば指弾もされようが、そんなことではないのであるからはばかる必要もない、一人の大事な娘を不幸に死なせた母親を、その子ののこした縁故から一家に名誉の及ぶことで慰めるほどの好意はぜひとも自分の見せてやらねばならないのが道であると薫は思った。
|
【わがもてなしの、それに穢るべく】- 『集成』は「浮舟とは正式な結婚をしたわけではないから、女の身分を云々されても、自分の落度にはならない、の意」と注す。
|
|
第七段 常陸介、浮舟の死を悼む
|
| 4.7.1 |
|
あちらでは、常陸介が、やって来て立ったままで、「こんな時に、こうしておいでになるとは」と腹を立てる。
長年、どこそこにいらっしゃるなどと、事実を知らせなかったので、「見すぼらしい有様でおいでになろう」と思い言ってもいたが、「京などにお迎えになった後は、名誉なことで、などと知らせよう」と思っていたうちに、このような事になってしまったので、今は隠すことも意味がなくて、生前の有様を泣きながら話す。
|
母の隠れ家へは常陸守が来て立ちながら話すのであったが、娘に出産のあったおりもおりにだれかの触穢を言い立てて引きこもっていることなどで腹だたしいふうに言っていた。去年の夏以来姫君がどこにいるかをありのままには夫人の言ってなかった常陸守であったから、寂しい生活をしていることであろうと思いもし、言いもしていたのを大将に京へ迎え入れられたあとで、名誉な結婚をしたと知らせようとも夫人が思っていたうちに浮舟は死んでしまったのであったから、隠しておくのもむだなことであると夫人は思い、薫と結婚をして宇治に住まわせられていたこと、そして病んで死んだ話を泣く泣く語るのであった。
|
【かしこには】- 三条の小家。浮舟母のいる所。
【立ちながら来て】- 『集成』は「ちょっとやって来て」と訳す。
【折しも、かくてゐたまへることなむ】- 常陸介の詞。娘の出産という重大な時期に、の意。
【いづくになむおはするなど】- 主語は浮舟。
【はかなきさまにておはすらむ】- 常陸介の心中。主語は浮舟。
【京になど迎へたまひて後】- 大島本は「むかへ給てのち」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「迎へたまひてむ後」と「む」を補訂する。『新大系』は底本のまま「迎へ給てのち」とする。以下「など知らせむ」まで、浮舟母の心中。
|
| 4.7.2 |
|
大将殿のお手紙も取り出して見せると、貴人を崇めて、田舎者で、何事にも感心する人なので、びっくりして気後れして、繰り返し繰り返し、
|
薫からもらった手紙も出して見せると、貴人を崇拝する田舎風な性質になっている守は驚きもし臆しもしながら繰り返し繰り返し薫の手紙を読んでいる。
|
【よき人かしこくして、鄙び、ものめでする人にて】- 高貴な人を崇めて田舎人らしく何にでも感心する性格。
|
| 4.7.3 |
|
「まことにめでたいご幸運を捨ててお亡くなりになった人だなあ。
自分も殿の家来として、参上してお仕えしていたが、近くにお召しになってお使いになることはなく、たいそう気高く思われる殿である。
幼い子供たちのことをおっしゃってくださったのは、頼もしいことだ」
|
「幸福で名誉な地位を得ていて死んだ方だ。自分も大将の家人の数にはしていただいている者で、お邸へはまいることがあっても近くお使いになることもなかった。とても気高い殿様なのだ。息子たちのことを言ってくだすったのは非常にあれらのために頼もしいことだ」
|
【いとめでたき御幸ひを】- 以下「頼もしきことになむ」まで、常陸介の詞。
【近く召し使ふこともなく】- 大島本は「めしつかふこともなく」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「召し使ひたまふ」と「たまふ」を補訂する。『新大系』は底本のまま「召し使ふ」とする。
【思はする殿なり】- 大島本は「おもはする」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「おはする」と「も」を削除する。『新大系』は底本のまま「思はする」とする。
|
| 4.7.4 |
|
などと、喜ぶのを見るにつけても、「それ以上に、生きておいでになったら」と思うと、臥し転んで泣けてくる。
|
こう言って喜ぶのを見ても、まして姫君が大将夫人として生きていたならばと思わないではいられない夫人は、臥しまろんで泣いていた。
|
【喜ぶを見るにも】- 主語は浮舟母。
|
| 4.7.5 |
|
介も今になって泣くのであった。
その反面、生きていらした時には、かえって、このような類の人を、お尋ねになるようなことはなかってたのだ。
「自分の過失によって亡くしたのもお気の毒だ。
慰めよう」とお思いになったため、「他人の非難は、こまごまと考えまい」とお思いなのであった。
|
守もこの時になってはじめて泣いた。しかしながら浮舟が生きているとすれば、かえって異父弟の世話を引き受けようなどと薫はしなかったことであろうと思われる。自身の過失から常陸夫人の愛女を死なせたのがかわいそうで、せめて慰めを与えることだけはしたいと思う心から、他の譏りがあろうとも深く気にとめまいという気になっているのである。
|
【さるは、おはせし世には--あらずかし】- 『万水一露』は「薫の心を草子の地にいへる也」と注す。
【わが過ちにて】- 以下「慰めむ」まで、薫の心中。
【人の誹り、ねむごろに尋ねじ】- 薫の心中。
|
|
第八段 浮舟四十九日忌の法事
|
| 4.8.1 |
|
四十九日の法事などもおさせになるにつけても、「いったいどういうことになったのか」とお思いになるので、いずれにしても罪になることではないから、たいそうこっそりと、あの律師の寺でおさせになった。
六十人の僧のお布施など、大がかりに仰せつけになっていた。
母君も来ていて、お布施を加えた。
|
薫は四十九日の法事の用意をさせながらも実際はどうあの人はなったのであろう、まだ一点の疑いは残されていると思うのであるが、仏への供養をすることは人の生死にかかわらず罪になることではないからと思い、ひそかに宇治の律師の寺で行なわせることにしているのであった。六十人の僧に出す布施の用意もいかめしく薫はさせた。母夫人も法会には来ていて、式をはなやかにする寄進などをした。
|
【いかなりけむことにかは」と】- 『集成』は「あるいは生きているかもしれない、とも思う」。『完訳』は「遺骸がないだけに不審が残る」と注す。
【とてもかくても】- 生きているにせよ亡くなったにせよ、法事は罪障消滅になる。
【かの律師の寺にて】- 大島本は「てらにて」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「寺にてなむ」と「なむ」を補訂する。『新大系』は底本のまま「寺にて」とする。
|
| 4.8.2 |
宮よりは、右近がもとに、白銀の壺に黄金入れて賜へり。人見とがむばかり大きなるわざは、えしたまはず、右近が心ざしにてしたりければ、心知らぬ人は、「いかで、かくなむ」など言ひける。殿の人ども、睦ましき限りあまた賜へり。 |
宮からは、右近のもとに、白銀の壷に黄金を入れて賜った。
人が見咎めるほどの大げさな法事は、おできになれず、右近の志として催したので、事情を知らない人は、「どうして、このような」などと言った。
殿の家来どもで、気心の知れた者ばかり大勢お遣わしになった。
|
兵部卿の宮からは右近の手もとへ銀の壺へ黄金の貨幣を詰めたのをお送りになった。人目に立つほどの派手なことはあそばせなかったのである。ただ右近が志として供物にしたのを、事情を知らぬ人たちはどうしてそんなことをしたかと不思議がった。薫のほうからは家司の中でも親しく思われる人たちを幾人もよこしてあった。
|
【宮よりは】- 匂宮から。
【殿の人ども】- 薫の家人。
|
| 4.8.3 |
「あやしく。音もせざりつる人の果てを、かく扱はせたまふ。誰れならむ」 |
「不思議なこと。
噂にも聞かなかった方の法事を、こんなに立派にあそばす。
いったい誰であろう」
|
在世中はだれもその存在を知らなんだ夫人の法事を、薫がこんなにまで丁寧に営むことによって、どんな婦人であったのか
|
【あやしく】- 以下「誰れならむ」まで、殿人の心中。
|
| 4.8.4 |
|
と、今になって驚く人ばかりが多かったが、常陸介が来て、主人顔でいるので、変だと人びとは見るのだった。
少将が子を産ませて、盛大なお祝いをさせようと大騷ぎし、邸の中にない物は少なく、唐土や新羅の装飾をもしたいのだが、限界があるので、まことにお粗末な有様であった。
この御法事が、人目に立たないようにとお思いであったが、感じが格別であるのを見ると、「もし生きていたらどんなにかと、わが身に比肩できない方のご運勢であったなあ」と思う。
|
と驚いて思ってみる人たちも多かったが、常陸守が来ていて、はばかりもなく法会の主人顔に事を扱っているのをいぶかしくだれも見た。少将の子の生まれたあとの祝いを、どんなに派手に行なおうかと腐心して、家の中にない物は少なく、支那、朝鮮の珍奇な織り物などをどうしてどう使おうと驕った考えを持っていた守ではあったが、それは趣味の洗練されない人のことであるから、美しい結果は上がらなかった。それに比べてこの法会の場内の荘厳をきわめたものになっているのを見て、生きていたならば、自分らと同等の階級に置かれる運命の人でなかったのであったと守は悟った。
|
【常陸守来て、主人がり居る】- 『完訳』は「浮舟の養父というだけでなく、薫からの後援があるという頼もしさも加わって、得意然とする」と注す。
【少将の子産ませて】- 左近少将、常陸介の婿。産養いを盛大に行おうとする。
【この御法事の、忍びたるやうに思したれど】- 『集成』は「この(浮舟の)ご法要が。以下わが家の産養と比べる常陸の介の心中」と注す。「思し」の主語は薫で、薫に対する敬語であろう。
【生きたらましかば】- 以下「宿世なりけり」まで、常陸介の心中。
|
| 4.8.5 |
|
宮の上も、誦経をなさり、七僧への饗応の事もおさせになった。
今になって、「このような人を持っていらしたのだ」と、帝までがお耳にあそばして、並々ならず大切に思っていた人を、宮にご遠慮申して隠していらしたのを、お気の毒にとお思いになった。
|
兵部卿の宮の夫人も誦経の寄付をし、七僧への供膳の物を贈った。今になって隠れた妻のあったことを帝もお聞きになり、そうした人を深く愛していたのであろうが、女二の宮への遠慮から宇治などへ隠しておいたのであろう、そして死なせたのは気の毒であると思召した。
|
【宮の上も】- 中君。
【七僧の前のこと】- 大島本は「まへの事」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「前のことも」と「も」を補訂する。『新大系』は底本のまま「前の事」とする。法会を行う役僧。講師、読師、呪願、三礼、唄、散花、堂達。
【かかる人持たまへりけり】- 帝の感想。「持つ」の主語は薫。
【帝までも聞こし召して】- 大島本は「みかとまても」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「帝まで」と「も」を削除する。『新大系』は底本のまま「みかどまでも」とする。
【おろかにもあらざりける人を】- 以下「いとほし」まで、帝の心中。「人」は浮舟をさす。
【宮にかしこまりきこえて】- 女二宮、薫の正妻。
【隠し置きたまひたりける】- 大島本は「かくしをき給たりける」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「隠しおきたまへりけるを」と校訂する。『新大系』は底本のまま「隠しをき給たりける」とする。
|
| 4.8.6 |
|
二人のお方のご心中は、いつまでも悲しく、あいにくな横恋慕の最中に亡くなってしまっては、ひどく悲しいが、浮気なお心は、慰められるかなどと、他の女に言い寄りなさることもだんだんとあるのだった。
|
浮舟の死のために若い二人の貴人の心の中はいつまでも悲しくて、正しくない情炎の盛んに立ちのぼっていたころにそのことがあったため、ことに宮のお歎きは非常なものであったが、元来が多情な御性質であったから、慰めになるかと恋の遊戯もお試みになるようなこともようやくあるようになった。
|
【二人の人の御心のうち】- 薫と匂宮。
【あやにくなりし御思ひの】- 匂宮についていう。
【いといみじければ】- 大島本は「いみしけれは」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「いみじけれど」と校訂する。『新大系』は底本のまま「いみじければ」とする。
【あだなる御心は、慰むやなど、こころみたまふこともやうやうありけり】- 匂宮の好色な性格。
|
| 4.8.7 |
|
あの殿は、このようにお心にかけて、何やかやとご心配なさって、残った人をお世話なさっても、やはり、言って効のないことを、忘れがたくお思いになる。
|
薫は故人ののこした身内の者の世話などを熱心にしてやりながらも、恋しさを忘られなく思っていた。
|
【かの殿は】- 薫。
【いふかひなきことを、忘れがたく思す】- 薫の性格。匂宮との対照性を語る。
|
|
第五章 薫の物語 明石中宮の女宮たち
|
|
第一段 薫と小宰相の君の関係
|
| 5.1.1 |
|
后の宮が、御軽服の間は、やはり里下がりしていらっしゃるうちに、二の宮が式部卿におなりになった。
重々しくなって、常には参上なさらない。
この宮は、もの寂しくて何となく悲しい気分のまま、一品の宮のお側を慰め所としていらっしゃる。
器量の良い女房の顔で、まだよく御覧にならない者が、多く残っていた。
|
中宮もまだそのまま叔父の宮の喪のために六条院においでになるのであったが、二の宮はそのあいた式部卿にお移りになった。お身柄が一段重々しくおなりになったために、始終母宮の所へおいでになることもできぬことになったが、兵部卿の宮は寂しく悲しいままによくおいでになっては姉君の一品の宮の御殿を慰め所にあそばした。すぐれた美貌であらせられる姫宮をよく御覧になれぬことを物足らぬことにしておいでになるのであった。
|
【后の宮の、御軽服のほどは】- 明石中宮の叔父の故蜻蛉式部卿宮の軽服、三か月間。
【二の宮なむ式部卿になりたまひにける】- 匂宮(三宮)の兄、式部卿となる。
【重々しうて、常にしも参りたまはず】- 主語は匂宮の兄、式部卿宮。母明石中宮のもとに。
【この宮は】- 匂宮。
【一品の宮】- 匂宮の同母の姉、女一宮。
【よき人の容貌をも】- 女一宮のもとに伺候している美貌の女房の顔を。
|
| 5.1.2 |
|
大将殿が、やっとのことで、たいそうこっそりと親しくなさっている小宰相の君という女房で、器量なども美しげで、気立ての良い人とお思いであった。
同じ琴をかき鳴らす、その爪音や、撥の音が、誰にもまさって、手紙を書き、何か言うのも、風流な事が加わっているのだった。
|
右大将が多数の女房の中で深い交際をしている小宰相という人は容貌などもきれいであった。価値の高い女として中宮も愛しておいでになった。琴の爪音も琵琶の撥音も人よりはすぐれていて、手紙を書いてもまた人と話しをしても洗練されたところの見える人であった。
|
【いと忍びて語らはせたまふ】- 大島本は「かたらハせ給」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「語らひたまふ」と校訂する。『新大系』は底本のまま「語らはせ給」とする。
【小宰相の君といふ人の】- 女一宮のもとに伺候している女房、小宰相君。『完訳』は「「--の」は、「同じ琴を--」に続く。その間は挿入句」と注す。
|
| 5.1.3 |
|
この宮も、長年、とても関心を寄せていらっしゃって、いつものように、悪口おっしゃるが、「どうして、そのようにありふれた女でいようか」と、気強くて従わないのを、真面目人間は、「少しは他の女と違っている」とお思いなのであった。
このように物思いに沈んでいらっしゃるのを知っていたので、思い余って差し上げた。
|
兵部卿の宮も長くこの人に恋を持っておいでになるのであって、例の上手に説き伏せようとお試みになるのであるが、誘惑をされてだれも陥るような御関係を作りたくないと強い態度を変えないのを、薫はおもしろい人であると思って好意が持たれるのである。このごろの薫が物思いにとらわれているのも知っていて、黙っていることができぬ気もして手紙を書いて送った。
|
【この宮も】- 匂宮も小宰相君に執心。
【言ひ破りたまへど】- 匂宮が薫と小宰相君の仲に水をさすような悪口を言う。
【などか、さしもめづらしげなくはあらむ】- 小宰相君の心中。世間一般の女と違って自分は簡単に匂宮に靡くまい。
【まめ人は】- 薫。
【すこし人よりことなり】- 薫の心中。小宰相君の貞操に共感。
【見知りければ】- 主語は小宰相君。
|
| 5.1.4 |
|
「お悲しみを知る心は誰にも負けませんが
一人前でもない身では遠慮して消え入らんばかりに過ごしております
|
哀れ知る心は人におくれねど
数ならぬ身に消えつつぞ経る
|
【あはれ知る心は人におくれねど--数ならぬ身に消えつつぞ経る】- 小宰相君から薫への贈歌。『完訳』は「暗に、浮舟にも劣らぬ己が恋情であるとほのめかす」と注す。
|
| 5.1.5 |
|
亡くなった方と入れ替れるものでたら」
|
私が代わって死んでおあげすればよかったように思われます。
|
【代へたらば】- 歌に添えた詞。『弄花抄』は「草枕紅葉むしろにかへたらば心をくだくものならましや」(後撰集羇旅、一三六四、亭子院御製)を指摘。
|
| 5.1.6 |
と、ゆゑある紙に書きたり。
ものあはれなる夕暮、しめやかなるほどを、いとよく推し量りて言ひたるも、憎からず。
|
と、由緒ある紙に書いてあった。
何となくしみじみとした夕暮で、しんみりした時に、まことによく推察して言って来たのも、気が利いている。
|
と感じのよい色の紙に書かれてあった。身にしむような夕方時のしめっぽい気持ちをよく察して訪ねの文を送った心持ちを薫は感謝せずにはおられなかった。
|
|
| 5.1.7 |
|
「無常の世を長年見続けて来たわが身でさえ
人が見咎めるまで嘆いてはいないつもりでしたが
|
つれなしとここら世を見るうき身だに
人の知るまで歎きやはする
|
【常なしとここら世を見る憂き身だに--人の知るまで嘆きやはする】- 薫の返歌。『集成』は「よくぞ察してお尋ね下さった」。『完訳』は「浮舟だけを深く思っているように思われるのは心外だと反発」と注す。
|
| 5.1.8 |
|
このお見舞いのお礼には、悲しい折柄、ひとしお嬉しかった」
|
これを返歌にした。答礼のつもりで、「寂しい時の御慰問のお手紙はことにありがたく思われました」
|
【このよろこび】- 以下「いとどなむ」まで、歌に続けた詞。「このよろこび」とは小宰相君の弔問に対するお礼、の意。
|
| 5.1.9 |
など言ひに立ち寄りたまへり。いと恥づかしげにものものしげにて、なべてかやうになどもならしたまはぬ、人柄もやむごとなきに、いとものはかなき住まひなりかし。局などいひて、狭くほどなき遣戸口に寄りゐたまへる、かたはらいたくおぼゆれど、さすがにあまり卑下してもあらで、いとよきほどにものなども聞こゆ。 |
などと言いに立ち寄りなさった。
たいそう気恥ずかしくなるほど堂々として、普段はこのようにはお立ち寄りなさらず、人柄もご立派なのに、たいそうささやかな住まいである。
局などと言って、狭く何程もない遣戸口に寄っていらっしゃるのは、体裁悪く思われるが、そうは言ってもむやみに卑下することもなく、とても良い具合にお話など申し上げる。
|
と言いに小宰相の家を薫は訪ねて行った。貴人らしい重々しさが十分に備わり、こんなふうに中宮の女房の自宅へなど、今までは一度も行ったことのない薫が訪ねて来た所としては貧弱な邸であった。局などと言われる狭い短い板の間の戸口に寄って薫の坐しているのを片腹痛いことに思う小宰相であったが、さすがにあまりに卑下もせず感じのよいほどに話し相手をした。
|
【いとものはかなき住まひなりかし】- 『全集』は「語り手の、小宰相の局への感想」と注す。
【かたはらいたくおぼゆれど】- 主語は小宰相君。
|
| 5.1.10 |
|
「亡き人よりも、この人は奥ゆかしい感じが加わっているな。
どうして、このように出仕したのだろう。
そのような人として、わたしも側に置いたらよかったものを」
|
失った人よりもこの人のほうに才識のひらめきがあるではないか、なぜ女房などに出たのであろう、自分の妻の一人として持っていてもよかった人であったのに
|
【見し人よりも】- 大島本は「みえし人」とある。『集成』『完本』『新大系』は諸本に従って「見し人」と校訂する。以下「置いたらましものを」まで、薫の心中。浮舟と比較した感想。
【かく出で立ちけむ】- 女房として出仕していること。
【さるものにて、我も置いたらましものを】- 隠し妻として囲って置きたい女だ、の意。
|
| 5.1.11 |
|
とお思いになる。
密やかな心の内は、少しもお見せにならない。
|
と薫は思っていた。しかしながら友情以上に進んでいこうとするふうを少しも薫は見せていなかった。
|
【人知れぬ筋】- 恋情。
|
|
第二段 六条院の法華八講
|
| 5.2.1 |
|
蓮の花の盛りに、法華八講が催される。
六条院の御ため、紫の上のなどと、皆それぞれに日をお分けになって、お経や仏などを供養あそばして、荘厳に、立派に催された。
五巻目の日などは、大変な見物だったので、あちらこちら、女房の縁故をたどって、見物に来る人が多かった。
|
蓮の花の盛りのころに中宮は法華経の八講を行なわせられた。六条院のため、紫夫人のため、などと、故人になられた尊親のために経巻や仏像の供養をあそばされ、いかめしく尊い法会であった。第五巻の講ぜられる日などは御陪観する価値の十分にあるものであったから、あちらこちらの女の手蔓を頼んで参入して拝見する人も多かった。
|
【蓮の花の盛りに】- 季節は夏六月ころに移る。
【御八講せらる】- 明石中宮主催の法華八講。
【五巻の日】- 薪行道が行われる日。
【女房につきて参りて】- 大島本は「女はうにつきて」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「女房につきつつ」と校訂する。『新大系』は底本のまま「女房につきて」とする。女房の縁故をたよって。
|
| 5.2.2 |
|
五日という朝座で終わって、御堂の飾りを取り外し、お部屋の飾りつけを改めるので、北の廂も、襖障子なども外してあったので、皆が入り込んで整えている間、西の渡殿に姫宮はいらっしゃった。
お経を聞き疲れて、女房たちもそれぞれの局にいて、御前はたいそう人少なな夕暮に、大将殿は、直衣に着替えて、今日退出する僧の中に、是非にお話なさらなければならない事があったので、釣殿の方にいらっしゃったが、皆が退出してしまったので、池の方で涼みなさって、人も少ないので、さきほどの小宰相の君などが、仮に几帳などを立てて、ちょっと休むための上局にしていた。
|
五日めの朝の講座が終わって仏前の飾りが取り払われ、室内の装飾を改めるために、北側の座敷などへも皆人がはいって、旧態にかえそうとする騒ぎのために、西の廊の座敷のほうへ一品の姫宮は行っておいでになった。日々の多くの講義に聞き疲れて女房たちも皆部屋へ上がっていて、お居間に侍している者の少ない夕方に、薫の大将は衣服を改めて、今日退出する僧の一人に必ず言っておく用で釣殿のほうへ行ってみたが、もう僧たちは退散したあとで、だれもいなかったから、池の見えるほうへ行ってしばらく休息したあとで、人影も少なくなっているのを見て、この人の女の友人である小宰相などのために、隔てを仮に几帳などでして休息所のできているのはここらであろうか、
|
【五日といふ朝座に果てて】- 法華八講は五日目の朝座で終わる。
【御堂の飾り】- 寝殿を御堂に見立てて法華八講が催された。
【姫宮】- 女一宮。
【もの聞き極じて】- 五日間の法華八講の聴聞に疲労。
【御前】- 女一宮の御前。
【皆まかでぬれば】- 『集成』は「皆退出していないので」。『完訳』は「法師たちは誰もみな退出してしまっていたので」と注す。
【かくいふ宰相の君など】- 『集成』は「(西の渡殿は)さきほどからの話に出ていた」。『完訳』は「先刻の話の」と訳す。
|
| 5.2.3 |
「ここにやあらむ、人の衣の音す」と思して、馬道の方の障子の細く開きたるより、やをら見たまへば、例さやうの人のゐたるけはひには似ず、晴れ晴れしくしつらひたれば、なかなか、几帳どもの立て違へたるあはひより見通されて、あらはなり。 |
「ここであろうか、衣ずれの音がする」とお思いになって、馬道の方の襖障子が細く開いているところから、そっと御覧になると、いつもそのような女房がいる感じと違って、広々と整頓されているので、かえって、几帳などがいくつもはすに立ててあって見通されて、丸見えである。
|
人の衣擦れの音がすると思い、内廊下の襖子の細くあいた所から、静かに中をのぞいて見ると、平生女房級の人の部屋になっている時などとは違い、晴れ晴れしく室内の装飾ができていて、幾つも立ち違いに置かれた几帳はかえって、その間から向こうが見通されてあらわなのであった。
|
【ここにやあらむ、人の衣の音す】- 薫の心中。小宰相君の存在を思う。
|
|
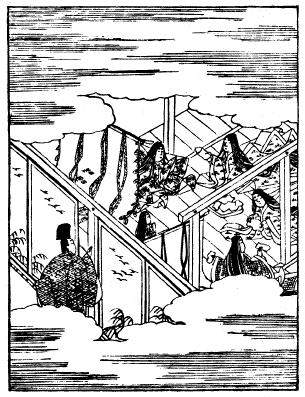 |
| 5.2.4 |
氷をものの蓋に置きて割るとて、もて騒ぐ人びと、大人三人ばかり、童と居たり。唐衣も汗衫も着ず、皆うちとけたれば、御前とは見たまはぬに、白き薄物の御衣着替へたまへる人の、手に氷を持ちながら、かく争ふを、すこし笑みたまへる御顔、言はむ方なくうつくしげなり。 |
氷を何かの蓋の上に置いて割ろうとして、騒いでいる女房たち、大人三人ほどと、童女とがいた。
唐衣も汗衫も着ず、みな打ち解けていたので、御前とはお思いでないが、白い薄物のお召物を着ていらっしゃる人で、手に氷を持ちながら、このように騒いでいるのを、少しほほ笑んでいらっしゃるお顔、何とも言いようもなくかわいらしげである。
|
氷を何かの蓋の上に置いて、それを割ろうとする人が大騒ぎしている。大人の女房が三人ほど、それと童女がいた。大人は唐衣、童女は袗も上に着ずくつろいだ姿になっていたから、宮などの御座所になっているものとも見えないのに、白い羅を着て、手の上に氷の小さい一切れを置き、騒いでいる人たちを少し微笑をしながらながめておいでになる方のお顔が、言葉では言い現わせぬほどにお美しかった。
|
【着替へたまへる人】- 大島本は「き(き+かへ)給へる」とある。すなわち「かへ」を補入する。『集成』『完本』は底本の訂正以前の本文と諸本に従って「着たまへる」と校訂する。『新大系』は底本の補入に従って「着かへ給へる」とする。大島本は独自異文。女一宮。
|
| 5.2.5 |
|
ひどく暑さの堪えがたい日なので、うるさい御髪が、暑苦しくお思いなされるのであろうか、少しこちら側に靡かして引いている様子、何物にも譬えようがない。
「大勢美しい女性を見て来たが、似ている人は誰もいないなあ」と思われる。
御前の女房は、まこと土人形のような気がするのを、冷静になって見ていると、黄色い生絹の単衣に薄紫色の裳を着ている女で、扇をちょっと使っているところなど、「いかにも嗜みがあるなあ」と、ふと見えて、
|
非常に暑い日であったから、多いお髪を苦しく思召すのか肩からこちら側へ少し寄せて斜めになびかせておいでになる美しさはたとえるものもないお姿であった。多くの美人を今まで見てきたが、それらに比べられようとは思われない高貴な美であった。御前にいる人は皆土のような顔をしたものばかりであるとも思われるのであったが、気を静めて見ると、黄の涼絹の単衣に淡紫の裳をつけて扇を使っている人などは少し気品があり、女らしく思われたが、
|
【苦しう思さるるにやあらむ】- 挿入句。語り手と薫の視点と一体化した叙述。
【ここらよき人を】- 以下「あらざりけり」まで、薫の心中。女一宮の美しさの感動。
【土などの心地ぞするを】- 『河海抄』は「上の心油然として怳たること遇へること有るが如し左右前後を顧みるに粉色土の如し」(白氏文集、長恨歌伝)を指摘。
【用意あらむはや】- 薫の感想。
|
| 5.2.6 |
|
「かえって、氷を扱うのに、とても暑苦しそうです。
ただ、そのままで御覧なさい」
|
そうした人にとって氷は取り扱いにくそうに見えた。「そのままにして、御覧だけなさいましよ」
|
【なかなか】- 以下「見たまへかし」まで、小宰相君の詞。仲間の女房に言ったもの。
【ただ、さながら】- 氷を割ろうとせず、そのまま、の意。
|
| 5.2.7 |
|
と言って、にっこりしている目もと、愛嬌がある。
声を聞くと、この目指している女と分かった。
|
と朋輩に言って笑った声に愛嬌があった。声を聞いた時に薫は、はじめてその人が友人の小宰相であることを知った。
|
【この心ざしの人】- 薫の意中の人、小宰相君。
|
|
第三段 小宰相の君、氷を弄ぶ
|
| 5.3.1 |
|
無理して割って、それぞれの手に持っていた。
頭の上に置いたり、胸に当てたりなど、体裁の悪い恰好をする女もいるのであろう。
他の人は、紙に包んで、御前にもこのようにして差し上げたが、とてもかわいらしいお手を差し出しなさって、拭わせなさる。
|
とどめた人のあったにもかかわらず氷を割ってしまった人々は、手ごとに一つずつの塊を持ち、頭の髪の上に載せたり、胸に当てたり見苦しいことをする人もあるらしかった。小宰相は自身の分を紙に包み、宮へもそのようにして差し上げると、美しいお手をお出しになって、その紙で掌をおぬぐいになった。
|
【さま悪しうする人もあるべし】- 語り手の批評。
【いとうつくしき御手をさしやりたまひて】- 女一宮の姿態動作。
【拭はせたまふ】- 「せ」使役助動詞。女房をして。
|
| 5.3.2 |
|
「いえ、持てません。
雫が嫌です」
|
「もう私は持たない、雫がめんどうだから」
|
【いな、持たらじ。雫むつかし】- 女一宮の詞。
|
| 5.3.3 |
|
とおっしゃるお声、とてもかすかに聞くのも、この上なく嬉しい。
「まだとても幼くいらしたときに、わたしも、何も分からず拝見したとき、何とかわいらしい姫宮か、と拝見した。
その後は、まったく姫宮のご様子をさえ聞かなかったが、どのような神仏が、このような機会をお見せになったのであろうか。
いつもの、心安からず物思いをさせようとするのであろうか」
|
と、お言いになる声をほのかに聞くことのできたのが薫のかぎりもない喜びになった。まだごくお小さい時に、自分も無心にお見上げして、美しい幼女でおありになると思った。それ以後は絶対にこの宮を拝見する機会を持たなかったのであるが、なんという神か仏かがこんなところを自分の目に見せてくれたのであろうと思い、また過去の経験にあるように、こうした隙見がもとで長い物思いを作らせられたと同じく、自分を苦しくさせるための神仏の計らいであろうか
|
【限りもなくうれし】- 大島本は「かきりもなく」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「限りなく」と「も」を削除する。『新大系』は底本のまま「限りもなく」とする。『完訳』は「薫の感動を直接的に叙述し、以下の心中叙述に連なる」と注す。
【まだいと小さく】- 以下「するにやあらむ」まで、薫の心中の思い。
【いかなる神仏の、かかる折見せたまへるならむ】- 『完訳』は「偶然のかいま見の感動の強さから神仏のなせるわざとする」と注す。
【例の、やすからずもの思はせむとするにやあらむ】- 前に浮舟の件で苦悩したのを思い起こす。
|
| 5.3.4 |
|
と、一方では落ち着かず、じっと見つめて佇んでいると、こちらの対の北面に住んでいた下臈の女房が、この襖障子は、急ぎの用事で、開けたままで下りて来たのを思い出して、「人が見つけて騒いだら大変だ」と思ったので、あわてて入って来る。
|
とも思われて、落ち着かぬ心で見つめていた。ここの対の北側の座敷に涼んでいた下級の女房の一人が、この襖子は急な用を思いついてあけたままで出て来たのを、この時分に思い出して、人に気づかれては叱られることであろうとあわてて帰って来た。
|
【こなたの対の北面に】- 西の対の北廂。
【人もこそ見つけて騒がるれ】- 下臈の女房の心中の思い。「もこそ」は懸念の気持ち。「るれ」受身助動詞。『集成』は「小言を言われては大変」と注す。
|
| 5.3.5 |
|
この直衣姿を見つけて、「誰だろう」とびっくりして、自分の姿を見られることも構わず、簀子からずんずんやって来たので、ふと立ち去って、「誰とも知られまい。
好色なようだ」と思って隠れなさった。
|
襖子に寄り添った直衣姿の男を見て、だれであろうと胸を騒がせながら、自分の姿のあらわに見られることなどは忘れて、廊下をまっすぐに急いで来るのであった。自分はすぐにここから離れて行ってだれであるとも知られまい、好色男らしく思われることであるからと思い、すばやく薫は隠れてしまった。
|
【この直衣姿】- 薫。
【ふと立ち去りて】- 主語は薫。
【誰れとも見えじ。好き好きしきやうなり】- 薫の心中の思い。
|
| 5.3.6 |
この御許は、
|
この女房は、
|
その女房は
|
|
| 5.3.7 |
|
「大変なことだわ。
御几帳までを丸見えにしていたことだわ。
右の大殿の公達であろうかしら。
疎遠な方は、また、ここまでは来るはずがない。
何かの噂が立ったら、誰が襖障子を開けていたのだろうかと、きっと出て来るだろう。
単衣も袴も、生絹のように見えた方のお姿なので、誰もお気づきになることができなかっただろう」
|
たいへんなことになった、自分はお几帳なども外から見えるほどの隙をあけて来たではないか、左大臣家の公達なのであろう、他家の人がこんな所へまで来るはずはないのである、これが問題になればだれが襖子をあけたかと必ず言われるであろう、あの人の着ていたのは単衣も袴も涼絹であったから、音がたたないで内側の人は早く気づかなかったのであろう
|
【いみじきわざかな】- 以下「聞きつけたまはぬならむかし」まで、下臈の女房の心中の思い。
【ものの聞こえあらば】- 垣間見られたという噂がたったら、の意。
【障子は】- 大島本は「さう/\(/\$し<朱>)」とある。すなわち「/\」を朱筆でミセケチにして「し」と訂正する。『集成』『完本』『新大系』は底本の訂正に従って「障子」と校訂する。
【出で来なむ】- 責任追求がなされる。
【単衣も袴も、生絹なめりと】- 薫の装束。生絹は薄く軽いので衣擦れの音がせず、その接近に気づかれない。
【聞きつけたまはぬならむかし】- 「たまふ」尊敬語は女房たちに対する敬意。下臈の女房の視点。
|
| 5.3.8 |
と思ひ極じてをり。
|
と困りきっていた。
|
と苦しんでいた。
|
|
| 5.3.9 |
|
あの方は、「だんだんと聖になって来た心を、一度踏み外して、さまざまに物思いを重ねる人となってしまったなあ。
その昔に出家遁世してしまったら、今は深い山奥に住みついて、このような心を乱すことはないものを」などとお思い続けるにつけても、落ち着かない。
「どうして、長年、お顔を拝見したものだと思っていたのであろう。
かえって苦しいだけで、何にもならないことであるのに」と思う。
|
薫は漸く僧に近い心になりかかった時に、宇治の宮の姫君たちによって煩悩を作り始め、またこれからは一品の宮のために物思いを作る人になる自分なのであろう、その二十のころに出家をしていたなら、今ごろは深い山の生活にも馴れてしまい、こうした乱れ心をいだくことはなかったであろうと思い続けられるのも苦しかった。なぜあの方を長い間見たいと願った自分なのであろう、何のかいがあろう、苦しいもだえを得るだけであったのにと思った。
|
【かの人は】- 『完訳』は「薫の視点に沿って語ってきた語り手は、「かの人」として距離を置き、その心中を語り直す」と注す。
【やうやう聖に】- 以下「乱れましや」まで、薫の心中の思い。
【ひとふし違へそめて】- 八宮の大君に恋情を寄せたこと。
【背きなましかば--乱れましや】- 大島本は「心みたれましやは」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「乱らましや」と校訂する。『新大系』は底本のまま「乱れましやは」とする。反実仮想の構文。出家を仮想。係助詞「やは」は、疑問の意。
【などて、年ごろ】- 以下「わざにこそ」まで、薫の心中の思い。
【見たてまつらばやと】- 女一宮を。
|
|
第四段 薫と女二宮との夫婦仲
|
| 5.4.1 |
|
翌朝、起きなさった女宮の御器量が、「とても美しくいらっしゃるようなのは、この宮よりもきっとまさっていらっしゃるだろうか」と思いながらも、「まったく似ていらっしゃらない。
驚くほど上品で、何とも言えないほどのご様子だなあ。
一つには気のせいか、時節柄か」とお思いになって、
|
翌朝起きた薫は夫人の女二の宮の美しいお姿をながめて、必ずしもこれ以上の御美貌であったのではあるまいと心を満ち足りたようにしいてしながら、また、少しも似ておいでにならない、超人間的にまであの方は気品よくはなやかで、言いようもない美しさであった。あるいは思いなしかもしれぬ、その場合がことさらに人の美を輝かせるものだったかもしれぬと薫は思い、
|
【女宮の】- 女二宮女一宮の異母妹、母は麗景殿女御。
【いとをかしげなめるは、これよりかならずまさるべきことかは】- 薫の心中の思い。女一宮は女二宮より。
【さらに似たまはずこそ】- 以下「折からか」まで、薫の心中の思い。
【あさましきまであてに】- 大島本は「あてに」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「あてにかをり」と「かをり」を補訂する。『新大系』は底本のまま「あてに」とする。
【御さまかな】- 女一宮のすぐれた美貌。
|
| 5.4.2 |
「いと暑しや。これより薄き御衣奉れ。女は、例ならぬ物着たるこそ、時々につけてをかしけれ」とて、「あなたに参りて、大弐に、薄物の単衣の御衣、縫ひて参れと言へ」 |
「ひどく暑いね。
これより薄いお召し物になさいませ。
女性は、変わった物を着ているのが、その時々につけ趣があるものです」と言って、「あちらに参上して、大弍に、薄物の単衣のお召し物を、縫って差し上げよと申せ」
|
「非常に暑い。もっと薄いお召し物を宮様にお着せ申せ。女は平生と違った服装をしていることなどのあるのが美しい感じを与えるものだからね。あちらへ行って大弐に、薄物の単衣を縫って来るように命じるがいい」
|
【いと暑しや】- 以下「をかしけれ」まで、薫の詞。
【あなたに参りて】- 以下「縫ひて参れと言へ」まで、薫の詞。「あなた」は薫の母女三宮方をさす。「参る」の主語は女房。
【大弐に】- 女三宮方の女房で衣服調達係の女房。
|
| 5.4.3 |
とのたまふ。御前なる人は、「この御容貌のいみじき盛りにおはしますを、もてはやしきこえたまふ」とをかしう思へり。 |
とおっしゃる。
御前の女房は、「宮のご器量がたいそう女盛りでいらっしゃるのを、さらに引き立てようとなさる」とおもしろく思っていた。
|
と言いだした。侍している女房たちは宮のお美しさにより多く異彩の添うのを楽しんでの言葉ととって喜んでいた。
|
【御前】- 女二宮の御前。
|
| 5.4.4 |
|
いつものように、念誦をなさるご自分のお部屋にいらっしゃったりなどして、昼頃にお渡りになると、お命じになっていたお召し物が、御几帳に懸けてあった。
|
いつものように一人で念誦をする室のほうへ薫は行っていて、昼ごろに来てみると、命じておいた夫人の宮のお服が縫い上がって几帳にかけられてあった。
|
【例の、念誦したまふ】- 主語は薫。念仏修行が日常化した生活。
【渡りたまへれば】- 正妻の女二宮のもとに。
|
| 5.4.5 |
「なぞ、こは奉らぬ。人多く見る時なむ、透きたる物着るは、ばうぞくにおぼゆる。ただ今はあへはべりなむ」 |
「どうして、これをお召しにならないのか。
人が大勢見る時に、透けた物を着るのは、はしたなく思われる。
今は構わないでしょう」
|
「どうしてこれをお着にならぬのですか、人がたくさん見ている時に肌の透く物を着るのは他をないがしろにすることにもあたりますが、今ならいいでしょう」
|
【なぞ、こは】- 以下「あへあhべりなむ」まで、薫の詞。
|
| 5.4.6 |
とて、手づから着せ奉りたまふ。御袴も昨日の同じ紅なり。御髪の多さ、裾などは劣りたまはねど、なほさまざまなるにや、似るべくもあらず。氷召して、人びとに割らせたまふ。取りて一つ奉りなどしたまふ、心のうちもをかし。 |
と言って、ご自身でお着せなさる。
御袴も昨日のと同じ紅色である。
御髪の多さや、裾などは負けないが、やはりそれぞれの美しさなのか、似るはずもない。
氷を召して、女房たちに割らせなさる。
取って一つ差し上げなどなさる、心の中もおもしろい。
|
と薫は言って、手ずからお着せしていた。宮のお袴も昨日の方と同じ紅であった。お髪の多さ、その裾のすばらしさなどは劣ってもお見えにならぬのであるが、美にも幾つの級があるものか女二の宮が昨日の方に似ておいでになったとは思われなかった。氷を取り寄せて女房たちに薫は割らせ、その一塊を取って宮にお持たせしたりしながら心では自身の稚態がおかしかった。
|
【劣りたまはねど】- 女一宮に。
【さまざまなるにや】- 『完訳』は「それぞれの個性的な美しさ。しかし薫は、女二の宮が姉宮に劣るとして絶望的な思いになる」と注す。
|
| 5.4.7 |
|
「絵に描いて、恋しい人を見る人は、いないだろうか。
ましてこの宮は、気持ちを慰めるのに似つかわしからぬご姉妹であると思うが、昨日あのようにして、自分があの中に混じっていて、心ゆくまで拝することができたなら」と思うと、われ知らずのうちに溜息が漏れてしまった。
|
絵に描いて恋人の代わりにながめる人もないのではない、ましてこれは代わりとして見るのにかけ離れた人ではないはずであると思うのであるが、昨日こんなにしてあの中に自分もいっしょに混じっていて、満足のできるほどあの方をながめることができたのであったならと思うと、心ともなく歎息の声が発せられた。
|
【絵に描きて、恋しき人見る人は】- 以下「見たてまつらましかば」まで、薫の心中の思い。『異本紫明抄』は、『白氏文集』巻四「李夫人」を指摘。
【似げなからぬ御ほど】- 女一宮と女二宮は姉妹であることをいう。
【と思へど】- 薫の心中思惟、自省、また語り手の客観描写とも、読める叙述。
【我混じりゐ】- 女一宮に。
|
| 5.4.8 |
|
「一品の宮に、お手紙は差し上げなさいましたか」
|
「一品の宮さんへお手紙をおあげになることがありますか」
|
【一品の宮に、御文は奉りたまふや】- 薫の詞。一品宮は女一宮。
|
| 5.4.9 |
と聞こえたまへば、
|
とお尋ね申し上げなさると、
|
|
|
| 5.4.10 |
|
「内裏にいたとき、主上が、そのようにおっしゃったので差し上げましたが、長いことそういたしてません」
|
「御所にいましたころ、お上がそうおっしゃったものですから、差し上げたこともありましたけれど、ずいぶん長く御交渉はなくなっています」
|
【内裏にありし時】- 以下「さもあらず」まで、女二宮の詞。
【さのたまひしかば】- 女一宮に手紙を出すこと。
|
| 5.4.11 |
とのたまふ。
|
とおっしゃる。
|
|
|
| 5.4.12 |
|
「臣下におなりあそばしたといって、あちらからお便りを下さらないのは、情けないことです。
今、大宮の御前に、お恨み申されています、と申し上げよう」
|
「人臣の妻におなりになったからといって、あちらからお手紙をくださらなくなったのでしょうが、悲観させられますね。そのうち私から中宮へあなたが恨んでおいでになると申し上げよう」
|
【ただ人に】- 以下「と啓せむ」まで、薫の詞。『完訳』は「臣下の妻室に降りたのを低く見られるのが不満だとする。女一の宮の文に自ら接したい思いから、文通のないのを大げさに言う」と注す。
【恨みきこえさせたまふ】- 女二宮が女一宮を。
|
| 5.4.13 |
とのたまふ。
|
とおっしゃる。
|
と薫は言う。
|
|
| 5.4.14 |
|
「どうしてお恨み申していましょう。
嫌ですわ」
|
「そんなこと、お恨みなど私はしているものでございますか。いやでございます」
|
【いかが恨みきこえむ。うたて】- 女二宮の詞。
|
| 5.4.15 |
とのたまへば、
|
とおっしゃるので、
|
|
|
| 5.4.16 |
|
「身分が低くなったからといって、軽んじていらっしゃるようだ、と思われるので、お便りも差し上げないのです、と申し上げましょう」
|
「身分が悪くなったからといって軽蔑をなさるらしいから、こちらからは御遠慮して消息を差し上げないとそんなふうに言いましょう」
|
【下衆になりにたりとて】- 以下「聞こえめ」まで、薫の詞。
【おどろかしきこえぬ】- 女二宮が女一宮に。
|
| 5.4.17 |
とのたまふ。
|
とおっしゃる。
|
|
|
|
第五段 薫、明石中宮に対面
|
| 5.5.1 |
|
その日は過ごして、翌朝に大宮に参上なさる。
いつものように、宮もいらっしゃった。
丁子色に深く染めた薄物の単衣を、濃い縹色の直衣の下に召していらっしゃったのは、たいそう好感がもてる女宮のお姿が素晴らしかったのにも負けず、白く清らかで、やはり以前よりは面痩せなさっているのは、とても見栄えがする。
|
こんなことを言ってその日は暮らし、翌日になって大将は中宮の御殿へまいった。例の兵部卿の宮も来ておいでになった。丁子の香と色の染んだ羅の上に、濃い直衣を着ておいでになる感じは美しかった。一品の宮のお姿にも劣らず、白く清らかな皮膚の色で、以前より少しお痩せになったのがなおさらお美しく見せた。
|
【宮も】- 匂宮。
【丁子に深く染めたる薄物の単衣を】- 匂宮の服装。
【いとこのましげなる】- 大島本は「このましけなる」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「このましげなり」と校訂する。『新大系』は底本のまま「このましげなる」とする。
【女の御身なりの】- 女一宮の身なり。『完訳』は「「女」の呼称は、恋情をこめた表現である」と注す。薫の心中を通しての叙述。
|
| 5.5.2 |
|
似ていらっしゃると見るにつけても、まっさきに恋しいのを、まことにけしからぬこと、と抑えるのは、拝見しなかった時よりもつらい。
絵をとてもたくさん持たせて参上なさったが、女房を介して、あちらに差し上げなさって、ご自分もお渡りになった。
|
女宮によく似ておいでになるということから、またおさえている恋しさがわき上がるのを、あるまじいことであると思い、静めようとするのもあの日の前には知らぬ苦しみであった。兵部卿の宮は絵をたくさんに持って来ておいでになったが、そのうちの幾つかを女房に姫宮のほうへ持たせておあげになり、御自身もあちらへおいでになった。
|
【まづ恋しきを】- 女一宮を。
【ただなりしよりは苦しき】- 語り手の批評を交えた叙述。
【絵をいと多く持たせて】- 主語は匂宮。
【あなたに】- 女一宮のもと。
【渡らせたまひぬ】- 大島本は「わたらせ給ぬ」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「我も渡らせ給ぬ」と「我も」を補訂する。『新大系』は底本のまま「渡らせ給ぬ」とする。
|
| 5.5.3 |
大将も近く参り寄りたまひて、御八講の尊くはべりしこと、いにしへの御こと、すこし聞こえつつ、残りたる絵見たまふついでに、
|
大将も近くに参り寄りなさって、御八講が立派であったことや、昔の御事を少し申し上げながら、残っている絵を御覧になる折に、
|
薫は后の宮のお近くへ寄って行き、御八講の尊かったことを言い、六条院のことも少しお話し申し上げながら、残った絵を拝見している時に、
|
|
| 5.5.4 |
|
「わたしの里にいらっしゃるこ皇女が、宮中から離れて、思い沈んでいらっしゃるのが、お気の毒に拝されます。
姫宮の御方から、お便りもございませんのを、このように身分が決定なさったので、お見捨てあそばされたように思って、気の晴れない様子ばかりしておりますが、こうした物を、時々お見せ下さいませ。
わたしが直接持って参りますのも、また、張り合いのないものです」
|
「私の所に来ておいでになります宮さんが、宮廷から離れて屈託した気持ちになっておられますのをお気の毒だと見ております。一品の宮様のお消息などをいただけませんことを人妻に降ったことで愛をお捨てになったように思って楽しまないふうなのでございますが、こういたしたものなどをときどき見せてあげてくだすってはいかがでしょう。私がその使いはいたします。私どものほうのも持ってまいります」
|
【この里に】- 以下「はべらじかし」まで、薫の詞。自邸にいる女二宮についていう。
【姫宮の御方】- 女一宮をさしていう。
【かやうのもの】- 絵をさしていう。
【ものせさせたまはなむ】- 大島本は「ものせさせ(せ+給イ、給イ#)ハなむ」とある。すなわち「給」を補入、のち抹消する。『集成』『完本』『新大系』は諸本に従って「ものせさせたまはなむ」と「たま」を補訂する。
【なにがしがおろして】- 『完訳』は「薫が持参するのではその絵も見るかいがないとする。女一の宮から直接贈られ、その手紙などに触れたいとする下心がある」と注す。
|
| 5.5.5 |
|
と申し上げなさると、
|
と中宮へ申し上げると、
|
【とのたまへば】- 大島本は「の給へハ」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「聞こえたまへば」と校訂する。『新大系』は底本のまま「の給へば」とする。
|
| 5.5.6 |
|
「変なこと。
どうしてお見捨て申し上げなさいましょう。
内裏では、近かったことにつけて、時々手紙のやりとりをなさったようですが、別々におなりになった時から、滞りがちになったのでしょう。
これから、お促し申し上げましょう。
そちらからもどうして差し上げなさらないのですか」
|
「まあそんなことで御交際をおやめになるものですか。同じ御所の中におられたころは、近いものですからときどき手紙が通ったのでしょうが、遠く離れ離れにおなりになった時からお手紙が途絶え始めて、そのままになったことなのでしょう。そのうち私からお勧めしてお書きになるようにしますよ。そちらからだってお手紙をお送りになればいいのにね」
|
【あやしく。などてか】- 以下「それよりもなどかは」まで、明石中宮の詞。
【近かりしにつきて、時々も聞こえたまふめりしを】- 大島本は「ちかゝりしにつきてとき/\もきこえ給めりしを」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「近かりしにつけて時々聞こえ通ひたまふめりしを」と校訂する。『新大系』は底本のまま「近かりしにつきて時/\も聞こえ給めりしを」とする。
【とだえたまへるに】- 大島本は「とたえ給へるに」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「とだえそめたまへるに」と「そめ」を補訂する。『新大系』は底本のまま「とだえ給へるに」とする。
【それよりもなどかは】- 女二宮のほうから。「などかは」の下に「聞こえたまはざらむ」などの語句が省略された形。
|
| 5.5.7 |
と聞こえたまふ。
|
と申し上げなさる。
|
と、宮は仰せられた。
|
|
| 5.5.8 |
「かれよりは、いかでかは。もとより数まへさせたまはざらむをも、かく親しくてさぶらふべきゆかりに寄せて、思し召し数まへさせたまはむをこそ、うれしくははべるべけれ。まして、さも聞こえ馴れたまひにけむを、今捨てさせたまはむは、からきことにはべり」 |
「あちらからは、どうしてできましょうか。
もともとお心に懸けていただけなかったとしても、こうして親しく伺候します縁にことよせて、お心を懸けてくださいましたら、嬉しいことでございます。
それ以上に、そのように親しくなさっていたのを、今お見捨てになるのは、つらいことでございます」
|
「そちらからは出過ぎたように思われておできにならないのでしょう。初めから御交渉のなかった方にいたしましても、私と宮様がたとの縁の続きに愛しておあげくださることになるのがうれしい成り行きなのですが、まして以前から御交際のあった間柄でおありになるのですから、私の所へ来られましたあとでお捨てになるのは、あの宮さんにとっておかわいそうなことです」
|
【かれよりは】- 以下「からきことにはべり」まで、薫の詞。
【数まへさせたまはむをこそ】- 大島本は「給ハんをこそ」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「たまはむこそ」と「を」を削除する。『新大系』は底本のまま「給はんをこそ」とする。
|
| 5.5.9 |
|
と申し上げなさるのを、「好色心があるのか」とは思いよりなさらなかった。
|
などと申しているのを、恋が言わせることと中宮はお悟りにならなかった。
|
【と啓せさせたまふを】- 大島本は「けいせさせ給を」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「啓したまふを」と校訂する。『新大系』は底本のまま「啓せさせ給を」とする。
【好きばみたるけしきあるか」とは思しかけざりけり】- 『全集』は「薫には女一の宮に近づこうとする計略があるとして、それへの語り手の評言をこめて言う」と注す。
|
| 5.5.10 |
立ち出でて、「一夜の心ざしの人に会はむ。ありし渡殿も慰めに見むかし」と思して、御前を歩み渡りて、西ざまにおはするを、御簾の内の人は心ことに用意す。げに、いと様よく限りなきもてなしにて、渡殿の方は、左の大殿の君たちなど居て、物言ふけはひすれば、妻戸の前に居たまひて、 |
お立ちになって、「先夜のお目当ての女に会おう。
先日の渡殿も慰めに見よう」とお思いになって、御前を渡って、西の方角にいらっしゃるのを、御簾の内側の女房は特に緊張する。
なるほど、たいそう風采よく、この上ない身のこなしで、渡殿の方では、左の大殿の公達などが座っていて、何か言っている様子がするので、妻戸の前にお座りになって、
|
薫は中宮のお居間を辞して、先夜の好意のある女友人にも逢おう、あの思い出の廊の座敷を心の慰めに見て行こうと思い、縁側伝いに西に向いて歩いて行った。御簾の中にいる女房たちはそれだけのことにすら心づかいのされる薫の大将であった。渡殿のほうには左大臣の息子らがいて、女房たちと話し合っている様子であったから、この人は妻戸のところにすわって、
|
【一夜の心ざしの人に】- 以下「慰めに見むかし」まで、薫の心中の思い。小宰相君をさす。
【げに、いと様よく】- 語り手が御簾の内の女房に同感した叙述。
|
| 5.5.11 |
「おほかたには参りながら、この御方の見参に入ることの、難くはべれば、いとおぼえなく、翁び果てにたる心地しはべるを、今よりは、と思ひ起こしはべりてなむ。ありつかず、若き人どもぞ思ふらむかし」 |
「よく参上はいたしますが、こちらの御方にはお目にかかることも、めったにございませんので、いつのまにか、老人めいた気持ちでございますが、今からは、と気を奮い起こしまして。
不似合いな振る舞いだと、若い人たちは思うでしょう」
|
「始終この院へはまいっている私ですが、こちらの宮様の御殿へ伺うことができないでいますと、自然老人めいた気持ちになるようになったのですが、これからはそうしていまいと決心してまいったのですよ。馴れない人間の恰好は滑稽なものに若い人たちからは見られることでしょう」
|
【おほかたには】- 以下「思ふらむかし」まで、薫の詞。
【この御方の】- 女一宮。
【ありつかず】- 大島本は「ありつかす」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「ありつかずと」と「と」を補訂する。『新大系』は底本のまま「ありつかず」とする。
|
| 5.5.12 |
|
と、甥の公達の方を御覧になる。
|
甥の公子たちのほうを見ながらこう言っていた。
|
【甥の君たち】- 薫の甥、すなわち夕霧の子息たち。
|
| 5.5.13 |
「今よりならはせたまふこそ、げに若くならせたまふならめ」 |
「今からお馴染みになられたら、なるほど若返りなされるでしょう」
|
「ただ今からお習いになりましたなら新鮮なお若さが拝見されることでしょう」
|
【今より】- 以下「ならせたまふならめ」まで、女房の詞。
|
| 5.5.14 |
など、はかなきことを言ふ人びとのけはひも、あやしうみやびかに、をかしき御方のありさまにぞある。
そのこととなけれど、世の中の物語などしつつ、しめやかに、例よりは居たまへり。
|
などと、とりとめもないことを言う女房たちの様子も、不思議と優雅で、風情のあるこちらの御方のご様子である。
特に用事ということはないが、世間話などをしながら、しんみりと、いつもよりは長居なさった。
|
などと戯れて言う女房らからも怪しいまでの高雅な感じの受け取られるのであった。何をおもな話題にするというのでもなく、世間話を平生よりもしんみりと話し込んで薫はいた。
|
|
|
第六段 明石中宮、薫と小宰相の君の関係を聞く
|
| 5.6.1 |
姫宮は、あなたに渡らせたまひにけり。大宮、 |
姫宮は、あちらにお渡りあそばした。
大宮が、
|
姫宮は中宮の御殿のほうへおいでになった。后の宮が、
|
【あなたに】- 寝殿東面の中宮のもとに。
|
| 5.6.2 |
|
「大将がそちらに参ったが」
|
「大将があちらへ行きましたか」
|
【大将のそなたに参りつるは】- 大宮、すなわち明石中宮の詞。「そなた」は女一宮のもとをさす。
|
| 5.6.3 |
|
とお尋ねになる。
お供して参った大納言の君が、
|
とお尋ねになると、一品の宮のお供をしてこちらへ来た大納言の君が、
|
【大納言の君】- 女一宮づきの女房。
|
| 5.6.4 |
|
「小宰相の君に、何かおっしゃろうとのことで、ございましょう」
|
「小宰相に話があると言っていらっしゃいました」
|
【小宰相の君に】- 以下「はべりつめれ」まで、大納言君の詞。
|
| 5.6.5 |
|
と申し上げると、
|
と申した。
|
【聞こゆるに】- 大島本は「きこゆるにれい」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「聞こゆれば」と校訂し「れい」を削除する。『新大系』は底本のまま「聞こゆるに例」とする。
|
| 5.6.6 |
「例、まめ人の、さすがに人に心とどめて物語するこそ、心地おくれたらむ人は苦しけれ。心のほども見ゆらむかし。小宰相などは、いとうしろやすし」 |
「いつもの、真面目人間が、やはり女性に心を止めて話をするのは、気のきかない人でしたら困ります。
心の底も見透かされるでしょう。
小宰相などは、とても安心です」
|
「まじめな人であって、さすがに女の友だちにも心の惹かれるところがあってむだ話もして行きたいのだろうがね。才能のない人が相手をしては恥ずかしい。女の価値がすぐ見破られるからね。小宰相ならまず安心だけれど」
|
【例、まめ人の】- 大島本は「れいまめ人の」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「まめ人の」と「れい」を削除する。『新大系』は底本のまま「例、まめ人の」とする。以下「いとうしろやすし」まで、中宮の詞。
|
| 5.6.7 |
|
とおっしゃって、ご姉弟であるが、この君を、やはり恥ずかしく思い、「女房たちも不注意に応対しないでほしい」とお思いになっていた。
|
こんなことをお言いになる宮は、御弟なのであるが、薫に周囲を観察されることを恥ずかしく思召し、女房らも飽き足らず思われるところを見せぬようにしてほしいと思召すのである。
|
【御姉弟なれど】- 明石中宮と薫は異母姉弟という間柄。
【人も用意なくて見えざらむかし】- 明石中宮の心中の思い。女房に対する要求。
|
| 5.6.8 |
|
「どの女房よりも心をお寄せになって、局などにお立ち寄りなさるのでしょう。
お話を親密になさって、夜が更けてお帰りになる時々もございましたが、普通のありふれた色恋沙汰ではないのでしょうか。
宮を、とても情けないお方と思って、お返事さえ差し上げないようでございます。
恐れ多いこと」
|
「あの人をだれよりも御ひいきになさいまして、部屋のほうへも寄ってお行きになることがよくあるようでございます。しんみりとお話をしておいでになることもございまして夜がふけてお帰りになることはありましても恋愛関係と申すようなことはなさそうに思われます。あの人兵部卿の宮様の御性情には反感を持っておりまして、お返辞すらよくいたさないようでございますのはもったいないことでございます」
|
【人よりは】- 以下「かたじけなきこと」まで、大納言君の詞。
【心寄せたまひて】- 主語は薫。
【夜更けて出でたまふ】- 大島本は「よふけてゐて給」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「出でなどしたまふ」と「などし」を補訂する。『新大系』は底本のまま「ゐ(い)で給」とする。
【宮を】- 匂宮。
【思ひて】- 主語は小宰相君。
|
| 5.6.9 |
と言ひて笑へば、宮も笑はせたまひて、
|
と言って笑うと、宮もにっこりあそばして、
|
と言い、大納言の君が笑うと、中宮もお笑いになって、
|
|
| 5.6.10 |
|
「ひどく見苦しいご様子を、知っているのがおもしろい。
何とかして、
あのようなお癖を止めさせ申したいもの
|
「あの宮の多情な本質が直感できるのだからいいね。どうしてあの方の悪癖を直させたらいいだろう、恥ずかしいと私は思う。だれも皆そう思っているだろうね」
|
【いと見苦しき御さまを】- 以下「この人びとも」まで、中宮の詞。
|
| 5.6.11 |
とのたまふ。
|
とおっしゃる。
|
こうお語りになった。
|
|
|
第七段 明石中宮、薫の三角関係を知る
|
| 5.7.1 |
|
「とても不思議な事を聞きました。
この大将殿が亡くしなさった人は、宮の二条の北の方のお妹君でした。
異腹なのでしょう。
常陸の前の介の何某の妻は、叔母とも母とも言っていますのは、どういうものでしょうか。
その女君に、宮が、まことにこっそりとお通いになりました。
|
「妙な話を私は聞いたのでございます。あの大将さんのお亡しになりました人は兵部卿の宮様の二条の院の奥様のお妹さんだったそうでございます。前常陸守の妻はその方の叔母であるとも、母であるとも申しますのはどういう理由であるのかよく存じません。
|
【いとあやしきことを】- 以下「泣き惑ひはべりけれ」まで、大納言君の詞。
【亡くなしたまひてし人は】- 浮舟をいう。
【常陸の前の守なにがしが妻は】- 『集成』は「「なにがし」は実名を言ったのをぼかして書く」と注す。
【叔母とも母とも】- 『完訳』は「中将の君(浮舟の母)の身分の低さが知られる叙述」と注す。
|
| 5.7.2 |
大将殿や聞きつけたまひたりけむ。
にはかに迎へたまはむとて、守り目添へなど、ことことしくしたまひけるほどに、宮も、いと忍びておはしましながら、え入らせたまはず、あやしきさまに、御馬ながら立たせたまひつつぞ、帰らせたまひける。
|
大将殿がお聞きつけになったのでしょうか。
急遽お迎えなさろうとして、番人を増やしなどして、厳重になさっているところに、宮も、とてもこっそりとお通いになりながら、お入りになることができず、粗末な姿で、お馬に乗って立ったまま、お帰りになりました。
|
その大将の愛人の所へそっと兵部卿の宮様も通ってお行きになったということでございまして、大将さんがそれをお聞きになりましたのか、にわかに宇治から京へ迎えようとなすって、監視の人などをきびしくお付けになりましたころに、宮様はまたおいでになったのでございますが、家の中へおはいりになることができませんで、危険なことでございますが、お馬のままで外に立っておいでになり、それなり帰っておしまいになったということでございまして、
|
|
| 5.7.3 |
|
女も、宮をお慕い申し上げていたのでしょうか、急に消えてしまいましたが、身投げしたようだと言って、乳母などの女房は、泣き暮れておりました」
|
女も宮様をお慕いしていたのでしょうか、にわかに行くえがわからなくなりましたのを、川へ身を投げたのであろうと、乳母というような者が泣き騒いで言っていたそうでございます」
|
【女も、宮を思ひきこえさせけるにや】- 『完訳』は「浮舟も匂宮になびいたために投身したと判断される点に注意。右近や侍従が真相をひた隠しにしていが、意外にも漏洩」と注す。
|
| 5.7.4 |
と聞こゆ。
宮も、「いとあさまし」と思して、
|
と申し上げる。
大宮も、「まことに呆れたことだ」とお思いになって、
|
大納言の君はこんな話を申し上げた。中宮がお驚きになったことは言うまでもない。
|
|
| 5.7.5 |
「誰れか、さることは言ふとよ。いとほしく心憂きことかな。さばかりめづらかならむことは、おのづから聞こえありぬべきを。大将もさやうには言はで、世の中のはかなくいみじきこと、かく宇治の宮の族の、命短かりけることをこそ、いみじう悲しと思ひてのたまひしか」 |
「誰が、そのようなことを言うのですか。
お気の毒な情けないことですね。
それほど珍しい事は、自然と噂になろうものを。
大将もそのようには言わないで、世の中のはかなく無常なこと、このような宇治の宮の一族の短命であったことを、ひどく悲しんでおっしゃっていたが」
|
「だれがまあそんな噂話をしていたの、ほんとうにかわいそうな話ではないか。そんな出来事はすぐ噂になるものだのに、そうでもなし、また大将もそんなふうには話さずに、人生の悲哀を強調して話すだけで、また宇治の宮さんの一族が皆短命で死ぬのは悲しいことだとは言っていたけれども」
|
【誰れか、さることは】- 以下「のたまひしか」まで、明石中宮の詞。
【いとほしく】- 大島本は「いとおしく」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「いといとほしく」と「いと」を補訂する。『新大系』は底本のまま「いとお(ほ)しく」とする。
【のたまひしか】- 主語は薫。
|
| 5.7.6 |
とのたまふ。
|
とおっしゃる。
|
|
|
| 5.7.7 |
|
「さあ、下衆は、確かでないことも申すものを、と思いますが、あちらに仕えておりました下童が、つい最近、小宰相の君の実家に出て参って、確かなことのように言いました。
このように不思議に亡くなったことは、誰にも聞かせまい。
大げさで、気味の悪い話だからといって、ひどく隠していたこととか。
そうして、詳しくはお聞かせ申し上げなかったのでしょう」
|
「ほんとうでございますか、どうでございますか、しもざまの者は確かでないこともほんとうらしく話にいたすものですが、その宇治の山荘におりました下童がついこのごろ宰相の実家のほうへ来まして、確かなことのように申していたそうでございます。そうした死に方をなさいましたことを世間へ知らすまい、自殺などという思いきったことをした人だと言わすまいと皆が隠すことに骨を折ったそうでございます。それで大将さんもくわしいお話をあそばさなかったのではないでしょうか」
|
【いさや、下衆は】- 以下「たてまつらぬにやありけむ」まで、大納言君の詞。
【かしこにはべりける下童】- 宇治宮邸の下童。
【隠しけることどもとて】- 大島本は「かくしける事ともとて」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「ことどもとや」と校訂する。『新大系』は底本のまま「事どもとて」とする。
【聞かせたてまつらぬにや】- 明石中宮に。
|
| 5.7.8 |
と聞こゆれば、
|
と申し上げると、
|
|
|
| 5.7.9 |
|
「まったく、このような話は、二度と他人には話さないように、と言わせなさい。
このような色恋沙汰で、お身の上を過ち、世人に軽々しく顰蹙をおかいになることになりましょう」
|
「その話をまたほかへ行ってするなと宰相からお言わせよ。そうした問題で宮は自身をだいなしにしておしまいになることにもなり、世間からも軽蔑されることにおなりになるだろう」
|
【さらに、かかること】- 以下「思はれぬべきなめり」まで、中宮の詞。
【思はれぬべきなめり】- 大島本は「思はれぬへきなめり」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「思はれたまふべきなめり」と「たまふ」を補訂する。『新大系』は底本のまま「思はれぬべきなめり」とする。
|
| 5.7.10 |
といみじう思いたり。
|
とたいそうご心配になった。
|
こうお言いになって、中宮は非常に御心配をあそばす御様子であった。
|
|
|
第六章 薫の物語 薫、断腸の秋の思い
|
|
第一段 女一の宮から妹二の宮への手紙
|
| 6.1.1 |
|
その後、姫宮の御方から、二の宮にお便りがあったのだった。
ご筆跡などが、たいそうかわいらしそうなのを見るにつけ、実に嬉しく、「こうしてこそ、もっと早く見るべきであった」とお思いになる。
|
それからまもなく一品の宮から女二の宮へお手紙が来た。御手跡のおみごとであるのを見ることのできたことが薫にはうれしくて、期待にはずれないごりっぱさである、もっと早くこれが拝見できる方法を講ずべきであったなどと思った。
|
【姫宮の御方より】- 女一宮。
【見るにも、いとうれしく】- 主語は薫。
【かくてこそ、とく見るべかりけれ】- 薫の心中の思い。
|
| 6.1.2 |
|
たくさんの趣のある絵をたくさん、大宮も差し上げあそばした。
大将殿は、それ以上に趣のある絵を集めて、差し上げなさる。
芹川の大将が遠君の、女一の宮に懸想をしている秋の夕暮に、思いあまって出かけて行った絵が、趣深く描けているのを、とてもよくわが身に思い当たるのである。
「あれほどまで思い靡いてくださる方があったら」と思うわが身が残念である。
|
多くの美しい絵などを中宮からもお送りになった。お礼として薫からもそれにまさった絵を集めて差し上げることにした。小説の芹川の大将が女一の宮を恋して秋の日の夕方に思い侘びて家から出て行くところを描いた絵はよく自身の心持ちが写されているように思われる薫であった。その人のように成功すべき恋でないのが残念であった。
|
【たてまつらせたまへり】- 「せたまふ」最高敬語。明石中宮が女二宮に。
【芹川の大将の遠君の、女一の宮思ひかけたる秋の夕暮に】- 『芹川物語』の主人公「遠君」(後に大将に昇進する若いころ)が女主人公の「女一宮」に恋慕する秋の夕暮場面。
【かばかり】- 以下「あらましかば」まで、薫の心中の思い。
|
| 6.1.3 |
|
「荻の葉に露が結んでいる上を吹く秋風も
夕方には特に身にしみて感じられる」
|
荻の葉に露吹き結ぶ秋風も
夕べぞわきて身にはしみにける
|
【荻の葉に露吹き結ぶ秋風も--夕べぞわきて身にはしみける】- 薫の独詠歌。
|
| 6.1.4 |
と書きても添へまほしく思せど、
|
と書き添えたく思うが、
|
と書き添えたい気がするのであるが、
|
|
| 6.1.5 |
|
「そのようなのを少しの様子にでも漏らしたら、とてもやっかいそうな世の中であるから、ちょっとしたことも、ちらっと出すことができない。
このようにいろいろと何やかやと、憂愁を重ねた果てに思うことは、亡き大君が生きていらっしゃったら、どうして他の女に心を傾けたりしようか。
|
そうしたことは気ぶりにも知れたならばどんなことの言われるかしれぬ世の中であるからと、思うことすらも洩らしがたい恋に心を悩ませ、はては宇治の大姫君さえ生きていてくれたならば、その人を妻とすることができていたのであれば、どんな人を見ても心の動揺することなどはなかったはずである。
|
【さやうなるつゆばかりの】- 以下「橋姫かな」まで、薫の心中の思い。故大君を追慕。『集成』は「以下、薫の心中に即した書き方」と注す。
【昔の人の】- 大島本は「むかしの人の」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「昔の人」と「の」を削除する。『新大系』は底本のまま「昔の人の」とする。
【心分けましや】- 大島本は「心わけましや」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「心を」と「を」を補訂する。『新大系』は底本のまま「心」とする。
|
| 6.1.6 |
|
今上の帝の内親王を賜うといっても、頂戴はしなかったろうに。
また、そのように思う女がいるとお耳にあそばしながら、このようなことはなかったろうが、やはり情けなく、わたしの心を乱しなさった宇治の橋姫だなあ」
|
現代の帝王の御女を賜わるといっても、自分はお受けをしなかったはずである、また自分がそれほど愛している妻があるとわかっておいでになって姫宮をお嫁がせになることもなかろう、何といっても自分の心の混乱し始めたのは宇治の橋姫のせいである
|
【得たてまつらざらまし】- 「まし」反実仮想の助動詞。女二宮と結婚しなかったろう、の意。
【聞こし召しながらは】- 主語は帝。
【橋姫かな】- 『完訳』は「大君。上に「なほ」とあり、やはり大君こそ憂愁の原点とする」と注す。
|
| 6.1.7 |
|
と思い余って、また宮の上に執着して、恋しく切なく、どうにもしようがないのを、馬鹿らしく思うまで悔しい。
この方に思い悩んで、その次には、呆れた恰好で亡くなった人が、とても思慮浅く、思いとどまるところのなかった軽率さを思いながら、やはり大変なことになったと、思いつめていたほどを、わたしの態度がいつもと違っていると、良心の呵責に苛まれて嘆き沈んでいた様子を、お聞きになったことも思い出されて、
|
と、こんなことを思ってゆくうちに薫の心はまた二条の院の女王の上に走って、恋しくも恨めしくもなり、取り返されぬ昔を愚かしいまでに残念に思った。もうどうすることもできないことなのであると、それを心に片づけたあとでは、また自殺をしてしまった浮舟が、思想的に幼稚でよこしまな情熱に逢ってたちまち動かされていった軽率さを認めながらも、さすがに煩悶を多くしていたこと、そのころに自分の気持ちの変わったことで、自責の念から歎きに沈んでいた様子を宇治で聞いて知ったことも思い出され、
|
【また宮の上に】- 以下「悔しき」まで、薫の心中に即した叙述。「宮の上」は中君をさす。
【これに思ひわびて、さしつぎには】- 中君に。『集成』は「以下、地の文」。『完訳』は「前の「思ひあまりては」に照応。憂愁が新たに女への執着を生み、それがまた新たな憂愁を生む趣」と注す。
【あさましくて亡せにし人の】- 浮舟をさす。『集成』は「思いもよらぬ死に方をした人(浮舟)」。『完訳』は「嘆かわしい有様で死んでいった宇治の女君」と注す。
【いみじとものを、思ひ入りけむほど】- 「思ひ入り」の主語は浮舟。「けむ」過去推量は薫の推量。
【わがけしき例ならずと】- 薫が浮舟の匂宮と通じていることを気づき、警戒し出した態度。
【聞きたまひしも思ひ出でられつつ】- 薫が右近から聞いたこと。
|
| 6.1.8 |
|
「重々しい方としての扱いでなく、ただ気安くかわいらしい愛人としておこう、と思ったわりには、実にかわいらしい人であったよ。
思い続けると、宮をお恨み申すまい。
女をもひどいと思うまい。
ただわが人生が世間ずれしていない失敗なのだ」
|
妻というような厳粛な意味の相手ではなく、心安く可憐な愛人としておきたいと思うのにはふさわしくかわいい女性であったと考えられ、もう宮に不快の念を持つまい、女をも恨むまい、ただ自分の非常識から若い愛人をああした場所へ置き放しにしていたのがあやまちの原因だったのである
|
【重りかなる方ならで】- 以下「おこたりぞ」まで、薫の心中の思い。
【思ひもていけば】- 薫の心中思惟。『完訳』は「ただわが--」に続く。あえて匂宮も浮舟も関わらぬ人としながら、己が人生に、現世に安住できぬ魂の彷徨の運命をみる。女一の宮への憂愁に満ちた追慕の情もここに重なるはず」と注す。
【宮をも】- 匂宮。
|
| 6.1.9 |
など、眺め入りたまふ時々多かり。
|
などと、物思いに耽りなさる時々が多かった。
|
と、こんなふうに物思いの末にはあきらめをつけることにもなった。
|
|
|
第二段 侍従、明石中宮に出仕す
|
| 6.2.1 |
|
悠長で、自制心が強くいらっしゃる人でさえ、このような方面には、身も苦しいことが自然と出て来るのを、宮は、彼以上に慰めかねながら、あの形見として、尽きない悲しみをおっしゃる相手さえいないが、対の御方だけは、「かわいそうに」などとおっしゃるが、深く親しんでいらっしゃらなかった、短い交際であったので、とても深くはどうしてお思いになろうか。
また、お気持ちのままに、「恋しい、悲しい」などとおっしゃるのは、気がひけるので、あちらにいた侍従を、例によって、迎えさせなさった。
|
静かな落ち着いた薫さえこんなふうに恋愛については身体にもさわるほどな苦しみも時には味わうのであるから、まして浮舟をお失いになった兵部卿の宮は心を慰めかねておいでになって、その人の形見の人として悲しみを語り合う人さえもおありでなく、対の夫人だけは哀れな人であったと言ってくれはするものの、姉妹として交わっていた期間はわずかなことであったから、深い悲しみは覚えているはずもない、また宮としては思召すままに恋しい悲しいとお言いになることも、夫人に向かってのことであるからお心のとがめられることであるために、あの山荘の侍従をお呼び寄せになった。
|
【心のどかに、さまよくおはする人だに】- 『細流抄』は「草子地也」と指摘。
【宮は、まして】- 匂宮は薫以上に。
【慰めかねつつ】- 大島本は「なくさめかねつゝ」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「慰めかねたまひつつ」と「たまひ」を補訂する。『新大系』は底本のまま「なぐさめかねつゝ」とする。
【かの形見に】- 浮舟をさす。
【対の御方ばかり】- 中君、浮舟の異母姉。
【深くも見馴れたまはざりける】- 主語は中君。中君と浮舟の交際は近年の二、三年前から。
【いと深くしも、いかでかはあらむ】- 語り手の感情移入による叙述。
【侍従をぞ】- 浮舟づきの女房、侍従。
|
| 6.2.2 |
|
皆女房たちは散り散りになって、乳母とこの人ら二人は、特別に目をかけてくださったのも忘れることができず、侍従は身内外の女房であるが、やはり話相手として暮らしていたが、どこにもないような川の音も、何か嬉しいこともあろうか、と期待していたうちは慰められたが、気持ち悪く大変に恐ろしくばかり思われて、京で、みすぼらしい所に、最近来ていたのを、捜し出しなさって、
|
女房たちは皆ちりぢりに去ってしまったあとに、乳母と右近、侍従だけは故人が最も親しんだ人たちであったから、喪の家から離れず、一方は親子であって、侍従は関係のない間柄ではあるが、いっしょに山荘へ残って暮らしていたのであったが、荒々しい川音を聞くのも、そのうち京の邸へ姫君の迎えられて行く日を楽しみにして辛抱されたものの、情けなく、気味悪くばかり思われて、京のちょっとした知り合いの家へこのごろは侍従だけが移って来ていた。宮がお捜させになって
|
【皆人どもは】- 宇治の女房たち。
【乳母とこの人二人】- 乳母とこの女房二人、すなわち右近と侍従の計三人。
【取り分きて思したりしも】- 主語は浮舟。特別に目をかけて下さった、の意。
【侍従はよそ人なれど】- 侍従は右近と違って乳母子でなく、後に仕えた普通の女房。
【世づかぬ川の音も、うれしき瀬もやある、と頼みしほどこそ】- 『弄花抄』は「祈りつつ頼みぞ渡る初瀬川うれしき瀬にも流れあふやと」(古今六帖三、川)を指摘。『源氏物語引歌』は「心みに猶おりたたむ涙川うれしき瀬にも流れあふやと」(後撰集恋二、六一二、藤原敏仲)を指摘。
【京になむ】- 係助詞「なむ」は「このころゐたりける」に係る。
【尋ねたまひて】- 大島本は「たつね給ひて」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「尋ね出でたまひて」と「出で」を補訂する。『新大系』は底本のまま「尋ね給ひて」とする。主語は匂宮。
|
| 6.2.3 |
|
「こうして仕えていなさい」
|
このまま二条の院の女房になるように
|
【かくてさぶらへ】- 匂宮の詞。
|
| 6.2.4 |
|
とおっしゃるが、「お心はお心としてありがたいが、女房たちが噂するのも、そのような方面のことが絡んでいるところでは、聞きにくいこともあろう」と思うと、お引き受け申さない。
「后の宮にお仕えしたい」と希望したので、
|
と仰せになるのであったが、夫人はともかくも、他の女房たちから浮舟の姫君と宮とのあるまじい情交の起こっていたことで何かと非難がましいことを言われるであろうことが思われお受けをしなかった。中宮の女房になってお仕えしたいとそれとなく内記に言ってもらうと、 |
【とのたまへば】- 大島本は「の給へハ」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「のたまへど」と校訂する。『新大系』は底本のまま「の給へば」とする。
【御心はさるものにて】- 以下「聞きにくきこともあらむ」まで、侍従の心中の思い。
【さる筋のこと混じりぬるあたりは】- 『完訳』は「浮舟が中の君の異母妹でありながら中の君の夫匂宮の情愛を受けたという、複雑な関係に遠慮」と注す。
【后の宮に参らむ】- 侍従の意向。
|
| 6.2.5 |
「いとよかなり。さて人知れず思し使はむ」 |
「とても結構なことだ。
それでは内々に目をかけてやろう」
|
「それはよい。そして自分が陰で勤めよくなるようにしてやろう」
|
【いとよかなり】- 以下「思しつかはむ」まで、匂宮の詞。
|
| 6.2.6 |
|
とおっしゃるのだった。
心細く頼りとするところのないのも慰むことがあろうかと、縁故を求めて出仕した。
「小ざっぱりとしたまあまあの下臈だ」と認めて、誰も非難しない。
大将殿もいつも参上なさるのを、見るたびごとに、何となくしみじみとする。
「とても高貴な大家の姫君ばかりが、大勢いらっしゃる宮邸だ」と女房が言うのを、だんだん目をとめて見るが、「やはりお仕えしていた方に似た美しい姫君はいないものだ」と思っている。
|
と言う宮のお返辞であった。侍従は姫君を失った心細さも慰むかと思い、手蔓を求めて目的の宮仕えをする身になった。見た目のきれいな下級女房であると人も認めて、侍従は悪くも言われていなかった。大将もよくまいるのを蔭で見るたびに昔が思われる物哀れな心になった。貴族の姫君たちだけのお仕えしている場所だと聞いていて、そうした上の女房たちの顔をこのごろ皆見知るようになってから考えても、浮舟の姫君ほどの美貌の人はないようであった。
|
【心細くよるべなきも慰むや】- 侍従の心中の思い。
【知るたより求め参りぬ】- 大島本は「もとめまいりぬ」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「求めて参りぬ」と「て」を補訂する。『新大系』は底本のまま「求めまいりぬ」とする。
【きたなげなくてよろしき下臈なり】- 明石中宮方の女房の侍従を見た評価。
【ものの姫君のみ、参り集ひたる宮】- 大島本は「まいりつとひたる」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「多く参り集ひたる」と「多く」を補訂する。『新大系』は底本のまま「まいりつどひたる」とする。明石中宮のもとには高貴な大家の姫君ばかりが女房として出仕している。
【見たてまつりし人に似たるはなかりけり】- 大島本は「見たてまつりし人に」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「なほ見たてまつりし人に」と「なほ」を補訂する。『新大系』は底本のまま「見たてまつりし人に」とする。侍従の感想。上流の貴族の娘ばかりだが、浮舟ほど美しい女房はいなかった、の意。
|
|
第三段 匂宮、宮の君を浮舟によそえて思う
|
| 6.3.1 |
|
今年の春お亡くなりになった式部卿宮の御娘を、継母の北の方が、特にかわいがらないで、その兄の右馬頭で人柄も格別なところもないのが、心を寄せているのを、不憫だとも思わずに縁づけている、とお耳にあそばしたことがあって、
|
今年の春お薨れになった式部卿の宮の姫君を、継母の夫人が愛しないで、自身の兄の右馬頭で平凡な男が恋をしているのに、姫君をかわいそうとも思わずに与えようとしていることを中宮へある人から申し上げると、
|
【式部卿宮】- 蜻蛉式部卿宮、桐壺帝の皇子、源氏の弟。
【継母の北の方】- 『完訳』は「式部卿宮の後妻。話題の「御むすめ」は先妻腹であろう」と注す。庶妻とも考えられよう。
【兄の馬頭】- 継母の北の方の兄弟。右馬頭、従五位上相当官。
【心懸けたるを】- 継母の北の方の兄弟の右馬頭が式部卿宮の御娘に懸想している。
【いとほしうなども思ひたらで】- 主語は継母の北の方。
【さるべきさまになむ契る】- 継母の北の方が縁づけた。
【聞こし召すたよりありて】- 主語は明石中宮。
|
| 6.3.2 |
「いとほしう。父宮のいみじくかしづきたまひける女君を、いたづらなるやうにもてなさむこと」 |
「お気の毒に。
父宮がたいそう大切になさっていた女君を、つまらないものにしてしまおうとは」
|
「気の毒な、宮様がたいへん大事になすった女王さんを、そんな廃り者にしてしまおうとするなどとは」
|
【いとほしう】- 以下「もてなさむこと」まで、明石中宮の詞。明石中宮と式部卿宮の御娘は従姉妹の間柄。
|
| 6.3.3 |
|
などと仰せになったので、ひどく心細くばかり思い嘆いていらっしゃる有様で、
|
と憐んで仰せられた。
「たよりない心細い思いをしているあなたに
|
【いと心細くのみ思ひ嘆きたまふありさま】- 式部卿宮の御娘の様子。
|
| 6.3.4 |
|
「やさしく、このようにおっしゃってくださるものを」
|
そうしたあたたかい同情を寄せてくださるのだから、中宮へお仕えしたら」
|
【なつかしう、かく尋ねのたまはするを】- 式部卿宮の御娘の兄弟の侍従の詞。明石中宮の詞を聞いてこう言う。
|
| 6.3.5 |
|
などと、ご兄妹の侍従も言って、最近迎え取らせなさった。
姫宮のお相手として、まことに最適のご身分の方なので、高い身分の方として特別の扱いで伺候なさる。
決まりがあるので、宮の君などと呼ばれて、裳くらいはお付けになるのが、ひどくおいたわしいことであった。
|
と、兄の侍従も宮仕えを勧めた女王を、このごろ中宮は手もとへ侍女にお迎えになった。女一の宮のお相手として置くのによい貴女と思召して、特別な御待遇を賜わって侍しているのであったが、お仕えする身であるかぎり、やはり宮の君などと言われ、唐衣までは着ぬが裳だけはつけて勤めているのは哀れなことであった。
|
【迎へ取らせたまひてけり】- 『完訳』は「中宮方で女房として引き取る」と注す。
【姫宮の御具にて】- 女一宮のお相手。
【限りあれば、宮の君などうち言ひて、裳ばかりひきかけたまふぞ、いとあはれなりける】- 『集成』は「(とはいえ)決りがあることなので(女房として出仕したものだから)、宮の君など名付けて。召名(女房としての呼び名)が付く」「裳くらいは。唐衣は略している体。主人の前では女房は裳、唐衣着用の正装が決りである」と注す。語り手の同情が移入された叙述。
|
| 6.3.6 |
|
兵部卿宮は、「この宮くらいは、恋しい人に思いよそえられる様子をしていようか。
父親王は兄弟であった」などと、例のお心は、故人を恋い慕いなさるにつけても、女を見たがる癖がやまず、早く見たいとお心にかけていらした。
|
兵部卿の宮は、この人だけは恋しい故人に似た顔をしているであろう。式部卿の宮と八の宮は御兄弟なのであるからなどと、例の多情なお心は、昔の人の恋しいために、新たな好奇心もお起こしになることがやまず、いつとなく宮の君を恋の対象としてお考えになるようになった。
|
【兵部卿宮】- 匂宮。
【この君ばかりや】- 以下「兄弟ぞかし」まで、匂宮の心中の思い。「この君」は式部卿の娘、宮の君をさす。
【恋しき人】- 浮舟をさす。
【父親王は兄弟ぞかし】- 宮の方の父故蜻蛉式部卿宮と浮舟の父宇治八宮の兄弟である、の意。
【人ゆかしき御癖やまで】- 『集成』は「女あさりの」。『完訳』は「女人にはまるで目がないというお癖がやまず」と注す。
|
| 6.3.7 |
|
大将は、「非難がましいことを言いたくなることだ。
昨日今日という間に、春宮に差し上げようかなどとお思いになり、わたしにもそのようなご様子をほのめかされたのだ。
このように無常な世の中の衰退を見ると、川の底に身を沈めても、非難されないことだ」などと思いながら、誰よりも同情をお寄せ申し上げなさった。
|
人生は味気ないとこの女王についても薫は思うのであった。まだ昨今というほどのことではないか、東宮の後宮へお入れになろうと父宮がお思いになり、自分へも娶らせようとされた姫君である、栄えた人のたちまち衰えてゆくのを見ては、水へはいってしまった人はそれを見ぬだけ賢明であったかもしれぬなどと薫は思い、他の女房に対するよりもこの女王に好意を寄せていた。
|
【大将】- 薫。
【もどかしきまでも】- 以下「わざにこそ」まで、薫の心中の思い。
【けしきばませたまひきかし】- 主語は蜻蛉式部卿宮。「東屋」巻に語られている。
【水の底に身を沈めても】- 浮舟の入水をさす。
【人よりは心寄せきこえたまへり】- 宮の方に対して。憐愍と同情から。
|
| 6.3.8 |
|
この院にいらっしゃるのを、内裏よりも広く興趣あって住みよい所として、いつもは伺候していない女房どもも、みな気を許して住みながら、広々とたくさんある対の屋や、渡廊や、渡殿などにいっぱいいる。
|
六条院に中宮のおいでになることは、宮中のお住居よりも広く住みよくだれも思い、時々まいるだけで始終は侍していぬ人までも皆上がって来ていて、はるばると多く続いた対、廊、渡殿の座敷は女房で満ちていた。
|
【この院におはしますをば】- 明石中宮が軽服のため六条院に里下りしている。
【常にしもさぶらはぬどもも】- 大島本は「さふらハぬともゝ」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「さぶらはぬ人どもも」と「人」を補訂する。『新大系』は底本のまま「さぶらはぬどもも」とする。
|
| 6.3.9 |
|
左大臣殿は、昔のご様子にも負けず、すべてこの上もなくお世話申し上げていらっしゃる。
盛んになったご一族なので、かえって昔以上に、華やかな点ではまさるのであった。
|
左大臣は父君の院の御在世当時にも劣らず中宮のためにあらゆる物をととのえて奉仕していた。末広がりになった一族であったから、かえって昔よりも六条院のはなやかさはまさってさえ見えた。
|
【左大臣殿】- 横山本や池田本は「右大殿」とある。『集成』は「右の大殿」と校訂。『完訳』は「左大臣殿」のまま、「「右大臣」とあるべきか。夕霧。六条院の現在の主である」と注す。
【営み仕うまつりたまふ】- 明石中宮の里下りをはじめとして万事に世話する。
【いかめしうなりたる】- 大島本は「なりたる」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「なりにたる」と「に」を補訂する。『新大系』は底本のまま「なりたる」とする。
|
| 6.3.10 |
|
この宮は、いつものお心ならば、幾月かの間に、どのような好色事でもなさっていたところが、すっかり落ち着きなさって、傍目には「少しは大人びてお直りになったなあ」と見えるが、最近は再び、宮の君に、ご本性を現して、まつわりつきなさるのであった。
|
兵部卿の宮が今までのようなふうでおありになれば、この集まった女性の中のある人々とこの幾月かのうちにはどんな問題を起こしておいでになるかもしれないのであるが、すっかりと冷静におなりになり、人から見れば少し性質がお変わりになったかと思われたのであるが、近ごろになってまた宮の君にお心を惹かれ、御本性どおりにつきまとっておいでになった。
|
【この宮】- 匂宮。
【例の御心ならば】- 『完訳』は「普通なら匂宮は、その好色な本性から宮の君などを相手に、浮気沙汰を引き起していたはず」と注す。現在、浮舟を失って悲嘆中。
【し出でたまはまし】- 「まし」反実仮想の助動詞。現在は悲嘆にくれて意気消沈。
【人目に「すこし生ひ直りたまふかな」と見ゆるを】- 大島本は「人めにすこしおいな越り給かな」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「人目には」「したまふかな」と「は」と「し」を補訂する。『新大系』は底本のまま「人目に」「給かな」とする。語り手の判断。
【このころぞまた】- 浮舟失踪後三か月が経過。
|
|
第四段 侍従、薫と匂宮を覗く
|
| 6.4.1 |
|
涼しくなったといって、后宮は、内裏に帰参なさろうとするので、
|
秋冷の日になって中宮は宮中へ帰ろうとあそばされるのであったが、
|
【涼しくなりぬとて】- 季節は初秋七月に推移。
【宮、内裏に参らせたまひなむと】- 明石中宮、蜻蛉式部卿の軽服三か月の喪が明けて、内裏に帰参。
|
| 6.4.2 |
|
「秋の盛りは、紅葉の季節を見ないというのは」
|
秋の盛りの紅葉の季にここで逢えないのは
|
【秋の盛り、紅葉のころを見ざらむこそ】- 女房の詞。係助詞「こそ」の下に「口惜しけれ」などの語句が省略。
|
| 6.4.3 |
|
などと、若い女房たちは残念がって、みな参集している時である。
池水に親しみ月を賞美して、管弦の遊びがひっきりなしに催され、いつもより華やかなので、この宮は、このような方面では実にこの上なく賞賛されなさる。
朝夕に見慣れていても、やはり今初めて見た初花のようなお姿でしていらっしゃるが、大将の君は、あまりそれほど入り込んだりなさらないので、こちらが恥ずかしくなるような気のおける方だと、みな思っていた。
|
残り惜しいことであると若い女房たちは言い、だれも皆実家にいず、このごろは六条院にまいっていた。水を愛し、月の景色を喜んで音楽の催しなども常にあった。兵部卿の宮は常よりもはなやかな六条院を愛して、この空気の中心のようになっておいでになるのである。朝夕にお顔を見ていながらも、いつも今咲きそめた花に逢う気のされる兵部卿の宮であった。薫はそれほど入り立っていないのであるために、若い中宮の女房たちは、この人が来れば緊張してしまうのであった。
|
【この宮ぞ】- 匂宮。
【かかる筋は】- 管弦の遊び。
【朝夕目馴れても、なほ今見む初花のさましたまへるに】- 匂宮の美しさ。『完訳』は「目のさめるような匂宮の美しさにいまさらながら感嘆させられる趣。女房の感想。次の薫のあり方と対比」と注す。
|
| 6.4.4 |
|
いつもの、お二方が参上なさって、御前にいらっしゃる間に、あの侍従は、物蔭から覗いて拝すると、
|
ちょうどこの二人の若い貴人の同時に中宮のお居間に来合わせている時であったが、宇治にいた侍従は物蔭からのぞいて、
|
【例の、二所参りたまひて】- 匂宮と薫、いつものように明石中宮のもとに参上。
【かの侍従は】- かつては浮舟づきの女房、現在は明石中宮のもとで下臈の女房として出仕。
|
| 6.4.5 |
|
「どちらの方なりとも縁付いて、幸運な運勢に思えたご様子で、この世に生きておいでだったらなあ。
あきれるほどあっけなく情けなかったお心であったよ」
|
どちらにもせよこのりっぱな方々の一人に愛されて生きておいでになればよかった。恵まれておいでになった幸運をわれから捨てておしまいになった姫君である
|
【いづ方にもいづ方にもよりて】- 以下「心憂かりける御心かな」まで、侍従の感想。浮舟の悲運を思う。「いづ方にも」は薫と匂宮。
【めでたき御宿世--おはせましかし】- 反実仮想の構文。浮舟が生きていたら。
【あさましくはかなく、心憂かりける御心かな】- 「御心」は浮舟の思慮。『集成』は「浮舟の入水を悔む、侍従のひそかな思い」。『完訳』は「自分だって下臈女房にならずにすんだろうに、との無念の気持」と注す。
|
| 6.4.6 |
|
などと、他人には、あの辺のことは少しも知っている顔をして言わないことなので、自分一人で尽きせず胸を痛めている。
宮は、内裏のお話など、こまごまとお話申し上げあそばすので、もうお一方はお立ちになる。
「見つけられ申すまい。
もう暫くの間は、ご一周忌も待たないで薄情な人だ、と思われ申すまい」と思うって、隠れた。
|
と思い、他の人には宇治の山荘のこと、薫の愛人であった姫君のことなどは知ったふうには言ってないことであったから心一つに残念がっていた。兵部卿の宮が御所のお話などを細かく母宮へしかかっておいでにもなったため、薫がお居間を出て行こうとするのを見、自分を見つけさすまい、一年の忌の来るのも済まさずに宇治を去ったのは故人へ情のないことであるとは思われたくないと思い、侍従はすぐに隠れてしまった。
|
【そのわたりのこと】- 宇治での出来事。
【宮は】- 匂宮。
【聞こえさせたまへば】- 匂宮が明石中宮に。
【いま一所は】- 薫をさす。
【見つけられたてまつらじ】- 以下「と見えたてまつらじ」まで、侍従の心中の思い。
【御果てをも過ぐさず心浅し】- 一周忌明けを待たず出仕したことをさす。
|
|
第五段 薫、弁の御許らと和歌を詠み合う
|
| 6.5.1 |
|
東の渡殿に、開いている戸口に、女房たちが大勢いて、話などをひっそりとしている所にいらして、
|
東の廊の座敷のあいた戸口に女房たちがおおぜいいてひそひそと話などをしている所へ薫は行き、
|
【物語などする所におはして】- 大島本は「ものかたりなとする所に」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「物語など忍びやかにする所」と「忍びやかに」を補訂する。『新大系』は底本のまま「もの語りなどする所」とする。主語は薫。
|
| 6.5.2 |
|
「わたしをこそ、女房は親しみやすくお思いになるべきではありませんか。
女でさえこのように気のおけない人はいません。
それでもためになることを、教えて上げられることもあります。
だんだんとお分かりになりそうですから、とても嬉しいです」
|
「私をあなたがたは親しい者として見てくださるでしょうか、女にだって私ほど安心してつきあえるものではありませんよ。それでも男ですから、あなたがたのまだ聞いていない新しい話も時にはお聞かせすることができるのですよ。おいおい私の存在価値がわかっていただけるだろうという自信がそれでもできましたからうれしく思っています」
|
【なにがしをぞ】- 以下「いとなむうれしき」まで、薫の詞。「なにがし」は薫自身をさす。
【女房は睦ましと思すべき。女だにかく心やすくはよもあらじかし】- 大島本は「女はうハむつましとおほすへき女たにかく心やすくハよもあらしかし」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「睦ましく思すべきや」「あらじかし」と「や」を補訂し「よも」を削除して校訂する。『新大系』は底本のまま「むつましとおぼすべき」「よもあらじかし」」とする。
【さるべからむこと】- 女房たちの知らないこと。
|
| 6.5.3 |
|
とおっしゃるので、とても答えにくくばかり思っている中で、弁のおもとといって、物馴れている年配の女房が、
|
こんな戯れを言いかけた。だれも晴れがましく思い、返辞をしにくく思っている中に、弁の君という少し年輩の女が、
|
【弁の御許】- 古参の女房。
|
| 6.5.4 |
|
「そのようにも親しくすべき理由のない者こそ、気兼ねなく振る舞えるのではないでしょうか。
物事はかえってそのようなものです。
必ずしもその理由を知ったうえで、くつろいでお話申し上げるというのでもございませんが、あれほど厚かましさが身についているわたしが引き受けないのも、見ていられませんで」
|
「お親しみくださる縁故のない者がかえって私のように恥じて引っ込んでいないことになります。ものは皆合理的にばかりなってゆくものではございませんですね。だれの家のだれの子でございますからと申しておつきあいを願うわけのものでもありませんけれど、羞恥心を取り忘れたようにお相手に出ました者はそれだけの御挨拶をいたしておきませんではと存じますから」
|
【そも睦ましく】- 以下「かたはらいたくてなむ」まで、弁御許の詞。
【恥ぢきこえはべらぬにや】- 大島本は「侍らぬにや」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「はべらぬや」と「に」を削除する。『新大系』は底本のまま「侍らぬにや」とする。
【面無くつくりそめてける身に負はさざらむも】- 『完訳』は「厚かましさが身についている私が応対の役を引き受けないのも、いたたまれぬ気がして」と注す。 【身に負はざらむも】-大島本は「おはささらんも」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「負はざらむも」と「さ」を削除する。『新大系』は底本のまま「負はさざらんも」とする。
|
| 6.5.5 |
と聞こゆれば、
|
と申し上げると、
|
と言った。
|
|
| 6.5.6 |
「恥づべきゆゑあらじ、と思ひ定めたまひてけるこそ、口惜しけれ」 |
「恥じる理由はあるまい、とお決めになっていらっしゃるのが、残念なことです」
|
「羞恥心も何も用のない相手だと私の見られましたのは残念ですね」
|
【恥づべきゆゑ】- 以下「口惜しけれ」まで、薫の詞。
|
| 6.5.7 |
|
などと、おっしゃりながら見ると、唐衣は脱いで押しやって、くつろいで手習いをしていたのであろう、硯の蓋の上に置いて、頼りなさそうな花の枝先を手折って、弄んでいた、と見える。
ある者は几帳のある所にすべり隠れ、またある者は背を向けて、押し開けてある妻戸の方に、隠れながら座っている、その頭の恰好を、興趣あると一回り御覧になって、硯を引き寄せて、
|
こんなことを薫は言いながら室の中を見ると、唐衣は肩からはずして横へ押しやり、くつろいだふうになって手習いなどを今までしていた人たちらしい。硯の蓋に短く摘んだ草花などが置かれてあるのはこの人らがもてあそんだものらしい。ある人は几帳の立ててある後ろへ隠れ、ある人は向こうを向き、ある者は押しあけられてある戸に姿の隠れるようにしてすわっているので、頭の形だけが美しく見えた。すべて感じよく思って薫は硯を引き寄せ、
|
【見れば、唐衣は】- 以下、薫の視点を通しての叙述。
【手習しけるなるべし】- 薫の推測。
【花の末手折りて】- 大島本は「はなのすゑ」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「花の末々」と「々」を補訂する。『新大系』は底本のまま「花の末」とする。
【かたへは】- 『集成』は「(女房の)半ばは」と注す。
|
|
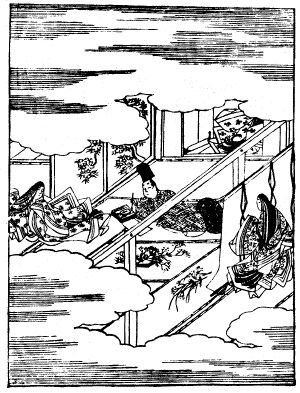 |
| 6.5.8 |
|
「女郎花が咲き乱れている野辺に入り込んでも
露に濡れたという噂をわたしにお立てになれましょうか
|
女郎花乱るる野べにまじるとも
露のあだ名をわれにかけめや
|
【女郎花乱るる野辺に混じるとも--露のあだ名を我にかけめや】- 薫の贈歌。「かけめや」反語表現。『河海抄』は「女郎花多かる野辺に宿りせばあやなくあだ名をや立ちなむ」(古今集秋上、二二九、小野美材)を指摘。
|
| 6.5.9 |
|
どなたも気を許してくださらないので」
|
こう書いて、「安心していらっしゃればいいのに」
|
【心やすくは思さで】- 歌に続けて書いた文言。
|
| 6.5.10 |
と、ただこの障子にうしろしたる人に見せたまへば、うちみじろきなどもせず、のどやかに、いととく、 |
と、ちょうどこの襖障子の後向きしていた女房にお見せになると、身動きもせずに、落ち着いて、すぐさま、
|
と言い、すぐ近くの襖子のほうを向いている人に見せると、相手は身動きもせず、しかもおおように早く、
|
【うしろしたる人】- 後向きにしている人。『完訳』は「中将のおもと」と注す。
|
| 6.5.11 |
|
「花と申せば名前からして色っぽく聞こえますが
女郎花はそこらの露に靡いたり濡れたりしません」
|
花といへば名こそあだなれをみなへし
なべての露に乱れやはする
|
【花といへば名こそあだなれ女郎花--なべての露に乱れやはする】- 中将の御許の返歌。『古今集』歌「女郎花多かる野辺に」歌を踏まえる。
|
| 6.5.12 |
|
と書いた筆跡は、ほんの一首ながら、風情があって、だいたいに無難なので、誰なのだろう、とお思いになる。
今参上した途中で、道をふさがれてとどまっていた者らしい、と思う。
弁のおもとは、
|
と書いた。手跡は、少ない文字であるが気品の見える感じよいものであるのを、薫は何という女房であろうと思って見ていた。今から中宮のお居間へこの戸口を通って行こうとして、薫の来たために出るにも出られずなった人らしく思われた。弁の君は、
|
【今参う上りける道に、塞げられてとどこほりゐたるなるべし】- 薫の推測。薫が中宮のもとに参上しようとした途中で戸口にいる薫に道を塞がれて留まっていた女房かと想像する。
|
| 6.5.13 |
|
「まことにはっきりした老人めいたお言葉、憎うございます」と言って、
|
「わざと老人じみたことをお言いになっては反感が起こるものですよ」と言い、
|
【いとけざやかなる翁言、憎くはべり】- 弁御許の詞。『完訳』は「薫の歌を、女に囲まれても浮気心を持たぬ老人言葉と戯れた」と注す。
|
| 6.5.14 |
|
「旅寝してひとつ試みて御覧なさい
女郎花の盛りの色にお心が移るか移らないか
|
「旅寝してなほ試みよをみなへし
盛りの色に移り移らず
|
【旅寝してなほこころみよ女郎花--盛りの色に移り移らず】- 弁御許の贈歌。薫を挑発する歌。
|
| 6.5.15 |
|
そうして後に、お決め申し上げましょう」
|
そのあとであなたをどんな性質で、お堅いともそうでないとも、きめましょう」
|
【さて後、定めきこえさせむ】- 歌に続けた詞。
|
| 6.5.16 |
と言へば、
|
と言うので、
|
とも言う。
|
|
| 6.5.17 |
|
「お宿をお貸しくださるなら、
一夜は泊まってみましょうそこらの花に
|
宿貸さば一夜は寝なんおほかたの
花に移らぬ心なりとも
|
【宿貸さば一夜は寝なむおほかたの--花に移らぬ心なりとも】- 薫の弁御許の挑発に応えた歌。
|
| 6.5.18 |
とあれば、
|
とあるので、
|
薫が言ったのである。
|
|
| 6.5.19 |
「何か、恥づかしめさせたまふ。おほかたの野辺のさかしらをこそ聞こえさすれ」 |
「どうして、恥をおかかせなさいます。
普通にいう野辺のしゃれを申し上げただけです」
|
「私を侮辱あそばすのでございますね。自分のことではございませんよ。一般的に抗議を申し上げただけでございます」
|
【何か】- 以下「聞こえさすれ」まで、弁御許の詞。ちょっと冗談を言っただけ、宿は貸しません、の意。
|
| 6.5.20 |
|
と言う。
とりとめのないことをほんのちょっとおっしゃっても、女房はその続きを聞きたくばかりお思い申し上げていた。
|
と弁は言う。こんなふうに戯れ言も薫は長くは言っていないらしく見えるのを若い女房たちは飽き足らず思っていた。
|
【はかなきことを--聞かまほしくのみ思ひきこえたり】- 女性からみた薫の魅力のあることを印象づけた叙述。
|
| 6.5.21 |
|
「うっかりしていました。
道を開けますよ。
特に意識して、あちらで恥ずかしがっていらやる理由が、きっとありそうな折ですから」
|
「思いやりのないことをしましたね。あなたの道をあけましょう。とりわけて私に顔をお見せにならない態度には理由のあることでしょう」
|
【心なし】- 以下「折にぞあめる」まで、薫の詞。
【分きても、かの御もの恥ぢのゆゑ】- 誰か他に男性がいて物陰に隠れていりのだろうという。暗に匂宮の存在をいう。
|
| 6.5.22 |
とて、立ち出でたまへば、「おしなべてかく残りなからむ、と思ひやりたまふこそ心憂けれ」と思へる人もあり。 |
と言って、お立ちになると、「だいたいこのような奥ゆかしいところがないだろう、とご想像なさるもがつらい」と思っている女房もいた。
|
と言い、薫の立って行くのを見て、だれもが弁のようにはしゃぐ者のように思われぬかと気にする人もあった。
|
【おしなべてかく】- 以下「心憂けれ」まで、ある女房の思い。自分たちまでが弁御許のようにあけすけに物を言う女房だと薫から思われてしまうのはいやだ、の意。
|
|
第六段 薫、断腸の秋の思い
|
| 6.6.1 |
|
東の高欄に寄り掛かって、夕日の影るにつれて、花が咲き乱れている御前の叢をお眺めやりになる。
何となくしみじみと思われて、「中んづく腸の断ち切れる思いがするのは秋の空だ」という詩句を、たいそう密やかに朗誦しながら座っていらっしゃった。
先程の衣ずれの音が、はっきり聞こえる感じがして、母屋の襖障子から通ってあちらに入って行くようである。
宮が歩いていらして、
|
東の高欄によりかかって、叢の中に夕明りを待って咲きそめる花のある植え込みを薫はながめていた。何も皆身にしむように思われる薫は、「就中断腸是秋天」と低い声で口ずさんでいた。先刻の人らしい衣擦れの音がして、中央の室から抜けてあちらへ行った。兵部卿の宮がそこへ歩いておいでになって、
|
【東の高欄に】- 寝殿の東の簀子にある高欄。
【中に就いて腸断ゆるは秋の天】- 「大抵四時は心惣べて苦なり中に就いて腸の断ゆるは是れ秋の天」(白氏文集、暮立)。『和漢朗詠集』秋にも所収の詩句。
【ありつる衣の音なひ、しるきけはひして】- 薫に道を塞がれ和歌を詠み交わした中将君が中宮のもとに参上。
【あなたに入るなり】- 「なり」伝聞推定の助動詞。薫が衣擦れの音で推測している叙述。
|
| 6.6.2 |
|
「こちらからあちらへ参ったのは誰か」
|
「ここから今あちらへ行ったのはだれか」
|
【これよりあなたに参りつるは誰そ】- 匂宮の詞。
|
| 6.6.3 |
と問ひたまへば、
|
とお尋ねになると、
|
と他の者に尋ねておいでになった。
|
|
| 6.6.4 |
|
「あちらの御方の中将の君です」
|
「一品の宮様のほうの中将さんでございます」
|
【かの御方の中将の君】- 女房の答え。中宮づきの女房、中将君だと言う。
|
| 6.6.5 |
|
と申し上げるのである。
|
と答える声も御簾の中でした。
|
【聞こゆなり】- 「なり」伝聞推定の助動詞。薫が女房の返事を耳にする。
|
| 6.6.6 |
「なほ、あやしのわざや。誰れにかと、かりそめにもうち思ふ人に、やがてかくゆかしげなく聞こゆる名ざしよ」と、いとほしく、この宮には、皆目馴れてのみおぼえたてまつるべかめるも口惜し。 |
「やはり、けしからぬ振る舞いだ。
誰だろうかと、ちょっとでも関心を持った人に、そのままこのように遠慮なく名前を教えてしまうとは」と、気の毒で、この宮に、皆が馴れ馴れしくお思い申し上げているようなのも残念だ。
|
おもしろくないことである、だれであろうとかりそめにもせよ好奇心の起こった人が、すぐにだれそれであると名ざしをして聞かれるではないか、とその女がかわいそうに思われ、また兵部卿の宮には皆よくお馴れしていて、隠すところもなくなっているのがなんとなくうらやましい気もする薫であった。
|
【なほ、あやしのわざや】- 以下「聞こゆる名ざしよ」まで、薫の感想。『完訳』は「浮気な男に問われるままに、安易に名を告げる女房の軽率さを非難」と注す。
【いとほしく】- 中将君に対する同情。
【この宮には】- 『集成』は「薫の心中に即した書き方」と注す。『完訳』は地の文扱い。
|
| 6.6.7 |
|
「無遠慮につっこんだお振る舞いに、女はきっとお負け申してしまおう。
わたしは、まことに残念なことに、こちらのご一族には、悔しくも残念なことばかりだ。
何とかして、ここの女房の中にでも、珍しいような女で、例によって熱心に夢中になっていらっしゃる女を口説き落として、自分が経験したように、穏やかならぬ気持ちを思わせ申し上げたい。
ほんとうに物事の分かる女なら、わたしの方に寄って来るはずだ。
けれども難しいことだな。
人の心というものは」
|
自由に接近してお行きになることができ、上手な技巧で誘惑をあそばされては女も負けることになるのであろう、自分にはそんなことができず、こちらの人たちとは、縁の遠いうとうとしいものになっているのが残念である。侍している人の中で、どうかして近ごろ兵部卿の宮がはげしく恋をしておいでになる人を自分のものにして、あの時に自分が苦しんだような思いを宮にもお味わわせしたい。聡明な女であれば自分のほうを愛するはずであるとは思われるが、こちらの考えどおりな心を持っているかどうかは頼みになるものでない
|
【おりたちてあながちなる御もてなしに】- 以下「人の心は」まで、薫の心中。匂宮の浮舟に対する振る舞い。
【女はさもこそ】- 女性一般。眼前の女房たちから浮舟まで含めた女性。
【この御ゆかり】- 匂宮とその同母の女一宮をさす。
【例の心入れて騷ぎたまはむを語らひ取りて】- 匂宮が熱中している女を横取りして、の意。
【わが思ひしやうに】- 自分がかつて味わったような苦い思いを匂宮にさせてやりたい。
【まことに心ばせあらむ人は、わが方にぞ寄るべきや】- 薫の自負。終助詞「や」詠嘆の気持ち。
|
| 6.6.8 |
|
と思うにつけても、対の御方の、あのお振る舞いを、身分にふさわしくないものとお思い申し上げて、まことに不都合な関係になって行くのが、その世間の評判をつらいと思いながらも、やはりすげなくはできない者とお分かりになってくださるのは、世にもまれな胸をうつことである。
|
と思われるにつけても、二条の院の女王が、宮のああした御放縦な恋愛生活を飽き足らず見て、自分の愛を頼むようになり、それを恋にまでなってはならぬ、世間の批評がうるさいと思いながら友情だけはいつも捨てぬのは珍しく聡明な態度で、自分としてはうれしいかぎりである、
|
【対の御方の】- 以下、薫の心中に即した叙述。
【かの御ありさまをば】- 匂宮の好色な振る舞い。
【いと便なき睦びになりゆくが】- 大島本は「なりゆくか」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「なりゆく」と「か」を削除する。『新大系』は底本のまま「なりゆくが」とする。自分薫との仲が不都合になって行く。
【さし放ちがたきものに思し知りたるぞ】- 主語は中君。
|
| 6.6.9 |
|
「そのような気立ての方は、大勢の中にいようか。
立ち入って深くは知らないので分からないことだ。
寝覚めがちに所在ないのを、少しは好色も習ってみたいものだ」
|
そんなすぐれた女性はこのおおぜいの若い女房たちの中に一人でもあるであろうか、深く接近して見ぬせいかないように思われる、物思いに寝ざめがちな慰めに恋愛の遊戯も少し習いたい
|
【さやうなる心ばせある人】- 以下「すこしは好きもならはばや」まで、薫の心中の思い。
【ここらの中に】- ここ明石中宮方に仕えている大勢の女房の中に。
【入りたちて深く見ねば知らぬぞかし】- 主語は薫。この中宮かたの様子を。
|
| 6.6.10 |
|
などと思うが、今はやはりふさわしくない。
|
と思うが、もう今は似合わしくないと薫は思った。
|
【今はなほつきなし】- 語り手の批評を含んだ叙述。
|
|
第七段 薫と中将の御許、遊仙窟の問答
|
| 6.7.1 |
|
例によって、西の渡殿を、先日に真似て、わざわざいらっしゃったのも変なことだ。
姫宮は、夜はあちらにお渡りあそばしたので、女房たちが月を見ようとして、この渡殿でくつろいで話をしているところであった。
箏の琴がたいそうやさしく弾いている爪音が、興趣深く聞こえる。
思いがけないところにお寄りになって、
|
例の氷を割られた日の西の渡殿へ、その日のようにふらふらと薫が来てしまったのも不思議であった。姫宮は夜だけ母宮の御殿のほうへおいでになるため、もうお留守になっていて、女房たちだけで月を見ると言い、渡殿に打ち解けて集まっていた。十三絃の琴を懐しい音で弾くのが聞こえた。人々の思いもよらぬこんな時に薫が出て来て、
|
【例の、西の渡殿を】- かつて女一宮を垣間見た場所。
【あやし】- 『評釈』は「そのような薫の行動を、「あやし」と評したのである」と注す。
【姫宮、夜はあなたに渡らせたまひければ】- 女一宮は夜は中宮方でお寝みになる。
【人びと月見るとて】- 女一宮づきの女房たち。
【寄りおはして】- 主語は薫。
|
| 6.7.2 |
|
「どうして、このように人を焦らすようにお弾きになるのですか」
|
「なぜ人を懊悩させるように琴など鳴らしていらっしゃるのですか。(遊仙窟。耳聞猶気絶、眼見若為憐)」
|
【など、かくねたまし顔にかき鳴らしたまふ】- 薫の詞。『源氏釈』は「故故将繊手 時時小絃 耳聞猶気絶 眼見若為怜」(遊仙窟)を指摘。女房の弾く箏琴のさまを遊仙窟の十娘が琴を弾くさまに比して言う。
|
| 6.7.3 |
|
とおっしゃると、皆驚いたにちがいないが、少し巻き上げた簾を下ろしなどもせず、起き上がって、
|
こう言うのに驚いたはずであるが、少し上げた御簾をおろしなどもせず、一人は身を起こして、
|
【皆おどろかるべけれど】- 大島本は「へけれと」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「べかるめれど」と「めれ」を補訂する。『新大系』は底本のまま「べけれど」とする。自分薫との仲が不都合になって行く。
|
| 6.7.4 |
|
「似ている兄様が、ございましょうか」
|
「崔季珪のようなお兄様がいらっしゃるかしら」
|
【似るべき兄やは、はべるべき】- 中将御許の詞。『遊仙窟』の「気調如兄 崔季珪之小妹」を踏まえた表現。
|
| 6.7.5 |
といらふる声、中将の御許とか言ひつるなりけり。
|
と答える声は、中将のおもととか言った人であった。
|
と言う。その声は中将の君といわれていた女であった。
|
|
| 6.7.6 |
|
「わたしこそが、御母方の叔父ですよ」
|
「私は宮様の母方の叔父なのですよ。(遊仙窟。容貌似舅潘安仁外甥、気調如兄崔季珪小妹)」
|
【まろこそ、御母方の叔父なれ】- 薫の詞。『遊仙窟』の「容貌似舅 潘安仁之外甥」を踏まえた表現。暗に自分は女一宮の叔父だ、話題を女一宮に転移。
|
| 6.7.7 |
と、はかなきことをのたまひて、
|
と、戯れをおっしゃって、
|
こんな冗談を言ったあとで、
|
|
| 6.7.8 |
|
「いつものように、あちらにいらっしゃるようですね。
どのようなことを、この里下がりのご生活の中でなさっておいでですか」
|
「いつものように中宮様のほうへ行っておしまいになったのでしょうね、宮様はお里住まいの間は何をしていらっしゃるのですか」
|
【例の、あなたに】- 以下「せさせたまふ」まで、薫の詞。女一宮が中宮方にいらっしゃる。
【御里住みの】- 六条院での生活。
|
| 6.7.9 |
|
などと、つまらないことをお尋ねになる。
|
思わずこんな問いを薫は発することになった。
|
【あぢきなく問ひたまふ】- 『集成』は「聞かでものことをお聞きになる」。『完訳』は「気もなさそうにお尋ねになる」と訳す。
|
| 6.7.10 |
「いづくにても、何事をかは。ただ、かやうにてこそは過ぐさせたまふめれ」 |
「どちらにいらしても、同じことです。
ただ、このような事をしてお過ごしでいらっしゃるようです」
|
「どこにいらっしゃいましても、別にこれという変わったことはあそばしません。ただいつもこんなふうでお暮らしになっていらっしゃるばかり」
|
【いづくにても】- 以下「過ぐさせたまふめれ」まで、中将御許の詞。
|
| 6.7.11 |
|
と言うと、「結構なご身分の方だ、と思うと、わけもない溜息を、うっかりしてしまったのも、変だと思い寄る人があっては」と紛らわすために、差し出した和琴を、ただそのまま掻き鳴らしなさる。
律の調べは、不思議と季節に合うと聞こえる音なので、聞き憎くもないが、最後までお弾きにならないのを、かえって気がもめると、熱心な人は、死ぬほど残念がる。
|
聞いていて美しいお身の上であると思うことで知らず知らず歎息の声の洩れて出たのを、怪しむ人があるかもしれぬと思う紛らわしに、女房たちが前へ出した和琴を、調子もそのままでかき鳴らす薫であった。律の調べは秋の季によく合うと言われるものであったから、気も入れて弾かぬ琴の音であるが、みずから感じの悪いものとは思われぬものの、長くも弾いていなかったのを、熱心に聞きいっていた人たちはかえって残り多さも出て苦しんだ。
|
【をかしの御身のほどや】- 以下「思ひ寄る人もこそ」まで、薫の心中の思い。『集成』は「優雅にお暮しのお身の上だな」。『完訳』は「なんと結構な御身の上よ」「自分に憂愁を抱かせる当人はもっぱら優雅な日々を暮しているとして、自らの苦悶が際だつ気持」と注す。
【あやしと思ひ寄る人もこそ】- 女一宮に寄せる思慕の情を女房たちに気どられてはならない。
【聞く声なれば】- 大島本は「きく」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「聞こゆる」と校訂する。『新大系』は底本のまま「聞く」とする。自分薫との仲が不都合になって行く。
【なかなかなり】- 女房たちの思い。かえって気がもめる、最後まで聞きたい。
|
| 6.7.12 |
|
「わたしの母宮もひけをおとりになる方だろうか。
后腹と申し上げる程度の相違だが、それぞれの父帝が大切になさる様子に、違いはないのだ。
がやはり、こちらのご様子は、たいそう格別な感じがするのが不思議なことだ。
明石の浦は奥ゆかしい所だ」などと思い続けることの中で、「自分の宿世は、とてもこの上ないものであった。
その上に、並べて頂戴したら」と思うのは、とても難しいことだ。
|
自分の母宮もこの姫宮に劣る御身分ではない、ただ后腹というわずかな違いがあっただけで朱雀院の帝の御待遇も、当帝の一品の宮を尊重あそばすのに変わりはなかったにもかかわらず、この宮をめぐる雰囲気とそれとに違ったもののあるのは不思議である。明石の女のもたらしたものはことごとく高華なものであったとこんなことを思う続きに薫は運命が自分を置いた所はすぐれた所であるに違いない、まして女二の宮とともに一品の宮までも妻に得ていたならばどれほど輝かしい運命であったであろうと思ったのは無理なことと言わねばならない。
|
【わが母宮も】- 以下「心にくかりける所かな」まで、薫の心中の思い。薫の母女三宮も中宮腹の女一宮に劣らない。
【隔てこそあれ】- 薫の母女三宮は女御腹。「こそあれ」の係結びは、逆接用法。
【帝々の思しかしづき】- 女三宮の父帝朱雀と女一宮の父今上帝の寵愛。
【明石の浦は心にくかりける所かな】- 明石一族の数奇な幸運を思う。
【わが宿世は】- 以下「持ちたてまつらば」まで、薫の心中の思い。今上帝の皇女女二宮を正室に迎えている。その上に女一宮までも頂戴したら、と夢想する。
【と思ふぞ、いと難きや】- 『全集』は「夢想としても、あまりしたたかな現世繁栄の欲望であろう。語り手が「いと難きや」と評するゆえんである」と注す。
|
|
第八段 薫、宮の君を訪ねる
|
| 6.8.1 |
|
宮の君は、こちらの西の対にお部屋を持っていた。
若い女房たちが大勢いる様子で、月を賞美していた。
|
宮の君はここの西の対の一所を自室に賜わって住んでいた。若い女房たちが何人もいる気配がそこにして皆月夜の庭の景色を見ていた。
|
【宮の君は】- 蜻蛉式部卿宮の女王。女一宮のもとに出仕。
【御方したりける】- お部屋をもっていた、の意。
|
| 6.8.2 |
|
「まあ、お気の毒に、こちらも同じ皇族の方であるのに」
|
そうであったあの人も浮舟らと同じ桐壺の帝の御孫であった
|
【いで、あはれ、これもまた同じ人ぞかし】- 薫の心中の思い。宮の御方も皇族の女王で、父親王にかわいがられていた方だ、の意。
|
| 6.8.3 |
|
とお思い出し申し上げて、「父親王が、生前に好意をお寄せになっていたものを」と口実にして、そちらにお出でになった。
童女が、かわいらしい宿直姿で、二、三人出て来てあちこち歩いたりしていた。
見つけて入る様子なども、恥ずかしそうだ。
これが世間普通のことだと思う。
|
と薫は思い出して、「式部卿の宮様に私を愛していただいたものなのだから」と独言を言いその座敷の前へ行ってみた。美しい姿の童女が略服になって、二、三人縁側へ出ていたが、薫を見て晴れがましいというように中へ隠れてしまった。これが普通の所の情景であると今見て来た廊の座敷と比べて薫は思った。
|
【親王の、昔心寄せたまひしものを】- 薫の心中の思い。生前に式部卿宮が薫に好意を寄せていた、薫を婿にと申し込まれたことを思う。
【見つけて入るさまども】- 大島本は「とも」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「どもも」と「も」を補訂する。『新大系』は底本のまま「ども」とする。童女たちが薫を見て室内に隠れ入る様子。
【これぞ世の常と思ふ】- 薫の思い。童女の振舞いを常識的な振舞いだと思う。男性から姿を見られまいとする態度。
|
| 6.8.4 |
|
南面の隅の間に近寄って、ちょっと咳払いをなさると、少し大人めいた女房が出て来た。
|
南の隅の間のそばで咳払いをすると、少し年のいったような女房が出て来た。
|
【南面の隅の間に寄りて】- 西の対の南廂の隅の間。
|
| 6.8.5 |
|
「人知れず好意をお寄せ申しておりますので、かえって、誰もが言い古るしてきたような言葉が、馴れない感じで、真似をしているようでございます。
真面目に、言葉以外の表現を探さずにおられません」
|
「人知れず好意を持っている者ですなどと申せば、それはだれも言うことだとお聞きになるでしょうし、またそうした若い人たちの口真似をすることも私にはできません。それよりも言葉でない実質的な御用に立つことはないかと捜しております」
|
【人知れぬ心寄せなど】- 以下「求められはべる」まで、薫の詞。
【言より外を】- 『異本紫明抄』は「思ふてふことよりほかにまたもがな君一人をばわきて忍ばむ」(古今六帖五、わきて思ふ)を指摘。
【求められはべる】- 「られ」自発の助動詞。
|
| 6.8.6 |
|
とおっしゃると、宮の君にも言い伝えず、利口ぶって、
|
と言うと、その女は女王にも取り次がず、賢がって、
|
【君にも言ひ伝へず】- 宮の君をさす。「君」は主人の、のニュアンスを含む。
|
| 6.8.7 |
|
「まことに思いもかけなかったご境遇につけても、故父宮がお考え申し上げていらっしゃった事などが、思い出されましてなりません。
このように、折々にふれて申し上げてくださるという。
蔭ながらのお言葉も、お礼申し上げていらっしゃるようです」
|
「思いがけぬお身の上におなりあそばしましたことにつきましても、宮様がどんなにいろいろなお望みを姫君の将来にかけておいでになりましたかと思われまして、悲しゅうございます。いつも御親切に仰せくださいまして、お宮仕えにおいでになりました御非難のお言葉なども、ごもっともだと女王様は言っておいでになることでございますよ」
|
【いと思ほしかけざりし】- 以下「よろこびきこえたまふめる」まで、女房の詞。思いもかけなかった宮仕え。
【思ひたまへ出でられてなむ】- この女房は式部卿宮家に仕えていた女房と分かる。「たまへ」謙譲の補助動詞、「られ」自発の助動詞。
【折々聞こえさせたまふなり】- 大島本は「給なり」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「たまふなる」と校訂する。『新大系』は底本のまま「給なり」とする。薫が宮の御方に対して。「なり」伝聞推定の助動詞。陰ながらのお言葉。
【よろこびきこえたまふめる】- 主語は宮の御方。
|
| 6.8.8 |
と言ふ。
|
と言う。
|
こんなことを言う。
|
|
|
第九段 薫、宇治の三姉妹の運命を思う
|
| 6.9.1 |
|
「世間並の扱いのようで、失礼ではないか」と気が進まないので、
|
並み並みの家の娘などのように聞こえることもはばからず言う女であるといやな気のした薫は、
|
【なみなみの人めきて、心地なのさまや】- 薫の感想。『集成』は「(取次の女房の挨拶だけでは)世間並みの扱いのようで、失礼ではないか、とおもしろくないので」と注す。
|
| 6.9.2 |
|
「もともと見捨てられない間柄としてよりも、今はそれ以上に、何か必要なことにつけても、お声をかけてくださったら嬉しく存じます。
よそよそしく人を介してなどでしたら、とてもお伺いできません」
|
「もとから血族であるためというようなことでなしに、好意を持つ男として、何かの御用をお命じくだすったらうれしいだろうと思います。うとうとしくお取り次ぎでお話などをしてくださるだけでは私も尽くしたいことがお尽くしできない」
|
【もとより思し捨つまじき筋よりも】- 以下「えこそ」まで、薫の詞。
【えこそ】- 下に「尋ねきこえざれ」などの語句が省略。『集成』は「とても(お話しできません)」。『完訳』は「とてもお伺いしかねます」と訳す。
|
| 6.9.3 |
とのたまふに、「げに」と、思ひ騷ぎて、君をひきゆるがすめれば、
|
とおっしゃるので、「おっしゃるとおりだ」と、あわてて気づいて、宮の君を揺さぶるらしいので、
|
と言った。そうであったというふうに女房たちは思い、姫君を引き動かすばかりにしたはずであったから、
|
|
| 6.9.4 |
|
「松も昔の知る人もいないとばかりに、つい物思いに沈んでしまいますにつけても、もとからの縁などとおっしゃる事は、ほんとうに頼もしく存じられます」
|
「松も昔の(たれをかも知る人にせん高砂の)と申すような孤立のたよりなさの思われます私を、血族の者とお認めくださいましておっしゃってくださいますあなたは頼もしい方に思われます」
|
【松も昔のとのみ】- 以下「頼もしうこそは」まで、宮の御方の詞。『源氏釈』は「誰れをかも知る人にせむ高砂の松も昔の友ならなくに」(古今集雑上、九〇九、藤原興風)を指摘。
【頼もしうこそは」--と】- 大島本は「たのもしうこそいと」とある。「い」は「ハ」の誤写であろう。『集成』『完本』『新大系』は諸本に従って「こそはと」と校訂する。
|
| 6.9.5 |
|
と、人を介してというのでなくおっしゃる声、まことに若々しく愛嬌があって、やさしい感じが具わっていた。
「ただ普通のこのような局住まいをする人と思へば、とても趣があるにちがいないが、ただ今では、どうしてほんのわずかでも、人に声を聞かせてよいという立場に馴れておしまいになったのだろう」と、何となく気になる。
「容貌などもとても優美であろう」と、見たい感じがしているが、「この人は、また例によって、あの方のお心を掻き乱す種になるにちがいなかろうと、興味深くもあり、めったにいないものだ」とも思っていらっしゃった。
|
取り次ぎの者に言うというふうにでもなしに、こういう声は若々しく愛嬌があって優しい味があった。ただの女房としてであればよい感じに受け取れたであろうが、今の身になっては、すぐに人に逢ってこれだけの言葉もみずから発しなければならぬものと思うようになったかと考えるとこの人を飽き足らぬものに薫は思われた。容貌も必ず艶な人であろうと思い、見たい心も覚えたが、この人がまた宮のお心を乱す原因になることであろうと思われ、絶対の信用の持てない人は相手にしたくない気にもなった。
|
【ただなべてのかかる住処の人と思はば】- 以下「ならひたまひけむ」まで、薫の心中の思い。ただ普通の局住まいする宮仕えの女房と思えば、しかし宮の御方は皇族の血をひく方である。
【ただ今は、いかでかばかりも、人に声聞かすべきものと】- 宮の御方が男性の薫に直接に声を聞かせること。『集成』は「身分にふさわしくない軽率さを批判する」。『完訳』は「親王の姫君ともあろうお方が。男に直接応答するような身分に下落した無残さを思う」と注す。 【人に声聞かすべき】-『集成』は「男に直接応答してもよいというふうに」。『完訳』は「人に声を聞かれなければならぬようなことに」と注す。
【容貌もいとなまめかしからむかし】- 薫の心中の思い。
【この人ぞ】- 以下「ありがたの世や」まで、薫の心中の思い。
【かの御心】- 匂宮の好色心。
【をかしうも、ありがたの世や】- 大島本は「ありかたのよやと」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「世やとも」と「も」を補訂する。『新大系』は底本のまま「世やと」とする。薫の感想。しっかりした女性というものは、めったにいないものだ。
|
| 6.9.6 |
|
「この方こそは、貴いご身分の父宮が大切にお世話して成人させなさった姫君だ。
また、この程度の女なら他にもそう多くいよう。
不思議であったことは、あの聖の近辺に、宇治の山里に育った姫君たちで、難のある方はいなかったことだ。
この、頼りないな、軽率だな、などと思われる女も、このようにちょっと会った感じでは、たいそう風情があったものだ」
|
この人こそは最上の家庭に生まれ、大事がられて育った、典型的な姫君というのに不足のない人で、他に幾人もない身の上だったのであるが、自分として頼もしい女性と思われぬのはどうしたことであろう、僧のような父宮に育てられ、都を離れた山里で大人になった人が姉女王にもせよ中の君にもせよ、皆完全な貴女になっていたではないか、このはかない性情の人、軽々しい人と今の心からは軽侮の念で見られる人も、こうしたわずかな接触で覚えさせた感じは悪いものでなかった、と薫は八の宮の姫君たちのことばかりがなつかしまれるのであった。
|
【これこそは】- 宮の御方をさす。以下「をかしかりしか」まで、薫の心中の思い。
【さる聖の御あたりに】- 宇治八宮のもとに。
【山のふところ】- 宇治をさす。
【この、はかなしや、軽々しや、など思ひなす人も】- 浮舟をさす。
|
|
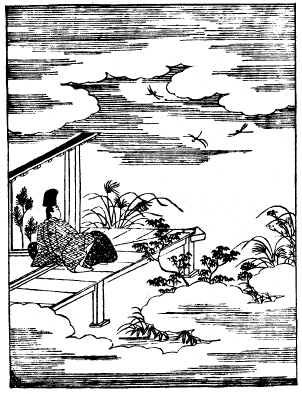 |
| 6.9.7 |
|
と、何事につけても、ただあのご一族の方をお思い出しなさるのであった。
不思議と、またつらい縁であった一つ一つを、つくづくと思い出し物思いにふけっていらっしゃる夕暮に、蜻蛉が頼りなさそうに飛び交っているのを、
|
宇治の姫君たちとはどれもこれも恨めしい結果に終わったのであったとつくづくと思い続けていた夕方に、はかない姿でかげろう蜻蛉の飛びちがうのを見て、
|
【かの一つゆかりをぞ】- 宇治八宮の一族。
【あやしう、つらかりける契りどもを】- 大君とは死別、中君は生別離の他人の妻、浮舟は行方不明、入水の噂。
【蜻蛉のものはかなげに飛びちがふを】- 蜉蝣目の昆虫。はかないものの象徴。
|
| 6.9.8 |
|
「そこにいると見ても、
手には取ることのできない見えたと思うとまた行く方
|
ありと見て手にはとられず見ればまた
行くへもしらず消えしかげろふ
|
【ありと見て手にはとられず見ればまた--行方も知らず消えし蜻蛉】- 薫の独詠歌。『花鳥余情』は「あはれとも憂しとも言はじかげろふのあるかなきかに消ぬる世なれば」(後撰集雑二、一一九一、読人しらず)「ありと見て頼むぞ難きかげろふのいつともしらぬ身とは知る知る」(古今六帖六、かげろふ)を指摘。
|
| 6.9.9 |
|
あるのか、ないのか」
|
「あはれともうしともいはじかげろふのあるかなきかに消ゆる世なれば」
|
【あるか、なきかの」--と】- 歌に続けた独り言。『源氏釈』は「たとへてもはかなきものは世の中のあるかなきかの身にこそありけれ」(出典未詳)を指摘。『対校』は「あはれとも憂しとも言はじかげろふのあるかなきかに消ぬる世なれば」(後撰集雑二、一一九一、読人しらず)。『新釈』は「世の中といひつるものはかげろふのあるかなきかのほどにぞありける」(後撰集雑四、一二六四、読人しらず)を指摘。
|
| 6.9.10 |
|
と、例によって、独り言をおっしゃった、とか。
|
と例のように独言を言っていた。
|
【例の、独りごちたまふ、とかや】- 『一葉抄』は「記者のわかかゝぬよしの詞也」と指摘。『全集』は「伝聞形式で余韻をこめる」。『集成』は「伝聞の形で語り手の存在を示す草子地」と注す。
|
| 著作権 |
| 底本 |
大島本 |
| 校訂 |
Last updated 8/29/2011(ver.2-2)
渋谷栄一校訂(C)
オリジナル
修正版
比較 |
| ローマ字版 |
Last updated 9/27/2011 (ver.2-1)
Written in Japanese roman letters
by Eiichi Shibuya(C)
オリジナル
修正版
比較 |
ルビ抽出
(ローマ字版から)
|
Powered by 再編集プログラム v4.05
ひらがな版
ルビ抽出 |
挿絵
(ローマ字版から)
|
'Eiri Genji Monogatari'
(1650 1st edition) |
|
Last updated 5/17/2002
渋谷栄一訳(C)(ver.1-2-2)
オリジナル
修正版
比較 |
|
|
Last updated 9/27/2011(ver.2-2)
渋谷栄一注釈(C)
オリジナル
修正版
比較 |
|