第二帖 帚木
#
本文
渋谷栄一訳
与謝野晶子訳
注釈
第一章 雨夜の品定めの物語
第一段 長雨の時節
【言ひ消たれたまふ】- 「光」の縁語で「言ひ消つ」と表現した(島津久基『講話』)。
【多かなるに】- 形容詞「多し」の連体形の活用語尾「る」が「ん」と撥音化されて無表記されたという説と、終止形「多かり」の「り」がナ行音の前で撥音化して無表記になったという説とがある。「なり」は、伝聞推定の助動詞。「に」は、接続助詞。下文の「いとど」との文脈から添加の意である。別本の陽明文庫本の「おほかめるに」(多いように見えるのに)は、語り手の視覚による推量となる。『全書』『集成』『完訳』に「多いそうだのに」「多いようだのに」「多いということだのに」とある。聞く人は物語享受者であるともに、源氏自身もまた聞き知って、「名をや流さむと忍びたまひける」という文脈。なお、『対訳』『大系』は「たくさんあるのに」「多くあるのに」という「なり」のニュアンスを訳出せず、『評釈』は「多いのだのに」という「なり」を断定の意味で訳出する。
【いとど、かかる好きごとどもを】- 以下「名をや流さむ」まで全体を、源氏の自戒の念とも解釈しうる。その場合、「いとど」は「流さむ」に係る。また、「かかる好きごとども」とは、源氏が心中密かに思っている内容をさす。地の文とすれば、「いとど」は「聞き伝へて」に係り、物語伝承者の行為をいうことになる。「かかる好きごとども」は世の中に知られた源氏の色恋沙汰をさす。それは、いまだ語られていないが、物語伝承者と物語筆記編集者をそれを知っているので、このような語り方をしたことになる。両方に解釈しうるところは、両方に解釈して、その幅と含みをもって読んでいく。いずれにしても、物語享受者に期待感を抱かせる表現である。
【軽びたる名をや流さむ】- 源氏の心。「や」(係助詞、疑問)、「む」(推量の助動詞)の主体者は源氏。それを、物語筆記編集者が間接的に伝える。
【語り伝へけむ人】- 物語伝承者。「けむ」は過去推量の助動詞。伝承を伝え聞いての想像。
【もの言ひさがなさよ】- 物語筆記編集者の物語伝承者のおしゃべりに対する非難。古注『河海抄』他に「ここにしも何匂ふらむ女郎花人の物言ひさがにくき世に」(拾遺集、雑秋、一〇九八、僧正遍昭)の和歌が指摘される。
【交野少将】- 交野少将は昔物語に色好みの人物として有名。しかし、当時の物語享受者は、物語中の人物も歴史上の人物も厳密に区別していなかった。
【笑はれたまひけむかし】- 物語筆記編集者がこの物語の主人公の行状に対して想像し(「けむ」)、かつ物語享受者に対し、同感を求め念を押した(「かし」)表現。
お浮気事かと、お疑い申すこともあったが、そんなふうに浮気っぽいありふれた思いつきの色恋事などは好きでないご性格で、時たまには、やむにやまれない予想を狂わせる気苦労の多い恋を、お心に思いつめなさる性癖が、あいにくおありで、よろしくないご素行もないではなかった。
【内裏】- 宮中。そこには父桐壺帝と憧れの継母藤壺がいる。
【大殿】- 左大臣邸。そこには正妻の葵の上がいる。当時の結婚形態は夫が妻の家へ通うという通い婚形態であった。
【忍ぶの乱れや】- 底本の明融臨模本には朱合点有り。「春日野の若紫の摺衣忍の乱れ限り知られず」(『伊勢物語』初段)の語句を引用。『源氏釈』が初指摘。『伊勢物語』初段の元服したばかりの色好みの主人公の世界を踏まえる。
【癖】- 「さしもあだめき目馴れたるうちつけの好き好きしさなどは好ましからぬ御本性」と「まれにはあながちに引き違へ心尽くしなることを御心に思しとどむる癖」の相背反する性格づけが好色人の伝統を継承するこの物語の主人公固有性をかたどっている。参考、秋山虔「好色人と生活者」(『王朝の文学空間』所収)。
【あやにくにて】- 「おりもおりというときに望ましからぬ方向に物事が起こって迷惑する状態」「おり悪く困ったことに」(小学館古語大辞典)。語り手の感想が言い込められている。挿入句。
【うち混じりける】- 過去の助動詞「けり」で、序段を語り上げる。
第二段 宮中の宿直所、光る源氏と頭中将
【調じ出でたまひつつ】- 接続助詞「つつ」は上に「よろづの」「何くれと」があるので、「調じ出づ」という動作の反復の意を表すと共に下文の御息子の君たちの「勤めたまふ」という動作も平行して行われている様子を表す。
【この御宿直所の】- 源氏の御宿直所、淑景舎(桐壺)。源氏を「この」という近称で呼称する。なお、青表紙本の大島本、伝冷泉為秀本には「御とのゐ所に」(御宿直所で)とある。その他の青表紙本、河内本、別本はすべて「--の」とある。『全集』『完訳』『新大系』が「に」とある本文を採用する。
右大臣が気を配ってお世話なさる住居には、この君もとても何となく気が進まずにいて、いかにも好色人らしい浮気人なのである。
【好きがましきあだ人なり】- 地の文とも読めるが、語り手の頭中将に対する批評が言い込められた表現。「あだ人」の語句について、『異本紫明抄』は「秋と言へばよそにぞ聞きしあだ人の我をふるせる名にこそありけれ」(古今集、恋五、八二四 、読人しらず)「あだ人もなきにはあらずありながら我が身にはまだ聞きぞ習はぬ」(後撰集、恋三、一一九七、左大臣)を指摘する。
【うち連れきこえたまひつつ】- 主語は頭中将。接続助詞「つつ」は同じ動作の反復・継続の意。
【学問】- 「学門 ガクモン」(『色葉字類抄』)「学文 ガクモン」(『文明本節用集』)。
【をさをさ立ちおくれず】- 副詞「をさをさ」は下の打消の助動詞「ず」と呼応して、少しも--ない、の意を表す。
【かしこまりもえおかず】- 副詞「え」は下の打消の助動詞「ず」と呼応して、--できない、の意を表す。
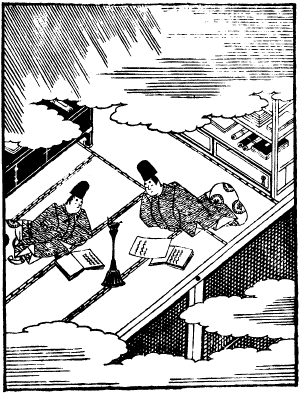
つれづれと降 り暮 らして、しめやかなる宵 の雨 に、殿上 にもをさをさ人少 なに、御宿直所 も例 よりはのどやかなる心地 するに、大殿油近 くて書 どもなど見 たまふ。
近 き御厨子 なる色々 の紙 なる文 どもを引 き出 でて、中将 わりなくゆかしがれば、
近くの御厨子にあるさまざまな色彩の紙に書かれた手紙類を取り出して、中将がひどく見たがるので、
【御宿直所】- 宮中の淑景舎(桐壺)、源氏の部屋
【書どもなど見たまふ】- 主語は源氏。この「書(ふみ)」は漢籍類。『新大系』は「手紙類をいろいろと。書物ではあるまい」と注す。
【色々の紙なる文どもを引き出でて】- 主語は頭中将。この「文(ふみ)」は恋文。当時の恋文は美しい色の紙に仮名文字の連綿体散らし書きで書かれていた。
【ゆかしがれば】- 「ゆかし」は、見たい、の意。頭中将は手紙の上包みを見ていたので、その中身を見たいのである。
不体裁なものがあってはいけないから」
【かたはなるべきもこそ】- 連語「もこそ」は、係助詞「も」+係助詞「こそ」は危惧・懸念を表す。下に「あれ」などの語が省略。
と、許 したまはねば、
普通のありふれたのは、つまらないわたしでも、身分相応に、互いにやりとりしては見ておりましょう。
それぞれが、恨めしく思っている折々や、心待ち顔でいるような夕暮などの文が、見る価値がありましょう」
【数ならねど】- 頭中将が謙遜して自分のことをいう。
【書き交はしつつ】- 接続助詞「つつ」は動作の反復・継続。
少しずつ見て行くと、「こんなにも、いろいろな手紙類がございますなあ」と言って、当て推量に「これはあの人か、あれはこの人か」などと尋ねる中で、言い当てるものもあり、外れているのをかってに推量して疑ぐるのも、おもしろいとお思いになるが、言葉少なに答えて何かと言い紛らわしては、取ってお隠しになった。
中将は少しずつ読んで見て言う。
「いろんなのがありますね」
自身の想像だけで、だれとか彼とか筆者を当てようとするのであった。上手に言い当てるのもある、全然見当違いのことを、それであろうと深く追究したりするのもある。そんな時に源氏はおかしく思いながらあまり相手にならぬようにして、そして上手に皆を中将から取り返してしまった。
【おほぞうなる】- 明融臨模本・大島本共に「おほそうなる」と表記する。「古写本の本文ではみな「おほぞう」で、「おほざう」ではない。」(岩波古語辞典)。『集成』は「おほざう」としている。
【片端づつ見るに】- 以下、再び物語の現在に戻って語る。主語は頭中将。「づつ」は接尾語、また副助詞とも。手紙の一部分ずつを見ていく。
【かくさまざまなる物どもこそはべりけれ】- 頭中将の詞。大島本を含め諸本「よく」とあるが、明融臨模本では「かく」と読める字形。「はべり」(動詞、丁寧の意を含む)+「けれ」(過去の助動詞、詠嘆の意、「こそ」を受け已然形)。「ございますなあ」という驚きのニュアンス。
【心あてに】- 『河海抄』は「心あてに折らばや折らむ初霜の置きまどはせる白菊の花」(古今集、秋下、二七七 、凡河内躬恒)を指摘する。
【それか、かれか】- 頭中将の詞。その手紙は誰々からのものか、あの手紙は誰々からのものか。
【をかしと思せど】- 主語は源氏。
【とかく紛らはしつつ】- 接続助詞「つつ」は動作の反復・継続。何かとごまかしごまししては、の意。
たくさんお有り
だろう。少し見たいね。そうしたら、この厨子も気持ちよく開け
【すこし見ばや】- 終助詞「ばや」は、話者の願望の意を表す。
「御覧 じ所 あらむこそ、難 くはべらめ」など聞 こえたまふついでに、「女 の、これはしもと難 つくまじきは、難 くもあるかなと、やうやうなむ見 たまへ知 る。
ただうはべばかりの情 けに、手走 り書 き、をりふしの答 へ心得 て、うちしなどばかりは、随分 によろしきも多 かりと見 たまふれど、そもまことにその方 を取 り出 でむ選 びにかならず漏 るまじきは、いと難 しや。
わが心得 たることばかりを、おのがじし心 をやりて、人 をば落 としめなど、かたはらいたきこと多 かり。
ただうはべばかりの
わが
ただ表面だけの風情で、手紙をさらさらと走り書きしたり、時節に相応しい返答を心得て、ちょっとするぐらいのは、身分相応にまあまあ良いと思う者は多くいると拝見しますが、それも本当にその方面の優れた人を選び出そうとすると、絶対に選に外れないという者は、本当にめったにないものですね。
自分の得意なことばかりを、それぞれ得意になって、他人を貶めたりなどして、見ていられないことが多いです。
こんな事から頭中将は女についての感想を言い出した。
「これならば完全だ、欠点がないという女は少ないものであると私は今やっと気がつきました。ただ上っつらな感情で達者な手紙を書いたり、こちらの言うことに理解を持っているような利巧らしい人はずいぶんあるでしょうが、しかもそこを長所として取ろうとすれば、きっと合格点にはいるという者はなかなかありません。自分が少し知っていることで得意になって、ほかの人を軽蔑することのできる厭味な女が多いんですよ。
【難くはべらめ】- 係助詞「こそ」の結び「はべらめ」已然形。強調のニュアンスを添える。ほとんどないでしょう。
【聞こえたまふついでに】- 申し上げる、その機会に、の意。
【女の、これはしもと】- 「女(をんな)」は、「男(をとこ)」の対。「女(め)」はやや卑しめられたニュアンスを伴う。「をんな」は、成人女性一般をさす。とくに結婚適齢期に達した女性、結婚関係を持つ女性に対して使われる。ここは、女性一般をさす。副助詞「しも」は強調の意。下に「めでたし」などの語が省略。頭中将の女性論。最初に結論を述べ、以下詳細に語るというのが、当時の論法である。
【見たまへ知る】- 「たまふ」は謙譲の補助動詞(下二段活用)。
【随分によろしきも多かり】- 「随分」は身分相応に、の意。「よろし」は、まあまあ良い、の意。「良し」よりは劣る。「わろし」よりは上。
【見たまふれど】- 「たまふ」は謙譲の補助動詞(下二段活用)已然形。
【かならず漏るまじきは】- 副詞「かならず」は下に打消し推量の助動詞「まじ」と呼応して、必ずしも--とは限らない、の意を表す。
容貌が魅力的でおっとりしていて、若々しくて家事にかまけることのないうちは、ちょっとした芸事にも、人まねに一生懸命に稽古することもあるので、自然と一芸をもっともらしくできることもあります。
【心を動かすこともあめり】- 「あめり」は「あるめり」が撥音便化して「あんめり」となり「ん」が無表記化された形。推量の助動詞「めり」(主観的推量のニュアンス)は話者である頭中将の推測。
【容貌をかしく】- 「をかし」は動詞「を(招)く」の形容詞形、好意をもって招き寄せたい、意。容貌に対しては、美しく心ひかれる、魅力的である、の意。
本物かと思って付き合って行くうちに、がっかりしないというのは、きっとないでしょう」
【さてありぬべき方】- 「さ」は、人に話してもよさそうな内容、「ぬ」(完了の助動詞、確述)、「べき」(推量の助動詞、当然)、「人に話しても確実に請け合えそうな」という、ニュアンス。
【なくなむあるべき】- 係助詞「なむ」は「べき」(連体形)に係り強調のニュアンスを添える。「べき」(推量の助動詞、推量)、頭中将の確信に満ちた推量、「きっと--であろう」。
【われ思し合はすることやあらむ】- 明融臨模本「我(我+モ)」の「モ」は後人の補入。大島本には「も」ナシ。『新大系』は大島本を底本として「我おぼしあはすること」とするが、『集成』『古典セレクション』は他本に拠って「我も思しあはする」と「も」を補っている。「われ」は源氏をさす。「思し合はする」の主語は、源氏。「や」(終助詞、疑問)、「む」(推量の助動詞)の疑問や推量の言語主体者は語り手。ここは語り手の源氏の心理を推量した挿入句。
「いと、さばかりならむあたりには、誰 れかはすかされ寄 りはべらむ。
取 るかたなく口惜 しき際 と、優 なりとおぼゆばかりすぐれたるとは、数等 しくこそはべらめ。
人 の品高 く生 まれぬれば、人 にもてかしづかれて、隠 るること多 く、自然 にそのけはひこよなかるべし。
中 の品 になむ、人 の心々 、おのがじしの立 てたるおもむきも見 えて、分 かるべきことかたがた多 かるべき。
下 のきざみといふ際 になれば、ことに耳 たたずかし」
何の取柄もなくつまらない身分の者と、素晴らしいと思われるほどに優れた者とは、同じくらいございましょう。
家柄が高く生まれると、家人に大切に育てられて、人目に付かないことも多く、自然とその様子が格別でしょう。
中流の女性にこそ、それぞれの気質や、めいめいの考え方や趣向も見えて、区別されることがそれぞれに多いでしょう。
下層の女という身分になると、格別関心もありませんね」
【誰れかはすかされ寄りはべらむ】- 反語表現の構文。誰がだまされ寄り付きましょうか、誰も騙されはしないの意。
【品高く生まれぬれば】- 「ぬれば」は(完了の助動詞「ぬ」已然形+接続助詞「ば」)順接の確定条件。以下、女性を「上の品(かみのしな)」「中の品(なかのしな)」「下の品(しものしな)」の三階層に分ける。
【ゆかしくて】- 主語は源氏。さらに聞きたい気持ち。
どれを三つの階級に分け置くことができるのか。
元の階層が高い生まれでありながら、今の身の上は落ちぶれ、位が低くて人並みでない人。
また一方で普通の人で上達部などまで出世して、得意顔して邸の内を飾り、人に負けまいと思っている人。
その区別は、どのように付けたらよいのだろうか」
【人げなき】- 以下の「劣らじと思へる」とは並立。「--人げなき人と、--劣らじと思へる人との、そのけじめは」という構文。
【直人】- 平凡な家柄の人、ここでは五位あるいは六位くらいの人を想定してよいか。なお、五位にも従五位下、従五位上、正五位下、正五位上の四段階がある。
【上達部】- 大臣・大中納言・参議及び三位以上の人。
当代の好色者で弁舌が達者なので、中将は待ち構えて、これらの品々の区別の議論を戦わす。
まことに聞きにくい話が多かった。
【いと聞きにくきこと多かり】- 語り手の登場人物たちの話の内容に対する評語。『一葉抄』他が草子地と指摘する。
第三段 左馬頭、藤式部丞ら女性談義に加わる
「なり上 れども、もとよりさるべき筋 ならぬは、世人 の思 へることも、さは言 へど、なほことなり。
また、元 はやむごとなき筋 なれど、世 に経 るたづき少 なく、時世 に移 ろひて、おぼえ衰 へぬれば、心 は心 としてこと足 らず、悪 ろびたることども出 でくるわざなめれば、とりどりにことわりて、中 の品 にぞ置 くべき。
また、
また、元は高貴な家筋であるが、世間を渡る手づるが少なく、時勢におし流されて、声望も地に落ちてしまうと、気位だけは高くても思うようにならず、不体裁なことなどが生じてくるもののようですから、それぞれに分別して、中の品に置くのが適当でしょう。
【時世に移ろひて】- 時勢に流されて、の意。
【出でくるわざなめれば】- 「なめれ」は「なるめれ」の「る」が撥音便化して「なんめれ」となり、さらに「ん」が無表記化された形。話者の断定と主観的推量のニュアンス。
なまなまの
なまじっかの上達部よりも非参議の四位連中で、世間の信望もまんざらでなく、元々の生まれも卑しくない人が、あくせくせずに暮らしているのが、いかにもさっぱりした感じですよ。
【なまなまの上達部よりも非参議の四位どもの】- 「なまじっかの上達部(三位)よりも非参議の四位連中で」という発言は、左馬頭などの発言としてはやや不遜な言い方になろう。頭中将なら許容されよう。
宮仕えに出て来て、思いもかけない幸運を得た例などもたくさんあるものです」などと言うと、
左馬頭がこう言う。
【宮仕へに出で立ちて】- 「宮仕へ」には、女房として出仕するというばかりでなく、帝の妃として仕えるという意もある。ここは後者の意。例えば、桐壺更衣の例などがある。
【など言へば】- 以上の話者には敬語が付いていない。
と源氏は笑っていた。
【笑ひたまふを】- 源氏の動作には「たまふ」という尊敬の補助動詞が付いて他の人々と区別される。
中将はたしなめるように言った。左馬頭はなお話し続けた。
【中将憎む】- 頭中将には、敬語が付かない。他者と区別するときは、「中将」と明記している。
「元 の品 、時世 のおぼえうち合 ひ、やむごとなきあたりの内々 のもてなしけはひ後 れたらむは、さらにも言 はず、何 をしてかく生 ひ出 でけむと、言 ふかひなくおぼゆべし。
うち合 ひてすぐれたらむもことわり、これこそはさるべきこととおぼえて、めづらかなることと心 も驚 くまじ。
なにがしが及 ぶべきほどならねば、上 が上 はうちおきはべりぬ。
うち
なにがしが
兼ね揃って優れているのも当たり前で、この女性こそは当然のことだと思われて、珍しいことだと気持ちも動かないでしょう。
わたくしごとき者の手の及ぶ範囲ではないので、上の品の上は措いておきましょう。
【さらにも言はず】- 副詞「さらに」は舌の「ず」と呼応して、まったく--ない、の意。全然論外である。
【さるべきこととおぼえて】- 「さる」は「すぐれたらむ」をさす。
【なにがしが及ぶべきほどならねば】- 「なにがし」は、謙遜の自称。左馬頭の詞と知られる。
さて、世 にありと人 に知 られず、さびしくあばれたらむ葎 の門 に、思 ひの外 にらうたげならむ人 の閉 ぢられたらむこそ、限 りなくめづらしくはおぼえめ。
いかで、はたかかりけむと、思 ふより違 へることなむ、あやしく心 とまるわざなる。
いかで、はたかかりけむと、
どうしてまあ、こんな人がいたのだろうと、想像していたことと違って、不思議に気持ちが引き付けられるものです。
【いかで、はたかかりけむと】- 「いかで--けむ」疑問表現の構文。「かかり」は、このような場所にこのような女性が、という内容をさす。「けむ」(過去推量の助動詞、「いかで」を受けて連体形)、どうして、このような場所にこのような素晴しい女性がいたのだろうと。
【いといたく思ひあがり】- 「思ひあがり」は、気位が高い、誇り高い、の意で、貴族としては賞賛される態度。
【いかが思ひの外にをかしからざらむ】- 「いかが--む」反語表現の構文。意外にも興味が惹かれる、の意。
【さる方にて】- 父親は老人で見苦しく太り過ぎ、兄弟も憎々しげな様子、思っても大したことのなさそうな家に、誇り高く暮らして、書、和歌、琴などの芸事なども雅趣ありげにこなし、生かじりの才能が窺える女性をさす。
【捨てがたきものをは】- 「をは」は、間投助詞「を」+終助詞「は」、共に詠嘆の意を表す。捨てたものではないなあ、の意。「をば」を格助詞「を」目的格+係助詞「は」濁音化(動作の対象を取り立てて強調する意)と解すると、「捨てたものではない人をば」どうするのか、それを受ける語句がない。『古典セレクション』は「「を」は間投助詞で詠嘆、「は」は係助詞で感動を表す。「をは」として文末にあるときは詠嘆を表す」と注す(待井新一も同説)。
「いでや、上 の品 と思 ふにだに難 げなる世 を」と、君 は思 すべし。
白 き御衣 どものなよらかなるに、直衣 ばかりをしどけなく着 なしたまひて、紐 などもうち捨 てて、添 ひ臥 したまへる御火影 、いとめでたく、女 にて見 たてまつらまほし。
この御 ためには上 が上 を選 り出 でても、なほ飽 くまじく見 えたまふ。
この
白いお召物で柔らかな物の上に、直衣だけを気楽な感じにお召しになって、紐なども結ばずに、物に寄り掛かっていらっしゃる灯影は、とても素晴らしく、女性として拝したいくらいだ。
この源氏の君のおんためには、上の上の女性を選び出しても、猶も満足ではなさそうにお見受けされる。
【白き御衣どもの】- 以下、源氏の服装や態度を描写する。
【なよらか】- 明融臨模本では本文「なよか」とあり、「ら」と「よ」がそれぞれ朱筆で左右行間に補入されている。右側に朱筆で補入された「ら」を採用した。『集成』『新大系』『古典セレクション』は「なよよか」とする。踊り字「ゝ」と「ら」の字体は大変よく似ている。『岩波古語辞典』は「なよよか」「なよらか」両語を掲出している。
【しどけなく着なしたまひて】- わざとだらしなくお召しになって、の意。
【女にて見たてまつらまほし】- 主語は一座の男たち。源氏を女性として拝見したい。源氏は中性的な容貌姿態をしていたのであろう。
【この御ためには】- 源氏をさす。
さまざまの人 の上 どもを語 り合 はせつつ、
「おほかたの世 につけて見 るには咎 なきも、わがものとうち頼 むべきを選 らむに、多 かる中 にも、えなむ思 ひ定 むまじかりける。
男 の朝廷 に仕 うまつり、はかばかしき世 のかためとなるべきも、まことの器 ものとなるべきを取 り出 ださむには、かたかるべしかし。
男性が朝廷にお仕えし、しっかりとした世の重鎮となるような方々の中でも、真の優れた政治家と言えるような人物を数え上げるとなると、難しいことでしょうよ。
【えなむ思ひ定むまじかりける】- 副詞「え」--打消推量の助動詞「まじかり」で不可能の意。係助詞「なむ」--過去の助動詞「ける」連体形、詠嘆の意。係結びの法則、強調のニュアンスを表す。
【男の朝廷に】- 以下、男性官吏の国政の運営の難しさを例にあげて、やがて家政の運営の難しさへと進めていく論法である。
【世のかためとなるべきも、まことの器ものとなるべき】- 「--べき、--べき」という並立の文章表現である。「世の固め」は世の中を治めること。国家の柱石。男性官吏でも国家の柱石となり大器を見つけ出すのは難しいと、結論から述べる。
とあればかかり、あふさきるさにて、なのめにさてもありぬべき
ああ思えばこうであったり、何かと食い違って、不十分ながらにもまあまあやって行けるような女性が少ないので、浮気心の勢いのままに、世の女性の有様をたくさん見比べようとの好奇心ではないが、ひたすら伴侶としたいばかりに、同じことなら、自ら骨を折って直したり教えたりしなければならないような所がなく、気に入るような女性はいないものかと、選り好みしはじめた人が、なかなか相手が決まらないのでしょう。
【とあればかかり、あふさきるさにて】- 明融臨模本は「あふさきるさにて」に朱合点有り。『源氏釈』は「そゑにとてとすればかかりかくすればあないひしらずあふさきるさに」(古今集、俳諧、一〇六〇、読人しらず)を指摘した(ただし、第一句が「しかありと」または「しかあれは」とある)。『古今集』の本文は「とすればかかり」であるが、『源氏物語』の本文では「とあればかかり」とするものが多い。「あふさきるさ」は、一方が良ければ一方が悪いこと、行き違って物事がうまく行かないさま。
【なのめにさてもありぬべき】- 【なのめにさても】-十分とは言えなくても、不十分ながらも、の意。 【さてもありぬべき】-「さ」は家庭の主婦として。「ぬ」(完了の助動詞、確述)+「べき」(推量の助動詞、可能)、家庭の主婦として必ずやって行けるだろう、のニュアンス。
【少なきを】- 接続助詞「を」原因理由を表す。--ので、の意。
かならずしもわが思 ふにかなはねど、見 そめつる契 りばかりを捨 てがたく思 ひとまる人 は、ものまめやかなりと見 え、さて、保 たるる女 のためも、心 にくく推 し量 らるるなり。
されど、何 か、世 のありさまを見 たまへ集 むるままに、心 に及 ばずいとゆかしきこともなしや。
君達 の上 なき御選 びには、まして、いかばかりの人 かは足 らひたまはむ。
されど、
しかし、なあに、世の中の夫婦の有様をたくさん拝見していくと、想像以上にたいして羨ましいと思われることもありませんよ。
公達の最上流の奥方選びには、なおさらのこと、どれほどの女性がお似合いになりましょうか。
【推し量らるるなり】- 「るる」自発の助動詞。「なり」断定の助動詞。自然と想像されるのです、の意。
【されど、何か】- 「何か」は下に係っていく語がない。よって、「何か」は感動詞、なんの、なあに、の意。「いやなあに、どうしてどうして。上のことを軽く打消し、反対のことを述べるときに用いる語」(待井新一)。
【君達の】- ここでは、源氏や頭中将を念頭において言った表現である。
【足らひたまはむ】- 明融臨模本「たら(ら=く)ひ」とある。「く」は後人の筆。大島本は「たくひ」とある。『集成』『新大系』『古典セレクション』は「たぐひ」と校訂する。明融臨模本の本行本文のままとする。推量の助動詞「む」連体形、推量の意。「いかばかりの人かは」と呼応して、疑問の意となる。反語とまではいえまい。
艶っぽくて女性的だと見えると、度を越して情趣にこだわって、調子を合わせると、浮わつきます。
これを、第一の難点と言うべきでしょう。
【思はせつつ】- 接続助詞「つつ」動作の反復・継続を表す。
【言少ななるが】- 「少な」形容詞、語幹、断定の助動詞「なる」連体形。以上の文の主語となっている。
【もて隠すなりけり】- 過去の助動詞「けり」詠嘆を表す。
【とりなせば、あだめく】- 「とりなせば」の主語は男、「あだめく」の主語は相手の女。相手の情趣に合わせて機嫌をとっていると、女はますます色っぽい態度をとるようになってくる、の意。
【もののあはれ知り過ぐし】- 風流性に傾き過ぎるタイプの女性評。
【見えたるに】- 接続助詞「に」逆接の意。
【まめまめしき筋を立てて】- 家事一点張りのタイプの女性評。
【ばかりをして】- これを受ける述語がない。したがって、ここで文が切れる。こうした女も困ったものだ、の意が下に略されている。
親しい妻で理解してくれそうな者とこそ語り合いたいものだと思われ、つい微笑まれたり、涙ぐんだり、あるいはまた、無性に公憤をおぼえたり、胸の内に収めておけないことが多くあるのを、理解のない妻に、何で聞かせようか、聞かせてもしかたがない、と思いますと、ついそっぽを向きたくなって、人知れない思い出し笑いがこみ上げ、『ああ』とも、つい独り言を洩らすと、『何事ですか』などと、間抜けた顔で見上げるようなのは、どうして残念に思われないでしょうか。
【疎き人に、わざとうちまねばむやは】- 係助詞「やは」反語の意を表す。親しくない他人にわざわざそっくり話して聞かせようか、そのようなことはしない、親しい妻と思えばこそ聞かせようとするのだ、意。
【見む人】- 妻をいう。
【おほやけ腹立たしく】- (1)「おほやけはらだたしき」(集成・新大系)、(2)「おほやけばら立たしき」(古典セレクション)。「公腹立つ」の語例は、『枕草子』二六八段にある。その形容詞形の「公腹立たし」であるが、どう連濁するか判然としない。『岩波古語辞典』『古語大辞典』では「おほやけはらだたし」を見出し語とする。
【何にかは聞かせむ】- 反語表現。「聞きわき思ひ知らぬ」妻であったら、の文意が省略されている。理解のない妻に、何で聞かせようか、聞かせてもしかたがない、の意。
【うち独りごたるるに】- 「るる」自発の助動詞。接続助詞「に」順接の意。
【いかがは口惜しからぬ】- 反語表現。どうして残念に思わないことがあろうか、そう思わずにはいられない、の意。以上、実務一点張りの妻の場合、家事や日常生活に埋没している妻の論。後に、夕霧の妻である雲居雁の例がこれに近い(「横笛」「夕霧」巻)。
ただひたふるに子 めきて柔 らかならむ人 を、とかくひきつくろひてはなどか見 ざらむ。
心 もとなくとも、直 し所 ある心地 すべし。
げに、さし向 ひて見 むほどは、さてもらうたき方 に罪 ゆるし見 るべきを、立 ち離 れてさるべきことをも言 ひやり、をりふしにし出 でむわざのあだ事 にもまめ事 にも、わが心 と思 ひ得 ることなく深 きいたりなからむは、いと口惜 しく頼 もしげなき咎 や、なほ苦 しからむ。
常 はすこしそばそばしく心 づきなき人 の、をりふしにつけて出 でばえするやうもありかし」
げに、さし
心配なようでも、きっと直し甲斐のある気持ちがするでしょう。
なるほど、一緒に生活するぶんには、そんなふうでもかわいらしさに欠点も許され世話をしてやれようが、離れていては必要な用事などを言いやり、時節に行なうような事柄の風流事にも実用事などにも、自分では判断ができず深い思慮がないのは、まことに残念で頼りにならない欠点が、やはり困ったものでしょう。
普段はちょっと無愛想で親しみの持てない女性が、何かの事に思わぬでき映えを発揮するようなこともありますからね」
【などか見ざらむ】- 反語表現。「見る」は結婚する意。どうして結婚しないでいられようか、そうするのも悪くないことだ、の意。
【さてもらうたき方に】- 連語「さても」の「さ」は「心もとなくとも」をさす。
【をりふし】- 「時節 ヲリフシ」(『名義抄』)。
第四段 女性論、左馬頭の結論
容貌はまったく問題ではありません。
ひどく意に満たないひねくれた性格でさえなければ、ただひたすら実直で、落ち着いた心の様子がありそうな女性を、生涯の伴侶としては考え置くのがよいですね。
【さらにも言はじ】- 副詞「さらに」--打消推量の助動詞「じ」、決して--ない、少しも--ない、の意を表す。
【ねぢけがましきおぼえだになくは】- 副助詞「だに」は下に打消しの語を伴って、最低限・最小限のニュアンスを添える。「なくは」(形容詞、連用形+係助詞「は」)は仮定条件を表す。「--さえなければ」の意。『河海抄』は「奈良山の児の手柏のふたおもてとににもかくにもねぢけ人かも」(古今六帖六、かしは、四三〇三)を指摘した。「ねぢけ」の語から連想される和歌である。
【よるべをぞ、つひの頼み所には思ひおくべかりける】- 係助詞「ぞ」は「べかりける」(推量の助動詞「べし」当然の意、連用形+過去の助動詞「けり」連体形、詠嘆の意)に係る。
安心できてのんびりとした性格さえはっきりしていれば、表面的な情趣は、自然と身に付けることができるものですからね。
【うち添へたらむをば】- 推量の助動詞「む」連体形、仮定・婉曲の意味。下に「女」などの語が省略されている。格助詞「を」目的格+係助詞「は」濁音化した形、動作の対象を取り立てて強調するニュアンスを表す。加わっているような女をば、の意。「よろこびに思ひ」に係る。
【後れたる方あらむをも】- 推量の助動詞「む」仮定・婉曲の意味。少し劣っている方面があるようでも、の意。係助詞「も」は同類を表す。「求め加へじ」に係る。
【所だに強くは】- 副助詞「だに」は最低限・最小限の希望ぼ意を表す。「強く」(連用形)+係助詞「は」仮定条件を表す。「おのづからもてつけつべき」に係る。
【もてつけつべきわざをや】- 「もてつけ」+「つ」(完了の助動詞、確述)+「べき」(推量の助動詞、可能)+「わざ」+「をや」(間投助詞+終助詞、詠嘆、強い感動の意を表す)。身に付けることがきっとできるものだからな、の意。
今から思うと、とても軽薄で、わざとらしいことです。
【女房などの物語読みしを聞きて】- 国宝『源氏物語絵巻』「東屋」第一段に、一人の女房が物語を読み上げているのを、浮舟は絵を見ながら、また中君は髪を梳かせながら、周囲の女房らとともに聞いている様子が描かれている。
【涙をさへ】- 副助詞「さへ」は添加の意を表す。
【心を見むとするほどに】- 下に、夫婦の縁が切れて、の意が省略されている。
『心深 しや』など、ほめたてられて、あはれ進 みぬれば、やがて尼 になりぬかし。
思 ひ立 つほどは、いと心澄 めるやうにて、世 に返 り見 すべくも思 へらず。
『いで、あな悲 し。
かくはた思 しなりにけるよ』などやうに、あひ知 れる人来 とぶらひ、ひたすらに憂 しとも思 ひ離 れぬ男 、聞 きつけて涙落 とせば、使 ふ人 、古御達 など、『君 の御心 は、あはれなりけるものを。
あたら御身 を』など言 ふ。
みづから額髪 をかきさぐりて、あへなく心細 ければ、うちひそみぬかし。
忍 ぶれど涙 こぼれそめぬれば、折々 ごとにえ念 じえず、悔 しきこと多 かめるに、仏 もなかなか心 ぎたなしと、見 たまひつべし。
濁 りにしめるほどよりも、なま浮 かびにては、かへりて悪 しき道 にも漂 ひぬべくぞおぼゆる。
『いで、あな
かくはた
あたら
みづから
思い立った当座は、まことに気持ちも悟ったようで、世俗の生活を振り返ってみようなどとは思わない。
『まあ、何とおいたわしい。
こうもご決心されたとは』などと言ったように、知り合いの人が見舞いに来たり、すっかり嫌だとも諦めてない夫が、聞きつけて涙を落とすと、召使いや、老女たちなどが、『殿のお気持ちは、愛情深かったのに。
惜しいおん身を』などと言う。
自分でも額髪を触って、手応えなく心細いので、泣顔になってしまう。
堪えても涙がこぼれ出してしまうと、何かの時々には我慢もできず、後悔も多いようなので、仏もかえって未練がましいと、きっと御覧になるでしょう。
濁世に染まっている間よりも、生悟りは、かえって悪道に堕ちさ迷うことになるに違いなく思われます。
【返り見すべくも思へらず】- 係助詞「も」強調の意。「思へらず」に係る。「思へ」已然形+完了の助動詞「ら」未然形+打消の助動詞「ず」。
【いで、あな悲し。かくはた思しなりにけるよ】- 知り合いの人の同情したことば。
【あへなく心細ければ】- 尼削ぎして髪が短くなっているので。
【折々ごとにえ念じえず】- 副詞「え」は打消の助動詞「ず」と呼応して不可能の意を表す。「念ず」は堪える、我慢する、意。
【濁りにしめるほどよりも、なま浮かびにては】- 明融臨模本は「にこりに」に朱合点有り。『源氏釈』は「はちす葉の濁りにしまぬ心もて何かは露を玉とあざむく」(古今集、夏、一六五、僧正遍正)を指摘した。生半可な悟りようではかえって悪道に堕ちることになる、の意。光る源氏(作者紫式部のと言ってもよい)の出家観は「御法」巻(第一章一段)に語られている。
【やがて】- 青表紙本系の大島本と別本群の国冬本には、この語の次に「そのおもひいてうらめしきふしあらんやあしくもよくも」(その時の思い出に恨めしいことがあるのだろうか、良くも悪くも)の句がある。
【見過ぐしたらむ仲こそ】- 係助詞「こそ」は「契り深くあはれならめ」に係る。推量の助動詞「め」已然形、下文に続く逆接用法。下の文との間に、それにも関わらず家出したりすると、の意が省略されている。
【心おかれじやは】- 自発の助動詞「れ」未然形、打消推量の助動詞「じ」終止形、係助詞「やは」反語の意。自然と気をつかわずにいられましょうか、気をつかわずにはいられません、の意。また、自然と気まずくならないでしょうか、気まずくならずにはいられません、の意。
また、なのめに移 ろふ方 あらむ人 を恨 みて、気色 ばみ背 かむ、はたをこがましかりなむ。
心 は移 ろふ方 ありとも、見 そめし心 ざしいとほしく思 はば、さる方 のよすがに思 ひてもありぬべきに、さやうならむたぢろきに、絶 えぬべきわざなり。
愛情が他の女に移ることがあったとしても、結婚した当初の愛情をいとしく思うならば、そうした縁の伴侶と思っていることもきっとあるでしょうに、そのようなごたごたから、夫婦の仲まで切れてしまうのです。
【はたをこがましかりなむ】- 副詞「はた」は、「ある一面についを認めながら、それとは別の一面について述べる語」(小学館古語大辞典)の用法。それはそれとしてまた、の意。完了の助動詞「な」未然形、確述の意。推量の助動詞「む」推量の意。
【心は移ろふ方ありとも】- 接続助詞「とも」は、動詞の終止形に接続して逆接の仮定条件を表す。--があったとしても、の意。
【見そめし心ざしいとほしく思はば】- 接続助詞「ば」は未然形の下に接続して仮定条件を表す。
【さる方のよすが】- 「さる方」は「見そめし心ざし」をさす。
【思ひてもありぬべきに】- 係助詞「も」強調の意、「ありぬべき」に係る。完了の助動詞「ぬ」確述の意、推量の助動詞「べき」当然の意、接続助詞「に」逆接の意を表す。きっとあるでしょうに、の意。
【さやうならむたぢろきに】- 「さやうならむ」は「人の心を見知らぬやうに逃げ隠れて、人をまどはし」や「あはれ進みぬれば、やがて尼になりぬ」、「移ろふ方あらむ人を恨みて、気色ばみ背かむ」など、女の態度をさす。
すべて、よろづのことなだらかに、怨 ずべきことをば見知 れるさまにほのめかし、恨 むべからむふしをも憎 からずかすめなさば、それにつけて、あはれもまさりぬべし。
多 くは、わが心 も見 る人 からをさまりもすべし。
あまりむげにうちゆるべ見放 ちたるも、心安 くらうたきやうなれど、おのづから軽 き方 にぞおぼえはべるかし。
繋 がぬ舟 の浮 きたる例 も、げにあやなし。
さははべらぬか」
あまりむげにうちゆるべ
さははべらぬか」
一般に、自分の浮気心も妻の態度から収まりもするのです。
あまりやたらに勝手にさせ放任しておくのも、気が楽でかわいらしいようだが、いつのまにか軽く見られるものです。
繋がない舟の譬えもあり、なるほど思慮がない。
そうではございませんか」
【わが心も見る人から】- 「わが心」は夫の浮気心、「見る人」は妻をさす。
【軽き方にぞおぼえはべるかし】- 妻が軽く見られる、意。
【繋がぬ舟の浮きたる例】- 明融臨模本は「つなかぬふねの」に朱合点有り。『源氏釈』は「観身岸額離根草論命江頭不繋船」(和漢朗詠集、無常、七九〇 、羅維)を指摘。なお、『文選』に「泛乎若不繋之船」(巻十三)、『荘子』に「汎若不繋之舟」(列禦寇)ともある。
【げにあやなし】- 副詞「げに」は「繋がぬ舟の浮きたる例」を受ける。なるほど繋がない舟の喩えどおり、の意。
【中将うなづく】- 頭中将の納得する様子。
「さしあたりて、をかしともあはれとも心 に入 らむ人 の、頼 もしげなき疑 ひあらむこそ、大事 なるべけれ。
わが心 あやまちなくて見過 ぐさば、さし直 してもなどか見 ざらむとおぼえたれど、それさしもあらじ。
ともかくも、違 ふべきふしあらむを、のどやかに見忍 ばむよりほかに、ますことあるまじかりけり」
わが
ともかくも、
自分が乱心せずに大目に見てやっていたら、気持ちを変えて添い遂げないこともないだろうと思われますが、そうとばかりも言えまい。
いずれにしても、夫婦仲がうまくいかないようことがあってもそれを、気長にじっと堪えているより以外に、良い手段はないようですな」
【をかしともあはれとも心に入らむ人】- 夫とも妻ともとれる。両説ある。「「人」は妻。通説は夫」(古典セレクション)。『集成』も「女」説。『新大系』は「男」説。いま、夫の方に浮気をしているような疑いがある場合と解釈して読む。暗に「夫」を妹の夫である源氏のこととして読むと、下の頭中将の「わが妹の姫君は、この定めにかなひたまへりと思へば」や源氏にとって耳の痛い話なので「君のうちねぶりて言葉まぜたまはぬ」ことによく整合する。
【わが心あやまちなくて見過ぐさば】- 妻が夫の浮気の疑いに取り乱したり乱心したりせずに、知らないふりする、の意と解す。
【さし直してもなどか見ざらむ】- 主語は妻。「さし直す」は、気持ちを入れ直すこと。「など」(副詞)+「か」(係助詞、反語)、「む」(推量の助動詞、推量)に係る。どうしてか、心を入れ変えて添い遂げることがないだろうか、きっと添い遂げるだろう、の意。
【それさしもあらじ】- 「それ」は「などか見ざらむ」をさす。副詞「さしも」は打消・反語の表現を伴って、そうとばかり、そのようには、の意を表す。打消推量の助動詞「じ」終止形、推量の意。
【違ふべきふしあらむを】- 推量の助動詞「む」連体形、仮定・婉曲の意。格助詞「を」目的格を表す。
【あるまじかりけり】- ラ変動詞「ある」連体形+打消推量の助動詞「まじかり」連用形+過去の助動詞「けり」詠嘆の意。ないようですなあ。
と言 ひて、わが妹 の姫君 は、この定 めにかなひたまへりと思 へば、君 のうちねぶりて言葉 まぜたまはぬを、さうざうしく心 やましと思 ふ。
馬頭 、物定 めの博士 になりて、ひひらきゐたり。
中将 は、このことわり聞 き果 てむと、心入 れて、あへしらひゐたまへり。
左馬頭がこの評定の博士になって、さらに弁じ立てていた。
頭中将は、この弁論を最後まで聴こうと、熱心になって、受け答えしていらっしゃった。
【この定めにかなひたまへり】- 「たまへ」尊敬の補助動詞。自分の妹ではあるが、源氏の妻であるため敬語を用いている。多少嫉妬し忍耐と寛容をもっていること。
【君のうちねぶりて】- 源氏は議論に退屈して居眠りしたふりをしているが、実は源氏夫婦に当てはまる耳の痛い話なので寝たふりをしている。
【心やましと思ふ】- 主語は頭中将。
【ひひらき】- 「囀 サヘヅル カマビスシ ヒヒラク」(『名義抄』)。清音である。
【あへしらひゐたまへり】- 尊敬の補助動詞「たまへ」は頭中将の態度・動作に対する敬語。
「よろづのことによそへて思 せ。
木 の道 の匠 のよろづの物 を心 にまかせて作 り出 だすも、臨時 のもてあそび物 の、その物 と跡 も定 まらぬは、そばつきさればみたるも、げにかうもしつべかりけりと、時 につけつつさまを変 へて、今 めかしきに目移 りてをかしきもあり。
大事 として、まことにうるはしき人 の調度 の飾 りとする、定 まれるやうある物 を難 なくし出 づることなむ、なほまことの物 の上手 は、さまことに見 え分 かれはべる。
木工の道の匠がいろいろの物を思いのままに作り出すのも、その場限りの趣向の物で、そうした型ときまりのないものは、見た目には洒落ているのも、なるほどこういうふうにも作るのだと、時々に従って趣向を変えて、目新しいのに目が移って趣のあるものもあります。
重大な物として、本当にれっきとした人の調度類で装飾とする、一定の様式というようなのがあるものを立派に作り上げることは、やはり本当の名人は、違ったものだと見分けられるものでございます。
【木の道の匠】- 指物師。木製の家具調度類を作る職人。
【作り出だすも】- 係助詞「も」は「をかしきもあり」に係る。
【臨時のもてあそび物の】- 「もてあそび物の」の格助詞「の」同格を表す。--で、の意。
【跡も定まらぬは】- 係助詞「は」は「そばつきさればみたる」に係る。
【そばつきさればみたるも】- 係助詞「も」は「かうもしつべかりけり」に係る。
【うるはしき人の調度の飾りとする】- 「人の」の格助詞「の」所有格、「調度の」の格助詞「の」同格。「--飾りとする」は下に「物を」が省略されている。次の「定まれるやうある物」と並列。「難なくし出づる」に続く。
【し出づることなむ】- 係助詞「なむ」は「見え分かれはべる」(連体形)に係る。
けれども、人の見ることもできない蓬莱山や、荒海の恐ろしい魚の形や、唐国の猛々しい獣の形や、目に見えない鬼の顔などで、仰々しく描いた物は、想像のままに格別に目を驚かして、実物には似ていないでしょうが、それはそれでよいでしょう。
【墨がきに選ばれて】- 墨で構図などの下絵を描く人。集団で製作する時の中心的役割をする人。彩色などは弟子が行った。なお『新大系』では「選はれて」と清音表記。『岩波古語辞典』では「えらひ」<金光明最勝王経 平安初期点>の用例を挙げ、「奈良時代にハ行の活用をした動詞は、オモヒ(思)のように、平安中期以後ワ行に発音するのが普通だったが、シノヒ(偲)がシノビと変化したように、稀にバ行に発音したものがある。エラビもその一つ」と指摘する。
【次々にさらに】- 「次々に」の下に「見るに」または「書くに」などの語句が省略されている。副詞「さらに」は「見え分かれず」に係る。打消の助動詞「ず」と呼応して、全然--ない、の意を表す。
【魚】- 「魚、ウヲ、俗云、イヲ」(『名義抄』)、「魚、宇乎<ウヲ>、俗云、伊遠<イヲ>」(『和名抄』)。
【目に見えぬ鬼の顔などの】- 「顔などの」の格助詞「の」同格を表す。鬼の顔などで、の意。『古今和歌集』仮名序の「目に見えぬ鬼神をもあはれと思はせ」の表現を下に敷く。
【さてありぬべし】- 唐絵は唐絵としてそれで結構でしょう、の意。
【げにと見え】- なるほど、見慣れた風景らしいと見えて、の意。
【け近き籬の内をば】- 『完訳』は「下に「描くに」ぐらいを補う」と指摘。この語句は、「上手は」と「悪ろ者は」に係る。
【ここかしこの】- 格助詞「の」主格を表す、あちらこちらが、の意。「気色ばめるは」に続く。
【点長に走り書き】- 挿入句。点を続けるような感じに筆を走らせて書く気取った書き方。
【気色ばめるは】- 係助詞「は」は「気色だちたれど」に係る。
【書き得たるは】- 係助詞「は」は「消えて見ゆれど」に係る。
【とり並べて見れば】- 接続助詞「ば」は已然形に付いて順接の確定条件を表す。
【実になむよりける】- 係助詞「なむ」、過去の助動詞「ける」連体形、詠嘆の意。係結びの法則、強調のニュアンスを添える。本物が良いものですなあ、の意。
まして人の気持ちの、折々に様子ぶっているような見た目の愛情は、信用がおけないものと存じております。
その最初の例を、好色がましいお話ですが申し上げましょう」
【まして人の心の】- 「心の」の格助詞「の」は同格を表す。「見る目の情けをば」と共に「え頼むまじく思うたまへ得てはべる」に続く。
【え頼むまじく思うたまへ得てはべる】- 副詞「え」は打消推量の助動詞「まじく」連用形と呼応して不可能の意を表す。「思う」は「思ひ」連用形のウ音便形。「たまへ」下二段活用の謙譲の補助動詞。丁寧語「はべる」連体形、連体中止法。含みをもたせた余情的表現。
【そのはじめのこと、好き好きしくとも申しはべらむ】- 以上、左馬頭の芸能に喩えた論。以下、体験談に移る。「そのはじめのこと」は、女性を知り始めたころのこと。
とて、近 くゐ寄 れば、君 も目覚 ましたまふ。
中将 いみじく信 じて、頬杖 をつきて向 かひゐたまへり。
法 の師 の世 のことわり説 き聞 かせむ所 の心地 するも、かつはをかしけれど、かかるついでは、おのおの睦言 もえ忍 びとどめずなむありける。
中将はひどく本気になって、頬杖をついて向かい合いに座っていらっしゃる。
法師が世の中の道理を説いて聞かせているような所の感じがするのも、もう一方ではおもしろいが、このような折には、それぞれがうちとけたお話などを隠しておくことができないのであった。
【君も目覚ましたまふ】- 源氏の君も目をお覚ましになる。再び興味をもって聞こうとする。
【中将いみじく信じて】- 頭中将はひどく本気になって。
【法の師の世のことわり説き聞かせむ所の心地するも】- 法師が説法をしている所の気がするのも。『花鳥余情』は、雨夜品定めの段の構成を『法華経』の三周説法による、と指摘する。すなわち、「法説一周」(方便品)、上根の者に直接仏の教えを説く。「ますことあるまじかりけり」まで、女性論の結論を述べる。次に「譬説一周」(譬喩品から薬草喩品)、中根の者に譬えをもって仏の教えを説く。「よろづのことによそへて思せ」以下「え頼むまじく思うたまへてはべる」まで、芸能の譬えをもって論じたところ。最後に「因縁説一周」(化城喩品)、下根の者に過去の因縁をもって仏の教えを説く。「そのはじめのこと好き好きしくとも申しはべらむ」以下に語られる体験談がそれに当る。
【かかるついでは、おのおの睦言もえ忍びとどめずなむありける】- 語り手の評言。
第二章 女性体験談
第一段 女性体験談(左馬頭、嫉妬深い女の物語)
「はやう、まだいと下臈 にはべりし時 、あはれと思 ふ人 はべりき。
聞 こえさせつるやうに、容貌 などいとまほにもはべらざりしかば、若 きほどの好 き心 には、この人 をとまりにとも思 ひとどめはべらず、よるべとは思 ひながら、さうざうしくて、とかく紛 れはべりしを、もの怨 じをいたくしはべりしかば、心 づきなく、いとかからで、おいらかならましかばと思 ひつつ、あまりいと許 しなく疑 ひはべりしもうるさくて、かく数 ならぬ身 を見 も放 たで、などかくしも思 ふらむと、心苦 しき折々 もはべりて、自然 に心 をさめらるるやうになむはべりし。
申し上げましたように、容貌などもたいして優れておりませんでしたので、若いうちの浮気心から、この女性を生涯の伴侶とも思い決めませんで、通い所とは思いながら、物足りなくて、何かと他の女性にかかずらっておりましたところ、大変に嫉妬をいたしましたので、おもしろくなく、本当にこうではなくて、おっとりとしていたらば良いものをと思い思い、あまりにひどく厳しく疑いましたのも煩わしくて、このようなつまらない男に愛想もつかさず、どうしてこう愛しているのだろうと、気の毒に思う時々もございまして、自然と浮気心も収められるというふうでもございました。
【聞こえさせつるやうに】- 実務一点張りの女、「まめまめしき筋を立てて耳はさみがちに美さうなき家刀自のひとへにうちとけたる後見ばかりして」をさす。
【若きほどの好き心】- 青表紙本系の明融臨模本と大島本は「すき心」、その他の青表紙本系の松浦本、池田本、伝冷泉為秀本、三条西家本、書陵部本と別本の国冬本は「すき心地」。河内本系諸本は「すさひ心」。別本群の陽明文庫本は「すさひ心」。すなわち、A「好き心」(明大)、B「好き心地」(松池秀三証・国)、C「すさび心」(河・陽)となる。Aは青表紙本系統内の単独共通異文、Bは青表紙本系諸本と別本の両方にわたる複数共通異文。Cは河内本系諸本と別本の両方にわたる共通異文である。『集成』『新大系』は「すき心」のまま、『古典セレクション』は「すき心地」と校訂する。
【とまりにとも思ひとどめはべらず、よるべとは思ひながら】- 「とまり」は生涯の伴侶、正妻。「よるべ」は通い妻、側室。
【とかく紛れはべりしを】- 接続助詞「を」順接を表す。他の女性に浮気しておりましたところ、の意。
【おいらかならましかばと思ひつつ】- 反実仮想の助動詞「ましか」未然形、下に「うれしからまし」または「良からまし」などの語句が省略されている。接続助詞「つつ」は動作の反復を表す。
【かく数ならぬ身を】- 以下「思ふらむ」まで、左馬頭の自問自答の心。主語は女。『花鳥余情』は「かつ見つつ影離れ行く水の面にかく数ならぬ身をいかにせむ」(拾遺集、恋四、八七九、斎宮女御)を指摘。
【などかくしも思ふらむ】- 副助詞「しも」強調のニュアンスを添える。推量の助動詞「らむ」原因推量を表す。なぜこんなにも愛しているのだろうか、の意。
【心苦しき折々】- 左馬頭が女を気の毒と思う時々。
この女 のあるやう、もとより思 ひいたらざりけることにも、いかでこの人 のためにはと、なき手 を出 だし、後 れたる筋 の心 をも、なほ口惜 しくは見 えじと思 ひはげみつつ、とにかくにつけて、ものまめやかに後見 、つゆにても心 に違 ふことはなくもがなと思 へりしほどに、進 める方 と思 ひしかど、とかくになびきてなよびゆき、醜 き容貌 をも、この人 に見 や疎 まれむと、わりなく思 ひつくろひ、疎 き人 に見 えば、面伏 せにや思 はむと、憚 り恥 ぢて、みさをにもてつけて見馴 るるままに、心 もけしうはあらずはべりしかど、ただこの憎 き方一 つなむ、心 をさめずはべりし。
【なき手を出だし、後れたる筋の心をも】- 無理な算段をして、不得手な方面も。
【思ひはげみつつ】- 接続助詞「つつ」動作の反復を表す。
【つゆにても心に違ふことはなくもがな】- 左馬頭が見たところの女の心。終助詞「もがな」願望を表す。夫の気持ちを損ねることがなければいいなあと、の意。
【進める方】- 「強 ススム」(名義抄)。気の強い意。
【この人に見や疎まれむと】- 「この人」は、このわたしにの意。係助詞「や」疑問、受身の助動詞「れ」未然形、推量の助動詞「む」連体形、係り結びの法則。夫に嫌われやしないかと、の意。
【わりなく思ひつくろひ】- 『集成』は「いじらしくお化粧をし」、『完訳』は「懸命に化粧し」と訳す。「わりなく」のニュアンスは微妙。理屈に合わない、が原義。すると、化粧してもしがいのないのに化粧する、という、やや冷やかなニュアンスがあろうか。
【疎き人に見えば、面伏せにや思はむと】- 「見え」未然形+接続助詞「ば」仮定条件を表す。係助詞「や」疑問、「思はむ」の主語は夫。女の心。なお、「思はむと」の箇所について、青表紙本系の明融臨模本、大島本、松浦本、伝冷泉為秀本は「思はんと」。池田本は「みえんと」。三条西家本と書陵部本は「思はれんと」。河内本系や別本群の国冬本も明融臨模本等と同文。陽明文庫本は「をもはれむと」とある。すなわち、A「思はんと」(明大松秀・河・国)、B「思はれんと」(三証・陽)、C「見えんと」(池)となる。Cは独自異文。Aは青表紙本系統、河内本系統、別本群の三系統にわたって見られる本文であるのに対して、Bは青表紙本系統と別本群にわたる本文である。『集成』は「(私が)恥ずかしく思いはせぬかと」と注す。しかし、自分が思いはせぬか、とは、やや不可解。『完訳』は「夫の面目をつぶすことにならぬかと」と注し、その主体者を女に訳すが、意訳である。Bの受身の助動詞が付加した本文は、「面目をつぶすように思われよう」となる。文意はもっとも通りよい。底本は、親しくない来客があったような折に、この醜い顔をその人の前に曝したら、夫が恥だと思うだろうか、という意。下級官人の妻などは客人の前に出て顔を見せるようなこともあったのであろう。
【ただこの憎き方一つ】- 嫉妬深い欠点。
そのかみ思 ひはべりしやう、かうあながちに従 ひ怖 ぢたる人 なめり、いかで懲 るばかりのわざして、おどして、この方 もすこしよろしくもなり、さがなさもやめむと思 ひて、まことに憂 しなども思 ひて絶 えぬべき気色 ならば、かばかり我 に従 ふ心 ならば思 ひ懲 りなむと思 うたまへ得 て、ことさらに情 けなくつれなきさまを見 せて、例 の腹立 ち怨 ずるに、
【さがなさもやめむと思ひて】- 「やめ」ヤ行下二段、他動詞。推量の助動詞「む」意志を表す。やめさせよう、と思っての意
【まことに憂しなども】- 以下「思ひ懲りなむ」まで、左馬頭の心。
【絶えぬべき気色ならば】- 完了の助動詞「ぬ」連用形、確述、推量の助動詞「べき」当然の意。断定の助動詞「なら」未然形+接続助詞「ば」仮定条件を表す。
【思ひ懲りなむと】- 完了の助動詞「な」未然形、確述、推量の助動詞「む」推量の意。主語は女。女はきっと懲りるだろう、の意。
【思うたまへ得て】- 「思う」は「思ひ」連用形のウ音便化。「たまへ」下二段活用の謙譲の補助動詞。存じまして、の意。
【さまを見せて】- 「見せ」下二段活用、連用形、他動詞。接続助詞「て」順接を表す。態度を見せて、の意。「かくおぞましくは」云々の詞に続く。「見せますと」「見せたところ」と訳す説がある(今泉忠義・古典セレクション)。しかし「見すれば」(已然形+接続助詞「ば」)ではない。
【例の腹立ち怨ずるに】- 連語「例の」は「怨ずる」を修飾する。主語は女。「に」を接続助詞と解して「恨んでかかって来ましたので」「恨みかかってきますので」(今泉忠義・古典セレクション)と訳す説がある。しかし、上の「見せて」が「態度を見せて」の意であると、続きがよくない。「に」を格助詞、時間を表す。「折」などの語が省略されている形と見ておく。
『かくおぞましくは、いみじき契 り深 くとも、絶 えてまた見 じ。
限 りと思 はば、かくわりなきもの疑 ひはせよ。
行 く先長 く見 えむと思 はば、つらきことありとも、念 じてなのめに思 ひなりて、かかる心 だに失 せなば、いとあはれとなむ思 ふべき。
人並々 にもなり、すこしおとなびむに添 へて、また並 ぶ人 なくあるべき』やうなど、かしこく教 へたつるかなと思 ひたまへて、われたけく言 ひそしはべるに、すこしうち笑 ひて、
最後と思うならば、このようなめちゃくちゃな邪推をするがよい。
将来も長く連れ添おうと思うならば、辛いことがあっても、我慢してたいしたことなく思うようになって、このような嫉妬心さえ消えたならば、とても愛しい女と思おう。
人並みに出世もし、もう少し一人前になったら、他に並ぶ人がない正妻になるであろう』などと、うまく教えたものよと存じまして、調子に乗って度を過ごして言いますと、少し微笑んで、
【絶えてまた見じ】- 副詞「絶えて」は打消推量の助動詞「じ」意志と呼応して、すっかり二度と逢うまいの意。
【念じてなのめに思ひなりて】- 女がいいかげんにあきらめるようになって、の意。
【かかる心だに失せなば】- 副助詞「だに」最小限を表す。せめて嫉妬心さえなくなったなら、の意。
【また並ぶ人なくあるべき』やうなど】- 正妻としての地位を与えようの意。『集成』は「あるべきやう」までを左馬頭の詞とするが、『完訳』では「あるべき」までを左馬頭の詞とし、「やう」に「直接話法から間接話法へと転換」と注す。
【思ひたまへて】- 「たまへ」謙譲の補助動詞。存じましての意。
【言ひそしはべるに】- 「に」接続助詞、順接を表す。
【すこしうち笑ひて】- 女が、少し微笑んで。冷笑のニュアンス。
『よろづに見立 てなく、ものげなきほどを見過 ぐして、人数 なる世 もやと待 つ方 は、いとのどかに思 ひなされて、心 やましくもあらず。
つらき心 を忍 びて、思 ひ直 らむ折 を見 つけむと、年月 を重 ねむあいな頼 みは、いと苦 しくなむあるべければ、かたみに背 きぬべききざみになむある』
つらき
辛い浮気心を我慢して、その心がいつになったら直るのだろうかと、当てにならない期待をして年月を重ねていくことは、まことに辛くもありましょうから、お互いに別れるのによいときです』
【いとのどかに思ひなされて】- 「れ」可能の助動詞。思いなすことができる、意。
【心やましくもあらず】- 夫の出世が遅いのは苦にならない、という。
【つらき心を忍びて】- 「つらき心」は夫の浮気心をさす。
【いと苦しくなむあるべければ】- 夫の浮気心がいつまでも直らないのがつらい、という。
【女もえをさめぬ筋】- 係助詞「も」同類を表す。わたし同様に、の意。「筋」は性格。『集成』は「黙っていられない問題なので」と解す。『完訳』は「黙っていられない性分で」と訳す。
【喰ひてはべりしを】- 接続助詞「て」が介在。「はべり」は「あり」の丁寧語。噛みついてまいりましたので、の意。
【おどろおどろしくかこちて】- 「かこつ」は口実にする意。
『かかる疵 さへつきぬれば、いよいよ交 じらひをすべきにもあらず。
辱 めたまふめる官位 、いとどしく何 につけてかは人 めかむ。
世 を背 きぬべき身 なめり』など言 ひ脅 して、『さらば、今日 こそは限 りなめれ』と、この指 をかがめてまかでぬ。
軽蔑なさるような官職で、ますます一層どのようにして出世して行けようか。
出家しかない身のようだ』などと言い脅して、『それでは、今日という今日がお別れのようだ』と言って、この指を折り曲げて退出しました。
【交じらひ】- 朝廷での官人どうしの交際。
【何につけてかは人めかむ】- 係助詞「かは」反語を表す。推量の助動詞「む」推量、連体形。
【世を背きぬべき身なめり】- 女の「かたみに背きぬべき」を受ける。売り言葉に買い言葉。離縁どころか、わたしは出家するしかない、と大袈裟に言う。
【さらば、今日こそは限りなめれ】- 左馬頭の捨て台詞。係助詞「こそ」、推量の助動詞「めれ」已然形、係り結びの法則。強調のニュアンスを添える。
【まかでぬ】- 「まかで」連用形、「出る」の謙譲語。女の家を出てきました、の意。

この一つだけがあなたの嫌な点なものか
これ一つやは君がうきふし
今は別れる時なのでしょうか』
こや君が手を別るべきをり』
など、言 ひしろひはべりしかど、まことには変 るべきこととも思 ひたまへずながら、日 ごろ経 るまで消息 も遣 はさず、あくがれまかり歩 くに、臨時 の祭 の調楽 に、夜更 けていみじう霙降 る夜 、これかれまかりあかるる所 にて、思 ひめぐらせば、なほ家路 と思 はむ方 はまたなかりけり。
【これかれまかりあかるる所にて】- 「これかれ」は調楽の仲間。「まかり」は宮中を退出する意。
【またなかりけり】- 過去の助動詞「けり」詠嘆を表す。「なかりき」ではない。
さればよと、
さるべき
やはりそうであったよと、得意になりましたが、本人はいません。
しかるべき女房連中だけが残っていて、『親御様の家に、今晩は行きました』と答えます。
【気色ばめるあたり】- 後に出てくる浮気な女の家。
【そぞろ寒くや】- 情愛よりも風流を優先するゆえに寒い思いをさせられるだろうと想像する。
【思ひたまへられしかば】- 謙譲の補助動詞「たまへ」下二段、未然形。「られ」受身の助動詞、また自発を表すとも考えられる。過去の助動詞「しか」已然形。存じられましたので、の意。
【恨みは解けなむ】- 「解け」は前の「雪」の縁語。言葉の洒落。完了の助動詞「な」未然形、確述、推量の助動詞「む」推量。きっと解けるだろう、の意。
【思うたまへしに】- 「思う」は「思ひ」連用形のウ音便形、謙譲の補助動詞「たまへ」下二段、連用形、過去の助動詞「し」連体形、接続助詞「に」順接。存じましたところ、の意。
【火ほのかに壁に背け】- 『白氏文集』「上陽人」の「耿々たる残灯壁に背ける影」を踏まえた表現。寝室用にほの暗くしていた。
【引き上ぐべきものの帷子などうち上げて】- 夫を迎える時は、帷子の垂れ絹を引き上げておくのが、通例であったらしい。『完訳』では「使わぬ際は引き上げておく」と注すが、下に「今宵ばかりや、と、待ちけるさまなり」とあるので、女は男の来訪を支度して待っていたと解釈すべき。
【今宵ばかりやと】- 係助詞「や」の下に「来らむ」等の語句が省略。女の心をを勝手に左馬頭が推測したもの。
【さればよ】- やはりそうであったよ。『集成』『完訳』は「それ見たことよ」というニュアンスで訳す。
【心おごりするに】- 接続助詞「に」逆接。
【さるべき女房どもばかりとまりて】- 夫の世話をすべき女房。夫を迎える準備をしておきながら本人がことさらいないというのは、女側のまだ夫を許していない意思表示。
【親の家に、この夜さりなむ渡りぬる】- 女房の詞。係助詞「なむ」完了の助動詞「ぬる」連体形、係り結びの法則。強調のニュアンスを添える。この女は親とは別の家に夫を通わせていた。
【我を疎みねと思ふ方の心やありけむ】- 「疎み」連用形、完了の助動詞「ね」命令形、確述。係助詞「や」は過去推量の助動詞「けむ」連体形に係る。左馬頭、女の心を推察。女の方から自分を嫌いになってください、という思いがあったのか、と左馬頭は解釈する。
【さしも見たまへざりしことなれど】- 挿入句。左馬頭の判断を加える。
【心やましきままに思ひはべりしに】- 接続助詞「に」逆接。『完訳』は「腹立ちまぎれに勘ぐったが」というニュアンスの注を付ける。
【わが見捨ててむ後をさへ】- わたしの方から女を見捨てたのに、女は今でもわたしのために、という左馬頭の思い上がり。「わが」について『古典セレクション』は「喧嘩別れしているとはいえ、自分(女)が見限った後の私(左馬頭)のことまでも、気づかって世話をしていてくれていた。女に自分への愛情がまだあるとの観察である」と注す。
さりとも、絶 えて思 ひ放 つやうはあらじと思 うたまへて、とかく言 ひはべりしを、背 きもせずと、尋 ねまどはさむとも隠 れ忍 びず、かかやかしからず答 へつつ、ただ、『ありしながらは、えなむ見過 ぐすまじき。
あらためてのどかに思 ひならばなむ、あひ見 るべき』など言 ひしを、さりともえ思 ひ離 れじと思 ひたまへしかば、しばし懲 らさむの心 にて、『しかあらためむ』とも言 はず、いたく綱引 きて見 せしあひだに、いといたく思 ひ嘆 きて、はかなくなりはべりにしかば、戯 れにくくなむおぼえはべりし。
あらためてのどかに
改心して落ち着くならば、また一緒に暮らしましょう』などと言いましたが、そうは言っても思い切れまいと存じましたので、少し懲らしめようという気持ちから、『そのように改めよう』とも言わず、ひどく強情を張って見せていたところ、とてもひどく思い嘆いて、亡くなってしまいましたので、冗談もほどほどにと存じられました。
【とかく言ひはべりしを】- その後、縒りを戻そうとあれこれ言ってみましたが、の意。時間的経過がある。
【背きもせずと】- 青表紙本系の明融臨模本、大島本、松浦本、伝冷泉為秀本は「せすと」。池田本、三条西家本、書陵部本は「せす」とある。引用の格助詞「と」がない。明融臨模本は後人が朱筆で「と」をミセケチにしている。『集成』『古典セレクション』は「せず」の本文を採用する。『新大系』は底本の大島本「せずと」に従う。
【かかやかしからず答へつつ】- 接続助詞「つつ」動作の反復・継続を表す。
【ありしながらは】- 以下「あひ見るべき」まで、女の詞。夫に浮気の改心を求める。
【えなむ見過ぐすまじき】- 副詞「え」、係助詞「なむ」打消推量の助動詞「まじき」連体形。とても我慢できません、の意。
【いたく綱引きて】- 明融臨模本には「ひ」に朱濁点有り。『源氏釈』は「引き寄せばただには寄らで春駒の綱引きするぞ名は立つと聞く」(拾遺集、雑賀、一一五八、平定文)を指摘する。
【はかなくなりはべりにしかば】- 「はかなく」は亡くなる意。
【戯れにくく】- 『異本紫明抄』は「有りぬやと心見がてら逢ひ見ねば戯れにくきまでぞ恋しき」(古今集、俳諧、一〇二五、読人しらず)を指摘する。冗談もほどほどにすべきであった、という後悔。
ひとへにうち頼 みたらむ方 は、さばかりにてありぬべくなむ思 ひたまへ出 でらるる。
はかなきあだ事 をもまことの大事 をも、言 ひあはせたるにかひなからず、龍田姫 と言 はむにもつきなからず、織女 の手 にも劣 るまじくその方 も具 して、うるさくなむはべりし」
はかなきあだ
ちょっとした風流事でも実生活上の大事でも、相談してもしがいがなくはなく、龍田姫と言っても不似合いでなく、織姫の腕前にも劣らないその方面の技術をもっていて、行き届いていたのでした」
【言ひあはせたるにかひなからず】- 接続助詞「に」順接。相談してもしがいがあって、の意。
【龍田姫】- 龍田姫は春の佐保姫に対して、秋の女神。紅葉を染めることから、染色の神様と見られていた。「見る毎に秋にもなるかな龍田姫紅葉染むとや山も霧るらむ」(後撰集、秋下、三七八、 読人しらず)。
【織女の手】- 織姫の技術。裁縫の神様と見られていた。
中将が、
【中将】- 頭中将。
「その織女 の裁 ち縫 ふ方 をのどめて、長 き契 りにぞあえまし。
げに、その龍田姫 の錦 には、またしくものあらじ。
はかなき花紅葉 といふも、をりふしの色 あひつきなく、はかばかしからぬは、露 のはえなく消 えぬるわざなり。
さあるにより、難 き世 とは定 めかねたるぞや」
げに、その
はかなき
さあるにより、
なるほど、その龍田姫の錦の染色の腕前には、誰も及ぶ者はいないだろうね。
ちょっとした花や紅葉といっても、季節の色合いが相応しくなく、はっきりとしていないのは、何の見映えもなく、台なしになってしまうものだ。
そうだからこそ、難しいものだと決定しかねるのですな」
【長き契りにぞあえまし】- 『異本紫明抄』は「逢ふ事は七夕姫に等しくて裁ち縫ふわざはあえずぞありける」(後撰集、秋上、二二五、閑院)を指摘する。係助詞「ぞ」、推量の助動詞「まし」連体形、反実仮想、係り結びの法則。あやかりたいものだったね。
【またしくものあらじ】- 『完訳』は「その女への男の尽くし方全般をさす」と注し、「「如く」に「敷く」をひびかし、「錦」の縁語とした」とも注す。
【露のはえなく消えぬるわざなり】- 「露」は副詞「つゆ」の意を懸ける。「消え」は「露」の縁語。
と、言 ひはやしたまふ。
第二段 左馬頭の体験談(浮気な女の物語)
見た目にも無難でございましたので、先程の嫉妬深い女を気の置けない通い所にして、時々隠れて逢っていました間は、格段に気に入っておりました。
今の女が亡くなって後は、どうしましょう、かわいそうだとは思いながらも死んでしまったものは仕方がないので、頻繁に通うようになってみますと、少し派手で婀娜っぽく風流めかしていることは、気に入らないところがあったので、頼りにできる女とは思わずに、途絶えがちにばかり通っておりましたら、こっそり心を通じている男がいたらしいのです。
【このさがな者を】- 嫉妬深い女。
【いかがはせむ】- 反語表現。どうしましょう、どうすることもできません、の意。
【目につかぬ所あるに】- 気に入らないところ。接続助詞「に」順接を表す。『完訳』は「しだいに女への熱がさめてくる」と注す。
【かれがれにのみ見せはべるほどに】- 副助詞「のみ」限定を表す。途絶えがちにばかり顔を見せておりましたうちに。
【人ぞありけらし】- 係助詞「ぞ」、推量の助動詞「らし」連体形、係り結びの法則。「けらし」は「ける」(連体形)「らし」の「る」が撥音便化(「ん」)してさらに無表記化した形。
【ある上人】- ある殿上人。この男が左馬頭が通っていた風流な女の「忍びて心交はせる人」。
【大納言の家】- 系図不明の人。『河海抄』は左馬頭の父親かとする。
【今宵人待つらむ宿なむ、あやしく心苦しき】- 上人(殿上人)の詞。推量の助動詞「らむ」視界外推量を表す。係助詞「なむ」は形容詞「心苦しき」連体形に係る、係り結びの法則。
【この女の家はた、避きぬ道なりければ】- 風流な女の家。副詞「はた」は下に打消の助動詞「ぬ」連体形に係って、これを強める。なんといっても避けられない道であったので、の意。『古典セレクション』は「この下に脱文があるとする説もあるが、会話の文には、この種の破格・省略が多い」と注す。
【荒れたる崩れ】- 風流な女の家の築地塀の崩れ。
【月だに宿る】- 副助詞「だに」最小限を表す。美しい夜には月でさえ宿ります、まして心ある人間は宿るのが当然です、の意を含む。『異本紫明抄』は「雲居にて相語らはぬ月だにも我が宿過ぎて行く時はなし」(拾遺集、雑上、四三七、伊勢)を指摘する。
【過ぎむもさすがにて】- 通り過ぎるの気がきかない、無風流なので。『古典セレクション』は「いろいろ事情はあるにせよ、素通りするのはやはり心ないしわざということで」と注す。
【下りはべりぬかし】- 主語はわたし左馬頭。「はべり」は自分の動作「下り」につけられた丁寧の補助動詞。まず殿上人が車から下りてわたしも下りた、という趣旨。終助詞「かし」念押しのニュアンス。車から降りたのでございます。二人して、下りて、邸内に入り込んだ。『新大系』は「月でさえ泊まる住みかを通り過ぎるようなのはいくらなんでも(無風流だ)という次第で、車をおりてしまうことでござるぞ。その殿上人が口実を言いながら、ほかでもない左馬頭の女の家のわきで下りてしまうという場面か。その人がその折に口ずさむ歌があるとすれば「雲ゐにてあひ語らはぬ月だにもわが宿過ぎてゆく時はなし」(拾遺集・雑上・伊勢)。左馬頭も下車して様子を見て取る、という垣間見に似る展開」と注す。
菊は一面にとても色美しく変色しており、風に勢いづいた紅葉が散り乱れているのなど、美しいものだなあと、なるほど思われました。
【この男】- 以下、左馬頭の目を通して、この男(殿上人)と女のやりとりを語る。
【門近き廊の簀子だつものに】- 「門」は中門であろう。大路に面した表門ではなかろう。中門は渡廊に繋がっておりその簀子に腰掛けたのであろう。
【菊いとおもしろく移ろひわたり、風に競へる紅葉の乱れ】- 明融臨模本「うつろひわたり(り+て)」とある。「て」は朱書による後人の補入。大島本は「うつろひわたり」とある。『集成』『新大系』は「うつろひわたり」のまま。『古典セレクション』は諸本に拠って「うつろひわたりて」と校訂する。『全集』は「秋をおきて時こそありけれ菊の花うつろふからに色のまされば」(古今集、秋下、二七九、平定文)と「秋の夜に雨と聞こえて降りつるは風に乱るる紅葉なりけり」(後撰集、秋下、四〇七、読人しらず)を指摘する。景情一致の描写。浮気な女、軽い女という性格を、変色(心変り)した菊や風に散る紅葉を描くことによって象徴し、この場の情調をつくる。
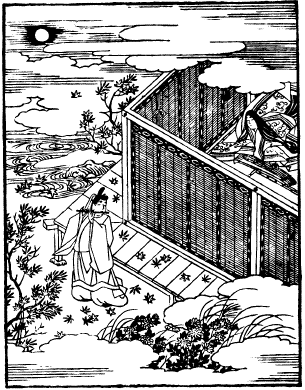
律の調子は、女性がもの柔らかく掻き鳴らして、御簾の内側から聞こえて来るのも、今風の楽の音なので、清く澄んでいる月にふさわしくなくもありません。
その男はひどく感心して、御簾の側に歩み寄って、
【蔭もよし】- 催馬楽の「飛鳥井」の一節。「飛鳥井に 宿りはすべし や おけ 蔭もよし みもひも寒し 御秣もよし」。ここに泊まりたい、の意。
【つづしり謡ふ】- 『集成』は「ぽつりぽつり歌う」と解し、『完訳』は「笛を吹きつつ合い間に歌う」と解す。「小食 ツヅシル」(『名義抄』)。
【調べととのへたりける】- 挿入句。既に調子が調整されていたもので、の意。男がいつやってきてもよいように準備していたもの。
【律の調べは】- 係助詞「は」は、「今めきたる物の声なれば」に係る。わが国固有の俗楽的音階、ややくだけた感じの調子。
菊を手折って、
【などねたます】- 「す」は使役の助動詞。などと言って、女を悔しがらせる、意。
薄情な方を引き止めることができなかったようですね
つれなき人を引きやとめける。
【今ひと声】- 以下「手な残いたまひそ」まで、引き続き、この男の詞。
【聞きはやすべき人】- 自分のこと。
【手な残いたまひそ】- 副詞「な」は終助詞「そ」と呼応して禁止を表す。
引きとどめる術をわたしは持ち合わせていません』
引きとどむべき言の葉ぞなき』
となまめき交 はすに、憎 くなるをも知 らで、また、箏 の琴 を盤渉調 に調 べて、今 めかしく掻 い弾 きたる爪音 、かどなきにはあらねど、まばゆき心地 なむしはべりし。
ただ時々 うち語 らふ宮仕 へ人 などの、あくまでさればみ好 きたるは、さても見 る限 りはをかしくもありぬべし。
時々 にても、さる所 にて忘 れぬよすがと思 ひたまへむには、頼 もしげなくさし過 ぐいたりと心 おかれて、その夜 のことにことつけてこそ、まかり絶 えにしか。
ただ
ただ時々に言葉を交わす宮仕え人などで、どこまでも色っぽく風流なのは、そうであっても付き合うには興味もありましょう。
時々であっても、通い妻として生涯の伴侶と致しますには、頼りなく風流すぎると嫌気がさして、その夜のことに口実をつくって、通うのをやめてしまいました。
【箏の琴を盤渉調に調べて】- 「箏 シャウ」(色葉字類抄)。呉音。「盤渉調」は「色葉字類抄には「盤」に濁符、「渉」に清符があって、バンシキと読んでいる。「調」については色葉字類抄には声点がなく不明であるが、運歩色葉集では濁音であり、楽家禄にも「浪牟志気伝宇」。調字濁」とあるので、古くから連濁仕手板と思われる」(小学館古語大辞典)。冬の調子。神無月(陰暦の冬)のころの曲としてふさわしい。
【まばゆき心地なむしはべりし】- 主語は左馬頭。「なむ」係助詞、「し」サ変動詞、連用形、「はべり」丁寧の補助動詞、「し」過去の助動詞、連体形。係り結びの法則。
【宮仕へ人などの】- 格助詞「の」同格を表す。宮仕え人などで、の意。
【さても見る限りは】- 風流で浮気な女と知ったうえで付き合うぶんには、の意。
【時々にても、さる所にて】- 通い婚であったので、このような表現が出てくる。
【思ひたまへむには】- 謙譲の補助動詞「たまへ」下二段、未然形、推量の助動詞「む」婉曲を表す。
【ことつけてこそ、まかり絶えにしか】- 係助詞「こそ」、過去の助動詞「しか」已然形、係り結びの法則。
この二 つのことを思 うたまへあはするに、若 き時 の心 にだに、なほさやうにもて出 でたることは、いとあやしく頼 もしげなくおぼえはべりき。
今 より後 は、ましてさのみなむ思 ひたまへらるべき。
御心 のままに、折 らば落 ちぬべき萩 の露 、拾 はば消 えなむと見 る玉笹 の上 の霰 などの、艶 にあえかなる好 き好 きしさのみこそ、をかしく思 さるらめ、今 さりとも、七年 あまりがほどに思 し知 りはべなむ。
なにがしがいやしき諌 めにて、好 きたわめらむ女 に心 おかせたまへ。
過 ちして、見 む人 のかたくななる名 をも立 てつべきものなり」
なにがしがいやしき
今から以後は、いっそうそのようにばかり思わざるを得ません。
お気持ちのままに、手折るとこぼれ落ちてしまいそうな萩の露や、拾ったと思うと消えてしまう玉笹の上の霰などのような、しゃれていてか弱く風流なのばかりが、興味深くお思いでしょうが、今はそうであっても、七年余りのうちにお分かりになるでしょう。
わたくしめごとき、わたくしごとき卑賤の者の忠告として、色っぽくなよなよとした女性にはお気をつけなさいませ。
間違いを起こして、相手の男の愚かな評判までも立ててしまうものです」
【思うたまへあはするに】- 「思う」は「思ひ」のウ音便形、謙譲の補助動詞「たまへ」下二段、連用形、動詞「あはする」下二段、連体形、接続助詞「に」順接を表す。
【若き時の心にだに】- 副助詞「だに」最小限を表す。「今より後はまして」に続く構文。
【さやうにもて出でたることは】- 風流好みの女の例をさす。係助詞「は」は「頼もしげなくおぼえはべりき」に係る。
【さのみなむ思ひたまへらるべき】- 副助詞「のみ」限定を表す。係助詞「なむ」は推量の助動詞「べき」連体形、当然の意に係る、係り結びの法則。謙譲の補助動詞「たまへ」下二段、未然形、自発の助動詞「らる」終止形。そのように思うほかございません、の意。
【御心のままに】- 源氏や頭中将のお気持ちのままに、という意。敬語「御」が付いている。
【折らば落ちぬべき萩の露】- 『異本紫明抄』は「折りてみば落ちぞしぬべき秋萩の枝もたわわにおける白露」(古今集、秋上、二二三、読人しらず)を指摘する。
【拾はば消えなむと見る玉笹の上の霰】- 明融臨模本「み(み+ゆ)る」とある。「ゆ」は朱書による後人の補入。大島本は「見る」とある。『新大系』は「見る」のまま。『集成』『古典セレクション』は「見ゆる」と校訂する。『源氏釈』は「いづこにか宿りとるらむあさひこがさすや岡辺の玉笹の上に」(古今六帖一、照日、二六九)を指摘する。
【好き好きしさのみこそ、をかしく思さるらめ】- 副助詞「のみ」限定を表す。係助詞「こそ」は「らめ」已然形に係る係り結びの法則、読点、逆接で下文に続く。「る」尊敬の助動詞、終止形。
【七年あまりがほどに思し知りはべなむ】- 「はべなむ」は「はべりなむ」の「り」が撥音便化してさらに無表記化された形。完了の助動詞「な」確述、推量の助動詞「む」推量を表す。左馬頭は源氏より七歳年長のようである。
【心おかせたまへ】- 「せ」「たまへ」二重敬語。会話文中での用法。
【過ちして、見む人の】- 「過ちして」の主語は女。「見む人」は交際相手の男性。
頭中将は例によってうなずく。
源氏の君は少し微笑んで、そういうものだろうとお思いのようである。
【身物語】- 明融臨模本と大島本は「み物かたり」と表記する。話者源氏の「身」と「御」を掛けた発言だろう。「身物語」は身の上を語った物語の意。
第三段 頭中将の体験談(常夏の女の物語)
「なにがしは、痴者 の物語 をせむ」とて、「いと忍 びて見 そめたりし人 の、さても見 つべかりしけはひなりしかば、ながらふべきものとしも思 ひたまへざりしかど、馴 れゆくままに、あはれとおぼえしかば、絶 え絶 え忘 れぬものに思 ひたまへしを、さばかりになれば、うち頼 めるけしきも見 えき。
頼 むにつけては、恨 めしと思 ふこともあらむと、心 ながらおぼゆるをりをりもはべりしを、見知 らぬやうにて、久 しきとだえをも、かうたまさかなる人 とも思 ひたらず、ただ朝夕 にもてつけたらむありさまに見 えて、心苦 しかりしかば、頼 めわたることなどもありきかし。
頼りにするとなると、恨めしく思っていることもあるだろうと、我ながら思われる折々もございましたが、女は気に掛けぬふうをして、久しく通って行かないのを、こういうたまにしか来ない男とも思っていないで、ただ朝夕にいつも心に掛けているという態度に見えて、いじらしく思えたので、ずっと頼りにしているようにと言ったこともあったのでした。
中将は前置きをして語り出した。
「私がひそかに情人にした女というのは、見捨てずに置かれる程度のものでね、長い関係になろうとも思わずにかかった人だったのですが、馴れていくとよい所ができて心が惹かれていった。たまにしか行かないのだけれど、とにかく女も私を信頼するようになった。愛しておれば恨めしさの起こるわけのこちらの態度だがと、自分のことだけれど気のとがめる時があっても、その女は何も言わない。久しく間を置いて逢っても始終来る人といるようにするので、気の毒で、私も将来のことでいろんな約束をした。
【いと忍びて見そめたりし人の】- 以下「撫子の花を折りておこせたりし」まで、頭中将の物語。格助詞「の」同格を表す。常夏の女(のちの夕顔)の物語。
【さても見つべかりしけはひなりしかば】- 「さ」は、通い妻(側室)をさす。完了の助動詞「つ」確述、終止形、推量の助動詞「べかり」適当、連用形、過去の助動詞「し」連体形。断定の助動詞「なり」連用形、過去の助動詞「しか」已然形+接続助詞「ば」、順接の確定条件を表す。側室の一人としてもよかった様子だったので、の意。「馴れゆくままに」に続く。
【ながらふべきものとしも思ひたまへざりしかど】- 挿入句。推量の助動詞「べき」当然、連体形、副助詞「しも」強調、謙譲の補助動詞「たまへ」下二段、未然形、打消の助動詞「ざり」連用形、過去の助動詞「しか」已然形+接続助詞「ど」逆接。
【さばかりになれば】- 「馴れゆくままに」から「忘れぬものに思ひたまへし」までの内容をさす。
【うち頼めるけしき】- 女が頭中将を頼りにする様子。
【恨めしと思ふこともあらむと】- 頭中将が女の心中を推測。動詞「あら」ラ変、未然形、推量の助動詞「む」終止形。例えば、途絶えがちに通っているさまなど。
【見知らぬやうにて】- 女は気に掛けない態度で。恨めしさを表面に出さない。
【朝夕にもてつけたらむありさま】- 朝に夕なに従順な態度。夫を、送り出し、出迎える、従順な妻の態度をいう。
【心苦しかりしかば】- 形容詞「心苦しかり」連用形、過去の助動詞「しか」已然形+接続助詞「ば」、順接の確定条件。
【頼めわたることなどもありきかし】- 末長く側室の一人として処遇するという約束などもした、という意。
かうのどけきにおだしくて、
このようにおっとりしていることに安心して、長い間通って行かないでいたころ、わたしの妻の辺りから、情けのないひどいことを、ある手づるがあってそれとなく言わせたことを、後になって聞きました。
【この見たまふるわたりより】- わたしの妻(右大臣の四君)の辺りから。右大臣家から。
【情けなくうたてあることをなむ】- 正妻側から側室への脅迫。係助詞「なむ」は過去の助動詞「ける」連体形に係る係り結びの法則。
【さるたよりありてかすめ言はせたりける】- 女に伝えるのに適当な機会、便宜。完了の助動詞「たり」連用形、過去の助動詞「ける」連体形、伝聞を表す。人づてに聞いた状況が現れている。
【後にこそ聞きはべりしか】- 係助詞「こそ」は、過去の「助動詞「しか」已然形に係る、係り結びの法則。丁寧の補助動詞「はべり」連用形。自身の直接体験であることを示す。
さる憂 きことやあらむとも知 らず、心 には忘 れずながら、消息 などもせで久 しくはべりしに、むげに思 ひしをれて心細 かりければ、幼 き者 などもありしに思 ひわづらひて、撫子 の花 を折 りておこせたりし」とて涙 ぐみたり。
中将は涙ぐんでいた。
【幼き者なども】- 頭中将と常夏の女の間にできた子。後の玉鬘をいう。
【撫子の花を】- 「撫子」は幼い子供を連想させる歌ことば。
「さて、その文 の言葉 は」と問 ひたまへば、
と源氏が聞いた。
【ことなることもなかりきや】- 形容詞「なかり」連用形、過去の助動詞「き」終止形、間投助詞「や」詠嘆を表す。
かわいがってやってください撫子の花を』
哀れはかけよ撫子の露』
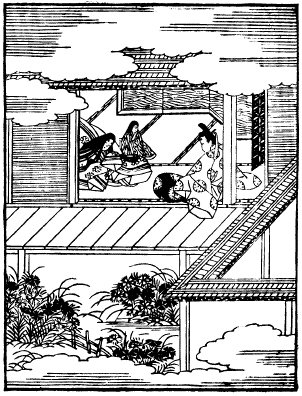
【うらもなきものから】- 係助詞「も」強調のニュアンス、接続助詞「ものから」逆接の確定条件を表す。信じきっているようでいてその一面では、という表現。
【荒れたる家の露しげきを眺めて】- 格助詞「の」所有格。「露」は涙を暗示する。「しげき」の下に「庭」などの語が省略されている。
【虫の音に競へるけしき】- 泣くさま。虫の音と泣き競っているかの様子。
【昔物語めきておぼえはべりし】- 「はべり」丁寧の補助動詞、「過去の助動詞「し」連体形止め、余情を残した表現。作品としての昔物語。陋屋に悲しみに暮れている姫君といった趣向の物語。
やはり常夏の花が一番美しく思われます』
なほ常夏にしくものぞなき』
【まづ『塵をだに】- 『源氏釈』は「塵をだに据ゑじとぞ思ふ咲きしより妹と我がぬる常夏の花」(古今集、夏、一六七、凡河内躬恒)を指摘する。床に塵が積もるようにはしません、これからは訪れますよ、の意。『新大系』は「床の塵を払うと男が訪ねてくるとの俗信(万葉集以下に見える)が背景にある歌」と注す。
さらに激しい風の吹きつける秋までが来ました』
嵐吹き添ふ秋も来にけり』
とはかなげに言 ひなして、まめまめしく恨 みたるさまも見 えず。
涙 をもらし落 としても、いと恥 づかしくつつましげに紛 らはし隠 して、つらきをも思 ひ知 りけりと見 えむは、わりなく苦 しきものと思 ひたりしかば、心 やすくて、またとだえ置 きはべりしほどに、跡 もなくこそかき消 ちて失 せにしか。
涙をもらし落としても、とても恥ずかしそうに遠慮がちに取り繕い隠して、薄情を恨めしく思っているということを知られるのが、とてもたまらないらしいことのように思っていたので、気楽に構えて、再び通わずにいましたうちに、跡形なく姿を晦ましていなくなってしまったのでした。
【つらきをも思ひ知りけりと見えむは、わりなく苦しきものと思ひたりしかば】- 「思ひ知りけり」の主語は女。「見えむ」は見える、表れる、の意。頭中将から知られること。「思ひたりしかば」の主語は女。女は、頭中将の薄情を恨めしく思っているのだと、男から知られることを、ひどく苦にしていた、の意。
【心やすくて】- 主語は頭中将。
【跡もなくこそかき消ちて失せにしか】- 係助詞「こそ」は過去の助動詞「しか」已然形に係る、係り結びの法則。動詞「失せ」下二段、連用形、完了の助動詞「に」完了の意。跡形もなく姿を隠していなくなってしまった、行方不明となってしまった、の意。
まだ世 にあらば、はかなき世 にぞさすらふらむ。
あはれと思 ひしほどに、わづらはしげに思 ひまとはすけしき見 えましかば、かくもあくがらさざらまし。
こよなきとだえおかず、さるものにしなして長 く見 るやうもはべりなまし。
かの撫子 のらうたくはべりしかば、いかで尋 ねむと思 ひたまふるを、今 もえこそ聞 きつけはべらね。
あはれと
こよなきとだえおかず、さるものにしなして
かの
愛しいと思っていましたころに、うるさいくらいにまつわり付くような様子に見えたならば、こういうふうには行方不明にはさせなかったものを。
こんなにも途絶えはせずに、通い妻の一人として末永く関係を保つこともあったでしょうに。
あの撫子がかわいらしうございましたので、何とか捜し出したいものだと存じておりますが、今でも行方を知ることができません。
【はかなき世にぞさすらふらむ】- 係助詞「ぞ」は推量の助動詞「らむ」視界外推量、連体形に係る、係り結びの法則。
【けしき見えましかば、かくもあくがらさざらまし】- 「ましかば--まし」の反実仮想の構文。態度が見えたらあのように行方不明にはさせなかったろうに、の意。
【さるものにしなして】- 側室の中でも相当な地位の人として待遇しよう、の意。
【長く見るやうもはべりなまし】- 「はべり」連用形は「有り」の丁寧語。完了の助動詞「な」未然形、完了の意、推量の助動詞「まし」反実仮想。反実仮想の構文。
【かの撫子】- のちの玉鬘のこと。女が「撫子」と詠んできたことばを受けて、用いる。
【いかで尋ねむと思ひたまふるを】- 副詞「いかで」、推量の助動詞「む」意志、謙譲の補助動詞「たまふる」下二段、連体形、接続助詞「を」逆接。
【今もえこそ聞きつけはべらね】- 係助詞「も」強調のニュアンスを添える。副詞「え」は打消の助動詞「ね」已然形と呼応して不可能の意を表す。係助詞「こそ」は「ね」已然形に係る、係り結びの法則。
これこそのたまへるはかなき例 なめれ。
つれなくてつらしと思 ひけるも知 らで、あはれ絶 えざりしも、益 なき片思 ひなりけり。
今 やうやう忘 れゆく際 に、かれはたえしも思 ひ離 れず、折々人 やりならぬ胸焦 がるる夕 べもあらむとおぼえはべり。
これなむ、え保 つまじく頼 もしげなき方 なりける。
つれなくてつらしと
これなむ、え
平気をよそおって辛いと思っているのも知らないで、愛し続けていたのも、無益な片思いでした。
今はだんだん忘れかけて行くころになって、あの女は女でまたわたしを忘れられず、時折自分のせいで胸を焦がす夕べもあるであろうと思われます。
この女は、永続きしそうにない頼りない例でしたなあ。
【つれなくてつらしと思ひけるも知らで】- 「つれなくて」の主語は女。「知らで」の主語は自分頭中将。
【あはれ絶えざりしも】- 「絶え」下二段、未然形、打消の助動詞「ざり」連用形、過去の助動詞「し」連体形、係助詞「も」。
【かれはたえしも思ひ離れず】- 副詞「はた」一面を認めながら別の一面を述べる、意。副詞「え」は打消の助動詞「ず」と呼応して不可能の意、副助詞「しも」強調。女は女で、またわたしのことを忘れられず。
【あらむとおぼえはべり】- 「あら」ラ変、未然形、推量の助動詞「む」推量。丁寧の補助動詞「はべり」終止形。
【これなむ、え保つまじく頼もしげなき方なりける】- 係助詞「なむ」は過去の助動詞「ける」連体形、詠嘆の意に係る、係り結びの法則。副詞「え」は打消推量の助動詞「まじく」連用形と呼応して不可能の意を表す。
されば、かのさがな者 も、思 ひ出 である方 に忘 れがたけれど、さしあたりて見 むにはわづらはしくよ、よくせずは、飽 きたきこともありなむや。
琴 の音 すすめけむかどかどしさも、好 きたる罪重 かるべし。
この心 もとなきも、疑 ひ添 ふべければ、いづれとつひに思 ひ定 めずなりぬるこそ。
世 の中 や、ただかくこそ。
とりどりに比 べ苦 しかるべき。
このさまざまのよき限 りをとり具 し、難 ずべきくさはひまぜぬ人 は、いづこにかはあらむ。
吉祥天女 を思 ひかけむとすれば、法気 づき、くすしからむこそ、また、わびしかりぬべけれ」とて、皆笑 ひぬ。
この
とりどりに
このさまざまのよき
琴が素晴らしい才能だったという女も、浮気な欠点は重大でしょう。
この頼りない女も、疑いが出て来ましょうから、どちらが良いとも結局は決定しがたいのだ。
男女の仲は、ただこのようなものだ。
それぞれに優劣をつけるのは難しいことで。
このそれぞれの良いところばかりを身に備えて、非難される点を持たない女は、どこにいましょうか。
吉祥天女に思いをかけようとすれば、抹香臭くなり、人間離れしているのも、また、おもしろくないでしょう」と言って、皆笑った。
中将がこう言ったので皆笑った。
【わづらはしくよ、よくせずは】- 明融臨模本には「よ」が二つある。大島本は「わつらハしくよくせすは」とある。前の「よ」に後人の朱筆でミセケチにするが、訂正以前本文の形を採用。これらの「よ」は行末と行頭にあるので、行移りの際の衍字か。終助詞また間投助詞「よ」とみた場合、その接続も連体形であってほしい所。
【飽きたきこともありなむや】- 完了の助動詞「な」確述。推量の助動詞「む」推量、間投助詞「や」詠嘆。嫌になることもきっとありましょうよ、の意。
【琴の音すすめけむ】- 左馬頭の体験談中の風流好みの浮気な女の例。
【この心もとなきも】- 頭中将の体験談中の常夏の女の例。
【思ひ定めずなりぬるこそ。世の中や、ただかくこそ】- 二つの係助詞「こそ」はいずれも受ける語句がない。そこで文は切れる。初めの「こそ」の下には「わりなけれ」などの語が省略。後の「こそ」の下には「あれ」などの語が省略。
【比べ苦しかるべき】- 連体中止法。余韻余情を表す。
【いづこにかはあらむ】- 反語表現。どこにもいない、の意。
【吉祥天女を思ひかけむ】- 『日本霊異記』中巻第十三や『古本説話集』巻下第六十二に吉祥天女に恋をした男の話がある。
【くすしからむこそ】- 「霊異 クスシキ」(西域記長寛点)。係助詞「こそ」は推量の助動詞「べけれ」已然形に係る、係り結びの法則。
【とて、皆笑ひぬ】- 頭中将の物語が終わって、一同どっと笑った。
第四段 式部丞の体験談(畏れ多い女の物語)
少しずつ、
と中将が言い出した。
【責めらる】- 「らる」は受身の助動詞。主語は藤式部丞。『古典セレクション』は「頭中将が催促される」と尊敬の助動詞とする。しかし下文に頭中将の動作には「責めたまへば」という尊敬の補助動詞「たまふ」が使用されているので、ここは受身の助動詞と解す。
「どんな話をいたしましてよろしいか考えましたが、こんなことがございます。
【何事をとり申さむ】- 藤式部丞の心、思案。
「まだ文章生 にはべりし時 、かしこき女 の例 をなむ見 たまへし。
かの、馬頭 の申 したまへるやうに、公事 をも言 ひあはせ、私 ざまの世 に住 まふべき心 おきてを思 ひめぐらさむ方 もいたり深 く、才 の際 なまなまの博士恥 づかしく、すべて口 あかすべくなむはべらざりし。
かの、
先程、左馬頭が申されましたように、公事をも相談し、私生活の面での心がけも考え廻らすこと深く、漢学の才能はなまじっかの博士が恥ずかしくなる程で、万事口出すことは何もございませんでした。
【かしこき女】- 『新大系』は「「かしこし」は、畏怖すべきだ。「賢い」という意味の原義である」と注す。
【見たまへし】- 謙譲の補助動詞「たまへ」下二段、連用形。過去の助動詞「し」連体形、係助詞「なむ」の係り結びの法則。自己の体験を語るニュアンス。
【馬頭】- 左馬頭のこと。話の中では、こう呼んでいる。
【申したまへるやうに】- 「公私の人のたたずまひ善き悪しきこと」云々をさす。源氏や頭中将を意識して左馬頭の発言を「申す」という謙譲語を用い、左馬頭に対しては「たまふ」という尊敬の補助動詞を用いている。
それは、ある博士 のもとに学問 などしはべるとて、まかり通 ひしほどに、主人 のむすめども多 かりと聞 きたまへて、はかなきついでに言 ひ寄 りてはべりしを、親聞 きつけて、盃持 て出 でて、『わが両 つの途歌 ふを聴 け』となむ、聞 こえごちはべりしかど、をさをさうちとけてもまからず、かの親 の心 を憚 りて、さすがにかかづらひはべりしほどに、いとあはれに思 ひ後見 、寝覚 の語 らひにも、身 の才 つき、朝廷 に仕 うまつるべき道々 しきことを教 へて、いときよげに消息文 にも仮名 といふもの書 きまぜず、むべむべしく言 ひまはしはべるに、おのづからえまかり絶 えで、その者 を師 としてなむ、わづかなる腰折文作 ることなど習 ひはべりしかば、今 にその恩 は忘 れはべらねど、なつかしき妻子 とうち頼 まむには、無才 の人 、なま悪 ろならむ振 る舞 ひなど見 えむに、恥 づかしくなむ見 えはべりし。
【聞きたまへて】- 謙譲の補助動詞「ためへ」下二段、連用形。
【わが両つの途歌ふを聴け】- 『白氏文集』秦中吟「議婚」の「聴我歌両途」の句。自分は貧しいが、貧家には姑に孝行を尽くす良い嫁がいる、と結婚を積極的に勧める意。式部丞の将来性を見込んでいるか、またはこの博士の家より少しは家柄や身分が高かったのでもあろうか。
【聞こえごちはべりしかど】- 丁寧の補助動詞「はべり」が第三者(博士)の動作に対して使用されている。こちらにはその気もなく、迷惑な、というニュアンスがある。
【をさをさうちとけてもまからず】- 副詞「をさをさ」は打消しの語と呼応して、少しも、ほとんど、の意。少しも気を許して通っていない。結婚してもよいという気持ちのないこと。
【いとあはれに思ひ後見】- 博士の娘が藤式部丞を。
【仮名といふもの】- 仮名文字という物を。当時、仮名は女性が多く使うものという考えがあり、男同士の話なので、「と言ふもの」と言っている。
【むべむべしく言ひまはし】- 正式な漢文体で表現する。
【腰折文】- 稚拙な漢詩文。謙遜して言ったもの。
【恩】- 学者の物言いとして、以下「妻子」「無才」「仔細」などの漢語が続出する。なお「妻子」の「子」には意味はなく「妻」の意。
【うち頼まむには】- 明融臨模本「は」の文字上に朱筆で「ヒ」とミセケチにする。後人の筆である。大島本にも「うちたのまむにハ」とある。『集成』『新大系』は「うち頼まむには」だが、『古典セレクション』では「うち頼まむに」と校訂する。
【見えむに】- 無才の人、すなわち、わたしがみっともない振る舞いをし出かすだろう、の意。
【恥づかしくなむ見えはべりし】- 係助詞「なむ」、過去の助動詞「し」連体形、係り結びの法則。わたしには思われました。
つまらない、残念だ、と一方では思いながらも、ただ自分の気に入り、宿縁もあるようでございますので、男という者は、他愛のないもののようでございます」
【宿世の引く方はべるめれば】- 丁寧語「はべる」連体形、推量の助動詞「めれ」主観的推量、已然形+接続助詞「ば」順接の確定条件。
【男しもなむ、仔細なきものははべめる】- 副助詞「しも」強調。係助詞「なむ」は推量の助動詞「める」主観的推量、連体形に係る、係り結びの法則。「はべめる」は「はべるめる」の撥音便無表記化。『古典セレクション』は「「ものははべる」は、慣用的語法。「ものにはあれ」と同意の「ものはあれ」に准ずるか」と注す。
「とてもおもしろい女じゃないか」
と言うと、その気持ちがわかっていながら式部丞は、自身をばかにしたふうで話す。
【さてさてをかしかりける女かな】- 頭中将の詞。頭中将の動作には「すかいたまふ」と敬語表現がある。藤式部丞をおだてる。
【鼻のわたりをこづきて語りなす】- 『古典セレクション』は「をこつきて」と清音に読む。『集成』は「うごめかせて」、『完訳』は「おどけて見せながら」と解す。おだてられていると十分承知していながら、調子に乗って話し続けている様子か。
「さて、いと久 しくまからざりしに、もののたよりに立 ち寄 りてはべれば、常 のうちとけゐたる方 にははべらで、心 やましき物越 しにてなむ逢 ひてはべる。
ふすぶるにやと、をこがましくも、また、よきふしなりとも思 ひたまふるに、このさかし人 はた、軽々 しきもの怨 じすべきにもあらず、世 の道理 を思 ひとりて恨 みざりけり。
ふすぶるにやと、をこがましくも、また、よきふしなりとも
嫉妬しているのかと、ばかばかしくもあり、また、別れるのにちょうど良い機会だと存じましたが、この畏れ多い女という者は、軽々しい嫉妬をするはずもなく、男女の仲を心得ていて恨み言を言いませんでした。
【物越しにてなむ逢ひてはべる】- 係助詞「なむ」、完了のの助動詞「て」連用形、確述の意、丁寧の補助動詞「はべる」連体形、係り結びの法則。いつもと違うことを強調するニュアンス。
【よきふしなりとも思ひたまふるに】- 謙譲の補助動詞「たまふる」下二段、連体形+接続助詞「に」逆接。別れるのにちょうどよい機会だと存じましたが、の意。
【世の道理を】- 男女の仲。
直接にでなくても、しかるべき雑用などは承りましょう』
【え対面賜はらぬ】- 副詞「え」、打消の助動詞「ぬ」連体形と呼応して不可能の意。係助詞「なむ」「ぬ」の係り結びの法則。
返事には何と言えようか。
ただ、『承知しました』とだけ言って、立ち去ります時に、物足りなく思ったのでしょうか、
【承りぬ】- 男の詞。
【さうざうしくやおぼえけむ】- 主語は女。藤式部丞の推測。係助詞「や」疑問、過去推量の助動詞「けむ」連体形に係る、係り結びの法則。
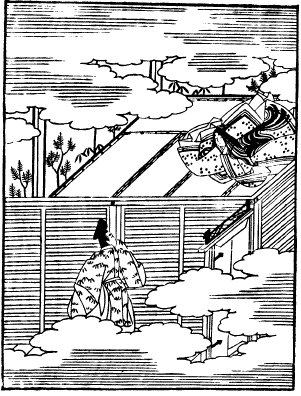
【逃げ目をつかひて】- 『集成』は「目つきもうろうろと」、『完訳』は「どうやって逃げだそうかと様子をうかがう」と解す。
蒜が臭っている昼間が過ぎるまでまで待てと言うのは訳がわかりません
ひるま過ぐせと言ふがあやなき。
【追ひて】- 主語は女。女が男の後を追って、の意。
蒜の臭っている昼間逢ったからとてどうして恥ずかしいことがありましょうか』
ひるまも何か眩ゆからまし』
と、しづしづと申 せば、君達 あさましと思 ひて、「嘘言 」とて笑 ひたまふ。
おとなしく鬼と向かい合っていたほうがましだ。
気持ちが悪い話よ」
と爪弾きをして見せて、
【鬼とこそ向かひゐたらめ】- 係助詞「こそ」、完了の助動詞「たら」未然形、推量の助動詞「め」已然形。鬼と向かい合っていよう、そのほうがましだ、の意。
「すこしよろしからむことを申 せ」と責 めたまへど、
式部丞は退って行った。
本格的に勉強しなくても、少しでも才能のあるような人は、耳から目から入って来ることが、自然に多いはずです。
【悟り明かさむこそ、愛敬なからめ】- 係助詞「こそ」、推量の助動詞「め」已然形、係り結び、逆接用法で下文に続く。
【などかは、女といはむからに】- 連語「などかは」(副詞「など」+係助詞「か」+係助詞「は」)は、「あらむ」に係る、反語表現。動詞「いは」未然形、推量の助動詞「む」連体形、仮定の意、格助詞「から」、接続助詞「に」。「む」と「から」の間には「こと」などの語が省略。
さるままには、真名 を走 り書 きて、さるまじきどちの女文 に、なかば過 ぎて書 きすすめたる、あなうたて、この人 のたをやかならましかばと見 えたり。
心地 にはさしも思 はざらめど、おのづからこはごはしき声 に読 みなされなどしつつ、ことさらびたり。
上臈 の中 にも、多 かることぞかし。
気持ちの上ではそんなにも思わないでしょうが、自然とごつごつした声に読まれ読まれして、わざとらしく感じられます。
上流の中にも多く見られることです。
【あなうたて、この人のたをやかならましかば】- 左馬頭の感想を挿入。推量の助動詞「ましか」未然形、仮想の意+接続助詞「ば」、下に「よからまし」などの語句が省略。反実仮想の構文。
【おのづからこはごはしき声に】- 漢字が混じった手紙文を声を出して読むと、自然と重々しくこわばった感じに読み上げられてしまう、という意。
【多かることぞかし】- 連語「ぞかし」(係助詞「ぞ」+終助詞「かし」)念押し、の意。
返歌しないと人情がないし、出来ないような人は体裁が悪いでしょう。
【取り込みつつ】- 接続助詞「つつ」動作の反復・継続を表す。
【すさまじき折々】- 『集成』は「こちらが迷惑するような時」と解し、『古典セレクション』は「場違いで歌を詠む気持になれないとき」と注す。
【詠みかけたるこそ、ものしきことなれ】- 係助詞「こそ」、断定の助動詞「なれ」已然形、係り結びの法則。強調のニュアンスを添える。
【えせざらむ人】- 『集成』は「できない事情にある人」と解す。副詞「え」は打消の助動詞「ざら」未然形と呼応して不可能の意を表す。推量の助動詞「む」連体形、婉曲を表す。
そんな時に菖蒲に寄せた歌が贈られる、九月の菊の宴に作詩のことを思って一所懸命になっている時に、菊の歌。こんな思いやりのないことをしないでも場合さえよければ、真価が買ってもらえる歌を、今贈っては目にも留めてくれないということがわからないでよこしたりされると、ついその人が軽蔑されるようになります。
【五月の節】- 五月の節句、すなわち、端午の節会。
【何のあやめも】- 五月の節会にちなんで、「文目」に「菖蒲(あやめ)」を掛けた言葉のしゃれ。
【九日の宴】- 九月九日の宴、すなわち、重陽の節会。
【思ひめぐらして】- 明融臨模本「思めくらし・て(て$)」とある。ミセケチは朱筆で「ヒ」とあるので、後人の訂正。句点もその時に付けられたもの。大島本は「思めくらし」とある。『集成』は「思ひめぐらして」、『新大系』『古典セレクション』は「思ひめぐらし」とする。
【げに後に思へば】- 副詞「げに」は「あべかりける」にかかる。
【あべかりけることの】- 「あるべかり」の「る」が撥音便化しさらに無表記の形。
【よしばみ情け立たざらむなむ目やすかるべき】- 打消の助動詞「ざら」未然形、推量の助動詞「む」連体形、係助詞「なむ」は、推量の助動詞「べき」連体形、推量に係る、係り結びの法則。
【言はまほしからむことをも】- 希望の助動詞「まほしから」未然形、推量の助動詞「む」連体形、婉曲の意。
【過ぐすべくなむあべかりける】- 推量の助動詞「べく」連用形、適当の意、係助詞「なむ」は過去の助動詞「ける」連体形、詠嘆の意に係る、係り結びの法則。「あべかり」は「あるべかり」(「ある」連体形+推量の助動詞「べかり」連用形、当然の意)の「る」が撥音便化しそれが無表記の形。言わないでおくのが良いのである。以上、雨夜の品定めの議論が終わる。
「この結論に足りないことまた出過ぎたところもない方でいらっしゃるなあ」と、比類ないことにつけても、ますます胸がいっぱいになる。
【これに足らず】- 以下「ものしたまひけるかな」まで、源氏の心。「これ」は左馬頭の意見をさす。
【ものしたまひけるかな】- 主語は藤壺宮。過去の助動詞「ける」連体形、詠嘆の意。終助詞「かな」詠嘆の意。
【あやしきことどもになりて】- 『集成』は「要領を得ない話になって」と注し、『完訳』は「埒もない話の数々になって」と訳す。『新大系』は「怪談やとりとめない世間話その他に落ちて行った感じ。夜を徹しての語りあいやその批評である」と注す。
【明かしたまひつ】- 主語は源氏の君たち。
第三章 空蝉の物語
第一段 天気晴れる
こうしてばかり籠っていらっしゃるのも、左大臣殿のお気持ちが気の毒なので、退出なさった。
【大殿の御心】- 左大臣をさす。
おほかたの気色 、人 のけはひも、けざやかにけ高 く、乱 れたるところまじらず、なほ、これこそは、かの、人 びとの捨 てがたく取 り出 でしまめ人 には頼 まれぬべけれ、と思 すものから、あまりうるはしき御 ありさまの、とけがたく恥 づかしげに思 ひしづまりたまへるをさうざうしくて、中納言 の君 、中務 などやうの、おしなべたらぬ若人 どもに、戯 れ言 などのたまひつつ、暑 さに乱 れたまへる御 ありさまを、見 るかひありと思 ひきこえたり。
【けざやかにけ高く、乱れたるところまじらず】- 葵の上の性格。はっきりと、端麗で気品高く見え、何事にもきちんとしている、という、源氏の目から見た鮮明な印象。「桐壺」巻の楊貴妃と桐壺更衣とを比較した「絵に描ける楊貴妃の容貌は、いみじき絵師といへども、筆限りありければいとにほひ少なし。「太液芙蓉未央柳」も、げに通ひたりし容貌を、唐めいたる装ひはうるはしうこそありけめ、(桐壺更衣の)なつかしうらうたげなりしを思し出づるに、花鳥の色にも音にもよそふべき方ぞなき」(第二章三段)を想起すれば、源氏が思慕する母桐壺更衣のイメージとは違った個性の人物である。
【なほ、これこそは】- 以下「頼まれぬべけれ」まで、源氏の心。「これ」は正妻の葵の上をさす。
【かの、人びとの捨てがたく取り出でし】- 左馬頭たちが高く評価した。
【あまりうるはしき御ありさまの、とけがたく恥づかしげに思ひしづまりたまへる】- 源氏の目から見た葵の上。度を過ぎて端麗な態度で、心が打ち解けず、こちらが気づまりに感じるばかりに相手はとり澄ましていらっしゃる、という印象。
【さうざうしくて】- 源氏は、そのような妻に物足りなさを感じる。
【中納言の君、中務などやうの】- 女房であるが、源氏のお手つきの女房。召人(めしうど)という。
【戯れ言などのたまひつつ】- 接続助詞「つつ」動作の反復・継続を表す。
【暑さに乱れたまへる御ありさま】- 暑さのためにお召物をくつろげていらっしゃる源氏の様子。
【見るかひありと思ひきこえたり】- 主語は女房たち。
「お静かに」と制して、脇息に寄り掛かっていらっしゃる。
いかにも大君らしい鷹揚なお振る舞いであるよ。
「暑いのに」
と源氏が顔をしかめて見せると、女房たちは笑った。
「静かに」
と言って、脇息に寄りかかった様子にも品のよさが見えた。
【御几帳隔てて】- くつろいでいるところに直接対座するのは不躾であろうと、左大臣と源氏の間に御几帳を立てて会った。舅である左大臣の聟である源氏に対する大変な気のつかいようが窺われる。
【御物語聞こえたまふを】- 左大臣が源氏に。源氏の官職は宰相兼中将。その人に左大臣が「聞こえたまふ」という敬意表現を用いるのは、桐壺帝の御子だからである。
【暑きに」とにがみたまへば、人びと笑ふ】- 源氏が苦々しい顔をすると、女房たちが笑う、というように、源氏は女房たちに囲まれた中にいる。
【あなかま】- 源氏の詞。
【おはす】- 前の「おはします」よりやや敬意は低い敬語である。左大臣より低く語られているが、次の批評の言葉と連動してであろう。
【いとやすらかなる御振る舞ひなりや】- 断定の助動詞「なり」終止形、係助詞「や」詠嘆の意。源氏の態度に対する語り手の感想。『岷江入楚』は「草子の評也」と注す。『古典セレクション』は「貴人らしいおおような源氏の態度についての、語り手の賞賛」と注す。
という、源氏の家従たちのしらせがあった。
とても気分が悪いのに」
「大変に具合悪いことです」と、誰彼となく申し上げる。
「このままになすってはよろしくございません」
また家従が言って来る。
「中川辺でございますがこのごろ新築いたしまして、水などを庭へ引き込んでございまして、そこならばお涼しかろうと思います」
【中川のわたりなる家なむ】- 二条以北の京極川の呼称。内裏からは東の方角に当たる。係助詞「なむ」は「はべる」連体形に係る、係り結びの法則。
【水せき入れて】- 京極川から水を邸内に堰き入れて。
気分が悪いから、牛車のままで入って行かれる所を」
【牛ながら引き入れつべからむ】- 接尾語「ながら」、牛車のまま、の意。
内密の方違えのお邸は、たくさんあるに違いないが、長いご無沙汰の後にいらっしゃったのに、方角が悪いからといって、期待を裏切って他へ行ったとお思いになるのは、気の毒だと思われたのであろう。
紀伊守に御用を言い付けなさると、お引き受けは致したものの、引き下がって、
【久しくほど経て渡りたまへるに】- 接続助詞「に」逆接を表す。源氏が左大臣邸へいらっしゃったのに。
【と思さむは、いとほしきなるべし】- 左大臣が、とお思いになるのは、お気の毒だと源氏は思われたのであろう、の意。「なる」「べし」は語り手が源氏の心を推測した表現。『古典セレクション』は「なるべし」の下に読点を打つ。語り手の挿入句と解する。
【紀伊守に仰せ言賜へば】- 主語は源氏。源氏のご意向を男の侍者が紀伊守に命じる。
【承りながら、退きて】- 接続助詞「ながら」逆接を表す。『新大系』は「(直接に)お下しになると、承諾しつつ(源氏のもとから)退出して。以下は紀伊守の嘆き」と注す。場面は源氏のいる所とは離れた所で。
【女房なむまかり移れるころにて】- 係助詞「なむ」は「移れる」に係るが、下文に続くため、結びの流れ。
【なめげなることやはべらむ】- 係助詞「や」疑問、推量の助動詞「む」連体形に係る、係り結びの法則。
女気のない旅寝は、何となく不気味な心地がするからね。
ちょうどその几帳の後ろに」とおっしゃるので、
冗談混じりにまたこう言わせたものである。
【もの恐ろしき心地すべきを】- 推量の助動詞「べき」当然の意、間投助詞「を」詠嘆を表す。
とてもこっそりと、格別に大げさでない所をと、急いでお出になるので、左大臣殿にもご挨拶なさらず、お供にも親しい者ばかり連れておいでになった。
と言って、紀伊守は召使を家へ走らせた。源氏は微行で移りたかったので、まもなく出かけるのに大臣へも告げず、親しい家従だけをつれて行った。
【人走らせやる】- 主語は紀伊守。使いの者を邸に遣わして源氏来訪の旨を伝えその準備をさせる。
【ことさらにことことしからぬ所をと】- 源氏の心。「ことことし」清音。「コトコトシイ Cotocotoxij」(日葡辞書)。『古典セレクション』は「ことごとし」と濁音に読む。
【大臣にも聞こえたまはず】- お暇乞いの挨拶を。行く先は告げずとも状況からして自ずと判断されたろう。
【御供にも睦ましき限りしておはしましぬ】- 紀伊守邸に御到着になった、という意。「おはします」という最高敬語は源氏と紀伊守との身分格差を印象づける。
第二段 紀伊守邸への方違へ
寝殿の東面をきれいに片づけさせて、急拵えのご座所を設けた。
遣水の趣向などは、それなりに趣深く作ってある。
田舎家風の柴垣を廻らして、前栽など気を配って植えてある。
風が涼しく吹いて、どこからともない微かな虫の声々が聞こえ、蛍がたくさん飛び交って、趣のある有様である。
【人も聞き入れず】- 「人」は源氏の供人たち。係助詞「も」強調のニュアンス。
【田舎家だつ柴垣して】- 京都神護寺蔵国宝「山水屏風」に似た風景が描かれている。
【前栽】- 「平安時代はセンサイと清音」(岩波古語辞典)。『集成』『新大系』『古典セレクション』は「せんざい」と濁音に読む。

主人の紀伊守もご馳走の準備に走り回っている間、源氏の君はゆったりとお眺めになって、あの人たちが、中の品の例に挙げていたのは、きっとこういう程度の家の女性なのだろう、とお思い出しになる。
【主人も肴求むと、こゆるぎのいそぎありくほど、君は】- 『源氏釈』は「玉垂れの 小瓶を中に据ゑて あるじはも や 肴まぎに 肴りに こゆるぎの磯の 若布と(わかめ)刈り上げに」(風俗歌 玉垂れ)を指摘する。その歌句によった表現である。「主人も」の係助詞「も」は、家人たちだけでなく主人も、の意。紀伊守が肩を揺すって忙しそうに接待に追われているのに対し、「君は」というように、源氏は一人悠然と構えている様子が対比されて語られる。
【かの、中の品に】- 以下「この並ならむかし」まで、源氏の心。昨夜の議論を想起する。「かの」は、あの人たちが、の意。
【この並ならむかしと】- 断定の助動詞「なら」未然形、推量の助動詞「む」終止形、終助詞「かし」念押しを表す。。
さすがに
衣ずれの音がさらさらとして、若い女性の声々が愛らしい。
そうは言っても小声で、笑ったりなどする様子は、わざとらしい。
【この西面にぞ人のけはひする】- 「この」は源氏のいる場所を軸にして。寝殿の西面。係助詞「ぞ」は「する」連体形に係る、係り結びの法則。強調のニュアンス。
【衣の音なひ】- 以下の描写は、源氏の耳を通して語った表現。
【若き声どもにくからず】- 若い女たちの声が愛らしい。源氏の感情を交えて語った表現。
【さすがに忍びて】- 活発で若い女房とはいえ客人に遠慮して、というニュアンス。
【ことさらびたり】- 来客を意識した振る舞い、と源氏は思う。
【心なし】- 紀伊守の詞。
【障子の上より漏りたるに】- 障子は襖のこと。「上(かみ)」は、上長押の上から光が漏れてくるのであろう。「かみ」を「紙」と解する説もある。『評釈』は「障子の紙よりもりたるに」とし、「「障子の紙」は「障子の上」と解する説もある。「上」説の理由は、襖障子の紙を透して火影がもれるはずがないからというのである。「紙より」と解して「障子の紙の間より漏る(障子ノ紙スナワチ襖ノ間カラ漏ル)」というのを、「障子の紙より漏る」と慣用句的に言ったのではないか、「襖の閉めてある合せ目から火影が漏れ出るのであろう」という島津久基博士説に従う」と注す。
【見ゆや】- 源氏の心。
【この近き母屋に集ひゐたるなるべし】- 源氏の耳からの推察。完了の助動詞「たる」連体形、存続の意、断定の助動詞「なる」連体形、推量の助動詞「べし」推量の意は、源氏の判断。語り手と登場人物の視点が一体化している。
【うちささめき言ふことどもを聞きたまへば】- 地の文。源氏に添った表現である。
【わが御上なるべし】- 源氏の耳からの推察。伝聞推定の助動詞「なる」連体形、推量の助動詞「べし」推量の意は、前同様に源氏の判断。自分で自分の事を「わが御上」という敬語の使い方は、今ではおかしいが、語り手の源氏に対する敬意が表れたものである。
まだお若いのに、高貴な北の方が定まっていらっしゃるとは、なんとつまらないのでしょう」
【定まりたまへるこそ、さうざうしかめれ】- 完了の助動詞「る」連体形、係助詞「こそ」。形容詞「さうざうしかる」連体形「る」が撥音便化し無表記の形。推量の助動詞「めれ」已然形、主観的推量のを表す。係り結びの法則。
【かやうのついでにも】- 以下「聞きつけたらむ時」まで、源氏の心。女房どうしの所在ない時の世間話。前に宿直の夜に男どうしの女性体験談が語られていた。
【人の言ひ漏らさむを】- 女房などが、藤壺と自分との関係を言い漏らすようなのを。
【聞きつけたらむ時】- 主語は他人と解す。完了の助動詞「たら」未然形、推量の助動詞「む」仮定の意。
式部卿宮の姫君に、朝顔の花を差し上げなさった時の和歌などを、少し文句を違えて語るのが聞こえる。
「ゆったりと和歌を口にすることよ、やはり見劣りすることだろう」とお思いになる。
【すこしほほゆがめて語る】- 動詞「頬歪め」下二段、連用形。事実を歪める、意。少し歌の文句を違えて語る。
【くつろぎがましく】- 以下「しなむかし」まで、源氏の心。明融臨模本の傍書に「カルカルシクシトケナキ也」とある。『集成』は「有閑婦人気取りで」と解し、『完訳』は「気楽な世間話の歌語り」と解す。
【歌誦じがちにもあるかな】- 何かと機会あれば、歌を口ずさむことよ、の意。
【なほ見劣りはしなむかし】- 完了の助動詞「な」未然形、確述、推量の助動詞「む」推量、終助詞「かし」念押し、の意。『古典セレクション』は「風流めかしていてもしょせん中流と見てとる。この軽蔑が、以下の好色の行動をたやすくさせる」と注す。
【御くだものばかり参れり】- 菓子、果物類。紀伊守は酒の肴類だけを差し上げる。副助詞「ばかり」は程度を表す。言外にこの程度では不足であるというニュアンスが下文の源氏の詞を導き出す。「参る」謙譲語は、差し上げる。
そうした方面の趣向もなくては、興醒めなもてなしであろう」とおっしゃると、
【さる方の心もとなくては】- 明融臨模本「心もとなくては」とある。大島本には「心もなくてハ」とある。明融臨模本のままとするが、『集成』『新大系』『古典セレクション』は「心もなくては」と校訂する。「さる方」は女のもてなし、の意。
端の方のご座所に、うたた寝といったふうに横におなりになると、供人たちも静かになった。
紀伊守は縁側でかしこまっていた。源氏は縁に近い寝床で、仮臥のように横になっていた。随行者たちももう寝たようである。
その子供で、童殿上している間に見慣れていらっしゃっるのもいる。
伊予介の子もいる。
大勢いる中で、とても感じが上品で、十二、三歳くらいになるのもいる。
【童なる、殿上のほどに】- 殿上童のこと。貴族の子弟で容姿端麗な子どもが殿上間で小間使いを努める。
【伊予介の子もあり】- 紀伊守の弟たち。
【十二、三ばかりなるもあり】- 後文から、小君、故衛門督の子で空蝉の弟と知れる。
「いづれかいづれ」など問 ひたまふに、
「これは、故衛門督 の末 の子 にて、いとかなしくしはべりけるを、幼 きほどに後 れはべりて、姉 なる人 のよすがに、かくてはべるなり。
才 などもつきはべりぬべく、けしうははべらぬを、殿上 なども思 ひたまへかけながら、すがすがしうはえ交 じらひはべらざめる」と申 す。
学問などもできそうで、悪くはございませんが、童殿上なども考えておりますが、すらすらとはできませんようで」と申し上げる。
と紀伊守が説明した。
【故衛門督の末の子にて】- 衛門府の長官。従四位下相当。後に柏木が衛門督として有名。名門の貴族子弟が着任している。
【姉なる人のよすがに】- その子の姉が伊予介と結婚した縁で、ここに一緒にいる。
【え交じらひはべらざめる】- 副詞「え」、打消の助動詞「ざる」と呼応して不可能の意。丁寧の補助動詞「はべら」未然形。打消の助動詞「ざ」は「ざる」連体形の「る」が撥音便化して無表記の形。推量の助動詞「める」連体形、主観的推量を表す。言い切らずに余情を残した連体中止法。
【と申す】- 明融臨模本は「申す」の次に朱筆で「ニ」を補入する。後人の筆であろう。大島本には「申」とある。
この子の姉君が、そなたの継母か」
「さなむはべる」と申 すに、
主上におかれてもお耳にお忘れにならず、『宮仕えに差し上げたいと、ちらと奏上したことは、その後どうなったのか』と、いつであったか仰せられた。
人の世とは無常なものだ」と、とても大人びておっしゃる。
老成者らしい口ぶりである。
【宮仕へに出だし立てむと漏らし奏せし】- 衛門督は、その娘を入内させようと、内々に帝に奏上していた、それを源氏は聞き知っていたという経緯である。「宮仕へ」は更衣として入内させること。推量の助動詞「む」意志を表す。「奏す」は天皇に申し上げる。
【世こそ定めなきものなれ】- 係助詞「こそ」「、断定の助動詞「なれ」已然形、係り結びの法則。強調のニュアンス。
【いとおよすけのたまふ】- 『集成』『古典セレクション』は「およすけ」と清音で読み、『新大系』は「およすげ」と濁音で読む。『河海抄』には濁符がある。『全集』は「不自然の感を免れるための作者の弁解でもある」と注す。
男女の仲と言うものは、所詮、そのようなものばかりで、今も昔も、どうなるか分からないものでございます。
中でも、女の運命は定めないのが、哀れでございます」などと申し上げて途中で止める。
などと紀伊守は言っていた。
【さのみこそ、今も昔も、定まりたることはべらね】- 係助詞「こそ」、打消の助動詞「ね」已然形、係り結びの法則。
【女の宿世は浮かびたるなむ、あはれにはべる】- 明融臨模本「うかひ(ひ=ミ)たる」とある。大島本は「いとうかひたる」と副詞「いと」がある。『集成』は「浮かびたる」のまま。『新大系』『古典セレクション』は「いと浮くかびたる」と校訂する。完了の助動詞「たる」連体形、主格となる。係助詞「なむ」は丁寧の補助動詞「はべる」連体形に係る、係り結びの法則。
【聞こえさす】- 「さす」は、中途で止める意。紀伊守は、少しでしゃばって物を言い過ぎたと感じたか、源氏の顔色を見て、議論を言いさした。
主君と思っているだろうな」
内々の主君として世話しておりますようですが、好色がましいことだと、わたくしめをはじめとして、納得できないほどでございます」などと申し上げる。
【私の主とこそは思ひてはべるめるを】- 明融臨模本「こそは(は$)」とあるが、「は」の左側に朱筆で「ヒ」と記された後人のミセケチ。大島本にも「こそハ」とある。『古典セレクション』は「こそ」と校訂。係助詞「こそ」は、「はべる」にかかるが、下文に続くため、結びの流れとなっている。推量の助動詞「める」連体形、話者の主観的推量を表す。接続助詞「を」逆接を表す。
【なにがしよりはじめて】- 自分をはじめとして兄弟一同、の意。
【うけひきはべらずなむ】- 係助詞「なむ」は結びの省略。
あの伊予介は、なかなか風流心があって、気取っているからな」などと、お話なさって、
などと話しながら、
【おろしたてむやは】- 推量の助動詞「む」推量、連語「やは」(「や」係助詞「は」係助詞)反語を表す。伊予介は後妻の空蝉を子の紀伊守に譲ろうか、譲るまい、の意。
【かの介は、いとよしありて気色ばめるをや】- 連語「をや」(終助詞「を」終助詞「や」)感動を表す。紫式部が結婚した相手の藤原宣孝も晩年に息子たちと同年齢の紫式部を後添えに迎えている。その彼も風流人であったエピソードが伝わっている。
「いづかたにぞ」
と紀伊守は言った。
【おろしはべりぬるを】- 完了の助動詞「ぬる」連体形、完了の意、接続助詞「を」逆接を表す。
【えやまかりおりあへざらむ】- 副詞「え」は打消の助動詞「ざら」と呼応して不可能の意を表す。係助詞「や」疑問の意、推量の助動詞「む」連体形、推量の意を表す。身分卑しい女たちは皆下屋に下ろしたが、全員は下ろしきれず、やや高い女は残っている、という意。
第三段 空蝉の寝所に忍び込む
【いたづら臥しと思さるるに】- 源氏の心。自発の助動詞「るる」連体形。接続助詞「に」順接、原因理由を表す。
【こなたや】- 以下「あはれや」まで、源氏の心。「あはれや」を、『集成』は「どうしているだろう」と解し、『完訳』は「かわいそうな」と訳す。『新大系』は「老受領の後妻になっている女への哀れみである。中の品に転じているらしい女への興味がかきたてられて様子を窺う」と注す。
【立ち聞きたまへば】- 以下、源氏の耳を通して語る描写。
どこにいらっしゃいますか」
と、かれたる声 のをかしきにて言 へば、
お客様はお寝みになりましたか。
どんなにお近かろうかと心配していましたが、でも、遠そうだわね」
【客人は寝たまひぬるか】- 「客人」は源氏の君をさす。完了の助動詞「ぬる」連体形、係助詞「か」疑問の意。
【いかに近からむと思ひつるを】- 副詞「いかに」、推量の助動詞「む」終止形、完了の助動詞「つる」連体形、完了の意。接続助詞「を」逆接を表す。
【け遠かりけり】- 接頭語「け」は、なんとなく、いくらか、などのニュアンスを添える。過去の助動詞「けり」詠嘆の意。
寝ていた声で取り繕わないのが、とてもよく似ていたので、その姉だなとお聞きになった。
【いもうとと聞きたまひつ】- 「いもうと」は男からみた異性の姉妹。ここは姉をいう。男の子(小君)の姉と理解。
噂に聞いていたお姿を拝見いたしましたが、噂通りにご立派でしたよ」と、ひそひそ声で言う。
一段声を低くして言っている。
【見たてまつりつる】- 完了の助動詞「つる」連体形、下に接続助詞「に」順接などの語が省略。
【げにこそめでたかりけれ】- 係助詞「こそ」過去の助動詞「けれ」已然形、詠嘆の意。係り結びの法則。
「惜しいな、
端に寝ましょう。
女君は、ちょうどこの襖障子口の斜め向こう側に臥しているのであろう。
【ほどにぞ臥したるべき】- 係助詞「ぞ」、推量の助動詞「べき」連体形、係り結びの法則。
誰もいないような感じで、何となく恐い」
【いづくにぞ】- 係助詞「ぞ」の下に「をる」連体形、などの語が省略。
【答へすなり】- 「す」終止形、伝聞推定の助動詞「なり」終止形。源氏の耳を通して語る描写。
『すぐに参ります』とのことでございます」と言う。
と言っていた。
なまわづらはしけれど、
几帳を襖障子口に立てて、灯火はほの暗いが、御覧になると唐櫃のような物どもを置いてあるので、ごたごたした中を、掻き分けて入ってお行きになると、ただ一人だけでとても小柄な感じで臥せっていた。
何となく煩わしく感じるが、上に掛けてある衣を押しのけるまで、呼んでいた女房だと思っていた。
小さな形で女が一人寝ていた。やましく思いながら顔を掩うた着物を源氏が手で引きのけるまで女は、さっき呼んだ女房の中将が来たのだと思っていた。
【あなたよりは鎖さざりけり】- 過去の助動詞「けり」詠嘆の意。その意外さに驚く。源氏の驚きの気持ちと語り手の気持ちが一体化したような表現。紀伊守が外しておいたものであろう。
【灯はほの暗きに】- 「暗き」連体形+接続助詞「に」逆接。
【なまわづらはしけれど】- 『集成』は「何となく気が咎めるけれども」と、源氏の君の心中と解す。『古典セレクション』は「うとうとししかけたところを寄り添われた女の意識」と解す。『新大系』も同じ。ここまで、源氏の耳、目を通して語ってきたが、ここで主語(語り手の視点)が女に転じたとみる。
【求めつる人】- 空蝉が召した人、女房の中将の君。
人知れずお慕いしておりました、その甲斐があった気がしまして」
このような機会を待ち受けていたのも、決していい加減な気持ちからではない深い前世からの縁と、お思いになって下さい」
【見たまふらむ】- 主語はあなた(空蝉)が。「たまふ」終止形+推量の助動詞「らむ」視界外推量を表す。下に「ことは」などの語句が省略、主格となって下文に続く。
【年ごろ思ひわたる心のうち】- 源氏の女を口説くときの常套句。
【聞こえ知らせむとてなむ】- 推量の助動詞「む」意志、係助詞「なむ」の下に「まゐりぬ」などの語句が省略。
【さらに浅くはあらじ】- 前の「深からぬ心のほど」と照応するが、またあなたとわたしの縁が浅くはない、の意も込められている。両義性をもった掛詞的な表現。副詞「さらに」は打消の助動詞「じ」と呼応して、決して、少しも、全然、の意を表す。
気分は辛く、あってはならない事だと思うと、情けなくなって、
「知らぬ人がこんな所へ」
ともののしることができない。
しかも女は情けなくてならないのである。
【えののしらず】- 副詞「え」打消の助動詞「ず」と呼応して不可能の意を表す。大声を出すことができない。
【あるまじきこと】- 空蝉は人妻である。他の男性との逢瀬はあってはならないこと。
「人違 へにこそはべるめれ」と言 ふも息 の下 なり。
やっと、息よりも低い声で言った。
好色めいた振る舞いは、決して致しません。
気持ちを少し申し上げたいのです」
【心のしるべを】- 格助詞「を」目的格を表す。
【思はずにもおぼめいたまふかな】- 「思はずにも」は、意外にも、理解せずに、の両義性をもった掛詞的表現。終助詞「かな」詠嘆を表す。
【よに見えたてまつらじ】- 副詞「よに」は下に打消推量の助動詞「じ」終止形、意志と呼応して、決して、の意を表す。
【聞こゆべきぞ】- 係助詞「ぞ」、文末にある場合、文全体を強調する。
【障子のもと出でたまふにぞ】- 「もと」の次に格助詞「に」場所が省略。係助詞「ぞ」は完了の助動詞「たる」連体形に係る、係り結びの法則。
「やや」とのたまふに、あやしくて探 り寄 りたるにぞ、いみじく匂 ひみちて、顔 にもくゆりかかる心地 するに、思 ひ寄 りぬ。
あさましう、こはいかなることぞと思 ひまどはるれど、聞 こえむ方 なし。
並々 の人 ならばこそ、荒 らかにも引 きかなぐらめ、それだに人 のあまた知 らむは、いかがあらむ。
心 も騷 ぎて、慕 ひ来 たれど、動 もなくて、奥 なる御座 に入 りたまひぬ。
あさましう、こはいかなることぞと
意外なことで、これはどうしたことかと、おろおろしないではいられないが、何とも申し上げようもない。
普通の男ならば、手荒に引き放すこともしようが、それでさえ大勢の人が知ったらどうであろうか。
胸がどきどきして、後からついて来たが、平然として、奥のご座所にお入りになった。
と源氏が言ったので、不思議がって探り寄って来る時に、薫き込めた源氏の衣服の香が顔に吹き寄ってきた。中将は、これがだれであるかも、何であるかもわかった。情けなくて、どうなることかと心配でならないが、何とも異論のはさみようがない。並み並みの男であったならできるだけの力の抵抗もしてみるはずであるが、しかもそれだって荒だてて多数の人に知らせることは夫人の不名誉になることであって、しないほうがよいのかもしれない。こう思って胸をとどろかせながら従ってきたが、源氏の中将はこの中将をまったく無視していた。初めの座敷へ抱いて行って女をおろして、
【あやしくて探り寄りたるにぞ】- 完了の助動詞「たる」連体形+接続助詞「に」順接+係助詞「ぞ」。「ぞ」は「心地する」に係るが、下文に続いて、結びの流れ。中将の君は不審に思って手探りで近付いたところ、の意。
【思ひ寄りぬ】- その声の主が源氏であると理解した。
【こはいかなることぞ】- 中将の君の心。係助詞「ぞ」、文末にある場合、文全体を強調する。源氏の君がわが主人の空蝉を抱いて部屋から連れ出そうとしているので。
【並々の人ならばこそ】- 以下「いかがはあらむ」まで、中将の君の心。係助詞「こそ」は「引きかなぐらめ」に係る、下文に続く逆接用法。
【それだに人のあまた知らむは】- 副助詞「だに」最小限を表す。推量の助動詞「む」婉曲を表す。
【動もなくて】- 主語は源氏。源氏の君の平然とした態度。
【奥なる御座】- 『評釈』は「端つ方の御座」に対して「母屋に設けられた源氏の寝所」と注す。『新大系』は「東の廂にある奥の座所。正式の寝所がしつらえられていたのだろうと言う」と注す。『古典セレクション』は「障子口の向こうの源氏の寝室にあてられた母屋の南半分」と注す。いずれにしても、紀伊守は源氏のために、「端つ方の御座」とは別に正式の寝所を準備していた。
「夜明けにお迎えに来るがいい」
と言った。中将はどう思うであろうと、女はそれを聞いただけでも死ぬほどの苦痛を味わった。流れるほどの汗になって悩ましそうな女に同情は覚えながら、女に対する例の誠実な調子で、女の心が当然動くはずだと思われるほどに言っても、女は人間の掟に許されていない恋に共鳴してこない。
【女は、この人の思ふらむことさへ】- 「女」は空蝉、「この人」は中将の君。推量の助動詞「らむ」視界外推量、副助詞「さへ」添加を表す。
【いと悩ましげなる】- 断定の助動詞「なる」連体中止法で下文に続く。
【例の】- 以下「べかめれど」まで、「例の」「にかあらむ」(疑問、推量)「べかめれど」(推量)は、語り手が源氏の態度に対して発したものである。挿入句。『湖月抄』は「地」と記して、いわゆる草子地であることを指摘する。
【なほいとあさましきに】- 主語は女に転じる。接続助詞「に」順接、原因理由を表す。やはりまことに情けないので。
しがない身の上ですが、お貶みなさったお気持ちのほどを、どうして浅いお気持ちと存ぜずにいられましょうか。
まことに、このような身分の女には、それなりの生き方がございます」
【思しくたしける】- 「くたす」は清音、「腐す」意。「下す」ではない。
【いかが浅くは思うたまへざらむ】- 反語表現。浅くは思わない、すなわち深く思う、の意。ただしかし、源氏の愛情を深く理解するというのではなく、源氏が私(空蝉)を蔑んだ気持ちが深い、というもの。『新大系』は「人数にも入らぬいやしいわが身のままであれ、その私を心から見下してこられた、あなたさまのお気持の程度につけてもどうして浅いと思い申さずにはいられよう。前頁に「さらに浅くはあらじ」とあった源氏の言葉を受けて、あなたの私への見下す心もまた浅からぬとせいいっぱい言い返す」と注す。『古典セレクション』でも「前文に源氏が「さらに浅くはあらじ」と言ったのを受けて、「心ばへ」の内容を自分に対する軽蔑にすりかえて、切り返したもの」と注す。
【かやうなる際は、際とこそはべなれ】- 「はべなれ」は「はべる」連体形の「る」が撥音便化してさらに無表記の形。断定の助動詞「なれ」已然形、係結びの法則。このようなしがない身分のわたしには、わたしらなりの、生き方というものがございます、源氏の君のような高貴な方とは無縁は世界の女です、の意。
【心恥づかしきけはひなれば】- 女(空蝉)の態度。こちらが恥じ入るほど立派な態度。
かえって、わたしを普通の人と同じように思っていらっしゃるのが残念です。
自然とお聞きになっているようなこともありましょう。
むやみな好色心は、まったく持ち合わせておりませんものを。
前世からの因縁でしょうか、おっしゃるように、このように軽蔑されいただくのも、当然なわが惑乱を、自分でも不思議なほどで」
【初事ぞや】- 係助詞「ぞ」文末におかれて強調の意、間投助詞「や」詠嘆を表す。
【あながちなる好き心】- 「帚木」巻冒頭部に源氏の本性について、「さしもあだめき目馴れたるうちつけの好き好きしさなどは好ましからぬ御本性にてまれにはあながちに引き違へ心尽くしなることを御心に思しとどむる癖なむあやにくにて」とあった。源氏は口では否定しても性分では「あながちなる好き心」の人間である。
【さるべきにや】- 前世からの宿縁であろうか、の意。
【あはめられたてまつるも】- あなたからわたしが「あはめられ」、軽蔑される、見下される。謙譲の補助動詞「たてまつる」、いただく。「見下されいただく」とはおかしな言い方だが、語法としては適っている。嫌味な言い方をしたもの。
【あやしきまでなむ】- 係助詞「なむ」の下に「ある」連体形などの語が省略。
など、まめだちてよろづにのたまへど、いとたぐひなき御 ありさまの、いよいようちとけきこえむことわびしければ、すくよかに心 づきなしとは見 えたてまつるとも、さる方 の言 ふかひなきにて過 ぐしてむと思 ひて、つれなくのみもてなしたり。
人柄 のたをやぎたるに、強 き心 をしひて加 へたれば、なよ竹 の心地 して、さすがに折 るべくもあらず。
人柄がおとなしい性質なところに、無理に気強く張りつめているので、しなやかな竹のような感じがして、さすがにたやすく手折れそうにもない。
【すくよかに】- 以下「過ぐしてむ」まで、女の心。
【さる方の言ふかひなきにて】- 「さる方」は「くよかに心づきなし」をさす。
【つれなくのみ】- 本心を隠してただそっけなくのみ振る舞っているというニュアンス。
【なよ竹の心地して】- 源氏には女がしなやかな竹のように感じられて。主語は源氏に転じる。『古典セレクション』は「次の「まことに--」の文文との間に、それまで拒み続けた女との間に、強姦に近い形で契りが果されたことが省かれている」と注す。
気の毒ではあるが、逢わなかったら心残りであったろうに、とお思いになる。
気持ちの晴らしようもなく、情けないと思っているので、
もうどんなに勝手な考え方をしても救われない過失をしてしまったと、女の悲しんでいるのを見て、
【あながちなる御心ばへ】- 源氏の無理無体ななされようをさす。
【言ふ方なしと思ひて、泣くさまなど、いとあはれなり】- 女に諦め折れたさまが読み取れる。『紹巴抄』は「空心を双地」と、空蝉の心を草子地で表現した、と指摘する。「あはれなり」は、空蝉に対する語り手の評言である。
【心苦しくはあれど、見ざらましかば】- 主語は源氏。女に対する同情に気持ちはあるが、自己満足を優先させている。「ましかば」は下文の「まし」と呼応して、反実仮想の意を表す。
【慰めがたく、憂しと思へれば】- 女の態度。
思いがけない逢瀬こそ、前世からの因縁だとお考えなさい。
むやみに男女の仲を知らない者のように、泣いていらっしゃるのが、とても辛い」と、恨み言をいわれて、
と、源氏が言うと、
【疎ましきものにしも思す】- 副助詞「しも」強調。あなたはわたしを嫌な男とお思いになる。
【契りあるとは思ひたまはめ】- 推量の助動詞「め」已然形、「こそ」の係り結び。
【世を思ひ知らぬやうに】- 「世」は男女の仲。既に人妻であり男を知っていながらそれを知らない生娘のように、の意。
【おぼほれ】- 『集成』は「悲しみに沈んで」と訳し、『完訳』は「ぼんやりして」と訳す。『古典セレクション』『新大系』は「とぼけていらっしゃる」と訳す。涙にむせんで、何もわからなくなっているさま、というニュアンスであろう。
【恨みられて】- マ上二段動詞「恨む」未然形、受身の助動詞「られ」連用形。源氏の君から恨まれて、の文意。
「いとかく憂 き身 のほどの定 まらぬ、ありしながらの身 にて、かかる御心 ばへを見 ましかば、あるまじき我 が頼 みにて、見直 したまふ後瀬 をも思 ひたまへ慰 めましを、いとかう仮 なる浮 き寝 のほどを思 ひはべるに、たぐひなく思 うたまへ惑 はるるなり。
よし、今 は見 きとなかけそ」
よし、
たとえ、こうとなりましても、
【ありしながらの身にて】- 『異本紫明抄』は「取り返すものにもがなや世の中をありしながらのわが身と思はむ」<昔の時代に戻りたいものだ、そうしたら今のあなたとの関係も昔のままのわたしでと思おう、できぬことで残念だ>(出典未詳)を指摘する。
【かかる御心ばへを見ましかば】- 反実仮想の助動詞「ましか」未然形+接続助詞「ば」、「慰めまし」に係る。
【あるまじき我が頼みにて】- 挿入句。
【後瀬をも】- 『源氏釈』は「若狭なる後瀬の山の後に逢はむわが思ふ人にけふならずとも」(古今六帖二、国、一二七二)を指摘する。「若狭なる後瀬の山の」は「後に」に係る序詞。
【思ひたまへ慰めましを】- 謙譲の補助動詞「たまへ」下二段、連用形。反実仮想の助動詞「まし」連体形+接続助詞「を」逆接。
【たぐひなく思うたまへ惑はるるなり】- 「おもう」は「思ひ」連用形のウ音便形。謙譲の補助動詞「たまへ」下二段、連用形、自発の助動詞「るる」連体形、断定の助動詞「なり」終止形。
【よし、今は見きとなかけそ】- 副詞「よし」。『源氏釈』は「それをだに思ふこととて我が宿を見きとないひそ人の聞かくに」(古今集、恋五、八一一、読人しらず)を指摘する。過去の助動詞「き」終止形。副詞「な」は終助詞「そ」と呼応して禁止を表す。
並々ならず行く末を約束し慰めなさる言葉は、
【おろかならず】- 以下「多かるべし」までの一文は、語り手の推量。『万水一露』は「双紙の批判の詞也」と指摘する。語り手は、その現場は見ていないが、きっとそうであったろう、という表現。
供びとが起き出して、
「いといぎたなかりける夜 かな」
「御車 ひき出 でよ」
紀伊守も起き出して来て、
暗いうちからお急きあそばさずとも」などと言っているのも聞こえる。
と言っているのは紀伊守であった。
【急がせたまふべきかは】- 「せ」「たまふ」最高敬語。連語「かは」反語表現。
奥にいた中将の君も出て来て、とても困っているので、お放しになっても、再びお引き留めになっては、
【またかやうの】- 以下「いとわりなき」まで、源氏の心。
【さしはへてはいかでか】- 「さしはへて」の下に「訪れむこと」などの語句が省略。「いかでか」反語表現。
【いとわりなきを】- 「わりなき」までが源氏の心。それを「を」で受けて、地の文に続ける。したがって、現行の括弧では括れない、心と地とが融合した源氏物語特有の表現構造である。
【奥の中将】- 女房の中将の君。奥から出てきてのニュアンスを「奥の」と表す。語り手の位置もわかる。
【許したまひても、また引きとどめたまひつつ】- 「桐壺」巻の「輦車の宣旨などのたまはせても、また入らせたまひて、さらにえ許させたまはず」という帝が更衣の里下がりをなかなか許そうとしない態度に類似する。
ほんとうに何とも言いようのない、あなたのお気持ちの冷たさといい、慕わしさといい、深く刻みこまれた思い出は、いろいろとめったにないことであったね」
【世に知らぬ】- 副詞「世に」程度のはなはだしいさまを表す。ほんとうに
【御心のつらさも、あはれも】- 『古典セレクション』は「あなたのつれなさにつけ、またわたしのせつなさにつけ」と訳す。
【浅からぬ世の思ひ出で】- 「浅からぬ世」は、男女の縁が浅くないという意と、夏の夜の短さを背後に響かせた表現となっている。
とて、うち泣 きたまふ気色 、いとなまめきたり。
鶏までが取るものも取りあえぬまであわただしく鳴いてわたしを起こそうとするのでしょうか」
とりあへぬまで驚かすらん
女は己を省みると、不似合いという晴がましさを感ぜずにいられない源氏からどんなに熱情的に思われても、これをうれしいこととすることができないのである。それに自分としては愛情の持てない良人のいる伊予の国が思われて、こんな夢を見てはいないだろうかと考えると恐ろしかった。
【伊予の方の思ひやられて】- 明融臨模本「いよのかたの(の+ミ)」とあるが、「ミ」は後人による朱書の補入。大島本は「いよのかたの」とある。『集成』『新大系』は「伊予のかたの」。『古典セレクション』は「伊予の方のみ」と校訂。自発の助動詞「れ」連用形。
【夢にや見ゆらむ】- 空蝉の心中の思い。係助詞「や」疑問、推量の助動詞「らむ」連体形、視界外推量を表す。当時はものを思えば魂があくがれ出てその人の前に現れると信じられていた。「見ゆ」は現れる、意。わたしが伊予介の夢の中に。
鶏の鳴く音に取り重ねて、
とり重ねても音ぞ泣かれける
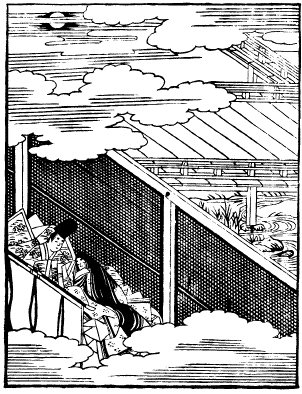
家の内も外も騒がしいので、引き閉てて、お別れになる時、心細い気がして、仲を隔てる関のように思われた。
ずんずん明るくなってゆく。女は襖子の所へまで送って行った。奥のほうの人も、こちらの縁のほうの人も起き出して来たんでざわついた。襖子をしめてもとの席へ帰って行く源氏は、一重の襖子が越えがたい隔ての関のように思われた。
【隔つる関】- 『源氏釈』は「逢坂の名をば頼みてこしかども隔つる関のつらくもあるかな」(新勅撰集、恋二、七三三、読人しらず)を指摘する。『伊勢物語』にも「彦星に恋はまさりぬ天の川隔つる関を今はやめてよ」(九十五段)とある。歌語である。
西面の格子を忙しく上げて、女房たちが覗き見しているようである。
簀子の中央に立ててある小障子の上から、わずかにお見えになるお姿を、身に感じ入っている好色な女もいるようである。
【人びと覗くべかめる】- 推量の助動詞「べか」連体形は「る」が撥音便化しさらに無表記の形。推量の助動詞「める」連体形は主観的推量を表す。語り手と源氏の目が一体になった推量、判断の表現。連体中止法で余情表現。
【好き心どもあめり】- 「ある」連体形の「る」が溌音便化してさらに無表記化された形。推量の助動詞「めり」主観的推量を表す。語り手と源氏の視覚が一体化して捉えた推量の表現。
無心なはずの空の様子も、ただ見る人によって、美しくも悲しくも見えるのであった。
人に言われぬお心には、とても胸痛く、文を通わす手立てさえないものをと、後ろ髪引かれる思いでお出になった。
【かげけざやかに見えて】- 明融臨模本「かほ(ほ=け歟、ほ$)けさやかにみえて」とある。傍書の「け歟」は本文と一筆と見られる。ただしミセケチ「ヒ」は後人の朱筆。大島本は「かけさやかに見えて」とある。『集成』は「かほけざやかに見えて」(月のおもてはくっきりと)と校訂、『新大系』『古典セレクション』は「影さやかに見えて」と校訂する。明融臨模本の本文一筆の「け歟」に従う。
【艶にもすごくも見ゆる】- 『集成』は「色めかしい感じにも、またもの悲しい感じにも」と解し、『新大系』は「華やかにも殺風景にも」と解し、『古典セレクション』は「ほのぼのと美しくも、あるいは恐ろしくも」と解す。
【言伝てやらむよすがだになきをと】- 推量の助動詞「む」婉曲、副助詞「だに」最小限、間投助詞「を」詠嘆を表す。手紙を遣る手段さえない、まして直接逢うことは、というニュアンス。
またあひ
「すぐれたることはなけれど、めやすくもてつけてもありつる
再び逢える手立てのないのが、自分以上に、あの女が悩んでいるであろう心の中は、どんなであろうかと、気の毒にご想像なさる。
「特に優れた所はないが、見苦しくなく身嗜みもとりつくろっていた中の品の女であったな。
何でもよく知っている人の言ったことは、なるほど」とうなずかれるのであった。
【まどろまれたまはず】- 可能の助動詞「れ」連用形。
【あひ見るべき方なきを】- 接続助詞「を」逆接を表す。
【まして、かの人の】- 以下「いかならむ」まで、地の文から源氏の心の文へと融合したような表現。
【すぐれたることはなけれど】- 以下「げに」まで、源氏の心。
【隈なく見集めたる人】- 左馬頭をいう。
【思し合はせられけり】- 自発の助動詞「られ」連用形、詠嘆の助動詞「けり」。
やはり、すっかりあれきり途絶えているので、思い悩んでいるであろうことが、気の毒にお心にかかって、心苦しく思い悩みなさって、紀伊守をお召しになった。
【大殿に】- 左大臣邸。正妻の葵の上のもとに。
【なほいとかき絶えて】- 副詞「なほ」は「御心にかかりて」に係る。「かき絶えて」は挿入句。副詞「いと」は「苦しく思しわびて」に係る。
かわいらしげに見えたが。
身近に使う者としたい。
主上にも、
と言うのであった。
【得させてむや】- 使役の助動詞「させ」連用形、完了の助動詞「て」連用形、推量の助動詞「む」、係助詞「や」疑問を表す。
【らうたげに見えしを】- 過去の助動詞「し」連体形、間投助詞「を」詠嘆を表す。
姉に当たる人に仰せ言を申し聞かせてみましょう」
【姉なる人にのたまひみむ】- 尊敬の動詞「のたまふ」四段は、「上位者との対話において、話者自身の支配下の身内をまたは目下に言い聞かせる意」(小学館古語大辞典)。
この二年ほどは、こうして暮らしておりますが、父親の意向と違ったと嘆いて、気も進まないでいるように、聞いております」
【親のおきて】- 前に「宮仕へに出だしたてむと漏らし奏せし」とあったことをさす。
【聞きたまふる】- 謙譲の補助動詞「たまふる」連体形、係助詞「なむ」と係り結びの法則。
まあまあの評判であった人だ。
本当に、
【よろしく聞こえし人ぞかし】- 連語「ぞかし」文末に用いられて強く念を押す意。まずまずの器量よしとの評判の人であった、の意。しかし、空蝉の容貌は、『源氏物語』の中ではむしろ不器量の部類に入る人である。ここは、実際以上のお世辞を使って尋ねたものか。
【まことによしや】- 「よし」は「よろし」よりも良い意。『古典セレクション』は「ほの暗い所で逢ったので、源氏はよく見ていない。先夜女との間に何事もなかったと思わせ、かつ小君についての斡旋の底意を、守に勘づかせないための用意もあろう」と注す。
離れて疎遠に致しておりますので、世間の言い草のとおり、親しくしておりません」と申し上げる。
と紀伊守は答えていた。
【世のたとひにて】- 継母と継子の関係は疎遠であるという世間一般の道理。
第四段 それから数日後
さて、五、六日 ありて、この子率 て参 れり。
こまやかにをかしとはなけれど、なまめきたるさまして、あて人 と見 えたり。
召 し入 れて、いとなつかしく語 らひたまふ。
童心地 に、いとめでたくうれしと思 ふ。
いもうとの君 のことも詳 しく問 ひたまふ。
さるべきことは答 へ聞 こえなどして、恥 づかしげにしづまりたれば、うち出 でにくし。
されど、いとよく言 ひ知 らせたまふ。
こまやかにをかしとはなけれど、なまめきたるさまして、あて
いもうとの
さるべきことは
されど、いとよく
きめこまやかに美しいというのではないが、優美な姿をしていて、良家の子弟と見えた。
招き入れて、とても親しくお話をなさる。
子供心に、とても素晴らしく嬉しく思う。
姉君のことも詳しくお尋ねになる。
答えられることはお答え申し上げなどして、こちらが恥ずかしくなるほどきちんとかしこまっているので、ちょっと言い出しにくい。
けれど、とても上手にお話なさる。
【この子率て参れり】- 主語は紀伊守。
【なまめきたるさまして、あて人と見えたり】- 源氏の目から見た判断である。小君が中納言兼衛門督の子という高貴な血筋の家柄であることを思わせる。
【いもうとの君】- 小君の姉君。
【恥づかしげにしづまりたれば】- 源氏が気恥ずかしくなるほど相手の小君が畏まっているので、の意。
【いとよく言ひ知らせたまふ】- 小君に彼の姉と源氏の間を手引きさせるべく言葉巧みに言い聞かせる意。
かかることこそはと、ほの心得 るも、思 ひの外 なれど、幼 な心地 に深 くしもたどらず。
御文 を持 て来 たれば、女 、あさましきに涙 も出 で来 ぬ。
この子 の思 ふらむこともはしたなくて、さすがに、御文 を面隠 しに広 げたり。
いと多 くて、
この
いと
お手紙を持って来たので、女は、あまりのことに涙が出てしまった。
弟がどう思っていることだろうかときまりが悪くて、そうは言っても、お手紙で顔を隠すように広げた。
とてもたくさん書き連ねてあって、
源氏の手紙を弟が持って来た。女はあきれて涙さえもこぼれてきた。弟がどんな想像をするだろうと苦しんだが、さすがに手紙は読むつもりらしくて、きまりの悪いのを隠すように顔の上でひろげた。さっきからからだは横にしていたのである。手紙は長かった。終わりに、
【御文を持て来たれば】- 小君が源氏のもとから姉君の所へ。
【あさましきに涙も出で来ぬ】- 『新大系』は「激しい動揺や悔悟の念いから」と注す。
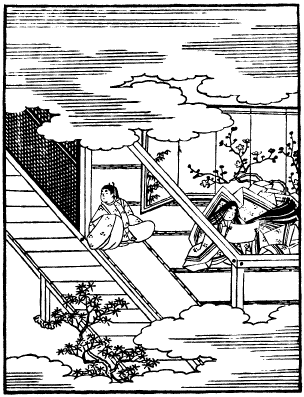
再び逢える夜があろうかと嘆いているうちに目までが合わさら
目さへあはでぞ頃も経にける
【身を思ひ続けて臥したまへり】- 明融臨模本は「ふし給へりける」とあり、「ける」にミセケチ符号が付いている。女の態度に対して初めて敬語が付く。『評釈』は「この女とても自分の邸では多くの人にかしずかれる女主人公である。こういう敬語の出てくる場合、自邸内での女主人公としての女を、読者は感ずるのであろう、と思う」と注す。今や源氏の愛人の一人になったことによる待遇の変化であろう。
【うち笑みて】- 小君の表情。自信ある顔つき。
どうして、そのように申し上げられましょうか」
【残りなくのたまはせ、知らせてける】- 女の心。源氏の君は弟の小君に自分と源氏の君との関係を。
それなら、
無理なことを言われて、弟は、
【さは】- 接続詞「さは」それならばの意。『古典セレクション』では「さば」と濁音に読む。
【な参りたまひそ】- 副詞「な」は終助詞「そ」と呼応して禁止を表す。
【むつかられて】- 動詞「むつから」未然形+尊敬の助動詞「れ」連用形。
と言って、そのまま行った。
やはり、わたしほどには思ってくれないようだね」
【待ち暮らししを】- 「暮らし」連用形、過去の助動詞「し」連体形、接続助詞「を」逆接を表す。
【あひ思ふまじきなめり】- 打消推量の助動詞「まじき」連体形、「なめり」は断定の助動詞「なる」連体形+推量の助動詞「めり」の「る」が撥音便化してさらに無表記の形、「めり」は主観的推量を表す。
小君はありのままに告げるほかに術はなかった。
【しかしか】- 小君の詞。語り手が言い換えた表現。これこれしかじかの理由でいただけませんでした、の意。『岩波古語辞典』に「江戸時代以後シカジカと濁音化した」とある。『古典セレクション』は「しかじか」と濁音に読む。
呆れた」と言って、またもお与えになった。
そう言ったあとで、また源氏から新しい手紙が小君に渡された。
【またも賜へり】- 再び手紙をお与えになった。係助詞「も」は強調のニュアンスを添える。
「あこは知 らじな。
その伊予 の翁 よりは、先 に見 し人 ぞ。
されど、頼 もしげなく頚細 しとて、ふつつかなる後見 まうけて、かく侮 りたまふなめり。
さりとも、あこはわが子 にてをあれよ。
この頼 もし人 は、行 く先短 かりなむ」
その
されど、
さりとも、あこはわが
この
わたしはあの伊予の老人よりは、先に関係していた人だよ。
けれど、頼りなく弱々しいといって、不恰好な夫をもって、このように馬鹿になさるらしい。
そうであっても、おまえはわたしの子でいてくれよ。
あの頼りにしている人は、どうせ老い先短いでしょう」
【先に見し人ぞ】- 「見し」(動詞「見」連用形+過去の助動詞「し」連体形)は、関係をもった、契りを結んだ、の意。係助詞「ぞ」文末にあって文全体を強調する。
【頼もしげなく頚細し】- 空蝉が源氏を評した言として、源氏が引用した文である。首が細い。頼りない、の意のニュアンスがある。源氏の容貌姿態を表現とすれば珍しい箇所である。
【かく侮りたまふなめり】- 主語は空蝉。「なめり」は断定の助動詞「なる」連体形の「る」が撥音便化してさらに無表記の形+推量の助動詞「めり」主観的推量。
【あこはわが子にてをあれよ】- 間投助詞「を」詠嘆、間投助詞「よ」呼びかけの意を表す。
【行く先短かりなむ】- 形容詞「短かり」連用形+完了の助動詞「な」未然形、確述の意+推量の助動詞「む」推量。どうせこの先長いことないでしょうよ、の意。
【と思へる、「をかし」と思す】- 完了の助動詞「る」連体中止法、そのまま下文の目的格になる。
ご自分の御匣殿にお命じになって、装束なども調達させ、本当に親のように面倒見なさる。
【御匣殿】- 摂関家などの上流貴族の家では裁縫する建物を自前で持っていた。それを宮中の貞観殿にあった裁縫所の呼び名に倣って同様に呼称した。
【装束などもせさせ】- 童殿上の装束。使役の助動詞「させ」連用形。
【まことに親めきて】- 「まことに」は「あこはわが子にてあれよ」を受ける。語り手の感想を交えた表現である。
されど、この
ほのかなりし
けれど、この子もとても幼い、うっかり落としでもしたら、軽々しい浮名まで背負い込む、我が身の風評も相応しくなく思うと、幸せも自分の身分に合ってこそはと思って、心を許したお返事も差し上げない。
ほのかに拝見した感じやご様子は、「本当に、並々の人ではなく素晴らしかった」と、思い出し申さずにはいられないが、「お気持ちにお応え申しても、今さら何になることだろうか」などと、考え直すのであった。
【この子もいと幼し】- 以下「いとつきなかるべく」まで、女の心。しかし、冒頭は「されど」「この子も」云々というように、地の文と空蝉の心の文が融合したような表現で始まる。
【心よりほかに散りもせば】- 源氏への返事を。サ変動詞「せ」未然形+接続助詞「ば」順接の仮定条件。
【軽々しき名さへとり添へむ】- 副助詞「さへ」添加は、身を受領の後妻に落とした上に源氏の君との不倫の噂まで立てたら、意。推量の助動詞「む」について、『集成』は、連体中止法。『古典セレクション』と『新大系』は連体形で「身」に係けて読む。
【つきなかるべく思へば】- 「つきなかるべく」が「思へば」を修飾しているように、心の文が地の文に融合した表現。いわば間接話法的心の文である。
【めでたきこともわが身からこそ】- 女の心。「わが身からこそ」について、『集成』は「結構なことも自分の身分次第のことなのだ」と解す。自分の身分が相手の身分に適う意であろう。
【ほのかなりし御けはひ】- 女の目や体験を通しての叙述。源氏の様子や態度について。過去の助動詞「し」連体形は自らの直接体験を表す助動詞。
【げに、なべてにやは】- 副詞「げに」は世間の噂通りだと納得する女の気持ちの現れ。女の心を語る。係助詞「やは」反語を表す。下に「おはせむ」などの語句が省略。
【をかしきさまを見えたてまつりても】- 源氏の愛情に対して、自分の気持ちをお応え申し上げたとしても、というニュアンス。
【何にかはなるべき】- 係助詞「かは」反語表現を表す。
悩んでいた様子などのいじらしさも、払い除けようもなく思い続けていらっしゃる。
軽々しくひそかに隠れてお立ち寄りなさるのも、人目の多い所で、不都合な振る舞いを見せはしまいかと、相手にも気の毒である、と思案にくれていらっしゃる。
【思へりし気色などのいとほしさも】- 空蝉がつらそうに悩んでいた様子を。形容詞「いとほし」は、かわいい、いじらしい、気の毒だ、不憫だ、などの幅広い意味がある。一義的には現代語訳できない。
【人目しげからむ所に】- 以下「いとほしく」まで、源氏の心を語る。しかし、その前の「這ひ紛れ立ち寄り」あたりから源氏の心のような文であるが、「立ち寄りたまはむも」と敬語があるので、地の文である。源氏の心に添った描写である。
【あらはれむと】- 明融臨模本「あら(ら+はれ)むと」とある。「補入「はれ」は本文と一筆みられ、親本の定家本にも補入の形で存在したものと思われる。大島本も「あらハれんと」とある。『古典セレクション』は他本に従って「あらはれむ」と校訂する。『集成』『新大系』は「あらはれむと」。
急に退出なさるふりをして、途中からお越しになった。
【さるべき方の忌み待ち出でたまふ】- 『評釈』によれば「中神」は中央に十六日間、次に四方に五日間ずつ、四隅に六日間ずつ遊行し、六十日で一巡するという。宮中から左大臣邸が方塞がりとなり紀伊守邸に方違えするのに都合の良い日。『古典セレクション』は「前の紀伊守邸への方違え後、暦のうえからいえば、中神の巡行周期の約六十日がたっているはずで、陰暦七月、初秋のころとなるが、文の内容からいえばやはり夏で、やや不審」と注す。
【にはかにまかでたまふまねして】- 源氏は左大臣邸へ行くように見せて、途中から中川の紀伊守邸へ行く。
小君には、昼から、「こうしようと思っている」とお約束なさっていた。
朝に夕に連れ従えていらっしゃったので、今宵も、まっさきにお召しになっていた。
「前栽の水の名誉でございます」
こんな挨拶をしていた。小君の所へは昼のうちからこんな手はずにすると源氏は言ってやってあって、約束ができていたのである。
始終そばへ置いている小君であったから、源氏はさっそく呼び出した。
【かくなむ思ひよれる】- 源氏の詞を間接話法的に表現した。紀伊守邸に行き女に再び逢うつもりでいることを告げる。
【思したばかりつらむほどは】- 主語は源氏。完了の助動詞「つ」終止形、完了の意+推量の助動詞「らむ」連体形、視界外推量の意。正妻の葵の上を欺いてやって来る源氏の気持ち。
【浅くしも思ひなされねど】- 主語は空蝉。副助詞「しも」強調、可能の助動詞「れ」未然形、打消の助動詞「ね」已然形+接続助詞「ど」逆接。
【さりとて】- 以下「またや加へむ」まで、女の心を語る。「さりとて」は接続詞。
【あぢきなく】- 「またや加へむ」に係る。
【なほさて】- 「なほ」は「まばゆければ」に係る。「さて」は、源氏の手紙に言いなりにの意。
気分が悪いので、こっそりと肩腰を叩かせたりしたいので、少し離れた所でね」
【ほど離れてを】- 間投助詞「を」詠嘆の意。
すべての場所を探し歩いて、渡殿に入りこんで、やっとのことで探し当てた。
ほんとうにあんまりなひどい、と思って、
【からうして】- 「カラウシテ[Caroxite]」(日葡辞書補遺)。『集成』と『新大系』は清音。『古典セレクション』は「からうじて」と濁音に読む。
【いとあさましくつらし】- 小君の心。
もう泣き出しそうになっている。
「かく、けしからぬ心 ばへは、つかふものか。
幼 き人 のかかること言 ひ伝 ふるは、いみじく忌 むなるものを」と言 ひおどして、「『心地悩 ましければ、人 びと避 けずおさへさせてなむ』と聞 こえさせよ。
あやしと誰 も誰 も見 るらむ」
あやしと
子供がこのような事を取り次ぐのは、ひどく悪いことと言うのに」ときつく言って、「『気分がすぐれないので、女房たちを側に置いて揉ませております』とお伝え申し上げなさい。
変だと皆が見るでしょう」
としかって、
「気分が悪くて、女房たちをそばへ呼んで介抱をしてもらっていますって申せばいいだろう。皆が怪しがりますよ、こんな所へまで来てそんなことを言っていて」
【つかふものか】- 動詞「つかふ」連体形+終助詞「ものか」反語表現。諌める気持ちを表す。
【忌むなるものを】- 「忌む」終止形+伝聞推定の助動詞「なる」連体形+接続助詞「ものを」逆接の意を表す。
【心地悩ましければ】- 以下「見るらむ」まで、姉君の詞。途中「おさへさせてなむ」まで、小君に源氏へ言わせた伝言。
【人びと避けず】- 女房たちを側に置いての意。
【おさへさせてなむ】- 使役の助動詞「させ」連用形、接続助詞「て」、係助詞「なむ」、下に「はべる」連体形などの語が省略。
【聞こえさせよ】- 源氏に申し上げなさい。「聞こえさす」は「聞こゆ」より一段と謙った謙譲語。
【あやしと誰も誰も見るらむ】- 『集成』は「お前がこんな所にうろうろしていては」と注す。「見るらむ」について、明融臨模本、大島本、松浦本は「みるらむ」とある。池田本、伝冷泉為秀筆本と書陵部本は「思らん」とある。三条西家本は「みる」をミセケチにして「思」と訂正する。
無理にお気持ちを分からないふうを装って無視したのも、どんなにか身の程知らぬ者のようにお思いになるだろう」と、心に決めたものの、胸が痛くて、そうはいってもやはり心が乱れる。
「どっちみち、今はどうにもならない運命なのだから、非常識な気にくわない女で、押しとおそう」と思い諦めた。
【いと、かく】- 以下「思すらむ」まで、空蝉の心。
【をかしうもやあらまし】- 間投助詞「や」詠嘆を表す。「まし」反実仮想の助動詞。
【心ながらも】- 空蝉が自分から思い決めたことながら、の意。
【とてもかくても】- 以下「止みなむ」まで、空蝉の心。
【無心に】- 明融臨模本「し」の左側に朱筆で濁点を付けている。『集成』『古典セレクション』は濁音「むじん」と読む。『新大系』は清音「むしん」と読む。
とばかりものものたまはず、いたくうめきて、
しばらくは何もおっしゃらず、ひどく嘆息なさって、辛いとお思いになっていた。
「私はもう自分が恥ずかしくってならなくなった」
気の毒なふうであった。それきりしばらくは何も言わない。そして苦しそうに吐息をしてからまた女を恨んだ。
【身もいと恥づかしくこそなりぬれ】- 源氏の心。面目丸つぶれだ、の意。
あなたの心も知
道にあやなくまどひぬるかな
女も、やはり、まどろむこともできなかったので、
見えても触れられない帚木のようにあなたの前から姿を消すのです」
あるにもあらず消ゆる帚木
と聞 こえたり。
【まどひ歩く】- 源氏と姉君との間をうろうろと往復する。
【人あやしと見るらむ】- 空蝉の心。「人」は女房たち。推量の助動詞「らむ」視界外推量を表す。
【わびたまふ】- 主語は空蝉。「たまふ」という敬語が付く。源氏の愛人の一人としての待遇であろう。
【一所すずろにすさまじく思し続けらるれど】- 「一所」は下に「かつは思しながら」と敬語表現があるので、源氏とわかる。自発の助動詞「らるれ」已然形。以下、源氏の心に添った叙述となる。
【人に似ぬ心ざまの】- 以下「上れりける」まで、源氏の心。空蝉の心ばえを賞賛。
【消えず立ち上れりける】- 「消えず」は女の返歌の「消ゆる」の語句を受ける。「立ち上る」は「消えず」の縁語。気位高く構えていたこと。
【かかるにつけてこそ心もとまれ】- 源氏の心。係助詞「こそ」「とまれ」已然形、係り結びの法則。強調のニュアンス。女の魅力が顧みられる。
【人あまたはべるめれば】- 「人」は女房たち。推量の助動詞「めれ」主観的推量を表す。
【かしこげに】- 下に「はべり」などの語が省略。
気の毒にと思っていた。
お若く優しいご様子を、嬉しく素晴らしいと思っているので、あの薄情な女よりも、かえってかわいく思われなさったということである。
【若くなつかしき御ありさま】- 源氏の様子。
【うれしくめでたしと思ひたれば】- 主語は小君。
【つれなき人よりは】- 空蝉をさす。主語は源氏に移る。
【なかなかあはれに思さるとぞ】- 女よりは、かえって小君のほうを可愛くお思われなさる、の意。「とぞ」は、この巻、この空蝉物語の語り収めの言葉。「とぞ」の下に「ある」などの語が省略されたかたち。『一葉集』は「紫式部か詞也」と注す。『評釈』では「以上は、ある人が語った話だ、というのである。この巻の冒頭にいう「語り伝へけむ」人の話はこうだったという、とことわるのである」とある。
| 底本 | 明融臨模本 |
| 校訂 | Last updated 11/16/2011(ver.2-6) 渋谷栄一校訂(C) オリジナル 修正版 比較 |
| ローマ字版 | Last updated 1/26/2009 (ver.2-1) Written in Japanese roman letters by Eiichi Shibuya (C) オリジナル 修正版 比較 |
| ルビ抽出 (ローマ字版から) |
Powered by 再編集プログラム v4.05 ひらがな版 ルビ抽出 |
| 挿絵 (ローマ字版から) |
'Eiri Genji Monogatari' (1654) |
| Last updated 6/25/2003 渋谷栄一訳(C)(ver.1-4-1) オリジナル 修正版 比較 |
| 現代語訳 | 与謝野晶子 |
| 電子化 | 上田英代(古典総合研究所) |
| 底本 | 角川文庫 全訳源氏物語 |
| 渋谷栄一訳 との突合せ |
宮脇文経 2003年8月14日 |
| Last updated 1/26/2009(ver.2-1) 渋谷栄一注釈(C) オリジナル 修正版 比較 |