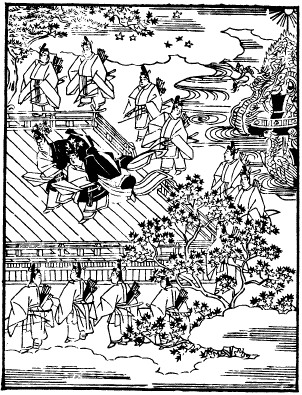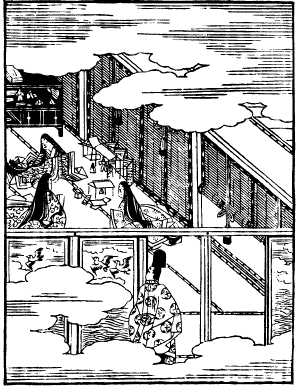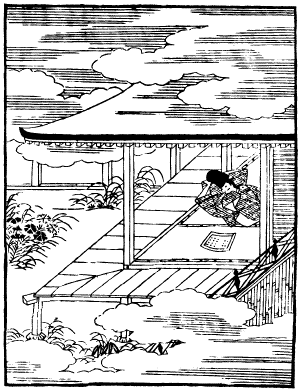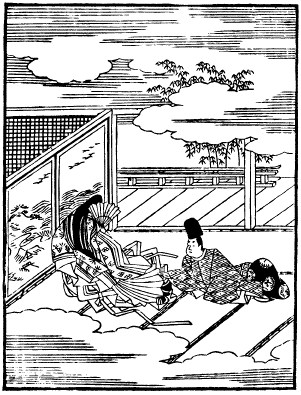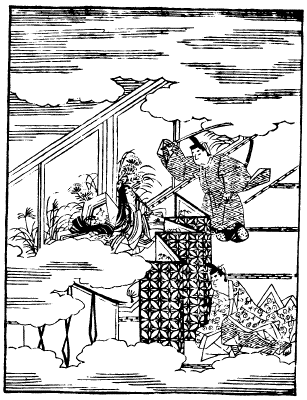第七帖 紅葉賀
光る源氏の十八歳冬十月から十九歳秋七月までの宰相兼中将時代の物語
|
# |
本文 |
渋谷栄一訳 |
与謝野晶子訳 |
注釈 |
|
第一章 藤壺の物語 源氏、藤壺の御前で青海波を舞う
|
|
第一段 御前の試楽
|
| 1.1.1 |
|
朱雀院への行幸は、神無月の十日過ぎである。
常の行幸とは違って、格別興趣あるはずの催しであったので、御方々、御覧になれないことを残念にお思いになる。
主上も、藤壷が御覧になれないのを、もの足りなく思し召されるので、試楽を御前において、お催しあそばす。
|
朱雀院の行幸は十月の十幾日ということになっていた。その日の歌舞の演奏はことに選りすぐって行なわれるという評判であったから、後宮の人々はそれが御所でなくて陪観のできないことを残念がっていた。帝も藤壺の女御にお見せになることのできないことを遺憾に思召して、当日と同じことを試楽として御前でやらせて御覧になった。
|
【朱雀院の行幸は、神無月の十日あまりなり】- この「朱雀院行幸」は「若紫」「末摘花」巻に予告されたもの。「行幸 ギャウガウ」(文明本節用集)、「ぎょうごう」と濁音に読む。この巻は新年立によれば、源氏十八歳の秋から十九歳の秋までの宰相中将時代の物語。まず、源氏、その試楽に青海波を舞う。
【世の常ならず】- 恒例の朱雀院行幸とは違って。朱雀院にいられる上皇(一院)の算賀の行幸であろう。『完訳』は「一院の四十賀か五十賀かを行うための行幸」「この一院は桐壺帝の父か」と注す。
【御方々】- 桐壺帝の後宮の妃方。
【口惜しがりたまふ】- 主語は御方々。
【主上も】- 帝を「主上」と呼称する。「も」(係助詞)は、並列を表す。御方々同様に主上ものニュアンス。
【藤壺の見たまはざらむを】- 藤壺の女御を殿舎名で「藤壺」と呼称する。
【思さるれば】- 「るれ」(自発の助動詞)、お思いにならずにはいらっしゃれないのニュアンス。
【試楽を御前にて、せさせたまふ】- 試楽は予行演習。御前は清涼殿の東庭をさす。「させ」(尊敬の助動詞)「たまふ」(尊敬の補助動詞)、最高敬語。帝は試楽を清涼殿の東庭でお催しあそばすの意。「御前にて」、横山本と陽明文庫本「御まへにて」とある。
|
| 1.1.2 |
|
源氏中将は、青海波をお舞いになった。
一方の舞手には大殿の頭中将。
容貌、心づかい、人よりは優れているが、立ち並んでは、やはり花の傍らの深山木である。
|
源氏の中将は青海波を舞ったのである。二人舞の相手は左大臣家の頭中将だった。人よりはすぐれた風采のこの公子も、源氏のそばで見ては桜に隣った深山の木というより言い方がない。
|
【源氏中将は、青海波をぞ舞ひたまひける】- 公の場では「源氏中将」と呼称される。「ける」(過去の助動詞)は過去の事件を伝承的に現在の人の前に語る。源氏の中将は青海波をお舞いになったということである。
【片手には】- 青海波は二人一対になって舞うので、その相手方にはの意。
【大殿の頭中将】- 大殿は左大臣、その子息頭中将、源氏の正妻葵上の兄。
|
| 1.1.3 |
入り方の日かげ、さやかにさしたるに、楽の声まさり、もののおもしろきほどに、同じ舞の足踏み、おももち、世に見えぬさまなり。詠などしたまへるは、「これや、仏の御迦陵頻伽の声ならむ」と聞こゆ。おもしろくあはれなるに、帝、涙を拭ひたまひ、上達部、親王たちも、みな泣きたまひぬ。詠はてて、袖うちなほしたまへるに、待ちとりたる楽のにぎははしきに、顔の色あひまさりて、常よりも光ると見えたまふ。 |
入り方の日の光、鮮やかに差し込んでいる時に、楽の声が高まり、感興もたけなわの時に、同じ舞の足拍子、表情は、世にまたとない様子である。
朗唱などをなさっている声は、「これが、仏の御迦陵頻伽のお声だろうか」と聞こえる。
美しくしみじみと心打つので、帝は、涙をお拭いになさり、上達部、親王たちも、皆落涙なさった。
朗唱が終わって、袖をさっとお直しになると、待ち構えていた楽の音が賑やかに奏され、お顔の色が一段と映えて、常よりも光り輝いてお見えになる。
|
夕方前のさっと明るくなった日光のもとで青海波は舞われたのである。地をする音楽もことに冴えて聞こえた。同じ舞ながらも面づかい、足の踏み方などのみごとさに、ほかでも舞う青海波とは全然別な感じであった。舞い手が歌うところなどは、極楽の迦陵頻伽の声と聞かれた。源氏の舞の巧妙さに帝は御落涙あそばされた。陪席した高官たちも親王方も同様である。歌が終わって袖が下へおろされると、待ち受けたようににぎわしく起こる楽音に舞い手の頬が染まって常よりもまた光る君と見えた。
|
【帝、涙を】- 地の文では「帝」と呼称される。
【上達部、親王たちも】- ここでは上達部、親王の順に紹介される。
【常よりも光ると見えたまふ】- 「光る」は当時の最高の美の形容。
|
| 1.1.4 |
|
春宮の女御は、このように立派に見えるのにつけても、おもしろからずお思いになって、「神などが、空から魅入りそうな容貌だこと。
嫌な、不吉だこと」とおっしゃるのを、若い女房などは、厭味なと、聞きとがめるのであった。
藤壷は、「大それた心のわだかまりがなかったならば、いっそう素晴らしく見えたろうに」とお思いになると、夢のような心地がなさるのであった。
|
東宮の母君の女御は舞い手の美しさを認識しながらも心が平らかでなかったのである。「神様があの美貌に見入ってどうかなさらないかと思われるね、気味の悪い」こんなことを言うのを、若い女房などは情けなく思って聞いた。藤壺の宮は自分にやましい心がなかったらまして美しく見える舞であろうと見ながらも夢のような気があそばされた。
|
【春宮の女御】- 春宮の母女御の意。一宮の母女御、弘徽殿の女御。
【神など、空にめでつべき容貌かな。うたてゆゆし】- 弘徽殿女御の詞。周囲の女房に洩らした独白であろう。
【若き女房などは、心憂しと耳とどめけり】- 弘徽殿女御方に仕える若女房か。
【おほけなき心のなからましかば、ましてめでたく見えまし】- 藤壺の心中。「おほけなき心」を『集成』は「藤壺に対する源氏の思慕の情をさす」というように、源氏の心と解し、源氏がそのような大それた気持ちを抱かずに青海波を舞ったのであったら一層すばらしく見えるであろうにの意に解す。それに対して、『完訳』は「帝に寵愛されながらも源氏と密通したという畏れ多い気持」「自分に大それた心のわだかまりがなかったら、この舞姿がいっそうすばらしく見えようものを」というように、藤壺自身の心と解す。一見相反するような両者の読みもそれぞれに可能なところが源氏物語独特の表現性の豊さであり深さでもある。和歌でいえば掛詞的表現の手法である。両意を汲んで以下読み進める。
|
| 1.1.5 |
|
宮は、そのまま御宿直なのであった。
|
その夜の宿直の女御はこの宮であった。
|
【宮は、やがて御宿直なりけり】- 「宮」は藤壺をさす。ただ「宮」とだけ呼称することによって、春宮の女御に対し血筋の高貴さを引き立たせる。清涼殿広廂の間から夜の御殿に移動し帝の御寝に侍することになる。それを「御宿直」と表現する。
|
| 1.1.6 |
|
「今日の試楽は、青海波に万事尽きてしまったな。
どう御覧になりましたか」
|
「今日の試楽は青海波が王だったね。どう思いましたか」
|
【今日の試楽は、青海波に事みな尽きぬな。いかが見たまひつる】- 帝の藤壺への詞。青海波の感想の問いかけ。場面は夜の御殿の寝所での会話。
|
| 1.1.7 |
|
と、お尋ね申し上げあそばすと、心ならずも、お答え申し上げにくくて、
|
宮はお返辞がしにくくて、
|
【あいなう、御いらへ聞こえにくくて】- 「あいなく」は心ならずもの意。『集成』は「ばつが悪く」と注し、『完訳』は「心ならずも、の意。帝の問いに対応すべきなのに、の気持」と注す。語り手自身の感想が言いこめられた用語。
|
| 1.1.8 |
|
「格別でございました」とだけお返事申し上げなさる。
|
「特別に結構でございました」とだけ。
|
【殊にはべりつ】- 藤壺の返事。「結構でございました」また「格別でございました」の意。無難に答えたもの。
|
| 1.1.9 |
「片手もけしうはあらずこそ見えつれ。舞のさま、手づかひなむ、家の子は殊なる。この世に名を得たる舞の男どもも、げにいとかしこけれど、ここしうなまめいたる筋を、えなむ見せぬ。試みの日、かく尽くしつれば、紅葉の蔭やさうざうしくと思へど、見せたてまつらむの心にて、用意せさせつる」など聞こえたまふ。 |
「相手役も、
悪くはなく見えた。舞の様子、手捌きは、良家の子
弟は格別であるな。世間で名声を博している舞の男どもも、確かに大したものであるが、大様で優美な趣きを、表
すことができない。試楽の日に、こんなに十分に催してしまったので、紅葉の木陰は寂しかろうかと思うが、お見せ申したいとの気持ちで、念入りに催させた」などと、お話し
|
「もう一人のほうも悪くないようだった。曲の意味の表現とか、手づかいとかに貴公子の舞はよいところがある。専門家の名人は上手であっても、無邪気な艶な趣をよう見せないよ。こんなに試楽の日に皆見てしまっては朱雀院の紅葉の日の興味がよほど薄くなると思ったが、あなたに見せたかったからね」など仰せになった。
|
【片手も】- 以下「用意せさせつる」まで、帝の詞。
【紅葉の蔭】- 朱雀院行幸当日の紅葉の下での舞を「紅葉の蔭」と表現。
|
|
第二段 試楽の翌日、源氏藤壺と和歌を贈答
|
| 1.2.1 |
|
翌朝、中将の君、
|
翌朝源氏は藤壺の宮へ手紙を送った。
|
【つとめて、中将君】- 以下、試楽の翌日、源氏と藤壺、和歌の贈答をしあう。「中将の君」は源氏。
|
| 1.2.2 |
|
「どのように御覧になりましたでしょうか。
何とも言えないつらい気持ちのままで。
|
どう御覧くださいましたか。苦しい思いに心を乱しながらでした。
|
【いかに御覧じけむ。世に知らぬ乱り心地ながらこそ】- 源氏の手紙文。係助詞「こそ」の下に「舞ひつれ」などの語句が省略された形。
|
| 1.2.3 |
|
つらい気持ちのまま立派に舞うことなどはとてもできそうもないわが身が
袖を振って舞った気持ちはお分りいただけたでしょうか
|
物思ふに立ち舞ふべくもあらぬ身の
袖うち振りし心知りきや
|
【もの思ふに立ち舞ふべくもあらぬ身の--袖うち振りし心知りきや】- 源氏の手紙に添えた贈歌。「立ち舞ふ」は舞を舞う意と立派に立ち振る舞うの両意がこめられる。「袖うち振りし」には舞の袖を振るしぐさの意と、袖振る動作が相手の魂を招き寄せるという信仰に基づく愛情を示すことの両意がこめられている。
|
| 1.2.4 |
|
恐れ多いことですが」
|
失礼をお許しください。
|
【あなかしこ】- 手紙の結語。当時は男性でも使用した。おそれ多いことですがの意。
|
| 1.2.5 |
|
とあるお返事、目を奪うほどであったご様子、容貌に、お見過ごしになれなかったのであろうか、
|
とあった。目にくらむほど美しかった昨日の舞を無視することがおできにならなかったのか、宮はお書きになった。
|
【とある御返り、目もあやなりし御さま、容貌に、見たまひ忍ばれずやありけむ】- 「とある御返り」は、とある源氏の贈歌に対する藤壺の御返歌はの意。それが緊密かつ簡潔に表現されている。「目もあやなりし」以下、挿入句。『完訳』は「藤壺が返歌した理由を語り手が推測」と注す。なお『細流抄』他の旧注は「御返り」以下を「草子の地のことはる也」と指摘するが、「とある」以下全体が語り手の意の介入された句とも見られなくもない。
|
| 1.2.6 |
|
「唐の人が袖振って舞ったことは遠い昔のことですが
その立ち居舞い姿はしみじみと拝見いたしました
|
から人の袖ふることは遠けれど
起ち居につけて哀れとは見き
|
【唐人の袖振ることは遠けれど--立ち居につけてあはれとは見き】- 藤壺の返歌。「ふる」は「振る」と「古」の掛詞。青海波は唐楽なので「唐人」と詠んだ。「あはれとは見き」という点にこの返歌の主旨がある。
|
| 1.2.7 |
|
並々のことには」
|
一観衆として。
|
【大方には】- 大体のところには、一通りにはの意。『完訳』は「「おほかたにはあらず」の意。一説には、「おほかたにはあはれと見き」」と注すが、どちらとも解せるような含みのある表現をあえて選んで答えたもので、二者択一的に判断するのは正しくない。感情を率直かつ直線的表現するようなことはしない。
|
| 1.2.8 |
とあるを、限りなうめづらしう、「かやうの方さへ、たどたどしからず、ひとの朝廷まで思ほしやれる御后言葉の、かねても」と、ほほ笑まれて、持経のやうにひき広げて見ゐたまへり。 |
とあるのを、この上なく珍しく、「このようなことにまで、お詳しくいらっしゃり、唐国の朝廷まで思いをはせられるお后としてのお和歌を、もう今から」と、自然とほほ笑まれて、持経のように広げてご覧になっていた。
|
たまさかに得た短い返事も、受けた源氏にとっては非常な幸福であった。支那における青海波の曲の起源なども知って作られた歌であることから、もう十分に后らしい見識を備えていられると源氏は微笑して、手紙を仏の経巻のように拡げて見入っていた。
|
【かやうの方さへ】- 以下「かねても」まで、源氏の心中。「かやうの方」は青海波の舞が唐土から舶来した唐楽であるという故事来歴をいう。
|
|
第三段 十月十余日、朱雀院へ行幸
|
| 1.3.1 |
|
行幸には、親王たちなど、宮廷を挙げて一人残らず供奉なさった。
春宮もお出ましになる。
恒例によって、楽の舟々が漕ぎ廻って、唐楽、高麗楽のと、数々を尽くした舞は、幾種類も多い。
楽の声、鼓の音、四方に響き渡る。
|
行幸の日は親王方も公卿もあるだけの人が帝の供奉をした。必ずあるはずの奏楽の船がこの日も池を漕ぎまわり、唐の曲も高麗の曲も舞われて盛んな宴賀だった。
|
【行幸には、親王たちなど、世に残る人なく仕うまつりたまへり】- 以下、神無月十日過ぎの朱雀院行幸の当日の物語。舞台は朱雀院。
|
| 1.3.2 |
|
先日の源氏の夕映えのお姿、不吉に思し召されて、御誦経などを方々の寺々におさせになるのを、聞く人ももっともであると感嘆申し上げるが、春宮の女御は、大仰であると、ご非難申し上げなさる。
|
試楽の日の源氏の舞い姿のあまりに美しかったことが魔障の耽美心をそそりはしなかったかと帝は御心配になって、寺々で経をお読ませになったりしたことを聞く人も、御親子の情はそうあることと思ったが、東宮の母君の女御だけはあまりな御関心ぶりだとねたんでいた。
|
【一日の源氏の御夕影】- 試楽の日の源氏の夕日を浴びた姿。
【ゆゆしう思されて】- 主語は帝。
【春宮の女御】- 弘徽殿の女御をここでは「春宮の女御」と呼称。後宮の妃の一人というより東宮の母である妃というニュアンスを強調。
|
| 1.3.3 |
|
垣代などには、殿上人、地下人でも、優秀だと世間に評判の高い精通した人たちだけをお揃えあそばしていた。
宰相二人、左衛門督、右衛門督が、左楽と右楽とを指揮する。
舞の師匠たちなど、世間で一流の人たちをそれぞれ招いて、各自家に引き籠もって練習したのであった。
|
楽人は殿上役人からも地下からもすぐれた技倆を認められている人たちだけが選り整えられたのである。参議が二人、それから左衛門督、右衛門督が左右の楽を監督した。舞い手はめいめい今日まで良師を選んでした稽古の成果をここで見せたわけである。
|
【宰相二人、左衛門督、右衛門督、左右の楽のこと行ふ】- 参議兼左衛門督一人と参議兼右衛門督一人の計二名が左の唐楽と右の高麗楽の指揮をおこなったものか。
【取りつつ】- 「つつ」は同じ動作の繰り返しを表す。それぞれの家で舞の師匠を迎え取っての意。
|
|
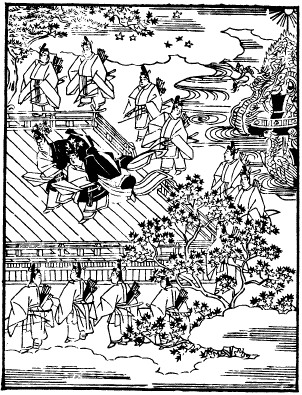 |
| 1.3.4 |
木高き紅葉の蔭に、四十人の垣代、言ひ知らず吹き立てたる物の音どもにあひたる松風、まことの深山おろしと聞こえて吹きまよひ、色々に散り交ふ木の葉のなかより、青海波のかかやき出でたるさま、いと恐ろしきまで見ゆ。かざしの紅葉いたう散り過ぎて、顔のにほひにけおされたる心地すれば、御前なる菊を折りて、左大将さし替へたまふ。 |
木高い紅葉の下に、四十人の垣代、何とも言い表しようもなく見事に吹き鳴らしている笛の音に響き合っている松風、本当の深山颪と聞こえて吹き乱れ、色とりどりに散り乱れる木の葉の中から、青海波の光り輝いて舞い出る様子、何とも恐ろしいまでに見える。
插頭の紅葉がたいそう散って薄くなって、顔の照り映える美しさに圧倒された感じがするので、御前に咲いている菊を折って、左大将が差し替えなさる。
|
四十人の楽人が吹き立てた楽音に誘われて吹く松の風はほんとうの深山おろしのようであった。いろいろの秋の紅葉の散りかう中へ青海波の舞い手が歩み出た時には、これ以上の美は地上にないであろうと見えた。挿しにした紅葉が風のために葉数の少なくなったのを見て、左大将がそばへ寄って庭前の菊を折ってさし変えた。
|
【散り過ぎて】- 『古典セレクション』は「散りすきて」と読み「紅葉が散って透けている意」と解す。『集成』『新大系』は「散り過ぎて」と解す。
【左大将さし替へたまふ】- 系図不明の人物。従三位相当官、源氏は中将だからその上司。その上司がわざわざ部下の源氏のために菊を挿し替えた、ということを強調。
|
| 1.3.5 |
日暮れかかるほどに、けしきばかりうちしぐれて、空のけしきさへ見知り顔なるに、さるいみじき姿に、菊の色々移ろひ、えならぬをかざして、今日はまたなき手を尽くしたる入綾のほど、そぞろ寒く、この世のことともおぼえず。もの見知るまじき下人などの、木のもと、岩隠れ、山の木の葉に埋もれたるさへ、すこしものの心知るは涙落としけり。 |
日の暮れかかるころに、ほんの少しばかり時雨が降って、空の様子までが感涙を催しているのに、そうした非常に美しい姿で、菊が色とりどりに変色し、その素晴らしいのを冠に插して、今日は又とない秘術を尽くした入綾の舞の時には、ぞくっと寒気がし、この世の舞とは思われない。
何も分るはずのない下人どもで、木の下、岩の陰、築山の木の葉に埋もれている者までが、少し物の情趣を理解できる者は感涙に咽ぶのであった。
|
日暮れ前になってさっと時雨がした。空もこの絶妙な舞い手に心を動かされたように。美貌の源氏が紫を染め出したころの白菊を冠に挿して、今日は試楽の日に超えて細かな手までもおろそかにしない舞振りを見せた。終わりにちょっと引き返して来て舞うところなどでは、人が皆清い寒気をさえ覚えて、人間界のこととは思われなかった。物の価値のわからぬ下人で、木の蔭や岩の蔭、もしくは落ち葉の中にうずもれるようにして見ていた者さえも、少し賢い者は涙をこぼしていた。
|
【入綾の】- 横山本「いりあひ(や)の」、陽明文庫本「いりいりあひの」とある。「入綾」(舞楽の退場の際、舞う舞)を「入相」(日没)に誤る。別本の御物本も「いりあひ」と誤る。
|
| 1.3.6 |
|
承香殿の女御の第四皇子、まだ童姿で、秋風楽をお舞いになったのが、これに次ぐ見物であった。
これらに興趣も尽きてしまったので、他の事には関心も移らず、かえって興ざましであったろうか。
|
承香殿の女御を母にした第四親王がまだ童形で秋風楽をお舞いになったのがそれに続いての見物だった。この二つがよかった。あとのはもう何の舞も人の興味を惹かなかった。ないほうがよかったかもしれない。
|
【承香殿の御腹の四の御子、まだ童にて】- この巻だけに登場。桐壺帝の後宮承香殿女御の第四親王。なお第一御子は弘徽殿女御の子で春宮(のちの朱雀院)、第二御子は桐壺更衣の子の源氏、第三御子は不明、という設定。さらにいえば、その後に螢兵部卿宮、帥宮、宇治八宮、冷泉帝(第十御子)という源氏の弟たちが登場する。今、第四親王が「童」で、第十親王が妊娠中ということになる。
【かへりてはことざましにやありけむ】- 語り手の評言。かえって興ざましであったろうかの意。
|
| 1.3.7 |
|
その夜、源氏の中将、正三位になられる。
頭中将、正四位下に昇進なさる。
上達部は、皆しかるべき人々は相応の昇進をなさるのも、この君の昇進につれて恩恵を蒙りなさるので、人の目を驚かし、心をも喜ばせなさる、前世が知りたいほどである。
|
今夜源氏は従三位から正三位に上った。頭中将は正四位下が上になった。他の高官たちにも波及して昇進するものが多いのである。当然これも源氏の恩であることを皆知っていた。この世でこんなに人を喜ばしうる源氏は前生ですばらしい善業があったのであろう。
|
【源氏中将、正三位したまふ。頭中将、正下の加階したまふ】- 中将は従四位下相当官、源氏の現在の位階は不明だが、正四位下から一階を飛び越して正三位に昇進したものであろう。頭中将は従四位上から正四位下に昇進した。なお「正三位」に『古典セレクション』は「じようさむゐ」と清音の振り仮名を付ける。『集成』『新大系』は「じやうざむゐ」と連濁の振り仮名を付ける。「じょうざんみ」、また「正下」は、「じょうげ」と読む。
【昔の世ゆかしげなり】- 前世をさす。源氏の善根を積んだ前世が知りたい、の意。
|
|
第四段 葵の上、源氏の態度を不快に思う
|
| 1.4.1 |
|
宮は、そのころご退出なさったので、例によって、お会いできる機会がないかと窺い回るのに夢中であったので、大殿では穏やかではいらっしゃれない。
その上、あの若草をお迎えになったのを、「二条院では女の人をお迎えになったそうだ」と、誰かが申し上げたので、まことに気に食わないとお思いになっていた。
|
それがあってから藤壺の宮は宮中から実家へお帰りになった。逢う機会をとらえようとして、源氏は宮邸の訪問にばかりかかずらっていて、左大臣家の夫人もあまり訪わなかった。その上紫の姫君を迎えてからは、二条の院へ新たな人を入れたと伝えた者があって、夫人の心はいっそう恨めしかった。
|
【宮は、そのころまかでたまひぬれば】- 藤壺の宮をさす。里邸の三条宮邸に退出。
【大殿には騒がれたまふ】- 「れ」(自発の助動詞)、左大臣家では穏やかでにはいらっしゃれない。
【かの若草たづね取り】- 紫の君をさす。地の文で「若草」と呼称。
【二条院には人迎へたまふなり】- 人の噂。二条院では女の人をお迎えになったそうだの意。
【心づきなしと思いたり】- 主語は葵の上。
|
| 1.4.2 |
「うちうちのありさまは知りたまはず、さも思さむはことわりなれど、心うつくしく、例の人のやうに怨みのたまはば、我もうらなくうち語りて、慰めきこえてむものを、思はずにのみとりないたまふ心づきなさに、さもあるまじきすさびごとも出で来るぞかし。人の御ありさまの、かたほに、そのことの飽かぬとおぼゆる疵もなし。人よりさきに見たてまつりそめてしかば、あはれにやむごとなく思ひきこゆる心をも、知りたまはぬほどこそあらめ、つひには思し直されなむ」と、「おだしく軽々しからぬ御心のほども、おのづから」と、頼まるる方はことなりけり。 |
「内々の様子はご存知なく、そのようにお思いになるのはごもっともであるが、素直で、普通の女性のように恨み言をおっしゃるのならば、自分も腹蔵なくお話して、お慰め申し上げようものを、心外なふうにばかりお取りになるのが不愉快なので、起こさなくともよい浮気沙汰まで起こるのだ。
相手のご様子は、不十分で、どこが不満だと思われる欠点もない。
誰よりも先に結婚した方なので、愛しく大切にお思い申している気持ちを、まだご存知ないのであろうが、いつかはお思い直されよう」と、「安心できる軽率でないご性質だから、いつかは」と、期待できる点では格別なのであった。
|
真相を知らないのであるから恨んでいるのがもっともであるが、正直に普通の人のように口へ出して恨めば自分も事実を話して、自分の心持ちを説明もし慰めもできるのであるが、一人でいろいろな忖度をして恨んでいるという態度がいやで、自分はついほかの人に浮気な心が寄っていくのである。とにかく完全な女で、欠点といっては何もない、だれよりもいちばん最初に結婚した妻であるから、どんなに心の中では尊重しているかしれない、それがわからない間はまだしかたがない。将来はきっと自分の思うような妻になしうるだろうと源氏は思って、その人が少しのことで源氏から離れるような軽率な行為に出ない性格であることも源氏は信じて疑わなかったのである。永久に結ばれた夫婦としてその人を思う愛にはまた特別なものがあった。
|
【うちうちのありさまは】- 以下「思し直されむ」まで、源氏の心内。
【さもあるまじきすさびごとも出で来るぞかし】- 「ついよろしくない浮気沙汰も引き起すといったことになるのだ」と自己弁解めいた感想。
【おだしく軽々しからぬ御心のほども、おのづから】- 源氏の心。葵の上の人柄を想像して、いずれは打ち解けてくれようと期待する。
|
|
第二章 紫の物語 源氏、紫の君に心慰める
|
|
第一段 紫の君、源氏を慕う
|
| 2.1.1 |
|
幼い人は馴染まれるにつれて、とてもよい性質、容貌なので、無心に懐いてお側からお放し申されない。
「暫くの間は、邸内の者にも誰それと知らせまい」とお思いになって、今も離れた対の屋に、お部屋の設備をまたとなく立派にして、ご自分も明け暮れお入りになって、ありとあらゆるお稽古事をお教え申し上げなさる。お手本を書いてお習字などさせては、まるで他で育ったご自分の娘をお迎えになったようなお気持ちでいらっしゃった。
|
若紫は馴れていくにしたがって、性質のよさも容貌の美も源氏の心を多く惹いた。姫君は無邪気によく源氏を愛していた。家の者にも何人であるか知らすまいとして、今も初めの西の対を住居にさせて、そこに華麗な設備をば加え、自身も始終こちらに来ていて若い女王を教育していくことに力を入れているのである。手本を書いて習わせなどもして、今までよそにいた娘を呼び寄せた善良な父のようになっていた。
|
【幼き人は】- 紫の君をさす。
【しばし、殿の内の人にも誰れと知らせじ】- 源氏の心。紫の君を自邸二条院の者にも誰とも知らせまいの意。
【離れたる対に】- 二条院の西の対。東の対は源氏の居室。
【教へきこえたまひ】- 大島本「ゝしへきこえ給い」とある。「ゝ」は「を」の踊り字。『集成』『古典セレクション』は他本に従って「教へきこえたまふ」と終止形に校訂する。『新大系』は底本のまま連用形。
|
| 2.1.2 |
|
政所、家司などをはじめとして、別に分けて、心配がないようにお仕えさせなさる。
惟光以外の人は、はっきり分からずばかり思い申し上げていた。
あの父宮も、ご存知ないのであった。
|
事務の扱い所を作り、家司も別に命じて貴族生活をするのに何の不足も感じさせなかった。しかも惟光以外の者は西の対の主の何人であるかをいぶかしく思っていた。
|
【政所、家司などをはじめ、ことに分かちて、心もとなからず仕うまつらせたまふ】- 二条院の源氏の執務家計とは別に紫の上の執務家計担当の者を独立して置いたことをいう。
|
| 2.1.3 |
姫君は、なほ時々思ひ出できこえたまふ時、尼君を恋ひきこえたまふ折多かり。君のおはするほどは、紛らはしたまふを、夜などは、時々こそ泊まりたまへ、ここかしこの御いとまなくて、暮るれば出でたまふを、慕ひきこえたまふ折などあるを、いとらうたく思ひきこえたまへり。 |
姫君は、やはり時々お思い出しなさる時は、尼君をお慕い申し上げなさる時々が多い。
君がおいでになる時は、気が紛れていらっしゃるが、夜などは、時々はお泊まりになるが、あちらこちらの方々にお忙しくて、暮れるとお出かけになるのを、お後を慕いなさる時などがあるのを、とてもかわいいとお思い申し上げていらっしゃった。
|
女王は今も時々は尼君を恋しがって泣くのである。源氏のいる間は紛れていたが、夜などまれにここで泊まることはあっても、通う家が多くて日が暮れると出かけるのを、悲しがって泣いたりするおりがあるのを源氏はかわいく思っていた。
|
【いとらうたく思ひきこえたまへり】- 主語は源氏。「らうたし」は、弱い者や幼い者をいたわってやりたい気持。
|
| 2.1.4 |
|
二、三日宮中に伺候し、大殿にもいらっしゃる時は、とてもひどく塞ぎ込んだりなさるので、気の毒で、母親のいない子を持ったような心地がして、外出も落ち着いてできなくお思いになる。
僧都は、これこれと、お聞きになって、不思議な気がする一方で、嬉しいことだとお思いであった。
あの尼君の法事などをなさる時にも、立派なお供物をお届けなさった。
|
二、三日御所にいて、そのまま左大臣家へ行っていたりする時は若紫がまったくめいり込んでしまっているので、母親のない子を持っている気がして、恋人を見に行っても落ち着かぬ心になっているのである。僧都はこうした報告を受けて、不思議に思いながらもうれしかった。尼君の法事の北山の寺であった時も源氏は厚く布施を贈った。
|
【心苦しうて】- 「心苦し」は、相手の不憫な様子に心を痛める気持。「母なき子持たらむ心地」というように、一つのパターンとして認識されている。
【静心なく】- 『集成』は「しづこころ」と清音に読み、『古典セレクション』は「しづごころ」と濁音に読む。『新大系』は振り仮名無し。
【かの御法事などしたまふにも】- 主語は源氏。源氏が紫の君の祖母の法事を営む。
|
|
第二段 藤壺の三条宮邸に見舞う
|
| 2.2.1 |
|
藤壷が退出していらっしゃる三条の宮に、ご様子も知りたくて、参上なさると、命婦、中納言の君、中務などといった女房たちが応対に出た。
「他人行儀なお扱いであるな」と、おもしろくなく思うが、落ち着けて、世間一般のお話を申し上げなさっているところに、兵部卿宮が参上なさった。
|
藤壺の宮の自邸である三条の宮へ、様子を知りたさに源氏が行くと王命婦、中納言の君、中務などという女房が出て応接した。源氏はよそよそしい扱いをされることに不平であったが自分をおさえながらただの話をしている時に兵部卿の宮がおいでになった。
|
【藤壺のまかでたまへる三条の宮に】- 源氏は三条宮邸に里下り中の藤壺を訪い、兵部卿宮に会う。
【けざやかにももてなしたまふかな】- 源氏の感想。他人行儀な扱いだと思う。
|
| 2.2.2 |
|
この君がいらっしゃるとお聞きになって、お会いなさった。
とても風情あるご様子をして、色っぽくなよなよとしていらっしゃるのを、「女性として見るにはきっと素晴らしいに違いなかろう」と、こっそりと拝見なさるにつけても、あれこれと睦まじくお思いになられて、懇ろにお話など申し上げなさる。
宮も、君のご様子がいつもより格別に親しみやすく打ち解けていらっしゃるのを、「じつに素晴らしい」と拝見なさって、婿でいらっしゃるなどとはお思いよりにもならず、「女としてお会いしたいものだ」と、色っぽいお気持ちにお考えになる。
|
源氏が来ていると聞いてこちらの座敷へおいでになった。貴人らしい、そして艶な風流男とお見えになる宮を、このまま女にした顔を源氏はかりに考えてみてもそれは美人らしく思えた。藤壺の宮の兄君で、また可憐な若紫の父君であることにことさら親しみを覚えて源氏はいろいろな話をしていた。兵部卿の宮もこれまでよりも打ち解けて見える美しい源氏を、婿であるなどとはお知りにならないで、この人を女にしてみたいなどと若々しく考えておいでになった。
|
【いとよしあるさまして、色めかしうなよびたまへるを】- 兵部卿宮の物腰や器量についていう。
【女にて見むはをかしかりぬべく】- 「む」(推量の助動詞、仮定)「ぬ」(完了の助動詞、確述)「べく」(推量の助動詞)、もし兵部卿宮を女性として見たらきっと素晴らしいにちがいないの意。源氏の仮想。心内文と地の文とが融合した表現。
【むつましく】- 『古典セレクション』は諸本に従って「睦ましう」とう音便形に改める。『集成』『新大系』は底本のまま。
【いとめでたし】- 兵部卿宮の感想。
【婿になどは思し寄らで】- 『集成』は「(源氏を)婿にしようなどとはお考えにもならず。自分の姫君が源氏に引き取られていようとはつゆしらず、という含みがある」と注すが、源氏が既に婿になっているという、「婿に」の下には「おはせり」などの語句が省略された形であろう。
【女にて見ばや】- 兵部卿宮が源氏を女性として見たいという感想。
|
| 2.2.3 |
|
日が暮れたので、御簾の内側にお入りになるのを、羨ましく、昔はお上の御待遇で、とても近くで直接にお話申し上げになさったのに、すっかり疎んじていらっしゃるのも、辛く思われるとは、理不尽なことであるよ。
|
夜になると兵部卿の宮は女御の宮のお座敷のほうへはいっておしまいになった。源氏はうらやましくて、昔は陛下が愛子としてよく藤壺の御簾の中へ自分をお入れになり、今日のように取り次ぎが中に立つ話ではなしに、宮口ずからのお話が伺えたものであると思うと、今の宮が恨めしかった。
|
【御簾の内に入りたまふを】- 主語は兵部卿宮。藤壺と兄妹なので、御簾の内側に入れる。しかし、藤壺はさらに几帳の内側にいる。
【昔は、主上の御もてなしに】- 以下「聞こえたまひしを」までは、源氏の心中とも解せる表現。「こよなううとみ給へる」は源氏の心中文であるとともに語り手の文でもある、境界語。源氏の心に添った語り口で、帝を「主上」と呼称する。
【わりなきや】- 『岷江入楚』は「草子地也」と指摘。『集成』『完訳』も「草子地(作者の評語)」また「語り手の評」と注し、それぞれ「うらめしく思われるのは、これもまた仕方のないことではある」「それもいたしかたのないことである」と解す。
|
| 2.2.4 |
「しばしばもさぶらふべけれど、事ぞとはべらぬほどは、おのづからおこたりはべるを、さるべきことなどは、仰せ言もはべらむこそ、うれしく」 |
「しばしばお伺いすべきですが、特別の事でもない限りは、参上するのも自然滞りがちになりますが、しかるべき御用などは、お申し付けございましたら、嬉しく」
|
「たびたび伺うはずですが、参っても御用がないと自然怠けることになります。命じてくださることがありましたら、御遠慮なく言っておつかわしくださいましたら満足です」
|
【しばしばも】- 以下「うれしく」まで、源氏の詞。女房を介して、藤壺に話した内容。
|
| 2.2.5 |
|
などと、堅苦しい挨拶をしてお出になった。
命婦も、手引き申し上げる手段もなく、宮のご様子も以前よりは、いっそう辛いことにお思いになっていて、お打ち解けにならないご様子も、恥ずかしくおいたわしくもあるので、何の効もなく、月日が過ぎて行く。
「何とはかない御縁か」と、お悩みになること、お互いに嘆ききれない。
|
などと堅い挨拶をして源氏は帰って行った。王命婦も策動のしようがなかった。宮のお気持ちをそれとなく観察してみても、自分の運命の陥擠であるものはこの恋である、源氏を忘れないことは自分を滅ぼす道であるということを過去よりもまた強く思っておいでになる御様子であったから手が出ないのである。はかない恋であると消極的に悲しむ人は藤壺の宮であって、積極的に思いつめている人は源氏の君であった。
|
【ありしより】- 懐妊以後をさす。
【心とけぬ御けしきも】- 藤壺の命婦に対する態度。『集成』は「(手引きをした自分に対して)快からずお思いのご様子も」と注す。
【恥づかしくいとほしければ】- 命婦の藤壺に対する気持ち。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「恥かしう」とウ音便形に改める。『新大系』は底本のまま。『完訳』は「命婦は、藤壺に対して気づまりであり、またいたわしくも思う」と注す。
【はかなの契りや】- 源氏と藤壺両人の心。下に「かたみに尽きせず」とある。
|
|
第三段 故祖母君の服喪明ける
|
| 2.3.1 |
|
少納言は、「思いがけず嬉しい運が回って来たこと。
これも、故尼上が、姫君様をご心配なさって、御勤行にもお祈り申し上げなさった仏の御利益であろうか」と思われる。
「大殿は、本妻として歴としていらっしゃる。
あちらこちら大勢お通いになっているのを、本当に成人されてからは、厄介なことも起きようか」と案じられるのだった。
しかし、このように特別になさっていらっしゃるご寵愛のうちは、とても心強い限りである。
|
少納言は思いのほかの幸福が小女王の運命に現われてきたことを、死んだ尼君が絶え間ない祈願に愛孫のことを言って仏にすがったその効験であろうと思うのであったが、権力の強い左大臣家に第一の夫人があることであるし、そこかしこに愛人を持つ源氏であることを思うと、真実の結婚を見るころになって面倒が多くなり、姫君に苦労が始まるのではないかと恐れていた。しかしこれには特異性がある。少女の日にすでにこんなに愛している源氏であるから将来もたのもしいわけであると見えた。
|
【少納言は】- 以下、物語は転じて、紫の君の物語となる。
【おぼえずをかしき世を見るかな】- 以下「仏の御しるしにや」まで、少納言の心中。
【大殿、いとやむごとなくて】- 以下「むつかしきこともや」まで、少納言の心中。
【おはします】- 大島本「おハします」とある。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「おはし」と校訂する。『新大系』は底本のままとする。
|
| 2.3.2 |
|
ご服喪は、母方の場合は三箇月であると、晦日には忌明け申し上げさせなさるが、他に親もなくてご成長なさったので、派手な色合いではなく、紅、紫、山吹の地だけで織った御小袿などを召していらっしゃる様子、たいそう当世風でかわいらしげである。
|
母方の祖母の喪は三か月であったから、師走の三十日に喪服を替えさせた。母代わりをしていた祖母であったから除喪のあとも派手にはせず濃くはない紅の色、紫、山吹の落ち着いた色などで、そして地質のきわめてよい織物の小袿を着た元日の紫の女王は、急に近代的な美人になったようである。
|
【御服、母方は三月こそはとて、晦日には脱がせたてまつりたまふを】- 『喪葬令』に母方の祖父母の服喪は三カ月(父方の祖父母の場合は五カ月)と規定。九月二十日ころ死去したので(「若紫」)、十二月下旬に除服となる。
【今めかしく】- 大島本「いまめかしく」とある。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「今めかしう」とウ音便形に校訂する。『新大系』は底本のままとする。
|
|
第四段 新年を迎える
|
| 2.4.1 |
|
男君は、朝拝に参内なさろうとして、お立ち寄りになった。
|
源氏は宮中の朝拝の式に出かけるところで、ちょっと西の対へ寄った。
|
【男君は、朝拝に】- 新年を迎える。「男君」という呼称は「夫君」というニュアンス。
|
|
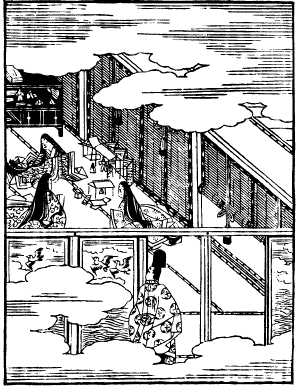 |
| 2.4.2 |
|
「今日からは大人らしくなられましたか」
|
「今日からは、もう大人になりましたか」
|
【今日よりは】- 以下「なりたまへりや」まで、源氏の詞。
|
| 2.4.3 |
とて、うち笑みたまへる、いとめでたう愛敬づきたまへり。いつしか、雛をし据ゑて、そそきゐたまへる。三尺の御厨子一具に、品々しつらひ据ゑて、また小さき屋ども作り集めて、たてまつりたまへるを、ところせきまで遊びひろげたまへり。 |
と言って微笑んでいらっしゃる、とても素晴らしく魅力的である。
早くも、お人形を並べ立てて、忙しくしていらっしゃる。
三尺の御厨子一具と、お道具を色々と並べて、他に小さい御殿をたくさん作って、差し上げなさっていたのを、辺りいっぱいに広げて遊んでいらっしゃる。
|
と笑顔をして源氏は言った。光源氏の美しいことはいうまでもない。紫の君はもう雛を出して遊びに夢中であった。三尺の据棚二つにいろいろな小道具を置いて、またそのほかに小さく作った家などを幾つも源氏が与えてあったのを、それらを座敷じゅうに並べて遊んでいるのである。
|
【たてまつりたまへるを】- 主語は源氏。紫の君のために。
|
| 2.4.4 |
|
「追儺をやろうといって、犬君がこれを壊してしまったので、直しておりますの」
|
「儺追いをするといって犬君がこれをこわしましたから、私よくしていますの」
|
【儺やらふとて、犬君が】- 以下「つくろひはべるぞ」まで、紫の君の詞。相変わらず子供っぽい遊びに熱中。「儺」(追儺)は大晦日の夜に行う行事。「犬君」は紫の君の遊び相手(「若紫」巻に登場)。
|
| 2.4.5 |
とて、いと大事と思いたり。
|
と言って、とても大事件だとお思いである。
|
と姫君は言って、一所懸命になって小さい家を繕おうとしている。
|
|
| 2.4.6 |
|
「なるほど、とてもそそっかしい人のやったことらしいですね。
直ぐに直させましょう。
今日は涙を慎んで、お泣きなさるな」
|
「ほんとうにそそっかしい人ですね。すぐ直させてあげますよ。今日は縁起を祝う日ですからね、泣いてはいけませんよ」
|
【げに、いと心なき人の】- 以下「な泣いたまひそ」まで、源氏の詞。紫の君に合わせた発言。
|
| 2.4.7 |
|
と言って、お出かけになる様子、辺り狭しのご立派さを、女房たちは端に出てお見送り申し上げるので、姫君も立って行ってお見送り申し上げなさって、お人形の中の源氏の君を着飾らせて、内裏に参内させる真似などなさる。
|
言い残して出て行く源氏の春の新装を女房たちは縁に近く出て見送っていた。紫の君も同じように見に立ってから、雛人形の中の源氏の君をきれいに装束させて真似の参内をさせたりしているのであった。
|
【姫君も立ち出でて見たてまつりたまひて】- 姫君が「立ち出で」という行動はや異例、普通は膝行するものである。紫の君の無心さあどけなさの現れ。
|
| 2.4.8 |
「今年だにすこし大人びさせたまへ。十にあまりぬる人は、雛遊びは忌みはべるものを。かく御夫などまうけたてまつりたまひては、あるべかしうしめやかにてこそ、見えたてまつらせたまはめ。御髪参るほどをだに、もの憂くせさせたまふ」 |
「せめて今年からはもう少し大人らしくなさいませ。
十歳を過ぎた人は、お人形遊びはいけないものでございますのに。
このようにお婿様をお持ち申されたからには、奥方様らしくおしとやかにお振る舞いになって、お相手申し上げあそばしませ。
お髪をお直しする間さえ、お嫌がりあそばして」
|
「もう今年からは少し大人におなりあそばせよ。十歳より上の人はお雛様遊びをしてはよくないと世間では申しますのよ。あなた様はもう良人がいらっしゃる方なんですから、奥様らしく静かにしていらっしゃらなくてはなりません。髪をお梳きするのもおうるさがりになるようなことではね」
|
【今年だに】- 以下「もの憂くせさせたまふ」まで、少納言の乳母の詞。
|
| 2.4.9 |
など、少納言聞こゆ。御遊びにのみ心入れたまへれば、恥づかしと思はせたてまつらむとて言へば、心のうちに、「我は、さは、夫まうけてけり。この人びとの夫とてあるは、醜くこそあれ。我はかくをかしげに若き人をも持たりけるかな」と、今ぞ思ほし知りける。さはいへど、御年の数添ふしるしなめりかし。かく幼き御けはひの、ことに触れてしるければ、殿のうちの人びとも、あやしと思ひけれど、いとかう世づかぬ御添臥ならむとは思はざりけり。 |
などと少納言も、
お諌め申し上げる。お人形遊びにばかり夢中になっていらっしゃるので、これではいけないと思わせ申そうと思って言うと、心の中で、「わたしは、それでは、夫
君を持ったのだわ。この女房たちの夫君というのは、何と醜い人
たちなのであろう。わたしは、こんなにも魅力的で若い男性を持ったのだわ」と、今になってお分かり
になるのであった。何と言っても、お年を一つ取った
証拠なのであろう。このように幼稚なご様子が、何かにつけてはっきり分かるので、殿の内の女房たちも変だと思ったが、とてもこのように夫婦らしくないお添い寝相手だろうとは思わ
|
などと少納言が言った。遊びにばかり夢中になっているのを恥じさせようとして言ったのであるが、女王は心の中で、私にはもう良人があるのだって、源氏の君がそうなんだ。少納言などの良人は皆醜い顔をしている、私はあんなに美しい若い人を良人にした、こんなことをはじめて思った。というのも一つ年が加わったせいかもしれない。何ということなしにこうした幼稚さが御簾の外まで来る家司や侍たちにも知れてきて、怪しんではいたが、だれもまだ名ばかりの夫人であるとは知らなんだ。
|
【我は、さは】- 以下「持たりけるかな」まで、紫の君の心中。
【さはいへど、御年の数添ふしるしなめりかし】- 『紹巴抄』は「双地」と指摘。『集成』も「諧謔めかした草子地。語り手(作者)が直接読者に語りかける趣」と注す。
|
|
第三章 藤壺の物語(二) 二月に男皇子を出産
|
|
第一段 左大臣邸に赴く
|
| 3.1.1 |
|
宮中から大殿にご退出なさると、いつものように端然と威儀を正したご態度で、やさしいそぶりもなく窮屈なので、
|
源氏は御所から左大臣家のほうへ退出した。例のように夫人からは高いところから多情男を見くだしているというようなよそよそしい態度をとられるのが苦しくて、源氏は、
|
【内裏より大殿にまかでたまへれば】- 物語は転じて、源氏の宮中参賀後の大殿邸退出、院や藤壺宮などへの参賀の様子を語る。
|
| 3.1.2 |
「今年よりだに、すこし世づきて改めたまふ御心見えば、いかにうれしからむ」 |
「せめて今年からでも、もう少し夫婦らしく態度をお改めになるお気持ちが窺えたら、どんなにか嬉しいことでしょう」
|
「せめて今年からでもあなたが暖かい心で私を見てくれるようになったらうれしいと思うのだが」
|
【今年よりだに】- 以下「いかにうれしからむ」まで、源氏の詞。
|
| 3.1.3 |
|
などとお申し上げなさるが、「わざわざ女の人を置いて、かわいがっていらっしゃる」と、お聞きになってからは、「重要な夫人とお考えになってのことであろう」と、隔て心ばかりが自然と生じて、ますます疎ましく気づまりにお感じになられるのであろう。
つとめて見知らないように振る舞って、冗談をおっしゃっるご様子には、強情もを張り通すこともできず、お返事などちょっと申し上げなさるところは、やはり他の女性とはとても違うのである。
|
と言ったが、夫人は、二条の院へある女性が迎えられたということを聞いてからは、本邸へ置くほどの人は源氏の最も愛する人で、やがては正夫人として公表するだけの用意がある人であろうとねたんでいた。自尊心の傷つけられていることはもとよりである。しかも何も気づかないふうで、戯談を言いかけて行きなどする源氏に負けて、余儀なく返辞をする様子などに魅力がなくはなかった。
|
【わざと人据ゑて、かしづきたまふ】- 人の噂。なお『万水一露』は「草子の批判の詞なるへし」と指摘し、また『完訳』は以下「思さるべし」まで、挿入句と解す。
【やむごとなく思し定めたることにこそは】- 葵の上の心。
【思さるべし】- 『湖月抄』師説は「草子地より察して書る詞也」と指摘。
【しひて見知らぬやうにもてなして】- 『集成』は「(しかし)そんな葵の上のお気持にわざと気づかぬふうをよそおって、冗談をおっしゃる源氏のお振舞に対しては」と、主語を源氏に解す。しかし、その前を挿入句とみる『完訳』は「しいて何気ないふうを装って、冗談口をたたかれる君のお仕向けに対しては」と、主語を葵の上に解す。両方の意に解せるところである。こういうところはそのような表現としての両義性を尊重して、主語をあえて補い特定するようなことはせず、原文のままに解す。
【乱れたる御けはひ】- 源氏の態度をいう。
【えしも心強からず、御いらへなどうち聞こえたまへるは】- 主語は葵の上。
|
| 3.1.4 |
|
四歳ほど年上でいらっしゃるので、姉様で、気後れがし、女盛りで非の打ちどころがなくお見えになる。
「どこにこの人の足りないところがおありだろうか。
自分のあまり良くない浮気心からこのようにお恨まれ申すのだ」と、お考えにならずにはいられない。
同じ大臣と申し上げる中でも、御信望この上なくいらっしゃる方が、宮との間にお一人儲けて大切にお育てなさった気位の高さは、とても大変なもので、「少しでも疎略にするのは、失敬である」とお思い申し上げていらっしゃるのを、男君は、「どうしてそんなにまでも」と、お躾なさる、お二人の心の隔てがあるの生じさせたのであろう。
|
四歳ほどの年上であることを夫人自身でもきまずく恥ずかしく思っているが、美の整った女盛りの貴女であることは源氏も認めているのである。どこに欠点もない妻を持っていて、ただ自分の多情からこの人に怨みを負うような愚か者になっているのだとこんなふうにも源氏は思った。同じ大臣でも特に大きな権力者である現代の左大臣が父で、内親王である夫人から生まれた唯一の娘であるから、思い上がった性質にでき上がっていて、少しでも敬意の足りない取り扱いを受けては、許すことができない。帝の愛子として育った源氏の自負はそれを無視してよいと教えた。こんなことが夫妻の溝を作っているものらしい。
|
【四年ばかりがこのかみにおはすれば】- 葵の上は源氏よりも四歳年上。
【何ごとかは】- 以下「怨みられたてまつるぞかし」まで、源氏の心中。葵の上の応対の態度に対する賞賛と自分の行動に対する反省。
【同じ大臣と聞こゆるなかにも】- 以下の文について、『細流抄』は「草子地也」と指摘。『評釈』も「作者の弁解。作者は、お二人の心のへだてを次のように説明している(中略)。このお二人のくい違いが、お互いを隔てているのであると。このような作者の説明に対して、われわれは必ずしも忠実である必要はない。作者は光る源氏を愛するあまり、時々かような弁解をするのである。いわゆる作者介入の詞には、いいわけや弁解がるのである」と注す。
【などかいとさしも】- 源氏の心。『集成』は「何もそうあがめ奉る必要はない」の意に解す。『完訳』は「なぜそれほど葵の上の機嫌を取らねばならぬのか」と注す。
【ならはいたまふ、御心の隔てどもなるべし】- 主語は源氏、葵の上に対してお仕向けなさるの意。語り手の推測といった表現。「ども」とあるように源氏と葵の上お互いにである。
|
| 3.1.5 |
大臣も、かく頼もしげなき御心を、つらしと思ひきこえたまひながら、見たてまつりたまふ時は、恨みも忘れて、かしづきいとなみきこえたまふ。つとめて、出でたまふところにさしのぞきたまひて、御装束したまふに、名高き御帯、御手づから持たせてわたりたまひて、御衣のうしろひきつくろひなど、御沓を取らぬばかりにしたまふ、いとあはれなり。 |
大臣も、このように頼りないお気持ちを、辛いとお思い申し上げになりながらも、お目にかかりなさる時には、恨み事も忘れて、大切にお世話申し上げなさる。
翌朝、お帰りになるところにお顔をお見せになって、お召し替えになる時、高名の御帯、お手ずからお持ちになってお越しになって、お召物の後ろを引き結び直しなどや、お沓までも手に取りかねないほど世話なさる、大変なお気の配りようである。
|
左大臣も二条の院の新夫人の件などがあって、頼もしくない婿君の心をうらめしがりもしていたが、逢えば恨みも何も忘れて源氏を愛した。今もあらゆる歓待を尽くすのである。翌朝源氏が出て行こうとする時に、大臣は装束を着けている源氏に、有名な宝物になっている石の帯を自身で持って来て贈った。正装した源氏の形を見て、後ろのほうを手で引いて直したりなど大臣はしていた。沓も手で取らないばかりである。娘を思う親心が源氏の心を打った。
|
【御手づから持たせて】- 『集成』は「せ」を使役の助動詞と解す。一方『完訳』は「助動詞「す」が単独で尊敬の意に用いられた特殊例か」と注す。
【いとあはれなり】- 語り手の評言。『評釈』は「作者がそばにいて、様子を見聞きしての書きざまである」と注す。
|
| 3.1.6 |
|
「これは、内宴などということもございますそうですから、そのような折にでも」
|
「こんないいのは、宮中の詩会があるでしょうから、その時に使いましょう」
|
【これは、内宴など】- 以下「折にこそ」まで、源氏の詞。下に「ささめ」などの語が省略。
|
| 3.1.7 |
|
などとお申し上げなさると、
|
と贈り物の帯について言うと、
|
【たまへば】- 本文異同がある。大島本、榊原家本、陽明文庫本は「たまへは」(順接)。横山本は「は」(順接)をミセケチにして「と」(逆接)と訂正する。池田本、肖柏本、三条西家本は書陵部本は「給へと」同文(逆接)。河内本と別本の御物本、伝二条為氏筆本も「と」(逆接)である。
|
| 3.1.8 |
|
「その時には、
もっと良いものがございます。これはちょっと目新しい感じ
|
「それにはまたもっといいのがございます。これはただちょっと珍しいだけの物です」
|
【それは、まされるもはべり】- 以下「さまなればなむ」まで、左大臣の詞。その折にはもっと良いものがあります、の意。
|
| 3.1.9 |
とて、しひてささせたてまつりたまふ。げに、よろづにかしづき立てて見たてまつりたまふに、生けるかひあり、「たまさかにても、かからむ人を出だし入れて見むに、ますことあらじ」と見えたまふ。 |
と言って、無理にお締め申し上げなさる。
なるほど、万事にお世話して拝見なさると、生き甲斐が感じられ、「たまさかであっても、このような方をお出入りさせてお世話するのに、これ以上の喜びはあるまい」とお見えである。
|
と言って、大臣はしいてそれを使わせた。この婿君を斎くことに大臣は生きがいを感じていた。たまさかにもせよ婿としてこの人を出入りさせていれば幸福感は十分大臣にあるであろうと見えた。
|
【たまさかにても】- 以下「ますことあらじ」まで、左大臣の心。
【見えたまふ】- 主語は源氏。お見えになる源氏の君の素晴らしさであるの意。
|
|
第二段 二月十余日、藤壺に皇子誕生
|
| 3.2.1 |
|
参賀のご挨拶といっても、多くの所にはお出かけにならず、内裏、春宮、一院だけ、その他では、藤壷の三条の宮にお伺いなさる。
|
源氏の参賀の場所は数多くもなかった。東宮、一院、それから藤壺の三条の宮へ行った。
|
【参座しにとても】- 主語は源氏。年賀の拝礼に参る。
【内裏、春宮、一院ばかり】- 「一院」について、『集成』は「上皇のこと。朱雀院で算賀を受けられた方であろう」と注す。『完訳』は「ここだけに見える呼称。巻頭の行幸はこの一院の賀。上皇が二人存在する場合、先に上皇になった方を「一院」、後の方を「新院」と呼ぶ。桐壺帝の一代前の帝(新院)は兵部卿宮や藤壺の父で、すでに崩御。この一院は桐壺帝の父か」と注す。
|
| 3.2.2 |
|
「今日はまた格別にお見えでいらっしゃるわ」
|
「今日はまたことにおきれいに見えますね、
|
【今日はまたことにも見えたまふかな】- 以下「御ありさまかな」まで、女房の詞。源氏賞賛。下に「人びと」とあるので、今、二人の女房の詞と解す。
|
| 3.2.3 |
「ねびたまふままに、ゆゆしきまでなりまさりたまふ御ありさまかな」
|
「ご成長されるに従って、恐いまでにお美しくおなりでいらっしゃるご様子ですわ」
|
年がお行きになればなるほどごりっぱにおなりになる方なんですね」
|
|
| 3.2.4 |
と、人びとめできこゆるを、宮、几帳の隙より、ほの見たまふにつけても、思ほすことしげかりけり。 |
と、女房たちがお褒め申し上げているのを、宮、几帳の隙間からわずかにお姿を御覧になるにつけても、物思いなさることが多いのであった。
|
女房たちがこうささやいている時に、宮はわずかな几帳の間から源氏の顔をほのかに見て、お心にはいろいろなことが思われた。
|
【ほの見たまふにつけても】- 主語は藤壺。源氏をちらっと御覧になるにつけてもの意。
|
| 3.2.5 |
|
御出産の予定の、十二月も過ぎてしまったのが、気がかりで、今月はいくら何でもと、宮家の人々もお待ち申し上げ、主上におかれても、そのお心づもりでいるのに、何事もなく過ぎてしまった。
「御物の怪のせいであろうか」と、世間の人々もお噂申し上げるのを、宮、とても身にこたえてつらく、「このお産のために、命を落とすことになってしまいそうだ」と、お嘆きになると、ご気分もとても苦しくてお悩みになる。
|
御出産のあるべきはずの十二月を過ぎ、この月こそと用意して三条の宮の人々も待ち、帝もすでに、皇子女御出生についてのお心づもりをしておいでになったが、何ともなくて一月もたった。物怪が御出産を遅れさせているのであろうかとも世間で噂をする時、宮のお心は非常に苦しかった。このことによって救われない悪名を負う人になるのかと、こんな煩悶をされることが自然おからだにさわってお加減も悪いのであった。
|
【この御ことの、師走も過ぎにしが】- 御出産の予定の十二月も過ぎてしまったの意。
【この月はさりともと】- 正月にはいくらなんでも、の意。
【御心まうけどもあり】- 大島本「御心まうけともあり」とある。『集成』は他本に従って「御心まうけどもありるに」と校訂、『古典セレクション』は「御心まうけどもある」と校訂する。『新大系』は底本のまま。
【つれなくて立ちぬ】- 何事もなく正月が過ぎてしまったの意。
【このことにより、身のいたづらになりぬべきこと】- 藤壺の心。「この事」は出産をさす。
|
| 3.2.6 |
|
中将の君は、ますます思い当たって、御修法などを、はっきりと事情は知らせずに方々の寺々におさせになる。
「世の無常につけても、このままはかなく終わってしまうのだろうか」と、あれやこれやとお嘆きになっていると、二月十日過ぎのころに、男御子がお生まれになったので、すっかり心配も消えて、宮中でも宮家の人々もお喜び申し上げなさる。
|
それを聞いても源氏はいろいろと思い合わすことがあって、目だたぬように産婦の宮のために修法などをあちこちの寺でさせていた。この間に御病気で宮が亡くなっておしまいにならぬかという不安が、源氏の心をいっそう暗くさせていたが、二月の十幾日に皇子が御誕生になったので、帝も御満足をあそばし、三条の宮の人たちも愁眉を開いた。
|
【中将君は】- 源氏をさす。ここでは官職名、公人的ニュアンスで呼称する。
【御修法】- 大島本「みすほう」とある。『集成』『古典セレクション』は濁音「みずほふ」と振り仮名を付ける。『新大系』は「みすほふ」と振り仮名を付ける。
【世の中の】- 以下「はかなくてや止みなむ」まで、源氏の心。「や」(係助詞、疑問)「な」(完了の助動詞、確述)「む」(推量の助動詞)、このままはかなく藤壺との仲も終わってしまうのだろうかの意。
【取り集めて嘆きたまふに】- 主語は源氏。
【二月十余日のほどに、男御子生まれたまひぬれば】- 後の冷泉帝。二月十何日に誕生。源氏との密通は、夏の「あやにくなる短夜」(「若紫」巻)、六月には妊娠「三月」とあったので、逆算四月と推定される。藤壺はそれより前に里邸に下がっていたので、人々はそれを妊娠のためかと思っていた。『集成』『古典セレクション』は「じふよ」と振り仮名を付ける。漢字表記なので「にぐぁつじふよにち」と読んでおく。
|
| 3.2.7 |
|
「長生きを」とお思いなさるのは、つらいことだが、「弘徽殿などが、呪わしそうにおっしゃっている」と聞いたので、「死んだとお聞きになったならば、物笑いの種になろう」と、お気を強くお持ちになって、だんだん少しずつ気分が快方に向かっていかれたのであった。
|
なお生きようとする自分の心は未練で恥ずかしいが、弘徽殿あたりで言う詛いの言葉が伝えられている時に自分が死んでしまってはみじめな者として笑われるばかりであるから、とそうお思いになった時からつとめて今は死ぬまいと強くおなりになって、御衰弱も少しずつ恢復していった。
|
【命長くも」と思ほすは心憂けれど】- 『集成』は「藤壺は、よくぞ生き永らえたものとお思いになると、情けないけれども。藤壺は、あわよくばこのお産で死にたいとも思っている」と注す。一方『完訳』は「人々の喜びから反転して、以下、藤壺の複雑な思念。生れ出た若君のためにも長く生きよう、の決意。一説には、死線を越えて生き延びた生命をいとおしむ気持」と注す。後者の説に従う。
【むなしく聞きなしたまはましかば、人笑はれにや】- 藤壺の心。「ましかば」は反実仮想。「人笑はれにや」の下に「ならまし」などの語句が省略された形。もしもわたしが死んでいたら物笑いの種となったのではなかろうか、死なずに幸いであったの意。『完訳』は「自分が死んだと弘徽殿が聞き及んだ場合の、堪えがたい不面目を仮想し、敗北してなるものかと立ち直る。「つよる」は「つよ(強)し」の動詞化、「思し」と複合。母となった藤壺の、弘徽殿の存在を意識してたくましく生きぬこうとする意志に注意。
|
| 3.2.8 |
|
お上が、早く御子を御覧になりたいとおぼし召されること、この上ない。
あの、密かなお気持ちとしても、ひどく気がかりで、人のいない時に参上なさって、
|
帝は新皇子を非常に御覧になりたがっておいでになった。人知れぬ父性愛の火に心を燃やしながら源氏は伺候者の少ない隙をうかがって行った。
|
【かの、人知れぬ御心にも、いみじう心もとなくて】- 源氏をさす。
【人まに参りたまひて】- 主語は源氏。場所は藤壺の三条宮邸に。
|
| 3.2.9 |
|
「お上が御覧になりたくあそばしてますので、まず拝見して詳しく奏上しましょう」
|
「陛下が若宮にどんなにお逢いになりたがっていらっしゃるかもしれません。それで私がまずお目にかかりまして御様子でも申し上げたらよろしいかと思います」
|
【主上のおぼつかながりきこえさせたまふを】- 以下「詳しく奏しはべらむ」まで、源氏の詞。主上に申し上げたいとは、源氏の口実で、わが子を見たい気持ち。
【見たてまつりて詳しく奏しはべらむ】- 大島本「見たてまつりて(て+くはしく)そうし侍らむ」とある。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って補入の「くはしく」を削除する。『新大系』は底本の補入を採用して校訂する。
|
| 3.2.10 |
と聞こえたまへど、
|
と申し上げなさるが、
|
と源氏は申し込んだのであるが、
|
|
| 3.2.11 |
|
「まだ見苦しい程ですので」
|
「まだお生まれたての方というものは醜うございますからお見せしたくございません」
|
【むつかしげなるほどなれば】- 藤壺の返事。産まれたばかりで見苦しいといって断る。
|
| 3.2.12 |
|
と言って、お見せ申し上げなさらないのも、ごもっともである。
実のところ、とても驚くほど珍しいまでに生き写しでいらっしゃる顔形、紛うはずもない。
宮が、良心の呵責にとても苦しく、「女房たちが拝見しても、不審に思われた月勘定の狂いを、どうして変だと思い当たらないだろうか。
それほどでないつまらないことでさえも、欠点を探し出そうとする世の中で、どのような噂がしまいには世に漏れようか」と思い続けなさると、わが身だけがとても情けない。
|
という母宮の御挨拶で、お見せにならないのにも理由があった。それは若宮のお顔が驚くほど源氏に生き写しであって、別のものとは決して見えなかったからである。宮はお心の鬼からこれを苦痛にしておいでになった。この若宮を見て自分の過失に気づかぬ人はないであろう、何でもないことも捜し出して人をとがめようとするのが世の中である。どんな悪名を自分は受けることかとお思いになると、結局不幸な者は自分であると熱い涙がこぼれるのであった。
|
【ことわりなり】- 語り手の評言。『首書源氏物語』所引或抄は「地よりいへり」と注す。
【さるは】- 以下「べくもあらず」まで、それというのも、実のところ、と切り出すように語り手の感想を交えた表現。『集成』は「だが」と注すが、単なる逆接ではない。『完訳』は「じつは」と訳す。
【違ふ】- 本文異同がある。大島本、榊原家本、池田本は「たかふ」(「違ふ」)とあり、横山本、陽明文庫本、肖柏本、三条西家本、書陵部本は「まかふ」(「紛ふ」)とある。河内本と別本の伝二条為氏筆本は大島本等と同文。御物本は横山本等と同文。
【宮の、御心の鬼にいと苦しく】- 『集成』は「人知れずお心に咎めて、とてもつらく。「心の鬼」は、良心の呵責というに近い」と注す。
【人の見たてまつるも】- 以下「漏り出づべきにか」まで、藤壺の心中。
【あやしかりつるほどのあやまり】- 『集成』は「不審に思われるに違いない月勘定の狂いを」と解し、「産み月が予想より遅れたのは、内裏退出後の源氏との密通による懐妊だからである。懐妊当時の帝への奏上の時期についてもすでに問題があった」と注す。一方『完訳』では「源氏との密会」と注し、「いかなることかと我ながら申し開きの立たぬあのときの異常な過ちを」と解す。
【人の思ひとがめじや】- 「や」(係助詞、反語)、どうして気づかずにすもうか、きっと感づくに違いないの意。
【疵を求むる世に】- 『伊行釈』『花屋抄』は「直き木に曲れる枝もあるものを毛を吹き疵を言ふがわりなき」(後撰集雑二、一一五六、高津内親王)を引歌として指摘。
|
| 3.2.13 |
|
命婦の君に、まれにお会いになって、切ない言葉を尽くしてお頼みなさるが、何の効果があるはずもない。
若宮のお身の上を無性に御覧になりたくお訴え申し上げなさるので、
|
源氏は稀に都合よく王命婦が呼び出された時には、いろいろと言葉を尽くして宮にお逢いさせてくれと頼むのであるが、今はもう何のかいもなかった。新皇子拝見を望むことに対しては、
|
【命婦の君に、たまさかに逢ひたまひて】- 主語は源氏。
【わりなくおぼつかながりきこえたまへば】- 主語は源氏。無性に若宮を拝見したく訴え申し上げなさるのでの意。
|
| 3.2.14 |
「など、かうしもあながちにのたまはすらむ。今、おのづから見たてまつらせたまひてむ」 |
「どうして、こうまでもご無理を仰せあそばすのでしょう。
そのうち、自然に御覧あそばされましょう」
|
「なぜそんなにまでおっしゃるのでしょう。自然にその日が参るのではございませんか」
|
【など、かうしも】- 以下「見たてまつらせたまひてむ」まで、王命婦の詞。「のたまはす」「見たてまつらせたまひ」という最高敬語は単に会話文中であるからでなく、源氏の気持ちを何とかなだめすかそうとする、命婦の丁重な物言いであろう。
|
| 3.2.15 |
と聞こえながら、思へるけしき、かたみにただならず。
かたはらいたきことなれば、まほにもえのたまはで、
|
と申し上げながら、悩んでいる様子、お互いに一通りでない。
気が引ける事柄なので、正面切っておっしゃれず、
|
と答えていたが、無言で二人が読み合っている心が別にあった。口で言うべきことではないから、そのほうのことはまた言葉にしにくかった。
|
|
| 3.2.16 |
|
「いったいいつになったら、直接に、お話し申し上げることができるのだろう」
|
「いつまた私たちは直接にお話ができるのだろう」
|
【いかならむ世に、人づてならで、聞こえさせむ】- 源氏の詞。
|
| 3.2.17 |
とて、泣いたまふさまぞ、心苦しき。
|
と言ってお泣きになる姿、お気の毒である。
|
と言って泣く源氏が王命婦の目には気の毒でならない。
|
|
| 3.2.18 |
|
「どのように前世で約束を交わした縁で
この世にこのような二人の仲に隔てがあるのだろうか
|
「いかさまに昔結べる契りにて
この世にかかる中の隔てぞ
|
【いかさまに昔結べる契りにて--この世にかかるなかの隔てぞ】- 源氏の藤壺への贈歌。「この世」に「子の世」を掛ける。『集成』は「藤壺にもわが子にも逢えぬつらさを嘆いた歌である」と注す。
|
| 3.2.19 |
|
このような隔ては納得がいかない」
|
わからない、わからない」
|
【かかることこそ心得がたけれ】- 歌に添えた詞。
|
| 3.2.20 |
とのたまふ。
|
とおっしゃる。
|
とも源氏は言うのである。
|
|
| 3.2.21 |
|
命婦も、宮のお悩みでいらっしゃる様子などを拝見しているので、そっけなく突き放してお扱い申し上げることもできない。
|
命婦は宮の御煩悶をよく知っていて、それだけ告げるのが恋の仲介をした者の義務だと思った。
|
【思ほしたるさまなど】- 『完訳』は「源氏を拒みつつも心ひかれている藤壺の、惑乱する心の状態」と注す。
【えはしたなうもさし放ちきこえず】- 『完訳』は「源氏・藤壺それぞれ苦悩する間に立つ命婦は、そっけなく放置することもできず、藤壺に代って返歌する」と注す。
|
| 3.2.22 |
|
「御覧になっている方も物思をされています。御覧にならないあなたはまたどんなにお嘆きのことでしょう
これが世の人が言う親心の闇でしょうか
|
「見ても思ふ見ぬはたいかに歎くらん
こや世の人の惑ふてふ闇
|
【見ても思ふ見ぬはたいかに嘆くらむ--こや世の人のまどふてふ闇】- 命婦の藤壺に代わって源氏への返歌。「この世」を踏まえて「こや世の人」と返した。「見ても思ふ」の主語は藤壺、「見ぬはたいかに嘆くらむ」の源氏をさす。「人の親の心は闇にあらねども子を思ふ道に惑ひぬるかな」(後撰集雑一、一一〇二、藤原兼輔)を踏まえる。
|
| 3.2.23 |
|
おいたわしい、お心の休まらないお二方ですこと」
|
どちらも同じほどお気の毒だと思います」
|
【あはれに、心ゆるびなき御ことどもかな】- 歌に添えた命婦の詞。「御ことどもかな」というように第三者の立場に戻っていう。
|
| 3.2.24 |
と、忍びて聞こえけり。
|
と、こっそりとお返事申し上げたのであった。
|
と命婦は言った。
|
|
| 3.2.25 |
かくのみ言ひやる方なくて、帰りたまふものから、人のもの言ひもわづらはしきを、わりなきことにのたまはせ思して、命婦をも、昔おぼいたりしやうにも、うちとけむつびたまはず。人目立つまじく、なだらかにもてなしたまふものから、心づきなしと思す時もあるべきを、いとわびしく思ひのほかなる心地すべし。 |
このように何とも申し上げるすべもなくて、お帰りになるものの、世間の人々の噂も煩わしいので、無理無体なことにおっしゃりもし、お考えにもなって、命婦をも、以前信頼していたように気を許してお近づけなさらない。
人目に立たないように、穏やかにお接しになる一方で、気に食わないとお思いになる時もあるはずなのを、とても身にこたえて思ってもみなかった心地がするようである。
|
取りつき所もないように源氏が悲しんで帰って行くことも、度が重なれば邸の者も不審を起こしはせぬかと宮は心配しておいでになって王命婦をも昔ほどお愛しにはならない。目に立つことをはばかって何ともお言いにはならないが、源氏への同情者として宮のお心では命婦をお憎みになることもあるらしいのを、命婦はわびしく思っていた。意外なことにもなるものであると歎かれたであろうと思われる。
|
【わりなきことにのたまはせ思して】- 主語は藤壺。
【人目立つまじく】- 大島本「人めたつましく」とある。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「人目立つまじう」とウ音便形に校訂する。『新大系』は底本のまま。
|
|
第三段 藤壺、皇子を伴って四月に宮中に戻る
|
| 3.3.1 |
四月に内裏へ参りたまふ。ほどよりは大きにおよすけたまひて、やうやう起き返りなどしたまふ。あさましきまで、まぎれどころなき御顔つきを、思し寄らぬことにしあれば、「またならびなきどちは、げにかよひたまへるにこそは」と、思ほしけり。いみじう思ほしかしづくこと、限りなし。源氏の君を、限りなきものに思し召しながら、世の人のゆるしきこゆまじかりしによりて、坊にも据ゑたてまつらずなりにしを、飽かず口惜しう、ただ人にてかたじけなき御ありさま、容貌に、ねびもておはするを御覧ずるままに、心苦しく思し召すを、「かうやむごとなき御腹に、同じ光にてさし出でたまへれば、疵なき玉」と思しかしづくに、宮はいかなるにつけても、胸のひまなく、やすからずものを思ほす。 |
四月に参内なさる。
日数の割には大きく成長なさっていて、だんだん寝返りなどをお打ちになる。
驚きあきれるくらい、間違いようもないお顔つきを、ご存知ないことなので、「他に類のない美しい人どうしというのは、なるほど似通っていらっしゃるものだ」と、お思いあそばすのであった。
たいそう大切にお慈しみになること、この上もない。
源氏の君を、限りなくかわいい人と愛していらっしゃりながら、世間の人々のがご賛成申し上げそうになかったことによって、坊にもお据え申し上げられずに終わったことを、どこまでも残念に、臣下としてもったいないご様子、容貌で、ご成人していらっしゃるのを御覧になるにつけ、おいたわしくおぼし召されるので、「このように高貴な人から、同様に光り輝いてお生まれになったので、疵のない玉だ」と、お思いあそばして大切になさるので、宮は何につけても、胸の痛みの消える間もなく、不安な思いをしていらっしゃる。
|
四月に若宮は母宮につれられて宮中へおはいりになった。普通の乳児よりはずっと大きく小児らしくなっておいでになって、このごろはもうからだを起き返らせるようにもされるのであった。紛らわしようもない若宮のお顔つきであったが、帝には思いも寄らぬことでおありになって、すぐれた子どうしは似たものであるらしいと思召した。帝は新皇子をこの上なく御大切にあそばされた。源氏の君を非常に愛しておいでになりながら、東宮にお立てになることは世上の批難を恐れて御実行ができなかったのを、帝は常に終生の遺憾事に思召して、長じてますます王者らしい風貌の備わっていくのを御覧になっては心苦しさに堪えないように思召したのであるが、こんな尊貴な女御から同じ美貌の皇子が新しくお生まれになったのであるから、これこそは瑕なき玉であると御寵愛になる。女御の宮はそれをまた苦痛に思っておいでになった。
|
【四月に内裏へ参りたまふ】- 四月、藤壺は若宮を伴って宮中に参内。大島本「四月」と漢字表記、その書き入れ注記に「う月」とあるので、「うづき」と読んでおく。
【思し寄らぬこと】- 主語は帝。若宮が藤壺と源氏の間の子であることをさす。
【またならびなきどちは、げにかよひたまへるにこそは】- 帝の心。世に比類のない者同士というのは、なるほど似通うものである、という納得の仕方。
|
| 3.3.2 |
|
いつものように、中将の君が、こちらで管弦のお遊びをなさっていると、お抱き申し上げあそばされて、
|
源氏の中将が音楽の遊びなどに参会している時などに帝は抱いておいでになって、
|
【中将の君】- 源氏。公的呼称のニュアンス。
【こなたにて】- 藤壺の御殿(飛香舎)をさす。
【抱き出でたてまつらせたまひて】- 主語は帝。「たてまつら」(謙譲の補助動詞、帝の若宮に対する敬意)「せ」(尊敬の助動詞)「たまひ」(尊敬の補助動詞、帝に対する最高敬語)。
|
| 3.3.3 |
「御子たち、あまたあれど、そこをのみなむ、かかるほどより明け暮れ見し。されば、思ひわたさるるにやあらむ。いとよくこそおぼえたれ。いと小さきほどは、皆かくのみあるわざにやあらむ」 |
「御子たち、大勢いるが、そなただけを、このように小さい時から明け暮れ見てきた。
それゆえ、
思い出されるのだろうか
。とてもよく似て見える。とても幼いうちは皆このよう
|
「私は子供がたくさんあるが、おまえだけをこんなに小さい時から毎日見た。だから同じように思うのかよく似た気がする。小さい間は皆こんなものだろうか」
|
【御子たち、あまたあれど】- 以下「皆かくのみあるわざにやあらむ」まで、帝の詞。
【そこをのみなむ】- 「そこ」は源氏をさしていう。
|
| 3.3.4 |
|
と言って、たいそうかわいらしいとお思い申し上げあそばされている。
|
とお言いになって、非常にかわいくお思いになる様子が拝された。
|
【思ひきこえさせたまへり】- 「きこえ」(謙譲の補助動詞、帝の若宮に対する敬意)「させ」(尊敬の助動詞)「たまへ」(尊敬の補助動詞、帝に対する最高敬語)。
|
| 3.3.5 |
|
中将の君は、顔色が変っていく心地がして、恐ろしくも、かたじけなくも、嬉しくも、哀れにも、あちこちと揺れ動く思いで、涙が落ちてしまいそうである。
お声を上げたりして、にこにこしていらっしゃる様子が、とても恐いまでにかわいらしいので、自分ながら、この宮に似ているのは大変にもったいなくお思いになるとは、身贔屓に過ぎるというものであるよ。
宮は、どうにもいたたまれない心地がして、冷汗をお流しになっているのであった。
中将は、かえって複雑な思いが、乱れるようなので、退出なさった。
|
源氏は顔の色も変わる気がしておそろしくも、もったいなくも、うれしくも、身にしむようにもいろいろに思って涙がこぼれそうだった。ものを言うようなかっこうにお口をお動かしになるのが非常にお美しかったから、自分ながらもこの顔に似ているといわれる顔は尊重すべきであるとも思った。宮はあまりの片腹痛さに汗を流しておいでになった。源氏は若宮を見て、また予期しない父性愛の心を乱すもののあるのに気がついて退出してしまった。
|
【面の色変はる心地して】- 『完訳』は「帝の歓喜と愛情の言辞が、源氏の心に緊張と興奮の渦を誘発する。「恐ろしうも」以下の情念の動きにその複雑な葛藤が語られる」と注す。
【恐ろしうも、かたじけなくも、うれしくも、あはれにも、かたがた移ろふ心地して】- 相反する感情の相剋。『集成』は「「うれしくも、あはれにも(胸を締めつけられるようにも)」は、わが子である若宮に対する気持、前の「恐ろしうも、かたじけなくも」は帝に対する気持」と解す。
【涙落ちぬべし】- 『集成』は「涙が落ちそうだ。源氏の主観的な気持をそのまま地の文とした叙法で、作者のよく用いるところである」と注す。
【もの語りなどして】- 若宮が声を上げること。
【わが身ながら、これに似たらむはいみじういたはしうおぼえたまふ】- 『集成』は「この若宮に似ているのなら大層大切なものだという気持におなりになるのは」と解し、『完訳』は「自分がそのままこの若宮に似ているのだとしたら、この身をよほど大事にいたわらねば、というお気持になられるが」と解す。
【あながちなるや】- 語り手の評言。『休聞抄』は「双也」と指摘、『完訳』は「身びいきだ、とする語り手の評。この評言によって源氏を読者の非難から守りつつ、源氏--若宮の血脈に注目させる」と注す。
【中将は、なかなかなる心地の】- 源氏の中将は若宮を拝見してかえっての意。
|
| 3.3.6 |
|
ご自邸でお臥せりになって、「胸のどうにもならない悩みが収まってから、大殿へ出向こう」とお思いになる。
お庭先の前栽が、どことなく青々と見渡される中に、常夏の花がぱあっと色美しく咲き出しているのを、折らせなさって、命婦の君のもとに、お書きになること、多くあるようだ。
|
源氏は二条の院の東の対に帰って、苦しい胸を休めてから後刻になって左大臣家へ行こうと思っていた。前の庭の植え込みの中に何木となく、何草となく青くなっている中に、目だつ色を作って咲いた撫子を折って、それに添える手紙を長く王命婦へ書いた。
|
【わが御かたに臥したまひて】- 場面は変わって、源氏の二条院の東の対。
【御前の前栽の、何となく青みわたれるなかに、常夏のはなやかに咲き出でたるを、折らせたまひて】- 「常夏」は「撫子」ともいう。「なつ」は「懐かしい」を連想させる。常夏の花が咲き出したという風景描写は、若宮、すなわち慕わしいわが子が産まれたという源氏の心象風景。 【御前の前栽】-大島本「おまえのせむさい」と表記する。「平安時代はセンサイと清音」(岩波古語辞典)。『集成』『古典セレクション』『新大系』は「せんざい」と濁音表記する。
【命婦の君のもとに、書きたまふこと、多かるべし】- 語り手の推測。『細流抄』は「草子地也」と指摘。
|
| 3.3.7 |
|
「思いよそえて見ているが、
気持ちは慰まず涙を催させる撫子
|
よそへつつ見るに心も慰まで
|
【よそへつつ見るに心はなぐさまで--露けさまさる撫子の花】- 源氏の藤壺への贈歌。『花鳥余情』は「よそへつつ見れど露だに慰まずいかがはすべきなでしこの花」(新古今集、雑上、一四九四、恵子女王)を指摘。「よそへつつ見る」は意味深長な表現。「撫子の花」を「若宮によそへつつ見る」、また「帝のお子と思って拝しているが、実はわが子であると思うと」。
|
| 3.3.8 |
|
花と咲いてほしい、と存じておりましたが、効ない二人の仲でしたので」
|
露けさまさる撫子の花
花を子のように思って愛することはついに不可能であることを知りました。
|
【花に咲かなむ、と】- 以下「世にはべりければ」まで、歌に添えた言葉。『集成』『完訳』は「我が宿の垣根に植ゑし撫子は花に咲かなむよそへつつ見む」(後撰集、夏、一九九、読人しらず)を引歌として指摘。『集成』は「(この撫子の花のように)若宮がお生まれになったらと思いましたが、そうなってもどうにもならない二人の仲でございましたので」と解す。
|
|
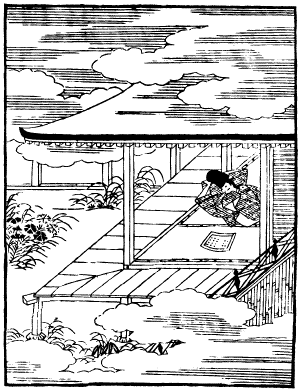 |
| 3.3.9 |
|
とある。
ちょうど人のいない時であったのであろうか、御覧に入れて、
|
とも書かれてあった。だれも来ぬ隙があったか命婦はそれを宮のお目にかけて、
|
【さりぬべき隙にやありけむ】- 語り手の挿入句。「さ」は、都合のよい機会をさす。「隙」は人のいない間。
|
| 3.3.10 |
|
「ほんの塵ほどでも、この花びらに」
|
「ほんの塵ほどのこのお返事を書いてくださいませんか。この花片にお書きになるほど、少しばかり」
|
【ただ塵ばかり、この花びらに】- 王命婦の藤壺への詞。『紹巴抄』は「塵をだに据ゑじとぞ思ふ咲きしよりいもとわがぬる常夏の花」(古今集、夏、一六七 、凡河内躬恒)を指摘。「ほんの少しでも、この手紙に返事を」という意。それを古歌の文句を踏まえた雅な表現をしたもの。
|
| 3.3.11 |
と聞こゆるを、わが御心にも、ものいとあはれに思し知らるるほどにて、
|
と申し上げるが、ご本人にも、もの悲しく思わずにはいらっしゃれない時なので、
|
と申し上げた。宮もしみじみお悲しい時であった。
|
|
| 3.3.12 |
|
「袖を濡らしている方の縁と思うにつけても
やはり疎ましくなってしまう大和撫子です」
|
袖濡るる露のゆかりと思ふにも
ふにもなほうとまれぬやまと撫子
|
【袖濡るる露のゆかりと思ふにも--なほ疎まれぬ大和撫子】- 藤壺の源氏への返歌。「袖濡るる」は「露けさまさる」と詠んでよこした源氏の袖をいう。「露のゆかり」は若宮があなたの子であるという意をこめる。『集成』は、「あなたのお袖の濡れる露に縁のあるもの(悲しんでおられるあなたのお子)と思うにつけても、やはり大和撫子(このお子)をいとしむ気にはなれません」と解し、『完訳』は「「ぬ」は完了の意。打消とする一説はとらない。「なほ--」で、一面には、若宮をいとおしむ気持」と注して、「このやまとなでしこ--若宮があなたのお袖を濡らす涙のゆかりと思うにつけても、やはりこれをいとおしむ気にはなれません」と訳す。この子が源氏の子であると思うと、やはり疎ましい気持ちが生じずにはいない、という真情を吐露した歌。しかし、藤壺がわが子を真底に「なほ疎まれぬ」と思っているわけではあるまい。「ぬ」を打消の助動詞と解せば、「疎むことのできないわが子」の意になり、藤壺のわが子をいとおしむ気持ちの表出になる。この感情は矛盾するものではない。源氏に対しては「いとおしむ気にはなれない」という一方で、わが子は「いとおしい」という。この歌を受け取った源氏もその両意に解したろう。
|
| 3.3.13 |
|
とだけ、かすかに中途で書き止めたような歌を、喜びながら差し上げたが、「いつものことで、返事はあるまい」と、力なくぼんやりと臥せっていらっしゃったところに、胸をときめかして、たいそう嬉しいので、涙がこぼれた。
|
とだけ、ほのかに、書きつぶしのもののように書かれてある紙を、喜びながら命婦は源氏へ送った。例のように返事のないことを予期して、なおも悲しみくずおれている時に宮の御返事が届けられたのである。胸騒ぎがしてこの非常にうれしい時にも源氏の涙は落ちた。
|
【よろこびながらたてまつれる】- 主語は王命婦、珍しく返歌をいただけたので。
【例のことなれば、しるしあらじかし】- 源氏の心。
|
|
第四段 源氏、紫の君に心を慰める
|
| 3.4.1 |
|
つくづくと物思いに沈んでいても、晴らしようのない気持ちがするので、いつものように、気晴らしには西の対にお渡りになる。
|
じっと物思いをしながら寝ていることは堪えがたい気がして、例の慰め場所西の対へ行って見た。
|
【つくづくと臥したるにも】- 源氏、西の対に行き、紫の君に心を慰める。
【例の、慰めには西の対にぞ渡りたまふ】- 紫の君のいる西の対。主語は源氏。紫の君は、源氏にとって、藤壺に対する気持ちの「慰め」の存在。
|
| 3.4.2 |
|
取り繕わないで毛羽だっていらっしゃる鬢ぐき、うちとけた袿姿で、笛を慕わしく吹き鳴らしながら、お立ち寄りになると、女君、先程の花が露に濡れたような感じで、寄り臥していらっしゃる様子、かわいらしく可憐である。
愛嬌がこぼれるようで、おいでになりながら早くお渡り下さらないのが、何となく恨めしかったので、いつもと違って、すねていらっしゃるのであろう。
端の方に座って、
|
少し乱れた髪をそのままにして部屋着の袿姿で笛を懐しい音に吹きながら座敷をのぞくと、紫の女王はさっきの撫子が露にぬれたような可憐なふうで横になっていた。非常に美しい。こぼれるほどの愛嬌のある顔が、帰邸した気配がしてからすぐにも出て来なかった源氏を恨めしいと思うように向こうに向けられているのである。座敷の端のほうにすわって、
|
【しどけなくうちふくだみたまへる鬢ぐき、あざれたる袿姿にて】- 源氏の藤壺に対する物思いにやつれた姿。
【女君、ありつる花の露に濡れたる心地して】- 「女君」は紫の君をいう。初めて「女君」という呼称がなされる。これまでは「若草」「幼き人」「姫君」などと呼称されてきた。「ありつる花」は常夏の花。『集成』は「源氏に対してやや怨みを含んだていの艶な姿態の形容である」と注す。
【愛敬こぼるるやうにて】- 紫の君の姿態をいう。
【おはしながら】- 主語は源氏。お帰りになりながらの意。『完訳』は以下「なるへし」まで、挿入句と解す。その訳文を見ると、「愛敬こぼるるやうにて」が挿入句全体に掛かるように訳されている。
【例ならず、背きたまへるなるべし】- 「なる」(断定の助動詞)「べし」(推量の助動詞)は、語り手の推測を交えた挿入句。
|
| 3.4.3 |
|
「こちらへ」
|
「こちらへいらっしゃい」
|
【こちや】- 源氏の詞。こちらへの意。
|
| 3.4.4 |
とのたまへど、おどろかず、
|
とおっしゃるが、素知らぬ顔で、
|
と言っても素知らぬ顔をしている。
|
|
| 3.4.5 |
|
「お目にかかることが少なくて」
|
「入りぬる磯の草なれや」(みらく少なく恋ふらくの多き)
|
【入りぬる磯の」--と口ずさみて】- 大島本「くちすさみて」とある。『古典セレクション』は諸本に従って「口すさびて」と校訂する。『集成』『新大系』は底本のまま「口ずさみて」とする。「くちすさみ(口遊み) 室町末期クチズサミとも」(岩波古語辞典)。『源氏釈』は「潮満てば入りぬる磯の草なれや見らく少なく恋ふらくの多き」(拾遺集、恋五、九六七、坂上郎女)を指摘、原歌は『万葉集』。その第二句の文句。紫の君は、磯の草のように、逢うことが少ないという不満の気持ちを訴えた。
|
| 3.4.6 |
|
と口ずさんで、口を覆っていらっしゃる様子、たいそう色っぽくてかわいらしい。
|
と口ずさんで、袖を口もとにあてている様子にかわいい怜悧さが見えるのである。
|
|
| 3.4.7 |
|
「まあ、憎らしい。
このようなことをおっしゃるようになりましたね。
みるめに人を飽きるとは、良くないことですよ」
|
「つまらない歌を歌っているのですね。始終見ていなければならないと思うのはよくないことですよ」
|
【あな、憎】- 以下「まさなきことぞよ」まで、源氏の詞。
【みるめに飽くは】- 『源氏釈』は「伊勢のあまの朝な夕なにかづくてふみるめに人をあくよしもがな」(古今集、恋四、六八三、読人しらず)を指摘、現行の注釈書でも引歌として指摘。『集成』は「しょっちゅう逢ってるなんてお行儀の悪いことなのですよ」の意と注す。
|
| 3.4.8 |
とて、人召して、御琴取り寄せて弾かせたてまつりたまふ。
|
と言って、人を召して、お琴取り寄せてお弾かせ申し上げなさる。
|
源氏は琴を女房に出させて紫の君に弾かせようとした。
|
|
| 3.4.9 |
|
「箏の琴は、中の細緒が切れやすいのが厄介だ」
|
「十三絃の琴は中央の絃の調子を高くするのはどうもしっくりとしないものだから」
|
【箏の琴は】- 以下「ところせけれ」まで、源氏の詞。
|
| 3.4.10 |
|
と言って、平調に下げてお調べになる。
調子合わせの小曲だけ弾いて、押しやりなさると、いつまでもすねてもいられず、とてもかわいらしくお弾きになる。
|
と言って、柱を平調に下げて掻き合わせだけをして姫君に与えると、もうすねてもいず美しく弾き出した。
|
【かき合はせばかり弾きて】- 主語は源氏。琴の調子合わせのための小曲。
【さしやりたまへれば】- 源氏が箏の琴を紫の君の前に差し出すとの意。
|
| 3.4.11 |
|
お小さいからだで、左手をさしのべて、弦を揺らしなさる手つき、とてもかわいらしいので、愛しいとお思いになって、笛吹き鳴らしながらお教えになる。
とても賢くて難しい調子などを、たった一度で習得なさる。
何事につけても才長けたご性格を、「期待していた通りである」とお思いになる。
「保曽呂具世利」という曲目は、名前は嫌だが、素晴らしくお吹きになると、合奏させて、まだ未熟だが、拍子を間違えず上手のようである。
|
小さい人が左手を伸ばして絃をおさえる手つきを源氏はかわいく思って、自身は笛を吹きながら教えていた。頭がよくてむずかしい調子などもほんの一度くらいで習い取った。何ごとにも貴女らしい素質の見えるのに源氏は満足していた。保曾呂倶世利というのは変な名の曲であるが、それをおもしろく笛で源氏が吹くのに、合わせる琴の弾き手は小さい人であったが音の間が違わずに弾けて、上手になる手筋と見えるのである。
|
【さしやりて、ゆしたまふ御手つき】- 「揺す」は、左手で絃を押えゆすって、音を響かせること。
【笛吹き鳴らしつつ教へたまふ】- 主語は源氏。『完訳』は「つつ」を「笛を吹き鳴らし吹き鳴らしして」と訳す。
【らうらうじう】- 大島本「らう/\しう」とある。『古典セレクション』は諸本に従って「らうらうじく」と校訂する。『集成』『新大系』は底本のままウ音便形。
【思ひしことかなふ】- 源氏の心。
【保曾呂惧世利】- 高麗壱越調の曲。
【吹きすさび】- 大島本と池田本は「ふきすさひ」とある。横山本は「ふきすまし」の「すまし」をミセケチにする。榊原家本、陽明文庫本、肖柏本、三条西家本、書陵部本は「ふきすまし」(吹き澄まし)とある。なお河内本は「吹すまし」、別本の御物本は「ふきすまし〔すまし-補入〕」とある。青表紙本は最初「吹きすさひ」とあったのが、後に「吹き澄まし」と訂正されたものか。それはしかも定家自身によってなされたものであろうか。『集成』『新大系』は「吹きすさび」、『古典セレクション』は「吹きすまし」と改訂する。
【拍子】- 大島本、榊原家本、池田本は「はうし」と表記。横山本と陽明文庫本は「ひやうし」と表記。肖柏本と三条西家本と書陵部本は「拍子」と漢字表記。
|
| 3.4.12 |
大殿油参りて、絵どもなど御覧ずるに、「出でたまふべし」とありつれば、人びと声づくりきこえて、
|
大殿油を燈して、絵などを御覧になっていると、「お出かけになる予定」とあったので、供人たちが咳払いし合図申して、
|
灯を点させてから絵などをいっしょに見ていたが、さっき源氏はここへ来る前に出かける用意を命じてあったから、供をする侍たちが促すように御簾の外から、
|
|
| 3.4.13 |
|
「雨が降って来そうでございます」
|
「雨が降りそうでございます」
|
【雨降りはべりぬべし】- 供人の詞。
|
| 3.4.14 |
など言ふに、姫君、例の、心細くて屈したまへり。絵も見さして、うつぶしておはすれば、いとらうたくて、御髪のいとめでたくこぼれかかりたるを、かき撫でて、 |
などと言うので、姫君、いつものように心細くふさいでいらっしゃった。
絵を見ることも止めて、うつ伏していらっしゃるので、とても可憐で、お髪がとても見事にこぼれかかっているのを、かき撫でて、
|
などと言うのを聞くと、紫の君はいつものように心細くなってめいり込んでいった。絵も見さしてうつむいているのがかわいくて、こぼれかかっている美しい髪をなでてやりながら、
|
【姫君】- 紫の君。再び「姫君」の呼称に戻る。その幼さが強調される。
|
| 3.4.15 |
|
「出かけている間は寂しいですか」
|
「私がよそに行っている時、あなたは寂しいの」
|
【他なるほどは恋しくやある】- 源氏の詞。
|
| 3.4.16 |
|
とおっしゃると、こっくりなさる。
|
と言うと女王はうなずいた。
|
【うなづきたまふ】- 主語は紫の君。
|
| 3.4.17 |
「我も、一日も見たてまつらぬはいと苦しうこそあれど、幼くおはするほどは、心やすく思ひきこえて、まづ、くねくねしく怨むる人の心破らじと思ひて、むつかしければ、しばしかくもありくぞ。おとなしく見なしては、他へもさらに行くまじ。人の怨み負はじなど思ふも、世に長うありて、思ふさまに見えたてまつらむと思ふぞ」 |
「わたしも、一日もお目にかからないでいるのは、とてもつらいことですが、お小さくいらっしゃるうちは、気安くお思い申すので、まず、ひねくれて嫉妬する人の機嫌を損ねまいと思って、うっとうしいので、暫く間はこのように出かけるのですよ。
大人におなりになったら、他の所へは決して行きませんよ。
人の嫉妬を受けまいなどと思うのも、長生きをして、思いのままに一緒にお暮らし申したいと思うからですよ」
|
「私だって一日あなたを見ないでいるともう苦しくなる。けれどあなたは小さいから私は安心していてね、私が行かないといろいろな意地悪を言っておこる人がありますからね。今のうちはそのほうへ行きます。あなたが大人になれば決してもうよそへは行かない。人からうらまれたくないと思うのも、長く生きていて、あなたを幸福にしたいと思うからです」
|
【我も】- 以下「見えたてまつらむと思ふぞ」まで、源氏の詞。
【あれど】- 大島本は「△(△#あ△、△#)れと」と「△(さカ)」を墨滅して「あ」と訂正、「あ」の下に一文字あったが、墨滅されて判読不能。その他の諸本は「されと」とある。河内本や別本の御物本も「されと」とある。大島本の訂正が他の青表紙諸本に継承されてないことは、後人の訂正によるものか。『集成』『古典セレクション』は「されと」と改訂する。『新大系』は訂正後の「あれど」を採用する。
【おとなしく見なしては】- 『集成』は清音「は」(係助詞)に読み、「あなたが大人になられてからは、よそへも全然ゆきませんよ」と解す。『古典セレクション』『新大系』は濁音「ば」(接続助詞)に読み、順接の仮定条件、「あなた(紫の上)が大人になったと、はっきり分ったならば」(古典セレクション)「あなたが成人したとわかったら、の意」(新大系)と解す。
|
| 3.4.18 |
など、こまごまと語らひきこえたまへば、さすがに恥づかしうて、ともかくもいらへきこえたまはず。
やがて御膝に寄りかかりて、寝入りたまひぬれば、いと心苦しうて、
|
などと、こまごまとご機嫌をお取り申されると、そうは言うものの恥じらって、何ともお返事申し上げなされない。
そのままお膝に寄りかかって、眠っておしまになったので、とてもいじらしく思って、
|
などとこまごま話して聞かせると、さすがに恥じて返辞もしない。そのまま膝に寄りかかって寝入ってしまったのを見ると、源氏はかわいそうになって、
|
|
| 3.4.19 |
|
「今夜は出かけないことになった」
|
「もう今夜は出かけないことにする」
|
【今宵は出でずなりぬ】- 源氏の詞。
|
| 3.4.20 |
とのたまへば、皆立ちて、御膳などこなたに参らせたり。姫君起こしたてまつりたまひて、 |
とおっしゃると、皆立ち上がって、御膳などをこちらに運ばせた。
姫君を起こしてさし上げにさって、
|
と侍たちに言うと、その人らはあちらへ立って行って。間もなく源氏の夕飯が西の対へ運ばれた。源氏は女王を起こして、
|
【皆立ちて】- 『集成』は「供人は皆引き上げて」の意に解し、『完訳』は「女房どもがみな座を立ち」の意に解す。どちらとも決めがたい。両意あるであろう。
|
| 3.4.21 |
|
「出かけないことになった」
|
「もう行かないことにしましたよ」
|
【出でずなりぬ】- 源氏の紫の君への詞。
|
| 3.4.22 |
と聞こえたまへば、慰みて起きたまへり。
もろともにものなど参る。
いとはかなげにすさびて、
|
とお話し申し上げなさると、機嫌を直してお起きになった。
ご一緒にお食事を召し上がる。
ほんのちょっとお箸を付けになって、
|
と言うと慰んで起きた。そうしていっしょに食事をしたが、姫君はまだはかないようなふうでろくろく食べなかった。
|
|
| 3.4.23 |
|
「では、お寝みなさい」
|
「ではお寝みなさいな」
|
【さらば、寝たまひねかし】- 紫の君の心。
|
| 3.4.24 |
|
と不安げに思っていらっしゃるので、このような人を放ってはどんな道であっても出かけることはできない、と思われなさる。
|
出ないということは嘘でないかと危ながってこんなことを言うのである。こんな可憐な人を置いて行くことは、どんなに恋しい人の所があってもできないことであると源氏は思った。
|
【かかるを見捨てては、いみじき道なりとも、おもむきがたく】- 源氏の心。心中文が地の文に続いた構文。「いみじき道」は死出の旅路をさす。
|
| 3.4.25 |
|
このように、引き止められなさる時々も多くあるのを、自然と漏れ聞く人が、大殿にも申し上げたので、
|
こんなふうに引き止められることも多いのを、侍などの中には左大臣家へ伝える者もあってあちらでは、
|
【かやうに】- 大島本「かやうに」とある。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「かうやうに」と校訂する。『新大系』は底本のまま。
【おのづから漏り聞く人、大殿に聞こえければ】- 自然と耳にする人が左大臣家に申し上げたので、の意。
|
| 3.4.26 |
|
「誰なのでしょう。
とても失礼なことではありませんか」
|
「どんな身分の人でしょう。失礼な方ですわね。
|
【誰れならむ】- 以下「聞こゆるは」まで、左大臣邸の女房の詞。複数の人々の詞と解す。
|
| 3.4.27 |
「今までその人とも聞こえず、さやうにまつはしたはぶれなどすらむは、あてやかに心にくき人にはあらじ」
|
「今まで誰それとも知れず、そのようにくっついたまま遊んだりするような人は、上品な教養のある人ではありますまい」
|
二条の院へどこのお嬢さんがお嫁きになったという話もないことだし、そんなふうにこちらへのお出かけを引き止めたり、またよくふざけたりしていらっしゃるというのでは、りっぱな御身分の人とは思えないじゃありませんか。
|
|
| 3.4.28 |
「内裏わたりなどにて、はかなく見たまひけむ人を、ものめかしたまひて、人やとがめむと隠したまふななり。心なげにいはけて聞こゆるは」 |
「宮中辺りで、ちょっと見初めたような女を、ご大層にお扱いになって、人目に立つかと隠していられるのでしょう。
分別のない幼稚な人だと聞きますから」
|
御所などで始まった関係の女房級の人を奥様らしく二条の院へお入れになって、それを批難さすまいとお思いになって、だれということを秘密にしていらっしゃるのですよ。幼稚な所作が多いのですって」
|
【隠したまふななり】- 「な」(断定の助動詞)「なり」(伝聞推定の助動詞)、隠しておいでなのでしょうの意。なお榊原家本は「かくし給なめり」(断定の助動詞+推量の助動詞)、陽明文庫本は「かくし給なり」(断定の助動詞)とある。
|
| 3.4.29 |
など、さぶらふ人びとも聞こえあへり。
|
などと、お仕えする女房たちも噂し合っていた。
|
などと女房が言っていた。
|
|
| 3.4.30 |
内裏にも、かかる人ありと聞こし召して、
|
お上におかれても、「このような女の人がいる」と、お耳に入れあそばして、
|
御所にまで二条の院の新婦の問題が聞こえていった。
|
|
| 3.4.31 |
|
「気の毒に、大臣がお嘆きということも、なるほど、まだ幼かったころを、一生懸命にこんなにお世話してきた気持ちを、それくらいのことをご分別できない年頃でもあるまいに。
どうして薄情な仕打ちをなさるのだろう」
|
「気の毒じゃないか。左大臣が心配しているそうだ。小さいおまえを婿にしてくれて、十二分に尽くした今日までの好意がわからない年でもないのに、なぜその娘を冷淡に扱うのだ」
|
【いとほしく】- 以下「もてなすなるらむ」まで、帝の詞。
【大臣の思ひ嘆かるなることも、げに、ものげなかりしほどを、おほなおほなかくものしたる心を、さばかりのことたどらぬほどにはあらじを。などか情けなくはもてなすなるらむ】- 大島本「おとゝの思ひなけかるなるなとのたまハすれと」とある。『集成』『古典セレクション』『新大系』は諸本によって末尾の「な」を削除して「こともげにものげなかりしほどをおほなおほなかくものしたる心をさばかりのことたどらぬほどにはあらじをなどか情けなくはもてなすなるらむ」を補う。大島本の脱文であろう。
|
| 3.4.32 |
|
と、仰せられるが、恐縮した様子で、お返事も申し上げられないので、「お気に入らないようだ」と、かわいそうにお思いあそばす。
|
と陛下がおっしゃっても、源氏はただ恐縮したふうを見せているだけで、何とも御返答をしなかった。帝は妻が気に入らないのであろうとかわいそうに思召した。
|
【かしこまりたるさまにて、御いらへも聞こえたまはねば】- 主語は源氏。恐縮したていであるが、何とも返事を申し上げない。
【心ゆかぬなめり】- 帝の心。源氏は葵の上が気に入ってないようであるの意。
|
| 3.4.33 |
「さるは、好き好きしううち乱れて、この見ゆる女房にまれ、またこなたかなたの人びとなど、なべてならずなども見え聞こえざめるを、いかなるもののくまに隠れありきて、かく人にも怨みらるらむ」とのたまはす。 |
「その一方では、好色がましく振る舞って、ここに見える女房であれ、またここかしこの女房たちなどと、浅からぬ仲に見えたり噂も聞かないようだが、どのような人目につかない所にあちこち隠れ歩いて、このように人に怨まれることをしているのだろう」と仰せられる。
|
「格別おまえは放縦な男ではなし、女官や女御たちの女房を情人にしている噂などもないのに、どうしてそんな隠し事をして舅や妻に恨まれる結果を作るのだろう」と仰せられた。
|
【さるは、好き好きしう】- 以下「人にも怨みらるらむ」まで、帝の詞。『集成』は「別の折に帝が側近にもらされた言葉である」と注す。『新大系』も「桐壺帝の言」と注す。『古典セレクション』は地の文と解し「「さるは」は、ここは逆接の用法で、とはいえ、の意。前述の推量から翻って、あらためて源氏について捉え直す」と注す。
|
|
第四章 源典侍の物語 老女との好色事件
|
|
第一段 源典侍の風評
|
| 4.1.1 |
|
帝のお年、かなりお召しあそばされたが、このような方面は、無関心ではいらっしゃれず、采女、女蔵人などの容貌や気立ての良い者を、格別にもてなしお目をかけあそばしていたので、教養のある宮仕え人の多いこの頃である。
ちょっとしたことでも、お話しかけになれば、知らない顔をする者はめったにいないので、見慣れてしまったのであろうか、「なるほど、不思議にも好色な振る舞いのないようだ」と、試しに冗談を申し上げたりなどする折もあるが、恥をかかせない程度に軽くあしらって、本気になってお取り乱しにならないのを、「真面目ぶってつまらない」と、お思い申し上げる女房もいる。
|
帝はもうよい御年配であったが美女がお好きであった。采女や女蔵人なども容色のある者が宮廷に歓迎される時代であった。したがって美人も宮廷には多かったが、そんな人たちは源氏さえその気になれば情人関係を成り立たせることが容易であったであろうが、源氏は見馴れているせいか女官たちへはその意味の好意を見せることは皆無であったから、怪しがってわざわざその人たちが戯談を言いかけることがあっても、源氏はただ冷淡でない程度にあしらっていて、それ以上の交際をしようとしないのを物足らず思う者さえあった。
|
【帝の御年、ねびさせたまひぬれど】- 以下、話変って、源氏と好色の源典侍との物語。
【采女、女蔵人などをも】- 大島本「うねへ女くら人なとをも」と表記する。「バ行子音bとマ行子音mとは交替する例が多いので、実際にはunemeと発音されたものであろう」(岩波古語辞典)。
【よしある宮仕へ人】- 『集成』は「気の利いた女房」と解し、『完訳』は「教養ある宮仕人」と解す。
【目馴るるにやあらむ】- 語り手の推測をはさんだ挿入句。『評釈』は「作者のつぶやきととるべきであろう。あるいは、宮仕人たちのつぶやきといってもよい。前者だと(中略)光る源氏が女にもてることを語りながらも、つい照れくさくて、作者は合の手を入れて呟いているのである」と指摘。
【げにぞ、あやしう好いたまはざめる】- 女房たちの源氏評。
【試みに戯れ事を聞こえかかりなどする】- 主語は女房。
【情けなからぬほどにうちいらへて】- 主語は源氏。
【まめやかにさうざうし】- 女房たちの源氏評。
|
| 4.1.2 |
|
年をたいそう取っている典侍、人柄も重々しく、才気があり、高貴で、人から尊敬されてはいるものの、たいそう好色な性格で、その方面では腰の軽いのを、「こう、年を取ってまで、どうしてそんなにふしだらなのか」と、興味深くお思いになったので、冗談を言いかけてお試しになると、不釣り合いなとも思わないのであった。
あきれた、とはお思いになりながら、やはりこのような女も興味があるので、お話しかけなどなさったが、人が漏れ聞いても、年とった年齢なので、そっけなく振る舞っていらっしゃるのを、女は、とてもつらいと思っていた。
|
よほど年のいった典侍で、いい家の出でもあり、才女でもあって、世間からは相当にえらく思われていながら、多情な性質であってその点では人を顰蹙させている女があった。源氏はなぜこう年がいっても浮気がやめられないのであろうと不思議な気がして、恋の戯談を言いかけてみると、不似合いにも思わず相手になってきた。あさましく思いながらも、さすがに風変わりな衝動を受けてつい源氏は関係を作ってしまった。噂されてもきまりの悪い不つりあいな老いた情人であったから、源氏は人に知らせまいとして、ことさら表面は冷淡にしているのを、女は常に恨んでいた。
|
【年いたう老いたる典侍】- 源典侍をいう。後文に「五十七、八の人」とある。
【人もやむごとなく】- 『集成』は「家柄も立派で」、『完訳』も「家柄も高く」と解す。
【心ばせあり】- 『古典セレクション』は諸本に従って「心ばせありて」と「て」を補入する。『集成』『新大系』は底本のままとする。
【かう、さだ過ぐるまで、などさしも乱るらむ】- 源氏の疑問。
【あさまし】- 源氏の驚き。
【古めかしきほどなれば】- 相手が老女なのでの意。
|
|
第二段 源氏、源典侍と和歌を詠み交わす
|
| 4.2.1 |
|
お上の御髪梳りに伺候したが、終わったので、お上は御袿係の者をお召しになってお出になりあそばした後に、他に人もなくて、この典侍がいつもよりこざっぱりとして、姿形、髪の具合が艶っぽくて、衣装や、着こなしも、とても派手に洒落て見えるのを、「何とも若づくりな」と、苦々しく御覧になる一方で、「どんな気でいるのか」と、やはり見過ごしがたくて、裳の裾を引っ張って注意をお引きになると、夏扇に派手な絵の描いてあるのを、顔を隠して振り返ったまなざし、ひどく流し目を使っているが、目の皮がげっそり黒く落ち込んで、肉が削げ落ちてたるんでいる。
|
典侍は帝のお髪上げの役を勤めて、それが終わったので、帝はお召かえを奉仕する人をお呼びになって出てお行きになった部屋には、ほかの者がいないで、典侍が常よりも美しい感じの受け取れるふうで、頭の形などに艶な所も見え、服装も派手にきれいな物を着ているのを見て、いつまでも若作りをするものだと源氏は思いながらも、どう思っているだろうと知りたい心も動いて、後ろから裳の裾を引いてみた。はなやかな絵をかいた紙の扇で顔を隠すようにしながら見返った典侍の目は、瞼を張り切らせようと故意に引き伸ばしているが、黒くなって、深い筋のはいったものであった。
|
【主上の御梳櫛にさぶらひけるを】- 主語は源典侍。
【好ましげに見ゆるを】- 『集成』は「しゃれて」と注すが、『完訳』は「見るからに好色者の感じ」と注す。
【さも古りがたうも】- 源氏の感想。
【いかが思ふらむ】- 源氏の心。
【かはぼり】- 『名義抄』に「蝙蝠 カハボリ」とある。『古典セレクション』は「かはほり」と清音に読んでいる。
【えならず画きたるを】- 『集成』は「見事に」と注し、『完訳』は「ひどく派手に描いてあるのを」と注す。
【見延べたれど】- 流し目をつかう意。
【はつれそそけたり】- 『集成』は「肉がそげて皺だらけだ」と注すが、『完訳』は「乱れほつれた毛髪が、扇で隠しきれず、はみ出すさま」と注す。
|
|
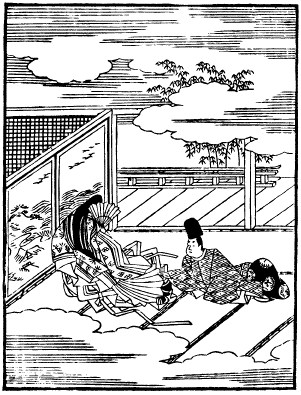 |
| 4.2.2 |
|
「似合わない派手な扇だな」と御覧になって、ご自分のお持ちのと取り替えて御覧になると、赤い紙で顔に照り返すような色合いで、木高い森の絵を金泥で塗りつぶしてある。
その端の方に、筆跡はとても古めかしいが、風情がなくもなく、「森の下草が老いてしまったので」などと書き流してあるのを、「他に書くことも他にあろうに、嫌らしい趣向だ」と微笑まれて、
|
妙に似合わない扇だと思って、自身のに替えて源典侍のを見ると、それは真赤な地に、青で厚く森の色が塗られたものである。横のほうに若々しくない字であるが上手に
|
【似つかはしからぬ扇のさまかな】- 源氏の心。
【塗り隠したり】- 大島本は「ぬりかへ(へ$く<朱>)したり」とある。横山本、榊原家本、陽明文庫本は「ぬりかへしたり」、池田本は「ぬりかへ(へ=く)したり」、肖柏本と三条西家本、書陵部本は「ぬりかくしたり」。河内本では七毫源氏、尾州家本、平瀬本は「ぬりかへしたり」、高松宮家本、大島本、一条兼良奥書本は「ぬりかくしたり」とある。別本の御物本は「ぬりかへしたり」とある。『集成』『新大系』は「ぬりかくしたり」、『古典セレクション』は「ぬりかへしたり」とするが、いずれも「金泥で塗りつぶして」「金泥で塗り隠して」と訳す。
【森の下草老いぬれば】- 「大荒木森の下草老いぬれば駒もすさめず刈る人もなし」(古今集、雑上、八九二、読人しらず)の第二句。年をとって誰も相手にしてくれないといった内容。
【ことしもあれ、うたての心ばへや】- 源氏の心中。他に書きようもあろうに、何と嫌らしいことを書いたものかの意。『完訳』は「源氏は、男ひでりを嘆く歌と読んだか」と注す。
|
| 4.2.3 |
|
「森こそ夏の、といったようですね」
|
「森の下草老いぬれば駒もすさめず刈る人もなし」
|
【森こそ夏の、と見ゆめる】- 源氏の詞。『集成』は「源氏釈」所引の「ひまもなく茂りにけりな大荒木森こそ夏の蔭はしるけれ」(出典未詳)を指摘し、「立ち寄ってもよさそうな森ではないか、と、扇の絵の批評にかこつけての皮肉」と注す。『完訳』は「時鳥来鳴くを聞けば大荒木森こそ夏の宿りなるらし」(信明集)を指摘し、「典侍の所は多くの男たちがの泊る宿、の寓意で用いた」と注す。両義あると見てよいだろう。
|
| 4.2.4 |
とて、何くれとのたまふも、似げなく、人や見つけむと苦しきを、女はさも思ひたらず、 |
と言って、いろいろとおっしゃるのも、不釣り合いで、人が見つけるかと気になるが、女はそうは思っていない。
|
という歌が書かれてある。厭味な恋歌などは書かずともよいのにと源氏は苦笑しながらも、「そうじゃありませんよ、『大荒木の森こそ夏のかげはしるけれ』で盛んな夏ですよ」こんなことを言う恋の遊戯にも不似合いな相手だと思うと、源氏は人が見ねばよいがとばかり願われた。女はそんなことを思っていない。
|
【人や見つけむ】- 源氏の心配。
|
| 4.2.5 |
|
「あなたがいらしたならば良く馴れた馬に秣を刈ってやりましょう
盛りの過ぎた下草であっても」
|
君し来ば手馴れの駒に刈り飼はん
盛り過ぎたる下葉なりとも
|
【君し来ば手なれの駒に刈り飼はむ--盛り過ぎたる下葉なりとも】- 源典侍の贈歌。『花鳥余情』は「我が門のひとむら薄刈り飼はむ君が手馴れの駒も来ぬかな」(後撰集、恋二、六一七、小町が姉)を指摘。「君」は源氏をさし、自分を「下葉」に譬える。歓待しましょうの意。
|
| 4.2.6 |
|
と詠み出す様子、この上なく色気たっぷりである。
|
とても色気たっぷりな表情をして言う。
|
【こよなく色めきたり】- 語り手の感想を交えた表現である。
|
| 4.2.7 |
|
「笹を分けて入って行ったら人が注意しましょう
いつでも馬を懐けている森の木陰では
|
「笹分けば人や咎めんいつとなく
駒馴らすめる森の木隠れ
|
【笹分けば人やとがめむいつとなく--駒なつくめる森の木隠れ】- 源氏の返歌。『花鳥余情』は「笹分けば荒れこそ増さめ草枯れの駒なつくべき森の下かは」(蜻蛉日記)を指摘。「笹分けば」の主語は自分、「駒」は他の男性を、「森の下」は相手の源典侍を喩える。
|
| 4.2.8 |
|
厄介なことだからね」
|
あなたの所はさしさわりが多いからうっかり行けない」
|
【わづらはしさに】- 歌に添えた詞。
|
| 4.2.9 |
とて、立ちたまふを、ひかへて、
|
と言って、お立ちになるのを、袖を取って、
|
こう言って、立って行こうとする源氏を、典侍は手で留めて、
|
|
| 4.2.10 |
|
「まだこんなつらい思いをしたことはございません。
今になって、身の恥に」
|
「私はこんなにまで煩悶をしたことはありませんよ。すぐ捨てられてしまうような恋をして一生の恥をここでかくのです」
|
【まだかかるものをこそ】- 以下「身の恥になむ」まで、源典侍の詞。『花鳥余情』は「黒髪に白髪まじり老ゆるまでかかる恋にはいまだあはなくに」(拾遺集、恋五、九六六、坂上郎女、原歌は万葉集巻四)を指摘。
|
| 4.2.11 |
とて泣くさま、いといみじ。
|
と言って泣き出す様子、とても大げさである。
|
非常に悲しそうに泣く。
|
|
| 4.2.12 |
|
「そのうち、
お便りを差し上げましょ
|
「近いうちに必ず行きます。いつもそう思いながら実行ができないだけですよ」
|
【いま、聞こえむ。思ひながらぞや】- 源氏の返事。『完訳』は「限りなく思ひながらの橋柱思ひながらに中や絶えなむ」(拾遺集、恋四、八〇四、読人しらず)を引歌として指摘。
|
| 4.2.13 |
とて、引き放ちて出でたまふを、せめておよびて、「橋柱」と怨みかくるを、主上は御袿果てて、御障子より覗かせたまひけり。「似つかはしからぬあはひかな」と、いとをかしう思されて、 |
と言って、振り切ってお出になるのを、懸命に取りすがって、「橋柱」と恨み言を言うのを、お上はお召し替えが済んで、御障子の隙間から御覧あそばしたのであった。
「似つかわしくない仲だな」と、とてもおかしく思し召されて、
|
袖を放させて出ようとするのを、典侍はまたもう一度追って来て「橋柱」(思ひながらに中や絶えなん)と言いかける所作までも、お召かえが済んだ帝が襖子からのぞいておしまいになった。不つり合いな恋人たちであるのを、おかしく思召してお笑いになりながら、帝は、
|
【橋柱】- 源典侍の詞。源氏が「思いながら」と言ったことから、「長柄の橋」を連想し、それから「橋柱」と言ったもの。『源氏釈』は「思ふこと昔ながらの橋柱ふりぬる身こそ悲しけれ」(新勅撰集、雑四、一二八五、読人しらず)を指摘。『完訳』も出典を『一条摂政御集』として同歌を指摘し、「嘆老を源氏に訴える」と注す。『集成』は「限りなく思ひながらの橋柱思ひながらに中や絶えなむ」(拾遺集、恋四、八〇四、読人しらず)を引歌として指摘し、「そんなことをおっしゃって、このまま切れてしまおうというおつもりですか」と注す。いずれにしても、源典侍の嘆老と切実な訴えが窺える。
【似つかはしからぬあはひかな】- 帝の感想。
|
| 4.2.14 |
|
「好色心がないなどと、いつも困っているようだが、そうは言うものの、見過ごさなかったのだな」
|
「まじめ過ぎる恋愛ぎらいだと言っておまえたちの困っている男もやはりそうでなかったね」
|
【好き心なしと】- 以下「過ぐさざりけるは」まで、帝の詞。
|
| 4.2.15 |
|
と言って、お笑いあそばすので、典侍はばつが悪い気がするが、恋しい人のためなら、濡衣をさえ着たがる類もいるそうだからか、大して弁解も申し上げない。
|
と典侍へお言いになった。典侍はきまり悪さも少し感じたが、恋しい人のためには濡衣でさえも着たがる者があるのであるから、弁解はしようとしなかった。
|
【なままばゆけれど】- 大島本「なまゝはゆけれと」とある。『古典セレクション』は諸本に従って「なまはゆけれど」と校訂する。『集成』『新大系』は底本のままとする。
【憎からぬ人ゆゑは、濡衣をだに着まほしがる】- 『源氏釈』は「憎からぬ人の着せけむ濡れ衣は思ひにあへず今乾きなむ」(後撰集、恋五、六五七、中将内侍)を指摘。『集成』は『古今六帖』五の「憎からぬ人の着すなる濡衣はいとひがたくも思ほゆるかな」を引歌として指摘し、「厭ひがたく」と「いと干がたく」を掛けると注す。
【あらがひきこえさせず】- 主語は源典侍。「聞こえさす」は「聞こゆ」よりさらに謙った謙譲語。
|
| 4.2.16 |
|
女房たちも、「意外なことだわ」と、取り沙汰するらしいのを、頭中将、聞きつけて、「知らないことのないこのわたしが、まだ気がつかなかったことよ」と思うと、いくつになっても止まない好色心を見たく思って、言い寄ったのであった。
|
それ以後御所の人たちが意外な恋としてこの関係を噂した。頭中将の耳にそれがはいって、源氏の隠し事はたいてい正確に察して知っている自分も、まだそれだけは気がつかなんだと思うとともに、自身の好奇心も起こってきて、まんまと好色な源典侍の情人の一人になった。
|
【思ひのほかなることかな】- 女房たちの意外な驚き。
【至らぬ隈なき心にて、まだ思ひ寄らざりけるよ】- 頭中将の心中。
【尽きせぬ好み心】- 源典侍のいくつになってもやまない好色心をいう。
【語らひつきにけり】- 主語は頭中将。
|
| 4.2.17 |
|
この君も、人よりは素晴らしいので、「あのつれない方の気晴らしに」と思ったが、本当に逢いたい人は、お一人であったとか。
大変な選り好みだことよ。
|
この貴公子もざらにある若い男ではなかったから、源氏の飽き足らぬ愛を補う気で関係をしたが、典侍の心に今も恋しくてならない人はただ一人の源氏であった。困った多情女である。
|
【この君も】- 頭中将をさす。『湖月抄』所引師説は以下「草子地也」と指摘。
【かのつれなき人】- 源氏をさす。
【見まほしきは、限りありけるをとや】- 『孟津抄』は「草子地也」と指摘、『完訳』は「逢いたいのは源氏だけだとか。以下、語り手の感想をこめた叙述」と注す。
【うたての好みや】- 『明星抄』は「草子地に見るへきにや」と指摘し、『評釈』は「作者の合の手批評である」、『全集』は「老女の度外れた好色への、語り手の評言」、『集成』は「とんでもない選り好みだこと。草子地である。お婆さんのくせに贅沢な、という諧謔」と注す。
|
|
第三段 温明殿付近で密会中、頭中将に発見され脅される
|
| 4.3.1 |
|
たいそう秘密にしているので、源氏の君はご存知ない。
お見かけ申しては、まず恨み言を申すので、お年の程もかわいそうなので、慰めてやろうとお思いになるが、その気になれない億劫さで、たいそう日数が経ってしまったが、夕立があって、その後の涼しい夕闇に紛れて、温明殿の辺りを歩き回っていられると、この典侍、琵琶をとても美しく弾いていた。
御前などでも殿方の管弦のお遊びに加わりなどして、殊にこの人に勝る人もない名人なので、恨み言を言いたい気分でいたところから、とてもしみじみと聞こえて来る。
|
きわめて秘密にしていたので頭中将との関係を源氏は知らなんだ。御殿で見かけると恨みを告げる典侍に、源氏は老いている点にだけ同情を持ちながらもいやな気持ちがおさえ切れずに長く逢いに行こうともしなかったが、夕立のしたあとの夏の夜の涼しさに誘われて温明殿あたりを歩いていると、典侍はそこの一室で琵琶を上手に弾いていた。清涼殿の音楽の御遊びの時、ほかは皆男の殿上役人の中へも加えられて琵琶の役をするほどの名手であったから、それが恋に悩みながら弾く絃の音には源氏の心を打つものがあった。
|
【いたう忍ぶれば】- 源典侍が頭中将との関係を秘密にしていたことをさす。
【見つけきこえては】- 源典侍が源氏をお見かけ申してはの意。
【夕立して、名残涼しき宵のまぎれに、温明殿のわたりを】- 季節は夏、夕立の後、場所は宮中賢所のある温明殿の付近。神聖な場所である。
|
| 4.3.2 |
|
「瓜作りになりやしなまし」
|
「瓜作りになりやしなまし」
|
【瓜作りになりやしなまし】- 『催馬楽』「山城」の「山城の狛のわたりの瓜つくりななよやらいしなやさいしなや瓜つくり瓜つくりはれ瓜つくり我を欲しといふいかにせむななよやらいしなやさいしなやいかにせむいかにせむはれいかにせむなりやしなまし瓜たつまてにやらいしなやさいしなや瓜たつま瓜たつまてに」。「瓜作りになりやしなまし」そのものの句はない。語り手の間接話法とみるべきか。
|
| 4.3.3 |
|
と、声はとても美しく歌うのが、ちょっと気に食わない。
「鄂州にいたという昔の人も、このように興趣を引かれたのだろうか」と、耳を止めてお聞きになる。
弾き止んで、とても深く思い悩んでいる様子である。
君が、「東屋」を小声で歌ってお近づきになると、
|
という歌を、美声ではなやかに歌っているのには少し反感が起こった。白楽天が聞いたという鄂州の女の琵琶もこうした妙味があったのであろうと源氏は聞いていたのである。弾きやめて女は物思いに堪えないふうであった。源氏は御簾ぎわに寄って催馬楽の東屋を歌っていると、
|
【すこし心づきなき】- 源氏の感想。
【鄂州にありけむ昔の人も、かくやをかしかりけむ】- 源氏の心。『白氏文集』巻第十「夜聞歌者」を連想した。詩中に「鄂州」の文言はないが、古本には題名に「宿鄂州」と注記があったらしい。
【君、「東屋」を忍びやかに歌ひて】- 『催馬楽』「東屋」をさす。源氏は、「東屋の真屋のあまりのその雨そそぎ我立ち濡れぬ殿戸開かせ鎹もとざしもあらばこそその殿戸我鎖さめおし開いて来ませ我や人妻」の「殿戸開かせ」までの前半部を謡って挑発した。
|
| 4.3.4 |
|
「押し開いていらっしゃいませ」
|
「押し開いて来ませ」
|
【押し開いて来ませ】- 源典侍は、それに対して、その後半部「鎹も」以下を謡って掛け合いに応じたもの。「押し開いて来ませ」はその歌詞の一部。どうぞ入っていらっしゃいませの意。
|
| 4.3.5 |
と、うち添へたるも、例に違ひたる心地ぞする。
|
と、後を続けて歌うのも、普通の女とは違った気がする。
|
という所を同音で添えた。源氏は勝手の違う気がした。
|
|
| 4.3.6 |
|
「誰も訪れて来て濡れる人もいない東屋に
嫌な雨垂れが落ちて来ます」
|
立ち濡るる人しもあらじ東屋に
うたてもかかる雨そそぎかな
|
【立ち濡るる人しもあらじ東屋に--うたてもかかる雨そそきかな】- 源典侍の贈歌。「立ち濡るる」「東屋」「雨そそき」などの語句は『催馬楽』「東屋」を踏まえた表現。誰も訪れないことを嘆く意。
|
| 4.3.7 |
|
と嘆くのを、自分一人が怨み言を負う筋ではないが、「嫌になるな。何をどうしてこんなに嘆くのだろう」と、思われなさる。
|
と歌って女は歎息をしている。自分だけを対象としているのではなかろうが、どうしてそんなに人が待たれるのであろうと源氏は思った。
|
【我ひとりしも聞き負ふまじけれど】- 挿入句。源氏一人がその恨み言に責任を負わねばならない筋合ではないがの意。
【うとましや、何ごとをかくまでは】- 源氏の感想。
|
| 4.3.8 |
|
「人妻はもう面倒です
あまり親しくなるまいと思います」
|
人妻はあなわづらはし東屋の
まやのあまりも馴れじとぞ思ふ
|
【人妻はあなわづらはし東屋の--真屋のあまりも馴れじとぞ思ふ】- 源氏の返歌。「人妻」「東屋」「真屋のあまり」の語句も『催馬楽』「東屋」を踏まえた表現。他に通う男のいるあなたは厄介だ、馴れ親しもうとは思いませんの意。
|
| 4.3.9 |
とて、うち過ぎなまほしけれど、「あまりはしたなくや」と思ひ返して、人に従へば、すこしはやりかなる戯れ言など言ひかはして、これもめづらしき心地ぞしたまふ。
|
と言って、通り過ぎたいが、「あまり無愛想では」と思い直して、相手によるので、少し軽薄な冗談などを言い交わして、これも珍しい経験だとお思いになる。
|
と言い捨てて、源氏は行ってしまいたかったのであるが、あまりに侮辱したことになると思って典侍の望んでいたように室内へはいった。源氏は女と朗らかに戯談などを言い合っているうちに、こうした境地も悪くない気がしてきた。
|
|
| 4.3.10 |
|
頭中将は、この君がたいそう真面目ぶっていて、いつも非難なさるのが癪なので、何食わぬ顔でこっそりお通いの所があちこちに多くあるらしいのを、「何とか発見してやろう」とばかり思い続けていたところ、この現場を見つけた気分、まこと嬉しい。
「このような機会に、少し脅かし申して、お心をびっくりさせて、これに懲りたか、と言ってやろう」と思って、油断をおさせ申す。
|
頭中将は源氏がまじめらしくして、自分の恋愛問題を批難したり、注意を与えたりすることのあるのを口惜しく思って、素知らぬふうでいて源氏には隠れた恋人が幾人かあるはずであるから、どうかしてそのうちの一つの事実でもつかみたいと常に思っていたが、偶然今夜の会合を来合わせて見た。頭中将はうれしくて、こんな機会に少し威嚇して、源氏を困惑させて懲りたと言わせたいと思った。それでしかるべく油断を与えておいた。
|
【いかで見あらはさむ】- 頭中将の心。
【これを見つけたる心地、いとうれし】- 地の文と作中人物の心理が一体化した表現。読み手が頭中将の気持ちになって心躍らせて読み上げるような一文である。
【かかる折に】- 以下「言はむ」まで、頭中将の心。
|
| 4.3.11 |
風ひややかにうち吹きて、やや更けゆくほどに、すこしまどろむにやと見ゆるけしきなれば、やをら入り来るに、君は、とけてしも寝たまはぬ心なれば、ふと聞きつけて、この中将とは思ひ寄らず、「なほ忘れがたくすなる修理大夫にこそあらめ」と思すに、おとなおとなしき人に、かく似げなきふるまひをして、見つけられむことは、恥づかしければ、 |
風が冷たく吹いて来て、次第に夜も更けかけてゆくころに、少し寝込んだろうかと思われる様子なので、静かに入って来ると、君は、安心してお眠りになれない気分なので、ふと聞きつけて、この中将とは思いも寄らず、「いまだ未練のあるという修理の大夫であろう」とお思いになると、年配の人に、このような似つかわしくない振る舞いをして、見つけられるのは何とも照れくさいので、
|
冷ややかに風が吹き通って夜のふけかかった時分に源氏らが少し寝入ったかと思われる気配を見計らって、頭中将はそっと室内へはいって行った。自嘲的な思いに眠りなどにははいりきれなかった源氏は物音にすぐ目をさまして人の近づいて来るのを知ったのである。典侍の古い情人で今も男のほうが離れたがらないという噂のある修理大夫であろうと思うと、あの老人にとんでもないふしだらな関係を発見された場合の気まずさを思って、
|
【すこしまどろむにや】- 頭中将の推測。
【なほ忘れがたくすなる修理大夫にこそあらめ】- 源氏の心。修理大夫は源典侍に通う男。
|
| 4.3.12 |
|
「ああ、厄介な。
帰りますよ。
夫が後から来ることは、分かっていましたから。
ひどいな、おだましになるとは」
|
「迷惑になりそうだ、私は帰ろう。旦那の来ることは初めからわかっていただろうに、私をごまかして泊まらせたのですね」
|
【あな、わづらはし】- 以下「心憂くすかしたまひけるよ」まで、源氏の詞。
【蜘蛛のふるまひは、しるかりつらむものを】- 『源氏釈』は「わがせこが来べき宵なりささがにの蜘蛛のふるまひかねてしるしも」(古今集、墨滅歌、一一一〇、衣通姫)を指摘。男が来ることは分かっていましたのですからの意。
|
| 4.3.13 |
|
と言って、直衣だけを取って、屏風の後ろにお入りになった。
中将、おかしさを堪えて、お引き廻らしになってある屏風のもとに近寄って、ばたばたと畳み寄せて、大げさに振る舞ってあわてさせると、典侍は、年取っているが、ひどく上品ぶった艶っぽい女で、以前にもこのようなことがあって、肝を冷やしたことが度々あったので、馴れていて、ひどく気は動転していながらも、「この君をどうなされてしまうのか」と心配で、震えながらしっかりと取りすがっている。
「誰とも分からないように逃げ出そう」とお思いになるが、だらしない恰好で、冠などをひん曲げて逃げて行くような後ろ姿を思うと、「まことに醜態であろう」と、おためらいなさる。
|
と言って、源氏は直衣だけを手でさげて屏風の後ろへはいった。中将はおかしいのをこらえて源氏が隠れた屏風を前から横へ畳み寄せて騒ぐ。年を取っているが美人型の華奢なからだつきの典侍が以前にも情人のかち合いに困った経験があって、あわてながらも源氏をあとの男がどうしたかと心配して、床の上にすわって慄えていた。自分であることを気づかれないようにして去ろうと源氏は思ったのであるが、だらしなくなった姿を直さないで、冠をゆがめたまま逃げる後ろ姿を思ってみると、恥な気がしてそのまま落ち着きを作ろうとした。
|
【引きたてまつる】- 大島本は「ひきたてまつる」とある。横山本、陽明文庫本、肖柏本は「ひきたて給へるに」。榊原家本、池田本、三条西家本、書陵部本は「ひきたて給へる」。河内本は高松宮家本の独自異文を除いて他は榊原家本等と同文。別本の御物本も榊原家本等と同文、伝二条為氏筆本は「ひきたゝみたる」の独自異文。『集成』『古典セレクション』は「引きたてたまへる」と校訂する。そして『集成』は「〔源氏が〕ひきめぐらされた」と注し、『古典セレクション』は「「引きたてたまへる」は源氏の動作。屏風をひろげて姿を隠すこと」と注す。共に「給ふ」を源氏の動作に対して用いられた敬語と見る。『新大系』は底本のままとする。
【ごほごほとたたみ寄せて】- 『集成』『古典セレクション』は「ごほごほ」と読む。『新大系』は「こほこほ」と清音で読む。『岩波古語辞典』では「こほこほ」を見出語に掲載。『完訳』は「源氏が屏風を広げるそばから、頭中将がたたみ寄せる」と注す。
【おどろおどろしく】- 『古典セレクション』は諸本に従って「おどろおどろしう」とウ音便形に改める。『集成』『新大系』は底本のまま。
【この君をいかにしきこえぬるか】- 『古典セレクション』は諸本に従って「きこえぬるにか」と「に」を補訂する。『集成』『新大系』は底本のまま。源典侍の心。
【誰れと知られで出でなばや】- 源氏の心。
【いとをこなるべし】- 源氏の判断。
|
| 4.3.14 |
中将、「いかで我と知られきこえじ」と思ひて、ものも言はず、ただいみじう怒れるけしきにもてなして、太刀を引き抜けば、女、 |
中将、「何とかして自分だとは知られ申すまい」と思って、何とも言わない。ただひどく怒った形相を作って、太刀を引き抜くと、女は、
|
中将はぜひとも自分でなく思わせなければならないと知って物を言わない。ただ怒ったふうをして太刀を引き抜くと、
|
【いかで我と知られきこえじ】- 頭中将の心。
|
| 4.3.15 |
|
「あなた様、あなた様」
|
「あなた、あなた」
|
【あが君、あが君】- 源典侍の嘆願の詞。
|
|
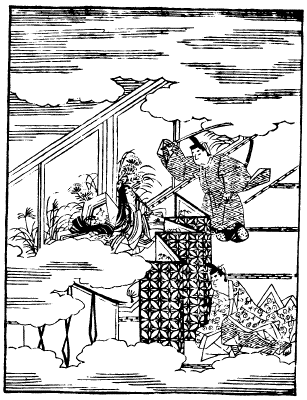 |
| 4.3.16 |
|
と、向かって手を擦り合わせて拝むので、あやうく笑い出してしまいそうになる。
好ましく若づくりして振る舞っている表面だけは、まあ見られたものであるが、五十七、八歳の女が、着物をきちんと付けず慌てふためいている様子、実に素晴らしい二十代の若者たちの間にはさまれて怖がっているのは、何ともみっともない。
このように別人のように装って、恐ろしい様子を見せるが、かえってはっきりとお見破りになって、「わたしだと知ってわざとやっているのだな」と、馬鹿らしくなった。
「あの男のようだ」とお分かりになると、とてもおかしかったので、太刀を抜いている腕をつかまえて、とてもきつくおつねりになったので、悔しいと思いながらも、堪え切れずに笑ってしまった。
|
典侍は頭中将を拝んでいるのである。中将は笑い出しそうでならなかった。平生派手に作っている外見は相当な若さに見せる典侍も年は五十七、八で、この場合は見得も何も捨てて二十前後の公達の中にいて気をもんでいる様子は醜態そのものであった。わざわざ恐ろしがらせよう自分でないように見せようとする不自然さがかえって源氏に真相を教える結果になった。自分と知ってわざとしていることであると思うと、どうでもなれという気になった。いよいよ頭中将であることがわかるとおかしくなって、抜いた太刀を持つ肱をとらえてぐっとつねると、中将は見顕わされたことを残念に思いながらも笑ってしまった。
|
【ほとほと笑ひぬべし】- 『湖月抄』師説は「中将心を草子地より云也」と指摘。作中人物と語り手の気持ちが一体化した表現。読み手は感情をこめて読み上げた文章。
【好ましう若やぎて】- 以下「いとつきなし」まで、語り手の源典侍の振る舞いに対する批評的文章。
【もの言ひ騒げるけはひ】- 『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「もの思ひ騒げるけはひ」と校訂する。『新大系』は底本のまま。
【かうあらぬさまにもてひがめて】- 主語は頭中将。別人を装うことをさす。
【我と知りて、ことさらにするなりけり】- 源氏の心。
【その人なめり】- 源氏の心。「その人」は頭中将をさす。
|
| 4.3.17 |
「まことは、うつし心かとよ。戯れにくしや。いで、この直衣着む」 |
「ほんと、正気の沙汰かね。
冗談も出来ないね。
さあ、この直衣を着よう」
|
「本気なの、ひどい男だね。ちょっとこの直衣を着るから」
|
【まことは】- 以下「直衣着む」まで、源氏の詞。
|
| 4.3.18 |
とのたまへど、つととらへて、さらに許しきこえず。
|
とおっしゃるが、しっかりとつかんで、全然お放し申さない。
|
と源氏が言っても、中将は直衣を放してくれない。
|
|
| 4.3.19 |
|
「それでは、一緒に」
|
「じゃ君にも脱がせるよ」
|
【さらば、もろともにこそ】- 源氏の詞。
|
| 4.3.20 |
とて、中将の帯をひき解きて脱がせたまへば、脱がじとすまふを、とかくひきしろふほどに、ほころびはほろほろと絶えぬ。
中将、
|
と言って、中将の帯を解いてお脱がせになると、脱ぐまいと抵抗するのを、何かと引っ張り合ううちに、開いている所からびりびりと破れてしまった。
中将は、
|
と言って、中将の帯を引いて解いてから、直衣を脱がせようとすると、脱ぐまいと抵抗した。引き合っているうちに縫い目がほころんでしまった。
|
|
| 4.3.21 |
|
「隠している浮名も洩れ出てしまいましょう
引っ張り合って破れてしまった二人の仲の衣から
|
「包むめる名や洩り出でん引きかはし
かくほころぶる中の衣に
|
【つつむめる名や漏り出でむ引きかはし--かくほころぶる中の衣に】- 頭中将の贈歌。「包む」「綻ぶ」は「衣」の縁語。「包む」は衣で包む意と秘密を包む意を掛け、「中」は衣と衣の中(間)と源氏と源典侍との仲を連想させる表現。
|
| 4.3.22 |
|
上に着たら、明白でしょうよ」
|
明るみへ出ては困るでしょう」
|
【上に取り着ば、しるからむ】- 歌に添えた詞。『奥入』は「紅のこそめの衣下に着て上にとり着ばしるからむかも」(古今六帖、衣)を指摘。下の句を引用したもの。綻びた衣を上に着たら浮気の沙汰が明白だの意。
|
| 4.3.23 |
と言ふ。
君、
|
と言う。
君は、
|
と中将が言うと、
|
|
| 4.3.24 |
|
「この女との仲まで知られてしまうのを承知の上でやって来て
夏衣を着るとは、
|
隠れなきものと知る知る夏衣
きたるをうすき心とぞ見る
|
【隠れなきものと知る知る夏衣--着たるを薄き心とぞ見る】- 源氏の返歌。「着たる」「薄き」は「夏衣」の縁語。「きたる」は「着たる」「と「来たる」の掛詞。
|
| 4.3.25 |
と言ひかはして、うらやみなきしどけな姿に引きなされて、みな出でたまひぬ。
|
と詠み返して、恨みっこなしのだらしない恰好に引き破られて、揃ってお出になった。
|
と源氏も負けてはいないのである。双方ともだらしない姿になって行ってしまった。
|
|
|
第四段 翌日、源氏と頭中将と宮中で応酬しあう
|
| 4.4.1 |
|
君は、「実に残念にも見つけられてしまったことよ」と思って、臥せっていらっしゃった。
典侍は、情けないことと思ったが、落としていった御指貫や、帯などを、翌朝お届け申した。
|
源氏は友人に威嚇されたことを残念に思いながら宿直所で寝ていた。驚かされた典侍は翌朝残っていた指貫や帯などを持たせてよこした。
|
【いと口惜しく見つけられぬること】- 源氏の心。
|
| 4.4.2 |
|
「恨んでも何の甲斐もありません
次々とやって来ては帰っていったお二人の波の後では
|
「恨みても云ひがひぞなき立ち重ね
引きて帰りし波のなごりに
|
【恨みてもいふかひぞなきたちかさね--引きてかへりし波のなごりに】- 源典侍の贈歌。「恨」と「浦」、「効」と「貝」、「立ち」と「太刀」の掛詞。「浦」「貝」「引き」「帰り」「名残」は「波」の縁語。『完訳』は「若者が老女を置去りにするのを、大波が引くさまにたとえた」と注す。
|
| 4.4.3 |
|
底もあらわになって」
|
悲しんでおります。恋の楼閣のくずれるはずの物がくずれてしまいました」
|
【底もあらはに】- 歌に添えた詞。『源氏釈』は「別ての後ぞ悲しき涙川底も露になりぬと思へば」(新勅撰集、恋四、九三九、読人しらず)を指摘。その第四句の言葉を引用。
|
| 4.4.4 |
とあり。「面無のさまや」と見たまふも憎けれど、わりなしと思へりしもさすがにて、 |
とある。
「臆面もないありさまだ」と御覧になるのも憎らしいが、困りきっているのもやはりかわいそうなので、
|
という手紙が添えてあった。面目なく思うのであろうと源氏はなおも不快に昨夜を思い出したが、気をもみ抜いていた女の様子にあわれんでやってよいところもあったので返事を書いた。
|
【面無のさまや】- 源氏の感想。
|
| 4.4.5 |
|
「荒々しく暴れた頭中将には驚かないが
その彼を寄せつけたあなたをどうして恨まずにはいられようか」
|
荒だちし波に心は騒がねど
よせけん磯をいかが恨みぬ
|
【荒らだちし波に心は騒がねど--寄せけむ磯をいかが恨みぬ】- 源氏の返歌。「浪」を頭中将に、「磯」を源典侍に喩える。「荒立つ」は波が荒立つと心が荒立つの両意。「荒立つ」「浪」「寄す」「磯」「浦見」は縁語。頭中将の乱暴は何とも思わないが、その彼を近づけたあなたは恨みますよの意。
|
| 4.4.6 |
|
とだけあった。
帯は、中将のであった。
ご自分の直衣よりは色が濃い、と御覧になると、端袖もないのであった。
|
とだけである。帯は中将の物であった。自分のよりは少し色が濃いようであると、源氏が昨夜の直衣に合わせて見ている時に、直衣の袖がなくなっているのに気がついた。
|
【わが御直衣よりは色深し】- 源氏の心。
|
| 4.4.7 |
|
「見苦しいことだ。
夢中になって浮気に耽る人は、このとおり馬鹿馬鹿しい目を見ることも多いのだろう」と、ますます自重せずにはいらっしゃれない。
|
なんというはずかしいことだろう、女をあさる人になればこんなことが始終あるのであろうと源氏は反省した。
|
【あやしのことどもや】- 以下「をこがましきことは多からむ」まで、源氏の心。
【をこがましきことは】- 『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「をこがましきことも」と校訂する。『新大系』は底本のまま。
|
| 4.4.8 |
|
中将が、宿直所から、「これを、まずはお付けあそばせ」といって、包んで寄こしたのを、「どうやって、持って行ったのか」と憎らしく思う。
「この帯を獲らなかったら、
大変だった」とお思い
|
頭中将の宿直所のほうから、何よりもまずこれをお綴じつけになる必要があるでしょう。と書いて直衣の袖を包んでよこした。どうして取られたのであろうと源氏はくやしかった。中将の帯が自分の手にはいっていなかったらこの争いは負けになるのであったとうれしかった。帯と同じ色の紙に包んで、
|
【これ、まづ綴ぢつけさせたまへ】- 頭中将の伝言。
【いかで取りつらむ】- 源氏の心。
【この帯を得ざらましかば】- 源氏の心。
|
| 4.4.9 |
|
「仲が切れたらわたしのせいだと非難されようかと思ったが
縹の帯などわたしには関係ありません」
|
中絶えばかごとや負ふと危ふさに
縹の帯はとりてだに見ず
|
【なか絶えばかことや負ふと危ふさに--はなだの帯を取りてだに見ず】- 『集成』は「かこと」と清音に読み、『古典セレクション』『新大系』は「かごと」と濁音に読む。『日葡辞書』には「かこと」「かごと」両方ある(小学館『古語大辞典』)。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「はなだの帯は」と校訂する。『新大系』は底本のまま。源氏の贈歌。『花鳥余情』は『催馬楽』「石川」の「石川の高麗人に帯を取られて辛き悔するいかなるいかなる帯ぞ縹の帯の中はたいれるかかやるかあやるか中はたいれたるか」を指摘。「中」は頭中将と源典侍との仲をさす。仲の切れた原因がわたしにあると言われないように、帯は取りませんよの意。
|
| 4.4.10 |
とて、やりたまふ。
立ち返り、
|
といって、
お遣りにな
|
と書いて源氏は持たせてやった。女の所で解いた帯に他人の手が触れるとその恋は解消してしまうとも言われているのである。中将からまた折り返して、
|
|
| 4.4.11 |
|
「あなたにこのように取られてしまった帯ですから
こんな具合に仲も切れてしまったものとしましょうよ
|
君にかく引き取られぬる帯なれば
かくて絶えぬる中とかこたん
|
【君にかく引き取られぬる帯なれば--かくて絶えぬるなかとかこたむ】- 頭中将の返歌。「帯」に源典侍の意をこめる。源典侍との仲が切れたのは、あなたにその帯(女)を取られたせいとしようの意。
|
| 4.4.12 |
え逃れさせたまはじ」
|
逃れることはできませんよ」
|
なんといっても責任がありますよ。
|
|
| 4.4.13 |
とあり。
|
とある。
|
と書いてある。
|
|
| 4.4.14 |
日たけて、おのおの殿上に参りたまへり。
いと静かに、もの遠きさましておはするに、頭の君もいとをかしけれど、公事多く奏しくだす日にて、いとうるはしくすくよかなるを見るも、かたみにほほ笑まる。
人まにさし寄りて、
|
日が高くなってから、それぞれ殿上に参内なさった。
とても落ち着いて、知らぬ顔をしていらっしゃると、頭の君もとてもおかしかったが、公事を多く奏上し宣下する日なので、実に端麗に真面目くさっているのを見るのも、お互いについほほ笑んでしまう。
人のいない隙に近寄って、
|
昼近くになって殿上の詰め所へ二人とも行った。取り澄ました顔をしている源氏を見ると中将もおかしくてならない。その日は自身も蔵人頭として公用の多い日であったから至極まじめな顔を作っていた。しかしどうかした拍子に目が合うと互いにほほえまれるのである。だれもいぬ時に中将がそばへ寄って来て言った。
|
|
| 4.4.15 |
|
「秘密事は懲りたでしょう」
|
「隠し事には懲りたでしょう」
|
【もの隠しは懲りぬらむかし】- 頭中将の詞。
|
| 4.4.16 |
|
と言って、とても憎らしそうな流し目である。
|
尻目で見ている。優越感があるようである。
|
【いとねたげなるしり目なり】- 『集成』は「えらく得意そうな横目でじろりとにらむ。「ねたげ」は、こちらが「ねたし」(しゃくだ)と思うような様子。こしゃくな感じで、というほどの意」と注す。
|
| 4.4.17 |
|
「どうして、そんなことがありましょう。
そのまま帰ってしまったあなたこそ、お気の毒だ。
本当の話、嫌なものだよ、男女の仲とは」
|
「なあに、それよりもせっかく来ながら無駄だった人が気の毒だ。まったくは君やっかいな女だね」
|
【などてか、さしもあらむ】- 以下「憂しや世の中よ」まで、源氏の返事。
【憂しや、世の中よ】- 『集成』は「引歌であるが未詳」と注す。『全書』『対校』『大系』『評釈』『全集』『完訳』『新大系』は「人ごとはあまの刈る藻にしげくとも思はましかばよしや世の中」(古今六帖四、恨み)を引歌として指摘する。『完訳』は「「うしや」と裏返して、世の噂を疎む気持」と注す。
|
| 4.4.18 |
|
と言い交わして、「鳥籠の山にある川の名」と、互いに口固めしあう。
|
秘密にしようと言い合ったが、それからのち中将はどれだけあの晩の騒ぎを言い出して源氏を苦笑させたかしれない。
|
【鳥籠の山なる】- 『源氏釈』は「犬上の鳥籠の山なるいさや川いさと答えよ我が名洩らすな」(古今集、墨滅歌、一一〇八)を指摘。『集成』は「いさや川」、『完訳』『新大系』は「名取川」として引用。
|
| 4.4.19 |
|
さて、それから後、ともすれば何かの折毎に、話に持ち出す種とするので、ますますあの厄介な女のためにと、お思い知りになったであろう。
女は、相変わらずまこと色気たっぷりに恨み言をいって寄こすが、興醒めだと逃げ回りなさる。
|
それは恋しい女のために受ける罰でもないのである。女は続いて源氏の心を惹こうとしていろいろに技巧を用いるのを源氏はうるさがっていた。
|
【さて、そののち】- 『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「さてその後は」と「は」を補入する。『新大系』は底本のまま。
【ものむつかしき人ゆゑ】- 源氏の心。「人」は源典侍をさす。
【わびしと思ひありきたまふ】- 『集成』は「〔源氏は〕やれやれと逃げまわっておられる」と注し、『完訳』は「困ったものよと思い続けていらっしゃる」と訳す。
|
| 4.4.20 |
|
中将は、妹の君にも申し上げず、ただ、「何かの時の脅迫の材料にしよう」と思っていた。
高貴な身分の妃からお生まれになった親王たちでさえ、お上の御待遇がこの上ないのを憚って、とても御遠慮申し上げていらっしゃるのに、この中将は、「絶対に圧倒され申すまい」と、ちょっとした事柄につけても対抗申し上げなさる。
|
中将は妹にもその話はせずに、自分だけが源氏を困らせる用に使うほうが有利だと思っていた。よい外戚をお持ちになった親王方も帝の殊寵される源氏には一目置いておいでになるのであるが、この頭中将だけは、負けていないでもよいという自信を持っていた。ことごとに競争心を見せるのである。
|
【さるべき折の脅しぐさにせむ】- 頭中将の心。
【主上の御もてなし】- 桐壺帝の源氏に対する待遇をさす。
【いとことにさりきこえたまへるを】- 主語は親王たち、相手は源氏をさす。
【さらにおし消たれきこえじ】- 頭中将の心。
|
| 4.4.21 |
|
この君一人が、姫君と同腹なのであった。
帝のお子というだけだ、自分だって、同じ大臣と申すが、ご信望の格別な方が、内親王腹にもうけた子息として大事に育てられているのは、どれほども劣る身分とは、お思いにならないのであろう。
人となりも、すべて整っており、どの面でも理想的で、満ち足りていらっしゃるのであった。
このお二方の競争は、変わっているところがあった。
けれども、煩わしいので省略する。
|
左大臣の息子の中でこの人だけが源氏の夫人と同腹の内親王の母君を持っていた。源氏の君はただ皇子であるという点が違っているだけで、自分も同じ大臣といっても最大の権力のある大臣を父として、皇女から生まれてきたのである、たいして違わない尊貴さが自分にあると思うものらしい。人物も怜悧で何の学問にも通じたりっぱな公子であった。つまらぬ事までも二人は競争して人の話題になることも多いのである。
|
【この君一人ぞ、姫君の御一つ腹なりける】- 以下「されどうるさくてなむ」まで、語り手の頭中将の人物についての補足説明的文章。
【帝の御子といふばかりにこそあれ】- 以下「劣るべき際」まで、頭中将の自負、心中文。だが、その文末は地の文に移る。なお頭中将の出自を語るあたり「桐壺」巻と重複するところがある。
【何ばかり劣るべき際と、おぼえたまはぬなるべし】- 心中文から地の文へ移行する。したがって、「何ばかり」「劣るべき際」は反語ではない。地の文に続いて、どれほども劣る身分とお思いにならないという程度を表す。
【されど、うるさくてなむ】- 『休聞抄』は「紫式双也」と指摘、『集成』は「省筆をことわる草子地。源典侍の話もその一つ、という含み」、『完訳』は「語り手の省筆の言葉で、典侍の物語を語りおさめる」と注す。
|
|
第五章 藤壺の物語(三) 秋、藤壺は中宮、源氏は宰相となる
|
|
第一段 七月に藤壺女御、中宮に立つ
|
| 5.1.1 |
|
七月に、
后がお立ちになるようであった。源
氏の君、宰相におなりになった。帝、御譲位あそばすお心づもりが近くなって、この若君を春宮に、とお考えあそばされるが、御後見な
さるべき方がいらっしゃらない。御母方が、みな親王方で、皇族が政治を執るべき筋合ではないので、せめて母宮だけでも不動の地位におつけ申して、お力
|
この七月に皇后の冊立があるはずであった。源氏は中将から参議に上った。帝が近く譲位をあそばしたい思召しがあって、藤壺の宮のお生みになった若宮を東宮にしたくお思いになったが将来御後援をするのに適当な人がない。母方の御伯父は皆親王で実際の政治に携わることのできないのも不文律になっていたから、母宮をだけでも后の位に据えて置くことが若宮の強味になるであろうと思召して藤壺の宮を中宮に擬しておいでになった。
|
【七月にぞ后ゐたまふめりし】- 大島本「七月」と表記する。『古典セレクション』は「ふみづき」と振り仮名を付けている。今音読みしておく。『集成』は「后がお立ちになったようだ。物語作者として重大な国事に関する記述を遠慮して、ぼかした書き方」と注す。『完訳』は「七月には、后がお立ちになるようであった」と訳す。
【源氏の君、宰相になりたまひぬ】- 源氏、参議(宰相)に昇進。位階は昨秋の朱雀院行幸の折に正三位に昇進。
【御母方の、みな親王たちにて、源氏の公事しりたまふ筋ならねば】- 『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「御母方」と「の」を削除する。『新大系』は底本のまま。「御母方」は外戚をさす。「親王」は皇族の意。この場合の「源氏」は狭義の源氏ではなく広い意味での源氏、すなわち皇族一般をさす。「公事」は国政の意。「知り」は治める、司る意。「源氏の公事知り給ふ筋ならねば」というところに、この物語作者または当時一般の政治観が現れている。
【母宮をだに動きなきさまにしおきたてまつりて、強りに】- 帝の考え。「動きなきさま」は后の地位に立てることをさす。
|
| 5.1.2 |
弘徽殿、いとど御心動きたまふ、ことわりなり。
されど、
|
弘徽殿、ますますお心穏やかでない、道理である。
けれども、
|
弘徽殿の女御がこれに平らかでないことに道理はあった。
|
|
| 5.1.3 |
|
「春宮の御世が、もう直ぐになったのだから、疑いない御地位である。
ご安心されよ」
|
「しかし皇太子の即位することはもう近い将来のことなのだから、その時は当然皇太后になりうるあなたなのだから、気をひろくお持ちなさい」
|
【春宮の御世、いと近うなりぬれば、疑ひなき御位なり。思ほしのどめよ】- 帝の弘徽殿女御に対する慰めの詞。「疑ひなき位」とは帝の母、すなわち皇太后の地位をさす。「皇后」も「皇太后」も「后」の地位に相違はないとする。
|
| 5.1.4 |
|
とお慰め申し上げあそばすのであった。
「なるほど、春宮の御母堂として二十余年におなりの女御を差し置き申して、先にお越し申されることは難しいことだ」と、例によって、穏やかならず世間の人も噂するのであった。
|
帝はこんなふうに女御を慰めておいでになった。皇太子の母君で、入内して二十幾年になる女御をさしおいて藤壺を后にあそばすことは当を得たことであるいはないかもしれない。例のように世間ではいろいろに言う者があった。
|
【げに、春宮の御母にて二十余年になりたまへる女御】- 「げに」は語り手の感情移入の表現で作中人物と共に共感を表し、なるほどの意。また「ことなりかし」まで、世人の噂でもある。『完訳』は「「いとど御心動きたまふ、ことわりなり」を受けて「げに」と納得、世人の思惑を語る文脈に続く」と注す。弘徽殿女御が春宮の母女御として、二十数年になったことを明らかにする。ただし、立坊後ではない。
【例の、やすからず】- 『完訳』は「政治的な話題にはいつも世人が敏感に反応」と指摘。
|
| 5.1.5 |
|
参内なさる夜のお供に、宰相君もお仕え申し上げなさる。
同じ宮と申し上げる中でも、后腹の内親王で、玉のように美しく光り輝いて、類ない御寵愛をさえ蒙っていらっしゃるので、世間の人々もとても特別に御奉仕申し上げた。
言うまでもなく、切ないお心の中では、御輿の中も思いやられて、ますます手も届かない気持ちがなさると、じっとしてはいられないまでに思われた。
|
儀式のあとで御所へおはいりになる新しい中宮のお供を源氏の君もした。后と一口に申し上げても、この方の御身分は后腹の内親王であった。全い宝玉のように輝やくお后と見られたのである。それに帝の御寵愛もたいしたものであったから、満廷の官人がこの后に奉仕することを喜んだ。道理のほかまでの好意を持った源氏は、御輿の中の恋しいお姿を想像して、いよいよ遠いはるかな、手の届きがたいお方になっておしまいになったと心に歎かれた。気が変になるほどであった。
|
【参りたまふ夜の】- 主語は藤壺。立后後の最初の参内の儀式。
【宰相君】- 源氏をさす。以後、公人としての呼称となる。三位の宰相。
【同じ宮と聞こゆるなかにも、后腹の皇女、玉光りかかやきて、たぐひなき御おぼえにさへものしたまへば】- 大島本は「宮」とあるが、榊原家本、池田本、肖柏本、三条西家本、書陵部本は「后」とある。横山本と陽明文庫本は「くらゐ」とある。河内本や別本の御物本も「后」とある。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「后」と校訂する。『新大系』は底本のままとする。藤壺の出自についていう。「桐壺」巻と重複するところがある。
【まして、わりなき御心には】- 源氏をさす。
【すずろはしき】- 大島本と池田本は「すゝろはしき」。その他の青表紙本諸本は「そゝろはしき」。意味は同じ。『小学館古語大辞典』に「動詞「すずろふ」の形容詞形で、喜び、悲しみ、不愉快さのために、(そうするつもりはないのに)平常の落ち着きを失って、じっとしていられない状態を表す。なお、「すぞろはし」「そぞろはし」などの変化形もあるが、用例は少ない」とある。
|
| 5.1.6 |
|
「尽きない恋の思いに何も見えない
はるか高い地位につかれる方を仰ぎ見るにつけても」
|
つきもせぬ心の闇にくるるかな
|
【尽きもせぬ心の闇に暮るるかな--雲居に人を見るにつけても】- 源氏の独詠歌。『完訳』は「人の親の心は闇にあらねども子を思ふ道にまどひぬるかな」(後撰集、雑一、一一〇二、藤原兼輔)と「かきくらす心の闇にまどひにき夢うつつとは今宵さだめよ」(伊勢物語、六十九段)を引歌として指摘し、「「心の闇」は、若宮ゆえの親心の闇に、藤壺恋慕ゆえの心の闇が重なる」とし、また「「雲居」に、雲の上の人として遠のいた藤壺への及びがたい思いをこめる。このあたり『伊勢物語』の、二条后関係の小塩山の段(七十六段)も投影」と指摘する。
|
| 5.1.7 |
とのみ、独りごたれつつ、ものいとあはれなり。
|
とだけ、独言が口をついて出て、何につけ切なく思われる。
|
雲井に人を見るにつけても
こう思われて悲しいのである。
|
|
| 5.1.8 |
|
皇子は、ご成長なさっていく月日につれて、とてもお見分け申しがたいほどでいらっしゃるのを、宮は、まこと辛い、とお思いになるが、気付く人はいないらしい。
なるほど、どのように作り変えたならば、負けないくらいの方がこの世にお生まれになろうか。
月と日が似通って光り輝いているように、世人も思っていた。
|
若宮のお顔は御生育あそばすにつれてますます源氏に似ておいきになった。だれもそうした秘密に気のつく者はないようである。何をどう作り変えても源氏と同じ美貌を見うることはないわけであるが、この二人の皇子は月と日が同じ形で空にかかっているように似ておいでになると世人も思った。
|
【皇子は、およすけたまふ月日に従ひて】- 若宮の成長、源氏に酷似した美しさを語る。
【いと苦し】- 藤壺の心。わが子の顔だちが源氏に酷似しているのを苦慮する。
【思ひ寄る人なきなめりかし】- 「な(る)」(断定の助動詞)「めり」(推量の助動詞)は、語り手の判断や推量。
【げに、いかさまに】- 以下「通ひたるやうにぞ」まで、世人の思い。
【やうに、ぞ世人も思へる】- 心中文が地の文に移行する。「ぞ」(係助詞)は「思へる」に係る。『完訳』は「二人は、桐壺帝かに寵愛されるのにとどまらず、世人一般からも支持されている」と注す。『新大系』は「二人とも皇統に連なるのにふさわしい美質と讃えられる」と注す。
|
| 著作権 |
| 底本 |
大島本 |
| 校訂 |
Last updated 9/20/2010(ver.2-2)
渋谷栄一校訂(C)
オリジナル
修正版
比較 |
| ローマ字版 |
Last updated 4/21/2009 (ver.2-2)
Written in Japanese roman letters
by Eiichi Shibuya (C)
オリジナル
修正版
比較 |
ルビ抽出
(ローマ字版から)
|
Powered by 再編集プログラム v4.05
ひらがな版
ルビ抽出 |
挿絵
(ローマ字版から)
|
'Eiri Genji Monogatari'
(1650 1st edition) |
|
Last updated 5/3/2001
渋谷栄一訳(C)(ver.1-2-2)
オリジナル
修正版
比較 |
|
|
Last updated 4/21/2009(ver.2-2)
渋谷栄一注釈(C)
オリジナル
修正版
比較 |
|