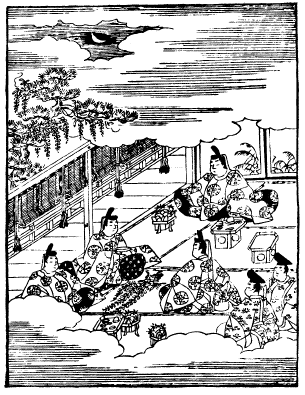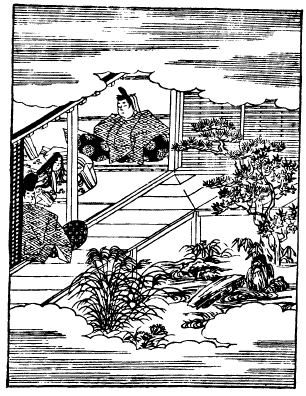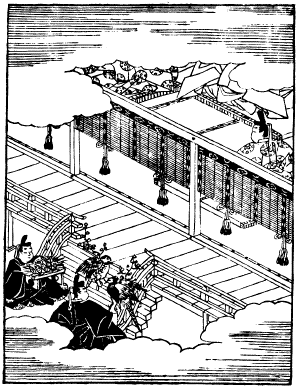第三十三帖 藤裏葉
光る源氏の太政大臣時代三十九歳三月から十月までの物語
|
# |
本文 |
渋谷栄一訳 |
与謝野晶子訳 |
注釈 |
|
第一章 夕霧の物語 雲居雁との筒井筒の恋実る
|
|
第一段 夕霧と雲居雁の相思相愛の恋
|
| 1.1.1 |
|
御入内の準備の最中にも、宰相中将は物思いに沈みがちで、ぼんやりした感じがするが、「一方では、不思議な感じで、自分ながら執念深いことだ。
むやみにこんなに恋しいことならば、関守が、目をつぶって許そうというほどに気弱におなりだという噂を聞きながら、同じことなら、体裁の悪くないよう最後まで通そう」と我慢するにつけても、苦しく思い悩んでいらっしゃる。
|
六条院の姫君が太子の宮へはいる仕度でだれも繁忙をきわめている時にも、兄の宰相中将は物思いにとらわれていて、ぼんやりとしていることに自身で気がついていた。自身で自身がわからない気もする中将であった。どうしてこんなに執拗にその人を思っているのであろう、これほど苦しむのであれば、二人の恋愛を認めてよいというほどに伯父が弱気になっていることも聞いていたのであるから、もうずっと以前から進んで昔の関係を復活さえさせればよかったのである。しかしできることなら、伯父のほうから正式に婿として迎えようと言って来る日までは昔の雪辱のために待っていたいと煩悶しているのである。
|
【御いそぎのほどにも、宰相中将は眺めがちにて】- 晩春三月下旬、六条院の姫君入内の準備のころ。
【かつはあやしく、わが心ながら】- 『集成』は「我心ながら」以下「人悪からぬさまに見果てむ」までを、夕霧の心中文と解し、「考えてみれば不思議で」と訳す。『完訳』は「あやしく」以下「人悪からぬさまに見果てむ」までを、夕霧の心中文と解し、「一方では、これはどうしたことなのだ、我ながら」と訳す。
【執念きぞかし】- 年立によれば「少女」巻以来六年の歳月の流れがある。
【関守の、うちも寝ぬべきけしきに】- 「人知れぬわが通ひ路の関守は宵々ごとにうちも寝ななむ」(古今集恋三、六三二、在原業平・伊勢物語五段、六)を踏まえた表現。
|
| 1.1.2 |
|
女君も、大臣がちらっとおっしゃった縁談のお話を、「もしも、そうなったら、わたしのことをすっかり忘れてしまうだろう」と嘆かわしくて、不思議と背を向けあった関係ながら、そうはいっても相思相愛の仲である。
|
雲井の雁のほうでも父の大臣の洩らした恋人の結婚話から苦しい物思いをしていた。もしもそんなことになったならもう永久に自分などは顧みられないであろうと思うと悲しかった。接近をしようとはせずに、しかもこの二人のしているのは熱烈な相思の恋であった。
|
【大臣のかすめたまひしことの筋】- 「梅枝」巻(第三章三段)の夕霧と中務家との縁談をさす。
【もし、さもあらば、何の名残かは】- 雲居雁の心中。夕霧と中務家との縁談が真実ならば、自分は忘れ捨てられるかもしれない、とする不安。
【御もろ恋】- みごもりの神しまことの神ならば我が片恋を諸恋になせ(古今六帖四-二〇二〇)(text33.html 出典2 から転載)
|
| 1.1.3 |
|
内大臣も、あれほど強情をお張りになったが、意地の張りがいのないのにご思案にあまって、「あの宮におかれても、そのようにお決めになってしまったら、再びあれこれと改めて別の相手を探す間、その相手にも悪いし、ご自分の方にも物笑いとなって、自然と軽率だという噂の種にされよう。
隠そうとしても、内輪の失敗も、世間に漏れているだろう。
何とか世間体をつくろって、やはり折れた方が良いようだ」と、お考えになった。
|
内大臣も甥の価値をしいて認めようとせずに、結婚問題には冷淡な態度をとり続けてきたのであったが、雲井の雁の心は今も依然とその人にばかり傾いているのを知っては、親心として宰相中将の他家の息女と結婚するのを坐視するに忍びなくなった。話が進行してしまって、中務の宮でも結婚の準備ができたあとでこちらの話を言い出しては中将を苦しめることにもなるし、自身の家のためにも不面目なことになって世上の話題にされやすい。秘密にしていても昔あった関係はもう人が皆知っていることであろう、何かの口実を作って、やはり自分のほうから負けて出ねばならないとまで大臣は決心するに至った。
|
【たけからぬに思しわづらひて】- 『集成』は「意地の張りがいのないのに思いあぐねられて」。『完訳』「事がうまく運ばないのに思いあまって」と訳す。
【かの宮にも】- 以下「負けぬべきなめり」まで、内大臣の心中。
【改め思ひかかづらはむほど】- 夕霧以外に別の婿を探すことをさす。
【うちうちのことあやまりも】- 『集成』は「内輪の過失も。祖母大宮のもとで、夕霧と雲居の雁がひそかに相愛の仲になっていたこと」。『完訳』は「ひそかな相愛関係にあること」と注す。
|
| 1.1.4 |
|
表面上は何気ないが、恨みの解けないご関係なので、「きっかけもなく言い出すのはどんなものか」と、ご躊躇なさって、「改まって申し出るのも、世間の人が思うところも馬鹿馬鹿しい。
どのような機会にそれとなく切り出したらよかろう」などと、お考えだったところ、三月二十日が、大殿の大宮の御忌日なので、極楽寺に参詣なさった。
|
表面は何もないふうをしていても、あのことがあってからは心から親しめない間柄になっているのであるから、突然言い出すのも如何なものであると大臣ははばかられた。新しい婿迎えの形式をとるのも他人が見ておかしく思うことであろうから、そんなふうにはせずによい機会に直接話してみたほうがよいかもしれないなどと思っていたが、三月の二十日は大宮の御忌日であって、極楽寺へ一族の参詣することがあった。
|
【ゆくりなく言ひ寄らむもいかが】- 内大臣の心中。
【ことことしくもてなさむも】- 以下「ほのめかすべき」(5行)まで、内大臣の心中。
【三月二十日、大殿の大宮の御忌日にて、極楽寺に詣でたまへり】- 大宮の一周忌。その薨去は物語に語られていないが、「行幸」巻に「去年の冬つ方より悩みたまふ」(第一章五段)とあり、「藤袴」巻(第一章二段)に玉鬘が祖母の喪に服している様が語られている。
|
|
第二段 三月二十日、極楽寺に詣でる
|
| 1.2.1 |
君達皆ひき連れ、勢ひあらまほしく、上達部などもあまた参り集ひたまへるに、宰相中将、をさをさけはひ劣らず、よそほしくて、容貌など、ただ今のいみじき盛りにねびゆきて、取り集めめでたき人の御ありさまなり。 |
ご子息たちを皆引き連れて、ご威勢この上なく、上達部なども大勢参集なさっていたが、宰相中将、少しも引けを取らず、堂々とした様子で、容貌など、ちょうど今が盛りに美しく成人されて、何もかもすべて結構なご様子である。
|
内大臣は子息たちを皆引き連れて行っていて、すばらしく権勢のある家のことであるから多数の高官たちも法会に参列したが、宰相中将はそうした高官たちに遜色のない堂々とした風采をしていて、容貌なども今が盛りなようにもととのっているのであるから、高雅な最も貴い若い朝臣と見えた。
|
【いみじき盛りにねびゆきて】- 夕霧、十八歳。
|
| 1.2.2 |
この大臣をば、つらしと思ひきこえたまひしより、見えたてまつるも、心づかひせられて、いといたう用意し、もてしづめてものしたまふを、大臣も、常よりは目とどめたまふ。御誦経など、六条院よりもせさせたまへり。宰相君は、まして、よろづをとりもちて、あはれにいとなみ仕うまつりたまふ。 |
この大臣を、ひどいとお思い申し上げなさってから、お目にかかるのも、つい気が張って、とてもひどく気をつかって、取り澄ましていらっしゃるのを、大臣も、いつもよりは注目なさっている。
御誦経など、六条院からもおさせになった。
宰相の君は、誰にもまして、万端のことを引き受けて、真心をこめて奉仕していらっしゃる。
|
恨めしかったあの時以来、いつも内大臣と逢うのは晴れがましいことに思われて、今日なども親戚じゅうの長者としての敬意だけを十分に見せて、そしてきわめて冷静に落ち着いた態度をとっている宰相中将に、今日の内大臣は特に関心が持たれた。仏前の誦経などは源氏からもさせた。中将は最も愛された祖母の宮の法事であったから、経巻や仏像その他の供養のことにも誠心をこめた奉仕ぶりを見せた。
|
【まして、よろづをとりもちて】- 『集成』は「(幼少の頃育てられた外祖母のこととて)誰にもまして、万端のことを引き受けて」。『完訳』は「自分を愛育してくれた祖母と思うと、誰にもまして」と訳す。
|
| 1.2.3 |
夕かけて、皆帰りたまふほど、花は皆散り乱れ、霞たどたどしきに、大臣、昔を思し出でて、なまめかしううそぶき眺めたまふ。宰相も、あはれなる夕べのけしきに、いとどうちしめりて、「雨気あり」と、人びとの騒ぐに、なほ眺め入りてゐたまへり。心ときめきに見たまふことやありけむ、袖を引き寄せて、 |
夕方になって、皆がお帰りになるころ、花はみな散り乱れ、霞の朧ろな中に、内大臣、昔をお思い出して、優雅に口ずさんで物思いに耽っていらっしゃる。
宰相も、しみじみとした夕方の景色に、ますます物思いに沈んだ面持ちで、「雨が降りそうです」と、人々が騒いでいるのに、依然として物思いに耽りきっていらっしゃった。
心をときめかせて御覧になることがあるのであろうか、袖を引き寄せて、
|
夕方になって参会者の次々に帰るころ、木の花は大部分終わりがたになって散り乱れた庭に霞もよどんで春の末の哀愁の深く身にしむ景色を、大臣は顔を上げて母宮のおいでになった昔の日を思いながら、雅趣のある姿でながめていた。宰相中将も身にしむ夕べの気に仏事中よりもいっそうめいった心持ちになって、「雨になりそうだ」などと退散して行く人たちの言い合っている声も聞きながらなお庭のほうばかりがながめられた。好機会であるとも大臣は思ったのか、源中将の袖を引き寄せて、
|
【心ときめきに見たまふことやありけむ】- 『完訳』は「夕霧が雲居雁とのことを思っているのかと、心ときめかせてごらんになったのか。語り手の推測」と注す。語り手が内大臣の心中を推測した挿入句。
|
| 1.2.4 |
「などか、いとこよなくは勘じたまへる。今日の御法の縁をも尋ね思さば、罪許したまひてよや。残り少なくなりゆく末の世に、思ひ捨てたまへるも、恨みきこゆべくなむ」 |
「どうして、そんなにひどく怒っておいでなのか。
今日の御法要の縁故をお考えになれば、不行届きはお許し下さいよ。
余命少なくなってゆく老いの身に、お見限りなさるのも、お恨み申し上げたい」
|
「どうしてあなたはそんなに私を憎んでいるのですか。今日の御法会の仏様の縁故で私の罪はもう許してくれたまえ。老人になってどんなに肉身が恋しいかしれない私に、あまり厳罰をあなたが加え過ぎるのも恨めしいことです」
|
【などか、いとこよなくは】- 以下「恨みきこゆべくなむ」まで、内大臣の詞。
|
| 1.2.5 |
とのたまへば、うちかしこまりて、
|
とおっしゃるので、ちょっと恐縮して、
|
などと言うと、中将は畏まって、
|
|
| 1.2.6 |
|
「故人のご意向も、お頼り申し上げるようにと、承っておりましたが、お許しのないご様子に、遠慮致しておりました」
|
「お亡れになりました方の御遺志も、あなたを御信頼申して、庇護されてまいるようにということであったように心得ておりましたが、私をお許しくださいません御様子を拝見するものですから御遠慮しておりました」
|
【過ぎにし御おもむけも】- 以下「はばかりつつ」まで、夕霧の返事。「過ぎにし御おもむけ」は故大宮の御意向の意。
|
| 1.2.7 |
と聞こえたまふ。
|
とお答え申し上げになる。
|
と言っていた。
|
|
| 1.2.8 |
心あわたたしき雨風に、皆ちりぢりに競ひ帰りたまひぬ。君、「いかに思ひて、例ならずけしきばみたまひつらむ」など、世とともに心をかけたる御あたりなれば、はかなきことなれど、耳とまりて、とやかうやと思ひ明かしたまふ。 |
気ぜわしい雨風に、皆ばらばらに急いでお帰りになった。
宰相の君は、「どのようにお考えになって、いつもとは違って、あのようなことをおっしゃったのだろうか」などと、絶えず気にかけていらっしゃる内大臣家のことなので、ちょっとしたことであるが、耳が止まって、ああかこうかと、考えながら夜をお明かしになる。
|
天侯が悪くなって雨風の中をこの人たちはそれぞれ急ぎ立てられるように家へ帰った。宰相中将は大臣がどうして平生と違った言葉を自分にかけたのであろうと、無関心でいる時のない恋人の家のことであるから、何でもないことも耳にとまって、いろいろな想像を描いていた。
|
【いかに思ひて】- 以下「見たまひつらむ」まで、夕霧の心中。
【けしきばみ】- 『集成』は「(雲居の雁とのことを)許してもよいような」。『完訳』「親しげな態度を」と訳す。
|
|
第三段 内大臣、夕霧を自邸に招待
|
| 1.3.1 |
ここらの年ごろの思ひのしるしにや、かの大臣も、名残なく思し弱りて、はかなきついでの、わざとはなく、さすがにつきづきしからむを思すに、四月の朔日ごろ、御前の藤の花、いとおもしろう咲き乱れて、世の常の色ならず、ただに見過ぐさむこと惜しき盛りなるに、遊びなどしたまひて、暮れ行くほどの、いとど色まされるに、頭中将して、御消息あり。 |
長い年月思い続けてきた甲斐あってか、あの内大臣も、すっかり気弱になって、ちょっとした機会で、特別にというのでなく、そうはいっても相応しい時期をお考えになって、四月の初旬ころ、お庭先の藤の花、たいそうみごとに咲き乱れて、世間にある藤の花の色とは違って、何もしないのも惜しく思われる花盛りなので、管弦の遊びなどをなさって、日が暮れてゆくころの、ますます色美しくなってゆく時分に、頭中将を使いとして、お手紙がある。
|
長い年月の間純情をもって雲井の雁を思っていた宰相中将の心が通じたのか、内大臣は昔のその人とは思われないほど謙遜な娘の親の心になって宰相中将を招くのにわざとらしくない機会を、しかも最もふさわしいような機会のあるのを願っていたが、四月の初めに庭の藤の花が美しく咲いて、すぐれた紫の花房のなびき合うながめを、もてはやしもせずに過ごしてしまうのが残念になって、音楽の遊びを家でした時に、藤の花が夕方になっていっそう鮮明に美しく見えるからといって、長男の頭中将を使いにして源中将を迎えにやった。
|
【ここらの年ごろの思ひのしるしにや】- 『集成』は「夕霧の側に立った叙述」。『完訳』は「「--にや」は、語り手の推測」。語り手の推測。
【四月の朔日ごろ】- 大島本は「四月のついたちころ」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「四月朔日ごろ」と「の」を削除する。四月上旬の意。後文に「七日の夕月夜」とある。
|
| 1.3.2 |
|
「先日の花の下でお目にかかったことが、堪らなく思われたので、お暇があったら、お立ち寄りなさいませんか」
|
「極楽寺の花蔭ではお話もゆっくりとする間のありませんでしたことが遺憾でなりませんでした。それでもしお閑暇があるようでしたらおいでくださいませんか」
|
【一日の花の蔭の対面】- 以下「立ち寄りたまひなむや」まで、内大臣からの伝言、頭中将が口頭で伝える。
|
| 1.3.3 |
とあり。
御文には、
|
とある。
お手紙には、
|
というのが大臣の伝えさせた言葉である。手紙には、
|
|
| 1.3.4 |
|
「わたしの家の藤の花の色が濃い夕方に
訪ねていらっしゃいませんか、
|
わが宿の藤の色濃き黄昏に
たづねやはこぬ春の名残を
|
【わが宿の藤の色濃きたそかれに--尋ねやは来ぬ春の名残を】- 内大臣から夕霧への贈歌。『白氏文集』の「惆悵す春帰って留むることを得ざることを紫藤の花の下に漸く黄昏たり」(和漢朗詠集、春、三月尽)を踏まえる。夕霧招待の主旨。
|
| 1.3.5 |
げに、いとおもしろき枝につけたまへり。待ちつけたまへるも、心ときめきせられて、かしこまりきこえたまふ。 |
おっしゃる通り、たいそう美しい枝に付けていらっしゃった。
心待ちしていらっしゃったのにつけても、心がどきどきして、恐縮してお返事を差し上げなさる。
|
とあった。歌われてあるとおりにすぐれた藤の花の枝にそれは付けてあった。使いを受けた中将は心のときめくのを覚えた。そして恐縮の意を返事した。
|
【待ちつけたまへるも】- 夕霧は極楽寺で内大臣に会って以後、心密かに期待するところがあった。
|
| 1.3.6 |
|
「かえって藤の花を折るのにまごつくのではないでしょうか
夕方時のはっきりしないころでは」
|
なかなかに折りやまどはん藤の花
たそがれ時のたどたどしくば
|
【なかなかに折りやまどはむ藤の花--たそかれ時のたどたどしくは】- 夕霧の返歌。本当に伺ってよいのでしょうか、というのが表面の意。「(花を)折る」には結婚する、の意がこめられている。
|
| 1.3.7 |
と聞こえて、
|
と申し上げて、
|
というのである。
|
|
| 1.3.8 |
|
「残念なほど、
気後れしてしまった。適当に
|
「気おくれがして歌になりませんよ。直してください」
|
【口惜しくこそ】- 以下「取り直したまへ」まで、夕霧の詞。意の満たないところの取りなしを柏木に依頼。
|
| 1.3.9 |
と聞こえたまふ。
|
と申し上げなさる。
|
と宰相中将は従兄に言った。
|
|
| 1.3.10 |
|
「お供しましょう」
|
「お供して行きましょう」
|
【御供にこそ】- 柏木の詞。お供をしてご案内しましょうと、いう意。
|
| 1.3.11 |
とのたまへば、
|
とおっしゃったが、
|
|
|
| 1.3.12 |
|
「面倒なお供はいりません」
|
「窮屈な随身はいやですよ」
|
【わづらはしき随身は、否】- 夕霧の詞。拒否。柏木が中将なので戯れて大袈裟に言ったもの。
|
| 1.3.13 |
とて、返しつ。
|
と言って、お帰しになった。
|
と言って、源中将は従兄を帰した。
|
|
| 1.3.14 |
大臣の御前に、かくなむ、とて、御覧ぜさせたまふ。 |
大臣の御前に、これこれしかじかです、と言って、御覧にお入れになる。
|
中将は父の源氏の居間へ行って、頭中将が使いに来たことを言って内大臣の歌を見せた。
|
【かくなむ】- 夕霧の詞。間接話法、語り手がまとめたもの。
|
| 1.3.15 |
|
「考えがあっておっしゃっているのであろうか。
そのように先方から折れて来られたのならば、故人への不孝の恨みも解けることだろう」
|
「ほかの意味があってお招きになるのかもしれない。そんなふうな態度に出てくればおもしろくなかった旧恨というものも消されるだろう。どうだね」
|
【思ふやうありて】- 以下「恨みも解けめ」まで、源氏の詞。
【ものしたまひつるにや】- 大島本は「ものし給つるにや」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「ものしたまへる」と校訂する。
|
| 1.3.16 |
|
とおっしゃる。
そのご高慢は、この上なく憎らしいほどである。
|
と源氏は言った。婿の親として源氏はこんなに自尊心が強かった。
|
【こよなうねたげなり】- 語り手の評言。
|
| 1.3.17 |
「さしもはべらじ。対の前の藤、常よりもおもしろう咲きてはべるなるを、静かなるころほひなれば、遊びせむなどにやはべらむ」 |
「そうではございますまい。
対の屋の前の藤が、例年よりも美しく咲いているというので、暇なころなので、管弦の遊びをしようなどというのでございましょう」
|
「そんな意味でもないでしょう。対の前の藤が例年よりもみごとに咲いていますからこのごろの閑暇なころに音楽の合奏でもしようとされるのでしょう」
|
【さしもはべらじ】- 以下「などにやはべらむ」まで、夕霧の詞。
|
| 1.3.18 |
と申したまふ。
|
と申し上げなさる。
|
と宰相中将は父に言うのであった。
|
|
| 1.3.19 |
|
「わざわざ使者をさし向けられたのだから、早くお出掛けなさい」
|
「特使がつかわされたのだから早く行くがよい」
|
【わざと使ひさされたりけるを、早うものしたまへ】- 源氏の詞。夕霧に内大臣邸に行くようを促す。
|
| 1.3.20 |
|
とお許しになる。
どんなだろうと、内心は不安で、落ち着かない。
|
と源氏は許した。中将はああは言っていても、心のうちは期待されることと、一種の不安とが一つになって苦しかった。
|
【許したまふ】- 源氏、夕霧の出向くこと、すなわち内大臣家の婿となることを承諾。
【いかならむ】- 夕霧の不安な心中。
|
| 1.3.21 |
「直衣こそあまり濃くて、軽びためれ。非参議のほど、何となき若人こそ、二藍はよけれ、ひき繕はむや」 |
「直衣はあまりに色が濃過ぎて、身分が軽く見えよう。
非参議のうちとか、何でもない若い人は、二藍はよいだろうが、お召し替えになるかね」
|
「その直衣の色はあまり濃くて安っぽいよ。非参議級とかまだそれにならない若い人などに二藍というものは似合うものだよ。きれいにして行くがよい」
|
【直衣こそ】- 以下「ひき繕はむや」まで、源氏の詞。夕霧が今着ている濃い二藍(赤みのある青色)の直衣を、縹色(薄い藍色)に着替えるようにと、自分の衣裳を贈る。非参議や若人は二藍の直衣を好んで着たらしい。が、それ以上の人(参議)は、縹色の直衣が相応しい、というのが源氏の考え。
|
| 1.3.22 |
とて、わが御料の心ことなるに、えならぬ御衣ども具して、御供に持たせてたてまつれたまふ。
|
とおっしゃって、ご自分のお召し物の格別見事なのに、何ともいえないほど素晴らしい御下着類を揃えて、お供に持たせて差し上げなさる。
|
と源氏は自身用に作らせてあったよい直衣に、その下へ着る小袖類もつけて中将の供をして来ていた侍童に持たせてやった。
|
|
|
第四段 夕霧、内大臣邸を訪問
|
| 1.4.1 |
|
ご自分のお部屋で、念入りにおめかしなさって、黄昏時も過ぎ、じれったく思うころに参上なさった。
主人のご子息たち、中将をはじめとして、七、八人うち揃ってお出迎えなさる。
どの方となくいずれも美しい器量の方々だが、やはり、その人々以上に、水際立って美しい一方、優しく、優雅で、犯しがたい気品がある。
|
中将は自身の居間のほうで念の入った化粧をしてから黄昏時も過ぎて、待つほうで気のもまれる時刻に内大臣家へ行った。公達が中将をはじめとして七、八人出て来て宰相中将を座に招じた。皆きれいな公子たちであるが、その中にも源中将は最もすぐれた美貌を持っていた。気高い貴人らしいところがことに目にたった。
|
【わが御方にて、心づかひいみじう化粧じて】- 夕霧、召替えて内大臣邸に出向く。「わが御方」は六条院の夏の御殿であろう。
【たそかれ】- 「誰別 タソカレ」(文明本節用集)。清音で読む。
【あざやかにきよらなるものから、なつかしう、よしづき、恥づかしげなり】- 夕霧の容姿。『完訳』は「すっきりとおきれいであるものの、やさしい魅力があり、風格もあっていかにも人を気おくれさせるご立派さである」と訳す。
|
| 1.4.2 |
大臣、御座ひきつくろはせなどしたまふ御用意、おろかならず。御冠などしたまひて、出でたまふとて、北の方、若き女房などに、 |
内大臣、お座席を整え直させたりなさるご配慮、並大抵でない。
御冠などお付けになって、お出になろうとして、北の方や、若い女房などに、
|
内大臣は若い甥のために座敷の中の差図などをこまごまとしていた。大臣は夫人や若い女房などに、
|
【冠などしたまひて】- 直衣姿は烏帽子を着けるが、束帯姿の時の冠を着けて、内大臣は改まった態度を示した。
|
| 1.4.3 |
「覗きて見たまへ。いと警策にねびまさる人なり。用意などいと静かに、ものものしや。あざやかに、抜け出でおよすけたる方は、父大臣にもまさりざまにこそあめれ。 |
「覗いて御覧なさい。
たいそう立派になって行かれる方だ。
態度などもとても沈着で、堂々としたものだ。
はっきりと、抜きん出て成人された点では、父の大臣よりも勝っているようだ。
|
「のぞいてごらん。ますますきれいになった人だよ。とりなしが静かで、堂々として鮮明な美しさは源氏の大臣以上だろう。
|
【覗きて見たまへ】- 以下「世におぼえためり」まで、内大臣も詞。
|
| 1.4.4 |
|
あの方は、ただ非常に優美で愛嬌があって、見るとついほほ笑みたくなり、世の中の憂さを忘れるような気持ちにおさせになる。
政治の面では、多少柔らかさ過ぎて、謹厳さに欠けるところがあったのは、もっともなことだ。
|
お父様のほうはただただ艶で、愛嬌があって、見ている者のほうも自然に笑顔が作られるようで、人生の苦というようなものを忘れ去ることのできる力があった。公務を執ることなどはそうまじめにできなかったものだ。しかもこれが道理だと思われたものだ。
|
【公ざまは、すこしたはれて、あざれたる方なりし、ことわりぞかし】- 『集成』は「政治家としては、少し謹厳さを欠いて、儀式ばらないところがあったが、それもあの人柄からすれば無理もないことだ。杓子定規な実務家タイプでないと言う。一世の源氏として、帝の膝下で育ったからである」と注す。
|
| 1.4.5 |
これは、才の際もまさり、心もちゐ男々しく、すくよかに足らひたりと、世におぼえためり」
|
この方は、学問の才能も優れ、心構えも男らしく、しっかりしていて申し分ないと、世間の評判のようだ」
|
この人のほうは学問が十分にできているし、性質がしっかりとしていてりっぱな官吏だと世間から認められているらしいよ」
|
|
| 1.4.6 |
などのたまひてぞ、対面したまふ。
ものまめやかに、むべむべしき御物語は、すこしばかりにて、花の興に移りたまひぬ。
|
などとおっしゃって、対面なさる。
儀礼的で、固苦しいご挨拶は、少しだけにして、花の美しさに興味はお移りになった。
|
などと言っていたが、身なりを正しく直して宰相中将に面会した。まじめな話は挨拶に続いて少ししただけであとは藤の宴に移った。
|
|
| 1.4.7 |
|
「春の花、どれもこれも皆咲き出す色ごとに、目を驚かさない物はないが、気ぜわしく人の気も構わず散ってしまうのが、恨めしく思われるころに、この藤の花だけがひとり遅れて、夏に咲きかかるのが、妙に奥ゆかしくしみじみと思われます。
色も色で、懐しい由縁の物といえましょう」
|
「春の花というものは、どの花だって咲いた最初に目ざましい気のしないものはないが、長くは人を楽しませずにどんどんと散ってしまうのが恨めしい気のするころに、藤の花だけが一歩遅れて、夏にまたがって咲くという点でいいものだと心が惹かれて、私はこの花を愛するのですよ。色だって人の深い愛情を象徴しているようでいいものだから」
|
【春の花、いづれとなく】- 以下「かこつべし」まで、内大臣の詞。
【目おどろかぬはなきを】- 大島本は「め越おとろかぬハなきを」とある。『集成』『古典セレクション』『新大系』は諸本に従って「目おどろかぬは」と「を」を削除する。
【夏に咲きかかる】- 「夏にこそ咲きかかりけれ藤の花松にとのみも思ひけるかな」(拾遺集夏、八三、源重之)をふまえる。
|
| 1.4.8 |
とて、うちほほ笑みたまへる、けしきありて、匂ひきよげなり。
|
と言って、ちょっとほほ笑んでいらっしゃる、風格があって、つややかでお美しい。
|
と言って微笑している大臣の顔も品がよくてきれいであった。
|
|
|
第五段 藤花の宴 結婚を許される
|
| 1.5.1 |
月はさし出でぬれど、花の色さだかにも見えぬほどなるを、もてあそぶに心を寄せて、大酒参り、御遊びなどしたまふ。大臣、ほどなく空酔ひをしたまひて、乱りがはしく強ひ酔はしたまふを、さる心して、いたうすまひ悩めり。 |
月は昇ったが、花の色がはっきりと見えない時分なのだが、花を愛でる心に寄せて、御酒を召して、管弦のお遊びなどをなさる。
大臣、程もなく空酔いをなさって、遠慮もせずに無理に酔わせなさるが、用心して、とても断るのに困っているようである。
|
月が出ても藤の色を明らかに見せるほどの明りは持たないのであるが、ともかくも藤を愛する宴として酒杯が取りかわされ、音楽の遊びをした。しばらくして大臣は酔った振りになって宰相中将に酒をしいようとした。源中将は酔いつぶされまいとして、それを辞し続けていた。
|
【さる心して、いたうすまひ悩めり】- 「めり」推量の助動詞、視界内推量。語り手がその場に居合わせて夕霧の心中や態度を忖度しているような臨場感ある表現。
|
|
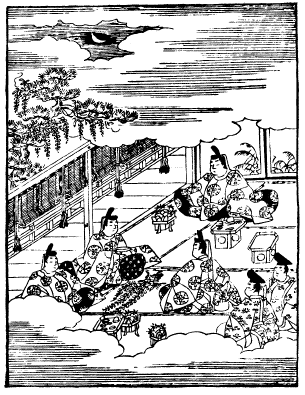 |
| 1.5.2 |
|
「あなたは、この末世にできすぎるほどの、天下の有識者でいらっしゃるようだが、年を取った者を、お忘れになっていらっしゃるのが辛いことだ。
古典にも、家礼ということがあるではありませんか。
誰それの教えにも、よくご存知でいらっしゃろうと存じますが、ひどく辛い思いをおさせになると、お恨み申し上げたいのです」
|
「あなたは末世に過ぎた学才のある人物でいながら、年のいった者を憐んでくれないのは恨めしい。書物にもあるでしょう、家の礼というものが。甥は伯父を愛して敬うべきものですよ。孔子の教えには最もよく通じていられるはずなのだが、私を悩まし抜かれたとそう恨みが言いたい」
|
【君は、末の世にはあまるまで】- 以下「恨みきこゆべくなむ」まで、内大臣の詞。夕霧の学殖をほめたたえ、自分の顧みられないさまを恨みごとに言う。
【文籍にも、家礼といふことあるべくや】- 『史記』「高祖五日に一たび大公に朝すること、家人父子の礼の如し」(高祖本紀)を踏まえた表現。父子の礼をいう、すなわち舅と婿との関係であることをいう。
【なにがしの教へも】- 聖賢の教え。儒教をさす。
|
| 1.5.3 |
|
などとおっしゃって、酔い泣きというのか、ほどよく抑えて意中を仄めかしなさる。
|
などと言って、それは酒に酔って感傷的になっているのか源中将を少しばかり困らせた。
|
【酔ひ泣きにや】- 「にや」連語(断定の助動詞「に」、係助詞「や」)。語り手の推測。臨場感ある表現。挿入句。
|
| 1.5.4 |
「いかでか。昔を思うたまへ出づる御変はりどもには、身を捨つるさまにもとこそ、思うたまへ知りはべるを、いかに御覧じなすことにかはべらむ。もとより、おろかなる心のおこたりにこそ」 |
「どうしてそのような。
今は亡き方々を思い出しますお身変わりとして、わが身を捨ててまでもと、存じておりますのに、どのように御覧になってのことでございましょうか。
もともと、わたしのうかつな心の至らなさのためです」
|
「伯父様を決して粗略には思っておりません。御恩のあるお祖父様の代わりと思いますだけでも、私の一身を伯父様の犠牲にしてもいいと信じているのですが、どんなことがお気に入らなかったのでしょう。もともと頭がよくないのでございますから、自身でも気づかずに失礼をしていたのでございましょう」
|
【いかでか】- 以下「おこたりにこそ」まで、夕霧の返事。内大臣の言葉を否定し、自分の至らなさであると詫びる。
|
| 1.5.5 |
と、かしこまりきこえたまふ。
御時よく、さうどきて、
|
と、恐縮して申し上げなさる。
頃合いを見計らって、はやし立てて、
|
とうやうやしく源中将は言うのであった。よいころを見て大臣は機嫌よくはしゃぎ出して
|
|
| 1.5.6 |
|
「藤の裏葉の」
|
「藤のうら葉の」(春日さす藤のうら葉のうちとけて君し思はばわれも頼まん)
|
【藤の裏葉の】- 内大臣の詞。「春日さす藤の裏葉のうらとけて君し思はば我も頼まむ」(後撰集春下、一〇〇、読人しらず)を口ずさむ。『完訳』は「結婚の許諾の意をこめた」と注す。
|
| 1.5.7 |
とうち誦じたまへる、御けしきを賜はりて、頭中将、花の色濃く、ことに房長きを折りて、客人の御盃に加ふ。取りて、もて悩むに、大臣、 |
とお謡いになった、そのお心をお受けになって、頭中将、藤の花の色濃く、特に花房の長いのを折って、客人のお杯に添えになる。
受け取って、もてあましていると、内大臣、
|
と歌った。命ぜられて頭中将が色の濃い、ことに房の長い藤を折って来て源中将の杯の台に置き添えた。源中将は杯を取ったが、酒の注がれる迷惑を顔に現わしている時、大臣は、
|
【房長きを折りて】- 聞得園中花養艶 請君許折一枝花(和漢朗詠下-七八四 無名)(text33.html 出典7から転載)
|
| 1.5.8 |
|
「紫色のせいにしましょう、
藤の花の待ち過ぎてしまって恨めし
|
紫にかごとはかけん藤の花
まつより過ぎてうれたけれども
|
【紫にかことはかけむ藤の花--まつより過ぎてうれたけれども】- 内大臣の夕霧への贈歌。「紫」は雲居雁をさす。「まつ」に「松」と「待つ」を掛け、「憂(う)れ」に「末(うれ)」を懸ける。「藤」と「末」は縁語。あなたを婿とすることが、藤が松の木を越えるほど長く待たされたことが恨めしい、しかし、それも藤(娘)のせいで、という。 【かこと】-「カコト カゴト」(日葡辞書)。
|
| 1.5.9 |
宰相、盃を持ちながら、けしきばかり拝したてまつりたまへるさま、いとよしあり。
|
宰相中将、杯を持ちながら、ほんの形ばかり拝舞なさる様子、実に優雅である。
|
と歌った。杯を持ちながら頭を下げて謝意を表した源中将はよい形であった。
|
|
| 1.5.10 |
|
「幾度も湿っぽい春を過ごして来ましたが
今日初めて花の開くお許しを得ることができました」
|
いく返り露けき春をすぐしきて
花の紐とく折に逢ふらん
|
【いく返り露けき春を過ぐし来て--花の紐解く折にあふらむ】- 「いくかへり咲き散る花をながめつつ物思ひくらす春に逢ふらむ」(新古今集恋一、一〇一七、大中臣能宣)の類歌がある。長年待ち続けた結婚の許諾が出た感激を歌う。
|
| 1.5.11 |
頭中将に賜へば、
|
頭中将にお廻しになると、
|
と歌った源中将は杯を頭中将にさした。
|
|
| 1.5.12 |
|
「うら若い女性の袖に見違える藤の花は
見る人の立派なためかいっそう美しさを増すことでしょう」
|
たをやめの袖にまがへる藤の花
見る人からや色もまさらん
|
【たをやめの袖にまがへる藤の花--見る人からや色もまさらむ】- 柏木の唱和歌。
|
| 1.5.13 |
|
次々と杯が回り歌を詠み添えて行ったようであるが、酔いの乱れに大したこともなく、これより優れていない。
|
頭中将の歌である。二男以下にもその型で杯がまわされ「みさかな」の歌がそれぞれ出たわけであるが、酔っている人たちの作ったものであったから、以上の三首よりよいというものもなかった。
|
【次々順流るめれど、酔ひの紛れにはかばかしからで、これよりまさらず】- 「めれ」推量の助動詞、視界内推量・主観的推量、「これより勝らず」という評言は、語り手。『集成』は「以下の歌を省略する旨の草子地」と注す。
|
|
第六段 夕霧、雲居雁の部屋を訪う
|
| 1.6.1 |
七日の夕月夜、影ほのかなるに、池の鏡のどかに澄みわたれり。
げに、まだほのかなる梢どもの、さうざうしきころなるに、いたうけしきばみ横たはれる松の、木高きほどにはあらぬに、かかれる花のさま、世の常ならずおもしろし。
|
七日の夕月夜、月の光は微かであるのに、池の水が鏡のように静かに澄み渡っている。
なるほど、まだ茂らない梢が、物足りないころなので、たいそう気取って横たわっている松の、木高くないのに、咲き掛かっている藤の花の様子、世になく美しい。
|
七日の夕月夜の中に池がほの白く浮かんで見えた。大臣の言葉のように、春の花が皆散ったあとで若葉もありなしの木の梢の寂しいこのごろに、横が長く出た松の、たいして大木でないのへ咲きかかった藤の花は非常に美しかった。
|
|
| 1.6.2 |
|
例によって、弁少将が、声をたいそう優しく「葦垣」を謡う。
大臣、
|
例の美音の弁の少将がなつかしい声で催馬楽の「葦垣」を歌うのであった。
|
【例の、弁少将】- 柏木の弟、紅梅大納言。「賢木」巻に初出、そこで催馬楽「高砂」を謡い、「梅枝」巻では催馬楽「梅が枝」を謡う。
【葦垣」を謡ふ】- 「葦垣真垣 真垣かきわけ てふ越すと 負ひ越すと 誰 てふ越すと 誰か 誰か この事を 親に 申よこし申しし とどろける この家 この家の 弟嫁 親に申よこしけらしも」(催馬楽・葦垣)。『集成』は「内大臣が結婚を許したことを口惜しく思う気持から、わが家の姫を盗んでゆくのは誰だとあてこすったもの」と注す。
|
| 1.6.3 |
|
「実に妙な歌を謡うものだな」
|
「すばらしいね」
|
【いとけやけうも仕うまつるかな】- 内大臣の詞。『完訳』は「歌の文句があてつけがましいとする」と注す。
|
| 1.6.4 |
と、うち乱れたまひて、
|
と、冗談をおっしゃって、
|
と大臣は戯談を言って、
|
|
| 1.6.5 |
|
「年を経たこの家の」
|
「年経にけるこの家の」
|
【年経にけるこの家の】- 内大臣の歌。催馬楽「葦垣」の「とどろけるこの家の」の文句を歌い替えたもの。『集成』は「古い家であるわが家の、と謙遜の意を示す」と注す。
|
| 1.6.6 |
と、うち加へたまへる御声、いとおもしろし。
をかしきほどに乱りがはしき御遊びにて、もの思ひ残らずなりぬめり。
|
と、お添えになるお声、誠に素晴らしい。
興趣ある中に冗談も混じった管弦のお遊びで、気持ちのこだわりもすっかり解けてしまったようである。
|
と上手に声を添えた。おもしろい夕月夜の藤の宴に宰相中将の憂愁は余す所なく解消された。
|
|
| 1.6.7 |
やうやう夜更け行くほどに、いたうそら悩みして、
|
だんだんと夜が更けて行くにつれて、ひどく苦しげな様子をして見せて、
|
夜がふけてから源中将は酔いに悩むふうを作って、
|
|
| 1.6.8 |
「乱り心地いと堪へがたうて、まかでむ空もほとほとしうこそはべりぬべけれ。宿直所譲りたまひてむや」 |
「酔いが回ってひどく辛いので、帰り道も危なそうです。
泊まる部屋を貸していただけませんか」
|
「あまり酔って苦しくてなりません。無事に帰りうる自信も持てませんからあなたの寝室を拝借できませんか」
|
【乱り心地】- 以下「宿直所譲りたまひてむや」まで、夕霧の詞。宿泊を所望する。
|
| 1.6.9 |
と、中将に愁へたまふ。
大臣、
|
と、頭中将に訴えなさる。
大臣が、
|
と頭中将に言っていた。大臣は、
|
|
| 1.6.10 |
|
「朝臣よ、お休み所になる部屋を用意しなさい。
老人はひどく酔いが回って失礼だから、引っ込むよ」
|
「ねえ朝臣、寝床をどこかで借りなさい。老人は酔っぱらってしまって失礼だからもう引き込むよ」
|
【朝臣や、御休み所求めよ】- 以下「まかり入りぬ」まで、内大臣の詞。息子の頭中将に部屋を準備するように言いつけて、退出。
|
| 1.6.11 |
と言ひ捨てて、入りたまひぬ。
|
と言い捨てて、お入りになってしまった。
|
と言い捨てて居間のほうへ行ってしまった。
|
|
| 1.6.12 |
中将、
|
頭中将が、
|
頭中将が、
|
|
| 1.6.13 |
|
「花の下の旅寝ですね。
どういうものだろう、辛い案内役ですね」
|
「花の蔭の旅寝ですね。どうですか、あとで迷惑になる案内役ではないかしら」
|
【花の蔭の旅寝よ】- 以下「はべるや」まで、柏木の詞。「花」は雲居雁を喩える。案内するにあたっての冗談。
|
| 1.6.14 |
と言へば、
|
と言うと、
|
|
|
| 1.6.15 |
|
「松と約束したのは、浮気な花なものですか。
縁起でもありません」
|
「寄りかかって松と同じ精神で咲く藤なのですから、これは軽薄な花なものですか。とにかくそんな縁起でもない言葉は使わないでおきましょう」
|
【松に契れるは】- 以下「ゆゆしや」まで、夕霧の返事。
|
| 1.6.16 |
と責めたまふ。
中将は、心のうちに、「ねたのわざや」と思ふところあれど、人ざまの思ふさまにめでたきに、「かうもあり果てなむ」と、心寄せわたることなれば、うしろやすく導きつ。
|
と反発なさる。
中将は、心中に、「憎らしいな」と思うところがあるが、人柄が理想通り立派なので、「最後はこのようになって欲しい」と、願って来たことなので、心許して案内した。
|
と言って、中将の先導をなお求める宰相中将であった。頭中将は負けたような気がしないでもなかったが、源中将はりっぱな公子であったから、ぜひ妹との結婚を成立させたいとはこの人の念願だったことであって、満足を感じながら従弟を妹の所へ導いた。
|
|
| 1.6.17 |
男君は、夢かとおぼえたまふにも、わが身いとどいつかしうぞおぼえたまひけむかし。女は、いと恥づかしと思ひしみてものしたまふも、ねびまされる御ありさま、いとど飽かぬところなくめやすし。 |
男君は、夢かと思われなさるにつけても、自分の身がますます立派に思われなさったことであろう。
女は、とても恥ずかしいと思い込んでいらっしゃるが、大人になったご様子は、ますます不足なところもなく素晴らしい。
|
宰相中将はこうした立場を与えられるに至った夢のような運命の変わりようにも自己の優越を感じた。雲井の雁はすっかり恥ずかしがっているのであったが、別れた時に比べてさらに美しい貴女になっていた。
|
【男君は】- 以下「おぼえたまひけむかし」まで、語り手の挿入句。『集成』は「草子地」と注す。
|
| 1.6.18 |
|
「世間の話の種となってしまいそうな身の上を、その誠実さをもって、このようにお許しになったのでしょう。
わたしの気持ちをお分りになって下さらないとは、変なことですね」
|
「みじめな失恋者で終わらなければならなかった私が、こうして許しを受けてあなたの良人になり得たのは、あなたに対する熱誠がしからしめたのですよ。だのにあなたは無関心に冷ややかにしておいでになる」
|
【世の例にもなりぬべかりつる身を】- 以下「さまことなるわざかな」まで、夕霧の雲居雁への詞。『集成』は「恋しきに死ぬるものとは聞かねども世のためしにもなりぬべきかな」(古今六帖四、恋、一九八六、伊勢)、『完訳』は「恋ひわびて死ぬてふことはまだなきを世のためしにもなりぬべきかな」(後撰集恋六、一〇三六、壬生忠岑)を引歌として指摘する。
【あはれを知りたまはぬも】- 「梅枝」巻の雲居雁の返歌「限りとて忘れがたきを忘るるもこや世に靡く心なるらむ」(第三章三段)を受ける。
|
| 1.6.19 |
と、怨みきこえたまふ。
|
と、お恨み申し上げなさる。
|
と男は恨んだ。
|
|
| 1.6.20 |
「少将の進み出だしつる『葦垣』の趣きは、耳とどめたまひつや。いたき主かな。『河口の』とこそ、さしいらへまほしかりつれ」 |
「少将が進んで謡い出した『葦垣』の心は、お分りでしたか。
ひどい人ですね。
『河口の』と、言い返したかったなあ」
|
「少将の歌われた『葦垣』の歌詞を聞きましたか。ひどい人だ。『河口の』(河口の関のあら垣や守れどもいでてわが寝ぬや忍び忍びに)と私は返しに謡いたかった」
|
【少将の】- 以下「さしいらへまほしかりつれ」まで、夕霧の詞。「河口の」は催馬楽・河口「河口の 関の荒垣や 関の荒垣や 守れども はれ 守れども 出でて我寝ぬや 出でて我寝ぬや 関の荒垣」。『新大系』は「(夕霧が夜這いをしたのではなく)雲居雁が親の目を盗んで逢ってくれたのだと(少将に)言い返してやりたかった、の意」と注す。
|
| 1.6.21 |
|
とおっしゃると、女は、とても聞き苦しい、とお思いになって、
|
女はあらわな言葉に羞恥を感じて、
|
【女、いと聞き苦し、と思して】- 催馬楽「河口」は、親の目を盗んで女がそっと抜け出して男と共寝したという内容だからである。
|
| 1.6.22 |
|
「軽々しい浮名を流したあなたの口は
どうしてお漏らしになったのですか
|
「浅き名を言ひ流しける河口は
いかがもらしし関のあら垣
|
【浅き名を言ひ流しける河口は--いかが漏らしし関の荒垣】- 雲居雁の贈歌。催馬楽の「河口」「荒垣」を詠み込む。「河口」に夕霧の「口」の意をこめる。「浅き」「流し」は「河」の縁語。「漏らし」は「関」の縁語。
|
| 1.6.23 |
あさまし」
|
あきれました」
|
いけないことでしたわ」
|
|
| 1.6.24 |
とのたまふさま、いとこめきたり。
すこしうち笑ひて、
|
とおっしゃる様子は、実におっとりしている。
少し微笑んで、
|
と言う様子が娘らしい。男は少し笑って、
|
|
| 1.6.25 |
|
「浮名が漏れたのはあなたの父大臣のせいでもありますのに
わたしのせいばかりになさらないで下さい
|
「もりにけるきくだの関の河口の
浅きにのみはおはせざらなん
|
【漏りにける岫田の関を河口の--浅きにのみはおほせざらなむ】- 夕霧の返歌。「関」「河口」「浅き」の語句を受けて「河口(わたし)の浅きにのみは仰せざらなむ」、あなたの父親のせいでもありますよ、と返す。「もり」に「守」と「漏り」を掛ける。
|
| 1.6.26 |
年月の積もりも、いとわりなくて悩ましきに、ものおぼえず」
|
長い歳月の思いも、本当に切なくて苦しいので、何も分りません」
|
長い年月に堆積した苦悩と、今夜の酒の酔いで私はもう何もわからなくなった」
|
|
| 1.6.27 |
|
と、酔いのせいにして、苦しそうに振る舞って、夜の明けて行くのも知らないふうである。
女房たちが、起こしかねているのを、大臣が、
|
と酔いに託して帳台の内の人になった。宰相中将は夜の明けるのも気がつかない長寝をしていた。女房たちが気をもんでいるのを見て、大臣は、
|
【明くるも知らず顔なり】- 「玉簾明くるも知らで寝しものを夢にも見じと思ひかけきや」(伊勢集、五五)を踏まえた表現。
|
| 1.6.28 |
「したり顔なる朝寝かな」
|
「得意顔した朝寝だな」
|
「得意になった朝寝だね」
|
|
| 1.6.29 |
|
と、文句をおっしゃる。
けれども、
すっかり夜が明け果てないうちにお帰りになる。その
|
と言っていた。そしてすっかり明るくなってから源中将は帰って行った。この中将の寝起き姿を見た人は美しく思ったことであろう。
|
【ねくたれの御朝顔、見るかひありかし】- 「寝くたれの朝顔の花秋霧に面隠しつつ見えぬ君かな」(河海抄所引、出典未詳)。語り手の評言。『集成』は「草子地」と指摘。
|
|
第七段 後朝の文を贈る
|
| 1.7.1 |
御文は、なほ忍びたりつるさまの心づかひにてあるを、なかなか今日はえ聞こえたまはぬを、もの言ひさがなき御達つきじろふに、大臣渡りて見たまふぞ、いとわりなきや。
|
お手紙は、やはり人目を忍んだ配慮で届けられたのを、かえって今日はお返事をお書き申し上げになれないのを、口の悪い女房たちが目引き袖引きしているところに、内大臣がお越しになって御覧になるのは、本当に困ったことよ。
|
第一夜の翌朝の手紙も以前の続きで忍んで送られたのであるが、はばかる必要のない日になって、かえって雲井の雁が返事の書けないふうであるのを、蓮葉な女房たちは肱を突き合って笑っている所へ大臣が出て来て手紙を読んでみた。雲井の雁はますます羞恥に堪えられなくなった。
|
|
| 1.7.2 |
|
「打ち解けて下さらなかったご様子に、ますます思い知られるわが身の程よ。
耐えがたいつらさに、
|
やはり昔と同じように冷ややかなあなたに逢っていよいよ自分が哀れな者に思われるのですが、おさえられぬ恋からまたこの手紙を書くのです。
|
【尽きせざりつる御けしきに】- 以下「袖のしづくを」まで、夕霧の文。後朝の文である。
|
| 1.7.3 |
|
お咎め下さいますな、
人目を忍んで絞る手も力なく今日は人目にも
|
咎むなよ忍びにしぼる手もたゆみ
今日あらはるる袖のしづくを
|
【とがむなよ忍びにしぼる手もたゆみ--今日あらはるる袖のしづくを】- 夕霧の贈歌。「咎むなよ」と禁止の意を倒置法で訴える初句切れ。率直で強い意志を表した歌。『集成』は「今日からは誰にも遠慮しませんよ、の意」と注す。
|
| 1.7.4 |
など、いと馴れ顔なり。
うち笑みて、
|
などと、たいそう馴れ馴れしい詠みぶりである。
微笑んで、
|
などと手紙はなれなれしく書いてあった。大臣は笑顔をして、
|
|
| 1.7.5 |
|
「筆跡もたいそう上手になられたものだなあ」
|
「字が非常に上手になったね」
|
【手をいみじうも書きなられにけるかな】- 内大臣の詞。夕霧の筆跡を誉める。
|
| 1.7.6 |
などのたまふも、昔の名残なし。
|
などとおっしゃるのも、昔の恨みはない。
|
などと言っていることも昔とはたいした変わりようである。
|
|
| 1.7.7 |
御返り、いと出で来がたげなれば、「見苦しや」とて、さも思し憚りぬべきことなれば、渡りたまひぬ。
|
お返事が、直ぐに出来かねているので、「みっともないぞ」とおっしゃって、ご躊躇なっているのももっともなことなので、あちらへお行きになった。
|
返事の歌を詠みにくそうにしている娘を見て、「どうしたというものだ。見苦しい」と言って、雲井の雁が父をはばかる気持ちも察して大臣は去ってしまった。
|
|
| 1.7.8 |
御使の禄、なべてならぬさまにて賜へり。
中将、をかしきさまにもてなしたまふ。
常にひき隠しつつ隠ろへありきし御使、今日は、面もちなど、人びとしく振る舞ふめり。
右近将監なる人の、むつましう思し使ひたまふなりけり。
|
お使いの者への褒禄は、並大抵でなくお与えになった。
頭中将が、風情のある様にお持てなしなさる。
いつも人目を忍んでは持ち運んでいたお使い、今日は顔の表情など、人かどに振る舞っているようである。
右近将監である人で、親しくお使いになっている者であった。
|
手紙の使いは派手な纏頭を得た。そして頭中将が饗応の役を勤めたのであった。始終隠して手紙を届けに来た人は、はじめて真人間として扱われる気がした。これは右近の丞で宰相中将の手もとに使っている男であった。
|
|
| 1.7.9 |
|
六条の大臣も、これこれとお聞き知りになったのであった。
宰相中将、いつもより美しさが増して、参上なさったので、じっと御覧になって、
|
源氏も内大臣邸であった前夜のことを知った。宰相中将が平生よりも輝いた顔をして出て来たのを見て、
|
【六条の大臣も、かくと聞こし召してけり】- 源氏も夕霧と雲居雁の結婚を承認。
|
| 1.7.10 |
「今朝はいかに。文などものしつや。賢しき人も、女の筋には乱るる例あるを、人悪ろくかかづらひ、心いられせで過ぐされたるなむ、すこし人に抜けたりける御心とおぼえける。 |
「今朝はどうした。
手紙など差し上げたか。
賢明な人でも、女のことでは失敗する話もあるが、見苦しいほど思いつめたり、じれたりせずに過ごされたのは、少し人より優れたお人柄だと思ったことだ。
|
「今朝はどうしたか、もう手紙は書いたか。聡明な人も恋愛では締まりのないことをするようにもなるものだが、最初の関係を尊重して、しかもあくせくとあせりもせず自然に解決される時を待っていた点で、平凡人でないことを認めるよ。
|
【今朝はいかに】- 以下「ところつきたまへる人なり」まで、源氏の夕霧への詞。女性問題に関する訓戒。
|
| 1.7.11 |
大臣の御おきての、あまりすくみて、名残なくくづほれたまひぬるを、世人も言ひ出づることあらむや。さりとても、わが方たけう思ひ顔に、心おごりして、好き好きしき心ばへなど漏らしたまふな。 |
内大臣のご方針が、あまりにもかたくなで、すっかり折れてしまわれたのが、世間の人も噂するだろうよ。
だからといって、自分の方が偉い顔をして、いい気になって、浮気心などをお出しなさるな。
|
内大臣があまりに強硬な態度をとり過ぎて、ついにはすっかり負けて出たということで世間は何かと評をするだろう。しかしあまり優越感を持ち過ぎて慢心的に放縦なほうへ転向することのないようにしなくてはならない。
|
【世人も言ひ出づることあらむや】- 「や」終助詞、詠嘆の意。『集成』は「世間もいずれ批判するだろう」、『完訳』は「世間でもとやかく話の種にするにちがいない」ち訳す。
|
| 1.7.12 |
さこそおいらかに、大きなる心おきてと見ゆれど、下の心ばへ男々しからず癖ありて、人見えにくきところつきたまへる人なり」
|
あのようにおおらかで、寛大な性格と見えるが、内心は男らしくなくねじけていて、付き合いにくいところがおありの方である」
|
今度の態度は寛大であっても、大臣の性格は、生一本でなくて気むずかしい点があるのだからね」
|
|
| 1.7.13 |
など、例の教へきこえたまふ。
ことうちあひ、めやすき御あはひ、と思さる。
|
などと、例によってご教訓申し上げなさる。
釣り合いもよく、恰好のご夫婦だ、とお思いになる。
|
などとまた源氏は教訓した。円満な結果を得て、宰相中将につりあいのよい妻のできたことで源氏は満足しているのである。
|
|
| 1.7.14 |
|
ご子息とも見えず、少しばかり年長程度にお見えである。
別々に見ると、同じ顔を写し取ったように似て見えるが、御前では、それぞれに、ああ素晴らしいとお見えでいらっしゃった。
|
宰相中将は子のようにも見えなかった。少し年上の兄というほどに源氏は見えるのである。別々に見る時は同じ顔を写し取ったように思われる中将と源氏の並んでいるのを見ると、二人の美貌には異なった特色があった。
|
【御子とも見えず、すこしがこのかみばかりと見えたまふ】- 源氏三十九歳、夕霧十八歳。源氏の若々しさをいう。
|
| 1.7.15 |
|
大臣は、薄縹色の御直衣に、白い御袿の唐風の織りが、紋様のくっきりと浮き出て艶やかに透けて見えるのをお召しになって、今もこの上なく上品で優美でいらっしゃる。
|
源氏は薄色の直衣の下に、白い支那風に見える地紋のつやつやと出た小袖を着ていて、今も以前に変わらず艶に美しい。
|
【薄き御直衣、白き御衣の唐めきたるが、紋けざやかにつやつやと透きたるをたてまつりて】- 源氏の装束。薄縹色の御直衣に、その下に唐織の生地で模様のくっきり浮き出た、つやつやと光沢のあるの白い袿を着ている。
|
| 1.7.16 |
|
宰相殿は、少し色の濃い縹色の御直衣に、丁子染めで焦げ茶色になるまで染めた袿と、白い綾の柔らかいのを着ていらっしゃるのは、格別に優雅にお見えになる。
|
宰相中将は少し父よりは濃い直衣に、下は丁字染めのこげるほどにも薫物の香を染ませた物や、白やを重ねて着ているのが、顔をことさら引き立てているように見えた。
|
【すこし色深き御直衣に、丁子染めの焦がるるまでしめる、白き綾のなつかしきを着たまへる】- 『完訳』は「父大臣より少し色の濃い御直衣に、丁子染の、焦げ茶色に見えるくらい濃く染めてあるのと、白い綾のやさしい感じの御衣を召していらっしゃる様子が」と訳す。
|
|
第八段 夕霧と雲居雁の固い夫婦仲
|
| 1.8.1 |
灌仏率てたてまつりて、御導師遅く参りければ、日暮れて、御方々より童女出だし、布施など、公ざまに変はらず、心々にしたまへり。御前の作法を移して、君達なども参り集ひて、なかなか、うるはしき御前よりも、あやしう心づかひせられて臆しがちなり。 |
灌仏会の誕生仏をお連れ申して来て、御導師が遅く参上したので、日が暮れてから、六条院の御方々から女童たちを使者に立てて、お布施など、宮中の儀式と違わず、思い思いになさった。
御前での作法を真似て、公達なども参集して、かえって、格式ばった御前での儀式よりも、妙に気がつかわれて気後れするのである。
|
今日は御所からもたらされて灌仏が六条院でもあることになっていたが、導師の来るのが遅くなって、日が暮れてから各夫人付きの童女たちが見物のために南の町へ送られてきて、それぞれ変わった布施が夫人たちから出されたりした。御所の灌仏の作法と同じようにすべてのことが行なわれた。殿上役人である公達もおおぜい参会していたが、そうした人たちもかえって六条院でする作法のほうを晴れがましく考えられて、気おくれが出るふうであった。
|
【灌仏率てたてまつりて】- 四月八日の釈迦誕生の日の潅仏会。寺から誕生仏を借り受けて行う。
|
| 1.8.2 |
|
宰相は、心落ち着かず、ますますおめかしし、衣服を整えてお出かけになるのを、特別にではないが、多少お情けをおかけの若い女房などは、恨めしいと思っている人もいるのであった。
長年の思いが加わって、理想的なご夫婦仲のようなので、水も漏れまい。
|
宰相中将は落ち着いてもいられなかった。化粧をよくして身なりを引き繕って新婦の所へ出かけるのであった。情人として扱われてはいないが、少しの関係は持っている若い女房などで恨めしく思っているのもあった。苦難を積んで護って来た年月が背景になっている若夫婦の間には水が洩るほどの間隙もないのである。
|
【宰相は、静心なく】- 四月八日夜、結婚第二夜。是非とも雲居雁のもとに行かねばならない。
【水も漏らむやは】- 「などてかくあふごかたみになりにけむ水漏らさじと結びしものを」(伊勢物語、六一)による表現。「やは」係助詞、反語。語り手の口吻。
|
| 1.8.3 |
主人の大臣、いとどしき近まさりを、うつくしきものに思して、いみじうもてかしづききこえたまふ。負けぬる方の口惜しさは、なほ思せど、罪も残るまじうぞ、まめやかなる御心ざまなどの、年ごろ異心なくて過ぐしたまへるなどを、ありがたく思し許す。 |
主人の内大臣、ますます側に近づくほど美しいのを、かわいらしくお思いになって、たいそう大切にお世話申し上げなさる。
負けたことの悔しさは、やはりお持ちだが、こだわりもなく、誠実なご性格などで、長年の間浮気沙汰などもなくてお過ごしになったのを、めったにないことだとお認めになる。
|
内大臣も婿にしていよいよ宰相中将の美点が明瞭に見えて非常に大事がった。負けたほうは自分であると意識することで大臣の自尊心は傷つけられたのであるが、中将の娘に対する誠実さは、今までだれとの結婚談にも耳をかさず独身で通して来た点でも認められると思うことで、不満の償われることは十分であった。
|
【罪も残るまじうぞ】- 係助詞「ぞ」は「思し許す」に係る。
|
| 1.8.4 |
|
弘徽殿女御のご様子などよりも、派手で立派で理想的だったので、北の方や、仕えている女房などは、おもしろからず思ったり言ったりする者もいるが、何の構うことがあろうか。
按察使大納言の北の方なども、このように結婚が決まって、嬉しくお思い申し上げていらっしゃるのであった。
|
女御よりもかえって雲井の雁のほうが幸福ではなやかな女性と見えるのを夫人や、そのほうの女房たちは不快がったのであるが、そんなことなどは何でもない。雲井の雁の実母である按察使大納言の夫人も、娘がよい婿を得たことで喜んだ。
|
【女御の御ありさまなどよりも】- 弘徽殿女御、雲居雁の異母姉。『完訳』は「この御仲らいが、弘徽殿女御のご様子などよりも」と訳す。
【北の方】- 弘徽殿女御の母、雲居雁の継母。継子の幸福を妬む。
【何の苦しきことかはあらむ】- 『集成』は「夕霧夫婦の立場に立っての草子地」、『完訳』「夕霧に即した語り手の評」と注す。
【按察使の北の方なども】- 雲居雁の実母、今按察大納言と再婚している。
【かかる方にて】- 娘が夕霧と結婚して落ち着いた、ということをさす。
|
|
第二章 光る源氏の物語 明石の姫君の入内
|
|
第一段 紫の上、賀茂の御阿礼に参詣
|
| 2.1.1 |
かくて、六条院の御いそぎは、二十余日のほどなりけり。対の上、御阿礼に詣うでたまふとて、例の御方々いざなひきこえたまへど、なかなか、さしも引き続きて心やましきを思して、誰も誰もとまりたまひて、ことことしきほどにもあらず、御車二十ばかりして、御前なども、くだくだしき人数多くもあらず、ことそぎたるしも、けはひことなり。 |
こうして、六条院の御入内の儀は、四月二十日のころであった。
対の上、賀茂の御阿礼に参詣なさろうとして、例によって御方々をお誘い申し上げなさったが、なまじ、そのように後に付いて行くのもおもしろくないのをお思いになって、どなたもどなたもお残りになって、仰々しいほどでなく、お車二十台ほどで、御前駆なども、ごたごたするほどの人数でなく、簡略になさったのが、かえって素晴らしい。
|
源氏の姫君の太子の宮へはいることはこの二十日過ぎと日が決定した。姫君のために紫夫人は上賀茂の社へ参詣するのであったが、いつものように院内の夫人を誘ってみた。花散里、明石などである。その人たちは紫夫人といっしょに出かけることはかえって自身の貧弱さを紫夫人に比べて人に見せるものであると思ってだれも参加しなかったから、たいして目に立つような参詣ぶりではなかったが、車が二十台ほどで、前駆も人数を多くはせずに人を精選してあった。
|
【かくて、六条院の御いそぎは】- 明石姫君の東宮への入内の準備。二月に予定されていたのが延期されていた。
【御阿礼に詣うでたまふとて】- 賀茂の御阿礼祭。四月中の申の日、深夜に行われる神降臨の神事。
|
| 2.1.2 |
|
祭の日の早朝に参詣なさって、帰りには、御見物なさる予定のお桟敷席におつきになる。
御方々の女房たち、それぞれの車を後から連ねて、御前に車を止めているのは、堂々として、「あれは誰それだ」と、遠くから見ても仰々しいご威勢である。
|
それは祭りの日であったから、参詣したあとで一行は見物桟敷にはいって勅使の行列を見た。六条院の他の夫人たちのほうからも女房だけを車に乗せて祭り見物に出してあった。その車が皆桟敷の前に立て並べられたのである。あれはだれのほう、それは何夫人のほうの車と遠目にも知れるほど華奢が尽くされてあった。
|
【祭の日の暁に詣うでたまひて】- 賀茂祭、通称葵祭。四月中の酉の日に行列が繰り出される。「暁」は夜深い刻限。
【かれはそれ」と】- 『集成』は「あれが紫の上だと」と訳す。
【おどろおどろしき】- 大島本は「おとろおとろ/\しき」とある。『集成』『古典セレクション』『新大系』は諸本に従って「おどろおどろしき」と衍字を削除する。
|
| 2.1.3 |
大臣は、中宮の御母御息所の、車押し避けられたまへりし折のこと思し出でて、
|
大臣は、中宮の御母御息所が、お車の榻を押し折られなさった時のことをお思い出しになって、
|
源氏は中宮の母君である、六条の御息所の見物車が左大臣家の人々のために押しこわされた時の葵祭りを思い出して夫人に語っていた。
|
|
| 2.1.4 |
「時により心おごりして、さやうなることなむ、情けなきことなりける。こよなく思ひ消ちたりし人も、嘆き負ふやうにて亡くなりにき」 |
「権勢をたのんで心奢りなさって、あのようなことを起こすのは、心ないことであった。
全然無視していた方も、その恨みを受けた形で亡くなってしまった」
|
「権勢をたのんでそうしたことをするのはいやなことだね。相手を見くびった人も、人の恨みにたたられたようになって亡くなってしまったのですよ」
|
【時により心おごりして】- 大島本は「時により」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「時による」と校訂する。以下「亡くなりにき」まで、源氏の詞。
|
| 2.1.5 |
と、そのほどはのたまひ消ちて、
|
と、そこのあたりは言葉をお濁しになって、
|
と源氏はその点を曖昧に言って、
|
|
| 2.1.6 |
|
「後に残った人で、中将は、このような臣下として、やっと立身した程度だ。
宮は並ぶ者のいない地位にいらっしゃるのも、考えてみれば、実にしみじみと感慨深い。
何もかもひどく定めない世の中なので、どのようなことも思い通りに、生きている間の世を過ごしたく思うが、後にお残りになる晩年などが、言いようもない衰えなどまでが、心配されるものですから」
|
「残した人だってどうだろう、中将は人臣で少しずつ出世ができるだけの男だが、中宮は類のない御身分になっていられる。その時のことから言えば何という変わり方だろう。人生は元来そうしたものなのですよ。無常の世なのだから、生きている間はしたいようにして暮らしたいとは思うが、私の死んだあとであなたなどがにわかに寂しい暮らしをするようなことがあっては、かえって今派手なことをしておかないほうがその場合に見苦しくないからと私はそんなことも思って、十分まで物はせずにいる」
|
【残りとまれる人の】- 以下「思ひ憚らるれ」まで、源氏の詞。葵の上と六条御息所の遺児の夕霧と秋好中宮の今の地位の逆転を鑑み、世の無常を思い、紫の上が源氏に先立たれた場合の心配をいう。
【思ふさまにて】- 大島本は「おもふさまにて」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「思ふままにて」と校訂する。
【残りたまはむ末の世などの】- 紫の上が源氏に先立たれて残った場合を心配。
|
| 2.1.7 |
と、うち語らひたまひて、上達部なども御桟敷に参り集ひたまへれば、そなたに出でたまひぬ。 |
と、親しくお話しなさって、上達部などもお桟敷に参集なさったので、そちらにお出ましになった。
|
などと言ったのち源氏は高官なども桟敷へ伺候して来るので男子席のほうへ出て行った。
|
【うち語らひたまひて】- 『集成』は「しみじみ述懐なさって」、『完訳』「お話しかけになって」と訳す。
|
|
第二段 柏木や夕霧たちの雄姿
|
| 2.2.1 |
|
近衛府の使者は、頭中将であった。
あの大殿邸を、出立する所から人々は参上なさったのであった。
藤典侍も使者であった。
格別に評判がよくて、帝、春宮をお初めとして、六条院などからも、御祝儀の数々が置き所もないほど、ご贔屓ぶりは実に素晴らしい。
|
今日近衛の将官として加茂へ参向を命ぜられた勅使は頭中将であった。内侍使いは藤典侍である。勅使の出発する内大臣家へ人々はまず集まったのであった。宮中からも東宮からも今日の勅使には特別な下され物があった。六条院からも贈り物があって、勅使の頭中将の背景の大きさが思われた。
|
【近衛司の使は】- 近衛府から出ている賀茂祭の勅使、柏木。他に、内蔵寮、馬寮、内侍所からもそれぞれ賀茂祭の勅使が出ている。
【藤典侍】- 惟光の娘。夕霧の愛人。「少女」巻(第六章一段)に五節舞姫として登場。
【御訪らひども所狭きまで】- 『集成』は「お祝いの贈り物が数々置き所がないまで届られて」と訳す。
|
| 2.2.2 |
宰相中将、出で立ちの所にさへ訪らひたまへり。
うちとけずあはれを交はしたまふ御仲なれば、かくやむごとなき方に定まりたまひぬるを、ただならずうち思ひけり。
|
宰相中将、出立の所にまでお手紙をお遣わしになった。
人目を忍んで恋し合うお間柄なので、このようにれっきとしたお方と結婚がお決まりになったのを、心穏やかならず思っているのであった。
|
宰相中将はいでたちのせわしい場所へ使いを出して典侍へ手紙を送った。思い合った恋人どうしであったから、正当な夫人のできたことで典侍は悲観しているのである。
|
|
| 2.2.3 |
|
「何と言ったのか、
今日のこの插頭は、目の前に見ていながら思
|
何とかや今日のかざしよかつ見つつ
おぼめくまでもなりにけるかな
|
【何とかや今日のかざしよかつ見つつ--おぼめくまでもなりにけるかな】- 夕霧から藤典侍への贈歌。
|
| 2.2.4 |
あさまし」
|
あきれたことだ」
|
想像もしなかったことです。
|
|
| 2.2.5 |
|
とあるのを、機会をお見逃しにならなかったことだけは、どう思ったことやら、たいそう忙しく、車に乗る時であるが、
|
というのであった。自分のためには晴れの日であることに男が関心を持っていたことだけがうれしかったか、あわただしい中で、もう車に乗らねばならぬ時であったが、
|
【折過ぐしたまはぬばかりを、いかが思ひけむ】- 語り手の挿入句。「を」は格助詞、目的格の意、また間投助詞、詠嘆の意にも。『集成』は「時宜に適ったお便りという点だけを、うれしく思ったのか。長い間逢って下さらないのは恨めしいど、という気持が裏にある」。『完訳』は「相手が感慨にふける機をのがさぬのを。以下、藤典侍の心内を測り難いとする語り手の弁」「折をはずさず歌をくださっただけだが、それを典侍はどう感じたのであろうか」と注す。
【もの騒がしく】- 大島本は「物さハかし」とある。『集成』『古典セレクション』『新大系』は諸本に従って「もの騒がしく」と「く」を補訂する。
|
| 2.2.6 |
|
「頭に插頭してもなおはっきりと思い出せない草の名は
桂を折られたあなたはご存知でしょう
|
かざしてもかつたどらるる草の名は
桂を折りし人や知るらん
|
【かざしてもかつたどらるる草の名は--桂を折りし人や知るらむ】- 藤典侍の返歌。「かざし」「かつ見つつ」「おぼめく」の語句を受けて、「かざしても」「かつたどらるる」と切り返す。「桂を折りし」は「久方の月の桂を折るばかり家の風をも吹かせてしがな」(拾遺集雑上、四七三、菅原道真母)を踏まえる。
|
| 2.2.7 |
博士ならでは」
|
博士でなくては」
|
博士でなければわからないでしょう。
|
|
| 2.2.8 |
|
と申し上げた。
つまらない歌であるが、悔しい返歌だとお思いになる。
やはり、この典侍を、忘れられず、こっそりお会いなさるのであろう。
|
と返事を書いた。ちょっとした手紙ではあったが、気のきいたものであると宰相中将は思った。この人とだけは隠れた恋人として結婚後も関係が続いていくらしい。
|
【はかなけれど、ねたきいらへと】- 『集成』は「たかが女の歌とはいえ、あざやかなお返しだと」、『完訳』は「これということもない歌であるが、してやられたと」と訳す。「はかなけれど」は語り手の批評を交えた表現。
【はひまぎれたまふべき】- 『完訳』は「語り手の推測」と注す。
|
|
第三段 四月二十日過ぎ、明石姫君、東宮に入内
|
| 2.3.1 |
|
こうして、御入内には北の方がお付き添いになるものだが、「いつまでも長々とお付き添い申していらっしゃることはできまい。
このような機会に、あの実の親をご後見役に付けようか」とお考えになる。
|
姫君が東宮へ上がった時に母として始終紫の女王がついて行っていねばならないはずであるが、女王はそれに堪えまい、これを機会に明石を姫君につけておくことにしようかと源氏は思った。
|
【かくて、御参りは】- 明石姫君の東宮への入内。
【北の方添ひたまふべきを】- 『完訳』は「一門を代表する女性が付き添うべきだが、の意。紫の上が相当」と注す。
【常に長々しう】- 大島本は「なか/\しう」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「ながながしうは」と「は」を補訂する。以下「添へまし」まで、源氏の心中。
|
| 2.3.2 |
上も、「つひにあるべきことの、かく隔たりて過ぐしたまふを、かの人も、ものしと思ひ嘆かるらむ。この御心にも、今はやうやうおぼつかなく、あはれに思し知るらむ。かたがた心おかれたてまつらむも、あいなし」と思ひなりたまひて、 |
対の上も、「結局は一緒になるはずなのに、このように離れて年月を過ごして来られたのを、あの方も、ひどいと思い嘆いていることだろう。
姫君のお胸の中でも、今ではだんだんと恋しくお感じになっていらっしゃろう。
お二方からおもしろくなく思われ申すのも、つまらないことだ」とお思いになって、
|
紫夫人も、それが自然なことで、いずれそうした日のなければならない母と子が今のように引き分けられていることを明石夫人は悲しんでいるであろうし、姫君も幼年時代とは違ってもう今はそのことを飽き足らぬことと悲しんでいるであろう、双方から一人の自分が恨まれることは苦しいと思うようになった。
|
【つひにあるべきことの】- 以下「あいなし」まで、紫の上の心中。
|
| 2.3.3 |
「この折に添へたてまつりたまへ。まだいとあえかなるほどもうしろめたきに、さぶらふ人とても、若々しきのみこそ多かれ。御乳母たちなども、見及ぶことの心いたる限りあるを、みづからは、えつとしもさぶらはざらむほど、うしろやすかるべく」 |
「この機会にお付き添わせ申しなさいませ。
まだとてもか弱くいらっしゃるのも不安なので、伺候する女房たちとしても、若々しい人ばかり多いです。
御乳母たちなども、気をつけるといっても行き届かない所がありますから、わたし自身は、ずっとお付きできません時、安心なように」
|
「この機会に真実のお母様をつけておあげなさいませ。まだ小さいのですから心配でなりませんのに、女房たちといっても若い人が多いのでございますからね。また乳母たちといっても、ああした人たちの周到さには限度があるのですものね、母がいなければと思いますが、私がそうずっとつききっていられないあいだあいだはあの方がいてくだすったら安心ができると思います」
|
【この折に添へ】- 以下「うしろやすかるべう」まで、紫の上の詞。源氏の心中思っていたことをいう。
|
| 2.3.4 |
|
と申し上げなさると、「よくお気が付いたなあ」とお思いになって、「これこれで」と、あちらにもご相談になったので、まことに嬉しく願っていたことが、すっかり叶った心地がして、女房の着る装束、その他のことまで、高貴な方のご様子に劣らないほどに準備し出す。
|
と女王は良人に言った。源氏は自身の心持ちと夫人の言葉とが一致したことを喜んで、明石へその話をした。明石は非常にうれしく思い、長い間の願いの実現される気がして、自身の女房たちの衣裳その他の用意を、紫夫人のするのに劣らず派手に仕度し始めた。
|
【いとよく思し寄るかな】- 源氏の心中。
【さなむ】- 源氏の明石御方への言葉内容を間接話法で、これこれしかじかと、の意。『集成』は「こうこうだと。紫の上が言ったと」。『完訳』は「そういうわけで」と訳す。
【思ふこと叶ひはべる心地して】- 大島本は「かなひ侍る心ち」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「かなひはつる」と校訂する。
|
| 2.3.5 |
|
尼君、やはりこの姫君のご将来を拝見したいお気持ちが深いのであった。
「もう一度拝見する時があろうか」と、生きることに執念を燃やして祈っているのであったが、「どうしたらお目にかかれるだろうか」と、思うにつけても悲しい。
|
姫君の祖母の尼君は姫君の出世をどこまでも観望したいと願っていた。そしてもう一度だけ顔を見たいと思う心から生き続けているのを、明石は哀れに思っていた。その機会だけは得られまいと思うからである。
|
【今一度見たてまつる世もや】- 明石尼君の心中。孫娘に今一度お目にかかりたい。
【いかにしてかは】- 明石尼君の心中。係助詞「かは」は疑問とも反語とも解せる。『集成』は「どうしたらお目にかかれるものやらと悲しい。生母の明石の上には姫君と再会の時が訪れたが、自分にはどんな機会があるのか、という気持」。『完訳』は「姫君の入内後は、今よりいっそう会いがたいと思う」「入内されたらもうお目にかかる機会はあるまい」と注す。
|
| 2.3.6 |
|
その夜は、対の上が付き添って参内なさるが、その際、輦車にも一段下がって歩いて行くなど、体裁の悪いことだが、自分は構わないが、ただ、このように大事に磨き申し上げなさった姫君の玉の瑕となって、自分がこのように長生きをしているのを、一方ではひどく心苦しく思う。
|
最初は紫夫人が付き添って行った。紫夫人には輦車も許されるであろうが、自身には御所のある場所を歩いて行かねばならない不体裁のあることなども、明石は自身のために歎かずに源氏夫婦が磨きたてて太子に奉る姫君に、自分という生母のあることが玉の瑕と見られるに違いないと心苦しがっていた。
|
【さて、車にも】- 大島本は「御(御$)/てくるま(てくるま$)さて車にも」とある。すなわち「御」と「てくるま」をミセケチにする。『新大系』は底本の訂正に従う。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「御輦車」と校訂する。以下、明石御方の心中を間接的に叙述。
【かく磨きたてまつりたまふ玉の疵にて】- 大島本は「みかきたてまつり給ふ」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「磨きたてたてまつりたまふ」と「たて」を補訂する。『集成』は「こうして立派にお扱い申し上げていられる姫君のそれこそ玉の疵のようなことで」、『完訳』は「ただこうもたいせつにお仕立てあげになった姫君にとって、それこそ玉の疵になりはせぬかと思われ」と訳す。
【かつはいみじう心苦しう思ふ】- 「心くるしう」までが明石の御方の心中だが、終止形+引用の助詞という明石の心中を顕在化させた形でなく、連用形の用言修飾の韜晦した形で地の文に流れている。
|
| 2.3.7 |
|
御入内の儀式、「世間の人を驚かすようなことはすまい」とご遠慮なさるが、自然と普通の入内とは違ったものとならざるをえない。
この上もなく大事にお世話申し上げていらっしゃって、対の上は、本当にしみじみとかわいいとお思い申し上げなさるにつけても、他人に譲りたくなく、「本当にこのような子があったらいいのに」とお思いになる。
大臣も宰相の君も、ただこのこと一点だけを、「物足りないことよ」と、お思いであった。
|
姫君が上がる式に人目を驚かすような華奢はしたくないと源氏は質素にしたつもりであったが、やはり並み並みのこととは見えなかった。限りもなく美しく姫君を仕立てて、紫夫人は真心からかわいくながめながらも、これを生母に譲らねばならぬようなことがなくて、真実の子として持ちたかったという気がした。源氏も宰相中将もこの一点だけを飽き足らず思った。
|
【御参りの儀式】- 大島本は「まいりのきしき」とある。『集成』『古典セレクション』『新大系』は諸本に従って「御参りの儀式」と「御」を補訂する。明石姫君の東宮入内の儀式。
【人の目おどろくばかりのことはせじ】- 源氏の心中。
【おのづから世の常のさまにぞあらぬや】- 語り手の評。『集成』は「どうしても並はずれた立派なことにならざるをえない。草子地」と注す。
【まことにかかることもあらましかば】- 紫の上の心中。明石姫君が自分の子であったらよいのに、の意。「ましか」反実仮想の助動詞。
【このことひとつを】- 明石姫君が紫の上の実子でないことをさす。
|
|
第四段 紫の上、明石御方と対面する
|
| 2.4.1 |
三日過ごしてぞ、上はまかでさせたまふ。たち変はりて参りたまふ夜、御対面あり。 |
三日間を過ごして、対の上はご退出あそばす。
入れ替わって参内なさる夜に、ご対面がある。
|
三日たって紫の女王は退出するのであったが、代わるために明石が御所へ来た。そして東宮の御息所の桐壺の曹司で二夫人ははじめて面会したのである。
|
【三日過ごして】- 『集成』は「新婚三日間に、正式の婚礼の行事(後朝の文、三日の夜の餅など)がある。紫の上がそれを取り仕切っていたのである」と注す。
|
| 2.4.2 |
|
「このようにご成人なさった節目に、長い歳月のほどが存じられますが、よそよそしい心の隔ては、ないでしょうね」
|
「こんなに大人らしくおなりになった方で、私たちは長い以前からの知り合いであることが証明されるのですから、もう他人らしい遠慮はしないでおきたいと思います」
|
【かくおとなびたまふ】- 以下「残るまじくや」まで、紫の上の詞。
【年月のほども】- 紫の上が明石の姫君を引き取って八年になる。
|
| 2.4.3 |
|
と、やさしくおっしゃって、お話などなさる。
このことも仲好くなった初めのようである。
お話などなさる態度に、「なるほどもっともだ」と、目を見張る思いで御覧になる。
|
となつかしいふうに紫夫人は言って、いろいろな話をした。これが初めで二夫人の友情は堅く結ばれていくであろうと思われた。明石のものを言う様子などに、あれだけにも源氏の愛を惹く力のあるのは道理である、すばらしい人であると夫人にはうなずかれるところがあった。
|
【これもうちとけぬる初めなめり】- 「なめり」連語(「な」断定の助動詞+「めり」推量の助動詞、視界内推量)。語り手の推測。『集成』は「草子地」。『完訳』は「語り手の言辞である」と注す。
【むべこそは】- 紫の上の心中。『集成』は「(源氏がこの人を重んずるのも)もっともだと、さすがな人だと御覧になる」と訳す。
|
| 2.4.4 |
|
また、実に気品高く女盛りでいらっしゃるご様子を、お互いに素晴らしいと認めて、「大勢の御方々の中でも優れたご寵愛で、並ぶ方がいない地位を占めていらっしゃったのを、まことにもっともなことだ」と理解されると、「こんなにまで出世し、肩をお並べ申すことができた前世の約束、いいかげんなものでない」と思う一方で、ご退出になる儀式が実に格別に盛大で、御輦車などを許されなさって、女御のご様子と異ならないのを、思い比べると、やはり身分の相違というものを感じずにはいられないのである。
|
今が盛りの気高い貴女と見える女王の美に明石は驚いていて、たくさんな女性の中で最も源氏から愛されて、第一夫人の栄誉を与えているのは道理のあることであると思ったが、同時に、この人と並ぶ夫人の地位を得ている自分の運命も悪いものでないという自信も持てたのであったが、入り代わって帰る女王はことさらはなばなしい人に付き添われ、輦車も許されて出て行く様子などは陛下の女御の勢いに変わらないのを見ては、さすがに溜息もつかれた。
|
【そこらの御中に】- 以下「いとことわり」まで、明石の君の心中。紫の上の美しく立派な態度を見て、大勢の妻妾の中でも大事にされるのがもっともだと思う。
【かうまで、立ち並びきこゆる契り、おろかなりやは】- 明石の君の心中。自分の宿世も大したものだと自身をもつ。「やは」反語。『完訳』は「このようなお方とこれほどまでに方を並べ申すわが身の運勢は並一通りのものではない」と訳す。
【さすがなる身のほどなり】- 『集成』は「(紫の上とは)やはり段違いのわが身の上である。明石の上の述懐」。『完訳』「一方では自信をもったものの、やはり受領の娘の身をかみしめる」と注す。
|
| 2.4.5 |
いとうつくしげに、雛のやうなる御ありさまを、夢の心地して見たてまつるにも、涙のみとどまらぬは、一つものとぞ見えざりける。年ごろよろづに嘆き沈み、さまざま憂き身と思ひ屈しつる命も延べまほしう、はればれしきにつけて、まことに住吉の神もおろかならず思ひ知らる。 |
とてもかわいげに、お人形のようなご様子を、夢のような心地で拝見するにつけても、涙ばかりが止まらないのは、同じ涙とは思われないのであった。
長年何かにつけ悲しみに沈んで、何もかも辛い運命だと悲観していた寿命も更に延ばしたく、気も晴れやかになったにつけても、本当に住吉の神も霊験あらたかだと思わずにいられない。
|
きれいな姫君を夢の中のような気持ちでながめながらも明石の涙はとまらなかった。しかしこれはうれしい涙であった。今までいろいろな場合に悲観して死にたい気のした命も、もっともっと長く生きねばならぬと思うような、朗らかな気分になることができて、いっさいが住吉の神の恩恵であると感謝されるのであった。
|
【一つものとぞ】- 「嬉しきも憂きも心は一つにて分れぬものは涙なりけり」(後撰集雑二、一一八八、読人しらず)を踏まえる。
|
| 2.4.6 |
思ふさまにかしづききこえて、心およばぬことはた、をさをさなき人のらうらうじさなれば、おほかたの寄せ、おぼえよりはじめ、なべてならぬ御ありさま容貌なるに、宮も、若き御心地に、いと心ことに思ひきこえたまへり。
|
思う通りにお世話申し上げて、行き届かないこと、それは、まったくない方の利発さなので、世人一般の人気、声望をはじめとして、並々ならぬご容姿ご器量なので、東宮も、お若い心で、たいそう格別にお思い申し上げていらっしゃった。
|
理想的な教養が与えられてあって、足りない点などは何もないと見える姫君は、絶大な勢力のある源氏を父としているほかに、すぐれた麗質も備えていることで、若くいらせられる東宮ではあるがこの人を最も御愛寵あそばされた。
|
|
| 2.4.7 |
|
競争なさっている御方々の女房などは、この母君がこうして伺候していらっしゃるのを、欠点に言ったりなどするが、それに負けるはずがない。
当世風で、並ぶ者がないことは、言うまでもなく、奥ゆかしく上品なご様子を、ちょっとしたことにつけても、理想的に引き立ててお上げになるので、殿上人なども、珍しい風流の才を競う所として、それぞれに伺候する女房たちも、心寄せている女房の、心構え態度までが、実に立派なのを揃えていらっしゃった。
|
東宮に侍している他の御息所付きの女房などは、源氏の正夫人でない生母が付き添っていることをこの御息所の瑕のように噂するのであるが、それに影響されるようなことは何もなかった。はなやかな空気が桐壺に作られて、芸術的なにおいをこの曹司で嗅ぎうることを喜んで、殿上役人などもおもしろい遊び場と思い、ここのすぐれた女房を恋の対象にしてよく来るようになった。女房たちのとりなし、人への態度も洗練されたものであった。
|
【いまめかしう、並びなきことをば】- 大島本は「いまめかしうならひなきこと越ハ」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「いかめしう並びなきことは」と校訂する。
【心をかけたる女房の、用意ありさまさへ、いみじくととのへなしたまへり】- 『集成』は「(殿上人たちが)懸想している女房のたしなみや態度まで、大層気を配って取り仕切っていらっしゃる」。『完訳』は「人々が心を寄せる女房のたしなみや物腰にまでも、それぞれに明石の御方はたいそう気をつかってお仕込みになっている」と訳す。
|
| 2.4.8 |
上も、さるべき折節には参りたまふ。
御仲らひあらまほしううちとけゆくに、さりとてさし過ぎもの馴れず、あなづらはしかるべきもてなし、はた、つゆなく、あやしくあらまほしき人のありさま、心ばへなり。
|
対の上も、しかるべき機会には参内なさる。
お二方の仲は理想的に睦まじくなって行くが、そうかといって出過ぎたり馴れ馴れしくならず、軽く見られるような態度、言うまでもなく、まったくなく、不思議なほど理想的な方の態度、心構えである。
|
紫夫人も何かのおりには出て来た。それで明石との間がおいおい打ち解けていった。しかも明石はなれなれしさの過ぎるほどにも出過ぎたことなどはせず、紫夫人はまた相手を軽蔑するようなことは少しもせずに怪しいほど雅致のある友情が聡明な二女性の間にかわされていた。
|
|
|
第三章 光る源氏の物語 准太上天皇となる
|
|
第一段 源氏、秋に准太上天皇の待遇を得る
|
| 3.1.1 |
|
大臣も、「いつまでも生きていられないと思わずにはいられない存命中に」と、お思いであったご入内を、立派な地位にお付け申し上げなさって、本人が求めてのことであるが、身の上が落ち着かず、体裁の悪かった宰相の君も、心配もなく安心した結婚生活に落ち着きなさったので、すっかりご安心なさって、「今は出家の本意を遂げよう」と、お思いになる。
|
源氏も、もう長くもいられないように思う自身の生きている間に、姫君を東宮へ奉りたいと思っていたことが、予期以上に都合よく実現されたし、それは彼自身に考えのあってのことではあるが、配偶者のない、たよりない男と見えた宰相中将も結婚して幸福になったことに安心して、もう出家をしてもよい時が来たと思われるのであった。
|
【長からずのみ思さるる御世のこなたに」と、思しつる】- 『集成』は「しきりに無常の感じられるこの世にご存命のうちにとお思いだった」。『完訳』は「いつまでも生きていられるわけではないと考えずにはいらっしゃれぬ御寿命とて、その命あるうちにと思っていらっしゃった」と訳す。
【御参りの、かひあるさまに】- 大島本は「御まいりの」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「御参り」と「の」を削除する。
【今は本意も遂げなむ】- 源氏の心中。明石姫君の入内、夕霧の結婚が決まり、出家願望を遂げようと思う。
|
| 3.1.2 |
対の上の御ありさまの、見捨てがたきにも、「中宮おはしませば、おろかならぬ御心寄せなり。この御方にも、世に知られたる親ざまには、まづ思ひきこえたまふべければ、さりとも」と、思し譲りけり。 |
対の上のご様子の、見捨て難いのにつけても、「中宮がいらっしゃるので、並々ならぬお味方である。
この姫君におかれても、表向きの親としては、真っ先にきっとお思い申し上げなさるだろうから、いくら何でも大丈夫」と、お任せになるのであった。
|
紫夫人は気がかりであるが、養女の中宮がおいでになるから、何よりもそれが確かな寄りかかりである、また、姫君のためにも形式上の母は女王のほかにないわけであるから、仕えるのに誠意を持つことであろうからと源氏は思っているのであった。
|
【中宮おはしませば】- 以下「さりとも」まで、源氏の心中。間接的に語る。秋好中宮は源氏の養女。紫の上には継子になる。
|
| 3.1.3 |
|
夏の御方が、何かにつけて華やかになりそうもないのも、「宰相がいらっしゃるので」と、皆それぞれに心配はなくお考えになって行く。
|
花散里のためには宰相中将がいるからよいとそれも安心していた。
|
【時に花やぎたまふまじきも】- 大島本は「時に」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「時々に」と校訂する。
|
| 3.1.4 |
|
明年、四十歳におなりになる、御賀のことを、朝廷をお初め申して、大変な世を挙げてのご準備である。
|
翌年源氏は四十になるのであったから、四十の賀宴の用意は朝廷をはじめとして所々でしていた。
|
【明けむ年、四十になりたまふ】- 源氏は明年四十歳になる。「桐壺」巻以来初めて源氏の年齢を語る。
|
| 3.1.5 |
|
その年の秋、太上天皇に準じる御待遇をお受けになって、御封が増加し、年官や年爵など、全部お加わりになる。
そうでなくても、世の中でご希望通りにならないことはないのが、やはりめったになかった昔の例を踏襲して、院司たちが任命され、格段に威儀厳めしくおなりになったので、宮中に参内なさることが、難しいだろうことを、一方では残念にお思いであった。
|
その秋三十九歳で源氏は準太上天皇の位をお得になった。官から支給されておいでになる物が多くなり、年官年爵の特権数がおふえになったのである。それでなくても自由でないことは何一つないのでおありになったが、古例どおりに院司などが、それぞれ任命されて、しかもどの場合の院付きの役人よりも有為な、勢いのある人々が選ばれたのであった。こんなことになって心安く御所へ行くことのおできにならないことになったのを六条院は物足らずお思いになった。
|
【その秋、太上天皇に准らふ御位得たまうて、御封加はり、年官年爵など、皆添ひたまふ】- 「太上天皇」は上皇の意。すなわち、臣下の域を超えて、皇族で天皇譲位者の地位と同待遇を受ける。史実にも例がない。その地位は「桐壷」巻の高麗人の予言と照応する。太上天皇の御封は二千戸、他に年官・年爵が加わる。そして院司が設けられる。
【なほめづらしかりける昔の例を改めで】- 『集成』は「それでもやはり滅多にないことであった過去の例にもう一度倣って。藤壷を准太上天皇にしたことをさす」。『完訳』は「歴史上の嵯峨天皇時代ごろからの太上天皇の例(または物語の藤壺女院の例)を踏襲して。一説に、「改めて」と読み、太政大臣の例とは変えて、の意」。『集成』は「改めて」、『完訳』は「改めで」と読む。先例どおりに、の意。
|
| 3.1.6 |
|
それでも、なおも物足りなく帝はお思いあそばして、世間に遠慮して、皇位をお譲り申し上げられないことが、朝夕のお嘆きの種であった。
|
この御処置をあそばしてもまだ帝は不満足に思召され、世間をはばかるために位をお譲りになることのできぬことを朝夕お歎きになった。
|
【なほ飽かず帝は思して】- 大島本は「おほして」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「思しめして」と校訂する。
|
| 3.1.7 |
|
内大臣は太政大臣にご昇進になって、宰相中将は、中納言におなりになった。
そのお礼言上にお出になる。
輝きがますますお加わりになった姿、容貌をはじめとして、足りないところのないのを、主人の大臣も、「なまじ人に圧倒されるような宮仕えよりはましであった」と、お考え直しになる。
|
内大臣が太政大臣になって、宰相中将は中納言になった。任官の礼廻りをするために出かける中納言はいっそう光彩の添うた気がして、身のとりなし、容貌の美に欠けた点のないのを、舅の大臣は見て、後宮の競争に負けた形になっているような宮仕えをさせるよりも、こうした婿をとるほうがよいことであるという気になった。
|
【内大臣上がりたまひて、宰相中将、中納言になりたまひぬ】- 内大臣は太政大臣に、夕霧の宰相中将は中納言に昇進。
【なかなか人に圧されまし宮仕へよりは】- 内大臣の心中。雲居雁を中途半端な宮仕えに出すより夕霧に縁づけて良かったと満足。
|
| 3.1.8 |
|
女君の大輔の乳母が、「六位の人との結婚」と、ぶつぶつ言った夜のことが、何かの機会ごとにお思い出しになったので、菊のたいそう美しくて、色の変化しているのをお与えになって、
|
雲井の雁の乳母の大輔が、「姫君は六位の男と結婚をなさる御運だった」とつぶやいた夜のことが中納言にはよく思い出されるのであったから、美しい白菊が紫を帯びて来た枝を大輔に渡して、
|
【六位宿世」と、つぶやきし宵のこと】- 「少女」巻(第五章五段)に見えた。
【おもしろくて】- 大島本は「おもしろく(く+て<朱>)」とある。すなわち底本は朱筆で「て」を補入する。『新大系』は底本の補訂に従う。『集成』『古典セレクション』は底本の訂正以前と諸本に従って「おもしろく」と校訂する。
|
| 3.1.9 |
|
「浅緑色をした若葉の菊を
濃い紫の花が咲こうとは夢にも思わなかっただろう
|
「あさみどりわか葉の菊をつゆにても
濃き紫の色とかけきや
|
【浅緑若葉の菊を露にても--濃き紫の色とかけきや】- 夕霧の大輔の乳母への贈歌。「浅緑」は六位の袍の色。「濃き紫の色」は中納言三位の袍の色。「菊」と「露」は縁語。「や」は詠嘆の終助詞。私が将来三位以上に出世するとは思わなかっただろう、の意。
|
| 3.1.10 |
|
辛かったあの時の一言が忘れられない」
|
みじめな立場にいて聞いたあなたの言葉は忘れないよ」
|
【からかりし折の一言葉こそ忘られね】- 歌に添えた言葉。
|
| 3.1.11 |
|
と、たいそう美しくほほ笑んでお与えになった。
恥ずかしく、お気の毒なことをしたと思う一方で、いとしくも、お思い申し上げる。
|
と朗らかに微笑して言った。乳母は恥ずかしくも思ったが、気の毒なことだったとも思いおかわいらしい恨みであるとも思った。
|
【恥づかしう、いとほしきものから、うつくしう見たてまつる】- 『集成』は「顔向けならず困惑しながら、いとしくお思い申し上げる」。『完訳』は「顔向けもならず困ったことになったと思うものの、またかわいいとも存じあげる」と訳す。
|
| 3.1.12 |
|
「二葉の時から名門の園に育つ菊ですから
浅い色をしていると差別する者など誰もございませんでした
|
「二葉より名だたる園の菊なれば
あさき色わく露もなかりき
|
【双葉より名立たる園の菊なれば--浅き色わく露もなかりき】- 大輔の乳母の返歌。夕霧の「浅緑」「若葉の菊」「露」の語句を受けて、「双葉より名立たる」「菊」なので「浅き色分く」「露もなかりき」と切り返す。
|
| 3.1.13 |
|
どのようにお気を悪くお思いになったことでしょうか」
|
どんなに憎らしく思召したでしょう」
|
【いかに心おかせたまへりけるにか】- 歌に添えた言葉。『集成』は「どんなふうに悪くおとりになったのでしょうか」。『完訳』は「どんなにかお気を悪くなさいましたことやら」。夕霧に詫びる気持ち。
|
| 3.1.14 |
|
と、いかにも物馴れた様子に言い訳をする。
|
と物馴れたふうに言って心苦しがった。
|
【いと馴れて苦しがる】- 『完訳』は「まったく物慣れた巧みさで苦しい言い訳をする」と注す。したたかな乳母という感じ。
|
|
第二段 夕霧夫妻、三条殿に移る
|
| 3.2.1 |
|
ご威勢が増して、このようなお住まいでは手狭なので、三条殿にお移りになった。
少し荒れていたのをたいそう立派に修理して、大宮がいらっしゃったお部屋を修繕してお住まいになる。
昔が思い出されて、懐しく心にかなったお部屋である。
|
納言になったために来客も多くなり、この住居が不便になって、源中納言はお亡くなりになった祖母の宮の三条殿へ引き移った。少し荒れていたのをよく修理して、宮の住んでおいでになった御殿の装飾を新しくして夫婦のいる所にした。二人にとっては昔を取り返しえた気のする家である。
|
【御勢ひまさりて、かかる御住まひも所狭ければ、三条殿に渡りたまひぬ】- 夕霧、中納言に昇進し威勢が増したので、内大臣邸から大宮の三条殿に雲居雁と共に移り住む。
|
|
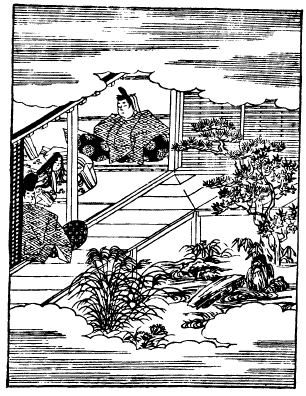 |
| 3.2.2 |
前栽どもなど、小さき木どもなりしも、いとしげき蔭となり、一村薄も心にまかせて乱れたりける、つくろはせたまふ。遣水の水草もかき改めて、いと心ゆきたるけしきなり。 |
前栽どもなど、小さい木であったのが、たいそう大きな木蔭を作り、一叢薄ものび放題になっていたのを、手入れさせなさる。
遣水の水草も取り払って、とても気持ちよさそうに流れている。
|
庭の木の小さかったのが大きくなって広い蔭を作るようになっていたり、ひとむら薄が思うぞんぶんに拡がってしまったりしたのを整理させ、流れの水草を掻き取らせもして快いながめもできるようになった。
|
【一村薄も】- 「君が植ゑし一群薄虫の音のしげき野辺ともなりにけるかな」(古今集哀傷、八五三、御春有助)などに基づく歌語。
|
| 3.2.3 |
をかしき夕暮のほどを、二所眺めたまひて、あさましかりし世の、御幼さの物語などしたまふに、恋しきことも多く、人の思ひけむことも恥づかしう、女君は思し出づ。古人どもの、まかで散らず、曹司曹司にさぶらひけるなど、参う上り集りて、いとうれしと思ひあへり。 |
美しい夕暮れ時を、お二人で眺めなさって、情けなかった昔の、子供時代のお話などをなさると、恋しいことも多く、女房たちが何と思っていたかも恥ずかしく、女君はお思い出しになる。
古い女房たちで、退出せず、それぞれの曹司に伺候していた人たちなど、参集して、実に嬉しく互いに思い合っていた。
|
美しい夕方の庭の景色を二人でながめながら、冷たい手に引き分けられてしまった少年の日の恋の思い出を語っていたが、恋しく思われることもまた多かった。当時の女房たちは自分をどう思って見たであろうと雲井の雁は恥ずかしく思っていた。祖母の宮に付いていた女房で、今までまだそれぞれの部屋に住んでいた女房などが出て来て、新夫婦がここへ住むことになったのを喜んでいた。
|
【古人どもの】- 三条殿に仕えていた老女房たち。
|
| 3.2.4 |
男君、
|
男君、
|
源中納言、
|
|
| 3.2.5 |
|
「おまえこそはこの家を守っている主人だ、
お世話になった人の
|
なれこそは岩もるあるじ見し人の
行くへは知るや宿の真清水
|
【なれこそは岩守るあるじ見し人の--行方は知るや宿の真清水】- 夕霧の歌。「汝」は「真清水」に呼び掛けた表現。擬人法。「見し人」は故大宮をさす。
|
| 3.2.6 |
女君、
|
女君、
|
夫人、
|
|
| 3.2.7 |
|
「亡き人の姿さえ映さず知らない顔で
心地よげに流れている浅い清水ね」
|
なき人は影だに見えずつれなくて
心をやれるいさらゐの水
|
【亡き人の影だに見えずつれなくて--心をやれるいさらゐの水】- 雲居雁の唱和歌。「見し人」「真清水」を受けて「亡き人」「いさらいの水」と和す。「心をやれる」は擬人法。「亡き人の影だに見えぬ遣水の底に涙を流してぞ来し」(後撰集哀傷、一四〇二、伊勢)を踏まえる。『完訳』は「二人を愛育してくれた大宮への感傷を通して夕霧に共感する歌」と注す。
|
| 3.2.8 |
|
などとおっしゃっているところに、太政大臣、宮中からご退出なさった途中、紅葉のみごとな色に驚かされてお越しになった。
|
などと言い合っている時に、太政大臣は宮中から出た帰途にこの家の前を通って、紅葉の色に促されて立ち寄った。
|
【大臣、内裏よりまかでたまひけるを】- 太政大臣が宮中を退出して三条殿に訪れる。
|
|
第三段 内大臣、三条殿を訪問
|
| 3.3.1 |
|
昔大宮がお住まいだったご様子に、たいして変わるところなく、あちらこちらも落ち着いてお住まいになっている様子、若々しく明るいのを御覧になるにつけても、ひどくしみじみと感慨が込み上げてくる。
中納言も、改まった表情で、顔が少し赤くなって、いつも以上にしんみりとしていらっしゃる。
|
宮がお住まいになった当時にも変わらず、幾つの棟に分かれた建物を上手にはなやかに住みなしているのを見て大臣の心はしんみりと濡れていった。中納言は美しい顔を少し赤らめて舅の前にいた。
|
【昔おはさひし御ありさまにも】- 「おはさひし」は「おはしあひし」(複合形)の約。太政大臣と大宮がお暮らしになった、の意。
【いとどしづまりてものしたまふ】- 『集成』は「いつも以上にしんみりとしていらっしゃる」。『完訳』は「いよいよ神妙にしていらっしゃる」と訳す。
|
| 3.3.2 |
|
理想的で初々しいご夫婦仲であるが、女は、他にこのような器量の人もいないこともなかろうと、お見えになる。
男は、この上なく美しくいらっしゃる。
古女房たちが御前で得意気になって、昔のことなどを申し上げる。
さきほどのお二人の歌が、散らかっているのをお見つけになって、ふと涙ぐみなさる。
|
美しい若夫婦ではあるが、女のほうはこれほどの容貌がほかにないわけはないと見える程度の美人であった。男はあくまでもきれいであった。老いた女房などは大臣の来訪に得意な気持ちになって、古い古い時代の話などをし出すのであった。そこに出たままになっていた二人の歌の書いた紙を取って、大臣は読んだが、しおれたふうになった。
|
【女は】- 以下「女は--男は--」という構文。
【またかかる容貌のたぐひも、などかなからむ】- 語り手の批評。雲居雁程の器量は他にいないこともない、絶世の美人という程でない。
【男は、際もなくきよらにおはす】- 夕霧は「きよら」で形容。源氏物語における美の最大限の讃辞である。
【古人ども】- 大島本は「ふる人とも」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「古人どもも」と校訂する。
|
| 3.3.3 |
|
「この清水の気持ちを尋ねてみたいが、老人は遠慮して」
|
「ここの水に聞きたいことが私にもあるが、今日は縁起を祝ってそれを言わないことにしよう」
|
【この水の心尋ねまほしけれど、翁は言忌して】- 大島本は「こといみしく」とある。『集成』『古典セレクション』『新大系』は諸本に従って「言忌(こといみ)して」と校訂する。太政大臣の詞。『集成』は「新婚の二人に対する斟酌。夕霧の歌の「見し人のゆくへは知るや」を受けて、水の心を辿りたい、といったもの」と注す。
|
| 3.3.4 |
とのたまふ。
|
とおっしゃる。
|
と言って、大臣は、
|
|
| 3.3.5 |
|
「その昔の老木はなるほど朽ちてしまうのも当然だろう
植えた小松にも苔が生えたほどだから」
|
そのかみの老い木はうべも朽ちにけり
植ゑし小松も苔生ひにけり
|
【そのかみの老木はむべも朽ちぬらむ--植ゑし小松も苔生ひにけり】- 太政大臣の歌。『集成』は「「植ゑし小松も」は、ここに新たに居を構えた若い二人に対する祝意」。『完訳』は「「老木」は故大宮、「小松」は大臣。一説では大臣、夕霧夫妻の対象とするが、「朽ち」を死とみたい」と注す。
|
| 3.3.6 |
男君の御宰相の乳母、つらかりし御心も忘れねば、したり顔に、
|
男君の宰相の御乳母、冷たかったお仕打ちを忘れなかったので、得意顔に、
|
この歌を告げた。中納言の乳母の宰相の君は、あの当時の大臣の処置に憤慨して、今も恨めしがっているのであったから、得意な気持ちで大臣に言った。
|
|
| 3.3.7 |
|
「どちら様をも蔭と頼みにしております、
二葉の時から互いに仲好く大きくおなりになった二本の松でいらっし
|
いづれをも蔭とぞ頼む二葉より
根ざしかはせる松の末々
|
【いづれをも蔭とぞ頼む双葉より--根ざし交はせる松の末々】- 宰相の乳母の唱和歌。太政大臣の「小松」の語句を受けて、「双葉」「松の末々」と夕霧夫妻を寿ぐ。「いづれをも」は夕霧と雲居雁をさす。
|
| 3.3.8 |
老人どもも、かやうの筋に聞こえ集めたるを、中納言は、をかしと思す。
女君は、あいなく面赤み、苦しと聞きたまふ。
|
老女房たちも、このような話題ばかりを歌に詠むのを、中納言は、おもしろいとお思いになる。
女君は、わけもなく顔が赤くなって、聞き苦しく思っていらっしゃる。
|
この感想がどの女房の歌にも出てくるのを中納言は快く思った。雲井の雁はむやみに顔が赤くなって恥ずかしくてならなかった。
|
|
|
第四段 十月二十日過ぎ、六条院行幸
|
| 3.4.1 |
|
神無月の二十日過ぎ頃に、六条院に行幸がある。
紅葉の盛りで、きっと興趣あるにちがいない今回の行幸なので、朱雀院にも御手紙があって、院までがお越しあそばすので、実に珍しくめったにない盛儀なので、世間の人も心をときめかす。
主人の六条院方でも、お心を尽くして、目映いばかりのご準備をあそばす。
|
十月の二十日過ぎに六条院へ行幸があった。興の多い日になることを予期されて、主人の院は朱雀院をも御招待あそばされたのであったから、珍しい盛儀であると世人も思ってこの日を待っていた。六条院では遺漏のない準備ができていた。
|
【神無月の二十日あまりのほどに、六条院に行幸あり】- 神無月二十日過ぎ、冷泉帝、朱雀院、共に六条院に行幸。康保二年(九六五)十月二十三日の村上天皇の朱雀院行幸が準拠とされる。
【朱雀院にも御消息ありて】- 冷泉帝から朱雀院へ御案内の手紙があって、の意。
【御心まうけをせさせたまふ】- 主語は主人の院、源氏。「させ」「たまふ」最高敬語。
|
| 3.4.2 |
巳の時に行幸ありて、まづ、馬場殿に左右の寮の御馬牽き並べて、左右近衛立ち添ひたる作法、五月の節にあやめわかれず通ひたり。未くだるほどに、南の寝殿に移りおはします。道のほどの反橋、渡殿には錦を敷き、あらはなるべき所には軟障を引き、いつくしうしなさせたまへり。 |
巳の時に行幸があって、まず、馬場殿に左右の馬寮の御馬を牽き並べて、左右近衛府の官人が立ち並んだ儀式、五月の節句に違わずよく似ていた。
未の刻を過ぎたころ、南の寝殿にお移りあそばす。
途中の反橋、渡殿には錦を敷き、よそから見えるにちがいない所には軟障を引き、厳めしくおしつらわせなさった。
|
午前十時に行幸があって、初めに馬場殿へ入御になった。左馬寮、右馬寮の馬が前庭に並べられ、左近衛、右近衛の武官がそれに添って列立した形は五月の節会の作法によく似ていた。午後二時に南の寝殿へお移りになったのであるが、その通御の道になる反橋や渡殿には錦を敷いて、あらわに思われる所は幕を引いて隠してあった。
|
【五月の節にあやめわかれず通ひたり】- 帝が宮中の武徳殿に行幸し騎射競馬を御覧になる儀式。「あやめ」は「五月」にちなんだ言葉遊び的表現。
|
| 3.4.3 |
|
東の池に舟を幾隻か浮かべて、御厨子所の鵜飼の長が、院の鵜飼を召し並べて、鵜を下ろさせなさった。
小さい鮒を幾匹もくわえた。
特別に御覧に入れるのではないが、お通りすがりになる一興ほどにである。
|
東の池に船などを浮けて、御所の鵜飼い役人、院の鵜飼いの者に鵜を下ろさせてお置きになった。小さい鮒などを鵜は取った。叡覧に供えるというほどのことではなく、お通りすがりの興におさせになったのである。
|
【東の池に】- 『集成』は「南の町の南庭の池。西の町の池に通じているので、こう言ったのであろう」。『完訳』は「池の東の部分(春の町の側)」と注す。
【御厨子所の鵜飼】- 宮中の御厨子所。内膳司に属し、天皇の食事や節会の饗を調じる。膳部があり、その下に鵜飼が属し、魚類を調進する。
【院の鵜飼】- 六条院の鵜飼。
【わざとの御覧とはなけれども】- 大島本は「なけれとも」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「なけれど」と「も」を削除する。
|
| 3.4.4 |
山の紅葉、いづ方も劣らねど、西の御前は心ことなるを、中の廊の壁を崩し、中門を開きて、霧の隔てなくて御覧ぜさせたまふ。
|
築山の紅葉、どの町のも負けない程であるが、西の御庭のは格別に素晴らしいので、中の廊の壁を崩し、中門を開いて、霧がさえぎることなく御覧にお入れあそばす。
|
山の紅葉はどこのも美しいのであるが、西の町の庭はことさらにすぐれた色を見せているのを、南の町との間の廊の壁をくずさせ、中門をあけて、お目をさえぎる物を省いて御覧にお供えになったのであった。
|
|
| 3.4.5 |
|
御座、二つ準備して、主人の御座は下にあるのを、宣旨があってお改めさせなさるのも、素晴らしくお見えになったが、帝は、やはり規定以上の礼をお現し申し上げられないのを、残念にお思いあそばすのであった。
|
二つの御座が上に設けられてあって、主人の院の御座が下がって作られてあったのを、宣旨があってお直させになった。これこそ限りもない光栄であるとお見えになるのであるが、帝の御心にはなお一段六条院を尊んでお扱いになれないことを残念に思召した。
|
【帝は、なほ限りあるゐやゐやしさを尽くして見せたてまつりたまはぬことをなむ、思しける】- 『集成』は「父子として定められた礼儀を尽してお見せ申し上げられないことを残念にお思いなのであった」。『完訳』は「定め以上の礼を尽してお見せ申しあげられぬことを残念におぼしめすのであった」と訳す。
|
|
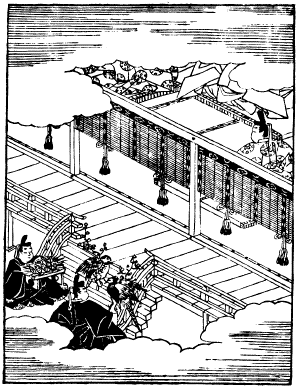 |
| 3.4.6 |
池の魚を、左少将捕り、蔵人所の鷹飼の、北野に狩仕まつれる鳥一番を、右少将捧げて、寝殿の東より御前に出でて、御階の左右に膝をつきて奏す。
太政大臣、仰せ言賜ひて、調じて御膳に参る。
親王たち、上達部などの御まうけも、めづらしきさまに、常の事どもを変へて仕うまつらせたまへり。
|
池の魚を、左少将が手に取り、蔵人所の鷹飼が、北野で狩をして参った鳥の一番を、右少将が捧げて、寝殿の東から御前に出て、御階の左右に膝まづいて奏上する。
太政大臣が、お言葉を賜り伝えて、料理して御膳に差し上げる。
親王方、上達部たちの御馳走も、珍しい様子に、いつものと目先を変えて差し上げさせなさった。
|
池の魚を載せた台を左近少将が持ち、蔵人所の鷹飼いが北野で狩猟してきた一つがいの鳥を右近少将がささげて、寝殿の東のほうから南の庭へ出て、階段の左右に膝をついて献上の趣を奏上した。太政大臣が命じてそれを大御肴に調べさせた。親王がた、高官たちの饗膳にも、常の様式を変えた珍しい料理が供えられたのである。
|
|
|
第五段 六条院行幸の饗宴
|
| 3.5.1 |
皆御酔ひになりて、暮れかかるほどに、楽所の人召す。わざとの大楽にはあらず、なまめかしきほどに、殿上の童べ、舞仕うまつる。朱雀院の紅葉の賀、例の古事思し出でらる。「賀王恩」といふものを奏するほどに、太政大臣の御弟子の十ばかりなる、切におもしろう舞ふ。内裏の帝、御衣ぬぎて賜ふ。太政大臣降りて舞踏したまふ。 |
皆お酔いになって、日が暮れかかるころに、楽所の人をお召しになる。
特別の大がかりの舞楽ではなく、優雅に奏して、殿上の童が、舞を御覧に入れる。
朱雀院の紅葉の御賀、例によって昔の事が自然と思い出されなさる。
「賀皇恩」という楽を奏する時に、太政大臣の御末子の十歳ほどになる子が、実に上手に舞う。
今上の帝、御召物を脱いで御下賜なさる。
太政大臣、
|
人々は陶然と酔って夕べに近いころ、伶人が召し出された。大楽というほどの大がかりなものでなく、感じのよいほどの奏楽の前で御所の侍童たちが舞った。朱雀院の紅葉の賀の日がだれにも思い出された。「賀王恩」という曲が奏されて、太政大臣の子息の十歳ぐらいの子が非常におもしろく舞った。帝は御衣を脱いで賜い、父の太政大臣が階前でお礼の舞踏をした。
|
【御弟子の十ばかりなる】- 『集成』は「御男(をとこ)の」。『完訳』は「御弟子(おとこ)の」「末の子、の意か」。横山本「御おと子」とある。
|
| 3.5.2 |
主人の院、菊を折らせたまひて、「青海波」の折を思し出づ。
|
主人の院、菊を折らせなさって、「青海波」を舞った時のことをお思い出しになる。
|
主人の院はお折らせになった菊を大臣へお授けになるのであったが、青海波の時を思い出しておいでになった。
|
|
| 3.5.3 |
|
「色濃くなった籬の菊も折にふれて
袖をうち掛けて昔の秋を思い出すことだろう」
|
色まさる籬の菊もをりをりに
袖打ちかけし秋を恋ふらし
|
【色まさる籬の菊も折々に--袖うちかけし秋を恋ふらし】- 源氏の歌。今と変わらぬ昔の盛時を恋う歌。
|
| 3.5.4 |
大臣、その折は、同じ舞に立ち並びきこえたまひしを、我も人にはすぐれたまへる身ながら、なほこの際はこよなかりけるほど、思し知らる。
時雨、折知り顔なり。
|
太政大臣、あの時は、同じ舞をご一緒申してお舞いなさったのだが、自分も人には勝った身ではあるが、やはりこの院のご身分はこの上ないものであったと、思わずにはいらっしゃれない。
時雨が、時知り顔に降る。
|
当時ごいっしょに舞った大臣は、自身も人にすぐれた幸福は得ていながらも、帝の御子であらせられた院の到達された所と自身とは非常な相違のあることに気がついた。時雨は彼の出て来るおりをうかがっていたようにはらはらと降りそそいだ。
|
|
| 3.5.5 |
|
「紫の雲と似ている菊の花は
濁りのない世の中の星かと思います
|
「紫の雲にまがへる菊の花
濁りなき世の星かとぞ見る
|
【紫の雲にまがへる菊の花--濁りなき世の星かとぞ見る】- 太政大臣の唱和歌。源氏の歌の「色」「菊」の語句を受けて「紫の雲」「菊の花」「濁りなき世」と和す。「久方の雲の上にて見る菊は天つ星とぞあやまたれける」(古今集秋下、二六九、藤原敏行)を踏まえる。
|
| 3.5.6 |
|
一段とお栄えの時を」
|
最もふさわしい時に咲いた花でございます」
|
【時こそありけれ】- 歌に添えた言葉。「秋をおきて時こそありけれ菊の花移ろふからに色のまされば」(古今集秋下、二七九、平貞文)の第二句の文句を引用したもの。『集成』は「いよいよお栄えですね」。『完訳』は「こうしていよいよ御栄えの時をお迎えあそばして」と訳す。
|
| 3.5.7 |
と聞こえたまふ。
|
と申し上げなさる。
|
と大臣は院へ申し上げた。
|
|
|
第六段 朱雀院と冷泉帝の和歌
|
| 3.6.1 |
|
夕風が吹き散らした紅葉の色とりどりの、濃いの薄いの、錦を敷いた渡殿の上、見違えるほどの庭の面に、容貌のかわいい童べの、高貴な家の子供などで、青と赤の白橡に、蘇芳と葡萄染めの下襲など、いつものように、例のみずらを結って、額に天冠をつけただけの飾りを見せて、短い曲目類を少しずつ舞っては、紅葉の葉蔭に帰って行くところ、日が暮れるのも惜しいほどである。
|
夕風が蒔き敷く紅葉のいろいろと、遠い渡殿に敷かれた錦の濃淡と、どれがどれとも見分けられない庭のほうに、美しい貴族の家の子などが、白橡、臙脂、赤紫などの上着を着て、ほんの額だけにみずらを結い、短い曲をほのかに舞って紅葉の木蔭へはいって行く、こんなことが夜の闇に消されてしまうかと惜しまれた。
|
【夕風の吹き敷く紅葉の色々、濃き薄き、錦を敷きたる渡殿の上】- 日暮れて、朱雀院、冷泉帝、感慨深く、和歌を詠じる。
【青き赤き白橡、蘇芳、葡萄染めなど】- 『集成』は「青白橡の袍に葡萄染(薄紫)の下襲、赤白橡の袍に蘇芳(やや暗い紅色)の下襲。それぞれ右方(高麗楽)と左方(唐楽)の舞楽の童の装束」と注す。
【額ばかりのけしきを見せて】- 『集成』は「額に天冠を着けただけの飾りで」と訳す。
|
| 3.6.2 |
楽所などおどろおどろしくはせず。
上の御遊び始まりて、書司の御琴ども召す。
ものの興切なるほどに、御前に皆御琴ども参れり。
宇多法師の変はらぬ声も、朱雀院は、いとめづらしくあはれに聞こし召す。
|
楽所など仰々しくはしない。
堂上での管弦の御遊が始まって、書司の御琴類をお召しになる。
一座の興が盛り上がったころに、お三方の御前にみな御琴が届いた。
宇多の法師の変わらぬ音色も、朱雀院は、実に珍しくしみじみとお聞きあそばす。
|
奏楽所などは大形に作ってはなくて、すぐに御前での管絃の合奏が始まった。御書所の役人に御物の楽器が召された。夜がおもしろく更けたころに楽器類が御前にそろった。「宇陀の法師」の昔のままの音を朱雀院は珍しくお聞きになり、身にしむようにもお感じになった。
|
|
| 3.6.3 |
|
「幾たびの秋を経て、
時雨と共に年老いた里人でもこのように美しい
|
秋をへて時雨ふりぬる里人も
かかる紅葉の折りをこそみね
|
【秋をへて時雨ふりぬる里人も--かかる紅葉の折をこそ見ね】- 朱雀院の歌。「ふり」に「降り」と「古り」を掛ける。今日の盛儀を羨む気持ち。
|
| 3.6.4 |
|
恨めしくお思いになったのであろうよ。
帝は、
|
現今の御境遇を寂しがっておいでになるような御製である。帝が、
|
【うらめしげにぞ思したるや】- 「や」詠嘆の終助詞。語り手の嘆息。
|
| 3.6.5 |
|
「世の常の紅葉と思って御覧になるのでしょうか
昔の先例に倣った今日の宴の紅葉の錦ですのに」
|
世の常の紅葉とや見るいにしへの
ためしにひける庭の錦を
|
【世の常の紅葉とや見るいにしへの--ためしにひける庭の錦を】- 冷泉帝の唱和歌。朱雀院の歌の「紅葉」「折をこそ見ね」の語句を受けて、「世の常の紅葉とや見る」と否定し、「古の例」すなわち、故桐壷院御世(朱雀院の東宮時代)の模倣だと謙遜して慰める。
|
| 3.6.6 |
|
と、おとりなし申し上げあそばす。
御器量は一段と御立派におなりになって、まるでそっくりにお見えあそばすのを、中納言が控えていらっしゃるが、また別々のお顔と見えないのには、目を見張らされる。
気品があって素晴らしい感じは、思いなしか優劣がつけられようか、目の覚めるような美しい点は、加わっているように見える。
|
と朱雀院へ御説明的に申された。帝の御容貌はますますお美しくおなりになるばかりであった。今ではまったく六条院と同じお顔にお見えになるのであるが、侍している源中納言の顔までが同じ物に見えるのは、この人として過分なしあわせであった。気高い美が思いなしによるのかいささか劣って見えた。鮮明にきわだってきれいな所などはこの人がよけいに持っているように見えた。
|
【聞こえ知らせたまふ】- 『集成』は「おとりなし申し上げる」。『完訳』は「お答え申し上げる」と訳す。
【めざましかめれ】- 語り手の感想。
【思ひなしに】- 語り手の「思ひなし」である。
【劣りまさらむ】- 『完訳』は「帝がまさり、夕霧が劣る意」と注す。
【あざやかに匂はしきところは】- 夕霧の美点。
|
| 3.6.7 |
|
笛を承ってお吹きになる、たいそう素晴らしい。
唱歌の殿上人、御階に控えて歌っている中で、弁少将の声が優れていた。
やはり前世からの宿縁によって優れた方々がお揃いなのだと思われるご両家のようである。
|
この人は笛の役をしたのである。合奏は非常におもしろく進んでいった。歌の役を勤める殿上人は階段の所に集まっていたが、その中で弁の少将の声が最もすぐれていた。前生の善果を持って生まれてきたような人たちというべきであろう。
|
【なほさるべきにこそと見えたる御仲らひなめり】- 語り手の批評。『集成』は「やはり前世からのしかるべき宿縁によって、このようにすぐれた方々がお揃いなのだと思われるご両家のようだ。草子地」。『完訳』は「やはり、めでたい御果報に恵まれていらっしゃるのだろう、と思われるご一統同士のようである」と注す。
|
| 著作権 |
| 底本 |
大島本 |
| 校訂 |
Last updated 9/21/2010(ver.2-3)
渋谷栄一校訂(C)
オリジナル
修正版
比較 |
| ローマ字版 |
Last updated 4/2/2010 (ver.2-2)
Written in Japanese roman letters
by Eiichi Shibuya (C)
オリジナル
修正版
比較 |
ルビ抽出
(ローマ字版から)
|
Powered by 再編集プログラム v4.05
ひらがな版
ルビ抽出 |
挿絵
(ローマ字版から)
|
'Eiri Genji Monogatari'
(1650 1st edition) |
|
Last updated 11/15/2001
渋谷栄一訳(C)(ver.1-2-2)
オリジナル
修正版
比較 |
|
|
Last updated 4/2/2010(ver.2-2)
渋谷栄一注釈(C)
オリジナル
修正版
比較 |
|