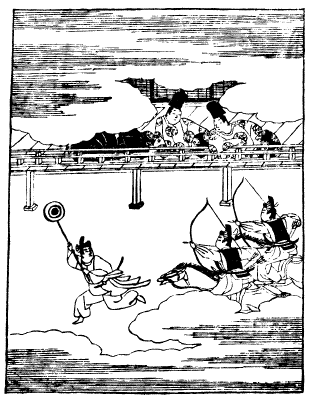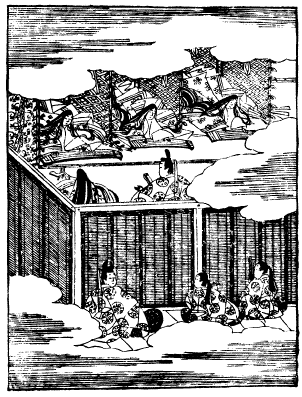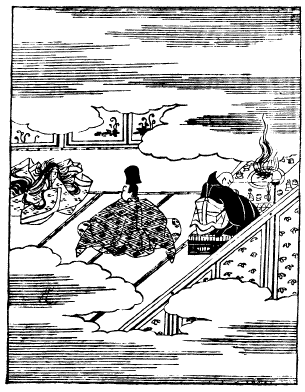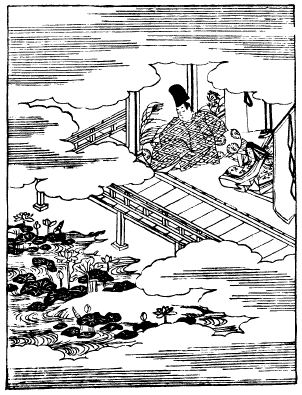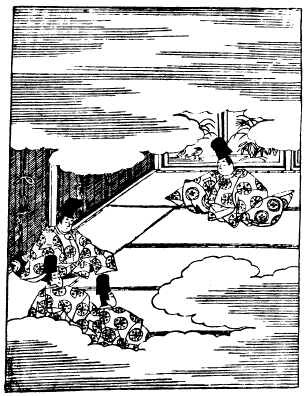第三十五帖 若菜下
光る源氏の准太上天皇時代四十一歳三月から四十七歳十二月までの物語
|
# |
本文 |
渋谷栄一訳 |
与謝野晶子訳 |
注釈 |
|
第一章 柏木の物語 女三の宮の結婚後
|
|
第一段 六条院の競射
|
| 1.1.1 |
|
もっともだとは思うけれども、
|
小侍従が書いて来たことは道理に違いないが
|
【ことわりとは思へども】- 主語は柏木。小侍従の返事をさす。「若菜上」巻末の小侍従の手紙の文面を直接受けた語り出し。『集成』は「「思へども」と敬語を使わないのは、「思ふ」とともに、柏木に密着した書き方」と注す。
|
| 1.1.2 |
|
「いまいましい言い方だな。
いや、しかし、なんでこのような通り一遍の返事だけを慰めとしては、どうして過ごせようか。
このような人を介してではなく、一言でも直接おっしゃってくださり、また申し上げたりする時があるだろうか」
|
また露骨なひどい言葉だとも衛門督には思われた。しかももう浅薄な女房などの口先だけの言葉で心が慰められるものとは思われないのである。こんな人を中へ置かずに一言でも直接恋しい方と問答のできることは望めないのであろうか
|
【うれたくも言へるかな】- 以下「世ありなむや」まで、柏木の心中。
【かかる人伝てならで】- 「いかにしてかく思ふてふことをだに人づてならで君に語らむ」(後撰集恋五、九六一、藤原敦忠)。
【のたまひ聞こゆる】- 「のたまひ」の主語は女三の宮、「聞こゆる」の主語は柏木。
|
| 1.1.3 |
|
と思うにつけても、普通の関係では、もったいなく立派な方だとお思い申し上げる院の御為には、けしからぬ心が生じたのであろうか。
|
と苦しんでいた。限りない尊敬の念を持っている六条院に穢辱を加えるに等しい欲望をこうして衛門督が抱くようになった。
|
【なまゆがむ心や添ひにたらむ】- 疑問の係助詞「や」、推量の助動詞「む」は、語り手の言辞。
|
| 1.1.4 |
|
晦日には、人々が大勢参上なさった。
何やら気が進まず、落ち着かないけれども、「あのお方のいらっしゃる辺りの桜の花を見れば気持ちが慰むだろうか」と思って参上なさる。
|
三月の終わる日には高官も若い殿上役人たちも皆六条院へ参った。気不精になっている衛門督はこのことを皆といっしょにするのもおっくうなのであったが、恋しい方のおいでになる所の花でも見れば気の慰みになるかもしれぬと思って出て行った。
|
【晦日の日は】- 三月晦日。六条院の競射。
【そのあたりの花の色をも見てや慰む】- 柏木の心中。
|
| 1.1.5 |
|
殿上の賭弓は、二月とあったが過ぎて、三月もまた御忌月なので、残念に人々は思っているところに、この院で、このような集まりがある予定と伝え聞いて、いつものようにお集まりになる。
左右の大将は、お身内という間柄で参上なさるので、中将たちなども互いに競争しあって、小弓とおっしゃったが、歩弓の勝れた名人たちもいたので、お呼び出しになって射させなさる。
|
賭弓の競技が御所で二月にありそうでなかった上に、三月は帝の母后の御忌月でだめであるのを残念がっている人たちは、六条院で弓の遊びが催されることを聞き伝えて例のように集まって来た。左右の大将は院の御養女の婿であり、御子息であったから列席するのがむろんで、そのために左右の近衛府の中将に競技の参加者が多くなり、小弓という定めであったが、大弓の巧者な人も来ていたために、呼び出されてそれらの手合わせもあった。
|
【殿上の賭弓】- 「賭弓」そのものは正月十八日に弓場殿で帝出御のもとに競射が催される。「殿上の賭弓」はそれに準じて殿上人が行う競射。二月三月に催されることが多い。
【三月はた御忌月なれば】- 冷泉帝の母后藤壺の忌月。
【かかるまとゐあるべしと】- 「まとゐ」は「円居」と「的射」の掛詞的表現。
【左右の大将、さる御仲らひにて】- 左大将鬚黒と右大将夕霧である。
【小弓とのたまひしかど】- 「若菜上」(第十三章四段)の源氏の言葉に見える。
【歩弓】- 「歩弓」は「馬弓(騎射)」の対語。十七日の射礼、十八日の賭弓なども歩射である。
|
|
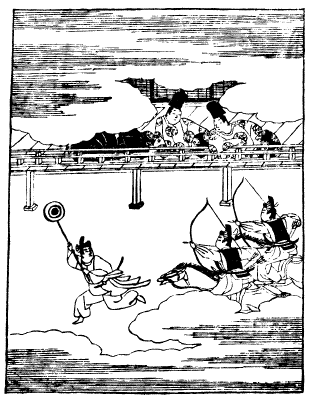 |
| 1.1.6 |
|
殿上人たちも、相応しい人は、すべて前方と後方との、交互に組分けをして、日が暮れてゆくにつれて、今日が最後の春の霞の感じも気ぜわしくて、吹き乱れる夕風に、花の蔭はますます立ち去りにくく、人々はひどく酔い過ごしなさって、
|
殿上役人でも弓の芸のできる者は皆左右に分かれて勝ちを争いながら夕べに至った。春が終わる日の霞の下にあわただしく吹く夕風に桜の散りかう庭がだれの心をも引き立てて、大将たちをはじめ、すでに酔っている高官たちが、
|
【前後の心、こまどりに方分きて】- 左方の先に射る者、右方の後に射る者と、奇数偶数の二組に分けること。
【今日にとぢむる霞のけしきも】- 今日が三月晦日で春の終わりの日であることをいう。惜春の情景。
【花の蔭いとど立つことやすからで】- 「今日のみと春を思はぬ時だにも立つことやすき花の蔭かは」(古今集春下、一三四、躬恒)。
|
| 1.1.7 |
|
「しゃれた賭物の数々は、あちらこちらの御婦人方のご趣味のほどが窺えようというものを。
柳の葉を百発百中できそうな舎人たちが、わがもの顔をして射取るのは、面白くないことだ。
少しおっとりした手並みの人たちこそ、競争させよう」
|
「奥のかたがたからお出しになった懸賞品が皆平凡な品でないのを、技術の専門家にだけ取らせてしまうのはよろしくない。少し純真な下手者も競争にはいりましょう」
|
【艶なる賭物ども】- 以下「こそ挑ませめ」まで、源氏の詞。
【柳の葉を百度当てつべき舎人どもの】- 『史記』周本紀の楚の養由基の故事。
|
| 1.1.8 |
とて、大将たちよりはじめて、下りたまふに、衛門督、人よりけに眺めをしつつものしたまへば、かの片端心知れる御目には、見つけつつ、 |
といって、大将たちをはじめとして、お下りになると、衛門督、他の人より目立って物思いに耽っていらっしゃるので、あの少々は事情をご存知の方のお目には止まって、
|
などと言って庭へ下りた。この時にも衛門督がめいったふうでじっとしているのがその原因を正確ではないにしても想像のできる大将の目について、
|
【心知れる御目には】- 夕霧をさす。
|
| 1.1.9 |
|
「やはり、様子が変だ。
厄介な事が引き起こるのだろうか」
|
困ったことである。不祥事が起こってくるのではないか
|
【なほ、いとけしき異なり。わづらはしきこと出で来べき世にやあらむ】- 夕霧の心中。『集成』は「やっかいなことがもちあがる二人の仲なのだろうか」。『完訳』は「面倒なことがもちあがってくるのではなかろうか」と訳す。
|
| 1.1.10 |
|
と、自分までが悩みに取りつかれたような心地がする。
この君たち、お仲が大変に良い。
従兄弟同士という中でも、気心が通じ合って親密なので、ちょっとした事でも、物思いに悩んで屈託しているところがあろうものなら、お気の毒にお思いになる。
|
と不安を感じだし、自分までも一つの物思いのできた気がした。この二人は非常に仲がよいのである。大将のために衛門督が妻の兄であるというばかりでなく、古くからの友情が互いにあって睦まじい青年たちであるから、一方がなんらかの煩悶にとらえられているのを、今一人が見てはかわいそうで堪えられがたくなるのである。
|
【さる仲らひ】- 従兄弟同士という意。
【もの思はしくうち紛るることあらむを】- 推量の助動詞「む」仮定の意。『集成』は「思い悩んでそれに屈託するようなことがあるのを」。『完訳』は「物思いがちに心を奪われるようなことがあろうものなら」と訳す。
|
| 1.1.11 |
みづからも、大殿を見たてまつるに、気恐ろしくまばゆく、 |
自分でも、大殿を拝見すると、何やら恐ろしく目を伏せたくなるようで、
|
衛門督自身も院のお顔を見ては恐怖に似たものを感じて、恥ずかしくなり、
|
【みづからも】- 柏木をさす。
|
| 1.1.12 |
「かかる心はあるべきものか。なのめならむにてだに、けしからず、人に点つかるべき振る舞ひはせじと思ふものを。ましておほけなきこと」 |
「このような考えを持ってよいものだろうか。
どうでもよいことでさえ、不行き届きで、人から非難されるような振る舞いはすまいと思うものを。
まして身のほどを弁えぬ大それたことを」
|
誤った考えにとらわれていることはわが心ながら許すべきことでない、少しのことにも人を不快にさせ、人から批難を受けることはすまいと決心している自分ではないか、ましてこれほどおそれおおいことはないではないか
|
【かかる心はあるべきものか】- 以下「おほけなきこと」まで、柏木の心中。
|
| 1.1.13 |
と思ひわびては、
|
と思い悩んだ末に、
|
と心を鞭うっている人が、また慰められたくなって、
|
|
| 1.1.14 |
「かのありし猫をだに、得てしがな。思ふこと語らふべくはあらねど、かたはら寂しき慰めにも、なつけむ」 |
「あの先日の猫でも、せめて手に入れたい。
思い悩んでいる気持ちを打ち明ける相手にはできないが、独り寝の寂しい慰めを紛らすよすがにも、手なづけてみよう」
|
せめてあの時に見た猫でも自分は得たい、人間の心の悩みが告げられる相手ではないが、寂しい自分はせめてその猫を馴つけてそばに置きたい
|
【かのありし猫をだに】- 以下「慰めにもなつけむ」まで、柏木の心中。
|
| 1.1.15 |
と思ふに、もの狂ほしく、「いかでかは盗み出でむ」と、それさへぞ難きことなりける。
|
と思うと、気違いじみて、「どうしたら盗み出せようか」と思うが、それさえ難しいことだったのである。
|
とこんな気持ちになった衛門督は、気違いじみた熱を持って、どうかしてその猫を盗み出したいと思うのであるが、それすらも困難なことではあった。
|
|
|
第二段 柏木、女三の宮の猫を預る
|
| 1.2.1 |
|
弘徽殿女御の御方に参上して、お話などを申し上げて心を紛らわそうとしてみる。
たいそう嗜み深く、気恥ずかしくなるようなご応対ぶりなので、直にお姿をお見せになることはない。
このような姉弟の間柄でさえ、隔てを置いてきたのに、「思いがけず垣間見したのは、不思議なことであった」とは、さすがに思われるが、並々ならず思い込んだ気持ちゆえ、軽率だとは思われない。
|
衛門督は妹の女御の所へ行って話すことで悩ましい心を紛らせようと試みた。貴女らしい慎しみ深さを多く備えた女御は、話し合っている時にも、兄の衛門督に顔を見せるようなことはなかった。同胞ですらわれわれはこうして慣らされているのであるが、思いがけないお顔を外にいる者へ宮のお見せになったことは不思議なことであると、衛門督もさすがに第三者になって考えれば肯定できないこととは思われるのであるが、熱愛を持つ人に対してはそれを欠点とは見なされないのである。
|
【女御の御方に参りて】- 柏木、妹の弘徽殿女御のもとに参上。弘徽殿女御の慎み深い態度、女三の宮の軽率さが比較される。
【いと奥深く、心恥づかしき御もてなしにて】- 弘徽殿女御の態度。女三の宮と対照的。
【かかる御仲らひにだに】- 兄妹の関係をいう。
【ゆくりかにあやしくは、ありしわざぞかし】- 柏木の心中。女三の宮を垣間見たことを想起する。
【浅くも思ひなされず】- 女三の宮の振る舞いを。
|
| 1.2.2 |
|
東宮に参上なさって、「当然似ていらっしゃるところがあるだろう」と、目を止めて拝すると、輝くほどのお美しさのご容貌ではないが、これくらいのご身分の方は、また格別で、上品で優雅でいらっしゃる。
|
衛門督は東宮へ伺候して、むろん御兄弟でいらせられるのであるから似ておいでになるに違いないと思って、お顔を熱心にお見上げするのであったが、東宮ははなやかな愛嬌などはお持ちにならぬが、高貴の方だけにある上品に艶なお顔をしておいでになった。
|
【春宮に参りたまひて】- 柏木、東宮のもとに参上し、女三の宮の猫を預かる。
【論なう通ひたまへるところあらむかし】- 柏木の心中。東宮と女三の宮が兄妹ゆえに似ているだろうと注意深く見る。
【あてになまめかしくおはします】- 東宮の器量。上文に「匂ひやかになどはあらぬ御容貌」。輝くほどの美しさではないが、東宮という心なしか、上品で優雅でいらっしゃる。参考、源氏の器量、「匂ひやかにきよら」(若菜上)とある。
|
| 1.2.3 |
内裏の御猫の、あまた引き連れたりけるはらからどもの、所々にあかれて、この宮にも参れるが、いとをかしげにて歩くを見るに、まづ思ひ出でらるれば、
|
内裏の御猫が、たくさん引き連れていた仔猫たちの兄弟が、あちこちに貰われて行って、こちらの宮にも来ているのが、とてもかわいらしく動き回るのを見ると、何よりも思い出されるので、
|
帝のお飼いになる猫の幾疋かの同胞があちらこちらに分かれて行っている一つが東宮の御猫にもなっていて、かわいい姿で歩いているのを見ても、衛門督には恋しい方の猫が思い出されて、
|
|
| 1.2.4 |
|
「六条院の姫宮の御方におります猫は、たいそう見たこともないような顔をしていて、かわいらしうございました。
ほんのちょっと拝見しました」
|
「六条院の姫宮の御殿におりますのはよい猫でございます。珍しい顔でして感じがよろしいのでございます。私はちょっと拝見することができました」
|
【六条の院の姫宮の御方に】- 以下「見たまふべし」まで、柏木の詞。
【猫こそ】- 明融臨模本は「ねこそ」とある。大島本は「ねここそ」とある。文末は「をかしうはべしか」と已然形であるから「こそ」が適切。『集成』『完本』は大島本や諸本に従って「猫こそ」と校訂する。『新大系』は底本(大島本)通り。
|
| 1.2.5 |
と啓したまへば、わざとらうたくせさせたまふ御心にて、詳しく問はせたまふ。 |
と申し上げなさると、猫を特におかわいがりあそばすご性分なので、詳しくお尋ねあそばす。
|
こんなことを申し上げた。東宮は猫が非常にお好きであらせられるために、くわしくお尋ねになった。
|
【わざとらうたく】- 明融臨模本と大島本は「わさとらうたく」とある。『集成』『新大系』は底本(明融臨模本・大島本)のままとする。『完本』は諸本に従って「猫わざとらうたく」と「猫」を補訂する。
|
| 1.2.6 |
「唐猫の、ここのに違へるさましてなむはべりし。同じやうなるものなれど、心をかしく人馴れたるは、あやしくなつかしきものになむはべる」 |
「唐猫で、こちらのとは違った恰好をしてございました。
同じようなものですが、性質がかわいらしく人なつっこいのは、妙にかわいいものでございます」
|
「支那の猫でございまして、こちらの産のものとは変わっておりました。皆同じように思えば同じようなものでございますが、性質の優しい人馴れた猫と申すものはよろしいものでございます」
|
【唐猫の】- からねこの-以下「ものになむはべる」まで、柏木の詞。
|
| 1.2.7 |
など、ゆかしく思さるばかり、聞こえなしたまふ。
|
などと、興味をお持ちになるように、特にお話し申し上げなさる。
|
こんなふうに宮がお心をお動かしになるようにばかり衛門督は申すのであった。
|
|
| 1.2.8 |
|
お耳にお止めあそばして、桐壷の御方を介してご所望なさったので、差し上げなさった。
「なるほど、たいそうかわいらしげな猫だ」と、人々が面白がるので、衛門督は、「手に入れようとお思いであった」と、お顔色で察していたので、数日して参上なさった。
|
あとで東宮は淑景舎の方の手から所望をおさせになったために、女三の宮から唐猫が献上された。噂されたとおりに美しい猫であると言って、東宮の御殿の人々はかわいがっているのであったが、衛門督は東宮は確かに興味をお持ちになってお取り寄せになりそうであると観察していたことであったから、猫のことを知りたく思って幾日かののちにまた参った。
|
【聞こし召しおきて】- 主語は東宮。以下、後日の話になる。
【桐壺の御方】- 明石女御をさす。
【聞こえさせたまひければ】- 『集成』は「その猫をご所望になったので」と訳す。
【参らせたまへり】- 女三の宮方から東宮に猫を差し上げなさった、の意。
【げに、いとうつくしげなる猫なりけり】- 東宮方の人々の詞。「げに」は柏木の言葉に納得する気持ちの表出。
【人びと興ずるを】- 『完訳』は「人々がおもしろがっているところへ」と訳す。
【尋ねむと思したりき」と、御けしきを見おきて】- 『集成』は「あの猫を手に入れたいとお思いだったと、(その時の)東宮のお顔色を見て取った上で」。『完訳』は「東宮があの猫をもらい受けようとおぼしめしだった、と察していたので」と訳す。このあたり、時間が前後して語られている。
|
| 1.2.9 |
童なりしより、朱雀院の取り分きて思し使はせたまひしかば、御山住みに後れきこえては、またこの宮にも親しう参り、心寄せきこえたり。御琴など教へきこえたまふとて、 |
子供であったころから、朱雀院が特別におかわいがりになってお召し使いあそばしていたので、御入山されて後は、やはりこの東宮にも親しく参上し、お心寄せ申し上げていた。
お琴などをお教え申し上げなさるついでに、
|
まだ子供であった時から朱雀院が特別にお愛しになってお手もとでお使いになった衛門督であって、院が山の寺へおはいりになってからは東宮へもよく伺って敬意を表していた。琴など御教授をしながら、衛門督は、
|
【御琴など教へきこえ】- 柏木は東宮に弦楽器を教授している。太政大臣家は特に和琴の名手である。
|
| 1.2.10 |
|
「御猫たちがたくさん集まっていますね。
どうしたかな、
|
「お猫がまたたくさんまいりましたね。どれでしょう、私の知人は」
|
【御猫ども】- 以下「この見し人は」まで、柏木の詞。猫を「見し人」と喩えて言っている。『集成』は「女三の宮の身代わりというほどの気持が「人」と言わせている」と注す。
|
| 1.2.11 |
と尋ねて見つけたまへり。
いとらうたくおぼえて、かき撫でてゐたり。
宮も、
|
と探してお見つけになった。
とてもかわいらしく思われて、撫でていた。
東宮も、
|
と言いながらその猫を見つけた。非常に愛らしく思われて衛門督は手でなでていた。宮は、
|
|
| 1.2.12 |
「げに、をかしきさましたりけり。心なむ、まだなつきがたきは、見馴れぬ人を知るにやあらむ。ここなる猫ども、ことに劣らずかし」 |
「なるほど、かわいい恰好をしているね。
性質が、まだなつかないのは、人見知りをするのだろうか。
ここにいる猫たちも、大して負けないがね」
|
「実際容貌のよい猫だね。けれど私には馴つかないよ。人見知りをする猫なのだね。しかし、これまで私の飼っている猫だってたいしてこれには劣っていないよ」
|
【げに、をかしきさましたりけり】- 以下「劣らずかし」まで、東宮の詞。猫の様子。
|
| 1.2.13 |
とのたまへば、
|
とおっしゃるので、
|
とこの猫のことを仰せられた。
|
|
| 1.2.14 |
|
「猫というものは、そのような人見知りは、普通しないものでございますが、その中でも賢い猫は、自然と性根がございますのでしょう」などとお答え申し上げて、「これより勝れている猫が何匹もございますようですから、これは暫くお預かり申しましょう」
|
「猫は人を好ききらいなどあまりせぬものでございますが、しかし賢い猫にはそんな知恵があるかもしれません」などと衛門督は申して、また、「これ以上のがおそばに幾つもいるのでございましたら、これはしばらく私にお預からせください」
|
【これは、さるわきまへ心も】- 以下「魂はべらむかし」まで、柏木の詞。「これは」は猫一般をさす。
【まさるどもさぶらふめるを】- 以下「預からむ」まで、柏木の詞。「まさるども」はこの猫より勝れている猫ども、の意。
|
| 1.2.15 |
|
と申し上げなさる。
心の中では、何とも馬鹿げた事だと、一方ではお考えになるが、この猫を手に入れて、夜もお側近くにお置きなさる。
|
こんなお願いをした。心の中では愚かしい行為をするものであるという気もしているのである。結局衛門督は望みどおりに女三の宮の猫を得ることができて、夜などもそばへ寝させた。
|
【かつはおぼゆるに】- 明融臨模本は「かつはおほゆるに」とある。大島本は「かつハおほゆるつゐに」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「おぼゆ。つひに」と校訂する。『新大系』は底本(大島本)のまま「おぼゆる。つひに」とする。
【これを尋ね取りて】- 柏木、猫を手に入れて女三の宮を偲ぶ。
|
| 1.2.16 |
明け立てば、猫のかしづきをして、撫で養ひたまふ。人気遠かりし心も、いとよく馴れて、ともすれば、衣の裾にまつはれ、寄り臥し睦るるを、まめやかにうつくしと思ふ。いといたく眺めて、端近く寄り臥したまへるに、来て、「ねう、ねう」と、いとらうたげに鳴けば、かき撫でて、「うたても、すすむかな」と、ほほ笑まる。 |
夜が明ければ、猫の世話をして、撫でて食事をさせなさる。
人になつかなかった性質も、とてもよく馴れて、ともすれば、衣服の裾にまつわりついて、側に寝そべって甘えるのを、心からかわいいと思う。
とてもひどく物思いに耽って、端近くに寄り臥していらっしゃると、やって来て、「ねよう、ねよう」と、とてもかわいらしげに鳴くので、撫でて、「いやに、積極的だな」と、思わず苦笑される。
|
夜が明けると猫を愛撫するのに時を費やす衛門督であった。人馴つきの悪い猫も衛門督にはよく馴れて、どうかすると着物の裾へまつわりに来たり、身体をこの人に寄せて眠りに来たりするようになって、衛門督はこの猫を心からかわいがるようになった。物思いをしながら顔をながめ入っている横で、にょうにょうとかわいい声で鳴くのを撫でながら、愛におごる小さき者よと衛門督はほほえまれた。
|
【ねう、ねう】- 猫の鳴き声。擬音語。柏木は「寝よう、寝よう」の意に解す。
【うたても、すすむかな」と、ほほ笑まる】- 『集成』は「いやに積極的だなと、苦笑が浮ぶ」。『完訳』は「いやに心のはやるやつよ、と苦笑せずにはいられない」と訳す。
|
| 1.2.17 |
|
「恋いわびている人のよすがと思ってかわいがっていると
どういうつもりでそんな鳴き声を立てるのか
|
「恋ひわぶる人の形見と手ならせば
汝よ何とて鳴く音なるらん
|
【恋ひわぶる人のかたみと手ならせば--なれよ何とて鳴く音なるらむ】- 柏木の独詠歌。
|
| 1.2.18 |
|
これも前世からの縁であろうか」
|
これも前生の約束なんだろうか」
|
【これも昔の契りにや】- 歌の後の独り言。「これ」は猫との縁をさす。
|
| 1.2.19 |
と、顔を見つつのたまへば、いよいよらうたげに鳴くを、懐に入れて眺めゐたまへり。
御達などは、
|
と、顔を見ながらおっしゃると、ますますかわいらしく鳴くので、懐に入れて物思いに耽っていらっしゃる。
御達などは、
|
顔を見ながらこう言うと、いよいよ猫は愛らしく鳴くのを懐中に入れて衛門督は物思いをしていた。女房などは、
|
|
| 1.2.20 |
|
「奇妙に、急に猫を寵愛なさるようになったこと。
このようなものはお好きでなかったご性分なのに」
|
「おかしいことですね。にわかに猫を御寵愛されるではありませんか。ああしたものには無関心だった方がね」
|
【あやしく、にはかなる猫の】- 以下「御心かな」まで、御達の詞。
|
| 1.2.21 |
と、とがめけり。
宮より召すにも参らせず、取りこめて、これを語らひたまふ。
|
と、不審がるのだった。
宮から返すようにとご催促があってもお返し申さず、独り占めして、この猫を話相手にしていらっしゃる。
|
と不審がってささやくのであった。東宮からお取りもどしの仰せがあって、衛門督はお返しをしないのである。お預かりのものを取り込んで自身の友にしていた。
|
|
|
第三段 柏木、真木柱姫君には無関心
|
| 1.3.1 |
|
左大将殿の北の方は、大殿の君たちよりも、右大将の君を、やはり昔のままに、親しくお思い申し上げていらっしゃった。
気立てに才気があって、親しみやすくいらっしゃる方なので、お会いなさる時々にも、親身に他人行儀になるところはなくお振る舞いになるので、右大将も、淑景舎などが、他人行儀で近づきがたいお扱いであるので、一風変わったお親しさで、お付き合いしていらっしゃった。
|
左大将夫人の玉鬘の尚侍は真実の兄弟に対するよりも右大将に多く兄弟の愛を持っていた。才気のあるはなやかな性質の人で、源大将の訪問を受ける時にも睦まじいふうに取り扱って、昔のとおりに親しく語ってくれるため、大将も淑景舎の方が羞恥を少なくして打ち解けようとする気持ちのないようなのに比べて、風変わりな兄弟愛の満足がこの人から得られるのであった。
|
【左大将殿の北の方は】- 玉鬘の近況、旧に変わらず夕霧と親しく交際。
【心ばへのかどかどしく、気近くおはする君にて】- 玉鬘についていう。
【疎々しく及びがたげなる御心ざまのあまりなるに】- 『集成』は「よそよそしくてとても近づきがたく取り澄ましていられるのが心外なので」と訳す。
|
| 1.3.2 |
|
夫君は、今では以前にもまして、あの前の北の方とすっかり縁が切れてしまって、並ぶ者がないほど大切にしていらっしゃる。
このお方の腹には、男のお子たちばかりなので、物足りないと思って、あの真木柱の姫君を引き取って、大切にお世話申したいとお思いになるが、祖父宮などは、どうしてもお許しにならず、
|
左大将は月日に添えて玉鬘を重んじていった。もう前夫人は断然離別してしまって尚侍が唯一の夫人であった。この夫人から生まれたのは男の子ばかりであるため、左大将はそれだけを物足らず思い、真木柱の姫君を引き取って手もとへ置きたがっているのであるが、祖父の式部卿の宮が御同意をあそばさない。
|
【男君、今はまして】- 鬚黒大将、娘の真木柱の姫君のことを恋しく思う。
【並びなくもてかしづききこえたまふ】- 鬚黒は玉鬘を。
【かの真木柱の姫君を】- 「真木柱の姫君」の呼称は、巻名にもとづくものか。当時、十二、三歳であったから、現在十六、七歳になっている。
【祖父宮など】- 式部卿宮。
|
| 1.3.3 |
|
「せめてこの姫君だけでも、物笑いにならないように世話しよう」
|
「せめてこの姫君にだけは人から譏られない結婚を自分がさせてやりたい」
|
【この君をだに、人笑へならぬさまにて見む】- 式部卿宮の詞。「見む」は立派な婿を迎えてやりたい、の意。
|
| 1.3.4 |
と思し、のたまふ。
|
とお思いになり、おっしゃりもしている。
|
と言っておいでになる。
|
|
| 1.3.5 |
|
親王のご声望はたいそう高く、帝におかせられても、この宮への御信頼は、並々ならぬものがあって、こうと奏上なさることはお断りになることができず、お気づかい申していらっしゃる。
だいたいのお人柄も現代的でいらっしゃる宮で、こちらの院、大殿にお次ぎ申して、人々もお仕え申し、世間の人々も重々しく申し上げているのであった。
|
帝は御伯父のこの宮に深い御愛情をお持ちになって、宮から奏上されることにお背きになることはおできにならないふうであった。もとからはなやかな御生活をしておいでになって、六条院、太政大臣家に続いての権勢の見える所で、世間の信望も得ておいでになった。
|
【内裏にも、この宮の御心寄せ、いとこよなくて】- 式部卿宮は冷泉帝の母藤壺の兄すなわち伯父にあたり、その娘が王女御として入内もしているという関係。
【心苦しきものに思ひきこえたまへり】- 冷泉帝が式部卿宮を。『集成』は「心にかけて大切なお方とお思い申し上げていられる」。『完訳』は「お気づかい申しておいであそばす」と訳す。
【この院、大殿にさしつぎたてまつりては】- 式部卿宮は、源氏、太政大臣家に次ぐ、第三の権勢家。「澪標」巻以来変わらない地位を確保。鬚黒左大将より上格。
|
| 1.3.6 |
|
左大将も、将来の国家の重鎮とおなりになるはずの有力者であるから、姫君のご評判、どうして軽いことがあろうか。
求婚する人々、何かにつけて大勢いるが、ご決定なさらない。
衛門督を、「そのような、態度を見せたら」とお思いのようだが、猫ほどにはお思いにならないのであろうか、まったく考えもしないのは、残念なことであった。
|
左大将も第一人者たる将来が約束されている人であったから、式部卿の宮の御孫女、左大将の長女である姫君を人は重く見ているのである。求婚者がいろいろな人の手を通じて来てすでに多数に及んでいるが、宮はまだだれを婿にと選定されるふうもなかった。かれにその気があればと宮が心でお思いになる衛門督は猫ほどにも心を惹かぬのかまったくの知らず顔であった。
|
【さる世の重鎮となりたまふべき下形なれば】- 『集成』は「東宮の伯父として、国家の柱石ともおなりになるはずの有力者でいられるから」と訳す。
【などてかは軽くはあらむ】- 「などてかは--む」反語表現。語り手の言辞。
【聞こえ出づる人びと】- 真木柱の姫君に求婚する人々。
【思しも定めず】- 主語は式部卿宮。真木柱の姫君の親権者は祖父式部卿宮。
【さも、けしきばまば】- 真木柱の姫君への求婚の意向。
【猫には思ひ落としたてまつるにや】- 『一葉抄』は「双紙詞也」と指摘。『集成』は「以下、前の話題とここの話題とをつないでの諧謔気味の草子地」。『完訳』は「語り手の皮肉めいた評言」と注す。
|
| 1.3.7 |
|
母君が、どうしたことか、今だに変な方で、普通のお暮らしぶりでなく、廃人同様になっていらっしゃるのを、残念にお思いになって、継母のお側を、いつも心にかけて憧れて、現代的なご気性でいらっしゃっるのだった。
|
左大将の前夫人は今も病的な、陰気な暮らしを続けて、若い貴女のために朗らかな雰囲気を作ろうとする努力もしてくれないために、姫君は寂しがって、人づてに聞く継母の生活ぶりにあこがれを持っていた。こうした明るい娘なのである。
|
【もて消ちたまへるを】- 『集成』は「廃人同様のありさまでいられるのを」。『完訳』は「世間と没交渉になっている意」「世間のことは意にも介しておられないのを」と注す。
【口惜しきものに思して】- 主語は真木柱の姫君。
【今めきたる御心ざまにぞものしたまひける】- 主語は真木柱の姫君。継母を慕うあたりが今風といわれるゆえん。
|
|
第四段 真木柱、兵部卿宮と結婚
|
| 1.4.1 |
|
蛍兵部卿宮は、やはり独身生活でいらっしゃって、熱心にお望みになった方々は、皆うまくいかなくて、世の中が面白くなく、世間の物笑いに思われると、「このまま甘んじていられない」とお思いになって、この宮に気持ちをお漏らしになったところ、式部卿大宮は、
|
兵部卿の宮は今も御独身で、熱心にお望みになった相手は皆ほかへ取られておしまいになる結果になって、世間体も恥ずかしくお思いになるのであったが、この姫君に興味をお感じになり、縁談をお申し入れになると、式部卿の宮は、
|
【兵部卿宮、なほ一所のみおはして】- 蛍兵部卿宮は北の方を亡くして以後、独身生活。
【御心につきて思しけることどもは、皆違ひて】- 玉鬘や女三の宮を望んだことをさす。
【さてのみやはあまえて過ぐすべき】- 蛍兵部卿宮の心中。「あまえて」について、『集成』は「こんなふうにのんびり構えてばかりもいられない」。『完訳』は「こんなふうにいい気になってばかりもいられまい」と訳す。
|
| 1.4.2 |
|
「いや何。
大切に世話しようと思う娘なら、帝に差し上げる次には、親王たちにめあわせ申すのがよい。
臣下の、真面目で、無難な人だけを、今の世の人が有り難がるのは、品のない考え方だ」
|
「私はそう信じているのだ。大事に思う娘は宮仕えに出すことを第一として、続いては宮たちと結婚させることがいいとね。普通の官吏と結婚させるのを頼もしいことのように思って親たちが娘の幸福のためにそれを願うのは卑しい態度だ」
|
【何かは】- 以下「品なきわざなり」まで、式部卿宮の詞。娘の結婚相手の第一は帝、次いで親王だ、という考え。実際、宮の中の君は王女御として入内。大君は臣下の鬚黒大将の北の方となったが、離縁となった。
【ただ人の、すくよかに、なほなほしきをのみ】- 鬚黒の性格が思い合わされる表現。
|
| 1.4.3 |
とのたまひて、いたくも悩ましたてまつりたまはず、受け引き申したまひつ。
|
とおっしゃって、そう大してお焦らし申されることなく、ご承諾なさった。
|
とお言いになって、あまり求婚期間の悩みもおさせにならずに御同意になった。
|
|
| 1.4.4 |
親王、あまり怨みどころなきを、さうざうしと思せど、おほかたのあなづりにくきあたりなれば、えしも言ひすべしたまはで、おはしましそめぬ。いと二なくかしづききこえたまふ。 |
蛍親王は、あまりに口説きがいのないのを、物足りないとお思いになるが、大体が軽んじ難い家柄なので、言い逃れもおできになれず、お通いになるようになった。
たいそうまたとなく大事にお世話申し上げなさる。
|
兵部卿の宮はこの無造作な決まり方を物足らぬようにもお思いになったが、軽蔑しがたい相手であったから、ずるずる延ばしで話の解消をお待ちになることもおできにならないで、通って行くようにおなりになった。
|
【いと二なくかしづききこえたまふ】- 式部卿宮家が蛍兵部卿宮を婿として。
|
| 1.4.5 |
大宮は、女子あまたものしたまひて、
|
式部卿大宮は、女の子がたくさんいらっしゃって、
|
式部卿の宮はこの婿の宮を大事にあそばすのであった。宮は幾人もの女王をお持ちになって、
|
|
| 1.4.6 |
|
「いろいろと何かにつけ嘆きの種が多いので、懲り懲りしたと思いたいところだが、やはりこの君のことが放っておけなく思えてね。
母君は、奇妙な変人に年とともになって行かれる。
大将は大将で、自分の言う通りにしないからと言って、いい加減に見放ちなされたようだから、まことに気の毒である」
|
その宮仕え、結婚の結果によって苦労をされることの多かったのに懲りておいでになるはずであるが、最愛の御孫女のためにまたこうした婿かしずきをお始めになったのである。「母親は時がたつにしたがって病的な女になるし、父親はそちらの意志には従わない子だと言ってそまつに見ている姫君だからかわいそうでならぬ」
|
【さまざまもの嘆かしき】- 以下「心苦しき」まで、式部卿宮の詞。
【物懲りしぬべけれど】- 式部卿宮の大君は鬚黒と離縁、中の君は入内はしたものの立后が叶わなかった。
【わがことに従はず】- 鬚黒の意見に式部卿宮が従わない、の意。
|
| 1.4.7 |
とて、御しつらひをも、立ちゐ、御手づから御覧じ入れ、よろづにかたじけなく御心に入れたまへり。
|
と言って、お部屋の飾り付けも、立ったり座ったり、ご自身でお世話なさり、すべてにもったいなくも熱心でいらっしゃった。
|
などとお言いになって、新夫婦の居間の装飾まで御自身で手を下してなされたり、またお指図をされたりもするのであった。
|
|
|
第五段 兵部卿宮と真木柱の不幸な結婚生活
|
| 1.5.1 |
|
宮は、お亡くなりになった北の方を、それ以来ずっと恋い慕い申し上げなさって、「ただ、亡くなった北の方の面影にお似申し上げたような方と結婚しよう」とお思いになっていたが、「悪くはないが、違った感じでいらっしゃる」とお思いになると、残念であったのか、お通いになる様子は、まこと億劫そうである。
|
兵部卿の宮はお亡くしになった先夫人をばかり恋しがっておいでになって、その人に似た新婦を得たいと願っておいでになったために、この姫君を、悪くはないが似た所がないと御覧になったせいか、通っておいでになるのにおっくうなふうをお見せになった。
|
【昔の御ありさまに似たてまつりたらむ人を見む】- 蛍兵部卿宮の心中。故北の方は、右大臣の三の君、太政大臣の北の方(四の君)や六の君(朧月夜尚侍)の姉。「花宴」に「帥宮の北の方、頭中将のすさめぬ四の君などこそよしと聞きしか」(第一章二段)とあるのが初出。「胡蝶」に「年ごろおはしける北の方も亡せたまひて、この三年ばかり独り住みにてわびたまへば」(第一章三段)とあった。「面影の人」を求めるのはこの物語の通貫したテーマ。
【悪しくはあらねど、さま変はりてぞものしたまひける】- 蛍兵部卿宮の感想。『集成』は「きれいな人ではあるが、全然感じの違うお方だった」。『完訳』は「ご器量がわるいというわけではないのだけれど、まるで感じがちがっていらっしゃる」と訳す。
【口惜しくやありけむ】- 語り手の挿入句。蛍兵部卿宮の心中を忖度。
|
| 1.5.2 |
|
式部卿大宮は、「まったく心外なことだ」とお嘆きになっていた。
母君も、あれほど変わっていらっしゃったが、正気に返る時は、「口惜しい嫌な世の中だ」と、すっかり思いきりなさる。
|
式部卿の宮は失望あそばした。病人である母君も気分の常態になっている時にはこの娘の思うようでない結婚を歎いて、いよいよ人生をいやなものにきめてしまった。
|
【いと心づきなきわざかな】- 式部卿宮の心中。蛍宮の態度に立腹。
【口惜しく憂き世」と、思ひ果てたまふ】- 『集成』は「ままならぬ、情けないこの世だと、すっかり悲観しておしまいになる」「自分も髭黒との結婚に破れ、娘もまた、という気持」。『完訳』は「残念な情けない縁組であったと、すっかり気落ちしていらっしゃる」「母君は女の幸不幸は母親次第と考えて娘を引き取っただけに落胆が大きい」と注す。
|
| 1.5.3 |
|
左大将の君も、「やはりそうであったか。
ひどく浮気っぽい親王だから」と、はじめからご自身お認めにならなかったことだからであろうか、面白からぬお思いでいらっしゃった。
|
父親の左大将もこの話を聞いて、自分のあやぶんだとおりの結果になったではないか、多情者の宮様であるからと思って、初めから自分が賛成しなかった婿であったから困ったことであると歎いていた。
|
【さればよ。いたく色めきたまへる親王を】- 鬚黒大将の心中。蛍宮の好色風流好みの性格に対する批判。
【はじめよりわが御心に許したまはざりしことなればにや】- 語り手の挿入句。鬚黒大将の心中を忖度。
|
| 1.5.4 |
|
尚侍の君も、このように頼りがいのないご様子を、身近にお聞きになるにつけ、「そのような方と結婚をしたのだったら、こちらにもあちらにも、どんなにお思いになり御覧になっただろう」などと、少々おかしくも、また懐かしくもお思い出しになるのだった。
|
玉鬘夫人は宮のお情けの薄さを継娘の不幸として聞いていながら、自分がもし結婚をしてそうした目にあっていたなら、六条院の人々へも、実父の家族へも不名誉なことになるのであったと思った。そして左大将の妻になった運命を悲しむ気もなくなり、継娘に限りなく同情した。その自分の処女時代にも兵部卿の宮を良人にしようとは少しも思わなかった。
|
【近く聞きたまふには】- 継母としての立場から身近に聞くの意。
【さやうなる世の中を】- 以下「思し見たまはまし」まで、玉鬘の心中。「ましかば--まし」反実仮想の構文。蛍宮と結婚しなくてよかったという感想。「こなたかなた」は源氏と太政大臣をさす。
|
| 1.5.5 |
|
「あの当時も、結婚しようとは、考えてもいなかったのだ。
ただ、いかにも優しく、情愛深くお言葉をかけ続けてくださったのに、張り合いなく軽率なように、お見下しになったであろうか」と、とても恥ずかしく、今までもお思い続けていらっしゃることなので、「あのような近いところで、わたしの噂をお聞きになることも、気をつかわねばならない」などとお思いになる。
|
ただあれだけの情熱を運んでくだすった方が、左大将と平凡な夫婦になってしまったことを軽蔑しておいでにならないかとそれ以来恥ずかしく思っていたのであると玉鬘夫人は思い、その宮が継娘の婿におなりになって、自分のことをどう聞いておいでになるであろうと思うと晴れがましいような気もするのであった。この夫人からも新婚した姫君の衣裳その他の世話をした。
|
【そのかみも、気近く見聞こえむとは】- 以下「聞き落としたまひけむ」まで、玉鬘の心中。
【かかるあたりにて、聞きたまはむことも、心づかひせらるべく】- 玉鬘の心中。夫婦の語らいの中で、蛍宮が継娘の真木柱から玉鬘の噂を聞く、の意。
|
| 1.5.6 |
|
こちらからも、しかるべき事柄はしてお上げになる。
兄弟の公達などを差し向けて、このようなご夫婦仲も知らない顔をして、親しげにお側に伺わせたりなどするので、気の毒になって、お見捨てになる気持ちはないが、大北の方という性悪な人が、いつも悪口を申し上げなさる。
|
前夫人がどう恨んでいるかというようなことは知らぬふうにして、長男、次男を中にして好意を寄せる尚侍に前夫人は友情をすら覚えているのであるが、式部卿の宮家には大夫人という性質の曲がった人が一人いて、この人は常にだれのことも憎んで、罵言をやめないのである。
|
【これよりも、さるべきことは】- 玉鬘方をさす。継母としての配慮。
【大北の方といふさがな者ぞ】- 式部卿宮の北の方。『集成』は「かつて継娘に当る紫の上の不幸を小気味よがったり(須磨)、玉鬘と髭黒の結婚について源氏をあしざまにののしったりした(真木柱)。そこにも「この大北の方ぞ、さがな者なりける」(真木柱)とあり、札付きといった扱い」と注す。この物語では、かつての右大臣の娘弘徽殿の大后とこの式部卿の北の方がつねに悪役といった感じ。
|
| 1.5.7 |
「親王たちは、のどかに二心なくて、見たまはむをだにこそ、はなやかならぬ慰めには思ふべけれ」 |
「親王たちは、おとなしく浮気をせず、せめて愛して下さるのが、華やかさがない代わりには思えるのだが」
|
「親王がたというものは一人だけの奥さんを大事になさるということで、派手な生活のできない補いにもなろうというものだのに」
|
【親王たちは】- 以下「思ふべけれ」まで、大北の方の詞。『集成』は「親王には政治的な権力がなく、婿取りしても世俗的な家の繁栄は望めないので、こうした愚痴にもなる」と注す。
|
| 1.5.8 |
とむつかりたまふを、宮も漏り聞きたまひては、「いと聞きならはぬことかな。昔、いとあはれと思ひし人をおきても、なほ、はかなき心のすさびは絶えざりしかど、かう厳しきもの怨じは、ことになかりしものを」 |
とぶつぶつおっしゃるのを、宮も漏れお聞きなさっては、「まったく変な話だ。
昔、とてもいとしく思っていた人を差し置いても、やはり、ちょっとした浮気はいつもしていたが、こう厳しい恨み言は、なかったものを」
|
と陰口をするのが兵部卿の宮のお耳にはいった時、不愉快なことを聞く、自分に最愛の妻があった時代にも他との恋愛の遊戯はやめなかった自分も、こうまではひどい恨み言葉は聞かないでいた
|
【いと聞きならはぬことかな】- 以下「なかりしものを」まで、蛍兵部卿宮の心中。末尾は地の文に続く。
|
| 1.5.9 |
心づきなく、いとど昔を恋ひきこえたまひつつ、故里にうち眺めがちにのみおはします。さ言ひつつも、二年ばかりになりぬれば、かかる方に目馴れて、ただ、さる方の御仲にて過ぐしたまふ。 |
と、気にくわなく、ますます故人をお慕いなさりながら、自邸に物思いに耽りがちでいらっしゃる。
そうは言いながらも、二年ほどになったので、こうした事にも馴れて、ただ、そのような夫婦仲としてお過ごしになっていらっしゃる。
|
とお思いになって、いっそう亡き夫人を恋しく思召すことばかりがつのって、自邸で寂しく物思いをしておいでになる日が多かった。そうはいうものの二年もその状態で続いて来た今では、ただそれだけの淡い関係の夫婦として済んで行った。
|
【昔を恋ひきこえたまひつつ】- 亡くなった北の方をさす。
|
|
第二章 光る源氏の物語 住吉参詣
|
|
第一段 冷泉帝の退位
|
| 2.1.1 |
|
これという事もなくて、年月が過ぎて行き、今上の帝、御即位なさってから十八年におなりあそばした。
|
歳月が重なり、帝が即位をあそばされてから十八年になった。
|
【はかなくて、年月もかさなりて、内裏の帝、御位に即かせたまひて、十八年にならせたまひぬ】- その後四年を経て、冷泉帝は譲位する。冷泉帝は十一歳で即位(澪標)。したがって現在二十八歳。源氏は四十六歳。つまり、源氏四十二歳から四十五歳までの四年間の空白がある。
|
| 2.1.2 |
|
「後を嗣いで次の帝におなりになる皇子がいらっしゃらず、物寂しい上に、寿命がいつまで続くか分からない気がするので、気楽に、会いたい人たちと会い、私人として思うままに振る舞って、のんびりと過ごしたい」
|
「将来の天子になる子のないことで自分には人生が寂しい。せめて気楽な身の上になって自分の愛する人たちと始終出逢うこともできるようにして、私人として楽しい生活がしてみたい」
|
【嗣の君とならせたまふべき御子】- 以下「過ぎまほしくなむ」まで、冷泉帝の詞。次の帝となるべき男皇子もいない寂しさを嘆く。
【世の中はかなくおぼゆるを】- 『完訳』は「この寿命もいつまで続くのか頼りなく思われてならないので」と訳す。
【のどかに過ぎまほしくなむ】- 明融臨模本と大島本は「すきまほしく」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「過ぐさまほしく」と校訂する。『新大系』は底本(大島本)のままとする。
|
| 2.1.3 |
|
と、長年お思いになりおっしゃりもしていたが、最近たいそう重くお悩みあそばすことがあって、急に御退位あそばした。
世間の人は、「惜しい盛りのお年を、このようにお退きになること」と惜しみ嘆いたが、東宮もご成人あそばしているので、お嗣ぎになって、世の中の政治など、特別に変わることもなかった。
|
以前からよくこう帝は仰せられたのであったが、重く御病気をあそばされた時ににわかに譲位を行なわせられた。世人は盛りの御代をお捨てあそばされることを残念がって歎いたが、東宮ももう大人になっておいでになったから、お変わりになっても特別変わったこともなかった。ゆるぎない大御代と見えた。
|
【飽かず盛りの御世を、かく逃れたまふこと】- 世の中の人の詞。冷泉帝の御譲位を惜しむ。
【春宮もおとなびさせたまひにたれば】- 東宮は二十歳。朱雀院の皇子、母承香殿女御で左大将鬚黒の妹。三歳で立坊(澪標)、十三歳で元服(梅枝)、源氏の娘明石女御が入内(藤裏葉)、第一皇子誕生(若菜上)。
【世の中の政事など、ことに変はるけぢめもなかりけり】- 冷泉帝から今上帝へ御世替わりがあったが、格別政治や政界の人事に大きな異動がなかったことをいう。
|
| 2.1.4 |
|
太政大臣は致仕の表を奉って、ご引退なさった。
|
太政大臣は関白職の辞表を出して自邸を出なかった。
|
【太政大臣、致仕の表たてまつりて】- 太政大臣が致仕し、鬚黒が右大臣となる。
|
| 2.1.5 |
|
「世間の無常によって、恐れ多い帝の君も、御位をお下りになったのに、年老いた自分が冠を掛けるのは、何の惜しいことがあろうか」
|
「人生の頼みがたさから賢明な帝王さえ御位をお去りになるのであるから、老境に達した自分が挂冠するのに惜しい気持ちなどは少しもない」
|
【世の中の常なきにより】- 以下「何か惜しからむ」まで、太政大臣の詞。
【冠を挂けむ】- 逢萌字子康 北海都昌人也 (中略) 即解冠挂東都城門 帰 将家属浮海 客於遼東(後漢書-逢萌伝)(text35.html 出典4 から転載)
|
| 2.1.6 |
|
とお考えになりおっしゃって、左大将が、右大臣におなりになって、政務をお勤めになったのであった。
承香殿女御の君は、このような御世にお会いにならず、お亡くなりになったので、規定のご称号を奉られたが、光の当たらない感じがして、何にもならなかった。
|
と言っていたに違いない。左大将が右大臣になって関白の仕事もした。御母君の女御は新帝の御代を待たずに亡くなっていたから、后の位にお上されになっても、それはもう物の背面のことになって寂しく見えた。
|
【と思しのたまひて】- 明融臨模本と大島本は「おほしの給て」とある。『完本』は諸本に従って「思しのたまふ」と校訂する。『集成』『新大系』は底本(明融臨模本・大島本)のままとする。
【女御の君は、かかる御世をも待ちつけたまはで、亡せたまひにければ】- 東宮の母承香殿女御はこれまでに死去。はじめてここに語られる。
【限りある御位を得たまへれど】- 皇太后の位を追贈されたことをいう。
|
| 2.1.7 |
|
六条院の女御腹の一の宮、東宮におつきになった。
当然のこととは以前から思っていたが、実現して見るとやはり素晴らしく、目を見張るようなことであった。
右大将の君、大納言におなりになった。
ますます理想的なお間柄である。
|
六条の女御のお生みした今上第一の皇子が東宮におなりになった。そうなるはずのことはだれも知っていたが、目前にそれが現われてみればまた一家の幸福さに驚きもされるのであった。右大将が大納言を兼ねて順序のままに左大将に移り、この人も幸福に見えた。
|
【六条の女御の御腹の一の宮、坊にゐたまひぬ】- 明石女御の第一皇子が皇太子となる。今年六歳。
【いよいよあらまほしき御仲らひなり】- 鬚黒右大臣と夕霧大納言の関係をいう。
|
| 2.1.8 |
|
六条院は、御退位あそばした冷泉院が、御後嗣がいらっしゃらないのを、残念なこととご心中ひそかにお思いになる。
同じ自分の血統であるが、御煩悶なさることなくて、無事にお過ごしなっただけに、罪は現れなかったが、子孫まで皇位を伝えることができなかった御運命を、口惜しく物足りなくお思いになるが、人と話し合えないことなので、気持ちが晴れない。
|
六条院は御譲位になった冷泉院に御後嗣のないのを御心の中では遺憾に思召された。実は新東宮だって六条院の御血統なのだが、冷泉院の御在位中には御煩悶もなくて過ごされたほど、例の密通の秘密は隠しおおされたが、そのかわりにこの御系統が末まで続かぬように運命づけられておしまいになったのを六条院は寂しくお思いになったが、御口外あそばすことでもないのでただお心で味けなくお感じになるだけであった。
|
【冷泉院】- 初めての呼称。退位後、冷泉院を院の御所としたことがわかる。またこの帝の呼称にもなる。
【御嗣おはしまさぬを、飽かず御心のうちに思す】- 源氏は、冷泉院に御継嗣のいないことを心中に残念に思う。
【同じ筋なれど】- 冷泉院と東宮をさす。
【思ひ悩ましき御ことならで】- 明融臨模本は「御事ならて」とある。大島本は「御事なくて」とある。『集成』『新大系』はそれぞれ底本(明融臨模本・大島本)のままとする。『完本』は諸本に従って「御事なうて」と校訂する。
【過ぐしたまへるばかりに、罪は隠れて、末の世まではえ伝ふまじかりける御宿世】- 接続助詞「て」逆接の意。『完訳』は「世間に知られずにすんだが、そのかわり帝のお血筋を」と訳す。
【口惜しくさうざうしく思せど】- 源氏の心中。間接的叙述。
|
| 2.1.9 |
|
東宮の母女御は、御子たちが大勢いらっしゃって、ますます御寵愛は並ぶ者がいない。
源氏が、引き続いて皇后におなりになることを、世間の人は不満に思っているのにつけても、冷泉院の皇后は、格別の理由もないのに、強引にこのようにして下さったお気持ちをお思いになると、ますます六条院の御事を、年月と共に、この上なく有り難くお思い申し上げになっていらっしゃった。
|
東宮の御母女御は皇子たちが多くお生まれになって帝の御寵はますます深くなるばかりであった。またも王氏の人が后にお立ちになることになっていることで、今度で三代にもなっていたから何かと飽き足らぬらしい世論があるのをお知りになった時、冷泉院の中宮は以前もこうした場合に六条院の強い御支持があって、自分の后の位は定ったのであると過去を回想あそばしてますます院の恩をお感じになった。
|
【春宮の女御は、御子たちあまた数添ひたまひて】- 明石女御は帝の寵愛が厚く御子たちも大勢いる。「春宮の女御」は東宮の母女御の意。帝の女御は複数いる。東宮の母女御は一人。そのほうが重々しい呼称。
【源氏の、うち続き后にゐたまふべきことを】- 藤壺(先帝の四宮)、秋好(故前坊の姫、源氏の養女)をさす。「源氏」は皇族の意で使われている。
【冷泉院の后は】- 秋好中宮。
【ゆゑなくて、あながちにかくしおきたまへる】- 秋好中宮は、立后がかなり強引で無理になったものだ、と思っている。
|
| 2.1.10 |
院の帝、思し召ししやうに、御幸も、所狭からで渡りたまひなどしつつ、かくてしも、げにめでたくあらまほしき御ありさまなり。 |
院の帝は、お考えになっていたように、御幸も、気軽にお出かけなさったりして、御退位後はかえって、確かに素晴らしく申し分ない御生活である。
|
冷泉院の帝は御期待あそばされたとおりに、御窮屈なお思いもなしに御幸などもおできになることになって、あちらこちらと御遊幸あそばされて、今日の御境遇ほどお楽しいものはないようにお見受けされるのであった。
|
【院の帝】- 冷泉院の日常。上皇を「院の帝」と呼称する。
|
|
第二段 六条院の女方の動静
|
| 2.2.1 |
|
姫宮の御事は、帝が、御配慮になってお気をつけて差し上げなさる。
世間の人々からも、広く重んじられていらっしゃるが、対の上のご威勢には、勝ることがおできになれない。
年月がたつにつれて、ご夫婦仲は互いにたいそうしっくりと睦まじくいらして、少しも不満なところなく、よそよそしさもお見えでないが、
|
帝は六条院においでになる御妹の姫宮に深い関心をお持ちになったし、世間がその方に払う尊敬も大きいのであるが、なお紫夫人以上の夫人として六条院の御寵を受けておいでになるのではなかった。年月のたつにしたがって女王と宮の御中にこまやかな友情が生じて、六条院の中は理想的な穏やかな空気に満たされているが、紫夫人は、
|
【姫宮の御ことは、帝、御心とどめて】- 女三の宮をさす。
【年月経るままに、御仲いとうるはしく睦びきこえ交はしたまひて】- 女三の宮降嫁後、五年を経ている。「麗はしく睦び交はす」とは外見的な振る舞いをいうのであろう。『集成』は「源氏とのお間柄はまことにしっくりと仲むつまじくいらして」。『完訳』は「院の殿と対の上とのご夫婦仲はまったく毛筋ほどの乱れもなく、お互いに仲睦まじくお過しになって」と訳す。
【いささか飽かぬことなく、隔ても見えたまはぬものから】- 紫の上の源氏から心の乖離が語られる。
|
| 2.2.2 |
|
「今は、このような普通の生活ではなく、のんびりと仏道生活に入りたい、と思います。
この世はこれまでと、すっかり見終えた気がする年齢にもなってしまいました。
そのようにお許し下さいませ」
|
「もう私はこうした出入りの多い住居から退きまして、静かな信仰生活がしたいと思います。人生とはこんなものということも経験してしまったような年齢にもなっているのですもの、もう尼になることを許してくださいませんか」
|
【今は、かうおほぞうの住まひならで】- 以下「思し許してよ」まで、紫の上の詞。出家の希望を述べる。『完訳』は「このような通り一遍の暮しでなく」「ありふれた物思いがちな愛人なみの生活」と注す。
【この世はかばかりと、見果てつる心地する齢にもなりにけり】- 紫の上、三十六歳。後文の翌年の記事に「今年は三十七にぞなりたまふ」(第六章二段)とある。
|
| 2.2.3 |
|
と、真剣に申し上げなさることが度々あるが、
|
と、時々まじめに院へお話しするのであるが、
|
【まめやかに聞こえたまふ折々あるを】- 紫の上は出家の希望を真剣に度々源氏に願っている。
|
| 2.2.4 |
|
「とんでもない、酷いおっしゃりようです。
わたし自身、強く希望するところですが、後に残って寂しいお気持ちがなさり、今までと違ったようにおなりになるのが、気がかりなばかりに、生き永らえているのです。
とうとう出家した後に、どうなりとお考え通りになさるがよい」
|
「もってのほかですよ。そんな恨めしいことをあなたは思うのですか。それは私自身が実行したいことなのだが、あなたがあとに残って寂しく思ったり、私といっしょにいる時と違った世間の態度を悲しく感じたりすることになってはという気がかりがあるために現状のままでいるだけなのですよ。それでもいつか私の実行の日が来るでしょう、あなたはそのあとのことになさい」
|
【あるまじく、つらき御ことなり】- 以下「ともかくも思しなれ」まで、源氏の詞。紫の上の出家の希望を阻止する。出家後の紫の身の上が心配、自分の出家後に出家するのがよい、という。
【とまりてさうざうしくおぼえたまひ】- 主語は紫の上。源氏が出家した場合を想定した発言。
【ある世に変はらむ御ありさまの】- 『集成』は「今までとは打って変ったお暮しが」。『完訳』は「わたしといっしょの時と比べてどんなに変ったお身の上になろうかと」と訳す。
|
| 2.2.5 |
などのみ、妨げきこえたまふ。
|
などとばかり、ご制止申し上げなさる。
|
などとばかり院はお言いになって、夫人の志を妨げておいでになった。
|
|
| 2.2.6 |
女御の君、ただこなたを、まことの御親にもてなしきこえたまひて、御方は隠れがの御後見にて、卑下しものしたまへるしもぞ、なかなか、行く先頼もしげにめでたかりける。 |
女御の君、ひたすらこちらを、本当の母親のようにお仕え申し上げなさって、御方は蔭のお世話役として、謙遜していらっしゃるのが、かえって、将来頼もしげで、立派な感じであった。
|
女御は今も女王を真実の母として敬愛していて、明石夫人は隠れた女御の後見をするだけの人になって謙遜さを失わないでいることは、かえって将来のために頼もしく思われた。
|
【御方は隠れがの】- 明石御方をさす。
|
| 2.2.7 |
尼君も、ややもすれば、堪へぬよろこびの涙、ともすれば落ちつつ、目をさへ拭ひただして、命長き、うれしげなる例になりてものしたまふ。
|
尼君も、ややもすれば感激に堪えない喜びの涙、ともすれば、落とし落としして、目まで拭い爛れさせて、長生きした、幸福者の例になっていらっしゃる。
|
尼君もうれし泣きの涙を流す日が多くて、目もふきただれて幸福な老婆の見本になっていた。
|
|
|
第三段 源氏、住吉に参詣
|
| 2.3.1 |
|
住吉の神に懸けた御願、そろそろ果たそうとなさって、春宮の女御の御祈願に参詣なさろうとして、あの箱を開けて御覧になると、いろいろな盛大な願文が多かった。
|
住吉の神への願果たしを思い立って参詣する女御は、以前に入道から送って来てあった箱をあけて、神へ約した条件を調べてみたが、それにはかなり大がかりなことを多く書き立ててあった。
|
【住吉の御願、かつがつ果たしたまはむとて】- 源氏、住吉詣でを思い立つ。
|
| 2.3.2 |
年ごとの春秋の神楽に、かならず長き世の祈りを加へたる願ども、げに、かかる御勢ひならでは、果たしたまふべきこととも思ひおきてざりけり。ただ走り書きたる趣きの、才々しくはかばかしく、仏神も聞き入れたまふべき言の葉明らかなり。 |
毎年の春秋に奏する神楽に、必ず子孫の永遠の繁栄を祈願した願文類が、なるほど、このようなご威勢でなければ果たすことがおできになれないように考えていたのであった。
ただ走り書きしたような文面で、学識が見え論旨も通り、仏神もお聞き入れになるはずの文意が明瞭である。
|
年々の春秋の神楽とともに必ず長久隆運の祈りをすることなどは、今日の女御の境遇になっていなければ実行のできぬことであった。ただ走り書きにした文章にも入道の学問と素養が見え、仏も神も聞き入れるであろうことが明らかに知られた。
|
【長き世の祈りを加へたる願ども】- 『集成』は「明石の上の将来を祈願した上に、その度に遠い行く末まで(姫君や東宮のこと)祈って立てた数多くの願は」。『完訳』は「子々孫々の繁栄をという祈りの添えてある願文は」と訳す。
|
| 2.3.3 |
|
「どうしてあのような山伏の聖心で、このような事柄を思いついたのだろう」と、感服し分を過ぎたことだと御覧になる。
「前世の因縁で、ほんの少しの間、仮に身を変えた前世の修行者であったのだろうか」などとお考えめぐらすと、ますます軽んじることはできなかった。
|
どうしてそんな世捨て人の心にこんな望みの楼閣が建てられたのであろうと、子孫への愛の深さが思われもし、神や仏に済まぬ気もされた。並みの人ではなくてしばらく自分の祖父になってこの世へ姿を現わしただけの、功徳を積んだ昔の聖僧ではなかったかなどと思われ、女御に明石の入道を畏敬する心が起こった。
|
【いかでさる山伏の】- 以下「思ひよりけむ」まで、源氏の感想。
【さるべきにて】- 以下「行なひ人にやありけむ」まで、源氏の感想。
【昔の世の行なひ人】- 『集成』は「遠い昔のすぐれた修行僧」。『完訳』は「前の世の行者」と訳す。
|
| 2.3.4 |
このたびは、この心をば表はしたまはず、ただ、院の御物詣でにて出で立ちたまふ。浦伝ひのもの騒がしかりしほど、そこらの御願ども、皆果たし尽くしたまへれども、なほ世の中にかくおはしまして、かかるいろいろの栄えを見たまふにつけても、神の御助けは忘れがたくて、対の上も具しきこえさせたまひて、詣でさせたまふ、響き世の常ならず。いみじくことども削ぎ捨てて、世の煩ひあるまじく、と省かせたまへど、限りありければ、めづらかによそほしくなむ。 |
今回は、この趣旨は表にお立てにならず、ただ、院の物詣でとしてご出立なさる。
浦から浦へと流離した事変の当時の数多くの御願は、すっかりお果たしなさったが、やはりこの世にこうお栄えになっていらっしゃって、このようないろいろな栄華を御覧になるにつけても、神の御加護は忘れることができず、対の上もご一緒申し上げなさって、ご参詣あそばす、その評判、大変なものである。
たいそう儀式を簡略にして、世間に迷惑があってはならないように、と省略なさるが、仕来りがあることゆえ、またとない立派さであった。
|
今度はまだ女御の行なうことにはせずに、六条院の参詣におつれになる形式で京を立ったのであった。須磨明石時代に神へお約しになったことは次々に果たされたのであるが、その以後もまた長く幸運が続き、一門子孫の繁栄を御覧になることによっても神の冥助は忘られずに六条院は紫の女王も伴って御参詣あそばされるのであって、はなやかな一行である。簡素を旨として国の煩いになることはお避けになったのであるが、この御身分であってはある所までは必ず備えられねばならぬ旅の形式があって、自然に大きなことにもなった。
|
【浦伝ひの】- 「浦伝ひ」は歌語。源氏の和歌にも詠まれる(明石)。
【皆果たし尽くしたまへれども】- 「澪標」巻の住吉詣での段に語られている。
【具しきこえさせたまひて、詣でさせたまふ】- 「きこえさせ」謙譲の補助動詞。紫の上に対する敬意。「きこゆ」より一段と深い敬意。「たまひ」尊敬の補助動詞。源氏の動作に対する敬意。「させ」尊敬の助動詞、「たまふ」尊敬の補助動詞、最高敬語。
【限りありければ】- いくら簡略にするといっても院としての格式があるので、という意。
|
|
第四段 住吉参詣の一行
|
| 2.4.1 |
上達部も、大臣二所をおきたてまつりては、皆仕うまつりたまふ。舞人は、衛府の次将どもの、容貌きよげに、丈だち等しき限りを選らせたまふ。この選びに入らぬをば恥に、愁へ嘆きたる好き者どもありけり。 |
上達部も、大臣お二方をお除き申しては、皆お供奉申し上げなさる。
舞人は、近衛府の中将たちで器量が良くて、背丈の同じ者ばかりをお選びあそばす。
この選に漏れたことを恥として、悲しみ嘆いている芸熱心の者たちもいるのだった。
|
公卿も二人の大臣以外は全部供奉した。神前の舞い人は各衛府の次将たちの中の容貌のよいのを、さらに背丈をそろえてとられたのであった。落選して歎く風流公子もあった。
|
【舞人は、衛府の次将ども】- 六衛府(左右近衛府・左右兵衛府・左右衛門府)の次官たち。東遊の舞人は十人である。
|
| 2.4.2 |
|
陪従も、岩清水、賀茂の臨時の祭などに召す人々で、諸道に殊に勝れた者ばかりをお揃えになっていらっしゃった。
それに加わった二人も、近衛府の世間に名高い者ばかりをお召しになっているのだった。
|
奏楽者も石清水や賀茂の臨時祭に使われる専門家がより整えられたのであるが、ほかから二人加えられたのは近衛府の中で音楽の上手として有名になっている人であった。
|
【陪従も、石清水、賀茂の臨時の祭などに召す人びとの】- 石清水の臨時の祭(三月中または下の午の日)、賀茂の臨時の祭(十一月下の酉の日)に東遊を奏する楽人(陪従)は、いずれも十二人(四位、五位、六位から各四人ずつ出る)。
【加はりたる二人】- 加陪従といい、臨時に加えた楽人。
|
| 2.4.3 |
御神楽の方には、いと多く仕うまつれり。内裏、春宮、院の殿上人、方々に分かれて、心寄せ仕うまつる。数も知らず、いろいろに尽くしたる上達部の御馬、鞍、馬副、随身、小舎人童、次々の舎人などまで、整へ飾りたる見物、またなきさまなり。 |
御神楽の方には、たいそう数多くの人々がお供申していた。
帝、東宮、院の殿上人、それぞれに分かれて、進んで御用をお勤めになる。
その数も知れず、いろいろと善美を尽くした上達部の御馬、鞍、馬添、随身、小舎人童、それ以下の舎人などまで、飾り揃えた見事さは、またとないほどである。
|
また神楽のほうを受け持つ人も多数に行った。宮中、院、東宮の殿上役人が皆御命令によって供奉の中にいるのも無数にあった。華奢を尽くした高官たちの馬、鞍、馬添い侍、随身、小侍の服装までもきらびやかな行列であった。
|
【小舎人童】- 「小舎人 コドネリ」(禁中方名目抄)。近衛の中将・少将が召し連れる少年。
|
| 2.4.4 |
女御殿、対の上は、一つに奉りたり。
次の御車には、明石の御方、尼君忍びて乗りたまへり。
女御の御乳母、心知りにて乗りたり。
方々のひとだまひ、上の御方の五つ、女御殿の五つ、明石の御あかれの三つ、目もあやに飾りたる装束、ありさま、言へばさらなり。
さるは、
|
女御殿と、対の上は、同じお車にお乗りになっていた。
次のお車には、明石の御方と、尼君がこっそりと乗っていらっしゃった。
女御の御乳母、事情を知る者として乗っていた。
それぞれお供の車は、対の上の御方のが五台、女御殿のが五台、明石のご一族のが三台、目も眩むほど美しく飾り立てた衣装、様子は、言うまでもない。
一方では、
|
院の御車には紫夫人と女御をいっしょに乗せておいでになって、次の車には明石夫人とその母の尼とが目だたぬふうに乗っていた。それには古い知り合いの女御の乳母が陪乗したのである。女房たちの車は夫人付きの者のが五台、女御のが五台、明石夫人に属したのが三台で、それぞれに違った派手な味のある飾りと服装が人目に立った。明石の尼君がいっしょに来たのは、
|
|
| 2.4.5 |
|
「尼君をば、どうせなら、老の波の皺が延びるように、立派に仕立てて参詣させよう」
|
「今度の参詣に尼君を優遇して同伴しよう。老人の心に満足ができるほどにして」
|
【尼君をば】- 以下「詣でさせむ」まで、源氏の詞。
【人めかしくて】- 『集成』は「家族の一人として」。『完訳』は「女御の祖母君らしく立派に仕立てて」と訳す。
|
| 2.4.6 |
と、院はのたまひけれど、
|
と、院はおっしゃったが、
|
と院がお言い出しになったのであって、はじめ明石夫人は、
|
|
| 2.4.7 |
|
「今回は、このような世を挙げての参詣に加わるのも憚られます。
もし希望通りの世まで生き永らえていましたら」
|
「今度は院と女王様が主になっての御参詣なんですから、あなたなどが混じっておいでになっては私の立場も苦しくなりますからね、女御さんがもう一段御出世をなすったあとで、その時に私たちだけでお参りをいたしましょう」
|
【このたびは、かくおほかたの】- 以下「世の中を待ち出でたらば」まで、明石御方の詞。
【思ふやうならむ世の中を】- 東宮の即位をいう。
|
| 2.4.8 |
と、御方はしづめたまひけるを、残りの命うしろめたくて、かつがつものゆかしがりて、慕ひ参りたまふなりけり。さるべきにて、もとよりかく匂ひたまふ御身どもよりも、いみじかりける契り、あらはに思ひ知らるる人の御ありさまなり。 |
と、御方はお抑えなさったが、余命が心配で、もう一方では見たくて、付いていらっしゃったのであった。
前世からの因縁で、もともとこのようにお栄えになるお身の上の方々よりも、まことに素晴らしい幸運が、はっきり分かるご様子の方である。
|
と言って、尼君をとどめていたのであるが、老人はそれまで長命で生きておられる自信もなく心細がってそっと一行に加わって来たのである。運命の寵児であることがしかるべきことと思われる女王や女御よりも、明石の母と娘の前生の善果がこの日ほどあざやかに見えたこともなかった。
|
【匂ひたまふ御身ども】- 紫の上、明石の女御、明石の君をさす。
|
|
第五段 住吉社頭の東遊び
|
| 2.5.1 |
|
十月の二十日なので、社の玉垣に這う葛も色が変わって、松の下紅葉などは、風の音にだけ秋を聞き知っているのではないというふうである。
仰々しい高麗、唐土の楽よりも、東遊の耳馴れているのは、親しみやすく美しく、波風の音に響き合って、あの木高い松風に吹き立てる笛の音も、他で聞く調べに変わって身にしみて感じられ、お琴に合わせた拍子も、鼓を用いないで調子をうまく合わせた趣が、大げさなところがないのも、優美でぞっとするほど面白く、場所が場所だけに、いっそう素晴らしく聞こえるのであった。
|
十月の二十日のことであったから、中の忌垣に這う葛の葉も色づく時で、松原の下の雑木の紅葉が美しくて波の音だけ秋であるともいわれない浜のながめであった。本格的な支那楽高麗楽よりも東遊びの音楽のほうがこんな時にはぴったりと、人の心にも波の音にも合っているようであった。高い梢で鳴る松風の下で吹く笛の音もほかの場所で聞く音とは変わって身にしみ、松風が琴に合わせる拍子は鼓を打ってするよりも柔らかでそして寂しくおもしろかった。
|
【十月中の十日】- 源氏一行、十月二十日に住吉参詣する。
【神の斎垣に】- 明融臨模本に合点と付箋「ちはやふる神のいかきにはふくすも秋にはあへすもみちしにけり」(古今集秋下、二六二、紀貫之)とある。
【松の下紅葉】- 『集成』は「松の下葉の紅葉。「下紅葉」は歌語」と注す。『完訳』は「下紅葉するをば知らで松の木の上の緑を頼みけるかな」(拾遺集恋三、八四四、読人しらず)を指摘。
【音にのみ秋を聞かぬ顔】- 明融臨模本は合点と付箋「もみちせぬときはの山は吹風のをとにや秋をきゝわたるらん」(古今集秋下、二五一、紀淑望)とある。『集成』は「音だけでなく、色にも秋を知らぬ顔である、の意」。『完訳』は「風の音にだけそれを聞くとは限らない秋の風情である」と注す。
【ことことしき高麗、唐土の楽よりも、東遊の耳馴れたるは、なつかしくおもしろく】- 仰々しい高麗や唐土の楽より日本の東遊のほうが耳馴れて「なつかしくおもしろ」いという。「桐壺」巻の楊貴妃と桐壺更衣の容貌を比較した文章が想起される。
【御琴】- 明融臨模本は「しみゝ(ゝ$御)こと(こと=琴)に」とある。すなわち「御琴」とする。大島本は「こと」とある。『集成』は底本(明融臨模本)の訂正に従う。『完本』は諸本に従って「琴」と校訂する。『新大系』は底本(大島本)のままとする。
|
| 2.5.2 |
|
山藍で摺り出した竹の模様の衣装は、松の緑に見間違えて、插頭の色とりどりなのは、秋の草と見境がつかず、どれもこれも目先がちらつくばかりである。
|
伶人の着けた小忌衣竹の模様と松の緑が混じり、挿頭の造花は秋の草花といっしょになったように見えるが、
|
【山藍に摺れる竹の節は】- 東遊の舞人の衣裳。山藍で摺った竹の葉も紋様の衣裳を着る。
【插頭の色々は】- 明融臨模本と大島本は「かさしの」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「插頭の花の」と「花の」を補訂する。『新大系』は底本(大島本)のままとする。
|
| 2.5.3 |
|
「求子」が終わった後に、若い上達部は、肩脱ぎしてお下りになる。
光沢のない黒の袍衣から、蘇芳襲で、葡萄染の袖を急に引き出したところ、紅の濃い袙の袂が、はらはらと降りかかる時雨にちょっとばかり濡れたのは、松原であることを忘れて、紅葉が散ったのかと思われる。
|
「求の子」の曲が終わりに近づいた時に、若い高官たちが正装の袍の肩を脱いで舞の場へ加わった。黒の上着の下から臙脂、紅紫の下襲の袖をにわかに出し、それからまた下の袙の赤い袂の見えるそれらの人の姿を通り雨が少しぬらした時には、松原であることも忘れて紅葉のいろいろが散りかかるように思われた。
|
【求子】- あはれ ちはやぶる 賀茂の社の 姫小松 あはれ 姫小松 よろづ世経とも 色はかは あはれ 色は変はらじ(求子)(text35.html 出典7 から転載)
【匂ひもなく黒き袍に】- 四位以上の黒の袍。平安中期の服飾の色を反映する。
【蘇芳襲の、葡萄染の袖を】- 『完訳』は「蘇芳襲や葡萄染の袖を」と訳す。 【蘇芳襲の】-『集成』は「蘇芳襲」と校訂。河内本と別本が「の」ナシ。
|
| 2.5.4 |
見るかひ多かる姿どもに、いと白く枯れたる荻を、高やかにかざして、ただ一返り舞ひて入りぬるは、いとおもしろく飽かずぞありける。
|
皆見栄えのする容姿で、たいそう白く枯れた荻を、高々と插頭に挿して、ただ一さし舞って入ってしまったのは、実に面白くもっといつまでも見ていたい気がするのであった。
|
その派手な姿に白くほおけた荻の穂を挿してほんの舞の一節だけを見せてはいったのがきわめておもしろかった。
|
|
|
第六段 源氏、往時を回想
|
| 2.6.1 |
|
大殿、昔の事が思い出されて、ひところご辛労なさった当時の有様も、目の前のように思い出されなさるが、その当時の事、遠慮なく語り合える相手もいないので、致仕の大臣を、恋しくお思い申し上げなさるのであった。
|
院は昔を追憶しておいでになった。中途で不幸な日のあったことも目の前のことのように思われて、それについては語る人もお持ちにならぬ院は、関白を退いた太政大臣を恋しく思召された。
|
【大殿】- 源氏をいう。
【思し出でられ】- 「られ」自発の助動詞。下文にも「思さるるに」と自発の助動詞が使用されている。
【うち乱れ語りたまふべき人も】- 『集成』は「遠慮なく」。『完訳』は「打ち解けてお話し合いになれそうな人も」。推量の助動詞「べし」可能・適当の両意。
|
| 2.6.2 |
|
お入りになって、二の車に目立たないように、
|
車へお帰りになった院は第二の車へ、
|
【二の車に】- 第二番目の車の意。明石御方と尼君が乗っている車。
|
| 2.6.3 |
|
「わたしの外に誰がまた昔の事情を知って住吉の
神代からの松に話しかけたりしましょうか」
|
たれかまた心を知りて住吉の
神代を経たる松にこと問ふ
|
【誰れかまた心を知りて住吉の--神代を経たる松にこと問ふ】- 源氏の贈歌。「神代を経る」は遠い昔の意。「松」は尼君をさす。
|
| 2.6.4 |
|
御畳紙にお書きになっていた。
尼君、
感涙にむせぶ。このような時世を見るにつけても、あの明石の浦で、これが最後とお別れになった時の事、女御の君が御方のお腹に中にいらっしゃった時の様子などを思い出すにつけても、まことにもったいない運
勢の程を思う。出家なさった方も恋しく、あれこれと物悲しく思われるので、一方では涙は縁起でもないと思い直して
|
という歌を懐中紙に書いたのを持たせておやりになった。尼君は心を打たれたように萎れてしまった。今日のはなやかな光景を見るにつけても、明石を源氏のお立ちになったころの歎かわしかったこと、女御が幼児であったころにした悲しい思いが追想されて、運命に恵まれていることを知った。そしてまた山へはいった良人も恋しく思われて涙のこぼれる気持ちをおさえて
|
【女御の君のおはせしありさまなど】- 『集成』は「姫君が明石でお暮しだった様子」。『完訳』は「女御の君が御腹に宿っておられた様子などを」と訳す。
【思ひ出づるも】- 主語は尼君。
【世を背きたまひし人も恋しく】- 明石入道をさす。主語は尼君。入道が深い山に入ってから五年の歳月がたつ。
【言忌して】- 『集成』は「言葉を選んで」。『完訳』は「言葉を慎んで」と訳す。
|
| 2.6.5 |
|
「住吉の浜を生きていた甲斐がある渚だと
年とった尼も今日知ることでしょう」
|
住の江を生けるかひある渚とは
年ふるあまも今日や知るらん
|
【住の江をいけるかひある渚とは--年経る尼も今日や知るらむ】- 尼君の返歌。「貝」と「効」、「尼」と「海人」の掛詞。
|
| 2.6.6 |
遅くは便なからむと、ただうち思ひけるままなりけり。
|
遅くなっては不都合だろうと、ただ思い浮かんだままにお返ししたのであった。
|
と書いた。お返事がおそくなっては見苦しいと思い、感じたままの歌をもってしたのである。
|
|
| 2.6.7 |
|
「昔の事が何よりも忘れられない
住吉の神の霊験を目の当たりにするにつけても」
|
昔こそ先づ忘られね住吉の
神のしるしを見るにつけても
|
【昔こそまづ忘られね住吉の--神のしるしを見るにつけても】- 尼君の独詠歌。
|
| 2.6.8 |
と独りごちけり。
|
とひとり口ずさむのであった。
|
とまた独言もしていた。
|
|
|
第七段 終夜、神楽を奏す
|
| 2.7.1 |
|
一晩中神楽を奏して夜をお明かしなさる。
二十日の月が遥かかなたに澄み照らして、海面が美しく見えわたっているところに、霜がたいそう白く置いて、松原も同じ色に見えて、何もかもが寒気をおぼえる素晴らしさで、風情や情趣の深さも一入に感じられる。
|
一行は終夜を歌舞に明かしたのである。二十日の月の明りではるかに白く海が見え渡り、霜が厚く置いて松原の昨日とは変わった色にも寒さが感じられて、快く身にしむ社前の朝ぼらけであった。
|
【二十日の月はるかに澄みて】- 十月二十日の月。月の出は午後十時ころ。
【そぞろ寒く、おもしろさも】- 『完訳』は「寒気をおぼえるすばらしさなので」と訳す。
|
|
 |
| 2.7.2 |
|
対の上は、いつものお邸の内にいらしたまま、季節季節につけて、興趣ある朝夕の遊びに、耳慣れ目馴れていらっしゃったが、御門から外の見物を、めったになさらず、ましてこのような都の外へお出になることは、まだご経験がないので、物珍しく興味深く思わずにはいらっしゃれない。
|
自邸での遊びには馴れていても、あまり外の見物に出ることを好まなかった紫の女王は京の外の旅もはじめての経験であったし、すべてのことが興味深く思われた。
|
【御門より外の物見、をさをさしたまはず、ましてかく都のほかのありきは、まだ慣らひたまはねば】- 当時の高貴な女性がめったに外出しないこと、また都以外の地にも行かないことをいう。「御門」は「みかど」と読む。
|
| 2.7.3 |
|
「住吉の浜の松に夜深く置く霜は
神様が掛けた木綿鬘でしょうか」
|
住の江の松に夜深く置く霜は
神の懸けたる木綿かづらかも
|
【住の江の松に夜深く置く霜は--神の掛けたる木綿鬘かも】- 紫の上の和歌。住吉の神の神慮をうたう。「住の江」は歌語。「霜」を「木綿鬘」に見立てる。
|
| 2.7.4 |
|
篁朝臣が、「比良の山さえ」と言った雪の朝をお思いやりになると、ご奉納の志をお受けになった証だろうかと、ますます頼もしかった。
女御の君、
|
紫夫人の作である。小野篁の「比良の山さへ」と歌った雪の朝を思って見ると、奉った祭りを神が嘉納された証の霜とも思われて頼もしいのであった。女御、
|
【篁の朝臣の、「比良の山さへ」と言ひける】- 小野篁(八〇二~八五二)。漢詩と和歌両面にすぐれた平安前期の文人。「ひもろぎは神の心にうけつらし比良の山さへゆふかづらせり」(河海抄所引、出典未詳)。なお『河海抄』は「文時卿歌也」と注記する。『花鳥余情』は「名違へか」ともいう。作者紫式部の記憶違いかまた別伝があったか。
【祭の心うけたまふしるしにや】- 紫の上の心中。『完訳』は「この霜景色も神が奉納の志をお受けになった証であろうかと」と訳す。
|
| 2.7.5 |
|
「神主が手に持った榊の葉に
木綿を掛け添えた深い夜の霜ですこと」
|
神人の手に取り持たる榊葉に
木綿かけ添ふる深き夜の霜
|
【神人の手に取りもたる榊葉に--木綿かけ添ふる深き夜の霜】- 明石女御の紫の上の和歌への唱和歌。「神」「木綿」「霜」を詠み込む。
|
| 2.7.6 |
|
中務の君、
|
中務の君、
|
【中務の君】- 紫の上づきの女房。もと左大臣家の葵の上の女房だが、源氏の召人でもあった(帚木・末摘花)。主人葵の上の死後、源氏の女房となり二条院に移り、須磨退去にあたり紫の上の女房となる(須磨)。
|
| 2.7.7 |
|
「神に仕える人々の木綿鬘と見間違えるほどに置く霜は
仰せのとおり神の御霊験の証でございましょう」
|
祝子が木綿うち紛ひ置く霜は
実にいちじるき神のしるしか
|
【祝子が木綿うちまがひ置く霜は--げにいちじるき神のしるしか】- 中務君の紫の上の和歌への唱和歌。「木綿」「霜」「神」を詠み込む。
|
| 2.7.8 |
|
次々と数え切れないほど多かったのだが、どうして覚えていられようか。
このような時の歌は、いつもの上手でいらっしゃるような殿方たちも、かえって出来映えがぱっとしないで、松の千歳を祝う決まり文句以外に、目新しい歌はないので、煩わしくて省略した。
|
そのほかの人々からも多くの歌は詠まれたが、書いておく必要がないと思って筆者は省いた。こんな場合の歌は文学者らしくしている男の人たちの作も、平生よりできの悪いのが普通で、松の千歳から解放されて心の琴線に触れるようなものはないからである。
|
【次々数知らず多かりけるを、何せむにかは聞きおかむ】- 以下「うるさくてなむ」まで、語り手の言辞。『細流抄』は「草子地也」と指摘。『集成』は「省筆をことわる草子地。一行中の女房の語る言葉をそのまま伝える体」。『完訳』は「語り手の、数多く詠まれた和歌を省筆する弁」と注す。
【松の千歳より離れて、今めかしきことなければ】- 『集成』は「「松の千歳」といった決り文句以外に目新しい趣向の歌もないので」と注す。
|
|
第八段 明石一族の幸い
|
| 2.8.1 |
|
夜がほのぼのと明けて行くと、霜はいよいよ深く、本方と末方とがその分担もはっきりしなくなるほど、酔い過ぎた神楽面が、自分の顔がどんなになっているか知らないで、面白いことに夢中になって、庭燎も消えかかっているのに、依然として、「万歳、万歳」と、榊の葉を取り直し取り直して、お祝い申し上げる御末々の栄えを、想像するだけでもいよいよめでたい限りである。
|
朝の光がさし上るころにいよいよ霜は深くなって、夜通し飲んだ酒のために神楽の面のようになった自身の顔も知らずに、もう篝火も消えかかっている社前で、まだ万歳万歳と榊を振って祝い合っている。この祝福は必ず院の御一族の上に形となって現われるであろうとますますはなばなしく未来が想像されるのであった。
|
【ほのぼのと明けゆくに】- 翌朝を迎える霜の白さ鮮明。
【本末もたどたどしきまで】- 神楽を歌う本方と末方とが混乱するほどまでの意。
【万歳、万歳】- 神楽「千歳法」の歌詞の一部。((本方)千歳 千歳 千歳や 千年の 千歳や (末方)万歳 万歳 万歳や 万代の 万歳や (本方)なほ千歳 (末方)なほ万歳(神楽歌-千歳法):text35.html 出典7 から転載)
【榊葉を取り返しつつ】- 『完訳』は「神楽は舞人が榊葉を持ち去ると終るが、終りそうで終らない」と注す。
【思ひやるぞいとどしきや】- 『湖月抄』は「地」(草子地の意)と指摘。語り手の詠嘆と讃辞。
|
| 2.8.2 |
|
万事が尽きせず面白いまま、千夜の長さをこの一夜の長さにしたいほどの今夜も、何という事もなく明けてしまったので、返る波と先を争って帰るのも残念なことと、若い人々は思う。
|
非常におもしろくて千夜の時のあれと望まれた一夜がむぞうさに明けていったのを見て、若い人たちは渚の帰る波のようにここを去らねばならぬことを残念がった。
|
【千夜を一夜になさまほしき夜の】- 明融臨模本、合点と付箋「秋の夜のちよを一夜になせりともこと葉のこりて鳥やなきなん」(伊勢物語)がある。『源氏釈』が初指摘(ただし、第一句「あきのよの」、第五句「とりやなきてん」)。『岷江入楚』は「私不用之」と注す。
|
| 2.8.3 |
|
松原に、遥か遠くまで立て続けた幾台ものお車が、風に靡く下簾の間々も、常磐の松の蔭に、花の錦を引き並べたように見えるが、袍の色々な色が位階の相違を見せて、趣きのある懸盤を取って、次々と食事を一同に差し上げるのを、下人などは目を見張って、立派だと思っている。
|
はるばると長い列になって置かれた車の、垂れ絹の風に開く中から見える女衣装は花の錦を松原に張ったようであったが、男の人たちの位階によって変わった色の正装をして、美しい膳部を院の御車へ運び続けるのが布衣たちには非常にうらやましく見られた。
|
【松原に、はるばると立て続けたる御車どもの】- 翌朝の明るくなってからの松原の景色。
【袍の色々けぢめおきて】- 袍衣の色。令制では、一位深紫、二位・三位浅紫、四位深緋、五位浅緋、六位深緑、七位浅緑、八位深縹、初位浅縹。ただし、一条天皇のころから、四位以上は黒袍。前に「匂ひもなく黒き袍に」(第二章五段)とあった。この住吉詣でには四位以上は黒袍で供奉していた。
【をかしき懸盤取り続きて、もの参りわたすをぞ】- 五位以下の者が食膳を準備している様子。
|
| 2.8.4 |
|
尼君の御前にも、浅香の折敷に、青鈍の表を付けて、精進料理を差し上げるという事で、「驚くほどの女性のご運勢だ」と、それぞれ陰口を言ったのであった。
|
明石の尼君の分も浅香の折敷に鈍色の紙を敷いて精進物で、院の御家族並みに運ばれるのを見ては、「すばらしい運を持った女というものだね」などと彼らは仲間で言い合った。
|
【浅香の折敷に、青鈍の表折りて】- 尼君は出家者なので、浅香の折敷に青鈍色の絹を折り畳んで敷いた上に精進料理が特別に用意された。
|
| 2.8.5 |
|
御参詣なさった道中は、ものものしいことで、もてあますほどの奉納品が、いろいろと窮屈げにあったが、帰りはさまざまな物見遊山の限りをお尽くしになる。
それを語り続けるのも煩わしく、厄介な事柄なので。
|
おいでになった時は神前へささげられる、持ち運びの面倒な物を守る人数も多くて、途中の見物も十分におできにならなかったのであったが、帰途は自由なおもしろい旅をされた。この楽しい旅行に山へはいりきりになった入道を与らせることのできなかったことを院は物足らず思召されたが、それまでは無理なことであろう。
|
【言ひ続くるもうるさく、むつかしきことどもなれば】- 『一葉抄』は「作者語也」と指摘。『集成』は「以上、省筆をことわる草子地」と注す。語り手の省筆と盛大さをいう言辞。
|
| 2.8.6 |
|
このようなご様子をも、あの入道が、聞こえないまた見えない山奥に離れ去ってしまわれたことだけが、不満に思われた。
それも難しいことだろう、出てくるのは見苦しいことであろうよ。
世の中の人は、これを例として、高望みがはやりそうな時勢のようである。
万事につけて、誉め驚き、世間話の種として、「明石の尼君」と、幸福な人の例に言ったのであった。
あの致仕の大殿の近江の君は、双六を打つ時の言葉にも、「明石の尼君、明石の尼君」と言って、賽を祈ったのである。
|
実際老入道がこの一行に加わっているとしたら見苦しいことでなかったであろうか。その人の思い上がった空想がことごとく実現されたのであるから、だれも心は高く持つべきであると教訓をされたようである。いろいろな話題になって明石の人たちがうらやまれ、幸福な人のことを明石の尼君という言葉もはやった。太政大臣家の近江の君は双六の勝負の賽を振る前には、「明石の尼様、明石の尼様」と呪文を唱えた。
|
【かかる御ありさまをも】- 『集成』は「尼君や明石の上の心中を察して書いたもの」。『完訳』は「「見苦しくや」まで、明石の君の心情に即して入道を語る」と注す。
【難きことなりかし】- 『一葉抄』は「記者語也」と指摘。『全集』は「このあたり、地の文ながら、「--飽かざりける」「難きことなりかし」「まじらはしくも見苦しくや」と、異なる視点から入道を捉えなおしている点に注意」と注す。明石の君と語り手が一体化した表現。
【世の中の人、これを例にて、心高くなりぬべきころなめり】- 『細流抄』は「草子地也」と指摘。語り手の主観的推量。
【近江の君は、双六打つ時の言葉にも、「明石の尼君、明石の尼君」とぞ、賽は乞ひける】- 近江君は双六が好き。「常夏」巻にもその場面が語られていた。
|
|
第三章 朱雀院の物語 朱雀院の五十賀の計画
|
|
第一段 女三の宮と紫の上
|
| 3.1.1 |
|
入道の帝は、仏道に御専心あそばして、内裏の御政道にはいっさいお口をお出しにならない。
春秋の朝覲の行幸には、昔の事をお思い出しになることもあった。
姫宮の御事だけを、今でも御心配でいらして、こちらの六条院を、やはり表向きのお世話役としてお思い申し上げなさって、内々の御配慮を下さるべく帝にもお願い申し上げていらっしゃる。
二品におなりになって、御封なども増える。
ますます華やかにご威勢も増す。
|
法皇は仏勤めに精進あそばされて、政治のことなどには何の干渉もあそばさない。春秋の行幸をお迎えになる時にだけ昔の御生活がお心の上に姿を現わすこともあるのであった。女三の宮をなお気がかりに思召されて、六条院は形式上の保護者と見て、内部からの保護を帝にお託しになった。それで女三の宮は二品の位にお上げられになって、得させられる封戸の数も多くなり、いよいよはなやかなお身の上になったわけである。
|
【入道の帝は】- 朱雀院をさす。
【春秋の行幸】- 今上帝の父朱雀院への朝覲行幸をさす。
【この院をば、なほおほかたの御後見に思ひきこえたまひて、うちうちの御心寄せあるべく奏せさせたまふ】- 朱雀院は源氏を「おほかたの御後見」と考え、帝に「うちうちの御心寄せあるべく」依頼している。
【二品になりたまひて、御封などまさる】- 女三の宮、二品になる。「禄令」によれば、親王は、一品は八百戸、二品は六百戸、三品は四百戸、四品は三百戸で、内親王はその半分とされる。すなわち、女三の宮の二品内親王は三百戸の御封。
|
| 3.1.2 |
|
対の上は、このように年月とともに何かにつけてまさって行かれるご声望に比べて、
|
紫夫人は一方の夫人の宮がこんなふうに年月に添えて勢力の増大していくのに対して、
|
【かく年月に添へて】- 紫の上の寂寥、女三の宮のはなやかさと対比されて語られる。『完訳』は「紫の上の心中に即す。直接、間接話法が混じる」と注す。
【かたがたにまさりたまふ御おぼえに】- 主語は女三の宮。『集成』は「何かにつけて盛んになられる〔女三の宮の〕ご声望に」。『完訳』は「六条院の他の御方々より盛んになられる女宮のご声望であるにつけても」と訳す。
|
| 3.1.3 |
「わが身はただ一所の御もてなしに、人には劣らねど、あまり年積もりなば、その御心ばへもつひに衰へなむ。さらむ世を見果てぬさきに、心と背きにしがな」 |
「自分自身はただ一人が大事にして下さるお蔭で、他の人には負けないが、あまりに年を取り過ぎたら、そのご愛情もしまいには衰えよう。
そのような時にならない前に、自分から世を捨てたい」
|
自分はただ院の御愛情だけを力にして今の所は負け目がないとしても、そのお志というものも遂には衰えるであろう、そうした寂しい時にあわない前に今のうちに善処したい
|
【わが身はただ】- 以下「心と背きにしがな」まで、紫の上の心中。
|
| 3.1.4 |
|
と、ずっと思い続けていらっしゃるが、生意気なようにお思いになるだろうと遠慮されて、はっきりとはお申し上げになることができない。
今上帝までが、御配慮を特別にして上げていらっしゃるので、疎略なと、お耳にあそばすことがあったらお気の毒なので、お通いになることがだんだんと同等になってなって行く。
|
とは常に思っていることであったが、あまりに賢がるふうに思われてはという遠慮をして口へたびたびは出さないのである。院は法皇だけでなく帝までが関心をお持ちになるということがおそれおおく思召されて、冷淡にする噂を立てさすまいというお心から、今ではあちらへおいでになることと、こちらにおられることとがちょうど半々ほどになっていた。
|
【さかしきやうにや思さむ】- 紫の上の心中。源氏の気持ちを忖度。
【内裏の帝さへ】- 副助詞「さへ」添加の意。『完訳』は「朱雀院はもちろん帝までが」と注す。
【おろかに聞かれたてまつらむもいとほしくて】- 主語は源氏。「れ」受身の助動詞。帝に女三の宮を疎略に扱っていると聞かれる、それが帝に申し訳ない、の意。
【渡りたまふこと、やうやう等しきやうになりゆく】- 源氏の女三の宮のもとに通うことが紫の上の場合と同等になる。
|
| 3.1.5 |
|
無理もないこと、当然なこととは思いながらも、やはりそうであったのかとばかり、面白からずお思いになるが、やはり素知らぬふうに同じ様にして過ごしていらっしゃる。
春宮のすぐお下の女一の宮を、こちらに引き取って大切にお世話申し上げていらっしゃる。
そのご養育に、所在ない殿のいらっしゃらない夜々を気をお紛らしていらっしゃるのだった。
どちらの宮も区別せず、かわいくいとしいとお思い申し上げていらっしゃった。
|
道理なこととは思いながらもかねて思ったとおりの寂しい日の来始めたことに女王は悲しまれたが、表面は冷静に以前のとおりにしていた。東宮に次いでお生まれになった女一の宮を紫夫人は手もとへお置きしてお育て申し上げていた。そのお世話の楽しさに院のお留守の夜の寂しさも慰められているのであった。御孫の宮はどの方をも皆非常にかわいく夫人は思っているのである。
|
【さるべきこと、ことわりとは思ひながら】- 紫の上は、やがて源氏の愛情も女三の宮のほうに傾斜していくことを予測していた。
【さればよ】- かねて懸念していたとおり。
【春宮の御さしつぎの女一の宮を】- 養女の明石女御が産んだ春宮のすぐ下の妹。孫娘として愛育する。
【その御扱ひになむ、つれづれなる御夜がれのほども慰めたまひける】- 紫の上も源氏の「夜離れ」を経験するようになる。愛孫の世話に所在なさを紛らわす。『蜻蛉日記』の作者が晩年養女を迎えて所在なさを紛らしたのに類似。
【いづれも分かず】- 明石女御が産んだ御子。春宮、三の宮(匂宮)、女一の宮を差別せず。
|
|
第二段 花散里と玉鬘
|
| 3.2.1 |
|
夏の御方は、このようなあれこれのお孫たちのお世話を羨んで、大将の君の典侍腹のお子を、ぜひにと引き取ってお世話なさる。
とてもかわいらしげで、気立ても、年のわりには利発でしっかりしているので、大殿の君もおかわいがりになる。
数少ないお子だとお思いであったが、孫は大勢できて、あちらこちらに数多くおなりになったので、今はただ、これらをかわいがり世話なさることで、退屈さを紛らしていらっしゃるのであった。
|
花散里夫人は紫夫人も明石夫人も御孫宮がたのお世話に没頭しているのがうらやましくて、左大将の典侍に生ませた若君を懇望して手もとへ迎えたのを愛して育てていた。美しい子でりこうなこの孫君を院もおかわいがりになった。院は御子の数が少ないように見られた方であるが、こうして広く繁栄する御孫たちによって満足をしておいでになるようである。
|
【夏の御方は】- 夏の御方すなわち花散里も養子夕霧大将の典侍腹の孫を引き取って世話をする。
【少なき御嗣と思ししかど、末に広ごりて】- 源氏の子の少ないこと。しかし、その子の孫は数多くできたことをいう。
【こなたかなたいと多く】- 夕霧方と明石姫君方とをさす。
【今はただ、これをうつくしみ扱ひたまひてぞ、つれづれも慰めたまひける】- 主語は源氏。源氏も晩年の所在なさを「御孫扱ひ」で過す。
|
| 3.2.2 |
|
右の大殿が参上してお仕えなさることは、昔以上に親密になって、今では北の方もすっかり落ち着いたお年となって、あの昔の色めかしい事は思い諦めたのであろうか、適当な機会にはよくお越しになる。
対の上ともお会いになって、申し分ない交際をなさっているのであった。
|
右大臣が院を尊敬して親しくお仕えすることは昔以上で、玉鬘ももう中年の夫人になり、何かの時には六条院へ訪ねて来て紫夫人にも逢って話し合うほかにも親しみ深い往来が始終あった。
|
【右の大殿の参り仕うまつりたまふこと、いにしへよりも】- 鬚黒右大臣兼左大将。今上帝の外戚。
【北の方もおとなび果てて】- 玉鬘は鬚黒の北の方、二児の母親としてすっかり落ち着いた年齢と地位にある。現在三十二歳。
【昔のかけかけしき筋思ひ離れたまふにや】- 語り手の挿入句。源氏の心中を忖度。
【渡りまうでたまふ】- 明融臨模本と大島本は「まうて給」とある。『集成』『新大系』は底本(明融臨模本・大島本)のままとする。『完本』は諸本に従って「まうでたまひつつ」と校訂する。
|
| 3.2.3 |
|
姫宮だけが、同じように若々しくおっとりしていらっしゃる。
女御の君は、今は主上にすべてお任せ申し上げなさって、この姫宮をたいそう心に懸けて、幼い娘のように思ってお世話申し上げていらっしゃる。
|
姫宮だけは今日もなお少女のようなたよりなさで、また若々しさでおいでになった。もう宮廷の人になりきってしまった女御に気づかいがなくおなりになった院は、この姫宮を幼い娘のように思召して、この方の教育に力を傾けておいでになるのであった。
|
【姫宮のみぞ、同じさまに若くおほどきておはします】- 六条院の源氏、紫の上、花散里らの「御孫扱ひ」、そこに出入りする玉鬘のすっかり落ち着いた年齢。そうした中で、女三の宮のみが変わらず若く幼いままでいる。二十一、二歳になっている。柏木との密通事件の伏線。
【いと心苦しく、幼からむ御女のやうに、思ひはぐくみたてまつりたまふ】- 『集成』は「大層心にかけて」「〔源氏は〕大事にお世話申し上げていられる」。『完訳』は「まことにいじらしくお思いになり、まるで幼い御娘でもあるかのように、たいせつにお世話申しあげていらっしゃる」と訳す。
|
|
第三段 朱雀院の五十の賀の計画
|
| 3.3.1 |
朱雀院の、
|
朱雀院が、
|
朱雀院の法皇は
|
|
| 3.3.2 |
|
「今はすっかり死期が近づいた心地がして、何やら心細いが、決してこの世のことは気に懸けまいと思い捨てたが、もう一度だけお会いしたく思うが、もし未練でも残ったら大変だから、大げさにではなくお越しになるように」
|
もう御命数も少なくなったように心細くばかり思召されるのであるが、この世のことなどはもう顧みないことにしたいとお考えになりながらも、女三の宮にだけはもう一度お逢いあそばされたかった。このまま亡くなって心の残るのはよろしくないことであるから、たいそうにはせず宮が訪ねておいでになること
|
【今はむげに世近くなりぬる心地して】- 以下「渡りたまふべく」まで、朱雀院から女三の宮への手紙。ただし、文末の引用句がなく、地の文に流れる。
【残りもこそすれ】- 懸念の語法。恨みが残ったら大変だ。
|
| 3.3.3 |
聞こえたまひければ、大殿も、
|
と、お便り申し上げなさったので、大殿も、
|
をお言いやりになった。院も、
|
|
| 3.3.4 |
「げに、さるべきことなり。かかる御けしきなからむにてだに、進み参りたまふべきを。まして、かう待ちきこえたまひけるが、心苦しきこと」 |
「なるほど、仰せの通りだ。
このような御内意が仮になくてさえ、こちらから進んで参上なさるべきことだ。
なおさらのこと、このようにお待ちになっていらっしゃるとは、おいたわしいことだ」
|
「ごもっともなことですよ。こんな仰せがなくともこちらから進んでお伺いをなさらなければならないのに、ましてこうまでお待ちになっておられるのだから、実行しないではお気の毒ですよ」
|
【げに、さるべきことなり】- 以下「心苦しきこと」まで、源氏の詞。「げに」は朱雀院の手紙を受ける。
|
| 3.3.5 |
と、参りたまふべきこと思しまうく。
|
と、ご訪問なさるべきことをご準備なさる。
|
とお言いになり、機会をどんなふうにして作ろうかと考えておいでになった。
|
|
| 3.3.6 |
|
「何のきっかけもなく、取り立てた趣向もなくては、どうして簡単にお出かけになれようか。
どのようなことをして、御覧に入れたらよかろうか」
|
何でもなくそっと伺候をするようなことはみすぼらしくてよろしくない。
|
【ついでなく、すさまじきさまにてやは】- 以下「御覧ぜさせたまふべき」まで、源氏の心中。「やは」係助詞、反語表現。
|
| 3.3.7 |
と、思しめぐらす。
|
と、ご思案なさる。
|
法皇をお喜ばせかたがた外見の整ったことがさせたいとお思いになるのである。
|
|
| 3.3.8 |
|
「来年ちょうどにお達しになる年に、若菜などを調進してお祝い申し上げようか」と、お考えになって、いろいろな御法服のこと、精進料理のご準備、何やかやと勝手が違うことなので、ご夫人方のお智恵も取り入れてお考えになる。
|
来年法皇は五十におなりになるのであったから、若菜の賀を姫宮から奉らせようかと院はお思いつきになって、それに付帯した法会の布施にお出しになる法服の仕度をおさせになり、すべて精進でされる御宴会の用意であるから普通のことと変わって、苦心の払われることを今からお指図になっていた。
|
【このたび足りたまはむ年、若菜など調じてや】- 源氏の心中。「足りたまはむ年」とは、朱雀院が来年ちょうど五十歳に達する年という意。
【人の御心しつらひども入りつつ】- 六条院のご夫人方の意見をさす。
【思しめぐらす】- 明融臨模本は「めくらす(す+に)」とある。すなわち「に」を補入する。大島本は「おほしめくらす」とある。『集成』『完本』は底本の訂正以前本文と諸本に従う。『新大系』は底本(大島本)のままとする。
|
| 3.3.9 |
いにしへも、遊びの方に御心とどめさせたまへりしかば、舞人、楽人などを、心ことに定め、すぐれたる限りをととのへさせたまふ。右の大殿の御子ども二人、大将の御子、典侍の腹の加へて三人、まだ小さき七つより上のは、皆殿上せさせたまふ。兵部卿宮の童孫王、すべてさるべき宮たちの御子ども、家の子の君たち、皆選び出でたまふ。 |
御出家以前にも、音楽の方面には御関心がおありでいらっしゃったので、舞人、楽人などを、特別に選考し、勝れた人たちだけをお揃えあそばす。
右の大殿のお子たち二人、大将のお子は、典侍腹の子を加えて三人、まだ小さい七歳以上の子は、皆童殿上させなさる。
兵部卿宮の童孫王、すべてしかるべき宮家のお子たちや、良家のお子たち、皆お選び出しになる。
|
昔から音楽がことにお好きな方であったから、舞の人、楽の人にすぐれたのを選定しようとしておいでになった。右大臣家の下の二人の子、大将の子を典侍腹のも加えて三人、そのほかの御孫も七歳以上の皆殿上勤めをさせておいでになった。それらと、兵部卿の宮のまだ元服前の王子、そのほかの親王がたの子息、御親戚の子供たちを多く院はお選びになった。
|
【まだ小さき七つより上のは】- 夕霧は自分の七歳以上の子を童殿上させる。
|
| 3.3.10 |
殿上の君達も、容貌よく、同じき舞の姿も、心ことなるべきを定めて、あまたの舞のまうけをせさせたまふ。いみじかるべきたびのこととて、皆人心を尽くしたまひてなむ。道々のものの師、上手、暇なきころなり。 |
殿上の君たちも、器量が良く、同じ舞姿と言っても、また格別な人を選んで、多くの舞の準備をおさせになる。
大層なこの度の催しとあって、誰も皆懸命に練習に励んでいらっしゃる。
その道々の師匠、名人が、大忙しのこのごろである。
|
殿上人たちの舞い手も容貌がよくて芸のすぐれたのを選りととのえて多くの曲の用意ができた。非常な晴れな場合と思ってその人たちは稽古を励むために師匠になる専門家たちは、舞のほうのも楽のほうのも繁忙をきわめていた。
|
【心ことなるべきを定めて】- 『集成』は「目立ちそうな者たちを」。『完訳』は「格別な芸を見せてくれそうなのを選定して」と訳す。
|
|
第四段 女三の宮に琴を伝授
|
| 3.4.1 |
|
姫宮は、もともと琴の御琴をお習いであったが、とても小さい時に父院にお別れ申されたので、気がかりにお思いになって、
|
女三の宮は琴の稽古を御父の院のお手もとでしておいでになったのであるが、まだ少女時代に六条院へお移りになったために、どんなふうにその芸はなったかと法皇は不安に思召して、
|
【院にもひき別れ】- 「ひき別れ」には琴の縁で「弾き」を響かす。
【たまひしかば】- 明融臨模本と大島本は「給ひしかは」とある。『集成』『新大系』は底本(明融臨模本・大島本)のままとする。『完本』は諸本に従って「たまひにしかば」と「に」を補訂する。
|
| 3.4.2 |
|
「お越しになる機会に、あの御琴の音をぜひ聞きたいものだ。
いくら何でも琴だけは物になさったことだろう」
|
「こちらへ来られた時に宮の琴の音が聞きたい。あの芸だけは仕上げたことと思うが」
|
【参りたまはむついでに】- 以下「弾き取りたまひつらむ」まで、朱雀院の詞。
【さりとも琴ばかりは】- 女三の宮、源氏に嫁して六年。『集成』は「琴の名手である源氏に嫁してもう七年にもなるのだから、といった気持がある」。『完訳』は「女宮の琴の巧拙に、源氏の情愛の厚薄を判断しようとする」と注す。
|
| 3.4.3 |
|
と、陰で申されなさったのを、帝におかせられてもお耳にあそばして、
|
と言っておいでになることが宮中へも聞こえて、
|
【しりうごとに聞こえたまひけるを】- 『完訳』は「朱雀院の言辞には、言辞の情愛の薄さが思われている」と注す。
|
| 3.4.4 |
|
「仰せの通り、何と言っても、格別のご上達でしょう。
院の御前で、奥義をお弾きなさる機会に、参上して聞きたいものだ」
|
「そう言われるのは決して平凡なお手並みでない芸に違いない。一所懸命に法皇の所へ来てお弾きになるのを自分も聞きたいものだ」
|
【げに、さりとも】- 以下「参り来て聞かばや」まで、帝の詞。「げに」について、『集成』は「これも、源氏の膝下にあるのだからという気持」。『完訳』は「院の「さりとも--」を肯定的に受けとめ、今は名手源氏の指導を得て上達していよう、とする」と注す。
【院の御前にて】- 朱雀院の御前をさす。
|
| 3.4.5 |
などのたまはせけるを、大殿の君は伝へ聞きたまひて、
|
などと仰せになったのを、大殿の君は伝え聞きなさって、
|
などと仰せられたということがまた六条院へ伝わって来た。院は、
|
|
| 3.4.6 |
|
「今までに適当な機会があるたびに、お教え申したことはあるが、その腕前は、確かに上達なさったが、まだお聞かせできるような深みのある技術には達していないのを、何の準備もなくて参上した機会に、お聞きあそばしたいと強くお望みあそばしたら、とてもきっときまり悪い思いをすることになりはせぬか」
|
「今までも何かの場合に自分からも教えているが、質はすぐれているがまだたいした芸になっていないのを、何心なくお伺いされた時に、ぜひ弾けと仰せになった場合に、恥ずかしい結果を生むことになってはならない」
|
【年ごろさりぬべきついでごとには】- 以下「いとはしたなかるべきことにも」まで、源氏の心中。適当な機会に源氏が女三の宮に琴の琴を教えたということがここに初めて語られている。
【まだ聞こし召しどころあるもの深き手には及ばぬを】- 『集成』は「院のお耳にご満足がゆくほどの深味のある曲はとても弾けないのに」。『完訳』は「まだ父院がお喜びあそばすほどの味わい深い技量にはほど遠いのだから」と訳す。
|
| 3.4.7 |
と、いとほしく思して、このころぞ御心とどめて教へきこえたまふ。
|
と、気の毒にお思いになって、ここのところご熱心にお教え申し上げなさる。
|
とお言いになって、それから女三の宮に熱心な琴の教授をお始めになった。
|
|
| 3.4.8 |
|
珍しい曲目、二つ三つ、面白い大曲類で、四季につれて変化するはずの響き、空気の寒さ温かさをその音色によって調え出して、高度な技術のいる曲目ばかりを、特別にお教え申し上げになるが、気がかりなようでいらっしゃるが、だんだんと習得なさるにつれて、大変上手におなりになる。
|
変わったものを二、三曲、また大曲の長いのが四季の気候によって変わる音、寒い時と空気の暖かい時によっての弾き方を変えねばならぬことなどの特別な奥義をお教えになるのであったが、初めはたよりないふうであったものの、お心によくはいってきて上手におなりになった。
|
【調べことなる手】- 『集成』は「珍しい旋律の曲」。『完訳』は「特別に調べの変った曲」と注す。
【おもしろき大曲どもの】- 『完訳』は「帖を曲の単位として、一帖だけのものを小曲、数帖を中曲、十数帖を大曲と称すという」と注す。
【空の寒さぬるさをととのへ出でて】- 琴(七絃琴)の音色に気候の温暖を調節させる霊妙な力があるという思想。『花鳥余情』所引「琴書」に見える。
|
| 3.4.9 |
「昼は、いと人しげく、なほ一度も揺し按ずる暇も、心あわたたしければ、夜々なむ、静かにことの心もしめたてまつるべき」 |
「昼間は、たいそう人の出入りが多く、やはり絃を一度揺すって音をうねらせる間も、気ぜわしいので、夜な夜なに、静かに奏法の勘所をじっくりとお教え申し上げよう」
|
昼は人の出入りの物音の多さに妨げられて、絃を揺すったり、おさえて変わる音の繊細な味を研究おさせになるのに不便なために、夜になってから静かに教うべきである
|
【昼は、いと人しげく】- 以下「心もしめたてまつるべき」まで、源氏の詞。
|
| 3.4.10 |
とて、対にも、そのころは御暇聞こえたまひて、明け暮れ教へきこえたまふ。
|
と言って、対の上にも、そのころはお暇申されて、朝から晩までお教え申し上げなさる。
|
とお言いになって、女王の了解をお求めになって院はずっと宮の御殿のほうへお泊まりきりになり、朝夕のお稽古の世話をあそばされた。
|
|
|
第五段 明石女御、懐妊して里下り
|
| 3.5.1 |
|
女御の君にも、対の上にも、琴の琴はお習わせ申されなかったので、この機会に、めったに耳にすることのない曲目をお弾きになっていらっしゃるらしいのを、聞きたいとお思いになって、女御も、特別にめったにないお暇を、ただ少しばかりお願い申し上げなさって御退出なさっていた。
|
女御にも女王にも琴はお教えにならなかったのであったから、このお稽古の時に珍しい秘曲もお弾きになるのであろうことを予期して、女御も得ることの困難なお暇をようやくしばらく得て帰邸したのであった。
|
【女御の君にも、対の上にも、琴は習はしたてまつりたまはざりければ】- この物語では、琴(きん)の琴は皇族の楽器と規定している。和琴は藤原氏が名手となっている。また琵琶は皇族圏の人々、源典侍、明石君、宇治大君等が名手、となっている。
|
| 3.5.2 |
|
お子様がお二方いらっしゃるが、再びご懐妊なさって、五か月ほどにおなりだったので、神事にかこつけてお里下がりしていらっしゃるのであった。
十一日が過ぎたら、参内なさるようにとのお手紙がしきりにあるが、このような機会に、このように面白い毎夜の音楽の遊びが羨ましくて、「どうしてわたしにはご伝授して下さらなかったのだろう」と、恨めしくお思い申し上げなさる。
|
もう皇子を二人お持ちしているのであるが、また妊娠して五月ほどになっていたから、神事の多い季節は御遠慮したいと言ってお暇を願って来たのである。十一月が過ぎるともどるようにと宮中からの御催促が急であるのもさしおいて、このごろの楽の音のおもしろさに女御は六条院を去りがたいのであった。なぜ自分には教えていただけなかったのかと院を恨めしくお思いもしていた。
|
【御子二所おはするを、またもけしきばみたまひて、五月ばかりにぞなりたまへれば】- 明石女御、妊娠五月になる。『集成』は「すでに女御の手許を離れている東宮と女一の宮は除いた、二の宮と三の宮であろう。前に「御子たちあまた数添ひたまひて」(若菜下)とあった」。『完訳』は「一皇子一皇女がいる」と注す。
【神事などにことづけておはしますなりけり】- 『集成』は「十一月から十二月の初旬にかけて神事が多い」と注す。『拾芥抄』に「凡そ宮女の懐妊せる者は、散斎の前に、退出すべし。月の事有る者は、祭日の前に、宿廬に退下すべし、殿に上るを得ず。其の三月・九月は、潔斎の前に、預り宮外に退出すべし」(触穢部)とある。明石女御は妊娠五月。散斎(祭に先立ち七日間の身体上の潔斎をすること)の前に、退出した。
【十一日】- 十二月十一日に宮中では神今食の神事がある。明石女御の退出はそれに先立つ七日前の、十二月初めに宮中退出となろう。
【などて我に伝へたまはざりけむ】- 明石女御の心中。源氏は女三の宮に琴の琴を教えたのに、どうして自分には伝授してくれないのか。
|
| 3.5.3 |
|
冬の夜の月は、人とは違ってご賞美なさるご性分なので、美しい雪の夜の光に、季節に合った曲目類をお弾きになりながら、伺候する女房たちも、少しはこの方面に心得のある者に、お琴類をそれぞれ弾かせて、管弦の遊びをなさる。
|
普通と変わって冬の月を最もお好みになる院は、雪のある月夜にふさわしい琴の曲をお弾きになって、女房の中の楽才のあるのに他に楽器で合奏をさせたりして楽しんでおいでになった。
|
【冬の夜の月は、人に違ひてめでたまふ御心なれば】- 源氏の性向。冬の夜の月を賞美する心は、「朝顔」巻(第三章二段)に語られていた。
【おもしろき夜の雪の光に、折に合ひたる手ども弾きたまひつつ】- 冬の夜の雪景色を背景にした管弦の遊び。
|
| 3.5.4 |
年の暮れつ方は、対などにはいそがしく、こなたかなたの御いとなみに、おのづから御覧じ入るることどもあれば、 |
年の暮れ方は、対の上などは忙しく、あちらこちらのご準備で、自然とお指図なさる事柄があるので、
|
年末などはことに対の女王が忙しくていっさいの心配りのほかに、女御、宮たちのための春の仕度に追われて、
|
【対などにはいそがしく】- 紫の上は六条院全体をとりしきる立場にある。衣配りなど正月の準備に余念がない。
|
| 3.5.5 |
|
「春のうららかな夕方などに、ぜひにこのお琴の音色を聞きたい」
|
「春ののどかな気分になった夕方などにこの琴の音をよくお聞きしたい」
|
【春のうららかならむ夕べなどに、いかでこの御琴の音聞かむ】- 紫の上の詞。
|
| 3.5.6 |
|
とおっしゃり続けているうちに、年が改まった。
|
などと言っていたが年も変わった。
|
【年返りぬ】- 源氏四十七歳。源氏の夫人方、紫の上三十七歳、女三の宮二十一、二歳、明石御方三十八歳。源氏の子、夕霧大納言兼右大将二十六歳、明石女御十九歳。その他の人々、皇族方、一の院(朱雀院)五十歳、新院(冷泉院)二十九歳、今上帝二十一歳、東宮七歳。一般臣下、柏木中納言兼衛門督三十一、二歳、鬚黒右大臣兼左大将四十二、三歳。
|
|
第六段 朱雀院の御賀を二月十日過ぎと決定
|
| 3.6.1 |
|
朱雀院の五十の御賀は、まず今上の帝のあそばすことがたいそう盛大であろうから、それに重なっては不都合だとお思いになって、少し日を遅らせなさる。
二月十日過ぎとお決めになって、楽人や、舞人などが参上しては、合奏が続く。
|
年の初めにまず帝からのはなやかな御賀を法皇はお受けになることになっていて、差し合ってはよろしくないと院は思召し、少したった二月の十幾日のころと姫宮の奉られる賀の日をお定めになり、楽の人、舞い手は始終六条院へ来てその下稽古を熱心にする日が多かった。
|
【院の御賀、まづ朝廷よりせさせたまふことども】- 朱雀院の御五十賀は子にあたる今上帝がまず初めに祝う。
【こちたきに】- 明融臨模本と大島本は「こちたきに」とある。『集成』『新大系』は底本(明融臨模本・大島本)のままとする。『完本』は諸本に従って「いとこちたきに」と「いと」を補訂する。
【二月十余日と定めたまひて】- 源氏から兄朱雀院への御五十祝賀は二月十余日と定めるが、次々といろいろな支障が生じて遅れていく。
|
| 3.6.2 |
|
「こちらの対の上が、いつも聞きたがっているお琴の音色を、ぜひとも他の方々の箏の琴や、琵琶の音色も合わせて、女楽を試みてみたい。
ただ最近の音楽の名人たちは、この院の御方々のお嗜みのほどにはかないませんね。
|
「対の女王がいつもお聞きしたがっているあなたの琴と、その人たちの十三絃や琵琶を一度合奏する女ばかりの催しをしたい。現代の大家といっても私の家族たちの音楽に対する態度より純真なものを持っていませんよ。
|
【この対に、常にゆかしくする】- 以下「をさをさあらじ」まで、源氏の詞。『完訳』は「「この対」は紫の上。女宮のもとにいながら身近な呼び方をする」と注す。
【かの人びとの箏、琵琶の音も合はせて、女楽試みさせむ】- 箏は明石女御、琵琶を明石御方、紫の上には和琴、そして女三の宮が琴の琴で女楽を演奏する。
|
| 3.6.3 |
はかばかしく伝へ取りたることは、をさをさなけれど、何ごとも、いかで心に知らぬことあらじとなむ、幼きほどに思ひしかば、世にあるものの師といふ限り、また高き家々の、さるべき人の伝へどもをも、残さず試みし中に、いと深く恥づかしきかなとおぼゆる際の人なむなかりし。 |
きちんと伝授を受けたことは、ほとんどありませんが、どのようなことでも、何とかして知らないことがないようにと、子供の時に思ったので、世間にいる道々の師匠は全部、また高貴な家々の、しかるべき人の伝えをも残さず受けてみた中で、とても造詣が深くてこちらが恥じ入るように思われた人はいませんでした。
|
私はたいした音楽者ではないが、すべての芸に通じておきたいと思って、少年の時から世間の専門家を師にしてつきもしたし、また貴族の中の音楽の大家たちにも教えを乞うたものですが、特に尊敬すべき芸を持った人と思われるのはなかった。
|
【世にあるものの師といふ限り】- 以下、源氏の音楽学習の体験と自信のほどを披瀝する。
|
| 3.6.4 |
|
その当時から、また最近の若い人々が、風流で気取り過ぎているので、全く浅薄になったのでしょう。
琴の琴は、琴の琴で、他の楽器以上に全然稽古する人がなくなってしまったとか。
あなたの御琴の音色ほどにさえも習い伝えている人は、ほとんどありますまい」
|
その時代よりもまた現在では音楽をやる人の素質が悪くなって、芸が浅薄になっていると思う。琴などはまして稽古をする者がなくなったということですからあなただけ弾ける人はあまりないでしょう」
|
【琴はた、まして、さらに、まねぶ人なくなりにたりとか】- 紫式部の時代には、琴の琴(七絃琴)の奏法は絶えてしまっていた。
【この御琴の音ばかりだに伝へたる人、をさをさあらじ】- この世にあなたしかいない、という。
|
| 3.6.5 |
|
とおっしゃると、無邪気にほほ笑んで、嬉しくなって、「このようにお認めになるほどになったのか」とお思いになる。
|
と院がお言いになると、宮は無邪気に微笑んで、自分の芸がこんなにも認められるようになったかと喜んでおいでになった。
|
【かくゆるしたまふほどになりにける】- 女三の宮の心中。『完訳』は「ご自分の技量もこれほどお認めくださるまで上達したのか」と訳す。
|
| 3.6.6 |
|
二十一、二歳ほどにおなりになりだが、まだとても幼げで、未熟な感じがして、ほっそりと弱々しく、ただかわいらしくばかりお見えになる。
|
もう二十一、二でおありになるのであるが、幼稚な所が抜けないで、そして見たお姿だけは美しかった。
|
【なほいといみじく片なりに、きびはなる心地して】- 『集成』は「まだ、とても幼げで。十分に女らしくなっていないさま」。『完訳』は「相変わらず成熟したところがなく幼げな感じで」と訳す。人として大人になっていない意。
|
| 3.6.7 |
|
「院にもお目にかかりなさらないで、何年にもなったが、ご成人なさったと御覧いただけるように、一段と気をつけてお会い申し上げなさい」
|
「長くお目にかからないでおいでになるのだから、大人になってりっぱになったと認めていただけるようにしてお目にかからなければいけませんよ」
|
【院にも】- 以下「見えたてまつりたまへ」まで、源氏の詞。
【年経ぬるを】- 女三の宮は十四、五歳で六条院に降嫁したから、父朱雀院とは七年ぶりの対面になる。
|
| 3.6.8 |
と、ことに触れて教へきこえたまふ。
|
と、何かの機会につけてお教え申し上げなさる。
|
と事に触れて院は教えておいでになるのであった。
|
|
| 3.6.9 |
|
「なるほど、このようなご後見役がいなくては、まして幼そうにいらっしゃいますご様子、隠れようもなかろう」
|
実際こうした良人がおいでにならなければ外間のいろいろな噂にさえされる方であったかもしれぬ
|
【げに、かかる御後見なくては】- 以下「隠れなからまし」まで、女三の宮付きの女房の感想。
|
| 3.6.10 |
と、人びとも見たてまつる。
|
と、女房たちも拝見する。
|
と女房たちは思っていた。
|
|
|
第四章 光る源氏の物語 六条院の女楽
|
|
第一段 六条院の女楽
|
| 4.1.1 |
|
正月二十日ほどなので、空模様もうららかで、風がなま温かく吹いて、御前の梅の花も盛りになって行く。
たいていの花の木も、みな蕾がふくらんで、一面に霞んでいた。
|
一月の二十日過ぎにはもうよほど春めいてぬるい微風が吹き、六条院の庭の梅も盛りになっていった。そのほかの花も木も明日の約されたような力が見えて、杜は霞み渡っていた。
|
【正月二十日ばかりになれば、空もをかしきほどに、風ぬるく吹きて、御前の梅も盛りになりゆく】- 正月二十日ほどの季節描写。六条院春の御殿の庭先の様子。「をかしき空」「風温し」「梅(白梅)の盛り」花の木の蕾」「霞みわたる」、新年正月二十日ころとしては標準的季節描写。
|
| 4.1.2 |
「月たたば、御いそぎ近く、もの騒がしからむに、掻き合はせたまはむ御琴の音も、試楽めきて人言ひなさむを、このころ静かなるほどに試みたまへ」 |
「来月になったら、ご準備が近づいて、何かと騒がしかろうから、合奏なさる琴の音色も、試楽のように人が噂するだろうから、今の静かなころに合奏なさってごらんなさい」
|
「二月になってからでは賀宴の仕度で混雑するであろうし、こちらだけですることもその時の下調べのように思われるのも不快だから、今のうちがよい、あちらで会をなさい」
|
【月たたば、御いそぎ近く】- 以下「試みたまへ」まで、源氏の紫の上への詞。来月になったら、朱雀院五十賀の準備でなにかと忙しくなるから、その前にという配慮。
|
| 4.1.3 |
|
とおっしゃって、寝殿にお迎え申し上げなさる。
|
と院はお言いになって女王を寝殿のほうへお誘いになった。
|
【寝殿に渡したてまつりたまふ】- 紫の上を女三の宮のいる寝殿へ。紫の上に対する丁重な敬語表現。
|
| 4.1.4 |
御供に、我も我もと、ものゆかしがりて、参う上らまほしがれど、こなたに遠きをば、選りとどめさせたまひて、すこしねびたれど、よしある限り選りてさぶらはせたまふ。 |
お供に、わたしもわたしもと、合奏を聞きたく参上したがるが、音楽の方面に疎い者は、残させなさって、すこし年は取っていても、心得のある者だけを選んで伺候させなさる。
|
供をしたいという希望者は多かったが、寝殿の人と知り合いになっている以外の人は残された。少し年はいっている人たちであるがりっぱな女房たちだけが夫人に添って行った。
|
【選りとどめさせたまひて】- 「させ」使役の助動詞。下の「さぶらはせたまふ」の「せ」も同じく使役の助動詞。
|
| 4.1.5 |
|
女童は、器量の良い四人、赤色の表着に桜襲の汗衫、薄紫色の織紋様の袙、浮紋の上の袴に、紅の打ってある衣装で、容姿、態度などのすぐれている者たちだけをお召しになっていた。
女御の御方にも、お部屋の飾り付けなど、常より一層に改めたころの明るさなので、それぞれ競争し合って、華美を尽くしている衣装、鮮やかなこと、またとない。
|
童女は顔のいい子が四人ついて行った。朱色の上に桜の色の汗袗を着せ、下には薄色の厚織の袙、浮き模様のある表袴、肌には槌の打ち目のきれいなのをつけさせ、身の姿態も優美なのが選ばれたわけであった。女御の座敷のほうも春の新しい装飾がしわたされてあって、華奢を尽くした女房たちの姿はめざましいものであった。
|
【赤色に桜の汗衫、薄色の織物の衵、浮紋の表の袴、紅の擣ちたる、さま】- 紫の上方の童女の衣裳。『完訳』は「赤色の表着に桜襲の汗衫、薄紫色の織物の衵、浮模様の表袴、それは紅の艶出しをしたもので」と訳す。
【女御の御方にも】- 明石女御方の描写に移る。
|
| 4.1.6 |
|
童は、青色の表着に蘇芳の汗衫、唐綾の表袴、袙は山吹色の唐の綺を、お揃いで着ていた。
明石の御方のは、仰々しくならず、紅梅襲が二人、桜襲が二人、いずれも青磁色ばかりで、袙は濃紫や薄紫、打目の模様が何とも言えず素晴らしいのを着せていらっしゃった。
|
童女は臙脂の色の汗袗に、支那綾の表袴で、袙は山吹色の支那錦のそろいの姿であった。明石夫人の童女は目だたせないような服装をさせて、紅梅色を着た者が二人、桜の色が二人で、下は皆青色を濃淡にした袙で、これも打ち目のでき上がりのよいものを下につけさせてあった。
|
【童は、青色に蘇芳の汗衫、唐綾の表の袴、衵は山吹なる唐の綺を、同じさまに調へたり】- 『完訳』は「女童は、青色の表着に蘇芳襲の汗衫、唐の綾織の表袴、衵は山吹色の唐の綺を、同じようにおそろいで着ている」と訳す。
|
| 4.1.7 |
|
宮の御方でも、このようにお集まりになるとお聞きになって、女童の容姿だけは特別に整えさせていらっしゃった。
青丹の表着に柳襲の汗衫、葡萄染の袙など、格別趣向を凝らして目新しい様子ではないが、全体の雰囲気が、立派で気品があることまでが、まことに並ぶものがない。
|
姫宮のほうでも女御や夫人たちの集まる日であったから、童女の服装はことによくさせてお置きになった。青丹の色の服に、柳の色の汗袗で、赤紫の袙などは普通の好みであったが、なんとなく気高く感ぜられることは疑いもなかった。
|
【青丹に柳の汗衫、葡萄染の衵など】- 『完訳』は「青丹の表着に、柳襲の汗衫、葡萄染の衵など」と訳す。
|
|
第二段 孫君たちと夕霧を召す
|
| 4.2.1 |
廂の中の御障子を放ちて、こなたかなた御几帳ばかりをけぢめにて、中の間は、院のおはしますべき御座よそひたり。
今日の拍子合はせには童べを召さむとて、右の大殿の三郎、尚侍の君の御腹の兄君、笙の笛、左大将の御太郎、横笛と吹かせて、簀子にさぶらはせたまふ。
|
廂の中の御障子を取り外して、あちらとこちらと御几帳だけを境にして、中の間には、院がお座りになるための御座所を設けてあった。
今日の拍子合わせの役には、子供を召そうとして、右の大殿の三郎君、尚侍の君の御腹の兄君、笙の笛、左大将の御太郎君、横笛と吹かせて、簀子に伺候させなさる。
|
縁側に近い座敷の襖子をはずして、貴女たちの席は几帳を隔てにしてあった。中央の室には院の御座が作られてある。今日の拍子合わせの笛の役には子供を呼ぼうとお言いになって、右大臣家の三男で玉鬘夫人の生んだ上のほうの子が笙の役をして、左大将の長男に横笛の役を命じ縁側へ置かれてあった。
|
|
| 4.2.2 |
内には、御茵ども並べて、御琴ども参り渡す。
秘したまふ御琴ども、うるはしき紺地の袋どもに入れたる取り出でて、明石の御方に琵琶、紫の上に和琴、女御の君に箏の御琴、宮には、かくことことしき琴はまだえ弾きたまはずやと、あやふくて、例の手馴らしたまへるをぞ、調べてたてまつりたまふ。
|
内側には御褥をいくつも並べて、お琴を御方々に差し上げる。
秘蔵の御琴類を、いくつもの立派な紺地の袋に入れてあるのを取り出して、明石の御方に琵琶、紫の上に和琴、女御の君に箏のお琴、宮には、このような仰々しい琴はまだお弾きになれないかと、心配なので、いつもの手馴れていらっしゃる琴を調絃して差し上げなさる。
|
演奏者の茵が皆敷かれて、その席へ院の御秘蔵の楽器が紺錦の袋などから出されて配られた。明石夫人は琵琶、紫の女王には和琴、女御は箏の十三絃である。宮はまだ名楽器などはお扱いにくいであろうと、平生弾いておいでになるので調子を院がお弾き試みになったのをお配らせになった。院は、
|
|
| 4.2.3 |
「箏の御琴は、ゆるぶとなけれど、なほ、かく物に合はする折の調べにつけて、琴柱の立処乱るるものなり。よくその心しらひ調ふべきを、女はえ張りしづめじ。なほ、大将をこそ召し寄せつべかめれ。この笛吹ども、まだいと幼げにて、拍子調へむ頼み強からず」 |
「箏のお琴は、弛むというわけではないが、やはり、このように合奏する時の調子によって、琴柱の位置がずれるものだ。
よくその点を考慮すべきだが、女性の力ではしっかりと張ることはできまい。
やはり、大将を呼んだ方がよさそうだ。
この笛吹く人たちも、まだ幼いようで、拍子を合わせるには頼りにならない」
|
「箏の琴は絃がゆるむわけではないが、他の楽器と合わせる時に琴柱の場所が動きやすいものなのだから、初めからその心得でいなければならないが、女の力では十分締めることがむずかしいであろうから、やはりこれは大将に頼まなければなるまい。それに拍子を受け持っている少年たちもあまり小さくて信用のできない点もあるから」
|
【箏の御琴は】- 以下「頼み強からず」まで、源氏の詞。
|
| 4.2.4 |
|
とお笑いになって、
|
とお笑いになりながら、
|
【笑ひたまひて】- 苦笑に近い笑い。
|
| 4.2.5 |
|
「大将、こちらに」
|
「大将にこちらへ」
|
【大将、こなたに】- 源氏の詞。
|
| 4.2.6 |
と召せば、御方々恥づかしく、心づかひしておはす。
明石の君を放ちては、いづれも皆捨てがたき御弟子どもなれば、御心加へて、大将の聞きたまはむに、難なかるべくと思す。
|
とお呼びになるので、御方々はきまり悪く思って、緊張していらっしゃる。
明石の君を除いては、どなたも皆捨てがたいお弟子たちなので、お気を遣われて、大将がお聞きになるので、難点がないようにとお思いになる。
|
とお呼び出しになるのを聞いて、夫人たちは恥ずかしく思っていた。明石夫人以外は皆院の御弟子なのであるから、院も大将が聞いて難のないようにとできばえを祈っておいでになった。
|
|
| 4.2.7 |
|
「女御は、ふだん主上がお聞きあそばすにも、楽器に合わせながら弾き馴れていらっしゃるので、安心だが、和琴は、たいして変化のない音色なのだが、奏法に決まった型がなくて、かえって女性は弾き方にまごつくに違いないのだ。
春の琴の音色は、おおよそ合奏して聞くものであるから、他の楽器と合わないところが出て来ようかしら」
|
女御は平生から陛下の前で他の人と合奏も仕馴れているからだいじょうぶ落ち着いた演奏はできるであろうが、和琴というものはむずかしい物でなく、きまったことがないだけ創作的の才が必要なのを、女の弾き手はもてあましはせぬか、春の絃楽は皆しっくり他に合ってゆかねばならぬものであるが、和琴がうまくいっしょになってゆかぬようなことはないか
|
【女御は】- 以下「乱るるところもや」まで、源氏の心中。初め地の文と融合した叙述、やがて心中文として明確化。
【和琴こそ】- 係助詞「こそ」は「たどりぬべけれ」に係る。
【春の琴の音は、皆掻き合はするものなるを】- 『集成』は「春の琴(絃楽器)の音色は、総じて合奏して聞くものと決っているものだが、の意に解されるが、古来不審とされている。河内本「さるものと琴の音は」」と注す。
|
| 4.2.8 |
|
と、何となく気がかりにお思いになる。
|
とも損な弾き手に同情もしておいでになった。
|
【なまいとほしく思す】- 『集成』は「何となく気がかりに」。『完訳』は「いささか心苦しくお思いになる」と訳す。
|
|
第三段 夕霧、箏を調絃す
|
| 4.3.1 |
|
大将は、とてもたいそう緊張して、御前での大がかりな、改まった御試楽以上に、今日の気づかいは、格別に勝って思われなさったので、鮮やかなお直衣に、香のしみたいく重ものお召し物で、袖に特に香をたきしめて、化粧して参上なさるころ、日はすっかり暮れてしまった。
|
左大将は晴れがましくて、音楽会のいかなる場合に立ち合うよりも気のつかわれるふうで、きれいな直衣を薫香の香のよく染んだ衣服に重ねて、なおも袖をたきしめることを忘れずに整った身姿のこの人が現われて来たころはもう日が暮れていた。
|
【あざやかなる御直衣、香にしみたる御衣ども、袖いたくたきしめて、引きつくろひて】- 夕霧の化粧した姿。すっきりした御直衣に香をたきしめる。特に袖に深く香をたきしめる。身動きのたびにもっとも香が発しやすい所だからである。
|
| 4.3.2 |
|
趣深い夕暮の空に、花は去年の古雪を思い出されて、枝も撓むほどに咲き乱れている。
緩やかに吹く風に、何とも言えず素晴らしく匂っている御簾の内側の薫りも一緒に漂って、鴬を誘い出すしるべにできそうな、たいそう素晴らしい御殿近辺の匂いである。
御簾の下から箏のお琴の裾、少しさし出して、
|
感じのよい早春の黄昏の空の下に梅の花は旧年に見た雪ほどたわわに咲いていた。ゆるやかな風の通り通うごとに御簾の中の薫香の香も梅花の匂いを助けるように吹き迷って鶯を誘うかと見えた。御簾の下のほうから箏の琴のさきのほうを少しお出しになって、院が、
|
【ゆゑあるたそかれ時の空に、花は去年の古雪思ひ出でられて、枝もたわむばかり咲き乱れたり】- 正月二十日ころ、夕暮時に、白梅が雪かと見間違えられるほに満開に咲いている様子。
【鴬誘ふ】- 明融臨模本、合点と付箋「花のかを風のたよりにたくへてそ鴬さそふしるへにはやる」(古今集春上、一三、紀友則)。『源氏釈』に初指摘、諸注指摘する。
|
| 4.3.3 |
「軽々しきやうなれど、これが緒調へて、調べ試みたまへ。ここにまた疎き人の入るべきやうもなきを」 |
「失礼なようですが、この絃を調節して、みてやって下さい。
ここには他の親しくない人を入れることはできないものですから」
|
「失礼だがこの絃の締まりぐあいをよく見て調音をしてほしい。他人に来てもらうことのできない場合だから」
|
【軽々しきやうなれど】- 以下「人の入るべきやうはなきを」まで、源氏の詞。
|
| 4.3.4 |
|
とおっしゃると、礼儀正しくお受け取りになる態度、心づかいも行き届いていて立派で、「壱越調」の音に発の緒を合わせて、すぐには弾き始めずに控えていらっしゃるので、
|
とお言いになると、大将はうやうやしく琴を受け取って、一越調の音に発の絃の標準の柱を置き全体を弾き試みることはせずにそのまま返そうとするのを院は御覧になって、
|
【用意多くめやすくて】- 『集成』は「いかにもたしなみ深く、非の打ち所のない所作で」。『完訳』は「心づかいも行き届いていかにも好ましく」と訳す。
【壱越調」の声に発の緒を立てて】- 「壱越調」は雅楽の六調子の一つ。「発の緒」は箏の琴の調絃で、調子の基準音にする絃。
|
| 4.3.5 |
|
「やはり、調子合わせの曲ぐらいは、一曲、興をそがない程度に」
|
「調子をつけるだけの一弾きは気どらずにすべきだよ」
|
【なほ、掻き合はせばかりは、手一つ、すさまじからでこそ】- 源氏の詞。『集成』は「興を殺がなぬように。お愛想までに、掻き合せくらいは一曲弾いてみなさい、というほどの意」と注す。
|
| 4.3.6 |
とのたまへば、
|
とおっしゃるので、
|
と院がお言いになった。
|
|
| 4.3.7 |
|
「まったく、今日の演奏会のお相手に、仲間入りできるような腕前では、ございませんから」
|
「今日の会に私がいささかでも音を混ぜますようなだいそれた自信は持っておりません」
|
【さらに、今日の御遊びの】- 以下「おぼえずはべりける」まで、夕霧の詞。言葉では遠慮しながら、態度はもったいぶった様子。
|
| 4.3.8 |
|
と、思わせぶりな態度をなさる。
|
大将は遠慮してこう言う。
|
【けしきばみたまふ】- 『集成』は「勿体ぶったご挨拶をなさる」と訳す。
|
| 4.3.9 |
「さもあることなれど、女楽にえことまぜでなむ逃げにけると、伝はらむ名こそ惜しけれ」 |
「もっともな言い方だが、女楽の相手もできずに逃げ出したと、噂される方が不名誉だぞ」
|
「もっともだけれども、女だけの音楽に引きさがった、逃げたと言われるのは不名誉だろう」
|
【さもあることなれど】- 以下「名こそ惜しけれ」まで、源氏の詞。夕霧をからかう。
|
| 4.3.10 |
|
と言ってお笑いになる。
|
院はお笑いになった。
|
【笑ひたまふ】- 冗談の後の笑い。
|
| 4.3.11 |
調べ果てて、をかしきほどに掻き合はせばかり弾きて、参らせたまひつ。この御孫の君達の、いとうつくしき宿直姿どもにて、吹き合はせたる物の音ども、まだ若けれど、生ひ先ありて、いみじくをかしげなり。 |
調絃を終わって、興をそそる程度に調子合わせだけを弾いて、差し上げなさった。
このお孫の君たちが、とてもかわいらしい宿直姿で、笛を吹き合わせている音色は、まだ幼い感じだが、将来性があって、素晴らしく聞こえる。
|
で大将は調子をかき合わせて、それだけで御簾の中へ入れた。院の御孫にあたる小さい人たちが美しい直衣姿をして吹き合わせる笛の音はまだ幼稚ではあるが、有望な未来の思われる響きであった。
|
【宿直姿ども】- 宮中で宿直するときに直衣を着るので、いま夜でもあるので、こう表現したもの。
|
|
第四段 女四人による合奏
|
| 4.4.1 |
|
それぞれのお琴の調絃が終わって、合奏なさる時、どれも皆優劣つけがたい中で、琵琶は特別上手という感じで、神々しい感じの弾き方、音色が澄みきって美しく聞こえる。
|
かき合わせが済んでいよいよ合奏になったが、どれもおもしろく思われた中に、琵琶はすぐれた名手であることが思われ、神さびた撥使いで澄み切った音をたてていた。
|
【御琴どもの調べども調ひ果てて】- 以下、女楽が始まる。
【神さびたる手づかひ、澄み果てておもしろく聞こゆ】- 明石御方の琵琶。住吉の神の縁で「神さびたる」と表現。『集成』は「由緒ある古風な撥さばきが、澄みきった音色で」。『完訳』は「年功を積んだ神々しいまでの弾きようが、音色も澄みとおるようなみごとさでおもしろく聞こえる」と訳す。
|
| 4.4.2 |
|
和琴に、大将も耳を留めていらっしゃるが、やさしく魅力的な爪弾きに、掻き返した音色が、珍しく当世風で、まったくこの頃名の通った名人たちが、ものものしく掻き立てた曲や調子に負けず、華やかで、「大和琴にもこのような弾き方があったのか」と感嘆される。
深いお嗜みのほどがはっきりと分かって、素晴らしいので、大殿はご安心なさって、またとない方だとお思い申し上げなさる。
|
大将は和琴に特別な関心を持っていたが、それはなつかしい、柔らかな、愛嬌のある爪音で、逆にかく時の音が珍しくはなやかで、大家のもったいらしくして弾くのに少しも劣らない派手な音は、和琴にもこうした弾き方があるかと大将の心は驚かされた。深く精進を積んだ跡がよく現われたことによって院は安心をあそばされて夫人をうれしくお思いになった。
|
【なつかしく愛敬づきたる御爪音に、掻き返したる音の、めづらしく今めきて】- 紫の上の和琴。「なつかし」「今めかし」は紫の上の人柄を特徴づける語句。
【大和琴にもかかる手ありけり】- 源氏の感想。紫の上の和琴に感嘆。
|
| 4.4.3 |
|
箏のお琴は、他の楽器の音色の合間合間に、頼りなげに時々聞こえて来るといった性質の音色のものなので、可憐で優美一筋に聞こえる。
|
十三絃の琴は他の楽器の音の合い間合い間に繊細な響きをもたらすのが特色であって、女御の爪音はその中にもきわめて美しく艶に聞こえた。
|
【ものの隙々に、心もとなく漏り出づる物の音がらにて、うつくしげになまめかしくのみ聞こゆ】- 明石女御の箏の琴。「うつくしげ」「なまめかし」」は女御の可憐な人柄を表す語句。『完訳』は「他の楽器の合間合間に、おぼつかなく聞こえてくる性質の音色なので」と訳す。
|
| 4.4.4 |
|
琴の琴は、やはり未熟ではあるが、習っていらっしゃる最中なので、あぶなげなく、たいそう良く他の楽器の音色に響き合って、「随分と上手になったお琴の音色だな」と、大将はお聞きになる。
拍子をとって唱歌なさる。
院も、時々扇を打ち鳴らして、一緒に唱歌なさるお声、昔よりもはるかに美しく、少し声が太く堂々とした感じが加わって聞こえる。
大将も、声はたいそう勝れていらっしゃる方で、夜が静かになって行くにつれて、何とも言いようのない優雅な夜の音楽会である。
|
琴は他に比べては洗練の足らぬ芸と思われたが、お若い稽古盛りの年ごろの方であったから、確かな弾き方はされて、ほかの楽器と交響する音もよくて、上達されたものであると大将も思った。この人が拍子を取って歌を歌った。院も時々扇を鳴らしてお加えになるお声が昔よりもまたおもしろく思われた。少し無技巧的におなりになったようである。大将も美音の人で、夜のふけてゆくにしたがって音楽三昧の境地が作られていった。
|
【琴は、なほ若き方なれど、習ひたまふ盛りなれば、たどたどしからず】- 女三の宮の琴の琴。その音色に人柄が反映されてない。あるとすれば、「若し」の未熟という人柄。未熟な技量だが、練習中なので、あぶなげなかった。
【優になりにける御琴の音かな】- 夕霧の感想。
【唱歌したまふ】- 旋律を譜で歌うこと。
【昔よりもいみじくおもしろく、すこしふつつかに、ものものしきけ添ひて聞こゆ】- 源氏の声、昔以上に美しくかつ堂々とした感じも加わって聞こえる。
【大将も、声いとすぐれたまへる人にて】- 夕霧も声のすぐれた人。他に柏木の弟紅梅大納言が上手と言われている(賢木)。
|
|
第五段 女四人を花に喩える
|
|
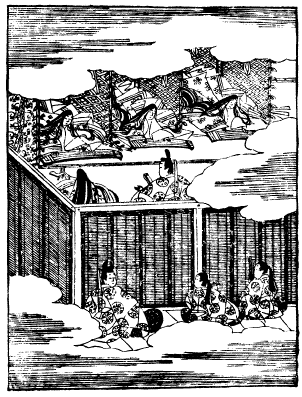 |
| 4.5.1 |
|
月の出が遅いころなので、灯籠をあちらこちらに懸けて、明かりを調度良い具合に灯させていらっしゃった。
|
月がややおそく出るころであったから、燈籠が庭のそこここにともされた。
|
【月心もとなきころなれば】- 後に「臥待の月」とある。
|
| 4.5.2 |
|
宮の御方をお覗きになると、他の誰よりも一段と小さくかわいらしげで、ただお召し物だけがあるという感じがする。
つややかな美しさは劣るが、ただとても上品に美しく、二月の二十日頃の青柳が、ようやく枝垂れ始めたような感じがして、鴬の羽風にも乱れてしまいそうなくらい、弱々しい感じにお見えになる。
|
院が宮の席をおのぞきになると、人よりも小柄なお姿は衣服だけが美しく重なっているように見えた。はなやかなお顔ではなくて、ただ貴族らしいお美しさが備わり、二月二十日ごろの柳の枝がわずかな芽の緑を見せているようで、鶯の羽風にも乱れていくかと思われた。
|
【小さくうつくしげにて、ただ御衣のみある心地す】- 女三の宮の小柄を強調した表現。
【匂ひやかなる方は後れて、ただいとあてやかにをかしく】- 女三の宮は美しさよりも気品高貴さが特徴。『集成』は「つややかな美しさといった点は劣るが、気品があって美しく」。『完訳』は「つやつやした美しさという点は劣るが、ただまことに気品があって美しく」と訳す。
【二月の中の十日ばかりの青柳の、わづかに枝垂りはじめたらむ心地して、鴬の羽風にも乱れぬべく、あえかに見えたまふ】- 女三の宮を植物に喩える。『紫式部日記』に小少将の君を描写したのと類似の文章がある。『河海抄』は「白雪の花繁くして空しく地を撲つ緑糸の条弱くして鴬に勝へず」(白氏文集、巻第六十四、楊柳枝詞八首の第三首)と「鴬の羽風になびく青柳の乱れてものを思ふころかな」(具平親王集)を指摘。
|
| 4.5.3 |
|
桜襲の細長に、御髪は左右からこぼれかかって、柳の糸のようであった。
|
桜の色の細長を着ておいでになるのであるが、髪は右からも左からもこぼれかかってそれも柳の糸のようである。
|
【柳の糸のさましたり】- 女三の宮の髪の様子。「青柳」の縁で「柳の糸」という。歌語。
|
| 4.5.4 |
|
「この方こそは、この上ないご身分の方のご様子というものだろう」と見えるが、女御の君は、同じような優美なお姿で、もう少し生彩があって、態度や雰囲気が奥ゆかしく、風情のあるご様子でいらっしゃって、美しく咲きこぼれている藤の花が、夏に咲きかかって、他に並ぶ花がない、朝日に輝いているような感じでいらっしゃった。
|
これこそ最上の女の姿というものであろうと院はおながめになるのであったが、女御には同じような艶な姿に今一段光る美の添って見える所があって、身のとりなしに気品のあるのは、咲きこぼれた藤の花が春から夏に続いて咲いているころの、他に並ぶもののない優越した朝ぼらけの趣であると院は御覧になった。
|
【これこそは、限りなき人の御ありさまなめれ】- 語り手の視点。女三の宮についていう。
【同じやうなる御なまめき姿の、今すこし匂ひ加はりて】- 明石女御は「なまめき姿」という点では女三の宮と同じだが、女三の宮のもってない「匂ひ」がこちらにはすこしある、という。
【よく咲きこぼれたる藤の花の、夏にかかりて、かたはらに並ぶ花なき、朝ぼらけの心地ぞしたまへる】- 明石女御を藤の花に喩える。「野分」巻にも明石女御を藤の花に喩えた描写がある。
|
| 4.5.5 |
|
とは言え、とてもふっくらとしたころにおなりになって、ご気分もすぐれない時期でいらっしゃったので、お琴も押しやって、脇息に寄りかかっていらっしゃった。
小柄なお身体でなよなよとしていらっしゃるが、ご脇息は並の大きさなので、無理に背伸びしている感じで、特別に小さく作って上げたいと見えるのが、とてもおかわいらしげにお見えになるのであった。
|
この人は身ごもっていて、それがもうかなりに月が重なって悩ましいころであったから、済んだあとでは琴を前へ押しやって苦しそうに脇息へよりかかっているのであるが、背の高くない身体を少し伸ばすようにして、普通の大きさの脇息へ寄っているのが気の毒で、低いのを作り与えたい気もされて憐まれた。紅梅の上着の上にはらはらと髪のかかった灯かげの姿の美しい横に、紫夫人が見えた。
|
【いとふくらかなるほどに】- 明石女御、妊娠五月となっている。
【ささやかになよびかかりたまへるに、御脇息は例のほどなれば、およびたる心地して】- 明石女御の姿態。小柄な点では女三の宮と同じ。女三の宮は着物の中に埋まっているという感じで描写、明石女御は脇息に背伸びして寄り掛かっているという描写。
【ことさらに小さく作らばや】- 語り手の感想、挿入。
【いとあはれげにおはしける】- 『集成』は「とても可憐にお見えになるのだった」。『完訳』は「いかにも痛々しいご様子であった」と訳す。
|
| 4.5.6 |
|
紅梅襲のお召物に、お髪がかかってさらさらと美しくて、灯台の光に映し出されたお姿、またとなくかわいらしげだが、紫の上は、葡萄染であろうか、色の濃い小袿に、薄蘇芳襲の細長で、お髪がたまっている様子、たっぷりとゆるやかで、背丈などちょうど良いぐらいで、姿形は申し分なく、辺り一面に美しさが満ちあふれている感じがして、花と言ったら桜に喩えても、やはり衆に抜ん出た様子、格別の風情でいらっしゃる。
|
これは紅紫かと思われる濃い色の小袿に薄臙脂の細長を重ねた裾に余ってゆるやかにたまった髪がみごとで、大きさもいい加減な姿で、あたりがこの人の美から放射される光で満ちているような女王は、花にたとえて桜といってもまだあたらないほどの容色なのである。
|
【紅梅の御衣に、御髪のかかりはらはらときよらにて、火影の御姿、世になくうつくしげなるに】- 明石女御の衣裳。紅梅襲。
【紫の上は、葡萄染にやあらむ】- 語り手の挿入句。上の「なるに」の接続助詞「に」で続ける。『完訳』は「「灯影の御姿」の無類の美貌が共通するとして、紫の上に転ずる」と注す。
【あたりに匂ひ満ちたる心地して】- 女三の宮や明石女御にはない紫の上の美質。『集成』は「あたり一面照り映えるほどの美しさで」。『完訳』は「あたり一面につややかな美しさがあふれているような風情」と注す。
【花といはば桜に喩へても、なほものよりすぐれたるけはひ、ことにものしたまふ】- 紫の上を桜に喩える。「野分」巻では樺桜に喩えられた。『完訳』は「他に比べようのない桜に喩えてもなお不足。最高の賛辞」と注す。
|
| 4.5.7 |
|
このような方々の中で、明石は圧倒されてしまうところだが、まったくそのようなことはなく、態度なども意味ありげにこちらが恥ずかしくなるくらいで、心の底を覗いてみたいほどの深い様子で、どことなく上品で優雅に見える。
|
こんな人たちの中に混じって明石夫人は当然見劣りするはずであるが、そうとも思われぬだけの美容のある人で、聡明らしい品のよさが見えた。
|
【かかる御あたりに、明石はけ圧さるべきを、いとさしもあらず】- 語り手の主観を交えた挿入句。明石御方についての描写。
【もてなしなどけしきばみ恥づかしく】- 『集成』は「身ごなしなどしゃれていて風格があり」。『完訳』は「物腰など気がきいていて、こちらが恥じ入りたいくらいだし」と訳す。
|
| 4.5.8 |
|
柳の織物の細長に、萌黄であろうか、小袿を着て、羅の裳の目立たないのを付けて、特に卑下していたが、その様子、そうと思うせいもあって、立派で軽んじられない。
|
柳の色の厚織物の細長に下へ萌葱かと思われる小袿を着て、薄物の簡単な裳をつけて卑下した姿も感じがよくて侮ずらわしくは少しも見えなかった。
|
【柳の織物の細長、萌黄にやあらむ、小袿着て、羅の裳のはかなげなる引きかけて】- 明石御方の衣裳。柳襲。薄い織物の裳を付ける。『完訳』は「裳の着用は女房の格。それをさりげなく着て「ことさら卑下」するのが、彼女の一貫した処世態度」と注す。「にやあらむ」は語り手の推測陰挿入句。
|
| 4.5.9 |
高麗の青地の錦の端さしたる茵に、まほにもゐで、琵琶をうち置きて、ただけしきばかり弾きかけて、たをやかに使ひなしたる撥のもてなし、音を聞くよりも、またありがたくなつかしくて、五月待つ花橘、花も実も具しておし折れる薫りおぼゆ。 |
高麗の青地の錦で縁どりした敷物に、まともに座らず、琵琶をちょっと置いて、ほんの心持ばかり弾きかけて、しなやかに使いこなした撥の扱いよう、音色を聞くやいなや、また比類なく親しみやすい感じがして、五月待つ花橘の、花も実もともに折り取った薫りのように思われる。
|
青地の高麗錦の縁を取った敷き物の中央にもすわらずに琵琶を抱いて、きれいに持った撥の尖を絃の上に置いているのは、音を聞く以上に美しい感じの受けられることであって、五月の橘の花も実もついた折り枝が思われた。
|
【五月待つ花橘】- 「五月待つ花橘の香をかげば昔の人の袖の香ぞする」(古今集夏、一三九、読人しらず)による表現。
|
|
第六段 夕霧の感想
|
| 4.6.1 |
これもかれも、うちとけぬ御けはひどもを聞き見たまふに、大将も、いと内ゆかしくおぼえたまふ。対の上の、見し折よりも、ねびまさりたまへらむありさまゆかしきに、静心もなし。 |
この方もあの方も、とりすましたご様子を見たり聞いたりなさると、大将も、まことに中を御覧になりたくお思いになる。
対の上が、昔見た時よりも、ずっと美しくなっていっらっしゃるだろう様子が見たいので、心が落ち着かない。
|
いずれもつつましくしているらしい内のものの気配に大将の心は惹かれるばかりであった。紫の女王の美は昔の野分の夕べよりもさらに加わっているに違いないと思うと、ただその一事だけで胸がとどろきやまない。
|
【うちとけぬ御けはひどもを】- 『集成』は「たしなみ深い婦人たちのご様子を」。『完訳』は「とりつくろっていらっしゃるご様子を」と訳す。
|
| 4.6.2 |
|
「宮を、もう少し運勢があったなら、自分の妻としてお世話申し上げられたであろうに。
まことにゆったり構えていたのが悔やまれるよ。
院は、度々そのように水を向けられ、蔭でおっしゃっていられたものを」と、残念に思うが、少し軽率なようにお見えになるご様子に、軽くお思い申すと言うのではないが、それほど心は動かなかったのである。
|
女三の宮に対しては運命が今少し自分に親切であったなら、自身のものとしてこの方を見ることができたのであったと思うと、自身の臆病さも口惜しかった。朱雀院からはたびたびそのお気持ちを示され、それとなく仰せになったこともあったのであるがと思いながらも、よく隙の見えることを知っていては女王に惹かれたほど心は動きもしないのであった。
|
【宮をば、今すこしの宿世】- 以下「のたまはせけるを」まで、夕霧の心中。
【及ばましかば】- 「ましかば」--「見たてまつらまし」反実仮想の構文。
【すこし心やすき方に見えたまふ御けはひに】- 夕霧の見た女三の宮。『集成』は「組しやすいようにお見えになる女三の宮のご様子に」。『完訳』は「多少気のおけない性分の方とお見受けされるご様子だから」と訳す。
【あなづりきこゆとはなけれど、いとしも心は動かざりけり】- 夕霧の女三宮に対する態度、関心。語り手が評す。
|
| 4.6.3 |
|
こちらの御方を、何事につけても手の届くすべなく、高嶺の花として、長年過ごして来たので、「ただ何とかして、義理の親子の関係として、好意をお寄せ申している気持ちをお見せ申し上げたい」とだけ、残念に嘆かわしいのであった。
むやみに、あってはならない大それた考えなどは、まったくおありではなく、実に立派に振る舞っていらっしゃった。
|
女王とはだれも想像ができぬほど遠い間隔のある所に置かれている大将は、その忘れがたい感情などは別として、せめて自分の持つ好意だけでも紫の女王に認めてもらうだけを望んでできないのを考えては煩悶しているのである。あるまじい心などはいだいていない、その思いを抑制することはできる人である。
|
【この御方をば、何ごとも】- 夕霧の紫の上に対する態度、関心。
【いかでか、ただおほかたに、心寄せあるさまをも見えたてまつらむ】- 夕霧の心中。紫の上に対する気持ち。 【おほかたに】-『集成』は「家族の一員として」。『完訳』は「ほんの一通りの意味で」と訳す。
【心地などは】- 明融臨模本と大島本は「心ちなとは」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「心などは」と「ち」を削除する。『新大系』は底本(大島本)のままとする。
|
|
第五章 光る源氏の物語 源氏の音楽論
|
|
第一段 音楽の春秋論
|
| 5.1.1 |
|
夜が更けて行く様子、冷え冷えとした感じがする。
臥待の月がわずかに顔を出したのを、
|
夜がふけてゆくらしい冷ややかさが風に感ぜられて臥待月が上り始めた。
|
【夜更けゆくけはひ】- 夜更けて、源氏、夕霧と音楽論をかわす。
【臥待の月はつかにさし出でたる】- 十九日の月。
|
| 5.1.2 |
「心もとなしや、春の朧月夜よ。秋のあはれ、はた、かうやうなる物の音に、虫の声縒り合はせたる、ただならず、こよなく響き添ふ心地すかし」 |
「おぼつかない光だね、春の朧月夜は。
秋の情趣は、やはりまた、このような楽器の音色に、虫の声を合わせたのが、何とも言えず、この上ない響きが深まるような気がするものだ」
|
「たよりない春の朧月夜だ。秋のよさというのもまたこうした夜の音楽と虫の音がいっしょに立ち上ってゆく時にあるものだね」
|
【心もとなしや】- 以下「心地すかし」まで、源氏の詞。春秋優劣論。秋の音楽がまさるという。
|
| 5.1.3 |
とのたまへば、大将の君、
|
とおっしゃると、大将の君、
|
と院は大将に向かってお言いになった。
|
|
| 5.1.4 |
|
「秋の夜の曇りない月には、すべてのものがくっきりと見え、琴や笛の音色も、すっきりと澄んだ気は致しますが、やはり特別に作り出したような空模様や、草花の露も、いろいろと目移りし気が散って、限界がございます。
|
「秋の明るい月夜には、音楽でも何の響きでも澄み通って聞こえますが、あまりきれいに作り合わせたような空とか、草花の露の色とかは、専念に深く音楽を味わわせなくなる気もいたします。
|
【秋の夜の】- 以下「ことにはべりけれ」まで、夕霧の詞。春がまさるという。
【なほことさらに作り合はせたるやうなる空のけしき、花の露も】- 秋の情緒のわざとらしさやことさららしさに対して否定的。
|
| 5.1.5 |
|
春の空のたどたどしい霞の間から、朧に霞んだ月の光に、静かに笛を吹き合わせたようなのには、どうして秋が及びましょうか。
笛の音色なども、優艶に澄みきることはないのです。
|
やはり春のたよりない雲の間から朧な月が出ますほどの夜に、静かな笛の音などの上ってゆくのを聞きますほうが、音楽そのものを楽しむのにはよいかと思われます。
|
【春の空のたどたどしき霞の間より、おぼろなる月影に】- 『完訳』は「忘れがたい紫の上の印象「春の曙の霞の間より--」(野分)に酷似。彼女への思慕を秘めて、春の夢幻的な情趣を高く評価」と注す。「秋の夜の隈なき月影」よりも「春の空のたどたどしき霞の間より朧なる月影を賞美する。「末摘花」巻の源氏、常陸宮邸訪問の場面参照。
【澄みのぼり果てずなむ】- 『集成』は「笛の音なども、秋は、しゃれた感じに高く澄みきって聞えるということがございません」。『完訳』は「秋は笛の音なども、澄みのぼるというところまではまいりません」。
|
| 5.1.6 |
|
女性は春をあわれぶと、昔の人が言っておりました。
なるほど、そのようでございます。
やさしく音色が調和する点では、春の夕暮が格別でございます」
|
女は春を憐むという言葉がございますがもっともなことと思われます。すべてのものの調子がしっくり合うのは春の夕方に限るように考えられますが」
|
【女は春をあはれぶと】- 明融臨模本、合点あり。巻末の奥入に「伊行/毛詩云/女ハ感陽気春思男々感陰気秋思」(毛詩、国風、七月、鄭箋)とある。しかし、『源氏釈』には指摘なし。
【なつかしく物のととのほることは、春の夕暮こそことにはべりけれ】- 夕霧の春がまさるとする結論。「なつかし」「ととのふ」という情趣を推奨。
|
| 5.1.7 |
と申したまへば、
|
と申し上げなさると、
|
と大将が言うと、
|
|
| 5.1.8 |
|
「いや、この議論だがね。
昔から皆が判断しかねた事を、末の世の劣った者には、決定しがたいことであろう。
楽器の調べや、曲目などは、なるほど律を二の次にしているが、そのようなことであろう」
|
「それは断定的には言えないことだ。古人でさえ決めかねたことなのだから、末世のわれわれの力で正しい批判のできるわけもない。ただ音楽のほうでは秋の律の曲を、春の呂の曲の下に置かれていることだけは今君が言ったような理由があるからだろう」
|
【いな、この定めよ】- 以下「さもありかし」まで、源氏の詞。『集成』は「夕霧が今夕の催しにかこつけて春をよしとするのに対して、やや留保をつける口調」と注す。
【律をば次のものにしたるは】- 『集成』は「呂は中国から伝来した雅楽の旋法、律は日本固有の俗楽の旋法に基づくものなので、呂の方を重く見たのである。『河海抄』は「呂は春のしらべ、律は秋のしらべといふ歟」という」。『完訳』は「春を推称する夕霧に納得。律は秋の、呂は春の調べ。日本古来の催馬楽などでは呂を重視」と注す。
|
| 5.1.9 |
などのたまひて、
|
などとおっしゃって、
|
院はこう仰せられた。また、
|
|
| 5.1.10 |
「いかに。ただ今、有職のおぼえ高き、その人かの人、御前などにて、たびたび試みさせたまふに、すぐれたるは、数少なくなりためるを、そのこのかみと思へる上手ども、いくばくえまねび取らぬにやあらむ。このかくほのかなる女たちの御中に弾きまぜたらむに、際離るべくこそおぼえね。 |
「どんなものであろう。
現在、演奏上手の評判の高い、その人あの人を、帝の御前などで、度々試みさせあそばすと、勝れた者は、数少なくなったようだが、その一流と思われる名人たちも、どれほども習得し得ていないのではなかろうか。
このような何でもないご婦人方の中で一緒に弾いたとしても、格別に勝れているようには思われない。
|
「どう思うかね。現在の優秀な音楽家とされている人たちの、宮中などのお催しなどの場合に演奏を命ぜられる人のを聴いても名人だと思われるのは少なくなったようだが、先輩についてよく研究をしようとするような熱心が足りないのかね。今日のような女ばかりの音楽の会に交じっても、格別きわだつと思われる人があるようにも思われない。
|
【いかに。ただ今】- 以下「いかにぞ」まで、源氏の詞。当代の名手の評判。
|
| 5.1.11 |
|
何年もこのように引き籠もって過ごしていると、鑑賞力も少し変になったのだろうか、残念なことだ。
妙に、人々の才能は、ちょっと習い覚えた芸事でも、見栄えがして他より勝れているところである。
あの、御前の管弦の御遊などに、一流の名手として選ばれた人々の、誰それと比較したらどうであろうか」
|
しかしそれは近年の私がどこへも行かずに一所に引きこもっていて、鑑識が悪く偏してしまったのかもしれないが、とにかく感激を覚えさせられる音楽者のいないのは残念だ。どんな芸事も演ぜられる場所によっては平生と違ったできばえを見せるものであるが、最も晴れの場所の宮中でのこのごろの音楽の遊びに選び出される人たちに、この女性たちのを比べて劣っていると思う点があるかね」
|
【年ごろかく埋れて過ぐすに】- 源氏が准太上天皇の待遇を受けたのは八年前の秋。その前後から六条院に引き籠もりがちの生活になっている。
【人の才、はかなくとりすることども】- 『集成』は「婦人たちの才芸はもとより、さしたることもない取りはからいも」と訳す。
【所なる】- 「なる」断定の助動詞、連体形中止。余意余情を残す表現。
|
| 5.1.12 |
とのたまへば、大将、
|
とおっしゃるので、大将は、
|
|
|
| 5.1.13 |
「それをなむ、とり申さむと思ひはべりつれど、あきらかならぬ心のままに、およすけてやはと思ひたまふる。上りての世を聞き合はせはべらねばにや、衛門督の和琴、兵部卿宮の御琵琶などをこそ、このころめづらかなる例に引き出ではべめれ。 |
「その事を、申し上げようと思っておりましたが、よくも弁えぬくせに、偉そうに言うのもどうかと存じまして。
古い昔の勝れた時代を聞き比べておりませんからでしょうか、衛門督の和琴、兵部卿宮の御琵琶などは、最近の珍しく勝れた例に引くようでございます。
|
「それを申し上げたいと思ったのでございますが、しかし頭の悪い私はでたらめを申すことになるかもしれません。今の世間の者は昔の音楽の盛んな時を知らないからでもありますか衛門督の和琴、兵部卿の宮様の琵琶などを激賞いたします。
|
【それをなむ】- 以下「はべりつれ」まで、夕霧の詞。
|
| 5.1.14 |
げに、かたはらなきを、今宵うけたまはる物の音どもの、皆ひとしく耳おどろきはべるは。
なほ、かくわざともあらぬ御遊びと、かねて思うたまへたゆみける心の騒ぐにやはべらむ。
唱歌など、いと仕うまつりにくくなむ。
|
なるほど、又とない演奏者ですが、今夜お聞き致しました楽の音色は、皆同じように耳を驚かしました。
やはり、このように特別のことでもない御催しと、かねがね思って油断しておりました気持ちが不意をつかれて騒ぐのでしょう。
唱歌など、とてもお付き合いしにくうございました。
|
私どもも妙技とはしておりますが、今晩の皆様の御演奏には驚愕いたしました。はじめはたいしたお遊びでもあるまいと軽く考えていたためにいっそう感激が大きいのでございましょうか。歌の役はまことに気がさして勤めにくうございました。
|
|
| 5.1.15 |
|
和琴は、あの太政大臣だけが、このように臨機応変に、巧みに操った音色などを、思いのままに掻き立てていらっしゃるのは、とても格別上手でいらっしゃったが、なかなか飛び抜けて上手には弾けないものでございますのに、まことに勝れて調子が整ってございました」
|
和琴は太政大臣によってだけすべての楽音を率いるような巧妙な音のたつものと思っておりまして、その境地へは一歩も他の者がはいれないものと思われるむずかしい芸でございますが、今晩のはまた特別なものでございました。結構でした」
|
【和琴は、かの大臣ばかりこそ】- 係助詞「こそ」は「ものしたまへ」已然形に係る逆接用法。
【いとかしこく整ひてこそ】- 紫の上の和琴についていう。
|
| 5.1.16 |
と、めできこえたまふ。
|
と、お誉め申し上げなさる。
|
大将はほめた。
|
|
| 5.1.17 |
|
「いや、それほど大した弾き方ではないが、特別に立派なようにお誉めになるね」
|
「そんな最大級な言葉でほめられるほどのものではないのだが」
|
【いと、さことことしき際には】- 以下「取りなさるるかな」まで源氏の詞。紫の上を自分の弟子として謙辞。
|
| 5.1.18 |
とて、したり顔にほほ笑みたまふ。
|
とおっしゃって、得意顔に微笑んでいらっしゃる。
|
得意な御微笑が院のお顔に現われた。
|
|
| 5.1.19 |
|
「なるほど、悪くはない弟子たちである。
琵琶は、わたしが口出しするようなことは何もないが、そうは言っても、どことなく違うはずだ。
思いがけない所で初めて聞いた時、珍しい楽の音色だと思われたが、その時からは、又格段上達しているからな」
|
「私にはまずできそこねの弟子はないようだね。琵琶だけは私に骨を折らせた弟子の芸ではないがすぐれたものであったはずだ。意外なところで私の発見した天性の弾き手なのだよ。ずいぶん感心したものだが、そのころよりはまた進歩したようだ」
|
【げに、けしうはあらぬ】- 以下「優りにたるをや」まで、源氏の詞。『集成』は「諧謔の語」と注す。
【さいへど、物のけはひ異なるべし】- 『集成』は「やはり(わたしの側にいるお蔭で)どことなく違うところがあるはずだ」と訳す。
|
| 5.1.20 |
|
と、強引に自分の手柄のように自慢なさるので、女房たちは、そっとつつきあう。
|
こうして皆御自身の功にしてお言いになるのを聞いていて、女房たちなどは肱を互いに突き合わせたりして笑っていた。
|
【せめて我かしこにかこちなしたまへば】- 『集成』は「強引に何もかも自分の手柄のように自慢なさるので」。『完訳』は「しいてご自分のお仕込みででもあるかのように仰せになるので」と訳す。 【我かしこ】-『集成』は「われがしこ」と濁音に読む。
|
|
第二段 琴の論
|
| 5.2.1 |
「よろづのこと、道々につけて習ひまねばば、才といふもの、いづれも際なくおぼえつつ、わが心地に飽くべき限りなく、習ひ取らむことはいと難けれど、何かは、そのたどり深き人の、今の世にをさをさなければ、片端をなだらかにまねび得たらむ人、さるかたかどに心をやりてもありぬべきを、琴なむ、なほわづらはしく、手触れにくきものはありける。 |
「何事も、その道その道の稽古をすれば、才能というもの、どれも際限ないとだんだんと思われてくるもので、自分の気持ちに満足する限度はなく、習得することは実に難しいことだが、いや、どうして、その奥義を究めた人が、今の世に少しもいないので、一部分だけでも無難に習得したような人は、その一面で満足してもよいのだが、琴の琴は、やはり面倒で、手の触れにくいものである。
|
「すべての芸というものは習い始めると奥の深さがわかって、自分で満足のできるだけを習得することはとうていできないものなのだが、しかしそれだけの熱を芸に持つ人が今は少ないから、少しでも稽古を積んだことに自身で満足して、それで済ませていくのだが、琴というものだけはちょっと手がつけられないものなのだよ。
|
【よろづのこと】- 以下「いとあはれになむ」まで、源氏の詞。琴の琴論。
【おぼえつつ】- 副助詞「つつ」、動作・思考の繰り返し。思われ思われしてくるもので、のニュアンス。
【たどり深き人】- 奥義を極めた人の意。
【ありぬべきを】- 「ぬべし」連語。接続助詞「を」逆接の機能。「ぬ」完了の助動詞、確述の意と推量の助動詞「べし」当然の意。確かにそうあってもよいのだが。
|
| 5.2.2 |
この琴は、まことに跡のままに尋ねとりたる昔の人は、天地をなびかし、鬼神の心をやはらげ、よろづの物の音のうちに従ひて、悲しび深き者も喜びに変はり、賤しく貧しき者も高き世に改まり、宝にあづかり、世にゆるさるるたぐひ多かりけり。 |
この琴は、ほんとうに奏法どおりに習得した昔の人は、天地を揺るがし、鬼神の心を柔らげ、すべての楽器の音がこれに従って、悲しみの深い者も喜びに変わり、賎しく貧しい者も高貴な身となり、財宝を得て、世に認められるといった人が多かったのであった。
|
この芸をきわめれば天地も動かすことができ、鬼神の心も柔らげ、悲境にいた者も楽しみを受け、貧しい人も出世ができて、富貴な身の上になり、世の中の尊敬を受けるようなことも例のあることなのだ。
|
【天地をなびかし】- 琴の琴の効用を説く。帝王の楽器である理由が分かる。以下の文体は対句じたての四六駢儷文に倣った表現。『花鳥余情』は「楽書云、琴は天地を動かし、鬼神を感ぜしむ」(原漢文)と「琴書」を指摘。また『詩経』にも「天地を動かし、鬼神を感ぜしむるは、詩より近きはなし」とある。『古今和歌集』序には「力をも入れずして天地を動かし、目に見えぬ鬼神をもあはれと思はせ」と和歌の効用を説く。
|
| 5.2.3 |
この国に弾き伝ふる初めつ方まで、深くこの事を心得たる人は、多くの年を知らぬ国に過ぐし、身をなきになして、この琴をまねび取らむと惑ひてだに、し得るは難くなむありける。げにはた、明らかに空の月星を動かし、時ならぬ霜雪を降らせ、雲雷を騒がしたる例、上りたる世にはありけり。 |
わが国に弾き伝える初めまで、深くこの事を理解している人は、長年見知らぬ国で過ごし、生命を投げうって、この琴を習得しようとさまよってすら、習得し得るのは難しいことであった。
なるほど確かに、明らかに空の月や星を動かしたり、時節でない霜や雪を降らせたり、雲や雷を騒がしたりした例は、遠い昔の世にはあったことだ。
|
この芸の伝わった初めの間は、これを学ぶ人は皆長く外国へ行っていて、あらゆる困難に打ち勝って、上達しようとしたものだが、そうまでして成功したものの数はわずかだったのだ。実際すぐれた琴の音は月や星の座を変えさせることもあったし、その時季でなしに霜や雪を降らせたり、黒雲が湧き出したり、雷鳴がそのためにしたりしたことも昔はあったのだよ。
|
【この国に弾き伝ふる初めつ方】- 以下『宇津保物語』「俊蔭」巻を念頭においた叙述。
|
| 5.2.4 |
かく限りなきものにて、そのままに習ひ取る人のありがたく、世の末なればにや、いづこのそのかみの片端にかはあらむ。されど、なほ、かの鬼神の耳とどめ、かたぶきそめにけるものなればにや、なまなまにまねびて、思ひかなはぬたぐひありけるのち、これを弾く人、よからずとかいふ難をつけて、うるさきままに、今はをさをさ伝ふる人なしとか。いと口惜しきことにこそあれ。 |
このように限りない楽器で、その伝法どおりに習得する人がめったになく、末世だからであろうか、どこにその当時の一部分が伝わっているのだろうか。
けれども、やはり、あの鬼神が耳を止め、傾聴した始まりの事のある琴だからであろうか、なまじ稽古して、思いどおりにならなかったという例があってから後は、これを弾く人、禍があるとか言う難癖をつけて、面倒なままに、今ではめったに弾き伝える人がいないとか。
実に残念なことである。
|
だれも音楽のうちの最高のものと知っていても、完全にその芸を習いおおせるものが少なかったし、末世にはなるし、今残っているのは昔のほんとうのものの断片だけの価値のものかとも思われる。それでもまだ鬼神が耳をとどめるものになっている琴の稽古をなまじいにして、上達はできずにかえっていろいろな不幸な終わりを見たりする人があるものだから、琴の稽古をする者は不吉を招くというような迷信もできて、近ごろではこの面倒な芸を習う人が少なくなったということだね。遺憾なことだ。
|
【かく限りなきものにて】- 『集成』は「この上もない楽器なので」。『完訳』は「このように琴は際限もなく霊力をそなえた楽器であるだけに」と訳す。
【片端にかはあらむ】- 反語表現に近い語気。『集成』は「その昔の一端も伝わっていようか」。『完訳』は「どこにその昔の秘法の一端でも伝わっているというのだろう」と訳す。
【思ひかなはぬたぐひ】- 『集成』は「立身が叶わなかったといった者」。『完訳』は「不如意な身の上となった例」と訳す。
|
| 5.2.5 |
琴の音を離れては、何琴をか物を調へ知るしるべとはせむ。
げに、よろづのこと衰ふるさまは、やすくなりゆく世の中に、一人出で離れて、心を立てて、唐土、高麗と、この世に惑ひありき、親子を離れむことは、世の中にひがめる者になりぬべし。
|
琴の音以外では、どの絃楽器をもって音律を調える基準とできようか。
なるほど、すべての事が衰えて行く様子は、たやすくなって行く世の中で、一人故国を離れて、志を立てて、唐土、高麗と、この世をさまよい歩き、親子と別れることは、世の中の変わり者となってしまうことだろう。
|
琴がなくては世の中の音楽が根本の音を持たないものになるのだからね。すべての物は衰えかけると早い速力で退化する一方なんだから、そんな中で一人の人間だけが熱心にその芸に志して、高麗、支那と渡り歩いて家族も何も顧みない者になってしまうのも狂的だから、
|
|
| 5.2.6 |
|
どうして、それほどまでせずとも、やはりこの道をだいたい知る程度の一端だけでも、知らないでいられようか。
一つの調べを弾きこなす事さえ、量り知れない難しいものであるという。
いわんや、多くの調べ、面倒な曲目が多いので、熱中していた盛りには、この世にあらん限りの、わが国に伝わっている楽譜という楽譜のすべてを広く見比べて、しまいには、師匠とすべき人もなくなるまで、好んで習得したが、やはり昔の名人には、かないそうにない。
まして、これから後というと、伝授すべき子孫がいないのが、何とも心寂しいことだ」
|
それほどはしないでも、この芸がどんなものであるかを知りうるだけのことを私はしたいと思って、一曲でも十分に習いうることは困難なものとしても、これにはむずかしい無数の曲目のあるものなのだから、若くて音楽熱の盛んな年ごろの私は世の中にあるだけの琴の譜を調べたり、あちらから来ているものは皆手もとへ取り寄せて、それによって研究をしたが、しまいには私以上の力のある先生というものもなくなって不便だったものの、独学で勉強をしたが、それでも古人の芸に及ぶものでは少しもなかったのだからね。ましてこれからは心細いものになるだろうとこの芸について私は悲しんでいる」
|
【などか、なのめにて、なほこの道を通はし知るばかりの端をば、知りおかざらむ】- 『集成』は「(しかし)どうして、それほどまでせずとも、やはり、なにとかこの琴の奏法に通暁するに足りる一端だけでも、心得ておかずにいられようか」。『完訳』は「とはいえ、一通りでも、やはらこの道をわきまえる糸口ぐらいは、どうして心得ておかずにいられましょう」と訳す。
【多かるを】- 接続助詞「を」順接。前の「いはむや」と呼応する文脈。『集成』は「多いのだが」。『完訳』は「たくさんあるものですから」と訳す。
【心に入りし盛りには】- 以下、源氏がいかに広く七絃琴の楽譜を調査して奏法を習得したかの経験談。
【当たるべくもあらじをや】- 『集成』は「かないそうもないことだろうね」。『完訳』は「追いつきそうにもありませんね」と訳す。
|
| 5.2.7 |
などのたまへば、大将、げにいと口惜しく恥づかしと思す。
|
などとおっしゃるので、大将は、なるほどまことに残念にも恥ずかしいとお思いになる。
|
などと院のお語りになるのを聞いていて大将は自身をふがいなく恥ずかしく思った。
|
|
| 5.2.8 |
|
「この御子たちの中で、望みどおりにご成人なさる方がおいでなら、その方が大きくなった時に、その時まで生きていることがあったら、いかほどでもないわたしの技にしても、すべてご伝授申し上げよう。
三の宮は、今からその才能がありそうにお見えになるから」
|
「今上の親王が御成人になれば、それまで生きているかどうかおぼつかないことだが、その時に私の習いえただけの琴の芸をお授けしようと願っている。二の宮は今からそうした天分を持たれるようだから」
|
【この御子たちの御中に】- 以下「見えたまふを」まで、源氏の詞。「この」は明石女御をさす。
【三の宮】- 明融臨模本には「三(三=二)宮」とある。すなわち「三」の右傍らに「二」という一筆が見える。大島本は「二(二=三イ、三イ#)宮」とある。すなわち、「二」の傍らに「三イ」と異本表記するが、後にそれを摺り消す。河内本は「三宮」、別本は「二宮」。『集成』は「三の宮」と整定し、「明融本、河内本に「三の宮」。後の匂宮である。これが原形であろう。青表紙本に「二の宮」とするものが多いが、拠りがたい」と注す。『完本』は諸本に従って「二の宮」と校訂する。『新大系』は底本の本行本文に従って「二宮」とする。『完訳』は「二の宮」と校訂し、「後の式部卿宮。「三の宮」(後の匂宮)とする伝本もある」と注す。
|
| 5.2.9 |
などのたまへば、明石の君は、いとおもだたしく、涙ぐみて聞きゐたまへり。
|
などとおっしゃると、明石の君は、たいそう面目に思って、涙ぐんで聞いていらっしゃった。
|
このお言葉を明石夫人は自身の名誉であるように涙ぐんで側聞きをしていたのであった。
|
|
|
第三段 源氏、葛城を謡う
|
| 5.3.1 |
女御の君は、箏の御琴をば、上に譲りきこえて、寄り臥したまひぬれば、和琴を大殿の御前に参りて、気近き御遊びになりぬ。「葛城」遊びたまふ。はなやかにおもしろし。大殿折り返し謡ひたまふ御声、たとへむかたなく愛敬づきめでたし。 |
女御の君は、箏の御琴を、紫の上にお譲り申し上げて、寄りかかりなさったので、和琴を大殿の御前に差し上げて、寛いだ音楽の遊びになった。
「葛城」を演奏なさる。
明るくおもしろい。
大殿が繰り返しお謡いになるお声は、何にも喩えようがなく情がこもっていて素晴らしい。
|
女御は箏を紫夫人に譲って、悩ましい身を横たえてしまったので、和琴を院がお弾きになることになって、第二の合奏は柔らかい気分の派手なものになって、催馬楽の葛城が歌われた。院が繰り返しの所々で声をお添えになるのが非常に全体を美しいものにした。
|
【葛城」遊びたまふ】- 明融臨模本、合点あり。催馬楽、呂「葛城」「葛城の 寺の前なるや 豊浦の寺の 西なるや 榎の葉井に 白玉沈くや 真白玉沈くや おおしとど おしとど しかしては 国ぞ栄えむや 我家らぞ 富せむや おおしとど としとんど おおしとんど としとんど」。子孫繁栄を寿ぐ歌謡。
|
| 5.3.2 |
|
月がだんだんと高く上って行くにつれて、花の色も香も一段と引き立てられて、いかにも優雅な趣である。
箏の琴は、女御のお爪音は、とてもかわいらしげにやさしく、母君のご奏法の感じが加わって、揺の音が深く、たいそう澄んで聞こえたのを、こちらのご奏法は、また様子が違って、緩やかに美しく、聞く人が感に堪えず、気もそぞろになるくらい魅力的で、輪の手など、すべていかにも、たいそう才気あふれたお琴の音色である。
|
月の高く上る時間になり、梅花の美もあざやかになってきた。十三絃の箏の音は、女御のは可憐で女らしく、母の明石夫人に似た揺の音が深く澄んだ響きをたてたが、女王のはそれとは変わってゆるやかな気分が出て、聴き手の心に酔いを覚えるほどの愛嬌があり、才のひらめきの添ったものであった。
|
【月やうやうさし上るままに】- 臥待ちの月、十九日の月である。
【花の色香ももてはやされて】- 梅の花。「御前の梅も盛りに」(第四章一段)とあった。
【この御手づかひは】- 紫の上の手さばきをさす。
【愛敬づきて】- 明融臨模本と大島本は「あい行つきて」とある。『集成』『新大系』は底本(明融臨模本・大島本)のままとする。『完本』は諸本に従って「愛敬づき」と「て」を削除する。
|
| 5.3.3 |
|
返り声に、すべて調子が変わって、律の合奏の数々が、親しみやすく華やかな中にも、琴の琴は、五箇の調べを、たくさんある弾き方の中で、注意して必ずお弾きにならなければならない五、六の発刺を、たいそう見事に澄んでお弾きになる。
まったくおかしなところはなく、たいそうよく澄んで聞こえる。
|
合奏の末段になって呂の調子が律になる所の掻き合わせがいっせいにはなやかになり、琴は五つの調べの中の五六の絃のはじき方をおもしろく宮はお弾きになって、少しも未熟と思われる点がなく、よく澄んで聞こえた。
|
【琴は、五個の調べ】- 『新大系』は「琴は胡笳の調べ」と整定。『河海抄』は「掻手片垂水宇瓶蒼海波雁鳴調」を指摘。奏者は女三の宮。
【五、六の発剌】- 明融臨模本は「五六のはち」とある。大島本は「五六のハち(ち=らイ、らイ#)」とある。すなわち、「はち」の右傍らに「はらイ」と異本表記するが、後にそれを削除する。『集成』は「青表紙本は「五六のはち」とあるが、河内本の中に「五六のはら」とするものがあり、それが正しいであろう。「はらとは溌剌とかく。七徽の七分あたりにて六の絃を按へて、五六を右手の人中名の三指にて内へ一声に弾ずるを撥と云ふ。外へ弾ずるを剌と云。つめて云へば発剌(はら)なり」(『玉堂雑記』)」と注して、「五六のはら」と校訂する。『新大系』は本文「はち」のままだが、脚注に「「はち」は誤りか。河内本「五六のはら」。「はら」は、「発剌(はつらつ)」がつまったもので、五絃六絃を三指をもって内へ弾じ外へ弾じて一声の如くする奏法という(山田孝雄)」と注す。『完本』は「五六の撥」のままとする。
【いとおもしろく澄まして弾きたまふ】- 主語は女三の宮。
|
| 5.3.4 |
春秋よろづの物に通へる調べにて、通はしわたしつつ弾きたまふ。
心しらひ、教へきこえたまふさま違へず、いとよくわきまへたまへるを、いとうつくしく、おもだたしく思ひきこえたまふ。
|
春秋どの季節の物にも調和する調べなので、それぞれに相応しくお弾きになる。
そのお心配りは、お教え申し上げたものと違わず、たいそうよく会得していらっしゃるのを、たいそういじらしく、晴れがましくお思い申し上げになる。
|
春と秋その他のあらゆる場合に変化させねばならぬ弾法の使いこなしようを院がお教えになったのを誤たずによく会得して弾いておいでになるのに、院は誇りをお覚えになった。
|
|
|
第四段 女楽終了、禄を賜う
|
| 5.4.1 |
この君達の、いとうつくしく吹き立てて、切に心入れたるを、らうたがりたまひて、 |
この若君たちが、とてもかわいらしく笛を吹き立てて、一生懸命になっているのを、おかわいがりになって、
|
小さい御孫たちが熱心に笛の役を勤めたのをかわいく院は思召して、
|
【この君達の】- 鬚黒の三男や夕霧の長男をさす。
|
| 5.4.2 |
「ねぶたくなりにたらむに。今宵の遊びは、長くはあらで、はつかなるほどにと思ひつるを。とどめがたき物の音どもの、いづれともなきを、聞き分くほどの耳とからぬたどたどしさに、いたく更けにけり。心なきわざなりや」 |
「眠たくなっているだろうに。
今夜の音楽の遊びは、長くはしないで、ほんの少しのところでと思っていたが。
やめるのには惜しい楽の音色が、甲乙をつけがたいのを、聞き分けるほどに耳がよくないので愚図愚図しているうちに、たいそう夜が更けてしまった。
気のつかないことであった」
|
「眠くなっただろうのに、今晩の合奏はそう長くしないはずでわずかな予定だったのがつい感興にまかせて長く続けていて、それも楽音で時間を知るほどの敏感がなく、思わずおそくなって、思いやりのないことをした」
|
【ねぶたくなりにたらむに】- 以下「心なきわざなりや」まで、源氏の詞。
【心なきわざなりや】- 『集成』は「気のつかぬことをしたものだ」。『完訳』は「どうもわたしはいい気になっていたのだね」と訳す。
|
| 5.4.3 |
|
と言って、笙の笛を吹く君に、杯をお差しになって、お召物を脱いでお与えになる。
横笛の君には、こちらから、織物の細長に、袴などの仰々しくないふうに、形ばかりにして、大将の君には、宮の御方から、杯を差し出して、宮のご装束を一領をお与え申し上げなさるのを、大殿は、
|
とお言いになり、笙の笛を吹いた子に酒杯をお差しになり、御服を脱いでお与えになるのであった。横笛の子には紫夫人のほうから厚織物の細長に袴などを添えて、あまり目だたせぬ纏頭が出された。大将には姫宮の御簾の中から酒器が出されて、宮の御装束一そろいが纏頭にされた。
|
【笙の笛吹く君に】- 鬚黒の三男。
【横笛の君には】- 夕霧の長男。
【こなたより】- 紫の上方からの意。
【宮の御方より】- 女三の宮からの意。
|
| 5.4.4 |
|
「妙なことだね。
師匠のわたしにこそ、さっそくご褒美を下さってよいものなのに。
情ないことだ」
|
「変ですね。まず先生に御褒美をお出しにならないで。私は失望した」
|
【あやしや。物の師をこそ、まづはものめかしたまはめ。愁はしきことなり】- 源氏の詞。冗談にいう。 【ものめかしたまはめ】-『集成』は「お引き立てになって頂きたいものだ」。『完訳』は「大事に扱っていただきたいものです」と訳す。
|
| 5.4.5 |
|
とおっしゃるので、宮のおいであそばす御几帳の側から、御笛を差し上げる。
微笑みなさってお取りになる。
たいそう見事な高麗笛である。
少し吹き鳴らしなさると、皆お返りになるところであったが、大将が立ち止まりなさって、ご子息の持っておいでの笛を取って、たいそう素晴らしく吹き鳴らしなさったのが、実に見事に聞こえたので、どなたもどなたも、皆ご奏法を受け継がれたお手並みが、実に又となくばかりあるので、ご自分の音楽の才能が、めったにないほどだと思われなさるのであった。
|
院がこう冗談をお言いになると、宮の几帳の下からお贈り物の笛が出た。院は笑いながらお受け取りになるのであったが、それは非常によい高麗笛であった。少しお吹きになると、もう退出し始めていた人たちの中で大将が立ちどまって、子息の持っていた横笛を取ってよい音に吹き合わせるのが、至芸と思われるこの音を院はうれしくお聞きになり、これもまた自分の弟子であったと満足されたのであった。
|
【うち笑ひたまひて取りたまふ】- 主語は源氏。
【御子の持ちたまへる笛を取りて】- 横笛である。
【いづれもいづれも、皆御手を離れぬものの伝へ伝へ、いと二なくのみあるにてぞ】- 夕霧やその子も含めて源氏の奏法を受け継いですばらしいことをいう。『完訳』は「以下、源氏の心中に即す叙述。女君たちの巧技が自分の伝授によると再確認し、わが優れた才能を思う。前の対話での、伝授されがたいとする慨嘆ともひびきあう」と注す。
【思し知られける】- 「られ」自発の助動詞。思わずにはいられない、というニュアンス。
|
|
第五段 夕霧、わが妻を比較して思う
|
| 5.5.1 |
|
大将殿は、若君たちをお車に乗せて、月の澄んだ中をご退出なさる。
道中、箏の琴が普通とは違ってたいそう素晴らしかった音色が、耳について恋しくお思い出されなさる。
|
大将は子供をいっしょに車へ乗せて月夜の道を帰って行ったが、いつまでも第二回のおりの箏の音が耳についていて、遣る瀬なく恋しかった。
|
【道すがら、箏の琴の変はりていみじかりつる音も】- 夕霧、紫の上の箏の琴の音色を忘れ難く思い出す。
|
| 5.5.2 |
|
ご自分の北の方は、亡き大宮がお教え申し上げなさったが、熱心にお習いなさらなかったうちに、お引き離されておしまいになったので、ゆっくりとも習得なさらず、夫君の前では、恥ずかしがって全然お弾きにならない。
何ごともただあっさりと、おっとりとした物腰で、子供の世話に、休む暇もなく次々となさるので、風情もなくお思いになる。
そうはいっても、機嫌を悪くして、嫉妬するところは、愛嬌があってかわいらしい人柄でいらっしゃるようである。
|
この人の妻は祖母の宮のお教えを受けていたといっても、まだよくも心にはいらぬうちに父の家へ引き取られ、十三絃もはんぱな稽古になってしまったのであるから、良人の前では恥じて少しも弾かないのである。すべておおまかに外見をかまわず暮らしていて、あとへあとへ生まれる子供の世話に追われているのであるから、大将は若い妻の感じのよさなどは少しも受け取りえない良人なのである。しかも嫉妬はして、腹をたてなどする時に天真爛漫な所の見える無邪気な夫人なのであった。
|
【わが北の方は】- 雲居雁。
【別れたてまつりたまひにしかば】- 『完訳』は「大宮の御もとからお離れ申しあげなさったので」。父内大臣によって雲居雁は大宮の三条宮邸から自邸の方に引き取られた。
【ゆるるかにも弾き取りたまはで】- 『集成』は「ゆっくり伝授をお受けになることもなくて」。『完訳』は「十分に稽古をお積みにならなかったものだから」と訳す。
【男君】- 『完訳』は「前の「大将」とは異なり、家庭内の夫婦関係を強調した呼称」と注す。
|
|
第六章 紫の上の物語 出家願望と発病
|
|
第一段 源氏、紫の上と語る
|
| 6.1.1 |
院は、対へ渡りたまひぬ。上は、止まりたまひて、宮に御物語など聞こえたまひて、暁にぞ渡りたまへる。日高うなるまで大殿籠れり。 |
院は、対へお渡りになった。
紫の上は、お残りになって、宮にお話など申し上げなさって、暁方にお帰りになった。
日が高くなるまでお寝みになった。
|
院は対のほうへお帰りになり、紫夫人はあとに残って女三の宮とお話などをして、明け方に去ったが、昼近くなるまで寝室を出なかった。
|
【対へ渡りたまひぬ】- 源氏は東の対へ帰った。
|
| 6.1.2 |
|
「宮のお琴の音色は、たいそう上手になったものだな。
どのようにお聞きなさいましたか」
|
「宮は上手になられたようではありませんか。あの琴をどう聞きましたか」
|
【宮の御琴の音は】- 以下「いかが聞きたまひし」まで、源氏の詞。
|
| 6.1.3 |
と聞こえたまへば、
|
とお尋ねなさるので、
|
と院は夫人へお話しかけになった。
|
|
| 6.1.4 |
|
「初めの方は、あちらでちらっと聞いた時には、どんなものかしらと思いましたが、とてもこの上なく上手になりましたわ。
どうして、あのように専心してお教え申し上げになったのですから」
|
「初めごろ、あちらでなさいますのを、聞いておりました時は、まだそうおできになるとは伺いませんでしたが、非常に御上達なさいましたね。ごもっともですわね、先生がそればかりに没頭していらっしゃったのですものね」
|
【初めつ方】- 以下「きこえたまはむには」まで、紫の上の詞。
【いかでかは、かく異事なく教へきこえたまはむには】- 「いかでかは」反語表現。『集成』は「どうしてご上達なさらないことがありましょう、こんなにかかりきりでお教え申し上げなさったのですから」。『完訳』は「それもそのはずでございましょう、ほかに何もなさらずこうしてかかりきりで教えておあげになるのですから」と訳す。
|
| 6.1.5 |
といらへきこえたまふ。
|
とお答えなさる。
|
|
|
| 6.1.6 |
「さかし。手を取る取る、おぼつかなからぬ物の師なりかし。これかれにも、うるさくわづらはしくて、暇いるわざなれば、教へたてまつらぬを、院にも内裏にも、琴はさりとも習はしきこゆらむとのたまふと聞くがいとほしく、さりとも、さばかりのことをだに、かく取り分きて御後見にと預けたまへるしるしにはと、思ひ起こしてなむ」 |
「そうなのだ。
手を取り取りの、たいした師匠なんだよ。
他のどなたにも、厄介で、面倒なことなので、お教え申さないが、院にも帝にも、琴の琴はいくらなんでもお教え申しているだろうとおっしゃると、耳にするのがおいたわしくて、そうは言っても、せめてその程度のことだけはと、このように特別なご後見にとお預けになった甲斐にはと、思い立ってね」
|
「そうですね、手を取りながら教えるのだからこんな確かな教授法はなかったわけですね。あなたにも教えるつもりでいたが、あれは面倒で時間のかかる稽古ですからね、つい実行ができなかったのだが、院の陛下も琴だけの稽古はさせているだろうと言っておられるということを聞くと、お気の毒で、せめてそれくらいのことは保護者に選ばれたものの義務としてしなければならないかという気になって、やり始めた先生なのですよ」
|
【さかし】- 以下「思ひ起こしてなむ」まで、源氏の詞。
【手を取る取る、おぼつかなからぬ物の師なりかし】- 『集成』は「手を取らんばかりの教授ぶりで、なかなかしっかりした師匠だというべきでしょう」。『完訳』は「いちいち手を取るようにして、わたしは頼りがいのある師匠というものです」と訳す。
|
| 6.1.7 |
など聞こえたまふついでにも、
|
などと申し上げなさるついでにも、
|
などと仰せられるついでに、
|
|
| 6.1.8 |
「昔、世づかぬほどを、扱ひ思ひしさま、その世には暇もありがたくて、心のどかに取りわき教へきこゆることなどもなく、近き世にも、何となく次々、紛れつつ過ぐして、聞き扱はぬ御琴の音の、出で栄えしたりしも、面目ありて、大将の、いたくかたぶきおどろきたりしけしきも、思ふやうにうれしくこそありしか」 |
「昔、まだ幼かったころ、お世話したものだが、当時は暇がなくて、ゆっくりと特別にお教え申し上げることなどもなく、近頃になっても、何となく次から次へと、とり紛れては日を送り、聞いて上げなかったお琴の音色が、素晴らしい出来映えだったのも、晴れがましいことで、大将が、たいそう耳を傾け感嘆していた様子も、思いどおりで嬉しいことであった」
|
「小さかったころのあなたを手もとへ置いて、理想的に育て上げたいとは思ったものの、そのころの私にはひまな時間が少なくて、特別なものの先生になってあげることもできなかったし、近年はまたいろいろなことが次から次へと私を駆使して、よく世話もしてあげなかった琴のできのよかったことで私は光栄を感じましたよ。大将が非常に感心しているのを見たこともうれしくてなりませんでしたよ」
|
【昔、世づかぬほどを】- 以下「うれしくこそありしか」まで、源氏の詞。
【面目ありて】- 自分にとって面目であったという意。
|
| 6.1.9 |
など聞こえたまふ。
|
などと申し上げなさる。
|
ともおほめになった。
|
|
|
第二段 紫の上、三十七歳の厄年
|
| 6.2.1 |
|
こういった音楽の方面のことも、今はまた年輩者らしく、若宮たちのお世話などを、引き受けなさっている様子も、至らないところなく、すべて何事につけても、非難されるような行き届かないところなく、世にもまれなご様子の方なので、まことにこのように何から何までそなわっていらっしゃる方は、長生きしない例もあるというのでと、不吉なまでにお思い申し上げなさる。
|
そうした芸術的な能力も豊かである上に、今は一方で祖母の義務を御孫の宮たちのために忠実に尽くしていて、家庭の実務をとることにも力の不足は少しも見せない夫人であることを院はお思いになり、こうまで完全な人というものは短命に終わるようなこともあるのであると、そんな不安をお覚えになった。
|
【宮たちの御扱ひ】- 明石女御腹の御子の世話。
【取りもちてしたまふさま】- 『集成』は「自分から買って出てなさる様子も」。『完訳』は「とりしきっていらっしゃるが」と訳す。
【例もあなるをと】- 「なる」伝聞推定の助動詞。
【ゆゆしきまで思ひきこえたまふ】- 源氏の心中を地の文で叙述。不安・不吉を心中に呼び込み、実際それが以後の物語展開に実現していくという表現構造。
|
| 6.2.2 |
|
いろいろな人の有様を多く御覧になっているために、何から何まで揃っている点では、本当に例があるまいと心底からお思い申し上げていらっしゃった。
今年は、
三十七歳におなりである。一緒にお暮らし申されてからの年月のことなどを、しみじみとお思
|
多くの女性を御覧になった院が、これほどにも物の整った人は断じてほかにないときめておいでになる紫の女王であった。夫人は今年が三十七であった。同棲あそばされてからの長い時間を院は追懐あそばしながら、
|
【たぐひあらじとのみ】- 『集成』は「二人とないお方だと心底から」と訳す。副助詞「のみ」強調のニュアンス。
【今年は三十七にぞなりたまふ】- 女の重厄の年。藤壺も三十七で崩御。『集成』は「源氏十八歳の若紫の巻で、紫の上は「十ばかりにやあらむと見えて」とあった。源氏は今四十七歳。多少の齟齬があると見るよりも大体符合するとすべきであろう。厄年にしたのは作者の意図である」。『完訳』は「源氏との年齢差を八歳と見るかぎり、紫の上の年齢は三十九歳のはず。作者の意識的過誤か」と注す。
|
| 6.2.3 |
|
「しかるべきご祈祷など、いつもの年よりも特別にして、今年はご用心なさい。
何かと忙しくばかりあって、考えつかないことがあるだろうから、やはり、あれこれとお思いめぐらしになって、大がかりな仏事を催しなさるなら、わたしの方でさせていただこう。
僧都が亡くなってしまわれたことが、たいそう残念なことだ。
一通りのお願いをするのにつけても、たいそう立派な方であったのに」
|
「祈祷のようなことを半生の年よりもたくさんさせて今年は無理をしないようにあなたは慎むのですね。私がそうしたことは常に気をつけてさせなければならないのだが、ほかのことに紛れてうっかりとしている場合もあるだろうから、あなた自身で考えて、ああしたいというようないくぶん大きな仏事の催しでもあれば、言ってくれればいくらでも用意をさせますよ。北山の僧都がなくなっておしまいになったことは惜しいことだ。親戚とせずに言ってもりっぱな宗教家でしたがね」
|
【さるべき御祈りなど】- 以下「かしこかりし人を」まで、源氏の詞。
【大きなることども】- 大がかりな仏事。厄除けの祈祷。
【おのづからせさせてむ】- 「させ」使役の助動詞。「て」完了の助動詞、確述。「む」推量の助動詞、意志。『集成』は「当然私の方でさせよう」。『完訳』は「たまにはわたしにさせてください」と訳す。
【故僧都のものしたまはず】- 北山の僧都。紫の上の祖母の兄。
|
| 6.2.4 |
などのたまひ出づ。
|
などとおっしゃる。
|
ともお言いになった。また、
|
|
|
第三段 源氏、半生を語る
|
| 6.3.1 |
|
「わたしは、幼い時から、人とは違ったふうに、大層な育ち方をして来て、現在の世の評判や有様、過去にも類例が少ないものであった。
けれども、また一方で、大変に悲しいめに遭ったことでも、人並み以上であったことです。
|
「私は生まれた初めからすでにたいそうに扱われる運命を持っていたし、今日になって得ている名誉も物質的のしあわせも珍しいほどの人間ともいってよいが、
|
【みづからは、幼くより】- 以下「さりともとなむ思ふ」まで、源氏の詞。生涯を述懐し、紫の上への愛情を語る。
【たぐひ少なくなむありける】- 以上、現世において無類の栄耀栄華を極めたことをいう。
【されど、また】- 反転して、以下に無類の憂愁を体験したともいう。
|
| 6.3.2 |
|
まず第一に、愛する方々に次々と先立たれ、とり残された晩年になっても、意に満たず悲しいと思う事が多く、不本意にも感心しないことにかかわったにつけても、妙に物思いが絶えず、心に満足のゆかず思われる事が身につきまとって過ごして来てしまったので、その代わりとででもいうのか、思っていたわりに、今まで生き永らえているのだろうと、思わずにはいられません。
|
また一方ではだれよりも多くの悲しみを見て来た人とも言えるのです。母や祖母と早く別れたことに始まって、いろいろな悲しいことが私のまわりにはありましたよ。それが罪業を軽くしたことになって、こうして思いのほか長生きもできるのだと思いますよ。
|
【まづは、思ふ人にさまざま後れ】- 源氏は三歳の時には母桐壺更衣に、六歳の時には祖母に、二十三歳で父桐壺院に先立たれた。
【残りとまれる齢の末にも、飽かず悲しと思ふこと多く】- 『集成』は「具体的には明らかではないが、次の言葉から、藤壺や六条の御息所など、悔恨にみちた青春時代を回想しての感慨と思われる」。『完訳』は「現実世界への不満。その具体内容が次の「あぢきなく--」に語られるが、冷泉帝の皇統の断絶した無念さもひびいていよう」と注す。
【あぢきなくさるまじきことにつけても】- 『集成』は「我ながら不本意な感心しないことにかかわったにつけても」。『完訳』は「道にはずれた大それたことにかかわったにつけても」「藤壺への恋情ゆえの物思い」と注す。
【それに代へてや、思ひしほどよりは】- 『完訳』は「憂愁ゆえに存命しうる。絵合にも見られる考え方」と注す。
|
| 6.3.3 |
君の御身には、かの一節の別れより、あなたこなた、もの思ひとて、心乱りたまふばかりのことあらじとなむ思ふ。后といひ、ましてそれより次々は、やむごとなき人といへど、皆かならずやすからぬもの思ひ添ふわざなり。 |
あなたご自身には、あの一件での離別のほかは、その前にも後にも、心配して、心をお痛めになるようなことはあるまいと思う。
后と言っても、ましてそれより下の方々は、身分が高いからと言っても、皆必ず物思いの種が付き纏うものなのです。
|
あなたは私とあの別居時代のにがい経験をしてからはもう物思いも煩悶もなかったろうと思われる。お后と言われる人、ましてそれ以下の宮廷の人には人との競争意識でみずから苦しまない人はないのですよ。
|
【かの一節の別れ】- 源氏の須磨明石への流離をさす。
|
| 6.3.4 |
|
高いお付き合いをするにつけても、気苦労があり、人と争う思いが絶えないのも、楽なことではないから、親のもとでの深窓生活同然に暮らしていらっしゃるような気楽さはありません。
その点では、人並み以上の運勢だとお分かりでしょうか。
|
親の家にいるままのようにして今日まで来たあなたのような気楽はだれにもないものなのですよ。この点だけではあなたがだれよりも幸福だったということがわかりますか。
|
【人に争ふ思ひの絶えぬも、やすげなきを】- 『集成』は「人と帝寵をきそう気持が絶えないのも楽なことではありませんが」。『完訳』は「主上のお情けを他人と争い合う気持の絶えないのも不安なものですから」と訳す。
【親の窓のうちながら過ぐしたまへるやうなる】- 「窓の内」は「長恨歌」の「養在深窓人未識」にもとづく表現。接尾語「ながら」は、さながら、同然の意。
【そのかた】- 明融臨模本と大島本は「そのかた」とある。『集成』『新大系』は底本(明融臨模本・大島本)のままとする。『完本』は諸本に従って「ほの方は」と「は」を補訂する。
|
| 6.3.5 |
思ひの外に、この宮のかく渡りものしたまへるこそは、なま苦しかるべけれど、それにつけては、いとど加ふる心ざしのほどを、御みづからの上なれば、思し知らずやあらむ。ものの心も深く知りたまふめれば、さりともとなむ思ふ」 |
思いもかけず、この宮がこのようにお輿入れなさったのは、何やら辛くお思いでしょうが、それにつけては、いっそう勝る愛情を、ご自分の身の上のことですから、あるいはお気づきでないかも知れません。
物のわけをよくお分りのようですから、きっとお分りだろうと思います」
|
思いがけなく姫宮をこちらへお迎えしなければならないことになってからは、少しの不愉快はあるでしょうがね、それによって私の愛はいっそう深まっているのだが、あなたは自身のことだからわかっていないかもしれない。しかし物わかりのいい人だから理解していてくれるかもしれないと頼みにしていますよ」
|
【さりともとなむ思ふ】- 『集成』は「それでも、そのことはよくわきまえておいでのことと私は安心しています」。『完訳』は「いくらなんでも分ってくださると思いますが」と訳す。
|
| 6.3.6 |
と聞こえたまへば、
|
と申し上げなさると、
|
と院がお言いになると、
|
|
| 6.3.7 |
|
「おっしゃるように、ふつつかな身の上には、過ぎた事と世間の目には見えましょうが、心に堪えない物思いばかりがつきまとうのは、それがわたし自身のご祈祷となっているのでした」
|
「お言葉のように、ほかから見ますれば私としては過分な身の上になっているのですが、心には悲しみばかりがふえてまいります。それを少なくしていただきたいと神仏にはただそれを私は祈っているのですよ」
|
【のたまふやうに】- 以下「祈りなりける」まで、紫の上の詞。
【さはみづからの祈りなりける】- 『集成』は「それでは、それが私のためのお祈祷になって今まで生き永らえているのかもしれません」「源氏が「それにかへてや、思ひしほどよりは、今までもながらふるならむとなむ、思ひ知らる」と言ったのにすがった形で、女三の宮降嫁後の苦衷を訴える」と注す。『完訳』は「それが自分自身のための祈りのようになっているのでした」と訳す。
|
| 6.3.8 |
とて、残り多げなるけはひ、恥づかしげなり。
|
と言って、多く言い残したような様子は、奥ゆかしそうである。
|
言いたいことをおさえてこれだけを言った女王に貴女らしい美しさが見えた。
|
|
| 6.3.9 |
「まめやかには、いと行く先少なき心地するを、今年もかく知らず顔にて過ぐすは、いとうしろめたくこそ。さきざきも聞こゆること、いかで御許しあらば」 |
「ほんとうのことを申しますと、もうとても先も長くないような心地がするのですが、今年もこのように知らない顔をして過ごすのは、とても不安なことです。
先々にも申し上げたこと、何とかお許しがあれば」
|
「ほんとうは私はもう長く生きていられない気がしているのでございますよ。この厄年までもまだ知らない顔でこのままでいますことは悪いことと知っています。以前からお願いしていることですから、許していただけましたら尼になります」
|
【まめやかには】- 以下「御許しあらば」まで、紫の上の詞。出家を再度願う。
【さきざきも聞こゆること】- 「今は、かうおほぞうの住まひならで、のどやかに行なひをも、となむ思ふ」(第三章二段))の出家の意志をさす。
|
| 6.3.10 |
と聞こえたまふ。
|
と申し上げなさる。
|
とも夫人は言った。
|
|
| 6.3.11 |
「それはしも、あるまじきことになむ。さて、かけ離れたまひなむ世に残りては、何のかひかあらむ。ただかく何となくて過ぐる年月なれど、明け暮れの隔てなきうれしさのみこそ、ますことなくおぼゆれ。なほ思ふさま異なる心のほどを見果てたまへ」 |
「それは、とんでもないことだ。
そうして、離れておしまいになった後に残ったわたしは、何の生き甲斐があろう。
ただこのように何ということもなく過ぎて行く月日だが、朝に晩に顔を合わせる嬉しさだけで、これ以上の事はないと思われるのです。
やはりあなたを人とは違って思う気持ちがどれほど深いものであるか最後まで見届けてください」
|
「それはもってのほかのことですよ。あなたが尼になってしまったあとの私の人生はどんなにつまらないものになるだろう。平凡に暮らしてはいるようなものの、あなたと睦まじくして生きているということよりよいことはないと私は信じているのです。あなただけをどんなに私が愛しているかということを、これからの長い時間に見ようと思ってください」
|
【それはしも、あるまじきことになむ】- 以下「心のほどを見果てたまへ」まで、源氏の詞。紫の上の出家の再度の願いを拒絶、制止する。
|
| 6.3.12 |
|
とばかり申し上げなさるのを、いつものことと胸が痛んで、涙ぐんでいらっしゃる様子を、たいそういとしいと拝見なさって、いろいろとお慰め申し上げなさる。
|
院がこうお言いになるのを、またもいつもの慰め言葉で自分の信仰にはいる道をおはばみになると聞いて、夫人の涙ぐんでいるのを院は憐れにお思いになって、いろいろな話をし出して紛らせようとおつとめになるのであった。
|
【とのみ聞こえたまふを】- 副助詞「のみ」限定と強調のニュアンス。と同じことばかり、というニュアンス。
【例のことと心やましくて】- 『集成』「(出家の願いを聞き届けて下さらない)いつもの口実だと、つらく思って」。『完訳』は「上は、いつもと同じおっしゃりようだと、まったくやりばのないお気持になられて」と訳す。
|
|
第四段 源氏、関わった女方を語る
|
| 6.4.1 |
「多くはあらねど、人のありさまの、とりどりに口惜しくはあらぬを見知りゆくままに、まことの心ばせおいらかに落ちゐたるこそ、いと難きわざなりけれとなむ、思ひ果てにたる。 |
「多くは知らないが、人柄が、それぞれにとりえのないものはないと分かって行くにつれて、ほんとうの気立てがおおらかで落ち着いているのは、なかなかいないものであると、思うようになりました。
|
「そうおおぜいではありませんが、私の接触した比較的優秀な女性について言ってみると、女は何よりも性質が善良で落ち着いた考えのある人が一等だと思われるが、それがなかなか望んで見いだせないものなのですよ。
|
【多くはあらねど】- 以下「悔しきことも多くなむ」まで、源氏の詞。源氏の女性観。過去の女性について語る。
|
| 6.4.2 |
|
大将の母君を、若いころにはじめて妻として、大事にしなければならない方とは思ったが、いつも夫婦仲が好くなく、うちとけぬ気持ちのまま終わってしまったのが、今思うと、気の毒で残念である。
|
大将の母とは少年時代に結婚をして、尊重すべき妻だとは思っていましたが、仲をよくすることができずに、隔てのあるままで終わったのを、今思うと気の毒で堪えられないし、残念なことをしたと後悔もしていながら、
|
【大将の母君を】- 葵の上をさす。源氏の詞中での呼称。以下、葵の上評。
【幼かりしほどに見そめて】- 源氏は十二歳で元服、その日の夜に葵の上と結婚。
【いとほしく悔しくもあれ】- 「こそ」の係結び、已然形。『集成』は句点で「お気の毒にも残念にも思われます」。『完訳』は読点で逆接用法の「おいたわしく悔やまれもするのですけれど」と訳す。
|
| 6.4.3 |
また、わが過ちにのみもあらざりけりなど、心ひとつになむ思ひ出づる。うるはしく重りかにて、そのことの飽かぬかなとおぼゆることもなかりき。ただ、いとあまり乱れたるところなく、すくすくしく、すこしさかしとやいふべかりけむと、思ふには頼もしく、見るにはわづらはしかりし人ざまになむ。 |
しかしまた、わたし一人の罪ばかりではなかったのだと、自分の胸一つに思い出される。
きちんとして重々しくて、どの点が不満だと思われることもなかった。
ただ、あまりにくつろいだところがなく、几帳面すぎて、少しできすぎた人であったと言うべきであろうかと、離れて思うには信頼が置けて、一緒に生活するには面倒な人柄であった。
|
また自分だけが悪いのでもなかったと一方では考えられもするのですよ。りっぱな貴婦人であったことは間違いのないことで、なんらの欠点はなかったが、ただあまりに整然とととのったのが堅い感じを受けさせてね。少し賢過ぎるといっていいような人で、話で聞けば頼もしいが、妻にしては面倒な気のするというような女性でしたよ。
|
【うるはしく重りかにて】- 『完訳』は「深窓の麗人という印象である」と注す。「麗し」という語句は、きちんとしすぎていてよそよそしく好感がもたれない、というニュアンス。女三の宮降嫁後の紫の上の態度に「うるはし」という表現が使われているのは、注意すべき。
【すこしさかしとやいふべかりけむ】- 『集成』は「どちらかというと頭のよすぎる人だったであろうと」。『完訳』は「少し立派すぎたとでもいうべきだったでしょうか」と訳す。
|
| 6.4.4 |
|
中宮の御母君の御息所は、人並すぐれてたしなみ深く優雅な人の例としては、まず第一に思い出されるが、逢うのに気がおけて、こちらが気苦労するような方でした。
恨むことも、なるほど無理もないことと思われる点を、そのままいつまでも思い詰めて、深く怨まれたのは、まことに辛いことであった。
|
中宮の母君の御息所は、高い見識の備わった才女の例には思い出される人だが、恋人としてはきわめて扱いにくい性格でしたよ。怨むのが当然だと一通りは思われることでも、その人はそのままそのことを忘れずに思いつめて深く恨むのですから、相手は苦しくてならなかった。
|
【中宮の御母御息所なむ】- 六条御息所。源氏の詞中での呼称。以下、六条御息所評。
【怨ぜられしこそ、いと苦しかりしか】- 「られ」受身の助動詞。源氏が御息所から怨まれたのはつらいことであった、の意。
|
| 6.4.5 |
心ゆるびなく恥づかしくて、我も人もうちたゆみ、朝夕の睦びを交はさむには、いとつつましきところのありしかば、うちとけては見落とさるることやなど、あまりつくろひしほどに、やがて隔たりし仲ぞかし。
|
緊張のし通しで気づまりで、自分も相手もゆっくりとして、朝夕睦まじく語らうには、とても気の引けるところがあったので、気を許しては軽蔑されるのではないかなどと、あまりに体裁をつくろっていたうちに、そのまま疎遠になった仲なのです。
|
自己を高く評価させないではおかないという自尊心が年じゅう付きまつわっているような気がして、そんな場合に自分は気に入らない男になるかもしれないと、あまりに見栄を張り過ぎるような私になって、そして自然に遠のいて縁が絶えたのですよ。
|
|
| 6.4.6 |
いとあるまじき名を立ちて、身のあはあはしくなりぬる嘆きを、いみじく思ひしめたまへりしがいとほしく、げに人がらを思ひしも、我罪ある心地して止みにし慰めに、中宮をかくさるべき御契りとはいひながら、取りたてて、世のそしり、人の恨みをも知らず、心寄せたてまつるを、かの世ながらも見直されぬらむ。今も昔も、なほざりなる心のすさびに、いとほしく悔しきことも多くなむ」 |
たいそうとんでもない浮名を立て、ご身分に相応しくなくなってしまった嘆きを、たいそう思い詰めていらっしゃったのがお気の毒で、なるほど人柄を考えても、自分に罪がある心地がして終わってしまったその罪滅ぼしに、中宮をこのようにそうなるべき前世からのご因縁とは言いながら、取り立てて、世の非難、人の嫉妬も意に介さず、お世話申し上げているのを、あの世からであっても考え直して下さったろう。
今も昔も、いいかげんな気まぐれから、気の毒な事や後悔する事が多いのです」
|
私が無二無三に進み寄ってあるまじい名の立つ結果を引き起こしたその人の真価を知っているだけなお捨ててしまったのが済まないことに思われて、せめて中宮にはよくお尽くししたいと、それも前生の約束だったのでしょうが、こうして子にしてお世話を申していることで、あの世からも私を見直しているでしょうよ。今も昔も浮わついた心から人のために気の毒な結果を生むことの多い私ですよ」
|
【身のあはあはしくなりぬる嘆きを】- 『集成』は「ご身分にふさわしからぬ身の上になられた嘆きを」。『完訳』は「ご身分を傷つけてしまったことが嘆かわしいと」と訳す。
【さるべき御契りとはいひながら】- 后という高い地位になるご宿縁とはいっても。
|
| 6.4.7 |
と、来し方の人の御上、すこしづつのたまひ出でて、
|
と、亡くなったご夫人方について少しずつおっしゃり出して、
|
なお幾人かの女の上を院はお語りになった。
|
|
| 6.4.8 |
「内裏の御方の御後見は、何ばかりのほどならずと、あなづりそめて、心やすきものに思ひしを、なほ心の底見えず、際なく深きところある人になむ。うはべは人になびき、おいらかに見えながら、うちとけぬけしき下に籠もりて、そこはかとなく恥づかしきところこそあれ」 |
「今上の御方のご後見は、大した身分の人でないと、最初から軽く見て、気楽な相手だと思っていたが、やはり心の底が見えず、際限もなく深いところのある人でした。
表面は従順で、おっとりして見えるながら、しっかりしたところが下にあって、どことなく気の置けるところがある人です」
|
「女御のあの後見役はたいしたものではあるまいと軽く見てかかった相手ですが、それが心の底の底までは見られないほどの深い所のある女でしたからね。うわべは素直らしく柔順には見えながら、自己を守る堅さが何かの場合に見える怜悧なたちなのですよ」
|
【内裏の御方の御後見は】- 以下「ところこそあれ」まで、源氏の詞。源氏の詞中での明石御方の呼称。以下明石御方評。
|
| 6.4.9 |
とのたまへば、
|
とおっしゃると、
|
と院がお言いになると、
|
|
| 6.4.10 |
「異人は見ねば知らぬを、これは、まほならねど、おのづからけしき見る折々もあるに、いとうちとけにくく、心恥づかしきありさましるきを、いとたとしへなきうらなさを、いかに見たまふらむと、つつましけれど、女御は、おのづから思し許すらむとのみ思ひてなむ」 |
「他の方は会ったことがないので知りませんが、この方は、はっきりとではないが、自然と様子を見る機会も何度かあったので、とても馴れ馴れしくできず、気の置ける嗜みがはっきりと分かりますにつけても、とても途方もない単純なわたしを、どのように御覧になっているだろうと、気の引けるところですが、女御は、自然と大目に見て下さるだろうとばかり思っています」
|
「ほかの方は見ないのですからわかりませんけれど、あの方にはおりおりお目にかかっていますが、聡明で聡明で御自身の感情を少しもお見せにならないのに比べて、だれにも友情を押しつける私をあの方はどう御覧になっていらっしゃるかときまりが悪くてね。しかしとにもかくにも女御は私をいいようにだけ解釈してくださるだろうと思っています」
|
【異人は見ねば知らぬを】- 以下「思ひてなむ」まで、紫の上の詞。
【まほならねど】- 『集成』は「はっきりとではありませんが」。『完訳』は「あらたまってではありませんが」と訳す。
|
| 6.4.11 |
とのたまふ。
|
とおっしゃる。
|
夫人にとってはねたましく思われた人であった
|
|
| 6.4.12 |
さばかりめざましと心置きたまへりし人を、今はかく許して見え交はしなどしたまふも、女御の御ための真心なるあまりぞかしと思すに、いとありがたければ、 |
あれほど目障りな人だと心を置いていらっしゃった人を、今ではこのように顔を合わせたりなどなさるのも、女御の御ためを思う真心の結果なのだとお思いになると、普通にはとても出来ないことなので、
|
明石夫人をさえこんなに寛大な心で見るようになったのも、女御を愛する心の深いからであろうと院はうれしく思召した。
|
【さばかりめざましと】- 以下「真心なるあまりぞかし」まで、地の文と源氏の心中が融合した表現。
|
| 6.4.13 |
|
「あなたこそは、それでもやはり心底に思わないこともないではないが、人によって、事によって、とても上手に心を使い分けていらっしゃいますね。
全く多くの女たちに接して来たが、あなたのご様子に似ている人はいませんでした。
とても態度は格別でいらっしゃいます」
|
「あなたは恨む心もある人だが思いやりもあるから私をそう困らせませんね。たくさんな女の中であなたの真似のできる人はない。あまりにりっぱ過ぎるわけですね」
|
【君こそは、さすがに】- 以下「こそものしたまへ」まで、源氏の詞。
【よく二筋に心づかひはしたまひけれ】- 『完訳』は「状況に応じて心の使い分けをする聰明さをいう」と注す。
【いとけしきこそものしたまへ】- 『集成』は「とても余人に代えがたい感心なお人柄です」と訳し、「「けしきあり」はひとかどの風情があるというほどの意」と注す。『完訳』は「まことにご機嫌ななめなところをお見せにはなりますけれど」と訳し、「嫉妬なさるところもあるが、と戯れた」と注す。
|
| 6.4.14 |
と、ほほ笑みて聞こえたまふ。
|
と、ほほ笑んで申し上げなさる。
|
微笑して院はこうお言いになる。夕方になってから、
|
|
| 6.4.15 |
|
「宮に、とても琴の琴を上手にお弾きになったお祝いを申し上げよう」
|
「宮がよくお弾きになったお祝いを言ってあげよう」
|
【宮に、いとよく】- 以下「喜び聞こえむ」まで、源氏の詞。
|
| 6.4.16 |
とて、夕つ方渡りたまひぬ。
我に心置く人やあらむとも思したらず、いといたく若びて、ひとへに御琴に心入れておはす。
|
と言って、夕方お渡りになった。
自分に気兼ねする人があろうかともお考えにもならず、とてもたいそう若々しくて、一途に御琴に熱中していらっしゃる。
|
と言って、院は寝殿へお出かけになった。自分があるために苦しんでいる人がほかにあることなどは念頭になくて、お若々しく宮は琴の稽古を夢中になってしておいでになった。
|
|
| 6.4.17 |
|
「もう、お暇を下さって休ませていただきたいものです。
師匠は満足させてこそです。
とても辛かった日頃の成果があって、安心出来るほどお上手になりになりました」
|
「もう琴は休ませておやりなさい。それに先生をよく歓待なさらなければならないでしょう。苦しい骨折りのかいがあって安心してよいできでしたよ」
|
【今は、暇許してうち休ませたまへかし】- 以下「たまひにたり」まで、源氏の詞。女三の宮が源氏に暇を許して琴の教授を休ませる、の意。「せ」使役の助動詞。
【物の師は心ゆかせてこそ】- 『集成』は「師匠というものは、(ご褒美を下さって)喜ばせないといけないものです」。『完訳』は「師匠を楽にさせてこそ弟子というものです」と訳す。
|
| 6.4.18 |
とて、御琴どもおしやりて、大殿籠もりぬ。
|
と言って、お琴類は押しやって、お寝みになった。
|
と院はお言いになって、楽器は押しやって寝ておしまいになった。
|
|
|
第五段 紫の上、発病す
|
| 6.5.1 |
|
対の上のもとでは、いつものようにいらっしゃらない夜は、遅くまで起きていらして、女房たちに物語などを読ませてお聞きになる。
|
対のほうでは寝殿泊まりのこうした晩の習慣で女王は長く起きていて女房たちに小説を読ませて聞いたりしていた。
|
【人びとに物語など読ませて聞きたまふ】- 当時の物語の観賞法を窺わせる。女房が物語を読みあげて姫君が耳で聞くというかたち。国宝『源氏物語絵巻』「東屋」第一段の図、参照。
|
| 6.5.2 |
|
「このように、世間で例に引き集めた昔語りにも、不誠実な男、色好み、二心ある男に関係した女、このようなことを語り集めた中にも、結局は頼る男に落ち着くようだ。
どうしたことか、浮いたまま過してきたことだわ。
確かにおっしゃったように、人並み勝れた運勢であったわが身の上だが、世間の人が我慢できず満足ゆかないこととする悩みが身にまといついて終わろうとするのだろうか。
つまらない事よ」
|
人生を写した小説の中にも多情な男、幾人も恋人を作る人を相手に持って、絶えず煩悶する女が書かれてあっても、しまいには二人だけの落ち着いた生活が営まれることに皆なっているようであるが、自分はどうだろう、晩年になってまで一人の妻にはなれずにいるではないか、院のお言葉のように自分は運命に恵まれているのかもしれぬが、だれも最も堪えがたいこととする苦痛に一生付きまとわれていなければならぬのであろうか、情けないことである
|
【かく、世のたとひに言ひ集めたる昔語りどもにも】- 「あぢきなくもあるかな」まで、紫の上の心中。「昔語り」の性格について、『集成』は「こうして世間によくある話としていろいろ物語っているたくさんの昔話でも」。『完訳』は「このように世間にありがちな話としていろいろと書いてある昔の数々の物語にも」と訳す。いずれにしても短編物語集的性格であろう。
【寄る方ありてこそあめれ】- 【寄る方ありてこそ】-明融臨模本、合点。付箋「よるかたもありといふなり(る)ありそ海にたつ白なみのおなし所に」(出典未詳)。前田家本『源氏釈』は「よるかたもありといふなるありそ海のたつ白浪もおなし心よ」(出典未詳)を指摘。定家自筆本『奥入』は「よる方もありといふなるありそうみの(に)たつしらなみのおなし所に」(出典未詳)と、第四五句に異同ある和歌を指摘。『異本紫明抄』『紫明抄』『河海抄』は『奥入』所引系の和歌、『休聞抄』『孟津抄』は『源氏釈』所引系の和歌を指摘する。現行の注釈書では『河海抄』指摘の「大幣と名にこそ立てれ流れてもつひに寄る瀬はありといふものを」(伊勢物語四十七段)を指摘する。 【こそあめれ】-係結び、逆接用法。
【あやしく、浮きても過ぐしつるありさまかな】- 以下、紫の上の述懐。『集成』は「ずっと源氏の正式な北の方としてではなく過してきたこと。それゆえ、今は北の方として女三の宮がいる」と注す。
【げに、のたまひつるやうに】- 源氏の言葉「そのかた人にすぐれたりける宿世とは思し知るや」(第六章三段)を受ける。
【人より異なる宿世もありける身ながら】- 『完訳』は「ここでも栄華と憂愁の半生とするが、宿命観が濃厚」と注す。
|
| 6.5.3 |
など思ひ続けて、夜更けて大殿籠もりぬる、暁方より、御胸を悩みたまふ。
人びと見たてまつり扱ひて、
|
などと思い続けて、夜が更けてお寝みになった、その明け方から、お胸をお病みになる。
女房たちがご看病申し上げて、
|
などと思い続けて、夫人は夜がふけてから寝室へはいったのであるが、夜明け方から病になって、はなはだしく胸が痛んだ。女房が心配して
|
|
| 6.5.4 |
|
「お知らせ申し上げましょう」
|
院へ申し上げよう
|
【御消息聞こえさせむ】- 女房の詞。源氏に知らせよう、の意。
|
| 6.5.5 |
と聞こゆるを、
|
と申し上げるが、
|
と言っているのを、
|
|
| 6.5.6 |
|
「とても不都合なことです」
|
「そんなことをしては済みませんよ」
|
【いと便ないこと】- 紫の上、制止の詞。今女三の宮と一緒にいるところに知らせを遣るのは不都合である、というニュアンスで断る。
|
| 6.5.7 |
と制したまひて、堪へがたきを押さへて明かしたまひつ。御身もぬるみて、御心地もいと悪しけれど、院もとみに渡りたまはぬほど、かくなむとも聞こえず。 |
とお制しなさって、苦しいのを我慢して夜を明かしなさった。
お身体も熱があって、ご気分もとても悪いが、院がすぐにお帰りにならない間、これこれとも申し上げない。
|
と夫人はとめて、非常な苦痛を忍んで朝を待った。発熱までもして夫人の容体は悪いのであるが、院が早くお帰りにならないのをお促しすることもなしにいるうち、
|
【御身もぬるみて】- 人知れぬ我が思ひに逢はぬ間は身にさへぬるみて思ほゆるかな(小町集-四九)(text35.html 出典18から転載)
|
|
第六段 朱雀院の五十賀、延期される
|
| 6.6.1 |
女御の御方より御消息あるに、
|
女御の御方からお便りがあったので、
|
女御のほうから夫人へ手紙を持たせて来た使いに、
|
|
| 6.6.2 |
|
「これこれと気分が悪くていらっしゃいます」
|
病気のことを
|
【かく悩ましくてなむ】- 紫の上方の女房の詞。
|
| 6.6.3 |
と聞こえたまへるに、驚きて、そなたより聞こえたまへるに、胸つぶれて、急ぎ渡りたまへるに、いと苦しげにておはす。 |
と申し上げなさると、びっくりして、そちらから申し上げなさったので、胸がどきりとして、急いでお帰りになると、とても苦しそうにしていらっしゃる。
|
女房が伝えたために、驚いた女御から院へお知らせをしたために、胸を騒がせながら院が帰っておいでになると、夫人は苦しそうなふうで寝ていた。
|
【そなたより聞こえたまへるに】- 明石女御方から源氏のもとへ、の意。
|
| 6.6.4 |
|
「どのようなご気分ですか」
|
「どんな気持ちですか」
|
【いかなる御心地ぞ】- 源氏の詞。
|
| 6.6.5 |
とて探りたてまつりたまへば、いと熱くおはすれば、昨日聞こえたまひし御つつしみの筋など思し合はせたまひて、いと恐ろしく思さる。
|
と手をさし入れなさると、とても熱っぽくいらっしゃるので、昨日申し上げなさったご用心のことなどをお考え合わせになって、とても恐ろしく思わずにはいらっしゃれない。
|
とお言いになり、手を夜着の下に入れてごらんになると非常に夫人の身体は熱い。昨日話し合われた厄年のことも思われて、院は恐ろしく思召されるのであった。
|
|
| 6.6.6 |
御粥などこなたに参らせたれど、御覧じも入れず、日一日添ひおはして、よろづに見たてまつり嘆きたまふ。はかなき御くだものをだに、いともの憂くしたまひて、起き上がりたまふこと絶えて、日ごろ経ぬ。 |
御粥などをこちらで差し上げたが、御覧にもならず、一日中付き添っていらして、いろいろと介抱なさりお心を痛めなさる。
ちょっとしたお果物でさえ、とても億劫になさって、起き上がりなさることはまったくなくなって、数日が過ぎてしまった。
|
粥などを作って持って来たが夫人は見ることすらもいやがった。院は終日病床にお付き添いになって看護をしておいでになった。ちょっとした菓子なども口にせず起き上がらないまま幾日かたった。
|
【御粥などこなたに】- 朝粥、源氏の朝食をいう。
【はかなき御くだものを】- 紫の上への軽い食事。『集成』は「果物、木の実、菓子などの軽い食事。ここは果物であろう」。『完訳』「お菓子」と注す。
|
| 6.6.7 |
いかならむと思し騒ぎて、御祈りども、数知らず始めさせたまふ。僧召して、御加持などせさせたまふ。そこところともなく、いみじく苦しくしたまひて、胸は時々おこりつつ患ひたまふさま、堪へがたく苦しげなり。 |
どうなるのだろうとご心配になって、御祈祷などを、数限りなく始めさせなさる。
僧侶を召して、御加持などをおさせになる。
どこということもなく、たいそうお苦しみになって、胸は時々発作が起こってお苦しみになる様子は、我慢できないほど苦しげである。
|
どうなることかと院は御心配になって祈祷を数知らずお始めさせになった。僧を呼び寄せて加持などもさせておいでになった。どこが特に悪いともなく夫人は非常に苦しがるのである。胸の痛みの時々起こるおりなども堪えがたそうな苦しみが見えた。
|
【いかならむと思し騒ぎて】- 主語は源氏。
|
| 6.6.8 |
さまざまの御慎しみ限りなけれど、しるしも見えず。重しと見れど、おのづからおこたるけぢめあらば頼もしきを、いみじく心細く悲しと見たてまつりたまふに、異事思されねば、御賀の響きも静まりぬ。かの院よりも、かく患ひたまふよし聞こし召して、御訪らひいとねむごろに、たびたび聞こえたまふ。 |
さまざまのご謹慎は数限りないが、効験も現れない。
重態と見えても、自然と快方に向かう兆しが見えれば期待できるが、たいそう心細く悲しいと見守っていらっしゃると、他の事はお考えになれないので、御賀の騷ぎも静まってしまった。
あちらの院からも、このようにご病気である由をお聞きあそばして、お見舞いを非常に御丁重に、度々申し上げなさる。
|
いろいろな養生もまじないもするがききめは見えない。重い病気をしていても時さえたてばなおる見込みのあるのは頼もしいが、この病人は心細くばかり見えるのを院は悲しがっておいでになった。もうほかのことをお考えになる余裕がないために、法皇の賀のことも中止の状態になった。法皇の御寺からも夫人の病をねんごろにお見舞いになる御使いがたびたび来た。
|
【けぢめあらば】- 明融臨模本と大島本は「あらは」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「あるは」と校訂する。『新大系』は底本(大島本)のままとする。
【御賀の響きも静まりぬ】- 最初正月に予定、次いで二月十余日に延期、それも中止になりそうとなる。
|
|
第七段 紫の上、二条院に転地療養
|
| 6.7.1 |
|
同じような状態で、二月も過ぎた。
言いようもない程にお嘆きになって、ためしに場所をお変えなさろうとして、二条院にお移し申し上げなさった。
院の中は上を下への大騒ぎで、嘆き悲しむ者が多かった。
|
夫人の病気は同じ状態のままで二月も終わった。院は言い尽くせぬほどの心痛をしておいでになって、試みに場所を変えさせたらとお考えになって、二条の院へ病女王をお移しになった。六条院の人々は皆大厄難が来たように、悲しんでいる。
|
【同じさまにて、二月も過ぎぬ】- 紫の上の病状、回復に向かうことなく二月が過ぎる。朱雀院の御賀も再び延期となる。
【院の内ゆすり満ちて、思ひ嘆く人多かり】- 六条院の人々の様子をいう。
|
| 6.7.2 |
冷泉院も聞こし召し嘆く。この人亡せたまはば、院も、かならず世を背く御本意遂げたまひてむと、大将の君なども、心を尽くして見たてまつり扱ひたまふ。 |
冷泉院にもお聞きあそばして悲しまれる。
この方がお亡くなりになったら、院もきっと出家のご素志をお遂げになるだろうと、大将の君なども、真心をこめてお世話申し上げなさる。
|
冷泉院も御心痛あそばされた。この夫人にもしものことがあれば六条院は必ず出家を遂げられるであろうことは予想されることであったから、大将なども誠心誠意夫人の病気回復をはかるために奔走しているのであった。
|
【この人亡せたまはば】- 以下「御本意遂げたまひてむ」まで、夕霧の心中。
|
| 6.7.3 |
御修法などは、おほかたのをばさるものにて、取り分きて仕うまつらせたまふ。いささかもの思し分く隙には、 |
御修法などは、普通に行うものはもとより、特別に選んでおさせになる。
少しでも意識がはっきりしている時には、
|
院が仰せられる祈祷のほかに大将は自身の志での祈祷もさせていた。少し知覚の働く時などに夫人は、
|
【取り分きて】- 『完訳』は「大将ご自身もとくにお命じになって」と訳す。
|
| 6.7.4 |
|
「お願い申し上げていることを、お許しなく情けなくて」
|
「お願いしていますことをあなたはお拒みになるのですもの」
|
【聞こゆることを、さも心憂く】- 紫の上の詞。かねて申し上げている出家の願いを聞き届けてくれず、辛いという意。
|
| 6.7.5 |
|
とだけお恨み申し上げなさるが、寿命が尽きてお別れなさるよりも、目の前でご自分の意志で出家なさるご様子を見ては、まったく少しの間でも耐えられず、惜しく悲しい気がしないではいられないので、
|
と、院をお恨みした。力の及ばぬ死別にあうことよりも、生きながら自分から遠く離れて行かせるようなことを見ては、片時も生きるに堪えない気があそばされる院は、
|
【とのみ恨みきこえたまへど】- 副助詞「のみ」限定と強調のニュアンスを添える。紫の上は出家を遂げられない恨みだけを言う。
【限りありて別れ果てたまはむよりも】- 『完訳』は「以下、源氏の心中に即した地の文」と注す。
【目の前に、わが心とやつし捨てたまはむ御ありさまを見ては】- 出家することは夫婦関係を絶つこと。いわゆる家庭内離婚の形になる。夫が先に出家した例として、明石入道夫妻の関係。妻が先に出家した例として、光源氏女三の宮の夫婦関係。その意味が違ってくる。男にとっては棄てられた関係になる。
|
| 6.7.6 |
「昔より、みづからぞかかる本意深きを、とまりてさうざうしく思されむ心苦しさに引かれつつ過ぐすを、さかさまにうち捨てたまはむとや思す」 |
「昔から、自分自身こそこのような出家の本願は深かったのだが、残されて物寂しくお思いなさる気の毒さに心引かれ引かれして過しているのに、逆にわたしを捨てて出家なさろうとお思いなのですか」
|
「昔から私のほうが出家のあこがれを多く持っていながら、あなたが取り残されて寂しく暮らすことを思うのは、堪えられないことなので、こうしてまだ俗世界に残っているのに、逆にあなたが私を捨てようと思うのですか」
|
【昔より、みづからぞ】- 以下「捨てたまはむとや思す」まで、源氏の詞。
|
| 6.7.7 |
|
とばかり、惜しみ申し上げなさるが、本当にとても頼りなさそうに弱々しく、もうこれきりかとお見えになる時々が多かったが、どのようにしようとお迷いになっては、宮のお部屋には、ちょっとの間もお出掛けにならない。
御琴類にも興が乗らず、みなしまいこまれて、院の内の人々は、すっかりみな二条院にお集まりになって、こちらの院では、火を消したようになって、ただ女君たちばかりがおいでになって、お一方の御威勢であったかと見える。
|
こんなにばかりお言いになって御同意をあそばされないのが悪いのか、夫人の病体は頼み少なく衰弱していった。もう臨終かと思われることも多いためにまた尼にさせようかとも院はお惑いになるのであった。こんなことで女三の宮のほうへは仮の訪問すらあそばされなかった。どこでも楽器はしまい込まれて、六条院の人々は皆二条のほうへ集まって行った。このお邸は火の消えたようであった。ただ夫人たちだけが残っているのであるが、これを見れば六条院のはなやかさは紫の女王一人のために現出されていたことのように思われた。
|
【とのみ、惜しみきこえたまふに】- 副助詞「のみ」限定と強調のニュアンスを添える。棄てられる側に立った源氏のエゴが剥き出し。
【思し惑ひつつ】- 接続助詞「つつ」は、同じ動作の繰り返し。
【女どちおはして】- 尊敬語「おはす」があるので六条院の女君たちをさす。接続助詞「て」弱い逆接用法。
【人ひとりの御けはひなりけり】- 「人ひとり」は紫の上をさす。『集成』は「(六条の院のはなやかさも)紫の上お一人がいられたせいであったのだと見える」と訳す。
|
|
第八段 明石女御、看護のため里下り
|
| 6.8.1 |
女御の君も渡りたまひて、もろともに見たてまつり扱ひたまふ。
|
女御の君もお渡りになって、ご一緒にご看病申し上げなさる。
|
女御も二条の院のほうへ来て御父子で看護をされた。
|
|
| 6.8.2 |
|
「普通のお身体でもいらっしゃらないので、物の怪などがとても恐ろしいから、早くお帰りあそばせ」
|
「あなたは普通のお身体でないのですから、物怪の徘徊する私の病室などにはおいでにならないで、早く御所へお帰りなさいね」
|
【ただにもおはしまさで】- 以下「参りたまひね」まで、紫の上の詞。「ただにもおはしまさで」の主語は明石姫君。身重の身体を案じる。接続助詞「で」原因理由の意で続くニュアンス。
|
| 6.8.3 |
|
と、苦しいご気分ながらも申し上げなさる。
若宮が、とてもかわいらしくていらっしゃるのを拝見なさっても、ひどくお泣きになって、
|
と、病苦の中でも夫人は心配して言うのであった。若宮のおかわいらしいのを見ても夫人は非常に泣くのであった。
|
【若宮の、いとうつくしうておはしますを】- 諸説ある。『集成』は「「三の宮」であろう」。『完訳』は「二の宮か。または紫の上の養育する女一の宮か」。『新大系』は「紫上の養育する女一宮か、源氏が音楽の才能を期待した二宮(あるいは三宮)か」と注す。
|
| 6.8.4 |
|
「大きくおなりになるのを、見ることができずになりましょうこと。
きっとお忘れになってしまうでしょうね」
|
「大きくおなりになるのを拝見できないのが悲しい。お忘れになるでしょう」
|
【おとなびたまはむを】- 以下「忘れたまひなむかし」まで、紫の上の詞。
|
| 6.8.5 |
とのたまへば、女御、せきあへず悲しと思したり。
|
とおっしゃるので、女御は、涙を堪えきれず悲しくお思いでいらっしゃった。
|
などと言うのを聞く女御も悲しかった。
|
|
| 6.8.6 |
「ゆゆしく、かくな思しそ。さりともけしうはものしたまはじ。心によりなむ、人はともかくもある。おきて広きうつはものには、幸ひもそれに従ひ、狭き心ある人は、さるべきにて、高き身となりても、ゆたかにゆるべる方は後れ、急なる人は、久しく常ならず、心ぬるくなだらかなる人は、長き例なむ多かりける」 |
「縁起でもない、そのようにお考えなさいますな。
いくら何でも悪いことにはおなりになるまい。
気持ちの持ちようで、人はどのようにでもなるものです。
心の広い人には、幸いもそれに従って多く、狭い心の人には、そうなる運命によって、高貴な身分に生まれても、ゆったりゆとりのある点では劣り、性急な人は、長く持続することはできず、心穏やかでおっとりとした人は、寿命の長い例が多かったものです」
|
「そんな縁起でもないことを思ってはいけませんよ。悪いようでもそんなことにはならないだろうと思う自身の性格で運命も支配していくことになりますからね。狭い心を持つ者は出世をしても寛大な気持ちでいられないものだから失敗する。善良な、おおような人は自然に長命を得ることになる例もたくさんあるのだから、あなたなどにそんな悲しいことは起こってきませんよ」
|
【ゆゆしく、かくな思しそ】- 以下「多かりける」まで、源氏の詞。 【かくな思しそ】-副詞「な」--終助詞「そ」禁止の構文。
【おきて広きうつはものには】- 『河海抄』は「小にして焉(これ)を取れば小さく福(さいはひ)を得。大にして焉を取れば大いに福を得」(孝経、至徳要道篇の注)と指摘する。
|
| 6.8.7 |
|
などと、仏神にも、この方のご性質が又とないほど立派で、罪障の軽い事を詳しくご説明申し上げなさる。
|
などと院はお慰めになるのであった。神仏にも夫人の善良さ、罪の軽さを告げて目に見えぬ加護を祈らせておいでになるのである。
|
【この御心ばせのありがたく】- 紫の上の性質をさす。
【罪軽きさまを申し明らめさせたまふ】- 前世での罪障が軽いことを、詳しく神や仏に言明申し上げて悪病を取り除いてもらうという趣旨。
|
| 6.8.8 |
御修法の阿闍梨たち、夜居などにても、近くさぶらふ限りのやむごとなき僧などは、いとかく思し惑へる御けはひを聞くに、いといみじく心苦しければ、心を起こして祈りきこゆ。すこしよろしきさまに見えたまふ時、五、六日うちまぜつつ、また重りわづらひたまふこと、いつとなくて月日を経たまへば、「なほ、いかにおはすべきにか。よかるまじき御心地にや」と、思し嘆く。 |
御修法の阿闍梨たち、夜居などでも、お側近く伺候する高僧たちは皆、たいそうこんなにまで途方に暮れていらっしゃるご様子を聞くと、何ともおいたわしいので、心を奮い起こしてお祈り申し上げる。
少しよろしいようにお見えになる日が五、六日続いては、再び重くお悩みになること、いつまでということなく続いて、月日をお過ごしになるので、「やはり、どのようにおなりになるのだろうか。
治らないご病気なのかしら」と、お悲しみになる。
|
修法をする阿闍梨たち、夜居の僧などは院の御心痛のはなはだしさを拝見することの心苦しさに一心をこめて皆祈った。少し快い日が間に五、六日あって、また悪いというような容体で、幾月も夫人は病床を離れることができなかったから、やはり助かりがたい命なのかと院はお歎きになった。
|
【思し惑へる御けはひを】- 源氏の態度をさす。
【月日を経たまへば】- 『集成』は「月日を経たまへば」、已然形+接続助詞「ば」、順接の確定条件。『完訳』『新大系』は「月日を経たまふは」、連体形+係助詞「は」、間に「の」が省略された形。強調のニュアンスを添える。
|
| 6.8.9 |
御もののけなど言ひて出で来るもなし。
悩みたまふさま、そこはかと見えず、ただ日に添へて、弱りたまふさまにのみ見ゆれば、いともいとも悲しくいみじく思すに、御心の暇もなげなり。
|
御物の怪などと言って出て来るものもない。
お悩みになるご様子は、どこということも見えず、ただ日がたつにつれて、お弱りになるようにばかりお見えになるので、とてもとても悲しく辛い事とお思いになると、お心の休まる暇もなさそうである。
|
物怪で人に移されて現われるものもない。どこが悪いということもなくて日に添えて夫人は衰弱していくのであったから、院は悲しくばかり思召されて、いっさいほかのことはお思いになれなかった。
|
|
|
第七章 柏木の物語 女三の宮密通の物語
|
|
第一段 柏木、女二の宮と結婚
|
| 7.1.1 |
まことや、衛門督は、中納言になりにきかし。今の御世には、いと親しく思されて、いと時の人なり。身のおぼえまさるにつけても、思ふことのかなはぬ愁はしさを思ひわびて、この宮の御姉の二の宮をなむ得たてまつりてける。下臈の更衣腹におはしましければ、心やすき方まじりて思ひきこえたまへり。 |
そうであったよ、衛門督は、中納言になったのだ。
今上の御治世では、たいそう御信任厚くて、今を時めく人である。
わが身の声望が高まるにつけても、思いが叶わない悲しさを嘆いて、この宮の御姉君の二の宮を御降嫁頂いたのであった。
身分の低い更衣腹でいらっしゃったので、多少軽んじる気持ちもまじってお思い申し上げていらっしゃった。
|
あの衛門督は中納言になっていた。衛門督の官も兼ねたままである。当代の天子の御信任を受けてはなやかな勢力のついてくるにつけても、失恋の苦を忘れかねて、女三の宮の姉君の二の宮と結婚をした。これは低い更衣腹の内親王であったから、心安い気がして格別の尊敬を妻に払う必要もないと思って、院からお引き受けをしたのである。
|
【まことや】- 話題を転じて、以前に途中のままになっていた物語を語り起こす発語。『完訳』は「話題を呼び返す語り口」と注す。
【この宮の御姉の二の宮】- 女三の宮の姉宮、女二の宮。落葉宮と呼ばれる人。
【下臈の更衣】- 一条御息所をさす。
|
| 7.1.2 |
|
人柄も、普通の人に比較すれば、感じはこの上なくよくていらっしゃるが、はじめから思い込んでいた方がやはり深かったのであろう、慰められない姨捨で、人に見咎められない程度に、お世話申し上げていらっしゃった。
|
普通の人に比べてはすぐれた女性ではおありになったが初めから心に沁んだ人に変えるだけの愛情は衛門督に起こらなかった。ただ人目に不都合でないだけの良人の義務を尽くしているに過ぎないのであった。
|
【もとよりしみにし方こそなほ深かりけれ】- 挿入句。係助詞「こそ」--「深かりけれ」已然形、読点。逆接用法。
【慰めがたき姨捨にて】- 『源氏釈』と明融臨模本、付箋「わか心なくさめかねつさらしなやをはすて山にてる月をみて」(古今集雑上、八七八、読人しらず)を指摘。
|
| 7.1.3 |
|
今なお、あの内心の思いを忘れることができず、小侍従という相談相手は、宮の御侍従の乳母の娘だった。
その乳母の姉があの衛門督の君の御乳母だったので、早くから親しくご様子を伺っていて、まだ宮が幼くいらっしゃった時から、とてもお美しくいらっしゃるとか、帝が大事にしていらっしゃるご様子など、お聞き申していて、このような思いもついたのであった。
|
今も以前の恋の続きにその方のことを聞き出す道具に使っている女三の宮の小侍従という女は、宮の侍従の乳母の娘なのである。その乳母の姉が衛門督の乳母であったから、この人は少年のころから宮のお噂を聞いていた。お美しいこと、父帝が溺愛しておいでになることなどを始終聞かされていたのがこの恋の萌芽になったのである。
|
【その乳母の姉ぞ、かの督の君の御乳母なりければ】- 女三の宮の乳母と柏木の乳母は姉妹。女三の宮の乳母子は柏木の乳母の姪。
【いときよらになむおはします】- 『集成』は「はじめは乳母が柏木に向って語る直接話法のような書き方で、すぐ間接話法に転じる」。『完訳』は「「--おはします」は、次の「帝の--たまふ」と並列。美貌とともに、帝最愛の姫宮である点に注意。その恋慕は彼の権勢志向に始まる」と注す。
|
|
第二段 柏木、小侍従を語らう
|
| 7.2.1 |
|
こうして、院も離れていらっしゃる時、人目が少なくひっそりした時を推量して、小侍従を度々迎えては、懸命に相談をもちかける。
|
六条院が病夫人と二条の院へお移りになっていて、ひまであろうことを思って小侍従を衛門督は自邸へ迎えて、熱心に話すのはまたそのことについてであった。
|
【かくて、院も離れおはしますほど】- 紫の上が病気療養のため二条院におり、源氏もそちらにいっているという意。
|
| 7.2.2 |
|
「昔から、このように寿命も縮むほどに思っていることを、このような親しい手づるがあって、ご様子を伝え聞いて、抑え切れない気持ちをお聞き頂いて、心丈夫にしているのに、全然その甲斐がないので、ひどく辛い。
|
「昔から命にもかかわるほどの恋をしていて、しかも都合のよいあなたという手蔓を持っていて、宮様の御様子も聞くことができ、私の煩悶していることも相当にお伝えしてもらっているはずなのだが、少しも見るに足る効果がないから残念でならない。
|
【昔より】- 以下「おぼゆるわざなりけれ」まで、柏木の詞。
【聞こし召させて】- 「聞く」の「聞こし召す」最高敬語。主語は女三の宮。
【頼もしきに】- 接続助詞「に」逆接。
|
| 7.2.3 |
|
院の上でさえ、『あのように大勢の方々と関わっていらっしゃって、他人に負けておいでのようで、独りでお寝みになる夜々が多く、寂しく過ごしていらっしゃるそうです』などと、人が奏上した時にも、少し後悔なさっている御様子で、
|
あなたが恨めしくなるよ。法皇様さえも、宮様が幾人もの妻の中の一人におなりになって、第一の愛妻はほかの方であるというわけで、一人お寝みになる夜が多く、つれづれに暮らしておいでになるのをお聞きになって、御後悔をあそばしたふうで、
|
【院の上だに】- 朱雀院をいう。柏木の会話中での呼称。「すこし悔い思したる」に係る。
【かくあまたにかけかけしく】- 『集成』は「以下、ある人の朱雀院への報告」と注す。源氏の態度についていう。
【人に圧されたまふやう】- 女三の宮のことをいう。
【過ぐしたまふなり】- 「たまふ」終止形+伝聞推定の助動詞「なり」。
【人の奏しける】- 朱雀院への奏上。
|
| 7.2.4 |
|
『同じ降嫁させるなら、臣下で安心な後見を決めるには、誠実にお仕えするような人を決めるべきであった』と、仰せになって、『女二の宮が、かえって安心で、将来長く幸福にお暮らしなさるようだ』
|
結婚をさせるのであったら普通人の忠実な良人を宮のために選ぶべきだったとお言いになり、女二の宮はかえって幸福で将来が頼もしく見えるではないか
|
【同じくは、ただ人の】- 以下「定むべかりけれ」まで、朱雀院の詞引用。
【女二の宮の】- 以下「ものしたまふなること」まで、朱雀院の詞引用。「たまふ」終止形+伝聞推定の助動詞「なり」の連体形。
|
| 7.2.5 |
と、のたまはせけるを伝へ聞きしに。
いとほしくも、口惜しくも、いかが思ひ乱るる。
|
と、仰せになったのを伝え聞いたが。
お気の毒にも、残念にも、どんなに思い悩んだことだろうか。
|
と仰せられたということを私は聞いて、お気の毒にも、残念にも思って煩悶しないではいられないではないか。
|
|
| 7.2.6 |
|
なるほど、同じご姉妹を頂戴したが、それはそれで別のことに思えるのだ」
|
私の宮さんも御姉妹ではあるが、それはそれだけの方としておくのだよ」
|
【げに、同じ御筋とは尋ねきこえしかど】- 同じお血筋の姉妹だが違う人だという。母方の身分の違い(下臈の更衣腹)に基づくのである。
【それはそれとこそおぼゆるわざなりけれ】- 『完訳』は「女二の宮と女三の宮では、実際には姉妹とも思われぬ、の気持」と注す。
|
| 7.2.7 |
と、うちうめきたまへば、小侍従、
|
と、思わず溜息をお漏らしになるので、小侍従は、
|
と衛門督が歎息をしてみせると、小侍従は、
|
|
| 7.2.8 |
「いで、あな、おほけな。それをそれとさし置きたてまつりたまひて、また、いかやうに限りなき御心ならむ」 |
「まあ、何と、大それたことを。
その方を別事とお置き申し上げなさって、さらにまた、なんと途方もないお考えをお持ちなのでしょう」
|
「まあもったいない。それはそれとしてお置きになって、また何をどうしようというのでしょう」
|
【いで、あな、おほけな】- 以下「御心ならむ」まで、小侍従の詞。
|
| 7.2.9 |
と言へば、うちほほ笑みて、
|
と言うと、ちょっとほほ笑んで、
|
ととがめた。衛門督は微笑を見せて、
|
|
| 7.2.10 |
|
「そうではあった。
宮に恐れ多くも求婚申し上げたことは、院にも帝にもお耳にあそばしていらっしゃるのだ。
どうして、そうとして相応しからぬことがあろうと、何かの機会に仰せになったのだ。
いやなに、
|
「まあ世の中のことは皆そうしたもので、表も裏もあるものなのだよ。私が三の宮さんの熱心な求婚者であったことは、法皇様も陛下もよく御承知で、陛下はその時代に十分見込みはありそうだよ、とも仰せられたものなのだが、もう少しの御好意が不足していたわけだと私は思っている」
|
【さこそはありけれ】- 以下「あらましかば」まで、柏木の詞。
【宮にかたじけなく聞こえさせ及びけるさま】- 『集成』は「女三の宮との結婚を、恐れ多いことながら若輩の私がお望み申し上げた次第は。「及ぶ」は、手を届かせる。柏木としては、背伸びして望んだというほどの気持がある」と注す。
【院にも内裏にも】- 朱雀院と今上帝。
【などてかは、さてもさぶらはざらまし】- 朱雀院の詞を間接的引用。反語表現。
【御いたはりあらましかば】- 朱雀院の柏木への恩顧。反実仮想の構文。
|
| 7.2.11 |
など言へば、
|
などと言うと、
|
などと言う。
|
|
| 7.2.12 |
|
「とてもお難しいことですわ。
ご宿運とか言うことがございますのに、それが本となって、あの院が言葉に出して丁重に求婚申し上げなさったのに、同じように張り合ってお妨げ申し上げることがおできになるほどのご威勢であったとお思いでしたか。
最近は、少し貫祿もつき、ご衣装の色も濃くおなりになりましたが」
|
「それはだめですよ。むずかしいことですよ。運命もありますし、六条院様が求婚者になって現われておいでになっては、どの競争者だって勝ち味はないと思いますけれど、あなただけはたいへんな御自信があったのですね。近ごろになりましてこそ御官服の色が濃くおなりになったようでございますがね」
|
【いと難き御ことなりや】- 以下「深くなりたまへれ」まで、小侍従の詞。
【かの院の言出でてねむごろに聞こえたまふに】- 明融臨模本と大島本は「きこえ給に」とある。『集成』『新大系』は底本(明融臨模本・大島本)のままとする。『完本』は諸本に従って「たまはんに」と校訂する。源氏が言葉に出して熱心に求婚したと、小侍従はいう。
【御身のおぼえとや思されし】- 係助詞「や」--過去の助動詞「し」連体形、疑問の意だが、裏に反語的意をこめる。
【御衣の色も深くなりたまへれ】- 中納言は従三位相当官。袍の色は浅紫。
|
| 7.2.13 |
と言へば、いふかひなくはやりかなる口強さに、え言ひ果てたまはで、
|
と言うので、言いようもなく遠慮のない口達者さに、最後までおっしゃり切れないで、
|
こんなふうにまくし立てる小侍従の攻撃にはかなわないことを衛門督は思った。
|
|
| 7.2.14 |
「今はよし。過ぎにし方をば聞こえじや。ただ、かくありがたきものの隙に、気近きほどにて、この心のうちに思ふことの端、すこし聞こえさせつべくたばかりたまへ。おほけなき心は、すべて、よし見たまへ、いと恐ろしければ、思ひ離れてはべり」 |
「今はもうよい。
過ぎたことは申し上げまい。
ただ、このようにめったにない人目のない機会に、お側近くで、わたしの心の中に思っていることを、少しでも申し上げられるようにとり計らって下さい。
大それた考えは、まったく、まあ見て下さい、たいそう恐ろしいので、思ってもおりません」
|
「もう昔のことは言わないよ。ただね、このごろのようなまたとない好機会にせめてお居間の近くへまで行って、私の苦しんでいる心を少しだけお話しさせてくれることを計らってくれないか。もったいない欲念などは見ていてごらん、もういっさい起こさないことにあきらめているのだから、いいだろう」
|
【今はよし】- 以下「思ひ離れてはべり」まで、柏木の詞。
【この心のうちに】- 明融臨模本は「このころ」とある。大島本は「このころ(ころ$<朱墨>心<墨>)」とある。『集成』『新大系』は底本(明融臨模本・大島本)のまますなわち、朱筆と墨筆で「ころ」をミセケチにして「心」と訂正する。『集成』『完本』は諸本に従って「この心」と校訂する。『新大系』はミセケチ訂正に従う。
|
| 7.2.15 |
とのたまへば、
|
とおっしゃると、
|
|
|
| 7.2.16 |
|
「これ以上大それた考えは、他に考えられますか。
何とも恐ろしいことをお考えになったことですよ。
どうして伺ったのでしょう」
|
「それ以上のもったいない欲心がありますかしら。恐ろしい望みをお起こしになったものですね、私は出てまいらなければよかった」
|
【これよりおほけなき心は】- 以下「参りつらむ」まで、小侍従の詞。反語表現。
|
| 7.2.17 |
と、はちふく。
|
と、口を尖らせる。
|
強硬に小侍従は拒む。
|
|
|
第三段 小侍従、手引きを承諾
|
| 7.3.1 |
|
「まあ、何と、聞きにくいことを。
あまり大げさな物の言い方をなさるというものだ。
男女の縁は分からないものだから、女御、后と申しても、事情がって、情を交わすことがないわけではあるまい。
まして、その宮のご様子よ。
思えば、たいそう又となく立派であるが、内情は面白くないことが多くあることだろう。
|
「ひどいことを言うものではないよ。たいそうらしく何を言うのだ。后といっても恋愛問題をかつてお起こしになった人もないわけではないよ。まして宮中のことではなしさ、ほかからは結構なお身の上に見られておいでになっても、口惜しいこともあれでは多かろうじゃないか。
|
【いで、あな、聞きにく】- 以下「なのたまひそよ」まで、柏木の詞。
【世はいと定めなきものを】- 「世」は男女の縁。男と女の縁というのは定めない、という思想。
【あるやうありて、ものしたまふたぐひなくやは】- 反語表現。『集成』は「わけがあって男と情けをかわされるようなお方がないわけでもあるまい」と訳す。
|
| 7.3.2 |
|
院が、大勢のお子様方の中で、他に肩を並べる者がないほど大切にお育て申し上げておいででしたのに、さほど同列とは思えないご夫人方の中にたち混じって、失礼に思うようなことがあるに違いない。
何もかも知っておりますよ。
世の中は無常なものですから、一概に決めつけて、取り付く島もなく、ぶっきらぼうにおっしゃるものではないよ」
|
法皇様からはどのお子様よりも大事がられて御成人なすって、今は同じだけの御身分でない方と同等の一人の夫人で、しかも最愛の方としてはお扱われにならないというくわしいことを私は知っているのだよ。人は無常の世界にいるのだから、君が宮の御幸福をこうして守ろうとしていることが皆むだなことになるかもしれないからね。私に冷酷なことを言っておかないほうがいいよ」
|
【ひとしからぬ際の御方々に】- 六条院の夫人方。
【世の中はいと常なき】- 明融臨模本、朱合点、付箋「恋しなはたか名はたゝし世中のつねなき物といひはなすとも」(古今集恋二、六〇三、深養父)。『源氏釈」が初指摘(第二句「誰が名か惜しき」)。『岷江入楚」は「私此引うたに及ばず」と注す。
|
| 7.3.3 |
とのたまへば、
|
とおっしゃるので、
|
|
|
| 7.3.4 |
「人に落とされたまへる御ありさまとて、めでたき方に改めたまふべきにやははべらむ。これは世の常の御ありさまにもはべらざめり。ただ、御後見なくて漂はしくおはしまさむよりは、親ざまに、と譲りきこえたまひしかば、かたみにさこそ思ひ交はしきこえさせたまひためれ。あいなき御落としめ言になむ」 |
「他の人から負かされていらっしゃるご境遇だからと言って、今さら別の結構な縁組をなさるというわけにも行きますまい。
このご結婚は世間一般の結婚ではございませんでしょう。
ただ、ご後見がなくて頼りなくお暮らしになるよりは、親代わりになって頂こう、というお譲り申し上げなさったご結婚なので、お互いにそのように思い合っていらっしゃるようです。
つまらない悪口をおっしゃるものです」
|
「人ほど大事がられない奥様だとお言いになって、それをあなたの力でよくしていただけるというのですか。六条院様と宮様は普通の夫婦というのでもありませんよ。保護者もなく一人でおいでになりますよりはという思召しで親代わりにお頼みになったのですもの。院がお引き受けになりましたのもその気持ちでなすったことですもの、つまらないことを言って、結局は宮様を悪くあなたはおっしゃるのですね」
|
【人に落とされたまへる】- 以下「御落としめ言になむ」まで、小侍従の詞。
【改めたまふべきにやははべらむ】- 反語表現。
|
| 7.3.5 |
と、果て果ては腹立つを、よろづに言ひこしらへて、
|
と、しまいには腹を立てるが、いろいろと言いなだめて、
|
ついには腹をたててしまった小侍従の機嫌を衛門督はとっていた。
|
|
| 7.3.6 |
|
「本当は、そのように世に又とないご様子を日頃拝見していらっしゃるお方に、人数でもない見すぼらしい姿を、気を許して御覧に入れようとは、まったく考えていないことです。
ただ一言、物越しに申し上げたいだけで、どれほどのご迷惑になることがありましょう。
神仏にも思っていることを申し上げるのは、罪になることでしょうか」
|
「ほんとうのことを言えば、あのまれな美貌の六条院様を良人にお持ちになる宮様に、お目にかかって自身が好意を持たれようとは考えても何もいないのだよ。ただ一言を物越しに私がお話しするだけのことで、宮様の尊厳をそこねることはないじゃないか。神や仏にでも思っていることを言って咎や罰を受けはしないじゃないか」
|
【まことは】- 以下「罪あるわざかは」まで、柏木の詞。
【数にもあらずあやしきなれ姿を】- 柏木の謙辞。『源氏釈』は「これを見よ人もすさめぬ恋すとて音を泣く虫のなれる姿を」(後撰集恋三、七九四、源重光朝臣)を指摘(第二句「人もとがめぬ」)。『岷江入楚』は「君が門今ぞ過ぎ行く出でて見よ恋する人のなれる姿を」(住吉物語)を指摘。「なれ姿」は歌語的表現。
【御身のやつれ】- 『集成』は「「やつれ」は、身を落すというほどの意」。『完訳』は「宮の御身の疵になるまいの意」と注す。
【神仏】- 仏神(大・横・池) 「柏木」にも明融臨模本と大島本とでは語順を逆にする例がある。
|
| 7.3.7 |
|
と、大変な誓言を繰り返しおっしゃるので、暫くの間は、まったくとんでもないことだと断っていたが、思慮の足りない若い女は、男がこのように命に代えてたいそう熱心にお頼みになるので、断り切れずに、
|
こう言って衛門督は絶対に不浄なことは行なわないという誓いまでも立てて、ひそかに御訪問をするだけの手引きを頼むのを、初めのうちは強硬にあるまじいことであると小侍従は突きはねていたが、もともとあさはかな若い女房であるから、こうまでも思い込むものかと、熱心な頼みに動かされて、
|
【誓言をしつつ】- 副助詞「つつ」同じ動作も繰り返し。
【しばしこそ、いとあるまじきことに言ひ返しけれ】- 挿入句。係結び「こそ」--「けれ」逆接用法。
|
| 7.3.8 |
「もし、さりぬべき隙あらば、たばかりはべらむ。院のおはしまさぬ夜は、御帳のめぐりに人多くさぶらひて、御座のほとりに、さるべき人かならずさぶらひたまへば、いかなる折をかは、隙を見つけはべるべからむ」 |
「もし、適当な機会があったら、手立ていたしましょう。
院がいらっしゃらない夜は、御帳台の回りに女房が大勢仕えていて、お寝みになる所には、しかるべき人が必ず伺候していらっしゃるので、どのような機会に、隙を見つけたらよいのだろう」
|
「もしそんなことによいような隙が見つかりましたら御案内いたしましょう。院がおいでにならぬ晩はお几帳のまわりに女房がたくさんいます。お帳台には必ずだれかが一人お付きしているのですから、どんな時にそうしたよいおりがあるものでしょうかね」
|
【もし、さりぬべき】- 以下「見つけはべらむ」まで、小侍従の詞。柏木の願いを聞きいれ、手引することを約束する。
|
| 7.3.9 |
と、わびつつ参りぬ。
|
と、困りながら帰参した。
|
と困ったように言いながら小侍従は帰って行った。
|
|
|
第四段 小侍従、柏木を導き入れる
|
| 7.4.1 |
|
どうなのか、どうなのかと、毎日催促され困って、適当な機会を見つけ出して、手紙をよこした。
喜びながら、ひどく粗末で目立たない姿でいらっしゃった。
|
どうだろう、どうだろうと毎日のように衛門督から責めて来られる小侍従は困りながらしまいにある隙のある日を見つけて衛門督へ知らせてやった。督は喜びながら目だたぬふうを作って小侍従を訪ねて行った。
|
【極じて】- 明融臨模本は「功」と傍書。『集成』『新大系』は「極じて」。『完訳』は「困じて」と宛てる。
【消息しおこせたり】- 主語は小侍従。
|
| 7.4.2 |
まことに、わが心にもいとけしからぬことなれば、気近く、なかなか思ひ乱るることもまさるべきことまでは、思ひも寄らず、ただ、 |
本当に、自分ながらまことに善くないことなので、お側近くに参って、かえって煩悶が勝ることまでは、考えもしないで、ただ、
|
衛門督自身もこの行動の正しくないことは知っているのであるが、物越しの御様子に触れては物思いがいっそうつのるはずの明日までは考えずに、ただ
|
【気近く】- 『集成』は「このあたり、柏木の気持を、その心事に即して書いているので、敬語がない」。『完訳』は「柏木の心情に即した文脈ながら、語り手が、恋ゆえの想外の事態の出来を想像」と注す。
|
| 7.4.3 |
「いとほのかに御衣のつまばかりを見たてまつりし春の夕の、飽かず世とともに思ひ出でられたまふ御ありさまを、すこし気近くて見たてまつり、思ふことをも聞こえ知らせては、一行の御返りなどもや見せたまふ、あはれとや思し知る」 |
「ほんの微かにお召し物の端だけを拝見した春の夕方が、いつまでも思い出されなさるご様子を、もう少しお側近くで拝見し、思っている気持ちをもお聞かせ申し上げたら、ほんの一くだりほどのお返事だけでも下さりはしまいか、かわいそういと思っては下さらないだろうか」
|
ほのかに宮のお召し物の褄先の重なりを見るにすぎなかったかつての春の夕べばかりを幻に見る心を慰めるためには、接近して行って自身の胸中をお伝えして、それからは一行の文のお返事を得ることにもなればというほどの考えで、宮が憐んでくださるかもしれぬ
|
【聞こえ知らせては】- 「は」について、『集成』は係助詞「は」、「自分の気持もお話し申し上げたら」。『完訳』は接続助詞「ば」仮定条件の意、「この意中をもお打ち明け申し上げたならば」と訳す。
|
| 7.4.4 |
とぞ思ひける。
|
と思うのであった。
|
というはかない希望をいだいている衛門督でしかなかった。
|
|
| 7.4.5 |
|
四月十日過ぎのことである。
御禊が明日だと言って、斎院に差し上げなさる女房を十二人、特別に上臈ではない若い女房、女の童など、それぞれ裁縫をしたり、化粧などをしいしい、見物をしようと準備するのも、それぞれに忙しそうで、御前の方がひっそりとして、人が多くない時であった。
|
これは四月十幾日のことである。明日は賀茂の斎院の御禊のある日で、御姉妹の斎院のために儀装車に乗せてお出しになる十二人の女房があって、その選にあたった若い女房とか、童女とかが、縫い物をしたり、化粧をしたりしている一方では、自身らどうしで明日の見物に出ようとする者もあって、仕度に大騒ぎをしていて、宮のお居間のほうにいる女房の少ない時で、
|
【四月十余日ばかりのことなり。御禊明日とて】- 賀茂祭(四月中酉の日)の前の御禊、吉日を選んで行う。
【斎院にたてまつりたまふ女房十二人】- 女三の宮方から賀茂祭の奉仕のために女房を十二人差し出した。後文から上臈の女房と推量される。
【ことに上臈にはあらぬ若き人、童女など】- 祭の奉仕には関係ない中臈の女房や若い女房そして童女ら、祭見物する側の人たち。
|
| 7.4.6 |
|
側近くに仕えている按察の君も、時々通って来る源中将が、無理やり呼び出させたので、下がっている間に、ただこの小侍従だけが、お側近くには伺候しているのであった。
ちょうど良い機会だと思って、そっと御帳台の東面の御座所の端に座らせた。
そんなにまですべきことであろうか。
|
おそばにいるはずの按察使の君も時々通って来る源中将が無理に部屋のほうへ呼び寄せたので、この小侍従だけがお付きしているのであった。よいおりであると思って、静かに小侍従はお帳台の中の東の端へ衛門督の席を作ってやった。これは乱暴な計らいである。
|
【按察使の君も、時々通ふ源中将、責めて呼び出ださせければ】- 女三の宮の側近の女房に通ってくる源中将。源中将は系図不詳の人だが、若い中将といえば、出世コースにある人。
【下りたる間に】- 局に下がっている間に。
【さまでもあるべきことなりやは】- 『一葉抄』は「双紙詞也」と指摘。『集成』は「小侍従の軽率さを批判する草子地」「そんな所にまで引き入れてよいものだろうか」。『完訳』は「小侍従への語り手の評言」「じっさいそんなことまですべきだったのだろうか」と注す。
|
|
第五段 柏木、女三の宮をかき抱く
|
| 7.5.1 |
|
宮は、無心にお寝みになっていらっしゃったが、近くに男性の感じがするので、院がいらっしゃったとお思いになったが、かしこまった態度で、浜床の下に抱いてお下ろし申したので、魔物に襲われたのかと、やっとの思いで目を見開きなさると、違う人なのであった。
|
宮は何心もなく寝ておいでになったのであるが、男が近づいて来た気配をお感じになって、院がおいでになったのかとお思いになると、その男はかしこまった様子を見せて、帳台の床の上から宮を下へ抱きおろそうとしたから、夢の中でものに襲われているのかとお思いになって、しいてその者を見ようとあそばすと、それは男であるが院とは違った男であった。
|
【うちかしこまりたるけしき見せて】- 柏木の態度。
【床の下に抱き下ろしたてまつるに】- 御帳台の浜床の下に。『河海抄』によれば、浜床の高さは三尺という。また『類聚雑要抄』には一尺あるいは九寸の例が見えるという。
【せめて見上げたまへれば】- 『集成』は「見上げ」。『完訳』は「見開け」と宛てる。
|
|
 |
| 7.5.2 |
|
妙なわけも分からないことを申し上げるではないか。
驚いて恐ろしくなって、女房を呼ぶが、近くに控えていないので、聞きつけて参上する者もいない。
震えていらっしゃる様子、水のように汗が流れて、何もお考えになれない様子、とてもいじらしく可憐な感じである。
|
これまで聞いたこともおありにならぬような話を、その男はくどくどと語った。宮は気味悪くお思いになって、女房をお呼びになったが、お居間にはだれもいなかったからお声を聞きつけて寄って来る者もない。宮はお慄い出しになって、水のような冷たい汗もお身体に流しておいでになる。失心したようなこの姿が非常に御可憐であった。
|
【あやしく聞きも知らぬことどもをぞ聞こゆるや】- 語り手の挿入句。『完訳』は「宮の、柏木への反応に即した叙述。「聞こゆる」の主語は柏木」と注す。
|
| 7.5.3 |
|
「人数の者ではありませんが、まことにこんなにまでも軽蔑されるべき身の上ではないと、存ぜずにはいられません。
|
「私はつまらぬ者ですが、それほどお憎まれするのが至当だとは思われません。
|
【数ならねど】- 以下「心もさらにはべるまじ」まで、柏木の詞。
【思うたまへられずなむ】- 「たまへ」謙譲の補助動詞、未然形。「られ」自発の助動詞、未然形。「ず」打消の助動詞、終止形。「なむ」係助詞、下に「ある」などの語句が省略されて、強調と余意のニュアンス。--と存ぜずにはいられない、の意。
|
| 7.5.4 |
|
昔から身分不相応の思いがございましたが、一途に秘めたままにしておきましたら、心の中に朽ちて過ぎてしまったでしょうが、かえって、少し願いを申し上げさせていただいたところ、院におかせられても御承知おきあそばされましたが、まったく問題にならないように仰せにはならなかったので、望みを繋ぎ始めまして、身分が一段劣っていたがために、誰よりも深くお慕いしていた気持ちを無駄なものにしてしまったことと、残念に思うようになりました気持ちが、すべて今では取り返しのつかないことと思い返しはいたしますが、どれほど深く取りついてしまったことなのか、年月と共に、残念にも、辛いとも、気味悪くも、悲しくも、いろいろと深く思いがつのることに、堪えかねて、このように大それた振る舞いをお目にかけてしまいましたのも、一方では、まことに思慮浅く恥ずかしいので、これ以上大それた罪を重ねようという気持ちはまったくございません」
|
昔からもったいない恋を私はいだいておりましたが、結局そのままにしておけば闇の中で始末もできたのですが、あなた様をお望み申すことを発言いたしましたために、院のお耳にはいり、その際はもってのほかのこととも院は仰せられませんでした。それも私の地位の低さにあなた様を他へお渡しする結果になりました時、私の心に受けました打撃はどんなに大きかったでしょう。もうただ今になってはかいのないことを知っておりまして、こうした行動に出ますことは慎んでいたのですが、どれほどこの失恋の悲しみは私の心に深く食い入っていたのか、年月がたてばたつほど口惜しく恨めしい思いがつのっていくばかりで、恐ろしいことも考えるようになりました。またあなた様を思う心もそれとともに深くなるばかりでございました。私はもう感情を抑制することができなくなりまして、こんな恥ずかしい姿であるまじい所へもまいりましたが、一方では非常に思いやりのないことを自責しているのですから、これ以上の無礼はいたしません」
|
【止みはべなましかば】- 明融臨模本は「はへなましかは」とある。大島本は「侍なましかハ」とある。『集成』は底本のままとする。『新大系』は明融臨模本の読みに従う。『完本』は諸本に従って「はべりなましかば」と校訂する。反実仮想の構文。「過ぎぬべかりけるを」に係る。
【なかなか、漏らしきこえさせて】- 主語は柏木。女三の宮への求婚を願い申し上げたことをいう。「きこえさす」は「きこゆ」よりも一段と敬意の深い謙譲語。
【院にも聞こし召されにしを】- 朱雀院も承知していたことをいう。「聞こし召す」は「聞く」の最高敬語。
【のたまはせざりけるに】- 「のたまはす」は「言ふ」の最高敬語。
【身の数ならぬひときはに】- 身分が源氏より劣っていたことをいう。
【動かしはべりにし心なむ】- 『集成』は「無念に思うようになりました気持が」。『完訳』は「その口惜しさを静めることのできません一念が」と訳す。
|
| 7.5.5 |
と言ひもてゆくに、この人なりけりと思すに、いとめざましく恐ろしくて、つゆいらへもしたまはず。
|
と言い続けるうちに、この人だったのだとお分りになると、まことに失礼な恐ろしいことに思われて、何もお返事なさらない。
|
こんな言葉をお聞きになることによって、宮は衛門督であることをお悟りになった。非常に不愉快にお感じにもなったし、怖ろしくもまた思召されもして少しのお返辞もあそばさない。
|
|
| 7.5.6 |
「いとことわりなれど、世に例なきことにもはべらぬを、めづらかに情けなき御心ばへならば、いと心憂くて、なかなかひたぶるなる心もこそつきはべれ、あはれとだにのたまはせば、それをうけたまはりてまかでなむ」 |
「まことにごもっともなことですが、世間に例のないことではございませんのに、又とないほどな無情なご仕打ちならば、まことに残念で、かえって向こう見ずな気持ちも起こりましょうから、せめて不憫な者よとだけでもおっしゃって下されば、その言葉を承って退出しましょう」
|
「あなた様がこうした冷ややかなお扱いをなさいますのはごもっともですが、しかしこんなことは世間に例のないことではないのでございますよ。あまりに御同情の欠けたふうをお見せになれば、私は情けなさに取り乱してどんなことをするかもしれません。かわいそうだとだけ言ってください。そのお言葉を聞いて私は立ち去ります」
|
【いとことわりなれど】- 以下「たまはりてまかでなむ」まで、柏木の詞。女三の宮を安心させ脅し懇願する。
【心もこそつきはべれ】- 「もこそ」係助詞の連語。--しては大変だ、という懸念の構文。
|
| 7.5.7 |
と、よろづに聞こえたまふ。
|
と、さまざまに申し上げなさる。
|
とも、手を変え品を変え宮のお心を動かそうとして説く衛門督であった。
|
|
|
第六段 柏木、猫の夢を見る
|
| 7.6.1 |
よその思ひやりはいつくしく、もの馴れて見えたてまつらむも恥づかしく推し量られたまふに、「ただかばかり思ひつめたる片端聞こえ知らせて、なかなかかけかけしきことはなくて止みなむ」と思ひしかど、いとさばかり気高う恥づかしげにはあらで、なつかしくらうたげに、やはやはとのみ見えたまふ御けはひの、あてにいみじくおぼゆることぞ、人に似させたまはざりける。 |
はたから想像すると威厳があって、馴れ馴れしくお逢い申し上げるのもこちらが気が引けるように思われるようなお方なので、「ただこのように思い詰めているほんの一部を申し上げて、なまじ色めいた振る舞いはしないでおこう」と思っていたが、実際それほど気品高く恥ずかしくなるような様子ではなくて、やさしくかわいらしくて、どこまでももの柔らかな感じにお見えになるご様子で、上品で素晴らしく思えることは、誰とも違う感じでいらっしゃるのであった。
|
想像しただけでは非常な尊厳さが御身を包んでいて、目前で恋の言葉などは申し上げられないもののように思われ、熱情の一端だけをお知らせし、その他の無礼を犯すことなどは思いも寄らぬことにしていた督であったにかかわらず、それほど高貴な女性とも思われない、たぐいもない柔らかさと可憐な美しさがすべてであるような方を目に見てからは、衛門督の欲望はおさえられぬものになり、
|
【なつかしくらうたげに、やはやはとのみ見えたまふ御けはひ】- 女三の宮の感じ。「なつかし」「らうたげなり」は桐壺更衣にも「なつかしうらうたげなりしを思し出づるにも」(桐壺)とあった。「やはやは」が女三の宮の特徴。
|
| 7.6.2 |
賢しく思ひ鎮むる心も失せて、「いづちもいづちも率て隠したてまつりて、わが身も世に経るさまならず、跡絶えて止みなばや」とまで思ひ乱れぬ。 |
賢明に自制していた分別も消えて、「どこへなりとも連れて行ってお隠し申して、自分もこの世を捨てて、姿を隠してしまいたい」とまで思い乱れた。
|
どこへでも宮を盗み出して行って夫婦になり、自分もそれとともに世間を捨てよう、世間から捨てられてもよいと思うようになった。
|
【いづちもいづちも】- 「跡絶えて止みなばや」まで、柏木の思念。『伊勢物語』六段、『大和物語』百五十四段、百五十五段に男が女を盗み出すという同じ発想の物語がある。『更級日記』にも、そのような話への憧れが書かれている。
|
| 7.6.3 |
|
ただちょっとまどろんだとも思われない夢の中に、あの手なずけた猫がとてもかわいらしく鳴いてやって来たのを、この宮にお返し申し上げようとして、自分が連れて来たように思われたが、どうしてお返し申し上げようとしたのだろうと思っているうちに、目が覚めて、どうしてあんな夢を見たのだろう、と思う。
|
少し眠ったかと思うと衛門督は夢に自分の愛している猫の鳴いている声を聞いた。それは宮へお返ししようと思ってつれて来ていたのであったことを思い出して、よけいなことをしたものだと思った時に目がさめた。この時にはじめて衛門督は自身の行為を悟ったのである。
|
【ただいささかまどろむともなき夢に】- 情交の最中の夢。『集成』は「この前後、宮との間に密通のことがあったことを暗示する」。『完訳』は「情交の象徴的表現」と注す。
【この手馴らしし猫の】- 以下、夢の中の描写。柏木が夢の中で不思議に思いながら見た夢という描写。『細流抄』は「懐妊の事也」。『岷江入楚』は「獣を夢みるは懐胎の相なり」と指摘する。当時の俗信。
【何しに奉りつらむと思ふほどに】- 夢の中の自分の行動をどうしてそういうことをするのだろうと、不審不思議に思いながらその夢を見ている。
【いかに見えつるならむ】- 夢から覚めて後の柏木の反省。
|
| 7.6.4 |
|
宮は、あまりにも意外なことで、現実のことともお思いになれないので、胸がふさがる思いで、途方に暮れていらっしゃるのを、
|
が宮はあさましい過失をして罪に堕ちたことで悲しみにおぼれておいでになるのを見て、
|
【思しおぼほるるを】- 「を」接続助詞。『集成』は「悲しみに沈んでいられるのに」。『完訳』は「正気もなくいらっしゃるが」と訳す。
|
| 7.6.5 |
「なほ、かく逃れぬ御宿世の、浅からざりけると思ほしなせ。みづからの心ながらも、うつし心にはあらずなむ、おぼえはべる」 |
「やはり、このように逃れられないご宿縁が、浅くなかったのだとお思い下さい。
自分ながらも、分別心をなくしたように、思われます」
|
「こうなりましたことによりましても、前生の縁がどんなに深かったかを悟ってくださいませ。私の犯した罪ですが、私自身も知らぬ力がさせたのです」
|
【なほ、かく】- 以下「おぼえはべる」まで、柏木の詞。引用句なし。
|
| 7.6.6 |
かのおぼえなかりし御簾のつまを、猫の綱引きたりし夕べのことも聞こえ出でたり。
|
あの身に覚えのなかった御簾の端を、猫の綱が引いた夕方のこともお話し申し上げた。
|
不意に猫が端を引き上げた御簾の中に宮のおいでになった春の夕べのことも衛門督は言い出した。
|
|
| 7.6.7 |
|
「なるほど、そうであったことなのか」
|
そんなことがこの悲しい罪に堕ちる因をなしたのか
|
【げに、さはたありけむよ】- 女三の宮の心中。
|
| 7.6.8 |
|
と、残念に、前世からの宿縁が辛い御身の上なのであった。
「院にも、今はどうしてお目にかかることができようか」と、悲しく心細くて、まるで子供のようにお泣きになるのを、まことに恐れ多く、いとしく拝見して、相手のお涙までを拭う袖は、ますます露けさがまさるばかりである。
|
と思召すと、宮は御自身の運命を悲しくばかり思召されるのであった。もう六条院にはお目にかかれないことをしてしまった自分であるとお思いになることは、非常に悲しく心細くて、子供らしくお泣きになるのを、もったいなくも憐れにも思って、自分の悲しみと同時に恋人の悲しむのを見るのは堪えがたい気のする督であった。
|
【契り心憂き御身なりけり】- 『一葉抄』は「双紙の詞也」と指摘。『全集』は「柏木のいう「のがれぬ御宿世」関係づけて、女三の宮のありようを評した草子地」。『集成』は「女三の宮の気持を、地の文で代弁した筆致」と注す。
【院にも、今はいかでかは見えたてまつらむ】- 女三の宮の心中。反語表現。
【人の御涙をさへ拭ふ袖は】- 副助詞「さへ」添加の意。自分の涙を拭う上に宮の涙までを拭う袖は、の意。
|
|
第七段 きぬぎぬの別れ
|
| 7.7.1 |
明けゆくけしきなるに、出でむ方なく、なかなかなり。 |
夜が明けてゆく様子であるが、帰って行く気にもなれず、かえって逢わないほうがましであったほどである。
|
夜が明けていきそうなのであるが、帰って行けそうにも男は思われない。
|
【なかなかなり】- 語り手の評言。『集成』は「柏木の気持を述べたもの」。『完訳』は「前の語り手の想像「なかなか思ひ乱ることもまさるべきことまでは思ひもよらず」どおり、逆の事態に陥った」と注す。
|
| 7.7.2 |
|
「いったい、
どうしたらよいのでしょう。ひどくお憎みになっていらっしゃるので、再びお話し申し上げることも難しいでしょうが、ただ一言だけで
|
「どうすればよいのでしょう。私を非常にお憎みになっていますから、もうこれきり逢ってくださらないことも想像されますが、ただ一言を聞かせてくださいませんか」
|
【いかがはしはべるべき】- 以下「御声を聞かせたまへ」まで、柏木の詞。宮の「あはれ」の一言を所望。
【ありがたきを】- 接続助詞「を」弱い順接の意。間投助詞「を」の詠嘆のニュアンスも添う。
|
| 7.7.3 |
と、よろづに聞こえ悩ますも、うるさくわびしくて、もののさらに言はれたまはねば、
|
と、さまざまに申し上げて困らせるのも、煩わしく情けなくて、何もまったくおしゃれないので、
|
宮はいろいろとこの男からお言われになるのもうるさく、苦しくて、ものなどは言おうとしてもお口へ出ない。
|
|
| 7.7.4 |
|
「しまいには、薄気味悪くさえなってしまいました。
他に、
|
「何だか気味が悪くさえなりましたよ。こんな間柄というものがあるでしょうか」
|
【果て果ては】- 以下「かかるやうはあらじ」まで、柏木の詞。末摘花の無口が想起される。
|
| 7.7.5 |
と、いと憂しと思ひきこえて、
|
と、まことに辛いとお思い申し上げて、
|
男は恨めしいふうである。
|
|
| 7.7.6 |
|
「それでは生きていても無用のようですね。
いっそ死んでしまいましょう。
生きていたいからこそ、こうしてお逢いもしたのです。
今晩限りの命と思うとたいそう辛うございます。
少しでもお心を開いて下さるならば、それを引き換えにして命を捨てもしましょうが」
|
「私のお願いすることはだめなのでしょう。私は自殺してもいい気にもとからなっているのですが、やはりあなたに心が残って生きていましたものの、もうこれで今夜限りで死ぬ命になったかと思いますと、多少の悲しみはございますよ。少しでも私を愛してくださるお心ができましたら、これに命を代えるのだと満足して死ねます」
|
【さらば不用なめり】- 以下「捨てはべりなまし」まで、柏木の詞。明融臨模本「不用」の傍書がある。『集成』は「あなたの気持を得ることはできないのですね、という気持」と注す。
【身をいたづらに】- 明融臨模本、朱合点あり。『河海抄』は「夏虫の身をいたづらになすことも一つ思ひによりてなりけり」(古今集恋一、五四四、読人しらず)を引く。しかし『岷江入楚』が「不及此歌」と批判して、現行の注釈書では引歌として指摘されない。
【それに代へつるにても捨てはべりなまし】- 反実仮想の構文。『集成』は「その代りということで命を捨てても何の惜しいこともありません」。『完訳』は「そのお情けとひきかえに命を捨ててしまうこともできましょうに」と訳す。
|
| 7.7.7 |
|
と言って、抱いて外へ出るので、しまいにはどうするのだろうと、呆然としていらっしゃる。
|
と言って、衛門督は宮をお抱きして帳台を出た。
|
【かき抱きて出づるに】- 柏木が女三の宮を抱いて御帳台の浜床の下から端の方へ出る。
【果てはいかにしつるぞ】- 宮の心中。
|
| 7.7.8 |
|
隅の間の屏風を広げて、妻戸を押し開けると、渡殿の南の戸の、昨夜入った所がまだ開いたままになっているが、まだ夜明け前の暗いころなのであろう、ちらっと拝見しようとの気があるので、格子を静かに引き上げて、
|
隅の室の屏風を引き拡げ蔭を作っておいて、妻戸をあけると、渡殿の南の戸がまだ昨夜はいった時のままにあいてあるのを見つけ、渡殿の一室へ宮をおおろしした。まだ外は夜明け前のうす闇であったが、ほのかにお顔を見ようとする心で、静かに格子をあげた。
|
【隅の間の屏風をひき広げて】- 寝殿の西側の西南の隅の柱と柱の間に屏風を広げる。人目を避けるため。
【戸を押し開けたれば】- 寝殿の西南の隅の妻戸。外の光で宮の顔をみるため。
【まだ明けぐれのほどなるべし】- 語り手の挿入句。
|
| 7.7.9 |
|
「このように、まことに辛い無情なお仕打ちなので、正気も消え失せてしまいました。
少しでも気持ちを落ち着けるようにとお思いならば、せめて一言かわいそうにとおっしゃって下さい」
|
「あまりにあなたが冷淡でいらっしゃるために、私の常識というものはすっかりなくされてしまいました。少し落ち着かせてやろうと思召すのでしたら、かわいそうだとだけのお言葉をかけてください」
|
【かう、いとつらき御心に】- 以下「あはれとだにのたまはせよ」まで、柏木の詞。
|
| 7.7.10 |
と、脅しきこゆるを、いとめづらかなりと思して物も言はむとしたまへど、わななかれて、いと若々しき御さまなり。 |
と、脅して申し上げると、とんでもないとお思いになって、何かおっしゃろうとなさったが、震えるばかりで、ほんとうに子供っぽいご様子である。
|
衛門督が威嚇するように言うのを、宮は無礼だとお思いになって、何かとがめる言葉を口から出したく思召したが、ただ慄えられるばかりで、どこまでも少女らしいお姿と見えた。
|
【いとめづらかなり】- 女三の宮の心中。『集成』は「何ということを言う人かと」。『完訳』は「なんと無体なことをと」と訳す。
|
| 7.7.11 |
ただ明けに明けゆくに、いと心あわたたしくて、
|
ただ夜が明けて行くので、とても気が急かれて、
|
ずんずん明るくなっていく。あわただしい気になっていながら、男は、
|
|
| 7.7.12 |
|
「しみじみとした夢語りも申し上げたいのですが、このようにお憎みになっていらっしゃるので。
そうは言っても、やがてお思い当たりなさることもございましょう」
|
「理由のありそうな夢の話も申し上げたかったのですけれど、あくまで私をお憎みになりますのもお恨めしくてよしますが、どんなに深い因縁のある二人であるかをお悟りになることもあなたにあるでしょう」
|
【あはれなる夢語りも】- 以下「思し合はすることもはべりなむ」まで、柏木の詞。猫の夢をさす。
【今思し合はすることもはべりなむ】- 懐妊の事実となって知られよう、という意。「な」完了の助動詞、確述。「む」推量の助動詞、推量。きっと--するだろう、という気持ちを込めたニュアンス。
|
| 7.7.13 |
|
と言って、気ぜわしく出て行く明けぐれ、秋の空よりも物思いをさせるのである。
|
と言って出て行こうとする男の気持ちに、この初夏の朝も秋のもの悲しさに過ぎたものが覚えられた。
|
【秋の空よりも心尽くしなり】- 「木の間より漏り来る月の影見れば心尽くしの秋は来にけり」(古今集秋上、一八四、読人しらず)を踏まえる。『集成』は「柏木の心事を述べたもの」と注す。
|
| 7.7.14 |
|
「起きて帰って行く先も分からない明けぐれに
どこから露がかかって袖が濡れるのでしょう」
|
おきて行く空も知られぬ明けぐれに
いづくの露のかかる袖なり
|
【起きてゆく空も知られぬ明けぐれに--いづくの露のかかる袖なり】- 柏木の贈歌。「起き」と「置き」の掛詞。「置く」と「露」は縁語。「露」は涙を象徴。「空も知られぬ」と「いづくの露」が響き合う。
|
| 7.7.15 |
と、ひき出でて愁へきこゆれば、出でなむとするに、すこし慰めたまひて、
|
と、袖を引き出して訴え申し上げるので、帰って行くのだろうと、少しほっとなさって、
|
宮のお袖を引いて督のこう言った時、宮のお心はいよいよ帰って行きそうな様子に楽になって、
|
|
| 7.7.16 |
|
「明けぐれの空にこの身は消えてしまいたいものです
夢であったと思って済まされるように」
|
あけぐれの空にうき身は消えななん
夢なりけりと見てもやむべく
|
【明けぐれの空に憂き身は消えななむ--夢なりけりと見てもやむべく】- 女三の宮の返歌。「あけぐれ」「空」の語句を受け、また「露」「置く」の語句を「夢」「消え」と返す。『完訳』は「「夢」は柏木のいう夢ともひびくが、源氏・藤壺の密会の贈答歌(若紫)にも発想が類似」と注す。
|
| 7.7.17 |
と、はかなげにのたまふ声の、若くをかしげなるを、聞きさすやうにて出でぬる魂は、まことに身を離れて止まりぬる心地す。 |
と、力弱くおっしゃる声が、若々しくかわいらしいのを、聞きも果てないようにして出てしまった魂は、ほんとうに身を離れて後に残った気がする。
|
とはかなそうにお言いになる声も、若々しく美しいのを聞きさしたままのようにして、出て行く男は魂だけ離れてあとに残るもののような気がした。
|
【出でぬる魂】- 飽かざりし袖の中にや入りにけむ我が魂のなき心地する(古今集雑下-九九二 陸奥)(text35.html 出典23から転載)
|
|
第八段 柏木と女三の宮の罪の恐れ
|
| 7.8.1 |
|
女宮のお側にもお帰りにならないで、大殿へこっそりとおいでになった。
横にはなったが目も合わず、あの見た夢が当たるかどうか難しいことを思うと、あの夢の中の猫の様子が、とても恋しく思い出さずにはいられない。
|
夫人の宮の所へは行かずに、父の太政大臣家へそっと衛門督は来たのであった。夢と言ってよいほどのはかない逢う瀬が、なおありうることとは思えないとともに、夢の中に見た猫の姿も恋しく思い出された。
|
【女宮の御もとにも参うでたまはで、大殿へぞ忍びておはしぬる】- 柏木の正室女二の宮邸へは行かず、父の大殿邸にこっそりと帰る。
【夢のさだかに合はむ】- むばたまの闇の現はさだかなる夢にいくらもまさらざりけり(古今集恋三-六四七 読人知らず)(text35.html 出典24から転載)
|
| 7.8.2 |
|
「それにしても大変な過ちを犯したものだな。
この世に生きて行くことさえ、できなくなってしまった」
|
大きな過失を自分はしてしまったものである。生きていることがまぶしく思われる自分になった
|
【さてもいみじき】- 以下「まばゆくなりぬれ」まで、柏木の心中。罪におののく。
【世にあらむことこそ、まばゆくなりぬれ】- 『集成』は「胸を張ってこの世に生きてゆくこともできなくなってしまった」。『完訳』は「まともな顔をしてこの世に生きてはいられなくなった」と訳す。
|
| 7.8.3 |
と、恐ろしくそら恥づかしき心地して、ありきなどもしたまはず。女の御ためはさらにもいはず、わが心地にもいとあるまじきことといふ中にも、むくつけくおぼゆれば、思ひのままにもえ紛れありかず。 |
と、恐ろしく何となく身もすくむ思いがして、外歩きなどもなさらない。
女のお身の上は言うまでもなく、自分を考えてもまことにけしからぬ事という中でも、恐ろしく思われるので、気ままに出歩くことはとてもできない。
|
と恐ろしく、恥ずかしく思って、督はずっとそのまま家に引きこもっていた。恋人の宮のためにも済まないことであるし、自身としてもやましい罪人になってしまったことは取り返しのつかぬことであると思うと、自由に外へ出て行ってよい自分とは思われなかったのである。
|
【女の御ためは】- 明融臨模本は「ためは」とある。大島本は「御ためは」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「御ためは」と「御」を補訂する。『新大系』は底本(大島本)のままとする。以下、柏木に即した叙述。途中から徐々に間接的叙述から直接的叙述、柏木の心中文的表現になり再び間接的叙述に戻る。
|
| 7.8.4 |
|
帝のお妃との間に間違いを起こして、それが評判になったような時に、これほど苦しい思いをするなら、そのために死ぬことも、苦しくないことだろう。
それほど、ひどい罪に当たらなくても、この院に睨まれ申すことは、まことに恐ろしく目も合わせられない気がする。
|
陛下の寵姫を盗みたてまつるようなことをしても、これほどの熱情で愛している相手であったなら、処罰を快く受けるだけで、このやましさはないはずである。そうした咎は受けないであろうが、六条院が憎悪の目で自分を御覧になることを想像することは非常な恐ろしい、恥ずかしいことであると衛門督は思っていた。
|
【帝の御妻をも取り過ちて】- このあたりから柏木の心中文的様相をおびてくる。
【かばかりおぼえむことゆゑは】- 「おぼゆ」の内容について、『集成』は「これほど不埒なと思われることのためなら」。『完訳』は「今の自分のように苦しい思いを味わわせられるのだったら」と訳す。
【おぼゆまじ】- 主体は柏木。打消推量の助動詞「まじ」意志の打消は、柏木自身のもの。
【恥づかしくおぼゆ】- 柏木の心中を地の文に韜晦させた表現。
|
| 7.8.5 |
限りなき女と聞こゆれど、すこし世づきたる心ばへ混じり、上はゆゑあり子めかしきにも、従はぬ下の心添ひたるこそ、とあることかかることにうちなびき、心交はしたまふたぐひもありけれ、これは深き心もおはせねど、ひたおもむきにもの懼ぢしたまへる御心に、ただ今しも、人の見聞きつけたらむやうに、まばゆく、恥づかしく思さるれば、明かき所にだにえゐざり出でたまはず。いと口惜しき身なりけりと、みづから思し知るべし。 |
この上ない高貴な身分の女性とは申し上げても、少し夫婦馴れした所もあって、表面は優雅でおっとりしていても、心中はそうでもない所があるのは、あれやこれやの男の言葉に靡いて、情けをお交わしなさる例もあるのだが、この方は深い思慮もおありでないが、ひたすら恐がりなさるご性質なので、もう今にも誰かが見つけたり聞きつけたりしたかのように、目も上げられず、後ろめたくお思いなさるので、明るい所へいざり出なさることさえおできになれない。
まことに情けないわが身の上だと、自分自身お分りになるのであろう。
|
貴女と言っても少し蓮葉な心が内にあって、表面が才女らしくもあり、無邪気でもあるような見かけとは違った人は誘惑にもかかりやすく、無理な恋の会合を相手としめし合わせてすることにもなりやすいのであるが、女三の宮は深さもないお心ではあるが、臆病一方な性質から、もう秘密を人に発見されてしまったようにも恐ろしがりもし、恥じもしておいでになって、明るいほうへいざって出ることすらおできにならぬまでになっておいでになって、悲しい運命を負った自分であるともお悟りになったであろうと思われる。
|
【いと口惜しき身なりけり】- 女三の宮の心中。
【と、みづから思し知るべし】- 語り手の挿入句。宮の心中を推測。
|
| 7.8.6 |
|
ご気分がすぐれない、とあったので、大殿はお聞きになって、たいそうお心をお尽くしになるご看病に加えて、またどうしたことかとお驚きあそばして、お渡りになった。
|
宮が御病気のようであるという知らせをお受けになって、六条院は、はなはだしく悲しんでおいでになる夫人の病気のほかに、またそうした心痛すべきことが起こったかと驚いて見舞いにおいでになった
|
【悩ましげになむ】- 源氏のもとに伝えられた使者の詞。
【いみじく御心を尽くしたまふ御事】- 紫の上の看病をさす。
【渡りたまへり】- 二条院から六条院へ。
|
| 7.8.7 |
そこはかと苦しげなることも見えたまはず、いといたく恥ぢらひしめりて、さやかにも見合はせたてまつりたまはぬを、「久しくなりぬる絶え間を恨めしく思すにや」と、いとほしくて、かの御心地のさまなど聞こえたまひて、 |
どこそこと苦しそうな事もお見えにならず、とてもひどく恥ずかしがり沈み込んで、まともにお顔をお合わせ申されないのを、「長くなった絶え間を恨めしくお思いになっていらっしゃるのか」と、お気の毒に思って、あちらのご病状などをお話し申し上げなさって、
|
が、宮は別にどこがお悪いというふうにも見えなかった。ただ非常に恥ずかしそうにして、そしてめいっておいでになった。院のお目を避けるようにばかりして、下を向いておいでになるのを、久しく訪ねなかった自分を恨めしく思っているのであろうと、院のお目にそれが憐れにも、いたいたしいようにも映って、紫夫人の容体などをお話しになり、
|
【かの御心地のさま】- 紫の上の病状をさす。
|
| 7.8.8 |
「今はのとぢめにもこそあれ。今さらにおろかなるさまを見えおかれじとてなむ。いはけなかりしほどより扱ひそめて、見放ちがたければ、かう月ごろよろづを知らぬさまに過ぐしはべるぞ。おのづから、このほど過ぎば、見直したまひてむ」 |
「もう最期かも知れません。
今になって薄情な態度だと思われまいと思いましてね。
幼いころからお世話して来て、放って置けないので、このように幾月も何もかもうち忘れて看病して来たのですよ。
いつか、この時期が過ぎたら、きっとお見直し頂けるでしょう」
|
「もうだめになるのでしょう。最後になって冷淡に思わせてやりたくないと考えるものですから付いていっているのですよ。少女時代から始終そばに置いて世話をした妻ですから、捨てておけない気もして、こんなに幾月もほかのことは放擲したふうで付ききりで看護もしていますが、またその時期が来ればあなたによく思ってもらえる私になるでしょう」
|
【今はのとぢめにもこそあれ】- 以下「見直したまひてむ」まで、源氏の詞。「もこそあれ」係結び。懸念の意。
|
| 7.8.9 |
|
などと申し上げなさる。
このようにお気づきでないのも、お気の毒にも心苦しくもお思いになって、宮は人知れずつい涙が込み上げてくる。
|
などとお言いになるのを、宮は聞いておいでになって、あの罪は気ぶりにもご存じないことを、お気の毒なことのようにも、済まないことのようにもお思いになって、人知れず泣きたい気持ちでおいでになった。
|
【いとほしく心苦しく思されて】- 「れ」自発の助動詞。下文の「おぼさる」の「る」も同じ。『集成』は「申しわけなくつらく」。『完訳』は「宮はおいたわしくも申し訳なくもお思いになって」と訳す。
|
|
第九段 柏木と女二の宮の夫婦仲
|
| 7.9.1 |
督の君は、まして、なかなかなる心地のみまさりて、起き臥し明かし暮らしわびたまふ。祭の日などは、物見に争ひ行く君達かき連れ来て言ひそそのかせど、悩ましげにもてなして、眺め臥したまへり。 |
督の君は、宮以上に、かえって苦しさがまさって、寝ても起きても明けても暮れても日を暮らしかねていらっしゃる。
祭の日などは、見物に先を争って行く公達が連れ立って誘うが、悩ましそうにして物思いに沈んで横になっていらっしゃった。
|
衛門督の恋はあのことがあって以来、ますますつのるばかりで、はげしい煩悶を日夜していた。賀茂祭りの日などは見物に出る公達がおおぜいで来て誘い出そうとするのであったが、病気であるように見せて寝室を出ずに物思いを続けていた。
|
【督の君は、まして】- 柏木。「まして」は女三の宮に比較してそれ以上にの意。
|
| 7.9.2 |
女宮をば、かしこまりおきたるさまにもてなしきこえて、をさをさうちとけても見えたてまつりたまはず、わが方に離れゐて、いとつれづれに心細く眺めゐたまへるに、童べの持たる葵を見たまひて、 |
女宮を、丁重にお扱い申しているが、親しくお逢い申されることもほとんどなさらず、ご自分の部屋に離れて、とても所在なさそうに心細く物思いに耽っていらっしゃるところに、女童が持っている葵を御覧になって、
|
夫人の女二の宮には敬意を払うふうに見せながらも、打ち解けた良人らしい愛は見せないのである。督は夫人の宮のそばでつれづれな時間をつぶしながらも心細く世の中を思っているのであった。童女が持っている葵を見て、
|
【わが方に離れゐて】- 自分の部屋をさす。柏木は宮の居間とは別に自分用の部屋があり、そこにばかりいることをいう。
|
| 7.9.3 |
|
「悔しい事に罪を犯してしまったことよ
神が許した仲ではないのに」
|
悔しくもつみをかしける葵草
|
【悔しくぞ摘み犯しける葵草--神の許せるかざしならぬに】- 柏木の独詠歌。柏木、女三の宮との密通を罪と自覚する。「摘み犯す」と「罪犯す」。「葵」と「逢ふ日」の掛詞。『集成』は「あのお方に無理無体にお逢いするという大それたあやまちを犯して、くやまれることだ、神様が大目に見て下さる--世間に許される--挿頭(葵草)ではないのに」と訳す。
|
| 7.9.4 |
と思ふも、いとなかなかなり。
|
と思うにつけても、まことになまじ逢わないほうがましな思いである。
|
神の許せる挿頭ならぬに
こんな歌が口ずさまれた。後悔とともに恋の炎はますます立ちぼるようなわけである。
|
|
| 7.9.5 |
世の中静かならぬ車の音などを、よそのことに聞きて、人やりならぬつれづれに、暮らしがたくおぼゆ。
|
世間のにぎやかな車の音などを、他人事のように聞いて、我から招いた物思いに、一日が長く思われる。
|
町々から聞こえてくる見物車の音も遠い世界のことのように聞きながら、退屈に苦しんでもいるのであった。
|
|
| 7.9.6 |
|
女宮も、このような様子のつまらなさそうなのがお分かりになるので、どのような事情とはお分かりにならないが、気が引け心外なと思われるにつけ、面白くない思いでいられるのであった。
|
女二の宮も衛門督の態度の誠意のなさをお感じになって、それは何がどうとはおわかりにならないのであるが、御自尊心が傷つけられているようで、物思わしくばかり思召された。
|
【女宮も】- 柏木の正室女二の宮をさす。
【恥づかしくめざましきに、もの思はしくぞ思されける】- 妻として夫に疎んじられ、また皇女として誇りを傷つけられた思い。
|
| 7.9.7 |
女房など、物見に皆出でて、人少なにのどやかなれば、うち眺めて、箏の琴なつかしく弾きまさぐりておはするけはひも、さすがにあてになまめかしけれど、「同じくは今ひと際及ばざりける宿世よ」と、なほおぼゆ。 |
女房などは、見物に皆出かけて、人少なでのんびりしているので、物思いに耽って、箏の琴をやさしく弾くともなしに弾いていらっしゃるご様子も、内親王だけあって高貴で優雅であるが、「同じ皇女を頂くなら、もう一段及ばなかった運命よ」と、今なお思われる。
|
女房などは皆祭りの見物に出て人少なな昼に、寂しそうな表情をあそばして十三絃の琴を、なつかしい音に弾いておいでになる宮は、さすがに高貴な方らしいお美しさと艶な趣は備わってお見えになるのであるが、ただもう少しの運が足りなかったのだと衛門督は自身のことを思っていた。
|
【さすがにあてに】- 『完訳』は「「さすがに--なほ--」と感情の起伏に注意」と注す。
【同じくは】- 以下「宿世よ」まで、柏木の心中。
|
| 7.9.8 |
|
「劣った落葉のような方をどうして娶ったのだろう
同じ院のご姉妹ではあるが」
|
もろかづら落ち葉を何に拾ひけん
名は睦まじき挿頭なれども
|
【もろかづら落葉を何に拾ひけむ--名は睦ましきかざしなれども】- 柏木の独詠歌。「もろかづら」は葵と桂の挿頭、「かざし」は姉妹、女三の宮と二の宮の姉妹をいう。
|
| 7.9.9 |
|
と遊び半分に書いているのは、まこと失礼な蔭口である。
|
こんな歌をむだ書きにしていた。もったいないことである。
|
【書きすさびゐたる、いとなめげなるしりう言なりかし】- 『一葉抄』は「双紙詞」と指摘。『集成』は「女二の宮をずいぶん馬鹿にした陰口というものだ。皇女に対して斟酌を加える意味合いもある草子地」。『完訳』は「柏木の蔑視を、語り手が評す」と注す。
|
|
第八章 紫の上の物語 死と蘇生
|
|
第一段 紫の上、絶命す
|
| 8.1.1 |
大殿の君は、まれまれ渡りたまひて、えふとも立ち帰りたまはず、静心なく思さるるに、
|
大殿の君は、たまたまお渡りになって、すぐにはお帰りになることもできず、落ち着いていらっしゃれないところに、
|
院はまれにお訪ねになった宮の所からすぐに帰ることを気の毒にお思いになり、泊まっておいでになったが、病夫人を気づかわしくばかり思っておいでになる所へ使いが来て、
|
|
| 8.1.2 |
|
「息をお引きとりになりました」
|
急に息が絶えたと知らせた。
|
【絶え入りたまひぬ】- 紫の上の絶命を伝える使者の詞。
|
| 8.1.3 |
とて、人参りたれば、さらに何事も思し分かれず、御心も暮れて渡りたまふ。
道のほどの心もとなきに、げにかの院は、ほとりの大路まで人立ち騒ぎたり。
殿のうち泣きののしるけはひ、いとまがまがし。
我にもあらで入りたまへれば、
|
と言って、使者が参上したので、まったく何を考えることもおできになれず、お心も真暗になってお帰りになる。
その道中気が気でないところ、なるほどあちらの院は、周囲の大路まで人が騷ぎ立っていた。
邸の中の泣きわめいている様子、まことに不吉である。
無我夢中で中にお入りになると、
|
院はいっさいの世界が暗くなったようなお気持ちで二条の院へ帰ってお行きになるのであったが、車の速度さえもどかしく思っておいでになると、二条の院に近い大路はもう立ち騒ぐ人で満たされていた。邸内からは泣き声が多く聞こえて、大きな不祥事のあることは覆いがたく見えた。夢中で家へおはいりになったが、
|
|
| 8.1.4 |
|
「ここのところ数日は、少しよろしいようにお見えになったのですが、急に、このようにおなりになりました」
|
「この二、三日は少しお快いようでございましたのに、にわかに絶息をあそばしたのでございます」
|
【日ごろは、いささか隙見え】- 以下「かくおはします」まで、女房の詞。
|
| 8.1.5 |
とて、さぶらふ限りは、我も後れたてまつらじと、惑ふさまども、限りなし。御修法どもの檀こぼち、僧なども、さるべき限りこそまかでね、ほろほろと騒ぐを見たまふに、「さらば限りにこそは」と思し果つるあさましさに、何事かはたぐひあらむ。 |
と言って、控えている女房たちは皆、自分も後を追おうと、うろうろしている者たちが、数限りない。
いく壇もの御修法の壇を壊して、僧たちも残るべき人は残っているが、ばらばらと立ち騒ぐのを御覧になると、「それではもう最期なのだ」とお思い切りなさるその情けなさに、他にどのような比べるものがあろうか。
|
こんな報告をした女房らが、自分たちも、いっしょに死なせてほしいと泣きむせぶ様子も悲しかった。もう祈祷の壇は壊たれて、僧たちもきわめて親しい人たちだけが残ってもそのほかのは仕事じまいをして出て行くのに忙しいふうを見せている。こうしてもう最愛の妻の命は人力も法力も施しがたい終わりになったのかと、院はたとえようもない悲しみをお覚えになった。
|
【さるべき限りこそまかでね】- 係助詞「こそ」--打消助動詞「ね」已然形、逆接用法。読点で下文に続く。
【思し果つる】- 明融臨模本と大島本は「はへる」とある。『集成』『完本』『新大系』は諸本に従って「はつる」と校訂する。
|
| 8.1.6 |
|
「そうは言っても、物の怪のすることであろう。
まことに、
|
「しかしこれは物怪の所業だろうと思われる。あまりに取り乱して泣くものでない」
|
【さりとも、もののけの】- 以下「な騒ぎそ」まで、源氏の詞。
|
| 8.1.7 |
と鎮めたまひて、いよいよいみじき願どもを立て添へさせたまふ。
すぐれたる験者どもの限り召し集めて、
|
と皆をお静めになって、ますます大層ないくつもの願をお立て加えさせなさる。
すぐれた験者たちをすべて召し集めて、
|
と院は泣く女房たちを制して、またまた幾つかの大願をお立てになった。そしてすぐれた修験の僧をお集めになり、
|
|
| 8.1.8 |
|
「有限なご寿命であるから、この世でのご寿命が終わったとしても、ただ、もう暫く延ばして下さい。
不動尊の御本の誓いがあります。
せめてその日数だけでも、この世にお引き止め申して下さい」
|
「これが定まった命数でも、しばらくその期をゆるめていただきたい、不動尊は人の終わりにしばらく命を返す約束を衆生にしてくだすった。それに自分たちはおすがりする。それだけの命なりとも夫人にお授けください」
|
【限りある御命にて】- 以下「止めたてまつりたまへ」まで、僧侶の詞。
【不動尊の御本の誓ひ】- 『河海抄』は『大般若経』の「定業亦能転」の『不動義軌』を引いて「又正報尽者、能延六月住」を注す。「その日数」とは六ケ月をさす。
|
| 8.1.9 |
と、頭よりまことに黒煙を立てて、いみじき心を起こして加持したてまつる。
院も、
|
と、頭から本当に黒い煙を立てて、大変な熱心さでご加持申し上げる。
院も、
|
こう僧たちは言って、頭から黒煙を立てると言われるとおりの熱誠をこめて祈っていた。院も
|
|
| 8.1.10 |
「ただ、今一度目を見合はせたまへ。いとあへなく限りなりつらむほどをだに、え見ずなりにけることの、悔しく悲しきを」 |
「ただ、もう一度目と目を見合わせて下さい。
まったくあっけなく臨終の時をさえ、会わずじまいであったことが、悔しく悲しいのですよ」
|
互いにただ一目だけ見合わす瞬間が与えられたい、最後の時に見合わせることのできなかった
|
【ただ、今一度】- 以下「悔しく悲しきを」まで、源氏の心中。または独り言。
|
| 8.1.11 |
|
と取り乱している様子は、生き残っていらっしゃることができそうにないのを、拝見する心地は、ただ想像できよう。
大変なご悲痛を、仏も御照覧申されたのであろうか、このいく月もまったく現れなかった物の怪が小さい童に乗り移って、大声でわめくうちに、だんだんと生き返っていらっしゃって、嬉しくも不吉にもお心が騒がずにはいらっしゃれない。
|
残念さ悲しさから長く救われたいと言ってお歎きになる御様子を見ては、とうていこの夫人のあとにお生き残りになることはむずかしかろうと思われて、そのことをまた人々の歎くことも想像するにかたくない。この院の夫人への大きな愛が御仏を動かしたのか、これまで少しも現われてこなかった物怪が、小さい子供に憑って来て、大声を出し始めたのと同時に夫人の呼吸は通ってきた。院はうれしくも思召され、また不安でならぬようにも思召された。
|
【見たてまつる心地ども】- 女房たちの心地。
【ただ推し量るべし】- 『完訳』は「語り手の言辞」と注す。
【仏も見たてまつりたまふにや】- 「にや」は語り手の判断推測の言辞。『完訳』は「以下の物の怪出現の理由を語り手が推測」と注す。
【思し騒がる】- 「る」自発の助動詞。冷静ではいらっしゃれない。
|
|
第二段 六条御息所の死霊出現
|
| 8.2.1 |
いみじく調ぜられて、
|
ひどく調伏されて、
|
物怪は僧たちにおさえられながら言う、
|
|
| 8.2.2 |
|
「他の人は皆去りなさい。
院お一人方のお耳に申し上げたい。
自分をこのいく月も調伏し困らせなさるのが薄情で辛いので、同じことならお知らせしようと思ったが、そうは言っても命が耐えられないほど、身を粉にして悲嘆に暮れていらっしゃるご様子を拝見すると、今でこそ、このようなあさましい姿に変わっているが、昔の愛執が残っていればこそ、このように参上したので、お気の毒な様子を放って置くことができなくて、とうとう現れ出てしまったのです。
決して知られまいと思っていたのに」
|
「皆ここから遠慮をするがよい。院お一人のお耳へ申し上げたいことがある。私の霊を長く法力で苦しめておいでになったのが無情な恨めしいことですから、懲らしめを見せようと思いましたが、さすがに御自身の命も危険なことになるまで悲しまれるのを見ては、今こそ私は物怪であっても、昔の恋が残っているために出て来る私なのですから、あなたの悲しみは見過ごせないで姿を現わしました。私は姿など見せたくなかったのだけれど」
|
【人は皆去りね】- 以下「思ひつるものを」まで、物の怪の詞。
【同じくは思し知らせむと思ひつれど】- 源氏に。「思し知らせむ」という敬語表現。『集成』は「どうせ取り憑いたのなら、思い知らせてさし上げようと思いましたが」「紫の上を絶息させたこと」。『完訳』は「どうせなら殿にこの私のつらさをお知りいただこうと思ったのだけれど」と訳す。
【命も堪ふまじく、身を砕き】- 源氏の紫の上を看病する態度。
【今こそ、かくいみじき身を受けたれ】- 成仏できずに魔界にさまよっていることをいう。
【いにしへの心の残りて】- 生前の心。『集成』は「昔の愛執の思いが残っているので」。『完訳』は「人間の世を生きた昔の心が残っていればこそ」「人間界にあった時の心。源氏への愛執をさす。それが残っているので、成仏できない」と注す。
|
|
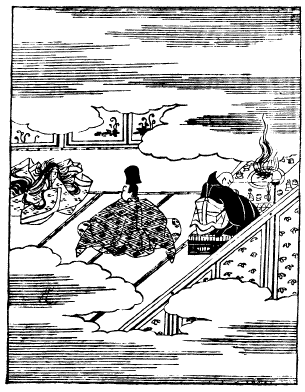 |
| 8.2.3 |
とて、髪を振りかけて泣くけはひ、ただ昔見たまひしもののけのさまと見えたり。あさましく、むくつけしと、思ししみにしことの変はらぬもゆゆしければ、この童女の手をとらへて、引き据ゑて、さま悪しくもせさせたまはず。 |
と言って、髪を振り掛けて泣く様子は、まったく昔御覧になった物の怪の恰好と見えた。
こんなことがこの世にあろうか、恐ろしいことだと、心底お思い込みになったことが相変わらず忌まわしいことなので、この童女の手を捉えて、じっとさせて、体裁の悪いようにはおさせにならない。
|
と物怪は叫んだ。髪を顔に振りかけて泣く様子は、昔一度御覧になった覚えのある物怪であった。その当時と同じ無気味さがお心に湧いてくるのも恐ろしい前兆のようにお思われになって、その子供の手を院はお捉えになって、前へおすわらせになり、あさましい姿はできるだけ人に見させまいとお努めになった。
|
【昔見たまひしもののけ】- 「葵」巻の六条御息所の生霊出現をさす。
|
| 8.2.4 |
「まことにその人か。よからぬ狐などいふなるものの、たぶれたるが、亡き人の面伏なること言ひ出づるもあなるを、たしかなる名のりせよ。また人の知らざらむことの、心にしるく思ひ出でられぬべからむを言へ。さてなむ、いささかにても信ずべき」 |
「本当にあなたか。
良くない狐などと言うもので、気の狂ったのが、亡くなった人の不名誉になることを言い出すということもあると言うから、はっきりと名乗りをせよ。
また誰も知らないようなことで、心にはっきりと思い出されるようなことを言いなさい。
そうすれば、少しは信じもしよう」
|
「ほんとうにその人なのか。悪い狐などが故人を傷つけるためにでたらめを言ってくることがあるから、確かなことを言うがいい。他人の知らぬことで私にだけ合点のゆくことを何か言ってみるがいい。そうすれば少しは信じてもいい」
|
【まことにその人か】- 以下「いささかにても信ずべき」まで、源氏の詞。「その人」は六条御息所をいう。
【たぶれたる】- 明融臨模本は「た(た+は)ふれたる」とある。すなわち「は」を補入するが、後人の筆蹟である。大島本は「たふれたる」とある。『集成』『完本』は底本(明融臨模本)の本行本文に従う。『新大系』は底本(大島本)のままとする。『和名抄』に「狂、太布流。俗云、毛乃久流比」。『名義抄』に「誑、タブロカス」とある。
|
| 8.2.5 |
とのたまへば、ほろほろといたく泣きて、
|
とおっしゃると、ぽろぽろとひどく泣いて、
|
院がこうお言いになると、物怪はほろほろと涙を流しながら、悲しそうに泣いた。
|
|
| 8.2.6 |
|
「わたしはこんな変わりはてた身の上となってしまったが
知らないふりをするあなたは昔のままですね
|
「わが身こそあらぬさまなれそれながら
空おぼれする君は君なり
|
【わが身こそあらぬさまなれそれながら--そらおぼれする君は君なり】- 六条御息所の死霊の歌。
|
| 8.2.7 |
|
とてもひどい方だわ、とてもひどい方だわ」
|
恨めしい、恨めしい」
|
【いとつらし、いとつらし】- 死霊の詞。『完訳』は「「つらし」は相手を恨む意。現身の御息所にはなかった発想。情念のむき出しになった物の怪のゆえんか」と注す。
|
| 8.2.8 |
|
と泣き叫ぶ一方で、そうはいっても恥ずかしがっている様子、昔に変わらず、かえってまことに疎ましい気がし、情けないので、何も言わせまいとお思いになる。
|
と泣き叫びながらもさすがに羞恥を見せるふうが昔の物怪に違う所もなかった。嘘でないことからかえってうとましい気がよけいにして情けなくお思われになるので、ものを多く言わすまいと院はされた。
|
【疎ましく、心憂ければ】- 『集成』は「いやらしく情けないので」。『完訳』は「無気味にも厭わしいので」と訳す。
|
| 8.2.9 |
|
「中宮の御事につけても、大変に嬉しく有り難いことだと、魂が天翔りながら拝見していますが、明幽境を異にしてしまったので、子の身の上までも深く思われないのでしょうか、やはり、自分自身がひどい方だとお思い申し上げた方への愛執が残るのでした。
|
「中宮に尽くしてくださいますことはうれしい、ありがたいこととはあの世からも見ておりますが、あの世界の人になっては子の愛というものを以前ほど深くは感じないのですか、恨めしいとお思いしたあなたへの執着だけがこんなふうにもなって残っています。
|
【中宮の御事にても】- 以下「ことになむありける」まで、六条御息所の死霊の詞。
【みづからつらしと思ひきこえし心の執なむ、止まるものなりける】- わが子の身の上よりも愛人としての源氏のほうに愛執の念がのこった、という。女として母であることよりも妻であることに執着した。
|
| 8.2.10 |
|
その中でも、生きているうちに、人より軽いお扱いをなさってお見捨てになったことよりも、お親しい者どうしのお話の時に、性格が善くない扱いにくい女であったとおっしゃったのが、まことに恨めしくて。
今はもう亡くなってしまったのだからとお許し下さって、他人が悪口を言うのでさえ、打ち消してかばって戴きたいと思うと、その思っただけで、このように恐ろしい身の上なので、このように大変なことになったのです。
|
その恨みの中でも、生きていますころにほかの人よりも軽くお扱いになったことよりも、夫婦のお話の中で私を悪くお言いになったことが私をくやしくさせました。もう私は死んでいるのですから、私が悪くってもあなたはよくとりなして言ってくだすっていいではありませんか。そうお恨みしただけで、こんな身になっていますと大形な表示にもなったのです。
|
【人より落として思し捨てしよりも】- 正妻の葵の上より低く扱われたことをいう。
【思ふどちの御物語のついでに】- 女楽の後に源氏が紫の上に六条御息所のことを語ったことをさす。
【心善からず憎かりしありさまを】- 御息所自身の性格や振る舞いをいう。
【かく所狭きなり】- 『集成』は「こんな大変なことになったのです」「魔界に身を堕した悪霊なので、ほんのちょっとした心のゆらぎでも、紫の上の大病の原因になった、と言う」と注す。
|
| 8.2.11 |
|
この方を、心底憎いと思い申すことはないが、あなたの神仏の加護が強くて、とてもご身辺は遠い感じがして、近づき参ることができず、お声さえもかすかに聞くだけでおります。
|
奥様を深く恨んでいませんが、法の護りが強くて近づけないので反抗してみただけです。あなたのお声もほのかに承ることができましたからもういいのです。
|
【この人を、深く憎しと思ひきこゆることはなけれど】- 紫の上をさす。御息所は紫の上に対しては恨み心はもたないという。
【守り強く、いと御あたり遠き心地して】- 源氏をさす。源氏の神仏の加護が厚く物の怪として近寄りがたいことをいう。
|
| 8.2.12 |
よし、今は、この罪軽むばかりのわざをせさせたまへ。
修法、読経とののしることも、身には苦しくわびしき炎とのみまつはれて、さらに尊きことも聞こえねば、いと悲しくなむ。
|
よし、今はもう、この罪障を軽めることをなさって下さい。
修法や読経の大声を立てることも、わが身には苦しく情けない炎となってまつわりつくばかりで、まったく尊いお経の声も聞こえないので、まことに悲しい気がします。
|
私の罪の軽くなるような方法を講じてください。修法、読経の声は私にとって苦しい焔になってまつわってくるだけです。尊い仏の慈悲の声に接したいのですが、それを聞くことのできないのは悲しゅうございます。
|
|
| 8.2.13 |
|
中宮にも、この旨をお伝え申し上げて下さい。
決して御宮仕え中に、他人と争ったり嫉妬したりする気をお持ちになってなりません。
斎宮でいらっしゃったころのご罪障を軽くするような功徳のことを、必ずなさるように。
ほんとうに残念なことでしたよ」
|
中宮にもこのことをお話しくださいませ。後宮の生活をするうちに人を嫉妬するような心を起こしてはならない、斎宮をお勤めになった間の罪を御仏に許していただけるだけの善根を必ずなさい、あの世で苦しむことをよく考えなければならないとね」
|
【御罪軽むべからむ】- 明融臨模本は「かるむ」とある。大島本は「かろむ」とある。『集成』『新大系』はそれぞれ底本(明融臨模本・大島本)のまま『かるむ」「かろむ」とする。『完本』は諸本に従って」かろむ」とす校訂する。
【いと悔しきことになむありける】- 斎宮となって仏道から離れた生活をしていたことを悔やまれることだ、という。当時の仏教思想の篤さを暗示する。
|
| 8.2.14 |
など、言ひ続くれど、もののけに向かひて物語したまはむも、かたはらいたければ、封じ込めて、上をば、また異方に、忍びて渡したてまつりたまふ。
|
などと、言い続けるが、物の怪に向かってお話なさることも、気が引けることなので、物の怪を封じ込めて、紫の上を、別の部屋に、こっそりお移し申し上げなさる。
|
などと言うが、物怪に向かってお話しになることもきまり悪くお思いになって、物怪がまた出ぬように法の力で封じこめておいて、病夫人を他の室へお移しになった。
|
|
|
第三段 紫の上、死去の噂流れる
|
| 8.3.1 |
かく亡せたまひにけりといふこと、世の中に満ちて、御弔らひに聞こえたまふ人びとあるを、いとゆゆしく思す。今日の帰さ見に出でたまひける上達部など、帰りたまふ道に、かく人の申せば、 |
このようにお亡くなりになったという噂が、世間に広がって、ご弔問に参上なさる方々がいるのを、まことに縁起でもなくお思いになる。
今日の祭の翌日の行列の見物にお出かけになった上達部などは、お帰りになる道すがら、このように人が申すので、
|
紫夫人が死んだという噂がもう世間に伝わって弔詞を述べに来る人たちのあるのを不吉なことに院はお思いになった。今日の祭りの帰りの行列を見物に出ていた高官たちが、帰宅する途中でその噂を聞いて、
|
【今日の帰さ見に】- 賀茂祭の翌日の上賀茂の神館に一泊した斎王の紫野に帰る行列を見るために、の意。
|
| 8.3.2 |
「いといみじきことにもあるかな。生けるかひありつる幸ひ人の、光失ふ日にて、雨はそほ降るなりけり」 |
「大変な事になったな。
この世の生甲斐を満喫した幸福な方が、光を失う日なので、雨がしょぼしょぼ降るのだな」
|
「たいへんなことだ。生きがいのあった幸福な女性が光を隠される日だから小雨も降り出したのだ」
|
【いといみじき】- 以下「雨はそほ降るなりけり」まで、上達部の詞。
【そほ降る】- 『万葉集』に「曾保零」。『日葡辞書補遺』に「ソヲフル」とある。しかし『易林本節用集』には「微降雨ソボフルアメ添雨ソボフルアメ」とある。古くは第二音節は清音であったらしいといわれる。
|
| 8.3.3 |
と、うちつけ言したまふ人もあり。
また、
|
と、思いつきの発言をなさる方もいる。
また、
|
などと解釈を下す人もあった。また、
|
|
| 8.3.4 |
|
「このようにすべてに満ち足りた方は、必ず寿命も長くはないことです。
『何を桜に』と言う古歌もあることよ。
このような方が、ますます世に長生きをして、この世の楽しみの限りを尽くしたら、はたの人が迷惑するだろう。
これでやっと、二品の宮は、本来のご寵愛をお受けになられることだろう。
お気の毒に圧倒されていたご寵愛であったから」
|
「あまりに何もかもそろった人というものは短命なものなのだ。『何をさくらに』(待てといふに散らでしとまるものならば何を桜に思ひまさまし)という歌のように、そうした人が長生きしておれば、一方で不幸に甘んじていなければならぬ人も多くできるわけだ。二品の宮が院の御寵愛を一身にお集めになる日もこれで来るだろう。あまりにお気の毒なふうだったからね」
|
【かく足らひぬる人は】- 以下「御おぼえを」まで、上達部の詞。前に「いとかく具しぬる人は世に久しからぬ例もあるを」(第六章二段)「取り集め足らひたることはまことにたぐひあらじ」(同)とあった。盈虚思想である。「絵合」巻末の源氏の嵯峨野の御堂建立もそうした思想に基づく造営であった。
【何を桜に】- 明融臨模本、合点と付箋「まてといふにちらてしとまる物ならはなにを桜に思まさまし」(古今集春下、七〇、読人しらず)がある。『源氏釈』が初指摘。
【今こそ、二品の宮は、もとの御おぼえ現はれたまはめ】- 紫の上が亡くなって、これで正妻としての本来のご身分に相応しい寵愛を得るであろう、という意。
|
| 8.3.5 |
など、うちささめきけり。
|
などと、ひそひそ噂するのであった。
|
などとも言う人があった。
|
|
| 8.3.6 |
|
衛門督は、昨日一日とても過ごしにくかったことを思って、今日は、弟の方々の、左大弁、藤宰相など、車の奥の方に乗せて見物なさった。
このように噂しあっているのを聞くにつけても、胸がどきっとして、
|
衛門督は引きこもっていた昨日の退屈さに懲りて今日は弟の左大弁、参議などの車の奥に乗って見物に出ていた町で、人の言い合っている噂が耳にはいった時に、この人は一種変わった胸騒ぎがした。
|
【昨日暮らしがたかりしを】- 明融臨模本と大島本は「くらしかたかりし」とある。『集成』『新大系』は底本(明融臨模本・大島本)のままとする。『完本』は諸本に従って「いと暮らしがたかりし」と「いと」を補訂する。昨日の賀茂祭の行列には苦しくて見物する気にもなれなかったことをいう。
【かく言ひあへるを聞くにも】- 紫の上絶命の噂を。主語は柏木。
|
| 8.3.7 |
|
「どうして嫌な世の中に長生きしようか」
|
「散ればこそいとど桜はめでたけれ」(何か浮き世に久しかるべき)
|
【何か憂き世に】- 明融臨模本、合点と付箋「のこりなくちるそめてたきさくら花有てよのなかはてのうけれは」(古今集春下、七一、読人しらず)とある。『源氏釈』が初指摘。ただし初句「なごりなく」とある。文句が合わない。現行の注釈書では「散ればこそいとど桜はめでたけれ憂き世に何か久しかるべき」(伊勢物語)を指摘。
|
| 8.3.8 |
と、うち誦じ独りごちて、かの院へ皆参りたまふ。
たしかならぬことなればゆゆしくや、とて、ただおほかたの御訪らひに参りたまへるに、かく人の泣き騒げば、まことなりけりと、立ち騷ぎたまへり。
|
と、独り口ずさんで、あちらの院に皆で参上なさる。
不確かなことなので縁起でもないことを言っては、と思って、ただ普通のお見舞いの形で参上したところ、このように人が泣き叫んでいるので、本当だったのだなと、驚きなさった。
|
などとも口ずさみながら同車の人々とともに二条の院へ参った。まだ確かでないことであるから、形式を病気見舞いにして行ったのであるが、女房の泣き騒いでいる時であったから、真実であったかとさらに驚かれた。
|
|
| 8.3.9 |
式部卿宮も渡りたまひて、いといたく思しほれたるさまにてぞ入りたまふ。人の御消息も、え申し伝へたまはず。大将の君、涙を拭ひて立ち出でたまへるに、 |
式部卿宮もお越しになって、とてもひどくご悲嘆なさった様子でお入りになる。
一般の方々のご弔問も、お伝え申し上げることがおできになれない。
大将の君が、涙を拭って出ていらっしゃったので、
|
ちょうど式部卿の宮がお駈けつけになった時で、萎れたふうで宮は内へおはいりになった。押し寄せて来た多数の見舞い客の挨拶はまだことごとくは取り次ぎきれずに、家従たちの忙しがっている所へ左大将が涙をふきながら出て来た。
|
【人の御消息も】- 明融臨模本と大島本は「人の」とある。『集成』『新大系』は底本(明融臨模本・大島本)のままとする。『完本』は諸本に従って「人々の」と校訂する。
|
| 8.3.10 |
「いかに、いかに。ゆゆしきさまに人の申しつれば、信じがたきことにてなむ。ただ久しき御悩みをうけたまはり嘆きて参りつる」 |
「いかがですか、
いかがですか。縁起でもないふうに皆が申しましたので、信じが
たいことです。ただ長い間のご病気と承って嘆いて参
|
「どんなふうでいらっしゃるのですか。不吉なことを言う人があるのを私たちは信じることができないで伺ったのです。ただ長い御疾患を御心配申し上げて参ったのです」
|
【いかに、いかに】- 以下「参りつる」まで、柏木の詞。
|
| 8.3.11 |
などのたまふ。
|
などとおっしゃる。
|
などと衛門督は言った。
|
|
| 8.3.12 |
「いと重くなりて、月日経たまへるを、この暁より絶え入りたまへりつるを、もののけのしたるになむありける。やうやう生き出でたまふやうに聞きなしはべりて、今なむ皆人心静むめれど、まだいと頼もしげなしや。心苦しきことにこそ」 |
「大変に重態になって、月日を送っていらっしゃったが、今日の夜明け方から息絶えてしまわれましたが、物の怪の仕業でした。
だんだんと息を吹き返しなさったふうに聞きまして、今ちょうど皆安心したようですが、まだとても気がかりでなりません。
おいたわしい限りです」
|
「重態のままで長く病んでおられたのですが、今朝の夜明けに絶息されたのは、それは物怪のせいだったのです。ようやく呼吸が通うようになったと言って皆一安心しましたが、まだ頼もしくは思われないのですからね。気の毒でね」
|
【いと重くなりて】- 以下「心苦しきことにこそ」まで、夕霧の詞。紫の上の病状について説明する。
|
| 8.3.13 |
|
と言って、本当にひどくお泣きになるご様子である。
目も少し腫れている。
衛門督は、自分のけしからぬ気持ちに照らしてか、『この君が、大して親しい関係でもない継母のご病気を、ひどく悲嘆していらっしゃるな』と、目を止める。
|
と言う大将には実際今まで泣き続けていたという様子が残っていた。目も少しは腫れていた。衛門督は自身のだいそれた心から、大将が親しむこともなかった継母のことでこうまで悲しむのは不思議なことであると目をつけた。
|
【衛門督、わがあやしき心ならひにや】- 語り手が柏木の心中を推測した挿入句。『集成』は「自分のまともでない恋心からであろうか」「源氏を裏切って及ばぬ恋に身をやつす自分の心事からおしはかって、夕霧も継母の紫の上に恋情を抱いているのかと疑う」。『完訳』は「衛門督は、自分のけしからぬ気持に照らして人の心をも推し量るのか」「柏木はわが体験を根拠に、夕霧の異様な悲嘆ぶりに、彼も継母の紫の上に懸想心を抱いているかと直感する」と注す。
【この君の】- 以下「心しめたまへるかな」まで、柏木の心中。
【継母の御ことを】- 明融臨模本と大島本は「まゝはゝの御こと越」とある。『集成』『新大系』は底本(明融臨模本・大島本)のままとする。『完本』は諸本に従って「御事に」と校訂する。
|
| 8.3.14 |
かく、これかれ参りたまへるよし聞こし召して、
|
このように、いろいろな方々がお見舞いに参上なさった旨をお聞きになって、
|
こんなふうに高官らも見舞いに集まって来たことをお聞きになって、院からの御挨拶が伝えられた。
|
|
| 8.3.15 |
「重き病者の、にはかにとぢめつるさまなりつるを、女房などは、心もえ収めず、乱りがはしく騷ぎはべりけるに、みづからもえのどめず、心あわたたしきほどにてなむ。ことさらになむ、かくものしたまへるよろこびは聞こゆべき」 |
「重病人が、急に息を引き取ったふうになったのですが、女房たちは、冷静さを失って、取り乱して騷ぎましたが、自分自身も落ちつきをなくして、取り乱しております。
後日改めて、このお見舞いにはお礼申し上げます」
|
「重い病人に急変が来たように見えましたために女房らが泣き騒ぎをいたしましたので、私自身もつい心の平静をなくしているおりからですから、またほかの日に改めて御好意に対するお礼を申しましょう」
|
【重き病者の】- 以下「聞こゆべき」まで、源氏の詞。
|
| 8.3.16 |
|
とおっしゃった。
督の君は胸がどきっとして、このようなのっぴきならぬ事情がなければ参上できそうになく、何がなし恐ろしい気がするのも、心中後ろめたいところがあるからなのであった。
|
院のお言葉というだけで、もう衛門督の胸は騒ぎ立っていたのである。こうした混雑紛れでなくては自分の来られない場所であることを知っているのであるから腹ぎたないふるまいである。
|
【心のうちぞ腹ぎたなかりける】- 『岷江入楚』は「草子地なり」と指摘。『集成』は「その心中は、立派とは癒えないものだ」「なにも知らない源氏に対して、露顕を恐れる柏木の心中を批判した趣の草子地」。『完訳』は「心中うしろめたいからなのであった」「柏木のうしろめたい秘め事への、語り手の評言」と注す。
|
|
第四段 紫の上、蘇生後に五戒を受く
|
| 8.4.1 |
かく生き出でたまひての後しも、恐ろしく思して、またまた、いみじき法どもを尽くして加へ行なはせたまふ。
|
このように生き返りなさった後は、恐ろしくお思いになって、再度、大変ないくつもの修法のあらん限りを追加して行わせなさる。
|
蘇生したのちをまだ恐ろしいことに院はお思いになって、夫人のためにもろもろの法力の加護をお求めになった。
|
|
| 8.4.2 |
|
生きていた時の人でさえ、嫌な気がしたご様子の方が、まして死後に、異形のものに姿を変えていらっしゃるのだろうことをご想像なさると、まことに気味が悪いので、中宮をお世話申し上げなさることまでが、この際は億劫になり、せんじつめれば、女性の身は、皆同様に罪障の深いものだと、すべての男女関係が嫌になって、あの、他人は聞かなかったお二人の睦言に、少しお話し出しになったことを言い出したので、確かにそうだとお思い出しになると、まことに厄介なことに思わずにはいらっしゃれない。
|
生霊で現われた時さえも恐ろしかった物怪が、今度は死霊になっているのであるから、宗教画に描かれてある恐ろしい形相も想像されて、気味悪く、情けなく思召された院は、中宮のお世話をされることもこの時だけは気の進まぬことに思召されたが、しかしその人には限らず女というものは皆同じように、人間の深い罪の原因を作るものであるから、人生のすべてがいやなものに思われるとお考えになり、あれは他人がだれも聞かぬ夫婦の間の話の中にただ少し言ったことに過ぎなかったのにと、そんなことをお思い出しになると、いよいよ愛欲世界がうるさくお考えられになるのであった。
|
【うつし人にてだに、むくつけかりし人の】- 以下、源氏の六条御息所についての述懐。
【世変はり、妖しきもののさまになりたまへらむを】- 『集成』は「魔道に堕ちて恐ろしい姿になっていられるであろうことを」。『完訳』は「生を変えて恐ろしい異形の姿になっていらっしゃるのを」と訳す。
【言ひもてゆけば、女の身は、皆同じ罪深きもとゐぞかし】- 源氏の心中思惟。
【世の中】- 特に男女関係をさす。
|
| 8.4.3 |
御髪下ろしてむと切に思したれば、忌むことの力もやとて、御頂しるしばかり挟みて、五戒ばかり受けさせたてまつりたまふ。御戒の師、忌むことのすぐれたるよし、仏に申すにも、あはれに尊きこと混じりて、人悪く御かたはらに添ひゐて、涙おし拭ひたまひつつ、仏を諸心に念じきこえたまふさま、世にかしこくおはする人も、いとかく御心惑ふことにあたりては、え静めたまはぬわざなりけり。 |
御髪を下ろしたいと切望なさっているので、持戒による功徳もあろうかと考えて、頭の頂を形式的に挟みを入れて、五戒だけをお受けさせ申し上げなさる。
御戒の師が、持戒のすぐれている旨を仏に申すにつけても、しみじみと尊い文句が混じっていて、体裁が悪いまでお側にお付きなさって、涙をお拭いになりながら、仏を一緒にお念じ申し上げなさる様子は、この世に又となく立派でいらっしゃる方も、まことにこのようにご心痛になる非常時に当たっては、冷静ではいらっしゃれないものなのであった。
|
ぜひ尼になりたいと夫人が望むので、頭の頂の髪を少し取って、五戒だけをお受けさせになった。戒師が完全に仏の戒めを守る誓いを、仏前で尊い言葉で述べる時に、院は体面もお忘れになり、夫人に寄り添って涙を拭いつつ夫人とともに仏を念じておいでになったのを見ると、聡明な貴人も御愛妻の病に仏へおすがりになる心は凡人に変わらないことがわかった。
|
【御髪下ろしてむ】- 紫の上の願い。完了の助動詞「て」未然形、確述の意、推量の助動詞「む」意志の意、強い意志を表す。
【忌むことの力もや】- 源氏の思念。
【五戒】- 殺生・偸盗・邪淫・妄語・飲酒の戒律。在家の信者の守るべき戒律。
【添ひゐて】- 明融臨模本と大島本は「そひゐて」とある。『集成』『新大系』は底本(明融臨模本・大島本)のままとする。『完本』は諸本に従って「添ひゐたまひて」と「たまひ」を補訂する。
|
| 8.4.4 |
いかなるわざをして、これを救ひかけとどめたてまつらむとのみ、夜昼思し嘆くに、ほれぼれしきまで、御顔もすこし面痩せたまひにたり。 |
どのような手立てをしてでも、この方をお救い申しこの世に引き止めておこうとばかり、昼夜お嘆きになっているので、ぼうっとするほどになって、お顔も少しお痩せになっていた。
|
どんな方法を講じて夫人の病を救い、長く生命を保たせようかと夜昼お歎きになるために、院のお顔にも少し痩せが見えるようになった。
|
【いかなるわざをして】- 以下「とどめたてまつらむ」まで、源氏の心中。
|
|
第五段 紫の上、小康を得る
|
| 8.5.1 |
五月などは、まして、晴れ晴れしからぬ空のけしきに、えさはやぎたまはねど、ありしよりはすこし良ろしきさまなり。されど、なほ絶えず悩みわたりたまふ。 |
五月などは、これまで以上に、s晴々しくない空模様で、すっきりした気分におなりになれないが、以前よりは少し良い状態である。
けれども、
|
五月などはまして気候が悪くて病夫人の容体がさわやいでいくとも見えなかったが、以前よりは少しいいようであった。しかもまだ苦しい日々が時々夫人にあった。
|
【五月などは、まして】- 五月雨の時期である。病人にはますますつらい季節である。
|
| 8.5.2 |
|
物の怪の罪障を救えるような仏事として、毎日法華経を一部ずつ供養させなさる。
毎日何やかやと尊い供養をおさせになる。
御枕元近くでも、不断の御読経を、声の尊い人だけを選んでおさせになる。
物の怪が正体を現すようになってからは、時々悲しげなことを言うが、まったくこの物の怪がすっかり消え去ったというわけではない。
|
院は物怪の罪を救うために、日ごとに法華経一巻ずつを供養させておいでになった。そのほか何かと宗教的な営みを多くあそばされた。病床のかたわらで不断の読経もさせておいでになるのであって、声のいい僧を選んでそれにはあてておありになった。一度現われて以来おりおり出て物怪は悲しそうなことを言うのであって、全然退いては行かないのである。
|
【日ごとに法華経一部づつ供養ぜさせたまふ】- 『法華経』二十八品を毎日一部(一品)ずつを写経させて、六条御息所の成仏のため供養させること。
【さらにこのもののけ去り果てず】- 副詞「さらに」は打消の助動詞「ず」にかかる。『完訳』は「すっかり離れ去るというのでもない」と訳す。
|
| 8.5.3 |
|
ますます暑いころは、息も絶え絶えになって、ますますご衰弱なさるので、何とも言いようがないほどお嘆きになった。
意識もないようなご病状の中でも、このようなご様子をお気の毒に拝見なさって、
|
暑い夏の日になっていよいよ病夫人の衰弱ははげしくなるばかりであるのを院は歎き続けておいでになった。病に弱っていながらも院のこの御様子を夫人は心苦しく思い、
|
【なきやうなる御心地にも】- 紫の上の思慮。以下、重い病状にありながら源氏を案じる紫の上のけなげな態度が語られる。
【かかる御けしき】- 源氏のやつれた表情。
|
| 8.5.4 |
|
「この世から亡くなっても、わたしには少しも残念だと思われることはないが、これほどご心痛のようなので、自分の亡骸をお目にかけるのも、いかにも思いやりのないことだから」
|
自分の死ぬことは何でもないがこんなにお悲しみになるのを知りながら死んでしまうのは思いやりのないことであろうから、その点で自分はまだ生きるように努めねばならぬ
|
【世の中に亡くなりなむも】- 以下「思ひ隈なかるべければ」まで、紫の上の思念。引用句はなく、地の文に続く。
【空しく見なされたてまつらむが】- 「れ」受身の助動詞。源氏から見られる、の意。『集成』は「はかなくなった自分の姿をお目にかけるのは」。『完訳』は「むなしく命の果てる姿をお目にかけてしまうことになっては」と訳す。
|
| 8.5.5 |
|
と、気力を奮い起こして、お薬湯などを少し召し上がったせいか、六月になってからは、時々頭を枕からお上げになった。
珍しいことと拝見なさるにつけても、やはり、とても危なそうなので、六条院にはわずかの間でもお出向きになることができない。
|
と、こんな気が起こったころから、米湯なども少しずつは取ることになったせいか、六月になってからは時々頭を上げて見ることもできるようになった。珍しくうれしくお思いになりながら、なお院は御不安で六条院へかりそめに行って御覧になることもなかった。
|
【六月になりてぞ、時々御頭もたげたまひける】- 六月は最も暑くつらい時期。その時に枕から頭を上げたとは、逆接的にけなげな姿を彷彿させるものである。
|
|
第九章 女三の宮の物語 懐妊と密通の露見
|
|
第一段 女三の宮懐妊す
|
| 9.1.1 |
|
姫宮は、わけの分からなかった出来事をお嘆きになって以来、そのまま普通のお具合ではいらっしゃらず、苦しそうにしておいでであったが、そうひどい状態でもなく、先月から、食べ物をお召し上がりにならず、ひどく蒼ざめてやつれていらっしゃる。
|
姫宮はあの事件があってから煩悶を続けておいでになるうちに、お身体が常態でなくなって行った。御病気のようにお見えになるが、それほどたいしたことではないのである。六月になってからはお食慾が減退してお顔色も悪くおやつれが見えるようになった。
|
【立ちぬる月より、物きこし召さで】- 『集成』は「月が改まってこのかた」「柏木に逢ったのは四月であるから五月になってから」と注す。悪阻の症状が現れる。
|
| 9.1.2 |
|
あの人は、無性に我慢ができない時々には、夢のようにお逢い申し上げたが、宮は、どこまでも無体なことだとお思いになっていた。
院をひどくお恐がり申されるお気持ちから、態度も人品も、同等に見られようか、たいそう風流っぽく優美にしているので、一般の目には、普通の人以上に誉められるが、幼い時から、そのように類例のないご様子の方に馴れ親しんでいらっしゃるお心にとっては、心外な者とばかり見ていらっしゃるうちに、このようにずっとお悩みになることは、気の毒なご運命であった。
|
衛門督は思いあまる時々に夢のように忍んで来た。宮のお心には今も愛情が生じているのではおありにならないのである。罪をお恐れになるばかりでなく、風采も地位もそれはこれに匹敵する価値のない人であることはむろんであったし、気どって風流男がる表面を見て、一般人からは好もしい美男という評判は受けていても、少女時代から光源氏を良人に与えられておいでになった宮が、比較して御覧になっては、それほど価値に思われる顔でもないのであるから、無礼者であるという御意識以外の何ものもない相手のために、妊娠をあそばされたというのはお気の毒な宿命である。
|
【かの人は】- 柏木をさす。
【夢のやうに見たてまつりけれど】- 『完訳』は「夢路を通うような思いで宮にお逢い申していたのであったが」「密会は一度ならず繰り返された」と注す。
【宮、尽きせずわりなきことに】- 明融臨模本と大島本は「宮」とある。『集成』『新大系』は底本(明融臨模本・大島本)のままとする。『完本』は諸本に従って「宮は」と「は」を補訂する。
【院をいみじく懼ぢきこえたまへる御心に】- 主語は女三の宮。「院」は源氏の六条院。異常な夫婦関係である。
【ありさまも人のほども】- 以下、女三の宮の心情に即した叙述。
【あはれなる御宿世にぞありける】- 軽蔑し愛情もないままに、その人の子を妊娠してしまった女三の宮の境涯をいう。『完訳』は「不運だったとする語り手の評」と注す。
|
| 9.1.3 |
|
御乳母たちは懐妊の様子に気がついて、院がお越しになることも実にたまにでしかないのを、ぶつぶつお恨み申し上げる。
|
気のついた乳母たちは、「たまにしかおいでにならないで、そしてまたこんなふうに重荷を宮様へお負わせになる」と院をお恨みしていた。
|
【見たてまつりとがめて】- 宮の懐妊に気がついて、の意。
【たまさかになるを】- 明融臨模本は「たまさかになる越」とある。大島本は「たまさかなる越」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「たまさかなるを」と「に」を削除する。『新大系』は底本のまま「たまさかなるを」とする。
|
| 9.1.4 |
|
このようにお苦しみでいらっしゃるとお聞きになってお出かけになる。
女君は、暑く苦しいと言って、御髪を洗って、少しさわやかにしていらっしゃった。
横になりながら髪を投げ出していらっしゃったので、すぐには乾かないが、少しもふくらんだり、乱れたりした毛もなくて、実に清らかにゆらゆらとたっぷりあって、蒼く痩せていらっしゃるのが、かえって青白くかわいらしげに見え、透き透ったように見えるお肌つきなどは、又とないほど可憐な感じである。
脱皮した虫の脱殻かのように、まだとても頼りない感じでいらっしゃる。
|
寝んでおいでになることをお知りになって、院は訪ねようとあそばされた。夫人は暑い時分を清くしていたいと思い、髪を洗ってやや爽快なふうになっていた。そしてそのまままた横になっていたのであるから、早くかわかず、まだぬれている髪は少しのもつれもなく清らかにゆらゆらと、病む麗人に添っていた。青みを帯びた白い顔は美しくてすきとおるような皮膚つきである。虫のもぬけのようにたよりない。
|
【かく悩みたまふ】- 宮が懐妊のため苦しんでいるということ。
【女君は】- 紫の上をいう。
【色は真青に白くうつくしげに、透きたるやうに見ゆる御肌つきなど、世になくらうたげなり】- 紫の上の病気のための青白さはかえって可憐でかわいらしい美と映る。『集成』は「この上なく痛々しい美しさに見える」。『完訳』は「世にまたとないくらい可憐なご様子である」と訳す。
|
| 9.1.5 |
年ごろ住みたまはで、すこし荒れたりつる院の内、たとしへなく狭げにさへ見ゆ。
昨日今日かくものおぼえたまふ隙にて、心ことにつくろはれたる遣水、前栽の、うちつけに心地よげなるを見出だしたまひても、あはれに、今まで経にけるを思ほす。
|
長年お住みにならなかったので、多少荒れていた院の内、喩えようもないくらい手狭な感じにさえ見える。
昨日今日とこのように意識のおありの時に、特別に手入れをさせた遣水、前栽が、急にさわやかに感じられるのを御覧になっても、しみじみと、今まで過ごしてきたことをお思いになる。
|
しかも長く捨てて置かれた二条の院は女王の美の輝きで狭げにさえ見えた。昨日今日になって人ごこちが夫人に帰ってきたことによって院内が活気づいてにわかに流れも木草も繕われだした。そうした庭をながめても、それが夏の終わりの景色であるのに病臥していた間の月日の長さが思われた。
|
|
|
第二段 源氏、紫の上と和歌を唱和す
|
| 9.2.1 |
池はいと涼しげにて、蓮の花の咲きわたれるに、葉はいと青やかにて、露きらきらと玉のやうに見えわたるを、
|
池はとても涼しそうで、蓮の花が一面に咲いているところに、葉はとても青々として、露がきらきらと玉のように一面に見えるのを、
|
池は涼しそうで蓮の花が多く咲き、蓮葉は青々として露がきらきら玉のように光っているのを、院が、
|
|
|
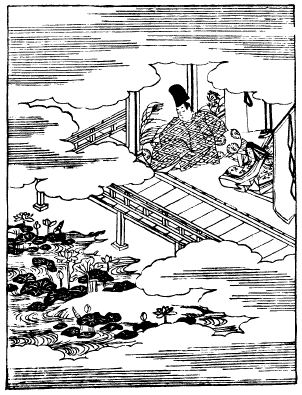 |
| 9.2.2 |
|
「あれを御覧なさい。
自分ひとりだけ涼しそうにしているね」
|
「あれを御覧なさい。自分だけが爽快がっている露のようじゃありませんか」
|
【かれ見たまへ】- 以下「涼しげなるかな」まで、源氏の詞。
|
| 9.2.3 |
とのたまふに、起き上がりて見出だしたまへるも、いとめづらしければ、
|
とおっしゃると、起き上がって外を御覧になるのも、実に珍しいことなので、
|
とお言いになるので、夫人は起き上がって、さらに庭を見た。こんな姿を見ることが珍しくて、
|
|
| 9.2.4 |
「かくて見たてまつるこそ、夢の心地すれ。いみじく、わが身さへ限りとおぼゆる折々のありしはや」 |
「このように拝見するのさえ、夢のような気がします。
ひどく、自分自身までが終わりかと思われた時がありましたよ」
|
「こうしてあなたを見ることのできるのは夢のようだ。悲しくて私自身さえも今死ぬかと思われた時が何度となくあったのだから」
|
【かくて見たてまつるこそ】- 以下「ありしはや」まで、源氏の詞。
|
| 9.2.5 |
と、涙を浮けてのたまへば、みづからもあはれに思して、
|
と涙を浮かべておっしゃると、自分自身でも胸がいっぱいになって、
|
と、院が目に涙を浮かべてお言いになるのを聞くと、夫人も身にしむように思われて、
|
|
| 9.2.6 |
|
「露が消え残っている間だけでも生きられましょうか
たまたま蓮の露がこうしてあるほどの命ですから」
|
消え留まるほどやは経べきたまさかに
蓮の露のかかるばかりを
|
【消え止まるほどやは経べきたまさかに--蓮の露のかかるばかりを】- 紫の上の詠歌。「消え」と「露」と「かかる」は縁語。「玉」と「露」も縁語。「たまさかに」に「玉」の音を響かす。「かかる」は「かくある」の縮と掛詞。わが命のはかなさを露の消え残る間に喩えて詠む。
|
| 9.2.7 |
とのたまふ。
|
とおっしゃる。
|
と言った。
|
|
| 9.2.8 |
|
「お約束して置きましょう、
この世ばかりでなく来世に蓮の葉の上に玉と置く露のように
|
契りおかんこの世ならでも蓮の葉に
玉ゐる露の心隔つな
|
【契り置かむこの世ならでも蓮葉に--玉ゐる露の心隔つな】- 源氏の返歌。紫の上の「蓮」「玉」「露」の語句を用いる。「消え止まる」の語句を「契り置かむ」と切り返す。この世のみならず来世までの永遠の愛を誓う。
|
| 9.2.9 |
|
お出かけになる先は億劫であるが、帝におかれても院おかれても、お耳にあそばすこともあるので、ご病気と聞いてしばらくたっているので、目の前の病人に心を混乱させていた間、お目にかかることもほとんどなかったので、このような雲の晴れ間にまで引き籠もっていては、とお思い立ちになって、お出かけになった。
|
これは院のお歌である。六条院へはお気が進まないのであるが、宮中の聞こえと法皇への御同情から、宮の床についておられる知らせを受けていながら、いっしょに住むほうの妻の大病の気づかわしさから訪ねて行くこともあまりしなかったのであるから、女王の病のこんなふうに少しよい間にしばらくあちらの家へ行っていようという心におなりになって院はお出かけになった。
|
【目に近きに心を惑はしつる】- 紫の上の病気をさす。
【かかる雲間にさへやは絶え籠もらむ】- 源氏の心中。「雲間」は天候状態と紫の上の小康状態を譬喩的にさす。
|
|
第三段 源氏、女三の宮を見舞う
|
| 9.3.1 |
宮は、御心の鬼に、見えたてまつらむも恥づかしう、つつましく思すに、物など聞こえたまふ御いらへも、聞こえたまはねば、日ごろの積もりを、さすがにさりげなくてつらしと思しけると、心苦しければ、とかくこしらへきこえたまふ。大人びたる人召して、御心地のさまなど問ひたまふ。 |
宮は、良心の呵責に苛まれて、お会いするのも恥ずかしく、気が引けてお思いになると、何かおっしゃるお言葉にも、お返事申し上げなさらないので、長い間会わずにいたことを、そうと言わないけれど辛くお思いになっているのだと、お気の毒なので、あれやこれやとお慰めになる。
年輩の女房を召して、ご気分の様子などをお尋ねになる。
|
宮は心の鬼に院の前へ出ておいでになることが恥ずかしく晴れがましくて、ものをお言いになる返辞もよくされないのを長い絶え間にこの子供らしい人もさすがに恨んでいるのであろうと院は心苦しくお思いになり、慰めることにかかっておいでになった。お世話役の女房をお呼び出しになり、宮の御不快の経過などを院がお聞きになると、それは妊娠の徴候があってのことであるという答えをした。
|
【物など聞こえたまふ】- 主語は源氏。
【日ごろの積もりを】- 以下「つらしと思しける」まで、源氏の心中。
|
| 9.3.2 |
|
「普通のお身体ではいらっしゃいません」
|
「今になって全く珍しいことが起こってきたね」
|
【例のさまならぬ御心地になむ】- 女房の詞。妊娠のことをいう。
|
| 9.3.3 |
と、わづらひたまふ御ありさまを聞こゆ。
|
と、ご気分のすぐれないご様子を申し上げる。
|
とだけ院はお言いになったが、
|
|
| 9.3.4 |
|
「妙だな。
今ごろになってご妊娠だとは」
|
お心の中では長くそばにいる人たちの中にもそうしたことはないのであるから、
|
【あやしく。ほど経てめづらしき御ことにも】- 源氏の詞。「あるかな」などの語句を言いさした形。「めづらしき御事」は妊娠をさす。無感動の発言。「とばかりのたまひて」という、無表情の振る舞い。
|
| 9.3.5 |
とばかりのたまひて、御心のうちには、
|
とだけおっしゃって、ご心中には、
|
|
|
| 9.3.6 |
|
「長年連れ添った妻たちでさえそのようなことはなかったのに、不確かなことなので、どうなのか」
|
不祥なことがこちらで起こっているのではないかというような疑いをお覚えになりながら、
|
【年ごろ経ぬる人びとだに】- 以下「御ことにもや」まで、源氏の心中。女三の宮が源氏に降嫁して七年たつ。「人びと」は、源氏の妻たちをさす。
【さることなきを】- 妊娠をさす。
【不定なる御事にもや」--と思せば】- 「もや」連語、係助詞「も」+係助詞「や」疑問の意。危ぶむ気持ちを表す。下に「ある」連体形を省略した形。女三の宮の懐妊に期待や関心もない。
|
| 9.3.7 |
と思せば、ことにともかくものたまひあへしらひたまはで、ただ、うち悩みたまへるさまのいとらうたげなるを、あはれと見たてまつりたまふ。 |
とお思いなさるので、特にあれこれとおっしゃらずに、ただ、お苦しみでいらっしゃる様子がとても痛々しげなのを、いたわしく拝見なさる。
|
それをくわしく聞こうとはされないで、ただ悪阻に悩む人の若い可憐な姿に愛を覚えておいでになった。
|
|
| 9.3.8 |
からうして思し立ちて渡りたまひしかば、ふともえ帰りたまはで、二、三日おはするほど、「いかに、いかに」とうしろめたく思さるれば、御文をのみ書き尽くしたまふ。 |
やっとのことでお思い立ちになってお越しになったので、すぐにはお帰りになることはできず、二、三日いらっしゃる間、「どうしているだろうか、どうしているだろうか」と気がかりにお思いになるので、お手紙ばかりをこまごまとお書きになる。
|
やっと思い立っておいでになったのであるから、すぐにお帰りになることもできず、二、三日おいでになる間にも、二条の院の女王の容体ばかりがお気づかわれになって、そのほうへ手紙ばかりを書き送っておいでになった。
|
【いかに、いかに】- 源氏の心中。紫の上を気づかう。
|
| 9.3.9 |
|
「いつの間にたくさんお言葉が溜るのでしょう。
まあ、何と、
|
「あんなにもしばらくの間にお言いになる感情がたまるのですかね。宮様をとうとうお気の毒な方様とお見上げする時が来ましたよ」
|
【いつの間に】- 以下「世をも見るかな」まで、女房の詞。
【いでや、やすからぬ世をも見るかな】- 女三の宮方を心配する言葉。『集成』は「「なんと、姫様のお身の上が心配なこと」。『完訳』は「いやもう、こちらとの御仲もそう油断してはいらせませぬ」と訳す。
|
| 9.3.10 |
と、若君の御過ちを知らぬ人は言ふ。侍従ぞ、かかるにつけても胸うち騷ぎける。 |
と、若君の御過ちを知らない女房は言う。
侍従だけは、このようなことにつけても胸騷ぎがするのであった。
|
などと宮の御過失などは知らぬ人たちが言う。秘密に携わっている小侍従は院の御滞留の間を無事に過ごしうるかと胸をとどろかせていた。
|
【若君】- 女三の宮をいう。『完訳』は「宮の、幼稚さをこめた呼称」と注す。
|
| 9.3.11 |
かの人も、かく渡りたまへりと聞くに、おほけなく心誤りして、いみじきことどもを書き続けて、おこせたまへり。対にあからさまに渡りたまへるほどに、人間なりければ、忍びて見せたてまつる。 |
あの人も、このようにお越しになっていると聞くと、大それた考え違いを起こして、大層な訴え事を書き綴っておよこしになった。
対の屋にちょっとお渡りになっている間に、人少なであったので、こっそりとお見せ申し上げる。
|
衛門督は院が六条のほうへ来ておいでになることを聞くと、だいそれた嫉妬を起こして、自己の恋のはげしさをさらに書き送る気になって手紙をよこした。院が暫時対のほうへ行っておいでになる時で、だれも宮のお居間にいない様子を見て、小侍従はそれを宮にお見せした。
|
【対にあからさまに渡りたまへるほどに】- 主語は源氏。東の対へ。
|
| 9.3.12 |
|
「厄介な物を見せるのは、とても辛いわ。
気分がますます悪くなりますから」
|
「いやなものを読めというのね。私はまた気分が悪くなってきているのに」
|
【むつかしきもの見するこそ】- 以下「いとど悪しきに」まで、女三の宮の詞。柏木からの手紙を見たいとは思わない、という。
|
| 9.3.13 |
とて臥したまへれば、
|
と言ってお臥せになっているので、
|
こう言って、宮はそのまま横におなりになった。
|
|
| 9.3.14 |
「なほ、ただ、この端書きの、いとほしげにはべるぞや」 |
「でも、ただ、このはしがきが、お気の毒な気がいたしますよ」
|
「この端書きがあまりに身にしむ文章なんでございますもの」
|
【なほ、ただ】- 以下「はべるぞや」まで、小侍従の詞。
|
| 9.3.15 |
とて広げたれば、人の参るに、いと苦しくて、御几帳引き寄せて去りぬ。
|
と言って、広げたところへ誰か参ったので、まこと困って、御几帳を引き寄せて出て行った。
|
小侍従は衛門督の手紙を拡げた。ほかの女房たちが近づいて来た気配を聞いて、手でお几帳を宮のおそばへ引き寄せて小侍従は去った。
|
|
| 9.3.16 |
いとど胸つぶるるに、院入りたまへば、えよくも隠したまはで、御茵の下にさし挟みたまひつ。 |
ますます胸がどきどきしているところに、院がお入りになったので、上手にお隠しになることもできず、御褥の下にさし挟みなさった。
|
宮のお胸がいっそうとどろいている所へ院までも帰っておいでになったために、手紙をよくお隠しになる間がなくて、敷き物の下へはさんでお置きになった。
|
【いとど胸つぶるるに】- 主語は女三の宮。
|
|
第四段 源氏、女三の宮と和歌を唱和す
|
| 9.4.1 |
夜さりつ方、二条の院へ渡りたまはむとて、御暇聞こえたまふ。
|
夜になってから、二条院にお帰りになろうとして、ご挨拶を申し上げなさる。
|
二条の院へ今夜になれば行こうと院はお思いになり、そのことを宮へお言いになるのであった。
|
|
| 9.4.2 |
「ここには、けしうはあらず見えたまふを、まだいとただよはしげなりしを、見捨てたるやうに思はるるも、今さらにいとほしくてなむ。ひがひがしく聞こえなす人ありとも、ゆめ心置きたまふな。今見直したまひてむ」 |
「こちらには、お具合は悪くないようにお見えですが、まだとても頼りなさそうなのを、放って置くように思われますのも、今さらお気の毒なので。
悪く申す者がありましても、決してお気になさいますな。
やがてきっとお分かりになりましょう」
|
「あなたはたいしたことがないようですから、あちらはまだあまりにたよりないようなのを見捨てておくように思われても、今さらかわいそうですから、また見に行ってやろうと思います。中傷する者があっても、あなたは私を信じておいでなさいよ。また忠実な良人になる日が必ずありますよ」
|
【ここには】- 以下「見直したまひてむ」まで、源氏の詞。女三の宮への暇乞いの挨拶。
【まだいとただよはしげなりしを】- 紫の上の容態をいう。
|
| 9.4.3 |
|
とお慰めになる。
いつもは、子供っぽい冗談事などを、気楽に申し上げなさるのだが、ひどく沈み込んで、ちゃんと目をお合わせ申すこともなさらないのを、ただ側にいないのを恨んでいらっしゃるのだとお思いなさる。
|
これまではこんな時にも、子供めいた冗談などをお言いになって、朗らかにしている方なのであったが、非常にめいっておしまいになり、院のほうへ顔を向けようともされないのを、内にいだく嫉妬の影がさしているとばかり院はお思いになった。
|
【例は、なまいはけなき戯れ言なども】- 主語は女三の宮。
【ただ世の恨めしき御けしきと心得たまふ】- 主語は源氏。「世」は源氏との夫婦仲をいう。『集成』は「(事情を知らぬ源氏は)ただ、夫にいつも側にいてもらえないのを恨めしく思っていられるのだと、お思いになる」と訳す。
|
| 9.4.4 |
昼の御座にうち臥したまひて、御物語など聞こえたまふほどに暮れにけり。すこし大殿籠もり入りにけるに、ひぐらしのはなやかに鳴くにおどろきたまひて、 |
昼の御座所に横におなりになって、お話など申し上げているうちに日が暮れてしまった。
少しお寝入りになってしまったが、ひぐらしが派手に鳴いたのに目をお覚ましになって、
|
昼の座敷でしばらくお寝入りになったかと思うと、蜩の啼く声でお目がさめてしまった。
|
【ひぐらしのはなやかに鳴くに】- 『完訳』は「秋の景物。夕暮時に鳴く。ここは夏の終りの夕べである」と注す。
|
| 9.4.5 |
|
「それでは、道が暗くならない間に」
|
「ではあまり暗くならぬうちに出かけよう」
|
【さらば、道たどたどしからぬほどに】- 源氏の詞。「夕闇は道たどたどし月待ちて帰れわが背子その間にも見む」(古今六帖一、三七一、夕闇)をの語句を引いた言葉。
|
| 9.4.6 |
とて、御衣などたてまつり直す。
|
と言って、お召し物などをお召し替えになる。
|
と言いながら院がお召しかえをしておいでになると、
|
|
| 9.4.7 |
|
「月を待って、と言うそうですから」
|
「『月待ちて』(夕暮れは道たどたどし月待ちて云々)とも言いますのに」
|
【月待ちて、とも言ふなるものを】- 女三の宮の詞。源氏の言葉中の引歌の文句を踏まえて応える。「なる」伝聞推定の助動詞。明融臨模本、合点、付箋「夕くれはみちたとたとし月待てかへれわかせこそのまにもみむ」とある。
|
| 9.4.8 |
|
と、若々しい様子でおっしゃるのはとてもいじらしい。
「その間でも、とお思いなのだろうか」と、いじらしくお思いになって、お立ち止まりになる。
|
若々しいふうで宮がこうお言いになるのが憎く思われるはずもない。せめて月が出るころまででもいてほしいとお思いになるのかと心苦しくて、院はそのまま仕度をおやめになった。
|
【憎からずかし】- 『集成』は「いかにも愛くるしい」「無下にことわりもならぬ源氏の気持を、草子地が代弁する」と注す。
【その間にも、とや思す】- 源氏の心中。女三の宮の気持を忖度する。
|
| 9.4.9 |
|
「夕露に袖を濡らせというつもりで、
ひぐらしが鳴くのを聞きながら起きて行
|
夕露に袖濡らせとやひぐらしの
鳴くを聞きつつ起きて行くらん
|
【夕露に袖濡らせとやひぐらしの--鳴くを聞く聞く起きて行くらむ】- 女三の宮から源氏への贈歌。「露」は涙の象徴。「起きて」は「露」との縁語「置きて」を響かす。『集成』は「夕方は尋ねて来て下さるはずの時ですのに、の余意があろう」。『完訳』は「蜩が鳴き露が置く夕べは男が女を尋ね来る時。それなのに立ち去るのだとして、源氏を恨む歌」と注す。係助詞「や」--「行くらむ」連体形は、反語の意を含んだ疑問、恨み言の余意余情がある。
|
| 9.4.10 |
片なりなる御心にまかせて言ひ出でたまへるもらうたければ、ついゐて、
|
子供のようなあどけないままにおっしゃったのもかわいらしいので、膝をついて、
|
幼稚なお心の実感をそのままな歌もおかわいくて、院は膝をおかがめになって、
|
|
| 9.4.11 |
|
「ああ、困りましたこと」
|
「苦しい私だ」
|
【あな、苦しや】- 源氏の心中。
|
| 9.4.12 |
と、うち嘆きたまふ。
|
と、溜息をおつきになる。
|
と歎息をあそばされた。
|
|
| 9.4.13 |
|
「わたしを待っているほうでもどのように聞いているでしょうか
それぞれに心を騒がすひぐらしの声ですね」
|
待つ里もいかが聞くらんかたがたに
心騒がすひぐらしの声
|
【待つ里もいかが聞くらむ方がたに--心騒がすひぐらしの声】- 源氏から女三の宮への返歌。「ひぐらし」の語句を受けて返す。「来めやとは思ふものからひぐらしの鳴く夕暮は立ち待たれつつ」(古今集恋五、七七二、読人しらず)を踏まえる。
|
| 9.4.14 |
など思しやすらひて、なほ情けなからむも心苦しければ、止まりたまひぬ。
静心なく、さすがに眺められたまひて、御くだものばかり参りなどして、大殿籠もりぬ。
|
などとご躊躇なさって、やはり無情に帰るのもお気の毒なので、お泊まりになった。
心は落ち着かず、そうは言っても物思いにお耽りになって、果物類だけを召し上がりなどなさって、お寝みになった。
|
などと躊躇をあそばしながら、無情だと思われることが心苦しくてなお一泊してお行きになることにあそばされた。さすがにお心は落ち着かずに、物思いの起こる御様子で晩饗はお取りにならずに菓子だけを召し上がった。
|
|
|
第五段 源氏、柏木の手紙を発見
|
| 9.5.1 |
まだ朝涼みのほどに渡りたまはむとて、とく起きたまふ。
|
まだ朝の涼しいうちにお帰りになろうとして、早くお起きになる。
|
まだ朝涼の間に帰ろうとして院は早くお起きになった。
|
|
| 9.5.2 |
|
「昨夜の扇を落として、これでは風がなま温いな」
|
「昨日の扇をどこかへ失ってしまって、代わりのこれは風がぬるくていけない」
|
【昨夜のかはほりを落として、これは風ぬるくこそありけれ】- 源氏の独言。「かはほり」は夏扇。「これ」は桧扇をさす。
|
| 9.5.3 |
|
と言って、御桧扇をお置きになって、昨日うたた寝なさった御座所の近辺を、立ち止まってお探しになると、御褥の少し乱れている端から、浅緑の薄様の手紙で、押し巻いてある端が見えるのを、何気なく引き出して御覧になると、男性の筆跡である。
紙の香りなどはとても優美で、気取った書きぶりである。
二枚にこまごまと書いてあるのを御覧になると、「紛れようもなく、あの人の筆跡である」と御覧になった。
|
とお言いになりながら、昨日のうたた寝に扇をお置きになった場所へ行ってごらんになったが、立ち止まって目をお配りになると、敷き物のある一所の端が少し縒れたようになっている下から、薄緑の薄様の紙に書いた手紙の巻いたのがのぞいていた。何心なく引き出して御覧になると、それは男の手で書かれたものであった。紙の匂いなどの艶な感じのするもので、骨を折った巧妙な字で書かれてあった。二重ねにこまごまと書いたのをよく御覧になると、それは紛れもない衛門督の手跡であった。
|
【浅緑の薄様なる文の、押し巻きたる】- 柏木から女三の宮への恋文。浅緑色の薄様の紙を巻紙につくろう。
【ことさらめきたる書きざまなり】- 『集成』は「気取った」。『完訳』は「わざとらしく意味ありげな書きぶりである」と訳す。
【紛るべき方なく、その人の手なりけり】- 源氏の心中。「その人」は柏木をさす。
|
| 9.5.4 |
御鏡など開けて参らする人は、見たまふ文にこそはと、心も知らぬに、小侍従見つけて、昨日の文の色と見るに、いといみじく、胸つぶつぶと鳴る心地す。御粥など参る方に目も見やらず、 |
お鏡の蓋を開けて差し上げる女房は、やはり殿が御覧になるはずの手紙であろうと、事情を知らないが、小侍従はそれを見つけて、昨日の手紙と同じ色と見ると、まことにたいそう、胸がどきどき鳴る心地がする。
お粥などを差し上げる方には見向きもせず、
|
院のお座の所で鏡をあけてお見せしている女房は御自分の御用の手紙を見ておいでになるものと思っていたが、小侍従がそれを見た時、手紙が昨日の色であることに気がついた。胸がぶつぶつと鳴り出した。粥などを召し上がる院のほうを小侍従はもう見ることもできなかった。
|
【見たまふ文にこそは】- 明融臨模本と大島本は「見給ふみ」とある。『集成』『新大系』は底本(明融臨模本・大島本)のままとする。『完本』は諸本に従って「なほ見たまふ文」と「なほ」を補訂する。主語は源氏。女房たちの心中を叙述。
|
| 9.5.5 |
|
「いいえ、いくら何でも、それはあるまい。
本当に大変で、そのようなことがあろうか。
きっとお隠しになったことだろう」
|
まさかそうではあるまい、そんな運命の悪戯が不意に行なわれてよいものか、宮はお隠しになったはずである
|
【いで、さりとも】- 以下「隠いたまひてむ」まで、小侍従の心中。
【さることはありなむや】- 反語表現。
|
| 9.5.6 |
と思ひなす。
|
としいて思い込む。
|
と小侍従は努めて思おうとしている。
|
|
| 9.5.7 |
宮は、何心もなく、まだ大殿籠もれり。
|
宮は、無心にまだお寝みになっていらっしゃった。
|
宮は何もお知りにならずになお眠っておいでになるのである。
|
|
| 9.5.8 |
「あな、いはけな。かかる物を散らしたまひて。我ならぬ人も見つけたらましかば」 |
「何と、
幼いのだろう。このような物をお散ら
かしになって。自分以外の人が
|
こんな物を取り散らしておいて、それを自分でない他人が発見すればどうなることであろう
|
【あな、いはけな】- 以下「見つけたらましかば」まで、源氏の心中。
|
| 9.5.9 |
と思すも、心劣りして、
|
とお思いになるにつけても、見下される思いがして、
|
とお思いになると、その人が軽蔑されて、これであるから始終自分はあぶながっていたのである。
|
|
| 9.5.10 |
「さればよ。いとむげに心にくきところなき御ありさまを、うしろめたしとは見るかし」 |
「やはりそうであったか。
本当に奥ゆかしいところがないご様子を、不安であると思っていたのだ」
|
あさはかな性格はついに堕落を招くに至ったのである
|
【さればよ】- 以下「とは見るかし」まで、源氏の心中。
|
| 9.5.11 |
と思す。
|
とお思いになる。
|
と院は解釈された。
|
|
|
第六段 小侍従、女三の宮を責める
|
| 9.6.1 |
|
お帰りになったので、女房たちが少しばらばらになったので、侍従がお側に寄って、
|
お帰りになったので、女房たちがあらかた宮のお居間から去った時に、小侍従が来て、
|
【出でたまひぬれば】- 主語は源氏。源氏が帰った後の場面。
|
| 9.6.2 |
「昨日の物は、いかがせさせたまひてし。今朝、院の御覧じつる文の色こそ、似てはべりつれ」 |
「昨日のお手紙は、どのようにあそばしましましたか。
今朝、院が御覧になっていた手紙の色が、似ておりましたが」
|
「昨日の物はどうなさいました。今朝院が読んでいらっしゃいましたお手紙の色がよく似ておりましたが」
|
【昨日の物は】- 以下「似てはべりつれ」まで、小侍従の詞。
|
| 9.6.3 |
|
と申し上げると、意外なことと驚きなさって、涙が止めどもなく出て来るので、お気の毒に思う一方で、「何とも言いようのない方だ」と拝し上げる。
|
と宮へ申し上げた。はっとお思いになって宮はただ涙だけが流れに流れる御様子である。おかわいそうではあるがふがいない方であると小侍従は見ていた。
|
【いとほしきものから、「いふかひなの御さまや】- 小侍従の心中を間接的に叙述する。気の毒に思う一方で、あきれた思いをする。
|
| 9.6.4 |
「いづくにかは、置かせたまひてし。人びとの参りしに、ことあり顔に近くさぶらはじと、さばかりの忌みをだに、心の鬼に避りはべしを。入らせたまひしほどは、すこしほど経はべりにしを、隠させたまひつらむとなむ、思うたまへし」 |
「どこに、お置きあそばしましたか。
女房たちが参ったので、子細ありげに近くに控えておりまいと、ちょっとしたぐらいの用心でさえ、気が咎めますので慎重にしておりましたのに。
お入りあそばしました時には、少し間がございましたが、お隠しあそばただろうと、存じておりました」
|
「どこへお置きになったのでございますか。あの時だれかが参ったものですから、秘密がありそうに思われますまいと、それほどのことは何でもなかったのですが、よいことをしておりませんと心がとがめまして、私は退いて行ったのでございますが、院がお座敷へお帰りになりましたまでにはちょっと時間があったのでございますもの、お隠しあそばしたろうと安心をしておりました」
|
【いづくにかは】- 以下「思うたまへし」まで、小侍従の詞。
|
| 9.6.5 |
と聞こゆれば、
|
と申し上げると、
|
|
|
| 9.6.6 |
|
「いいえ、それがね。
見ていた時にお入りになったので、すぐに起き上がることもできないで、褥に差し挟んで置いたのを、忘れてしまったの」
|
「それはね、私が読んでいた時にはいっていらっしゃったものだから、どこへしまうこともできずに下へはさんでおいたのをそのまま忘れたの」
|
【いさ、とよ】- 以下「忘れにけり」まで、女三の宮の詞。「いさとよ」について、『集成』は「自信なげに応ずる言葉」と注す。
【置きあへで】- 明融臨模本は「えをきあか(か=へ)ら(ら=無イ)て」とある。すなわち異本には「えをきあへて」とあるとする。大島本は「えおきあからて」とある。『集成』は底本(明融臨模本)の訂正に従う。『完本』は底本の(明融臨模本)の訂正以前本文従う。『新大系』は底本(大島本)のままとする。
|
| 9.6.7 |
|
とおっしゃるので、何ともまったく申し上げる言葉もない。
近寄って探すが、どこにもあろうはずがない。
|
こう伺った小侍従は、この場合の気持ちをどう表現すればよいかも知らなかった。そこへ行って見たが手紙のあるはずもない。
|
【いづくのかはあらむ】- 反語表現。語り手の口吻がまじった表現。
|
| 9.6.8 |
|
「まあ、大変。
かの君も、とてもひどく恐れ憚って、素振りにもお聞かせ申されるようなことがあったら大変と、恐縮申していられたものを。
まだいくらもたたないのに、もうこのような事になってしまってよ。
全体、子供っぽいご様子でいらして、人にお姿をお見せあそばしたので、長年あれほどまで忘れることができず、ずっと恨み言を言い続けていらっしゃったが、こうまでなるとは存じませんでした事ですわ。
どちら様のためにも、お気の毒な事でございますわ」
|
「たいへんでございますね。あちらも非常に恐れておいでになりまして、毛筋ほどでも院のお耳にはいることがあったら申し訳がないと言っておいでになりましたのに、すぐもうこんなことができたではございませんか。全体御幼稚で、男性に対して何の警戒もあそばさなかったものですから、長い年月をかけた恋とは申しながら、こうまで進んだ関係になろうとはあちらも考えておいでにならなかったことでございますよ。だれのためにもお気の毒なことをなさいましたね」
|
【あな、いみじ】- 以下「いとほしくはべるべきこと」まで、小侍従の詞。
【ほどだに経ず】- 『完訳』は「あっけない露顕の気持」と注す。
【すべて、いはけなき御ありさまにて】- 小侍従、女三の宮の性格をなじる、非難の言葉。
【人にも見えさせたまひければ】- 六年前に六条院での蹴鞠の折に柏木に姿を見られたことをいう。
|
| 9.6.9 |
|
と、遠慮もなく申し上げる。
気安く子供っぽくいらっしゃるので、ずけずけと申し上げたのであろう。
お答えもなさらず、ただ泣いてばかりいらっしゃる。
とても苦しそうで、まったく何もお召し上がりにならないので、
|
と無遠慮に小侍従は言う。お若い御主人を気安く思って礼儀なしになっているのであろう。宮はお返辞もあそばさないで泣き入っておいでになった。御気分がお悪いばかりのようでなく、少しも物を召し上がらないのを見て、
|
【心やすく若くおはすれば、馴れきこえたるなめり】- 『一葉抄』は「双紙詞也」と指摘。『集成』は「小侍従は女三の宮と乳母子という親しい間柄でもある。以下、草子地」と注す。
|
| 9.6.10 |
|
「このようにお苦しみでいらっしゃるのを、放っていらっしゃって、今はもうすっかりお治りになったお方のお世話に、熱心でいらっしゃること」
|
「こんなにもお苦しそうでいらっしゃるのに、それを捨ててお置きになって、もうすっかり快くなっておいでになる奥様の御介抱を一所懸命になさらなければならないとはね」
|
【かく悩ましくせさせたまふを】- 以下「心を入れたまへること」まで、女房の詞。源氏への非難。
【今はおこたり果てたまひにたる御扱ひに】- 紫の上の看病をさす。
|
| 9.6.11 |
と、つらく思ひ言ふ。
|
と、薄情に思って言う。
|
と乳母たちは恨めしがった。
|
|
|
第七段 源氏、手紙を読み返す
|
| 9.7.1 |
|
大殿は、この手紙をやはり不審に思わずにはいらっしゃれないので、人の見ていない方で、繰り返し御覧になる。
「伺候している女房の中で、あの中納言の筆跡に似た書き方で書いたのだろうか」とまでお考えになったが、言葉遣いがはっきりしていて、本人に間違いないことがいろいろと書いてある。
|
院はお帰りになってから、まだ不審のお晴れにもならぬ今朝の手紙をよく調べて御覧になった。女房のうちであの中納言に似た字を書く女があるのではないかという疑いさえお持ちになったのであるが、言葉づかいは明らかに男性であって、他の者の書くはずのないことが内容になってもいた。
|
【さぶらふ人びとの中に】- 以下「書きたるか」まで、源氏の心中。
【言葉づかひきらきらと、まがふべくもあらぬことどもあり】- 『完訳』は「その言葉づかいは美しくととのったあやがあって、当の本人としか考えられぬふしぶしがある」と訳す。
|
| 9.7.2 |
|
「長年慕い続けてきたことが、偶然に念願が叶って、心にかかってならないといった事を書き尽くした言葉は、まことに見所があって感心するが、本当に、こんなにまではっきりと書いてよいものだろうか。
惜しいことに、あれほどの人が、思慮もなく手紙を書いたものだ。
人目に触れることがあってはいけないと思ったので、昔、このようにこまごまと書きたい時も、言葉を簡略に簡略にして書き紛らわしたものだ。
人が用心するということは難しいことなのだ」
|
昔からの恋がようやく遂げられたのではあるが、なお苦しい思いに悩み続けていることが、文学的に見ておもしろく書かれてあって、同情は惹くが、こんな関係で書きかわす手紙には人目に触れた時の用意がかねてなければならぬはずで、露骨に一目瞭然に秘密を人が悟るようなことはすべきでないものをと、院はお思いになり、りっぱな男ではあるが、こうした関係の女への手紙の書き方を知らない、落ち散ることも思って、昔の日の自分はこれに類する場合も文章は簡単にして書き紛らしたものであるが、そこまでの細心な注意はできないものらしい
|
【年を経て】- 以下「難きわざなりけり」まで、柏木の手紙を見た源氏の感想。係助詞「や」反語表現。はっきり書くべきでない、という。『集成』は「以下、その手紙の内容の概略」と注す。『新大系』も「以下、柏木の文面の大体」と注す。『完本』は地の文として処理。『集成』『完本』『新大系』は「いとかくさやかには」以下を源氏の心中文(心内、感想)とする。
【あたら人の】- 柏木をさす。あれほどにすぐれた人が、という評価と失望。
【落ち散ることもこそと】- 連語「もこそ」懸念の気持ち。
【思ひしかば、昔、かやうに】- 過去の助動詞「しか」自己の体験。以下、自分の過去の体験を振り返る。
|
| 9.7.3 |
|
と、その人の心までお見下しなさった。
|
と、衛門督を軽蔑あそばされるのであった。
|
【かの人の心をさへ】- 柏木をさす。副助詞「さへ」添加は女三の宮に加えてのニュアンス。
|
|
第八段 源氏、妻の密通を思う
|
| 9.8.1 |
|
「それにしても、
この宮をどのようにお扱いしたら良いものだろうか。おめでたい
ことのご懐妊も、このようなこ
とのせいだったのだ。ああ、何と、厭わしいことだ。このような、目の当たりに嫌な事を知りなが
|
それにしても宮を今後どうお扱いすればよいであろうか、妊娠もそうした不純な恋の結果だったのである。情けないことである。人から言われたことでもなく、直接に証拠も見ながら、以前どおりにあの人を愛することは、自分のことながら不可能らしい。
|
【さても、この人をば】- 以下「見たてまつらむよ」まで、源氏の心中。今後の女三の宮の処遇について悩む。
【めづらしきさまの御心地も、かかることの紛れにてなりけり】- 源氏は、女三の宮の懐妊も柏木との過ちによって起こったことなのだ、と理解する。
|
| 9.8.2 |
と、わが御心ながらも、え思ひ直すまじくおぼゆるを、
|
と、自分のお心ながらも、とても思い直すことはできないとお思いになるが、
|
一時的の情人として初めから重くなどは思っていない相手さえ、
|
|
| 9.8.3 |
|
「浮気の遊び事としても、初めから熱心でない女でさえ、また別の男に心を分けていると思うのは、気にくわなく疎んじられてしまうものなのに、ましてこの宮は、特別な方で、大それた男の考えであることよ。
|
ほかの愛人を持っていることを知っては不愉快でならぬものであるが、これはそうした相手でもない自分の妻である。無礼な男である。
|
【なほざりのすさびと】- 以下「たぐひあらじ」まで、源氏の心中。
【おほけなき人の心にもありけるかな】- 源氏の柏木に対する非難の思い。
|
| 9.8.4 |
|
帝のお妃と過ちを生じる例は、昔もあったが、それはまた事情が違うのだ。
宮仕えと言って、自分も相手も同じ主君に親しくお仕えするうちに、自然と、そのような方面で、好意を持ち合うようになって、みそか事も多くなるというものだ。
|
お上の後宮と恋の過失に陥る者は昔からあったが、それとこれとは問題が違う。宮仕えは男女とも一人の君主にお仕えするのであって、同輩と見る心から友情が恋となって不始末を起こす結果も作られるのである。
|
【帝の御妻をも過つたぐひ、昔もありけれど】- 『河海抄』は在原業平と五条后や二条后の例、花山院女御と藤原実資や藤原道信、源頼定と三条院麗景殿女御や一条院承香殿女御との例を指摘。光源氏自身、桐壺帝の藤壺女御と過ちを犯している。
【宮仕へといひて、我も人も同じ君に馴れ仕うまつるほどに、おのづから、さるべき方につけても、心を交はしそめ】- 女性が入内することも男性が官僚として仕えることも共に「宮仕え」といった。帝との結婚も「宮仕え」なのであった。「同じ君に馴れ仕うまつるほどに」という状況は、桐壺帝の下での源氏と藤壺女御との関係によく似ている。 【さるべき方につけても】-異性間の愛情問題をさす。
|
| 9.8.5 |
|
女御、更衣と言っても、あれこれいろいろあって、どうかと思われる人もおり、嗜みが必ずしも深いとは言えない人も混じっていて、意外なことも起こるが、重大な確かな過ちと分からないうちは、そのままで宮仕えを続けて行くようなこともあるから、すぐには分からない過ちもきっとあることだろう。
|
女御や更衣といってもよい人格の人ばかりがいるわけではないから、浮き名を流す者はあっても、破綻を見せない間は宮仕えを辞しもせずしていて、批難すべきことも起こったであろうが、
|
【おぼろけの定かなる過ち見えぬほどは、さても交じらふやうもあらむに】- 『集成』は「重大な、はっきりした不始末が人目につかない間は、そのまま宮仕えを続けるというこもあろうから」。『完訳』は「格別の不始末であることがはっきり人目につかない間は、そのまま宮仕えを続けていくことにもなろうから」と訳す。
|
| 9.8.6 |
|
このように、又となく大事にお扱い申し上げて、内心愛情を寄せている人よりも、大切な恐れ多い方と思ってお世話しているような自分をさしおいて、このような事を起こすとは、まったく例がない」
|
自分の宮に対する態度は第一の妻としてのみ待遇してきたではないか、心ではより多く愛する人をもさしおいて、最大級の愛撫を加えていた自分を裏切っておしまいになるようなことと、そんなことは同日に論ずべきでない、これは罪深いことではないか
|
【かくばかり、またなきさまに】- 以下、自分の女三の宮の扱いについていう。
【うちうちの心ざし引く方よりも】- 紫の上をさす。その人よりも。
【思ひはぐくまむ人をおきて】- 自分光源氏をさす。
|
| 9.8.7 |
と、爪弾きせられたまふ。
|
と、つい非難せずにはいらっしゃれない。
|
と反感のお起こりになる院でおありになった。
|
|
| 9.8.8 |
|
「帝とは申し上げても、ただ素直に、お仕えするだけでは面白くもないので、深い私的な思いを訴えかける言葉に引かれて、お互いに愛情を傾け尽くし、放って置けない折節の返事をするようになり、自然と心が通い合うようになった間柄は、同様に良くない事柄だが、まだ理由があろうか。
自分自身の事ながら、あの程度の男に宮が心をお分けにならねばならないとは思われないのだが」
|
侍している君主のほうでもただ一通りの後宮の女性と御覧になるだけで、御愛情に接することもないような不幸な人に、異性の持つ友情が恋愛にも進んでゆけば、あるまじいこととは知りながらも、苦しむ男に一言の慰めくらいは書き送ることになり、相互の間に恋愛が成長してしまう結果を見るような間柄で犯す罪には十分同情してよい点もあるが、自分のことながらも、あの男くらいに比べて思い劣りされるほどの無価値な者でないと思うが
|
【帝と聞こゆれど】- 以下「おぼえぬものを」まで、源氏の心中。
【ただ素直に、公ざまの心ばへばかりにて、宮仕へのほどもものすさまじきに】- 後宮の女御更衣たちの宮仕えの心境について忖度する。
【ねぎ言になびき】- 「ねぎごとをさのみ聞きけむ社こそ果てはなげきの森となるらめ」(古今集俳諧歌、一〇五五、讃岐)。
【寄る方ありや】- 『集成』は「まだ許せるところがある」。『完訳』は「同情の余地があるというもの」と訳す。人情の自然な発露から出た行為というものは尊重する。
|
| 9.8.9 |
と、いと心づきなけれど、また「けしきに出だすべきことにもあらず」など、思し乱るるにつけて、
|
と、まことに不愉快ではあるが、また「顔色に出すべきことではない」などと、ご煩悶なさるにつけても、
|
と、院は宮を飽き足らずお思いになるのであったが、またこの問題はほかへ知らせてはならぬと思うことで御煩悶もされた。
|
|
| 9.8.10 |
|
「故院の上も、このように御心中には御存知でいらして、知らない顔をあそばしていられたのだろうか。
それを思うと、その当時のことは、本当に恐ろしく、あってはならない過失であったのだ」
|
父帝もこんなふうに自分の犯した罪を知っておいでになって知らず顔をお作りになったのではなかろうか、考えてみれば恐ろしい自分の過失であったと、
|
【故院の上も、かく御心には】- 以下「あるまじき過ちなりけれ」まで、源氏の心中。自分と藤壺との過ちを思い出し、帝の心境を忖度し、我が行為を深く反省する。
|
| 9.8.11 |
|
と、身近な例をお思いになると、恋の山路は、非難できないというお気持ちもなさるのであった。
|
御自身の過去が念頭に浮かんできた時、恋愛問題で人を批難することは自分にできないのであると思召された。
|
【恋の山路】- 明明融臨模本、合点あり、付箋に「いかはかり恋の山路のしけゝれはいりといりぬる人まとふらん」(古今六帖四、一九七四)とある。
|
|
第十章 光る源氏の物語 密通露見後
|
|
第一段 紫の上、女三の宮を気づかう
|
| 10.1.1 |
つれなしづくりたまへど、もの思し乱るるさまのしるければ、女君、消え残りたるいとほしみに渡りたまひて、「人やりならず、心苦しう思ひやりきこえたまふにや」と思して、 |
平静を装っていらっしゃるが、ご煩悶の様子がはっきりと見えるので、女君は、生き返ったのをいじらしそうに思ってこちらにお帰りになって、「ご自身どうにもならず、宮をお気の毒に思っていらっしゃるのだろうか」とお思いになって、
|
素知らぬふりはしておいでになるが、物思わしいふうは他からもうかがわれて、夫人は危い命を取りとめた自分をお憐みになる心から、こちらへはお帰りになったものの、六条院の宮をお思いになると心苦しくてならぬ煩悶がお起こりになるのであろうと解釈していた。
|
【人やりならず】- 以下「思ひやりきこえたまふにや」まで、紫の上の心中。源氏が「心くるしう思ひやる」対象は女三の宮。
|
| 10.1.2 |
|
「気分は良ろしくなっておりますが、あちらの宮がお悪くいらっしゃいましょうに、早くお帰りになったのが、お気の毒です」
|
「私はもう恢復してしまったのでございますのに、宮様のお加減のお悪い時にお帰りになってお気の毒でございます」
|
【心地はよろしく】- 以下「いとほしけれ」まで、紫の上の詞。
【とく渡りたまひにしこそ】- 源氏が六条院から二条院へ戻ってきたこと。
|
| 10.1.3 |
と聞こえたまへば、
|
とお申し上げなさるので、
|
|
|
| 10.1.4 |
「さかし。例ならず見えたまひしかど、異なる心地にもおはせねば、おのづから心のどかに思ひてなむ。内裏よりは、たびたび御使ありけり。今日も御文ありつとか。院の、いとやむごとなく聞こえつけたまへれば、上もかく思したるなるべし。すこしおろかになどもあらむは、こなたかなた思さむことの、いとほしきぞや」 |
「そうですね。
普通のお身体ではないようにお見えになりましたが、別段のご病気というわけでもいらっしゃらないので、何となく安心に思っていましてね。
宮中からは、何度もお使いがありました。
今日もお手紙があったとか。
院が、特別大切になさるようにとお頼み申し上げていらっしゃるので、主上もそのようにお考えなのでしょう。
少しでも宮を疎かになどあるようであれば、お二方がどうお思いになるかが、心苦しいことです」
|
「そう。少し悪い御様子だけれど、たいしたことでないのだから安心して帰って来たのですよ。宮中からはたびたび御使いがあったそうだ。今日もお手紙をいただいたとかいうことです。法皇の特別なお頼みを受けておられるので、お上もそんなにまで御関心をお持ちになるのですね。私が冷淡であればあちらへもこちらへも御心配をかけて済まない」
|
【さかし。例ならず】- 以下「いとほしきぞや」まで、源氏の詞。
【こなたかなた思さむことの、いとほしきぞや】- 朱雀院と今上帝をさす。
|
| 10.1.5 |
とて、うめきたまへば、
|
と言って、嘆息なさると、
|
院が歎息をされると、
|
|
| 10.1.6 |
|
「帝がお耳にあそばすことよりも、宮ご自身が恨めしいとお思い申し上げなさることのほうが、お気の毒でしょう。
ご自分ではお気になさらなくても、良からぬように蔭口を申し上げる女房たちが、きっといるでしょうと思うと、とてもつろう存じます」
|
「宮中への御遠慮よりも、宮様御自身が恨めしくお思いになるほうがあなたの御苦痛でしょう。宮様はそれほどでなくてもおそばの者が必ずいろいろなことを言うでしょうから、私の立場が苦しゅうございます」
|
【内裏の聞こし召さむよりも】- 以下「いと苦しくなむ」まで、紫の上の詞。
【我は思し咎めずとも】- 「我」は女三の宮をさす。
|
| 10.1.7 |
などのたまへば、
|
などとおっしゃるので、
|
などと女王は言う。
|
|
| 10.1.8 |
「げに、あながちに思ふ人のためには、わづらはしきよすがなけれど、よろづにたどり深きこと、とやかくやと、おほよそ人の思はむ心さへ思ひめぐらさるるを、これはただ、国王の御心やおきたまはむとばかりを憚らむは、浅き心地ぞしける」 |
「なるほど、おっしゃるとおり、ひたすら愛しく思っているあなたには、厄介な縁者はいないが、いろいろと思慮を廻らすことといったら、あれやこれやと、一般の人が思うような事まで考えを廻らされますが、わたしのただ、国王が御機嫌を損ねないかという事だけを気にしているのは、考えの浅いことだな」
|
「私の愛しているあなたにとって、あちらのことは迷惑千万に違いないが、それをあなたは許して、つまらない者の感情をまで思いやってくれる寛大な愛に比べて、私のはただお上が悪くお思いにならないかという点だけで苦労をしているのは、あさはかな愛の持ち主というべきですね」
|
【げに、あながちに】- 以下「心地ぞしける」まで、源氏の詞。
【思ひめぐらさるるを】- 主語は紫の上。思慮深く行き届いた心づかいをいう。
【これはただ】- 「これは」、私はの意。一人称代名詞。
|
| 10.1.9 |
|
と、苦笑して言い紛らわしなさる。
お帰りになることは、
|
微笑をしてお言い紛らわしになる。
|
【ほほ笑みてのたまひ紛らはす】- 苦笑して問題の本質には触れない。『集成』は「苦笑して本心には触れずにおしまいになる」。『完訳』は「苦笑して言い紛らわしていらっしゃる」「密通への複雑な思念を隠す気持」と注す。
|
| 10.1.10 |
「もろともに帰りてを。心のどかにあらむ」 |
「一緒に帰ってよ。
ゆっくりと過すことにしよう」
|
「六条院へはあなたが快くなった時にいっしょに帰ればいいのですよ。宮の御訪問をするのもそれからあとのことです」
|
【もろともに】- 以下「心のどかにを」まで、源氏の詞。「帰りてを」の「を」は、間投助詞、詠嘆の気持。
|
| 10.1.11 |
とのみ聞こえたまふを、
|
とだけ申し上げなさるのを、
|
そうきめておいでになるように仰せられた。
|
|
| 10.1.12 |
「ここには、しばし心やすくてはべらむ。まづ渡りたまひて、人の御心も慰みなむほどにを」 |
「ここでもう暫くゆっくりしていましょう。
先にお帰りになって、宮のご気分もよくなったころに」
|
「私は静かな独棲みというものもしてみとうございますから、あちらへおいでになって、宮様のお心のお慰みになりますまでずっといらっしゃい」
|
【ここには、しばし】- 以下「慰みなむほどにを」まで、紫の上の詞。
|
| 10.1.13 |
と、聞こえ交はしたまふほどに、日ごろ経ぬ。
|
と、話し合っていらっしゃるうちに、数日が過ぎた。
|
夫人からこんな勧めを聞いておいでになるうちに日数がたった。
|
|
|
第二段 柏木と女三の宮、密通露見におののく
|
| 10.2.1 |
|
姫宮は、このようにお越しにならない日が数日続くのも、相手の薄情とばかりお思いであったが、今では、「自分の過失も加わってこうなったのだ」とお思いになると、院も御存知になって、どのようにお思いだろうかと、身の置き所のない心地である。
|
院のおいでにならぬ間の長いことで今までは院をお恨みにもなった宮でおありになるが、今はその一部を自身の罪がしからしめているのであるということをお知りになって、しまいに法皇のお耳へもはいったならどう思召すことであろうと、生きておいでになることすらも恐ろしくばかりお思われになるのであった。
|
【わが御おこたりうち混ぜてかくなりぬる】- 明融臨模本は「なりぬる」とある。大島本は「かくなりぬる」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「かくなりぬる」と「かく」を補訂する。『新大系』は底本(大島本)のままとする。女三の宮の心中。
【院も聞こし召しつけて、いかに思し召さむ】- 女三の宮の心中。父の朱雀院に知られたらどう思うだろうと心配する。
【世の中つつましくなむ】- 係助詞「なむ」で下文を省略。強調と余意余情。『集成』は「世間に顔向けできない思いでいられる」。『完訳』は「身の置き所もない心地でいらっしゃる」と訳す。
|
| 10.2.2 |
かの人も、いみじげにのみ言ひわたれども、小侍従もわづらはしく思ひ嘆きて、「かかることなむ、ありし」と告げてければ、いとあさましく、 |
かの人も、熱心に手引を頼み続けるが、小侍従も面倒に思い困って、「このような事が、ありました」と知らせてしまったので、まこと驚いて、
|
お逢いしたいとしきりに衛門督は言ってくるが、小侍従は面倒な事件になりそうなのを恐れて、こんなことがあったと緑の手紙のことを書いてやった。衛門督は驚いて、
|
【かの人も】- 柏木をさす。
|
| 10.2.3 |
「いつのほどにさること出で来けむ。かかることは、あり経れば、おのづからけしきにても漏り出づるやうもや」 |
「いつの間にそのような事が起こったのだろうか。
このような事は、いつまでも続けば、自然と気配だけで感づかれるのではないか」
|
いつの間にそうしたことができたのであろう、月日の重なるうちにはいろいろな秘密が外へ洩れるかもしれぬ
|
【いつのほどに】- 以下「漏り出づるやうもや」まで、柏木の心中。
|
| 10.2.4 |
|
と思っただけでも、まことに気が引けて、空に目が付いているように思われたが、「ましてあんなに間違いようもない手紙を御覧になったのでは」と、顔向けもできず、恐れ多く、居たたまれない気がして、朝夕の、涼しい時もないころであるが、身も凍りついたような心地がして、何とも言いようもない気がする。
|
と思うだけでも恐ろしくて、罪を見る目が空にできた気がしていたのに、ましてそれほど確かな証拠が院のお手にはいったということは何たる不幸であろうと恥ずかしくもったいなくすまない気がして、朝涼も夕涼もまだ少ないこのごろながらも身に冷たさのしみ渡るもののある気がして、たとえようもない悲しみを感じた。
|
【ましてさばかり】- 以下「見たまひてけむ」あたりまで、柏木の心中。ただし引用句はなく、地の文に融合。
【見たまひてけむ】- 完了の助動詞「つ」連用形、確述。過去推量の助動詞「けむ」。御覧になってしまったのだろう、の意。
【恥づかしく、かたじけなく、かたはらいたきに】- 柏木の心中と地の文が融合した叙述。『完訳』は「心中叙述が、心情語を重畳させた地の文に転換」と注す。
【朝夕、涼みもなきころ】- 明融臨模本、合点と付箋「夏のひのあさゆふすゝみある物をなとにか恋のひまなかるらん」(出典未詳)とある。『源氏釈』に初指摘。
|
| 10.2.5 |
|
「長年、公事でも遊び事でも、お呼び下さり親しくお伺いしていたものを。
誰よりもこまごまとお心を懸けて下さったお気持ちが、しみじみと身にしみて思われるので、あきれはてた大それた者と不快の念を抱かれ申したら、どうして目をお合わせ申し上げることができようか。
そうかと言って、ふっつりと参上しなくなるのも、人が変だと思うだろうし、あちらでもやはりそうであったかと、お思い合わせになろう、それが堪らない」
|
長い歳月の間、まじめな御用の時も、遊びの催しにもお身近の者として離れず侍してきて、だれよりも多く愛顧を賜わった院の、なつかしいお優しさを思うと、無礼な者としてお憎しみを受けることになっては、自分は御前で顔の向けようもない。
|
【年ごろ、まめごとにも】- 以下「ことのいみじさ」まで、柏木の心中。
【人よりはこまかに思しとどめたる御けしきの】- 明融臨模本と大島本は「こまかに」とある。『集成』『新大系』は底本(明融臨模本・大島本)のままとする。『完本』は諸本に従って「こまやかに」と「や」を補訂する。源氏が柏木を厚遇。
【いかでかは目をも見合はせたてまつらむ】- 反語表現。
【かの御心にも】- 源氏をさす。
|
| 10.2.6 |
|
などと、気が気でない思いでいるうちに、気分もとても苦しくなって、内裏へも参内なさらない。
それほど重い罪に当たるはずではないが、身も破滅してしまいそうな気がするので、「やっぱり懸念していたとおりだ」と、一方では自分ながら、まことに辛く思われる。
|
そうかといって、すっかりお出入りをせぬことになれば人が怪しむことであろうし、院をばさらに御不快にすることになろうと煩悶する衛門督は、健康もそこねてしまい、御所へ出仕もしなかった。大罪の犯人とされるわけはないが、もう自分の一生はこれでだめであるという気のすることによって、このことを予想しないわけでもなかったではないかと、あやまった大道に踏み入った最初の自分が恨めしくてならなかった。
|
【さして重き罪には当たるべきならねど、身のいたづらになりぬる心地すれば】- 姦通罪に相当するが、柏木はそのこと以上に身の破滅、源氏から睨まれ疎んぜられることを恐れる。
【さればよ」と、かつはわが心も、いとつらくおぼゆ】- 『集成』は「やはり思わぬことではなかったと」「この前後、地の文に柏木への敬語を欠き、その真理に密着した筆致」と注す。
|
| 10.2.7 |
「いでや、しづやかに心にくきけはひ見えたまはぬわたりぞや。まづは、かの御簾のはさまも、さるべきことかは。軽々しと、大将の思ひたまへるけしき見えきかし」 |
「考えて見れば、
落ち着いた嗜み深いご様子がお見えでない方であった。まず第一
に、あの御簾の隙間の事も、あっていいことだろうか。
|
だいたい御身分相当な奥深い感じなどの見いだせなかった最初の御簾の隙間も、しかるべきことではない。大将も軽々しいと思ったことはあの時の表情にも見えたなどと、こんなことも今さら思い合わせたりした。
|
【いでや、しづやかに】- 以下「見えきかし」まで、柏木の心中。女三の宮の人柄や嗜みを冷静に回顧する。
|
| 10.2.8 |
など、今ぞ思ひ合はする。しひてこのことを思ひさまさむと思ふ方にて、あながちに難つけたてまつらまほしきにやあらむ。 |
などと、今になって気がつくのである。
無理してこの思いを冷まそうとするあまり、むやみに非難つけお思い申し上げたいのであろうか。
|
しいてその人から離れたいと願う心から欠点を捜すのかもしれない。
|
【しひてこのことを】- 以下「たてまつらまほしきにやあらむ」まで、語り手の言辞。『一葉抄』は「双紙の詞也」と指摘。『集成』は「以下、草子地。手の平をかえしたような宮の欠点のあげつらいを、軽く揶揄するような筆致」。『完訳』は「柏木は恋の情念を払うべく、強いて宮の欠点をあげつらうのだとする、語り手の揶揄的な評言」と注す。
|
|
第三段 源氏、女三の宮の幼さを非難
|
| 10.3.1 |
「良きやうとても、あまりひたおもむきにおほどかにあてなる人は、世のありさまも知らず、かつ、さぶらふ人に心おきたまふこともなくて、かくいとほしき御身のためも、人のためも、いみじきことにもあるかな」 |
「良いことだからと言って、あまり一途におっとりし過ぎている高貴な人は、世間の事もご存知なく、一方では、伺候している女房に用心なさることもなくて、このようにおいたわしいご自身にとっても、また相手にとっても、大変な事になるのだ」
|
どんなに貴人といっても、おおようで、気持ちの柔らかい一方な人は世間のこともわからず、侍女というものに警戒をしなければならぬこともお知りにならないで、取り返しのつかぬあやまちを御自身のためにも作り、
|
【良きやうとても】- 以下「いみじきことにもあるかな」まで、柏木の心中。宮の境遇への同情。
|
| 10.3.2 |
と、かの御ことの心苦しさも、え思ひ放たれたまはず。
|
と、あのお方をお気の毒だと思う気持ちも、お捨てになることができない。
|
人にも罪を犯させる結果になったと思い、衛門督の心は、
|
|
| 10.3.3 |
|
宮はまことに痛々しげにお苦しみ続けなさる様子が、やはりとてもお気の毒で、このようにお見限りになるにつけては、妙に嫌な気持ちに消せない恋しい気持ちが苦しく思われなさるので、お越しになって、お目にかかりなさるにつけても、胸が痛くおいたわしく思わずにはいらっしゃれない。
|
宮のお気の毒なことを思いやって堪えがたい苦悶をするのであった。宮が可憐な姿で悪阻に悩んでおいでになるのが院のお目に浮かんで、心苦しく哀れにお思われになった。良人としての愛は消えたように思っておいでになっても、恨めしいのと並行して恋しさもおさえがたくおなりになり、六条院へおいでになった。お顔を御覧になると胸苦しくばかりおなりになる院でおありになった。
|
【かく思ひ放ちたまふにつけては】- 主語は源氏。源氏が女三の宮を。
【あやにくに、憂きに紛れぬ恋しさの苦しく思さるれば】- 源氏の「あやにく」な性癖。「紛れ」「ぬ」打消の助動詞。『集成』は「あいにくなことに、情けない思いだけではごまかされない、宮恋しさの思いが、せつないまでにこみ上げるので」。『完訳』は「あいにくなことに、厭わしく思う気持だけからはとりつくろえぬ恋しさをどうすることもならず」と訳す。
【胸いたくいとほしく思さる】- 源氏の女三の宮に対する気持ち。
|
| 10.3.4 |
|
御祈祷などを、いろいろとおさせになる。
大体のことは、以前と変わらず、かえって労り深く大事にお持てなし申し上げる態度がお加わりさる。
身近にお話し合いなさる様子は、まことにすっかりお心が離れてしまって、体裁が悪いので、人前だけは体裁をつくろって、苦しみ悩んでばかりなさっているので、ご心中は苦しいのであった。
|
祈祷を寺々へ命じてさせてもおいでになるのである。表面のお扱いでは以前と何も変わっていない。かえって御優遇をあそばされるようにも見えるのであるが、夫婦としてお親しみになることはそれ以来断えてしまった。人目を紛らすために御同室にお寝みになりながら、院がお一人で煩悶をしておいでになるのを御覧になる宮のお心は苦しかった。
|
【ありしに変らず、なかなか労しくやむごとなくもてなしきこゆるさまを】- 源氏の女三の宮に対する態度やもてなしは以前以上の丁重さが加わる。
【気近くうち語らひきこえたまふさまは、いとこよなく御心隔たりて】- その反面、二人だけとなると気持ちの隔たりが消しがたい。気持ちと行動が別々な源氏の矛盾した行動。「あやにく」な性格の具体的現れ。
【この御心のうちしもぞ苦しかりける】- 語り手の批評。『休聞抄』は『双也」と指摘。『完訳』は「宮もお心の中にはいっそうつらくお感じになるのであった」「宮の心。表向きの世話だけで物思いがちな源氏に、隔意を痛感」と注す。耳から文章を聞いて、どちらに主点が置かれて語られているかによって「御心」が決定しよう。
|
| 10.3.5 |
|
そうした手紙を見たともはっきり申し上げなさらないのに、ご自分でとてもむやみに苦しみ悩んでいらっしゃるのも子供っぽいことである。
|
秘密を知ったともお言いにならぬ院でおありになったが、女宮は御自身で罪人らしく萎縮しておいでになるのも幼稚な御態度である。
|
【みづからいとわりなく思したるさまも、心幼し】- 語り手の女三の宮批評。
|
| 10.3.6 |
「いとかくおはするけぞかし。良きやうといひながら、あまり心もとなく後れたる、頼もしげなきわざなり」 |
「まことにこんなお人柄である。
良い事だとは言っても、あまりに気がかりなほどおっとりし過ぎているのは、何とも頼りないことだ」
|
こんなふうの人であるから不祥事も起こったのであろう。貴女らしいとはいってもあまりに柔らかな性質は頼もしくないものであるとお考えになると、
|
【いとかくおはするけぞかし】- 以下「頼もしげなきわざなり」まで、源氏の心中。
|
| 10.3.7 |
と思すに、世の中なべてうしろめたく、
|
とお思いになると、男女の仲の事がすべて心もとなく、
|
いろいろの人の上がお気がかりになった。
|
|
| 10.3.8 |
|
「女御が、あまりにやさしく穏やかでいらっしゃるのは、このように懸想するような人は、これ以上にきっと心が乱れることであろう。
女性は、このように内気でなよなよとしているのを、男も甘く見るのだろうか、あってはならぬが、ふと目にとまって、自制心のない過失を犯すことになるのだ」
|
女御があまりに柔軟な様子であることは、この宮における衛門督のような恋をする男があるとすれば、その目に触れた以上精神を取り乱して大過失を引き起こすに至るかもしれぬ、女性のこうした柔らかい一方である人は、軽侮してよいという心を異性に呼ぶのか、刹那的に不良な行為をさせてしまうものである
|
【女御の、あまりやはらかにおびれたまへるこそ】- 以下「し出づるなりけり」まで、源氏の心中。転じて明石の女御を心配する。
【女は、かうはるけどころなくなよびたるを】- 女の弱点。
|
| 10.3.9 |
と思す。
|
とお思いになる。
|
と、院はこんなこともお思いになった。
|
|
|
第四段 源氏、玉鬘の賢さを思う
|
| 10.4.1 |
|
「右大臣の北の方が、特にご後見もなく、幼い時から、頼りない生活を流浪するような有様で、ご成人なさったが、利発で才気があって、自分も表向きは親のようにしていたが、憎からず思う心がないでもなかったが、穏やかにさりげなく受け流して、あの大臣が、あのような心ない女房と心を合わせて入って来たときにも、はっきりと受け付けなかった態度を、周囲の人にも見せて分からせ、改めて許された結婚の形にしてから、自分のほうに落度があったようにはしなかった事など、今から思うと、何とも賢い身の処し方であった。
|
右大臣夫人がそれという世話を受ける人もなくて、幼年時代から苦労をしながら才も見識もあって、自分なども義父らしくはしながらも、恋人に擬しておさえがたい情念を内に包んでいたのを、かどだたず気がつかぬふうに退け続けて、右大臣が軽佻な女房の手引きでしいて結婚を遂げた時にも、自身は単なる受難者であることを、それ以後の態度で明らかにして、親や身内の意志で成立した夫婦の形を作らせたことなどは、今思ってみてもきわめてりっぱなことであったと、玉鬘のこともこのふがいない人に比べてお思われになった。
|
【右の大臣の北の方の】- 以下「もてなしてしわざなり」まで、源氏の心中。転じて玉鬘のことを思い出す。
【憎き心】- けしからぬ好色心。
【なだらかにつれなくもてなして過ぐし】- 源氏をうまく拒み続けた玉鬘の態度。
【ことさらに許されたるありさまにしなして】- 『集成』は「わざわざ、源氏や実の父内大臣に許されての結婚というように事を運んで」と訳す。
【わが心と罪あるにはなさずなりにしなど】- 玉鬘は鬚黒大将との結婚をいっさい自分の方には落度がなかったようにした身の処し方を立派であったと、改めて感心する。
|
| 10.4.2 |
|
宿縁の深い仲であったので、長くこうして連れ添ってゆくことは、その初めがどのような事情からであったにせよ、同じような事であったろうが、自分の意志でしたのだと、世間の人も思い出したら、少しは軽率な感じが加わろうが、本当に上手に身を処したことだ」とお思い出しになる。
|
深い宿縁があって夫婦になった人であるから、離婚をしようとは考えないが、品行問題で世評の立つことになれば、それにしたがって知らず知らず多少の侮蔑を自分は加えることになるであろう。あまりにも実質に伴わない尊敬をしてきたと、以前からのことを思ってもごらんになった。
|
【心もてありしこととも】- 自分の方から望んでおこなったの意。結婚における女性の態度は主体的よりも受動的な身の処し方をよしとした。
【すこし軽々しき思ひ加はりなまし】- 反実仮想の構文。玉鬘には軽々しいという非難がいっさいなかった。
|
|
第五段 朧月夜、出家す
|
| 10.5.1 |
二条の尚侍の君をば、なほ絶えず、思ひ出できこえたまへど、かくうしろめたき筋のこと、憂きものに思し知りて、かの御心弱さも、少し軽く思ひなされたまひけり。
|
二条の尚侍の君を、依然として忘れず、お思い出し申し上げなさるが、このように気がかりな方面の事を、厭わしくお思いになって、あの方のお心弱さも、少しお見下しなさるのだった。
|
院は二条の朧月夜の尚侍になお心を惹かれておいでになるのであったが、女三の宮の事件によって、後ろ暗い行動はすべきでないという教訓を得たようにお思いになって、その人の弱さにさえ反感に似たようなものをお覚えになった。
|
|
| 10.5.2 |
つひに御本意のことしたまひてけりと聞きたまひては、いとあはれに口惜しく、御心動きて、まづ訪らひきこえたまふ。今なむとだににほはしたまはざりけるつらさを、浅からず聞こえたまふ。 |
とうとうご出家の本懐を遂げられたとお聞きになってからは、まことにしみじみと残念に、お心が動いて、さっそくお見舞いを申し上げなさる。
せめて今出家するとだけでも知らせて下さらなかった冷たさを、心からお恨み申し上げなさる。
|
尚侍が以前から希望していたとおりに尼になったことをお聞きになった時には、さすがに残念な気がされてすぐに手紙をお書きになった。その場合に臨んで、されてよい予報のなかったことをお恨みになる言葉がつづられてあった。
|
【つひに御本意のことしたまひてけり】- 朧月夜尚侍が出家したという話。
|
| 10.5.3 |
|
「出家されたことを他人事して聞き流していられましょうか
わたしが須磨の浦で涙に沈んでいたのは誰ならぬあなたのせいなのですから
|
あまの世をよそに聞かめや須磨の浦に
藻塩垂れしもたれならなくに
|
【海人の世をよそに聞かめや須磨の浦に--藻塩垂れしも誰れならなくに】- 源氏から朧月夜尚侍への贈歌。出家を聞いて贈る。「尼」に「海人」を掛ける。
|
| 10.5.4 |
さまざまなる世の定めなさを心に思ひつめて、今まで後れきこえぬる口惜しさを、思し捨てつとも、避りがたき御回向のうちには、まづこそはと、あはれになむ」 |
いろいろな人生の無常さを心の内に思いながら、今まで出家せずに先を越されて残念ですが、お見捨てになったとしても、避けがたいご回向の中には、まず第一にわたしを入れて下さると、しみじみと思われます」
|
人世の無常さを味わい尽くしながらも、今日まで出家を実行しえない私を、あなたはどんなに冷淡になっておいでになってもさすがに回向の人数の中にはお入れくださるであろうと、頼みにされるところもあります。
|
【さまざまなる世の】- 以下「あはれになむ」まで、和歌に続けた源氏の文。
|
| 10.5.5 |
など、多く聞こえたまへり。
|
などと、たくさんお書き申し上げなさった。
|
などという長いお文であった。
|
|
| 10.5.6 |
|
早くからご決意なさった事であるが、この方のご反対に引っ張られて、誰にもそのようにはお表しなさらなかった事だが、心中ではしみじみと昔からの恨めしいご縁を、何と言っても浅くはお思いになれない事など、あれやこれやとお思い出さずにはいらっしゃれない。
|
早くからの志であったが、六条院がお引きとめになるために、それでない表面の理由は別として、尚侍は尼になるのを躊躇するところがあったのでさえあるから、このお手紙を見て青春時代から今日までの二人のつながりの深さも今さらに思われて身にしむ尚侍であった。
|
【この御妨げにかかづらひて】- 源氏が朧月夜尚侍の出家を引き止めること。
【かたがたに思し出でらる】- 『集成』は「つらかったことといい、また深いかかわりといい、それぞれ昔のことが思い出される」と訳す。
|
| 10.5.7 |
御返り、今はかくしも通ふまじき御文のとぢめと思せば、あはれにて、心とどめて書きたまふ、墨つきなど、いとをかし。
|
お返事は、今となってはもうこのようなお手紙のやりとりをしてはならない最後とお思いになると、感慨無量となって、念入りにお書きになる、その墨の具合などは、実に趣がある。
|
返事はもう今後書きかわすことのない終わりのものとして心をこめて書いた尚侍の手跡が美しかった。
|
|
| 10.5.8 |
|
「無常の世とはわが身一つだけと思っておりましたが、先を越されてしまったとの仰せを思いますと、おっしゃるとおり、
|
無常は私だけが体験から知ったものと思っておりましたが、しおくれたと仰せになりますことで、こんなにも思われます。
|
【常なき世とは】- 以下「いかがは」まで、朧月夜尚侍の源氏への返書。
|
| 10.5.9 |
|
尼になったわたしにどうして遅れをおとりになったのでしょう
明石の浦に海人のようなお暮らしをなさっていたあなたが
|
あま船にいかがは思ひおくれけん
明石の浦にいさりせし君
|
【海人舟にいかがは思ひおくれけむ--明石の浦にいさりせし君】- 朧月夜尚侍の源氏への返歌。「海人の世」「須磨の浦」の語句を受けて「海人舟」「明石の浦」と返す。「あま」に「尼」と「海人」を掛ける。「いさり」は漁りの意だが、裏に明石君との結婚をこめるか。『完訳』は「流離の真意は明石の君との邂逅にあったと切り返す」と注す。
|
| 10.5.10 |
|
回向は、一切衆生の為のものですから、どうして含まれないことがありましょうか」
|
回向には、この世のすぐれた方として決してあなた様を洩らしはいたしません。
|
【回向には、あまねきかどにても、いかがは】- 『集成』は「「あまねきかど」は「普門」をそのまま和らげたもの。「是の観世音菩薩の自在の業、普門示現の神通力を聞かむ者は、当に知るべし、是の人は功徳少なからじ」(『法華経』観世音菩薩普門品第二十五)」と注す。
|
| 10.5.11 |
とあり。
濃き青鈍の紙にて、樒にさしたまへる、例のことなれど、いたく過ぐしたる筆づかひ、なほ古りがたくをかしげなり。
|
とある。
濃い青鈍色の紙で、樒に挟んでいらっしゃるのは、通例のことであるが、ひどく洒落た筆跡は、今も変わらず見事である。
|
これが内容である。濃い鈍色の紙に書かれて、樒の枝につけてあるのは、そうした人のだれもすることであっても、達筆で書かれた字に今も十分のおもしろみがあった。
|
|
|
第六段 源氏、朧月夜と朝顔を語る
|
| 10.6.1 |
二条院におはしますほどにて、女君にも、今はむげに絶えぬることにて、見せたてまつりたまふ。
|
二条院にいらっしゃる時なので、女君にも、今ではすっかり関係が切れてしまったこととて、お見せ申し上げなさる。
|
この日は二条の院においでになったので、夫人にも、もう実際の恋愛などは遠く終わった相手のことであったから、院はお見せになった。
|
|
| 10.6.2 |
|
「とてもひどくやっつけられたものです。
本当に、
気にくわないよ。いろいろと心細い世の中の様子を、よく見過して
来たものですよ。普通の世間話でも、ちょっと何か言い交わしあい、四季折々に寄せて、情趣をも知り、風情を見逃さず、色恋を離れて付き合いのできる人は、斎院とこの君とが生き残っているが、このように皆出家してしまって、斎院は斎院で、熱心にお勤めして、余念なく勤行に精進していらっしゃ
|
「こんなふうに侮辱されたのが残念だ。どんな目にあっても平気なように思われて恥ずかしい。恋愛的な交際ではなしに、友人として同程度の趣味を解する人で、仲よくできる異性はこの人と斎院だけが私に残されていたのだが、今はもう尼になってしまわれた。ことに斎院などは尼僧の勤めをする一方の人になっておしまいになった。
|
【いといたくこそ】- 以下「助けられぬるを」まで、源氏の詞。
【よそながらの睦び交はしつべき人は、斎院とこの君とこそは】- 『集成』は「さっぱりとした親しい付合いをすることのできる人は」。『完訳』は「離れていても親しくお付合いのできる人としては」と訳す。
【かくみな背き果てて、斎院はた、いみじうつとめて】- 朝顔斎院の出家はここに初めて語られる。
【たまひにたなり】- 「に」完了の助動詞。「た(る)」完了の助動詞、存続の意。「なり」伝聞推定の助動詞。
|
| 10.6.3 |
なほ、ここらの人のありさまを聞き見る中に、深く思ふさまに、さすがになつかしきことの、かの人の御なずらひにだにもあらざりけるかな。女子を生ほし立てむことよ、いと難かるべきわざなりけり。 |
やはり、大勢の女性の様子を見たり聞いたりした中で、思慮深い人柄で、それでいて心やさしい点では、あの方にご匹敵する人はいなかったなあ。
女の子を育てることは、まことに難しいことだ。
|
多くの女性を見てきているが、高い見識をお持ちになって、しかもなつかしい匂いの備わっているような点であの方に及ぶ人はなかった。女を教育するのはむずかしいものですよ。
|
【かの人の御なずらひに】- 朝顔斎院をさす。
|
| 10.6.4 |
宿世などいふらむものは、目に見えぬわざにて、親の心に任せがたし。
生ひ立たむほどの心づかひは、なほ力入るべかめり。
よくこそ、あまたかたがたに心を乱るまじき契りなりけれ。
年深くいらざりしほどは、さうざうしのわざや、さまざまに見ましかばとなむ、嘆かしきをりをりありし。
|
宿世などと言うものは、目に見えないことなので、親の心のままにならない。
成長して行く際の注意は、やはり力を入れねばならないようです。
よくぞまあ、大勢の女の子に心配しなくてもよい運命であった。
まだそれほど年を取らなかったころは、もの足りないことだ、何人もいたらと嘆かわしく思ったことも度々あった。
|
夫婦になる宿命というものは、目に見えないもので、親の力でどうしようもないものだから、結婚するまでの女の子の教育に親は十分力を尽くすべきだと思う。私は娘を一人しか持たなくてその責任の少ないのがうれしい。まだ若くて人生のよくわからなかったころは、子の少ないことが寂しく思われもしたものですがね。
|
|
| 10.6.5 |
|
若宮を、注意してお育て申し上げて下さい。
女御は、物の分別を十分おわきまえになる年頃でなくて、このようにお暇のない宮仕えをなさっているので、何事につけても頼りないといったふうでいらっしゃるでしょう。
内親王たちは、やはりどこまでも人に後ろ指をさされるようなことなくして、一生をのんびりとお過ごしなさるように、不安でない心づかいを、付けたいものです。
身分柄、あれこれと夫をもつ普通の女性であれば、自然と夫に助けられるものですが」
|
まあ孫の内親王をよくお育てしておあげなさい。女御はまだ大人になりきらないで宮廷へはいってしまったのだから、すべてがいまだに不完全なものだろうと思われる。姫宮の教育は最高の女性を作り上げる覚悟で、微瑕もない方にして、一生を御独身でお暮らしになってもあぶなげのない素養をつけたいものですね。結婚をすることになっている普通の家の娘はまた良人さえりっぱであれば、それに助けられてゆくこともできますがね」
|
【若宮を、心して】- 明石女御所生の女一の宮をさす。
【かく暇なき交らひをしたまへば】- 帝の寵愛が厚く、里下がりもままならぬ状況をさす。
【点つかるまじくて】- 欠点や後ろ指をさされるようなことなく。
【とざまかうざまの後見まうくるただ人は】- 『完訳』は「それぞれに相応の夫をもつ普通の女であれば」と訳す。
|
| 10.6.6 |
など聞こえたまへば、
|
などと申し上げなさると、
|
などと院がお言いになると、
|
|
| 10.6.7 |
「はかばかしきさまの御後見ならずとも、世にながらへむ限りは、見たてまつらぬやうあらじと思ふを、いかならむ」 |
「しっかりしたしたご後見はできませんでも、世に生き永らえています限りは、是非ともお世話してさし上げたいと思っておりますが、どうなることでしょう」
|
「りっぱなお世話はできませんでも、生きています間は姫宮のおためになりたい心でございますが、健康がこんなのではね」
|
【はかばかしきさまの】- 以下「いかならむ」まで、紫の上の詞。
【いかならむ】- 『集成』は「どうなりますことやら。いつまでお世話できるか心もとないと、余命をあやぶむ」と注す。
|
| 10.6.8 |
とて、なほものを心細げにて、かく心にまかせて、行なひをもとどこほりなくしたまふ人びとを、うらやましく思ひきこえたまへり。
|
と言って、やはり何か心細そうで、このように思いどおりに、仏のお勤めを差し障りなくなさっている方々を、羨ましくお思い申し上げていらっしゃった。
|
と答えて夫人は心細いふうにわが身を思い、自由に信仰生活へはいることのできた人々をうらやましく思った。
|
|
| 10.6.9 |
|
「尚侍の君に、尼になられた衣装など、まだ裁縫に馴れないうちはお世話すべきであるが、袈裟などはどのように縫うものですか。
それを作って下さい。
一領は、六条院の東の君に申し付けよう。
正式の尼衣のようでは、見た目にも疎ましい感じがしよう。
そうはいっても、法衣らしいのが分かるのを」
|
「尚侍の所は尼装束などもまだよくととのっていないことだろうから、早く私から贈りたいと思うが、袈裟などというものはどんなふうにしてこしらえるものだろう。あなたがだれかに命じて縫わせてください。一そろいは六条の東の人にしてもらいましょう。あまりに法服らしくなっては見た感じもいやだろうから、その点を考慮して作るのですね」
|
【尚侍の君に】- 以下「心ばへ見せてを」まで、源氏の詞。
【それせさせたまへ】- 源氏、紫の上に朧月夜尚侍の袈裟を作ることを依頼する。
【六条の東の君にものしつけむ】- 花散里に申し付けよう。花散里が裁縫にたけた女性であることは「少女」巻に語られている。
|
| 10.6.10 |
など聞こえたまふ。
|
などと申し上げなさる。
|
と院はお言いになった。
|
|
| 10.6.11 |
青鈍の一領を、ここにはせさせたまふ。作物所の人召して、忍びて、尼の御具どものさるべきはじめのたまはす。御茵、上席、屏風、几帳などのことも、いと忍びて、わざとがましくいそがせたまひけり。 |
青鈍の一領を、こちらではお作らせになる。
宮中の作物所の人を呼んで、内々に、尼のお道具類で、しかるべき物をはじめとしてご下命なさる。
御褥、上蓆、屏風、几帳などのことも、たいそう目立たないようにして、特別念を入れてご準備なさったのであった。
|
青鈍色の一そろいを夫人は新尼君のために手もとで作らせた。院は御所付きの工匠をお呼び寄せになって、尼用の手道具の製作を命じたりしておいでになった。座蒲団、上敷、屏風、几帳などのこともすぐれた品々の用意をさせておいでになった。
|
【作物所の人召して】- 蔵人所に属し、宮中の調度類や細工物を作製する役所。その人たちに作製を私的に依頼する。
|
|
第十一章 朱雀院の物語 五十賀の延引
|
|
第一段 女二の宮、院の五十の賀を祝う
|
| 11.1.1 |
|
こうして、山の帝の御賀も延期になって、秋にとあったが、八月は大将の御忌月で、楽所を取り仕切られるのには、不都合であろう。
九月は、院の大后がお崩れになった月なので、十月にとご予定を立てたが、姫宮がひどくお悩みになったので、再び延期になった。
|
紫夫人の大病のために法皇の賀宴も延びて秋ということになっていたが、八月は左大将の忌月で音楽のほうをこの人が受け持つのに不便だと思われたし、九月はまた院の太后のお崩れになった月で、それもだめ、十月にはと六条院は思っておいでになったが、女三の宮の御健康がすぐれないためにまた延びた。
|
【かくて、山の帝の御賀も延びて】- 朱雀院の五十賀。「山の帝」の呼称は初見。源氏主催の御賀は、最初、二月二十余日の予定だったが、紫の上の発病によって延期になっていた。『集成』は、女三の宮主催の御賀という。源氏主催といっても、女三の宮の夫としての主催である。
【八月は大将の御忌月にて】- 夕霧大将の母葵の上は八月に逝去。賀宴には近衛府の楽人が演奏するので、その長官である夕霧が取り仕切るのは不都合だという。
【九月は、院の大后の崩れたまひにし月なれば】- 弘徽殿大后の御忌月。
【姫宮いたく悩みたまへば】- 女三の宮、妊娠七月になる。
|
| 11.1.2 |
|
衛門督がお引き受けになっている宮が、その月には御賀に参上なさったのだった。
太政大臣が奔走して、盛大にかつこまごまと気を配って、儀式の美々しさ、作法の格式の限りをお尽くしなさっていた。
督の君も、その機会には、気力を出してご出席なさったのだった。
やはり、気分がすぐれず、普通と違って病人のように日を送ってばかりいらっしゃる。
|
衛門督の夫人になっておいでになる宮はその月に参入された。舅の太政大臣が力を入れて豪奢な賀宴がささげられたのである。病気で引きこもっていた衛門督もその時はじめて外出をしたのであった。しかもそのあとはまた以前にかえって、病床に親しむ督であった。
|
【衛門督の御預かりの宮なむ】- 朱雀院の女二の宮、通称、落葉宮。「御預かりの宮」という呼称表現が注目される。『集成』は「衛門督が、正室としてお世話申し上げている女二の宮」。『完訳』は「衛門督がお迎えしている女二の宮が」と訳す。
【その月には参りたまひける】- 十月に、朱雀院の御所に御賀に参上した、という意。
|
| 11.1.3 |
|
宮も、引き続いて何かと気がめいって、ただつらいとばかりお思い嘆いていられるせいであろうか、懐妊の月数がお重なりになるにつれて、とても苦しそうにいらっしゃるので、院は、情けないとお思い申し上げなさる気持ちはあるが、とても痛々しく弱々しい様子をして、このようにずっとお悩みになっていらっしゃるのを、どのようにおなりになることかと心配で、あれこれとお心をお痛めになられる。
ご祈祷など、今年は取り込み事が多くてお過ごしになる。
|
女三の宮も御煩悶ばかりをあそばされるせいか、月が重なるにつれてますますお身体がお苦しいふうに見えた。院は恨めしいお気持ちはあっても、可憐な姿をして病んでおいでになる宮を御覧になっては、どうなるのであろうと不安を覚えてお歎きになることが多かった。祈祷をおさせになることで御多忙でもあった。
|
【思し嘆くにやあらむ】- 係助詞「や」疑問、推量の助動詞「む」。語り手の推測の気持ちをを介在させた挿入句。
【月多く重なりたまふままに】- 懐妊の月数をさす。
【院は、心憂しと思ひきこえたまふ方こそあれ】- 係助詞「こそ」「あれ」已然形、係結び、逆接で下文に続く。
【御祈りなど、今年は紛れ多くて過ぐしたまふ】- 紫の上、女三の宮の病気平癒のための御祈祷。何かととりこみ事が多い、という意。
|
|
第二段 朱雀院、女三の宮へ手紙
|
| 11.2.1 |
|
お山におかせられてもお耳にあそばして、いとおしくお会いしたいとお思い申し上げなさる。
いく月もあのように別居していて、お越しになることもめったにないように、ある人が奏上したので、どうしたことにかとお胸が騒いで、俗世のことも今さらながら恨めしくお思いになって、
|
法皇も宮の御妊娠のことをお聞きになって、かわいく想像をあそばされ、逢いたく思召された。長く六条院は二条の院のほうに別れておいでになって、お訪ねになることもまれまれであると申し上げた人も以前あったことによって、御妊娠がただ事の結果でなくはないのであるまいかとふとこんなことを思召すとお胸が鳴るのでもあった。人生のことが今さら皆お恨めしくて、
|
【御山にも聞こし召して】- 朱雀院が女三の宮懐妊の事をお聞きになって、の意。
【をさをさなきやうに、人の奏しければ】- 源氏は紫の上の病気もほぼ平癒したにもかかわらず、六条院にはほとんどもどらず、二条院にとどまったままでいる。
【いかなるにかと御胸つぶれて】- 朱雀院の心中。懐妊してめでたいというのに、夫婦別居しているとは、いかなる事情があってか、という気持ちだろう。
【世の中も今さらに恨めしく思して】- 「世の中」は夫婦の仲。係助詞「も」強調のニュアンスを添える。「今さらに」とは出家した身でという気持ち。
|
| 11.2.2 |
|
「対の方が病気であったころは、やはりその看病でとお聞きになってでさえ、心穏やかではなかったのに、その後も、変わらずにいらっしゃるとは、そのころに、何か不都合なことが起きたのだろうか。
宮自身に責任がおありのことでなくても、良くないお世話役たちの考えで、どんな失態があったのだろうか。
宮中あたりなどで、風雅なやりとりをし合う間柄などでも、けしからぬ評判を立てる例も聞こえるものだ」
|
紫夫人の病気のころは院があちらにばかり行っておいでになったのを、もっともなこととはいえ、思いやりのないこととして聞いておいでになったが、夫人の病後も院の御訪問はまれになったというのは、その間に不祥なことが起こったのではあるまいか。宮が自発的に堕落の傾向をおとりになったのではなく、軽薄な女房の仕業などで不快な事件があったのではなかろうか、宮廷における男女の間は清潔な交際で終始しなければならないものであるのに、その中にさえ醜聞を作る者があるのであるから
|
【対の方のわづらひけるころは】- 以下「聞こゆかし」まで、朱雀院の心中。途中に語り手の朱雀院に対する敬意が混入する。『集成』は「以下、朱雀院の心中」「「聞こしめしてだに」は、語り手の敬意の表れたものと見る」と注す。
【そののち、直りがたく】- 『完訳』は、以下を朱雀院の心中とする。
【そのころほひ、便なきことや出で来たりけむ】- 「そのころほひ」は妊娠のきっかけをさそう。
【みづから知りたまふことならねど】- 宮御自身関知しないことでも、の意。
【いかなることかありけむ】- 『集成』は「どんな失態があったのだろう」。『完訳』は「何かがあったのだろうか」と訳す。
|
| 11.2.3 |
|
とまでお考えになるのも、肉親の情愛はお捨てになった出家の生活だが、やはり親子の愛情は忘れ去りがたくて、宮にお手紙を心をこめて書いてあったのを、大殿も、いらっしゃった時なので、御覧になる。
|
と、こんなことまでも御想像あそばされるのは、いっさいをお捨てになった御心境にもなお御子をお思いになる愛情だけは影を残しているからである。法皇が愛のこもったお手紙を宮へお書きになったのを、六条院も来ておいでになる時で拝見されたのであった。
|
【こまやかなること思し捨ててし世なれど】- 「こまやかなること」について、『集成』は「肉親の情愛などは」、『完訳』は「俗世のわずらわしいことは」と訳す。
|
| 11.2.4 |
|
「特に用件もないので、たびたびはお便りを差し上げなかったうちに、あなたの様子も分からないままに歳月が過ぎるのは、気がかりなことです。
お具合がよろしくなくいらっしゃるという様子は、詳しく聞いてからは、念仏誦経の時にも気にかかってならないが、いかがいらっしゃいますか。
ご夫婦仲が寂しくて意に満たないことがあっても、じっと堪えてお過ごしなさい。
恨めしそうな素振りなどを、いい加減なことで、心得顔にほのめかすのは、まことに品のないことです」
|
用事もないものですから無沙汰をしているうちに月日がたつということもこの世の悲しみです。あなたが普通でない身体になって健康もそこねているということをくわしく聞きましたが、今はどうですか。世の中が寂しくなるような運命に出あっても、忍んでお暮らしなさい。恨めしがる様子をお見せになったり、妬みを告げたりすることは上品なものではありません。
|
【そのこととなくて】- 以下「おくれたるわざになむ」まで、朱雀院から女三の宮への手紙。
【あはれなりける】- 『集成』は「気がかりなことです」。『完訳』は「悲しいことです」。『新大系』はさびしいことであった」と訳す。
【思ひやらるるは、いかが】- 『完訳』は「現世への未練が残るのはどうしたことか。自分自身の心を疑う」と注す。
【恨めしげなるけしきなど、おぼろけにて、見知り顔にほのめかす、いと品おくれたるわざになむ】- 皇女の身の処し方についての教訓。「帚木」巻の夫婦処世術と比較。『集成』は「いい加減なことで、心得顔にちらつかすのは、はしたないことです」と訳す。
|
| 11.2.5 |
など、教へきこえたまへり。
|
などと、お教え申し上げていらっしゃった。
|
などと訓しておありになるのである。
|
|
| 11.2.6 |
|
まことにお気の毒で心が痛み、「このような内々の宮の不始末を、お耳にあそばすはずはなく、わたしの怠慢のせいにと、御不満にばかりお思いあそばすことだろう」とばかりにお思い続けて、
|
院はお気の毒で、心苦しくて、宮に秘密のあることなどはお知りあそばされずに、自分の不誠意とばかり解釈しておいでになるのであろうとお思いになって、
|
【かかるうちうちのあさましきをば】- 以下「思すらむことを」まで、源氏の心中。「うちうちのあさましきこと」は女三の宮の不始末をさす。そうした自分の娘の不始末は朱雀院は知らないで、の意。
【わがおこたりに、本意なくのみ聞き思すらむことを】- 源氏の愛情の薄い原因ばかりに思っていることだろう、の意。「を」終助詞、詠嘆。
|
| 11.2.7 |
|
「このお返事は、どのようにお書き申し上げなさいますか。
お気の毒なお手紙で、わたしこそとても辛い思いです。
たとえ心外にお思い申す事があったとしても、疎略なお扱いをして、人が変に思うような態度はとるまいと思っております。
誰が申し上げたのでしょうか」
|
「お返事はどうお書きになりますか。心苦しいお手紙で私はつらい気がしますよ。あなたにどんなことがあっても、人に変わった様子は見せまいと私は努めているのですよ。だれがいろいろなことを申し上げたのだろう」
|
【この御返りをば、いかが聞こえたまふ】- 以下「誰が聞こえたるにかあらむ」まで、源氏の詞。
【まろこそいと苦しけれ】- 『完訳』は「私こそ、じつにつらい。不義ゆえの不快さをこめていう」と注す。
【思はずに思ひきこゆることありとも】- 柏木との不義ををさす。
|
| 11.2.8 |
|
とおっしゃると、恥ずかしそうに横を向いていらっしゃるお姿も、まことに痛々しい。
ひどく面やつれして、物思いに沈んでいらっしゃるのは、ますます上品で美しい。
|
とお言いになると、恥じて顔をおそむけになる宮のお姿が可憐であった。顔がすっかり痩せて物思いに疲れておいでになるのが上品に美しい。
|
【とのたまふに、恥ぢらひて背きたまへる】- 柏木との過失を暗に言われて恥じる。源氏のいじわるな態度である。
【いたく面痩せて、もの思ひ屈したまへる、いとどあてにをかし】- 深刻な局面も唯美的関心に移り、この場面は切り上げられる。
|
|
第三段 源氏、女三の宮を諭す
|
| 11.3.1 |
|
「とても幼い御気性を御存知で、たいそう御心配申し上げていらっしゃるのだと、拝察されますので、今後もいろいろと心配でなりません。
こんなにまでは決して申し上げまいと思いましたが、院の上が、御心中にわたしが背いているとお思いになろうことが、不本意であり、心の晴れない思いであるが、せめてあなたにだけは申し上げておかなくてはと思いまして。
|
「あなたの幼稚な性質を知っておいでになって、こんなにもお言いになるのだと、私は他のことと思い合わせてごもっともだと思われる点がありますよ。それで今後も危なかしく思われてならない。こんなふうに言ってしまおうとは思わなかったことですが、院が私を頼みがいなく思召すだろうと思うことが苦痛ですからね。あなただけにでも私が軽薄な者でないことを認めてほしいと思うのですよ。
|
【いと幼き御心ばへを】- 以下「罪いと恐ろしからむ」まで、源氏の詞。この冒頭の「幼し」「うしろめたがる」などの発言は女三の宮の幼さを面と向かってののしっているにも等しいきつい表現。
【よろづになむ】- 言いさした形。下に、心配でならない、また同様な過ちを犯すかもしれないのが気がかりだ、という意をこめる、余意・含みのある表現。
【ここにだに聞こえ知らせでやはとてなむ】- 源氏の薄情に見える態度の原因をいう。以下、柏木との密通が原因であることを暗にいう。
|
| 11.3.2 |
|
思慮が浅く、ただ、人が申し上げるままにばかりお従いになるようなあなたとしては、ただ冷淡で薄情だとばかりお思いで、また、今ではわたしのすっかり年老いた様子も、軽蔑し飽き飽きしてばかりお思いになっていられるらしいのも、それもこれも残念にも忌ま忌ましくも思われますが、院の御存命中は、やはり我慢して、あちらのお考えもあったことでしょうから、この年寄をも、同じようにお考え下さって、ひどく軽蔑なさいますな。
|
深く物をお考えにならないで、人のいいかげんな言葉にお動きになるあなたには、私のほんとうの愛が浅いものに見えもするでしょうし、またあなたとは年齢の差のはなはだしい良人を軽蔑したくもなるでしょうけれど、私としてそれを残念に思わないわけはありませんが、院の御在世中だけは、これを幸福な道としてお選びになったことですから、老いた良人をもあまり無視するようなことはお慎みになるがいいのですよ。
|
【いたり少なく、ただ、人の聞こえなす方にのみ】- 女三の宮には思慮分別がないと、面と向かっていう。罵倒するに等しい発言。
【ただおろかに浅きとのみ思し】- 源氏の態度をさしていう。
【今はこよなくさだ過ぎにたるありさまも、あなづらはしく目馴れてのみ見なしたまふらむも】- 源氏の老齢をさしていう。『集成』は「以下、自分の薄情を怨んで、若い柏木と通じたと、暗に怨んで言う」。『完訳』は「自らを老醜と自嘲し、以下に、柏木と通じた宮を暗に非難」と注す。
【かたがたに口惜しくもうれたくもおぼゆるを】- 「ただ愚かに浅き」と「こよなくさだ過ぎたる」とをさしていう。
【院のおはしまさむほどは、なほ心収めて】- 主語は女三の宮。しかし、この部分だけでは、源氏にもとれる。朱雀院が生きていらっしゃるうちは、自分は我慢して、となるが、かなりきつい表現。後文にいって女三の宮が主語と判明。どちらともとれるような両義性のある表現をしたものか。
|
| 11.3.3 |
|
昔からの出家の本願も、考えの不十分なはずのご婦人方にさえ、みな後れを取り後れを取りして、とてものろまなことが多いのですが、自分自身の心には、どれほどの思いを妨げるものはないのですが、院がこれを最後と御出家なさった後のお世話役にわたしをお譲り置きになったお気持ちが、しみじみと嬉しかったが、引き続いて後を追いかけるようにして、同じようにお見捨て申し上げるようなことが、院にはがっかりされるであろうと差し控えているのです。
|
昔から願っている出家の志望も、自分よりは幼稚な宗教心しか持つまいと思っていた女の人たちが先に実行するのを傍観しているのも、私自身がこの世の欲を捨てえないのではなくて、出家をあそばす際にはあなたをお託しになった院のお志に感激した心が、すぐまた続いてあなたを捨てて行くような行動を取らせなかったのですよ。
|
【たどり薄かるべき女方にだに、皆思ひ後れつつ】- 光源氏の女性蔑視の思想は当時の社会一般の風潮か。
【今はと捨てたまひけむ】- 主語は朱雀院。
【ひき続き争ひきこゆるやうにて】- 朱雀院の出家に引き続いて、先を争うようにして、の意。
【同じさまに見捨てたてまつらむことの】- 出家して女三の宮を捨てる意。
【あへなく思されむに】- 主語は朱雀院。
【つつみてなむ】- 主語は源氏。係助詞「なむ」の下に、出家しないでいるの意が含まれる。
|
| 11.3.4 |
心苦しと思ひし人びとも、今はかけとどめらるるほだしばかりなるもはべらず。女御も、かくて、行く末は知りがたけれど、御子たち数添ひたまふめれば、みづからの世だにのどけくはと見おきつべし。その他は、誰れも誰れも、あらむに従ひて、もろともに身を捨てむも、惜しかるまじき齢どもになりにたるを、やうやうすずしく思ひはべる。 |
気にかかっていた人々も、今では出家の妨げとなるほどの者もおりません。
女御も、あのようにして、将来の事は分かりませんが、皇子方がいく人もいらっしゃるようなので、わたしの存命中だけでもご無事であればと安心してよいでしょう。
その他の事は、誰も彼も、状況に従って、一緒に出家するのも、惜しくはない年齢になっているのを、だんだんと気持ちも楽になっております。
|
以前は気がかりに思われた人も今ではもう出家の絆にならないだけになっているのです。女御だってどうなるか知りませんが、皇子たちがお殖えにもなってゆくのですから、後宮の地位などは問題にさえせねば苦労のない立場を得られることだけはできると私も見ておけます。そのほかの人たちは成り行きのままで、私といっしょに出家をしてしまってももういいほどの年齢になっているとこのごろでは思われます。
|
【みづからの世だにのどけくはと見おきつべし】- 自分が生きている間だけは無事でいればと考えておいけばよいだろう、その先のことまでは考えない、の意。
|
| 11.3.5 |
|
院の御寿命もそう長くはいらっしゃらないでしょう。
とても御病気がちにますますなられて、何となく心細げにばかりお思いでいられるから、今さら感心しないお噂を院のお耳にお入れ申して、お心を乱したりなさらないように。
現世はまことに気にかけることはありません。
どうということもありません。
が、来世の御成仏の妨げになるようなのは、罪障がとても恐ろしいでしょう」
|
院ももう長くはおいでにならないでしょう。以前よりいっそうお身体が弱くおなりになって、心細い御様子でいらっしゃるとのことですから、今になって悪い名などをお耳に入れて御心配をかけてはいけませんよ。この世は何でもありませんが、来世のお妨げになることをしてはあなたの罪も大きくなりますよ」
|
【院の御世の残り久しくもおはせじ】- 朱雀院の御寿命もそう長くはないだろう、の意。
【御名の】- 明融臨模本は「御な(な+の)」とある。すなわち「の」を補入する。大島本は「御な」とある。『集成』『完本』は諸本に従って底本の訂正以前本文に従う。『新大系』は底本(大島本)のままとする。
【この世はいとやすし。ことにもあらず】- 『集成』は「この現世については、何の気にかけることもありません。どうということもないのです」「現世だけのことなら、問題はない、の意」。『完訳』は「この世は、じっさいどうというものでもない、別段のこともないのです」と訳す。世間虚仮、この世は仮の世であるとする現世観。
|
| 11.3.6 |
|
などと、はっきりとその事とはお明かしにならないが、しみじみとお話し続けなさるので、涙ばかりがこぼれては、正体もない様子で悲しみに沈んでいらっしゃるので、ご自分もお泣きになって、
|
そのことと露骨にお言いにならないのであるが、しみじみとお説きになるために、宮は涙ばかりがこぼれて、知らず知らずめいり込んでおしまいになったのを御覧になる院も、お泣きになって、
|
【まほにそのこととは明かしたまはねど】- 『完訳』は「密通事件。しかしそれを暗に語り、宮を責めていることになる」と注す。
【涙のみ落ちつつ、我にもあらず】- 主語は女三の宮。
【我もうち泣きたまひて】- 源氏、自嘲の涙。
|
| 11.3.7 |
|
「他人の身の上でも、嫌なものだと思って聞いていた老人のおせっかいというものを。
自分がするようになったことよ。
どんなに嫌な老人かと、不愉快で厄介なと思うお気持ちがつのることでしょう」
|
「他の人がこうしたことを言うのを、聞く必要もない老人の理窟だと思った私だが、いつのまにかそれを言うほうの人に私がなっている。よけいなことを言う老人だとお思いになっていっそういやになるでしょう」
|
【人の上にても】- 以下「御心添ふらむ」まで、源氏の詞。『集成』は「若い柏木に対するねたみの気持が言わせる言葉」。『完訳』は「自分に無関係な他人事でも、いらいらした思いで聞いていた老人のおせっかい、それを自分が言うようになったとは。いやな老人と自嘲する物言いの底に、若い柏木や宮への嫉妬と憎悪がくすぶる」と注す。光源氏の老醜。紫式部の老いに対する思想感懐。
【御心添ふらむ】- 女三の宮の心をさす。源氏を嫌な老人と思う心が増すことであろう、の意。
|
| 11.3.8 |
と、恥ぢたまひつつ、御硯引き寄せたまひて、手づから押し磨り、紙取りまかなひ、書かせたてまつりたまへど、御手もわななきて、え書きたまはず。
|
と、お恥になりながら、御硯を引き寄せなさって、自分で墨を擦り、紙を整えて、お返事をお書かせ申し上げなさるが、お手も震えて、お書きになることができない。
|
ともお言いになって、硯を引き寄せて御自身で墨をおすりになり、紙をお選りになりなどして、お返事を書かせようとされるのであるが、宮は手も慄えてお書きになれない。
|
|
| 11.3.9 |
|
「あのこまごまと書いてあった手紙のお返事は、とてもこのように遠慮せずやりとりなさっていたのだろう」とご想像なさると、実に癪にさわるので、一切の愛情も冷めてしまいそうであるが、文句などを教えてお書かせ申し上げなさる。
|
あの濃厚な言葉の盛られてあった衛門督の手紙の返事はこんなに渋らずに書かれたであろうとお思いになると、また反感が起こるのでもおありになったが、それでも院は言葉などを口授してお書かせになった。
|
【かのこまかなりし返事は、いとかくしもつつまず通はしたまふらむかし】- 源氏の心中、間接的叙述。源氏の嫉妬と憎悪の気持ち。
【いと憎ければ、よろづのあはれも冷めぬべけれど】- 源氏の憎悪の心中が語り手によって浮き彫りにされて語られている。
|
|
第四段 朱雀院の御賀、十二月に延引
|
| 11.4.1 |
|
参賀なさることは、この月はこうして過ぎてしまった。
二の宮が格別のご威勢で参賀なさったのに、身籠もられたお身体で、競うようなのも、遠慮され気が引けるのであった。
|
「お伺いになることはこんなことで今月もだめでしたね。それに新婚者の女二の宮が派手な御賀をおささげになった時に、老人の妻であるあなたが競争的に出て行くのは遠慮すべきだと思いましたよ。
|
【この月かくて過ぎぬ】- 十月が過ぎた。
【二の宮の御勢ひ殊にて】- 女二の宮の落葉宮の参賀が舅の太政大臣のきもいりで盛大に催されたことをさす。
【古めかしき御身ざまにて】- 『集成』は「子を身篭られたお身体で」と訳す。『完訳』「懐妊八か月の様態をいうか」と注す。
【憚りある心地しけり】- 『集成』は「源氏の気持を敬語抜きで直接書いたもの」と注す。
|
| 11.4.2 |
「霜月はみづからの忌月なり。年の終りはた、いともの騒がし。また、いとどこの御姿も見苦しく、待ち見たまはむをと思ひはべれど、さりとて、さのみ延ぶべきことにやは。むつかしくもの思し乱れず、あきらかにもてなしたまひて、このいたく面痩せたまへる、つくろひたまへ」 |
「十一月はわたしの忌月です。
年の終わりは歳末で、とても騒々しい。
また、ますますこのお姿も体裁悪く、お待ち受けあそばす院はいかが御覧になろうと思いますが、そうかと言って、そんなにも延期することはでません。
くよくよとお思いあそばさず、明るくお振る舞いになって、このひどくやつれていらっしゃるのを、お直しなさい」
|
十一月はあなたのお母様の忌月でしょう。十二月はあまりに押しつまってよろしくないし、あなたの身体も見苦しくなるだろうから、久しぶりにお姿を御覧に入れるのはいかがかと思いますが、しかしそうそう延ばしてよいことでありませんからね、あまり物思いをしないようにして、朗らかな心になって、痩せたお顔のなおるようにまずなさい」
|
【霜月はみづからの忌月なり】- 以下「つくろひたまへ」まで、源氏の詞。桐壺院の崩御の月。「賢木」巻に語られている。
|
| 11.4.3 |
|
などと、とてもおいたわしいと、それでもお思い申し上げていらっしゃる。
|
などとお言いになって、さすがにかわいくは思召すのであった。
|
【いとらうたしと、さすがに見たてまつりたまふ】- 源氏は女三の宮に対して、嫉妬と憎悪の気持ちもあるが一方で憐愍の情もないではない、という意。
|
| 11.4.4 |
|
衛門督をどのような事でも、風雅な催しの折には、必ず特別に親しくお召しになっては、ご相談相手になさっていたのが、全然そのようなお便りはない。
皆が変だと思うだろうとお思いになるが、「顔を見るにつけても、ますます自分の間抜けさが恥ずかしくて、顔を見てはまた自分の気持ちも平静を失うのではないか」と思い返され思い返されて、そのままいく月も参上なさらないのにもお咎めはない。
|
衛門督をどんな催し事にも必要な人物としてお招きになって御相談相手に今まではあそばす院でおありになったが、今度の法皇の賀に限って何の仰せもない。人が不審がるであろうとはお思いになるのであるが、その人が来てはずかしめられた老人である自分の見られることも不快であるし、自分が彼を見ては平静で心がありえなくなるかもしれぬと院はお思いになって、もう幾月も参殿しない人を、なぜかとお尋ねになることもないのである。
|
【何ざまのことにも、ゆゑあるべきをりふしには】- 源氏は柏木を何につけ風雅な趣の催し事には必ず相談相手にしてきた。今後の朱雀院の五十賀宴などは当然相談されると世間の人も思っている。
【見むにつけても、いとどほれぼれしきかた恥づかしく】- 『集成』は「いよいよ自分の間抜けさ加減を相手の目にさらすようで、気がひけるし」「女三の宮とのことを知っていながら、源氏としては素知らぬふりをしなくてはならぬからである」。『完訳』は「宮の前への対話で繰り返された老醜の自嘲と照応。ここは妻を奪われた老人のぶざまさをいう」と注す。
|
| 11.4.5 |
|
世間一般の人は、ずっと普通の状態でなく病気でいらっしゃったし、院でもまた、管弦のお遊びなどがない年なので、とばかりずっと思っていたが、大将の君は、「何かきっと事情があることに違いない。
風流者は、さだめし自分が変だと気がづいたことに、我慢できなかったのだろうか」と考えつくが、ほんとうにこのようにはっきりと何もかも知れるところにまでなっているとは、想像もおつきにならなかったのである。
|
ただの人たちは衛門督が病気続きであったし、六条院にもまた音楽その他のお催しの全くない年であるからと解釈していたが、左大将だけは何か理由のあることに違いない、多感多情な男であるから、自分が推測していたあの恋で自制の力を失うようなことがあったのではないかとは見ていても、まだこれほど不祥なことが暴露してしまったとは想像しなかった。
|
【例ならず悩みわたりて】- 主語は柏木。
【院にはた】- 明融臨模本は「院に(に+ハ)」とある。すなわち「は」を補入する。大島本は「院に」とある。『集成』『完本』は底本(明融臨模本)の訂正以前本文と諸本に従う。『新大系』は底本(大島本)のままとする。六条院では六条院で、やはり紫の上、女三の宮と病人続出続きで、の意。
【あるやうあることなるべし】- 以下「忍ばぬにやありけむ」まで、夕霧の心中。六年前の蹴鞠の日の柏木が女三の宮を垣間見て、以来執心していたことを思う。
【わがけしきとりしことには】- 「わが」は夕霧をいう。自分(夕霧)が気づいたこと、六年前の蹴鞠の日のこと。挿入句。
|
|
第五段 源氏、柏木を六条院に召す
|
| 11.5.1 |
|
十二月になってしまった。
十何日と決めて、数々の舞を練習し、御邸中大騒ぎしている。
二条院の上は、まだお移りにならなかったが、この試楽のために、落ち着き払ってもいられずお帰りになった。
女御の君も里にお下がりになっていらっしゃる。
今度御誕生の御子は、また男御子でいらっしゃった。
次々とおかわいらしくていらっしゃるのを、一日中御子のお相手をなさっていらっしゃるので、長生きしたお蔭だと、嬉しく思わずにはいらっしゃれないのだった。
試楽には、右大臣殿の北の方もお越しになった。
|
十二月になった。十幾日と法皇の御賀の日が定められて六条院の中は用意に忙しくなった。二条の院の夫人はまだそのまま帰らずにいたが、御賀の試楽があるのに興味を覚えてもどってきた。女御も実家にいた。今度のお産でお生まれになったのもまた男宮であった。次々に皆かわいい宮様を夫人はお世話することに生きがいを覚えていた。試楽の日は右大臣夫人も六条院へ来た。
|
【この試楽によりてぞ】- 明融臨模本は「よりそ(そ=て)」とある。すなわち「そ」の右傍に「て」を傍書する。大島本は「より(り+て<墨>、$<朱>)そ」とある。すなわち本行本文「よりそ」に「て」を補入しのち抹消している。『集成』『完本』は底本(明融臨模本)の訂正以前本文と諸本に従う。『新大系』も底本(大島本)の訂正以前本文に従う。
【このたびの御子は、また男にて】- 『集成』は「前に見えた「三の宮」に次ぐ方である」。『完訳』は「女楽のころ懐妊五か月。第三皇子(後の匂宮)か、その兄の二の宮か」。『新大系』は「「二の宮」の次の皇子」と注す。
【うれしく思されける】- 主語は紫の上。大病を克服して生き延び、孫を見ることができた喜び。
【右大臣殿の北の方も渡りたまへり】- 玉鬘。右大臣鬚黒の北の方の地位におさまっている。
|
| 11.5.2 |
|
大将の君は、丑寅の町で、まず内々に調楽のように、毎日練習なさっていたので、あの御方は、御前での試楽は御覧にならない。
|
左大将は東北の御殿でそれ以前にすでに毎日監督する舞曲の練習をさせていたから、花散里夫人は試楽の見物には出て来なかった。
|
【かの御方は、御前の物は見たまはず】- 花散里は春の御殿においての源氏御前の試楽は見ない、の意。
|
| 11.5.3 |
衛門督を、かかることの折も交じらはせざらむは、いと栄なく、さうざうしかるべきうちに、人あやしと傾きぬべきことなれば、参りたまふべきよしありけるを、重くわづらふよし申して参らず。
|
衛門督を、このような機会に参加させないようなのは、まことに引き立たず、もの足りなく感じられるし、皆が変だと思うに違いないことなので、参上なさるようにお召しがあったが、重病である旨を申し上げて参上しない。
|
衛門督をこの試楽の日に除外するのは惜しく物足らぬことであると院はお思いになったし、それ以上にまた人の不審を引くことをお恐れにもなって、来るようにと使いをお向けになったが、病の重いことを申して督は出て来ようとしなかった。
|
|
| 11.5.4 |
さるは、そこはかと苦しげなる病にもあらざなるを、思ふ心のあるにやと、心苦しく思して、取り分きて御消息つかはす。父大臣も、 |
しかし、どこがどうと苦しい病気でもないようなのに、自分に遠慮してのことかと、気の毒にお思いになって、特別にお手紙をお遣わしになる。
父の大臣も、
|
病気といっても何という名のある病をしているのでもないわけであるが、やましく思う点があるのであろうと、心苦しく思召して、特使をさえもおやりになって招こうとあそばされた。父の大臣も、
|
【心苦しく思して】- 源氏の、柏木への憐愍の情。
|
| 11.5.5 |
|
「どうしてご辞退申されたのか。
いかにもすねているように、院におかれてもお思いあそばそうから、大した病気でもない、何とかして参上なさい」
|
「なぜ御辞退をしたかね。何か含むことでもあるように院がお思いになるだろうに。大病というのではないのだから、無理をしても参ったほうがよい」
|
【などか返さひ申されける】- 以下「助け参りたまへ」まで、致仕太政大臣の詞。柏木に六条院に参るよう勧める。
|
| 11.5.6 |
|
とお勧めなさっているところに、このように重ねておっしゃってきたので、苦しいと思いながらも参上した。
|
と勧めていたところへ再度のお使いが来たのであったから、つらい気持ちをいだきながら参った。
|
【苦しと思ふ思ふ参りぬ】- 尊敬語なしの直接的表現。不気味な事件の展開を暗示。
|
|
第六段 源氏、柏木と対面す
|
| 11.6.1 |
|
まだ上達部なども参上なさっていない時分であった。
いつものようにお側近くの御簾の中に招き入れなさって、母屋の御簾を下ろしていらっしゃる。
なるほど、実にひどく痩せて蒼い顔をしていて、いつもの陽気で派手な振る舞いは、弟の君たちに気圧されて、いかにも嗜みありげに落ち着いた態度でいるのが格別であるのを、いつもより一層静かに控えていらっしゃる様子は、「どうして内親王たちのお側に夫として並んでも、全然遜色はあるまいが、ただ今度の一件については、どちらもまことに思慮のない点に、ほんとうに罪は許せないのだ」などと、お目が止まりなさるが、平静を装って、とてもやさしく、
|
それはまだ他の高官などの集まって来ない時分であった。これまでのようにお座敷の御簾の中へ衛門督をお入れになって、院御自身はまた一つの御簾を隔てた奥のお居間においでになった。噂のとおりに非常に痩せて顔色が悪かった。平生もはなやかな派手な美しさは弟たちのほうに多くて、この人は深く落ち着いた静かな風采によさのあった人であるが、今日はことにおとなしい身のとりなしで侍している姿を、内親王の配偶者として見ても相応らしい男であるが、その関係の正しくないのが不快だ、憎悪を覚えずにはおられないのであると院は思召したが、さりげなくしておいでになった。
|
【例の気近き御簾の内に入れたまひて、母屋の御簾下ろしておはします】- 前者の「御簾」は簀子と廂の間とを仕切る御簾、後者の「御簾」は廂の間と母屋を仕切る御簾である。柏木は廂の間、源氏は母屋の御簾の中にいる。光の関係で、柏木の表情は源氏から見えるが、母屋の中の源氏の表情は柏木から見えない。
【げに、いといたく痩せ痩せに青みて】- 以下、源氏の目に映った柏木の姿。源氏の目と地の文とが融合した叙述。
【いと用意あり顔にしづめたるさまぞことなるを】- 『集成』は「いかにもたしなみありげに、もの静かに振舞うところが、人にすぐれて目立つのだが」。『完訳』は「じっさいたしなみも深そうに落ち着いているところが余人とちがうのであるが」と訳す。
【などかは皇女たちの御かたはらに】- 以下「いと罪許しがたけれ」まで、源氏の心中。『集成』は「柏木は現に女二の宮を正室としているが、源氏の念頭には女三の宮のことがある」と注す。
【ただことのさまの】- 密通事件をさす。
【いと罪許しがたけれ】- 『集成』は「柏木が自分の恩顧を忘れて正室を犯し、女三の宮も源氏の配慮を考慮しない点を、許しがたく思う」。『完訳』は「宮も柏木も自分(源氏)を無視した。その無分別を「罪」とする」と注す。
|
| 11.6.2 |
「そのこととなくて、対面もいと久しくなりにけり。月ごろは、いろいろの病者を見あつかひ、心の暇なきほどに、院の御賀のため、ここにものしたまふ皇女の、法事仕うまつりたまふべくありしを、次々とどこほることしげくて、かく年もせめつれば、え思ひのごとくしあへで、型のごとくなむ、斎の御鉢参るべきを、御賀などいへば、ことことしきやうなれど、家に生ひ出づる童べの数多くなりにけるを御覧ぜさせむとて、舞など習はしはじめし、そのことをだに果たさむとて。拍子調へむこと、また誰れにかはと思ひめぐらしかねてなむ、月ごろ訪ぶらひものしたまはぬ恨みも捨ててける」 |
「特別の用件もなくて、お会いすることも久し振りになってしまった。
ここいく月は、あちこちの病人を看病して、気持ちの余裕もなかった間に、院の御賀のために、こちらにいらっしゃる内親王が、御法事をして差し上げなさる予定になっていたが、次々と支障が続出して、このように年もおし迫ったので、思うとおりにもできず、型通りに精進料理を差し上げる予定だが、御賀などと言うと、仰々しいようだが、わが家に生まれた子供たちの数が多くなったのを御覧に入れようと、舞などを習わせ始めたが、その事だけでも予定どおり執り行おうと思って。
調子をきちんと合わせることは、誰にお願いできようかと思案に窮していたが、いく月もお顔を見せにならなかった恨みも捨てました」
|
「機会がなくてあなたにも長く逢いませんでしたね。長く病人の介抱をしていて何の余裕もなくてね、前からここへ来ておいでになる宮が、院の賀に法事をして差し上げたいと言っておられたのが、いろいろな故障で滞っていてね、今年も暮れになったので、これ以上延ばすこともできず、以前に計画したとおりのことはととのわないが、形だけでも精進のお祝い膳を差し上げる運びになって、賀宴などというとたいそうだが、親戚の子供たちの数がたくさんにもなっているのだから、それだけでも御覧に入れようと思って舞の稽古などをさせ始めたものだから、せめてそれだけでもうまくゆくようにと思って、拍子が合うか試してみるのですが、指導をしていただくのに、だれがよいかともよく考える間がなくてあなたに御面倒を見てもらうのがよいときめて、長くおいでもなかったお恨みも捨てたわけですよ」
|
【そのこととなくて】- 以下「恨みも捨ててける」まで、源氏の詞。
【法事仕うまつりたまふべくありしを】- 出家者である朱雀院の五十賀が仏事で催されるので「法事」という。
【え思ひのごとくしあへで】- 明融臨模本と大島本は「ことく」とある。『集成』『新大系』は底本(明融臨模本・大島本)のままとする。『完本』は諸本に従って「ごとくも」と「も」を補訂する。
|
|
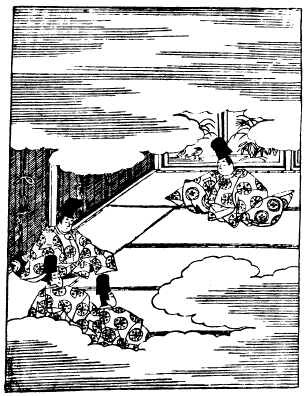 |
| 11.6.3 |
|
とおっしゃるご様子が、何のこだわりないような一方で、とてもとても顔も上げられない思いに、顔色も変わるような気がして、お返事もすぐには申し上げられない。
|
とお言いになる院の御様子に、昔と変わった所もないのであるが、衛門督は羞恥を感じて自身ながらも顔色が変わっている気がして、急にお返辞ができないのであった。
|
【いといと恥づかしきに】- 主語は柏木。
【とみに聞こえず】- 明融臨模本は「きこえす」とある。大島本は「えきこえす」とある。『集成』と『新大系』はそれぞれ底本(明融臨模本・大島本)のままとする。『完本』は諸本に従って「え聞こえず」と「え」を補訂する。
|
|
第七段 柏木と御賀について打ち合わせる
|
| 11.7.1 |
「月ごろ、かたがたに思し悩む御こと、承り嘆きはべりながら、春のころほひより、例も患ひはべる乱り脚病といふもの、所狭く起こり患ひはべりて、はかばかしく踏み立つることもはべらず、月ごろに添へて沈みはべりてなむ、内裏などにも参らず、世の中跡絶えたるやうにて籠もりはべる。 |
「ここいく月、あちらの方こちらの方のご病気にご心配でいらっしゃったお噂を、お聞きいたしてお案じ申し上げておりましたが、春ごろから、普段も病んでおりました脚気という病気が、ひどくなって苦しみまして、ちゃんと立ち歩くこともできませんで、月日が経つにつれて臥せっておりまして、内裏などにも参内せず、世間とすっかり没交渉になったようにして家に籠もっておりました。
|
「長らく奥様がたが御病気をしておいでになりますことを承っておりまして、御心配を申し上げながら、前からございました脚気がしきりに出てまいりまして、歩行が困難でございましたために御所へ上がることができませんで、すっかり世の中から隔離されましたような寂しい生活をいたしておりました。
|
【月ごろ、かたがた】- 以下「まさりてはべるべき」まで、柏木の返事。
|
| 11.7.2 |
|
院のお年がちょうどにおなりあそばす年であり、誰よりも人一倍しっかりしたお祝いをして差し上げるよう、致仕の大臣も思って申されましたが、『冠を挂け、車を惜しまず捨てて官職を退いた身で、進み出てお祝い申し上げるようなのも身の置き所がない。
なるほど、そなたは身分が低いと言っても、自分と同じように深い気持ちは持っていよう。
その気持ちを御覧に入れなさい』と、催促申されることがございましたので、重病をあれこれ押して、参上いたしました。
|
院がおめでたい年に達せられますので、年来の御交誼に対してまずお祝いを申し上げなければと父が申しておりましたが、関白を拝辞しました自分が表だって出ることよりも、地位は低くとも中納言の私が主催するのが妥当であると父は考えるようになりまして、私の誠意をお目にかくべきだと勧められましたものですから、病体をおしてあちらへはお伺いいたしたのでございます。
|
【院の御齢足りたまふ年なり】- 朱雀院のお年齢がちょうど五十にお達しになる年である、の意。
【申されしを】- 「申す」は「言ふ」の謙譲語。「れ」尊敬の助動詞。「し」過去の助動詞、連体形。父の致仕大臣が自分(柏木)に申されたという敬語表現。
【冠を掛け、車を惜しまず捨ててし身にて】- 明融臨模本、合点あり、『奥入』に「掛冠」と「懸車」の故事を『蒙求』から引用する。以下「御覧ぜられよ」まで、致仕大臣の言葉を引用。
【下臈なりとも】- 柏木をさす。
【申さるることの】- 前の「申されし」と同じ語法。『集成』は「相手の源氏に斟酌しての言葉遣い」と注す。
|
| 11.7.3 |
|
このごろは、ますますひっそりとしたご様子で俗世間のことはお考えにならずお過ごしあそばしていらっしゃいまして、盛大なお祝いの儀式をお待ち受け申されることは、お望みではありますまいと拝察いたしましたが、諸事簡略にあそばして、静かなお話し合いを心からお望みであるのを叶えて差し上げるのが、上策かと存じられます」
|
いよいよお寂しい静かな御生活のように拝見いたしましたあちらの御様子では、はなやかな賀宴をお持ち込みあそばすようなことは恐縮なされるだけではないかと拝察されまして、こちら様の御質素な御計画はかえって御満足になることかと存ぜられます」
|
【今は、いよいよいとかすかなるさまに思し澄まして】- 朱雀院の出家生活をいう。
【静かなる御物語の深き御願ひ】- 朱雀院と女三の宮との親子の親密な語らいを願っている院の希望をいう。
|
| 11.7.4 |
|
とお申し上げなさったので、盛大であったと聞いた御賀の事を、女二の宮の事とは言わないのは、大したものだとお思いになる。
|
と衛門督が申すと、華奢を尽くしてお目にかけたという前日の賀宴を女二の宮の関係でしたとは言わずに、父のためにしたと話すのに心の鍛錬のできていることがうかがわれると院は思召された。
|
【いかめしく聞きし御賀の事を】- 女二の宮主催、致仕大臣後援の朱雀院五十賀をさす。
|
| 11.7.5 |
「ただかくなむ。こと削ぎたるさまに世人は浅く見るべきを、さはいへど、心得てものせらるるに、さればよとなむ、いとど思ひなられはべる。大将は、公方は、やうやう大人ぶめれど、かうやうに情けびたる方は、もとよりしまぬにやあらむ。 |
「ただこのとおりだ。
簡略な様子に世間の人は浅薄に思うに違いないが、さすがに、よく分かってくれるので、思ったとおりで良かったと、ますます安心して来ました。
大将は、朝廷の方では、だんだん一人前になって来たようだが、このように風流な方面は、もともと性に合わないのであろうか。
|
「私の所でやらせていただくことはこのとおりに簡単なことであるのを見て、一概に悪く言う人もあるであろうと思っていたが、理解のあるお言葉を聞いて、さすがにとあなたにはいよいよ敬意が払われる。大将は役人としては少しは経験ができたようでも、そうした繊細な観察をすることなどは、得意でもないだろうがいっこうだめですよ。
|
【ただかくなむ】- 以下「いと口惜しきものなり」まで、源氏の詞。
【さればよと】- やはりこれでよかった、の意。
|
| 11.7.6 |
かの院、何事も心及びたまはぬことは、をさをさなきうちにも、楽の方のことは御心とどめて、いとかしこく知り調へたまへるを、さこそ思し捨てたるやうなれ、静かに聞こしめし澄まさむこと、今しもなむ心づかひせらるべき。かの大将ともろともに見入れて、舞の童べの用意、心ばへ、よく加へたまへ。物の師などいふものは、ただわが立てたることこそあれ、いと口惜しきものなり」 |
あちらの院は、どのような事でもお心得のないことは、ほとんどない中でも、音楽の方面には御熱心で、まことに御立派に精通していらっしゃるから、そのように世をお捨てになっているようだが、静かにお心を澄まして音楽をお聞きになることは、このような時にこそ気づかいすべきでしょう。
あの大将と一緒に面倒を見て、舞の子供たちの心構えや、嗜みをよく教えてやって下さい。
音楽の師匠などというものは、ただ自分の専門についてはともかくも、他はまったくどうしようもないものです」
|
法皇はあらゆる芸術に通じておいでになるが、その中でも最も音楽の御造詣が深いから、それらに遠ざかっておいでになる御出家後といえども院が御覧になるのだと思うと晴れがましいのですよ。あの大将といっしょに、舞い手になる子供へ、心得べきことをよく注意しておいてくれたまえ。専門家の師匠というものは自身の芸には偉くても融通のきかないものだから」
|
【さこそ思し捨てたるやうなれ】- 柏木の詞を受ける。朱雀院の出家生活をさしていう。
|
| 11.7.7 |
など、いとなつかしくのたまひつくるを、うれしきものから、苦しくつつましくて、言少なにて、この御前をとく立ちなむと思へば、例のやうにこまやかにもあらで、やうやうすべり出でぬ。 |
などと、たいそうやさしくお頼みになるので、嬉しく思う一方で、辛く身の縮む思いがして、口数少なくこの御前を早く去りたいと思うので、いつものようにこまごまと申し上げず、やっとの思いで下がりになった。
|
などとお命じになるなつかしい味のある院の御様子をうれしく拝しながらもまた衛門督は恥ずかしく、きまり悪く思われて、言葉少なにしていて少しも早く御前を立って行きたいと願われる心から、以前のように細かい話しぶりは見せずにいるうち、ようやく願いどおりにここを去るによい時を見つけた。
|
【いとなつかしくのたまひつくるを】- 『完訳』は「源氏の親しい言葉づかいが、かえって無気味さを感じさせる」と注す。
|
| 11.7.8 |
|
東の御殿で、大将が用意なさった楽人、舞人の装束のことなどを、さらに重ねて指図をお加えになる。
できるかぎり立派になさっていた上に、ますます細やかな心づかいが加わるのも、なるほどこの道には、まことに深い人でいらっしゃるようである。
|
東北の御殿で大将が掛りになって十分に用意してあった舞い手と楽人の衣装などが、また衛門督の意見によって加えられるものもできた、その道には深く通じている衛門督であったから。
|
【東の御殿にて】- 六条院丑寅の町。花散里の御殿。
【尽くしたまへるに】- 接続助詞「に」添加の意。『完訳』は「夕霧が念入りに整えていたうえに、柏木が細かな趣向を加える」と注す。
【げにこの道は、いと深き人にぞものしたまふめる】- 『一葉抄』は「双紙詞也」と指摘。語り手の納得の言辞。副詞「げに」。推量の助動詞「めり」主観的推量のニュアンス。
|
|
第十二章 柏木の物語 源氏から睨まれる
|
|
第一段 御賀の試楽の当日
|
| 12.1.1 |
|
今日は、このような試楽の日であるが、ご夫人方が見物なさるので、見がいのないようにはしまいと思って、あの御賀の日は、赤い白橡に葡萄染の下襲を着るのであろう、今日は、青色に蘇芳襲の下襲を着て、楽人三十人は、今日は白襲を着ているが、東南の方の釣殿に続いている廊を楽所にして、山の南の側から御前に出る所で、「仙遊霞」という楽を奏して、雪がほんのわずか散らついたので、春の隣に近い、梅の花の様子が見栄えがしてほころびかけていた。
|
今日は試楽の日なのであるが、これだけを見物するのにとどまる夫人たちも多いため、目美しくして見せるのに、賀の当日の舞い人の衣装は、明るい白橡に紅紫の下襲を着るはずであったが、今日は青い色を上に臙脂を重ねさせた。今日の楽人三十人は白襲であった。南東の釣殿へ続いた廊の室を奏楽室にして、山の南のほうから舞い人が前庭へ現われて来る間は「仙遊霞」という楽が奏されていた。ちらちらと雪が降って、もう隣へ近づいた春を見せて梅の微笑む枝が見える林泉の趣は感じのよいものであった。
|
【かの御賀の日は、赤き白橡に、葡萄染の下襲を着るべし】- 御賀の当日の衣裳と試楽の日の衣裳とを異にする。
【楽所にて】- 明融臨模本と大島本は「かく所にて」とある。『集成』『新大系』は底本(明融臨模本・大島本)のままとする。『完本』は諸本に従って「楽所にして」と「し」を補訂する。
【春のとなり近く】- 明融臨模本、合点と付箋に「冬なから春のとなりのちかけれは中かきよりそ花はちりく(け)る」(古今集誹諧歌、一〇二一、清原深養父)とある。
【梅のけしき見るかひありて】- 「匂はねどほほゑむ梅の花をこそ我もをかしと折りてながめむ」(好忠集、二六)。
|
| 12.1.2 |
|
廂の御簾の内側にいらっしゃるので、式部卿宮、右大臣ぐらいがお側に伺候していらっしゃるだけで、それ以下の上達部は簀子で、特別の日でないので、御饗応などは、お手軽な物を用意してあった。
|
縁側に近い御簾の中に院のお席があって、そこにはただ式部卿の宮が御同席され、右大臣の陪覧する座があっただけである。以下の高官たちは皆縁側に席をして、そこには形式を省いた饗応の物が出されてあった。
|
【式部卿宮、右大臣ばかりさぶらひたまひて】- 紫の上の父宮と鬚黒右大臣。いずれも源氏の身内。
【御饗応など、気近きほどに仕うまつりなしたり】- 『完訳』は「ご馳走などはそう仰々しくはなくお出ししてある」と訳す。
|
| 12.1.3 |
右の大殿の四郎君、大将殿の三郎君、兵部卿宮の孫王の君たち二人は、「万歳楽」。まだいと小さきほどにて、いとらうたげなり。四人ながら、いづれとなく高き家の子にて、容貌をかしげにかしづき出でたる、思ひなしも、やむごとなし。 |
右の大殿の四郎君、大将殿の三郎君、兵部卿宮の孫王の公達二人は、「万歳楽」。
まだとても小さい年なので、とてもかわいらしげである。
四人とも、誰彼となく高貴な家柄のお子なので、器量もかわいらしく装い立てられている姿は、そう思うせいか、気品がある。
|
右大臣の四男と、左大将の三男、それに兵部卿の宮の御幼年の王子お二人の四人立ちで万歳楽が舞われるのであるが、皆小さい姿でかわいかった。四人とも皆高い貴族の子供たちで風貌が凡庸でない。皆にいたわれながら小公子たちは登場した。
|
【兵部卿宮の孫王の君たち二人は】- 蛍兵部卿宮の子二人。「孫王」は帝の孫の意。
|
| 12.1.4 |
また、大将の典侍腹の二郎君、式部卿宮の兵衛督といひし、今は源中納言の御子、「皇麞」。右の大殿の三郎君、「陵王」。大将殿の太郎、「落蹲」。さては「太平楽」、「喜春楽」などいふ舞どもをなむ、同じ御仲らひの君たち、大人たちなど舞ひける。 |
また、大将の典侍がお生みになった二郎君と、式部卿宮の兵衛督と言った人で、今では源中納言になっている方の御子は「皇じょう」。
右の大殿の三郎君は、「陵王」。
大将殿の太郎は、「落蹲」。
その他では「太平楽」、「喜春楽」などと言ういくつもの舞を、同じ一族の子供たちや大人たちなどが舞ったのであった。
|
また大将の典侍腹の二男と、式部卿の宮の御長男でもとは兵衛督であって今は源中納言となっている人の子のこの二人が「皇麞こうじょう」、右大臣の三男が「陵王」、大将の長男の「落蹲」のほかにも「太平楽」「喜春楽」などの舞曲も若い公達が演じた。
|
【兵衛督といひし、今は源中納言】- 式部卿宮の御子の兵衛督、真木柱姫君と兄妹。「藤袴」「梅枝」に登場。臣籍降下して源氏となっている。
|
| 12.1.5 |
|
日が暮れて来たので、御簾を上げさせなさって、感興が高まっていくにつれて、実にかわいらしいお孫の君たちの器量や、姿で、舞の様子も、又とは見られない妙技を尽くして、お師匠たちも、それぞれ技のすべてをお教え申し上げたうえに、深い才覚をそれに加えて、素晴らしくお舞いになるのを、どの御子もかわいいとお思いになる。
年老いた上達部たちは、皆涙を落としなさる。
式部卿宮も、お孫のことをお思いになって、お鼻が赤く色づくほどお泣きになる。
|
日が暮れてしまうと御前の御簾は巻き上げられて、音楽にも舞にもおもしろみが加わってゆく。かわいい姿の御孫の公達は秘伝を惜しまずそれぞれの師匠が教えた芸に、よい遺伝からの才気の加味された舞をだれもだれもおもしろく見せるのを、皆かわいく院は思召した。老いた高官たちは皆落涙をしていた。式部卿の宮も御孫の芸にお鼻の色も変わるほど感動されたのであった。
|
【いとうつくしき御孫の君たちの】- 源氏は孫たちの瑞々しく可愛らしい舞姿に自らの老いが自覚されていく。
【いづれをもいとらうたしと思す】- 源氏の感想。
【老いたまへる上達部たちは、皆涙落としたまふ】- 右大臣以下の老人の上達部たち。
【式部卿宮も、御孫を】- 孫の源中納言を思う。この中の最年長者か。
【御鼻の色づくまでしほたれたまふ】- 『完訳』は「老いの涙を戯画化。次の源氏の酔泣きに効果的に続けていく」と注す。
|
|
第二段 源氏、柏木に皮肉を言う
|
| 12.2.1 |
主人の院、
|
ご主人の院は、
|
六条院が、
|
|
| 12.2.2 |
|
「寄る年波とともに、酔泣きの癖は止められないものだな。
衛門督が目を止めてほほ笑んでいるのは、まことに恥ずかしくなるよ。
そうは言っても、もう暫くの間だろう。
さかさまには進まない年月さ。
老いは逃れることのできないものだよ」
|
「年のゆくにしたがって酔い泣きをすることがますます烈しくなってゆく。衛門督のおかしそうに笑っておられるのが恥ずかしい。歳月はさかさまに進むものではないからね。あなたがたでも老いはのがれられないのですよ」
|
【過ぐる齢に添へて】- 以下「え逃れぬわざなり」まで、源氏の詞。『完訳』は「自分を老醜の人とする。これまで女三の宮を前に繰り返し言われてきた。この自嘲の言葉が相手への痛烈な皮肉に転ずる」と注す。
【衛門督、心とどめてほほ笑まるる】- 『完訳』は「柏木が嘲笑するはずのないのを知りながら、自分の老いを蔑視しているとして、皮肉る」と注す。
【いと心恥づかしや】- 『集成』は「全く気のひけることです」。『完訳』は「なんともきまりがわるいことですよ」と訳す。
【さかさまに行かぬ年月よ】- 「さかさまに年もゆかなむとりもあへず過ぐる齢やともに返ると」(古今集雑上、八九六、読人しらず)。
|
| 12.2.3 |
|
と言って、ちらっと御覧やりなさると、誰よりも一段とかしこまって塞ぎ込んで、真実に気分もたいそう悪いので、試楽の素晴らしさも目に入らない気分でいる人をつかまえて、わざと名指しで、酔ったふりをしながらこのようにおっしゃる。
冗談のようであるが、ますます胸が痛くなって、杯が回って来るのも頭が痛く思われるので、真似事だけでごまかすのを、お見咎めなさって、杯をお持ちになりながら何度も無理にお勧めなさるので、いたたまれない思いで、困っている様子、普通の人と違って優雅である。
|
と言ってその人の顔を御覧になる。だれよりもまじめに堅くなっていて、偽りでなく身体の具合も悪く思われ、おもしろいことも目にとまらぬ気持ちになっている衛門督を、お名ざしになり、酔態に託してこう仰せられるのは戯れらしくはあったが、その人ははっと胸がとどろいて、めぐって来た杯は手に取ってもただ少ししか飲まないのを、院は見とがめになって、御座からたびたび侍者に酒を持たせておつかわしになり、おしいになるのを、困りながら辞退する取りなしなども、平凡な人とは見えず感じよく院はお思いになった。
|
【空酔ひをしつつかくのたまふ】- 源氏の態度。『完訳』は「酔いを装って本心を吐露する」と注す。
【けしきばかりにて紛らはすを、御覧じ咎めて、持たせながらたびたび強ひたまへば】- 源氏が柏木に。『完訳』は「柏木の酔ったふりを許さない。源氏の鋭くきびしい凝視は持続」と注す。
【なべての人に似ずをかし】- 柏木の態度を優雅な振る舞いとしてこの場を語り収める。
|
| 12.2.4 |
心地かき乱りて堪へがたければ、まだことも果てぬにまかでたまひぬるままに、いといたく惑ひて、
|
気分が悪くて我慢できないので、まだ宴も終わらないのにお帰りになったが、そのままひどく苦しくなって、
|
身心の苦痛に堪えられなくなって衛門督はまだ宴の終わらぬうちに辞して帰ったが、
|
|
| 12.2.5 |
|
「いつものような、大した深酔いしたのでもないのに、どうしてこんなに苦しいのであろうか。
何か気が咎めていたためか、上気してしまったのだろうか。
そんなに怖気づくほどの意気地なしだとは思わなかったが、何とも不甲斐ない有様だった」
|
悪酔いからさめることのできないのは、院を目のあたり見て罪の自責に苦しんだために逆上したのであろうが、それほど臆病な自分ではなかったはずであるが
|
【例の、いとおどろおどろしき酔ひにもあらぬを】- 以下「ありけるかな」まで、柏木の心中。
【つつましとものを思ひつるに】- 『集成』は「何か頭の上がらぬ臆した思いだったので」。『完訳』は「何か気が咎めていたために」と訳す。
|
| 12.2.6 |
|
と自分自身思わずにはいられない。
|
と悲しんだ。
|
【みづから思ひ知らる】- 「る」自発の助動詞。『集成』は「敬語抜きで、柏木の思いに密着した書き方」と注す。
|
| 12.2.7 |
|
一時の酔の苦しみではなかったのであった。
そのまままことひどくお病みになる。
大臣、母北の方が心配なさって、別々に住んでいたのでは気がかりであると考えて、邸にお移し申されるのを、女宮がお悲しみになる様子、それはそれでまたお気の毒である。
|
一時的な酒精の毒ではなくてそのまま衛門督は寝ついて重い容体になった。衛門督の父母がよそに置いてあるのが不安になり、自邸へつれもどすことにしたのを、夫人の宮の悲しがっておいでになるのがまた衛門督には苦しく思われた。
|
【よそよそにていとおぼつかなしとて】- 別々に住んでいたのでは気掛かりでならない、の意。太政大臣の長男である柏木は妻の落葉宮邸に住む。婿入り婚の生活をしている。
【殿に渡したてまつりたまふを】- 柏木を実家に引き取って看護しようとする。
【またいと心苦し】- 夫婦の仲を引き裂かれる思い。
|
|
第三段 柏木、女二の宮邸を出る
|
| 12.3.1 |
|
特別の事がない月日は、のんびりと当てにならない将来のことを当てにして、格別深い愛情もかけなかったが、今が最後と思ってお別れ申し上げる門出であろうかと思うと、しみじみと悲しく、自分に先立たれてお嘆きになるだろうことの恐れ多さを、とても辛いと思う。
母御息所も、ひどくお嘆きになって、
|
何事もなかった間は、衛門督自身も、宮をお愛しする情熱のありなしすら忘れているほどの良人であったが、もうこの世での別れかもしれぬと予感される今日の心には、宮をお残しして行くことが悲しくて、未亡人の寂しい人におさせするのが堪えられない苦痛に思われ、またもったいなくも思われ歎かれるのであった。宮の御母の御息所も非常に悲しんだ。
|
【ことなくて過ぐす月日は】- 明融臨模本は「すくすへきひ(ひ=比)は」とある。大島本は「すくすへきひ比ハ」とある。その他の青表紙本は「すくすへき日は」(横池)「すくす月(月$へき)日(日+ころ)は」(榊)「すくへき日は」(陽)「すくすへき比は」(肖)「すくへき比は」(三)とある。『集成』は「へ」を「つ」の誤写と見て「過ぐす月日は」と整定する。『完本』は底本(明融臨模本)の訂正と肖柏本に従って「過ぐすべき頃は」と整定する。『新大系』は底本(大島本)や榊原家本に従って「過ぐすべき日比は」と整定する。以下「かたじけなきをいみじ」まで、柏木の心中に即した叙述。『集成』は「何事もなく過して来た今までは、のんきに当てにならない先のことを当てにして」「いつかは女二の宮と愛情を交わす仲になるだろうと思って、の意」と注す。
【今はと別れたてまつるべき門出にやと】- 「かりそめの行きかひ路とぞ思ひ来し今は限りの門出なりけり」(古今集哀傷、八六二、在原滋春)。
【いみじと思ふ】- 敬語抜きの表現。心中文と地の文が融合し、柏木の心中に密着した表現となっている。
【母御息所も】- 女二の宮の母一条御息所。
|
| 12.3.2 |
「世のこととして、親をばなほさるものにおきたてまつりて、かかる御仲らひは、とある折もかかる折も、離れたまはぬこそ例のことなれ、かく引き別れて、たひらかにものしたまふまでも過ぐしたまはむが、心尽くしなるべきことを、しばしここにて、かくて試みたまへ」 |
「世間普通の事として、親は親としてひとまずお立て申しても、このような夫婦のお間柄は、どのような時でも、お離れにならないのが常のことですが、このように離れて、よくお治りになるまであちらでお過ごしになるのが、心配でならないでしょうから、もう暫くこちらで、このままご養生なさって下さい」
|
「世間の慣いでは親は親として、御夫婦というものはどんな時にもごいっしょにおいでになることになっています。あちらへ移っておしまいになって、御回復なさるまで別々においでになるのは、宮様のためにおかわいそうなことですから、せめてもうしばらくの間こちらで養生をなさいませ」
|
【世のこととして】- 以下「かくて試みたまへ」まで、母御息所の詞。夫婦仲を割いてまで子息を迎え取ろうという大臣夫妻の処置を非難し、柏木にここで養生するよう依頼する。
【心尽くしなるべきことを】- 娘の女二の宮が心配でたまらないだろうからと言う。
|
| 12.3.3 |
と、御かたはらに御几帳ばかりを隔てて見たてまつりたまふ。
|
と、お側に御几帳だけを間に置いてご看病なさる。
|
この人が病床との隔てに几帳だけを置いて看護をしているのである。
|
|
| 12.3.4 |
「ことわりや。数ならぬ身にて、及びがたき御仲らひに、なまじひに許されたてまつりて、さぶらふしるしには、長く世にはべりて、かひなき身のほども、すこし人と等しくなるけぢめをもや御覧ぜらるる、とこそ思うたまへつれ、いといみじく、かくさへなりはべれば、深き心ざしをだに御覧じ果てられずやなりはべりなむと思うたまふるになむ、とまりがたき心地にも、え行きやるまじく思ひたまへらるる」 |
「ごもっともなことです。
取るに足りない身の上で、及びもつかないご結婚を、なまじお許し頂きまして、こうしてお側におりますその感謝には、長生きをしまして、つまらない身の上も、もう少し人並みとなるところを御覧に入れたいと存じておりましたが、とてもひどく、このようにまでなってしまいましたので、せめて深い愛情だけでも御覧になって頂けずに終わってしまうのではないか存じられまして、生き永らえられそうにない気がするにつけても、まこと安心してあの世に行けそうにも存じられません」
|
「ごもっともです。私ごとき者と結婚をしてくださいました宮様のためには、せめて私が長生きをして相当な地位を得るように努力せねばならぬと心がけてはいたのですが、こんな病人になってしまいましては、私の愛がどれほどのものであったかを宮様にわかっていただけないで終わるかと思いますことで、もう命の助からぬような気のしますうちでも、死なれぬ気がするのです」
|
【ことわりや】- 以下「思ひたまへらるる」まで、柏木の詞。
【数ならぬ身にて、及びがたき御仲らひに】- 『集成』は「臣下として朱雀院の皇女を頂戴したからには、それ相応の義務がある、という意」と注す。
|
| 12.3.5 |
|
などと、お互いにお泣きになって、すぐにもお移りにならないので、再び母北の方が、気がかりにお思いになって、
|
などと泣き合っていて、迎えようとするのに、すぐに移っても来ないのを母の夫人は気づかわしがって、
|
【また母北の方、うしろめたく思して】- 自己中心的な母親像。右大臣家四の君としての敵役的性格。
|
| 12.3.6 |
「などか、まづ見えむとは思ひたまふまじき。われは、心地もすこし例ならず心細き時は、あまたの中に、まづ取り分きてゆかしくも頼もしくもこそおぼえたまへ。かくいとおぼつかなきこと」 |
「どうして、まずは顔を見せようとはお思いになさらないのだろうか。
わたしは、少しでも気分のいつもと違って心細い時は、大勢の子らの中で、まず第一に会いたくなり頼りに思っているのです。
このように大変に気がかりなこと」
|
「そんな場合に、どうして親の所へ来ようとあなたは思ってくれないのだろう。私が病気をする時には、おおぜいの子供の中でも特にあなたがそばにいてほしく、またいてくれれば頼もしくてうれしいのだのに、いつまでもなぜそちらにあなたはいる」
|
【などか、まづ見えむとは】- 以下「おぼつかなきこと」まで、母北の方の催促の詞。
|
| 12.3.7 |
|
とお恨み申し上げなさるのも、これもまた、もっともなことである。
|
こんなことを使いに言わせて来るのにももっともなところがあって、衛門督は母へ同情をせずにはおられないのであった。
|
【また、いとことわりなり】- 明融臨模本は「ことわり」とある。大島本は「ことハりなり」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「ことわりなり」と「なり」を補訂する。『新大系』は底本(大島本)のままとする。母親が子の身の上を案じるというのも、もっともなことである、という意。
|
| 12.3.8 |
|
「他の兄弟より先に生まれたせいでしょうか、特別にかわいがっていたので、今でもやはりいとしくお思いになって、少しの間でも会わないのを辛くお思いになっているので、気分がこのように最期かと思われるような時に、お目にかからないのは、罪障深く、気が塞ぐことでしょう。
|
「私がいちばん初めに生まれたためなのでしょうが、大事にされていまして、こんなになってもまだ母はかわいがりまして、しばらくの間でも逢わずにいることを苦しがるのですから、もう頼み少ない病状になっている際に、母の逢いたがる心を満足させないのは未来の世までの罪になるだろうと思われますから、とにかく病床をあちらへ移します。
|
【人より先なりけるけぢめにや】- 以下「思ひはべりけること」まで、柏木の詞。
【罪深く、いぶせかるべし】- 『完訳』は「親に先立つ最悪の不孝。しかも親の立ち会わぬ子の臨終はいっそう罪深い。柏木は死ぬために親もとに帰ろうとしている」と注す。
|
| 12.3.9 |
|
今はいよいよ危篤とお聞きあそばしたら、たいそうこっそりお越しになってお会い下さい。
必ず再びお会いしましょう。
妙に気がつかないふつつかな性分で、何かにつけて疎略な扱いであったとお思いになることがおありだったでしょうと、後悔されます。
このような寿命とは知らないで、将来末長くご一緒にとばかり思っておりました」
|
もういよいよ危篤になったというしらせがありましたら、そっと大臣邸へおいでなさい。必ずもう一度お目にかかりましょう。ぼんやりとした性質なものですから、気もつかずにあなたを不愉快におさせしたような場合もあったであろうと思われますのが残念でなりません。こんなに短命で終わろうとは思いませんで、長い将来に誠意をくんでいただける日が必ずあるもののように思って安心していました」
|
【今はと頼みなく聞かせたまはば】- 柏木の臨終をさす。
【あやしくたゆくおろかなる本性にて】- 柏木、みずからの性格を反省。『集成』は「どうしたわけか、気がつかない、なおざりな性分で」。『完訳』は「なぜか意気地もなく思慮も足りない私の性分でして」「密通事件への自戒もこもる」と注す。
【おろかに思さるること】- 妻の女二の宮に対する疎略な待遇、謙遜した言葉。
|
| 12.3.10 |
|
と言って、泣き泣きお移りになった。
宮はお残りになって、何とも言いようもなく恋い焦がれなさった。
|
と、衛門督は宮に申して、泣く泣く父の家へ移って行った。宮はあとに思いこがれておいでになった。
|
【泣く泣く渡りたまひぬ】- 柏木、父太政大臣邸に移る。
|
|
第四段 柏木の病、さらに重くなる
|
| 12.4.1 |
|
大殿ではお待ち受け申し上げなさって、いろいろと大騒ぎをなさる。
そうはいえ、急変するようなご病気の様子でもなく、ここいく月も食べ物などをまったくお召し上がりにならなかったが、ますますちょっとした柑子などでさえお手を触れにならず、ただ、冥界に引き込まれていくようにお見えになる。
|
大臣家では病人の扱いに大騒ぎをして、祈祷やその他に全力を尽くすのであった。病は最悪という容態でもない。ただ食慾がひどく減退して、もうこちらへ来てからは果物をさえ取ろうとしなかった。
|
【よろづに騷ぎたまふ】- 加持祈祷などのための大騒ぎ。
【参らざりけるに】- 接続助詞「に」順接、原因理由を表す。
【ただ、やうやうものに引き入るるやうに見えたまふ】- 明融臨模本と大島本は「やうに」とある。『集成』『新大系』は底本(明融臨模本・大島本)のままとする。『完本』は諸本に従って「やうにぞ」と「ぞ」を補訂する。『集成』は「次第に何かに引き入れられるように、弱っていかれる」。『完訳』は「ただ、だんだんと何かに引き込まれていくようにお見えになるばかりである」「冥界に引き込まれていくような感じ。しだいに衰弱していく」と注す。
|
| 12.4.2 |
さる時の有職の、かくものしたまへば、世の中惜しみあたらしがりて、御訪らひに参りたまはぬ人なし。内裏よりも院よりも、御訪らひしばしば聞こえつつ、いみじく惜しみ思し召したるにも、いとどしき親たちの御心のみ惑ふ。 |
このような当代の優れた人物が、こんなでいらっしゃるので、世間中が惜しみ残念がって、お見舞いに上がらない人はいない。
朝廷からも院の御所からも、お見舞いを度々差し上げては、ひどく惜しんでいらっしゃるのにつけても、ますますご両親のお心は痛むばかりである。
|
教養の足りた優秀な高官と見られている人が、こんなふうに頼み少ない容体になっていることを世間は惜しんで、見舞いを申し入れに来ぬ人もない。宮中からも法皇の御所からもしばしばお見舞いの御使いが来て、衛門督の病状を御心痛あそばされているのを見ても、両親は悲しくばかり思われた。
|
【御心のみ惑ふ】- 副助詞「のみ」強調のニュアンスを添える。『集成』は「いよいよ深まるご両親の悲しみは、気も狂わんばかりである」と訳す。
|
| 12.4.3 |
|
六条院におかれても、「まことに残念なことだ」とお嘆きになって、お見舞いを頻繁に丁重に父大臣にも差し上げなさる。
大将は、それ以上に仲の好い間柄なので、お側近くに見舞っては、大変にお嘆きになっておろおろしていらっしゃる。
|
六条院も非常に残念に思召して、たびたび懇切なお見舞いの手紙を大臣へ下された。左大将はまして仲のよい友人であったから、病床へもよく訪ねて来て、衛門督をいたましがっていた。
|
【父大臣にも聞こえたまふ】- 係助詞「も」同類の意。柏木はもちろん父大臣にも、の意。
【大将は、ましていとよき御仲なれば】- 副詞「まして」は、源氏と柏木との関係以上に、のニュアンス。
【ものしたまひつつ】- 副助詞「つつ」は、同じ動作の繰り返し。たびたびお見舞いに伺っては、のニュアンス。
|
| 12.4.4 |
|
御賀は、二十五日になってしまった。
このような時に重々しい上達部が重病でいらっしゃるので、親、兄弟たち、大勢の方々、そういう高貴なご縁戚や友人方が嘆き沈んでいらっしゃる折柄なので、何か興の冷めた感じもするが、次々と延期されて来た事情さえあるのに、このまま中止にすることもできないので、どうして断念なされよう。
女宮のご心中を、おいたわしくお察し上げになる。
|
法皇の御賀は二十五日になった。現在での花形の高官が重い病気をしてその一家一族の人たちが愁いに沈んでいる時に決行されるのは寂しいことのように院はお思いになったが、月々に支障があって延びてきたことであったし、ぜひ今年じゅうにせねばならぬことでもあったから、やむをえぬことだったのである。院は姫宮の心情を哀れにお思いになっていた。
|
【御賀は、二十五日になりにけり】- 前に「十二月になりにけり十余日と定めて」(第十一章五段)とあった。「なりにけり」には、その予定がさらに延びてしまったというニュアンスがこめられている。
【かかる時のやむごとなき上達部の】- 『集成』は「当世の下にも置かれぬ」。『完訳』は「こういうときにぜひご列席にならねばならない大事な上達部が」と訳す。
【次々に滞りつることだにあるを】- 副助詞「だに」打消や反語の表現をともなった文脈の中で、例外的・逆接的な事態であることを強調するニュアンス。『集成』は「御賀が次々延引になったことだけでも不都合なことであるのに」。『完訳』は「これまで次々と延引を重ねたことだけでも申し訳のないことなのに」と訳す。
【いかでかは思し止まらむ】- 語り手が、源氏の心中を忖度した表現。
【いとほしく思ひきこえさせたまふ】- 主語は源氏。
|
| 12.4.5 |
|
例によって、五十寺の御誦経、それから、あちらのおいでになる御寺でも、摩訶毘廬遮那の御誦経が。
|
かねての計画のように五十か寺での御誦経が最初にあって、法皇のおいであそばされる寺でも大日如来の御祈りが行なわれた。
|
【例の、五十寺の御誦経】- 五十賀にちなむ五十寺での御誦経。
【摩訶毘盧遮那の】- 『集成』は「こうした中断の形で擱筆したとするのが古来の通説であるが、この帖の終りの一葉が何らかの事情で失われた可能性もあろう。次の柏木の巻の末尾にも同じような状況がある」と注す。
|
| 著作権 |
| 底本 |
明融臨模本 |
| 校訂 |
Last updated 9/21/2010(ver.2-3)
渋谷栄一校訂(C)
オリジナル
修正版
比較 |
| ローマ字版 |
Last updated 5/27/2010 (ver.2-2)
Written in Japanese roman letters
by Eiichi Shibuya (C)
オリジナル
修正版
比較 |
ルビ抽出
(ローマ字版から)
|
Powered by 再編集プログラム v4.05
ひらがな版
ルビ抽出 |
挿絵
(ローマ字版から)
|
'Eiri Genji Monogatari'
(1650 1st edition) |
|
Last updated 1/13/2002
渋谷栄一訳(C)(ver.1-2-2)
オリジナル
修正版
比較 |
|
|
Last updated 5/27/2010(ver.2-2)
渋谷栄一注釈(C)
オリジナル
修正版
比較 |
|