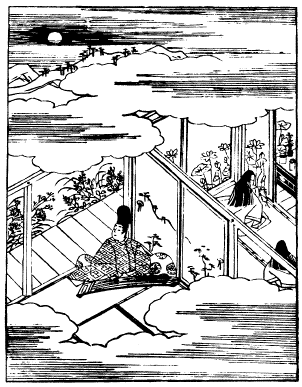第三十八帖 鈴虫
光る源氏の准太上天皇時代五十歳夏から秋までの物語
|
# |
本文 |
渋谷栄一訳 |
与謝野晶子訳 |
注釈 |
|
第一章 女三の宮の物語 持仏開眼供養
|
|
第一段 持仏開眼供養の準備
|
| 1.1.1 |
|
夏頃、蓮の花の盛りに、入道の姫宮が御持仏の数々をお造りになったのを、開眼供養を催しあそばす。
|
夏の蓮の花の盛りに、でき上がった入道の姫宮の御持仏の供養が催されることになった。
|
【夏ごろ、蓮の花の盛りに】- 源氏五十歳の夏、「横笛」巻の翌年。
【入道の姫宮の御持仏どもあらはしたまへる、供養ぜさせたまふ】- 『集成』は「お念持仏(身辺に安置して、朝夕礼拝する仏像)の数々をお造りになったのを、開眼供養なさる」。「あらはしたまへる」「供養ぜさせたまふ」の主語は、女三の宮。
|
| 1.1.2 |
|
今回は、大殿の君のお志で、御念誦堂の道具類も、こまごまとご準備させていたのを、そっくりそのままお飾りあそばす。
幡の様子など優しい感じで、特別な唐の錦を選んでお縫わせなさった。
紫の上が、ご準備させなさったのであった。
|
御念誦堂のいっさいの装飾と備え付けの道具は六条院のお志で寄進されてあった。柱にかける幡なども特別にお選びになった支那錦で作られてあった。
|
【調へさせたまへるを】- 「させ」使役の助動詞。源氏が家人をして。
【紫の上ぞ、急ぎせさせたまひける】- 「させ」使役の助動詞。過去の助動詞「ける」は事の終わった後から事情を明かすニュアンス。
|
| 1.1.3 |
花机の覆ひなどのをかしき目染もなつかしう、きよらなる匂ひ、染めつけられたる心ばへ、目馴れぬさまなり。夜の御帳の帷を、四面ながら上げて、後ろの方に法華の曼陀羅かけたてまつりて、銀の花瓶に、高くことことしき花の色を調へてたてまつり、名香に、唐の百歩の薫衣香を焚きたまへり。 |
花机の覆いなどの美しい絞り染も優しい感じで、美しい色艶が、染め上げられている趣向など、またとない素晴らしさである。
夜の御帳台の帷子を、四面とも上げて、後方に法華の曼陀羅をお掛け申して、銀の花瓶に、高々と見事な蓮の花を揃えてお供えになって、名香には、唐の百歩の衣香を焚いていらっしゃる。
|
紫夫人の手もとで調製された花机の被いは鹿の子染めを用いたものであるが、色も図柄も雅味に富んでいた。帳台の四方の帷を皆上げて、後ろのほうに法華経の曼陀羅を掛け、銀の華瓶に高く立華をあざやかに挿して供えてあった。仏前の名香には支那の百歩香がたかれてある。
|
【をかしき目染もなつかしう】- 「目染(めぞめ)」、鹿の子絞り。絞り染。
【たてまつり】- 大島本は「奉り」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「たてまつれり」と文を結ぶ。『新大系』は底本のままとする。
【名香に】- 大島本は「名かうに」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「名香には」と「は」を補訂する。『新大系』は底本のままとする。
【薫衣香】- 大島本は「くのえかう」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「衣香(えかう)」と「くの」を削除する。『新大系』は底本のままとする。
|
| 1.1.4 |
|
阿彌陀仏、脇士の菩薩、それぞれ白檀でお造り申してあるのが、繊細で美しい感じである。
閼伽の道具は、例によって、際立って小さくて、青色、白色、紫の蓮の色を揃えて、荷葉香を調合したお香は、蜜を控えてぼろぼろに崩して、焚き匂わしているのが、一緒に匂って、とても優しい感じがする。
|
阿弥陀仏と脇士の菩薩が皆白檀で精巧な彫り物に現わされておいでになった。閼伽の具はことに小さく作られてあって、白玉と青玉で蓮の花の形にした幾つかの小香炉には蜂蜜の甘い香を退けた荷葉香が燻べられてある。
|
【阿弥陀仏、脇士の菩薩】- 阿弥陀仏とその脇士の観音菩薩と勢至菩薩。
【荷葉の方を合はせたる名香】- 「荷葉の方」は夏の薫香。
【一つ薫りに】- 大島本は「ひとつかをりに」とある。『完本』は諸本に従って「ひとつかをり」と「に」を削除する。『集成』『新大系』は底本のままとする。
|
| 1.1.5 |
|
経は、六道の衆生のために六部お書きあそばして、ご自身の御持経は、院がご自身でお書きあそばしたのであった。
せめてこれだけでも、この世の結縁として、互いに極楽浄土に導き合いなさるようにとの旨を願文にお作りあそばした。
|
経巻は六道を行く亡者のために六部お書かせになったのである。宮の持経は六条院がお手ずからお書きになったものである。これを御仏への結縁としてせめて愛する者二人が永久に導かれたい希望が御願文に述べられてあった。
|
【六部書かせたまひて】- 「せたまひて」最高敬語。主語は女三の宮。
【みづからの御持経は、院ぞ御手づから書かせたまひける】- 女三の宮御自身の御持経は、源氏の御親筆による。「書かせたまひける」最高敬語、過去の助動詞「けり」後から事情を明かすニュアンス。
|
| 1.1.6 |
|
その他には、阿彌陀経、唐の紙はもろいので、朝夕のご使用にはどのようなものかしらと考えて、紙屋院の官人を召して、特別にご命令を下して、格別美しく漉かせなさった紙に、この春頃から、お心を込めて急いでお書きあそばしたかいがあって、その片端を御覧になった方々、目も眩むほどに驚いていらっしゃる。
|
朝夕に読誦される阿弥陀経は支那の紙ではもろくていかがかと思召され、紙屋川の人をお呼び寄せになり特にお漉かせになった紙へ、この春ごろから熱心に書いておいでになったこの経巻は、片端を遠く見てさえ目がくらむ気のされるものであった。
|
【さては、阿弥陀経】- これも源氏親筆。
【朝夕の御手慣らしにも】- 女三の宮が始終使うには、の意。
【御心とどめて急ぎ書かせたまへるかひありて】- 「書かせたまひ」最高敬語。『完訳』は「お心をこめてせっせとお書きになっただけのことはあって」と訳す。
|
| 1.1.7 |
|
罫に引いた金泥の線よりも、墨の跡の方がさらに輝くように立派な様子などが、まことに見事なものであった。
軸、表紙、箱の様子など、言うまでもないことである。
これは特に沈の花足の机の上に置いて、仏と同じ御帳台の上に飾らせなさった。
|
罫に引いた黄金の筋よりも墨の跡がはるかに輝いていた。軸、表紙、箱に用いられた好みの優雅さはことさらにいうまでもない。この巻き物は特に沈の木の華足の机に置いて、仏像を安置した帳台の中に飾ってあった。
|
【罫かけたる金の筋よりも、墨つきの上に】- 罫に引いた金泥の線よりも、源氏の書いた墨筆の方が目も眩むほど素晴らしい。
【軸、表紙、筥のさま】- 巻物にしたお経の軸、表紙、収納箱。
【これはことに】- 阿弥陀経をさす。
【飾らせたまへり】- 大島本は「かさらせ給へり」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「飾られ」と校訂する。『新大系』は底本のままとする。
|
|
第二段 源氏と女三の宮、和歌を詠み交わす
|
| 1.2.1 |
|
お堂を飾り終わって、講師が壇上して、行道の人々も参集なさったので、院もそちらに出ようとなさって、宮のいらっしゃる西の廂の間にお立ち寄りなさると、狭い感じのする仮の御座所に、窮屈そうに暑苦しいほどに、仰々しく装束をした女房たちが五、六十人ほど集まっていた。
|
堂の準備ができて講師が座に着き行香をする若い殿上人などが皆そろった時に、院もその仏間のほうへおいでになろうとして、尼宮の西の庇のお座敷へまずはいって御覧になると、狭い気のするこの仮のお居間の中に、暑いほどにも着飾った女房が五、六十人集まっていた。
|
【行道の人びと】- 大島本「行た(た=かイ<朱><右>、た=か<墨><左>)うの人/\」とある。『集成』は本文を「行香の人々」とし、「法会の時、僧に香を配ること。殿上人が勤める」と注す。『完訳』は「行道の人々」とし、「仏像の周囲を巡り歩く礼法。「行香」とする本も多い」と注す。『完本』は「行道の人々」する。『新大系』は「行香の人/\」とする。
【宮のおはします西の廂に】- 『集成』は「寝殿の西面の西の廂。女三の宮の常の居間である母屋は法会の場になっているので、西廂に移っている」と注す。
【ことことしく装束きたる女房、五、六十人ばかり集ひたり】- 女三の宮付きの女房の勢揃いであろう。五、六十人伺候していた。
|
| 1.2.2 |
|
北の廂の間の簀子まで、女童などはうろうろしている。
香炉をたくさん使って、煙いほど扇ぎ散らすので、近づきなさって、
|
童女などは北側の室の外の縁にまで出ているのである。火入れがたくさん出されてあって、薫香をけむいほど女房たちが煽ぎ散らしているそばへ院はお寄りになって、
|
【北の廂の簀子まで、童女などはさまよふ】- 女房以外の女童は北の廂をはみ出して簀子に伺候した。
【火取りども】- 香炉。接尾語「ども」は複数を表す。
|
| 1.2.3 |
|
「空薫物は、どこで焚いているのか分からないくらいなのがよいのだ。
富士山の噴煙以上に、煙がたちこめているのは、感心しないことだ。
お経の御講義の時には、あたり一帯の音は立てないようにして、静かにお説教の意味を理解しなければならないことだから、遠慮のない衣ずれの音、人のいる感じは、出さないのがよいのです」
|
「空だきというものは、どこで焚いているかわからないほうが感じのいいものだよ。富士の山頂よりももっとひどく煙の立っているのなどはよろしくない。説教の間は物音をさせずに静かに細かく話を聞かなければならないものだから、無遠慮に衣擦れや起ち居の音はなるべくたてぬようにするがいい」
|
【空に焚くは、いづくの煙ぞと】- 以下「静めてなむよかるべき」まで、源氏の詞。「空に焚くは」は空薫物はの意。
【富士の嶺よりもけに、くゆり満ち出でたる】- 富士山の噴煙よりも多く煙が出ている意。当時の富士山は噴煙を上げていた。伊勢物語、更級日記等参照。
|
| 1.2.4 |
など、例の、もの深からぬ若人どもの用意教へたまふ。
宮は、人気に圧されたまひて、いと小さくをかしげにて、ひれ臥したまへり。
|
などと、いつものとおり、思慮の足りない若い女房たちの心用意をお教えになる。
宮は、人気に圧倒されなさって、とても小柄で美しい感じに臥せっていらっしゃった。
|
などと、例の軽率な若い女房などをお教えになった。宮は人気に押されておしまいになり、小さいお美しい姿をうつ伏せにしておいでになる。
|
|
| 1.2.5 |
|
「若君が、騒がしかろう。
抱いてあちらへお連れ申せ」
|
「若君をここへ置かずに、どちらか遠い部屋へ抱いて行くがよい」
|
【若君、らうがはしからむ。抱き隠したてまつれ】- 源氏の詞。「若君」は薫。
|
| 1.2.6 |
などのたまふ。
|
などとおっしゃる。
|
とまた院は女房へ注意をあそばされた。
|
|
|
 |
| 1.2.7 |
|
北の御障子も取り放って、御簾を掛けてある。
そちらに女房たちをお入れになっている。
静かにさせて、宮にも、法会の内容がお分かりになるように予備知識をお教え申し上げなさるのも、とても親切に見える。
御座所をお譲りなさった仏のお飾り付け、御覧になるにつけても、あれこれと感慨無量で、
|
北側の座敷との間も今日は襖子がはずされて御簾仕切りにしてあったが、そちらの室へ女房たちを皆お入れになって、院は尼宮に今日の儀式についての心得をお教えになるのであったが、その方を可憐にばかりお思われになった。昔の鴛鴦の夢の跡の仏の御座になっている帳台が御簾越しにながめられるのも院を物悲しくおさせすることであった。
|
【北の御障子も取り放ちて、御簾かけたり】- 『完訳』は「母屋の北側の障子(襖)。北の廂にも女房の聴聞所を設営。御簾で女房たちの姿を隠す」と注す。
【そなたに人びとは入れたまふ】- 「そなた」は北の廂の間。「人びと」は女房。
【下形】- 予備知識。
【御座を譲りたまへる】- 女三の宮の常の御座所を。
【見やりたまふも】- 主語は源氏。
【さまざまに】- 『完訳』は「源氏は宮の御帳台を見て、これまでの夫婦仲、宮と柏木の密通などを回想、複雑な思念を抱く」と注す。
|
| 1.2.8 |
|
「このような仏事の御供養を、ご一緒にしようとは思いもしなかったことだ。
まあ、しかたない。せめて来世では、あの蓮の花の中の宿を、一緒に仲好くしよう、と思って下さい」
|
「こんな儀式をあなたのためにさせる日があろうなどとは予想もしなかったことですよ。これはこれとして来世の蓮の花の上では睦まじく暮らそうと期していてください」
|
【かかる方の】- 以下「とを思ほせ」まで、源氏の詞。『集成』は「若い女三の宮は、源氏よりもあと、その死後か出家の後に、世を背くことになろうと思っていたのに、逆に今生で自分が宮から厭い捨てられたことを恨む」と注す。
【かの花の中の宿りに、隔てなく、とを】- 『集成』は「極楽の往生人は、蓮華の上に半座をあけて同行の人を待つとされた」と注す。『河海抄』所引、五会讃。
|
| 1.2.9 |
とて、うち泣きたまひぬ。
|
とおっしゃって、お泣きになった。
|
と言って院はお泣きになった。
|
|
| 1.2.10 |
|
「来世は同じ蓮の花の中でと約束したが
その葉に置く露のように別々でいる今日が悲しい」
|
蓮葉を同じうてなと契りおきて
露の分かるる今日ぞ悲しき
|
【蓮葉を同じ台と契りおきて--露の分かるる今日ぞ悲しき】- 源氏から女三の宮への贈歌。主旨は、一蓮托生と約束したが、別々に暮らすのが悲しい。「蓮葉」「置き」「露」が縁語。
|
| 1.2.11 |
と、御硯にさし濡らして、香染めなる御扇に書きつけたまへり。
宮、
|
と、御硯に筆を濡らして、香染の御扇にお書き付けになった。
宮は、
|
硯に筆をぬらして、香染めの宮の扇へお書きになった。宮が横へ、
|
|
| 1.2.12 |
|
「蓮の花の宿を一緒に仲好くしようと約束なさっても
あなたの本心は悟り澄まして一緒にとは思っていないでしょう」
|
隔てなく蓮の宿をちぎりても
君が心やすまじとすらん
|
【隔てなく蓮の宿を契りても--君が心や住まじとすらむ】- 女三の宮の返歌。「蓮」「契り」の語句を引用して、「君が心やすまじとすらむ」と切り返す。「すまじ」は「住まじ」と「清まじ」の掛詞。
|
| 1.2.13 |
と書きたまへれば、
|
とお書きになったので、
|
こうお書きになると、
|
|
| 1.2.14 |
|
「せっかくの申し出をかいなくされるのですね」
|
「そんなに私が信用していただけないのだろうか」
|
【いふかひなくも思ほし朽たすかな】- 源氏の詞。
|
| 1.2.15 |
|
と、苦笑しながらも、やはりしみじみと感に堪えないご様子である。
|
笑いながら院は言っておいでになるのであるが身にしむものがある御様子であった。
|
【うち笑ひながら、なほあはれとものを思ほしたる御けしきなり】- この「笑ひ」は苦笑。「なほ」以下、語り手の源氏評。女三の宮になお執着している源氏の態度に対する客観的コメント。
|
|
第三段 持仏開眼供養執り行われる
|
| 1.3.1 |
|
例によって、親王たちなども、とても大勢参上なさった。
御夫人方から、我も我もと作り出した御供物の様子、格別立派で、所狭しと見える。
七僧の法服など、総じて一通りのことは、皆紫の上がご準備させなさった。
綾織物で、袈裟の縫目まで、分かる人は、世間にはめったにない立派な物だと誉めたとか。
うるさく細かい話であるよ。
|
例のことであるが親王がたも多く参会された。六条院の夫人たちから仏前へささげられた物の数も多かった。七僧の法服とか、この法事についての重だった布施は皆紫夫人が調製させたものである。綾地の法服で、袈裟の縫い目までが並み並みの物でないことを言って当時の僧がほめたそうである。こんなこともむずかしいものらしい。
|
【例の、親王たちなども、いとあまた参りたまへり】- 「例の」は「参りたまへり」を修飾する。したがって、「例の」の下に読点必要。
【御方々より】- 六条院の源氏のご夫人方をさす。
【営み出でたまへる】- 大島本は「いとなミ」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「いどみ」と校訂する。『新大系』は底本のままとする。
【紫の上せさせたまへり】- 「させ」使役の助動詞。
【綾のよそひにて、袈裟の縫目まで、見知る人は、世になべてならずとめでけりとや。むつかしうこまかなることどもかな】- 『一葉抄』は「作者の詞也」と指摘。『集成』は「草子地」。『完訳』は「語り手の言辞。省筆しながら、紫の上の用意した法服を賞賛」と注す。
|
| 1.3.2 |
|
講師が大変に尊く、法要の趣旨を申して、この世でご立派であった盛りのお身の上を厭い離れなさって、未来永劫にわたって絶えることのない夫婦の契りを、法華経に結びなさる、尊く深いお心を表わして、ただ現在、才学も優れ、豊かな弁舌を、ますます心をこめて言い続ける、とても尊いので、参会者全員、涙をお流しなさる。
|
講師が宮の御遁世を讃美して、この世におけるすぐれた栄華をなお盛りの日にお捨てになり、永久の縁を仏にお結びになったということを、豊かな学才のある僧が美辞麗句をもって言い続けるのに感動して萎たれる人が多かった。
|
【この世にすぐれたまへる盛りを】- 以下「尊く深きさま」まで、講師の読み上げた趣旨(表白)の内容、間接的に要約して叙述。
【長き世々に絶ゆまじき御契り】- 源氏と女三の宮との夫婦の契り。
【ただ今の世の】- 大島本は「たゝいまのよの」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「今の世に」と校訂する。『新大系』は底本のままとする。
【才もすぐれ、豊けきさきらを】- 講師の学才、弁舌文才をいう。
|
| 1.3.3 |
これは、ただ忍びて、御念誦堂の初めと思したることなれど、内裏にも、山の帝も聞こし召して、皆御使どもあり。御誦経の布施など、いと所狭きまで、にはかになむこと広ごりける。 |
この持仏開眼供養は、ただこっそりと、御念誦堂の開き初めとお考えになったことだが、帝におかせられても、また山の帝もお耳にあそばして、いずれもお使者があった。
御誦経のお布施など、大変置ききれないほど、急に大げさになったのであった。
|
今日のはただ御念誦堂開きとしてお催しになった法会であったが、宮中からも御寺の法皇からもお使いがあって、御誦経の布施などが下されてにわかに派手なものになった。
|
【これは】- 今回の持仏開眼供養をさす。
【内裏にも、山の帝も】- 主上は女三の宮の兄弟、山の帝は父朱雀院である。
|
| 1.3.4 |
|
院でご準備あそばしたことも、簡略にとはお思いになったが、それでも並々ではなかったのだが、それ以上に、華やかなお布施が加わったので、夕方のお寺に置き場もないほど沢山になって、僧たちは帰って行ったのであった。
|
初めの設けは簡単にしたように院は思召しても、それは決して並み並みの物でなかった上、宮廷の御寄進が添ったので、出席した僧たちは、置き所もない布施を得て寺へ帰った。
|
【院にまうけさせたまへりける】- 六条院。「させ」尊敬の助動詞。最高敬語待遇。
【夕べの寺に置き所なげなるまで、所狭き勢ひになりてなむ、僧どもは帰りける】- 『集成』は「夕方、寺に置き所もなさそうなほど、豪勢な様子で僧たちは帰って行った」。『完訳』は「夕方になって退出する僧たちは、寺に持ち帰っても置場があるまいと思われるくらいお布施をいただいて、豪勢な様子で帰っていったのであった」と訳す。「重畳せる煙嵐の断えたる処に晩寺に僧帰る」(和漢朗詠集下、僧)。
|
|
第四段 三条宮邸を整備
|
| 1.4.1 |
|
今となって、おいたわしく思われる気持ちが加わって、この上もなく大切にお世話申し上げなさる。
院の帝は、御相続なさった宮に離れてお住みになることも、結局のことなのだから、世間体がよいように申し上げなさるが、
|
御出家をあそばされた今になって宮を院がごたいせつにあそばすことは非常で、無限の御愛情が運ばれていると見えた。御寺の帝は宮へ御分配になった邸宅へ今はもうお移りになるほうが世間体もよいとお勧めになるのであったが、六条院は、
|
【今しも、心苦しき御心添ひて】- 副助詞「しも」強調のニュアンス。『完訳』は「宮の出家生活が本格化する今になって、源氏の執心が強まる」と注す。
【この御処分の宮に】- 朱雀院から女三の宮に遺贈された三条宮邸。
【つひのことにて】- 『完訳』は「出家の身ゆえ、どうせ別居するのだから、居間のうちが世間体もよかろうと。その時期が遅れては、世人が疑念を抱くだろう、の判断」と注す。
|
| 1.4.2 |
「よそよそにては、おぼつかなかるべし。明け暮れ見たてまつり、聞こえ承らむこと怠らむに、本意違ひぬべし。げに、あり果てぬ世いくばくあるまじけれど、なほ生ける限りの心ざしをだに失ひ果てじ」 |
「離れ離れでいては、気掛かりであろう。
毎日お世話申し上げて、こちらから申し上げたり用向きを承ることができないようでは、本意に外れることであろう。
なるほど、いつまでも生きていられない世であるが、やはり生きている限りはお世話したい気持ちだけはなくしたくない」
|
「遠くなっては始終お目にかかることもできないので困ります。毎日お逢いしてお話ができたり、あなたの用を聞いたりすることができなくなっては、私の期していたことが皆画餠になってしまう。そういっても私に残された命はもう何ほどでもないのでしょうが、生きている間はせめてその志だけでも尽くさせてください」
|
【よそよそにては】- 以下「失ひ果てじ」まで、源氏の詞。下文に「聞こえたまひつつ」とあるので、直接話法というより間接話法的内容。
【あり果てぬ世】- 「ありはてぬ命待つ間のほどばかり憂きことしげく思はずもがな」(古今集雑下、九六五、平貞文)。
|
| 1.4.3 |
|
と申し上げ申し上げなさっては、あちらの宮も大変念入りに美しくご改築させなさって、御封の収入、国々の荘園、牧場などからの献上物で、これはと思われる物は、全てあちらの三条宮の御倉に納めさせなさる。
さらに又、増築させて、いろいろな御宝物類、院の御遺産相続の時に無数にお譲り受けなさった物など、宮の関係の品物は、全てあちらの宮に運び移して、念を入れて厳重に保管させなさる。
|
とお言いになって賛成をあそばさないのである。院はまたそのほうの邸宅もきれいに修繕させてお置きになって、宮が官から給されておいでになる収入や、御私有の荘園や牧から上がって来る物の中でも、貯蔵しておく価値のある物は皆その三条の宮の倉庫へ納めさせてお置きになった。新しい倉庫の建て増しまでおさせになって、それへは法皇がこの宮へ無数に御分配になった貴重品の今まで六条院にあったのを移してお蔵わせになった。
|
【聞こえたまひつつ】- 接続助詞「つつ」同じ動作の反復。
【この宮を】- 大島本は「この宮」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「かの宮」と校訂する。『新大系』は底本のままとする。三条宮邸をさす。
【いとこまかにきよらに造らせたまひ】- 「せ」使役の助動詞。『集成』は「念入りに立派に改築させなさって」と訳す。
【またも、建て添へさせたまひて】- 源氏がさらにまた御倉を建て加えさせなさって、の意。「させ」使役の助動詞。三条宮邸の家司等をしての意。
【あなたざまの物は】- 女三の宮関係の物は、の意。
|
| 1.4.4 |
|
日常のお世話、大勢の女房の事ども、上下の人々の面倒は、全てご自分の経費のまかないでなどと、急いでお手入れをして差し上げる。
|
これは永久に宮の御家を経済的に保証する価値ある財産というべきものである。そして六条院における宮の御生活とおおぜいの女房、男女の召使に要する費用は院の御負担とお決めになったのである。
|
【そこらの女房】- 女三の宮付きの女房は五、六十人いる。
【御扱ひにてなど】- 大島本は「なと」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「なむ」と校訂する。『新大系』は底本のままとする。
【急ぎ仕うまつらせたまひける】- 『完訳』は「お手入れをお進めになるのであった」と訳す。「つかうまつる」は、目上の人に~してさしあげるというニュアンス。「せ」尊敬の助動詞、源氏に対する最高敬語。
|
|
第二章 光る源氏の物語 六条院と冷泉院の中秋の宴
|
|
第一段 女三の宮の前栽に虫を放つ
|
| 2.1.1 |
|
秋頃、西の渡殿の前、中の塀の東側を、辺り一帯を野原の感じにお作らせになった。
閼伽の棚などを作って、その方面の生活にふさわしくお整えになったお道具類など、とても優美な感じである。
|
秋になって院は尼宮のお住居の西の渡殿の前の中の塀から東の庭を草原にお作らせになった。閼伽棚などをそのほうへお作らせになったのが優美に見える。
|
【西の渡殿の前、中の塀の東の際を】- 寝殿と西の対を結ぶ渡廊の前(南)側でその間にある塀の東側。
【その方に】- 仏道方面の生活に。
|
| 2.1.2 |
|
お弟子としてお従い申し上げている尼たち、御乳母、老女たちは、それはそれとして、若い盛りの女房でも、決心固く、尼として一生を送れる者だけを選んで、おさせになったのであった。
|
宮の御出家のお供をして乳母そのほかの老いた女たちは必然的に尼になったが、若盛りの人でも、他日動揺する恐れのない、信念の堅そうな人たちだけを御弟子にされることになり、
|
【従ひきこえたる】- 大島本は「したかひ」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「慕ひ」と校訂する。『新大系』は底本のままとする。
【さる方にて】- 尼として。
【選りてなむ、なさせたまひける】- 主語は源氏。
|
| 2.1.3 |
さるきほひには、我も我もときしろひけれど、大殿の君聞こしめして、
|
その当座の競争気分の折には、我も我もと競って申し出たが、大殿がお聞きになって、
|
われもわれもと希望する者の多いのを、院がお聞きになって、
|
|
| 2.1.4 |
|
「それは良くないことだ。
本心からでない人が少しでも混じってしまうと、周囲の人が困るし、浮ついた噂が出て来るものだ」
|
「群衆心理で今はその気になっているでしょうが、それをお許しになってはいけませんよ。不純な者が少しでも混じっていては他の者の迷惑になりますよ」
|
【あるまじきことなり】- 以下「出で来るわざなり」まで、源氏の詞。
【かたへの人苦しう】- 「人」「苦しう」は主語-述語の関係。
|
| 2.1.5 |
と諌めたまひて、十余人ばかりのほどぞ、容貌異にてはさぶらふ。
|
とお諌めになって、十何人かだけが尼姿になってお付きしている。
|
と御忠告になり、全部の中から十幾人だけが尼姿で侍することになった。
|
|
| 2.1.6 |
|
この野原に虫どもを放たせなさって、風が少し涼しくなってきた夕暮に、たびたびお越しになっては、虫の音を聴くふりをなさって、今でも断ちがたい思いのほどを申し上げ悩ましなさるので、
|
今度の草原に院は虫をお放ちになって、夕風が少し涼しくなるころに宮の所へおいでになり、虫の音を愛しておいでになるふうでしきりに宮を誘惑しようとしておいでになった。
|
【虫ども放たせたまひて】- 主語は源氏。「せ」使役の助動詞。
【渡りたまひつつ】- 主語は源氏。接続助詞「つつ」同じ動作の繰り返し。源氏の女三の宮に対する執心。
【虫の音を聞きたまふやうにて、なほ思ひ離れぬさまを聞こえ悩ましたまへば】- 源氏の女三の宮に対する執心。『完訳』は「「--やうにて」とあり、虫の音の観賞は二の次で、宮との対面が目的」と注す。
|
| 2.1.7 |
|
「いつものお心癖はとんでもないことになろう」
|
今さらそうした行ないはあるまじいことである
|
【例の御心はあるまじきことにこそはあなれ】- 女三の宮の心中。『完訳』は「以下、宮の心内に即した叙述。「例の」の注意。源氏の好色心ゆえの頻繁な訪問と思われ、困惑する」と注す。「なれ」断定の助動詞。
|
| 2.1.8 |
と、ひとへにむつかしきことに思ひきこえたまへり。
|
と、一途に厄介なことにお思い申し上げていらっしゃった。
|
と、宮はただ恐ろしがっておいでになった。
|
|
| 2.1.9 |
|
他人の目には変わったところなくお扱いになっているが、内心では嫌な事件をご存知の様子がはっきり分かり、すっかり変わってしまったお心を、何とかお目に掛からずにいたいお気持ちで、それが主な動機でご決心なさったご出家なので、今は離れて安心していたのに、
|
人目には以前と変わらぬようにあそばしながら、あの秘密をお知りになってからは、汚れたものとして嫌悪をお続けになった自分の肉体を悲しむ心が出家のおもな動機になり、尼になった時からはいっさいの愛欲を忘れることができて、静かな平和な心を楽しんでいる自分に、
|
【人目にこそ】- 以下、女三の宮の心中に即した叙述。「人目にこそ--もてなし給ひしか、うちには--けしきしるく」という対比の構文。
【こよなう変はりにし御心を】- 源氏の心。女三の宮への愛情。愛情のない執心のみが依然として続く。しかし、愛情は最高の概念ではない。
【いかで見えたてまつらじの御心にて】- 女三の宮の考え、気持ち。
|
| 2.1.10 |
|
「やはり、このように」
|
またこうしたことを
|
【なほ、かやうに」--など聞こえたまふぞ】- 「なほ思ひ離れぬさまを聞こえ悩ましたまへれば」をさす。
|
| 2.1.11 |
|
などとお耳に入れたりなどなさるのが辛くて、「人里離れた所に住みたい」とお思いになるが、大人ぶってとてもそのように押して申し上げることはおできになれない。
|
求められるのは苦しいことであると宮はお思いになり、六条院でない所へ住み移りたくおなりになるのであったが、これをはきはきと言っておしまいになることもできぬ弱い御性質であった。
|
【人離れたらむ御住まひにもがな】- 女三の宮の心中。
|
|
第二段 八月十五夜、秋の虫の論
|
| 2.2.1 |
十五夜の夕暮に、仏の御前に宮おはして、端近う眺めたまひつつ念誦したまふ。若き尼君たち二、三人、花奉るとて鳴らす閼伽坏の音、水のけはひなど聞こゆる、さま変はりたるいとなみに、そそきあへる、いとあはれなるに、例の渡りたまひて、 |
十五夜の夕暮に、仏の御前に宮はいらっしゃって、端近くに物思いに耽りながら念誦なさる。
若い尼君たち二、三人が花を奉ろうとして鳴らす閼伽、坏の音、水の感じなどが聞こえるのは、今までとは違った仕事に、忙しく働いているが、まことに感慨無量なので、いつものようにお越しになって、
|
十五夜の月がまだ上がらない夕方に、宮が仏間の縁に近い所で念誦をしておいでになると、外では若い尼たち二、三人が花をお供えする用意をしていて、閼伽の器具を扱う音と水の音とをたてていた。青春の夢とこれとはあまりに離れ過ぎたことと見えて哀れな時に、院がおいでになった。
|
【十五夜の夕暮に】- 八月の十五夜。中秋の名月の夜。
|
| 2.2.2 |
|
「虫の音がとてもうるさく鳴き乱れている夕方ですね」
|
「むやみに虫が鳴きますね」
|
【虫の音いとしげう乱るる夕べかな】- 源氏の詞。
|
| 2.2.3 |
|
と言って、自分もひっそりと朗誦なさる阿彌陀経の大呪が、たいそう尊くかすかに聞こえる。
いかにも、虫の音がいろいろ聞こえる中で、鈴虫が声を立てているところは、華やかで趣きがある。
|
こう言いながら座敷へおはいりになった院は御自身でも微音に阿弥陀の大誦をお唱えになるのがほのぼのと尊く外へ洩れた。院のお言葉のように、多くの虫が鳴きたてているのであったが、その時に新しく鳴き出した鈴虫の声がことにはなやかに聞かれた。
|
【げに、声々聞こえたる中に】- 「げに」は源氏の詞を受けた語り手の発語。
【鈴虫のふり出でたるほど】- 「鈴」と「振り」は縁語。
|
| 2.2.4 |
|
「秋の虫の声は、どれも素晴らしい中で、松虫が特に優れているとおっしゃって、中宮が、遠い野原から、特別に探して来てはお放ちになったが、はっきり鳴き伝えているのは少ないようだ。
名前とは違って、寿命の短い虫のようである。
|
「秋鳴く虫には皆それぞれ別なよさがあっても、その中で松虫が最もすぐれているとお言いになって、中宮が遠くの野原へまで捜しにおやりになってお放ちになりましたが、それだけの効果はないようですよ。なぜと言えば、持って来ても長くは野にいた調子には鳴いていないのですからね。名は松虫だが命の短い虫なのでしょう。
|
【秋の虫の声】- 以下「らうたけれ」まで、源氏の詞。
【中宮の、はるけき野辺を分けて】- 秋好中宮。「野辺」歌語。
【しるく鳴き伝ふる】- 『集成』は「はっきり野の声さながらに鳴き続ける」と注す。
【名には違ひて】- 「松虫」の「松」は長寿をイメージする。
|
| 2.2.5 |
心にまかせて、人聞かぬ奥山、はるけき野の松原に、声惜しまぬも、いと隔て心ある虫になむありける。
鈴虫は、心やすく、今めいたるこそらうたけれ」
|
思う存分に、誰も聞かない山奥、遠い野原の松原で、声を惜しまず鳴いているのも、まことに分け隔てしている虫であるよ。
鈴虫は、親しみやすく、にぎやかに鳴くのがかわいらしい」
|
人が聞かない奥山とか、遠い野の松原とかいう所では思うぞんぶんに鳴いていて、人の庭ではよく鳴かない意地悪なところのある虫だとも言えますね。鈴虫はそんなことがなくて愛嬌のある虫だからかわいく思われますよ」
|
|
| 2.2.6 |
などのたまへば、宮、
|
などとおっしゃると、宮は、
|
などと院はお言いになるのを聞いておいでになった宮が、
|
|
| 2.2.7 |
|
「秋という季節はつらいものと分かっておりますが
やはり鈴虫の声だけは飽きずに聴き続けていたいものです」
|
大かたの秋をば憂しと知りにしを
振り捨てがたき鈴虫の声
|
【おほかたの秋をば憂しと知りにしを--ふり捨てがたき鈴虫の声】- 女三の宮から源氏への贈歌。「秋」と「飽き」の掛詞。「鈴」「振り」は縁語。『完訳』は「源氏の「鈴虫は--」を受け、庭に虫を放つなどの源氏の厚志に感謝しながらも、自分を飽きた源氏への恨みを言い込めた歌」と注す。
|
| 2.2.8 |
と忍びやかにのたまふ。
いとなまめいて、あてにおほどかなり。
|
とひっそりとおっしゃる。
とても優雅で、上品でおっとりしていらっしゃる。
|
と低い声でお言いになった。非常に艶で若々しくお品がよい。
|
|
| 2.2.9 |
「いかにとかや。いで、思ひの外なる御ことにこそ」とて、 |
「何とおしゃいましたか。
いやはや、思いがけないお言葉ですね」と言って、
|
「何ですって、あなたに恨ませるようなことはなかったはずだ」と院はお言いになり、
|
【いかにとかや】- 以下「御ことにこそ」まで、源氏の詞。『完訳』は「宮の歌の「飽き」への反発」と注す。
|
| 2.2.10 |
|
「ご自分からこの家をお捨てになったのですが
やはりお声は鈴虫と同じように今も変わりません」
|
心もて草の宿りを厭へども
なほ鈴虫の声ぞふりせぬ
|
【心もて草の宿りを厭へども--なほ鈴虫の声ぞふりせぬ】- 源氏の返歌。「振り」「鈴虫」の語句を受けて、「声ぞふりせぬ」あなたは昔どおり若く美しい、と返す。「振り」「古り」掛詞、「鈴」「振り」縁語。「草のやどり」は六条院、「鈴虫」は女三の宮を喩える。『完訳』は「源氏には、「心やすく、いまめい」た鈴虫が、女三の宮の美質として顧みられる。秋虫を放った六条院庭園は、執心を捨て得ない源氏の心象風景たりうる」と注す。
|
| 2.2.11 |
など聞こえたまひて、琴の御琴召して、珍しく弾きたまふ。
宮の御数珠引き怠りたまひて、御琴になほ心入れたまへり。
|
などと申し上げなさって、琴の御琴を召して、珍しくお弾きになる。
宮が御数珠を繰るのを忘れなさって、お琴の音色に依然として聴き入っていらっしゃった。
|
ともおささやきになった。琴をお出させになって珍しく院はお弾きになった。宮は数珠を繰るのも忘れて院の琴の音を熱心に聞き入っておいでになる。
|
|
|
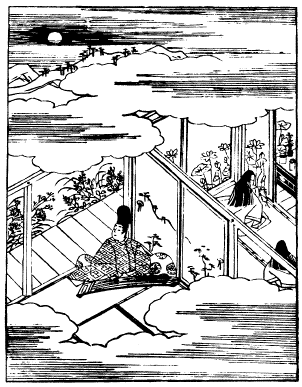 |
| 2.2.12 |
月さし出でて、いとはなやかなるほどもあはれなるに、空をうち眺めて、世の中さまざまにつけて、はかなく移り変はるありさまも思し続けられて、例よりもあはれなる音に掻き鳴らしたまふ。 |
月が出て、とても明るくなったのもしみじみと心を打つので、空をちょっと眺めて、人の世のあれこれにつけて、無常に移り変わる有様が次々と思い出されて、いつもよりもしみじみとした音色でお弾きになる。
|
月が上がってきてはなやかな光に満ちた空も人の心にはしみじみと秋を覚えさせた。院は移り変わることのすみやかな人生を寂しく思い続けておいでになって平生よりも深く身にしむ音をかき立てておいでになった。
|
【世の中さまざまにつけて】- 『集成』は「女三の宮をはじめ、朧月夜や朝顔の前斎院などのこと」と注す。
|
|
第三段 六条院の鈴虫の宴
|
| 2.3.1 |
|
今夜は、いつものとおり管弦のお遊びがあろうかと推量して、兵部卿宮がお越しになった。
大将の君、殿上人で音楽の素養のある人々を連れていらっしゃっていたので、こちらにいらっしゃると、お琴の音をたよりにして、そのまま参上なさる。
|
毎年の例のように今夜は音楽の遊びがあるであろうとお思いになって、兵部卿の宮が来訪された。左大将も若い音楽に趣味を持つ人々を伴って参院したのであるが、こちらの御殿で琴の音のするのを聞いて出て来た。
|
【今宵は、例の御遊びにやあらむと】- 今夜は八月十五夜である。六条院で管弦の遊びが催されるだろうことを期待。
【兵部卿宮】- 蛍兵部卿宮。
【大将の君】- 夕霧。
|
| 2.3.2 |
|
「とても所在ないので、特別の音楽会というのではなくても、長い間弾かないでいた珍しい楽器の音など、聴きたかったので独りで弾いていたのを、たいそうよく聴きつけて来て下さった」
|
「退屈でね、わざとする会合というほどのことでなしに、しばらく聞かれなかった音楽を人が来て聞かせてくれないだろうかと思って、誘い出すことが可能かどうかと、まず一人で始めていたのを、よく聞きつけて来てもらえたね」
|
【いとつれづれにて】- 以下「いとよう尋ねたまひける」まで、源氏の詞。
【独り琴を】- 「を」格助詞、目的格を表す。
【尋ねたまひける】- 「ける」過去の助動詞、詠嘆の意。連体中止法、余意・余情の気持ちを表す。
|
| 2.3.3 |
|
とおっしゃって、宮にも、こちらに御座所を設けてお入れ申し上げなさる。
宮中の御前で、今夜は月の宴が催される予定であったが、中止になって物足りない気がしたので、こちらの院に方々が参上なさると伝え聞いて、誰や彼やと上達部なども参上なさった。
虫の音の批評をなさる。
|
と院はお言いになった。宮のお席もこちらへ作らせてお招じになった。今夜は御所で月見の宴のあるはずであったのが、中止になって寂しがっていた人たちが、六条院へだれかれが集まっていると聞いて、あとからも来るのであった。虫の声の批評をしたあとで、
|
【内裏の御前に、今宵は月の宴あるべかりつるを、とまりて】- 宮中の帝の御前における八月十五夜の月の宴が中止となる。その理由は語られていない。
【聞き伝へて】- 主語は、これかれの上達部。
|
| 2.3.4 |
御琴どもの声々掻き合はせて、おもしろきほどに、
|
お琴類を合奏なさって、興が乗ってきたころに、
|
音楽の合奏があっておもしろい夜になった。
|
|
| 2.3.5 |
|
「月を見る夜は、いつでももののあわれを誘わないことはない中でも、今夜の新しい月の色には、なるほどやはり、この世の後の世界までが、いろいろと想像されるよ。
故大納言が、いつの折にも、亡くなったことにつけて、一層思い出されることが多く、公、私、共に何かある機会に物の栄えがなくなった感じがする。
花や鳥の色にも音にも、美をわきまえ、話相手として、大変に優れていたのだったが」
|
「月をながめる夜というものにいつでも寂しくないことはないものだが、この中秋の月に向かっていると、この世以外の世界のことまでもいろいろと思われる。亡くなった衛門督はどんな場合にも思い出される人だが、ことに何の芸術にも造詣が深かったから、こうした会合にあの人を欠くのはもののにおいがこの世になくなった気がしますね」
|
【月見る宵の】- 以下「いとうるさかりしものを」まで、源氏の詞。
【新たなる月の色には】- 「三五夜中新月の色二千里の外故人心」(白氏文集、八月十五夜禁中独直対月憶元九)。
【思ひ流さるれ】- 「るれ」自発の助動詞。係結びの已然形、強調のニュアンス。
【故権大納言】- 柏木。亡くなる直前に「大納言」となった。
【花鳥の色にも音にも】- 「花鳥の色をも音をもいたづらにもの憂かる身には過ぐすのみなり」(後撰集夏、二一二、藤原雅正)。
|
| 2.3.6 |
などのたまひ出でて、みづからも掻き合はせたまふ御琴の音にも、袖濡らしたまひつ。御簾の内にも、耳とどめてや聞きたまふらむと、片つ方の御心には思しながら、かかる御遊びのほどには、まづ恋しう、内裏などにも思し出でける。 |
などとお口に出されて、ご自身でも合奏なさる琴の音につけても、お袖を濡らしなさった。
御簾の中でも耳を止めてお聴きになって入るだろうと、片一方のお心ではお思いになりながら、このような管弦のお遊びの折には、まずは恋しく、帝におかせられてもお思い出しになられるのであった。
|
とお言いになった院は、御自身の音楽からも愁いが催されるふうで涙をこぼしておいでになるのである。御簾の中で女三の宮が今の言葉に耳をおとめになったであろうかと片心にはお思いになりながらもそうであった。こんな音楽の遊びをする夜などに最も多くだれからも忍ばれる衛門督であった。帝も御遊のたびに故人を恋しく思召されるのであった。
|
【御琴の音にも】- 柏木は和琴の名手であったことを回想。
【御簾の内にも】- 以下「聞きたまふらむ」まで、源氏の心中。「御簾の内」は女三の宮をさす。
|
| 2.3.7 |
|
「今夜は鈴虫の宴を催して夜を明かそう」
|
「今夜は鈴虫の宴で明かそう」
|
【今宵は鈴虫の宴にて明かしてむ】- 源氏の詞。
|
| 2.3.8 |
と思しのたまふ。
|
とお考えになっておっしゃる。
|
こう六条院は言っておいでになった。
|
|
|
第四段 冷泉院より招請の和歌
|
| 2.4.1 |
|
お杯が二回りほど廻ったころに、冷泉院からお手紙がある。
宮中の御宴が急に中止になったのを残念に思って、左大弁や、式部大輔らが、また大勢人々を引き連れて、詩文に堪能な人々ばかりが参上したところ、大将などは六条院に伺候していらっしゃる、とお耳にあそばしてなのであった。
|
杯が二回ほどめぐった時に、冷泉院から御使いが来た。宮中の御遊がないことになったのを残念がって、左大弁、式部大輔その他の人々が院へ伺候したのであって、左大将などは六条院に侍しているとお聞きになった院からの御消息には、
|
【左大弁、式部大輔、また人びと率ゐて】- 左大弁は、柏木の弟、後の紅梅大納言。式部大輔は系図不詳のここだけに登場する人物。
【さるべき限り】- 『完訳』は「詩文に堪能な人々か」と注す。
【聞こし召してなりけり】- 主語は冷泉院。語り手の説明的叙述。
|
| 2.4.2 |
|
「宮中から遠く離れて住んでいる仙洞御所にも
忘れもせず秋の月は照っています
|
雲の上をかけはなれたる住家にも
物忘れせぬ秋の夜の月
|
【雲の上をかけ離れたるすみかにも--もの忘れせぬ秋の夜の月】- 冷泉院から源氏への贈歌。『完訳』は「中秋の名月はめぐり来るのに、源氏は訪れぬと訴えた歌」と注す。
|
| 2.4.3 |
|
同じことならあなたにも」
|
「おなじくは」(あたら夜の月と花とを同じくは心知られん人に見せばや)
|
【同じくは」--と】- 「あたら夜の月と花とを同じくはあはれ知れらむ人に見せばや」(後撰集春下、一〇三、源信明)。ここに見に来ていただきたい、の意。
|
| 2.4.4 |
|
とお申し上げなさったので、
|
とあった。
|
|
| 2.4.5 |
|
「どれほどの窮屈な身分ではないのだが、今はのんびりとしてお過ごしになっていらっしゃるところに、親しく参上することもめったにないことを、不本意なことと思し召されるあまりに、お便りをお寄越しあばされている、恐れ多いことだ」
|
「自分はたいそうにせずともよい身分でいて、閑散な御境遇でいらっしゃる院の御機嫌を伺いに上がることをあまりしない私の怠惰を、お忍びのあまりになってくだすったお手紙だからおそれおおい」
|
【何ばかり所狭き身のほどにも】- 以下「かたじけなし」まで、源氏の詞。「何ばかり所狭き身」は源氏自身をさす。
【今はのどやかにおはしますに】- 冷泉院をいう。
|
| 2.4.6 |
とて、にはかなるやうなれど、参りたまはむとす。
|
とおっしゃって、急な事のようだが、参上なさろうとする。
|
と六条院はお言いになって、にわかなことではあるが冷泉院へ参られることになった。
|
|
| 2.4.7 |
|
「月の光は昔と同じく照っていますが
わたしの方がすっかり変わってしまいました」
|
月影は同じ雲井に見えながら
わが宿からの秋ぞ変はれる
|
【月影は同じ雲居に見えながら--わが宿からの秋ぞ変はれる】- 源氏の返歌。「月影」は冷泉院を喩える。「試みに他の月をも見てしがなわが宿からのあはれなるかと」(詞花集雑上、二九九、花山院)。
|
| 2.4.8 |
|
特に変わったところはないようであるが、ただ昔と今とのご様子が思い続けられての歌なのであろう。
お使者にお酒を賜って、禄はまたとなく素晴らしい。
|
このお歌は文学的の価値はともかくも、冷泉院の御在位当時と今日とをお思い比べになって、寂しくお思いになる六条院の御実感と見えた。御使いは杯を賜わり、御纏頭をいただいた。
|
【異なることなかめれど、ただ昔今の御ありさまの思し続けられけるままなめり】- 『一葉抄』は「作者の詞」と指摘。『集成』は「なにほどのこともないご返歌だが、ご在位の昔に変る冷泉院のご様子に、何かと感慨を催されてのお作であろう。草子地」。『完訳』は「「めり」まで語り手の評。この歌には往時述懐があるとして、源氏の心の深さに注意させる言辞」と注す。
|
|
第五段 冷泉院の月の宴
|
| 2.5.1 |
人びとの御車、次第のままに引き直し、御前の人びと立ち混みて、静かなりつる御遊び紛れて、出でたまひぬ。院の御車に、親王たてまつり、大将、左衛門督、藤宰相など、おはしける限り皆参りたまふ。 |
人々のお車を、身分に従って並べ直し、御前駆の人々が大勢集まって来て、しみじみとした合奏もうやむやになって、お出ましになった。
院のお車に、親王をお乗せ申し、大将、左衛門督、藤宰相など、いらっしゃった方々全員が参上なさる。
|
参っていた人々の車を出て行く順序どおりに直したり、そちらこちらの前駆を勤める人たちが門内を右往左往するのとで、静かであった音楽の夜も乱れてしまった。六条院のお車に兵部卿の宮も御同乗になった。左大将、左衛門督、藤参議などという人たちも皆お供をして出た。
|
【院の御車に、親王たてまつり】- 六条院の御車。源氏と蛍兵部卿宮と同乗。
|
| 2.5.2 |
直衣にて、軽らかなる御よそひどもなれば、下襲ばかりたてまつり加へて、月ややさし上がり、更けぬる空おもしろきに、若き人びと、笛などわざとなく吹かせたまひなどして、忍びたる御参りのさまなり。 |
直衣姿で、皆お手軽な装束なので、下襲だけをお召し加えになって、月がやや高くなって、夜が更けた空が美しいので、若い方々に、笛などをさりげなくお吹かせになったりなどして、お忍びでの参上の様子である。
|
軽い直衣姿であったのが下襲を加えて院参をするのであった。月がやや高くなって美しくふけた夜に、若い殿上人などに、わざとらしくなく笛をお吹かせになって、微行の御外出をされるのである。
|
【わざとなく吹かせたまひなどして】- 『集成』は「興のままにお吹かせになったりして」。『完訳』は「さりげなく笛をお吹かせになったりして」と訳す。
|
| 2.5.3 |
|
改まった公式の儀式の折には、仰々しく厳めしい威儀の限りを尽くして、お互いにご対面なさり、また一方で、昔の臣下時代に戻った気持ちで、今夜は手軽な恰好で、急にこのように参上なさったので、大変にお驚きになり、お喜び申し上げあそばす。
|
威儀の必要な時には正しく備うべきを備えて御往復になるのであるが、今夜は昔の一源氏の大臣のお気持ちで突然にお訪ねになったのであるから、冷泉院は非常にお喜びになった。
|
【よだけき儀式】- 大島本は「よたけけき」とある。「け」は衍字である。『新大系』も諸本によって「よだけき」と校訂する。
【御覧ぜられたまひ】- 逆接で下文に続く。
【また、いにしへのただ人ざまに思し返りて】- 「いにしへ」は冷泉帝在位中をさす。源氏は准太上天皇の待遇を得たとはいうものの、皇族に復籍せず、あくまでも臣下のままである。
|
| 2.5.4 |
|
御成人あそばした御容貌、ますますそっくりである。
お盛りの最中であったお位を、御自分から御退位あそばして、静かにお過ごしになられる御様子に、心打たれることが少なくない。
|
御美貌の整いきった冷泉院と、六条院はいよいよ別のものとはお見えにならなかった。まだ盛りの御年齢で御自発的に御位をお退きになった君に六条院は悲しみを覚えておいでになった。
|
【ねびととのひたまへる御容貌】- 冷泉院三十二歳。
【御盛りの世を、御心と思し捨てて】- 冷泉院は二十八歳で退位。「若菜下」巻に語られている。
|
| 2.5.5 |
|
その夜の詩歌は、漢詩も和歌も共に、趣深く素晴らしいものばかりである。
例によって、一端を言葉足らずにお伝えするのも気が引けて。
明け方に漢詩などを披露して、早々に方々はご退出なさる。
|
この夜できた詩歌は皆非常におもしろかったが、片端だけを例の至らぬ筆者が写しておくのもやましい気がしてすべてを省くことにした。明け方にそれらの作が講ぜられて、人々は早朝に院から退出した。
|
【その夜の歌ども】- 『林逸抄』は「さうしの詞」と指摘。『集成』は「以下、草子地」。
【例の、言足らぬ片端は、まねぶもかたはらいたくてなむ】- 『集成』は「省筆をことわる草子地。上皇御前では漢詩を第一とするが、それは女性の口にすべきことではないからである」。『完訳』は「語り手の省筆の弁。言葉足らずの片端だけでは気がひける」と注す。
|
|
第三章 秋好中宮の物語 出家と母の罪を思う
|
|
第一段 秋好中宮、出家を思う
|
| 3.1.1 |
|
六条の院は、中宮の御方にお越しになって、お話など申し上げなさる。
|
六条院は中宮のお住居のほうへおいでになってしばらくお話しになった。
|
【中宮の御方に渡りたまひて】- 主語は源氏。冷泉院御所の秋好中宮方に。
|
| 3.1.2 |
|
「今はこのように静かなお住まいに、しばしば伺うことができ、特にどうということはないけれども、年をとるにつれて、忘れない昔話など、お聞きしたり申し上げたりしたく存じますが、中途半端な身の有様で、やはり気が引け、窮屈な思いが致しまして。
|
「ただ今はこうして御閑散なのですから、始終お伺いして、何ということもありませんが年のいくのとさかさまにますます濃くなる昔の思い出についてお話もし、承りもしたいのを果たすことがなかなか困難です。出家をしたのでもなし、俗人でもないような身の上で、行動の窮屈な点があります。
|
【今はかう】- 以下「思しとどめてものせさせたまへ」まで、源氏の詞。
【何にもつかぬ身のありさまにて】- 『集成』は「どっちつかずの身の有様で。ただの臣下でもなく、真の上皇でもない、准太上天皇の身分をいう。源氏の卑下の言葉」。『完訳』は「中途半端な身分と卑下。准太上天皇は上皇でも臣下でもない」と注す。
【所狭くもはべりてなむ】- 下に「参らぬ」という内容が省略。
|
| 3.1.3 |
|
わたしより若い方々に、何かにつけて先を越されて行く感じが致しますのも、まことに無常の世の心細さが、のんびり構えていられぬ気持ちがしますので、世を離れた生活をしようかと、だんだん気持ちが進んできましたが、後に残された方々が頼りないでしょうから、おちぶれさせなさらないように、と以前にもお願い申し上げました通り、その気持ちを変えずにお世話してやって下さい」
|
どちらにも私よりあとに志を起こして先へ進まれる求道者が多いのですから心細くて、思いきって田舎の寺へはいることにしようかともいよいよ近ごろは思われるのですが、あとの家族たちに関心をお持ちくださるようには以前からもお頼みしていることですが、その時になりましたら憐みをお垂れになってください」
|
【我より後の人びとに、方々につけて後れゆく心地しはべるも】- 『集成』は「柏木との死別、女三の宮、朧月夜、朝顔の前斎院の出家などが念頭にある」と注す。
【残りの人びとのものはかなからむ、漂はしたまふな、と】- 「人びとの」主格を表し、「ものはかなからむ」は原因理由を述べて、下文に「漂はしたまふな」という禁止の句を続ける構文。
【先々も聞こえつけし心違へず】- 源氏が秋好中宮に後事を託したことは、「薄雲」巻、「藤裏葉」巻に見える。
|
| 3.1.4 |
|
などと、方々の生活面のことについてお願い申し上げなさる。
|
などと六条院はまじめな御様子でお語りになった。
|
【聞こえさせたまふ】- 「聞こえさせ」+「たまふ」の形。中宮に対する源氏の厚い謙譲表現。
|
| 3.1.5 |
例の、いと若うおほどかなる御けはひにて、
|
例によって、大変に若くおっとりしたご様子で、
|
今も若々しくおおような調子で、中宮は、
|
|
| 3.1.6 |
|
「宮中の奥深くに住んでおりましたころよりも、お目に掛かれないことが多くなったように存じられます今の有様が、ほんとうに思いもしなかったことで、面白くなく思われまして、皆が出家して行くこの世を、厭わしく思われることもございますが、その心の中を申し上げてご意向を伺っておりませんので、何事もまずは頼りにしている癖がついていますため、気に致しております」
|
「宮中住まいをしておりましたころよりも、お目にかかります機会がだんだん少なくなってまいりますことも、予期せぬことでございましたから寂しゅうございましてね。皆様が御出家をあそばすこの世というものから私も離れてしまいたい望みを持っておりますことにつきましても、御相談が申し上げたくてそしてそれができないのでございますわ。昔からどんなことにもお力になっていただきつけて、独立心がなくなっているのでございましょうね。御意見を伺わないでは何もできません私は」
|
【九重の隔て】- 以下「いぶせくはべる」まで、秋好中宮の詞。
【皆人の背きゆく世を】- 「皆人の背き果てにし世の中にふるの社の身をいかにせむ」(斎宮女御集)。
【いぶせくはべる】- 連体形止め。余意・余情効果。
|
| 3.1.7 |
と聞こえたまふ。
|
と申し上げなさる。
|
と言っておいでになった。
|
|
| 3.1.8 |
|
「おっしゃる通り、宮中にいらっしゃった時には、決まりに従った折々のお里下がりも、ほんとうにお待ち申し上げておりましたが、今は何を理由として、御自由にお出であそばすことがございましょうか。
無常な世の習いとは言いながらも、特に世を厭う理由のない人が、きっぱりと出家することも難しいことで、容易に出家できそうな身分の人でさえ、自然とかかわり合う係累ができて世を背くことが出来ませんのに、どうして、そんな人真似をして負けずに出家なさろうとするのは、かえって変なお心掛けとご推量申し上げる者があっては困ります。
絶対にあってはならない御事でございます」
|
「そうですね。宮中にいらっしゃるころは年に幾度かの御実家帰りを楽しんでお待ち受けすることができたのですがね。ただ今では形式どおりのお暇をお取りになって御実家住まいをなさることのおできにならなくなりましたのもごもっともです。もうお上とお后と申すより一家の御夫婦のようなものですからね。ただ今のお話ですが、さして厭世的になる理由のない人が断然この世の中を捨てることは至難なことでしょう。われわれでさえやはりいよいよといえば絆になることが多いのですからね。人真似の御道心はかえって誤解を招くことになりますから、断じてそれはいけません」
|
【げに、公ざまにては】- 以下「いとあるまじき御ことになむ」まで、源氏の詞。冷泉院の在位中をさしていう。
【今は何事につけてかは、御心にまかせさせたまふ御移ろひもはべらむ】- 反語表現。お心のままに里下がりもできない、の意。
【さして厭はしきことなき人】- 『完訳』は「中宮を、特に世を厭う理由のない人として、その出家に反対」と注す。
【心やすかるべきほどにつけてだに、おのづから思ひかかづらふほだしのみはべるを】- 家族に対する思いのため出家のし難さをいう。
【などか】- 『集成』は読点で「どうしてそんな人真似をして負けじと競われるようなご出家のお志では」と訳し「御道心」にかけて読む。『完訳』は句点で「なぜ出家などお考えなのか」と訳す。
【人もこそはべれ】- 「もこそ」--已然形。懸念の気持ちを表す。
【御ことになむ】- 係助詞「なむ」の下に「はべる」などの語句が省略。
|
| 3.1.9 |
|
と申し上げなさるので、「深くは汲み取っ下さっていないようだ」と、恨めしくお思い申し上げなさる。
|
と院がおとめになるのを、宮は深く自分の心が汲んでもらえないからであろうと恨めしく思召した。
|
【深うも汲みはかりたまはぬなめりかし】- 秋好中宮の心中。
|
|
第二段 母御息所の罪を思う
|
| 3.2.1 |
|
母御息所が、ご自身お苦しみになっていらっしゃろう様子、どのような業火の中で迷っていらっしゃるのだろう様子、亡くなった後までも、人から疎まれ申される物の怪となって名乗り出たことは、あちらの院では大変に隠していらっしゃったが、自然と人の口は煩しいもので、伝え聞いた後は、とても悲しく辛くて、何もかもが厭わしくお思いになって、たとい憑坐にのり移った言葉にせよ、そのおっしゃった内容を詳しく聞きたいのだが、まともには申し上げかねなさって、ただ、
|
母君の御息所の霊が宙宇にさまよって、どんな苦しみを経験しておいでになることかとは中宮の夢寐にもお忘れになれないことで、今も人に故人を憎悪させるばかりである名のりを物怪が出てするということも六条院はあくまでも秘密にしておいでになったが、自然に人が噂をしてお耳にはいってからは、非常に母君を悲しく思召して、人生そのものまでがいとわしくおなりになって、仮にもせよ御息所の物怪が言ったという言葉を六条院からお聞きになりたいのであるが、正面から言うことはおできにならないで、
|
【御息所の】- 『集成』は「以下、中宮の気持を直接書く体であるが、「かの院には」あたり以下は、自然に地の文ふうの書き方になる」と注す。
【御身の苦しうなりたまふらむありさま】- 推量の助動詞「らむ」視界外推量。地獄に堕ちて苦しんでいる母六条御息所を推量しているニュアンス。
【いかなる煙の中に】- 『完訳』は「以下、「出で来けること」まで、中宮の心中に即した叙述」と注す。
【亡き影にても、人に疎まれたてまつりたまふ御名のりなどの】- 死霊となって、紫の上を仮死状態に陥れたり(「若菜下」巻)、女三の宮を出家させたりした(「柏木」巻)という話をさす。
【かの院には】- 六条院をさす。冷泉院を基準にした言い方。
【仮にても、かののたまひけむありさま】- 『集成』は「憑坐にのり移った物の怪の言葉にせよ」。『完訳』は「憑坐のかりそめの言いぐさでもよい」と訳す。
|
| 3.2.2 |
|
「亡くなった母上のあの世でのご様子が、罪障の軽くない様子と、かすかに聞くことがございましたので、そのような証拠がはっきりしているのでなくとも、推し量らねばならないことでしたのに、先立たれた時の悲しみばかりを忘れずにおりまして、あの世での苦しみを想像しなかった至らなさを、何とかして、ちゃんと教えてくれる人の勧めを聞きまして、せめてわたしでも、その業火の炎を薄らげて上げたいと、だんだんと年をとるにつれて、考えられるようになったことでございます」
|
「お母様の霊魂が罪の深いふうに苦しんでおいでになりますことを私はほかから話に聞きまして、それは確かでなくとも想像いたされることなのでございましたが、ただお死に別れしましたことだけを悲しんでおりまして、後世のことまでも幼稚な心の私は考えませんでしたのが悪いことでございました。気がついてみますと、宗教のほうの人にくわしい説明もしていただきたくなりましたし、私の力で及ぶだけの罪の炎をお消ししてお救いもしたいという望みも起こってまいったのでございます」
|
【亡き人の御ありさまの、罪】- 以下「思ひ知らるることもありける」まで、秋好中宮の詞。
【推し量り伝へつべき】- 大島本は「つたへつへき」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「つべき」と「つたへ」を削除する。『新大系』は底本のままとする。
【もののあなた思うたまへやらざりけるがものはかなさを】- 『集成』は読点で「後世の苦しみにまで思いをめぐらしませんでしたとはほんとにいたらぬことでしたので」。『完訳』は句点で「後生のお苦しみまでは考えてあげようともいたしませんでした、それがなんとも至らぬことでございました」と訳す。
【やうやう積もるになむ、思ひ知らるることもありける】- 『集成』は「出家の志が、長年の間に自然に固まったものだという」と注す。
|
| 3.2.3 |
など、かすめつつぞのたまふ。
|
などと、それとなしにおっしゃる。
|
などとかすめたふうにしてお語りになるのであった。
|
|
| 3.2.4 |
|
「なるほど、そのようにお考えになるのももっともなことだ」と、お気の毒に拝し上げなさって、
|
そういう御決心のできるのもごもっともであると哀れに院はお思いになって、
|
【げに、さも思しぬべきこと】- 源氏の心中。中宮の言葉に納得する気持ち。
|
| 3.2.5 |
|
「その業火の炎は、誰も逃れることはできないものだと分かっていながら、朝露のようにはかなく生きている間は、執着を去ることはできないものなのです。
目蓮が仏に近い聖僧の身で、すぐに救ったという故事にも、真似はお出来になれないでしょうが、玉の簪をお捨てになって出家なさったとしても、この世に悔いを残すようなことになるでしょう。
|
「炎ののがれたいのを知りながら、愛欲の念をだれも捨てることができないものなのです。目蓮が仏に近いほどの高僧になっていたために、すぐに母を地獄から救い出すこともできたのでしょうが、その真似はおできにならないで、しかも御自身のはなやかな人間としての生活をしいて断ち切っておしまいになることも、知らず知らず煩悩を作る結果になるではありませんか。
|
【その炎なむ】- 以下「心幼きことなれ」まで、源氏の詞。
【朝の露】- 大島本は「あしたの露」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「朝露」と校訂する。『新大系』は底本のままとする。
【目蓮が仏に近き聖の身にて、たちまちに救ひけむ例にも】- 「仏説盂蘭盆経」に見える目蓮が餓鬼道に堕ちた母親を救ったという話。
【え継がせたまはざらむものから】- 主語は中宮。目蓮の真似はできない意。
【玉の簪捨てさせたまはむも】- 『集成』「「玉の簪」は、玉で飾った中国風の髪飾り。中宮に対してふさわしい言葉遣い」。『完訳』は「出家して后の位を捨てても母を救えず現世に悔恨が残るとする」と注す。
|
| 3.2.6 |
|
だんだんそのようなお気持ちを強くなさって、あの母君のお苦しみが救われるような供養をなさいませ。
そのように存じますことお持ちしながら、何か落ち着かないようで、静かな出家の本意もないような有様で毎日を過ごしておりまして、自分自身の勤行に加えて、供養もそのうちゆっくりと存じておりますのも、おしゃるとおり、浅はかなことでした」
|
急がずにその道を御研究になることになさいまして、そのほかの方法で故人の妄執を晴らさせておあげになることをなさるべきです。私自身もそれを十分にして差し上げたい心を持っておりながら、ほかのことが多いものですから、そのうち私が本意を達する日が来れば、静かに私自身の手で冥福をお祈りしようと予定しているのですが、これも中途半端な心でしょうね」
|
【かの御煙晴るべきこと】- 大島本は「はるへき」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「はるくべき」と「く」を補訂する。『新大系』は底本のままとする。
【しか思ひたまふる】- 主語は源氏、自分自身。
【げにこそ、心幼きことなれ】- 『集成』は「「心をさなし」は、無常の世に、いつまでも命があるかのように油断していることへの自嘲」。『完訳』は「中宮の言う「物のあなた--ものはかなさを」に納得し、出家に踏みきれぬ自分を苦々しく顧みる」と注す。
|
| 3.2.7 |
|
などと、世の中の事が何もかも無常であり、出家したいことをお互いに話し合いなさるが、やはり、出家することは難しいお二方の身の上である。
|
などとお言いになって、人生のはかなさ、いとわしさをお語り合いになっているのであるが、まだどちらも出家するには御縁が遠いような盛りのお姿と見えた。
|
【なほ、やつしにくき御身のありさまどもなり】- 『細流抄』は「草子地也」と指摘。『完訳』は「語り手の評」と注す。
|
|
第三段 秋好中宮の仏道生活
|
| 3.3.1 |
昨夜はうち忍びてかやすかりし御歩き、今朝は表はれたまひて、上達部ども、参りたまへる限りは皆御送り仕うまつりたまふ。 |
昨夜はこっそりとお気軽なお出ましであったが、今朝は世間に知れわたりなさって、上達部なども、参上していた方々は皆お帰りのお供を申し上げなさる。
|
昨夜は微行の御参院であったが、今朝はもう表だって準太上天皇の儀式をお用いになるほかはなくて、院に参っていた高官たちは皆供奉をして六条院をお送り申すのであった。
|
【上達部ども】- 大島本は「上達部とん」とある。「ん」は「も」に同じ。『集成』『完本』は諸本に従って「上達部なども」と「な」を補訂する。『新大系』は底本のままとする。
|
| 3.3.2 |
|
春宮の女御のご様子、他に並ぶ方がなく、大切にお世話申し上げなさっているだけのことは十分あり、大将がまた大変に格別に優れているご様子をも、どちらも安心だとお思いになるが、やはり、この冷泉院をお思い申し上げるお気持ちは、特に深くいとしくお思いなさる。
院もいつも気に掛けていらっしゃったが、ご対面がめったになく気掛かりにお思いだったため、気がせかれなさって、このように気楽なご境遇にとお考えになったのであった。
|
院は東宮の御母君の女御が御教育のかいの見える幸福な女性になっていることも、だれよりもすぐれた左大将の存在もうれしく思っておいでになるのであるが、その二人にお持ちになる愛は冷泉院をお思いになる愛の片端にも価しないのである。冷泉院も常に恋しく思召しながらたやすく御会合のおできにならないことを物足らぬことに思召してただ今の御境遇を早くお選びにもなったのである。
|
【春宮の女御】- 明石姫君をさす。
【御ありさま】- 大島本は「御有様」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「御ありさまの」と「な」を補訂する。『新大系』は底本のままとする。
【いづれとなくめやすしと思すに】- 源氏の心中。「に」接続助詞、逆接の意。『集成』は「どちらも結構なことと満足にお思いになるのだが」。『完訳』は「どちらがどうと優り劣りなくご満足であるが」と訳す。
【院も】- 冷泉院。
【御対面のまれに】- 冷泉院の在位中をさす。
【かく心安きさまにと思しなりけるになむ】- 『集成』は「草子地」と注す。係助詞「なむ」の下に「ある」などの語句が省略された形。
|
| 3.3.3 |
|
中宮は、かえって里下がりなさることが大変に難しくなって、臣下の夫婦のようにいつもご一緒にいられて、当世風に、かえって御在位中よりも華やかに、管弦の御遊などもなさる。
どのようなことにもご満足のゆくご様子であるが、ただあの母御息所の御事をお考えなさっては、勤行のお心が深まって行ったのを、院がお許し申されるはずのないことなので、追善供養をひたすら熱心にお営みになって、ますます道心深く、この世の無常をお悟りになったご様子におなりになって行かれる。
|
中宮は御実家へお帰りになることが以前よりもむずかしくおなりになって、普通の家の夫婦のようにいつもごいっしょにお暮らしになり、お催し事などは昔よりはなやかなふうにあそばされて、どの点から申しても御幸福なのであるが、母君の御息所のことのために専心信仰の道へ進みたいと願いもあそばされるのであったが、だれも御同意にならぬことであったから、せめて功徳を作ることで亡き霊を弔いたいというお考えになって、以前にもまして善根をつもうと精進あそばされた。六条院も中宮のお志をお助けになって、法華経の八講を近日行なわせられるそうである。
|
【ただ人の仲のやうに並びおはしますに】- 『集成』は「帝は在位中は後宮の后妃にあまねく心を配らねばならないが、譲位後は、お気に召した方と思いのままに暮すことができる」と注す。
【ただかの御息所の御事を】- 中宮の母御息所をさす。
【人の許しきこえたまふまじきことなれば】- 「人」について、『集成』『新大系』は「源氏」、『完訳』は「冷泉院」とする。両説ある。
【世の中を思し取れるさまになりまさりたまふ】- 『集成』は「人の世の無常をお悟りになったご日常になってゆかれる」。『完訳』は「世の中の無常をお悟りになるお気持もいよいよ深くおなりになる」と訳す。
|
| 著作権 |
| 底本 |
大島本 |
| 校訂 |
Last updated 6/10/2010(ver.2-2)
渋谷栄一校訂(C)
オリジナル
修正版
比較 |
| ローマ字版 |
Last updated 7/20/2010 (ver.2-2)
Written in Japanese roman letters
by Eiichi Shibuya (C) (ver.1-3-2)
オリジナル
修正版
比較 |
ルビ抽出
(ローマ字版から)
|
Powered by 再編集プログラム v4.05
ひらがな版
ルビ抽出 |
挿絵
(ローマ字版から)
|
'Eiri Genji Monogatari'
(1650 1st edition) |
|
Last updated 1/31/2002
渋谷栄一訳(C)(ver.1-2-2)
オリジナル
修正版
比較 |
|
|
Last updated 7/20/2010(ver.2-2)
渋谷栄一注釈(C)
オリジナル
修正版
比較 |
|