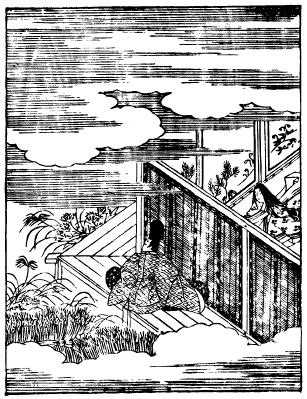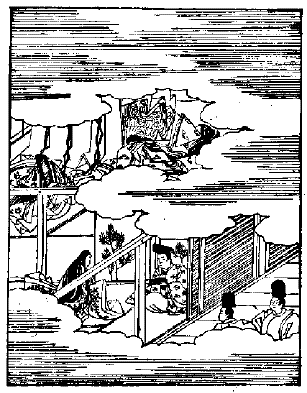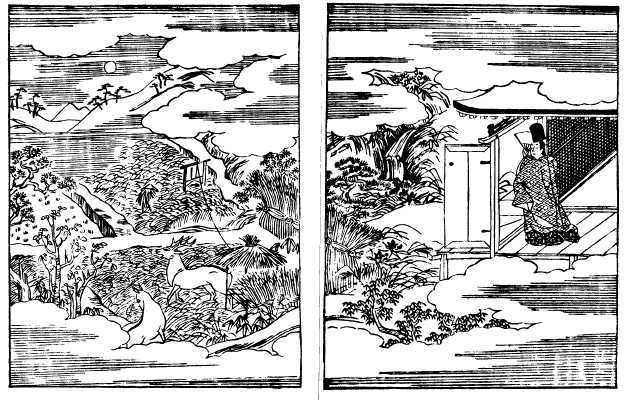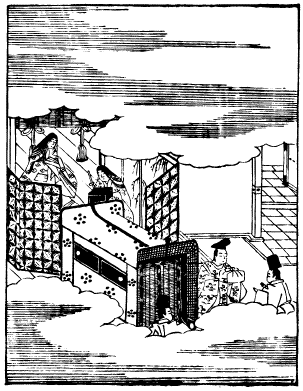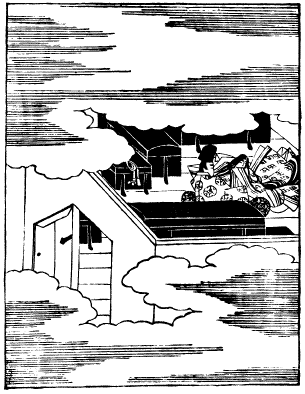第三十九帖 夕霧
光る源氏の准太上天皇時代五十歳秋から冬までの物語
|
# |
本文 |
渋谷栄一訳 |
与謝野晶子訳 |
注釈 |
|
第一章 夕霧の物語 小野山荘訪問
|
|
第一段 一条御息所と落葉宮、小野山荘に移る
|
| 1.1.1 |
|
堅物との評判を取って、こざかしそうにしていらっしゃる大将、この一条宮のご様子を、やはり理想的だと心に止めて、世間の人目には、昔の友情を忘れていない心遣いを見せながら、とても懇切にお見舞い申し上げなさる。
内心では、このままではやめられそうになく、月日を経るに従って思いが募って行かれるのであった。
|
一人の夫人の忠実な良人という評判があって、品行方正を標榜していた源左大将であったが、今は女二の宮に心を惹かれる人になって、世間体は故人への友情を忘れないふうに作りながら、引き続いて一条第をお訪ねすることをしていた。しかもこの状態から一歩を進めないではおかない覚悟が月日とともに堅くなっていった。
|
【まめ人の名をとりて、さかしがりたまふ大将】- 『集成』は「やや揶揄的な筆致。真木柱の巻に、髭黒が「名に立てるまめ人」とされており、同じ巻に、夕霧も「この世に目馴れぬまめ人」とされていた」。『完訳』は「夕霧は「まめ人」と称されてきたが、ここでは自らそれを意識して落葉の宮接近を合理化する。「さかしが」るのも、そのため。実直な男が盲目的な恋に陥る点で、鬚黒大将とも類似。『宇津保物語』の源実忠や藤原仲頼も、妻子を捨てて貴宮への恋に溺れる」と注す。
【この一条の宮の御ありさまを】- 邸宅の雰囲気をさす表現。
【なほ】- 副詞「なほ」は「思して」を修飾。『完訳』は「まめ人と言われながらやはり」と訳す。
|
| 1.1.2 |
御息所も、「あはれにありがたき御心ばへにもあるかな」と、今はいよいよもの寂しき御つれづれを、絶えず訪づれたまふに、慰めたまふことども多かり。 |
御息所も、「大変にもったいないご親切であることよ」と、今ではますます寂しく所在ないお暮らしを、絶えず訪れなさるので、お慰めになることがいろいろと多かった。
|
一条の御息所も珍しい至誠の人であると、近ごろになってますます来訪者が少なく、寂れてゆく邸へしばしば足を運ぶ大将によって慰められていることが多いのであった。
|
【御息所も】- 落葉宮の母一条御息所。
|
| 1.1.3 |
初めより懸想びても聞こえたまはざりしに、
|
初めから色めいたことを申し上げたりなさらなかったのだが、
|
初めから求婚者として現われなかった自分が、
|
|
| 1.1.4 |
「ひき返し懸想ばみなまめかむもまばゆし。ただ深き心ざしを見えたてまつりて、うちとけたまふ折もあらじやは」 |
「打って変わって色めかしく艶めいた振る舞いをするのも気恥ずかしい。
ただ深い愛情をお見せ申せば、心を許してくれる時がなくはないだろう」
|
急に変わった態度に出るのはきまりが悪い、ただ真心で尽くしているところをお認めになったなら、自然に宮のお心は自分へ向いてくるに違いないから時を待とう
|
【ひき返し】- 以下「あらじやは」まで、夕霧の心中。『集成』は「ここから夕霧の心」と注して、括弧にはくくらない。
|
| 1.1.5 |
|
と思いながら、何かの用事にかこつけても、宮のご様子や態度をお伺いなさる。
ご自身がお応え申し上げなさることはまったくない。
|
と、こう大将は思って一日も早く宮と御接近する機会を得たいとうかがい歩いているのである。宮が御自身でお話をあそばすようなことはまだ絶対にない。
|
【宮の御けはひありさまを見たまふ】- 落葉の宮の雰囲気や様子を。「見たまふ」は、注意を払う、関心をもつ、意。几帳が間にあるので直接見ているのではない。
【みづからなど聞こえたまふことはさらになし】- 落葉宮御自身が夕霧に直接返事をすること。
|
| 1.1.6 |
「いかならむついでに、思ふことをもまほに聞こえ知らせて、人の御けはひを見む」 |
「どのような機会に、思っていることをまっすぐに申し上げて、相手のご様子を見ようか」
|
いつか好機会をとらえて自分の持つ熱情を直接にお告げすることもし、御様子もよく見たい
|
【いかならむついでに】- 以下「けはひを見む」まで、夕霧の心中。
|
| 1.1.7 |
|
と、お考えになっていたところ、御息所が、物の怪にひどくお患いになって、小野という辺りに、山里を持っていらっしゃった所にお移りになった。
早くから御祈祷師として、物の怪などを追い払っていた律師が、山籠もりして里には出まいと誓願を立てていたのを、麓近くなので、下山して頂くためなのであった。
|
と大将は心に願っていた。御息所は物怪で重く煩って小野という叡山の麓へ近い村にある別荘へ病床を移すようになった。以前から祈祷を頼みつけていて、物怪を追い払うのに得意な律師が叡山の寺にこもっていて、京へは当分出ない誓いを御仏にしたというのを招くのに都合がよかったからである。
|
【御息所、もののけにいたう患ひたまひて】- 一条御息所は二年前から病気がちであった。「柏木」巻に語られている。
【小野といふわたりに、山里持たまへるに】- 二つの「に」格助詞、いずれも場所を表す。京都の北の郊外。修学院離宮のあたり。
【御祈りの師に】- 大島本は「御いのりのしに」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「御祈りの師にて」と「て」を補訂する。『新大系』は底本のままとする。
【山籠もりして里に出でじ】- 律師の考え、間接話法、その要旨。
【誓ひたるを】- 『集成』は「請願を立てているのを」。『完訳』は「誓いを立てているそのお方に」と訳す。「を」格助詞、目的格に解す。また接続助詞「を」順接、原因理由を表す、とも解せる。
【麓近くて、請じ下ろしたまふゆゑなりけり】- 『集成』は「近くに来て、下山して頂きなさるためなのだった」。『完訳』は「麓近くまで下りてもらうようお願いになるためなのだった」と訳す。集成は「麓近くて」を御息所が「麓近くに来て」の意に解している。
|
| 1.1.8 |
|
お車をはじめとして、御前駆など、大将殿から差し向けなさったのであるが、かえって故人の親しい弟君たちは、仕事が忙しく自分の事にかまけて、お思い出し申し上げることができなかった。
|
その日の幾つかの車とか前駆の人たちとかは皆大将からよこされた。かえって柏木の弟たちなどは自身のせわしさに紛れてか、そうした気はつかないふうであった。
|
【なかなか昔の近きゆかりの君たちは】- 大島本は「中/\むかしの」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「なかなかまことの昔の」と「まことの」を補訂する。『新大系』は底本のままとする。柏木の弟たちをいう。もって回った言い方。
|
| 1.1.9 |
|
弁の君、彼は彼で、気がないわけでもなくて、素振りを匂わせたのだが、思ってもみない程のおあしらいだったので、無理に参上してお世話なさることもできなくなっていた。
|
左大将は兄の未亡人の宮を得たい心でそれとなく申し込んだ時に、もってのほかであるというような強い拒絶的な態度をとられて以来、羞恥心から出入りもしなくなっているのである。
|
【弁の君、はた、思ふ心なきにしもあらで、けしきばみけるに、ことの外なる御もてなし】- 『完訳』は「一条の宮に出入りするうちに宮に求婚し、皇女降嫁に反対の母御息所に拒まれたか」と注す。 【けしきばみけるに】-接続助詞「に」逆接の意。
|
| 1.1.10 |
|
この君は、とても賢く、何とはない様子で自然と馴れ親しみなさったようである。
修法などをおさせになると聞いて、僧の布施、浄衣などのような、こまごまとした物まで差し上げなさる。
病気でいらっしゃる方は、お書きになるとができない。
|
それに比べて大将は非常に上手な方法をとったものといわねばならない。修法をさせていると聞いて大将は僧たちへ出す布施や浄衣の類までも細かに気をつけて山荘へ贈ったのであった。その際病人の御息所は返事を書くべくもない容体であったし、
|
【さりげなくて聞こえ馴れたまひにためり】- 推量の助動詞「めり」主観的推量は、語り手の推量。
【悩みたまふ人は】- 御息所をいう。
【え聞こえたまはず】- 夕霧へのお礼の返事を書くことができない。
|
| 1.1.11 |
|
「通り一遍の代筆は、けしからぬとお思いでしょう、重々しい身分のお方です」
|
女房から挨拶書きなどを出しておいては、先方の好意が徹底しなかったもののようにお思いになるであろうし、宮様がお高ぶりになりすぎるようにもお思われになるであろうから
|
【なべての宣旨書きは】- 以下「御さまなり」まで、女房の詞。その要旨、間接的話内容であろう。
|
| 1.1.12 |
|
と、女房たちが申し上げるので、宮がお返事をさし上げなさる。
|
と女房らがお願いしたために、宮が引き受けて礼状をお書きになった。
|
【宮ぞ御返り聞こえたまふ】- 落葉の宮が返事を書く。係助詞「ぞ」--「たまふ」連体形の係結び、強調のニュアンス。
|
| 1.1.13 |
|
とても美しく、ただ一くだりほど、おっとりとした筆づかいに、言葉も優しい感じを書き添えなさっているので、ますます見たく目がとまって、頻繁に手紙を差し上げなさる。
|
美しい字のおおような短いお手紙ではあるが、なつかしい味のあるものであったから、いよいよ大将の心は傾いて、それ以後たびたびお手紙を差し上げるようになった。
|
【ただ一行りなど】- 『完訳』は「和歌を一行書きにしたものか」と注す。
【言葉もなつかしきところ書き添へたまへるを】- 『完訳』は「和歌に添えた言葉か」と注す。
【いよいよ見まほしう目とまりて、しげう聞こえ通ひたまふ】- 主語は夕霧。ますます落葉の宮に引きつけられていく。
|
| 1.1.14 |
|
「やはり、いつかは事の起こるに違いないご関係のようだ」
|
結局自分の疑いは疑いでなくなってゆきそうである
|
【なほ、つひにあるやうあるべきやう御仲らひなめり」--と】- 大島本は「あるへきやう」とあり、その右側に「此やうノ二字定家本ニ朱ニテ書入難心詞也<朱>」と紙片を貼付して注記する。『集成』『完本』は諸本に従って「あるべき」と校訂する。『新大系』は底本のままとする。「定家本」には「やう」が有ると注記しているのが注目される。雲居雁の心中。『集成』は「やはり結局は何か事が起るに違いないお二人の仲なのだろう」。『完訳』は「こんな様子では、お二人がやはりしまいには特別の仲になってしまいかねないと」と訳す。大島本の「あるやうあるべきやう」という「やう」の重複はいかにもくどい拙文の感じだが、定家本にはそうあるのである。
|
| 1.1.15 |
|
と、北の方は様子を察していられたので、めんどうに思って、訪問したいとはお思いになるが、すぐにはお出かけになることができない。
|
と、雲井の雁夫人が早くも観察していることにはばかられて、大将は小野の山荘を訪ねたく思いながらも実行をしかねていた。
|
【北の方けしきとり】- 夕霧の北の方、すなわち雲居雁。
|
|
第二段 八月二十日頃、夕霧、小野山荘を訪問
|
| 1.2.1 |
|
八月二十日のころなので、野辺の様子も美しい時期だし、山里の様子もとても気になるので、
|
八月の二十日ごろで、野のながめも面白いころなのであるから、山荘住まいをしておいでになる恋人を大将はお訪ねしたい心がしきりに動いて、
|
【八月中の十日ばかりなれば、野辺のけしきもをかしきころなるに】- 八月二十日ころ、中秋をや過ぎたころ。
|
| 1.2.2 |
|
「何某律師が珍しく下山していると言うので、是非に相談したいことがある。
御息所が病気でいらっしゃると言うのもお見舞いがてら、お伺いしよう」
|
「珍しく山から下っていられる某律師にぜひ逢って相談をしなければならぬことがあったし、御病気の御息所の別荘へお見舞いもしがてらに小野へ行こうと思う」
|
【なにがし律師の】- 以下「とぶらひがてら参でむ」まで、夕霧の詞。「某律師」は雲居雁の前では実名で言ったのを、語り手が読者には「某」とぼかして表現したもの。『完訳』は「語り手が固有名詞をぼかした」と注す。
【下りたなるに】- 「た」は完了の助動詞「たる」の「る」が撥音便化し無表記。「なる」伝聞推定の助動詞。接続助詞「に」順接の意。
【患ひたまふなるも】- 「なる」伝聞推定の助動詞。
|
| 1.2.3 |
|
と、さりげない用件のように申し上げてお出かけになる。
御前駆、大げさにせず、親しい者だけ五、六人ほどが、狩衣姿で従う。
特別深い山道ではないが、松が崎の小山の色なども、それほどの岩山ではないが、秋らしい様子になって、都で又となく善美を尽くした住居より、やはり、情趣も風情も立ち勝って見えることであるよ。
|
と何げなく言って大将は邸を出た。前駆もたいそうにはせず親しい者五、六人を狩衣姿にさせて大将は伴ったのである。たいして山深くはいる所ではないが、松が崎の峰の色なども奥山ではないが、紅葉をしていて、技巧を尽くした都の貴族の庭園などよりも美しい秋を見せていた。
|
【おほかたにぞ聞こえて】- 大島本は「きこえて」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「聞こえごちて」と「ごち」を補訂する。『新大系』は底本のままとする。『集成』は「さりげない用件のように申し上げて」。『完訳』は「一通りの訪問のようにお申し出になって」と訳す。
【御前、ことことしからで、親しき限り五、六人ばかり】- 大将の公式の前駆は定員十二名。それを親しい者五、六名に限って追従させている。
【松が崎の小山の色など】- 『集成』は「尾山」と宛て、「歌枕。修学院の対岸、高野川の右岸に張り出した形の山。所々に岩盤が露出し、松の木が多い。「尾山」の「尾」は、峯の意」と注す。
【都に二なくと尽くしたる家居には】- 『完訳』は「六条院の秋の町と対比して、小野の秋の美しさを称揚」と注す。連語「には」比較を表す。
【まさりてぞ見ゆるや】- 「や」詠嘆の終助詞。語り手の言辞。臨場感ある措辞。視点が夕霧と一体化して語られている。
|
| 1.2.4 |
はかなき小柴垣もゆゑあるさまにしなして、かりそめなれどあてはかに住まひなしたまへり。
寝殿とおぼしき東の放出に、修法の檀塗りて、北の廂におはすれば、西面に宮はおはします。
|
ちょっとした小柴垣も風流な様に作ってあって、仮のお住まいだが品よくお暮らしになっていらっしゃった。
寝殿と思われる東の放出に、修法の壇を塗り上げて、北の廂の間にいらっしゃるので、西表の間に宮はいらっしゃる。
|
そこは簡単な小柴垣なども雅致のあるふうにめぐらせて、仮居ではあるが品よく住みなされた山荘であった。寝殿ともいうべき中央の建物の東の座敷のほうに祈祷の壇はできていて、北側の座敷が御息所の病室となっているために、西向きの座敷に宮はおいでになった。
|
|
| 1.2.5 |
|
御物の怪が厄介だからと言って、お止め申し上げなさったが、どうしてお側を離れ申そうと、慕ってお移りになったのだが、物の怪が他の人に乗り移るのを恐れて、わずかの隔てを置く程度にして、そちらにはお入れ申し上げなさらない。
|
物怪を恐れて御息所は宮を京の邸へおとどめしておこうとしたのであるが、どうしてもいっしょにいたいとついておいでになった宮を、物怪のほかへ散るのを恐れて少しの隔てではあるが病室へはお近づけ申し上げないのである。
|
【とどめたてまつりたまひけれど】- 落葉の宮を京の邸に留めたが、の意。
【いかでか離れたてまつらむ】- 落葉の宮の心中。間接的叙述。「いかでか」--「む」反語表現。
【あなたには渡したてまつりたまはず】- 落葉の宮を御息所のいる北廂の間にはお入れしない、の意。
|
| 1.2.6 |
|
客人のお座りになる所がないので、宮の御方の簾の前にお入れ申して、上臈のような女房たちが、ご挨拶をお伝え申し上げる。
|
客を通す座敷がないために、宮のおいでになる室とは御簾で隔てになった西の縁側についた座敷へ大将を入れて、上級の女房らしい人たちが御息所との話の取り次ぎに出て来た。
|
【宮の御方】- 落葉の宮。
【御簾の前に】- 大島本は「みす」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「簾(す)」と「み」を削除する。『新大系』は底本のままとする。
|
| 1.2.7 |
|
「まことにもったいなく、こんなにまで遠路はるばるお見舞いにお越し下さいまして。
もしこのままはかなくなってしまいましたならば、このお礼をさえ申し上げることができないのではないかと、存じておりましたが、もう暫く生きていたいという気持ちになりました」
|
「まことにもったいなく存じます。御親切にたびたびお尋ねくださいました上に、御自身でまたお見舞いくださいますあなた様に対して、もう亡くなってしまいますれば自分でお礼を申し上げることができないと考えますことで、もう少し生きようといたします努力をしますことになりました」
|
【いとかたじけなく】- 以下「心つきはべりぬる」まで、御息所の詞。
【このかしこまりをだに】- 副助詞「だに」最小限の意。
【聞こえさせでや】- 「聞こえさす」謙譲表現。接続助詞「で」否定の意。「や」間投助詞、詠嘆の意。
|
| 1.2.8 |
と、聞こえ出だしたまへり。
|
と、奥から申し上げなさった。
|
これが御息所からの挨拶である。
|
|
| 1.2.9 |
|
「お移りあそばした時のお供を致そうと存じておりましたが、六条院から仰せつけられていた事が中途になっていまして。
このところも、何かと忙しい雑事がございまして、案じておりました気持ちよりも、ずっと誠意がない者のように御覧になられますのが、辛うございます」
|
「こちらへお移りになります日に、私もお送りをさせていただきたかったのですが、あやにく六条院の御用の残ったものがありましたものですから失礼をいたしました。その以後も何かと忙しいことがあったものですから、お案じいたしております心だけのことができておらないのを、不本意に心苦しく存じております」
|
【渡らせたまひし】- 以下「ことの苦しうはべる」まで、夕霧の詞。
【六条院に承りさしたることはべりしほどにてなむ】- 『完訳』は「口実である。雲居雁の嫉妬で訪問できなかったのが真相」と注す。 【ほどにてなむ】-係助詞「なむ」の下に、できなかった、という意の言葉が省略された形。
|
| 1.2.10 |
など、聞こえたまふ。
|
などと、申し上げなさる。
|
などと大将は取り次がせている。
|
|
|
第三段 夕霧、落葉宮に面談を申し入れる
|
| 1.3.1 |
|
宮は、奥の方にとてもひっそりとしていらっしゃるが、おおげさでない仮住まいのお設備で、端近な感じのご座所なので、宮のご様子も自然とはっきり伝わる。
とても物静かに身じろぎなさる時の衣ずれの音、あれがそうなのだろうと、聞いていらっしゃった。
|
奥のほうに静かにして宮はおいでになるのであるが、簡単な山荘のことであるから、奥といっても深いことはないのであって、若い内親王様がそこにおいでになる気配はよく大将にわかるのである。柔らかに身じろぎなどをあそばす衣擦れの音によって、宮のおすわりになったあたりが想像された。
|
【ことことしからぬ旅の御しつらひ】- 小野の山荘の様子。
【人の御けはひ】- 落葉の宮。
【さばかりななり】- 連語「ななり」断定の助動詞+推量の助動詞。『集成』は「あれが宮なのだろう」。『完訳』は「あのあたりらしい」と訳す。
|
| 1.3.2 |
|
心も上の空になって、あちらへのご挨拶を伝えている間、少し長く手間取っているうちに、例の少将の君などの、伺候している女房たちにお話などなさって、
|
魂はそこへ行ってしまったようなうつろな気になりながら、御息所の病室とここを通う取り次ぎの女房の往復の暇どる間を、これまでから話し相手にする少将とかそのほかの宮の女房とかを相手にして大将は語っているのであった。
|
【あなたの御消息通ふほど】- 格助詞「の」は、御息所への、の意。
【すこし遠う隔たる隙に】- 「少し遠う隔たる」は空間の理由を説明して「隙」を修飾、時間的な間合のあることをいう。
【例の少将の君など、さぶらふ人びとに】- 『完訳』は「落葉の宮づきの女房。小少将。御息所の姪で、その養女格。大和守の妹」と注す。
|
| 1.3.3 |
|
「このように参上して親しくお話を伺うことが、何年という程になったが、まったく他人行儀にお扱いなさる恨めしさよ。
このような御簾の前で、人伝てのご挨拶などを、ほのかにお伝え申し上げるとはね。
いまだ経験したことがないね。
どんなにか古くさい人間かと、宮様方は笑っていらっしゃるだろうと、きまりの悪い思いがする。
|
「宮様のほうへ伺うようになりましてから、もう何年と年で数えなければならないほどになりますが、まだきわめてよそよそしいお取り扱いを受けておりますことで、恨めしい気がしますよ。こうした御簾の前で、人づてのお言葉をほのかに承りうるだけではありませんか。私はまだこんな冷たい御待遇というものを知りませんよ。どんなに古風な気のきかない男に皆さんは私を思っておられるだろうと恥ずかしく思います。
|
【かう参り来馴れ】- 以下「たぐひあらじかし」まで、夕霧の詞。『完訳』は「宮に聞えよがしに言う」と注す。
【年ごろといふばかりに】- 柏木が亡くなって足掛け三年になる。その間、夕霧は落葉の宮に援助し続けてきた。
【恨めしさなむ】- 係助詞「なむ」の下に、辛く思われる、などの意が省略。
【いかに古めかしきさまに】- 『完訳』は「私を野暮な人間と。自分を貶めながら、好色とは無縁であるかのように言い、相手を安心させる」と注す。
【人びとほほ笑みたまふらむと】- 『集成』は「あなた方がおかしがっておいでだろうと」。『完訳』は「落葉の宮や御息所など」と注す。
【はしたなくなむ】- 係助詞「なむ」の下に「はべる」などの語句が省略、強調のニュアンス。
|
| 1.3.4 |
|
年齢も若く身分も低かったころに、多少とも色めいたことに経験が豊かであったら、こんな恥ずかしい思いはしなかったろうに。
まったく、このように生真面目で、愚かしく年を過ごして来た人は、他にいないだろう」
|
青年で気楽な位置におりましたころから、続いて恋愛を生活の一部にして来ていますれば、こんなに不器用な恋の悩みをしないでも済んだろうと思います。私のように長く心の病気をおさえている人はないでしょう」
|
【齢積もらず軽らかなりしほどに】- 『完訳』は「「軽らか」は身分について。ここでも自嘲的でありながら、若年からの律儀さを強調し、相手を安心させる」と注す。
【面馴れなましかば】- 「ましかば」--「まし」反実仮想の構文。
【おれて年経る人は、たぐひあらじかし】- 『集成』は「いつまでもうかうかと過す人間は、またといまいと思われます。もういい加減に、親しい扱いをしてほしい、と言う」と注す。
|
| 1.3.5 |
|
とおっしゃる。
なるほど、まことに軽々しくお扱いできないご様子でいらっしゃるので、やはりそうであったかと、
|
大将はこの言葉のとおりにもう軽々しい多情多感な青年ではない重々しい風采を備えているのであるから、その人の切り出して言ったことがこれであるのを、女房たちはこんなことになるかともかねてあやぶんでいたと、途方に暮れた気がするのであった。
|
【げに、いとあなづりにくげなるさましたまひつれば】- 大島本は「給つれは」とある。「つ」と「へ」は紛らわしい字体である。『集成』『完本』は諸本に従って「たまへれば」と校訂する。『新大系』は底本のままとする。「げに」は語り手の納得の意。女房の気持と一体化した表現。
【さればよ】- 女房の心中。『集成』は「やはり、ただではすまないことだと。宮の挨拶がなくては事がすむまいという気持」。『完訳』は「夕霧の宮への恋情に気づく」と注す。
|
| 1.3.6 |
|
「中途半端なお返事を申し上げるのは、気が引けます」
|
「私が拙い御挨拶などをしてはかえっていけませんから、あなたが」
|
【なかなかなる御いらへ聞こえ出でむは、恥づかしう】- 女房の詞。連体中止法。余意余情効果がある。
|
| 1.3.7 |
などつきしろひて、
|
などとつっ突き合って、
|
こんなことを皆ひそかに言い合っていて、
|
|
| 1.3.8 |
|
「このようなご不満に対し情趣を解さないように思われます」
|
「あんなにもお言いになります方に、あまり無関心らしくあそばさないほうがよろしゅうございましょう。何とかおっしゃってくださいませ」
|
【かかる御愁へ】- 以下「知らぬやうなり」まで、女房の詞。「御愁へ」は夕霧のそれ。「聞こしめし知らぬ」は人情や情趣を解さない意。主語は落葉の宮なので敬語表現が使用されている。
|
| 1.3.9 |
と、宮に聞こゆれば、
|
と、宮に申し上げると、
|
と宮へ申し上げると、
|
|
| 1.3.10 |
|
「ご自身で直接申し上げなさらないようなご無礼につき、代わって致さねばならないところですが、大変に恐いほどのご病気でいらっしゃったようなのを、看病致しておりましたうちに、ますます生きているのかどうなのか分からない気分になって、お返事申し上げることができません」
|
「病人が自身でお話を申し上げることのできませんような失礼な際に、私でも代わりをいたしましてお逢い申し上げたいのでございますが、病人が一時非常に悪うございましたために、私までも健康を害しまして、それでよんどころなく」
|
【みづから聞こえたまはざめるかたはらいたさに】- 「みづから」は母御息所ご自身が、の意。下に「たまふ」という敬語表現があるので。
【代はりはべるべきを】- 主語は落葉の宮。丁寧語表現。
【いとどあるかなきかの心地になりて】- 『完訳』は「恐ろしいほど物の怪に病むような御息所を看病するうちに、自分も人心地が失せた。口実である」と注す。
|
| 1.3.11 |
とあれば、
|
とおっしゃるので、
|
こうお取り次がせになった。
|
|
| 1.3.12 |
|
「これは、宮のお返事ですか」と居ずまいを正して、「お気の毒なご病気を、わが身に代えてもとご心配申し上げておりましたのも、他ならぬあなたのためです。
恐れ多いことですが、物事のご判断がお出来になるご様子などを、ご快復を御覧になられるまでは、平穏にお過ごしになられるのが、どなたにとっても心強いことでございましょうと、ご推察申し上げるのです。
ただ母上様へのご心配ばかりとお考えになって、積もる思いをご理解下さらないのは、不本意でございます」
|
「それは宮様のお言葉ですか」と大将は居ずまいを正した。「御息所の御容体を、私自身の病などと比較にもなりませんほどお案じいたしておりますのも何の理由からでございましょう。もったいない話ではございますが、御憂鬱な御気分が朗らかになられますまで、あの方様が御健康でおいでくださいますことは願わしいことだと存じ上げるからでございます。あの方様へお尽くしいたすだけのものとして、私のあなた様へ持ちます真心をお認めくださいませんことはお恨めしいことでございます」
|
【こは、宮の御消息か】- 夕霧の詞。または心中、いづれか不明。
【心苦しき御悩みを】- 以下「本意なき心地なむ」まで、夕霧の詞。「御悩み」は御息所の病気。『完訳』は「以下、宮に直接話しかける趣。宮の居場所の近さを知っている」と注す。
【嘆ききこえさせはべるも】- 「聞こえさす」最も丁重な謙譲表現。
【何のゆゑにか】- 『完訳』は「ほかならぬ、あなたのため」と訳す。
【ものを思し知る御ありさまなど】- 『集成』は「物の怪は、おうおうにして明晰な理解、判断を狂わせる症状を呈するので、「ものをおぼし知る御ありさまなど」と、日頃の御息所の聰明さを特に言う」。『完訳』は「何かと思いにひたっていらっしゃる宮の日々のお暮しなどが」「憂愁に沈む落葉の宮が晴れ晴れしくなるまで、御息所が生きていてほしい、の意。暗に、宮は自分と結ばれて幸福になる、と主張」と注す。
【推し量りきこえさするによりなむ】- 係助詞「なむ」の下に「侍る」などの語句が省略。
【ただあなたざまに思し譲りて】- 主語は落葉の宮。あなたは、わたしの訪問をただ母御息所へのご心配とばかりお思いになって、の意。
【本意なき心地なむ】- 係助詞「なむ」の下に「する」などの語句が省略。
|
| 1.3.13 |
と聞こえたまふ。
「げに」と、人びとも聞こゆ。
|
と申し上げなさる。
「おっしゃる通りだ」と、女房たちも申し上げる。
|
と大将は言う。「ごもっともでございます」と女房らが言う。
|
|
|
第四段 夕霧、山荘に一晩逗留を決意
|
| 1.4.1 |
|
日も入り方になるにつれて、空の様子もしんみりと霧が立ち籠めて、山の蔭は薄暗い感じがするところに、蜩がしきりに鳴いて、垣根に生えている撫子が、風になびいている色も美しく見える。
|
日は落ちて行く刻で、空も身にしむ色に霧が包んでいて、山の蔭はもう小暗い気のする庭にはしきりに蜩が鳴き、垣根の撫子が風に動く色も趣多く見えた。
|
【ひぐらしの鳴きしきりて】- 大島本は「ひくらしの」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「ひぐらし」と「の」を削除する。『新大系』は底本のままとする。「ひぐらしの鳴きつるなべに日は暮れぬと思ふは山の蔭にぞありける」(古今集秋上、二〇四、読人しらず)。
【垣ほに生ふる撫子の】- 「あな恋し今も見てしが山賤の垣ほに咲ける大和撫子」(古今集恋四、六九五、読人しらず)。「日入方になり行くに--山の蔭は--垣ほに生ふる撫子の」の情景は右の古今集歌二首にもとづく。
【うちなびける色も】- 『集成』は「くびをかしげた花の淡い紅色も」。『完訳』は「風に揺れなびいている色合いも」と訳す。
|
|
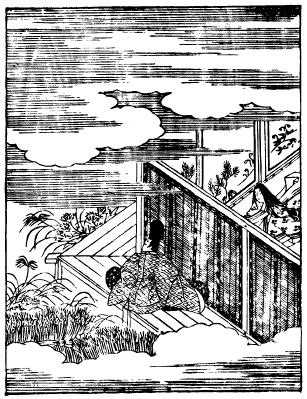 |
| 1.4.2 |
前の前栽の花どもは、心にまかせて乱れあひたるに、水の音いと涼しげにて、山おろし心すごく、松の響き木深く聞こえわたされなどして、不断の経読む、時変はりて、鐘うち鳴らすに、立つ声もゐ変はるも、一つにあひて、いと尊く聞こゆ。
|
前の前栽の花々が、思い思いに咲き乱れているところに、水の音がとても涼しそうに聞こえて、山下ろしの風がぞっとするように、松風の響きが奥にこもってそこらじゅう聞こえたりなどして、不断の経を読むのが、交替の時刻になって、鐘を打ち鳴らすと、立つ僧の声も変って座る僧の声も、一緒になって、まことに尊く聞こえる。
|
植え込みの灌木や草の花が乱れほうだいになった中を行く水の音がかすかに涼しい。一方では凄いほどに山おろしが松の梢を鳴らしていたりなどして、不断経の僧の交替の時間が来て鐘を打つと、終わって立つ僧の唱える声と、新しい手代わりの僧の声とがいっしょになって、一時に高く経声の起こるのも尊い感じのすることであった。
|
|
| 1.4.3 |
所から、よろづのこと心細う見なさるるも、あはれにもの思ひ続けらる。出でたまはむ心地もなし。律師も、加持する音して、陀羅尼いと尊く読むなり。 |
場所柄ゆえ、あらゆる事が心細く思われるのも、しみじみと感慨が湧き起こる。
お帰りなる気持ちも起こらない。
律師の加持する声がして、陀羅尼を大変に尊く読んでいる様子である。
|
所が所だけにすべてのことが人に心細さを思わせるのであったから、恋する大将の物思わしさはつのるばかりであった。帰る気などには少しもなれない。律師が加持をする音がして、陀羅尼経を錆びた声で読み出した。
|
【もの思ひ続けらる】- 「らる」自発の助動詞。
【読むなり】- 「なり」伝聞推定の助動詞。語り手の言辞。臨場感のある表現。
|
| 1.4.4 |
|
たいそうお苦しそうでいらっしゃるということで、女房たちもそちらの方に集まって、大体が、このような仮住まいに大勢はお供しなかったので、ますます人少なで、宮は物思いに耽っていらっしゃった。
ひっそりしていて、「思っていることも話し出すによい機会かな」と思って座っていらっしゃると、霧がすぐこの軒の所まで立ち籠めたので、
|
御息所の病苦が加わったふうであると言って、女房たちはおおかたそのほうへ行っていて、もとから療養の場所で全部をつれて来ておいでになるのでない女房が、宮のおそばに侍しているのは少なくて、宮は寂しく物思いをあそばされるふうであった。非常に静かなこんな時に自分の心もお告げすべきであると大将が思っていると、外では霧が軒にまで迫ってきた。
|
【いと苦しげにしたまふなりとて】- 主語は御息所。「なり」伝聞推定の助動詞。
【あまた参らざりけるに】- 接続助詞「に」順接、原因理由を表す。
【思ふこともうち出でつべき折かな】- 夕霧の心中。
|
| 1.4.5 |
|
「帰って行く方角も分からなくなって行くのは、どうしたらよいでしょうか」と言って、
|
「私の帰る道も見えなくなってゆきますようなこんな時に、どうすればいいのでしょう」と大将は言って、
|
【まかでむ方も見えずなり行くは、いかがすべき】- 夕霧の詞。『完訳』は「霧で帰れない。恋の常套句」と注す。
|
| 1.4.6 |
|
「山里の物寂しい気持ちを添える夕霧のために
帰って行く気持ちにもなれずおります」
|
山里の哀れを添ふる夕霧に
立ち出でんそらもなきここちして
|
【山里のあはれを添ふる夕霧に--立ち出でむ空もなき心地して】- 夕霧から落葉の宮への贈歌。「霧」「立ち」「空」が縁語。「夕霧に衣は濡れて草枕旅寝するかも逢はぬ君ゆゑ」(古今六帖、霧)。
|
| 1.4.7 |
と聞こえたまへば、
|
と申し上げなさると、
|
と申し上げると、
|
|
| 1.4.8 |
|
「山里の垣根に立ち籠めた霧も
気持ちのない人は引き止めません」
|
山がつの籬をこめて立つ霧も
心空なる人はとどめず
|
【山賤の籬をこめて立つ霧も--心そらなる人はとどめず】- 落葉の宮の返歌。「山」「立つ」「霧」「心」「空」の語句を受けて、「霧」を落葉の宮自身に、「心そらなる人」を夕霧に喩えて、「とどめず」と切り返す。
|
| 1.4.9 |
ほのかに聞こゆる御けはひに慰めつつ、まことに帰るさ忘れ果てぬ。
|
かすかに申し上げるご様子に慰めながら、ほんとうに帰るのを忘れてしまった。
|
こうほのかにお答えになる優美な宮の御様子がうれしく思われて、大将はいよいよ帰ることを忘れてしまった。
|
|
| 1.4.10 |
|
「どうしてよいか分からない気持ちです。
家路は見えないし、霧の立ち籠めたこの家には、立ち止まることもできないようにせき立てなさる。
物馴れない男は、こうした目に遭うのですね」
|
「どうすることもできません。道はわからなくなってしまいましたし、こちらはお追い立てになる。だれも経験することを少しも経験せずに始めようとする者は、すぐこうした目にあいます」
|
【中空なるわざかな】- 以下「かかることこそ」まで、夕霧の詞。「中空」「家路」「籬」など宮の和歌の中の語句の歌語を使用して優美にいう。
【つきなき人は、かかることこそ】- 夕霧自身をいう。恋に馴れない人は、の意。『集成』は「不馴れな男は、こんな目に会うのですね」。『完訳』は「こうしたことの不似合いな男でしたらこのお仕打ちももっともなことでしょうが」と訳す。係助詞「こそ」の下に「あらめ」などの語句が省略された形。
|
| 1.4.11 |
|
などとためらって、これ以上堪えられない思いをほのめかして申し上げなさると、今までも全然ご存知でなかったわけではないが、知らない顔でばかり通して来なさったので、このように言葉に出されてお恨み申し上げなさるのを、面倒に思って、ますますお返事もないので、たいそう嘆きながら、心の中で、「再び、このような機会があるだろうか」と、思案をめぐらしなさる。
|
などと言って、もうここに落ち着くふうを見せ、忍び余る心もほのめかしてお話しする大将を、宮は今までからもその気持ちを全然お知りにならないのでもなかったが、気づかぬふうをしておいでになったのを、あらわに言葉にして言うのをお聞きになっては、ただ困ったこととお思われになって、いっそうものを多くお言いにならぬことになったのを、大将は歎息していて、心の中ではこんな機会はまたとあるわけもない、思い切ったことは今でなければ実行が不可能になろうとみずからを励ましていた。
|
【忍びあまりぬる筋も】- 『集成』は「もはや抑えがたい胸の内も」。『完訳』は「これ以上包みきれない胸の中をも」と訳す。
【年ごろもむげに見知りたまはぬにはあらねど、知らぬ顔にのみもてなしたまへるを】- 主語は落葉の宮。宮自身も実は夕霧の気持ちを知っていたのだがという解説的叙述。
【また、かかる折ありなむや】- 夕霧の心中。連語「なむや」は、「な」完了の助動詞、確述の意と「む」推量の助動詞、推量の意。「や」係助詞、疑問の意。強い疑問の推量のニュアンスを表す。
|
| 1.4.12 |
|
「薄情で軽薄な者と思われ申そうとも、どうすることもできない。
せめて思い続けて来たことだけでもお打ち明け申そう」
|
同情のない軽率な人間であるとお思われしてもしかたがない、せめて長く秘めてきた苦しい思いだけでもおささやきしたい
|
【情けなうあはつけきものには】- 以下「知らせたてまつらむ」まで、夕霧の心中。
【思はれたてまつるとも】- 自分が思われ申す、という謙譲表現。
【いかがはせむ】- 反語表現。仕方のないことだ、の意。
|
| 1.4.13 |
|
と思って、供人をお呼びになると、近衛府の将監から五位になった、腹心の家来が参った。
人目に立たないように呼び寄せなさって、
|
と思った大将は、従者を呼ぶと、もとは右近衛府の将監であって、五位になった男が出て来た。大将は近く招いて、
|
【人を召せば】- 夕霧の供人。
【御司の将監よりかうぶり得たる、睦ましき人】- 「御司」は左近衛府をさす。「将監」は近衛府第三等官で従六位下相当官。「かうぶり得たる」は五位に叙せられた、の意。
|
| 1.4.14 |
「この律師にかならず言ふべきことのあるを。護身などに暇なげなめる、ただ今はうち休むらむ。今宵このわたりに泊りて、初夜の時果てむほどに、かのゐたる方にものせむ。これかれ、さぶらはせよ。随身などの男どもは、栗栖野の荘近からむ、秣などとり飼はせて、ここに人あまた声なせそ。かやうの旅寝は、軽々しきやうに人もとりなすべし」 |
「この律師に是非とも話したいことがあるのだが。
護身などに忙しいようだが、ちょうど今は休んでいるだろう。
今夜はこの近辺に泊まって、初夜の時刻が終わるころに、あの控えている所に参ろう。
誰と誰とを、控えさせておけ。
随身などの男たちは、栗栖野の荘園が近いから、秣などを馬に食わせて、ここでは大勢の声を立てるではない。
このような旅寝は、軽率なように人が取り沙汰しようから」
|
「こちらへ来ておられる律師にぜひ逢って話すことがあるのだが、御病人の護身の法などをしておられて疲れておられる律師は休息もしなければならないことと思うから、私はこちらで泊まって、初夜のお勤めを終わられたころに律師のいるほうへ行こうと思う。二、三人だけはこの山荘のほうへ人を残しておいて、そのほか随身などの者は栗栖野の荘が近いはずだから、そのほうへ皆やって、馬に糧秣をやったりさせることにして、ここで騒がしく人声などは立てさせぬようにしてくれ。こんな外泊は人の中傷の種になるのだから気をつけてくれるように」
|
【この律師に】- 以下「人もとりなすべし」まで、夕霧の詞。
【随身などの男どもは】- 随身たちは栗栖野に遣って人少なにさせる。
【栗栖野の荘】- 小野の近くにある夕霧の荘園。
|
| 1.4.15 |
とのたまふ。あるやうあるべしと心得て、承りて立ちぬ。 |
とお命じになる。
何かきっと子細があるのだろうと理解して、仰せを承って立った。
|
と命じた。訳のあることに相違ないと思ってその男は去った。
|
【あるやうあるべし】- 将監の心中。
|
|
第五段 夕霧、落葉宮の部屋に忍び込む
|
| 1.5.1 |
さて、
|
そうしてから、
|
それから大将は女房に、
|
|
| 1.5.2 |
|
「帰り道が霧でまことにはっきりしないので、この近辺に宿をお借りしましょう。
同じことなら、この御簾の側をお許し下さい。
阿闍梨が下がって来るまでは」
|
「道もわからなくなりましたからここでごやっかいになりましょう、かないますならこの御簾の前を拝借させてください。阿闍梨の御用が済むまでです」
|
【道いとたどたどしければ】- 以下「下るるほどまでなむ」まで、夕霧の詞。
【宿借りはべる】- 連体中止法、余意余情表現。
【許されあらなむ】- 「なむ」終助詞、願望の意。
【まで」--など】- 大島本は「まてなと」とある。『完本』は諸本に従って「までなむと」と「む」を補訂する。『集成』『新大系』は底本のままとする。
|
| 1.5.3 |
|
などと、さりげなくおっしゃる。
いつもは、このように長居して、くだけた態度もお見せなさらないのに、「嫌なことだわ」と、宮はお思いになるが、わざとらしくして、さっさとあちらにお移りになるのは、人の体裁の悪い気がなさって、ただ音を立てずにいらっしゃると、何かと申し上げて、お言葉をお伝えに入って行く女房の後ろに付いて、御簾の中に入っておしまいになった。
|
と落ち着いたふうで言うのであった。これまではこんなに長居をしたこともなく、浮薄な言葉も出した人ではなかったのに、困ったことであると宮はお思いになったが、わざとがましく隣室へ行ってしまうことも体裁のよいものでないような気があそばされるので、ただ音をたてぬようにしてそのままおいでになると、思ったことを吐露し始めた大将は、お心の動くまでというように、いろいろと言葉を尽くすのであったが、宮へお取り次ぎにいざり入る人の後ろからそっと御簾をくぐって来た。
|
【つれなくのたまふ】- 『完訳』は「さりげなく。一方的な態度」と注す。
【例は、かやうに】- 以下「うたてもあるかな」まで、落葉の宮の心中と地の文が融合した形。
【はひ渡りたまふは、人も】- 大島本は「はひ(△&ひ)わたり給ハ人も」とある。「人」と「ん」の字体の類似から生じた異文。『集成』『完本』は諸本に従って「はひわたりたまはむも」と「校訂する。『新大系』は底本のまま「はひわたり給(たまは)ば人も」と整定する。
【御消息聞こえ伝へにゐざり入る人】- 夕霧から落葉の宮へのご口上を伝えるために膝行して中へ入っていく女房の意。
|
| 1.5.4 |
|
まだ夕暮のころで、霧に閉じ籠められて、家の内は暗くなった時分である。
驚いて振り返ると、宮はとても気味悪くおなりになって、北の御障子の外にいざってお出あそばすが、実によく探し当てて、お引き止め申した。
|
夕霧が盛んに家の中へ流れ込むころで、座敷の中が暗くなっているのである。その女房は驚いて後ろを見返ったが、宮は恐ろしくおなりになって、北側の襖子の外へいざって出ようとあそばされたのを、大将は巧みに追いついて手でお引きとめした。
|
【あさましうて見返りたるに】- 主語は女房。
【北の御障子の外にゐざり出でさせたまふを】- 母屋から母御息所のいる北廂間に通じる襖障子の向う側へ、の意。「出でさせたまふ」という最高敬語表現。
【いとようたどりて、ひきとどめたてまつりつ】- 主語は夕霧。夕霧には敬語表現のないことに注意。
|
| 1.5.5 |
|
お身体はお入りになったが、お召し物の裾が残って、襖障子は、向側から鍵を掛けるすべもなかったので、閉めきれないまま、総身びっしょりに汗を流して震えていらっしゃる。
|
もうお身体は隣の間へはいっていたのであるが、お召し物の裾がまだこちらに引かれていたのである。襖子は隣の室の外から鍵のかかるようにはなっていないために、それをおしめになったままで、水のように宮は慄えておいでになった。
|
【障子は、あなたより鎖すべき方なかりければ】- 落葉の宮は母屋の外側に出たので、外側からは錠が掛けられない。
|
| 1.5.6 |
|
女房たちも驚きあきれて、どうしたらよいかとも考えがつかない。
こちら側からは懸金もあるが、困りきって、手荒くは、引き離すことのできるご身分の方ではないので、
|
女房たちも呆然としていていかにすべきであるかを知らない。こちらの室には鍵があっても、この場合をどうすればよいかに皆当惑したのである。無理やりに荒々しく手を宮のお召し物から引き放させるようなこともできる相手ではなかった。
|
【こなたよりこそ鎖す錠などもあれ】- 係助詞「こそ」--「あれ」已然形、逆接用法。
|
| 1.5.7 |
「いとあさましう。思たまへ寄らざりける御心のほどになむ」 |
「何ともひどいことを。
思いも寄りませんでしたお心ですこと」
|
「御尊敬申し上げておりますあなた様がこんなことをなさいますとは思いもよらぬことでございます」
|
【いとあさましう】- 以下「御心のほどになむ」まで、女房の詞。「あさましう」連体中止法、余意余情表現。下に「なむある」などの語句が省略。
|
| 1.5.8 |
と、泣きぬばかりに聞こゆれど、
|
と、今にも泣き出しそうに申し上げるが、
|
と言って、泣かんばかりに退去を頼むのであるが、
|
|
| 1.5.9 |
|
「この程度にお側近くに控えているのが、誰にもまして疎ましく、目障りな者とお考えになるのでしょうか。
人数にも入らないわが身ですが、お耳馴れになった年月も長くなったでしょう」
|
「これほどの近さでお話を申し上げようとするのを、なぜあなたがたは不思議になさるのでしょう。つまらぬ私ですが、真心をお見せすることになって長い年月も重なっているはずです」
|
【かばかりにて】- 以下「重なりぬらむ」まで、夕霧の詞。
【数ならずとも、御耳馴れぬる年月も重なりぬらむ】- 『完訳』は「夕霧のいやみな自卑。多年、この邸に昵懇を重ねてきた、の気持のみならず、権勢家としての自分の名声を誇る気持もこめる」と注す。
|
| 1.5.10 |
|
とおっしゃって、とても静かに体裁よく落ち着いた態度で、心の中をお話し申し上げなさる。
|
と女房らに答えてから、大将は優美な落ち着きを失わずに、美しいこの恋を成り立たせなければならぬことを宮へお説きするのであった。
|
【いとのどやかにさまよくもてしづめて】- 『集成』は「とてももの静かにたしなみよく落着いた態度で」と訳す。『完訳』は「簾中に入ってもまるであわてない。夕霧らしい態度というべき」「まことにもの静かな様子で、見苦しからず落ち着いて」と注す。
|
|
第六段 夕霧、落葉宮をかき口説く
|
| 1.6.1 |
聞き入れたまふべくもあらず、悔しう、かくまでと思すことのみ、やる方なければ、のたまはむことはたましておぼえたまはず。 |
お聞き入れになるはずもなく、悔しい、こんな事にまでと、お思いになることばかりが、心を去らないので、返事のお言葉はまったく思い浮かびなさらない。
|
宮は御同意をあそばすべくもない。こんな侮辱までも忍ばねばならぬかというお気持ちばかりが湧き上がるのであるから何を言うこともおできにならない。
|
【悔しう、かくまで】- 落葉の宮の心中。『集成』は「不覚だった、こんなにまでこの人を近づけてしまってと、悔む気持ばかり先立って、やり場のない思いなので。皇女としての誇りが深く傷つけられた思い」。『完訳』は「こうまでもご自分をお見下しになるのかと」「夕霧のぶしつけな態度に自尊心が傷つけられた思い」と注す。
|
| 1.6.2 |
|
「まことに情けなく、子供みたいなお振る舞いですね。
人知れない胸の中に思いあまった色めいた罪ぐらいはございましょうが、これ以上馴れ馴れし過ぎる態度は、まったくお許しがなければ致しません。
どんなにか、千々に乱れて悲しみに堪え兼ねていますことか。
|
「あまりに少女らしいではありませんか。思い余る心から、しいてここまで参ってしまったことは失礼に違いございませんが、これ以上のことをお許しがなくてしようとは存じておりません。この恋に私はどれだけ煩悶に煩悶を重ねてきたでしょう。
|
【いと心憂く】- 以下「いとかたじけなければ」まで、夕霧の詞。
【御心許されでは御覧ぜられじ】- 主語は落葉の宮。「で」接続助詞、打消の意。「られ」受身の助動詞。「じ」打消推量の助動詞。
【千々に砕けはべる思ひに堪へぬぞや】- 「堪へ」未然形。「ぬ」打消の助動詞。係助詞「ぞ」。間投助詞「や」詠嘆の意。『集成』は「君恋ふと心は千々にくだくるをなど数ならぬわが身なるらむ」(曽丹集)を指摘。『完訳』は「君恋ふる心は千々にくだくれど一つも失せぬものにぞありける」(後拾遺集恋四、八〇一、和泉式部)を指摘。
|
| 1.6.3 |
さりともおのづから御覧じ知るふしもはべらむものを、しひておぼめかしう、け疎うもてなさせたまふめれば、聞こえさせむ方なさに、いかがはせむ、心地なく憎しと思さるとも、かうながら朽ちぬべき愁へを、さだかに聞こえ知らせはべらむとばかりなり。言ひ知らぬ御けしきの辛きものから、いとかたじけなければ」 |
いくらなんでも自然とご存知になる事もございましょうに、無理に知らぬふりに、よそよそしくお扱いなさるようなので、申し上げるすべもないので、しかたがない、わきまえもなくけしからぬとお思いなさっても、このままでは朽ちはててしまいかねない訴えを、はっきりと申し上げて置きたいと思っただけです。
言いようもないつれないおあしらいが辛く思われますが、まことに恐れ多いことですから」
|
私が隠しておりましても自然お目にとまっているはずなのですが、しいて冷たくお扱いになるものですから、私としてはこのほかにいたしようがないではございませんか。思いやりのない行動として御反感をお招きしても、片思いの苦しさだけは聞いていただきたいと思います。それだけです。御冷淡な御様子はお恨めしく思いますが、もったいないあなた様なのですから、決して、決して」
|
【いかがはせむ】- 反語表現。もはやどうすることもできない、の意。
【知らせはべらむとばかりなり】- 「む」推量の助動詞、意志。副助詞「ばかり」限定のニュアンス。
【いとかたじけなければ】- 『集成』は「これ以上のことには及ばぬ、という含意」と注す。
|
| 1.6.4 |
|
と言って、努めて思いやり深く、気をつかっていらっしゃった。
|
と言って、大将はしいて同情深いふうを見せていた。
|
【あながちに情け深う、用意したまへり】- 『完訳』は「無作法な態度を省みて自己を抑制」と注す。
|
| 1.6.5 |
|
襖を押さえていらっしゃるのは、頼りにならない守りであるが、あえて引き開けず、
|
あるところまでよりしまらぬ襖子を宮がおさえておいでになるのは、これほど薄弱な防禦もないわけなのであるが、それをしいてあけようとも大将はしないのである。
|
【障子を押さへたまへるは】- 主語は落葉の宮。
【引きも開けず】- 副助詞「も」強調のニュアンス。開けようと思えば簡単に開けられるのに開けないで、の意。
|
| 1.6.6 |
|
「この程度の隔てをと、無理にお思いになるのがお気の毒です」
|
「これだけで私の熱情が拒めると思召すのが気の毒ですよ」
|
【かばかりのけぢめをと】- 以下「あはれなれ」まで、夕霧の詞。
|
| 1.6.7 |
|
と、ついお笑いになって、思いやりのない振る舞いはしない。
宮のご様子の、優しく上品で優美でいらっしゃること、何と言っても格別に思える。
ずっと物思いに沈んでいらっしゃったせいか、痩せてか細い感じがして、普段着のままでいらっしゃるお袖の辺りもしなやかで、親しみやすく焚き込めた香の匂いなども、何もかもがかわいらしく、なよなよとした感じがしていらっしゃった。
|
と笑っていたが、やがておそばへ近づいた。しかも御意志を尊重して無理はあえてできない大将であった。宮はなつかしい、柔らかみのある、貴女らしい艶なところを十分に備えておいでになった。続いてあそばされたお物思いのせいかほっそりと痩せておいでになるのが、お召し物越しに接触している大将によく感ぜられるのである。しめやかな薫香の匂いに深く包まれておいでになることも、柔らかに大将の官能を刺激する、きわめて上品な可憐さのある方であった。
|
【人の御ありさま】- 落葉の宮をいう。
【さはいへどことに見ゆ】- 『集成』は「そうは言っても(そう美しい方ではないといっても)格段にすぐれている。宮様だけのことはある」。『完訳』は「夫柏木の情の薄さから宮の容貌が劣ると推測した。それを受けて「さはいへど」」と注す。
【うちとけたまへるままの】- くつろいだ姿、すなわち普段着のままの姿。
【気近うしみたる匂ひなど】- 「気近し」は親しみやすい意。
|
|
第七段 迫りながらも明け方近くなる
|
| 1.7.1 |
|
風がとても心細い感じで、更けて行く夜の様子、虫の音も、鹿の声も、滝の音も、一つに入り乱れて、風情をそそるころなので、まるで情趣など解さない軽薄な人でさえ、寝覚めするに違いない空の様子を、格子もそのまま、入方の月が山の端に近くなったころ、涙を堪え切れないほど、ものあわれである。
|
吹く風が人を心細くさせる山の夜ふけになり、虫の声も鹿の啼くのも滝の音も入り混じって艶な気分をつくるのであるから、ただあさはかな人間でも秋の哀れ、山の哀れに目をさまして身にしむ思いを知るであろうと思われる山荘に、格子もおろさぬままで落ち方になった月のさし入る光も大将の心に悲しみを覚えさせた。
|
【艶あるほどなれど】- 大島本は「えむあるほとなれと」とある。『集成』『完訳』は諸本に従って「艶なるほどなれば」と校訂する。『新大系』は底本のままとする。
【ただありのあはつけ人だに】- 『集成』は「何の趣味もない間抜けな人でも」。『完訳』は「情趣など解せぬ軽薄な人でさえ」と訳す。
【格子もさながら】- 格子を上げたままの状態。
【とどめがたう】- 涙を留めがたく、の意。
|
| 1.7.2 |
|
「やはり、このようにお分かりになって頂けないご様子は、かえって浅薄なお心底と思われます。
このような世間知らずなまで愚かしく心配のいらないところなども、他にいないだろうと思われますが、どのようなことでも手軽にできる身分の人は、このような振る舞いを愚か者だと笑って、同情のない心をするものです。
|
「まだ私の心持ちを御理解くださらないのを拝見しますと、私はかえってあなた様に失望いたしますよ。こんなに愚かしいまでに自己を抑制することのできる男はほかにないだろうと思うのですが、御信用くださらないのですか。何をいたしても責任感を持たぬ種類の男には、私のようなのをばかな態度だとして、直ちに同情もなく力で解決をはかってしまうのです。
|
【なほ、かう思し知らぬ】- 以下「思し知らぬにしもあらじを」まで、夕霧の詞。
【世づかぬまでしれじれしきうしろやすさなども】- 夕霧自身の態度振る舞いをいう。『完訳』は「相手(女)に安心な男とする」と注す。
|
| 1.7.3 |
|
あまりにひどくお蔑みなさるので、もう抑えてはいられないような気が致します。
男女の仲というものを全くご存知ないわけではありますまいに」
|
あまりに私の恋の価値を軽く御覧になりますから、知らず知らず私も危険性がはぐくまれてゆく気がいたします。男性とはどんなものかを過去にまだご存じでなかったあなた様でもないでしょう」
|
【えなむ静め果つまじき心地しはべる】- 『集成』は「「つれなき心もつかふ」かもしれないとおどす」。『完訳』は「自分も薄情に強引に出るか、と反転」と注す。「やすきほどの人」と同様に「つれなき心を使」おうか、と脅しに出る。
|
| 1.7.4 |
|
と、いろいろと言い迫られなさって、どのようにお答えしたらよいものかと、困り切って思案なさる。
|
こう責められておいでになる宮は、どう返辞をしてよいかと苦しく思っておいでになる。
|
【よろづに聞こえせめられたまひて】- 主語は落葉の宮。「られ」受身の助動詞。
|
| 1.7.5 |
|
結婚した経験があるから気安いように、時々口にされるのも、不愉快で、「なるほど、又とない身の不運だわ」と、お思い続けていらっしゃると、死んでしまいそうに思われなさって、
|
もう処女でないからということを言葉にほのめかされるのを残念に宮はお思いになった。薄命とは自分のような女性をいうのであろうともお悲しまれになって、大将のいどんで来るのを死ぬほど苦しく思召された。
|
【世を知りたる方の心やすきやうに】- 以下「身の憂さなりや」まで、落葉の宮の心中に沿った叙述と心中文。『集成』は「夫を持ったことがあるから組みしやすいと言わんばかりに、時折夕霧が匂わすのも、不愉快で。落葉の宮の気持。「世」は、前の「世の中」とともに、男女の仲の意」。『完訳』は「結婚の経験があるので言い寄りやすいといわんばかりに。以下、宮の心中に転ずる」と注す。
|
| 1.7.6 |
|
「情けない我が身の過ちを知ったとしても、とてもこのようなひどい有様を、どのように考えたらよいものでしょうか」
|
「私のこれまでの運命はどんなにまずいものでございましても、それだからといって、これを肯定しなければならないとは思われない」
|
【憂きみづからの罪を】- 以下「思ひなすべきにかはあらむ」まで、落葉の宮の詞。不本意にも柏木と結婚したことをいう。
|
| 1.7.7 |
と、いとほのかに、あはれげに泣いたまうて、
|
と、とてもかすかに、悲しそうにお泣きになって、
|
と、ほのかに可憐な泣き声をお立てになって、
|
|
| 1.7.8 |
|
「わたしだけが不幸な結婚をした女の例として
さらに涙の袖を濡らして悪い評判を受けなければならないのでしょうか」
|
われのみや浮き世を知れるためしにて
濡れ添ふ袖の名を朽たすべき
|
【我のみや憂き世を知れるためしにて--濡れそふ袖の名を朽たすべき】- 落葉宮の歌。『完訳』は「夕霧の「世の中を--あらじを」に対応。「濡れ添ふ」は、柏木との結婚で流した涙に、夕霧との仲で流す涙を添える意。「くたす」は評判を朽たす、涙で袖を朽たす、の両意。己が身の不幸を痛恨する歌」と注す。係助詞「や」疑問の意は「朽たすべき」連体形に係る。
|
| 1.7.9 |
|
とおっしゃるともないのに、わが気持ちのままに、ひっそりとお口ずさみなさるのも、いたたまれない思いで、どうして歌など詠んだのだろうと、悔やまずいらっしゃれないでいると、
|
ほかへお言いになるともなくお言いになったのを、大将がさらに自身の口にのせて歌うのさえ宮は苦痛にお思いになった。
|
【わが心に続けて、忍びやかにうち誦じたまへるも】- 主語は夕霧。よく聞き取れないないところを推測して補い一首に仕立て上げて口ずさんだ。
【かたはらいたく】- 落葉宮の心中。
【いかに言ひつることぞと】- どうして歌など詠んだのだろうと、後悔の気持ち。
|
| 1.7.10 |
|
「おっしゃるとおり、悪い事を申しましたね」
|
「誤解をお受けしやすいようなことを私が申したものですから」
|
【げに、悪しう聞こえつかし】- 夕霧の詞。
|
| 1.7.11 |
など、ほほ笑みたまへるけしきにて、
|
などと、微笑んでいらっしゃるご様子で、
|
などと言って、微笑するふうで、
|
|
| 1.7.12 |
|
「だいたいがわたしがあなたに悲しい思いをさせなくても
既に立ってしまった悪い評判はもう隠れるものではありません
|
「おほかたはわが濡れ衣をきせずとも
朽ちにし袖の名やは隠るる
|
【おほかたは我濡衣を着せずとも--朽ちにし袖の名やは隠るる】- 夕霧の返歌。「濡れ添ふ袖」「名を朽たす」の語句を受けて、「濡衣」「朽ちにし袖」と返す。「名やは隠るる」反語表現、汚名は歴然としているではないか、と切り返した。『完訳』は「すでに汚名を立てたのだから、自分との間に悪評を立てても構わぬではないか、の意。宮を傷つける歌だが、宮の微妙な心の動きを顧慮しない」と注す。
|
| 1.7.13 |
|
一途にお心向け下さい」
|
もうしかたがないと思召してくだすったらどうですか」
|
【ひたぶるに思しなりねかし】- 夕霧の歌に添えた詞。『集成』は「何もかも捨てた気持におなり下さい」と訳す。
|
| 1.7.14 |
|
と言って、月の明るい方にお誘い申し上げるのも、心外な、とお思いになる。
気強く応対なさるが、たやすくお引き寄せ申して、
|
こう言って、月の光のあるほうへいっしょに出ようと大将はお勧めするのであるが、宮はじっと冷淡にしておいでになるのを、大将はぞうさなくお引き寄せして、
|
【あさまし、と思す】- 主語は落葉宮。
【心強うもてなしたまへど】- 主語は落葉宮。
【はかなう引き寄せたてまつりて】- 主語は夕霧に変わる。
|
| 1.7.15 |
|
「これほど例のない厚い愛情をお分かり下さって、お気を楽になさって下さい。
お許しがなくては、けっして、けっして」
|
「安価な恋愛でなく、最も高い清い恋をする私であることをお認めになって、御安心なすってください。お許しなしに決して、無謀なことはいたしません
|
【かばかりたぐひなき】- 以下「さらにさらに」まで、夕霧の詞。
【さらに、さらに】- 『集成』は「無体な振舞には及ばないと誓う」。『完訳』は「ぶしつけな言葉である」と注す。
|
| 1.7.16 |
と、いとけざやかに聞こえたまふほど、明け方近うなりにけり。
|
と、たいそうはっきりと申し上げなさっているうちに、明け方近くなってしまった。
|
こうきっぱりとしたことを大将が言っているうちに明け方に近くもなった。
|
|
|
第八段 夕霧、和歌を詠み交わして帰る
|
| 1.8.1 |
月隈なう澄みわたりて、霧にも紛れずさし入りたり。
浅はかなる廂の軒は、ほどもなき心地すれば、月の顔に向かひたるやうなる、あやしうはしたなくて、紛らはしたまへるもてなしなど、いはむかたなくなまめきたまへり。
|
月は曇りなく澄みわたって、霧にも遮られず光が差し込んでいる。
浅い造りの廂の軒は、奥行きもない感じがするので、月の顔と向かい合っているようで、妙にきまり悪くて、顔を隠していらっしゃる振る舞いなど、言いようもなく優美でいらっしゃった。
|
澄み切った月の、霧にも紛れぬ光がさし込んできた。短い庇の山荘の軒は空をたくさんに座敷へ入れて、月の顔と向かい合っているようなのが恥ずかしくて、その光から隠れるように紛らしておいでになる宮の御様子が非常に艶であった。
|
|
| 1.8.2 |
|
亡き君のお話も少し申し上げて、当たり障りのない穏やかな話を申し上げなさる。
それでもやはり、あの故人ほどに思って下さらないのを、恨めしそうにお恨み申し上げなさる。
お心の中でも、
|
故人の話も少ししだして、閑雅な態度で大将は語っているのであった。しかもその中で故人に対してよりも劣ったお取り扱いを恨めしがった。宮のお心の中でも、
|
【故君の御こともすこし聞こえ出でて】- 柏木のこと。主語は夕霧。
【過ぎにし方に思し貶すをば】- 落葉宮が柏木よりも夕霧を軽く思うこと。
|
| 1.8.3 |
|
「かの亡き君は、位などもまだ十分ではなかったのに、誰も彼もがお許しになったので、自然と成り行きに従って、結婚なさったのだが、それでさえ冷淡になって行ったお心の有様は、ましてこのようなとんでもないことに、まったくの他人というわけでさえないが、大殿などがお聞きになってどうお思いになることか。
世間一般の非難は言うまでもなく、父の院におかれてもどのようにお聞きあそばしお思いあそばされることだろうか」
|
故人はこの人に比べて低い地位にいた人であるが、院も御息所も御同意のもとでお嫁がせになって自分はその人の妻になったのである、その良人すら自分に対していだいていた愛はいささかなものであった、ましてこうしてあるまじい恋に堕ちては、しかも知らぬ中でなく、故人の妹を妻に持つこの人との名が立っては、太政大臣家ではどう自分を不快に思うことであろう、世間で譏られることも想像されるが、それよりも院がお聞きになってどう思召すであろう、必ずお悲しみあそばすであろう
|
【かれは、位なども】- 以下「思ほされむ」まで、落葉宮の心中。
【誰れ誰れも】- 大島本は「たれ/\も」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「誰も誰も」と校訂する。『新大系』は底本のままとする。
【見馴れたまひにしを】- 『集成』は「「たまふ」と敬語があるのは、地の文の気持が混入したもの」。『完訳』は「宮の心中叙述ながら、語り手の宮への尊敬「たまふ」が混入」と注す。
【よそに聞くあたりにだにあらず】- 夕霧は柏木の異母妹雲居雁を北の方にしている、という縁者。
【大殿などの聞き思ひたまはむことよ】- 故夫柏木の父致仕の大臣。
【院にもいかに聞こし召し思ほされむ】- 落葉宮の父朱雀院。
|
| 1.8.4 |
|
などと、ご縁者のあちらこちらの方々のお心をお考えなさると、とても残念で、自分の考え一つに、
|
などと、切り離すことのできぬ関係の所々のことをお考えになると、このことが非常に情けなくお思われになって、
|
【わが心一つに】- 以下、落葉の宮の心中に即した地の文。初めは心中文、文末の「わびしければ」が地の文に融合。
|
| 1.8.5 |
「かう強う思ふとも、人のもの言ひいかならむ。
御息所の知りたまはざらむも、罪得がましう、かく聞きたまひて、心幼く、と思しのたまはむ」もわびしければ、
|
「このように強く思っても、世間の人の噂はどうだろうか。
母御息所がご存知でないのも、罪深い気がするし、このようにお聞きになって、考えのないことだと、お思いになりおっしゃろうこと」が辛いので、
|
自分はやましいところもなく、大将の情人では断じてなくとも噂はどんなふうに立てられることか、御息所が少しも関与しておいでにならぬことが子として罪であるように思召され、こんなことをあとでお聞きになり、幼稚な心からときがたい誤解の原因を作ったとお言いになろうこともわびしく御想像あそばされる宮は、
|
|
|
 |
| 1.8.6 |
|
「せめて夜を明かさずにお帰り下さい」
|
「せめて朝までおいでにならずにお帰りなさい」
|
【明かさでだに出でたまへ】- 落葉宮の詞。
|
| 1.8.7 |
と、やらひきこえたまふより外の言なし。
|
と、せき立て申し上げなさるより他ない。
|
と大将をお促しになるよりほかのことはおできにならないのである。
|
|
| 1.8.8 |
|
「驚いたことですね。
意味ありげに踏み分けて帰る朝露が変に思うでしょうよ。
やはり、それならばお考え下さい。
愚かな姿をお見せ申して、うまく言いくるめて帰したとお見限り考えなさるようなら、その時はこの心もおとなしくしていられない、今までに致した事もない、不埒な事どもを仕出かすようなことになりそうに存じられます」
|
「悲しいことですね。恋の成り立った人のように分けて出なければならない草葉の露に対してすら私は恥ずかしいではありませんか。ではお言葉どおりにいたしますから、私の誠意だけはおくみとりください。馬鹿正直に仰せどおりにして帰ります私に、若し、上手に追いやってしまったのだというふうを今後お見せになることがありましたなら、その時にはもう自制の力をなくして情熱のなすがままに自分をまかせなければならなくなることと思いますよ」
|
【あさましや】- 以下「思ひたまへらるれ」まで、夕霧の詞。
【ことあり顔に分けはべらむ朝露の思はむところよ】- 『集成』は「実際は、逢って帰るわけでもないので、言う」。『完訳』は「契り交したかのように」「朝露が一晩中起きていた二人を変に思うだろう。「露」の縁で、「置く」「起く」を連想させる」と注す。
【をこがましきさまを】- 大島本は「おこかましきさまを」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「かうをこがましきを」と「かう」を補訂する。『新大系』は底本のままとする。『集成』は「手出しをしなかったことを言う」と注す。
【知らぬことと】- 大島本は「し(し$<朱>)か(か$し<朱>)らぬことゝ」とある。すなわち初め「し」を朱筆でミセケチにし次いで「か」を朱筆でミセケチにして「し」と訂正する。『集成』『完本』は諸本に従って「知らぬことこと」と校訂する。『新大系』は底本のままとする。
|
| 1.8.9 |
とて、いとうしろめたく、なかなかなれど、ゆくりかにあざれたることの、まことにならはぬ御心地なれば、「いとほしう、わが御みづからも心劣りやせむ」など思いて、誰が御ためにも、あらはなるまじきほどの霧に立ち隠れて出でたまふ、心地そらなり。
|
と言って、とても後が気がかりで、中途半端な逢瀬であったが、いきなり色めいた態度に出ることが、ほんとうに馴れていないお人柄なので、「お気の毒で、ご自身でも見下げたくならないか」などとお思いになって、どちらにとっても、人目につきにくい時分の霧に紛れてお帰りになるのは、心も上の空である。
|
大将は心残りを多く覚えるのであるが、放縦な男のような行為は、言っているごとく過去にも経験したことがなく、またできない人であって、恋人の宮のためにもおかわいそうなことであり、自分自身の思い出にも不快さの残ることであろうなどと思って、自他のために人目を避ける必要を感じ、深い霧に隠れて去って行こうとしたが、魂がもはや空虚になったような気持ちであった。
|
|
| 1.8.10 |
|
「荻原の軒葉の荻の露に濡れながら幾重にも
立ち籠めた霧の中を帰って行かねばならないのでしょう
|
「萩原や軒端の露にそぼちつつ
八重立つ霧を分けぞ行くべき
|
【荻原や軒端の露にそぼちつつ--八重立つ霧を分けぞ行くべき】- 夕霧から落葉宮への贈歌。『完訳』は「露と霧の中を涙ながらに帰る自分に同情を引こうとする歌」と注す。「夕霧に衣は濡れて草枕旅寝するかも逢はぬ君ゆゑ」(古今六帖一)。
|
| 1.8.11 |
|
濡れ衣はやはりお免れになることはできますまい。
このように無理にせき立てなさるあなたのせいですよ」
|
あなたも濡衣をお乾しになれないでしょう。それも無情に私をお追いになった報いとお思いになるほかはないでしょう」
|
【濡衣はなほえ干させたまはじ】- 以下「御心づからこそは」まで、歌に続けた夕霧の詞。
|
| 1.8.12 |
|
と申し上げなさる。
なるほど、ご自分の評判が聞きにくく伝わるに違いないが、「せめて自分の心に問われた時だけでも、潔白だと答えよう」とお思いになると、ひどくよそよそしいお返事をなさる。
|
と大将が言った。そのとおりである。名はどうしても立つであろうが、自分自身をせめてやましくないものにしておきたいと思召す心から、宮は冷ややかな態度をお示しになって、
|
【げに、この御名の】- 以下「口ぎよう答へむ」まで、落葉宮の心中に沿った叙述。語り手の落葉の宮への敬語が混入して「御名」とある。
【心の問はむにだに】- 「なき名ぞと人には言ひてありぬべし心の問はばいかが答へむ」(後撰集恋三、七二六、読人しらず)。
|
| 1.8.13 |
|
「帰って行かれる草葉の露に濡れるのを言いがかりにして
わたしに濡れ衣を着せようとお思いなのですか
|
「わけ行かん草葉の露をかごとにて
なほ濡衣をかけんとや思ふ
|
【分け行かむ草葉の露をかことにて--なほ濡衣をかけむとや思ふ】- 落葉宮の返歌。「露」の語句を受けて返す。
|
| 1.8.14 |
|
心外なことですわ」
|
ひどい目に私をおあわせになるのですね」
|
【めづらかなることかな】- 歌に添えた詞。『完訳』は「心外な。非難めく気持」と注す。
|
| 1.8.15 |
|
と、お咎めになるご様子、とても風情があり気品がある。
長年、人とは違った人情家になって、いろいろと思いやりのあるところをお見せ申していたのに、それとうって変わって、油断させ、好色がましいのが、おいたわしく、気恥ずかしいので、少なからず反省し反省しては、「このように無理をしてお従い申したとしても、後になって馬鹿らしく思われないか」と、あれこれと思い乱れながらお帰りになる。
帰り道の露っぽさも、まことにいっぱいある。
|
と批難をあそばすのが、非常に美しいことにも、貴女らしいふうにもお見えになった。今まで古い情誼を忘れない親切な男になりすまして、好意を見せ続けて来た態度を一変して好色漢になってしまうことが宮にお気の毒でもあり、自身にも恥ずかしいと、大将は心に燃え上がるものをおさえていたが、またあまり過ぎた謙抑は取り返しのつかぬ後悔を招くことではないかともいろいろに煩悶をしながら帰って行くのであった。
|
【年ごろ、人に違へる】- 以下、夕霧の心中に沿った叙述。
【心ばせ人になりて】- 『集成』は「よく気を配る人というほどの意」と注す。
【かうあながちに】- 以下「をこがましくや」まで、夕霧の心中。
【道の露けさも、いと所狭し】- 『集成』は「帰り路の露けさも一方ならぬものがある。歩みなずむ気持と悲しみを同時に言う」。『異本紫明抄』は「帰るさの路やは変はる変はらねど解くるに惑ふ今朝の沫雪」(後拾遺集恋二、六七一、藤原道信)を指摘。朝帰りは同じ趣向だが、露と雪との違いがある。
|
|
第二章 落葉宮の物語 律師の告げ口
|
|
第一段 夕霧の後朝の文
|
| 2.1.1 |
|
このような出歩き、馴れていらっしゃらないお人柄なので、興をそそられまた気のもめることだとも思われながら、三条殿にお帰りになると、女君が、このような露に濡れているのを変だとお疑いになるに違いないので、六条院の東の御殿に参上なさった。
まだ朝霧も晴れず、それ以上にあちらではどうであろうか、とお思いやりになる。
|
深い山里の朝露は冷たかった。夫人がこの濡れ姿を見とがめることを恐れて大将は家へは帰らずに六条院の東の花散里夫人の住居へ行った。まだ朝霧は晴れなかった。町でもこんなのであるから、小野の山荘の人はどんなに寂しい霧を眺めておいでになるであろうと大将は思いやった。
|
【殿におはせば】- 夕霧の自邸、三条殿。ここは夕霧の心中に即した仮定の文脈。
【六条院の東の御殿に】- 花散里のもとをさす。夕霧の養母。
|
| 2.1.2 |
|
「いつにないお忍び歩きだったのですわ」
|
「珍しくお忍び歩きをなさいましたのですよ」
|
【例ならぬ御歩きありけり】- 女房たちの詞。「けり」過去の助動詞、詠嘆の意。
|
| 2.1.3 |
|
と、女房たちはささやき合う。
暫くお休みになってから、お召し物を着替えなさる。
いつでも夏服冬服と大変きれいに用意していらっしゃるので、香を入れた御唐櫃から取り出して差し上げなさる。
お粥など召し上がって、院の御前に参上なさる。
|
と女房たちはささやいていた。夕霧の大将はしばらく休息をしてから衣服を脱ぎかえた。平生からこの人の夏物、冬物を幾襲となく作って用意してある養母であったから、香の唐櫃からすぐに品々が選び出されたのである。朝の粥を食べたりしたあとで夫人の居間へ夕霧ははいって行った。
|
【香の御唐櫃】- 『集成』は「香を入れて、収めた装束に匂いを移らせる唐櫃」。『完訳』は「香を着物に移らせるための唐櫃」と注す。
【御前に参りたまふ】- 源氏の御前をさす。挨拶のためである。
|
| 2.1.4 |
|
あちらにお手紙を差し上げなさったが、御覧になろうともなさらない。
唐突にも心外であった有様、腹だたしくも恥ずかしくもお思いなさると、不愉快で、母御息所がお聞き知りになることもまことに恥ずかしく、また一方、こんなことがあったとは全然御存知でないのに、普段と変わった態度にお気づきになり、人の噂もすぐに広まる世の中だから、自然と聞き合わせて、隠していたとお思いになるのがとても辛いので、
|
夕霧はそこから小野へ手紙をお送りした。山荘の宮は予想もあそばさなかった、にわかな変わった態度を男のとり出した昨夜のことで、無礼なとも、恥を見せたともお思いになることで夕霧への御反感が強かった。御息所の耳へはいることがあったならと羞恥をお覚えになるのであるが、またそんなことがあったとは少しも御息所が知らずにいて、不意に何かのことから気のついた時に、隔て心があるように思われるのも苦しい、
|
【かしこに御文たてまつりたまへれど、御覧じも入れず】- 源氏のもとに行く前に夕霧は手紙を小野に差し出したもの。場面は小野に移る。「御覧じも入れず」の主語は落葉宮。
【にはかにあさましかりし】- 以下、落葉の宮の心中に沿った叙述。
【人のもの言ひ隠れなき世なれば】- 『異本紫明抄』は「ここにしも何匂ふらむ女郎花人の物言ひさがにくき世に」(拾遺集雑、一〇九八、僧正遍昭)を指摘。
|
| 2.1.5 |
|
「女房たちがありのままに申し上げて欲しい。
困ったことだとお思いになってもしかたがない」とお思いになる。
|
女房がありのままを話すことによって母を悲しませることがあってもやむをえないと宮はおあきらめになるよりほかはなかった。
|
【人びとありしままに聞こえ漏らさなむ】- 以下「いかがはせむ」まで、落葉の宮の心中文。心中に即した地の文の中に直接話法のように嵌め込まれている。『集成』は「夕霧が近づいたけれども何ごともなかったその実情を、いっそ告げてほしいと思う」と注す。
|
| 2.1.6 |
親子の御仲と聞こゆる中にも、つゆ隔てずぞ思ひ交はしたまへる。よその人は漏り聞けども、親に隠すたぐひこそは、昔の物語にもあめれど、さはた思されず。人びとは、 |
母子の御仲と申す中でも、少しも互いに隠さず打ち明けていらっしゃる。
他人は漏れ聞いても、親には隠している例は、昔の物語にもあるようだが、そのようにはお思いなさらない。
女房たちは、
|
親子と申してもこれほど親しみ合う仲は少ない母と御子なのである。世間に噂の立っていることも親にはなお秘密にしておくことがよく昔の小説などにはあるが、宮にそれはおできになれないことであった。女房たちは
|
【昔の物語にもあめれど】- 『完訳』は「他人には知られても親には隠しだてをする話。『伊勢物語』や『平中物語』などに多い」と注す。「あめれど」の主体は語り手。
|
| 2.1.7 |
|
「何の、少しばかりお聞きになって、子細ありそうに、あれこれと御心配なさることがありましょうか。
まだ何事もないのに、おいたわしい」
|
昨夜のことを御息所が片端だけ聞いてもほんとうにあやまちが起こったことのように歎かれるのであろうから、今はまだそうした思いをさせる必要はないと相談をしていながらも、まだどの程度の関係にまで進んだのか進まなかったのか
|
【何かは、ほのかに聞きたまひて】- 以下「まだきに心苦し」まで、女房の詞。「ほのかに聞きたまひて」の主語は御息所。
|
| 2.1.8 |
など言ひあはせて、いかならむと思ふどち、この御消息のゆかしきを、ひきも開けさせたまはねば、心もとなくて、 |
などと言い合わせて、この御仲がどうなるのだろうと思っている女房どうしは、このお手紙が見たいと思うが、すこしも開かせなさらないので、じれったくて、
|
に疑問を持っていて、今来た大将の手紙が真相を説明してくれるであろうと思う好奇心から、宮がお読みになる時に盗み見をしたいと願っているのであるが、宮はお開きになろうともあそばされないのに気を揉んで、
|
【いかならむと思ふどち】- 宮と夕霧の仲がこれからどうなるのかと関心をもっている女房同士。「心もとなくて」にかかる。
|
| 2.1.9 |
|
「やはり、全然お返事をなさらないのも、不安だし、子供っぽいようでございましょう」
|
「全然御返事をあそばさないことも、たよりない御性質のように想像をなさることでもございましょうし、お若々し過ぎることでもございます」
|
【なほ、むげに聞こえさせたまはざらむも】- 以下「若々しきやうにぞはべらむ」まで、女房の詞。夕霧からの手紙を開いて見るように勧める。
|
| 2.1.10 |
など聞こえて、広げたれば、
|
などと申し上げて、広げたので、
|
などと言って、大将の手紙を拡げると、
|
|
| 2.1.11 |
|
「見苦しく、呆然としていて、相手にあの程度でお会いした至らなさを、わが身の過ちと思ってみるが、遠慮のなかったあまりの態度を、情けなく思われるのです。
拝見できませんと言いなさい」
|
「思いがけないことで、たとえあれだけのことにもせよ男の人を接近させたことは、皆私自身の軽率から起こした過失だとは思うがね、思いやりのないことをした人を、私の憎む心がまだ直らないのだから、読まなかったと言ってやるがいい」
|
【あやしう、何心もなきさまにて】- 以下「え見ずとを言へ」まで、落葉宮の詞。
【人にかばかりにても見ゆるあはつけさの】- 『集成』は「男の人にあの程度にせよお逢いした至らなさを」と訳す。
【慰めがたくなむ】- 係助詞「なむ」の下に「思ふ」などの語句が省略。
【え見ずとを言へ】- 「を」間投助詞、強調の意。
|
| 2.1.12 |
と、ことのほかにて、寄り臥させたまひぬ。
|
と、もってのほかだと、横におなりあそばした。
|
と不機嫌に仰せられて宮は横になっておしまいになった。
|
|
| 2.1.13 |
|
実のところは、憎い様子もなく、とても心をこめてお書きになって、
|
夕霧の手紙は宮の御迷惑になるようなことを避けて書かれたものであった。
|
【さるは、憎げもなく】- 『集成』は「とはいえ。落葉の宮のご不興にもかかわらず、というほどの含み」と注す。語り手の夕霧弁護の句。
|
| 2.1.14 |
|
「魂をつれないあなたの所に置いてきて
自分ながらどうしてよいか分かりません
|
たましひをつれなき袖にとどめおきて
わが心から惑はるるかな
|
【魂をつれなき袖に留めおきて--わが心から惑はるるかな】- 夕霧から落葉の宮への贈歌。『河海抄』は「飽かざりし袖の中にや入りにけむ我が魂のなき心地する」(古今集雑下、九九二、陸奥)を指摘。
|
| 2.1.15 |
|
思うにまかせないものは心であるとか、昔も同じような人があったのだと存じてみますにも、まったくどうしてよいものか分かりません」
|
「ほかなるものは」(身を捨てていにやしにけん思ふよりほかなるものは心なりけり)と歌われておりますから、昔もすでに私ほど苦しんだ人があったと思いまして、みずからを慰めようとはいたすにもかかわらずなお魂は身に添いません。
|
【ほかなるものはとか】- 以下「さらに行く方知らずのみなむ」まで、歌に続けた手紙文。『奥入』は「身を捨てて行きやしにけむ思ふよりほかなるものは心なりけり」(古今集雑下、九七七、躬恒)を指摘。
【さらに行く方知らず】- 『一葉集』は「我が恋はむなしき空に満ちぬらし思ひやれども行く方もなし」(古今集恋一、四八八、読人しらず)を指摘。
|
| 2.1.16 |
|
などと、とても多く書いてあるようだが、女房はよく見ることができない。
通常の後朝の手紙ではないようであるが、やはりすっきりとしない。
女房たちは、ご様子もお気の毒なので、心を痛めて拝見しながら、
|
こんなことが長く書かれてあるようであったが、女房も細かに読むことは遠慮されてできないのである。事の成り立ったのちに書かれた文ではないようであるとは見ながらも、なお疑いを消してはいなかった。女房たちは宮の御気分のすぐれぬことを歎きながら、
|
【人はえまほにも見ず】- 女房は正面から手紙を見ることができない。
【例のけしきなる今朝の御文にもあらざめれど】- 後朝の文らしくないことをいう。「あらざめれど」は女房の視点を通しての叙述。
【なほえ思ひはるけず】- 『集成』は「普通の後朝の文のような今朝のお手紙でもないようだが、女房たちにはどうも十分に納得がいかない」。『完訳』は「昨夜何事があったのかと不審がる」と注す。
|
| 2.1.17 |
|
「どのような御事なのでしょう。
どのような事につけても、素晴らしく思いやりのあるお気持ちは長年続いているけれども」
|
「昨晩のことがまだ不可解なことに思われます。非常に御親切だということは長い間に私どももお認めしている方ですけれど、
|
【いかなる御ことにかはあらむ】- 以下「思ふも危うく」まで、女房の詞。
|
| 2.1.18 |
|
「ご結婚相手としてお頼み申しては、がっかりなさるのではないか、と思うのも不安で」
|
良人という御関係におなりになった時と、熱のある友情期間とが同じでありうるでしょうかどうかが心配ですよ」
|
【かかる方に頼みきこえては】- 「かかる方」は、夫としての意。
【見劣りやしたまはむ】- 『集成』は「夫になったら、夕霧は思ったほどでもないかもしれない、と危ぶむ。柏木の前例もあるからであろう」。『完訳』は「夕霧の予測に反して宮が劣って見え、彼が宮を冷遇するのではないかと、女房たちは以前の柏木と宮の関係を根拠に不安に思うらしい」と注す。
|
| 2.1.19 |
など、睦ましうさぶらふ限りは、おのがどち思ひ乱る。
御息所もかけて知りたまはず。
|
などと、親しく伺候している者だけは、皆それぞれ心配している。
御息所もまったく御存知でない。
|
などと言い、親しく宮にお仕えしている女房たちもこのことに重い関心をもって宮のためにお案じ申し上げているのであった。御息所はまだこのことを少しも知らずにいた。
|
|
|
第二段 律師、御息所に告げ口
|
| 2.2.1 |
もののけにわづらひたまふ人は、重しと見れど、さはやぎたまふ隙もありてなむ、ものおぼえたまふ。日中の御加持果てて、阿闍梨一人とどまりて、なほ陀羅尼読みたまふ。よろしうおはします、喜びて、 |
物の怪にお悩みになっていらっしゃる方は、重病と見えるが、爽やかな気分になられる合間もあって、正気にお戻りになる。
昼日中のご加持が終わって、阿闍梨一人が残って、なおも陀羅尼を読んでいらっしゃる。
好くおなりあそばしたのを、喜んで、
|
物怪に煩っている病人は重態に見えるかと思うと、またたちまちに軽快らしくなることもあって、平常に近い気分になっていたこの日の昼ごろに、日中の加持が終わり、律師一人だけが病床に近くいて陀羅尼経を読んでいた。病人の苦痛のやや去ったことを律師は喜んで、祈りの終わりに、
|
【日中の御加持果てて】- 大島本は「日中の」とある。『集成』『新大系』は底本のままとする。『完本』は諸本に従って「昼日中の」と「昼」を補訂する。
|
| 2.2.2 |
|
「大日如来は嘘をおっしゃいません。
どうして、このような拙僧が心をこめて奉仕するご修法に、験のないことがありましょうか。
悪霊は執念深いようですが、業障につきまとわれた弱いものである」
|
「大日如来が嘘を仰せられたのでなければ、私が熱誠をこめて行なう修法に効果の見えぬわけはありません。悪霊は執拗であっても、それは業にまとわれたつまらぬ亡者ではありませんか」
|
【大日如来虚言したまはずは】- 以下「はかなものなり」まで、阿闍梨の詞。『集成』は「は」を係助詞に解し、読点で下に掛けて読む。『完訳』は「は」を終助詞に解し詠嘆の意にとって、句点で文を完結する。
【などてか】- 「なきやうはあらむ」に係る。反語表現。
【御修法】- 大島本は「御す法」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「御修法に」と「に」を補訂する。『新大系』は底本のままとする。
|
| 2.2.3 |
|
と、声はしわがれて荒々しくいらっしゃる。
たいそう俗世離れした一本気な律師なので、だしぬけに、
|
と太い枯れ声で言っていた。俗離れのした強い性格の律師で、突然、
|
【声はかれて怒りたまふ】- 『集成』は「修法に声は嗄れて、いかめしく言い放たれる」。『完訳』は「声はしわがれて肩をいからしておられる」と訳す。
|
| 2.2.4 |
|
「そうでした。
あの大将は、いつからここにお通い申すようになられましたか」
|
「あ、左大将はいつごろから宮様の所へ通って来ておいでになりますか」
|
【そよや。この大将は、いつよりここには参り通ひたまふぞ】- 阿闍梨の詞。
|
| 2.2.5 |
と問ひ申したまふ。
御息所、
|
とお尋ねになる。
御息所は、
|
と問うた。
|
|
| 2.2.6 |
「さることもはべらず。故大納言のいとよき仲にて、語らひつけたまへる心違へじと、この年ごろ、さるべきことにつけて、いとあやしくなむ語らひものしたまふも、かくふりはへ、わづらふを訪らひにとて、立ち寄りたまへりければ、かたじけなく聞きはべりし」 |
「そのようなことはございません。
亡くなった大納言と大変仲が好くて、お約束なさったことを裏切るまいと、ここ数年来、何かの機会につけて、不思議なほど親しくお出入りなさっているのですが、このようにわざわざ、患っていますのをお見舞いにと言って、立ち寄って下さったので、もったいないことと聞いておりました」
|
「そんなことはありません、亡くなられた大納言の親友でしたから、あの方が遺言して宮様のことも頼んでお置きになったものですから、その約束をお守りになって、それ以来親切によく訪ねて来てくださることが、もう何年も続いています。そんなお交際の仲なのですが、この遠い所まで私の病気を見舞いに来てくださいましたそうですから、恐縮して私は聞いておりましたよ」
|
【さることもはべらず】- 以下「かたじけなく聞きはべりし」まで、御息所の詞。
|
| 2.2.7 |
と聞こえたまふ。
|
と申し上げなさる。
|
御息所の答えはこうであった。
|
|
| 2.2.8 |
|
「いや、何とおかしい。
拙僧にお隠しになることもありますまい。
今朝、後夜の勤めに参上した時に、あの西の妻戸から、たいそう立派な男性がお出になったのを、霧が深くて、拙僧にはお見分け申すことができませんでしたが、この法師どもが、『大将殿がお出なさるのだ』と、『昨夜もお車を帰してお泊りになったのだ』と、口々に申していた。
|
「とんでもない。私に隠しだてをなさる必要はない。今朝後夜の勤めにこちらへ参った時に、あちらの西の妻戸からりっぱな若い方が出ておいでになったのを、霧が深くて私にはよく顔が見えませんじゃったが、弟子どもは左大将が帰って行かれるのじゃ、昨夜も車をお返しになってお泊まりになったのを見たと口々に言っておりました。
|
【いで、あなかたは】- 以下「もはら受けひかず」まで、阿闍梨の詞。『集成』は「いや、それは見苦しい。いらざる弁解だというほどの意」と注す。
【後夜に参う上りつるに】- 六時の勤行の一つ。夜半から暁にかけて行われる。
【かの西の妻戸より】- 落葉宮のいる寝殿の西表の妻戸。
【昨夜も御車も返して】- 係助詞「も」、最初の「も」は同例の意、後出の「も」は強調の意。過去にも見掛けたことがあったという含み。
|
| 2.2.9 |
|
なるほど、まことに香ばしい薫りが満ちていて、頭が痛くなるほどであったので、なるほどそうであったのかと、合点がいったのでござった。
いつもまことに香ばしくいらっしゃる君である。
このことは、決して望ましいことではあるまい。
相手はまことに立派な方でいらっしゃる。
|
そうだろうと私もうなずかれました。よい匂いのする方じゃからな。しかしこの御関係は結構なことじゃありませんなあ。あちらがりっぱな方であることに異議はないが、しかしどうも賛成ができん。
|
【げに、いと香うばしき香の】- 「げに」は、法師ばらの言うことを受けた意。
【げにさなりけり】- 「げに」は、自分自身で納得した気持ち。『集成』は「なるほどそうだったのかと」。『完訳』は「個人個人特有の薫香を用いるので誰であるか分る」と注す。
【このこと、いと切にもあらぬことなり】- 『集成』は「このご縁組は、たって望ましいことでもありませぬ」。『完訳』は「この大将のこちらへのお通いは、まったくどうしても是非にといったものではございません」と訳す。
|
| 2.2.10 |
なにがしらも、童にものしたまうし時より、かの君の御ためのことは、修法をなむ、故大宮ののたまひつけたりしかば、一向にさるべきこと、今に承るところなれど、いと益なし。本妻強くものしたまふ。さる、時にあへる族類にて、いとやむごとなし。若君たちは、七、八人になりたまひぬ。 |
拙僧らも、子供でいらっしゃったころから、あの君の御為の事には、修法を、亡くなられた大宮が仰せつけになったので、もっぱらしかるべき事は、今でも承っているところであるが、まことに無益である。
本妻は勢いが強くていらっしゃる。
ああした、今を時めく一族の方で、まことに重々しい。
若君たちは七、八人におなりになった。
|
子供でいられたころからあの方の御祈祷は御祖母の宮様から私が命ぜられていたものじゃから、今も何かといっては私に頼まれるのですがな、そのことはよくありませんな。奥さんの勢力が強くてしかたがない。盛んな一族が背景になっていますからな。お子さんはもう七、八人もできているでしょう。
|
【童にものしたまうし時より】- 主語は夕霧。敬語が付いている。
【いと益なし】- 『集成』は「お二人のご縁組は何のためにもなりませぬ」と訳す。
|
| 2.2.11 |
|
皇女の君とて圧倒できまい。
また、女人という罪障深い身を受け、無明長夜の闇に迷うのは、ただこのような罪によって、そのようなひどい報いを受けるものである。
本妻のお怒りが生じたら、長く成仏の障りとなろう。
全く賛成できぬ」
|
こちらの宮様がそれにお勝ちになることはできないでしょうな。また一方から言えば女という罪障の深いものに生まれて、救いのない長夜の闇に迷うのもこうした関係から生じる煩悩が原因になり、恐ろしい報いを受けることになりますからな、長い絆が付きまとわることですからな、絶対によろしくないことじゃ」
|
【女人の悪しき身をうけ】- 女は罪深いとする仏教思想。
【長夜の闇】- 『完訳』は「無明長夜の闇。煩悩ゆえに、死後も未来永劫に迷いさまよって真理の光明を見られないこと」と注す。
【ただかやうの罪により】- 愛欲の罪。
【さるいみじき報いをも受くるものなる】- 「さる」は、女性に生まれて無明長夜の闇に迷うことをさす。
|
| 2.2.12 |
と、頭振りて、ただ言ひに言ひ放てば、
|
と、頭を振って、ずけずけと思い通りに言うので、
|
律師は頭を振り立てながら、興奮して乱暴なことも言うのである。
|
|
| 2.2.13 |
|
「何とも妙な話です。
まったくそのようにはお見えにならない方です。
いろいろと気分が悪かったので、一休みしてお目にかかろうとおっしゃって、暫くの間立ち止まっていらっしゃると、ここの女房たちが言っていたが、そのように言ってお泊まりになったのでしょうか。
だいたいが誠実で、実直でいらっしゃる方ですが」
|
「私には腑に落ちないことですよ。そんな様子などは少しもお見せにならなかった方ですもの、昨日は私があまり苦しんでいたものですから、しばらく休息をしてからまた話そうとお言いになって、あちらにいらっしゃると女房たちは言っていましたが、そんなふうで夜明けまでおいでになったのでしょう。至極まじめな堅い方をそんなふうに言う人があるのはよくありません」
|
【いとあやしきことなり】- 以下「すくよかにものしたまふ人を」まで、御息所の詞。
【うち休みて対面せむ】- 以下「立ち止まりたまへる」まで、御達の詞を引用。その中にさらに夕霧の詞を引用。「うち休みて」の主語は夕霧。
【さやうにて泊りたまへるにやあらむ】- 「さやうにて」は「昨夜も御車も返して」の内容をさす。
【ものしたまふ人を】- 「を」間投助詞、詠嘆。接続助詞の逆接的ニュアンスもある。『完訳』は「夕霧が宮に通じるはずがない、の気持をこめる。しかし律師の説得力ある言葉に、夕霧への信頼感が揺れる」と注す。
|
| 2.2.14 |
と、おぼめいたまひながら、心のうちに、
|
と、不審がりなさりながら、心の中では、
|
と御息所はなお不審をいだくふうを僧に見せながらも、
|
|
| 2.2.15 |
|
「そのような事があったのだろうか。
普通でないご様子は、時々見えたが、お人柄がたいそうしっかりしていて、努めて人の非難を受けるようなことは避けて、真面目に振る舞っていらっしゃったのに、たやすく納得できないことはなさるまいと、安心していたのだ。
人少なでいらっしゃる様子を見て、忍び込みなさったのであろうか」とお思いになる。
|
心のうちではそんなことがあったのかもしれない、宮を恋しくお思いする様子はおりおり見えたが、りっぱな人格のある人は人の批難の種になるようなことは避けて、まじめな友情だけを見せていたために、危険はないものとして自分は油断をしていたが、おそばに人も少ないのを見てお居間へはいるようなこともしたのではないかと思われもした。
|
【さることもやありけむ】- 以下「はひ入りもやしたまひけむ」まで、御息所の心中。
【たはやすく心許されぬことはあらじ】- 主語は御息所。夕霧を信頼。
【人少なにておはするけしき】- 落葉宮の周辺。
【たまへりけむ】- 大島本は「給へりけむ」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「たまひけむ」と校訂する。『新大系』は底本のままとする。
|
|
第三段 御息所、小少将君に問い質す
|
| 2.3.1 |
律師立ちぬる後に、小少将の君を召して、
|
律師が立ち去った後に、小少将の君を呼んで、
|
律師が立って行ったあとで、小少将を呼んで、こうこうしたことを聞いたとまず御息所は言った。
|
|
| 2.3.2 |
「かかることなむ聞きつる。いかなりしことぞ。などかおのれには、さなむ、かくなむとは聞かせたまはざりける。さしもあらじと思ひながら」 |
「これこれの事を聞きました。
どうした事ですか。
どうしてわたしには、これこれ、しかじかの事があったとお聞かせ下さらなかったのですか。
そんな事はあるまいと思いますが」
|
「ほんとうのことはどれほどのことだったのかね。なぜ私にくわしく報告してくれなかったの。人の言うようなことは決してあるまいとは思っていても私の心は不安でならない」
|
【かかることなむ聞きつる】- 以下「あらじとは思ひながら」まで、御息所の詞。「かかること」は、小少将の君には具体的に言った内容を、語り手が要約したもの。
|
| 2.3.3 |
とのたまへば、いとほしけれど、初めよりありしやうを、詳しう聞こゆ。
今朝の御文のけしき、宮もほのかにのたまはせつるやうなど聞こえ、
|
とおっしゃると、お気の毒であるが、最初からのいきさつを、詳しく申し上げる。
今朝のお手紙の様子、宮もかすかに仰せになった事などを申し上げ、
|
聞く御息所に気の毒な思いをしながらも、小少将は昨日のことを初めからくわしく話した。今朝の手紙の内容、宮がその時にお洩らしになった言葉なども言って、
|
|
| 2.3.4 |
|
「長年、秘めていらしたお胸の中を、お耳に入れようというほどでございましたでしょうか。
めったにないお心づかいで、夜も明けきらないうちにお帰りになりましたが、人はどのようなふうに申し上げたのでございましょうか」
|
「ながくおさえ続けておいでになりました心を、お知らせなさろうというだけのことだったかと存じます。宮様への敬意をお失いになるようなことはございませんで、御迷惑とお考えになって朝まではおいでになられませんで早く出てお行きになりましたのを、ほかの人はどんなふうに申し上げたのでしょう」
|
【年ごろ、忍びわたり】- 以下「いかに聞こえはべるにか」まで、小少将の君の詞。
【心の内を、聞こえ知らせむ】- 夕霧の心の中を落葉の宮に。
【ありがたう用意ありてなむ】- 『完訳』は「無体な行為には出なかったと弁明」と注す。
【いかに聞こえはべるにか】- 会話文の引用句がなく、即地の文に続く文章の呼吸。
|
| 2.3.5 |
|
律師とは思いもよらず、こっそりと女房が申し上げたものと思っている。
何もおっしゃらず、とても残念だとお思いになると、涙がぽろぽろとこぼれなさった。
拝見するのも、まことにお気の毒で、「どうして、ありのままを申し上げてしまったのだろう。
苦しいご気分を、ますますお胸を痛めていらっしゃるだろう」と後悔していた。
|
と、律師とは知らずに、ほかに密告した女房があったのだと小少将は思って言った。御息所は何も言わずに、残念そうな表情をしていたが涙がほろほろとこぼれ出した。見ていて小少将は気の毒で、なぜありのままのことを言ったのだろう、病気の上に御息所は煩悶をして、どんなに堪えがたいことであろうと悔いた。
|
【律師とは思ひも寄らで】- 主語は小少将の君。
【人の】- 他の女房をさす。
【ものものたまはで】- 主語は御息所。『完訳』は「小少将の言葉から、夕霧を見たとする律師の話を信頼し、二人に実事があったと思い込む。宮に裏切られた思い」と注す。
【見たてまつるも、いといとほしう】- 小少将の君が御息所を。
【何に、ありのままに】- 以下「いとど思し乱るらむ」まで、小少将の君の心中。
|
| 2.3.6 |
|
「襖は懸金が懸けてありました」と、いろいろと適当に言いつくろって申し上げるが、
|
「襖子はしめたままでございました」などと、今になって、少しでもよいように取りなそうと努めるのであったが、
|
【障子は鎖してなむ】- 小少将の詞。係助詞「なむ」の下に「はべりつる」などの語句が省略。実事はなかったように言う。
|
| 2.3.7 |
|
「どうあったにせよ、そのように近々と、何の用心もなく、軽々しく人とお会いになったことが、とんでもないのです。
内心のお気持ちが潔白でいらっしゃっても、こうまで言った法師たちや、口さがない童などは、まさに言いふらさずには置くまい。
世間の人には、どのように抗弁をし、何もなかった事と言うことができましょうか。
皆、思慮の足りない者ばかりがここにお仕えしていて」
|
そんなことはどうでも、なぜそんなに近くへ男の寄って来るようなことを宮がおさせになったかと思うと悲しい。やましいところはおありにならなくても、さっき聞いたようなことを言って騒いでいる律師の弟子たちは、宮様のためにこれは不利であると思って隠すようなことをするはずもない、どう人に言いわけをすればいいことかわからない、絶対にないことと打ち消すことはしなければなるまい、何にしても心の幼稚な女房ばかりがお付きしていて
|
【とてもかくても】- 以下「ここにさぶらひて」まで、御息所の詞。『完訳』は「掛け金があろうとなかろうと。襖を隔てただけで。二人の実事を思い込む御息所には、小少将の気休めの言葉もかえって逆効果」と注す。
【うちうちの御心きようおはすとも】- 落葉宮の心をさす。
【よからぬ童べなど】- 『集成』は「たちのよくない京童べ。都の無頼の若者たち」。『完訳』は「口さがない若者。ここは、僧たちに従う召使か」と注す。
【まさに言ひ残してむや】- 「言い残す」は、言わずに置くの意。係助詞「や」反語の意が加わって、言わないことがあろうか、きっと言い触らすにちがいない。「てむ」連語、当然の結果を予想する。
【人には、いかに言ひあらがひ】- 世間の人に対して。
【言ふべきにかあらむ】- 反語表現。
|
| 2.3.8 |
とも、えのたまひやらず。いと苦しげなる御心地に、ものを思しおどろきたれば、いといとほしげなり。気高うもてなしきこえむとおぼいたるに、世づかはしう、軽々しき名の立ちたまふべきを、おろかならず思し嘆かる。 |
と、最後までおっしゃれない。
とても苦しそうなご容態の上に、心を痛めてびっくりなさったので、まことにお気の毒である。
品高くお扱い申そうとお思いになっていたのに、色恋事の、軽々しい浮名がお立ちになるに違いないのを、並々ならずお嘆きにならずにはいられない。
|
とも思う心を御息所は口へ出しては言えなかった。病気が重い上に大きい衝動を受けたのであったからこの人はいたましいほどにも苦しんだ。神聖な方としてお守り立てしていきたかった宮様も、世間の女並みに浮き名を立てられておしまいになることがもってのほかに思われてならなかった。
|
【いといとほしげなり】- 大島本は「いと/\ほしけなる」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「いとほしげなり」と校訂する。『新大系』は底本のままとする。
【思し嘆かる】- 主語は御息所。「る」自発の助動詞。
|
| 2.3.9 |
|
「このように少しはっきりしている間に、お越しになるよう申し上げなさい。
あちらへお伺いすべきですが、動けそうにありません。
お会いしないで、長くなってしまった気がしますわ」
|
「今日のような私の気分の少しよい間に、宮様がこちらへおいでくださるように申し上げなさい。あちらへ伺うはずだけれど動けそうではないのだからね。ずいぶんながくお目にかからない気がする」
|
【かうすこしものおぼゆる隙に】- 以下「久しうなりぬる心地すや」まで、御息所の詞。主語は御息所自身。
【渡らせたまうべう聞こえよ】- 落葉宮にこちらにいらっしゃるよう申し上げなさい、の意。
【そなたへ参り来べけれど】- 主語は御息所。娘ではあるが皇女なので、自らは「参る」という謙譲語表現をし、宮には「渡らせたまふ」という尊敬語表現を使う。
|
| 2.3.10 |
|
と、涙を浮かべておっしゃる。
参上して、
|
御息所は目に涙を浮かべてこう言っているのであった。
|
【参りて】- 主語は小少将の君。会話文をはさんで「とばかり聞こゆ」に係る。
|
| 2.3.11 |
|
「しかじかと申されていらっしゃいます」
|
小少将は宮のお居間へ帰って、
|
【しかなむ聞こえさせたまふ】- 小少将の君の詞。「しか」は語り手が言い換えたもの。
|
| 2.3.12 |
|
とだけ申し上げる。
|
御息所の最後の言葉だけをお伝えした。
|
【とばかり聞こゆ】- 『完訳』は「小少将は自分が密告者のようになりかねないので、ばつがわるい。御息所の言葉だけを伝えた」と注す。副助詞「ばかり」限定の意に注意。
|
|
第四段 落葉宮、母御息所のもとに参る
|
| 2.4.1 |
|
お越しになろうとして、額髪が濡れて固まっている、繕い直し、単重のお召し物が綻びているが、着替えなどなさっても、すぐにはお動きになれない。
|
宮は母君の所へ行こうとあそばされて、額髪の涙でかたまったのをお直しになり、お召し物の綻んでいた単衣をお着かえになっても、お気が進まないでじっとすわっておいでになるのであった。
|
【濡れまろがれたる】- 連体中止法。以下にも「ほころびたる」も連体中止法。助詞を省略した間合をもたせる余意余情表現である。
【御衣ほころびたる】- 『完訳』は「夕霧に引っぱられて綻びていた」と注す。
|
| 2.4.2 |
|
「この女房たちもどのように思っているだろう。
まだご存知なくて、後に少しでもお聞きになることがあったとき、素知らぬ顔をしていたよ」
|
この女房たちもどう自分を見ているのであろう、御息所も今は何もお知りにならないで、あとで少しでも昨夜のことをお聞きになることがあったなら、素知らぬ顔をしていた
|
【この人びともいかに思ふらむ】- 以下「つれなくてありしよ」まで、落葉宮の心中。
【まだえ知りたまはで】- 主語は母御息所。
|
| 2.4.3 |
と思しあはせむも、いみじう恥づかしければ、また臥したまひぬ。
|
とお思い当たられるのも、ひどく恥ずかしいので、再び臥せっておしまいになった。
|
と今日の自分が思われることであろうとお考えになると、非常に恥ずかしくおなりになり、宮はまた横になっておしまいになって、
|
|
| 2.4.4 |
|
「気分がひどく悩ましいわ。
このまま治らなくなったら、とてもいい都合だろう。
脚の気が上がった気がする」
|
「私はどうも気分がよくない。このまま病気になって死んでしまうのはいいことだけれどね、脚からのぼせ上がってきたようだから」
|
【心地のいみじう悩ましきかな】- 以下「上りたる心地す」まで、落葉宮の詞。
【直らぬさまにもありなむ】- 「なり」動詞、連用形に、完了の助動詞「な」確述の意と推量の助動詞「む」、推量の意が付いて、強い推量の意を表す。以下の文の主語になっている。
【いとめやすかりぬべくこそ】- 係助詞「こそ」の下に「あれ」已然形、などの語句が省略された形。強い意志を表す。『集成』は「何もかも好都合というものです」。『完訳』は「そのほうがいやな噂も立たず見苦しいこともなかろうに」と訳す。
|
| 2.4.5 |
|
と、脚を指圧させなさる。
心配事をとてもつらく、あれこれ気にしていらっしゃる時には、気が上がるのであった。
|
とお言いになり、宮は脚をお揉ませになった。あまり物思いをあそばすためにおのぼせになったのである。
|
【ものをいと苦しう、さまざまに思すには、気ぞ上がりける】- 『万水一露』は「双紙の地也」と指摘。
|
| 2.4.6 |
少将、
|
小少将の君は、
|
|
|
| 2.4.7 |
|
「母上に、あの御事をそれとなく申し上げた人がいたようでございます。
どのような事であったのかと、お尋ねあそばしたので、ありのままに申し上げて、御襖障子の掛金の点だけを、少し誇張して、はっきりと申し上げました。
もし、そのように何かお尋ねなさいましたら、同じように申し上げなさいまし」
|
「御息所に昨晩のことをほのめかしてお話しした人があったのでございますよ。ほんとうのことが聞きたいとお言いになるものでございますから、正直にお話しいたしましたが、お襖子のことだけは少し誇張をいたしまして、しまいまで皆はあいたのでないように申し上げておきましたから、もしくわしいお話を聞こうとなさいましたら、私のと同じようにおっしゃってくださいまし」
|
【上に、この御こと】- 以下「同じさまに聞こえさせたまへ」まで、小少将の君の詞。
【いかなりしことぞ、と問はせたまひつれば】- 主語は御息所。
|
| 2.4.8 |
と申す。
|
と申し上げる。
|
こう小少将が言った。
|
|
| 2.4.9 |
|
お嘆きでいらっしゃる様子は申し上げない。
「やはりそうであったか」と、とても悲しくて、何もおっしゃらない御枕もとから涙の雫がこぼれる。
|
御息所が悲しんでいることは申さない。宮はそれでお呼びになったのであると、いっそう侘しい気におなりになり、何も仰せられなかったが、お枕から雫が落ちていた。
|
【嘆いたまへるけしきは】- 御息所が。
【さればよ」と】- 落葉宮の心中。
|
| 2.4.10 |
|
「このことだけでない、不本意な結婚をして以来、ひどくご心配をお掛け申していることよ」
|
この問題だけではなく、自分の意志でなくした結婚からこの方、母に物思いばかりをさせる自分である
|
【このことにのみもあらず】- 以下「思はせたてまつること」まで、落葉宮の心中。『完訳』は「以下、不本意なわが身を柏木との過往に遡って思念」と注す。
【身の思はずになりそめしより】- 柏木との不本意な結婚をさす。
【いみじうものをのみ思はせたてまつること】- 母御息所に対して。
|
| 2.4.11 |
|
と、生きている甲斐もなくお思い続けなさって、「この方は、このまま引き下がることはなく、何かと言い寄ってくることも、厄介で聞き苦しいだろう」と、いろいろとお悩みになる。
「まして、言いようもなく、相手の言葉に従ったらどんなに評判を落とすことになるだろう」
|
と、宮は子としてのかいのないことを悲しんでおいでになって、あの大将もこのままで心をひるがえすことはせずに、いろいろと自分を苦しめるであろうことが煩わしい、それについて立つ噂もあろうと御煩悶をあそばした。弁明することのできない弱い女の自分は、無根のことでどんなに悪名をきせられることになるのであろう
|
【生けるかひなく思ひ続けたまひて】- 『源注余滴』は「ねぬなはの苦しかるらむ人よりも我ぞ益田の生けるかひなき」(拾遺集恋四、八九四、読人しらず)を指摘。
【この人は】- 夕霧をさす。以下「聞き苦しかるべう」まで、落葉宮の心中。ただし、その引用句はなく、地の文に続く。
【まいて、いふかひなく】- 以下「いかなる名を朽たさまし」まで、落葉の宮の心中。『完訳』「実事がなくともこんなにつらいのだから、まして、意気地なく夕霧の言いなりになっていたら」と注す。
【人の言によりて】- 「人」は夕霧。接続助詞「て」順接、下文の反実仮想の助動詞「まし」と呼応して、仮定の意を含む。
【いかなる名を朽たさまし】- 『完訳』は「「まし」に注意。夕霧の言葉に従わずによかったとするが、実は法師たちの噂にのぼされている」と注す。
|
| 2.4.12 |
|
などと、多少はお気持ちの慰められる面もあるが、「内親王ほどにもなった高貴な人が、こんなにまでも、うかうかと男と会ってよいものであろうか」と、わが身の不運を悲しんで、夕方に、
|
と、穢れのない自信は持っておいでになるのであるが、皇女に生まれた者があれほど異性と近くいて夜の何時間かを過ごしたというようなことはありうることでなく、あってよいわけのものでもないとお思いになることで、御自身の運命がお悲しまれになり、憂鬱にされておいでになったが、夕方にまた、
|
【かばかりになりぬる高き人の】- 以下「人に見ゆるやうはあらじかし」まで、落葉宮の心中。「かばかりになりぬる貴き人」とは皇女の意。
【夕つ方ぞ】- 係助詞「ぞ」は「渡りたまへる」に係る。
|
| 2.4.13 |
|
「やはり、お出で下さい」
|
「ぜひおいでなさいますように」
|
【なほ、渡らせたまへ】- 御息所からの消息。
|
| 2.4.14 |
|
とあるので、中の塗籠の戸を両方を開けて、お越しになった。
|
と、御息所のほうから言って来たので、間にある座敷倉の戸を、向こうとこちらと両方であけて宮は御息所の東の病室へおいでになった。
|
【中の塗籠の戸開けあはせて】- 『完訳』は「女房や僧などの目を避けるべく、この塗籠を通り抜けるか」と注す。
|
|
第五段 御息所の嘆き
|
| 2.5.1 |
|
苦しいご気分ながら、並々ならずかしこまって丁重にご応対申し上げなさる。
いつものご作法と違わず、起き上がりなさって、
|
病苦がありながらも御息所はうやうやしく宮をお取り扱いした。平生の作法どおりに起き上がってもいた。
|
【苦しき御心地にも、なのめならずかしこまりかしづききこえたまふ】- 主語は御息所。母が娘の皇女に対して礼儀を尽くす態度。
|
| 2.5.2 |
|
「とても見苦しい有様でおりますので、お越し頂くにもお気の毒に存じます。
ここ二、三日ほど、拝見しませんでした期間が、年月がたったような気がし、また一方では心細い気がします。
後の世で、必ずしもお会いできるとも限らないもののようでございます。
再びこの世に生まれて参っても、何にもならないことでございましょう。
|
「だらしなくいたしているのでございますから、お迎えいたしますことも心が引けてなりません。ただ二、三日だけお目にかからなかったのでございますのを、何年もお逢いすることのできなかったほど寂しく思われますのも味気ないことでございます。親子の縁では未来で必然的にお逢いできますともきまらないのでございますからね。もう一度生まれてまいりましてもだめなのでございますのに、
|
【いと乱りがはしげにはべれば】- 以下「悔しきまでなむ」まで、御息所の詞。
【心苦しうてなむ】- 係助詞「なむ」の下に「はべる」などの語句が省略。
【はかなくなむ】- 係助詞「なむ」の下に「はべる」などの語句が省略。
【後、かならずしも、対面のはべるべきにもはべらざめり】- 「後」は、来世。親子は一世の縁という。『河海抄』は「一世には二たび見えぬ父母を置きてや長く吾が別れなむ」(万葉集巻五、八九一)を引歌として指摘。
【まためぐり参るとも、かひやははべるべき】- 仏教の輪廻転生の考え。反語表現。『集成』は「もう一度この世に生を享けましても、何にもならぬことでございます。お互い顔も見知らぬであろうからである」と注す。『源注拾遺』は「契りありて此の世にまたも生まるとも面変はりして見もや忘れむ」(後拾遺集哀傷、五六六、藤原実方)を引歌として指摘。
|
| 2.5.3 |
|
考えてみれば、ただ一瞬一瞬の間に別れ別れにならねばならない世の中を、無理に馴れ親しんでまいりましたのも、悔しい気がします」
|
考えますれば瞬間で永遠の別れになりますわれわれがあまりに愛し過ぎて暮らしましたのが、後悔いたされます」
|
【ただ時の間に隔たりぬべき世の中を】- 『集成』は「思えば、ほんの一時のうちに別れ別れにならねばならない無常迅速のこの世ですのに、それを勝手についつい親子の情にほだされてきましたのも、今となってはくやまれるほどでございます」と訳す。
【あながちにならひはべりにけるも】- 『休聞抄』は「思ふとていとこそ人に馴れざらめしか習ひてぞ見ねば恋しき」(拾遺集恋四、九〇〇、読人しらず)を引歌として指摘。
【悔しきまでなむ】- 係助詞「なむ」の下に「思ふ」などの語句が省略。
|
| 2.5.4 |
など泣きたまふ。
|
などとお泣きになる。
|
などと、御息所は泣くのであった。
|
|
| 2.5.5 |
|
宮も、物悲しい思いばかりがせられて、申し上げる言葉もなくてただ拝見なさっている。
ひどく内気なご性格で、はきはきと弁明をなさるような方ではないから、恥ずかしいとばかりお思いなので、とてもお気の毒になって、どのような事であったのですかなどと、お尋ね申し上げなさらない。
|
宮もいろいろなことがお心にあってお悲しい時で、何もお言いになることができずに、ただ母君の顔をながめておいでになった。非常にお内気で思うことをはきはきとお告げになることもおできにならずに、恥ずかしいお様子ばかりのお見えになるのがおかわいそうで、御息所は昨日のことをお尋ねすることもできない。
|
【ものづつみをいたうしたまふ本性に、際々しうのたまひさはやぐべきにもあらねば】- 落葉宮の性格。『完訳』は「宮の遠慮深く寡黙な性分。ここで宮が夕霧との一件を弁明せず、御息所も不憫さから何も尋ねない」と注す。
【問ひきこえたまはず】- 主語は御息所。御息所の誤解思い込みは解消されないまま、母と娘の間の気まずさは続く。
|
| 2.5.6 |
|
大殿油などを急いで灯させて、お膳など、こちらで差し上げなさる。
何も召し上がらないとお聞きになって、あれこれと自分自身で食事を整え直しなさるが、箸もおつけにならない。
ただご気分がよろしくお見えなので、少し胸がほっとなさる。
|
灯を早くつけさせてお夕食などもこちらで差し上げさせることに御息所はした。今朝から何も召し上がらないことを御息所は聞いて、ある物は自身で料理をし変えさせることを命じまでしてお勧めするのであるが、宮は御箸をお触れになる気にもおなりになれなかった。ただ母君の容体がよさそうである点だけで少しの慰めを得ておいでになった。
|
【とかう手づからまかなひ直しなどしたまへど】- 主語は御息所。病床から起き上がって礼儀を尽くしていた御息所が自ら宮に食事の給仕をする。
【ただ御心地のよろしう見えたまふぞ、胸すこしあけたまふ】- 御息所のご気分がよく見えたので、宮はわずかほっとなさる、というさま。
|
|
第三章 一条御息所の物語 行き違いの不幸
|
|
第一段 御息所、夕霧に返書
|
| 3.1.1 |
かしこよりまた御文あり。
心知らぬ人しも取り入れて、
|
あちらからまたお手紙がある。
事情を知らない女房が受け取って、
|
夕霧の大将からまた手紙が来た。事情を知らない女房が使いから受け取って、
|
|
| 3.1.2 |
|
「大将殿から、少将の君にと言って、お使者があります」
|
「大将さんから少将さんにというお手紙がまいりました」
|
【大将殿より、少将の君にとて、御使ひあり】- 大島本は「御つかひ」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「御文」と校訂する。『新大系』は底本のままとする。女房の取り次ぎの詞。
|
| 3.1.3 |
と言ふぞ、またわびしきや。少将、御文は取りつ。御息所、 |
と言うのが、また辛いことであるよ。
少将の君は、お手紙は受け取った。
母御息所が、
|
と、この座敷で披露したことは、宮のお心をさらに苦しくさせたことであった。少将はすぐにそれを手もとへ取ってしまった。
|
【またわびしきや】- 『集成』は「宮の思いを直接地の文として書く」。『完訳』は「宮や小少将の立場に即した語り手の感想」と注す。
|
| 3.1.4 |
|
「どのようなお手紙ですか」
|
「どんなお手紙」
|
【いかなる御文にか】- 御息所の詞。
|
| 3.1.5 |
|
と、やはりお尋ねになる。
人知れず弱気な考えも起こって、内心はお待ち申し上げていらしたのに、いらっしゃらないようだとお思いになると、胸騷ぎがして、
|
と、今までそのことに一言も触れなかった御息所も問うた。反抗的になっていた御息所の心も、何時間かのうちに弱くなり、人知れず大将の今夜の来訪を待っていたのであるから、手紙が来るのは自身で来ぬことであろうと胸が騒いだのである。
|
【さすがに問ひたまふ】- 前に「いかなりしなども問ひきこえたまはず」を受けて、そうは言ってもやはり気がかりで、という文脈。『完訳』は「二人の実事を確信する御息所は、その結婚を不本意としながらも、結ばれた上は夕霧が今夜も来るのを当然と考え、手紙だけ来たのを不審に思う」と注す。
【人知れず思し弱る心も添ひて、下に待ちきこえたまひけるに、さもあらぬなめりと思ほすも】- 主語は御息所。『集成』は「御息所は、ひそかに、宮を夕霧に許そうと、折れる気持にもなっていられて。事ここに及んでは止むを得ないという気持になっていたのである」と注す。
|
| 3.1.6 |
「いで、その御文、なほ聞こえたまへ。あいなし。人の御名を善さまに言ひ直す人は難きものなり。そこに心きよう思すとも、しか用ゐる人は少なくこそあらめ。心うつくしきやうに聞こえ通ひたまひて、なほありしままならむこそ良からめ。あいなき甘えたるさまなるべし」 |
「さあ、そのお手紙には、やはりお返事をなさい。
失礼ですよ。
一度立った噂を良いほうに言い直してくれる人はいないものです。
あなただけ潔白だとお思いになっても、そのまま信用してくれる人は少ないものです。
素直にお手紙のやりとりをなさって、やはり以前と同様なのが良いことでしょう。
いいかげんな馴れ過ぎた態度というものでしょう」
|
「およこしになった手紙のお返事はなさいまし、しかたがございません。一度立てた名を取り消すような評判はだれがしてくれましょう。きれいな御自信はおありになっても、だれがそれを認めてくれましょう。素直にお返事もあそばして、冷淡になさらないほうがよろしゅうございます。わがままな性格だと思われてはなりません」
|
【いで、その御文】- 以下「甘えたるさまなるべし」まで、御息所の詞。
【あいなき甘えたるさまなるべし】- この文の前に、返事をしないのは、という内容が略されている。前文の「こそよからめ」という係結びの構文が、逆接的文脈のニュアンスを介在させるので、このような言い方になっている。
|
| 3.1.7 |
|
とおっしゃって、取り寄せなさる。
辛いけれども差し上げた。
|
宮に申し上げて、御息所は手紙を少将から受け取ろうとした。少将は心に当惑をしながらも渡すよりほかはなかった。
|
【召し寄す】- 夕霧からの手紙を。
|
| 3.1.8 |
|
「驚くほど冷淡なお心をはっきり拝見しては、かえって気楽になって、一途な気持ちになってしまいそうです。
|
冷ややかなお心を知りましたことによってかえっておさえがたいものに私の恋はなっていきそうです。
|
【あさましき御心のほどを】- 以下、和歌の末尾「つつみ果てずは」まで、夕霧の消息文。
|
| 3.1.9 |
|
拒むゆえに浅いお心が見えましょう
山川の流れのように浮名は包みきれませんから」
|
せくからに浅くぞ見えん山河の
流れての名をつつみはてずば
|
【せくからに浅さぞ見えむ山川の--流れての名をつつみ果てずは】- 「塞く」「浅さ」「流れ」が「山川」の縁語。
|
| 3.1.10 |
と言葉も多かれど、見も果てたまはず。
|
と言葉も多いが、最後まで御覧にならない。
|
まだいろいろに書かれてある手紙であったが、御息所は終わりまでを読まなかった。
|
|
| 3.1.11 |
この御文も、けざやかなるけしきにもあらで、めざましげに心地よ顔に、今宵つれなきを、いといみじと思す。 |
このお手紙も、はっきりした態度でもなく、いかにも癪に障るようないい気な調子で、今夜訪れないのを、とてもひどいとお思いになる。
|
この手紙も宮との関係を明瞭に説明したものでなくて恋人の冷ややかであったことにこうして酬いるというように、今夜も来ない大将の態度を御息所は悲しんだ。
|
【今宵つれなきを】- 今夜の訪問のないのを、の意。
|
| 3.1.12 |
|
「故衛門督君が心外に思われた時、とても情けないと思ったが、表向きの待遇は、またとなく大事に扱われたので、こちらに権威のある気がして慰めていたのでさえ、満足ではなかったのに。
ああ、何ということであろう。
大殿のあたりでどうお思いになりおっしゃっていることだろうか」
|
柏木が宮にお持ちする愛情のこまやかでないのを知った時に、御息所は悲観したものであるが、ただ一人の妻として形式的には鄭重をきわめたお取り扱いを故人がしたことで、強みのある気がして慰められはした。それでも心から御息所は宮が御幸福におなりになったとは思わなかった。それさえもそうであったのに、今度のことは何たる悲しいことであろう。太政大臣家での取り沙汰は想像するだにいやである
|
【故督の君の】- 以下「思ひのたまはむこと」まで、御息所の心中。
【こなたに力ある心地して慰めしだに】- 『完訳』は「皇女で正妻ゆえの強みがある気がして慰めた、それでさえけっして満足できなかった」と注す。
|
| 3.1.13 |
と思ひしみたまふ。
|
と心をお痛めになる。
|
と御息所は思うのである。
|
|
| 3.1.14 |
|
「やはり、どのようにおっしゃるかと、せめて様子を窺ってみよう」と、気分がひどく悪く涙でかき曇ったような目、おし開けて、見にくい鳥の足跡のような字でお書きになる。
|
なおどう大将が言ってくるかと見たい心から、非常に苦しい身体の調子であるのを忍んで、目を無理にあけるようにもして書いた力のない、鳥の足跡のような字で返事をするのであった。
|
【なほ、いかがのたまふと、けしきをだに見む】- 御息所の心中。
【くるるやうにしたまふ目、おし絞りて】- 「したまふ」は連体形で下の「目」を修飾する。
|
| 3.1.15 |
|
「すっかり弱ってしまった、お見舞いにお越しになった折なので、お勧め申したのですが、まことに沈んだような様子でいらっしゃるようなので、見兼ねまして。
|
もう私はなおる見込みもなくなりました。宮様はただ今こちらへ見舞いに来ておいでになるのでございまして、お勧めをしてみましたが、めいったふうになっておいでになりまして、お返事もお書けにならないようでございますから、私が見かねまして、
|
【頼もしげなく】- 以下、和歌の末尾「宿を借りけむ」まで、御息所の返書。
【渡りたまへる】- 主語は、落葉宮。
|
| 3.1.16 |
|
女郎花が萎れている野辺をどういうおつもりで
一夜だけの宿をお借りになったのでしょう」
|
女郎花萎るる野辺をいづくとて
一夜ばかりの宿を借りけん
|
【女郎花萎るる野辺をいづことて--一夜ばかりの宿を借りけむ】- 『河海抄』は「秋の野に狩りぞ暮れぬる女郎花今宵ばかりの宿もかさなむ」(古今六帖二、小鷹狩)を指摘。「女郎花」を宮に、「野辺」を小野山荘に喩える。『集成』は「今宵の訪れのないのを責めた歌であるが、同時に、母親として娘を許すという意志表示にもなっている」。『完訳』は「二人の結婚を前提に夕霧の訪れぬのをなじる歌」と注す。
|
| 3.1.17 |
と、ただ書きさして、おしひねりて出だしたまひて、臥したまひぬるままに、いといたく苦しがりたまふ。御もののけのたゆめけるにやと、人びと言ひ騒ぐ。 |
と、ただ途中まで書いて、捻り文にしてお出しなさって、臥せっておしまいになったまま、とてもお苦しがりなさる。
御物の怪が油断させていたのかと、女房たちは騒ぐ。
|
こう書きさしただけで紙を巻いて出した。そのまままた病床に横たわった御息所ははなはだしく苦しみだした。物怪が油断をさせようと一時的に軽快ならしめていたのかと女房たちは騒ぎだした。
|
【御もののけのたゆめけるにや】- 女房の詞。今まで御息所の気分が良かったのは、の意が省略されている。
|
| 3.1.18 |
例の、験ある限り、いと騒がしうののしる。
宮をば、
|
いつもの、効験のある僧すべてが、とても大声を出して祈祷する。
宮に、
|
効験のいちじるしい僧が皆呼び集められて、病室は混雑していた。あちらへお帰りになるように女房たちはお勧めするのであるが、宮は
|
|
| 3.1.19 |
|
「やはり、あちらにお移りあそばせ」
|
御自身をお悲しみになる心から、いっしょに死のう
|
【なほ、渡らせたまひね】- 女房の詞。物の怪が落葉の宮に移らないように。
|
| 3.1.20 |
|
と、女房たちが申し上げるが、ご自身が辛く思うと同時に、後れ申すまいとお思いなので、ぴったりと付き添っていらっしゃった。
|
と思召して母君からお離れにならないのであった。
|
【御身の憂きままに】- 副詞「ままに」。--につれての意と、--と同時にの意があるが、ここは後者の意であろう。『集成』は「情けなさを思うあまり」。『完訳』は「情けなさにつけても」と訳す。
|
|
第二段 雲居雁、手紙を奪う
|
| 3.2.1 |
|
大将殿は、この昼頃に、三条殿にいらっしゃったが、今晩再び小野にお伺いなさるのに、「何かわけがありそうで、まだ何もないのに外聞が悪かろう」などと気持ちをお抑えになって、ほんとにかえって今までの気がかりさよりも、幾重にも物思いを重ねて嘆息していらっしゃる。
|
夕霧はこの日の昼ごろから三条の家にいた。今夜また小野の山荘へ行くことは、まだない事実をあることらしく人に思わせるだけで、自分のためにはよい結果をもたらすことでないと行きたい心をしいておさえることに努力していたが、これまで恋しくお思いしていたことは物の数でもないほどに昨日からにわかに千倍した恋に苦しむ大将であった。
|
【三条殿におはしにける】- 連体中止法。間合が生きている。
【今宵立ち返り参でたまはむに】- 小野山荘に行くことをさす。昨晩一泊した。今夜も行けば結婚の三日通いにとられる。以下「聞き苦しかるべし」まで、夕霧の心中に即した地の文。そのため敬語「たまふ」がある。
【千重にもの思ひ重ねて】- 『源氏釈』は「心には千重に思へど人にいはぬ我が恋ひ妻を見むよしもがな」(古今六帖四、恋)を指摘。『源注余滴』は「和泉なる信太の森の楠の木の千重に別れて物をこそ思へ」(古今六帖二、森)を指摘。
|
| 3.2.2 |
北の方は、かかる御ありきのけしきほの聞きて、心やましと聞きゐたまへるに、知らぬやうにて、君達もて遊び紛らはしつつ、わが昼の御座に臥したまへり。 |
北の方は、このようなお忍び歩きの様子をちらっと聞いて、面白くなく思っていらっしゃるので、知らないふりをして、若君たちをあやして気を紛らしながら、ご自分の昼のご座所で臥していらっしゃった。
|
夫人は山荘の昨日の訪問の様子をほかから聞き出して不快がっていたのであるが、知らぬ顔をして子供の相手をしながら自身の昼の居間のほうで横になっていた。
|
【昼の御座に臥したまへり】- 以下「御心ならひなべかめり」まで、国宝「源氏物語絵巻」詞書にある。
|
| 3.2.3 |
|
ちょうど宵過ぎるころに、このお返事を持って参ったが、このようにいつもと違った鳥の足跡のような筆跡なので、直ぐにはご判読できないで、大殿油を近くに取り寄せて御覧になる。
女君、物を隔てていたようであるが、とてもすばやくお見つけになって、這い寄って、殿の後ろから取り上げなさなった。
|
八時過ぎに小野の山荘で書いた御息所の返事は大将の所へ持って来られたのであるが、大病人の書いた鳥の跡は一度見たのではわかりにくい。夕霧が灯を近くへ持って来させてさらに丁寧に読もうとしている時に、あちらにいたのであるが夫人はそれを見つけて、そっと寄って来て後ろから奪ってしまった。夕霧はあきれて、
|
【この御返り持て参れるを】- 母御息所が代筆した返書。「頼もしげなくなりにて」以下「宿を借りけむ」までの内容をさす。
【女君、もの隔てたるやうなれど】- 『集成』は「人ごとのような顔をしていらしたが」。『完訳』は「女君は、その場からは何か隔て越しのようであったけれど」と訳す。
【はひ寄りて、御後ろより取りたまうつ】- 国宝「源氏物語絵巻」には夕霧の背後から右手を伸ばした雲居雁の立ち姿が描かれている。
|
| 3.2.4 |
|
「あきれたことを。
これは、何をなさるのですか。
何と、
けしからん。六条の東の上様の
お手紙です。今朝、風邪をひいて苦しそうでいらっしゃったが、院の御前におりまして、帰る時に、もう一度伺わないままになってしまったので、お気の毒に思って、ただ今の加減はいかかがですかと、申し上
げたのです。御覧なさい。恋文めいた手紙の
様子ですか。そ
れにしても、はしたないなさりようです。年月とともに、ひ
どく馬鹿になさるのが情けないことです。どう
|
「どうするのですか。けしからんじゃありませんか。六条の東のお母様のお手紙ですよ。今朝から風邪でお悪かったから、院の御殿へ伺ったままでこちらへ帰って来て、もう一度お訪ねすることをしなかったのがお気の毒だったから、御様子を聞く手紙を持たせてやったのじゃありませんか。御覧なさい、恋の手紙というような書き方ですか、これは。はしたない下品なことをするじゃありませんか。年月に添って私を侮ることがひどくなるのは困ったものだ。女房たちがどう思うかを少しも考慮に入れないのですね」
|
【あさましう。こは、いかにしたまふぞ】- 以下「むげに恥ぢたまはぬよ」まで、夕霧の詞。
【六条の東の上の御文なり】- 花散里からの手紙であると嘘をつく。花散里は、夕霧の養母。
【院の御前にはべりて】- 源氏の御前をさす。
【今の間いかに】- 『大系』は「あはざりし時いかなりし物とてかただ今の間も見ねば恋しき(後撰集恋一、五六四、読人しらず)「いかなれや昔思ひしほどよりも今の間思ふ事のまさるは」(落窪物語)を指摘。
【思はむところを、むげに恥ぢたまはぬよ】- 『集成』は「わたしがどう思おうと、ちっとも気になさらないことだ」。『完訳』は「わたしがどう思おうとまるではずかしいとお思いにならないのですね」と訳す。
|
| 3.2.5 |
とうちうめきて、惜しみ顔にもひこしろひたまはねば、さすがに、ふとも見で持たまへり。 |
と慨嘆して、大切そうに無理に取り返そうとなさらないので、それでもやはり、すぐには見ずに持ったままでいらっしゃった。
|
と言って歎息はしたが、惜しそうにしてしいて夫人の手から取り上げることはしなかったから、雲井の雁夫人もさすがにこの場で読むこともできずにじっと持っていた。
|
【さすがに】- 奪ってはみたものの、やはり、の意。本当に養母からの手紙であったらとも思う。はしたなさと嫉妬心むきだしにするのも体裁悪いので。
|
| 3.2.6 |
|
「年月につれて馬鹿になさるのは、あなたのほうこそそうでございますわ」
|
「年月に添って侮るなどとは、あなた御自身がそうでいらっしゃるから、私のことまでも臆測なさるのよ」
|
【年月に添ふるあなづらはしさは、御心ならひなべかめり】- 雲居雁の詞。夕霧の「とし月にそへていたうあなつりたまふこそうれたけれ」の言葉を取って返す。
|
| 3.2.7 |
|
とだけ、このように泰然としていらっしゃる態度に気後れして、若々しくかわいらしい顔つきでおっしゃるので、ふとお笑いになって、
|
夫人は良人があまりにまじめな顔をしているのに気おくれがして、若々しく甘えてみせた。夕霧は笑って、
|
【かくうるはしだちたまへるに】- 夕霧の態度をさす。
【若やかにをかしきさましてのたまへば】- 主語は雲居雁。
|
| 3.2.8 |
|
「それは、どちらでも良いことでしょう。
夫婦とはそのようなものです。
二人といないでしょうね、相当な地位に上った男が、このように気を紛らすことなく、一人の妻を守り続けて、びくびくしている雄鷹のような者はね。
どんなに人が笑っているでしょう。
そのような愚か者に守られていらっしゃるのは、あなたにとっても名誉なことではありますまい。
|
「それはどちらのことでもいい。世間のどこにもあることだからね。けれどもこれだけはほかにないことですよ。相当な身分の男がただ一人の妻を愛して、何かに怖れている鷹のように、じっと一所を見守っているようなのに似た私を、どんなに人が笑っていることだろう。そんな偏屈な男に愛されていることはあなたにとっても名誉じゃありませんよ。
|
【そは、ともかくもあらむ】- 以下「いづこの栄えかあらむ」まで、夕霧の詞。代名詞「そ」は、互いに相手が悪くなったと言ったことをさす。
【またあらじかし】- 読点で、下文にかけて読む句。
【もの懼ぢしたる鳥の兄鷹やうのもののやうなるは】- 「兄鷹(せう)」。雄鷹は雌鷹にびくびくしているという譬えによる。終助詞「は」詠嘆の意。句点で文が切れる。
【さるかたくなしき者に】- 夕霧自身をさしていう。
|
| 3.2.9 |
|
大勢の妻妾の中で、それでも一段と際立って、格別に重んじられていることが、世間の見る目も奥ゆかしく、わが気持ちとしてもいつまでも新鮮な感じがして、興をそそることもしみじみとしたことも続くでしょう。
このように翁が何かを守ったように、愚かしく迷っているので、大変に残念なことです。
どこに見栄えがありましょうか」
|
おおぜいの妻妾の中ですぐれて愛される人は、見ない人までもが尊敬を寄せるものだし、自分でも始終緊張していることができて、若々しい血はなくならないであろうし、真の生きがいを感じることが多いだろうと思われる。私のように、昔の何かの小説にある老いぼれの良人のようにあなた一人をただ夢中に愛しているようなことはあなたのために結構なことではありませんよ。そんなことはあなたが世間からはなやかに見られることでは少しもないからね」
|
【あまたが中に、なほ際まさり、ことなるけぢめ見えたるこそ】- 『完訳』は「大勢の妻妾の中でれっきとした地位を保つこと」と注す。
【わが心地もなほ古りがたく】- 夕霧の気持ち。
【翁のなにがし守りけむやうに】- 走り出た兎が偶然に当たって首を折った切株を再度期待して見守ったという、「韓非子」五蠹篇に見える話。『源注拾遺』は「住吉の小集楽(をづめ)に出でてうつつにもおの妻すらを鏡と見つも(万葉集巻十六、三八〇八)を指摘。
|
| 3.2.10 |
|
と、そうはいっても、この手紙を欲しそうな態度を見せずにだまし取ろうとのつもりで、嘘を申し上げると、とても高かにお笑いになって、
|
夕霧は小野の手紙をいざこざなしに取ってしまいたい心から妻を欺くと、夫人は派手に笑って、
|
【この文のけしきなく】- この手紙を取り返そうの素振り。
【をこつり取らむの心にて】- 大島本は「をこつりとゝむ」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「取らむ」と校訂する。『新大系』は底本のままとする。「をこつり」清音。だましとる。『源注拾遺』は「あだ人のをこつり棹の危うさにうけ引くことのかたくもあるかな」(古今六帖五 思ひわづらふ)を指摘。
|
| 3.2.11 |
|
「見栄えのある事をお作りになるので、年取ったわたしは辛いのです。
とても若々しくなられたご様子がぞっとしてなりませんことも、今まで経験したことのない事なので、とても辛いのです。
以前から馴れさせてお置きにならないで」
|
「はなやかなことをあなたがしようとしていらっしゃるから、古いじみな女の私が一方で苦しんでいるのですよ。にわかにすっかりまじめでなくおなりになったのですもの、私にはそうした習慣がついていないのですから苦しくてなりません。初めからそうしておいでになればよかったのよ」
|
【ものの映え映えしさ作り出でたまふほど】- 以下「ならはしたまはで」まで、雲居雁の詞。落葉宮との関係をいう。
【古りぬる人苦しや】- 雲居雁自身をいう。三十一歳。夕霧は二十九歳。
【今めかしくなり変はれる御けしきのすさまじさも】- 大島本は「いまめかしさも」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「今めかしくなり変はれる御けしきのすさまじさも」と、「くなり変はれる御けしきのすさまじ」を補訂する。『新大系』は底本のままとし、脚注に「底本の脱文である」と注す。夕霧を諷していう。
【かねてよりならはしたまはで】- 『源氏釈』は「かねてよりつらさを我にならはさでにはかに物を思はするかな」(出典未詳)を指摘。
|
| 3.2.12 |
とかこちたまふも、憎くもあらず。
|
と文句をおっしゃるのも、憎くはない。
|
と恨めしがる妻も憎くはなかった。
|
|
| 3.2.13 |
|
「急にとお考えになる程に、どこが変わって見えるのでしょう。
とても嫌なお心の隔てですね。
良くないことを申し上げる女房がいるのでしょう。
不思議と、昔からわたしのことを良く思っていないのです。
依然として、あの緑の六位の袍の名残で、軽蔑しやすいことにつけて、あなたをうまく操ろうと思っているのではないでしょうか。
いろいろと聞きにくいことをほのめかしているらしい。
関わりのない方にとっても、お気の毒です」
|
「にわかにとあなたが思うようなことが私のどこにあるのですか、あなたは疑い深いのですね。私を中傷する人があるのでしょう。そうした人たちは初めから私に敵意を見せていたものだ。浅葱の色の位階服が軽蔑すべきであった私を、今だってあなたの良人にさせておくのが残念で、何かほかの考えを持っている者などがあって、いろんなない噂をあなたに聞かせるのだろう。一方で私のためにそうした濡衣を着せられておいでになる方もお気の毒なものだ」
|
【にはかにと】- 以下「いとほしう」まで、夕霧の詞。
【よからずもの聞こえ知らする人ぞあるべき】- 後文から大輔の乳母を指して言っていることがわかる。
【かの緑の袖の名残】- 夕霧が六位の叙せられたことをさす。「少女」巻に見える。『河海抄』は「松ならば引く人けふはありなまし袖の緑ぞかひなかりける」(拾遺集雑春、一〇二七、大中臣能宣)を指摘。
【もてなしたてまつらむと】- あなた雲居雁を。
【思ふやうあるにや】- 『集成』は「魂胆でもあるのでしょうか」、「や」を係助詞に解す。『完訳』は「意趣でもあるのでしょうよ」、「や」を間投助詞に解す。
【あいなき人の御ためにも】- 『集成』は「巻き添えにされたお人(落葉の宮)にとってもご迷惑なことです」と訳す。
|
| 3.2.14 |
|
などとおっしゃるが、結局はそうなることだとお考えなので、特に言い争いはしない。
大輔の乳母は、とても辛いと聞いて、何も申し上げない。
|
などと言いながらも夕霧は、女二の宮の御良人となることも堅く期しているのであるから、深く弁明はしようとしないのであった。乳母の大輔は気術ながって何も言おうとしなかった。
|
【つひにあるべきことと思せば】- 『完訳』は「結局は宮を得ることになろうと」と注す。
【大輔の乳母、いと苦しと聞きて】- 雲居雁の乳母。「少女」巻で夕霧を蔑んだ人。
|
|
第三段 手紙を見ぬまま朝になる
|
| 3.3.1 |
とかく言ひしろひて、この御文はひき隠したまひつれば、せめても漁り取らで、つれなく大殿籠もりぬれば、胸はしりて、「いかで取りてしがな」と、「御息所の御文なめり。何ごとありつらむ」と、目も合はず思ひ臥したまへり。 |
あれこれと言い合いをして、このお手紙はお隠しになってしまったので、無理しても探し出さず、さりげない顔してお寝みになったので、胸騷ぎがして、「何とかして奪い返したいものだ」と、「御息所のお手紙のようだ。
何事があったのだろう」と、目も合わず考えながら臥せっていらっしゃった。
|
なお夫人は奪った手紙を返そうとはせずにどこかへ隠してしまった。夕霧は無理に取り返そうとはせずに、冷静に見せて寝についたのであるが、動悸ばかり高く打ってならなかった。どうかして取り返したい、御息所の手紙らしい、どんな内容なのであろうと思うと眠ることもできないのである。
|
【つれなく大殿籠もりぬれば】- 主語は夕霧。『異本紫明抄』は「人にあはむ月のなきには思ひおきてむね走り火に心焼けをり(古今集誹諧歌、一〇三〇、小野小町)を指摘。
【いかで取りてしがな」と】- 以下「何ごとありつらむ」まで、夕霧の心中。途中に地の文の引用句「と」が介在する。『完訳』は「「と」は「--ありつらむと」と並列で、夕霧の心中叙述の文脈を構成」と注す。
|
| 3.3.2 |
|
女君が眠っていらっしゃる間に、昨夜のご座所の下などを、何げなくお探しになるが、ない。
お隠しなさる場所もないのに、とても悔しい思いで、夜も明けてしまったが、すぐにはお起きにならない。
|
夫人が寝入ってしまったので、宵にいた所の敷き物の下などをさりげなく大将は捜すのであるが見つからなかった。深く隠すだけの時間のなかったのを思うと、近い所に置かれてあるに違いないと思うのに見つけられないのが歯がゆくて、悩ましい気持ちになり、夜が明けてもなお起きようとしなかった。
|
【女君の寝たまへるに】- 『集成』は「眠っていられる間」、「に」を格助詞に解す。『完訳』は「眠っていらっしゃるので」、「に」を接続助詞、順接の意に解す。
【御座の下などに】- 大島本は「したなとに」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「下など」と「に」を削除する。『新大系』は底本のままとする。
|
| 3.3.3 |
|
女君は、若君たちに起こされて、いざり出ていらっしゃったので、自分も今お起きになったようにして、あちこちとお探しになるが、見つけることがおできになれない。
妻は、このように探そうとお思いなさらないので、「なるほど、恋文ではないお手紙であったのだ」と、気にもかけていないので、若君たちが騒がしく遊びあって、人形を作って、立て並べて遊んでいらっしゃり、漢籍を読んだり、習字をしたりなど、いろいろと雑然としていて、小さい稚児が這ってきて裾を引っ張るので、奪い取った手紙のこともお思い出しにならない。
|
夫人は子供に起こされて寝所からいざって出る時に、夕霧も今目をさましたふうに半身を起こして、昨夜の手紙をまたも捜そうとするのであったが、見つけることは不可能であった。夫人は良人がそんなふうにほしがらぬ手紙はやはり恋の消息ではなかったのであろうと思って、もう気にもかからなかった。子供がそばで騒ぎまわったり、やや大きい子が人形を作って遊んだり、本を読んだり、手習いをしたりするのをいちいち見てやらねばならぬ忙しい時にも、また一人の小さい子が後ろから這いかかって来てつかまり立ちをしようとするような、母であるための繁忙に追われて、夫人はもう奪った手紙のことなどは忘れ切っていた。
|
【女は、かく求めむとも】- 大島本は「女なは」とある。「な」は衍字であろう。『集成』は「「女君」と呼ばず、敬語抜きなのは、その人に遠慮抜きで親しく密着した書き方。次に夕霧も単に「男」と呼ばれる」。『完訳』は「「男」とともに、夫婦のあり方を強調した呼称」と注す。
【心にも入れねば】- 「取りし文のことも」にかかる。「君達のあわて遊び」以下「引きしろへば」まで、挿入句。
【書読み、手習ひなど】- 『集成』は「漢籍の素読をしたり、お習字をしたりなど。これは少し大きい子たちのお勉強である」と注す。
【取りし文のことも思ひ出でたまはず】- 主語は雲居雁。
|
| 3.3.4 |
|
夫は、他の事もお考えにならず、あちらに早く返事を差し出そうとお思いになると、昨夜の手紙の内容も、よく読まないままになってしまったので、「見ないで書いたというようなのも、なくしたのだとお察しになるだろう」などと、お思い乱れなさる。
|
男は他のことはいっさい思われないほど手紙がほしかった。小野へ今朝早く消息をしたいと思うのであるが、昨夜の手紙に書かれてあったことをよく見なかったのであるから、それに触れずに手紙を書いては、先方のものをそまつに取り扱って散らせてしまったことが知れてまずいことになると煩悶をしていた。
|
【見ぬさまならむも、散らしてけると推し量りたまふべし】- 夕霧の心中。苦悩。
|
| 3.3.5 |
誰れも誰れも御台参りなどして、のどかになりぬる昼つ方、思ひわづらひて、
|
どなたもどなたもお食事などを召し上がったりして、のんびりとなった昼ころに、困りきって、
|
夫婦も子供たちも食事を済ませてのどかになった昼ごろに、大将は思いあまって夫人に言うのであった。
|
|
| 3.3.6 |
|
「昨夜のお手紙には、何が書いてありましたか。
けしからん事にお見せにならないで。
今日もお見舞い申そう。
気分が悪くて、六条院にも参上することができないようなので、手紙を差し上げたい。
何が書いてあったのだろうか」
|
「昨夜のお手紙には何と書いてあったのですか。ばかなことを言ってあなたが見せてくれないものだから、今日もこれからお見舞いをしなければならないのに困ってしまう。私は気分が悪くて今日は六条へも行きたくないから、手紙で言ってあげなければならないのだが、昨日のことがわからないでは不都合だから」
|
【昨夜の御文は】- 以下「何ごとかありけむ」まで、夕霧の詞。
【見せたまはで】- 句点。余意余情効果。
【何ごとかありけむ】- 『集成』は「どんなご用だったのだろう」。下文の「さりげなく」と呼応させて自問のように訳す。『完訳』は「どんなことだったのでしょうか」。相手への問い掛けとして訳す。
|
| 3.3.7 |
|
とおっしゃるのが、とてもさりげないので、「手紙を、愚かにも奪い取ってしまった」と興醒めがして、そのことはおっしゃらずに、
|
夕霧の様子はきわめてさりげないものであったから、手紙を隠した自身の所作が、むだなことをしたものであると思うと、急に恥ずかしくなったが、それは言わずに、
|
【文は、をこがましう取りてけり】- 雲居雁の心中。後悔、反省の気持ち。
|
| 3.3.8 |
|
「昨夜の深山風に当たって、具合を悪くされたらしいと、風流気取りで訴えられたらよいでしょう」
|
「先夜の山風に身体を悪くいたしましたからとお言いわけをなさればいいじゃありませんか」
|
【一夜の深山風に】- 以下「聞こえたまへかし」まで、雲居雁の詞。「御山風」は小野山荘訪問を喩える。皮肉を込める。
【あやまりたまへる】- 小野の山風に当たって身体の具合を悪くした、の意。
【悩ましさななり】- 「ななり」は断定の助動詞+伝聞推定の助動詞。--であるようだ、の意。
|
| 3.3.9 |
と聞こえたまふ。
|
と申し上げなさる。
|
と言った。
|
|
| 3.3.10 |
「いで、このひがこと、な常にのたまひそ。何のをかしきやうかある。世人になずらへたまふこそ、なかなか恥づかしけれ。この女房たちも、かつはあやしきまめざまを、かくのたまふと、ほほ笑むらむものを」 |
「さあ、そんな冗談、いつまでもおっしゃいませんな。
何の風流なことがあろうか。
世間の人と一緒になさるのは、かえって気が引けます。
ここの女房たちも、一方では不思議なほどの堅物を、このようにおっしゃると、笑っていることでしょうよ」
|
「つまらんことばかり言うのですね。何もおもしろくないじゃありませんか。私が世間並みの男のように言われるのを聞くとかえってきまりが悪くなりますよ。女房たちなども不思議な堅い男を疑うあなたを笑うだろうに」
|
【いで、このひがこと】- 以下「ほほ笑むらむものを」まで、夕霧の詞。『集成』は「何と、そんな見当違いなことを、いつもいつもおっしゃるでない。邪推だと、たしなめる」と注す。『完訳』は「まあ、そんなつまらぬことをいつも口になさらぬがよい」と訳す。
|
| 3.3.11 |
と、戯れ言に言ひなして、
|
と、冗談に言いなして、
|
冗談にして、また、
|
|
| 3.3.12 |
|
「その手紙ですよ。
どこですか」
|
「昨夜の手紙はどこ」
|
【その文よ。いづら】- 夕霧の詞。
|
| 3.3.13 |
とのたまへど、とみにも引き出でたまはぬほどに、なほ物語など聞こえて、しばし臥したまへるほどに、暮れにけり。
|
とお尋ねになるが、すぐにはお出しにならないままに、またお話などを申し上げて、暫く横になっていらっしゃるうちに、日が暮れてしまった。
|
と言ったが、なおすぐに取り出そうとは夫人のしないままで、ほかの話などをしてしばらく寝ていたが、そのうちに日が暮れた。
|
|
|
第四段 夕霧、手紙を見る
|
| 3.4.1 |
|
蜩の鳴き声に目が覚めて、「小野の麓ではどんなに霧が立ち籠めているだろう。
何ということか。
せめて今日中にお返事をしよう」と、お気の毒になって、ただ知らない顔をして硯を擦って、「どのように取り繕って書こうか」と、物思いに耽っていらっしゃる。
|
蜩の声に驚いて目をさました大将は、この時刻に山荘の庭を霧がどんなに深くふさいでいることであろう、情けないことである、今日のうちに昨日の手紙の返事をすら自分は送ることができなかったのであると思って、何でもないふうに硯の墨をすりながら、どんなふうに書いて送ったものであろうと歎息をして
|
【ひぐらしの声におどろきて】- 『源氏物語引歌』は「ひぐらしの鳴きつるなべに日は暮れぬと思ふは山の蔭にぞありける」(古今集秋上、二〇四、読人しらず)を指摘。
【山の蔭いかに霧りふたがりぬらむ】- 以下「御返事をだに」まで、夕霧の心中。「山の蔭」は小野山荘をさす。直前の「ひぐらしの」歌による措辞。 【いかに霧りふたがりぬらむ】-『完訳』は「涙に濡れて思い屈する意」と注す。
【いとほしうて】- 『集成』は「困ってしまって」。『完訳』は「あの宮がおいたわしく思われるので」と訳す。
【眺めおはする】- 連体中止法。
|
| 3.4.2 |
|
ご座所の奥の少し盛り上がった所を、試しにお引き上げなさったところ、「ここに差し挟みなさったのだ」と、嬉しくもまた馬鹿らしくも思えるので、にっこりして御覧になると、あのようなおいたわしいことが書いてあったのであった。
胸がどきりとして、「先夜の出来事を、何かあったようにお聞きになったのだ」とお思いになると、おいたわしくて胸が痛む。
|
一所を見つめていた目に敷き畳の奥のほうの少し上がっている所を発見した。試みにそこを上げてみると、昨日の手紙は下にはさまれてあった。うれしくも思われまたばかばかしくも夕霧は思った。微笑をしながら読んでみると、それは苦しい複雑な心を重態の病人が伝えているものであったから、大将の鼓動は急に高くなって、自分がしいて結合を遂げたものとして書かれてあると思うと気の毒で心苦しくて、
|
【御座の奥の】- 『集成』は「夕霧のだろう」。『完訳』は「夕霧の。一説に雲居雁の」と注す。
【これにさし挟みたまへるなりけり】- 夕霧の心中。「けり」過去の助動詞、詠嘆の意。
【一夜のことを、心ありて聞きたまうける】- 夕霧の心中。『完訳』は「意味ありげに。御息所の「女郎花--」の歌から宮との実事が思われていると察する」と注す。
|
| 3.4.3 |
|
「昨夜でさえ、どれほどの思いで夜をお明かしになったことだろう。
今日も、今まで手紙さえ上げずに」
|
第二の夜の昨夜に自分の行かなかったことでどんなに御息所は煩悶したことであろう、今日さえまだ手紙が送ってないということは、
|
【昨夜だに、いかに】- 以下「文をだに」まで、夕霧の心中。『集成』は「昨夜だって、どんな思いで夜をお明かしだったろう、今日も、今までお返事もさし上げないでと」。『完訳』は「御息所の判断では昨夜は結婚の第二夜。それを無視したと気づく」と注す。「昨夜だに」の副助詞「だに」は、軽いほうを示して重いほうを暗示する文脈を作る。昨夜すらまして今日は、の気持ち。「文をだに」の下には「差し上げないで」の意が省略。否定の語句と呼応して最小限のそれさえ、という気持ちを含む表現。
|
| 3.4.4 |
と、言はむ方なくおぼゆ。
いと苦しげに、言ふかひなく、書き紛らはしたまへるさまにて、
|
と、何とも言いようなく思われる。
とても苦しそうに、言いようもなく、書き紛らしていらっしゃる様子で、
|
新婚の良人としていえばきわめて無情な態度である。
|
|
| 3.4.5 |
「おぼろけに思ひあまりてやは、かく書きたまうつらむ。つれなくて今宵の明けつらむ」 |
「よほど思案にあまって、このようにお書きになったのだろう。
返事のないまま、
|
露骨に言わずに自分の行くのを促してある消息を受けていながら、自分を待ちつけることがしまいまでできずに今朝になったのであったかと思うと、
|
【おぼろけに】- 以下「今宵の明けつらむ」まで、夕霧の心中。『集成』は「娘を許すとまで書いた御息所の苦衷を察する」と注す。
|
| 3.4.6 |
|
と、申し上げる言葉もないので、女君が、まことに辛く恨めしい。
|
大将は妻が恨めしくも憎くも思われた。
|
【女君ぞ、いとつらう心憂き】- 雲居雁をさす。
|
| 3.4.7 |
|
「いいかげんな、あなようなことをして、悪ふざけに隠すとは。
いやはや、自分がこのようにしつけたのだ」と、あれこれとわが身が情けなくなって、全く泣き出したい気がなさる。
|
無法なことをして大事な手紙を隠させるようなしぐさも皆自分がつけさせたわがままな癖であると思うと、自分自身にすら反感を覚えて泣きたい気がした。
|
【すずろに、かく】- 以下「わがならはしぞや」まで、夕霧の心中。
【わがならはしぞや」と--すべて泣きぬべき心地】- 『源氏釈』は「海人のかるもに棲む虫のわれからと音をこそ泣かめ世をば恨みじ(古今集恋五、八〇七、典侍藤原直子朝臣)を引歌指摘。「や」詠嘆の意。
【身もつらく】- 大島本は「身もつらく」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「身もつらくて」と「て」を補訂する。『新大系』は底本のままとする。
|
| 3.4.8 |
やがて出で立ちたまはむとするを、
|
そのままお出かけなさろうとするが、
|
これからすぐに行こうと夕霧は思うのであったが、
|
|
| 3.4.9 |
|
「気安く対面することもできないだろうから、御息所もあのようにおっしゃっているし、どうであろうか。
坎日でもあったが、もし万が一にお許し下さっても、日が悪かろう。
やはり縁起の良いように」
|
たやすく宮は逢おうとなされないであろうということは予想されることであったし、妻はこうして昨日から嫉妬をし続けているのであるし、それに今日が坎日にあたることはもし宮のお心が解けた場合を考えると、永久に幸福を得なければならぬ結婚の最初に避けなければならぬことでもあるから
|
【心やすく対面も】- 以下「なほ吉からむことをこそ」まで、夕霧の心中。
【人もかくのたまふ】- 「人」は御息所をさす。
【坎日にもありけるを】- 「ありける」という過去表現。「坎日」は陰陽道で外出その他を忌む日。『完訳』は「宮との結婚を一方的にきめこんで、それが凶日から始るのを避けようとする夕霧には、宮や御息所の苦悩が想像できない」と注す。
|
| 3.4.10 |
|
と、几帳面な性格から判断なさって、まずは、このお返事を差し上げなさる。
|
と、まじめな性格からは、恋しい方との将来に不安がないように慎重に事をすべきであると考えられて、行くことはおいて、まず御息所への返事を書いた。
|
【うるはしき心に】- 『完訳』は「几帳面な心に。語り手の皮肉」と注す。
|
| 3.4.11 |
|
「とても珍しいお手紙を、何かと嬉しく拝見しましたが、このお叱りは。
どのようにお聞きあそばしたのですか。
|
珍しいお手紙を拝見いたしましたことは、御病気をお案じ申し上げるほうから申しても非常にうれしいことでしたが、おとがめを受けましたことにつきましては何かお聞き違えになったのではないかと思われるのでございます。
|
【いとめづらしき御文を】- 以下「ひたやごもりにや」まで、夕霧から一条御息所への返書。
【この御咎めをなむ】- 句点で文が切れる。係助詞「なむ」の下に「いかにせむ」などの語句が省略された形。『集成』は「このお叱りは何としたことなのでしょう」。『完訳』は「このお咎めをどうお受けしたらよいのでしょうか」と訳す。
|
| 3.4.12 |
|
秋の野の草の茂みを踏み分けてお伺い致しましたが
仮初の夜の枕に契りを結ぶようなことを致しましょうか
|
秋の野の草の繁みは分けしかど
仮寝の枕結びやはせし
|
【秋の野の草の茂みは分けしかど--仮寝の枕結びやはせし】- 「草」「枕」「結び」が縁語。「結びやはせし」反語表現。仮初の契りを結んだおぼえはありません、の意。
|
| 3.4.13 |
|
言い訳を申すのも筋違いですが、昨夜の罪は、一方的過ぎませんでしょうか」
|
弁明をいたしますのもおかしゅうございますが、宮様に対して御想像なさいますような無礼を申し上げた私では決してございません。
|
【昨夜の罪は、ひたやごもりにや】- 『異本紫明抄』は「憂きによりひたやごもりと思へども近江の海は打出てみよ」(和泉式部集)を指摘。『集成』は「一方的な決めつけ方だという気持」と注す。『完訳』は「それを黙ってお受けしなければならないのでしょうか」と訳す。「にや」の下に「あらむ」などの語句が省略された形。
|
| 3.4.14 |
|
とある。
宮には、たいそう多くお書き申し上げなさって、御厩にいる足の速いお馬に移し鞍を置いて、先夜の大夫を差し向けなさる。
|
という文である。宮へは長い手紙を書いた。そして夕霧は厩の中の駿足の馬に鞍を置かせて、一昨夜の五位の男を小野へ使いに出すことにした。
|
【御厩に足疾き御馬に移し置きて】- 『源注拾遺』は「常陸なるをのだの御牧の露草をうつしは駒のおくにぞありける」(閑院左大将朝光卿集)を指摘。『集成』は「移鞍(うつしぐら)という。移馬(うつしうま、官吏の公用の乗馬用として左右の馬寮に飼われている馬)に置く一定の型式の鞍。駿足の馬に公用の鞍を用いさせたというのは、使命の重さを印象づける」と注す。
|
| 3.4.15 |
「昨夜より、六条の院にさぶらひて、ただ今なむまかでつると言へ」 |
「昨夜から、六条院に伺候していて、たった今退出してきたところだと言え」
|
「昨夜から六条院に御用があって行っていて、今帰ったばかりだと申してくれ」
|
【昨夜より】- 以下「まかでつると言へ」まで、夕霧の詞。大夫に嘘を言うように命じる。
|
| 3.4.16 |
とて、言ふべきやう、ささめき教へたまふ。
|
と言って、言うべきさま、ひそひそとお教えになる。
|
大将は山荘へ行ってからのことでなおいろいろに注意を与えた。
|
|
|
第五段 御息所の嘆き
|
| 3.5.1 |
|
あちらでは、昨夜も薄情なとお見えになったご様子を、我慢することができないで、後のちの評判をもはばからず恨み申し上げなさったが、そのお返事さえ来ずに、今日がすっかり暮れてしまったのを、どれ程のお気持ちかと、愛想が尽きて、驚きあきれて、心も千々に乱れて、すこしは好ろしかったご気分も、再びたいそうひどくお苦しみになる。
|
小野の御息所は、昨夜は夕霧の来ないらしいことに気がもまれて、あとの評判になっては不名誉であろうこともはばかられずに、促すような手紙も書いたのに、その返事すら送られなかったことに失望をしていてそのまま次の今日さえも暮れてきたことに煩悶を多く覚えて、やや軽くなったふうであった容体がまた非常に険悪なものになってきた。
|
【昨夜もつれなく見えたまひし御けしきを】- 「つれなく」は訪問のなかったことをさす。副助詞「も」は強調のニュアンスを添える。
【後の聞こえをもつつみあへず】- 後々の評判とは、御息所のほうから手紙を贈って宮の結婚を許した、ということをさす。
【いかばかりの御心にかはと】- 以下、御息所の心中に即した地の文。「御心」は夕霧の心を推測したもの。
|
| 3.5.2 |
|
かえってご本人のお気持ちは、このことを特に辛いこととお思いになり、心を動かすほどのことではないので、ただ思いも寄らない方に、気を許した態度で会ったことだけが残念であったが、たいしてお心にかけていなかったのに、このようにひどくお悩みになっているのを、言いようもなく恥ずかしく、弁解申し上げるすべもなくて、いつもよりも恥ずかしがっていらっしゃる様子にお見えになるのを、「とてもお気の毒で、ご心労ばかりがお加わりになって」と拝するにつけても、胸が締めつけられて悲しいので、
|
かえって宮御自身は御息所の思い悩む点を何ともお思いになるわけはなくて、ただ異性の他人をあれほどまでも近づかせたことが残念に思われる自分であって、彼の愛の厚薄は念頭にも置いていないにもかかわらず、それを一大事として母君が煩悶していると、恥ずかしくも苦しくも思召されて、母君ながらそのことはお話しになることもできずに、ただ平生よりも羞恥を多くお感じになるふうの見える宮を、御息所は心苦しく思い、この上にまた多くの苦労をお積みにならねばなるまいと、悲しさに胸のふさがる思いをした。
|
【なかなか正身の御心のうちは】- 『集成』は「夕霧の訪れのないのをかえって幸いとするほどの気持であろう」。『完訳』は「世間体を気にする御息所とは対照的」と注す。
【おぼえぬ人に、うちとけたりし】- 夕霧をさす。
【いみじうおぼいたるを】- 主語は落葉宮。
【いと心苦しう】- 以下「添ふべかりける」まで、御息所の心中。
|
| 3.5.3 |
|
「今さら厄介なことは申し上げまいと思いますが、やはり、ご運命とは言いながらも、案外に思慮が甘くて、人から非難されなさることでしょうが。
それを元に戻れるものではありませんが、今からは、やはり慎重になさいませ。
|
「今さらお小言らしいことは申したくないのでございますが、それも運命とは申しながら、異性に対する御認識が不足していましたために、人がどう批難をいたすかしれませんことが起こってしまいましたのですよ。それは取り返されることではございませんが、これからはそうしたことによく御注意をなさいませ。
|
【今さらに】- 以下「はべりけるかな」まで、御息所の詞。
【心幼くて】- 大島本は「をさなくて」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「心幼くて」と「心」を補訂する。『新大系』は底本のままとする。
【負ひたまふべきことを】- 『集成』は「を」格助詞、目的格の意に解し、読点で文を下に続ける。『完訳』は「を」間投助詞、詠嘆の意に解し、句点で文を結ぶ。
【さる心したまへ】- 『完訳』は「世間の非難をつのらせぬよう、慎重にふるまってほしい、の意」と注す。
|
| 3.5.4 |
|
物の数に入るわが身ではありませんが、いろいろとお世話申し上げてきましたが、今ではどのようなことでもお分かりになり、世の中のあれやこれやの有様も、お分かりになるほどに、お世話申してきたことと、そうした方面は安心だと拝見していましたが、やはりとても幼くて、しっかりしたお心構えがなかったことと、思い乱れておりますので、もう暫く長生きしたく思います。
|
つまらぬ私でございますが、今までは御保護の役を勤めましたが、もうあなた様はいろいろな御経験をお積みになりまして、お一人立ちにおなりになりましても充分なように思って、私は安心していたのでございますよ。けれどまだ実際はそうした御幼稚らしいところがあって、隙をお見せになったのかと思いますと、御後見のために私はもう少し生きていたい気がいたします。
|
【数ならぬ身ながらも、よろづに育みきこえつるを】- 御息所は落葉の宮に対して宮様ゆえに、母子の関係ではあるが、自ら遜り娘に尊敬語を使用する。
【見たてまつりおきつることと】- お世話申してきた、の意。
【いといはけて、強き御心おきての】- 『源注拾遺』は「逢ふことの片寄せにする網の目にいはけなきまで恋ひかかりぬる」(古今六帖三、網)を指摘。
【とどめまほしうなむ】- 係助詞「なむ」の下に「思ひはべる」などの語句が省略。
|
| 3.5.5 |
|
普通の人でさえ、多少とも人並みの身分に育った女性で、二人の男性に嫁ぐ例は、感心しない軽薄なことですのに、ましてこのようなご身分では、そのようないい加減なことで、男性がお近づき申してよいことでもないのに、思ってもいませんでした心外なご結婚と、長年来心を痛めてまいりましたが、そのようなご運命であったのでしょう。
|
普通の女でも貴族階級の人は再婚して二人めの良人を持つことをあさはかなことに人は見ているのでございますからね、まして尊貴な内親王様であなたはいらっしゃるのでございますから、あそばすならすぐれた結婚をなさらなければならなかったのでございますが、以前の御縁組みの場合にも、私はあなた様の最上の御良人とあの方を見ることができませんで、御賛成申さなかったのですが、前生のお約束事だったのでしょうか、
|
【ただ人だに】- 臣下の人でさえ、まして皇女は、のニュアンス。
【女の、人二人と見るためしは、心憂くあはつけきわざなるを】- 『河海抄』は「忠臣不事二君、貞女不更二夫」(史記、田単列伝)を指摘。
【さばかりおぼろけにて】- そんないい加減なことで、の意。
【人の近づききこゆべきにもあらぬを】- 推量の助動詞「べき」当然の意。「を」について、『集成』は接続助詞、逆接の意に解し、読点で下文に続けて読み、『完訳』は間投助詞、詠嘆の意に解し、句点で文を結ぶ。
【思ひのほかに心にもつかぬ御ありさまと】- 御息所は落葉宮の柏木との結婚を不本意なことと思っていた。
【御宿世にこそは】- 係助詞「こそ」「は」の下に「あれ」などの語句が省略。
|
| 3.5.6 |
|
院をお始め申して、御賛成なさり、この父大臣にもお許しなさろうとの御内意があったのに、わたし一人が反対を申し上げても、どんなものかと思いよりましたことですが、のちのちまで面白からぬお身の上を、あなたご自身の過ちではないので、天命を恨んでお世話してまいりましたが、とてもこのような相手にとってもあなたにとっても、いろいろと聞きにくい噂が加わって来ましょうが、そうなっても、世間の噂を知らない顔をして、せめて世間並のご夫婦としてお暮らしになれるのでしたら、自然と月日が過ぎて行くうちに、心の安まる時が来ようかと、思う気持ちにもなりましたが、この上ない薄情なお心の方でございますね」
|
院の陛下がお乗り気になりまして許容をあそばす御意志をあちらの大臣へまずもってお示しになったものですから、私一人が御反対をいたし続けるのもいかがかと思いまして、負けてしまいましたのですが、予想してすでに御幸福なように思われませんでしたことは皆そのとおりでお気の毒なあなた様にしてしまいましたことを、私自身の過失ではないのですが、天を仰いで歎息しておりました。その上また今度のことでございます。あの方のためにも、あなた様のためにも、これは世間が騒ぐはずのことですから、どんなに堪えがたい誹謗の声を忍ばなければならぬかしれませんが、しかしそれはしいて忘れることにいたしましても、あの人の愛情さえ深ければながい月日のうちには見よいことにもなろうかと、私はしいて思おうとするのですが、まったく冷淡な人でございますね」
|
【この父大臣】- 落葉宮の夫の父親である致仕太政大臣。
【許いたまふべき御けしき】- 朱雀院の御内意。
【思ひ寄りはべりし】- 大島本は「おもひより」とある。『集成』『新大系』は底本のままとする。『完本』は諸本に従って「思ひ弱り」と「わ」を補訂する。
【大空をかこちて見たてまつり過ぐすを】- 『異本紫明抄』は「身の憂きを世の憂きとのみながむればいかに大空苦しかるらむ」(出典未詳)を指摘。『源注拾遺』は「世の中はいかに苦しと思ふらむここらの人に恨みらるれば」(古今集雑体、一〇六二、在原元方)「大空は恋しき人の形見かはもの思ふごとに眺めらるらむ」(古今集恋四、七四三、境人実)を指摘。『評釈』は「逢ふことはいとど雲居の大空に立つ名のみしてやみぬばかりか」(後撰集恋一、五三五、読人しらず)を指摘する。
【よその御名をば】- 世間でのあなたの評判、の意。
【世の常の御ありさまにだにあらば】- 世間並の夫婦、の意。副助詞「だに」せめて--だけでも、という最低限のニュアンスを添える。
|
| 3.5.7 |
|
と、ほろほろとお泣きになる。
|
と言い続けて御息所は泣くのであった。
|
【つぶつぶと泣きたまふ】- 『集成』は「かきくどいて」。『完訳』は「しきりに涙をおこぼしになる」と訳す。
|
|
第六段 御息所死去す
|
| 3.6.1 |
|
ほんとうにどうしようもなく独りぎめにしておっしゃるので、抗弁して申し開きをする言葉もなくて、ただ泣いていらっしゃる様子、おっとりとしていじらしい。
じっと見つめながら、
|
あった事実と独断してこう言うのを、御弁明あそばすこともおできにならない宮が、ただ泣いておいでになる御様子は、おおようで可憐なものであった。御息所はじっと宮をながめながら、
|
【いとわりなくおしこめてのたまふを】- 主語は御息所。
【ただうち泣きたまへるさま】- 落葉宮の様子。
【うちまもりつつ】- 主語は御息所。
|
| 3.6.2 |
|
「ああ、どこが、人に劣っていらっしゃろうか。
どのようなご運命で、心も安まらず、物思いなさらなければならない因縁が深かったのでしょう」
|
「あなたはどこが人より悪いのでしょう。そんなことは絶対にない。何という運命でこうした御不幸な目にばかりおあいになるのだろう」
|
【あはれ、何ごとかは】- 以下「契り深かりけむ」まで、御息所の詞。「何ごとかは--劣りたまへる」反語表現。
【いかなる御宿世にて】- 疑問表現。前世の因果を思う。
|
| 3.6.3 |
|
などとおっしゃるうちに、ひどくお苦しみになる。
物の怪などが、このような弱り目につけ込んで勢いづくものだから、急に息も途絶えて、見る見るうちに冷たくなっていかれる。
律師も騷ぎ出しなさって、願などを立てて大声でお祈りなさる。
|
などと言っているうちに御息所の容体は最悪なものになっていった。物怪などというものもこうした弱り目に暴虐をするものであるから、御息所の呼吸はにわかにとまって、身体は冷え入るばかりになった。律師もあわてて願などを立て、祈祷に大声を放っているのである。
|
【のたまふままに】- 連語「ままに」、同時進行の意。おっしゃっているうちに。
【もののけなども、かかる弱目に所得るものなりければ】- 『湖月抄』は「地」と注す。
【願など立て】- 蘇生の願文。
|
| 3.6.4 |
深き誓ひにて、今は命を限りける山籠もりを、かくまでおぼろけならず出で立ちて、壇こぼちて帰り入らむことの、面目なく、仏もつらくおぼえたまふべきことを、心を起こして祈り申したまふ。宮の泣き惑ひたまふこと、いとことわりなりかし。 |
深い誓いを立てて、命果てるまでと決心した山籠もりを、こんなにまで並々の思いでなく出てきて、壇を壊して退出することが、面目なくて、仏も恨めしく思わずいはいらっしゃれない趣旨を、一心不乱にお祈り申し上げなさる。
宮が泣き取り乱していらっしゃること、まことに無理もないことではある。
|
御仏に約して、自身の生存する最後の時まで下山せず寺にこもると立てた堅い決心をひるがえして、この人を助けようとする自分の祈祷が効を奏せずに失敗して山へ帰るほど不名誉なことはなくて、その場合には御仏さえも恨むであろうことを言葉にして祈っているのである。宮が泣き惑うておいでになるのもごもっともなことに思われた。
|
【深き誓ひにて】- 以下「仏もつらくおぼえたまふべきこと」まで、願文の趣旨。
【出で立ちて、壇こぼちて】- 最初の接続助詞「て」逆接用法、後出の接続助詞「て」順接用法。「壇壊つ」は、修法の護摩壇。加持の僧侶は効験がないと判断すると護摩壇を壊して帰山する。
|
|
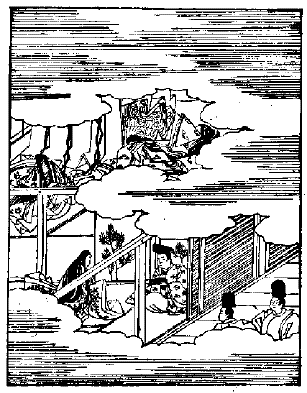 |
| 3.6.5 |
|
このように騒いでいる最中に、大将殿からお手紙を受け取ったと、かすかにお聞きになって、今夜もいらっしゃらないらしい、とお聞きになる。
|
この騒ぎの中で、大将の消息が来たという者の声を、御息所はほのかに聞いてそれでは今夜も来ないのであろうと思った。
|
【ほのかに聞きたまひて】- 主語は御息所。『完訳』は「御息所は少し意識を回復する」と注す。
【今宵もおはすまじきなめり】- 御息所の心中。
|
| 3.6.6 |
|
「情けない。
世間の話の種にも引かれるに違いない。
どうして自分まであのような和歌を残したのだろう」
|
情けないことである、こうした恥ずかしい名を宮はまたお受けになるのであろう、自分までがなぜ受け入れるふうな手紙などを書いてやったのであろう
|
【心憂く。世のためしにも】- 以下「残しけむ」まで、御息所の心中。「世の例」は、『完訳』は「皇女なのに一夜で男に捨てられる例」と注す。
【さる言の葉を】- 夕霧に贈った手紙、特に「女郎花」の歌をさす。
|
| 3.6.7 |
|
と、あれこれとお思い出しなさると、そのまま息絶えてしまわれた。
あっけなく情けないことだと言っても言い足りない。
昔から、物の怪には時々お患いになさる。
最期と見えた時々もあったので、「いつものように物の怪が取り入ったのだろう」と考えて、加持をして大声で祈ったが、臨終の様子は、明らかであったのだ。
|
と悶えるうちに御息所の命は終わった。悲しいことである。昔から物怪のためにたびたび大病をしてもうだめなように見えたこともおりおりあったのであるから、また物怪が一時的に絶息をさせたのかもしれぬと僧たちは加持に力を入れたのであるが、今度はもう何の望みもなく終焉の体はいちじるしかった。
|
【あへなくいみじと言へばおろかなり】- 『全集』は「語り手のことば」と注す。
【例のごと取り入れたるなめり】- 僧たちの心中。『集成』は「いつものように物の怪が気を失わせたのだろうと」。『完訳』は「物の怪が魂を奪って、自分のほうに取り込める意」と注す。
|
| 3.6.8 |
|
宮は、一緒に死にたいとお悲しみに沈んで、ぴったりと添い臥していらっしゃった。
女房たちが参って、
|
宮はともに死にたいと思召す御様子でじっと母君の遺骸に身を寄せておいでになった。女房たちがおそばに来て、
|
【人びと参りて】- 女房たち。
|
| 3.6.9 |
|
「もう、何ともしかたありません。
まことこのようにお悲しみになっても、定められた運命の道は、引き返すことはできるものでありません。
お慕い申されようとも、どうしてお思いどおりになりましょう」
|
「もういたしかたがございません。そんなにお悲しみになりましても、お死にになった方がお帰りになるものでございません。お慕いになりましてもあなた様のお思いが通るものでもございません」
|
【今は、いふかひなし】- 以下「御心にはかなふべき」まで、女房の詞。
【限りある道は】- 『集成』は「きまった運命の死出の旅路では」。『完訳』は「決められた死出の御旅路から」と訳す。
【いかでか】- 「--かなふべき」反語表現。
|
| 3.6.10 |
と、さらなることわりを聞こえて、
|
と、言うまでもない道理を申し上げて、
|
とわかりきった生死の別れをお説きして、
|
|
| 3.6.11 |
|
「とても不吉です。
亡くなったお方にとっても、罪深いことです。
もうお離れなさいまし」
|
「こうしておいであそばすことは非常によろしくないことでございます。お亡れになりました方をお迷わせすることになりますから、あちらへおいであそばせ」
|
【いとゆゆしう】- 以下「去らせたまへ」まで、女房の詞。
【亡き御ためにも、罪深きわざなり】- 『完訳』は「死者に執して後を追うようなのは、死者の成仏を妨げるとする」と注す。
|
| 3.6.12 |
と、引き動かいたてまつれど、すくみたるやうにて、ものもおぼえたまはず。
|
と、引き動かし申し上げるが、身体もこわばったようで、何もお分かりにならない。
|
お引き立て申して行こうとするのであるが、宮のお身体はすくんでしまって御自身の思召すようにもならないのであった。
|
|
| 3.6.13 |
|
修法の壇を壊して、ばらばらと出て行くので、しかるべき僧たちだけ、一部の者が残ったが、今は全てが終わった様子、まことに悲しく心細い。
|
祈祷の壇をこわして僧たちは立ち去る用意をしていた。少数の者だけはあとへ残るであろうが、そうしたことも心細く思われた。
|
【さるべき限り、片へこそ立ちとまれ】- 『集成』は「しかるべき僧たちだけ。近親者とともに三十日の忌に篭る僧たちであろう」、完訳「葬儀を行うべき人々だけ。三十日の忌に篭る僧たちか」と注す。係助詞「こそ」--「とまれ」係結び、逆接用法。
【いと悲しう心細し】- 『評釈』は「第三者として眺めている作者(物語の語り手)の判断なのである。この語はなくてもよい。しかし語り手はつぶやかずにはいられないのだ」と注す。
|
|
第七段 朱雀院の弔問の手紙
|
| 3.7.1 |
所々の御弔ひ、いつの間にかと見ゆ。
大将殿も、限りなく聞き驚きたまうて、まづ聞こえたまへり。
六条の院よりも、致仕の大殿よりも、すべていとしげう聞こえたまふ。
山の帝も聞こし召して、いとあはれに御文書いたまへり。
宮は、この御消息にぞ、御ぐしもたげたまふ。
|
あちこちからのご弔問、いつの間に知れたのかと見える。
大将殿も、限りなく驚きなさって、さっそくご弔問申し上げなさった。
六条院からも、致仕の大臣からも、皆々頻繁にご弔問申し上げなさる。
山の帝もお聞きあそばして、まことにしみじみとしたお手紙をお書きなさっていた。
宮は、このお手紙には、おぐしをお上げなさる。
|
ほうぼうから弔問の使いが来た。いつの間に知ったかと思われるほどである。夕霧の大将は非常に驚いてさっそく使いを立てた。六条院からも太政大臣家からも来た。ひっきりなしにそうした使いが来るのである。御寺の院もお聞きになって、御愛情のこもったお手紙を宮へお書きになった。この御消息が参ったことによって、悲しみにおぼれておいでになった宮もはじめて頭をお上げになったのであった。
|
|
| 3.7.2 |
|
「長らく重く患っていらっしゃるとずっと聞いていましたが、いつも病気がちとばかり聞き馴れておりましたので、つい油断しておりました。
言ってもしかたのないことはそれとして、お悲しみ嘆いていらっしゃるだろう有様、想像するのがお気の毒でおいたわしい。
すべて世の中の定めとお諦めになって慰めなさい」
|
いつかから病気がだいぶ重いということは聞いていましたが、平生から弱い人だったために、つい怠って尋ねてあげることもしませんでした。故人の死をいたむことはむろんですが、あなたがどんなに悲しんでおられるだろうと、それを最も私は心苦しく思います。死はだれも免れないものであるからという道理を思って心を平静にしなさい。
|
【日ごろ重く悩みたまふと】- 以下「思し慰めたまへ」まで、朱雀院から落葉の宮への弔問の手紙文。
【うちたゆみてなむ】- 係助詞「なむ」の下に「はべりける」などの語句が省略。余意余情の効果表現。
【思ひ嘆いたまふらむありさま】- 『完訳』は「御息所の死よりも、宮の悲嘆ぶりを想像して同情する」と注す。
【なべての世のことわりに思し慰めたまへ】- 『集成』は「世間の人誰しも逃れられぬ(無常の)道理なのだと、お心をお慰めなさい。出家人らしい言い方」と注す。
|
| 3.7.3 |
とあり。
目も見えたまはねど、御返り聞こえたまふ。
|
とある。
目もお見えにならないが、お返事は申し上げなさる。
|
とあった。宮は涙でお目もよく見えないのであるが、このお返事だけはお書きになった。
|
|
| 3.7.4 |
|
普段からそうして欲しいとおっしゃっていたことなので、今日直ちに葬儀を執り行い申すことになって、御甥の大和守であった者が、万事お世話申し上げたのであった。
|
平生からすぐに遺骸は火葬にするようにと御息所は遺言してあったので、葬儀は今日のうちにすることになって、故人の甥の大和守である人が万端の世話をしていた。
|
【さこそあらめ】- 御息所の遺言の趣旨。死後すぐに葬られることを希望していた。地の文で語る。
【今日やがてをさめたてまつるとて】- 『完訳』は「当時は蘇生を期待して葬儀を延ばすのが普通」と注す。当時の葬儀(火葬)は夜に行われた。
【御甥の大和守にてありけるぞ】- 御息所の甥の大和守。『完訳』は「大和守(従五位上)が親類縁者の代表だけに、家柄の低い一族と知れる」と注す。
|
| 3.7.5 |
|
せめて亡骸だけでも暫くの間拝していたいと思って、宮は惜しみ申し上げなさったが、いくら別れを惜しんでもきりがないので、皆準備にとりかかって、忌中の最中に、大将がいらっしゃった。
|
亡骸だけでもせめて見ていたいと宮はお惜しみになるのであったが、そうしたところでしかたのないことであると皆が申し上げて、入棺などのことをしている騒ぎの最中に左大将は来た。
|
【骸をだにしばし見たてまつらむとて】- 『伊行釈』は「空蝉はからを見つつも慰めつ深草の山煙だに立て」(古今集哀傷、八三一、僧都勝延)を指摘。
【宮は惜しみきこえたまひけれど】- 『集成』は「葬儀の日延べを希望する趣」と注す。
|
| 3.7.6 |
|
「今日から後は、日柄が悪いのだ」
|
「今日弔問に行っておかないでは、あとは皆、そうしたことに私の携われない暦になっているから」
|
【今日より後、日ついで悪しかりけり】- 夕霧の詞。『完訳』は「以下、時間を遡って、夕霧が自邸を出る様子。弔問に赴く口実」と注す。場面は夕霧の三条殿。
|
| 3.7.7 |
|
などと、人前ではおっしゃって、とても悲しくしみじみと、宮がお悲しみであろうことをご推察申し上げなさって、
|
などと、表面は言って、心の中では宮のお悲しみが悲しく想像され、少しでも早く小野へ行きたく思っているのに、
|
【宮の思し嘆くらむことを推し量りきこえたまうて】- 夕霧の心中。「人聞きには」と対照させて語る。推量の助動詞「らむ」視界外推量や「推し量りきこえ」などに、これから出向く様子がうかがえる。
|
| 3.7.8 |
|
「こんなに急いでお出掛けになる必要はありません」
|
「そんなにまですぐにお駆けつけになるほどの御関係でもないではございませんか」
|
【かくしも急ぎわたりたまふべきことならず】- 女房の詞。特別に御息所の縁者でもない夕霧が急いで弔問に出かける必要はない、という。
|
| 3.7.9 |
と、人びといさめきこゆれど、しひておはしましぬ。
|
と、女房たちがお引き止め申したが、無理にいらっしゃった。
|
と家従たちが諫めるのを退けてしいて出て来たのである。
|
|
|
第八段 夕霧の弔問
|
| 3.8.1 |
|
道のりまでも遠くて、山麓にお入りになるころ、じつにぞっとした気がする。
不吉そうに幕を引き廻らした葬儀の方は目につかないようにして、この西面にお入れ申し上げる。
大和守が出て来て、泣きながら挨拶を申し上げる。
妻戸の前の簀子に寄り掛かりなさって、女房をお呼び出しなさるが、伺候する者みな、悲しみも収まらず、何も考えられない状態である。
|
しかも遠距離ですぐにも行き着くことのできない道は夕霧をますます悲しませたのであった。山荘は凄惨の気に満ちていた。最後の式の行なわれる所は仕切りで隠して人々は例の西の縁側のほうへ大将にまわってもらった。妻戸の前の縁側によりかかって夕霧は女房を呼び出したが、だれも皆平静な気持ちでいる者はないのである。
|
【ほどさへ遠くて】- 副助詞「さへ」添加の意。『完訳』は「気がせくうえ、道のりまでも」と注す。
【ゆゆしげに引き隔てめぐらしたる儀式の方は隠して】- 死の穢れを忌むために祭場との間に幕が引き廻らされている。
【この西面に】- 落葉宮が居間として使っている部屋。
【妻戸の簀子におし掛かりたまうて】- 主語は夕霧。妻戸の前の簀子の高欄に寄り掛かった姿。
【女房呼び出でさせたまふに】- 「させ」使役の助動詞。接続助詞「に」逆接用法。
|
| 3.8.2 |
|
このようにお越しになったので、すこし気持ちもほっとして、小少将の君は参った。
何もおっしゃることができない。
涙もろくはいらっしゃらない気丈な方であるが、場所柄、人の様子などをお思いやりになると、ひどく悲しくて、無常の世の有様が、他人事でもないのも、まことに悲しいのであった。
少し気を落ち着けてから、
|
大将が来たことで少し慰められるところがあって少将が応接に出た。夕霧も急にものは言えないのであった。すぐ泣くふうの人ではないのであるが、ここの悲しい空気に人々の様子も想像されて無常の世の道理も自身に近い人の上に実証されたことにひどく心を打たれているのである。ややしばらくして、
|
【少将の君は参る】- 落葉の宮づきの女房、小少将の君。夕霧の前に出る。
【涙もろにおはせぬ心強さなれど】- 夕霧の性格。感傷的でなく意志がしっかりしている性格。理性的で頑迷な性格。
【所のさま、人のけはひなどを】- 『完訳』は「小野という場所柄、宮の悲嘆する様子などを。狭い山荘で、隣室の様子も感取。「けはひ」に注意」と注す。
【ややためらひて】- 主語は夕霧。
|
| 3.8.3 |
「よろしうおこたりたまふさまに承りしかば、思うたまへたゆみたりしほどに。夢も覚むるほどはべなるを、いとあさましうなむ」 |
「好くおなりになったように承っておりましたので、油断しておりました時に。
夢でも醒める時がございますというのに、何とも思いがけないことで」
|
「少しおよろしいように伺ったものですから、安心していたのですが、何たることが起こったのでしょう。どんな悪夢でもさめる時はあるのですが、これはそうした希望も持てませんことを悲しく思います」
|
【よろしうおこたりたまふさまに】- 以下「あさましうなむ」まで、夕霧の詞。
|
| 3.8.4 |
と聞こえたまへり。「思したりしさま、これに多くは御心も乱れにしぞかし」と思すに、さるべきとは言ひながらも、いとつらき人の御契りなれば、いらへをだにしたまはず。 |
と申し上げなさった。
「ご心痛であったご様子、この方のために多くはお心も乱れになったのだ」とお思いになると、そうなる運命とはいっても、まことに恨めしい人とのご因縁なので、お返事さえなさらない。
|
と宮への御挨拶を申し入れた。御息所が煩悶していたことをお思いになって、大将が原因で免れがたい運命とはいえ母君はお亡くなりになったとお思いになると、恨めしい因縁の人の弔問に宮はお返辞すらあそばさない。
|
【思したりしさま】- 以下「乱れにしぞかし」まで、落葉宮の心中。「思したりし」の主語は御息所。
|
| 3.8.5 |
|
「どのように申し上げあそばしたかと、申し上げましょうか」
|
「どう仰せられますと申し上げればよろしゅうございましょう。
|
【いかに聞こえさせたまふとか】- 以下「あまりにはべりぬべし」まで、女房たちの詞。
|
| 3.8.6 |
|
「とても重々しいご身分で、このように遠路急いでお越しになったご厚志を、お分かりにならないようなのも、あまりというものでございましょう」
|
重いお身柄をお忘れになってすぐにこの遠い所をお弔みにおいでくださいました御好意を無視あそばすようなお扱いもあまりでございましょうから」
|
【いと軽らかならぬ御さまにて】- 夕霧をさす。近衛大将。遠路はるばる自ら急いで弔問に訪れたことをいう。
|
| 3.8.7 |
と、口々聞こゆれば、
|
と、口々に申し上げるので、
|
女房が口々に言うと、
|
|
| 3.8.8 |
|
「ただ、よいように返事せよ。
わたしはどう言ってよいか分かりません」
|
「いいかげんに言っておくがいい。何を何と言っていいか今はそんなこともわからない」
|
【ただ、推し量りて】- 以下「言ふべきこともおぼえず」まで、落葉宮の詞。『集成』は「そなたたちのはからい次第に。よいように返事せよ、の意」。『完訳』は「私の気持を察して。宮は、母の死は夕霧との一件ゆえと思うので、応対する気にもなれない」と注す。
|
| 3.8.9 |
とて、臥したまへるもことわりにて、
|
とおっしゃって、臥せっていらっしゃるのも道理なので、
|
宮がこう言って横になっておしまいになったのももっともなこの場合のことであったから、女房が、
|
|
| 3.8.10 |
|
「ただ今は、亡き人と同然のご様子でありまして。
お出あそばしました旨は、お耳に入れ申し上げました」
|
「ただ今のところ宮様はお亡れになった方同然でいらっしゃいます。おいでくださいましたことは申し上げておきました」
|
【ただ今は】- 以下「聞こえさせはべりぬ」まで、小少将の君の詞。
【御ありさまにてなむ】- 係助詞「なむ」の下に「おはす」などの語句が省略された形。
|
| 3.8.11 |
と聞こゆ。
この人びともむせかへるさまなれば、
|
と申し上げる。
この女房たちも涙にむせんでいる様子なので、
|
と夕霧へ言った。この人たちは涙にむせかえっているのであるから、
|
|
| 3.8.12 |
|
「お慰め申し上げようもありませんが。
もう少し、私自身も気が静まって、またお静まりになったころに、参りましょう。
どうしてこのように急にと、そのご様子が知りたい」
|
「何とも申し上げようのないことですから、私の心も少し落ち着き、宮様の御気分もお静まりになったころにまた参りましょう。どうしてそんな急変が来たのか、私はその理由だけを知りたい」
|
【聞こえやるべき方もなきを】- 以下「なむゆかしき」まで、夕霧の詞。
【いかにしてかくにはかに】- 主語は御息所。
|
| 3.8.13 |
とのたまへば、まほにはあらねど、かの思ほし嘆きしありさまを、片端づつ聞こえて、
|
とおっしゃると、すっかりではないが、あのお悩みになり嘆いていた様子を、少しずつお話し申し上げて、
|
と大将は女房に言った。露骨には言わないが少将は御息所の煩悶した一昼夜のことを少し夕霧に知らせて、
|
|
| 3.8.14 |
|
「恨み言を申し上げるようなことに、きっとなりましょう。
今日は、いっそう取り乱したみなの気持ちのせいで、間違ったことを申し上げることもございましょう。
それゆえ、このようにお悲しみに暮れていらっしゃるご気分も、きりのあるはずのことで、少しお静まりあそばしたころに、お話を申し上げ承りましょう」
|
「そう申してまいればお恨み言になっていけません。今日は頭が混乱しておりまして間違ってお話し申し上げることがあるかもしれません。それでは宮様のお悲しみもいずれはおあきらめにならなければならないことでございますから、御気分のお落ち着きになりますころにまたおいでくださいまし」
|
【かこちきこえさする】- 以下「聞こえさせ承らむ」まで、小少将の君の詞。「かこちきこえさする」の相手は夕霧。
【乱りがはしき心地どもの惑ひに】- 女房たちの「心惑ひ」複数形。
【さらば、かく】- 『集成』は「夕霧が「またしづまりたまひなむに、参り来む」と、辞去する旨を告げたのに応ずる」と注す。
【思し惑へる御心地も】- 落葉宮の悲しみの気持ち。
【聞こえさせ承らむ】- 主語は小少将君。小少将君が落葉宮に夕霧の言葉をお話し申し上げ宮の返事を承りましょう、の意。
|
| 3.8.15 |
とて、我にもあらぬさまなれば、のたまひ出づることも口ふたがりて、
|
と言って、正気もない様子なので、おっしゃる言葉も口に出ず、
|
と言った。その人たちも気を顛倒させている様子を見ては、大将も言いたいことが口から出ない。
|
|
| 3.8.16 |
|
「なるほど、闇に迷った気がします。
やはり、お慰め申し上げなさって、わずかのお返事でもありましたら」
|
「私の心なども暗闇になったように思われるのですから、宮様としてはごもっともです。極力お慰め申し上げて、あなたがたの力で今後少しのお返事でもいただけるように計らってください」
|
【げにこそ】- 以下「御返りもあらばなむ」まで、夕霧の詞。『完訳』は「小少将の言葉を受け、宮と同様に自分も悲嘆が深いとする」と注す。
【聞こえ慰めたまひて】- 主語はあなた、小少将君が落葉宮を。
【御返りもあらばなむ】- 係助詞「なむ」の下に「うれしく思ふ」などの語句が省略。
|
| 3.8.17 |
|
などと言い残しなさって、ぐずぐずしていらっしゃるのも、身分柄軽々しく思われ、そうはいっても人目が多いので、お帰りになった。
|
などと言いおいて、長い立ち話をしていることもさすがに出入りの人の多い今日の山荘では軽々しく見られることであろうとはばかって大将は帰ることにした。
|
【立ちわづらひたまふも、軽々しう】- 『完訳』は「葬儀当日、縁者でもないのにぐずぐずしている自分を、高貴の身分柄、軽率と反省」と注す。夕霧の心中を地の文で語る。
|
|
第九段 御息所の葬儀
|
| 3.9.1 |
|
まさか今夜ではあるまいと思っていた葬儀の準備が、実に短時間にてきぱきと整えられたのを、いかにもあっけないとお思いになって、近くの御荘園の人々をお呼びになりお命じになって、しかるべき事どもをお仕えするように、指図してお帰りになった。
事が急なので、簡略になりがちであったのが、盛大になり、人数も多くなった。
大和守も、
|
今夜のうちに済ませるために納棺その他のことを着々進行させている物音にも、盛大ならぬ葬儀の悲哀が感ぜられて、大将はこの近くにある自家の荘園から侍たちを招いて、いろいろな役を分担して助けることを命じていった。急なことであったから自然簡単で済ませることになった葬儀が、これによって外見をきわめてよくすることができるようになった。大和守も、
|
【今宵しもあらじと思ひつる】- 主語は夕霧。以下「いとあへなし」まで、夕霧の心中に即して語る。
【近き御荘の人びと】- 夕霧の荘園、栗栖野の人々。
【添ひてなむ】- 係助詞「なむ」の下に「ありける」などの語句が省略。
|
| 3.9.2 |
|
「有り難い殿のお心づかいだ」
|
「すべて殿様のありがたい御親切のおかげでございます」
|
【ありがたき殿の御心おきて】- 大和守の詞。『集成』は「めったにない大将殿(夕霧)のご配慮です」。『完訳』は「願ってもない殿のご配慮で」と訳す。
|
| 3.9.3 |
|
などと、喜んでお礼申し上げる。
「跡形もなくあっけないこと」と、宮は身をよじってお悲しみになるが、どうすることもできない。
親と申し上げても、まことにこのように仲睦まじくするものではないのだった。
拝見する女房たちも、このご悲嘆を、また不吉だと嘆き申し上げる。
大和守は、後始末をして、
|
と感謝していた。母君を何も残らぬ無にしておしまいになったことで、宮は伏し転んで悲しんでおいでになった。親は子にこのかたがたのような片時離れぬ習慣はつけておくべきでないと思い、宮のこの御状態を女房たちはまた歎き合った。大和守が葬儀の跡の始末を皆してから、
|
【名残だになくあさましきこと】- 落葉宮の心中。
【親と聞こゆとも、いとかくはならはすまじきものなりけり】- 『完訳』は「語り手の言辞。親子の間柄とはいえ、異常に仲睦まじくしすぎたために、こうも悲嘆しなければならないのだ」と注す。真淵『新釈』は「思ふとていとこそ人に馴れざらめしかならひてぞ見ねば恋しき」(拾遺集恋四、九〇〇、読人しらず)を指摘。
|
| 3.9.4 |
|
「このように心細い状態では、いらっしゃれまい。
とてもお心の紛れることはありますまい」
|
「こんなふうになさいまして、まだながく寂しい山荘においでになることは御無理です。いっそうお悲しみが紛れないことになりましょう」
|
【かく心細くては】- 以下「心の隙あらじ」まで、大和守の詞。
|
| 3.9.5 |
|
などと申し上げるが、やはり、せめて峰の煙だけでも、側近くお思い出し申そうと、この山里で一生を終わろうとお考えになっていた。
|
などと宮へ申し上げるのであったが、宮は母君の煙におなりになった場所にせめて近くいたいと思召す心から、このままここへ永住あそばすお考えを持っておいでになった。
|
【なほ、峰の煙をだに】- 以下「住み果てなむ」まで、落葉宮の心中に即した地の文。
|
| 3.9.6 |
|
御忌中に籠もっていた僧は、東面や、そちらの渡殿、下屋などに、仮の仕切りを立てて、ひっそりとしていた。
西の廂の間の飾りを取って、宮はお住まいになる。
日の明け暮れもお分かりにならないが、いく月かが過ぎて、九月になった。
|
忌中だけこもっている僧たちは東の座敷からそちらの廊の座敷、下屋までを使って、わずかな仕切りをして住んでいた。西の端の座敷を急ごしらえの居間にして宮はおいでになるのである。朝になることも夜になることも宮は忘れておいでになるうちに日がたって九月になった。
|
【御忌に籠もれる】- 『集成』は「死穢のため、三十日間、近親者が忌に籠る」。『完訳』は「喪中の四十九日間」と注す。
【そなたの渡殿】- 「そなた」は寝殿の西表と西の対を結ぶ方面をさす。
【月ごろ経ければ、九月になりぬ】- 一条御息所の逝去は八月二十日ごろであった。八月九月と両月にわたるので、「月ごろ」といったもの。
|
|
第四章 夕霧の物語 落葉宮に心あくがれる夕霧
|
|
第一段 夕霧、返事を得られず
|
| 4.1.1 |
|
山下ろしがたいそう烈しく、木の葉の影もなくなって、何もかもがとても悲しく寂しいころなので、だいたいがもの悲しい秋の空に催されて、涙の乾く間もなくお嘆きになり、「命までが思いどおりにならなかった」と、厭わしくひどくお悲しみになる。
伺候する女房たちも、何かにつけ悲しみに暮れていた。
|
山おろしが烈しくなり、もう葉のない枝は防風林でも皆なくなった。寂しさの身にしむこの季節のことであるから、空の色にも悲しみが誘われて、宮は歎きを続けておいでになる。命さえも思うどおりにならぬと悲しんでおいでになるのであった。女房たちも二重三重に悲しみをするばかりである。
|
【山下ろしいとはげしう、木の葉の隠ろへなくなりて、よろづの事いといみじきほどなれば】- 九月の小野山里の様子。いちはやく晩秋を迎えた風情。
【干る間もなく思し嘆き】- 涙の乾く間もなく、の意。
【命さへ心にかなはず」と】- 『異本紫明抄』は「命だに心にかなふものならば何か別れの悲しからまし」(古今集離別、三八七、白女)を指摘。『集成』は「意味するところは逆だが、この歌を踏んだものか」と注す。『河海抄』は「命さへ心にかなふものならば死には安くぞあるべかりける」(出典未詳)を指摘。『源注拾遺』は「恋しきに命をかふるものならば死には安くぞあるべかりける」(古今集恋一、五一七、読人しらず)も指摘する。
|
| 4.1.2 |
|
大将殿は、毎日お見舞いの手紙を差し上げなさる。
心細げな念仏の僧などが、気の紛れるように、いろいろな物をお与えになりお見舞いなさり、宮の御前には、しみじみと心をこめた言葉の限りを尽くしてお恨み申し上げ、一方では、限りなくお慰め申し上げなさるが、手に取って御覧になることさえなく、思いもしなかったあきれた事を、弱っていらしたご病状に、疑う余地なく信じこんで、お亡くなりになったことをお思い出しになると、「ご成仏の妨げになりはしまいか」と、胸が一杯になる心地がして、この方のお噂だけでもお耳になさるのは、ますます恨めしく情けない涙が込み上げてくる思いが自然となさる。
女房たちもお困り申し上げていた。
|
夕霧からは毎日のようにお見舞いの手紙が送られた。寂しい念仏僧を喜ばせるに足るような物もしばしば贈られた。宮へは真心の見える手紙を次々にお送りして、自分の恋に対して御冷淡である恨みを語るほかには、今も御息所の死を悲しむ真情を言い続けた消息であった。しかも宮はそれらを手に取ってながめようともあそばさないのである。あのいまわしかった事件を、衰弱しきった病体で御息所は確かに悲しみもだえて死んだことをお思いになると、そのことが母君の後世の妨げにもなったような気があそばされて、悲しさが胸に詰まるほどにも思召されるのであるから、大将に触れたことを言うと、その人を恨めしく思召してお泣きになるのを見て、女房たちも手の出しようがないのである。
|
【大将殿は、日々に訪らひきこえ】- お見舞いの使者を差し向ける、の意。
【念仏の僧など、慰むばかり】- 『集成』は「一息つけるようにと」。『完訳』は「気が紛れるようにと」と訳す。
【取りてだに御覧ぜず】- 主語は落葉宮。夕霧からの手紙を手に取りさえしない。
【すずろにあさましき】- 以下、落葉宮の心中に即した叙述。『集成』は「以下、落葉の宮の思い」。『完訳』は「以下、心内語に転ずる」と注す。夕霧との一件をさす。
【弱れる御心地に】- 御息所の病状をいう。
【後の世の御罪にさへやなるらむ】- 成仏の妨げ、の意。
|
| 4.1.3 |
一行の御返りをだにもなきを、「しばしは心惑ひしたまへる」など思しけるに、あまりにほど経ぬれば、 |
ほんの一行ほどのお返事もないのを、「暫くの間は気が転倒していらっしゃるのだ」などとお考えになっていたが、あまりに月日も過ぎたので、
|
一行のお返事さえ得られないのを、初めの間は悲しみにおぼれておいでになるからであろうと大将は解釈していたが、今に至るも同じことであるのを見ては、
|
【心惑ひしたまへる】- 夕霧の心中を地の文に語る。
|
| 4.1.4 |
|
「悲しい事でも限度があるのに。
どうして、こんなに、
あまりにお分かりにならないことがあろうか。言いようもなく子供のようで」と恨めしく、「これとは筋違いに、花や蝶だのと書いたのならともかく、自分の気持ちに同情してくれ、悲しんでいる状態を、いかがですかと尋
|
どんな悲しみにも際限はあるはずであるのに、今になってもまだ自分の音信に取り合わぬ態度をお続けになるのはどうしたことであろう、あまりに人情がおわかりにならぬと恨めしがるようになった。関係もないことをただ文学的につづり、花とか蝶とか言っているのであったなら、冷眼に御覧になることもやむをえないことであるが、自身の悲しいことに同情して音信をする人には、親しみを覚えていただけるわけではないか、
|
【悲しきことも】- 以下「若々しきやうに」まで、夕霧の心中。
【若々しきやうに】- 『完訳』は「結婚の経験があるのに、世間知らずのようではないか、の気持」と注す。
【異事の筋に】- 以下「なつかしうおぼえし」まで、夕霧の心中。
【花や蝶やと】- 当時の慣用句。「男女などを寄せつつ、花や蝶やと言へれば」(三宝絵、序)とある。『源注拾遺』は「みな人は花や蝶やと急ぐ日も我が心をば君ぞ知りける」(枕草子)を指摘。
【書けばこそあらめ】- 係助詞「こそ」--「あらめ」逆接用法。書いたのならばともかく、そうではないのに、の意。
【いかにと問ふ人は】- 夕霧自身をさす。
|
| 4.1.5 |
|
大宮がお亡くなりになったのを、実に悲しいと思ったが、致仕の大臣がそれほどにもお悲しみにならず、当然の死別として、世間向けの盛大な儀式だけを供養なさったので、恨めしく情けなかったが、六条院が、かえって心をこめて、後のご法事をもお営みになったのが、自分の父親ということを超えて、嬉しく拝見したその時に、故衛門督を、特別に好ましく思うようになったのだった。
|
祖母の大宮がお亡れになって、自分が非常に悲しんでいる時に、太政大臣はそれほどにも思わないで、だれも経験しなければならぬ尊親の死であるというふうに見ていて、儀式がかったことだけを派手に行なって万事了るという様子であったのに、自分は反感を感じたものだし、かえって昔の婿でおありになった六条院が懇切に身を入れてあとの仏事のことなどをいろいろとあそばされたのに感激したものである。これは自分の父であるというだけで思ったことではない、その時に故人の柏木が自分は好きになったのである。
|
【大宮の亡せたまへりしを】- 夕霧の祖母死去の折。
【公々しき作法ばかり】- 表向きの儀式。『集成』は「源氏も、致仕の大臣の人柄について「人柄あやしうはなやかに、男々しきかたによりて、親などの御孝をも、いかめしきさまをばたてて、人にも見おどろかさむの心あり、まことにしみて深きところはなき人になむものせられける」(野分)と夕霧に語ったことがある」と注す。
【六条院の、なかなかねむごろに】- 『完訳』は「六条院が、実の親でもないのにかえって懇切に」と訳す。
【わが方ざまといふ中にも】- 『集成』は「自分の親というひいき目からだけでなく」と訳す。
【その折に、故衛門督をば、取り分きて思ひつきにしぞかし】- 『完訳』は「柏木が祖母大宮の死を心から哀悼していたので、自分は彼に共感し親しみをおぼえた、の意」と注す。
|
| 4.1.6 |
人柄のいたう静まりて、物をいたう思ひとどめたりし心に、あはれもまさりて、人より深かりしが、なつかしうおぼえし」
|
人柄がたいそう冷静で、何事にも心を深く止めていた性格で、悲しみも深くまさって、誰よりも深かったのが、慕わしく思われたのだ」
|
静かな性質で人情のよくわかる彼は、自分と同じように祖母の宮の死を深く悲しんでいたのに心を惹かれたものであった。
|
|
| 4.1.7 |
など、つれづれとものをのみ思し続けて、明かし暮らしたまふ。
|
などと、所在なく物思いに耽るばかりで、毎日をお過ごしになる。
|
この宮は何という感受性の乏しいお心なのであろうと、こんなことを毎日思い続けていた。
|
|
|
第二段 雲居雁の嘆きの歌
|
| 4.2.1 |
|
女君、やはりこのお二人のご様子を、
|
夫人は山荘の宮と大将の関係はどうなっていたのであろう、
|
【女君、なほこの御仲のけしきを】- 雲居雁、夕霧と落葉宮の関係を疑う。「女君」の述語は「たてまつれたまへる」。
|
| 4.2.2 |
|
「どのような関係だったのだろうか。
御息所と、手紙を遣り取りしていたのも、親密なようになさっていたようだが」
|
御息所とは始終手紙の往復をしていたようであるが
|
【いかなるにかありけむ】- 以下「こまやかにしたまふめりしか」まで、雲居雁の心中。
【こそ、文通はしも】- 係助詞「こそ」は「たまふめりしか」已然形に係る。「文通はし」名詞。
|
| 4.2.3 |
|
などと納得がゆきがたいので、夕暮の空を眺め入って臥せっていらっしゃるところに、若君を使いにして差し上げなさった。
ちょっとした紙の端に、
|
と腑に落ちず思って、夕方空にながめ入って物思いをしている良人の所へ、若君に短い手紙を持たせてやった。ちょっとした紙の端なのである。
|
【夕暮の空を眺め入りて臥したまへるところに】- 文脈は主語が夕霧に変わる。
【若君して】- 夕霧と雲居雁の子。
【はかなき紙の端に】- 『集成』は「ありあわせた」。『完訳』は「これといったことのない紙の端に」と訳す。
|
| 4.2.4 |
|
「お悲しみを何が原因と知ってお慰めしたらよいものか
生きている方が恋しいのか、
|
哀れをもいかに知りてか慰めん
在るや恋しき無きや悲しき
|
【あはれをもいかに知りてか慰めむ--あるや恋しき亡きや悲しき】- 雲居雁から夕霧への贈歌。「ある」は落葉宮をさし、「亡き」は御息所をさす。
|
| 4.2.5 |
|
はっきりしないのが情けないのです」
|
どちらだか私にはわからないのですから。
|
【おぼつかなきこそ心憂けれ】- 歌に添えた言葉。夕霧の本心を知りたいが、はっきりしないのが情けない、の意。
|
| 4.2.6 |
とあれば、ほほ笑みて、
|
とあるので、にっこりとして、
|
夕霧は微笑しながら
|
|
| 4.2.7 |
|
「以前にも、このような想像をしておっしゃる、見当違いな、故人などを持ち出して」
|
嫉妬が夫人にいろいろなことを言わせるものであると思った。
|
【先ざきも、かく】- 大島本は「さま(ま$き)/\も」とある。すなわち「ま」をミセケチにして「き」と訂正する。『集成』『新大系』は底本の訂正に従う。『完本』は底本の訂正以前と諸本に従って「さまざまも」と校訂する。以下「亡きがよそへや」まで、夕霧の心中。
【似げなの、亡きがよそへや】- 『集成』は「「亡きや悲しき」と、自分が御息所の死を悲しんでいるのかもしれないといった言い方は、今さらしらじらしい。落葉の宮とのことをはっきり疑っているくせに、という気持」と注す。『休聞抄』は「むら鳥の立ちにし我が名今さらにことなしぶともしるしあらめや」(古今集恋三、六七四、読人しらず)指摘。
|
| 4.2.8 |
|
とお思いになる。
ますます、何気ないふうに、
|
御息所を対象にしていたろうとはあまりにも不似合いな忖度であると思ったのである。すぐに返事を書いたが、それは実際問題を避けた無事なものである。
|
【いとどしく】- 大島本は「いとゝしく」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「いととく」と校訂する。『新大系』は底本のままとする。
|
| 4.2.9 |
|
「特に何がといって悲しんでいるのではありません
消えてしまう露も草葉の上だけでないこの世ですから
|
何れとも分きて眺めん消えかへる
露も草葉の上と見ぬ世に
|
【いづれとか分きて眺めむ消えかへる--露も草葉のうへと見ぬ世を】- 夕霧から雲居雁への返歌。「ある」「亡き」から「消えかへる露」と詠み返した。『集成』は「落葉の宮のことははぐらかした返歌」。『弄花抄』は「我が宿の菊の垣根におく霜の消えかへりてぞ恋しかりける」(古今集恋二、五六四、紀友則)を指摘。『源注拾遺』は「露をだにあだなるものと思ひけむ我が身も草もおかぬばかりを」(古今集哀傷、八六〇、藤原これもと)を指摘。
|
| 4.2.10 |
|
世間一般の無常が悲しいのです」
|
人生のことがことごとく悲しい。
|
【おほかたにこそ悲しけれ】- 一般論としてはぐらかす。
|
| 4.2.11 |
|
とお書きになっていた。
「やはり、このように隔て心を持っていらっしゃること」と、露の世の悲しさは二の次のこととして、並々ならず胸を痛めていらっしゃる。
|
まだこんなふうに隠しだてをされるのであるかと、人生の悲しみはさしおいて夫人は歎いた。
|
【露のあはれをばさしおきて】- 『集成』は「この世の無常を悲しむなどということは、知ったことではなくて。夕霧の歌の言葉によっていう」。『完訳』は「露の世の悲しみは二の次のこととして」と注す。
|
| 4.2.12 |
|
やはり、このように気がかりでたまらなくなって、改めてお越しになった。
「御忌中などが明けてからゆっくり訪ねよう」と、気持ちを抑えていらっしゃったが、そこまでは我慢がおできになれず、
|
恋しさのおさえられない大将はまたも小野の山荘に宮をお訪ねしようとした。四十九日の忌も過ごしてから静かに事の運ぶようにするのがいいのであるとも知っているのであるが、それまでにまだあまりに時日があり過ぎる、
|
【なほ、かくおぼつかなく思しわびて】- 主語は夕霧。
【御忌など過ぐして】- 『集成』は「三十日の忌籠り」。『完訳』は「忌中の四十九日」と注す。
|
| 4.2.13 |
|
「今はもうこのおん浮名を、どうして無理に隠していようか。
ただ世間一般の男性と同様に、目的を遂げるまでのことだ」
|
もう噂を恐れる必要もない、この際はどの男性でも取る方法で進みさえすれば成り立ってしまう結合であろう
|
【今はこの御なき名の】- 以下「かなふべきにこそは」まで、夕霧の心中。『集成』は「「御」は地の文の気持の混入したもの」。『完訳』は「世間一般の男性と同様に、無遠慮な態度で宮を得ようと居直る」と注す。
|
| 4.2.14 |
|
と、ご計画なさったので、北の方のご想像を、無理に打ち消そうとなさらない。
|
とこんな気になっているのであるから、夫人の嫉妬も眼中に置かなかった。
|
【思したばかりにければ】- 大島本は「おほしたハかりにけれは」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「思したちにけり」と校訂する。『新大系』は底本のままとする。
|
| 4.2.15 |
|
ご本人はきっぱりとお気持ちがなくても、あの「一夜ばかりの宿を」といった恨みのお手紙を理由に訴えて、「潔白を言い張ることは、おできになれまい」と、心強くお思いになるのであった。
|
宮のお心はまだ自分へ傾くことはなくても、「一夜ばかりの」といって長い契りを望んだ御息所の手紙が自分の所にある以上は、もうこの運命からお脱しになることはできないはずであると恃むところがあった。
|
【かの一夜ばかりの御恨み文を】- 御息所からの手紙をさす。『完訳』は「夕霧は、これを拠りどころに宮をくどき、世間にも二人には実事があったとしらしめようとする」と注す。
|
|
第三段 九月十日過ぎ、小野山荘を訪問
|
| 4.3.1 |
|
九月十余日、野山の様子は、十分に分からない人でさえ、何とも思わずにはいられない。
山風に堪えきれない木々の梢も、峰の葛の葉も、気ぜわしく先を争って散り乱れているところに、尊い読経の声がかすかに、念仏などの声ばかりして、人の気配がほとんどせず、木枯らしが吹き払ったところに、鹿は籬のすぐそばにたたずんでは、山田の引板にも驚かず、色の濃くなった稲の中に入って鳴いているのも、もの悲しそうである。
|
九月の十幾日であって、野山の色はあさはかな人間をさえもしみじみと悲しませているころであった。山おろしに木の葉も峰の葛の葉も争って立てる音の中から、僧の念仏の声だけが聞こえる山荘の内には人げも少なく、蕭条とした庭の垣のすぐ外には鹿が出て来たりして、山の田に百姓の鳴らす鳴子の音にも逃げずに、黄になった稲の中で啼く声にも愁いがあるようであった。
|
【九月十余日、野山のけしきは】- 晩秋九月十日過ぎの小野の野山の景色。後文に「十三日の月のいとはなやかにさし出でぬれば」とある。
【ただにやはおぼゆる】- 反語表現。
【山風に堪へぬ木々の梢も、峰の葛葉も、心あわたたしう争ひ散る紛れに】- 『異本紫明抄』は「風はやみ峰の葛葉のともすればあやかりやすき人の心か」(拾遺集哀傷、一二五一、藤原これもと)を指摘。
【木枯の吹き払ひたるに、鹿はただ籬のもとにたたずみつつ】- 『完訳』は「木枯らしが吹きはらうと、鹿は垣根のすぐ近くにたたずんでは」と訳し、前出「に」接続助詞、後出「に」格助詞、に解す。「吹き払ひたる」を準体言と見て両方とも格助詞「に」場所、所を表す意とも解せる。 【たたずみつつ】-「つつ」接続助詞、同じ動作の反復・継続。
【うち鳴くも、愁へ顔なり】- 夕霧の感情移入による表現。『完訳』は「妻を恋い慕って鳴く鹿に、宮を恋い慕う夕霧の心をかたどる」と注す。
|
|
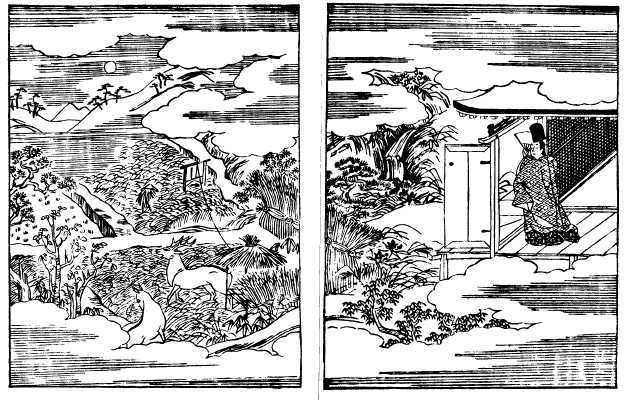 |
| 4.3.2 |
|
滝の音は、ますます物思いをする人をはっとさせるように、耳にうるさく響く。
叢の虫だけが、頼りなさそうに鳴き弱って、枯れた草の下から、龍胆が、自分だけ茎を長く延ばして、露に濡れて見えるなど、みないつもの時節のことであるが、折柄か場所柄か、実に我慢できないほどの、もの悲しさである。
|
滝の水は物思いをする人に威嚇を与えるようにもとどろいていた。叢の中の虫だけが鳴き弱った音で悲しみを訴えている。枯れた草の中から竜胆が悠長に出て咲いているのが寒そうであることなども皆このごろの景色として珍しくはないのであるが、折と所とが人を寂しがらせ、悲しがらせるのであった。
|
【滝の声は】- 音羽の滝。
【草むらの虫のみぞ、よりどころなげに鳴き弱りて】- 『完訳』は「草が枯れて隠れ処のない虫に、頼るべき人のない宮をかたどる」と注す。下文の龍胆を宮に、虫は仕える女房たちをかたどるとも解せよう。
【枯れたる草の下より、龍胆の、われひとりのみ心長うはひ出でて、露けく見ゆるなど】- 『河海抄』は「我が宿の花ふみしだく鳥うたむ野はなければやここにしもくる」(古今集物名、紀友則)を指摘。『集成』は「龍胆は、枝ざしなどもむつかしけれど、異花どもの皆霜枯れたるに、いと花やかなる色あひにさし出でたる、いとをかし」(枕草子、草の花は)を指摘。擬人法。
【折から所からにや、いと堪へがたきほどの、もの悲しさなり】- 『異本紫明抄』は「ただ思ふ人のかたみにいかになどみなはらわたのたゆる声なり」(出典未詳)を指摘。
|
| 4.3.3 |
|
いつもの妻戸のもとに立ち寄りなさって、そのまま物思いに耽りながら立っていらっしゃった。
やさしい感じの直衣に、紅の濃い下襲の艶が、とても美しく透けて見えて、光の弱くなった夕日が、それでも遠慮なく差し込んできたので、眩しそうに、さりげなく扇をかざしていらっしゃる手つきは、「女こそこうありたいものだが、それでさえできないものを」と、拝見している。
|
夕霧は例の西の妻戸の前で中へものを言い入れたのであるが、そのまま立って物思わしそうにあたりをながめていた。柔らかな気のする程度に着馴らした直衣の下に濃い紫のきれいな擣目の服が重なって、もう光の弱った夕日が無遠慮にさしてくるのを、まぶしそうに、そしてわざとらしくなく扇をかざして避けている手つきは女にこれだけの美しさがあればよいと思われるほどで、それでさえこうはゆかぬものをなどと思って女房たちはのぞいていた。
|
【例の妻戸のもとに】- 寝殿の西南の妻戸。
【影弱りたる夕日】- 光の弱くなった夕日。九月十三日の夕方。
【何心もなうさし来たるに】- 『完訳』は「愁傷の場に夕陽のさす趣」と注す。擬人法。「に」接続助詞、順接の意。
【わざとなく扇をさし隠したまへる】- 夕霧の動作、姿態。『完訳』は「粋な懸想人の風姿でもある」と評す。
【女こそかうはあらまほしけれ、それだにえあらぬを】- 女房の視点・心中で夕霧の美しさを語る。係助詞「こそ」--「あらまほしけれ」已然形、逆接用法。
|
| 4.3.4 |
もの思ひの慰めにしつべく、笑ましき顔の匂ひにて、少将の君を、取り分きて召し寄す。簀子のほどもなけれど、奥に人や添ひゐたらむとうしろめたくて、えこまやかにも語らひたまはず。 |
物思いの時の慰めにしたいほどの、笑顔の美しさで、小少将の君を、特別にお呼びよせになる。
簀子はさほどの広さもないが、奥に人が一緒にいるだろうかと不安で、打ち解けたお話はおできになれない。
|
寂しい人たちにとってはよい慰安になるであろうと思われる美しい様子で、特に名ざして少将を呼び出した。狭い縁側ではあるが、他の女がまたその後ろに聞いているかもしれぬ不安があるために、声高には話しえない大将であった。
|
【奥に人や添ひゐたらむと】- 「人」は他の女房をさす。『完訳』は「夕霧は狭い簀子にいて、簾中の小少将の君と対座。簾の奥に誰か一緒にいるかと警戒する」と注す。
|
| 4.3.5 |
|
「もっと近くに。
放っておかないでください。
このように山の奥にやって来た気持ちは、他人行儀でよいものでしょうか。
霧もとても深いのですよ」
|
「もう少し近くへ寄ってください。好意を持ってくれませんか、この遠方へまで御訪問して来る私の誠意を認めてくだすったら、最も親密なお取り扱いがあってしかるべきだと思いますよ。霧がとても深くおりてきますよ」
|
【なほ近くて】- 大島本は「な越ちかくて」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「なほ近くてを」と「を」を補訂する。『新大系』は底本のままとする。以下「いと深しや」まで、夕霧の詞。
【隔て残るべくやは】- 「やは」反語表現。他人行儀でよいはずがない。
【霧もいと深しや】- 『集成』は「霧も深いから、姿も見えまいと、小少将をさそう」と注す。
|
| 4.3.6 |
|
と言って、特に見るでもないふりをして、山の方を眺めて、「もっと近く、もっと近く」としきりにおっしゃるので、鈍色の几帳を、簾の端から少し外に押し出して、裾を引き繕って横向きに座わっている。
大和守の妹なので、お近い血縁の上に、幼い時からお育てになったので、着物の色がとても濃い鈍色で、橡の喪服一襲に、小袿を着ていた。
|
と言って、ちょっと山のほうをながめてから大将がぜひもっと近くへ来てくれと言うので、余儀なく鈍色の几帳を簾から少し押し出すほどにして、裾を細く巻くようにした少将は近くへ身を置いた。この人は大和守の妹で、御息所の姪であるというほかにも、子供の時から御息所のそばで世話になっていた人であったから喪服の色は濃かった。黒を重ねた上に黒の小袿を着ていた。
|
【裾をひきそばめつつゐたり】- 『集成』は「着物の裾が簀子に出たのを横に引き隠して」。『完訳』は「着物の裾を片寄せながらすわっている」と注す。
【大和守の妹なれば】- 小少将の君は大和守の妹という紹介。落葉宮とは従姉妹。
【幼くより生ほし立てたまうければ】- 御息所が小少将の君を。
【橡の衣一襲】- 大島本は「つるはミのきぬ」とある。『集成』『完本』は「橡の喪衣」と「喪」を補訂する。『新大系』は底本のままとする。
|
| 4.3.7 |
|
「このようにいくら悲しんでもきりのない方のことは、それはそれとして、申し上げようもないお気持ちの冷たさをそれに加えて思うと、魂も抜け出てしまって、会う人ごとに怪しまれますので、今はまったく抑えることができません」
|
御息所のお亡れになったのを悲しむことと宮様のいつまでも御冷淡であらせられるのをお恨みするのが私の心の全部になって、ほかのことは頭にありませんから、だれからも私は怪しまれてしかたがありません。もう私に忍耐の力というものがなくなりましたよ」
|
【かく尽きせぬ御ことは】- 以下「忍ぶべき方なし」まで、夕霧の詞。
【聞こえなむ方なき】- 大島本は「きこえなむ」とある。『集成』『完本』は「聞こえむ」と「な」を削除する。『新大系』は底本のままとする。
【御心のつらさ】- 落葉宮の冷淡な心。
【見る人ごとに咎められはべれば、今はさらに忍ぶべき方なし】- 『休聞抄』は「忍ぶれど色に出でにけり我が恋は物や思ふと人の問ふまで」(拾遺集恋一、六二二、平兼盛)を指摘。
|
| 4.3.8 |
と、いと多く恨み続けたまふ。
かの今はの御文のさまものたまひ出でて、いみじう泣きたまふ。
|
と、とても多く恨み続けなさる。
あの最期の折のお手紙の様子もお口にされて、ひどくお泣きになる。
|
これを初めにして、夕霧はいろいろと恋の苦しみを訴えた。御息所の最後の手紙に書かれてあったことも言って非常に泣く。
|
|
|
第四段 板ばさみの小少将君
|
| 4.4.1 |
|
この人も、それ以上にひどく泣き入りながら、
|
少将もまして非常に泣く。
|
【この人も、ましていみじう泣き入りつつ】- 小少将の君も夕霧以上に。
|
| 4.4.2 |
|
「その夜のお返事さえ拝見せずじまいでしたが、もう最期という時のお心に、そのままお思いつめなさって、暗くなってしまいましたころの空模様に、ご気分が悪くなってしまいましたが、そのような弱目に、例の物の怪が取りつき申したのだ、と拝見しました。
|
「その時のことでございますがね、あなた様がおいでにならぬばかりか、御自身のお返事もおもらいになれないままで暗くなってまいりますのに悲観をあそばしましてとうとう意識をお失いになりましたのに物怪がつけこんで、そのまま蘇生がおできにならなかったのだと私は拝見いたしました。
|
【その夜の御返りさへ】- 以下「暮らさせたまうし」まで、小少将の君の詞。
【見えはべらずなりにしを】- 主語は御息所。
【暗うなりにしほどの空のけしきに】- 『集成』は「いよいよ大将の訪れがないと確信された頃」と注す。
【引き入れたてまつる】- 物の怪が御息所の魂を。
|
| 4.4.3 |
|
以前の御事でも、ほとんど人心地をお失いになったような時々が多くございましたが、宮が同じように沈んでいらっしゃったのを、お慰め申そうとのお気を強くお持ちになって、だんだんとお気をしっかりなさいました。
このお嘆きを、宮におかれては、まるで正体のないようなご様子で、ぼんやりとしていらっしゃるのでした」
|
以前の御不幸のございました時にも、もうそんなふうにおなりになるのでないかと私どもがお案じいたしましたようなことがおりおりございましたが、宮様がお悲しみになってめいっておいであそばすのをおなだめになりたいとお思いになるお心の強さから、御健康をお持ち直しになったのでございます。あなた様についての御息所のこのお悲しみ方を宮様はただ呆然として見ておいでになりました」
|
【過ぎにし御ことにも】- 柏木逝去の折をさす。
【ほとほと御心惑ひぬべかりし】- 主語は御息所。
【こしらへきこえむ】- 御息所が落葉宮を。
【この御嘆きをば】- 御息所の逝去。
【御前には、ただわれかの御けしきにて】- 『河海抄』は「夢にだに何かも見えぬ見ゆれども我かも惑ふ恋の繁きに」(万葉集巻十一)を指摘する。
|
| 4.4.4 |
など、とめがたげにうち嘆きつつ、はかばかしうもあらず聞こゆ。
|
などと、涙を止めがたそうに悲しみながら、はきはきとせず申し上げる。
|
あきらめられぬようにこんなことを少将は言っていて、まだ頭はかなり混乱しているふうであった。
|
|
| 4.4.5 |
|
「そうですね。
それもあまりに頼りなく、情けないお心です。
今は、恐れ多いことですが、誰を頼りにお思い申し上げなさるのでしょう。
御山暮らしの父院も、たいそう深い山の中で、世の中を思い捨てなさった雲の中のようなので、お手紙のやりとりをなさるにも難しい。
|
「そうではあっても、宮様はもう常態にお復しになってしかるべきだと思う。私に対してあまりな知らず顔をお作りになるのは、思いやりのないことではありませんか。もったいないことですが、孤独におなりになった宮様にだれがお力になるとお思いになるのだろう。法皇様はいっさい塵界と交渉を絶っておいでになる御生活ぶりですから、御相談事などは申し上げられないでしょう。
|
【そよや。そもあまりに】- 以下「あるべきことかは」まで、夕霧の詞。
【誰をかはよるべに思ひきこえたまはむ】- 反語表現。暗に自分をおいて他に頼る人はいない、という。
【御山住みも、いと深き峰に】- 西山に籠もっている朱雀院をさす。
|
| 4.4.6 |
|
ほんとうにこのような冷たいお心を、あなたからよく申し上げてください。
万事が、前世からの定めなのです。
この世に生きていたくないとお思いになっても、そうはいかない世の中です。
第一、このような死別がお心のままになるなら、この死別もあるはずがありません」
|
あなたがたが熱心になって宮様の私に対する御冷酷さをお改めになるようによくお話し申し上げてください。皆宿命があって、一生孤独でいようとあそばしても、そうなって行かないということもお話し申すといい。人生が望みどおりに皆なるものであれば、この悲しい死別はなされなくてもよかったわけではありませんか」
|
【心憂き御けしき、聞こえ知らせたまへ】- 落葉宮にあなた小少将の君からよく申し上げて下さい、の意。
【よろづのこと、さるべきにこそ】- 万事が前世からの宿縁である。係助詞「こそ」の下に「あれ」などの語句が省略。
【まづは、かかる御別れの、御心にかなはば】- 『源氏物語引歌』は「命だに心にかなふものならば何か別れの悲しからまし」(古今集離別、三八七、白女)を指摘。
【あるべきことかは】- 反語表現。主語、突然の御息所の逝去という意が省略されている。
|
| 4.4.7 |
|
などと、いろいろと多くおっしゃるが、お返事申し上げる言葉もなくて、ただ溜息をつきながら座っていた。
鹿がとても悲しそうに鳴くのを、「自分も鹿に劣ろうか」と思って、
|
などと夕霧は多く言うのであるが、少将は返事もできずに歎息ばかりしていた。鹿がひどく啼くのを聞いていて、「われ劣らめや」(秋なれば山とよむまで啼く鹿にわれ劣らめや独り寝る夜は)と吐息をついたあとで、
|
【鹿のいといたく鳴くを、「われ劣らめや」とて】- 『源氏釈』は「秋なれば山とよむまで鳴く鹿に我劣らめや独り寝る夜は」(古今集恋二、五八二、読人しらず)を指摘。
|
| 4.4.8 |
|
「人里が遠いので小野の篠原を踏み分けて来たが
わたしも鹿のように声も惜しまず泣いています」
|
里遠み小野の篠原分けて来て
われもしかこそ声も惜しまね
|
【里遠み小野の篠原わけて来て--我も鹿こそ声も惜しまね】- 夕霧から小少将の君への贈歌。「鹿」「然(しか)」の掛詞。『河海抄』は「山城の小野の山人里遠み仮の宿りをとりぞかねつる」(出典未詳)を指摘。『集成』は「山城の小野の山辺の里遠み仮の宿りもとりぞかねつる」(能宣集)を指摘。『全集』は「浅茅生の小野の篠原忍ぶとも人こそ知るらめや言ふ人なしに」(古今集恋一、五〇五、読人しらず)「浅茅生の小野の篠原忍ぶれどなどか人の恋しき」(後撰集恋一、五七八、源等)を指摘。
|
| 4.4.9 |
とのたまへば、
|
とおっしゃると、
|
と大将が言うと、
|
|
| 4.4.10 |
|
「喪服も涙でしめっぽい秋の山里人は
鹿の鳴く音に声を添えて泣いています」
|
ふぢ衣露けき秋の山人は
鹿のなく音に音をぞ添へつる
|
【藤衣露けき秋の山人は--鹿の鳴く音に音をぞ添へつる】- 小少将の君の返歌。「鹿」の語句を受けて返す。『全集』は「山里は秋こそことにわびしけれ鹿の鳴く音に目を覚ましつつ」(古今集秋上、二一四、壬生忠岑)を指摘。
|
| 4.4.11 |
|
上手な歌ではないが、時が時とて、ひっそりとした声の調子などを、けっこうにお聞きになった。
|
将のこの返歌はよろしくもないが、低く忍んで言う声づかいなどを優美に感じる夕霧であった。
|
【よからねど、折からに--聞きなしたまへり】- 『岷江入楚』は「草子地歟」と指摘。
|
| 4.4.12 |
御消息とかう聞こえたまへど、
|
ご挨拶をあれこれ申し上げなさるが、
|
宮へいろいろとお取り次ぎもさせたが、
|
|
| 4.4.13 |
|
「今は、このように思いがけない夢のような世の中を、少しでも落ち着きを取り戻す時がございましたら、たびたびのお見舞いにもお礼申し上げましょう」
|
「この悲しみの中から自分を取りもどす日がございましたら、始終お心にかけてお尋ねくださいますお礼も申し上げられるかと思います」
|
【今は、かくあさましき】- 以下「聞こえやるべき」まで、落葉宮の詞。伝言。
【夢の世を、すこしも思ひ覚ます折】- 「夢」「覚ます」縁語表現。
|
| 4.4.14 |
|
とだけ、素っ気なく言わせなさる。
「ひどく何とも言いようのないお心だ」と、嘆きながらお帰りになる。
|
と礼儀としてだけのことより宮からはお返辞がない。大将は失望して歎きながら帰って行くのであった。
|
【言はせたまふ】- 「せ」使役の助動詞。落葉宮が小少将の君をして夕霧に。
【いみじういふかひなき御心なりけり】- 夕霧の心中。
|
|
第五段 夕霧、一条宮邸の側を通って帰宅
|
| 4.5.1 |
|
道すがら、しみじみとした空模様を眺めて、十三日の月がたいそう明るく照り出したので、薄暗い小倉の山も難なく通れそうに思っているうちに、一条の宮邸はその途中であった。
|
途中も車の中から身にしむ秋の終わりがたの空をながめていると、十三日の月が出て暗い気持ちなどにはふさわしくないはなやかな光を地上に投げかけた。それにも誘われて一条の宮の前で車をしばらくとどめさせた。
|
【道すがらも、あはれなる空を眺めて、十三日の月のいとはなやかにさし出でぬれば】- 小野山荘からの帰途。九月十三日の月がさし昇る。十三夜の月として賞美されている。
【小倉の山もたどるまじう】- 『源氏釈』は「秋の夜の月の光し明ければ小倉の山も越えぬべらなり」(古今集秋上、一九五、在原元方)、『紹巴抄』は「いづくにか今宵の月の曇るべき小倉の山も名をや変ふらむ」(新古今集秋上、四〇五、大江千里)、『源注拾遺』は「大堰川浮かべる舟の篝火に小倉の山も名のみなりけり」(後撰集雑三、一二三二、在原業平)「秋の色は千種ながらにさやけきを誰か小倉の山といふらむ」(是則集)を指摘。
【一条の宮は道なりけり】- 落葉宮の本邸。
|
| 4.5.2 |
|
以前にもまして荒れて、南西の方角の築地の崩れている所から覗き込むと、ずっと一面に格子を下ろして、人影も見えない。
月だけが遣水の表面をはっきりと照らしているので、大納言が、ここで管弦の遊びなどをなさった時々のことを、お思い出しになる。
|
以前よりもまた荒れた気のするお邸であった。南側の土塀のくずれた所から中をのぞくと、大きな建物の戸は皆おろされてあって人影も見えない。月だけが前の流れに浮かんでいるのを見て、柏木がよくここで音楽の遊びなどをしたその当時のことが思い出された。
|
【はるばると下ろし籠めて】- ずっと一面に格子を下ろしているさま。
【人影も見えず。月のみ遣水の面をあらはに澄みましたるに】- 「(人)影」「月」縁語。 【月のみ遣水の面をあらはに澄みましたるに】-「澄む」「住む」の掛詞。月を擬人化した表現。
【大納言、ここにて遊びなどしたまうし】- 柏木をさす。死の直前に権大納言に任じられた。
|
| 4.5.3 |
|
「あの人がもう住んでいないこの邸の池の水に
独り宿守りしている秋の夜の月よ」
|
見し人の影すみはてぬ池水に
ひとり宿守る秋の夜の月
|
【見し人の影澄み果てぬ池水に--ひとり宿守る秋の夜の月】- 夕霧の独詠歌。柏木を偲ぶ。「人の影」「(月の)影」、「住み」「澄み」の掛詞。「影」「澄み」「月」縁語。『異本紫明抄』は「亡き人の影だに見えぬ遣水の底に涙を流してぞこし」(後撰集哀傷、一四〇三、伊勢)を指摘。
|
| 4.5.4 |
|
と独言を言いながら、お邸にお帰りになっても、月を見ながら、心はここにない思いでいらっしゃった。
|
こう口ずさみながら家へ帰って来た大将は、そのまま縁に近い座敷で月にながめ入りながら恋人の冷たさばかりを歎いていた。
|
【殿におはしても】- 夕霧の邸。三条邸。
【月を見つつ、心は空にあくがれ】- 「月」「空」縁語。
|
| 4.5.5 |
|
「何ともみっもない。
今までになかったお振る舞いですこと」
|
「あんなふうにしていらっしゃることは以前になかったことですね。およしになればいいのに」
|
【さも見苦しう。あらざりし御癖かな】- 女房のひそひそ話。
|
| 4.5.6 |
|
と、おもだった女房たちも憎らしがっていた。
北の方は、真実嫌な気がして、
|
と言って女房らは譏った。夫人は痛切に良人のこの変わりようを悲しんでいた。
|
【上は、まめやかに】- 雲居雁。『集成」は「「上」は、北の方の称。「御達」に対する」と注す。
|
| 4.5.7 |
|
「魂が抜け出たお方のようだ。
もともと何人もの夫人たちがいっしょに住んでいらっしゃる六条院の方々を、ともすれば素晴らしい例として引き出し引き出しては、性根の悪い無愛想な女だと思っていらっしゃる、やりきれないわ。
わたしも昔からそのように住むことに馴れていたならば、人目にも無難に、かえってうまくいったでしょうが。
世の男性の模範にしてもよいご性質と、親兄弟をはじめ申して、けっこうなあやかりたい者となさっていたのに、このままいったら、あげくの果ては恥をかくことがあるだろう」
|
これは心がほかへ飛んで行っているという状態なのであろう、そうしたことに馴らされた六条院の夫人たちを何かといえばよい例に引いて、自分をがさつな、思いやりのない女のように言う良人は無理である、自分も結婚した初めからそう馴らされて来たのであったなら、穏健なあきらめができていて、こんな時の辛抱もしよいに違いない、珍しく忠実な良人を持つ妻として親兄弟をはじめとして世間からあやかり者のように言われて来た自分が、最後にみじめな捨てられた女になるのであろうか
|
【あくがれたちぬる御心なめり】- 以下「末に恥がましきことやあらむ」まで、雲居雁の心中。
【さる方にならひたまへる】- 一夫多妻の同居生活をさす。
【ひき出でつつ】- 接続助詞「つつ」同じ動作の反復継続。
【しかならひなましかば】- 「ましかば」--「過ぐしてまし」反実仮想の構文。
【なかなか過ごしてまし】- 大島本は「すこして」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「過ぐして」と校訂する。『新大系』は底本のままとする。
|
| 4.5.8 |
など、いといたう嘆いたまへり。
|
などと、とてもひどく嘆いていらっしゃった。
|
と歎いているのである。
|
|
| 4.5.9 |
|
夜明け方近く、お互いに口に出すこともなくて、背き合いながら夜を明かして、朝霧の晴れる間も待たず、いつものように、手紙を急いでお書きになる。
とても気にくわないとお思いになるが、以前のようには奪い取りなさらない。
たいそう情愛をこめて書いて、ちょっと下に置いて歌を口ずさみなさる。
声をひそめていらっしゃったが、漏れて聞きつけられる。
|
夜も明けがた近くなるのであるが、夫婦はどちらも離れた気持ちで身をそむけたまま何を言おうともしなかった。起きるとまたすぐに、朝霧の晴れ間も待たれぬようにして大将は山荘への手紙に筆を取っていた。不愉快に思いながらも夫人はもういつかのように奪おうとはしなかった。書いてしばらくそれをながめながら読んで見ているのが、低い声ではあったが、一部だけは夫人の耳にもはいって来た。
|
【夜明け方近く】- 「朝霧の晴れ間も待たず」に係る。
【かたみにうち出でたまふことなくて、背き背きに嘆き明かして】- 挿入句。『源注拾遺』は「我が背子をいづく行かめとさき竹の背向(そがひ)に寝しく今し悔しも」(万葉集巻七)指摘。
【いと心づきなしと思せど】- 主語は雲居雁。
【漏りて聞きつけらる】- 雲居雁の耳に入る。「らる」尊敬の助動詞。
|
| 4.5.10 |
|
「いつになったらお訪ねしたらよいのでしょうか
明けない夜の夢が覚めたらとおっしゃったことは
|
いつとかは驚かすべきあけぬ夜の
夢さめてとか言ひし一言
|
【いつとかはおどろかすべき明けぬ夜の--夢覚めてとか言ひしひとこと】- 夕霧から落葉宮への贈歌。宮の「あさましき夢の世をすこしも思ひ覚ます折あらば」と言った言葉を受けて詠み贈る。
|
| 4.5.11 |
|
お返事がありません」
|
「上よりおつる」(いかにしていかによからん小野山の上よりおつる音無しの滝)
|
【上より落つる】- 『源氏釈』は「いかにしていかに住むらむ奥山の上より落つる音無の滝」(出典未詳)を指摘。
|
| 4.5.12 |
|
とでもお書きになったのであろうか、手紙を包んで、その後も、「どうしたらよかろう」などと口ずさんでいらっしゃった。
人を召してお渡しになった。
「せめてお返事だけでも見たいものだわ。
やはり、本当はどうなのかしら」と、様子を窺いたくお思いになっている。
|
と書かれたものらしい。巻いて上包みをしたあとでも「いかによからん」などと夕霧は口にしていた。侍を呼んで手紙の使いはすぐに小野へ出された。内容の全部はよくわからなかったが、返事だけは手に入れて読みたいものである、それによって真相が明らかになるであろうと夫人は思っていた。
|
【とや書いたまひつらむ】- 大島本は「かい給つらむ」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「書いたまへらむ」と校訂する。『新大系』は底本のままとする。『弄花抄』は「双紙詞歟いかてよからんと夕霧の吟し給ふによて也」と指摘。三光院説「いかてよからんなとの給ふを雲居雁の聞とかめて文の内を推し給ふ也」。『評釈』は「語り手の注釈である」と注す。
【いかでよからむ】- 『集成』は「前注に引く歌(源氏釈所引歌)とは別の引歌があるかとも考えられるが、「いかにしていかによからむ」の調べにならって口ずさんだものか」と注す。
【御返り事をだに見つけてしがな。なほ、いかなることぞ】- 雲居雁の心中。
|
|
第六段 落葉宮の返歌が届く
|
| 4.6.1 |
日たけてぞ持て参れる。紫のこまやかなる紙すくよかにて、小少将ぞ、例の聞こえたる。ただ同じさまに、かひなきよしを書きて、 |
日が高くなってから返事を持って参った。
紫の濃い紙が素っ気ない感じで、小少将の君が、いつものようにお返事申し上げた。
いつもと同じで、何の甲斐もないことを書いて、
|
朝おそくなってから小野の返事が来た。濃い紫色の、堅苦しい紙へ例の少将が書いたものであった。今日もまた自分たちの力で宮をお動かしすることのできなかったことが書かれてあって、
|
【かひなきよしを書きて】- 宮の返事が頂けない旨を書いて。
|
| 4.6.2 |
|
「お気の毒なので、あの頂戴したお手紙に、手習いをしていらしたのをこっそり盗みました」
|
お気の毒に存じますものですから、あなた様のお手紙へむだ書きをあそばしたのを盗んでまいりました。
|
【いとほしさに】- 以下「盗みたる」まで、小少将の君の文言。
【かのありつる御文に】- 『完訳』は「以前夕霧が贈った手紙の余白に、宮が古歌や自作の歌を書きつけた。小少将がその部分をひそかに盗んで破り、同封してきた」と注す。
【手習ひすさびたまへるを】- 主語は落葉宮。
|
| 4.6.3 |
|
とあって、中に破いて入っていたが、「御覧になったのだ」と、お思いになるだけで嬉しいとは、とても体裁の悪い話である。
とりとめもなくお書きになっているのを、見続けていらっしゃると、
|
と書いて、中へその所だけを破ったのが入れてあった。読んでだけはもらえたのであるということでうれしくなる大将の心もみじめなものである。むだ書きふうにお書きになったお歌は、骨を折って読んでみると、
|
【ひき破りて入れたる】- 大島本は「入たる」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「入たり」と校訂する。『新大系』は底本のままとする。
【目には見たまうてけり】- 夕霧の心中。完了の助動詞「て」確述。過去助動詞「けり」詠嘆。驚嘆のニュアンス。
【いと人悪ろかりける】- 『休聞抄』は「双」と指摘。『完訳』は「語り手の夕霧への評語」と注す。
【見続けたまへれば】- 『集成』は「文句を続けてご覧になると」。『完訳』は「散らし書きの文字を継いで」と訳す。
|
| 4.6.4 |
|
「朝な夕なに声を立てて泣いている小野山では
ひっきりなしに流れる涙は音無の滝になるのだろうか」
|
朝夕に泣く音を立つる小野山は
たえぬ涙や音無しの滝
|
【朝夕に泣く音を立つる小野山は--絶えぬ涙や音無の滝】- 落葉宮の手習歌。『完訳』は「亡母追慕の歌」と注す。『大系』は「恋ひ侘びぬ音をだに泣かむ声立てていづれなるらむ音無の滝」(拾遺集恋二、七四九、読人しらず)を指摘。
|
| 4.6.5 |
とや、とりなすべからむ、古言など、もの思はしげに書き乱りたまへる、御手なども見所あり。 |
とか、読むのであろうか、古歌などを、悩ましそうに書き乱れていらっしゃる、ご筆跡なども見所がある。
|
と解すべきものらしい。また寂しいお心に合いそうな古歌などの書かれてある宮のお字は美しかった。
|
【とや、とりなすべからむ】- 夕霧と語り手の視点が一体化した表現。
|
| 4.6.6 |
「人の上などにて、かやうの好き心思ひ焦らるるは、もどかしう、うつし心ならぬことに見聞きしかど、身のことにては、げにいと堪へがたかるべきわざなりけり。あやしや。など、かうしも思ふべき心焦られぞ」 |
「他人の事などで、このような浮気沙汰に心焦がれているのは、はがゆくもあり、正気の沙汰でもないように見たり聞いたりしていたが、自分の事となると、なるほどまことに我慢できないものであるなあ。
不思議だ。
どうして、こんなにもいらいらするのだろう」
|
他人のことで、こんなことを夢中になるまでの関心をもって楽しんだり、悲しんだりしているのを、歯がゆく病的なことに思っていたが、自分のことになると恋する心は堪えがたいものである、どうしてこうまでになったのか
|
【人の上などにて】- 以下「心焦られそ」まで、夕霧の心中。「人の上」は柏木のことをさす。
【身のことにては】- 夕霧、我が身を反省。
|
| 4.6.7 |
と思ひ返したまへど、えしもかなはず。
|
と反省なさるが、思うにまかせない。
|
と反省をしようとするのであるが、それもできないことであった。
|
|
|
第五章 落葉宮の物語 夕霧執拗に迫る
|
|
第一段 源氏や紫の上らの心配
|
| 5.1.1 |
|
六条院にもお聞きあそばして、とても落ち着いていて何につけ冷静で、人の非難もなく、無難に過ごしていらっしゃるのを、誇りに思い、自分の若いころ、少し風流すぎて、好色家だという評判をおとりになった名誉回復に、嬉しくお思い続けていらしたが、
|
六条院も大将の恋愛問題をお聞きになって、この人がなんらの浮いたこともせず、批難のしようもない堅実な人物であることに満足しておいでになって、御自身の青春時代に好色な評判を多少お取りになった不面目をこの人がつぐなってくれるもののように思っておいでになったことが裏切られていくような寂しさをお感じになった。
|
【いとおとなしう】- 以下「口入るべきことならず」まで、源氏の心中。前半、源氏の心中と地の文とが混合した表現。「いとほしう」以下が直接心中文。
【わがいにしへ、すこしあざればみ、あだなる名を取りたまうし】- 源氏、好色の半生を振り返り反省する。「たまうし」という敬語表現が混在する。
【面起こしに】- 夕霧を我が不名誉を挽回してくれた子だと賞賛。
【うれしう思しわたるを】- 「思し」という敬語が混在。
|
| 5.1.2 |
|
「かわいそうに、どちらにとってもお気の毒なことがきっとあるだろうことよ。
赤の他人の間でさえなく、大臣なども、どのようにお思いになろうか。
それくらいのこと、分からないではないだろう。
宿世というものからは、逃れられないのだ。
とやかく口を出すべきことではない」
|
この事件の気の毒な影響から双方で犠牲を払う結果になるのであろう、全然関係のないところの女性ではなくて、妻の兄の未亡人の宮との問題であるから、舅の大臣などもどう思うことであろう、それほどの思慮を持たないのではあるまいが、宿命というものから人はのがれられずに起こってきたことであろう、ともかくも自分の干渉すべきことでない
|
【いとほしう、いづ方にも】- 以下、純粋な源氏の心中文となる。雲居雁に対してもまた落葉宮に対しても。
【さし離れたる仲らひにてだにあらで】- 夕霧と雲居雁と落葉宮の関係。致仕太政大臣から見れば、夕霧は我が甥であり、娘雲居雁の夫、落葉宮は我が子柏木の妻であった人。その女性に甥であり娘婿である夕霧が懸想をしている、ということ。
【大臣なども】- 致仕太政大臣。
【さばかりのこと、たどらぬにはあらじ】- 『完訳』は「大将がそれくらいのことことは考えつかぬわけでもあるまい」と訳す。主語は夕霧。
|
| 5.1.3 |
|
とお思いになる。
女の身にとっては、どちらに対してもお気の毒だと、困った事にお聞きあそばしてお心をお痛めになる。
|
と院はお考えになった。結局双方とも婦人の損になることで気の毒であると歎いておいでになるのであった。
|
【いとほしけれと、あいなく聞こしめし嘆く】- 『集成』は「困ったことになったものだと、そんなことにまで気を廻してこの話を心配なさる」と訳す。
|
| 5.1.4 |
|
紫の上に対しても、今までのことや将来のことをお考えになりながら、このような噂を聞くにつけても、亡くなった後、不安にお思い申し上げる様子をおっしゃると、お顔をぽっと赤らめて、「情けないこと。そんなに長く後にお残しなさるおつもりか」とお思いになっていた。
|
御自身の経験されたことに照らして見、また大将のこの現状によって、亡きのちの世が不安になったことを紫夫人にお言いになると女王は顔を赤くして自分があとに残らねばならぬほど、早くこの世から去っておしまいになる心でおいでになるのであろうかと恨めしく思うふうであった。
|
【思し出でつつ】- 主語は源氏。
【亡からむ後、うしろめたう思ひきこゆるさまをのたまへば】- 源氏が亡くなった後のこと、後に遺された紫の上の身の上を落葉宮のようになりはせぬかと、心配する。
【心憂く、さまで後らかしたまふべきにや】- 紫の上の心中。『源注余滴』は「限りなき雲居のよそに別るとも人を心におくらさむやは」(古今集離別、三六七、読人しらず)を指摘する。
|
| 5.1.5 |
|
「女ほど、身の処し方も窮屈で、痛ましいものはない。
ものの情趣も、折にふれた興趣深いことも、見知らないふうに身を引いて黙ってなどいては、いったい何によって、この世に生きている晴れがましさを味わい、無常なこの世の所在なさをも慰めることができよう。
|
女ほど窮屈なものはありませんね。心の惹かれることも、恋しい感情も皆おさえて知らぬふうをしておとなしくしていなければならないのでは生きがいもなし、人生の退屈さと悲哀とを紛らすことができないではありませんか。
|
【女ばかり、身をもてなすさまも所狭う、あはれなるべきものはなし】- 以下「いかで保つべきぞ」まで、紫の上の心中。『集成』は「落葉の宮に同情する紫の上の思い」。『完訳』は「宮と雲居雁へお同情から、一般論を導く」と注す。
【何につけてか】- 係助詞「か」は「慰むべきぞは」に係る。反語表現。「は」終助詞、詠嘆の意。
|
| 5.1.6 |
|
だいたい、ものの道理も弁えないで、つまらない者のようになってしまったのでは、育てた親も、とても残念に思うはずではないか。
|
そうかといって感情に乏しい女になっては無価値だし、どうしてこんなふうに育ったのかと親さえも軽蔑したくなりますからね。
|
【生ほしたてけむ親も、いと口惜しかるべきものにはあらずや】- 『伊行釈』は「かかる身に生ほし立てけむたらちねのおやさへつらき恋をするかな」(出典未詳)。『源注拾遺』は「たらちねの親もつらしなかくばかり思ひに迷ふ世にとどめたる」(新撰万葉集下)と「身の憂きに思ひあまりのはてはては親さへつらきものにぞありける」(玉葉集恋五、一七七二、藤原慶子)を指摘。
|
| 5.1.7 |
|
心の中にばかり思いをこめて、無言太子とか言って、小法師たちが辛い修行の例とする昔の喩えのように、悪い事良い事を弁えながら、口に出さずにいるのは、つまらない。
自分ながらも、ほど好い身の処し方をするには、どのようにしたらよいものか」
|
ただ心でだけ思って、お坊様が気の毒がる無言太子のようになって、細かな感情も動きながら黙っていなければならない人にするのも無慈悲な親になる。こうであればああであり、それであればこうになる、どうして中庸を得るようにすればいいかと、そんなことを私が考えるのも、他の女性のためではなく女一の宮を完全な女性にしたいからですよ」
|
【無言太子とか】- 「仏説太子慕魄経」に見える。
【悲しきことにする昔のたとひのやうに】- 『集成』は「つらい無言の行を引合に出す昔の言い伝えのように」と訳す。
|
| 5.1.8 |
|
とご思案なさるのも、今はただ女一の宮の御身のためを思ってのことである。
|
と院は言っておいでになった。
|
【今はただ女一の宮の御ためなり】- 『評釈』は「作者は、女一の宮を考えてであると弁解した。つまりここは、紫の上の心に託して作者が自身の心を書き過ぎたため、言いわけのつもりなのである」と注す。女一宮は明石女御が生んだ今上の第一皇女。紫の上が手もとに引き取って養育している(若菜下)。
|
|
第二段 夕霧、源氏に対面
|
| 5.2.1 |
|
大将の君が、参上なさった機会があって、悩んでいらっしゃる様子も知りたいので、
|
夕霧が六条院へ来た時に、実状を知りたく思召す心から、院が、
|
【思ひたまへらむけしきもゆかしければ】- 主語は源氏。夕霧が悩んでいる様子を。
|
| 5.2.2 |
|
「御息所の忌中は明けたのだろうね。
昨日今日と思っているうちに、三年以上の昔になる世の中なのだ。
ああ、悲しく味気ないものだ。
夕方の露がかかっている間の寿命を貪っているとは。
何とかこの髪を剃って、何もかも捨て去ろうと思うが、なんといつまでものんびりと過ごしていることか。
まことに悪いことだ」
|
「御息所の忌がもう済んだだろうね。時はずんずんとたつからね。私が遁世の望みを持ち始めた時からももう三十年たっている。味気ないことだ。夕べの露にも異ならない命を持って安んじていられるわけはないのだからね。どうかして髪を剃り落としたいと望みながらのんきなふうを装っている。これはいけないことだね」
|
【御息所の忌果てぬらむな】- 以下「いと悪ろきわざなりや」まで、源氏の詞。
【三年】- みそとせ横山本・池田本・三条西家本 『集成』は「三十年」と校訂し「人の死後、月日のたつことの早さをいう当時の諺と思われる。朝顔の巻にも同様の表現がある」と注す。
【夕べの露かかるほどのむさぼりよ】- 「朝の露に名利を貪り、夕の陽に子孫を憂ふ」(白氏文集、不致仕)。
|
| 5.2.3 |
とのたまふ。
|
とおっしゃる。
|
こんな話をおしかけになった。
|
|
| 5.2.4 |
|
「ほんとうに、惜しくない人でさえ、めいめい離れがたく思っている人の世でございましょう」などと申し上げて、「御息所の四十九日の法事など、大和守某朝臣が、独りでお世話致しますのは、とてもお気の毒なことです。
しっかりした縁者がいない方は、生きている間だけのことで、このような死後は、悲しゅうございます」
|
「不幸ばかりで、もうこの世に未練はなかろうと思われます人でも、さて遁世はなかなかできないものらしいのでございますから、あなた様などは御無理もございません」などと言って、また大将は、「御息所の四十九日の仏事のことなども大和守一人の手でやっております。気の毒なことでございます。よい身寄りのない人は自身についた幸福だけで生きている間はよろしゅうございますが、死んだあとになってみますと気の毒なものです」
|
【まことに惜しげなき人だにこそ、はべめれ】- 大島本は「たにこそはへめれ」とある。『集成』『完本』は底本に従って「人だにおのがじしは離れがたく思ふ世にこそはべめれ」と「おのがじしは離れがたく思ふ世に」を補訂する。『新大系』は底本のままとする。夕霧の詞。
【御息所の四十九日のわざなど】- 以下「悲しうはべりけれ」まで、夕霧の詞。
【大和守なにがしの朝臣、一人】- 夕霧の詞。大和守某朝臣一人。「某」は実名を語り手が朧化した表現。
|
| 5.2.5 |
と、聞こえたまふ。
|
と、お申し上げになる。
|
とも言った。
|
|
| 5.2.6 |
|
「朱雀院からも御弔問があるだろう。
あの内親王、どんなにお嘆きでいらっしゃるだろう。
昔聞いていた時よりは、つい最近、何かにつけ聞いたり見たりするに、この更衣は、しっかりした無難な人の中に入っていた。
世間一般のことにつけて、惜しいことをしたものだ。
生きていてもよいと思う方が、このように亡くなってゆくことよ。
|
「御息所の仏事は院からもお世話をあそばすだろうよ。女二の宮はどんなに悲しんでおいでになることだろう。その当時はよくわからなかったが、近年になって事に触れて私の見たところではあの御息所は相当にりっぱな人らしい。
|
【院よりも】- 以下「人ざまもよくおはすべし」まで、源氏の詞。『集成』は「夕霧の言葉を受けて、院からのお世話もあろうから御息所の御法事に疎漏はあるまい、と言う」。『完訳』は「以下、源氏は遠まわしに、夕霧の反応を試そうとする」と注す。
【この近き年ごろ】- 柏木の死後。
【この更衣こそ】- 一条御息所。
【さてもありぬべき人の】- 『集成』は「もっと生きていて欲しい人が」。『完訳』は「まずまずと思うような人が」と訳す。
|
| 5.2.7 |
院も、いみじう驚き思したりけり。
かの皇女こそは、ここにものしたまふ入道の宮よりさしつぎには、らうたうしたまひけれ。
人ざまもよくおはすべし」
|
朱雀院も、ひどく驚きお悲しみになっていた。
あの内親王は、ここにいらっしゃる入道の宮の次には、かわいがっていらっしゃった。
人柄も良くいらっしゃるのだろう」
|
院の後宮の才女には違いなかった。そんな人の亡くなっていくことは惜しい。生きておればよいと思う人がそんなふうに皆死んでゆくではないか。院もお悲しみになったということだ。あの宮さんはここに来ておられる宮さんに次いでの御愛子だったのだよ。きっとごりっぱだろう」
|
|
| 5.2.8 |
とのたまふ。
|
とおっしゃる。
|
|
|
| 5.2.9 |
|
「お気立てはどのようでいらっしゃいましょう。
御息所は、申し分のない人柄や、気立てでいらっしゃいました。
親しく気をお許して接したわけではありませんでしたが、ちょっとした事の機会に、自然と人の心配りというものがよく分かるものでございます」
|
「さあ宮様はどんな方でございますか。御息所は無難な女性と見受けました。そう親密につきあっていたのではございませんが、しかし、何でもない時に人格の片影は見えるものでございますからね」
|
【御心はいかがものしたまふらむ】- 以下「ものになむはべる」まで、夕霧の詞。『完訳』は「夕霧は誘導尋問をかわし、御息所の話題に転換」と注す。推量の助動詞「らむ」視界外推量、夕霧の空とぼけ。
【心ばせになむ】- 係助詞「なむ」の下に「おはしき」などの語句が省略された形。
【親しううちとけたまはざりしかど】- 『完訳』は「親しく話を交わしたことがあるのに、そらとぼけて言う」と注す。
|
| 5.2.10 |
|
とお申し上げになって、宮の御事は口にかけず、まったく素知らぬふりをしている。
|
などと言って、女二の宮のことを話題にせず大将は素知らぬふうを見せているのである。
|
【宮の御こともかけず、いとつれなし】- 『集成』は「源氏の目に映じた夕霧の態度」と注す。
|
| 5.2.11 |
「かばかりのすくよけ心に思ひそめてむこと、諌めむにかなはじ。用ゐざらむものから、我賢しに言出でむもあいなし」 |
「これほどの一本気の性格の者が思い染めたことは、忠告しても聞き入れないだろう。
聞き入れもしないだろうことを分かっていながら、自分が分別くさく口を出してもしようがない」
|
これほど強い心でしている恋は、親の言葉くらいで思いとどまらせえられるものでない、用いない忠告を賢げに言うのもおもしろいことではないとお思いになって、
|
【かばかりのすくよけ心に】- 以下「あいなし」まで、源氏の感想。
|
| 5.2.12 |
と思して止みぬ。
|
とお思いになっておやめになった。
|
院は何の勧告をもあそばさなかった。
|
|
|
第三段 父朱雀院、出家希望を諌める
|
| 5.3.1 |
|
こうしてご法事に、万端を取り仕切っておさせなさる。
その評判は、自然に知れることなので、大殿などにおかれてもお聞きになって、「そんなことがあって良いことか」などと、妻方が思慮が浅いようにお考えになるのは、困ったことである。
あの故人とのご縁もあるので、ご子息たちも、ご法要に参集なさる。
|
大将は御息所の法事をするのにあらゆる尽力をしていた。こんなことはすぐに評判になるもので、太政大臣家へも聞こえていった。不都合な話であると女性の側の悪いようにそこでは言われておいでになる宮がお気の毒である。法事の当日は昔の縁故で大臣家の子息たちも参会した。
|
【御法事に、よろづとりもちてせさせたまふ】- 主語は夕霧。「せ」「させ」(使役の助動詞)「たまふ」(尊敬の補助動詞)。『完訳』は「御息所の四十九日の法事。夕霧が主宰し、大和守がこれを準備」と注す。
【さやはあるべき】- 『集成』は「おだやかならぬことだ」。『完訳』は「そんなことがあってよいものか」「致仕の大臣は、自分が依頼されると思っていたので腹を立てる」と注す。
【わりなきや】- 『評釈』は「作者も読みあげる女房も、聞く姫君、女君、傍らの女房たちも、女たちは皆一様に顔をあげ、悔しいため息をつく」。『集成』は「宮にとっては濡衣だというほどの気持の草子地」と注す。
【昔の御心あれば】- 「昔」は故人柏木をさし、「御心」は御縁というほどの意。
【君達、参で訪らひたまふ】- 大島本は「きむたちまて」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「君達も」と校訂する。『新大系』は「君達まで」と整定する。柏木の弟たち。ここは法要に参列。
|
| 5.3.2 |
誦経など、殿よりもいかめしうせさせたまふ。
これかれも、さまざま劣らずしたまへれば、時の人のかやうのわざに劣らずなむありける。
|
読経など、大殿からも盛大におさせになる。
誰も彼も、いろいろ負けず劣らずなさったので、時めく人のこのような法事に負けないほどであった。
|
派手な誦経の寄付が大臣からもあった。寄付はまだほかからも多く来た。競争的にこうしたことをするのが今日の流行である。
|
|
| 5.3.3 |
|
宮は、このまま小野で一生を送ろうとご決心なさったことがあったが、朱雀院に、誰かがそっとお告げ申し上げたので、
|
宮はこのまま小野の山荘で遁世の身になっておしまいになる志望がおありになったのであるが、御寺の院にこのことをお報じ申し上げた人があって、
|
【宮は、かくて住み果てなむと思し立つことありけれど】- 落葉宮は小野に籠もったまま出家しようと決心。
|
| 5.3.4 |
|
「それはとんでもないことです。
なるほど、何人とも、あれこれと身の関わりをお持ちになることは良いことではないが、後見のない人は、なまじ尼姿になってから、けしからぬ噂がたち、罪を得るような時、現世も来世も、どっちつかずの非難されるというものです。
|
「そんなことはよろしくない。皆がいろいろな変わった境遇にいることも望ましいことではないが、保護者のない者が尼になったために、かえって浮いた名を立てられることがあったり、俗でいる以上に煩悩を作らなければならないことができたりしては、この世の幸福も未来の幸福も共に無にしてしまうことになる。
|
【いとあるまじきことなり】- 以下「ともかうも」まで、朱雀院から落葉宮への手紙文の趣旨。
【げに、あまた、とざまかうざまに身をもてなしたまふべきことにもあらねど】- 「げに」は落葉宮が夕霧を避けて出家したいと言った趣旨を受けたもの。『集成』は「柏木との結婚、そして夕霧とのことを婉曲に言ったもの」と注す。
【あるまじき名を立ち】- 『完訳』は「夕霧と宮の仲は断ち切れまいとも懸念し、さらには尼の身で愛欲の罪を犯すのを恐れる」と注す。
【この世後の世、中空に】- 現世における幸福、来世における極楽往生、どちらも得ることなく、中途半端におわる。
|
| 5.3.5 |
ここにかく世を捨てたるに、三の宮の同じごと身をやつしたまへる、すべなきやうに人の思ひ言ふも、捨てたる身には、思ひ悩むべきにはあらねど、かならずさしも、やうのことと争ひたまはむも、うたてあるべし。 |
自分がこのように世を捨てているのに、三の宮が同じように出家なさったのを、何ともなす手がないように人が思ったり言ったりするのも、世を捨てた身には、思い悩むべきことではないが、必ずそんなにも、同じように競って出家なさるのも、感心しないことでしょう。
|
自分が僧になっている上に、三の宮が出家をしている。今また二の宮が同じことをしては、子孫の絶えていく一家と見られるのも、世の中を捨てた自分にとってはかまわないことであるが、必ずしもまた今競って出家は実現するに及ばないことだということは自分にもできる。
|
【すべなきやうに人の思ひ言ふも】- 大島本は「すへなき」とある。『集成』『完本』は「末(すゑ)なき」と整定する。『新大系』は「すべなき」とする。父親娘揃って出家したことを指していう。
|
| 5.3.6 |
|
世の辛さに負けて世を厭うのは、かえって体裁の悪いことです。
自分でしっかり考えて、もう少し冷静になって、心を澄ましてから、どうなりとも」
|
不幸な時にこの世を捨てることをするのは見苦しいものである。自然に悟りができてくる時節を待って、冷静に判断をしてしなければならぬことです」
|
【世の憂きにつけて厭ふは】- 『完訳』は「夕霧の言い寄る時に出家するのは、かえってよからぬ噂が立つ、の気持」と注す。
【心と思ひ取る方ありて、今すこし思ひ静め】- 大島本は「心とおもひしつめ」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「心と思ひ取る方ありて今すこし思ひ静め」と「取る方ありて今すこし」を補訂する。『新大系』は底本のままとする。
|
| 5.3.7 |
|
と度々申し上げなさった。
この浮いたお噂をお耳にあそばしたのであろう。
「噂のようなことが思うとおりに行かないので世をお厭いになった」と言われなさることを御心配なさったのであった。
そうかといって、また、「公然と再婚なさるのも軽薄で、感心しないこと」と、お思いになりながら、恥ずかしいとお思いになるのもお気の毒なので、「どうして、自分までが噂を聞いて口出ししたりしようか」とお思いになって、このことは、全然一言もお出し申し上げなさらないのだった。
|
こんな意味のことをたびたび御忠告になった。大将との恋愛事件がお耳にはいっていたのである。大将の愛が十分でないために悲観して尼になったと宮がお言われになることを院はおあやぶみになるのであった。そうとはお思いになっても公然大将の夫人になっておしまいになることを姫宮の完全な幸福とお認めになることもおできにならないのであるが、その問題に触れていっては宮が羞恥に堪えられないであろうと思召すとかわいそうなお気持ちがして、せめてこの際は自分だけでも知らぬ顔をしていてやりたいと思召した。
|
【この浮きたる御名をぞ聞こし召したるべき】- 『細流抄』は「草子地也」と指摘。『全集』は「朱雀院の文面の背後を補足説明した語り手のことば」と注す。
【さやうのことの思はずなるにつけて倦じたまへる」と】- 『集成』は「夕霧との間に実事があり、その後、夕霧の態度が煮えきらないので出家したと世間に取り沙汰されることを朱雀院は心配する」と注す。
【表はれてものしたまはむも】- 公然と夕霧と再婚すること。
【何かは、我さへ聞き扱はむ】- 朱雀院の心中。夕霧のことをはっきりと言えば、落葉の宮が恥ずかしく思うのが、気の毒だ、という気持ち。
【この筋は】- 夕霧の件をさす。
|
|
第四段 夕霧、宮の帰邸を差配
|
| 5.4.1 |
大将も、
|
大将も、
|
大将も
|
|
| 5.4.2 |
「とかく言ひなしつるも、今はあいなし。かの御心に許したまはむことは、難げなめり。御息所の心知りなりけりと、人には知らせむ。いかがはせむ。亡き人にすこし浅き咎は思はせて、いつありそめしことぞともなく、紛らはしてむ。さらがへりて、懸想だち、涙を尽くしかかづらはむも、いとうひうひしかるべし」 |
「あれこれと言ってみたが、今は無駄なことだ。
宮のお心ではお聞き入れなさることは、難しいことのようだ。
御息所が承知済みであったと、世間の人には知らせよう。
どうしようもない。
亡くなった方に少し思慮が浅かったと罪を思わせて、いつからそうなったということもなく、分からなくさせてしまおう。
年がいもなく若返って、懸想をし、涙を流し尽くして口説いたりするのも、いかにも身にふさわしからぬことだろう」
|
立てられる噂に言いわけをしてきたこれまでの態度はもう改めるほうがよい時期になったと思い、女二の宮が結婚を御承諾になるのを待つことはせずに、御息所の希望したことであったからというように世間へは思わせることにして、この場合はしかたがないから故人にちょっとした責任を負わせることくらい許してもらうことにして、いつから始まったということをあいまいにして夫婦になろう、今さら恋の涙のありたけを流して、宮のお心を動かそうと努めるのも自分に似合わしくないことである
|
【とかく言ひなしつるも】- 以下「いとうひうひしかるべし」まで、夕霧の心中。
【かの御心に許したまはむことは】- 落葉宮をさす。
【いかがはせむ】- 反語表現。どうしようもない。
|
| 5.4.3 |
|
と決心なさって、一条邸にお帰りになる予定の日を、何日ほどにと決めて、大和守を呼んで、しかるべき諸式をお命じになり、邸内を掃除し整え、何といっても、女世帯では、草深く住んでいらっしゃったので、磨いたように整備し直して、お気づかいぶりなどは、しかるべきやり方も立派に、壁代、御屏風、御几帳、御座所などまでお気を配りなさり、大和守にお命じになって、あちらの家で急いで準備させなさる。
|
と思って、山荘を引き上げて一条の邸へお移りになる日をおよそいつということもこちらできめた夕霧は、大和守を呼んで、大将夫人としての宮のお帰りになる儀式等についての設けを命じたのであった。邸の修理をさせ、勝ち気な御息所が旧態を保たせていたとはいうものの、行き届かない所のあった家の中を、みがき出したように美しくして、壁代、屏風、几帳、帳台、昼の座席なども最も高雅な、洗練された趣味で製作させるように命じてあった。
|
【一条に渡りたまふべき日、その日ばかりと定めて】- 『集成』は「帰宅、しかも結婚と夕霧は決め込んでいるので、暦によって吉日を選ぶ」と注す。
【あるべき作法めでたう】- 『集成』は「婚儀にふさわしい諸式」「しかるべき立派な品々を整え」。『完訳』は「移転のためのしかるべき儀礼」「必要な諸式も立派に」と訳す。
【かの家にぞ】- 大和守の家で。
|
| 5.4.4 |
|
その日、自分でいらっしゃって、お車や、御前駆などを差し向けなさる。
宮は、どうしても帰るまいとお思いになりおっしゃるのを、女房たちが熱心に説得申し上げ、大和守も、
|
当日は夕霧自身が一条に来ていて、車や前駆の役を勤める人たちを山荘へ迎えに出した。宮はどうしても帰らぬと言っておいでになるのを、女房たちは百方おなだめしていたし、大和守も意見を申し上げた。
|
【御車、御前などたてまつれたまふ】- 夕霧が小野山荘の落葉宮に差し向けなさる。
【思しのたまふを】- 「を」格助詞、目的格を表す。
【人びといみじう聞こえ】- 落葉宮付きの女房たち。『集成』は「きつくご意見申し」。『完訳』は「無理にお勧め申し」と訳す。
|
| 5.4.5 |
|
「まったくご承知するわけには行きません。
心細く悲しいご様子を拝見し心を痛め、これまでのお世話は、できるだけのことはさせていただきました。
|
「その仰せは承ることができません。お一人きりのお心細い御境遇が悲しく存ぜられまして、御葬送以来ただ今までは、私としてお尽くしいたしうるだけのことはいたしてまいりました。
|
【さらに承らじ】- 以下「仕うまつりそめたまうて」まで、大和守の詞。『集成』は「有無を言わせぬ口調で帰京をすすめる」と注す。
【このほどの宮仕へは】- 落葉宮の世話を「宮仕へ」という。
|
| 5.4.6 |
|
今は、任国の公務もございますし、下向しなければなりません。
お邸内のことも任せられる人もございません。
まことに不行届なことで、どうしたものかと心配いたしておりますが、このように万事お世話なさいますのを、なるほど、ご結婚ということを考えてみますと、必ずしも今すぐに移転するのが良いというのではないお身の上ですが、そのように、昔もお心のままにならなかった例は、多くございます。
|
しかし私は地方長官でございますから、お預かりしております国の用がうちやってはおけませんので、近くまた大和へまいらねばならないのでございます。あなた様のただ今からのお世話をだれに頼んでまいってよいという人もございませんから、どうすればよいかと思っております場合に左大将が力を入れてくださるのでございますから、あなた様御一身について考えますれば、御再婚をあそばすことをこれが最上のこととは申されませんのでございますが、しかし昔の内親王様がたにもそうした例は幾つもあったことで、御自分の御意志でもなく、運命に従って皆そうおなりになったのでございますから、
|
【かくよろづに思しいとなむを】- 主語は夕霧。
【この方にとりて思たまふるには】- 『集成』は「ご結婚ということで考えてみますと」。『完訳』は「あちらさまのご懸想からというふうに考えますと」と訳す。
【御心にかなはぬためし、多くはべれ】- 皇女が自分の意に反して再婚した例は多くある。
|
| 5.4.7 |
一所やは、世のもどきをも負はせたまふべき。いと幼くおはしますことなり。たけう思すとも、女の御心ひとつに、わが御身をとりしたため、顧みたまふべきやうかあらむ。なほ、人のあがめかしづきたまへらむに助けられてこそ、深き御心のかしこき御おきても、それにかかるべきものなり。 |
あなたお一方だけが、世間の非難をお受けになることでしょうか。
とても幼稚なお考えです。
いくら強がっても、女一人のご分別で、ご自分の身の振りをきちんとなさり、お気をつけなさることがどうしてできましょうか。
やはり、男性から大事にお世話なされるのに助けられて、初めて深いお考えによる立派なご方針も、それに依存するものなのです。
|
何もあなた様お一方が世間から批難されるはずもないのでございます。これほどのお方のお志をお退けになりますのは、あまりにも御幼稚なことと申すほかはございません。女性の方でも独立して行けぬことはないと思召すでしょうが、実際問題になりますと、御自身をお護りになることと、経済的のこととで御苦労ばかりがどんなに多いかしれません。それよりも十分大事に尊重申される御良人にお助けられになってこそ、あなた様の御天分も十分に発揮させることができるのでございます。どうかそのお心におなりくださいませ」大和守はまた、
|
【一所やは】- 落葉宮をさす。「やは」--「負はせたまふべき」反語表現。あなた一人だけが非難を受けるのでない。
【顧みたまふべきやうかあらむ】- 反語表現。お気をつけなさることはできない。
|
| 5.4.8 |
|
あなた方がよくお教え申し上げなさらないのです。
一方では、けしからぬことをも、ご自分たちの判断でかってにお取り計らい申し上げなさって」
|
「あなたたちが宮様へよく御会得のゆくようにお話し申し上げないのが悪いのです。そうかというとまたこうしたことに立ち至る最初の動機などはあなたがたの不注意でお起こしになったりして」
|
【君たちの聞こえ知らせたてまつりたまはぬなり】- 「君たち」は女房たちをさす。『集成』は「一転して、女房たちに苦情を言う」と注す。
【さるまじきことをも】- 手紙の取り次ぎなどをさす。
|
| 5.4.9 |
|
と、言い続けて、左近の君や、小少将の君を責める。
|
と少将や左近を責めた。
|
【左近、少将を責む】- 宮付きの女房。左近の君と小少将の君。前の「君たち」。
|
|
第五段 落葉宮、自邸へ向かう
|
| 5.5.1 |
|
寄ってたかって説得申し上げるので、とても困りきって、色鮮やかなお召し物を、女房たちがお召し替え申し上げるにも、夢心地で、やはり、とても一途に削き落としたく思われなさる御髪を、掻き出して御覧になると、六尺ほどあって、少し細くなったが、女房たちは不完全だとは拝見せず、ご自身のお気持ちでは、
|
女房が皆集まって来て口々にお促しするのに御反抗がおできにならないで、きれいな色のお召し物などをお着せかえ申したりするままに宮はなっておいでになるのであるが、切り捨ててしまいたく思召すお髪を後ろから前へ引き寄せてごらんになると、それは六尺ほどの長さで、以前よりは少し量が減っていても、他の者の目にはやはりきわめておみごとなものに見えるのであるが、
|
【集りて聞こえこしらふるに】- 主語は女房たち。
【いとわりなく】- 以下、落葉宮の心に即した叙述。
【あざやかなる御衣ども、人びとのたてまつり替へさするも】- 喪服から婚儀にふさわしい華やかな衣裳に着替えさせる。
|
| 5.5.2 |
|
「ひどく衰えたこと。
とても男の人にお見せできなる有様ではない。
いろいろと情けない身の上であるものを」
|
御自身では非常に衰えてしまった、もう結婚などのできる自分ではない、いろいろな不幸にむしばまれた自分なのだから
|
【いみじの衰へや】- 以下「心憂き身を」まで、落葉の宮の心中。
|
| 5.5.3 |
と思し続けて、また臥したまひぬ。
|
とお思い続けなさって、また臥せっておしまいになった。
|
とお思い続けになって、お召しかえになった姿をまたそのまま横たえておしまいになった。
|
|
| 5.5.4 |
|
「時刻に遅れます。
夜も更けてしまいます」
|
「時間が違ってしまう。夜がふけてしまうだろう」
|
【時違ひぬ。夜も更けぬべし】- 女房の詞。『集成』は「出発の時刻も吉時を選ぶ」と注す。
|
| 5.5.5 |
|
と、皆が騷ぐ。
時雨がとても心急かせるように風に吹き乱れて、何事にもつけ悲しいので、
|
などと言って、お供をする人たちは騒いでいた。時雨があわただしく山荘を打って、全体の気分が非常に悲しくなった。
|
【時雨いと心あわたたしう吹きまがひ、よろづにもの悲しければ】- 『完訳』は「宮の心象風景でもある」と注す。時雨は晩秋から初冬にかけての季節の景物。
|
| 5.5.6 |
|
「母君が上っていった峰の煙と一緒になって
思ってもいない方角にはなびかずにいたいものだわ」
|
上りにし峰の煙に立ちまじり
思はぬ方になびかずもがな
|
【のぼりにし峰の煙にたちまじり--思はぬ方になびかずもがな】- 落葉宮の独詠歌。『河海抄』は「須磨の海人の塩焼く煙風をいたみ思はぬ方にたなびきにけり」(古今集恋四、七〇八、読人しらず)を指摘。夕霧の意のままになるよりは、ここで死にたい、の意。
|
| 5.5.7 |
|
ご自分では気強く思っていらっしゃるが、そのころは、お鋏などのような物は、みな取り隠して、女房たちが目をお離し申さずいたので、
|
とお口ずさみになったとおりに宮は思召すのであるが、そのころは鋏刀などというものを皆隠して、お手ずから尼におなりになるようなことのないように女房たちが警戒申し上げていたから、
|
【御鋏などやうのものは】- 髪を下ろさないように。
|
| 5.5.8 |
|
「このように騒がないでいても、どうして惜しい身の上で、愚かしく、子供っぽくもこっそり髪を下ろしたりしようか。
人聞きも悪いとお思いなさることを」
|
そんなふうにお騒ぎをせずとも、惜しく尊重すべき自分でもないものを、しいて尼になってみずからを清くしようとも思わず、すればかえって人の反感を買うにすぎないことも知っているのであるから、
|
【かくもて騒がざらむにてだに】- 以下「思すまじかべきわざを」まで、落葉宮の心中。
【身にてか】- 係助詞「か」は「忍ばむ」連体形に係る。こっそり髪を下ろそうか、けっしてせぬ。反語表現。
|
| 5.5.9 |
と思せば、その本意のごともしたまはず。
|
とお思いになると、ご希望通り出家もなさらない。
|
と思召して宮は御本意を遂げようともあそばさないのである。
|
|
|
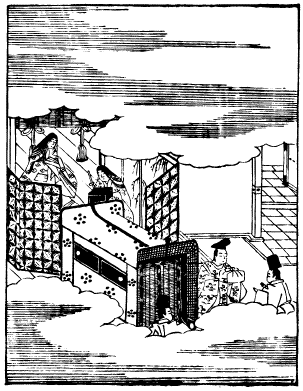 |
| 5.5.10 |
|
女房たちは、全員急ぎ出して、それぞれ、櫛や、手箱や、唐櫃や、いろいろな道具類を、つまらない袋入れのような物であるが、全部前もって運んでしまっていたので、独り居残っているわけにもゆかず、泣く泣くお車にお乗りになるのも、隣の空席ばかりに自然と目が行きなさって、こちらにお移りになった時、ご気分が優れなかったにも関わらず、御髪をかき撫でて繕って、降ろしてくださったことをお思い出しになると、目も涙にむせんでたまらない。
御佩刀といっしょに経箱を持っているが、いつもお側にあるので、
|
女房は皆移転の用意に急いで、お櫛箱、お手箱、唐櫃その他のお道具を、それも仮の物であったから袋くらいに皆詰めてすでに運ばせてしまったから、宮お一人が残っておいでになることもおできにならずに、泣く泣く車へお乗りになりながらも、あたりばかりがおながめられになって、こちらへおいでになる時に、御息所が病苦がありながらも、お髪をなでてお繕いして車からお下ろししたことなどをお思い出しになると、涙がお目を暗くばかりした。お護り刀とともに経の箱がお席の脇へ積まれたのを御覧になって、
|
【傍らのみまもられたまて】- 『集成』は「誰もいないお側が見つめられるばかりで。御息所がお側にいないさびしさである」。『完訳』は「『蜻蛉日記』康保元年秋、母を喪った作者が京の邸に変える条に、また鳴滝から京に連れ戻される条に類似」と注す。
【こち渡りたまうし時】- 「こち」は小野山荘をさす。「し」過去の助動詞。小野に来たころを回想。
【御心地の苦しきにも、御髪かき撫で】- 母御息所が気分悪いながらも宮の御髪を、の意。
【御佩刀に添へて経筥を添へたるが、御傍らも離れねば】- 「御佩刀」は守刀。「経」は法華経か。いずれも亡き母御息所から贈られた形見の品。
|
| 5.5.11 |
|
「恋しさを慰められない形見の品として
涙に曇る玉の箱ですこと」
|
恋しさの慰めがたき形見にて
涙に曇る玉の箱かな
|
【恋しさの慰めがたき形見にて--涙にくもる玉の筥かな】- 落葉宮の独詠歌。「形見」「筺」の掛詞。
|
| 5.5.12 |
|
黒造りのもまだお調えにならず、あの日頃親しくお使いになっていた螺鈿の箱なのであった。
お布施の料としてお作らせになったのだが、形見として残して置かれたのであった。
浦島の子の気がなさる。
|
とお歌いあそばされた。黒塗りのをまだお作らせになる間がなくて、御息所が始終使っていた螺鈿の箱をそれにしておありになるのである。御息所の容体の悪い時に誦経の布施として僧へお出しになった品であったが、形見に見たいからとまたお手もとへお取り返しになったものである。浦島の子のように箱を守ってお帰りになる宮であった。
|
【黒きもまだしあへさせたまはず】- 喪中に用いる黒漆塗の経箱もまだ新調せずに。
【誦経にせさせたまひしを、形見にとどめたまへるなりけり】- 僧へのお布施の料として作らせたのだが、の意。『細流抄』は「草子地也」と注す。
【浦島の子が心地なむ】- 浦島子が龍宮から玉手筥を持ち帰った気分。『奥入』は「夏の夜は浦島の子が箱なれやはかなく明けて悔しかるらむ」(拾遺集夏、一二一、中務)。『河海抄』は「常世べに雲立ちわたる水の江の浦島の子が言持ちわたる大和べに風吹き上げて雲放れ退き居りともよ吾を忘るな」(丹後国風土記)。『孟津抄』は「明けてだに何かはせむ水の江の浦島の子を思ひやりつつ」(後撰集雑一、一一〇五、中務)を指摘。
|
|
第六段 夕霧、主人顔して待ち構える
|
| 5.6.1 |
|
ご到着なさると、邸内は悲しそうな様子もなく、人の気配が多くて、様子が違っている。
お車を寄せてお降りになるに、全然、以前に住んでいた所とは思われず、よそよそしく嫌な気がなさるので、すぐにはお降りにならない。
とてもおかしな子供っぽいお振る舞いですわと、女房たちも拝見し困っている。
殿は、東の対の南面を、自分のお部屋として、仮に設けて、主人気取りでいらっしゃる。
三条殿では、女房たちが、
|
一条へお着きになると、ここは悲しい色などはどこにもなく、人が多く来ていて他家のようになっていた。車を寄せてお下りになろうとする時に、御自邸という気がされない不快な心持ちにおなりになって、動こうとあそばさないのを、あまりに少女らしいことであると言って女房たちは困っていた。大将は東の対の南のほうの座敷を仮に自身の使う座敷にこしらえて、もう邸の主人のようにしていた。三条の家では、だれもが、
|
【降りたまふを】- 接続助詞「を」逆接の気分。
【いとあやしう、若々しき御さまかな】- 女房たちの心中。
【殿は、東の対の南面を、わが御方を、仮にしつらひて、住みつき顔におはす】- 大島本は「わか御方を」とある。『集成』は諸本に従って「わが御方」と「を」を削除する。『完本』は諸本に従って「わが御方に」と校訂する。『新大系』は底本のままとする。夕霧は東対の南面を自分の部屋に設えて主人顔をしている。宮にとっては疎ましいさま。
【三条殿には】- 夕霧の本邸、北の方の雲居雁がいる邸。
|
| 5.6.2 |
|
「突然あきれたことにおなりになったこと。
いつからのことだったのかしら」
|
「急に別なお家と別な奥様がおできになったとはどうしたことでしょう。いつごろから始まった関係なのでしょう」
|
【にはかにあさましうも】- 以下「ありしことぞ」まで、女房の詞。
|
| 5.6.3 |
|
とあきれるのだった。
色めいた風流事を、お好きでなくお思いになる方は、このように突然な事がおありになるのだった。
けれども、何年も前からあった事を、噂にもならず素振り知られずにお過ごしになって来られたのだ、とばかりに思い込んで、このように、女のお気持ちは不承知であると、気づく人もいない。
いずれにしても宮の御ためにはお気の毒なことである。
|
と言って驚いていた。多情な恋愛生活などをしなかった人は、こうした思いがけぬことを実行してしまうものである。しかしだれも以前からあった関係をはじめて公表したことと解釈していて、まだ宮のお心は結婚に向いていぬことなどを想像する人もない。いずれにもせよ宮の御ために至極お気の毒なことばかりである。
|
【なよらかにをかしばめることを】- 『孟津抄』は「草子地也」と指摘。『完訳』は「以下、語り手の評言」と注す。
【好ましからず思す人は】- 夕霧をいう。「思す」という敬語は皮肉にも聞こえる。
【されど、年経にけることを】- 「年経にけること」以下、「たまうけるなり」まで、夕霧の心中に即した語り手の文。「年経にけること」は落葉宮との関係。
【過ぐしたまうける】- 夕霧に対する敬語。
【思ひなして】- 主語は夕霧。
【思ひ寄る人もなし】- 夕霧の振る舞いと宮の気持ちの違いを女房は誰一人気づかない意。
【とてもかうても、宮の御ためにぞいとほしげなる】- 『細流抄』は「草子地也」と指摘。『完訳』は「語り手の評言」と注す。
|
| 5.6.4 |
|
お調度類なども普段と変わって、新婚としては縁起が悪いが、お食事を差し上げたりした後、皆が寝静まったころにお渡りになって、少将の君をひどくお責めになる。
|
御結婚の最初の日の儀式が精進物のお料理であることは縁起のよろしくなく見えることであったが、お食事などのことが終わって、一段落のついた時に、夕霧はこちらへ来て宮の御寝室への案内を、少将にしいた。
|
【御まうけなどさま変はりて】- 新婚の祝儀、喪中のため普通の祝儀とは違うさま。
【もののはじめゆゆしげなれど】- 新婚の諸式が縁起でもないようだが。
【もの参らせなど】- 「など」の下に「して」などの語句が省略。
|
| 5.6.5 |
|
「ご愛情が本当に末長くとお思いでしたら、今日明日を過ぎてから申し上げて下さいませ。
お帰りになって、かえって、悲しみに沈み込んで、亡くなった方のようにお臥せりになってしまわれました。
おとりなし申し上げても、辛いとばかりお思いでいらっしゃるので、何事もわが身あってでございますもの。
まことに困って、申し上げにくうございます」
|
「いつまでもお変わりにならぬ長いお志でございますなら、今日明日だけをお待ちくださいませ。もとのお住居へお帰りになりますとまたお悲しみが新しくなりまして、生きた方のようでもなく泣き寝におやすみになったのでございます。おなだめいたしましてもかえってお恨みになるのでございますから、私どももその苦痛をいたしたくございません。殿様のことを宮様に申し上げることはできないのでございます」
|
【御心ざしまことに長う】- 以下「聞こえさせにくくなむ」まで、小少将君の詞。
【立ち帰りてもの思し沈みて】- 『完訳』は「宮は、自邸に帰ってうれしいはずなのに、かえって」と注す。
【こしらへきこゆるをも】- 小少将君ら女房が、夕霧との結婚を納得するように執り成し申し上げる。
【何ごとも身のためこそはべれ】- 「身」は、我が身。『集成』は「挿入句。女房の分際として、不興を買うわけにはいかない、の意」。『完訳』は「「はべれ」まで挿入句。主人の機嫌を損ねては、女房として身が立たない意。使用人根性の弁」と注す。
【いとわづらはしう】- 『集成』は「ご不興がいかにも恐ろしく」。『完訳』は「ほんとに面倒なことで」と訳す。
【聞こえさせにくくなむ】- 係助詞「なむ」の下に「はべる」などの語句が省略。
|
| 5.6.6 |
と言ふ。
|
と言う。
|
と少将は言う。
|
|
| 5.6.7 |
「いとあやしう。推し量りきこえさせしには違ひて、いはけなく心えがたき御心にこそありけれ」 |
「まことに妙なことです。
ご推量申し上げていたのとは違って、子供っぽく理解しがたいお考えでありますね」
|
「変なことではないか、聡明な方のように想像していたのに、こんなことでは幼稚なところの抜けぬ方と思うほかはないではないか」
|
【いとあやしう】- 以下「御心にこそありけれ」まで、夕霧の詞。
|
| 5.6.8 |
|
とおっしゃって、考えていらっしゃる処遇は、宮の御ためにも、自分のためにも、世間の非難のないようにおっしゃり続けるので、
|
夕霧が自分の考えを言って、宮のためにも、自分のためにも世間の批議を許さぬ用意の十分あることを説くと、
|
【思ひ寄れるさま】- 『集成』は「落葉の宮の処遇についてのこと。雲居の雁と並ぶ正室としてお扱いするということなのであろう」と注す。
【人の御ためも】- 落葉宮をさす。
|
| 5.6.9 |
|
「いえもう、ただ今は、またもお亡くし申し上げてしまうのではないかと、気が気ではなく取り乱しておりますので、万事判断がつきません。
お願いでございます、あれこれと無理押しなさって、乱暴なことはなさいませぬように」
|
「それはそうでございましょうが、ただ今ではお命がこのお悲しみでどうかおなりになるのでないかということだけを私どもは心配いたしておりまして、そのほかのことは何も考えられないのでございます。殿様、お願いでございますから、しいて御無理なことはあそばさないでくださいませ」
|
【いでや、ただ今は】- 以下「御心なつかはせたまひそ」まで、小少将の君の詞。
【またいたづら人に見なしたてまつるべきにや】- 御息所に続いて宮も亡くなってしまうのではないか、の意。
【あが君】- 集成「多く、相手に懇願する時に呼び掛ける言葉」と注す。
|
| 5.6.10 |
と手をする。
|
と手を擦って頼む。
|
と少将は手をすり合わせて頼んだ。
|
|
| 5.6.11 |
|
「これはまだ経験のないことだ。
憎らしく嫌な者だと、人より格段に軽蔑される身の上が情けない。
是非とも誰かにでも判断してもらいたい」
|
「聞いたことも見たこともないお取り扱いだ。過去の一人の男ほどにも愛していただけない自分が哀れになる。世間へも何の面目があると思う」
|
【いとまだ知らぬ世かな】- 以下「ことわらせむ」まで、夕霧の詞。『集成』は「まだ知らぬ」。『完訳』は「また知らぬ」と整定。
【人よりけに思し落とすらむ身こそ】- 『完訳』は「柏木よりも。「身」は夕霧自身」と注す。
|
| 5.6.12 |
と、いはむかたもなしと思してのたまへば、さすがにいとほしうもあり、
|
と、言いようもないとお思いになっておっしゃるので、やはりお気の毒でもあり、
|
失望してこう言う夕霧を見てはさすがに同情心も起こった。
|
|
| 5.6.13 |
|
「まだ知らないとおっしゃるのは、なるほど恋愛経験の少ないお人柄だからでしょうと、道理は、仰せのとおり、どちら様を正しいと申す人がございますでしょうか」
|
「聞いたことも見たこともないと申しますことは、あなた様のあまりにお早まりになった御用意のことでございましょう。道理はどちらにあると世間が申すでございましょうか」
|
【まだ知らぬは】- 以下「はべらむとすらむ」まで、小少将の君の詞。「まだ知らぬ」は夕霧の言葉を受けて返した。『集成』は「まだ知らぬ」。『完訳』は「また知らぬ」と整定。
【世づかぬ御心がまへの】- 夕霧を恋愛経験未熟ゆえだと非難する。『集成』は「夕霧のやり方を軽くたしなめる」。『完訳』は「恋愛体験に乏しく、情愛の機微が分らぬ、とからかう」と注す。
【いづ方にかは】- 「すらむ」にかかる。疑問形の構文だが、趣旨は夕霧の方を道理に反するとしよう、という含み。
|
| 5.6.14 |
|
と、少しほほ笑んだ。
|
と少し少将は笑った。
|
【すこしうち笑ひぬ】- 『完訳』は「少将は少し笑顔になる」。やや皮肉をこめた微笑。
|
|
第七段 落葉宮、塗籠に籠る
|
| 5.7.1 |
|
このように強情であるが、今となっては、邪魔立てされなさるおつもりもないので、そのままこの人を引き立てて、当て推量にお入りになる。
|
こんなふうに強く抵抗をしてみても、今はよその人でなく主人と召使の関係になっている相手であるから、拒み続けることはさせないで、少将をつれて、おおよその見当をつけた宮の御寝室へはいって行った。
|
【かく心ごはけれど】- 小少将の君をさす。『湖月抄』は「草子地よりいふ也」と注す。
【堰かれたまふべきならねば】- 主語は夕霧。「れ」受身の助動詞。
|
| 5.7.2 |
|
宮は、「まことに嫌でたまらない、思いやりのない浅薄な心の方だった」と、悔しく辛いので、「大人げないようだと言われようとも」とご決意なさって、塗籠にご座所を一つ敷かせなさって、内側から施錠して、お寝みになってしまった。
「これもいつまで続くことであろうか。
これほどに浮き足立っている女房たちの気持ちは、何と悲しく残念なことか」とお思いなさる。
|
宮はあまりに思いやりのない心であると恨めしく思召されて、若々しいしかただと女房たちが言ってもよいという気におなりになって、内蔵の中へ敷き物を一つお敷かせになって、中から戸に錠をかけてお寝みになった。しかもこうしておられることもただ時間の問題である、こんなふうにも常規を逸してしまった人は、いつまで自分をこうさせてはおくまいと悲しんでおいでになった。
|
【いと心憂く】- 以下「人の心なりけり」まで、落葉宮の心中。
【人の心なりけり】- 小少将の君をさす。完訳「夕霧への憤りはもちろん、手引した小少将にも裏切られたと、今にして「--けり」と気づく」と注す。
【若々しきやうには言ひ騒ぐとも】- 落葉宮の心中。居直りの気持ち。
【これもいつまでにかは】- 『集成』は「以下、落葉の宮の心」。『全集』は「語り手の言辞。情交は時間の問題」と注す。
【かばかりに乱れ立ちにたる人の心どもは】- 夕霧に心をかよわしている浮足立った女房たちの思慮。宮の心中に立った視点。
|
| 5.7.3 |
|
男君は、心外なひどい仕打ちとお思い申し上げなさるが、このようなことで、どうして逃れることができようかと、気長にお考えになって、いろいろと思案しながら夜をお明かしなさる。
山鳥の気がなさるのであった。
やっとのことで明け方になった。
こうしてばかり、取り立てて言うと、にらみ合いになりそうなので、お出になろうとして、
|
大将は驚くべき冷酷なお心であると恨めしく思ったが、これほどの抵抗を受けたからといって、自分の恋は一歩もあとへ退くものではない、必ず成功を見る時が来るのであるというこんな自信を持ってこの夜を明かすのであって、渓を隔てて寝るという山鳥の夫婦のような気がした。ようやく明けがたになった。こうして冷淡に扱われた顔を皆に見せることが恥ずかしくて大将は出て行こうとする時に、
|
【男君は】- 『集成』は「夫の君といった感じの呼び方」。『完訳』は「男女関係強調の呼称」と注す。
【かばかりにては、何のもて離るることかはと】- 『集成』は「もうこうなっては、相手ものがれようのないことだと」。『完訳』は「これくらいのことでどうしてあきらめられるものかと」と訳す。宮が塗籠に隠れたことをさす。「なにの--かは」反語表現。
【山鳥の心地ぞしたまうける】- 『異本紫明抄』は「昼は来て夜は別るる山鳥の影見る時ぞ音は泣かれける」(新古今集恋五、一三七一、読人しらず)。『河海抄』は「あしびきの山鳥の尾のしだり尾の長々し夜を一人かも寝む」(拾遺集恋三、七七八、柿本人麿)を指摘。山鳥は雌雄が峯を隔てて別々に寝るとされていた(俊頼髄脳・奥義抄・袖中抄)。
【かくてのみ、ことといへば、直面なべければ】- 『集成』は「こんなことでは、下手をすると、露骨なにらみ合いということになりかねないので」。『完訳』は「いつまでもこうしていたのでは、人に顔を見られてきまりわるい思いをするのがおちだから」と注す。
|
| 5.7.4 |
|
「ただ、少しの隙間だけでも」
|
「ただ少しだけ戸をおあけください。お話ししたいことがあるのですから」
|
【ただ、いささかの隙をだに】- 夕霧の詞。
|
| 5.7.5 |
と、いみじう聞こえたまへど、いとつれなし。
|
と、しきりにお頼み申し上げなさるが、まったくお返事がない。
|
としきりに望んだがなんらの反応も見えない。
|
|
| 5.7.6 |
|
「怨んでも怨みきれません、
胸の思いを晴らすことのできない冬の夜に
|
「うらみわび胸あきがたき冬の夜に
またさしまさる関の岩かど
|
【怨みわび胸あきがたき冬の夜に--また鎖しまさる関の岩門】- 夕霧から落葉宮への贈歌。
|
| 5.7.7 |
|
何とも申し上げようのない冷たいお心です」
|
言いようもない冷たいお心です」
|
【聞こえむ方なき御心なりけり】- 歌に添えた言葉。
|
| 5.7.8 |
と、泣く泣く出でたまふ。
|
と、泣く泣くお出になる。
|
と言って、それから泣く泣く出て行った。
|
|
|
第六章 夕霧の物語 雲居雁と落葉宮の間に苦慮
|
|
第一段 夕霧、花散里へ弁明
|
| 6.1.1 |
|
六条院にいらっしゃって、ご休息なさる。
東の上は、
|
大将は六条院へ来て休息をした。花散里夫人が、
|
【東の上】- 花散里。夕霧の母代。
|
| 6.1.2 |
|
「一条の宮をお移し申し上げなさったと、あの大殿あたりなどでお噂申しているのは、どのようなことなのですか」
|
「一条の宮様と御結婚なすったと太政大臣家あたりではお噂しているようですが、ほんとうのことはどんなことなのでしょう」
|
【一条の宮】- 以下「いかなる御ことにかは」まで、花散里の詞。
【いかなる御ことにかは】- 疑問の構文。下に「あらむ」などの語句が省略。
|
| 6.1.3 |
|
と、とてもおっとりとお尋ねになる。
御几帳を添えているが、端からちらちらと、それでも顔をお見せ申し上げなさる。
|
とおおように尋ねた。御簾に几帳を添えて立ててあったが、横から優しい継母の顔も見えるのである。
|
【御几帳添へたれど】- 夕霧との間に御簾の他にさらに御几帳を添えて隔てている、意。
【側よりほのかには、なほ見えたてまつりたまふ】- 主語は花散里。『集成』は「養母としての花散里の飾らない人柄が示されている」。『完訳』は「彼女が夕霧を見たいためでもある」と注す。
|
| 6.1.4 |
|
「そのようにも、やはり世間の人は取り沙汰しそうなことでございます。
故御息所は、とても気強く、とんでもないことときっぱりおっしゃいましたが、最期の様子の時に、お気持ちが弱られた折に、わたし以外に後見を依頼できる人のないのが悲しかったのでしょうか、亡くなった後の後見というようなことがございましたので、もともとの心積もりもございましたことなので、このようにお引き受け致すことになりましたが、あれこれと、どのように世間の人は噂するのでございましょう。
そうでないことをも、不思議と世間の人は、口さがないものです」
|
「そんなふうに噂もされるでしょう。亡くなられた御息所は、最初私が申し込んだころにはもってのほかのことのように言われたものですが、病気がいよいよ悪くなったころに、ほかに託される人のないのが心細かったのですか、自分の死後の宮様を御後見するようにというような遺言をされたものですから、初めから好きだった方でもあるのですから、こういうことにしたのですが、それをいろいろに付会した噂もするでしょう。そう騒ぐことでないことを人は問題にしたがりますね」
|
【さやうにも、なほ人の】- 以下「さかなきものにあれ」まで、夕霧の詞。
【また見譲るべき人のなき】- 大島本は「ゆつる」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「見譲る」と「見」を補訂する。『新大系』は底本のままとする。自分夕霧以外に世話をする人はいない、意。
【亡からむ後の後見にとやうなることのはべりしかば】- 御息所から夕霧に贈られた「女郎花」歌を踏まえて言う。
【もとよりの心ざしもはべりしことにて】- 『完訳』は「柏木の遺言をさすか」「もとより故人とのよしみもございますこととて」と注す。
【かく思たまへなりぬるを】- 落葉宮を宮邸に迎えて結婚したことをさす。
【あやしう人こそ、もの言ひさがなきものにあれ】- 『河海抄』は「ここにしも何匂ふらむ女郎花人の物言ひさがにくき世に」(拾遺集雑秋、一〇九八、僧正遍昭)を指摘。
|
| 6.1.5 |
|
と、ほほ笑みながら、
|
と夕霧は笑って、
|
【と、うち笑ひつつ】- 夕霧の会話文と会話文の間に挿入した地の文。余裕を見せた笑み。
|
| 6.1.6 |
|
「あのご本人の宮は、もう普通の暮らしはするまいと深く決心なさって、尼になってしまいたいと思い詰めていらっしゃるようなので、どうしてどうして。
あちら方こちら方に聞きずらいことでもございますが、そのように嫌疑を招かぬことになったとしても、また一方で、あの遺言に背くまいと存じまして、ただこのようにお世話申しているのでございます。
|
「ところが御本人はまだ尼になりたいとばかり考えておいでになるのですから、それもそうおさせして、いろいろに続き合った面倒な人たちから悪く言われることもなくしたほうがよいとは思われますが、私としては御息所の遺言を守らねばならぬ責任感があって、ともかくも形だけは私が良人になって同棲することにしたのです。
|
【かの正身なむ】- 以下「はべりけれ」まで、夕霧の詞。落葉宮をさす。
【尼になりなむと】- 「なり」動詞、連用形、「な」完了の助動詞、確述の意、「む」推量の助動詞、意志の意。尼になってしまいたい、の意。なお願望の終助詞「なむ」は未然形に接続し、他に対する誂えの願望を表す。自らの願望は終助詞「ばや」である。
【何かは】- 『集成』は「正しくは反語で受けるべきであるが、「またかの遺言は違へじ」で受けられる」と注す。
【さやうに嫌疑離れても】- 夕霧との仲の嫌疑を離れるとは、出家し尼になったとしても、の意。
【かの遺言は違へじと】- 御息所が宮の後見を頼むという遺言。
|
| 6.1.7 |
|
院がお渡りあそばしたような時に、よい機会がございましたら、このようにわたしの申したとおりに申し上げてください。
この年になって、感心しない浮気心を起こしたと、お思いになりおっしゃりもするだろうと気にいたしておりますが、なるほど、このようなことには、人の意見にも、自分の心にも従えないものだということが分かりました」
|
院がこちらへおいでになりました時にもお話のついでにそのとおりに申し上げておいてください。堅く通して来ながら、今になって人が批難をするような恋を始めるとはけしからんなどとお言いにならないかと遠慮をしていたのですが、実際恋愛だけは人の忠告にも自身の心にも従えないものなのですからね」
|
【院の渡らせたまへらむにも】- 源氏がこちらにいらっしゃった時に。
【思しのたまはむを】- 主語は源氏。
【げに、かやうの筋にてこそ】- 『完訳』は「恋は盲目と世間で言うとおり」と注す。
|
| 6.1.8 |
と、忍びやかに聞こえたまふ。
|
と、声を小さくして申し上げなさる。
|
とも忍びやかに言うのだった。
|
|
| 6.1.9 |
|
「誰かの間違いではないかと思っておりましたが、本当にそのようなご事情があったのですね。
すべて世間によくある事ですが、三条の姫君がご心配なさるのも、お気の毒です。
平穏無事に馴れていらっしゃって」
|
「私は人の作り事かと思って聞いていましたが、そんなことでもあるのですね。世間にはたくさんあることですが、三条の姫君がどう思っていらっしゃるだろうかとおかわいそうですよ。今まであんなに幸福だったのですから」「可憐な人のようにお言いになる姫君ですね。がさつな鬼のような女ですよ」
|
【人のいつはりにやと】- 以下「のとやかに慣らひたまうて」まで、花散里の詞。
【三条の姫君の思さむことこそ、いとほしけれ】- 雲居雁をさす。夕霧の北の方を「姫君」と、ちょっと変わった言い方をした。
【慣らひたまうて】- 接続助詞「て」逆接の意で言いさした、余情表現。
|
| 6.1.10 |
と聞こえたまへば、
|
と申し上げなさると、
|
と言って、また、
|
|
| 6.1.11 |
|
「かわいらしくおっしゃいますね、姫君とはね。
まるで鬼のようでございます性悪な者を」とおっしゃって、「どうして、その人をいい加減に扱っておりましょうか。
恐れ多いですが、こちらのご夫人方のご様子からご推量ください。
|
「決してそのほうもおろそかになどはいたしませんよ。失礼ですがあなた様御自身の御境遇から御推察なすってください。
|
【らうたげにも】- 以下「さがなものを」まで、夕霧の詞。「らうたげに」は花散里の「姫君」という呼称のしかたをさしていう。
【などてか、それをも】- 「見たてまつり果てはべりぬれ」まで、夕霧の詞。「それ」は雲居雁をさす。「などてか--はべらむ」反語構文。
【御ありさまどもにても、推し量らせたまへ】- 六条院のご夫人方のお互いに嫉妬しないありさまからご想像してほしい、の意。
|
| 6.1.12 |
なだらかならむのみこそ、人はつひのことにははべめれ。さがなくことがましきも、しばしはなまむつかしう、わづらはしきやうに憚らるることあれど、それにしも従ひ果つまじきわざなれば、ことの乱れ出で来ぬる後、我も人も、憎げに飽きたしや。 |
穏やかである事だけが、女性として結局良いことのようでございます。
口やかましく事を荒立てるのも、暫くの間は煩しく、面倒くさいように遠慮することもありますが、それに必ずしも最後まで従うものではないので、浮気沙汰が出てきた後、自分も相手も、憎らしそうに嫌気のさすものです。
|
穏やかにだれへも好意を持って暮らすのが最後の勝利を得る道ではございませんか。嫉妬深いやかましく言う女に対しては、当座こそ面倒だと思ってこちらも慎むことになるでしょうが、永久にそうしていられるものではありませんから、ほかに対象を作る日になると、いっそうかれはやかましくなり、こちらは倦怠と反感をその女から覚えるだけになります。
|
【ことの乱れ出で来ぬる後】- 浮気沙汰が表面化した後。
|
| 6.1.13 |
|
やはり、南の殿の上のお心遣いこそが、いろいろとまたとないことで、それに次いではこちらのお気立てなどが、素晴らしいものとして、拝見するようになりました」
|
そうしたことで、こちらの南の女王の態度といい、あなた様の善良さといい、皆手本にすべきものだと私は信じております」
|
【南の御殿の御心もちゐこそ】- 紫の上の気立てをいう。
【さてはこの御方の御心などこそは】- 紫の上に次いでは、こちら花散里の気立てが、の意。
|
| 6.1.14 |
など、ほめきこえたまへば、笑ひたまひて、
|
などと、お誉め申し上げなさると、お笑いになって、
|
と継母をほめると、夫人は笑って、
|
|
| 6.1.15 |
|
「そうした女性の例に出したりなさるので、我が身の体裁の悪い評判がはっきりしてしまいそうで。
|
「物の例にお引きになればなるほど、私が愛されていない妻であることが明瞭になりますよ。
|
【もののためしに】- 以下「おぼえはべれ」まで、花散里の詞。
【引き出でたまふほどに】- 目的語は花散里自分を。
【身の人悪ろきおぼえこそあらはれぬべう】- 『完訳』は「夫からの冷遇に腹も立てない女の手本にされるのでは、名誉でもない、の気持。軽い皮肉である」と注す。係助詞「こそ」の結びは流れている。「べけれ」と言い切った表現よりも言いさした表現に余情効果が生じる。
|
| 6.1.16 |
|
ところで、おかしなことは、院が、ご自分の女癖を誰も知らないように、ちょっとした好色めいたお心遣いを、重大事とお思いになって、お諌め申し上げなさる。
陰口をも申し上げなさっているらしいのは、賢ぶっている人が、自分のことは知らないでいるように思われます」
|
それにしましてもおかしいことは、院は御自身の多情なお癖はお忘れになったように、少しの恋愛事件をお起こしになるとたいへんなことのようにお訓しになろうとしたり、蔭でも御心配になったりするのを拝見しますと、賢がる人が自己のことを棚に上げているということのような気がしてなりませんよ」
|
【さて、をかしきことは、院の、みづからの】- 話題転換、源氏の身の上について話題を転じる。
【いささかあだあだしき御心づかひをば】- 夕霧の「あだあだしき御心遣ひ」をさす。
【大事と思いて】- 主語は源氏。
|
| 6.1.17 |
とのたまへば、
|
とおっしゃると、
|
こう花散里夫人が言った。
|
|
| 6.1.18 |
|
「さように、
いつも女性の事では厳しくお仰せになります。しかし、恐れ多い教えを戴かなくて
|
「そうですよ。始終品行のことで教訓を受けますよ。親の言葉がなくても私は浮気なことなどをする男でもないのに」
|
【さなむ、常に】- 以下「をさめてはべる心を」まで、夕霧の詞。「仰せらるる」は連体中止法、余情表現と見る。
【この道を】- 女性関係の問題をさす。
【をさめてはべる心を】- 夕霧自身の心。「を」間投助詞、詠嘆の意。
|
| 6.1.19 |
とて、げにをかしと思ひたまへり。
|
とおっしゃって、なるほどおかしいと思っていらっしゃった。
|
大将は非常におかしいと思うふうであった。
|
|
| 6.1.20 |
|
御前に参上なさると、あの事件はお聞きあそばしていらしたが、どうして知っている顔をしていられようかとお思いになって、ただじっと顔を窺っていらっしゃると、
|
院のお居間へも来た大将を御覧になって、院は新事実を知っておいでになったが、知った顔を見せる必要はないとしておいでになって、ただ顔をながめておいでになるのであった。
|
【御前に参りたまへれば】- 夕霧が源氏の御前に。
【何かは聞き顔にも】- 源氏の心中。「何かは」反語表現。「聞き顔にも」の下に「見えむ」などの語句が省略。
|
| 6.1.21 |
|
「実に素晴らしく美しくて、最近特に男盛りになったようだ。
そのような浮気事をなさっても、人が非難すべきご様子もなさっていない。
鬼神も罪を許すに違いなく、鮮やかでどことなく清らかで、若々しく今を盛りに生気溌剌としていらっしゃる。
|
それは非常に美しくて今が男の美の盛りのような夕霧であった。今問題になっているような恋愛事件をこの人が起こしても、だれも当然のことと認めてしまうに違いないと思召された。鬼神でも罪を許すであろうほどな鮮明な美貌からは若い光と匂いが散りこぼれるようである。
|
【いとめでたくきよらに】- 以下「などかおごらざらむ」まで、源氏の目に映じた夕霧の姿を心中に思う。『完訳』は「夕霧二十九歳。父親としての源氏の目と心にそって貫祿十分なその風姿が語られる」と注す。
【さるさまの好き事をしたまふとも】- 落葉宮との関係をさす。
|
| 6.1.22 |
|
何の分別もない若い人ではいらっしゃらず、どこからどこまですっかり成人なさっている、無理もないことだ。
女性として、どうして素晴らしいと思わないでいられようか。
鏡を見ても、どうして心奢らずにいられようか」
|
感情にまだ多少の欠陥のある青年者でもなく、どこも皆完全に発達したきれいな貴人であると院は御覧になって、問題の起こるのももっともである。女でいてこの人を愛せずにおられるはずもなく、鏡を見てみずから慢心をせぬわけもなかろう
|
【もの思ひ知らぬ若人のほどにはたおはせず】- 夕霧をさしていう。
【ことわりぞかし】- 挿入句。上の「ねびととのほりたまへる」は下の「女にて」の原因理由を表す。
【などかめでざらむ】- 反語表現。誰でも素晴らしいと思う、の意。
|
| 6.1.23 |
と、わが御子ながらも、思す。
|
と、ご自分のお子ながらも、そうお思いになる。
|
とわが子ながらもお思いになる院でおありになった。
|
|
|
第二段 雲居雁、嫉妬に荒れ狂う
|
| 6.2.1 |
|
日が高くなって、殿にお帰りになった。
お入りになるや、若君たちが、次々とかわいらしい姿で、纏わりついてお遊びになる。
女君は、御帳台の中に臥せっていらっしゃった。
|
昼近くなって大将は三条の家へ帰ったのであった。家へはいるともうすぐに何人もの同じほどの子供たちがそばへまつわりに来た。夫人は帳台の中に寝ていた。
|
【日たけて、殿には渡りたまへり】- 夕霧、日が高くなってから三条殿に帰邸。
【入りたまふより、若君たち】- 格助詞「より」時間の起点を表す、入るや否や、の意。
【女君は、帳の内に臥したまへり】- 『完訳』は「雲居雁は一睡もせず夕霧の帰邸を待っていたのだろう」と注す。
|
| 6.2.2 |
|
お入りになったが、目もお合わせにならない。
ひどいと思っているのであろう、と御覧になるのもごもっともであるが、遠慮した素振りもお見せにならず、お召し物を引きのけなさると、
|
大将がそこへ行っても目も見合わせようとしない。恨めしいのであろう、もっともであると夕霧も知っているのであるが、気にとめぬふうをして夫人の顔の上にかかった夜着の端をのけると、
|
【入りたまへれど】- 夕霧が御帳台の中に。
【つらきにこそはあめれ】- 夕霧の心中。雲居雁の気持を推察。
|
| 6.2.3 |
|
「ここをどこと思っていらっしゃったのですか。
わたしはとっくに死にました。
いつも鬼とおっしゃるので、同じことならすっかりなってしまおうと思って」
|
「ここをどこと思っておいでになったのですか。私はもう死んでしまいましたよ。平生から私のことを鬼だとお言いになりますから、いっそほんとうの鬼になろうと思って」
|
【いづことておはしつるぞ】- 以下「なり果てなむとて」まで、雲居雁の詞。皮肉をこめた言い方。
【まろは早う死にき】- 『源注拾遺』は「あらばこそ初めも果ても思ほえめ今日にも逢はで消えにしものを」(大和物語)「恋しとも今は思はず魂の逢ひ見ぬさきに亡くなりぬれば」(興風集)を指摘。
|
| 6.2.4 |
とのたまふ。
|
とおっしゃる。
|
と夫人は言った。
|
|
| 6.2.5 |
|
「お心は、鬼以上でいらっしゃるが、姿形は憎らしくもないので、すっかり嫌いになることはできないな」
|
「あなたの気持ちは鬼以上だけれど、あなたの顔はそうでないから私はきらいになれないだろう」
|
【御心こそ、鬼より】- 以下「え疎みはつまじ」まで、夕霧の詞。『完訳』は「相手の言葉じりを捉えてからかい、美貌をほめて機嫌をとる」と注す。係助詞「こそ」--「おはすれ」已然形、読点、逆接用法。『源注拾遺』は「恋しくは影をだに見て慰めよ我が打ち解けて忍ぶ顔なり」(後撰集恋五、九一〇、読人しらず)「影見ればいとど心ぞ惑はるる近からぬけの疎きなりけり」(後撰集恋五、九一一、伊勢)を指摘。
|
| 6.2.6 |
|
と、何くわぬ顔でおっしゃるのも、癪にさわって、
|
何一つやましいこともないようにこんな冗談を言う良人を夫人は不快に思って、
|
【心やましうて】- 『完訳』は「雲居雁は真剣なだけに、夫のごまかしの冗談に腹が立つ」と訳す。
|
| 6.2.7 |
|
「結構な姿形で優美に振る舞っていらっしゃるお方に、いつまでも連れ添っていられる身でもありませんので、どこへなりとも消え失せようと思うのを、このようにさえお思い出しますな。
いつのまにか過ごした年月さえ、惜しく思われるものを」
|
「美しい恋をする人たちの中に混じって生きていられない私ですから、どんな所でも行ってしまいます、もうあなたの念頭になぞ置かれたくない。長くいっしょにいたことすら後悔しているのですから」
|
【めでたきさまに】- 以下「くやしきものを」まで、雲居雁の詞。夕霧の姿をさしていう。
【あり経べき身にもあらねば】- 雲居雁わが身をいう。
【失せなむとするを、かくだにな思し出でそ】- 大島本は「うせなむとする越」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「失せなむとす。なほ」と校訂する。『新大系』は底本のままとする。『集成』は「今日のようにたまに思い出して尋ねてくるようなこともしてほしくない、の意」。『完訳』は「「さまは憎げも--」を受け、私を美貌とさえ思い出すな、の意。相手のうれしがらせが快く耳に残った。人の好さが躍如」と注す。
|
| 6.2.8 |
|
と言って、起き上がりなさった様子は、たいそう愛嬌があって、つやつやとして赤くなった顔、実に美しい。
|
と言って、起き上がった夫人の愛嬌のある顔が真赤になっていて一種の魅力をもっていた。
|
【匂ひやかにうち赤みたまへる顔】- 『完訳』は「興奮して赤らむ顔も魅力的」と注す。
|
| 6.2.9 |
「かく心幼げに腹立ちなしたまへればにや、目馴れて、この鬼こそ、今は恐ろしくもあらずなりにたれ。神々しき気を添へばや」 |
「このように子供っぽく腹を立てていらっしゃるからでしょうか、見慣れて、この鬼は、今では恐ろしくもなくなってしまったなあ。
神々しい感じを加わえたいものだ」
|
「子供らしく始終腹をたてる鬼だから、もう見なれて怖ろしい気はしなくなった。少し恐ろしいところを添えたいね」
|
【かく心幼げに】- 以下「神々しき気を添へばや」まで、夕霧の詞。からかいの言葉。
|
| 6.2.10 |
と、戯れに言ひなしたまへど、
|
と、冗談事におっしゃるが、
|
と良人が冗談事にしてしまおうとするのを、
|
|
| 6.2.11 |
「何ごと言ふぞ。おいらかに死にたまひね。まろも死なむ。見れば憎し。聞けば愛敬なし。見捨てて死なむはうしろめたし」 |
「何を言うの。
あっさりと死んでおしまいなさい。
わたしも死にたい。
見ていると憎らしい。
聞くも気にくわない。
後に残して死ぬのは気になるし」
|
「何を言っているのですか。おとなしく死んでおしまいなさいよ。私も死にますよ。いろんなことを聞いているとますますあなたがいやになりますよ。置いて死ねばまたどんなことをなさるかと気がかりだから」
|
【何ごと言ふぞ】- 以下「うしろめたし」まで、雲居雁の詞。『完訳』は「雲居雁はいよいよ興奮。相手への敬語も省く。以下、短い言葉を矢つぎばやに発する」と注す。
|
| 6.2.12 |
|
とおっしゃるが、とても愛らしさが増すばかりなので、心からにっこりして、
|
と腹をたてるのであるが、ますます愛嬌の出てくる夫人を夕霧は笑顔で見ながら、
|
【こまやかに笑ひて】- 『集成』は「こみあげるように」。『完訳』は「にこやかな笑顔になって」と訳す。
|
| 6.2.13 |
「近くてこそ見たまはざらめ、よそにはなにか聞きたまはざらむ。さても、契り深かなる瀬を知らせむの御心ななり。にはかにうち続くべかなる冥途のいそぎは、さこそは契りきこえしか」 |
「近くで御覧にならなくても、よそながらどうして噂をお聞きにならないわけには行きますまい。
そうして、夫婦の縁の深いことを分からせようとのおつもりのようですね。
急に続くような冥土への旅立ちは、そのようにお約束申したからね」
|
「近くで見るのがいやになっても、私の噂を無関心には聞かないでしょう。あなたはどんなに二人の宿縁の深いかを知らすために、私を殺して自分も死のうというのですね。二人の葬儀をいっしょにしてもらうというような約束は前にしてあったのだからね」
|
【近くてこそ】- 以下「契りきこえしか」まで、夕霧の詞。係助詞「こそ」--「見たまはざらめ」已然形、逆接用法。「見たまはざらめ」の目的語は、わたし夕霧を。
【よそにはなにか】- 大島本は「なにか」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「などか」と校訂する。『新大系』は底本のままとする。「なにか」--「聞きたまはざらむ」反語表現。
|
| 6.2.14 |
|
と、まこと素っ気なく言って、何やかやと宥めすかし申し慰めなさると、とても若々しく素直で、かわいらしいお心の持ち主でいらっしゃる方なので、口からの出まかせの言葉とはお思いになりながら、自然と和らいでいらっしゃるのを、とても愛しい人だとお思いになる一方で、心はうわの空で、
|
大将はまだ夫人の嫉妬に取り合わないふうをして、いろいろにすかしたり、なだめたりしていると、若々しく単純な性質の夫人であるから、良人の言葉はいいかげんな言葉であると思いながらも機嫌が直ってゆくのを、哀れに思いながらも、大将の心は一条の宮へ飛んでいた。
|
【いとつれなく言ひて】- 『集成』は「相手にもせずあしらって」。『完訳』は「まったく取り合う様子もなくあしらって」と訳す。
【何くれと慰めこしらへきこえ慰めたまへば】- 大島本は「なにくれとなくさめこしらへきこえなくさめ給へハ」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「何くれとこしらへきこえ慰めたまへば」と「慰め」を削除する。『新大系』は底本のままとする。
【いと若やかに心うつくしう】- 雲居雁の心根。
【いとあはれと思すものから】- 主語は夕霧。
|
| 6.2.15 |
|
「あの方も、とても我を張って、強く頑固な人の様子にはお見えではないが、もしやはり不本意なことと思って、尼などになっておしまいになったら、馬鹿らしくもあるな」
|
あちらも意志の強いばかりの女性とはお見えにならぬが、やはり自分との結婚を肯定することはできずに、尼にでもなっておしまいになれば、自分の不名誉である
|
【かれも、いとわが心を】- 以下「あべいかな」まで、夕霧の詞。落葉宮を思う。
【本意ならぬことにて】- 夕霧との結婚を不本意なことと考えて。
|
| 6.2.16 |
|
と思うと、暫くの間は絶え間なく通おうと、落ち着いていられない気がして、日が暮れて行くにつれて、「今日もお返事さえなかったな」とお思いになって、気にかかりながら、ひどく物思いに耽っていらっしゃる。
|
と思うと、当分は毎夜あちらに行っていねばならぬとあわただしい気がして、日の暮れていく空をながめても、まだ今日でさえお返事をくださらないではないかと煩悶された。
|
【しばしはとだえ置くまじう】- 結婚当初だから絶え間なく通おうと。
【今日も御返りだになきよ】- 夕霧の心中。落葉宮のもとからの返書。
【心にかかりつつ】- 大島本は「心にかゝりつゝ」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「心にかかりて」と校訂する。『新大系』は底本のままとする。
|
|
第三段 雲居雁、夕霧と和歌を詠み交す
|
| 6.3.1 |
|
昨日今日と全然お召し上がりにならなかった食事を、少々はお召し上がりになったりなどしていらっしゃる。
|
昨日から今日へかけて何一つ食べなかった夫人が夕食をとったりしていた。
|
【つゆも参らざりけるもの】- 主語は雲居雁。
|
| 6.3.2 |
|
「昔から、あなたのために愛情が並大抵でなかった事情は、大臣がひどいお扱いをなさったために、世間から愚かな男だとの評判を受けたが、堪えがたいところを我慢して、あちらこちらが、進んで申し込まれた縁談を、たくさん聞き流して来た態度は、女性でさえそれほどの人はいるまいと、世間の人も皮肉った。
|
「昔から私はあなたのために、どれほどの苦労をしたことだろう。大臣が冷酷な処置をおとりになったから、失恋男とだれにも言われるのを我慢して、あちこちからある縁談を皆断わって、すべて棄権をしてしまっていたようなことは女だってそうはできないことだと皆言いましたよ。どうしてそんなにしていられただろうと、自分ながら若い時の自重心を認めないではいられないのですからね。
|
【昔より、御ために心ざしの】- 以下「命こそ定めなき世なれ」まで、夕霧の詞。 【御ために心ざしの】-あなたのためにわたしの気持ちの、の意。
【ここかしこ、すすみけしきばみしあたりを】- 「ここかしこ」が主語。縁談を申し込んできた。
【女だにさしもあらじ】- 女性には多数の縁談の申し込みを断ることがよくある、というのが前提になっている。
【人ももどきし】- 世間の人が皮肉った。
|
| 6.3.3 |
|
今思うにつけても、どうしてそうであったのかと、自分ながらも、昔でさえ重々しかったと反省されるが、今は、このようにお憎みになっても、お捨てになることのできない子供たちが、とても辺りせましと数増えたようなので、あなたのお気持ち一つで出てお行きになることはできません。
また、まあ見ていてくださいよ。
寿命とは分からないのがこの世の常です」
|
今のあなたは私をあくまで憎んでいても、愛すべき人たちが家の中いっぱいにいるのだから、あなた一人の問題ではなくなったような現在に、軽々しい挙動はできないではありませんか。よく見ていてください。どんなに変わらぬ愛を持っている私であるかを、長い将来に見てください。命だけではあなたとさえ引き離されることがあるでしょうがね」
|
【いにしへだに重かりけり】- まして現在は昔以上に重々しい、の含み。
【思し捨つまじき人びと、いと所狭きまで数添ふめれば】- 夕霧と雲居雁の間にできた子供たちをさす。
【御心ひとつに】- あなた雲居雁の考え一つで。
【命こそ定めなき世なれ】- 『集成』は「人の命は不定だが、私のあなたへの情愛は不変だ、の意」と注す。係助詞「こそ」--「なれ」已然形の係結び、逆接のニュアンスの余意余情表現。
|
| 6.3.4 |
とて、うち泣きたまふこともあり。女も、昔のことを思ひ出でたまふに、 |
と言って、お泣きになったりすることもある。
女も、往時を思い出しなさると、
|
こんな話になって大将は泣き出した。夫人も昔のことを思い出すと、
|
【女も】- 『完訳』は「男女関係強調の呼称」と注す。
|
| 6.3.5 |
|
「しみじみとも世に又となく仲睦まじかった二人の仲が、何と言っても前世の約束が深かったのだな」
|
あんなにもして周囲に打ち勝って育ててきた恋から夫婦になっている自分たちではないかと、さすがに宿縁の深さも
|
【さすがに契り深かりけるかな】- 『完訳』は「恨めしくもあるが、やはり。雲居雁は素直な性格を印象づける」と注す。
|
| 6.3.6 |
と、思ひ出でたまふ。なよびたる御衣ども脱いたまうて、心ことなるをとり重ねて焚きしめたまひ、めでたうつくろひ化粧じて出でたまふを、灯影に見出だして、忍びがたく涙の出で来れば、脱ぎとめたまへる単衣の袖をひき寄せたまひて、 |
と、お思い出しなさる。
柔らかくなったお召し物をお脱ぎになって、新調の素晴らしいのを重ねて香をたきしめなさり、立派に身繕いし化粧してお出かけになるのを、灯火の光で見送って、堪えがたく涙が込み上げて来るので、脱ぎ置きなさった単衣の袖を引き寄せなさって、
|
思われるのであった。畳み目の消えた衣服を脱ぎ捨てて、ことにきれいなのを幾つも重ね、薫香で袖を燻べることもして、化粧もよくした良人が出かけて行く姿を、灯の明りで見ていると涙が流れてきた。夕霧の脱いだ単衣の袖を、夫人は自分の座のほうへ引き寄せて、
|
【なよびたる御衣ども脱いたまうて】- 主語は夕霧。
|
| 6.3.7 |
|
「長年連れ添って古びたこの身を恨んだりするよりも
いっそ尼衣に着替えてしまおうかしら
|
「馴るる身を恨みんよりは松島の
あまの衣にたちやかへまし
|
【馴るる身を恨むるよりは松島の--海人の衣に裁ちやかへまし】- 雲居雁の独詠歌。手にとった源氏の下着から「馴るる」と出る。「恨む」「裏」、「尼」「海人」は掛詞。「馴るる」「裏」「衣」「裁ち」、「浦」「松島」は縁語。『完訳』は「夫に飽きられた悲しみを、衣の縁語表現でまとめた歌」と注す。
|
| 6.3.8 |
|
やはり俗世の人のままでは、生きて行くことができないわ」
|
どうしてもこのままでは辛抱ができない」
|
【なほうつし人にては、え過ぐすまじかりけり】- 歌に付いて出た言葉。『源氏釈』は「かひすらも妹背ぞなべてある物をうつし人にて我ひとり寝る」(出典未詳)を指摘。
|
| 6.3.9 |
と、独言にのたまふを、立ち止まりて、
|
と、独言としておっしゃるのを、立ち止まって、
|
と独言するのに夕霧は気づくと、出かける足をとめて、
|
|
| 6.3.10 |
|
「何とも嫌なお心ですね。
|
「ほんとうに困った心ですね。
|
【さも心憂き御心かな】- 夕霧の詞。
|
| 6.3.11 |
|
いくら長年連れ添ったからといって、
わたしを見限って尼になったという噂が立ってよ
|
松島のあまの濡衣馴れぬとて
脱ぎ変へつてふ名を立ためやは」
|
【松島の海人の濡衣なれぬとて--脱ぎ替へつてふ名を立ためやは】- 夕霧の返歌。「松島」「海人」「馴る」「裁つ」の語句を受けて返す。「やは」反語表現。私を捨てて尼になったという噂が立ってよいものか。『河海抄』は「松島や小島の磯にあさりせし海人の袖こそかくは濡れしか」(後拾遺集恋四、八二八、源重之)。『源氏物語事典』は「音に聞く松が浦島今日ぞ見るむべも心あるあまは住みけり」(後撰集雑一、一〇九四、素性法師)を指摘。
|
| 6.3.12 |
|
急いでいて、とても平凡な歌であるよ。
|
と言った。急いだからであろうが平凡な歌である。
|
【うち急ぎて、いとなほなほしや】- 三光院説「草子地也」と指摘。『全集』は「語り手の夕霧に対するからかい。読者の夕霧に対する非難を先取りする軽い諧謔」と注す。
|
|
第四段 塗籠の落葉宮を口説く
|
| 6.4.1 |
|
あちらには、やはり籠もっていらっしゃるのを、女房たちが、
|
一条ではまだ前夜のまま宮が内蔵からお出にならないために、女房たちが、
|
【かしこには】- 一条宮邸の落葉宮をさす。
【なほさし籠もりたまへるを】- 塗籠の中に落葉宮が。
|
| 6.4.2 |
|
「こうしてばかりいらしてよいものでしょうか。
子供っぽく良くない噂も立つでございましょうから、いつものご座所に戻って、お考えのほどを申し上げなさいませ」
|
「こんなふうにいつまでもしておいでになりましては、若々しい、もののおわかりにならぬ方だという評判も立ちましょうから、平生のお座敷へお帰りになりまして、そちらでお心持ちを殿様の御了解なさいますようにお話しあそばせばよろしいではございませんか」
|
【かくてのみやは】- 以下「聞こえたまはめ」まで、女房たちの詞。
【例の御ありさまにて】- いつものご座所に戻って。
|
| 6.4.3 |
|
などと、いろいろと申し上げたので、もっともなことだとお思いになりながら、今から以後の世間での噂も、自分のどのようなお気持ちで過ごして来たかも、気にくわなく、恨めしかった方のせいだとお考えになって、その夜もお会いなさらない。
「冗談ではなく、変わった方だ」と、言葉を尽くして恨みのたけを申し上げなさる。
女房もお気の毒だと拝す。
|
と言うのを、もっともなことに宮もお思いになるのであるが、世間でこれからの御自身がお受けになる譏りもつらく、過去のあるころにその人に好意を持っておいでになった御自身をさえ恨めしく、そんなことから母君を失ったとお考えになると最もいとわしくて、この晩もお逢いにはならなかった。「あまりに、御冷酷過ぎる」こんな気持ちをいろいろに言って取り次がせて夕霧はいた。女房たちも同情をせずにおられないのであった。
|
【心づきなく、恨めしかりける人のゆかりと】- 夕霧をさす。『一葉抄』は「双紙の地也」と注す。『集成』は「夕霧と結婚することに対する外部の悪評、夕霧のせいで母御息所の亡くなったを落葉の宮は思う」と注す。
【戯れにくく、めづらかなり】- 夕霧の詞。『異本紫明抄』は「ありぬやと試みがてら逢ひ見ねば戯れにくきまでぞ恋しき」(古今集誹諧、一〇二五、読人しらず)を指摘。『完訳』は「冗談も言いにくく、非常識で融通もきかないほど珍しい、の意」と注す。
【人もいとほしと見たてまつる】- 主語は小少将の君。目的語は夕霧とも落葉宮とも、また二人とも解せる。
|
| 6.4.4 |
|
「『わずかでも人心地のする時があろうときに、お忘れでなかったら、何なりとお返事申し上げましょう。
この御服喪期間中は、せめて他の事で頭を思い乱すことなく過ごしたい』と、深くお思いになりおっしゃっていますが、このようにまことに都合悪く、知らない人のなくなってしまったようなことを、やはりひどくお辛いことと申し上げておいでです」
|
「少しでも普通の人らしい気分が帰ってくる時まで、忘れずにいてくだすったならとおっしゃるのでございます。母君の喪中だけはほかのことをいっさい思わずに謹慎して暮らしたいという思召しが濃厚でおありあそばす一方では、知らぬ者がないほどにあなた様のことが世間へ知れましたのを残念がっておいでになるのでございます」
|
【いささかも人心地する折あらむに】- 以下「聞こえたまふ」まで、小少将の君の詞。ただし「いささかも」から「過ぐさむ」までは宮の言葉を伝えたもの。
【忘れたまはずは】- 主語は夕霧。あなたがわたしを。
【ともかうも聞こえむ】- 主語はわたし落葉宮。
【この御服のほどは】- 『集成』は「御息所の喪に服している間は。一年間ということになる」と注す。
【あやにくに】- 母親の服喪中にも関わらず夕霧と結婚したことをさす。
【知らぬ人なくなりぬめるを】- 目的語、夕霧とのことを、が省略。
|
| 6.4.5 |
と聞こゆ。
|
と申し上げる。
|
|
|
| 6.4.6 |
「思ふ心は、また異ざまにうしろやすきものを。思はずなりける世かな」とうち嘆きて、「例のやうにておはしまさば、物越などにても、思ふことばかり聞こえて、御心破るべきにもあらず。あまたの年月をも過ぐしつべくなむ」 |
「愛する気持ちは、また普通の人とは違って安心ですのに。
思いも寄らない目に遭うものですね」と嘆息して、「普通のご気分でいらっしゃったら、物越しなどでも、自分の気持ちだけでも申し上げて、お心を傷つけるようなことはしません。
何年でもきっとお待ちしましょう」
|
「私の愛は噂とか何とかいうものに左右されない絶大なものなのだがね。そんなことが理解していただけないとは苦しいものだ」
と大将は歎息して、「普通にお居間のほうへおいでになれば、物越しで私の心持ちをお話しするだけにとどめて、それ以上のことはまだいつまでも待っていていいのです」
|
【思ふ心は】- 以下「思はずなりける世かな」まで、夕霧の詞。
【例のやうにて】- 以下「過ぐしつべくなむ」まで、夕霧の詞。
|
| 6.4.7 |
など、尽きもせず聞こえたまへど、
|
などと、どこまでも申し上げなさるが、
|
同じようなことをまた取り次がせるのであったが、
|
|
| 6.4.8 |
|
「やはり、このような喪中の心の乱れに加えて、無理をおっしゃるお心がひどく辛い。
他人が聞いて想像することも、すべていい加減なことで済まされないわが身の辛さは、それはそれとして措いても、格別に情けないお心づもりです」
|
「弱いものがこんなに悲しみに疲れております際に、しいていろいろなことをおっしゃるのが非常にお恨めしく思われるのでございます。人が見てどう私が思われることでしょう。その一部は私の不幸なせいでもあるでしょうが、あなた様がお一人ぎめをあそばしたからだとこれを思います」
|
【なほ、かかる乱れに添へて】- 以下「御心がまへなり」まで、落葉宮の詞。小少将の君を介して。喪中の悲しみに取り乱している折に、の意。
【わりなき御心】- 夕霧の求婚。
|
| 6.4.9 |
|
と、重ねて拒否してお恨みになりながら、つき放してお相手していらっしゃった。
|
とまた御抗弁になった。
|
【はるかにのみもてなしたまへり】- 『異本紫明抄』は「陸奥のちかの塩釜近ながら遥けくのみも思ほゆるかな」(古今六帖、しほ)を指摘。
|
|
第五段 夕霧、塗籠に入って行く
|
| 6.5.1 |
|
「そうかといって、こうしてばかりいられようか。
人が洩れ聞くことも当然だ」と、きまり悪く、こちらの人目も気にかかりなさるので、
|
まだ親しもうとあそばすふうはない。そうは言っても、いつまでも真の夫婦になりえないことは、人の口から世間へも伝わるであろうから恥ずかしいと、この女房たちに対してさえきまり悪く思う大将であった。
|
【さりとて、かくのみやは。人の聞き漏らさむこともことわり】- 夕霧の心中。
|
| 6.5.2 |
|
「内々のお気づかいは、このおっしゃることに適っても、暫くの間はお気持ちに逆らわないでいよう。
夫婦らしからぬ様子が、とても嫌である。
また、こうだからといって、まったく参らなくなったら、あなたのご評判がどんなにかおいたわしいことでしょうか。
一方的にお考えになって、大人げないのが困ったことです」
|
「実際のことは宮様の御意志どおりの関係にとどめるにしても、この状態はあまりに変則だ。またそうであるからといって、私が断然来なくなったら、宮様はどういう世評をお取りになるだろう。あまりに人生を悲観なされ過ぎて、御幼稚な態度をお改めにならないのを私は宮様のために惜しむ」
|
【うちうちの御心づかひは】- 以下「いとほしけれ」まで、夕霧の詞。
【情けばまむ】- 『完訳』は「宮の気持に逆わず、表向きだけの夫婦でいよう。本心ではない」と注す。
【人の御名】- あなた落葉宮の評判。
【いかがはいとほしかるべき】- 「いかがは」--「べき」は強調表現。
|
| 6.5.3 |
|
など、この女房をお責めになるので、なるほどと思って、拝するのも今はお気の毒になって、恐れ多くも思われる様子なので、女房を出入りさせなさる塗籠の北の口から、お入れ申し上げてしまった。
|
などと大将が責めるのに道理があるように少将は思い、また夕霧の様子には気の毒で見ておられぬところがあって、女房たちが通って行く出入り口にしてある内蔵の北の戸から大将を入れた。
|
【この人を責めたまへば】- 夕霧が小少将の君を。
【げにと思ひ】- 大島本は「けにとも(も$)」とある。すなわち「も」をミセケチにする。『集成』『完本』は諸本に従って「げにとも」と校訂する。『新大系』は底本の訂正に従う。主語は小少将の君。『一葉集』は「双紙の地也」と指摘。『林逸抄』は「双紙の地也又は少将か心也」と注す。
【見たてまつるも今は】- 目的語は夕霧。
【人通はしたまふ塗籠の北の口より】- 宮が女房の出入りを許していらっしゃる塗籠の北の口から。
|
| 6.5.4 |
|
ひどく驚いて情けなくむごいと、伺候している女房も、なるほどこのような世間の人の心だから、これ以上ひどい目に遭わせるに違いないと、頼りにする人もいなくなってしまった我が身を、かえすがえす悲しくお思いになる。
|
ひどいことをする恨めしい人たちであると宮は女房をお思いになり、こうしてだれの心も利己的になるのであるから、これ以上のことを女房たちからされないものでもないとお考えになると、その人ら以外に頼む者のない今の御境遇をかえすがえす悲しくお思いになった。
|
【いみじうあさましうつらし】- 落葉宮の心。
【さぶらふ人をも】- 以下「見せつべかりけり」まで落葉宮の心。
【頼もしき人もなくなり果てたまひぬる御身を】- 『完訳』は「信頼していた小少将の君にも裏切られた感じ」と注す。
|
| 6.5.5 |
|
男は、いろいろと納得なさるような条理を尽くしてお説き申し上げ、言葉数多く、しみじみと気を引くようなことをどこまでも申し上げなさるが、辛く気にくわないとばかりお思いになっていた。
|
男は宮のお心の動かねばならぬようにして多くささやくのであるが、宮はただ恨めしくばかりお思いになって、この人に親しみを見いだそうとはあそばさない。
|
【男は】- 『集成』は「男女対座の場面なので、「男」と端的に呼ぶ」。『完訳』は「男女関係強調の呼称」と注す。
【つらく心づきなしとのみ思いたり】- 主語は落葉宮。
|
| 6.5.6 |
|
「まったく、このように、何とも言いようもない者に思われなさった身のほどは、例のないくらい恥ずかしいので、あってはならない考えがつき始まったのも、迂闊にも悔しく思われますが、昔に戻ることのできない関係で、何の立派なご評判がございましょうか。
もう仕方のないこととお諦めください。
|
「こんなふうにあらん限りの侮蔑を加えられております私が非常に恥ずかしくて、あるまじい恋をし始めました初めの自分を後悔いたしますが、これは取り返しうるものではありませんし、あなた様のためにももうそれはしてならないことです。
|
【いと、かう、言はむ方なきものに】- 以下「捨てつる身と思しなせ」まで、夕霧の詞。
【身のほどは】- 夕霧の身。我が身のつたなさは、の意。
【あるまじき心のつきそめけむも】- 『完訳』は「人臣の身で皇女を娶ろうとする心づもりをいう」と注す。
【とり返すものならぬうちに】- 『奥入』は「取り返すものにもがなや世の中をありしながらの我が身と思はむ」(出典未詳)。『弄花抄』は「むら鳥の立ちにし我が名今さらにことなしぶともしるしあらめや」(古今集恋三、六七四、読人しらず)を指摘。
【何のたけき御名にかはあらむ】- 反語表現、いまさら何にもならない。
|
| 6.5.7 |
|
思い通りにならない時、淵に身を投げる例もございますそうですが、ただこのような愛情を深い淵だとお思いになって、飛び込んだ身だとお思いください」
|
ですからもう御自分はどうでもよいという徹底した弱い心におなりなさい。思うことのかなわない時に身を投げる人があるのですから、私のこの愛情を深い水とお思いになって、それへ身を捨てるとお思いになればよいと思います」
|
【深き淵になずらへたまて、捨てつる身と思しなせ】- 『異本紫明抄』は「身を捨てて深き淵にも入りぬべし底の知らまほしさに」(後拾遺集恋一、六四七、源道済)。『河海抄』は「世の中の憂きたびごとに身を投げば深き谷こそ浅くなりなめ」(古今集誹諧、一〇六一、読人しらず)。『評釈』は「そこひなき淵やは騒ぐ山川の浅き瀬にこそあだ波は立て」(古今集恋四、七二二、素性法師)を指摘。
|
| 6.5.8 |
と聞こえたまふ。
単衣の御衣を御髪込めひきくくみて、たけきこととは、音を泣きたまふさまの、心深くいとほしければ、
|
と申し上げなさる。
単衣のお召し物をお髪ごと被って、できることといっては、声を上げてお泣きになる様子が、心底お気の毒なので、
|
と夕霧は言った。単衣の着物にお身体を包むようにして、ほかへお見せになる強さといっては声を出してお泣きになることよりおできにならないのも、あくまで女らしくお気の毒なのをながめていて、
|
|
| 6.5.9 |
|
「まったく困ったことだ。
どうしてまったくこのようにまでお嫌いになるのだろう。
強情を張っている人でも、これほどになってしまえば、自然と弱くなる様子もあるのだが、石や木よりもほんとうに心を動かさないのは、前世の因縁が薄いために、恨むようなことがあるが、そのようにお思いなのだろうか」
|
なぜこうであろう、こんなにまで自分をお愛しになることが不可能なのであろうか、どんなに許しがたく思う人といっても、これほどの志を見ていては自然に心のゆるんでくるものであるが、岩や木以上に無情なふうをお見せになるのは、前生の約束がそうであるためで、自分に憎悪をお持ちにならねばならぬ運命を持っておいでになるのではなかろうかと、
|
【いとうたて。いかなれば】- 以下「さやおぼすらむ」まで、夕霧の心中。
【いみじう思ふ人も】- 『集成』は「どんなに決心の固い人でも」。『完訳』は「どんなに気強い女でも」と訳す。
【岩木よりけになびきがたきは】- 「人、木石に非ざれば皆情あり」(白氏文集、李夫人)。
|
| 6.5.10 |
|
と思い当たると、あまりひどいので情けなくなって、三条の君がお悲しみであろうことや、昔も何の疑いもなく、お互いに愛情を交わし合った当時のこと、長年にわたり、もう安心と信頼し、打ち解けていらっしゃった様子を思い出すにつけても、自分のせいで、まことにつまらなく思い続けられずにはいられないので、無理にもお慰め申し上げなさらず、嘆息しながら夜をお明かしになった。
|
こんなことを思った時から大将はあまりなお扱いに憤りに似た気持ちが起こって、三条の夫人が今ごろどう思っているかと考えだすと、単純な幼心に思い合った昔のこと、近年になって望みがかない、同棲することのできて以来の信頼し合った夫婦の情味などが思われて、自身のし始めたことではあるが、この恋が味気なくなって、もうしいて宮の御機嫌をとろうとも努めずに歎き明かした。
|
【と思ひ寄るに】- 『集成』は「「と思ひ寄るに」以下、地の文だが、「思ひ出づるも」「思ひ続けらるれば」と、敬語を欠き、夕霧の思いに密着した書き方」と注す。
【三条の君の思ひたまふらむこと】- 雲居雁がお悲しみであろうこと。推量の助動詞「らむ」視界外推量、遥かに思い遣るニュアンス。
【うち頼み、解けたまへるさまを】- 雲居雁が夕霧を信頼し打ち解けていらした、の意。
【思ひ続けらるれば】- 「らるれ」自発の助動詞。『集成』は「落葉宮にうとまれ、雲居の雁からは怨まれる結果になったのも、皆自分の招いたことだ、と苦い思いを反芻する」と注す。
【契り遠うて憎しなど思ふやうあなるを】- 『完訳』は「前世の因縁で憎むのなら、これはどうしょうもないが、の意」と注す。
|
|
第六段 夕霧と落葉宮、遂に契りを結ぶ
|
| 6.6.1 |
|
こうしてばかり馬鹿らしく出入りするのもみっともないので、今日は泊まって、ゆっくりとしていらっしゃる。
こんなにまで一途なのを、あきれたことと宮はお思いになって、ますます疎んずる態度が増してくるのを、愚かしい意地の張りようだと、思う一方で、情けなくもおいたわしい。
|
こんなみじめなことで来たり出て行ったりすることもきまり悪くこの人は思って、今日はこちらにとどまっていることにして落ち着いているのにも、宮は反感がお持たれになって、いよいようといふうをお見せになることが増してくるのを、幼稚なお心の方であると、恨めしく思いながらも哀れに感じていた。
|
【かうのみ痴れがましうて出で入らむもあやしければ】- 『集成』は「いつもこんなことでおめおめ間抜け者然と出入りするのも不体裁なので」。『完訳』は「こうして、いかにもばかげた有様で出入りするのも変なものであるから」。「かく」副詞、「痴れがまし」を修飾。副助詞「のみ」のニュアンスを添える。
【宮は思いて】- 主語「宮は」を添えて強調する。「女は」とはないことに注意。
【をこがましき御心かな】- 夕霧の心中。『集成』は「みっともないほどの意地の張りようかと」。『完訳』は「大将は、愚かしい方よと」と訳す。
【かつは、つらきもののあはれなり】- 地の文から語り手の夕霧と落葉宮に対する評語に移る表現。
|
|
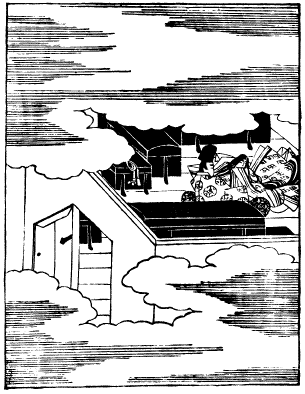 |
| 6.6.2 |
|
塗籠も、格別こまごまとした物も多くはなくて、香の御唐櫃や、御厨子などばかりがあるのは、あちらこちらに片づけて、親しみの持てる感じに設えていらっしゃるのだった。
内側は暗い感じがするが、朝日がさし昇った感じが漏れて来たので、被っていた単衣をひき払って、とてもひどく乱れていたお髪、かき上げたりなどして、わずかに拝見なさる。
|
蔵の中も別段細かなものがたくさん置かれてあるのでなく、香の唐櫃、お置き棚などだけを体裁よくあちこちの隅へ置いて、感じよく居間に作って宮はおいでになるのである。中は暗い気のする所へ、出たらしい朝日の光がさして来た時に、夕霧は被いでおいでになる宮の夜着の端をのけて、乱れたお髪を手でなで直しなどしながらお顔を少し見た。
|
【埋もれたる御衣ひきやり】- 主語は夕霧。落葉宮の被っていた御衣を払いのける。
【御髪、かきやりなどして】- 主語は夕霧。
【ほの見たてまつりたまふ】- 『完訳』は「宮の顔をほのかに見る。情交のあったことをにおわせる表現」と注す。
|
| 6.6.3 |
|
まことに気品高く女性的で、優美な感じでいらっしゃった。
夫君のご様子は、凛々しくしていらっしゃる時よりも、くつろいでいらっしゃる時は、限りなく美しい感じである。
|
上品で、あくまで女らしく艶なお顔であった。男は正しく装っている時以上に、部屋の中での柔らかな姿が顔を引き立ててきれいに見えた。
|
【男の御さまは】- 『完訳』は「以下、宮の心情に即した行文。「男」の呼称も情交の場を強調」と注す。
【うちとけてものしたまふは】- 『完訳』は「肌を許し合う仲として見直すと、夕霧の美しさが際だつ。契り交した後の女の心の変化に注意」と注す。
|
| 6.6.4 |
|
「亡き夫君が特別すぐれた容貌というわけでなかったが、その彼でさえ、すっかり気位高く持って、ご器量がお美しくないと、何かの折に思っていたらしい様子をお思い出しになると、それ以上に、このようにひどく衰えた様子を、少しの間でも我慢できようか」と思うのも、ひどく恥ずかしく、あれやこれやと思案しながら、自分のお気持ちを納得させなさる。
|
柏木が普通の風采でしかないのにもかかわらず思い上がり切っていて、宮を美人でないと思うふうを時々見せたことを宮はお思い出しになると、その当時よりも衰えてしまった自分をこの人は愛し続けることができないであろうとお考えられになって、恥ずかしくてならぬ気があそばされるのであった。宮はなるべく楽観的にものを考えることにお努めになってみずから慰めようとしておいでになるのであった。
|
【故君の異なることなかりしだに】- 以下「見忍びなむや」まで、落葉宮の心中。『集成』は「以下、落葉の宮の思い」。『完訳』は「女三の宮を思う柏木は、ことさら宮を低く見た。宮の劣等感の原因」と注す。
【御容貌まほにおはせずと】- 柏木が思いまた落葉宮に言ったこと。落葉宮の心中文に敬語「思す」がまじる。
【まして、かういみじう衰へにたるありさまを】- 柏木との結婚当時以上に年衰え醜くなった、の意。『完訳』は「宮は二十代後半であろう。ちなみに女三の宮は二十四、五歳。確かに、女盛りは過ぎている」と注す。
【見忍びなむや】- 主語は夕霧。敬語がないことに注意。結婚後の夫婦間の心情。
【と思ふも、いみじう恥づかしう】- 大島本は「はつかしう」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「恥づかし」と校訂する。『新大系』は底本のままとする。作中人物の気持ちと地の文が一体化した表現。
|
| 6.6.5 |
|
ただ外聞が悪く、こちらでもあちらでも、人がお聞きになってどうお思いなさろうかの罪は避けられないうえ、喪中でさえあるのがとても情けないので、気持ちの慰めようがないのであった。
|
ただ複雑な関係になって、あちらへもこちらへも済まぬわけになることを苦しくお思いになるのと、おりが母君の喪中であることによってこうした冷ややかな態度をおとり続けになるのである。
|
【ただかたはらいたう】- 『集成』は「以下、宮の心中を説明する」と注す。
【ここもかしこも】- 朱雀院や致仕の太政大臣をさす。
【折さへいと心憂ければ】- 母御息所の喪中であることをさす。
|
| 6.6.6 |
御手水、御粥など、例の御座の方に参れり。色異なる御しつらひも、いまいましきやうなれば、東面は屏風を立てて、母屋の際に香染の御几帳など、ことことしきやうに見えぬ物、沈の二階なんどやうのを立てて、心ばへありてしつらひたり。大和守のしわざなりけり。 |
御手水や、お粥などを、いつものご座所の方で差し上げる。
色の変わった御調度類も、縁起でもないようなので、東面には屏風を立てて、母屋との境に香染の御几帳など、大げさに見えない物、沈の二階棚などのような物を立てて、気を配って飾ってある。
大和守のしたことであったのだ。
|
大将の手水や朝餉の粥が宮のお居間のほうへ運ばれた。この際に喪の色を不吉として、なるべく目につかぬようにこの室の東のほうには屏風を立て、中央の室との仕切りの所には香染めの几帳を置いて、目に立つ巻き絵物などは避けた沈の木製の二段の棚などを手ぎわよく配置してあるのは皆大和守のしたことであった。
|
【例の御座の方に】- 塗籠から出ていつもの御座所に移る。
【大和守のしわざなりけり】- 語り手の説明的叙述。
|
| 6.6.7 |
|
女房たちも、派手でない色の、山吹襲、掻練襲、濃い紫の衣、青鈍色などを着替えさせ、薄紫色の裳、青朽葉などを、何かと目立たないようにして、お食膳を差し上げる。
女主人の生活で、諸事しまりなくいろいろ習慣になっていた宮邸の中で、有様に気を配って、わずかの下人たちにも声をかけてきちんとさせ、この大和守一人だけで取り仕切っている。
|
派手な色でない山吹色、黒みのある紅、深い紫、青鈍などに喪服を着かえさせ、薄紫、青朽葉などの裳を目だたせず用いさせた女房たちが大将の給仕をした。今まで婦人がただけのお住居であって、規律のくずれていたのを引き締めて、少数の侍を巧みに使い不都合のないようにしているのも、皆一人の大和守が利巧な男だからである。
|
【人びとも、鮮やかならぬ色の】- 女房たち。喪中ゆえに服飾の色も目立たないものを用いる。
【女所にて、しどけなくよろづのことならひたる宮の内に】- 『集成』は「女世帯なので、諸事しまりもなく今までやってこられた邸内に」。『完訳』は「女ばかりの住いとて、万事締りのないのが習慣になっていた邸内だったのを」と訳す。
【この人一人のみ扱ひ行ふ】- 大和守一人が取り仕切る。
|
| 6.6.8 |
|
このように思いがけない高貴な来客がいらっしゃったと聞いて、もとから怠けていた家司なども、急に参上して、政所などという所に控えて仕事をするのだった。
|
こうして思いがけず勢力のある宮の御良人がおできになったことを聞いて、もとは勤めていなかった家司などが突然現われて来て事務所に詰め、仕事に取りかかっていた。
|
【やむごとなき客人のおはする】- 夕霧をさす。
【もと勤めざりける家司など、うちつけに参りて】- 以前には真面目に勤めなかった家司が急にやって来て、の意。
|
|
第七章 雲居雁の物語 夕霧の妻たちの物語
|
|
第一段 雲居雁、実家へ帰る
|
| 7.1.1 |
|
このように無理して馴染んだ顔をしていらっしゃるので、三条殿は、
|
実質はともかくも、この家の主人らしい生活を大将が一条で始めている数日間を、三条の夫人はもう捨てられ果てたもののように見て、
|
【作りたまふほど】- 主語は夕霧。
|
| 7.1.2 |
「限りなめりと、さしもやはとこそ、かつは頼みつれ、まめ人の心変はるは名残なくなむと聞きしは、まことなりけり」 |
「これが最後のようだと、まさかそんなことはあるまいと、一方では信頼していたが、実直な人が浮気したら跡形もなくなると聞いていたことは、本当のことであった」
|
これほど愛をことごとく新しい人に移すこともしないであろうと信頼していたのは自分の誤解であった、忠実であった良人がほかに恋人のできた時は、愛の痕跡も残さず変わってしまうものだ
|
【限りなめりと】- 以下「まことなりけり」まで、雲居雁の心中、地の文に織り交ぜて叙述。
|
| 7.1.3 |
|
と、夫婦の仲を見届けてしまった感じがして、「どうにしてこの侮辱を味わっていようか」とお思いになったので、大殿邸へ、方違えしようと思って、お移りになったところ、弘徽殿の女御が里にいらっしゃる時でもあり、お会いなさって、少し悩みが晴れることとお思いになって、いつものように急いでお帰りにならない。
|
と人の言うのは嘘でないと、苦しい体験をはじめてするという気もしてこの侮辱にじっと堪えていることはできないことであると思って、父の大臣家へ方角除けに行くと言って邸を出て行った。女御が実家に帰っている時でもあったから、姉君にも逢って、悩ましい気持ちの少し紛らすこともできた雲井の雁夫人は、平生のようにすぐ翌日に邸へ帰るようなこともせず父の家の客になっていた。
|
【世を試みつる心地して】- 『集成』は「夫婦の仲を見届けてしまった気がして」。『完訳』は「男女の仲らいの定めなさがすっかり分ってしまったような心地がして」と訳す。
【女御の里におはするほどなどに】- 弘徽殿の女御。雲居雁とは異母姉妹。
【急ぎ渡りたまはず】- 三条邸に急いで帰らない。
|
| 7.1.4 |
大将殿も聞きたまひて、
|
大将殿もお聞きになって、
|
これはすぐに左大将へも聞こえて行った。
|
|
| 7.1.5 |
|
「やはりそうであったか。
まことせかっちでいらっしゃる性格だ。
この大殿の方も、また、年輩者らしくゆったりと落ち着いているところが、何といってもなく、実に性急で派手でいらっしゃる方々だから、気にくわない、見るものか、聞くものかなどと、不都合なことをおっしゃり出すかも知れない」
|
そんなことがあるようにも予感されたことである、はげしい性質の人であるからと大将は思った。大臣もまたりっぱな人物でありながら大人らしい寛大さの欠けた性格であるから、一徹に目にものを見せようとされないものでもない、失敬である、もう絶交するというような態度をとられて、家庭の醜態が外へ知られることになってはならぬ
|
【さればよ。いと急に】- 以下「し出でたまうつべき」まで、夕霧の心中。
【ひがひがしきことどもし出でたまうつべき】- 『集成』は「相手が相手だから、離縁話に発展しかねない、とあやぶむ」。「し出でつべき」連体中止法、余情余意表現。
|
| 7.1.6 |
|
と、驚きなさって、三条殿にお帰りになると、子供たちも、半ばは残っていらっしゃって、姫君たちと、それからとても幼い子は連れていらっしゃっていたのだが、見つけて喜んで纏わりつき、ある者は母上を恋い慕い申して、悲しんで泣いていらっしゃるのを、かわいそうにとお思いになる。
|
と驚いて、三条へ帰って見ると、子供は半分ほどあとに残されているのであった。姫君たちと幼少な子だけを夫人はつれて行ったのである。父を見つけて喜んでまつわりに来る子もあれば、母を恋しがって泣く子もあるのを、大将は心苦しく思った。
|
【姫君たち、さてはいと幼きとをぞ率ておはしにける】- 挿入句。直前の「止まりたまへれば」はこの句の下の「見つけて」に続く。
【上を恋ひたてまつりて】- 母上を恋しがって。
|
| 7.1.7 |
消息たびたび聞こえて、迎へにたてまつれたまへど、御返りだになし。かくかたくなしう軽々しの世やと、ものしうおぼえたまへど、大臣の見聞きたまはむところもあれば、暮らして、みづから参りたまへり。 |
手紙を頻繁に差し上げて、お迎えに参上なさるが、お返事すらない。
このように頑固で軽率な夫婦仲だと、嫌に思われなさるが、大殿が見たり聞いたりなさる手前もあるので、日が暮れてから、自分自身で参上なさった。
|
手紙をたびたびやって迎えの車を出すが、夫人からは返事もして来なかった。こうして妻に意地を張られるようなことは、自分らの貴族の間にはないことであるがと、うとましく思いながらも、大臣へ対しての義理を思って、日の暮れるのを待って自身で夕霧は迎えに行った。
|
【迎へにたてまつれたまへど】- 人をして迎えに差し向けなさるが、の意。
|
|
第二段 夕霧、雲居雁の実家へ行く
|
| 7.2.1 |
|
寝殿にいらっしゃると聞いて、いつもお帰りの時に使う部屋は、年配の女房たちだけが控えている。
若君たちは、乳母と一緒にいらっしゃった。
|
「寝殿にいらっしゃいます」ということで、平生行って使っている座敷のほうには女房だけがいた。男の子供たちだけは乳母に添ってここにいた。
|
【寝殿になむおはする】- 弘徽殿女御が里下りの時に用いる寝殿の部屋に雲居雁も一緒にいる。
【例の渡りたまふ方は、御達のみさぶらふ】- 雲居雁が実家に帰った時に用いる部屋は女房たちがいる。
|
| 7.2.2 |
|
「今になって若々しいお付き合いをなさることだ。
このような子を、あちらやこちらにほって置きなさって。
どうして寝殿でお話に熱中なさっているのですか。
不似合いなご性格とは、長年見知っていたが、前世からの宿縁だろうか、昔から忘れられない人とお思い申し上げて、今ではこのように、手のかかった子供たちも大勢かわいくなっているのを、お互いに見捨ててよいものかと、お頼み申しているのです。
ちょっとしたことで、こんなふうになさってよいものでしょうか」
|
今さら若々しい態度をとるあなたではありませんか。かわいい人たちをあちらこちらへ置きはなしにして、自身は寝殿でお姫様に帰った気でいられるあなたの気持ちは解釈に苦しむ。私への愛情がそんなふうに少ないとは私にもわかっているのですが、昔からあなたにばかり惹かれる心を私は持っているし、今ではおおぜいのかわいそうな子供ができているのですから、二人の結合のゆるむことはないと信じていたのに、ちょっとしたことにこだわって、こんな扱いを私になさることはいいことだろうか」
|
【今さらに若々しの御まじらひや】- 以下「もてなしたまふべくや」まで、夕霧の詞。女房を介して雲居雁に伝える。弘徽殿の女御と一緒にいることをさす。当時の若い女性は宮廷に仕える人からその有様や情報などを聞くのを喜んだ。
【など寝殿の御まじらひは】- 女御と話しこんで子供をほったらかしているのを非難。「は」終助詞、詠嘆の意。
【ふさはしからぬ御心の筋とは】- わたし夕霧には似合わなしくないあなたのご気性は、の意。
【さるべきにや】- 前世からの宿縁か、の意。
【くだくだしき人の数々】- 夕霧と雲居雁の間にできた大勢の子供たち。
【かたみに見捨つべきにやは】- 「やは」反語表現。お互いに見捨ててよいはずでない。
【はかなき一節に】- 落葉の宮との一件をいう。
|
| 7.2.3 |
と、いみじうあはめ恨み申したまへば、
|
と、ひどく非難しお恨み申し上げなさると、
|
取り次ぎによって夕霧はこう妻を責めた。
|
|
| 7.2.4 |
|
「何もかも、もう飽き飽きしたと見限られてしまった身ですので、今さらまた、直るものでないのを、どうして直そうかと思いまして。
見苦しい子供たちは、お忘れにならなければ、嬉しく思いましょう」
|
「もうすべてのことがお気に入らないものになってしまったのですから、お困りになる私の性質は今さら直す必要もないと思います。かわいそうな子供たちだけを愛してくださればうれしく思います」
|
【何ごとも、今はと】- 以下「うれしうこそはあらめ」まで、雲居雁の詞。
【見飽きたまひにける身なれば】- 主語は夕霧。夕霧がわたし雲居雁を見飽きた、の意。
【何かはとて】- 『集成』は「何もおとなしくしているに及ぶまいと思いまして。夕霧の非難に答えて、勝手にこうしていますと、居直った言いぶり」と注す。「なにかは」の下に「直さむ」などの語句が省略。反語表現。
【あやしき人びとは】- 子供たちをいう。自分の生んだ子なので「あやしき」とへりくだって言う。夕霧の「くだくだしき人」に対応した言い方。
|
| 7.2.5 |
と聞こえたまへり。
|
とお答え申し上げなさった。
|
と夫人は返事をさせた。
|
|
| 7.2.6 |
|
「穏やかなお返事ですね。
言い続けていったら、誰が悪く言われるでしょう」
|
「おとなしい御挨拶だ。結局はだれの不名誉になることとお思いになるのだろう」
|
【なだらかの御いらへや。言ひもていけば、誰が名か惜しき】- 皮肉。『完訳』は「あなたが悪く噂されるのがおち、の気持」と注す。『奥入』は「言ひ立てば誰が名か惜しき信濃なる木曾路の橋のふみし絶えなば」(出典未詳)。『異本紫明抄』は「恋ひ死なば誰が名は立たじ世の中の常なきものと言ひはなすとも」(古今集恋二、六〇三、清原深養父)。『源注拾遺』は「里人も語り継ぐがねよしゑやし恋ひても誰が名ならめや」(万葉集巻十二)「人目多みただに逢はずてけだしくも我が恋ひ死なば誰が名あらむも」(万葉集巻十二)を指摘。
|
| 7.2.7 |
とて、しひて渡りたまへともなくて、その夜はひとり臥したまへり。
|
と言って、無理にお帰りになりなさいとも言わずに、その夜は独りでお寝みになった。
|
と言って、しいて夫人の出て来ることも求めずに、この晩は一人で寝ることにした。
|
|
| 7.2.8 |
|
「変に中途半端なこのごろだ」と思いながら、子供たちを前にお寝せになって、あちらではまた、どんなにお悩みになっていらっしゃるだろう様子を、ご想像申し上げ、気の安まらない心地なので、「どのような人が、このようなことを興味もつのだろう」などと、懲り懲りした感じがなさる。
|
どちらつかずの境遇になったと思いながら、子供たちをそばへ寝させて大将は女二の宮の御様子も想像するのであった。どんなにまた煩悶をしておいでになる夜であろうなどと考えると苦しくなって、こんな遣る瀬ない苦しみばかりをせねばならぬ恋というものをなぜおもしろいことに人は思うのであろうと、懲りてしまいそうな気もした。
|
【あやしう中空なるころかな】- 夕霧の心中。
【かしこにまた、いかに】- 落葉宮を思う。
【いかなる人、かうやうなることをかしうおぼゆらむ】- 夕霧の心中。「人」は一般男性をす。「かうやうのこと」は色恋沙汰をさす。推量の助動詞「らむ」原因推量のニュアンス。
|
| 7.2.9 |
明けぬれば、
|
夜が明けたので、
|
夜が明けた時に、
|
|
| 7.2.10 |
|
「誰が見聞きしても大人げないことですから、もう最後だとおっしゃるならば、そのようにしましょう。
あちらにいる子供たちも、かわいらしそうに恋い慕い申しているようでしたが、選び残されたのには、何かわけがあるのかと思いながら、放っておくことができませんから、どうなりともいたしましょう」
|
「こんなことを若夫婦のように言い合っているのも恥ずかしいことですから、だめならだめとあきらめますが、もう一度だけもとどおりになってほしいという私の希望をいれたらどうですか。三条にいる小さい人たちもかわいそうな顔をして母を恋しがっていましたが、選って残しておいでになったのにはそれだけの考えがあるのでしょうから、あなたに愛されない子供達を私の手でどうにか育てましょう」
|
【人の見聞かむも若々しきを】- 以下「もてなしはべりなむ」まで、夕霧の詞。
【限りとのたまひ果てば】- 主語はあなた雲居雁が。
【さて試みむ】- 「さて」は雲居雁が言うように、「試みむ」は自分夕霧がしよう、の意。
【かしこなる人びとも、らうたげに】- 三条邸に残っている子供たち。
【選り残したまへる、やうあらむとは】- 『集成』は「出来の悪いのだけを残して行ったのだろうという嫌味」と注す。
|
| 7.2.11 |
|
と、脅し申し上げなさると、いかにもきっぱりしたご性格なので、この子供たちまで、知らない所へお連れなさるのだろうか、と心配になる。
姫君を、
|
とまた多少威嚇的なことを夫人へ言ってやった。一本気なこの人は自分の生んだ子供たちまでもほかの家へつれて行くかもしれぬという不安を夫人は覚えた。
|
【すがすがしき御心にて】- 以下「渡したまはむ」まで、雲居雁の心中。『集成』は「まっすぐなご性分だから。以下、雲居の雁の心中。子供を全部取られはしないかと恐れる」。『完訳』は「夕霧の思いきりのよい性格。一説に、雲居雁は素直な性格」と注す。
【この君達をさへ】- 副助詞「さへ」は三条邸に残してきた子供たちに加えてこの連れて来た子供たちまでが、のニュアンス。
【知らぬ所に率て渡したまはむ】- 落葉宮の一条邸へ。
|
| 7.2.12 |
|
「さあ、いらっしゃい。
お目にかかるために、このように参上するのも体裁が悪いので、いつも参上できません。
あちらにも子供たちがかわいいので、せめて同じ所でお世話申そう」
|
「姫君を本邸のほうへ帰してください。顔を見に来ることもこうしたきまりの悪い思いを始終しなければならないことですから、たびたびはようしません。あちらに残っている子供たちも寂しくてかわいそうですから、せめていっしょに置いてやりたいと思います」
|
【いざ、たまへかし】- 以下「見たてまつらむ」まで、夕霧の詞。
【かしこにも人びとのらうたきを】- 三条邸にいる兄弟たちをさす。
|
| 7.2.13 |
と聞こえたまふ。
まだいといはけなく、をかしげにておはす、いとあはれと見たてまつりたまひて、
|
と申し上げなさる。
まだとても小さく、かわいらしくいらっしゃるのを、しみじみといとしいと拝見なさって、
|
とまた大将は言ってよこした。そうしてから小さくてきれいな顔をした姫君たちが父のいる座敷へつれられて来た。夕霧はかわいく思って女の子たちを見た。
|
|
| 7.2.14 |
|
「母君のお言葉にお従いになってはなりませんよ。
とても情けなく、物事の分別がつかないのは、とても良くないことです」
|
「お母様の言うとおりになってはいけませんよ。ものの判断のできない女になっては悪いからね」
|
【母君の御教へに】- 以下「いと悪しきわざなり」まで、夕霧の詞。
|
| 7.2.15 |
と、言ひ知らせたてまつりたまふ。
|
と、お教え申し上げなさる。
|
などと教えていた。
|
|
|
第三段 蔵人少将、落葉宮邸へ使者
|
| 7.3.1 |
|
大殿は、このようなことをお聞きになって、物笑いになることとお嘆きになる。
|
大臣は娘と婿のこの事件を聞いて外聞を悪がっていた。
|
【大臣、かかることを聞きたまひて】- 致仕の太政大臣。雲居雁の父、夕霧の舅。
|
| 7.3.2 |
|
「もう少しの間、そのまま様子を見ていらっしゃらないで。
自然と反省するところも生じてこようものを。
女がこのように性急であるのも、かえって軽く思われるものだ。
仕方ない、このように言い出したからには、どうして間抜け顔をして、おめおめとお帰りになれよう。
自然と相手の様子や考えが分かるだろう」
|
「しばらく静観をしているべきだった。大将にも考えがあってしていたことだろうからね。婦人が反抗的に家を出て来るようなことは軽率なことに見られて、かえって人の同情を失ってしまう。しかしもうそうした態度を取りかけた以上は、すぐに負けて出てはならない。そのうちに先方の誠意のありなしもわかることだから」
|
【しばしは、さても見たまはで】- 以下「心ばへも見えなむ」まで、致仕の太政大臣の詞。ここで文が切れる。「見たまはで」の下に「かく渡りたまふ」などの語句が省略。雲居雁の短慮に対する諌めの言葉。
【おのづから思ふところものせらるらむものを】- 夕霧の行動についていう。
【よし、かく言ひそめつとならば】- 「言ひそめつ」の主語は雲居雁。ただし敬語はない。娘の立場にたっていう。
【何かは愚れて、ふとしも帰りたまふ】- 「何かは」--「たまふ」連体形、反語表現。
|
| 7.3.3 |
|
と仰せになって、この一条宮邸に、蔵人少将の君をお使いとして差し向けなさる。
|
と娘に言って、一条の宮へ蔵人少将を使いにして大臣は手紙をお送りするのであった。
|
【のたまはせて】- 大臣に対する重い敬語表現。
【この宮に】- 一条宮邸の落葉の宮へ。
【蔵人少将の君を御使にて】- 致仕太政大臣の子息、柏木の弟。
|
| 7.3.4 |
|
「前世からの因縁があってか、
あなたのことをお気の
|
契りあれや君を心にとどめおきて
哀れと思ひ恨めしと聞く
|
【契りあれや君を心にとどめおきて--あはれと思ふ恨めしと聞く】- 致仕太政大臣から故柏木の妻の落葉宮への贈歌。『完訳』は「「あはれ」は宮が長男柏木の妻だったから、「うらめし」は宮が娘雲居雁の夫を奪ったから。怒りを皮肉に言い込めた」と注す。『異本紫明抄』は「よそに我人々ごとを聞きしかばあはれとも思ふあな憂とも思ふ」(朝忠集)を指摘。
|
| 7.3.5 |
|
やはり、お忘れにはなれないでしょう」
|
無関心にはなれません因縁があるのでございますね。
|
【なほ、え思し放たじ】- 歌に添えた言葉。『完訳』は「こちらをも顧みよ、の気持」と注す。
|
| 7.3.6 |
|
とあるお手紙を、少将が持っていらっしゃって、ただずんずんとお入りになる。
|
この手紙を持って、少将はずんずん宮家へはいって来た。
|
【ただ入りに入りたまふ】- 『集成』は「もの馴れた様子でずんずん入って行かれる。一条の宮には以前から出入りし馴れた様子」。『完訳』は「門内まで乗り入れる。普通、貴人の邸では門前で挨拶して下車」と注す。
|
| 7.3.7 |
|
南面の簀子に円座をさし出したが、女房たちは、応対申し上げにくい。
宮は、それ以上に困ったことだとお思いになる。
|
南の縁側に敷き物を出したが、女房たちは応接に出るのを気づらく思った。まして宮はわびしい気持ちになっておいでになった。
|
【南面の簀子に円座さし出でて】- 寝殿の南面の簀子。普通の応対待遇。接続助詞「て」逆接のニュアンス。
【人びと、もの聞こえにくし】- 女房たち。
|
| 7.3.8 |
|
この君は、兄弟の中でとても器量がよく、難のない態度で、ゆったりと見渡して、昔を思い出している様子である。
|
この人は兄弟の中で最も風采のよい人で、落ち着いた態度で邸の中を見まわしながらも、亡き兄のことを思い出しているふうであった。
|
【この君は、なかにいと容貌よく、めやすきさまにて】- 蔵人少将。柏木の兄弟の中で。
【いにしへを思ひ出でたるけしきなり】- 柏木在世中を。
|
| 7.3.9 |
|
「参上し馴れた気がして、久しぶりの感じもしませんが、そのようにはお認めいただけないでしょうか」
|
「始終伺っている所のような気になって私はいるのですが、そちらでは親しい者とお認めくださらないかもしれませんね」
|
【参り馴れにたる心地して】- 以下「許さずやあらむ」まで、少将の詞。
【さも御覧じ許さずやあらむ】- 『完訳』は「来なれた者として大目には見ていただけないのか、の意」と注す。
|
| 7.3.10 |
などばかりぞかすめたまふ。
御返りいと聞こえにくくて、
|
などとだけそれとなくおっしゃる。
お返事はとても申し上げにくくて、
|
などと皮肉を少し言う。大臣への返事をしにくく宮は思召して、
|
|
| 7.3.11 |
|
「わたしはとても書くことできない」
|
「私にはどうしても書かれない」
|
【われはさらにえ書くまじ】- 落葉宮の詞。女房たちに言ったもの。
|
| 7.3.12 |
とのたまへば、
|
とおっしゃるので、
|
こうお言いになると、
|
|
| 7.3.13 |
「御心ざしも隔て若々しきやうに。宣旨書き、はた聞こえさすべきにやは」 |
「お気持ちも通じず子供っぽいように思われます。
代筆のお返事は、差し上げるべきではありません」
|
「お返事をなさいませんと、あちらでは礼儀のないようにお思いになるでございましょうし、私どもが代わって御挨拶をいたしておいてよい方でもございませんから」
|
【御心ざしも】- 以下「聞こえさすべきにやは」まで、女房の詞。反語表現。
|
| 7.3.14 |
と、集りて聞こえさすれば、まづうち泣きて、
|
と寄ってたかって申し上げるので、何より先涙がこぼれて、
|
女房たちが集まって、なおもお書きになることをお促しすると、宮はまずお泣きになって、
|
|
| 7.3.15 |
|
「亡くなった母上が生きていらっしゃったら、どんなに気にくわない、とお思いになりながらも、罪を庇ってくれたであろうに」
|
御息所が生きていたなら、どんなに不愉快なことと自分の今日のことを思っても、身に代えて罪は隠してくれるであろう
|
【故上おはせましかば】- 以下「隠いたまはまし」まで、落葉宮の心中。「ましかば」--「まし」反実仮想の構文。
|
| 7.3.16 |
と思ひ出でたまふに、涙のみつらきに先だつ心地して、書きやりたまはず。
|
とお思い出しなさると、涙ばかりが辛さに先走る気がして、お書きになれない。
|
と母君の大きな愛を思い出しながら、お書きになる紙の上には、墨よりも涙のほうが多く伝わって来てお字が続かない。
|
|
| 7.3.17 |
|
「どういうわけで、
世の中で人数にも入らないわたしのような身を辛
|
何故か世に数ならぬ身一つを
憂しとも思ひ悲しとも聞く
|
【何ゆゑか世に数ならぬ身ひとつを--憂しとも思ひかなしとも聞く】- 落葉宮の返歌。『完訳』は「「数ならぬ身ひとつ」と、夕霧とは無関係に、一人を強調。下の句は、大臣の歌の下句に照応」と注す。『奥入』は「月やあらぬ春や昔の春ならぬ我が身一つはもとの身にして」(古今集恋五、七四七、在原業平)を指摘。
|
| 7.3.18 |
とのみ、思しけるままに、書きもとぢめたまはぬやうにて、おしつつみて出だしたまうつ。少将は、人びと物語して、 |
とだけ、お心にうかんだままに、終わりまで書かなかったような書きぶりで、ざっと包んでお出しになった。
少将は、女房と話して、
|
と実感のままお書きになり、それだけにして包んでお出しになった。少将は女房たちとしばらく話をしていたが、
|
【おしつつみて】- 上包みに包んで。
|
| 7.3.19 |
|
「時々お伺いしますのに、このような御簾の前では、頼りない気がいたしますが、今からは御縁のある気がして、常に参上しましょう。
御簾の中にもお許しいただけそうな、長年の忠勤の結果が現れましたような気がいたします」
|
「時々伺っている私が、こうした御簾の前にお置かれすることは、あまりに哀れですよ。これからはあなたがたを友人と思って始終まいりますから、お座敷の出入りも許していただければ、今日までの志が酬いられた気がするでしょう」
|
【時々さぶらふに】- 以下「心地なむしはべる」まで、少将の詞。
【今よりはよすがある心地して】- 『完訳』は「暗に、姉婿の夕霧が夫になった縁から訪れやすく、常に参上しよう、といやがらせに言う」と注す。
【内外なども許されぬべき】- 御簾の内側と外側、御簾の中への自由な出入りをいう。
【年ごろのしるし現はれはべる心地なむしはべる】- 『完訳』は「自分も夕霧同様にしばしば参上して忠勤に励んだので、同じように扱ってもらえそう。宮を好色の女と言わんばかりのいやみ」と注す。
|
| 7.3.20 |
など、けしきばみおきて出でたまひぬ。
|
などと、思わせぶりな態度を見せてお帰りになった。
|
などという言葉を残して蔵人少将は帰った。
|
|
|
第四段 藤典侍、雲居雁を慰める
|
| 7.4.1 |
|
ますますおもしろからぬご気分に、気もそぞろにうろうろなさっているうちに、大殿邸にいる女君は、何日も経るうちに、お悲しみ嘆くことしばしばである。
藤典侍は、このようなことを聞くと、
|
こんなことから宮の御感情はまたまた硬化していくのに対して、夕霧が煩悶と焦躁で夢中になっている間、一方で雲井の雁夫人の苦悶は深まるばかりであった。こんな噂を聞いている典侍は、
|
【いとどしく心よからぬ御けしき】- 落葉宮の機嫌。致仕太政大臣からの手紙によってますます不機嫌となる。
【あくがれ惑ひたまふほど】- 主語は夕霧。
【大殿の君は】- 雲居雁。大殿邸にいる女君のニュアンス。
【典侍、かかることを聞くに】- 藤典侍。惟光の娘、「少女」巻に初出、「藤裏葉」「若菜下」巻にも登場。
|
| 7.4.2 |
|
「わたしを長年ずっと許さないとおっしゃっていたと聞いているが、このように馬鹿にできない相手が現れたこと」
|
自分を許しがたい存在として嫉妬し続ける夫人にとって今度こそ侮りがたい相手が出現したではないか
|
【われを世とともに】- 以下「出で来にけるを」まで、藤典侍の心中。
【かくあなづりにくきことも】- 『完訳』は「雲居雁は北の方とはいえ、皇女の身の宮を軽視できない。藤典侍の同情の裏には、今まで雲居雁に見下げられてきた恨みがこもる」と注す。
|
| 7.4.3 |
|
と思って、手紙などは時々差し上げていたので、お見舞い申し上げた。
|
と思って、手紙などは時々送っているのであったから、見舞いを書いて出した。
|
【文などは時々たてまつれば】- 挿入句。今までに文通はしていたので。直前の「思ひて」はこの句の下の「聞こえたり」に続く。
|
| 7.4.4 |
|
「わたしが人数にも入る女でしたら夫婦仲の悲しみを思い知られましょうが
あなたのために涙で袖をぬらしております」
|
数ならば身に知られまし世の憂さを
人のためにも濡らす袖かな
|
【数ならば身に知られまし世の憂さを--人のためにも濡らす袖かな】- 藤典侍から雲居雁への贈歌。「身」は我が身、「人」はあなた雲居雁。『異本紫明抄』は「我が身にはきにけるものを憂き事は人の上とも思ひけるかな」(小町集)を指摘。
|
| 7.4.5 |
|
何となく出過ぎた手紙だとは御覧になったが、何となくしみじみと物思いに沈んでいる時の所在なさに、「あの人もとても平気ではいられまい」とお思いになる気にも、幾分おなりになった。
|
失敬なというような気も夫人はするのであったが、物の身にしむころで、しかも退屈な中にいてはこれにも哀れは覚えないでもなかった。
|
【なまけやけしとは見たまへど】- 主語は雲居雁。
【かれもいとただにはおぼえじ】- 雲居雁の心中。「かれ」は藤典侍をさす。
|
| 7.4.6 |
|
「他人の夫婦仲の辛さをかわいそうにと思って見てきたが
わが身のこととまでは思いませんでした」
|
人の世の憂きを哀れと見しかども
身に代へんとは思はざりしを
|
【人の世の憂きをあはれと見しかども--身にかへむとは思はざりしを】- 雲居雁の返歌。「身」「世」「憂」「人」の語句を用いて返す。『集成』は「よく同情して下さいました、の意」と注す。
|
| 7.4.7 |
|
とだけあるのを、お思いになったままだと、しみじみと見る。
|
とだけ書かれた返事に、典侍はそのとおりに思うことであろうと同情した。
|
【思しけるままと】- 藤典侍は雲居雁がお心のままに詠んだ歌と理解する。
【あはれに見る】- 『集成』は「同情する」。『完訳』は「しみじみお気の毒に思っている」と訳す。
|
| 7.4.8 |
|
あの、昔、二人のお仲が遠ざけられていた期間は、この典侍だけを、密かにお目をかけていらっしゃったのだが、事情が変わってから後は、とてもたまさかに、冷たくおなりになるばかりであったが、そうは言っても、子供たちは大勢になったのであった。
|
夫人と結婚のできた以前の青春時代には、この典侍だけを隠れた愛人にして慰められていた大将であったが、夫人を得てからは来ることもたまさかになってしまった。さすがに子供の数だけはふえていった。
|
【この、昔、御中絶えのほどに】- 夕霧と雲居雁の仲が父大臣によって妨げられていた間、「少女」巻から「藤裏葉」巻で結婚するまで、六年間あった。
【内侍のみこそ】- 「思ひとめたまへりしか」にかかる。逆接用法。
【こと改めて後は】- 夕霧と雲居雁が結婚して後。
|
| 7.4.9 |
この御腹には、太郎君、三郎君、五郎君、六郎君、中の君、四の君、五の君とおはす。内侍は、大君、三の君、六の君、次郎君、四郎君とぞおはしける。すべて十二人が中に、かたほなるなく、いとをかしげに、とりどりに生ひ出でたまひける。 |
こちらがお生みになったのは、太郎君、三郎君、五郎君、六郎君、中の君、四の君、五の君といらっしゃる。
藤典侍は、大君、三の君、六の君、二郎君、四郎君といらっしゃった。
全部で十二人の中で、出来の悪い子供はなく、とてもかわいらしく、それぞれに大きくおなりになっていた。
|
夫人の生んだのは、長男、三男、四男、六男と、長女、二女、四女、五女で、典侍は三女、六女、二男、五男を持っていた。大将の子は皆で十二人であるが、皆よい子で、それぞれの特色を持って成長していった。
|
【この御腹には】- 雲居雁腹をさす。
【太郎君】- 『完訳』は「以下の子供の人数、雲居雁腹と藤典侍腹の割り振りは諸本によっても異同が多く、そのいずれによっても他の巻の記述と矛盾する」と注す。
【とりどりに生ひ出でたまひける】- 大島本は「たま(ま+ウ<朱>)ける」とある。すなわち朱筆で「う」を補入する。『集成』は「たまひける」と整定する。『完本』『新大系』は底本の訂正以前の「たまける」と整定する。
|
| 7.4.10 |
|
藤典侍のお生みになった子供は、特に器量がよく、才気が見えて、みな立派であった。
三の君と、二郎君は、六条院の東の御殿で、特別に引き取ってお世話申していらっしゃる。
院も日頃御覧になって、とてもかわいがっていらっしゃる。
|
典侍の生んだ男の子は顔もよく、才もあって皆すぐれていた。三女と二男は六条院の花散里夫人が手もとへ引き取って世話をしていた。その子供たちは院も始終御覧になって愛しておいでになった。
|
【三の君、次郎君は、東の御殿にぞ、取り分きてかしづきたてまつりたまふ】- 六条院の東町、花散里の御殿で養育。
【院も見馴れたまうて】- 源氏も日頃御覧になって、の意。
|
| 7.4.11 |
|
このお二方の話は、いろいろとあって語り尽くせない、とのことである。
|
それはまったく理想的にいっているわけである。
|
【この御仲らひのこと、言ひやるかたなく、とぞ】- 『弄花抄』は「紫式部か語也巻々如此」。『細流抄』は「例の作者の語也」。『評釈』は「いま姫君に語って聞かせる女房(この物語の本文をよみあげる女房)の言葉となる。「言ひやる方なく」とは、昔の、源氏を見た古女房の言葉であり、それをここに伝えるのだ、と、ことわるのである」。『集成』は「このご一統のお話は、とても語り尽せたものではないとのことです。語り手の口ぶりをそのまま伝える草子地の筆法」「夕霧と落葉の宮の物語を、夕霧の家庭に生じた一波瀾という印象で収束しようとする語り手の意図がうかがえる」。『完訳』は「問題が複雑すぎて語り尽せないとする。語り手の省筆の弁」「律儀者の子沢山を印象づけながら、ほろ苦い家庭喜劇の幕が閉じられる。次巻からは本筋へ復帰」。
|
| 著作権 |
| 底本 |
大島本 |
| 校訂 |
Last updated 9/22/2010(ver.2-3)
渋谷栄一校訂(C)
オリジナル
修正版
比較 |
| ローマ字版 |
Last updated 7/29/2010 (ver.2-2)
Written in Japanese roman letters
by Eiichi Shibuya (C)
オリジナル
修正版
比較 |
ルビ抽出
(ローマ字版から)
|
Powered by 再編集プログラム v4.05
ひらがな版
ルビ抽出 |
挿絵
(ローマ字版から)
|
'Eiri Genji Monogatari'
(1650 1st edition) |
|
Last updated 2/3/2002
渋谷栄一訳(C)(ver.1-2-2)
オリジナル
修正版
比較 |
|
|
Last updated 7/29/2010(ver.2-2)
渋谷栄一注釈(C)
オリジナル
修正版
比較 |
|