第三帖 空蝉
#
本文
渋谷栄一訳
与謝野晶子訳
注釈
光る源氏十七歳夏の物語
第一段 空蝉の物語
いとらうたしと
あながちにかかづらひたどり
とてもかわいいとお思いになる。
手触りから、ほっそりした小柄な体つきや、髪のたいして長くはなかった感じが似通っているのも、気のせいか愛しい。
むやみにしつこく探し求めるのも、体裁悪いだろうし、本当に癪に障るとお思いになりながら夜を明かしては、いつものように側につきまとわせおっしゃることもない。
夜の深いうちにお帰りになるので、この子は、たいそうお気の毒で、つまらないと思う。
「私はこんなにまで人から冷淡にされたことはこれまでないのだから、今晩はじめて人生は悲しいものだと教えられた。恥ずかしくて生きていられない気がする」
などと言うのを小君は聞いて涙さえもこぼしていた。非常にかわいく源氏は思った。思いなしか手あたりの小柄なからだ、そう長くは感じなかったあの人の髪もこれに似ているように思われてなつかしい気がした。この上しいて女を動かそうとすることも見苦しいことに思われたし、また真から恨めしくもなっている心から、それきり言づてをすることもやめて、翌朝早く帰って行ったのを、小君は気の毒な物足りないことに思った。
【我は、かく人に】- 以下「思ひなりぬれ」まで、源氏の詞。小君に向かって言う。
【今宵なむ】- 係助詞「なむ」は「知りぬれ」に係るが、下文に続いて、結びの流れとなっている。「今宵なむ世を憂しと初めて思ひ知りぬれば」が通常の語順。
【涙をさへこぼして臥したり】- 主語は小君。
【いとらうたしと思す】- 主語は源氏。小君を可愛いとお思いになる。
【手さぐりの】- 以下、源氏は小君を愛撫しながら、先夜、空蝉と契った時の感触を思い出す。
【思ひなしにや】- 小君を空蝉の姉弟と思うせいか。
【あながちに】- 以下「めざまし」まで、源氏の心を語る。
【例のやうにものたまひまつはさず】- 源氏は、いつものように、小君を側に召していろいろとものを命じることをなさらない。
【夜深う出でたまへば】- 「夜深し」は明け方からみて、夜がまだ深い、深夜、の意。「夜更け」は宵からみて夜が更けていく、意。女のもとから帰るには早すぎる時刻。
【いといとほしく、さうざうし】- 小君の源氏に対する気持ち。
お懲りになったのだと思うにつけても、「このまま冷めておやめになってしまったら嫌な思いであろう。
強引に困ったお振る舞いが絶えないのも嫌なことであろう。
適当なところで、こうしてきりをつけたい」と思うものの、平静ではなく、物思いがちである。
【御消息も絶えてなし】- 接頭語「御」があるので源氏からの手紙の意。副詞「絶えて」、下に打消しの語を伴って、全然、まったく、の意を表す。源氏からの御消息もまったく来ない。
【思し懲りにけると思ふにも】- 主語は空蝉。源氏の君は懲り懲りとお思いになっているのだと思うと、の意。
【やがてつれなくて】- 以下「閉ぢめてむ」まで、空蝉の心を語る。「止みたまひなましかば」の主語は源氏。「ましかば--まし」の反実仮想の構文。源氏が、あのまま音沙汰なしでおやめになってしまったら嫌な思いがするだろうが、そうともなるまい、の意。
【憂からまし】- 嫌な思いをすることであろう。源氏に対する同情の気持ちとも、また自分自身のつらい気持ちともとれるが、前者に解す。『集成』は「あのまま音沙汰なしでおやめになってしまったら、つらい思いをしていることであろう」と解し、『完訳』は「もしこのまま、何事もなくそれきりになってしまうとしたなら、恨めしいことだろうに」と解す。
【うたてあるべし】- 自分にとって、困ったことであろう。
【よきほどに】- 『古典セレクション』は諸本に従って「よきほどにて」と校訂する。
さりぬべきをり
適当な機会を見つけて、逢えるように手立てせよ」とおっしゃり続けるので、やっかいに思うが、このような事柄でも、お命じになって使ってくださることは、嬉しく思われるのであった。
「あんな無情な恨めしい人はないと私は思って、忘れようとしても自分の心が自分の思うようにならないから苦しんでいるのだよ。もう一度逢えるようないい機会をおまえが作ってくれ」
こんなことを始終小君は言われていた。困りながらこんなことででも自分を源氏が必要な人物にしてくれるのがうれしかった。
【心にしも従はず苦しきを】- 副助詞「しも」強調。間投助詞「を」詠嘆の意、と解す。
【わづらはしけれど】- 主語は小君。
第二段 源氏、再度、紀伊守邸へ
【夕闇の道たどたどしげなる紛れに】- 『源氏釈』は「夕闇は道たどたどし月待ちて帰れわが背子その間にも見む」(古今六帖一、夕闇、三七一)を指摘する。この和歌の上の句の言葉を使って表現する。
【わが車にて】- 小君の車で源氏を。
【のどむまじければ】- 大島本「のとむましけれは」とある。打消助動詞「まじけれ」已然形+接続助詞「ば」の形。『集成』『古典セレクション』は「まじかりければ」と諸本に従って校訂。『新大系』も「底本「ましけれは」、青表紙諸本「ましかりけれは」。底本の誤記と認めて訂正する」と「かり」を補訂する。とすれば、打消助動詞「まじかり」連用形+過去助動詞「けれ」已然形+接続助詞「ば」の形となり、過去の意味が明確化する。
【さりげなき姿にて】- お忍びの姿。狩衣であろう。
子供なので、宿直人なども特別に気をつかって機嫌をとらず、安心である。
【追従せず】- 大島本「ついせう」と表記する。『岩波古語辞典』は「ついしょう」を見出語とする。他に「ついそう」を立項し「ソウはショウの直音化」と説明。小学館『古語大辞典』では「ついしょう」の他に「ついせう」「ついそう」も立項し同様の説明をする。
御達は、
【立てたてまつりて】- 小君が源氏の君をお待たせ申して。
【我は南の隅の間】- 寝殿の南面に回ってその東隅の間から。
【御達、--「あらはなり」と言ふなり】- 「言ふ」終止形+「なり」は伝聞推定の助動詞。部屋の中の御達の声が源氏の耳に聞こえてくる。
と小言を言っている。
【下ろされたる】- 尊敬の助動詞「れ」連用形。軽い尊敬の意。
と女房は言った。
【渡らせたまひて、碁打たせたまふ】- 尊敬の助動詞「せ」+尊敬の補助動詞「たまひ」、最高敬語。会話文中では軒端荻のような人に対しても使われる。
【はさま】- 「交 アハヒ ハサマ」(名義抄)。室町時代以後「はざま」と濁音化する。
【隙見ゆるに、寄りて西ざまに】- 源氏は寝殿の東面の妻戸口から小君が入っていったに南面の格子の所に移動し、その簾の脇の隙間から母屋の中を東から西の方角に覗く。
【この際に立てたる屏風】- 「この」は小君が上げて入っていった格子のもと。
【おし畳まれたるに】- 接続助詞「に」は添加の意を表す。畳まれているうえに、の意。
【暑ければにや】- 断定の助動詞「に」、疑問の係助詞「や」は、源氏の判断や推量を表す。源氏の目を通して語る。
【うち掛けて】- 几帳の帷子をまくり上げてそれを几帳の上の横木に掛けてある様子。
【いとよく見入れらる】- 可能の助動詞「らる」終止形。
第三段 空蝉と軒端荻、碁を打つ
母屋の中柱に横向きになっている人が自分の思いを寄せている人かと、まっさきに目をお留めになると、濃い紫の綾の単重襲のようである。
何であろうか、その上に着て、頭の恰好は小さく小柄な人で、見栄えのしない姿をしているのだ。
顔などは、向かい合っている人などにも、特に見えないように気をつけている。
手つきも痩せ痩せした感じで、ひどく袖の中に引き込めているようだ。
【母屋の中柱に側める人やわが心かくる】- 語り手の文章、すなわち地の文と、源氏の心を語る文とが融合したような性格の叙述である。
【濃き綾の単衣襲なめり】- 以下、源氏の目を通して語る叙述のしかた。「なめり」は断定の助動詞「なる」連体形の「る」が撥音便化しさらに無表記化された形。推量の助動詞「めり」終止形、主観的推量の意。空蝉の服装は、濃い紫の綾の単衣の上に何かよくわからないがやはり単衣の表着を襲着している。「単衣襲(ひとえがさね)」とは、夏、表着(うわぎ)の下に着る単(ひとえ)。すなわち、単(ひとえ)を二枚を重ね着したもの。
【何にかあらむ】- 源氏の推測。
【頭つき細やかに】- 頭の恰好が小さいのは、源氏物語絵巻などに見える。美しい形である。
【ものげなき姿ぞしたる】- 『集成』は「見ばえのしない姿」、『完訳』は「目だたぬ姿」、『新大系』は「いかにも貫祿のない。物々しくない。見栄えのしない空蝉のさま」と注す。係助詞「ぞ」とその係結び、強調のニュアンス。初めて明かりの中で見る空蝉の姿。質素で地味な姿をいうのであろう。
【わざと見ゆまじうもてなしたり】- 空蝉の慎み深い態度をいう。
【いたうひき隠しためり】- 空蝉の慎み深い態度。完了の助動詞「たる」連体形の「る」が撥音便化してさらに無表記の形。推量の助動詞「めり」は見る人源氏の主観的推量のニュアンス。
いま一人 は、東向 きにて、残 るところなく見 ゆ。
白 き羅 の単衣襲 、二藍 の小袿 だつもの、ないがしろに着 なして、紅 の腰 ひき結 へる際 まで胸 あらはに、ばうぞくなるもてなしなり。
いと白 うをかしげに、つぶつぶと肥 えて、そぞろかなる人 の、頭 つき額 つきものあざやかに、まみ口 つき、いと愛敬 づき、はなやかなる容貌 なり。
髪 はいとふさやかにて、長 くはあらねど、下 り端 、肩 のほどきよげに、すべていとねぢけたるところなく、をかしげなる人 と見 えたり。
いと
白い羅の単衣に、二藍の小袿のようなものを、しどけなく引っ掛けて、紅の袴の腰紐を結んでいる際まで胸を露わにして、嗜みのない恰好である。
とても色白で美しく、まるまると太って、大柄の背の高い人で、頭の恰好や額の具合は、くっきりとしていて、目もと口もとが、とても愛嬌があり、はなやかな容貌である。
髪はとてもふさふさとして、長くはないが、垂れ具合や、肩のところがすっきりとして、どこをとっても悪いところなく、美しい女だ、と見えた。
【白き羅の単衣襲、二藍の小袿だつもの】- 軒端荻の服装は、白い羅の単衣の上に紅と藍の中間色の小袿らしいものを着ている。襲の色目では、「二藍」は表が赤みがかった濃い縹色で、裏は縹色をいうが、ここは夏だから、紅色と藍色の中間色をいうものであろうか。婦人の略礼装の姿である。
【ばうぞくなるもてなしなり】- しまりのない姿。「放俗」また「凡俗」かとされる。
【をかしげなる人と見えたり】- 源氏の視点を通しての叙述。
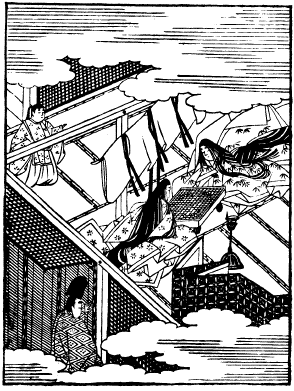
むべこそ親 の世 になくは思 ふらめと、をかしく見 たまふ。
心地 ぞ、なほ静 かなる気 を添 へばやと、ふと見 ゆる。
かどなきにはあるまじ。
碁打 ち果 てて、結 さすわたり、心 とげに見 えて、きはぎはとさうどけば、奥 の人 はいと静 かにのどめて、
かどなきにはあるまじ。
心づかいに、もう少し落ち着いた感じを加えたいものだと、ふと思われる。
才覚がないわけではないらしい。
碁を打ち終えて、だめを押すあたりは、機敏に見えて、陽気に騷ぎ立てると、奥の人は、とても静かに落ち着いて、
【なほ静かなる気を添へばやと】- 終助詞「ばや」話者の願望を表す。
【かどなきにはあるまじ】- 『岷江入楚』に「三光院実枝説」として「草子地なり」、また萩原広道の『源氏物語評釈』に「源氏君の心になりて草子地より評じたる也」とある。源氏の批評と語り手の批評が重なったような表現。
【結さすわたり】- 「結」は囲碁用語。いわゆる「だめ」。『集成』は「「闕」は、双方の地の境界で、どちらの地にもならない所」と注す。
そこは、持でありましょう。
このあたりの、
などと言うが、
【持】- 大島本は「持」と表記。勝ち負けのない所。『集成』は「勝ち負けのない個所。いわゆる「せき」であろう。攻め合いでどちらが先に石を置いても置いた方が取られてしまうような形になった所」と注す。
【劫をこそ】- 『集成』は「「劫」は、一目を交互に取り返す形になった所。互いにほかの所に打って相手に受けさせてから取る。ここは石の死活には関係のないいわゆる半劫であろう」と注す。
隅の所は、どれどれ」と指を折って、「十、二十、三十、四十」などと数える様子は、伊予の湯桁もすらすらと数えられそうに見える。
少し下品な感じがする。
指を折って、十、二十、三十、四十と数えるのを見ていると、無数だという伊予の温泉の湯桁の数もこの人にはすぐわかるだろうと思われる。少し下品である。
【隅のところ】- 大島本「すみの所」とある。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「隅の所どころ」と校訂する。
【伊予の湯桁も】- 『体源抄』所引「風俗歌」に「伊予の湯の 湯桁は幾つ いさ知らず や 算(かず)へず数(よ)まず やれ そよや なよや 君ぞ知るらう や」とある。伊予の湯は湯桁の数多いことで知られていた。
【すこし品おくれたり】- 萩原広道の『源氏物語評釈』は「源氏君の心になりて草子地より評じたる也」と指摘する。源氏の批評と語り手の批評が重なったような表現。
たとしへなく口 おほひて、さやかにも見 せねど、目 をしつけたまへれば、おのづから側目 も見 ゆ。
目 すこし腫 れたる心地 して、鼻 などもあざやかなるところなうねびれて、にほはしきところも見 えず。
言 ひ立 つれば、悪 ろきによれる容貌 をいといたうもてつけて、このまされる人 よりは心 あらむと、目 とどめつべきさましたり。
目が少し腫れぼったい感じがして、鼻筋などもすっきり通ってなく老けた感じで、はなやかなところも見えない。
言い立てて行くと、悪いことばかりになる容貌をとてもよく取り繕って、傍らの美しさで勝る人よりは嗜みがあろうと、目が引かれるような態度をしている。
【目をしつけたまへれば】- 主語は源氏。大島本「めをしつけたまへれは」とある。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「目をしつとつけたまへれば」と校訂する。「し」は強意の副助詞、「つと」はぴったりとの意の副詞。『新大系』は底本のまま。「目をばとめていらっしゃると。「目押し付けたまへれば」ではあるまい。他本多く「めをしつとつけたまへれは」。底本は尾州家本に一致する」と注している。
【言ひ立つれば】- 源氏の心と語り手のことばが一体化した表現。
【悪ろきによれる容貌を】- 「帚木」巻では、空蝉の容貌について、源氏の発言「よろしく聞こえし人ぞかし」に対して、紀伊守も「けしうははべらざるべし」と答え(第三章三段)、空蝉の父衛門督が「宮仕へに出だし立てむと漏らし奏せし」(第三章二段)と考えていたくらいだから、まずまずの美人であったはず。ところが、「空蝉」巻では不美人だが嗜みのよさによって素晴しい女性として語られている。
【このまされる人よりは】- 軒端荻をさす。
にぎははしう愛敬 づきをかしげなるを、いよいよほこりかにうちとけて、笑 ひなどそぼるれば、にほひ多 く見 えて、さる方 にいとをかしき人 ざまなり。
あはつけしとは思 しながら、まめならぬ御心 は、これもえ思 し放 つまじかりけり。
あはつけしとは
軽率であるとはお思いになるが、お堅くないお心には、この女も捨てておけないのであった。
【笑ひなどそぼるれば】- 「戯(そぼ)る」自ラ下二段動詞、「戯(そば)ふ」と同根。
【さる方に】- 少し下品はするが、それなりに、の意。
【まめならぬ御心は】- 「御心」は源氏の心。語り手の批評の加わった表現。『岷江入楚』所引の三光院実枝説に「草子地なり」と指摘、萩原広道の『源氏物語評釈』には「草子地より戯れて評じたるなり」とある。
【うはべをのみこそ見たまへ】- 係助詞「こそ」は尊敬の補助動詞「たまへ」已然形に係るが、下文に続く逆接用法。
【何心もなうさやかなるはいとほしながら】- 源氏と語り手の気持ちが一体化した叙述。
【久しう見たまはまほしきに】- 希望の助動詞「まほしき」連体形、接続助詞「に」逆接。
とても恐れ多いと思って、
【いとかたじけなしと思ひて】- 主語は小君。源氏をいつまでも待たせたことに。
まったくあきれて、ひどいではないか」とおっしゃると、
【あべけれ】- 「あるべけれ」の「る」が撥音便化してさらに無表記の形。
あちらに帰りましたら、きっと手立てを致しましょう」と申し上げる。
と言った。
【あなたに帰りはべりなば】- 主語は軒端荻。完了の助動詞「な」未然形+接続助詞「ば」仮定条件を表す。
【たばかりはべりなむ】- 完了の助動詞「な」未然形、推量の助動詞「む」意志を表す。
子供であるが、物事の事情や、人の気持ちを読み取れるくらい落ち着いているから」と、お思いになるのであった。
【しづまれるを】- 接続助詞「を」理由を表す。
【人びとあかるる】- 空蝉、軒端荻付きの女房たち。このような遊び事の場面には必ず女房たちも女主人の側に付きしたがっているものである。
【けはひなどすなり】- サ変動詞「す」終止形+「なり」伝聞推定の助動詞。
この御格子は閉めましょう」と言って、物音を立てさせているのが聞こえる。
と言って格子をことことと中から鳴らした。
【いづくにおはしますならむ】- 指示代名詞「いづく」。「おはします」連体形は小君に対する敬語表現。「おはす」より高い敬意。断定の助動詞「なら」未然形、推量の助動詞「む」連体形。
【この御格子は鎖してむ】- 先程小君が入ってきたところの御格子。完了の助動詞「て」連用形、確述の意、推量の助動詞「む」意志を表す。閉めてしまいましょう、のニュアンス。
【鳴らすなり】- 使役の助動詞「す」終止形+伝聞推定の助動詞「なり」終止形。
入って、それでは、うまく工夫せよ」とおっしゃる。
と源氏は言った。
【いもうとの御心はたわむところなくまめだちたれば】- 姉の空蝉の性格について説明した挿入句。 【いもうとの御心】-「いもうと」は小君の姉、空蝉。
【人少なならむ折に入れたてまつらむ】- 小君の心。女房などが空蝉の側から少なくなったころに、の意。
ここにいるのか。わたしにのぞき見させよ」
格子には几帳が添え立ててあります」と申し上げる。
と小君が言う。
【さははべらむ】- 連語「さは」。推量の助動詞「む」連体形。
【見つとは知らせじ、いとほし】- 源氏の心中。完了の助動詞「つ」終止形、既に見てしまった、の意。打消推量の助動詞「じ」終止形、意志の打消し。「いとほし」は小君に対する、気の毒だ、の気持ち。
妻戸を叩いて入って行く。女房たちは
女房たちは皆寝てしまった。
【皆人びと静まり寝にけり】- 女房たち。完了の助動詞「に」連用形、完了の意。過去の助動詞「けり」終止形。静かになってなって眠った。
風よ吹き抜けておくれ」と言って、畳を広げて横になる。
女房たちは、東廂に大勢寝ているのだろう。
妻戸を開けた女童もそちらに入って寝てしまったので、しばらく空寝をして、灯火の明るい方に屏風を広げて、うす暗くなったところに、静かにお入れ申し上げる。
と言って、小君は板間に上敷をひろげて寝た。女房たちは東南の隅の室に皆はいって寝たようである。小君のために妻戸をあげに出て来た童女もそこへはいって寝た。しばらく空寝入りをして見せたあとで、小君はその隅の室からさしている灯の明りのほうを、ひろげた屏風で隔ててこちらは暗くなった妻戸の前の室へ源氏を引き入れた。
【まろは寝たらむ】- 完了の助動詞「たら」未然形、存続の意。推量の助動詞「む」意志を表す。
【畳広げて臥す】- 上敷きの畳。当時の寝殿造りの室内には一部に畳が敷かれている。平安末期に作製された国宝「源氏物語絵巻」鈴虫第二段など参照。後世の源氏絵では室内一面に畳が敷き詰められている。
【寝たるべし】- 推量の助動詞「べし」は、小君と語り手の視点が一体化した叙述。
【灯明かき方に屏風を広げて】- 光を遮るためである。
【影ほのかなるに】- 断定の助動詞「なる」連体形、下に「ところ」などの語が省略されている。格助詞「に」場所を表す。
「いかにぞ、をこがましきこともこそ」と思 すに、いとつつましけれど、導 くままに、母屋 の几帳 の帷子引 き上 げて、いとやをら入 りたまふとすれど、皆静 まれる夜 の、御衣 のけはひやはらかなるしも、いとしるかりけり。
それはきわめて細心に行なっていることであったが、家の中が寝静まった時間には、柔らかな源氏の衣摺れの音も耳立った。
【導くままに】- 主語は小君。
【やはらかなるしも、いとしるかりけり】- 副助詞「しも」強調の意。源氏の高貴な柔らかな衣装の音がかえって静かな室内に顕著に際立たせる様子。
第四段 空蝉逃れ、源氏、軒端荻と契る
人知れぬ恋は昼は終日物思いをして、夜は寝ざめがちな女にこの人をしていた。碁の相手の娘は、今夜はこちらで泊まるといって若々しい屈託のない話をしながら寝てしまった。
【心とけたる寝だに寝られず】- 副助詞「だに」打消の助動詞「ず」を伴って、述語の表す動作・状態に対して、例外的、逆接的な事物、事態であることを示す。--でさえ、--さえも、の意。『紫明抄』は「君恋ふる涙の凍る冬の夜は心とけたるいやは寝らるる」(拾遺集、恋二、七二七、読人しらず)を指摘する。
【昼はながめ、夜は寝覚めがちなれば】- 『河海抄』は「夜は覚め昼はながめに暮らされて春はこのめぞいとなかりける」(一条摂政御集、一三二)を指摘する。
【春ならぬ木の芽】- 「木の芽」と「この目」を掛ける。
【いとなく嘆かしきに】- 形容詞「暇(いと)なく」連用形。接続助詞「に」逆接を表す。
【碁打ちつる君】- 軒端荻。
【今めかしくうち語らひて】- 軒端荻と空蝉は継子と継母の関係で、昔の古物語では仲好くないというのが通例。それに比して、仲良く一緒に寝ようというので、当世風にといったもの。
【寝にけり】- 完了の助動詞「に」連用形、過去の助動詞「けり」終止形。語り手が読者だけにそっと事情を知らせたニュアンス。源氏はこのことを知らない。
このような感じが、とても香り高く匂って来るので、顔を上げると、単衣の帷子を打ち掛けてある几帳の隙間に、暗いけれども、にじり寄って来る様子が、はっきりとわかる。
あきれた気持ちで、何とも分別もつかず、そっと起き出して、生絹の単衣を一枚着て、そっと抜け出したのだった。
【かかるけはひ】- 源氏が忍び込んで来た様子。
【うち匂ふに】- 接続助詞「に」原因・理由を表す。
【顔をもたげたるに】- 主語は空蝉。接続助詞「に」順接、--すると、の意を表す。
【単衣うち掛けたる几帳の隙間に】- 几帳の単衣の帷子。風通しをよくするためうち掛けてあったのだろう。夏用の几帳。『集成』は「几帳の帷(かたびら)(表と裏二枚)のうち裏一枚を几帳の手(横木)に掛けてあるのであろう」と注す。『古典セレクション』は「空蝉の寝床のすぐ傍らの几帳で。前文の「母屋の几帳の帷子(かたびら)ひき上げて」とあったものとは別」と注す。
【あさましくおぼえて】- 空蝉の気持ち。
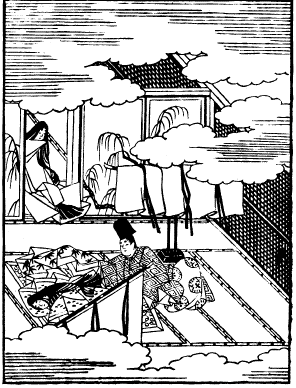
いぎたなきさまなどぞ、あやしく
かのをかしかりつる
床の下の方に二人ほど寝ている。
衣を押しやってお寄り添いになると、先夜の様子よりは、大柄な感じに思われるが、お気づきなさらない。
目を覚まさない様子などが、妙に違って、だんだんとおわかりになって、意外なことに癪に思うが、「人違いをしてまごまごしていると見られるのも愚かしく、変だと思うだろう、目当ての女を探し求めるのも、これほど避ける気持ちがあるようなので、甲斐なく、間抜けなと思うだろう」とお思いになる。
あの美しかった灯影の女ならば、何ということはないとお思いになるのも、けしからぬご思慮の浅薄さと言えようよ。
【床の下に二人ばかり】- この「床」は、御帳台の浜床ではなく、紀伊守という中流貴族の別荘のような建物の中だから、普通の板間よりはわずかに高くなっている所を「床」と呼称したものであろう。『古典セレクション』は「母屋の下長押(しもなげし)の下で、北廂。廂は母屋よりも一段低い」と注す。「二人ばかり」は女房。
【衣を押しやりて】- 寝るとき上に掛けてある夜着。
【思ほしうも寄らずかし】- 語り手の源氏を評した文章。『集成』は「草子地(作者の口吻のそのまま出た文章)である」と指摘する。「思ほしう」(形容詞シク活用、連用形ウ穏便形)の「う」。『岩波古語辞典』『古語大辞典』(小学館)も「思ほし」(形容詞シク活用)を立項する。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「思ほしも」と校訂。『新大系』は「他の多くの青表紙本により「う」を衍字と認めて削除する」とする。
【人違へとたどりて見えむも】- 以下「をこにこそ思はめ」まで、源氏の心。「見ゆ」は見られる、意。
【心あめれば】- 「あるめれば」の「る」が撥音便化してさらに無表記の形。推量の助動詞「めれ」已然形、主観的推量+接続助詞「ば」順接の確定条件を表す。
【かのをかしかりつる灯影ならば】- 以下「いかがはせむ」まで、源氏の心。軒端荻であったら、その女でも構わないという気持ち。「灯影」は軒端荻の譬喩。断定の助動詞「なら」未然形+接続助詞「ば」順接の仮定条件を表す。
【いかがはせむに】- 「いかがはせむ」反語表現。推量の助動詞「む」連体形の下に「こと」などの語が省略。格助詞「に」帰結を表す。
【悪ろき御心浅さなめりかし】- 語り手の源氏の心に対する批評。「なるめり」の「る」が撥音便化してさらに無表記形。『細流抄』は「草子地也」と指摘。『評釈』は「この一文を、むかしの注釈家は「草子地」といっている。作中世界の外の人、物語の語り手が源氏を批評していう言葉である」と指摘する。
やうやう目覚 めて、いとおぼえずあさましきに、あきれたる気色 にて、何 の心深 くいとほしき用意 もなし。
世 の中 をまだ思 ひ知 らぬほどよりは、さればみたる方 にて、あえかにも思 ひまどはず。
我 とも知 らせじと思 ほせど、いかにしてかかることぞと、後 に思 ひめぐらさむも、わがためには事 にもあらねど、あのつらき人 の、あながちに名 をつつむも、さすがにいとほしければ、たびたびの御方違 へにことつけたまひしさまを、いとよう言 ひなしたまふ。
たどらむ人 は心得 つべけれど、まだいと若 き心地 に、さこそさし過 ぎたるやうなれど、えしも思 ひ分 かず。
たどらむ
男女の仲をまだ知らないわりには、ませたところがある方で、消え入るばかりに思い乱れるでもない。
自分だとは知らせまいとお思いになるが、どうしてこういうことになったのかと、後から考えるだろうことも、自分にとってはどうということはないが、あの薄情な女が、強情に世間体を憚っているのも、やはり気の毒なので、度々の方違えにかこつけてお越しになったことを、うまくとりつくろってお話しになる。
よく気のつく女ならば察しがつくであろうが、まだ経験の浅い分別では、あれほどおませに見えたようでも、そこまでは見抜けない。
【あさましきに】- 形容詞「あさましき」連体形、下に「こと」などの語が省略。格助詞「に」対象を表す。
【我とも知らせじと思ほせど】- 主語は源氏。
【いかにしてかかることぞと】- 以下、源氏の心中文が地の文に自然と移っていく。
【あのつらき人】- 空蝉をさす。
【さすがにいとほしければ】- 空蝉との関係が軒端荻に知られるのは、やはり、空蝉に対して気の毒である、の意。『古典セレクション』は「軒端荻が後日、どうしてかといろいろ推測すれば、源氏と空蝉との仲を疑うだろう、そうなると空蝉に気の毒だ」と注す。
【たびたびの御方違へにことつけたまひしさまを】- 心中文に語り手の源氏に対する尊敬の補助動詞「たまふ」が混じった叙述となって以下は地の文へと流れている。
【たどらむ人は】- 察しのつく女なら、の意。以下、語り手の軒端荻に対する批評を交えた文。
「どこにはい隠れて、愚か者だと思っているのだろう。
このように強情な女はめったにいないものを」とお思いになるのも、困ったことに、気持ちを紛らすこともできず思い出さずにはいらっしゃれない。
この女の、何も気づかず、初々しい感じもいじらしいので、それでも愛情こまやかに将来をお約束しおかせなさる。
しかし何の疑いも持たない新しい情人も可憐に思われる点があって、源氏は言葉上手にのちのちの約束をしたりしていた。
【かのうれたき人】- 空蝉をさす。
【いづくにはひ紛れて】- 以下「ありかたきものを」まで、源氏の心。空蝉のことを思う。
【ありがたきものを】- 間投助詞「を」詠嘆を表す。
【と思すしも】- 大島本「とおほすしも」とある。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「と思すにしも」と校訂する。『新大系』は底本のまま。
【あやにくに】- 語り手の源氏の心に対する批評を交えた表現。
【思ひ出でられたまふ】- 「られ」は自発の助動詞。
【この人の】- 軒端荻。
【なま心なく、若やかなる】- 『今泉忠義訳』では「何も気づかずにゐる、若々しい」と訳す。『集成』は「別に気に病むふうもなく屈託なげな」と解す。『古典セレクション』は「なまじ無邪気で若々しい」と解す。「なま心」は、生半可な心。はっきりと思慮分別の定まらない気持ち。さらに、軽い恋情、好き心、という意もあるが、ここでは前者の意。
【契りおかせたまふ】- 「せ」は使役の助動詞。源氏は軒葉荻にお約束し置かせなさる意。
「人知 りたることよりも、かやうなるは、あはれも添 ふこととなむ、昔人 も言 ひける。
あひ思 ひたまへよ。
つつむことなきにしもあらねば、身 ながら心 にもえまかすまじくなむありける。
また、さるべき人 びとも許 されじかしと、かねて胸 いたくなむ。
忘 れで待 ちたまへよ」など、なほなほしく語 らひたまふ。
あひ
つつむことなきにしもあらねば、
また、さるべき
あなたもわたし同様に愛してくださいよ。
世間を憚る事情がないわけでもないので、わが身ながらも思うにまかすことができなかったのです。
また、あなたのご両親も許されないだろうと、今から胸が痛みます。
忘れないで待っていて下さいよ」などと、いかにもありきたりにお話しなさる。
などと、安っぽい浮気男の口ぶりでものを言っていた。
【つつむことなきにしもあらねば】- なきにしもあらずという二重否定は、あるということ。高貴な身分ゆえに自由な振る舞いも思うにまかせない、という意。
【さるべき人びとも許されじかし】- 軒端荻の後見人をいう。父伊予介と継母の空蝉。『評釈』は「こっちの都合で望むのでなく、そっちの都合でやむなくこうせざるをえないのだ、という運び方である」と指摘する。
女は素直に言っていた。
【恥づかしきになむ、え聞こえさすまじき】- 係助詞「なむ」は打消推量の助動詞「まじき」連体形に係る、係り結びの法則。副詞「え」は打消推量の助動詞「まじき」と呼応して不可能の意を表す。
何げなく振る舞っていて下さい」
【知らせばこそあらめ】- 主語はあなた軒端荻。「こそあらめ」は、係り結びの下文に続く逆接用法。--しては困るが、という懸念の意。
【この小さき上人に】- 小君をさす。童殿上しているので「小さき上人」という。
妻戸を静かに押し開けると、年老いた女房の声で、
「あれは誰 そ」
厄介に思って、
「まろぞ」と答 ふ。
と言う。
とても腹立たしく、
【いと憎くて】- 小君の気持ち。
ここに出るだけです」
と言った老女が、また、
けっこうな背丈ですこと」
背丈の高い人でいつも笑われている人のことを言うのであった。
老女房は、その人を連れて歩いていたのだと思って、
困ったが、押し返すこともできず、渡殿の戸口に身を寄せて隠れて立っていらっしゃると、この老女房が近寄って、
【わびしければ】- 大島本のみ「わひしけれは」とある。他の青表紙本系諸本「わひしけれと」とある。逆接の接続助詞「ど」の方が通りよいが、本文のままとする。『新大系』でも「わびしければ」のままとする。
【押し返さで】- 主語は小君。民部のおもとを室内へ押しもどすことができなくて。
【隠れ立ちたまへれば】- 主語は源氏。
【このおもとさし寄りて】- 老いたる御達。
一昨日からお腹の具合が悪くて、我慢できませんでしたので、下におりていましたが、人少なであると言ってお召しがあったので、昨夜参上しましたが、やはり我慢ができないようなので」
【一昨日より腹を病みて】- 主語は、わたし老いたる御達。
【召ししかば】- 御達の主人である空蝉が。
と、憂 ふ。
答 へも聞 かで、
返事も聞かないで、
また後で」と言って通り過ぎて行ったので、ようやくのことでお出になる。
やはりこうした忍び歩きは軽率で良くないものだと、ますますお懲りになられたことであろう。
と言って行ってしまった。やっと源氏はそこを離れることができた。冒険はできないと源氏は懲りた。
【からうして】- 「カラクシテの音便形。古くはカラウシテと清音か。「カラウシテ」<日葡>」(岩波古語辞典)。『集成』『新大系』は清音に読むが、『古典セレクション』は「からうじて」と濁音に読んでいる。
【なほかかる歩きは】- 以下「あやしかりけり」まで、源氏の心を語り手が推測して語る。『細流抄』は「草子地也」と指摘。『評釈』は「作者はぬけぬけと、こんな道学者めいた物言いをする(中略)光る源氏とその物語について、読者に弁解するのだ」と指摘する。
【あやしかりけり】- 大島本は「あやしかりけり」とある。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「あやふかりけり」と校訂。『新大系』は底本のままとする。
第五段 源氏、空蝉の脱ぎ捨てた衣を持って帰る
出来事をおっしゃって、「幼稚であった」と軽蔑なさって、あの女の気持ちを爪弾きをしいしいお恨みなさる。
気の毒で、何とも申し上げられない。
【かの人の心を】- 空蝉の心。
【爪弾きをしつつ恨みたまふ】- 接続助詞「つつ」動作の反復継続を表す。--をしいしい。
【いとほしうて】- 小君は源氏を。
【ものもえ聞こえず】- 副詞「え」は打消の助動詞「ず」と呼応して不可能を表す。
どうして、逢って下さらないまでも、親しい返事ぐらいはして下さらないのだろうか。
伊予介にも及ばないわが身だ」
【憎みたまふべかめれば】- 主語は空蝉。「べかめれ」は「べかるめれ」の「る」が撥音便化してさらに無表記の形。源氏はそのように想像する。
【などか、よそにても】- 連語「などか」は打消推量の助動詞「まじき」連体形に係る。どうして、--してくださらないのだろうか。「よそにても」は、逢ってくれないまでも、の意。
【答へばかりは】- 副助詞「ばかり」程度を表す。--ぐらいは、の意。
先程の小袿を、そうは言うものの、お召物の下に引き入れて、お寝みになった。
小君をお側に寝かせて、いろいろと恨み言をいい、かつまた、優しくお話しなさる。
【御衣の下に引き入れて】- 『評釈』は「御衣」は「寝る時、上にかける衣であろう」と注す。
【つらきゆかりにこそ、え思ひ果つまじけれ】- 係助詞「こそ」打消推量の助動詞「まじけれ」已然形、係り結びの法則。副詞「え」は「まじけれ」と呼応して不可能を表す。
御硯を急に用意させて、わざわざのお手紙ではなく、畳紙に手習いのように思うままに書き流しなさる。
衣を脱ぎ捨てて逃げ去っていったあな
なほ人がらのなつかしきかな
と書 きたまへるを、懐 に引 き入 れて持 たり。
かの人 もいかに思 ふらむと、いとほしけれど、かたがた思 ほしかへして、御 ことつけもなし。
かの薄衣 は、小袿 のいとなつかしき人香 に染 めるを、身近 くならして見 ゐたまへり。
かの
かの
あの女もどう思っているだろうかと、気の毒に思うが、いろいろとお思い返しなさって、お言伝てもない。
あの薄衣は、小袿のとても懐かしい人の香が染み込んでいるので、それをいつもお側近くに置いて見ていらっしゃった。
あの薄衣は小袿だった。なつかしい気のする匂いが深くついているのを源氏は自身のそばから離そうとしなかった。
【かの人も】- 軒端荻をさす。
【御ことつけもなし】- 源氏からは軒端荻へは何のお伝言もない、の意。源氏は軒端荻には小君に伝言すると言っていた。「ことつけ」には「ことづけ」「ことつけ」の清濁二説ある。『日葡辞書』では濁音。『集成』は濁音表記。『新大系』『古典セレクション』は清音表記。
【かの薄衣は】- 「かの脱ぎすべしたると見ゆる薄衣」(第四段)とあったもの。小袿の薄衣。
【人香に染めるを】- 「を」について、『今泉忠義訳』は接続助詞、順接の確定条件と解し、「--だから」と訳し、『古典セレクション』では、格助詞、目的格と解し、「しみている、それを」と訳す。この「を」は二者択一的には決めがたい、両義性の語。
【いみじくのたまふ】- 主語は空蝉。小君との対座の場面では空蝉に敬語がつく。相対的地位の高さを表す。
まことにこのように幼く浅はかな考えを、また一方でどうお思いになっていらっしゃろうか」
【人の思ひけむこと】- 世間の人、おもに女房の間で噂に立つことをいう。
【いかに思ほすらむ】- 主語は源氏。推量の助動詞「らむ」終止形、視界外推量を表す。
どちらからも叱られて辛く思うが、あの源氏の君の手すさび書きを取り出した。
お叱りはしたものの、手に取って御覧になる。
あの脱ぎ捨てた小袿を、どのように、「伊勢をの海人」のように汗臭くはなかったろうか、と思うのも気が気でなく、いろいろと思い乱れて。
【かの御手習】- 源氏の歌「空蝉の身をかへてける木のもとになほ人がらのなつかしきかな」を小君は「懐に引き入れて持たり」。
【取りて見たまふ】- 主語は空蝉。
【伊勢をの海人の】- 『源氏釈』は「鈴鹿山伊勢をの海人の捨て衣潮なれたりと人や見るらむ」を引歌として指摘。その歌の詞書には「女のもとに衣を脱ぎ置きて取りに遣はすとて」(後撰集、恋三、七一八、伊尹朝臣)とある。『新大系』は「引歌の歌意により、いかにしてその衣を取り返すか、という気持を下に込める。(中略)衣を取り返すことは源氏との関係が完全に断ち切られることを意味する」と注す。
【いとよろづに乱れて】- この句を受ける語句がない。余韻余情を残して文がここで切れている。
他に知っている人もいない事なので、一人物思いに耽っていた。
小君が行き来するにつけても、胸ばかりが締めつけられるが、お手紙もない。
あまりのことだと気づくすべもなくて、陽気な性格ながら、何となく悲しい思いをしているようである。
【わたりたまひにけり】- 自分の部屋である西の対に。『古典セレクション』は「軒端荻の行為に敬語をつけるのは不審。彼女が源氏と逢ったことを意識して、誇らしげな様子を見せることに対する作者の揶揄かという説もある」と注す。
【また知る人もなき】- 『異本紫明抄』は「枕よりまた知る人もなき恋を涙せきあへずもらしつるかな」(古今集、恋三、六七〇、平定文)を指摘する。
【御消息もなし】- 源氏から軒端荻への手紙。後朝の文。
【あさましと思ひ得る方もなくて、されたる心に、ものあはれなるべし】- 語り手の推量。『細流抄』は「草子地也」と指摘する。
【さこそしづむれ】- 挿入句。係助詞「こそ」「しづむれ」已然形。係り結び、逆接用法。
【ありしながらのわが身ならば】- 『源氏釈』は「取り返すものにもがなや世の中をありしながらの我が身と思はむ」(源氏釈所引、出典未詳歌)を指摘する。
わたしもひそかに、
忍び忍びに濡るる袖かな
| 底本 | 大島本 |
| 校訂 | Last updated 11/23/2010(ver.2-3) 渋谷栄一校訂(C) オリジナル 修正版 比較 |
| ローマ字版 | Last updated 9/04/2012 (ver.2-2) Written in Japanese roman letters by Eiichi Shibuya (C) オリジナル 修正版 比較 |
| ルビ抽出 (ローマ字版から) |
Powered by 再編集プログラム v4.05 ひらがな版 ルビ抽出 |
| 挿絵 (ローマ字版から) |
'Eiri Genji Monogatari' (1650 1st edition) |
| Last updated 6/25/2003 渋谷栄一訳(C)(ver.1-3-1) オリジナル 修正版 比較 |
| 現代語訳 | 与謝野晶子 |
| 電子化 | 上田英代(古典総合研究所) |
| 底本 | 角川文庫 全訳源氏物語 |
| 渋谷栄一訳 との突合せ |
宮脇文経 2003年8月14日 |
| Last updated 8/31/2010(ver.2-2) 渋谷栄一注釈(C) オリジナル 修正版 比較 |