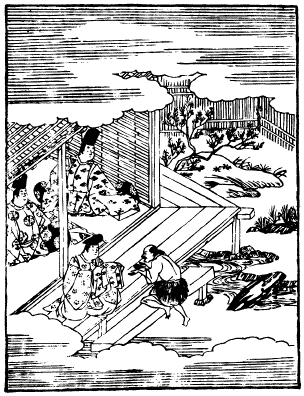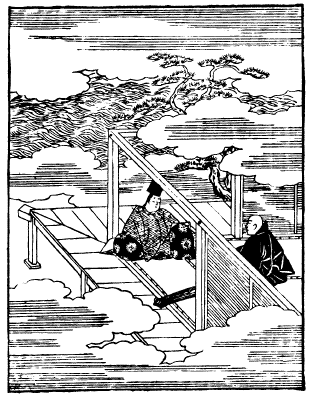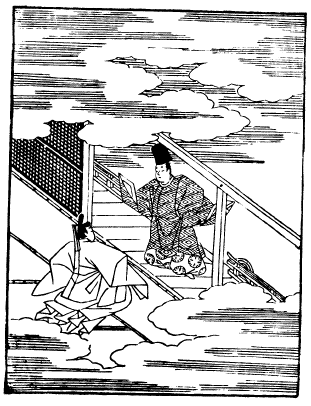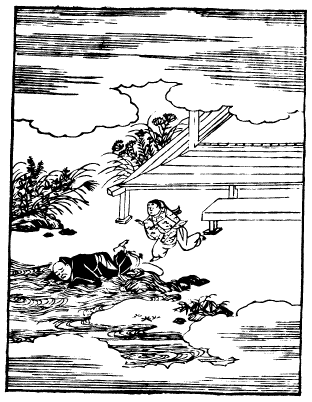第十三帖 明石
光る源氏の二十七歳春から二十八歳秋まで、明石の浦の別れと政界復帰の物語
|
# |
本文 |
渋谷栄一訳 |
与謝野晶子訳 |
注釈 |
|
第一章 光る源氏の物語 須磨の嵐と神の導きの物語
|
|
第一段 須磨の嵐続く
|
| 1.1.1 |
|
依然として雨風が止まず、雷も鳴り静まらないで、数日がたった。
ますます心細いこと、数限りなく、過去も未来も、悲しいお身の上で、気強くもお考えになることもできず、「どうしよう。
こうだからといって、都に帰るようなことも、まだ赦免がなくては、物笑いになることが増そう。
やはり、ここより深い山を求めて、姿をくらましてしまおうか」とお思いになるにつけても、「波風に脅かされてなど、人が言い伝えるようなこと、後世にまで、たいそう軽率な浮名を流してしまうことになろう」とお迷いになる。
|
まだ雨風はやまないし、雷鳴が始終することも同じで幾日かたった。今は極度に侘しい須磨の人たちであった。今日までのことも明日からのことも心細いことばかりで、源氏も冷静にはしていられなかった。どうすればいいであろう、京へ帰ることもまだ免職になったままで本官に復したわけでもなんでもないのであるから見苦しい結果を生むことになるであろうし、まだもっと深い山のほうへはいってしまうことも波風に威嚇されて恐怖した行為だと人に見られ、後世に誤られることも堪えられないことであるからと源氏は煩悶していた。
|
【なほ雨風やまず】- 「須磨」巻末の三月上巳の日の暴風雨を直接受けた語り出し。『河海抄』は『尚書』金縢篇の周公旦の故事を指摘。
【いかにせまし】- 以下「あと絶えなまし」まで、源氏の心中。長徳二年(九六六)藤原伊周が大宰帥に左遷されて播磨国に留まっていたが、許可なく密かに上京したことが露顕して、遂に大宰府に流された例がある。
【かかりとて】- 風雨雷鳴の脅威をさす。
【なほ、これより】- 完訳「「なほ」は、今までも考えてきた意」と注す。
【波風に騒がれて】- 以下「流し果てむ」まで、源氏の心中。
【軽々しき名や流し果てむ】- 大島本は「名や」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「名をや」と「を」を補訂する。「流し果つ」複合語。「や」(係助詞、疑問)「む」(推量の助動詞、推量)係結び、強調のニュアンス。
|
| 1.1.2 |
|
夢にも、まるで同じ恰好をした物ばかりが現れては現れて、お引き寄せ申すと御覧になる。
雲の晴れ間もなくて、明け暮らす日数が過ぎていくと、京の方面もますます気がかりになって、「こうしたまま身を滅ぼしてしまうのだろうか」と、心細くお思いになるが、頭をさし出すこともできない空の荒れ具合に、やって参る者もいない。
|
このごろの夢は怪しい者が来て誘おうとする初めの夜に見たのと同じ夢ばかりであった。幾日も雲の切れ目がないような空ばかりをながめて暮らしていると京のことも気がかりになって、自分という者はこうした心細い中で死んで行くのかと源氏は思われるのであるが、首だけでも外へ出すことのできない天気であったから京へ使いの出しようもない。
|
【夢にも、ただ同じさまなる物のみ】- 大島本は「夢」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「御夢」と「御」を補訂する。「須磨」巻の源氏の夢に現れた異形の物をいう。
【来つつ】- 「つつ」接続助詞、反復の意。異形の物が繰り返し現れた。
【雲間なくて】- 大島本は「雲まなくて」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「雲間もなくて」と「も」を補訂する。
【かくながら身をはふらかしつるにや】- 源氏の心中。「つる」完了の助動詞、確述。「に」断定の助動詞。「や」(疑問の終助詞)。~してしまうのであろうかのニュアンス。
【さし出づべくもあらぬ】- 「べく」推量の助動詞、可能。「も」(係助詞、強調)。
【人もなし】- 「も」(係助詞、強調)。
|
| 1.1.3 |
|
二条院から、無理をしてみすぼらしい姿で、ずぶ濡れになって参ったのだ。
道ですれ違っても、人か何物かとさえ御覧じ分けられない、早速追い払ってしまうにちがいない賤しい男を、慕わしくしみじみとお感じになるのも、自分ながらももったいなくも、卑屈になってしまった心の程を思わずにはいられない。
お手紙に、
|
二条の院のほうからその中を人が来た。濡れ鼠になった使いである。雨具で何重にも身を固めているから、途中で行き逢っても人間か何かわからぬ形をした、まず奇怪な者として追い払わなければならない下侍に親しみを感じる点だけでも、自分はみじめな者になったと源氏はみずから思われた。夫人の手紙は、
|
【二条院よりぞ】- 「ぞ」(係助詞)「そほち参れる」、係結び、強調。
【道かひにてだに--御覧じわくべくもあらず】- 「だに」副助詞、下に打消や反語の表現を伴って、述語の表す動作・状態に対して、例外的、逆接的な事物、事態であることを示す。「べく」推量の助動詞、可能。「も」係助詞、強調。道ですれちがってでさえも--まったくお見分けになれないの意。主語は源氏。
【追ひ払ひつべき】- 「つ」完了の助動詞、確述。「べき」推量の助動詞、当然。当然追い返してしまうにちがいないのニュアンス。
【むつましうあはれに思さるるも】- 源氏の心中を叙述。「るる」自発の助動詞。「も」係助詞、一例を挙げて他を暗示する。自然そのような気持ちになるにつけても。
【我ながらかたじけなく、屈しにける心のほど思ひ知らる】- 源氏の心中を叙述。『完訳』は「高貴な自分がこんな下々の者にまで親しみを感ずるとは、という気持」「源氏の気持をそのまま地の文として書いているので、「思ひ知らる」と敬語がない」と注す。
|
| 1.1.4 |
|
「驚くほどの止むことのない日頃の天気に、ますます空までが塞がってしまう心地がして、心の晴らしようがなく、
|
申しようのない長雨は空までもなくしてしまうのではないかという気がしまして須磨の方角をながめることもできません。
|
【あさましくを止みなきころの】- 以下「波間なきころ」まで、紫君の文。
【空さへ】- 『完訳』は「胸の中はもちろん、空までも」と注す。
【方なくなむ】- 「なむ」係助詞、結びの省略。言いさした形、余情表現。
|
| 1.1.5 |
|
須磨の浦ではどんなに激しく風が吹いていることでしょう
心配で袖を涙で濡らしている今日このごろです」
|
浦風やいかに吹くらん思ひやる
袖うち濡らし波間なき頃
|
【浦風やいかに吹くらむ思ひやる--袖うち濡らし波間なきころ】- 紫君の独詠歌。「浦風」「波間」は縁語。「らむ」推量の助動詞、視界外推量。紫君が都から須磨の浦の源氏を思いやるニュアンス。
|
| 1.1.6 |
|
しみじみとした悲しい気持ちがいっぱい書き連ねてある。
ますます涙があふれてしまいそうで、まっ暗になる気がなさる。
|
というような身にしむことが数々書かれてある。開封した時からもう源氏の涙は潮時が来たような勢いで、内から湧き上がってくる気がしたものであった。
|
【いとど汀まさりぬべく】- 大島本は「ひきあくるより(ひきあくるより$<朱墨>)いとゝみきはまさりぬへく」とあり「ひきあくるより」を墨筆と朱筆でミセケチにする。『新大系』は底本に従って「ひきあくる」を削除する。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「ひきあくる」を生かした本文とする。「君惜しむ涙落ち添ひこの川の汀まさりて流るべらなり」(古今六帖・別れ)による。「ぬ」完了の助動詞、確述。「べく」推量の助動詞、推量。涙があふれてしまいそうにの意。
|
| 1.1.7 |
|
「京でも、この雨風は、不思議な天の啓示であると言って、仁王会などを催す予定だと噂していました。
宮中に参内なさる上達部なども、まったく道路が塞がって、政道も途絶えております」
|
「京でもこの雨風は天変だと申して、なんらかを暗示するものだと解釈しておられるようでございます。仁王会を宮中であそばすようなことも承っております。大官方が参内もできないのでございますから、政治も雨風のために中止の形でございます」
|
【京にも、この雨風】- 以下「絶えてなむはべる」まで、使者の詞。
【あやしき物のさとしなり】- 大島本は「いと(いと$<朱墨>)あやしき物のさとしなり」とあり「いと」を墨筆と朱筆でミセケチにする。『新大系』は底本に従って「いと」を削除する。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「いと」を生かした本文とする。「なり」は断定の助動詞。
【仁王会など行はるべし】- 国家鎮護・七難即滅のために「仁王護国般若経」を宮中で講じる。これは春秋の臨時の仁王会以外の特に行われるもの。「る」(受身の助動詞)「べし」(推量の助動詞)、行われる予定であるの意。
【なむ聞こえはべりし】- 「なむ」係助詞。「し」過去の助動詞。係結び、強調。
【絶えてなむはべる】- 「なむ」係助詞。「侍る」丁寧語。係結び。強調のニュアンス。
|
| 1.1.8 |
|
などと、はきはきともせず、たどたどしく話すが、京のこととお思いになると知りたくて、御前に召し出して、お尋ねあそばす。
|
こんな話を、はかばかしくもなく下士級の頭で理解しているだけのことを言うのであるが、京のことに無関心でありえない源氏は、居間の近くへその男を呼び出していろいろな質問をしてみた。
|
【御前に召し出でて、問はせたまふ】- 「せ」尊敬の助動詞。「たまふ」尊敬の補助動詞。二重敬語。身分の差異を表現したもの。
|
| 1.1.9 |
|
「ただ、例によって雨が小止みなく降って、風は時々吹き出して、数日来になりますのを、ただ事でないと驚いているのです。
まことにこのように、地の底に通るほどの雹が降り、雷の静まらないことはございませんでした」
|
「ただ例のような雨が少しの絶え間もなく降っておりまして、その中に風も時々吹き出すというような日が幾日も続くのでございますから、それで皆様の御心配が始まったものだと存じます。今度のように地の底までも通るような荒い雹が降ったり、雷鳴の静まらないことはこれまでにないことでございます」
|
【風は時々吹き出でて】- 大島本は「風ハ時/\吹いて(て+て)つゝ(つゝ$)」と「て」を補訂し「つゝ」をミセケチにする。『新大系』は底本の訂正に従って「吹き出でて」とする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「吹き出でつつ」とする。
【驚きはべるなり】- 「なり」断定の助動詞。
【はべらざりき】- 「き」過去の助動詞。自ら体験したことがないというニュアンス。
|
| 1.1.10 |
|
などと、大変な様子で驚き脅えて畏まっている顔がとてもつらそうなのにつけても、心細さがつのるのだった。
|
などと言う男の表情にも深刻な恐怖の色の見えるのも源氏をより心細くさせた。
|
【心細さまさりける】- 主語は供人たち。大島本は「心ほそさまさりける」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「心細さぞ」と係助詞「ぞ」を補訂する。
|
|
第二段 光る源氏の祈り
|
| 1.2.1 |
|
「こうしながらこの世は滅びてしまうのであろうか」と思わずにはいらっしゃれないでいると、その翌日の明け方から、風が激しく吹き、潮が高く満ちきて、波の音の荒々しいこと、巌も山をも無くしてしまいそうである。
雷の鳴りひらめく様子、さらに言いようがなくて、「そら、落ちてきた」と思われると、その場に居合わせた者でしっかりした人はいない。
|
こんなことでこの世は滅んでいくのでないかと源氏は思っていたが、その翌日からまた大風が吹いて、海潮が満ち、高く立つ波の音は岩も山も崩してしまうように響いた。雷鳴と電光のさすことの烈しくなったことは想像もできないほどである。この家へ雷が落ちそうにも近く鳴った。もう理智で物を見る人もなくなっていた。
|
【かくしつつ世は尽きぬべきにや】- 源氏の思念。「ぬ」完了の助動詞、確述。「べき」推量の助動詞、推量。「に」断定の助動詞。「や」終助詞、疑問。きっと滅びてしまうのであろうかの意。
【思さるるに】- 「るる」自発の助動詞。「に」接続助詞、順接。
【落ちかかりぬ】- 「ぬ」完了の助動詞、完了。『完訳』は「落ちかかってきた」と訳す。
【ある限り】- その場にい合わせる者みな、の意。
|
| 1.2.2 |
|
「自分はどのような罪を犯して、このような悲しい憂き目に遭うのだろう。
父母にも互いに顔を見ず、いとしい妻や子どもにも会えずに、死なねばならぬとは」
|
「私はどんな罪を前生で犯してこうした悲しい目に逢うのだろう。親たちにも逢えずかわいい妻子の顔も見ずに死なねばならぬとは」
|
【我はいかなる罪を】- 以下「死ぬべきこと」まで、供人の詞。
【見るらむ】- 「らむ」推量の助動詞、原因推量。どうして酷い目に遭うのであろうかの意。
【父母にも--妻子の顔をも】- 「も」副助詞、最初は強調と次は類例の意。
【死ぬべきこと】- 「べき」推量の助動詞、当然。死なねばならないこと、の意。
|
| 1.2.3 |
|
と嘆く。
君は、お心を静めて、「どれほどの過失によって、この海辺に命を落とすというのか」と、気を強くお持ちになるが、ひどく脅え騒いでいるので、色とりどりの幣帛を奉らせなさって、
|
こんなふうに言って歎く者がある。源氏は心を静めて、自分にはこの寂しい海辺で命を落とさねばならぬ罪業はないわけであると自信するのであるが、ともかくも異常である天候のためにはいろいろの幣帛を神にささげて祈るほかがなかった。
|
【何ばかりのあやまちにてか】- 以下「命をば極めむ」まで、源氏の心中。悲運の不当を訴える。「か」(係助詞、疑問)--「極め」「む」推量の助動詞。反語表現。命を落とそうか、そのようなことはけっしてない、の意。『完訳』は「源氏の無実の主張」と注す。
【幣帛ささげさせたまひて】- 「させ」使役の助動詞。「たまひ」尊敬の補助動詞。供人をして幣帛を奉らせなさる。
|
| 1.2.4 |
「住吉の神、近き境を鎮め守りたまふ。まことに迹を垂れたまふ神ならば、助けたまへ」 |
「住吉の神、この近辺一帯をご鎮護なさる。
真に現世に迹を現しなさる神ならば、我らを助けたまえ」
|
「住吉の神、この付近の悪天候をお鎮めください。真実垂跡の神でおいでになるのでしたら慈悲そのものであなたはいらっしゃるはずですから」
|
【住吉の神】- 以下「助けたまへ」まで、源氏の祈りの詞。神は一定の地域を支配するという神道思想と神は仏の垂迹であるという本地垂迹思想とが見られる。『完訳』は「神が畏怖の対象であっても、仏の垂迹であるなら助けてくれるはず、の意」と注す。
|
| 1.2.5 |
|
と、数多くの大願を立てなさる。
各自めいめいの命は、それはそれとして、このような方がまたとない例にお命を落としてしまいそうなことがひどく悲しい、心を奮い起こして、わずかに気を確かに持っている者は皆、「わが身に代えて、この御身ひとつをお救い申し上げよう」と、大声を上げて、声を合わせて仏、神をお祈り申し上げる。
|
と源氏は言って多くの大願を立てた。惟光や良清らは、自身たちの命はともかくも源氏のような人が未曾有な不幸に終わってしまうことが大きな悲しみであることから、気を引き立てて、少し人心地のする者は皆命に代えて源氏を救おうと一所懸命になった。彼らは声を合わせて仏神に祈るのであった。
|
【沈みたまひぬべきことの】- 「ぬ」完了の助動詞、確述。「べき」推量の助動詞。「の」格助詞、主格。命を落としてしまいそうな事が、の意。
【いみじう悲しき】- 大島本は「かなしき」とある。青表紙諸本「かなしきに」。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「に」を補訂する。「に」接続助詞、原因・理由。悲しいので、の意。
【身に代へてこの御身一つを救ひたてまつらむ】- 供人の心中。「たてまつら」謙譲の補助動詞、源氏に対する敬意。「む」推量の助動詞、意志。お救い申そうの意。
【とよみて】- 下の「念じたてまつる」に掛かる。
|
| 1.2.6 |
|
「帝王の、深宮に育てられなさって、さまざまな楽しみをほしいままになさったが、深い御仁徳は、大八洲にあまねく、沈淪していた人々を数多く浮かび上がらせなさった。
今、何の報いによってか、こんなに非道な波風に溺れ死ななければならないのか。
天地の神々よ、ご判断ください。
罪なくして罪に当たり、官職、爵位を剥奪され、家を離れ、都を去って、日夜お心の安まる時なく、お嘆きになっていらっしゃる上に、このような悲しい憂き目にまで遭い、命を失ってしまいそうになるのは、前世からの報いか、この世での犯しによるのかと、神、仏、確かにいらっしゃるならば、この災いをお鎮めください」
|
「帝王の深宮に育ちたまい、もろもろの歓楽に驕りたまいしが、絶大の愛を心に持ちたまい、慈悲をあまねく日本国じゅうに垂れたまい、不幸なる者を救いたまえること数を知らず、今何の報いにて風波の牲となりたまわん。この理を明らかにさせたまえ。罪なくして罪に当たり、官位を剥奪され、家を離れ、故郷を捨て、朝暮歎きに沈淪したもう。今またかかる悲しみを見て命の尽きなんとするは何事によるか、前生の報いか、この世の犯しか、神、仏、明らかにましまさばこの憂いを息めたまえ」
|
【帝王の深き宮に】- 以下「この愁へやすめたまへ」まで、供人の祈りと訴えの詞。ただし、後半「かく悲しき」あたりから源氏の詞に変わっている。
【養はれたまひて】- 「れ」受身の助動詞。「たまひ」尊敬の補助動詞。育てられなさっての意。源氏の仁徳と身の潔白を訴える。
【深き御慈しみ】- 源氏の御仁徳。
【何の報いにか--溺ほれたまはむ】- 「か」(係助詞、疑問)--「む」(推量の助動詞)、係結び、反語表現。なんで波風に溺れ死ななければならないのか、そんなことがあってよいはずがないというニュアンス。
【罪なくて罪に当たり】- 『完訳』は「以下、源氏への敬語が不統一。「罪なくて--嘆きたまふに」を地の文とする説、また「かく悲しき--やすめたまへ」を源氏の言葉とする説などもある」と指摘。初め、供人たちが唱え、途中から源氏も一緒に唱え出した。
【嘆きたまふに】- 「に」接続助詞、添加の意。
【悲しき目をさへ】- 「さへ」副助詞、添加の意。
【命尽きなむと】- 「な」完了の助動詞、確述。「む」推量の助動詞。命が尽きてしまいそうになるというニュアンス。
【この世の犯しか】- 大島本は「此世のをかしか」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「この世の犯しかと」と「と」を補訂する。
|
| 1.2.7 |
|
と、お社の方を向いて、さまざまな願を立てなさる。
|
住吉の御社のほうへ向いてこう叫ぶ人々はさまざまの願を立てた。
|
【と、御社の方に向きて】- 『集成』は「次に「立てたまふ」と敬語があるから主語は源氏。前の祈願の言葉、後半は敬語がなく源氏自身の言葉のように読める。源氏もともに和した趣であろうか」と注す。
|
|
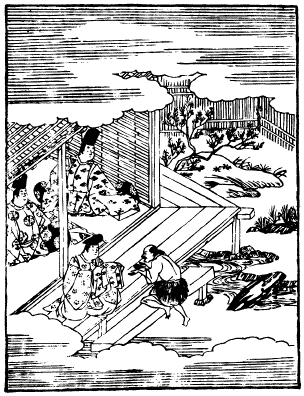 |
| 1.2.8 |
|
また、海の中の龍王、八百万の神々に願をお立てさせになると、ますます雷が鳴り轟いて、いらっしゃるご座所に続いている廊に落ちてきた。
炎が燃え上がって、廊は焼けてしまった。
生きた心地もせず、皆が皆あわてふためく。
後方にある大炊殿とおぼしい建物にお移し申して、上下なく人々が入り込んで、ひどく騒がしく泣き叫ぶ声、雷鳴にも負けない。
空は黒墨を擦ったようで、日も暮れてしまった。
|
また竜王をはじめ大海の諸神にも源氏は願を立てた。いよいよ雷鳴ははげしくとどろいて源氏の居間に続いた廊へ落雷した。火が燃え上がって廊は焼けていく。人々は心も肝も皆失ったようになっていた。後ろのほうの廚その他に使っている建物のほうへ源氏を移転させ、上下の者が皆いっしょにいて泣く声は一つの大きな音響を作って雷鳴にも劣らないのである。空は墨を磨ったように黒くなって日も暮れた。
|
【海の中の龍王】- 『集成』は「仏経における異類。嵐をその所為かとも見ている」と注す。
【立てさせたまふに】- 「させ」使役の助動詞。「たまふ」尊敬の補助動詞。「に」接続助詞、順接。願をお立てさせなさると。
【いよいよ鳴りとどろきて】- 『完訳』は「神々の感応とみられる」と注す。
【おはしますに】- 「に」格助詞、体言「所」「寝殿」などの語句が省略されている。
【落ちかかりぬ】- 「ぬ」完了の助動詞、確述。雷が落ちてきた。『完訳』は「無実の罪のまま死んで雷となり寝殿を焼いたという、菅原道真の伝説も投影しているか」と注す。
【後の方なる】- 「なる」断定の助動詞、存在。後方にある。
【大炊殿とおぼしき屋に】- 「おぼしき」(形容詞)は、語り手の想像を交えた臨場感ある表現。大炊殿らしい家屋に。
【移したてまつりて】- 「たてまつり」(謙譲の補助動詞)、源氏の君をお移し申し上げて。
【日も暮れにけり】- 「に」(完了の助動詞)「けり」(過去の助動詞)。日も暮れてしまったのであるというニュアンス。
|
|
第三段 嵐収まる
|
| 1.3.1 |
|
だんだん風が弱まり、雨脚が衰え、星の光も見えるので、このご座所もひどく見慣れないのも、まことに恐れ多いので、寝殿にお戻りいただこうとするが、
|
そのうち風が穏やかになり、雨が小降りになって星の光も見えてきた。そうなるとこの人々は源氏の居場所があまりにもったいなく思われて、寝殿のほうへ席を移そうとしたが、
|
【見ゆるに】- 「に」接続助詞、順接、原因・理由。見えるので。
【この御座所】- 大炊殿をさす。
【かたじけなくて】- 「て」接続助詞、順接。恐れ多いので。
【返し移したてまつらむとするに】- 「たてまつら」謙譲の補助動詞。「む」推量の助動詞、意志。「に」接続助詞、逆接。源氏の君を寝殿にお戻らせ申し上げようとするが。
|
| 1.3.2 |
|
「焼け残った所も気味が悪く、おおぜいの人々が踏み荒らした上に、御簾などもみな吹き飛んでしまった」
|
そこも焼け残った建物がすさまじく見え、座敷は多数の人間が逃げまわった時に踏みしだかれてあるし、御簾なども皆風に吹き落とされていた。
|
【焼け残りたる方も】- 以下「夜を明かしてこそは」まで、供人たちの詞。『完訳』は「吹ちらしてけり」までと「夜を」以下の二つの詞文に分ける。
【そこらの人の踏みとどろかし惑へるに】- 『集成』は「「とどろかし」は、雷の縁でこう言った」と注す。散文における縁語表現。「る」完了の助動詞。「に」接続助詞、添加。踏み鳴らして右往左往した上に。
【吹き散らしてけり】- 「て」完了の助動詞、完了。「けり」過去の助動詞。吹き飛んでしまったというニュアンス。
|
| 1.3.3 |
|
「夜を明かしてからは」
|
今夜夜通しに
|
【夜を明してこそは】- 供人の詞。下に「移したてまつらめ」などの語句が省略。
|
| 1.3.4 |
|
とあれこれしている間に、君は御念誦を唱えながら、いろいろお考えめぐらしになるが、気持ちが落ち着かない。
|
後始末をしてからのことに決めて、皆がそんなことに奔走している時、源氏は心経を唱えながら、静かに考えてみるとあわただしい一日であった。
|
【たどりあへるに】- 「る」完了の助動詞、存続。「に」接続助詞、順接、時間。供人が戸惑っている間。
【御念誦したまひて】- 「て」接続助詞、動作の並行。御念誦を唱えながら。
【思しめぐらすに】- 主語は源氏。「に」接続助詞、逆接。あれこれ御思案なさるが。すっきり解明できない、というニュアンスを含む。
|
| 1.3.5 |
|
月が出て、潮が近くまで満ちてきた跡がはっきりと分かり、その後も依然として寄せては返す波の荒いのを、柴の戸を押し開けて、物思いに耽りながら眺めていらっしゃる。
この界隈には、ものの道理をわきまえ、過去将来のことを判断して、あれこれとはっきりと理解する者もいない。
賤しい海人どもなどが、高貴な方のいらっしゃるところといって、集まって参って、お聞きになっても分からないようなことがらをぺちゃくちゃしゃべり合っているのも、ひどく珍しいことであるが、追い払うこともできない。
|
月が出てきて海潮の寄せた跡が顕わにながめられる。遠く退いてもまだ寄せ返しする浪の荒い海べのほうを戸をあけて源氏はながめていた。今日までのこと明日からのことを意識していて、対策を講じ合うに足るような人は近い世界に絶無であると源氏は感じた。漁村の住民たちが貴人の居所を気にかけて、集まって来て訳のわからぬ言葉でしゃべり合っているのも礼儀のないことであるが、それを追い払う者すらない。
|
【とやかくやとはかばかしう悟る人もなし】- 『集成』は「あれこれとたしかにこの天変の意味を解き明かせる人もいない。当時の政治家が求める賢人である」と注す。『完訳』は「陰陽師や、宿曜道の人」と注す。
【聞きも知りたまはぬ】- 「も」係助詞、強調。「給は」尊敬の補助動詞。聞いてもお分かりにならない。
【さへづりあへるも】- 「る」完了の助動詞、存続。ぺちゃくちゃしゃべっているのも。
【え追ひも払はず】- 主語は供人。「も」係助詞、強調。追い払うこともできない。
|
| 1.3.6 |
|
「この風が、今しばらく止まなかったら、潮が上がって来て、残るところなく攫われてしまったことでしょう。
神のご加護は大変なものであった」
|
「あの大風がもうしばらくやまなかったら、潮はもっと遠くへまで上って、この辺なども形を残していまい。やはり神様のお助けじゃ」
|
【この風、今しばし止まざらましかば】- 以下「おろかならざりけり」まで、供人の詞。『集成』は「『細流抄』に「あまどものいふなり」とするが、地元の漁師たちの話を聞いて語る供人の言葉であろう」と注す。『完訳』は海人の詞とする。「ましかば--まし」反実仮想。風が止まなかったら--残る所がなかったでろうに、止んだので残ったの意。
|
| 1.3.7 |
|
と言うのをお聞きになるのも、とても心細いといったのでは言い足りないくらいである。
|
こんなことの言われているのも聞く身にとっては非常に心細いことであった。
|
【聞きたまふも】- 「も」係助詞、一例を挙げて他を暗示。
【いと心細しといへばおろかなり】- 言葉では言い表せない、という語り手の寸評。
|
| 1.3.8 |
|
「海に鎮座まします神の御加護がなかったならば
潮の渦巻く遥か沖合に流されていたことであろう」
|
海にます神のたすけにかからずば
潮の八百会にさすらへなまし
|
【海にます神の助けにかからずは--潮の八百会にさすらへなまし】- 源氏の独詠歌。「ます」「潮の八百会」は祝詞の用語。「は」係助詞、仮定条件。「な」完了の助動詞、確述。「まし」推量の助動詞、反実仮想。もし助けがなかったら行方知れずになっていただろうに、助けがあったのでそうならずにすんだ、の意。住吉の神に感謝を述べる。
|
| 1.3.9 |
|
一日中、激しく物を煎り揉みしていた雷の騷ぎのために、そうはいっても、ひどくお疲れになったので、思わずうとうととなさる。
恐れ多いほど粗末なご座所なので、ちょっと寄り掛かっていらっしゃると、故院が、まるで御生前おいであそばしたお姿のままお立ちになって、
|
と源氏は口にした。終日風の揉み抜いた家にいたのであるから、源氏も疲労して思わず眠った。ひどい場所であったから、横になったのではなく、ただ物によりかかって見る夢に、お亡くなりになった院がはいっておいでになったかと思うと、すぐそこへお立ちになって、
|
【騷ぎに】- 「に」格助詞、原因・理由。騷ぎのために。
【さこそいへ】- 源氏の落ち着いて念誦を唱えたり、戸の外を眺めていた態度をさす。
【困じたまひにければ】- 「に」完了の助動詞、完了。「けれ」過去の助動詞。「ば」接続助詞、確定条件。疲れてしまったので。
【寄りゐたまへるに】- 「る」完了の助動詞、存続。「に」接続助詞、順接。物に寄り掛かって座っていらっしゃると、の意。
【故院、ただおはしまししさまながら】- 以下、源氏の夢の中の出来事。「おはします」は「おはす」よりさらに重い最高敬語。「し」過去の助動詞。「ながら」接尾語。故院がまるで生前おいであそばした姿そのままで。
|
| 1.3.10 |
|
「どうして、このような見苦しい所にいるのだ」
|
「どうしてこんなひどい所にいるか」
|
【など、かくあやしき所にものするぞ】- 大島本は「所に」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「所には」と「は」を補訂する。院の詞。「ぞ」係助詞、文全体を強調。どうしてこのような賤しい所にいるのだ、というユアンス。
|
| 1.3.11 |
とて、御手を取りて引き立てたまふ。
|
と仰せになって、
|
こうお言いになりながら、源氏の手を取って引き立てようとあそばされる。
|
|
| 1.3.12 |
|
「住吉の神がお導きになるのに従って、早く船出して、この浦を去りなさい」
|
「住吉の神が導いてくださるのについて、早くこの浦を去ってしまうがよい」
|
【住吉の神の導きたまふままには】- 大島本は「まゝにハ」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「ままに」と「は」を削除する。以下「この浦を去りね」まで、院の詞。「ね」完了の助動詞、完了。去ってしまいなさい。
|
| 1.3.13 |
|
と仰せあそばす。
とても嬉しくなって、
|
と仰せられる。源氏はうれしくて、
|
【のたまはす】- 「のたまふ」よりさらに重い最高敬語。
|
| 1.3.14 |
|
「畏れ多い父上のお姿にお別れ申して以来、さまざまな悲しいことばかり多くございますので、今はこの海辺に命を捨ててしまいましょうかしら」
|
「陛下とお別れいたしましてからは、いろいろと悲しいことばかりがございますから私はもうこの海岸で死のうかと思います」
|
【かしこき御影に】- 以下「身をや捨てはべりなまし」まで、源氏の詞。
【別れたてまつりにしこなた】- 「たてまつり」謙譲の補助動詞。「に」完了の助動詞。「し」過去の助動詞。お別れ申し上げて以来。
【悲しきことのみ】- 「のみ」副助詞、限定と強調。悲しい事だけそればかりが、の意。
【身をや捨てはべりなまし】- 「や」係助詞、疑問。「はべり」丁寧の補助動詞。「な」完了の助動詞。「まし」推量の助動詞、仮想。身を捨ててしまおうかしら、どうしたらよいものだろうか、という非現実的な仮想とためらいのニュアンス。『集成』は「命を終わろうかと存じます」。『完訳』は「身を捨ててしまいとうございます」。
|
| 1.3.15 |
|
と申し上げなさると、
|
|
【聞こえたまへば】- 「聞こえ」は「言う」の謙譲語。「たまへ」尊敬の補助動詞。源氏が院に申し上げなさると。
|
| 1.3.16 |
|
「実にとんでもないことだ。
これは、ちょっとしたことの報いである。
朕は、在位中に、過失はなかったけれど、知らず知らずのうちに犯した罪があったので、その罪を償うのに暇がなくて、この世を顧みなかったが、大変な難儀に苦しんでいるのを見ると、堪え難くて、海に入り渚に上がり、たいそう疲れたけれど、このような機会に、奏上しなければならないことがあるので、急いで上るのだ」
|
「とんでもない。これはね、ただおまえが受けるちょっとしたことの報いにすぎないのだ。私は位にいる間に過失もなかったつもりであったが、犯した罪があって、その罪の贖いをする間は忙しくてこの世を顧みる暇がなかったのだが、おまえが非常に不幸で、悲しんでいるのを見ると堪えられなくて、海の中を来たり、海べを通ったりまったく困ったがやっとここまで来ることができた。このついでに陛下へ申し上げることがあるから、すぐに京へ行く」
|
【いとあるまじきこと】- 以下「急ぎ上りぬる」まで、院の詞。
【これは】- 天変地異をさす。
【我は、位に在りし時、あやまつことなかりしかど、おのづから犯しありければ】- 『北野天神縁起』に醍醐天皇は生前犯した五つの罪によって地獄に落ちたという説話がある。「し」「しか」過去の助動詞、自己の体験を語るニュアンス。「けれ」過去の助動詞、過去から現在まで継続している事実の回想、また地獄に落ちて初めて伝聞した過去の事実を回想した婉曲的表現というニュアンス。
【顧みざりつれど】- 「つれ」完了の助動詞、完了。顧みなかったが。
【いみじき愁へに沈むを】- 源氏の難儀をいう。敬語は付けない。
【海に入り、渚に上り】- 桐壺院の霊魂がやって来た道程、海上の彼方からという思想。
【困じにたれど】- 「に」完了の助動詞、完了。「たれ」完了の助動詞、存続。「ど」接続助詞、逆接の確定条件。疲れてしまっているけれど。
【かかるついでに】- 天変地異の折をさす。
【奏すべきことの】- 大島本は「ことの」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「こと」と「の」を削除する。「べき」推量の助動詞、当然。帝に奏上しなければならない事が。
【あるにより】- 「に」断定の助動詞、「より」格助詞、原因・理由。あるために。
【なむ、急ぎ上りぬる】- 「なむ」係助詞、「ぬる」完了の助動詞、完了。係結び、強調のニュアンスを添える。『完訳』は「急いで京へ上るところだ」と訳す。
|
| 1.3.17 |
とて、立ち去りたまひぬ。
|
と言って、お立ち去りになってしまった。
|
と仰せになってそのまま行っておしまいになろうとした。
|
|
| 1.3.18 |
|
名残惜しく悲しくて、「お供して参りたい」とお泣き入りになって、お見上げなさると、人影もなく、月の面だけが耿々として、夢とも思えず、お姿が残っていらっしゃるような気がして、空の雲がしみじみとたなびいているのであった。
|
源氏は悲しくて、「私もお供してまいります」と泣き入って、父帝のお顔を見上げようとした時に、人は見えないで、月の顔だけがきらきらとして前にあった。源氏は夢とは思われないで、まだ名残がそこらに漂っているように思われた。空の雲が身にしむように動いてもいるのである。
|
【飽かず悲しくて】- 『完訳』は「以下、夢から現実に戻る」と注す。
【参りなむ】- 「な」完了の助動詞、完了。「む」推量の助動詞、意志。連語で意志を強調確述する。参ってしまいたい。「参ら」「なむ」(終助詞、他者に対する希望)とはいわない。「参ら」「ばや」(終助詞、自身の希望)より、「参りなむ」の方が、強いニュアンスを表す。「ばや」は実現可能のことを願望するが、連語「な」「む」は不可能なことまで含む。
【見上げたまへれば】- 「れ」完了の助動詞、完了。「ば」接続助詞、順接。「たまたま--したところ」というニュアンス。お見上げなさったところ。『集成』は「ここからが、夢からさめた趣」と注す。
【人もなく、月の顔のみ】- 「も」係助詞、強調。「月の顔」は擬人法。「人」の縁で「月の顔」と表現。「のみ」副助詞、限定と強調のニュアンスを添える。いったい人はいず、月の顔だけ、それだけが。
【たなびけり】- 「けり」過去の助動詞、過去から現在まで継続している事実の回想。たなびいていたのである。
|
| 1.3.19 |
|
ここ数年来、夢の中でもお会い申さず、恋しくお会いしたいお姿を、わずかな時間ではあるが、はっきりと拝見したお顔だけが、眼前にお浮かびになって、「自分がこのように悲しみを窮め尽くし、命を失いそうになったのを、助けるために天翔っていらした」と、しみじみと有り難くお思いになると、「よくぞこんな騷ぎもあったものよ」と、夢の後も頼もしくうれしく思われなさること、限りない。
|
長い間夢の中で見ることもできなかった恋しい父帝をしばらくだけではあったが明瞭に見ることのできた、そのお顔が面影に見えて、自分がこんなふうに不幸の底に落ちて、生命も危うくなったのを、助けるために遠い世界からおいでになったのであろうと思うと、よくあの騒ぎがあったことであると、こんなことを源氏は思うようになった。なんとなく力がついてきた。
|
【夢のうちにも見たてまつらで】- 「も」副助詞、強調。「たてまつら」謙譲の補助動詞、源氏の桐壺院に対する敬意。「で」接続助詞、打消。現実では不可能だが、夢の中でさえお目にかかれないというニュアンス。
【ほのかなれど、さだかに見たてまつりつるのみ】- 「つる」完了の助動詞、完了、確述のニュアンスも添う。下に「顔」「姿」等の語句が省略。「のみ」副助詞、限定と強調。確かに拝見したことだけ、そればかりがというニュアンス。『完訳』は「「ほのか」は、夢に見る時間の短さ。「さだか」は、夢の中の故院の映像の鮮明さ」と注す。
【面影におぼえたまひて】- 『集成』は「ありありと心にお残りになって」。『完訳』は「いつまでも目先に幻となって感じられ」と訳す。
【我かく悲しびを極め】- 以下「翔りたまへる」まで、源氏の心中。
【命尽きなむとしつるを】- 「な」完了の助動詞、完了。「む」推量の助動詞。「つる」完了の助動詞。「を」格助詞、目的格。もうすんでのところで命が尽きようとしたところを。
【翔りたまへる」と】- 「たまへ」尊敬の補助動詞、故院に対する敬意。「る」完了の助動詞、完了、連体形中止。下に「事」「なり」等の語句が省略。言外に余情余韻を表す。
【よくぞかかる騷ぎもありける】- 源氏の心中。「かかる騷ぎ」は天変地異をさす。「ぞ」係助詞。「も」係助詞、強調。「ける」過去の助動詞、詠嘆。係結び、強調。
【名残頼もしう、うれしうおぼえたまふこと、限りなし】- 「おぼえ」動詞、自然そう思われるというニュアンス。源氏は夢の中の院の詞に期待感と希望を抱く。『完訳』は「このあたり、源氏救助の故院の霊力が、天変地異の「物のさとし」であったとも了解されよう」と注す。
|
| 1.3.20 |
|
胸がぴたっと塞がって、かえってお心の迷いに、現実の悲しいこともつい忘れ、「夢の中でお返事をもう少し申し上げずに終わってしまったこと」と残念で、「再びお見えになろうか」と、無理にお寝みになるが、さっぱりお目も合わず、明け方になってしまった。
|
その時は胸がはっとした思いでいっぱいになって、現実の悲しいことも皆忘れていたが、夢の中でももう少しお話をすればよかったと飽き足らぬ気のする源氏は、もう一度続きの夢が見られるかとわざわざ寝入ろうとしたが、眠りえないままで夜明けになった。
|
【なかなかなる御心惑ひに】- 現実では忘れていたが、夢で院に会ったばかりにかえって悲しみに心乱れるというニュアンス。
【夢にも御応へを今すこし聞こえずなりぬること】- 源氏の心中。「も」係助詞、願望・仮定を控え目に例示。仮に夢であるにせよどうしてというニュアンス。「聞こえ」謙譲の動詞、院に対する敬意。「ぬる」完了の助動詞。体言止め、余情余韻を残す。
【いぶせさに】- 『集成』は「みたされぬ思いで」と注す。
【さらに御目も合はで】- 「さらに」副詞、「で」接続助詞、打消し、全然お目も合わないでというニュアンス。
|
|
第四段 明石入道の迎えの舟
|
| 1.4.1 |
|
渚に小さい舟を寄せて、人が二、三人ほど、この旅のお館をめざして来る。
何者だろうと尋ねると、
|
渚のほうに小さな船を寄せて、二、三人が源氏の家のほうへ歩いて来た。だれかと山荘の者が問うてみると、
|
【渚に小さやかなる舟寄せて】- 明石入道の使者、源氏を迎えに来る。
【人二、三人ばかり】- 「ばかり」副助詞、程度。人が二、三人ほど。
【御宿りをさして参る】- 大島本は「まいる」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「来」と校訂する。
【何人ならむと問へば】- 「問ふ」の主語は供人。
|
| 1.4.2 |
|
「明石の浦から、前の播磨守の新発意が、お舟支度して参上したのです。
源少納言、伺候していらしたら、面会して事の子細を申し上げたい」
|
明石の浦から前播磨守入道が船で訪ねて来ていて、その使いとして来た者であった。
「源少納言さんがいられましたら、お目にかかって、お訪ねいたしました理由を申し上げます」
|
【明石の浦より】- 以下「とり申さむ」まで、使者の詞。
【前の守新発意の、御舟装ひて】- 「の」格助詞、主格。「御」は源氏を乗せるべき舟という意で用いた敬語。
【参れるなり】- 「参れ」は「来る」の謙譲語。源氏に対する敬意。「る」完了の助動詞。「なり」断定の助動詞。参上したのである。
【源少納言、さぶらひたまはば、対面して】- 良清をさしていう。「さぶらふ」は「あり」の謙譲語、また丁寧語。「たまは」尊敬の補助動詞、良清に対する敬意。
【とり申さむ】- 「申さ」は「言ふ」の謙譲語。「む」推量の助動詞、意志。説明申し上げたい。
|
| 1.4.3 |
と言ふ。
良清、おどろきて、
|
と言う。
良清、驚いて、
|
と使いは入道の言葉を述べた。驚いていた良清は、
|
|
| 1.4.4 |
|
「入道は、あの国での知人として、長年互いに親しくお付き合いしてきましたが、私事で、いささか恨めしく思うことがございまして、特別の手紙でさえも交わさないで、久しくなっておりましたが、この荒波に紛れて、何の用であろうか」
|
「入道は播磨での知人で、ずっと以前から知っておりますが、私との間には双方で感情の害されていることがあって、格別に交際をしなくなっております。それが風波の害のあった際に何を言って来たのでしょう」
|
【入道は、かの国の得意にて】- 以下「いかなることかあらむ」まで良清の詞。丁寧の補助動詞「はべり」が使用されている。「に」断定の助動詞。「て」接続助詞。
【年ごろあひ語らひはべりつれど】- 大島本は「侍れ(れ+つれイ)と」と「つれ」を異本に拠って補入する。『新大系』は本行本文のままとする。『集成』『古典セレクション』は異本に従って「はべりつれど」とする。「はべり」丁寧の補助動詞、「つれ」完了の助動詞。長年互いに交際しておりましたが。
【ことなる消息をだに通はさで】- 「だに」副助詞、打消しの語句と呼応して例外的・逆接的意味を表す。普通の消息はもちろんのこと、これぞという特別の消息でさえも通わさないで。
|
| 1.4.5 |
|
と言って、不審がる。
君が、お夢などもご連想なさることもあって、「早く会え」とおっしゃるので、舟まで行って会った。
「あれほど激しかった波風なのに、いつの間に船出したのだろう」と、合点が行かず思っていた。
|
と言って訳がわからないふうであった。源氏は昨夜の夢のことが胸中にあって、「早く逢ってやれ」と言ったので、良清は船へ行って入道に面会した。あんなにはげしい天気のあとでどうして船が出されたのであろうと良清はまず不思議に思った。
|
【おぼめく】- 『集成』は「不審がる」。『完訳』は「入道の誘いに浮き立つ心を、源氏に気づかれまいと、とぼける」と注す。
【君の】- 「の」格助詞、主格。「のたまへば」に続く。「御夢なども」以下「ありて」までは挿入句。
【行きて会ひたり】- 「たり」完了の助動詞。主語は良清。
【さばかり激しかりつる波風に】- 以下「舟出しつらむ」まで、良清の心中。「つる」完了の助動詞。「つ」完了の助動詞。「らむ」推量の助動詞、視界外推量。
【心得がたく思へり】- 「り」完了の助動詞、存続。
|
| 1.4.6 |
|
「去る上旬の日の夢に、異形のものが告げ知らせることがございましたので、信じがたいこととは存じましたが、『十三日にあらたかな霊験を見せよう。
舟の準備をして、必ず、この雨風が止んだら、この浦に寄せ着けよ』と、前もって告げていたことがございましたので、
|
「この月一日の夜に見ました夢で異形の者からお告げを受けたのです。信じがたいこととは思いましたが、十三日が来れば明瞭になる、船の仕度をしておいて、必ず雨風がやんだら須磨の源氏の君の住居へ行けというようなお告げがありましたから、
|
【去ぬる朔日の日、夢に】- 大島本は「ついたちのひ夢に」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「朔日の日の夢に」と「の」を補訂する。以下「このよし申したまへ」まで、入道の詞。三月上旬の日、源氏が海に出て祓いをしたころ。
【十三日にあらたなるしるし見せむ】- 以下「この浦にを寄せよ」まで、夢の告げ。「あらた」は霊験あらたかなの意。「む」推量の助動詞、推量また神の意志。
【舟装ひまうけて】- 大島本は「舟よそひまうけて」とある。『新大系』『集成』は底本のままとする。『古典セレクション』は諸本に従って「舟を」と「を」を補訂する。
【この浦にを寄せよ】- 大島本は「この浦にを」とある。『新大系』『集成』は底本のままとする。『古典セレクション』は諸本に従って「この浦に」と「を」を削除する。
【示すことのはべりしかば】- 「の」格助詞、主格。「はべり」は「有り」の丁寧語。「しか」過去の助動詞。示すことがございましたので。
|
| 1.4.7 |
|
試しに舟の用意をして待っておりましたところ、激しい雨、風、雷がそれと気づかせてくれましたので、異国の朝廷でも、夢を信じて国を助けるた例が多くございましたので、お取り上げにならないにしても、この予告の日をやり過さず、この由をお知らせ申し上げましょうと思って、舟出しましたところ、不思議な風が細く吹いて、この浦に着きましたこと、ほんとうに神のお導きは間違いがございません。
こちらにも、もしやお心あたりのこともございましたでしょうか、と存じまして。
大変に恐縮ですが、この由、お伝え申し上げてください」
|
試みに船の用意をして待っていますと、たいへんな雨風でしょう、そして雷でしょう、支那などでも夢の告げを信じてそれで国難を救うことができたりした例もあるのですから、こちら様ではお信じにならなくても、示しのあった十三日にはこちらへ伺ってお話だけは申し上げようと思いまして、船を出してみますと、特別なような風が細く、私の船だけを吹き送ってくれますような風でこちらへ着きましたが、やはり神様の御案内だったと思います。何かこちらでも神の告げというようなことがなかったでしょうか、と申すことを失礼ですがあなたからお取り次ぎくださいませんか」
|
【いかめしき雨、風、雷のおどろかしはべりつれば】- 『集成』は「大変な雨や風、雷が、それと思い当らせてくれましたので。この天変地異が源氏の身の上にかかわることだと悟った、の意」と注す。
【人の朝廷にも、夢を信じて国を助くるたぐひ多うはべりけるを】- 中国の『史記』殷本紀に武丁が夢に傅説(ふえつ)を得た話が指摘される。
【用ゐさせたまはぬまでも】- 主語は源氏。「させ」尊敬の助動詞。「給は」尊敬の補助動詞。最高敬語。「ぬ」打消の助動詞。「まで」副助詞、「も」係助詞と複合。打消の語の下につき、--にしても、の意。お取り上げあそばされぬしても。
【このいましめの日を】- 十三日をいう。
【あやしき風細う吹きて】- 『集成』は「「細う」は、入道の舟の行路にあたる所だけ順風が吹いたさまをいう」と注す。
【この浦に着きはべること】- 大島本は「侍ること」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「はべりつること」と完了助動詞「つる」を補訂する。
【神のしるべ違はずなむ】- 「ず」打消の助動詞。「なむ」係助詞、結びの省略。余情余意をこめた表現。
【はべりつらむ、とてなむ】- 「はべり」は「有り」の丁寧語。「つ」完了の助動詞。「らむ」推量の助動詞、視界外推量。「とて」連語(格助詞+接続助詞)。「なむ」係助詞、下に「参りぬる」などの語句が省略。余情・余意を表す。ございましたでしょうかと存じまして参りました。
【申したまへ】- 「申し」は源氏に対する敬意。「たまへ」は良清に対する敬意。
|
| 1.4.8 |
と言ふ。
良清、忍びやかに伝へ申す。
|
と言う。
良清、こっそりとお伝え申し上げる。
|
と入道は言うのである。良清はそっと源氏へこのことを伝えた。
|
|
| 1.4.9 |
君、思しまはすに、夢うつつさまざま静かならず、さとしのやうなることどもを、来し方行く末思し合はせて、
|
君、お考えめぐらすと、夢や現実にいろいろと穏やかでなく、もののさとしのようなことを、過去未来とお考え合わせになって、
|
源氏は夢も現実も静かでなく、何かの暗示らしい点の多かったことを思って、
|
|
| 1.4.10 |
|
「世間の人々がこれを聞き伝えるような後世の非難も穏やかではないだろうことを恐れて、本当の神の助けであるのに、背いたものなら、またそれ以上に、物笑いを受けることになるだろうか。
現実の世界の人の意向でさえ背くのは難しい。
ちょっとしたことでも慎重にして、自分より年齢もまさるとか、もしくは爵位が高いとか、世間の信望がいま一段まさる人とかには、言葉に従って、その意向を考え入れるべきである。
謙虚に振る舞って非難されることはないと、昔、賢人も言い残していた。
|
世間の譏りなどばかりを気にかけ神の冥助にそむくことをすれば、またこれ以上の苦しみを見る日が来るであろう、人間を怒らせることすら結果は相当に恐ろしいのである、気の進まぬことも自分より年長者であったり、上の地位にいる人の言葉には随うべきである。退いて咎なしと昔の賢人も言った、あくまで謙遜であるべきである。
|
【世の人の聞き伝へむ後のそしりも】- 以下「また何ごとか疑はむ」まで、源氏の心中。最初、入道の言葉に盲従することを躊躇、やがて入道の言葉に従うことを決意する。
【神の助けにもあらむを】- 「に」断定の助動詞。「も」係助詞、強調。「む」推量の助動詞、仮想・婉曲。「を」接続助詞、逆接。神の御加護であるかもしれないのに。
【これより】- 『完訳』は「入道に従っての明石移住を、後人に笑われる以上に」と注す。
【うつつざまの人の心だになほ苦し】- 大島本は「うつゝ(+さま<朱>)の」と朱筆で「さま」を補入する。『新大系』は朱筆補訂に従う。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「現の」と校訂する。「だに」副助詞、最小限の限定。『完訳』は「人間にそむくことさえつらい。まして神慮にそむくのは、の意」と注す。
【今一際まさる人】- 明石入道をさす。
【退きて咎なし】- 『河海抄』に「孝経に曰く、退かざれば咎あり」とあるが、現存本『孝経』には見えない語句。『完訳』は「「退キテ謗言ナカリキ」(春秋左氏伝・哀公二十)などによるか」。『新大系』は「老子「富貴にして驕れば自ら其の咎を遺す。功成り名遂げて身退くは天の道なり」(運夷第九)などに由来する言か」と注す。
【こそ--言ひ置きけれ】- 「こそ」係助詞、「けれ」過去助動詞、係結び。強調のニュアンス。源氏の得心した気持ち。
【昔、さかしき人】- 大島本は「昔さかしき人」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「昔のさかしき人」と「の」を補訂する。
|
| 1.4.11 |
|
なるほど、このような命の極限まで辿り着き、この世にまたとないほどの困難の限りを体験し尽くした。
今さら後世の悪評を避けたところで、たいしたこともあるまい。
夢の中にも父帝のお導きがあったのだから、また何を疑おうか」
|
もう自分は生命の危いほどの目を幾つも見せられた、臆病であったと言われることを不名誉だと考える必要もない。夢の中でも父帝は住吉の神のことを仰せられたのであるから、疑うことは一つも残っていない
|
【げに、かく命を極め】- 大島本は「けふ(ふ$に)かく」と「ふ」をミセケチにして「に」と訂正する。『新大系』『集成』は訂正に従って「げに」と校訂する。『古典セレクション』は諸本に従って「けふ」と校訂する。
【さらに後のあとの名をはぶくとても】- 『集成』は「今さら後世に残る悪評を避けたところで(入道の迎えに応じなかったところで)たいしたこともあるまい。これ以上の悪評を受けることもあるまい、の意」と注す。
【また何ごとか疑はむ】- 大島本は「なにことかハ(ハ#)」と「ハ」を抹消する。『新大系』は訂正に従って「何ごとか」と校訂する。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「何ごとをか」と「を」を補訂する。「か」係助詞、反語。「む」推量。また一方で何事を疑おうか、疑うものはない。強い決意。
|
| 1.4.12 |
と思して、御返りのたまふ。
|
と思いになって、お返事をおっしゃる。
|
と思って、源氏は明石へ居を移す決心をして、入道へ返辞を伝えさせた。
|
|
| 1.4.13 |
|
「知らない世界で、珍しい困難の極みに遭ってきたが、都の方からといって、安否を尋ねて来る人もいない。
ただ茫漠とした空の月と日の光だけを、故郷の友として眺めていますが、うれしい釣舟と思うぞ。
あちらの浦で、静かに隠れていられる所がありますか」
|
「知るべのない所へ来まして、いろいろな災厄にあっていましても、京のほうからは見舞いを言い送ってくれる者もありませんから、ただ大空の月日だけを昔馴染のものと思ってながめているのですが、今日船を私のために寄せてくだすってありがたく思います。明石には私の隠栖に適した場所があるでしょうか」
|
【知らぬ世界に】- 以下「隈はべりなむや」まで、源氏の詞。
【うれしき釣舟をなむ】- 「波にのみ濡れつるものを吹く風のたよりうれしき海人の釣舟」(後撰集雑三、一二二四、紀貫之)を踏まえる。好意に感謝する。「を」格助詞、目的格。また間投助詞、感動。「なむ」係助詞。結びの省略。余情・余意を残す。
【隠ろふべき隈】- 「べき」推量の助動詞、当然。ひっそり暮らすことのできる隠棲場所。
|
| 1.4.14 |
とのたまふ。
限りなくよろこび、かしこまり申す。
|
とおっしゃる。
この上なく喜んで、お礼申し上げる。
|
入道は申し入れの受けられたことを非常によろこんで、恐縮の意を表してきた。
|
|
|
 |
| 1.4.15 |
|
「ともかくも、夜のすっかり明けない前にお舟にお乗りください」
|
ともかく夜が明けきらぬうちに船へお乗りになるがよい
|
【ともあれ】- 以下「たてまつれ」まで、供人の詞。
【御舟にたてまつれ」--とて】- 「たてまつれ」は「乗る」の尊敬語。「とて」連語(格助詞+接続助詞)、理由・動機。お舟にお乗りなさい、ということで。
|
| 1.4.16 |
|
ということで、いつもの側近の者だけ、四、五人ほど供にしてお乗りになった。
|
ということになって、例の四、五人だけが源氏を護って乗船した。
|
【例の親しき限り、四、五人ばかりして】- 「ばかり」副助詞、程度・限定。「し」動詞、供としての意。「て」接続助詞、順接。須磨に随行したのは七、八人であった(須磨)。そのうち四、五人が身辺に仕えていた。
|
| 1.4.17 |
|
例の不思議な風が吹き出してきて、飛ぶように明石にお着きになった。
わずか這って行けそうな距離は時間もかからないとはいえ、やはり不思議にまで思える風の動きである。
|
入道の話のような清い涼しい風が吹いて来て、船は飛ぶように明石へ着いた。それはほんの短い時間のことであったが不思議な海上の気であった。
|
【例の風】- 前に「あやしき風細く吹きて」とあった風をいう。
【ただはひ渡るほどに】- 大島本は「たゝはひわたる程に」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「ほどは」と校訂する。
【風の心なり】- 『完訳』は「擬人法で、神慮を強調」と注す。
|
|
第二章 明石の君の物語 明石での新生活の物語
|
|
第一段 明石入道の浜の館
|
| 2.1.1 |
|
浜の様子は、なるほどまことに格別である。
人が多く見える点だけが、ご希望に添わないのであった。
入道の所領している所々、海岸にも山蔭にも、季節折々につけて、興趣をわかすにちがいない海辺の苫屋、勤行をして来世のことを思い澄ますにふさわしい山川のほとりに、厳かな堂を建てて念仏三昧を行い、この世の生活には、秋の田の実を刈り収めて、余生を暮らすための稲の倉町が幾倉もなど、四季折々につけて、場所にふさわしい見所を多く集めている。
|
明石の浦の風光は、源氏がかねて聞いていたように美しかった。ただ須磨に比べて住む人間の多いことだけが源氏の本意に反したことのようである。入道の持っている土地は広くて、海岸のほうにも、山手のほうにも大きな邸宅があった。渚には風流な小亭が作ってあり、山手のほうには、渓流に沿った場所に、入道がこもって後世の祈りをする三昧堂があって、老後のために蓄積してある財物のための倉庫町もある。
|
【浜のさま、げにいと心ことなり】- 明石の浜の様子。「げに」は良清の話を受ける(若紫)。
【人しげう見ゆるのみなむ、御願ひに背きける】- 「のみ」副助詞、限定・強調。「なむ」係助詞、「ける」過去の助動詞、詠嘆、係結び。強調のニュアンスを添える。
【興をさかすべき渚の苫屋】- 「べき」推量の助動詞、当然。きっと興趣を催させるような渚の苫屋。「苫屋」は歌語。
【思ひ澄ましつべき山水】- 「つ」完了の助動詞、確述。「べき」推量の助動詞、適当。思いを静かにするにふさわしい山水。
【秋の田の実を刈り収め】- 「たのみ」は「田の実」と「頼み」を懸ける。歌語。
【齢積むべき稲の倉町ども】- 「つむ」は「齢を積む」と「積む稲の蔵」の両句に掛かる掛詞。「べき」推量の助動詞、当然。
|
| 2.1.2 |
高潮に怖ぢて、このころ、娘などは岡辺の宿に移して住ませければ、この浜の館に心やすくおはします。 |
高潮を恐れて、近頃は、娘などは岡辺の家に移して住ませていたので、この海辺の館に気楽にお過ごになる。
|
高潮を恐れてこのごろは娘その他の家族は山手の家のほうに移らせてあったから、浜のほうの本邸に源氏一行は気楽に住んでいることができるのであった。
|
【心やすくおはします】- 主語は源氏。『完訳』は「男女を意識しない気安さ」と注す。あらかじめその生活を語る。
|
| 2.1.3 |
|
舟からお車にお乗り移りになるころ、日がだんだん高くなって、ほのかに拝するやいなや、老いも忘れ、寿命も延びる心地がして、笑みを浮かべて、まずは住吉の神をとりあえず拝み申し上げる。
月と日の光を手にお入れ申した心地がして、お世話申し上げること、ごもっともである。
|
船から車に乗り移るころにようやく朝日が上って、ほのかに見ることのできた源氏の美貌に入道は老いを忘れることもでき、命も延びる気がした。満面に笑みを見せてまず住吉の神をはるかに拝んだ。月と日を掌の中に得たような喜びをして、入道が源氏を大事がるのはもっともなことである。
|
【舟より御車にたてまつり移るほど】- 話は戻って、源氏が舟から車に乗り換えるところに戻る。「たてまつり」は「乗る」の尊敬語。
【ほのかに見たてまつるより】- 主語は明石入道。「ほのか」は「光・色・音・様子などが、うっすらとわずかに現われるさま。その背後に、大きな、厚い、濃い、確かなものの存在が感じられる場合にいう。類義語カスカは、今にも消え入りそうで、あるか無いかのさま」(岩波古語辞典)。「より」格助詞、するやいなや。『集成』は「源氏をそれとなく拝見するやたちまち」。『完訳』は「一目お見上げ申すなり、たちまち」。
【月日の光を手に得たてまつりたる心地して】- 無上の喜び。後の「若菜上」に入道は夢に「山の左右より月日の光さやかにさし出でて世を照らす」という様を見て、それが中宮と東宮の誕生の暗示と解したとある。
|
| 2.1.4 |
|
天然の景勝はいうまでもなく、こしらえた趣向、木立、立て石、前栽などの様子、何とも表現しがたい入江の水など、もし絵に描いたならば、修業の浅いような絵師ではとても描き尽くせまいと見える。
数か月来の住まいよりは、この上なく明るく、好もしい感じがする。
お部屋の飾りつけなど、立派にしてあって、生活していた様子などは、なるほど都の高貴な方々の住居と少しも異ならず、優美で眩しいさまは、むしろ勝っているように見える。
|
おのずから風景の明媚な土地に、林泉の美が巧みに加えられた庭が座敷の周囲にあった。入り江の水の姿の趣などは想像力の乏しい画家には描けないであろうと思われた。須磨の家に比べるとここは非常に明るくて朗らかであった。座敷の中の設備にも華奢が尽くされてあった。生活ぶりは都の大貴族と少しも変わっていないのである。それよりもまだ派手なところが見えないでもない。
|
【絵に描かば、心のいたり少なからむ絵師は描き及ぶまじ】- 「ば」接続助詞、順接の仮定条件。「む」推量の助動詞、仮定・婉曲。「え」副詞--「まじ」打消推量の助動詞と呼応して、不可能を表す。風景の素晴しさをいう。
【月ごろの御住まひよりは、こよなくあきらかに、なつかしき】- 大島本は「なつかし(し+き)」と「き」を補入する。『新大系』は底本の補入に従う。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「なつかし」と校訂する。「より」格助詞、比較。「明らか」「懐かし」、須磨の暗く侘しい世界から明るく好ましい世界へと転換。
【御しつらひなど、えならずして】- 「御」は源氏が住むという意味で付けられた敬語。
【住まひけるさまなど、げに都のやむごとなき所々に】- 明石入道の生活。「げに」は良清の言葉を受ける。
|
|
第二段 京への手紙
|
| 2.2.1 |
|
少しお心が落ち着いて、京へのお手紙をお書き申し上げになる。
参っていた使者は、現在、
|
明石へ移って来た初めの落ち着かぬ心が少しなおってから、源氏は京へ手紙を書いた。
|
【すこし御心静まりては、京の御文ども聞こえたまふ】- 源氏、明石に移ってから京へ手紙を遣る。「京の御文」は京への手紙の意。「聞こえ」は「言ふ」の謙譲語。源氏の都の人々に対する敬意。「たまふ」尊敬の補助動詞、源氏に対する敬意。お気持ちが落ち着いてからどうしたかというと、実は京の人々へお手紙を差し上げたのだ、というニュアンス。
【参れりし使は、今は】- 「り」完了の助動詞、存続。紫君のもとから参上していた使者。『集成』は「今は」以下「悲しき目を見る」まで、使者の詞とする。『完訳』は「今は」は「言ひつかはすべし」に掛かると解す。
|
| 2.2.2 |
|
「ひどい時に使いに立って辛い思いをした」
|
「こんなことになろうとは知らずに来て、ここで死ぬ運命だった」
|
【いみじき道に】- 以下「悲しき目を見る」まで、使者の詞。
|
| 2.2.3 |
|
と泣き沈んで、あの須磨に留まっていたのを召して、身にあまるほどの褒美を多く賜って遣わす。
親しいご祈祷の師たち、しかるべき所々には、このほどのご様子を、詳しく書いて遣わすのであろう。
|
などと言って、悲しんでいた京の使いが須磨にまだいたのを呼んで、過分な物を報酬に与えた上で、京でするいろいろの用が命ぜられた。頼みつけの祈りの僧たちや寺々へはこの間からのことが言いやられ、新たな祈りが依頼されたのである。
|
【身にあまれる物ども多くたまひて遣はす】- 「る」完了の助動詞、存続。「ども」接尾語、複数。「遣はす」、都に遣わすとは、あらかじめ結果を語った表現。
【むつましき御祈りの師ども、さるべき所々には】- 「御祈りの師ども」は源氏の祈祷の師たち。「さるべき所々」とは、『集成』は「そのほか関係の深い陰陽師、呪禁師などの類いであろう。改めて祈祷その他を依頼するためである」と解し、『完訳』は「親族・友人・妻妾など」と解す。
|
| 2.2.4 |
|
入道の宮だけには、不思議にも生き返った様子などをお書き申し上げなさる。
二条院からの胸を打つ手紙のお返事には、すらすらと筆もお運びにならず、筆をうち置きうち置き、涙を拭いながらお書き申し上げになるご様子、やはり格別である。
|
私人には入道の宮へだけ、稀有にして命をまっとうした須磨の生活の終わりを源氏はお知らせした。二条の院の憐れな手紙の返事は一気には書かれずに、一章を書いては泣き一章を書いては涙を拭きして書いている様子にも源氏がその人を思う深さが見られるのであった。
|
【入道の宮ばかりには】- 「ばかり」副助詞、限定・特立。「に」断定の助動詞。「は」係助詞、他との区別。他の人と違って、入道の宮だけには、というニュアンス。
【めづらかにてよみがへるさまなど聞こえたまふ】- 「など」副助詞、漠然・婉曲、また例示・同類の存在。「聞こえ」は「言ふ」の謙譲語。源氏の藤壺に対する敬意。「たまふ」尊敬の補助動詞、源氏に対する敬意。『集成』は「不思議なめぐり合せで命をとりとめた事情などを」と訳すが、『完訳』は「天変での命拾いを蘇生であるとする点に注意。源氏の生命の再生されるイメージ」と注す。
|
| 2.2.5 |
|
「繰り返し繰り返し、恐ろしい目の極限を体験し尽くした状態なので、今は俗世を離れたいという気持ちだけが募っていますが、『鏡を見ても』とお詠みになった面影が離れる間がないので、このように遠く離れたまま出来ようかと思うと、たくさんのさまざまな心配事は、二の次に自然と思われて、
|
あとへあとへと悲しいことが起こってきて、もう苦しい経験はし尽くしたような私ですからしきりに出家したい心も湧きますが、鏡を見てもとお言いになったあなたの面影が目を離れないのですから、あなたに再会をしないでは、それを実行することもできません。何の苦しみよりも私にはあなたと離れている苦痛が最もつらいことに思われます。あなたにまた逢うことができれば、ほかのいとわしいことは皆忍んでいこうと思います。
|
【返す返すいみじき目の限りを尽くし果てつる】- 大島本は「つくし」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「見尽くし」と「見」を補訂する。以下「いかにひがこと多からむ」まで、源氏の文。
【今はと世を思ひ離るる心のみまさりはべれど】- 「のみ」副助詞、限定・強調。「はべれ」丁寧の補助動詞。出家願望の気持ちが強まる。
【鏡を見ても』とのたまひし】- 紫の上が詠んだ「別れても影だにとまるものならば鏡を見てもなぐさめてまし」(須磨、第一章三段)という和歌をさす。
【かくおぼつかなながらや】- 『集成』は「こうして遠く離れて逢えぬまま出家してしまうのかと思うと(その悲しみに比べれば)」。『完訳』は「「--や」の下に「別れたてまらむ」ぐらいを補い読む」と注す。
|
| 2.2.6 |
|
遠く遥かより思いやっております
知らない浦からさらに遠くの浦に流れ来ても
|
はるかにも思ひやるかな知らざりし
浦より遠に浦づたひして
|
【遥かにも思ひやるかな知らざりし--浦よりをちに浦伝ひして】- 源氏の贈歌。
|
| 2.2.7 |
夢のうちなる心地のみして、覚め果てぬほど、いかにひがこと多からむ」
|
夢の中の心地ばかりして、まだ覚めきらないでいるうちは、どんなにか変なことを多く書いたことでしょう」
|
まだ夢の続きで、明石の浦にまで来ているような気がしてなりません。こんな時に書く手紙はまちがったこともあるでしょうが許してください。
|
|
| 2.2.8 |
|
と、なるほど、とりとめもなくお書き散らしになっているが、まことに側からのぞき込みたくなるようなのを、「たいそう並々ならぬご寵愛のほどだ」と、供の人々は拝見する。
|
正しくは書かれずに乱れ書きになっているような美しい手紙を、横から見ていて、源氏が二条の院の夫人を愛する深さを惟光たちは思った。
|
【げに、そこはかとなく】- 「げに」語り手が源氏の手紙の文面に納得した表現。
【書き乱りたまへるしもぞ、いと見まほしき側目なるを】- 「たまへ」尊敬の補助動詞、源氏に対する敬意。「る」完了の助動詞、存続。「しも」連語(副助詞+係助詞)特立・強調。「ぞ」係助詞、「側目なる」と結ばれるところが「を」接続助詞に続いて、結びの流れとなる。
|
| 2.2.9 |
|
それぞれも、故郷に心細そうな言伝をしているようである。
|
そうした人たちもわが家への音信をこの使いへ託した。
|
【言伝てすべかめり】- 「べかめり」連語(推量の助動詞「べかる」連体形の撥音便形「べかん」の「ん」が無表記+推量の助動詞「めり」)。語り手の推量。--のように思われる。
|
| 2.2.10 |
を止みなかりし空のけしき、名残なく澄みわたりて、漁する海人ども誇らしげなり。須磨はいと心細く、海人の岩屋もまれなりしを、人しげき厭ひはしたまひしかど、ここはまた、さまことにあはれなること多くて、よろづに思し慰まる。 |
絶え間なく降り続いた空模様も、すっかり晴れわたって、漁をする海人たちも元気がよさそうである。
須磨はとても心細く、海人の岩屋さえ数少なかったのに、人の多い嫌悪感はなさったものの、ここはまた一方で、格別にしみじみと心を打つことが多くて、何かにつけて自然と慰められるのであった。
|
あの晴れ間もないようだった天気は名残なく晴れて、明石の浦の空は澄み返っていた。ここの漁業をする人たちは得意そうだった。須磨は寂しく静かで、漁師の家もまばらにしかなかったのである。最初ここへ来た時にはそれと変わった漁村のにぎやかに見えるのを、いとわしく思った源氏も、ここにはまた特殊ないろいろのよさのあるのが、発見されていって慰んでいた。
|
【漁する海人ども誇らしげなり】- 「漁りする与謝の海人びと誇るらむ浦風ぬるく霞みわたれり」(恵慶法師集)の句による表現。
|
|
第三段 明石の入道とその娘
|
| 2.3.1 |
|
明石の入道、その勤行の態度は、たいそう悟り澄ましているが、ただその娘一人を心配している様子は、とても側で見ているのも気の毒なくらいに、時々愚痴をこぼし申し上げる。
|
主人の入道は信仰生活をする精神的な人物で、俗気のない愛すべき男であるが、溺愛する一人娘のことでは、源氏の迷惑に思うことを知らずに、注意を引こうとする言葉もおりおり洩らすのである。
|
【明石の入道】- 『集成』は「あるじの入道」とする。『大成』校異篇にはに「青」異同ナシ。「河」は「入道」とある。『集成』は「この居館の主人である入道。客人たる源氏に対していう」と注す。
【かたはらいたきまで、時々漏らし愁へきこゆ】- 「まで」副助詞、極まり及ぶ程度。「きこゆ」は「言ふ」の謙譲語、入道の源氏に対する敬意。
|
| 2.3.2 |
|
ご心中にも、興味をお持ちになった女なので、「このように意外にも廻り合わせなさったのも、そうなるはずの前世からの宿縁があるのか」とお思いになるものの、「やはり、このように身を沈めている間は、勤行より他のことは考えまい。
都の人も、普通の場合以上に、約束したことと違うとお思いになるのも、気恥ずかしい」と思われなさると、素振りをお見せになることはない。
|
源氏もかねて興味を持って噂を聞いていた女であったから、こんな意外な土地へ来ることになったのは、その人との前生の縁に引き寄せられているのではないかとも思うことはあるが、こうした境遇にいる間は仏勤め以外のことに心をつかうまい。京の女王に聞かれてもやましくない生活をしているのとは違って、そうなれば誓ってきたことも皆嘘にとられるのが恥ずかしいと思って、入道の娘に求婚的な態度をとるようなことは絶対にしなかった。
|
【御心地にも、をかしと聞きおきたまひし人なれば】- 「御心地」は源氏の心をさす。「たまひ」尊敬の補助動詞、源氏に対する敬意。「し」過去の助動詞。「若紫」巻の北山での良清の話を受ける。
【かくおぼえなくてめぐりおはしたるも、さるべき契りあるにや】- 源氏の心中を地の文で語る。間接話法。「おはし」は「来る」の尊敬語。語り手の源氏に対する敬意。「たる」完了の助動詞。「にや」連語(断定の助動詞+係助詞、疑問)。「さるべき」連語(動詞+推量の助動詞、当然)。『完訳』は「前世の因縁。源氏は明石の君との出会いを運命的なと実感する」と注す。
【思しながら】- 「思し」は「思ふ」の尊敬語。源氏に対する敬意。「ながら」接続助詞、逆接。「--ものの」などと同様に、心理の両面を語る常套表現の一つ。
【なほ、かう身を沈めたるほどは】- 以下「心恥づかしう」まで、源氏の心中文。ただしその引用句がなく地の文に続く構文。『完訳』は「以下、源氏の心内語。「心恥づかしう」で、間接話法に移る」。「たる」完了の助動詞、存続。
【行なひより他のことは思はじ】- 「じ」打消推量の助動詞。意志の打ち消し。勤行以外の事は考えまいとする源氏の決意。
【都の人も】- 紫の君をさす。
【ただなるよりは、言ひしに違ふと思さむも、心恥づかしう」思さるれば】- 「言ひしに違ふ」は「程ふるもおぼつかなくは思ほえず言ひしに違ふとばかりはしも」(源氏釈所引、出典未詳)を踏まえた表現。『集成』は「都にいる普通の場合より、愛を誓った言葉に嘘があったとお思いになるであろうことも気はずかしく思われなさるので。「ただなるよりは--」は、遠く離れているからこそ操を守りたい、という気持」と注す。「より」格助詞、比較。「は」係助詞、区別・強調。「思さ」は「思ふ」の尊敬語、源氏の紫の君に対する敬意。「む」推量の助動詞、婉曲。「るれ」自発の助動詞。
|
| 2.3.3 |
|
折にふれて、「気立てや、容姿など、並み大抵ではないのかなあ」と、心惹かれないでもない。
|
何かのことに触れては平凡な娘ではなさそうであると心の動いて行くことはないのではなかった。
|
【心ばせ、ありさま、なべてならずもありけるかな】- 源氏の心中。明石の君に関心を抱く。「ける」過去の助動詞、詠嘆。「かな」終助詞、詠嘆。
【ゆかしう思されぬにしもあらず】- 「れ」自発の助動詞。「ぬ」打消の助動詞。「に」完了の助動詞、確述。「しも」連語(副助詞+係助詞)、強調。「ず」打消の助動詞。二重否定の構文。委曲を尽くした心情表現。『集成』「お気持がひかれないわけでもない」と注す。
|
| 2.3.4 |
|
こちらではご遠慮申し上げて、自身はめったに参上せず、離れた下屋に控えている。
その実、毎日お世話申し上げたく思い、物足りなくお思い申して、「何とか願いを叶えたい」と、仏、神をますますお祈り申し上げる。
|
源氏のいる所へは入道自身すら遠慮をしてあまり近づいて来ない。ずっと離れた仮屋建てのほうに詰めきっていた。心の中では美しい源氏を始終見ていたくてならないのである。ぜひ希望することを実現させたいと思って、いよいよ仏神を念じていた。
|
【ここにはかしこまりて】- 源氏の御座所をさす。「かしこまりて」の主語は明石入道。
【さるは】- その実は、の意。
【明け暮れ見たてまつらまほしう】- 『集成』は「朝夕いつも(婿として)源氏をお世話もうしあげたく」と注す。
【思ふ心を叶へむ】- 大島本は「おもふ心越」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「いかで思ふ心を」と「いかで」を補訂する。入道の心中。「思ふ心」、『完訳』は「娘を源氏に縁づけたい気持」と注す。「む」推量の助動詞、願望・意志。
|
| 2.3.5 |
|
年齢は六十歳くらいになっているが、とてもこざっぱりとしていかにも好ましく、勤行のために痩せぎみになって、人品が高いせいであろうか、頑固で老いぼれたところはあるが、故事をもよく知っていて、どことなく上品で、趣味のよいところもまじっているので、古い話などをさせてお聞きになると、少しは所在なさも紛れるのであった。
|
年は六十くらいであるがきれいな老人で、仏勤めに痩せて、もとの身柄のよいせいであるか、頑固な、そしてまた老いぼけたようなところもありながら、古典的な趣味がわかっていて感じはきわめてよい。素養も相当にあることが何かの場合に見えるので、若い時に見聞したことを語らせて聞くことで源氏のつれづれさも紛れることがあった。
|
【年は六十ばかりになりたれど】- 明石入道の年齢、六十歳ほど。
【あらまほしう、行なひさらぼひて】- 『完訳』は「勤行に痩せ細るのを好ましいとする、語り手の気持」と注す。
【人のほどのあてはかなればにやあらむ】- 『集成』は「次の「いにしへのものを見知りて」以下に掛る」と注す。「にや」連語(断定の助動詞+係助詞、疑問)。「む」推量の助動詞。語り手の疑問・推量を差し挟んだ挿入句。
【いにしへのことをも知りて】- 大島本は「いにしへのか(か$こ)と越もしりて」と「か」をミセケチにして「こ」と訂正する。『新大系』は底本の訂正に従う。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「ものをも見知りて」と校訂する。
【昔物語などせさせて聞きたまふに】- 「させ」使役の助動詞。源氏が明石入道に。
|
| 2.3.6 |
|
ここ数年来、公私にお忙しくて、こんなにお聞きになったことのない世の中の故事来歴を少しずつ説きおこすので、「このような土地や人をも、知らなかったら、残念なことであったろう」とまで、おもしろいとお思いになることもある。
|
昔から公人として、私人として少しの閑暇もない生活をしていた源氏であったから、古い時代にあった実話などをぼつぼつと少しずつ話してくれる老人のあることは珍重すべきであると思った。この人に逢わなかったら歴史の裏面にあったようなことはわからないでしまったかもしれぬとまでおもしろく思われることも話の中にはあった。
|
【年ごろ、公私御暇なくて】- 源氏の過去数年来の生活をさす。
【かかる所をも人をも、見ざらましかば、さうざうしくや】- 源氏の心中。「ざら」打消の助動詞。「ましか」推量の助動詞、反実仮想。「や」係助詞、反語。見なかったらもの足りないことであったろうに、見たので満足だというニュアンス。
【とまで、興ありと思すことも交る】- 「まで」副助詞、極まり及ぶ程度。--というまでに。
|
| 2.3.7 |
|
このようにお親しみ申し上げてはいるが、たいそう気高く立派なご様子に、そうはいったものの、遠慮されて、自分の思うことは思うようにもお話し申し上げることができないので、「気がせいてならぬ、残念だ」と、母君と話して嘆く。
|
こんなふうで入道は源氏に親しく扱われているのであるが、この気高い貴人に対しては、以前はあんなに独り決めをしていた入道ではあっても、無遠慮に娘の婿になってほしいなどとは言い出せないのを、自身で歯がゆく思っては妻と二人で歎いていた。
|
【さこそ言ひしか】- 「こそ」係助詞--「しか」過去助動詞、已然形。逆接用法。娘を源氏に縁づけたいと妻に言ったことを受ける。
【えうち出できこえぬを】- 「え」副詞、「ぬ」打消の助動詞、不可能を表す構文。
【心もとなう、口惜し】- 入道の詞。
【母君と言ひ合はせて嘆く】- 入道と母君が一致して事に当たっている様子。
|
| 2.3.8 |
|
ご本人は、「普通の身分の男性でさえ、まあまあの人は見当たらないこの田舎に、世の中にはこのような方もいらっしゃっるのだ」と拝見したのにつけても、わが身のほどが思い知らされて、とても及びがたくお思い申し上げるのであった。
両親がこのように事を進めているのを聞くにも、「不釣り合いなことだわ」と思うと、何でもなかった時よりもかえって物思いがまさるのであった。
|
娘自身も並み並みの男さえも見ることの稀な田舎に育って、源氏を隙見した時から、こんな美貌を持つ人もこの世にはいるのであったかと驚歎はしたが、それによっていよいよ自身とその人との懸隔を明瞭に悟ることになって、恋愛の対象などにすべきでないと思っていた。親たちが熱心にその成立を祈っているのを見聞きしては、不似合いなことを思うものであると見ているのであるが、それとともに低い身のほどの悲しみを覚え始めた。
|
【おしなべての人だに、めやすきは見えぬ世界に、世にはかかる人もおはしけり】- 明石の君の心中。「だに」副助詞、最小限の希望・期待。「に」格助詞、場所。「は」係助詞、区別・強調。「も」係助詞、強調。「けり」過去の助動詞、初めて気づいた感動。
【見たてまつりしにつけて】- 「たてまつり」謙譲の補助動詞、明石の君の源氏に対する敬意。「し」過去の助動詞、体験の回想。『集成』は「源氏の姿をほのかに見た趣に書いてある」。『完訳』は「実際には岡辺の邸の明石の君は海辺の邸の源氏に会っていないが、噂に高い源氏の来訪を、まぢかに認識した」と注す。
【身のほど知られて】- 「れ」自発の助動詞。明石の君の自己意識。帝の御子である光る源氏と受領の娘である自分という歴然たる身分の差異。
【いと遥かにぞ思ひきこえける】- 「ぞ」係助詞、「ける」過去の助動詞、連体形。係結び、強調。
【似げなきことかな」と思ふに】- 「に」接続助詞、順接。明石の君の心中。源氏との縁談を不釣り合いと思う。
【ただなるよりはものあはれなり】- 『集成』は「何事もなかったこれまでよりは、ものを思うことも多い。源氏のことが気にかかる娘心をいう」。『完訳』は「源氏との縁談がなかった時に比べて。源氏の出現が、自らの身のわびしさを痛感させる」と注す。
|
|
第四段 夏四月となる
|
| 2.4.1 |
|
四月になった。
衣更えのご装束、御帳台の帷子など、風流な様に作って調進しながら、万事にわたってお世話申し上げるのを、「気の毒でもあり、これほどしてくれなくてもよいものを」とお思いになるが、人柄がどこまでも気位を高くもって上品なので、そのままになさっていらっしゃる。
|
四月になった。衣がえの衣服、美しい夏の帳などを入道は自家で調製した。よけいなことをするものであるとも源氏は思うのであるが、入道の思い上がった人品に対しては何とも言えなかった。
|
【四月になりぬ。更衣の御装束、御帳の帷子など】- 季節は夏四月に推移。源氏、琴を弾じて京を思う。
【よしあるさまにし出でつつ】- 大島本は「しいてつゝ」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「しいづ」と校訂する。
【いとほしう、すずろなり】- 源氏の心中。『集成』は「困ったものだ、こうまでしなくても、とお思いになるが。入道の献身ぶりをなかば迷惑に思う気持」と注す。
|
| 2.4.2 |
|
京からも、ひっきりなしにお見舞いの手紙が、つぎつぎと多かった。
のんびりとした夕月夜の晩に、海上に雲もなくはるかに見渡されるのが、お住みなれたお邸の池の水のように、思わず見間違えられなさると、何とも言いようなく恋しい気持ちは、どこへともなくさすらって行く気がなさって、ただ目の前に見やられるのは、淡路島なのであった。
|
京からも始終そうした品物が届けられるのである。のどかな初夏の夕月夜に海上が広く明るく見渡される所にいて、源氏はこれを二条の院の月夜の池のように思われた。恋しい紫の女王がいるはずでいてその人の影すらもない。ただ目の前にあるのは淡路の島であった。
|
【故郷の池水】- 大島本は「故郷の池水」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「池水に」と「に」を補訂する。
【言はむかたなく恋しきこと、何方となく行方なき心地したまひて】- 「わが恋は行方も知らず果てもなし逢ふを限りと思ふばかりぞ」(古今集恋二、六一一、凡河内躬恒)による。
|
| 2.4.3 |
|
「ああ、と遥かに」などとおっしゃって、
|
「泡とはるかに見し月の」などと源氏は口ずさんでいた。
|
【あはと、遥かに】- 源氏の詞。「淡路にてあはと遥かに見し月の近き今宵は所からかも」(新古今集雑上、一五一五、凡河内躬恒)による。
|
| 2.4.4 |
|
「ああと、しみじみ眺める淡路島の悲しい情趣まで
すっかり照らしだす今宵の月であることよ」
|
泡と見る淡路の島のあはれさへ
残るくまなく澄める夜の月
|
【あはと見る淡路の島のあはれさへ--残るくまなく澄める夜の月】- 源氏の独詠歌。旅愁を詠んだ歌。
|
| 2.4.5 |
|
長いこと手をお触れにならなかった琴を、袋からお取り出しになって、ほんのちょっとお掻き鳴らしになっているご様子を、拝し上げる人々も心が動いて、しみじみと悲しく思い合っている。
|
と歌ってから、源氏は久しく触れなかった琴を袋から出して、はかないふうに弾いていた。惟光たちも源氏の心中を察して悲しんでいた。源氏は
|
【久しう手触れたまはぬ琴を】- 須磨に持参した七絃琴。昨年の秋そして冬に、琴を弾いたことがある。
【見たてまつる人も】- 源氏の従者。
|
| 2.4.6 |
|
「広陵」という曲を、秘術の限りを尽くして一心に弾いていらっしゃると、あの岡辺の家でも、松風の音や波の音に響き合って、音楽に嗜みのある若い女房たちは身にしみて感じているようである。
何の楽の音とも聞き分けることのできそうにないあちこちの山賤どもも、そわそわと浜辺に浮かれ出て、風邪をひくありさまである。
|
「広陵」という曲を細やかに弾いているのであった。山手の家のほうへも松風と波の音に混じって聞こえてくる琴の音に若い女性たちは身にしむ思いを味わったことであろうと思われる。名手の弾く琴も何も聞き分けえられそうにない土地の老人たちも、思わず外へとび出して来て浜風を引き歩いた。
|
【広陵」といふ手を、ある限り弾きすましたまへるに】- 「広陵散」は晋の*(ケイ)康という人が夢の中で尭の時代の楽人伶倫から伝え聞いたという秘曲(晋書・*(ケイ)康伝)。
【身にしみて思ふべかめり】- 「べかめり」連語(推量の助動詞「べし」の連体形「べかる」の撥音便「ん」の無表記「べか」+推量の助動詞「めり」)。--に違いない。--のように思われる。語り手の推量。
【浜風をひきありく】- 「浜風」は「風」と「風邪」の掛詞、言葉遊び。
|
|
第五段 源氏、入道と琴を合奏
|
| 2.5.1 |
入道もえ堪へで、供養法たゆみて、急ぎ参れり。
|
入道もじっとしていられず、供養法を怠って、急いで参上した。
|
入道も供養法を修していたが、中止することにして、急いで源氏の居間へ来た。
|
|
| 2.5.2 |
|
「まったく、一度捨て去った俗世も改めて思い出されそうでございます。
来世に願っております極楽の有様も、かくやと想像される今宵の、妙なる笛の音でございますね」
|
「私は捨てた世の中がまた恋しくなるのではないかと思われますほど、あなた様の琴の音で昔が思い出されます。また死後に参りたいと願っております世界もこんなのではないかという気もいたされる夜でございます」
|
【さらに、背きにし世の中も】- 以下「夜のさまかな」まで、入道の詞。源氏の奏でる琴の音を聞いて極楽もかくやと感嘆する。
【思ひ出でぬべくはべり】- 「ぬべく」連語(完了の助動詞「ぬ」確述+推量の助動詞「べく」当然)、当然・強調。「侍り」は「あり」の丁寧語。
|
| 2.5.3 |
と泣く泣く、めできこゆ。
|
と感涙にむせんで、お褒め申し上げる。
|
入道は泣く泣くほめたたえていた。
|
|
| 2.5.4 |
|
ご自身でも、四季折々の管弦の御遊、その人あの人の琴や笛の音、または声の出し具合、その時々の催しにおいて絶賛されなさった様子、帝をはじめたてまつり、多くの方々が大切に敬い申し上げなさったことを、他人の身の上もご自身の様子も、お思い出しになられて、夢のような気がなさるままに、掻き鳴らしなさっている琴の音も、寂寞として聞こえる。
|
源氏自身も心に、おりおりの宮中の音楽の催し、その時のだれの琴、だれの笛、歌手を勤めた人の歌いぶり、いろいろ時々につけて自身の芸のもてはやされたこと、帝をはじめとして音楽の天才として周囲から自身に尊敬の寄せられたことなどについての追憶がこもごも起こってきて、今日は見がたい他の人も、不運な自身の今も深く思えば夢のような気ばかりがして、深刻な愁いを感じながら弾いているのであったから、すごい音楽といってよいものであった。
|
【わが御心にも、折々の御遊び】- 以下、源氏往古を回顧。地の文と心中文とが融合した叙述。
【声の出でしさまに】- 大島本は「いてしさまに」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「出でしさま」と「に」を削除する。
【もてかしづきあがめたてまつりたまひしを】- 主語は宮中の身分ある人々。「たてまつり」謙譲の補助動詞。人々の源氏に対する敬意。「たまひ」尊敬の補助動詞。宮中の身分ある人々に対する敬意。「し」過去の助動詞。
【心すごく聞こゆ。--古人は涙もとどめあへず】- 大島本は「きこゆる人ハ」とある。大島本は独自異文、文意不通。『新大系』は「本文不審」としながらも底本のまま「聞こゆる人は」とする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「ふ」の脱字と認め「聞こゆ。古人は」と校訂する。諸本に従って改める。 【古人は涙もとどめあへず】-明石入道をいう。感激しやすい老人のイメージで「古人」と呼称。
|
| 2.5.5 |
|
老人は涙も止めることができず、岡辺の家に、琵琶、箏の琴を取りにやって、入道は、琵琶法師になって、たいそう興趣ある珍しい曲を一つ二つ弾き出した。
|
老人は涙を流しながら、山手の家から琵琶と十三絃の琴を取り寄せて、入道は琵琶法師然とした姿で、おもしろくて珍しい手を一つ二つ弾いた。
|
【入道、琵琶の法師になりて】- 即席の琵琶法師になっての意。
【手一つ二つ弾きたり】- 大島本は「ひきたり」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「弾き出でたり」と「いて」を補訂する。
|
| 2.5.6 |
|
箏の琴をお進め申したところ、少しお弾きになるのも、さまざまな方面にも、たいそうご堪能だとばかり感じ入り申し上げた。
実際には、さほどだと思えない楽の音でさえ、その状況によって引き立つものであるが、広々と何物もない海辺である上に、かえって、春秋の花や紅葉の盛りである時よりも、ただ何ということなく青々と繁っている木蔭が、美しい感じがするので、水鶏が鳴いているのは、「誰が門さして」と、しみじみと興趣が催される。
|
十三絃を源氏の前に置くと源氏はそれも少し弾いた。また入道は敬服してしまった。あまり上手がする音楽でなくても場所場所で感じ深く思われることの多いものであるから、これははるかに広い月夜の海を前にして春秋の花紅葉の盛りに劣らないいろいろの木の若葉がそこここに盛り上がっていて、そのまた陰影の地に落ちたところなどに水鶏が戸をたたく音に似た声で鳴いているのもおもしろい庭も控えたこうした所で、
|
【箏の御琴参りたれば】- 「参り」は「出づ」の謙譲語。「たれ」完了の補助動詞、完了。「ば」接続助詞、順接。箏の御琴を差し出し申したところ。
【いと、さしも聞こえぬ物の音だに、折からこそはまさるものなるを】- 「いと」(副詞)、「ぬ」(打消の助動詞)と呼応して、たいして--でないの意。「だに」副助詞、否定構文の中で、例外的・逆接的事態。--でさえ。「こそ」係助詞、「なる」断定の助動詞、に掛かるが、「を」接続助詞、逆接、に続いているので、結びが流れている。たいしてそれほどにも聞こえぬ琴の音でさえ折によっては優れて聞こえるものだが。『完訳』は「実際にはさほどと思えぬ音色でさえ。「--だに」の文脈は、まして源氏の弾奏する秀でた音色は、の気持で、「はるばると」に続く」と注す。
【はるばると物のとどこほりなき海づらなるに、なかなか、春秋の花紅葉の盛りなるよりは】- 「なる」断定の助動詞、「に」接続助詞、逆接。何も情趣をおこす物のない広々とした海辺であるにもかかわらず、という文脈。『集成』『完訳』は、添加の意に解す。「なかなか」は「なまめかしき」に掛かる。「なる」断定の助動詞。「より」格助詞、比較。『完訳』は「春秋の情趣を重んずる一般論を否定、夏の木陰の景に注目」と注す。
【誰が門さして】- 「まだ宵にうち来てたたく水鶏かな誰が門さして入れぬなるらむ」(源氏釈所引、出典未詳)。誰が門を鎖しての意。
|
| 2.5.7 |
音もいと二なう出づる琴どもを、いとなつかしう弾き鳴らしたるも、御心とまりて、
|
音色もまこと二つとないくらい素晴らしく出す二つの琴を、たいそう優しく弾き鳴らしたのも、感心なさって、
|
優秀な楽器に対していることに源氏は興味を覚えて、
|
|
| 2.5.8 |
|
「この琴は、女性が優しい姿態でくつろいだ感じに弾いたのが、おもしろいですね」
|
「この十三絃という物は、女が柔らかみをもってあまり定まらないふうに弾いたのが、おもしろくていいのです」
|
【これは、女のなつかしきさまにてしどけなう弾きたるこそ、をかしけれ】- 源氏の詞。箏の琴をさす。男が緊張して弾くより、女性がやさしい感じで、くつろいで弾いたほうが好いものだ。
|
| 2.5.9 |
|
と、何気なくおっしゃるのを、入道はわけもなく微笑んで、
|
などと言っていた。源氏の意はただおおまかに女ということであったが、入道は訳もなくうれしい言葉を聞きつけたように、笑みながら言う、
|
【おほかたにのたまふを】- 一般論としていうの意。「を」格助詞、目的格。また接続助詞、逆接という解も可能。『完訳』は「源氏の発言は、弾き手が女でなくて残念、の意を含むが、娘とは無関係な一般論」と注す。
【入道はあいなくうち笑みて】- 「あいなく」、語り手の価値判断を含んだ感情移入の語。『完訳』は「勝手に娘のことと直感する入道への語り手の評」と注す。
|
| 2.5.10 |
|
「お弾きあそばす以上に優しい姿態の人は、どこにございましょうか。
わたくしは、延喜の帝のご奏法から弾き伝えること、四代になるのでございますが、このようにふがいない身の上で、この世のことは捨て忘れておりましたが、ひどく気の滅入ります時々は、掻き鳴らしておりましたが、不思議にも、それを見よう見真似で弾く者がおりまして、自然とあの先大王のご奏法に似ているのでございます。
山伏のようなひが耳では、松風をその音を妙なる音と聞き誤ったのでございましょうか。
何とかして、
|
「あなた様があそばす以上におもしろい音を出しうるものがどこにございましょう。私は延喜の聖帝から伝わりまして三代目の芸を継いだ者でございますが、不運な私は俗界のこととともに音楽もいったんは捨ててしまったのでございましたが、憂鬱な気分になっております時などに時々弾いておりますのを、聞き覚えて弾きます子供が、どうしたのでございますか私の祖父の親王によく似た音を出します。それは法師の僻耳で、松風の音をそう感じているのかもしれませんが、一度お聞きに入れたいものでございます」
|
【あそばすより】- 以下「聞こしめさせてしがな」まで、入道の詞。娘の明石の君をほのめかす。
【延喜の御手より弾き伝へたること、四代に】- 大島本は「し(し=三イ)たいに」とあり、本行本文「四代」に対して「三代」とする異本があることを傍記する。他の青表紙諸本「三代に」とある。『新大系』は本行本文のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「三代に」と校訂する。
【かき鳴らしはべりしを】- 「し」過去の助動詞、入道の過去・体験を振り返ったニュアンス。「を」接続助詞、弱い逆接。
【あやしう、まねぶ者のはべるこそ、自然にかの先大王の御手に通ひてはべれ】- 娘のことを暗に言った表現。「こそ」係助詞、「侍れ」丁寧の補助動詞に掛る。強調のニュアンス。
【山伏のひが耳に、松風を聞きわたしはべるにやあらむ】- 娘の琴の上手を誉めた入道の謙遜の詞。「松風に耳慣れにける山伏は琴を琴とも思はざりけり」(花鳥余情所引、拾遺集歌人の寿玄法師の歌、出典未詳)。
【これも忍びて聞こしめさせてしがな】- 大島本は「これの(の#も<朱墨>)」とあり、「の」を朱筆と墨筆で抹消して「も」と訂正する。『新大系』は訂正に従って「これも」とする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「これ」と校訂する。「これ」は娘の琴。「聞こしめさ」(他サ四段)は「聞く」の最高敬語。「て」完了の助動詞、確述。「し」副助詞、強調。「がな」終助詞、願望。こっそりと娘の琴の音をお耳に入れたいものだ。
|
| 2.5.11 |
|
と申し上げるにつれて、身をふるわして、涙を落としているようである。
|
興奮して慄えている入道は涙もこぼしているようである。
|
【涙落とすべかめり】- 「べかめり」連語(「べか」推量の助動詞、強い推量、連体形「べかる」が撥音便化して「ん」が表記されない形+「めり」推量の助動詞、主観的推量)、語り手のその場に居合わせて見ているようなニュアンス。
|
| 2.5.12 |
君、
|
君は、
|
君は、
|
|
| 2.5.13 |
|
「琴など、琴ともお聞きになるなずのない名人揃いの所で、悔しいことをしたなあ」
|
「松風が邪魔をしそうな所で、よくそんなにお稽古ができたものですね、うらやましいことですよ」
|
【琴を琴とも聞きたまふまじかりけるあたりに、ねたきわざかな】- 源氏の謙遜の詞。入道の踏まえた和歌を源氏も踏まえて応答。「たまふ」尊敬の補助動詞。源氏の入道に対する敬意。「まじかり」打消推量の助動詞。「ける」過去の助動詞、詠嘆。「かな」終助詞、感動。『集成』は「私の琴など琴ともお聞きになるはずのない所で、うっかりしたことをしたものです」と注す。
|
| 2.5.14 |
とて、押しやりたまふに、
|
と言って、押しやりなさって、
|
源氏は琴を前へ押しやりながらまた言葉を続けた。
|
|
| 2.5.15 |
|
「不思議なことに、昔から箏は、女が習得するものであった。
嵯峨の帝のご伝授で、女五の宮が、その当時の名人でいらっしゃったが、その御系統で、格別に伝授する人はいません。
総じて、ただ現在に著名な人々は、通り一遍の自己満足程度に過ぎないが、ここにそのように隠れて伝えていらっしゃるとは、実に興味深いものですね。
ぜひとも、聴いてみたいものです」
|
「不思議に昔から十三絃の琴には女の名手が多いようです。嵯峨帝のお伝えで女五の宮が名人でおありになったそうですが、その芸の系統は取り立てて続いていると思われる人が見受けられない。現在の上手というのは、ただちょっとその場きりな巧みさだけしかないようですが、ほんとうの上手がこんな所に隠されているとはおもしろいことですね。ぜひお嬢さんのを聞かせていただきたいものです」
|
【あやしう、昔より】- 以下「いかでかは聞くべき」まで、源氏の詞。
【嵯峨の御伝へにて、女五の宮、さる世の中の上手にものしたまひけるを】- 嵯峨天皇の第五皇女繁子内親王。嵯峨天皇、繁子内親王が共に箏の琴に巧みであったということは、『秦箏相承血脈』には見えない。
【掻き撫での心やりばかりにのみあるを】- 「ばかり」副助詞、程度。「に」断定の助動詞。「のみ」副助詞、限定・強調。「を」接続助詞、逆接。『集成』は「通りいっぺんの自己満足程度にすぎませんが」と注す。
【弾きこめたまへりける】- 「たまへ」尊敬の補助動詞、源氏の明石の君に対する敬意。「り」完了の助動詞、存続。「ける」過去の助動詞。『完訳』は「奏法を人知れず隠し伝える意」と注す。
|
| 2.5.16 |
とのたまふ。
|
とおっしゃる。
|
|
|
| 2.5.17 |
|
「お聴きあそばすについては、何の支障がございましょう。
御前にお召しになっても。
商人の中でさえ、古曲を賞美した人も、ございました。
琵琶は、本当の音色を弾きこなす人、昔も少のうございましたが、少しも滞ることない優しい弾き方など、格別でございます。
どのように習得したものでございましょう。
荒い波の音と一緒なのは、悲しく存じられますが、積もる愁え、慰められる折々もございます」
|
「お聞きくださいますのに何の御遠慮もいることではございません。おそばへお召しになりましても済むことでございます。潯陽江では商人のためにも名曲をかなでる人があったのでございますから。そのまた琵琶と申す物はやっかいなものでございまして、昔にもあまり琵琶の名人という者はなかったようでございますが、これも宅の娘はかなりすらすらと弾きこなします。品のよい手筋が見えるのでございます。どうしてその域に達しましたか。娘のそうした芸をただ荒い波の音が合奏してくるばかりの所へ置きますことは私として悲しいことに違いございませんが、不快なことのあったりいたします節にはそれを聞いて心の慰めにいたすこともございます」
|
【聞こしめさむには】- 以下「折々もはべり」まで、入道の詞。
【商人の中にてだにこそ、古琴聞きはやす人は、はべりけれ】- 白楽天の「琵琶行」を踏まえる。「だに」副助詞、最低限の限定。高貴な中では当然だが、身分の賎しい商人の中でさえも、というニュアンス。「こそ」係助詞、「侍れ」已然形に係る。強調。「ふること」は「古事」に「古琴」を連想させた表現。「は」係助詞、区別・特立。
【琵琶なむ、まことの音を】- 「琵琶行」を引いたことから、話題が娘の琵琶について移る。「なむ」係助詞、「すくなう侍し」に掛かるが、「を」接続助詞、逆接に続き、結びが流れている。
【をさをさとどこほることなう】- 娘の琵琶の奏法についていう。
【筋ことになむ】- 「なむ」係助詞、下に「ある」などの語句が省略された、余意を残した表現。
【いかでたどるにかはべらむ】- 「いかで」副詞、疑問。「たどる」は真似して習得する意。「に」断定の助動詞。「か」係助詞、疑問。「侍ら」は「あり」の丁寧語。「む」推量の助動詞、連体形、係結び。主語は明石の君。娘はどのようにして琵琶の奏法を習得したのだろうか。
|
| 2.5.18 |
など好きゐたれば、をかしと思して、箏の琴取り替へて賜はせたり。
|
などと風流がっているので、おもしろいとお思いになって、箏の琴を取り替えてお与えになった。
|
音楽通の自信があるような入道の言葉を、源氏はおもしろく思って、今度は十三絃を入道に与えて弾かせた。
|
|
| 2.5.19 |
|
なるほど、たいそう上手に掻き鳴らした。
現在では知られていない奏法を身につけていて、手さばきもたいそう唐風で、揺の音が深く澄んで聞こえた。
「伊勢の海」ではないが、「清い渚で貝を拾おう」などと、声の美しい人に歌わせて、自分でも時々拍子をとって、お声を添えなさるのを、琴の手を度々弾きやめて、お褒め申し上げる。
お菓子など、珍しいさまに盛って差し上げ、供の人々に酒を大いに勧めたりして、いつしか物憂さも忘れてしまいそうな夜の様子である。
|
実際入道は玄人らしく弾く。現代では聞けないような手も出てきた。弾く指の運びに唐風が多く混じっているのである。左手でおさえて出す音などはことに深く出される。ここは伊勢の海ではないが「清き渚に貝や拾はん」という催馬楽を美音の者に歌わせて、源氏自身も時々拍子を取り、声を添えることがあると、入道は琴を弾きながらそれをほめていた。珍しいふうに作られた菓子も席上に出て、人々には酒も勧められるのであったから、だれの旅愁も今夜は紛れてしまいそうであった。
|
【げに、いとすぐして】- 「げに」、明石の入道が言っていたとおりの意。語り手の納得した気持ち。また、源氏の納得の気持ち。
【伊勢の海」ならねど、「清き渚に貝や拾はむ】- ここは明石の地、伊勢の海ではないが。次の「清き渚に」という語句をいうための枕。催馬楽「伊勢の海」の歌詞。「伊勢の海の清き渚にしほかひになのりそや摘まむ貝や拾はむや玉や拾はむや」。
【琴弾きさしつつ、めできこゆ】- 主語は入道。「つつ」接尾語、同じ動作の繰り返し。「きこゆ」謙譲の補助動詞、入道の源氏に対する敬意。
【もの忘れしぬべき夜のさまなり】- 「もの」は憂い、物思い。「ぬべき」連語(完了の助動詞、確述+推量の助動詞、推量)、当然・強調。物思いも忘れてしまうに違いない素晴しい夜の様子である。
|
|
第六段 入道の問わず語り
|
| 2.6.1 |
|
たいそう更けて行くにつれて、浜風が涼しくなってきて、月も入り方になるにつれて、ますます澄みきって、静かになった時分に、お話を残らず申し上げて、この浦に住み初めたころの心づもりや、来世を願う模様など、ぽつりぽつりお話し申して、自分の娘の様子を、問わず語りに申し上げる。
おかしくおもしろいと聞く一面で、やはりしみじみ不憫なとお聞きになる点もある。
|
夜がふけて浜の風が涼しくなった。落ちようとする月が明るくなって、また静かな時に、入道は過去から現在までの身の上話をしだした。明石へ来たころに苦労のあったこと、出家を遂げた経路などを語る。娘のことも問わず語りにする。源氏はおかしくもあるが、さすがに身にしむ節もあるのであった。
|
【いたく更けゆくままに】- 入道、源氏に娘のことを問わず語りにかたる。
【静かなるほどに】- 供の人々が酒に酔い眠ったころ。
【御物語残りなく聞こえて】- 「御」は源氏の耳に入れるというで冠せられた敬語。
【をかしきものの、さすがにあはれと聞きたまふ節もあり】- 「をかし」は滑稽である、ほほえましいのニュアンス。「あはれ」は不憫である、しみじみと胸をうつのニュアンス。相対立する概念。『完訳』は「いささかおかしみを感じられるが、それでもさすがにしみじみと胸をうたれる思いでお聞きになる所どころもある」と注す。
|
| 2.6.2 |
|
「とても取り立てては申し上げにくいことでございますが、あなた様が、このような思いがけない土地に、一時的にせよ、移っていらっしゃいましたことは、もしや、長年この老法師めがお祈り申していました神仏がお憐れみになって、しばらくの間、あなた様にご心労をお掛け申し上げることになったのではないかと存ぜられます。
|
「申し上げにくいことではございますが、あなた様が思いがけなくこの土地へ、仮にもせよ移っておいでになることになりましたのは、もしかいたしますと、長年の間老いた法師がお祈りいたしております神や仏が憐みを一家におかけくださいまして、それでしばらくこの僻地へあなた様がおいでになったのではないかと思われます。
|
【いと取り申しがたきことなれど】- 以下「交り失せねとなむ掟てはべる」まで、入道の詞。娘のことを源氏に語る。
【移ろひおはしましたるは】- 主語は源氏。「おはしまし」は「おはす」より更に高い最高敬語。「たる」完了の助動詞、存続。おいであそばしていますのは。
【老法師の祈り申しはべる】- 入道の謙遜の自称。源氏が須磨明石とさすらって来られたのは自分が祈ってそうさせたものだという。
【御心をも悩ましたてまつるにやとなむ思うたまふる】- 「御心」は源氏の心をいう。「たてまつる」謙譲の補助動詞、入道の源氏に対する敬意。「に」断定の助動詞。「や」係助詞、疑問。「なむ」係助詞、「給ふる」下二段、謙譲の補助動詞、連体形に掛る。強調のニュアンス。『完訳』は「源氏の流離を、わが信仰の利益ゆえと必然化する」と注す。
|
| 2.6.3 |
|
そのわけは、住吉の神をご祈願申し始めて、ここ十八年になりました。
娘がほんの幼少でございました時から、思う子細がございまして、毎年の春秋ごとに、必ずあの住吉の御社に参詣することに致しております。
昼夜の六時の勤行に、自分自身の極楽往生の願いは、それはそれとして、ただ自分の娘に高い望みを叶えてくださいと、祈っております。
|
その理由は住吉の神をお頼み申すことになりまして十八年になるのでございます。女の子の小さい時から私は特別なお願いを起こしまして、毎年の春秋に子供を住吉へ参詣させることにいたしております。また昼夜に六回の仏前のお勤めをいたしますのにも自分の極楽往生はさしおいて私はただこの子によい配偶者を与えたまえと祈っております。
|
【住吉の神を頼みはじめたてまつりて、この十八年になりはべりぬ】- 娘の出生と年齢に関係する記事だが、「若紫」巻と「須磨」「明石」巻との間で、ややつじつまの合わない年齢記述。今、娘が十八歳ころとすると、「若紫」巻で九歳ころとなり、代々の国司が求婚したという良清の話と合わない。
【女の童いときなうはべりしより】- 大島本は「めのわらは」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「女の童の」と「の」を補訂する。娘をさしていう。
【かの御社に】- 摂津国住吉神社。
【昼夜の六時の勤め】- 晨朝・日中・日没・初夜・中夜・後夜の勤行。
【蓮の上の願ひをば、さるものにて】- 極楽往生の願いはそれはそれとして。
【ただこの人を高き本意叶へたまへと、なむ念じはべる】- 「ただ」副詞は「念じ侍る」に掛かる。「この人」は娘をさす。「を」間投助詞、詠嘆。「高き本意」とは後の「いかにして宮このたかき人にたてまつらむ」をいう。「なむ」係助詞、「侍る」連体形に掛かる。強調のニュアンス。
|
| 2.6.4 |
|
前世からの宿縁に恵まれませんもので、このようなつまらない下賤な者になってしまったのでございますが、父親は、大臣の位を保っておられました。
自分からこのような田舎の民となってしまったのでございます。
子々孫々と、落ちぶれる一方では、終いにはどのようになってしまうのかと悲しく思っておりますが、わが娘は生まれた時から頼もしく思うところがございます。
何とかして都の高貴な方に差し上げたいと思う決心、固いものですから、身分が低ければ低いなりに、多数の人々の嫉妬を受け、わたしにとってもつらい目に遭う折々多くございましたが、少しも苦しみとは思っておりません。
自分が生きておりますうちは微力ながら育てましょう。
このまま先立ってしまったら、海の中にでも身を投げてしまいなさい、と申しつけております」
|
私自身は前生の因縁が悪くて、こんな地方人に成り下がっておりましても、親は大臣にもなった人でございます。自分はこの地位に甘んじていましても子はまたこれに準じたほどの者にしかなれませんでは、孫、曾孫の末は何になることであろうと悲しんでおりましたが、この娘は小さい時から親に希望を持たせてくれました。どうかして京の貴人に娶っていただきたいと思います心から、私どもと同じ階級の者の間に反感を買い、敵を作りましたし、つらい目にもあわされましたが、私はそんなことを何とも思っておりません。命のある限りは微力でも親が保護をしよう、結婚をさせないままで親が死ねば海へでも身を投げてしまえと私は遺言がしてございます」
|
【親、大臣の位を保ちたまへりき】- 入道の父は大臣、その弟が按察大納言で源氏の母桐壺更衣の父という家系。
【これは、生れし時より頼むところなむはべる】- 「これ」は娘をさす。「なむ」係助詞、「侍る」連体形に掛かる、係結び。強調のニュアンス。後の「若菜」上巻に入道の夢の話として語られる。
【ほどほどにつけて、あまたの人の嫉みを負ひ】- 「程ほどにつけて」は入道自身の身分についていう。『集成』は「私のようなしがない者でもしがない者なりに」。「あまたの人」は求婚を断った相手の人々。
【命の限りは】- 以下「交り失せね」まで、入道の娘に言った詞の引用。「命の限り」は入道の生きている間の意。
|
| 2.6.5 |
|
などと、全部はお話できそうにもないことを、泣く泣く申し上げる。
|
などと書き尽くせないほどのことを泣く泣く言うのであった。
|
【すべてまねぶべくもあらぬことどもを】- 語り手の意を介入させた表現。『集成』は「それはもうここにそのまま伝えるのも憚られるような奇妙な話を」。『完訳』は「語り手も語り伝えられぬとする。話の内容の異様さを強調」と注す。
|
| 2.6.6 |
|
君も、いろいろと物思いに沈んでいらっしゃる時なので、涙ぐみながら聞いていらっしゃる。
|
源氏も涙ぐみながら聞いていた。
|
【折からは】- 「は」係助詞、区別・強調。時が時なだけに。
【うち涙ぐみつつ聞こしめす】- 「つつ」接尾語、二つの動作が並行して行われているさま。「聞こしめす」は「聞く」の最高敬語。
|
| 2.6.7 |
|
「無実の罪に当たって、思いもよらない地方にさすらうのも、何の罪によるのかと分からなく思っていたが、今夜のお話をうかがって考え合わせてみると、なるほど浅くはない前世からの宿縁であったのだと、しみじみと分かった。
どうして、このようにはっきりとご存じであったことを、今までお話してくださらなかったのか。
都を離れた時から、世の無常に嫌気がさし、勤行以外のことはせずに月日を送っているうちに、すっかり意気地がなくなってしまった。
そのような人がいらっしゃるとは、ほのかに聞いてはいたが、役立たずの者では縁起でもなく思って相手にもなさらぬであろうと、自信をなくしていたが、それではご案内してくださるというのだね。
心細い独り寝の慰めにも」
|
「冤罪のために、思いも寄らぬ国へ漂泊って来ていますことを、前生に犯したどんな罪によってであるかとわからなく思っておりましたが、今晩のお話で考え合わせますと、深い因縁によってのことだったとはじめて気がつかれます。なぜ明瞭にわかっておいでになったあなたが早く言ってくださらなかったのでしょう。京を出ました時から私はもう無常の世が悲しくて、信仰のこと以外には何も思わずに時を送っていましたが、いつかそれが習慣になって、若い男らしい望みも何もなくなっておりました。今お話のようなお嬢さんのいられるということだけは聞いていましたが、罪人にされている私を不吉にお思いになるだろうと思いまして希望もかけなかったのですが、それではお許しくださるのですね、心細い独り住みの心が慰められることでしょう」
|
【横さまの罪に当たりて】- 以下「一人寝の慰めにも」まで、源氏の詞。入道の申し出、娘との結婚を受諾。「横さま」と清音に読む。北野本「日本書紀」神功摂政元年二月条の訓点。
【おぼつかなく思ひつる】- 大島本は「思ひつる」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「思ひつるを」と「を」を補訂する。
【契りにこそは】- 「こそ」係助詞、「は」係助詞、区別・強調。下に「ありけめ」などの語句が省略。
【あはれになむ】- 「なむ」係助詞。下に「思ふ」などの語句が省略。
【思ひ知りたまひけることを】- 「たまひ」尊敬の補助動詞。源氏の入道に対する敬意。「ける」過去の助動詞。「を」格助詞、目的。
【月日を経るに】- 「経る」連体形。「に」格助詞、時間、--しているうちに。また接続助詞、原因・理由のニュアンスも可能。--していたので。『完訳』は「月日を送っているうちに」と訳す。
【かかる人】- 明石の君をさす。
【いたづら人】- 源氏自身をいう。
【ゆゆしきものにこそ思ひ捨てたまふらめと】- 「こそ」係助詞。「たまふ」尊敬の補助動詞、終止形。源氏の明石の君に対する敬意。「らめ」推量の助動詞、已然形。視界外推量。お思い捨てなさることであろう。
【導きたまふべきにこそあなれ】- 「たまふ」尊敬の補助動詞、終止形、源氏の入道に対する敬意。「べき」推量の助動詞、連体形、当然。「に」断定の助動詞。「こそ」係助詞。「あなれ」連語(「ある」動詞、連体形+「なれ」伝聞推定の助動詞、「あんなれ」の撥音の無表記)。
【心細き一人寝の慰めにも】- 「に」断定の助動詞。「も」係助詞、強調。下に「あらむ」「せむ」「ならむ」などの語句が省略。余意・余情を表す。
|
|
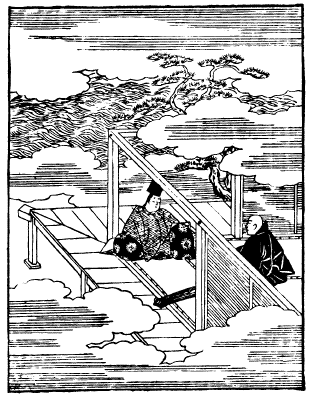 |
| 2.6.8 |
などのたまふを、限りなくうれしと思へり。
|
などとおっしゃるのを、この上なく光栄に思った。
|
などと源氏の言ってくれるのを入道は非常に喜んでいた。
|
|
| 2.6.9 |
|
「独り寝はあなた様もお分かりになったでしょうか
所在なく物思いに夜を明かす明石の浦の心淋しさを
|
「ひとり寝は君も知りぬやつれづれと
思ひあかしのうら寂しさを
|
【一人寝は君も知りぬやつれづれと--思ひ明かしの浦さびしさを】- 入道の贈歌。「も」係助詞、同類。娘の他にあなたもの意。「ぬ」完了の助動詞。「や」係助詞、疑問。「あかし」は「明かし」と「明石」の掛詞。「うら」は「浦」と「心(うら)」の掛詞。
|
| 2.6.10 |
|
まして長い年月ずっと願い続けてまいった気のふさぎようを、お察しくださいませ」
|
私はまた長い間口へ出してお願いすることができませんで悶々としておりました」
|
【まして年月思ひたまへわたるいぶせさを】- 「まして」は娘や源氏以上にの意。入道自身をいう。「たまへ」下二段、謙譲の補助動詞。
【推し量らせたまへ】- 「せ」尊敬の助動詞、「給へ」尊敬の補助動詞、最高敬語。
|
| 2.6.11 |
|
と申し上げる様子、身を震わせていたが、それでも気品は失っていない。
|
こう言うのに身は慄わせているが、さすがに上品なところはあった。
|
【聞こゆるけはひ、うちわななきたれど、さすがにゆゑなからず】- 「聞ゆる」は「言ふ」の謙譲語。「けはひ」は直観的に捉えられる人や物の様子をいう。「けしき」が事物の外形を視覚によって捉えたものであるのに対して、「けはひ」は漠然とした全体的な感じをいい、主として聴覚によって捉えられた事物の様子をさす。入道の態度・物腰。『集成』は「老人の興奮のてい」。『完訳』は「打ち明けて感動」。「さすがに」はそうはいっても。前の様子を否定する。「ゆゑなからず」は、『集成』は「品格を失わない」。『完訳』は「やはり気品がにじみ出ている」と注す。
|
| 2.6.12 |
|
「それでも、
|
「寂しいと言ってもあなたはもう法師生活に慣れていらっしゃるのですから」それから、
|
【されど、浦なれたまへらむ人は】- 源氏の詞。「されど」は入道の詞を受けて否定する。「たまへ」尊敬の補助動詞、已然形。「ら」完了の助動詞、存続。「む」推量の助動詞、婉曲。「人」は明石の君をさす。
|
| 2.6.13 |
|
「旅の生活の寂しさに夜を明かしかねて
安らかな夢を見ることもありません」
|
旅衣うら悲しさにあかしかね
草の枕は夢も結ばず
|
【旅衣うら悲しさに明かしかね--草の枕は夢も結ばず】- 源氏の返歌。「浦悲し」「明かし侘び」と受けて返す。「衣」「裏」は縁語。「あかし」に「明かし」と「明石」を掛ける。
|
| 2.6.14 |
|
と、ちょっと寛いでいらっしゃるご様子は、たいそう魅力的で、何ともいいようのないお美しさである。
数えきれないほどのことどもを申し上げたが、何とも煩わしいことよ。
誇張をまじえて書いたので、ますます、馬鹿げて頑固な入道の性質も、現れてしまったことであろう。
|
戯談まじりに言う、源氏にはまた平生入道の知らない愛嬌が見えた。入道はなおいろいろと娘について言っていたが、読者はうるさいであろうから省いておく。まちがって書けばいっそう非常識な入道に見えるであろうから。
|
【うち乱れたまへる御さま】- 『集成』は「うちとけて本心をお明かしになるご様子は」。『完訳』は「くつろいでいらっしゃる君のお姿は」と訳す。
【数知らぬことども聞こえ尽くしたれど、うるさしや】- 主語は入道。「うるさしや」は語り手の評言。『集成』は「入道はそのほか数多くのことを源氏にいろいろ申し上げたが、わずらわしいので書かない。以下草子地」と注す。『完訳』は「入道の多弁への語り手の評」と注す。
【ひがことどもに書きなしたれば、いとど、をこにかたくなしき入道の心ばへも、あらはれぬべかめり】- 「僻事どもに書きなしたれば」の主語は語り手自身。「たれ」完了の助動詞、已然形、「ば」接続助詞、順接の確定条件。書きなしたので。『集成』は「入道の言葉を誇張もまじえて書いたから、一層、馬鹿げて愚かしい入道の性格も、はっきりしたことであろう。「ひがこと」は、間違いの意。入道の話の内容の奇怪さを読者に対して弁解する草子地」。『完訳』は「数々取り違えて書きすぎたので、愚かしく偏屈な入道の気性も、いっそうあらわになってしまいそうである」「語り手は、前の「すべて--」とともに、源氏と明石一族の宿運を異様なものとして強調し、さらに、入道の滑稽で偏屈な人柄に帰して、物語の構想を隠蔽する」と注す。
|
|
第七段 明石の娘へ懸想文
|
| 2.7.1 |
|
願いが、まずまず叶った心地がして、すがすがしい気持ちでいると、翌日の昼頃に、岡辺の家にお手紙をおつかわしになる。
奥ゆかしい方らしいのも、かえって、このような辺鄙な土地に、意外な素晴らしい人が埋もれているようだと、お気づかいなさって、高麗の胡桃色の紙に、何ともいえないくらい念入りに趣向を調えて、
|
やっと思いがかなった気がして、涼しい心に入道はなっていた。その翌日の昼ごろに源氏は山手の家へ手紙を持たせてやることにした。ある見識をもつ娘らしい、かえってこんなところに意外なすぐれた女がいるのかもしれないからと思って、心づかいをしながら手紙を書いた。朝鮮紙の胡桃色のものへきれいな字で書いた。
|
【思ふこと、かつがつ叶ひぬる心地して】- 主語は明石入道。
【またの日の昼つ方、岡辺に御文つかはす】- 入道の申し出のあった翌日の昼ころ。源氏は手紙を送る。
【心恥づかしきさまなめるも】- 以下「籠もるべかめる」まで、源氏の心中。「心恥づかしきさま」は明石の君についていう。「なめる」連語(「なる」断定の助動詞、連体形+「める」推量の助動詞、主観的推量)、断定するところを婉曲的にいう表現で、推量の意味は極めて軽いニュアンス。
【なかなか、かかるものの隈にぞ】- 「なかなか」は都よりかえっての意。
【高麗の胡桃色の紙に、えならずひきつくろひて】- 高麗産の胡桃色の紙。舶来の高級品を使用。
|
| 2.7.2 |
|
「何もわからない土地にわびしい生活を送っていましたが
お噂を耳にしてお便りを差し上げます
|
遠近もしらぬ雲井に眺めわび
かすめし宿の梢をぞとふ
|
【をちこちも知らぬ雲居に眺めわび--かすめし宿の梢をぞ訪ふ】- 源氏の明石の君への贈歌。「かすめし」は入道が源氏に話したという意。
|
| 2.7.3 |
|
『思ふには』」
|
思うには。(思ふには忍ぶることぞ負けにける色に出でじと思ひしものを)
|
【思ふには】- 和歌に添えた言葉。「思ふには忍ぶることぞ負けにける色には出でじと思ひしものを」(古今集恋一、五〇一、読人しらず)の第一句の語句を引き、真意をこめる。
|
| 2.7.4 |
|
というぐらいあったのであろうか。
|
こんなものであったようである。
|
【とばかりやありけむ】- 「ばかり」副助詞、程度。「や」係助詞、疑問。「けむ」過去推量の助動詞。語り手の判断と推量。
|
| 2.7.5 |
入道も、人知れず待ちきこゆとて、かの家に来ゐたりけるもしるければ、御使いとまばゆきまで酔はす。 |
入道も、こっそりとお待ち申し上げようとして、あちらの家に来ていたのも期待どおりなので、御使者をたいそうおもはゆく思うほど酔わせる。
|
人知れずこの音信を待つために山手の家へ来ていた入道は、予期どおりに送られた手紙の使いを大騒ぎしてもてなした。
|
【来ゐたりけるもしるければ】- 主語は明石入道。「たりける」連語(「たり」完了の助動詞、存続+「ける」過去の助動詞)、過去に成立した動作の存在や継続の回想。来ていたのであった。「も」係助詞、強調。「しるけれ」形容詞、予想どうりである。「ば」接続助詞、順接の確定条件。
|
| 2.7.6 |
|
お返事には、たいそう時間がかかる。
奥に入って催促するが、娘は一向に聞き入れない。
気後れするようなお手紙の様子に、お返事をしたためる筆跡も、恥ずかしく気後れする。
相手のご身分と、わが身の程を思い比べると、比較にもならない思いがして、気分が悪いといって、物に寄り伏してしまった。
|
娘は返事を容易に書かなかった。娘の居間へはいって行って勧めても娘は父の言葉を聞き入れない。返事を書くのを恥ずかしくきまり悪く思われるのといっしょに、源氏の身分、自己の身分の比較される悲しみを心に持って、気分が悪いと言って横になってしまった。
|
【内に入りてそそのかせど】- 主語は入道。娘を促す。
【さらに聞かず】- 「さらに」副詞、「ず」打消の助動詞に係って、全然、少しも--しない、の意。
【恥づかしげなる御文】- 大島本は「はつかしけなる御文」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「いと恥づかしげなる御文」と「いと」を補訂する。
【恥づかしうつつまし】- 大島本は「はつかし(し+う)つゝまし」と「う」を補入する。『新大系』は底本の「う」補訂のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「恥づかしうつつましう」と「う」を補訂し、文を続ける。
【人の御ほど、わが身のほど思ふに、こよなくて】- 「人」は源氏、「わが身」は自分、明石の君をさす。明石の君は身分の相違を痛感する。
|
| 2.7.7 |
言ひわびて、入道ぞ書く。
|
説得に困って、入道が書く。
|
これ以上勧められなくなって入道は自身で返事を書いた。
|
|
| 2.7.8 |
|
「とても恐れ多い仰せ言は、田舎者には、身に余るほどのことだからでございましょうか。
まったく拝見させて戴くことなど、思いも及ばぬもったいなさでございます。
それでも、
|
もったいないお手紙を得ましたことで、過分な幸福をどう処置してよいかわからぬふうでございます。それをこんなふうに私は見るのでございます。
|
【いとかしこきは】- 以下「好き好きしや」まで、父入道が娘の返事を代筆したもの。
【袂に、つつみあまりぬるにや】- 「うれしきを何に包まむ唐衣袂ゆたかに裁てと言はましを」(古今集雑上、八六五、読人しらず)を踏まえた表現。「ぬる」完了の助動詞。「に」断定の助動詞。「や」係助詞、疑問。入道が娘の気持ちを忖度して書いている表現。
【さらに見たまへも、及びはべらぬかしこさになむ】- 「さらに」副詞、「ぬ」打消の助動詞に係って、全然、少しも--ない、の意。「たまへ」下二段、謙譲の補助動詞、源氏に対する敬意。「に」断定の助動詞。「なむ」係助詞。下に「はべる」などの語句が省略。強調と余意・余情。「はべら」丁寧の補助動詞。『集成』は「今まで経験したこともございませぬ恐れ多い仰せでございます」。『完訳』は「まったく拝見させていただくこともなりませぬもったいなさでございます」と訳す。
|
| 2.7.9 |
|
物思いされながら眺めていらっしゃる空を同じく眺めていますのは
きっと同じ気持ちだからなのでしょう
|
眺むらん同じ雲井を眺むるは
思ひも同じ思ひなるらん
|
【眺むらむ同じ雲居を眺むるは--思ひも同じ思ひなるらむ】- 入道の代筆歌。「眺む」「同じ」「思ひ」がそれぞれ二度づつ繰り返し使用。娘も源氏と同じ気持ちであることを強調。
|
| 2.7.10 |
|
と拝見してます。
大変に色めいて恐縮でございます」
|
だろうと私には思われます。柄にもない風流気を私の出しましたことをお許しください。
|
【いと好き好きしや】- 出家の身で恋文の代筆をしているので、恐縮して見せた。
|
| 2.7.11 |
|
と申し上げた。
陸奥紙に、ひどく古風な書き方だが、筆跡はしゃれていた。
「なるほど、色っぽく書いたものだ」と、目を見張って御覧になる。
御使者に、並々ならぬ女装束などを与えた。
|
とあった。檀紙に古風ではあるが書き方に一つの風格のある字で書かれてあった。なるほど風流気を出したものであると源氏は入道を思い、返事を書かぬ娘には軽い反感が起こった。使いはたいした贈り物を得て来たのである。
|
【陸奥紙に、いたう古めきたれど、書きざまよしばみたり】- 「陸奥紙」は恋文には普通使用しないのだが、父の入道が代筆したので、あえて使用。しかし、風流な書きぶりである。
【げにも、好きたるかな】- 源氏の心中。「げに」は入道の文句を受ける。
【めざましう見たまふ】- 『集成』は「出過ぎた振舞とご覧になる」。『完訳』は「いささか驚き入ったお気持でごらんになる」と訳す。
【なべてならぬ玉裳などかづけたり】- 海辺の縁で、「玉裳」(玉藻)「被く」(潜く)という表現。
|
| 2.7.12 |
またの日、
|
翌日、
|
翌日また源氏は書いた。
|
|
| 2.7.13 |
|
「代筆のお手紙を頂戴したのは、初めてです」とあって、
|
代筆のお返事などは必要がありません。と書いて、
|
【宣旨書きは、見知らずなむ】- 源氏の文中の句。「なむ」係助詞、下に「侍る」などの語句が省略。
|
| 2.7.14 |
|
「悶々として心の中で悩んでおります
いかがですかと尋ねてくださる人もいないので
|
いぶせくも心に物を思ふかな
やよやいかにと問ふ人もなみ
|
【いぶせくも心にものを悩むかな--やよやいかにと問ふ人もなみ】- 源氏の贈歌。「も」係助詞、強調。「かな」終助詞、詠嘆。「やよや」連語(「やよ」感動詞+「や」間投助詞)。「無み」連語(「な」形容詞語幹+「み」接尾語)無いのでの意。
|
| 2.7.15 |
|
『言ひがたみ』」
|
言うことを許されないのですから。
|
【言ひがたみ】- 和歌に添えた言葉。「恋しともまだ見ぬ人の言ひがたみ心にもののむつましきかな」(『弄花抄』所引、出典未詳)を引く。『集成』は「まだ見ぬあなたに恋しいとも言いかねまして」と注す。
|
| 2.7.16 |
|
と、今度は、たいそうしなやかな薄様に、とても美しそうにお書きになっていた。
若い女性が素晴らしいと思わなかったら、あまりに引っ込み思案というものであろう。
ご立派なとは思うものの、比較にならないわが身の程が、ひどくふがいないので、かえって、自分のような女がいるということを、お知りになり訪ねてくださるにつけて、自然と涙ぐまれて、まったく例によって動こうとしないのを、責められ促されて、深く染めた紫の紙に、墨つきも濃く薄く書き紛らわして、
|
今度のは柔らかい薄様へはなやかに書いてやった。若い女がこれを不感覚に見てしまったと思われるのは残念であるが、その人は尊敬してもつりあわぬ女であることを痛切に覚える自分を、さも相手らしく認めて手紙の送られることに涙ぐまれて返事を書く気に娘はならないのを、入道に責められて、香のにおいの沁んだ紫の紙に、字を濃く淡くして紛らすようにして娘は書いた。
|
【いといたうなよびたる薄様に、いとうつくしげに書きたまへり】- 源氏の二回めの恋文。鳥の子の薄様を使用。
【若き人のめでざらむも、いとあまり埋れいたからむ】- 最初の「む」推量の助動詞、仮定。後の「む」推量の助動詞、推量。語り手の推量。『集成』は「この手紙を若い女がすばらしいと思わなかったら、あまりに風情が分からぬというものであろう。草子地」、句点で文を独立させる。『完訳』は「若い女の身で、もし心を動かさなかったとしたら、あまり引っ込み思案の木石というものであろう、娘は」云々と、読点で文を下に続ける。
【めでたしとは見れど】- 主語は明石の君。
【浅からず染めたる紫の紙に、墨つき濃く薄く紛らはして】- 明石の君の返書。深く香をたきしめた紫色の紙を使用。濃淡のある墨つき。
|
| 2.7.17 |
|
「思って下さるとおっしゃいますが、
その真意はいかがなものでしょうかまだ見たこともない方が噂だけで
|
思ふらん心のほどややよいかに
まだ見ぬ人の聞きか悩まん
|
【思ふらむ心のほどややよいかに--まだ見ぬ人の聞きか悩まむ】- 明石の君の返歌。源氏の贈歌の第四句の文句と源氏が添えた『弄花抄』所引の出典未詳歌の第二句の文句も引用して応える。教養の深さを窺わせる。「らむ」推量の助動詞、視界外推量。「や」係助詞、疑問。「やよ」感動詞。「いかに」形容動詞、連用形。「か」係助詞、疑問。「なやま」「む」推量の助動詞、連体形。二つの疑問が呈されている。
|
| 2.7.18 |
|
筆跡や、出来ぐあいなど、高貴な婦人方に比べてもたいして見劣りがせず、貴婦人といった感じである。
|
手も書き方も京の貴女にあまり劣らないほど上手であった。
|
【手のさま、書きたるさまなど、やむごとなき人にいたう劣るまじう、上衆めきたり】- 源氏が見た評価。筆跡、内容など、都の高貴な人々に対して劣らず上流人である。
|
| 2.7.19 |
|
京の事が思い出されて、興趣深いと御覧になるが、続けざまに手紙を出すのも、人目が憚られるので、二、三日置きに、所在ない夕暮や、もしくは、しみじみとした明け方などに紛らわして、それらの時々に、同じ思いをしているにちがいない時を推量して、書き交わしなさると、不似合いではない。
|
こんな女の手紙を見ていると京の生活が思い出されて源氏の心は楽しかったが、続いて毎日手紙をやることも人目がうるさかったから、二、三日置きくらいに、寂しい夕方とか、物哀れな気のする夜明けとかに書いてはそっと送っていた。あちらからも返事は来た。
|
【二、三日隔てつつ】- 「つつ」接尾語、同じ動作の繰り返し。
【紛らはして】- 『集成』は「恋文らしくなうよそおって」。『完訳』は「女恋しさの気持を隠す気持」と注す。
【同じ心に】- 大島本は「おなし心に」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「人も同じ心に」と「人も」を補訂する。
【似げなからず】- 主語は明石の君。源氏の相手として適当である。
|
| 2.7.20 |
|
思慮深く気位高くかまえている様子も、是非とも会わないと気がすまないと、お思いになる一方で、良清がわがもの顔に言っていた様子もしゃくにさわるし、長年心にかけていただろうことを、目の前で失望させるのも気の毒にご思案されて、「相手が進んで参ったような恰好ならば、そのようなことにして、うやむやのうちに事をはこぼう」とお思いになるが、女は女で、かえって高貴な身分の方以上に、たいそう気位高くかまえていて、いまいましく思うようにお仕向け申しているので、意地の張り合いで日が過ぎて行ったのであった。
|
相手をするに不足のない思い上がった娘であることがわかってきて、源氏の心は自然惹かれていくのであるが、良清が自身の縄張りの中であるように言っていた女であったから、今眼前横取りする形になることは彼にかわいそうであるとなお躊躇はされた。あちらから積極的な態度をとってくれば良清への責任も少なくなるわけであるからと、そんなことも源氏は期待していたが女のほうは貴女と言われる階級の女以上に思い上がった性質であったから、自分を卑しくして源氏に接近しようなどとは夢にも思わないのである。結局どちらが負けるかわからない。
|
【心深う思ひ上がりたるけしきも】- 『完訳』は「思慮深く、気位の高い様子。結婚をはばかる明石の君の態度を、源氏がそのように受けとめる」と注す。
【見ではやまじと思すものから】- 主語は源氏。「ものから」接続助詞、逆接の確定条件。同時に源氏の心のもう一面を語る常套表現。
【良清が領じて言ひしけしき】- 「若紫」巻参照。以下「紛らはしてむ」まで、源氏の心中間接叙述。
【めざましう】- 『集成』は「こしゃくなと思われるし」。『完訳』は「おもしろくないし」と訳す。
【いとほしう思しめぐらされて】- 「いとほしう」まで、源氏の心中間接叙述。引用句なし。「思しめぐらされて」という地の文が間に入り、以下再び源氏の心中叙述。
【人進み参らば、さる方にても、紛らはしてむ】- 『集成』は「入道の方から進んでこちらに女房として出仕させるのなら、そういうことで仕方なかったのだということでもして、うやむやのうちに事を運んでしまおうとお思いになるけれども」。『完訳』は「女のほうから進んでこちらにやってくるのなら、そういうことでやむを得なかったというように取りつくろってしまおうとお考えになるけれども」と注す。
【女はた、なかなかやむごとなき際の人よりも、いたう思ひ上がりて】- 「女」明石の君をさす。「女」という、身分関係を抜きにした、男に対する女という対等の関係での呼称に注意。「はた」副詞。「思ひ上がり」は気位いや自尊心を高くもつことで、貴族としては大事なこと。
【心比べにてぞ過ぎける】- 「ぞ」係助詞、「過ぎ」「ける」過去の助動詞、過去。係結び。強調のニュアンス。
|
| 2.7.21 |
|
京の事を、このように関よりも遠くに行った今では、ますます気がかりにお思い申し上げなさって、「どうしたものだろう。
冗談でないことだ。
こっそりと、お迎え申してしまおうか」と、お気弱になられる時々もあるが、「そうかといって、こうして何年も過せようかと、今さら体裁の悪いことを」と、お思い静めになった。
|
何ほども遠くなってはいないのであるが、ともかくも須磨の関が中にあることになってからは、京の女王がいっそう恋しくて、どうすればいいことであろう、短期間の別れであるとも思って捨てて来たことが残念で、そっとここへ迎えることを実現させてみようかと時々は思うのではあるが、しかしもうこの境遇に置かれていることも先の長いことと思われない今になって、世間体のよろしくないことはやはり忍ぶほうがよいのであるとして、源氏はしいて恋しさをおさえていた。
|
【関隔たりては、いよいよおぼつかなく】- 須磨の関を越えて、須磨から明石に移ったことをいう。関を隔てて、須磨は摂津国、畿内の一国。明石は播磨国、地方の一国である。
【いかにせまし】- 以下「迎へたてつりてまし」まで、源氏の心中。
【たはぶれにくくもあるかな】- 「ありぬやとこころみがてらあひ見ねばた戯れにくきまでぞ恋しき」(古今集雑体、一〇二五、読人しらず)を踏まえる。
【迎へたてまつりてまし】- 「奉り」謙譲の補助動詞、源氏の紫の君に対する敬意。「てまし」連語(「て」完了の助動詞、未然形+「まし」推量の助動詞)、思い迷う気持ちを強調するニュアンス。
【さりとも、かくてやは、年を重ねむと】- 以下「人悪ろきことをば」まで、源氏の心中。 【かくてやは年を重ねむと】-大島本は「としをかさねんと」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「重ねむ」と「と」を削除する。「やは」係助詞(「や」係助詞+「は」間投助詞)、反語を表す。「重ね」「む」推量の助動詞、連体形、係結び。強調のニュアンス。
【人悪ろきことをば】- 「をば」連語(「を」格助詞+「は」係助詞、連濁)、対象を強調するニュアンス。下に「せじ」などの語句が省略。
|
|
第八段 都の天変地異
|
| 2.8.1 |
|
その年、朝廷では、神仏のお告げが続いてあって、物騒がしいことが多くあった。
三月十三日、雷が鳴りひらめき、雨風が激しかった夜に、帝の御夢に、院の帝が、御前の階段の下にお立ちあそばして、御機嫌がひどく悪くて、お睨み申し上げあそばすので、畏まっておいであそばす。
お申し上げあそばすこと多かった。
源氏のお身の上の事であったのだろう。
|
この年は日本に天変地異ともいうべきことがいくつも現われてきた。三月十三日の雷雨の烈しかった夜、帝の御夢に先帝が清涼殿の階段の所へお立ちになって、非常に御機嫌の悪い顔つきでおにらみになったので、帝がかしこまっておいでになると、先帝からはいろいろの仰せがあった。それは多く源氏のことが申されたらしい。
|
【その年、朝廷に】- 朝廷では天変地異を神仏のお告げではないかと取り沙汰する。
【三月十三日、雷鳴りひらめき】- 前にあった入道の言葉と同じ日。
【院の帝】- 故桐壺院の亡霊。
【御前の御階のもとに】- 清涼殿の東庭に面した階段の下。
【立たせたまひて】- 「せ」尊敬の助動詞、「給ひ」尊敬の補助動詞。院の帝に対する最高敬語。
【にらみきこえさせたまふを】- 「きこえ」謙譲の補助動詞。桐壺院の朱雀帝に対する敬意。「させ」尊敬の助動詞、「たまふ」尊敬の補助動詞。桐壺院に対する最高敬語。「を」接続助詞、順接。源氏物語では、父の院が子の帝に対しても、このような敬語の使われ方がする。
【かしこまりておはします】- 主語は朱雀帝。帝が帝自身恐縮している様を夢に見る。
【聞こえさせたまふことも多かり】- 大島本は「こともおほかり」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「ことども」と校訂する。主語は桐壺院。帝自身が聞いている様を夢に見る。
【源氏の御事なりけむかし】- 「なり」断定の助動詞。「けむ」過去推量の助動詞。「かし」終助詞、念押し。語り手の推量。『集成』は「政治向きのことは憚って省略した書き方」。『完訳』は「語り手の推測。詳述をはばかりながらも、政治的な内容を暗示」と注す。
|
|
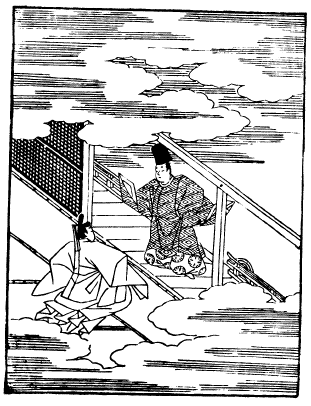 |
| 2.8.2 |
|
たいそう恐ろしく、またおいたわしく思し召して、大后にお申し上げあそばしたのだが、
|
おさめになったあとで帝は恐ろしく思召した。また御子として、他界におわしましてなお御心労を負わせられることが堪えられないことであると悲しく思召した。太后へお話しになると、
|
【いと恐ろしう、いとほし】- 帝の心中。桐壺院に対する気持ち。『完訳』は「成仏できぬ故院への同情」と注す。
【后に聞こえさせたまひければ】- 「后」は弘徽殿大后をさす。「聞こえさせ」連語(「きこえ」動詞+「させ」使役の助動詞)、「聞こゆ」より一段と謙譲の度合が高い表現。「たまひ」尊敬の補助動詞。「けれ」過去の助動詞。
|
| 2.8.3 |
|
「雨などが降り、天候が荒れている夜には、思い込んでいることが夢に現れるのでございます。
軽々しい態度に、お驚きあそばすものではありませぬ」
|
「雨などが降って、天気の荒れている夜などというものは、平生神経を悩ましていることが悪夢にもなって見えるものですから、それに動かされたと外へ見えるようなことはなさらないほうがよい。軽々しく思われます」
|
【雨など降り、空乱れたる夜は】- 以下「思し驚くまじきこと」まで、大后の詞。
|
| 2.8.4 |
と聞こえたまふ。
|
とお諌めになる。
|
と母君は申されるのであった。
|
|
| 2.8.5 |
|
お睨みになったとき、眼をお見合わせになったと思し召してか、眼病をお患になって、堪えきれないほどお苦しみになる。
御物忌み、宮中でも大后宮でも、数知れずお執り行わせあそばす。
|
おにらみになる父帝の目と視線をお合わせになったためでか、帝は眼病におかかりになって重くお煩いになることになった。御謹慎的な精進を宮中でもあそばすし、太后の宮でもしておいでになった。
|
【にらみたまひしに、目見合はせたまふ】- 大島本は「め見あハせ」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「見合はせ」と「目」を削除する。帝の心中、間接叙述。「に」格助詞、時。「たまひ」は故桐壺院に対する敬意。「せ」尊敬の助動詞、「たまふ」尊敬の補助動詞、最高敬語は朱雀帝に対する敬意。
【御目患ひたまひて】- 大島本は「御め△(△#)わつらひ」と「め」の下一字分抹消している。『新大系』は底本の訂正に従う。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「御目に」と「に」を補訂する。
|
| 2.8.6 |
|
太政大臣がお亡くなりになった。
無理もないお年であるが、次々に自然と騒がしいことが起こって来る上に、大后宮もどことなくお具合が悪くなって、日がたつにつれ弱って行くようなので、主上におかれてもお嘆きになること、あれやこれやと尽きない。
|
また太政大臣が突然亡くなった。もう高齢であったから不思議でもないのであるが、そのことから不穏な空気が世上に醸されていくことにもなったし、太后も何ということなしに寝ついておしまいになって、長く御平癒のことがない。御衰弱が進んでいくことで帝は御心痛をあそばされた。
|
【太政大臣亡せたまひぬ】- もとの右大臣。朱雀帝の外戚、後見者。
【騒がしきことあるに】- 「に」格助詞、添加。
【大宮もそこはかとなう患ひたまひて】- 弘徽殿大后。
【弱りたまふやうなる】- 「なる」断定の助動詞、連体中止形、余意・余情。
【内裏に思し嘆く】- 「に」格助詞、敬意。
|
| 2.8.7 |
|
「やはり、この源氏の君が、真実に無実の罪でこのように沈んでいるならば、必ずその報いがあるだろうと思われます。
今は、やはり元の位階を授けよう」
|
「私はやはり源氏の君が犯した罪もないのに、官位を剥奪されているようなことは、われわれの上に報いてくることだろうと思います。どうしても本官に復させてやらねばなりません」
|
【なほ、この源氏の君】- 以下「賜ひてむ」まで、帝の考えと口にした内容。源氏召還のことを弘徽殿大后にいう。
【もとの位をも】- 「も」係助詞、強調。源氏のもとの官職は右大将。
【賜ひてむ】- 「与える」の尊敬語。帝が自分の動作に敬語を用いた表現になる。「てむ」連語(「て」完了の助動詞+「む」推量の助動詞)、主体者帝の強い意志を表す。『完訳』は「元の位を授けることにいたしましょう」と訳す。
|
| 2.8.8 |
とたびたび思しのたまふを、
|
と度々お考えになり仰せになるが、
|
このことをたびたび帝は太后へ仰せになるのであった。
|
|
| 2.8.9 |
|
「世間の非難、軽々しいようでしょう。
罪を恐れて都を去った人を、わずか三年も過ぎないうちに赦されるようなことは、世間の人もどのように言い伝えることでしょう」
|
「それは世間の非難を招くことですよ。罪を恐れて都を出て行った人を、三年もたたないでお許しになっては天下の識者が何と言うでしょう」
|
【世のもどき、軽々しきやうなるべし】- 以下「いかが言ひ伝へはべらむ」まで大后の詞。帝の言動を諌め制す。
【罪に懼ぢて】- 「に」格助詞、対象を表す。「怖ぢ」また「落ち」とも解せる。
【三年をだに過ぐさず】- 「獄令」によれば、流罪の処せられた者は六年たたないと出仕を許されない、また流罪に処せられないまでも配流された者は三年たたないと出仕を許されないとある。「だに」副助詞、最小限の意、強調。
|
| 2.8.10 |
|
などと、大后は固くお諌めになるので、ためらっていらっしゃるうちに月日がたって、お二方の御病気も、それぞれ次第に重くなって行かれる。
|
などとお言いになって、太后はあくまでも源氏の復職に賛成をあそばさないままで月日がたち、帝と太后の御病気は依然としておよろしくないのであった。
|
【御悩みども】- 「ども」接尾語、複数を表す。帝と大后の病気をさす。
【重りまさらせたまふ】- 「させ」尊敬の助動詞、「給ふ」尊敬の補助動詞、最高敬語。
|
|
第三章 明石の君の物語 結婚の喜びと嘆きの物語
|
|
第一段 明石の侘び住まい
|
| 3.1.1 |
|
明石では、例によって、秋、浜風が格別で、独り寝も本当に何となく淋しくて、入道にも時々話をおもちかけになる。
|
明石ではまた秋の浦風の烈しく吹く季節になって、源氏もしみじみ独棲みの寂しさを感じるようであった。入道へ娘のことをおりおり言い出す源氏であった。
|
【明石には、例の、秋、浜風のことなるに、一人寝もまめやかにものわびしうて】- 【明石には、例の、秋、浜風の】-源氏、明石の君を呼び寄せようとするが、明石の君は動じない。第十二段。 【秋浜風のことなるに一人寝もまめやかにものわびしうて】-大島本は「秋」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「秋は」と「は」を補訂する。「に」格助詞、時また添加。また接続助詞、順接。
【折々語らはせたまふ】- 「せ」尊敬の助動詞。また使役の助動詞とも解せる。「たまふ」尊敬の補助動詞。『集成』は「話をおもちかけさせなさる」と使役の意に。『完訳』は「話をもちかけられる」と尊敬の意に訳す。
|
| 3.1.2 |
|
「何とか人目に立たないようにして、こちらに差し向けなさい」
|
「目だたぬようにしてこちらの邸へよこさせてはどうですか」
|
【とかく紛らはして、こち参らせよ】- 源氏の詞。娘を源氏のもとに差し出せという趣旨。
|
| 3.1.3 |
|
とおっしゃって、いらっしゃることは決してないようにお思いになっているが、娘は娘でまた、まったく出向く気などない。
|
こんなふうに言っていて、自分から娘の住居へ通って行くことなどはあるまじいことのように思っていた。女にはまたそうしたことのできない自尊心があった。
|
【渡りたまはむことをばあるまじう思したるを】- 主語は源氏。「む」推量の助動詞、仮定また婉曲。「まじう」打消の推量、意志の打消。「たる」完了の助動詞、存続。「を」接続助詞、逆接。
【正身はた、さらに】- 明石の君をさす。「さらに」副詞、下に打消の語に係って、全然の意を表す。また比較の意で、源氏以上に、の意も含もう。
|
| 3.1.4 |
|
「とても取るに足りない身分の田舎者は、一時的に下向した人の甘い言葉に乗って、そのように軽く良い仲になることもあろうが、一人前の夫人として思ってくださらないだろうから、わたしはたいへんつらい物思いの種を増すことだろう。
|
田舎の並み並みの家の娘は、仮に来て住んでいる京の人が誘惑すれば、そのまま軽率に情人にもなってしまうのであるが、自身の人格が尊重されてかかったことではないのであるから、そのあとで一生物思いをする女になるようなことはいやである。
|
【いと口惜しき際の】- 以下「心をや尽くさむ」まで、明石の君の心中。
【田舎人こそ】- 「こそ」係助詞、「わざをもす」「なれ」に係る。逆接用法。
【人数にも思されざらむものゆゑ】- 明石の君の身の程意識。「思さ」は「思ふ」の尊敬語。主体そのものは源氏。「れ」受身の助動詞、源氏から思われるの意。「む」推量の助動詞、推量。
【もの思ひをや添へむ】- 「を」格助詞、目的。「や」間投助詞、詠嘆。「む」推量の助動詞、推量。『集成』は「物思いの種を加えるだけのことだろう」。『完訳』は「たいへんな苦労を背負いこむにちがいない」。「や」を係助詞、疑問の意と解することも可能だろう。
|
| 3.1.5 |
|
あのように及びもつかぬ高望みをしている両親も、未婚の間で過ごしているうちは、当てにならないことを当てにして、将来に希望をかけていようが、かえって心配が増ることであろう」と思って、「ただこの浦にいらっしゃる間は、このようなお手紙だけをやりとりさせていただけるのは、並々ならぬこと。
長年噂にだけ聞いて、いつの日にかそのような方のご様子をちらっとでも拝見しようなどと、思いもしなかったお住まいで、よそながらもちらと拝見し、世にも素晴らしいと聞き伝えていたお琴の音をも風に乗せて聴き、毎日のお暮らしぶりもはっきりと見聞きし、このようにまでわたしに対してご関心いただくのは、このような海人の中に混じって朽ち果てた身にとっては、過分の幸せだわ」
|
不つりあいの結婚をありがたいことのように思って、成り立たせようと心配している親たちも、自分が娘でいる間はいろいろな空想も作れていいわけなのであるが、そうなった時から親たちは別なつらい苦しみをするに違いない。源氏が明石に滞留している間だけ、自分は手紙を書きかわす女として許されるということがほんとうの幸福である。長い間噂だけを聞いていて、いつの日にそうした方を隙見することができるだろうと、はるかなことに思っていた方が思いがけなくこの土地へおいでになって、隙見ではあったがお顔を見ることができたし、有名な琴の音を聞くこともかない、日常の御様子も詳しく聞くことができている、その上自分へお心をお語りになるような手紙も来る。もうこれ以上を自分は望みたくない。こんな田舎に生まれた娘にこれだけの幸いのあったのは確かに果報のあった自分と思わなければならない
|
【世籠もりて過ぐす年月こそ】- 「こそ」係助詞、「らめ」推量の助動詞、視界外推量に係り、逆接用法で下文に続く。明石の君の未婚時代、源氏が眼前に現れる以前をいう。
【行く末心にくく思ふらめ】- 『集成』は「将来立派にと望みをいだいてもいようが」。『完訳』「行く末を楽しみにしているのだろうが」と訳す。
【なかなかなる心をや尽くさむ】- 結婚したら、かえって今まで以上に、の意。「や」間投助詞、詠嘆。「む」推量の助動詞。「や」を係助詞、疑問の意と解することも可能だろう。
【ただこの浦におはせむほど】- 以下「身にあまることなれ」まで、再び明石の君の心中。
【かかる御文ばかりを聞こえかはさむこそ、おろかならね】- 「ばかり」副助詞、程度。「む」推量の助動詞、婉曲。「こそ」係助詞、「ね」打消の助動詞、已然形に係る。
【かくまで世にあるものと思し尋ぬるなどこそ】- 「こそ」係助詞、「なれ」断定の助動詞、已然形に係り、強調のニュアンス。『集成』は「こうまで人並みにお心にかけてお声をかけて下さるなどということは」と訳す。
|
| 3.1.6 |
など思ふに、いよいよ恥づかしうて、つゆも気近きことは思ひ寄らず。
|
などと思うと、ますます気後れがして、少しもお側近くに上がることなどは考えもしない。
|
と思っているのであって、源氏の情人になる夢などは見ていないのである。
|
|
| 3.1.7 |
|
両親は、長年の念願が今にも叶いそうに思いながら、
|
親たちは長い間祈ったことの事実になろうとする時になったことを知りながら、
|
【叶ふべきを思ひながら】- 「べき」推量の助動詞、当然。「ながら」接続助詞、逆接の意を含む。
|
| 3.1.8 |
|
「不用意にお見せ申して、もし相手にもしてくださらなかった時は、どんなに悲しい思いをするだろうか」
|
結婚をさせて源氏の愛の得られなかった時はどうだろうと、」
|
【ゆくりかに見せたてまつりて】- 以下「いかなる嘆きをかせむ」まで、明石入道夫妻の心中。間接叙述。もしもの場合の娘の身を心配。
|
| 3.1.9 |
と思ひやるに、ゆゆしくて、
|
と想像すると、心配でたまらず、
|
悲惨な結果も想像されて、
|
|
| 3.1.10 |
|
「立派な方とは申しても、辛く堪らないことであるよ。
目に見えない仏、神を信じ申して、君のお心や、娘の運命をも分からないままに」
|
どんなりっぱな方であっても、その時は恨めしいことであろうし、悲しいことでもあろう、目に見ることもない仏とか神とかいうものにばかり信頼していたが、それは源氏の心持ちも娘の運命も考えに入れずにしていたことであった
|
【めでたき人と聞こゆとも】- 以下「宿世をも知らで」まで、主として入道の心中。『完訳』は「直接話法による心内叙述」と注す。
【目にも見えぬ仏、神】- 大島本は「めにも」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「目に」と「も」を削除する。
【人の御心をも、宿世をも知らで】- 「人」は「御」があるので源氏、「宿世」は娘のをさす。
|
| 3.1.11 |
など、うち返し思ひ乱れたり。
君は、
|
などと、改めて思い悩んでいた。
君は、
|
などと、今になって二の足が踏まれ、それについてする煩悶もはなはだしかった。源氏は、
|
|
| 3.1.12 |
|
「この頃の波の音に合わせて、あの琴の音色を聴きたいものだ。
それでなかったら、何にもならない」
|
「この秋の季節のうちにお嬢さんの音楽を聞かせてほしいものです。前から期待していたのですから」
|
【このころの波の音に、かの物の音を聞かばや。さらずは、かひなくこそ】- 源氏の詞。「このころ」は秋の季節をいう。「波」「貝」(効)は縁語、一種の言葉遊び。「ばや」終助詞、願望。「ずは」連語(「ず」打消の助動詞、連用形+「は」係助詞)、順接の仮定条件。「こそ」係助詞、下に「あれ」已然形、などの語句が省略された文。「波の音に合わせて」。
|
| 3.1.13 |
など、常はのたまふ。
|
などと、いつもおっしゃる。
|
などとよく入道に言っていた。
|
|
|
第二段 明石の君を初めて訪ねる
|
| 3.2.1 |
|
こっそりと吉日を調べて、母君があれこれと心配するのには耳もかさず、弟子たちにさえ知らせず、自分の一存で世話をやき、輝くばかりに整えて、十三日の月の明るくさし出た時分に、ただ「あたら夜の」と申し上げた。
|
入道はそっと婚姻の吉日を暦で調べさせて、まだ心の決まらないように言っている妻を無視して、弟子にも言わずに自身でいろいろと仕度をしていた。そうして娘のいる家の設備を美しく整えた。十三日の月がはなやかに上ったころに、ただ「あたら夜の」(月と花とを同じくば心知られん人に見せばや)とだけ書いた迎えの手紙を浜の館の源氏の所へ持たせてやった。
|
【忍びて吉しき日見て】- 明石入道、吉日を占って、八月十三夜に源氏を招く。
【弟子どもなどにだに】- 「だに」副助詞、最小限の程度。腹心となって下働きをする弟子にさえの意。
【十三日の月】- 青表紙本諸本は「十二三日の月」(横陽)「十二三日の月の月の」(池)とある。河内本も「十二三日の月」。大島本と肖柏本、書陵部本、三条西家本が同文。『集成』『新大系』は底本のままとする。『古典セレクション』は「十二三日の月」と校訂する。
【あたら夜の】- 入道の文。「あたら夜の月と花とを同じくは心知れらむ人に見せばや」(後撰集春下、一〇三、源信明)を踏まえる。『集成』は「娘を許す意をほのめかす」と注す。
|
|
 |
| 3.2.2 |
|
君は、「風流ぶっているな」とお思いになるが、お直衣をお召しになり身なりを整えて、夜が更けるのを待ってお出かけになる。
お車はまたとなく立派に整えたが、仰々しいと考えて、お馬でお出かけになる。
惟光などばかりをお従わせになる。
少し遠く奥まった所であった。
道すがら、四方の浦々をお見渡しになって、恋人どうしで眺めたい入江の月影を見るにつけても、まずは恋しい人の御ことをお思い出し申さずにはいらっしゃれないので、そのまま馬で通り過ぎて、上京してしまいたく思われなさる。
|
風流がりな男であると思いながら源氏は直衣をきれいに着かえて、夜がふけてから出かけた。よい車も用意されてあったが、目だたせぬために馬で行くのである。惟光などばかりの一人二人の供をつれただけである。山手の家はやや遠く離れていた。途中の入り江の月夜の景色が美しい。紫の女王が源氏の心に恋しかった。この馬に乗ったままで京へ行ってしまいたい気がした。
|
【好きのさまや】- 源氏の心中。入道を批評。『集成』は「風流ぶったものよ」と訳す。
【御直衣たてまつり】- 「たてまつり」は「着る」の尊敬語。
【夜更かして出でたまふ】- 夜の更けるのを待って。『完訳』は「噂や良清の思惑を憚るためか」と注す。
【惟光などばかりをさぶらはせたまふ】- 「など」副助詞、婉曲。「ばかり」副助詞、範囲。「せ」使役の助動詞。「たまふ」尊敬の補助動詞。
【思ふどち見まほしき入江の月影にも】- 「思ふどちいざ見に行かむ玉津島入江の底に沈む月影」(源氏釈所引、出典未詳)の語句を踏まえる。『集成』は「いとしい人と一緒に眺めたい入江に映る月影につけても」。『完訳』は「古歌にいうように「思ふどち」で行って見たいような入江の月影を御覧になるにつけても」と訳す。
【まづ恋しき人の御ことを思ひ出できこえたまふに】- 「まづ」副詞、「思ひ出できこえたまふ」に係る。「に」接続助詞、順接。紫の君のことがまっさきに思い出されるので。
【やがて馬引き過ぎて、赴きぬべく思す】- 「やがて」副詞、「赴きぬべく」に係る。「引き過ぎて」は明石の君の家を通り過ぎて都への意。「ぬべく」連語(「ぬ」完了の助動詞+「べく」推量の助動詞)、強い当然のニュアンス。行ってしまいそうに。
|
| 3.2.3 |
|
「秋の夜の月毛の駒よ、
わが恋する都へ天翔っておくれ束
|
秋の夜の月毛の駒よ我が恋ふる
雲井に駈けれ時の間も見ん
|
【秋の夜の月毛の駒よ我が恋ふる--雲居を翔れ時の間も見む】- 源氏の独詠歌。紫の君を恋うる歌。「雲居を」の格助詞「を」は空間の移動を表す。「む」推量の助動詞、源氏の意志。見たい。「月毛の駒」に「月」という名を負うなら、天翔って都まで行き、しばしの間でもよいから紫の君に一目逢いたい。
|
| 3.2.4 |
|
とつい独り口をついて出る。
|
と独言が出た。
|
【うちひとりごたれたまふ】- 「うち」接頭語、つい、思わずというニュアンス。「れ」自発の助動詞、源氏の心情の底流を語る。
|
| 3.2.5 |
|
造りざまは、木が深く繁って、ひどく感心する所があって、結構な住まいである。
海辺の住まいは堂々として興趣に富み、こちらの家はひっそりとした住まいの様子で、「ここで暮らしたら、どんな物思いもし残すことはなかろう」と自然と想像されて、しみじみとした思いにかられる。
三昧堂が近くにあって、鐘の音、松風に響き合って、もの悲しく、巌に生えている松の根ざしも、情趣ある様子である。
いくつもの前栽に虫が声いっぱいに鳴いている。
あちらこちらの様子を御覧になる。
|
山手の家は林泉の美が浜の邸にまさっていた。浜の館は派手に作り、これは幽邃であることを主にしてあった。若い女のいる所としてはきわめて寂しい。こんな所にいては人生のことが皆身にしむことに思えるであろうと源氏は恋人に同情した。三昧堂が近くて、そこで鳴らす鐘の音が松風に響き合って悲しい。岩にはえた松の形が皆よかった。植え込みの中にはあらゆる秋の虫が集まって鳴いているのである。源氏は邸内をしばらくあちらこちらと歩いてみた。
|
【造れるさま、木深く、いたき所まさりて】- 場面変わって明石の君のいる岡辺の家。
【これは心細く住みたるさま】- 海辺の家と岡辺の家を比較。『完訳』は「「ものあはれなり」に続く」と注す。
【思ひ残すことはあらじ」と】- 大島本は「あらしと」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は「あらじとすらむと」と「すらむと」を補訂する。諸本には視界外推量の助動詞「らむ」がある。
【思しやらるるに】- 「るる」自発の助動詞。「に」接続助詞、順接。『集成』は「娘の人柄がしのばれて」。『完訳』は「おもいやらずにはいらっしゃれないにつけても」と注す。
【岩に生ひたる松の根ざしも、心ばへあるさまなり】- 岩に生えていえう松の根も風情のあるさまだの意。
【虫の声を尽くしたり】- 『集成』は「あらゆる虫を放って鳴かせている」。『完訳』は「秋の虫がいっせいに鳴きたてている」と訳す。
|
| 3.2.6 |
|
娘を住ませている建物は、格別に美しくしてあって、月の光を入れた真木の戸口は、ほんの気持ちばかり開けてある。
|
娘の住居になっている建物はことによく作られてあった。月のさし込んだ妻戸が少しばかり開かれてある。
|
【月入れたる真木の戸口、けしきばかり押し開けたり】- 大島本は「月いれたるま木の戸くちけしきこと(こと#)/に(に#はかり)をしあけたり」とある。すなわち「ことに」を抹消して「はかり」と訂正している。他の青表紙本諸本は「けしきことに」(横陽三)「けしきはかり」(池肖)と大別される。河内本は「気色ことに」とする。古注釈書『源氏釈』(冷泉家本)『河海抄』所引本文は「けしきことに」とする。一条兼良『花鳥余情』は「けしきことに」の本文を引用して「定家卿の青表紙にはけしきはかりをしあけたりとあり」といい、続けて「明石入道源氏を引導申につきてけしきはかりといふは源氏にこのとくちより入らせ給へと思へる心むけにことさらはかりあけたる也」と解説し、それに対して「けしきことにといふはもとよりみちひきたてまつるうへはこれより入らせ給へとわさとかましくをしあけたるへし」と解説する。そして「両説ともに其謂なきにあらす人の所存にしたかふへし」と結論づけ、「この月入たるまきの戸口は源氏第一の詞と定家卿は申侍るとかや」(松永本)と伝えている。大島本の傍注にも「月いれたる槙戸口ハ源氏第一詞と定家卿ハ申侍ると也」と伝える。『集成』『新大系』は底本の訂正に従う。『古典セレクション』は諸本に従って「けしきことに」と校訂する。引き歌「君や来む我や行かむのいさよひに真木の板戸もささず寝にけり」(古今集恋四、六九〇、読人しらず)。『集成』は「月のさし入った妻戸の出入口が、ほんのわずか押し開けてある。「月入れたる」の措辞に、あたかも源氏を閨に誘うかのように、という感じが表されている」「この戸口を木戸口とするのは当たらない」と注す。『完訳』は「月の光のさしこんだ木戸口がおもわせぶりに押し開けてある」と注す。『新大系』は「源氏の訪れに備えて少し開けてある妻戸から月光がさし込んでいる情景」と注す。
|
| 3.2.7 |
|
少しためらいがちに、何かと言葉をおかけになるが、「こんなにまでお側近くには上がるまい」と深く決心していたので、何となく悲しくて、気を許さない態度を、「ずいぶんと貴婦人ぶっているな。
容易に近づきがたい高貴な身分の女でさえ、これほど近づき言葉をかけてしまえば、気強く拒むことはないのであったが、このように落ちぶれているので、見くびっているのだろうか」としゃくで、いろいろと悩んでいるようである。
「容赦なく無理じいするのも、意向に背くことになる。
根比べに負けたりしたら、体裁の悪いことだ」などと、千々に心乱れてお恨みになるご様子、本当に物の情趣を理解する人に見せたいものである。
|
そこの縁へ上がって、源氏は娘へものを言いかけた。これほどには接近して逢おうとは思わなかった娘であるから、よそよそしくしか答えない。貴族らしく気どる女である。もっとすぐれた身分の女でも今日までこの女に言い送ってあるほどの熱情を見せれば、皆好意を表するものであると過去の経験から教えられている。この女は現在の自分を侮って見ているのではないかなどと、焦慮の中には、こんなことも源氏は思われた。力で勝つことは初めからの本意でもない、女の心を動かすことができずに帰るのは見苦しいとも思う源氏が追い追いに熱してくる言葉などは、明石の浦でされることが少し場所違いでもったいなく思われるものであった。
|
【うちやすらひ、何かとのたまふにも】- 主語は源氏。ためらいながら話かける。
【かうまでは見えたてまつらじ】- 明石の君の心中。「かうまで」このように近々との意。「じ」打消推量の助動詞。明石の君の意志。
【うちとけぬ心ざまを】- 「ぬ」打消の助動詞。気を許さない態度を。
【こよなうも人めきたるかな】- 以下「あなづらはしきにや」まで、源氏の心中。『集成』は「なんとまあいっぱしの貴婦人めいた振舞であることか」と訳す。
【さしもあるまじき際の人だに】- 「さしも」副詞(「さ」副詞+「しも」副助詞)は明石の君をさす。「まじ」打消推量の助動詞。「だに」副助詞、最低限を表す。『集成』は「そんな態度をとりそうもない(簡単に男になびきそうもない)高い身分の女性でも」。『完訳』は「容易に近寄りがたい高貴な身の女でさえも」と注す。
【いとかくやつれたるに】- 源氏の流離の身をさす。「に」接続助詞、原因理由。
【あなづらはしきにや】- 「に」断定の助動詞、「や」係助詞、疑問。『集成』は「見くびっているのだろうか」と訳す。
【情けなう】- 以下「人悪ろけれ」まで、源氏の心中。
【げにもの思ひ知らむ人にこそ見せまほしけれ】- 語り手の批評。『集成』「前の「あたら夜の」という入道の誘いを受けて「げに」という」。
|
| 3.2.8 |
|
近くの几帳の紐に触れて、箏の琴が音をたてたのも、感じが取り繕ってなく、くつろいだ普段のまま琴を弄んでいた様子が想像されて、興趣あるので、
|
几帳の紐が動いて触れた時に、十三絃の琴の緒が鳴った。それによってさっきまで琴などを弾いていた若い女の美しい室内の生活ぶりが想像されて、源氏はますます熱していく。
|
【近き几帳の紐に、箏の琴の弾き鳴らされたるも】- 『完訳』は「几帳の紐が、女君の身動きで、箏の絃にふれ音をたてる。彼女の心の琴線がふれる感じである」と注す。
【けはひしどけなく、うちとけながら】- 『集成』は「取り片付けた様子もなく、くつろいだふだんのまま」。『完訳』は「「けはひしどけなく」は、上からは述語、下へは連用修飾で続く」「取り散らかしたままうちくつろいだ格好で」と注す。
|
| 3.2.9 |
|
「この、噂に聞いていた琴までも聴かせてくれないのですか」
|
「今音が少ししたようですね。琴だけでも私に聞かせてくださいませんか」
|
【この、聞きならしたる琴をさへや】- 源氏の詞。「聞きならす」は入道から常日頃聞かされていたという意。「たる」完了の助動詞、存続。「こと」は「事」と「琴」の掛詞、言葉遊び。琴が巧みだという話と琴そのもの。「さへ」副助詞、言葉はもちろん琴までもの意。「や」係助詞、疑問。下に「聞かせたまはぬ」などの語句が省略。最後まで明言しないところに余意余情が生まれる。
|
| 3.2.10 |
など、よろづにのたまふ。
|
などと、いろいろとおっしゃる。
|
とも源氏は言った。
|
|
| 3.2.11 |
|
「睦言を語り合える相手が欲しいものです
この辛い世の夢がいくらかでも覚めやしないかと」
|
むつ言を語りあはせん人もがな
うき世の夢もなかば覚むやと
|
【むつごとを語りあはせむ人もがな--憂き世の夢もなかば覚むやと】- 源氏の贈歌。「憂き世の夢」は現実世界の流浪の身をいう。『集成』は「「むつごと」「夢」は縁語」。『完訳』は「「うき世の夢」は、現在の流離の身を夢ととらえた表現。あなたと親しく語り合えば、その夢から覚められる、と親交を訴えた歌。なお逢瀬の歌の「夢」は、情交を暗示する」と注す。
|
| 3.2.12 |
|
「闇の夜にそのまま迷っておりますわたしには
どちらが夢か現実か区別してお話し相手になれましょう」
|
明けぬ夜にやがてまどへる心には
何れを夢と分きて語らん
|
【明けぬ夜にやがて惑へる心には--いづれを夢とわきて語らむ】- 明石の君の返歌。源氏の「夢」を受けて、それを「明けぬ夜に」「惑へる」を自分の「夢」として返す。
|
| 3.2.13 |
|
かすかな感じは、伊勢の御息所にとてもよく似ていた。
何も知らずにくつろいでいたところを、こう意外なお出ましとなったので、たいそう困って、近くにある曹司の中に入って、どのように戸締りしたものか、固いのだが、無理して開けようとはなさらない様子である。
けれども、
|
前のは源氏の歌で、あとのは女の答えたものである。ほのかに言う様子は伊勢の御息所にそっくり似た人であった。源氏がそこへはいって来ようなどとは娘の予期しなかったことであったから、それが突然なことでもあって、娘は立って近い一つの部屋へはいってしまった。そしてどうしたのか、戸はまたあけられないようにしてしまった。源氏はしいてはいろうとする気にもなっていなかった。しかし源氏が躊躇したのはほんの一瞬間のことで、結局は行く所まで行ってしまったわけである。
|
【ほのかなるけはひ】- 『集成』は「ほのかに言う様子」。『完訳』は「暗闇の中で想像される様子」と注す。
【かうものおぼえぬに】- 「に」接続助詞、順接、原因理由。このように意外な事なので。
【いとわりなくて】- 『完訳』は「源氏の直接行動を無我夢中の女の心に即していう表現」と注す。
【いかで固めけるにか】- 「いかで」副詞、方法、どのように。「に」完了の助動詞。「か」係助詞、疑問。源氏の心中、また語り手の疑問。どのように鎖してしまったのか。
【されど、さのみもいかでかあらむ】- 「さ」明石の君が曹司の内側から固く閉めたことさす。「のみ」副助詞、限定・強調。そうとばかり。「も」係助詞、強調のニュアンス。「いかでかは」連語(「いかで」副詞+「か」係助詞+「は」係助詞)、反語。やや強調のニュアンス。「む」推量の助動詞、推量。語り手の事態の推量。どうしていつまでそうしてばかりいられようか、ついには開けてしまった。
|
| 3.2.14 |
|
人柄は、とても上品で、すらりとして、気後れするような感じがする。
このような無理に結んだ契りをお思いになるにつけても、ひとしおいとしい思いが増すのである。
情愛が、逢ってますます思いが募るのであろう、いつもは嫌でたまらない秋の夜の長さも、すぐに明けてしまった気持ちがするので、「人に知られまい」とお思いになると、気がせかれて、心をこめたお言葉を残して、お立ちになった。
|
女はやや背が高くて、気高い様子の受け取れる人であった。源氏自身の内にたいした衝動も受けていないでこうなったことも、前生の因縁であろうと思うと、そのことで愛が湧いてくるように思われた。源氏から見て近まさりのした恋と言ってよいのである。平生は苦しくばかり思われる秋の長夜もすぐ明けていく気がした。人に知らせたくないと思う心から、誠意のある約束をした源氏は朝にならぬうちに帰った。
|
【人ざま、いとあてに、そびえて、心恥づかしきけはひぞしたる】- 閨房の中の明石の君の容姿や態度。「ぞ」係助詞、「たる」完了の助動詞、存続、連体形、係結び、強調のニュアンス。
【かうあながちなりける契りを】- 源氏の心に即して語る表現。『集成』は「こんな結ばれるはずもない二人がむすばれたという深い縁をお思いになるにつけても」。『完訳』は「こうして無理強いして一方的に結んだ二人の仲をお思いになるにつけても」と訳す。
【浅からずあはれなり】- 「なり」断定の助動詞、語り手の批評。御心さしのちかまさりするなるへし-「なる」断定の助動詞、「べし」推量の助動詞。源氏の心を語り手が推量した表現。集成「草子地」。集成、句点で文を完結。完訳、読点で文を下に続ける。
【常は厭はしき夜の長さも、とく明けぬる心地すれば】- 季節は秋(八月十三日)、夜が長く感じられるころ。
【人に知られじ】- 源氏の心中。
|
| 3.2.15 |
|
後朝のお手紙、こっそりと今日はある。
つまらない良心の呵責であるよ。
こちらでも、このようなことを何とか世間に知られまいと隠して、御使者を仰々しくもてなさないのを、残念に思った。
|
その翌日は手紙を送るのに以前よりも人目がはばかられる気もした。源氏の心の鬼からである。入道のほうでも公然のことにはしたくなくて、結婚の第二日の使いも、そのこととして派手に扱うようなことはしなかった。こんなことにも娘の自尊心は傷つけられたようである。
|
【御文、いと忍びてぞ今日はある】- 「御文」は後朝の文。「は」係助詞、区別、強調のニュアンス。『集成』は「今までの文通は大っぴらだったのである」と注す。
【あいなき御心の鬼なりや】- 「あいなき」形容詞。「なり」断定の助動詞。「や」間投助詞、詠嘆。語り手の批評。『集成』は「草子地。源氏としては京への聞えを憚るのである」。『完訳』は「語り手の評。紫の上など気にせずともよい、無用の良心の呵責」と注す。
【ここにも】- 明石入道方をさす。
【かかることいかで漏らさじ】- 明石入道の心中。娘と源氏の結婚をさす。源氏の意向に従って、内密にする。
【ことことしうも】- 「コトコトシイ」(日葡辞書)。
【胸いたく思へり】- 『集成』は「入道は残念に思っている。結婚第一夜の後朝の文の使いは盛大にもてなすしきたりであった」。
|
| 3.2.16 |
|
こうして後は、こっそりと時々お通いになる。
「距離も少し離れているので、自然と口さがない海人の子どもがいるかも知れない」とおためらいになる途絶えを、「やはり、思っていたとおりだわ」と嘆いているので、「なるほど、どうなることやら」と、入道も極楽往生の願いも忘れて、ただ君のお通いを待つことばかりである。
今さら心を乱すのも、とても気の毒なことである。
|
それ以後時々源氏は通って行った。少し道程のある所でもあったから、土地の者の目につくことも思って間を置くのであるが、女のほうではあらかじめ愁えていたことが事実になったように取って、煩悶しているのを見ては親の入道も不安になって、極楽の願いも忘れたように、仏勤めは怠けて、源氏の君の通って来ることを大事だと考えている。入道からいえば事が成就しているのであるが、その境地で新しく物思いをしているのが憐れであった。
|
【ほどもすこし離れたるに】- 以下「立ちまじらむ」まで、源氏の心中。「に」接続助詞、順接、原因理由。
【思し憚るほどを】- 「程」名詞、時間・程度を表す。具体的には途絶え。
【さればよ】- 明石の君の心中。出来心を想像していた。
【思ひ嘆きたるを】- 「を」、『集成』は「悲しむのを」と格助詞に解し、『完訳』は「嘆いているので」と接続助詞、順接に解す。
【げに、いかならむ】- 入道の心中。『集成』は「げに」を、本当に、全くの意に解し、また「いかならむ」を事態の成り行きを心配する意に解し、「ほんとにどうなることかと」と訳す。『完訳』は「げに」を娘の気持ちを受けて、なるほど、娘が嘆いているように、の意に解し、「いかならむ」を源氏の真意を推測する意に解し、「いかにも、源氏のお気持ちはどうなのだろうと」と訳す。いずれにも解せる両義を含んだ表現。
【この御けしきを待つことにはす】- 「御けしき」は源氏の通って来ることをさす。「に」断定の助動詞。「は」係助詞、強調のニュアンス。
【今さらに心を乱るも、いといとほしげなり】- 語り手の入道に対する同情。
|
|
第三段 紫の君に手紙
|
| 3.3.1 |
|
二条院の君が、風の便りにも漏れお聞きなさるようなことは、「冗談にもせよ、隠しだてをしたのだと、お疎み申されるのは、申し訳なくも恥ずかしいことだ」とお思いになるのも、あまりなご愛情の深さというものであろう。
「こういう方面のことは、穏和な方とはいえ、気になさってお恨みになった折々、どうして、つまらない忍び歩きにつけても、そのようなつらい思いをおさせ申したのだろうか」などと、昔を今に取り戻したく、女の有様を御覧になるにつけても、恋しく思う気持ちが慰めようがないので、いつもよりお手紙を心こめてお書きになって、
|
二条の院の女王にこの噂が伝わっては、恋愛問題では嫉妬する価値のあることでないとわかっていても、秘密にしておく自分の態度を恨めしがられては苦しくもあり、気恥ずかしくもあると思っていた源氏が紫夫人をどれほど愛しているかはこれだけでも想像することができるのである。女王も源氏を愛することの深いだけ、他の愛人との関係に不快な色を見せたそのおりおりのことを今思い出して、なぜつまらぬことで恨めしい心にさせたかと、取り返したいくらいにそれを後悔している源氏なのである。新しい恋人は得ても女王へ焦れている心は慰められるものでもなかったから、平生よりもまた情けのこもった手紙を源氏は京へ書いたのであるが、奥に今度のことを書いた。
|
【二条の君】- 紫の君。
【たはぶれにても】- 以下「恥づかしう」まで、源氏の心中。自然と心中文に移り、再び引用句がなく地の文に流れる。
【思ひ疎まれたてまつらむ】- 大島本は「たてまつらん」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「たてまつらむは」と「は」を補訂する。「れ」受身の助動詞、「たてまつら」謙譲の補助動詞。源氏が紫の君から疎まれ申す、と自卑した表現。「む」推量の助動詞、仮定・婉曲のニュアンス。『集成』は「不愉快な思いをおさせ申すことになるのは」、「れ」尊敬の助動詞に解し、紫の君を主体にした解釈。『完訳』は「お疎まれ申すようなことがあっては」、「れ」受身の助動詞に解し、源氏自身を主体にした解釈。
【心苦しう恥づかしう」思さるるも】- 「心苦し」は紫の君に対する源氏の気持ち、「恥づかし」は源氏自身に対する気持ち。
【あながちなる御心ざしのほどなりかし】- 語り手の源氏の紫の君を思う気持ちの厚いことについての批評。
【かかる方のことをば】- 以下「思はれたてまつりけむ」まで、源氏の心中。「かかる方のこと」とは源氏の浮気沙汰をいう。
【さすがに】- 温厚な紫の君とはいえというニュアンス。
【怨みたまへりし折々】- 「し」過去の助動詞。『完訳』は「紫の上の嫉妬の事実は、これまで具体的には語られていない」と注す。ここが初見。紫の君の人間性を増幅。
【あやなきすさびごとにつけても】- 過去の浮気沙汰をさす。
【さ思はれたてまつりけむ】- 「さ」、『完訳』「つらい思い」。嫉妬ともとれる。「れ」尊敬の助動詞と解せば、辛い思い。受身の助動詞と解せば、嫉妬されること。前の「思ひ疎まれたてまつらむ」と同じ表現。
【人のありさまを見たまふにつけても、恋しさの慰む方なければ】- 明石の君と逢うにつけ紫の君を恋しく思われるの意。源氏の心情。
|
| 3.3.2 |
「まことや、我ながら心より外なるなほざりごとにて、疎まれたてまつりし節々を、思ひ出づるさへ胸いたきに、また、あやしうものはかなき夢をこそ見はべりしか。かう聞こゆる問はず語りに、隔てなき心のほどは思し合はせよ。『誓ひしことも』」など書きて、 |
「ところで、そうそう、自分ながら心にもない出来心を起こして、お恨まれ申した時々のことを、思い出すのさえ胸が痛くなりますのに、またしても、変なつまらない夢を見たのです。
このように申し上げます問わず語りに、隠しだてしない胸の中だけはご理解ください。
『誓ひしことも』」などと書いて、
|
私は過去の自分のしたことではあるが、あなたを不快にさせたつまらぬいろいろな事件を思い出しては胸が苦しくなるのですが、それだのにまたここでよけいな夢を一つ見ました。この告白でどれだけあなたに隔てのない心を持っているかを思ってみてください。「誓ひしことも」(忘れじと誓ひしことをあやまたば三笠の山の神もことわれ)という歌のように私は信じています。と書いて、また、
|
【まことや】- 以下「誓ひし事ことも」まで、源氏の紫の君への手紙。「心より外なる」「なほざりごと」「疎まれ」「思ひ出づるさへ」と続け「また」「あやしうものはかなき夢をこそ見はべりしか」と明石の地の女との情交をほのめかす。
【誓ひしことも】- 「忘れじと誓ひし事を過たず三笠の山の神もことわれ」(出典未詳)を踏まえる。
|
| 3.3.3 |
|
「何事につけても、
|
何事も、
|
【何事につけても】- 手紙文が「しほしほと」の和歌に係る。
|
| 3.3.4 |
|
あなたのことが思い出されて、
さめざめと泣けてしまいますかりそめの恋は海人の
|
しほしほと先づぞ泣かるるかりそめの
みるめは海人のすさびなれども
|
【しほしほとまづぞ泣かるるかりそめの--みるめは海人のすさびなれども】- 源氏の紫の君への贈歌。掛詞、「しほしほと」(擬態語)と「塩」、「見る目」(女に逢う)と「海松布」(海草)。縁語、「塩」「刈り」「海松布」「海人」。大変に技巧的な和歌。他の女と逢った後ろめたさの自己韜晦がある。
|
| 3.3.5 |
|
とあるお返事、何のこだわりもなくかわいらしげに書いて、
|
と書き添えた手紙であった。京の返事は無邪気な可憐なものであったが、それも奥に源氏の告白による感想が書かれてあった。
|
【とある御返り】- 間髪を入れず一続きに続ける。
【らうたげに書きて】- 大島本は「かきて・はてに(はてに#)」と「はてに」を抹消している。『集成』『新大系』はその抹消に従う。『古典セレクション』は諸本に従って「書きて、はてに」とする。
|
| 3.3.6 |
|
「隠しきれずに打ち明けてくださった夢のお話につけても、思い当たることが多くございますが、
|
お言いにならないではいらっしゃれないほど現在のお心を占めていますことをお報らせくださいまして承知いたしましたが、私には新しい恋人に傾倒していらっしゃる御様子が昔のいろいろな場合と思い合わせて想像することもできます。
|
【忍びかねたる】- 以下「波は越えじものぞと」まで、紫の君の返信。
【御夢語り】- 源氏の「問はず語り」の「夢を見はべりし」を「夢語り」とし、源氏の告白を合点する。
【思ひ合はせらるること多かるを】- これも次の和歌の「うらなくも」に係る。手紙の地の文から和歌へ直接続く表現。源氏と同じ手法を用いる。「を」接続助詞は、順接・逆接、いづれにも解せる表現。
|
| 3.3.7 |
|
固い約束をしましたので、
何の疑いもなく信じ
|
うらなくも思ひけるかな契りしを
松より波は越えじものぞと
|
【うらなくも思ひけるかな契りしを--松より波は越えじものぞと】- 紫の君の返歌。「君をおきてあだし心をわが持たば末の松山波も越えなむ」(古今集、一〇九三、陸奥歌)。「契りきなかたみに袖をしぼりつつ末の松山波越さじとは」(後拾遺集恋四、七七〇、清原元輔)などを踏まえる。「うらなく」(思慮なくの意)に「浦」を響かす。「浦」「波」縁語。
|
| 3.3.8 |
|
鷹揚な書きぶりながら、お恨みをこめてほのめかしていらっしゃるのを、とてもしみじみと思われ、下に置くこともできず御覧になって、その後は、久しい間忍びのお通いもなさらない。
|
おおようではあるがくやしいと思う心も確かにかすめて書かれたものであるのを、源氏は哀れに思った。この手紙を手から離しがたくじっとながめていた。この当座幾日は山手の家へ行く気もしなかった。
|
【名残久しう、忍びの旅寝もしたまはず】- その後、明石の君を訪うことが久しくなくなったの意。
|
|
第四段 明石の君の嘆き
|
| 3.4.1 |
|
女は、予想通りの結果になったので、今こそほんとうに身を海に投げ入れてしまいたい心地がする。
|
女は長い途絶えを見て、この予感はすでに初めからあったことであると歎いて、この親子の間では最後には海へ身を投げればよいという言葉が以前によく言われたものであるが、いよいよそうしたいほどつらく思った。
|
【女、思ひしもしるきに】- 明石の君の嘆き。女という呼称に変わる。
【今ぞまことに身も投げつべき心地する】- 明石の君の深い絶望感。
|
| 3.4.2 |
|
「老い先短い両親だけを頼りにして、いつになったら人並みの境遇になれる身の上とは思っていなかったが、ただとりとめもなく過ごしてきた年月の間は、何事に心を悩ましたろうか、このようにひどく物思いのする結婚生活であったのだ」
|
年取った親たちだけをたよりにして、いつ人並みの娘のような幸福が得られるものとも知れなかった過去は、今に比べて懊悩の片はしも知らない自分だった。世の中のことはこんなに苦しいものなのであろうか、恋愛も結婚も処女の時に考えていたより悲しいものであると、
|
【行く末短げなる親ばかりを】- 以下「世にこそありけれ」まで、明石の君の心中。
【人並々になるべき身と】- 大島本は「身と」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「身とは」と「は」を補訂する。
【そこはかとなくて過ぐしつる年月】- 明石の君の娘時代。
【何ごとをか心をも悩ましけむ】- 「か」係助詞、「けむ」過去推量の助動詞、連体形、係結び。反語表現。読点で下文に続く。
【世にこそありけれ】- 「こそ」係助詞、「けれ」過去の助動詞、詠嘆、已然形、係結び。強調のニュアンス。
|
| 3.4.3 |
|
と、以前から想像していた以上に、何事につけ悲しいけれど、穏やかに振る舞って、憎らしげのない態度でお会い申し上げる。
|
女は心に思いながらも源氏には平静なふうを見せて、不快を買うような言動もしない。
|
【なだらかにもてなして、憎からぬさまに見えたてまつる】- 明石の君のたしなみのある態度。
|
| 3.4.4 |
|
いとしいと月日がたつにつれてますますお思いになっていくが、れっきとした方が、いつかいつかと帰りを待って年月を送っていられるのが、一方ならずご心配なさっていらっしゃるだろうことが、とても気の毒なので、独り寝がちにお過ごしになる。
|
源氏の愛は月日とともに深くなっていくのであるが、最愛の夫人が一人京に残っていて、今の女の関係をいろいろに想像すれば恨めしい心が動くことであろうと思われる苦しさから、浜の館のほうで一人寝をする夜のほうが多かった。
|
【あはれとは月日に添へて思しませど】- 主語は源氏。明石の君に対し月日とともに愛情が増してゆく。「ど」接続助詞、逆接の確定条件。
【やむごとなき方の】- 都の紫の君をさす。
【年月を過ぐしたまひ】- 大島本は「すくし給ひ(△&ひ)」と元の文字(判読不明)の上に重ねて「ひ」と書く。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「過ぐしたまふが」と校訂する。
【ただならずうち思ひおこせたまふらむが】- 『集成』は「心おだやかでなくこちらのことをお思いであろうが」。『完訳』は「ひとかたならず自分に思いを寄せていらっしゃるか」と訳す。「らむ」視界外推量、源氏が都の紫の君を想像しているニュアンス。
|
| 3.4.5 |
|
絵をいろいろとお描きになって、思うことを書きつけて、返歌を聞かれるようにという趣向にお作りなった。
見る人の心にしみ入るような絵の様子である。
どうして、お心が通じあっているのであろうか、二条院の君も、悲しい気持ちが紛れることなくお思いになる時々は、同じように絵をたくさんお描きになって、そのままご自分の有様を、日記のようにお書きになっていた。
どうなって行かれるお二方の身の上であろうか。
|
源氏はいろいろに絵を描いて、その時々の心を文章にしてつけていった。京の人に訴える気持ちで描いているのである。女王の返辞がこの絵巻から得られる期待で作られているのであった。感傷的な文学および絵画としてすぐれた作品である。どうして心が通じたのか二条の院の女王もものの身にしむ悲しい時々に、同じようにいろいろの絵を描いていた。そしてそれに自身の生活を日記のようにして書いていた。この二つの絵巻の内容は興味の多いものに違いない。
|
【絵をさまざま描き集めて、思ふことどもを書きつけ、返りこと聞くべきさまにしなしたまへり】- 絵の余白に和歌を書きつけ、さらにその絵や歌に対する紫の君の返歌も載せるべく余白を残した体裁。
【見む人の心に染みぬべきもののさまなり】- 語り手の批評。
【いかでか、空に通ふ御心ならむ】- 語り手の推量の挿入句。『集成』は「どうしてお話し合いもないのにお互いのお気持が通じ合うのであろうか」と注す。「雲居にもかよふ心のおくれねば別ると人に見ゆばかりなり」(古今集離別、三七八、清原深養父)。
【同じやうに絵を描き集めたまひつつ、やがて我が御ありさま、日記のやうに書きたまへり】- 紫の君も源氏同様に、絵の余白に歌日記のような体裁に書きつけた。
【いかなるべき御さまどもにかあらむ】- 語り手の推量。『集成』は「草子地。どんな二人の身の上が絵日記に書かれてゆくのだろうか、の意」。『完訳』は「語り手の、今後の源氏と紫の上に期待を抱かせる言辞」と注す。
|
|
第四章 明石の君の物語 明石の浦の別れの秋の物語
|
|
第一段 七月二十日過ぎ、帰京の宣旨下る
|
| 4.1.1 |
|
年が変わった。
主上におかせられては御不例のことがあって、世の中ではいろいろと取り沙汰する。
今上の御子は、右大臣の娘で、承香殿の女御がお生みになった男御子がいらっしゃるが、二歳におなりなので、たいそう幼い。
東宮に御譲位申されることであろう。
朝廷の御後見をし、政権を担当すべき人をお考え廻らすと、この源氏の君がこのように沈んでいらっしゃること、まことに惜しく不都合なことなので、ついに皇太后の御諌言にも背いて、御赦免になられる評定が下された。
|
春になったが帝に御悩があって世間も静かでない。当帝の御子は右大臣の女の承香殿の女御の腹に皇子があった。それはやっとお二つの方であったから当然東宮へ御位はお譲りになるのであるが、朝廷の御後見をして政務を総括的に見る人物にだれを決めてよいかと帝はお考えになった末、源氏の君を不運の中に沈淪させておいて、起用しないことは国家の損失であると思召して、太后が御反対になったにもかかわらず赦免の御沙汰が、源氏へ下ることになった。
|
【年変はりぬ】- 源氏二十八歳。
【内裏に御薬のことありて】- 帝の病気の事を間接的婉曲に表現。
【世の中さまざまにののしる】- 世間でいろいろと取り沙汰する意。
【当代の御子は】- 『集成』は「以下「ゆづりきこえたまはめ」までは世間の取り沙汰を書く趣」。世間の噂から帝の心中そして地の文へと文章が推移していく書き方。
【右大臣の女、承香殿の女御の御腹に男御子生まれたまへる、二つになりたまへば】- 後に登場する鬚黒大将の父。承香殿の女御は「賢木」巻に初出。男御子、二歳。
【春宮にこそは譲りきこえたまはめ】- 東宮、後の冷泉院。現在十歳、まだ元服前。『集成』は、ここまで世間の取り沙汰とする。『完訳』は「帝は東宮への譲位を考慮」と注し、「当然御位を東宮にお譲り申しあげることになるのであろうが」、読点で下文に続ける。
【后の御諌めを】- 大島本は「御いさめ越」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「御諌めをも」と「も」を補訂する。
【赦されたまふべき定め出で来ぬ】- 主語は源氏。「れ」受身の助動詞。
|
| 4.1.2 |
|
去年から、皇太后も御物の怪をお悩みになり、さまざまな前兆ががしきりにあり、世間も騒がしいので、厳重な御物忌みなどをなさった効果があってか、悪くなくおいであそばした御眼病までもが、この頃重くおなりあそばして、何となく心細く思わずにはいらっしゃれなかったので、七月二十日過ぎに、再度重ねて、帰京なさるよう宣旨が下る。
|
去年から太后も物怪のために病んでおいでになり、そのほか天の諭しめいたことがしきりに起こることでもあったし、祈祷と御精進で一時およろしかった御眼疾もまたこのごろお悪くばかりなっていくことに心細く思召して、七月二十幾日に再度御沙汰があって、京へ帰ることを源氏は命ぜられた。
|
【去年より、后も御もののけ悩みたまひ】- 弘徽殿皇太后の病気は前に「大宮もそこはかとなうわづらひたまひて」とあった。
【いみじき御つつしみどもをしたまふしるしにや】- 「に」断定の助動詞。「や」係助詞、疑問。語り手の疑問の挿入句。下の「よろしうおはしましける」に係る。
【七月二十余日のほどに、また重ねて、京へ帰りたまふべき宣旨下る】- 二度めの召還という書き方。物語は「年変りぬ」から「七月二十余日」までいっきにとぶ。
|
| 4.1.3 |
つひのことと思ひしかど、世の常なきにつけても、「いかになり果つべきにか」と嘆きたまふを、かうにはかなれば、うれしきに添へても、また、この浦を今はと思ひ離れむことを思し嘆くに、入道、さるべきことと思ひながら、うち聞くより胸ふたがりておぼゆれど、「思ひのごと栄えたまはばこそは、我が思ひの叶ふにはあらめ」など、思ひ直す。 |
いつかはこうなることと思っていたが、世の中の定めないことにつけても、「どういうことになってしまうのだろうか」とお嘆きになるが、このように急なので、嬉しいと思うとともに、また一方で、この浦を今を限りと離れることをお嘆き悲しみになるが、入道は、当然そうなることとは思いながら、聞くなり胸のつぶれる気持ちがするが、「思い通りにお栄えになってこそ、自分の願いも叶うことなのだ」などと、思い直す。
|
いずれはそうなることと源氏も期していたのではあるが、無常の人生であるから、それがまたどんな変わったことになるかもしれないと不安がないでもなかったのに、にわかな宣旨で帰洛のことの決まったのはうれしいことではあったが、明石の浦を捨てて出ねばならぬことは相当に源氏を苦しませた。入道も当然であると思いながらも、胸に蓋がされたほど悲しい気持ちもするのであったが、源氏が都合よく栄えねば自分のかねての理想は実現されないのであるからと思い直した。
|
【つひのことと思ひしかど】- 以下「いかになりはつべきにか」まで、源氏の心中。前半は間接的に叙述。「いかに成はつへきにか」の部分が直接叙述。
【かうにはかなれば】- 三年に満たずに赦免されたことをいう。
【さるべきこと】- 源氏の赦免と復帰の予想。
【思ひのごと】- 以下「叶ふにはあらめ」まで、明石入道の心中。
|
|
第二段 明石の君の懐妊
|
| 4.2.1 |
|
そのころは、毎夜お通いになってお語らいになる。
六月頃から懐妊の兆候が現れて苦しんでいるのであった。
このようにお別れなさらねばならない時なので、あいにくご愛情もいや増すというのであろうか、以前よりもいとしくお思いになって、「不思議と物思いせずにはいられない、わが身であることよ」とお悩みになる。
|
その時分は毎夜山手の家へ通う源氏であった。今年の六月ごろから女は妊娠していた。別離の近づくことによってあやにくなと言ってもよいように源氏は女を深く好きになった。どこまでも恋の苦から離れられない自分なのであろうと源氏は煩悶していた。
|
【六月ばかりより心苦しきけしきありて悩みけり】- 妊娠の悪阻をいう。
【あやにくなるにやありけむ】- 語り手の挿入句。『集成』は「源氏はあいにくと愛情が増すのであろうか」。『完訳』は「語り手の感想。間近な離別が、かえって執着をつのらせる。それが「あやにく」(皮肉な)」と注し「あいにくと執着がまさるのであろうか」と注す。
【あやしうもの思ふべき身にもありけるかな】- 源氏の心中。
|
| 4.2.2 |
|
女は、さらにいうまでもなく思い沈んでいる。
まことに無理もないことであるよ。
思いもかけない悲しい旅路にお立ちになったが、「けっきょくは帰京するであろう」と、一方ではお慰めになっていた。
|
女はもとより思い乱れていた。もっともなことである。思いがけぬ旅に京は捨ててもまた帰る日のないことなどは源氏の思わなかったことであった。慰める所がそれにはあった。
|
【いとことわりなりや】- 語り手の批評。『完訳』は「語り手の、明石の君の苦悩は当然であるとする言辞」と注す。
【つひには行きめぐり来なむ】- 源氏の心中。「な」完了の助動詞、確述。「む」推量の助動詞、強調のニュアンス。きっといつの日にかは帰れよう。
|
| 4.2.3 |
|
今度は嬉しい都へのご出発であるが、「二度とここに来るようなことはあるまい」とお思いになると、しみじみと感慨無量である。
|
今度は幸福な都へ帰るのであって、この土地との縁はこれで終わると見ねばならないと思うと、源氏は物哀れでならなかった。
|
【御出で立ちの】- 「の」格助詞、提示。--だが、それは、の意。同例、「相おはします人の、そなたにて見れば」(桐壺)、「煩ひ給ふさまの、そこはかとなく」(柏木)。
【またやは帰り見るべき】- 「やは」係助詞、反語。「べき」推量の助動詞、連体形に係る。源氏の心中。
|
| 4.2.4 |
さぶらふ人びと、ほどほどにつけてはよろこび思ふ。京よりも御迎へに人びと参り、心地よげなるを、主人の入道、涙にくれて、月も立ちぬ。 |
お供の人々は、それぞれ身分に応じて喜んでいる。
京からもお迎えに人々が参り、愉快そうにしているが、主人の入道、涙にくれているうちに、月が替わった。
|
侍臣たちにも幸運は分かたれていて、だれもおどる心を持っていた。京の迎えの人たちもその日からすぐに下って来た者が多数にあって、それらも皆人生が楽しくばかり思われるふうであるのに、主人の入道だけは泣いてばかりいた。そして七月が八月になった。
|
【涙にくれて、月も立ちぬ】- 「くれて」は涙に「暮れて」と月が「暮れて」の意を掛けた表現。季節は中秋の八月となる。
|
| 4.2.5 |
|
季節までもしみじみとした空の様子なので、「どうして、自分から求めて今も昔も、埒もない恋のために憂き身をやつすのだろう」と、さまざまにお思い悩んでいられるのを、事情を知っている人々は、
|
色の身にしむ秋の空をながめて、自分は今も昔も恋愛のために絶えない苦を負わされる、思い死にもしなければならないようにと源氏は思い悶えていた。女との関係を知っている者は、
|
【なぞや、心づから】- 以下「身をはふらかすらむ」まで、源氏の心中。
【心知れる人びとは】- 源氏と明石の君の関係を知る供人。
|
| 4.2.6 |
|
「ああ、困った方だ。いつものお癖だ」
|
「反感が起こるよ。例のお癖だね」
|
【あな憎、例の御癖ぞ】- 供人の詞。「帚木」巻に「まれには、あながちに引き違へ心尽くしなることを、御心に思しとどむる癖なむ、あやにくにて」とあった癖。
|
| 4.2.7 |
|
と拝、
|
と言って、困ったことだと思っていた。
|
【見たてまつりむつかるめり】- 「めり」推量の助動詞、視界内推量。語り手が眼前に見て供人たちの心中を推量しているニュアンス。臨場感ある描写。
|
| 4.2.8 |
「月ごろは、つゆ人にけしき見せず、時々はひ紛れなどしたまへるつれなさを」 |
「ここ数月来、全然、誰にもそぶりもお見せにならず、時々人目を忍んでお通いになっていらっしゃった冷淡さだったのに」
|
源氏が長い間この関係を秘密にしていて、人目を紛らして通っていたことが近ごろになって人々にわかったのであったから、
|
【月ごろは】- 以下「人の心づくしにか」まで、供人の詞。
|
| 4.2.9 |
|
「最近は、あいにくと、かえって、女が嘆きを増すことであろうに」
|
「女からいえば一生の物思いを背負い込んだようなものだ」
|
【人の心づくしにか】- 大島本は「心つくしにか」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「心づくしに」と「か」を削除する。
|
| 4.2.10 |
と、つきしろふ。少納言、しるべして聞こえ出でし初めのことなど、ささめきあへるを、ただならず思へり。 |
と、互いに陰口をたたき合う。
源少納言は、ご紹介申した当初の頃のことなどを、ささやき合っているのを、おもしろからず思っていた。
|
とも言ったりした。少納言がよく話していた女であるともその連中が言っていた時、良清は少しくやしかった。
|
【ただならず思へり】- 主語は源少納言良清。
|
|
第三段 離別間近の日
|
| 4.3.1 |
|
明後日ほどになって、いつものようにあまり夜が更けないうちにお越しになった。
まだはっきりと御覧になっていない容貌などを、「とても風情があり、気高い様子をしていて、目を見張るような美しさだ」と、見捨てにくく残念にお思いになる。
「しかるべき手筈を整えて迎えよう」とお考えになった。
そのように約束してお慰めになる。
|
出発が明後日に近づいた夜、いつもよりは早く山手の家へ源氏は出かけた。まだはっきりとは今日までよく見なかった女は、貴女らしい気高い様子が見えて、この身分にふさわしくない端麗さが備わっていた。捨てて行きがたい気がして、源氏はなんらかの形式で京へ迎えようという気になったのであった。そんなふうに言って女を慰めていた。
|
【明後日ばかりになりて】- 源氏と明石の君の離別が目前となる。
【いとよしよししう】- 以下「ありけるかな」まで、源氏の明石の君を明るい中で初めて見た感想。
【さるべきさまにして迎へむ】- 源氏の心中。『集成』は「しかるべき扱いにして都に迎えようという気になられた。身分が身分なので処遇の問題は微妙である」と注す。
【さやうにぞ語らひ慰めたまふ】- 「さやう」は「さるべきさまにして迎へてむ」をさす。明石の君にも口に出して約束。
|
| 4.3.2 |
|
男のお顔だち、お姿は、改めていうまでもない。
長い間のご勤行にひどく面痩せなさっていらっしゃるのが、いいようもなく立派なご様子で、痛々しいご様子に涙ぐみながら、しみじみと固いお約束なさるのは、「ただ一時の逢瀬でも、幸せと思って、諦めてもいいではないか」とまで思われもするが、ご立派さにつけて、わが身のほどを思うと、悲しみは尽きない。
波の音、秋の風の中では、やはり響きは格別である。
塩焼く煙が、かすかにたなびいて、何もかもが悲しい所の様子である。
|
女からもつくづくと源氏の見られるのも今夜がはじめてであった。長い苦労のあとは源氏の顔に痩せが見えるのであるが、それがまた言いようもなく艶であった。あふれるような愛を持って、涙ぐみながら将来の約束を女にする源氏を見ては、これだけの幸福をうければもうこの上を願わないであきらめることもできるはずであると思われるのであるが、女は源氏が美しければ美しいだけ自身の価値の低さが思われて悲しいのであった。秋風の中で聞く時にことに寂しい波の音がする。塩を焼く煙がうっすり空の前に浮かんでいて、感傷的にならざるをえない風景がそこにはあった。
|
【心苦しげなるけしきに】- 源氏の態度をいう。
【ただかばかりを、幸ひにても、などか止まざらむ】- 明石の君の心中。「などか」連語(「など」副詞+「か」係助詞)、反語。「ざら」打消の助動詞、「む」推量の助動詞、意志。どうしてあきらめられないだろうか、あきらめてもいいではないか、という自問自答のニュアンス。
【見ゆめれど】- 「めれ」推量の助動詞、視界内推量。明石の君の推量。
【波の声、秋の風には、なほ響きことなり。塩焼く煙かすかにたなびきて、とりあつめたる所のさまなり】- 明石の浜の秋の季節描写。海岸の物寂しい風景に源氏と明石の君の別れを語る。
|
| 4.3.3 |
|
「今はいったんお別れしますが、
藻塩焼く煙のように上京したら一
|
このたびは立ち別るとも藻塩焼く
煙は同じ方になびかん
|
【このたびは立ち別るとも藻塩焼く--煙は同じ方になびかむ】- 源氏の贈歌。「たひ」に「旅」と「度」を掛ける。「立ち」と「煙」が縁語。一時は別れ別れになるがやがて都に迎えようの意。
|
| 4.3.4 |
とのたまへば、
|
とお詠みになると、
|
と源氏が言うと、
|
|
| 4.3.5 |
|
「何とも悲しい気持ちでいっぱいですが
今は申しても甲斐のないことですから、
|
かきつめて海人の焼く藻の思ひにも
今はかひなき恨みだにせじ
|
【かきつめて海人のたく藻の思ひにも--今はかひなき恨みだにせじ】- 明石の君の返歌。源氏の「焼く」「煙」を受けて「火」と返す。「ものおもひ」に「物思ひ」と「藻」「火」、「かひなき」に「効」と「貝」、「うらみ」に「恨み」と「浦」を響かせる。恨みさえもしませんの意。
|
| 4.3.6 |
|
せつなげに涙ぐんで、言葉少なではあるが、しかるべきお返事などは心をこめて申し上げる。
あの、いつもお聴きになりたがっていらした琴の音色など、まったくお聴かせ申さなかったのを、たいそうお恨みになる。
|
とだけ言って、可憐なふうに泣いていて多くは言わないのであるが、源氏に時々答える言葉には情のこまやかさが見えた。源氏が始終聞きたく思っていた琴を今日まで女の弾こうとしなかったことを言って源氏は恨んだ。
|
【さるべき節の】- 別れに臨んでの返歌。心をとり乱さずに申し上げたことをいう。
【この、常にゆかしがりたまふ物の音など】- 「この」は源氏をさす。「物の音」は琴の音。明石の君は琴が上手だと入道から聞かされていた。
【さらに聞かせたてまつらざりつるを】- 「さらに」副詞、「ざり」打消の助動詞に係って、全然、まったく、一度も--でないの意。
|
| 4.3.7 |
|
「それでは、形見として思い出になるよう、せめて一節だけでも」
|
「ではあとであなたに思い出してもらうために私も弾くことにしよう」
|
【さらば、形見にも偲ぶばかりの一琴をだに】- 源氏の詞。「だに」副助詞、最小限の願望。「ひとこと」に「一言」と「一琴」を掛ける。
|
| 4.3.8 |
|
とおっしゃって、京から持っていらした琴のお琴を取りにやって、格別に風情のある一曲をかすかに掻き鳴らしていらっしゃる、夜更けの澄んだ音色は、たとえようもなく素晴しい。
|
と源氏は、京から持って来た琴を浜の家へ取りにやって、すぐれたむずかしい曲の一節を弾いた。深夜の澄んだ気の中であったから、非常に美しく聞こえた。
|
【琴の御琴取りに遣はして】- 岡辺の家から浜辺の家に取りにやる。
|
| 4.3.9 |
|
入道も、たまりかねて箏の琴を取って差し入れた。
娘自身も、ますます涙まで催されて、止めようもないので、気持ちをそそられるのであろう、ひっそりと音色を調べた具合、まことに気品のある奏法である。
入道の宮のお琴の音色を、今の世に類のないものとお思い申し上げていたのは、「当世風で、ああ、素晴らしい」と、聴く人の心がほれぼれとして、御器量までが自然と想像されることは、なるほど、まことにこの上ないお琴の音色である。
|
入道は感動して、娘へも促すように自身で十三絃の琴を几帳の中へ差し入れた。女もとめどなく流れる涙に誘われたように、低い音で弾き出した。きわめて上手である。入道の宮の十三絃の技は現今第一であると思うのは、はなやかにきれいな音で、聞く者の心も朗らかになって、弾き手の美しさも目に髣髴と描かれる点などが非常な名手と思われる点である。
|
【みづからも、いとど涙さへそそのかされて】- 「みづから」は明石の君をさす。「さへ」副助詞、添加。琴ばかりでなく涙までがのニュアンス。「そそのかす」は琴を勧められる、涙が催されるの両方の意。
【誘はるるなるべし】- 「なる」断定の助動詞。「べし」推量の助動詞。語り手の推量の挿入句。
【入道の宮の御琴の音を】- 『集成』は「以下、明石上の弾奏を藤壺のそれと思い比べる源氏の心」と注す。以下「きゝならさゝりつらむ」まで、源氏の心に添った叙述。
|
| 4.3.10 |
|
これはどこまでも冴えた音色で、奥ゆかしく憎らしいほどの音色が優れていた。
この君でさえ、初めてしみじみと心惹きつけられる感じで、まだお聴きつけにならない曲などを、もっと聴いていたいと感じさせる程度に、弾き止め弾き止めして、物足りなくお思いになるにつけても、「いく月も、どうして無理してでも、聴き親しまなかったのだろう」と、残念にお思いになる。
心をこめて将来のお約束をなさるばかりである。
|
これはあくまでも澄み切った芸で、真の音楽として批判すれば一段上の技倆があるとも言えると、こんなふうに源氏は思った。源氏のような音楽の天才である人が、はじめて味わう妙味であると思うような手もあった。飽満するまでには聞かせずにやめてしまったのであるが、源氏はなぜ今日までにしいても弾かせなかったかと残念でならない。熱情をこめた言葉で源氏はいろいろに将来を誓った。
|
【これは】- 明石の君の弾奏をさす。
【この御心にだに】- 「この」は源氏をさす。「だに」副助詞、限定。源氏のような人でさえ。源氏のような人とは、音楽に関して幅広い知識と深い教養を身につけた人というニュアンス。下の「初めて」「耳馴れたまはぬ手」に係る。
【弾きさしつつ】- 「つつ」接尾語、同一動作の反復の意。
【月ごろ、など強ひても、聞きならさざりつらむ】- 源氏の心中。後悔。
【心の限り行く先の契りをのみしたまふ】- 「かぎり」名詞、極限、極み、ありったけというニュアンス。「のみ」副助詞、限定・強調。--だけ、そればかりというニュアンス。『集成』は「心をこめて再会のお約束をなさるばかりだ」。『完訳』は「心底から固く将来のことをお約束になる」と訳す。
|
| 4.3.11 |
|
「琴は、再び掻き合わせをするまでの形見に」
|
「この琴はまた二人で合わせて弾く日まで形見にあげておきましょう」
|
【琴は、また掻き合はするまでの形見に】- 源氏の詞。『集成』は「ここに残してゆこう」の余意を指摘。
|
| 4.3.12 |
とのたまふ。
女、
|
とおっしゃる。
女、
|
と源氏が琴のことを言うと、女は、
|
|
| 4.3.13 |
|
「軽いお気持ちでおっしゃるお言葉でしょうが
その一言を悲しくて泣きながら心にかけて、
|
なほざりに頼めおくめる一ことを
つきせぬ音にやかけてしのばん
|
【なほざりに頼め置くめる一ことを--尽きせぬ音にやかけて偲ばむ】- 明石の君の贈歌。「ひとこと」に「一言」と「一琴」を掛ける。「琴」と「音」は縁語。「に」断定の助動詞。「や」係助詞、疑問。「む」推量の助動詞、推量、連体形、係結び。強調のニュアンス。
|
| 4.3.14 |
言ふともなき口すさびを、恨みたまひて、
|
と言うともなく口ずさみなさるのを、お恨みになって、
|
言うともなくこう言うのを、源氏は恨んで、
|
|
| 4.3.15 |
|
「今度逢う時までの形見に残した琴の中の緒の調子のように
二人の仲の愛情も、
|
逢ふまでのかたみに契る中の緒の
しらべはことに変はらざらなん
|
【逢ふまでのかたみに契る中の緒の--調べはことに変はらざらなむ】- 源氏の返歌。「かたみ」に「形見」と「互いに」。「中のを」に琴の「中の緒」と二人の「仲」。「ことに」に「異に」と「琴に」を掛ける。「なむ」終助詞、願望。互いに心変わりせずにいたいものだの意。
|
| 4.3.16 |
|
この琴の絃の調子が狂わないうちに必ず逢いましょう」
|
と言ったが、なおこの琴の調子が狂わない間に必ず逢おうとも言いなだめていた。
|
【この音違はぬさきにかならずあひ見む】- 『集成』は地の文に解す。
|
| 4.3.17 |
と頼めたまふめり。されど、ただ別れむほどのわりなさを思ひ咽せたるも、いとことわりなり。 |
とお約束なさるようである。
それでも、ただ別れる時のつらさを思ってむせび泣いているのも、まことに無理はない。
|
信頼はしていても目の前の別れがただただ女には悲しいのである。もっともなことと言わねばならない。
|
【頼めたまふめり】- 「めり」推量の助動詞、視界内推量。語り手がその場に居合わせて見ているような語り方。
|
|
第四段 離別の朝
|
| 4.4.1 |
立ちたまふ暁は、夜深く出でたまひて、御迎への人びとも騒がしければ、心も空なれど、人まをはからひて、 |
ご出立になる朝は、まだ夜の深いうちにお出になって、お迎えの人々も騒がしいので、心も上の空であるが、人のいない隙間を見はからって、
|
もう出立の朝になって、しかも迎えの人たちもおおぜい来ている騒ぎの中に、時間と人目を盗んで源氏は女へ書き送った。
|
【立ちたまふ暁は】- 源氏、出立の朝。
|
| 4.4.2 |
|
「あなたを置いて明石の浦を旅立つわたしも悲しい気がしますが
後に残ったあなたはさぞやどのような気持ちでいられるかお察しします」
|
うち捨てて立つも悲しき浦波の
名残いかにと思ひやるかな
|
【うち捨てて立つも悲しき浦波の--名残いかにと思ひやるかな】- 源氏の贈歌。「立つ」「浦波」「余波」は縁語。後に残された明石の君の気持ちを思いやった歌。
|
| 4.4.3 |
御返り、
|
お返事は、
|
返事、
|
|
| 4.4.4 |
|
「長年住みなれたこの苫屋も、
あなた様が立ち去った後は荒れ
|
年経つる苫屋も荒れてうき波の
帰る方にや身をたぐへまし
|
【年経つる苫屋も荒れて憂き波の--返る方にや身をたぐへまし】- 明石の君の返歌。「返る方に身をたぐへまし」について、『完訳』は「投身をも想像する」「あなたがお帰りになる京の方へ、できることならこの身もいっしょに添わせてやりたい、お後を慕って身を投げてしまいたいです」と注す。「まし」推量の助動詞、仮想し、躊躇を含み、相手に判断を求める気持ち。--しようかしら。「帰る」の主語が、源氏と波との両方であるため、後を慕って都に上りたいと、海に入りたいとの、両義性を含んだ表現。
|
| 4.4.5 |
|
と、気持ちのままなのを御覧になると、堪えていらっしゃったが、ほろほろと涙がこぼれてしまった。
事情を知らない人々は、
|
これは実感そのまま書いただけの歌であるが、手紙をながめている源氏はほろほろと涙をこぼしていた。
|
【忍びたまへど、ほろほろとこぼれぬ】- 主語は源氏。
|
| 4.4.6 |
|
「やはりこのようなお住まいであるが、一年ほどもお住み馴れになったので、いよいよ立ち去るとなると、悲しくお思いになるのももっともなことだ」
|
女の関係を知らない人々はこんな住居も、一年以上いられて別れて行く時は名残があれほど惜しまれるものなのであろうと単純に同情していた。
|
【なほかかる御住まひなれど】- 以下「あることぞかし」まで、供人の心中。
|
| 4.4.7 |
など見たてまつる。
|
などと、拝見する。
|
|
|
| 4.4.8 |
|
良清などは、「並々ならずお思いでいらっしゃるようだ」と、いまいましく思っている。
|
良清などはよほどお気に入った女なのであろうと憎く思った。
|
【おろかならず思すなめりかし】- 良清の心中。「思す」の主語は源氏。「な」(断定の助動詞、連体形、活用語尾、撥音便化して無表記)「めり」(推量の助動詞、視界内推量)。良清が源氏の様を見ながら推量しているニュアンス。
|
| 4.4.9 |
|
嬉しいにつけても、「なるほど、今日限りで、この浦を去ることよ」などと、名残を惜しみ合って、口々に涙ぐんで挨拶をし合っているようだ。
けれど、いちいちお話する必要もあるまい。
|
侍臣たちは心中のうれしさをおさえて、今日限りに立って行く明石の浦との別れに湿っぽい歌を作りもしていたが、それは省いておく。
|
【げに、今日を限りに、この渚を別るること】- 供人の心中。『完訳』は「源氏の悲嘆が納得される」と注す。
【言ひあへることどもあめり】- 「あ」(動詞、連体形、活用語尾、撥音便化して無表記)「めり」(推量の助動詞、視界内推量)。語り手がその場で見て推量しているニュアンス。
【されど、何かはとてなむ】- 語り手の省略の言葉。『集成』は「けれども、書きとめるにおよばないと思って。家来たちの歌などは省略したとことわる草子地」。『完訳』は「詳しく語るまでもないとする、語り手の省筆の弁」と注す。
|
| 4.4.10 |
入道、今日の御まうけ、いといかめしう仕うまつれり。人びと、下の品まで、旅の装束めづらしきさまなり。いつの間にかしあへけむと見えたり。御よそひは言ふべくもあらず。御衣櫃あまたかけさぶらはす。まことの都の苞にしつべき御贈り物ども、ゆゑづきて、思ひ寄らぬ隈なし。今日たてまつるべき狩の御装束に、 |
入道、今日のお支度を、たいそう盛大に用意した。
お供の人々、下々のまで、旅の装束を立派に整えてある。
いつの間にこんなに準備したのだろうかと思われた。
ご装束はいうまでもない。
御衣櫃を幾棹となく荷なわせお供をさせる。
実に都への土産にできるお贈り物類、立派な物で、気のつかないところがない。
今日お召しになるはずの狩衣のご装束に、
|
出立の日の饗応を入道は派手に設けた。全体の人へ餞別にりっぱな旅装一揃いずつを出すこともした。いつの間にこの用意がされたのであるかと驚くばかりであった。源氏の衣服はもとより質を精選して調製してあった。幾個かの衣櫃が列に加わって行くことになっているのである。今日着て行く狩衣の一所に女の歌が、
|
【御衣櫃あまたかけさぶらはす】- 大島本は「あまたかけたまハす」とある。主語は明石入道。『集成』『新大系』『古典セレクション』は諸本に従って「あまたかけさぶらはす」と校訂する。
|
| 4.4.11 |
|
「ご用意致しました旅のご装束は寄る波の
涙に濡れていまので、
|
寄る波にたち重ねたる旅衣
しほどけしとや人のいとはん
|
【寄る波に立ちかさねたる旅衣--しほどけしとや人の厭はむ】- 明石の君の贈歌。「たち」は「裁ち」と「立ち」の掛詞。「波」「立つ」「塩どけし」は縁語。「寄る波に」から「旅衣」まで下句に係る序詞。「人」は源氏をさす。
|
| 4.4.12 |
とあるを御覧じつけて、騒がしけれど、
|
とあるのを御発見なさって、騒がしい最中であるが、
|
と書かれてあるのを見つけて、立ちぎわではあったが源氏は返事を書いた。
|
|
| 4.4.13 |
|
「お互いに形見として着物を交換しましょう
また逢える日までの間の二人の仲の、
|
かたみにぞかふべかりける逢ふことの
日数へだてん中の衣を
|
【かたみにぞ換ふべかりける逢ふことの--日数隔てむ中の衣を】- 源氏の返歌。「旅衣」に対して「中の衣」と返す。「かたみに」に「形見」と「互いに」。「中の」は「中の衣」と「仲」。「隔てむ」は上からは「日数隔てむ」、下へは「隔てむ中の衣」と両方に係る掛詞。
|
| 4.4.14 |
|
とおっしゃって、「せっかくの好意だから」と言って、お召し替えになる。
お身につけていらしたのをお遣わしになる。
なるほど、もう一つお偲びになるよすがを添えた形見のようである。
素晴らしいお召し物に移り香が匂っているのを、どうして相手の心にも染みないことがあろうか。
|
というのである。「せっかくよこしたのだから」と言いながらそれに着かえた。今まで着ていた衣服は女の所へやった。思い出させる恋の技巧というものである。自身のにおいの沁んだ着物がどれだけ有効な物であるかを源氏はよく知っていた。
|
【心ざしあるを】- 源氏の心中。
【げに、今一重偲ばれたまふべきことを添ふる形見なめり】- 「げに」語り手の納得。「今一重」は一層の意と衣の縁で「一重」との掛詞。「偲ばれ給ふ」の主語は源氏。「れ」受身の助動詞。「なめり」は「な」(断定の助動詞、連体形、活用語尾が撥音便化して無表記)「めり」(推量の助動詞、視界内推量)。語り手がその場で見て心中を推量しているニュアンス。
【いかが人の心にも染めざらむ】- 「人」は明石の君をさす。語り手の推量、反語表現で強調。
|
| 4.4.15 |
入道、
|
入道は、
|
|
|
| 4.4.16 |
|
「きっぱりと世を捨てました出家の身ですが、今日のお見送りにお供申しませんことが」
|
「もう捨てました世の中ですが、今日のお送りのできませんことだけは残念です」
|
【今はと世を離れ】- 以下「仕うまつらぬこと」まで、明石の入道の詞。
|
| 4.4.17 |
など申して、かひをつくるもいとほしながら、若き人は笑ひぬべし。 |
などと申し上げて、べそをかいているのも気の毒だが、若い人ならきっと笑ってしまうであろう。
|
などと言っている入道が、両手で涙を隠しているのがかわいそうであると源氏は思ったが、他の若い人たちの目にはおかしかったに違いない。
|
【かひをつくる】- べそをかく意。また海辺の縁で「貝」を連想させる語句。
|
| 4.4.18 |
|
「世の中が嫌になって長年この海浜の汐風に吹かれて暮らして来たが
なお依然として子の故に此岸を離れることができずにおります
|
「世をうみにここらしほじむ身となりて
なほこの岸をえこそ離れね
|
【世をうみにここらしほじむ身となりて--なほこの岸をえこそ離れね】- 入道の贈歌。「うみ」に「海」と「憂み」。「この岸」の「こ」に「子」と「此」を掛け、「此岸」を「彼岸」の対で用いる。「潮じむ」は「海」の縁語。娘のことが案じられてならない。
|
| 4.4.19 |
|
娘を思う親の心は、ますます迷ってしまいそうでございますから、せめて国境までなりとも」と申し上げて、
|
子供への申しわけにせめて国境まではお供をさせていただきます」と入道は言ってから、
|
【心の闇は、いとど惑ひぬべく】- 以下「境までだに」まで、入道の詞。「人の親の心は闇にあらねども子を思ふ道に惑ひぬるかな」(後撰集雑一、一一〇二、藤原兼輔)。「境」は、播磨国と摂津国境。「だに」副助詞、最小限の願望。
|
| 4.4.20 |
|
「あだめいた事を申すようでございますが、もしお思い出しあそばすことがございましたら」
|
「出すぎた申し分でございますが、思い出しておやりくださいます時がございましたら御音信をいただかせてくださいませ」
|
【好き好きしきさまなれど】- 以下「折はべらば」まで、入道の詞。「折はべらば」の下に、お便りをください、の意が込められている。
|
| 4.4.21 |
など、御けしき賜はる。
いみじうものをあはれと思して、所々うち赤みたまへる御まみのわたりなど、言はむかたなく見えたまふ。
|
などと、ご内意を頂戴する。
たいそう気の毒にお思いになって、お顔の所々を赤くしていらっしゃるお目もとのあたりがなどが、何ともいいようなくお見えになる。
|
などと頼んだ。悲しそうで目のあたりの赤くなっている源氏の顔が美しかった。
|
|
| 4.4.22 |
|
「放っておきがたい事情もあるので、きっと今すぐにお思い直しくださるでしょう。
ただ、この住まいが見捨てがたいのです。
どうしたものでしょう」とおっしゃって、
|
「私には当然の義務であることもあるのですから、決して不人情な者でないとすぐにまたよく思っていただくような日もあるでしょう。私はただこの家と離れることが名残惜しくてならない、どうすればいいことなんだか」と言って、
|
【思ひ捨てがたき筋】- 以下「いかがすべき」まで、源氏の詞。明石の君が源氏の子を懐妊していることをさす。
【見直したまひてむ】- 「見直し」の主語は明石の君。「て」完了の助動詞、確述。「む」推量の助動詞、きっと思い直して下さるであろうの意。
|
| 4.4.23 |
|
「都を立ち去ったあの春の悲しさに決して劣ろうか
年月を過ごしてきたこの浦を離れる悲しい秋は」
|
都出でし春の歎きに劣らめや
年ふる浦を別れぬる秋
|
【都出でし春の嘆きに劣らめや--年経る浦を別れぬる秋】- 源氏の返歌。一昨年の春三月二十日余りに離京した。その時の別離の悲しみに変わらないという。
|
| 4.4.24 |
とて、おし拭ひたまへるに、いとどものおぼえず、しほたれまさる。立ちゐもあさましうよろぼふ。 |
とお詠みになって、涙を拭っていらっしゃると、ますます分別を失って、涙をさらに流す。
立居もままならず転びそうになる。
|
と涙を袖で源氏は拭っていた。これを見ると入道は気も遠くなったように萎れてしまった。それきり起居もよろよろとするふうである。
|
【いとどものおぼえず】- 以下の主語は明石入道。
|
|
第五段 残された明石の君の嘆き
|
| 4.5.1 |
|
娘ご本人の気持ちは、たとえようもないくらいで、こんなに深く悲嘆していると誰にも見せまいと気持ちを沈めていたが、わが身のつたなさがもとで、無理のないことであるが、お残しになって行かれた恨みの晴らしようがないが、せいぜいできることは、ただ涙に沈むばかりである。
母君も慰めるのに困って、
|
明石の君の心は悲しみに満たされていた。外へは現わすまいとするのであるが、自身の薄倖であることが悲しみの根本になっていて、捨てて行く恨めしい源氏がまた恋しい面影になって見えるせつなさは、泣いて僅かに洩らすほかはどうしようもない。母の夫人もなだめかねていた。
|
【かうしも人に見えじ】- 明石の君の心中。
【わりなきことなれど】- 語り手の挿入句。『完訳』は「自分の運命に原因があるとしながら、次に源氏への「恨み」を抱くところから、語り手が「わりなき」(理屈に合わぬ)と評す」と注す。
【恨みのやる方なきに】- 大島本は「うらみのやるかたなきに」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「恨みのやる方なきに、面影にそひて忘れがたきに」と「面影にそひて忘れがたきに」を補訂する。
【慰めわびては】- 大島本は「なくさめわひてハ」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「慰めわびて」と「は」を削除する。
|
| 4.5.2 |
「何に、かく心尽くしなることを思ひそめけむ。すべて、ひがひがしき人に従ひける心のおこたりぞ」 |
「どうして、こんなに気を揉むようなことを思いついたのでしょう。
あれもこれも、
|
「どうしてこんなに苦労の多い結婚をさせたろう。固意地な方の言いなりに私までもがついて行ったのがまちがいだった」
|
【何に、かく】- 以下「心のおこたりぞ」まで、母君の詞。偏屈な夫の言い分に従った自分の責任だといって慰める。
|
| 4.5.3 |
と言ふ。
|
と言う。
|
と夫人は歎息していた。
|
|
| 4.5.4 |
|
「まあ、静かに。
お捨て置きになれない事情もおありになるようですから、今は別れたといっても、お考えになっていることがございましょう。
気持ちを落ち着かせて、せめてお薬湯などでも召し上がれ。
ああ、縁起でもない」
|
「うるさい、これきりにあそばされないことも残っているのだから、お考えがあるに違いない。湯でも飲んでまあ落ち着きなさい。ああ苦しいことが起こってきた」
|
【あなかまや】- 以下「あなゆゆしや」まで、入道の詞。慰め。
【思し捨つまじきこと】- 娘が源氏の子を懐妊していることをさす。
【思すところあらむ】- 主語は源氏。
|
| 4.5.5 |
|
と言って、片隅に座っていた。
乳母、母君などは、偏屈な心をそしり合いながら、
|
入道はこう妻と娘に言ったままで、室の片隅に寄っていた。妻と乳母とが口々に入道を批難した。
|
【片隅に寄りゐたり】- 『集成』は「口では強がりを言うものの、意気銷沈のてい」。『完訳』は「強弁はしながら、内心では自信を失って小さくなっている様子」と注す。
|
| 4.5.6 |
「いつしか、いかで思ふさまにて見たてまつらむと、年月を頼み過ぐし、今や、思ひ叶ふとこそ頼みきこえつれ、心苦しきことをも、もののはじめに見るかな」 |
「早く早く、何とか願い通りにしてお世話申そうと、長い年月を期待して過ごしてき、今や、その願いが叶ったと頼もしくお思い申したのに、気の毒にも、事の初めから味わおうとは」
|
「お嬢様を御幸福な方にしてお見上げしたいと、どんなに長い間祈って来たことでしょう。いよいよそれが実現されますことかと存じておりましたのに、お気の毒な御経験をあそばすことになったのでございますね。最初の御結婚で」
|
【いつしか、いかで】- 以下「もののはじめに見るかな」まで、乳母の詞。「いつしか」は早く早くの意。
【こそ頼みきこえつれ】- 「こそ」係助詞。「つれ」完了の助動詞、已然形、係結び、逆接用法で、下文に続く。
|
|
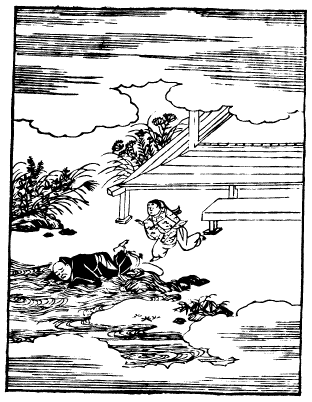 |
| 4.5.7 |
|
と嘆くのを見るにつけても、かわいそうなので、ますます頭がぼんやりしてきて、昼は一日中、寝てばかり暮らし、夜はすっくと起き出して、「数珠の在りかも分からなくなってしまった」と言って、手をすり合わさせて茫然としていた。
|
こう言って歎く人たちもかわいそうに思われて、そんなこと、こんなことで入道の心は前よりずっとぼけていった。昼は終日寝ているかと思うと、夜は起き出して行く。「数珠の置き所も知れなくしてしまった」と両手を擦り合わせて絶望的な歎息をしているのであった。
|
【いとどほけられて】- 「られ」自発の助動詞。以下、入道の源氏が去って以後の日常の様子。
【数珠の行方も知らずなりにけり】- 入道の詞。
|
| 4.5.8 |
弟子どもにあはめられて、月夜に出でて行道するものは、遣水に倒れ入りにけり。よしある岩の片側に腰もつきそこなひて、病み臥したるほどになむ、すこしもの紛れける。 |
弟子たちに軽蔑されて、月夜に庭先に出て行道をしたにはしたのだが、遣水の中に落ち込んだりするのであった。
風流な岩の突き出た角に腰をぶっつけて怪我をして、寝込むことになってようやく、物思いも少し紛れるのであった。
|
弟子たちに批難されては月夜に出て御堂の行道をするが池に落ちてしまう。風流に作った庭の岩角に腰をおろしそこねて怪我をした時には、その痛みのある間だけ煩悶をせずにいた。
|
【行道するものは】- 「は」係助詞、区別・強調のニュアンス。『集成』は「一念発起、月夜に庭に出て行道したまではよかったが、なんと遣水にころげ込んでしまった」。『完訳』は「「--するものは--けり」は、これはしたり、と揶揄する語法」、「月夜に出て行道しようとしたところ、これはしたり、遣水の中にころげ落ちるという始末なのであった」と訳す。
|
|
第五章 光る源氏の物語 帰京と政界復帰の物語
|
|
第一段 難波の御祓い
|
| 5.1.1 |
|
君は、難波の方面に渡ってお祓いをなさって、住吉の神にも、お蔭で無事であったので、改めていろいろと願ほどき申し上げる旨を、お使いの者に申させなさる。
急に大勢の供回りとなったので、ご自身は今回はお参りすることがおできになれず、格別のご遊覧などもなくて、急いで京にお入りになった。
|
源氏は浪速に船を着けて、そこで祓いをした。住吉の神へも無事に帰洛の日の来た報告をして、幾つかの願を実行しようと思う意志のあることも使いに言わせた。自身は参詣しなかった。途中の見物などもせずにすぐに京へはいったのであった。
|
【君は、難波の方に渡りて】- 源氏の都への帰路。
【平らかにて】- 「て」接続助詞、順接、原因・理由。
【御使して申させたまふ】- 「させ」使役の助動詞、「給ふ」尊敬の補助動詞。源氏は後日改めてお礼参りに詣でる。
|
| 5.1.2 |
|
二条院にお着きあそばして、都の人も、お供の人も、夢のような心地がして再会し、喜んで泣くのも縁起が悪いくらいまで大騷した。
|
二条の院へ着いた一行の人々と京にいた人々は夢心地で逢い、夢心地で話が取りかわされた。喜び泣きの声も騒がしい二条の院であった。
|
【御供の人も】- 大島本は「御との人」とある。『集成』『新大系』『古典セレクション』は諸本に従って「御供の人」と「も」を補訂して「供」とする。
【喜び泣きども】- 大島本は「よろこひなきとも」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「よろこびび泣きも」と「と」を削除する。
|
| 5.1.3 |
|
女君も、生きていても甲斐ないとまでお思い棄てていた命、嬉しくお思いのことであろう。
とても美しくご成人なさって、ご苦労の間に、うるさいほどあったお髪が少し減ったのも、かえってたいそう素晴らしいのを、「今はもうこうして毎日お会いできるのだ」と、お心が落ち着くにつけて、また一方では、心残りの別れをしてきた人が悲しんでいた様子、痛々しくお思いやらずにはいられない。
やはり、いつになっても、このような方面では、お心の休まる時のないことよ。
|
紫夫人も生きがいなく思っていた命が、今日まであって、源氏を迎ええたことに満足したことであろうと思われる。美しかった人のさらに完成された姿を二年半の時間ののちに源氏は見ることができたのである。寂しく暮らした間に、あまりに多かった髪の量の少し減ったまでもがこの人をより美しく思わせた。こうしてこの人と永久に住む家へ帰って来ることができたのであると、源氏の心の落ち着いたのとともに、またも別離を悲しんだ明石の女がかわいそうに思いやられた。源氏は恋愛の苦にどこまでもつきまとわれる人のようである。
|
【かひなきものに思し捨てつる命】- 紫の君は源氏と別れる時に「惜しからぬ命にかへて目の前の別れをしばしとどめてしがな」(須磨)と詠んだ。
【思さるらむかし】- 「らむ」推量の助動詞、視界外推量、語り手がやや離れた所から見て推量しているニュアンス。
【今はかくて見るべきぞかし】- 源氏の心中。「べき」推量の助動詞、可能。一緒に暮らすことができるのだ。
【かの飽かず別れし人】- 明石の君をさす。
【思しやらる】- 「る」自発の助動詞。
【なほ世とともに、かかる方にて御心の暇ぞなきや】- 「なほ」副詞。「や」終助詞、詠嘆。語り手の源氏の女性に対する態度への批評。
|
| 5.1.4 |
|
その女のことなどをお話し申し上げなさった。
お思い出しになるご様子が一通りのお気持ちでなく見えるので、並々のご愛着ではないと拝見するのであろうか、さりげなく、「わたしの身の上は思いませんが」などと、ちらっと嫉妬なさるのが、しゃれていていじらしいとお思い申し上げなさる。
また一方で、「見ていてさえ見飽きることのないご様子を、どうして長い年月会わずにいられたのだろうか」と、信じられないまでの気持ちがするので、今さらながら、まことに世の中が恨めしく思われる。
|
源氏は夫人に明石の君のことを話した。女王はどう感じたか、恨みを言うともなしに「身をば思はず」(忘らるる身をば思はず誓ひてし人の命の惜しくもあるかな)などとはかなそうに言っているのを、美しいとも可憐であるとも源氏は思った。見ても見ても見飽かぬこの人と別れ別れにいるようなことは何がさせたかと思うと今さらまた恨めしかった。
|
【その人のことども】- 明石の君に関する事柄。
【思し出でたる御けしき】- 源氏の態度・表情をいう。
【ただならずや見たてまつりたまふらむ】- 「や」係助詞、疑問。「らむ」推量の助動詞、視界外推量。語り手の紫の君の心中を推量した挿入句。
【身をば思はず】- 「忘らるる身をば思はず誓ひてし人の命の惜しけもあるかな」(拾遺集恋四、八七〇、右近)の第二句を引く。自分のことはかまわないが、神仏に誓ったあなたの命が心配だという意。
【かつ、「見るにだに】- 以下「隔てつる年月ぞ」まで、源氏の心中。『完訳』は「陸奥の安積の沼の花がつみかつ見る人に恋ひやわたらむ」(古今集恋四、六七七、読人しらず)を指摘。
【世の中も】- 『集成』は「あの時のいきさつも」。『完訳』は「この世の中が」と注す。
|
| 5.1.5 |
|
まもなく、元のお位に復して、員外の権大納言におなりになる。
以下の人々も、しかるべき者は皆元の官を返し賜わり、世に復帰するのは、枯れていた木が春にめぐりあった有様で、たいそうめでたい感じである。
|
間もなく源氏は本官に復した上、権大納言も兼ねる辞令を得た。侍臣たちの官位もそれぞれ元にかえされたのである。枯れた木に春の芽が出たようなめでたいことである。
|
【ほどもなく、元の御位あらたまりて、員より外の権大納言になりたまふ】- いったん元の位であった参議右大将に復し、改めて権大納言右大将に昇進。中納言を経ず異例の昇進。
【次々の人も】- 『集成』は「源氏に連座して罷免された家臣たち」。『完訳』は「源氏方には、須磨への供人など、昇進の滞った者も多かった」と注す。
|
|
第二段 源氏、参内
|
| 5.2.1 |
|
お召しがあって、参内なさる。
御前に伺候していられると、いよいよ立派になられて、「どうしてあのような辺鄙な土地で、長年お暮らしになったのだろう」と拝見する。
女房などの中で、故院の御在世中にお仕えして、年老いた連中は、悲しくて、今さらのように泣き騒いでお褒め申し上げる。
|
お召しがあって源氏は参内した。お常御殿に上がると、源氏のさらに美しくなった姿をあれで田舎住まいを長くしておいでになったのかと人は驚いた。前代から宮中に奉仕していて、年を取った女房などは、悲しがって今さらまた泣き騒いでいた。
|
【召しありて、内裏に参りたまふ】- 源氏、参内し、兄の朱雀帝としめやかに語る。
【ねびまさりて】- 源氏の姿をいう。
【いかで、さるものむつかしき住まひに年経たまひつらむ】- 御前の女房の心中。
【院の御時さぶらひて】- 大島本は「院の御時さふらひて」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「院の御時よりさぶらひて」と「より」を補訂する。
|
| 5.2.2 |
主上も、恥づかしうさへ思し召されて、御よそひなどことに引きつくろひて出でおはします。御心地、例ならで、日ごろ経させたまひければ、いたう衰へさせたまへるを、昨日今日ぞ、すこしよろしう思されける。御物語しめやかにありて、夜に入りぬ。 |
主上も、恥ずかしくまで思し召されて、御装束なども格別におつくろいになってお出ましになる。
お加減が、すぐれない状態で、ここ数日おいであそばしたので、ひどくお弱りあそばしていらっしゃったが、昨日今日は、少しよろしくお感じになるのであった。
お話をしみじみとなさって、夜に入った。
|
帝も源氏にお逢いになるのを晴れがましく思召されて、お身なりなどをことにきれいにあそばしてお出ましになった。ずっと御病気でおありになったために、衰弱が御見えになるのであるが、昨今になって陛下の御気分はおよろしかった。しめやかにお話をあそばすうちに夜になった。
|
【主上も、恥づかしう】- 『完訳』は「源氏を罪に陥れた慚愧の念に、源氏の美麗さがいっそうまぶしい」と注す。
|
| 5.2.3 |
|
十五夜の月が美しく静かなので、昔のことを、一つ一つ自然とお思い出しになられて、お泣きあそばす。
何となく心細くお思いあそばさずにはいられないのであろう。
|
十五夜の月の美しく静かなもとで昔をお忍びになって帝はお心をしめらせておいでになった。お心細い御様子である。
|
【十五夜の月おもしろう静かなるに】- 二年前、源氏は須磨で眺めた。
【かき尽くし思し出でられて】- 大島本は「かき(き+つ<朱>)くつ(つ#<朱>)し」と朱筆で「つ」を補入し本行の「つ」を抹消する。すなわち本行の「かきくつし」を「かきつくし」と改めている。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「かきくづし」と校訂する。
【もの心細く思さるるなるべし】- 語り手の帝の心中を推測した挿入句。
|
| 5.2.4 |
「遊びなどもせず、昔聞きし物の音なども聞かで、久しうなりにけるかな」 |
「管弦の催しなどもせず、昔聞いた楽の音なども聞かないで、久しくなってしまったな」
|
「音楽をやらせることも近ごろはない。あなたの琴の音もずいぶん長く聞かなんだね」
|
【遊びなどもせず】- 以下「久しうなりにけるかな」まで、帝の詞。
|
| 5.2.5 |
とのたまはするに、
|
と仰せになるので、
|
と仰せられた時、
|
|
| 5.2.6 |
|
「海浜でうちしおれて落ちぶれながら蛭子のように
立つこともできず三年を過ごして来ました」
|
わたつみに沈みうらぶれひるの子の
足立たざりし年は経にけり
|
【わたつ海にしなえうらぶれ蛭の児の--脚立たざりし年は経にけり】- 源氏の贈歌。「かぞいろはあはれと見ずや蛭の子は三歳になりぬ脚立たずして」(日本紀竟宴和歌、大江朝綱)を踏まえる。いざなぎ・いざなみの国生みの神話にもとづく和歌。
|
| 5.2.7 |
|
とお応え申し上げなさった。
とても胸をうち心恥しく思わずにはいらっしゃれないで、
|
と源氏が申し上げると、帝は兄君らしい憐みと、君主としての過失をみずからお認めになる情を優しくお見せになって、
|
【と聞こえたまへり】- 大島本は「給へり」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「たまへば」と文を続ける。
|
| 5.2.8 |
|
「こうしてめぐり会える時があったのだから
あの別れた春の恨みはもう忘れてください」
|
宮ばしらめぐり逢ひける時しあれば
別れし春の恨み残すな
|
【宮柱めぐりあひける時しあれば--別れし春の恨み残すな】- 帝の返歌。「宮柱」は、いざなぎ・いざなみの国生みの神話にもとづく。皇族にふさわしい和歌の贈答。
|
| 5.2.9 |
いとなまめかしき御ありさまなり。
|
実に優美な御様子である。
|
と仰せられた。艶な御様子であった。
|
|
| 5.2.10 |
|
故院の御追善供養のために、法華御八講を催しなさることを、何より先にご準備させなさる。
東宮にお目にかかりなさると、すっかりと御成人あそばして、珍しくお喜びになっているのを、感慨無量のお気持ちで拝しなさる。
御学問もこの上なくご上達になって、天下をお治めあそばすにも、何の心配もいらないように、ご立派にお見えあそばす。
|
源氏は院の御為に法華経の八講を行なう準備をさせていた。東宮にお目にかかると、ずっとお身大きくなっておいでになって、珍しい源氏の出仕をお喜びになるのを、限りもなくおかわいそうに源氏は思った。学問もよくおできになって、御位におつきになってもさしつかえはないと思われるほど御聡明であることがうかがわれた。
|
【急がせたまふ】- 主語は源氏。「せ」使役の助動詞。「たまふ」尊敬の補助動詞。
【めづらしう思しよろこびたるを】- 東宮の表情。
【あはれと見たてまつりたまふ】- 主語は源氏。
【御才もこよなくまさらせたまひて、世をたもたせたまはむに、憚りあるまじく、かしこく見えさせたまふ】- このとき東宮、十歳。即位するにふさわしい成長ぶりと資質を語る。
|
| 5.2.11 |
|
入道の宮にも、お心が少し落ち着いて、ご対面の折には、しみじみとしたお話がきっとあったであろう。
|
少し日がたって気の落ち着いたころに御訪問した入道の宮ででも、感慨無量な御会談があったはずである。
|
【あはれなることどもあらむかし】- 「む」推量の助動詞。「かし」終助詞、念押し、語り手の推量表現。
|
|
第三段 明石の君への手紙、他
|
| 5.3.1 |
|
そうそう、あの明石には、送って来た者たちの帰りにことづけて、お手紙をお遣はしになる。
人目に立たないようにして情愛こまやかにお書きになるようである。
|
源氏は明石から送って来た使いに手紙を持たせて帰した。夫人にはばかりながらこまやかな情を女に書き送ったのである。毎夜毎夜悲しく思っているのですか、
|
【まことや、かの明石には】- 源氏、明石の君に歌を贈り、また五節の君と和歌を贈答する。
【返る波に】- 大島本は「かへる浪に」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「返る波につけて」と「つけて」を補訂する。「返る波」は明石から源氏を送ってきた人々をいう。歌語的表現。
【ひき隠して】- 紫の君への遠慮。
【こまやかに書きたまふめり】- 「めり」推量の助動詞、視界内推量。語り手が側で見て語っているニュアンス。
|
| 5.3.2 |
|
「波の寄せる夜々は、
|
|
【波のよるよるいかに】- 以下、源氏の文。「よるよる」は「寄る寄る」と「夜々」の掛詞。和歌に係っていく表現。
|
| 5.3.3 |
|
お嘆きになりながら暮らしていらっしゃる明石の浦に
嘆きの息が朝霧となって立ちこめているのではないかと想像しています」
|
歎きつつ明石の浦に朝霧の
立つやと人を思ひやるかな
|
【嘆きつつ明石の浦に朝霧の--立つやと人を思ひやるかな】- 源氏の贈歌。「あかし」は「明かし」と「明石」の掛詞。「君が行く海辺の宿に霧立たば吾が立ち嘆く息と知らませ」(万葉集、巻十五)、「ほのぼのと明石の浦の朝霧に島隠れゆく舟をしぞ思ふ」(古今集羈旅、四〇九、柿本人麿)などを踏まえる。
|
| 5.3.4 |
|
あの大宰帥の娘の五節は、どうにもならないことだが、人知れずご好意をお寄せ申していたのもさめてしまった感じがして、目くばせさせて置いて行かせたのであった。
|
こんな内容であった。大弐の娘の五節は、一人でしていた心の苦も解消したように喜んで、どこからとも言わせない使いを出して、二条の院へ歌を置かせた。
|
【かの帥の娘五節】- 大島本は「むすめ」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「むすめの」と「の」を補訂する。「須磨」巻に登場。
【あいなく、人知れぬもの思ひさめぬる心地して】- 『完訳』は「「あいなく」は、源氏への思慕を不似合いとする、語り手の評言」と注す。
【まくなぎつくらせて】- 『集成』は「使いにどこからの文とも言わせず、ただ目くばせさせて」。『完訳』は「紫の上に気づかれぬよう、女房に手紙を渡させる」と注す。
|
| 5.3.5 |
|
「須磨の浦で好意をお寄せ申した舟人が
そのまま涙で朽ちさせてしまった袖をお見せ申しとうございます」
|
須磨の浦に心を寄せし船人の
やがて朽たせる袖を見せばや
|
【須磨の浦に心を寄せし舟人の--やがて朽たせる袖を見せばや】- 五節の贈歌。「舟人」に自分を喩える。
|
| 5.3.6 |
|
「筆跡などもたいそう上手になったな」と、お見抜きになって、お遣わしになる。
|
字は以前よりずっと上手になっているが、五節に違いないと源氏は思って返事を送った。
|
【手などこよなくまさりにけり】- 源氏の感想。五節の筆跡の上達に感心。
|
| 5.3.7 |
|
「かえってこちらこそ愚痴を言いたいくらいです、
ご好意を寄せていただいてそれ以来涙に濡れて
|
かへりてはかごとやせまし寄せたりし
名残に袖の乾がたかりしを
|
【帰りてはかことやせまし寄せたりし--名残に袖の干がたかりしを】- 源氏の返歌。「朽たせる袖」を「却りて」「袖の干難かりし」と返す。「いたづらに立ちかへりにし白波のなごりに袖の干る時もなし」(後撰集恋四、八八四、藤原朝忠)。「かこと」は『日葡辞書』には「カコト」「カゴト」両方ある。
|
| 5.3.8 |
「飽かずをかし」と思しし名残なれば、おどろかされたまひて、いとど思し出づれど、このごろは、さやうの御振る舞ひ、さらにつつみたまふめり。 |
「いかにもかわいい」とお思いになった昔の思い出もあるので、はっとびっくりさせられなさって、ますますいとしくお思い出しになるが、最近は、そのようなお忍び歩きはまったく慎んでいらっしゃるようである。
|
源氏はずいぶん好きであった女であるから、誘いかけた手紙を見ては訪ねたい気がしきりにするのであるが、当分は不謹慎なこともできないように思われた。
|
【このごろ】- 上代は清音。『図書寮本名義抄』に「コノゴロ」とある。
【つつみたまふめり】- 「めり」推量の助動詞、視界内推量。語り手が実際に源氏の行動を目にして語っているニュアンス。
|
| 5.3.9 |
花散里などにも、ただ御消息などばかりにて、おぼつかなく、なかなか恨めしげなり。
|
花散里などにも、ただお手紙などばかりなので、心もとなく思われて、かえって恨めしい様子である。
|
花散里などへも手紙を送るだけで、逢いには行こうとしないのであったから、かえって京に源氏のいなかったころよりも寂しく思っていた。
|
|
| 著作権 |
| 底本 |
大島本 |
| 校訂 |
Last updated 9/21/2010(ver.2-3)
渋谷栄一校訂(C)
オリジナル
修正版
比較 |
| ローマ字版 |
Last updated 10/3/2009 (ver.2-2)
Written in Japanese roman letters
by Eiichi Shibuya(C)
オリジナル
修正版
比較 |
ルビ抽出
(ローマ字版から)
|
Powered by 再編集プログラム v4.05
ひらがな版
ルビ抽出 |
挿絵
(ローマ字版から)
|
'Eiri Genji Monogatari'
(1650 1st edition) |
|
Latest updated 6/21/2001
渋谷栄一訳(C)(ver.1-2-2)
オリジナル
修正版
比較 |
|
|
Last updated 10/3/2009(ver.2-2)
渋谷栄一注釈(C)
オリジナル
修正版
比較 |
|