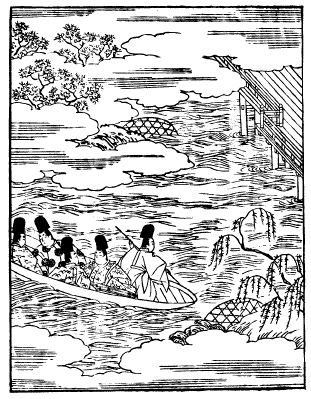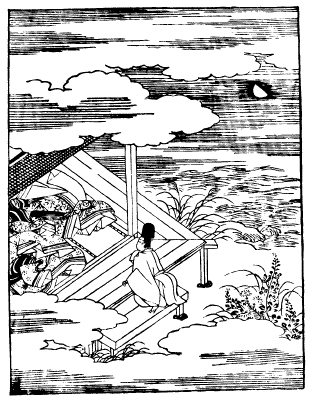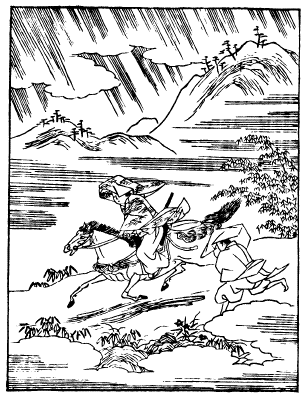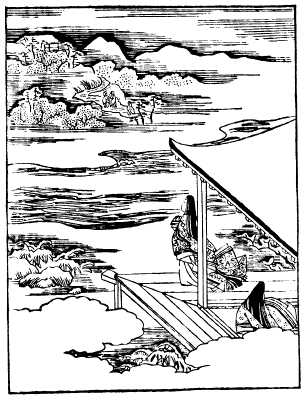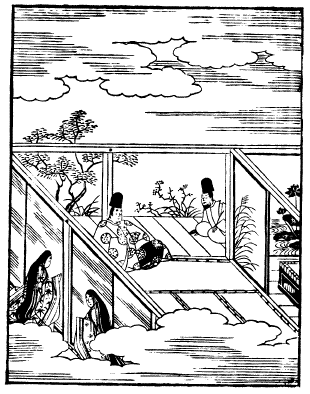第四十六帖 椎本
薫君の宰相中将時代二十三歳春二月から二十四歳夏までの物語
|
# |
本文 |
渋谷栄一訳 |
与謝野晶子訳 |
注釈 |
|
第一章 匂宮の物語 春、匂宮、宇治に立ち寄る
|
|
第一段 匂宮、初瀬詣での帰途に宇治に立ち寄る
|
| 1.1.1 |
|
二月の二十日ころに、兵部卿宮、初瀬にお参りになる。
昔立てた御願のお礼参りであったが、お思い立ちにもならないで数年になってしまったのを、宇治の辺りのご休息宿の興味で、大半の理由は出かける気になられたのであろう。
恨めしいと言う人もあった里の名が、総じて慕わしくお思いなされる理由もたわいないことであるよ。
上達部がとても大勢お供なさる。
殿上人などはさらに言うまでもない、世に残る人はほとんどなくお供申した。
|
二月の二十日過ぎに兵部卿の宮は大和の初瀬寺へ参詣をあそばされることになった。古い御宿願には相違ないが、中に宇治という土地があることからこれが今度実現するに及んだものらしい。宇治は憂き里であると名をさえ悲しんだ古人もあるのに、またこのように心をおひかれになるというのも、八の宮の姫君たちがおいでになるからである。高官も多くお供をした。殿上役人はむろんのことで、この行に漏れた人は少数にすぎない。
|
【如月の二十日のほどに】- 薫二十三歳二月。仲春、花の盛りとなる。
【兵部卿宮、初瀬に詣でたまふ】- 匂宮が初瀬(長谷寺)に参詣する。宇治はその経路。
【古き御願なりけれど】- 『新大系』は「ずっと以前に願をお立てになったが、(お礼参りを)お思い立ちにならぬまま幾年も経ってしまったのを。立願の内容は不明」と注す。
【年ごろになりにけるを】- 「年ごろ」は複数年、の意。年越しの足掛け二年でも「年ごろ」。
【宇治のわたりの御中宿りのゆかしさに】- 薫が匂宮に宇治の姉妹について興味関心をそそるように話した「橋姫」巻の内容を受ける。
【多くは催されたまへるなるべし】- 推量の助動詞「べし」は語り手の推量。三光院実枝「草子地なり」。『評釈』は「作者が匂宮の心中を推量した形である」と注す。
【うらめしと言ふ人もありける里の名の、なべて睦ましう思さるるゆゑ】- 『異本紫明抄』は「忘らるる身を宇治橋の中絶えて人も通はぬ年ぞへにける」(古今集恋五、八二五、読人しらず)。『花鳥余情』は「わが庵は都の巽しかぞ住む世を宇治山と人はいふなり」(古今集雑下、九八三、喜撰法師)を指摘。
【はかなしや】- 語り手の感想。『細流抄』は「草子地の書也」。『完訳』は「語り手が、宇治に執着する匂宮を評す」と注す。
|
| 1.1.2 |
|
六条院から伝領して、右の大殿が所有していらっしゃる邸は、川の向こうで、たいそう広々と興趣深く造ってあるので、ご準備をさせなさった。
大臣も、帰途のお迎えに参るおつもりであったが、急の御物忌で、厳重に慎みなさるよう申したというので、参上できない旨のお詫びを申された。
|
六条院の御遺産として右大臣の有になっている土地は河の向こうにずっと続いていて、ながめのよい別荘もあった。そこに往復とも中宿りの接待が設けられてあり、大臣もお帰りの時は宇治まで出迎えることになっていたが、謹慎日がにわかにめぐり合わせて来て、しかも重く慎まねばならぬことを陰陽師から告げられたために、自身で伺えないことのお詫びの挨拶を持って代理が京から来た。
|
【六条院より伝はりて、右大殿知りたまふ所は、川より遠方に】- 『花鳥余情』は、藤原道長から頼通に伝領された宇治平等院を準拠とする。京から見れば宇治川の対岸、南にある。なお八宮の邸は此岸にある。
【にはかなる御物忌みの、重く慎みたまふべく申したなれば】- 陰陽師が進言した。「申したなれば」は完了の助動詞「たる」の撥音便、無表記形に、伝聞推定の助動詞「なれ」が接続した形。
|
| 1.1.3 |
|
宮は、いささか興をそがれた思いがしたが、宰相中将が、今日のお迎えに参上なさっていたので、かえって気が楽で、あの辺りの様子も聞き伝えることができようと、ご満足なさった。
大臣には、気楽にお会いしがたく、気のおける方とお思い申し上げていらっしゃった。
|
宮は苦手としておいでになる右大臣が来ずに、お親しみの深い薫の宰相中将が京から来たのをかえってお喜びになり、八の宮邸との交渉がこの人さえおれば都合よく運ぶであろうと満足しておいでになった。右大臣という人物にはいつも気づまりさを匂宮はお覚えになるらしい。
|
【宰相中将】- 薫。
【かのわたりのけしきも伝へ寄らむと】- 八宮の姫君たちのこと。
|
| 1.1.4 |
|
ご子息の公達の、右大弁、侍従の宰相、権中将、頭少将、蔵人兵衛佐などは、みなお供なさる。
帝、后も特別におかわいがり申されていらっしゃる宮なので、世間一般のご信望もたいそう限りなく、それ以上に六条院のご縁者方は、次々の人も、みな私的なご主君として、親身にお仕え申し上げていらっしゃる。
|
右大臣の息子の右大弁、侍従宰相、権中将、蔵人兵衛佐などは初めからお随きしていた。帝も后の宮もすぐれてお愛しになる宮であったから、世間の尊敬することも大きかった。まして六条院一統の人たちは末の末まで私の主君のようにこの宮にかしずくのであった。
|
【御子の君たち、右大弁、侍従の宰相、権中将、頭少将、蔵人兵衛佐など】- 夕霧の子息。『完訳』は「(夕霧の子は)もともと六人いるが、ここは次男以下か」と注す。右大弁(従四位上相当)、侍従宰相(正四位下相当)、権中将(従四位下相当)、頭少将(正五位下相当)、蔵人兵衛佐(従五位上相当)。
【さぶらひたまふ】- 大島本は「さふらひ給」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「みなさぶらひたまふ」と「みな」を補訂する。『新大系』は底本のままとする。
【六条院の御方ざまは、次々の人も】- 『完訳』は「源氏一門の方々は、夕霧をはじめ子息たちも、匂宮を内輪の主君と思う意。明石の中宮腹の匂宮は、源氏や紫の上に特に愛されただけに、一族はこう思う」と注す。
|
|
第二段 匂宮と八の宮、和歌を詠み交す
|
| 1.2.1 |
|
土地に相応しい、ご設営などを興趣深く整えて、碁、双六、弾棊の盤類などを取り出して、思い思いに遊びに一日をお過ごしなさる。
宮は、お馴れにならない御遠出に、疲れをお感じになって、ここに泊まろうとのお考えが強いので、ちょっとご休憩なさって、夕方は、お琴などを取り寄せてお遊びになる。
|
別荘には山里らしい風流な設備がしてあって、碁、双六、弾碁の盤なども出されてあるので、お供の人たちは皆好きな遊びをしてこの日を楽しんでいた。宮は旅なれぬお身体であったから疲労をお覚えになったし、この土地にしばらく休養していたいという思召しも十分にあって、横たわっておいでになったが、夕方になって楽器をお出させになり、音楽の遊びにおかかりになった。
|
【碁、双六、弾棊の盤どもなど】- 『完訳』は「文人好みの室内遊戯」と注す。
【すさび暮らしたまふ】- 大島本は「すさひくらし給」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「すさび暮らひたまひつ」と完了助動詞「つ」を補訂する。『新大系』は底本のままとする。
【夕つ方ぞ、御琴など召して】- 『完訳』は「八の宮邸に聞こえるのを期待」と注す。
|
| 1.2.2 |
例の、かう世離れたる所は、水の音ももてはやして、物の音澄みまさる心地して、かの聖の宮にも、たださし渡るほどなれば、追風に吹き来る響きを聞きたまふに、昔のこと思し出でられて、 |
例によって、このような世間離れした所は、水の音も引立て役となって、楽の音色もひときわ澄む気がして、あの聖の宮にも、ただ棹一さしで漕ぎ渡れる距離なので、追い風に乗って来る響きをお聞きになると、昔の事が自然と思い出されて、
|
こうした大きい河のほとりというものは水音が横から楽音を助けてことさらおもしろく聞かれた。聖人の宮のお住居はここから船ですぐに渡って行けるような場所に位置していたから、追い風に混じる琴笛の音を聞いておいでになりながら昔のことがお心に浮かんできて、
|
【かの聖の宮にも、たださし渡るほどなれば】- 対岸の八宮邸。
|
| 1.2.3 |
|
「笛がたいそう美しく聞こえてくるなあ。
誰であろう。
昔の六条院のお笛の音を聞いたのは、それは実に興趣深げな愛嬌ある音色にお吹きになったものだ。
これは澄み上って、大げさな感じが加わっているのは、致仕の大臣のご一族の笛の音に似ているな」などと、独り言をおっしゃる。
|
「笛を非常におもしろく吹く。だれだろう。昔の六条院の吹かれたのは愛嬌のある美しい味のものだった。今聞こえるのは音が澄みのぼって重厚なところがあるのは、以前の太政大臣の一統の笛に似ているようだ」など独言を言っておいでになった。
|
【笛をいとをかしうも】- 以下「笛の音にこそ似たなれ」まで、八宮の独言。
【六条院の御笛の音聞きしは】- 源氏が吹いた笛の音を聴いたのは。
【致仕大臣の御族の笛の音に】- 致仕太政大臣一族の奏法。笛の奏法が、源氏は「いとをかしげに愛敬づきたる音」、致仕太政大臣は「澄み上りてことことしき気の添ひたる」と対比される。
|
| 1.2.4 |
「あはれに、久しうなりにけりや。かやうの遊びなどもせで、あるにもあらで過ぐし来にける年月の、さすがに多く数へらるるこそ、かひなけれ」 |
「ああ、何と昔になってしまったことよ。
このような遊びもしないで、生きているともいえない状態で過ごしてきた年月が、それでも多く積もったとは、ふがいないことよ」
|
「ずいぶん長い年月が私をああした遊びから離していた。人間の愉楽とするものと遠ざかった寂しい生活を今日までどれだけしているかというようなことをむだにも数えられる」
|
【あはれに、久しうなりにけりや】- 大島本は「久しう」とある。『完本』は諸本に従って「久しく」と整定する。『集成』『新大系』は底本のままとする。以下「かひなけれ」まで、八宮の独言。
|
| 1.2.5 |
|
などとおっしゃる折にも、姫君たちのご様子がもったいなく、「このような山中に引き止めたままにはしたくないものだ」とついお思い続けになられる。
「宰相の君が、同じことなら近い縁者としたい方だが、そのようには考えるわけには行かないようだ。
まして近頃の思慮の浅いような人を、どうして考えられようか」などとお考え悩まれ、所在なく物思いに耽っていらっしゃる所は、春の夜もたいへん長く感じられるが、打ち興じていらっしゃる旅寝の宿は、酔いの紛れにとても早く夜が明けてしまう気がして、物足りなく帰ることを、宮はお思いになる。
|
こんなことをお言いになりながらも、姫君たちの人並みを超えたりっぱさがお思われになって、宝玉を埋めているような遺憾もお覚えにならぬではなく、源宰相中将という人を、できるなら婿としてみたいが、かれにはそうした心がないらしい、しかも自分はその人以外の浮薄な男へ女王たちは与える気になれないのであるとお思いになって、物思いを八の宮がしておいでになる対岸では、春の夜といえども長くばかりお思われになるのであるが、右大臣の別荘のほうの客たちはおもしろい旅の夜の酔いごこちに夜のあっけなく明けるのを歎いていた。匂宮はこの日に宇治を立って帰京されるのが物足らぬこととばかりお思われになった。
|
【かかる山懐にひき籠めてはやまずもがな】- 八宮の心中の思い。『集成』は「都のしかるべき貴公子に縁づかせたいという気持」。『完訳』は「貴人との結縁を願う気持」と注す。
【宰相の君の、同じうは】- 以下「人をばいかでか」まで、八宮の心中の思い。
【近きゆかりにて見まほしげなるを】- 『集成』は「親しく姫君たちの婿にしたいようなお人柄だが」。『完訳』は「縁の深い、姫君の夫として」「親しい縁者として迎えたくなるようなお人柄であるのを」と訳す。
【さしも思ひ寄るまじかめり】- 『集成』は「薫はそんなふうに考えてみようともしないようだ。仏道に専心する薫の人柄を思ってのこと」。『完訳』は「しかしそんな期待を寄せてはなるまい」「仏道に専心する薫ゆえ。宮は薫との結縁を願いながらも断念」と注す。
【春の夜もいと明かしがたきを】- 短い春の夜も長く感じられる意。
【心やりたまへる旅寝の宿りは】- 匂宮一行。
|
|
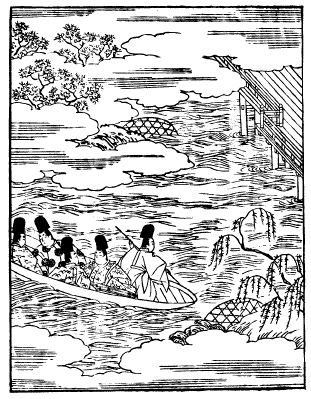 |
| 1.2.6 |
|
はるばると霞わたっている空に、散る桜があると思うと今咲き始めるのなどもあり、色とりどりに見渡されるところに、川沿いの柳が風に起き臥し靡いて水に映っている影などが、並々ならず美しいので、見慣れない方は、たいそう珍しく見捨てがたいとお思いになる。
|
遠くはるばると霞んだ空を負って、散る桜もあり、今開いてゆく桜もあるのが見渡される奥には、晴れやかに起き伏しする河添い柳も続いて、宇治の流れはそれを倒影にしていた。都人の林泉にはないこうした広い風景を見捨てて帰りがたく思召されるのである。
|
【散る桜あれば今開けそむるなど】- 『源氏釈』は「咲く桜さくらの山の桜花散る桜あれば咲く桜あり」(出典未詳)を指摘。
【川沿ひ柳の起きふしなびく水影など】- 『河海抄』は「いな筵河ぞひ柳水ゆけば起き臥しすれどその根絶えせず」(古今六帖六、柳)を指摘。
【見ならひたまはぬ人は】- 匂宮。
【いとめづらしく見捨てがたし】- 匂宮の心中の思い。
|
| 1.2.7 |
宰相は、「かかるたよりを過ぐさず、かの宮にまうでばや」と思せど、「あまたの人目をよきて、一人漕ぎ出でたまはむ舟わたりのほども軽らかにや」と思ひやすらひたまふほどに、かれより御文あり。 |
宰相は、「このような機会を逃さず、あの宮に伺いたい」とお思いになるが、「大勢の人目を避けて独り舟を漕ぎ出しなさるのも軽率ではないか」と躊躇していらっしゃるところに、あちらからお手紙がある。
|
薫はこの機会もはずさず八の宮邸へまいりたく思うのであったが、多数の人の見る前で、自分だけが船を出してそちらへ行くのは軽率に見られはせぬかと躊躇している時に八の宮からお使いが来た。お手紙は薫へあったのである。
|
【かかるたよりを】- 以下「まうでばや」まで、薫の心中。
【かれより御文あり】- 八宮から薫に手紙が届く。
|
| 1.2.8 |
|
「山風に乗って霞を吹き分ける笛の音は聞こえますが
隔てて見えますそちらの白波です」
|
山風に霞吹き解く声はあれど
隔てて見ゆる遠の白波
|
【山風に霞吹きとく声はあれど--隔てて見ゆる遠方の白波】- 八宮から薫への贈歌。『集成』は「前日聞えた笛の音の主を薫と推察しての歌。「遠方」は宇治に存した地名(今、宇治橋東詰め近くに彼方(をちかた)神社がある)で、「をち」(遠方、彼方)の意に掛ける。薫の来訪をうながす心の歌」。『完訳』は「笛の音を薫のそれと聞いて、彼の不訪を恨んだ歌」と注す。
|
| 1.2.9 |
|
草仮名でたいそう美しくお書きなっていた。
宮、「ご関心の所からの」と御覧になると、たいそう興味深くお思いになって、「このお返事はわたしがしよう」と言って、
|
字のくずし字が美しく書かれてあった。兵部卿の宮は、少なからぬ関心を持っておいでになる所からのおたよりとお知りになり、うれしく思召して、「このお返事は私から出そう」とお言いになって、次の歌をお書きになった。
|
【思すあたりの】- 大島本は「おほすあたりの」とある。『完本』は諸本に従って「思すあたり」と「の」を削除する。『集成』『新大系』は底本のままとする。匂宮の心中の思い。格助詞「の」の下に「文」などの語句が省略。
【この御返りはわれせむ】- 匂宮の詞。
|
| 1.2.10 |
|
「そちらとこちらの汀に波は隔てていても
やはり吹き通いなさい宇治の川風よ」
|
遠近の汀の波は隔つとも
なほ吹き通へ宇治の川風
|
【遠方こちの汀に波は隔つとも--なほ吹きかよへ宇治の川風】- 匂宮から八宮への返歌。「吹く」「隔つ」「彼方」「波」の語句を用いて返す。
|
|
第三段 薫、迎えに八の宮邸に来る
|
| 1.3.1 |
中将は参うでたまふ。遊びに心入れたる君たち誘ひて、さしやりたまふほど、酣酔楽遊びて、水に臨きたる廊に造りおろしたる階の心ばへなど、さる方にいとをかしう、ゆゑある宮なれば、人びと心して舟よりおりたまふ。 |
中将はお伺いなさる。
遊びに夢中になっている公達を誘って、棹さしてお渡りになるとき、「酣酔楽」を合奏して、水に臨んだ廊に造りつけてある階段の趣向などは、その方面ではたいそう風流で、由緒ある宮邸なので、人びとは気をつけて舟からお下りになる。
|
薫は自身でまいることにした。音楽好きな公達を誘って同船して行ったのであった。船の上では「酣酔楽」が奏された。河に臨んだ廊の縁から流れの水面に向かってかかっている橋の形などはきわめて風雅で、宮の洗練された御趣味もうかがわれるものであった。
|
【酣酔楽】- 高麗壱越調の曲。
【水に臨きたる】- 以下「宮なれば」まで、八宮の山荘の造作を説明した挿入句。
|
| 1.3.2 |
|
ここはまた、趣が違って、山里めいた網代屏風などで、格別に簡略にして、風雅なお部屋のしつらいを、そのような気持ちで掃除し、たいそう心づかいして整えていらっしゃった。
昔の、楽の音などまことにまたとない弦楽器類を、特別に用意したようにではなく、次々と弾き出しなさって、壱越調に変えて、「桜人」を演奏なさる。
|
右大臣の別荘も田舎らしくはしてあったが、宮のお邸はそれ以上に素朴な土地の色が取り入れられてあって、網代屏風などというものも立っていた。寂の味の豊かにある室内の飾りもおもしろく、あるいは兵部卿の宮の初瀬詣での御帰途に立ち寄る客があるかもしれぬとして、よく清掃されてもあった。すぐれた名品の楽器なども、わざとらしくなく宮はお取り出しになって、参入者たちへ提供され、一越調で「桜人」の歌われるのをお聞きになった。
|
【さる心して】- 『集成』は「薫一行を迎える心積りで」と注す。
【壱越調の心に、桜人遊びたまふ】- 『完訳』は「高麗楽「桜人」が呂の曲であるのを、壱越調(律の調子)に移して」と注す。
|
| 1.3.3 |
|
主人の宮の、お琴をこのような機会にと、人びとはお思いになるが、箏の琴を、さりげなく、時々掻き鳴らしなさる。
耳馴れないせいであろうか、「たいそう趣深く素晴らしい」と若い人たちは感じ入っていた。
|
名手の誉れをとっておいでになる八の宮の御琴の音をこの機会にお聞きしたい望みをだれも持っていたのであるが、十三絃を合い間合い間にほかのものに合わせてだけお弾きになるにとどまった。平生お聞きし慣れないせいか、奥深いよい音として若い人々は承った。
|
【主人の宮】- 大島本は「あるしの宮」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「主人の宮の」と「の」を補訂する。『新大系』は底本のままとする。
【かかるついでに】- 人々の心中の思い。八宮が琴の琴の名手であることは人々に知られていた。
【耳馴れぬけにやあらむ、「いともの深くおもしろし】- 若い同行の人々の感想。
|
| 1.3.4 |
|
土地柄に相応しい饗応を、たいそう風流になさって、はたから想像していた以上に、かすかに皇族の血筋を引くといった素性卑しからぬ人びとが大勢、王族で、四位の年とった人たちなどが、このように大勢客人が見える時にはと、以前からご同情申し上げていたせいか、適当な方々が皆参上し合って、瓶子を取る人もこざっぱりしていて、それはそれとして古風で、風雅にお持てなしなさった。
客人たちは、宮の姫君たちが住んでいらっしゃるご様子、想像しながら、関心を持つ人もいるであろう。
|
山里らしい御饗応が綺麗な形式であって、皆人がほかで想像していたに似ず王族の端である公達が数人、王の四位の年輩者というような人らが、常に八の宮へ御同情申していたのか、縁故の多少でもあるのはお手つだいに来ていた。酒瓶を持って勧める人も皆さっぱりとしたふうをしていた。一種古風な親王家らしいよさのある御歓待の席と見えた。船で来た人たちには女王の様子も想像して好奇心の惹かれる気のしたのもあるはずである。
|
【なま孫王めくいやしからぬ人あまた】- 『集成』は「かすかに皇族のお血につながるといった素姓いやしからぬ人が大勢」。『完訳』は「どうやら皇族のお血筋といった卑しからぬ人たちがたくさん」と注す。
【大君、四位の古めきたるなど】- 『集成』は「王(二世以下の親王宣下のない皇胤)で四位の人」。『完訳』は「それにまた四位で年配の孫王がたが」「これらは八の宮ゆかりの人々か」と注す。
【かねていとほしがりきこえけるにや】- 語り手の推測を挿入。
【さるべき限り参りあひて、瓶子取る人もきたなげならず】- 宴会や接待のために宮家ゆかりの人々が参集してお酌をしたりする。
【客人たちは】- 『細流抄』は「草子地也」と指摘。
【心つく人もあるべし】- 『完訳』は「語り手の推測。客人らの好色心から、匂宮のいらだちに続ける」と注す。
|
|
第四段 匂宮と中の君、和歌を詠み交す
|
| 1.4.1 |
|
あの宮は、それ以上に気軽に動けないご身分までをも、窮屈にお思いであるが、せめてこのような機会にでもと、たまらなくお思いになって、美しい花の枝を折らせなさって、お供に控えている殿上童でかわいい子を使いにして差し上げなさる。
|
兵部卿の宮はまして美しいと薫から聞いておいでになった姉妹の姫君に興味をいだいておいでになって、自由な行動のおできにならぬことを、今までから憾みに思っておいでになったのであるから、この機会になりとも女王への初めの消息を送りたいとお思いになり、そのお心持ちがしまいに抑えきれずに、美しい桜の枝をお折らせになって、お供に来ていた殿上の侍童のきれいな少年をお使いにされお手紙をお送りになった。
|
【かの宮は、まいて】- 匂宮。対岸に残っているので「かの」という。
【かかる折にだに】- 匂宮の心中の思い。
【おもしろき花の枝を】- 美しく咲いている桜の枝。
|
| 1.4.2 |
|
「山桜が美しく咲いている辺りにやって来て
同じこの地の美しい桜を插頭しに手折ったことです
|
山桜にほふあたりに尋ね来て
同じ挿頭を折りてけるかな
|
【山桜匂ふあたりに尋ね来て--同じかざしを折りてけるかな】- 匂宮から姫君たちへの贈歌。「同じかざし」は同じ皇族の血縁、親しみをこめていう。『河海抄』は「我が宿と頼む吉野に君し入らば同じかざしをさしこそはせめ」(後撰集恋四、八一〇、伊勢)を指摘。
|
| 1.4.3 |
|
野が睦まじいので」
|
野を睦まじみ(ひと夜寝にける)
|
【野を睦ましみ」--とやありけむ】- 【野を睦ましみ】-歌に添えた言葉。『源氏釈』は「紫のひともとゆゑに武蔵野の草は見ながらあはれとぞ思ふ」(古今集雑上、八六七、前太政大臣)「春の野に菫摘みにとこし我ぞ野をなつかしみ一夜寝にける」(古今六帖六、すみれ)を指摘。三光院は「草子の地なり」と指摘。 【とやありけむ】-語り手の推測。
|
| 1.4.4 |
とやありけむ。「御返りは、いかでかは」など、聞こえにくく思しわづらふ。 |
とでもあったのであろうか。
「お返事は、とてもできない」などと、差し上げにくく当惑していらっしゃる。
|
というような御消息である。お返事はむずかしい、自分にはと二人の女王は譲り合っていたが、
|
|
| 1.4.5 |
|
「このような時のお返事は、特別なふうに考えて、時間をかけ過ぎるのも、かえって憎らしいことでございます」
|
こんな場合はただ風流な交際として軽く相手をしておくべきで、あとまで引くことのないように、大事をとり過ぎた態度に出るのはかえって感じのよくないものである
|
【かかる折のこと】- 以下「しはべりし」まで、女房の詞。
【憎きことになむしはべりし】- 『完訳』は「過去の宮仕えの経験を語る形」と注す。
|
| 1.4.6 |
|
などと、老女房たちが申し上げるので、中の君にお書かせ申し上げなさる。
|
というようなことを、古い女房などが申したために、宮は中姫君に返事をお書かせになった。
|
【中の君にぞ書かせたてまつりたまふ】- 主語は八宮。
|
| 1.4.7 |
|
「插頭の花を手折るついでに、
山里の家は通り過ぎてしまう春の旅人
|
挿頭折る花のたよりに山賤の
垣根を過ぎぬ春の旅人
|
【かざし折る花のたよりに山賤の--垣根を過ぎぬ春の旅人】- 中君から匂宮への返歌。「かざし」「折る」の語句を用いて返す。
|
| 1.4.8 |
|
わざわざ野を分けてまでもありますまい」
|
野を分きてしも
|
【野をわきてしも】- 『源氏釈』は「分きてしもなに匂ふらむ秋の野にいづれともなくなびく尾花に」(出典未詳)を指摘。
|
| 1.4.9 |
と、いとをかしげに、らうらうじく書きたまへり。
|
と、たいそう美しく、上手にお書きになっていた。
|
これが美しい貴女らしい手跡で書かれてあった。
|
|
| 1.4.10 |
|
なるほど、川風も隔て心をおかずに吹き通う楽の音を、面白く合奏なさる。
お迎えに、藤大納言が、勅命によって参上なさった。
人びとが大勢参集して、何かと騒がしくして先を争ってお帰りになる。
若い人たちは、物足りなく、ついつい後を振り返ってばかりいた。
宮は、「また何かの機会に」とお思いになる。
|
河風も当代の親王、古親王の隔てを見せず吹き通うのであったから、南の岸の楽音は古宮家の人の耳を喜ばせた。迎えの勅使として藤大納言が来たほかにまた無数にまいったお迎えの人々をしたがえて兵部卿の宮は宇治をお立ちになった。若い人たちは心の残るふうに河のほうをいつまでも顧みして行った。宮はまたよい機会をとらえて再遊することを期しておいでになるのである。
|
【げに、川風も】- 「げに」は語り手の感情移入による表現。匂宮の贈歌にに納得した気持ち。
【藤大納言、仰せ言にて】- 紅梅大納言。故柏木の弟。帝の勅命によって。
【若き人びと】- 匂宮に最初から付き従っていた若い供人たち。
【返り見のみせられける】- 大島本は「かへりミのミ」とある。『完本』は諸本に従って「のみなん」と「なん」を補訂する。『集成』『新大系』は底本のままとする。
【さるべきついでして】- 匂宮の心中の思い。
|
| 1.4.11 |
|
花盛りで、四方の霞も眺めやる見所があるので、漢詩や和歌も、作品が多く作られたが、わずらわしいので詳しく尋ねもしないのである。
|
一行の人々の山と水の風景を題にした作が詩にも歌にも多くできたのであるが細かには筆者も知らない。
|
【唐のも大和のも、歌ども多かれど、うるさくて尋ねも聞かぬなり】- 語り手の省筆の辞。『孟津抄』は「草子地也」と指摘。『全集』は「人の語るのを聞いたものを書きとめている体を装っている表現。和歌や漢詩を並べ立てることを避ける技法である」と注す。
|
| 1.4.12 |
|
何かと騒々しくて、思うようにも意を尽くして言いやることもできずじまいだったことを、残念に宮はお思いになって、手引なしでもお手紙は常にあるのだった。
宮も、
|
周囲に御遠慮があって宇治の姫君へ再三の消息のおできにならなかったことを匂宮は飽き足らぬように思召して、それからは薫の手をわずらわさずに、直接のお文がしばしば八の宮へ行くことになった。父君の宮も、
|
【しるべなくても御文は常にありけり】- 『花鳥余情』は「近江路をしるべなくても見てしがな関のこなたはわびしかりけり」(後撰集恋三、七八六、源中正)を指摘。
【宮も】- 八宮。
|
| 1.4.13 |
|
「やはり、お返事は差し上げなさい。
ことさら懸想文のようには扱うまい。
かえって心をときめかさせることになってしまいましょう。
たいそう好色の親王なので、このような姫がいる、とお聞きになると、放っておけないと思うだけの戯れ事なのでしょう」
|
「初めどおりにお返事を出すがよい。求婚者風にこちらでは扱わないでおこう。交友として無聊を慰める相手にはなるだろう。風流男でいられる方が若い女王のいることをお聞きになっての軽い遊びの心持ちだろうから」
|
【なほ、聞こえたまへ】- 以下「すさびなめり」まで、八宮の詞。
【なほもあらぬすさびなめり】- 『集成』は「ほっておかれないというだけのお遊びだろう」。『完訳』は「放っておけぬと思うだけの戯れ事なのだろう」と訳す。
|
| 1.4.14 |
と、そそのかしたまふ時々、中の君ぞ聞こえたまふ。姫君は、かやうのこと、戯れにももて離れたまへる御心深さなり。 |
と、お促しなさる時々、中の君がお返事申し上げなさる。
姫君は、このようなことは、冗談事にもご関心のないご思慮深さである。
|
こんなふうにお勧めになる時などには中姫君が書いた。大姫君は遊びとしてさえ恋愛を取り扱うことなどはいとわしがるような高潔な自重心のある女性であった。
|
【姫君は】- 大君。匂宮の手紙に中君が返事を書く。大君はこうした事にまったく関心のない様子を強調。
|
| 1.4.15 |
|
いつとなく心細いご様子で、春の日長の所在なさは、ますます過ごしがたく物思いに耽っていらっしゃる。
ご成長なさったご容姿器量も、ますます優れ、申し分なく美しいのにつけても、かえっておいたわしく、「不器量であったら、もったいなく、惜しいなどの思いは少なかったろうに」などと、明け暮れお悩みになる。
|
いつでも心細い山荘住まいのうちにも、春の日永の退屈さから催される物思いは二人の女王から離れなかった。いよいよ完成された美は父宮のお心にかえって悲哀をもたらした。欠点でもあるのであれば惜しい存在であると歎かれることは少なかろうがなどと煩悶をあそばされるのであった。
|
【春のつれづれは、いとど暮らしがたく眺めたまふ】- 『花鳥余情』は「思ひやれ霞こめたる山ざとに花まつほどの春のつれづれ」(後撰集春上、六六、上東門院中将)を指摘。
【ねびまさりたまふ御さま容貌ども】- 接尾語「ども」複数は、大君と中君を表す。
【心苦しく】- 大島本は「心くるしく」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「心苦しう」と校訂する。『新大系』は底本のままとする。
【かたほにもおはせましかば】- 以下「薄くやあらまし」まで、八宮の心中の思い。反実仮想の構文。
|
| 1.4.16 |
|
姉君は二十五歳、中の君は二十三歳におなりであった。
|
大姫君は二十五、中姫君は二十三になっていた。
|
【姉君二十五、中の君二十三にぞなりたまひける】- 『完訳』は「当時の上流貴族の姫君は、十五、六歳で結婚するのが普通」と注す。結婚適齢期という通念はないが、婚期を過ごした姉妹である。
|
|
第五段 八の宮、娘たちへの心配
|
| 1.5.1 |
|
宮は、重く身を慎むべきお年なのであった。
何となく心細くお思いになって、ご勤行を例年よりも弛みなくなさる。
この世に執着なさっていないので、死出の旅立ちの用意ばかりをお考えなので、極楽往生も間違いないお方だが、ただこの姫君たちの事に、たいそうお気の毒で、この上ない道心の強さだが、「かならず、今が最期とお見捨てなさる時のお気持ちは、きっと乱れるだろう」と、拝する女房もご推察申し上げるが、お思いの通りではなくても、並に、それでも人聞きの悪くなく、世間から認めてもらえる身分の人で、真実に後見申し上げよう、などと、思ってくれる方がいたら、知らぬ顔をして黙認しよう、一人一人が人並みに結婚する縁があったら、その人に譲って安心もできようが、そこまで深い心で言い寄る人はいない。
|
宮のために今年は重く謹慎をあそばされねばならぬ年と占われていた。心細い気をお覚えになって、仏勤めを平生以上にゆるみなくあそばす八の宮であった。この世に何の愛着をも今はお持ちにならぬお心であったから、未来の世のためにいっさいを捨てて仏弟子の生活にもおはいりになりたいのであったが、ただ二女王をこのままにしておく点に御不安があって、深い信仰はおありになっても、このことでなすべからぬ煩悶をするようになるのは遺憾であると思召すらしいのを、奉仕する女房たちはお察ししていたが、そのことについて宮は、必ずしも理想どおりではなくとも、世間体もよく、親として、それくらいであれば譲歩してもよいと思われる男が求婚して来たなら、立ち入って婿としての世話はやかないままで結婚を許そう、一人だけがそうした生活にはいれば、それに大体のことは頼みうることにもなって安心は得られるであろうが、それほどにまで誠意を見せて婚を求める人もない。
|
【宮は、重く慎みたまふべき年なりけり】- 八宮は男の厄年六十一歳。
【出で立ちいそぎをのみ思せば】- 『集成』は「後世安楽の支度のことばかりお考えなので」。『完訳』は「死出の旅への出発の用意」と訳す。
【涼しき道にも】- 極楽浄土。
【かならず、今はと見捨てたまはむ御心は、乱れなむ】- 女房たちの思い。
【思すさまにはあらずとも】- 以下「慰めおくべきを」まで、八宮の心中の苦慮を地の文に叙述。
【一所一所世に住みつきたまふよすがあらば】- 『集成』は「姫君たちのうちどちらかお一人が、この世に暮していかれるより所があるならば(どちらか一人が夫を迎えたら)」。『完訳』は「大君、中君それぞれが」「姫君たちのお一人お一人がお暮しになられるような縁があったら」と注す。
【さまで深き心に尋ねきこゆる人もなし】- 八宮の心中の苦慮を地の文で受ける。
|
| 1.5.2 |
|
時たまちょっとしたきっかけで、懸想めいたことを言う人は、まだ年若い人の遊び心で、物詣での中宿りや、その往来の慰み事に、それらしいことを言っても、やはり、このように落ちぶれた様子などを想像して、軽んじて扱うのは、心外なので、なおざりの返事をさえおさせにならない。
三の宮は、やはりお会いしないではいられないとのお思いが深いのであった。
前世からの約束事でいらしたのであろうか。
|
まれまれにはちょっとした機会と仲介人を得て、そうした話もあるが、皆まだ若々しい人たちが一時的に好奇心を動かして、初瀬、春日への中休みの宇治での遊び心のような恋文を送って来る程度にとどまり、こうした閑居をあそばすだけの宮として、女王にはたいした敬意も持たず礼のない軽蔑的な交渉をして来るのなどには、その場だけの返事をすら女王にお書かせにならない。兵部卿の宮だけはどうしてもこの恋を遂げたいという熱意を持っておいでになる。これも前生の約束事であったのかもしれぬ。
|
【物詣での中宿り、行き来のほどのなほざりごとに】- 宇治は、京から初瀬へ行く交通要衝で、その中継、休憩所である。
【三の宮】- 匂宮。
【さるべきにやおはしけむ】- 『新釈』は「草子地である」と指摘。『全集』は「匂宮と宇治の姫君とが結ばれる必然性は、現世の状況からは考えられないだけに、こうした語り手のことばが必要になってくる」。『集成』は「物語の成行きを予告する気持の草子地」と注す。
|
|
第二章 薫の物語 秋、八の宮死去す
|
|
第一段 秋、薫、中納言に昇進し、宇治を訪問
|
| 2.1.1 |
宰相中将、その秋、中納言になりたまひぬ。いとど匂ひまさりたまふ。世のいとなみに添へても、思すこと多かり。いかなることと、いぶせく思ひわたりし年ごろよりも、心苦しうて過ぎたまひにけむいにしへざまの思ひやらるるに、罪軽くなりたまふばかり、行ひもせまほしくなむ。かの老い人をばあはれなるものに思ひおきて、いちじるきさまならず、とかく紛らはしつつ、心寄せ訪らひたまふ。 |
宰相中将は、その年の秋に、中納言におなりになった。
ますますご立派におなりになる。
公務が多忙になるにつけても、お悩みになることが多かった。
どのような事かと、気がかりに思い続けてきた往年よりも、おいたわしくお亡くなりになったという故人の様子が思いやられるので、罪障が軽くおなりになる程の、勤行もしたく思う。
あの老女をもお気の毒な人とお思いになって、目立ってではなく、何かと紛らわし紛らわししては、好意を寄せお見舞いなさる。
|
源宰相中将はその秋中納言になった。いよいよはなやかな高官になったわけであるが、心には物思いが絶えずあった。自身の出生した初めの因縁に疑いを持っていたころよりも、真相を知った時に始まった過去の肉親に対する愛と同情とともに、かの世でしているであろう罪についての苦闘を思いやることが重苦しい負担に覚えられ、その父の罪の軽くなるほどにも自身で仏勤めがしたいと願われるのであった。あの話をした老女に好意を持ち、人目を紛らすだけの用意をして常に物質の保護を怠らぬようになった。
|
【いかなることと、いぶせく思ひわたりし】- 薫の出生の秘密。
【あはれなるものに】- 『集成』は「しみじみといとしい者と」。『完訳』は「不憫な者よと」と訳す。
|
| 2.1.2 |
|
宇治に参らず久しくなってしまったのを、思い出してご訪問なさった。
七月ごろになってしまったのだ。
都ではまだ訪れない秋の気配を、音羽山近くの、風の音もたいそう冷やかで、槙の山辺もわずかに色づき初めて、やはり山路に入ると、趣深く珍しく思われるが、宮はそれ以上に、いつもよりお待ち喜び申し上げなさって、今回は、心細そうな話を、たいそう多く申し上げなさる。
|
中納言はしばらく宇治の宮をお訪ねせずにいたことを急に思い出して出かけた。街の中にはまだはいって来ぬ秋であったが、音羽山が近くなったころから風の音も冷ややかに吹くようになり、槙の尾山の木の葉も少し色づいたのに気がついた。進むにしたがって景色の美しくなるのを薫は感じつつ行った。
中納言をお迎えになった宮は平生にも増して喜びをお見せになり、心細く思召すことを何かと多くこの人へお話しになるのであった。
|
【七月ばかりになりにけり】- 春の二月二十日ころに初瀬詣での匂宮を迎えに宇治に行って以来の訪問。
【音羽の山近く、風の音も】- 『花鳥余情』は「松虫の初声誘ふ秋風は音羽山より吹きそめにけり」(後撰集秋上、二五一、読人しらず)を指摘。
【宮はまいて、例よりも待ち喜びきこえ】- 『集成』は「八の宮は、なおさらのこと。薫以上に久々のさいかい喜ぶ風情」。「例よりも」とは死期の近いことの伏線。
|
| 2.1.3 |
「亡からむ後、この君たちを、さるべきもののたよりにもとぶらひ、思ひ捨てぬものに数まへたまへ」 |
「亡くなった後、この姫君たちを、何かの機会にはお尋ね下さり、お見捨てにならない中にお数え下さい」
|
お亡くなりになったあとでは女王たちを時々訪ねて来てやってほしい
|
【亡からむ後】- 以下「数まへたまへ」まで、八宮の詞。姫君たちを託す。
|
| 2.1.4 |
|
などと、意中をそれとなく申し上げなさると、
|
と思召すこと、親戚の端の者として心にとめておいてほしいと思召すことを、正面からはお言いにならぬのではあるが、御希望として仰せられることで、薫は、
|
【おもむけつつ聞こえたまへば】- 『集成』は「意中をそれとなく申し上げなさるので」。『完訳』は「そちらへ話を向けながらお申し上げになるので」と訳す。
|
| 2.1.5 |
|
「一言なりとも先に承っておりましたので、決して疎かには致しません。
現世に執着しまいと、係累を持たないでおります身なので、何事も頼りがいのなく将来性のない身でございますが、そのようなふうでしても生き永らえておりますうちは、変わらない気持ちを御覧になっていただこうと存じます」
|
「一言でも承っておきます以上、決して私はなすべきを怠る者ではございません。この世に欲望を持つことのないようにと心がけまして、世の中に対して人よりは冷淡な態度をとっておりますから、立身をいたすことも望まれませんが、私の生きておりますかぎりは、ただ今と変わりのない志を御家族にお見せ申したいと考えております」
|
【一言にても】- 以下「なむ思うたまふる」まで、薫の返事。八宮もの申し出を応諾する。
【はぶきはべる身にて】- 『集成』は「切り捨てております身の上で」。『完訳』は「妻子など係累をもたない意」と注す。
【めぐらいはべらむ限りは】- 自分がこの世に生きております限りは、の意。
【御覧じ知らせむ】- 姫君たちに。
|
| 2.1.6 |
など聞こえたまへば、うれしと思いたり。
|
などと申し上げなさると、嬉しくお思いになった。
|
とお答えしたのを、八の宮はうれしく思召し御満足をあそばされた。
|
|
|
第二段 薫、八の宮と昔語りをする
|
| 2.2.1 |
|
まだ夜明けには遠い月が明るく差し出して、山の端が近い感じがするので、念誦をたいそうしみじみと唱えなさって、昔話をなさる。
|
おそく昇るころの月が出て山の姿が静かに現われた深夜に、宮は念誦をあそばしながら薫へ昔の話をお聞かせになった。
|
【山の端近き心地するに】- 『完訳』は「宮の死期の近きを擬えた表現」と注す。
【念誦いとあはれにしたまひて】- 『集成』は「心に仏を念じて真言をとなえ、成仏を願う」と注す。
|
| 2.2.2 |
|
「最近の世の中は、どのようになったのでしょうか。
宮中などでは、このような秋の月の夜に、御前での管弦の御遊の時に伺候する人達の中で、楽器の名人と思われる人びとばかりが、それぞれ得意の楽器を合奏しあった調子などは、仰々しいのよりも、嗜みがあると評判の女御、更衣の御局々が、それぞれは張り合っていて、表面的な付き合いはしているようで、夜更けたころの辺りが静まった時分に、悩み深い風情に掻き調べ、かすかに流れ出た楽の音色などが、聞きどころのあるのが多かったな。
|
「近ごろの世の中というものはどうなっているのか私には少しもわからない。御所などでこうした秋の月夜に音楽の演奏されるのに私も侍していて、その当時感じたことですが、名人ばかりが集まって、とりどりな技術を発揮させる御前の合奏よりも、上手だという名のある女御、更衣のいる局々で心の内では競争心を持ち、表面は風流に交際している人たちの曹司の夜ふけになって物音の静まった時刻に、何ということのない悩ましさを心に持って、ほのかに弾き出される琴の音などにすぐれたものがたくさんありましたよ。
|
【このころの世は】- 以下「心苦しかるべき」まで、八宮の詞。
【宮中などにて】- 『集成』は「見馴れない言葉であるが、仏者としての八の宮の特殊な用語なのであろう。「宮(く)」は呉音」と注す。「宮内庁(くないちょう)」など。
【拍子など】- 『集成』は「ここは、調子、リズムの意であろう」と注す。
【夜深きほどの人の気しめりぬるに、心やましく掻い調べ、ほのかにほころび出でたる物の音など】- 【夜深きほどの人の気しめりぬるに心やましく掻い調べ】-『休聞抄』は「秋の夜は人を静めてつれづれとかきなす琴の音にぞ泣きぬる」(後撰集秋中、三三四、読人しらず)を指摘。 【心やましく掻い調べほのかにほころび出でたる物の音など】-『集成』は「悩み深い風情にかき鳴らして。閨怨を訴える趣」と注す。
|
| 2.2.3 |
|
何事につけても、女性というのは、慰み事の相手にちょうどよく、何となく頼りないものの、人の心を動かす種であるのでしょう。
それだから、罪が深いのでしょうか。
子を思う道の闇を思いやるにも、男の子は、それほども親の心を乱さないであろうか。
女の子は、運命があって、何とも言いようがないと諦めてしまうような場合でも、やはり、とても気にかかるもののようです」
|
何事にも女は人の慰めになることで能事が終わるほどのものですが、それがまた人を動かす力は少なくないのですね。だから女は罪が深いとされているのでしょう。親として子の案ぜられる点でも、男の子はさまで親を懊悩させはしないだろうが、女はどうせ女で、親が何と思っても宿命に従わせるほかはないのでしょうが、それでも愍然に思われて、親のためには大きな羈絆になりますよ」
|
【何ごとにも、女は、もてあそびのつまにしつべく、ものはかなきものから】- 『集成』は「何ごとにつけても、女というものは、なぐさみのきっかけになるもので。「もてあそび」は、愛玩の対象。後宮の女性についての思い出話から、一般論に転ずる」と注す。
【子の道の闇を思ひやるにも】- 『伊行釈』は「人の親の心は闇にあらねども子を思ふ道に惑ひぬるかな」(後撰集雑一、一一〇二、藤原兼輔)を指摘。
【女は、限りありて】- 『完訳』は「女なりの宿運。女は結婚の相手次第、として、その相手がまともでない場合を想定した物言い」と注す。
|
| 2.2.4 |
など、おほかたのことにつけてのたまへる、いかがさ思さざらむ、心苦しく思ひやらるる御心のうちなり。 |
などと、一般論としておっしゃるが、どうしてそのようにお思いにならないことがあろうか、おいたわしく推察される宮のご心中である。
|
と抽象論としてお言いになる言葉を聞いてもお道理至極である、どんなに女王がたを御心配になっておられるかということが薫にわかるのであった。
|
【いかがさ思さざらむ】- 『一葉抄』は「草子詞」と指摘。『集成』は「いかにもそうおぼしめすに違いないことだ。地の文であるが、以下、聞いている薫の心中」。薫の心中を挿入句で挟み込む。
|
| 2.2.5 |
|
「すべて、ほんとうに、先程申し上げましたようにすべてこの世の事は執着を捨ててしまったせいでしょうか、自分自身のことは、どのようなこととも深く分かりませんが、なるほどつまらないことですが、音楽を愛する心だけは、捨てることができません。
賢く修業する迦葉も、そうですから、立って舞ったのでございましょう」
|
「あなた様のお教えのとおりに、私も苦しい羈絆を持つまいと決心してまいりましたせいですか、自身にはそうした苦しい親心というものを経験いたしませんが、ただ一つ私には音楽という愛着の覚えられるものがございまして、それによって遁世もできずにおります。賢明な迦葉もやはりそんな心があって舞をしたりしたものでしょうか」
|
【すべて、まことに】- 以下「はべりけむ」まで、薫の詞。
【しか思うたまへ捨てたるけにや】- 薫の前言「世の中に心をとどめじと、はぶきはべる身にて」(第二章一段)をさす。
【声にめづる心こそ】- 音楽を愛する心。
【迦葉も、さればや、立ちて舞ひはべりけむ】- 『完訳』は「釈迦の十大弟子の一人。頭陀(乞食修行)の第一人者といわれた。香山大樹緊那羅が仏前で瑠璃琴を弾き、八万四千音楽を奏した時、迦葉が威儀を忘れ、起って舞ったという(大樹緊那羅経)」と注す。
|
| 2.2.6 |
など聞こえて、飽かず一声聞きし御琴の音を、切にゆかしがりたまへば、うとうとしからぬ初めにもとや思すらむ、御みづからあなたに入りたまひて、切にそそのかしきこえたまふ。箏の琴をぞ、いとほのかに掻きならしてやみたまひぬる。いとど人のけはひも絶えて、あはれなる空のけしき、所のさまに、わざとなき御遊びの心に入りてをかしうおぼゆれど、うちとけてもいかでかは弾き合はせたまはむ。 |
などと申し上げて、名残惜しく聞いたお琴の音を、切にご希望なさるので、親しくなるきっかけにでもとお思いになってか、ご自身はあちらにお入りになって、切にお勧め申し上げなさる。
箏の琴を、とてもかすかに掻き鳴らしてお止めになった。
常にもまして人の気配もなくひっそりとして、しみじみとした空の様子、場所柄から、ことさらでない音楽の遊びが心にしみて興趣深く思われるが、気を許してどうして合奏なさろうか。
|
などと言って、いつぞや少し聞いた琴と琵琶の調べを今一度聞きたいと熱心に宮へお願いする薫であった。家族と薫を親しくさせる第一歩にそれをさせようと思召すのか、宮は御自身で女王たちの室へお行きになって、ぜひにと弾奏をお勧めになった。十三絃の琴がほのかにかき鳴らされてやんだ。人けの少ない宮の内に、身にしむ初秋の夜のわざとらしからぬ琴の音のするのは感じのよいものであったが、女王たちにすれば、よい気になって合奏などはできぬと思うのが道理だと思われた。
|
【うとうとしからぬ初めにもとや思すらむ】- 語り手の八宮の心中の思いを推測。『集成』は「薫と姫君たちがこれから親しく付き合うことになるきっかけにしようというおつもりなのか。自分の亡きあとのことを考えた八の宮の配慮」と注す。
【うちとけてもいかでかは弾き合はせたまはむ】- 反語表現。
|
| 2.2.7 |
「おのづからかばかりならしそめつる残りは、世籠もれるどちに譲りきこえてむ」 |
「自然とこれくらい引き合わせた後は、若い者同士にお任せ申そう」
|
「こんなにして御交際する初めを作ったのですから、若い子らにしばらく客人をまかせておくことにしよう」
|
【おのづから】- 以下「譲りきこえてむ」まで、八宮の詞。『完訳』は「薫と姫君たちを引き合せたとする。「馴らす」「鳴らす」が掛詞」と注す。
|
| 2.2.8 |
とて、宮は仏の御前に入りたまひぬ。
|
と言って、宮は仏の御前にお入りになった。
|
それから宮は仏間へおはいりになるのだったが、
|
|
| 2.2.9 |
|
「わたしが亡くなって草の庵が荒れてしまっても
この一言の約束だけは守ってくれようと存じます
|
「われなくて草の庵は荒れぬとも
この一ことは枯れじとぞ思ふ
|
【われなくて草の庵は荒れぬとも--このひとことはかれじとぞ思ふ】- 以下「多くもなりぬるかな」まで、八宮から薫への贈歌。「一言」と「一琴」、「枯れ」と「離れ」の掛詞。「草」と「枯れ」は縁語。
|
| 2.2.10 |
かかる対面もこのたびや限りならむと、もの心細きに忍びかねて、かたくなしきひが言多くもなりぬるかな」 |
このようにお目にかかることも今回が最後になるだろうと、何となく心細いのに堪えかねて、愚かなことを多くも言ってしまったな」
|
こうしてお話のできるのもこれが最終になるような心細い感情を私はおさえることができずに、親心のたあいないこともたくさん言ったでしょう。すまないことです」
|
【かたくなしきひが言】- 『完訳』は「姫君への心配を、仏道者にあるまじきことと恥じた」と注す。
|
| 2.2.11 |
とて、うち泣きたまふ。
客人、
|
と言って、お泣きになる。
客人は、
|
と言ってお泣きになった。薫は、
|
|
| 2.2.12 |
|
「どのような世になりましても訪れなくなることはありません
この末長く約束を結びました草の庵には
|
「いかならん世にか枯れせん長き世の
契り結べる草の庵は
|
【いかならむ世にかかれせむ長き世の--契りむすべる草の庵は】- 薫の返歌。「草の庵」「かれ」の語句を用いて返す。「草」と「結ぶ」は縁語。
|
| 2.2.13 |
相撲など、公事ども紛れはべるころ過ぎて、さぶらはむ」 |
相撲など、公務に忙しいころが過ぎましたら、伺いましょう」
|
御所の相撲などということも済みまして、時間のできますのを待ちましてまた伺いましょう」
|
【相撲など】- 以下「過ぎてさぶらはむ」まで、薫の詞。相撲の節会は七月下旬。
|
| 2.2.14 |
など聞こえたまふ。
|
などと申し上げなさる。
|
などと言っていた。
|
|
|
第三段 薫、弁の君から昔語りを聞き、帰京
|
| 2.3.1 |
|
こちらで、あの問わず語りの老女を召し出して、残りの多い話などをおさせになる。
入方の月が、すっかり明るく差し込んで、透影が優美なので、姫君たちも奥まった所にいらっしゃる。
世の常の懸想人のようではなく、思慮深くお話を静かに申し上げていらっしゃるので、しかるべきお返事などを申し上げなさる。
|
別室で薫はあの昔語りを聞かせてくれた老女を呼び出して、悲しくもなつかしくも思われる話の続きをさせて聞いた。落ちようとする月は明るく座敷の中を照らして、薫の透き影は艶に御簾のあちらから見えた。隣の室には奥へ寄って女王たちがすわっていた。普通の求婚者の言葉ではなく、優雅な話題をこしらえてその人たちにも薫は話していたが、言うべき時には姫君も返辞をした。
|
【入り方の月】- 大島本は「いりかたの月」とある。『完本』は諸本に従って「入方の月は」と「は」を補訂する。『集成』『新大系』は底本のままとする。
【透影なまめかしきに】- 御簾越しに見える薫の優美な姿。
【さるべき御いらへなど聞こえたまふ】- 主語は姫君たち。
|
| 2.3.2 |
|
「三の宮が、たいそうご執心でいられる」と、心中には思い出しながら、「自分ながら、やはり普通の人とは違っているぞ。
あれほど宮ご自身がお許しになることを、それほどにも急ぐ気にもなれないことよ。
が、結婚など思いもよらないことだとは、さすがに思われない。
このようにして言葉を交わし、季節折々の花や紅葉につけて、感情や情趣を通じ合うのに、憎からず感じられる方でいらっしゃるので、自分と縁がなく、他人と結婚なさるのは」、やはり残念なことだろうと、自分のもののような気がするのであった。
|
兵部卿の宮が非常に興味を持っておいでになる女性たちであるということを思って、自分ながらもこんなに接近していながら一歩を進めようとすることをしないのは、これを普通の男と違った点とすべきである。自然に自分への愛を相手が覚えてくれるのを急ぐこととも思われないと考えているのが薫の本心であった。しかも恋愛の成立を希望していないわけではないのである。こうした交際でおりふしの風物について書きかわす相手としては満足を与える女性であったから、宿縁のために他と結婚するようなことが女王にあっては遺憾を覚えるであろう、自分の存在している以上は断じてそれはさせたくないというふうに思っていた。
|
【わが心ながら】- 以下「なりたまはむは」あたりまで、薫の心中。末尾は地の文に流れる。
【さばかり御心もて許いたまふことの】- 大島本は「ゆるひ給」とある。「ひ」は「い」の誤り。よって訂す。『『集成』は「ここまで宮がご自分から進んでお許しになることが。姫君たちとの結婚のこと。将来の世話を頼むとは、暗黙のうちに結婚を前提とした依頼と考えてよいのである」と注す。
【もて離れて、はたあるまじきこととは、さすがにおぼえず】- 『集成』は「しかし結婚が全然問題にならないことだとは思われず」と訳す。
【かやうにてものをも聞こえ交はし】- 『完訳』は「以下、清らかな親交をと考えもするが、それも不可能かと思う」と注す。
【宿世異にて】- 姫君たちが自分とは縁がなくて、他人と結婚する場合を想像。
【領じたる心地しけり】- 『集成』は「もう自分のものという気がするのだった。ここの文末は、地の文の形で薫の気持を直接に書く」。『完訳』は「直接話法は間接話法に転ずる。すでに自分のもの、という気持。語り手の評言の加わった文末」と注す。
|
| 2.3.3 |
まだ夜深きほどに帰りたまひぬ。
心細く残りなげに思いたりし御けしきを、思ひ出できこえたまひつつ、「騒がしきほど過ぐして参うでむ」と思す。
兵部卿宮も、この秋のほどに紅葉見におはしまさむと、さるべきついでを思しめぐらす。
|
まだ夜明けに間のあるうちにお帰りになった。
心細く先も長くなさそうにお思いになったご様子を、お思い出し申し上げながら、「忙しい時期を過ごしてから伺おう」とお思いになる。
兵部卿宮も、今年の秋のころに紅葉を見にいらっしゃりたいと、適当な機会をお考えになる。
|
まだ夜の明けきらぬ時刻に薫は帰って行った。心細い御様子でみずから余命の少ないふうに観じておいでになった八の宮の御事が始終心にかかって、忙しい時が過ぎたならまた宇治をお訪ねしようと薫は考えていた。兵部卿の宮も秋季のうちに紅葉見として行きたいと思召してよい機会をうかがっておいでになった。
|
|
| 2.3.4 |
御文は、絶えずたてまつりたまふ。女は、まめやかに思すらむとも思ひたまはねば、わづらはしくもあらで、はかなきさまにもてなしつつ、折々に聞こえ交はしたまふ。 |
お手紙は、絶えず差し上げなさる。
女は、本気でお考えになっているのだろうとはお思いでないので、厄介にも思わず、何気ない態度で、時々ご文通なさる。
|
お手紙はしばしば行く。女のほうでは真心からの恋とは認めていないのであるから、うるさがるふうは見せずに、微温的に扱った返事だけは時々出していた。
|
【女は】- 『完訳』は「匂宮の贈答の相手、中の君。男女関係を強調した呼称に注意」と注す。
【はかなきさまにもてなしつつ】- 『集成』は「軽く応じるといったあしらいぶりで」と注す。
|
|
第四段 八の宮、姫君たちに訓戒して山に入る
|
| 2.4.1 |
|
秋が深まって行くにつれて、宮は、ひどく何となく心細くお感じになったので、「いつものように、静かな場所で、念仏を専心に行おう」とお思いになって、姫君たちにもしかるべきことを申し上げなさる。
|
秋がふけてゆくにしたがって八の宮は健康でなくおなりになって、いつもおいでになる山の寺へ行って、念仏だけでも専念にしたいと思召しになり、女王たちにも現在の感想と、知りがたい明日についての注意などをお話しになるのであった。
|
【宮は】- 八宮。
【例の、静かなる所にて】- 阿闍梨のいる山寺。『集成』は「例年のように、もの静かな阿闍梨の山寺で」。『完訳』は「例のごとく静かな山寺で」と訳す。
【君たちにもさるべきこと聞こえたまふ】- 『完訳』は「最期の別れになるかもしれぬという予感から、言葉が遺言めく」と注す。
|
| 2.4.2 |
|
「この世の習いとして、永遠の別れは避けられないもののようだが、気の慰まるようなことがあれば、悲しさも薄らぐもののようです。
また後事を託せる人もなく、心細いご様子の二人を、うち捨てて行くことがまことに辛い。
|
「人生のそれが常で、皆死んで行かねばならないのだが、その際にも家族の上のことで、何か安心が見いだせれば、それを慰めにして悲しみに勝つこともできるものらしいが、私の場合は、このあとをだれが引き受けて行ってくれるという人もないあなたがたを残して行くのだから非常に悲しい。
|
【世のこととして】- 以下「なむよかるべき」まで、八宮の詞。
【思ひ慰まむ方ありてこそ、悲しさをも覚ますものなめれ】- 『集成』は「何か気持の安まるようなことでもあるのでしたら、(死別の)悲しみも薄らぐというものでしょう。後顧の憂いがないなら、自分もいささか心を安んじて死ねるのだが、の意」と注す。
|
| 2.4.3 |
|
けれども、その程度のことで妨げられて、無明長夜の闇にまで迷うのは無益なことだ。
一方でお世話して来た今でさえ執着を断ち切っていたのだから、亡くなった後のことは、知ることはできないものであるが、私一人だけのためでなく、お亡くなりになった母君の面目をもつぶさぬよう、軽率な考えをなさいますな。
|
けれどもこんなことに妨げられて純一な信仰を得ることができなくなれば、すべてがだめなことになって、永久の闇に迷っていなければならなくなります。あなたがたを眼前に置きながらも死んで行く日は別れねばならないのだから、死後のことにまで干渉をするのではないが、私だけでなく、あなたがたの祖父母の方がたの不名誉になるような軽率な結婚などはしてならない。
|
【さばかりのことに妨げられて】- 「さばかり」は直前の「見譲る人もなく心細げなる御ありさまどもをうち捨ててむが」という、姫君たちの将来の不安をさす。
【長き夜の闇にさへ惑はむが】- 無明長夜の闇。現世に執着する煩悩のために真の悟りを得ず(極楽浄土に成仏することを得ず)、六道に輪廻することをいう。
【去りなむうしろのこと、知るべきことにはあらねど】- 『集成』は「死んでしまったそのあとのことをとやかく思うべきことではありませんが」。『完訳』は「死後のことに口出しすべきでもないのですが」と訳す。「知るべき」の主体は八宮。
【わが身一つにあらず】- 八宮をさす。
【過ぎたまひにし御面伏せに】- 亡き母君の面目。
|
| 2.4.4 |
|
しっかりと頼りになる人以外には、相手の言葉に従って、この山里を離れなさるな。
ただ、このように世間の人と違った運命の身とお思いになって、ここで一生を終わるのだとお悟りなさい。
一途にその気になれば、何事もなく過ぎてしまう歳月なのである。
まして、女性は、女らしくひっそりと閉じ籠もって、ひどくみっともない、世間からの非難を受けないのがよいでしょう」
|
根底もない一時的な人の誘惑に引かれてこの山荘を出て行くようなことはしないようになさい。ただ自分は普通の人の運命と違った運命を持っている人間であると自分を思って、生涯をここで果たす気になっているがいい。その堅い信念さえ持っておれば、長いと思う人生もいつか済んでゆくものなのだ。ことに女であるあなたたちは、世間並みの幸福を願わずに堪え忍んでいることでいろいろと人から批難をされるようなこともなく一生を過ごすがいいでしょう」
|
【おぼろけのよすがならで】- 『完訳』は「軽薄な人との結婚を戒めて、山里での隠棲を勧める」と注す。
【ただ、かう人に違ひたる契り異なる身と思しなして】- 『集成』は「ただこのように、人とは違った特別の運命(さだめ)の身の上とお考えになって。結婚というようなことは考えるな、の意」と注す。
【ひたぶるに思ひなせば、ことにもあらず過ぎぬる年月なりけり】- 大島本は「思なせは」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「思ひしなせば」と強調の意の副助詞「し」を補訂する。『新大系』は底本のままとする。八宮の人生経験に基づく説得。現世は仮の世であり、あの世に真実の世がある、という仏教思想がある。
|
| 2.4.5 |
|
などとおっしゃる。
どうなるかの将来の身の上のありようまでは、お考えも及ばず、ただ、「どのようにして、先立たれ申して後は、この世に片時も生きていられようか」とお思いになると、このように心細い状態を前もっておっしゃるので、何とも言いようもないお二方の嘆きである。
心の中でこそ執着をお捨てになっていらしたようであるが、明け暮れお側に馴れ親しみなさって、急に別れなさるのは、冷淡な心からではないが、なるほど恨めしいに違いないご様子だったのである。
|
お聞きしている姫君らは、どう自分たちがなって行くかというような不安さよりも、父君がお亡れになっては人生に片時も生きていられるものでないという平生からの心持ちが、こんなふうな孤児になっての将来のことなどをお言いになることによって、言いようもない悲しみになって、宮は心の中でこそ娘への愛情から離れようと努力はしておいでになったであろうが、明け暮れそばにいてあたたかい手で育んでおいでになったのであるから、にわかにそうした意見をお言いだしになったのは、冷酷なのではないが、女王たちにとってうらめしく思われるのはもっともと見えた。
|
【ともかくも身のならむやうまでは】- 姫君たちの身の上の将来について。
【いかにしてか】- 以下「ながらふべき」まで、姫君たちの心中。
【御心惑ひどもになむ】- 係助詞「なむ」の下に「ある」などの語句が省略。省略によって強調される。
【心のうちにこそ思ひ捨てたまひつらめど】- 『一葉抄』は「双紙のことは也」と指摘。『集成』は「以下、姫君たちの悲しみをもっともとする草子地」と注す。
|
| 2.4.6 |
明日、入りたまはむとての日は、例ならず、こなたかなた、たたずみ歩きたまひて見たまふ。いとものはかなく、かりそめの宿りにて過ぐいたまひける御住まひのありさまを、「亡からむのち、いかにしてかは、若き人の絶え籠もりては過ぐいたまはむ」と、涙ぐみつつ念誦したまふさま、いときよげなり。 |
明日、ご入山なさるという日は、いつもと違って、あちらこちらと、邸内を歩きなさって御覧になる。
たいそう頼りなく、仮の宿としてお過ごしになったお住まいの様子を、「亡くなった後、どのようにして、若い姫君たちが絶え籠もってお過ごしになれようか」と、涙ぐみながら念誦なさる様子は、たいそう清らかである。
|
明日は寺へおはいりになろうとする日、平生のようでなくそちらこちら家の中を宮はながめまわっておいでになった。一時的に仮り住居となされたまま年月をお過ごしになった、あまりにも簡単な建物についても、自分の亡くなったあとでこんな家に若い女王たちがなお辛抱を続けて住んでいられるであろうかとお思いになり、宮は涙ぐみながら念誦をあそばされる御容姿にも、清楚な美があった。
|
【明日、入りたまはむとての日は】- 明日山寺にお籠もりになろうとする前日は、の意。
【こなたかなた】- 山荘のあちこちの部屋。仏間居間など。
【亡からむのち】- 以下「過ぐいたまはむ」まで、八宮の心中の思い。
|
| 2.4.7 |
おとなびたる人びと召し出でて、
|
年配の女房たちを召し出して、
|
年をとった女房らをお呼び出しになって、
|
|
| 2.4.8 |
|
「心配のないようにお仕えしなさい。
何事も、もともと気がねなく暮らして、世間に噂にならないような身分の人は、子孫の零落することもよくあることで、目立ちもしないようだ。
このような身分になると、世間の人は何とも思わないだろうが、みじめな有様で流浪するのは、至尊の血筋に生まれた宿縁に対して不面目で、心苦しいことが、多いだろう。
物寂しく心細い世の中を送ることは、世の常である。
|
「私がどんな所にいても安心していられるように女王たちへ仕えてくれ。何事があっても初めから人目を惹かぬ家であったなら、そこの娘がのちに堕落しようとも問題にする者もない。自分らの家では、それはしかしもう世間の人の眼中にはないであろうがね。ともかくもふがいない堕落をしていっては御先祖にすまないのだからね。貧しい簡素な生活よりできないのはほかにもあることだから、それはいいのだ。
|
【うしろやすく仕うまつれ】- 以下「もてなしきこゆな」まで、八宮の女房たちに対する詞、訓戒。
【かやすく、世に聞こえあるまじき際の人は】- とかく評判にされがちな宮家のような家柄でない人は。
【紛れぬべかめり】- 「ぬ」完了の助動詞、「べかめり」連語、推量の助動詞。話者八宮の主観的推量。
【かかる際】- 宮家の家柄。
【人は何と思はざらめど、口惜しうてさすらへむ、契りかたじけなく、いとほしきこと】- 八宮には、世間の噂や評判よりも皇族として無念であり姫君たちがいとおしい、という思いが強い。
|
| 2.4.9 |
|
生まれた家の格式、しきたり通りに身を処するというのが、人聞きにも、自分の気持ちとしても、間違いのないように思われるだろう。
贅沢な人並みの生活をしようと望んでも、その思う通りにならない時勢であったら、決して決して軽々しく、良くない男をお取り持ち申すな」
|
貴族の娘は貴族らしく品位を落とさないで他の軽侮を受けない身の持ち方で終始するのが世間へ対しても、それら自身にも潔いことだろうと思う。世間並みな幸福を得させようとしてすることも、そのとおりにならないではかえって悲惨だから、決して軽率な考えでおまえがたが女王らに過失をさせるような計らいをしてはならない」
|
【にぎははしく人数めかむと】- 『完訳』は「豊かで世間並に暮そうとしても。零落しても皇族の誇りを失いたくないとして、「よからぬ」(普通の身分の)男を姫君の夫として迎えるなと、女房たちを戒める」と注す。
【よからぬ方にもてなしきこゆな】- 『集成』は「身分を汚すようなお取り持ちをしてはならぬ」と注す。
|
| 2.4.10 |
などのたまふ。
|
などとおっしゃる。
|
などとお言い聞かせになった。
|
|
| 2.4.11 |
|
まだ夜の明けないうちにお出になろうとして、こちらにお渡りになって、
|
いよいよその朝早くお出かけになろうとする時にも、宮は女王たちの居間へおいでになって、
|
【こなたに渡りたまひて】- 女房の部屋から姫君たちの部屋に。
|
| 2.4.12 |
|
「留守の間、心細くお嘆きなさるな。
気持ちだけは明るく持って音楽の遊びなどはなさい。
何事も思うに適わない世の中だ。
深刻に思い詰めなさるな」
|
「私の留守の間を心細く思わずにお暮らしなさい。機嫌よく音楽でももてあそんでいるがよい。何事も思うままにならぬ人生なのだから悲観ばかりはせずにいなさい」
|
【無からむほど】- 以下「思し入られそ」まで、八宮の姫君たちへの詞。「無からむほど」は留守中の意だが、暗に死後のこと(「亡からむのち」)も含めて言っている響きがある。
【心ばかりはやりて】- 気持ちだけは明るく持って。
【思し入られそ】- 大島本は「おほしいられそ」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「なおぼし入れそ」と「な」を補訂する。『新大系』は底本のままとする。
|
| 2.4.13 |
|
などと、振り返りながらお出になった。
お二方は、ますます心細く物思いに閉ざされて、寝ても起きても語り合いながら、
|
ともお言いになり、顧みがちに寺へおいでになったのであった。たださえ寂しい境遇の女王たちはいっそう心細さを感じて、物思いばかりがされ、明け暮れ二人はいっしょにいて話し合いながら、
|
【返り見がちにて出でたまひぬ】- 後髪引かれる思い。姫君たちへの執着心を語る。
|
| 2.4.14 |
|
「どちらか一方がいなくなったら、どのようにして暮らしていけましょうか」
|
「どちらか一人がいなかったらどうして暮らされるでしょう。
|
【一人一人なからましかば】- 以下「別るるやうもあらば」まで、姫君たちの詞。『河海抄』は「思ふどちひとりひとりが恋ひしなば誰によそへて藤衣着む」(古今集恋三、六五四、読人しらず)を指摘。
|
| 2.4.15 |
「今、行く末も定めなき世にて、もし別るるやうもあらば」
|
「今は、将来もはっきりしないこの世で、もし別れるようなことがあったら」
|
でも明日のことはわかりませんからね。もし二人が別れてしまうことになったらどうしましょう」
|
|
| 2.4.16 |
など、泣きみ笑ひみ、戯れごともまめごとも、同じ心に慰め交して過ぐしたまふ。
|
などと、泣いたり笑ったりしながら、冗談も真実も、同じ気持ちで慰め合いながらお過ごしになる。
|
などとも言い、泣きも笑いもするのであった。遊戯に属したことも、勉強事もいっしょにして慰め合っていた。
|
|
|
第五段 八月二十日、八の宮、山寺で死去
|
| 2.5.1 |
|
あの勤行なさる念仏三昧は、今日終わることだろうと、今か今かとお待ち申し上げていらっしゃる夕暮に、使者が参って、
|
御寺で行なっておいでになる三昧の日数が今日で終わるはずであるといって、女王たちは父宮のお帰りになるのを待っていた日の夕方に山の寺から宮のお使いが来た。
|
【かの行ひたまふ三昧、今日果てぬらむ】- 姫君たちの心中の思い。
【人参りて】- 山から八宮の使者が参上して。
|
| 2.5.2 |
|
「今朝から、気分が悪くなって、参ることができない。
風邪かと思って、あれこれと手当てしているところです。
それにしても、
|
「今朝から身体のぐあいが悪くて家のほうへ帰られぬ。風邪かと思うのでその手当てなどを今日はしています。平生以上にあなたがたと逢いたく思う時なのにあやにくなことです」
|
【今朝より、悩ましくて】- 以下「心もとなきを」まで、使者の詞。
【さるは、例よりも対面心もとなきを】- 『完訳』は「八の宮の死別を感取する気持」と注す。「を」接続助詞、逆接の意、無念の余情。また間投助詞、詠嘆の気持ちも響く。
|
| 2.5.3 |
と聞こえたまへり。胸つぶれて、いかなるにかと思し嘆き、御衣ども綿厚くて、急ぎせさせたまひて、たてまつれなどしたまふ。二、三日怠りたまはず。「いかに、いかに」と、人たてまつりたまへど、 |
と申し上げなさっていた。
胸がどきりとして、どのようなことでかとお嘆きになり、御法衣類に綿を厚くして、急いで準備させなさって、お届け申し上げなさる。
二、三日良くおなりにならない。
「どのようですか、どのようですか」と、使者を差し向けなさるが、
|
というお言葉が伝えられた。姫君たちは驚きに胸が一時にふさがれた気もしながら、綿の厚い宮のお衣服を作らせてお送りなどした。それに続いて二、三日もまだ宮は山をお出になることができない。御容体を聞きに出荘から手紙の使いを出すと、
|
【二、三日】- 大島本は「二三日」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「二三日は」と「は」を補訂する。『新大系』は底本のままとする。
【怠りたまはず】- 大島本は「おこ(こ+た)り給ハす」とある。すなわち「た」を補入する。『集成』『完本』は諸本と底本の訂正以前本文に従って「下りたまはず」と整定する。『新大系』は底本の補訂に従う。
|
| 2.5.4 |
|
「特にひどく悪いというのではない。
どことなく苦しいのです。
もう少し良くなっら、じきに、我慢してでも帰ろう」
|
「大病にかかったとは思われない。ただどことなく苦しいだけであるから、少しでもよろしくなれば帰ろうと思う。今はつとめて心身を安静にしようとしている」
|
【ことにおどろおどろしくはあらず】- 以下「今念じて」まで、八宮の詞。使者に言わせる。
【今、念じて】- 『集成』は「近いうちに、無理をしてでも(帰りましょう)。「念ず」は、我慢する」。『完訳』は「すぐにでも、がまんしてでも。希望的観測による言葉」「じきに、我慢してでも下山しよう」と注す。
|
| 2.5.5 |
|
などと、口上で申し上げなさる。
阿闍梨がぴったりと付き添ってお世話申し上げているのであった。
|
と言葉でのお返事があった。阿闍梨はずっと付き添って御看護をしていた。
|
【言葉にて聞こえたまふ】- 『集成』は「使者の口上で。筆を執る力もないのであろう」と注す。
【仕うまつりける】- 大島本は「つかうまつりける」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「仕うまつりけり」と終止形に校訂する。『新大系』は底本のままとする。
|
| 2.5.6 |
|
「ちょっとしたご病気と見えるが、最期でいらっしゃるかも知れない。
姫君たちのご将来の事は、何のお嘆きになることがありましょうか。
人は皆、それぞれ運命というものは別々なので、ご心配なさっても何にもなりません」
|
「たいした御病患とは思われませんが、あるいはこれが御寿命の終わりになるのかもしれません。姫君がたのことを何も心配あそばすには及びません。人にはそれぞれ独立した宿命というものがあるのでございますから、あなた様は決して気がかりとあそばされることはないのでございます」
|
【はかなき御悩みと見ゆれど】- 以下「おはしまさす」まで、阿闍梨の詞。
【限りのたびにもおはしますらむ】- これが最期となるかもしれない。
【君たちの御こと、何か思し嘆くべき】- 反語表現。『集成』は「八の宮の妄執をさまそうとする仏者としての配慮」と注す。
【人は皆、御宿世といふもの異々なれば、御心にかかるべきにもおはしまさず】- 『完訳』は「宿世は各人別々なので、あなたの意のままにならぬ、の意」と注す。
|
| 2.5.7 |
|
と、ますます出離なさらねばならないことを申し上げ知らせながら、「いまさら下山なさいますな」と、ご忠告申し上げるのであった。
|
こう阿闍梨は言い、いよいよ恩愛の情をお捨てになることをお教え申し上げて、「今になりまして、ここからお出になるようなことはなさらぬがよろしゅうございます」といさめるのであった。
|
【今さらにな出でたまひそ】- 阿闍梨の詞。『集成』は「もうこの期に及んでは山をお下りになりませぬように。心静かに臨終を迎えさせたいという配慮」と注す。
|
| 2.5.8 |
|
八月二十日のころであった。
ただでさえ空の様子のひときわ物悲しいころ、姫君たちは、朝夕の、霧の晴間もなく、お嘆きになりながら物思いに沈んでいらっしゃる。
有明の月がたいそう明るく差し出して、川の表面もはっきりと澄んでいるのを、そちらの蔀を上げさせて、お覗きになっていらっしゃると、鐘の音がかすかに響いて来て、「夜が明けたようだ」と申し上げるころに、人びとが来て、
|
これは八月の二十日ごろのことであった。深くものが身にしむ時節でもあって、姫君がたの心には朝霧夕霧の晴れ間もなく歎きが続いた。有り明けの月が派手に光を放って、宇治川の水の鮮明に澄んで見えるころ、そちらに向いて揚げ戸を上げさせて、二人は外の景色にながめ入っていると、鐘の声がかすかに響いてきた。夜が明けたのであると思っているところへ、寺から人が来て、
|
【八月二十日のほどなりけり】- 八の宮逝去の月日。
【朝夕、霧の晴るる間もなく、思し嘆きつつ眺めたまふ】- 『紫明抄』は「雁の来る峰の朝霧晴れずのみ思ひつきせぬ世の中の憂さ」(古今集雑下、九三五、読人しらず)を指摘。
【有明の月のいとはなやかにさし出でて、水の面もさやかに澄みたるを】- 二十日ころの月。秋の夜更けの清澄な感じ。
【そなたの蔀上げさせて】- 邸の、山寺の方の蔀を上げさせて。
【鐘の声かすかに響きて、「明けぬなり」と】- 山寺の夜明けを知らせる鐘の音。八宮成仏の時と重なる。「なり」伝聞推定の助動詞。
|
|
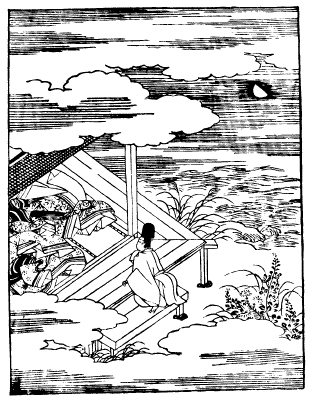 |
| 2.5.9 |
|
「この夜半頃に、お亡くなりになりました」
|
「宮様はこの夜中ごろにお薨れになりました」
|
【この夜中ばかりになむ、亡せたまひぬる】- 使者の詞。八宮の逝去を告げる。
|
| 2.5.10 |
|
と泣く泣く申し上げる。
心に懸けて、どうしていられるかと絶えずご心配申し上げていらっしゃったが、突然お聞きになって、驚いて真暗な気持ちになって、ますますこのようなことには、涙もどこに行っておしまいになったのであろうか、ただうつ伏していらっしゃった。
|
と泣く泣く伝えた。その一つの報らせが次の瞬間にはあるのでないかと、気にしない間もなかったのであったが、いよいよそれを聞く身になった姫君たちは失心したようになった。あまりに悲しい時は涙がどこかへ行くものらしい。二人の女王は何も言わずに俯伏しになっていた。
|
【心にかけて、いかにとは】- 以下、報せを受けた姫君たちの心中を語る。
【いとどかかることには】- 父の死。
【涙もいづちか去にけむ】- 語り手の感情移入をこめた挿入句。
|
| 2.5.11 |
|
悲しい死別といっても、目の当たりに立ち会ってはっきり見届けるのが、世の常のことであるが、どのような最期であったのかの心残りも添わって、お嘆きになることは、もっともなことである。
片時の間でも、先立たれ申しては、この世に生きていられようとは考えていらっしゃらなかったお二方なので、是非とも後を追いたいと泣き沈んでいらっしゃるが、寿命の定まった運命のある死出の旅路だったので、何の効もない。
|
父君の死というものも日々枕頭にいて看護してきたあとに至ったことであれば、世の習いとしてあきらめようもあるのであろうが、病中にお逢いもできなかったままでこうなったことを姫君らの歎くのももっともである。しばらくでも父君に別れたあとに生きているのを肯定しない心を二人とも持っていて、自分も死なねばならぬと泣き沈んでいるが、命は失った人にも、失おうとする人にも、左右する自由はないものであるからしかたがない。
|
【いみじき目も、見る目の前にて】- 以下、『湖月抄』は「姫君達の心を草子地にいへり」と指摘。語り手の姫君たちの心情への同情の気持ち。
【こそ、常のことなれ】- 係結び、逆接用法。
【限りある道なりければ】- 『集成』は「寿命には運命(さだめ)のある死出の道なので、願いの叶えられるはずもない」と注す。
|
|
第六段 阿闍梨による法事と薫の弔問
|
| 2.6.1 |
|
阿闍梨は、長年お約束なさっていたことに従って、後のご法事も万事にお世話致す。
|
阿闍梨にはずっと以前から御遺言があったことであるから、葬送のこともお約束の言葉どおりにこの僧が扱ってした。
|
【契りおきたまひける】- 主語は八宮。
|
| 2.6.2 |
|
「亡き人におなりになってしまわれたというお姿ご様子だけでも、もう一度拝見したい」
|
御遺骸になっておいでになる父君でも、もう一度見たい
|
【亡き人になりたまへらむ】- 以下「見たてまつらむ」まで、姫君の詞。「たまへ」尊敬の補助動詞、已然形。「ら」完了の助動詞、未然形、存続の意。「む」推量の助動詞。
|
| 2.6.3 |
と思しのたまへど、
|
とお考えになりおっしゃるが、
|
と姫君たちは望んだのであるが、
|
|
| 2.6.4 |
|
「いまさら、どうしてそのような必要がございましょうか。
この日頃も、お会いしてはならないとお諭し申し上げていたので、今はそれ以上に、お互いにご執心なさってはいけないとのお心構えを、お知りになるべきです」
|
「今さらそんなことをなさるべきではありません。御病中にも私は姫君がたにもお逢いにならぬがよろしいと申し上げていたのですから、こうなりましてから、互いに無益な執着を作ることになり、あなたがたの将来のためにもなりません」
|
【今さらに】- 以下「ならひたまふべきなり」まで、阿闍梨の詞。
【日ごろも、また会ひたまふまじきことを聞こえ知らせつれば】- 大島本は「又あひ給ましき」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「またあひ見たまふまじき」と「見」を補訂する。『新大系』は底本のままとする。八宮の山籠もりの間、阿闍梨が八宮に諭して言った。
【今はまして】- 死者への妄執は成仏の妨げとなる。『完訳』は「臨終の際の執心が往生の妨げと考えられた」と注す。
【かたみに御心とどめたまふまじき】- 『集成』は「互いに親子のご愛執をお持ちにはならないようにとの」と訳す。
|
| 2.6.5 |
|
とだけ申し上げる。
山籠もりしていらっしゃった時のご様子をお聞きになるにつけても、阿闍梨のあまりに悟り澄ました聖心を、憎く辛いとお思いになるのであった。
|
阿闍梨は許そうとしなかった。御臨終までの御様子を話されることによっても、阿闍梨のあまりな出世間ぶりを姫君たちは恨めしく憎くさえ思った。
|
【おはしましける御ありさまを】- 八宮が山寺に籠もっていた間の様子。
【阿闍梨のあまりさかしき聖心を、憎くつらしとなむ思しける】- 『完訳』は「俗事を顧みない仏道一筋の冷静な心。俗人には非情とも見える」と注す。物語作者の立場も姫君方に同情的で、こうした仏教者に対しては批判的か。
|
| 2.6.6 |
|
出家のご本願は、昔から深くいらっしゃったが、このように見譲る人もない姫君たちのご将来の見捨てがたいことを、生きている間は明け暮れ離れずに面倒を見て上げるのを、本当に侘しい暮らしの慰めとも、お思いになって離れがたく過ごしていらしたのだが、限りある運命の道には、先立ちなさる心配も後を慕いなさるお心も、思うにまかせないことであった。
|
出家のお志は昔から深かった宮でおありになったが、まったくの孤児になる姫君を置いておおきになるのが心がかりで、生きている間はせめてかたわらを離れず守る父になっておいでになることで、また一方のやる瀬ない人の世の寂しさも紛らしておいでになったのである。それも永久のことにはならなくて、生死の線に隔てられておしまいになったことは、亡き宮のためにも、お慕いする女王がたのためにも悲しいことであった。
|
【入道の御本意は】- 八宮の出家の素志。
【御ことどもの見捨てがたきを】- 格助詞「の」同格。「--見捨てがたきを」と「--見たてまつるを」は並列の構文。
【過ぐいたまへるを】- 「を」接続助詞、逆接の意。
【先だちたまふも慕ひたまふ御心も】- 『集成』は「お先立ちになるご心配もおあとを追いたいお気持も」。『完訳』は「先立たれる宮のお気持も、あとに残って恋い慕う姫君たちのお気持も」と訳す。
|
| 2.6.7 |
|
中納言殿におかれては、お耳になさって、まことにあっけなく残念に、もう一度、ゆっくりとお話申し上げたいことがたくさん残っている気がして、人の世の無常が思い続けられて、ひどくお泣きになる。
「再びお目にかかることは難しいだろうか」などとおっしゃっていたが、やはりいつものお心にも、朝夕の隔ても当てにならない世のはかなさを、誰よりも殊にお感じになっていたので、耳馴れて、昨日今日とは思わなかったが、繰り返し繰り返し諦め切れず悲しくお思いなさる。
|
薫も宇治の八の宮の訃を承った。あまりにはかない人の命が悲しまれ、尊い人格の御方が惜しまれて、もう一度ゆっくりお話のしたかったことが多く残っているように思われて、人生の悲哀がしみじみ痛感されて泣いた。これが最終の会見であるかもしれぬとお言いになったが、いつの時にも人生のはかなさ脆さをお感じになっておられる方のお言葉であったから、特別なお気持ちで仰せられるとも聞かず、このように早くその悲しい期が至るとも思わなかったと考えると、かえすがえすも悲しかった。
|
【中納言殿には、聞きたまひて】- 薫、八宮の訃報を聞く。
【今一度、心のどかにて】- 薫は七月下旬に行われる相撲の節会が過ぎたら宇治に行きたいと八宮に言っていた。
【おほかた世のありさま思ひ続けられて】- 世の無常観。
【またあひ見ること難くや】- 八宮が生前に言った詞。
【朝夕の隔て知らぬ世のはかなさを】- 『集成』は「朝に紅顔有つて世路に誇れども、暮には白骨と為つて郊原に朽ちぬ」(和漢朗詠集、無常、藤原義孝)を指摘。
【昨日今日と思はざりけるを】- 『源氏釈』は「つひに行く道とはかねて聞きしかど昨日今日とは思はざりしを」(古今集哀傷、八六一、在原業平)を指摘。
|
| 2.6.8 |
|
阿闍梨のもとにも、姫君たちのご弔問も、心をこめて差し上げなさる。
このようなご弔問など、また他に誰も訪れる人さえいないご様子なのは、悲しみにくれている姫君たちにも、年来のご厚誼のありがたかったことをお分かりになる。
|
阿闍梨の所へも、山荘のほうへも弔問の品々を多く薫は贈った。こんな好意を見せる人はほかになかったのであるから、悲しみに沈んでいながらも二人の女王は昔からもこうした好意のある補助は絶えずしてくれる薫であることを思わざるをえなかった。
|
【かかる御弔らひなど】- 故八宮への弔問客。
【ものおぼえぬ御心地どもにも】- 大君と中君。
【年ごろの御心ばへのあはれなめりしなどをも】- 薫は故八宮の法の友として三年間の交誼がある。「なめりし」は姫君の目を通しての叙述。
|
| 2.6.9 |
|
「世間普通の死別でさえ、その当座は、比類なく悲しいようにばかり、誰でも悲しみにくれるようなのに、まして気を慰めようもないお身の上では、どのようにお悲しみになっていられるだろう」と想像なさりながら、後のご法事など、しなければならないことを想像して、阿闍梨にも挨拶なさる。
こちらにも、老女たちにかこつけて、御誦経などのことをご配慮なさる。
|
普通の家の親の死でも、その場合にはこれほどの悲しいことはないように思われるのであるから、ましてただお一人を頼みにして今日まで来た姫君たちはどれほど深い悲しみをしていることであろうと薫は宇治の山荘を想像して、仏事のための費用などを多く阿闍梨に寄せた。邸のほうへも老いた弁の君の所へというようにして金品を贈り、誦経の用にすべき物などさえも送った。
|
【世の常のほどの別れだに】- 以下「心地どもしたまふらむ」まで、薫の心中。姫君たちの思いを想像。
【阿闍梨にも訪らひたまふ】- 『完訳』は「法事のための費用などを贈る」と注す。
【思ひやりたまふ】- 大島本は「思やり給」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「思ひやりきこえたまふ」と「きこえ」を補訂する。『新大系』は底本のままとする。
|
|
第三章 宇治の姉妹の物語 晩秋の傷心の姫君たち
|
|
第一段 九月、忌中の姫君たち
|
| 3.1.1 |
|
夜の明けない心地のまま、九月になった。
野山の様子、まして時雨が涙を誘いがちで、ややもすれば先を争って落ちる木の葉の音も、水の響きも、涙の滝も、一緒のように分からなくなって、「こうしていては、どうして、定めのあるご寿命も、しばらくの間もお保ちになれようか」と、お仕えする女房たちは、心細く、ひどくお慰め申し上げ、お慰め申し上げしつつ。
|
いつも夜のままのような暗い月日もたって九月になった。野山の色はまして人に涙を催させることが多く、争って落ちる木の葉の音、宇治川の響き、滝なす涙も皆一つのもののようになって、この女王たちをますます深い悲しみの谷へ追った。こんなふうでは、命は前生からきまったものとは言え、そのしばらくの間さえ堪えて生きがたいことにならぬかと女房たちは姫君らを思い、心細がっていろいろに慰めようとするのであった。
|
【明けぬ夜の心地ながら、九月にもなりぬ】- 『河海抄』は「明けぬ夜の心地ながらにやみにしを朝倉といひし声は聞ききや」(後拾遺集雑四、一〇八二、読人しらず)。『休聞抄』は「人知れぬねやは絶えするほととぎすただ明けぬ夜の心地のみして」(清正集)を指摘。『集成』は「いつまでも明けない夜の中をさまようなような悲しみのうちに。歌の表現を借りたものであろう」。『完訳』は「深い悲しみを無明長夜の闇をさまよう気持とする」と注す。
【袖の時雨をもよほしがちに】- 「袖の時雨」歌語的表現。『集成』は「姫君たちの涙をそそりがちで。折しも時雨(晩秋、初冬の景物)の候なので修飾的にいう」と注す。
【涙の滝も、一つもののやうに暮れ惑ひて】- 『河海抄』は「我が世をば今日か明日かに待つかひの涙の滝といづれ高けむ」(伊勢物語、八十七段)を指摘。
【かうては、いかでか】- 以下「めぐらひたまはむ」まで、女房たちの思い。
【慰めきこえつつ】- 大島本は「なくさめきこえつゝ」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「慰めきこえつつ思ひまどふ」と「思ひまどふ」を補訂する。『新大系』は底本のままとし、読点で下文に続ける。
|
| 3.1.2 |
ここにも念仏の僧さぶらひて、おはしましし方は、仏を形見に見たてまつりつつ、時々参り仕うまつりし人びとの、御忌に籠もりたる限りは、あはれに行ひて過ぐす。 |
こちらにも念仏の僧が伺候して、故宮のいらした部屋は、仏像を形見と拝し上げながら、時々参上してお仕えしていた者たちで、御忌に籠もっている人びとは皆、しみじみと勤行して過ごす。
|
この山荘にも念仏をする僧が来ていて、宮のお住みになった座敷は安置された仏像をお形見と見ねばならぬ今となっては、そこに時々伺候した人たちが忌籠りをして仏勤めをしていた。
|
【ここにも】- 山荘。山寺に対していう。
【おはしましし方は】- 生前に八宮がいらっしゃった部屋。
|
| 3.1.3 |
|
兵部卿宮からも、度々ご弔問申し上げなさる。
そのようなお返事など、差し上げる気もなさらない。
何の返事もないので、「中納言にはこうではないだろうに、自分をやはり疎んじていらっしゃるらしい」と、恨めしくお思いになる。
紅葉の盛りに、詩文などを作らせなさろうとして、お出かけになるご予定だったが、こうしたことになって、この近辺のご逍遥は、不都合な折なのでご中止なさって、残念に思っていらっしゃる。
|
兵部卿の宮からもたびたび慰問のお手紙が来た。このおりからそうした性質のお文には返事を書こうとする気にもならず打ち捨ててあったから、中納言にはこんな態度をとらないはずであるのに、自分だけはいつまでもよそよそしく扱われると女王を恨めしがっておいでになった。紅葉の季節に詩会を宇治でしようと匂宮はしておいでになったのであるが、恋しい人の所が喪の家になっている今はそのかいもないとおやめになったが、残念に思召した。
|
【兵部卿宮よりも】- 匂宮。中君と手紙の贈答をしている。
【中納言には】- 以下「思ひ放ちたまへるなめり」まで、匂宮の心中の思い。
【紅葉の盛りに、文など作らせたまはむとて】- 前に「兵部卿宮もこの秋のほどに紅葉見におはしまさむと」(第二章三節)とあった。「文」は漢詩文をさす。「せ」使役の助動詞。文人官人たちを引き連れて行き、彼等に作らせるという趣向であろう。
|
|
第二段 匂宮からの弔問の手紙
|
| 3.2.1 |
|
御忌中も終わった。
限りがあるので、涙も絶え間があろうかとお思いやりになって、とてもたくさんお書き綴りなさった。
時雨がちの夕方、
|
八の宮の四十九日の忌も済んだ。時間は悲しみを緩和するはずであると宮は思召して、長い消息を宇治へお書きになった。時雨が時をおいて通って行くような日の夕方であった。
|
【御忌も果てぬ】- 『集成』は「八の宮が亡くなったのは八月二十日だから、忌の三十日を過ぎて九月二十日過ぎの頃」。『完訳』は「三十日の忌を過ぎた九月二十日過ぎか。四十九日の忌とすれば十月初冬で、時期が合わない」と注す。
【思しやりて】- 主語は匂宮。
|
| 3.2.2 |
|
「牡鹿の鳴く秋の山里はいかがお暮らしでしょうか
小萩に露のかかる夕暮時は
|
牡鹿鳴く秋の山里いかならん
小萩が露のかかる夕暮れ
|
【牡鹿鳴く秋の山里いかならむ--小萩が露のかかる夕暮】- 匂宮から中君への贈歌。「小萩」は姫君を準え、「露」は涙を象徴。「かかる」は「露が懸かる」と「かかる夕暮」という掛詞表現。
|
| 3.2.3 |
|
ちょうど今の空の様子、ご存知ないふりをなさるのでしたら、あまりにひどいことでございます。
枯れて行く野辺も、特別のものとして眺められるころでございます」
|
こうした空模様の日に、恋する人はどんなに寂しい気持ちになっているかを思いやってくださらないのは冷淡にすぎます。枯れてゆく野の景色も平気でながめておられぬ私です。
|
【ただ今の空のけしき】- 大島本は「空のけしき」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「空のけしきを」と「を」を補訂する。『新大系』は底本のままとする。以下「眺めらるるころになむ」まで、歌に添えた手紙文。
【枯れゆく野辺も、分きて眺めらるるころになむ】- 『全書』は「鹿の棲む尾上の萩の下葉より枯れ行く野辺も哀れとぞ見る」(新千載集秋下、五二六、具平親王)を指摘。
|
| 3.2.4 |
などあり。
|
などとある。
|
などという文字である。
|
|
| 3.2.5 |
|
「おしっしゃるとおり、とても情け知らずの有様で、何度にもなってしまいましたから、やはり、差し上げなさい」
|
「このお言葉のように、あまりに尊貴な方を無視する態度を取り続けてきたのですからね、何かあなたからお返事をお出しなさい」
|
【げに、いとあまり】- 以下「聞こえたまへ」まで、大君の詞。中君に返事を書くように勧める。
【たびたびになりぬるを】- 返事を怠ることが度重なった意。
|
| 3.2.6 |
|
などと、中の宮を、いつものように、催促してお書かせ申し上げなさる。
|
と、大姫君は例のように中の君に勧めて書かせようとした。
|
【中の宮を】- 中君のこと。『集成』は「この呼称はここが初出で、これ以後、この人は「中の宮」と呼ばれる」。『新大系』は「「中の宮」は、中君の、親王の娘であることを強調した呼称。八宮死去後のここが初出。これ以後、大君を「姫宮」と呼ぶのと応じあっている」と注す。当時、親王の娘「女王」を「宮」と呼称することもあった。
|
| 3.2.7 |
「今日までながらへて、硯など近くひき寄せて見るべきものとやは思ひし。心憂くも過ぎにける日数かな」と思すに、またかきくもり、もの見えぬ心地したまへば、押しやりて、 |
「今日まで生き永らえて、硯などを身近に引き寄せて使おうなどと思ったろうか。
情けなくも過ぎてしまった日数だわ」とお思いになると、また涙に曇り、何も見えない気がなさるので、硯を押しやって、
|
中の君は今日まで生きていて硯などを引き寄せてものを書くことがあろうなどとはあの際に思われなかったのである、情けなく、時というものがたってしまったではないかなどと思うと、また急に涙がわいて目がくらみ、何も見えなくなったので、硯は横へ押しやって、
|
【今日までながらへて】- 以下「日数かな」まで、中君の心中。
|
| 3.2.8 |
|
「やはり、書くことはできませんわ。
だんだんこのように起きてはいられますが、なるほど、限りがあるのだわと思われますのも、疎ましく情けなくて」
|
「やっぱり私は書けません。こんなふうに近ごろは起きてすわったりできるようになりましたことでも、悲しみの日も限りがあるというのはほんとうなのだろうかと思うと、自分がいやになるのですもの」
|
【なほ、えこそ】- 以下「心憂くて」まで、中君の詞。
【げに、限りありけるにこそと】- 『完訳』は「以下、日数の経過が悲嘆を薄めるのを自覚し、父娘の情にも限界があるのかと、我ながら思う」と注す。
|
| 3.2.9 |
|
と、可憐な様子で泣きしおれていらっしゃるのも、まことにいたいたしい。
|
と可憐な様子で言って、泣きしおれているのも、姉君の身には心苦しく思われることであった。
|
【らうたげなるさまに泣きしをれておはするも】- 『集成』は「可憐な様子で泣き沈んでいらっしゃるのも」。『完訳』は「いかにも、痛々しく泣きくずれていらっしゃるのも」と訳す。
|
| 3.2.10 |
|
夕暮のころに出立したお使いが、宵が少し過ぎたころに着いた。
「どうして、帰参することができましょう。
今夜は泊まって行くように」と言わせなさるが、「すぐ引き返して、帰参します」と急ぐので、お気の毒で、自分は冷静に落ち着いていらっしゃるのではないが、見るに見かねなさって、
|
夕方に来た使いが、「もう十時がだいぶ過ぎてまいりました。今夜のうちに帰れるでしょうか」と言っていると聞いて、今夜は泊まってゆくようにと言わせたが、「いえ、どうしても今晩のうちにお返事をお渡し申し上げませんでは」と急ぐのがかわいそうで、大姫君は自分は悲しみから超越しているというふうを見せるためでなく、ただ中の君が書きかねているのに同情して、
|
【いかでか、帰り参らむ。今宵は旅寝して】- 大君の詞。反語表現。
【言はせたまへど】- 「せ」使役の助動詞。大君が女房をして言わせる。
【立ち帰りこそ、参りなめ】- 使者の詞。
|
| 3.2.11 |
|
「涙ばかりで霧に塞がっている山里は
籬に鹿が声を揃えて鳴いております」
|
涙のみきりふさがれる山里は
籬に鹿ぞもろ声に鳴く
|
【涙のみ霧りふたがれる山里は--籬に鹿ぞ諸声に鳴く】- 大君の代作歌。「山里」をそのまま、「牡鹿」を「鹿」と替えて返す。「鹿」を自分たちに譬え、「鳴く」は「泣く」を響かす。
|
| 3.2.12 |
黒き紙に、夜の墨つきもたどたどしければ、ひきつくろふところもなく、筆にまかせて、おし包みて出だしたまひつ。 |
黒い紙に、夜のため墨つきもはっきりしないので、体裁を整えることもなく、筆に任せて書いて、そのまま包んでお渡しになった。
|
という返事を、黒い紙の上の夜の墨の跡はよくも見分けられないのであるが、それを骨折ろうともせず、筆まかせに書いて包むとすぐに女房へ渡した。
|
【黒き紙に】- 服喪中なので黒色を用いた。
|
|
第三段 匂宮の使者、帰邸
|
| 3.3.1 |
|
お使いは、木幡の山の辺りも、雨降りでとても恐ろしそうだが、そのような物怖じしないような者をお選びになったのであろうか、気味悪そうな笹の蔭を、馬を止める間もなく早めて、わずかの時間に参り着いた。
宮の御前においても、ひどく濡れて参ったので、禄を賜る。
|
お使いの男は木幡山を通るのに、雨気の空でことに暗く恐ろしい道を、臆病でない者が選ばれて来たのか、気味の悪い篠原道を馬もとめずに早打ちに走らせて一時間ほどで二条の院へ帰り着いた。御前へ召されて出た時もひどく服の濡れていたのを宮は御覧になって物を賜わった。
|
【さやうの】- 以下「選り出でたまひけむ」まで、挿入句。過去推量の助動詞「けむ」は語り手の推量。
【笹の隈を、駒ひきとどむるほどもなくうち早めて】- 『源氏釈』は「笹の隈桧の隈川に駒とめてしばし水かへ影をだに見む」(古今集、大歌所御歌、一〇八〇、神遊びの歌)を指摘。『弄花抄』は「山科の木幡の里に馬はあれど徒歩よりぞ来る君を思へば」(拾遺集雑恋、一二四三、読人しらず)を指摘。
|
|
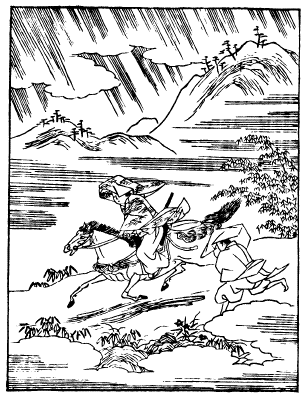 |
| 3.3.2 |
|
以前に見たのとは違った筆跡で、もう少し大人びていて、風情ある書き方などを、「どちららの姫君が書いたものだろうか」と、下にも置かず御覧になりながら、すぐにもお寝みにならないので、
|
これまで書いて来た人の手でない字で、それよりは少し年上らしいところがあり、才識のある人らしい書きぶりなどを宮は御覧になって、しかしどちらが姉の女王か、中姫君なのかと熱心にながめ入っておいでになり、寝室へおはいりにならないで
|
【さきざき御覧ぜしにはあらぬ手の】- 匂宮の目を通して語る。今までの文との筆跡の違いに気づく。
|
| 3.3.3 |
|
「待つとおっしゃって、起きていらして」
|
起きたままでいらせられる、
|
【待つとて】- 以下「ことならむ」まで、女房の詞。
|
| 3.3.4 |
「また御覧ずるほどの久しきは、いかばかり御心にしむことならむ」
|
「また御覧になることの長いことは、どれほどご執心なのでしょう」
|
この時間の長さに、どれほどお心にしむお手紙なのであろう
|
|
| 3.3.5 |
と、御前なる人びと、ささめき聞こえて、憎みきこゆ。ねぶたければなめり。 |
と、御前に仕える女房たちは、ささやき申して、お妬み申し上げる。
眠たいからなのであろう。
|
などと女房たちはささやいて反感も持った。眠たかったからであろう。
|
【ねぶたければなめり】- 『一葉抄』は「草子詞也され事也」と指摘。語り手が女房たちの心中を推測した表現。
|
| 3.3.6 |
まだ朝霧深き朝に、いそぎ起きてたてまつりたまふ。
|
まだ朝霧の深い明け方に、急いで起きて手紙を差し上げなさる。
|
兵部卿の宮はまだ朝霧の濃く残っている刻にお起きになって、また宇治への消息をお書きになった。
|
|
| 3.3.7 |
|
「朝霧に友を見失った鹿の声を
ただ世間並にしみじみと悲しく聞いておりましょうか
|
朝霧に友惑はせる鹿の音を
大方にやは哀れとも聞く
|
【朝霧に友まどはせる鹿の音を--おほかたにやはあはれとも聞く】- 匂宮から中君への返歌。「霧」「鹿」の語句を用いて返す。『異本紫明抄』は「声立てて鳴きぞしぬべき秋霧に友惑はせる鹿にはあらねど」(後撰集秋下、三七二、紀友則)、『大系』は「夕されば佐保の河原の河霧に友惑はせる千鳥鳴くなり」(拾遺集冬、二三八、紀友則)を指摘。
|
| 3.3.8 |
|
一緒に鳴く声には負けません」
|
私の心から発するものは二つの鹿の声にも劣らぬ哀音です。
|
【諸声は劣るまじくこそ】- 大島本は「ましく」とある。『完本』は諸本に従って「まじう」と校訂する。『集成』『新大系』は底本のままとする。歌に添えた言葉。前の歌の文句「諸声に鳴く」を受けて言ったもの。
|
| 3.3.9 |
|
とあるが、「あまりに風情を知りすぎるようなのも厄介だ。
お一方のお蔭に隠れていられたのを頼み所として、何事も安心して過ごしていた。
思いもかけず長生きして、不本意な間違い事が、少しでも起こったら、気がかりでならないようにお考えであった亡きみ魂にまで、瑕をおつけ申すことになろう」と、何事にも引っ込み思案に恐れて、お返事申し上げなさらない。
|
というのである。風流遊びに身を入れ過ぎるのも余所見がよろしくない、父宮がついておいでになるというのを力にして、今まではそうした戯れに答えたりすることも安心してできたのであるが、孤児の境遇になって思わぬ過失を引き起こすようなことがあっては、ああして気がかりなふうに仰せられた自分たちのために、この世においでにならぬ御名にさえ疵をおつけすることになってはならぬと、何事にも控え目になっている女王はどちらからも返事をしなかった。
|
【あまり情けだたむも】- 以下「疵やつけたてまつらむ」まで、大君の心中。
【一所の御蔭に】- 故父宮をさす。
【過ごしつれ】- 大島本は「すこし」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「過ぐし」と校訂する。『新大系』は底本のままとする。
【うしろめたげにのみ思しおくめりし】- 主語は父宮。
|
| 3.3.10 |
|
この宮などを、軽薄な世間並の男性とはお思い申し上げていらっしゃらない。
何でもない走り書きなさったご筆跡や言葉遣いも、風情があり優美でいらっしゃるご様子を、多くはご存知でないが、御覧になりながら、「その嗜み深く風情あるお手紙に、お返事申し上げるのも、似合わしくない二人の身の上なので、いっそ、ただ、このような山里人めいて過ごそう」とお思いになる。
|
この兵部卿の宮などは軽薄な求婚者と同じには女王たちも見ていなかった。ちょっとした走り書きの消息の文章にもお墨の跡にも美しい艶な趣の見えるのを、たくさんはそうした意味を扱った手紙を見てはいなかったが、これこそすぐれた男の文というものであろうとは思いながらも、そうした尊貴な風流男につきあうことも、今の自分らに相応せぬことであるから、感情を傷つけることがあっても、世外の人のようにして超然としていようと姫君たちは思っていた。
|
【この宮などを】- 大島本は「この宮なとを」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「この宮などをば」と「ば」を補訂する。『新大系』は底本のままとする。
【軽らかにおしなべてのさまにも思ひきこえたまはず】- 『完訳』は「世間並の軽薄なお方などとは。匂宮には好色の噂もあるが、姫君たちはまだそれを見聞していない」と注す。
【見知りたまはねど】- 大島本は「見しり給ハねと(と+イこれこそハめてたきなめれと)」とある。すなわち、「これこそハめてたきなめれと」を異文として補入する。『集成』『完本』は諸本に従って「見知りたまはねど、これこそはめでたきなめれと」と「これこそはめでたきなめれと」を補訂する。『新大系』は底本の訂正以前のままとする。
【そのゆゑゆゑしく情けある方に】- 匂宮をさす。
【つきなき身のありさまどもなれば】- 自分たち姉妹の身の程を思う。
【何か、ただ、かかる山伏だちて過ぐしてむ】- 大君の心中。
|
|
第四段 薫、宇治を訪問
|
| 3.4.1 |
|
中納言殿へのお返事だけは、あちらからも誠意あるように手紙を差し上げなさるので、こちらからも、よそよそしくなくお返事申し上げなさる。
ご忌中が終わっても、自分自身でお伺いなさった。
東の廂の下がった所に喪服でいらっしゃるところに、近く立ち寄りなって、老女を召し出した。
|
薫からの手紙だけはあちらからもまじめに親切なことを多く書かれてくるのであったから、こちらからも冷淡なふうは見せず常に返事が出された。忌中が過ぎてから薫が訪ねて来た。東の縁に沿った座敷を、父宮の服喪のために一段低くした所にこのごろはいる姫君たちの所へ来て、まず老いた弁を薫は呼び出した。
|
【東の廂の下りたる方に】- 寝殿の東廂の一段低くなった所。服喪中は一段低い所で過す。
【やつれておはするに】- 姫君たちが質素な喪服姿でいる。
【古人】- 弁の君。
|
| 3.4.2 |
|
闇に閉ざされていらっしゃるお側近くに、たいそう眩しいばかりの美しさに満ちてお入りになったので、恥ずかしくなって、お返事などでさえもおできになれないので、
|
悲しみに暗い日を送っている女王らに近く、まばゆい感じのするほどの芳香を放つ人が来たのであったから、きまり悪く姫君たちは思って、言いかけられることにも返辞ができないでいると、
|
【かたはらいたうて、御いらへなどをだにえしたまはねば】- 主語は姫君。
|
| 3.4.3 |
「かやうには、もてないたまはで、昔の御心むけに従ひきこえたまはむさまならむこそ、聞こえ承るかひあるべけれ。なよびけしきばみたる振る舞ひをならひはべらねば、人伝てに聞こえはべるは、言の葉も続きはべらず」 |
「このようには、お扱い下さらないで、故宮のご意向にお従い申されるのが、お話を承る効があるというものです。
風流に気取った振る舞いには馴れていませんので、人を介して申し上げますのは、言葉が続きません」
|
「こんなふうな隔てがましい扱いはなさらないで、昔の宮様が私を御待遇くださいましたように心安くさせていただけばお見舞いにまいりがいもあるというものです。柔らかいふうに気どった若い人たちのするようなことは経験しないものですから、お取り次ぎを中にしてでは言葉も次々に出てまいりません」
|
【かやうには】- 以下「続きはべらず」まで、薫の詞。
【昔の御心むけに】- 故宮のご意向。
|
| 3.4.4 |
とあれば、
|
と言うので、
|
と薫は言った。
|
|
| 3.4.5 |
「あさましう、今までながらへはべるやうなれど、思ひさまさむ方なき夢にたどられはべりてなむ、心よりほかに空の光見はべらむもつつましうて、端近うもえみじろきはべらぬ」 |
「思いのほかに、今日まで生き永らえておりますようですが、思い覚まそうにも覚ましようもない夢の中にいるように思われまして、心ならず空の光を見ますのも遠慮されて、端近くに出ることもできません」
|
「どうしてそれで生きていたかと思われるような私たちで、生きてはおりましてもまだ悲しい夢に彷徨しているばかりでございます。知らず知らず空の光を見るようになりますことも遠慮がされまして、外に近い所までは出られないのでございます」
|
【あさましう】- 以下「みじろきはべらぬ」まで、大君の詞。
|
| 3.4.6 |
と聞こえたまへれば、
|
と申し上げなさっているので、
|
という姫君の挨拶が伝えられてきた。
|
|
| 3.4.7 |
「ことといへば、限りなき御心の深さになむ。月日の影は、御心もて晴れ晴れしくもて出でさせたまはばこそ、罪もはべらめ。行く方もなく、いぶせうおぼえはべり。また思さるらむは、しばしをも、あきらめきこえまほしくなむ」 |
「おっしゃることといえば、この上ないご思慮の深さです。
月日の光は、ご自身その気になって晴れ晴れしく振る舞いなさるならば、罪にもなりましょう。
どうしてよいか分からず、気持ちが晴れません。
またお悩みを、少しでも、お晴らし申し上げたく思います」
|
「それを申せば限りもない御孝心を持たれますこととは深く存じております。日月の光のもとへ晴れ晴れしく御自身からお出ましになることこそはばかりがおありになるでしょうが、私としましてはまた宮様をお失いいたしましての悲しみをほかのだれに告げようもないことですし、あなた様がたのお歎きの慰みにもなることも申し上げたいものですから、しいて近くへお出ましを願っているわけです」
|
【ことといへば】- 以下「あきらめ聞こえまほしくなむ」まで、薫の詞。
【きこえまほしくなむ】- 係助詞「なむ」の下に「思ふ」などの語句が省略されている。
|
| 3.4.8 |
と申したまへば、
|
と申し上げなさると、
|
こう薫が言うと、それを取り次いだ女房が、
|
|
| 3.4.9 |
|
「ほんとうですこと。
まことに例のないようなご愁傷を、お慰め申し上げなさるお気持ちも並一通りでないこと」などと、お諭し申し上げる。
|
「あちらで仰せになりますとおりに、お悲しみにお沈みあそばすのをお慰めになりたいと思召す御好意をおくみになりませんでは」などと言葉を添えて姫君を動かそうとする。
|
【げに、こそ】- 以下「浅からぬほど」まで、女房の詞。
【御ありさまを】- 姫君たちの哀傷を。
【慰めきこえたまふ御心ばへの浅からぬほど】- 薫が。
【聞こえ知らす】- 大島本は「きこえしらす」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「人々聞こえ知らす」と「人々」を補訂する。『新大系』は底本のままとする。
|
|
第五段 薫、大君と和歌を詠み交す
|
| 3.5.1 |
|
お気持ちも、そうはいっても、だんだんと落ち着いて、いろいろと分別がおつきになったので、亡き父宮への厚志からも、こんなにまで遥か遠い野辺を分け入っていらしたご誠意なども、お分りになったのであろう、少しいざり寄りなさった。
|
ああは言いながらも大姫君の心にもようやく悲しみの静まって来たこのごろになって、宮の御葬送以来薫の尽くしてくれたいろいろな親切がわかっているのであるから、亡き父宮への厚情からこんな辺鄙な土地へまで遺族を訪ねてくれる志はうれしく思われて、少しいざって出た。
|
【御心地にも、さこそいへ】- 『湖月抄』は「大君の心を草子地よりいへり」と指摘。
【昔ざまにても】- 『集成』は「亡き父宮への交誼からであるにしても」。『完訳』は「薫の殊勝な厚志は姫君たちも分るはずと、語り手が推測」と注す。『岷江入楚』所引の三光院実枝説は「此段大君の心を察して草子地にかけるなり」と指摘。
【思ひ知りたまふべし】- 推量の助動詞「べし」語り手が大君の心中を推量。
|
| 3.5.2 |
|
お嘆きのご心中、またお約束なさったことなどを、たいそう親密に優しく言って、嫌な粗野な態度などはお現しにならない方なので、気味悪く居心地悪くなどはないが、関係ない人にこのように声をお聞かせ申し、何となく頼りにしていたことなどもあった日頃を思い出すのも、やはり辛くて、遠慮されるが、かすかに一言などお返事申し上げなさる様子が、なるほど、いろいろと悲しみにぼうっとした感じなので、まことにお気の毒にとお聞き申し上げなさる。
|
薫は大姫君に持っている愛を語り、また宮が最後に御委託の言葉のあったのなどをこまごまとなつかしい調子で語っていて、荒く強いふうなどはない人であるからうとましい気などはしないのであるが、親兄弟でない人にこうして声を聞かせ、力にしてたよるように思われるふうになるのも、父君の御在世の時にはせずとよいことであったと思うと、大姫君はさすがに苦しい気がして恥ずかしく思われるのであったが、ほのかに一言くらいの返辞を時々する様子にも、悲しみに茫然となっているらしいことが思われるのに薫は同情していた。
|
【思すらむさま】- 大君の心中。
【のたまひ契りしこと】- 故八宮が薫に約束したこと。
【雄々しきけはひ】- 『完訳』は「女の気持を解せぬ粗野な態度」と注す。
【知らぬ人に】- 『集成』は「親しくもない男に」。『完訳』は「他人であるお方に」と訳す。
【すずろに頼み顔なることなどもありつる日ごろを】- 『集成』は「こんなことでいいのかと思いながらも(薫を)頼りにするような具合でもあったこの日頃を思い続けるにつけても。父宮亡きあと、薫の手紙には返事を出していたことをさすのであろう」。『完訳』は「なんとなく薫を頼りにしてきたところもある。昔のなりゆきから薫を頼っている負い目を思う」と注す。
【げに】- 薫の、なるほど、という気持ち。
|
| 3.5.3 |
|
黒い几帳の透影が、たいそういたいたしげなので、ましてどれほどのご悲嘆でいられるかと、かすかに御覧になった明け方などが思い出されて、
|
御簾の向こうの黒い几帳の透き影が悲しく、その人の姿はまして寂しい喪の色に包まれていることであろうと思い、あの隙見をした夜明けのことと思い比べられた。
|
【ましておはすらむさま】- 『集成』は「まして姫君たちご本人の喪服に身をやつしていられるであろうお姿(が思われ)」と注す。
【ほの見し明けぐれなど思ひ出でられて】- 「橋姫」巻の垣間見の場面をさす(第三章三段)。
|
| 3.5.4 |
|
「色の変わった浅茅を見るにつけても墨染に
身をやつしていらっしゃるお姿をお察しいたします」
|
色変はる浅茅を見ても墨染めに
やつるる袖を思ひこそやれ
|
【色変はる浅茅を見ても墨染に--やつるる袖を思ひこそやれ】- 薫の歌。
|
| 3.5.5 |
と、独り言のやうにのたまへば、
|
と、独り言のようにおっしゃると、
|
これを独言のように言う薫であった。
|
|
| 3.5.6 |
|
「喪服に色の変わった袖に露はおいていますが
わが身はまったく置き所もありません
|
色変はる袖をば露の宿りにて
わが身ぞさらに置き所なき
|
【色変はる袖をば露の宿りにて--わが身ぞさらに置き所なき】- 大君の返歌。「色変はる」「袖」の語句を用いて返す。「露」「置く」縁語。
|
| 3.5.7 |
|
ほつれる糸は涙に」
|
はずるる糸は(侘び人の涙の玉の緒とぞなりぬる)
|
【はつるる糸は】- 歌に添えた言葉。『源氏釈』は「藤衣はつるる糸は侘び人の涙の玉の緒とぞなりける」(古今集哀傷、八四一、壬生忠岑)を指摘。喪服を着て涙ながら暮らしている、意。
|
| 3.5.8 |
|
と下は言いさして、たいそうひどく堪えがたい様子でお入りになってしまったようである。
|
とだけ、あとの声は消えたまま非常に悲しくなったふうで奥へはいったことが感じられた。
|
【入りたまひぬなり】- 「なり」伝聞推定の助動詞。
|
|
第六段 薫、弁の君と語る
|
| 3.6.1 |
|
引き止めてよい場合でもないので、心残りにいたわしくお思いになる。
老女が、とんでもないご代役に出て来て、昔や今のあれこれと、悲しいお話を申し上げる。
世にも稀な驚くべきことの数々を見て来た人だったので、このようにみすぼらしく落ちぶれた人と見限らず、たいそう優しくお相手なさる。
|
それをひきとめて話し続けうるほどの親しみは見せがたい薫は、身にしむ思いばかりをしていた。老いた弁が極端に変わった代理役に出て来て、古い昔のこと、最近に昔となった宮のことを混ぜていずれも悲しい思いを薫に与える話ばかりをした。自身にかかわる夢のような古い秘密に携わった女であったから、醜く衰えた女と毛ぎらいもせず薫は親しく向き合っているのであった。
|
【こよなき御代はりに出で来て】- 『集成』は「大君のとんでもない代役として」。『完訳』は「大君との交替を揶揄」と注す。語り手の感情移入による表現。
【昔今をかき集め、悲しき御物語ども聞こゆ】- 大島本は「きこゆ」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「聞こゆる」と校訂する。『新大系』は底本のままとする。昔は柏木のこと、今は八宮のこと、をさす。
|
| 3.6.2 |
|
「幼かったころに、故院に先立たれ申して、ひどく悲しい世の中だと、悟ってしまったので、成長して行く年齢とともに、官位や、世の中の栄花も、何とも思いません。
|
「私は幼年時代に院とお別れした不幸な者で、悲しいものは人生だとその当時から身にしみ渡るほど思い続けているのですから、大人になっていくにしたがって進んでいく官位や、世間から望みをかけられていることなどはうれしいこととも思われないのです。
|
【いはけなかりしほどに】- 以下「なりにたりや」まで、薫の詞。
【故院に後れたてまつりて】- 六条院、源氏に。
|
| 3.6.3 |
|
ただ、このように静かなご生活などが、心にお適いになっていらっしゃったが、このようにあっけなく先立ち申されたので、ますますひどく、無常の世の中が思い知らされる心も、催されたが、おいたわしい境遇で、後に遺されたお二方の事が、妨げだなどと申し上げるようなのは、懸想めいたように聞こえますが、生き永らえても、あの遺言を違えずに、相談申し上げ承りたく思います。
|
私の願うのはこうした静かな場所に閑居のできることでしたから、八の宮の御生活がしっくり私の理想に合ったように思って近づきたてまつったのですが、こんなふうに悲しく一生をお終わりになったので、また人生をいとわしいものに思うことが深くなったのです。しかしあとの御遺族のことなどを申し上げるのは失礼ですが、自分が生きていくのに努力してでも御遺言をまちがいなく遂行したい心に今はなっています。
|
【静やかなる御住まひなどの】- 故八宮の生活をさす。敬語「御」がある。
【心にかなひたまへりしを】- 主語は故八宮。
【もよほされにたれど】- 出家を思わぬでもないが、の意。
【心苦しうて】- 姫君たちがおいたわしい状態で。
【かの御言あやまたず】- 八宮との生前の約束や遺言に違わず、の意。
【承らまほしさになむ】- 係助詞「なむ」の下に「思ひはべる」などの語句が省略。
|
| 3.6.4 |
|
実は、思いがけない昔話を聞いてからは、ますますこの世に跡を残そうなどとは思われなくなったのですよ」
|
なぜ私が努力を要するかと言いますと、思いも寄らぬ昔話をあなたがお聞かせになったものですから、いっそうこの世に跡を残さない身になりたい欲求が大きくなったのです」
|
【おぼえなき御古物語聞きしより】- 柏木と薫の出生に関する話。
【おぼえずなりにたりや】- 大島本は「おほえすなりけたりや」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「おぼえずなりにたりや」と」と「と」を補訂する。『新大系』は底本のままとする。
|
| 3.6.5 |
うち泣きつつのたまへば、この人はましていみじく泣きて、えも聞こえやらず。御けはひなどの、ただそれかとおぼえたまふに、年ごろうち忘れたりつるいにしへの御ことをさへとり重ねて、聞こえやらむ方もなく、おぼほれゐたり。 |
泣きながらおっしゃるので、この老女はそれ以上にひどく泣いて、何とも申し上げることができない。
ご様子などが、まるであの方そっくりに思われなさるので、長年来忘れていた昔の事までを重ね合わせて、申し上げようもなく、涙にくれていた。
|
と、薫の泣きながら言うのを聞いている弁はまして大泣きに泣いて、言葉も出しえないふうであった。薫の容姿には柏木の再来かと思われる点があったから、年月のたつうちに思い紛れていた故主のことがまた新しい悲しみになってきて、弁は涙におぼれていた。
|
【ただそれかとおぼえたまふに】- 柏木そっくりに思われる。「たまふ」は薫に対してつけられた敬語。
|
| 3.6.6 |
|
この人は、あの大納言の御乳母子で、父親は、この姫君たちの母北の方の叔父で、左中弁で亡くなった人の子であった。
長年、遠い国に流浪して、母君もお亡くなりになって後、あちらの殿には疎遠になり、この宮邸で、引き取っておいて下さったのであった。
人柄も格別というわけでなく、宮仕え馴れもしていたが、気の利かない者でないと宮もお思いになって、姫君たちのご後見役のようになさっていたのであった。
|
この女は柏木の大納言の乳母の子であって、父はここの女王たちの母夫人の母方の叔父の左中弁で、亡くなった人だったのである。長い間田舎に行っていて、宮の夫人もお亡くなりになったのち、昔の太政大臣家とは縁が薄くなってしまい、八の宮が夫人の縁でお呼び寄せになった人なのである。身分もたいした者でなく、奉公ずれのしたところもあるが、賢い女であるのを宮はお認めになって、姫君たちのお世話役にしてお置きになったのである。
|
【この人は、かの大納言の御乳母子にて】- 以下、弁の素姓についての説明。 【かの大納言の御乳母子】-柏木の乳母子。
【父は、この姫君たちの母北の方の、母方の叔父、左中弁にて亡せにけるが子】- 弁の父親は姫君たちの故母北の方の叔父にあたる人で左中弁で亡くなった人。弁と姫君たちの母親は従姉妹どうし。弁にとって姫君たちは従姉妹の娘たち。弁の呼称は父左中弁に由来する。
【年ごろ、遠き国にあくがれ】- 「橋姫」巻に「西の海の果て」(西海道の薩摩国)まで流浪したとあった(第四章四段)。
【母君も亡せたまひてのち】- 姫君たちの母北の方。敬語があるので、弁の母ではない。
【かの殿には疎くなり】- 弁がかつて仕えていた故柏木の太政大臣家。
【この宮には、尋ね取りてあらせたまふなりけり】- 主語は八宮。八宮邸で引き取って。
【人もいとやむごとなからず】- 『完訳』は「人柄も格別というわけでなく。八の宮の北の方の従姉妹という血筋のよさが消え失せたような感じ」と注す。
|
| 3.6.7 |
|
昔の事は、長年このように朝夕に拝し馴れて、隔意なく全部思い申し上げる姫君たちにも、一言も申し上げたこともなく、隠して来たけれど、中納言の君は、「老人の問わず語りは、皆、通例のことなので、誰彼なく軽率に言いふらしたりしないにしても、まことに気のおける姫君たちは、ご存知でいらっしゃるだろう」と自然と推量されるのが、忌まわしいとも困った事とも思われるので、「また疎遠にしてはおけない」と、言い寄るきっかけにもなるのであろう。
|
柏木の大納言と女三の宮に関したことは、長い月日になじんで何の隠し事もたいていは持たぬ姫君たちにも今まで秘密を打ち明けて言ってはなかったのであるが、薫は、老人は問わず語りをするものになっているのであるから、普通の世間話のような誇張は混ぜて言わなかったまでも、あの貴女らしい貴女の二人は知っているのであるかもしれぬと想像されるのが残念でもあり、また気の毒な者に自分を思わせていることがすまぬようにも思われたりもした。こんなことによっても女王の一人を自分は得ておかないではならぬという心を薫に持たせることになるかもしれない。
|
【昔の御ことは】- 故柏木の事。
【古人の問はず語り】- 以下「聞きおきたまへらむかし」まで、薫の心中の思い。姫君たちは自分の出生の秘密を知っているだろうと推測する。
【いと恥づかしげなめる御心ども】- 姫君たちをさす。
【推し量らるるが】- 「るる」自発の助動詞、格助詞「が」主格を表す。
【またもて離れてはやまじ」と、思ひ寄らるるつまにもなりぬべき】- 『集成』は「自分の出生の秘密を守るためという動機も、薫の姫君たちへの思わくの中にあることを説明する草子地」。『完訳』は「語り手の評。自分の出生の秘密を封じ込めるとして、姫君接近を合理化することにもなる」と注す。
|
|
第七段 薫、日暮れて帰京
|
| 3.7.1 |
|
今は泊まるのも落ち着かない気がして、お帰りなさるにも、「これが最後か」などとおっしゃったが、「どうして、そのようなことがあろうか、と信頼して、再び拝しなくなった、秋は変わったろうか。
多くの日数も経ていないのに、どこにいらしたのかも分からず、あっけないことだ。
格別に普通の人のようなご装飾もなく、とても簡略になさっていたようだが、まことにどことなく清らかに手入れがしてあって、周囲が趣深くなさっていたお住まいも、大徳たちが出入りし、あちら側とこちら側と隔てなさって、御念誦の道具類なども変わらない様子であるが、『仏像は皆あちらのお寺にお移し申そうとする』」と申し上げるのを、お聞きなさるにつけても、このような様子の人影などまでが見えなくなってしまった時、後に残ってお悲しみになっているお二方の気持ちを推察申し上げなさるのも、まことに胸が痛く思い続けられずにはいらっしゃれない。
|
女ばかりの家族の所へ泊まって行くこともやましい気がして、帰ろうとしながらも薫は、これが最終の会見になるかもしれぬと八の宮がお言いになった時、近い日のうちにそんなことになるはずもないという誤った自信を持って、それきりお訪ねすることなしに宮をお失いした、それも秋の初めで、今もまだ秋ではないか、多くの日もたたぬうちに、どこの世界へお行きになったかもわからぬことになるとははかないことではないかと歎かれた。別段普通の貴人めいた装飾がしてあるのでもなく簡素にお住まいをしておいでになったが、いつも浄く掃除の行き届いた山荘であったのに、荒法師たちが多く出入りして、ちょっとした隔ての物を立てて臨時の詰め所をあちこちに作っているような家に今はなっていた。念誦の室の飾りつけなどはもとのままであるが、仏像は向かいの山の寺のほうへ近日移されるはずであるということを聞いた薫は、こんな僧たちまでもいなくなったあとに残る女王たちの心は寂しいことであろうと思うと、胸さえも痛くなって、その人たちが憐れまれてならない。
|
【これや限りの」などのたまひしを】- 以下「移したてまつりてむとす」あたりまで、薫の心中と目に沿った叙述。『集成』は「この前後、山荘を去るに当っての薫の感慨をそのまま地の文として書く」と注す。故八宮と最後の対面の折の言葉をさす。『新釈』は「逢ふことはこれや限りの旅ならむ草の枕も霜枯れにけり」(新古今集恋三、一二〇九、馬内侍)を指摘。
【秋やは変はれる】- 『完訳』は「八の宮と対面したのも八の宮の死に遭ったのも、同じ今年の秋ではないか。短日月の間に移り変る無常を詠嘆」と注す。
【あへなきわざなりや】- 薫の感想。
【ことそぎたまふめりしかど】- 推量の助動詞「めり」主観的推量の主体は薫。
【こなたかなたひき隔てつつ】- 『完訳』は「姫君たちの住む東面と、宮の住んでいた西面」と注す。
【仏は皆かの寺に移したてまつりてむとす】- 大徳たちの詞。
【かかるさまの人影など】- 僧侶たちの姿。
【心地どもを】- 接尾語「ども」複数を表す。大君と中君の気持ち。
|
| 3.7.2 |
|
「たいそう暮れました」と申し上げるので、物思いを中断してお立ちなさると、雁が鳴いて飛んで渡って行く。
|
「もう非常に暗い時刻になりました」と従者が告げて来たために、外をながめていた所から立ち上がった時に雁が啼いて通った。
|
【いたく暮れはべりぬ】- 供人の詞。主人薫の帰京を促す。
|
| 3.7.3 |
|
「秋霧の晴れない雲居でさらにいっそう
この世を仮の世だと鳴いて知らせるのだろう」
|
秋霧の晴れぬ雲井にいとどしく
この世をかりと言ひ知らすらん
|
【秋霧の晴れぬ雲居にいとどしく--この世をかりと言ひ知らすらむ】- 薫の独詠歌。『河海抄』は「雁の来る峰の朝霧晴れずのみ思ひつきせぬ世の中の憂さ」(古今集雑下、九三四、読人しらず)。『河海抄』は「行き帰りここもかしこも旅なれや来る秋ごとにかりかりと鳴く」(後撰集秋下、三六二、読人しらず)「ひたすらに我が思はなくに己さへかりかりとのみ鳴き渡るらむ」(後撰集秋下、三六四、読人しらず)。『源註拾遺』は「常ならぬ身を秋来れば白雲に飛ぶ鳥すらもかりとねをなく」(新撰万葉集、秋)を指摘。「雁」と「仮り」の掛詞。「雁」は鳴く音でもある。
|
|
第八段 姫君たちの傷心
|
| 3.8.1 |
|
兵部卿宮に対面なさる時は、まずこの姫君たちの御事を話題になさる。
「今はそうはいっても気がねも要るまい」とお思いになって、宮は、熱心に手紙を差し上げなさるのであった。
ちょっとしたお返事も、申し上げにくく気後れする方だと、女方はお思いになっていた。
|
兵部卿の宮に薫がお逢いする時にはいつも宇治の姫君たちが話題の中心になった。反対されるかもしれぬ父君の親王もおいでにならなくなって、結婚はただ女王の自由意志で決まるだけであると見ておいでになって、宮は引き続き誠意を書き送っておいでになった。女のほうではこの相手に対しては短いお返事も書きにくいように思っていた。
|
【兵部卿宮に対面したまふ時は】- 主語は薫。
【今はさりとも心やすきを】- 匂宮の心中。八宮が亡くなった今となってはけむたい存在もいなくなって、の意。
|
| 3.8.2 |
|
「世間にとてもたいそう風流でいらっしゃるお名前が広がって、好ましく優美にお思いなさるらしいが、このようにとても埋もれた葎の下のようなところから差し出すお返事を、まことに場違いな感じがして、古めかしいだろう」などとふさいでいらっしゃった。
|
好色な風流男というお名が拡まっていて、好奇心からいいようにばかり想像をしておいでになる方へ、はなやかな世間とは没交渉のような侘び居をするものが、出す返事などはどんなに時代おくれなものと見られるかしれぬと歎じているのであった。
|
【世にいといたう】- 以下「古めきたらむ」まで、姫君たちの心中。特に大君。『完訳』は「好色と噂に聞える匂宮を敬遠したい」と注す。
【いかにうひうひしく、古めきたらむ】- 『集成』は「どんなに場違いな感じで、気の利かぬものだろう」。『完訳』は「どんなにか世なれず古めかしく見えることだろう」と訳す。
|
| 3.8.3 |
|
「それにしても、思いのほかに過ぎ行くものは、月日ですわ。
このように、頼りにしにくかったご寿命を、昨日今日とも思わず、ただ人生の大方の無常のはかなさばかりを、毎日のこととして見聞きしてきましたが、自分も父宮も後に遺されたり先立ったりすることに月日の隔たりがあろうか、などと思っていましたたよ」
|
いつとなくたってしまうのは月日でないか、人生のはかなさ脆さを知りながらも、自分らに悲しい日の近づいているものとも知らずに、ただ一般的に頼みがたいものは人生であるとしていて、親子三人が別々な時に死ぬるものともせず、滅ぶのはいっしょであるような妄想を持ち、
|
【さても、あさましうて】- 以下「堪へがたきこと」まで、大君と中君の会話。
【かく、頼みがたかりける御世を】- 父宮の寿命。
【昨日今日とは思はで】- 『河海抄』は「遂に行く道とはかねて聞きしかど昨日今日とは思はざりしを」(古今集哀傷、八六一、在原業平)を指摘。
【我も人も後れ先だつほどしもやは経む】- 『源氏釈』は「末の露本の雫や世の中の後れ先立つためしなるらむ」(古今六帖一、雫)を指摘。『集成』は「父宮に先立たれて自分たちが生き永らえようなどとは思ってもみなかった、の意」と注す。
|
| 3.8.4 |
|
「過去を思い続けても、何の頼りがいのありそうな世でもなかったが、ただいつのまにかのんびりと眺め過ごして来て、何の恐ろしい目にも気がねすることもなく過ごして来ましたが、風の音も荒々しく、いつもは見かけない人の姿が、連れ立って案内を乞うと、まっさきに胸がどきりとして、何となく恐ろしく侘しく思われることまでが加わったのが、ひどく堪え難いことですわ」
|
それをまた慰めにもしていた過去を思ってみても幸福な世を自分らは持っていたのではないが、父君がおいでになるということによって、何とない安心が得られ、他から威す者もない、他を恐れることもないとして生きていた、それが今日では風さえ荒い音をして吹けば心がおびえるし、平生見かけない人たちが幾人も門をはいって来て案内を求める声を聞けばはっと思わせられもするし、恐ろしく情けないことの多くなったのは堪えられぬことである
|
【例見ぬ人影も、うち連れ声づくれば、まづ胸つぶれて、もの恐ろしくわびしうおぼゆることさへ】- 今までは応対に当たられていた父宮がいなくなったことを改めて思い知る。
|
| 3.8.5 |
と、二所うち語らひつつ、干す世もなくて過ぐしたまふに、年も暮れにけり。
|
と、お二方で語り合いながら、涙の乾く間もなくて過ごしていらっしゃるうちに、年も暮れてしまった。
|
と、涙の中で姉妹が語り合っているうちにその年も暮れるのであった。
|
|
|
第四章 宇治の姉妹の物語 歳末の宇治の姫君たち
|
|
第一段 歳末の宇治の姫君たち
|
| 4.1.1 |
雪霰降りしくころは、いづくもかくこそはある風の音なれど、今はじめて思ひ入りたらむ山住みの心地したまふ。
女ばらなど、
|
雪や霰が降りしくころは、どこもこのような風の音であるが、今初めて決心して入った山住み生活のような心地がなさる。
女房たちなどは、
|
雪や霰の多いころはどこでもはげしくなる風の音も、今はじめて寂しい恐ろしい山住みをする身になったかのごとく思って宇治の姫君たちは聞いていた。女房らが話の中で、
|
|
| 4.1.2 |
|
「ああ、新しい年がやってきます。
心細く悲しいこと。
年の改まった春を待ちたいわ」
|
「いよいよ年が変わりますよ。心細い悲しい生活が改まるような春の来ることが待たれますよ」
|
【あはれ、年は替はりなむとす】- 以下「春待ち出でてしがな」まで、女房の詞。
【改まるべき春待ち出でてしがな】- 『集成』は「百千鳥囀る春はものごとに改まれども我ぞふりゆく」(古今集春上、二八、読人しらず)を指摘。
|
| 4.1.3 |
|
と、気を落とさずに言う者もいる。
「難しいことだわ」とお聞きになる。
|
などと言っているのが聞こえる。何かに希望をつないでいるらしい。そんな春は絶対にないはずであると姫君たちは思っていた。
|
【難きことかな】- 姫君たちの心中の思い。
|
| 4.1.4 |
|
向かいの山でも、季節季節の御念仏に籠もりなさった縁故で、人も行き来していたが、阿闍梨も、いかがですかと、一通りはたまにお見舞いを申し上げはしても、今では何の用事でちょっとでも参ろうか。
|
宮が時々念仏におこもりになったために、向かいの山寺に人の出はいりすることもあったのであるが、阿闍梨も音問の使いはおりおり送っても、宮のおいでにならぬ山荘へ彼自身は来てもかいのないこととして顔を見せない。
|
【時々の御念仏に籠もりたまひし】- 四季毎の念仏。主語は八宮。
【こそ、人も参り通ひしか】- 「こそ--しか」係結びの法則。逆接用法。
【今は何しにかはほのめき参らむ】- 『完訳』は「挿入句」と注す。語り手の感情移入をともなった表現。
|
| 4.1.5 |
|
ますます人目も絶え果てたのも、そのようなこととは思いながらも、まことに悲しい。
何とも思えなかった山賤も、宮がお亡くなりになって後は、たまに覗きに参る者は、珍しく思われなさる。
この季節の事とて、薪や、木の実を拾って参る山賤どももいる。
|
時のたつにつれて山荘の人の目にはいる人影は少なくなるばかりであった。気にとまらなかった村民などさえもたまさかに訪ねてくれる時はうれしく思うようになった。寒い日に向かうことであるから燃料の枝とか、木の実とかを拾い集めてささげる山の男もあった。
|
【さるべきことと】- 『集成』は「これが当り前だと」。『完訳』は「無理からぬことと」と訳す。
【めづらしく思ほえたまふ】- 主語は姫君たち。
【薪、木の実拾ひて参る山人ども】- 『集成』は「『法華経』提婆達多品の「即ち仙人に随ひて、所須を供給し、果を採り水を汲み、薪を拾ひ食を設け」の文が念頭にあろう」と注す。
|
| 4.1.6 |
阿闍梨の室より、炭などやうのものたてまつるとて、
|
阿闍梨の庵室から、炭などのような物を献上すると言って、
|
阿闍梨の寺から炭などを贈って来た時に、
|
|
| 4.1.7 |
|
「長年馴れました宮仕えが、今年を最後として絶えてしまうのが、心細く思われますので」
|
年々のことになっておりますのが、ただ今になりまして中絶させますのは寂しいことですから。
|
【年ごろにならひはべりにける宮仕への】- 以下「心細さになむ」まで、阿闍梨の文言。
【絶えはつらむが】- 大島本は「たえは△(△#つ)らんか」とある。すなわち元の文字「△(判読不能、「へ」カ)」を抹消して「つ」と訂正する。『集成』『完本』は諸本に従って「絶えはべらむが」と校訂する。『新大系』は底本の訂正に従う。
【心細さになむ】- 係助詞「なむ」の下には「送りはべる」などの語句が省略。
|
|
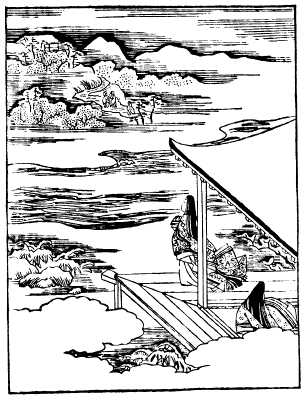 |
| 4.1.8 |
|
と申し上げていた。
必ず冬籠もり用の山風を防ぐための綿衣などを贈っていたのを、お思い出しになってお遣りになる。
法師たち、童などが山に上って行くのが、見えたり隠れたり、たいそう雪が深いのを、泣く泣く立ち出てお見送りなさる。
|
という挨拶があった。冬季の僧たちのために、必ず毎年綿入れの衣服類を宮が寺へ納められたのを思い出して、女王もそれらの品々を使いに託した。荷を運んで来た僧や子供侍が向かいの山の寺へ上がって行く姿が見え隠れに山荘から数えられた。雪の深く積もった日であった。泣く泣く姫君は縁側の近くへ出て見送っていたのである。
|
【かならず】- 「遣はししを」にかかる。『完訳』は「阿闍梨への返礼に、綿入れの着物を贈るのが例になっていたか」と注す。
【泣く泣く立ち出でて見送りたまふ】- 主語は姫君たち。
|
| 4.1.9 |
|
「お髪などを下ろしなさったが、そのようなお姿ででも生きていて下さったら、このように通って参る人も、自然と多かったでしょうに」
|
宮はたとい出家をあそばされても、生きてさえおいでになればこんなふうに使いが常に往来することによって自分らは慰められたであろう、
|
【御髪など】- 以下「やまましやは」まで、姫君たちの詞。
【おはしまさましかば】- 「ましかば--まし」反実仮想の構文。
|
| 4.1.10 |
|
「どんなに寂しく心細くても、お目にかかれないこともなかったでしょうに」
|
どんなに心細い日を送っても、また父君にお逢いのできる日はあったはずである
|
【いかにあはれに】- 以下、父宮が生きていて、山寺に出家した姿ででもいたのであったら、という仮想のもとの詞。
【絶えてやまましやは】- 「絶えて」副詞。「やは」連語、係助詞、反語。
|
| 4.1.11 |
など、語らひたまふ。
|
などと、語り合っていらっしゃる。
|
などと二人は語り合って、大姫君、
|
|
| 4.1.12 |
|
「父上がお亡くなりになって岩の険しい山道も絶えてしまった今
松の雪を何と御覧になりますか」
|
君なくて岩のかけ道絶えしより
松の雪をも何とかは見る
|
【君なくて岩のかけ道絶えしより--松の雪をもなにとかは見る】- 大君から中君への贈歌。「君」は父宮、「見る」の主語は中君。「岩のかけ道」は、山荘と山寺を結ぶ桟道。『河海抄』は「世にふれば憂さこそまされ吉野の岩のかけ道踏みならしてむ」(古今集雑下、九五一、読人しらず)を指摘。
|
| 4.1.13 |
中の宮、
|
中の宮、
|
中の君、
|
|
| 4.1.14 |
|
「奥山の松葉に積もる雪とでも
亡くなった父上を思うことができたらうれしゅうございます」
|
奥山の松葉に積もる雪とだに
消えにし人を思はましかば
|
【奥山の松葉に積もる雪とだに--消えにし人を思はましかば】- 中君の返歌。「松」「雪」の語句を用いる。「雪」「消え」縁語。「思はましかば」反実仮想。『細流抄』は「奥山の松には凍る雪よりも我が身世にふるほどぞはかなき」(伊勢集)「消えやすき露の命にくらぶればげに滞る松の雪かな」(伊勢集)を指摘。雪と同様に思えたらうれしい、雪は消えても再び降り積もるものであるから、しかし、人は一度死ねば再び会えない。
|
| 4.1.15 |
|
うらやましくいことに、消えてもまた雪は降り積もることよ。
|
消えた人でない雪はまたまた降りそって積もっていく、うらやましいまでに。
|
【うらやましくぞ、またも降り添ふや】- 『新釈』は「記者の詞」。『評釈』は「中の宮が歌を受けて、そのまま言ったのだ。中の宮の言葉だ、とも解しうる。しかし、その一人の言葉というより、姉妹二人の心と見るほうがよかろう。期せずして二人は、同じ思いをもったのだと。また同時に、これは、語り手の言葉である。いま現実に目に見ながら語る思い、現場からの放送である。すなわち読者の目に雪が見え、この言葉が姉妹の言葉として聞こえるであろう」と注す。
|
|
第二段 薫、歳末に宇治を訪問
|
| 4.2.1 |
|
中納言の君は、「新年は、少しも訪問することができないだろう」とお思いになっていらっしゃった。
雪もたいそう多い上に、普通の身分の人でさえ見えなくなってしまったので、並々ならぬ立派な姿をして、気軽に訪ねて来られたお気持ちが、浅からず思い知られなさるので、いつもよりは心をこめて、ご座所などをお設けさせなさる。
|
薫は新年になれば事が多くて、行こうとしても急には宇治へ出かけられまいと思って山荘の姫君がたを訪ねてきた。雪の深く降り積もった日には、まして人並みなものの影すら見がたい家に、美しい風采の若い高官が身軽に来てくれたことは貴女たちをさえ感激させたのであろう、平生よりも心を配って客の座の設けなどについて大姫君は女房らへ指図を下していた。
|
【新しき年は】- 以下「きこえざらむ」まで、薫の心中。新年早々はいろいろと年中行事が多くて宇治へは行けまい、の意。
【よろしき人だに】- 普通の身分の人。普通といっても貴族として普通。
【なのめならぬけはひして、軽らかに】- 薫の姿。並々ならぬ立派な風采でしかも気軽に訪問、その親密さをうかがわせる。
|
| 4.2.2 |
|
服喪者用でない御火桶を、部屋の奥にあるのを取り出して、塵をかき払いなどするにつけても、父宮がお待ち喜び申し上げていたご様子などを、女房たちもお噂申し上げる。
直接お話なさることは、気の引けることとばかりお思いになっていたが、好意を無にするように思っていらっしゃるので、仕方のないことと思って、応対申し上げなさる。
|
喪の黒漆でない火鉢を、しまいこんだ所から取り出して塵を払いなどしながらも、女房は亡き宮がこの客をどのように喜んでお迎えになったかというようなことを姫君に申しているのであった。みずから出て話すことはなお晴れがましいこととして姫君は躊躇していたが、あまりに思いやりのないように薫のほうでは思うふうであったから、しかたなしに物越しで相手の言葉を聞くことになった。
|
【奥なる取り出でて】- 大島本は「おくなるとりいてゝ」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「物の奥なる」と諸本に従って「物の」を補訂する。『新大系』は底本のままとする。
【宮の待ち喜びたまひし御けしき】- 生前に父宮が薫を。
【対面したまふことをば】- 『集成』は「直接お話しなさることを」。『完訳』は「この「対面」は、几帳や御簾などを隔てながらも直接会話を交す対座」と注す。
【思ひ隈なきやうに】- 好意を無にしたように、の意。
【人の思ひたまへれば】- 「人」は薫をさす。
|
| 4.2.3 |
|
気を許すというのではないが、以前よりは少し言葉数多く、ものをおっしゃる様子が、たいそうそつがなく、奥ゆかしい感じである。
「こうしてばかりは、続けられそうにない」とお思いになるにつけても、「まことにあっさり変わってしまう心だな。
やはり、恋心に変わってまう男女の仲なのだな」と思っていらっしゃった。
|
打ち解けたとまではいわれぬが、前の時分よりは少し長く続けた言葉で応答をする様子に、不完全なところのない貴女らしさが見えた。こうした性質の交際だけでは満足ができぬと薫は思い、これはやや突然な心の動き方である、人は変わるものである、本来の自分はそうした方面へ進むはずではないのであるが、どうなっていくことかなどと自己を批判していた。
|
【かやうにてのみは、え過ぐし果つまじ】- 薫の心中の思い。『完訳』は「結婚を前提とする深い親交を望む」と注す。
【と思ひなりたまふも】- 地の文。薫の心中文に地の文を挿入し、客観化する。
【いとうちつけなる心かな】- 以下「世なりけり」まで、薫の心中の思い。前の思いを反省する。
|
|
第三段 薫、匂宮について語る
|
| 4.3.1 |
|
「匂宮が、たいそう不思議とお恨みになることがございましたね。
しみじみとしたご遺言を一言承りましたことなどを、何かのついでに、ちらっとお洩らし申し上げたことがあったのでしょうか。
またとてもよく気の回るお方で、推量なさったのでしょうか、わたしに、うまく申し上げてくれるようにと頼むのに、冷淡なご様子なのは、うまくお取り持ち申さないからだと、度々お恨みになるので、心外なこととは存じますが、山里への案内役は、きっぱりとお断り申し上げることもできかねるのですが、なにも、そのようにおあしらい申し上げなさいますな。
|
「兵部卿の宮が、私に御自身への同情心が欠けていると恨んでおられることがあるのです。故人の宮様が、姫君がたについて私への最後のお言葉などを、何かのついでに申し上げたのかもしれません。また女性に興味をお持ちになるお心から想像をたくましくあそばしての恋であるかもしれません。私が女王がたにこの御縁談を取りなして成功させるだけの好意を示すべきであるのに、こちらでは御冷淡な態度をおとり続けになりますので、私がかえって妨げをしているのではないかというふうにたびたび仰せられるものですから、そうしましたことは私のしたいと思うことではありませんが、また御紹介しておつれ申し上げるくらいを断然お断わりするというふうにもまいらないのです。どうしてお手紙などをそう御冷淡にお扱いになるのでしょう。
|
【宮の、いとあやしく】- 以下「痛からめ」まで、薫の詞。「宮」は匂宮をさす。
【あはれなりし御一言を】- 八宮の遺言をさす。
【ことのついでにもや、漏らし聞こえたりけむ】- 何かの機会に薫が匂宮に話したことがあったのだろうか、の意。
【いと隈なき御心のさがにて】- 匂宮の性格をいう。女性関係に関心深い性格。
【ここになむ、ともかくも聞こえさせなすべきと】- 私薫に中君との仲を何とか執り成すようにと、の意。以下、匂宮の詞を間接話法で語る。
【つれなき御けしきなるは】- 主語は中君。
【もてそこなひきこゆるぞと】- 主語は薫。『完訳』は「薫のとりなし方が悪い、の意」と注す。
【里のしるべ】- 『源氏釈』は「あまの住む里のしるべにあらなくに恨みむとのみ人の言ふらむ」(古今集恋四、七二七、小野小町)を指摘。匂宮を案内すること。
【何かは、いとさしももてなしきこえたまはむ】- 主語は姫君たち。匂宮に対して。反語表現。
|
| 4.3.2 |
|
好色でいらっしゃるように、人はお噂申し上げているようですが、心の奥は不思議なほど深くいらっしゃる宮です。
軽い冗談などをおっしゃる女たちで、軽はずみに靡きやすいという人などを、珍しくない女として軽蔑なさるのだろうか、と聞くこともございます。
どのようなことも成り行きにまかせて、我を張ることもなく、穏やかな人こそが、ただ世間の習わしに従って、どうなるもこうなるも適当に我慢し、少し思いと違ったことがあっても、仕方のないことだ、そういうものだ、などと諦めるようですので、かえって長く添い遂げるような例もあります。
|
好色な方のように世間では言うようですが、普通に恋を漁る方ではありません。女に対して一つの見識を立てておいでになる方ですよ。遊戯的に手紙をおやりになる相手があさはかで、たやすく受け入れようとするのなどは軽蔑して接近されるようなこともないという話です。何事の上にも自意識が薄くてなるにまかせている人は他から勧められるままに結婚もして、欠点が目について気に入らぬところはあっても、これが運命なのであろう、今さらしかたがないと我慢して済ますでしょうから、かえってほかから見てまじめな移り気のない男に見えもするでしょう。
|
【なほざりごと】- 以下「思ひおとしたまふにや」まで、人の詞の引用。
【のたまふわたりの、心軽うてなびきやすなる】- 格助詞「の」同格。
【思ひおとしたまふにや】- 主語は匂宮。
【おどけたる人こそ】- 係助詞「こそ」は「なるやうもあり」に係るが、結びの流れとなっている。
【さるべきぞ】- 『集成』は「これも定めだ」。『完訳』は「これも因縁というものだろう」と訳す。
【なかなか心長き例になるやうもあり】- 『集成』は「かえって(浮気沙汰などあっても)相手の夫がその女を妻として末長く添い遂げるといった例になることもあります」と訳す。
|
| 4.3.3 |
|
壊れ始めては、龍田川が濁る名を汚し、言いようもなくすっかり破綻してしまうようなことなども、あるようです。
心から深く愛着を覚えていらっしゃるらしいご性分にかない、特に御意に背くようなことが多くおありでない方には、全然、軽々しく、始めと終わりが違うような態度などを、お見せなさらないご性格です。
|
しかしそうでない場合もあって、男はそのために身を持ちくずし、一方は捨てられた妻で終わるという悲惨なことにもなるのです。お心を惹く点の多い女性にお逢いになって、その女性が宮をお愛しするかぎりは軽々しく初めに変わった態度をおとりになるような恐れのない方だと私は思っています。
|
【崩れそめては、龍田の川の濁る名をも汚し】- 『源氏釈』は「神奈備の三室の岸や崩るらむ龍田の川の水の濁れる」(拾遺集物名、三八九、高向草春)を指摘。
【うちまじるめれ】- 係助詞「こそ」はないが、文末、已然形。
【初め終り違ふやうなることなど、見せたまふまじきけしきになむ】- 『集成』は「気に入られた人なら、気持の変るようなことはないお人柄だ、という」。係助詞「なむ」の下に「おはす」などの語句が省略。
|
| 4.3.4 |
|
誰も存じ上げていないことを、とてもよく存じておりますから、もし似つかわしく、ご縁をとお考になったら、その取りなしなどは、できる限りのお骨折りを致しましょう。
京と宇治との間を奔走して、脚の痛くなるまで尽力しましょう」
|
だれもよく観察申し上げないようなことも私だけは細かくお知り申し上げている宮です。もし似合わしい御縁だと思召すようでしたら、私はこちらの者としてできるだけのことを御新婦のためにいたしましょう。ただ道が遠い所ですから奔走する私の足が痛くなることでしょう」
|
【いとよう見きこえたるを】- 主語は薫。接続助詞「を」順接、原因理由を表す。
【もし似つかはしく、さもやと思し寄らば】- 匂宮と中君の縁談。
【御中道のほど、乱り脚こそ痛からめ】- 『集成』は「(そうなれば)京とこの宇治との間を奔走して、定めし脚の痛い思いをすることになりましょう。「乱り脚」は、「乱りごこち」「乱り風」などと同じ言い方」と注す。
|
| 4.3.5 |
|
と、実に真面目に、おっしゃり続けなさるので、ご自身のことはお考えにもならず、「妹君の親代わりになって返事しよう」とご思案なさるが、やはりお答えすべき言葉も出ない気がして、
|
忠実に話し続ける薫の言葉を聞いていて、これを自分の問題であるとは思わぬ大姫君は、姉として年長者らしい、母代わりのよい挨拶がしたいと思うのであったが、その言葉が見つからないままに、
|
【わが御みづからのこと】- 大君自身のこと。
【人の親めきていらへむかし】- 大君の心中の思い。「人の」は妹をさす。
|
| 4.3.6 |
「いかにとかは。かけかけしげにのたまひ続くるに、なかなか聞こえむこともおぼえはべらで」 |
「何と申し上げてよいものでしょうか。
いかにもご執着のようにおっしゃり続けるので、かえってどのようにお答えしてよいか存じません」
|
「何とも申し上げることはございません。一つのことをあまり熱心にお話しなさいますものですから、私は戸惑いをして」
|
【いかにとかは】- 以下「おぼえはべらで」まで、大君の詞。この下に「のたまはむ」または「きこえむ」などの語句が省略。『集成』は「どういうお話なのでしょう」。『完訳』は「なんと申し上げたらよいのでしょう」と訳す。
|
| 4.3.7 |
と、うち笑ひたまへるも、おいらかなるものから、けはひをかしう聞こゆ。
|
と、ほほ笑みなさるのが、おっとりとしている一方で、その感じが好ましく聞こえる。
|
と笑ってしまったのもおおようで、美しい感じを相手に受け取らせた。
|
|
|
第四段 薫と大君、和歌を詠み交す
|
| 4.4.1 |
|
「必ずしもご自身のこととしてお考えになることとも存じません。
それは、雪を踏み分けて参った気持ちぐらいは、ご理解下さる姉君としてのお考えでいらっしゃって下さい。
あの宮のご関心は、また別な方のほうにあるようでございます。
わずかに文をお取り交わしなさることもございましたが、さあ、それも他人にはどちらかと判断申し上げにくいことです。
お返事などは、どちらの方が差し上げなさるのですか」
|
「あなたの問題として御判断を願っていることではございません。そちらは雪の中を分けてまいりました志だけをお認めになっていただけばよろしいのです。先ほどの話は姉君としてお考えおきください。宮の対象にあそばされる方はまた別の方のようです。御手跡の主の不分明な点についてのお話も少し承ったことがあるのですが、あちらへのお返事はどちらの女王様がなさっていらっしゃいますか
|
【かならず御みづから】- 以下「聞こえたまふ」まで、薫の詞。
【雪を踏み分けて参り来たる心ざしばかりを】- 『全書』は「忘れては夢かとぞ思ふ雪踏み分けて君を見むとは」(古今集雑下、九七〇、在原業平)を指摘。
【御このかみ心にても過ぐさせたまひてよかし】- 『集成』は「姉としてこの話を喜んでくれれば、それだけで今の自分は満足だ、と言う」と注す。
【かの御心寄せは、また異にぞはべべかめる】- 匂宮の関心はあなた以外の方すなわち妹君の中君らしい、の意。
【ほのかにのたまふさまも】- 主語は匂宮。『集成』は「中の君が相手だと自分も宮から伺ったことばあるように思うが、の意」。『完訳』は「匂宮が中の君に」と注す。
【人の分ききこえがたきことなり】- 他人には匂宮が大君と中君のどちらに関心があるのか判断つきかねる、の意。
【御返りなどは】- 匂宮への返事は、の意。
|
| 4.4.2 |
|
とお尋ね申し上げるので、「よくまあ、冗談にも差し上げなくてよかったことよ。
何ということはないが、このようにおっしゃるにつけても、どんなに恥ずかしく胸が痛んだことだろう」と思うと、お返事もおできになれない。
|
と薫は尋ねていた。よくも自分が戯れにもお相手になってそののちの手紙を書くことをしなかった、それはたいしたことではないが、こんなことを言われた際に、どれほど恥ずかしいかもしれないからと大姫君は思っていても、返辞はできないで、
|
【ようぞ、戯れにも】- 以下「胸つぶれまし」まで、大君の心中。『完訳』は「返事の主を問う言葉に、自分が返事を書かなくてよかったと胸をなでおろす」と注す。
【胸つぶれまし】- 推量の助動詞「まし」反実仮想。自分が返事を書いた場合を想定した気持ち。
|
| 4.4.3 |
|
「雪の深い山の懸け橋は、
あなた以外に誰も踏み分けて訪れる人
|
雪深き山の桟道君ならで
またふみ通ふ跡を見ぬかな
|
【雪深き山のかけはし君ならで--またふみかよふ跡を見ぬかな】- 「文」と「踏み」の掛詞。大君の詠歌。あなた薫以外とは文を交わしたことはない、という。
|
| 4.4.4 |
と書きて、さし出でたまへれば、
|
と書いて、差し出しなさると、
|
こう書いて出すと、
|
|
| 4.4.5 |
|
「お言い訳をなさるので、かえって疑いの気持ちが起こります」と言って、
|
「釈明のお言葉を承りますことはかえって私としては不安です」と薫は言って、
|
【御ものあらがひこそ、なかなか心おかれはべりぬべけれ】- 薫の詞。
|
| 4.4.6 |
|
「氷に閉ざされて馬が踏み砕いて歩む山川を
宮の案内がてら、
|
「つららとぢ駒踏みしだく山河を
導べしがてらまづや渡らん
|
【つららとぢ駒ふみしだく山川を--しるべしがてらまづや渡らむ】- 薫の返歌。「ふみ」の語句を用いて返す。わたしのほうが先にあなたと契りを結びたい、の意。
|
| 4.4.7 |
|
そうなったら、わたしが訪ねた効も、あるというものでしょう」
|
それが許されましたなら影さえ見ゆる(浅香山影さへ見ゆる山の井の浅くは人をわれ思はなくに)の歌の深い真心に報いられるというものです」
|
【さらばしも、影さへ見ゆるしるしも、浅うははべらじ】- 歌に添えた詞。『源氏釈』は「浅香山影さへ見ゆる山の井の浅きは人を思ふものかは」(古今六帖二、山の井)を指摘。
|
| 4.4.8 |
|
と申し上げなさると、意外な懸想に、嫌な気がして、特にお答えなさらない。
きわだって、よそよそしい様子にはお見えにならないが、今風の若い人たちのように、優美にも振る舞わずに、まことに好ましく、おおらかな気立てなのだろうと、推察されなさるご様子の方である。
|
といどむふうを見せた。思わぬ方向に話の転じてきたことから大姫君はやや不快になって返辞らしい返辞もしない。俗界から離れた聖人のふうには見えぬが、現代の若い人たちのように気どったところはなく、落ち着いた気安さのある人らしいと大姫君は薫を見ていた。
|
【思はずに、ものしうなりて】- 主語は大君。以外な薫の懸想に不愉快になる。
【けざやかに、いともの遠くすくみたるさまには見えたまはねど】- 以下「心ばへならむ」まで、薫の見た大君の感じ。
【のどかなる心ばへ】- 大島本は「のとかなる」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「のどやかなる」と校訂する。『新大系』は底本のままとする。
|
| 4.4.9 |
|
こうあってこそは、理想的だと、期待する気持ちに違わない気がなさる。
何かにつけて、懸想心を態度にお現しになるのに対しても、気づかないふりばかりをなさるので、気恥ずかしくて、昔の話などを、真面目くさって申し上げなさる。
|
若い男はそうあるべきであると思うとおりの人のようであった。言葉の引っかかりのできる時々に、ややもすれば薫は自身の恋を語ろうとするのであるが、気づかないふうばかりを相手が作るために気恥ずかしくて、それからは八の宮の御在世になったころの話をまじめにするようになった。
|
【ことに触れて、けしきばみ寄るも】- 薫の大君に対する懸想の態度。
【昔物語など】- 亡き八宮の思い出話。
|
|
第五段 薫、人びとを励まして帰京
|
| 4.5.1 |
|
「すっかり暮れてしまうと、雪がますます空まで塞いでしまいそうでございます」
|
日が暮れたならば雪は空も見えぬまでに高くなるであろう
|
【暮れ果てなば】- 以下「閉ぢぬべうはべり」まで、供人の声。
|
| 4.5.2 |
と、御供の人びと声づくれば、帰りたまひなむとて、
|
と、お供の人びとが促すので、お帰りになろうとして、
|
と思う従者たちは、主人の注意を促す咳払いなどをしだしたために、帰ろうとして薫は、
|
|
| 4.5.3 |
|
「おいたわしく見回されるお住まいの様子ですね。
ただ山里のようにたいそう静かな所で、人の行き来もなくございますのを、もしそのようにお考え下さるなら、どんなに嬉しいことでございましょう」
|
「何たる寂しいお住居でしょう。全然山荘のような静かな家を私は別に一つ持っておりまして、うるさく人などは来ない所ですが、そこへ移ってみようかとだけでも思ってくださいましたらどんなにうれしいでしょう」
|
【心苦しう】- 以下「いかにうれしくはべらむ」まで、薫の詞。
【ただ山里のやうにいと静かなる所の、人も行き交じらぬはべるを】- 京の三条の薫の邸をいう。「交じらぬ」と「はべる」の間に「邸」の語句が省略。
【さも思しかけば】- 京の邸に移ることに同意されたら。
|
| 4.5.4 |
|
などとおっしゃるのにつけても、「とてもおめでたいことだわ」と、小耳にはさんで、ほほ笑んでいる女房連中がいるのを、中の宮は、「とても見苦しい、どうしてそのようなことができようか」とお思いでいらっしゃった。
|
こんなことを女王に言っていた。けっこうなお話であると、片耳に聞いて笑顔を見せる女房のあるのを、醜い考え方をする人たちである、そんな結果がどうして現われてこようと、姫君は見もし聞きもしていた。
|
【いとめでたかるべきことかな】- 女房たちの感想。
【いと見苦しう、いかにさやうにはあるべきぞ】- 中君の心中の思い。
|
| 4.5.5 |
|
御果物を風流なふうに盛って差し上げ、お供の人びとにも、肴など体裁よく添えて、酒をお勧めさせなさるのであった。
あの殿の移り香を騒がれた宿直人は、鬘鬚とかいう顔つきが、気にくわないが、「頼りない家来だな」と御覧になって、召し出した。
|
菓子などが品よく客に供えられ、従者たちへは体裁のいい酒肴が出された。いつぞや薫からもらった衣服の芳香を持ちあぐんだ宿直の侍も鬘髭といわれる見栄のよくない顔をして客の取り持ちに出ていた。こんな男だけが守護役を勤めているのかと薫は見て、前へ呼んだ。
|
【また御移り香】- 大島本は「又」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「かの」と校訂する。『新大系』は底本のままとする。
【宿直人ぞ】- 係助詞「ぞ」は、「召し出でたり」に係るが、結びが流れている。
【鬘鬚とかいふつらつき、心づきなくてある】- 宿直人の容貌を説明する挿入句。
【はかなの御頼もし人や】- 薫の感想。
|
| 4.5.6 |
|
「どうだね。
お亡くなりになってからは、心細いだろうな」
|
「どうだね。宮がおいでにならなくなって心細いだろうが、よく勤めをしていてくれるね」
|
【いかにぞ】- 以下「心細からむな」まで、薫の詞。
【おはしまさでのち】- 八宮が亡くなって後。
|
| 4.5.7 |
など問ひたまふ。
うちひそみつつ、心弱げに泣く。
|
などとお尋ねになる。
べそをかきながら、弱そうに泣く。
|
と優しく慰めてやった。悲しそうな顔になって髭男は泣き出した。
|
|
| 4.5.8 |
|
「世の中に頼る身寄りもございません身の上なので、お一方様のお蔭にすがって、三十数年過ごしてまいりましたので、今はもう、野山にさすらっても、どのような木を頼りにしたらよいのでしょうか」
|
「何の身寄りも助け手も持たない私でございまして、ただお一方のお情けでこの宮に三十幾年お世話になっております。若い時でさえそれでございましたから、今日になりましてはましてどこを頼みにして行く所がございましょう」
|
【世の中に頼むよるべも】- 以下「頼むべくはべらむ」まで、宿直人の詞。
【一所の御蔭に】- 八宮の御庇護。
【いかなる木のもとをかは頼むべくはべらむ】- 『花鳥余情』は「侘び人のわきて立ち寄る木のもとは頼む蔭なく紅葉散りけり」(古今集秋下、二九二、僧正遍昭)を指摘。反語表現。
|
| 4.5.9 |
と申して、いとど人悪ろげなり。
|
と申し上げて、ますますみっともない様子である。
|
こんな話をするので、ますますみじめに見える髭男であった。
|
|
|
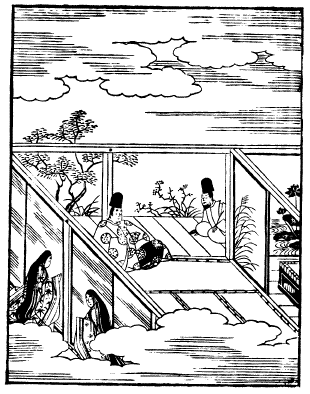 |
| 4.5.10 |
|
生前お使いになっていたお部屋を開けさせなさると、塵がたいそう積もって、仏像だけが花の飾りが以前と変わらず、勤行なさったと見えるお床などを取り外して、片づけてあった。
本願を遂げた時にはと、お約束申し上げたことなどを思い出して、
|
宮のお居間だったお座敷の戸を薫があけてみると、床には塵が厚く積もっていたが、仏だけは花に飾られておわしました。姫君たちが看経したあとと思われる。畳などは皆取り払われてあるのであった。御自分に出家の遂げられる日があったならと、それに薫が追随して行くことをお許しになったことなどを思い出して、
|
【おはしましし方開けさせたまへれば】- 八宮が生前に使用していた部屋。宿直人に開けさせた。
【御床など取りやりて】- 仏前に一段と高く設けた床。
【本意をも遂げば、と】- 自分薫が出家した暁には、の意。
|
| 4.5.11 |
|
「立ち寄るべき蔭とお頼りしていた椎の本は
空しい床になってしまったな」
|
立ち寄らん蔭と頼みし椎が本
むなしき床になりにけるかな
|
【立ち寄らむ蔭と頼みし椎が本--空しき床になりにけるかな】- 薫の詠歌。『異本紫明抄』は「優婆塞が行ふ山の椎が本あなそばそばし床にしあらねば」(宇津保物語、嵯峨院)を指摘。
|
| 4.5.12 |
|
といって、柱に寄り掛かっていらっしゃるのも、若い女房たちは、覗いてお誉め申し上げる。
|
と歌い、柱によりかかっている薫を、若い女房などはのぞき見をしてほめたたえていた。
|
【若き人びとは】- 若い女房たち。
|
| 4.5.13 |
|
日が暮れてしまったので、近い所々に、御荘園などに仕えている人びとに、み秣を取りにやったのを、主人もご存知なかったが、田舎びた人びとは、大勢引き連れて参ったのを、「妙に、体裁の悪いことだな」と御覧になるが、老女に用事で来たかのようにごまかしなさった。
いつもこのようにお仕えするように、お命じおきになってお帰りになった。
|
この近くの薫の領地の用を扱っている幾つかの所へ馬の秣などを取りにやると、主人は顔も知らぬような田舎男がおおぜい隊をなさんばかりにして山荘にいる薫へ敬意を表しに来た。見苦しいことであると薫は思ったのであるが、髭男を取り次ぎにして命じることだけを伝えさせた。この邸のために今夜も用を勤めるようにと荘園の者へ言い置かせて薫は山荘を出た。
|
【御荘など仕うまつる人びとに】- 薫の荘園に仕える人々。
【御秣取りにやりける、君も知りたまはぬに】- 供人が気を利かせて荘園の人々に今夜明朝の馬の飼料を取りにやらせた、それを主人の薫は知らないでいた、という趣。
【田舎びたる人びとは】- 大島本は「人々ハ」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「人々」と「は」を削除する。『新大系』は底本のままとする。
【あやしう、はしたなきわざかな】- 薫の思い。お忍びで来たのが表沙汰になってしまったので具合が悪い思い。
【老い人に紛らはしたまひつ】- 弁のもとに用事があって来たかのようにごまかした、の意。
【おほかたかやうに仕うまつるべく、仰せおきて】- いつもこのように姫君たちのお世話をするようにと、荘園の人々に命じおいた、の意。今まで宿直人一人が世話をしていたのが、急に薫の荘園の大勢の人々も世話をするようになった。
|
|
第五章 宇治の姉妹の物語 匂宮、薫らとの恋物語始まる
|
|
第一段 新年、阿闍梨、姫君たちに山草を贈る
|
| 5.1.1 |
|
年が変わったので、空の様子がうららかになって、汀の氷が一面に解けているのを、不思議な気持ちで眺めていらっしゃる。
聖の僧坊から、「雪の消え間で摘んだものでございます」といって、沢の芹や、蕨などを差し上げた。
精進のお膳にして差し上げる。
|
一月にはもう空もうららかに春光を見せ、川べりの氷が日ごとに解けていくのを見ても、山荘の女王たちはよくも今まで生きていたものであるというような気がされて、なおも父宮の御事が偲ばれた。あの阿闍梨の所から、雪解の水の中から摘んだといって、芹や蕨を贈って来た。斎めの置き台の上に載せられてあるのを見て、
|
【年替はりぬれば】- 薫二十四歳となる。
【ありがたくもと眺めたまふ】- 主語は宇治の姫君たち。『集成』は「不思議なことのように、姫君たちは相変らず悲しみに沈んでいられる」。『完訳』は「姫君たちは、よくも生き長らえたものと、悲嘆に沈んでいる」と訳す。
【雪消えに摘みてはべるなり】- 阿闍梨の伝言。
|
| 5.1.2 |
「所につけては、かかる草木のけしきに従ひて、行き交ふ月日のしるしも見ゆるこそ、をかしけれ」 |
「場所柄によって、このような草木の有様に従って、行き交う月日の節目も見えるのは、興趣深いことです」
|
山ではこうした植物の新鮮な色を見ることで時の移り変わりのわかるのがおもしろいと女房たちが言っているのを、
|
【所につけては】- 以下「をかしけれ」まで、女房たちの詞。
|
| 5.1.3 |
|
などと、人びとが言うのを、「何の興趣深いことがあろうか」とお聞きになっている。
|
姫君たちは何がおもしろいのかわからぬと聞いていた。
|
【何のをかしきならむ】- 姫君たちの心の内。反語表現。
|
| 5.1.4 |
|
「父宮が摘んでくださった峰の蕨でしたら
これを春が来たしるしだと知られましょうに」
|
君が折る峰のわらびと見ましかば
知られやせまし春のしるしも
|
【君が折る峰の蕨と見ましかば--知られやせまし春のしるしも】- 大君の詠歌。「君」は父をさす。「折る」「居る」の掛詞。「ましかば--まし」反実仮想の構文。
|
| 5.1.5 |
|
「雪の深い汀の小芹も誰のために摘んで楽しみましょうか
親のないわたしたちですので」
|
雪深き汀の小芹誰がために
摘みかはやさん親無しにして
|
【雪深き汀の小芹誰がために--摘みかはやさむ親なしにして】- 中君の唱和歌。「小芹」の「小」に「子」を響かす。「親」と「子」は縁語。
|
| 5.1.6 |
|
などと、とりとめのないことを語り合いながら、日をお暮らしになる。
|
二人はこんなことを言い合うことだけを慰めにして日を送っていた。
|
【はかなきことどもをうち語らひつつ】- 『集成』は「ふと心に浮ぶお歌を詠み交わしたりしながら」。『完訳』は「あれこれととりとめのないことをお話し合いになりなっては」と訳す。
|
| 5.1.7 |
|
中納言殿からも宮からも、折々の機会を外さずお見舞い申し上げなさる。
厄介で何でもないことが多いようなので、例によって、書き漏らしたようである。
|
薫からも匂宮からも春が来れば来るで、おりを過ぐさぬ手紙が送られる。例のようにたいしたことも書かれていないのであるから、話を伝えた人も、それらの内容は省いて語らなかった。
|
【うるさく何となきこと多かるやうなれば、例の、書き漏らしたるなめり】- 『一葉抄』は「紫式部か詞也」と指摘。『全集』は「薫、匂宮の言動に立ち合った人が見聞を書きとめたものによって、語り手が語っているという形式。このときの薫や匂宮の手紙は書きとめてなかったとする語り手の省筆の技法」と注す。
|
|
第二段 花盛りの頃、匂宮、中の君と和歌を贈答
|
| 5.2.1 |
|
花盛りのころ、宮は、「かざし」の和歌を思い出して、その時お供でご一緒した公達なども、
|
兵部卿の宮は春の花盛りのころに、去年の春の挿頭の花の歌の贈答がお思い出されになるのであったが、その時のお供をした公達などの
|
【花盛りのころ】- 桜の花の盛りのころ。二月下旬ころ。
【宮、「かざし」を思し出でて】- 匂宮が中君に「山桜匂ふあたりを尋ね来て同じかざしを折りてけるかな」という和歌を贈ったことを思い出す。
【見聞きたまひし君たちなども】- 匂宮に同行した公達。
|
| 5.2.2 |
「いとゆゑありし親王の御住まひを、またも見ずなりにしこと」 |
「実に趣のあった親王のお住まいを、再び見ないことになりました」
|
河を渡ってお訪ねした八の宮の風雅な山荘を、宮が薨去になってあれきり見られぬことになったのは残念である
|
【いとゆゑありし】- 以下「見ずなりにしこと」まで、公達の詞。
|
| 5.2.3 |
|
などと、世の中一般のはかなさを口々に申し上げるので、たいそう興味深くお思いになるのであった。
|
と口々に話し合っていた時にも、宮のお心は動かずにいるはずもなかった。
|
【いとゆかしう思されけり】- 主語は匂宮。再度宇治を訪問したく思う。
|
| 5.2.4 |
|
「この前は、
事のついでに眺めたあなたの桜を今年の春
|
つてに見し宿の桜をこの春に
霞隔てず折りて挿頭さん
|
【つてに見し宿の桜をこの春は--霞隔てず折りてかざさむ】- 匂宮から中君への贈歌。
|
| 5.2.5 |
|
と、気持ちのままおっしゃるのであった。
「とんでもないことだわ」と御覧になりながら、とても所在ない折なので、素晴らしいお手紙の、表面だけでも無にすまいと思って、
|
積極的なこんなお歌が宮から贈られた時に、思いも寄らぬことを言っておいでになるとは思ったが、つれづれな時でもあったから、美しい文字で書かれたものに対し、表面の意にだけむくいる好意をお示しして、
|
【心をやりてのたまへりけり】- 『集成』は「思いのままのお歌をおくられるのであった」。『完訳』は「何の気がねもなくお言い送りになるのであった」と訳す。
【あるまじきことかな】- 中君の心中の思い。
【見所ある御文の、うはべばかりをもて消たじ】- 中君の心中の思い。『集成』は「情趣をこわさないように、当りさわりのない返歌くらいはしよう、の意」と注す。
|
| 5.2.6 |
|
「どこと尋ねて手折るのでしょう
墨染に霞み籠めているわたしの桜を」
|
いづくとか尋ねて折らん
墨染めに霞こめたる宿の桜を
|
【いづことか尋ねて折らむ墨染に--霞みこめたる宿の桜を】- 大島本は「いつことか」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「いづく」と校訂する。『新大系』は底本のままとする。中君の返歌。「宿の桜」「霞」「折る」の語句を用いて返す。
|
| 5.2.7 |
なほ、かくさし放ち、つれなき御けしきのみ見ゆれば、まことに心憂しと思しわたる。
|
やはり、このように突き放して、素っ気ないお気持ちばかりが見えるので、ほんとうに恨めしいとお思い続けていらっしゃる。
|
とお返しをした。中姫君である。いつもこんなふうに遠い所に立つものの態度を変えないのを宮は飽き足らずに思っておいでになった。
|
|
|
第三段 その後の匂宮と薫
|
| 5.3.1 |
|
お胸に抑えきれなくなって、ただ中納言を、あれやこれやとお責め申し上げなさるので、おもしろいと思いながら、いかにも誰憚らない後見役の顔をしてお返事申し上げて、好色っぽいお心が表れたりする時々には、
|
こうしたお気持ちのつのっている時にはいつも中納言をいろいろに言って責めも恨みもされるのである。おかしく思いながらも、ひとかどの後見人顔をして、
「浮気な御行跡が私の目につく時もございますからね。
|
【をかしと思ひながら、いとうけばりたる後見顔に】- 主語は薫。薫は匂宮の前でいかにも姫君たいの後見人という顔をする。
【あだめいたる御心ざまをも見あらはす時々は】- 主語は匂宮。
|
| 5.3.2 |
|
「どうしてか、このようなお心では」
|
そうした方であってはと将来が不安でならなくなるのでございましょう」
|
【いかでか、かからむには】- 薫の詞。匂宮が浮気っぽい態度では、とても姫君をやれぬ、という。
|
| 5.3.3 |
|
など、お咎め申し上げなさるので、宮もお気をつけなさるのであろう。
|
などと申すと、
|
【宮も御心づかひしたまふべし】- 推量の助動詞「べし」は語り手の推量。
|
| 5.3.4 |
|
「気に入った相手が、まだ見つからない間のことです」とおっしゃる。
|
「気に入った人が発見できない過渡時代だからですよ」宮はこんな言いわけをあそばされる。
|
【心にかなふあたりを、まだ見つけぬほどぞや】- 匂宮の詞。
|
| 5.3.5 |
|
大殿の六の君をお気にかけないことは、何となく恨めしそうに、大臣もお思いになっているのであった。
けれど、
|
右大臣は末女の六の君に何の関心もお持ちにならぬ宮を少し怨めしがっていた。宮は
|
【大殿の六の君を】- 夕霧の六の君。藤典侍腹の姫君。「匂宮」巻に初出。
|
| 5.3.6 |
「ゆかしげなき仲らひなるうちにも、大臣のことことしくわづらはしくて、何ごとの紛れをも見とがめられむがむつかしき」 |
「珍しくない間柄の仲でも、大臣が仰々しく厄介で、どのような浮気事でも咎められそうなのがうっとうしくて」
|
親戚の中でのそれはありきたりの役まわりをするにすぎないことで、世間体もおもしろくないことである上に、大臣からたいそうな婿扱いを受けることもうるさく、蔭でしていることにも目をつけてかれこれと言われるのもめんどうだから結婚を承諾する気にはなれないのである
|
【ゆかしげなき】- 以下「むつかしき」まで、匂宮の詞。
|
| 5.3.7 |
と、下にはのたまひて、すまひたまふ。
|
と、内々ではおっしゃって、嫌がっていらっしゃる。
|
とひそかに言っておいでになって、以前から予定されているようでありながら実現する可能性に乏しかった。
|
|
| 5.3.8 |
|
その年、三条宮が焼けて、入道宮も、六条院にお移りになり、何かと騒々しい事に紛れて、宇治の辺りを久しくご訪問申し上げなさらない。
生真面目な方のご性格には、また普通の人と違っていたので、たいそうのんびりと、「自分の物と期待しながらも、女の心が打ち解けないうちは、不謹慎な無体な振る舞いはしまい」と思いながら、「故宮とのお約束を忘れていないことを、深く知っていただきたい」とお思いになっている。
|
その年に三条の宮は火事で焼けて、入道の宮も仮に六条院へお移りになることがあったりして、薫は繁忙なために宇治へも久しく行くことができなかった。まじめな男の心というものは、匂宮などの風流男とは違っていて、気長に考えて、いずれはその人をこそ一生の妻とする女性であるが、あちらに愛情の生まれるまでは力ずくがましい結婚はしたくないと思い、故人の宮への情誼を重く考える点で女王の心が動いてくるようにと願っているのであった。
|
【三条宮焼けて、入道宮も、六条院に移ろひたまひ】- 薫の本邸。薫は六条院に移り、母女三の宮も六条院に移る。
【いと異なりければ】- 生真面目な性格は常人とは格別違っていた、の意。
【いとのどかに、「おのがものとはうち頼みながら】- 『集成』は「至極のんびり構えて、きっと自分の妻になる人だとは信じていながら」と訳す。「おのがものとは」以下「情けなきさまは見えじ」まで、薫の心中。
【女の心ゆるびたまはざらむ限りは】- 大君の心がとけない限りは、の意。『完訳』は「大君が薫を夫として迎え入れる気持にならない限りは」と訳す。
【昔の御心忘れぬ方を、深く見知りたまへ】- 薫の心中。故八宮との約束。
|
|
第四段 夏、薫、宇治を訪問
|
| 5.4.1 |
|
その年は、例年よりも暑さを人がこぼすので、「川辺が涼しいだろうよ」と思い出して、急に参上なさった。
朝の涼しいうちにご出発になったので、折悪く差し込んでくる日の光も眩しくて、宮が生前おいでになった西の廂の間に、宿直人を召し出してお控えになる。
|
その夏は平生よりも暑いのをだれもわびしがっている年で、薫も宇治川に近い家は涼しいはずであると思い出して、にわかに山荘へ来ることになった。朝涼のころに出かけて来たのであったが、ここではもうまぶしい日があやにくにも正面からさしてきていたので、西向きの座敷のほうに席をして髭侍を呼んで話をさせていた。
|
【その年、常よりも暑さを人わぶるに】- 季節は夏に推移。
【川面涼しからむはや】- 薫の心中。「川面」は宇治川の河畔。
【あやにくにさし来る日影もまばゆくて、宮のおはせし西の廂に】- 日頃は西面に招じ入れられたのが、あいにく、日差しが強く差し込んで暑いので、日蔭の西面に招じ入れられた、という意。
【宿直人召し出でておはす】- 『完訳』は「宿直人をお召し寄せになって休息していらっしゃる」と訳す。
|
| 5.4.2 |
そなたの母屋の仏の御前に、君たちものしたまひけるを、気近からじとて、わが御方に渡りたまふ御けはひ、忍びたれど、おのづから、うちみじろきたまふほど近う聞こえければ、なほあらじに、こなたに通ふ障子の端の方に、かけがねしたる所に、穴のすこし開きたるを見おきたまへりければ、外に立てたる屏風をひきやりて見たまふ。 |
そちらの母屋の仏像の御前に、姫君たちがいらっしゃったが、近すぎないようにと、ご自分のお部屋にお渡りになるご様子、音を立てないようにしていたが、自然と、お動きになるのが近くに聞こえたので、じっとしていられず、こちらに通じている障子の端の方に、掛金がしてある所に、穴が少し開いているのを見知っていたので、外に立ててある屏風を押しやって御覧になる。
|
その時に隣の中央の室の仏前に女王たちはいたのであるが、客に近いのを避けて居間のほうへ行こうとしているかすかな音は、立てまいとしているが薫の所へは聞こえてきた。このままでいるよりも見ることができるなら見たいものであると願って、こことの間の襖子の掛け金の所にある小さい穴を以前から薫は見ておいたのであったから、こちら側の屏風は横へ寄せてのぞいて見た。
|
【気近からじとて】- 姫君たちの思い。薫に近い所にいては具合悪いと思って。
【わが御方に渡りたまふ】- 寝殿の西側の母屋の仏間から自分たちの東側の部屋へ移動。
【なほあらじに】- 薫はじっとしていられず。
|
| 5.4.3 |
ここもとに几帳を添へ立てたる、「あな、口惜し」と思ひて、ひき帰る、折しも、風の簾をいたう吹き上ぐべかめれば、 |
こちらに几帳を立て添えてある、「ああ、残念な」と思って、引き返す、ちょうどその時、風が簾をたいそう高く吹き上げるようなので、
|
ちょうどその前に几帳が立てられてあるのを知って、残念に思いながら引き返そうとする時に、風が隣室とその前の室との間の御簾を吹き上げそうになったため、
|
【吹き上ぐべかめれば】- 薫の目を通して叙述。「べかめれば」は薫の推量。
|
| 5.4.4 |
|
「丸見えになったら大変です。
その御几帳を押し出して」
|
「お客様のいらっしゃる時にいけませんわね、そのお几帳をここに立てて、十分に下を張らせたらいいでしょう」
|
【あらはにもこそあれ】- 以下「おし出でてこそ」まで、女房の詞。
【その几帳】- 大島本は「木丁」とある。『集成』『漢訳』は諸本に従って「御几帳」と「御」を補訂する。『新大系』は底本のままとする。
|
| 5.4.5 |
|
という女房がいるようである。
愚かなことをするようだが、嬉しくて御覧になると、高いのも低いのも、几帳を二間の簾の方に押し寄せて、この障子の正面の、開いている障子から、あちらに行こうとしているところなのであった。
|
と言い出した女房がある。愚かしいことだとみずから思いながらもうれしさに心をおどらせて、またのぞくと、高いのも低いのも几帳は皆その御簾ぎわへ持って行かれて、あけてある東側の襖子から居間へはいろうと姫君たちはするものらしかった。
|
【と言ふ人あなり】- 「なり」伝聞推定の助動詞。
【をこがましきものの、うれしうて】- 薫の心中。それまで穴を塞いでいた几帳が取り除かれたので、見えるようになった。
【高きも短きも】- 几帳の高さは五尺・三尺・二尺とある。以下「かうざまにもおはすべき」まで、薫の目を通して叙述する。
【几帳を二間の簾におし寄せて】- 仏間の南側に位置する廂間を二間に仕切った部屋。その南側の簾の前に几帳を移動する。
【この障子に向かひて】- 薫が覗いている障子の内側の正面を姫君たちが移動。
|
|
第五段 障子の向こう側の様子
|
| 5.5.1 |
|
まず、一人が立って出て来て、几帳から覗いて、このお供の人びとが、あちこち行ったり来たりして、涼んでいるのを御覧になるのであった。
濃い鈍色の単衣に、萱草の袴が引き立っていて、かえって様子が違って華やかであると見えるのは、着ていらっしゃる人のせいのようである。
|
その二人の中の一方が庭に向いた側の御簾から庇の室越しに、薫の従者たちの庭をあちらこちら歩いて涼をとろうとするのをのぞこうとした。濃い鈍色の単衣に、萱草色の喪の袴の鮮明な色をしたのを着けているのが、派手な趣のあるものであると感じられたのも着ている人によってのことに違いない。
|
【まづ、一人立ち出でて】- 後文から中君と知られる。
【几帳よりさし覗きて】- 中君の行動。若い姫君らしく好奇心が旺盛。
【この御供の人びとの、とかう行きちがひ、涼みあへるを】- 薫の供人。
【見たまふなりけり】- 主語は中君。
【袴】- 大島本は「はかま」とある。『集成』『完本』は諸本に従って「袴の」と「の」を補訂する。『新大系』は底本のままとする。
|
| 5.5.2 |
|
帯を形ばかり懸けて、数珠を隠して持っていらっしゃった。
たいそうすらりとした、姿態の美しい人で、髪が、袿に少し足りないぐらいだろうと見えて、末まで一筋の乱れもなく、つやつやとたくさんあって、可憐な風情である。
横顔などは、実にかわいらしげに見えて、色つやがよく、物やわらかにおっとりした感じは、女一の宮も、このようにいらっしゃるだろうと、ちらっと拝見したことも思い比べられて、嘆息を漏らされる。
|
帯は仮なように結び、袖口に引き入れて見せない用意をしながら数珠を手へ掛けていた。すらりとした姿で、髪は袿の端に少し足らぬだけの長さと見え、裾のほうまで少しのたるみもなくつやつやと多く美しく下がっている。正面から見るのではないが、きわめて可憐で、はなやかで、柔らかみがあっておおような様子は、名高い女一の宮の美貌もこんなのであろうと、ほのかにお姿を見た昔の記憶がまたたどられた。
|
【帯はかなげにしなして】- 掛け帯。仏前で誦経などするときの女性の身仕度。
【塵のまよひなく】- 『集成』は「一筋の乱れもなく」と訳す。
【女一の宮も、かうざまにぞおはすべき】- 明石中宮腹の女一の宮。『完訳』は「もともと薫には彼女への憧れのような恋慕があるらしい。薫の恋を規制する存在として重要である」と注す。
【ほの見たてまつりしも】- 薫は女一の宮をちらっと拝見したことがある趣である。
|
| 5.5.3 |
|
もう一人がいざり出て、「あの障子は、丸見えではないかしら」と、こちらを御覧になっている心づかいは、気を許さない様子で、嗜みがあると思われる。
頭の恰好や、髪の具合は、前の人よりもう少し上品で優美さが勝っている。
|
いざって出て、「あちらの襖子は少しあらわになっていて心配なようね」と言い、こちらを見上げた今一人にはきわめて奥ゆかしい貴女らしさがあった。頭の形、髪のはえぎわなどは前の人よりもいっそう上品で、艶なところもすぐれていた。
|
【またゐざり出でて】- 以下、巻末まで薫の目を通して叙述する。大君をさす。
【かの障子は、あらはにもこそあれ】- 大君の詞。『完訳』は「薫がのぞく仏間の西側の襖。そこに隙間などがあれば自分たちがのぞき見られるという懸念。慎重な性格で、中の君と対照的」と注す。
【今すこしあてになまめかしきさまなり】- 大島本は「なまめかしきさまなり」とある。『完本』は諸本に従って「なまめかしさまさりたり」と校訂する。『集成』『新大系』は底本のままとする。中君に比較して、気品高さや優雅さでまさる、という。
|
| 5.5.4 |
|
「あちらに屏風を添えて立ててございました。
すぐにも、お覗きなさるまい」
|
「あちらのお座敷には屏風も引いてございます。何もこの瞬間にのぞいて御覧になることもございますまい」
|
【あなたに屏風も添へて】- 以下「覗きたまはじ」まで、女房の詞。向う側、薫の覗いている所をさす。外側、したがって、薫は屏風を動かすことは可能である。
|
| 5.5.5 |
と、若き人びと、何心なく言ふあり。
|
と、若い女房たちは、何気なしに言う者もいる。
|
と安心しているふうに言う若い女房もあった。
|
|
| 5.5.6 |
|
「大変なことですよ」
|
「でも何だか気が置かれる。ひょっとそんなことがあればたいへんね」
|
【いみじうもあるべきわざかな】- 大君の詞。『完訳』は「見られたりしたらたいへんなことになりましょう」と訳す。
|
| 5.5.7 |
|
と言って、不安そうにいざってお入りなるとき、気高く奥ゆかしい感じが加わって見える。
黒い袷を一襲、同じような色合いを着ていらっしゃるが、これはやさしく優美で、しみじみと、おいたわしく思われる。
|
なお気がかりそうに言って、東の室へいざってはいる人に気高い心憎さが添って見えた。着ているのは黒い袷の一襲で、初めの人と同じような姿であったが、この人には人を惹きつけるような柔らかさ、艶なところが多くあった。また弱々しい感じも持っていた。
|
【ゐざり入りたまふほど】- 大君が寝殿の東面の間に入る。
【同じやうなる色合ひを】- 中君と同じような喪服の色。
|
| 5.5.8 |
|
髪は、さっぱりした程度に抜け落ちているのであろう、末の方が少し細くなって、見事な色とでも言うのか、翡翠のようなとても美しそうで、より糸を垂らしたようである。
紫の紙に書いてあるお経を片手に持っていらっしゃる手つきが、前の人よりほっそりとして、痩せ過ぎているのであろう。
立っていた姫君も、障子口に座って、何であろうか、こちらを見て笑っていらっしゃるのが、とても愛嬌がある。
|
髪も多かったのがさわやいだ程度に減ったらしく裾のほうが見えた。その色は翡翠がかり、糸を縒り掛けたように見えるのであった。紫の紙に書いた経巻を片手に持っていたが、その手は前の人よりも細く痩せているようであった。立っていたほうの姫君が襖子の口の所へまで行ってから、こちらを向いて何であったか笑ったのが非常に愛嬌のある顔に見えた。
|
【色なりとかいふめる、翡翠だちて】- 『集成』は「「色なり」は、髪のつやつやした美しさをいう成語であるらしい」と注す。かわせみの青羽のような光沢のある美しさをいう。
【かれより】- 妹の中君と比較して。
【痩せ痩せなるべし】- 薫と語り手の目が一体化した表現。
【立ちたりつる君も、障子口にゐて】- 『完訳』は「先刻立っていた女君も、襖の戸口におすわりになって」と訳す。「たりつる」は先刻--していた、というニュアンス。
【何ごとにかあらむ】- 挿入句。薫の疑問、声が聞こえない。
|
| 著作権 |
| 底本 |
大島本 |
| 校訂 |
Last updated 2/1/2011(ver.2-2)
渋谷栄一校訂(C)
オリジナル
修正版
比較 |
| ローマ字版 |
Last updated 4/21/2011 (ver.2-1)
Written in Japanese roman letters
by Eiichi Shibuya(C)
オリジナル
修正版
比較 |
ルビ抽出
(ローマ字版から)
|
Powered by 再編集プログラム v4.05
ひらがな版
ルビ抽出 |
挿絵
(ローマ字版から)
|
'Eiri Genji Monogatari'
(1650 1st edition) |
|
Last updated 3/28/2002
渋谷栄一訳(C)(ver.1-2-2)
オリジナル
修正版
比較 |
|
|
Last updated 4/21/2011(ver.2-2)
渋谷栄一注釈(C)
オリジナル
修正版
比較 |
|