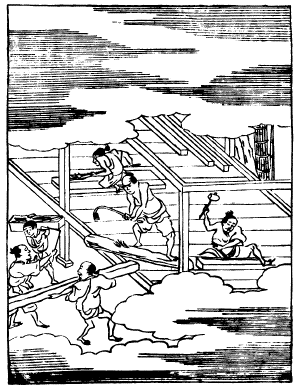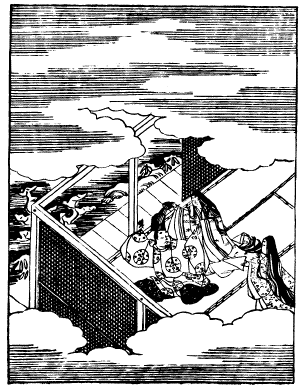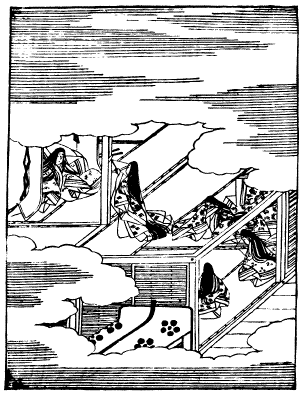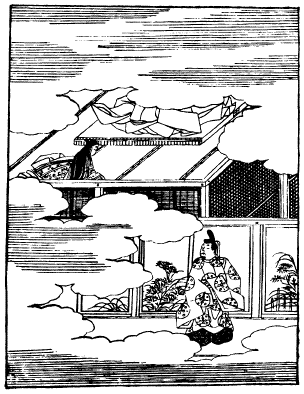第三十一帖 真木柱
光る源氏の太政大臣時代三十七歳冬十月から三十八歳十一月までの物語
|
# |
本文 |
渋谷栄一訳 |
与謝野晶子訳 |
注釈 |
|
第一章 玉鬘の物語 玉鬘、鬚黒大将と結婚
|
|
第一段 鬚黒、玉鬘を得る
|
| 1.1.1 |
|
「帝がお聞きあそばすことも恐れ多い。
少しの間は広く世間には知らせまい」とご注意申し上げなさるが、そう隠してもお隠しきれになれない。
何日かたったが、少しもお心を開くご様子もなく、「思いの他の不運な身の上だわ」と、思い詰めていらっしゃる様子がいつまでも続くので、「ひどく恨めしい」と思うが、浅からぬご縁、しみじみと嬉しく思う。
|
「帝のお耳にはいって、御不快に思召すようなことがあってもおそれおおい。当分世間へ知らせないようにしたい」
と源氏からの注意はあっても、右大将は、恋の勝利者である誇りをいつまでも蔭のことにはしておかれないふうであった。時日がたっても新しい夫人には打ち解けたところが見いだせないで、自身の運命はこれほどつまらないものであったかと、気をめいらせてばかりいる玉鬘を、大将は恨めしく思いながらも、この人と夫婦になれた前生の因縁が非常にありがたかった。
|
【内裏に聞こし召さむこと】- 以下「漏らさじ」まで、源氏の鬚黒大将に注意する詞である。しかし、源氏の心ともとれるような表現。「漏らさ」「じ」(打消推量の助動詞)は、自分自身に向かって戒めているような表現である。『完訳』は「源氏自身の無念さもこもるか」と指摘する。十月に尚侍として出仕することが予定されていた(「藤袴」第一章七段)。その前に鬚黒大将が玉鬘に通じてしまったことをさす。
【諌めきこえたまへど】- 源氏が鬚黒大将にお諌め申し上げなさるが。
【さしもえつつみあへたまはず】- 鬚黒大将は源氏が忠告するようにお隠し通しになれない。
【ほど経れど】- 鬚黒大将が玉鬘のもとに通うようになって暫くしたが。
【いささかうちとけたる御けしきもなく】- 玉鬘の鬚黒大将に対する態度には少しも気を許した御様子もなく。
【思はずに憂き宿世なりけり】- 玉鬘の感慨。鬚黒大将との結婚を「憂き宿世」と感想する。
【いみじうつらし」と思へど】- 鬚黒大将はひどく辛いと思うが。
|
| 1.1.2 |
|
見れば見るほどにご立派で、理想的なご器量、様子を、「他人のものにしてしまうところであったよ」と思うだけでも胸がどきどきして、石山寺の観音も、弁の御許も並べて拝みたく思うが、女君がほんとうに不愉快だと嫌ったので、出仕もせずに自宅に引き籠もっているのであった。
|
予想したにも過ぎた佳麗な人を見ては、自分が得なかった場合にはこのすぐれた人は他人の妻になっているのであると、こんなことを想像する瞬間でさえ胸がとどろいた。石山寺の観世音菩薩も、女房の弁も並べて拝みたいほどに大将は感激していたが、玉鬘からは最初の夜の彼を導き入れた女として憎まれていて、弁は新夫人の居間へ出て行くことを得しないで、部屋に引き込んでいた。
|
【見るままにめでたく】- 以下、鬚黒の目を通して語られる。「よそものに見果ててやみなましよ」は鬚黒大将の心中。「見るままにめでたく」というように、文末が過去の助動詞「けり」で結ばれる。以下「あらはれける」までの段、語り手が鬚黒の気持ちに添って、またその周辺から語った内容である。
【よそのものに見果ててやみなましよ】- 他人の妻としてしまうところであったよ。「まし」は反実仮想の助動詞。
【石山の仏】- 滋賀県大津市にある石山寺。本尊は如意輪観音像。当時霊験あらたかな観音として女性の信仰を多くあつめた。ここは男性の鬚黒大将が熱心に祈願した。
【弁の御許】- 玉鬘付きの女房で、「藤袴」巻に登場。鬚黒と玉鬘の結婚に一役果たしたらしい。
【女君】- 玉鬘。
【疎みにければ】- 大島本は「うとみ」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本によって「思し疎み」と「思し」を補訂する。
【え交じらはで籠もりゐにけり】- 弁は他の女房に混じって出仕することもできず、里に謹慎しているのであった。
|
| 1.1.3 |
|
なるほど、たくさんお気の毒な例を、いろいろと見て来たが、思慮の浅い人のために、お寺の霊験が現れたのであった。
|
仏の御心にもその祈願は取り上げずにいられまいと思われた風流男たちの恋には効験がなくて、荒削りな大将に石山観音の霊験が現われた結果になった。
|
【げに、そこら心苦しげなることどもを、とりどりに見しかど、心浅き人のためにぞ、寺の験も現はれける】- 『一葉抄』が「双紙の言葉也」と指摘。『評釈』では「女房の感想これは、そのとき傍観している女房のことばと考える」。『全集』は「語り手のことば」。『集成』は「草子地」。『完訳』は「玉鬘の意外な結婚への、語り手の評言」と指摘する。「げに」「とりどりに見しかど」(過去の助動詞「しか」は直接体験を意味する)という語句は、登場人物らの傍らで見ていた者の感想を表現したものである。物語の伝承者とその筆記編集者が一体化している。
|
| 1.1.4 |
大臣も、「心ゆかず口惜し」と思せど、いふかひなきことにて、「誰れも誰れもかく許しそめたまへることなれば、引き返し許さぬけしきを見せむも、人のためいとほしう、あいなし」と思して、儀式いと二なくもてかしづきたまふ。 |
大臣も「不満足で残念だ」とお思いになるが、今さら言ってもしかたのないことなので、「誰も彼もこのようにご承知なさったことなので、今さら態度を変えるのも、相手のためにたいそうお気の毒であり、筋違いである」とお考えになって、結婚の儀式をたいそうまたとなく立派にお世話なさる。
|
源氏も快心のこととはこの問題を見られなかったが、もう成立したことであって、当人はもとより実父も許容した婿を自分だけが認めない態度をとることは、自分の愛している玉鬘のためにもかわいそうであると思って、新婦の家としてする儀式を華麗に行なって、婿かしずきも重々しくした。
|
【誰れも誰れもかく許しそめたまへることなれば】- 尊敬語「たまへ」があるので、内大臣や源氏自身をさす。源氏の心内文中に語り手の源氏に対する敬意が紛れ込んだ語法。
|
| 1.1.5 |
|
一日も早く、自分の邸にお迎え申し上げることをご準備なさるが、軽率にひょいとお移りなさる場合、あちらに待ち受けて、きっと好ましく思うはずのない人がいらっしゃるらしいのが、気の毒なことにかこつけなさって、
|
早くそのうちに自邸へ新夫人を引き取って行きたいと大将は思っているのであるが、源氏は簡単に良人の家へ移るとしても、そこにはうれしく思っては迎えぬはずの第一夫人もいるのが、玉鬘のために気の毒であるということを理由にしてとめていた。
|
【いつしかと】- 鬚黒の心に添って語る。
【軽々しく】- 以下、視点が源氏の心に移る。
【よくも思ふまじき人】- 鬚黒の北の方。大島本は「よくも」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本によって「よくしも」と「し」を補訂する。
【ものしたまふなるが】- 「なる」(伝聞推定の助動詞)。いらっしゃというふうに聞いているのが。
【ことづけたまひて】- 源氏はかこつけなさって。
|
| 1.1.6 |
「なほ、心のどかに、なだらかなるさまにて、音なく、いづ方にも、人のそしり恨みなかるべくをもてなしたまへ」 |
「やはり、ゆっくりと、波風を立てないようにして、騒がれないで、どこからも人の非難や妬みを受けないよう、お振る舞いなさい」
|
「何もかも穏やかに行くようにして、双方とも譏られたり、恨んだりすることを避けなければならない」
|
【なほ、心のどかに】- 以下「もてなしたまへ」まで、源氏の玉鬘への忠告の詞。
|
| 1.1.7 |
とぞ聞こえたまふ。
|
とお申し上げなさる。
|
と源氏は言うのである。
|
|
|
第二段 内大臣、源氏に感謝
|
| 1.2.1 |
|
父内大臣は、
|
実父の大臣は、
|
【父大臣】- 玉鬘の父大臣、すなわち内大臣。以下の段、「思ひきこえたまひける」まで、文末が過去の助動詞「けり」で結ばれる。語り手が物語の時間を結婚の三日夜の過去に遡らせ、その折の内大臣に関する態度について補足説明を挿入したような内容である。
|
| 1.2.2 |
|
「かえって無難であろう。
格別親身に世話してくれる後見のない人が、なまじっかの色めいた宮仕えに出ては、辛いことであろうと、不安に思っていた。
大切にしたい気持ちはあるが、女御がこのようにいらっしゃるのを差し置いて、どうして世話できようか」
|
この結婚がかえってあなたのために幸福だと思う。忠実な支持者がなくて派手な宮仕えに出ては苦しいことであろうと自分は心配でならなかった。助けたい志は十分にあるが、もう後宮には女御が出ているのであるから、私としてはどうしてあげようもないのだから
|
【なかなか】- 以下「いかがもてなさまし」まで、内大臣の詞。なまじ宮仕えするよりは結婚したほうが無難なようである。「めり」(推量の助動詞、視界内推量)は内大臣が自らの経験の中で判断したニュアンス。
【うしろめたかりし】- 「し」(過去の助動詞)は内大臣自身不安に思っていた、というニュアンス。
【女御かくてものしたまふを】- 弘徽殿女御をさす。「澪標」巻に入内。内大臣と右大臣の娘四の君との間の姫君。
【いかがもてなさまし】- 反語表現。どのようにお世話できようか、しようがない。
|
| 1.2.3 |
|
などと、内々におっしゃっているのであった。
なるほど、帝だと申しても、人より軽くおぼし召し、時たまお目にかかりなさって、堂々としたお扱いをなさらなかったら、軽率な出仕ということになりかねないのであった。
|
と、こんな意味の手紙を玉鬘へ送った。それは真理である。相手が帝でおありになっても、第一の寵はなくて、ただ御愛人であるにとめられて、あやふやな後宮の地位を与えられているようなことは、女として幸福なことではないのである。
|
【げに、帝と聞こゆとも、人に思し落とし、はかなきほどに見えたてまつりたまひて、ものものしくももてなしたまはずは、あはつけきやうにもあべかりけり】- 『休聞抄』は「双ノ地也又玉鬘の心也」と指摘。『全書』は「草子地」と指摘。『評釈』は「内大臣の考えを、作者は、「げに」と、賛成する」といい、『全集』『集成』は「草子地」という言い方で、『完訳』は「語り手」という言い方で指摘する。「なるほど」は内大臣の詞を受け、語り手がそれに賛成の意を表した口ぶり、また「あべかりけり」も語り手の推察である。
|
| 1.2.4 |
|
三日の夜のお手紙を、取り交わしなさった様子を伝え聞きなさって、こちらの大臣のお気持ちを、「ほんとうにもったいなく、ありがたい」と感謝申し上げなさるのであった。
|
三日の夜の式に源氏が右大将と応酬した歌のことなどを聞いた時に、内大臣は非常に源氏の好意を喜んだ。
|
【聞こえ交はしたまひける】- 親代わりの源氏と婿の鬚黒大将との間でやりとりなさった。
【伝へ聞きたまひて】- 実の父親の内大臣が伝え聞きなさって。
【この大臣の君】- 源氏。
【あはれにかたじけなく、ありがたし】- 内大臣の源氏に対する感謝の気持ち。
|
| 1.2.5 |
|
このように隠れたご関係であるが、自然と、世間の人がおもしろい話として語り伝えては、次から次へと漏れ聞いて、めったにない世間話として言いはやすのであった。
帝におかれてもお聞きあそばしたのであった。
|
皆ともかくも人に知らすまいとした結婚であったが、まもなくおもしろい新事実として世間はこのことを話題にし出した。帝もお聞きになった。
|
【かう忍びたまふ御仲らひのことなれど】- 「かう」は以上の経緯を語った内容をさす。さらに角度を変えて、世間の人々の様子、さらに帝へと及んでいく。文末は過去の助動詞「けり」で結ばれている。『湖月抄』は「草子地也」と指摘する。
|
| 1.2.6 |
|
「残念にも、縁のなかった人であるが、あのように望んでいられた願いもあるのだから。
宮仕えなど、妃の一人としてでは、お諦めになるのもよかろうが」
|
「残念だが、しかしそうした因縁だった人も、一度自分の決めたことだから後宮にはいることとは違った尚侍の職は辞める必要がない」
|
【口惜しう】- 以下「思ひ絶えたまはめ」まで帝の独り言。
【さ思しし本意】- 尚侍の君としての宮仕えをさす。
【こそは、思ひ絶えたまはめ】- 「こそ--め」の係結び。文末であるが、文意は逆接的または反語的表現である。断念なさるのもよいだろうが、入内するのではないから、何構うまい、という意である。下に「内侍所にも」(第三段)とあるように、帝のこのことばによって、玉鬘の尚侍としての出仕が決定したことを暗示している。
|
| 1.2.7 |
|
などと仰せられるのであった。
|
という仰せを源氏へ下された。
|
【などのたまはせけり】- 以上、過去の助動詞「けり」で語られてきた段が終了し、以下は物語の現在時間に添って語られる。
|
|
第三段 玉鬘、宮仕えと結婚の新生活
|
| 1.3.1 |
霜月になりぬ。神事などしげく、内侍所にもこと多かるころにて、女官ども、内侍ども参りつつ、今めかしう人騒がしきに、大将殿、昼もいと隠ろへたるさまにもてなして、籠もりおはするを、いと心づきなく、尚侍の君は思したり。 |
十一月になった。
神事などが多く、内侍所にも仕事の多いころなので、女官連中、内侍連中が参上しては、はなやかに騒々しいので、大将殿は、昼もたいそう隠れたようにして籠もっていらっしゃるのを、たいそう気にくわなく、尚侍の君はお思いになっていた。
|
十月になった。神事が多くて内侍所が繁忙をきわめる時節で、内侍以下の女官なども長官の尚侍の意見を自邸へ聞きに来たりすることで、派手に人の出入りの多くなった所に、大将が昼も帰らずに暮らしていたりすることで尚侍は困っていた。
|
【霜月になりぬ】- 新年立では源氏三十七年十一月。
【参りつつ】- 女官や内侍司の人々が六条院に尚侍の玉鬘の決裁を仰ぎに参上する。接尾語「つつ」は同じ行動が繰り返しなされる意。
|
| 1.3.2 |
|
兵部卿宮などは、それ以上に残念にお思いになる。
兵衛督は、妹の北の方の事までを外聞が悪いと嘆いて、重ね重ね憂鬱であったが、「馬鹿らしく、恨んでみても今はどうにもならない」と考え直す。
|
失恋の悲しみをした人のたくさんある中にも兵部卿の宮などはことに残念がっておいでになる一人であった。左兵衛督は姉の大将夫人のこともいっしょにして世間体を悪く思ったが、恨みを言っても今さら何にもならぬのを知って沈黙していた。
|
【宮などは】- 蛍兵部卿宮。
【兵衛督】- 左兵衛督。紫の上の異母兄弟。式部卿宮の息子。その姉妹が鬚黒の北の方になっている。「藤袴」巻に初出の玉鬘求婚者の一人。
【妹の北の方の御ことをさへ】- 「さへ」には、玉鬘への求婚争いに敗れ、その上、姉妹の北の方が夫の鬚黒から顧みられなくなったことまで。
|
| 1.3.3 |
大将は、名に立てるまめ人の、年ごろいささか乱れたるふるまひなくて過ぐしたまへる、名残なく心ゆきて、あらざりしさまに好ましう、宵暁のうち忍びたまへる出で入りも、艶にしなしたまへるを、をかしと人びと見たてまつる。 |
大将は、有名な堅物で、長年少しも浮気沙汰もなくて過ごしてこられたのが、すっかり変わってご満悦で、別人のようなご様子で、夜や早朝の人目を忍んでいらっしゃる出入りも、恋人らしく振る舞っていらっしゃるのを、おもしろいと女房たちは拝する。
|
大将は以前からまじめで通った人で、過去においては何らの恋愛問題も起こさずに来たことなどは忘れたように、生まれ変わったような恋の奴の役に満足して、風流男らしく宵暁に新夫人の六条院へ出入りする様子をおもしろく人々は見ていた。
|
【大将は、名に立てるまめ人の】- 鬚黒大将の堅物なる人物像。
|
| 1.3.4 |
女は、わららかににぎははしくもてなしたまふ本性も、もて隠して、いといたう思ひ結ぼほれ、心もてあらぬさまはしるきことなれど、「大臣の思すらむこと、宮の御心ざまの、心深う、情け情けしうおはせし」などを思ひ出でたまふに、「恥づかしう、口惜しう」のみ思ほすに、もの心づきなき御けしき絶えず。 |
女は、陽気にはなやかにお振る舞いなさるご性分も表に出さず、とてもひどくふさぎ込んで、自分から求めて一緒になったのでないことは誰の目からも明らかであるが、「大臣がどうお思いであろうか、兵部卿宮のお気持ちの深くやさしくいらっしゃったこと」などを思い出しなさると、「恥ずかしく、残念だ」とばかりお思いになると、何かと気に入らないご様子が絶えない。
|
玉鬘ははなやかな心も引き込めて思い悩んでいた。自発的にできた結果でないことは第三者にもわかることであるが、源氏がどう思っているであろうということが玉鬘にはやる瀬なく苦しく思われるのであった。兵部卿の宮のお志が最も深く思われたことなどを思い出すと恥ずかしくくやしい気ばかりがされて、大将を愛することがまだできない。
|
【女は、わららかににぎははしくもてなしたまふ本性も】- 玉鬘の山吹の花のように明るく朗らかで何の屈託もなくはなやかな性格。
【あらぬさま】- 大島本は「あかぬ」とある。『新大系』『集成』『古典セレクション』は諸本によって「あらぬ」と校訂する。
|
|
第四段 源氏、玉鬘と和歌を詠み交す
|
| 1.4.1 |
|
殿も、気の毒だと女房たちも疑っていたことに、潔白であることを証明なさって、「自分の心中でも、その場限りの間違ったことは好まないのだ」と、昔からのこともお思い出しになって、紫の上にも、
|
源氏は幾十度となく一歩をそこへまで進めようとした自身を引きとめ、世間も疑った関係が美しく清いもので終わったことを思って、自身ながらも正しくないことはできない性質であることを知った。紫夫人にも、
|
【殿も】- 「心きよくあらはしたまひて」に繋る。
【いとほしう】- 以下「疑ひける筋を」まで挿入句。源氏は玉鬘を愛人にしようとしたのではないかという疑い。
【わが心ながら、うちつけにねぢけたることは好まずかし】- 源氏の心。
|
| 1.4.2 |
「思し疑ひたりしよ」
|
「お疑いでしたね」
|
「あなたは疑ってもいたではありませんか」
|
|
| 1.4.3 |
|
などと申し上げなさる。
「今さら、厄介な癖が出ても困る」とお思いになる一方で、何かたまらなくお思いになった時、「いっそ自分の物にしてしまおうか」と、お考えになったこともあるので、やはりご愛情も切れない。
|
と言ったのであった。しかし常識的には考えられないこともする物好きがあるのであるから、この先はどうなることかと源氏はみずから危うく思いながらも、恋しくてならなかった人であった玉鬘の所へ、
|
【今さらに人の心癖もこそ】- 源氏の心を語り手が語る。
【さてもや】- 源氏の心を語り手が語る。「さ」は玉鬘を自分の愛人にすることをさす。
【思し寄りたまひしことなれば】- 語り手は源氏の側近くから観察して語る。
|
| 1.4.4 |
|
大将のおいでにならない昼ころ、
お渡りになった。女君は、不思議なほど悩ましそうにばかりお振る舞いになって、さわやかな気分の時もなく萎れていらっしゃったが、このようにしてお越しになると、少し起き上がりなさって、御几帳に隠れ
|
大将のいない昼ごろに行ってみた。玉鬘はずっと病気のようになっていて、朗らかでいる時間もなくしおれてばかりいるのであったが、源氏が来たので、少し起き上がって、几帳に隠れるようにしてすわった。
|
【大将のおはせぬ昼つ方】- 源氏、玉鬘の夫の鬚黒のいない間に訪れ思いを訴える。
【かくて渡りたまへれば】- 大島本は「かくて」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本によって「かく」と「て」を削除する。
|
| 1.4.5 |
|
殿も、改まった態度で、少し他人行儀にお振る舞いになって、世間一般の話などを申し上げなさる。
真面目な普通の人を夫として迎えるようになってからは、今まで以上に言いようのないご様子や有様をお分りになるにつけ、意外な運命の身の、置き所もないような恥ずかしさにも、涙がこぼれるのであった。
|
源氏も以前と違った父の威厳というようなものを少し見せて、普通の話をいろいろした。平凡な大将の姿ばかりを見ているこのごろの玉鬘の目に、源氏の高雅さがつくづく映るについても、意外な運命に従っている自分がきまり悪く恥ずかしくて涙がこぼれるのであった。
|
【世の常の人にならひては】- 普通の人、鬚黒との結婚生活に馴れて。源氏は「世の常の人」ではなかった、という反対の意のニュアンスが込められる。
【御けはひありさま】- 源氏の御様子や態度。
【見知りたまふにも】- 玉鬘が源氏の素晴らしさをお分かりになるにつけても。
【思ひのほかなる身】- 玉鬘は鬚黒との結婚を思いの外のことだったと感じ取っている。
|
| 1.4.6 |
|
だんだんと、情のこもったお話になって、近くにある御脇息に寄り掛かって、少し覗き見しながら、お話し申し上げになさる。
たいそう美しげに面やつれしておいでの様子が、見飽きず、いじらしさがお加わりになっているにつけても、「他人に手放してしまうのも、あまりな気まぐれだな」と残念である。
|
繊細な人情の扱われる話になってから、玉鬘は脇息によりかかりながら、几帳の外の源氏のほうをのぞくようにして返辞を言っていた。少し痩せて可憐さの添った顔を見ながら源氏は、それを他人に譲るとは、自身ながらもあまりに善人過ぎたことであると残念に思われた。
|
【らうたいことの添ひたまへる】- 結婚生活後の玉鬘に表れた変化。
【よそに見放つも、あまりなる心のすさびぞかし】- 源氏の心。
【口惜し】- 語り手が源氏の心中を忖度した表現。
|
| 1.4.7 |
|
「あなたと立ち入った深い関係はありませんでしたが、
三途の川を渡る時、他の男に背負われて渡るようにはお約束
|
「下り立ちて汲みは見ねども渡り川
人のせとはた契らざりしを
|
【おりたちて汲みは見ねども渡り川--人の瀬とはた契らざりしを】- 源氏から玉鬘への贈歌。「汲み」「瀬」は「川」の縁語。「せ」は「瀬」と「背」との掛詞。女は初めて逢った男に背負われて三途の川を渡る、という俗信をふまえる。
|
| 1.4.8 |
|
思ってもみなかったことです」
|
意外なことになりましたね」
|
【思ひのほかなりや】- 玉鬘が鬚黒のものとなってしまい、永遠に自分のもとから離れて行ってしまったという感慨。
|
| 1.4.9 |
|
と言って、鼻をおかみになる様子、やさしく心を打つ風情である。
|
涙をのみながらこう言う源氏がなつかしく思われた。
|
【なつかしうあはれなり】- 語り手の感想をこめた評言。
|
| 1.4.10 |
女は顔を隠して、
|
女は顔を隠して、
|
女は顔を隠しながら言う。
|
|
| 1.4.11 |
|
「三途の川を渡らない前に何とかしてやはり
涙の流れに浮かぶ泡のように消えてしまいたいものです」
|
みつせ川渡らぬさきにいかでなほ
涙のみをの泡と消えなん
|
【みつせ川渡らぬさきにいかでなほ--涙の澪の泡と消えなむ】- 玉鬘から源氏への返歌。「渡り川」を「みつせ川」と言い換えて返す。人は死んだら、三途の川を渡らねばならないものであるのに、その前に死んでしまいたいとは理屈にあわない歌であるが、その理不尽な気持ちを詠んでこたえた。
|
| 1.4.12 |
|
「幼稚なお考えですね。
それにしても、あの三途の川の瀬は避けることのできない道だそうですから、お手先だけは、引いてお助け申しましょうか」と、ほほ笑みなさって、
|
源氏は微笑を見せて、
「悪い場所で消えようというのですね。しかし三途の川はどうしても渡らなければならないそうですから、その時は手の先だけを私に引かせてくださいますか」
と言った。
|
【心幼なの御消えどころや】- 以下「きこえてむや」まで、源氏の詞。
|
| 1.4.13 |
|
「真面目な話、お分かりになることもあるでしょう。
世間にまたといない馬鹿さ加減も、また一方で安心できるのも、この世に類のないくらいなのを、いくら何でもと、頼もしく思っています」
|
また、「あなたはお心の中でわかっていてくださるでしょう。類のないお人よしの、そして信頼のできる者は私で、他の男性のすることはそんなものでないことを経験なすったでしょう。と思うと私はみずから慰めることもできます」
|
【まめやかには】- 以下「頼もしき」まで、源氏の詞。
【世になき痴れ痴れしさ】- 機会がありながらも自分の妻妾の一人にしなかった迂闊さをさして、自嘲ぎみにいう。
【さりともとなむ、頼もしき】- 執拗な物言い。源氏の執拗な未練が言葉に出る。
|
| 1.4.14 |
と聞こえたまふを、いとわりなう、聞き苦しと思いたれば、いとほしうて、のたまひ紛らはしつつ、
|
と申し上げなさるのを、ほんとうにどうすることもできず、聞き苦しいとお思いでいらっしゃるので、お気の毒になって、話をおそらしになりながら、
|
こんなことも言われて、苦しそうに見える玉鬘に同情して、源氏は話を言い紛らせてしまった。
|
|
| 1.4.15 |
|
「帝が仰せになることがお気の毒なので、やはり、ちょっとでも出仕おさせ申しましょう。
自分の物と家の中に閉じ込めてしまってからでは、そのようなお勤めもできにくいお身の上となりましょう。
当初の考えとは違ったかっこうですが、二条の大臣は、ご満足のようなので、安心です」
|
「陛下は御同情のされるもったいない仰せを下さいましたから、形式的にだけでもあなたを参内させようと思っています。家庭の妻になってしまっては、そうした務めのために御所へ出るようなことは困難らしい。単なる尚侍であることは最初の私の精神とは違っても、三条の大臣はかえって満足しておいでになることですから安心です」
|
【内裏にのたまはすることなむ】- 帝の「口惜しう宿世異なりける人なれど思しし本意もあるを。宮仕へなど、かけかけしき筋ならばこそは、思ひ絶えたまはめ」(第一章二段)という言葉をさす。以下「心やすくなむ」まで、源氏の詞。
【おのがもの】- 公人である尚侍を私物化してしまう。
【さやうの御交じらひ】- 尚侍として出仕して他の内侍司の官人たちと付き合うこと。
【思ひそめきこえし心は違ふさまなめれど】- 源氏は最初、玉鬘を尚侍として出仕させることを考えていた。しかし、鬚黒と結婚してしまったために、尚侍定員二名のうち、実務官としての尚侍になってしまったことをいう。
【二条の大臣】- 内大臣をさす。会話の中では、このように呼ぶ。二条に邸があった。
|
| 1.4.16 |
|
などと、こまごまとお話し申し上げなさる。
ありがたくも気恥ずかしくもお聞きになることが多いけれど、ただ涙に濡れていらっしゃる。
たいそうこんなにまで悩んでおいでの様子がお気の毒なので、お思いのままに無体な振る舞いはなさらず、ただ、心得や、ご注意をお教え申し上げなさる。
あちらにお移りになることを、直ぐにはお許し申し上げなさらないご様子である。
|
などと源氏は情味のこもった話をしていた。身にしむとも思い、恥ずかしいとも聞かれることは多いが、玉鬘はただ涙にとらわれていた。こんなに悲観的になっているのが哀れで、源氏は恋をささやくこともできなかった。ただ今後の大将と、その一家に対する態度などをよく教えていた。ただそのほうへ行ってしまうことは急に許そうとしないふうが見えた。
|
【あるべきやう】- 尚侍としての心得をいう。
【かしこに渡りたまはむこと】- 鬚黒大将邸にお移りになること。
【とみにも許しきこえたまふまじき御けしきなり】- 「まじき」(打消推量の助動詞、推量)、「なり」(断定の助動詞)は、語り手の推量と断定である。以上、源氏と玉鬘との対座の場面が終了する。
|
|
第二章 鬚黒大将家の物語 北の方、乱心騒動
|
|
第一段 鬚黒の北の方の嘆き
|
| 2.1.1 |
|
宮中に参内なさることを、心配なことと大将はお思いになるが、その機会に、そのまま退出おさせ申そうかとのお考えを思いつかれて、ただちょっとの暇のお許しを申し上げなさる。
このように人目を忍んでお通いになることも、お慣れにならない感じで辛いので、ご自分の邸内の修理し整えて、長年荒れさせ埋もれ、放って置かれたお部屋飾り、すべての飾りつけを立派にしてご準備なさる。
|
御所へ尚侍を出すことで大将は不安をさらに多く感じるのであるが、それを機会に御所から自邸へ尚侍を退出させようと考えるようになってからは、短時日の間だけを宮廷へ出ることを許すようになった。こんなふうに婿として通って来る様式などは馴れないことで大将には苦しいことであったから、自邸を修繕させ、いっさいを完全に設けて一日も早く玉鬘を迎えようとばかり思っていた。今日までは邸の中も荒れてゆくに任せてあったのである。
|
【内裏へ参りたまはむことを、やすからぬことに大将思せど】- 以下の段、場面変わって、視点を鬚黒の立場において語る。
【そのついでにや】- 大島本は「そのついてにや(△△&にや)まかて」とある。すなわち「そのついて」の次の元の文字の上に重ねて「にや」と書く。『新大系』はその訂正に従う。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「そのついでにやがて」と校訂する。玉鬘が出仕した機会をさす。
【まかでさせたてまつらむ】- 宮中から鬚黒の自邸に退出おさせ申そう、の意。
【許しきこえたまふ】- 「許し」は名詞、許可の意。鬚黒は源氏にお許しを願い申し上げなさる、意。
【忍び隠ろへたまふ御ふるまひ】- 夫婦でありながら鬚黒が人目を忍んで玉鬘のもとにお通いになることをいう。
【ならひたまはぬ心地】- 経験のないこと。鬚黒の堅物らしい性格を示す。
【儀式を改め】- 格式を立派に改めて、の意。
|
|
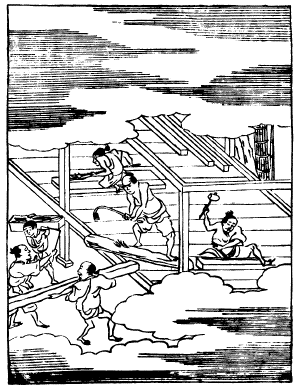 |
| 2.1.2 |
北の方の思し嘆くらむ御心も知りたまはず、かなしうしたまひし君達をも、目にもとめたまはず、なよびかに情け情けしき心うちまじりたる人こそ、とざまかうざまにつけても、人のため恥がましからむことをば、推し量り思ふところもありけれ、ひたおもむきにすくみたまへる御心にて、人の御心動きぬべきこと多かり。 |
北の方がお嘆きになろうお気持ちもお考えにならず、かわいがっていらっしゃったお子たちにも、お目もくれなさらず、やさしく情け深い気持ちのある人ならば、何かのことにつけても、女にとって恥になるようなことには、考え及ぶところもあろうが、一徹で融通のきかないご性分なので、人のお気に障るようなことが多いのであった。
|
夫人の悲しむ心も知らず、愛していた子供たちも大将の眼中にはもうなかった。好色な風流男というものは、ただ一人の人だけを愛するのでなしに、だれのため、彼のためも考えて思いやりのある処置をとるものであるが、生一本な人のこうした場合の態度には一方の夫人としてはたまるまいと憐まれるものがあった。
|
【なよびかに】- 以下「思ふところもありけれ」まで、挿入句。
|
| 2.1.3 |
|
女君は、人にひけをお取りになるようなところはない。
お人柄も、あのような高貴な父親王がたいそう大切にお育て申された世間の評判、けっして軽々しくなく、ご器量なども、たいそう素晴らしくいらっしゃったが、妙に、しつこい物の怪をお患いになって、ここ数年来、普通の人とはお変わりになって、正気のない時々が多くおありになって、ご夫婦仲も疎遠になって長くなったが、れっきとした本妻としては、また並ぶ人もなくお思い申し上げていらっしゃったが、珍しくお心惹かれる方が、一通りどころの方でなく、人より勝れていらっしゃるご様子よりも、あの疑いを持って皆が想像していたことさえ、潔白の身でお過ごしになっていらしたことなどを、めったにない立派な態度だと、ますます深くお思い申し上げなさるのも、もっともなことである。
|
夫人は人に劣った女性でもなかった。身分は尊貴な式部卿の宮の最も大切にされた長女であって、世の中から敬われてもいた。美人でもあったが、ひどい物怪がついて、この何年来は尋常人のようでもないのである。狂っている時が多くて、夫婦の中も遠くなっていたが、なお唯一の妻として尊重していた大将に新しい夫人ができ、それがすぐれた美しい人である点ではなくて、世間も疑っていた源氏との関係もないことであった清い処女であった点に大将の愛は強く惹かれてしまった。それで第一夫人はそれだけの愛を損しているわけである。
|
【女君、人に劣りたまふべきことなし】- 鬚黒の北の方は、父は式部卿宮、藤壷中宮の姪、源氏の紫の上とは異母姉妹。『紹巴抄』は「女君」以下「ことわりになむ」までを「双地」と指摘する。以下、文体がやや変化する。
【また並ぶ人なく思ひきこえたまへるを】- 鬚黒がれっきとした北の方としてお思い申し上げていらしたが。
【人にすぐれたまへる御ありさまよりも】- 『万水一露』は「草地に批判したる詞成へし」と指摘する。
【推し量りしことさへ】- 過去の助動詞「し」は直接体験した出来事をいう。鬚黒の心に即して語り手が語っている。
【ありがたうあはれと】- 『孟津抄』は「草子地也」と指摘する。
【ことわりになむ】- 『岷江入楚』は「草子の地なるへし」と指摘する。もっともなことである、という批評判断は語り手の感想である。以上、客観的物語の地の文から次第に語り手中心の文体に変化してきた。
|
| 2.1.4 |
式部卿宮聞こし召して、
|
式部卿宮がお聞きになって、
|
式部卿の宮はこの事情をお聞きになって、
|
|
| 2.1.5 |
「今は、しか今めかしき人を渡して、もてかしづかむ片隅に、人悪ろくて添ひものしたまはむも、人聞きやさしかるべし。おのがあらむこなたは、いと人笑へなるさまに従ひなびかでも、ものしたまひなむ」 |
「今は、あのような若い女を迎えて、大切にするだろう片隅で、みっともなく連れ添っていらっしゃるのも、外聞も痩せるほど恥ずかしいだろう。
自分が生きているうちは、まことに世間に恥をさらして言いなりにならなくても、お過ごしになられよう」
|
「今後そうした若い夫人を入れて派手に暮らさせようとしている邸の片すみに小さくなって住んでいるようなことをしては、世間体もよろしくない。私の生きている間はそんな屈辱的な待遇を受けて良人の家にいる必要はない」
|
【今は、しか】- 以下「ものしたまひなむ」まで、式部卿宮の詞。
【従ひなびかでも】- 鬚黒の言いなりにならなくても。
|
| 2.1.6 |
|
とおっしゃって、宮邸の東の対を掃除し整えて、「お迎え申そう」とお考えになっておっしゃるのを、「親の御家と言っても、夫に捨てられた身の上で、再び実家に戻ってお顔を合わせ申すのも」と、思い悩みなさると、ますますご気分も悪くなって、ずっと病床にお臥せりになる。
|
と御意見をお言いになった。御自邸の東の対を掃除させて、大将夫人の移って来る場所に決めておいでになるのであった。親の家ではあっても、良人の愛を失った女になって帰って行くことは、夫人の決心のできかねることであった。
|
【親の御あたりといひながら】- 以下「見えたてまつらむこと」まで、北の方の心。
【今は限りの身】- 『集成』は「夫に捨てられた身の上」と解し、『完訳』は「ひとたび人の妻となった身の上」と解す。
|
| 2.1.7 |
|
生まれつきは、たいそう静かで気立てもよく、おっとりとしていらっしゃる方で、時々、気がおかしくなって、人から嫌われてしまうようなことが、時たまおありなのであった。
|
性質の静かな善良な人で、子供らしいおおようさもある人でいながら、時々人からうとまれるような病的な発作があるのである。
|
【本性は】- 以下「うち混じりたまひける」まで、語り手の説明的文章が挿入される。
【時々、心あやまりして】- 物の怪の発作によって気がおかしくなること。
|
|
第二段 鬚黒、北の方を慰める(一)
|
| 2.2.1 |
住まひなどの、あやしうしどけなく、もののきよらもなくやつして、いと埋れいたくもてなしたまへるを、玉を磨ける目移しに、心もとまらねど、年ごろの心ざしひき替ふるものならねば、心には、いとあはれと思ひきこえたまふ。 |
お住まいなどが、とんでもなく乱雑で、綺麗さもなく汚れて、たいそう塞ぎ込んでいらっしゃるのを、玉を磨いたような所を見て来た目には、気に入らないが、長年連れ添ってきた愛情が急に変わるものでもないので、心中では、たいそう気の毒にとお思い申し上げる。
|
住居なども始終だらしなくなっていて、きれいなことは何一つ残っていない家にいる夫人を、玉鬘の六条院にいるのとは比べようもないのであるが、青年時代から持ち続けた大将の愛は根を張っていて、一朝一夕に変わるものでも、変えられるものでもないから、今も心では非常に妻を哀れに思っていた。
|
【玉を磨ける目移しに】- 玉を磨いたように素晴らしい玉鬘の邸を見て来た目には、の意。「磨く」には、「玉を磨く」(素晴らしい)意と「目を磨く」(鑑識眼を高める)の両意が掛けられた表現であろう。
|
| 2.2.2 |
|
「昨日今日の、たいそう浅い夫婦仲でさえ、悪くはない身分の人となれば、皆我慢することがあって添い遂げるものだ。
たいそう身体も苦しそうにしていらっしゃったので、申し上げなければならないこともお話し申し上げにくくてね。
|
「ただ昨日今日にできた夫婦でも、貴族の人たちは気に入らないことも、気に入らないふうを見せずに済ますものなのだ。全然人を捨ててしまうようなことをわれわれの階級の者はしないものなのだ。あなたには病苦というものがつきまとっていて、それを見るだけでも気の毒で、私の恋愛問題などを話しておこうとしても話す時がなかったのだよ。
|
【昨日今日の】- 以下「たまふべきにやあらむ」まで、鬚黒の北の方への慰めの詞。
【よろしき際になれば、皆思ひのどむる方ありてこそ見果つなれ】- ある程度の身分ある貴族の夫婦となると、みなお互いに我慢し合って最後まで添い遂げるもののようだ。「なれ」(伝聞推定の助動詞)。鬚黒の忠告は当時の貴族の夫婦生活をいうものか。
|
| 2.2.3 |
年ごろ契りきこゆることにはあらずや。世の人にも似ぬ御ありさまを、見たてまつり果てむとこそは、ここら思ひしづめつつ過ぐし来るに、えさしもあり果つまじき御心おきてに、思し疎むな。 |
長年添い遂げ申して来た仲ではありませんか。
世間の人と違ったご様子を、最後までお世話申そうと、ずいぶんと我慢して過ごして来たのに、とてもそうは行かないようなお考えで、お嫌いなさるのですね。
|
以前からあなたと約束していることでしょう、あなたに病気はあっても私は一生あなたといるつもりだって、私はどんな辛抱も続けてするつもりなのに、あなたはほかのことを考え出したのですね。別れてしまうようなことは考えずに私を愛してください。
|
【世の人にも似ぬ御ありさま】- 世間の人と違った御病気の様子。
|
| 2.2.4 |
幼き人びともはべれば、とざまかうざまにつけて、おろかにはあらじと聞こえわたるを、女の御心の乱りがはしきままに、かく恨みわたりたまふ。ひとわたり見果てたまはぬほど、さもありぬべきことなれど、まかせてこそ、今しばし御覧じ果てめ。 |
幼い子どもたちもいますので、何かにつけて、いいかげんにはしまいとずっと存じ上げてきたのに、女心の考えなさから、このように恨み続けていらっしゃる。
最後まで見届けないうちは、そうかも知れないことですが、信頼してこそ、もう少し御覧になっていてください。
|
子供もあるのだから、その点から言っても私は一生あなたを大事にすると言っているのに、女の人には困った嫉妬というものがあって、私を恨んでばかりあなたはいる。現在だけを見ておれば、あるいはそのほうが道理かもしれないが、私を信用してしばらく冷静に見ていてくれたなら、私のあなたを思う志はどんなものかが理解できる日があるだろうと思う。
|
【幼き人びともはべれば】- 後文によれば、姫君一人、男君二人と見える。
|
| 2.2.5 |
宮の聞こし召し疎みて、さはやかにふと渡したてまつりてむと思しのたまふなむ、かへりていと軽々しき。
まことに思しおきつることにやあらむ、しばし勘事したまふべきにやあらむ」
|
式部卿宮がお聞きになりお疎みになって、はっきりとすぐにお迎え申そうとお考えになっておっしゃっているのが、かえってたいそう軽率です。
ほんとうに決心なさったことなのか、暫く懲らしめなさろうというのでしょうか」
|
宮様が不快にお思いになって、今すぐにお邸へあなたをつれて帰ろうとお言いになるのは、かえってそのほうが軽率なことでないだろうか。実際別れさせてしまおうと思っておいでになるのだろうか。しばらく懲らしめてやろうとお思いになるのだろうか」
|
|
| 2.2.6 |
|
と、ちょっと笑っておっしゃる、たいそう憎らしくおもしろくない。
|
と笑いながら言う大将の様子には、だれからも反感を持たれるのに十分な利己主義者らしいところがあった。
|
【うち笑ひてのたまへる】- 冗談めかした笑い。
【いとねたげに心やまし】- 『集成』は「北の方の心を書いたもの」とある。語り手が北の方の立場になって気持ちを語ったところ。
|
|
第三段 鬚黒、北の方を慰める(二)
|
| 2.3.1 |
|
殿の召人といったふうで、親しく仕えている木工の君、中将の御許などという女房たちでさえ、身分相応につけて、「おもしろくなく辛い」と思い申し上げているのだから、まして北の方は、正気でいらっしゃる時なので、たいそうしおらしく泣いていらっしゃった。
|
大将の妾のようにもなっていた木工の君や中将の君なども、それ相応に大将を恨めしく思っていたが、夫人は普通な精神状態になっている時で、なつかしいふうを見せて泣いていた。
|
【御召人だちて】- 妻に準じる待遇の鬚黒の女房。
【木工の君、中将の御許】- 女房名。
【人びとだに】- 女房たちでさえ~であるのだから、まして北の方は。
|
| 2.3.2 |
|
「わたしを、惚けている、僻んでいる、とおっしゃって、馬鹿にするのは、けっこうなことです。
父宮のことまでを引き合いに出しておっしゃるのは、もし、お耳に入ったらお気の毒だし、つたないわが身の縁から軽々しいようです。
耳馴れていますから、今さら何とも思いません」
|
「私を老いぼけた、病的な女だと侮辱なさいますのはごもっともなことですが、そんなお言葉の中に宮様のことをお混ぜになるのを聞きますと、私のような者と親子でおありになるばかりにと思われて宮様がお気の毒でなりません。私はあなたのお噂を聞くことが近ごろ始まったことでも何でもないのですから、悲しみはいたしません」
|
【みづからを】- 以下「思ひはべらず」まで、北の方の詞。
【宮の御ことを】- 父兵部卿宮の悪口。
【取り混ぜのたまふぞ】- 大島本は「とりませの給う」とある。『新大系』『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「取りまぜのたまふぞ」と「ぞ」を補入する。
【漏り聞きたまはむは】- 兵部卿宮が悪口を漏れ聞きなさったら。推量の助動詞「む」は仮定の意。
【軽々しき】- 皇族の身にとって軽々しい、すなわち、傷がつくようだの意。
【耳馴れ】- 自分への悪口は聞き馴れている。
|
| 2.3.3 |
|
と言って、横を向いていらっしゃる、いじらしい。
|
と言って横向く顔が可憐であった。
|
【らうたげなり】- 語り手の、北の方をいじらしいという評言。以下、北の方の若かったころの美貌が語られる。
|
| 2.3.4 |
いとささやかなる人の、常の御悩みに痩せ衰へ、ひはづにて、髪いとけうらにて長かりけるが、わけたるやうに落ち細りて、削ることもをさをさしたまはず、涙にまつはれたるは、いとあはれなり。 |
たいそう小柄な人で、いつものご病気で痩せ衰え、ひ弱で、髪はとても清らかに長かったが、半分にしたように抜け落ちて細くなって、櫛梳ることもほとんどなさらず、涙で固まっているのは、とてもお気の毒である。
|
小柄な人が持病のために痩せ衰えて、弱々しくなり、きれいに長い髪が分け取られたかと思うほど薄くなって、しかもその髪はよく梳くこともされないで、涙に固まっているのが哀れであった。
|
【涙にまつはれたるは】- 大島本は「まつはれたる」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「まろがれたる」と校訂する。
【いとあはれなり】- 語り手の、北の方をとてもかわいそうだどいう評言。
|
| 2.3.5 |
|
つややかに美しいところはなくて、父宮にお似申して、優美な器量をなさっていたが、身なりを構わないでいられるので、どこに華やかな感じがあろうか。
|
一つ一つの顔の道具が美しいのではなくて、式部卿の宮によく似て、全体に艶なところのある顔を、構わないままにしてあっては、はなやかな、若々しいというような点はこの人に全然見られない。
|
【いづこのはなやかなるけはひかはあらむ】- 反語表現。どこにも派手やかなところはない、という語り手の感想。以上、北の方への解説が終わり、再び物語の現時点に戻る。
|
| 2.3.6 |
|
「宮の御事を、軽んじたりどうして思い申そう。
恐ろしい、人聞きの悪いおっしゃりようをなさいますな」となだめて、
|
「宮様のことを軽々しくなど私が言うものですか。人に聞かれても恐ろしいようなことを言うものでない」などと大将はなだめて、
|
【宮の御ことを】- 以下「なのたまひなしそ」まで、鬚黒の北の方への慰めの詞。下に「こしらへて」とある。
【軽くは】- 軽んじる、ないがしろにするの意。
|
| 2.3.7 |
|
「あの通っております所の、たいそう眩しい玉の御殿に、もの馴れない、生真面目な恰好で出入りしているのも、あれこれ人目に立つだろうと、気がひけるので、気楽に迎えてしまおうと考えているのです。
|
「私の通って行く所はいわゆる玉の台なのだからね。そんな場所へ不風流な私が出入りすることは、よけいに人目を引くことだろうと片腹痛くてね、自分の邸へ早くつれて来ようと私は思うのだ。
|
【かの通ひはべる所の】- 以下「かたみに後見むと思せ」まで、引き続き、鬚黒の北の方への慰めの詞。同じく下に「こしらへ聞こえたまへば」とある。六条院をいう。
【玉の台】- 六条院をいう。歌語的表現をした。
【人目たつらむ】- 眩しいほどの六条院に不格好なさまをして通っていたのでは人目にたって見苦しいとする、鬚黒自身認めており、またその解消策として玉鬘の迎えとりを持ち出す。
【心やすく移ろはしてむ】- 気安く玉鬘を自分の邸に迎えてしまおうと。
|
| 2.3.8 |
|
太政大臣が、ああした世に比べるものもないご声望を、今さら申し上げるまでもなく、恥ずかしくなるほど、行き届いていらっしゃるお邸に、よくない噂が漏れ聞こえては、たいそうお気の毒であるし、恐れ多いことでしょう。
|
太政大臣が今日の時代にどれだけ勢力のある方だというようなことは今さらなことだが、あのりっぱな人格者の所へ、ここの嫉妬騒ぎが聞こえて行くようではあの方に済まない。
|
【太政大臣】- 源氏を「太政大臣」と呼ぶ。以下、その権勢をかさに着たものものしい言い方をする。
【憎げなること】- 北の方と玉鬘との不和の噂。
【いとなむいとほしう、かたじけなかるべき】- 『集成』では「まことに不都合千万で、申しわけないことでしょう」と解し、『完訳』では「あなたにはまったく気の毒なことだし、大臣にも畏れ多いことになりましょう」と解す。
|
| 2.3.9 |
なだらかにて、御仲よくて、語らひてものしたまへ。宮に渡りたまへりとも、忘るることははべらじ。とてもかうても、今さらに心ざしの隔たることはあるまじけれど、世の聞こえ人笑へに、まろがためにも軽々しうなむはべるべきを、年ごろの契り違へず、かたみに後見むと、思せ」 |
穏やかにして、お二人仲を好くして、親しく付き合ってください。
宮邸にお渡りになっても、忘れることはございませんでしょう。
いずれにせよ、今さらわたしの気持ちが遠ざかることはあるはずはないのですが、世間の噂や物笑いに、わたしにとっても軽々しいことでございましょうから、長年の約束を違えず、お互いに力になり合おうと、お考えください」
|
穏やかに仲よく暮らすように心がけなければならないよ。宮のお邸へあなたが行ってしまったからといっても、私はやはりあなたを愛するだろう。夫婦の形はどうなっても今さら愛のなくなることはないのだが、世間があなたを軽率なように言うだろうし、私のためにも軽々しいことになる。長い間愛し合ってきた二人なのだから、これからも私のためになることをあなたも考えて、世話をし合おうじゃありませんか」
|
【世の聞こえ人笑へ】- 『完訳』は「家の体面をつぶし、北の方も身を滅ぼす危惧」と解す。
【まろがためにも】- 係助詞「も」同類の意。あなたはもちろんのこと、わたにとっても。
|
| 2.3.10 |
と、こしらへ聞こえたまへば、
|
と、とりなし申し上げなさると、
|
とも言った。
|
|
| 2.3.11 |
|
「あなたのお仕打ちは、どうこうと申しません。
世間の人と違った身の病を、父宮におかれてもお嘆きになって、今さら物笑いになることと、お心を痛めていらっしゃるとのことなので、お気の毒で、どうしてお目にかかれましょう、と思うのです。
|
「あなたの冷酷なことがいいことか悪いことか私はもう考えません。何とも思いません。ただ私が健全な女でないことを悲しんでいます。宮様がお案じになって、娘の私の名誉などをたいそうにお考えになったり、御煩悶をなすったりするのがお気の毒で、私は邸へ帰りたくないと思っています。
|
【人の御つらさは】- 以下「見るばかり」まで、北の方の詞。
【世の人にも似ぬ身の憂き】- 世間の人と違った身の不運、病い持ち。
【乱りたまふなれば】- 「なれ」(伝聞推定の助動詞)。お心を砕いていらっしゃるというので。
|
| 2.3.12 |
|
大殿の北の方と申し上げる方も、他人でいらっしゃいましょうか。
あの方は、知らない状態で成長なさった方で、後になって、このように人の親のように振る舞っていらっしゃる辛さを考えて、お口になさるようですが、わたしの方では何とも思っていませんわ。
なさりよう見ているばかりです」
|
六条の大臣の奥様は私のために他人ではありません。よそで育ったその人が大人になって、養女のために姉の私の良人を婿に取ったりするということで宮様などは恨んでいらっしゃるのですが、私はそんなことも思いませんよ。あちらでしていらっしゃることをながめているだけ」
|
【大殿の北の方】- 六条院の北の方、すなわち紫の上をさしてこう呼ぶ。
【異人にやはものしたまふ】- 反語表現。鬚黒の北の方と紫の上は異腹の姉妹である。
【かれは】- 紫の上をさす。以下「つらさをなむ」まで、北の方が父宮の詞を間接的にいったもの。
【親だち】- 紫の上が玉鬘の親代わりとなって結婚の世話をすることをいう。
【思ほしのたまふなれど】- 「なれ」(伝聞推定の助動詞)。父宮はおっしゃるようだが。
【ここには】- わたしには。
【もてないたまはむさま】- 『集成』は「どうしようと紫の上の勝手で、私は構わない」と解し、『完訳』は「あなたのなさることを」と解す。
|
| 2.3.13 |
とのたまへば、
|
とおっしゃるので、
|
|
|
| 2.3.14 |
|
「たいそう良いことをおっしゃるが、いつものご乱心では、困ったことも起こるでしょう。
大殿の北の方がご存知になることでもございません。
箱入り娘のようでいらっしゃっるので、このように軽蔑された人の身の上まではご存知のはずがありません。
あの人の親らしくなくおいでのようです。
このようなことが耳に入ったら、ますます困ることでしょう」
|
「こんなにあなたはよく筋道の立つ話ができるのだがね。病気の起こることがあって、取り返しもつかないようなことがこれからも起こるだろうと気の毒だね。この問題に六条院の女王は関係していられないのだよ。今でもたいせつなお嬢様のように大臣から扱われていらっしゃる方などが、よそから来た娘のことなどに関心を持たれるわけもないのだからね。まあまったく親らしくない継母様だともいえるね。それだのに恨んだりしていることがお耳にはいっては済まないよ」
|
【いとようのたまふを】- 以下「苦しかるべきこと」まで、鬚黒の詞。
【大殿の北の方の知りたまふことにもはべらず】- 「知る」は単に知っているという意でなく、関知し指図する意。紫の上が関知し指図したことではありません。
【かく思ひ落とされたる人】- 玉鬘をさす。自分の結婚相手を卑下した言い方。
【知りたまひなむや】- 係助詞「や」は反語。関知していらっしゃろうか、そんなことはない。
【ものしたまふべかめれ】- 「べか」(推量の助動詞、推量)「めれ」(推量の助動詞、視界内推量)、鬚黒の体験から判断して「~でいらっしゃるようだ」。
【かかることの聞こえ】- 紫の上が玉鬘の結婚を指図しているという非難。
【いとど苦しかるべきこと】- 大島本は「いとゝ」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「いと」と校訂する。
|
| 2.3.15 |
など、日一日入りゐて、語らひ申したまふ。 |
などと、一日中お側で、お慰め申し上げなさる。
|
などと、終日夫人のそばにいて大将は語っていた。
|
【入りゐて】- 北の方の部屋に入って座り続けて。
|
|
第四段 鬚黒、玉鬘のもとへ出かけようとする
|
| 2.4.1 |
|
日が暮れたので、気もそぞろになって、何とか出かけたいとお思いになるが、雪がまっくらにして降っている。
このような天候にあえて出かけるのも、人目に立ってお気の毒であるし、このご様子も憎らしく嫉妬して恨みなどなさるならば、かえってそれを口実にして、自分も対抗して出て行くのだが、たいそうおっとりと、気にかけていらっしゃらない様子が、たいそうお気の毒なので、どうしようか、と迷いながら、格子なども上げたまま、端近くに物思いに耽っていらっしゃった。
|
日が暮れると大将の心はもう静めようもなく浮き立って、どうかして自邸から一刻も早く出たいとばかり願うのであったが、大降りに雪が降っていた。こんな天候の時に家を出て行くことは人目に不人情なことに映ることであろうし、妻が見さかいなしの嫉妬でもするのでもあれば自分のほうからも十分に抗争して家を出て行く機会も作れるのであるが、おおように静かにしていられては、ただ気の毒になるばかりであると、大将は煩悶して格子も下ろさせずに、縁側へ近い所で庭をながめているのを、
|
【雪かきたれて降る】- 前に「霜月になりぬ」とあった。季節は冬である。雪が空をまっくらにして降る様子が描写される。
【かかる空にふり出でむも】- 「ふり」は「雪」の縁語。「雪が降る」と「振り出す」の両意をこめた掛け詞的表現。以下、鬚黒の心情に添った語りとなる。言葉遊び的表現が見られる。
【人目いとほしう】- ひどい雪の中をわざわざ出掛けて行ったとあっては、人目に立って北の方にも気の毒である。
【ふすべ】- 下文の「火」の縁語。
【迎ひ火】- 大島本は「むかひ火」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「むかへ火」と校訂する。『日本書紀』巻第七に倭建命が相模野で迎え火をつけて難を逃れた故事がある。こちらから対抗して。
|
| 2.4.2 |
|
北の方がその様子を見て、
|
夫人が見て、
|
【けしきを見て】- 物思いにふけっている鬚黒の様子を見て。
|
| 2.4.3 |
「あやにくなめる雪を、いかで分けたまはむとすらむ。夜も更けぬめりや」 |
「あいにくな雪ですが、どう踏み分けてお出かけなさろうとするのでしょう。
夜も更けたようですわ」
|
「あやにくな雪はだんだん深くなるようですよ。時間だってもうおそいでしょう」
|
【あやにくなめる】- 以下「更けぬめりや」まで、北の方の詞。
|
| 2.4.4 |
|
とお促しになる。
「今はもうおしまいだ、引き止めたところで」と思案なさっている様子、まことに不憫である。
|
と外出を促して、もう自分といることに全然良人は興味を失っているのであるから、とめてもむだであると考えているらしいのが哀れに見られた。
|
【今は限り、とどむとも】- 北の方の心。「いかならむ」などの語句が省略されている。鬚黒の気持ちはもう元には戻るまいという諦めの気持ち。
|
| 2.4.5 |
|
「このような雪では、どうして出かけられようか」
|
「こんな夜にどうして」
|
【かかるには、いかでか】- 鬚黒の詞。「え出でむ」などの語句が省略されている。このようにひどい雪ではどうして出掛けられようかの意。
|
| 2.4.6 |
とのたまふものから、
|
とおっしゃる一方で、
|
と大将は言ったのであるが、そのあとではまた反対な意味のことを、
|
|
| 2.4.7 |
「なほ、このころばかり。心のほどを知らで、とかく人の言ひなし、大臣たちも、左右に聞き思さむことを憚りてなむ、とだえあらむはいとほしき。思ひしづめて、なほ見果てたまへ。ここになど渡しては、心やすくはべりなむ。かく世の常なる御けしき見えたまふ時は、ほかざまに分くる心も失せてなむ、あはれに思ひきこゆる」 |
「やはり、ここ当分の間だけは。
わたしの気持ちを知らないで、何かと人が噂し、大臣たちもあれこれとお耳になさろうことを憚って、途絶えを置くのは気の毒です。
落ち着いて、やはりわたしの気持ちをお見届けください。
こちらになど迎えたら、気がねもなくなるでしょう。
このように普通のご様子をしていらっしゃる時は、他の女に心を移すこともなくなって、いとおしくお思い申し上げます」
|
「当分はこちらの心持ちを知らずに、そばにいる女房などからいろんなことを言われたりして疑ったりすることもあるだろうし、また両方で大臣がこちらの態度を監視していられもするのだから、間を置かないで行く必要がある。あなたは落ち着いて、気長に私を見ていてください。邸へつれて来れば、それからはその人だけを偏愛するように見えることもしないで済むでしょう。今日のように病気が起こらないでいる時には、少し外へ向いているような心もなくなって、あなたばかりが好きになる」
|
【なほ、このころばかり】- 以下「思ひきこゆる」まで、引き続き鬚黒の詞。結婚したばかりのころ。文はここで、いったん切れる。この語を受ける述語はない。
【大臣たち】- 源氏太政大臣や内大臣。
|
| 2.4.8 |
など、語らひたまへば、
|
などと、お慰めなさると、
|
こんなに言っていた。
|
|
| 2.4.9 |
|
「お止まりになっても、お心が他に行っているのなら、かえってつらいことでございましょう。
他の所にいても、せめて思い出してくだされば、涙に濡れた袖の氷もきっと解けることでしょう」
|
「家においでになっても、お心だけは外へ行っていては私も苦しゅうございます。よそにいらっしってもこちらのことを思いやっていてさえくだされば私の氷った涙も解けるでしょう」
|
【立ちとまりたまひても】- 以下「解けなむかし」まで、北の方の詞。
【袖の氷も】- 『奥入』は「思ひつゝねなくに明くる冬の夜の袖の氷はとけずもあるかな」(後撰集冬。四八二、読人しらず)<あの人を思いながら泣き明かした冬の夜は涙に濡れて凍った袖も解けないままであることよ>を指摘し、現在の注釈書でも指摘する。
【解けなむかし】- きっと解けましょう。「な」(完了の助動詞、確述)「む」(推量の助動詞)。
|
| 2.4.10 |
など、なごやかに言ひゐたまへり。
|
などと、穏やかにおっしゃっていられる。
|
夫人は柔らかに言っていた。
|
|
|
第五段 北の方、鬚黒に香炉の灰を浴びせ掛ける
|
| 2.5.1 |
|
御香炉を取り寄せて、ますます香をたきしめさせてお上げになる。
自分自身は、皺になったお召物類で、身なりを構わないお姿が、ますますほっそりとか弱げである。
沈んでいらっしゃるのは、たいそうお気の毒である。
お目をたいそう泣き腫らしているのは、少し疎ましいが、しみじみといとおしいと見る時は、咎める気もお消えになって、
|
火入れを持って来させて夫人は良人の外出の衣服に香を焚きしめさせていた。夫人自身は構わない着ふるした衣服を着て、ほっそりとした弱々しい姿で、気のめいるふうにすわっているのをながめて、大将は心苦しく思った。目の泣きはらされているのだけは醜いのを、愛している良人の心にはそれも悪いとは思えないのである。
|
【焚きしめさせたてまつりたまふ】- 北の方が女房をして鬚黒の衣装に香をたきこめさせ申し上げなさる。
【萎えたる御衣ども】- 大島本は「御そとも」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「御衣どもに」と「に」を補訂する。
【いと心苦し】- 語り手の北の方に対する同情の句。
【すこしものしけれど】- 鬚黒と語り手の感情が重なったような表現。
【いとあはれ】- 鬚黒の心。鬚黒が北の方をたいそういとおしいと思う。
|
| 2.5.2 |
|
「どうして今まで疎遠にしてきたのか」と、「すっかり心変わりした自分が何とも軽薄だ」とは思いながらも、やはり気持ちははやって、溜息をつきながら、やはりお召物を整えなさって、小さい香炉を取り寄せて、袖に入れてたきしめていらっしゃった。
|
長い年月の間二人だけが愛し合ってきたのであると思うと、新しい妻に傾倒してしまった自分は軽薄な男であると、大将は反省をしながらも、行って逢おうとする新しい妻を思う興奮はどうすることもできない。心にもない歎息をしながら、着がえをして、なお小さい火入れを袖の中へ入れて香をしめていた。
|
【いかで過ぐしつる年月ぞ】- 鬚黒の感想。『集成』は「どうして今まで長の年月、疎遠に過してきたのか」と訳し、『完訳』は「よくもこの長い年月いっしょに過してきたものよ」と訳す。前者は鬚黒の反省、後悔と解し、後者は鬚黒が北の方との仲を不思議に思っているところと解す。「いかで」は疑問であるとともに反語でもあろう。
【名残なう移ろふ心のいと軽きぞや】- 引き続き、鬚黒の反省、後悔。
【思ふ思ふ、なほ心懸想は進みて】- 「思ふ思ふ」「なほ」というように、その反面ではやはり玉鬘を思う気持ちははやって、という複雑な心理を捉えて語る。
【そら嘆きをうちしつつ】- 嘘の嘆息を何度もして見せる。あなたを置いて出掛けるのは億劫だというポーズである。
【しめゐたまへり】- 大島本は「しゐ給へり」とある。『新大系』『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「しめゐたまへり」と「め」を補訂する。
|
| 2.5.3 |
|
やさしいほどに着馴れたお召物で、器量も、あの並ぶ人のないお方には圧倒されるが、たいそうすっきりした男性らしい感じで、普通の人とは見えず、気おくれするほど立派である。
|
ちょうどよいほどに着なれた衣服に身を装うた大将は、源氏の美貌の前にこそ光はないが、くっきりとした男性的な顔は、平凡な階級の男の顔ではなかった。貴族らしい風采である。
|
【なつかしきほどに】- 鬚黒の様子について語る。
【容貌も】- 『万水一露』は「草子の批判の詞也」と指摘する。「心恥づかしげなり」は語り手の評言ともいえよう。
【かの並びなき御光】- 源氏の美しさを譬喩していう。
|
| 2.5.4 |
|
侍所で、供人たちが声立てて、
|
侍所に集っている人たちが、
|
【侍】- 名詞。侍所のこと、供人の詰所。
|
| 2.5.5 |
|
「雪が小止みです。
夜が更けてしまいましょう」
|
「ちょっと雪もやんだようだ。もうおそかろう」
|
【雪すこし隙あり。夜は更けぬらむかし】- 供人の声。「ぬ」(完了の助動詞、確述)「らむ」(推量の助動詞、視界外推量)「かし」(終助詞、強調)。夜が更けてしまいましょうの意。
|
| 2.5.6 |
|
などと、それでもあらわには言わないで、お促し申して、咳払いをし合っている。
|
などと言って、さすがに真正面から促すのでなく、主人の注意を引こうとするようなことを言う声が聞こえた。
|
【さすがにまほにはあらで】- 供人たちの北の方への遠慮した態度動作。
|
| 2.5.7 |
|
中将の君や、木工の君などは、「おいたわしいことだわ」などと嘆きながら、話し合って臥しているが、ご本人は、ひどく落ち着いていじらしく寄りかかっていらっしゃる、と見るうちに、急に起き上がって、大きな籠の下にあった香炉を取り寄せて、殿の後ろに近寄って、さっと浴びせかけなさる間、人の制止する間もなく、不意のことなので、呆然としていらっしゃる。
|
中将の君や木工などは、
「悲しいことになってしまいましたね」
などと話して、歎きながら皆床にはいっていたが、夫人は静かにしていて、可憐なふうに身体を横たえたかと見るうちに、起き上がって、大きな衣服のあぶり籠の下に置かれてあった火入れを手につかんで、良人の後ろに寄り、それを投げかけた。人が見とがめる間も何もないほどの瞬間のことであった。大将はこうした目にあってただあきれていた。
|
【中将、木工など】- 召人の中将の御許や木工の君など。
【あはれの世や】- 中将の御許や木工の君など感慨。北の方への同情。「世」は鬚黒と北の方の夫婦仲をいう。
【正身は】- 以下「あきれてものしたまふ」まで北の方の一連の動作。その間の緩急の行動が「~と見るほどに、~て、~ほど、~のほどもなう、~に」という語りの口調の上に巧みに語られている。
【ややみあふる】- 『集成』は「「ややみ」「あふる」と複合動詞と見るべきであろうが、語義不詳。「ややむ」は驚きあるいは呼び掛けの語「やや」を活用させたものか。「あふる」は煽るか。「やや見敢ふる」と見るのは無理であろう」と注す。『完訳』は「「見敢ふ」で見届ける意。人の目にもとまらぬ瞬時の出来事」と注す。
【あきれてものしたまふ】- 鬚黒の態度。すでに灰を浴びせ掛けられて茫然自失しているさま。
|
|
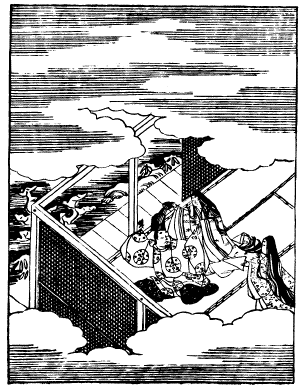 |
| 2.5.8 |
さるこまかなる灰の、目鼻にも入りて、おぼほれてものもおぼえず。払ひ捨てたまへど、立ち満ちたれば、御衣ども脱ぎたまひつ。 |
あのような細かい灰が、目や鼻にも入って、ぼうっとして何も分からない。
払い除けなさるが、立ちこめているので、お召物をお脱ぎになった。
|
細かな灰が目にも鼻にもはいって何もわからなくなっていた。やがて払い捨てたが、部屋じゅうにもうもうと灰が立っていたから大将は衣服も脱いでしまった。
|
【さるこまかなる】- 以下、その様子を細かく具体的に語る。
|
| 2.5.9 |
|
正気でこのようなことをなさると思ったら、二度と見向く気にもなれず驚くほかないが、
|
正気でこんなことをする夫人であったら、だれも顧みる者はないであろうが、
|
【うつし心にてかくしたまふぞと思はば】- 鬚黒の気持ちに添って語る。
|
| 2.5.10 |
|
「例の物の怪が、人から嫌われるようにしようとしていることだ」
|
いつもの物怪が夫人を憎ませようとしていることであるから、
|
【例の御もののけの】- 以下「するわざ」まで、鬚黒の感想であるとともに、「御前なる人びとも」とあるように女房たちの感想へと移る。
|
| 2.5.11 |
と、御前なる人びとも、いとほしう見たてまつる。
|
と、お側の女房たちもお気の毒に拝し上げる。
|
夫人は気の毒であると女房らも見ていた。
|
|
| 2.5.12 |
立ち騷ぎて、御衣どもたてまつり替へなどすれど、そこらの灰の、鬢のわたりにも立ちのぼり、よろづの所に満ちたる心地すれば、きよらを尽くしたまふわたりに、さながら参うでたまふべきにもあらず。 |
大騒ぎになって、お召物をお召し替えなどするが、たくさんの灰が鬢のあたりにも舞い上がり、すべての所にいっぱいの気がするので、善美を尽くしていらっしゃる所に、このまま参上なさることはできない。
|
皆が大騒ぎをして大将に着がえをさせたりしたが、灰が髪などにもたくさん降りかかって、どこもかしこも灰になった気がするので、きれいな六条院へこのままで行けるわけのものではなかった。
|
【きよらを尽くしたまふわたり】- 六条院の玉鬘の所を指していう。
|
| 2.5.13 |
|
「気が違っているとはいっても、やはり珍しい、見たこともないご様子だ」と愛想も尽き、疎ましくなって、いとしいと思っていた気持ちも消え失せたが、「今、事を荒立てたら、大変なことになるだろう」と心を鎮めて、夜中になったが、僧などを呼んで、加持をさせる騷ぎとなる。
わめき叫んでいらっしゃる声など、お嫌いになるのもごもっともである。
|
大将は爪弾きがされて、妻に対する憎悪の念ばかりが心につのった。先刻愛を感じていた気持ちなどは跡かたもなくなったが、現在は荒だてるのに都合のよろしくない時である。どんな悪い影響が自分の新しい幸福の上に現われてくるかもしれないと、大将は夫人に腹をたてながらも、もう夜中であったが僧などを招いて加持をさせたりしていた。夫人が上げるあさましい叫び声などを聞いては、大将がうとむのも道理であると思われた。
|
【心違ひとはいひながら】- 以下「さまなりや」まで、鬚黒の気持ち。
【爪弾きせられ】- 「られ」(自発の助動詞)。自然と~とういう気持ちになって。
【あはれと思ひつる心】- 『集成』は「いとしいと思っていた気持」と解し、『完訳』は「憐憫」と注し「いじらしいと思っていた気持」と訳すが、憐憫よりも愛情であろう。
【このころ、荒立てては、いみじきこと出で来なむ】- 鬚黒の心。この時期に事を荒立てては源氏方からも式部卿宮方からも厄介な事が出てこようという懸念。
【呼ばひののしりたまふ声など】- 北の方に乗り移った物の怪の声。
|
|
第六段 鬚黒、玉鬘に手紙だけを贈る
|
| 2.6.1 |
|
一晩中、打たれたり引かれたり、泣きわめいて夜をお明かしになって、少しお静かになっているころに、あちらへお手紙を差し上げなさる。
|
夜通し夫人は僧から打たれたり、引きずられたりしていたあとで、少し眠ったのを見て、大将はその間に玉鬘へ手紙を書いた。
|
【夜一夜、打たれ引かれ、泣きまどひ】- 北の方が僧から打たれたり引き回されたり、また北の方自身泣き叫んだりしている様子。
【かしこへ】- 鬚黒は玉鬘のもとへ。
|
| 2.6.2 |
|
「昨夜、急に意識を失った人が出まして、雪の降り具合も出掛けにくく、ためらっておりましたところ、身体までが冷えてしまいました。
あなたのお気持ちはもちろんのこと、周囲の人はどのように取り沙汰したことでございましょう」
|
昨夜から容体のよろしくない病人ができまして、おりから降る雪もひどく、こんな時に出て行くことはどうかと、そちらへ行くのをやむなく断念することにしましたが、外界の雪のためでもなく、私の身の内は凍ってしまうほど寂しく思われました。あなたは信じていてくださるでしょうが、そばの者が何とかいいかげんなことを忖度して申し上げなかったであろうかと心配です。
|
【昨夜、にはかに消え入る人のはべしにより】- 以下「とりなしはべりけむ」まで、鬚黒の文。北の方が物の怪に苦しめられて、と言わずに、漠然と昨夜急に瀕死の状態に陥った人が生じてと、言い訳をしている。
【ふり出でがたく】- 「ふり」は雪の縁語。また「降る」と「振る」の掛詞的表現。
【身さへ】- 心はもちろん身体までがの意。
|
| 2.6.3 |
と、きすくに書きたまへり。
|
と、生真面目にお書きになっている。
|
という文学的でない文章であった。
|
|
| 2.6.4 |
|
「心までが中空に思い乱れましたこの雪に
独り冷たい片袖を敷いて寝ました
|
心さへそらに乱れし雪もよに
一人さえつる片敷の袖
|
【心さへ空に乱れし雪もよに--ひとり冴えつる片敷の袖】- 鬚黒から玉鬘への贈歌。空模様ばかりでなく心までが。
|
| 2.6.5 |
|
耐えられませんでした」
|
堪えがたいことです。
|
【堪へがたくこそ】- 歌に添えた言葉。
|
| 2.6.6 |
|
と、白い薄様に、重々しくお書きになっているが、格別風情のあるところもない。
筆跡はたいそうみごとである。
漢学の才能は高くいらっしゃるのであった。
|
ともあった。白い薄様に重苦しい字で書かれてあった。字は能書であった。大将は学問のある人でもあった。
|
【白き薄様に】- 雪にあわせて白の薄様の紙を選んだ。
【ことにをかしきところもなし】- 語り手の鬚黒の手紙に対する評言。以下「ものしたまひける」まで、鬚黒についての評言が続く。
|
| 2.6.7 |
|
尚侍の君は、夜離れを何ともお思いなさらないので、このように心はやっていらっしゃるのを、御覧にもならないので、お返事もない。
男は、落胆して、一日中物思いをなさる。
|
尚侍は大将の来ないことで何の痛痒も感じていないのに、一方は一所懸命な言いわけがしてあるこの手紙も、玉鬘は無関心なふうに見てしまっただけであるから、返事は来なかった。大将は自宅で憂鬱な一日を暮らした。
|
【尚侍の君】- 玉鬘。
【かく心ときめきしたまへるを】- 鬚黒がはらはらしてお書きになった手紙を。「を」は下の「見も入れたまはねば」の目的格を表すとともに、内容的には逆接的に繋がっていくので、逆接の接続助詞とも見られる。両義性をもった用法である。
【男】- 鬚黒を「男」と呼ぶことに注意。男と女の場面。
|
| 2.6.8 |
北の方は、なほいと苦しげにしたまへば、御修法など始めさせたまふ。心のうちにも、「このころばかりだに、ことなく、うつし心にあらせたまへ」と念じたまふ。「まことの心ばへのあはれなるを見ず知らずは、かうまで思ひ過ぐすべくもなきけ疎さかな」と、思ひゐたまへり。 |
北の方は、依然としてたいそう苦しそうになさっているので、御修法などを始めさせなさる。
心の中でも、「せめてもう暫くの間だけでも、何事もなく、正気でいらっしゃってください」とお祈りになる。
「ほんとうの気立てが優しいのを知らなかったら、こんなにまで我慢できない気味悪さだ」と、思っていらっしゃった。
|
夫人はなお今日も苦しんでいたから、大将は修法などを始めさせた。大将自身の心の中でも、ここしばらくは夫人に発作のないようにと祈っていた。物怪につかれないほんとうの妻は愛すべき性質であるのを自分は知っているから我慢ができるのであるが、そうでもなかったら捨てて惜しくない気もすることであろうと大将は思っていた。
|
【心のうちにも】- 鬚黒の心をいう。
【このころばかりだに】- 以下「あらせたまへ」まで、鬚黒の心。仏への祈り。
【まことの心ばへの】- 以下「け疎さかな」まで、鬚黒の心。
|
|
第七段 翌日、鬚黒、玉鬘を訪う
|
| 2.7.1 |
|
日が暮れると、いつものように急いでお出かけになる。
お召物のことなども、体裁よく整えなさらず、まことに奇妙で身にそぐわないとばかり不機嫌でいらっしゃるが、立派な御直衣などは、間に合わせることがおできになれず、たいそう見苦しい。
|
大将は日が暮れるとすぐに出かける用意にかかったのである。大将の服装などについても、夫人は行き届いた妻らしい世話の十分できない人なのである。自分の着せられるものは流行おくれの調子のそろわないものだと大将は不足を言っていたが、きれいな直衣などがすぐまにあわないで見苦しかった。
|
【暮るれば、例の】- 「例の」とあることによって、日が暮れると鬚黒は玉鬘のもとへ出掛けて行くことが習慣化していることが知られる。
【めやすくしなしたまはず】- 大島本は「めやすくしなしたまはす」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「めやすくもしなしたまはず」と「も」を補訂する。
【世にあやしう、うちあはぬさまにのみむつかりたまふを】- 鬚黒の身につかない風流事を自分自身でも認め不快がっている。
|
| 2.7.2 |
昨夜のは、焼けとほりて、疎ましげに焦れたるにほひなども、ことやうなり。
御衣どもに移り香もしみたり。
ふすべられけるほどあらはに、人も倦じたまひぬべければ、脱ぎ替へて、御湯殿など、いたうつくろひたまふ。
|
昨夜のは、焼け穴があいて、気味悪く焦げた匂いがするのも異様である。
御下着にまでその匂いが染みていた。
嫉妬された跡がはっきりして、相手もお嫌いになるに違いないので、脱ぎ替えて、御湯殿などで、たいそう身繕いをなさる。
|
昨夜のは焼け通って焦げ臭いにおいがした。小袖類にもその臭気は移っていたから、妻の嫉妬にあったことを標榜しているようで、先方の反感を買うことになるであろうと思って、一度着た衣服を脱いで、風呂を立てさせて入浴したりなどして大将は苦心した。
|
|
| 2.7.3 |
木工の君、御薫物しつつ、
|
木工の君、お召物に香をたきしめながら、
|
木工の君は主人のために薫物をしながら言う、
|
|
| 2.7.4 |
|
「北の方が独り残されて、
思い焦がれる胸の苦しさが思い余って炎と
|
「一人ゐて焦るる胸の苦しきに
思ひ余れる焔とぞ見し
|
【ひとりゐて焦がるる胸の苦しきに--思ひあまれる炎とぞ見し】- 木工の君の贈歌。「ひとり」に「独り」と「火取り」を掛ける。「焦がるる」「炎」は「火」の縁語。「思ひ」の「ひ」に「火」を掛ける。
|
| 2.7.5 |
名残なき御もてなしは、見たてまつる人だに、ただにやは」
|
すっかり変わったお仕打ちは、お側で拝見する者でさえも、平気でいられましょうか」
|
あまりに露骨な態度をおとりになりますから、拝見する私たちまでもお気の毒になってなりません」
|
|
| 2.7.6 |
|
と、口もとをおおっている、目もとは、たいそう魅力的である。
けれども、「どのような気持ちからこのような女に情けをかけたのだろう」などとだけ思われなさるのであった。
薄情なことであるよ。
|
袖で口をおおうて言っている木工の君の目つきは大将を十分にとがめているのであったが、主人のほうでは、どうして自分はこんな女などと情人関係を作ったのであろうとだけ思っていた。情けない話である。
|
【いかなる心にて】- 以下「言ひけむ」まで鬚黒の心。
【情けなきことよ】- 『細流抄』は「草子地の評也」と注し、『評釈』は「木工の君がそう思い、この物語を読み上げる女房がそう思い、男心と秋の空、と、物語の読者たる女性は思う」と解説する。『全集』『集成』『完訳』等も「草子地」と注す。鬚黒の木工の君に対する態度を薄情なことだという語り手の評言。
|
| 2.7.7 |
|
「嫌なことを思って心が騒ぐので、
あれこれと後悔の炎がます
|
「うきことを思ひ騒げばさまざまに
くゆる煙ぞいとど立ち添ふ
|
【憂きことを思ひ騒げばさまざまに--くゆる煙ぞいとど立ちそふ】- 鬚黒の返歌。「思ひ」の「ひ」に「火」を掛け、「くゆる」に「燻る」と「悔ゆる」を掛ける。「燻る煙」は「火」の縁語。
|
| 2.7.8 |
|
まったくとんでもない事が、もし先方の耳に入ったら、宙ぶらりな身の上となるだろう」
|
ああした醜態が噂になれば、あちらの人も私を悪く思うようになって、どちらつかずの不幸な私になるだろうよ」
|
【いとことの】- 以下「身なめり」まで鬚黒の詞が歌の後に続く。
【中間になりぬべき】- どっちつかずの状態。北の方は式部卿宮に引き取られ、玉鬘は源氏方から仲を裂かれるような状態。
|
| 2.7.9 |
と、うち嘆きて出でたまひぬ。
|
と、溜息ついてお出かけになった。
|
などと歎息を洩らしながら大将は出て行った。
|
|
| 2.7.10 |
|
一夜会わなかっただけなのに、改めて珍しいほどに、美しさが増して見えなさるご様子に、ますます心を他の女に分けることもできないように思われて、憂鬱なので、長い間居続けていらっしゃった。
|
中一夜置いただけで美しさがまた加わったように見える玉鬘であったから、大将の愛はいっそうこの一人に集まる気がして、自邸へ帰ることができずにそのままずっと玉鬘のほうにいた。
|
【いとど心を分くべくもあらずおぼえて】- 玉鬘のことを思うとますます他の女性に愛情を分けることはできないように思われて。
【心憂ければ】- 北の方のことを思うと憂鬱なので。
【久しう籠もりゐたまへり】- 鬚黒が六条院の玉鬘のもとに。
|
|
第三章 鬚黒大将家の物語 北の方、子供たちを連れて実家に帰る
|
|
第一段 式部卿宮、北の方を迎えに来る
|
| 3.1.1 |
修法などし騒げど、御もののけこちたくおこりてののしるを聞きたまへば、「あるまじき疵もつき、恥ぢがましきこと、かならずありなむ」と、恐ろしうて寄りつきたまはず。 |
修法などを盛んにしたが、物の怪がうるさく起こってわめいているのをお聞きになると、「あってはならない不名誉なことにもなり、外聞の悪いことが、きっと出てこよう」と、恐ろしくて寄りつきなさらない。
|
大騒ぎして修法などをしていても夫人の病気は相変わらず起こって大声を上げて人をののしるようなことのある報知を得ている大将は、妻のためにもよくない、自分のためにも不名誉なことが必ず近くにいれば起こることを予想して、怖ろしがって近づかないのである。
|
【あるまじき疵もつき】- 以下「ありなむ」まで、鬚黒の心。
|
| 3.1.2 |
|
邸にお帰りになる時も、別の部屋に離れていらして、子どもたちだけを呼び出してお会い申しなさる。
女の子が一人、十二、三歳ほどで、またその下に、男の子が二人いらっしゃるのであった。
最近になって、ご夫婦仲も離れがちでいらっしゃるが、れっきとした方として、肩を並べる人もなくて暮らして来られたので、「いよいよ最後だ」とお考えになると、お仕えしている女房たちも「ひどく悲しい」と思う。
|
邸へ帰る時にもほかの対に離れていて、子供たちを呼び寄せて見るだけを楽しみにしていた。女の子が一人あって、それは十二、三になっていた。そのあとに男の子が二人あった。近年はもう夫婦の間も隔たりがちに暮らしていたが、ただ一人の夫人として尊重することは昔に変わらなかったのが、こんなふうになったのであるから、夫人ももう最後の時が来たのだと思うし、女房たちもそう見て悲しむよりほかはなかった。
|
【殿に渡りたまふ】- 鬚黒の自邸。
【異方に離れゐたまひて】- 北の方の部屋から離れていらして。
【呼び放ちて】- 子供たちを北の方のもとから引き離して鬚黒のもとに呼び寄せて。
【女一所、十二、三ばかりにて】- 鬚黒と北の方の子供の紹介文。女子は一人、真木柱の姫君という。年齢十二、三歳は成人式を迎え結婚適齢期にさしかかった女性である。
【次々、男二人なむおはしける】- 弟君が二人が続いていらっしゃるのであった。
【御仲も隔たりがちにて】- 鬚黒と北の方の夫婦仲が疎遠がちである。
【今は限り」と見たまふに】- 北の方が結婚生活もいよいよ最後だとお思いになると。
|
| 3.1.3 |
|
父宮が、お聞きになって、
|
父宮がそのことをお聞きになって、
|
【父宮、聞きたまひて】- 北の方の父式部卿宮が鬚黒夫婦のことを。
|
| 3.1.4 |
「今は、しかかけ離れて、もて出でたまふらむに、さて、心強くものしたまふ、いと面なう人笑へなることなり。おのがあらむ世の限りは、ひたぶるにしも、などか従ひくづほれたまはむ」 |
「今は、あのように別居して、はっきりした態度をとっておいでだというのに、それにしても、辛抱していらっしゃる、たいそう不面目な物笑いなことだ。
自分が生きている間は、そう一途に、どうして相手の言いなりに従っていらっしゃることがあろうか」
|
「そんな冷酷な扱いを受けてもまだ辛抱強くあなたはしているのですか。それは自尊心も名誉心もない女のすることです。私の生きている間はまだあなたはそう奴隷的になっていないでもいいのです」
|
【今は】- 以下「くづほれたまはむ」まで、式部卿宮の詞。
【しか】- 鬚黒が玉鬘に熱中して入りびたっている生活態度をさす。
|
| 3.1.5 |
と聞こえたまひて、にはかに御迎へあり。
|
と申し上げなさって、急にお迎えがある。
|
と言うお言葉をお伝えさせになって、にわかに迎えをお立てになった。
|
|
| 3.1.6 |
北の方、御心地すこし例になりて、世の中をあさましう思ひ嘆きたまふに、かくと聞こえたまへれば、
|
北の方は、ご気分が少し平常になって、夫婦仲を情けなく思い嘆いていらっしゃると、このようにお申し上げになっているので、
|
夫人はやっと常態になっていて、自身の不幸な境遇を悲しんでいる時に、このお言葉を聞いたのであったから、今になってまだ父宮のお言葉に従わずここにいて、
|
|
| 3.1.7 |
|
「無理して立ち止まって、すっかり見捨てられるのを見届けて、諦めをつけるのも、さらに物笑いになるだろう」
|
まったく良人から捨てられてしまう日を待つことは、現在以上の恥になることであろう
|
【しひて立ちとまりて】- 以下「こそあらめ」まで、北の方の心。
【人の】- 夫鬚黒が。
|
| 3.1.8 |
など思し立つ。
|
などと、ご決心なさる。
|
などと思って、実家へ行くことにしたのであった。
|
|
| 3.1.9 |
|
ご兄弟の公達、兵衛督は、上達部でいらっしゃるので、仰々しいというので、中将、侍従、民部大輔など、お車三台程でいらっしゃった。
「きっとそうなるだろう」と、以前から思っていたことであるが、目の前に、今日がその終わりと思うと、仕えている女房たちも、ぽろぽろと涙をこぼし泣き合っていた。
|
夫人の弟の公子たちは、左兵衛督は高官であるから人目を引くのを遠慮して、そのほかの中将、侍従、民部大輔などで三つほどの車を用意して夫人を迎えに来たのであった。結局はこうなることを予想していたものの、いよいよ今日限りにこの家を離れなければならぬかと思うと、女房たちは皆悲しくなって泣き合った。
|
【兵衛督】- 「藤袴」巻(第三章二段)に初出。
【上達部におはすれば】- 兵衛督は従四位下相当官であるが、従三位に叙されていたものか。
【中将】- 従四位下相当官。
【さこそはあべかめれ】- 女房たちの予測。「さ」は北の方が父式部卿宮に引き取られることをさす。
|
| 3.1.10 |
|
「長年ご経験のないよそでのお住まいで、手狭で気の置ける所では、どうして大勢の女房が仕えられようか。
何人かは、それぞれ実家に下がって、落ち着きになられてから」
|
「これまでのようでないかかり人におなりになるのだから、お狭いところにおおぜいがお付きしていることはできません。幾人かの人だけはお供してあとは自分たちの家へ下がることにして、とにかくお落ち着きになるのを待ちましょう」
|
【年ごろならひたまはぬ】- 以下「たまひなむに」まで女房たちの詞。「たまはぬ」は北の方に対する敬語。
【旅住み】- これから始まる式部卿宮家での慣れない生活をいう。
【かたへは】- 女房の半分の人は。
【しづまらせたまひなむに】- 「せ」(尊敬の助動詞)「給」(尊敬の補助動詞)「な」(完了の助動詞、確述)「む」(推量の助動詞)。女房の会話どうしでも二重敬語を使う。
|
| 3.1.11 |
|
などと決めて、女房たちはそれぞれ、ちょっとした荷物など、実家に運び出したりして、散り散りになるのであろう。
お道具類は、必要な物は皆荷作りなどしながら、上の者や下の者が泣き騒いでいるのは、たいそう不吉に見える。
|
などと女房たちは言って、それぞれの荷物を自宅へ運ばせ、別れ別れになるものらしい。夫人の道具の運ばれる物は皆それぞれ荷作りされて行く所で、上下の人が皆声を立てて泣いている光景は悲しいものであった。
|
【はかなきものどもなど】- 女房のそれぞれの持物や荷物などをさす。
【里に払ひやりつつ】- 大島本は「はらひ」とある。『新大系』『古典セレクション』は底本のままとする。『集成』は諸本に従って「運びやりつつ」と校訂する。
【乱れ散るべし】- 語り手の推量。
|
|
第二段 母君、子供たちを諭す
|
| 3.2.1 |
君たちは、何心もなくてありきたまふを、母君、皆呼び据ゑたまひて、
|
お子様たちは、無心に歩き回っていられるのを、母君、皆を呼んで座らせなさって、
|
姫君と二人の男の子が何も知らぬふうに無邪気に家の中を歩きまわっているのを呼んで、夫人は前へすわらせた。
|
|
| 3.2.2 |
「みづからは、かく心憂き宿世、今は見果てつれば、この世に跡とむべきにもあらず、ともかくもさすらへなむ。生ひ先遠うて、さすがに、散りぼひたまはむありさまどもの、悲しうもあべいかな。 |
「わたしは、このようにつらい運命を、今は見届けてしまったので、この世に生き続ける気もありません。どうなりとなって行くことでしょう。
将来があるのに、何といっても、散り散りになって行かれる様子が、悲しいことです。
|
お母様は不幸な運命でお父様から捨てられてしまったのだから、どちらかへ行ってしまわなければならない。あなたがたはまだ小さいのにお母様から離れてしまわなければならないのはかわいそうだね。
|
【みづからは、かく】- 以下「いみじきこと」まで、北の方の子供たちへの詞。
【生ひ先遠うて】- 子供たちのことをいう。
|
| 3.2.3 |
|
姫君は、どうなるにせよ、わたしについていらっしゃい。
かえって、男の子たちは、どうしてもお父様のもとに参上してお会いしなければならないでしょうが、構ってもくださらないでしょうし、どっちつかずの頼りない生活になるでしょう。
|
姫君はどうなるかしれないお母様だけれど私といっしょにいることになさい。男の子も私について来て、時々ここへ来るようなことだけにしてはお父様がかわいがってくださらないよ。大人になって出世もできないような不幸の原因にそれがなるかもしれないからね。お祖父様の宮様のいらっしゃる間は、ともかくも役人の端にはしてもらえるにもせよね、
|
【姫君は】- 北の方は女の子は自分と一緒に生活させようと考える。
【男君たちは】- 北の方は男子はどうしても政治の世界で父親と一緒に暮らして行かねばならないと考えている。
【人の】- 父親の鬚黒が。
|
| 3.2.4 |
|
父宮が生きていらっしゃるうちは、型通りに宮仕えはしても、あの大臣たちのお心のままの世の中ですから、あの気を許せない一族の者よと、やはり目をつけられて、立身することも難しい。
それだからといって、山林に続いて入って出家することも、来世まで大変なこと」
|
お父様が今度親類におなりになった二人の大臣次第の世の中なのだから、その方たちにきらわれている私についていてはあなたがたは損で、出世などはできませんよ。そうかといってお坊様になって山や林へはいってしまうことは悲しいことだからね。それに不自然な出家をしては死んでからのちまで罪になります」
|
【宮のおはせむほど】- 祖父の式部卿宮。
【かの大臣たちの御心にかかれる世にて】- あの太政大臣の源氏や内大臣たちのお心のままの世の中だから。
【心おくべきわたり】- 源氏方から見れば、気を許せない所の者だ。
【山林に引き続きまじらむこと】- 自分が出家遁世し、息子たちも後を追って出家し山林に姿をくらますこと。
|
| 3.2.5 |
と泣きたまふに、皆、深き心は思ひ分かねど、うちひそみて泣きおはさうず。
|
とお泣きになると、皆、深い事情は分からないが、べそをかいて泣いていらっしゃる。
|
と言って泣く母を見ては、深い意味はわからないままで子は皆悲しがって泣く。
|
|
| 3.2.6 |
|
「昔物語などを見ても、世間並の愛情深い親でさえ、時勢に流され、人の言うままになって、冷たくなって行くものです。
まして、形だけの親のようで、見ている前でさえすっかり変わってしまったお心では、頼りになるようなお扱いをなさるまい」
|
「昔の小説の中でも普通にお子様を愛していらっしゃるお父様でも片親ではね、いろんなことの影響を受けてだんだん子供に冷淡になっていくものですよ。そしてこちらの殿様は現在でさえもああしたふうをお見せになるじゃありませんか。お子様の将来を思ってくださるようなことはないと思います」
|
【昔物語などを】- 以下「もてないたまはじ」まで、北の方の詞。『住吉物語』『落窪物語』などの父親が後妻と結婚生活を続けるうちにやがて先妻の子供は父親の愛情も薄れてゆき、さらには継母からも苛められていくような話を想定する。
【人に従へば】- 具体的には後妻をさすが、一般論として読める。
【おろかにのみこそなりけれ】- 大島本は「のミこそ」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「のみこそは」と「は」を補訂する。
|
| 3.2.7 |
|
と、乳母たちも集まって、おっしゃり嘆く。
|
と乳母たちは乳母たちでいっしょに集まって、悲しんでいた。
|
【御乳母どもさし集ひて、のたまひ嘆く】- 子供たちの乳母も北の方と一緒になっておっしゃり嘆く。敬語があるので、北の方を中心にした表現。
|
|
第三段 姫君、柱の隙間に和歌を残す
|
| 3.3.1 |
|
日も暮れ、雪も降って来そうな空模様も、心細く見える夕方である。
|
日も落ちたし雪も降り出しそうな空になって来た心細い夕べであった。
|
【日も暮れ、雪降りぬべき空のけしきも】- 冬の雪の日の別れの場面。「薄雲」巻には大堰山荘を舞台にして明石の母子の別れの場面が語られていた。物語の季節と主題との類同的発想の一つである。
|
| 3.3.2 |
|
「ひどく荒れて来ましょう。
お早く」
|
「天気がずいぶん悪くなって来たそうです。早くお出かけになりませんか」
|
【いたう荒れはべりなむ。早う】- 迎えの君達の詞。「な」(完了の助動詞、確述)「む」(推量の助動詞)、~してしまいましょう、の意。
|
| 3.3.3 |
|
と、お迎えの公達はお促し申し上げるが、お目を拭いながら物思いに沈んでいらっしゃる。
姫君は、殿がたいそうかわいがって、懐いていらっしゃっるので、
|
と夫人の弟たちは急がせながらも涙をふいて悲しい肉親たちをながめていた。姫君は大将が非常にかわいがっている子であったから、父に逢わないままで行ってしまうことはできない、
|
【おし拭ひつつ眺めおはす】- 迎えの君達の動作。
【姫君は、殿いとかなしうしたてまつりたまふならひに】- 姫君は殿がふだんからとてもおかわいがり申し上げなさっていたのでの意。
|
| 3.3.4 |
「見たてまつらではいかでかあらむ。『今』なども聞こえで、また会ひ見ぬやうもこそあれ」 |
「お目にかからないではどうして行けようか。
『これで』などと挨拶しないで、再び会えないことになるかもしれない」
|
今日父とものを言っておかないでは、もう一度そうした機会はないかもしれない
|
【見たてまつらでは】- 以下「こそあれ」まで、姫君の心。
|
| 3.3.5 |
と思ほすに、うつぶし伏して、「え渡るまじ」と思ほしたるを、
|
とお思いになると、突っ伏して、「とても出かけられない」とお思いでいるのを、
|
と思ってうつぶしになって泣きながら行こうとしないふうであるのを夫人は見て、
|
|
| 3.3.6 |
|
「そのようなお考えでいらっしゃるとは、とても情けない」
|
「そんな気にあなたのなっていることはお母様を悲しくさせます」
|
【かく思したるなむ、いと心憂き】- 北の方の姫君への詞。
|
| 3.3.7 |
|
などと、おなだめ申し上げなさる。
「今すぐにも、お父様がお帰りになってほしい」とお待ち申し上げなさるが、このように日が暮れようとする時、あちらをお動きなさろうか。
|
などとなだめていた。そのうち父君は帰るかもしれぬと姫君は思っているのであるが、日が暮れて夜になった時間に、どうして逆にこの家へ大将が帰ろう。
|
【ただ今も渡りたまはなむ】- 姫君の心。「なむ」は願望の意の終助詞。今すぐにでも父が帰ってきてほしいの意。
【かく暮れなむに】- 「な」(完了の助動詞、確述)「む」(推量の助動詞)。このように今にも日が暮れようとしている時に、の意。以下、語り手の評言。『孟津抄』は「推量也」と指摘する。『集成』も「草子地」と指摘、『完訳』は「語り手の推測。父の恋狂いなど思わぬ娘の純真さを暗示」と指摘する。
【まさに動きたまひなむや】- 反語表現。これから夜になっていこうとする時、鬚黒が玉鬘のもとから帰って来ようか、そんなことはまずあるまいという。
|
|
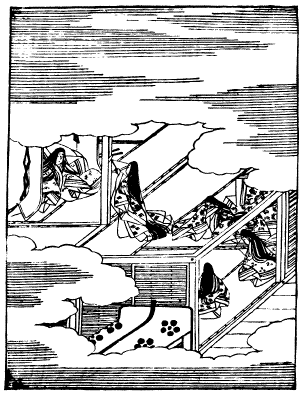 |
| 3.3.8 |
常に寄りゐたまふ東面の柱を、人に譲る心地したまふもあはれにて、姫君、桧皮色の紙の重ね、ただいささかに書きて、柱の干割れたるはさまに、笄の先して押し入れたまふ。
|
いつも寄りかかっていらっしゃる東面の柱を、他人に譲る気がなさるのも悲しくて、姫君、桧皮色の紙を重ねたのに、ほんのちょっと書いて、柱のひび割れた隙間に、笄の先でお差し込みなさる。
|
姫君は始終自身のよりかかっていた東の座敷の中の柱を、だれかに取られてしまう気のするのも悲しかった。姫君は檜皮色の紙を重ねて、小さい字で歌を書いたのを、笄の端で柱の破れ目へ押し込んで置こうと思った。
|
|
| 3.3.9 |
|
「今はもうこの家を離れて行きますが、
わたしが馴れ親しんだ真木の柱は
|
今はとて宿借れぬとも馴れ来つる
真木の柱はわれを忘るな
|
【今はとて宿かれぬとも馴れ来つる--真木の柱はわれを忘るな】- 姫君の歌。「真木」は歌語。『大系』『評釈』『全集』『完訳』は「東風吹かば匂いおこせよ梅の花主なしとて春を忘るな」(拾遺集雑春、一〇〇六、菅原道真)を引歌として指摘する。この和歌が姫君の呼称となり、さらに巻名となる。
|
| 3.3.10 |
えも書きやらで泣きたまふ。
母君、「いでや」とて、
|
最後まで書き終わることもできずお泣きになる。
母君、「いえ、なんの」と言って、
|
この歌を書きかけては泣き泣いては書きしていた。夫人は、「そんなことを」と言いながら、
|
|
| 3.3.11 |
|
「長年馴れ親しんで来た真木柱だと思い出しても
どうしてここに止まっていられましょうか」
|
馴れきとは思ひ出づとも何により
立ちとまるべき真木の柱ぞ
|
【馴れきとは思ひ出づとも何により--立ちとまるべき真木の柱ぞ】- 北の方の返歌。
|
| 3.3.12 |
御前なる人びとも、さまざまに悲しく、「さしも思はぬ木草のもとさへ恋しからむこと」と、目とどめて、鼻すすりあへり。
|
お側に仕える女房たちも、それぞれに悲しく、「それほどまで思わなかった木や草のことまで、恋しいことでしょう」と、目を止めて、鼻水をすすり合っていた。
|
と自身も歌ったのであった。女房たちの心もいろいろなことが悲しくした。心のない庭の草や木と別れることも、あとに思い出して悲しいことであろうと心が動いた。
|
|
| 3.3.13 |
木工の君は、殿の御方の人にてとどまるに、中将の御許、
|
木工の君は、殿の女房として留まるので、中将の御許は、
|
木工の君は初めからこの家の女房であとへ残る人であった。中将の君は夫人といっしょに行くのである。
|
|
| 3.3.14 |
|
「浅い関係のあなたが残って、
邸を守るはずの北の方様が出て行かれること
|
「浅けれど石間の水はすみはてて
宿守る君やかげはなるべき
|
【浅けれど石間の水は澄み果てて--宿もる君やかけ離るべき】- 中将の御許から木工の君への贈歌。「石間の水」に木工の君をたとえる。「宿守る君」は北の方をさす。「すみ」に「住み」と「澄み」を掛け、「かけ」に「かけ離る」と水に映る「影」とを響かせる。「や~べき」反語表現。~することがあっていいものでだろうか、おかしなことだ。
|
| 3.3.15 |
|
思いもしなかったことです。
こうしてお別れ申すとは」
|
思いも寄らなかったことですね、こうしてあなたとお別れするようになるなどと」
|
【思ひかけざりしことなり。かくて別れたてまつらむことよ】- 中将の御許の歌に続く詞。木工の君と別れることをいう。
|
| 3.3.16 |
と言へば、木工、
|
と言うと、木工の君は、
|
と中将の君が言うと、木工は、
|
|
| 3.3.17 |
|
「どのように言われても、
わたしの心は悲しみに閉ざされて
|
「ともかくも石間の水の結ぼほれ
かげとむべくも思ほえぬ世を
|
【ともかくも岩間の水の結ぼほれ--かけとむべくも思ほえぬ世を】- 木工の君の返歌。「言はま」に「岩間」を掛ける。「結ぼほれ」は、水の流れが滞る意と思いが鬱屈する意とこめる。「かけ」は「かけ留む」と「影留む」を響かす。
|
| 3.3.18 |
いでや」
|
いや、そのような」
|
何が何だかどうなるのだか」
|
|
| 3.3.19 |
とてうち泣く。
|
と言って泣く。
|
と言って泣いていた。
|
|
| 3.3.20 |
|
お車を引き出して振り返って見るのも、「再び見ることができようか」と、心細い気がする。
梢にも目を止めて、見えなくなるまで振り返って御覧になるのであった。
君が住んでいるからではなく、長年お住まいになった所が、どうして名残惜しくないことがあろうか。
|
車が引き出されて人々は邸の木立ちのなお見える間は、自分らはまたもここを見る日はないであろうと悲しまれて、隠れてしまうまで顧みられた。住んでいる主人のために家と別れるのが惜しいのではなくて、家そのものに愛着のある心がそうさせるのである。
|
【またはいかでかは見む】- 中将の御許の木工の君に二度と会えまいという思い。
【はかなき心地す】- 中将の御許の気持ち。
【梢をも目とどめて、隠るるまでぞ返り見たまひける】- 『源氏釈』は「君が住む宿の梢を行くゆくと隠るるまでに返り見しはや」(拾遺集別、三五一 、菅原道真)を引歌として指摘。現行の注釈書でも指摘する。
【君が住むゆゑにはあらで】- 前掲「拾遺集」歌の語句を引く。ここでは夫の鬚黒をさす。
【いかでか偲びどころなくはあらむ】- 語り手の感情移入のこもった表現。
|
|
第四段 式部卿宮家の悲憤慷慨
|
| 3.4.1 |
宮には待ち取り、いみじう思したり。
母北の方、泣き騷ぎたまひて、
|
宮邸では待ち受けて、たいそうお悲しみである。
母の北の方、泣き騷ぎなさって、
|
大将夫人をお迎えになって、宮は非常にお悲しみになった。母の夫人は泣き騒いだ。
|
|
| 3.4.2 |
|
「太政大臣を、結構なご親戚とお思い申し上げていらっしゃるが、どれほどの昔からの仇敵でいらっしゃったのだろうと思われます。
|
「太政大臣のことをよい親戚を持ったようにあなたは喜んでいらっしゃいますが、私には前生にどんな仇敵だった人かと思われます。
|
【太政大臣を】- 以下「いかがつらからぬ」まで、大北の方の詞。
【思ひきこえたまへれど】- あなたはお思い申し上げていらっしゃいますが、の意。大北の方の夫式部卿宮への皮肉。
|
| 3.4.3 |
|
女御にも、何かにつけて、冷淡なお仕打ちをなさったが、それは、お二人の間の恨み事が解けなかったころ、思い知れということであったであろうと、思ったりおっしゃったりもし、世間の人もそう言っていたのでさえ、やはり、そあってよいことでしょうか。
|
女御などにも何かの場合に好意のない態度を露骨にお見せになりましたが、そのころは須磨時代の恨みが忘られないのだろうとあなたがお言いになり、世間でもそう批評されたのでも私には腑に落ちなかったのです。
|
【女御をも、ことに触れ】- 大北の方の姫君、王女御をさす。「澪標」巻に初出。入内して女御となるが、源氏方の養女として入内した前斎宮が「少女」巻で中宮に立ち、立后が叶わなかった。
【御仲の恨み】- 源氏の須磨流謫前後に式部卿宮が源氏に対して冷淡な態度をとったことへの恨み。
|
| 3.4.4 |
|
一人を大切になさるのであれば、その周辺までもお蔭を蒙るという例はあるものだと、納得行きませんでしたが、まして、このような晩年になって、わけの分からない継子の世話をして、自分が飽きたのを気の毒に思って、律儀者で浮気しそうのない人をと思って、婿に迎えて大切になさるのは、どうして辛くないことでしょうか」
|
それだのにまた今になって、養女を取ったりなどして、自分が御寵愛なすって古くなすった代償にまじめな堅い男を取り寄せて婿にするなどということをなさる。これが恨めしくなくて何ですか」
|
【人一人を思ひかしづきたまはむゆゑは、ほとりまでも】- 源氏が紫の上を大事にするからには、その親類縁者までも厚遇してよい、の意。
【末に、すずろなる継子かしづきをして】- 源氏が晩年の今頃になってから玉鬘の世話をして、の意。
【おのれ古したまへるいとほしみに】- 「古し」「いとをしみ」は、自分が玉鬘を愛人として長い間付き合ってきたのに飽きて、そのことを気の毒に思っての意。大北の方は、源氏と玉鬘の関係をこのように理解している。
【実法なる人】- 鬚黒をさす。
【ゆるぎどころ】- 大島本は「ゆき所」とある。『集成』『新大系』『古典セレクション』は諸本に従って「ゆるぎ所」と校訂する。
|
| 3.4.5 |
と、言ひ続けののしりたまへば、宮は、
|
と、大声で言い続けなさるので、宮は、
|
こう言い続けるのである。
|
|
| 3.4.6 |
「あな、聞きにくや。世に難つけられたまはぬ大臣を、口にまかせてなおとしめたまひそ。かしこき人は、思ひおき、かかる報いもがなと、思ふことこそはものせられけめ。さ思はるるわが身の不幸なるにこそはあらめ。 |
「ああ、聞き苦しい。
世間から非難されることのおありでない大臣を、口から出任せに悪くおっしゃるものではありませんよ。
賢明な方は、かねてから考えていて、このような報復をしようと、思うことがおありだったのだろう。
そのように思われるわが身の不幸なのだろう。
|
「聞き苦しい。世間から何一つ批難をお受けにならない大臣を、出まかせな雑言で悪く言うのはおよしなさい。
|
【あな、聞きにくや】- 以下「やみぬべきなめり」まで、式部卿宮の詞。
|
| 3.4.7 |
|
なにげないふうで、すべてあの苦しみなさった報復は、引き上げたり落としたり、たいそう賢く考えていらっしゃるようだ。
わたし一人は、しかるべき親戚だと思って、先年も、あのような世間の評判になるほどに、わが家には過ぎたお祝賀があった。
そのことを生涯の名誉と思って、
|
聡明な人はこちらの罪を目前でどうしようとはしないで、自然の罰にあうがいいと考えていられたのだろう。そう思われる私自身が不幸なのだ。冷静にしていられるようで、そしてあの時代の報いとして、ある時はよくしたり、ある時はきびしくしたりしようと考えていられるのだろう。私一人は妻の親だとお思いになって、いつかも驚くべき派手な賀宴を私のためにしてくだすった。まあそれだけを生きがいのあったこととして、そのほかのことはあきらめなければならないのだろう」
|
【皆かの沈みたまひし世の報いは】- 源氏の須磨退去の不遇当時に疎遠にしたことをさす。
【一年も、さる世の響きに、家よりあまることどももありしか】- 式部卿宮の五十賀を新築の六条院で祝ってくれたことをいう。「少女」巻(第七章三段)に見える。
|
| 3.4.8 |
|
とおっしゃると、ますます腹が立って、不吉な言葉を言い散らしなさる。
この大北の方は、性悪な人だったのである。
|
と宮がお言いになるのを聞いて、夫人はいよいよ猛り立つばかりで、源氏夫婦への詛いの言葉を吐き散らした。この夫人だけは善良なところのない人であった。
|
【この大北の方ぞ、さがな者なりける】- 語り手の大北の方に対する人物批評。『孟津抄』は「草子地」と指摘。『集成』も「草子地」と指摘。『完訳』は「語り手の評言。継子物語の性悪の継母像として語り収める」と指摘する。
|
| 3.4.9 |
|
大将の君は、このようにお移りになってしまったことを聞いて、
|
大将は夫人が宮家へ帰ったことを聞いて
|
【大将の君】- 場面は六条院の玉鬘のもとに変わる。
【かく渡りたまひにける】- 北の方が実家に移ってしまったこと。
|
| 3.4.10 |
「いとあやしう、若々しき仲らひのやうに、ふすべ顔にてものしたまひけるかな。正身は、しかひききりに際々しき心もなきものを、宮のかく軽々しうおはする」 |
「まことに妙な、年若い夫婦のように、やきもちを焼いたようなことをなさったものだなあ。
ご本人には、そのようなせっかちできっぱりした性分もないのに、宮があのように軽率でいらっしゃる」
|
ほんとうらしくもなく、若夫婦の中ででもあるような争議を起こすものである、自分の妻はそうした愛情を無視するような態度のとれる性質ではないのであるが、宮が軽率な計らいをされるのである
|
【いとあやしう】- 以下「おはする」まで鬚黒の心。
|
| 3.4.11 |
|
と思って、御子息もあり、世間体も悪いので、いろいろと思案に困って、尚侍の君に、
|
と思って、子供もあることであったし、夫人のために世間体も考慮してやらねばならないと煩悶してのちに、こうした奇怪な出来事が家のほうであったと話して、
|
【尚侍の君に】- 玉鬘。
|
| 3.4.12 |
|
「こんな妙なことがございましたようです。
かえって気楽に存じられますが、そのまま邸の片隅に引っ込んでいてもよい気楽な人と、安心しておりましたのに、急にあの宮がなさったのでしょう。
世間が見たり聞いたりことも薄情なので、ちょっと顔を出して、すぐに戻ってまいりましょう」
|
「かえってさっぱりとした気もしないではありませんが、しかしそのままでおとなしく家の一隅に暮らして行けるはずの善良さを私は妻に認めていたのですよ。にわかに無理解な宮が迎えをおよこしになったのであろうと想像されます。世間へ聞こえても私を誤解させることだから、とにかく一応の交渉をしてみます」
|
【かくあやしきことなむはべる】- 大島本は「侍る」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』はそれぞれ諸本に従って「はべるなる」「はべなる」と校訂する。以下「参り来なむ」まで、鬚黒の玉鬘への詞。
【なかなか心やすくは思ひたまへなせど】- 北の方が実家に帰ってくれて、かえって気が楽になったとは思ってみるが。「たまへ」は鬚黒が自分自身「思う」謙譲表現である。
【さて片隅に】- そのまま北の方が鬚黒の邸にいて。
【かの宮ものしたまふならむ】- 大島本は「かの宮ものし給ならむ」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「かの宮のしたまふならむ」と校訂する。
【人の聞き見ることも】- 世間の人が鬚黒の態度を聞いたり見たりすることも。
|
| 3.4.13 |
とて出でたまふ。
|
と言って、お出になる。
|
とも言って出かけるのであった。
|
|
| 3.4.14 |
よき上の御衣、柳の下襲、青鈍の綺の指貫着たまひて、引きつくろひたまへる、いとものものし。「などかは似げなからむ」と、人びとは見たてまつるを、尚侍の君は、かかることどもを聞きたまふにつけても、身の心づきなう思し知らるれば、見もやりたまはず。 |
立派な袍のお召物に、柳の下襲、青鈍色の綺の指貫をお召しになって、身なりを整えていらっしゃる、まことに堂々としている。
「どうして不似合いなところがあろうか」と、女房たちは拝見するが、尚侍の君は、このようなことをお聞きになるにつけても、わが身が情けなく思わずにはいらっしゃれないので、見向きもなさらない。
|
よいできの袍を着て、柳の色の下襲を用い、青鈍色の支那の錦の指貫を穿いて整えた姿は重々しい大官らしかった。決して不似合いな姫君の良人でないと女房たちは見ているのであったが、尚侍は家庭の悲劇の伝えられたことでも、自分の立場がつらくなって、大将の好意がうるさく思われて、あとを見送ろうともしなかった。
|
【いとものものし】- 女房の目と一体化した語り手の評言。
【などかは似げなからむ】- 反語表現。鬚黒の堂々とした姿と玉鬘の美しさが似つかわしい。
【かかることども】- 鬚黒の話。主として北の方や式部卿宮のことをさす。
|
|
第五段 鬚黒、式部卿宮家を訪問
|
| 3.5.1 |
宮に恨み聞こえむとて、参うでたまふままに、まづ、殿におはしたれば、木工の君など出で来て、ありしさま語りきこゆ。姫君の御ありさま聞きたまひて、男々しく念じたまへど、ほろほろとこぼるる御けしき、いとあはれなり。 |
宮に苦情を申し上げようと思って、参上なさるついでに、先に、自邸にいらっしゃると、木工の君などが出てきて、その時の様子をお話し申し上げる。
姫君のご様子をお聞きになって、男らしく堪えていらっしゃるが、ぽろぽろと涙がこぼれるご様子、たいそうお気の毒である。
|
宮へ抗議をしに大将は出かけようとしているのであったが、先に邸のほうへ寄って見た。木工の君などが出て来て、夫人の去った日の光景をいろいろと語った。姫君のことを聞いた時に、どこまでも自制していた大将も堪えられないようにほろほろと涙をこぼすのが哀れであった。
|
【宮に恨み聞こえむとて】- 以下、場面が変わって、鬚黒の自邸を舞台となる。
【いとあはれなり】- 語り手の感情移入の表現。『評釈』は「大将の涙を見ると、木工も、許す気になったことであろう。「いとあはれなり」は、作者が読者に報告するだけのことばではない」と指摘。
|
| 3.5.2 |
|
「それにしても、世間の人と違い、おかしな振る舞いの数々を大目に見てきた長年の気持ちを、ご理解なさらなかったのかな。
ひどくわがままな人は、今までも一緒にいただろうか。
まあよい、あの本人は、どうなったところで、廃人にお見えになるから、同じことだ。
子どもたちも、どうなさろうというのだろうか」
|
「どうしたことだろう。常人でない病気のある人を、長い間どんなにいたわって私が来たかがわかってもらえないのだね。軽薄な男なら今日までだって決して連れ添ってはいなかったろう。でもしかたがない、あの人はどこにいても廃人なのだから同じだ。子供たちをどうしようというのだろう」
|
【さても、世の人にも似ず】- 以下「たまはむとすらむ」まで鬚黒の詞。
【見知りたまはずありけるかな】- 北の方はおわかりではなかったのだな。
【いと思ひのままならむ人】- 鬚黒が自分自身のことをいうが、自分はそのようなわがままな人ではないの意。
【立ちとまるべくやはある】- 「べく」(推量の助動詞、可能)「や」(係助詞、反語)。とどまっていられるものであろうか、そんなことはできないの意。
【同じことなり】- 邸に残るも実家に帰るも同じことである意。
【いかやうにもてなしたまはむとすらむ】- 北の方は幼い子供たちまでどのように巻き添えにしようとなさるのだろうか。
|
| 3.5.3 |
|
と、嘆息しながら、あの真木の柱を御覧になると、筆跡も幼稚だが、気立てがしみじみといじらしくて、道すがら、涙を押し拭い押し拭い参上なさると、お会いになれるはずもない。
|
大将は泣きながら真木柱の歌を読んでいた。字はまずいが優しい娘の感情はそのまま受け取れることができて、途中も車の中で涙をふきふき宮邸へ向かった。夫人は逢おうとしなかった。
|
【かの真木柱を】- 姫君が歌を詠み残して挟んでいった真木柱。
【道すがら】- 場面は鬚黒邸から式部卿宮邸に向かう道中に変わる。
【参うでたまへれば】- 鬚黒が式部卿宮邸に参上なさると。
【対面したまふべくもあらず】- 北の方にお会いなされるはずもない。「べくもあらず」は語り手の感情がこめられた表現。『完訳』は「北の方の固い覚悟による」と解す。
|
| 3.5.4 |
|
「何の。
ただ時勢におもねる心が、今初めてお変わりになったのではない。
年来うつつを抜かしていらっしゃる様子を、長いこと聞いてはいたが、いつを再び改心する時かと待てようか。
ますます、奇妙な姿を現すばかりで終わることにおなりになろう」
|
「逢う必要はない。新しい女に心の移っているという話は、今度始まったことでもない。あの人が若い妻をほしがっている話を聞いてから長い月日もたっている。そんな良人の愛があなたへ帰ってくることなどは期待されないことだ。そして健全な女でないという点だけをいよいよ認めさせることになります」
|
【何か。ただ時に移る心の】- 以下「見え果てたまはめ」まで、式部卿宮の娘北の方への諌めの詞。「何か」の下には「会はむ」などの語句が省略されている。「か」(係助詞、反語)。どうしてお会うことがあろうか、会う必要はないの意。式部卿宮は鬚黒を、源氏におもねって玉鬘と結婚したと解釈する。
【折とか待たむ】- 「か」(係助詞、反語)。心の改まる時と待とうか、そのような時はないの意。
【さまにのみこそ】- 大島本は「さまにのミこそ」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「さまのみこそ」と「に」を削除する。
|
| 3.5.5 |
|
とご意見申される、もっともなことである。
|
と言う宮の御注意が大将夫人へあったのである。もっともなことである。
|
【諌め申したまふ、ことわりなり】- 式部卿宮が諌めるのも当然であるとする語り手の評言。『明星抄』は「いさめ申給」以下に「草子地也」と指摘。『評釈』は「ことはりなり」に「もっともな判断と、語り手も、作者も、同意する」と指摘する。
|
| 3.5.6 |
|
「まったく、大人げない気がしますな。
お見捨てになるはずもない子供たちもいますのでと、のんきに構えておりましたわたしの不行届を、繰り返しお詫び申しても、お詫びの申しようがありません。
今はただ、穏便に大目に見て下さって、罪は免れがたく、世間の人にも分からせた上で、このようにもなさるのがよい」
|
「何だか若い夫婦の仲で起こった事件のようで勝手の違った気がします。二人の中には愛すべき子もあるのだからと信頼を持ち過ぎてのんきであった私のあやまちは、どんな言葉ででも許してもらえないだろうと思いますが、それはそれとして穏便にだけはしてくだすって、今後私のほうによくないことがあれば世間も許さないでしょうから、その時に断然としたこういう処置もとられたらいいでしょう」
|
【いと、若々しき心地も】- 以下「もてないたまはめ」まで、鬚黒の詞。北の方に申し上げている内容である。
【罪さりどころなう】- わたしの罪は免れ難い、弁解の余地がないの意。
【かやうに】- 実家に戻ることをさす。
|
| 3.5.7 |
|
などと、説得申すのに苦慮していらっしゃる。
「せめて姫君にだけでもお会いしたい」と申し上げなさっているが、お出し申すはずもない。
|
などと大将は困りながら取り次がせていた。姫君にだけでも逢いたいと言ったのであるが出しそうもない。
|
【姫君をだに見たてまつらむ】- 鬚黒の詞。せめて姫君にだけでもお会い申したい。
【出だしたてまつるべくもあらず】- 北の方が姫君を鬚黒の前にお出しするはずもない。「べくもあらず」という言い回しは、語り手の判断をも言い込めた表現。
|
| 3.5.8 |
男君たち、十なるは、殿上したまふ。
いとうつくし。
人にほめられて、容貌などようはあらねど、いとらうらうじう、ものの心やうやう知りたまへり。
|
男の子たち、十歳になるのは、童殿上なさっている。
とてもかわいらしい。
人からほめられて、器量など優れてはいないが、たいそう利発で、物の道理をだんだんお分りになっていらした。
|
男の子の十歳になっているのは童殿上をしていて、愛らしい子であった。人にもほめられていて、容貌などはよくもないが、貴族の子らしいところがあって、その子はもう父母の争いに関心が持てるほどになっていた。
|
|
| 3.5.9 |
次の君は、八つばかりにて、いとらうたげに、姫君にもおぼえたれば、かき撫でつつ、
|
次の君は、八歳ほどで、とても可憐で、姫君にも似ているので、撫でながら、
|
二男は八つくらいである。かわいい顔で姫君にも似ていたから、大臣は髪をなでてやりながら、
|
|
| 3.5.10 |
「あこをこそは、恋しき御形見にも見るべかめれ」 |
「おまえを恋しい姫君のお形見と思って見ることにしよう」
|
「おまえだけを恋しい形見にこれからは見て行くのだねお父様は」
|
【あこをこそは】- 以下「見るべかめれ」まで、鬚黒の詞。二郎君を目の前にして、これからおまえをかわいがって行くことになるのだろうというニュアンス。
|
| 3.5.11 |
|
などと、涙を流してお話しなさる。
宮にも、ご内意を伺ったが、
|
などと泣きながら言っていた。大将は宮へ御面会を願ったのであるが、
|
【宮にも、御けしき賜はらせたまへど】- 鬚黒は式部卿宮にも面会の御意向をお伺いになるが、の意。
|
| 3.5.12 |
|
「風邪がひどくて、養生しております時なので」
|
「風邪で引きこもっている時ですから」
|
【風邪おこりて】- 以下「ほどにて」まで、式部卿宮の謝絶の詞。
|
| 3.5.13 |
とあれば、はしたなくて出でたまひぬ。
|
と言うので、不体裁な思いで退出なさった。
|
と断わられて、きまりが悪くなって宮邸を出た。
|
|
|
第六段 鬚黒、男子二人を連れ帰る
|
| 3.6.1 |
|
幼い男の子たちを車に乗せて、親しく話しながらお帰りになる。
六条殿には連れて行くことがおできになれないので、邸に残して、
|
二人の男の子を車に乗せて話しながら来たのであったが、六条院へつれて行くことはできないので、自邸へ置いて、
|
【六条殿には、え率ておはせねば】- 玉鬘のいる六条院には子供たちを連れて行くことができないので。鬚黒の生活の中心は今や六条院の玉鬘の所に移っている。
|
| 3.6.2 |
|
「やはり、ここにいなさい。
会いに来るのにも安心して来られるであろうから」
|
「ここにおいで。お父様は始終来て見ることができるから」
|
【なほ、ここにあれ】- 以下「心やすかるべく」まで、鬚黒の詞。「ここ」は鬚黒の自邸をさす。
【来て見むにも】- 大島本は「きてみ(み+んイ<朱>)にも」とある。『集成』『新大系』『古典セレクション』は諸本及び底本の朱筆補入に従って「来て見むにも」と「む」を補訂する。
|
| 3.6.3 |
|
とおっしゃる。
悲しみにくれて、たいそう心細そうに見送っていらっしゃる様子、たいそうかわいそうなので、心配の種が増えたような気がするが、女君のご様子が、見がいがあって立派なので、気違いじみたご様子と比べると、格段の相違で、すべてお慰めになる。
|
と大将は言っていた。悲しそうに心細いふうで父を見送っていたのが哀れに思われて、大将は予期しなかった物思いの加わった気がしたものの、美しい玉鬘と、廃人同様であった妻を比べて思うと、やはり何があっても今の幸福は大きいと感ぜられた。
|
【うち眺めて】- 子供たち二人が物思いに沈んで。
【見送り】- 鬚黒を見送る。鬚黒は子供たちを残して六条院へ出掛ける。
【女君】- 玉鬘。
【ひがひがしき御さま】- 北の方の気違いじみた御様子。
|
| 3.6.4 |
うち絶えて訪れもせず、はしたなかりしにことづけ顔なるを、宮には、いみじうめざましがり嘆きたまふ。
|
さっぱり途絶えてお便りもせず、体裁の悪かったことを口実にしているふうなのを、宮におかれて、ひどく不愉快にお嘆きになる。
|
それきり夫人のほうへ大将は何とも言ってやらなかった。侮辱的なあの日の待遇がもたらした反動的な現象のように、冷淡にしていると宮邸の人をくやしがらせていた。
|
|
| 3.6.5 |
|
春の上もお聞きになって、
|
紫の女王もその情報を耳にした。
|
【春の上】- 紫の上をいう。この呼称は「胡蝶」「常夏」の巻に見えた。
|
| 3.6.6 |
「ここにさへ、恨みらるるゆゑになるが苦しきこと」 |
「わたしまで、恨まれる原因になるのがつらいこと」
|
「私までも恨まれることになるのがつらい」
|
【ここにさへ】- 以下「苦しきこと」まで、紫の上の詞。
|
| 3.6.7 |
|
とお嘆きになるので、大臣の君は、気の毒だとお思いになって、
|
と歎いているのを源氏はかわいそうに思った。
|
【大臣の君】- 源氏をいう。
|
| 3.6.8 |
|
「難しいことだ。
自分の一存だけではどうすることもできない人の関係で、帝におかせられても、こだわりをお持ちになっていらっしゃるようだ。
兵部卿宮なども、お恨みになっていらっしゃると聞いたが、そうは言っても、思慮深くいらっしゃる方なので、事情を知って、恨みもお解けになったようだ。
自然と、男女の関係は、人目を忍んでいると思っても、隠すことのできないものだから、そんなに苦にするほどの責任もない、と思っております」
|
「むつかしいものですよ。自分の思いどおりにもできない人なのだから、この問題で陛下も御不快に思召すようだし、兵部卿の宮も恨んでおいでになると聞いたが、あの方は思いやりがあるから、事情をお聞きになって、もう了解されたようだ。恋愛問題というものは秘密にしていても真相が知れやすいものだから、結局は私が罪を負わないでもいいことになると思っている」
|
【難きことなり】- 以下「となむ思ひはべる」まで、源氏の紫の上への詞。
【人のゆかり】- 玉鬘との関係をさす。
【思したなり】- 「た」(完了の助動詞、存続の意。連体形「たる」の「る」が撥音便化し、無表記された形)「なり」(伝聞推定の助動詞)。下文の「恨み解けたまひにたなり」も同じ。お思いになっているようだ。
【聞きあきらめ】- 式部卿宮は鬚黒と玉鬘との結婚が源氏のしわざではないと知る。
【人の仲らひ】- 男女関係をさしていう。
【しか思ふべき罪もなし】- そんなに苦にする責任はない。男女関係は自然と明らかになってくるものであるからという考えによる。
|
| 3.6.9 |
とのたまふ。
|
とおっしゃる。
|
とも言っていた。
|
|
|
第四章 玉鬘の物語 宮中出仕から鬚黒邸へ
|
|
第一段 玉鬘、新年になって参内
|
| 4.1.1 |
かかることどもの騷ぎに、尚侍の君の御けしき、いよいよ晴れ間なきを、大将は、いとほしと思ひあつかひきこえて、
|
このようなことの騒動に、尚侍の君のご気分は、ますます晴れる間もないでいるのを、大将は、お気の毒にとお気づかい申し上げて、
|
大将のもとの夫人とのそうしたいきさつはいっそう玉鬘を憂鬱にした。大将はそれを哀れに思って慰めようとする心から、
|
|
| 4.1.2 |
|
「あの参内なさる予定であったことも、沙汰止みになって、お妨げ申したのを、帝におかせられても、快からず何か含むところがあるようにお聞きあそばし、方々もお考えになるところがあるだろう。
宮仕えの女性を妻にしている男もいないではないが」
|
尚侍として宮中へ出ることをこれまでは反対をし続けたのであるが、陛下がこの態度を無礼であると思召すふうもあるし、両大臣もいったん思い立ったことであるから、自分らとしていえば公職を持つ女の良人である人も世間にあることであり、構わないことと考えて宮中へ出仕することに賛成する
|
【この参りたまはむと】- 以下「なくやはある」まで、鬚黒の心。「この」は尚侍としての出仕をさす。
【妨げきこえつるを】- 鬚黒が玉鬘の尚侍としての宮中出仕をお妨げ申し上げてしまったことを、の意。
【人びとも思すところあらむ】- 「人びと」は「思す」という敬語が使われているので、源氏や内大臣などをさす。「思すところ」とは不快にお思いになることをいう。
|
| 4.1.3 |
|
と思い返して、年が改まってから、参内させ申し上げなさる。
男踏歌があったので、ちょうどその折に、参内の儀式をたいそう立派に、この上なく整えて参内なさる。
|
と言い出したので、春になっていよいよ尚侍の出仕のことが実現された。男踏歌があったので、それを機会として玉鬘は御所へ参ったのである。すべての儀式が派手に行なわれた。
|
【男踏歌ありければ】- 正月十四日に行われる行事。「末摘花」「初音」巻にも見えた。ここでは、玉鬘参内が「けれ」(過去の助動詞)「ば」とあり、過去の出来事という視点に立って語られる。
【儀式いといまめかしく】- 玉鬘の尚侍出仕の儀式。大島本は「いまめかしく」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「いかめしう」と校訂する。
|
| 4.1.4 |
|
お二方の大臣たち、この大将のご威勢までが加わり、宰相中将、熱心に気を配ってお世話申し上げなさる。
兄弟の公達も、このような機会にと集まって、ご機嫌を取りに近づいて、大事になさる様子、たいそう素晴らしい。
|
二人の大臣の勢力を背景にしている上に大将の勢いが添ったのであるから、はなばなしくなるのが道理である。源宰相中将は忠実に世話をしていた。兄弟たちも玉鬘に接近するよい機会であると、誠意を見せようとして集まって来て、うらやましいほどにぎわしかった。
|
【かたがたの大臣たち】- 源氏と内大臣をいう。
【宰相中将】- 夕霧をさす。
【兄弟の君達】- 柏木や弁少将など。
|
| 4.1.5 |
|
承香殿の東面にお局を設けてある。
西に宮の女御がいらしたので、馬道だけの間隔であるが、お心の中は、遠く離れていらっしゃったであろう。
御方々は、どの方となく競争なさい合って、宮中では、奥ゆかしくはなやいだ時分である。
格別家柄の劣った更衣たち、多くも伺候なさっていない。
|
承香殿の東のほう一帯が尚侍の曹司にあてられてあった。西のほう一帯には式部卿の宮の王女御がいるのである。一つの中廊下だけが隔てになっていても、二人の女性の気持ちははるかに遠く離れていたことであろうと思われる。後宮の人たちは競い合って、ますます宮廷を洗練されたものにしていくようなはなやかな時代であった。あまりよい身分でない更衣などは多くも出ていなかった。
|
【承香殿の東面に御局したり】- 承香殿は東西に長い建物。玉鬘はその東面の間をお部屋とした。以下、語り手の説明的文章が続く。
【西に宮の女御はおはしければ】- 承香殿の西面の間を式部卿宮の女御がお部屋としていた。
【馬道ばかりの隔てなるに、御心のうちは、遥かに隔たりけむかし】- 「けむ」(過去推量の助動詞)「かし」(終助詞、念を押す)は語り手の宮の女御と玉鬘との心を推測した表現。『一葉抄』は「双紙地也」と指摘。『細流抄』は「草子地をしはかりていへり」と指摘。『集成』も「草子地」と指摘する。
【御方々、いづれとなく】- 冷泉帝の後宮の様子を語る。
|
| 4.1.6 |
|
中宮、弘徽殿女御、この宮の王女御、左大臣の女御などが伺候していらっしゃる。
その他には、中納言、宰相の御息女が二人ほどが伺候していらっしゃるのであった。
|
中宮、弘徽殿の女御、この王女御、左大臣の娘の女御などが後宮の女性である。そのほかに中納言の娘と宰相の娘とが二人の更衣で侍していた。
|
【左の大殿の女御】- 大島本は「左大殿のの女御」とある。衍字である。「左大殿」は「行幸」巻(第一章一段)に出てきた大臣。
【中納言、宰相の御女二人ばかり】- 中納言、宰相は系図不明の人々。更衣である。以上、冷泉帝の後宮は、秋好中宮(源氏方養女)、弘徽殿女御(内大臣娘)、王女御(式部卿娘)、左大臣女御(左大臣娘)、中納言更衣、宰相更衣などがいる。
|
|
第二段 男踏歌、貴顕の邸を回る
|
| 4.2.1 |
|
踏歌は、局々に実家の人が参内し、ふだんとは違って、ことに賑やかな見物なので、どなたもどなたも綺羅を尽くし、袖口の色の重なり、うるさいほど立派に整えていらっしゃる。
春宮の女御も、たいそう華やかになさって、春宮は、まだお若くいらっしゃるが、すべての面でたいそう風流である。
|
踏歌は女御がたの所へ実家の人がたくさん見物に来ていた。これは御所の行事のうちでもおもしろいにぎやかなものであったから、見物の人たちも服装などに華奢を競った。東宮の母君の女御も人に負けぬ派手な方であった。東宮はまだ御幼年であったから、そのほうの中心は母君の女御であった。
|
【春宮の女御】- 朱雀院の女御で鬚黒の妹。今、春宮の母女御として梨壺に住む。「澪標」巻参照。
【宮は、まだ若くおはしませど】- 春宮はまだお若くいらっしゃるが。十二歳。元服適齢期である。
|
| 4.2.2 |
|
帝の御前、中宮の御方、朱雀院と参って、夜がたいそう更けてしまったので、六条院には、今回は仰々しいのでとお取り止めになる。
朱雀院から帰参して、春宮の御方々を回るうちに、夜が明けた。
|
御前、中宮、朱雀院へまわるのに夜が更けるために、今度は六条院へ寄ることを源氏が辞退してあった。朱雀院から引き返して、東宮の御殿を二か所まわったころに夜が明けた。
|
【御前、中宮の御方、朱雀院とに参りて】- 踏歌の一行が巡る順路である。帝の御前、すなわち清涼殿東庭から梅壺の中宮の御前、内裏を出て、上皇御所の朱雀院へと向かう。そして最後に内裏の梨壺の春宮の御前へと帰って来る。
【六条の院には、このたびは所狭しとはぶきたまふ】- 源氏の太政大臣邸の六条院は今回は仰々しいとという理由から省略なさる。「六条の院に」の格助詞「に」は尊敬の意、主格を表す。六条院におかれては。
|
| 4.2.3 |
ほのぼのとをかしき朝ぼらけに、いたく酔ひ乱れたるさまして、「竹河」謡ひけるほどを見れば、内の大殿の君達は、四、五人ばかり、殿上人のなかに、声すぐれ、容貌きよげにて、うち続きたまへる、いとめでたし。 |
ほのぼのと美しい夜明けに、たいそう酔い乱れた恰好をして、「竹河」を謡っているところを見ると、内大臣家の御子息が、四、五人ほど、殿上人の中で、声が優れ、器量も美しくて、うち揃っていらっしゃるのが、たいそう素晴らしい。
|
ほのぼのと白む朝ぼらけに、酔い乱れて「竹河」を歌っている中に、内大臣の子息たちが四、五人もいた。それはことに声がよく容貌がそろってすぐれていた。
|
【竹河】- 催馬楽、呂。「竹河の橋の詰めなるや橋の詰めなるや花園にはれ花園に我をば放てや少女たぐへて」。「初音」巻の踏歌の折にも謡われた。
【いとめでたし】- その場の情景を見ている語り手の感想を交えた表現。
|
| 4.2.4 |
|
殿上童の八郎君は、正妻腹の子で、たいそう大切になさっているのが、とてもかわいらしくて、大将殿の太郎君と立ち並んでいるのを、尚侍の君も、他人とはお思いにならないので、お目が止まった。
高貴な身分で長く宮仕えしていらっしゃる方々よりも、この御局の袖口は、全体の感じが今風で、同じ衣装の色合い、襲なりであるが、他の所より格別華やかである。
|
童形である八郎君は正妻から生まれた子で、非常に大事がられているのであったが、愛らしかった。大将の長男と並んでいるこの二人を尚侍も他人とは思えないで目がとどめられた。宮中の生活に馴れた女御たちの曹司よりも、新しい尚侍の見物する御殿の様子のほうがはなやかで、同じような物ではあるが、女房の袖口の重ねの色目も、ここのがすぐれたように公達は思った。
|
【大将殿の太郎君】- 鬚黒の長男、十歳。
【立ち並みたるを】- 大島本は「たちなミたるを」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「立ち並びたるを」と校訂する。
【尚侍の君も、よそ人と見たまはねば】- 尚侍の君すなわち玉鬘にとって、内大臣の子は異母兄弟。鬚黒大将の子は先妻の子、いわゆる継子関係になる。
【この御局の袖口】- 承香殿の東面の玉鬘の局の女房たちの袖口。
|
| 4.2.5 |
正身も女房たちも、かやうに御心やりて、しばしは過ぐいたまはまし、と思ひあへり。
|
ご本人も女房たちも、このようにご気分を晴らして、暫くの間は宮中でお過ごせになれたら、と思い合っていた。
|
尚侍自身も女房たちもこうした、悪いことが悪く見え、よいことはことによく見える御所の中の生活をしばらくは続けてみたいと思っていた。
|
|
| 4.2.6 |
|
どこでも同じように、肩にお被けになる綿の様子も、色艶も格別に洗練なさって、こちらは水駅であったが、様子が賑やかで、女房たちが心づかいし過ぎるほどで、一定の作法通りの御饗応など、用意がしてある様子は、特別に気を配って、大将殿がおさせになったのであった。
|
どちらでも纏頭に出すのは定った真綿であるが、それらなどにも尚侍のほうのはおもしろい意匠が加えられてあった。こちらはちょっと寄るだけの所なのであるが、はなやかな空気のうかがわれる曹司であったから、公達は晴れがましく思い、緊張した踏歌をした。饗応の法則は越えないようにして、ことに手厚く演者はねぎらわれたのであった。それは大将の計らいであった。
|
【皆同じごと、かづけわたす綿のさま】- 踏歌の人々に褒美として被ける綿の様子。
【こなたは】- 玉鬘の局。
【水駅なりけれど】- 水駅であったが、というように「皆同じごと」以下の一文を過去の助動詞「けり」でもって過去の出来事として語る。
【人びと心懸想しそして】- 踏歌の一行たちが緊張して。
【大将殿せさせたまへりける】- 「ける」という過去の助動詞でもって、この一段を語り収める。
|
|
第三段 玉鬘の宮中生活
|
| 4.3.1 |
|
宿直所にいらっしゃって、一日中、申し上げなさることは、
|
大将は禁中の詰め所にいて、終日尚侍の所へ、
|
【宿直所にゐたまひて】- 鬚黒が宿直所(陰明門内南廊、右大将直廬)に。
【日一日、聞こえ暮らしたまふことは】- 踏歌の翌日。一日中、鬚黒は玉鬘に何かと話し掛けなさる内容は。
|
| 4.3.2 |
|
「夜になったら、ご退出おさせ申そう。
このような機会にと、急にお考えが変わる宮仕えは安心でない」
|
退出を今夜のことにしたいと思います。出仕した以上はなおとどまっていたいと、あなたが考えるであろう宮仕えというものは、私にとって苦痛です。
|
【夜さり、まかでさせたてまつりてむ】- 以下「やすからぬ」まで、鬚黒の詞。
【かかるついでにと】- このように宮中に上がった機会にそのままいようと。
|
| 4.3.3 |
とのみ、同じことを責めきこえたまへど、御返りなし。
さぶらふ人びとぞ、
|
とばかり、同じことをご催促申し上げなさるが、お返事はない。
伺候している女房たちが、
|
こんなことばかりを書いて送るのであったが、玉鬘は何とも返事を書かない。女房たちから、
|
|
| 4.3.4 |
|
「大臣が、『急いで退出することなく、めったにない参内なので、ご満足あそばされるくらいに。
お許しがあってから、退出なさるよう』と、申し上げていらしたので、今夜は、あまりにも急すぎませんか」
|
源氏の大臣が、あまり短時日でなく、たまたま上がったのであるから、陛下がもう帰ってもよいと仰せになるまで上がっていて帰るようにとおっしゃいましたことですから。それに今晩とはあまり御無愛想なことになりませんかと私たちは存じます。
|
【大臣の、『心あわたたしきほどならで】- 以下「すがすがしうや」まで、女房の詞。「大臣」は源氏をさしていう。「心あわたたしき」以下「まかでさせたまへ」まで、源氏の詞を引用。
【御心ゆかせたまふばかり】- 帝のお心に御満足あそばされるほど。
|
| 4.3.5 |
|
と申し上げたのを、たいそうつらく思って、
|
と大将の所へ書いて来た。大将は尚侍を恨めしがって、
|
【いとつらしと思ひて】- 鬚黒はとてもひどいと思って。
|
| 4.3.6 |
「さばかり聞こえしものを、さも心にかなはぬ世かな」 |
「あれほど申し上げたのに、何とも思い通りに行かない夫婦仲だなあ」
|
「あんなに言っておいたのに、自分の意志などは少しも尊重されない」
|
【さばかり】- 以下「世かな」まで、鬚黒の心。
|
| 4.3.7 |
とうち嘆きてゐたまへり。
|
とお嘆きになっていらっしゃった。
|
と歎息をしていた。
|
|
| 4.3.8 |
|
兵部卿宮、御前の管弦の御遊に伺候していらっしゃっても、気が落ち着かず、このお局あたりを思わずにはいらっしゃれないので、堪えきれずにお便りを申し上げなさった。
大将は、近衛府の御曹司にいらっしゃる時であった。
「そこから」と言って取り次いだので、しぶしぶと御覧になる。
|
兵部卿の宮は御前の音楽の席に、その一員として列席しておいでになったのであるが、お心持ちは平静でありえなかった。尚侍の曹司ばかりがお思われになってならないのであった。堪えがたくなって宮は手紙をお書きになった。大将は自身の直廬のほうにいたのである。宮の御消息であるといって使いから女房が渡されたものを、尚侍はしぶしぶ読んだ。
|
【大将は、司の御曹司にぞおはしける】- 挿入句。蛍兵部卿宮から手紙が来た時、鬚黒はちょうど近衛府の右大将直廬にいらっしゃったのであったという説明を挿入した。
【これより」とて】- 大島本は「これより」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「それより」と校訂する。女房が鬚黒のもとからといって。
【しぶしぶに見たまふ】- 玉鬘が渋々と御覧になる。
|
| 4.3.9 |
|
「深山木と仲よくしていらっしゃる鳥が
またなく疎ましく思われる春ですねえ
|
深山木に翅うち交はしゐる鳥の
またなく妬き春にもあるかな |
【深山木に羽うち交はしゐる鳥の--またなくねたき春にもあるかな】- 蛍兵部卿宮からの贈歌。鬚黒を「深山木」に見立て、玉鬘を「鳥」に見立てる。「深山木」は無風流な木の譬えである。「またなくねたき」には「またなく妬き」に「また鳴く音」「また泣く声」を響かせる。「羽うち交はし」は「長恨歌」の比翼連理を踏まえた夫婦仲の睦まじいことをいう。楽しいはずの春が自分には悔しい思いでいる。
|
| 4.3.10 |
|
鳥の囀る声が耳に止まりまして」
|
さえずる声にも耳がとどめられてなりません。
|
【さへづる声も耳とどめられてなむ】- 蛍兵部卿宮の歌に添えた詞。『源氏釈』は「百千鳥囀る春はものごとに改まれども我ぞふりゆく」(古今集春上、二八、読人しらず)を指摘。現行の注釈書でも指摘する。
|
| 4.3.11 |
|
とある。
お気の毒に思って、顔が赤くなって、お返事のしようもなく思っていらっしゃるところに、主上がお越しあそばす。
|
とあった。気の毒なほど顔を赤めて、何と返事もできないように尚侍が思っている所へ帝がおいでになった。
|
【主上渡らせたまふ】- 主上が承香殿の東面の玉鬘の局にお渡りあそばす。
|
|
第四段 帝,玉鬘のもとを訪う
|
| 4.4.1 |
|
月が明るいので、ご容貌は言いようもなくお美しくて、まるで、あの大臣のご様子に違うところなくいらっしゃる。
「このような方が二人もいらっしゃったのだ」と、拝見なさる。
あの方のお気持ちは浅くはないが、嫌な物思いをしたけれど、こちらは、どうしてそのように思わせなさろう。
たいそうやさしそうに、期待していたことと違ってしまった恨み事を仰せられるので、顔のやり場もないほどにお思いなさるよ。
顔を袖で隠して、お返事も申し上げなさらないので、
|
明るい月の光にお美しい竜顔がよく拝された。源氏の顔をただそのまま写したようで、こうしたお顔がもう一つあったのかというような気が玉鬘にされるのであった。源氏の愛は深かったがこの人が受け入れるのに障害になるものがあまりに多かった。帝との間にはそうしたものはないのである。帝はなつかしい御様子で、お志であったことが違ってしまったという恨みをお告げになるのであったが、尚侍は恥ずかしくて顔の置き場もない気がした。顔を隠して、お返辞もできないでいると、
|
【ただ、かの大臣の御けはひに違ふところなくおはします】- 月の光に照らされた主上のご容貌は源氏の大臣にそっくりでいらっしゃる。
【かかる人はまたもおはしけり】- 玉鬘の感想。源氏のように美しい方がもう一人いらっしゃったのだ。
【見たてまつりたまふ】- 玉鬘は主上を拝見なさる。
【かの御心ばへは】- 以下「おぼえさせたまはむ」あたりまで玉鬘の心。源氏と主上を比較する。
【などかはさしもおぼえさせたまはむ】- 反語表現。どうして主上がお思いあそばそうか、それはない。
【いとなつかしげに】- 玉鬘の気持ちに添った語り口。「のたまはするに」に係る。
【思ひしことの違ひにたる怨み】- 主上が独身の身での尚侍としての出仕を期待していたことに相違してしまった恨み言。主上が「思って」いたことだが、ここでは敬語表現がない。
【面おかむかたなくぞおぼえたまふや】- 「や」(詠嘆の終助詞)、語り手の玉鬘に同情した表現。
【御応へもえ聞こえたまはねば】- 大島本は「えきこえ」とある。『集成』『新大系』は底本のままとする。『古典セレクション』は諸本に従って「聞こえ」と「え」を削除する。主上の恨み言に玉鬘は何とも返事を申し上げられないので。
|
| 4.4.2 |
「あやしうおぼつかなきわざかな。よろこびなども、思ひ知りたまはむと思ふことあるを、聞き入れたまはぬさまにのみあるは、かかる御癖なりけり」 |
「妙に黙っていらっしゃるのですね。
昇進なども、ご存知であろうと思うことがあるのに、何もお聞き入れなさらない様子でばかりいらっしゃるのは、そのようなご性格なのですね」
|
「たよりない方だね。好意を受けてもらおうと思ったことにも無関心でおいでになるのですね。何にもそうなのですね。あなたの癖なのですね」
|
【あやしうおぼつかなきわざかな】- 以下「御癖なりけり」まで、主上の玉鬘への詞。
【よろこび】- 叙位の喜び。
|
| 4.4.3 |
とのたまはせて、
|
と仰せになって、
|
と仰せになって、
|
|
| 4.4.4 |
|
「どうしてこう一緒になりがたいあなたを
深く思い染めてしまったのでしょう
|
「などてかくはひ合ひがたき紫を
心に深く思ひ初めけん
|
【などてかく灰あひがたき紫を--心に深く思ひそめけむ】- 帝の贈歌。「紫」は三位の服色。玉鬘を三位に叙したことをいう。また紫は椿の灰を混ぜて染料を作る。「灰合ひ」に「逢ひ」を掛け、「深く」「染め」は「紫」の縁語。
|
| 4.4.5 |
|
これ以上深くはなれないのでしょうか」
|
濃くはなれない運命だろうか」
|
【濃くなり果つまじきにや】- これ以上深い関係にはなれないのでしょうかの意。「濃く」は「紫」の縁語。会話文の中にも縁語を使う。ここまで、主上の歌に添えた詞。
|
| 4.4.6 |
|
と仰せになる様子、たいそう若々しく美しくて気恥ずかしいので、「どこが違っていらっしゃろうか」と気を取り直して、お返事申し上げなさる。
宮仕えの年功もなくて、今年、位を賜ったお礼の気持ちなのであろうか。
|
若々しくておきれいな所は源氏と同じである。源氏と思ってお話を申し上げようと尚侍は思った。陛下が好意と仰せられるのは、去年尚侍になって以来、まだ勤労らしいことも積まずに、三位に玉鬘を陞叙されたことである。紫は三位の男子の制服の色であった。
|
【違ひたまへるところやある】- 玉鬘の心。源氏と主上を比較し、少しも違わないと思う。
【宮仕への労もなくて、今年、加階したまへる心にや】- 語り手が玉鬘が次のような返歌をした気持ちを先回りして語った挿入文。『細流抄』は「此哥の注を草子地かく也」と指摘。『集成』も「あらかしめ次の歌に説明を加えた草子地」と指摘する。
|
| 4.4.7 |
|
「どのようなお気持ちからとも存じませんでした
この紫の色は、
|
「いかならん色とも知らぬ紫を
心してこそ人はそめけれ
|
【いかならむ色とも知らぬ紫を--心してこそ人は染めけれ】- 玉鬘の返歌。帝への感謝の気持ちを詠む。「色」「染め」は「紫」の縁語。
|
| 4.4.8 |
|
ただ今からはそのように存じましょう」
|
ただ今から改めて御恩を思います」
|
【今よりなむ思ひたまへ知るべき】- ここまで、玉鬘の返歌に添えた詞。
|
| 4.4.9 |
と聞こえたまへば、うち笑みて、
|
と申し上げなさると、ほほ笑みなさって、
|
と尚侍が言うと、帝は微笑をあそばして、
|
|
| 4.4.10 |
|
「その、今から思って下さろうとしても、何の役にも立たないことです。
訴えを聞いてくれる人があったら、その判断を聞いてみたいものです」
|
「その今からということがだめになったのだからね。私に抗議する人があれば理論が聞きたい。私のほうが先にあなたを愛していたのだから」
|
【その、今より染めたまはむこそ】- 以下「聞かまほしくなむ」まで主上の詞。「そめ」は「初め」と「染め」とを掛け、「染め」は「紫」の縁語。
【愁ふべき人あらば】- 私の愁えを聞いてくださる人がいたら。
|
| 4.4.11 |
|
と、たいそうお恨みあそばす御様子が、真面目で厄介なので、「とても嫌だわ」と思われて、「愛想の良い態度をお見せ申すまい、男の方の困った癖だわ」と思うと、真面目になって伺候していらっしゃるので、お思い通りの冗談も仰せになれずに、「だんだんと親しみ馴れて行くことだろう」とお思いあそばすのであった。
|
と恨みをお告げになる。言葉の遊戯ではなく皆まじめに思召すらしいのであったから、尚侍は困ったことであると思った。自分が陛下の愛に感激しているほんとうの気持ちなどはお見せすべきでない。帝といえども男性に共通した弱点は持っておいでになるのであるからと考えて、玉鬘はただきまじめなふうで黙って侍していた。帝はもう少し突込んだ恋の話もしたく思召してここへおいでになったのであるが、それがお言い出せにならないで、そのうち馴れてくるであろうからと見ておいでになった。
|
【いとうたてもあるかな】- 玉鬘の心。
【をかしきさまをも】- 以下「世の癖なりけり」まで玉鬘の心。
【世の癖】- 男女の仲、特に男性の悪い性分の意。
【やうやうこそは目馴れめ】- 主上の心。玉鬘もだんだんと宮仕え生活に慣れてこよう。
【思しけり】- 帝はお思いあそばすのであった。「けり」(過去の助動詞)でもって、この段を語り収める。
|
|
第五段 玉鬘、帝と和歌を詠み交す
|
| 4.5.1 |
|
大将は、このようにお越しあそばしたのをお聞きになって、ますます心が落ち着かないので、急いでせき立てなさる。
ご自身も、「身分不相応なことも出て来かねない身の上だなあ」と情けなく思うので、落ち着いていらっしゃれず、退出させなさる段取り、もっともらしい口実を作り出して、父大臣など、うまく取り繕いなさって、御退出を許されなさったのであった。
|
大将は帝が曹司へおいでになったと聞いて危険がることがいよいよ急になって、退出を早くするようにとしきりに催促をしてきた。もっともらしい口実も作って実父の大臣を上手に賛成させ、いろいろと策動した結果、ようやく今夜退出する勅許を得た。
|
【大将は】- 以下、鬚黒に視点を移して語る。
【みづからも】- 「も」(係助詞、並列)があることによって、鬚黒はもちろんのこと、玉鬘自身でものニュアンス。
【似げなきことも出で来ぬべき身なりけり】- 「似げなきこと」とは帝の寵愛を得ることをさす。既に夫があり、それはまた異母姉妹の弘徽殿女御や秋好中宮らと寵愛を競うことになると懸念した。
【父大臣】- 玉鬘の父、内大臣。
|
| 4.5.2 |
|
「それでは。
これに懲りて、二度と出仕をさせない人があっては困る。
たいそうつらい。
誰より先に望んだ気持ちが、人に先を越されて、その人の御機嫌を伺うことよ。
昔の誰それの例も、持ち出したい気がします」
|
「今夜あなたの出て行くのを許さなければ、懲りてしまって、これきりあなたをよこしてくれない人があるからね。だれよりも先にあなたを愛した人が、人に負けて、勝った男の機嫌をとるというようなことをしている。昔の何とかいった男(時平に妻を奪われた平貞文の歌、昔せしわがかねごとの悲しきはいかに契りし名残なるらん)のように、まったく悲観的な気持ちになりますよ」
|
【さらば】- 以下「心地なむする」まで、帝の詞。それならしかたがないの意。
【物懲りして】- 玉鬘を出仕させたことに懲りての意。
【もぞある】- ~があっては困る、の意。
【人に後れて、けしき取り従ふよ】- 「人」は鬚黒をさす。鬚黒に先を越されて、今やその人の御機嫌を伺うことになったとはの意。
【昔のなにがしが例も】- 「大納言国経の朝臣の家にはべりける女に、平定文いとしのびて語らひはべりて、行末まで契りはべりけるころ、この女にはかに贈太政大臣にむかへられてわたりはべりにければ、文だにも通はすかたなくなりにければ、かの女の子の五ばかりなるが、本院の西の対に遊びありきけるを呼び寄せて、母に見せたてまつれとて腕にかきつけはべりける、平定文 昔せしわがかねごとの悲しきはいかに契りし名残なるらむ。 返し、読人しらず うつつにて誰契りけむ定めなき夢路にまどふ我は我かは」(後撰集恋三、七一一、平定文・七一二、読人しらず)の話が指摘されている。
|
| 4.5.3 |
とて、まことにいと口惜しと思し召したり。
|
と仰せになって、
|
と仰せになって、真底からくやしいふうをお見せになった。
|
|
| 4.5.4 |
|
お聞きあそばしていた時よりも、格段に実際に素晴らしいのを、初めからそのような気持ちがないにせよ、お見逃しになれないだろうに、なおさらたいそう悔しく、残念にお思いなさる。
|
聞こし召したのに数倍した美貌の持ち主であったから、初めにそうした思召しはなくっても、この人を御覧になっては公職の尚侍としてだけでお許しにならなかったであろうと思われるが、まして初めの事情がそうでもなかったのであったから、帝は妬ましくてならぬ御感情がおありになって、最初の求婚者の権利を主張あそばしたくなるのを、あさはかな恋と思われたくないと御自制をあそばして、熱情を認めさせようとしてのお言葉だけをいろいろに下された。
|
【聞こし召ししにも、こよなき近まさりを】- 帝は玉鬘の美しさをお聞きあそばしていた以上に、実際間近で御覧になると格段に美しいのを、の意。
【さる御心】- 妃の一人にしようとするお考え。
|
|
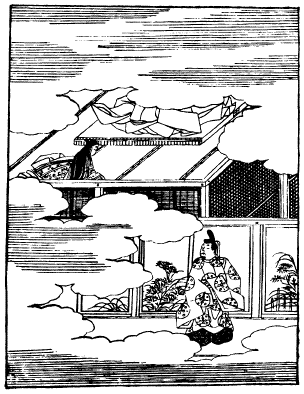 |
| 4.5.5 |
されど、ひたぶるに浅き方に、思ひ疎まれじとて、いみじう心深きさまにのたまひ契りて、なつけたまふも、かたじけなう、「われは、われ、と思ふものを」と思す。 |
けれども、まったく出来心からと、疎んじられまいとして、たいそう愛情深い程度にお約束なさって、親しみなさるのも、恐れ多く、「わたしは、わたしだわ、と思っているのに」とお思いになる。
|
こうしてなつけようとあそばす御好意がかたじけなくて、結婚しても自分の心は自分の物であるのに、良人にことごとく与えているものでないのにと玉鬘は思っていた。
|
【われは、われ、と思ふものを】- 玉鬘は、心に前出の「後撰集」の女の返歌、「うつつにて誰契りけむ定めなき夢路にまどふ我は我かは」の語句を引用して、わが身を省みる。夫をもったわが身は昔のわたしではない。しかし、いまだ「夢路に惑う」という心の底に帝を思い続けている気持ちがあるのか、否、もう「我は我かは」という確固とした鬚黒の妻としての自覚なのか。二者択一というより両方の気持ちが揺れ動いているというのが玉鬘の真実に近いのではなかろうか。『完訳』は女の返歌による叙述としながら、「あるいはこれと無関係に、自分自身としてはみかどに仕えたいのに、と解すべきか」と注す。
|
| 4.5.6 |
|
御輦車を寄せて、こちら方、あちら方の、お世話役の人々が待ち遠しがって、大将も、たいそううるさいほどお側を離れず、世話をお焼きになる時まで、お離れあそばされない。
|
輦車が寄せられて、内大臣家、大将家のために尚侍の退出に従って行こうとする人たちが、出立ちを待ち遠しがり、大将自身もむつかしい顔をしながら、人々へ指図をするふうにしてその辺を歩きまわるまで帝は尚侍の曹司をお離れになることができなかった。
|
【御輦車寄せて】- 御輦車は、女性では女御、妃などのうち、特に帝の勅許を得て許された者が乗用する。したがって、帝の玉鬘に対する特別な措置といえる。
【こなた、かなたの、御かしづき人ども】- 源氏方内大臣方のお世話役連中。
【えおはしまし離れず】- 帝は玉鬘のお側をお離れにならない。
|
| 4.5.7 |
|
「こんなに厳重な付ききりの警護は不愉快だ」
|
「近衛過ぎるね。これでは監視されているようではないか」
|
【かういと厳しき近き守りこそむつかしけれ】- 帝の詞。鬚黒が右大将なので、それにひっかけて揶揄する。
|
| 4.5.8 |
と憎ませたまふ。
|
とお憎みあそばす。
|
と帝はお憎みになった。
|
|
| 4.5.9 |
|
「幾重にも霞が隔てたならば、
梅の花の香は宮中まで匂って来な
|
九重に霞隔てば梅の花
ただかばかりも匂ひこじとや
|
【九重に霞隔てば梅の花--ただ香ばかりも匂ひ来じとや】- 帝の玉鬘への贈歌。別れの挨拶といった内容。「九重」は宮中の意と九重、すなわち幾重にもの意を掛ける。また「かはかり」にも「香はかり」と副詞の「かばかり」とを掛ける。「霞」に暗に鬚黒のことをいう。「梅の花」は玉鬘を譬喩する。
|
| 4.5.10 |
|
格別どうという歌ではないが、ご様子、物腰を拝見している時は、結構に思われたのであろうか。
|
何でもない御歌であるが、お美しい帝が仰せられたことであったから、特別なもののように尚侍には聞かれた。
|
【殊なることなきことなれども】- 以下「をかしくもやありけむ」まで語り手の判断の交じえた表現。『休聞抄』は「双也」と指摘。『孟津抄』は「紫式部が批判也」。『評釈』は「語り手の批評この歌はたいしたものでない、と、語り手はことわる。しかし、その時は、主上を拝していたのだから、結構なお歌と思ったことでしょうか。そう思ったひとを非難することはできない、と言うのである」と注す。『集成』は「草子地」と指摘。『完訳』は「語り手が、玉鬘の動揺を推測」と注す。
|
| 4.5.11 |
|
「野原が懐かしいので、このまま夜明かしをしたいが、そうさせたくないでいる人が、自分の身につまされて気の毒に思う。
どのようにお便りしたらよいものか」
|
「私は話し続けて夜が明かしたいのだが、惜しんでいる人にも、私の身に引きくらべて同情がされるからお帰りなさい。しかし、どうして手紙などはあげたらいいだろう」
|
【野をなつかしみ】- 以下「聞こゆべき」まで帝の詞。「春の野に菫摘みにと来しわれぞ野をなつかしみ一夜寝にける」(古今六帖六、菫、三九一六・万葉集巻八、一四二四、山部赤人)の和歌の句を引用する。
【惜しむべかめる人】- 鬚黒をさす。
【身をつみて】- 前出の和歌の語句「菫摘みに」に引っ掛けた表現。
|
| 4.5.12 |
|
とお悩みあそばすのも、「まことに恐れ多いこと」と、拝する。
|
と御心配げに仰せられるのがもったいなく思われた。
|
【と思し悩むも】- と帝は玉鬘に仰せになってお悩みあそばすのもの意。「と」の下には「仰せて」などの語句が省略されている。
【いとかたじけなし」と、見たてまつる】- 玉鬘は帝をまことに恐れ多いと拝する。
|
| 4.5.13 |
|
「香りだけは風におことづけください
美しい花の枝に並ぶべくもないわたしですが」
|
かばかりは風にもつてよ花の枝に
立ち並ぶべき匂ひなくとも
|
【香ばかりは風にもつてよ花の枝に--立ち並ぶべき匂ひなくとも】- 玉鬘の返歌。帝の贈歌から、「香ばかり」の語句を引用して応える。「花の枝」は後宮の妃方を隠喩。また帝をさすと考えることもできよう。わが身を「匂ひなくとも」と謙遜する。
|
| 4.5.14 |
|
やはり冷たく扱われない様子を、しみじみとお思いになりながら、振り返りがちにお帰りあそばした。
|
と言って、さすがに忘られたくない様子の女に見えるのを哀れに思召しながら、顧みがちに帝はお立ち去りになった。
|
【さすがにかけ離れぬけはひを】- 帝の目から見た玉鬘の冷淡にあしらわない態度。
【あはれと思しつつ】- 帝の気持ち。
【渡らせたまひぬ】- 帝はお戻りあそばした。以上、承香殿東間の玉鬘と帝の別れの場面終わる。帝の玉鬘に寄せる愛執はその後も語られる。
|
|
第六段 玉鬘、鬚黒邸に退出
|
| 4.6.1 |
|
そのまま今夜、あの邸にとお考えになっていたが、前もってはお許しが出ないだろうから、打ち明け申されずに、
|
すぐに大将は自邸へ玉鬘を伴おうと思っているのであるが、初めから言っては源氏の同意が得られないのを知って、この時までは言わずに、突然、
|
【やがて今宵、かの殿にと思しまうけたるを】- 場面は変わって、鬚黒を中心に語る。
【かねては許されあるまじきにより、漏らしきこえたまはで】- 誰が許さないのか不分明。『集成』は内大臣とし、『完訳』は源氏とする。『新大系』は「源氏や内大臣」とする。
|
| 4.6.2 |
「にはかにいと乱り風邪の悩ましきを、心やすき所にうち休みはべらむほど、よそよそにてはいとおぼつかなくはべらむを」 |
「急にたいそう風邪で気分が悪くなったものですから、気楽な所で休ませます間、よそに離れていてはたいそう不安でございますから」
|
「にわかに風邪気味になりまして、自宅で養生をしたく存じますが、別々になりましては妻も気がかりでございましょうから」
|
【にはかにいと】- 以下「おぼつかなくはべらむを」まで、鬚黒の詞。
|
| 4.6.3 |
|
と、穏やかに申し上げなさって、そのままお移し申し上げなさる。
|
と穏やかに了解を求めて、大将はそのまま尚侍をつれて帰ったのであった。
|
【申しないたまひて】- 「申しない」は「申しなし」のイ音便形。ここも誰に申し上げなさってなのか不分明。
【やがて渡したてまつりたまふ】- 鬚黒は玉鬘をそのまま自邸にお移し申し上げなさる。
|
| 4.6.4 |
父大臣、にはかなるを、「儀式なきやうにや」と思せど、「あながちに、さばかりのことを言ひ妨げむも、人の心おくべし」と思せば、 |
父内大臣は、急なことで、「格式が欠けるようではないか」とお思いになるが、「強引に、そのくらいのことで反対するのも、気を悪くするだろう」とお思いになると、
|
内大臣は婚家へ娘のにわかな引き取られ方を、形式上不満にも思ったが、小さなことにこだわっていては婿の大将の感情を害することになろうと思って、
|
【儀式なきやうにや】- 退出の作法が疎略ではないか。当時は格式を重んじた。
|
| 4.6.5 |
|
「どのようにでも。
もともとわたしの自由にならないお方のことだから」
|
「どちらでも私のほうの意志でどうすることもできない娘になっているのですから」
|
【ともかくも。もとより進退ならぬ人の御ことなれば】- 内大臣の詞。内大臣にとって玉鬘はもともと自分の思うままにならなかった人であるという意。
|
| 4.6.6 |
|
と、申し上げなさるのであった。
|
という返事を内大臣はした。
|
【とぞ、聞こえたまひける】- 内大臣は鬚黒に申し上げるのであったという意。玉鬘のいわゆる親権者は内大臣に移っているのか。あるいは、よく儀式の格式を重んじる内大臣側に焦点を当てて玉鬘の退出を語ったものか。
|
| 4.6.7 |
|
六条殿は、「あまりに急で不本意だ」とお思いになるが、どうしようもない。
女も、思ってもみなかった身の上を、情けないとお思いになるが、盗んで来たらと、たいそう嬉しく安心した。
|
源氏は思いがけないことになったと失望を感じたが、それは無理なことのようである。玉鬘も心にない良人を持ったことは苦しいと思いながらも、盗んで行かれたのであればあきらめるほかはないという気になって、大将家へ来たことではじめて心が落ち着いてうれしかった。
|
【六条殿ぞ】- 場面は変わって、六条院の源氏の立場を語る一文を挿入し、鬚黒の自邸に戻った鬚黒と玉鬘を語る。
【などかはあらむ】- 語り手の批評を挿入。『集成』は「何の不都合なことがあろう。鬚黒としては、もう源氏の意向など意に介する必要はない、という意味の草子地」と注す。
【塩やく煙のなびきけるかたを】- 『源氏釈』は「須磨の海人の塩焼く煙風をいたみ思はぬ方にたなびきにけり」(古今集恋四、七〇八、読人しらず)を指摘。現行の諸注釈書でも指摘する。
【盗みもて行きたらまし】- 鬚黒の気持ち。女を盗んだ時の気持ちを想像し、うれしく思っている。『伊勢物語』六段の二条の后の物語や、この物語の「夕顔」や「若紫」巻の物語がある。また、『更級日記』の作者も美しい男性に連れ出されることに憧れていた当時の読者の気持ちを反映していよう。
|
| 4.6.8 |
|
あの、お入りあそばしたことを、たいそう嫉妬申し上げなさるのも、不愉快で、やはりつまらない人のような気がして、夫婦仲は疎々しい態度で、ますます機嫌が悪い。
|
帝が曹司に長くおいでになったことで大将が非常に嫉妬していろいろなことを言うのも、凡人らしく思われて、良人を愛することのできない玉鬘の機嫌はますます悪かった。
|
【かの、入りゐさせたまへりしことを】- 帝が玉鬘のお部屋にお入りあそばしたことを。最高敬語が使われているので、帝のことと分かる。
【怨じきこえさせたまふも】- 鬚黒が帝に嫉妬申し上げなさるのも。
【心づきなく】- 玉鬘の心。鬚黒がぶつぶつ嫉妬しているのを側で聞いて気にくわなく思っている。
【なほなほしき心地して】- 玉鬘にとって鬚黒は普通の人のような気がして。
【世には】- 夫婦仲は。
|
| 4.6.9 |
|
あの宮家でも、あのようにきつくおっしゃったが、たいそう後悔なさっているが、まったく音沙汰もない。
ただ念願が叶ったお世話で、毎日いそしんでお過ごしになる。
|
式部卿の宮もあのように強い態度をおとりになったものの、大将がそれきりにしておくことで煩悶をしておいでになった。大将はもう交渉することを断念したふうである。一方では理想が実現された気になって、明け暮れ玉鬘をかしずくことに心をつかっていた。
|
【かの宮にも】- 式部卿宮家でも。母娘を引き取ったその後の宮家の様子を語る。
【絶えて訪れず】- 鬚黒はまったく宮家に音沙汰もない。
【いとなみて過ぐしたまふ】- 鬚黒は玉鬘のお世話にいそしんで過ごしていらっしゃる。
|
|
第七段 二月、源氏、玉鬘へ手紙を贈る
|
| 4.7.1 |
|
二月になった。
大殿は、
|
二月になった。源氏は大将を無情な男に思われてならなかった。
|
【二月にもなりぬ】- 源氏三十八年二月、仲春の季節となる。玉鬘のいなくなった六条院の源氏を語る。
|
| 4.7.2 |
|
「それにしても、
無愛想な仕打ちだ。まったくこのようにきっぱりと自分のものにしようとは思いもかけないで、油断させられたのが悔しい」、と、体裁悪く、何から何までお気にならない時とてなく、恋しく思い出さずには
|
これほどはっきりと玉鬘を自分から引き放すこととは思わずに油断をさせられていたことが、人聞きも不体裁に思われ、自身のためにも残念で、玉鬘が恋しくばかり思われた。
|
【さても、つれなきわざなりや】- 以下「ねたさを」まで、源氏の心であるが、この文を受ける引用句がなく、「ねたさを人悪く」というように地の文に繋がっている。
【際々しうとしも思はで】- 自分(源氏)は鬚黒が玉鬘をきっぱり自分のものにしようとは少しも考えないでの意。
【たゆめられたるねたさを】- 「られ」(受身の助動詞)。源氏は被害者意識をもっている。結婚して他人の妻となってもまだ心底から執着心を拭いきれないでいる。 【ねたさを】-ここまでが源氏の心。しかし、この文を受ける引用句、例えば「と」などがない。そして、「ねたさを」は下の「人悪ろく」の目的格のようになっている。
【恋しう思ひ出でられたまふ】- 「られ」自発の助動詞。源氏は玉鬘が恋しく思い出さずにはいらっしゃれない。
|
| 4.7.3 |
|
「運命などと言うのも、軽く見てはならないものだが、自分のどうすることもできない気持ちから、このように誰のせいでもなく物思いをするのだ」
|
宿縁は無視できないものであっても、自身の思いやりのあり過ぎたことからこうした苦しみを買うことになったのである
|
【宿世などいふもの】- 以下「思ふぞかし」まで、源氏の心。
【わがあまりなる心にて】- 自分のどうすることもできない心から。『完訳』は「自分があまりにうかつすぎたために」と訳す。
|
| 4.7.4 |
と、起き臥し面影にぞ見えたまふ。
|
と、寝ても起きても幻のようにまぶたにお見えになる。
|
と、日夜面影にその人を見ていた。
|
|
| 4.7.5 |
|
大将のような、趣味も、愛想もない人に連れ添っていては、ちょっとした冗談も遠慮されつまらなく思われなさって、我慢していらっしゃるとき、雨がひどく降って、とてものんびりとしたころ、このような所在なさも気の紛らし所にお行きになって、お話しになったことなどが、たいそう恋しいので、お手紙を差し上げなさる。
|
風流気の少ない大将といることを思っては、手紙で、戯れのようにして今日このごろの気持ちを玉鬘に伝えることも気が置かれて得しなかった。雨がよく降って静かなころ、源氏はこうした退屈な時間も紛らすことが玉鬘の所でできたこと、その時分の様子などが目に浮かんできて、非常に恋しくなって手紙を書いた。
|
【雨いたう降りて】- 二月の雨、春雨。『伊勢物語』などにも春の物思いの景物として描かれる。
【紛らはし所に渡りたまひて】- かつて玉鬘がいた部屋に。
【語らひたまひしさま】- 過去の助動詞「し」、源氏は自らの体験を回想する。
|
| 4.7.6 |
|
右近のもとにこっそりと差し出すのも、一方では、それをどのように思うかとお思いになると、詳しくは書き綴ることがおできになれず、ただ相手の推察に任せた書きぶりなのであった。
|
右近の所へそっとその手紙は送られたのであるが、そうはしながらも右近が怪しく思わないかということも考えられて、思うことはそのまま皆書き続けられなかった。ただ推察のできそうなことだけを書いたのであった。
|
【右近】- もと夕顔の女房。その死後、源氏のもとに身を寄せ、「玉鬘」巻で、長谷寺に参詣した折、椿市で玉鬘に邂逅し、玉鬘が六条院に入ってからは玉鬘付きの女房となり、鬚黒と結婚して以後も女房として付き従って仕えている。
【思はむことを思すに】- 源氏は右近がどう思うかとお思いになると。相手の思うことに敬語がないから、右近が思うことであろう。
【ぞありける】- なのであった、という後からの回想的語り方。
|
| 4.7.7 |
|
「降りこめられてのどやかな春雨のころ
昔馴染みのわたしをどう思っていらっしゃいますか
|
かきたれてのどけきころの春雨に
ふるさと人をいかに忍ぶや
|
【かきたれてのどけきころの春雨に--ふるさと人をいかに偲ぶや】- 源氏の贈歌。「ふる」は「春雨に降る」と「古る里人」との掛詞。「ふるさと人」は、源氏自身をさす。
|
| 4.7.8 |
|
所在なさにつけても、恨めしく思い出されることが多くございますが、どのようにして分かるように申し上げたらよいのでしょうか」
|
私も退屈なものですから、いろいろ恨めしくなったりすることがあるのですが、どうしてそれをお聞かせしてよいかわかりません。
|
【つれづれに添へて】- 大島本は「そへても(も#)」とある。すなわち「も」をミセケチにする。『集成』『古典セレクション』は底本の訂正以前本文と諸本に従って「添へても」とする。『新大系』は底本の訂正に従って「添へて」と校訂する。以下「聞こゆべからむ」まで、歌に添えられた文面。
【いかでか分き聞こゆべからむ】- 大島本は「いかてかわ(△&わ)きゝ(△&ゝ)こゆへからむ」とある。すなわち「か」の次の文字「△」(判読不能)を摺り消して「わ」と重ね書きし、「き」の次の文字「△」(判読不能)を摺り消して「ゝ」と重ね書きする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「いかでかは聞こゆべからむ」とする。『新大系』は底本の訂正に従って「いかでかわき聞こゆべからむ」と校訂する。
|
| 4.7.9 |
などあり。
|
などとある。
|
などと書かれてあった。
|
|
| 4.7.10 |
|
人のいない間にこっそりとお見せ申し上げると、ほろっと泣いて、自分の心でも、月日のたつにつれて、思い出さずにはいらっしゃれないご様子を、正面きって、「恋しい、何とかしてお目にかかりたい」などとは、おっしゃることのできない親なので、「おっしゃるとおり、どうしてお会いすることができようか」と、もの悲しい。
|
人が玉鬘のそばにいない時を見計らって右近はこの手紙を見せた。玉鬘も泣いた。自身の心にも時がたつままに思い出されることの多い源氏は、感情そのままに、恋しい、どうかして逢いたいというのを遠慮しないではならない親であったから、実際問題として考えてもいつ逢えることともわからないので悲しかった。
|
【隙に】- 鬚黒のいない時。
【見せたてまつれば】- 右近が玉鬘にお見せ申し上げると。
【わが心にも】- 相手の源氏同様に玉鬘自身の気持ちも、というニュアンスの表現。
【思ひ出でられたまふ】- 「られ」自発の助動詞。
【御さまを】- 源氏のお姿。
【恋しや、いかで見たてまつらむ】- 玉鬘の心。源氏を慕う気持ち。
【げに、いかでかは対面もあらむ】- 玉鬘の心。「げに」は源氏の手紙の「いかでか分き聞こゆべからむ」を受ける。
|
| 4.7.11 |
|
時々、厄介であったご様子を、気にくわなくお思い申し上げたことなどは、この人にもお知らせになっていないことなので、自分ひとりでお思い続けていらっしゃるが、右近は、うすうす感じ取っていたのであった。
実際、どんな仲であったのだろうと、今でも納得が行かず思っていたのであった。
|
時々源氏の不純な愛撫の手が伸ばされようとして困った話などは、だれにも言ってないことであったが、右近は怪しく思っていた。ほんとうのことはまだわからないようにこの人は思っているのである。
|
【時々、むつかしかりし御けしきを、心づきなう思ひきこえしなど】- 過去の助動詞「し」で叙述。玉鬘の心に添った語り方。
【この人にも】- 右近をさす。
【ほのけしき見けり】- 過去の助動詞「けり」で叙述。右近について、本当はうすうす感じ取っていたのであった、というように語り手が真実を語り明かすニュアンス。
【いかなりけることならむ】- 右近の心。玉鬘と源氏はいったいどのような関係であったのだろうか、というので、やはり過去の助動詞「けり」で叙述される。
【心得がたく思ひける】- 連体中止形で、余韻をもたせた表現。
|
| 4.7.12 |
|
お返事は、「差し上げるのも気が引けるが、ご不審に思われようか」と思って、お書きになる。
|
返事を、「書くのが恥ずかしくてならないけれど、あげないでは失望をなさるだろうから」
と言って、玉鬘は書いた。
|
【聞こゆるも】- 以下「おぼつかなくやは」まで玉鬘の心。『集成』は心内文と解し、『完訳』は手紙文と解す。
【おぼつかなくやは】- 「申し上げずは」などの語句がその上に省略されている。
|
| 4.7.13 |
|
「物思いに耽りながら軒の雫に袖を濡らして
どうしてあなた様のことを思わずにいられましょうか
|
ながめする軒の雫に袖ぬれて
うたかた人を忍ばざらめや
|
【眺めする軒の雫に袖ぬれて--うたかた人を偲ばざらめや】- 玉鬘の返歌。源氏の歌の「春雨」に応じて「長雨」と応える。「うたかた人」は源氏をさす。「ながめ」は「長雨」と「眺め」の掛詞。「うたかた」は水の泡の「泡沫(うたかた)」の意とかりそめの意を掛ける。「雫」「濡れ」「泡沫」は縁語。わたしも涙に袖を濡らして恋い慕っております、という主旨の歌。
|
| 4.7.14 |
ほどふるころは、げに、ことなるつれづれもまさりはべりけり。あなかしこ」 |
時がたつと、おっしゃるとおり、格別な所在なさも募りますこと。
あなかしこ」
|
それが長い時間でございますから、憂鬱的退屈と申すようなものもつのってまいります。失礼をいたしました。
|
【ほどふるころは】- 以下「あなかしこ」まで、手紙の文。『河海抄』は「君見ずて程のふるやの廂には逢ことなしの草ぞ生ひける」(新勅撰集恋五、九四五、読人しらず)を指摘、『集成』も指摘する。
|
| 4.7.15 |
|
と、恭しくお書きになっていた。
|
とうやうやしく書かれてあった。
|
【書きなしたまへり】- 「なす」はわざと、意識的にのニュアンスを添える。
|
|
第八段 源氏、玉鬘の返書を読む
|
| 4.8.1 |
|
手紙を広げて、玉水がこぼれるように思わずにはいらっしゃれないが、「人が見たら、体裁悪いことだろう」と、平静を装っていらっしゃるが、胸が一杯になる思いがして、あの昔の、尚侍の君を朱雀院の母后が無理に逢わせまいとなさった時のことなどをお思い出しになるが、目前のことだからであろうか、こちらは普通と変わって、しみじみと心うつのであった。
|
それを前に拡げて、源氏はその雨だれが自分からこぼれ落ちる気もするのであったが、人に悪い想像をさせてはならないと思って、しいておさえていた。昔の尚侍を朱雀院の母后が厳重な監視をして、源氏に逢わせまいとされた時がちょうどこんなのであったと、その当時の苦しさと今を比較して考えてみたが、これは現在のことであるせいか、その時にもまさってやる瀬ないように思われた。
|
【引き広げて】- 場面は六条院に移る。源氏がその返書を広げて。
【玉水のこぼるるやうに】- 玉鬘の返歌にあった「軒の雫」から「玉水のこぼるる」と連想。『河海抄』は「雨止まぬ軒の玉水数知らず恋しきことのまさるころかな」(後撰集恋一、五七八、兼盛)を指摘、『集成』も指摘する。
【人も見ば、うたてあるべし】- 源氏の懸念。
【かの昔の、尚侍の君】- 源氏は、昔の朧月夜尚侍とのことを思い出す。
【朱雀院の后】- 朱雀院の母后、すなわち弘徽殿の大后をさす。
【取り籠めたまひし折】- 弘徽殿の大后が朧月夜尚侍を閉じ込めなさった時。過去の助動詞「し」によって、自らの体験を思い起こしている表現。
【さしあたりたることなればにや】- 語り手の挿入句。「なれ」(断定の助動詞)「ば」(係助詞)「に」(断定の助動詞)「や」(係助詞)。~であればであろうか、という疑問の主体は語り手である。
【ぞあはれなりける】- しみじみと心打つのであった。過去の助動詞「けり」によって、客観的に源氏の心を語る。
|
| 4.8.2 |
「好いたる人は、心からやすかるまじきわざなりけり。今は何につけてか心をも乱らまし。似げなき恋のつまなりや」 |
「色好みの人は、本心から求めて物思いの絶えない人なのだ。
今は何のために心を悩まそうか。
似つかわしくない恋の相手であるよ」
|
好色な男はみずから求めて苦しみをするものである、もうこんなことに似合わしくない自分でないか
|
【好いたる人は】- 以下「つまなりや」まで源氏の心。多感なる自分の「色好み」の性分を述懐する。
|
| 4.8.3 |
|
と、冷静になるのに困って、お琴を掻き鳴らして、やさしくしいてお弾きになった爪音が、思い出さずにはいらっしゃれない。
和琴の調べを、すが掻きにして、
|
と源氏は思って、忘れようとする心から琴を弾いてみたが、なつかしいふうに弾いた玉鬘の爪音がまた思い出されてならなかった。和琴を清掻きに弾いて、
|
【御琴】- 和琴。下に「東の調べ」とある。
【弾きなしたまひし爪音】- 過去の助動詞「し」で叙述。源氏の体験に添った語り方。「常夏」巻に語られた。
|
| 4.8.4 |
|
「玉藻はお刈りにならないで」
|
「玉藻はな刈りそ」
|
【玉藻はな刈りそ】- 「鴛鴦たかべ鴨さへ来居る原の池のや玉藻は真根な刈りそや生ひも継ぐがにや生ひも継ぐがに」(風俗歌・鴛鴦)の一節。
|
| 4.8.5 |
|
と、謡い興じていらっしゃるのも、恋しい人に見せたならば、感動せずにはいられないご様子である。
|
と歌っているこのふうを、恋しい人に見せることができたなら、どんな心にも動揺の起こらないことはないであろうと思われた。
|
【恋しき人に】- 玉鬘をさす。
|
| 4.8.6 |
内裏にも、ほのかに御覧ぜし御容貌ありさまを、心にかけたまひて、 |
帝におかせられても、わずかに御覧あそばしたご器量ご様子を、お忘れにならず、
|
帝もほのかに御覧になった玉鬘の美貌をお忘れにならずに、
|
【内裏にも】- 以下、場面は宮中の帝に移る。
|
| 4.8.7 |
|
「赤裳を垂れ引いて去っていってしまった姿を」
|
「赤裳垂れ引きいにし姿を」(立ちて思ひゐてもぞ思ふくれなゐの赤裳垂れ引き)
|
【赤裳垂れ引き去にし姿を】- 「立ちて思ひ居てもぞ思ふ紅の赤裳垂れ引き去にし姿を」(古今六帖五、裳、三三三三)の下の句。
|
| 4.8.8 |
|
と、耳馴れない古歌であるが、お口癖になさって、物思いに耽っておいであそばすのであった。
お手紙は、そっと時々あるのであった。
わが身を不運な境遇と思い込みなさって、このような軽い気持ちのお手紙のやりとりも、似合わなくお思いになるので、うち解けたお返事も申し上げなさらない。
|
という古歌は露骨に感情を言っただけのものであるが、それを終始お口ずさみになって物思いをあそばされた。お手紙がそっと何通も尚侍の手へ来た。玉鬘はもう自身の運命を悲観してしまって、こうした心の遊びも不似合いになったもののように思い、御好意に感激したようなお返事は差し上げないのであった。
|
【憎げなる古事なれど】- 語り手の判断を介在させた挿入句。
【眺めさせたまひける】- 帝は物思いに耽りあそばすのであった。この段はすべて過去の助動詞「けり」で叙述される。
【身を憂きものに思ひしみたまひて】- 場面は転じて、玉鬘に変わる。玉鬘はわが身を不運な運命と思い込みなさって。
【かやうの】- 大島本は「かやの」とある。諸本に従って「う」を補訂する。
|
| 4.8.9 |
|
やはり、あの、またとないほどであったお心配りを、何かにつけて深くありがたく思い込んでいらっしゃるお気持ちが、忘れられないのであった。
|
玉鬘は今になって源氏が清い愛で一貫してくれた親切がありがたくてならなかった。
|
【かの、ありがたかりし御心おきて】- 源氏の御配慮をさす。玉鬘にとって「あの」と想起され、「し」(過去の助動詞)というように追憶される。
【忘られざりける】- 玉鬘は忘れることができないのであった。この段終わり。
|
|
第九段 三月、源氏、玉鬘を思う
|
| 4.9.1 |
|
三月になって、六条殿の御前の、藤、山吹が美しい夕映えを御覧になるにつけても、まっさきに見る目にも美しい姿でお座りになっていらしたご様子ばかりが思い出さずにはいらっしゃれないので、春の御前を放って、こちらの殿に渡って御覧になる。
|
三月になって、六条院の庭の藤や山吹がきれいに夕映えの前に咲いているのを見ても、まずすぐれた玉鬘の容姿が忍ばれた。南の春の庭を捨てておいて、源氏は東の町の西の対に来て、さらに玉鬘に似た山吹をながめようとした。
|
【三月になりて】- 晩春、いよいよ玉鬘の山吹の花のイメージにぴったりの季節となる。舞台は六条院。
【見たまふにつけても】- 主語は源氏。
【ゐたまへりし御さま】- 玉鬘の座っていらした御様子。過去の助動詞「し」で回想される。
【こなたに渡りて】- 六条院の夏の御殿、西の対。もと、玉鬘がいた部屋。
|
| 4.9.2 |
|
呉竹の籬に、自然と咲きかかっている色艶が、たいそう美しい。
|
竹のませ垣に、自然に咲きかかるようになった山吹が感じよく思われた。
|
【呉竹の籬に、わざとなう咲きかかりたるにほひ】- 呉竹の籬に自然と咲きかかっている山吹の花の色艶。
|
| 4.9.3 |
|
「色に衣を」
|
「思ふとも恋ふとも言はじ山吹の色に衣を染めてこそ着め」
|
【色に衣を】- 『河海抄』は「梔子の色に衣を染めしより言はで心にものをこそ思へ」(河海抄所引古今六帖五くちなし)を指摘し、『全書』『対校』『集成』がこの和歌を指摘する。また『弄花抄』は「思ふとも恋ふとも言はじ梔子の色に衣を染めてこそ着め」(古今六帖五、くちなし、三五〇八)を指摘し、『評釈』『全集』『集成』がこの和歌を指摘する。「梔子」で染めた色は黄色、山吹の花から連想され、さらにこの和歌へと連想が及ぶ。前者の和歌では下の句に、また後者の和歌では上の句にそれぞれ源氏の気持ちがこめられている。
|
| 4.9.4 |
などのたまひて、
|
などとおっしゃって、
|
この歌を源氏は口ずさんでいた。
|
|
| 4.9.5 |
|
「思いがけずに二人の仲は隔てられてしまったが
心の中では恋い慕っている山吹の花よ
|
思はずも井手の中みち隔つとも
言はでぞ恋ふる山吹の花
|
【思はずに井手の中道隔つとも--言はでぞ恋ふる山吹の花】- 源氏の独詠歌。玉鬘への絶ちがたい恋情を訴えた内容。「井手の中道」は山吹の名所の井手へ通じる道。和歌に数多く詠まれた地名、歌枕。山城国綴喜郡井手町。
|
| 4.9.6 |
|
面影に見え見えして」
|
とも言っていた。
|
【顔に見えつつ】- 『河海抄」は「夕されば野辺に鳴くてふかほ鳥の顔に見えつつ忘られなくに」(古今六帖六、かほどり、四四八八)を指摘。現行の注釈書でも指摘する。
|
| 4.9.7 |
|
などとおっしゃっても、聞く人もいない。
このように、さすがに諦めていることは、今になってお分かりになるのであった。
なるほど、妙なおたわむれの心であるよ。
|
「夕されば野辺に鳴くてふかほ鳥の顔に見えつつ忘られなくに」などとも口にしていたが、ここにはだれも聞く人がいなかった。こんなふうに徹底的に恋人として玉鬘を思うことはこれが初めてであった。風変わりな源氏の君と言わねばならない。
|
【などのたまふも、聞く人なし】- 「も」は逆接の接続助詞。他人に聞かれては困る内容だが、幸いにそれを聞いている者がいないというニュアンス。『完訳』は「聞いてくれる人がいるわけでもない」というニュアンスで訳す。
【げに、あやしき御心のすさびなりや】- 語り手の批評。『林逸抄』は「双紙也」と注し、『評釈』も「ねえ、そうでしょう、と語り手は、作者は、読者に言うのである」、『全集』は「語り手の評、草子地」、『完訳』でも「語り手の評言。源氏自身の述懐とも呼応」と注す。なお、『一葉抄』は「かくさすがに」以下を「双紙詞也」と注す。
|
| 4.9.8 |
かりの子のいと多かるを御覧じて、柑子、橘などやうに紛らはして、わざとならずたてまつれたまふ。御文は、「あまり人もぞ目立つる」など思して、すくよかに、 |
鴨の卵がたいそうたくさんあるのを御覧になって、柑子や、橘などのように見せて、何気ないふうに差し上げなさる。
お手紙は、「あまり人目に立っては」などとお思いになって、そっけなく、
|
雁の卵がほかからたくさん贈られてあったのを源氏は見て、蜜柑や橘の実を贈り物にするようにして卵を籠へ入れて玉鬘へ贈った。手紙もたびたび送っては人目を引くであろうからと思って、内容を唯事風に書いた。
|
【あまり人もぞ目立つる】- 「もぞ」は~があってはならないという懸念。あまり鬚黒の目に立ってはいけないの意。
|
| 4.9.9 |
「おぼつかなき月日も重なりぬるを、思はずなる御もてなしなりと恨みきこゆるも、御心ひとつにのみはあるまじう聞きはべれば、ことなるついでならでは、対面の難からむを、口惜しう思ひたまふる」 |
「お目にかからない月日がたちましたが、思いがけないおあしらいだとお恨み申し上げるのも、あなたお一人のお考えからではなく聞いておりますので、特別の場合でなくては、お目にかかることの難しいことを、残念に存じております」
|
お逢いできない月日が重なりました。あまりに同情がないというように恨んではいますが、しかし御良人の御同意がなければ万事あなたの御意志だけではできないことを承知していますから、何かの場合でなければお許しの出ることはなかろうと残念に思っています。
|
【おぼつかなき】- 以下「口惜しう思ひたまふる」まで源氏の文。
【御心ひとつにのみはあるまじう】- あなた一人のお考えだけではないように。夫の鬚黒のせいにしたニュアンス。
|
| 4.9.10 |
など、親めき書きたまひて、
|
などと、親めいてお書きになって、
|
などと親らしく言ってあるのである。
|
|
| 4.9.11 |
|
「せっかくわたしの所でかえった雛が見えませんね
どんな人が手に握っているのでしょう
|
おなじ巣にかへりしかひの見えぬかな
いかなる人か手ににぎるらん
|
【同じ巣にかへりしかひの見えぬかな--いかなる人か手ににぎるらむ】- 源氏の贈歌。「かひ」には「卵(かひ)」と「効」を掛ける。鬚黒が玉鬘を手放さないことを恨んだ歌。
|
| 4.9.12 |
|
どうして、こんなにまでもなどと、おもしろくなくて」
|
そんなにまでせずともとくやしがったりしています。
|
【などか、さしも】- 「さ」は鬚黒が玉鬘を手放さないことをさす。どうしてそこまでする必要があるのかという源氏の恨み。
|
| 4.9.13 |
などあるを、大将も見たまひて、うち笑ひて、
|
などとあるのを、大将も御覧になって、ふと笑って、
|
この手紙を大将も見て笑いながら、
|
|
| 4.9.14 |
「女は、まことの親の御あたりにも、たはやすくうち渡り見えたてまつりたまはむこと、ついでなくてあるべきことにあらず。まして、なぞ、この大臣の、をりをり思ひ放たず、恨み言はしたまふ」 |
「女性は、実の親の所にも、簡単に行ってお会いなさることは、適当な機会がなくてはなさるべきではない。
まして、どうして、この大臣は、度々諦めずに、恨み言をおっしゃるのだろう」
|
「女というものは実父の所へだって理由がなくては行って逢うことをしないものになっているのに、どうしてこの大臣が始終逢えない逢えないと恨んでばかしおよこしになるだろう」
|
【女は】- 以下「恨み言はしたまふ」まで、鬚黒の詞。
【まして】- 親に会うことは適当な機会がなくてはするべきでない、まして実の親でもない人に気軽に会おうなど、とんでもないことだというニュアンス。しかし、「まして」の直接係る語句はない。下の文脈は、別の内容にズレている。
|
| 4.9.15 |
|
と、ぶつぶつ言うのも、憎らしいとお聞きになる。
|
こんな批評めいたことを言うのも、玉鬘には憎く思われた。返事を、
|
【憎しと聞きたまふ】- 玉鬘は鬚黒の不平を憎らしいとお聞きになる。
|
| 4.9.16 |
|
「お返事は、わたしは差し上げられません」
|
「私は書けない」
|
【御返り、ここにはえ聞こえじ】- 玉鬘の詞。わたしはとてもお返事を差し上げられません。
|
| 4.9.17 |
と、書きにくくおぼいたれば、
|
と、書きにくくお思いになっているので、
|
と玉鬘が渋っていると、
|
|
| 4.9.18 |
|
「わたしがお書き申そう」
|
「今日は私がお返事をしよう」
|
【まろ聞こえむ】- 鬚黒の詞。わたしが差し上げよう。
|
| 4.9.19 |
|
と代わるのも、はらはらする思いである。
|
大将が代わろうというのであるから、玉鬘が片腹痛く思ったのはもっともである。
|
【かたはらいたしや】- 語り手の玉鬘に同情した評言。『休聞抄』は「双」と指摘。『集成』も「玉鬘の気持ちを代弁した草子地」。『完訳』は「玉鬘の心に即した、語り手の評」と指摘する。
|
| 4.9.20 |
|
「巣の片隅に隠れて子供の数にも入らない雁の子を
どちらの方に取り隠そうとおっしゃるのでしょうか
|
巣隠れて数にもあらぬ雁の子を
いづ方にかはとりかくすべき
|
【巣隠れて数にもあらぬかりの子を--いづ方にかは取り隠すべき】- 大島本は「とりかへ(へ#く)すへき」とある。すなわち「へ」を抹消して「く」と訂正する。『集成』『古典セレクション』は底本の訂正以前本文と諸本に従って「とりかへす」と整定する。『新大系』は底本の訂正に従って「取り隠す」と整定する。鬚黒が玉鬘に代わって返歌。「かりの子」に「雁の子」と「仮の子」を掛け、「とり」に「鳥」と「取り」を掛ける。
|
| 4.9.21 |
|
不機嫌なご様子にびっくりしまして。
懸想文めいていましょうか」
|
御機嫌をそこねておりますようですからこんなことを申し上げます。風流の真似をいたし過ぎるかもしれません。
|
【よろしからぬ】- 以下「すきずきしや」まで、歌に添えた文。源氏の不機嫌な態度にびっくりいたしまして。「すきずきしきや」は玉鬘に代わって返歌したことに弁解の気持ちを表したもの。
|
| 4.9.22 |
と聞こえたまへり。
|
とお返事申し上げた。
|
大将の書いたものはこうであった。
|
|
| 4.9.23 |
|
「この大将が、このような風流ぶった歌を詠んだのも、まだ聞いたことがなかった。
珍しくて」
|
「この人が戯談風に書いた手紙というものは珍品だ」
|
【この大将の】- 以下「めづらしう」まで源氏の詞。
【かかるはかなしごと】- 玉鬘に代わって返歌したことをさす。
【めづらしう】- 連用中止法。余韻を残した表現。
|
| 4.9.24 |
とて、笑ひたまふ。
心のうちには、かく領じたるを、いとからしと思す。
|
と言って、お笑いになる。
心中では、このように一人占めにしているのを、とても憎いとお思いになる。
|
と源氏は笑ったが、心の中では玉鬘をわが物顔に言っているのを憎んだ。
|
|
|
第五章 鬚黒大将家と内大臣家の物語 玉鬘と近江の君
|
|
第一段 北の方、病状進む
|
| 5.1.1 |
かの、もとの北の方は、月日隔たるままに、あさましと、ものを思ひ沈み、いよいよ呆け疾れてものしたまふ。大将殿のおほかたの訪らひ、何ごとをも詳しう思しおきて、君達をば、変はらず思ひかしづきたまへば、えしもかけ離れたまはず、まめやかなる方の頼みは、同じことにてなむものしたまひける。 |
あの、もとの北の方は、月日のたつにしたがって、あまりな仕打ちだと、物思いに沈んで、ますます気が変になっていらっしゃる。
大将殿の一通りのお世話、どんなことでも細かくご配慮なさって、男の子たちは、変わらずかわいがっていらっしゃるので、すっかり縁を切っておしまいにならず、生活上の頼りだけは、同様にしていらっしゃるのであった。
|
もとの大将夫人は月日のたつにしたがって憂鬱になって、放心状態でいることも多かった。生活費などはこまごまと行き届いた仕送りを大将はしていた。子供たちをも以前と同じように大事がって育てていたから、前夫人の心は良人からまったく離れず唯一の頼みにもしていた。
|
【かの、もとの北の方】- 鬚黒の元の北の方。場面は実家の式部卿宮邸に帰った北の方に転じる。「かのもとの」と表現したところに玉鬘が今の北の方におさまっていることをいう。
【なむものしたまひける】- 過去の助動詞「けり」で叙述。後から補足して語ったニュアンス。
|
| 5.1.2 |
|
姫君を、たまらなく恋しくお思い申し上げなさるが、全然お会わせ申し上げなさらない。
子供心にも、この父君を、誰もが、みな許すことなくお恨み申し上げて、ますます遠ざけることばかりが増えて行くので、心細く悲しいが、男の子たちは、いつも一緒に行き来しているので、尚侍の君のご様子などを、自然と何かにつけて話し出して、
|
大将は姫君を非常に恋しがって逢いたく思うのであったが、宮家のほうでは少しもそれを許さない。少女の心には自身の愛する父を祖父も祖母も皆口をそろえて悪く言い、ますます逢わせてもらう可能性がなくなっていくのを心細がっていた。男の子たちは始終訪ねて来て、尚侍の様子なども話して、
|
【絶えて見せたてまつりたまはず】- 元の北の方は姫君を鬚黒に全然お会わせ申し上げなさらない。
【若き御心のうちに】- 「心細く悲しきに」に係る。
【この父君を、誰れも誰れも】- 以下「のみまされば」は挿入句。
【いよいよ隔てたまふこと】- 式部卿宮が鬚黒をますます疎遠になさること。
【心細く悲しきに】- 「に」は逆接の接続助詞。女君と男君たちが対比されて語られている。
|
| 5.1.3 |
|
「わたしたちをも、かわいがってやさしくして下さいます。
毎日おもしろいことばかりして暮らしていらっしゃいます」
|
「私たちなどもかわいがってくださる。毎日おもしろいことをして暮らしていらっしゃる」
|
【まろらをも】- 以下「ものしたまふ」まで、子供たちの詞。
【明け暮れをかしきことを好みてものしたまふ】- 男の子たちの無邪気な表現である。
|
| 5.1.4 |
|
などと言うと、羨ましくなって、このようにして自由に振る舞える男の身に生まれてこなかったことをお嘆きになる。
妙に、男にも女にも物思いをさせる尚侍の君でいらっしゃるのであった。
|
などと言っているのを夫人は聞いて、うらやましくて、そんなふうな朗らかな心持ちで人生を楽しく見るようなことをすればできたものを、できなかった自身の性格を悲しがっていた。男にも女にも物思いをさせることの多い尚侍である。
|
【など言ふに】- 姉君に。
【うらやましう】- 姫君の心を語り手が叙述。
【かやうにても安らかに振る舞ふ身ならざりけむ】- 姫君の心。「けむ」(過去推量の助動詞)。どうして自由に振る舞える男の子の身に生まれてこなかったのだろう、という悔恨。しかし、これを受ける「と」(格助詞)などの引用の語句がなく、「を」(格助詞、目的)で受け、直接地の文に繋がっている。
【あやしう、男女につけつつ、人にものを思はする尚侍の君にぞおはしける】- 語り手の玉鬘評。『一葉抄』は「双紙の詞なり」と指摘。『評釈』は「玉鬘のせいで心を悩ます者がいた、と作者は言う」。『全集』は「語り手のことば」。『集成』は「草子地」。『完訳』は「語り手の言辞」と指摘する。文末は過去の助動詞「けり」で叙述。以上で、この段を語り収める。
|
|
第二段 十一月に玉鬘、男子を出産
|
| 5.2.1 |
|
その年の十一月に、たいそうかわいい赤子までお生みになったので、大将も、願っていたようにめでたいと、大切にお世話なさること、この上ない。
その時の様子、言わなくても想像できることであろう。
父大臣も、自然に願っていた通りのご運命だとお思いになっていた。
|
その十一月には美しい子供さえも玉鬘は生んだ。大将は何事も順調に行くと喜んで、愛妻から生まれた子供を大事にしていた。産屋の祝いの派手に行なわれた様子などは書かないでも読者は想像するがよい。内大臣も玉鬘の幸福であることに満足していた。
|
【その年の十一月に】- 春の物語から、夏秋を経過して、冬十一月の物語となる。
【いとをかしき稚児をさへ抱き出でたまへれば】- 玉鬘が鬚黒と結婚したのは昨年の冬であった。およそ一年のうちに第一子を誕生。「稚児をさへ」とあるように、鬚黒との結婚生活も順調で安定した趣である。
【そのほどのありさま、言はずとも思ひやりつべきことぞかし】- 語り手の省筆の弁。『一葉抄』は「作者詞也」と指摘。『評釈』は「大将の喜びよう、子供の扱いぶり、申さずともおわかりでしょう、と、作者は急いでいる」。『全集』は「草子地」。『完訳』は「語り手の、省筆の弁」と指摘する。
|
| 5.2.2 |
わざとかしづきたまふ君達にも、御容貌などは劣りたまはず。頭中将も、この尚侍の君を、いとなつかしきはらからにて、睦びきこえたまふものから、さすがなる御けしきうちまぜつつ、 |
特別に大切にお世話なさっているお子様たちにも、ご器量などは劣っていらっしゃらない。
頭中将も、この尚侍の君を、たいそう仲の好い姉弟として、お付き合い申し上げていらっしゃるものの、やはりすっきりしない御そぶりを時々は見せながら、
|
大将の大事にする長男、二男にも今度の幼児の顔は劣っていなかった。頭中将も兄弟としてこの尚侍をことに愛していたが、幸福であると無条件で喜んでいる大臣とは違って、少し尚侍のその境遇を物足りなく考えていた。
|
【劣りたまはず】- 玉鬘の器量は他の異母姉妹にもひけをとらない。
【さすがなる御けしき】- 大島本は「御気しき」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「けしき」と「御」を削除する。やはり諦めきれなきお気持ち。
|
| 5.2.3 |
|
「入内なさって、その甲斐あってのご出産であったらよかったのに」
|
尚侍として君側に侍した場合を想像していて、
|
【宮仕ひに】- 大島本は「宮つかひ」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「宮仕へ」と校訂する。以下「たまはましものを」まで、頭中将(柏木)の心。
【ものしたまはましものを】- 「まし」反実仮想の助動詞。御出産であったらよかったのに。
|
| 5.2.4 |
と、この若君のうつくしきにつけても、
|
と、この若君のかわいらしさにつけても、
|
生まれた大将の三男の美しい顔を見ても、
|
|
| 5.2.5 |
|
「今まで皇子たちがいらっしゃらないお嘆きを拝見しているので、どんなに名誉なことであろう」
|
「今まで皇子がいらっしゃらない所へ、こんな小皇子をお生み申し上げたら、どんなに家門の名誉になることだろう」
|
【今まで皇子たちのおはせぬ嘆きを】- 以下「面目あらまし」まで、頭中将の詞。帝に今まで皇子たちなどがいらっしゃらないお嘆き。
|
| 5.2.6 |
|
と、あまりに身勝手なことを思っておっしゃる。
|
となおこの上のことを言って残念がった。
|
【あまりのことをぞ】- 大島本は「あまりのこと」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「あまりごと」と校訂する。語り手の感想を交えた表現。自分勝手なことをの意。
|
| 5.2.7 |
|
公務は、しかるべく取り仕切っているが、参内なさることは、このままこうして終わってしまいそうである。
それもやむをえないことである。
|
尚侍の公務を自宅で不都合なく執ることにして、玉鬘はもう宮中へ出ることはないだろうと見られた。それでもよいことであった。
|
【やがてかくてやみぬべかめる】- 語り手の判断を交えた表現。出仕なさることはこのまま終わってしまいそうである。『湖月抄』は「公事は」以下を「地」と指摘。『孟津抄』は「やかて」以下を「草子地也」と指摘する。
【さてもありぬべきことなりかし】- 語り手の評言。「細流抄」は「草子地也」と指摘、『全書』『集成』は「草子地」と指摘する。以上で、玉鬘の物語を切り上げる。
|
|
第三段 近江の君、活発に振る舞う
|
| 5.3.1 |
|
そうそう、あの内の大殿のご息女で、尚侍を望んでいた女君も、ああした類の人の癖として、色気まで加わって、そわそわし出して、持て余していらっしゃる。
女御も、「今に、軽率なことが、この君はきっとしでかすだろう」と、何かにつけ、はらはらしていらっしゃるが、大臣が、
|
あの内大臣の令嬢で尚侍になりたがっていた近江の君は、そうした低能な人の常で、恋愛に強い好奇心を持つようになって、周囲を不安がらせた。女御も一家の恥になるようなことを近江の君が引き起こさないかと、そのことではっとさせられることが多く、神経を悩ませていたが、大臣から、
|
【まことや】- 話題転換の発語。話題は近江の君の物語にうつる。
【尚侍のぞみし君も】- 近江の君。「行幸」巻(第三章六段)に見える。
【さるものの癖なれば】- 大島本は「さるをゝくせなれは」とある。大島本の誤写である。『集成』『古典セレクション』『新大系』は諸本に従って「さるものの癖なれば」に改める。語り手の感想を交えた表現。ああした類の人の癖としてのニュアンス。『集成』は「そうした賎しい生れの者の性としてよくあることなので」と注す。
【もてわづらひたまふ】- 内大臣は近江の君をもてあましていらっしゃる。
|
| 5.3.2 |
|
「今後は、人前に出てはいけません」
|
「もう女御の所へ行かないように」
|
【今は、なまじらひそ】- 内大臣が近江の君を制した詞。
|
| 5.3.3 |
|
と、戒めておっしゃるのさえ聞き入れず、人中に出て仕えていらっしゃる。
|
と止められているのであったが、やはり出て来ることをやめない。
|
【まじらひ出でてものしたまふ】- 近江の君は人中に出て仕えていらっしゃる。
|
| 5.3.4 |
|
どのような時であったろうか、殿上人が大勢、立派な方々ばかりが、この女御の御方に参上して、いろいろな楽器を奏して、くつろいだ感じの拍子を打って遊んでいる。
秋の夕方の、どことなく風情のあるところに、宰相中将もお寄りになって、いつもと違ってふざけて冗談をおっしゃるのを、女房たちは珍しく思って、
|
どんな時であったか、女御の所へ殿上役人などがおおぜい来ていて選りすぐったような人たちで音楽の遊びをしていたことがあった。源宰相中将も来ていて、平生と違って気軽に女房などとも話しているのを、ほかの女房たちが、
|
【いかなる折にかありけむ】- 語り手の疑問を挿入した文。『完訳』は「一つの挿話を語り出す語り口」と注す。
【秋の夕べのただならぬに】- 『集成』『完訳』は「秋はなほ夕まぐれこそただならね荻の上風萩の下風」(和漢朗詠集巻上、秋興、二二九、藤原義孝)を指摘。近江の君の物語は、秋に遡った物語である。
【宰相中将】- 夕霧。
【例ならず乱れてものなどのたまふを】- 『集成』『完訳』は「いつとても恋しからずはあらねども秋の夕べはあやしかりけり」(古今集恋一、五四六、読人しらず)を指摘する。
|
| 5.3.5 |
|
「やはり、どの人よりも格別だわ」
|
「やはり出抜けていらっしゃる方」
|
【なほ、人よりことにも】- 女房の詞。
|
| 5.3.6 |
とめづるに、この近江の君、人びとの中を押し分けて出でゐたまふ。
|
と誉めると、この近江の君、女房たちの中を押し分けて出ていらっしゃる。
|
とも評していた時に、近江の君は女房たちの座の中を押し分けるようにして御簾の所へ出ようとしていた。女房らは危険に思って、
|
|
| 5.3.7 |
|
「あら、嫌だわ。
これはどうなさるおつもり」
|
「あさはかなことをお言い出しになるのじゃないかしら」
|
【あな、うたてや。こはなぞ】- 女房の制止する詞。
|
| 5.3.8 |
と引き入るれど、いとさがなげににらみて、張りゐたれば、わづらはしくて、
|
と引き止めるが、たいそう意地悪そうに睨んで、目を吊り上げているので、厄介になって、
|
とひそかに肱で言い合ったが、近江の君はこのまれな品行方正な若公達を指さして、
|
|
| 5.3.9 |
|
「軽率なことを、おっしゃらないかしら」
|
「これでしょう、これでしょう」
|
【あうなきことや、のたまひ出でむ】- 女房の詞。「あうなき」は「奥なき」。
|
| 5.3.10 |
と、つき交はすに、この世に目馴れぬまめ人をしも、
|
と、お互いにつつき合っていると、この世にも珍しい真面目な方を、
|
と言って源中将のきれいであることをほめて
|
|
| 5.3.11 |
|
「この人よ、この人よ」
|
|
【これぞな、これぞな」--と】- 大島本は「これそなゝと」とある。「な」と「と」の間の踊り字を「ゝ」とみるか「/\」とみるかの違い。大島本は「ゝ」に読める。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「これぞなこれぞな」と校訂する。近江の君の詞。
|
| 5.3.12 |
|
と誉めて、小声で騷ぎ立てる声、まことにはっきり聞こえる。
女房たち、とても困ったと思うが、声はとてもはっきりした調子で、
|
騒ぐ声が外の男の座へもよく聞こえるのであった。女房たちが困って苦しんでいる時、高く声を張り上げて、近江の君が、
|
【声いとさはやかにて】- 近江の君の声はとてもはっきりした調子で。
|
| 5.3.13 |
|
「沖の舟さん。寄る所がなくて波に漂っているなら
わたしが棹さして近づいて行きますから、
|
「おきつ船よるべ浪路にただよはば
棹さしよらん泊まりをしへよ
|
【沖つ舟よるべ波路に漂はば--棹さし寄らむ泊り教へよ】- 近江の君の夕霧への贈歌。「沖つ舟」に夕霧を喩える。「なみ」は「寄る辺なみ」(寄る辺がないのでの意)と「波路」の掛詞。「漂はば」は夕霧と雲居雁との結婚が決まっていないことをいう。「棹さし寄らむ」は自分の方から近寄って行こうの意。
|
| 5.3.14 |
|
棚なし小舟みたいに、いつまでも一人の方ばかり思い続けていらっしゃるのね。
あら、ごめんなさい」
|
『たななし小舟漕ぎかへり』(同じ人にや恋ひやわたらん)いけないわね」
|
【棚なし小舟漕ぎ返り、同じ人をや】- 「堀江漕ぐ棚なし小舟漕ぎかへり同じ人にや恋ひわたりなむ」(古今集恋四、七三二、読人しらず)の第二句から第四句まで引用する。引き過ぎであるところが近江の君らしく普通と変わっている。以下「あな悪や」まで和歌に添えた文。
|
| 5.3.15 |
と言ふを、いとあやしう、
|
と言うので、たいそう不審に思って、
|
と言った。源中将は異様なことであると思った。
|
|
| 5.3.16 |
「この御方には、かう用意なきこと聞こえぬものを」と思ひまはすに、「この聞く人なりけり」 |
「こちらの御方には、このようなぶしつけなこと、聞かないのに」と思いめぐらすと、「あの噂の姫君であったのか」
|
女御の所には洗練された女房たちがそろっているはずで、こうした露骨な戯れを言いかける人はないわけであると思って、考えてみるとそれは噂に聞いた令嬢であった。
|
【この御方には】- 以下「聞こえぬものを」まで夕霧の心。
|
| 5.3.17 |
と、をかしうて、
|
と、おもしろく思って、
|
|
|
| 5.3.18 |
|
「寄る所がなく風がもてあそんでいる舟人でも
思ってもいない所には磯伝いしません」
|
よるべなみ風の騒がす船人も
思はぬ方に磯づたひせず
|
【よるべなみ風の騒がす舟人も--思はぬ方に磯伝ひせず】- 夕霧の返歌。「なみ」は「寄る辺なみ」(寄る辺がないのでの意)と「波風」の掛詞。「舟人」は自分を喩える。「思はぬ方」は近江の君を喩える。
|
| 5.3.19 |
|
とおっしゃったので、引っ込みがつかなかったであろう、とか。
|
と源中将に言われた。「そんなことをしては恥知らずです」とも。
|
【とて、はしたなかめり、とや】- 「とて」はと応えての意。「はしたなかめり」との間にやや飛躍がある。語り手は物語の世界から享受者の世界に移動して語る。「とや」は語り手のこの巻の語り収めのことば。「~とかいう話です」と結ぶ。『湖月抄』は「とて」に「地」、『岷江入楚』所引「或抄」は「はしたなかめりとや」に「御説草子地」と注し、『集成』は「その場に居合わせた女房の感想を伝える趣で巻を閉じる技巧」と注す。
|
| 著作権 |
| 底本 |
大島本 |
| 校訂 |
Last updated 2/6/2010(ver.2-2)
渋谷栄一校訂(C)
オリジナル
修正版
比較 |
| ローマ字版 |
Last updated 2/18/2010 (ver.2-2)
Written in Japanese roman letters
by Eiichi Shibuya (C)
オリジナル
修正版
比較 |
ルビ抽出
(ローマ字版から)
|
Powered by 再編集プログラム v4.05
ひらがな版
ルビ抽出 |
挿絵
(ローマ字版から)
|
'Eiri Genji Monogatari'
(1650 1st edition) |
|
Last updated 9/29/2001
渋谷栄一訳(C)(ver.1-2-2)
オリジナル
修正版
比較 |
|
|
Last updated 2/18/2010(ver.2-2)
渋谷栄一注釈(C)
オリジナル
修正版
比較 |
|