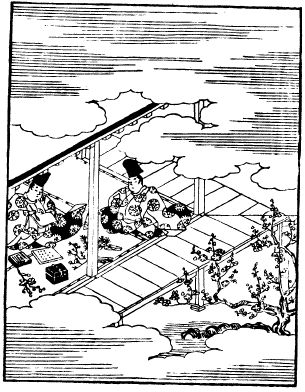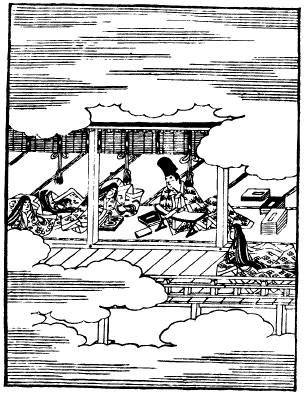第三十二帖 梅枝
光る源氏の太政大臣時代三十九歳一月から二月までの物語
|
# |
本文 |
渋谷栄一訳 |
与謝野晶子訳 |
注釈 |
|
第一章 光る源氏の物語 薫物合せ
|
|
第一段 六条院の薫物合せの準備
|
| 1.1.1 |
|
御裳着の儀式、ご準備なさるお心づかい、並々ではない。
春宮も同じ二月に、御元服の儀式がある予定なので、そのまま御入内も続くのであろうか。
|
源氏が十一歳の姫君の裳着の式をあげるために設けていたことは並み並みの仕度でなかった。東宮も同じ二月に御元服があることになっていたが、姫君の東宮へはいることもまた続いて行なわれて行くことらしい。
|
【御裳着のこと、思しいそぐ御心おきて、世の常ならず】- 明石姫君の裳着。明石姫君、十一歳。裳着の儀式は女性の成人式。
【春宮も同じ二月に、御かうぶりのことあるべければ】- 朱雀院の皇子、十三歳。元服は男性の成人式。明石姫君と東宮が共に成人式を挙げ結婚の準備に入る。
【やがて御参りもうち続くべきにや】- 「御参り」は入内をいう。「べき」(推量の助動詞)「に」(断定の助動詞)「や」(係助詞、疑問の意)は語り手の推測を表す。
|
| 1.1.2 |
|
正月の月末なので、公私ともにのんびりとした頃に、薫物合わせをなさる。
大宰大弐が献上したいくつもの香を御覧になると、「やはり、昔の香には劣っていようか」とお思いになって、二条院の御倉を開けさせなさって、唐の品々を取り寄せなさって、ご比較なさると、
|
一月の末のことで、公私とも閑暇な季節に、源氏は薫香の調合を思い立った。大弐から贈られてあった原料の香木類を出させてみたが、これよりも以前に渡って来た物のほうがあるいはよいかもしれぬという疑問が生じて、二条の院の倉をあけさせて、支那から来た物を皆六条院へ持って来させたのであったが、源氏はそれらと新しい物とを比較してみた。
|
【正月の晦日なれば】- 時節は春正月の下旬。正月の年中行事なども終わってのんびりとしたころ。
【大弐の奉れる香ども】- 太宰大弍は系図不詳の人。源氏に献上した香。中国舶来の品である。
【御覧ずるに】- 主語は源氏。
【なほ、いにしへのには劣りてやあらむ】- 源氏の感想。今のものより昔のものがよかったとする尚古思想が窺える。
|
| 1.1.3 |
|
「錦、綾なども、やはり古い物が好ましく上品であった」
|
「織物などもやはり古い物のほうに芸術的なものが多い」
|
【錦、綾なども、なほ古きものこそなつかしうこまやかにはありけれ】- 源氏の感想。「なつかし」は、手放したくない、慕わしいの意。昔が思い出されるの意は後世。しかし文脈上「古きものこそなつかしう」とあるから、一種の懐古趣味。
|
| 1.1.4 |
|
とおっしゃって、身近な調度類の、物の覆いや、敷物、座蒲団などの端々に、故院の御代の初め頃、高麗人が献上した綾や、緋金錦類など、今の世の物には比べ物にならず、さらにいろいろとご鑑定なさっては、今回の綾、羅などは、女房たちにご下賜なさる。
|
といって、式場用の物の覆、敷き物、褥などの端を付けさせるものなどに、故院の御代の初めに朝鮮人が献げた綾とか、緋金錦とかいう織物で、近代の物よりもすぐれた味わいを持った切れ地のそれぞれの使い場所を決めたりした。今度大弐のほうから来た綾や薄物は他へ分けて贈った。
|
【故院の御世の初めつ方】- 桐壷院をさす。
【このたびの綾、羅などは】- 大弍が献上した品物をいう。
|
| 1.1.5 |
香どもは、昔今の、取り並べさせたまひて、御方々に配りたてまつらせたまふ。
|
数々の香は、昔のと今のを、取り揃えさせなさって、ご夫人方にお配り申し上げさせなさる。
|
香の原料に昔のと今のとを両方取り混ぜて六条院内の夫人たちと、源氏の尊敬する女友だちに送って、
|
|
| 1.1.6 |
|
「二種類づつ調合なさって下さい」
|
二種類ずつの薫香を作られたい
|
【二種づつ合はせさせたまへ】- 源氏の言葉。使者に言わせた内容。「させ」「給へ」二重敬語。会話文中の用法。
|
| 1.1.7 |
|
と、お願い申し上げさせなさった。
贈物や、上達部への禄など、世にまたとないほどに、内にも外にも、お忙しくお作りなさるに加えて、それぞれに材料を選び準備して、鉄臼の音が喧しく聞こえる頃である。
|
と告げた。裳着の式日の贈り物、高官たちへの纏頭の衣服類の製作を手分けして各夫人の所でしているかたわらで、またそれぞれ撰び出した香の原料の鉄臼でひかれる音も立って忙しい気のされるころであった。
|
【聞こえさせたまへり】- 「聞こえ」(「言う」の謙譲語)「させ」(使役の助動詞)「給へ」(尊敬の補助動詞)「り」(完了の助動詞)。使者をして御夫人方に申し上げさせなさったの意。
【内にも外にも】- 「内」は六条院、「外」は二条院、二条東院などをさす。
【かしかまし】- 「姦 カシカマシ」(名義抄)。近世以後「かしがまし」と濁音化する。
|
| 1.1.8 |
|
大臣は、寝殿に離れていらっしゃって、承和の帝の御秘伝の二つの調合法を、どのようにしてお耳にお伝えなさったのであろうか、熱心にお作りになる。
|
源氏は南の町の寝殿へ、夫人の所から離れてこもりながら、どうして習得したのか承和の帝の秘法といわれる二つの合わせ方で熱心に薫香を作っていた。
|
【承和の御いましめの二つの方を】- 承和の御戒め。仁明天皇が男子には伝えぬようにと戒めた二種の調合法。「黒方」と「侍従」である。『河海抄』所引「合香秘方」に「此両種方不伝男耳。承和仰事也」とある。
【いかでか御耳には伝へたまひけむ】- 語り手の疑問、挿入句。
|
| 1.1.9 |
|
紫の上は、東の対の中の放出に、御設備を特別に厳重におさせになって、八条の式部卿の御調合法を伝えて、互いに競争して調合なさっている間に、たいそう秘密にしていらっしゃるので、
|
夫人は東の対のうちの離れへ人を避ける設備をして、そこで八条の式部卿の宮の秘伝の法で香を作っていた。
|
【上は、東の中の放出に】- 紫の上をいう。「上」という呼称。
【御しつらひことに深う】- 『完訳』は「秘法保持のため格別に慎重」と注す。
【しなさせたまひて】- 「させ」使役の助動詞。女房らをして準備させなさって。
【八条の式部卿の御方を】- 仁明天皇の第七皇子本康親王。「御方」は黒方と侍従をさす。
【かたみに挑み合はせたまふほど】- 源氏と紫の上。
|
| 1.1.10 |
|
「匂いの深さ浅さも、勝負けの判定にしよう」
|
こうして夫婦の中にも、秘密をうかがわれまいと苦心する香の優劣を勝負にしよう
|
【匂ひの深さ浅さも、勝ち負けの定めあるべし】- 源氏の言葉。
|
| 1.1.11 |
|
と大臣がおっしゃる。
子を持つ親御らしくない競争心である。
|
と言っていた。姫君の親である人たちらしくない競争である。
|
【人の御親げなき御あらそひ心なり】- 語り手の評言。『一葉抄』が「草子詞也」と指摘。「人」は明石の姫君をさす。
|
| 1.1.12 |
いづ方にも、御前にさぶらふ人あまたならず。御調度どもも、そこらのきよらを尽くしたまへるなかにも、香壺の御筥どものやう、壺の姿、火取りの心ばへも、目馴れぬさまに、今めかしう、やう変へさせたまへるに、所々の心を尽くしたまへらむ匂ひどもの、すぐれたらむどもを、かぎあはせて入れむと思すなりけり。 |
どちらにも、御前に伺候する女房は多くいない。
御調度類も、多く善美を尽くしていらっしゃる中でも、いくつもの香壷の御箱の作り具合、壷の恰好、香炉の意匠も、見慣れない物で、当世風に、趣向を変えさせていらっしゃるのが、あちらこちらで一生懸命にお作りになったような香の中で、優れた幾種かを、匂いを比べた上で入れようとお考えなのである。
|
どの夫人の所にもこの調合の室に侍している女房は選ばれた少数の者であった。式用の小道具を精巧をきわめて製作させた中でも、特に香合の箱の形、壺、火入れの作り方に源氏は意匠を凝らさせていたが、その壺へ諸所でできた中のすぐれた薫香を、試みた上で入れようと思っているのであった。
|
【調度】- 『色葉字類抄』には「調」「度」ともに濁点を付す。『集成』「でうど」のルビを付ける。
【所々の心を尽くしたまへらむ】- あちらこちらで一生懸命に薫物を調合していらっしゃるであろう。「らむ」は推量の助動詞、視界外推量の意。源氏の所から推量するニュアンス。
|
|
第二段 二月十日、薫物合せ
|
| 1.2.1 |
|
二月の十日、雨が少し降って、御前近くの紅梅の盛りに、色も香も他に似る物がない頃に、兵部卿宮がお越しになった。
御裳着の支度が今日明日に迫ってお忙しいことについて、ご訪問なさる。
昔から特別にお仲が好いので、隠し隔てなく、あの事この事、とご相談なさって、紅梅の花を賞美なさっていらっしゃるところに、前斎院からと言って、散って薄くなった梅の枝に結び付けられているお手紙を持ってまいった。
宮、お聞きになっていたこともあるので、
|
二月の十日であった。雨が少し降って、前の庭の紅梅が色も香もすぐれた名木ぶりを発揮している時に、兵部卿の宮が訪問しておいでになった。裳着の式が今日明日のことになっているために、心づかいをしている源氏に見舞いをお述べになった。昔からことに仲のよい御兄弟であったから、いろいろな御相談をしながら花を愛していた時に、前斎院からといって、半分ほど花の散った梅の枝に付けた手紙がこの席へ持って来られた。宮は源氏と前斎院との間に以前あった噂も知っておいでになったので、
|
【二月の十日、雨すこし降りて、御前近き紅梅盛りに、色も香も似るものなきほどに】- 二月十日、六条院に蛍兵部卿宮参上し、薫物合せを試みる。
【兵部卿宮渡りたまへり】- 源氏の弟宮蛍兵部卿宮。趣味人、風流人である。
【御いそぎの今日明日になりにけることども、訪らひきこえたまふ】- 大島本「こととも」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「ことと」と校訂する。明石の姫君の裳着の儀式が間近に迫ったことへの挨拶に参上。
【花をめでつつ】- 「花」は紅梅をさす。
【前斎院】- 朝顔斎院をさす。
【散りすきたる梅の枝につけたる御文】- 『異本紫明抄』は「春過ぎて散りはてにける梅の花ただ香ばかりぞ枝に残れる」(拾遺集雑春、一〇六三、如覚法師)を指摘する。その歌の詞書に「比叡の山に住みはべりけるころ、人の薫物を乞ひてはべりければ、はべりけるまゝに、少しを、梅の花のわづかに散り残りてはべる枝につけてつかはしける」とある。その趣向を踏まえる。『集成』は「散り過ぎたる」と解し、『新大系』『古典セレクション』は「散りすきたる」と解す。
【聞こしめすこともあれば】- 源氏が朝顔姫君に執心であったということ。「朝顔」巻に語られている。
|
|
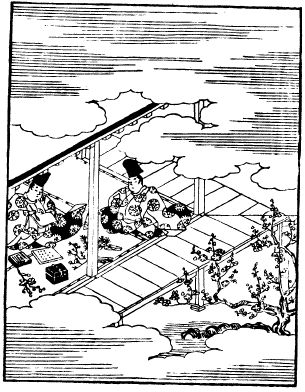 |
| 1.2.2 |
|
「どのようなお手紙があちらから参ったのでしょうか」
|
「どんなおたよりがあちらから来たのでしょう」
|
【いかなる御消息のすすみ参れるにか】- 蛍兵部卿宮の詞。
|
| 1.2.3 |
とて、をかしと思したれば、ほほ笑みて、
|
とおっしゃって、興味をお持ちになっているので、にっこりして、
|
とお言いになって、好奇心を起こしておいでになるふうの見えるのを、源氏はただ、
|
|
| 1.2.4 |
|
「たいそう無遠慮なことをお願い申し上げたところ、几帳面に急いでお作りになったのでしょう」
|
「失礼なお願いを私がしましたのを、すぐにその香を作ってくだすったのです」
|
【いと馴れ馴れしき】- 以下「たまへるなめり」まで、源氏の返事。薫物合せの依頼をさす。「いと馴れ馴れしきこと」(大層無遠慮なこと)と謙辞する。「を」接続助詞、順接の意。「な」(断定の助動詞)「めり」(推量の助動詞)。
|
| 1.2.5 |
とて、御文は引き隠したまひつ。
|
とおっしゃって、お手紙はお隠しになった。
|
こう言って、お手紙は隠してしまった。
|
|
| 1.2.6 |
|
沈の箱に、瑠璃の香壷を二つ置いて、大きく丸めてお入れになってある。
心葉は、紺瑠璃のには五葉の枝を、白いのには白梅を彫って、同じように結んである糸の様子も、優美で女性的にお作りになってある。
|
沈の木の箱に瑠璃の脚付きの鉢を二つ置いて、薫香はやや大きく粒に丸めて入れてあった。贈り物としての飾りは紺瑠璃のほうには五葉の枝、白い瑠璃のほうには梅の花を添えて、結んである糸も皆優美であった。
|
【瑠璃の坏二つ据ゑて】- 紺瑠璃と白瑠璃の坏、二脚。前者に黒方、後者に梅花香が入れてある。
【梅を選りて】- 古来二説あり、『集成』は「選りて」と解し、『古典セレクション』は「彫りて」と解す。『新大系』は仮名表記「えりて」とし、「古来、「彫(ゑ)りて」、「選りて」両説あり。「彫りて」は、彫金の心葉をいう」と注する。
【なよびやかに】- 大島本は「なよひやかに」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「なよびかに」と校訂する。
|
| 1.2.7 |
|
「優雅な感じのする出来ばえですね」
|
「艶にできていますね」
|
【艶あるもののさまかな】- 大島本は「えんある」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「艶なる」と校訂する。蛍兵部卿宮の詞。感嘆の気持ち。
|
| 1.2.8 |
|
とおっしゃって、お目を止めなさると、
|
と宮は言って、ながめておいでになったが、
|
【御目止めたまへるに】- 大島本は「とめ」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「とどめ」と校訂する。
|
| 1.2.9 |
|
「花の香りは散ってしまった枝には残っていませんが、
香を焚きしめた袖には深く残るでしょう
|
花の香は散りにし袖にとまらねど
うつらん袖に浅くしまめや
|
【花の香は散りにし枝にとまらねど--うつらむ袖に浅くしまめや】- 「散りにし枝」は自分(朝顔)を譬え、「うつらむ袖」は明石姫君を喩える。「浅くしま」「め」(推量の助動詞)「や」(係助詞)、反語表現。浅く薫りましょうか、いや深く薫ることでしょうの意。『集成』は「自分を卑下し、姫君の若さを讃えた歌」という。
|
| 1.2.10 |
ほのかなるを御覧じつけて、宮はことことしう誦じたまふ。 |
薄墨のほんのりとした筆跡を御覧になって、宮は仰々しく口ずさみなさる。
|
という歌が小さく書かれてあるのにお目がついて、わざとらしくお読み上げになった。
|
【ほのかなるを】- 薄墨でうっすらと書いてある筆跡。
|
| 1.2.11 |
|
宰相中将、お使いの者を捜し出して引き止めさせなさって、たいそう酔わせなさる。
紅梅襲の唐の細長を添えた女装束をお与えになる。
お返事も同じ紙の色で、御前の花を折らせてお付けになる。
|
宰相の中将が来た使いを捜させ饗応した。紅梅襲の支那の切れ地でできた細長を添えた女の装束が纏頭に授けられた。返事も紅梅の色の紙に書いて、前の庭の紅梅を切って枝に付けた。
|
【宰相中将】- 夕霧。
【御使尋ねとどめさせたまひて、いたう酔はしたまふ】- 主語は夕霧。「させ」使役の助動詞。
【御返りもその色の紙にて】- 源氏の返事。紅梅襲と同じ色の紙。
【御前の花を折らせてつけさせたまふ】- 紅梅の花。「せ」使役の助動詞。
|
| 1.2.12 |
宮、
|
宮、
|
|
|
| 1.2.13 |
「うちのこと思ひやらるる御文かな。何ごとの隠ろへあるにか、深く隠したまふ」 |
「どんな内容か気になるお手紙ですね。
どのような秘密があるのか、深くお隠しになさるな」
|
「何だか内容の知りたくなるお手紙ですが、なぜそんなに秘密になさるのだろう」
|
【うちのこと】- 以下「隠したまふ」まで、蛍兵部卿宮の心中。「うちのこと」は手紙の中身の意。好奇心と嫉妬心。
|
| 1.2.14 |
と恨みて、いとゆかしと思したり。
|
と恨んで、ひどく見たがっていらっしゃった。
|
と言って、宮は見たがっておいでになる。
|
|
| 1.2.15 |
|
「何でもありません。
秘密があるようにお思いになるのが、かえって迷惑です」
|
「何があるものですか、そんなふうによけいな想像をなさるから困るのです」
|
【何ごとかはべらむ】- 大島本は「なにことか」とある。「新大系』は底本のまま。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「何ごとかは」と「は」を補訂する。以下「苦しけれ」まで、源氏の詞。
|
| 1.2.16 |
とて、御硯のついでに、
|
とおっしゃって、御筆のついでに、
|
と言って、斎院へ今書いた歌をまた紙にしたためて宮へお見せした。
|
|
| 1.2.17 |
|
「花の枝にますます心を惹かれることよ
人が咎めるだろうと隠しているが」
|
花の枝にいとど心をしむるかな
人のとがむる香をばつつめど
|
【花の枝にいとど心をしむるかな--人のとがめむ香をばつつめど】- 源氏の返歌。「花の枝」は朝顔を譬える。ますます魅力を感じるという意。「梅の花立ち寄るばかりありしより人のとがむる香にぞしみぬる」(古今集春上、三五、読人しらず)「梅の花香を吹きかくる春風に心をそめば人やとがめむ」(後撰集春上、三一、読人しらず)
|
| 1.2.18 |
|
とでもあったのであろうか。
|
というのであるらしい。
|
【とやありつらむ】- 語り手の推測。『集成』は「と書いてあったのだろうか。そっと兵部卿の宮に見せた様子を窺わせる書き方。草子地」と注す。『完訳』は「語り手の推測。宮もこの返歌を見ていないことになる」と注す。
|
| 1.2.19 |
|
「実のところ、物好きなようですが、二人といない娘のことですから、こうするのが当然の催しであろうと、存じましてね。
たいそう不器量ですから、疎遠な方にはきまりが悪いので、中宮を御退出おさせ申し上げてと存じております。
親しい間柄でお慣れ申し上げているが、気の置ける点が深くおありの宮なので、何事も世間一般の有様でお見せ申しては、恐れ多いことですから」
|
「少し物好きなようですが、一人娘の成年式だからやむをえないと自分では定めまして、こうした騒ぎをしているのですが、ほめたことではありませんから、ほかの方を頼むことはやめまして、中宮を御所から退出していただいて腰結いをお願いしようと思っています。一家の方になっていらっしゃっても、晴れがましい気のする人格を持っておられますから、並み並みの儀式にしておいてはもったいない気がするのです」
|
【まめやかには、好き好きしきやうなれど】- 以下「かたじけなくてなむ」まで、源氏の詞。『集成』は「(薫物合せなどを方々に依頼するのは)物好きのようですが」の意に解し、『完訳』は「薫物合せへの熱中は物好きに過ぎるようだが、の意」と解す。
【またもなかめる人の上にて】- 明石姫君をさす。
【思ひたまへなしてなむ】- 「たまへ」(謙譲の補助動詞)、主語は源氏。
【いと醜ければ】- 娘の明石姫君の器量をさしていう。源氏の謙辞。
【中宮まかでさせたてまつりて】- 秋好中宮。「させ」(使役の助動詞)「たてまつり」(謙譲の補助動詞)。『完訳』は「姫君を格上げすべく、秋好中宮を裳着の腰結役とする魂胆」と注す。
【思ひたまふる】- 「たまふる」(謙譲の補助動詞、連体中止法)は、言いさした形で含みのあるニュアンス。
【何ごとも世の常にて見せたてまつらむ、かたじけなくてなむ】- 『完訳』は「姫君の裳着、入内に関して」と注する。「世の常」以上のことを源氏は考えていると示唆する。
|
| 1.2.20 |
など、聞こえたまふ。
|
などと、申し上げなさる。
|
などと源氏は言っていた。
|
|
| 1.2.21 |
|
「あやかるためにも、おっしゃるとおり、きっとお考えになるはずのことなのでしたね」
|
「そうですね。あやかる人は選ばねばなりませんね。それにはこの上もない方ですよ」
|
【あえものも、げに、かならず思し寄るべきことなりけり】- 蛍兵部卿宮の詞。「あえもの」は、あやかりもの、の意。「げに」は源氏の真意を理解して発した言葉。おっしゃる通り将来の中宮の位にということなのですね、の意。
|
| 1.2.22 |
と、ことわり申したまふ。
|
と、ご判断申し上げなさる。
|
と宮は源氏の計らいの当を得ていることをお言いになった。
|
|
|
第三段 御方々の薫物
|
| 1.3.1 |
このついでに、御方々の合はせたまふども、おのおの御使して、
|
この機会に、ご夫人方がご調合なさった薫物を、それぞれお使いを出して、
|
前斎院から香の届けられたことと、宮のおいでになったのを機会にして、夫人らの調製した薫香も取り寄せる使いが出された。
|
|
| 1.3.2 |
|
「今日の夕方の雨じめりに試してみよう」
|
「湿りけのある今日の空気が香の試験に適していると思いますから」
|
【この夕暮れのしめりにこころみむ】- 源氏の詞を使者に言わせたもの。
|
| 1.3.3 |
|
とお話申し上げなさっていたので、それぞれに趣向を凝らして差し上げなさった。
|
と言いやられたのである。夫人たちからは、いろいろに作られた香が、いろいろに飾られて来た。
|
【奉りたまへり】- 大島本は「たてまつり」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「奉れ」と校訂する。
|
| 1.3.4 |
|
「これらをご判定ください。
あなたでなくて誰に出来ましょう」
|
「これを審判してください。あなたのほかに頼む人はない」
|
【これ分かせたまへ。誰れにか見せむ】- 源氏の詞。「君ならで誰にか見せむ梅の花色をも香をも知る人ぞ知る」(古今集春上、三八、紀友則)
|
| 1.3.5 |
と聞こえたまひて、御火取りども召して、こころみさせたまふ。
|
と申し上げなさって、いくつもの御香炉を召して、お試しになる。
|
こう源氏は言って、火入れなどを取り寄せて香をたき試みた。
|
|
| 1.3.6 |
|
「知る人というほどの者ではありませんが」
|
「知る人(君ならでたれにか見せむ梅の花色をも香をも知る人ぞ知る)でもないのですがね」
|
【知る人にもあらずや】- 蛍兵部卿宮の返事。「君ならで」歌の文句を引用して答える。
|
| 1.3.7 |
と卑下したまへど、言ひ知らぬ匂ひどもの、進み遅れたる香一種などが、いささかの咎を分きて、あながちに劣りまさりのけぢめをおきたまふ。かのわが御二種のは、今ぞ取う出させたまふ。 |
と謙遜なさるが、何とも言えない匂いの中で、香りの強い物や弱い物の一つなどが、わずかの欠点を識別して、強いて優劣の区別をお付けになる。
あのご自分の二種の香は、今お取り出させになる。
|
と宮は謙遜しておいでになったが、においの繊細なよさ悪さを嗅ぎ分けて、微瑕も許さないふうに詮索され、等級をおつけになろうとするのであった。源氏の二種の香はこの時になってはじめて取り寄せられた。
|
【かのわが御二種のは】- 「承和の御いましめの二つの方」の「黒方」と「侍従」の香。
|
| 1.3.8 |
|
右近の陣の御溝水の辺に埋める例に倣って、西の渡殿の下から湧き出る遣水の近くに埋めさせなさっていたのを、惟光の宰相の子の兵衛尉が、掘り出して参上した。
宰相中将が、受け取って差し上げさせなさる。
宮、
|
右近衛府の溝川のあたりにうずめるということに代えて、西の渡殿の下から流れて出る園の川の汀にうずめてあったのを、惟光宰相の子の兵衛尉が掘って持って来たのである。それを宰相中将が受け取って座へ運んで来た。
|
【右近の陣の御溝水のほとりになずらへて】- 『河海抄』に「承和御時、右近陣の御溝の辺の地にうづまる。後代相伝して其所をたがへず云々」とある。承和の御時になぞらえた趣向。
【惟光の宰相の子の兵衛尉】- 惟光は宰相(参議)に昇進。その子も兵衛尉の任官。初出。
|
| 1.3.9 |
|
「とても難しい判者に任命されたものですね。
とても煙たくて閉口しますよ」
|
「苦しい審判者になったものですよ。第一けむい」
|
【いと苦しき判者にも当たりてはべるかな。いと煙たしや】- 蛍兵部卿宮の素晴しさに辟易した詞。
|
| 1.3.10 |
と、悩みたまふ。同じうこそは、いづくにも散りつつ広ごるべかめるを、人びとの心々に合はせたまへる、深さ浅さを、かぎあはせたまへるに、いと興あること多かり。 |
と、お困りになる。
同じのは、どこにでも伝わって広がっているようだが、それぞれの好みで調合なさった、深さ浅さを、聞き分けて御覧になると、とても興味深いものが数多かった。
|
と宮は苦しそうに言っておいでになった。同じ法が広く伝えられていても、個人個人の趣味がそれに加わってでき上がった薫香のよさ悪さを比較して嗅ぐことは興味の多いものであった。
|
【同じうこそは】- 以下「いと多かり」まで、語り手の推量や判断を交えた叙述。『評釈』は「兵部卿の宮が心に思ったのか、語り手の批評か、作者の言葉か。いずれとも決しがたいところが物語らしい」という。
|
| 1.3.11 |
さらにいづれともなき中に、斎院の御黒方、さいへども、心にくくしづやかなる匂ひ、ことなり。侍従は、大臣の御は、すぐれてなまめかしうなつかしき香なりと定めたまふ。 |
まったくどれと言えない香の中で、斎院の御黒方、そうは言っても、奥ゆかしく落ち着いた匂い、格別である。
侍従の香は、大臣のその御香は、優れて優美でやさしい香りである、とご判定になさる。
|
どれが第一の物とも決められない中にも斎院のお作りになった黒方香は心憎い静かな趣がすぐれていた。侍従香では源氏の製作がすぐれて艶で優美であると宮はお言いになった。
|
【さいへども】- 前斎院が和歌で謙遜していたことをさす。
【すぐれてなまめかしうなつかしき香なり】- 蛍宮の源氏の「侍従」の判定。斎院の黒方は地の文に折り込んで語る。
|
| 1.3.12 |
対の上の御は、三種ある中に、梅花、はなやかに今めかしう、すこしはやき心しつらひを添へて、めづらしき薫り加はれり。 |
対の上の御香は、三種ある中で、梅花の香が、ぱっと明るくて当世風で、少し鋭く匂い立つように工夫を加えて、珍しい香りが加わっていた。
|
紫の女王のは三種あった中で、梅花香ははなやかで若々しく、その上珍しく冴えた気の添っているものであった。
|
【三種ある中に】- 黒方、侍従、梅香をさす。「黒方」は冬の香、「心にくくしづやかなる匂い」。「侍従」は秋の香、「なまめかしくなつかしき香」。「梅花」は春の香、「はなやかに今めかし」とある。
|
| 1.3.13 |
|
「今頃の風に薫らせるには、まったくこれに優る匂いはあるまい」
|
「このごろの微風に焚き混ぜる物としてはこれに越したにおいはないでしょう」
|
【このころの風にたぐへむには、さらにこれにまさる匂ひあらじ】- 蛍宮の梅香に対する批評。梅香方は春の香である。「風にたぐへむ」は「花の香を風のたよりにたぐへてぞ鴬誘ふしるべにはやる」(古今集春上、一三、紀友則)を踏まえる。
|
| 1.3.14 |
とめでたまふ。
|
と賞美なさる。
|
と宮はおほめになる。
|
|
| 1.3.15 |
|
夏の御方におかれては、このようにご夫人方が思い思いに競争なさっている中で、人並みにもなるまいと、煙にさえお考えにならないご気性で、ただ荷葉の香を一種調合なさった。
一風変わって、しっとりした香りで、しみじみと心惹かれる。
|
花散里夫人は皆の競争している中へはいることなどは無理であると、こんなことにまで遺憾なく内気さを見せて、荷葉香を一種だけ作って来た。変わった気分のするなつかしいにおいがそれからは嗅がれた。
|
【夏の御方には】- 花散里をいう。
【煙をさへ思ひ消え】- 「薫物」の縁で「煙」「消え」という。
【荷葉を一種】- 夏の香。「しめやかなる香」「あはれになつかし」とある。
|
| 1.3.16 |
|
冬の御方におかれても、季節季節に基づいた香が決まっているから、負けるのもつまらないとお考えになって、薫衣香の調合法の素晴らしいのは、前の朱雀院のをお学びなさって、源公忠朝臣が、特別にお選び申した百歩の方などを思いついて、世間にない優美さを調合した、その考えが素晴らしいと、どれも悪い所がないように判定なさるのを、
|
冬の夫人である明石の君は、四季を代表する香は決まったものになっているのであるから、冬だけを卑下させておくのもよろしくないと思って、薫衣香の製法の中にも、すぐれた物とされている以前の朱雀院の法を原則にして公忠朝臣が精製したといわれる百歩の処方などを参考として作った物は、製作に払われた苦心の効果の十分に表われた、優美な香を豊かに持たせたものであると、どれにも同情のある批評を宮があそばされるのを、
|
【冬の御方にも】- 明石御方をいう。
【時々によれる匂ひの定まれるに消たれむもあいなし】- 『完訳』は「黒方が冬、侍従が秋、梅花が春、荷葉が夏などと季節が一定。その型どおりの調合では他に圧倒されよう、そこで一趣向を案出」と注す。 【消たれむは】-「は」(係助詞)際立たせるニュアンスが加わる。「消つ」は「薫物」の縁でいう。
【前の朱雀院のをうつさせたまひて、公忠朝臣の、ことに選び仕うまつれりし百歩の方など】- 「させ」(尊敬の助動詞)「たまひ」(尊敬の補助動詞)、最高敬語。『集成』は「前の朱雀院のご調合法を(朱雀院が)お学びあそばして、公忠の朝臣が特に工夫を凝らして献上した百歩の方」と解す。「百歩の方」は薫衣香の調合法の一つ。「なまめかしき」とある。
【世に似ずなまめかしさを取り集めたる、心おきてすぐれたり】- 地の文が蛍の宮の詞に移っている。
|
| 1.3.17 |
|
「当たりさわりのない判者ですね」
|
「八方美人の審判者だ」
|
【心ぎたなき判者なめり】- 源氏の詞。『完訳』は「当りさわりのない批評と冗談にけなす」と注す。
|
| 1.3.18 |
と聞こえたまふ。
|
と申し上げなさる。
|
と言って源氏は笑っていた。
|
|
|
第四段 薫物合せ後の饗宴
|
| 1.4.1 |
|
月が出たので、御酒などをお召し上がりになって、昔のお話などをなさる。
霞んでいる月の光が奥ゆかしいところに、雨上がりの風が少し吹いて、梅の花の香りが優しく薫り、御殿の辺りに何とも言いようもなく匂い満ちて、皆のお気持ちはとてもうっとりしている。
|
月が出てきたので酒が座に運ばれて、宮と源氏は昔の話を始めておいでになった。うるんだ月の光の艶な夜に、雨ののちの風が少し吹いて、花の香があたりを囲んでいた。だれも皆艶な気持ちに酔っていった。
|
【月さし出でぬれば】- 十日の月。夕刻やや早めに出る。
【霞める月の影心にくきを、雨の名残の風すこし吹きて、花の香なつかしきに、御殿のあたり言ひ知らず匂ひ満ちて、人の御心地いと艶あり】- 二月十日の六条院の風情。 【人の御心地いと艶あり】-大島本は「えんあり」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「艶なり」と校訂する。語り手の評言。
|
| 1.4.2 |
蔵人所の方にも、明日の御遊びのうちならしに、御琴どもの装束などして、殿上人などあまた参りて、をかしき笛の音ども聞こゆ。 |
蔵人所の方にも、明日の管弦の御遊の試演に、お琴類の準備などをして、殿上人などが大勢参上して、美しい幾種もの笛の音が聞こえて来る。
|
侍所のほうでは明日ある音楽の合奏のために、下ならしに楽器を出して、たくさん集まっていた殿上役人などが鳴らしてみたり、おもしろい笛の音をたてたりしていた。
|
【蔵人所の方にも】- 六条院の蔵人所。摂関家にも置かれた。
|
| 1.4.3 |
|
内の大殿の頭中将、弁少将なども、挨拶だけで退出するのを、お止めさせになって、いくつも御琴をお取り寄せになる。
|
内大臣の子の頭中将や弁の少将なども伺候の挨拶だけをしに来て帰ろうとしたのを、源氏はとめて、そして楽器を侍にこちらへ運ばせた。
|
【内の大殿の頭中将、弁少将なども】- 内大臣の太郎君柏木と二郎君、後の紅梅大納言。
|
| 1.4.4 |
|
宮の御前に琵琶、大臣に箏の御琴を差し上げて、頭中将は、和琴を賜って、賑やかに合奏なさっているのは、たいそう興趣深く聞こえる。
宰相中将、横笛をお吹きになる。
季節にあった調べを、雲居に響くほど吹き立てた。
弁少将は拍子を取って、「梅が枝」を謡い出したところ、たいそう興味深い。
子供の時、韻塞ぎの折に、「高砂」を謡った君である。
宮も大臣も一緒にお謡いになって、仰々しくはないが、趣のある夜の管弦の催しである。
|
頭中将は和琴の役を命ぜられて、はなやかに掻き立てて合奏はおもしろいものになった。源宰相中将は横笛を受け持った。春の調子が空までも通るほどに吹き立てた。弁の少将が拍子を取って、美しい声で梅が枝を歌い出した。この人は子供の時韻塞に父と来て高砂を歌った公子である。宮も源氏も時々歌を助けて、たいそうな音楽ではないが、おもしろい音楽の夜ではあった。
|
【折にあひたる調子】- 『集成』は「春だから双調であろう」と注す。
【梅が枝」出だしたるほど】- 催馬楽「梅が枝」呂。「梅が枝に 来居る鴬 や 春かけて はれ 春かけて 鳴けどもいまだ や 雪は降りつつ あはれ そこよしや 雪は降りつつ」
【童にて、韻塞ぎの折、「高砂」謡ひし君なり】- 「賢木」巻(第六章三段)に見える。
|
| 1.4.5 |
御土器参るに、宮、
|
お杯をお勧めになる時に、宮が、
|
酒杯がさされた時に、宮は、
|
|
| 1.4.6 |
|
「鴬の声にますます魂が抜け出しそうです
心を惹かれた花の所では、
|
「うぐひすの声にやいとどあくがれん
心しめつる花のあたりに
|
【鴬の声にやいとどあくがれむ--心しめつる花のあたりに】- 蛍宮の和歌。「鴬」は催馬楽「梅が枝」の語句を受け、「しめつる」は薫物の縁で用いたもの。
|
| 1.4.7 |
|
千年も過ごしてしまいそうです」
|
千年もいたくなってます」
|
【千代も経ぬべし】- 「いつまでか野辺に心のあくがれむ花し散らずは千代も経ぬべし」(古今集春下、九六、素性法師)
|
| 1.4.8 |
と聞こえたまへば、
|
とお詠み申し上げなさると、
|
と源氏へお言いになった。
|
|
| 1.4.9 |
|
「色艶も香りも移り染まるほどに、
今年の春は花の咲くわたしの家を絶えず訪
|
色も香もうつるばかりにこの春は
花咲く宿をかれずもあらなん
|
【色も香もうつるばかりにこの春は--花咲く宿をかれずもあらなむ】- 源氏の唱和歌。「なむ」終助詞、他者に対するあつらえの気持ちを表す。
|
| 1.4.10 |
頭中将に賜へば、取りて、宰相中将にさす。
|
頭中将におさずけになると、受けて、宰相中将に廻す。
|
と源氏は歌ってから、杯を頭の中将へさした。中将は杯を受けたあとで宰相の中将へ杯をまわした。
|
|
| 1.4.11 |
|
「鴬のねぐらの枝もたわむほど
夜通し笛の音を吹き澄まして下さい」
|
うぐひすのねぐらの枝も靡くまで
なほ吹き通せ夜半の笛竹
|
【鴬のねぐらの枝もなびくまで--なほ吹きとほせ夜半の笛竹】- 柏木の唱和歌。夕霧の横笛を誉める。
|
| 1.4.12 |
宰相中将、
|
宰相中将は、
|
と頭の中将は歌ったのである。
|
|
| 1.4.13 |
|
「気づかって風が避けて吹くらしい梅の花の木に
むやみに近づいて笛を吹いてよいものでしょうか
|
「心ありて風のよぐめる花の木に
とりあへぬまで吹きやよるべき
|
【心ありて風の避くめる花の木に--とりあへぬまで吹きや寄るべき】- 夕霧の唱和歌。「取りあへぬ」の音に「鳥」(鴬)を響かす。「吹き」に風が吹くと笛を吹くの意を掛ける。「や」(係助詞)「べき」(推量の助動詞)反語表現。
|
| 1.4.14 |
|
無風流ですね」
|
少しひどいでしょうね」
|
【情けなく】- 和歌に添えた言葉。『集成』は「(それでは花が散るではありませんか)思いやりのないことだ、おっしゃると」の意に解す。
|
| 1.4.15 |
と、皆うち笑ひたまふ。
弁少将、
|
と言うと、
皆お笑いに
|
と宰相中将が言うと皆笑った。弁の少将が、
|
|
| 1.4.16 |
|
「霞でさえ月と花とを隔てなければ
ねぐらに帰る鳥も鳴き出すことでしょう」
|
かすみだに月と花とを隔てずば
ねぐらの鳥もほころびなまし
|
【霞だに月と花とを隔てずは--ねぐらの鳥もほころびなまし】- 弁少将の唱和歌。「ほころぶ」は「花」の縁語。
|
| 1.4.17 |
まことに、明け方になりてぞ、宮帰りたまふ。御贈り物に、みづからの御料の御直衣の御よそひ一領、手触れたまはぬ薫物二壺添へて、御車にたてまつらせたまふ。宮、 |
ほんとうに、明け方になって、宮はお帰りになる。
御贈物に、ご自身の御料の御直衣のご装束一揃い、手をおつけになっていない薫物を二壷添えて、お車までお届けになる。
宮は、
|
と言った。長居のしたくなる所であるとお言いになったとおりに、宮は明け方になってお帰りになるのであった。源氏は贈り物に、自身のために作られてあった直衣一領と、手の触れない薫香二壺を宮のお車へ載せさせた。
|
【御車にたてまつらせたまふ】- 「せ」(使役の助動詞)「給ふ」(尊敬の補助動詞)。源氏が人をして宮のお車までお届させなさる意。
|
| 1.4.18 |
|
「この花の香りを素晴らしい袖に移して帰ったら
女と過ちを犯したのではないかと妻が咎めるでしょう」
|
花の香をえならぬ袖に移しても
ことあやまりと妹や咎めん
|
【花の香をえならぬ袖にうつしもて--ことあやまりと妹やとがめむ】- 蛍宮のお礼の歌。「花の香」は梅花香をさす。「妹」は妻をいう。
|
| 1.4.19 |
とあれば、
|
と言うので、
|
宮がこうお歌いになったと聞いて、
|
|
| 1.4.20 |
|
「たいそう弱気ですな」
|
「何と言いわけをしようと御心配なのだね」
|
【いと屈したりや】- 大島本は「くつしたりや」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「屈(くん)じたりや」と校訂する。源氏の詞。『集成』は「(奥方を怖れて)ひどく気弱ですね」の意に解す。『新大系』は「大変な恐妻家ですね。ただし兵部卿宮には現在、北の方はいない」と注す。
|
| 1.4.21 |
|
と言ってお笑いになる。
お車に牛を繋ぐところに、追いついて、
|
と源氏は笑った。お車はもう走り出そうとしていたのであったが、使いを追いつかせて、
|
【御車かくるほどに】- お車の轅を牛に付ける時に、の意。
|
| 1.4.22 |
|
「珍しいと家の人も待ち受けて見ましょう
この花の錦を着て帰るあなたを
|
「めづらしとふるさと人も待ちぞ見ん
花の錦を着て帰る君
|
【めづらしと故里人も待ちぞ見む--花の錦を着て帰る君】- 源氏の返歌。「故里人」は家にいる妻をさす。『完訳』は「宮邸にいる人の意」と解す。「錦を着て帰る」は『史記』項羽本紀の「富貴にして故郷に帰らざるは、繍を着て夜行くが如し」による。
|
| 1.4.23 |
|
めったにないこととお思いになるでしょう」
|
この上ないことだと御満足なさるでしょう」
|
【またなきことと思さるらむ】- 源氏の歌に添えた詞。『集成』は「夫人のない兵部卿の宮を、めったに外泊しない恐妻家に見立ててからかう」と注す。
|
| 1.4.24 |
とあれば、いといたうからがりたまふ。次々の君達にも、ことことしからぬさまに、細長、小袿などかづけたまふ。 |
とおっしゃるので、とてもつらがりなさる。
以下の公達にも、大げさにならないようにして、細長、小袿などをお与えになる。
|
と源氏がお伝えさせると宮は苦笑をあそばされた。頭中将や弁の少将などにも目だつほどの纏頭でなく、細長とか小袿とかを源氏は贈ったのであった。
|
【いといたうからがりたまふ】- 『完訳』は「宮は六条院を讃美したつもりだが、源氏の大仰な表現に屈伏」と解す。
|
|
第二章 光る源氏の物語 明石の姫君の裳着
|
|
第一段 明石の姫君の裳着
|
| 2.1.1 |
|
こうして、西の御殿に、戌の刻にお渡りになる。
中宮のいらっしゃる西の放出を整備して、御髪上の内侍なども、そのままこちらに参上した。
紫の上も、この機会に、中宮にご対面なさる。
お二方の女房たちが、一緒に来合わせているのが、数えきれないほど見えた。
|
裳着の式を行なう西の町へ源氏夫婦と姫君は午後八時に行った。中宮のおいでになる御殿の西の離れに式の設けがされてあって、姫君のお髪上げ役の(正装の場合には前髪を少しくくるのである)内侍などもこちらへ来たのである。紫夫人もこのついでに中宮へお目にかかった。中宮付き、夫人付き、姫君付きの盛装した女房のすわっているのが数も知れぬほどに見えた。
|
【かくて、西の御殿に】- 六条院の秋の町の寝殿。
【戌の時に渡りたまふ】- 午後七時から九時までの頃。主語は明石姫君。
【やがてこなたに参れり】- 御髪上の内侍たちが中宮に従って六条院西の御殿に参上していた、の意。
【上も、このついでに、中宮に御対面あり】- 「上」は紫の上をいう。明石姫君の養母という立場。「このついで」とはその姫君の御裳着の儀式の折の意。初対面。
|
| 2.1.2 |
|
子の刻に御裳をお召しになる。
大殿油は微かであるが、御器量がまことに素晴らしいと、中宮はご拝見あそばす。
大臣は、
|
裳を付ける式は十二時に始まったのである。ほのかな灯の光で御覧になったのであるが、姫君を美しく中宮は思召した。
|
【子の時に御裳たてまつる】- 中宮が腰結役を務める。
|
| 2.1.3 |
|
「お見捨てになるまいと期待して、失礼な姿を、進んでお目にかけたのでございます。
後世の前例になろうかと、狭い料簡から密かに考えております」
|
「お愛しくださいますことを頼みにいたしまして、失礼な姿も御前へ出させましたのです。尊貴なあなた様がかようなお世話をくださいますことなどは例もないことであろうと感激に堪えません」
|
【思し捨つまじきを頼みにて】- 以下「忍びたまふる」まで、源氏の詞。「思し捨つ」の主語は中宮、目的語は明石姫君。
【なめげなる姿を】- 娘の童女姿を親として失礼な姿と謙っていう。
【後の世のためしにやと】- 『集成』は「中宮の行啓を仰いで、腰結役をお願いするのは、前例がない名誉という」と注す。
|
| 2.1.4 |
など聞こえたまふ。
宮、
|
などと申し上げなさる。
中宮、
|
と源氏は申し上げていた。
|
|
| 2.1.5 |
|
「どのようなこととも判断せず致したことを、このように大層におっしゃって戴きますと、かえって気が引けてしまいます」
|
「経験の少ない私が何もわからずにいたしておりますことに、そんな御挨拶をしてくださいましてはかえって困ります」
|
【いかなるべきこととも思うたまへ分きはべらざりつるを】- 以下「心おかれぬべく」まで、中宮の返事。
|
| 2.1.6 |
|
と、否定しておっしゃる御様子、とても若々しく愛嬌があるので、大臣も、理想通りに立派なご様子の婦人方が、集まっていらっしゃるのを、お互いの間柄も素晴らしいとお思いになる。
母君が、このような機会でさえお目にかかれないのを、たいそう辛い事と思っているのも気の毒なので、参列させようかしらと、お考えになるが、世間の悪口を慮って、見送った。
|
と御謙遜して仰せられる中宮の御様子は若々しくて愛嬌に富んでおいでになるのを見て、この美しい人たちは皆自身の一家族であるという幸福を源氏は感じた。明石が蔭にいてこの晴れの式も見ることのできないことを悲しむふうであったのを哀れに思って、こちらへ呼ぼうかとも源氏は思ったのであるが、やはり外聞をはばかって実行はしなかった。
|
【のたまひ消つほどの御けはひ】- 『集成』は「何でもないことのようにおっしゃるご様子が」。『完訳』は「こともなげに仰せになる」と解す。
【母君の、かかる折だにえ見たてまつらぬを】- 明石御方が娘の姫君を裳着の儀式に。
【参う上らせやせまし】- 源氏の心。儀式に参列させようかしら、の意。
|
| 2.1.7 |
かかる所の儀式は、よろしきにだに、いとこと多くうるさきを、片端ばかり、例のしどけなくまねばむもなかなかにやとて、こまかに書かず。 |
このような邸での儀式は、まあまあのものでさえ、とても煩雑で面倒なのだが、一部分だけでも、例によってまとまりなくお伝えするのも、かえってどうかと思い、詳細には書かない。
|
こうした式についての記事は名文で書かれていてもうるさいものであるのを、自分などがだらしなく書いていっては、かえってきれいなりっぱなことをこわしてしまう結果になるのを恐れて、細かにはしるさない。
|
【かかる所の儀式は】- 以下「こまかに書かず」まで、語り手の省筆の弁。『評釈』は「作者の言葉。「書く」という言葉を用いるのは珍しい。普通は「語る」「言ふ」である。この所は私の物語音読論の立場からすると困る例と見られようが、これは我々に語ってくれる女房に資料を提供してくれる女房がいて、それが現実に前の「御方々の女房、おし合せたる、数しらず見えたり」の中にいて、後々の例になるようにと思ってこの儀式のことを書き記した。それにこのように「こまかに書かず」という断わり書があった。それを物語り手が我々にそのまま語ってくれると解したい」と注す。『集成』は「物語筆記者が省筆をことわる草子地」と注す。
|
|
第二段 明石の姫君の入内準備
|
| 2.2.1 |
|
春宮の御元服は、二十日過ぎの頃に行われたのであった。
たいそう大人でおいであそばすので、人々が娘たちを競争して入内させることを、希望していらっしゃるというが、この殿がご希望していらっしゃる様子が、まことに格別なので、かえって中途半端な宮仕えはしないほうがましだと、左大臣なども、お思い留まりになっているということをお耳になさって、
|
東宮の御元服は二十幾日にあった。もうりっぱな大人のようでいらせられたから、だれも令嬢たちを後宮へ入れたい志望を持ったが、源氏がある自信を持って、姫君を東宮へ奉ろうとしているのを知っては、強大な競争者のあるこの宮仕えはかえって娘を不幸にすることではなかろうかと、左大臣、左大将などもまた躊躇していることを源氏は聞いて、
|
【春宮の御元服は、二十余日のほどになむありける】- 東宮の御元服も同じ二月の二十日過ぎに行われた。「けり」過去の助動詞。儀式の終わった後から語るという語り口。
【心ざし思すなれど】- 「なれ」伝聞推定の助動詞。
【左の大臣なども】- 系図不詳の人。「行幸」「真木柱」に登場。
【思しとどまるなるを】- 「なる」伝聞推定の助動詞。
|
| 2.2.2 |
|
「じつにもってのほかのことだ。
宮仕えの趣旨は、大勢いる中で、僅かの優劣の差を競うのが本当だろう。
たくさんの優れた姫君たちが、家に引き籠められたならば、何ともおもしろくないだろう」
|
「それではお上へ済まないことになる。宮仕えは多数のうちで、ただ少しの御愛寵の差を競うのに意義があるのだ。貴族がたのりっぱな姫君がお出にならないではこちらも張り合いのないことになる」
|
【いとたいだいしきことなり】- 以下「世に映えあらじ」まで、源氏の詞。
【宮仕への筋は、あまたあるなかに、すこしのけぢめを挑まむこそ本意ならめ】- 宮仕えというものは大勢の妃方の中でわずかの優劣を競うのが本当だという考え。作者紫式部の後宮に対する考え方である。
|
| 2.2.3 |
|
とおっしゃって、御入内が延期になった。
その次々にもと差し控えていらっしゃったが、このようなことをあちこちでお聞きになって、左大臣の三の君がご入内なさった。
麗景殿女御と申し上げる。
|
と言って、姫君の宮仕えの時期を延ばした。たとえ娘を出すにしてもあとのことにしようとしていた人たちはそれを聞いて、最初に左大臣が三女を東宮へ入れた。麗景殿と呼ばれることになった。
|
【御参り延びぬ】- 『集成』は「ほかの人々に譲る気持。余裕のある態度」と注す。
【左大臣殿の三の君参りたまひぬ。麗景殿と聞こゆ】- 「真木柱」巻の冷泉帝の後宮に「中宮、弘徽殿の女御、この宮の女御、左の大殿の女御などさぶらひたまふ」(第四章一段)とあるから、冷泉帝の左大臣の女御の妹三の君であろう。麗景殿女御。後の「宿木」巻に藤壷女御と呼称される。『集成』は「元服の副臥(春宮、皇子などの元服の夜、選ばれて添い寝する姫)である。権勢のある公卿の娘が選ばれ、皇妃の中では重い地位を占める」と注す。なお花散里が三の君でその姉が桐壺帝の麗景殿女御とあったという設定同じである。
|
| 2.2.4 |
|
こちらの御方は、昔の御宿直所の、淑景舎を改装して、ご入内が延期になったのを、春宮におかれても待ち遠しくお思いあそばすので、四月にとお決めあそばす。
ご調度類も、もとからあったのを整えて、御自身でも、道具類の雛形や図案などを御覧になりながら、優れた諸道の専門家たちを呼び集めて、こまかに磨きお作らせになる。
|
源氏のほうは昔の宿直所の桐壺の室内装飾などを直させることなどで時日が延びているのを、東宮は待ち遠しく思召す御様子であったから、四月に参ることに定めた。姫君の手道具類なども、もとからあるのにまた新しく作り添えて、源氏自身が型を考えたり、図案をこしらえたりしては専門家の名人を集めて、美術的な製作を命じていた。
|
【この御方は、昔の御宿直所、淑景舎を改めしつらひて】- 明石の姫君は源氏の昔の宿直所、淑景舎を修繕して局とする。東宮は梨壷にいるので、桐壺はその北隣の殿舎である。
【宮にも心もとながらせたまへば】- 春宮も明石姫君の入内を待ち遠しく思っている。
【四月にと定めさせたまふ】- 「させ」「たまふ」(最高敬語)、主語は春宮。明石姫君の入内を四月にと春宮が御決定あそばすという意。
|
| 2.2.5 |
草子の筥に入るべき草子どもの、やがて本にもしたまふべきを選らせたまふ。
いにしへの上なき際の御手どもの、世に名を残したまへるたぐひのも、いと多くさぶらふ。
|
冊子の箱に入れるべき冊子類を、そのまま手本になさることのできるのを選ばせなさる。
昔のこの上もない名筆家たちが、後世にお残しになった筆跡類も、たいそうたくさんある。
|
草紙の箱というような物に入れる草紙で、いずれは製本もさせて書物になるようなものを源氏は選んでいた。故人で、書道のほうの大家と言われている人たちの書いた物も源氏のところにはたくさんあった。
|
|
|
第三段 源氏の仮名論議
|
| 2.3.1 |
|
「すべての事が、昔に比べて劣って、浅くなって行く末世だが、仮名だけは、現代は際限もなく発達したものだ。
昔の字は、筆跡が定まっているようではあるが、ゆったりした感じがあまりなくて、一様に似通った書法であった。
|
「すべてのことは昔より悪くなっていく末世ではあっても、仮名の字だけは、どこまでおもしろくなっていくかと思われるほど、近ごろのほうがよくなった。昔の仮名は正確ではあるが、融通がきかないで、変化の妙がなく単調だ。
|
【よろづのこと】- 以下「かどや後れたらむ」まで、源氏の詞。当代の女性の仮名論。尚古思想。仮名だけは現代の方が優れているという。
【古き跡は、定まれるやうにはあれど、広き心ゆたかならず、一筋に通ひてなむありける】- 昔の書は一定の書法があるが、窮屈で一様で、個性的な豊さがないと批判。
|
| 2.3.2 |
|
見事で上手なものは、近頃になって書ける人が出て来たが、平仮名を熱心に習っていた最中に、特に難点のない手本を数多く集めていた中で、中宮の母御息所が何気なくさらさらとお書きになった一行ほどの、無造作な筆跡を手に入れて、格段に優れていると感じたものです。
|
巧妙な仮名を書く人は近代になってふえたが、私も仮名を習うのに熱心だったころ、無難な仮名字を手本にいろいろ集めたものだが、中宮の母君の御息所が何ともなしに書かれた一行か二行の字が手にはいって、最上の仮名字はこれだと心酔してしまったものです。
|
【外よりてこそ】- 『集成』は「近頃になってから」、『完訳』は「後の時代になってはじめて」の意に解す。文字は「外によりて」と当てる。
【女手】- 『集成』は「「女手」は、一般に「男手」(漢字)に対する語で、女の書く文字、すなわち平仮名のこととされるが、後文によると、仮名の一体とすべきもののようである」と注す。
【中宮の母御息所の】- 六条御息所の筆跡について、「際ことにおぼえしはや」と感想を述べる。
|
| 2.3.3 |
|
そういうことで、
とんでもない浮名までもお流し申してしまったことよ。残念なことと思い込ん
でいらっしゃったが、それほど薄情ではなかったのだ。中宮にこのように御後見申し上げていることを、思慮深くいらっしゃっ
|
それがもとになって浮き名を立てることになり、私との関係をにがい経験だったように思って、くやしがったままで亡くなられたが、必ずしもそうではなかったのだ。今は中宮をお援けしていることで、聡明な人だったから、あの世ででも私の誠意を認めておいでになることだろう。
|
【さて、あるまじき御名も立てきこえしぞかし】- 源氏は、御息所の筆跡の見事さに引かれて恋するようになったと、紫の上を前にしていう。
【さしもあらざりけり】- 源氏の自己弁護。それほど冷淡ではなかったのだ、という。
|
| 2.3.4 |
|
中宮の御筆跡は、こまやかで趣はあるが、才気は少ないようだ」
|
中宮のお字はきれいなようだけれど才気が少ない」
|
【宮の御手は】- 秋好中宮の筆跡について、「こまかにをかしげなれど、才や遅れたらむ」と批評。
|
| 2.3.5 |
と、うちささめきて聞こえたまふ。
|
と、ひそひそと申し上げなさる。
|
と源氏は夫人にささやいていた。
|
|
| 2.3.6 |
|
「故入道宮の御筆跡は、たいそう深味もあり優美な手の筋はおありだったが、なよなよした点があって、はなやかさが少なかった。
|
「入道の中宮様は最上の貴婦人らしい品のある字をお書きになったが、弱い所があって、はなやかな気分はない。
|
【故入道宮の御手は】- 以下「ここにとこそは書きたまはめ」まで、源氏の詞。藤壷の筆跡について、「いと気色深くなまめいたる筋はありしかど弱き所つきてにほひぞ少なかりし」と批評。
|
| 2.3.7 |
|
朱雀院の尚侍は、当代の名人でいらっしゃるが、あまりにしゃれすぎて欠点があるよだ。
そうは言っても、あの尚侍君と、前斎院と、あなたは、上手な方だと思う」
|
院の尚侍は現代の最もすぐれた書き手だが、奔放すぎて癖が出てくる。しかし、ともかくも院の尚侍と前斎院と、あなたをこの草紙の書き手に擬していますよ」
|
【院の尚侍こそ】- 朧月夜の筆跡について、「今の世の上手にはおはすれど、あまりそぼれて癖ぞ添ひためる」と批評。
【かの君と、前斎院と、ここにとこそは、書きたまはめ】- 朧月夜君と朝顔姫君と紫の上は上手に書く人だ、の意。
|
| 2.3.8 |
と、聴しきこえたまへば、
|
と、お認め申し上げなさるので、
|
源氏から認められたことで、夫人は、
|
|
| 2.3.9 |
|
「この方々に仲間入りするのは、恥ずかしいですわ」
|
「そんな方たちといっしょになすっては恥ずかしくてなりませんよ」
|
【この数には、まばゆくや】- 紫の上の謙遜の詞。
|
| 2.3.10 |
と聞こえたまへば、
|
と申し上げなさると、
|
と言っていた。
|
|
| 2.3.11 |
|
「ひどく謙遜なさってはいけません。
柔和という点の好ましさは、格別なものですよ。
漢字が上手になってくると、仮名は整わない文字が交るようですがね」
|
「謙遜をしすぎますよ。柔らかな調子のとてもいい所がある。漢字は上手に書けますが、仮名には時々力の抜けた字の混じる欠点はありますね」
|
【いたうな過ぐしたまひそ】- 以下「しどけなき文字こそ混じるめれ」まで、源氏の詞。紫の上の筆跡について、「にこやかなるかたの御なつかしさはことなるものを」と批評。
【真名のすすみたるほどに、仮名はしどけなき文字こそ混じるめれ】- 漢字と仮名文字を用いる男性への一般論。「ほどに」を、『集成』は「すればするだけ」の意に、『完訳』は「するわりには」の意に解す。
|
| 2.3.12 |
とて、まだ書かぬ草子ども作り加へて、表紙、紐などいみじうせさせたまふ。
|
とおっしゃって、まだ書写してない冊子類を作り加えて、表紙や、紐など、たいへん立派にお作らせになる。
|
などとも源氏は言っていて、書かない無地の草紙もまた何帳か新しく綴じさせた。表紙や紐などを細かく精選したことは言うまでもない。
|
|
| 2.3.13 |
|
「兵部卿宮、左衛門督などに書いてもらおう。
わたし自身も二帖は書こう。
いくら自信がおありでも、並ばないことはあるまい」
|
「兵部卿の宮とか左衛門督とかにもお頼みしよう。私も一冊書く。気どっておられても私といっしょに書くことは晴れがましいだろう」
|
【兵部卿宮、左衛門督などにものせむ】- 以下「え書き並べじや」まで、源氏の詞。「兵部卿宮」は蛍宮、「左衛門督」はここだけに登場する系図不明の人。
|
| 2.3.14 |
と、われぼめをしたまふ。
|
と、自賛なさる。
|
と源氏は自讃していた。
|
|
|
第四段 草子執筆の依頼
|
| 2.4.1 |
墨、筆、並びなく選り出でて、例の所々に、ただならぬ御消息あれば、人びと、難きことに思して、返さひ申したまふもあれば、まめやかに聞こえたまふ。
高麗の紙の薄様だちたるが、せめてなまめかしきを、
|
墨、筆、最上の物を選び出して、いつもの方々に、特別のご依頼のお手紙があると、方々は、難しいこととお思いになって、ご辞退申し上げなさる方もあるので、懇ろにご依頼申し上げなさる。
高麗の紙の薄様風なのが、はなはだ優美なのを、
|
墨も筆も選んだのを添えて、いつもそうした交渉のある所々へ執筆を源氏は頼んだのであったが、だれもこの委嘱に応じるのを困難なことに思って、その中には辞退してくる人もあったが、そんな時に源氏は再三懇切な言葉で執筆を望んだ。朝鮮紙の薄様風な非常に艶な感じのする紙の綴じられた帳を源氏は見て、
|
|
| 2.4.2 |
|
「あの、風流好みの若い人たちを、試してみよう」
|
「風流好きな青年たちにこれを書かせてみよう」
|
【この、もの好みする若き人びと、試みむ】- 源氏の詞。
|
| 2.4.3 |
とて、宰相中将、式部卿宮の兵衛督、内の大殿の頭中将などに、
|
とおっしゃって、宰相中将、式部卿宮の兵衛督、内の大殿の頭中将などに、
|
と言った。宰相中将、式部卿の宮の兵衛督、内大臣家の頭中将などに、
|
|
| 2.4.4 |
|
「葦手、歌絵を、各自思い通りに書きなさい」
|
蘆手とか、歌絵とか、何でも思い思いに書くように
|
【葦手、歌絵を、思ひ思ひに書け】- 源氏の詞。
|
| 2.4.5 |
とのたまへば、皆心々に挑むべかめり。
|
とおっしゃると、皆それぞれ工夫して競争しているようである。
|
と源氏は言ったのであった。若い人たちは競って製作にかかった。
|
|
| 2.4.6 |
|
いつもの寝殿に独り離れていらっしゃってお書きになる。
花盛りは過ぎて、浅緑色の空がうららかなので、いろいろ古歌などを心静かに考えなさって、ご満足のゆくまで、草仮名も、普通の仮名も、女手も、たいそう見事にこの上なくお書きになる。
|
いつもこんな時にするように、源氏は寝殿のほうへ行っていて書いた。花の盛りが過ぎて淡い緑色がかった空のうららかな日に、源氏は古い詩歌を静かに選びながら、みずから満足のできるだけの字を書こうと、漢字のも仮名のも熱心に書いていた。
|
【例の寝殿に離れおはしまして書きたまふ】- 源氏、寝殿で草子を書く。「例の」は薫物合せの時と同様にの意。
【花ざかり過ぎて、浅緑なる空うららかなるに】- 「花」は桜の花。晩春の景色。
【草のも、ただのも、女手も、いみじう書き尽くしたまふ】- 「草」は草仮名。しかし、「ただ」と「女手」の相違がはっきりしない。『集成』は「「女手」は、一般に「男手」(漢字)に対する語で、女の書く文字、すなわち平仮名のこととされるが、後文(この箇所)によると、仮名の一体とすべきもののようである」という。『完訳』は「「ただ」は普通の仮名、平仮名か。「女て」も平仮名とすると、「ただ」との違いが不明。「ただ」と「女て」を同格とみるべきか」と注す。
|
|
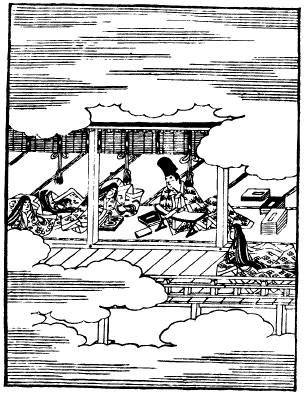 |
| 2.4.7 |
御前に人しげからず、女房二、三人ばかり、墨など擦らせたまひて、ゆゑある古き集の歌など、いかにぞやなど選り出でたまふに、口惜しからぬ限りさぶらふ。
|
御前に人は多くいず、女房が二、三人ほどで、墨などをお擦らせになって、由緒ある古い歌集の歌など、どんなものだろうかなどと、選び出しなさるので、相談相手になれる人だけが伺候している。
|
その部屋には女房も多くは置かずにただ二、三人、墨をすらせたり、古い歌集の歌を命ぜられたとおりに捜し出したりするのに役にたつような者を呼んであった。
|
|
| 2.4.8 |
|
御簾を上げ渡して、脇息の上に冊子をちょっと置いて、端近くに寛いだ姿で、筆の尻をくわえて、考えめぐらしていらっしゃる様子、いつまでも見飽きない美しさである。
白や赤などの、はっきりした色の紙は、筆を取り直して、注意してお書きになっていらっしゃる様子までが、情趣を解せる人は、なるほど感心せずにはいられないご様子である。
|
部屋の御簾は皆上げて、脇息の上に帳を置いて、縁に近い所でゆるやかな姿で、筆の柄を口にくわえて思案する源氏はどこまでも美しかった。白とか赤とかきわだった片は、筆を取り直して特に注意して書いたりする態度なども、心のある者は敬意を払わずにいられないことであった。
|
【飽く世なくめでたし】- その場を見聞した語り手の感想。『評釈』は「作者はその姿を「あく世なくめでたし」と賞賛する」という。
【見知らむ人は、げにめでぬべき御ありさまなり】- その場を見聞した語り手の感想。『評釈』は「作者はその姿を「見しらむ人は、げにめでぬべき御有様なり」と賞賛した」という。
|
|
第五段 兵部卿宮、草子を持参
|
| 2.5.1 |
「兵部卿宮渡りたまふ」と聞こゆれば、おどろきて、御直衣たてまつり、御茵参り添へさせたまひて、やがて待ち取り、入れたてまつりたまふ。この宮もいときよげにて、御階さまよく歩み昇りたまふほど、内にも人びとのぞきて見たてまつる。うちかしこまりて、かたみにうるはしだちたまへるも、いときよらなり。 |
「兵部卿宮がお越しになりました」と申し上げたので、驚いて御直衣をお召しになって、御敷物を持って来させなさって、そのまま待ち受けて、お入れ申し上げなさる。
この宮もたいそう美しくて、御階を体裁よく歩いて上がっていらっしゃるところを、御簾の中からも女房たちが覗いて拝見する。
丁重に挨拶して、お互いに威儀を正していらっしゃるのも、たいそう美しい。
|
兵部卿の宮がおいでになったということを聞いて源氏は驚いて上に直衣を着たり、座敷へさらに褥を取り寄せたりしてお迎えした。この宮もきれいなお姿で、階段を艶に上っておいでになるのを、女房たちは御簾からのぞいていた。互いに正しい礼儀で御挨拶がかわされた。
|
【兵部卿宮渡りたまふ】- 女房の詞。
|
| 2.5.2 |
|
「することもなく邸に籠もっておりますのも、辛く存じられますこの頃ののんびりとした折に、ちょうどよくお越し下さいました」
|
「引きこもっていますのが苦しいほど退屈なおりからでしたよ。よくおいでくださいました」
|
【つれづれに籠もり】- 以下「渡らせたまへる」まで、源氏の詞。歓迎の挨拶言葉。
【心ののどけさに】- 大島本は「こゝろの」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「ころの」と校訂する。
|
| 2.5.3 |
|
と、歓迎申し上げなさる。
あの御依頼の冊子を持たせてお越しになったのであった。
その場で御覧になると、たいして上手でもないご筆跡を、ただ一本調子に、たいそう垢抜けした感じにお書きになってある。
和歌も、技巧を凝らして、風変わりな古歌を選んで、わずか三行ほどに、文字を少なくして好ましく書いていらっしゃった。
大臣、御覧になって驚いた。
|
と源氏は言っていた。お頼まれになった書き物を宮は持っておいでになったのである。すぐこの席で源氏は拝見した。非常に巧妙な字というのではないが、一部分に澄み切った芸術味の見えるものだった。歌も常識的なものは避けて、変わったものが選ばれてあって、ただ三行ほどに字数を少なく感じよく書かれてあった。源氏は予想に越えたおできばえに驚いた。
|
【かの御草子待たせて渡りたまへるなりけり】- 蛍宮が来訪した事情を説明した文。『細流抄』は「草子地」と指摘。「せ」(使役の助動詞)、供人に持たせての意。
【やがて御覧ずれば】- 人々の仮名を批評する。源氏の目(批評眼)を通して語る。
【すぐれてしもあらぬ御手を】- 蛍宮の筆跡についての批評。
【ただかたかどに】- 『集成』は「未熟ながら才気にまかせて」の意に解し、『完訳』は「それが一つの才能だが、の意。具体的には、次の「いといたう--けしき」(じつにすっきりと、あかぬけた感じ、の意)」と注す。
【いといたう筆澄みたるけしきありて】- 蛍宮の筆跡についての批評。
【歌も、ことさらめき、そばみたる古言どもを選りて】- 『完訳』は「技巧をこらして、変った好みの古歌。風流人らしい撰歌である」という。
【文字少なに】- 「文字」について『集成』は「仮名だけで書かず、漢字まじりにしたので、字数が少なくなっているのであろう」と字数の意に解し、『完訳』は「ほとんど全部仮名で」と漢字の意に解す。
|
| 2.5.4 |
「かうまでは思ひたまへずこそありつれ。さらに筆投げ捨てつべしや」 |
「こんなにまで上手にお書きになるとは存じませんでした。
まったく筆を投げ出してしまいたいほどですね」
|
「これほどにもとは思いませんでした。自分の書くことなどはいやになるほどです」
|
【かうまでは】- 以下「投げ捨てつべしや」まで、源氏のお世辞の詞。
|
| 2.5.5 |
と、ねたがりたまふ。
|
と、悔しがりなさる。
|
とも言っていた。
|
|
| 2.5.6 |
|
「このような名手の中で臆面もなく書く筆跡の具合は、いくら何でもさほどまずくはないと存じます」
|
「大家たちの中へ混じって書く自信だけはえらいものだと思っていますよ」
|
【かかる御中に】- 以下「思うたまふる」まで、蛍宮の冗談をまじえた返答。自負も窺える。
|
| 2.5.7 |
など、戯れたまふ。
|
などと、冗談をおっしゃる。
|
と宮は戯談を言っておいでになる。
|
|
| 2.5.8 |
書きたまへる草子どもも、隠したまふべきならねば、取う出たまひて、かたみに御覧ず。
|
お書きになった冊子類を、お隠しすべきものでもないので、お取り出しになって、お互いに御覧になる。
|
すでにできた源氏の帳などもお隠しすべきでないから出して宮の御覧に入れた。
|
|
| 2.5.9 |
|
唐の紙で、たいそう堅い材質に、草仮名をお書きになっている、まことに結構であると、御覧になると、高麗の紙で、きめが細かで柔らかく優しい感じで、色彩などは派手でなく、優美な感じのする紙に、おっとりした女手で、整然と心を配って、お書きになっている、喩えようもない。
|
支那の紙のじみな色をしたのへ、漢字を草書で書かれたのがすぐれて美しいと宮は見ておいでになったが、またそのあとで、朝鮮紙の地のきめの細かい柔らかな感じのする、色などは派手でない艶なのへ、仮名文字が、しかも正しく熱の見える字で書かれてある絶妙な物をお見つけになった。
|
【唐の紙の、いとすくみたるに、草書きたまへる】- 中国舶来の紙、ぱりっとした紙に草仮名で書いた。「いとすぐれてめでたし」と批評する。
【高麗の紙の、肌こまかに和うなつかしきが、色などははなやかならで、なまめきたるに、おほどかなる女手の、うるはしう心とどめて書きたまへる】- 高麗舶来の紙、紙質がきめこまやかで柔らかく温かい感じのする紙で、色も落ち着いた優雅な感じのする紙に女手で書いた。「たとふべきかたなし」と批評する。
|
| 2.5.10 |
見たまふ人の涙さへ、水茎に流れ添ふ心地して、飽く世あるまじきに、また、ここの紙屋の色紙の、色あひはなやかなるに、乱れたる草の歌を、筆にまかせて乱れ書きたまへる、見所限りなし。しどろもどろに愛敬づき、見まほしければ、さらに残りどもに目も見やりたまはず。 |
御覧になる方の涙までが、筆跡に沿って流れるような感じがして、見飽きることのなさそうなところへ、さらに、わが国の紙屋院の色紙の、色合いが派手なのに、乱れ書きの草仮名の和歌を、筆にまかせて散らし書きになさったのは、見るべき点が尽きないほどである。
型にとらわれず自在に愛嬌があって、ずっと見ていたい気がしたので、他の物にはまったく目もおやりにならない。
|
それは見る人の感動した涙も添って流れる気のする墨蹟で、いつまでも目をお放しになることができないのであったが、また日本製の紙屋紙の色紙の、はなやかな色をしたのへ奔放に散らし書きをした物には無限のおもしろさがあるようにもお思われになって、乱れ書きにした端々にまで人を酔わせるような愛嬌がこもっているこの片以外の物はもう見ようともされないのであった。
|
【色あひはなやかなるに】- 大島本は「色あひ」とある。『集成』『新大系』は底本のままとする。『古典セレクション』は諸本に従って「色あはひ」と校訂する。
【しどろもどろに】- 「よしとてもよき名も立たず刈萱のいざ乱れなむしどろもどろに」(紫明抄所引、出典未詳)「まめなれどよき名も立たず刈萱のいざ乱れなむしどろもどろに」(古今六帖六、かるかや、三七八五)
|
|
第六段 他の人々持参の草子
|
| 2.6.1 |
左衛門督は、ことことしうかしこげなる筋をのみ好みて書きたれど、筆の掟て澄まぬ心地して、いたはり加へたるけしきなり。
歌なども、ことさらめきて、選り書きたり。
|
左衛門督は、仰々しくえらそうな書風ばかりを好んで書いているが、筆法の垢抜けしない感じで、技巧を凝らした感じである。
和歌なども、わざとらしい選び方をして書いていた。
|
左衛門督の字は本格的に書いてあるのであるが、俗気が抜け切らずに、技巧が技巧として目についた。歌などもわざとらしいものが選ばれてある。
|
|
| 2.6.2 |
|
女君たちのは、そっくりお見せにならない。
斎院のなどは、言うまでもなく取り出しなさらないのであった。
葦手の冊子類が、それぞれに何となく趣があった。
|
女の手になったほうの帳は少しよりお見せしなかった。ことに斎院のなどはまったく隠してお出ししない源氏であった。青年たちによって蘆手の書かれた幾冊かの帳はとりどりにおもしろかった。
|
【女の御は】- 大島本は「女の御ハ」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「女のは」と校訂する。
【はかなうをかしき】- 『集成』は「整った正式の書体に対して下絵に合せて乱れ書いたものについての感じ」という。
|
| 2.6.3 |
宰相中将のは、水の勢ひ豊に書きなし、そそけたる葦の生ひざまなど、難波の浦に通ひて、こなたかなたいきまじりて、いたう澄みたるところあり。また、いといかめしう、ひきかへて、文字やう、石などのたたずまひ、好み書きたまへる枚もあめり。 |
宰相中将のは、水の勢いを豊富に書いて、乱れ生えている葦の様子など、難波の浦に似ていて、あちこちに入り混じって、たいそうすっきりした所がある。
また、たいそう大仰に趣を変えて、字体、石などの様子、風流にお書きになった紙もあるようだ。
|
源中将のは水を豊かに描いて、そそけた蘆のはえた景色に浪速の浦が思われるのへ、そちらへあちらへ美しい歌の字が配られているような、澄んだ調子のものがあるかと思うと、また全然変わった奇岩の立った風景に相応した雄健な仮名の書かれてある片もあるというような蘆手であった。
|
【こなたかなた】- 『集成』は「〔流れや葦が〕あちらこちらと」と解し、『完訳』は「葦と文字があちこち入り交じり」と解す。
【いといかめしう】- 大島本は「いかめかしう」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「いまめかしう」と校訂する。
|
| 2.6.4 |
|
「目も及ばぬ素晴らしさだ。
これは手間のかかったにちがいない代物だね」
|
「驚いたものですね。これは見るのに時間を要するものですね」
|
【目も及ばず。これは暇いりぬべきものかな】- 蛍宮の讃辞。『集成』は「手間のかかりそうなものですね」の意に解し、『完訳』は「観賞に時間がかかるの意。一説に葦手書きするのに、とする」と注す。
|
| 2.6.5 |
と、興じめでたまふ。
何事ももの好みし、艶がりおはする親王にて、いといみじうめできこえたまふ。
|
と、興味深くお誉めになる。
どのようなことにも趣味を持って、風流がりなさる親王なので、とてもたいそうお誉め申し上げなさる。
|
と宮はおもしろがっておいでになった。芸術家風の風流気に富んだ方であったから、お気にいったものはどこまでもおほめになるのである。
|
|
|
第七段 古万葉集と古今和歌集
|
| 2.7.1 |
今日はまた、手のことどものたまひ暮らし、さまざまの継紙の本ども、選り出でさせたまへるついでに、御子の侍従して、宮にさぶらふ本ども取りに遣はす。
|
今日はまた、書のことなどを一日中お話しになって、いろいろな継紙をした手本を、何巻かお選び出しになった機会に、御子息の侍従をして、宮邸に所蔵の手本類を取りにおやりになる。
|
この日はまた書の話ばかりをしておいでになって、色紙の継いだ巻き物が幾本となく席上へ現われるのであったが、宮は子息の侍従を邸へおやりになって、御蔵品もお取り寄せになった。
|
|
| 2.7.2 |
嵯峨の帝の、『古万葉集』を選び書かせたまへる四巻、延喜の帝の、『古今和歌集』を、唐の浅縹の紙を継ぎて、同じ色の濃き紋の綺の表紙、同じき玉の軸、緞の唐組の紐など、なまめかしうて、巻ごとに御手の筋を変へつつ、いみじう書き尽くさせたまへる、大殿油短く参りて御覧ずるに、 |
嵯峨の帝が、『古万葉集』を選んでお書かせあそばした四巻。延喜の帝が、『古今和歌集』を、唐の浅縹の紙を継いで、同じ色の濃い紋様の綺の表紙、同じ玉の軸、だんだら染に組んだ唐風の組紐など、優美で、巻ごとに御筆跡の書風を変えながら、あらん限りの書の美をお書き尽くしあそばしたのを、大殿油を低い台に燈して御覧になると、
|
嵯峨帝が古万葉集から撰んでお置きになった四巻、延喜の帝が古今集を支那の薄藍色の色紙を継いだ、同じ色の濃く模様の出た唐紙の表紙、同じ色の宝石の軸の巻き物へ、巻ごとに書風を変えてお書きになったものなどがそれであった。台を短くした灯を置いて二人で見ておいでになったが、
|
【古万葉集】- 『万葉集』をさす。『万葉集』の古称。
|
| 2.7.3 |
|
「いつまで見ていても見飽きないものだ。
最近の人は、ただ部分的に趣向を凝らしているだけにすぎない」
|
「よくこんなにいろいろなふうにお書きになれたものですね。近ごろの人はほんのこの一部分の仕事をするのに骨を折っているという形ですね」
|
【尽きせぬものかな】- 以下「こそありけれ」まで、源氏の詞。
|
| 2.7.4 |
など、めでたまふ。
やがてこれはとどめたてまつりたまふ。
|
などと、お誉めになる。
そのままこれらはこちらに献上なさる。
|
などと源氏はおほめしていた。この二種の物は宮から源氏へ御寄贈になった。
|
|
| 2.7.5 |
|
「女の子などを持っていましたにしても、たいして見る目を持たない者には、伝えたくないのですが、まして、埋もれてしまいますから」
|
「女の子を持っていたとしましても、たいしてこうした物の価値のわからないような子には残してやりたくない気のする物ですからね。それに私には娘もありませんから、お手もとへ置いていただいたほうがよい」
|
【女子などを持てはべらましにだに、をさをさ見はやすまじきには伝ふまじきを、まして、朽ちぬべき】- 蛍宮の詞。「まし」(推量の助動詞、反実仮想)、「だに」は打消や反語の表現を伴って、述語の表す動作・状態に対して、例外的、逆接的な事物、事態であることを示す。~でさえ、~さえもの意。女の子を仮にもっていましたにしても、その時でさえも、見る目を持たない者には、伝えないでしょうが、まして、女の子がいないのだから、このまま持っているのは、埋もれさせてしまうことだから、の意。
|
| 2.7.6 |
など聞こえてたてまつれたまふ。
侍従に、唐の本などのいとわざとがましき、沈の筥に入れて、いみじき高麗笛添へて、奉れたまふ。
|
などと申し上げて差し上げなさる。
侍従に、唐の手本などの特に念入りに書いてあるのを、沈の箱に入れて、立派な高麗笛を添えて、差し上げなさる。
|
などと宮はお言いになったのである。源氏は侍従へ唐本のりっぱなのを沈の木の箱に入れたものへ高麗笛を添えて贈った。
|
|
| 2.7.7 |
|
またこの頃は、ひたすら仮名の論評をなさって、世間で能書家だと聞こえた、上中下の人々にも、ふさわしい内容のものを見計らって、探し出してお書かせになる。
この御箱には、身分の低い者のはお入れにならず、特別に、その人の家柄や、地位を区別なさりなさり、冊子、巻物、すべてお書かせ申し上げなさる。
|
近ごろの源氏は書道といってもことに仮名の字を鑑賞することに熱中して、よい字を書くと言われる人は上中下の階級にわたってそれぞれの物を選んで書を頼んでいた。源氏の書いた帳のはいる箱には、高い階級に属した人たちの手になった書だけを、帳も巻き物も珍しい装幀を加えて納めることにしていた。
|
【またこのころは、ただ仮名の定めをしたまひて】- 源氏、姫君のための書画類を調える。
【尋ねつつ書かせたまふ】- 大島本は「尋つゝ」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「尋ねて」と校訂する。
|
| 2.7.8 |
|
何もかも珍しい御宝物類、外国の朝廷でさえめったにないような物の中で、この何冊かの本を見たいと心を動かしなさる若い人たちが、世間に多いことであった。
御絵画類をご準備なさる中で、あの『須磨の日記』は、子孫代々に伝えたいとお思いになるが、「もう少し世間がお分りになったら」とお思い返しなさって、まだお取り出しなさらない。
|
他の国の宮廷にもないと思われる華奢を尽くした姫君の他の調度品よりも、この墨蹟の箱を若い人たちはうかがいたく思った。源氏は絵なども整理して姫君に与えるのであったが、須磨で日記のようにして書いた絵巻は姫君へ伝えたいとは思っていたが、もう少し複雑な人生がわかるまではそれをしないほうがよいという見解をもってその中へは加えなかった。
|
【かの『須磨の日記』は、末にも伝へ知らせむと思せど、「今すこし世をも思し知りなむに」と思し返して】- 源氏の心中を叙述。
|
|
第三章 内大臣家の物語 夕霧と雲居雁の物語
|
|
第一段 内大臣家の近況
|
| 3.1.1 |
|
内大臣は、この入内の御準備を、他人事としてお聞きになるが、たいそう気が気でなく、つまらないとお思いになる。
姫君のご様子、女盛りに成長して、もったいないほどにかわいらしい。
所在なげに塞ぎ込んでいらっしゃる様子は、たいへんなお嘆きの種であるが、あの方のご様子は、どうかといえば、いつも変わらず平気なので、「弱気になってこちらから歩み寄るようなのも、体裁が悪いし、相手が夢中だった時に、言うことを聞いていたら」などと、一人お嘆きになって、一途に悪いと責めることもおできになれない。
|
内大臣は宮廷へはいる大がかりな仕度を、自家のことでなく源氏の姫君のこととして噂に聞くのを、非常に物足らず寂しく思っていた。妙齢に達した雲井の雁の姫君は美しくなっていた。結婚もせず結婚談もなくて引きこもっているこの娘が内大臣には苦労の種であった。宰相中将は少しも焦燥するふうを見せずに、冷静な態度を取り続けているのであったから、こちらから、結婚談をしかけることも世間体の悪いことと思われて、熱心に彼が娘を思っていた時に許せばよかったなどと人知れず後悔もしていて、宰相中将の態度ばかりが悪いとも内大臣は思えないのであった。
|
【姫君の御ありさま、盛りにととのひて】- 雲居雁、二十歳。
【心弱く進み寄らむも】- 以下「なびきなましかば」まで、内大臣の心中。「なりし」の「し」(過去の助動詞)、過去を振り返ったニュアンス。「な」(完了の助動詞)「ましか」(反実仮想の助動詞)「ば」(係助詞、仮定)。
【罪をもおほせたまはず】- 大島本は「おほせ給ハす」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「え負ほせたまはず」と校訂する。
|
| 3.1.2 |
かくすこしたわみたまへる御けしきを、宰相の君は聞きたまへど、しばしつらかりし御心を憂しと思へば、つれなくもてなし、しづめて、さすがに他ざまの心はつくべくもおぼえず、心づから戯れにくき折多かれど、「浅緑」聞こえごちし御乳母どもに、納言に昇りて見えむの御心深かるべし。 |
このように少し弱気になられたご様子を、宰相の君はお聞きになるが、ひところ冷たかったお心を酷いと思うと、平気を装い、落ち着いた態度で、そうはいっても他の女をという考えお持ちにならず、自分から求めてやるせない思いをする時は多いが、「浅緑の六位」と申して馬鹿にした御乳母どもに、中納言に昇進した姿を見せてやろうとのお気持ちが強いのであろう。
|
こんなふうに少し気の折れてきたことも宰相中将は聞いているのであったが、まだしばらく恨めしい記憶のなくなるまでは落ち着いていないではならないと思って、内大臣に求めることをしなかった。しかも他の恋の対象を作ろうとするような気もしなかった。自身ながらもこうした窮屈な考え方に反感を持つこともあったが、宰相中将は六位であったことを譏った雲井の雁の乳母たちに対して納言の地位に上ることが先決問題だと信じていた。
|
【戯れにくき折】- 「ありぬやとこころみがてらあひ見ねばたはぶれにくきまでぞ恋しき」(古今集俳諧歌、一〇二五、読人しらず)
【浅緑」聞こえごちし】- 浅緑の袍は六位の装束。
|
|
第二段 源氏、夕霧に結婚の教訓
|
| 3.2.1 |
|
大臣は、「妙に身の固まらないことだ」と、ご心配になって、
|
源氏はどっちつかずに宙に浮いたふうで中将が結婚もしないでいることを見かねて、
|
【大臣は】- 源氏をさす。
【あやしう浮きたるさまかな】- 源氏の心中。結婚の決まらない夕霧の身の上を心配。
|
| 3.2.2 |
「かのわたりのこと、思ひ絶えにたらば、右大臣、中務宮などの、けしきばみ言はせたまふめるを、いづくも思ひ定められよ」 |
「あちらの姫君のこと、思い切ってしまったら、右大臣、中務宮などが娘を縁づけたいご意向であるらしいから、どちらなりともお決めなさい」
|
「あちらとの話をあきらめているのなら、左大臣とか、中務の宮とかからのお話が来ているのだから、だれと結婚をするか決めてしまうとよい」
|
【かのわたりのこと】- 以下「思ひ定められよ」まで、源氏の夕霧への詞。「かのわたり」は雲居雁をさす。「右大臣」「中務宮」はここだけの登場人物。「気色ばみいはせ給ふ」は娘を夕霧に縁づけたい意向をいう。「られ」は尊敬の助動詞。比較的軽い敬語。
|
| 3.2.3 |
|
とおっしゃるが、何ともお返事申し上げず、恐縮したご様子で伺候していらっしゃる。
|
とも言うのであったが、宰相中将は黙って恐縮したふうを見せているだけであった。
|
【御さまにてさぶらひたまふ】- 大島本は「御さまにて」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「さまにて」と「御」を削除する。
|
| 3.2.4 |
「かやうのことは、かしこき御教へにだに従ふべくもおぼえざりしかば、言まぜま憂けれど、今思ひあはするには、かの御教へこそ、長き例にはありけれ。 |
「このようなことは、恐れ多い父帝の御教訓でさえ従おうという気にもならなかったのだから、口をさしはさみにくいが、今考えてみると、あの御教訓こそは、今にも通じるものであった。
|
「こんな問題ではお上の御忠告にも昔の私はお服しすることができなかったのだから、口を出したくはないのだが、今になって考えると、その時の御教訓は永久の真理だったとよくわかる。
|
【かやうのことは】- 以下「ぞ深うあるべき」まで、源氏の夕霧への諭しの詞。
【かしこき御教へに】- 故桐壺院の諭をさす。
|
| 3.2.5 |
つれづれとものすれば、思ふところあるにやと、世人も推し量るらむを、宿世の引く方にて、なほなほしきことにありありてなびく、いと尻びに、人悪ろきことぞや。
|
所在なく独身でいると、何か考えがあるのかと、世間の人も推量するであろうから、運命の導くままに、平凡な身分の女との結婚に結局落ち着くことになるのは、たいそう尻すぼまりで、みっともないことだ。
|
長く独身でいれば、実現されない幻を描いているかのように人も見るだろうし、それが宿命であるかはしらないが、ついには何の価値もない女といっしょになってしまうような結果を生むことにもなっては、初めよし、後わろしになってしまう。
|
|
| 3.2.6 |
|
ひどく高望みしても、思うようにならず、限界があることから、浮気心を起こされるな。
幼い時から宮中で成人して、思い通りに動けず、窮屈に、ちょっとした過ちもあったら、軽率の非難を受けようかと、慎重にしていたのでさえ、それでもやはり好色がましい非難を受けて、世間から非難されたものだ。
|
思い上がっていても若い間はほかから誘惑があるからね、多情な行為におちやすいものだが、堕落をしないように心がけねばならない。宮中に育って、自由らしいことは何一つできずに、ただ過失らしいことが一つあるだけでも世間はやかましく批難するだろうと戦々兢々としていた青年の私でも、やはり恋愛をあさる男のように言われて悪く思われたものなのだ。
|
【限りのあるものから】- 大島本は「かきりのある」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「限りある」と「の」を削除する。
【いはけなくより、宮の内に生ひ出でて】- 以下、源氏の幼少時代の回想。
|
| 3.2.7 |
位浅く、何となき身のほど、うちとけ、心のままなる振る舞ひなどものせらるな。心おのづからおごりぬれば、思ひしづむべきくさはひなき時、女のことにてなむ、かしこき人、昔も乱るる例ありける。 |
位階が低く、気楽な身分だからと、油断して、思いのままの行動などなさるな。
心が自然と思い上がってしまうと、好色心を抑えるべき妻子がいない時、女性関係のことで、賢明な人が、昔も失敗した例があったのだ。
|
身分が低くて注目するものがないなどと思って放縦なことをしてはいけないよ。驕慢の心の盛んな時に、女の問題で賢い人が失敗するようなことは歴史の上にもあることだからね。
|
【思ひしづむべきくさはひ】- 妻子などをさす。
|
| 3.2.8 |
さるまじきことに心をつけて、人の名をも立て、みづからも恨みを負ふなむ、つひのほだしとなりける。とりあやまりつつ見む人の、わが心にかなはず、忍ばむこと難き節ありとも、なほ思ひ返さむ心をならひて、もしは親の心にゆづり、もしは親なくて世の中かたほにありとも、人柄心苦しうなどあらむ人をば、それを片かどに寄せても見たまへ。わがため、人のため、つひによかるべき心ぞ深うあるべき」 |
けしからぬことに熱中して、相手の浮名を立て、自分も恨まれるのは、後世の妨げとなるのだ。
結婚に失敗したと思いながら共に暮らしている相手が、自分の理想通りでなく、我慢することのできない点があっても、やはり思い直す気を持って、もしくは女の親の心に免じて、もしくは親がいなくなって生活が不十分であっても、人柄がいじらしく思われるような人は、その人柄一つを取柄としてお暮らしなさい。
自分のため、相手のため、末長く添い遂げるような思慮が深くあって欲しいものだ」
|
思ってならない人を思って、女の名も立て自身も人の恨みを負うようなことをしては一生の心の負担になる。不運な結婚をして、女の欠点ばかりが目について苦しいようなことがあっても、そうした時に忍耐をして万人を愛する人道的な心を習得するようにつとめるとか、もしくは娘の親たちの好意を思うことで足りないことを補うとか、また親のない人と結婚した場合にも、不足な境遇も妻が価値のある女であればそれで補うに足ると認識すべきだよ。そうした同情を持つことは自身のためにも妻のためにも将来大きな幸福を得る過程になるのだ」
|
【人の名をも立て】- 相手の浮名を立てること。
|
| 3.2.9 |
|
などと、のんびりとした所在のない時は、このような心づかいをしきりにお教えになる。
|
こんなことも言って閑暇のある時にはよく宰相中将を教える源氏であった。
|
【御心づかひをのみ】- 大島本は「御心つかひ」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「心づかひ」と「御」を削除する。
|
|
第三段 夕霧と雲居の雁の仲
|
| 3.3.1 |
|
このようなご教訓に従って、冗談にも他の女に心を移すようなことは、かわいそうなことだと、自分からお思いになっている。
女も、いつもより格別に、大臣が思い嘆いていらっしゃるご様子に、顔向けのできない思いで、つらい身の上と悲観していらっしゃるが、表面はさりげなくおっとりとして、物思いに沈んでお過ごしになっている。
|
この教訓の精神から言っても、仮にも初恋の人を忘れて他の女を思うようなことはできないように中将は思っていた。雲井の雁も近ごろになってことさら父が愁色を見せることを知って恥ずかしく思い、自分は不幸な女であると深く思われるのであったが、表面は素知らぬふうを見せて、おおように物思いをしていた。
|
【恥づかしう、憂き身と思し沈めど】- 『集成』は「顔向けできぬ思いで、情けない身の上と悲観していらっしゃるが。親不孝を恥じる気持」と注す。『完訳』は「自分のせいで父を嘆かせる思うと恥ずかしい。深窓の姫君らしい素直な性格」と注す。
【上はつれなくおほどかにて】- 「葦根はふうきは上こそつれなけれ下はえならず思ふ心を(拾遺集恋四、八九三、読人しらず)
|
| 3.3.2 |
|
お手紙は、我慢しきれない時々に、しみじみと深い思いをこめて書いて差し上げなさる。
「誰の誠実を信じたらよいのか」と思いながら、男を知っている女ならば、むやみに男の心を疑うであろうが、しみじみと御覧になる文句が多いのであった。
|
宰相中将は思い余る時々にだけ情熱のこもった手紙を雲井の雁へ書いた。だが誠をか(偽りと思ふものから今さらにたが誠をかわれは頼まん)と心に思っても、世ずれた人のようにむやみに人を疑うことのない純真な雲井の雁は、中将の手紙に沁んで読まれるところが多いように思われた。
|
【御文は、思ひあまりたまふ折々】- 夕霧から雲居雁への手紙。
【誰がまことをか」と】- 「いつはりと思ふものから今さらに誰がまことをか我は頼まむ(古今集恋四、七一三、読人しらず)
【世馴れたる人こそ、あながちに人の心をも疑ふなれ、あはれと見たまふふし多かり】- 語り手の批評。『新釈』は「記者の批評を挿入したものである」と注す。
|
| 3.3.3 |
|
「中務宮が、大殿のご内意をも伺って、そのようにもと、お約束なさっているそうです」
|
「中務の宮がお嬢さんと宰相中将との縁組みを太政大臣へお申し込みになって大臣も賛成されたようです」
|
【中務宮なむ】- 以下「思し交したなる」まで、女房の内大臣への注進。
|
| 3.3.4 |
|
と女房が申し上げたので、大臣は、改めてお胸がつぶれることであろう。
こっそりと、
|
とこんな噂を内大臣に伝えた者のあった時に、内大臣の心は愁いにふさがれた。大臣はそうした噂の耳にはいったことを雲井の雁にそっと告げた。
|
【大臣は、ひき返し御胸ふたがるべし】- 語り手の内大臣の心中を推測。『完訳』は「雲居雁入内を断念したのに続いて夕霧との結婚をも危ぶむ気持」と注す。
|
| 3.3.5 |
|
「こういうことを聞いた。
薄情なお心の方であったな。
大臣が、口添えなさったのに、強情だというので、他へ持って行かれたのだろう。
気弱になって降参しても、人に笑われることだろうし」
|
「あの人がほかの結婚をしてもよいという気になるとはひどい。太政大臣も口をお入れになったことがあるのに、それでも私が強硬だったものだから、今になって大臣はそんなふうに勧められるのだろう。しかしその場合に私が先方の言いなりに結婚を許しても体面上恥ずかしいことだったのだから」
|
【さることをこそ聞きしか】- 以下「人笑へならましこと」まで、内大臣の詞。雲居雁を前にしていう。
【情けなき人の御心にもありけるかな】- 夕霧をさす。
【大臣の、口入れたまひしに、執念かりきとて】- 源氏の大臣が夕霧と雲居雁との結婚に口添えなさったのに(「行幸」第二章二段にみえる)、強情にも内大臣がそれに従わなかったからといって、の意。
【引き違へたまふなるべし】- 夕霧と中務宮の姫君とを結婚させようとなさるのだろう、の意。
【心弱くなびきても】- 『完訳』は「源氏におもねる不面目。内大臣はこれまでも「人笑へ」を頻発。権門特有の家の恥の意識である」と注す。
|
| 3.3.6 |
など、涙を浮けてのたまへば、姫君、いと恥づかしきにも、そこはかとなく涙のこぼるれば、はしたなくて背きたまへる、らうたげさ限りなし。
|
などと、涙を浮かべておっしゃるので、姫君、とても顔も向けられない思いでいるにも、何とはなしに涙がこぼれるので、体裁悪く思って後ろを向いていらっしゃる、そのかわいらしさ、この上もない。
|
などと、目に涙を浮けて父が言うのを、雲井の雁は恥ずかしく思って聞きながらも、一方では何とはなしに涙が流れ出してくるのをきまり悪く思って、顔をそむけているのが可憐であった。
|
|
| 3.3.7 |
|
「どうしよう。
やはりこちらから申し出て、先方の意向を聞いてみようか」
|
どうすればいいだろう。やはりこちらから折れて出るべきであろうか
|
【いかにせまし。なほや進み出でて、けしきをとらまし】- 内大臣の心中。
|
| 3.3.8 |
など、思し乱れて立ちたまひぬる名残も、やがて端近う眺めたまふ。
|
などと、お気持ちも迷ってお立ちになった後も、そのまま端近くに物思いに沈んでいらっしゃる。
|
などと煩悶をしながら大臣の去ったあとまでも雲井の雁は庭をながめて物思いを続けていた。
|
|
| 3.3.9 |
|
「妙に、思いがけず流れ出てしまった涙だこと。
どのようにお思いになったかしら」
|
これはなんという愚かな涙であろう、どう父は思ったであろう
|
【あやしく、心おくれても進み出でつる涙かな。いかに思しつらむ】- 雲居雁の心中。
|
| 3.3.10 |
|
などと、あれこれと思案なさっているところに、お手紙がある。
それでもやはり御覧になる。
愛情のこもったお手紙で、
|
などと心を悩ましている所へ、宰相中将の手紙が届いた。恨めしく今まで思っていた人ではあるが、さすがに手紙はすぐあけて読んだ。情のこもった手紙であった。
|
【さすがにぞ見たまふ】- 『集成』は「夕霧が怨めしいが、それでもやはりお手紙を御覧になる」と注す。
|
| 3.3.11 |
|
「あなたの冷たいお心は、
つらいこの世の習性となって行きますがそれでも忘れないわた
|
つれなさは浮き世の常になり行くを
忘れぬ人や人にことなる
|
【つれなさは憂き世の常になりゆくを--忘れぬ人や人にことなる】- 夕霧から雲居雁への贈歌。
|
| 3.3.12 |
|
とある。
「そぶりにも仄めかさない、冷たいお方だわ」と、思い続けなさるのはつらいけれども、
|
とも書いてある。父がした話のことなどは少しも書いてないことを雲井の雁は恨めしく思ったが返事を書いた。
|
【けしきばかりもかすめぬ、つれなさよ】- 夕霧の和歌を見た雲居雁の心。「けしき」は夕霧と中務宮の姫君との縁談をさす。
|
| 3.3.13 |
|
「もうこれまでだと、
忘れないとおっしゃるわたしのことを忘れるのは
|
限りとて忘れがたきを忘るるも
こや世に靡く心なるらん
|
【限りとて忘れがたきを忘るるも--こや世になびく心なるらむ】- 雲居雁の返歌。「世」「忘れ」の語句を用いて返す。「世になびく」に縁談のことを言い含む。
|
| 3.3.14 |
とあるを、「あやし」と、うち置かれず、傾きつつ見ゐたまへり。 |
とあるのを、「妙だな」と、下にも置かれず、首をかしげながらじっと座ったまま手紙を御覧になっていた。
|
この歌の意味が腑に落ちないで宰相中将はいつまでも首を傾けていたということである。
|
【あやし】- 夕霧が雲居雁の和歌を見た心。『集成』は「夕霧は、変なことが書いてあると、手紙を下にも置かず、じっと持ったまま不審そうに見ていらっしゃる。ほかの縁談に心を移すことなど、夢にも考えられないので、雲居の雁の歌の意味がすぐに分らないのである」と注す。
|
| 著作権 |
| 底本 |
大島本 |
| 校訂 |
Last updated 9/21/2010(ver.2-3)
渋谷栄一校訂(C)
オリジナル
修正版
比較 |
| ローマ字版 |
Last updated 2/27/2010 (ver.2-2)
Written in Japanese roman letters
by Eiichi Shibuya(C)
オリジナル
修正版
比較 |
ルビ抽出
(ローマ字版から)
|
Powered by 再編集プログラム v4.05
ひらがな版
ルビ抽出 |
挿絵
(ローマ字版から)
|
'Eiri Genji Monogatari'
(1650 1st edition) |
|
Last updated 10/7/2001
渋谷栄一訳(C)(ver.1-2-2)
オリジナル
修正版
比較 |
|
|
Last updated 2/27/2010(ver.2-2)
渋谷栄一注釈(C)
オリジナル
修正版
比較 |
|