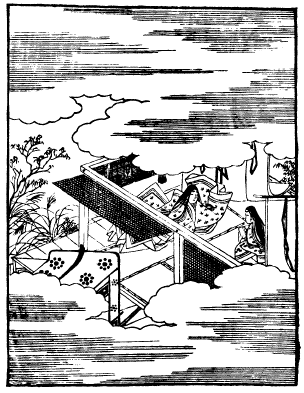第十五帖 蓬生
光る源氏の須磨明石離京時代から帰京後までの末摘花の物語
|
# |
本文 |
渋谷栄一訳 |
与謝野晶子訳 |
注釈 |
|
第一章 末摘花の物語 光る源氏の須磨明石離京時代
|
|
第一段 末摘花の孤独
|
| 1.1.1 |
|
須磨の浦で涙に暮れながら過ごしていらっしゃったころ、都でも、あれこれとお嘆きになっていらっしゃる方々が多かったが、そうはいっても、ご自身の生活のよりどころのある方は、ただお一方をお慕いする思いだけは辛そうであったが、二条の上なども、平穏なお暮らしで、旅のお暮らしをご心配申し、お手紙をやりとりなさっては、位をお退きになってからの仮りのご装束をも、この世の辛い生活をも、季節ごとにご調進申し上げなさることによって、心を慰めなさったであろうが、かえって、その妻妾の一人として世の人にも認められず、ご離京なさった時のご様子にも、他人事のように聞いて思いやった人々で、内心をお痛めになった人も多かった。
|
源氏が須磨、明石に漂泊っていたころは、京のほうにも悲しく思い暮らす人の多数にあった中でも、しかとした立場を持っている人は、苦しい一面はあっても、たとえば二条の夫人などは、源氏が旅での生活の様子もかなりくわしく通信されていたし、便宜が多くて手紙を書いて出すこともよくできたし、当時無官になっていた源氏の無紋の衣裳も季節に従って仕立てて送るような慰みもあった。真実悲しい境遇に落ちた人というのは、源氏が京を出発した際のこともよそに想像するだけであった女性たち、無視して行かれた恋人たちがそれであった。
|
【藻塩垂れつつわびたまひしころほひ、都にも、さまざまに思し嘆く人多かりしを】- 大島本は「さま/\に」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「さまざま」と「に」を削除する。源氏が須磨明石に謫去していた間の都の女性たちの動向。「藻塩垂れつつ」は「わくらばに問ふ人あらば須磨の浦に藻塩垂れつつわぶと答へよ」(古今集雑下、九六二、在原行平)にもとづく表現。
【一方の思ひこそ苦しげなりしか】- 「一方」は源氏をさす。「こそ」係助詞。「しか」過去の助動詞、已然形。係結び。読点で逆接の文脈。
【旅の御住みかをも】- 「聞こえ通ひたまひつつ」に係り、「仮の御よそひをも--時々につけてあつかひきこえたまふに」と並ぶ並列の構文。
【竹の子の世の憂き節を】- 「今さらに何生ひ出づらむ竹の子の憂き節しげき世とは知らずや」(古今集雑下、九五七、凡河内躬恒)を踏まえる。
|
| 1.1.2 |
|
常陸宮の姫君は、父の親王がお亡くなりになってから、他には誰もお世話する人もないお身の上で、ひどく心細い有様であったが、思いがけないお通いが始まって、お気をつけてくださることは絶えなかっが、大変なご威勢には、大したこともない、お情け程度とお思いであったが、それを待ち受けていらっしゃる貧しい生活には、大空の星の光を盥の水に映したような気持ちがして、お過ごしになっていたところ、あのような世の中の騒動が起こって、おしなべて世の中が嫌なことに思い悩まれた折に、格別に深い関係でない方への愛情は、何となく忘れたようになって、遠く旅立ちなさった後は、わざわざお訪ね申し上げることもおできになれない。
かつてのご庇護のお蔭で、しばらくの間は、泣きながらもお過ごしになっていらっしゃったが、歳月が過ぎるにしたがって、実にお寂しいご様子である。
|
常陸の宮の末摘花は、父君がおかくれになってから、だれも保護する人のない心細い境遇であったのを、思いがけず生じた源氏との関係から、それ以来物質的に補助されることになって、源氏の富からいえば物の数でもない情けをかけていたにすぎないのであったが、受けるほうの貧しい女王一家のためには、盥へ星が映ってきたほどの望外の幸福になって、生活苦から救われて幾年かを来たのであるが、あの事変後の源氏は、いっさい世の中がいやになって、恋愛というほどのものでもなかった女性との関係は心から消しもし、消えもしたふうで、遠くへ立ってからははるばると手紙を送るようなこともしなかった。まだ源氏から恵まれた物があってしばらくは泣く泣くも前の生活を続けることができたのであるが、次の年になり、また次の年になりするうちにはまったく底なしの貧しい身の上になってしまった。
|
【常陸宮の君は、父親王の亡せたまひにし名残に】- 末摘花の生活窮乏し、その邸も荒廃する。
【思ひかけぬ御ことの出で来て、訪らひきこえたまふこと絶えざりしを】- 源氏との関係が生じたこと。「訪らひきこえたまふこと」は、源氏本人が直接通って来ることではなく手紙などで間接的に見舞ってやることであろう。
【大空の星の光を盥の水に映したる心地して】- 『完訳』は「さほどでもない源氏の援助も困窮の末摘花には無上の恵みと思われる気持を、大空の無数の星も水面には目だって映るのにたとえた。また盥の水に星影を映すのが七夕行事の一つだという。その七夕の甘美な恋物語のような夢見心地も重なっていよう」と注す。
【かかる世の騷ぎ出で来て】- 源氏の須磨明石流謫事件をさす。
|
| 1.1.3 |
古き女ばらなどは、
|
昔からの女房などは、
|
古くからいた女房たちなどは、
|
|
| 1.1.4 |
|
「いやはや、まったく情けないご運であった。
思いがけない神仏がご出現なさったようであったお心寄せを受けて、このような頼りになることも出ていらっしゃるのだと、ありがたく拝見しておりましたが、世間一般のこととはいいながらも、また他には誰をも頼りにできないお身の上は、悲しいことです」
|
「ほんとうに運の悪い方ですよ。思いがけなく神か仏の出現なすったような親切をお見せになる方ができて、人というものはどこに幸運があるかわからないなどと、私たちはありがたく思ったのですがね、人生というものは移り変わりがあるものだといっても、またまたこんな頼りない御身分になっておしまいになるって、悲しゅうございますね、世の中は」
|
【いでや、いと口惜しき御宿世なりけり】- 以下「悲しけれ」まで、女房の詞。
【おほかたの世の事といひながら】- 『集成』は「(源氏の訪れなくなったのは)ご政治向きのことのためとはいいながら。「おほかたの世のこと」は、ここでは末摘花との個人的な関係に対して、世間一般にかかわる事件。須磨退去をさす」。『完訳』は「移り変わるのは世間の習いとは申すものの」と注す。
|
| 1.1.5 |
|
と、ぶつぶつ言って嘆く。
あのような生活に馴れていた昔の長い年月は、何とも言いようもない寂しさに目なれてお過ごしになっていたが、なまじっか少し世間並みの生活になった年月を送ったばかりに、かえってとても堪え難く嘆くのであろう。
少しでも、女房としてふさわしい者たちは、自然と参集して来たが、みな次々と後を追って離散して行ってしまった。
女房たちの中には亡くなった者もいて、月日の過ぎるにしたがって、上下の女房の数が少なくなって行く。
|
と歎くのであった。昔は長い貧しい生活に慣れてしまって、だれにもあきらめができていたのであるが、中で一度源氏の保護が加わって、世間並みの暮らしができたことによって、今の苦痛はいっそう烈しいものに感ぜられた。よかった時代に昔から縁故のある女房ははじめてここに皆居つくことにもなって、数が多くなっていたのも、またちりぢりにほかへ行ってしまった。そしてまた老衰して死ぬ女もあって、月日とともに上から下まで召使の数が少なくなっていく。
|
【さる方にありつきたりしあなたの年ごろ】- 昔の貧しい生活に慣れていた時代をさす。
【さてありぬべき】- 女房としてふさわしいの意。
【月日に従ひては、上下人数少なくなりゆく】- 大島本は「月日にしたかひてハかみしも」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「従ひて上下の」と「は」を削除し「の」を補訂する。
|
|
第二段 常陸宮邸の窮乏
|
| 1.2.1 |
|
もともと荒れていた宮の邸の中、ますます狐の棲みかとなって、気味悪く、人気のない木立に、梟の声を毎日耳にして、人気のあるによって、そのような物どもも阻まれて姿を隠していたが、木霊などの怪異の物どもが、我がもの顔になって、だんだんと姿を現し、何ともやりきれないことばかりが数知らず増えて行くので、たまたま残っていてお仕えしている女房は、
|
もとから荒廃していた邸はいっそう狐の巣のようになった。気味悪く大きくなった木立ちになく梟の声を毎日邸の人は聞いていた。人が多ければそうしたものは影も見せない木精などという怪しいものも次第に形を顕わしてきたりする不快なことが数しらずあるのである。まだ少しばかり残っている女房は、
|
【もとより荒れたりし宮の内】- 末摘花、荒廃した邸を守りながら生き抜く。
【狐の棲みかになりて】- 以下の文章は、「梟は松桂の枝に鳴き狐は蘭菊の叢に蔵る」(白氏文集、諷諭詩、「凶宅詩」)を踏まえた表現。同様の荒廃した邸の描写に「凶宅詩」を踏まえた表現は「夕顔」巻にも見られる。
【人気にこそ】- 以下「隠しけれ」まで、挿入句。係り結び。逆接の文脈。
【所得て】- 大島本は「ところえて」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「所を得て」と「を」を補訂する。
|
| 1.2.2 |
「なほ、いとわりなし。この受領どもの、おもしろき家造り好むが、この宮の木立を心につけて、放ちたまはせてむやと、ほとりにつきて、案内し申さするを、さやうにせさせたまひて、いとかう、もの恐ろしからぬ御住まひに、思し移ろはなむ。立ちとまりさぶらふ人も、いと堪へがたし」 |
「やはり、まこと困ったことです。
最近の受領どもで、風流な家造りを好む者が、この宮の木立に心をかけて、お手放しにならないかと、伝を求めて、ご意向を伺わせていますが、そのようにあそばして、とてもこう、恐ろしくないお住まいに、ご転居をお考えになってください。
今も残って仕えている者も、とても我慢できません」
|
「これではしようがございません。近ごろは地方官などがよい邸を自慢に造りますが、こちらのお庭の木などに目をつけて、お売りになりませんかなどと近所の者から言わせてまいりますが、そうあそばして、こんな怖しい所はお捨てになってほかへお移りなさいましよ。いつまでも残っております私たちだってたまりませんから」
|
【なほ、いとわりなし】- 以下「いと堪へがたし」まで、女房の詞。姫君に邸を手放し、他の恐しくない邸に移るよう進言する。
|
| 1.2.3 |
など聞こゆれど、
|
などと申し上げるが、
|
などと女主人に勧めるのであったが、
|
|
| 1.2.4 |
「あな、いみじや。人の聞き思はむこともあり。生ける世に、しか名残なきわざ、いかがせむ。かく恐ろしげに荒れ果てぬれど、親の御影とまりたる心地する古き住みかと思ふに、慰みてこそあれ」 |
「まあ、とんでもありません。
世間の外聞もあります。
生きているうちに、そのようなお形見を何もかも無くしてしまうなんて、どうしてできましょう。
このように恐ろしそうにすっかり荒れてしまったが、親の面影がとどまっている心地がする懐かしい住まいだと思うから、慰められるのです」
|
「そんなことをしてはたいへんよ。世間体もあります。私が生きている間は邸を人手に渡すなどということはできるものでない。こんなに恐い気がするほど荒れていても、お父様の魂が残っていると思う点で、私はあちこちをながめても心が慰むのだからね」
|
【あな、いみじや】- 以下「慰みてこそあれ」まで末摘花の返答。
【しか名残なきわざ、いかがせむ】- 大島本は「わさ」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『新大系』は諸本に従って「わざは」と「は」を補訂する。反語表現。父親の形見を何もかも失うことはできない。
|
| 1.2.5 |
と、うち泣きつつ、思しもかけず。
|
と、泣く泣くおっしゃって、お考えにも入れない。
|
女王は泣きながらこう言って、女房たちの進言を思いも寄らぬことにしていた。
|
|
| 1.2.6 |
御調度どもを、いと古代になれたるが、昔やうにてうるはしきを、なまもののゆゑ知らむと思へる人、さるもの要じて、わざとその人かの人にせさせたまへると尋ね聞きて、案内するも、おのづからかかる貧しきあたりと思ひあなづりて言ひ来るを、例の女ばら、 |
お道具類も、たいそう古風で使い馴れているのが、昔風で立派なのを、なまはんかに由緒を尋ねようとする者、そのような物を欲しがって、特別にあの人この人にお作らせになったのだと聞き出して、お伺いを立てるのも、自然とこのような貧しいあたりと侮って言って来るのを、いつもの女房、
|
手道具なども昔の品の使い慣らしたりっぱな物のあるのを、生物識りの骨董好きの人が、だれに製作させた物、某の傑作があると聞いて、譲り受けたいと、想像のできる貧乏さを軽蔑して申し込んでくるのを、例のように女房たちは、
|
【御調度どもを】- 大島本は「御てうとゝも越」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「御調度どもも」と校訂する。
|
| 1.2.7 |
|
「しかたがございません。
そうすることが世間一般のこと」
|
「しかたのないことでございますよ。困れば道具をお手放しになるのは」
|
【いかがはせむ。そこそは世の常のこと】- 女房の心中。『集成』は「もはや仕方がない。それこそ、世間の習いよ」と訳す。
|
| 1.2.8 |
とて、取り紛らはしつつ、目に近き今日明日の見苦しさを繕はむとする時もあるを、いみじう諌めたまひて、
|
と思って、目立たぬように取り計らって、眼前の今日明日の生活の不自由を繕う時もあるのを、きつくお叱りになって、
|
と言って、それを金にかえて目前の窮迫から救われようとする時があると、末摘花は頑強にそれを拒む。
|
|
| 1.2.9 |
「見よと思ひたまひてこそ、しおかせたまひけめ。などてか、軽々しき人の家の飾りとはなさむ。亡き人の御本意違はむが、あはれなること」 |
「わたしのためにとお考えになって、お作らせになったのでしょう。
どうして、賤しい人の家の飾り物にさせましょうか。
亡きお父上のご遺志に背くのが、たまりません」
|
「私が見るようにと思って作らせておいてくだすったに違いないのだから、それをつまらない家の装飾品になどさせてよいわけはない。お父様のお心持ちを無視することになるからね、お父様がおかわいそうだ」
|
【見よと思ひたまひて】- 以下「あはれなること」まで、末摘花の詞。家財道具を売り払うことをきつく諌める。自分の家の家財道具が賎しい家の物になることを不本意と思う。
|
| 1.2.10 |
とのたまひて、さるわざはせさせたまはず。
|
とおっしゃって、そのようなことはおさせにならない。
|
ただ少しの助力でもしようとする人をも持たない女王であった。
|
|
|
第三段 常陸宮邸の荒廃
|
| 1.3.1 |
|
ちょっとした用件でも、お訪ね申す人はないお身の上である。
ただ、ご兄弟の禅師の君だけが、たまに京にお出になる時には、お立ち寄りになるが、その方も、世にもまれな古風な方で、同じ法師という中でも、処世の道を知らない、この世離れした僧でいらっしゃって、生い茂った草、蓬をさえ、かき払うものともお考えつきにならない。
|
兄の禅師だけは稀に山から京へ出た時に訪ねて来るが、その人も昔風な人で、同じ僧といっても生活する能力が全然ない、脱俗したとほめて言えば言えるような男であったから、庭の雑草を払わせればきれいになるものとも気がつかない。
|
【見訪らひ】- 大島本は「見とふらひ」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「とぶらひ」と「見」を削除する。
【御兄の禅師の君】- 末摘花の兄君。後の「初音」巻に「醍醐の阿闍梨の君」と呼称される。今、「まれにも京に出でたまふ時は」とあるのも、山科の醍醐寺あたりを想定してよい。
【たづきなく、この世を離れたる聖にものしたまひて】- 『集成』は「処世のすべを知らず、現世とは縁のない聖のようなお暮しぶりで」と訳す。
|
|
 |
| 1.3.2 |
|
このような状態で、浅茅は庭の表面も見えず、生い茂った蓬生は軒と争って成長している。
葎は西と東の御門を鎖し固めているのは心強いが、崩れかかった周囲の土築を馬、牛などが踏みならした道にして、春夏ともなると、放ち飼いする子どもの料簡も、けしからぬことである。
|
浅茅は庭の表も見えぬほど茂って、蓬は軒の高さに達するほど、葎は西門、東門を閉じてしまったというと用心がよくなったようにも聞こえるが、くずれた土塀は牛や馬が踏みならしてしまい、春夏には無礼な牧童が放牧をしに来た。
|
【葎は西東の御門を閉ぢこめたるぞ頼もしけれど】- 『集成』は「今さらにとふべき人も思ほえず八重葎して門鎖せりてへ」(古今集雑下、九七五、読人しらず)を指摘。
|
| 1.3.3 |
八月、野分荒かりし年、廊どもも倒れ伏し、下の屋どもの、はかなき板葺なりしなどは、骨のみわづかに残りて、立ちとまる下衆だになし。
煙絶えて、あはれにいみじきこと多かり。
|
八月、野分の激しかった年、渡廊類が倒れふし、幾棟もの下屋の、粗末な板葺きであったのなどは、骨組みだけがわずかに残って、居残る下衆さえいない。
炊事の煙も上らなくなって、お気の毒なことが多かった。
|
八月に野分の風が強かった年以来廊などは倒れたままになり、下屋の板葺きの建物のほうはわずかに骨が残っているだけ、下男などのそこにとどまっている者はない。廚の煙が立たないでなお生きた人が住んでいるという悲しい邸である。
|
|
| 1.3.4 |
盗人などいふひたぶる心ある者も、思ひやりの寂しければにや、この宮をば不要のものに踏み過ぎて、寄り来ざりければ、かくいみじき野良、薮なれども、さすがに寝殿のうちばかりは、ありし御しつらひ変らず、つややかに掻い掃きなどする人もなし。塵は積もれど、紛るることなきうるはしき御住まひにて、明かし暮らしたまふ。 |
盗人などという情け容赦のない連中も、想像するだけで貧乏と思ってか、この邸を無用のものと通り過ぎて、寄りつきもしなかったので、このようにひどい野原、薮原であるが、それでも寝殿の中だけは、昔の装飾と変わらないが、ぴかぴかに掃いたり拭いたりする人もいない。
塵は積もっても、れっきとした荘厳なお住まいで、お過ごしになっている。
|
盗人というようながむしゃらな連中も外見の貧弱さに愛想をつかせて、ここだけは素通りにしてやって来なかったから、こんな野良藪のような邸の中で、寝殿だけは昔通りの飾りつけがしてあった。しかしきれいに掃除をしようとするような心がけの人もない。埃は積もってもあるべき物の数だけはそろった座敷に末摘花は暮らしていた。
|
【寄り来ざりければ】- この句の直接係る語句はなく、文脈が別に流れている。
|
|
第四段 末摘花の気紛らし
|
| 1.4.1 |
はかなき古歌、物語などやうのすさびごとにてこそ、つれづれをも紛らはし、かかる住まひをも思ひ慰むるわざなめれ、さやうのことにも心遅くものしたまふ。わざと好ましからねど、おのづからまた急ぐことなきほどは、同じ心なる文通はしなどうちしてこそ、若き人は木草につけても心を慰めたまふべけれど、親のもてかしづきたまひし御心掟のままに、世の中をつつましきものに思して、まれにも言通ひたまふべき御あたりをも、さらに馴れたまはず、古りにたる御厨子開けて、『唐守』、『藐姑射の刀自』、『かぐや姫の物語』の絵に描きたるをぞ、時々のまさぐりものにしたまふ。 |
たわいもない古歌、物語などみたいな物を慰み事にして、無聊を紛らわし、このような生活でも慰める方法なのであろうが、そのような方面にも関心が鈍くいらっしゃる。
特に風流ぶらずとも、自然と急ぐ用事もない時には、気の合う者どうしで手紙の書き交わしなど気軽にし合って、若い人は木や草につけて心をお慰めになるはずなのだが、父宮が大事にお育てになったお考えどおりに、世間を用心すべきものとお思いになって、たまには文通なさってもよさそうなご関係の家にも、まったくお親しみにならず、古くなった御厨子を開けて、『唐守』『藐姑射の刀自』『かぐや姫の物語』などの絵に描いてあるのを、時々のもて遊び物にしていらっしゃる。
|
古い歌集を読んだり、小説を見たりすることでつれづれが慰められることにもなるし、物質的に不足の多い境遇も忍んで行けるのであるが、末摘花はそんな趣味も持っていない。それは必ずしもよいことではないが、暇な女性の間で友情を盛った手紙を書きかわすことなどは、多感な年ごろではそれによって自然の見方も深くなっていき、木や草にも慰められることにもなるが、この女王は父宮が大事にお扱いになった時と同じ心持ちでいて、普通の人との交際はいっさい避けて友人を持っていないのである。親戚関係があっても親しもうとせず、好意を寄せようとしない態度は手紙を書かぬ所にうかがわれもするのである。
|
【すさびごとにてこそ】- 「こそ」は「なめれ」に係る。読点で、逆接の文脈。
【唐守】- 散逸した物語。内容未詳。『宇津保物語』「国譲上」「楼上下」に見える。
【藐姑射の刀自】- 散逸した物語。内容未詳。平安時代から鎌倉時代初期までの物語作品中の和歌を集めた『風葉和歌集』(文永八年撰進)に見える。
【かぐや姫の物語】- 『竹取物語』の別名。
|
| 1.4.2 |
|
古歌といっても、優雅な趣向で選び出して、題詞や読人をはっきりさせて鑑賞するのは見所もあるが、きちんとした紙屋紙、陸奥紙などの厚ぼったいのに、古歌のありふれた歌が書かれているのなどは、実に興醒めな感じがするが、つとめて物思いに耽りなさるような時々には、お広げになっている。
今の時代の人が好んでするような、読経をちょっとしたり、勤行などということは、とてもきまり悪いものとお考えになって、拝見する人もいないのだが、数珠などをお取り寄せにならない。
このように万事きちんとしていらっしゃるのであった。
|
古くさい書物棚から、唐守、藐姑射の刀自、赫耶姫物語などを絵に描いた物を引き出して退屈しのぎにしていた。古歌などもよい作を選って、端書きも作者の名も書き抜いて置いて見るのがおもしろいのであるが、この人は古紙屋紙とか、檀紙とかの湿り気を含んで厚くなった物などへ、だれもの知っている新味などは微塵もないようなものの書き抜いてしまってあるのを、物思いのつのった時などには出して拡げていた。今の婦人がだれもするように経を読んだり仏勤めをしたりすることは生意気だと思うのかだれも見る人はないのであるが、数珠を持つようなことは絶対にない。こんなふうに末摘花は古典的であった。
|
【をかしきやうに選り出で、題をも読人をもあらはし心得たるこそ見所もありけれ】- 『集成』は「おもしろい趣向で選択編集し、詞書(歌の成立事情)や作者をもはっきりさせて、歌の気持のよく分るのが興をそそるのだが」「歌物語風のものであろう」。『完訳』「味わい深い趣向で選び出し、題詞や詠み人がはっきり書いてあって、その意味のよく分るのは見ごたえもあるのだが」「歌を、題詞・作者など作歌事情とともに観賞。当時の観賞法」と注す。
【うるはしき紙屋紙、陸奥紙などのふくだめる】- 『新大系』は「紙屋(製紙所)で漉いた紙の意で、陸奥紙とともに、撰集の清書、女の手紙などには用いない。「うるはしき」は、色気のないの意」「陸奥紙の厚くて毛ばだった状態をいう」と注す。
|
|
第五段 乳母子の侍従と叔母
|
| 1.5.1 |
侍従などいひし御乳母子のみこそ、年ごろあくがれ果てぬ者にてさぶらひつれど、通ひ参りし斎院亡せたまひなどして、いと堪へがたく心細きに、この姫君の母北の方のはらから、世におちぶれて受領の北の方になりたまへるありけり。 |
侍従などと言った御乳母子だけが、長年お暇も取ろうともしない者としてお仕えしていたが、お出入りしていた斎院がお亡くなりなったりなどして、まことに生活が苦しく心細い気がしていたところ、この姫君の母北の方の姉妹で、落ちぶれて受領の北の方におなりになっていた人がいた。
|
侍従という乳母の娘などは、主家を離れないで残っている女房の一人であったが、以前から半分ずつは勤めに出ていた斎院がお亡くれになってからは、侍従もしかたなしに女王の母君の妹で、その人だけが身分違いの地方官の妻になっている人があって、
|
【侍従などいひし御乳母子のみこそ】- 「末摘花」巻に既出の人物。
|
| 1.5.2 |
娘どもかしづきて、よろしき若人どもも、「むげに知らぬ所よりは、親どももまうで通ひしを」と思ひて、時々行き通ふ。この姫君は、かく人疎き御癖なれば、むつましくも言ひ通ひたまはず。 |
娘たちを大切にしていて、見苦しくない若い女房たちも、「全然知らない家よりは、親たちが出入りしていた所を」と思って、時々出入りしている。
この姫君は、このように人見知りするご性格なので、親しくお付き合いなさらない。
|
娘をかしずいて、若いよい女房を幾人でもほしがる家へ、そこは死んだ母もおりふし行っていた所であるからと思って、時々そこへ行って勤めていた。末摘花は人に親しめない性格であったから、叔母ともあまり交際をしなかった。
|
【よろしき若人ども】- 「よろし」は「よし」よりも一段劣った意味。
|
| 1.5.3 |
「おのれをばおとしめたまひて、面伏せに思したりしかば、姫君の御ありさまの心苦しげなるも、え訪らひきこえず」 |
「わたしを軽蔑なさって、不名誉にお思いであったから、姫君のご生活が困窮しているようなのも、お見舞い申し上げられないのです」
|
「お姉様は私を軽蔑なすって、私のいることを不名誉にしていらっしゃったから、姫君が気の毒な一人ぼっちでも私は世話をしてあげないのだよ」
|
【おのれをばおとしめたまひて】- 以下「え訪らひきこえず」まで、叔母の詞。末摘花の母親が受領と結婚したことを軽蔑し、一門の不名誉に思っていたという。侍従を前にして述べているので、敬語を使っている。
|
| 1.5.4 |
など、なま憎げなる言葉ども言ひ聞かせつつ、時々聞こえけり。
|
などと、こ憎らしい言葉を言って聞かせては、時々手紙を差し上げた。
|
などという悪態口も侍従に聞かせながら、時々侍従に手紙を持たせてよこした。
|
|
| 1.5.5 |
もとよりありつきたるさやうの並々の人は、なかなかよき人の真似に心をつくろひ、思ひ上がるも多かるを、やむごとなき筋ながらも、かうまで落つべき宿世ありければにや、心すこしなほなほしき御叔母にぞありける。
|
もともと生まれついたそのような並みの人は、かえって高貴な人の真似をすることに神経をつかって、お高くとまっている人も多くいるが、高貴なお血筋ながらも、こうまで落ちぶれる運命だったからであろうか、心が少し卑しい叔母だったのであった。
|
初めから地方官級の家に生まれた人は、貴族をまねて、思想的にも思い上がった人になっている者も多いのに、この夫人は貴族の出でありながら、下の階級へはいって行く運命を生まれながらに持っていたものか、卑しい性格の叔母君であった。
|
|
| 1.5.6 |
「わがかく劣りのさまにて、あなづらはしく思はれたりしを、いかで、かかる世の末に、この君を、わが娘どもの使人になしてしがな。心ばせなどの古びたる方こそあれ、いとうしろやすき後見ならむ」と思ひて、 |
「わたしがこのように落ちぶれたさまを、軽蔑されていたのだから、何とかして、このような宮家の衰退した折に、この姫君を、自分の娘たちの召し使いにしたいものだ。
考え方の古風なところがあるが、それはいかにも安心できる世話役といえよう」と思って、
|
自身が、家門の顔汚しのように思われていた昔の腹いせに、常陸の宮の女王を自身の娘たちの女房にしてやりたい、昔風なところはあるが気だてのよい後見役ができるであろうとこんなことを思って、
|
【わがかく劣りのさまにて】- 以下「後見ならむ」まで、叔母の心中。末摘花を自分の娘たちの使用人にして復讐してやろう、末摘花の古風なところはあるが、かえって安心だ、と考える。
【いかで】- 大島本は「いかて」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「いかでか」と「か」を補訂する。
|
| 1.5.7 |
|
「時々こちらにお出あそばして。
お琴の音を聴きたがっている人がおります」
|
時々私の宅へもおいでくだすったらいかがですか。あなたのお琴の音も伺いたがる娘たちもおります。
|
【時々ここに渡らせたまひて】- 以下「人なむはべる」まで、叔母の詞。末摘花を叔母の家に誘い出す。
|
| 1.5.8 |
と聞こえけり。
この侍従も、常に言ひもよほせど、人にいどむ心にはあらで、ただこちたき御ものづつみなれば、さもむつびたまはぬを、ねたしとなむ思ひける。
|
と申し上げた。
この侍従も、いつもお勧めするが、人に張り合う気持ちからではないが、ただ大変なお引っ込み思案なので、そのように親しくなさらないのを、憎らしく思うのであった。
|
と言って来た。これを実現させようと叔母は侍従にも促すのであるが、末摘花は負けじ魂からではなく、ただ恥ずかしくきまりが悪いために、叔母の招待に応じようとしないのを、叔母のほうではくやしく思っていた。
|
|
| 1.5.9 |
|
こうしているうちに、あの叔母の夫が、大宰大弍になった。
娘たちをしかるべく縁づけて、筑紫に下向しようとする。
この姫君を、なおも誘おうという執念が深くて、
|
そのうちに叔母の良人が九州の大弐に任命された。娘たちをそれぞれ結婚させておいて、夫婦で任地へ立とうとする時にもまだ叔母は女王を伴って行きたがって、
|
【かかるほどに、かの家主人、大弐になりぬ】- 叔母の夫が大宰大弍になったので、末摘花を筑紫に連れて行こうとする。娘たちは都の人に縁づけて、今度は自分の使用人にするつもりである。
|
| 1.5.10 |
「はるかに、かくまかりなむとするに、心細き御ありさまの、常にしも訪らひきこえねど、近き頼みはべりつるほどこそあれ、いとあはれにうしろめたくなむ」 |
「遥か遠方に、このように赴任することになりましたが、心細いご様子が、つねにお見舞い申し上げていたわけではありませんでしたが、近くにいるという安心感があった間はともかく、とても気の毒で心配でなりません」
|
「遠方へ行くことになりますと、あなたが心細い暮らしをしておいでになるのを捨てておくことが気になってなりません。ただ今までもお構いはしませんでしたが、近い所にいるうちはいつでもお力になれる自信がありましたので」
|
【はるかに、かく】- 以下「うしろめたくなむ」まで、叔母の詞。末摘花を筑紫に連れて行こうとする言葉巧みな誘い。
【まかりなむとするに】- 大島本は「ま△(△#)か(か$)りなむ」とある。すなわち二文字を抹消とミセケチにしたために、語形が壊れてしまっている。おそらく原文「まかかりなむ」とあったところを、初め後出の「か」をミセケチにしたのだが、後人がその小さなミセケチ符号を見落とし、その前の「か(可)」をまで抹消してしまったのであろう。その結果、語形が壊れてしまったものであろう。
|
| 1.5.11 |
など、言よがるを、さらに受け引きたまはねば、
|
などと、言葉巧みに言うが、まったくご承知なさらないので、
|
と体裁よく言づてて誘いかけるのも、女王が聞き入れないから、
|
|
| 1.5.12 |
「あな、憎。ことことしや。心一つに思し上がるとも、さる薮原に年経たまふ人を、大将殿も、やむごとなくしも思ひきこえたまはじ」 |
「まあ、憎らしい。
ご大層なこと。
自分一人お高くとまっていても、あのような薮原に過ごしていらっしゃる人を、大将殿も、大事にお思い申し上げないでしょう」
|
「まあ憎らしい。いばっていらっしゃる。自分だけはえらいつもりでも、あの藪の中の人を大将さんだって奥様らしくは扱ってくださらないだろう」
|
【あな、憎。ことことしや】- 以下「思ひきこえたまはじ」まで、叔母の詞。『完訳』は「末摘花にではなく、第三者に漏らした発言であろう」と注す。
|
| 1.5.13 |
など、怨じうけひけり。
|
などと、恨んだり呪ったりしているのであった。
|
と言ってののしった。
|
|
|
第二章 末摘花の物語 光る源氏帰京後
|
|
第一段 顧みられない末摘花
|
| 2.1.1 |
さるほどに、げに世の中に赦されたまひて、都に帰りたまふと、天の下の喜びにて立ち騒ぐ。我もいかで、人より先に、深き心ざしを御覧ぜられむとのみ、思ひきほふ男、女につけて、高きをも下れるをも、人の心ばへを見たまふに、あはれに思し知ること、さまざまなり。かやうに、あわたたしきほどに、さらに思ひ出でたまふけしき見えで月日経ぬ。 |
そうこうしているうちに、はたして天下に赦免されなさって、都にお帰りになるというので、世の中の慶事として大騷ぎする。
自分も何とか、人より先に、深い誠意をご理解いただこうとばかりに、競い合っている男、女につけても、身分の貴い人も賤しい人も、人の心の動きを御覧になるにつけ、しみじみと考えさせられること、さまざまである。
このように、あわただしいうちに、まったくお思い出しになる様子もなく月日が過ぎた。
|
そのうちに源氏宥免の宣旨が下り、帰京の段になると、忠実に待っていた志操の堅さをだれよりも先に認められようとする男女に、それぞれ有形無形の代償を喜んで源氏の払った時期にも、末摘花だけは思い出されることもなくて幾月かがそのうちたった。
|
【人の心ばへを見たまふに、あはれに思し知ること、さまざまなり】- 『完訳』は「源氏は、不遇の時期の世人の向背のさまを見てきたが、それと比べて人間の本性を思う」と注し、「人の心の動きをお察しになり、胸中しみじみとお悟りになることがさまざまである」と訳す。
|
| 2.1.2 |
|
「今はもうお終いだ。
長い年月、ご不運な生活を、悲しくお気の毒なことと思いながらも、万物の蘇る春にめぐりあっていただきたいと願っていたが、とるにたらない下賤な者までが喜んでいるという、ご昇進などするのを、他人事として聞かねばならないのだった。
悲しかった時の嘆かしさは、ただ自分ひとりのために起こったのだと思ったが、嘆いても甲斐のない仲だわ」とがっかりして、辛く悲しいので、人知れず声を立ててお泣きになるばかりである。
|
もう何の望みもかけられない。長い間不幸な境遇に落ちていた源氏のために、その勢力が宮廷に復活する日があるようにと念じ暮らしたものであるのに、賤しい階級の人でさえも源氏の再び得た輝かしい地位を喜んでいる時にも、ただよそのこととして聞いていねばならぬ自分でなければならなかったか、源氏が京から追われた時には自分一人の不幸のように悲しんだが、この世はこんな不公平なものであるのかと思って末摘花は恨めしく苦しく切なく一人で泣いてばかりいた。
|
【今は限りなりけり】- 以下「かひなき世かな」まで、末摘花の心中。源氏の無事帰京を祈りながらも、帰京の後、まったく顧みられないことに絶望していく。
【萌え出づる春に逢ひたまはなむ】- 「岩そそくたるひの上の早蕨の萌え出づる春になりにけるかな」(古今六帖、一月、志貴皇子)を踏まえる。
【わが身一つのために】- 「世の中は昔よりやは憂かりけむわが身一つのためになれるか」(古今集雑下、九四八、読人しらず)の言葉によったもの。
|
| 2.1.3 |
大弐の北の方、
|
大弍の北の方、
|
大弐の夫人は、
|
|
| 2.1.4 |
「さればよ。まさに、かくたづきなく、人悪ろき御ありさまを、数まへたまふ人はありなむや。仏、聖も、罪軽きをこそ導きよくしたまふなれ、かかる御ありさまにて、たけく世を思し、宮、上などのおはせし時のままにならひたまへる、御心おごりの、いとほしきこと」 |
「それ見たことか。
いったい、このように不如意で、体裁の悪い人のご様子を、一人前にお扱いになる方がありましょうか。
仏、聖も、罪の軽い人をよくお導きもなさるというものだが、このようなご様子で、偉そうに世間を見下しなさって、宮、上などが生きていらした時のままと同じようでいらっしゃる、ご高慢が、不憫なこと」
|
私の言ったとおりじゃないか。どうしてあんな見る影もない人を源氏の君が奥様の一人だとお思いになるものかね、仏様だって罪の軽い者ほどよく導いてくださるのだ。手もつけられないほどの貧乏女でいて、いばっていて、宮様や奥さんのいらっしゃった時と同じように思い上がっているのだから始末が悪いなどと思っていっそう軽蔑的に末摘花を見た。
|
【さればよ】- 以下「いとほしきこと」まで、叔母の心中。侮蔑と憐愍。
【いとほしきこと】- 『集成』は「困ったものだ」。『完訳』は「じつに不憫なこと」と訳す。
|
| 2.1.5 |
と、いとどをこがましげに思ひて、
|
と、ますます馬鹿らしく思って、
|
|
|
| 2.1.6 |
|
「やはり、ご決心なさい。
何かとうまく行かない時は、何も見なくてすむ山奥へ入りこむというものですよ。
地方などは、むさ苦しい所とお思いでしょうが、むやみに体裁の悪いもてなしは、けっして、致しません」
|
「ぜひ決心をして九州へおいでなさい。世の中が悲しくなる時には、人は進んでも旅へ出るではありませんか。田舎とはいやな所のようにお思いになるかしりませんが、私は受け合ってあなたを楽しくさせます」
|
【なほ、思ほし立ちね】- 以下「もてなしきこえじ」まで、叔母の詞。言葉巧みに筑紫へ誘う。
【世の憂き時は、見えぬ山路をこそは尋ぬなれ】- 「み吉野の山のあなたに宿もがな世の憂き時の隠れ家にせむ」(古今集雑下、九五〇、読人しらず)「世の憂き目見えぬ山路へ入らむには思ふ人こそほだしなりけれ」(古今集雑下、九五五、物部吉名)を踏まえた表現。古歌の文句を引用して説得する。
|
| 2.1.7 |
など、いとよく言へば、むげに屈んじにたる女ばら、
|
などと、とても言葉巧みに言うと、すっかり元気をなくしている女房たちは、
|
口前よく熱心に同行を促すと、貧乏に飽いた女房などは、
|
|
| 2.1.8 |
「さもなびきたまはなむ。たけきこともあるまじき御身を、いかに思して、かく立てたる御心ならむ」 |
「そのようにご承知なさってほしい。
たいしたこともなさそうなお身の上を、どうお考えになって、このように意地をお張りになるのだろう」
|
「そうなればいいのに、何のたのむ所もない方が、どうしてまた意地をお張りになるのだろう」
|
【さもなびきたまはなむ】- 以下「御心ならむ」まで、女房たちのつぶやき。「なむ」終助詞、他に対する願望の意。
|
| 2.1.9 |
と、もどきつぶやく。
|
と、ぶつぶつと非難する。
|
と言って、末摘花を批難した。
|
|
| 2.1.10 |
侍従も、かの大弐の甥だつ人、語らひつきて、とどむべくもあらざりければ、心よりほかに出で立ちて、
|
侍従も、あの大弍の甥に当たる人に、契りを結んで、残して行くはずもなかったので、不本意ながら出発することになって、
|
侍従も大弐の甥のような男の愛人になっていて、京へ残ることもできない立場から、その意志でもなく女王のもとを去って九州行きをすることになっていた。
|
|
| 2.1.11 |
|
「お残し申したままで出立するのが、とても心残りです」
|
「京へお置きして参ることは気がかりでなりませんからいらっしゃいませ」
|
【見たてまつり置かむが、いと心苦しきを】- 侍従の詞。
|
| 2.1.12 |
とて、そそのかしきこゆれど、なほ、かくかけ離れて久しうなりたまひぬる人に頼みをかけたまふ。御心のうちに、「さりとも、あり経ても、思し出づるついであらじやは。あはれに心深き契りをしたまひしに、わが身は憂くて、かく忘られたるにこそあれ、風のつてにても、我かくいみじきありさまを聞きつけたまはば、かならず訪らひ出でたまひてむ」と、年ごろ思しければ、おほかたの御家居も、ありしよりけにあさましけれど、わが心もて、はかなき御調度どもなども取り失はせたまはず、心強く同じさまにて念じ過ごしたまふなりけり。 |
と言って、お誘い申し上げるが、やはり、このように離れてしばらくになってしまった方に期待をかけなさっている。
お心の中では、「いくら何でも、時のたつうちには、お思い出しくださる機会のないことがあろうか。
しみじみと深いお約束をなさったのだから、わが身の上はつらくて、このように忘れられているようであるが、風の便りにでも、わたしのこのようにひどい暮らしをお耳になさったら、きっとお訪ねになってくださるにちがいない」と、長年お思いになっていたので、おおよそのお住まいも以前より実に荒廃してひどいが、ご自分のお考えで、ちょっとした御調度類なども失くさないようにさせなさって、辛抱強く同じように堪え忍んでてお過ごしになっているのであった。
|
と誘うのであるが、女王の心はなお忘れられた形になっている源氏を頼みにしていた。どんなに時がたっても自分の思い出される機会のないわけはない、あれほど堅い誓いを自分にしてくれた人の心は変わっていないはずであるが、自分の運の悪いために捨てられたとも人からは見られるようなことになっているのであろう、風の便りででも自分の哀れな生活が源氏の耳にはいればきっと救ってくれるに違いないと、これはずっと以前から女王の信じているところであって、邸も家も昔に倍した荒廃のしかたではあるが、部屋の中の道具類をそこばくの金に変えていくようなことは、源氏の来た時に不都合であるからと忍耐を続けているのである。
|
【さりとも】- 以下「訪らひ出でたまひてむ」まで、末摘花の心中。源氏がいつの日にか思い出してくれるだろうという期待。
【あらじやは】- 「じ」打消推量の助動詞。「やは」係助詞、反語。ないことがあろうか、きっとあろう。強い期待がこめられている。
【したまひしに】- 「に」接続助詞。『集成』は「して下さったのに」。『完訳』は「なさったのだから」と訳す。
【取り失はせたまはず】- 「せ」使役の助動詞。女房らに失わさせなさらずの意。
|
| 2.1.13 |
音泣きがちに、いとど思し沈みたるは、ただ山人の赤き木の実一つを顔に放たぬと見えたまふ、御側目などは、おぼろけの人の見たてまつりゆるすべきにもあらずかし。詳しくは聞こえじ。いとほしう、もの言ひさがなきやうなり。 |
声を立てて泣き暮らしながら、ますます悲嘆に暮れていらっしゃるのは、まるで山人が赤い木の実一つを顔から放さないようにお見えになる、その横顔などは、普通の男性ではとても堪えて拝見できないご容貌である。
詳しくお話し申し上げられない。
お気の毒で、あまりに口が悪いようであるから。
|
気をめいらせて泣いている時のほうが多い末摘花の顔は、一つの木の実だけを大事に顔に当てて持っている仙人とも言ってよい奇怪な物に見えて、異性の興味を惹く価値などはない。気の毒であるからくわしい描写はしないことにする。
|
【詳しくは】- 以下「なきやうなり」まで、語り手の文章。『集成』は「草子地」。『完訳』は「気の毒で語れぬとする語り手の省筆」と注す。
|
|
第二段 法華御八講
|
| 2.2.1 |
冬になりゆくままに、いとど、かき付かむかたなく、悲しげに眺め過ごしたまふ。かの殿には、故院の御料の御八講、世の中ゆすりてしたまふ。ことに僧などは、なべてのは召さず、才すぐれ行なひにしみ、尊き限りを選らせたまひければ、この禅師の君参りたまへりけり。 |
冬になってゆくにつれて、ますます、すがりつくべきてだてもなく、悲しそうに物思いに沈んでお過ごしになる。
あの殿におかれては、故院の御追善の御八講を、世間でも大騷ぎとなって盛大に催しなさる。
特に僧侶などは、普通の僧はお召しにならず、学問の優れ修行を積んだ、高徳の僧だけをお選びあそばしたので、この禅師の君も参上なさっていた。
|
冬にはいればはいるほど頼りなさはひどくなって、悲しく物思いばかりして暮らす女王だった。源氏のほうでは故院のための盛んな八講を催して、世間がそれに湧き立っていた。僧などは平凡な者を呼ばずに学問と徳行のすぐれたのを選んで招じたその物事に、
|
【冬になりゆくままに】- 季節は冬に推移。冬、神無月、源氏御八講を催し、末摘花の兄の禅師招かれる。叔母、侍従を連れて筑紫に下る。末摘花の孤独、一層深まる。
【選らせたまひければ】- 「せ」尊敬の助動詞。源氏の動作を二重敬語で表現。
|
| 2.2.2 |
帰りざまに立ち寄りたまひて、
|
帰りがけにお立ち寄りになって、
|
女王の兄の禅師も出た帰りに妹君を訪ねて来た。
|
|
| 2.2.3 |
「しかしか。権大納言殿の御八講に参りてはべるなり。いとかしこう、生ける浄土の飾りに劣らず、いかめしうおもしろきことどもの限りをなむしたまひつる。仏菩薩の変化の身にこそものしたまふめれ。五つの濁り深き世に、などて生まれたまひけむ」 |
「これこれでした。
権大納言殿の御八講に参上しておったのです。
たいそう立派で、この世の極楽浄土の装飾に負けず、荘厳で興趣のぜいをお尽くしになっていた。
仏か菩薩の化身でいらっしゃるのだろう。
五濁に深く染まっているこの世に、どうしてお生まれになったのだろう」
|
「源大納言さんの八講に行ったのです。たいへんな準備でね、この世の浄土のように法要の場所はできていましたよ。音楽も舞楽もたいしたものでしたよ。あの方はきっと仏様の化身だろう、五濁の世にどうして生まれておいでになったろう」
|
【しかしか】- 以下「生まれたまひけむ」まで、禅師の詞。御八講の日の源氏の素晴らしさを礼讃する。「この形は江戸時代以後シカジカと濁音化した」(岩波古語辞典)。
【参りてはべるなり】- 大島本は「まいりて侍へるなり」とある。『新大系』は底本のまま「侍へるなり」とする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「はべりつるなり」と校訂する。
|
| 2.2.4 |
と言ひて、やがて出でたまひぬ。
|
と言って、そのまますぐにお帰りになってしまった。
|
こんな話をして禅師はすぐに帰った。
|
|
| 2.2.5 |
言少なに、世の人に似ぬ御あはひにて、かひなき世の物語をだにえ聞こえ合はせたまはず。「さても、かばかりつたなき身のありさまを、あはれにおぼつかなくて過ぐしたまふは、心憂の仏菩薩や」と、つらうおぼゆるを、「げに、限りなめり」と、やうやう思ひなりたまふに、大弐の北の方、にはかに来たり。 |
言葉少なで、世間の人と違ったご兄妹どうしであって、ちょっとした世間話でさえお交わしなされない。
「それにしても、このように不甲斐ない身の上を、悲しく不安なままに放ってお過ごしになるとは、辛い仏菩薩様だわ」と、辛く思われるが、「いかにも、これきりの縁なのだろう」と、だんだんお考えになっているところに、大弐の北の方が、急に来た。
|
普通の兄弟のようには話し合わない二人であるから、生活苦も末摘花は訴えることができないのである。それにしてもこの不幸なみじめな女を捨てて置くというのは、情けない仏様であると末摘花は恨めしかった。こんな気のした時から、自分はもう顧みられる望みがないのだろうとようやく思うようになった。そんなころであるが大弐の夫人が突然訪ねて来た。
|
【さても、かばかりつたなき身の】- 以下「心憂の仏菩薩や」まで、末摘花の心中。源氏を仏菩薩に喩えるも訪れてくれないことを恨めしく思う。
【げに、限りなめり】- 末摘花の心中。「げに」は叔母の言葉を受けて、なるほど、の意。絶望的に思う。
|
|
第三段 叔母、末摘花を誘う
|
| 2.3.1 |
例はさしもむつびぬを、誘ひ立てむの心にて、たてまつるべき御装束など調じて、よき車に乗りて、面もち、けしき、ほこりかにもの思ひなげなるさまして、ゆくりもなく走り来て、門開けさするより、人悪ろく寂しきこと、限りもなし。左右の戸もみなよろぼひ倒れにければ、男ども助けてとかく開け騒ぐ。いづれか、この寂しき宿にもかならず分けたる跡あなる三つの径と、たどる。 |
いつもはそんなに親しくしないのに、お誘い申そうとの考えで、お召しになるご装束など準備して、よい車に乗って、顔つき、態度も、得意に物思いのない様子で、予告もなくやって来て、門を開けさせるや、見苦しく寂しい様子、この上もない。
左右の戸もみな傾き倒れてしまっていたので、男どもが手助けして、あれこれと大騷ぎして開ける。
どれがそれか、この寂しい宿にも必ず踏み分けた跡があるという三つの道はと、探し当てて行く。
|
平生はそれほど親密にはしていないのであるが、つれて行きたい心から、作った女王の衣裳なども持って、よい車に乗って来た得意な顔の夫人がにわかに常陸の宮邸へ現われたのである。門をあけさせている時から目にはいってくるものは荒廃そのもののような寂しい庭であった。門の扉も安定がなくなっていて倒れたのを、供の者が立て直したりする騒ぎである。この草の中にもどこかに三つだけの道はついているはずであると皆が捜した。
|
【ゆくりもなく走り来て】- 『集成』は「都合も聞かずに」。『完訳』は「不意に車を走らせてきて」と訳す。
【限りもなし】- 大島本は「かきりもなし」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「限りなし」と「も」を削除する。
【跡あなる三つの径】- 「なる」伝聞推定の助動詞。漢蒋*(言+羽)が庭に三逕を作り松・菊・竹を植えたという故事(蒙求)。「三径ハ荒ニ就ケドモ、松菊猶存セリ」(文選、帰去来の辞・陶淵明)の隠遁者の住まいをいう。日本では「門へ行く道、井へ行く道、厠へ行く道」(紫明抄)という説がある。
|
|
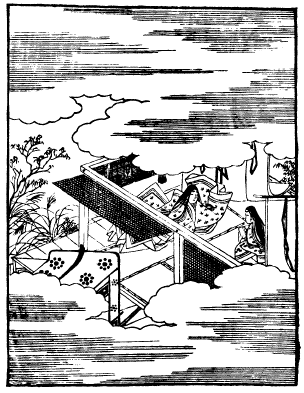 |
| 2.3.2 |
わづかに南面の格子上げたる間に寄せたれば、いとどはしたなしと思したれど、あさましう煤けたる几帳さし出でて、侍従出で来たり。
容貌など、衰へにけり。
年ごろいたうつひえたれど、なほものきよげによしあるさまして、かたじけなくとも、取り変へつべく見ゆ。
|
かろうじて南面の格子を上げている一間に車を寄せたので、ますますどうしてよいか分からなくお思いになったが、あきれるくらい煤けた几帳を差し出して、侍従が出て来た。
容貌など、衰えてしまっていた。
長年のうちにひどくやせ細っているが、やはりどことなく品のある感じで、恐れ多いことであるが、姫君と取り替えたいくらいに見える。
|
そしてやっと建物の南向きの縁の所へ車を着けた。きまりの悪い迷惑なことと思いながら女王は侍従を応接に出した。煤けた几帳を押し出しながら侍従は客と対したのである。容貌は以前に比べてよほど衰えていた。しかしやつれながらもきれいで、女王の顔に代えたい気がする。
|
|
| 2.3.3 |
「出で立ちなむことを思ひながら、心苦しきありさまの見捨てたてまつりがたきを。侍従の迎へになむ参り来たる。心憂く思し隔てて、御みづからこそあからさまにも渡らせたまはね、この人をだに許させたまへとてなむ。などかうあはれげなるさまには」 |
「旅立とうと思いながらも、お気の毒な様子がお見捨て申し上げにくくて。
侍従の迎えに参上しました。
お嫌いになりよそよそしくして、ご自身ではちょっとでもお越しあそばされませんが、せめてこの人だけはお許しいただきたく思いまして。
どうしてこのような寂しいさまで」
|
「もう出発しなければならないのですが、こちらのことが気がかりなものですから、今日は侍従の迎えがてらお訪ねしました。私の好意をくんでくださらないで、御自分がちょっとでも来てくださることを御承知にならないことはやむをえませんが、せめて侍従だけをよこしていただくお許しをいただきに来たのです。まあお気の毒なふうで暮らしていらっしゃるのですね」
|
【出で立ちなむことを】- 以下「さまには」まで、叔母の詞。侍従を迎えに来た旨を告げる。
|
| 2.3.4 |
|
と言って、つい泣き出してしまうはずのところだ。
けれども旅先に思いを馳せて、とても気分よさそうである。
|
こう言ったのであるから、続いて泣いてみせねばならないのであるが、実は大弐夫人は九州の長官夫人になって出発して行く希望に燃えているのである。
|
【うちも泣くべきぞかし】- 『集成』は「(世の常の人なら)ここで思わず泣きもするところだ。叔母を皮肉った草子地」と注す。
|
| 2.3.5 |
「故宮おはせしとき、おのれをば面伏せなりと思し捨てたりしかば、疎々しきやうになりそめにしかど、年ごろも、何かは。やむごとなきさまに思しあがり、大将殿などおはしまし通ふ御宿世のほどを、かたじけなく思ひたまへられしかばなむ、むつびきこえさせむも、憚ること多くて、過ぐしはべるを、世の中のかく定めもなかりければ、数ならぬ身は、なかなか心やすくはべるものなりけり。及びなく見たてまつりし御ありさまの、いと悲しく心苦しきを、近きほどはおこたる折も、のどかに頼もしくなむはべりけるを、かく遥かにまかりなむとすれば、うしろめたくあはれになむおぼえたまふ」 |
「故宮がご存命でいらした時、わたしを不名誉な者とお思い捨てになっていらしたので、疎遠なようになってしまいましたが、今までにも、どうしてそう思ったでしょうか。
高貴なお身の上に気位い高くお持ちになり、大将殿などがお通いになるご運勢のほどを、もったいなくも存ぜずにはいられませんでしたので、親しく交際させていただきますのも、遠慮いたすことが多くて、ご無沙汰いたしておりましたが、世の中がこのように定めないものなので、人数にも入らない身の上は、かえって気安いものでございました。
及びもつかなく拝見いたしましたご様子が、実に悲しく気の毒なのを、近くにいますうちは御無沙汰いたしていた折も、そのうちにと呑気に思っておりましたが、このように遥か遠くに下ってしまうことになると、気がかりで悲しく存じられます」
|
「宮様がおいでになったころ、私の結婚相手が悪いからって、交際するのをおきらいになったものですから、私らもついかけ離れた冷淡なふうになっていましたものの、それからもこちら様は源氏の大将さんなどと御結婚をなさるような御幸運でいらっしゃいましたから、晴れがましくてお出入りもしにくかったのです。しかし人間世界は幸福なことばかりもありませんからね、その中でわれわれ階級の者がかえって気楽なんですよ。及びもない懸隔のあるお家でしたが、こちらはお気の毒なことになってしまいまして、私も心配なんですが、近くにおりますうちは、何かの場合に力にもなれると思っていましたものの、遠い所へ出て行くことになりますと、とてもあなたのことが気になってなりません」
|
【故宮おはせしとき】- 以下「おぼえたまふ」まで、叔母の詞。御無沙汰を謝し、末摘花を筑紫に誘う。
|
| 2.3.6 |
など語らへど、心解けても応へたまはず。
|
などと話を持ち掛けるが、心を許してお返事もなさらない。
|
と夫人は言うのであるが、女王は心の動いたふうもなかった。
|
|
| 2.3.7 |
「いとうれしきことなれど、世に似ぬさまにて、何かは。かうながらこそ朽ちも失せめとなむ思ひはべる」 |
「とても嬉しいことですが、世間離れしたわたしなどには、どうして一緒に行けましょうか。
こうしたまま朽ち果てようと存じております」
|
「御好意はうれしいのですが、人並みの人にもなれない私はこのままここで死んで行くのが何よりもよく似合うことだろうと思います」
|
【いとうれしきことなれど】- 以下「なむ思ひはべる」まで、末摘花の返事。誘いに感謝しながらも拒絶する。『完訳』は「世間離れを自認」と注す。
|
| 2.3.8 |
とのみのたまへば、
|
とだけおっしゃるので、
|
とだけ末摘花は言う。
|
|
| 2.3.9 |
|
「なるほど、そのようにお思いになるのもごもっともですが、せっかく生きている身をだいなしにして、このように気味の悪い所に暮らしている例はございませんでしょう。
大将殿がお手入れしてくだされば、うって変わって元の美しい御殿にもなり変わろうと、頼もしうございますが、ただ今のところは、式部卿宮の姫君より他には、心をお分けになる方もないということです。
昔から浮気なお心で、かりそめにお通いになった人々は、みなすっかりお心が離れておしまいになったということです。
ましてや、このようにみすぼらしい様子で、薮原にお過ごしになっていらっしゃる人を、貞淑に自分を頼っていらっしゃる様子だと、お訪ね申されることは、とても難しいことです」
|
「それはそうお思いになるのはごもっともですが、生きている人間であって、こんなひどい場所に住んでいるのなどはほかにめったにないでしょう。大将さんが修繕をしてくだすったら、またもう一度玉の台にもなるでしょうと期待されますがね。近ごろはどうしたことでしょう、兵部卿の宮の姫君のほかはだれも嫌いになっておしまいになったふうですね。昔から恋愛関係をたくさん持っていらっしゃった方でしたが、それも皆清算しておしまいになりましたってね。ましてこんなみじめな生き方をしていらっしゃる人を、操を立てて自分を待っていてくれたかと受け入れてくださることはむずかしいでしょうね」
|
【げに、しかなむ】- 以下「かたくなむあるべき」まで、叔母の詞。説得を諦める。
【生ける身を捨て】- 大島本は「すて」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「捨てて」と「て」を補訂する。
【式部卿宮の】- 紫の上の父宮。「澪標」「絵合」巻では「兵部卿宮」とあり、式部卿宮に転じるのは「少女」巻である。本文上問題のある箇所。
【心分けたまふ方もなかなり】- 「なかるなり」の「る」が撥音便化し、さらに無表記の形。「なり」伝聞推定の助動詞。
【皆思し離れにたなり】- 「に」完了の助動詞。「たなり」は「たるなり」の「る」が撥音便化し、さらに無表記化された形。
|
| 2.3.10 |
など言ひ知らするを、げにと思すも、いと悲しくて、つくづくと泣きたまふ。
|
などと説得するが、本当にそのとおりだとお思いになるのも、実に悲しくて、しみじみとお泣きになる。
|
こんなよけいなことまで言われてみると、そうであるかもしれないと末摘花は悲しく泣き入ってしまった。
|
|
|
第四段 侍従、叔母に従って離京
|
| 2.4.1 |
されど、動くべうもあらねば、よろづに言ひわづらひ暮らして、
|
けれども、動きそうにもないので、一日中いろいろと説得したものの困りはてて、
|
しかも九州行きを肯うふうは微塵もない。夫人はいろいろと誘惑を試みたあとで、
|
|
| 2.4.2 |
|
「それでは、侍従だけでも」
|
「では侍従だけでも」
|
【さらば、侍従をだに】- 叔母の詞。侍従を連れて行くことを言う。
|
| 2.4.3 |
と、日の暮るるままに急げば、心あわたたしくて、泣く泣く、
|
と、日が暮れるままに急ぎ立てるので、気がせいて、泣く泣く、
|
と日の暮れていくのを見てせきたてた。侍従は名残を惜しむ間もなくて、泣く泣く女王に、
|
|
| 2.4.4 |
|
「それでは、ともかく今日のところは。
このようにお勧めになるお見送りだけでも参りましょう。
あのように申されることもごもっともなことです。
また一方、お迷いになることもごもっともなことですので、間に立って拝見するのも辛くて」
|
「それでは、今日はあんなにおっしゃいますから、お送りにだけついてまいります。あちらがああおっしゃるのももっともですし、あなた様が行きたく思召さないのも御無理だとは思われませんし、私は中に立ってつらくてなりませんから」
|
【さらば、まづ今日は】- 以下「心苦しくなむ」まで、侍従の詞。末摘花にこっそりと言う。
【かう責めたまふ送りばかりにまうではべらむ】- 「見送り」は目的地あるいは国境まで送っていくこと。侍従はそのまま筑紫国に住み着いてしまう。『完訳』は「こんなにお勧めになるので、せめて、叔母君をお見送りするつもりで参ろう、の意。下向の決意のゆらぐ気持であろう」と注す。
|
| 2.4.5 |
と、忍びて聞こゆ。
|
と、小声で申し上げる。
|
と言う。
|
|
| 2.4.6 |
この人さへうち捨ててむとするを、恨めしうもあはれにも思せど、言ひ止むべき方もなくて、いとど音をのみたけきことにてものしたまふ。
|
この人までが自分を見捨てて行ってしまおうとするのが、恨めしくも悲しくもお思いになるが、引き止めるすべもないので、ますます声を立てて泣くことばかりでいらっしゃる。
|
この人までも女王を捨てて行こうとするのを、恨めしくも悲しくも末摘花は思うのであるが、引き止めようもなくてただ泣くばかりであった。
|
|
| 2.4.7 |
形見に添へたまふべき身馴れ衣も、しほなれたれば、年経ぬるしるし見せたまふべきものなくて、わが御髪の落ちたりけるを取り集めて、鬘にしたまへるが、九尺余ばかりにて、いときよらなるを、をかしげなる箱に入れて、昔の薫衣香のいとかうばしき、一壺具して賜ふ。
|
形見にお与えになるべき着用の衣も垢じみているので、長年の奉公に報いるべき物がなくて、ご自分のお髪の抜け落ちたのを集めて、鬘になさっていたのが、九尺余りの長さで、たいそうみごとなのを、風流な箱に入れて、昔の薫衣香のたいそう香ばしいのを、一壷添えてお与えになる。
|
形見に与えたい衣服も皆悪くなっていて長い間のこの人の好意に酬いる物がなくて、末摘花は自身の抜け毛を集めて鬘にした九尺ぐらいの髪の美しいのを、雅味のある箱に入れて、昔のよい薫香一壺をそれにつけて侍従へ贈った。
|
|
| 2.4.8 |
|
「あなたを絶えるはずのない間柄だと信頼していましたが
思いのほかに遠くへ行ってしまうのですね
|
「絶ゆまじきすぢを頼みし玉かづら
思ひのほかにかけ離れぬる
|
【絶ゆまじき筋を頼みし玉かづら--思ひのほかにかけ離れぬる】- 末摘花から侍従への贈歌。「絶ゆ」「筋」「掛け」は「かづら」の縁語。離別を惜しみ恨むような気持ちの表出。『完訳』は「身分の劣る者からの贈歌が普通。ここは逆」と指摘。
|
| 2.4.9 |
故ままの、のたまひ置きしこともありしかば、かひなき身なりとも、見果ててむとこそ思ひつれ。うち捨てらるるもことわりなれど、誰に見ゆづりてかと、恨めしうなむ」 |
亡くなった乳母が、遺言なさったこともありましたから、不甲斐ない我が身であっても、最後までお世話してくれるものと思っていましたのに。
見捨てられるのももっともなことですが、この後誰に世話を頼むのかと、恨めしくて」
|
死んだ乳母が遺言したこともあるからね、つまらない私だけれど一生あなたの世話をしたいと思っていた。あなたが捨ててしまうのももっともだけれど、だれがあなたの代わりになって私を慰めてくれる者があると思って立って行くのだろうと思うと恨めしいのよ」
|
【故ままの】- 以下「恨めしうなむ」まで、末摘花の歌に続けた詞。乳母子にまで見捨てられた絶望的気持ち。『新大系』は「乳母を親しんで呼ぶ語。ここは侍従の亡母」と注す。
|
| 2.4.10 |
とて、いみじう泣いたまふ。
この人も、ものも聞こえやらず。
|
と言って、ひどくお泣きになる。
この人も、何も申し上げることができない。
|
と言って、女王は非常に泣いた。侍従も涙でものが言えないほどになっていた。
|
|
| 2.4.11 |
「ままの遺言は、さらにも聞こえさせず、年ごろの忍びがたき世の憂さを過ぐしはべりつるに、かくおぼえぬ道にいざなはれて、遥かにまかりあくがるること」とて、 |
「乳母の遺言は、もとより申し上げるまでもなく、長年の堪えがたい生活を堪えて参りましたのに、このように思いがけない旅路に誘われて、遥か遠くに彷徨い行くことになるとは」と言って、
|
「乳母が申し上げましたことはむろんでございますが、そのほかにもごいっしょに長い間苦労をしてまいりましたのに、思いがけない縁に引かれて、しかも遠方へまで行ってしまいますとは」と言って、また、
|
【ままの遺言は】- 以下「あくがるること」まで、侍従の詞。感情に溺れて思慮を失ったしゃべり出し。
|
| 2.4.12 |
|
「お別れしましてもお見捨て申しません
行く道々の道祖神にかたくお誓いしましょう
|
「玉かづら絶えてもやまじ行く道の
たむけの神もかけて誓はん
|
【玉かづら絶えてもやまじ行く道の--手向の神もかけて誓はむ】- 侍従の玉鬘の贈歌に対する返歌。「絶ゆ」「玉かづら」「掛け」の語句を受けて、「玉かづら」「絶えても止まじ」「掛けて誓はむ」と切り返す。手向けの神に誓って決してお見捨て申しません、という気持ち。
|
| 2.4.13 |
|
寿命だけは分りませんが」
|
命のございます間はあなた様に誠意をお見せします」
|
【命こそ知りはべらね】- 侍従の返歌に添えた詞。「こそ---ね」係結び。寿命、運命の意。
|
| 2.4.14 |
など言ふに、
|
などと言うと、
|
などとも言う。
|
|
| 2.4.15 |
|
「どこにいますか。
暗くなってしまいます」
|
「侍従はどうしました。暗くなりましたよ」
|
【いづら。暗うなりぬ】- 叔母の詞。侍従を急かせる。
|
| 2.4.16 |
と、つぶやかれて、心も空にて引き出づれば、かへり見のみせられける。 |
と、ぶつぶつ言われて、心も上の空のまま引き出したので、振り返りばかりせずにはいられないのであった。
|
と大弐夫人に小言を言われて、侍従は夢中で車に乗ってしまった。そしてあとばかりが顧みられた。
|
【かへり見のみ】- 君が住む宿の梢のゆくゆくと隠るるまでにかへり見しはや(拾遺集別-三五一 菅原道真)(text15.html 出典7から転載)
|
| 2.4.17 |
|
長年辛い思いをしながらも、お側を離れなかった人が、このように離れて行ってしまったことを、たいそう心細くお思いになると、世間では役に立ちそうにもない老女房までが、
|
困りながらも長い間離れて行かなかった人が、こんなふうにして別れて行ったことで、女王はますます心細くなった。だれも雇い手のないような老いた女房までが、
|
【年ごろわびつつも行き離れざりつる人の】- 『集成』は「今まで長年の間、迷惑がりながらもお側を離れなかった人(侍従)が」と訳す。
|
| 2.4.18 |
「いでや、ことわりぞ。いかでか立ち止まりたまはむ。われらも、えこそ念じ果つまじけれ」 |
「いやはや、無理もないことです。
どうしてお残りになることがありましょうか。
わたしたちも、とても我慢できそうにありませんわ」
|
「もっともですよ。どうしてこのままいられるものですか。私たちだってもう我慢ができませんよ」
|
【いでや、ことわりぞ】- 以下「念じ果つまじけれ」まで、老女房の詞。侍従に対して敬語を使うのは、姫君の側近であるから。
|
| 2.4.19 |
と、おのが身々につけたるたよりども思ひ出でて、止まるまじう思へるを、人悪ろく聞きおはす。
|
と、それぞれに関係ある縁故を思い出して、残っていられないと思っているのを、体裁の悪いことだと聞いていらっしゃる。
|
こんなことを言って、ほかへ勤める手蔓を捜し始めて、ここを出る決心をしたらしいことを言い合うのを聞くことも末摘花の身にはつらいことであった。
|
|
|
第五段 常陸宮邸の寂寥
|
| 2.5.1 |
|
霜月ころになると、雪、霰の降る日が多くなって、他では消える間もあるが、朝日、夕日をさえぎる雑草や葎の蔭に深く積もって、越の白山が思いやられる雪の中で、出入りする下人さえもいなくて、所在なく物思いに沈んでいらっしゃる。
とりとめもないお話を申し上げてお慰めし、泣いたり笑ったりしながらお気を紛らした人さえいなくなって、夜も塵の積った御帳台の中も、寄り添う人もなく、何となく悲しく思わずにはいらっしゃれない。
|
十一月になると雪や霙の日が多くなって、ほかの所では消えている間があっても、ここでは丈の高い枯れた雑草の蔭などに深く積もったものは量が高くなるばかりで越の白山をそこに置いた気がする庭を、今はもうだれ一人出入りする下男もなかった。こんな中につれづれな日を送るよりしかたのない末摘花の女王であった。泣き合い笑い合うこともあった侍従がいなくなってからは、夜の塵のかかった帳台の中でただ一人寂しい思いをして寝た。
|
【霜月ばかりになれば、雪、霰がちにて】- 源氏、帰京の年の十一月、雪や霰の降ることの多い日々、末摘花は独り邸で寂しく暮らす。『完訳』は「末摘花の巻でも、雪が重要な景物。生活の辛苦を寒冷さで象徴」と注す。
【越の白山思ひやらるる雪のうちに】- 「越の白山」は歌枕。『集成』は「消え果つる時しなければ越路なる白山の名は雪にぞありける」(古今集羈旅、四一四、躬恒)。『新大系』では「音に聞く越の白山白雪の降り積もりての事にぞありける」(公任集)を指摘する。
【泣きみ笑ひみ紛らはしつる人】- 侍従をさす。
【塵がましき御帳のうちも】- 『集成』は「男の訪れが絶えて久しく、整えることを怠った帳台をいう」と注す。
|
| 2.5.2 |
かの殿には、めづらし人に、いとどもの騒がしき御ありさまにて、いとやむごとなく思されぬ所々には、わざともえ訪れたまはず。まして、「その人はまだ世にやおはすらむ」とばかり思し出づる折もあれど、尋ねたまふべき御心ざしも急がであり経るに、年変はりぬ。 |
あちらの殿では、久々に再会した方に、ますます夢中なご様子で、たいして重要にお思いでない方々には、特別ご訪問もおできになれない。
まして、「あの人はまだ生きていらっしゃるだろうか」という程度にお思い出しになる時もあるが、お訪ねになろうというお気持ちも急に起こらずにいるうちに、年も変わった。
|
源氏は長くこがれ続けた紫夫人のもとへ帰りえた満足感が大きくて、ただの恋人たちの所などへは足が向かない時期でもあったから、常陸の宮の女王はまだ生きているだろうかというほどのことは時々心に上らないことはなかったが、捜し出してやりたいと思うことも、急ぐことと思われないでいるうちにその年も暮れた。
|
【年変はりぬ】- 帰京の翌年、源氏二十九歳の年となる。
|
|
第三章 末摘花の物語 久しぶりの再会の物語
|
|
第一段 花散里訪問途上
|
| 3.1.1 |
|
卯月ころに、花散里をお思い出し申されて、こっそりと対の上にお暇乞い申し上げてお出かけになる。
数日来降り続いていた雨の名残、まだ少しぱらついて、風情ある折に、月が差し出ていた。
昔のお忍び歩きが自然と思い出されて、優艷な感じの夕月夜に、途上、あれこれの事柄が思い出されていらっしゃるうちに、見るかたもなく荒れた邸で、木立が鬱蒼とした森のような所をお通り過ぎになる。
|
四月ごろに花散里を訪ねて見たくなって夫人の了解を得てから源氏は二条の院を出た。幾日か続いた雨の残り雨らしいものが降ってやんだあとで月が出てきた。青春時代の忍び歩きの思い出される艶な夕月夜であった。車の中の源氏は昔をうつらうつらと幻に見ていると、形もないほどに荒れた大木が森のような邸の前に来た。
|
【卯月ばかりに、花散里を思ひ出できこえたまひて】- 春三か月が過ぎ去って、夏四月となる。源氏が花散里を訪問する途上、たまたま末摘花邸に立ち寄るという語り方。
【いますこしそそきて】- 大島本は「いますこし」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「すこし」とし「いま」を削除する。
【をかしきほどに、月さし出でたり】- 『集成』は「風情を添えるように」。『完訳』は「風情のある空に月がさし出ている」と訳す。
|
| 3.1.2 |
|
大きな松の木に藤が咲きかかって、月の光に揺れているのが、風に乗ってさっと匂うのが慕わしく、どれがそれからともない香りである。
橘のとは違って風趣があるので、のり出して御覧になると、柳もたいそう長く垂れて、築地も邪魔しないから、乱れ臥していた。
|
高い松に藤がかかって月の光に花のなびくのが見え、風といっしょにその香がなつかしく送られてくる。橘とはまた違った感じのする花の香に心が惹かれて、車から少し顔を出すようにしてながめると、長く枝をたれた柳も、土塀のない自由さに乱れ合っていた。
|
【松に藤の咲きかかりて】- 松と藤という取り合わせの構図。当時の和歌や源氏物語中に多く見られる。
【月影になよびたる、風につきてさと匂ふがなつかしく】- 【月影になよびたる風につきて】-『集成』は「月の光に揺れているのが、風に乗って」。『完訳』は「月光のなかになよなよ揺れている、それが吹く風とともにさっと匂ってくるのが」。「たる」と「風」の間に読点が入る。連体中止で、下文の主格となる。 【風につきてさと匂ふがなつかしく】-『完訳』は「人もなき宿ににほへる藤の花風にのみこそ乱るべらなれ」(貫之集)を指摘。
【橘に変はりて】- 大島本は「たちはなに」とある。『新大系』『集成』は底本のままとする。『古典セレクション』は諸本に従って「橘には」とし「は」を補訂する。
|
| 3.1.3 |
「見し心地する木立かな」と思すは、早う、この宮なりけり。いとあはれにて、おし止めさせたまふ。例の、惟光はかかる御忍びありきに後れねば、さぶらひけり。召し寄せて、 |
「かつて見た感じのする木立だなあ」とお思いになると、それもそのはず、この宮邸なのであった。
ひどく胸を打たれて、お車を止めさせなさる。
例によって、惟光はこのようなお忍び歩きに外れることはないので、お供していたのであった。
お召しになって、
|
見たことのある木立ちであると源氏は思ったが、以前の常陸の宮であることに気がついた。源氏は物哀れな気持ちになって車を止めさせた。例の惟光はこんな微行にはずれたことのない男で、ついて来ていた。
|
【早う、この宮なりけり】- 『集成』は「それもそのはず、例の常陸の宮だったのだ。「早う」は、「もともと」「すでに」の原義から転じた用法」。『完訳』は「もともとそのはず、の語感」「それもそのはず、常陸の宮のお邸なのだった」と注す。
|
| 3.1.4 |
|
「ここは常陸宮であったな」
|
「ここは常陸の宮だったね」
|
【ここは、常陸の宮ぞかしな】- 源氏の詞。問いかけ。終助詞「な」は質問の意。
|
| 3.1.5 |
|
「さようでございます」
|
「さようでございます」
|
【しかはべる】- 惟光の詞。返答。源氏の問いかけに間髪を入れず答える。
|
| 3.1.6 |
と聞こゆ。
|
と申し上げる。
|
|
|
| 3.1.7 |
|
「ここにいた人は、今も物思いに沈んでいるのだろうか。
お見舞いすべきであるが、わざわざ訪ねるのも大げさである。
このような機会に、入って便りをしてみよ。
よく調べてから、言い出しなさい。
人違いをしては馬鹿らしいから」
|
「ここにいた人がまだ住んでいるかもしれない。私は訪ねてやらねばならないのだが、わざわざ出かけることもたいそうになるから、この機会に、もしその人がいれば逢ってみよう。はいって行って尋ねて来てくれ。住み主がだれであるかを聞いてから私のことを言わないと恥をかくよ」
|
【ここにありし人は】- 以下「をこならむ」まで、源氏の詞。惟光に邸の中を尋ねさせる。
【尋ね入りてを】- 大島本は「たつね入てを」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「たづね寄りてを」と校訂する。「を」について、『集成』は「驚意の助詞」。『完訳』は「感嘆の助詞」と解す。
|
| 3.1.8 |
とのたまふ。
|
とおっしゃる。
|
と源氏は言った。
|
|
| 3.1.9 |
ここには、いとど眺めまさるころにて、つくづくとおはしけるに、昼寝の夢に故宮の見えたまひければ、覚めて、いと名残悲しく思して、漏り濡れたる廂の端つ方おし拭はせて、ここかしこの御座引きつくろはせなどしつつ、例ならず世づきたまひて、 |
こちらでは、ひとしお物思いのまさるころで、つくづくと物思いに沈んでいらっしゃると、昼寝の夢に故宮がお見えになったので、目が覚めて、実に名残が悲しくお思いになって、雨漏りがして濡れている廂の端の方を拭かせて、あちらこちらの御座所を取り繕わせてなどしながら、いつになく人並みになられて、
|
末摘花の君は物悩ましい初夏の日に、その昼間うたた寝をした時の夢に父宮を見て、さめてからも名残の思いにとらわれて、悲しみながら雨の洩って濡れた廂の室の端のほうを拭かせたり部屋の中を片づけさせたりなどして、平生にも似ず歌を思ってみたのである。
|
【ここには、いとど眺めまさるころにて】- 常陸宮邸の中。末摘花、昼寝の夢から覚めて物思いに耽っている。
|
| 3.1.10 |
|
「亡き父上を恋い慕って泣く涙で袂の乾く間もないのに
荒れた軒の雨水までが降りかかる」
|
亡き人を恋ふる袂のほどなきに
荒れたる軒の雫さへ添ふ
|
【亡き人を恋ふる袂のひまなきに--荒れたる軒のしづくさへ添ふ】- 末摘花の独詠歌。「亡き人」は父常陸宮。この和歌の末尾が地の文に続く。
|
| 3.1.11 |
も、心苦しきほどになむありける。
|
というのも、
|
こんなふうに、寂しさを書いていた時が、源氏の車の止められた時であった。
|
|
|
第二段 惟光、邸内を探る
|
| 3.2.1 |
惟光入りて、めぐるめぐる人の音する方やと見るに、いささかの人気もせず。「さればこそ、往き来の道に見入るれど、人住みげもなきものを」と思ひて、帰り参るほどに、月明くさし出でたるに、見れば、格子二間ばかり上げて、簾動くけしきなり。わづかに見つけたる心地、恐ろしくさへおぼゆれど、寄りて、声づくれば、いともの古りたる声にて、まづしはぶきを先にたてて、 |
惟光が邸の中に入って、あちこちと人の音のする方はどこかと探すが、すこしも人影が見えない。
「やはりそうだ、今までに行き帰りに覗いたことがあるが、人は住んでいないのだ」と思って、戻って参る時に、月が明るく照らし出したので、見ると、格子が二間ほど上がっていて、簾の動く気配である。
やっと見つけた感じ、恐ろしくさえ思われるが、近寄って、訪問の合図をすると、ひどく老いぼれた声で、まずは咳払いしてから、
|
惟光は邸の中へはいってあちらこちらと歩いて見て、人のいる物音の聞こえる所があるかと捜したのであるが、そんな物はない。自分の想像どおりにだれもいない、自分は往き返りにこの邸は見るが、人の住んでいる所とは思われなかったのだからと思って惟光が足を返そうとする時に、月が明るくさし出したので、もう一度見ると、格子を二間ほど上げて、そこの御簾は人ありげに動いていた。これが目にはいった刹那は恐ろしい気さえしたが、寄って行って声をかけると、老人らしく咳を先に立てて答える女があった。
|
【惟光入りて、めぐるめぐる】- 惟光、邸内を探り、案内を乞う。
【いささかの人気もせず】- 大島本は「いさゝかの」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「いささか」とし「の」を削除する。
【さればこそ】- 以下「なきものを」まで、惟光の心中。
|
| 3.2.2 |
|
「そこにいる人は誰ですか。
どのような方ですか」
|
「いらっしゃったのはどなたですか」
|
【かれは誰れぞ。何人ぞ】- 老女房の声。外の人に向かって問う。
|
| 3.2.3 |
と問ふ。
名のりして、
|
と聞く。
名乗りをして、
|
惟光は自分の名を告げてから、
|
|
| 3.2.4 |
|
「侍従の君と申した方に、面会させていただきたい」
|
「侍従さんという方にちょっとお目にかかりたいのですが」
|
【侍従の君と聞こえし人に、対面賜はらむ】- 惟光の詞。案内を乞う。惟光は侍従を通じて常陸宮邸に出入りしていた。
|
| 3.2.5 |
と言ふ。
|
と言う。
|
と言った。
|
|
| 3.2.6 |
|
「その人は、
他へ行って
|
「その人はよそへ行きました。けれども侍従の仲間の者がおります」
|
【それは、ほかになむ】- 以下「女なむはべる」まで、老女房の詞。侍従は既に筑紫国へ下っていた。
|
| 3.2.7 |
と言ふ声、いたうねび過ぎたれど、聞きし老人と聞き知りたり。
|
と言う声は、ひどく年とっているが、聞いたことのある老人だと聞きつけた。
|
と言う声は、昔よりもずっと老人じみてきてはいるが、聞き覚えのある声であった。
|
|
| 3.2.8 |
|
室内では、思いも寄らない、狩衣姿の男性が、ひっそりと振る舞い、物腰も柔らかなので、見馴れなくなってしまった目には、「もしや、狐などの変化のものではないか」と思われるが、近く寄って、
|
家の中の人は惟光が何であったかを忘れていた。狩衣姿の男がそっとはいって来て、柔らかな調子でものを言うのであったから、あるいは狐か何かではないかと思ったが、惟光が近づいて行って、
|
【もし、狐などの変化にや】- 女房の心中。狐の化物かと疑う。
【近う寄りて】- 惟光の動作。前の「おぼゆれど」の主語は、女房たち。ここで、主語が変わる。
|
| 3.2.9 |
|
「はっきりと、お話を承りたい。
昔と変わらないお暮らしならば、お訪ね申し上げなさるべきお気持ちも、今も変わらずにおありのようです。
今宵も素通りしがたくて、お止まりあそばしたのだが、どのようにお返事申し上げましょう。
どうぞご安心を」
|
「確かなことをお聞かせくださいませんか。こちら様が昔のままでおいでになるかどうかお聞かせください。私の主人のほうでは変心も何もしておいでにならない御様子です。今晩も門をお通りになって、訪ねてみたく思召すふうで車を止めておいでになります。どうお返辞をすればいいでしょう、ありのままのお話を私には御遠慮なくして下さい」
|
【たしかになむ】- 以下「うしろやすくを」まで、惟光の詞。
【尋ねきこえさせたまふべき御心ざしも】- 「きこえさせ」(「きこゆ」より一段と謙譲の度合の高い動詞、末摘花に対する敬意)「たまふ」(尊敬の補助動詞、源氏に対する敬意)「べき」(推量の助動詞、当然の意)。
|
| 3.2.10 |
と言へば、女どもうち笑ひて、
|
と言うと、女房たちは笑って、
|
と言うと、女たちは笑い出した。
|
|
| 3.2.11 |
「変はらせたまふ御ありさまならば、かかる浅茅が原を移ろひたまはでははべりなむや。ただ推し量りて聞こえさせたまへかし。年経たる人の心にも、たぐひあらじとのみ、めづらかなる世をこそは見たてまつり過ごしはべれ」 |
「お変わりあそばす御身の上ならば、このような浅茅が原をお移りにならずにおりましょうか。
ただご推察申されてお伝えください。
年老いた女房にとっても、またとあるまいと思われるほどの、珍しい身の上を拝見しながら過ごしてまいったのです」
|
「変わっていらっしゃればこんなお邸にそのまま住んでおいでになるはずもありません。御推察なさいましてあなたからよろしくお返辞を申し上げてください。私どものような老人でさえ経験したことのないような苦しみをなめて今日までお待ちになったのでございますよ」
|
【変はらせたまふ御ありさまならば】- 以下「すこしはべれ」まで、老女房の返事。
【はべりなむや】- 「はべり」丁寧の動詞、「なむ」複合語(「な」完了の助動詞、確述+「む」推量の助動詞、推量)強調、「や」係助詞、反語。
|
| 3.2.12 |
と、ややくづし出でて、問はず語りもしつべきが、むつかしければ、
|
と、ぽつりぽつりと話し出して、問わず語りもし出しそうなのが、厄介なので、
|
女たちは惟光にもっともっと話したいというふうであったが、惟光は迷惑に思って、
|
|
| 3.2.13 |
|
「よいよい、
分かった。まずは、そのように、申し上げま
|
「いやわかりました。ともかくそう申し上げます」
|
【よしよし。まづ、かくなむ、聞こえさせむ】- 惟光の詞。
|
| 3.2.14 |
とて参りぬ。
|
と言って帰参した。
|
と言い残して出て来た。
|
|
|
第三段 源氏、邸内に入る
|
| 3.3.1 |
|
「どうしてひどく長くかかったのだ。
どうであったか。
昔の面影も見えないほど雑草の茂っていることよ」
|
「なぜ長くかかったの、どうだったかね、昔の路を見いだせない蓬原になっているね」
|
【などかいと久しかりつる】- 以下「しけさかな」まで源氏の詞。
|
| 3.3.2 |
とのたまへば、
|
とおっしゃると、
|
源氏に問われて惟光は初めからの報告をするのであった。
|
|
| 3.3.3 |
「しかしかなむ、たどり寄りてはべりつる。侍従が叔母の少将といひはべりし老人なむ、変はらぬ声にてはべりつる」 |
「これこれの次第で、ようやく分かりました。
侍従の叔母で少将と言いました老女が、昔と変わらない様子でおりました」
|
「そんなふうにして、やっと人間を発見したのでございます。侍従の叔母で少将とか申しました老人が昔の声で話しました」
|
【しかしかなむ】- 以下「声にてはべりける」まで、惟光の詞。
|
| 3.3.4 |
と、ありさま聞こゆ。
|
と、その様子を申し上げる。
|
惟光はなお目に見た邸内の様子をくわしく言う。
|
|
| 3.3.5 |
いみじうあはれに、
|
ひどく不憫な気持ちになって、
|
源氏は非常に哀れに思った。
|
|
| 3.3.6 |
|
「このような蓬生の茂った中に、どのようなお気持ちでお過ごしになっていられたのだろう。
今までお訪ねしなかったとは」
|
この廃邸じみた家に、どんな気持ちで住んでいることであろう、それを自分は今まで捨てていたと思うと、
|
【かかるしげき中に】- 以下「訪はざりけるよ」まで、源氏の心中。『完訳』は「荒廃の中で自分を待ち続けた末摘花への感動から、自らの冷淡な仕打ちへの反省へと、反転していく」と注す。
|
| 3.3.7 |
と、わが御心の情けなさも思し知らる。
|
と、ご自分の薄情さを思わずにはいらっしゃれない。
|
源氏は自分ながらも冷酷であったと省みられるのであった。
|
|
| 3.3.8 |
「いかがすべき。かかる忍びあるきも難かるべきを、かかるついでならでは、え立ち寄らじ。変はらぬありさまならば、げにさこそはあらめと、推し量らるる人ざまになむ」 |
「どうしたらよいものだろう。
このような忍び歩きも難しいであろうから、このような機会でなかったら、立ち寄ることもできまい。
昔と変わっていない様子ならば、なるほどそのようであろうと、推量されるお人柄である」
|
「どうしようかね、こんなふうに出かけて来ることも近ごろは容易でないのだから、この機会でなくては訪ねられないだろう。すべてのことを綜合して考えてみても昔のままに独身でいる想像のつく人だ」
|
【いかがすべき】- 以下「人ざまになむ」まで、源氏の詞。『完訳』は「形式的には惟光への発言ながら、心語に続く自問自答」と注す。
【忍びあるき】- 大島本は「しのひあるき」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「忍びありき」と校訂する。
|
| 3.3.9 |
|
とはおっしゃるものの、すぐにお入りになること、やはり躊躇される。
趣き深いご消息も差し上げたくお思いになるが、かつてご経験された返歌の遅いのも、まだ変わっていなかったなら、お使いの者が待ちあぐねるのも気の毒で、お止めになった。
惟光も、
|
と源氏は言いながらも、この邸へはいって行くことにはなお躊躇がされた。この実感からよい歌を詠んでまず贈りたい気のする場合であるが、機敏に返歌のできないことも昔のままであったなら、待たされる使いがどんなに迷惑をするかしれないと思ってそれはやめることにした。惟光も源氏がすぐにはいって行くことは不可能だと思った。
|
【ゆゑある御消息もいと聞こえまほしけれど】- 『集成』は「きちんとしたお歌などさし上げたいのは山々だが」。『完訳』は「じっさい何か気のきいた御消息も申し上げたいけれども」と訳す。
|
|
 |
| 3.3.10 |
|
「とてもお踏み分けになれそうにない、ひどい蓬生の露けさでございます。
露を少し払わせて、お入りあそばすよう」
|
「とても中をお歩きになれないほどの露でございます。蓬を少し払わせましてからおいでになりましたら」
|
【さらにえ分けさせたまふまじき】- 以下「入らせたまふべき」まで、惟光の詞。
|
| 3.3.11 |
と聞こゆれば、
|
と申し上げるので、
|
この惟光の言葉を聞いて、源氏は、
|
|
| 3.3.12 |
|
「誰も訪ねませんがわたしこそは訪問しましょう
道もないくらい深く茂った蓬の宿の姫君の変わらないお心を」
|
尋ねてもわれこそ訪はめ道もなく
深き蓬のもとの心を
|
【尋ねても我こそ訪はめ道もなく--深き蓬のもとの心を】- 源氏の独詠歌。貞淑な末摘花の真意を理解し訪問しようという意。
|
| 3.3.13 |
|
と独り言をいって、やはりお車からお下りになると、御前の露を、馬の鞭で払いながらお入れ申し上げる。
|
と口ずさんだが、やはり車からすぐに下りてしまった。惟光は草の露を馬の鞭で払いながら案内した。
|
【なほ下りたまへば】- 前に「なほつつましう」を受けて、躊躇しながらもやはり下車した、の意。
【馬の鞭して】- 大島本は「むち」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「ぶち」と校訂する。「鞭 夫知」(新撰字鏡)。
|
| 3.3.14 |
|
雨の雫も、やはり秋の時雨のように降りかかるので、
|
木の枝から散る雫も秋の時雨のように荒く降るので、傘を源氏にさしかけさせた。惟光が、
|
【雨そそきも、なほ秋の時雨めきて】- 「東屋の真屋のあまりのその雨そそき我立ち濡れぬ殿戸開かせかすがひもとざしもあらばこそその殿戸我鎖さめ押し開いて来ませ我や人妻」(催馬楽「東屋」)による描写。雨に茅屋の女を訪ねる類型。
|
| 3.3.15 |
|
「お傘がございます。
なるほど、木の下露は雨にまさって」
|
「木の下露は雨にまされり(みさぶらひ御笠と申せ宮城野の)でございます」
|
【御傘さぶらふ。げに、木の下露は、雨にまさりて】- 惟光の詞。「みさぶらひみかさと申せ宮城野の木の下露は雨にまさりて」(古今集東歌、一〇九一)を踏まえる。傘を差し出す。
|
| 3.3.16 |
と聞こゆ。
御指貫の裾は、いたうそほちぬめり。
昔だにあるかなきかなりし中門など、まして形もなくなりて、入りたまふにつけても、いと無徳なるを、立ちまじり見る人なきぞ心やすかりける。
|
と申し上げる。
御指貫の裾は、ひどく濡れてしまったようである。
昔でさえあるかないかであった中門など、昔以上に跡形もなくなって、お入りになるにつけても、何の役に立たないのであるが、その場にいて見ている人がないのも気楽であった。
|
と言う。源氏の指貫の裾はひどく濡れた。昔でさえあるかないかであった中門などは影もなくなっている。家の中へはいるのもむき出しな気のすることであったが、だれも人は見ていなかった。
|
|
|
第四段 末摘花と再会
|
| 3.4.1 |
姫君は、さりともと待ち過ぐしたまへる心もしるく、うれしけれど、いと恥づかしき御ありさまにて対面せむも、いとつつましく思したり。大弐の北の方のたてまつり置きし御衣どもをも、心ゆかず思されしゆかりに、見入れたまはざりけるを、この人びとの、香の御唐櫃に入れたりけるが、いとなつかしき香したるをたてまつりければ、いかがはせむに、着替へたまひて、かの煤けたる御几帳引き寄せておはす。 |
姫君は、いくら何でもとお待ち暮らしになっていた期待どおりで、嬉しいけれど、とても恥ずかしいご様子で面会するのも、たいそうきまり悪くお思いであった。
大弐の北の方が差し上げておいたお召し物類も、不愉快にお思いであった人からの物ゆえに、見向きもなさらなかったが、この女房たちが、香の唐櫃に入れておいたのが、とても懐かしい香りが付いているのを差し上げたので、どうにも仕方がなく、お着替えになって、あの煤けた御几帳を引き寄せてお座りになる。
|
女王は望みをかけて来たことの事実になったことはうれしかったが、りっぱな姿の源氏に見られる自分を恥ずかしく思った。大弐の夫人の贈った衣服はそれまで、いやな気がしてよく見ようともしなかったのを、女房らが香を入れる唐櫃にしまって置いたからよい香のついたのに、その人々からしかたなしに着かえさせられて、煤けた几帳を引き寄せてすわっていた。
|
【姫君は、さりともと】- 常陸宮邸の室内。
|
| 3.4.2 |
入りたまひて、
|
お入りになって、
|
源氏は座に着いてから言った。
|
|
| 3.4.3 |
|
「長年のご無沙汰にも、心だけは変わらずに、お思い申し上げていましたが、何ともおっしゃってこないのが恨めしくて、今まで様子をお伺い申し上げておりましたが、あのしるしの杉ではないが、その木立がはっきりと目につきましたので、通り過ぎることもできず、根くらべにお負け致しました」
|
「長くお逢いしないでも、私の心だけは変わらずにあなたを思っていたのですが、何ともあなたが言ってくださらないものだから、恨めしくて、今までためすつもりで冷淡を装っていたのですよ。しかし、三輪の杉ではないが、この前の木立ちを目に見ると素通りができなくてね、私から負けて出ることにしましたよ」
|
【年ごろの隔てにも】- 以下「負けきこえにける」まで、源氏の詞。冗談を交えながら長年の無沙汰を詫びる。
【杉ならぬ木立のしるさに】- 「我が庵は三輪の山もと恋しくはとぶらひ来ませ杉立てる門」(古今集雑下、九八二、読人しらず)を引く。
|
| 3.4.4 |
とて、帷子をすこしかきやりたまへれば、例の、いとつつましげに、とみにも応へきこえたまはず。
かくばかり分け入りたまへるが浅からぬに、思ひ起こしてぞ、ほのかに聞こえ出でたまひける。
|
とおっしゃって、帷子を少しかきやりなさると、例によって、たいそうきまり悪そうにすぐにも、お返事申し上げなさらない。
こうまでして草深い中をお訪ねになったお心の浅くないことに、勇気を奮い起こして、かすかにお返事申し上げるのであった。
|
几帳の垂れ絹を少し手であけて見ると、女王は例のようにただ恥ずかしそうにすわっていて、すぐに返辞はようしない。こんな住居にまで訪ねて来た源氏の志の身にしむことによってやっと力づいて何かを少し言った。
|
|
| 3.4.5 |
|
「このような草深い中にひっそりとお過ごしになっていらした年月のおいたわしさも、一通りではございませんが、また昔と心変わりしない性癖なので、あなたのお心中も知らないままに、分け入って参りました露けさなどを、どのようにお思いでしょうか。
長年のご無沙汰は、それはまた、どなたからもお許しいただけることでしょう。
今から後のお心に適わないようなことがあったら、言ったことに違うという罪も負いましょう」
|
「こんな草原の中で、ほかの望みも起こさずに待っていてくだすったのだから私は幸福を感じる。またあなただって、あなたの近ごろの心持ちもよく聞かないままで、自分の愛から推して、愛を持っていてくださると信じて訪ねて来た私を何と思いますか。今日まであなたに苦労をさせておいたことも、私の心からのことでなくて、その時は世の中の事情が悪かったのだと思って許してくださるでしょう。今後の私が誠実の欠けたようなことをすれば、その時は私が十分に責任を負いますよ」
|
【かかる草隠れに】- 以下「罪も負ふべき」まで、源氏の詞。
【あはれも、おろかならず】- 末摘花を不憫と思う気持ちが並々でないという。
【また変はらぬ心ならひに】- 末摘花同様に自分を心変わりしない性格だという。
【露けさ】- 景情一致の表現。自分の気持ちを露に象徴する。
【言ひしに違ふ罪】- 「いとどこそまさりにまされ忘れじと言ひしに違ふことのつらさは」(奥入所引、出典未詳)を踏まえる。
|
| 3.4.6 |
|
などと、それほどにもお思いにならないことでも、深く愛しているふうに申し上げなさることも、いろいろあるようだ。
|
などと、それほどに思わぬことも、女を感動さすべく源氏は言った。
|
【さしも思されぬことも、情け情けしう聞こえなしたまふことども、あむめり】- 『完訳』は「以下、語り手の評。源氏の口説の抜群な巧みさをいう」と注す。「聞こえなす」という言い方に注意。 【あむめり】-大島本は「あへめり」とある。『新大系』は底本のままとし、「へ」は「ん」の誤写から生じた形か、と注する。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「あめり」と校訂する。今、『新大系』の説に従う。
|
| 3.4.7 |
立ちとどまりたまはむも、所のさまよりはじめ、まばゆき御ありさまなれば、つきづきしうのたまひすぐして、出でたまひなむとす。引き植ゑしならねど、松の木高くなりにける年月のほどもあはれに、夢のやうなる御身のありさまも思し続けらる。 |
お泊まりになるのも、あたりの様子をはじめとして、目を背けたいご様子なので、体よく言い逃れなさって、お帰りになろうとする。
ひき植えた松ではないが、松の木が高くなった長い歳月の程がしみじみと、夢のようであったお身の上の様子も自然とお思い続けられる。
|
泊まって行くこともこの家の様子と自身とが調和の取れないことを思って、もっともらしく口実を作って源氏は帰ろうとした。自身の植えた松ではないが、昔に比べて高くなった木を見ても、年月の長い隔たりが源氏に思われた。そして源氏の自身の今日の身の上と逆境にいたころとが思い比べられもした。
|
【引き植ゑしならねど】- 「引き植ゑし人はうべこそ老いにけれ松の木高くなりにけるかな」(後撰集雑一、一一〇七、凡河内躬恒)を踏まえる。
|
| 3.4.8 |
|
「松にかかった藤の花を見過ごしがたく思ったのは
その松がわたしを待つというあなたの家の目じるしであったのですね
|
「藤波の打ち過ぎがたく見えつるは
まつこそ宿のしるしなりけれ
|
【藤波のうち過ぎがたく見えつるは--松こそ宿のしるしなりけれ】- 源氏の末摘花への贈歌。「松」に「待つ」を掛ける。『完訳』は「偶然の再会と認めつつ、末摘花の誠実さへの感動を歌った」と注す。
|
| 3.4.9 |
数ふれば、こよなう積もりぬらむかし。都に変はりにけることの多かりけるも、さまざまあはれになむ。今、のどかにぞ鄙の別れに衰へし世の物語も聞こえ尽くすべき。年経たまへらむ春秋の暮らしがたさなども、誰にかは愁へたまはむと、うらもなくおぼゆるも、かつは、あやしうなむ」 |
数えてみると、すっかり月日が積もってしまったようだね。
都で変わったことが多かったのも、あれこれと胸が痛みます。
そのうち、のんびりと田舎に離別して下ったという苦労話もすべて申し上げましょう。
長年過ごして来られた折節のお暮らしの辛かったことなども、わたし以外の誰に訴えることがおできになれようかと、衷心より思われますのも、一方では、不思議なくらいに思われます」
|
数えてみればずいぶん長い月日になることでしょうね。物哀れになりますよ。またゆるりと悲しい旅人だった時代の話も聞かせに来ましょう。あなたもどんなに苦しかったかという辛苦の跡も、私でなくては聞かせる人がないでしょう。とまちがいかもしれぬが私は信じているのですよ」
|
【数ふれば】- 以下「あやしうなむ」まで、歌に続く源氏の詞。
【鄙の別れに衰へし】- 「思ひきや鄙の別れに衰へて海人の縄たき漁りせむとは」(古今集雑下、九六一、小野篁)。
|
| 3.4.10 |
など聞こえたまへば、
|
などとお申し上げになると、
|
などと源氏が言うと、
|
|
| 3.4.11 |
|
「長年待っていた甲斐のなかったわたしの宿を
あなたはただ藤の花を御覧になるついでにお立ち寄りになっただけなのですね」
|
年を経て待つしるしなきわが宿は
花のたよりに過ぎぬばかりか
|
【年を経て待つしるしなきわが宿を--花のたよりに過ぎぬばかりか】- 末摘花の返歌。「藤波」「過ぎ」「松」「宿」「しるし」の語句を受けて、「待つ」「しるしなき」「我が宿を」「花(藤)のたよりに」「過ぎぬばかりか」と切り返す。藤の花を愛でるついでに立ち寄っただけなのですね、という意。
|
| 3.4.12 |
と忍びやかにうちみじろきたまへるけはひも、袖の香も、「昔よりはねびまさりたまへるにや」と思さる。
|
とひっそりと身動きなさった気配も、袖の香りも、「昔よりは成長なされたか」とお思いになる。
|
と低い声で女王は言った。身じろぎに知れる姿も、袖に含んだにおいも昔よりは感じよくなった気がすると源氏は思った。
|
|
| 3.4.13 |
|
月は入り方になって、西の妻戸の開いている所から、さえぎるはずの渡殿のような建物もなく、軒先も残っていないので、たいそう明るく差し込んでいるため、ここかしこが見えるが、昔と変わらないお道具類の様子などが、忍ぶ草に荒れているというよりも、雅やかに見えるので、昔物語に塔を壊したという人があったのをお考え併せになると、それと同じような状態で歳月を経て来たことも胸を打たれる。
ひたすら遠慮している態度が、そうはいっても上品なのも、奥ゆかしく思わずにはいらっしゃれなくて、それを取柄と思って忘れまいと気の毒に思っていたが、ここ数年のさまざまな悩み事に、うっかり疎遠になってしまった間、さぞ薄情者だと思わずにはいられなかっただろうと、不憫にお思いになる。
|
落ちようとする月の光が西の妻戸の開いた口からさしてきて、その向こうにあるはずの廊もなくなっていたし、廂の板もすっかり取れた家であるから、明るく室内が見渡された。昔のままに飾りつけのそろっていることは、忍ぶ草のおい茂った外見よりも風流に見えるのであった。昔の小説に親の作った堂を毀った話もあるが、これは親のしたままを長く保っていく人として心の惹かれるところがあると源氏は思った。この人の差恥心の多いところもさすがに貴女であるとうなずかれて、この人を一生風変わりな愛人と思おうとした考えも、いろいろなことに紛れて忘れてしまっていたころ、この人はどんなに恨めしく思ったであろうと哀れに思われた。
|
【月入り方になりて】- 「艶なるほどの夕月夜に」外出した。上弦の月の入りは夜半ごろ。
【忍草にやつれたる上の見るめよりは】- 「君忍ぶ草にやつるる故里は松虫の音ぞ悲しかりける」(古今集秋上、二〇〇、読人しらず)を踏まえる。
【昔物語に塔こぼちたる人もありけるを】- 『集成』は「未詳。『奥入』に、昔、顔叔子という婦人が、夫の留守中、夫の疑いを避けるために、塔の壁を壊し、夜通し明りをつけていたという、貞淑な女の話をあげる」。『完訳』は「未詳。親が建てた供養塔を親不孝の子が壊す物語とも。また散佚の『桂中納言物語』の、貧女が几帳の帷子を衣に仕立てた話とも」。「塔」の語句、青表紙本異同ナシ。河内本は二本(七大)が「堂」、四本(宮尾鳳曼)が「丁」とある。別本(陽)は「丁」とある。定家は「塔」の意に解したが、「堂」「丁」の意に解釈する説もあった。
【さる方にて忘れじと心苦しく思ひしを】- 『集成』は「末摘花をそういう人として(恋人としてではなく、庇護すべき人として)忘れずにお世話しようと、おいたわしく思っていたのに」と注す。
|
| 3.4.14 |
かの花散里も、あざやかに今めかしうなどは花やぎたまはぬ所にて、御目移しこよなからぬに、咎多う隠れにけり。
|
あの花散里も、人目に立つ当世風になどはなやかになさらない所なので、比較しても大差はないので、欠点も多く隠れるのであった。
|
ここを出てから源氏の訪ねて行った花散里も、美しい派手な女というのではなかったから、末摘花の醜さも比較して考えられることがなく済んだのであろうと思われる。
|
|
|
第四章 末摘花の物語 その後の物語
|
|
第一段 末摘花への生活援助
|
| 4.1.1 |
祭、御禊などのほど、御いそぎどもにことつけて、人のたてまつりたる物いろいろに多かるを、さるべき限り御心加へたまふ。中にもこの宮にはこまやかに思し寄りて、むつましき人びとに仰せ言賜ひ、下部どもなど遣はして、蓬払はせ、めぐりの見苦しきに、板垣といふもの、うち堅め繕はせたまふ。かう尋ね出でたまへりと、聞き伝へむにつけても、わが御ため面目なければ、渡りたまふことはなし。御文いとこまやかに書きたまひて、二条院近き所を造らせたまふを、 |
賀茂祭、御禊などのころ、ご準備などにかこつけて、人々が献上した物がいろいろと多くあったので、しかるべき夫人方にお心づけなさる。
中でもこの宮には細々とお心をかけなさって、親しい人々にご命令をお下しになって、下べ連中などを遣わして、雑草を払わせ、周囲が見苦しいので、板垣というもので、しっかりと修繕させなさる。
このようにお訪ねになったと、噂するにつけても、ご自分にとって不名誉なので、お渡りになることはない。
お手紙をたいそう情愛こまやかにお認めになって、二条院近くの所をご建築なさっているので、
|
賀茂祭り、斎院の御禊などのあるころは、その用意の品という名義で諸方から源氏へ送って来る物の多いのを、源氏はまたあちらこちらへ分配した。その中でも常陸の宮へ贈るのは、源氏自身が何かと指図をして、宮邸に足らぬ物を何かと多く加えさせた。親しい家司に命じて下男などを宮家へやって邸内の手入れをさせた。庭の蓬を刈らせ、応急に土塀の代わりの板塀を作らせなどした。源氏が妻と認めての待遇をし出したと世間から見られるのは不名誉な気がして、自身で訪ねて行くことはなかった。手紙はこまごまと書いて送ることを怠らない。二条の院にすぐ近い地所へこのごろ建築させている家のことを、源氏は末摘花に告げて、
|
【祭、御禊などのほど】- 四月の賀茂祭のころとなる。
【板垣といふもの、うち堅め繕はせたまふ】- 二条東院に迎え入れるまでの一時的な修理という意味である。
【二条院近き所を】- 大島本は「ちかきところ」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「いと近き」と、副詞「いと」を補訂する。
|
| 4.1.2 |
|
「そこにお移し申し上げましょう。
適当な童女など、お探しになって仕えさせなさい」
|
そこへあなたを迎えようと思う、今から童女として使うのによい子供を選んで馴らしておおきなさい。
|
【そこになむ渡したてまつるべき】- 以下「さぶらはせたまへ」まで、源氏の手紙文。その一部分。
|
| 4.1.3 |
など、人びとの上まで思しやりつつ、訪らひきこえたまへば、かくあやしき蓬のもとには、置き所なきまで、女ばらも空を仰ぎてなむ、そなたに向きて喜びきこえける。
|
などと、女房たちのことまでお気を配りになって、お世話申し上げなさるので、このようにみすぼらしい蓬生の宿では、身の置きどころのないまで、女房たちも空を仰いで、そちらの方角を向いてお礼申し上げるのであった。
|
ともその手紙には書いてあった。女房たちの着料までも気をつけて送って来る源氏に感謝して、それらの人々は源氏の二条の院のほうを向いて拝んでいた。
|
|
| 4.1.4 |
なげの御すさびにても、おしなべたる世の常の人をば、目止め耳立てたまはず、世にすこしこれはと思ほえ、心地にとまる節あるあたりを尋ね寄りたまふものと、人の知りたるに、かく引き違へ、何ごともなのめにだにあらぬ御ありさまを、ものめかし出でたまふは、いかなりける御心にかありけむ。これも昔の契りなめりかし。 |
かりそめのお戯れにしても、ありふれた普通の女性には、目を止めたり聞き耳を立てたりはなさらず、世間で少しでもこの人はと噂されたり、心に止まる点のある女性をお求めなさるものと、皆思っていたが、このように予想を裏切って、どのような点においても人並みでない方を、ひとかどの人物としてお扱いなさるのは、どのようなお心からであったのであろうか。
これも前世からのお約束なのであろうよ。
|
一時的の恋にも平凡な女を相手にしなかった源氏で、ある特色の備わった女性には興味を持って熱心に愛する人として源氏をだれも知っているのであるが、何一つすぐれた所のない末摘花をなぜ妻の一人としてこんな取り扱いをするのであろう。これも前生の因縁ごとであるに違いない。
|
【いかなりける御心にかありけむ。これも昔の契りなめりかし】- 『集成』は「草子地」と注す。
|
|
第二段 常陸宮邸に活気戻る
|
| 4.2.1 |
今は限りと、あなづり果てて、さまざまに迷ひ散りあかれし上下の人びと、我も我も参らむと争ひ出づる人もあり。心ばへなど、はた、埋もれいたきまでよくおはする御ありさまに、心やすくならひて、ことなることなきなま受領などやうの家にある人は、ならはずはしたなき心地するもありて、うちつけの心みえに参り帰り、君は、いにしへにもまさりたる御勢のほどにて、ものの思ひやりもまして添ひたまひにければ、こまやかに思しおきてたるに、にほひ出でて、宮の内やうやう人目見え、木草の葉もただすごくあはれに見えなされしを、遣水かき払ひ、前栽のもとだちも涼しうしなしなどして、ことなるおぼえなき下家司の、ことに仕へまほしきは、かく御心とどめて思さるることなめりと見取りて、御けしき賜はりつつ、追従し仕うまつる。 |
もうこれまでだと、馬鹿にしきって、それぞれさまよい離散して行った上下の女房たち、我も我もとお仕えし直そうと、争って願い出て来る者もいる。
気立てなど、それはそれはで、引っ込み思案なまでによくていらっしゃるご様子ゆえに、気楽な宮仕えに慣れて、これといったところのないつまらない受領などのような家にいる女房は、今までに経験したこともないきまりの悪い思いをするのもいて、げんきんな心をあけすけにして帰って参り、源氏の君は、以前にも勝るご権勢となって、何かにつけて物事の思いやりもさらにお加わりになったので、細々と指図して置かれているので、明るく活気づいて、宮邸の中がだんだんと人の姿も多くなり、木や草の葉もただすさまじくいたわしく見えたのを、遣水を掃除し、前栽の根元をさっぱりなどさせて、大して目をかけていただけない下家司で、格別にお仕えしたいと思う者は、このようにご寵愛になるらしいと見てとって、ご機嫌を伺いながら、追従してお仕え申し上げている。
|
もう暗い前途があるばかりのように見切りをつけて、女王の家を去った人々、それは上から下まで幾人もある旧召使が、われもわれもと再勤を願って来た。善良さは稀に見るほどの女性である末摘花のもとに使われて、気楽に暮らした女房たちが、ただの地方官の家などに雇われて、気まずいことの多いのにあきれて帰って来る者もある。見えすいたような追従も皆言ってくる。昔よりいっそう強い勢力を得ている源氏は、思いやりも深くなった今の心から、扶け起こそうとしている女王の家は、人影もにぎやかに見えてきて、繁りほうだいですごいものに見えた木や草も整理されて、流れに水の通るようになり、立ち木や草の姿も優美に清い感じのするものになっていった。職を欲しがっている下家司級の人は、源氏が一人の夫人の家として世話をやく様子を見て、仕えたいと申し込んで来て、宮家に執事もできた。
|
【さまざまに迷ひ散りあかれし】- 大島本は「まよひちり」とある。諸本は「きをひちり」(御横為榊池肖三)とある。書陵部本が大島本と同文。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は「きほひ散り」と校訂する。『完訳』は「源氏の庇護で豊になると、戻って来る者もいる。「競ひ散り」「あらそい出づる」とあり、離散も帰参も、先を競う軽薄さ」と注す。
【うちつけの心みえに参り帰り】- 大島本は「まいりかへり」とある。『新大系』は底本のままとし、文を続ける。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「参り帰る」と校訂し、文を結ぶ。『集成』は「てきめんに変る心をあけすけに」と注す。
【追従し仕うまつる】- 下家司の態度も女房と同様にげんきんな心の変わりようである。
|
|
第三段 末摘花のその後
|
| 4.3.1 |
|
二年ほどこの古いお邸に寂しくお過ごしになって、東の院という所に、後はお移し申し上げたのであった。
お逢いになることなどは、とても難しいことであるが、近い敷地内なので、普通にお渡りになった時、お立ち寄りなどなさっては、そう軽々しくお扱い申し上げなさらない。
|
末摘花は二年ほどこの家にいて、のちには東の院へ源氏に迎えられ、夫婦として同室に暮らすようなことはめったになかったのであるが、近い所であったから、ほかの用で来た時に話して行くようなことくらいはよくして、軽蔑した扱いは少しもしなかったのである。
|
【二年ばかりこの古宮に眺めたまひて、東の院といふ所になむ、後は渡したてまつりたまひける】- 二年後、末摘花は二条東院に移り住むことになる。 【眺めたまひて】-『集成』は「さびしくお暮しになって」。『完訳』は「無聊の日々をお過しになるが」と訳す。
|
| 4.3.2 |
|
あの大弐の北の方が、上京して来て驚いた様子や、侍従が、嬉しく思う一方で、もう少しお待ち申さなかった思慮の浅さを、恥ずかしく思っていたところなどを、もう少し問わず語りもしたいが、ひどく頭が痛く、厄介で、億劫に思われるので。
今後また機会のある折に思い出してお話し申し上げよう、ということである。
|
大弐の夫人が帰京した時に、どんな驚き方をしたか、侍従が女王の幸福を喜びながらも、時が待ち切れずに姫君を捨てて行った自身のあやまちをどんなに悔いたかというようなことも、もう少し述べておきたいのであるが、筆者は頭が痛くなってきたから、またほかの機会に思い出して書くことにする。
|
【かの大弐の北の方、上りて】- 『集成』は「「かの大弍の北の方」以下「聞こゆべき」まで、物語の語り手の言葉。実際に、末摘花の身の上を見聞したことのある者が語る体」。『完訳』は「以下、語り手の言辞。省筆しながらも、叔母・侍従の複雑な反応を暗示して、物語をしめくくる」と注す。
【せまほしけれど】- 大島本は「せましけれと」とある。「せまほしけれと」の「ほ」脱字であろう。『集成』『新大系』『古典セレクション』は「せまほしけれど」と補訂する。
【思ひ出でて】- 大島本は「思いてゝ」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「思ひ出でてなむ」と、副詞「なむ」を補訂する。
【とぞ】- 『集成』「--ということです。最初の語り手の話を聞き伝えた者が付け加えた体の言葉」と注す。
|
| 著作権 |
| 底本 |
大島本 |
| 校訂 |
Last updated 10/9/2009(ver.2-2)
渋谷栄一校訂(C)
オリジナル
修正版
比較 |
| ローマ字版 |
Last updated 10/11/2009 (ver.2-2)
Written in Japanese roman letters
by Eiichi Shibuya (C)
オリジナル
修正版
比較 |
ルビ抽出
(ローマ字版から)
|
Powered by 再編集プログラム v4.05
ひらがな版
ルビ抽出 |
挿絵
(ローマ字版から)
|
'Eiri Genji Monogatari'
(1650 1st edition) |
|
Last updated 6/27/2001
渋谷栄一訳(C)(ver.1-2-2)
オリジナル
修正版
比較 |
|
|
Last updated 10/11/2009(ver.2-2)
渋谷栄一注釈(C)
オリジナル
修正版
比較 |
|