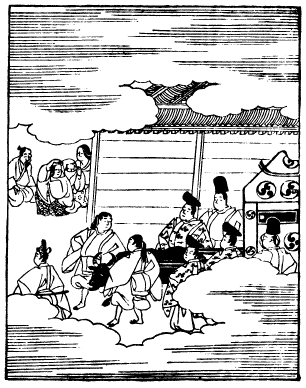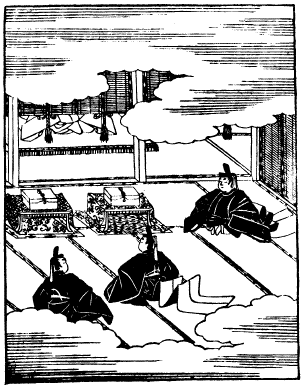第十七帖 絵合
光る源氏の内大臣時代三十一歳春の後宮制覇の物語
|
# |
本文 |
渋谷栄一訳 |
与謝野晶子訳 |
注釈 |
|
第一章 前斎宮の物語 前斎宮をめぐる朱雀院と光る源氏の確執
|
|
第一段 朱雀院、前斎宮の入内に際して贈り物する
|
| 1.1.1 |
|
前斎宮のご入内のこと、中宮が御熱心に御催促申される。
こまごまとしたお世話まで、これといったご後見役もいないとご心配になるが、大殿は、朱雀院がお聞きあそばすことをはばかりなさって、二条の院にお迎え申すことをも、この度はご中止になって、まったく知らない顔に振る舞っていらっしゃるが、一通りの準備は、受け持って親のように世話してお上げになる。
|
前斎宮の入内を女院は熱心に促しておいでになった。こまごまとした入用の品々もあろうがすべてを引き受けてする人物がついていないことは気の毒であると、源氏は思いながらも院への御遠慮があって、今度は二条の院へお移しすることも中止して、傍観者らしく見せてはいたが、大体のことは皆源氏が親らしくしてする指図で運んでいった。
|
【前斎宮の御参りのこと】- 源氏三十一歳春の物語。源氏二十九歳の秋、六条御息所死去し、一年の喪中期間をおいて、その娘前斎宮が冷泉帝に入内する話題。
【こまかなる】- 以下「御後見もなし」まで、源氏の心中。
【大殿は、院に】- 「大殿」は源氏をさし、「院」は朱雀院をさす。あえて内大臣源氏を強調した。
【二条院に渡したてまつらむことをも】- 既に「澪標」巻に語られていた。
【ただ知らず顔にもてなしたまへれど】- 朱雀院が前斎宮に好意を寄せていることに対して。
|
| 1.1.2 |
院はいと口惜しく思し召せど、人悪ろければ、御消息など絶えにたるを、その日になりて、えならぬ御よそひども、御櫛の筥、打乱の筥、香壺の筥ども、世の常ならず、くさぐさの御薫物ども、薫衣香、またなきさまに、百歩の外を多く過ぎ匂ふまで、心ことに調へさせたまへり。大臣見たまひもせむにと、かねてよりや思しまうけけむ、いとわざとがましかむめり。 |
朱雀院はたいそう残念に思し召されるが、体裁が悪いので、お手紙なども絶えてしまっていたが、その当日になって、何ともいえない素晴らしいご装束の数々、お櫛の箱、打乱の箱、香壷の箱など幾つも、並大抵のものでなく、いろいろのお薫物の数々、薫衣香のまたとない素晴らしいほどに、百歩の外を遠く過ぎても匂うくらいの、特別に心をこめてお揃えあそばした。
内大臣が御覧になろうからと、前々から御準備あそばしていたのであろうか、いかにも特別誂えといった感じのようである。
|
院は残念がっておいでになったが、負けた人は沈黙すべきであると思召して、手紙をお送りになることも絶えた形であった。しかも当日になって院からのたいしたお贈り物が来た。御衣服、櫛の箱、乱れ箱、香壺の箱には幾種類かの薫香がそろえられてあった。源氏が拝見することを予想して用意あそばされた物らしい。
|
【打乱の筥】- 大島本は「うちみたれのハこ」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「うちみだり」と校訂する。
【大臣見たまひもせむに】- 朱雀院の心中。
【かねてよりや思しまうけけむ】- 語り手の推測を介在させた表現。
【わざとがましかむめり】- 大島本は「わさとかましかむめり」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「わざとがましかめり」と「む」を削除する。「わざとがましかるめり」の「る」が撥音便化して「わざとがましかむめり」と表記。推量の助動詞「めり」の主体は語り手。
|
| 1.1.3 |
殿も渡りたまへるほどにて、「かくなむ」と、女別当御覧ぜさす。
ただ、御櫛の筥の片つ方を見たまふに、尽きせずこまかになまめきて、めづらしきさまなり。
挿櫛の筥の心葉に、
|
殿もお渡りになっていた時なので、「これこれの次第で」と言って、女別当が御覧に入れさせる。
ちょっと、お櫛の箱の片端を御覧になると、この上もなく精巧で優美に、めったにない作りである。
さし櫛の箱の心葉に、
|
源氏の来ていた時であったから、女別当はその報告をして品々を見せた。源氏はただ櫛の箱だけを丁寧に拝見した。繊細な技巧でできた結構な品である。挿し櫛のはいった小箱につけられた飾りの造花に御歌が書かれてあった。
|
|
| 1.1.4 |
|
「別れの御櫛を差し上げましたが、
それを口実にあなたとの仲を遠く離れたものと神がお決めになった
|
別れ路に添へし小櫛を
かごとにてはるけき中と神やいさめし
|
【別れ路に添へし小櫛をかことにて--遥けき仲と神やいさめし】- 朱雀院から前斎宮への贈歌。遂げられない恋の怨みを含んだ歌。
|
| 1.1.5 |
|
大臣、これを御覧になって、いろいろとお考えめぐらすと、たいそう恐れ多く、おいたわしくて、ご自分の性癖の、ままならぬ恋に惹かれるわが身をつまされて、
|
この御歌に源氏は心の痛くなるのを覚えた。もったいないことを計らったものであると、源氏は自身のかつてした苦しい思いに引き比べて院の今のお心持ちも想像することができてお気の毒でならない。
|
【いとかたじけなく】- 『完訳』は「以下、源氏の反省的な心中」と注す。源氏の心を地の文で語る。
【身を抓みて】- 心中文の後の「思し続けたまふに」に掛かる。
|
| 1.1.6 |
「かの下りたまひしほど、御心に思ほしけむこと、かう年経て帰りたまひて、その御心ざしをも遂げたまふべきほどに、かかる違ひ目のあるを、いかに思すらむ。御位を去り、もの静かにて、世を恨めしとや思すらむ」など、「我になりて心動くべきふしかな」と、思し続けたまふに、いとほしく、「何にかくあながちなることを思ひはじめて、心苦しく思ほし悩ますらむ。つらしとも、思ひきこえしかど、また、なつかしうあはれなる御心ばへを」など、思ひ乱れたまひて、とばかりうち眺めたまへり。 |
「あのお下りになった時、お心にお思いになっただろうこと、このように何年も経ってお帰りになって、そのお気持ちを遂げられる時に、このように意に反することが起こったのを、どのようにお思いであろう。
御位を去り、もの静かに過ごしていらして、世を恨めしくお思いだろうか」などと、「自分がその立場であったなら、きっと心を動かさずにはいられないだろう」と、お思い続けなさると、お気の毒になって、「どうしてこのような無理強引なことを思いついて、おいたわしくお苦しめ悩ますのだろう。
恨めしいとも、お思い申したが、また一方では、お優しく情け深いお気持ちの方を」などと、お思い乱れなさって、しばらくは物思いに耽っていらっしゃった。
|
斎王として伊勢へおいでになる時に始まった恋が、幾年かの後に神聖な職務を終えて女王が帰京され御希望の実現されてよい時になって、弟君の陛下の後宮へその人がはいられるということでどんな気があそばすだろう。閑暇な地位へお退きになった現今の院は、何事もなしうる主権に離れた寂しさというようなものをお感じにならないであろうか、自分であれば世の中が恨めしくなるに違いないなどと思うと心が苦しくて、何故女王を宮中へ入れるようなよけいなことを自分は考えついて御心を悩ます結果を作ったのであろう、お恨めしく思われた時代もあったが、もともと優しい人情深い方であるのにと、源氏は歎息をしながらしばらく考え込んでいた。
|
【かの下りたまひしほど】- 以下「心動くべきふしかな」まで、途中「など」の引用句を挟んで、源氏の心中。朱雀院に同情し、もし自分がその立場だったらと、深く自分の行為を反省する。
【いかに思すらむ】- 以下「思すらん」まで、源氏が朱雀院の心中を忖度した文。
【何にかく】- 以下「御心ばへを」まで、源氏の心中。自分の行動を後悔し、朱雀院の人柄を賞揚する。
|
| 1.1.7 |
|
「このご返歌は、どのように申し上げあそばすのでしょうか。
また、お手紙はどのように」
|
「この御返歌はどうなさるだろう、またお手紙もあったでしょうがお答えにならないではいけないでしょう」
|
【この御返りは】- 以下「御消息もいかが」まで、源氏の詞。女別当を介して、前斎宮に申し上げた。「御消息」は朱雀院からの手紙をさす。どのように書かれていたか、という意。
|
| 1.1.8 |
|
などと、お尋ね申し上げなさるが、とても具合が悪いので、お手紙はお出しになれない。
宮はご気分も悪そうにお思いになって、ご返事をとても億劫になさったが、
|
などと源氏は言ってもいたが、女房たちはお手紙だけは源氏に見せることをしなかった。宮は気分がおすぐれにならないで、御返歌をしようとされないのを、
|
【御文はえ引き出でず】- 朱雀院からの和歌は見せたが、手紙の方は見せることができないという意。
【思ほして】- 大島本は「お(お+も)ほして」と「も」を補訂する。『新大系』は底本の補訂に従う。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「おぼして」と校訂する。
|
| 1.1.9 |
|
「ご返事申されないのも、とても情けなく、恐れ多いことでしょう」
|
「それではあまりに失礼で、もったいないことでございます」
|
【聞こえたまはざらむも】- 以下「かたじけなかるべし」まで、女房たちの詞。返事を差し上げることを催促。
|
| 1.1.10 |
と、人びとそそのかしわづらひきこゆるけはひを聞きたまひて、
|
と、女房たちが催促申し上げ困っている様子をお聞きになって、
|
こんなことを言って、女房たちが返事をお書かせしようと苦心している様子を知ると、源氏は、
|
|
| 1.1.11 |
|
「とても良くないことです。
かたちだけでもご返事差し上げなさいませ」
|
「むろんお返事をなさらないではいけません。ちょっとだけでよいのですからお書きなさい」
|
【いとあるまじき御ことなり。しるしばかり聞こえさせたまへ】- 源氏の詞。朱雀院に形ばかりのお礼の返事を差し上げるよう、言う。
|
| 1.1.12 |
と聞こえたまふも、いと恥づかしけれど、いにしへ思し出づるに、いとなまめき、きよらにて、いみじう泣きたまひし御さまを、そこはかとなくあはれと見たてまつりたまひし御幼心も、ただ今のこととおぼゆるに、故御息所の御ことなど、かきつらねあはれに思されて、ただかく、 |
と申し上げなさるにつけても、ひどく恥ずかしいが、昔のことをお思い出しになると、たいそう優しくお美しくいらして、ひどくお泣きになったご様子を、どことなくしみじみと拝見なさった子供心にも、つい昨日のことと思われると、故御息所のお事など、それからそれへとしみじみと悲しく思い出さずにはいらっしゃれないので、ただこのように、
|
と言った。源氏にそう言われることが斎宮にはまたお恥ずかしくてならないのであった。昔を思い出して御覧になると、艶に美しい帝が別れを惜しんでお泣きになるのを、少女心においたわしくお思いになったことも目の前に浮かんできた。同時に、母君のことも思われてお悲しいのであった。
|
【御幼心も】- 斎宮下向当時十四歳、現在は二十二歳。
|
| 1.1.13 |
|
「別れの御櫛をいただいた時に仰せられた一言が
帰京した今となっては悲しく思われます」
|
別るとてはるかに言ひしひと言も
かへりて物は今ぞ悲しき
|
【別るとて遥かに言ひし一言も--かへりてものは今ぞ悲しき】- 斎宮の返歌。「遥かに言ひし一言」は、斎宮下向の儀式で別れの御櫛を挿す時に、「帰りたまふな」という言葉をさす。斎宮の帰京は、御世交替または親族に不幸があった場合である。斎宮の帰京「帰りて」は朱雀帝の退位により、「今ぞ」の状況は母六条御息所の死去後の孤独な生活をさす。
|
| 1.1.14 |
とばかりやありけむ。御使の禄、品々に賜はす。大臣は、御返りをいとゆかしう思せど、え聞こえたまはず。 |
と、ぐらいにあったのであろうか。
お使いへの禄、身分に応じてお与えになる。
大臣は、お返事をひどく御覧になりたくお思いになったが、お口にはお出しになれない。
|
とだけお書きになったようである。お使いの幾人かはそれぞれ差のあるいただき物をして帰った。源氏は斎宮の御返歌を知りたかったのであるが、それも見たいとは言えなかった。
|
【とばかりやありけむ】- 『集成』は「とだけ、書いていたであろうか。草子地」。『完訳』は「とぐらいお書きになったようである」「読者の想像に委ねる語り口」と注す。
|
|
第二段 源氏、朱雀院の心中を思いやる
|
| 1.2.1 |
|
「院のご様子は、女性として拝見したい美しさだが、この宮のご様子も不似合いでなく、とても似つかわしいお間柄のようであるが、主上は、まだとてもご幼少でいらっしゃるようなので、このように無理にお運び申すことを、人知れず、不快にお思いでいらっしゃろうか」などと、立ち入ったことまで想像なさって、胸をお痛めになるが、今日になって中止するわけにもいかないので、万事しかるべきさまにお命じになって、ご信頼になっている参議兼修理大夫に委細お世話申し上げるべくお命じになって、宮中に参内なさった。
|
院は美男でいらせられるし、女王もそれにふさわしい配偶のように思われる、少年でいらせられる帝の女御におさせすることは、女王の心に不満足なことであるかもしれないなどと思いやりのありすぎることまでも考えてみると、源氏は胸が騒いでならなかったが、今日になって中止のできることでもなかったから儀式その他についての注意を言い置いて、親しい修理大夫参議である人にすべてを委託して源氏は六条邸を出て御所へ参った。
|
【院の御ありさまは】- 源氏参内し、故六条御息所を回想する。以下「ものしとや思すらむ」まで、源氏の心中。
【似げなからず、いとよき御あはひなめるを、内裏は、まだいといはけなくおはしますめるに】- 朱雀院三十四歳、斎宮二十二歳、冷泉帝十三歳。朱雀院と斎宮は結婚するのにも適当な年齢のお間柄であるが、冷泉帝はまだ子供であると、源氏は思う。斎宮の冷泉帝入内を強引な政略結婚であることを自ら認めている。
【引き違へきこゆるを】- 『集成』は「こうして、無理の多い筋にお運び申し上げるのも」。『完訳』は「このように院のお気持にさからってお取り持ちするのを」と訳す。
【憎きことをさへ思しやりて】- 語り手の挿入句。『完訳』は「宮の内心を想像する源氏を、いやな気づかいと、語り手が批評」と注す。
【今日になりて思し止むべきことにしあらねば】- 源氏の反省と後悔は、斎宮入内の中止まで考えさせたが、もはや不可能の事態まで進行。
【修理宰相】- 参議兼修理大夫、従四位下相当官。
|
|
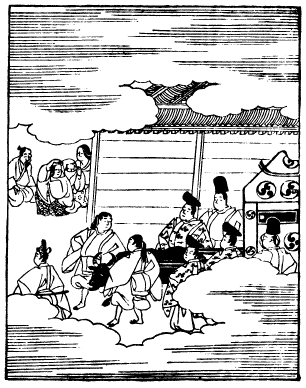 |
| 1.2.2 |
「うけばりたる親ざまには、聞こし召されじ」と、院をつつみきこえたまひて、御訪らひばかりと、見せたまへり。よき女房などは、もとより多かる宮なれば、里がちなりしも参り集ひて、いと二なく、けはひあらまほし。 |
「表立った親のようには、お考えいただかれないように」と、院にご遠慮申されて、ただご挨拶程度と、お見せになった。
優れた女房たちが、もともと大勢いる宮邸なので、里に引き籠もりがちであった女房たちも参集して、実にまたとなく、その感じは理想的である。
|
養父として一切を源氏が世話していることにしては院へ済まないという遠慮から、単に好意のある態度を取っているというふうを示していた。もとからよい女房の多い宮であったから、実家に引いていがちだった人たちも皆出て来て、すでにはなやかな女御の形態が調ったように見えた。
|
【うけばりたる親ざまには、聞こし召されじ】- 源氏の心中。朱雀院に気兼ねする気持ち。
|
| 1.2.3 |
「あはれ、おはせましかば、いかにかひありて、思しいたづかまし」と、昔の御心ざま思し出づるに、「おほかたの世につけては、惜しうあたらしかりし人の御ありさまぞや。さこそえあらぬものなりけれ。よしありし方は、なほすぐれて」、物の折ごとに思ひ出できこえたまふ。 |
「ああ、生きていらしたら、どんなにかお世話の仕甲斐のあることに思って、お世話なさったことだろう」と、故人のご性質をお思い出しになるにつけ、「特別な関係を抜きにして考えれば、まことに惜しむべきお人柄であったよ。
ああまではいらっしゃれないものだ。
風流な面では、やはり優れて」と、何かの時々にはお思い出し申し上げなさる。
|
御息所が生きていたならば、どんなにこうしたことをよろこぶことであろう、聡明な後見役として女御の母であるのに最も適した性格であったと源氏は故人が思い出されて、恋人としてばかりでなく、あの人を失ったことはこの世の損失であるとも源氏は思った。洗練された高い趣味の人といっても、あれほどにすぐれた人は見いだせないのであると、源氏は物のおりごとに御息所を思った。
|
【あはれ、おはせましかば】- 以下「思しいたづかまし」まで、源氏の心中。御息所が生きていたらどんなに甲斐あったことだろう、と思う。
【おほかたの世につけては】- 以下「なをすぐれて」まで、源氏の心中。ただし、その引用句はなく、地の文に続く。『完訳』は「心内語が直接、地の文に続く」と注す。
|
|
第三段 帝と弘徽殿女御と斎宮女御
|
| 1.3.1 |
|
中宮も宮中においであそばしたのであった。
主上は、新しい妃が入内なさるとお耳にあそばしたので、たいそういじらしく緊張なさっていらっしゃる。
お年よりはたいそうおませで大人びていらっしゃる。
中宮も、
|
このごろは女院も御所に来ておいでになった。帝は新しい女御の参ることをお聞きになって、少年らしく興奮しておいでになった。御年齢よりはずっと大人びた方なのである。女院も、
|
【中宮も内裏にぞおはしましける】- 「中宮」は藤壺の宮。
【めづらしき人】- 前齋宮をさす。『集成』は「新しいお妃」。『完訳』は「立派なお方」と訳す。
|
| 1.3.2 |
|
「このような立派な妃が入内なさるのだから、よくお気をつけてお会い申されませ」
|
「りっぱな方が女御に上がって来られるのですから、お気をおつけになってお逢いなさい」
|
【かく恥づかしき人】- 以下「見えたてまつらせたまへ」まで、藤壺の冷泉帝への詞。
|
| 1.3.3 |
と聞こえたまひけり。
|
と申し上げなさるのであった。
|
と御注意をあそばした。
|
|
| 1.3.4 |
|
お心の中で、「大人の妃は気がおけるのではなかろうか」とお思いであったが、たいそう夜が更けてからご入内なさった。
実に慎み深くおっとりしていて、小柄で華奢な感じがしていらっしゃるので、たいそうおきれいな、とお思いになったのであった。
|
帝は人知れず大人の女御は恥ずかしいであろうと思召されたが、深更になってから上の御局へ上がって来た女御は、おとなしいおおような、そして小柄な若々しい人であったから自然に愛をお感じになった。
|
【大人は恥づかしうやあらむ】- 冷泉帝の心中。
【参う上りたまへり】- 当時、入内の儀式は夜に行われた。
|
| 1.3.5 |
弘徽殿には、御覧じつきたれば、睦ましうあはれに心やすく思ほし、これは、人ざまもいたうしめり、恥づかしげに、大臣の御もてなしもやむごとなくよそほしければ、あなづりにくく思されて、御宿直などは等しくしたまへど、うちとけたる御童遊びに、昼など渡らせたまふことは、あなたがちにおはします。 |
弘徽殿女御には、おなじみになっていらしたので、親しくかわいく気がねなくお思いになり、この方は、人柄も実に落ち着いて、気が置けるほどで、内大臣のご待遇も丁重で重々しいので、軽々しくはお扱いできにくく自然お思いになって、御寝の伺候などは対等になるが、気を許した子供どうしのお遊びなどに、昼間などにお出向きになることは、あちら方に多くいらっしゃる。
|
弘徽殿の女御は早くからおそばに上がっていたからその人を睦まじい者に思召され、この新女御は品よく柔らかい魅力があるとともに、源氏が大きな背景を作って、きわめて大事に取り扱う点で侮りがたい人に思召されて宿直に召される数は正しく半々になっていたが、少年らしくお遊びになる相手には弘徽殿がよくて、昼などおいでになることは弘徽殿のほうが多かった。
|
【弘徽殿には】- 弘徽殿女御、権中納言の娘。冷泉帝より一歳年上、十四歳。「澪標」巻で入内、既に二年を経過。冷泉帝の両妃に対する複雑な心境を長文で語る。
【等しくしたまへど】- 大島本は「ひとしくしまへと」と「た」を脱字する。『集成』『新大系』『古典セレクション』は諸本に従って「したまへど」と補訂する。
|
| 1.3.6 |
権中納言は、思ふ心ありて聞こえたまひけるに、かく参りたまひて、御女にきしろふさまにてさぶらひたまふを、方々にやすからず思すべし。 |
権中納言は、考えるところがあってご入内おさせ申したのだが、このように入内なさって、ご自分の娘と競争する形で伺候なさるのを、何かにつけて穏やかならずお思いのようである。
|
権中納言は后にも立てたい心で後宮に入れた娘に、競争者のできたことで不安を感じていた。
|
【思ふ心ありて】- 立后をいう。
|
|
第四段 源氏、朱雀院と語る
|
| 1.4.1 |
院には、かの櫛の筥の御返り御覧ぜしにつけても、御心離れがたかりけり。 |
院におかせられては、あの櫛の箱のお返事を御覧になったにつけても、お諦めにくくお思いであった。
|
院は櫛の箱の返歌を御覧になってからいっそう恋しく思召された。
|
【院には】- 朱雀院。
|
| 1.4.2 |
そのころ、大臣の参りたまへるに、御物語こまやかなり。ことのついでに、斎宮の下りたまひしこと、先々ものたまひ出づれば、聞こえ出でたまひて、さ思ふ心なむありしなどは、えあらはしたまはず。大臣も、かかる御けしき聞き顔にはあらで、ただ「いかが思したる」とゆかしさに、とかうかの御事をのたまひ出づるに、あはれなる御けしき、あさはかならず見ゆれば、いといとほしく思す。 |
そのころ、内大臣が参上なさったので、しみじみとお話なさった。
事のついでに、斎宮がお下りになったこと、以前にもお話し出されたので、お口に出されたが、あのように恋い慕っていたお気持ちがあったなどとは、お打ち明けになれない。
大臣も、このようなご意向を知っているふうに顔にはお出しにならず、ただ「どうお思いでいらっしゃるか」とだけ知りたくて、何かとあの御事をお話に出されると、御傷心の御様子、並々ならず窺えるので、たいそう気の毒にお思いになる。
|
ちょうどそのころに源氏は院へ伺候した。親しくお話を申し上げているうちに、斎宮が下向されたことから、院の御代の斎宮の出発の儀式にお話が行った。院も回想していろいろとお語りになったが、ぜひその人を得たく思っていたとはお言いにならないのである。源氏はその問題を全然知らぬ顔もしながら、どう思召していられるかが知りたくて、話をその方向へ向けた時、院の御表情に失恋の深い御苦痛が現われてきたのをお気の毒に思った。
|
【さ思ふ心なむありし】- 朱雀院の心中を語り手が間接的に語る。斎宮を恋い慕っていた気持ちをさす。
【かかる御けしき】- 朱雀院が斎宮を妃にと所望していたことをさす。
【いかが思したる】- 源氏が朱雀院の心中を忖度。
|
| 1.4.3 |
「めでたしと、思ほししみにける御容貌、いかやうなるをかしさにか」と、ゆかしう思ひきこえたまへど、さらにえ見たてまつりたまはぬを、ねたう思ほす。 |
「素晴らしい器量だと、御執着していらっしゃるご容貌、いったいどれほどの美しさなのか」と、拝見したくお思い申されるが、まったく拝見おできになれないのを悔しくお思いになる。
|
美しい人としてそれほど院が忘れがたく思召す前斎宮は、どんな美貌をお持ちになるのであろうと源氏は思って、おりがあればお顔を見たいと思っているが、その機会の与えられないことを口惜しがっていた。
|
【めでたしと、思ほし】- 以下「をかしさにか」まで、源氏の心中。朱雀院の斎宮への執着の深さから好色心を触発される。
|
| 1.4.4 |
いと重りかにて、夢にもいはけたる御ふるまひなどのあらばこそ、おのづからほの見えたまふついでもあらめ、心にくき御けはひのみ深さまされば、見たてまつりたまふままに、いとあらまほしと思ひきこえたまへり。 |
まことに重々しくて、仮にも子どもっぽいお振る舞いなどがあれば、自然とちらりとお見せになることもあろうが、奥ゆかしいお振る舞いが深くなっていく一方なので、拝見するにつれて、実に理想的だとお思い申し上げた。
|
貴女らしい奥深さをあくまで持っていて、うかとして人に見られる隙のあるような人でない斎宮の女御を源氏は一面では敬意の払われる養女であると思って満足しているのであった。
|
【あらばこそ】- 係助詞「こそ」は「あらめ」に係るが、逆接で文は続く。
|
| 1.4.5 |
|
このように隙間もない状態で、お二方が伺候していらっしゃるので、兵部卿宮、すらすらとはご決意になれず、「主上が、御成人あそばしたら、いくらなんでも、お見捨てあそばすことはあるまい」と、その時機をお待ちになる。
お二方の御寵愛は、それぞれに競い合っていらっしゃる。
|
こんなふうに隙間もないふうに二人の女御が侍しているのであったから、兵部卿の宮は女王の後宮入りを実現させにくくて煩悶をしておいでになったが、帝が青年におなりになったなら、外戚の自分の娘を疎外あそばすことはなかろうとなお希望をつないでおいでになった。宮廷の二人の女御ははなやかに挑み合った。
|
【兵部卿宮、すがすがともえ思ほし立たず】- 中君入内の件である。「澪標」巻にその希望が語られていた。
【帝、おとなびたまひなば、さりとも、え思ほし捨てじ】- 兵部卿宮の心中。帝のもうしばらくの成長に期待をよせる。
|
|
第二章 後宮の物語 中宮の御前の物語絵合せ
|
|
第一段 権中納言方、絵を集める
|
| 2.1.1 |
|
主上は、いろいろのことの中でも、特に絵に興味をお持ちでいらっしゃった。
取り立ててお好みあそばすせいか、並ぶ者がなく上手にお描きあそばす。
斎宮の女御、たいそう上手にお描きあそばすことができるので、この方にお心が移って、しじゆうお渡りになっては、互いに絵を描き心を通わせ合っていらっしゃる。
|
帝は何よりも絵に興味を持っておいでになった。特別にお好きなせいかお描きになることもお上手であった。斎宮の女御は絵をよく描くのでそれがお気に入って、女御の御殿へおいでになってはごいっしょに絵をお描きになることを楽しみにあそばした。
|
【主上は、よろづのことに、すぐれて絵を】- 冷泉帝は絵を好み、後宮では絵の蒐集に競い合う。
【をかしう描かせたまふべければ】- 大島本は「かゝせ給へけれは」とある。『新大系』は底本に従って「給べければ」と整定する。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「たまひければ」と校訂する。斎宮女御に対しても「せたまふ」という最高敬語が地の文で使われている。
【描き通はさせたまふ】- 「通はす」は心を通わす意。親密さがまして行く様子。
|
| 2.1.2 |
殿上の若き人びとも、このことまねぶをば、御心とどめてをかしきものに思ほしたれば、まして、をかしげなる人の、心ばへあるさまに、まほならず描きすさび、なまめかしう添ひ臥して、とかく筆うちやすらひたまへる御さま、らうたげさに御心しみて、いとしげう渡らせたまひて、ありしよりけに御思ひまされるを、権中納言、聞きたまひて、あくまでかどかどしく今めきたまへる御心にて、「われ人に劣りなむや」と思しはげみて、すぐれたる上手どもを召し取りて、いみじくいましめて、またなきさまなる絵どもを、二なき紙どもに描き集めさせたまふ。 |
殿上の若い公達でも、この事を習う者をお目に掛けになり、お気に入りにあそばしたので、なおさらのこと、お美しい方が、趣のあるさまに、型にはまらずのびのびと描き、優美に物に寄り掛かって、ああかこうかと筆を止めて考えていらっしゃるご様子、そのかわいらしさにお心捉えられて、たいそう頻繁にお渡りあそばして、以前にもまして格段に御寵愛が深くなったのを、権中納言、お聞きになって、どこまでも才気煥発な現代風なご性分で、「自分は人に負けるものか」と心を奮い立てて、優れた名人たちを呼び集めて、厳重な注意を促して、またとない素晴らしい絵の数々を、またとない立派な幾枚もの紙に描き集めさせなさる。
|
殿上の若い役人の中でも絵の描ける者を特にお愛しになる帝であったから、まして美しい人が、雅味のある絵を上手に墨で描いて、からだを横たえながら、次の筆の下ろしようを考えたりしている可憐さが御心に沁んで、しばしばこちらへおいでになるようになり、御寵愛が見る見る盛んになった。権中納言がそれを聞くと、どこまでも負けぎらいな性質から有名な画家の幾人を家にかかえて、よい絵をよい紙に、描かせることをひそかにさせていた。
|
【まして】- 副詞「まして」の係る語句について、『集成』は「まして美しいご様子のお方が」と解し、『完訳』は「御心しみて」に係る、と解す。
【あくまでかどかどしく今めきたまへる御心にて】- 権中納言の性格。
【われ人に劣りなむや】- 権中納言の心中。負けてなるものか、という気持ち。
|
|
第二段 源氏方、須磨の絵日記を準備
|
| 2.2.1 |
|
「とりわけ物語絵は、趣向も現れて、見所のあるものだ」
|
「小説を題にして描いた絵が最もおもしろい」
|
【物語絵こそ、心ばへ見えて、見所あるものなれ】- 権中納言の詞。物語絵が見応えするといって、絵師に描かせる。
|
| 2.2.2 |
とて、おもしろく心ばへある限りを選りつつ描かせたまふ。例の月次の絵も、見馴れぬさまに、言の葉を書き続けて、御覧ぜさせたまふ。 |
と言って、おもしろく興趣ある場面ばかりを選んでは描かせなさる。
普通の月次の絵も、目新しい趣向に、詞書を書き連ねて、御覧に供される。
|
と言って、権中納言は選んだよい小説の内容を絵にさせているのである。一年十二季の絵も平凡でない文学的価値のある詞書きをつけて帝のお目にかけた。
|
【月次の絵】- 一年十二か月の風物や年中行事を描いた絵。
|
| 2.2.3 |
わざとをかしうしたれば、また、こなたにてもこれを御覧ずるに、心やすくも取り出でたまはず、いといたく秘めて、この御方へ持て渡らせたまふを惜しみ、領じたまへば、大臣、聞きたまひて、 |
特別に興趣深く描いてあるので、また、こちらで御覧あそばそうとすると、気安くお取り出しにならず、ひどく秘密になさって、こちらの御方へ御持参あそばそうとするのを惜しんで、お貸しなさらないので、内大臣、お聞きになって、
|
おもしろい物であるがそれは非常に大事な物らしくして、帝のおいでになっている間にも、長くは御前へ出して置かずにしまわせてしまうのである。帝が斎宮の女御に見せたく思召して、お持ちになろうとするのを弘徽殿の人々は常にはばむのであった。源氏がそれを聞いて、
|
【こなたにても】- 『集成』は「弘徽殿方」と解し、『完訳』は「斎宮の女御方」と解す。
|
| 2.2.4 |
|
「相変わらず、権中納言のお心の大人げなさは、変わらないな」
|
「中納言の競争心はいつまでも若々しく燃えているらしい」
|
【なほ、権中納言の】- 以下「改まりがたかめれ」まで、源氏の詞。
|
| 2.2.5 |
など笑ひたまふ。
|
などとお笑いになる。
|
などと笑った。
|
|
| 2.2.6 |
「あながちに隠して、心やすくも御覧ぜさせず、悩ましきこゆる、いとめざましや。古代の御絵どものはべる、参らせむ」 |
「むやみに隠して、素直に御覧に入れず、お気を揉ませ申すのは、ひどくけしからぬことだ。
古代の御絵の数々ございます、差し上げましょう」
|
「隠そう隠そうとしてあまり御前へ出さずに陛下をお悩ましするなどということはけしからんことだ」
|
【あながちに隠して】- 以下「参らせむ」まで、源氏の詞。
|
| 2.2.7 |
と奏したまひて、殿に古きも新しきも、絵ども入りたる御厨子ども開かせたまひて、女君ともろともに、「今めかしきは、それそれ」と、選り調へさせたまふ。 |
と奏上なさって、殿に古いのも新しいのも、幾つもの絵の入っている御厨子の数々を開けさせになさって、女君と一緒に、「現代風なのは、これだあれだ」と、お選び揃えなさる。
|
と源氏は言って、帝へは「私の所にも古い絵はたくさんございますから差し上げることにいたしましょう」と奏して、源氏は二条の院の古画新画のはいった棚をあけて夫人といっしょに絵を見分けた。古い絵に属する物と現代的な物とを分類したのである。
|
【今めかしきは、それそれ】- 源氏と紫の君が絵を選んでいる様子。当世風な絵を選んでいる。
|
| 2.2.8 |
|
「長恨歌」「王昭君」などのような絵は、おもしろく感銘深いものだが、「縁起でないものは、このたびは差し上げまい」とお見合わせになる。
|
長恨歌、王昭君などを題目にしたのはおもしろいが縁起はよろしくない。そんなのを今度は省くことに源氏は決めたのである。
|
【事の忌みあるは、こたみはたてまつらじ】- 源氏の考え。「長恨歌」の楊貴妃や王昭君は帝と死別する、縁起でない内容。
|
| 2.2.9 |
|
あの旅の御日記の箱をもお取り出しになって、この機会に、女君にもお見せ申し上げになったのであった。
ご心境を深く知らなくて今初めて見る人でさえ、多少物の分かるような人ならば、涙を禁じえないほどのしみじみと感銘深いものである。
まして、忘れがたく、その当時の夢のような体験をお覚ましになる時とてないお二方にとっては、当時に戻ったように悲しく思い出さずにはいらっしゃれない。
今までお見せにならなかった恨み言を申し上げなさるのであった。
|
旅中に日記代わりに描いた絵巻のはいった箱を出して来て源氏ははじめて夫人にも見せた。何の予備知識を備えずに見る者があっても、少し感情の豊かな者であれば泣かずにはいられないだけの力を持った絵であった。まして忘れようもなくその悲しかった時代を思っている源氏にとって、夫人にとって今また旧作がどれほどの感動を与えるものであるかは想像するにかたくはない。夫人は今まで源氏の見せなかったことを恨んで言った。
|
【かの旅の御日記】- 源氏が須磨・明石のに流浪したころに書いた絵日記。「明石」巻第三章四段参照。
【取り出でさせたまひて】- 「させ」使役の助動詞。女房をして取り出させる意。
【御心深く知らで】- 大島本は「(+御)心ふかくしらて」と「御」を補訂する。『集成』『新大系』は底本の補訂に従う。『古典セレクション』は諸本に従って「心深く知らで」と底本の補訂以前の形にする。
【御心どもには】- 大島本は「御心とともにハ」とある。『集成』『新大系』『古典セレクション』共に諸本に従って「御心どもには」と「と」を削除する。
|
| 2.2.10 |
|
「独り京に残って嘆いていた時よりも、
海人が住んでいる干潟を絵に描いてい
|
「一人居て眺めしよりは海人の住む
かたを書きてぞ見るべかりける
|
【一人ゐて嘆きしよりは海人の住む--かたをかくてぞ見るべかりける】- 紫の君から源氏への贈歌。「絵(かた)」と「潟」の掛詞。「見る」に「海松(みる)」を響かせ、「海人」「潟」「海松」が縁語。
|
| 2.2.11 |
|
頼りなさも、慰められもしましたでしょうに」
|
あなたにはこんな慰めがおありになったのですわね」
|
【慰みなましものを】- 「な」完了の助動詞、未然形。「まし」反実仮想の助動詞、連体形。「を」詠嘆の間投助詞。心細さも慰められたでしょうに、しかし、一緒でなかったから、そうではなかった、の意。
|
| 2.2.12 |
|
とおっしゃる。
まことにもっともだと、お思いになって、
|
源氏は夫人の心持ちを哀れに思って言った。
|
【いとあはれと、思して】- 『集成』は「まことにもっともだと」。『完訳』は「まことにいとおしくお思いになって」と訳す。
|
| 2.2.13 |
|
「辛い思いをしたあの当時よりも、
今日はまた再び過去を思い出していっそう涙が流
|
「うきめ見しそのをりよりは今日はまた
過ぎにし方に帰る涙か
|
【憂きめ見しその折よりも今日はまた--過ぎにしかたにかへる涙か】- 源氏の紫の君への返歌。「潟」「海松」の語句を受けて、「憂き目」「浮海布(うきめ)」、「方」「潟」の掛詞、「涙」に「波」を響かせ、「浮海布」「潟」「波」の縁語を用い、自分もその当時を思い出して、同じ気持ちでいると応える。
|
| 2.2.14 |
中宮ばかりには、見せたてまつるべきものなり。
かたはなるまじき一帖づつ、さすがに浦々のありさまさやかに見えたるを、選りたまふついでにも、かの明石の家居ぞ、まづ、「いかに」と思しやらぬ時の間なき。
|
中宮だけにはぜひともお見せ申し上げなければならないものである。
不出来でなさそうなのを一帖ずつ、何といっても浦々の景色がはっきりと描き出されているのを、お選びになる折にも、あの明石の住居のことが、まっさきに、「どうしているだろうか」とお思いやりにならない時がない。
|
中宮にだけはお目にかけねばならない物ですよ」源氏はその中のことにできのよいものでしかも須磨と明石の特色のよく出ている物を一帖ずつ選んでいながらも、明石の家の描かれてある絵にも、どうしているであろうと、恋しさが誘われた。
|
|
|
第三段 三月十日、中宮の御前の物語絵合せ
|
| 2.3.1 |
かう絵ども集めらると聞きたまひて、権中納言、いと心を尽くして、軸、表紙、紐の飾り、いよいよ調へたまふ。 |
このように幾つもの絵を集めていらっしゃるとお聞きになって、権中納言、たいそう対抗意識を燃やして、軸、表紙、紐の飾りをいっそう調えなさる。
|
源氏が絵を集めていると聞いて、権中納言はいっそう自家で傑作をこしらえることに努力した。巻物の軸、紐の装幀にも意匠を凝らしているのである。
|
【いと心を尽くして】- 大島本は「いと」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「いとど」と校訂する。
|
| 2.3.2 |
|
三月の十日ころなので、空もうららかで、人の心ものびのびとし、ちょうどよい時期なので、宮中あたりでも、節会と節会の合間なので、ただこのようなことをして、どなたもどなたもお過ごしになっていらっしゃるのを、同じことなら、いっそう興味深く御覧あそばされるようにして差し上げようとのお考えになって、たいそう特別に集めて献上させなさった。
|
それは三月の十日ごろのことであったから、最もうららかな好季節で、人の心ものびのびとしておもしろくばかり物が見られる時であったし、宮廷でも定まった行事の何もない時で、絵画や文学の傑作をいかにして集めようかと苦心をするばかりが仕事になっていた。これを皆陛下へ差し上げることにして公然の席で勝負を決めるほうが興味のあってよいことであると源氏がまず言い出した。
|
【弥生の十日のほどなれば、空もうららかにて、人の心ものび、ものおもしろき折なるに、内裏わたりも、節会どものひまなれば】- 三月十日ころ、気候と宮中の人心の延び延びとした様子。景情一致の描写。
【御覧じ所もまさりぬべく】- 主語は帝。
【御心つきて】- 主語は源氏。
|
| 2.3.3 |
こなたかなたと、さまざまに多かり。物語絵は、こまやかになつかしさまさるめるを、梅壺の御方は、いにしへの物語、名高くゆゑある限り、弘徽殿は、そのころ世にめづらしく、をかしき限りを選り描かせたまへれば、うち見る目の今めかしきはなやかさは、いとこよなくまされり。 |
こちら側からとあちら側からと、いろいろと多くあった。
物語絵は、精巧でやさしみがまさっているようなのを、梅壷の御方では、昔の物語、有名で由緒ある絵ばかり、弘徽殿の女御方では、現代のすばらしい新作で、興趣ある絵ばかりを選んで描かせなさったので、一見したところの華やかさでは、実にこの上なく勝っていた。
|
双方から出すのであるから宮中へ集まった絵巻の数は多かった。小説を絵にした物は、見る人がすでに心に作っている幻想をそれに加えてみることによって絵の効果が倍加されるものであるからその種類の物が多い。梅壺の王女御のほうのは古典的な価値の定まった物を絵にしたのが多く、弘徽殿のは新作として近ごろの世間に評判のよい物を描かせたのが多かったから、見た目のにぎやかで派手なのはこちらにあった。
|
【梅壺の御方は】- 斎宮女御の局、凝香舎。初めて局名が明かされる。
|
| 2.3.4 |
主上の女房なども、よしある限り、「これは、かれは」など定めあへるを、このころのことにすめり。
|
主上付きの女房なども、絵に嗜みのある人々はすべて、「これはどうの、あれはどうの」などと批評し合うのを、近頃の仕事にしているようである。
|
典侍や内侍や命婦も絵の価値を論じることに一所懸命になっていた。
|
|
|
第四段 「竹取」対「宇津保」
|
| 2.4.1 |
中宮も参らせたまへるころにて、方々、御覧じ捨てがたく思ほすことなれば、御行なひも怠りつつ御覧ず。この人びとのとりどりに論ずるを聞こし召して、左右と方分かたせたまふ。 |
中宮も参内あそばしていらっしゃる時なので、あれやこれや、お見逃しになれなくお思いのことなので、御勤行も怠りながら御覧になる。
この人々が銘々に議論しあうのをお聞きあそばして、左右の組にお分けあそばす。
|
女院も宮中においでになるころであったから、女官たちの論議する者を二つにして説をたたかわせて御覧になった。左右に分けられたのである。
|
【中宮も参らせたまへるころにて】- 藤壺の宮が宮中に参内している。出家しても宮中に参内することはある。「中宮」という呼称。
|
| 2.4.2 |
梅壺の御方には、平典侍、侍従の内侍、少将の命婦。
右には、大弐の典侍、中将の命婦、兵衛の命婦を、ただ今は心にくき有職どもにて、心々に争ふ口つきどもを、をかしと聞こし召して、まづ、物語の出で来はじめの祖なる『竹取の翁』に『宇津保の俊蔭』を合はせて争ふ。
|
梅壷の御方には、平典侍、侍従内侍、少将命婦。
右方には、大弍典侍、中将命婦、兵衛命婦を、当時のすぐれた識者たちとして、思い思いに論争する弁舌の数々を、興味深くお聞きになって、最初、物語の元祖である『竹取の翁』と『宇津保の俊蔭』を番わせて争う。
|
梅壺方は左で、平典侍、侍従の内侍、少将の命婦などで、右方は大弐の典侍、中将の命婦、兵衛の命婦などであった。皆世間から有識者として認められている女性である。思い思いのことを主張する弁論を女院は興味深く思召して、まず日本最初の小説である竹取の翁と空穂の俊蔭の巻を左右にして論評をお聞きになった。
|
|
| 2.4.3 |
「なよ竹の世々に古りにけること、をかしきふしもなけれど、かくや姫のこの世の濁りにも穢れず、はるかに思ひのぼれる契り高く、神代のことなめれば、あさはかなる女、目及ばぬならむかし」 |
「なよ竹の代々に歳月を重ねたこと、特におもしろいことはないけれども、かぐや姫がこの世の濁りにも汚れず、遥かに気位も高く天に昇った運勢は立派で、神代のことのようなので、思慮の浅い女には、きっと分らないでしょう」
|
「竹取の老人と同じように古くなった小説ではあっても、思い上がった主人公の赫耶姫の性格に人間の理想の最高のものが暗示されていてよいのです。卑近なことばかりがおもしろい人にはわからないでしょうが」
|
【なよ竹の】- 以下「目及ばぬならむかし」まで、左方の『竹取りの翁』を推奨する詞。枕詞「なよたけ」、縁語「ふし」を使って朗々と、その素晴らしさをいう。
|
| 2.4.4 |
と言ふ。
右は、
|
と言う。
右方は、
|
と左は言う。右は、
|
|
| 2.4.5 |
「かぐや姫ののぼりけむ雲居は、げに、及ばぬことなれば、誰も知りがたし。この世の契りは竹の中に結びければ、下れる人のこととこそは見ゆめれ。ひとつ家の内は照らしけめど、百敷のかしこき御光には並ばずなりにけり。阿部のおほしが千々の黄金を捨てて、火鼠の思ひ片時に消えたるも、いとあへなし。車持の親王の、まことの蓬莱の深き心も知りながら、いつはりて玉の枝に疵をつけたるをあやまち」となす。 |
「かぐや姫が昇ったという雲居は、おっしゃるとおり、及ばないことなので、誰も知ることができません。
この世での縁は、竹の中に生まれたので、素性の卑しい人と思われます。
一つの家の中は照らしたでしょうが、宮中の恐れ多い光と並んで妃にならずに終わってしまいました。
阿部の御主人が千金を投じて、火鼠の裘に思いを寄せて片時の間に消えてしまったのも、まことにあっけないことです。
車持の親王が、真実の蓬莱の神秘の事情を知りながら、偽って玉の枝に疵をつけたのを欠点とします」
|
「赫耶姫の上った天上の世界というものは空想の所産にすぎません。この世の生活の写してある所はあまりに非貴族的で美しいものではありません。宮廷の描写などは少しもないではありませんか。赫耶姫は竹取の翁の一つの家を照らすだけの光しかなかったようですね。安部の多が大金で買った毛皮がめらめらと焼けたと書いてあったり、あれだけ蓬莱の島を想像して言える倉持の皇子が贋物を持って来てごまかそうとしたりするところがとてもいやです」
|
【かぐや姫の】- 以下「あやまちとなす」まで、『集成』は「右方(弘徽殿方)の反論の大略を述べる」といい、地の文にし、『完訳』は「 」に括り、訳文は「と言う」という言葉を補って、直接話法的に解す。竹の中から生まれた素性の卑しいこと、帝の妃とならなかったこと、その他、登場人物の失敗と欠点をいう。
【あへなし】- 「あへなし」(形容詞)に「阿倍なし」を掛ける。議論の中にことば遊びを交える。
【玉の枝に疵をつけたる】- 「玉に疵」の格言に合わせて欠点とする。
|
| 2.4.6 |
絵は、巨勢相覧、手は、紀貫之書けり。
紙屋紙に唐の綺をばいして、赤紫の表紙、紫檀の軸、世の常の装ひなり。
|
絵は、巨勢相覧、書は、紀貫之が書いたものであった。
紙屋紙に唐の綺を裏張りして、赤紫の表紙、紫檀の軸、ありふれた表装である。
|
この竹取の絵は巨勢の相覧の筆で、詞書きは貫之がしている。紙屋紙に唐錦の縁が付けられてあって、赤紫の表紙、紫檀の軸で穏健な体裁である。
|
|
| 2.4.7 |
「俊蔭は、はげしき波風におぼほれ、知らぬ国に放たれしかど、なほ、さして行きける方の心ざしもかなひて、つひに、人の朝廷にもわが国にも、ありがたき才のほどを広め、名を残しける古き心を言ふに、絵のさまも、唐土と日の本とを取り並べて、おもしろきことども、なほ並びなし」 |
「俊蔭は、激しい波風に溺れ、知らない国に流されましたが、やはり、目ざしていた目的を叶えて、遂に、外国の朝廷にもわが国にも、めったにない音楽の才能を知らせ、名を残した昔の伝えからいうと、絵の様子も、唐土と日本とを取り合わせて、興趣深いこと、やはり並ぶものがありません」
|
「俊蔭は暴風と波に弄ばれて異境を漂泊しても芸術を求める心が強くて、しまいには外国にも日本にもない音楽者になったという筋が竹取物語よりずっとすぐれております。それに絵も日本と外国との対照がおもしろく扱われている点ですぐれております」
|
【俊蔭は】- 『集成』は「以下、右方が俊蔭の巻の主人公のすぐれた点を挙げる」と注し、地の文扱い。『完訳』は、以下「なほ並びなし」まで、「 」に括り、右方の直接話法とする。
|
| 2.4.8 |
と言ふ。白き色紙、青き表紙、黄なる玉の軸なり。絵は、常則、手は、道風なれば、今めかしうをかしげに、目もかかやくまで見ゆ。左は、そのことわりなし。 |
と言う。
白い色紙、青い表紙、黄色の玉の軸である。
絵は、飛鳥部常則、書は、小野道風なので、現代風で興趣深そうで、目もまばゆいほどに見える。
左方には、反論の言葉がない。
|
と右方は主張するのであった。これは式紙地の紙に書かれ、青い表紙と黄玉の軸が付けられてあった。絵は常則、字は道風であったから派手な気分に満ちている。左はその点が不足であった。
|
【左は、そのことわりなし】- 大島本は「みきハ」とある。文脈から「左は」とあるべきところ。池田本は「みき($左)には」とある。肖は柏本「ひたりには」とある。河内本は「又左に」とある。『集成』は河内本に従って『また左に』と校訂する。『新大系』『古典セレクション』は底本のまま「右は」とする。『集成』は「反論する言葉がない」。『完訳』は「反論の決め手がない」と訳す。
|
|
第五段 「伊勢物語」対「正三位」
|
| 2.5.1 |
次に、『伊勢物語』に『正三位』を合はせて、また定めやらず。これも、右はおもしろくにぎははしく、内裏わたりよりうちはじめ、近き世のありさまを描きたるは、をかしう見所まさる。 |
次に、『伊勢物語』と『正三位』を番わせて、また結論がでない。
これも、右方は興味深く華やかで、宮中あたりをはじめとして、近頃の様子を描いたのは、興趣深く見応えがする。
|
次は伊勢物語と正三位が合わされた。この論争も一通りでは済まない。今度も右は見た目がおもしろくて刺戟的で宮中の模様も描かれてあるし、現代に縁の多い場所や人が写されてある点でよさそうには見えた。
|
【正三位】- 散逸物語。
|
| 2.5.2 |
平内侍、
|
平典侍は、
|
平典侍が言った。
|
|
| 2.5.3 |
|
「『伊勢物語』の深い心を訪ねないで
単に古い物語だからといって価値まで落としめてよいものでしょうか
|
「伊勢の海の深き心をたどらずて
古りにし跡と波や消つべき
|
【伊勢の海の深き心をたどらずて--ふりにし跡と波や消つべき】- 左方の平典侍の歌。「海」「深き」「波」が縁語。『伊勢物語』の「深き心」といって、その価値を弁護強調する。
|
| 2.5.4 |
|
世間普通の色恋事のおもしろおかしく書いてあることに気押されて、業平の名を汚してよいものでしょうか」
|
ただの恋愛談を技巧だけで綴ってあるような小説に業平朝臣を負けさせてなるものですか」
|
【世の常のあだことのひきつくろひ飾れるに】- 以下「名をや朽たすべき」まで、歌に続けた平典侍の詞。「世の常のあだこと」とは『正三位』物語に対する批判。
|
| 2.5.5 |
と、争ひかねたり。
右の典侍、
|
と、反論しかねている。
右方の大弍の典侍は、
|
右の典侍が言う。
|
|
| 2.5.6 |
|
「雲居の宮中に上った『正三位』の心から見ますと
『伊勢物語』の千尋の心も遥か下の方に見えます」
|
雲の上に思ひのぼれる心には
千尋の底もはるかにぞ見る
|
【雲の上に思ひのぼれる心には--千尋の底もはるかにぞ見る】- 大島本は「ちいろ」と表記する。正しく「ちひろ」と改める。右方の大弍典侍の歌。平典侍の言った『伊勢物語』の「深き心」を受けて、『正三位』物語の「雲の上に思ひのほれる心」から見れば、「千尋の底も遥か」だと批判した。
|
| 2.5.7 |
|
「兵衛の大君の心高さは、なるほど捨てがたいものですが、在五中将の名は、汚すことはできますまい」
|
女院が左の肩をお持ちになるお言葉を下された。「兵衛王の精神はりっぱだけれど在五中将以上のものではない。
|
【兵衛の大君の】- 以下「え朽たさじ」まで、藤壺の詞。兵衛大君の心も素晴らしいが、在五中将業平の名を汚すことはできない、という。
|
| 2.5.8 |
とのたまはせて、宮、
|
と仰せになって、中宮は、
|
|
|
| 2.5.9 |
|
「ちょっと見た目には古くさく見えましょうが
昔から名高い『伊勢物語』の名を落とすことができましょうか」
|
見るめこそうらぶれぬらめ年経にし
伊勢をの海人の名をや沈めん」
|
【みるめこそうらふりぬらめ年経にし--伊勢をの海人の名をや沈めむ】- 藤壺の歌。『集成』は「藤壺が、歌で判定を下し、左方を支持したのである」と注す。「海松布(みるめ)」と「見る目」、「浦古り」と「心(うら)古り」の掛詞。「海松布」「浦」「海人」「沈む」が縁語。
|
| 2.5.10 |
|
このような女たちの論議で、とりとめもなく優劣を争うので、一巻の判定に数多くの言葉を尽くしても容易に決着がつかない。
ただ、思慮の浅い若い女房たちは、死ぬほど興味深く思っているが、主上づきの女房も、中宮づきの女房も、その一部分さえ見ることができないほど、たいそう隠していらっしゃった。
|
婦人たちの言論は長くかかって、一回分の勝負が容易につかないで時間がたち、若い女房たちが興味をそれに集めている陛下と梅壺の女御の御絵はいつ席上に現われるか予想ができないのであった。
|
【一巻に言の葉を尽くして】- 『集成』は「物語絵一巻の判定に、あらん限りの論陣を張って」。『完訳』は「一巻の勝負に詞の限りを尽し」と訳す。
【いといたう秘めさせたまふ】- 主語は藤壺。中宮御前における物語絵合せを大層内密にしていらした、という意。
|
|
第三章 後宮の物語 帝の御前の絵合せ
|
|
第一段 帝の御前の絵合せの企画
|
| 3.1.1 |
|
内大臣が参上なさって、このようにそれぞれが優劣を競い合っている気持ちを、おもしろくお思いになって、
|
源氏も参内して、双方から述べられる支持と批難の言葉をおもしろく聞いた。
|
【大臣参りたまひて】- 源氏、参内し物語絵を争っている所に参上する。
|
| 3.1.2 |
|
「同じことなら、主上の御前において、この優劣の決着をつけましょう」
|
「これは御前で最後の勝負を決めましょう」
|
【同じくは、御前にて、この勝負定めむ】- 源氏の詞。物語絵合せの続きを帝御前において催すことに決定。
|
| 3.1.3 |
|
と、おっしゃるまでになった。
このようなこともあろうかと、以前からお思いになっていたので、その中でも特別なのは選び残していらっしゃったが、あの「須磨」「明石」の二巻は、お考えになるところがあって、お加えになったのであった。
|
と源氏が言って、絵合わせはいっそう広く判者を求めることになった。こんなこともかねて思われたことであったから、須磨、明石の二巻を左の絵の中へ源氏は混ぜておいたのである。
|
【のたまひなりぬ】- 『完訳』は「「なり」に注意。源氏個人の意志よりも、宮廷全体の関心による」と注す。
【かかることもや】- 源氏の心中。かねてからの心づもり。
【取り交ぜさせたまへり】- 大島本は「給へり」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「たまへりけり」と「けり」を補訂する。源氏に対して二重敬語表現を用いる。
|
| 3.1.4 |
中納言も、その御心劣らず。
このころの世には、ただかくおもしろき紙絵をととのふることを、天の下いとなみたり。
|
権中納言も、そのお気持ちは負けていない。
最近の世では、ただこのような美しい紙絵を揃えること、世の中の流行になっていた。
|
中納言も劣らず絵合わせの日に傑作を出そうとすることに没頭していた。世の中はもうよい絵を製作することと、捜し出すことのほかに仕事がないように見えた。
|
|
| 3.1.5 |
|
「今新たに描くことは、つまらないことだ。
ただ持っているものだけで」
|
「今になって新しく作ることは意味のないことだ。持っている絵の中で優劣を決めなければ」
|
【今あらため描かむことは】- 以下「限りをこそ」まで、源氏の詞。持ち合わせの絵で競うことを提案。
|
| 3.1.6 |
|
とおっしゃったが、権中納言は他人にも見せないで、秘密の部屋を準備して、お描かせになったが、院におかれても、このような騷ぎがあるとお耳にあそばして、梅壷に幾つかの御絵を差し上げなさった。
|
と源氏は言っているが、中納言は人にも知らせず自邸の中で新画を多く作らせていた。院もこの勝負のことをお聞きになって、梅壺へ多くの絵を御寄贈あそばされた。
|
【わりなき窓を開けて】- 当時の諺か。秘密の部屋を用意しての意。
【院にも】- 朱雀院。「に」格助詞、尊敬のニュアンスを添える。
【かかること】- 梅壺方と弘徽殿方との絵合せの競技をさす。
【たてまつらせたまへり】- 「たてまつら」謙譲の意を含む動詞。「せ」尊敬の助動詞。「たまへ」尊敬の補助動詞。「り」完了の助動詞。朱雀院が梅壺女御に御献上あそばした。
|
| 3.1.7 |
年の内の節会どものおもしろく興あるを、昔の上手どものとりどりに描けるに、延喜の御手づから事の心書かせたまへるに、またわが御世の事も描かせたまへる巻に、かの斎宮の下りたまひし日の大極殿の儀式、御心にしみて思しければ、描くべきやう詳しく仰せられて、公茂が仕うまつれるが、いといみじきをたてまつらせたまへり。 |
一年の内の数々の節会のおもしろく興趣ある様を、昔の名人たちがそれぞれに描いた絵に、延喜の帝がお手ずからその趣旨をお書きあそばしたものや、また御自身の御世のこともお描かせになった巻に、あの斎宮がお下りになった日の、大極殿での儀式を、お心に刻みこまれてあったので、描くべきさまを詳しく仰せになって、巨勢公茂がお描き申したのが、たいそう素晴らしいのを差し上げなさった。
|
宮中で一年じゅうにある儀式の中のおもしろいのを昔の名家が描いて、延喜の帝が御自身で説明をお添えになった古い巻き物のほかに、御自身の御代の宮廷にあったはなやかな儀式などをお描かせになった絵巻には、斎宮発足の日の大極殿の別れの御櫛の式は、御心に沁んで思召されたことなのであったから、特に構図なども公茂画伯に詳しくお指図をあそばして製作された非常にりっぱな絵もあった。
|
【描かせたまへる】- 「せ」使役の助動詞。「たまへ」尊敬の補助動詞。「る」完了の助動詞。延喜の帝が昔の名人に描かせように、朱雀院も当代の名人にお描かせになった。
【仰せられて】- 「仰せらる」連語、最高敬語。「仰せ」+「らる」受身また尊敬の助動詞が、発令者に重点が置かれると、最高敬語になる。
|
| 3.1.8 |
艶に透きたる沈の箱に、同じき心葉のさまなど、いと今めかし。御消息はただ言葉にて、院の殿上にさぶらふ左近中将を御使にてあり。かの大極殿の御輿寄せたる所の、神々しきに、 |
優美に透かし彫りのある沈の箱に、同じ趣旨の心葉のさまなど、実に現代的である。
お便りはただ口上だけで、院の殿上に伺候する左近中将をご使者としてあった。
あの大極殿の御輿を寄せた場面の、神々しい絵に、
|
沈の木の透かし彫りの箱に入れて、同じ木で作った上飾りを付けた新味のある御贈り物であった。御挨拶はただお言葉だけで院の御所への勤務もする左近の中将がお使いをしたのである。大極殿の御輿の寄せてある神々しい所に御歌があった。
|
【左近中将】- 系図不詳の人。
|
| 3.1.9 |
|
「わが身はこのように内裏の外におりますが
あの当時の気持ちは今でも忘れずにおります」
|
身こそかくしめの外なれそのかみの
心のうちを忘れしもせず
|
【身こそかくしめの外なれそのかみの--心のうちを忘れしもせず】- 朱雀院から斎宮女御への贈歌。「そのかみ」に「神」を掛ける。「注連(しめ)」は「神」の縁語。「注連の外」は内裏を離れた院の御所にいる意。「そのかみ」は斎宮であった当時をさす。
|
| 3.1.10 |
とのみあり。
聞こえたまはざらむも、いとかたじけなければ、苦しう思しながら、昔の御簪の端をいささか折りて、
|
とだけある。
お返事申し上げなさらないのも、たいそう恐れ多いので、辛くお思いになりながら、昔のお簪の端を少し折って、
|
と言うのである。返事を差し上げないこともおそれおおいことであると思われて、斎宮の女御は苦しく思いながら、昔のその日の儀式に用いられた簪の端を少し折って、それに書いた。
|
|
| 3.1.11 |
|
「内裏の中は昔とすっかり変わってしまった気がして
神にお仕えしていた昔のことが今は恋しく思われます」
|
しめのうちは昔にあらぬここちして
神代のことも今ぞ恋しき
|
【しめのうちは昔にあらぬ心地して--神代のことも今ぞ恋しき】- 斎宮女御の返歌。院の「注連」「そのかみ」同様に「注連」「昔」「神代」の語句を用いて、「忘れしもせず」に対して「今ぞ恋しき」と、自分も同じ気持ちであることをいう。
|
| 3.1.12 |
とて、縹の唐の紙に包みて参らせたまふ。
御使の禄など、いとなまめかし。
|
とお書きになって、
縹の唐の紙に包んで差し上げなさる。ご使者
|
藍色の唐紙に包んでお上げしたのであった。
|
|
| 3.1.13 |
院の帝御覧ずるに、限りなくあはれと思すにぞ、ありし世を取り返さまほしく思ほしける。大臣をもつらしと思ひきこえさせたまひけむかし。過ぎにし方の御報いにやありけむ。 |
院の帝が御覧になって、限りなくお心がお動きになるにつけ、御在位中のころを取り戻したく思し召すのであった。
内大臣をひどいとお思い申しあそばしたことであろう。
過去の御報いでもあったのであろうか。
|
院はこれを限りもなく身に沁んで御覧になった。このことで御位も取り返したく思召した。源氏をも恨めしく思召されたに違いない。かつて源氏に不合理な厳罰をお加えになった報いをお受けになったのかもしれない。
|
【大臣をも】- 以下「御報ひにやありけむ」まで、語り手の文章。「けむ」過去推量の助動詞は、語り手の推量。『集成』は「草子地」。『完訳』「語り手の想像、推測」と注す。
|
| 3.1.14 |
|
院の御絵は、大后の宮から伝わって、あの弘徽殿の女御のお方にも多く集まっているのであろう。
尚侍の君も、このようなご趣味は人一倍優れていて、興趣深い絵を描かせては集めていらっしゃる。
|
院のお絵は太后の手を経て弘徽殿の女御のほうへも多く来ているはずである。尚侍も絵の趣味を多く持っている人であったから、姪の女御のためにいろいろと名画を集めていた。
|
【院の御絵は、后の宮より伝はりて、あの女御の御方にも】- 朱雀院の母弘徽殿大后からその妹の四君の夫権中納言の娘弘徽殿女御へ。弘徽殿大后と弘徽殿女御は伯母と姪、という関係。
|
|
第二段 三月二十日過ぎ、帝の御前の絵合せ
|
| 3.2.1 |
|
何日と決めて、急なようであるが、興趣深いさまにちょっと設備をして、左右の数々の御絵を差し出させなさる。
女房が伺候する所に玉座を設けて、北と南とにそれぞれ分かれて座る。
殿上人は、後涼殿の簀子に、それぞれが心を寄せながら控えている。
|
定められた絵合わせの日になると、それはいくぶんにわかなことではあったが、おもしろく意匠をした風流な包みになって、左右の絵が会場へ持ち出された。女官たちの控え座敷に臨時の玉座が作られて、北側、南側と分かれて判者が座についた。それは清涼殿のことで、西の後涼殿の縁には殿上役人が左右に思い思いの味方をしてすわっていた。
|
【その日と定めて】- 帝御前における絵合を三月二十日過ぎに決定。
【女房のさぶらひに御座よそはせて】- 台盤所に帝の玉座を設ける。
|
| 3.2.2 |
左は、紫檀の箱に蘇芳の花足、敷物には紫地の唐の錦、打敷は葡萄染の唐の綺なり。
童六人、赤色に桜襲の汗衫、衵は紅に藤襲の織物なり。
姿、用意など、なべてならず見ゆ。
|
左方は、紫檀の箱に蘇芳の華足、敷物には紫地の唐の錦、打敷は葡萄染めの唐の綺である。
童六人、赤色に桜襲の汗衫、衵は紅に藤襲の織物である。
姿、心用意など、並々でなく見える。
|
左の紫檀の箱に蘇枋の木の飾り台、敷き物は紫地の唐錦、帛紗は赤紫の唐錦である。六人の侍童の姿は朱色の服の上に桜襲の汗袗、袙は紅の裏に藤襲の厚織物で、からだのとりなしがきわめて優美である。
|
|
| 3.2.3 |
右は、沈の箱に浅香の下机、打敷は青地の高麗の錦、あしゆひの組、花足の心ばへなど、今めかし。
童、青色に柳の汗衫、山吹襲の衵着たり。
|
右方は、沈の箱に浅香の下机、打敷は青地の高麗の錦、脚結いの組紐、華足の趣など、現代的である。
童、青色に柳の汗衫、山吹襲の衵を着ている。
|
右は沈の木の箱に浅香の下机、帛紗は青地の高麗錦、机の脚の組み紐の飾りがはなやかであった。侍童らは青色に柳の色の汗袗、山吹襲の袙を着ていた。
|
|
| 3.2.4 |
|
皆、御前に御絵を並べ立てる。
主上つきの女房、前に後に、装束の色を分けている。
|
双方の侍童がこの絵の箱を御前に据えたのである。
|
【皆、御前に舁き立つ】- 『集成』は「机を肩にして運び、帝の御前に並べ立てる」と注す。
|
|
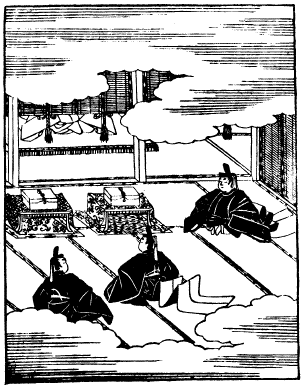 |
| 3.2.5 |
|
お召しがあって、内大臣、権中納言、参上なさる。
その日、帥宮も参上なさった。
たいそう風流でいらっしゃるうちでも、絵を特にお嗜みでいらっしゃるので、内大臣が、内々お勧めになったのでもあろうか、仰々しいお招きではなくて、殿上の間にいらっしゃるのを、御下命があって御前に参上なさる。
|
源氏の内大臣と権中納言とが御前へ出た。太宰帥の宮も召されて出ておいでになった。この方は芸術に趣味をお持ちになる方であるが、ことに絵画がお好きであったから、初めに源氏からこのお話もしてあった。公式のお召しではなくて、殿上の間に来ておいでになったのに仰せが下ったのである。
|
【大臣の、下にすすめたまへるやうやあらむ】- 「やうやあらむ」、「や」疑問の係助詞、「む」推量の助動詞。語り手の推測。挿入句。
【ことことしき】- 『日葡辞書』に「コトコトシイ」とある。
【御前に】- 大島本は「御こせむ」とある。『集成』『新大系』は「御」を衍字と看做して「御前(ごぜん)」と整定する。『古典セレクション』は諸本に従って「御前(おまへ)」と校訂する。
|
| 3.2.6 |
この判仕うまつりたまふ。
いみじう、げに描き尽くしたる絵どもあり。
さらにえ定めやりたまはず。
|
この判者をお勤めになる。
たいそう、なるほど上手に筆の限りを尽くしたいくつもの絵がある。
全然判定することがおできになれない。
|
この方に今日の審判役を下命された。評判どおりに入念に描かれた絵巻が多かった。優劣をにわかにお決めになるのは困難なようである。
|
|
| 3.2.7 |
|
例の四季の絵も、昔の名人たちがおもしろい画題を選んでは、筆もすらすらと描き流してある風情、譬えようがないと見ると、紙絵は紙幅に限りがあって、山水の豊かな趣を現し尽くせないものなので、ただ筆先の技巧、絵師の趣向の巧みさに飾られているだけで、当世風の浅薄なのも、昔のに劣らず、華やかで実におもしろい、と見える点では優れていて、多数の論争なども、今日は両方ともに興味深いことが多かった。
|
例の四季を描いた絵も、大家がよい題材を選んで筆力も雄健に描き流した物は価値が高いように見えるが、今度は皆紙絵であるから、山水画の豊かに描かれた大作などとは違って、凡庸な者に思われている今の若い絵師も昔の名画に近い物を作ることができ、それにはまた現代人の心を惹くものも多量に含まれていて、左右はそうした絵の優劣を論じ合っているが、今日の論争は双方ともまじめであったからおもしろかった。
|
【例の四季の絵も】- 以下「たとへむかたなし」まで、帥宮の目を通して語る文章。その始まりは地の文、やがて心中文へと変移する。この四季絵は左方。朱雀院が斎宮女御に贈った絵。
【紙絵は限りありて】- 『集成』は「画面が狭くて」。『完訳』は「紙絵は、屏風絵などに比べて紙幅に限りのあること」。紙絵そのものについていう。両方が四季の紙絵を出品。
【ただ筆の飾り】- 以下「あなおもしろ」まで、帥宮の目を通して語る文章。右方の四季絵についていう。
【昔のあと恥なく】- 大島本は「むかしのあと△(△#)」とある。すなわち「と」の次に一文字有ったのを、抹消している。『集成』『新大系』は底本の抹消に従って「あと」と整定する。『古典セレクション』は諸本に従って「跡に」と校訂する。
|
| 3.2.8 |
|
朝餉の間の御障子を開けて、中宮も御覧になっていらっしゃるので、深く絵に御精通であろうと思うと、内大臣もたいそう素晴らしいとお思いになって、所々の判定の不安な折々には、時々ご意見を述べなさった様子、理想的である。
|
襖子をあけて朝餉の間に女院は出ておいでになった。絵の鑑識に必ず自信がおありになるのであろうと思って、源氏はそれさえありがたく思われた。
|
【深うしろしめしたらむ】- 源氏の心中。藤壺が絵に精通していることを思う。
【大臣もいと優におぼえたまひて】- 『完訳』は「源氏には自分の旅日記の絵の用意があるだけに、藤壺に大きな期待を寄せる」と注す。
|
|
第三段 左方、勝利をおさめる
|
| 3.3.1 |
定めかねて夜に入りぬ。
左はなほ数一つある果てに、「須磨」の巻出で来たるに、中納言の御心、騒ぎにけり。
あなたにも心して、果ての巻は心ことにすぐれたるを選り置きたまへるに、かかるいみじきものの上手の、心の限り思ひすまして静かに描きたまへるは、たとふべきかたなし。
|
勝負がつかないで夜に入った。
左方、なお一番残っている最後に、「須磨」の絵巻が出て来たので、権中納言のお心、動揺してしまった。
あちらでも心づもりして、最後の巻は特に優れた絵を選んでいらっしゃったのだが、このような大変な絵の名人が、心ゆくばかり思いを澄ませて心静かにお描きになったのは、譬えようがない。
|
判者が断定のしきれないような時に、お伺いを女院へするのに対して、短いお言葉の下されるのも感じのよいことであった。左右の勝ちがまだ決まらずに夜が来た。最後の番に左から須磨の巻が出てきたことによって中納言の胸は騒ぎ出した。右もことに最後によい絵巻が用意されていたのであるが、源氏のような天才が清澄な心境に達した時に写生した風景画は何者の追随をも許さない。
|
|
| 3.3.2 |
親王よりはじめたてまつりて、涙とどめたまはず。その世に、「心苦し悲し」と思ほししほどよりも、おはしけむありさま、御心に思ししことども、ただ今のやうに見え、所のさま、おぼつかなき浦々、磯の隠れなく描きあらはしたまへり。 |
親王をはじめまいらせて、感涙を止めることがおできになれない。
あの当時に、「お気の毒に、悲しいこと」とお思いになった時よりも、お過ごしになったという所の様子、どのようなお気持ちでいらしたかなど、まるで目の前のことのように思われ、その土地の風景、見たこともない浦々、磯を隈なく描き現していらっしゃった。
|
判者の親王をはじめとしてだれも皆涙を流して見た。その時代に同情しながら想像した須磨よりも、絵によって教えられる浦住まいはもっと悲しいものであった。作者の感情が豊かに現われていて、現在をもその時代に引きもどす力があった。須磨からする海のながめ、寂しい住居、崎々浦々が皆あざやかに描かれてあった。
|
【心苦し悲し】- この座の方々の心中。源氏の須磨明石流謫を悲しく気の毒に思ったこと。
|
| 3.3.3 |
|
草書体に仮名文字を所々に書き交ぜて、正式の詳しい日記ではなく、しみじみとした歌などが混じっている、その残りの巻が見たいくらいである。
誰も他人事とは思われず、いろいろな御絵に対する興味、これにすっかり移ってしまって、感慨深く興趣深い。
万事みなこの絵日記に譲って、左方、勝ちとなった。
|
草書で仮名混じりの文体の日記がその所々には混ぜられてある。身にしむ歌もあった。だれも他の絵のことは忘れて恍惚となってしまった。圧巻はこれであると決まって左が勝ちになった。
|
【まほの詳しき日記にはあらず】- 正式の詳細な日記、すなわち、漢文体で書かれた日記ではなく、の意。
【まじれる、たぐひゆかし】- 「まじれる」連体中止、下には係らず、理由を表す連文節となって、一呼吸置いて「類ゆかし」という文が続く。
【こと事思ほさず】- 『完訳』は「誰も誰ももう他のことは念頭になく」と注す。
|
|
第四章 光る源氏の物語 光る源氏世界の黎明
|
|
第一段 学問と芸事の清談
|
| 4.1.1 |
|
夜明けが近くなったころに、何となくしみじみと感慨がこみ上げてきて、お杯など傾けなさる折に、昔のお話などが出てきて、
|
明け方近くなって古い回想から湿った心持ちになった源氏は杯を取りながら帥の宮に語った。
|
【夜明け方近くなるほどに】- 絵合せ後の宴会で、源氏と帥宮、才芸について語り合う。
|
| 4.1.2 |
「いはけなきほどより、学問に心を入れてはべりしに、すこしも才などつきぬべくや御覧じけむ、院ののたまはせしやう、『才学といふもの、世にいと重くするものなればにやあらむ、いたう進みぬる人の、命、幸ひと並びぬるは、いとかたきものになむ。品高く生まれ、さらでも人に劣るまじきほどにて、あながちにこの道な深く習ひそ』と、諌めさせたまひて、本才の方々のもの教へさせたまひしに、つたなきこともなく、またとり立ててこのことと心得ることもはべらざりき。 |
「幼いころから、学問に心を入れておりましたが、少し学才などがつきそうに御覧になったのでしょうか、故院が仰せになったことに、『学問の才能というものは、世間で重んじられるからであろうか、たいそう学問を究めた人で、長寿と、幸福とが並んだ者は、めったにいないものだ。
高い身分に生まれ、そうしなくても人に劣ることのない身分なのだから、むやみにこの道に深入りするな』と、お諌めあそばして、正式な学問以外の芸を教えてくださいましたが、出来の悪いものもなく、また特にこのことはと上達したこともございませんでした。
|
「私は子供の時代から学問を熱心にしていましたが、詩文の方面に進む傾向があると御覧になったのですか、院がこうおっしゃいました、文学というものは世間から重んぜられるせいか、そのほうのことを専門的にまでやる人の長寿と幸福を二つともそろって得ている人は少ない。不足のない身分は持っているのであるから、あながちに文学で名誉を得る必要はない。その心得でやらねばならないって。以来私に本格的な学問をいろいろとおさせになりましたが、できが悪い課目もなく、またすぐれた深い研究のできたこともありませんでした。
|
【いはけなきほどより】- 以下「きこえやあらむ」まで、源氏の詞。
【才学といふもの】- 以下「な深く習ひそ」まで、故院の詞を引用。
【さらでも】- 学問をすることをさす。
【本才の方々のもの教へ】- 『集成』は「実際の役に立つ技能。儀式、典礼など、政治家に必要な知識、技能。作詩、書道、舞、楽など諸方面が「かたがた」という」と注す。
|
| 4.1.3 |
|
ただ、絵を描くことだけが、妙なつまらないことですが、どうしたら心のゆくほど描けるだろうかと、思う折々がございましたが、思いもよらない賤しい身の上となって、四方の海の深い趣を見ましたので、まったく思い至らぬ所のないほど会得できましたが、絵筆で描くにはは限界がありまして、心で思うとおりには事の運ばぬように存じられましたが、機会がなくて、御覧に入れるわけにも行きませんので、このように物好きのようなのは、後々に噂が立ちましょうか」
|
絵を描くことだけは、それは大きいことではありませんが、満足のできるほど精神を集中させて描いて見たいという希望がおりおり起こったものですが、思いがけなく放浪者になりました時に、はじめて大自然の美しさにも接する機会を得まして、描くべき物は十分に与えられたのですが、技巧がまずくて、思いどおりの物を紙上に表現することはできませんでした。そんなものですからこれだけをお目にかけることは恥ずかしくていたされませんから、今度のような機会に持ち出しただけなのですが、私の行為が突飛なように評されないかと心配しております」
|
【いかにしてかは】- 連語。手段に迷う気持ち。どのようにしたら--だろうか、の意。
【思ひ寄らぬ隈なく至られにしかど】- 『集成』「もはや思い及ばぬ所もないほど、十分に会得されましたが」。『完訳』は「まったく思い至らぬところのない境地にしぜん到達いたしましたけれども」。助動詞「れ」について、『集成』は可能の意、『完訳』は自発の意に解釈。
【思うたまへられしを】- 「たまへ」下二段、謙譲の補助動詞。助動詞「られ」自発の意。
【かう好き好きしきやうなる、後の聞こえやあらむ】- 『集成』は「(そんなものを)この機会に持ち出したりして、いかにも物好きなようなのは、後世から批判されるかもしれません」と訳す。
|
| 4.1.4 |
と、親王に申したまへば、
|
と、親王に申し上げなさると、
|
|
|
| 4.1.5 |
「何の才も、心より放ちて習ふべきわざならねど、道々に物の師あり、学び所あらむは、事の深さ浅さは知らねど、おのづから移さむに跡ありぬべし。筆取る道と碁打つこととぞ、あやしう魂のほど見ゆるを、深き労なく見ゆるおれ者も、さるべきにて、書き打つたぐひも出で来れど、家の子の中には、なほ人に抜けぬる人、何ごとをも好み得けるとぞ見えたる。 |
「何の芸道も、心がこもっていなくては習得できるものではありませんが、それぞれの道に師匠がいて、学びがいのあるようなものは、度合の深さ浅さは別として、自然と学んだだけの事は後に残るでしょう。
書画の道と碁を打つことは、不思議と天分の差が現れるもので、深く習練したと思えぬ凡愚の者でも、その天分によって、巧みに描いたり打ったりする者も出て来ますが、名門の子弟の中には、やはり抜群の人がいて、何事にも上達すると見えました。
|
「何の芸でも頭がなくては習えませんが、それでもどの芸にも皆師匠があって、導く道ができているものですから、深さ浅さは別問題として、師匠の真似をして一通りにやるだけのことはだれにもまずできるでしょう。ただ字を書くことと囲碁だけは芸を熱心に習ったとも思われない者からもひょっくりりっぱな書を書く者、碁の名人が出ているものの、やはり貴族の子の中からどんな芸も出抜けてできる人が出るように思われます。
|
【何の才も】- 以下「けしからぬわざなり」まで、帥宮の詞。
【人に抜けぬる人】- 大島本は「ぬけぬる人の(の#<朱墨>)」とある。すなわち「の」を朱筆と墨筆で抹消する。『集成』『新大系』は底本の抹消に従って「人」とする。『古典セレクション』は底本の訂正以前本文と諸本に従って「人の」と校訂する。
|
| 4.1.6 |
院の御前にて、親王たち、内親王、いづれかは、さまざまとりどりの才習はさせたまはざりけむ。その中にも、とり立てたる御心に入れて、伝へ受けとらせたまへるかひありて、『文才をばさるものにて言はず、さらぬことの中には、琴弾かせたまふことなむ一の才にて、次には横笛、琵琶、箏の琴をなむ、次々に習ひたまへる』と、主上も思しのたまはせき。世の人、しか思ひきこえさせたるを、絵はなほ筆のついでにすさびさせたまふあだこととこそ思ひたまへしか、いとかう、まさなきまで、いにしへの墨がきの上手ども、跡をくらうなしつべかめるは、かへりて、けしからぬわざなり」 |
故院のお膝もとで、親王たち、内親王、どなたもいろいろさまざまなお稽古事を習わさせなかったことがありましょうか。
その中でも、特にご熱心になって、伝授を受けご習得なさった甲斐があって、『詩文の才能は言うまでもなく、それ以外のことの中では、琴の琴をお弾きになることが第一番で、次には、横笛、琵琶、箏の琴を次々とお習いになった』と、故院も仰せになっていました。
世間の人、そのようにお思い申し上げていましたが、絵はやはり筆のついでの慰み半分の余技と存じておりましたが、たいそうこんなに不都合なくらいに、昔の墨描きの名人たちが逃げ出してしまいそうなのは、かえって、とんでもないことです」
|
院が御自身の親王、内親王たちに皆何かの芸はお仕込みになったわけですが、その中でもあなたへは特別に御熱心に御教授あそばしましたし、熱心にもお習いになったのですから、詩文のほうはむろんごりっぱだし、そのほかでは琴をお弾きになることが第一の芸で、次は横笛、琵琶、十三絃という順によくおできになる芸があると院も仰せになりました。世間もそう信じているのですが、絵などはほんのお道楽だと私も今までは思っていましたのに、あまりにお上手過ぎて墨絵描きの画家が恥じて死んでしまう恐れがある傑作をお見せになるのは、けしからんことかもしれません」
|
【いづれかは】- 下文の「習はさせたまはざりけむ」に係る反語表現。『完訳』は「院の御前で、親王や内親王たちは、いずれも芸能のそれぞれをお習いにならなかった方はございませんでしょう」と訳す。
【さまざま】- 大島本は「さま」とある。『集成』『新大系』『古典セレクション』は諸本に従って「さまざま」と「さま」を補訂する。
【習はさせたまはざりけむ】- 「させ」使役の助動詞。主語は院。院が親王や内親王たちに。
【伝へ受けとらせたまへるかひありて】- 大島本は「う(う=つイ<墨朱>)たへ」とある。すなわち本行本文「う」の右傍らに朱筆と墨筆で「つイ」と異本との校合を記す。『集成』『新大系』『古典セレクション』は「つたへ」と校訂する。「せたまへ」二重敬語。主語は源氏。
【文才をばさるものにて】- 以下「習ひたまへる」まで、院の詞を引用。
【こそ思ひたまへしか】- 「こそ」係助詞、「しか」已然形の係結びは、逆接用法で、下文に続く。
|
| 4.1.7 |
と、うち乱れて聞こえたまひて、酔ひ泣きにや、院の御こと聞こえ出でて、皆うちしほれたまひぬ。 |
と、酔いに乱れて申し上げなさって、酔い泣きであろうか、故院の御事を申し上げて、皆涙をお流しになった。
|
宮はしまいには戯談をお言いになったが酔い泣きなのか、故院のお話をされてしおれておしまいになった。
|
【うちしほれたまひぬ】- 大島本は「しほ△(△#)れ給ぬ」とある。すなわち元の文字(不明)を抹消して「しほれ」とする。『新大系』は底本の抹消に従って「しほれ」と整定する。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「しほたれ」と校訂する。
|
|
第二段 光る源氏体制の夜明け
|
| 4.2.1 |
二十日あまりの月さし出でて、こなたは、まださやかならねど、おほかたの空をかしきほどなるに、書司の御琴召し出でて、和琴、権中納言賜はりたまふ。さはいへど、人にまさりてかき立てたまへり。親王、箏の御琴、大臣、琴、琵琶は少将の命婦仕うまつる。上人の中にすぐれたるを召して、拍子賜はす。いみじうおもしろし。 |
二十日過ぎの月がさし出して、こちら側は、まだ明るくないけれども、いったいに空の美しいころなので、書司のお琴をお召し出しになって、和琴、権中納言がお引き受けなさる。
そうは言っても、他の人以上に上手にお弾きになる。
帥親王、箏の御琴、内大臣、琴の琴、琵琶は少将の命婦がおつとめする。
殿上人の中から勝れた人を召して、拍子を仰せつけになる。
たいそう興趣深い。
|
二十幾日の月が出てまだここへはさしてこないのであるが、空には清い明るさが満ちていた。書司に保管されてある楽器が召し寄せられて、中納言が和琴の弾き手になったが、さすがに名手であると人を驚かす芸であった。帥の宮は十三絃、源氏は琴、琵琶の役は少将の命婦に仰せつけられた。殿上役人の中の音楽の素養のある者が召されて拍子を取った。稀なよい合奏になった。
|
【おほかたの空をかしきほどなるに】- 三月二十日過ぎの天象模様。
|
| 4.2.2 |
|
夜が明けていくにつれて、花の色も人のお顔形なども、ほのかに見えてきて、鳥が囀るころは、快い気分がして、素晴らしい朝ぼらけである。
禄などは、中宮の御方から御下賜なさる。
親王は御衣をまた重ねて頂戴なさる。
|
夜が明けて桜の花も人の顔もほのかに浮き出し、小鳥のさえずりが聞こえ始めた。美しい朝ぼらけである。下賜品は女院からお出しになったが、なお親王は帝からも御衣を賜わった。
|
【明け果つるままに、花の色も人の御容貌ども、ほのかに見えて、鳥のさへづるほど、心地ゆき、めでたき朝ぼらけなり】- 大島本は「御かたちとも」とある。『集成』『新大系』は底本のままとする。『古典セレクション』は諸本に従って「御容貌も」と校訂する。冷泉朝の開幕を象徴する表現。
【また重ねて賜はりたまふ】- 帝から頂戴することをいう。
|
|
第三段 冷泉朝の盛世
|
| 4.3.1 |
|
その当時のことぐさには、この絵日記の評判をなさる。
|
この当座はだれもだれも絵合わせの日の絵の噂をし合った。
|
【そのころのことには】- その当時の話題としては、の意。
|
| 4.3.2 |
|
「あの浦々の巻は、中宮にお納めください」
|
「須磨、明石の二巻は女院の御座右に差し上げていただきたい」
|
【かの浦々の巻は、中宮にさぶらはせたまへ】- 源氏の詞。須磨、明石の絵日記は藤壺の宮に献上する。
|
| 4.3.3 |
|
とお申し上げさせになったので、この初めの方や、残りの巻々を御覧になりたくお思いになったが、
|
こう源氏は申し出た。女院はこの二巻の前後の物も皆見たく思召すとのことであったが、
|
【残りの巻々ゆかしがらせたまへど】- 大島本は「のこりのまきまき」とある。『新大系』は底本のままとする。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「また残りの巻々」と「また」を補訂する。主語は藤壺。「せ」尊敬の助動詞、「たまへ」尊敬の補助動詞。最高敬語。
|
| 4.3.4 |
|
「いずれそのうちに、ぼつぼつと」
|
「またおりを見まして」
|
【今、次々に】- 源氏の詞。
|
| 4.3.5 |
|
とお申し上げさせになる。
主上におかせられても、御満足に思し召していらっしゃるのを、嬉しくお思い申し上げなさる。
|
と源氏は御挨拶を申した。帝が絵合わせに満足あそばした御様子であったのを源氏はうれしく思った。
|
【主上にも御心ゆかせたまひて】- 主語は帝。「せ」尊敬の助動詞、「たまひ」尊敬の補助動詞、最高敬語。
【うれしく見たてまつりたまふ】- 主語は源氏。
|
| 4.3.6 |
|
ちょっとしたことにつけても、このようにお引き立てになるので、権中納言は、「やはり、世間の評判も圧倒されるのではなかろうか」と、悔しくお思いのようである。
主上の御愛情は、初めから馴染んでいらっしゃったので、やはり、御寵愛厚い御様子を、人知れず拝見し存じ上げていらっしゃったので、頼もしく思い、「いくら何でも」とお思になるのであった。
|
二人の女御の挑みから始まったちょっとした絵の上のことでも源氏は大形に力を入れて梅壺を勝たせずには置かなかったことから中納言は娘の気押されて行く運命も予感して口惜しがった。帝は初めに参った女御であって、御愛情に特別なもののあることを、女御の父の中納言だけは想像のできる点もあって、頼もしくは思っていて、すべては自分の取り越し苦労であるとしいて思おうとも中納言はしていた。
|
【なほ、おぼえ圧さるべきにや】- 権中納言の心中。「おぼえ」は世の評判。
【思さるべかめり】- 「べかめり」連語、推量の助動詞。この主観的推量は語り手。
【なほ、こまやかに】- 『完訳』は「以下、権中納言の心中」と解す。
【人知れず見たてまつり知りたまひてぞ】- 主語は権中納言。
【さりとも】- 権中納言の心中。『集成』は「いくら源氏方の勢力が強くとも、まさかお見捨てになるまい」。『完訳』は「わが女御への帝寵は衰えまい」と注す。
【思されける】- 「れ」自発の助動詞。自然とそのように思われるの意。
|
| 4.3.7 |
|
しかるべき節会などにつけても、「この帝のご時代から始まったと、末の世の人々が言い伝えるであろうような新例を加えよう」とお思いになり、私的なこのようなちょっとしたお遊びも、珍しい趣向をお凝らしになって、大変な盛りの御代である。
|
宮中の儀式などもこの御代から始まったというものを起こそうと源氏は思うのであった。絵合わせなどという催しでも単なる遊戯でなく、美術の鑑賞の会にまで引き上げて行なわれるような盛りの御代が現出したわけである。
|
【この御時よりと、末の人の言ひ伝ふべき例を添へむ】- 源氏の心中。『集成』は「聖代と仰がれるような立派な前例を遺すのが補佐の役目である。以下、今上の治世を聖代と印象づける筆致」と注す。
|
|
第四段 嵯峨野に御堂を建立
|
| 4.4.1 |
|
内大臣は、やはり無常なものと世の中をお思いになって、主上がもう少し御成人あそばすのを拝したら、やはり出家しようと深くお思いのようである。
|
しかも源氏は人生の無常を深く思って、帝がいま少し大人におなりになるのを待って、出家がしたいと心の底では思っているようである。
|
【今すこしおとなび】- 以下「世を背きなむ」まで、源氏の心中。
【思ほすべかめる】- 「べかめる」連語、推量の助動詞。源氏の心中を推量。この主観的推量は語り手。
|
| 4.4.2 |
|
「昔の例を見たり聞いたりするにも、若くして高位高官に昇り、世に抜きん出てしまった人で、長生きはできないものなのだ。
この御代では、身のほど過ぎてしまった。
途中で零落して悲しい思いをした代わりに、今まで生き永らえたのだ。
今後の栄華は、やはり命が心配である。
静かに引き籠もって、後の世のことを勤め、また一方では寿命を延ばそう」とお思いになって、山里の静かな所を手に入れて、御堂をお造らせになり、仏像や経巻のご準備をさせていらっしゃるらしいけれども、幼少のお子たちを、思うようにお世話しようとお思いになるにつけても、早く出家するのは、難しそうである。
どのようにお考えなのかと、まことに分からない。
|
昔の例を見ても、年が若くて官位の進んだ、そして世の中に卓越した人は長く幸福でいられないものである、自分は過分な地位を得ている、以前不幸な日のあったことで、ようやくまだ今日まで運が続いているのである、今後もなお順境に身を置いていては長命のほうが危い、静かに引きこもって後世のための仏勤めをして長寿を得たいと、源氏はこう思って、郊外の土地を求めて御堂を建てさせているのであった。仏像、経巻などもそれとともに用意させつつあった。しかし子供たちをよく教育してりっぱな人物、すぐれた女性にしてみようと思う精神と出家のことは両立しないのであるから、どっちがほんとうの源氏の心であるかわからない。
|
【昔のためしを】- 以下「齢をも延べむ」まで、源氏の心中。
【世に抜けぬる人の、長くえ保たぬわざなりけり】- 「の」格助詞。『完訳』は「世にぬきんでてしまった人は、とても長寿を保つことができなかったのだった」と訳す。
【今より後の栄えは、なほ命うしろめたし】- 『集成』は「今後も栄華を貪っては、やはり命が心配だ」。『完訳』は「今よりのちの栄華は、やはり寿命がともなわず危ぶまれる」と訳す。
【山里ののどかなるを占めて、御堂を造らせ】- 次の「松風」巻によれば、嵯峨野の御堂。清涼寺がモデルとされる。
【仏経のいとなみ添へてせさせたまふめるに】- 「させ」使役の助動詞。「める」推量の助動詞。この主観的推量は語り手。以下の文章にも語り手の言辞がうかがえる。
【末の君たち、思ふさまにかしづき出だして見む】- 源氏の心中を間接的に語る表現。夕霧十歳、明石姫君三歳。
【いかに思しおきつるにかと、いと知りがたし】- 『集成』は「草子地」。『完訳』は「源氏の人生の奥行の深さを暗示させる、語り手の言辞」と注す。
|
| 著作権 |
| 底本 |
大島本 |
| 校訂 |
Last updated 9/21/2010(ver.2-3)
渋谷栄一校訂(C)
オリジナル
修正版
比較 |
| ローマ字版 |
Last updated 10/20/2009 (ver.2-2)
Written in Japanese roman letters
by Eiichi Shibuya(C)
オリジナル
修正版
比較 |
ルビ抽出
(ローマ字版から)
|
Powered by 再編集プログラム v4.05
ひらがな版
ルビ抽出 |
挿絵
(ローマ字版から)
|
'Eiri Genji Monogatari'
(1650 1st edition) |
|
Last updated 7/8/2001
渋谷栄一訳(C)(ver.1-2-2)
オリジナル
修正版
比較 |
|
|
Last updated 10/20/2009(ver.2-2)
渋谷栄一注釈(C)
オリジナル
修正版
比較 |
|